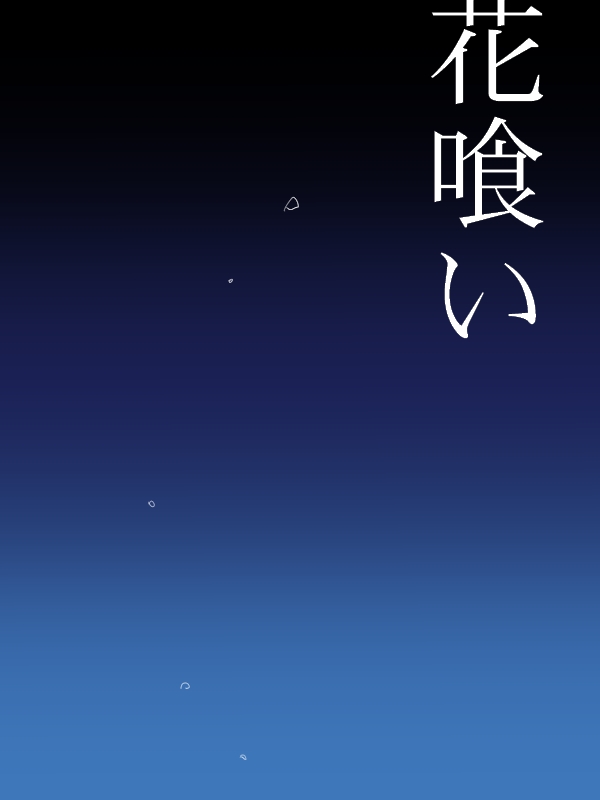
花喰い
苧環----------おだまき
夜の道をただ、走る。
なぜなら、追いかけられているからだ。
なぜ追いかけられるのか、毛利ミチルにはわからない。
ただ、ひとつ思い当たるものがあるとすれば、それは「異能者」、いわゆる「ネクター」だからだろうか。
必死に走って、走って、走って、とうとう行き止まりに、という漫画やドラマでよくある展開になった。
「止まってください」
機械的な声がきこえる。
実際機械なのではないかというほどつめたく、凹凸がない。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ」
ミチルの呼吸音だけが、この都会のすすけた道にひびく。
あれほど走り回ったのに、目の前の女はまったく、ひとつも、息切れをせず、たんたんと話している。
「止まってください。こちらは、警視庁異能捜査課です。異能を使わないでください。使えば、反抗とみなします」
「・・・」
闇から出てきたのは、まるで、ロボットのような――機械的なものではなく、すべらかな塗装をされている、女性だった。
これは、ニンゲンではない。
ロボットだ。
これまで、掃除ロボットとか、AIを搭載されたロボットだとか、そんなあいまいなものしか見たことがない。
「あ、あんた、一体…」
「繰り返します。こちらは、警視庁異能捜査課です。異能を使わないでください――」
うなじまでの短く、金糸雀色の髪をした女性型のロボットは、こちらに手をむけたまま、こつこつと歩いてくる。
一字一句まちがえず、淡々と話してくる女性型ロボットに、両手をあげた。
ああ、なぜおれに異能など、備わってしまったのだろう。
おれはただ、ふつうに暮らしたかっただけなのに。
そんなミチルの思考など、知らぬ存ぜぬ、ただ女性型ロボットはミチルを軽々ともちあげて夜の街を飛んだ。
「う、うわあ…っ」
なさけない声を出し、屋根の上や電柱の上を軽々と飛んでいくロボットにただ担がれたまま、びゅうびゅうと夜の秋風を頬にまともにぶつかる。
「このまま、あなたを警視庁異能捜査課に輸送します。繰り返します。このまま、あなたを警視庁異能捜査課に輸送します」
おなじ言葉をこわれた人形のように繰り返しているロボットが、まるで危ないから手を離すな、とでも言っているかのようで、必死にすがりつく。
夜の街を、ミチルと女性型ロボットはまるで、流れ星のように駆けて行った。
こんな夜中でも、警察というものはよく動いている。
まるで見せ物だ。
遠慮のない、「じろじろ」という視線を背中に受けながら、ミチルはロボットに「連行」されて、奥の部屋へと歩いてゆく。
どうしてこうなった。
ミチルはぐるぐると頭をかける疑問を整理していた。
たしか、友人と課題を一緒にやろうと、友人宅で課題を必死に片付けていて、そうしたらすでに夜。ついでに夕飯を馳走になって、帰ろうとした途中こんなことに。
「うう…」
ミチルは祖父に警察に連行された、などと馬鹿正直に言ったら、どんな雷がおりてくるか分からない恐怖に苛まれていた。
警察よりも、祖父が怖い。
それにしても、よく見れば見るほどよくできたロボットだ。
白い装甲が、照明に反射してとてもまぶしい。
金糸雀色の髪も、きらきらとしていて、まるでほんもののカナリヤのようだ。
「失礼します。連行しました」
銀色の扉のむこうに話しかけた後、すぐに女性の声で「入って」と簡潔に伝えられる。
ドアがスライドして、小心者のように中に入ると、そこはごくごく普通の「部屋」だった。
刑事ドラマでよく見る、すこし散らかった、書類なんかを挟むファイルや、ロッカー、そして本棚が並んでいるだけの、生活感がある部屋が、目の前に広がっている。
「おや」
おや、とすこし間の抜けた女性の声。
きいきいと軋んでいる椅子に足を組んですわっているのは、肩までの亜麻色の髪、むらさき色の目をした、綺麗な女性だった。
「おやおや、サキウス。その子は『違う』よ」
女性はおおきくため息をついて、こめかみに手をあてる。
人の顔を見て、ため息をつかれてしまった。
ミチルはわずかに腹がたったが、警察内だ。下手に声をあげてもどうにもならないだろう。
サキウスと呼ばれた女性型ロボットは、意味がわからないのか頸を傾けている。
「どうやら、まだ人物認識が充分に働いていないようだ…。かんさき、おい、かんさき。いないのか」
つれてこられたというのに、ミチルの存在をおもいきり無視している。
呆然としているミチルの前に立つ、サキウスの顔がこちらをむいた。
「あなたは、『違う』そうです」
「…そうみたいだね。よく分からないけど」
金糸雀色の髪の毛がゆれて、露草色の目がこちらをじっと見据える。
やはり、ロボットであるからか、表情がない。
まるでガラス玉のように、ミチルの顔を映しているだけだ。
「はいはい、なんですか、櫻木さん」
隣の部屋からでてきた和服姿の男性は、ぼんやりとした目でミチルを見下ろす。
「ああ、きみ、運が悪かったね」
「は…?」
「間違って連れてきてしまったみたいだ。ほら、サキウス。謝りなさい」
長身の男性は、まるでサキウスをみずからの子どもを謝らせるように、肩に手をあてた。
彼女はこうべを垂れて、「ごめんなさい」と子どものように謝ってくる。
「あ、い、いえ…」
「まあ、ここに座ってくれ」
早く帰りたい思いを押し殺して、素直に椅子にすわった。
「櫻木さん。いいから落ち着いて、こっちにすわりなさい」
「ん?ああ、はいはい」
サキウスは立ったまま、どこかへ視線をさまよわせている。
なにかを探しているのだろうか。ロボットが考えている事など、ミチルには分かりはしないが、妙に気になる。
櫻木と呼ばれた女性が椅子にすわると、ふたたび彼女は足を組んだ。
「まずは、自己紹介をしようか。俺はかんさき。こっちは櫻木鐙子。で、そこに立っているアンドロイドはサキウス。きみは?」
なまえを知らないということは、やはり彼女――サキウスの、人違いだったのだろう。
「毛利ミチルです。あのう…何故おれは、連れてこられたんでしょうか…」
「それは、ま、人違いってことで許してくれるかな」
かんさきは亜麻色の髪をゆらしながら、軽く手をあわせた。
勘違いで連れてこられたということはわかった。
それよりも、ミチル自身、『警視庁異能捜査課』というやっかいな組織に目をつけられないように、びくびくとしながら生きてきたのだ。
いまさら、せっかくの日常を壊したくない。
そう思考するミチルの心情をあざわらうかのように、かんさきは言い切った。
「きみは、異能者だね?」
「・・・」
「隠すと、のちのちやっかいなことになるよ」
鐙子が、どこからか持ってきたマグカップにくちびるをつけて、こちらを見つめる。
その目は、ひどく獰猛で、今にも噛み付いてきそうな目の色をしていた。
「…そう、ですけど…おれは別に、悪用していないし…」
「それが問題なのさ。私はね、毛利君。きみが保守派だということは知っている」
「!!」
「どうしてわかったかって?そりゃ、分かるさ。いい言い回しがないけど、目を見ればね。きみは臆病なうさぎのような目をしている」
うさぎとたとえられたのは、ミチル自身二回目だ。
しかも、臆病とまで。
だが、ミチル自身ほんとうのことだからか、喉につっかえた虚偽を飲み込むしかない。
「中立派は、私たち異捜と張り合ったり、過激派と張り合ったりしていることを楽しんでいるふしがある。だから、臆病者はいないのよ。だからといって、過激派っぽくないし」
「はぁ…」
鐙子はまるで誇らしげに言い切ったあと、コーヒーを一気に飲み込んだ。
まるで、酒でもあおっているようだ。
「まあ、私たちとしても、罪のない異能者たちを捕まえる権限なんてない…と言いたいところだが、なにが何でも異捜以外の異能者たちを捕まえようっていう人間もいる」
「・・・」
「脅しているわけじゃないんだが…そういう異捜の人間もいるってことだ。だからこそ、アンドロイドが必要なんだけどね…」
「私たちは、感情がある。怒り、悲しみ、とかね。そんな感情があるから、罪のない異能者たちをしょっ引いてしまう事もある。でも、サキウスは違う。AIは確かに搭載されているけど、自分の意思で動くことはない。常に誰かが命令し、そのとおりに動くのよ」
そういわれてみれば、今まで、自分から何かを伝えようとする彼女を見たことがない。
だからだったのか。
同じ言葉を繰り返していたのは。
「でも、知っているとおり、異能者たちは『異能』を使わなければ、いずれ能力に喰われて発狂し、そして死んでしまう。まあ、意思が強ければ強いほど、殺されずにはすむけど。私が思うに毛利君。きみみたいな子は、発狂してしまう確率が高いわ」
「…分かっています」
自分のこの臆病な性格は、生まれもったものだ。
変えようとするつもりもなかったし、これからもたぶん、変えられない。
だから、自分と言う存在がこの世から消えるときは、きっと狂い死になんだろうな、と薄々分かっていた。
「…そう。分かっているのなら、いいわ」
鐙子はうなずいて、立ったまま、一ミリも動かないサキウスを見上げた。
「じゃあ、悪かったね。サキウス。毛利君を送っていってあげて」
「了解しました」
「おれは一人で大丈夫です」
「まあまあ、いいじゃないか。最近は物騒だ。きみだってまだ未成年だろう?」
ほほえむかんさきの目が、わずかに細められる。
その笑みは何なのか。
まるでこれから先におこることを予知しているような表情をしていた。
警察署の外に出ると、ひどく冷たい風がミチルを襲った。
いまだ10月になったばかりだというのに、寒い。
トレンチコートを着てくるのを忘れた自分を、すこしだけ呪う。
インナーとして着ているパーカーの袖を無意味に引っ張る。
「…寒いな…」
すでにこのあたりの地形を読み込んであるのか、サキウスは真っ直ぐミチルの家へとむかっていた。
ひとりむなしく呟いても、サキウスは反応しない。
それはそうだろう。
先刻、鐙子が言っていた。
あらかじめ命令していなければ、無意味な行動はしない、と。
それって、さみしくないのだろうか、とやはりアンドロイドに対して無意味な事を思うも、無意味だと知っているからこそ余計、むなしくなる。
「あの…サキウス、さん」
とりあえず話しかけてみることにしたミチルは、いきなり立ち止まったサキウスに思いっきりぶつかりそうになった。
「私の名前はサキウスサンではありません。サキウスです」
くるりときれいにターンして、彼女はふたたび歩き出す。
それでも初めて、会話らしきものができたような気がする。キャッチボールにはまだ遠いが。
「敵影感知」
それは、いきなりだった。サキウスの凹凸のない声が、ミチルの耳朶を通り過ぎる。
「!?」
サキウスがいない。
今、ついさっき、ここにいたというのに。
ひゅっ、という風を切る音が聞こえ、ミチルの足元に、何かが突き刺さる。
それはすんでのところで足を下げて地面に突き刺さる何かを受けることはなかったが、代わりに腕にわずかな痛みがうまれた。
「…異能者か?」
せっかくのパーカーが腕ごと切られてしまって、すこしだけ憤慨する。
ひとりごちると、うしろでひどい爆風が背中を押した。
「うわっ」
ミチルが情けなく悲鳴をあげてうしろを振り返ると、そこに一人の女が立っている事に気付く。
そこには、街灯がなくともわかるような、派手な朱色の髪をパーマでゆるく巻いているのだろう、長い髪を風にゆらゆらとゆらせていた。
「うふふ。こんばんは、よい夜ね」
「・・・」
サキウスはミチルに背を向け、守るように背を低くし、いつでも飛びかかれるような体制をしている。
女の声はとても朗らかで、まるで「ごきげんよう」とでも言えるような声色をしていた。
「だ、だれだ、あんた…異能者か?」
「ええ、そうよ」
女は躊躇うことなくうなずいて、すうっとサキウスを微笑みながら見据える。
「私は天谷ちなみ。何の派閥かはもう分かっているみたいだけど…ねえ?サキウスちゃん」
「私の名前はサキウスチャンではありません。サキウスです」
「ああ、分かっているわ、サキウスちゃん。今日はね、私、…あなたを破壊しにきたの」
天谷という女は、いきなり物騒な事をささやき、頸にかけているペンダントをむしりとって、そのなかのものを手にかける。
そうして、コンダクターのように両腕を広げた後、透明な大きな粒が天谷のまわりをとりかこむ。
「水だ…。サキウス、逃げろ!!」
思わず叫ぶも、サキウスにとって、「逃げろ」という表現は意味のない信号になってしまうのか、抵抗とみなして天谷に突っ込んでゆく。
天谷ちなみは、たぶん水を操る異能を持っているのだろう。
100パーセントの力を出せる純血だったならば、ミチルに勝てる要素はない。
なぜなら、ミチルはふたつの異能を持つ、混血だからだ。
混血はどちらか一方の異能の、100パーセントの力は出せない。
せいぜいふたつあわせて100パーセント程度だ。
ぱっ、と水しぶきが頬にかかる。
「…!?」
その直後、水蒸気が視界を遮った。
視界が閉じられて、なにがなんだか分からない。ただ、上も下も右も左もないような、不可思議な空間に閉じ込められてしまったかのように。
「サキウス!」
がちゃ、がちゃ、となにかを引き摺るような音をたてて、水蒸気のなかから誰かが現れようとしている。
それがサキウスだとねがって、ミチルはただ、固唾を呑むしかなかった。
「…サキ…」
朱色の長い髪。
それをたゆらせながら、天谷が水蒸気のなかから出てくる。
「…あらぁ。残念。サキウスちゃんじゃなくて。ねえ、あなた」
スニーカーを履いた足が、一歩、さがった。
「サキウスちゃんに逃げられちゃったみたい。だから、あなたが遊んでくれ、る?」
少女のように純粋で、無邪気な声で以って、頸をかたむける。
逃げられた。
サキウスは、逃げたのか。
ミチルの内心はわずかに複雑だった。
アンドロイドとはいえ、女性に守られることが恥ずかしかったのかもしれないし、守ってくれると確信していたからかもしれない。
「…いやだ、と言っても、どうせ『遊ぶ』んだろ?」
「まぁっ。よく、分かったわね。じゃあ、ご褒美に苦しまずに殺してあげる!」
ころころと、鈴がころがるように笑う天谷のまわりに、ふたたび水が集まってくる。
水蒸気中の水を利用したのだろう。
ここは、天谷のテリトリーだ。
だが、ミチル自身のテリトリーでも、ある。
ミチルには、冷気を操る異能があったからだ。
水の鎌が、ミチルが避けた場所を切り裂く。
わずかに残った髪先が切れたが、ミチルにとってはどうでもいいことだ。
今の最優先事項は、生き延びること。ただそれだけだが、今はいちばん難しい。
なぜなら、相手が純血なのか混血なのか分からないからだ。
「くっ」
うめき声が自分の喉から搾り出されて、地べたに這いつくばる。
その立っていた場所を、水の鎌が切り裂いた。
直後、ミチルは立ち上がって、廃墟となっている工場の塀へ『飛び乗る。』
ミチルのもうひとつの異能、重力を操る異能を持っているから、身体の重力をそれなりに抑えることはできる。
だから、どこかからどこかへ飛び乗ったり、空中の重力を操り、体を押さえつけたりできるが、純血ではないから決して重力を「ゼロ」、無重力状態にはできない。
ひゅっ、と空気を切り裂き、次々と塀を凍らせて粉砕してゆく。
それで分かった。
天谷ちなみは、純血ではないということが。
水を操るだけでは凍らせて粉砕するなどということはできない。
たぶん、ミチルとおなじ――冷気を、扱うことができるのだろう。
ミチルはただ、塀の上を思い切り走って、足を踏み外しても重力を操り、落ちないようにしているが、天谷のほうが戦いなれているのだろう、足が速い。
「ほらほらほら!どこまで逃げ切れるかしら!?」
こういう、異能でヒトを傷つけるような感覚と言うのが、ミチルには分からない。
そもそも、ヒトを傷つけてなんの得があるというのか。
ただ疲れるだけだ。
びゅんっ、
空気が振動する。
その風は熱をおびていて、涼しい秋風というよりも、夏の、湿った熱風といえばいいのか。
それが頬をかすめた。
暑い、というよりも、熱い。
ミチルは自身の体を軽くして、廃墟に一本飛び出ている、電柱のうえに飛び乗った。
「あ…?」
どん、と何かが爆発するような音が耳をつんざく。
そして、ふたたび目下でひどい範囲の水蒸気が立ち込めてゆく。
「サキウス…?」
じわじわと地面を湿らせながら、水蒸気が晴れていく合間に見えたのは、サキウスの月夜に銀色にかがやく装甲だった。
金糸雀色の短い髪の毛をゆらしながら、こちらに気付いたのか視線をあげる。
電柱のうえから飛び降りると、そこに天谷ちなみの姿はなかった。
「敵影消失。逃げられました」
「逃げたんじゃ、なかったのか」
「逃げる…?私は、逃げる事ができません」
「そうなのか?」
サキウスは何事もなかったかのように、廃工場を後にしようと足を動かす。
しかたなく、この数分で蓄積された疲労をむりやり無視して、彼女のあとをついていく。
「逃げる事ができない、か…」
ひとりごとを呟いても、彼女にはやはり、意味のない信号なのだろう。答えは返ってこなかった。
逃げる事ができないって、それは、ものすごく怖い事なのではないだろうか。
ミチルはそう思うも、彼女にとって感情は無意味な信号で、不必要なゴミのようなものなのだろうか。
そう考えると、すこしだけ、「かわいそうかな」とおもう。
だが、それをすぐに打ち消す。
かわいそう、と思うことなんて、柄じゃないし、そこまで強くない。
ミチルは、自分は決して強くなんかない、と自負しているのだから。
中秋の満月も過ぎても、月はきれいだ。
ぼんやりと月を見上げながら歩いて、そろそろだろうと視線を下に戻す。
そろそろ、つく。
赤い鳥居と、石階段。
「亜由多神社。ここがあなたの家ですね」
「ああ…そう」
サキウスは鳥居を確認して、「任務完了」と独り言をつぶやいた。
「サキウス、…その、今日はありがとうな」
「私は任務を遂行したまでのことです。それでは」
彼女は一度もふり返ることなく、金属音を鳴らしながら去ってゆく。
今日のことは、たぶん、すぐ忘れるだろう。
ミチルは、ただ漠然とそう考えた。
特別なことだって、いずれ忘れるのだ。
かわいがっていたペットの存在を、ときおり忘れてしまうように。
--------女郎花
「ああ、何だお前、帰ってたのか」
祖父の水位が冷えた、くらい廊下に立っていた。
白い寝巻きを着ているから、幽霊かとおもった。
「な、なんだよ。起きてたの?」
「おお。隣のうちに寄ってただけだ。さっさと風呂入って寝ろよ。飯、食ってきたんだろ」
「うん…」
祖父は大きな欠伸をして、ぼりぼりと肩をかきながら自分の部屋へもどっていく。
静まり返った家は、まるで深夜のせいか眠っているようにも思える。
「・・・」
祖父には、ミチルが異能者だということを話していない。
水位は年のせいか心臓がよわく、ミチルがもしも異能を持っているということが知られてしまったら、どうなるか分からない。
実際、ニュースや新聞で見かける、あきらかに過激派の異能者の仕業だと思われる事件を、祖父はひどく嫌悪しているのだから。
唯一の肉親である祖父に、嘘をつきとおさねばならない。
それは決して容易いことではない。必死に、びくびくとしながら神経を尖らせているミチルは、嘘をつくことが上手ではないから、どこまでつきとおすことができるのか。
今日は大失態だった。
異捜に目をつけられるとは。
必死に物陰にかくれて生きてきたというのに、今までの努力がだいなしだ。
すこしだけ長くなった青緑の髪をかいて、はあ、と息を吐き出す。
湯浴みをして自分の部屋にもどると、携帯が点滅していた。
「萩野かな」
タオルを肩にかけて、携帯を開くと見知らぬメールアドレスの下に、驚愕に値するなまえがあった。
それは今日、共に必死に課題を片付けた秋草満載の名前である『萩野芒』ではなく、『櫻木鐙子』の名前であった。
思わず携帯を落とす。
なんてことだ。
携帯のアドレスを何故、異捜が知っているんだ。
「・・・」
黙って、携帯を閉じる。
今じゃスマートフォンなんかが流行っているみたいだが、まだミチルはガラケーだった。
理由は変えるのが面倒くさいからだ。
「見なかったことにしよう…」
布団を敷いて布団の中に入ると、いきなり携帯が鳴りはじめる。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの「ピアノソナタ第8番ハ短調作品13『大ソナタ悲愴』」が悲愴感たっぷりに鳴り響く。
短調らしい、暗くかなしい曲が流れている。
「・・・」
これは、メール受信の音楽だ。
そのうち止まったが、ぴかぴかと緑色に点滅している携帯は、「早く見ろ」とでも言っているようだ。
仕方なく布団のなかで身動きして、携帯を開く。
「…櫻木鐙子です…」
一回目のメールの文章は見なかったが、たぶんおなじような文章が書いてあるのだと勝手に決めて、二回目に送信されてきた文章を、諦めて読むことにした。
今日のことを、サキウスから聞きました。
なんでも過激派とやりあったらしいですね。
このメールを読んでいるということは、五体満足で家に帰れたということ。よかったわね。
本題ですが、明日、大学の講義が終わり次第、警察署に来てください。
なにも、出頭と言うものではありません。
あなたには、なんの罪もないのだから。
ただ、サキウスがあなたに興味を持ち始めたようです。
なぜかは分かりません。それゆえに、調べたいのです。
かんさきもあなたを気に入ったようす。
美味しいコーヒーでも用意して、待っています。
かしこ
「かしこ…」
いや、問題はそこではない。
ミチルの静かな生活が、一転しようとしている。
だが、異能を持ってしまった身。
けっして、静かな生活を送れるわけがないと、どこかで分かっていた。
理解したわけではないが。
この理不尽で、矛盾に満ちた世界で、平穏な生活だけを送れる人間は、きっといない。
どこかで曲がって、歪曲してしまっているのだろう。
「分かって、いたけどね」
独り言がまるで、子守唄のように聞こえる。
結局、携帯をにぎりしめたまま翌朝までねむってしまった。
講義の合間をぬって、併設されている喫茶で紅茶を飲んだ。
頭が痛い。
コーヒーを飲める気分ではない。
余計頭痛がしそうだ。
「どうした、ミチル。頭痛いのか」
「あ、ああ、うん。芒、課題は大丈夫なのか」
「うおっ!そうだった!今日提出だったよ…」
真向かいで必死に課題に精を出している萩野のつむじを見下ろす。
ミチルの課題は、すでに昨日終わらせてあるからいいものの、どうしても頭痛が思考を邪魔する。
こめかみを押さえて、眉をしかめた。
「・・・」
「ミチル!ミーチール!」
どこか興奮している芒の声で、重たい頭をむりやり上げると、スマートフォンの画面をつきつけられる。
「?」
「合コン、今日だってさ。どうする?行く?俺は行くけど!」
「元気だな…。けど、おれは今日、けいさ…いや、行くところがあってさ…」
「ふうん…。じゃ、しょうがないか」
浮かれているのか芒は、ミチルが言いかけた言葉を特別追求せず、ふたたび課題のA4用紙に目をおろした。
特別、ミチルとて合コンやコンパに出たくないような人間ではない。
確かに面倒くさいということもあるが、祖父である水位には「人間とはコミュニティーがあるからこそ成長できる」という、神主らしいような、らしくないような言葉を受けている。
なるほどそのとおりかもしれないと思い、ミチルは積極的ではないがそこそこ、浅く広く人と接してきた。
あまりにも人と接しないというのも、それなりに目立つ。
「そろそろ時間だ。芒、課題終わったなら行くぞ」
「お、おう!」
せわしなく鞄に課題を詰め込む芒を待ってから、教室に向かった。
次の講義は心理学だ。
なぜ心理学をとったかというと、特別理由はないが、人の心理にすこしだけ興味があったから、としかいえない。
人はなぜ悩むのか。
人はなぜ考えるのか。
そう、原初的なものに、ミチルはわずかな興味があった。
心理学の教授は壮年の男性で、白髪まじりだがきびきびとした声で、分かりやすく、丁寧に教えてくれている。
その教授の名は、|琴柱という。ミチルが初めて覚えた、教授の名だった。
「このように、愛とは、恋愛、友情、親子の愛、そして、祖国愛なのがある。もっとも重要なのは…」
人間愛である。
人間を人間として愛する心を、人間愛というらしい。
そういえば、プルーストの「失われた時をもとめて」という本に、
『愛するということは不運である。おとぎばなしのなかの人々のように、魔法が解けるまでそれに対してどうすることもできないからだ』
と言っていた。
ファンタスティックな文章だ。
ミチルはいちばん初めに読んだとき、『魔法が解けるまで』という言葉に目がいった。
そうだ。
きっと、そういうことなのだ、とわけも分からず納得してしまったものだ。
はっ、と頭をあげると、すでに90分は過ぎ、講義は終わっていた。
芒の姿もなく、ただミチル一人、机にむかっていた。
「…薄情なやつめ…」
置いていった芒に悪態をつくも、いないのだから仕方がない。
この後、とった講義はない。
ゆえに、あの警察署へ赴かねばならないのだ。
憂鬱が頭痛に変わる。
せめて時間を遅らせようと、ゆっくりと鞄に筆記用具を仕舞った。
そんな事をしても、無駄なのだが。
知っているからすこしだけ、むなしい。
校門を通り過ぎて、頭痛がする頭を抱えながら警察署に向かう。
澄んだ秋空をみあげて、ここはもしかすると御伽噺のなかのものなのではないだろうか、とファンタジックな思いにかられた。
きっと、この御伽噺の作者は神で、ミチルはただの大根役者。
そして、芝居のへたな大根役者は、きっと死んでしまうのだ。
死ぬためだけに踊らされているのかもしれない。
それをむなしい、とミチルは思わない。
人の生は、どうにもならないことが多いのだ。
自由だとしても、その「自由」という枠にとらわれてしまっている。
人が死ぬまで、それは囚われたままなのだろう。
花喰い


