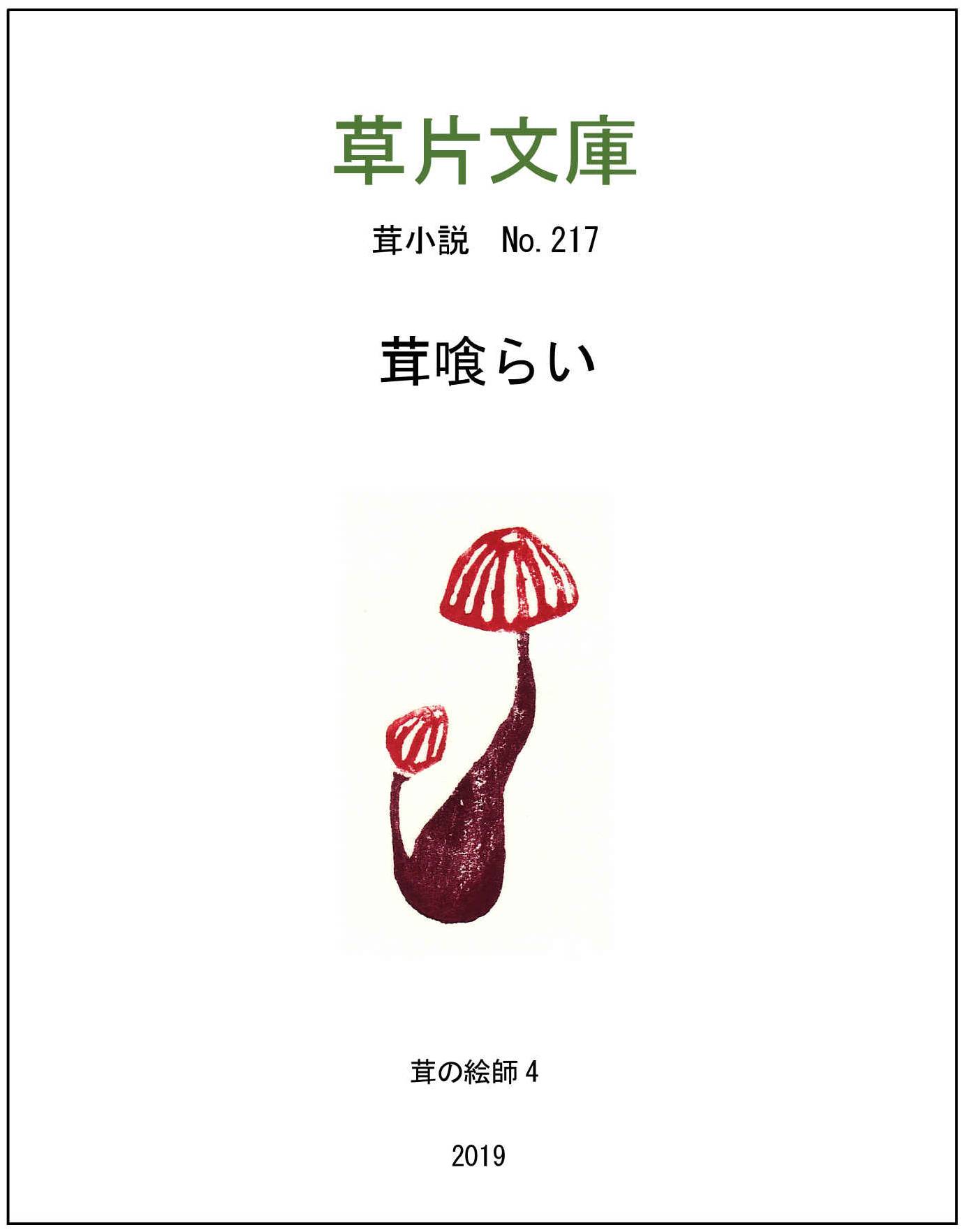
茸喰らいー茸の絵師4
ここのところ、「茸喰らいて候」と書かれた旗をもって歩いている、侍姿の男が噂になっている。うまい茸の佃煮も売っているが、それだけではない、旗に書かれているように、茸を食べてくれるのだ。
「おじさん、茸喰らいの侍、寺町の方にでたっていう話よ」
茸絵師、茸酔の家に奉公している姪の木野が、夕飯の支度をしながら、炊事場に水をとりにきた茸酔に言った。
その侍は町人が採ってきた茸を、毒か食べることができるか見分けてもくれるが、たのめば本人が食べて大丈夫かどうか試してくれるという。いうなれば毒味である。そのかわり、それなりの食事をださなければならない。
「頼む人なんかいるのかい」
「かなり繁盛しているということよ」
茸酔は毒味など頼む者などいるわけはないと思ったが、そうでもないらしい。
木野の話ではまず武家屋敷。そこの殿様が茸を好きだとなおさらで、仕入れた珍しい茸を実際に食べてもらうのはお毒味役だが、毒味役などおいていない武家の家にとって、助かることらしい。主が死ぬとお家が絶えることもあるので気をつけなければならない。
商人の家では必要はなかろうと思うが、むしろ茸好きな主人は、賄いの者たちに毒味しろなどというと、どのような目で見られるか分からない。そこでその侍をもてなして、食べてもらうということらしい。特に大商人の家から声がかかるという。時として茸ではなく、釣り上げた見知らぬ魚や、山野草なども毒味を依頼することがあるそうだが、草は引き受けるが、魚は断られるそうだ。
「その侍さんどこからきたのかな」
「知らない」
「茸を食べるだけでよくやっていけるものだ」
「売っている茸の佃煮がおいしいという話し、樽に入れて小さな大八車で押してくるんだって、よく売れてるんだって」
「その侍が、近くに来たら呼んでくれるか」
「うん」
茸酔はその侍からおもしろい茸の話が聞けるのではないかと期待。茸酔は茸の絵だけではなく、話も書くようになっていた。不思議な茸の話に絵をつけて本にするのである。
江戸の中堅どころの版元が、売れる読本を作りたいとその話をもちかけてきた。茸酔はせっせと茸を探しに行き、きれいな絵図にしていたが、文を書くことにはなれていなかった。話を書く人に書いてもらってそれに絵をつけたいと言ったのだが、版元は、素人の文章でいい、その方が身近に感じてよい、と言って、版元のほうで間違いを直すことを条件に引き受けたのだ。
それがやってみると意外と面白い。変な茸の話を江戸の人から聞くことができる。だれそれがどこの山で採った茸を食ったら、ひょっとこのような顔になって踊り出したとか、ばあさんが長屋の板塀に生えていた茶色い茸を醤油で煮て食った。すると急に色づいて、化粧を始めたとか、話しはいくらでもころがっていた。
一方、茸酔は茸採りの名人に会ってその極意を教えてもらったり、茸をおいしく料理する者に話を聞いて、茸に関する解説本も書こうと思うほどにもなっていた。ともかく、茸に関わる面白そうな事柄を拾い出し、話しにまとめる作業は、茸酔にとって今までになかった楽しみとなった。毎日が忙しく充実している。
そのようなある日、紙屋の旦那が顔を出した。頼んでおいた紙をもってきたのだ。
「茸酔さん、昨日ね、茸喰らいの侍さんから茸の佃煮を買いましたよ、そりゃあ、美味いものでしたよ、白い飯に茸の佃煮がとてもよかった、食べると何というか、幸せ感にひたりますな」
「それは何の茸でしたか」
「聞いたら紅茸半分に紅天狗半分といっていましたがね、そんな毒茸食えるわけがない、本当のところは教えてくれないってことざんしょ」
「そうだね、紅天狗は食べると気持ちがよくなって、頭がどうかなっちまうからね」
茸酔は紅天狗茸を食べて、知らない間に裸になって踊ったことがあった。
「茸喰らいのお侍にはどこに行ったら会えるでしょうか」
「気ままに歩いているようだから、どこにいるのかわからないですね、だけど一度きたところには現れないようだから、ここらがまだなら、いつか来ますよ」
待っていることしかできないようだ。
「それから、今日の朝早く、釣りに行ってきましてな、平目がたくさんかかりました、木野さんにわたしときましたよ」
「それはごちそうになります」
「それじゃ、あたしはこれで、今度越後の紙が入りますからもってきますね」
「おねがいします」
越後紙は茸酔お気に入りの紙である。
次の日の夕方のことである。木野が「茸喰らいて候」と旗をたてて車を押しているお侍が、雑貨屋の前を歩いていると言いにきた。
「どうしよう、おじさん」
「呼んできておくれ」
ほどなく木野に案内されて髭面の侍が茸酔の家の玄関にやってきた。
「おじさん。茸喰らいの人つれてきた」
茸酔が玄関に迎えにでると、でっぷり太った恵比寿さんのような男がにこにこと笑顔で立っていた。
「お役に立てることがありますかな」
丁寧な言葉遣いである。
「あ、よく来ていただきました、私は茸酔と申す絵師でございます。茸のお話をしていただければと思い、この娘に声をかけさせていただいたわけでございます」
「あ、こりゃ失礼、ためし食いじゃないのですな、わしゃ、信州の浪人者、田辺草衛門と申す者で、茸の佃煮や茸の薬などを売っておりましてな、茸の見分けを教えたりもしております。
一度江戸の地を踏んでみたいと思いまして、今年こうやって出てきた次第、茸の話とはどういうことでございましょうな」
「失礼しました、どうぞお上がりください、うえでお話をさせていただければと思います、木野、案内しておくれ」
「それでは、失礼して」
小さな大八車を玄関のわきにおくと、草衛門は玄関に入った。
座敷に上がった草衛門は、棚に積んである本をちらっと見ると、「お、ずいぶんたくさんの茸の本がございますな」と見たそうなそぶり。
「ごらんになりますか、どうぞ」
「よろしいですかな」、本を手に取ると開いた。
「これはすばらしい、特に佐渡の本は圧巻でございますな、これはみな茸酔どのが描かれたものですか」
「はい、薬を作る医師の手伝いに佐渡まで行って参りました、茸ばかりでなく、草木、魚、石からいろいろな薬を作る先生が、その方法を書き残したいとのことで、私は絵を描かせていただきました」
「わしも薬を作るが、この本はどこに行けば求めることができるのですかな」
「この出版元は今でも私の茸の本を出してくれています、越後の本屋ですが、私のところで取り次いでおります」
「高いのであろうな」
「はい、かなりのお値段がついております」
「いずれ、買いたい」
「そのときには、おとり計らいいたします」
「信州にはこられたことはあるかな」
「一度ありますが、まだ若い頃でした」
「奇妙な茸がたくさんありますぞ」
「また行きたいと思ってはおります、どうぞおすわりになってください」
茸酔は座敷に案内して、草衛門に座布団を勧めた。
そこに木野がお茶をもってきた。
「この娘は私の姪でして、木野と申します、茸採りも手伝ってもらっております」
「元気な娘子さんだ、大きな声で、茸喰らいさんと呼ばれましてな、びっくりしましたわ」
「はは、それは失礼をしました」
「いや、いや、元気が一番、茶をいただきます」
草衛門は手を伸ばした。
「それで、草衛門さま、今、わたくし本屋から頼まれまして、茸のおもしろい話を集めております、それに茸の絵をつけ、本にするわけでございます、茸のことはよくご存知のことと思います、茸について面白い経験などございましたら聞かせていただきたく、お呼びした次第です」
「おお、あるある、いろいろあるが、忘れることのできない、わし自身に関わる不思議なめにあったことがありますぞ」
「それはぜひお聞きしたいと存じます、話がつきるまでこの家にお泊りいただければ幸いでございます、ここから茸の佃煮や薬を売りに行かれるのもよいかと思いますが、いかがでございましょう」
「おお、それはありがたい」
「草衛門さまはお酒に強そうでございますな、すぐ用意させます」
「あ、それは結構、結構というのは、いらないと言うことでござる、わしゃ、下戸でな、飯はたくさん食うが、こんな顔をしておるが、酒は一滴も飲めませんのじゃ」
「失礼しました、魚は食べないと言うことも聞きましたが」
「そんなことはありませんぞ、魚の毒のことは知らぬので、魚の毒味はできないとは申しておりますが、食える魚は大好きでござる」
「それはよかった、昨日、平目をもらいまして煮てあります。一日たって、じっくり味がしみこんだ平目も旨いものです」
「それはいい、味が濃くなって、飯が何杯も食える、あ、いや、わしの茸の佃煮も食ってくだされ」
草衛門が小包にしてあった茸の佃煮を懐から出した。
草衛門とは気楽に話ができそうだ。
「それでは、湯でもお使いください。その間に夕飯の用意をします、食べた後にでもゆっくりとお話を聞かせてください」
「おお、それはありがたい、内湯とは贅沢なものですな、三日も湯に入っておりませんでな」
「この屋敷は、我が師、虎酔のものでしたが、亡くなったあと、私が住まわせていただいているものです、虎酔師匠は加賀のとある偉い方のお子さまだったことから贅沢な作りになっております」
「ほう、加賀の方の屋敷であったか」
「木野、草衛門さまを部屋に案内して、湯殿におつれしてくれ」
その後、草衛門は平目の煮付けで三杯も飯を食ったが、至っておとなしいもので、茸酔が思っていたほど豪放な御仁ではなく、かなり繊細な人間であることが知れた。
夕餉の後、茸酔は草衛門と自分の画室で話をした。
「草衛門さまはどうして、茸が好きになられたのでしょう」
「そうだのう、父も母もいたって平凡な人で、これといって際立った趣味があったわけではないが、食事は細やかで、手を抜くことをしなかったな。それも父の舌が肥えておったからだと思っている。決して贅沢をしたわけではないが、食材そのものの味を損ねることのないような料理を母は工夫していたな。兄が二人に似て、やることが細やかで、今は江戸の城で勘定方の一人として仕えておる、わしも父の跡をついで、松本の城で働き始めたのだが、見ての通り、城をやめ、茸の佃煮作りなどをやって暮らしておるのですわ」
「お城をおやめになって、ご両親様はなんとおっしゃいましたか」
「はは、あきらめておる、実は両親は江戸の兄の家に居候をしておるわ」
「それで兄上様やご両親様に会いに江戸にいらっしたのですか」
「いやいや、兄のところには顔をださん、小汚いわしが行ったら迷惑だろうからな、冬になる前に、信州に帰るつもりじゃ」
「そうでございますか、さて、茸の話をお聞かせいただけますでしょうか」
「わしには茸の師匠と呼べる人がおってな、その人に生きることを教わったんじゃ、その人のことを話すのはあまり気がすすまんのですがな、奇妙な茸の話でもあるし、おもいきって話してしんぜましょうかな、わしにとってつらい話でもござるのだよ」
「そうでございますか、お話いただける気持ちになられたときに、ゆるりと時間をかけてお聞かせください」
それから草衛門は半月ほど茸酔の家に滞在した。草衛門は少しずつだが、その奇妙な話をしてくれた。
「わしは城をやめ、家でぶらぶらしておりましてな、川で釣りをしたり、山で茸や木の実を採ったり、野菜を作ったりしておった。少しは飯の足しになるからな。
町のはずれの山を登ったときじゃ、おかしなばあさんに出会った。林の中でだ。旨そうな茸が生えていたから採ろうとしたら、そりゃ毒だよお侍さんと声がした、見ると籠をしょった白髪のばあさまがのぞき込んでおった。
そりゃ月夜茸じゃ、と教えてくれた。わしが礼を言うと、ばあさんは後ろを向いて林の奥にすたすた行っちまった。あとでそのばあさんが綿毛ばあさんと呼ばれている茸の神様のような人だと知ったんだ。
綿毛ばあさんは畑も耕さない、よその田の手伝いもしない、それなのに不自由なく暮らしていましてな、それはばあさんが周りに生えている草や木、茸、それに魚のことに精通していからだと後で知りましたな。
ばあさんは野、山、川から食材を集め、それにめっぽう料理が上手でな、それはうまいものを食っていたんじゃ。自分の子供はとうの昔に離れた村に嫁にいったきり顔は出さない、亭主は十年前になくなり、一人暮らしをしておった。
ばあさんは田菜を好んで食べた。田菜の葉はだれもが食べておったが、あのふわふわした綿毛を甘くおいしい菓子にしてしまうのだ。それで綿毛ばあさんと呼ばれていたわけだ」
田菜とは蒲公英のことである。
「魚だって捕まえて食べる。鯰を捕るのが上手だった。男の子たちが綿毛ばあさんを誘って、田圃の脇の水路にいく。最初に鯰を捕まえるのはいつも綿毛ばあさんだ。男の子たちはばあさんの鯰の捕まえ方を見て覚えようとする。
こうやって、そうっと水に入ってな、とばあさんは水の中で腰を落として、両手を、音を立てないように岸辺の草の覆ったところに差し入れ、おらよ、と大きな鯰を捕まえてしまう。鯰のいそうなところと動きをよく知っているのだ。子供たちもまねをしてだんだん上手くなっていく。
女子はばあさんについて野道を歩く。これはイタドリ、アララギ(ノビル)だ、と食べられる草を教わり、さらに親も知らない草の料理も教わる。
『そりゃあ、スベリヒユっていってな、食えるんじゃ』とばあさんが指さす。
『どうやって食べるの』子どもが聞くと、ばあさんは、
『生でもいいけどな、茹でると粘って旨いんだ』と教える。
『田菜はどうするの』
子供は田菜が好きでのう。黄色い菊のような花がきれいに咲いていると、ついつまみたくなる。咲き終わった後の綿毛もふっとふくと宙に舞う。
『これだってうまいんだよ、ごまとあえたってええ、ぺんぺん草やハコベラだって食える』
秋になると綿毛ばあさんの得意な茸狩りがはじまる。何しろ、どのような毒茸も簡単に見分けることができるんだ。茸の季節には、大人も子供もばあさんと一緒に山にはいる。茸だけではなく、木の実もいろいろ採れる。
綿毛ばあさんのところには、町の人たちが採ってきた茸を見せに来る。そこで毒茸と食べられる茸をわけてやる。もってきた人は毒茸をばあさんのところにおいて帰る。
ばあさんがほかってくれると言うからだ。
そうなると毒茸がたくさんばあさんのところに集まる。秋になると毎日のように毒茸が持ち込まれるので山となって残ってしまうんじゃ。
ここからが不思議なのである。ばあさんが村人のもってきた毒茸を捨てるのをだれ一人として見た者がいなかった。
ばあさんは毒茸を、少しだけならそのまま食べられるもの、ゆでれば食べられるもの、塩漬けにすると食べられるもの、すり潰すと薬になるものに分けて処理をする。
薬になる毒の茸は、乾燥させ粉にして蓄えておく。それを知っている者が買いにくる。多くは町の薬師からの使いだった。
ある毒茸は粉にして服用すると、怖い者知らずになり、戦で力を発揮する。それは武士が買いもとめた。ばあさんは今の世にそんなものいらんのに、と思いながらも売っている。ということで、綿毛ばあさんは食べるに困らないのだ」
「春のある日、ばあさんが子供たちをつれて土手を歩き、周りに生えている草を教えていたときのことじゃ、わしは川で釣りを終えて家に帰るために土手に上った。
ばあさんが子供に草を指さしてなにやら言っている。こりゃ、編笠じゃ、変なかたちだろ、と言っている。こどもたちは、気持ちわりい、とうなずいている。じゃけんど食えるんじゃ、うまいんだぞ、炒めてみろ、生じゃだめだがな、とかがんで採った。子供たちもまねをして採った。
わしゃな、どこかで聞いたことがある声だと思いながら、土手で子供たちがしゃがんでいるところを見た。でこぼこの色の悪い茸がたくさん生えていた。
ばあさんが振り返ってわしを見た。
わしはおもわず「あ、あのときの、ばあさま」と叫んだな、林の中で月夜茸を教えてくれたばあさんだ。
『いや、助かりました、危なく毒茸を採るところでした』
わしゃ礼を言った。ばあさんも覚えていたようで、
『おお、あのときのお侍さんかね、今日はなにかね』としわくちゃの顔をほころばせた。
『釣りじゃ、こんなに釣れたわい』
わしは魚籠の中を見せた。ウグイがたくさんはいっている。
『豊漁じゃな、この茸もうまいよ』
ばあさんは編笠茸を指差した。条件がよかったのかあちこちにたくさん生えている。
『お侍さん、採っていくといいよ』
ばあさんがそういうのでわしも茸を採った。
『本当に食えるんかい』
『そりゃあ、うまいよ、これから家に帰って、この子たちに茸炒めを作ってやろうと思うんじゃ、お侍さんもくるかい』
面倒見のいいばあさんだ。
『ばあちゃんが作るの旨いんだ』
一人の男の子がわしにそう言うと、周りの子供もみなうなずいていたな。
『この子ら、父ちゃん母ちゃんがでかけてるんで、ちょっとあずかってるんじゃ』
それではと、わしも、釣った魚も一緒に料理してもらえんかな、みなに食わしてくれ、とついていった。
ばあさんの家はわしの家とは方向が違う。町のはずれだが、なかなかいい作りの家であった。あとできくと、亭主がやり手の行商人だったそうだ。それで家を造るまでに出世した。亭主をなくしたばあさんは独りで住んでいた。
大きな土間があって、大きな竈があった。そこで小魚や茸の佃煮を作って、亭主が商をしていたということだった。
ばあさんは、ウグイを煮て甘露煮をつくり、編笠茸を炒めた。
子供たちは喜んで食べた。草衛門もその美味さに驚いた。最後にばあさんは壷から水飴のようなものを子供たちに食べさせた。
水飴の中に白いものが浮いている。甘い水飴だがその白いものがとてもきれいだ。
『こりゃなんでござる』わしゃ聞いた。
『タンポポの綿毛じゃよ、子供はこれが目当てじゃ』
そこで、このばあさんが綿毛ばあさんと呼ばれていることを知ったのだ。
食事を終えると、一人の子供に粉を飲ませた。
なにかなとわしが尋ねると、この子は咳の病でな、夜苦しくなるんじゃ、あたしが作った薬を飲ませておる、と言っておった。
今で言う喘息である。そのことで草衛門は綿毛ばあさんが薬の知識も豊富なことを知った。
『おばば、どうでござろう、佃煮の作り方を教えてくださらんか、それに茸の薬の作り方も知りたいのだが、いかがだろう』
『お侍さん、それでどうするね』
『わしゃ、はずれ者で、勤めもなく、なにか手に職をつけなければと思っておってなあ』
『そんな殊勝なことを、むずかしかないね、教えてやるから、売ったらどうだい、この竈を使っていいよ、それに薬も教えてやるから』
ばあさんは誰にでも親切でな、
『ありがたいことで、売れるようなものが作れるようになったあかつきには、売れた半分はおもちする』
そう言っても、
『いらないよ、今のままで十分だよ、もう先もないしね、佃煮の作り方を覚えてもらえりゃあええ、爺さまの作り出した方法じゃ、誰か知っててくれれば爺さま浮かばれるで』と、手をふるばかりじゃ。
『それなれば力仕事など何なりと申し付けてくだされ』
それで、茸の毒の見分けからから、茸の佃煮、薬の作り方まで教えてもらうことになったんじゃ」
そういう出会いから、草衛門は綿毛ばあさんから茸の佃煮や薬の作り方を教えてもらったそうである。
それだけではない、草衛門がばあさんの家にかよい、いろいろ教わっていると、秋になって、周りの人たちが知らないことを知ることになったという。ばあさんが茸毒にめっぽう強いのである。町の人たちがもってきた茸から食べられる茸をより分けて返すと、残していった毒茸をゆでたり、塩付けにしたりしながら毒を抜いて食べてしまう。しかも、たまに猛毒の茸を生のままで口に入れ、食べていることもあった。
草衛門はばあさんに聞いたそうだ。
「おばばはどうしてそんな毒茸を食っても平気なんだ」
ばあさんは答えたという。
「だんだんとだなあ、そうなったんだ」
草衛門の話だと、ばあさんは貧しい家に育ったという。
「綿毛ばあさんは、子供のころまともな物を口にすることはなかったそうだ。山のものを採って飢えをしのいでいた、多くの茸は毒なことを知っていたが、少しならいいだろうと思って、草と一緒に食ったそうだ。生のままだ。体質もあったのだろうが、そのうち毒茸を丸ごと一本食っても大丈夫になったという。
大きくなり、毒茸と食茸と区別ができるようになった頃は、どの毒茸を食っても大丈夫な体になっていた。ただやはり何本もいっぺんに食べるとおかしくなる。そこのところは自分の体の調子などを考えながら食べたそうだ。
年頃になったときには、毒そのものの味がわかるようになり、さらに毒の種類によって味が違うことに気がついた。
要するに知らない間に舌が毒を判別することができるようになっていたわけだ。その特技のおかげで、商売上手の男の嫁になることができたというのだ。それからは、亭主の売り歩く佃煮づくりや、薬づくりを手伝うようになったということである。
年をとって一人になってからは、先に話したように、綿毛ばあさんと呼ばれ、周りから頼られるようになったわけだ」
草衛門は半年ほどばあさんのところで、毎日佃煮を作ったり薬を作ったりした。毒茸と食茸の違いはわかるようになったが、毒茸の毒の違いまではわからなかった。それでも毒茸を少しばかり食べてもからだにさわらなくになり、ばあさんの佃煮や薬も一人で作ることができるようになったということだった。
それからは山の奥に自分の掘っ立て小屋をつくり、竈をつくった。一人で佃煮などを作ることができるようになったそうである。
「それで、その綿毛ばあさんは今どうしているんですか」
茸酔は聞いた。
「そこが信じられないような茸の話になるんじゃ、綿毛ばあさんは珍しい茸をずいぶんみつけて、自分で名前を付けて、食べられるものかどうか調べたんだ、いくつもそういう茸があるのだが、還暦になろうとするときに、ばあさんはこれから話す奇妙な茸にであってしまっての、ばあさんがいつものように、面白い茸がないかさがしながら、山の中を歩いているときだったそうだ。奇妙な舞茸をみつけたのだ、舞茸は白い奴と黒い奴があることは茸酔殿も知っておられるだろう」
茸酔はうなずいた。
「その舞茸は青色をしていたのだ、しかも毒だ。ばあさんがその舞茸に遭遇していたころ、わしは忙しくなり、ばあさんのところに顔を出すことをしなくなった。ともかく自分で茸も保存できるようになっていたし、薬を作ることも覚えたからそれを売り歩いていたのだ。それに茸を採りやすいように作った山奥のわしの家は、ばあさんの家まで半日かかるほど遠かった。佃煮を作って近隣の村に売りにでるとき、たまにばあさんの家によるぐらいじゃった。
久々に言ったときじゃ、ばあさんが青い舞茸を見つけたことを話してくれた。だがそのときその舞茸はなくて、本物を見ることはできなかった。
秋になったらまた採ると言っていたので、次に見せてもらうことにした。その舞茸は毒だが美味よ、と口元にしわを寄せて嬉しそうに笑っていたわい、そのころまだまだばあさんは元気だった。
わしもちょっといい薬を作ることができた。腰掛けの仲間から胃の腑がすっきりする薬をみつけた。これは腹の具合が何となく悪いと思うときに飲むとすぐよくなる。熊の胃は痛みを止めるものだが、わしが作ったのは、胃もたれ、食欲不振のときに、胃がすっきりしてな、食欲が増すのだ、わしが自分で試してみたところ、茸の毒に対してもわずかだが効くようだ。毒消しまでにはならんが、症状を和らげることができそうだった。それにかかりっきりになって、ばあさんには半年も会わなかった。
胃の薬ができたときばあさんのことが気になった、もういい年だ、それだけではなく青い舞茸はどうなったか、見てみたいという気持ちもあった。何か手伝ってやることはないかと、できた胃薬を持って、久しぶりに綿毛ばあさんのところへ行った。
家の入り口に顔を出したばあさんは元気そうだったが顔色が悪い。青味がかっておった。
『おばば、なんだか顔の色が違うがどうかしたのかね』
だが、ばあさんはいつものようにしわしわの笑い顔になった。
『青くなったと思ったんじゃろ』
わしははうなずいた。
『元気じゃよ、だが体が青色になりおった、ほら』
ばあさんが袖をめくると、腕がみな青っぽかった。
『どうしたんだ』
『これを食った、話ししたろうじゃ、青い毒の舞茸だ、たくさんみつけての』
ばあさんは乾燥させた大きな舞茸を小屋からもってきて見せてくれた。青い舞茸を乾燥して、いつでも食えるようにする方法もあみだしておった。
乾燥していても青色だった。大きさはそうだな、大きな釜ほどもあったかな、それで、さぞ大きなブナの木の下にでも生えていたのだろうと思ってそう尋ねた。
すると、いや、細いブナの木の下だということだった、まだ若い木の根本に大きく開いておったということだった」
「若い木に宿る舞茸だったのですね」
「わしも最初はそう思った、ところが綿毛ばあさんが言うにはな、最初、その林の古いブナ、おそらく何百年もたった奴だろう、その根本にもまだ小さな青色の舞茸が生えていたそうだ。それで、もっと大きくなってから採ろうと、数日たってから行ってみたが、大きなブナの木が見当たらない、しかし大きく育った青い舞茸は、覚えていたところに生えていた。脇には細いブナが生えていたわけだ。古いブナの木は倒れたわけではなく、どこかに消えてしまっていた」
「どういうことだかわかりませんが」
「そうなんじゃ、それでわしも不思議なのでそのことは聞いた、すると、ばあさんも何がなんだか分からんが、今年はこれから青い舞茸を採りに行く、一緒にいくかとわしに言った。わしはもちろん行くと答えたよ。
ばあさんが
『明日朝早いから、行くならうちに泊まれや』
と言うので、わしはそのままばあさんの家に泊まった。
夕時、おばばは乾燥した青色の舞茸をもどして、味噌をつけて食った。わしにもちょっと食ってみるかと、ほんの一かけらをくれた、それに味噌をつけて食ったらな、大変なことがおきちまった、苦いだけじゃない、口の中はひりひりする。わしはほきだしちまった、ばあさんは平気な様子で食べている。そのうち、頭の中がくらくらしてきてな、目の前に星がちらついてきた。すると、おばばが言ったのだ。
『星が出てきたら、今度は月がでてくるぞ、空を泳いだ気持ちになって、終りじゃ』
わしはその通りになって元に戻った。わしは聞いた。
『おばば、なぜ、こんな毒茸を食らってもだいじょうぶなのだ』
『なぜかのう、はじめはおまえさんが食ったようになったが、何度目からか甘く感じるようになっての、味噌をつけるとうまくて飯がすすんだんじゃ、ただ、体が青色になりおった』
『長寿の薬になるかもしれん』
『そうかもしれんな』
『わしが作った、腹がさっぱりする薬をもってきた、それを飲んだらどうなるだろう、毒消しになるかもしれん』
『どうじゃろ、もう一回青の舞茸を食ってみるか、それで、その薬を飲んでみたらよかろう、わしゃ、もう毒に強くなっているから、その薬がきくかどうかわからんよ、あんたさんならいいんじゃないね』
そう言われた草衛門は自分で作った薬を飲んで、青の舞茸を食ってみたそうだ。すると、苦くてひりひりするのは変わりがなかったが、星が見えたり月がでたりはしなかった。少しは効果がありそうだと思ったそうである。
草衛門はその話をおばばにした。
『そりゃあ、他の毒の茸にはもっと効くかもしれんな、やってみるといいのう』
おばばは青い舞茸をうまそうに食べながら言った」
草衛門は話を続けた。
「明くる朝、おばばにつれられて、山にはいった、大きなブナの木の根元に生えた青い舞茸をいくつかみつけた。しかしまだ小さかったので採るのはやめたが、ばあさんが、一つもっていきなと持たせてくれた。
ばあさんは至極元気でな、古希どころか傘寿までも生きる勢いだった。青い舞茸の効果かもしれんでな、それで安心して家にもどったんだ。もらった若い青い舞茸は乾燥させてとってある。
次にたずねたのは一年後の秋、茸の季節だった。青い舞茸をもう一度探してみたいと思ったからだ。
おばばの家に行って戸を開けるとな、土間のところに青色のおばばがふーっと立っていて、わしのほうを見ようとしないんだ、目がうつろなんじゃ、何じゃと思って足下を見ると、土間に青い舞茸が生えていた。おばばの目は宙を見ておったな、何も言わぬしな。こりゃおかしい、病に冒されているとわしは思った。
戸を開けたんで、日の光がおばばに当たった、すると見る間に青い舞茸がぐんぐんと大きくなってな、おばばは縮んでいくじゃないか、舞茸が釜の大きさほどになると、おばばは犬ほどの大きさになり、猫ほどにも小さくなって土間の上にたっておった、わしゃぞーっとして家を飛び出したんじゃ。
その足でわしはもう一度、おばばと行った青い舞茸の生えている森の奥に入った。
するとな、大きなブナの木の下にやっぱり青い舞茸が生えていたな、わしゃ、しばらく見ていたんだ、ちょうど日の光が少しばかりだがそのブナの根本に当たったんだ。するとな、青い舞茸がぐんぐんと大きくなって、ブナの木が細くなっていったんだ。とうとうブナの木は細い若木になってしまった、青い舞茸はブナの生を吸い取って細くしてしまう、そうして自分が成長したんだ。見ていたが全部吸い取ることはなかった。若木を残して、年をとったらまた青い茸の餌になるわけだ、そこでわしゃ気がついた」
草衛門は一息ついた。そして、あわててまたばあさんの家に戻ったと言った。
家にはいると、土間に、大きな青い舞茸の脇で、青い赤子がころんところがっていたそうだ。もう事切れていたという。
「わしゃ、途方に暮れた、おばばを見殺しにしたんだ、最後までみておれば生きていただろう、だが、もう一つ気がついたことがあった。もし、この赤子が大きくなったらどうなっただろうとな、青い色の人間など、誰も生かしておいてくれないだろう、見せ物小屋行きだ。これでよかったんだと、わしゃ自分にいいきかせたな」
草衛門はそれから、死んだ青い赤子を林の中に埋め、木の墓標をたてたそうだ。
一年後、草衛門が墓参りに行くと、その木の墓標は青い色に変わり、脇から青い舞茸が生え、墓標が消えてしまったということである。やがて舞茸はしおれ、茸虫が食ってしまったようだが、周りにたくさんの茸虫が青くなって死んでいたのだそうだ。恐ろしい茸である。
「まだ青い舞茸は生えているのでしょうか」
「わからん、わしはおばばを埋めてから、青い舞茸の生えている森の奥に行って、生えておった青い舞茸はみんなひっこぬいてやった、それで、燃してしもうた、だが、胞子は何処にでも飛んでおる、またどこかで生えておるやもしらぬ、青い舞茸は毒であることを、茸酔殿、ぜひ絵に描いて広めていただきたい」
「家に持っていかれた乾燥した若い青い舞茸はどうなさいました」
「あれもうめてしまった」
この話を聞いて、茸酔は青い舞茸の絵を書いた。その当時の青は空の青はもちろんであるが、木々の葉の緑も含まれる。草衛門の話では草の青に近いということであった。青の舞茸の下に丸まった青い赤子も書いた。不思議な話であった。
草衛門は昼間には茸酔の家をでて、茸の佃煮を車にのせて町の中を歩いた。よく売れているようだ。
綿毛ばあさんの話から三日ほどたった夕刻、二人の男が茸酔の家にやってきた。木野が玄関にでると、主人に会いたいという。
木野は茸酔を呼んだ。
「何かご用でしょうか」
二人ともさっぱりとした身なりをした二本差しである。
「城に勤めておるものでござる、こちらに茸喰らいの御仁が寄宿しておると聞きおおよび、会わせていただきたく参りました」
「私は、ここの主人、茸酔にございます、たしかに茸喰らいのお侍さまがおりますが、なにようでございましょうか」
「茸喰らいの御仁は侍なのか、それは知らぬことであった、わしは篠田三郎助と申す殿のおそばに使えるもの、実はあの茸の佃煮を城のみなみなが旨いと申して、城に入れてもらおうと思い参った次第」
「そういうことでございますか、おられます、お取り次ぎいたしますのでしばらくお待ちいただきたく存じます」
おいそれと家に上げて、草衛門様に迷惑がかかるといけないと思った茸酔は、すぐには侍を上にあげなかった。
草衛門に来客のことを伝えた。
「あいわかった、先だって、城の下働きのものが茸の佃煮を買っていった、気に入ってもらえたなら嬉しいこと、お会いしたい」
茸酔は玄関に戻り、丁重に二人を座敷に通し、木野に茶の用意をさせた。
おそば侍が茸酔に、
「茸絵師の茸酔殿でござるよな、わしは毒味役をしておって、茸酔殿の茸の図譜は大変役に立っておりますぞ」
「ありがとうございます」
篠田は茸酔のことを知っていた。
「こちらは勘定方の田辺長衛門殿でござる」
「わしも茸は好きでござってな、篠田殿についてまいった」
そこに木野が草衛門をつれてきた。
すると、いきなり長衛門が大きな声を上げた。
「なんということだ、草衛門じゃないか」
茸酔もびっくりしたが、草衛門ももっと驚いた。篠田三郎助も木野も何が起こったかわからず長衛門を見た。
「兄上ではないか」
草衛門が言った。それで茸酔も理解した。
「茸喰らいは長衛門どのの弟御でございましたか」
篠田がびっくりしていると、長衛門が説明をした。
「これは失礼いたしました、こいつは信州で好きかってに生きている弟、草衛門にございます、茸の薬など作っておりましたが、まさか江戸にきて茸喰らいと大声を出して、佃煮を売り歩いているとは思いもしませんでした、申し訳ないことで」
「いや、田辺殿がそのように申されることはない、美味いものは美味い、しかも弟ごなら安心できる、茸の佃煮、用件の話しをすすめてよろしゅうございますな」
篠田が田辺をおさえるように言った。
「兄じゃ、申し訳ない、訪ねると迷惑かと思い、行かなかった、父や母は元気でござりますか」
「ああ、元気じゃ、後でよりなさい」
「はあ」
「それでは、私の方から、草衛門どのにお願いでござる、あの茸の佃煮を城に入れてくださいませんかな、一年中茸が食べられると、殿も喜んでおられるのでな」
草衛門は顔をほころばせ、
「いや、ありがたいお話でございます、味などは保証いたしますが、一度にたくさん作ることができません、小さな樽一つほどしかできません」
「どうでしょう、勘定方の田辺殿、草衛門どのに人をつけて、城用に作ってもらってよろしいでしょうか」
「その程度の費用は出せるが、身内のものに出すのはいかがかと思いますな」
「田辺殿、弟御と考えずによろしいのではないでしょうか」
聞いていた草衛門が口を開いた。
「いかがでございましょうや、私はもう城勤めもやめたただの百姓、茸採りの人間にすぎません。これからも信州で佃煮や薬を作っていたいと思っております、そこで、作ったものをどこかに卸し、それを買い求めていただけるのなら、そちらの自由でございます、量を作るとなると、人を雇わねばなりません、値が高くなります」
「値が上がるのはかまいませんぞ、城の人をやるより安上がりでござる、それでどこかに知っている店はあるのか」
「いえ、江戸ははじめてでございます」
それを聞いていた茸酔が言った。
「どうでございましょう、作った茸の佃煮は私のところが仕入れて、お城に卸すのはいかがでしょう、手間賃も何もいりません、草衛門様からは茸のおもしろいお話を聞かせていただきました。そのお礼でございます」
「そのような迷惑はおかけできませんな」
草衛門はそう言ったが、二人はうなずいている。
「そうしていただければ問題ないが、手間賃なしというのはまずい」
篠田三郎助は首を横に振った。
「では、奉公人の木野に運ばせますので、木野に手間賃を出していただくというのはいかがなものでしょうか」
「それでよければ、もちろんでござる」
こうして茸喰らいの作る佃煮は、茸酔のところを通して城に売られることになった。
「茸の薬なども必要なものがあったら作ります」
草衛門はそう言った。
「城にいる薬師に伝えてみよう、いい話ではないですか、田辺殿は立派な弟御をおもちだ」
篠田にほめられ、草衛門は兄の顔を見た。田辺はうつむいているが喜んでいるようにも見える。
「篠田殿、ありがとうございました、茸酔殿にはやっかいをかけますがよろしく願います、それに草衛門がお世話になり、礼を申します」
「いえ、草衛門さまには教えていただいたことが多く、感謝している次第です、これからもよろしくお願いいたします」
草衛門はそれからまもなく、茸酔の家から兄者の長衛門の家に移った。
そのようなことがあった。
「木野、茸の佃煮のことは頼んだよ」
「うん、草衛門さんおもしろいおじさんだったね」
「ああ、いつか、信州の草衛門さんのところを訪ねてみよう」
茸酔は草衛門の話してくれた綿毛ばあさんの話を一つの本にするつもりである。
その後、信州に帰った草衛門から綿毛ばあさんの家を買い取り、人を雇って茸の佃煮や薬を作り始めたという手紙をもらった。
茸酔は佐渡でつくった薬の本を草衛門に送った。
茸喰らいー茸の絵師4
第十五茸小説「茸の絵師、2023年、一粒書房」所収
版画:著者


