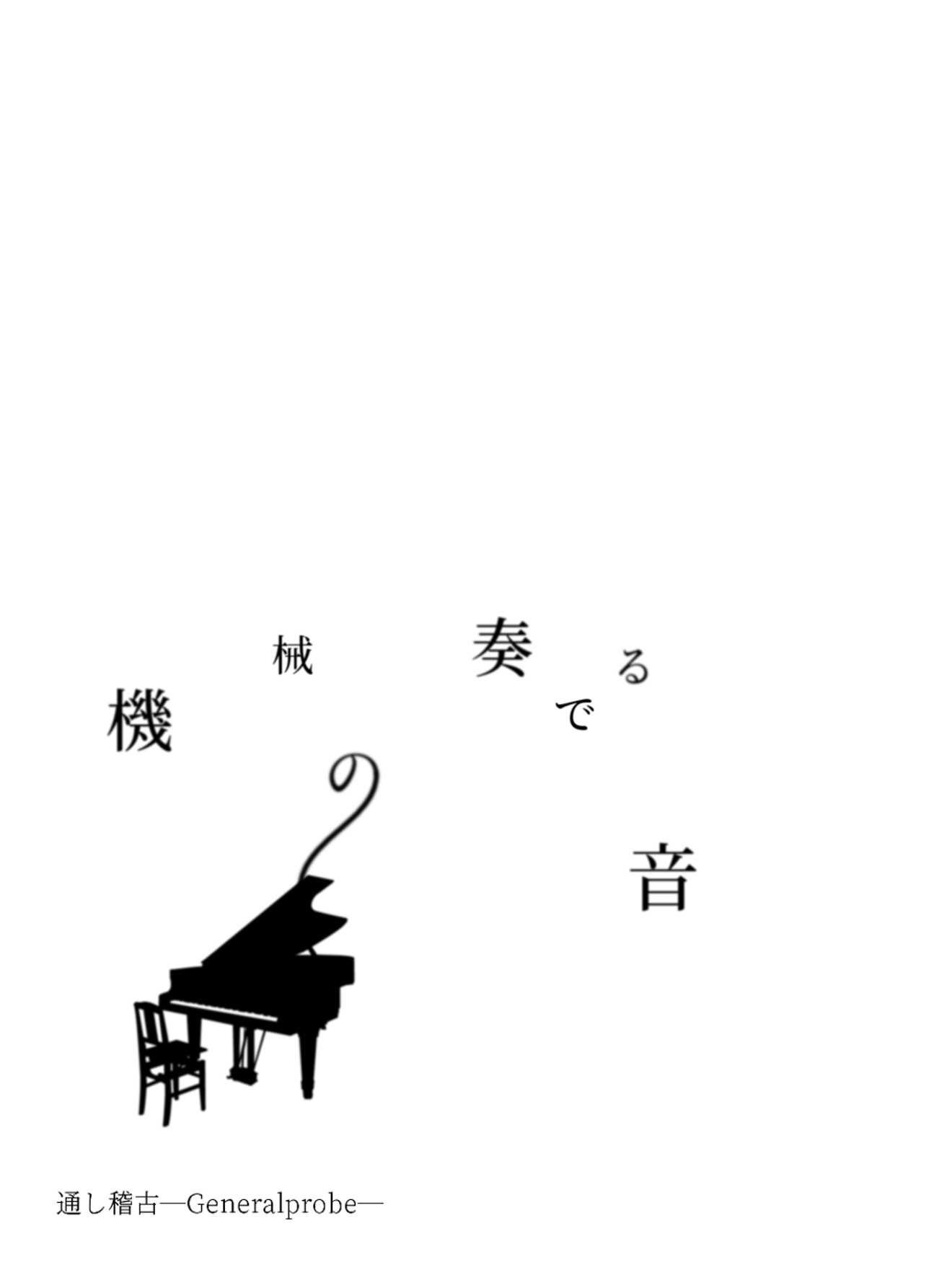
機械の奏でる音
――以前から、不思議だと思っていたんです。
どうして作曲する機械はないのだろうって。当然のことだと先生は思うでしょう。考えるまでもないことだと。しかし、僕にはずっと不思議だったのです。それこそ、先生に出会う前から疑問に思っていました。
あれは僕が大学三年生の頃です。その頃の僕は酷く悩んでいました。
大学に入学した直後から、友人たちは将来へ向けての準備を着実に進めていた。でも僕は、大学から始めた音楽に夢中になって、将来のことなんて何も考えていなかったし、考えようとも思っていなかった。
何故、と聞かれると上手く答えられませんね。ただ、漠然と違和感のようなものを抱いていたんです。サークルの活動や大学の勉強もそっちのけで、将来に向かって走ること。それは、|現在を空っぽにしてしまうような気がしていました。そして空っぽになってしまった自分は、何もない、ガラクタのようになってしまうのではないかと思っていたんです。
実際、僕よりも遥かに音楽の才能があった人達が、就職活動や試験の勉強のために、その才能を失ったり、捨て去ったりしていきました。それでも彼らは未来を手に入れて喜んでいましたが、僕はそれをとても厭(いや)に思っていました。自分もそういったものになってしまうのが怖くもありました。
同時に、生活のために音楽を捨て去ることなく、曲を作るために曲を作るような。そういった「純粋」なものに僕は憧れていました。例えば機械のように。作曲をするためだけに存在する、作曲をする機械。そういったものに焦がれていたんです。
馬鹿だと思うでしょう?
以前、先生にも叱られましたね。「どんなことも、生活と切り離すことはできない」と。創造的な仕事であっても、それを続けていくためには、生活していくということを考えなければならない。身も蓋もない言い方をしてしまえば、死んでしまったら意味がないですからね。作曲する機械なんていうものは夢想に過ぎない。人間である以上、そんな存在になることはできない。――確かにそうなんです。
でも、僕はこの憧れを拭い去ることができなかった。大学の友人たちのように、生きていくために音楽を忘れてしまうのが怖いんです。僕も今は作曲家として生きていますが、もし生活に追われるあまりに、自分の音楽を失ってしまったらと思うと。おそらく僕は空っぽになってしまうのでしょう。大学生の時分、僕が恐れていたように。
突然何の話をしているんだ、という顔ですね。話が回りくどくてわかりづらいのは僕の悪い癖です。つまり、僕はずっと「作曲する機械」に憧れていたということが言いたかったんですよ。それが今日、先生をここに連れてきた理由に繋がるんですから。
先生、僕は美しい音楽を創り出す機械に出会ってしまったんです。
疑っている顔ですね。僕も最初は信じられませんでした。無理もないことです。「作曲する機械」なんて、存在し得ないもののはずです。確かに機械ゆえに、僕達が持っているよりも遥かに多くの音楽的知識を詰め込むことはできます。しかし、どれだけ楽典の知識や、世界中の全ての音楽を詰め込んだとしても、そこから作られる音楽は醜悪なコラージュでしかない。しかも、そのコラージュに独創性を持たせることは極めて困難でしょう。
僕も、作曲するために作られた機械という純粋な存在に憧れてはいましたが、作曲する機械を実際に作るのは無理だと思っていました。少なくとも、現在の技術では不可能だろうと。
しかしどういうわけか、作曲する機械が僕の前に現れたのです。しかも、僕にとって最悪の形で。今日は先生にそれをお見せしたいんです。
|件の機械の名は「Habseligkeiten」と言います。酷い名前の付け方ですよね。「ガラクタ」なんて。しかし、確かにガラクタなんです。本来は作曲するために作られたものではありませんから。
奥の方にクリスタルピアノがあるでしょう? あの鍵盤の下についている白い箱のような機械が「Habseligkeiten」なんです。
そうです。元々は普通のピアノをコンピューター制御の自動ピアノに変えるための転換キットとして作られました。自動ピアノはファイルがなければ動かないものですが、「Habseligkeiten」はファイルがなくても勝手に動くんです。しかもその曲は誰も聞いたことのない新しい曲ときている。だから本当は使えない機械なんですが、今日はこの店のマスターに無理を言って、特別に動かしてもらっているんです。
コンピューターが起動されましたから、もうすぐ演奏が始まりますよ。お話はこれくらいにして、少し機械の奏でる音に耳を傾けてみましょうか。
どうですか、先生。
僕の正直な感想は、「機械の作る音とは思えない」ということに尽きます。僕の抱く機械のイメージからかけ離れているんです。機械には「完璧」や「完全」というイメージがありますが、「Habseligkeiten」の音楽は完璧でも完全でもありません。どの曲も確かに緻密ではありますが、その中に幾つかの|空隙がある。謎や矛盾と言ってもいいかもしれません。
先生は以前、「名曲と呼ばれるものに完璧な曲は存在しない」と僕に言いましたね。名曲と言われ、ずっと演奏され続けている作品であっても、必ず何らかの瑕を抱えている。いや、それを抱えているからこそ名曲たりえるのではないかと。
例えば能の『卒都婆小町』という演目では、老婆の姿をした落ちぶれた小野小町が登場しますね。あれは老婆の姿という瑕が、過去の美しさをより引き立てるものになっています。
音楽も同じなのでしょう。瑕は、もしそれがなかった場合の美しさを人に想像させる。それが人を魅了する要因となることも多いのでしょう。
でも、今や機械が私達のように曲を作るのです。人間を魅了する不思議な瑕を持った音を奏でるのです。勿論「Habseligkeiten」は偶発的な存在なので、このような機械がこれから次々出てくるとは考えにくいですが。
先生はどう思いますか?
僕は――正直言って怖いです。
機械が奏でる音にどうしても魅了されておきながら、そしてかねてから作曲する機械というものに憧れていながら、僕はその存在に恐怖を感じるんです。
多くの機械は、一つの目的を遂行するためだけに存在しています。現在の「Habseligkeiten」は本来の働きとは違う動きをしていますが、作曲させるためだけに同じような機械が作られたら。僕達人間のように自力で生活する必要のない機械は、作曲することだけを目的とする「純粋」な存在になるのです。
そうです。僕達なんかより遥かに純粋に音を奏でる存在。僕はそれに憧れと恐れを同時に感じるのです。
ああ、もうすぐ演奏が終わるようですね。
僕が「Habseligkeiten」と出会ったのは半年前のことです。覚えていますか。丁度僕が先生の下で作った最後の曲――『遊色』が完成した頃です。
あの曲は先生に唯一褒められた作品でしたね。和音の響きに拘泥しすぎて旋律が疎かになっていたり、逆に速いパッセージのために調和を犠牲にしていたりと、あの曲は僕の作品の中でも最も粗っぽいものなんですが、先生はそれがいいと言っていましたね。いつもは楽譜をゴミ箱に捨てるくらいのことはするのに。
先生には話していませんでしたが、実はあの曲は「Habseligkeiten」に出会ったからこそ完成した作品なんです。生活に追われることなく、ただ純粋に音を鳴らし続ける機械。あの曲はそういった存在への畏敬の念を込めて作ったんです。僕の中でも気持ちが整理できていなかったので、ああいう粗い曲になってしまったんでしょうね。
あの曲は僕の中では最高傑作でした。自分の出せる全てを注ぎ込むことができたと思っていました。
でも、僕はその曲に熱心になりすぎるあまり、先生が苦しんでいることに気づくことができなかった。
先生が一年ほど前から曲が書けなくなっているということには気づいていました。子どもが産まれて、生活に追われるうちに、自分の音を失っていったのだろうということもわかっていました。でも僕は信じていたんです。あなたの音が戻ってくることを。僕の尊敬する先生の音は、簡単に死んだりしないと思っていたんです。
先生、聞いてください。
僕はあの曲で先生を苦しめるつもりではなかったのです。僕は、ただ気づいていなかっただけなのです。僕と先生は同じ恐れを抱いていた。生活に追われ、自分の音楽を失うこと。そして、音楽を失うことで自分が空っぽになってしまうこと。
そうでしょう、先生?
それと同時にあなたは純粋なものに憧れてもいたのではないですか。作曲する機械――生きるためではなく、音を奏でることだけを目的にできるものに。
先生は、最後まで純粋な存在であるために命を絶ったのではありませんか。そうだとしたら僕は先生の死を責めることができません。哀しむことはできますが。
――おそらく僕も、その道を選ぶと思うのです。
◆◆
理人の手から、オパールのカフスボタンが落ちた。グラスを拭いていた店主は手を止め、炎のように色を変えるそれを拾い上げた。
「落ちましたよ、理人さん」
「ああ……ありがとうございます」
力のない声で理人は答えた。カフスボタンは酒で|火照った手に、滲むような冷たさを伝えてくる。ずっと手の中にあったのに、その冷たさは失われることはなかった。それを贈った人間が、もうこの世にはいないということを象徴するかのようだった。
「――思えば、これをもらったときに気づくべきだったのかもしれませんね」
オパールの虹色の輝きは「遊色」と呼ばれる。それは理人が半年前に書いた曲の題名と同じだ。贈ったのには意図があったのだろう。もしかしたら置き土産のつもりだったのかもしれない。そのときに気づいていれば。
しかし、全てがもう遅いのだ。
「理人さん……」
「マスターまでそんな顔をしないでください。ただでさえ、たくさん迷惑をかけてしまっているんですから」
理人は店の奥にあるピアノに目を向けた。店の雰囲気に合わせるために、大部分がアクリル樹脂製のクリスタルピアノだ。「Habseligkeiten」は、今は何の音も発していない。
「――マスター、『Habseligkeiten』はやはり廃棄してしまうのですか?」
「そうですね。店で使うのに、作曲してしまうのは困りものですから。それに、もう明日には新しい機械が届くそうなので」
「そうですか……」
理人は目を伏せた。ガラクタという名前をつけられた機械が、明日には本当にガラクタになる。静かな店内に、氷とグラスがぶつかる音が響いた。
「Habseligkeiten」との出会いは、最悪だった。機械は理人の入力したデータを拒否して、自ら新しい曲を作ったのだ。もしあのとき、普通の自動演奏ピアノとして動いてくれていたなら。
でも、と理人は独りごちる。
「『遊色』を作ったことは後悔していないんです。あの曲が先生の死の引き金を引いたというのはわかっていても、僕は捨てることができない」
きっと自分は変わっていないのだ。
将来のために現在を捨てることができなかった、昔の自分のままなのだ。今は捨てることのできないものが形を変えて存在しているだけで。
何も変わっていないし、この部分だけは変わらないだろう。
グラスの底に少しだけ残った琥珀色の酒を、理人はゆっくりと喉に流し込む。左手の中にあるオパールのカフスボタンがその冷たさを徐々に失っていく。
理人が飲み干したグラスをテーブルに置いた瞬間、クリスタルピアノの鍵盤がひとりでに動いた。しかしそれは、旋律のように秩序のある動きではなかった。子どもがめちゃくちゃに鍵盤を叩いているかのように、何の意味もない音。マスターが溜息を吐いてピアノに近づく。
「壊れてしまったようですね。まあ、作曲し始めた段階で壊れてはいるんでしょうけれど」
そう言いながら、電源ボタンに手を伸ばす。しかし理人は静かにそれを制した。
「止めないでください。まだ、曲を作ろうとしているんです」
無意味な音の羅列の中に、理人は途切れ途切れの旋律を聞き取る。最後まで作曲する機械で在り続けようとするその姿は、どこか自分に似ているような気がしていた。
目を閉じる。
どんな仕事も、生活と切り離すことはできない。かつて先生に言われた。だから先生は割り切っているものとばかり思っていた。人間は純粋な存在になどなれない。それを受け入れていると思っていたのだ。
しかし、自分の音を失う恐れから来る純粋への憧れは、どうやっても消せない。甘いことを言うな、という先生の叱責が聞こえてきた気がして、理人は苦笑した。
耳の中で、聞いたことのない旋律が鳴る。それは機械の奏でる最後の音と重なって、奇妙なうねりを生む。そのうねりは遊色のように、角度で色を変えて光る。
理人は握りしめていたカフスボタンを袖口につけ、静かに店を後にした。
機械の奏でる音

