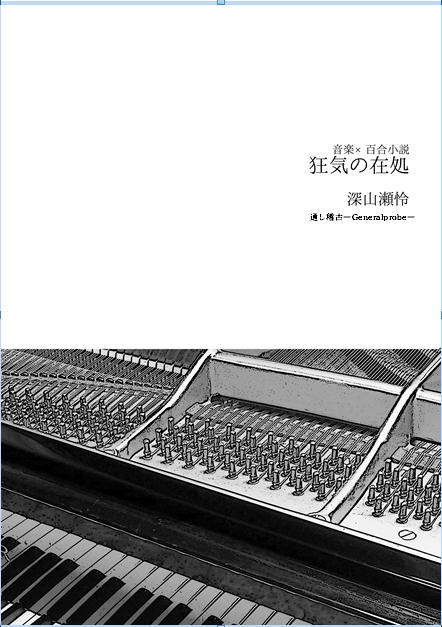
狂気の在処
「二六番。演奏曲は――」
そのアナウンスと同時に、ステージ中央に鎮座する怪物のように大きなピアノの前まで歩く。背筋は伸ばして、前だけを見つめて。舞台の中央に立つと同時に客席に向かって礼をして、一瞬客席に座る人たちを見回す。
真ん中から少し後ろのところには審査員がテーブルの上に紙を広げてこちらを見ている。このホールではそこが一番いい音が聞ける場所。流石に審査員がいるのは特等席だ。
椅子の高さを調整してから、ピアノに向かう。けれど鍵盤の高さに少し違和感があった。ああ、そういえばこのピアノはスタインウェイで、うちにあるものとは違うのだ。私は静かに立ち上がって、椅子を一段階下げた。うん、これでちょうどいい。
手に持っていたハンカチで軽く手を拭いてから、本来ならば譜面台が設置されている場所の下に入れる。このコンクールでは楽譜を見ることはないから、最初から譜面台は外されているのだ。決まったルーティンを片付けた私は、鍵盤に指を乗せる前に、深く息を吐き出した。
最近、このあたりのコンクールを荒らし回っている人がいる。名前を入山繭。繭なんて名前なのだから、大人しく綺麗な人なのかと思いきや、彼女はその対極にいる。まず絶対にワンピースなんて着てこない。Tシャツとジーンズという、その辺のコンビニにでも行くような出で立ちでコンクールにやってくる。そして何よりその演奏が、粗野で、破天荒で、狂っているのだ。
もちろんコンクールでそんな演奏が評価されることはない。それが許されるならもう課題曲なんて必要ないだろう。演奏の優劣を決めるためには、ある程度は同じにしなければならない。理科の実験だってそうだろう。
けれど入山繭は楽譜など完全に無視したような、自由で破天荒な演奏をする。そしてその音は悔しいが魅力的ではあって、コンクールでは勝てないが、客からは愛されていた。退屈なコンクールに開いた大きな風穴。それが入山繭ということだろう。
でも私は入山繭の演奏が嫌いだ。自由で、固定観念に囚われない? じゃあ何のために楽譜があるというのだ。そこに記されているのは作曲家が込めた思いの全てだ。その作曲家にとってはその音こそが、その表現こそが一番相応しかったから、そう楽譜に残したのだ。もちろん後世でその解釈が違ったということがわかることもある。古楽を研究している人の中には、自分の新しい解釈を発表するために、それまでの楽譜にはない表現で演奏する人もいる。けれど入山繭の演奏はそれとも違う。あれは彼女の気が赴くままに、勝手に弾いているだけだ。
あんなものは作曲家に対する冒瀆だ。楽譜に記された意図を全て無視して、好き勝手に弾いているだけだ。そんなに自分の好きなように演奏したいなら、自分で作曲して弾けばいいのだ。でも入山繭はそれをしない。それは彼女が曲なんて作れないからだ。
要するに彼女は中途半端なのだ。そんな彼女が固定観念に囚われない自由で新しい演奏だと評価されるのが私は気にくわない。評価する方もする方だ。かつて誰かが表現したかったものをわざわざ踏み躙ってまで自分の表現を押し通すなんて、絶対に許せない。
だから私は、入山繭を超えると決めた。私の全身全霊の演奏で、彼女の鼻を明かしてやりたい。いや、彼女だけではない。彼女を評価する、何も知らない観客たちもだ。
見せてあげる――この曲が持つ本当の姿だ。
自由な演奏を評価する人たちは言う。楽譜の奴隷になったコンクール向きの演奏はつまらない、と。私は楽譜通りに弾いてつまらない演奏になるのは、ひとえに演奏者の実力が足りないからだと思う。だいたい一口にフォルテと言っても、全ての人のフォルテが同じというわけではないのだ。同じ楽譜を見て、それに従って弾いていても演奏者によって違いが出るから面白いのだ。それに気付かずに、目新しい奇抜な演奏ばかりする入山繭も、彼女を評価する人たちも私は嫌いだ。
そんなに自由にやりたいなら、自分で一から作ればいいのだ。どうして私たちは人が作った曲を弾くのか。それを一度くらい真剣に考えてみればいい。
私の答えはもう決まっている。でも決まったのはつい先日だ。考え始めたのは、初めて入山繭の演奏を聴いた三年前のコンクールから。それからずっと考えていた。彼女のように自由に弾くのがいいのか、それとも楽譜に従うのがいいのか。実のところ、最初は自由に弾く方に傾きかけていた。理由は明確だ。――私は狂いたかったのだ。
現代に名を残す作曲家の中には、狂気的とも言えるエピソードが残っている人が多くいる。音楽だけではない。とかく芸術というものは個性的なものが良いとされる。そして際だった個性というものは、ときに他人には理解されず、狂気と見なされがちだ。私は幼い頃から様々な作曲家に触れ、狂気への憧れを抱くようになっていた。狂ってみたくて、何時間もぶっ続けで練習してみたり、曲を破壊するような弾き方をしてみたりもした。けれどそうしているうちに気が付いてしまった。狂気に憧れているような人は、逆に狂うことなんて出来ない、と。私は狂えなかったのだ。ただ憧れるだけのあまりに健全な精神。狂うことが出来ない自分に気付いてしまった頃に、私は入山繭に出会った。
最初、彼女は私が持ちえなかった狂気を手にしていると思った。だから彼女に一瞬憧れてしまった。私にはなれないもの。私の手には届かないもの。でも何かが引っかかっていた。入山繭は間違っているのではないか、という疑念がずっと心の奥底にあったのだ。
けれどその疑念を暫くは言語化できず、私はもやもやとした気持ちを抱えながらも、入山繭の活躍を耳にしていた。
私の考えが変わったのは、彼女が私の好きな曲を弾いた昨年のコンクール。楽譜を無視した彼女の演奏に、目の前が真っ赤に染まって、ひとりでに涙が出てきてしまうほどの怒りを覚えた。違う。その曲はそんな弾き方をするものではない。入山繭の弾き方は曲に対する冒瀆でしかない。それなのに彼女の演奏は喝采を浴びた。同時に批判の声も浴びていたが、褒め称える声が大きかったのは事実だ。
許せないと思った。作曲家の思いを踏み躙っている彼女が評価されるなんて間違っている。そもそも他人が作った曲を弾く以上、作曲家には敬意を払わなければならない。私が持ち得なかった純粋な狂気を持つものに対して。楽譜という形で記された狂気の断片を、自分勝手に塗り潰していいはずがないのだ。
私は自分自身の狂気は手に入れられなかった。でも楽譜に残されたものをその場に具現化することはできる。そこに眠る狂気に息を吹き込み、どこでも蘇らせることが出来る。それが他人の曲を演奏する意味だ。何かを作る人間というよりは、役を演じる俳優に近い。
誰かが息を吹き込まなければ、ただの白と黒で表現された紙でしかないもの。それをこの世界に現出されることが出来るのは私たち演奏者だけだ。個性だとか何だとか考える必要はない。ただ目の前にある音楽のことだけを思えばいい。
鍵盤を押した瞬間に音が立ち上ってくる。音は私の腕をゆっくり昇っていって、やがて全身を包み込んでいった。でもまだ足りない。もっと深く音に潜り込みたい。音と自分が溶け合って、それが音なのか自分なのかさえわからなくなるほどに。そこに達することが出来たら、私は入山繭のことを超えられる。
今日は調子がいい方だ。指が自在に動くし、ピアノも私に合っている。指の動きに対するレスポンスが早いのはやりやすい。ピアノに対するストレスがない方が音楽に溶けるまで早くなるのだ。
曲が進むごとに、余計なことは消え去っていく。ここにあるのは私と音楽だけ。そしてそれもだんだん境目がわからなくなっていくのだ。
音楽と混ざり合うと、私の中にどろりとした黒いものが流れ込んでくる。それは腹の底にゆっくりと溜まっていき、私自身を少しずつ変化させていくのだ。
演奏が終わると、礼をして舞台を降りる。先生が私をねぎらってくれるけれど、それを聞いている余裕はなくて、ホワイエのソファーに体を預けた。まだ体と音楽が離れきっていない。腹の底の黒いものも消えてはいなかった。暫く休めば普通に戻るのだが、ピアノに触れていないときにも自分と音楽が混ざり合っているのは正直やりにくかった。
「よう」
頭上から声が降ってくる。短く切られた髪。左耳だけのピアス。そしてTシャツにジーパンというこの場所に似つかわしくない格好。入山繭がそこに立っていた。
「……入山繭」
「いい加減フルネームで呼ぶのやめてくれない、蝶子?」
「私、あなたのこと嫌いだもの」
馴れ合うつもりはない。けれど彼女は非常に人懐っこくもあり、他のコンクール出場者にも普通に話し掛けている。私はそんな彼女のことがあまり理解出来なかった。コンクールのときは誰もが気が立っている。だいたいは目的があって参加しているからだ。でも彼女は違う。彼女にはコンクールに参加する目的自体がないように見えた。
「好かれてはないとは思ってたけど、はっきり言うね」
「陰口よりマシでしょ」
「でも私だって傷つくんだからね?」
わかっている。でも、入山繭と仲良く会話する気はさらさらない。私と彼女はあまりにも相容れない存在だ。それに気付いてしまったのだ。
「とりあえずお疲れ。今日の演奏よかったよ」
「そりゃどうも。でもあなた私の演奏嫌いでしょ」
私が入山繭の演奏を嫌っているように、入山繭も私の演奏を嫌っている。それは直接聞いたわけではないけれど、肌で感じるのだ。
「嫌いっていうか……蝶子のようには弾けないな、って思うよ」
「やろうと思えば出来るでしょ。あんな弾けるんだから」
「いや、無理だよ。少なくとも私は、楽譜通りに弾いて人を引き込む力はない」
「もっと信じればいいのよ。その曲自体が持ってる力を」
私に大した力がなくても、曲そのものを現出できればいいものができる。でも入山繭はそうは思っていないだろう。
「蝶子はすごいと思うよ。私はそこまでできない」
「……じゃあやめればいいのに」
「辛辣だなぁ。でもね、私は私の戦いをしてるんだよ」
「ふぅん」
入山繭には目的なんてないと思っていたけれど、どうやらそれは違うらしい。彼女の戦いは何なのだろうか。少し聞いてみたい気がした。
「戦い、ねぇ……」
「幼稚園のときに好きな人がいたんだ。でもその人は寝ても覚めてもピアノばっかりで、多分私のことなんて全然見てなかった」
「ふぅん。それで?」
「だから、その人が絶対無視できないようなピアニストになってやろうと思って」
確かに入山繭を無視できる人はいないだろう。彼女のピアノは良くも悪くも気になってしまう。もちろん私もその一人だ。
「まぁ当初の目的は達成したんだけどさ、でも全然私のことには気付かないんだよね。多分そもそも認識してなかったんだろうな」
「それは残念だね」
「そんな一ミリも思ってなさそうに言われてもね」
溜息を吐きながら入山繭は立ち上がった。そういえば入山繭の出番はこれからだったか。演奏前だというのに随分と余裕がある。
「じゃあそろそろ行くよ。じゃあね」
「うん」
私も客席に戻ろう。入山繭と話しているうちに少し落ち着いてきた。いつもの、狂うことが出来ない私がここにいる。前の人の演奏が終わるのを待って、私は客席に繋がる重いドアを押し開けた。
その日、入山繭はいつもと同じように自由で、破天荒で、冒瀆的な演奏を披露した。けれど彼女の音は魅力的ではある。一音だけで人を惹きつける。
「――でも、私は認めないから」
彼女と私は対極にある。おそらく入山繭は音楽に溶け込むことなんてないのだろう。自由で勝手に弾いているわりには、彼女は冷静だ。彼女は音楽から離れて、一つ一つの音を完全に制御している。
その弾き方で、作曲家に敬意を払った弾き方をしたら、きっと私を超えてもっと上まで行けるだろうに。納得できない。入山繭は勿体ないことをしている。そのことを思うと、彼女の好きな人とやらが少し憎らしくなった。
*
「あーあ、やっぱり気付いてないよなぁ」
昔から蝶子のことが気になっていた。他の人とは少し違う雰囲気。澄ました顔。一目で惹かれて、それからは目が離せなくなった。
でも蝶子は私のことなんて一度も見てはくれなかった。幼い頃から音楽漬けで、それ以外のものにはほとんど興味がなかったのだ。
「……まあ気にしてくれてはいるのかな」
絶対に蝶子の気に障る弾き方をしている自覚はある。わざとやっているのだ。蝶子の心を奪ってやまない音楽たちが憎らしくて、妬ましくて、壊したくなってしまう。
「さて、どうしたものかなぁ……」
蝶子はもう私のことには気付かないだろう。このまま押し通すというのもいいけれど、どうすれば蝶子が振り向くか、全く見えていないのが現状だ。
「……次はいつ会えるかな、蝶子」
狂気の在処

