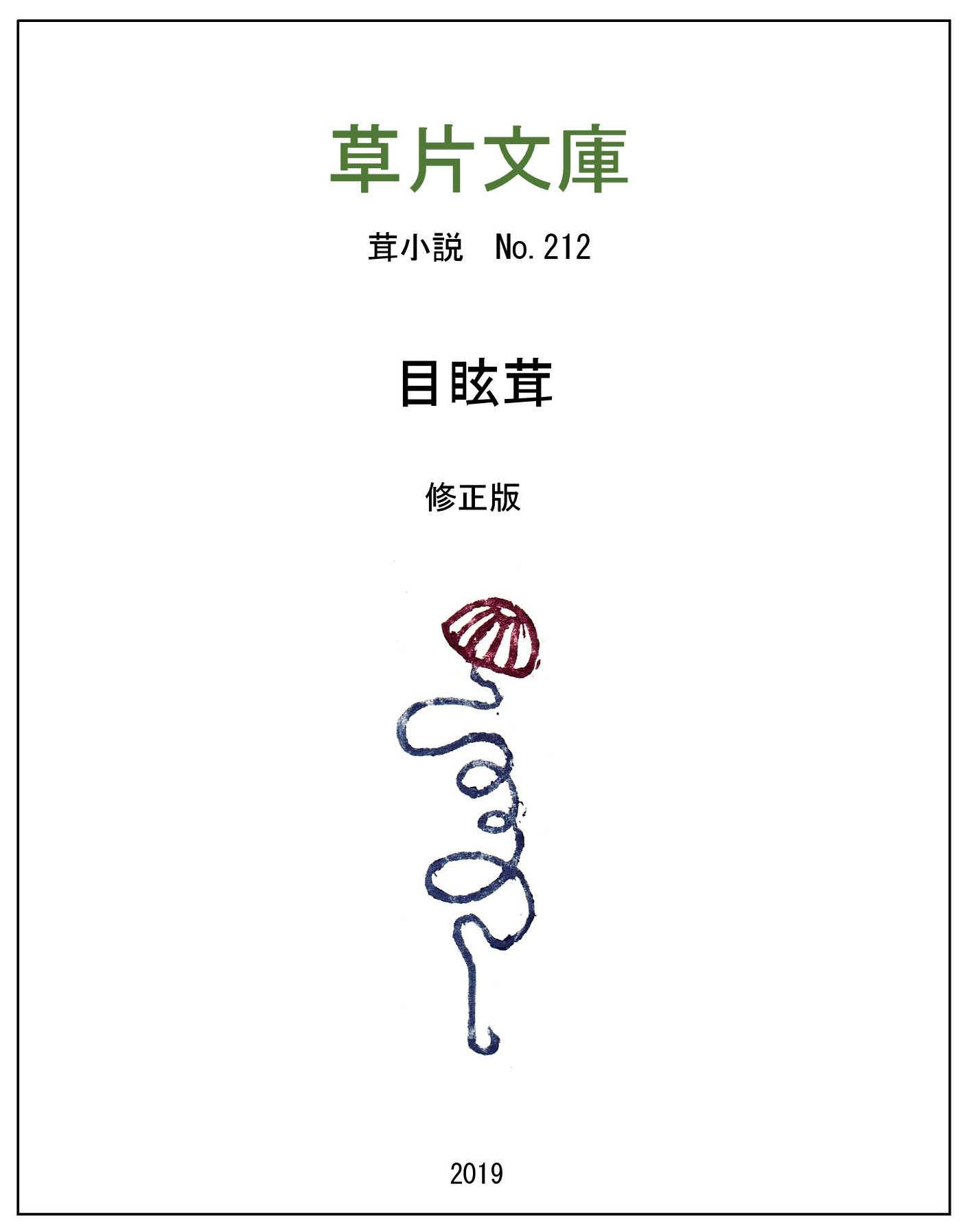
目眩茸
茸の絵師、茸酔の物語3 縦書きでお読みください。
園生が茸採りから帰ってきた。
園生は朝日が顔をだすと裏の林にいって、食べられる茸を背負い駕籠いっぱいに採ってくる。ところがその日、長屋の縁台でたばこを吸っていた新生(しんしょう)が驚いた。
二人は今助長屋に住む売れない落語家である。
「おい、園生、籠が空っぽじゃねえか」
園生はうなだれて隣に腰掛けた。
「林に茸が全くないってことはないだろう、だれかに盗まれたか」
園生は首を横に振った。
「茸はいろいろあった」
「それで何で採らなかったんだ」
「くしゃみしてた」
「なんだそりゃ」
「咳もしてた」
「どうやって」
「頭を曲げて、こほこほいってた」
「狢にでもだまくらされたんじゃねえか」
園生はまたも首を横に振った。
「赤い茸が言ったんだ、はやり風邪ってな」
はやり風邪とは今のインフルエンザである。
「茸がしゃべるわきゃねえだろ、おまえに熱があるんじゃねえのか」
「いんや熱なんかない」
そこへ黄色い声が聞こえた。
「いいお医者さん知らない」
「誰が言ったんだ」
新生が園生を見ます。
「俺じゃねえよ」
「ここよ」
園生は空の籠を背負ったまま腰掛けている。その籠から声が聞こえたような気がして、新生が見ると籠の底に赤い小さな茸が転がっている。
「こんな小さいの採ってきたのか」
新生が赤い茸をつまみ出した。
「おれこんな赤い茸採らんよ」
園生が首を傾げた。
そのとたん、赤い茸が新生の手の中でぴょいと立ち上がった。
「おっかさんたちの風邪を治す医者しらない」
新生がびっくりして、手の平をひっこめそうになった。
「落ちちゃうじゃない、気をつけてよ」
そう言われて、改めて見ると赤い茸の傘がぱくぱく動いている。
園生が言った。
「おれたちゃ、医者知らずでね、それに人の医者じゃ茸の病を治せねえ」
「そうなの、困ったわ」
「茸に医者いないのかい」
「うん、でも茸の長老もはやり風邪ははじめてなんだって、人間じゃだめなら、梟にでも頼もうかしら、それじゃ帰ろう」
「どうやって帰るんだ」
そこに黒い烏が降りてきて、茸を咥えると山へ戻っていた。
「なんだい、あいつは」
「烏じゃねえな、少しちっちぇ」
「椋鳥じゃねえか」
「それより茸がしゃべりやがった」
「うん、夢かもな、茸が風邪引くなんてな」
「俺たち二人が見たじゃねえか、ほんとなんだよ」
「二人とも何かにとりつかれんじゃねえか」
「大丈夫だとおもうがな」
「茸の医者なんぞいないが、茸をよく知っている人に聞いてみるか」
「そうだな、大家の隠居だって茸のことはよく知っている」
「そうだ、大家に言ってみよう」
「俺たちまともじゃねえような気がする、きっと酔っ払ってたんだろうとか何とか言われそうだがそうするか」
二人は大家の家に行った。
「大屋さん」
「二人そろってなんだい」
「茸の医者はいますかね」
「なんだいそれは」
「裏山の茸がはやり風邪で、皆熱を出してます」
「茸がかい」
「園生が見てきました、あたしも茸と話しました、まともでしょうか」
「ふーむ、お前さんがた噺家はいつもまともじゃないから、まともなんだろう」
なんとも信じたくなるような理屈です。
「茸が医者をさがしてます」
「茸の医者はしらんが、茸と仲のよい人は知っておるよ」
「教えてください」
「深川にすんでる茸狂さんだ、ほんとうの名は円山茸酔さんだ」
「なにやってる人です」
「茸絵だ」
「病気のことも詳しいんですかい」
「そりゃわからんが、茸酔さんは佐渡の医者の元で、薬の本の為の絵を描いていたことがある、そのとき医師がいろいろな病気の患者を診察するのを見たり、手伝ったんじゃないか、そういえば茸が夜歩くなんてことも言ってたから、茸の変なことを見たことがあるんじゃないか、お前さんがたの仲間だろう」
「そりゃいいですね、茸酔さんとやらの家を教えてくださいよ」
そういうことで、園生と新生は茸酔のところに行った。
「随分立派な家じゃねえか」
茸酔の家はその昔、師匠の虎酔の家だった。亡くなるときに虎酔にすべてやると言われて茸酔は住み続けている。虎酔は加賀の偉い殿様の外腹だったこともあり、瀟洒な屋敷である。
「へえい、こんちは」
玄関で新生が中に声をかけると。「はーい」と若い女の返事が返ってきた。出てきたのはまだ十三、四のおかっぱ頭の子供である。
「ハイ、何でしょう」
「あの、茸の医者探してるんで」
新生がそこまで言ったら、女の子は笑い出した。
「茸の医者はいないけど、絵描きならいるわよ」
「あ、そいつだ」
園生が頭をかく。
「おじさん、お客さん」
女の子が中に声をかけた。
「どなたかな」
茸酔が玄関に出てきた。
「なんでしょう」
「いえ、長屋の家主が茸の医者はいないが、茸の絵を描く人がここにいると言うんで、きやした」
「どこの長屋ですかな」
「今助長屋で」
「おお、そうですか、今助さんは元気かな、まあ入ってください」
「ありがとうさんで、私は新生、こいつは園生です」
「茸酔です、今助さんは私の師匠の虎の絵が好きで、屏風を買ってくださった」
「大家さんの部屋においてあります、みんなにみせびらかせて喜んでます」
そこへさっきの女の子がお茶をもってきた。
「私の姪で、キノといいます、今は木野と書くんですよ、私が佐渡に行っている間に、虎酔師匠がこの字を使えとキノに書いて渡したそうです」
木野は茸酔が佐渡に言っている間、師匠の虎酔の面倒をみるため、この家で働いていた、茸酔の姉の娘である。師匠が亡くなった後もこの家に奉公している。
「はい、おじさんたち茸のお医者を捜しているそうです」
木野が笑いながら言った。
「へえ、裏の林に生えている茸が風邪を引いてくしゃみをしていまして、治してやろうと思うんで」
それを聞いた茸酔は,おやここにも生きものと話ができる人がいると園生を見た。
「園生の奴、茸がしゃべるなんていうものだからおかしくなっちまったかと思いましたが、駕籠の中に入っていたちっこい赤い茸がやっぱりしゃべりやした。あたしも見ています、ほんとうにしゃべりやした」
新生が言うと茸酔はうなずいた。こいつもだ。
「茸だって人と同じように眠るし夢を見るし、夢遊病にもなる。私も経験があります。だが私は茸の医者じゃない、ただの絵描きですよ」
「今助の大家さんは、茸酔さんは佐渡でお医者の手伝いをなさっていたから、病気のことはよく知ってなさる、それに茸のことは江戸で一番よく知っている方だと言っておりやした」
「いや、病気の名前は耳で覚えましたが、治療の仕方はわからない、まして、茸の病気についちゃ知りませんな」
「だけどぜひ、茸の風邪をみてやってください」
「風邪を引いた茸の絵を描くのも面白い、昼過ぎてから木野と一緒に伺いましょう」
というわけで、茸酔は木野をともなって今助長屋にやってきた。木野はいつでも絵の道具をもって茸酔のお供をする。
「茸を見る前に、今助さんに挨拶をしておこう」
茸酔は大家さんの家に顔を出した。
「おや、茸酔さん、園生と新生がとんだ話をもっていっちまて、すまんことですが、まあ聞いてやってください」
「ご無沙汰しています、私の師匠がお世話になりました、話しは聞きましたよ、お二人ともいい人たちだ」
「それなら、よござんした。茸酔師匠の目に金の入った虎、いいですな、毎日楽しんでおりますよ」
虎酔晩年の虎の絵はこの今助がどうしてもほしいと買っていったのである。金を絵に施すことは江戸では御法度、茸酔が佐渡から茸を土から吸い取って貯める茸を見つけ、みつからないように虎酔にもってきたのである。
「それじゃあ、園生さんと新生さんと茸を見て参ります」
「後で様子を聞かせてくださらんか」
「ええ、茸の風邪引きとは珍しいですから」
茸酔と木野は長屋で待っている二人のところへ行った。
「あ、先生お待ちしてました」
園生と新生は茸酔を裏の林に案内した。
林の中はひんやりとして、少し寒いほどである。
林の中をちょっと進むと茸酔は目を見張った。下草の間で色とりどり、形が様々な茸が転がっている。
「みんな寝込んじまってる」
園生がしゃがむと、そこへ赤い小さな茸が飛び出してきた。
「おじさん、お医者見つけたの」
園生に向かって傘をふるわした。
「いや、医者じゃないが、茸のことをよく知っている先生をつれてきたよ、ほら茸酔先生だ」
「母ちゃん、父ちゃん、姉ちゃん、兄ちゃんみんな風邪引いた」
確かに茸が話をしている。茸酔は夢遊茸ことを思い出した。茸酔も茸と話をしたことがある。
「おまえさんは大丈夫かい」
園生が赤い茸に聞いている。
「うん、あたいは傘を露でよく洗って清潔にしてるから大丈夫」
「えらいね」
「さて、どうやって治すかな、佐渡の東経先生は風邪を引いた患者に卵酒を飲ませていたな」
「俺だったら嬉しいが、茸が酒を飲みますか、だいたい口がない」
新生は大酒飲みだ。
すると、茸酔の足もとに転がっていた茶色の茸の笠に大きな口が開いた。
「何でえ、茸も飲兵衛じゃねえか」
「父ちゃんは猿酒が大好きだ」
赤い茸の子供が言った。
「子供茸にゃあ何がいいでしょう」
「うむ、甘酒がよかろう」
「あたい、風邪引いていんないけど甘酒飲みたい」
「ああ、もってきてやろう」
茸酔は茸の父親に聞いた。
「ところで、どうして風邪などを引いたのだ、寒いとこに生えていたり、雨の中に立ってたりしても風邪を引いた茸など見たことがない」
「いつだったか、茸を採りにきた人間がくしゃみをしてましてな、何度も何度も大きなくしゃみをして、唾が林の中を充満しおった、俺の笠のてっぺんに唾がかかったら、よろよろとなりました
「きっとそいつに違いない、はやり風邪が出始めておるようだ、今年のは茸にもうつったようだ」
「茸酔さん、大家に言って酒を都合してもらやしょうや、いったん長屋に戻って大家に談判じゃ」
酒飲みの新生がはりきっている。
「そうしましょうか、茸のみなさん、百薬の長を都合してきます」
茸たちは寝っ転がりながら、「よろしくお願いします」と声を合わせた。
茸粋は木野がもってきた画帳をとりだすと、寝ている茸たちの絵を描いた。
と言うことで、長屋に戻りますと、大家の今助にこれこれこうだと話をした。
「茸がしゃべるなんてことはよくわかりませんが、茸酔さんがそういうのなら、濁酒を用意しますか」
と今助はほとんど信じられなようだが、それでも頷いた。三人で飲むつもりではないかと勘ぐっているようでもある。
「いや清酒じゃないときかないそうです」と言ったのは新生。
今助は茸酔が黙っているものだから「茸も元気なやつじゃなきゃ巧くないな」
とぶつぶつ言いながらも、「それじゃ、一本買っといで」と園生を酒屋に走らせた。
「子供の茸には甘酒がよいようで」
茸酔がいうと「ばあさんにすぐ作らせますよ、ところで、元気になった茸は採ってくることができるんでしょうな」
今助は元気になった茸を食うつもりのようである。もっともそのために酒を買わせに行ったわけである。
「そうですが風邪が治るのは数日、今の茸は枯れるでしょう、だが新しく生えてくる茸に風邪はうつらない、それは食えるでしょう」
今助はそれを聞いておやおやと思いながら、それでもうなずいた。
園生が酒を買ってきた。甘酒はすぐにはできないが、白い炊いた飯に酒を少しかけ、甘味を少しばかり入れて、ぐつぐつにて、即席甘酒にした。
「茸酔さん、どうやって茸に飲ますのかね」
口もないのにと思った今助はまだ信じていない。だが茸酔はまじめに反応した。
「そうですね、小さい徳利を持って行きましょう」
「寝ている茸一つ一つに飲ましたら、いつ終わるかわからない、鉄瓶のほうがっよかないですか」
新生の思いつきである。
結局、背負い籠に清酒の入った一升徳利、甘酒の入った鉄瓶を、それに大きめのお茶の茶碗を三つ入れて三人は裏山に入った。今助に茸酔が行きますかと尋ねたのだが、やはり家で待っていると答えた。そういうところは得意ではなさそうだ。
「薬を持ってきたぞ」
茸酔が大きな声で叫ぶと、木の下で横になっていた茸達が立ち上がり、
道に沿ってずらりとならんだ。
「こりゃあいい」
茸粋は茶碗を三つならべ酒をいれた。鉄瓶はふたを取っておいた。
すると茸たちが、茶碗の酒の中に笠を浸した、鉄瓶には子供の茸がごろごろと入った。次から次へと茸が酒浴びをした。
酒に頭を浸した茸は「こりゃあ暖まる」と林の中に散っていくと、ごろりと横になった。
三人は茶碗に酒が足りなくなると徳利からたした。
こうして林の茸がみんな酒を浴びた。
赤い子供の茸が「ありがとう」と三人に礼を言うと兄弟のところに戻っていった。
茸酔はその様子を絵にした。
新生は「みんな飲んじまいやがった」と残念そうだ。
「いや面白い絵が描けました、これもお二人のおかげ、戻って我家で一杯のみましょうか、酒を一本買ってきていただけると助かります」
「もちろんで」
茸酔が銭を二人に渡すと、「先に行って買っときやす」と二人の足は軽やかになった。
その日は茸酔の家で酒となった。木野が茸の煮しめを作り、つまみをいくつか用意した。
「木野さんは料理がうまいね」
二人は美味そうに酒を飲んだ。茸酔はさほど飲むほうではない。
「いや、園生が茸がしゃべったと言ったときにゃ、こいつおかしくなりやがったと思ったが、みると本当に茸がしゃべった、俺もおかしくなったんじゃないか、誰も信じないだろうと思ったら、茸酔さんも茸はしゃべるという、嬉しかったね、俺たちはおかしくなかった」
「茸に限らず、植物、動物、石ころ、みなよくしゃべります、なのに、それが聞こえる人は少ない、今度のことが終わったら、落語にして話しにしたらいいでしょう、きっと受けます」
「そうだ、それにちがいない、新生、一緒に小咄をつくろうぜ」
「ああ、そうしよう」
「それに三日も経てば子供の茸が大きくなる、採ってきて食べよう」
「大家さんにも持ってってやろう」
その日は楽しい飲み会で終わった。
それから三日目の朝。園生と新生が二人して茸酔のところにやってきた。
「おや、今日わ、おじさん落語やる人がまたきたわよ」
木野が奥に声をかける。茸の絵を描いていた茸酔が玄関に出てきた。
「園生さんに新生さん、おいしい茸が採れましたか」
園生は首を横に振った。新生がこんなことを言った。
「園生の奴、茸をとりに行ったんだが、こないだと同じで、駕籠は空っぽ、しょげて帰ってきやがった、それでどうしたいと聞いたら、林の茸がみんな、ふらついているって言うので、俺も見に行ったら、この前に子供だった茸がみんな大きくなって旨そうになっていた、ところが園生の言うとおり、皆よろよろしていた」
「それで茸はどうしたと言っているのです」
「茸の心の臓がどきどきして、目が回ってしまったと言ってました」
「めまいというやつですかな」
「どうもそうのようで」
「しかし、めまいといいうのは流行病ではないと思いますよ」
「それで茸にどうしたと聞いたんです、そうしたら、暑さのせいだと言うんです」
「そんなに暑い日がありましたか」
「ありやせんね」
「あたしがもう一度行ってみましょう」
「茸酔さんに診てもらえば茸もすぐ治ると思います」
そういうことで、茸酔は木野をともなって、二人について長屋の裏の林に行った。
林に入ると黒っぽい鳥が一斉に飛び立った。中の一羽がぎゃああと鳴いた
「やな声だなあれは何でしょう」
新生が茸酔に尋ねた。
「ぎゃあと鳴いたのは鵺ではないか、周りの鳥は椋だな」
「鵺ってと、あの妖怪のたぐいですか」
「そう言われてているな」
鳥に気を取られていた三人が下草の中を見ると、茸たちがよろよろと動いている。
「確かに目を回したときの歩き方だな」
ところが茸酔が離れたところに目をやると、真っ赤な茸や黄色い茸はすっくと立派に立っていた。
特に大きな赤い茸が茸酔の目に止まった。
「おまえさん、もしかすると、あの子供だった赤い茸じゃないかい」
「そうでございますよ、親が風邪を引いたときには私は甘酒をいただき、親はお酒をいただきました、親はもう枯れてしまいましたが、とても喜んでおりました、お礼を申しあげます」
「随分立派な紅天狗茸になったものだ」
「ありがとうございます、甘酒のおかげだと思いますが、大きくなることができました」
「ところで、おまえさんは目を回さなかったのかい」
「ほほ、そこの二人のお兄さんには悪いのですが、目を回しているのはおいしい茸たち、食べられないあちきのような毒茸は立っています」
茸酔には様子がわかってきた。
「食べられる茸は親になにか言われたのだな」
「病気になると人間に採られることはないから、病気になりなさいと親の茸に言われたのでしょう」
「それで、目が回ったふりをしているんだな」
「さあ、どうでしょう、私のような毒茸にはわかりませんが、あそこに目を回した猪口がいます、聞いてみてくださいな」
ちょっと離れたところで、猪口がふらふらと揺れている。
「これ、猪口、なぜ目がまわっておるんだ」
「自分でもわからない、急に目が回ったんだ」
「あそこの紅天狗茸が、風邪を引いた親に病気になれば人に食われないと教えたから、おまえさん方は目を回したふりをしていると言っていたが」
「あの毒茸は食べられる茸がうらやましくてそんなことを言うんだ」
「どういうことかね」
「茸は人間に食べられるのは本望なんだ、おいしく食べてもらってこそ茸のすばらしい一生になる、毒茸は虫には食われるが、毛の生えた動物には食われない、もちろん人間も食べない、それでそんなことを言うんだ」
「ということは、目を回している茸達は食べられてもいいんだな」
「もちろん、だが、どうして目が回ったのか、原因がわからない、そんな俺たちを食べて、どうなるかしらんけどな」
それを聞いていた新生は不思議そうに聞いた。
「目を回しているのは食べられる茸なわけだ、だがあそこの壷のある真っ赤な茸が目を回している、紅茸だ、あれは毒じゃないのか」
茸酔が「あの茸はよその国ではうまい茸として食われているようだ」と説明した。
紅茸とは卵茸のことである。
「ほー、食ってみるか」
園生が猪口に尋ねている。
「目を回しているのが食べられる茸だとすると、選ぶのに容易だが、採ってかまわないかい」
「ああ、茸は食べられたいのだよ」
「それはありがたい」
「さっき言ったように、めまいの茸が人の体に悪さをしなければいいが」
「目を回すと言っても、おまえさん方目はどこにある」
新生が聞いた。
「傘は目でも、耳でも、口でもあるんだ」
「そういうもんか、それじゃ、いただくよ」
園生と新生は目を回している茸をかごに入れた。茸酔は茸が目を回している様子を描いた。
それで、ふと思い立って、紅天狗茸のところに戻ると尋ねた。
「おまえさん方、毒茸も動物に食われたいのかね」
紅天狗茸は答えた。
「そりゃあそうですよ、わちきなど、赤くて綺麗とよく言われる、それはそれでうれしいけど、旨いね、と言われるのが茸の本望よ」
「毒茸は塩漬けにすると毒が抜けると言うが、おまえさんもそうして食ってみようか」
「お願いしますよ、あたしらは猛毒といわれているが、それほどの毒じゃありゃしませんよ、一つ二つ食べても大丈夫」
「それじゃ、採っていこう、木野、袋はないか」
「小さな籠を持ってきてます、食べられる茸を少し採っていこうと思っていました」
「おお、それはよい、籠をかしておくれ、食べられる茸は園生さんと新生さんが採っている、わたしはこの紅天狗茸を採っていって食してみようと思う」
「大丈夫ですか」
木野は手籠を茸酔に渡した。茸酔は紅天狗茸を一つ採って籠にいれた。
「あたしを食べてくれるのかい」
「ああ、食べてみよう」
「嬉しいね、おいしく食べてくださいよ」
紅天狗茸は手籠に横たわった。
「茸酔師匠、わてらの駕籠が茸でいっぱいになりましたよ、こんな楽な茸採りははじめてだ」
こうして、園生と新生は食べられる茸を持って今助長屋にもどり、茸酔と木野は二人から食べられる茸を分けてもらって、それに紅天狗茸をもって家に戻った。
家に戻った茸酔は「紅天狗を食べてみよう」と木野に言った。
「どうやって食べる、おじさん」
「生は危ないから、煮るか焼くか炒めるか」
「熱を入れるということね」
木野は小さいながら頭の回る娘である。
「それじゃ、食べられる茸の煮つけと、紅天狗茸の天ぷら作ってあげましょう」
木野は料理も上手である。
夕餉には茸の煮付けと紅天狗茸の天ぷらがお膳にのった。
「うまそうだ、お酒をつけておくれ」
家にいるときは木野と差し向かいで食事をとる。使用人主人という関係ではない。姪っ子と一緒に住んでいるといった関係である。
「おじさん、あたし初めてしゃべる茸を見た」
「ああ、そうだね、茸も草もみんなよくしゃべるのだよ、木野も茸に慣れたね」
「うん、私茸料理の店をやりたい」
「ああ、そうなったら、この広い家を直して、お店をつくればよいな」
「いいの」
「いいよ、木野がもっと大きくなってからだけどな」
茸酔は茸の煮しめを食べた。
「これは栗茸だ、なかなかうまい」
「平茸もおいしいわ」
茸酔は酒をちびちび飲みながら茸を摘まんだ。木野は茸の煮しめでご飯を食べている。
「おじさん、なぜ食べられる茸はめまいを起こしたのかしら」
「人間だと風邪をこじらせたり、首がこったりしたときにめまいをおこす、耳が悪くてもめまいが起きる」
「もう風邪は下火だし、茸の首はこるかしら」
「そうだな、とすると耳だな、耳に何か聞こえてめまいを起こしたんだろう」
そう言った茸酔は林に入ったときのことを思い出した。椋鳥に混じって鵺がいた。
「鵺かもしれない、夜に大きな声で鳴く、しかも血をはくような不吉な声だ」
「それで、茸は目眩を起こしたのね」
茸酔は紅天狗茸の天ぷらに箸をのばした。
塩をちょっとつけるとかじり付いた。
「お、うまい」
「おじさん、その茸大丈夫なの」
まだ子供の木野には紅天狗茸を食べさせなかったのだ。
「いい味だ」
そう言ったとき、茸酔は徳利を持って部屋の中を歩き出した。
「おじさんどうしたの」
心配そうに木野が茸酔を見た。
茸粋は徳利から酒を飲みながら、ゆらゆらと部屋の中を歩きまわった。
「おじさん、目が回っているみたい」
そしてとうとう、着ているものをすべてとってしまうと、畳の上に大の字になって寝てしまった。
「恥ずかしいこと」
木野は茸酔に脱いだ着物を掛けた。
園生が茸採りから帰ってきた。
園生は朝日が顔をだすと裏の林にいって、食べられる茸を背負い籠いっぱいに採ってくる。ところが園生のかごの中を見た、長屋の縁台でたばこを吸っていた新生(しんしょう)が驚いた。
二人は今助長屋に住む売れない落語家である。
「おい、園生、籠が空っぽじゃねえか」
園生はうなだれて隣に腰掛けた。
「林に茸が全くないってことはないだろう、だれかに盗まれたか」
園生は首を横に振った。
「茸はいつものようにたくさんいたんだ」
「それで何で採らなかったんだ」
「くしゃみしてた」
「なんだそりゃ」
「咳もしてた」
「どうやって」
「頭を曲げて、こほこほいってた」
「狢にでもだまくらされたんじゃねえか」
園生はまたも首を横に振った。
「赤い茸が言ったんだ、はやり風邪ってな」
はやり風邪とは今のインフルエンザである。
「茸がしゃべるわきゃねえだろ、おまえに熱があるんじゃねえのか」
「いんや熱なんかない」
そこへ黄色い声が聞こえた。
「いいお医者さん知らない」
「誰が言ったんだ」
新生が園生を見ます。
「俺じゃねえよ」
「ここよ」
園生は空の籠を背負ったまま腰掛けている。その籠から声が聞こえたような気がして、新生が見ると籠の底に赤い小さな茸が転がっている。
「こんな小さいの採ってきたのか」
新生が赤い茸をつまみ出した。
「おれこんな赤い茸採らんよ」
園生が首を傾げた。
そのとき、赤い茸が新生の手の中でぴょいと立ち上がった。
「おっかさんたちの風邪を治す医者しらない」
新生がびっくりして、手の平をひっこめそうになった。
「落ちちゃうじゃない、気をつけてよ」
そう言われて、改めて見ると赤い茸の傘がぱくぱく動いている。
園生が言った。
「おれたちゃ、医者知らずでね、それに人の医者じゃ茸の病を治せねえ」
「そうなの、困ったわ」
「茸に医者いないのかい」
「うん、でも茸の長老もはやり風邪ははじめてなんだって、人間じゃだめなら、梟にでも頼もうかしら、それじゃ帰ろう」
「どうやって帰るんだ」
そこに黒い鳥が降りてきて、茸を咥えると山へ戻っていた。
「なんだい、あいつは」
「烏じゃねえな、少しちっちぇ」
「椋鳥じゃねえか」
「ちょいと違うな、それより茸がしゃべりやがった」
「うん、夢かもな、茸が風邪ひくなんてな」
「俺たち二人が見たじゃねえか、ほんとなんだよ」
「二人とも何かにとりつかれたんじゃねえか」
「大丈夫だとおもうがな」
「茸の医者なんぞいないが、茸をよく知っている人に聞いてみるか」
「そうだな、大家の隠居だって茸のことはよく知っている」
「そうだ、大家に話してみよう」
「俺たちまともじゃねえような気がする、きっと酔っ払ってたんだろうとか何とか言われそうだがそうするか」
二人は大家の家に行った。
「大家さん」
「二人そろってなんだい」
「茸の医者はいますかね」
「なんだいそれは」
「裏山の茸がはやり風邪で、みな熱を出してます」
「茸がかい」
「園生が見てきました、あたしも茸と話しました、まともでしょうか」
「ふーむ、お前さんがた噺家はいつもまともじゃないから、まともなんだろう」
なんとも信じたくなるような理屈です。
「茸が医者をさがしてます」
「茸の医者はしらんが、茸と仲のよい人は知っておるよ」
「教えてください」
「深川にすんでる茸狂さんだ、ほんとうの名は円山茸酔さんだ」
「なにやってる人です」
「茸絵かきだ」
「病気のことも詳しいんですかい」
「そりゃわからんが、茸酔さんは佐渡の医者の元で、薬の本のための絵を描いていたことがある、そのとき医師がいろいろな病気の患者を診察するのを見たり、手伝ったんじゃないかな、そういえば茸が夜歩くなんてことも言ってたから、茸の変なことを見たことがあるんじゃないか、お前さんがたの仲間だろう」
「そりゃいいですね、茸酔さんとやらの家を教えてくださいよ」
そういうことで、園生と新生は茸酔のところに行った。
「随分立派な家じゃねえか」
茸酔の家はその昔、師匠の虎酔の家だった。亡くなるときに虎酔にすべてやると言われて茸酔は住み続けている。虎酔は加賀の偉い殿様の外腹だったこともあり、瀟洒た屋敷である。
「へえい、こんちは」
玄関で新生が中に声をかけると。「はーい」と若い女の返事が返ってきた。出てきたのはまだ十三、四のおかっぱ頭の子供である。
「ハイ、何でしょう」
「あの、茸の医者探してるんで」
新生がそこまで言ったら、女の子は笑い出した。
「茸の医者はいないけど、絵描きならいるわよ」
「あ、そいつだ」
園生が頭をかく。
「おじさん、お客さん」
女の子が中に声をかけた。
「どなたかな」
茸酔が玄関に出てきた。
「なんでしょう」
「いえ、長屋の家主が茸の医者はいないが、茸の絵を描く人がここにいると言うんで、きやした」
「どこの長屋ですかな」
「今助長屋で」
「おお、そうですか、今助さんは元気かな、まあ入ってください」
「ありがとうさんで、私は新生、こいつは園生です」
「茸酔です、今助さんは私の師匠の虎の絵が好きで、屏風を買ってくださった」
「へえ、大家さんの部屋においてあります、みんなにみせびらかせて喜んでます」
そこへさっきの女の子がお茶をもってきた。
「私の姪で、キノといいます、今は木野と書くんですよ、私が佐渡に行っている間に、虎酔師匠がこの字を使えとキノに書いて渡したそうです」
木野は茸酔が佐渡に言っている間、師匠の虎酔の世話をするため、この家で働いていた、茸酔の姉の娘である。師匠が亡くなった後もこの家に奉公している。
「おじさんたち茸のお医者を捜しているそうです」
木野が笑いながら言った。
「へえ、裏の林に生えている茸が風邪をひいてくしゃみをしていまして、治してやろうと思うんで」
それを聞いた茸酔は,おやここにも生きものと話ができる人がいると園生を見た。
「園生の奴、茸がしゃべるなんていうものだからおかしくなっちまったかと思いましたが、籠の中に入っていたちっこい赤い茸がやっぱりしゃべりやした。あたしも見ています、ほんとうにしゃべりやした」
新生が言うと茸酔はうなずいた。こいつもだ。
「茸だって人と同じように眠るし夢を見るし、夢遊病にもなる。私も経験があります。だが私は茸の医者じゃない、ただの絵描きですよ」
「今助の大家さんは、茸酔さんは佐渡でお医者の手伝いをなさっていたから、病気のことはよく知ってなさる、それに茸のことは江戸で一番よく知っている方だと言っておりやした」
「いや、病気の名前は耳で覚えましたが、治療の仕方はわからない、まして、茸の病気についちゃ知りませんな」
「だけどぜひ、茸の風邪をみてやってください」
「風邪を引いた茸の絵を描くのも面白い、昼過ぎてから木野と一緒に伺いましょう、今助長屋の裏の林には何度か言ったことがあります、確かに色々な茸が生えていましたな」
というわけで、茸酔は木野をともなって今助長屋にやってきた。木野はよく絵の道具をもって茸酔のお供をする。
「茸を見る前に、今助さんに挨拶をしておこう」
茸酔は大家さんの家に顔を出した。
「おや、茸酔さん、園生と新生がとんだ話をもっていっちまって、すまんことですが、まあ聞いてやってください」
「ご無沙汰しています、私の師匠がお世話になりました、話しは聞きましたよ、お二人ともいい人たちだ」
「それなら、よござんした。茸酔師匠の目に金の入った虎、いいですな、毎日楽しんでおりますよ」
虎酔晩年の虎の絵はこの今助がどうしてもほしいと買っていったのである。金を絵に施すことは江戸では御法度、茸酔が佐渡で土から金を吸い取って貯める茸を見つけ、お上にみつからぬよう、乾燥させ虎酔に土産としてもってきたのである。
「それじゃあ、園生さんと新生さんと茸を見て参ります」
「後で様子を聞かせてくださらんか」
「ええ、茸の風邪ひきとは珍しいですから」
茸酔と木野は長屋で待っている二人のところへ行った。
「あ、先生お待ちしてました」
園生と新生は茸酔を裏の林に案内した。
林の中はひんやりとして、少し寒いほどである。
ちょっと歩いていくと、茸酔は目を見張った。下草の間で色とりどり、形が様々な茸が転がっている。
「みんな寝込んじまってる」
園生がしゃがむと、そこへ赤い小さな茸が飛び出してきた。
「おじさん、お医者見つけたの」
園生に向かって傘をふるわした。
「いやな、医者じゃないが、茸のことをよく知っている先生をつれてきたよ、ほら茸酔先生だ」
「母ちゃん、父ちゃん、姉ちゃん、兄ちゃんみんな風邪ひいた」
確かに茸が話をしている。茸酔は夢遊茸ことを思い出した。茸酔も茸と話をしたことがある。
「おまえさんは大丈夫かい」
園生が赤い茸に聞いている。
「うん、あたいは傘を露でよく洗って清潔にしてるから大丈夫」
「えらいね」
「さて、どうやって治すかな、佐渡の東経先生は風邪を引いた患者に卵酒を飲ませていたな」
「俺だったら嬉しいが、茸が酒を飲みますかい、だいたい口がない」
新生は大酒飲みだ。
すると、茸酔の足もとに転がっていた茶色の茸の笠に大きな口が開いた。
「何でえ、茸も飲兵衛じゃねえか」
「父ちゃんは猿酒が大好きだ」
赤い茸の子供が言った。
「子供茸にゃあ何がいいでしょう」
「うむ、甘酒がよかろう」
「あたい、風邪ひいていないけど甘酒いいな」
「ああ、もってきてやろう」
茸酔は茸の父親に聞いた。
「ところで、どうして風邪などをひいたのだ、寒いとこに生えていたり、雨の中に立っていても風邪をひいた茸など見たことがない」
「いつだったか、茸を採りにきた人間がくしゃみをしてましてな、何度も何度も大きなくしゃみをして、唾が林の中を充満しおった、俺の笠のてっぺんに唾がかかったら、よろよろとなりました。
「きっとそいつに違いない、はやり風邪が出始めておるようだ、今年のは茸にもうつったようだ」
「茸酔さん、大家に言って酒を都合してもらやしょうや、いったん長屋に戻って大家に談判だ」
大酒飲みの新生がはりきっている。
「そうしましょうか、茸のみなさん、百薬の長を都合してきます」
茸たちは寝っ転がりながら、「よろしくお願いします」と声を合わせた。
茸粋は木野がもってきた画帳をとりだすと、寝ている茸たちの絵を描いた。
と言うことで、茸酔は、長屋に戻りますと、大家の今助にこれこれこうだと話をした。
「茸がしゃべるなんてことはよくわかりませんが、茸酔さんがそういうのなら、濁酒を用意しますか」
今助はほとんど信じられなようだが、それでも頷いた。三人で飲むつもりではないかと勘ぐっているようでもある。
「いや清酒じゃないときかないそうです」と言ったのは新生。
今助は茸酔が黙っているものだから、
「茸も元気なやつじゃなきゃ巧くないな」
ぶつぶつ言いながらも、「それじゃ、一本買っといで」と園生を酒屋に走らせた。
「子供の茸には甘酒がよいようで」
茸酔がいうと「ばあさんにすぐ作らせますよ、ところで、元気になった茸は採ってくることができるんでしょうな」
今助は元気になった茸を食うつもりのようである。もっともそのために酒を買わせにいったわけだ。長屋を経営する大家さん損得勘定はおてのものだ。
「そうですが風邪が治るのは数日、今の茸は枯れるでしょう、だが新しく生えてくる茸に風邪はうつらない、それは食えるでしょう」
今助はそれを聞いておやおやと思いながら、それでもうなずいた。
園生が酒を買ってきた。甘酒はすぐにはできないが、白い炊いた飯に酒を少しかけ、甘味を少しばかり入れて、ぐつぐつにて、即席甘酒にした。
「茸酔さん、どうやって茸に飲ますのかね」
口もないのにと思った今助はまだ信じていない。だが茸酔はまじめに反応した。
「そうですね、小さい徳利を持って行きましょう」
「寝ている茸一つ一つに飲ましたら、いつ終わるかわからない、鉄瓶のほうがよかねえですか」
新生の思いつきである。
茸酔が今助に一緒に行きますかと訊ねたのだが、やはり家で待っていると答えた。そういうところは得意ではなさそうだ。
結局、背負い籠に清酒の入った一升徳利、甘酒の入った鉄瓶、それに大きめのお茶の茶碗を三つ入れて、三人は裏の林に入った。
「薬を持ってきたぞ」
茸酔が大きな声で叫ぶと、木の下で横になっていた茸たちが立ち上がり、
道に沿ってずらりとならんだ。
「こりゃあいい」
茸粋は茶碗を三つならべ酒をいれた。鉄瓶はふたを取っておいた。
すると茸たちが、茶碗の酒の中に笠を浸した、鉄瓶には子供の茸がごろごろと入った。次から次へと茸が酒浴びをした。
酒に頭を浸した茸は「こりゃあ暖まる」と林の中に散っていくと、ごろりと横になった。
三人は茶碗に酒が足りなくなると徳利からたしてやった。
こうして林の茸がみんな酒を浴びた。
赤い子供の茸が「ありがとう」と三人に礼を言うと兄弟のところに戻っていった。
茸酔はその様子を絵にした。
新生は「みんな飲んじまいやがった」と残念そうだ。
「いや面白い絵が描けました、これもお二人のおかげ、戻って我家で一杯のみましょうか、酒を一本買ってきていただけると助かります」
「もちろんで」
茸酔が銭を二人に渡すと、「先に行って買っときやす」
二人の足は軽やかになった。
その日は茸酔の家で酒宴となった。木野が茸の煮しめを作り、つまみをいくつか用意した。
「木野さんは料理がうまいね」
二人は美味そうに酒を飲んだ。茸酔はというと、ちびりちびり。さほど飲むほうではない。
「いや、園生が茸がしゃべったと言ったときにゃ、こいつおかしくなりやがったと思ったが、みると本当に茸がしゃべった、俺もおかしくなったんじゃないか、誰も信じないだろうと思ったら、茸酔さんも茸はしゃべるという、嬉しかったね、俺たちはおかしくなかった」
「茸に限らず、植物、動物、石ころ、みなよくしゃべります、なのに、それが聞こえる人は少ない、今度のことが終わったら、落語にして話しにしたらいいでしょう、きっと受けます」
「そうだ、それにちがいない、新生、一緒に小咄をつくろうぜ」
「ああ、そうしよう」
「それに三日も経てば子供の茸が大きくなる、採ってきて食べよう」
「大家さんにも持ってってやろう」
その日は楽しい飲み会で終わった。
それから三日目の朝。園生と新生が二人して茸酔のところにやってきた。
「おや、今日わ、おじさん落語やる人がまたきたわよ」
木野が奥に声をかける。茸の絵を描いていた茸酔が玄関に出てきた。
「園生さんに新生さん、おいしい茸が採れましたか」
園生は首を横に振った。新生がこんなことを言った。
「園生の奴、茸をとりに行ったんだが、こないだと同じで、籠は空っぽ、しょげて帰ってきやがった、それでどうしたいと聞いたら、林の茸がみんな、ふらついているって言うので、俺も見に行ったら、この前に子供だった茸がみんな大きくなって旨そうになっていた、ところが園生の言うとおり、皆よろよろしていた」
「それで茸はどうしたと言っているのです」
「茸の心の臓がどきどきして、目が回ってしまったと言ってました」
「めまいというやつですかな」
「どうもそうのようで」
「しかし、めまいは流行病ではないと思いますよ」
「それで茸にどうしたと聞いたんです、そうしたら、暑さのせいだと言うんです」
「そんなに暑い日がありましたか」
「ありやせんね」
「あたしがもう一度行ってみましょう」
「茸酔さんに診てもらえば茸もすぐ治ると思います」
そういうことで、茸酔は木野をともなって、二人について長屋の裏の林に行った。
林に入ると黒っぽい鳥が一斉に飛び立った。中の一羽がぎゃああと鳴いた
「やな声だなあれは何でしょう」
新生が茸酔に尋ねた。
「ぎゃあと鳴いたのは鵺(ぬえ)ではないか、周りの鳥は椋だな」
「鵺ってと、あの妖怪のたぐいですかい」
「そう言われているな」
鳥に気を取られていた三人が下草の中を見ると、茸たちがよろよろと動いている。
「確かに目を回したときの歩き方だな」
ところが茸酔が離れたところに目をやると、真っ赤な茸や黄色い茸はすっくと立派に立っていた。
特に大きな赤い茸が茸酔の目に止まった。
「おまえさん、もしかすると、あの子供だった赤い茸じゃないかい」
「そうでございますよ、親が風邪をひいたときには、私は甘酒をいただき、親はお酒をいただきました、親はもう枯れてしまいましたが、とても喜んでおりました、お礼を申しあげます」
「随分立派な紅天狗茸になったものだ」
「ありがとうございます、甘酒のおかげだと思いますが、大きくなることができました」
「ところで、おまえさんは目を回さなかったのかい」
「ほほ、そこの二人のお兄さんには悪いのですが、目を回しているのはおいしい茸たち、食べられないあちきのような毒茸は立っています」
茸酔には様子がわかってきた。
「食べられる茸は親になにか言われたのだな」
「病気になると人間に採られることはないから、病気になりなさいと親の茸に言われたのでしょう」
「それで、目が回ったふりをしているんだな」
「さあ、どうでしょう、私のような毒茸にはわかりませんが、あそこに目を回した猪口がいます、聞いてみてくださいな」
ちょっと離れたところで、猪口がふらふらと揺れている。
「これ、猪口、なぜ目がまわっておるんだ」
「自分でもわからない、急に目が回ったんだ」
「あそこの紅天狗茸が、風邪をひいた親に病気になれば人に食われないといわれたから、おまえさん方は目を回したふりをしていると言っていたが」
「あの毒茸は食べられる茸がうらやましくてそんなことを言うんだ」
「どういうことかね」
「茸は人間に食べられるのは本望なんだ、おいしく食べてもらってこそ茸のすばらしい一生になる、毒茸は虫には食われるが、毛の生えた動物には食われない、もちろん人も食べない、それでそんなことを言うんだ」
「ということは、目を回している茸達は食べられてもいいんだな」
「もちろん、だが、どうして目が回ったのか、原因がわからない、そんな俺たちを食べて、どうなるかしらんけどな」
それを聞いていた新生は不思議そうに聞いた。
「目を回しているのは食べられる茸なわけだ、だがあそこの壷のある真っ赤な茸が目を回している、紅茸だ、あれは毒じゃないのか」
茸酔が「あの茸はよその国ではうまい茸として食われているようだ」と説明した。
紅茸とは卵茸のことである。
「ほー、食ってみるか」
園生が猪口に尋ねている。
「目を回しているのが食べられる茸だとすると、選ぶのに容易だが、採ってかまわないかい」
「ああ、茸は食べられたいのだよ」
「それはありがたい」
「さっき言ったように、めまいの茸が人の体に悪さをしなければいいが」
「目を回すと言っても、おまえさん方目はどこにある」
新生が聞いた。
「傘は目でも、耳でも、口でもあるんだ」
「そういうもんか、それじゃ、いただくよ」
園生と新生は目を回している茸をかごに入れた。茸酔は茸が目を回している様子を描いた。
それで、ふと思い立って、紅天狗茸のところに戻ると尋ねた。
「おまえさん方、毒茸も動物に食われたいのかね」
紅天狗茸は答えた。
「そりゃあそうですよ、わちきなど、赤くて綺麗とよく言われる、それはそれでうれしいけど、旨いね、と言われるのが茸の本望よ」
「毒茸は塩漬けにすると毒が抜けると言うが、おまえさんもそうして食ってみようか」
「お願いしますよ、あたしらは猛毒といわれているが、それほどの毒じゃありゃしませんよ、一つ二つ食べても大丈夫」
「それじゃ、採っていこう、木野、袋はないか」
「小さな籠を持ってきてる、食べられる茸を少し採っていこうと思ってたから」
「おお、それはよい、籠をかしておくれ、食べられる茸は園生さんと新生さんが採っている、わたしはこの紅天狗茸を採って食してみようと思う」
「大丈夫ですか」
木野は手籠を茸酔に渡した。茸酔は紅天狗茸を一つ採って籠にいれた。
「あたしを食べてくれるのかい」
「ああ、食べてみよう」
「嬉しいね、おいしく食べてくださいよ」
紅天狗茸は手籠に横たわった。
「茸酔師匠、わてらの籠が茸でいっぱいになりましたよ、こんな楽な茸採りははじめてだ」
こうして、園生と新生は食べられる茸を持って今助長屋にもどり、茸酔と木野は二人から食べられる茸を分けてもらって、それに紅天狗茸をもって家に戻った。
家に戻った茸酔は「紅天狗を食べてみよう」と木野に言った。
「どうやって食べる、おじさん」
「生は危ないから、煮るか焼くか炒めるか」
「熱を入れるということね」
木野は小さいながら頭の回る娘である。
「それじゃ、食べられる茸の煮つけと、紅天狗茸の天ぷら作ってあげましょう」
木野は料理も上手である。
夕餉には茸の煮付けと紅天狗茸の天ぷらがお膳にのった。
「うまそうだ、お酒をつけておくれ」
家にいるときは木野と差し向かいで食事をとる。使用人主人という関係ではない。姪っ子と一緒に住んでいるといった関係である。
「おじさん、あたし初めてしゃべる茸を見た」
「ああ、そうだね、茸も草もみんなよくしゃべるのだよ、木野も茸に慣れたね」
「うん、私茸料理の店をやりたい」
「ああ、そうなったら、この広い家を直して、お店をつくればよいな」
「いいの」
「いいよ、木野がもっと大きくなってからだけどな」
茸酔は茸の煮しめを食べた。
「これは栗茸だ、なかなかうまい」
「平茸もおいしいわ」
茸酔は酒をちびちび飲みながら茸を摘まんだ。木野は茸の煮しめでご飯を食べている。
「おじさん、なぜ食べられる茸はめまいを起こしたのかしら」
「人間だと風邪をこじらせたり、首がこったりしたときにめまいをおこす、耳が悪くてもめまいが起きる」
「もう風邪は下火だし、茸の首はこるかしら」
「そうだな、とすると耳だな、耳に何か聞こえてめまいを起こしたんだろう」
そう言った茸酔は林に入ったときのことを思い出した。椋鳥に混じって鵺がいた。
「鵺かもしれない、夜に大きな声で鳴く、しかも血をはくような不吉な声だ」
「それで、茸は目眩を起こしたのね」
茸酔は紅天狗茸の天ぷらに箸をのばした。
塩をちょっとつけると口に入れた。
「お、うまい」
そういいながらあっという間に全部食してしまった。
「おじさん、その茸大丈夫なの」
まだ子供の木野には紅天狗茸を食べさせなかった。
「いい味だ」
そう言ったとき、茸酔は徳利を持って部屋の中を歩き出した。
「おじさんどうしたの」
心配そうに木野が茸酔を見た。
茸粋は徳利から酒を飲みながら、ゆらゆらと部屋の中を歩きまわった。
「おじさん、目が回っているみたい」
そしてとうとう、着ているものをすべてとってしまうと、畳の上に大の字になって寝てしまった。
「恥ずかしいこと」
木野は茸酔に脱いだ着物を掛けた。
四半刻もすると、茸酔が目を覚ました。
「おじさん目を覚ましたね、大丈夫なの」
茸酔は自分が裸であることに気がついて、あわてて着物の袖に手を通した、
「わしはどうしたのだ」
木野は見たことを話して聞かせた。
「おおそりゃあ、驚いたろう、悪いことをしたな、紅天狗茸を食したら、目の前にいろいろな色が現れてくるくるまわった。真ん中に紅天狗茸が現れ、わしゃ、それを追いかけた、目は回ったが周りは光にかこまれ、気持ちがよくなって寝てしまったんだ、紅天狗茸は目眩の茸だ、だがとても美味いものだった」
その後、茸酔が茸の病気という絵草紙をだしたら飛ぶように売れた、園生と新生は茸の病という新作落語で大当たり、二人ともども真打ちになったのでございます
四半刻もすると、茸酔が目を覚ました。
「おじさん目を覚ましたね、大丈夫なの」
茸酔は自分が裸であることに気がついて、あわてて着物の袖に手を通した、
「わしはどうしたのだ」
木野は見たことを話して聞かせた。
「おおそりゃあ、驚いたろう、悪いことをしたな、紅天狗茸を食したら、目の前にいろいろな色が現れてくるくるまわった。真ん中に紅天狗茸が現れ、わしゃ、それを追いかけた、目は回ったが周りはいろいろな光にかこまれ、気持ちがよくなって寝てしまったんだ、紅天狗茸は目眩の茸だ、だがとても美味いものだった」
その後、茸酔が茸の病気という絵草紙をだしたら飛ぶように売れた、園生と新生は茸の病という新作落語で大当たり、二人供も真打ちになったのでございます
目眩茸


