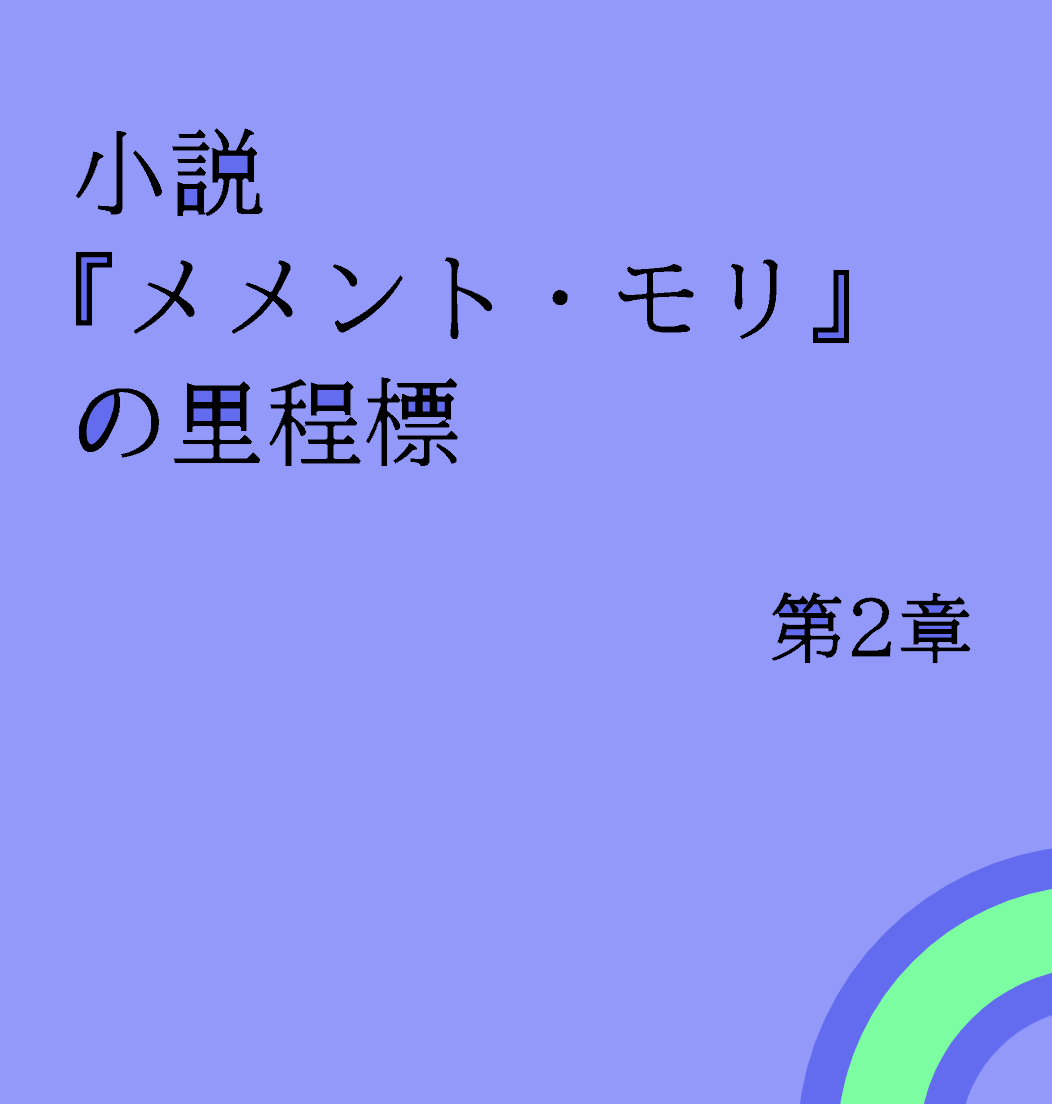
小説『メメント・モリ』の里程標 第二章
一 お会いしてみたい憧れの「あの方」のこと
ウェイトレスの運ぶコーヒーの香りが、柔らかく辺りを包む。
「こちらホットコーヒーとアイスティーになります」
テーブルに白いソーサーとカップが置かれる。遠目から見ても気付くほど、持ち手の部分が特徴的な作りのカップだ。
「ありがとうございます」
男性は顔を上げずにウェイトレスへ礼を告げる。彼の向いに座るもう一人の男性は、彼女の顔の方を見て軽く頷いた。
「以上でご注文の品はお揃いでしょうか」
「はい」
「では、ごゆっくりどうぞ」
彼女の淡白な声音は、今ここへ向かっている待ち合わせ相手の声に、少し似ている気がする。
そうして隣のテーブルの配膳を終え、私の横を通り過ぎて行くウェイトレスの後ろ姿に、ちらりと目を遣った。それは丁度、腰の白いリボンがふわりと揺れる瞬間だった。その清潔そうな白を見つめながら、開いていた手帳をぱたんと閉じ、明るく声を掛ける。
「すみません。私も注文、いいですか?」
待ち合わせの十三時までは、まだ十分な時間がある。
私は目の前に並んだホットコーヒーと軽食のセットをまじまじと眺めた。サンドウィッチには、ハムとたまごと、私が追加注文したスライスチーズが三枚も挟み込まれている。サラダには緑を覆い尽くすようにエビとトマトがたっぷりで、テーブルの上が一気に華やいだようだ。
とりあえずコーヒーを片手に、今朝駅で購入した新聞を広げる。パンの端を擦らないように一枚、一枚と、嵩張る紙を捲りながら見出しの文字を注意深く目で追った。
「あった」
お目当ての記事は、大分後ろの方、それも新聞の折目部分に近い下段に、小さく掲載されていた。
「若き異彩小説家ダルト・スリオルト 没後三十周年」
不遇の新進気鋭作家であったダルト・スリオルトの没後三十周年を記念し、初の全集が満を持して刊行。未発表原稿多数収録。再来月より隔月一冊刊行予定。
たった数行のその囲みを、鋏を使って丁寧に真っ直ぐ切り抜く。そして、革の大きな黒鞄からスクラップブックを取り出し、新たなページの上段に貼り付けた。
また一つ、私の大好きな先生コレクションが増えたのだ。
私はサンドウィッチに齧り付きながら、今度はスクラップブックの歴史を、現在から過去へと捲って行く。
最初に目に入る十数ページは、ほとんど私の手書きメモばかりが貼り付けてある。それより遡ると、途端に随分と年期の入った新聞記事が現われる。急いで鋏を入れたからか、あの人のせっかちな性格からか、切り抜きの周囲はどれも極端に歪んでいた。
カラン。
喫茶店の扉が開くのと同時に、上部に取り付けられた鐘が鳴る。さっと顔を上げると、私の待ち侘びた彼女の姿が店の入り口にあった。
「あ、クランベさん! こっちです!」
私は慌てて立ち上がり、右手を振る。直ぐに彼女は此方へ気付き、柔和に微笑んだ。
「ごめんなさい、メリアさん。お待たせしてしまったみたいで」
「いいえ、私が早めに来てしまっただけですから」
彼女の着こなしたスーツから、薬品のような、それでいてほんのり甘いような香りがする。
高鳴る胸を抑えつつ、私は彼女の顔を真っ直ぐ見つめた。
「寧ろ、本来ならこちらからお訪ねしなくてはいけないのに。わざわざありがとうございます」
「それは良いのよ。この喫茶店、以前から入ってみたかったの」
彼女はテーブルの上をちらっと見て目尻を下げた。
「お食事中、だったかしら」
「あ、すみません!」
放り出していた新聞と鋏を脇に寄せ、サラダボウルと齧り掛けのサンドウィッチの皿を手前に引く。
「クランベさんも、何か召し上がりますか?」
「私はもう済ませてしまったから、コーヒーだけ。気にしないでゆっくり食べてね」
席に着いた彼女は、優雅な仕草で先程のウェイトレスを呼び、慣れた様子でコーヒーを注文した。
「暫くぶりね」
「そうですね。今日お会いできるの楽しみすぎて、昨夜は全然眠れませんでした」
私は笑いながら、お言葉に甘えて、とトマトへフォークを突き立てた。
「前回お会いしたのは……私がまだ大学に通っていた頃でしたから、ええと」
「もう十年くらいになるかしら」
「たぶん、そのくらいに」
「じゃあもう、あの事件の頃のお父さんのお歳、並んでしまったのね」
「そうなんです」
レタスと小ぶりなエビを重ねてフォークに差す。
「最近父に似て来たって、母にも言われて。娘としてはすごく複雑な気分です」
「ふふ。でもメリアさん、昔からお母さん似だったわね。アマンダさんにお会いしたのはあの時の一度だけだけれど、彼女の穏やかな雰囲気、ちゃんとメリアさんに受け継がれているわ」
「母は穏やかっていうより、のんびり屋って感じですけどね」
「今でも変わらずお元気で?」
「はい。父の手伝いも板に付いて。最近は母の方が、文壇の方と交流深いんですよ。結構楽しんでるみたいです」
柔らかく微笑んだ後、クランベさんは頬杖を突いた。
「メリアさん、髪、かなり長くなったわね。手紙で髪を伸ばし始めたって読んでから、色々想像したのよ。もしかして想い人でも出来たのかしら」
「えへへ、内緒です」
「似合ってる。本当に綺麗になったわ」
「ありがとうございます」
思わず頬が緩んでしまう。以前は肩に付くと直ぐに切っていた髪を、今は思い切ってロングにしている。理由は少し恥ずかしくて誰にも明かしていない。
「クランベさんだって。十年前と全然お変わりなくて、やっぱり綺麗」
「ありがとう。そう言って貰えると嬉しいわ」
お世辞では無かった。目の前の彼女は、十年前に会った時と変わらず、否、初めてお会いした三十年前から変わらず、知的で涼しげで、何処となく深みのある淑女のままだった。とても、もう五十歳を超えているとは思えない。
「先程から気になっていたのだけれど」
店内の蓄音機から流れる音が一瞬止んで、再び上品なクラシック曲が流れ出す。
「何を見ていたの?」
彼女は私の手元を覗き込んだ。
「これですか? 私の秘蔵コレクションです」
私はスクラップブックの表紙を上にして、彼女へ手渡した。
「『ダルト・スリオルト先生の記録』。随分年季の入った表紙ね。題字、メリアさんの字では無い様だけれど」
「はい。それ、父の筆跡です。誕生祝いに強請って、譲り受けたものなんです」
「開いても?」
「良いですよ。クランベさんからしたら、真新しい情報は無いでしょうけど」
最初に彼女が開いたページは、小説『嘴に緑のオリーブを』に登場する鳥の描写について、私なりに論じたメモが貼ってある箇所だった。
「白い鳩の最初の登場シーン……かなり深く読み込んであるわね。ふふ。本当に好きなのね」
私は齧ったサンドイッチを急いで飲み込み、大きく頷く。
「はい! 私の人生を変えてくれた人ですから、スリオルト先生は」
彼女はさらに中程のページを開いた。
「あら、この記事……」
今度は私が、彼女の手元を覗き込む。
そこには何度も読み返した、あの新聞記事の歪な切り抜きが貼ってあった。澄まし顔のうら若き青年の写真が、ぼんやりと正面を向いている。
「人気の若手小説家 ダルト・スリオルト氏死去」
先日、ガロンネッツ通りのスリオルト邸書斎から出火。数時間後に鎮火も屋敷は全焼。邸内から男性一名の遺体発見。調査の結果、遺体は当主で小説家のダルト・スリオルト氏と判明。また、火災発生時、同邸を訪れた担当編集者ルルボッチ・バルフォン氏も全身火傷により現在意識不明。ランプ用の燈油缶に暖炉の炎が引火か。現場は気密性が高く、バックドラフト現象により被害が拡大した模様。当局は事故として処理。
店の奥で柱時計が時を知らせる鐘を打っている。十三時だ。
クランベさんは、いつの間にか運ばれて来ていたコーヒーカップの持ち手に、指を絡ませていた。
「……報道陣の踊らされようと言ったら、まるで滑稽なマリオネット」
彼女は溜め息混じりにそう呟いた。そして瞬時に、はっとしたように眉間の辺りを片手で覆った。
「ごめんなさい、メリアさん。自身の知らない分野について、とやかく言うものでは無いわね。もし気を悪くしたなら謝るわ」
「いいえ」
私は首を大きく横に振る。
「私もこういうのにうんざりしている一人ですから。同じ業界の人間として情けない話です」
すっかり冷めてしまったコーヒーと相まって、少ししんみりとした声が出てしまう。
「あの日の詳しい話は、お父さんから聞いているのでしょう?」
「はい。でも、あの父ですから、大袈裟と言うか、感情的と言うか。何処まで鵜呑みにして良いのやらって感じです」
私が苦笑いをしたのを見て、彼女は口元を隠すようにして笑った。
「楽しい方ですものね。そうね、私の口から話しても良いのだけれど……」
思わぬ言葉に鼓動が一気に速くなる。
「本当ですか! 聞きたいです!」
クランベさんとは直接お会いできなくなってからも頻繁に文通していたが、あの日の事は何と尋ねたものか迷ったまま話題にした事は無かった。
「これは個人的な話だから、記事には含めないって約束してくれるなら」
「勿論です! 今日の取材は対談ってことになってますから、遅れている対談相手の先生がいらっしゃるまでは、全て古い友人との唯のおしゃべりです」
私はテーブルに半身を乗り出さんばかりにして、クランベさんの顔を覗き込んだ。
「あなたのそういう所、お父さん譲りね」
「それは……褒めてますか?」
「勿論、褒め言葉よ」
「うーん、喜んでいいのか、ちょっと複雑です」
落ち着きのまるで無い父の姿が思い浮かび、私は照れ臭くなって笑った。
「メモを取っても?」
「ええ。でも、メリアさんや先生方のように、上手くは話せないわよ」
こうして雑誌記者の私は暫し職務を放棄した。
穴が開くほど繰り返し読んだあの小説たちの生みの親、お会いしたくても叶わない“あの方”の新たなエピソードを、我が家宝に書き加える機会を得たのだ。
二 私と「意地悪な人」の稀有な顛末
「白き翼の天使よ、我が心は貴女の元へ……」
ベッドに横たわったまま、顔の上で万年筆の側面をなぞる。感覚の研ぎ澄まされた指先が、その文字列を詠んだ。コバルトブルーの胴軸に、銀色の箔押し、今は遠く離れてしまった祖国の言語だ。
「この私に向かって白い翼の天使だなんて。ほんと、意地悪な人」
消毒液の香る薄暗い部屋で、私は独り言を呟いた。
明後日は久しぶりに、古い友人と会う約束をしている。メリアーヌという二十も年下の彼女との繋がりは、この万年筆から始まったと言っても過言ではない。
私は壁掛け時計に視線を移し、時間を確認して起き上がった。椅子の背に掛けていた白衣に、さっと腕を通す。胸ポケットにペン先の無い万年筆を差しながら、足を前へと踏み出した。
ドアノブに手を掛けようとした所で、先にノブが回る。
「ああ、クランベ先生! やはり仮眠室だったんですね」
顔を出した大柄な看護婦長が、安堵の息を吐いた。
「何かありましたか?」
「はい、また急患で」
「容態は?」
「外傷が酷すぎて、副主任クラスでは対応し切れないっておっしゃって。直ぐ出られます?」
「ええ。このまま行きましょう」
胸元の硬い感触を確かめてから、私は院内の仮眠室を後にした。
万年筆の贈り主、私の人生の筋書きを一新した方、はたまた私では手の届かない意地悪な初恋の人。
あの人との関係を言葉で適切に表現する術を、私は知らない。
先生、ダルト・スリオルト、出会った当時はナナと呼ばれていた彼に、私は一目惚れをした。否、心酔したという方が、或いは適切かもしれない。
彼、“メメント・モリのナナ”は、私達ノモモギ出身者の仇であり、ノモモギ生存者の英雄だった。
辺りに響く大人達の怒声、立ち込める鼻をつんと刺すような黒煙の臭い、風に煽られ舞い上がる炎の粉を、今でも鮮明に思い出す事が出来る。戦渦に取り残された十三歳の少女は、地獄の果てで、涼しげな目をした救世主を見た。
あの時、あの場に居たのが他の人間であっても、彼は迷わず助けたのだと思う。だから彼にとって、私は特別な誰かでは無かった。それでも、私にとっては唯一の希望で、憧れのヒーローで、同時に魂を絡め取る悪魔だった。
戦後の混乱の中、姿を消したナナを私は必死に捜し出し、あなたの手足にして欲しいと頼み込んだ。
彼は当初、私に“ダルト・スリオルト”と名乗り、ナナと同一人物である事を認めようとはしなかった。それでも一向に引き下がらずまとわりつく十三歳の戦争孤児を、彼はどんな思いで眺めていたのだろう。
私が彼の名にちなんで、“ダルタエ”という新たなファーストネームを使い始めた時、彼は苦笑しながら“クランベ”という姓をくれた。当初の私は無邪気に喜んだ。彼が私を認めてくれた、傍に居る事を許してくれた、そんな気がしたからだ。
しかし程無くして、彼は一度もダルタエという名を口にしてはいない、という事実に気が付いた。彼は大抵私に“君”と呼び掛け、時折思い出したかのようにクランべと姓で呼んだ。それらが意味する距離感を、私は何となく察した。
その時期からだったか、私は彼を“先生”と呼ぶようになった。物書きを生業にすると告げた彼に対して、丁度都合が良かった。
私は必死で先生の隣に居続けるための、自身の存在価値を模索した。そうして志したのが医学の道だ。
人命救助に尽力したいと願う戦争経験者達に混じって、ただ先生に必要とされるため、その隣に立って遜色無い地位を手に入れるために私は奮闘した。その先にあるのが、今の私である。
果たしてダルタエ・クランベは、彼の理想の手足と成れたのだろうか。その問いの答えは未だ与えられていない。
胸騒ぎがした。
あの事件、小説家ダルト・スリオルトが死んだ日の、前日の事だ。
私は奇妙な事件の一端を、先生の相棒として担う最後の幸運を得た。
当時、アデックケナー病院という国立大病院の研修医となっていた私はあの日非番で、日用品の買い出しのために街へ出ていた。
紙袋を二つ、両腕で抱えるように持ち、路肩に停めていた車へ近付いた時、後方から声が聞こえた。
「やあ、クランベ」
振り返ると、少し先にスリオルト先生がいて、此方を手招きしていた。私はこれ見よがしに溜息を吐いてから、其方へ歩いて行った。
「買い物?」
「これが先生には一体何に見えるのですか?」
「たまの休日を有効利用した、まとめ買いの産物、かな」
「ええ、その通りです」
「持とうか?」
「いえ、直ぐ其処に車を停めてありますから。先生に呼び止められなければ、もう重い荷物を降ろして、席に着いて一息吐いていた所です」
「それはごめん。タイミングが悪かったね。特別話す事は無いんだけど」
「そうでしょうね。では」
立ち去る素振りを見せたにも関わらず、先生は全く調子を変えなかった。
「これからそこの喫茶店で、担当編集さんと打ち合わせなんだ」
「そうですか」
「会わせたことあったっけ? ミデルフォーネさん」
「ありませんよ」
「凄く面白い人でね」
「そうですか」
「近い内に紹介する事になるけど……道の向こう側」
先生が其方へふと顔を向けたのに釣られて、道路の反対側に目を遣った。
「黄色の」
路肩に数台駐車されている中に、小ぶりで鮮やかな黄色をした車があった。
「あの車、そのミデルフォーネさんのなんだ」
「つまりは既に待たせている、という事ですね。早く行ったら如何ですか」
「うん、そうするよ。ところでさ」
「はい?」
「あの車、緑色の方がいいと思うんだけど、どうかな?」
「それは」
「呼び止めて悪かったね。じゃ、また後で」
先生は何時も唐突に現われては、猫のように気紛れにふらりと去って行く。
私は店へ入って行く先生の後ろ姿を紙袋の間から見送ってから、車に戻った。
荷物を抱え続けていた両腕がすっかり痺れてしまっていた。だるさが抜けるまで暫く、運転席から黄色の小型乗用車を眺めた。丸みを帯びたそのフォルムに何処となく愛嬌を感じ、それがそのまま、車の所有者である担当編集ミデルフォーネ氏のイメージとなった。
下宿先に着いてからだったと記憶している。妙な胸騒ぎがした。
先生が別れ際に言った「また後で」の一言が無性に気になった。あの先生の事だ、意味のない言葉の選択はしない。“後日”と言わず“後で”と言ったのは恐らく、今日の事を指しているからだ。そして、私と先生が明確な場所の指定も無しに会えるような所は、片手で数えられる程しかない。
ふと私は最近院内で持て囃されている噂話を思い出し、呆れながらハンガーへ手を伸ばした。出勤日と同じように白衣と鞄の支度をした。先生はあの病院で会う心算なのだと思い至ったからだ。
私の研修中の病院には、先生のご友人が長い事入院されている。勿論、それが理由で其処を研修先にと願い出た。
その方の病室があるという東病棟を、何故か先生は面会可能時間外に、受付を通さずに訪れる。今まで院内関係者に見つかっていないのが不思議なくらいだった。ここ数カ月は訪問頻度が増したせいか、患者からの目撃情報が相次いでいた。
戦争の後遺症から精神を病んでいる患者が多いアデックケナー病院において、掴み所無くふらりと廊下に現われる人影は、戦禍に犠牲となった特別な誰かに見えるのかもしれない。既に亡くなった人物の名を口にしながら、医師に縋り付く患者の姿をもう何度も見ている。
病院の消灯時間を過ぎたのを確認してから、私は白衣を片手にゆっくり部屋を出た。
念のためと言うべきか癖と言うべきか、病院とは逆方向へ車を走らせ、遠回りをして目的の場所に向かう。
随分昔に、先生に教わった事だった。
「何かもし、如何しても辿り着きたい場所がある時」
手に持った麦の穂をくるりと回しながら、青空を見上げたまま彼は言った。
「君ならどうする?」
「私なら……必死に努力します。自身の持てる力全てを使って、其処へ辿り着く最短ルートを探して」
「うん、全く、君らしい」
「先生なら、如何されますか?」
「僕か。僕なら兎に角、真っ直ぐには進まない。まず、真逆の方向へ走り出すかな」
「真逆?」
「そう。思いっきり遠回りをしてから向かうってこと」
「何故です? 敵を撒くため、ですか?」
「その方が楽しみを後に取っておけるから。それに時間の隙間が生まれる」
「時間の隙間。それは……何かの例え話ですか?」
「どうかな?」
「私には……よく分かりません」
「クランベは真っ直ぐな性格だからね。長所だよ。僕はほら、こんなだから」
「全くあの人は」
闇の中、私はハンドルを切りながら、頬が緩むのを感じた。
三 私と「彼」の粋狂な顛末 甲
アデックケナー病院の大きな建造物が視界に入る。
病院の正面にはレンガ造りの塀があり、内側は広々とした石畳になっているが、裏手は生い茂る大木が生垣代わりに敷地を囲んでいた。先生の訪れるであろう東側の病棟は、その鬱蒼とした森を直ぐ背にして建っている。
私は運転のスピードを緩めながら、次の自身の行動の仕方について考えた。
ふいに同期の研修医だった男との思い出したくもない遣り取りが甦り、悪寒が走る。
「特別病棟はね、表側に出したくない落伍者を押し込んでいるのですよ。いひひっ、気違いの収容所という訳です。それで東の森を開拓せずに、まるで埋め込むように建ててある。あそこの最上階を使っている奴は、実は一人しかいないと知っていましたか? 否、一人等と言っては語弊がある。化け物一匹です」
勿体ぶった様に男はそう言った。
「随分と博識でいらっしゃるようですね。その胡乱な情報は何処からのものですか」
「いひひっ、僕はアデックケナーの遠縁にあたる血筋なのです」
「成程、どうやら私と貴方とでは、会話の水準が雲泥万里のようですね」
「いひひひっ、クランベはあの病棟にご執心だと聞いてね。どうです? 今夜ワインでも飲みながら、僕の“ウロン”な知識をお分けするというのは?」
下卑た笑い方とはああいうものを言うのだと、感心したのを覚えている。
後日あの男が研修を追われたのは、私の崇高なる姓を軽々しく呼び捨てにしたからではなく、単に極度の阿呆であったからだろう。仮にも医師を志す者が、胡乱な知識等よく口にしたものだ。
時刻は何時の間にか二十三時を過ぎていた。
とりあえず病院の敷地を迂回してさらに東へ回り、未舗装の道端に駐車する。先生は東病棟方面の森を抜け出て来ると予想し、車内でじっとその時を待った。
夜勤の看護婦の見回り時間は深夜零時前後、見回りの目を避けるなら、その前には病棟から出ると考えたのだ。
しかし、先生は現われなかった。
「意識の、し過ぎかしら……」
ハンドルに凭れて呟いた。
傍に居たいという思いが強過ぎて、「また後で」との他愛ない一言を誇大解釈しているのかもしれない。十三の頃から全く進歩の無い自身に心底脱帽する。
「それとも……」
それでも、考えることを辞める訳には行かなかった。
先生は何れ私の手の届かぬ所へ行ってしまう、出会った時から絶えずその空気を感じていた。その最後の瞬間は今かもしれないと何時も不安に駆られ、ならばせめてその場に立ち会いたいと願い続けた。
「願いは叶える前に、願うという行為其の物が必要になる」
彼から繰り返し聞いた“ナナ”の思想が口を突いて出た。
「そして、願うためには、あらゆる可能性に敏感である事……」
会合場所を私が間違えたのか、若しくはまだ、先生は病棟内に残って居るのか。私は後者の可能性に賭けることにした。
病院の関係者用の駐車場を素通りし、敷地内西端の緊急外来スペースの木陰に駐車した。流石に私まで院内に無断侵入する訳にはいかない。小走りに中央棟入口横の守衛室へ向かい、そのガラス窓を控えめにノックした。
「夜分にすみません」
息を切らした白衣姿の私をガラス越しに見て、守衛の男性が眉を下げる。
「何だあ?」
気怠げな声を上げて緑の制帽を被った中年男性が、守衛室の扉を大きく開けた。
「ああ、あんた、研修で来てる子だなあ、見たことがある。こんな時間にどうした?」
「あの、遅くに突然申し訳ありません。此方に、遺失物で徽章は届いていないでしょうか?」
「キショウ?」
「此処に着ける小さなバッジです」
私は白衣の左襟を少し指で摘みながら目を伏せた。
「ああ、お医者先生が着けてるあれかあ。いや、見てねぇな」
「そうですか……」
「失くしたのかい?」
「はい……研修中の大事な預かりものですので、何時も帰宅時に外す事にしていて。しっかりハンカチに包んだつもりだったのですが……気付いたら見当たらなくて」
「そうかあ、そりゃ参っちまうよなあ。いや、力になれなくてすまねぇなあ。明日、明るくなってから探したらどうだい? 何なら守衛の奴らから暇なの、手伝いに行かせて遣るからよ」
「いえ、実は……」
「何だ、どうした?」
「明日の研修医担当がマルク先生だとお聞きして、その……」
「ああー、なるほどなあ」
男性は歯を見せて笑いながら、困ったという顔をした。
外科主任補佐のマルク医師は、そのヒステリックで非常識な怒声で院内でも有名人だった。もし本当にアデックケナー病院の誇りの象徴たる徽章を失くした等とあの医師に言おうものなら、冗談ではなく鼓膜が片方破られかねない。
「あの先生の前に徽章無しで立つ姿を想像して、居ても経っても居られなくなってしまって」
私は自身の片方の耳たぶをゆっくりと指で撫でた。
「でも、すみません、そんな理由でこんな時間に押し掛けてしまって。失礼しました」
「いやいや、あんた!」
項垂れて引き返そうとする私を守衛の男性は呼び止めた。
「そんな事なら、今ちょいと探して来な」
「いえ、そんな」
「平気さ。あんたの事は何度も見掛けてるし。ここの研修さんなら、夜の見回りだって言やあ、お医者先生だって誤魔化せるだろ。特別に出入りの記録には、名前書かないで置いてやるから」
「そんな事をしたら、何かあった時に……」
咄嗟に男性の胸元の名札を確認する。
「パウティスさんにご迷惑が掛かります」
「いや何、俺は良く居眠りしてるからな。さっきも急に眠気が襲ってきてなあ、あんたがノックしなきゃ、今頃夢の中で、あんたみたいな綺麗なねぇちゃんとランデブーさ」
守衛の男性はげらげらと大声で笑った。私は少し戸惑った様に頷いた後、しおらしく告げる。
「それでは、お言葉に甘えて」
「健闘を祈ってるぜ!」
パウティスは節くれ立った親指を力強く立てた。
白衣の左ポケットへ忍ばせた指先で、徽章の冷たく尖った感触を弄びながら、私はその場を立ち去った。
「先生の、声……」
二度目の予想は辛うじて的中した。聞き間違う事など有る筈も無い、スリオルト先生の声が件の病室から微かに漏れていた。
ドアをうっすらと開け、中の様子をそっと窺う。先生は此方に背を向けて、楽しげにベッドの上の患者に話し掛けていた。
「でしょ? やっぱりあの味は最高だったよね」
先生のご友人に、面と向かってお会いした事はまだ無かった。恐らく先生と年齢の近い人物で、“メメント・モリ”と呼ばれた彼らの内の一人なのだろう。
「あれから何度も探してみたんだけどね」
水入らずの逢瀬の邪魔をするつもりは無かった。
先生はご友人について多くを語らなかった。この部屋へ入らないよう忠告された事は無い。しかし一度も「一緒に会いに行こう」とは言ってくれなかった。先生にとってその方は、共に生き抜いた掛け替えの無い誰かなのだ。代わりの利く私では、二人の間に入って行けない。
「そう言えば、僕らの作ったあの歌もね」
時折先生は幼い笑い声を上げた。
うっすらと鉄の味がした。私は知らず下唇を噛んでいた。彼か彼女かも分からぬ全く意識の無い相手に、私は嫉妬している様だった。
幸い、次の看護婦の見回りまで大分時間があった。私はそっと東病棟の四階から距離を置いた。
濃い雲の狭間から月明かりが漏れていた。
幾つも延びる階段や渡り廊下をふらふらと歩きながら、先生の事を思い巡らす。これでは私の方が、院内を徘徊する幽霊だった。
「約束……」
頻りに先生は“約束”という語を繰り返していた。盗み聞いた単語だけでは、話の全貌は見えて来なかった。
そう言えばこの病院では来月、生命維持装置の大掛かりな撤去計画が持ち上がっていたはずだ。先生からは何も伝えられていないが、あの部屋で使われているのはその生命維持装置ではないだろうか。
由緒あるアデックケナー病院に十年近く入院し続けるための莫大な資金は、矢張り先生が独りで払い続けてきたのだろうか。小説家を生業にすると告げた頃の先生の様子を思い出す。果たして書き物の原稿料だけで、全てを賄えるものだろうか。私の学費だけでも先生にかなりの負担を強いているはずだ。
「クランベは、お金の心配なんてしなくていいんだよ」
先生は何時も、さも可笑しそうに笑いながらそう言った。
「早く一人前になって、先生にお返ししなければ……」
私は東病棟と中央棟を繋ぐ二階連絡通路の窓を一つ置きに開け放ちながら、自分自身に言い聞かせた。
東側の窓は森に阻まれ、朝日こそ差し込んではいなかったが、外がうっすらと明るくなっているのが分かった。
再度訪れた東病棟の四階の廊下で、私は先生に声を掛けるタイミングを只管計っていた。
「薄情者のナナが、聞いて呆れるよね」
その聞き捨てならない一言に弾かれるように、私は病室の入り口から声を発した。
「先生が薄情者、ですか?」
ゆっくりと先生は振り返った。その顔を見て、高鳴る胸中を悟られぬよう思い切り冷めた視線を送りながら、告げる。
「自己分析もままならないようでは、作家は務まりませんよ」
不可侵だった領土へ、私は足を踏み入れる。
「そうだね。もうそろそろ潮時かもしれない」
先生が少し、嬉しそうに目を細めたように見えた。
四 私と「彼」の粋狂な顛末 乙
「やはり、先生には“薄情”より“意地悪”の方がお似合いです」
精一杯の虚勢が先生に通じない事は分かっていた。
「褒め言葉として受け取っておくよ」
今にも吹き出しそうな笑顔で、撫でるように優しい声を出すなんて、反則だ。私はつい表情を崩した。
病室のドアを後ろ手で閉めてから、その場で数秒、息を整えた。
「先生が、私に……」
鼓動が平常時の何倍も早く感じられる。私は自らの頬を平手で軽く叩いた。冷静さを欠いている場合では無いが、多少浮かれるのは致し方無い。
胸ポケットに差したはずの万年筆は、もしや幻だったのではないかと不安になり、手を遣る。其処には硬く確かな感触があった。私は指先でその輪郭を弄びながら、廊下をゆっくり歩き出した。
「また、ご旅行ですか?」
私が十五の頃だ。
片手で下げられる程のトランクに紙の束を詰めながら鼻歌を歌う先生に、私は声を掛けた。
「うん。旅行というより、冒険って感じだけど。君も一緒にどう?」
「旅費が倍になりますよ」
「お金の心配? それくらい、平気だよ。久しぶりに国外に出てみるのも気分転換になるし、良いものだよ」
「いえ、私は結構です。勉学に遅れが出ますから」
私は先程まで解いていた机上の数式に目を遣った。数カ月後に迫った入学試験まで、さらに自分を高めたい。
「クランべの学力なら、今のままで十分合格出来るよ」
「それは、正規の入学ではないから試験の中身は関係が無い、という事ですか?」
意地の悪い尋ね方だと、自己嫌悪する。
「流石に正解の問題が半分も無い様だったら、賄賂は積めても日々の授業フォローに無理が出そうだね」
「矢張り……」
肩を落とした私の頭に、彼は手を置いた。
「先生?」
「君は寧ろ、物事を単純に見る能力を磨かないとね。僕は賄賂なんて積んで無いよ」
「……本当ですか?」
「勿論。社会貢献に積極的な学校だからね。僕が如何こうせずとも、戦争孤児の入学補助は手厚いらしい。ただ、クランべの夢には少々レベルが合わないのが難点かな」
「私の夢?」
「高い目標を目指すには、少し物足りないかも」
怪訝な顔をする私に向かって、先生は何でもない事のように言った。
「医者になるなら、誰かに家庭教師を頼んだ方が良さそうかな」
思わず私は息を飲んだ。
「え、先生、どうしてそれを……」
「入学は心配無いけれど、あの学校の授業だけじゃ、その上に進む時に苦労するかもしれない。なんて、まだまだ先の話だけどね」
先生は再度トランクに向き直り、蓋を閉め鍵を掛けた。
「はぐらかさないで下さい、先生。如何して私が医者になりたいと知っているのですか?」
「うーん、野生の勘かな」
「先生!」
私は顔を真っ赤にした。取り合ってくれない先生への怒りと、内緒にしていたはずの大それた夢を知られていた恥ずかしさからだ。
先生は肩を奮わせて笑っていた。
「とりあえず、僕は明後日出発するけれど、気が変わったら何時でも言ってね。四日程で帰る予定」
「いえ、私は……でも、そうですね、一つお願いを聞いて貰えますか?」
もうこの際だと、思ったままを素直に口にした。
「お願い?」
「はい。安物で構いませんので、何か……お土産が欲しいです」
「お土産かぁ、何がいいかな。確か名産のフルーツがあったけど、長持ちしないからなぁ。あ、駅前通りに伝統焼き菓子の専門店があったか。食べた事は無いけれど、あれ美味しいのかな」
「食べ物以外というのは」
言い掛けた私の言葉を、先生はやんわりと遮った。
「そうだね、あの辺り木製彫刻も有名だけど、趣味の悪いデザインばかりだし。ベッドサイドに置いたら毎晩悪夢を見ることになるかも」
「……矢張り、形に残る物は駄目なのですね」
先生は思考を巡らすようにぐるりと目を回した後、笑顔で言った。
「まだ時間はあるし、ゆっくり考えよう」
あの時、結局土産として貰ったのは、名産フルーツで拵えた瓶詰ジャムだった。私が学校の寄宿舎に入るまでの数カ月、それは私達の食卓に毎朝現れた。
ジャムの味はとうの昔に忘れてしまったが、瓶に巻かれていた鮮やかなコバルトブルーのリボンは、随分長いこと手元にあった。寄宿舎を出る引っ越しの際に失くしてしまい、先生に泣いて訴えたのを覚えている。
無性に込み上げて来る恥ずかしさを振り払うように、私は少し足を速めた。
突き当たりの階段に差し掛かった時、遠くの闇からガシャンという大きな音が響いた。
「規定時間より、少し早い……」
噛み合わせの悪い窓を強引に閉める音だった。明方の見回り時間には少し早かったが、見回りの看護婦以外にわざわざ窓を閉めて回る者はいない筈だ。
私が開けておいたのは、中央棟と東病棟を結ぶ二階通路の窓だった。あの通路の窓は枠がほんの少し傾いており、慎重に水平を保ちながら閉めないと、左右の窓がぶつかり大袈裟な音を立てる。
私は一つ下の階へ移動し、手近な窓を静かに開けながら三階病室前を端から端まで進んだ。その間にも、ガシャン、ガシャシャンとガラスが擦れるような高音が鳴り響いている。
さらに東病棟二階の窓も一通り開け、脇の階段に差し掛かった時、通路に響く足音と共に女性の唸り声が聞こえた。
「だからこの病棟は、嫌いなのよ!」
私は直ぐに手近な病室に滑り込む。
ドアをうっすらと開け隙間から覗くと、目の前の開いた窓から身を乗り出している人影が見えた。足元に置かれたランプのオレンジ色の光の中で、年若い看護婦が繰り返し悪態を吐いている。
この東病棟の東側の窓は下の階ほど廊下が薄暗く、例に漏れず建て付けも悪い。
見回りの看護婦は思うように閉まらない窓に気を取られていて、真後ろの病室から覗き見る私には気付いていない様だった。
東病棟三階の端の入院患者が疑われるだろう、と他人事のように思った。彼は元軍人で、戦時中に負った心の傷から、この病棟の古株となっていた。以前にも「少年兵が暴動を起こした!」等と騒ぎ立て、夜中に院内の窓という窓を開けて回った前科がある。
看護婦が二階の窓を閉め終わり三階へ上がるのを待って、病室の取っ手を握り直した時だった。
「貴様、此処で何をしている」
背後から聞こえたのは、低い男の声だった。一気に跳ね上がる心音と電気が走ったように痺れた神経が、まともな判断を鈍らせた。
「あ、あの……」
病室内からの声なのだから、恐らくこの部屋の入院患者なのだ。私は今白衣を羽織っているのだから、見回りだの点検だのと言って、さっさと立ち去ってしまえば良いのだ。そう分かっているのに、背中に浴びる鋭い視線と威圧感で、振り返る事が出来なかった。
「さては、あいつらの仲間だな。医者の振りなぞしても、俺の目は誤魔化せんぞ」
「え……」
その時、取っ手に掛けたままの私の手が独りでに下がった。
誰かが向こう側から、この部屋の扉を開けたのだ。
私は呼吸を忘れ、挟まれた、と心の中で呟いた。
五 私と「彼」の珍妙な顛末
「やあ」
「え?」
扉の向こうから現れたのは、あろうことか満面の笑みを浮かべたスリオルト先生だった。
私は呆気に取られ、その場にしゃがみ込んだ。
「先生、どうして、此処に……」
「ごめん、随分と驚かせたみたいだね」
先生は声を上げて笑うと、ゆっくり室内に入り、後ろ手で扉を閉めた。
「何だ貴様は!」
棘のある男の声が背後から続いている。
「見回りの看護婦さん、足止めしてくれて助かったよ。あの人何時も、歩くのが早くてね」
緊迫した空気の中、相変わらずの飄々とした話し方で先生は私に話し掛ける。
「おい」
「でもお陰でゆっくり最後の挨拶が出来た」
「おい女! その奇妙な奴は何だ!」
「本当はもっと早く、あの部屋へ招待しようと思っていたんだけど」
「貴様等、どういう積もりだ。俺を馬鹿にしているのか!」
私は今度こそ振り返った。そこには鬼気迫る形相の男が一人、ライフルを手に身構えていた。
「え……?」
言葉を失う私に対して、先生は咳払いを一つして落ち着いた声を出した。
「どうも、ご挨拶が遅れまして申し訳ありません、ライランド上等。お元気そうで何よりです」
余裕たっぷりの先生の態度に、ライランドと呼ばれた男は苛々と歯軋りした。
「そのご様子では、今日も傭兵の少年達をお探しのようですね」
「気安く俺に話しかけるな! さては貴様もナナの回し者だな」
ライランドの口から“ナナ”の名が出た事で、私は明らかに動揺した。
「ああ、例の彼ですか。それなら、さっき上の階で見かけたと思いますが」
「何だと!? 嘘を吐け! 俺を騙そうったって、その手には乗らんぞ」
「先生、彼は一体……」
「大丈夫、任せて」
先生は私に耳打ちしながら手を差し伸べると、腕を優しく引いて立ち上がらせてくれた。
「ライランド上等のお探しの少年兵は、歳の頃十五、これくらいの身長ではないですか?」
掌で少し小柄な子供の背丈を指し示しながら、先生は首を傾げた。
「……そうだ」
警戒心を剥き出しにしながらも、ライランドは頷いた。
「それならやっぱり。僕は割と夜目が利くんです。さっきまで上の階を彷徨いていました。貴方を狙っているのか、はたまたバルフォン曹長からのあの指令書を狙っているのか」
その名を耳にした途端、ライランドの目の色が変わった。バルフォン、私も何処かで聞き覚えのある名だった。
「……貴様、何故曹長の名を知っている?」
「僕も部隊は違えど戦闘員の一人ですからね。バルフォン曹長の隊にも知り合いは大勢。曹長の恵まれた体躯に冴え渡る采配。数々の勲章に彩られた軍服。まさに軍人の鑑のような方ですね」
ライランドはふんと鼻を鳴らした。
「何だ、分かっているじゃないか。口の効き方には問題があるがな。お前、一体何処の隊だ」
「バルフォン曹長には最近お会いになりましたか?」
「……曹長は前線に赴いて居られる。お戻りになるのはまだ先だろう」
「そうですか……」
先生は首を傾げたまま、顎に指を当て考え込む様な素振りを見せた。
「……何だ」
「いえ、それでしたら私の方がバルフォン曹長にお会いしたのは新しいようですね。今は随分後方に居られますよ。いえ、寧ろ最前線かもしれませんが」
「どういう意味だ」
二人の会話の内容は全く分からなかったが、先生は共通の関係者の話から上手く相手の興味を引いたらしい。ライランドの構えていたライフルの銃口は次第に下を向いた。
「私は一月ほど前にお会いしたのです」
「何だと?」
「直筆の書面も頂きましてね」
「曹長手ずから……見せてみろ」
「何です?」
「曹長自らお書きになった書面とあらば、肌身離さず持ち歩いて居るのだろうな? 見せてみろ」
「困りましたね」
「矢張り嘘か。そんな書面は無いのだろう!」
「いえ、密命というものは、例え味方の隊に所属している方であっても、おいそれと明かせるものでは……」
「密命だと!?」
彼は私と先生を値踏みするように睨んだ。
「先程、別の者があなたの潜伏先にも書面を届けに行ったと報告を受けたのですが、そのご様子ではまだご覧になっておられないのですね」
「俺宛てに? 曹長が密命を?」
明らかにライランドは動揺していた。目を泳がせながら思案している。
「あなたの手元にないとなると、密命の書状は一体今どこに……? 機密事項の漏洩は命に関わる失態。少年兵の目的が隊の混乱なら、格好の標的と成り得ますね」
「そ、それは……」
「こうしている間にも……何なら今すぐに見て来ましょう」
先生はくるりとライランドに背を向け、扉に近付いた。
「いや、動くな! まだ信用はできん」
「なら、僕は此処に残りますから、彼女を行かせましょう。女性の方が、少年達も油断するかもしれません」
急に話を振られ、私は先生の意図を必死に汲み取ろうと目をしばたたかせた。
「いや、白衣の女等、より信用できん。貴様等は此処に居ろ。俺が戻るまで絶対に動くなよ、命令だ」
最後に念を押すように私達を睨みつけた後、ライランドは慌ただしく病室を飛び出して行った。
「先生、良かったのですか、あのまま上の階へ戻らせて」
「大丈夫。彼、あんな権幕だけれど、美人の看護婦さんには結構奥手らしいから」
「でも、ライフルを……」
「あれ、良く出来てるよね。日の下で見たらびっくりするよ」
「偽物だったのですか……それはそうですね、失念していました」
「木彫りなんだ、あれ。悪趣味な作品だよね。あ、そうそう、君に凄い剣幕だったのは、白衣のせいだよ」
一瞬先生が何を言っているか分からなかったが、その冗談に気付き、私は冷静さを取り戻した。
「白衣の白さが反射して、私の美しさが見えなかったという事ですね」
「それもあるかもね。まあ彼、白衣の女性に相当トラウマがあるから」
「過去に何かなさったんですか」
「まあ、その話はいずれ。早く出てあげよう、彼が可哀想だ」
先生が視線で差した病室奥のベッドには、この部屋の真の入院患者が怯えた子猫のような目で震えていた。
私達は中央棟入口へ戻った。
先程は動転していて気が付かなかったが、先生は白衣をはためかせ、鼻の下に立派な髭を蓄えていた。片足を不自然に曲げ、特徴的な歩き方のまま平然と守衛室の前を通って行く。
私は訪問時に声を掛けた手前、挨拶をしてから行こうと歩く速度を落とした。白衣の左ポケットから徽章を出し、ありましたと告げようと立ち止まる。
守衛のパウティスは上を向いて制帽を鼻の上に被り、彼の発言通り眠りこけていた。守衛室の扉は数時間前に開けた時のままなのか、異様に大きく開かれている。
一瞬、冷や水を浴びせられたように心臓が締め付けられた。
「……パウティスさん?」
そっと近付き、彼の制帽を恐る恐る持ち上げる。
その下には幸せそうな寝顔があり、パウティスは軽くいびきをかいていた。
安堵の溜息が漏れる。随分と深いその眠り方は不自然であったが、詮索はしない事にした。
ふと通り過ぎ掛けた時、カウンターの上に倒れた小瓶が目に入った。態とらしく床へ水滴を垂らしているそれを、私は溜息交じりに白衣のポケットへ仕舞った。
白衣を脱ぎ、車に乗り込む。
異変には勿論直ぐに気が付いたが、平然と普段通りの手順で発進の準備をした。
「どちらに行かれますか?」
「うーん、そうだね」
前を見据えたままの私の問い掛けに、隣から眠たげな声が返る。
「珍しいですね。何時もの先生でしたら、この車には乗らずに、反対方向へ行かれるのでは?」
「最近ゆっくり話してなかったなと思って。たまには助手席も悪くない」
「そうですか」
辺りはどんどんと明るさを増す。このまま勤務先の病院の敷地内に居て、先生との繋がりが明るみに出るのは都合が悪い。
私は行き先を聞かずにハンドルを切った。
「まさか、君があの病室に来るとはね。予想外だった」
「その割には驚いておられなかったようですが」
「まあ、予想外だったけれど、納得は行ったからね。僕が昨日、また後で、なんて言ったから、会う可能性の高い場所を攻めたってところかな」
図星過ぎて面白くない私は無表情のまま尋ねた。
「元々の先生のご予定では、どうなさるお心算だったのですか」
「病院を出た後に、君の下宿を訪ねる予定だった」
「こんな朝早くに起きていませんよ」
「君の事だから、微かな物音で目覚めるか、それこそ、また後でに反応して一晩中起きているか」
「どのルートを選んでも、私の睡眠は妨害される運命だったのですね」
「冗談だよ。でも、また後で、は我ながら無かったな。ごめん、あの時君がそっちの一言を気にするとは考えて無くて。ただ、次の日に下宿先のポストへ、さっきの箱を投函する積もりだった」
「さっきの……万年筆の箱」
「お察しの通り、メインは中身より箱でね」
運転しながら、先程の小箱を入れたズボンのポケットへ視線を遣る。先生の意図が贈り物でなかったとしても、手元に形のあるものが残ったという事実に私の心は打ち震えていた。
「あ、まだ開かないでね」
「開きませんよ。このまま市場の野菜をジュースにする訳には行きませんから」
「それもそうか。くれぐれも安全運転で……なんて、君には不要なアドバイスだったね」
私は得意顔で首を縦に振った。
「箱は後でじっくり見てもらうとして……直接会ってゆっくり話せるとは思ってなかったから、どうしようかな」
「何か厄介事を抱えているのですね」
「まあね」
六 私と「彼」の主情な顛末
車の窓の外は、もうすっかり穏やかな朝の風景だった。
眠っていた街が起き出す気配を感じながら、私は自身の動かし方について考えあぐねていた。そんな折は何時だって、先生から次の一手がもたらされると相場は決まっている。
「実はね、僕、今夜殺されると思うんだ」
朗らかな先生の声が、片耳から私の中に入って来て、行き場を失い蜷局を巻いた。突拍子も無い発言は先生の十八番だが、厄介事のレベルを超えていて閉口する。
私はただ静かにハンドルを強く握った。
「バルフォンって人が居てね。先の大戦の軍の関係者で、名の知れた軍人の一人だったんだ。彼、今は大手出版社に勤める民間人なんだけれど」
答えない私に構わず、先生は話し続ける。
「彼は今日、裏事情を全く知らないある人物から、とある話を聞く事になる。過去を掘り返し、日の元に晒そうという計画についてね。そして、このままではこの先自分の立場が危うくなると勘付いて、大慌てで僕を消しに来る」
「そして、予め敵の計画を知り尽くしている先生は、意表を突き、まんまと逃げ果せる、というシナリオで?」
澄まし顔を装った私は、先生のストーリーを淡々と補足した。
「そんなに上手く行くと良いんだけれど」
「……平時の、威勢はどうされたのですか」
「今回は久しぶりに手強そうでね」
動き出す前の住宅街を抜け、小さな川を渡った所で、私は車を停めた。
運転席側の扉を少し開け、外の空気を吸う。
「先程、病院内で話したライランドという男、今回の件に関係しているのですか」
「いや、彼は僕らが生み出した戦争被害者の一人だよ」
先生が助手席側の扉を開けた事で、冷たい空気が私達の顔を勢いよく撫でた。
「心が壊れてしまって、未だに少年の僕らを探しているだけだ」
先生の口から出る“僕ら”という言葉が、心に痛かった。
「バルフォンという名、何処かで聞いたことがあったと思いましたが。先生の良く寄稿されている文芸雑誌の、確か編集長でしたね」
「彼と面識は?」
「ありませんよ。先生から何度かお話を聞いた位です。背が高くて目付きが鋭いと」
「そう言えば、そんな事を言ったかもね」
「先生は随分前からその男と仕事をなさっていましたね。まさか、気付いておられたのでしょう、危険人物だと」
「バルフォン編集長が既知の人、というのは、ね。でも真っ当に業界人の顔をしていたし、まさかまだ過去に囚われているとは思わなかったな」
「過去に、囚われている……」
その言葉は私にも、そして勿論先生にも当て嵌まる。果たしてこの舞台上に、過去に囚われていない人間が居ただろうか。
「それで、立場が危うくなるというのは?」
「四階の病室で僕が言った事、覚えている?」
「……薄情者」
先生は本当に楽しそうに笑い声を上げた。
「そこは君の提案通り、意地悪に訂正しておこう。その後に僕はこうも言った、次の作品の構想を練ってるって。小説家ダルト・スリオルトはあの頃の僕らの日常を、世に出す心算でいる。そうすると困る人間が一定数存在する」
「軍の暴露本という事ですか」
「近からず遠からず、かな」
戦争から十年が経った。
もう十年と言いたいところだが、実際はまだたったの十年だ。国が負った根深い傷は未だ癒えず、情勢の不安定な世の中で言論の自由が建て前でしかない事は、仕方のない現実として多くの者が受け止めている。
先生もそれを承知の上で、戦争を描いた作品を幾つか書いていた。脚色の無い事実を冷静に並べたような小説やフィクションの皮を被った物悲しい真実の断片。案の定、世間の評価はいまいちだった。その作品群の影響か、作家として賞には今一歩届かないままだが、先生は意に介していない様子だ。
「戦争反対を声高に叫んでいるって言われたよ」
「読者にですか」
「もしかすると世間の読者の代弁者だったのかもしれない、彼は。僕の担当編集のミデルフォーネさんにね」
「まあ、その様な見方もあるのでしょう」
「君もそう思う?」
「私は……」
真っ赤に染まり行くノモモギの街中で、瓦礫の山に立ったナナが、私へ伸ばした白い腕をふと思い出した。
「戦争は悪です。もうあんな事を繰り返さないために、反戦を唱えるのは、表に立てる者の義務だと思います。でも……あの時の私達にあったのは、単なる日常です。戦禍と地続きの日常でした」
「うん」
「先生が小説内で描かれるのは、当時の、直中のあの空気に似ています。主義主張は、振り返って初めて沸いて来るものです。戦争に賛成だ反対だ等と、あの頃の私達にはそんな事を考える余裕すら無かった……」
「うん。あの空気は、あの場で息をした人同士でしか、共有は難しいだろうね。この感覚を言葉にして人に分かってもらうのは、本当に至難の業だ」
「それが先生のお仕事でしょう」
「やっぱり、僕は引退だな」
二人の間にふと沈黙が降りて、小鳥の囀りが鮮明に聞こえた。平和な日常の音だ。
「先生」
今なら、そう思った。
「ずっと聞けなかった事があります」
「うん」
正確には、ずっと尋ねる素振りで上手くかわされてきた事が、だ。
「……“メメント・モリ”とは、一体何ですか?」
珍しく先生は私から目を逸らし遠くを見た。
「私はずっと、元傭兵の少年達のチーム名か、自分達を奮い立たせるための合言葉か何かだと思っていました。“メメント・モリ”、その名は一体」
「その問いに答えるには、ちょっと夜が明け過ぎたかな」
私は続ける積りの言葉を飲み込んだ。
はっきりとした返答で区切りを付けたかったような気もするし、曖昧なまま正解を探し続ける方が良い気もした。それでも予想していた通り、“メメント・モリ”には世間の認識とは違う、何かがあるのだという確信が残った。
「ごめん、そろそろ準備しないといけない事があって。そうだな、コルンバルトリー中央病院の裏手に降ろして貰えると助かるんだけれど、いいかな?」
「私の返事は聞かずともご存知でしょう」
二人の扉を閉めるタイミングがぴったり重なり、そんな些細な事を嬉しく感じた。
エンジンをかけ、車を発進させる。少し窓を開け、空気を切る音を聞いた。
そう言えば、こうして隣に並んで長く話すのは何時ぶりだろう。
私は、すっかり肩の力が抜けたのを感じた。
「先生、この後のご予定は?」
「そうだね……心残りが少ない様に、遣りたい事をするって感じかな」
「好き勝手に生きて来られた先生に、まだ心残りがあるのですか」
「山のように、ね。僕はほら、欲張りだから」
人間の三大欲求を全く意に介しない先生の台詞とは思えない。私は目を剥いて黙っていた。
「一番はそうだな、まだ君に診察してもらっていないって事かな」
「残念ですが、精神科に進む予定はありませんよ」
「頭脳明晰、冷静沈着、それでいて意外と泥臭い行動派」
「それは褒めているのですか」
「褒めてるよ。君はペンよりもメスが似合う気がする。外科なんてどうかな」
「似合わないと分かっていて、私に万年筆を贈ったのですか」
「出世に万年筆は必需品だよ。アデックケナーの偉い人になって、病院の腐敗を内部から食い止めて貰いたいなあ。いやそれより、コルンバルトリーの外科部長の椅子の方がぴったりかもしれない」
「一介の研修医に向かって、何をとぼけた事を」
「きっと大丈夫だよ、君なら」
「でしたら、その時まで責任を持って見届けて頂かないと」
さっと視線を横へ遣ると、先生は肩を竦めながら優しく微笑んだ。しかし、私の発言についての返答は無かった。
「そう言えば、私の今日の予定は、あの箱を開ければ解るのでしたね」
「うーん、それなんだけれど……」
先生は低く唸った後、そのままゼンマイが切れた人形のように黙り込んだ。
コルンバルトリー中央病院まで数分で到着するという頃になって、唐突に先生は口を開いた。
「やっぱり自由だ」
「え?」
咄嗟の事で、気の抜けた返事をしてしまう。
「君を解放するよ、フェリス」
エンジン音と風の音とが煩わしい。それらに交じり合いながらも、強烈な台詞は私の耳に届いた。言葉が出なかった。
「僕は君に、命の恩人という枷を嵌めて利用して来た」
落ち着いた冷たい声だった。
「箱の中のそれはね、協力の域を超えている。夢を棒に振るかもしれないし、命を危険に晒す可能性もある。そうまでして、この計画に君が乗り続ける必要はない」
「……先生のおっしゃる意味が分かりません」
「ねぇ、フェリス」
「その名は……」
心の内で先生を罵った。先生は私の気持ちを見通している。その上で、戦禍に消えた街で全てを失った、十三の少女の名を口にするなんて、矢張りこの人は意地が悪い。
「その名は、ノモモギの中央記念公園、あの戦没者慰霊碑に刻まれた時に捨てて来ました。今此処に居るのはダルタエ・クランベ、先生の優秀な助手です」
悲痛な表情を浮かべた先生は、こちらをじっと見つめていた。その瞳は、今にも零れ出しそうな涙で潤んでいる。
私は眉根を寄せた。
「三文芝居もいい加減にして下さい」
息を細く吐き出しながら、ハンドルを人差し指でとんとんと叩く。
「人心掌握術の実験ですか。そうやって突き離して、余計に離れ難くさせようと」
「もし、そうだと言ったら?」
「意地悪な人」
ついに堪えられなくなったのか、先生は表情を崩した。
「言うと思った」
深く溜息を吐きながら、私は額に片手を当て首を大げさに左右に振った。
「そんな事をなさらなくても、私が先生にぞっこんなのは百も承知でしょう」
子供の様な無邪気さで先生が頷く。
「クランべは本当に、素直なんだかそうじゃないんだか」
謀ったかのように大きな木が視界に入った。
コルンバルトリー中央病院の裏手に植えられている、戦争を生き延びた老木だ。
「着きましたよ」
「うん、ありがとう」
先生は車を降り、そのままドアを閉め掛けて手を止めると、顔だけを車内へ向けた。
「からかってごめん。でもクランベ、君ならこの場面で、僕を見捨てないって信じていたよ」
「先生にはもう少し演技力を磨いて頂かないと。騙され甲斐がありませんから」
「クランべがどう騙されてくれるのか楽しみだな」
一瞬片目を瞑って合図を送った先生の顔を、その後何年も、私は夜の夢に見ることになる。
七 「あの方」から繋がってきた様々なこと
「ごめんなさい。私、やっぱり話すのは下手ね。話が右往左往してしまって、解り辛いでしょう?」
そう言ってクランベさんは、コーヒーカップを唇に当てた。
「そんなことないです。私、色んな意味でどきどきしっぱなしです」
ずっと息を詰めて聞いていた私は、胸に手を当て、深呼吸をして気持ちを落ち着ける。
「何だか凄く新鮮です。クランベさんが取り乱す所も、スリオルト先生が悪戯っぽい事言う所も。全然、想像出来ませんね」
彼女はカップを静かにソーサーへ乗せると、口元に人差し指を当てて上品に笑った。
クランベさんと私の交友は長い。
例のあの日に出会ってからの二週間は勿論の事、幼い頃はよく遊んで貰っていた。大きくなって、大学の寄宿舎へ入ってからは直接お会い出来なくなったが、手紙の遣り取りは続けていた。
彼女は二十歳近く年の離れた私を子ども扱いせず、ずっと友人として接してくれた。それでも私から見れば、彼女はいつも気品溢れる大人の女性だった。取り乱したり大声を出したりする所など、一度も見た事は無い。
ましてやスリオルト先生とは一度もお会いしたことは無いし、敬愛する作品世界から透けて見える作家像が、私の抱く“あの方”のイメージの大半を占めている。
カラン。
喫茶店の扉の隅で鐘が鳴り、私は我に返った。
「あ、すみません。ちょっと呆けちゃいました」
「お店、貸し切りみたいね」
何時の間にか、隣のテーブルについていた二人組の男性客は居なくなっていた。
「少し話は休憩しましょうか」
彼女の視線は目の前のテーブルへ注がれていて、漸く私はある事を思い出した。
「あ……」
齧りかけのサンドウィッチの表面は、すっかり乾燥してしまっている。
「ありがとうございます……」
食べ残す、という習慣は我が家には無かった。それは矢張り、戦時中疎開先の国で食糧難を味わった、父の教訓から来たものだと思う。
私はサンドウィッチに齧り付きながら、店の奥の柱時計を確認した。十三時四十分を回っている。
待ち合わせ相手のもう一人が未だ現れない。私は少々むっとしながら、お皿の上を素早く空にした。
「お待たせしました」
クランベさんはお代わりのコーヒーを飲みながら、穏やかに頷いた。
「それで……その後、クランベさんはどうされたんですか?」
鉛筆を握り直し、私は身を乗り出す。彼女がスリオルト先生から手渡された小箱に、気になる点があるという事は何となく察していた。
「やっぱり箱にからくりが?」
「ええ、一見ただの紙箱だったのだけれど、一枚の紙を何度か折り重ねて、それを上手く組んで作られたものだったの」
「じゃあそれを開いたら……」
「ええ、中に先生からのメッセージが」
「洒落た手紙ですね」
「手紙……というより、暗号ね。他の人に見られる可能性を考えて、念には念をと思ったのか、唯単に私を困らせたかったのか」
「解読出来たんですか?」
「暗号と言っても、簡単なものよ。祖国の言葉でね、二つ文字飛ばしで読んで行くと、意味の通る文章になるの」
「良く気が付きましたね」
そう言えば話の中で、スリオルト先生から贈られた万年筆に、生まれ故郷の言葉でメッセージが彫り込まれて居たと聞いた。もしかするとそれは、あの方からクランベさんへのヒントの一つだったのかもしれない。
「私だったら、読めずに焦って、スリオルト先生の事直接尾行しちゃうかも」
彼女は目を細めて微笑んだ。
「私も焦ったのよ、最初に気付いたのは、別のメッセージだったから」
「え?」
「一枚の紙を折り込んでいる事に気付いて、紙を広げてね。最初に、私の名前を見つけたの」
「名前……」
「そう。こう、ぱっと犇き合う文字を見た瞬間、目が私の名前の綴りを拾って」
合わせた両の手をさっと開く身振りの後、彼女は左手の平に“クランべ”と書いた。
「あ、それが二つ文字飛ばしだったんですね」
「ええそう。それで、そのまま読んで行ったら、酷いのよ。私へのお説教」
「お説教?」
「もっと普段から笑った方が良いとか、休日は暖色系の女の子らしい服装をしたらどうかとか」
こんな言い方をしたら失礼かもしれない。けれど本当に、ほんのり頬を染めて唇を尖らせているクランベさんは、うんと年下の私から見ても可愛らしかった。
「チーズは栄養価が高いから、好き嫌いせずに食べようね、なんて」
「スリオルト先生、父親みたい」
「戦争で両親を失って、身寄りも無かったし、まあ、先生が親代わりではあったけれど。でも五つ位しか違わないのよ、私達。余りの子供扱いに、納得が行かなかったわ」
「スリオルト先生とクランベさん、五歳違いなんですか?」
「恐らく、ね」
「恐らく、と言うと?」
「私達に限らず、戦争で出生の記録を失くした者は多いから」
「焼けてしまったからですか」
クランベさんは肩を竦めた。
「軍が持ち出したケースも多かったみたい。先生の場合のような目的でね」
「やっぱり、そういう子供達、沢山居たんですね」
「そのようね。その持ち出し文書も、最後は人為的に燃やしてしまったでしょうから、結局焼けてしまった事に変わりないけれど」
皮肉めいた発言とは裏腹に、彼女の表情は昔を懐かしむ様に穏やかだった。焼失した過去について、何か思う所があるのかもしれない。
「それに場所によって、年齢の数え方や出生に関連した状況が様々でね。異国間の年齢の統一って、当初は大変だったのよ」
「零の概念が無い国の話は聞いた事があります。生まれた瞬間を一歳って数えるって」
私の発言に、クランベさんは頷いて肯定してくれた。
「他にもね、そもそも一年と考える日数が特有の民族もあったし、生誕に多額の税を課す国も問題だった」
「日数が異なる民族については、学生時代に文献で読みました。でも、生まれる事に税金が掛かる国は初耳です。親御さんとしては大変でしょうけれど、何が年齢統一の障害になったんですか?」
「戦前の話だけれどね。届け出をしない家が多かったらしいの」
「納税回避のために、ですか。それって、見つかったら大変ですよね」
「そうね。でも、子供にとっては、見つけて貰えない事の方が悪夢だった」
「悪夢?」
「出生記録が無いために、公的には存在しない事になる。当然、学校には通えないから読み書きは出来ないし、病院にも行けないから医療は受けられない」
「そんな……」
「その内、戦争が始まって、より生活が苦しくなった。真っ先にその影響を受けたのが、そういう子供達だったの。実の親からも居ない者として扱われるようになって、傭兵に流れた子が多かった」
言葉が出なかった。
「戦後の調査で、その地域の出身とされる人が一気に三倍になったそうよ」
「三倍、そんなに……」
「身元不明の大戦犠牲者に含まれる人達も合わせれば、統計以上になるでしょうね」
学校にも行けず、家族からも見放され、そして人知れず死んでいった子供達。想像するだけで、胸が張り裂けそうだ。
「私、雑誌記者になって、少しは見聞を広めた気になっていたんですけど……まだまだ知らない事、いっぱいあって恥ずかしいです」
唖然としながら、私は鉛筆の先を紙の上に向けて、とんと滑らせた。視界に一つの黒い点が現れる。でも、それはそう見えるだけで、本来一つのものではない。砕かれ散らばった無数の黒鉛の粉の集まりだ。
何だってそう、きちんと意志を持って注視しなければ、物事の本質に辿り着くのは難しい。
「まだまだ、学ぶべき事が沢山あるわね」
クランベさんの言葉はどこまでも優しく、私の心に染みた。彼女は矢張り尊敬する愛すべき友人だ。
「夢があるんです、私」
大それた夢だと分かっていても、彼女ならきっと理解してくれると思えるから、臆さず言葉に出来る。
「大戦を経て、色々な国で価値観や制度が変わったと知りました。以前の出来事はまだまだ不透明で、私が辿り着いていない事実も沢山あります。でも、不透明にしておきたい、隠したいって思いが働いているっていう事は、少なくとも、その時行った事は間違いだったと認めている証拠でもあると思うんです」
「そうね」
この数年で大分、“過去”が“歴史”に変わりつつある。過去を穿り返されたくないという人も、案外歴史としてなら向き合ってくれるかもしれない。私はそうしてでも良い、皆に真実と正面からぶつかって欲しかった。
「まだまだ、私なんかが出来る事、少ないですけれど。今回のスリオルト先生の物語が世に出る事で、不透明な部分にさらに光が当たればって、私、そう思っています。それが先生達から託された使命だって」
「ええ」
ウェイトレスがテーブルの横を通り過ぎて行った。つい、ふわりと揺れる腰の白いリボンに目が行き、ダルト・スリオルト著『廃屋に風船を浮かべて』の一説が脳裏に浮かぶ。
「ところで、ちょっと話は戻るんですけれど、出生の記録が無い方達って、戦後どうされたんですか、公的な身分証明とか」
「親戚、知人が生きていた場合はその人達の証言も有効だったけれど、それ以外はほぼ自己申告ね」
「自己申告、ですか」
「物凄く幼い内に戦争に巻き込まれた訳でなければ、出身地や両親の名、自分の名前等は言えるから。勿論、正直に話せばの話だけれど」
「これは聞いてもいいのか迷ったんですけれど、クランベさんとスリオルト先生って……」
「メリアさんの想像通り、二人とも全部作り物の申告よ。私の以前の名はフェリスミカ。たった十三年しか使っていない名前だから、もう本名って気はしないわね」
「スリオルト先生の本名は、お聞きになったんですか?」
クランベさんは首を横に振った。
「何度も尋ねたのだけれど、終ぞ教えて下さらなかったの。元々自分の過去については、話したがらない人だから」
「ミステリアスな感じ、スリオルト先生っぽいですね」
「そうね」
カラン。
本日数度目の鐘の音が聞こえた。
「あ!」
その響きを纏うように、肩で大きく息をした初老の男性が店内に現れる。彼は胸ポケットからハンカチを取り出すと、汗を拭きながら店内を見回した。
「やっと、作家先生のご到着ですね。全くもう、クランベさんをこんなにお待たせするなんて」
私は背中を丸めてクランベさんに顔を寄せ、小声で言った。立ち上がって手を振る気になれず、そのまま口を尖らせて頬杖を突いた。
「私はメリアさんと沢山話せて楽しかったわ」
彼女は店の出入り口を振り返らず、私と同じ格好をすると、にっこり微笑んだ。
「私も物凄く楽しかったです。それならまあ、仕方ないですね。今回はお説教、少なめにしてあげないと」
対談取材のメイン作家は、そっぽを向いている私達に気付き、帽子を外しながら苦笑いで近付いて来た。
「いやあ、すみません! 久しぶりにこっちへ来たもので。こんなに道が混んでいるとは」
八 いやあ、「先生」大変な事になりました
「遅いです!」
メリアーヌがこちらに向かって口を尖らせていた。私はこめかみをぽりぽりと掻きながら、とりあえず彼女から目をそらす。体の向きをくるりと変えて、メリアーヌの隣で微笑むクランべさんへ頭を下げた。
「いやいや、お待たせしてしまって申し訳ありません、クランベさん」
「いいえ。私はメリアさんと、久しぶりにゆっくり過ごせましたから。寧ろ充実した時間を頂いて、感謝しているくらいです」
どこまでも穏やかで気品溢れるクランベさんの澄んだ声に、ほっと息が漏れた。むくれたメリアーヌは、コツコツと鉛筆でテーブルを突いて音を立てる。
「スリオルト先生との待ち合わせには遅れたためしが無いって自慢してたのは、何処の誰でしょうね? クランべさんの美貌に目がくらんじゃって、なかなか喫茶店の扉をくぐれなかったって事かしら」
私は苦笑いするより無かった。昔の私は時間厳守の申し子だった。そんな自慢話を娘に聞かせたような気がする。実際は心配性から来る困った性質によるもので、自慢するようなものではなかったのだが。でもそう言えば一度……
「いや、遅刻と言えば実の所だな。正確には一度、それもそう、大事なあの日の待ち合わせだけは遅刻してしまって」
「今はそういう話をしているんじゃありません!」
メリアーヌのあまりの剣幕に、私は辺りをきょろきょろと見回した。幸い他に客の姿はなく、ウェイトレスが来る気配もない。それにしても説教をする時の口調が、最近どんどんメリアーヌの祖母、つまり私の母に似て来ている。これを言うとメリアーヌはさらに怒るから、無論言葉にはしない。
「いいじゃない、メリアさん」
口元にそっと人差し指を当て笑いを堪えた様子で、クランべさんがメリアーヌを宥めて下さった。
「丁度良い機会だし、あの日の話、このままお父様に聞いてみるのはどうかしら?」
クランベさんの落ち着いた提案に、メリアーヌはぴたりと静かになった。
「ミデルフォーネさん、どうぞお掛けになって下さい。実は先程まで、メリアさんとあの日の話をしていたんです」
「あの日……と言いますと?」
凡そ予想は付いている。我々の共通点、ダルト・スリオルト先生の関係する“あの日”と言えば、無論あの日以外に有り得ない。
「先程ミデルフォーネさんがおっしゃった、待ち合わせの日のことです。丁度私達がお会いするきっかけになった、スリオルト先生からの暗号について話し終えた所で。続きをミデルフォーネさん、あなたからお話し頂くというのは」
「わ、私が?!」
私は思わず咳き込んでしまった。
「れ、例のあの日の話を、今ここで、という事ですか。こりゃ参ったな」
迂闊に口を開くものではない。案の定、私の言葉にいち早くメリアーヌから反論が飛ぶ。
「何が参ったなの? やっぱり今まで私が聞いてた話、大袈裟に脚色してあったんでしょう。当事者のクランベさんの前じゃ、嘘がばれちゃうから、おいそれと話せないって事?」
「い、いや。そ、そんなことは……」
決してそんなつもりはなかった。だが、若かりし頃の自分の話をじっくりする機会は暫くなかったし、矢張り私なんぞより物事全体を把握しておられたクランベさんのいらっしゃる前で、あの日の話をするというのは、かなり難易度の高い試練だ。
たじろぐ私の姿をメリアーヌは値踏みするかのような目でじっと見ている。クランベさんはそんな私達を、指を組んで微笑ましそうに眺めていた。
「し、仕方ない……」
やっと絞り出した肯定の返事で、メリアーヌの表情が弾けるように明るくなった。まるでおもちゃを買って貰った少女のようだ。
「やったー! これで今日の遅刻の償い、半分は差し引いてあげなくちゃ」
「は、半分か……」
残りの半分は恐らく、スリオルト流サンドウィッチ十個分で手を打つ破目になるだろう。
メリアーヌは鉛筆をしっかりと持ち、テーブルに向き直った。彼女の手元には紙の束を糸で綴じた特製のメモ帳が、その隣には私が昔、誕生日プレゼントとして譲った、あのスクラップブック『ダルト・スリオルト先生の記録』があった。
九 はて、「先生」一体どういう事でしょう 甲
「さあ」
スリオルト先生の二度目の掛け声で私は腹を決めた。そのつもりだった。
隣の書斎にはバルフォン編集長の亡骸、屋敷の外には先生の命を付け狙う旧陸軍の関係者達。この状況で躊躇いは命取りだ。
だが私を階下へ逃がし、自分はこの場に残ると言い張る先生の顔が一瞬苦痛に歪んだように見えて、その脆い決意が崩れた。
先生は嘘を吐いている、若しくは何か重大な点を隠している。そう私の直感が叫んだ。
しかし、時既に遅し。
頭上でぴったりと嵌ってしまった床板(否、既に私からすれば天井板)は、叩いても押し上げてもびくともしない。こうなっては一刻も早く今居る部屋を出、玄関脇の階段を使って再度二階の書斎へ戻るしか方法はない。先生の安否を確認せねば、そう考えた。
私はするすると掴まっていた梯子を下り、地に足を付けると同時に身を翻してドアに駆け寄った。
一階の廊下へ出るドアノブを勢い良く回し……と思ったが、動かない。ドアを開く事が出来ない。ドアノブ自体はあるのだが、それはくるくると回るだけで一向に本来の役割を果たしてはくれなかった。
「やむを得ん。最終手段だ」
こうなっては体当たりでドアを破るしかないと閃いた。勢いを付けるために身体をドアから離し、いざと思った瞬間だった。“一旦止まれ”の合図が私の脳から発せられる。ノブの直ぐ下の何か、その真っ黒な正方形に目が行ったのだ。白塗りのドアに、炭を固めたような真っ黒な紙が貼られていた。そこに書かれていた文言は次の様なものだった。
「扉を体当たりで破るなんて、君はそんな野暮な事をするのかい?」
何処からか聞こえて来た台詞にはっとする。
落ち着け落ち着けと念じながら、深く息を吐いた。そして最初に言われた事、あの使命を思い出した。
私もまた、はっとした。どう見ても先生の字だ。
「小説の一節……だろうか?」
作品の一部を抜粋したようにも見えるが、過去に読んだ覚えは無い(スリオルト先生の書かれた作品は無論、全て目を通してある)。何よりも、内容が今の私に余りにぴったり合い過ぎる。
どうやら私がドアを開けに行くだろうと予想し、忠告としてメモを貼っておいたらしい。頭の回転の早い先生ならではの所業だ。
「それにしても、体当たりまでお見通しとは」
少し迷ったが、私はドアからメモ用紙を剥がし、コートのポケットへ捻じ込んだ(実のところ、一節とはいえ“恐らく私のためだけに書かれた小説”という、一ファンとして垂涎の品に心が躍っていた)。と同時に、はたと手が止まった。
「ん? そう言えば……」
手にある品を捻じ込む先、私の太腿の辺りに大きなポケットがある。それは、私が今コートを着ているという事を意味した(その事実に今の今まで気が付かなかった!)。
つまり私は遅刻した失態にすっかり気を取られ、スリオルト邸到着時の恰好のまま先生の前に座っていたという事になる。招待を受けた訪問先で帽子やコートを外さないのは、この国ではマナー違反だ。
「私とした事が、な、何という失礼を!」
スリオルト先生はこの辺りの出身では無いようだが、それでもこの国での生活はもう長いはずだ。後で先生と合流した際に、速やかに非礼を謝罪せねばなるまい。私の使命は、こうしてまた一つ増えた。
私は振り返って、部屋を見回した。
そこは先生に言われた通りキッチンだった。
「なんだこれは」
大きなオーブンに変わった野菜や果物の置かれた食材棚、見た事も無い不思議な調理器具。恐らく書斎と同じくらいの広さがあるキッチンスペースに、所狭しとものが並べられている。お洒落な空間の演出より、機能性重視といった雰囲気だ。
そう言えば今日は軽食を用意して下さるという話だったが(約束に遅れてしまったため食べ損ねてしまったが)、普段から先生は料理をされるのだろうか(これまた失礼ながら、先生は生活感が希薄でキッチンに立つ姿が想像出来ない)。
「ああ! いけない、いけない。ぼんやり眺めている場合では無かった」
またしてもはっとして、私は目的の流し台を目指してせかせかと移動した。
見ると確かに、取っ手の付いた金属製の板のような扉が、流し台の下部に設置されている(それ以外に引き出しや戸らしきものは何も無かった)。開けば人一人が入り込めそうな大きさだ。
私はその鉤爪のような取っ手に二本の指を掛け、手前に思いっきり引いた。だが、扉はびくともしない。
「ん? これではないのか、先生のおっしゃっていた流し台の下というのは」
だが他に水の出そうな場所は見当たらないし、開けられる場所はこの扉しかない。
私はズボンの膝の部分を少し引っ張り、どっしりと下半身に重心を構えてから、今度は狭い取っ手にぎゅうぎゅうと三本の指を掛け、もう一度力任せに取っ手を引いた。
「む、む、む……!」
あわや取っ手が壊れるか! との心配は杞憂に終わった。
原因は私の手汗だろうか。
つるっと取っ手を外れた指は空を掻き、私は豪快に硬い床のタイルへ尻もちを突いた。と、そのまま勢いが付き過ぎて流しの反対側、つまり私の背の方にあった大きなオーブンのドアに頭をぶつけた(ごがごんという、何とも表現し難い音がした)。と、思った矢先、オーブンのドアが体重でそのまま奥へと倒れ込み、私はオーブンの中へ頭を突っ込む形でやっと静止した。見つめた先はオーブンの内側天井である。
「あいたたた……」
後頭部も痛いが、尻も相当痛い。文字通りの急展開に頭がぐるぐる回る。
歯を食いしばり、歯の隙間からしーっと空気を出して息を整えた。
先生の家のオーブンを壊してしまったのだろうか。私はおろおろと狼狽しながら腰を捻って身を起こす。その刹那、今度は何やら黒光りするものを視界に捉えた。
「な、なんだこれは?!」
オーブンの内側に留め具のようなもので何かが固定されている。
「これは……け、拳銃……?!」
ひやあと声を上げそうになったが、片手で口を押さえてごくりと飲み込んだ。
一丁や二丁と言った話では無い。整然と並べられた幾つもの小型の拳銃が、オーブン内部を埋め尽くしていた。
先生は一体何者なのか。
なるべく深く考えないようにして来た最大の疑問がふつふつと湧き出て来るのを、留める事が出来なかった(もしや、オーブンとは本来こういう作りになっているのかもしれないという希望的観測も、最後の砦として思考に加えておいた)。
私は戦争の時代を生き抜いて来た人間、当然ながら本物の銃を見た事はある。だが幸いなことに、戦時中は実際にそれが使われる現場に居合わせることはなかったし、すっかりこの十年で平和呆けしてしまった。現在の穏やかな日常と人命を奪う恐ろしい武器との間に、埋められない溝を感じてしまう。
一般市民の銃の所持が禁じられたこの国において、温厚な若き小説家ダルト・スリオルト氏が法を犯しているという事実は、私の精神の許容範囲を超えてしまっているのだ。
私は震える右手を左手で懸命に抑え込み、何とか立ちあがった。
勿論、発見してしまった一切に付いて、然るべき所へ告げに行く積りは毛頭ない。とりあえずスリオルト先生本人の口から説明を聞くまで、全てを胸の奥へ仕舞い込んで鍵を掛ける事に決めた。
十 はて、「先生」一体どういう事でしょう 乙
スリオルト邸は本当にからくり屋敷のようだ。ここでは固定観念や先入観ほど役に立たないものは無いのだろう。そこで私は一つのことを思い付いた。
「引いて開かないのなら、別の開け方をしてみれば良いのか」
奇抜なオーブンの経験を活用し、流し台の下の扉を奥へ押してみる……が、開かない。さらに力強く身体全体を使って押し込む。しかしびくともしない。
「むむむ、ではこれならば」
今度は取っ手に指を掛けたままゆっくり扉を回すように(実際には回らないのだが)ぐるりと円を描いてみる。
丁度私の腕の力が右横へ向かった途端、それを待ち侘びていたかのように板がするっと滑った。どうやら右方向へスライドさせるのが正解だったらしい。大きな金属板はすんなりと、流し台の右にあるかまどの土台部分に吸い込まれるようにして消えた。
恐る恐る覗き込むと、中は何も無い真っ暗な空洞になっていた。また一枚のメモ用紙(今度は闇の中にぼんやり白い紙が浮かび上がって見えた)が貼ってある。先程と同様、小説の一節のような文章が先生の直筆で書かれていた。
寄り道をしている暇は無かった。勿論余所見をする猶予もだ。
進むべき道は開かれた。光差すあの場所に辿り着くまで、この迷路を通って行くのだ。先に待つものについては、その時に考えれば良い。
先生は矢張り、何でもお見通しのようだ。
私は二枚目の紙もまた、ポケットへそっと仕舞い込んだ。
流し台の下の空間は、金属板の取り付けられていた位置より下へ沈み込むように造られていた。奥行きはあまりないが、人間の大人が四つん這いで入り込める程の(無論、少々肉付きの良い私でも平気な程の)大きさだった。
手をついて身を乗り出す。覗いてみると、穴は扉の吸い込まれた側へ広がっていると分かった。
「かまどは張りぼてだったのか」
先生からの伝言小説に依れば、これが出口までの通路になっているようだ。
先程までいた書斎と、その隣の寝室、そして寝室の真下のキッチン。屋敷の奥行きと部屋の配置からして、このキッチンは建物内の北の角部屋付近にあたるだろう。つまり灌木の茂る裏庭に面しているはずだ(思えばこのキッチンには、窓が一つも無い)。きっと穴を辿れば直ぐ外へ出られるだろう。
私は意を決して暗闇の中に身を捻じり込んだ。
四、五歩で(正確には四、五這いで)屋敷の外へ出られると軽く考えていた私は甘かった。
入口を正面として右方向に伸びていると思った真っ暗闇は、這い進むと直ぐに左方向に折れた(まさか曲がり道があるとは思わず頭をぶつけた)。その先には緩やかな下り坂とやや急な上り坂があり、私はただ手足の感覚に頼って前進することしか出来なかった。
這い進みながら私が考えた事と言えば、もう少し日頃から運動をして、体型をスリムに保つべきだったという事だ。そうすればこの穴も余裕を持って進めたかもしれない。否、一体何処の誰が、隠し通路に潜り込み逃走劇を繰り広げる人生など想像出来ただろう(スリオルト先生なら出来るかもしれない)。
そうこう思案する内に、壁面に擦っていた肩や頭が何処にもぶつからない場所へ辿り着いた。どのくらいの広さか全く見当はつかなかったが、私は恐る恐る頭を持ち上げた。高さが十分ある空間のようで、首をそろそろと伸ばしてもぶつかる気配は無い。
「ふう」
息を吐きながら肩に込めていた緊張をほんの少し解いた。脱力したのが良かったのだろうか、前方の闇の中、うっすらと縦に伸びた光の線に気付く。私は右手をそっと伸ばした。
「おお!?」
指先に予想外の触感があり、私はかなりの大声を上げてしまった。直ぐに口を噤み、じっと堪える。
もしこの光の先が屋外で、先生を付け狙う連中が家の四方を取り囲んでいるのだとしたら、「何だ、この辺りから声がしたぞ!」等と駆け寄って来る可能性は高い。此処までやって来た苦労を水の泡にはしたくない。更に捕獲されようものなら、先生に合わせる顔が(文字通り)無くなってしまう。
だが、どうやら心配のし過ぎだったようで、一向に外部からの物音はしなかった。私は思い切って身体ごとその光に近付いた。
「うわあ」
顔の周りにわさわさとしたものが纏わり付き、不覚にもまた声を上げてしまった。だが、存外柔らかいもののようだし、心なしか良い匂いもする、等と考えている内に私は光の直中にいた。
暗闇に長く居たせいで全てが眩しく感じられる。何度か瞬きを繰り返し、少し明るさに馴らした目で見上げると、私を取りまいているものの正体が判明した。
フリルを贅沢にあしらった女性物のドレスが、私を左右から挟み込むようにぶら下がっている。私が惚けて手を掛けているのは、どうやら開いたクローゼットの扉のようだった。
「何処だ、一体ここは?」
そこは寝室だった。私はこぢんまりとした部屋の隅に設えられたクローゼットの中から、誰かの寝室を眺めているのだ。
クリーム色の壁紙に花柄のカーテン、薄桃色のベッドカバー。女性らしく可愛らしい作りの部屋だ。中央には曲線美の麗しいテーブルと椅子が一組ある。
一通り彷徨った視線は、テーブル上に置かれているメモ用紙に引き寄せられた(今度は落ち着いた黄色の紙だった)。
私はメモ用紙を見つけた瞬間、安堵の息を漏らした。この何とも形容し難い状況もまた先生の計画の内だと言うのなら、まだ先に進めそうな気がする。メモがあるという事は、きちんとその正解の道を私が辿っているという証しでもあるのだ。
クローゼットから這い出た私は三枚目の伝言小説を手に取った。
そこにはこう書かれていた。
コートと帽子はすっぽりとクローゼットに収まった。
そうして彼女はすっかり着替えてしまうと、その見慣れぬ館の玄関からしおらしく出て行った。
右手に掲げた黒い傘でその顔はすっぽりと覆われ、彼女の表情は窺えない。愛する家族の待つ、帰るべき場所へ背を向けると、早足に彼女は歩き出した。
その先に、彼が待っているとは知らずに。
何処かで見覚えのある文章に思えた(否、以前先生の書かれた小説に、雰囲気が似ているだけかもしれない)。
今回のメモもスリオルト先生の筆跡に間違い無かった(先生は丸みを帯びた、少し癖のある書き方をするのだ)。しかし唯一つ今までと違い、明らかに異質な文字が書き加えられている。「着替えてしまうと」という言葉の下に、流麗な筆記体で「白衣を羽織って」とあるのだ。
確かにベッドサイドには、丁寧に畳まれた白い布があった。あれがきっと、その白衣なのだろう。どういう意図があるのか、誰がこの言葉を追加したのかは分からないが、外衣が一枚加わった所で命の危険が増すとは考えにくい。ここは白衣も含めて、全て書かれている通りにしようと私は考えた。
「どの程度まで、忠実に従えば良いものか……」
私は悩んだ。否、悩みたかった。
寄り道をしている暇は無いのだ。先生は怪我をしているし、命を狙う人間が踏みこんで来ると言っていた。だから悩んでいる場合では無いのだ、等と理屈を捏ねた。
「ううむ」
クローゼットの中を通ってこの部屋へ来たのだから、勿論その中身が何なのかは分かっていた。振り返って見ると、素晴らしく気の効いた衣装に入れ替わっている、等という出来過ぎたお伽話的展開に期待は出来ない。
そう、この部屋の雰囲気にピッタリな女性用のドレスしか、ここには用意が無いのだ。しかし、それでも急がねばなるまい。
私は中でも一番色合いが暗く、裾の長いワンピース風の衣装を選び出した。
小柄な美女が着ればくるぶし丈で見目麗しい状態なのだろうが、私が着ると脛の部分が醜く剥き出しになる。だがやむを得まい。
白衣を身に付けるようにという指示はスリオルト先生からのものでは無かったが、このドレスだけで居るよりは、多少なりとも隠せる部分が増える。何処の誰とも知らぬ筆記体の主に感謝した(欲を言えば男性用の衣装が望ましかったが、これ以上の贅沢は言えまい)。
袖を通す時、白衣からは薬品のような、それでいて甘いような香りがした。肩と二の腕部分がはち切れないようにと私は密かに祈った。
部屋の中に姿見は無かった。それがせめてもの救いだ。今の私の恰好は目も当てられないだろう。妻に見せたら気を失ってしまうかもしれない。
「先生は一体、何を考えているのだろうか」
口の中でぶつぶつと呟きながら、私は自分のコートと帽子をクローゼットに仕舞って扉を閉じた。勿論、コートの左右のポケットへ仕舞っていた大事な品を、白衣のポケットへ移し替えるのを忘れるなんて失態は犯さなかった。
十一 ああ「先生」、私はこれからどうすれば 甲
三十過ぎ、娘持ちの男が、薄紫色のワンピースを翻してファンシーな桃色の部屋に居る(否、辛うじて、スカートを翻してはいない)。
敵の目を欺くために女装をさせられているのだとは思うが、これで本当に変装になっているのだろうか。
部屋を出ると、玄関の傘立てには、落ち着いた黒の傘が一本立てられていた。
私は見慣れぬその玄関口でドア板に耳を当て、神経を研ぎ澄ませて外の様子を窺った。矢張り何の物音もしない。私はごくりと生唾を飲み込むと、意を決してドアノブに手を掛けた。
外界の空気に触れると同時に、急いで傘を広げた。もう十分暗いとはいえ、万が一という事もある。例え敵に見つからなくとも、こんな醜態を通行人やご近所さんに晒す訳にはいかない。
玄関から薔薇の木を縫うような砂利の小道を辿って庭を抜け、腰の高さ程の木製の門を押して通りに出ると、はて見覚えのある景色だった。街並みも何処か親近感がある。
通りを挟んで向かいに見える、あのガス灯の明かりに浮かび上がる文字は、頑固者で有名な爺さんの店の看板だ。先生の本をぞんざいに並べた事件を巡って、三時間も談義を繰り広げた古書店だ。
「そうか、先生の屋敷の裏通りだ」
思えばそのはず、いきなりピンク色の部屋にクローゼットから入り込み、ドレスを纏った変質者になって出て来たからといって、私が御伽噺に紛れ込む等という事は有り得ない。
振り返ると巨大なお屋敷が聳えていた。無論スリオルト邸ではない。先生の屋敷の真北に位置するのだろう、全く別の建物だ(スリオルト邸よりも或いは大きいかもしれないが、何分暗くて全容は解らない)。
どうやら先生の家のシンク下から隣家のクローゼットへと秘密の通路が作られていたらしい。私の頭上にあった地上部分を外部から確認したい衝動に駆られたが、今はそれどころではない(私の逡巡は実は一瞬である。勿論命を狙われて逃避行中である事を忘れてはいなかった)。
「帰るべき場所に背を向けて」
そう、あれは先生の作品『去りて尚走り』の一節に似ているのだ。勿論女装した三十歳男なぞは出て来ないが、ヒロインが愛する人の待つ家のある方角へ背を向け、歩き出す印象的なワンシーンがあった。
「ということは、私も自宅と逆方向へ歩いて行けばいいのだろうか……」
自宅はここからだと西になる(おっとりした妻と指しゃぶりが止まらない娘の待つ家だ)。私は通りを東に向かって早足で歩き出した。
移動しながら私は頭の中を整理しようとした。
先の大戦の終結に一枚、否それ以上噛んでいる“メメント・モリ”のリーダー、ナナであるダルト・スリオルト先生の事(これだけで大混乱だ)。正直な所、実感がまるで沸かなかった。虫も殺さない様な物静かな先生が先の大戦の戦犯だ等と。
さらに、解体したはずのこの国の陸軍と通じ、先生へ銃口を向けたバルフォン編集長の事。
編集長とは確かに反りが合わず良く衝突したが、今の文芸誌の地位を確立したのは他でもない彼で、現代文学界への貢献度は高い。社会的に成功している彼が、一体どんな因縁で過去に捕らわれていたのか。否、それを言うなら先生も同様か。
ぐるぐると無意味な思考を繰り返す。真実は何処にあるのだろう。
どの位歩いたのか分からない。幸い差ほど人に出くわすことは無く、偶に見掛ける人々は酒に酔っていたり家路を急いでいたりと、こちらに注意を向ける様子は無かった。怪しい人物も見当たら無い(私が一番怪しい格好なのは最早致し方無い)。
「先生は、ちゃんと私の後ろから付いて来られているんでしょうね?」
私は背後のスリオルト先生へ呼び掛けた。
「とっくに追いついていらっしゃるのに、からかうお積もりなんでしょう? 私は足が遅いですから、どうぞ追い抜いて行って頂いて構いませんよ」
返事は無かった。無いと分かっていて話し続けた。怖くて振り返る事は出来なかった。
血を流すスリオルト先生の姿が脳裏を掠める。私が先生の不在を認識さえしなければ、其処に、直ぐ後ろに先生が居られる可能性は零にならない。そんなしょうもないない希望に今は縋りたかった。
そうして不毛な会話(実の所一人語りだが)をしながらどれ程進んだか。薄暗い通りの先にぼんやりと見覚えのある形を見つけ、私は漸く足を止めた。
車だ。ガス灯の真下に一台、車が止まっている。
「あれは……」
もしやという期待に胸が膨らんだ。
駆け寄った私の目が捉えた其れは、紛れもない私の車だった。スリオルト邸を訪れ、慌てて正門の前に横付けしたあの車だ。傷や凹みまで記憶通り、正しく私の相棒だ。
「何だ、先生。私の車で先回りをされるとは! いやはや先生もお人が悪い。もっと早く言って下されば」
意外な先生の機転に顔が綻ぶ。私はさっと助手席のドアノブに手を掛けた。が、鍵が掛かっていて開かない。
「先生! 私です」
ドレス姿の男がいきなり暗がりから現れたので驚いているのだろう。それにしても酷い格好だが、元はと言えば先生の注文だ。
「それにしても何時の間に車の鍵を? それとも私が鍵を差したままでしたかね? いやあ、あの時は随分慌てていたもので」
私はこんこんと車窓をノックした。
そして同時にはたと気が付いた。白衣のポケットにそっと外から手を当てる。少し前に白衣のポケットへ移したもの、先生の手書きメモとは逆の方に、持ち慣れたあるものの感触がある。
「そんなはずは。いやでもしかしこれは…車のか、ぎ?」
小説『メメント・モリ』の里程標 第二章


