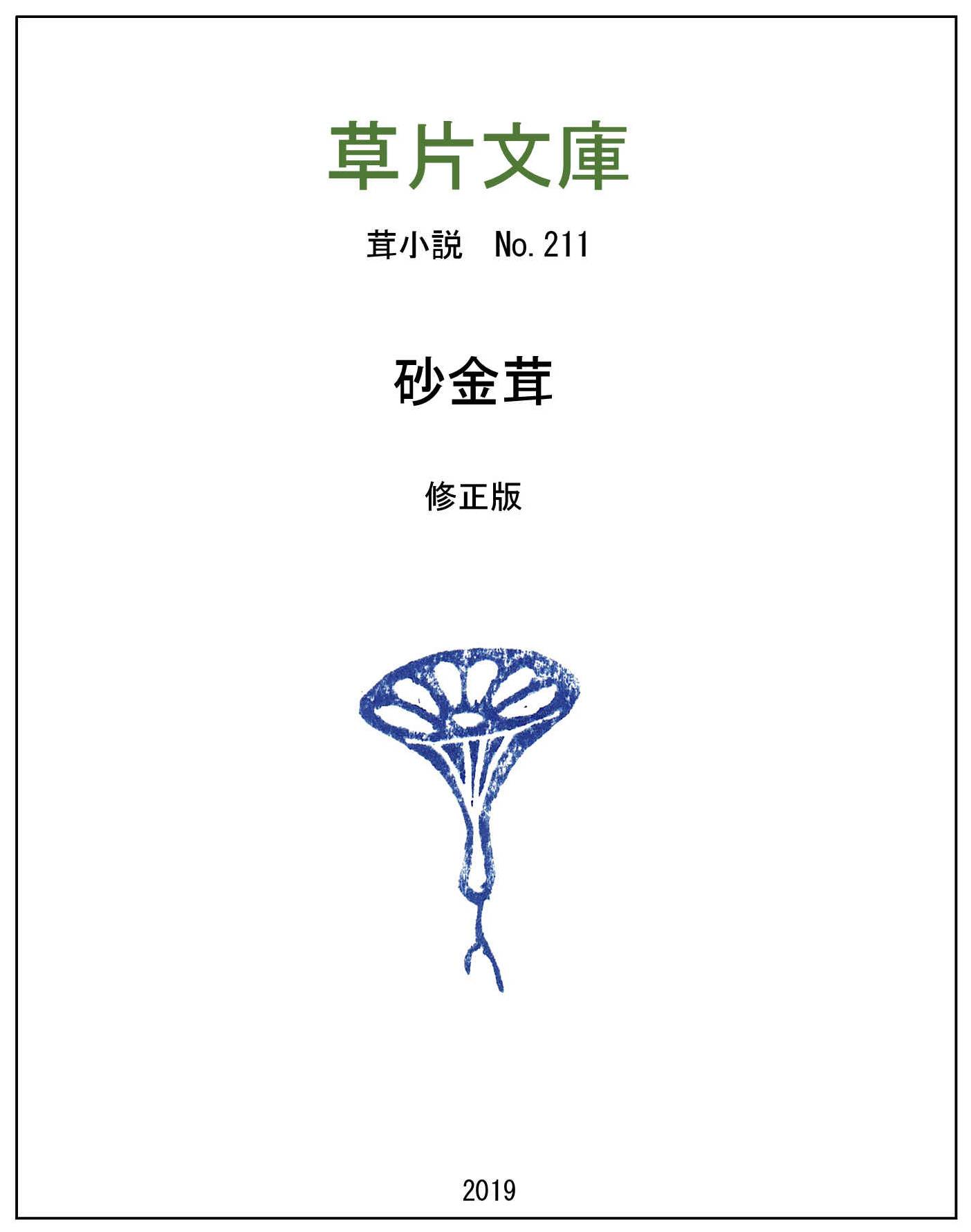
砂金茸
茸の絵師の物語2 縦書きでお読みください。
これは茸酔(じすい)が二十六になろうとするときの経験である。師匠の虎酔が存命中で茸酔と一緒に暮らしている時である。茸酔はそのとき「円山茸酔」として活躍していた。
「今金箔を使うことができないが、昔は豊富に使って絵が描けたものじゃ、金の光は必ずしもわしの好みではなかったが、虎の目が輝くだろうな」
江戸徳川の世になり贅沢な金を使った絵は禁止されてしまった。
「本当をいうとな、今でも加賀では密やかに金を楽しんでおる、お前にも金を使った絵を書かせてやりたかったな」
虎酔はそう言ったが、本心は最近仕上げた絵の虎の目に金を使いたかったのである。
そのころになると虎酔よりも茸酔の絵のほうが売れていた。というより師匠は虎の絵しか描かないことから、あまり頼まれることはない。茸酔は茸の絵なのでかなり需要がある。毒茸と食べられる茸の解説本がかなり出版されることと、薬としての茸の説明書も多く出される。そういった書には必ず茸の絵が必要になる。茸酔の関わった本はすでにかなりの数になる。
「金色に光る茸はないのかね」
師匠は金にこだわる。
「聞いたことはございません、黄金茸という黄色のきれいな茸がありますが、それが日の光で輝くと金のようだといいます、しかし江戸のどこででるかわかりません」
「だが金箔のようには使えまい」
「はい、残念ながら」
師匠は金の代わりになるものがほしかったのだ。そのようなものはないが、何か代わりになるようなものがないか考えてみたのだが、お上は本物の金だろうが、そうじゃなかろうが、きらきら光るものを禁止したわけで、なににしてもおとがめは受けてしまう。
師匠はそれ以降、金のことを言わなくなった。
そのようなとき、佐渡の養生所から茸の絵を頼まれた。佐渡の金山で働く男たちの病を治す医院である。そこの一人の医師は漢方に通じており、佐渡の山野草、茸、海のものから薬を作って、ずいぶん病人を救ってきた。だがよる歳なみでそろそろ隠居を考えており、後輩たちの為に生薬の処方をまとめていた。その絵を茸酔は頼まれたのである。今回は茸だけではなく、動物、植物、鉱物、薬になるすべての物の絵を描くことになる。半年後に佐渡に来てくれないかということだった。医者の名前は鴨居東経と言った。
佐渡には興味があったが、留守をするとなると虎酔師匠を一人にしておくのが心配である。師匠はかなりの歳になる。そんなことを実家の両親に漏らすと、すぐ上の姉の娘が十二になるので、今から奉公に出してもいいという。半年あれば姪っ子も様子を覚えることができるだろう。
そのような話を師匠にすると、たいそう喜んでくれた。
姉の三女、キノがそれから七日後にきた。無口だがよく働く娘で言ったことはよく覚えていた。虎酔師匠も気に入ったようで、茸酔もほっとしたところである。
佐渡は冬になると寒い。茸酔にとって未知の場所、彼は江戸育ちなので寒さになじめるかどうか心配だった。小さな島で流人のいるところでもある。しかし、佐渡で暮らしたことのある人が、それは間違いだと正してくれた。佐渡という島は確かに寒いが、江戸より広く、流人といっても、島の中では規律を守って自由に暮らしているということだった。ただ金山で働いている人たちは大変な肉体労働で、体を悪くする者も多いということである。そう教えてくれた人は、佐渡は海の物もいいし、産物も多い、なによりも茸酔さんの好きな茸がいろいろ採れる、という話もしてくれた。茸酔も佐渡が待ち遠しくなった。
江戸から佐渡まで半月ほどで行くことができる。だが無理をせず、行く先々で茸の絵を描きながら一月ほどかけて歩く予定をたてた。
知り合いの絵師に絵の道具や材料、特に色を付ける絵の具を月に一度ほど送ってもらう算段をした。佐渡で紙や絵の具がどの程度手にはいるかわからなかったからだ。
出かけたのは七月の半ばである。梅雨が明けてすぐ出発した。姪のキノがよく面倒を見てくれているおかげで、師匠の虎酔もにこやかに見送ってくれた。
江戸日本橋から京都に通ずる中山道を高崎まですすみ、そこから佐渡道の三国街道で日本海にでる。江戸から遠く離れるのは京都の応瑞に会いに行った時以来である。幸い身体は丈夫で足には自信があった。
といっても歩きはじめてすぐに足が考えていたほど動かないことに気が付いた。はじめて長く江戸を空けることになり、緊張していたのだろう。蕨で一泊して、大宮桶川、熊谷、深谷と宿があるたびに泊まってしまい。自分の甘さをつくづく感じた。七泊した後にやっと三国街道の入り口、上州高崎に到着した。その間、筆をとる余裕すらなかった。ただ宿では商人や初めての里帰りの人、湯に入りにきた人、さまざまな人たちを見ることができた。
上州の榛名山に行く一行にあったのは幸いである。榛名神社に詣でる人たちはそのあたりに詳しく、高崎の榛名山にはいい湯もあるし茸もたくさん採れるので、寄るといいと教えてくれた。そのお陰で、茸酔の緊張も少しばかり和らぎ、数日榛名山に行って茸を描こうという気持ちの余裕ができた。
榛名山麓で宿を探して歩いていると、榛名山講の一行は茸酔より一日先に着いていたようで、山頂への道を歩いていくのが見えた。榛名山自身は高い山ではないが、上の神社には岩の切り立った修行の場があるという。
茸酔は宿を見つけ何泊かすることを告げると、宿の者が、さっき榛名山講の方たちが山に入ったと言った。今日は月夜なので、夜に登るという。偶然同じ宿に泊まることになったようだ。
榛名山の麓には茸の生えている森がたくさんあった。泊まっている間、方々を歩きまわって、茸の絵を描いた。好きな茸の絵が描けるのが茸酔にとって一番の薬である。久しぶりにゆったりとした気分になった。
宿にきて三日目の夕、その宿の湯に入ったとき佐渡島の様子を知ることができた。
野天湯に藁の屋根をかけだけの粗末なものだったが、周りの景色も湯加減も今までになくくつろげる気持ちのよいところだった。先客が二人いた。どちらも坊主頭で体格がいい割になぜかなまっ白かった。
「入らせていただきます」と茸酔はいつものように、丁寧な言葉をかけ湯に身を沈めた。
「この湯はいい湯だぜ、得した気分だ」
一人がこんな具合に話しかけてきた。
「他はどこの湯がよかったのです」
「ああ、佐渡の島の湯だ、あそこだって悪かねえが、ここの湯のように柔らかじゃねえ」
茸酔には湯の堅さなどはわからなかった。
「佐渡にいらっしたんですか」
「遊び遊山じゃねえよ、おれたちゃ稼がなきゃ暮らしていけねえからよ、銀山で働いてたんだ」
佐渡には銀山もある。
「私もこれから佐渡に行きます」
「その様子じゃ、金山、銀山で働こうって訳じゃなさそうだな、医者か」
「いえ、絵師です」
「いいね、楽しみに行くだけか」
「いや、お医者さんが薬の本を書くのでその手伝いに」
「そうか、ご苦労なこった、医者はあまりたくさんいねえがよ、ずいぶん世話になった、みないい医者だったぜ、何しろ怪我人はしょっちゅうだからな」
「佐渡はもうやめたのですか」
「ああ、借金返すぐらいは貯まったので出てきたんだ、あそこで働いていたら死んじまう」
もう一人が誰の手伝いかと聞いた。
「東経という医者に頼まれました」
「なに、東経先生か、先生たちの先生だ、いい先生だぜ、だけどもう年で、佐渡じゃつれえだろうな」
「はい、それで若い先生のために薬草、茸、海のものの説明や、薬の作り方をまとめるそうで、その絵を描く手伝いに行きます」
「そりゃあいい、うまい海のものを食いな」
「おれたちゃお先に、明日は江戸に向かうんだ、おまえさんは三国街道だな」
二人はそういって湯からあがった。
茸酔は部屋に戻ると、ここで描いた茸の絵を見直した。おもしろい形の茸ばかり描いたようだ。普通の形の茸も描くべきだ。と自嘲した。それにしても榛名山では久々に茸をじっくりと描くことができて楽しかった。江戸の中だけでは見ることのできないような茸に出会えた。茸に囲まれて幸せであった。
それから二日おいて高崎をでた。
三国街道でも金古、渋川、中山、などいくつもの宿場にとまり、高崎から半月ほどかけて寺泊についた。ここから船で佐渡にわたる。
寺泊の宿では海の具合で三日足止めを食った。やっと船が出せるようになったが、船は混み合った。客達の荷物がかなり積んであり、馬が三頭繋がれている。佐渡まで一日かかる。
やっと船がでた。
力に自信がありそうな男たちが何人か集まって札で遊んだりしている。金を掘る人足なのだろう。商人風の男たちもかなりいる。茸酔は船の端に寄りかかり中の人々の動きを眺めていた。船に一日乗るというのもはじめての経験である。いったん絵筆を取り出したのだがあまりにも船が揺れるのでしまってしまった。
「なにをしに行かれるのかな」
茸粋よりだいぶ歳のいったと思われる侍姿の男が声をかけてきた。
「何もすることがなくてのう、わしゃ畑中伝衛門と申す」
丁寧な物言いにちょっと安心した茸酔は名乗った。
「円山茸酔と申します、お医者様の薬の本の絵を描きに参ります」
「絵師であったか、わしは奉行所で人足たちの見張りじゃ、つまらん役割よ、人相書きなどはできるかな」
「はい、一度手伝ったことがあります」
「実はな、わしも絵は得意でな、奉行所でそういったことをさせられるようじゃ、佐渡は魚が美味いそうだから志願した」
「私は一年いますが畑中様はいつまでですか」
「わからんなあ、わしみたいに三男坊で独り身じゃいつ帰してもらえるか、まあ楽しいことを見つけようと思ってまずぞ、あそこは能の舞台が有名じゃ、寺も立派なのがある」
伝衛門は笑った。流人の行くところと思いこんでいた茸酔は伝衛門の話しに驚くと同時に安心した。
佐渡島の赤泊についたのは夕刻である。船を下りると、待ち構えるように役人が伝衛門に駆け寄った。役人が深く腰を曲げて挨拶をしている。姿格好ではわからないが、彼はかなり位の上の人のようだ。
目的のところへは歩いて一日かかる。赤泊に宿を取って、のんびりしてから行くかどうするか茸酔がまよっていると、伝衛門が声をかけてきた。
「茸酔殿は馬にのれますかな」
「師匠に少しですが教わりました」
子供の頃、実家の宿に馬で来る人もあり、その馬を裏の小屋につなぎに行ったことは何度かある。大人になってからは虎酔に加賀の屋敷に連れて行かれて、馬屋で馬の絵を書く練習をさせられたことがある。そのとき虎酔が馬を描くには馬に乗ってみるとよいと言った。虎酔がひょいと裸馬にまたがった。馬の扱いなれることは他の生き物を見るときにも大事だと乗り方を教えてくれた。
「師匠はなんと申されるのか」
「虎酔と申します」
「おお、存じておる、虎ばかりかいている絵師だな、加賀ゆかりの者であろう、いい虎の目を描く」
「はい」
「虎酔は武士であろう、わしと同じような生まれじゃ、虎酔は絵がうまかったので絵師で身を起こせたが、わしはそのような才がなく、髷をゆっておるのでござる」
「そうでございますか」
「どちらに行かれる」
「相川と言うところです」
「なんだ奉行所のあるところではないか、金山のあるところだ」
「そうでございますか」
「わしは馬が好きでな、わしの馬を連れてくる条件で佐渡に来たんじゃ、三頭連れてな、佐渡で馬を増やして、足がわりにするのよ、同じ方向だし、よかったら馬に乗りませんかな」
「うまく乗れるかどうかわかりませんが」
「またがることができれば大丈夫」
そこに年を取った男が伝衛門のところにやってきて、
「支度が整いました」と言った。
「おお、茸酔殿、これは平佐じゃ、馬の扱いになれておるばかりではない、馬の病などにも詳しいので一緒にきてもらった、船の中では馬に寄り添ってくれておったのじゃ」
「絵師の茸酔にございます、お世話をかけます」
「これで男三人になった、平佐が二頭を引き連れる予定だったが、おかげで、馬を走らせることができる」
茸粋にとってもとても助かる申し出だった。
佐渡は本土よりを小佐渡、大洋に面したほうは大佐渡と呼ばれる。赤泊まりは小佐渡であり、奉行所も相川も大佐渡にある。歩くとなると半日かかる。
三人はゆっくりと馬を歩かせ、急ぐこともなく大佐渡に入った。金山近くの奉行所は厳重な立派な構えだった。
大きな門構えで長い堀に囲まれている。後で知ったことだが、掘り出した金銀を抽出する工場があり、それを管理するために、お城のように頑丈な作りになっているという。佐渡島は徳川直轄の地、すなわち天領である。
馬が奉行所の前につくと、
「畑中さまがいらっしゃいました」と門番が中に声をかけた。
その声であわてて大勢の役人が外に出てきた。
「畑中様、お久しぶりです、よく佐渡にいらして下されました」
馬から下りた伝衛門に正装をした役人が深々とお辞儀をした。
「おお、奉行殿、こちらこそよろしく頼みます」
伝衛門は馬から下りた。
茸酔は奉行より伝衛門の方が上の役柄なのには驚いた。
伝衛門は茸酔を紹介した。
「茸酔どのだ、医者のところで薬の本を作りに来なすった」
茸粋も馬から下りた。
「奉行の松川真之介でございます」
「今日から一年、東経先生のところで働きます、よろしくお願いします」
「おお、東経先生とお仕事をなさるのですか、奉行所の者はだれもが東経先生にやっかいになっております。先生はここからほど遠くないところの養生所にいらっしゃいます」
「そりゃあよかった、茸酔どのちょっと休んでから行かれたらどうです」
「はい、ありがとうございます」
「松川どのよろしく」
そう言って伝衛門は奉行所の中に入っていく、茸酔は後を追った。伝衛門とはどのような男なのか。
座敷に通され、茶が出された。
「伝衛門様には海の近くに家を用意いたしております。釣りが楽しめるかと思います」
「それはありがたい、馬も一緒に願いたいが」
「はい、馬屋もございます」
「仕事は明日からで良いな」
「どうぞゆっくりなさってから、奉行所の方においでいただければけっこうです」
「そうしよう、松川殿、金山の者たちはどうです」
「さまざまで、のらりくらりしている奴らにはきびしくしております」
「働かせすぎて体が悪くなる者が多いと聞くが」
「はい、少ないとはいえませんが、無茶には働かせておりません、ただ穴の中は落盤が絶えませんで、怪我人が多いことは確かです」
「気をつけてくだされ」
「一度ごらんになってください」
「そうしたいと思う、茸酔どの、なにかあったら、松川どのに相談されるがいい、江戸の殿の信頼厚い、やり手ですからな」
「よろしくお願いします」
「必要なことがありましたら、何なりと申し付けください」
「ありがとうございます」
そのあと、伝衛門の家に馬にまたがって行った。海に近い広々とした庭のある屋敷である。わざわざ彼のために作られたようで新しい。いったいこの御仁はなんなのか。
「茸酔どの、平佐と馬で行きなされ、平佐が奉行所から東経殿の養生所は聞いておる、馬は平佐が連れて帰る。たまには酒でも飲みにきてくだされよ、退屈だからな、いや、わしがじゃましに行くかもしれん」
「何から何までありがとうございます、どうぞ私のところにもおでかけください」
「退屈になったら行きますぞ」
平佐に案内されたおかげで、鴨居東経の養生所はすぐにわかった。平佐に礼を言い、鴨居養生所と書いた門をくぐると、たくさんの人が入り口の縁台に腰掛けていた。
ごめんください、と声をかけても誰も出てこない。
茸粋は草履を脱ぐと勝手にあがった。廊下にも人が腰を下ろしている。
ごめんくださいと、また声をかける。今度ははいという若い女性の声が聞こえた。
東経と書かれた部屋の障子戸が開くと、割烹着すがたの女性が顔を出した。
「患者さんはならんで待っててくださいな」
そういって引っ込もうとする女性に、
「鴨居先生に茸酔がきましたとお伝えください」と告げると、
「あら、患者さんじゃないの、ちょっとまってて」そう言って女性は奥に入った。
すぐに東経が顔を出した。白い髭を生やした大男だ。
「東経です、茸酔さんですな、よく来てくれました、見ての通り、夕刻まで暇なしでしてな、紅葉に宿所に案内させますので、それまで休んでいてくださらんか」
さっき顔を出した女性が
「茸酔さん、わらじをもってどうぞこちらへ」
と診察室の中に手招きをしたので中に入った。そこでは東経先生が患者の口の中をのぞいている。
「こちらです」
反対側の廊下にでると、同じような部屋がいくつかならんでいて、中で医者が患者を診ているようだ。
「たくさん先生がいらっしゃるのですね」
「はい、今通った部屋で東経先生が最初に患者見て、薬をちょっと塗るだけの人はそこで終わりです、もっと詳しく診なければならない患者をこちらの方に回すのです、急患の人をみる場所もあります」
「患者さんがずいぶん待っていますね」
「金、銀を掘り出す人は危ないところで仕事をしていますから、怪我が絶えません」
「先生は何人ほどいらっしゃるのです」
「東経先生を入れて五人です、それに私たち女が十人います、傷薬を塗るくらいのことは私たちでおこないます」
案内されたのは診療所のはずれの屋敷だった。東経先生の家だそうで、その部屋の一つに案内された。中にはいると江戸から送った荷物がとどいている。
養生所の庭はとても広く、いくつもの屋敷が建っている。医師たちが住むところだとのことだった。手伝いの女たちは自宅から通う者もいるが、多くは養生所の二階に自分の部屋があるという。
ありがたいことに、敷地の中に野天湯があり、自由にはいることができるとのことだった。患者の湯は別に養生所の中にある。
荷物を解いて絵の道具を並べているところに東経が入ってきた。
「おじゃましますよ、よく来てくださったな、あちらに書をしたためるところがありますでな、見てくださらんか」
東経についていくと、二階に案内された。その部屋にはいくつもの机がおいてあり、様々なものがのっている。
「この机の上のものはこのあたりで採れる薬に使う草木などの標本でしてな、この机は茸じゃ、こちらは石、ここは海のものだが、腐るものはわしの下手な絵で描いてすててしまいます。どれも名前は調べてあるので、生えているところにいって、生きているところを描いてくださらんか」
かなりの量になる。一年で終わるだろうかと心配になった。
「本文は八分ほど出来あがっとるので、後で見せましょう、そこに色の付いた絵を入れたいんじゃ」
「わかりました、精一杯力を注ぎます」
「よろしく頼みます、茸酔殿に助手をつけますので、植物や茸取りに行くときは手伝わせてくだされ、海のものは漁師に言ってあるので、採れた時には持ってこさせますから、絵を描いてくだされ」
助手は山歩きの達者な巖(いわ)という老人だった、東経が佐渡にきたときから家に出入りして、東経の薬草取りなどを手伝っている。佐渡で生まれて漁師をしていたのだが、左の小指と薬指を得体の知れない魚に食いちぎられ、それからは畑をやりながら山菜や茸を採って暮らしていたという。東経先生が薬草を採ってくれる人を募集したところ、巖さんが応募してきた。海のことばかりか、佐渡の山を隅々まで知っており、東経先生の薬づくりに貢献している。その巖さんは茸が好きで、珍しい茸を採ってくると言う。
佐渡には相川の金山から、大佐渡を縦に走る大きな山々が連なっている。
その中でも金北山は高くそびえた立派な山である。
茸酔は巖さんとは次の日に会った。
巖さんは「巖でごぜえます、お手伝いさせていただきます」と日に焼け、しわくちゃの小さな顔に満面の笑顔でおじぎをした。
「こちらこそよろしく願います」と答えながら、この人とならとてもうまくいくと茸粋は嬉しくなって自然と笑みが浮かんだ。
「海のものは、このあたりの漁師に声かけときゃ、あがったら教えてくれますで、わしがもらってきます、薬の草と茸は茸酔先生がこれをとおっしゃれば採ってきますので言いつけてくらっしゃい、薬の石は養成所の方にあるのでいつでも見ることができます」
「私は名前の通り茸の絵師です、巖さんが山にはいるとき、一緒につれてってもらえますか」
「ええですが、ちっと危ないとこもあるで、茸酔先生に何かあると、わしが困りますがの、すぐ近くの山でも茸は採れますで」
「東経先生に許可をもらいます、それならいいでしょ」
「へえ」
それから茸酔は精力的に絵を書き始めた。貝、魚、海老、蟹、海の草は初めてのものばかりで、形のおもしろさ、色の美しさに魅せられ、筆がすすんだ。薬草に関しては道ばたに生えているいつも見慣れている草が薬になるということを知り、東経先生が作ろうとしている本が、世に出ると大変役に立つものだと改めて感心した。絵を精確に描く努力をしなければと、葉の生え方、花の色など熱心に観察をした。
茸は好きなこともあり、巖さんと何度も山に行き、初めて見る茸を見つけると、薬と関係なくすべてを写生した。
「ほう、まだ一月なのにこんなにたくさん描かれたのか」
東経先生が仕事場に入ってきて目を見張った。
「海のものを描くのは初めてで、とても面白く描かせていただいています、それに巖さんが山のあちこちに連れて行ってくださったので、薬草もかなり描けました」
「これは何かな」
東経は別の机の上に積んであった紙をめくった。
茸酔の描いた茸の図である。採った場所、日時、天気も書き添えられている。
「お、これは茸酔殿のお仕事でござるな、みごとだ、まとまったら図譜を出されるとよいのう」
「いえ、そういうつもりでなく、茸の姿を写したくなり、山に行くたびに描きためたものです」
「ともかくたいしたものだ」
東経は薬に使う魚介類の図をめくった。
「よく描けておりますぞ、おやこんなものもあがりましたかな、珍しい」
一つの絵を手に取った。
「はい、巖さんがこれは珍しいといっていたので絵を描いておいたものです」
橙色の風船のようなものが描かれている。
「これはこの辺では採れないものでな、睦のほうでとれる、ホヤと申して、あちらじゃ食うそうだ」
「いい匂いはしませんでした」
茸酔がそういうと、東経もうなずいた。
また一枚の絵を手にした。
「これはバイ貝と申して、時によって毒がある、ご存じかもしれないが海の魚や貝、それに蟹などは、元々は毒をもっていなくても、季節によって毒を持つ、それを食べると腹をこわしたり、死ぬことさえある」
「それはどうしてでしょう」
「ある季節に毒を持つ小さな生き物が海に発生して、それを食べた魚や貝の体に毒がたまるからだと言われている」
「それは怖いことです、人間も同じように食べれば毒をもつでしょうか」
「ハハハ、毒をもった人間か、いないことはないな、いや、それは冗談だが、人間の体には悪いものを吐き出す臓器がある、しかしたくさんの毒がいっぺんに体にはいると、臓器が働かなくなり死んじまう」
「それはどこでしょうか」
「肝の臓じゃ」
「それでは食べ物のなかに金がはいっていると、そこに貯まるのでしょうか」
「いや、金は胃や腸からからだの中に入らないからクソと一緒にでる」
「草、木も同じですか、毒を貯めますか」
「草木や茸には臓器がないが水などと一緒に吸い上げるかもしれんな、からだにいれて貯めることもあるだろ、白い花を切って赤い水にさしておくと赤くなるであろう、水に入っているものは草に吸い取られるだろうな」
「茸も同じでしょうか」
「おそらくそうじゃろう」
茸酔はそれを聞いて、金の粒を土から吸い取り、金色になった白い茸を想像した。
「川に砂金がありますが、植物が吸って葉などに貯めることがありますか」
「砂金の大きさにもよろうが、ないとはいえないな、茸粋殿は植物を使って金を土から吸い取らせようというお考えだな、それは面白い。できるできないは別にして、茸酔殿の発想は普通の人ではありませんぞ」
茸粋はただ金色の茸はきれいだろうなと思っただけで、そこまでは考えていなかった、むしろ東経の才気に茸粋は驚き、薬の本は立派にしなければと、意を新たにした。
伝衛門は釣った魚などを持って東経先生の養生所にふらっとやってくることがあった。時には佐平さんが馬に積んで採れたものを持ってきてくれる。
「茸酔殿、忙しそうでよいのう、わしゃつまらん仕事ばかりでくさっとる」
伝衛門はそうぐちる。
「この海はあまりいろいろなものはおらんな、江戸の海は色とりどりの魚がおるに、ここは海が黒い」
釣りの好きな伝衛門には面白くなさそうである。
「能舞台はよいな、馬を走らせるにもいい島じゃ、しかし、もう少しなにかほしいな、茸酔殿はどうですかな、この島は気に入りましたかな」
佐渡には日連聖人や世阿弥が島流しになり、住んでいたこともあって、寺や能楽堂などが作られていた。
「はい、とても面白い、私にとって海のものを絵に描くなど初めてのことですが、おかしな生き物がこんなにもいるものだと驚いています、ともかく、山には茸がたくさんでてとても楽しく暮らしております」
「それはよかった、一度儂も茸採りにつれてってくれまいか」
「はい、ここには巖さんという東経先生の片腕がおります、茸ばかりではなく、どんな植物がいつ頃どこに生えるかよく知っています、その人について行くと、面白い茸に出会うことがあります、私はとても楽しんでおります」
「うまい茸もあるのであろうな」
「舞茸はうまい茸で、巖さんはそれが出るところをよく知っております」
そこにぐあいよく、巖さんが庭に入って来た。
「あ、伝衛門さま、巖さんがきました」
巖さんは客がいるのを見て引き返そうとした。茸粋が呼び止めて上にあげた。
「巖さん、奉行所の畑中伝衛門さまです」
それを聞くと、巖さんはいきなり畳の上に座って蛙のように平べったくなった。
「巖でございます、畑中の殿様にはお世話になりました」
「おー、もしかすると、父がすごい漁師が佐渡にいるといっておったが、その巖さんか、父が世話になった」
「いえ、よくしていただきました」
「どういう関係なのです」
茸粋が聞くと巖が答えた。
「伝衛門さまのお父様は、私が若く、漁師をしている頃、勘定奉行をなさりながら、佐渡のお奉行をもなさっておられました。とてもよくしていただきました。佐渡が住みやすくなったのは、畑中様のおかげと皆申しております。畑中様は江戸にもどられ、お子さまが跡を継がれたと聞いておりました」
「いや、跡を継いだのは長男でな、儂は外腹で、のらりくらりしていただけじゃ」
茸酔にはだんだん伝衛門のことがわかってきた。
「ところで、巖どの、面白いものが釣れるところはないか」
「へえ、蟹釣りは面白いのではないかと思います、ここの海にはうまい蟹がいます、蟹を釣るやつなどいませんが、釣り針を工夫して、餌をつけて海に沈めますと、意地汚い蟹は挟んで放そうとしません」
「面白そうだ、いつか教えてもらいたい」
「へえ、いつでもかまいません」
「まず茸狩りにつれてってくれ」
「へえ、明日金北山へ猿の腰掛けを探しにいきます、そこには面白い茸も生えています」
「猿の腰掛けにもいろいろな種類があって、明日探しに行くのは薬の効能が強い茸です、巖さんしかわかりません」
茸酔が付け加えた。
「面白いのう、巖は馬に乗れるか」
「へえ」
「ならば我家にきたらどうだろう、馬が三頭いるが」
「ありがとうございます」
いつもは歩いていく。金北山までは三里ほどで、かなり時間がかかる。相川の山からも続いているので山の頂沿いに行けないことはないが、金北山だけの目当ての時は、平野を歩いていく。
朝にでて昼につき、飯を食って山にはいる。
「遠いので、山の近くの寺に泊まらせてもらって、寺で採ってきたものの絵を描きます」
「野天湯はあるかね」
「近くにあります」
「おおそれはいい、そこに泊まろうじゃないか、儂は釣りの道具は持たなくてよいから、食料を担いでいく」
次の日、茸酔は巖と伝衛門の屋敷に行った。平佐が出迎えてくれた。馬が四頭もいる。
「久しぶりです」
「茸酔様、奉行所の馬を一頭借りてきました、私も参ります」
そこに伝衛門がでてきた。大きな風呂敷包みを背負っている。
「や、待たせましたな、四人分の飯を作ってもらいました」
伝衛門の後ろから若い娘が二人出てきた。
「お気をつけて行ってらっしゃいませ」
「おう、後は頼む」
伝衛門はすぐに自分の馬にまたがった。
「手伝いの女子を雇いましてな、うまい飯を炊きます」
そういって背負っている風呂敷包を指さした。
伝衛門の家を出て、四頭のウマにまたがった四人はゆったりと、金北山にむかった。茸酔も馬の上から見る道々の景色はまた違うもので、新しい佐渡を見るような気持ちで馬を歩かせた。
馬だと早い。昼よりかなり前に、金北山の麓にある禅寺についた。
いつものように、住職の六庵にいくらかの寄進をし部屋を借りた。
「こちらは奉行所の畑中伝衛門さま」
そう紹介すると「あ、畑中様でいらっしゃいますか、お父上様に私の父がお世話になりました、おかげでこの寺も細々ではありますが、生き延びております」
聞くと、この寺をほかの宗派がつぶそうとしていたところを、伝衛門の父親が宗派間の争いごとがないように取り計らってくれたそうである。
茸酔たちは寺の部屋で飯を食って金北山にはいった。兵佐は残って馬の世話と夕飯の買出しということになった。
金北山は真冬でなければ、登るのにすこぶる危険という山ではない、しかしなれていない者だけでいくことはやってはいけないことだ。どの山でもそうだ。茸酔は養生所から近い山に一人で入ったことがあった。茸がいろいろ生えていて夢中になって絵を描き、奥に入っていったとき、帰る道がわからなくなった。山になれた人ならば日の位置から方角が分かるのだろうが、そんな初歩的なことも知らなかった茸酔は帰ろうと思ったとき、あっちこっちを一刻もうろうろして、気がつくとすぐそばにいつもの道があって安堵するということがあった。
それからは山にはいるときの注意を巖さんに教わり、自分一人で行くときには方角を確かめながら歩いていくことを守った。
金北山は近くの山とは違う。
巌がたずねた。
「伝衛門さまは山になれていらっしゃいますか」
「儂は暇人だったのでな、山はよく歩いた。だが山はすべて違う、その山のことをよく知っている人間に案内をこうのが一番安心でな」
強者になるには深く広い経験と、それに裏打ちされた慎重さだと茸酔は納得した。
巖さんは道と呼べない草深い斜面から山に入った。いつものところと違う。
「今日は東経先生の茸を探しますので、ちょっと大変かもしれんが、途中に神の穴がございます、そこからちょろちょろ水が流れ出し、草木に囲まれていましてな、茸もかわったものがでます。もちろん旨い奴も生えております」
「東経先生の茸とはどのような茸です」
茸酔が訪ねた。
「真っ黒な腰掛けでごぜえます」
「名前は何というのです」
「東経先生もわからんとおっしゃっていましたので、おらは東経茸と呼んでいます」
「何に利くのだ」
「腹の出来物がなくなるのだそうで」
「それはすごい」
茸酔は茸を描きながらいくので、二人からだいぶ遅れる。ともかく茸の種類が多い。
「すみません」
おいつくと、二人は祠の入り口をのぞいている。人が一人しゃがんで通れるくらいの祠だ。伝衛門が巖に聞いている。
「洞の中はどうなっている」
「わからんですが、その昔、入った人がおって、立って歩けるくらいだそうです、だがその男は病を患って死にました、神の穴だと言われておりますだ」
「深いんじゃろうな」
「誰も知らんです」
「面白そうよの、巖は入らなかったんだな」
「へえ、この洞は金色に光る神様が佐渡においでの時に、ここでお休みになるという話が伝わってますで、恐れ多くて」
「いつからそのよう話があるのだ」
「儂はじいさんから聞きましたから、大昔からだと思います」
「なにかありそうだ、入ってみたいが、どうだろうな」
「へえ、畑中様がそうおっしゃるならかまわないかもしれません、東経茸を採ったらここに戻ります、あとでよろしいでしょうか」
「そうしよう」
それから下草の覆った斜面を、巖を先頭に登ること半刻、急斜面の一角に樹齢千年といってもいいほどの大きな老木があった。三人が手をつないでも囲えないだろう。
「これは楠でございますが、ほれ、あそこに東経茸が生えております」
確かに黒光りをしている猿の腰掛けがいくつもついている。
「この茸は大きくなるのに五年かかりますだ、それで一年に一つだけ大きくなったものを採っていきます」
「この木にしか生えないのか」
「へえ、若い楠にはありません、この楠だけに生えますだ」
そう言うと巖は袋から鎌を二本取り出し、一本をのばした手の先の幹に刺した、それをつかんで木に飛びつくと、ぐいと木にかけた足に力をいれ、左の鎌を上に刺し、両足を同時に上の方に飛ばし、体を上に持ち上げた、右の手の鎌で黒い猿の腰掛けを払い落とした。
その様子を茸酔は素早く絵にした。
巖は木から飛び降りると落ちた茸を拾って駕籠に入れた。
「みごとなものよのう、隠れの者のようじゃ」
伝衛門はしきりと感心した。
「これで儂の仕事は終わりましたで、神の穴にまいりましょう」
三人はまた神の穴に戻った。伝衛門が入り口に顔を近づけた。
「冷たい風が吹いておる」
洞窟からちょろちょろと水が流れ出て、小さな流れになっている。流れの周りそって、傘は真っ白で、柄が黄色っぽい茸が、たくさん生えている。茸酔は画帳を開いて茸の様子を描いた。
小さな流れの水底にキラッと光るものがある。
茸酔は顔を水面に近づけると、自分の頭が陰になって、水底がよく見えた。きらきら光るものがゆっくり動いている。
茸酔ははっとした。
「砂金だ、砂金が流れています」
「なに、砂金とな」
その声に伝衛門が流れの中を覗いた。
「たしかにそうだ、とすると、この洞窟の中に金のでる石があるやもしれんな、ちょっと儂が入ってみる、茸酔どのはどうなさる」
「はい、まいります」
「儂ははいらんでもいいでしょうか、昔からの話には何かありますで」
「もちろんじゃ、まっててくれ」
「蝋燭を持っております、お使いください」
「用意がいいのう」
「山から降りれなくなったこともあり、そのようなときは野宿をいたします、明かりは必要になります」
「確かにそうだな、では借りていく」
巖はなれた手つきで、火打ち石を打った。蝋燭に火がついた。
「たすかる、すぐにもどる」
伝衛門と茸酔はかがんで中に入った。中は人が立って歩けるほどの高さがあった。外にもあった白い傘の茸が壁から生えている。
穴は二人並んで歩くほどの幅があり、下にはちょろちょろと水が流れている。壁から染み出した水が流れに加わっていく。それにそって茸がたくさん生えている。
ほんの少し歩いただけであるが、行き止まりになっていた。下には水が溜まっている。水を覗き込むと、底からポコポコと泡がでている。
「水がわき出ているが」
伝衛門は茸酔に指差した。水は澄んでいる。泡と一緒に蝋燭の火の元でもきらきらと光るものが吹き出ている。
「砂金じゃないか」
明らかに砂とは違う。
茸酔も見た。確かに砂金のようだ。
「ここには金鉱があるかもしれんな、茸粋殿、願いがあるんじゃが」
「はい、なんでしょう」
「このことは言わんでほしい」
「はい、またどうして、新しい金鉱が見つかれば将軍さまも潤うのではないですか」
「なあ、茸酔殿、将軍が潤っても、民は潤わぬ、それに金北山は人が入れんようになり、赤裸になる、そんなにはしたくないからのう」
伝衛門の言葉に茸酔は胸が打たれた。
「はい、申しません」
「巖には、神聖な場所で途中で怖くなって引き返したという」
「はい」
茸酔は穴の壁に生えている白い傘の茸を指差した。
「穴の外の流れにそって、この茸が生えています」
「ほう、なんという茸かな」
「私もはじめて見ます、採ってもよいでしょうか」
「茸はかまわんだろう」
茸粋が白い茸を引っこ抜いて、手の平の上にのせた。茸の柄の裂け目から砂が落ちてきた。あれっと思って、茸粋が手の上を見ると、砂ではなく砂金である。
「伝衛門さま、茸から砂金がでて参りました」
伝衛門も驚いている。
「この茸は砂金を吸い上げておるようだ」
「師匠の虎酔は虎の目に金を使いたいと常々申しております」
「そうであろうのう、だがお上が許さぬわけだ」
「はい」
「茸を江戸に送るのはとがめられんだろ、この茸を採って、送ればよいではないか」
「よろしいでしょうか」
「茸ならみつからん」
「干した茸を送ります」
「この茸は美味なのかのう」
「私が食べてみます」
二人は穴から出てきた。
巖が「どうでしたでしょうか」と心配そうに尋ねた。
「穴の奥に行くと、妖気を感じたので、戻って参った、やはり神聖な場所のようだ」
「そうでございましょう」
巖は穴に向かって深くお辞儀をした。
「巖さん、この白い茸はなんでしょう」
「さあ、わしゃ知りませんが」
「きれいだから少し採っていこうと思います」
そう言って茸酔は流れの脇の茸も採って袋に入れた。
「うまい茸は向こうにありますで」
巖はちょっと下に二人を連れていった。
古い樺の木の根元に、見事な舞茸がどでんと生えていた。
「おお、美味そうじゃな」
「毎年ここに生える舞茸はお奉行様に差し上げているものです、伝衛門様に今年は召し上がっていただきたいと思います」
「それは嬉しい、屋敷にもどったら、二人とも茸飯にご招待だ、あの奉公の娘たちは旨いものを作る」
「ありがとうございます」
こうして次の日、馬を走らせ屋敷に戻った。
茸酔は自分の部屋に戻ると、傘の白い茸の柄を裂いた。紙の上に砂金がこぼれた。明らかに金を取り込んでいる。この茸を陰干しにして持って帰り、師匠への土産にしよう、そう思った茸酔は畳の上に紙を敷き茸をならべた。
そこに東経が入ってきた。
「巖が持ってきた黒い腰掛けは見事じゃったな」
「はい、巖さんは大した人です」
「たしかにな、あいつがいなけりゃ、儂の薬も作れなかったじゃろう、それでな、巖と儂の一緒のところを描いてくれませんかな、薬草や薬茸採りの名人として本にのせたいのじゃが」
茸酔は喜んだ。
「はい、わかりました」
「そこの白い茸はなんですかな」
砂金をためる茸をみた。茸酔は迷ったが、伝衛門の言ったこともすべて東経に話した。
「すごい茸じゃ、土から砂金を吸い上げて貯めるとは」
「師匠にもって帰ってよろしいでしょうか」
「もちろんじゃ、それに伝衛門殿のおっしゃったこと身にしみる、さすが畑中様のお子、金北山を守ってくださったのだな、儂も人には言わぬ」
「ありがとうございます」
「それで、ちと頼みがある、その茸、わしにも一つくださらんか」
「はい、どうぞお好きなのをお持ちください」
「それはありがたい、その茸を増やしてみたい、庭に池があるじゃろ、水は湧水じゃ、池に金鉱から彫りだしたくず石を壊していれ、周りにこの茸を生やすのだ、くずの石といっても少しは金を含んでおる。ほんの少しでも茸が取り込んでくれれば、砂金茸としてお偉方に高く売りつける、この療養所の資金にすれば貧乏人はただで見てやれる、金はからだによいと信じられているからのう、若返る薬とでもいうと、みんな買うわい」
東経が笑った。
「金北山に行けばまだたくさん生えています」
「いや、それをすると、伝衛門さまの意にそむいてしまう、いつか知られてしまうかもしれんからな、ただ、うまく増やせるまでは種茸を巖に採ってきてもらうかもしれないが、あそこのことは言うまいぞ」
「わかりました、私も場所は知っていますのでお手伝いします」
こうして、茸酔は砂金茸の育成も手伝うことになった。
次の日、伝衛門から茸飯の誘いがきた。茸酔ばかりではなく東経も誘われた。
伝衛門の屋敷は海が見える。座敷に座布団が三つおいてある。伝衛門、東経、茸粋がすわった。同じ部屋にもうひとつ席があった。座布団が四つある。平佐と巌が座った。二人の若いお手伝いが三人に膳を運び、銚子をおいた。
「眺めがよいですな」
伝衛門から酌をされて東経が恐縮している。
「東経先生は酒が強そうだ」
伝衛門も相当強い。
二人のお手伝いの女性は、膳を佐平と巖の前におくと、さらに二つの膳をもってきて、自分達も座った。
「お前たちも好きなようにやってくれ、酒も良いぞ」
伝衛門が四人に声をかけた。茸酔は驚いた。
「茸粋どの、伝衛門さまは人のあるべき本当をよくご存じだ」
東経が茸酔に言った。
「はい」
よくわからなかった茸酔にさらに東経が言った。
「人は皆同じ、侍も農民もない、私も常々そう思っていましてな、袴を脱ぎ着物をとって素っ裸になった侍は、農作業の野良着をとって素っ裸になった農民とどこにも違いがない」
それをきいて、茸酔は佐渡にきて本当によかったと思った。考えたこともないことをこの二人の先達から随分教わった。
「ところで、ご相談がありまして、金北山から茸酔さんが持って帰った白い茸ですが」
東経がそこまで言ったときに伝衛門が「砂金茸ですな、東経殿は薬になさいますか」と自ら砂金のことを言った。茸酔は他人にしゃべらないと約束したことを破ってしまい、どう伝衛門に謝ったものか頭を悩ましていた。
「伝衛門様、私が東経先生に説明をしてしまいました、申し訳ありません」
そう茸酔がいったのだが、伝衛門は「いや、わしからもあの洞窟のことは東経先生に相談するつもりじゃった」と軽くいなした。
「金を吸った茸は体によいと、江戸の偉い連中に宣伝して差し上げよう、決して採れる場所は言わんでほしい」
「はい、決して外には漏らしません、実は我が屋敷の池に金の石を砕いて沈め、砂金茸をはやし、体の生気を養う薬茸として売るつもりです」
「それで東経先生は貧乏人をただで見てやるご所存でござろう」
「はい、おっしゃるとおりです」
「これは美味い」
伝衛門は焼いた舞茸を箸で摘まんだ。
「どうぞ箸を進めてくだされ」
茸酔と東経も舞茸の煮しめをたべた。とてもうまい舞茸である。
「実は茸酔殿が砂金茸を見つけたとき、この茸を金山にはやすと、人間の代わりに茸が金を吸い上げてくれるのではないかと考えた、金山には掘ったが、金の多い石が出てこなかったので放棄された穴がいくつもある。儂ならば奉行に言って、その穴を東経殿が薬になる茸を栽培することを頼める、穴は水も滲み出すし茸をつくるにはよいのではないだろうか」
東経もうなずいた。
「それはすばらしい考え、そのようなことができるのなら、それに越したことにありません」
茸酔も伝衛門の知恵の回るのにはおどろいた。
こうして、使われなかった金の採掘の穴で、砂金茸を栽培することになったのである。それに試しに食べてみたところ、なかなか味の良い茸であることもわかった。
茸はぽつぽつと生えた。冬の寒い時期に雪に覆われても、廃抗の中は暖かかった。砂金茸は増えてくれた。
茸酔の絵も冬の間にほぼ完成した。
東経は絵と原稿を越後の本屋に渡し、次の秋には本がでることになった。
春になると、茸酔は乾燥した砂金茸を持って帰途についた。途中で馬を使ったこともあり、行きと違って半月ほどで江戸に戻った。
虎酔師匠は随分弱っていたが、茸酔が戻ってくると喜んで、キノを酒屋に走らせ、ウナギを焼かせた。
「師匠、私が見つけた茸を持って帰りました」
紙に包んだ干した砂金茸を師匠の前に置いた。
「この茸はからだにいいのかい」
「はい、食べることのできる茸だとわかりましたが、それより師匠、茸の傘をとってみてください」
言われた通りに虎酔が茸を一つ手にとり、萎びた傘をちぎると、さらさらと金の粉が紙の上に落ちた。
「お、金か」
「はい、これで虎の目を光らせてください」
虎酔が潤んだ眼で茸酔をみた。
「嬉しいことよの」
虎酔は茸の傘を皆ちぎり、金を皿に集めると膠にとき、虎の目にまぶした。絵の虎は眼光まぶしく獲物をねらう顔になった。
「出来たのう、茸酔」
虎酔は声が詰まってそれしか言えなかった。
それから一月後、虎酔は天昇した、齢六十六であった。
東経先生の本は秋になって出来上がり、茸酔に届けられた。絵師、円山茸酔とある。最後には茸酔の描いた東経先生と巌さんの姿があった。すでに国中で引っ張りだこという東経の手紙が添えられていた。
伝衛門からも書状が届いた、廃坑の砂金茸は増え、よく売れているということであった。
二人がいる間に佐渡にはもう一度行ってみよう、茸酔はなつかしく思い出している。
砂金茸


