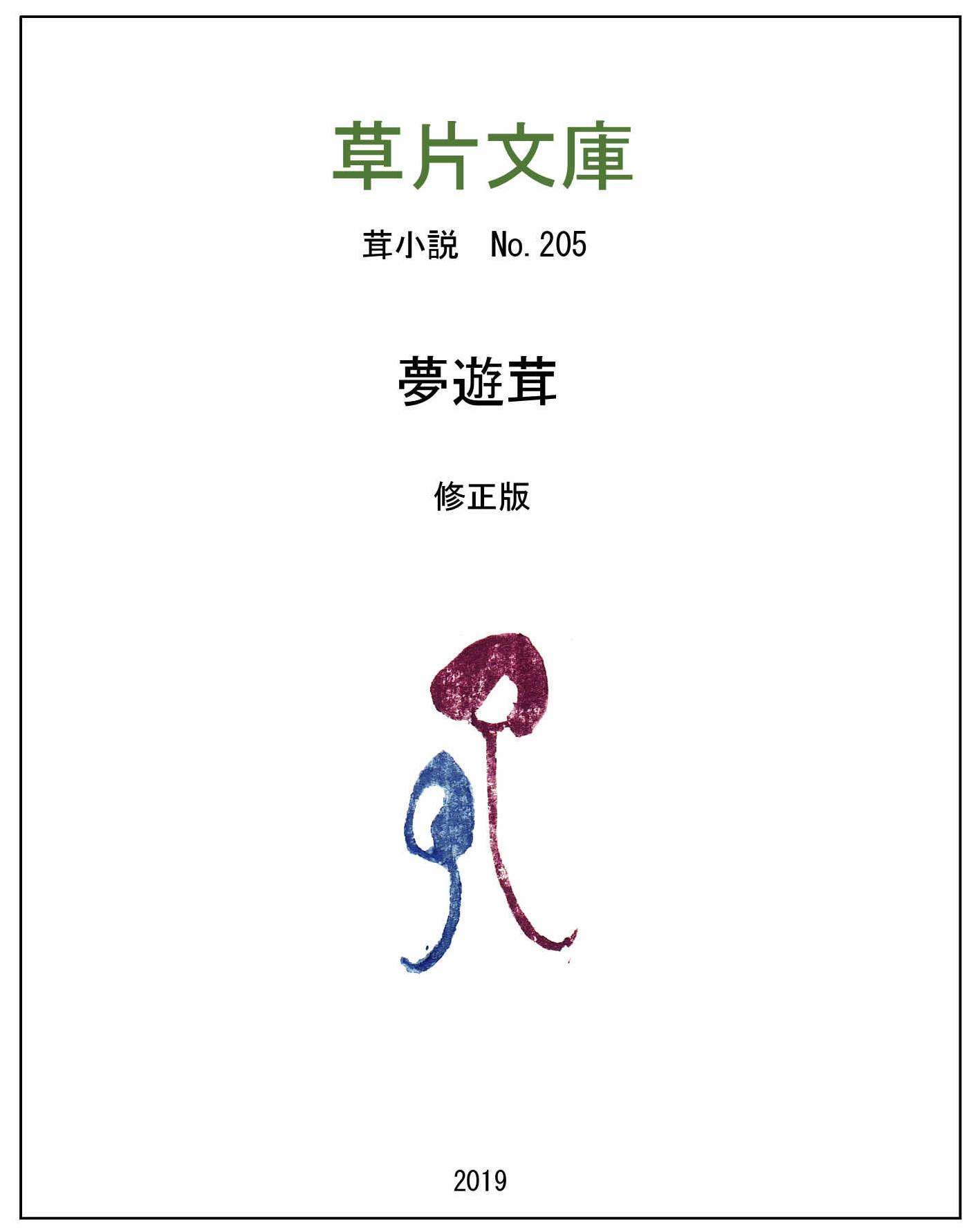
夢遊茸
茸の絵師「茸酔、じすい」のお話1 縦書きでお読みください。
茸酔 プロローグ
江戸に茸酔という茸の絵師がいた。茸酔は茸狂(じきょう)と呼ばれたほど茸好き。江戸随一の茸絵師である。茸酔帖という魔苛不思議な茸たちの出会いの書も残した。
茸酔は江戸のはずれ、内藤新宿の旅籠屋の次男坊で、名前は二助であった。子供の頃から兄の伊助、二人の姉のアキとキクとともに、飯炊きや部屋の掃除、洗濯の手伝いをして両親を助けていた。その旅籠屋「井草」はなぜか絵描や歌詠み、それに学者が使う宿であった。おそらく宿賃がほどほどであり、飯もそれなりのもので、宿の前に小さなせせらぎがあり、絵になるばかりではなく、落ち着く場所だったためであろう。
二助は宿に泊まる絵師が小川の土手で絵筆を走らせているのをよく見ていた。小川には翡翠(かわせみ)の姿がよく見られる。二助は青く輝く羽を持った翡翠が好きだった。絵師が筆をささっと走らせ、一気に翡翠を描くのを見たとき、二助は大きくなったら自分も描いてみたいと思ったという。
宿には行商人もよく泊まった。信州からくる熊蔵は茸や熊の胃、毛皮などを江戸に持ってきて売りさばき、江戸のものを買って帰り、信州で売るという商売をやっていた。井草でも熊蔵から茸や熊の胃を買っていた。
ある時、熊蔵が荷物の中から両手で抱えるほど大きな茸をとりだした。
「舞茸だ、昨日の夜採ってきたので新しいぞ」
夜通し歩いて、昼過ぎに宿に着いたのである。
「お、こりゃみごとだ、うちにおいてっておくれ」
熊蔵は二助の母、クサに舞茸の調理法を教えた。
「味噌汁、澄まし汁、煮ものもいい、うめえ出汁のある茸だ、舞茸飯もいいな、天ぷらときちゃあこんなうめえ茸のないぜ」
「焼くのはどうかね」
「松茸みてえにか」
「ああ」
「もちろんうめえさ、松茸のように匂わんけどな」
二助はその様子を見ていたのだが、食うより、その茸がとてもきれいに見えた。
熊蔵から買われた舞茸が土間の竈の脇におかれていた。それに気付いた二助は帳場の筆と墨を持ち出して、破れて捨てられていたふすま紙に舞茸を画いた。
そこへ水が欲しいと一人の絵師がやってきた。絵師はこどもがなにやら一心に描いているのをのぞきこんだ。
「ぼうず、いくつだ」と尋ねた。
二助は八つと答えたところ、「うまいぞ、もっと描いてみろ」と絵師は部屋に紙をとりに帰り、半紙を二助に渡した。二助はその紙に舞茸を描いた。
「うまいものだな、頭の中に見えたとおりにかいておる、茸が元気だ、わしも子供にかえらねば」
そこにクサと姉たちが夕飯の準備にやってきた。
「おや、お客さま、なにかご用でしたか」
「いや、筆のために水をもらいにきたのだが、坊主がずいぶん上手い絵を描いておった」
「二助がですか」
「二助というのか、絵は誰ぞに教わったのか」
「いえ、絵師の方が川縁で絵を描いておられますのをよく見ていますが、絵を画くのは今がはじめだと思います」
「家の者で絵を描く者はおるのか」
「いえ、主人の井造は筆が達者でございますが絵はどうでございますか、私どもも不調法で」
「ほう、そうか、わしの父は絵師でな、跡継ぎだといわれておるが、父の力量の半分もなくての、子供の頃から父と同じ絵描きになると思っていたことが災いしている、二助のように頭から自然にわき出るように画けぬ」
二助は自分がほめられているようでなぜか嬉しかった。
「水はすぐに部屋の方にお持ちします、お客様どの部屋でございますか」
「楓じゃ」
「ああ、円山様でございまね、京都からいらした」
「そうじゃ」
「でも、なぜ、江戸のはずれにお泊りなのでございます」
「明後日、信州にまいる、ここで連れが来るのをまっておる」
「そうでございますか、今日は舞茸ご飯にいたします」
「ほう、それは豪勢な、二助ちょっと部屋においで」
絵師はそう言うと、二助に手招きをした。
二助が後をついて部屋にはいると、絵師は硯箱のふたを開け、筆を三本とりだした。
「これは長く使っておった筆で、捨てようと思ったが、二助にやろう、まだまだ使えなくはない、これでいろいろなものを描いてみるとよいぞ」
そう言うと絵師は筆を二助に渡し、さらに、
「これは、先ほどそこの川で描いたものだ、記念にやろう」
描いたばかりの絵をみせた。絵には青い桔梗と赤い茸が描かれていた。
「桔梗のそばにこの茸が生えておってな、いつもは描かぬのだが、あまりにもきれいなので描いてみた、できはよくないが、楽しめたものだ」
この絵師は円山応挙の長男、円山応瑞であった。父親の応挙があまりにも偉大であることから、いつも陰になってはいたが、やはり超一流の画家である。もらった絵は子供の目から見て、あまりにもきれいなものであった。
それからというもの、二助は筆をもって、河原に行くと、長い時間飽きず、草や虫や鳥を描くようになった。時々茸を見かけて描いた。石ころでもおもしろいかたちだとおもうと描いた。あの絵師にもらった絵のように、いつか色をつけて描いてみたいと思っていた。
そのようなことがあって二年経ち、二助も十になった。長男の伊助と同じように、武家屋敷に奉公することになった。井草屋は知り合いの口入屋をかいし、子供たちを武家の家に奉公にやる。長男の伊助は十の時に江戸の信州の殿様の武家屋敷で三年働いてもどってきた。娘たちはもう少し大きくなったら、どこぞに見習い奉公にだすつもりである。
二助の奉公先は加賀の武家屋敷であった。二助の小さな荷物の中には絵師にもらった筆と親にねだってもらった古い墨と硯があった。
小者になった二助は広い屋敷の拭き掃除、飯炊き、庭掃き、なんでもやった。
一年も経つと仕事にもなれ、働く合間に絵を描いたりする時間がとれるようになった。二助は庭に生えている草を絵に描いた。
加賀の屋敷の中はとてもきれいだった。襖には豪華な絵が画かれており、置いてある焼き物などは目を見張るように美しい物ばかりであった。その当時ご法度だったことから、金は使っていないにもかかわらずきらびやかだった。そういった絵の修復のために屋敷には絵師たちがよく出入りしていた。
庭に出てきた絵師の一人が、二助が庭でなにやらしているのに気付いた。
まだ十そこいらの子供が墨で一心不乱に絵を描いている。のぞきこむと、これまた絵師顔負けの趣のある絵である。
「おい、小僧、上手いものだな」
二助はしかられるかと思って立ち上がると絵を後ろに隠した。
「大丈夫だ、ちょっと見せてみろ」
二助は描きかけの春蘭の絵を見せた。
「誰かにならったのか」
二助は首を横に振った。
絵師は二助のもっていた絵筆を見た。
「この筆はどうした」
絵師の顔が怖かったのだろうか、二助の顔がこわばった。
「どうした」
絵師がまた聞いた。二助は自分の家の旅篭に泊まった絵師からもらったことを言った。
「名前を覚えているか」
二助は首を横に振った。
二助に声をかけた男は深川に住んでいる「虎酔」と呼ばれる五十になる絵師だった。絵の腕は誰もが認めていたが、仕事をしているところをあまりみない。好きで虎の絵は描くがそれ以外のものは描かないという。ただ加賀の屋敷の仕事は引き受けていた。理由はわからないが、虎酔が加賀の生まれのためではないかと噂されていた。
男には二助のもらった絵筆が、そこいらの絵師では持つことができないようなものであることがわかったのである。
「ぼうず、わしのところに来ないか」
二助には意味がわからなかった。
「絵を描かせてやる」
その言葉も二助には理解できなかった。
「まあ、いい、あとで屋敷の者が言ってきたら考えろ」
初老の絵師は仕事に戻っていった。
その夜、仕事が終わり、奉公部屋に戻っていると中間の男が入ってきた。
「二助はだれだ」
小者部屋には五人が生活していた。一番年下の二助ははいと答えた。
「おまえか、ちょっときてくれ」
二助は女中頭のところに連れて行かれた。
「二助、お前、虎酔先生に家にこないかと言われただろう」
二助はうなずいた。
「その気はあるのかい」
まさか本当に言われるとは思わなかった二助は、まともに考えてはいなかった。だけど絵が描けるのは嬉しい。
「お父とお母がどういうか分かりません」
「いいと言ったら行くかい」
二助はちょっと戸惑ったが頷いた。
「なにをさせられるか知っているのかい」
「絵を描かせてくれるそうです」
「あの先生、嘘は言わないよ、だけど、買い物、家の掃除から食事の支度もしなければならないよ、ここより大変だよ」
「今と同じです」
「確かにね、それじゃ、おまえの家の方に使いをやって、きいてみようかね」
それから数日後、女中頭から話を聞いた。
「いいと言うことだよ、お前の兄さん、よくやっているということだよ、それにおまえの姉が嫁に行くそうだが、その婿さんがおまえのところの宿も手伝ってくれるそうだ、男手が増えるので、自分の好きなことをしていいということだよ、よかったじゃないか、祝言をあげるときには戻ってくるようにということだが、それは虎酔先生にいっとくよ」
いい武家屋敷に奉公したものである。姉のアキは武家屋敷に奉公するつもりだったが、雑司ケ谷の大きな宿屋の次男坊との見合いが整い、しかも井草の手伝いをすることになったということだった。
二助はそれから半年ほど加賀の屋敷に奉公したあと、虎酔の住み込み弟子となった。二助、十二の時である。
虎酔の家は深川にあった。虎酔はほとんど仕事をせず、虎の絵を頼まれたときだけ、熱心に絵を描くことに励んだ。いつもはというと、庭に来る野良猫、虎と呼んでいたが、その猫の姿を絵にしたり、たまに気が向くと庭にきた狸に餌をやって、慣れてくると、絵筆をとった。紙に描かれた狸は今にもかみつきそうなのもいれば、懸命に餌を食べているものもいた。二助はその絵は生きているみたいだと思った。虎酔は花を描くこともある。それはもうすぐしぼみそうな朝顔だったり、黒く細かい種がこぼれおちそうな松葉ボタンだったりした。どれもみな風にゆられていた。二助にはそう見えた。
加賀の屋敷で言われたこととは違い、二助の雑用は少なかった。掃除、洗濯、飯炊き、水くみくらいで、食事の用意は毎回虎酔がくれる小銭を持って豆腐を買ってきたり、漬け物を買ってきたり、焼き魚を買ってきて食べた。ただ、味噌汁だけは二助に上手に作れと言って、上等な味噌を買ってこさせた。
二助はどこからお金が出てくるのかと不思議に思っていた。しかし、絵を描く時間ができたことは嬉しかった。しかも虎酔はこれを使えと、自分が使っていた墨や絵の具を渡してくれた。だが筆は貸してもらえなかった。
虎酔は「おまえの持っている筆の方が数段に上等だ、俺のを使っても上手くならん」と言った。二助にその意味はまだわからなかった。
二助は練習用ではあるが、紙をふんだんに使うことができた。時間があるときは虎酔のように草や虫を描いた。
虎酔は二助が描いているとき、覗き込んだりすることはあるが、なにを言うでもなかった。
そんなある日、虎酔に茶を持っていった二助に、珍しくこんなことを言った。
「二助、俺が描いているものと同じものばかり描いているが、他の物を描いてみろ」
自分の描きたいものを探せということだったのだろうが、二助はそうとらなかった。虎酔と違ったものを描けと命令されたと理解した。真似をしていたわけではなく二助も草や虫や獣、生き物が好きだったのである。それはともかく、師匠の言葉はいいきっかけになった。
まじめな二助は、いわれたとおり家の中のものを描くようにした。火鉢や団扇、茶碗、皿、土間では薬缶、鍋釜、しかし虎酔はそれを見ても何もいわなかった。家の中のものは何度も描いた。ときどき土間に現れる蜘蛛やカマドウマなども描いた。
梅雨のある日、土間におり、また柄杓を描こうと思って水瓶の脇にいくと、塗り壁の崩れたところから黄色い茸が二つ生えていた。とても新鮮に見えた。
壁から生えている茸の絵を一気に描いた。黄色い色もつけてみた。
描き終わったとき、虎酔が水をとりに土間におりてきた。
虎酔が二助の茸の絵を見た。立ち止まったまま動かない。
「よく描けている」
そう言われて、嬉しかったのはもちろんだが、筆をくれた絵師のことを思い出した。あの時、絵師が筆と一緒に本人が桔梗と赤い茸を描いた絵をくれた。奉公に出るとき小さく畳んで手籠にしまった。今も入ったままだ。
「お師匠さま」
「なんだ」
「筆をくれた絵師の人が描いた絵を持っています」
「ほう、なにを描いた絵だ」
「桔梗と茸です」
「珍しい取り合わせだな」
「うちの宿の近くの川岸に桔梗がたくさん咲きます、茸がたまたま生えていたようです」
「みせてくれ」
虎酔は二助が自分の部屋として使っている納戸についてきた。
二助は自分の荷物の中から手籠を引っ張り出すと、黄色っぽくなった、折り畳まれた紙を取り出し、虎酔にわたした。
虎酔はいい紙だと言いながら広げると驚きを露わにした。
「応瑞だ」
「ご存知ですか」
「わしと一緒に絵を学んだ、円山応瑞という名の絵師だ、わしはその父親の応挙の弟子だったことがあった」
虎酔はそれ以上のことは言わなかった。後で二助が知ったことだが。師匠は加賀から京都に絵の修行に出かけ、円山応挙の弟子になった。初めは応挙の絵をまねたが、いつしか虎に魅せられた。虎ばかり描くようになった。虎の奔放な絵を描くことから、虎酔と呼ばれるようになり、一部の者からは支持されたが、端正な応挙とは一線を隔すことから、なかなか認めてもらえなかった。それでも虎酔は円山応虎を名乗ることをいったんは許された。しかし名前をもらわず自分から離れ、京都から江戸に渡ってきたのである。
虎酔は「おまえのもらった筆はわしでももてぬほどよいもの、応瑞なら使っていても不思議はない、それにその絵、手本にするがよい、応瑞もおまえの力がわかったようだ、もらったその絵はわしが一幅の軸にしてやろう、一生の宝になる、預けぬか」
二助はよくわからずにうなずいてその絵を渡した。その後、それは立派な掛け軸になり、二助に渡された。
「茸が好きか」
「はい」
「江戸の茸を描いて見ろ」
そう言われて、二助は好んで茸の絵を描くようになった。町の中を歩くと思わぬところに茸が生えている。虎酔の手伝いの合間に、近くの長屋に入れてもらって、生えている小さな茸を描いた。ちょっと長く時間がとれるときは武家屋敷を歩いた。草地に生えていた赤い茸が応瑞の描いたものと同じだった。紅茸である。それを熱心に画いた。しかし、家に戻り応瑞の紅茸を見ると、自分の描いたものとは全く違っていた。応瑞の茸は今にも胞子を散らしそうである。
長屋では子供たちがよってきて、二助の描く茸の絵を喜んだ。二助は本物とは違った色をつけて子供たちに配ったりした。武家屋敷あたりでも、二助の茸絵が知られるようになり、茸が生えていると呼び止められ、庭の中に入れてくれて、描くように勧めてくれるようになった。
岡っ引きたちの間でも二助のことは知られるようになり、顔見知りになった岡っ引きが、向こうの地蔵の脇に、こんな茸が生えてたぜ、と教えてくれもした。
ある時、二助が武家屋敷を歩いていると、悲鳴が聞こえ、飛んでいくと若い女性が男につかまっていた。物取りのようである。二助が行くと男はあわてて逃げたが、二助が襲った男の顔をすぐさま絵にして駆けつけた岡っ引きに渡した。それが元でその男がお縄になったのである。物取りではなく思慕による誘拐のようであった。そんなことから番所に頼まれ、似顔絵も描くようになった。
虎酔に仕えて五年、茸酔十七の頃である。虎酔が加賀屋敷の襖の修復に呼ばれ、二助も手伝うことになった。昔奉公にいたときの女中や中間もまだ働いていた。
「二助も虎酔さんの手伝いができるようになったんだね、たいしたもんだ」
と言ってくれた。
「まだ、まともには描けません」
そうは言ったが嬉しくないはずはない。
そのとき初めて、虎酔は襖のあまり目立たないところの修復を二助にさせた。
「よくできた」
虎酔にほめられたのが一番嬉しかった。
それからは師匠の絵の手伝いもたびたびするようになった。
ある日、師匠に言われ、茶を二つもって部屋に行くと、恰幅のいい老人が一緒にいた。
二助は茶を客人の前に置いた。
「二助だ」
客人に紹介された。
頭を下げると、虎酔が「座れ」とうながした。
「この男は加賀の医師でな、秋鸞という、わしの幼なじみじゃ、こいつがな」
と話そうとしたところ、
「おれが話すよ」と秋鸞が遮った。
「実はな、俺の作り出した茸の薬のことを、書としてしたためようと思っておる、山に行って薬になりそうな茸をとってきて、新しい薬を作っておる、もう八十ほどの薬がある、風薬、眼の薬、精力の薬、心の臓、肝に効く薬、様々じゃ。採ってきた茸は干したものを絵にしてあるのだが、なにせわしは絵が苦手じゃ、それで誰かに生のままの茸の絵を頼もうと虎酔に相談したんじゃ、そうしたら、弟子に茸の好きな男がいるというじゃないか、それじゃ、その男に絵をたのめんかと思って今日きたわけだ、二助さんどうじゃろう」
いきなりの話に二助は面食らった。自分でいいのだろうかと師匠の顔を見た。師匠はいつもと変わらない顔をしている。自分で判断しろということだろう。
「私でいいんでしょうか」
ここで虎酔が口を開いた。
「おまえの茸の絵を持ってきて見せなさい」
二助は書きためた茸の絵を持ってきた。色つきの茸の絵の下には、日付、描いた場所、状態が描かれている。江戸の茸帖である。
それを見た秋鸞はうなった。
「見事だ、これだけでも本になる、是非頼みたい」
二助はまた虎酔をみた。今度は虎酔がうなずいた。二助は両手を畳について頭を下げた。
「私ごときでよければ」
「たのみますぞ」
二助は加賀屋敷の隣にある秋鸞の療養所に出入りするようになった。
秋鸞の指示のもとに茸の絵を描き、またその茸が生えて様子を描くためいろいろな山にまで出かけた。遠くは信州近くまでも行った。その途中で、自分の生まれた宿、「井草」にも客として泊まった。
両親や兄弟は絵師の仲間入りをした二助を喜んだ。二助は宿の襖や屏風に茸の絵を描いた。宿屋、井草の茸の絵は評判になり、宿の繁盛にも貢献した。
二助は秋鸞のもとで茸を描いているときに、秋鸞の幼なじみだったという虎酔の生い立ちを聞くこととなった。それで虎酔が加賀の身分の高いお侍の外の子であることを知り、京都の円山応挙に弟子入りしたいきさつも知ったわけである。応挙に虎の図を描くようにいわれ、虎酔は虎の毛皮から勇猛な虎を書いた。それに至るまで狂ったように虎を追い求め、何枚も虎の図を描き、最後には酔うようにして虎の図を作りあげたそうである。それは応挙の名で世にでた。虎酔と呼ばれたのにはそのような背景もあった。
こうして師匠が虎酔と呼ばれるわけと江戸の加賀の屋敷のお抱え絵師であることの理由がわかった。
二年の歳月をかけて、秋鸞の薬茸草子はできあがった。そのとき虎酔は二助に茸酔(じすい)という名を与えたのである。
二助は茸を真っ正面ばかりではなく、後ろや斜めからも眺めすがめつしながら酔ったように観察していた様子から、二助にその名前を考えたようである。
茸酔と名を変えた二助は、それから七十年にわたり茸の絵を描き続けた。特に江戸の隅々まで歩き回り、江戸の茸図譜はその当時流行はじめた浮世絵と同じように、江戸の人々に好かれたという。茸酔はおもしろい茸を見つけると狂ったように喜んだ。そんなことから江戸の人たちには茸酔を茸狂とも呼んだという。
茸酔という名になって、しばらくたったときである。円山一門の者が江戸で売られていた茸酔の茸の絵を持って京都に帰ったところ、円山応瑞の目に止まり、茸酔に会いたいとの手紙が茸酔のもとにとどいた。京に行ったことのなかった茸酔は喜んで旅をした。しかも、あの井草の宿で筆をくれた人からの誘いである。
京都の宿に落ち着き、応瑞と話をすると、応瑞は茸酔が宿屋井草で筆を与えた子供であったことを知り、しかもあの虎酔の唯一の弟子と知った時には驚くほど喜んで、円山の名を与えられた。それからは円山茸酔となったが、茸酔自身はあまりにも恐れ多いと、まるやまとは名のらず、自からはえんざんと呼ぶようにしていたということである。
江戸に帰り、その名をもらったとことを虎酔に告げると、六十を越していた虎酔は涙をうかべて喜んだということである。茸酔二十三のときのことであった。
茸酔は九十をすぎるまで茸の絵を描き続け、茸にまつわる出来事を集めた文も書くようになり、草子もたくさんだした。生涯嫁をとらなかったことから、茸酔が亡くなったあと、終生手助けをした姪の木野に遺品は渡された。茸酔は不思議な茸の話をずいぶん書いた。未刊の下書きもたくさんあった。木野はそれをまとめて茸酔帖として年ごとに整理した。その中から、特に奇妙な茸のことが書かれているものを選び書肆、蔦屋にみせた。蔦屋はぜひ本にしたいと言った。
茸酔帖は「わたし」で書かれていたが、版元は「わたし」を「茸酔」と直し、「茸の絵師」という草子に仕立てたのである。
夢遊茸
虎酔師匠の家からしばらく歩いたところに一つの長屋があった。松笠長屋である。その入り口には大きな赤松が植えられている。なぜ赤松なのかわけがある。長屋の大家であり家主の治兵衛が大の松茸好きで、秋になると、江戸からちょっと離れてはいるが山に行って松茸をとってきて味を楽しんでいた。しかし江戸市中で松茸はほとんどとれない。赤松があったにしても松茸がはえたところを見たことはなかった。
凝り性な治兵衛は、身近に松茸を生やしてみたいと考え、大きな赤松の木を八王子の植木屋に運ばせた。植えて十年、赤松は立派に根付いたが、松茸が生える様子がなかった。長屋の入り口にはただ松笠だけがころころところがっていた。それで誰からとなく松笠長屋と呼ぶようになってしまった。
松茸こそ生えなかったが赤松の根元にはあやしげな茸が生えることはあった。その年は黄色かかった白っぽい見たこともない茸が生えた。だが数日で枯れてしまう。
形が面白い。茸酔と名のるようになったばかりの二助は、毎朝松笠長屋に出かけていって茸の絵を描いた。
傘は饅頭型ではなく、よじれていたり、二つに丸まったような形をしていたり、それは奇妙な茸である。高さは両手の指を重ねたほどだから三寸ほどだろうか、面白いことにどれも形が違った。
そのころになると茸酔も茸の図譜をもっていたが、その茸は載っていなかった。似ているのに登竜というのがあった。それも頭の部分はいろいろな形をしているようだが、松笠長屋の茸はもっと大きい。登竜の仲間かもしれないが、まだ名前のない茸のようだ。
毎朝通ったことからかなりの数の絵がたまったとき、この茸は最後はどうなるのか見てみたいと思った。
茸酔は師匠の食事の用意をし、握り飯をもって、暮れ六に松笠長屋に行った。秋半ばになる。薄暗くなってきた時間である。朝生えていた茸がしぼんでいくところだった。握り飯を食いながら、その様子を絵にした。
その茸が縮んでいく様はかなり変わっていた。柄の根本がとろけて短くなっていく、まるで茸が土の中に沈み込むように見える。最後には奇妙な形をした傘の部分が土に触れ、とろりと溶け出すと、土の中に吸いこまれていった。松がすべてを吸い尽くすようにである。
それではこの茸はいつ生えてくるのだろうか。そう思った茸酔は夜中におきあがると、提灯に明かりをいれて松笠長屋に行った。
松の木の根元で待つこと一時、夜の五つ頃だろう、松のうねった根の端から白く小さな粒がでてきた。筆を持って紙に向かったときにはぐんぐん大きくなった。四半時もすると凸凹の傘をもった茸になった。
しばらく経ち、これ以上は伸びないだろうと思ったときである。茸が松の根から離れ、ぴょこぴょこと跳ねながら動き始めた。茸が動くわけはない。茸の中に何かいるのだろうと思った茸酔は、茸がどうなるのか見届けるためついて行った。茸は松笠長屋の中に入っていく。木戸が閉まっているので茸酔は中に入れない。外から見ていると、茸は長屋の中を飛び跳ねるように進むと端までいって戻ってきた。
長屋の木戸から出てくると、今度は道の端を滑るように動いて、一軒の大きな武家の屋敷に入ってしまった。少し待っていたが庭からなかなか出てこない。眠くなってきた茸酔は家に戻ることにした。虎酔師匠が寝ている。そうっと自分の部屋にはいった。
朝日が差してきたとき、眠い目を無理やりに開けると、師匠の朝食を用意して松笠長屋に行った。松の木の根本には昨夜生えた茸が崩れていくところだった。
やっぱり動いたわけじゃない。夜中に無理をして起きて、眠い目でみていたから動いたように見えたのだろう。狸にでも騙されたのかもしれん、と思い家にもどった。
朝餉を食べていた虎酔がどこに行っていたのかと尋ねた。
昨日の夜のことを話すと師匠は嬉しそうに笑った。
「さすが茸に酔っぱらう絵描きだ」
師匠におちょくられたと思った茸酔は「すみません」と謝った。
「何で謝るのだ、おまえは自分を信じろ」
そう言われた。
「はい、明日確認してみます、朝餉がおくれるかもしれません」
「ああ、かまわんとも」
昨夜と同じころ、茸酔は画帳をもって、松の木のところに行った。しばらく見ていると提灯の明かりの下で、新しい茸が生えてきた。薄黄色の頭をもたげ、一時もすると大人の茸になった。
絵を描こうと筆をとったとき、また茸が根っこから飛び出した。大きくなった茸はそのままゆるゆると動いて道の脇を進んで行った。
茸酔が見送ると、やがて茸が角を曲がって見えなくなった。
茸が動いていたのは間違いではない。生えたはずの茸は松の根元にはない。自分の目をこすった。やっぱりいない。
松の木の脇に腰をおろした。
かなりの時間が経った。眠くもなってきたし、自信も揺らぎ始めたとき、道の端をちょこちょこ動く白っぽいものが見えてきた。目を凝らしていると目の前に現れたのはあの茸だった。どこかに行って帰ってきたのだ。
茸は茸酔の目の前で、松の木の根本の自分が生えたところに立った。
目の錯覚ではない。茸はもう動かない。茸酔はようやく腰を上げ家にもどた。
それから寝たにもかかわらず、いつもの時間に目が覚めた。茸酔が朝食の支度をしていると虎酔師匠が起きてきた。
「お、なんだ、いつもの通りじゃないか」
「はい、目が覚めました、師匠、松の木の下に生えた茸は確かに動いてどこかに行き、朝の暗いうちに戻ってきました」
「ほー、そんな茸があるのだな、その茸は何という名前だ」
「茸の図譜にはありませんでした」
「ではおまえが名前を付ければよいではないか」
「はい、もっとよく見てから付けることにします」
その夜も松の木のところで待つと茸が生えてきた。大人になった茸は、いままでと同じように、松の根から離れると道の端を動き始めた。茸酔は追いかけ、その茸をつまみ上げようとした。指が茸に触れたとたん、茸は人で言うと、はっとしたような面持ちで立ち止まり、慌てて松の根本に戻った。それからはまったく動かなくなってしまった。
次の夜にも同じようなことが起きた。動き出した茸に触れると松の木に戻った。
この茸は生えてしばらくすると動きだし、触ると気がついて元に戻る。
そのおかしな様子を虎酔師匠に話すと、
「茸は立っているばかりでは疲れるものなのかな」
とまじめな顔で聞くので、茸酔は、
「きっと、茸も草木も生えてきたときは動きたいのかもしれません」と答えた。
「そうであろうな、子供は良く動くものよの、そしてよく眠る」
「茸も寝るものでしょうか」
「寝る子は育つだ、よく遊んでよく寝るのが子供のしごとだ」
虎酔師匠が言わんとすることはわからないでもないが、顔を出した茸が動くなど信じられない。それを察した師匠が言った。
「寝ているときに歩き出す病があるのを知っておるか」
「知りません」
「わしは一度かかったことがある、師匠の代わりに絵を描いていたときだ、これはわしには大変な仕事だった、それをやり遂げたとき、丸一日寝ておった。そのときからしばらくの間、寝ていると起き出してなにやら絵を描いていたそうだ、それは弟子の仲間が見ていたことで、わしはなにも知らなかった、寝ているのに体が勝手に動くのじゃ、夢遊病とかいうものだそうだ、しかしいつの間にか治っておった」
「茸が夢遊病になっていたとおっしゃるのですか」
「そうじゃ、生えてきて、ぐっすり寝ていた茸が夢遊病で動きだしたんじゃ」
「夢遊茸でございますね」
「よい名前が付いたじゃないか」
その茸は茸酔が夢遊茸と名付けたことになってしまった。
確かにその茸は松の木から生えてきて、しばらくすると動き出す。しかし触ると目が覚めたように慌てて松の木にもどった。
夢遊茸がどこまで行くのか後をついていったことがある。茸たちはかなり遠くまで行く。ある茸は深川の土手を歩いて戻ったり、ある茸は武家屋敷の方までいって戻ってきたりした。神社の境内の中をぐるぐる回る茸もいた。
茸酔も夜中に茸を追いかけるのがだんだん疲れてきた。しばらくして夢遊茸を追いかけるのをやめたが夢遊茸の絵はたくさんたまった。
茸酔は夢遊茸を追うのを止めた後は、別の茸の絵を書き始めた。近くの神社や寺、それに林にいくといろいろな茸が生えている。彼の今まで続けてきた日課である。
秋ももうすぐ終わりという頃、夜になると奇妙な思いをした。夢を見たという記憶もなく、朝気持ちよく目覚めたのであるが、枕元に茸がおいてあった。そのころ茸酔は茸の名前をずいぶん覚えていた。枕元にあったのは、猪口であったり、紅茸であったり、さまざまであった。どれも林の中で描いたことのある茸たちである。
誰が枕元に置いたのであろうか。虎酔師匠だろうか。虎酔師匠は酒を飲んで寝てしまうとちょっとやそっとでは目が覚めない。おそらく違うだろうが聞いてみた。
「師匠、ここ三日ほど枕元に茸がおいてあります、もしや、師匠がおいたのではないでしょうか」
「わしは茸を採ることはない」
確かに師匠は茸を食べることは好きだが、自分から採りに行ったりしない。
「なぜ枕元に茸があるのか、全く心当たりがありません」
「その茸がみな夢遊病になったのであろう、林からおまえの枕元に歩いてきおったんだ、お前が茸の絵を描いているから慕われたのだ」
そう言われて松笠長屋の夢遊茸のことを思い出した。だがほかの茸も夢遊病になるものなのだろうか。
「この茸が夢遊病になるかどうか、今日の夜、林に行って見てみます」
「どのような茸も夢遊病になるなら、松茸あたりが夢遊病になって、おまえの枕元にくるとよいなあ、食ってやる」
虎酔師匠は笑った。
その日の夜、屋敷から少し離れてはいるが、茸がよく生える林に画帳をもって行った。林の中は真っ暗で、提灯を持っているとはいえ何か気味が悪い。林の一角にいつも紅茸の生える草原があった。紅茸は白い卵から生えてくる。今で言う卵茸のことである。
赤い顔をのぞかせた子供や、傘が饅頭型で大人になっていないものなど、様々な大きさの紅茸があった。
朝まで見ていたが、その茸たちは動こうとはしなかった。やはり夢遊病になるのは松笠長屋の茸だけのようである。それではなぜ茸が枕元においてあるのか。
その夜、寝たふりをして床に入っていた、しかし朝になってみたら椎茸が一つおいてあった。
「昨日寝たふりをしておりましたら、いつのまにか椎茸がおいてありました」
「おお、食える奴がおいてあったとはいいじゃないか」
「しかし、誰も忍び寄ってきませんでした」
「やはり椎茸が突然飛んできたか、それともだ、いいか、自分が寝ていないということに自信を持てるか」
「ええ」
「それは自信を持ってはいけないことなのだ、寝てないと思っても寝ていて、その間に誰かがもってきたかもしれんぞ」
「いえ、目をつむってはいましたが、起きておりました」
「知っておるか、年寄りは眠れん眠れんと言いおるが、傍で寝ていた家族の者は年寄りが寝息を立てているのを聞いておるもんよ」
「そういうものでございますか」
茸酔は納得がいかなかった。その日から毎日、平茸、滑子、占地、そしてとうとう松茸、その後は黒皮までが枕元にあった。
師匠は「なんと、食べられる茸が茸粋の枕元に現れるとはたいしたものだ、黒皮とはおそれいった」と驚いた。
虎酔は松茸よりもほろ苦い男の茸、黒皮に心酔していたのである。
「だがますます不思議でございます」
「たしかにな、それで、おまえの草履を見たら松葉がついておる、松茸や黒皮の生える場所に行ったのではないか」
松茸と黒皮は同じようなところに生える。しかしこのあたりで松茸がとれるところは知らない。あっても日野の宿とか八王子にいかなければならないだろう。まして、寝ている私が自分で採ってきたということはない。草履の松の葉は松笠長屋のところのものだろう。
ところが、ある所で奇妙なことを言われた。
師匠にたのまれた薬を買いにでて、松笠長屋の木戸の前を通ったときである。
「おじちゃん、夜になにしてたの」
長屋の入り口で遊んでいた男の子が寄ってきた。木戸を入ってすぐのところの坊主だ。何度か話したことがある。
「なにって」
「昨日の夜、しょんべんしたくて外に行ったら、おじちゃん松の木のとこでなにかしていた」
男の子は夜中におしっこをしに家の外にでたという。以前、夢遊茸の絵を描いていた頃のことだろうと思い、「ああ、松の木に茸が生えてくるのを見ていたんだよ」
と答えた。男の子はふーんという顔で長屋に入っていった。
用事をすませて師匠の家に戻ると、師匠が「咳止めはあったかな」と聞くので、買ってきた薬を渡した。ここのところ喘息持ちの師匠の咳がとまらない。
「ところでな、いま松笠長屋の家主の治兵衛がきてな、変なことを言っていたぞ」
「なんでしょう」
「なんでもな、店子が言うには、茸酔さんが夜中に大きな茸と歩いていて気味が悪いそうだ、あれはなんだと聞いてきたよ」
「少し前、そこで茸が大きくなるのを見ていたからでしょうか」
「いや、今の話じゃ、このごろ毎日だそうだ、あそこの長屋の人が何度もみているそうだ、なんでも大きな奇妙な茸と手をつないで、歩いていって、しばらくすると、戻ってくるそうだ」
「そんな変なことはしておりません、だいたい人と同じ大きさの茸などあるわけがない、しかも茸と手をつなぐなどというのはもっとおかしい、茸に手はないではありませんか、長屋の人が夢遊病にでもなったのではないでしょうか」
「確かにそうだが、茸から手がでていて、仲がよさそうだったとみなそう言っているそうな」
「私はよく寝ておりますが」
「そうだな、だが枕元に茸がおいてあるのはどういうものかな」
「いっこうにわかりません」
「わしが食える茸ならいいといったら、食える茸に変わったな」
「はあ、たしかにそうでございますが」
「まあいい、しばらく様子を見よう」
「はい、私も気をつけています」
その夜のことである。茸酔にとって驚くことがおきた。
寝ているといきなり肩をたたかれたのである。
「茸酔、目を覚ませ」
茸酔が驚いて目を覚ますと、茸酔は道の真ん中にいた。手に万年茸をもっていた。
目の前に虎酔と治兵衛が立っている。隣を見ると大きな茸がいて、茸酔が目を向けると、小さく縮んで、すーっと滑るように行ってしまった。
「私はなにをしてたのでしょう」
なにもわからずに尋ねると、師匠が答えた。
「今日、わしは寝ないでおまえを見張っていた。するとな、夜中に部屋を出てきた。寝たまま歩いていたのだ。そうして松笠長屋の前に行った。わしはそこで家主と待ち合わせをしておった。
おまえさんはの松の木のところに行くと、生えていた夢遊茸に「さー行こう」と声をかけた、するとな夢遊茸はむくむくと大きくなって、おまえと同じほどになると手を伸ばした。おまえは茸の手を取ると、一緒に歩きだした。茸は川の縁に立っていた梅の木のところにおまえを連れて行くと、指さした。霊芝が生えておった。おまえさんはそれを嬉しそうに採ると、また茸と手をつないで戻ってきた、それでわしが長屋の手前で声をかけたというわけだ」
家主も「不思議なことでございますな」と神妙な顔をしている。
「茸酔、おまえは茸が好きになり、茸もお前が好きになり、あの茸の夢遊病がうつったのだ。茸も寝たままお前も寝たまま、夜中を夢遊しておったのだ、毎夜林に行って茸を採ってきて自分の枕元においた。わしが食べられる茸がいいと言ったら、夢遊茸に教わって松茸や黒皮までで採ってきた。師匠思いよのう、今日はほれ見ろ」
虎酔は私の手を指さした。
「それは万年茸、なににでも効く薬じゃ、わしの咳を止めようと採ってきたのだろう、ありがたいことだ、もらっておくぞ」
そう言って茸酔のもっていた霊芝を懐に入れた。茸酔はただただぼーっとしていた。
「家主殿、この不思議なできごとは、みな茸酔が茸に酔いしれていることからでたこと、誰にも迷惑をかけないこと故、長屋の皆にはそう伝えていただけないか」
「はいはい、とてもよいお話でございます、師匠思いのお弟子様をおもちで虎酔さんもお幸せで」
「茸酔、帰るぞ」
三人は歩きだし、松笠長屋の前まできた。松の木の根本には先ほどの夢遊茸が、何事もなかったように立っていた。
茸酔と師匠は家主とわかれて家に戻った。
それから松笠長屋の松の木から夢遊茸が生えなくなるまで、彼の夢遊病は治らなかった。
そんな茸がこの世にあるのである。
夢遊茸はその後、茸酔がだした茸図譜「江戸の茸帖」にあったが、あれ以後誰も見つけることはなかった。
それから何年もたち、虎酔師匠は六十六で世を去った。茸酔は虎酔の養子として加賀のお屋敷から家のあとを継ぐように頼まれた。加賀屋敷の襖絵の補修などを続けるよう言付かったのである。
夢遊茸


