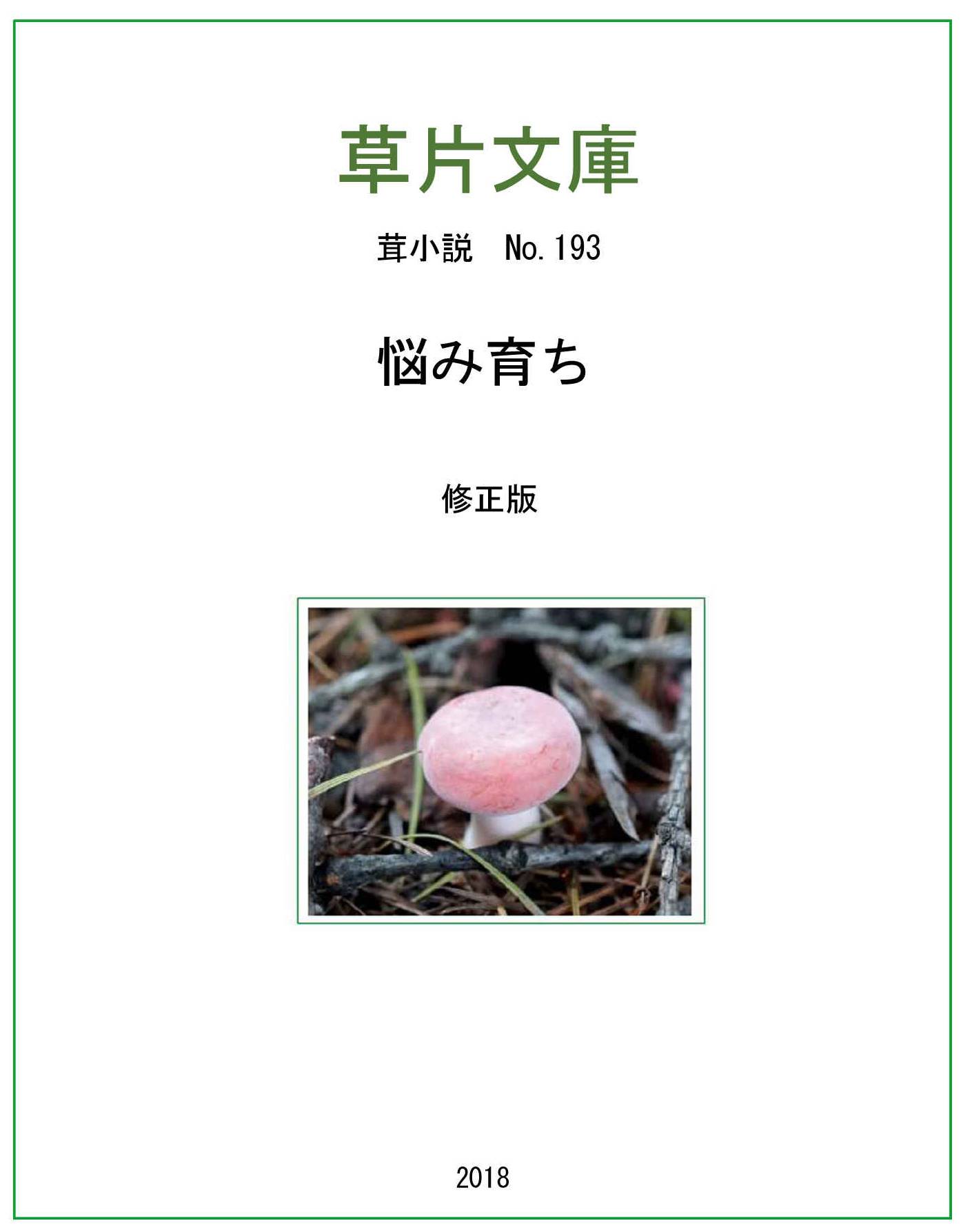
悩み育ち
おかしな茸のお話です。
朝、駅に歩いていくと、道沿いにあるコンビニで開店20周年記念セールをやっていた。この町のマンションに越して5年だから、ずい分前からある店だったのだ。会社帰りに毎日のように夕飯を買うので店員とも店主とも顔なじみである。
その日の帰りがけにも、会社の仕事がごたついて憂鬱な気持ちでコンビニに入った。その店で一番高いステーキ弁当とビールを持ってレジに並んだ。
珍しく店主が店員の脇に立っている。
自分の番になると店主が愛想よく挨拶した。彼の前に八角形の福引器がある。ガラガラポンと言うやつだ。
「いつもありがとうございます、20周年記念の福引です、千円ごとに一回です」
店員が買ったものを袋にいれお釣りをくれた。
「博多さん、二回回してください」
一回おまけのようだ。ガラポンを回すのは子供のとき以来だ。面倒だと思いながら回すと青い玉がでた。店主が大きな声で三等賞とどなって、「恵比寿ビール1本どうぞ、おめでとうございます」と渡してくれた。悪くない。
「もう一度まわしてください」
もう一回回した。出てきたのは赤い玉だった。店主がぎょっとなって、
「大当たり、特等賞、産地直送高級食材」とベルをからんからんと振りまわした。数人いた客が一斉にこちらを見た。
「用紙に名前、住所、電話番号お願いします」
「今くれるのじゃないんだな」
「収穫季節に送られてきます」
「なんだろう」
「それは届いたときのお楽しみです、というか、私も知らないので、すみません」
そのあと話を聞いたら、そういう福引をマネージする会社に委託をしているという。特等賞の内容は、依頼主にも教えていないらしい、普通の福引だと五千円から一万円ほどのものだという。
この特等賞で、仕事場でのことをちょっと忘れることができた。おかげで、その夜は、ステーキ弁当をおいしく食べ、ビールを飲んで機嫌よくベッドにはいった。
最近夢を三日に一度ほど見る。ほとんどが仕事の夢ばっかりだった。慢性的に仕事のトラブルが頭の上に乗っかっているためだ。私の部署の誰かが必ずミスをしている。大したことではないのでそれほど気にすることは無いのだが、部署長の私の責任で解決しなければならないことであり、些細な問題でも自分としては悩むことになる。そのためだろう、夢の中でもいつも悩んでいて、気持ちが晴れない。
ところが例のくじ引きに当たった日から夢の内容が変化した。夢の中に茸が現れるようになったのである。
その日の夢の中では、黄色っぽい茸が目の前でふわふわ浮いて、くちゃくちゃなにかを食べている。そういう音が聞こえたので、なにか食べていると思ったわけだが、茸に口があるわけではない。いや、傘と柄のあいだがパクパクしたり、グニョグニョ動いて、なにか言っているようにも見える。
夢の中で自分の方から茸に声をかけていた。
「何食ってるんだ」
「あんたの悩みだ」
その茸は青っぽい傘を動かしながら答えた。
自分の悩みを喜んで食べてくれているという。ありがたい。
「だけどあんたの悩みはあんまりうまくない」
「どうしてだ」
「自分の失敗で悩んでいるのはうまい、あんたのはそうじゃないからな」
「しょうがないだろう部下の失敗は自分の失敗になっちまう世の仕組みだよ、自分ですべてやったほうがうまく行くが、体がもたないしな、部下を育てるのも俺の仕事だからな、いたしかたなしさ」
今日、部下の明石という男が契約を旨く取り交わしてきて褒めてやった。ところがちょっとお調子者の彼は手痛いミスをした。金額が38万5千円で納品するはずのものを書き間違えて33万5千円で契約をしてしまった。相手は安くしてくれたと思ったことだろう。5万円の損失だから儲けはかなり低くなる。全く儲けがなくなるわけではないから助かったが、部長にはお目玉をいただいた。
「そう言うばかばかしい悩みはいただけないね、本気で悩みなさいよ、それは旨いから」
「まあ、自分自身の失敗なんかの悩みが無いのは少し気楽だよな」
そう自分で言って、なるほどと思い、悩みが少しすっきりした。これも茸が悩みを食ってくれたからだろうか。
それにしてもしゃべっている相手の茸の種類はなんだろう。茸の名前は松茸、椎茸、マッシュルーム、エレンギー、舞茸ぐらいしか知らない。夢の中の奴は強いて言えば椎茸的な形をしているが、傘は椎茸よりきれいに丸くてマッシュルームにも似ている。
すると、それを聞こうと思っていたら、そいつは俺の悩みを飲み込んだところで、こちらが声を出す前にすっと消えてしまった。
次の日の夕方、外回りから帰ってきた女性の部下がぷんぷん怒っている。渡辺文子という。
「どうしたの」
と聞くと、いつもは静かな彼女がきっとなって、
「あの会社の課長が、いつもより化粧が濃いねといいました、セクシャルハラスメントです」と、涙まで流した。
会社周りをやっている女の子で成績はいい。だがいつもとちょっと違う調子だ。
「触られたりしたのか」と聞くと、首を横に振った。それじゃ訴えても問題にされない今の世だ。それで「お得意さんだし、穏便にな」と私が言うと爆発した。
「触られなければセクシャルハラスメントにならないのですか、得意先だから我慢しろと言うのは課長のパワハラです」と怒った。
こりゃ大変。「いやごめん。そんなつもりじゃあなかったんだ」と謝るしかなかった。
すると隣に座っている彼女と同期の明石明が「渡辺、おまえ、生理だろ」というと、彼女は急におとなしくなった。
なんなんだ、そう言う彼の方がずーっとハラスメント野郎だ、とは思ったが、そいつの言ったことに彼女は怒らなかった。ともかくありがたい。よくわからんものだ。気分が晴れないのは私のほうである。
その夜の夢に出てきた茸が「今日の悩みも旨くなかった」と言った。今日の茸の色は真っ白だ。それこそ柄の長いマッシュルームだ。
「どうしてだ」と聞くと、
「言葉は人間の特権だが、最近人間の頭が退化してきて、言葉を正確に理解できない、おそらく、あんたの女の部下は、その得意先の課長を不細工と思っているんだ、それに化粧が濃いと言われ、生理中のヒステリーを起こしたんだ、あんたが言ったように、女に向かって生理だという方がずーっとひどい」
茸というのはなかなかしっかり見ているもんだ。
「それで、茸さんはどんな悩みを美味しいと思うんだね」
「本能の悩みだ」
「本能とは生きること、子どもを作ることか」
「よく知ってるじゃないか、動物のからだはその目的で作られている」
「本能の悩みって何だ」
「青春時代に悩まなかったのか、あの子に惚れて、だけど彼氏がいる、とか」
なんだそんなことかと思った。そんなこと青春時代は誰だってあるだろう。
「そう言うのが、フレッシュで旨い、だけど熟したものもいい」
「何だ、熟したのってのは」
「ほれ、あんたぐらいの年になると、若い女の子に目がいくだろう、あんたは盆暗でだめだが、本気で惚れる年寄りもいる、そのまじめな悩みはなかなか熟柿みたいだ」
俺には関係ない。どうも苦手だ、それでまだ独身。
「このあいだ、小料理屋で好物のもつ煮が売り切れで、がっかりしてただろう、それがもっとこだわりになれば、本当の悩みになって、俺の旨い食料になる、食べる悩みも本能の悩みだ」
「なんと変なものを食っているんだ、茸なら草の露くらいにしろ、人の悩みなんか食べてどうするんだ」
「はは、おれらは夢の中に生えている茸だ、夢の世界に菌糸を這わし、ちょうどいい季節になると、その菌糸から茸が生える。この頃のあんたの夢は、温度湿度が俺たち生えるのにちょうどよかったんだ」
おとといステーキ弁当を食ったために、こんな茸が夢の中に生えたのだろうか。
「それで夢の中の茸はみんな人の悩みを食うのか」
「いや違う、悩みを食べる茸、妬みを食べる茸、憤慨を食べる茸、不安を食べる茸、我慢を食べる茸いろいろいるのだよ」
「それで、そういったものを食われた人間はどうなるんだ」
「体の調子がよくなるさ、精神は自律神経に直結だ」
「そりゃあ嬉しいね」
「おれたちゃいい茸だからね」
「悪い茸があるのか」
「ああ、毒茸がいるよ、夢の中の毒茸だ、その毒茸が悩みを舐めたとすると、あんたは悩みがひどくなるし、ストレスがたまって病気になる」
「夢の中の茸は勝手に生えるのか」
「そうだな、たまたま、俺が生えたが、毒茸が生える可能性だってある」
「そりゃいやだな、夢の中の茸の寿命はどのくらいだ」
「あんたの世界の茸と同じだよ、だいたい一週間だな、夢の中に胞子をとばして、崩れていくんだよ」
「次はどんな茸が夢に現れるかわからんのだな」
「そうだ、俺のあとは嫉妬を食べる茸かもしれんし、憤慨を食う茸かもしれん、毒茸の可能性だってある」
「そうか」
次の朝、便通がとてもよかった。夢の中の白い茸のおかげかもしれない。
それから一週間ほど夢の中に茸があらわれなかった。それでも便通はいい状態のままなので、ともかく茸が体にいい結果をもたらしたようである。
我が社の株が、アメリカの影響を受けて暴落した。一時のことだろうと、高をくくっていたら、一週間経っても回復しない。社長から、様子見だが、新たな事業の展開を促され、それによって、株が戻らないようだと、いくつかの部署の閉鎖をしなければならないことを告げられた。と言うことは、我々のマーケティング部署でも新たなお得意先を開発し、売り上げを伸ばさなければならない。そうなると、アイデアを出さなければならないのは部署の長ということになる。こう言うときに頼りになる部下がたくさんいれば、ちょっとは楽だが、うちの部下たちは悪くはないが突出しているのがいない。
我社は紙の会社である。紙はいろいろな用途があるが、主に本に使う紙を作っている。マーケティング部門としてはそれを出版社で使ってもらうよう会社回りをする。しかし、この経済非常時だ、出版社にも限りがある、紙を他の業種に売り込まなければ売り上げはのびないだろう。新たな開発も含めて考えなければならない。紙を開発する部門とタイアップしていく必要がある。
マーケティング部門は三つの部署がある。写真関係の出版社担当、文学本出版社担当、それに漫画出版社担当である。我々の第二マーケティング部門は文学本を出している会社担当である。大きな出版社だと漫画も写真も文学本も出している。そのような会社には三つの担当からそれぞれがそれぞれの部署に出向いていく。
しかし、今は、紙で何か作ることを考えて、そのアイデアを持って違う業種へアプローチしなければならない。大変なことだ。それで悩んでいるとき、夢の中にピンク色の太り気味の茸が出てきた。
「ふふ、おいしい悩み」
そう言いながら、目の前でフラダンスを始めたように。ように見えた。また悩みを食べる茸がでてきたようだ。
「前出てきた茸はこういう悩みは旨くないと言っていたぞ」
「あーら、そう、食べないほうがいいの」
そんなことはない。首を横に振った。いや寝ているわけだから、本人の首は動いていないのだろう。
ピンク色はかわいい、無毒の色にもなるが、怪しい毒の色にもなる。茸にも女と男があるのかな。こいつは女の子だ。などと思っていると、ピンクの茸が笑った。ように見えた。
「紙の悩みは食べてあげる、だけど、本能の悩みをほじくり出すわよ、それが一番美味しいの」
ピンクの茸は体をひねくった。楽しそうだ、前に出てきた茸より愛嬌がある。そう、女っぽい茸だ。もしこいつが男だったらセクハラになる言葉だ。そんなことにもなやまなければならない。
三日続けてピンクの茸が夢に出てきた。
三日目の朝、テレビのニュースでこんなことを言っていた。海で死んだ魚や鯨、海鳥のお腹から沢山プラスティックゴミが出てくる、環境を守るためいくつかの国がプラスチックのストローの生産を禁止する宣言をした。
日本は禁止した場合にどのような影響が及ぶか明らかではないということで、そのような措置はしなかった。外に捨てない、すなわち再利用を促進するという考え方をもっているようだ。
プラスチックのストローが無くなったらどうなるか。年寄りは麦藁のストローを思い出しただろう。昔ストローと言うと麦藁で作られていて、一部が裂けているとそこから吸ったジュウスが漏れたりしたものである。ストローなど天然物は高くなることは確かで大量に作るには向いていない。
水に溶けやすい紙で作ったら問題ない。まあ、誰でも思いつくことである。カップヌードルの容器が発泡スチロールだったのにいつの間にか紙に変わっている。先見の明がある。
「テレビでプラスチックのストローをなくそうと言っていたけど、紙を使って作るのは誰でも考え付く、ストローに限らず、紙でなにか便利なものが作れないかな」
第二マーケティング部門の部下たちを集めて、いくつかのアイデアを検討した。
「出版用の紙を他のものに使うのはむずかしいですよ」
明石の言うのも確かである。
「いや、新しい紙を開発の連中と一緒になって考えるから、今の紙を使おうというのじゃないんだよ、もちろん出版用の紙そのものが何かに使えたらいいけどね」
「紙でドレスを作ったり、シェードを作ったりいろいろあるけど、大量に消費してもらわなければならないから、やはり使い捨ての商品になりますね」
生理でヒステリーを起こした渡辺文子は家庭用品がいいという。
「家庭用品というとやっぱり部長さんがおっしゃったストローなんかがいいですよね」
「だけど、そのままじゃダメでしょうね、楽しさだとか、かっこよさだとかが加わらないと」
「色をつけて、お子様用にするのは」
「色をつけるのはいいね」
「色が変わっていくのがあると楽しいかもしれない」
「俺、大学のサークルの友達でリトマス試験紙作っている会社に勤めているのがいますよ、大学では化学科で酸やアルカリと発色の研究をやってたやつです。今その会社の研究部門で主任やってます」
明石明の言ったことはかなり要になるかもしれない。
「そりゃ、面白い、どうだろう、飲み物を飲むと色の変わるストローを考えてみようか、明石君はそのリトマス試験紙の会社をあたってよ、ストローにするにはどんな紙がいいか、宗像君はうちの開発部門と協議、ストローの作製会社は渡辺さん探してくれないかな、一本いくらで作れれば商品になりうるか水田さん計算してくれるかな、今までと全く違うジャンルだから大変だけどね、うまくいくかどうかは別にして試みて見ようや、こういう経験もいいだろうから」
そう言って、手探りで新たなものを考えはじめたのである。
まさか、それが大当たり。といっても開発には半年かかった。リトマス試験紙は酸だと赤くなる。フルーツの飲み物が多いので、リトマス試験紙だとみんな赤くなってしまう。炭酸が入っていても同じだ。酸性の飲み物が多い。そこで、酸性の中でも酸の強いのはストローが真っ赤になるが、PHが7にならなくても、すなわち弱い酸性だと青くなり、中くらいなら緑、それより強いと紫と色が変わる物質を探してもらったのだ。
このマジックストローに我が社で開発した紙を使った。すごい増収とはならないまでも、新しい部門に進出できた功績は大変なものである。今までは紙を出版社に売るだけの会社で、一般の人にはそんなに知られていなかったのが、ストローを作っただけでテレビにはでるし、社会に会社の名前が知られるようになったのである。おかげで我々の部署の人員を一名増やしてくれることになった。私も課長補佐から課長になった。
そう言ったことで、しばらく夢の中に茸は現れなかった。
四月になると我々の部署に一人入ってくる。新入社員ではなく、他の部署から移動ということだ。
新入りに何を担当してもらおうか考えていたところに、その社員は入ってきた。
ドアが開いて、一斉にスタッフの目がいった。
太めの足が現れた。ミニスカートだ。上半身がドアから現れた。みんなはっとした。
マリリンモンローではなくて、ジェーンマンスフィールド。こういっても今の若いスタッフはわからないだろう。目が大きくて色が白くてぽっちゃりしている。
その女性はおどおどしながら中に入ってくると、私の前に立って、
「浅見です、よろしくお願いします」と頭を下げた。
書類が回ってきていたので新部員が女性であることは知っていた。浅見赤子という。名前は「あかこ」と読むのではなく「あこ」である。親はどういうつもりでこの名をつけたのだろう。
「これからよろしくお願いしますね」
私は立ち上がって、それぞれの机で神妙にしていたスタッフにむかって、
「浅見赤子さんだ、これから我々マーケティング部門のスタッフです、まずみんなからいろいろ教えてあげてください」
そう紹介した。
彼女はなにも言わずに、だが丁寧におじぎをした。これでうちのスタッフは女性3人男性2人、それに私という男女同数の6人体制になった。
「席はあそこ」と、女性陣の端の机を指さした。
彼女が席に座ると、早速前からいる二人の女性が彼女に話しかけている。
その日の夜、彼女の歓迎会を近くの飲み屋でおこなった。宴会係の明石がはりきって予約をいれておいたところだ。
浅見赤子は寡黙だがいつも笑顔で、男どもはその新人ばかり見ている。前からいる二人もなかなか個性的な魅力のある女性ではあるのだが、なにごともそうだが、見慣れていない、新鮮なものは刺激になる。前の二人よりかなり豊満な女性である。
しゃべると、ゆったりとしていて心地よさがある。酒は相当飲めそうで、ビールをぐいぐい空けている。ぽーっと赤くなったところはなかなかいい。ジェーンマンスフィールドのようにアメリカアメリカしていない。日本の女性だ。
私はいつものようにお金だけおいて先に帰った。そういうのを昔は勘定殿様といったそうだ。いつもそうしている。若い者たちにのびのびとしてもらうためだ。
その夜、夢の中にあのピンクのふっくら茸があらわれた。ちょっと浅見赤子的であることに気がついた。
「どう、久しぶりね、仕事うまくいって、私の出てくる夜がなかったわね」
「おかげさまで、茸は一週間しかもたないのじゃないか」
「菌糸は死んじゃうわけじゃないわよ、菌糸に記憶があるの、だから前出てきたピンクの茸は枯れたけど、私はあたらしいの、だけど同じ茸と思っていいわよ」
「そういうことか、なんで出てきたんだ」
「そりゃ、あんたのためじゃないの、悩みを食べてあげるのよ」
「今悩みなんてないよ」
「ふふ、脳の奥の方に、本能の悩みの卵があるわよ、その卵を孵させて、私がおいしくいただくの」
なんだ、ピンクの茸の奴、美味い悩みを食いたいために出てきやがったんじゃないか。
「悩みを作ると言うことは毒茸か」
「ははははは、そういうことになる、毒は薬にもなるわよ」
「本能の悩みなんてつくらないよ」
「本能って言うのは動物に備わっているものなのよ、遺伝子の中に入っているわ、消しちゃうことはできないのよ、でもあんたの本能はまだ卵、しかもちいちゃくて堅いのよ、いい年して困ったもんよ、でも勝手に表に出てくるわよ、私が後押ししちゃうの」
ピンクの茸はそう言うと、いつの間にか消えていた。悪い奴だ。どこに行ったのだろうか、夢はまだ続いている。
おやおや今度は森の中にいる。目の先の羊歯の間をハリネズミがうろうろ餌を探している。おやとおもったら、ハリネズミが持ち上がった。何だと見ていると、ハリネズミの腹の下からピンク色のものが見えてきた。例の茸の傘だ。ハリネズミを頭にのせて土の中からピンクの茸が生えてきた。ぴょこんと跳ねるとハリネズミをのせたまま自分の方にやってきた。
なんだ、と思ったとたん、脳の中でぱちんという音が聞こえた。
なにが起こっているのだろう、脳溢血でも起こしたんじゃないかと心配になったとき、夢の画面が変わって、ピンク色の卵がころがっている。その上にハリネズミがひっくり返って、ばやばやしている。ピンクの茸がハリネズミを卵の上に放り投げたようだ。
「こうしないとあんたの卵割れないのよ」
ピンクの茸の声が聞こえたと思ったら、ピンクの卵にひびが入って、パカット割れた。ピンク色の煙が立ちこめ目が覚めた。
なんていう夢なんだ。
その朝、会社に行くと、すでに浅見赤子がきていて、自分の机でマニュアルを一生懸命読んでいた。
私が部屋にはいると、立ち上がっておはようございますと丁寧に頭を下げた。ブラウスの胸の中がちらりと見えた。豊満な膨らみにドキッとして彼女の顔を見ると、大きな目で見つめられた。
「おはよう、はやいね、勉強しているの」
目をそらして声をかけると、「はい、わからないところがあったら教えてください」と席に座った。
今風の娘とはだいぶ違う。
私も席に座って今日のスケジュールを見ると会議が一つはいっている。社長もでる販売戦略会議である。いつも係長候補の宗方勲を連れて出席するのだが、経験の為に浅見も一度連れて行こうと浅見の予定を聞いた。
「今日は明石さんにストロー会社の販売会議に出席するように言われています」
「明石と行くことになっていたならしょうがないね、今度一度、会社の販売戦略会議に出てください。営業には役立つ情報もあるだろうし経験のためだからね、社長も出るよ」
と言ったが、女に手の早い明石明の奴大丈夫だろうかとちょっと頭の奥に不安の芽がでてきた。明石は口も上手で確かに外回りは任せておける。それも経験だと自分に納得させた。
やがて、みんな出社してきて9時半になると、それぞれの仕事に散っていった。
課長秘書の役割を持つ水田香だけ残っている。
「課長、明石君に浅見さんまかせて大丈夫なの、あんなかわいい娘、なんでこの部署にきたのですか」
そう言われてもわかるわけがない。私が答えないので彼女は続けた。
「きっと、恋愛沙汰で追い出されたのよ」
そんなことはあるまいと思っていたら、後で聞いたところによると、前の部署の中心だった部長と部下の男子が彼女の取り合いになり、仕事が手に着かなくなって部署の成績が上がらなくなったという。本人は全くどちらも相手にしていなかったようだが、統括部長が仕事にならないという他の者からの訴えで、ちょうど我々の部署の成績が良く人手が要るだろうということで配慮したようである。
前の部署の部長も部下も生真面目だからこんがらがったようだ。その点、うちの部署は、皆それなりに遊んでいるから大丈夫、課長の私は、そっちはからっきしだめ、ということらしい。確かに会社の判断は間違ってはいないようだ。だから私は45にもなって独り身なのだ。
夕方、浅見が出先から帰ってきて。
「ただいま戻りました、明石さんもすぐきます」
私のところに報告に来た。
「会社との対応覚えましたか」
「はい、明石さんが優しく細かく教えてくださいました」
にこにこしている。そこに明石が入ってきた。
「今日はうまく行きました、新たなストローにうちの紙を使うことになりました」
「それはすごいね、どんなストローなの」
「ストローの紙に栄養剤や薬をしみこませて、それで水を吸うと薬も溶けて、自然に飲んじゃうというものです」
「誰が考えたの」
「浅見さんです」
浅見が手を横に振った。
「いえ、明石さんが、私に子供に薬を飲ますのにストローを使えないか聞いてみなさいと耳打ちをされたので、そう言ったら向こうの開発担当の方や社長さんが、そりゃいい考えだと議論がはずんだのです」
「そう、二人ともよくやったな、引き続きやってください」
また我々第二マーケッティング部は増収だ。
二人は帰り支度をすると肩を並べて出ていった。
帰り支度をしていた秘書の水田は、
「浅見さん大丈夫かしら、明石の奥さん嫉妬深いのよ」と言って出て行った。
なんだか余計なことのように聞こえるが。
しかし明石の肩に寄りかかっている浅見の顔を思い浮かべてドキッとした。
その夜、夢の中にピンクの茸がでてきた。浅見赤子も現れた。ピンクの茸と手をつないでいる。茸に手があるわけがないが、夢の中ではそのように見えた。赤子は特に短いミニスカートをはいている。彼女のふっくらとした足を見て夢の中でどきっとした。
「ほら、卵が割れて、出てきたわ、おいしい悩みが出てきたじゃない」
そう言えば昨日、浅見は明石赤子と飲みに行ったのだろうか、その後どうしたのだろう。
「そう、その調子」
夢の中でピンクの茸が踊り出した。
そこで突然目が覚めた。もう朝だ。なぜか早く会社に行きたくなった。
浅見は来ているかどうかと気になりながら部署の戸を開けた。
浅見はもう来ていた。後ろ姿がふっくらしていて引き寄せられていく。
「おはよう」
ちょっとばかり彼女の肩をぽんとたたいた。なぜだろう、今までこんなことをしたことがないのに。彼女も振り返って「おはよございます」と笑顔になった。
なかなかかわいらしい。
「昨日はご苦労様、あれから呑みにでも行ったの」
「いえ、明石さんに誘われましたけど用事があったので帰りました」
「そう、新しい契約ができそうでよかった、ビギナーズラックにならないように、がんばってね」
「はい」彼女はうなずいた。
「前の部署では経理担当だったそうだね」
「はい、外回りはこの部署にきて初めてです」
「いずれ今後の役割についてはゆっくり話をしましょう」
彼女はうなずいた。今まで女性の部下を誘うなどしたことはしたことがなかった。
「今日はまたストローの会社に行くのかな」
「はい、明石さんと一緒です」
「それじゃ、明日の夜あたりいろいろ聞かせてもらおうかな」
彼女はうなずいた。
その日、行きなれていないフレンチレストランに連れていった。
「こんな高いところきたことありません」
「いや、僕もめったにこないよ」
本当は始めてである。
「好きなものをどうぞ」
彼女は口で言うのとはずいぶん違った。臆することなくメニューから食べたいものを選んで注文をした。本当にきたことが無いのだろうか。
「課長さんはどうなさいます」
「僕も同じのにしよう」と言うにとどまった。
かなり高い赤ワインも彼女が注文した。
「外回りに向いているようですね」との問いかけに、首を横に振って「いえ、今度のことは明石さんがなさったことで、私は売り込みだとか開発だとか苦手なのです、デスクワークがむいています」
「今、水田君に受付、経理、それに秘書の役目をたのんでいるのだけど、彼女が外回りをやりたいといったら、替わってもらうよ」
もう一人の女性、渡辺も外回りが大好きな人間である。水田もやりたそうな素振りを見せることがある。うまくいけば浅見を秘書にすることができる。まあその日の三万の食事代は高いとは思わなかったくらいうきうきと家に帰った。
その夜の夢の中のピンクの茸はおとなしく目の前に浮かんでふらふらしている。
「おとなしいね」
「今あんたに悩みがないもん、お腹すいた」
「そりゃわるいね」
「でももうすぐたくさんごちそうが食べれそう」
そう言うとパチンと消えてしまった。それでぐっすり眠れた。
次の日、水田に話をもっていくと、私販売をやってみたかったんですと大乗気だった。それで浅見をデスクワークにすえた。前の部署でも経理などを担当していたこともあり、彼女は水田から難なく受付、経理それに秘書役のポイントを会得した。頭もなかなかよい。
ストローの会社との新商品の開発は順調に行き、帳簿を見るとかなり伸びている。
浅見の経理はしっかりしており帳簿のチェックをしなくても大丈夫のようになった。そのころになると、彼女を嫁さんにしようと思うようになっていた。履歴を改めて見ると結婚していない。今32歳、ちょうどいい年頃である。たまにフレンチレストランに一緒に行くようになった。しかし私がそういうことが苦手なせいもあるが、彼女からはそのようなそぶりを感じることが出来ないのでなかなか言い出せない。
夢の中ではピンクの茸が楽しそうに踊っていた。
「本能の悩みはおいしいね」
半年がたった頃、明石が「また新たなストローを開発しました」
と言ってきた。
「そりゃすごいね、なんだい」
「アルコール検知ストローです」
「どういうの」
「アルコールの量で色が変わります」
「酒をストローで飲んでもうまくないよ」
「いや、アルコール検出に使うんです、ストローをくわえて息を吹くとアルコールの量で色が変わるんです」
「ああそうか、ドライバーのチェックか」
「ええ、警察やいろいろなところで使えます」
「明石君たいしたもんだ」
「水田さんがずいぶん助けてくれます、これでうちの部署の収入が独走ですね」
こうしてなにもかもうまくいっていた。
ところが部長に会ったときこんなことを言われた。
「君のところの売り上げはダントツなんだが、接待が多いねえ」
それを聞いてちょっと驚いた。接待費とは何だろう。
「はあすみません、気をつけます」としか答えようがなかった。
「明石君、ストローの会社や試薬作成会社の人とよく飲むの」
「はい」
「接待費節約しろといわれてるんだが」
「はい、気をつけます」
やっぱり明石か、だがおかげでうまく行っている。
「いや、必要ならいいんだ」
「月に一度ほどです、一回3人で2万ほどです」
そんなもんなら問題ない。
「まあ、まかせたよ」
そのくらいで部長はなぜあんなこと言ったんだろう。
浅見が部署にきて一年になる。月に数度はちょっと値の張るレストランに浅見を誘った。彼女はいつもにこやかに相手をしてくれる。
一度手を握ったら、やんわりと解かれてしまった。何も言わないでにこにこしている。
彼氏がいるかなどと聞くのはハラスメントになるそうだ。セクハラ、パワハラ、両方になっちまう。考え過ぎてなにもできない。
そういうときは明石ならなにも考えずに突っ走るのだろう。
どうしたらいいんだ、こんな悩み今まで経験がない。夢の中に必ずピンクの茸が夢に出てきて、楽しそうに踊っている。
「もっとうじうじしなさい、本能の悩みはおいしいわよ」
ピンクの茸のエンタシス型の柄が彼女の足に見えてくる。
「ほほほ」
ピンクの茸はそれがわかっているように傘をひらひらさせる。
ミニスカートみたいだ。
そろそろ結婚を申し込もう、そう思って会社に行ったところ、彼女は休みをとっていた。
部長室に呼ばれた。
「君ね、君の部署の経理帳簿見ているかい」
もう浅見にまかせっきりである。
「今会社に監査がはいっていてね、ちょっと雲行きが怪しいんだよ、この5年間に何か不正がありそうだと事前に通告があってね」
「うちの部署も関係していますか」
「うん、おかしな支出が多いらしいんだ」
「例の接待ですか」
「だろうね、君も調べたほうがいい、監査の結果は明日結論がでる」
そう言われて部屋に戻ると、今日は外回りに出ていない水田に言った
「浅見さんの経理帳簿が見たいんだけど、どこに置いてあるのかな」
「浅見さんも私と同じように、机の一番下の引き出しに入れていました」
鍵のかかるところだ。
浅見の机の引き出しを開けようとするとやはり鍵がかかってる。
水田が私は鍵を上の引き出しの奥に入れてましたと、浅見の引き出しを引き出した。中はきちんと整理されている。だがそこには見当たらない。
「しょうがない明日出てきたら聞いてみるよ」と、自分の机にもどった。
その夜はピンクの茸がでてきてこんなことを言った。
「あら、本能の悩みに仕事の悩みが加わったわね、ミックスの味もいいものよ」
「太りやがって」
「おほほ、やつあたりね、ますます美味しいわ」
ピンクの茸は天井のあたりでタッタラタッタラ踊っている。だけど、なんで茸が出てくる夢ばかり見るのだ。
「あっちいけ」
どなったら、いきなり浅見赤子の顔がでてきた。大きな目でこちらを見ている。心臓がどきどきしている。と、そこで目が覚めた。早く会社に行こう。
はやる気持ちで部署の戸を開けた。浅見はまだ来ていなかった。そのかわり明石が自分の机を前にして座っていた。
「おはよう、早いね」
「あ、課長、おはようございます、やっぱりあの件ですか」
「なにそれ」
「課長にはまだ連絡ないのですか」
「なにを」
明石は唖然としている。
「ちょっと前から気になっていたのですが、うちの部署の稼ぎがおかしいでしょ」
「部長にもちらっと言われてる」
「やっぱり、今日査定が下るそうですね」
部長に言われたことだろうと想像できた。
「誰からなにを聞いたのだい」
「総務に同期に入った男がいましてね」
そこに水田と宗像が出勤してきた。しかし浅見は来なかった。
電話が鳴った。前秘書の水田がとった。
「課長、統括部長がすぐに部長室に来てほしいということです」
私は部長室にいった。
「浅見赤子が経費を横領していた」
信じられない話である。
「前いた部署で一億、君の部署ではまだ一千万だ」
「え、どういうことですか」
「収支簿はみたのかね」
「昨日浅見は休みで、机の鍵がなかったもので見ていません」
「すでに総務の方で警察に連絡したのだが、内縁の夫と逃げた後だった」
「君と仕事の打ち合わせで、レストランの領収書が経費から落とされていて、年間100万ほどになってるぞ」
何も言えなかった。
「それはたいしたことはないが、取引先の小切手を自分で換金して着服して帳簿はあわせていたようだ」
私が驚いているとこうも言った。
「君の部署は我社の頼みの部署でもあったのだが、けじめとして、君も処分の対象になってる、だけど首にはならないと思うよ、どうなるか私にも何も言えなくてねえ、浅見の前の部署の課長はどこかの下請けの会社に行くことになると思う」
私は呆然として部長室をでた。部屋に戻るとみなに部長に言われたことを伝えた。正直に浅見とたまに食事をしたことも言った。それは自分が払ったのだが、浅見がその領収書をもらって必要経費として引き落としていたことも言った。
「申し訳ない、私は処分されるが、みんなは大丈夫だよ」
「課長さんが浅見さんを誘っていたのは知ってました、真面目な課長さんだからちょっと心配だったけど」
水田が同情するように言った。
「そう、課長まじめだからみんなで心配してたんですよ、ああいう一見おとなしい娘はほどほどに近づいたほうがいいんです」
明石は人間がよくできている。みんないいやつだ。この年になって教わることばかりだ。
「誰かが経理がおかしいと言ったらしいんだ」
明石は総務にいる同期の男から何か聞いているのだろうか。
「知ってるの」
「いえ、誰かは知りません、きっと浅見の前の部署の誰かでしょう、あそこの課長も真面目だったから、奥さんいるのに浅見に熱上げちゃって、被害は大きいと総務のやつはいっていました。うちの被害はどのくらいだったんですか」
「いや、すまん、部長の話だと、この一年で一千万ほどだそうだ」
「たいしたこと無かったんですね」
宗像がほっとした表情をした。
「課長さん、早く結婚した方がいいですよ、お見合いでも何でも」
水田が話を締めた。
私はただうなずいた。
その晩、夢の中に青い茸とピンクの茸がでてきて宙に浮かぶとなにかむしゃむしゃと食べている。食べるのに忙しくて何も言わない。
「美味いだろう、こんちくしょう」
と怒鳴っちまったら、
「怒ってる、いいわねおいしい悩みが怒りのスパイスでもっといい味になる」
と言いやがった。
青い茸もうなずいてただ食べ続けた。なんだか泣きたくなる。
目が覚めると、肩が凝っていて疲れた。
その状態で会社に行くとすぐに部長に呼ばれた。
「浅見赤子の内縁の夫は香港で捕まったよ、だけど浅見は内縁の夫を捨てて一人で逃げたらしい、内縁の夫が言うには本当の恋人がいてそいつのところに行ったということだよ、フランス人らしいということだ」
私はうなだれて聞いていただけだった。
「君の処遇だけど、取締役会議で、今一番うまく行っている部署から君を移動させると仕事に差し障りがでるといけないという指摘があって、半年、30パーセント減給ということになった、まあ気落ちしないでがんばってください」
「ありがとうございます」
私はお礼を言って部屋に戻った。
「課長、どうでした」
皆心配そうに私をみた。部長に言われた通りのことを話すと皆喜んでくれた。
その夜、夢の中に真っ黒な茸がどでんと宙に浮いて何かをしきりに食べていた。
毒茸だ、何とか追い払おうと夢の中で手を伸ばした。
黒い茸はひょいと体をかわすと、
「おまえの落ち込みはうまいね、食ってやるから明日はあんたも腹が減って朝飯がうまくなるよ、それにうんちもよくでるさ」
そう言ってぱくぱくと傘を動かして、俺の落ち込みを食べてくれた。
明くる朝、確かに朝飯もおいしかったし、便通もよかった。
部署はまた5人体制になったが立て直しのミーティングを行い、水田がまた秘書をやってくれることになった。
水田が冗談に「秘書になったら毎月おいしいものがレストランで食べられるのでしょう」と言ったら、みなが「いいなー」と返した。そこで「半年後、給料が元に戻ったら、毎月みんなにごちそうするよ」と約束してまとまりをつけることができた。
その日、会社から帰ると、宅急便の再配達表がポストに入っていた。まだ間に合うので電話を入れると、八時前にそれは届いた。
「長野の旬の茸」とあった。コンビニの特等賞の賞品だった。
包装を解いて箱の蓋を開けると太い茸が八本はいっていた、白黒青ピンク黄紫赤緑のカラフル茸だ。説明書きに「おいしい水と空気であなたの夢が育てた色とりどりの茸、美味しく召し上がれ」とあった。確かにおれの夢が育てたやつだ。
ピンクの茸を手にとってみた、夢の中のピンクの茸にそっくりだ。俺の悩みを食って育った奴だ。
さてと思った。俺の悩みや落ち込みを食って育った奴を食べたとすると、また悩みが腹にたまるのではないか。とても食えるものではない。明日誰かにやろう。
次の朝、駅にいく途中にコンビニによった。
店主が暇そうにカウンターにいた。
私はできるだけにこにこして「特等の茸が送られてきました」
箱を開けて中を見せた。
「こりゃみごとだ、新しく改良された茸でしょう、きっと美味いものですよ」
「食べたことがありますか」
「こんな高いもんありませんよ、茸は好物ですけどね」
「実は事情があって、茸は今食べられないんですよ、それでご主人食べていただけませんか」
「ええ、いいんですか」
「もちろん、ご家族で楽しんでください」
私は押しつけるようにして茸の入った箱を渡した。
「それじゃ申し訳ない、これをもってってください、少しだけど」
主人は季節限定のチョコ菓子「茸の山」を袋に入れてくれた。
「あ、すいません」
私はそれをもって出勤した。
それから半年、給料は元に戻り、みんなをレストランに連れていった。部署の仕事はとてもうまくいっていた。みんながお見合いの相手を見つけてくれることになった。浅見はまだ捕まっていない。
ただ一つ気になっていることがある。あのコンビニがつぶれたのである。私の悩みを家族で食べてしまったためでないといいのだが。それがちょっとした今の悩みである。いや悔やみかもしれない。
悩み育ち


