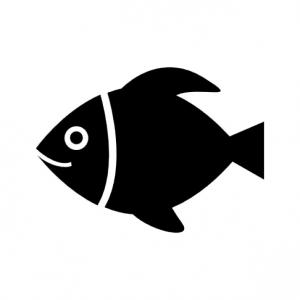野菜コロッケ80円
僕は彼女の背中にそっと手を回して抱きしめようとした。生き物特有の柔らかくて暖かい感触が伝わってきた。しかしそれと同時に腕やら胸やらになにか違和感のある感触があった。刃物のような薄くて鋭いものが僕の肉に食いこむような感触だ。このまま強く抱きしめたら、それが僕の体を突き破ってしまいそうだ。
僕は彼女の体を見ようとしたが、どういうわけか彼女は輪郭が曖昧なわけのわからない存在になっていた。さっきまではっきりと見えていたはずの彼女の顔も、消しゴムをかけたあとのように消え去っている。それでも手や体に感じる感触はいまだに強く残り、彼女自身は確かに存在しているのだった。
僕は何かを言おうとした。しかし声が出なかった。それどころか口すら動かなかった。何を言いたいのかもわからないまま僕は彼女を見るが、彼女には耳がついていなかった。
そして、いつのまにか僕と彼女は距離をとっていた。彼女は何かを言った。本来なら口があるはずの部分の空間が割れ、それがぱくぱくと何度か動いた。そうして彼女の声は遅れて僕に聞こえてきた。
「死んで」
じりじりと鳴り続ける目覚まし時計を手のひらで思いっきり叩いた。しかし、税込価格一九八〇円のアルミボディはそれくらいでは沈黙しなかった。よくわからない音を立てて床を転がりながら、相変わらずじりじりと鳴り続けている。僕は情けないような思いになりながら起き上がって、床に転がっているそれに手を伸ばしてスイッチを切った。それからそいつを掴んだ。
アルミの手触りは冷たくて、僕はそれでいっきに眠気が醒めたような気がする。でもこの目覚まし時計は本物のアルミじゃない。大きくて丸い曲線を描き、手触りも気持ちいいが、しょせん一九八〇円は一九八〇円、アルミなのは外側のわずかな部分だけだ。本物なのは一ミリの何十分の一くらいの厚みしかない。それより内側にはきっと一九八〇円なりのプラスチックが詰まっている。
しょせんニセモノだ。そのくせ、冬になると外気温に敏感に反応して、僕の手を拒絶するように冷たくなる。だから僕は冬になると遅刻が多くなるのだ。
「そう、じつは目覚まし時計こそが遅刻の元凶なのです」
もちろん誰も答えない。
目覚まし時計を定位置に戻した僕は、そのまま万年床の上に座りこんだ。それから部屋の中の惨状を見回した。
ロフトの柵が折れて、床に横たわっていた。そして、そこには先端がわっかになった紐がしっかりと結わいつけられていた。結び目は強固で、ちょっとやそっとでは外れそうにない。そこでようやく、僕は後頭部に感じる鈍痛の正体に思い至った。どうやら、僕は床に頭を強く打ちつけたらしかった。手で後頭部を探ってみると、ごわごわした髪の毛の中に膨らんだコブがあった。あまりいい手触りじゃない。ついコブの大きさを確認したくなったが、自分の後頭部を確認するすべがなかったので諦めた。それから僕は、またぼうっと部屋の中の観察を始めた。そしておもしろいことに気づいた。
中途半端な部分から折れた元ロフトの柵が、鳥居みたいなかたちになっていた。そして、その鳥居の横棒の部分に紐が括りつけてあるのだ。僕はなぜだか神々しい気持ちになった。
しかしつぎの瞬間にはすぐに落胆した。外から見ればつやつやといい色をしていた鳥居の内部には、やはりというべきか安っぽいプラスチックが顔を覗かせていた。僕はここでもニセモノを発見する。
どうやらニセモノ同士が足を引っ張りあう、というのが今回のオチのようだった。
体調不良を理由にサボって二度寝してしまおうかとも思ったが、なんとかその誘惑を振りきった。それにさほど眠気もなかった。皮肉にも、どうやら適切な睡眠時間をとることができたようだった。
そして僕はいつものように歩いて「公園」に向かった。
公園、というのは少し語弊があるかもしれない。そこには砂場や滑り台は無いし、かといってたいして広くもない。しかし春には桜が咲き誇るような、夏には野芝が青々と生え揃ってそのあいだをバッタが行き交うような、白塗りの手すりが設置された遊歩道が申し訳程度にあるような、そんなところだった。周回すれば三分とかからないその「公園」を毎朝散歩するのが僕の日課だ。冬場はさすがに寒くてここには来ない。僕が冬に遅刻しがちな本当の理由は、冬は早起きをする必要がなくなるからなのだ。
僕は初春の朝の空気を感じながら歩きつづけた。今日の朝刊の天気予報欄には快晴を示す太陽のマークが三つ並んでいた。一日中晴れ、ということだ。最低気温は十六度で、最高気温は二十三度の予想だった。最近は肌寒い日が続いていたが、今日は絶好の散歩日よりといえた。僕の服装はジーパンに長袖シャツ一枚だった。アパートを出たときにはさすがに少し寒かったが、歩いているうちにちょうどいい感じになってきて、「公園」に着くころには少し汗ばむくらいになっていた。
僕は遊歩道を歩いた。遊歩道の手すりはトタンで、その上から白いペンキが塗られている。ところどころ赤錆が浮かんではいるが、肌に触れると冷たくて気持ちがいい。なだらかなカーブを描く手すりをぺたぺたと触りながら、僕は遊歩道を散歩していった。道沿いの桜の花は二分咲きといったところで、花見客で賑わう時期もそう遠くはないであろうと思われた。風が吹くと桜がゆるやかにそよいだが、桜の花はひとつの花弁も散らさずに、強く強く成長していることを僕に実感させた。
ここにあるものは何もかも本物で、ニセモノは無かった。「公園」の散歩は、いつだって僕の精神を和らげる。
しかしこの時期だけはそう簡単にもいかない。
「この時期はいつだって鬱になる」
部屋に鍵をかけながら、ついそんなことが口に出る。もちろん誰も答えない。その代わりに、すれ違った二つ隣の住人に変な目で見られた。こうして僕はこのアパートで不審人物Aという称号を獲得していく。
日当たり不良、六畳一間、ロフト・ユニットバス付き、家賃四万三千円。駅まで徒歩十分、大学までも徒歩十分。どちらに行くにしても上り坂は長く険しい。新潟に来てからコメリで買った自転車は入学二日目にして盗まれた。前かがみになって上り坂を上りながら、この坂が無ければこの大学の遅刻率は激減するはずだと毎度のように確信する。
中門から入って教養棟へ。指定された教室に行って後ろのほうの入り口から中を覗いてみると、始業の十分前だというのに席は八割がた埋まっていた。後ろの壁にもすでに人が連なっている。入るのをためらうが、今期にこの授業をとらないと来年が辛くなる。来年などあれば、の話だが。
僕はなんとか勇気を振り絞って中に入った。後ろのほうから空いている席を探すが、あまり多くはない。そうこうしているうちにも席はどんどん埋まっていく。結局僕は教室の中ほど、3人がけの席の端に腰を落ち着けた。隣には女子が二人座っていた。時計を見ると八時二十五分。五分間の空き時間を過ごすすべを持たない僕は、やはりここでも寝たふりをすることを選択する。
腕に顔を押しつけて視覚を閉じると、そのほかの器官が鋭敏になる気がする。まずは臭覚だ。
隣の女子から柑橘系の香水の強い匂いが漂ってくる。きっとこの香水もニセモノだ。その証拠に、冬場にコタツに入りながらみかんを十個食べたあとの手の匂いに似ている。そういえばもう三年ほどみかんを食べていない。
そして聴覚も敏感になって、声も聞こえてくる。
「おはよー」
おはよう。
「すっごい混んでるね」
そうだね。きみもまたその混雑に一役買ってるわけだけどね。
「あたし座る場所ないしー」
ん? だったら俺の場所を代わろうか?
「…………」
ん、どうした? 言ってくれればいつだって代わってあげるよ。
「あ、そういえばさ」
なんだいいのか。
「ねぇねぇねぇ聞いてよ」
聞いてるよ。
「うわ、聞く気ないし!」
聞いてるって。
「あ、それかわいいね」
そうかな?
「あたしも欲しいなー」
ユニクロで週末特価一四八〇円だったよ。
「えー、あははは」
あははは、キモいだろ?
「先生遅くない?」
そういえば遅いね。もう五分は経ってるはずだけど。
「いいじゃんべつに。初日から休講かもよ」
いやそれは困るな。またこれを繰り返すかと思うと。
「ねーあれって」
え? どれ?
「指さしちゃだめだって」
へー、行儀いいんだね。
「え? コブ?」
コブ?
「なんかぷっくりしてる」
――そっか。最近髪の毛薄くなってきたかなー。
「あ、先生来たよ」
やっとか。
「じゃーね」
ああ、またね。
それから、教室のざわめきがだんだん小さくなっていって、担当教員が、人数が多いので抽選にすると言いだした。そのとたんにざわめきが復活した。抽選方法は配られた紙に学籍番号と名前を書くという、ある意味で古式ゆかしい方法だった。
僕は紙が回されはじめたころを見計らって顔をあげた。誰も見ていないことなど重々承知のうえで寝ぼけているふりをする。僕たちの机に紙が回ってくると、受け取った隣の女子は僕に一枚滑らしてよこした。それを何も言わずに受け取って、僕は言われたとおりに書きこんだ。隣の女子は当然のように四枚取り、携帯を見ながらそれぞれに書きこんでいた。僕は僕で、こんなときに帽子とかあったら便利なんだな、とか考えていた。
幸楽苑は深夜までやっているから便利だと思う。それに安い。味についてとやかく言う人もいるようだが、僕は問題なくおいしいと思う。
店に入って、いつものようにカウンターの端につく。そして、中華そばのAセットを注文した。
ラーメンが来るまでの時間を使って、僕は店内をできるだけゆっくりと見回した。
じつは僕には昨年の秋あたりから気になっている人がいた。
その人はだいたい夜に僕と同じくらいの時間にひとりでやってきて中華そばを食べていた。不思議と僕と時間がバッティングしていた。いつももよれよれのジーパンに似たような色あいのワイシャツを着ていた。そして、しだいに気になる存在になっていっていたのだ。
「中華そばください」
その人の声を聞く機会は注文をするときしかなかった。それでも、それだけで僕はもうかなりの回数その人の声を聞いていた。ときにはその人の声ががらがらだったりいつも以上に小さいときもあったりして、僕はそんなことがいちいち気にかかった。しかし僕はどう話しかけたらいいものかわからなかった。
もちろんときどきキャンパスの中で見つけることもあった。大学のキャンパスなんて広いようでやっぱり狭いものだから、いつも気を配って注意深く周りを見回してみると案外見つけることができた。そしてもちろんその人のほうは僕のことになんかまったく気づかなかった。いくら時間がかぶることが多いといっても、ただ同じ店で食事をしているというだけが共通点の僕のことなんか覚えているわけがなく、その人は颯爽と僕の目の前を横切っていったりした。颯爽と、なんて古い小説の中でしか使えない死んだ言葉だとは思うけど、しかしその人のことを表現するときだけは適切なのだ。
そう、まさにその人は颯爽と歩く。その前夜にどんな暗い声を出していたとしても、翌日には颯爽と歩く。自分の目の前に立ちふさがるものすべてを空気ごと切り裂くように、僕には逆立ちしてもできないような格好よさで颯爽と歩くのだ。
そしてその颯爽とした後ろ姿が農学部棟に消えていったりするのを見ては、偶然にも同じ講義を取ることがあったら声をかけてみようと思っていた人文学部の僕は少し軽いショックに見舞われた。せめて教養の授業で、と思ってはみたが一度もその人を見かけたことはなかった。どうやら僕とは趣味嗜好、単位に対する心構えなどがなにから何まで違うようだった。
つまり、僕がやるべきなのは、ここ幸楽苑で声をかけるということにほかならなかったが、つい二の足を踏んでしまっていた。少しだけ勇気を出しさえすれば決意は鋭敏になって、あとのもろもろは勝手についてくるということぐらいは僕にもわかっていた。しかしまごまごしているうちにその人の姿をまったく見かけなくなって、幸楽苑は定期的な中華そばの売り上げを失うことになった。
それが一ヶ月くらい前の話だ。
もちろん、その人が単に実家に帰っていただけだとも考えた。だから僕は先週くらいからこうして幸楽苑に来るたび、その人のことを見逃さないように注意している。しかしいまだに見つけられたことがない。
そして、今日もまた僕はその人のことを見つけることができなかった。
Aセットは二十分くらいで食べ終えた。勘定を済まして外へ出ると思ったより冷えこみが厳しく、鼻水が出そうになった。僕は自分の体を抱くようにして、ひとり部屋に戻った。
「ふむ、きみはあれだね、重度だね」
女性の明朗な声が響いた。確かに重度かもしれないとは自分でも思うけれど、でも実際自分で重度だと認識しているうちはたいして重度ではないものじゃないか、というような主旨のことを僕は言いたかったが、どうしてか口が動いてくれなかった。
「いや、これは重症だな」
女性は腕を胸の前で組んで、呆れたように呟いた。
女性は僕が知っている制服を着ていた。紺のブレザーにえんじのネクタイ、赤いチェックのスカート。しかし僕は彼女が何者なのか思い出すことができない。きれいなグレーの髪の毛は腰のあたりまで届きそうなほど長く、前髪は眉毛のあたりで切り揃えられている。目は大きい。肌はしみひとつなく、まるで磁器のようだ、という比喩を僕に連想させる。その顔も、制服も確かに見覚えがあるが、しかしあいかわらず彼女がいったい誰なのか思い出せない。
「ん? どうしたかね」
女性は僕の顔を覗きこむように前かがみになった。長い髪の毛が揺れた。髪の毛の先は重力的にありえない位置でぴたりと静止した。
「まあ悩むのも若いうちの特権だね。大いに悩め、少年」
女性は妙に達観したような口調でそう言って、また腕を組んだ体勢に戻った。僕は少年といわれるのには年をとりすぎていたが、それを訂正しようにも声が出せなかった。
「頑張って頑張って頑張って、それでもなんともならないならお姉さんが助けてあげるよ」
そう言って、女性は僕の反応を確かめようともせずに振り返った。髪の毛が体の動きにつれてくるんと回ったが、やはりどういうわけか髪の先はカールしたまま空中で静止した。それで僕は話すことができるようになったことを悟った。
「頑張って頑張って、って言うけど、いったい何をどう頑張ればいいのか俺にはもうわからない。頑張る気持ちだけはある。だから具体的な行動を教えてほしい」
女性はまた振り返って僕を見た。しかしそれだけだった。彼女は後ろ手になって僕のほうに顔を向けたまま永久に固まってしまった。彼女は僕ではなく、僕の後ろにある何かを見ているみたいだ、と僕は思った。
人は緊急事態になると思いもよらない行動力を発揮する。なにも火事場でなくても馬鹿力は出る。たとえば寝起きで異常に気づいたときがそうだ。
そして、目覚めたとたんに自分の中から湧き上がる吐き気に気づいた僕は、自分でも驚くほどの行動力を発揮した。全身の力を使って一気に起き上がり風呂場に直行する。そしてバスタブを見た瞬間、その中に嘔吐した。けっこうな量のゆるい液体がバスタブの底を黄色く染めた。消化しきれてなかったようで、麺状のものがその中に浮かんでいた。それから第二陣も吐き出した。今度は若干白色に染まっていた。
水道で口をゆすぎ、風呂場を出る。部屋のテーブルにはドメスト(風呂場用洗剤)と冬みかんが昨夜のままの状態で載っていた。十個入りネットの冬みかんは四個にまで減っていて、ドメストを入れていたはずの紙コップは床に転がっている。どうやら僕はみかんを食べながらドメストを一杯飲み干したところで気を失ったようだった。季節外れのみかんは高かったので少々もったいない。
「用途以外には使わないでください」とドメストにはそんな注意書きが書かれている。しかし、と僕は思う。僕は最終的に用途どおりに使ったのだ。風呂場用洗剤はちゃんと風呂場にばら撒かれたのだ。僕は自分の考えにひとりで笑った。
油断していた。
直後に襲ってきた吐き気を堪えることができず、僕は自分の万年床を黄色く染め上げることになってしまった。
「公園」の桜は、成長の早いものになると四分咲きくらいにまで成長していた。野芝の生育もおおむね順調だった。
しかし相変わらず聴講登録期間は僕にとって鬼門だった。とりわけ週の最後のG棟での講義はまさに鬼の住む門のようなものだった。広い講義室にも関わらず人が詰めかけ、座る場所が無くなるのもそうだが、何より三限の授業では扉の開くのが遅いのだ。そのため、席を確保しようと思えば必然的に秩序のない行列に巻きこまれる。手持ち無沙汰になった僕は、しかし立ちながら寝たふりをすることもできない。明らかな苦痛だった。
たとえばこんなことがある。
列に並んでいるときに、騒いでいた集団のひとりがよろけて僕にぶつかってきたりする。ある人は何も言わない。またある人は頭を軽く下げて済ませる。そしてまたある人はすみませんと言う。そしてそしてまたある人は僕に鋭い一瞥を加えて大仰に僕から離れ、隣にいる恋人らしき男の手を握ったりする。
こういうとき、僕はどうしたらいいのだろう。
「とにかくやるしかないんじゃない?」
だからなにを?
「ん……わかんない」
彼女は顎に手をあて、首を傾けてそう言うのだ。
わからないってなにさ。無責任だなぁ。
「そんなこと言ったってしょうがないでしょ! わたしのせいじゃないんだから」
彼女は怒ったように唇をとがらせた。
僕はいつのまにか海沿いの田舎道にいた。彼女は白いワンピースを着て、白くてつばの広いソフトな風合いの帽子をかぶっていた。横から風が吹くと、ワンピースの裾がひらひらと舞って、帽子が飛ばされかけた。彼女は慌てて片手で防止を掴んだ。その動作が微笑ましくて僕が笑うと、彼女は俯いて照れたように笑った。彼女のもう片方の手は風にはためく髪の毛を押さえていた。肩の高さまでの髪は若干栗色が混ざっていて、さらさらだ。
彼女がかなりかわいい部類に入ることは理解できた。しかし目は? 鼻は? 口は? 化粧はしているのだろうか? そういう具体的なことが、僕にはいっさいわからなかった。彼女はまるでデータ上の存在のようだった。
「みっくん、お母さんによく言われたでしょ?」
そうだったかもしれない。何を言われたのかもわからないまま僕はそう思った。そして、僕は「みっくん」であるという事実を自然に受け入れている自分に気づいた。不自然だとは思わなかった。
「わたしもみっくんのこと信じてる。お母さんだって、お父さんだって……船口さんだってきっとそうだったんだよ」
船口――そうだった。彼女の名前は三上夏美。僕の義理の妹。そして、養父の名前は三上忠晴。養母が三上千鶴。船口は船口瞬といって、僕の親友だった。
「そう。親友……だった」
彼女は――夏美は僕の実の妹でもあった。
「そう。実の妹……でもあったの」
「だった」「でもあった」と繰り返す夏美の真意が僕にはわからなかった。いや、本当はわかっていたのかもしれない。しかし、本当に自分がわかっているのかいないのか、それすらも僕はすぐにわからなくなってしまった。
「わたしたちは、ひょっとしたらみっくんの人生にありえたかもしれない無数の可能性。でもみっくんの今の人生はわたしとは関係ない」
僕はそっちがいい。幼馴染のような夏美と、僕を引き取ってくれた伯母さんと、いつも笑いに満ちていて、けれどもいつも的確な示唆を与えてくれる忠晴といっしょに、いつまでもあの島で暮らしていたい。そしてみんなを呼ぶんだ。僕の友だちたちを。最高の友だちたちを。
「だめ」
どうして!
「わたしもあの二日間は楽しかった。でも、三日目に悲劇が起こる」
知ってる。だって僕がつくった世界だ。僕が引き起こした悲劇だ。
「…………」
夏美は最後まで僕を信じてくれたじゃないか。伯母さんも忠晴も、船口だって、最後の最後まで僕を信じてくれた。信じようとしてくれた!
「みんながみっくんのこと好きだったから」
好きだった、なんて、そんな……!
「さようなら、みっくん。みっくんの人生に、わたしたちはもう必要ないから」
夏美は身を翻して、そのまま歩き去っていく。いつのまにか風もやんでいた。
僕はよっぽど叫びたかった。しかしいつものように/いつかのように、声は出なかった。そして夏美は風景に溶けこむようにして消えた。
我に返ったとき、僕はG棟の階段で女子に腕を掴まれていた。周りには人がいなくなっていた。
「大丈夫ですか?」
「……大丈夫、です」
「そうですか、よかった」
その女子はそう言って僕の腕から手を離した。「いきなり倒れそうになるからびっくりしましたよ」
「……すみません」
その女子は僕が知っているはずの女の子に似ていた。白いワンピースを着ていたある女の子に似ていた。しかし似ているといっても、彼女ほどかわいいというわけではなかった。栗色の髪はくせっ毛で、襟足のところが思い思いの方向に跳ねていた。それでも、こげ茶色の瞳をしていること、小柄でかたちのいい鼻をしていること、下唇より上唇のほうがほんの少しだけ大きいこと、そしてどうやら化粧があまり上手くなさそうなこと。そういうことはよくわかった。
「ありがとうございました」
僕は授業に出ようと階段を上った。しかしすぐに後ろから「あの」と声をかけられて振り返った。
「G410の授業に出るんですか?」
「そうですけど?」
「あの授業、なんか人文学部はお断りだそうですよ。なんか人が多かったから急遽そうしたとかで。だからわたしもはねられて、それで仕方なく帰ろうとしてたところで……」
それはつまり同じく人文学部の僕も、この階段を上っても意味がないということだった。
しかし僕は本物じゃない。ニセモノだ。だから僕はこの階段を上る。
そしてもう一度「あの」と言われても、もう振り返らなかった。
「人文学部の人……ですよね?」
「違いますよ」
僕は振り返らずに階段を上りつづけた。
「農学部です」
女子に掴まれた二の腕がまだじんわりと熱を持っていた。しかし僕はすべてを無視して410の扉を開けた。
断食を始めてから六日が経っていたらしい。
二日目はなんともなかった。「公園」への散歩もつつがなくこなせた。
「公園」は日に日に春の趣を増していくようだった。花粉や黄砂が空気中に混じる初春の雰囲気を過ぎ、一気に空気がきれいに、おいしくなる。桜はその空気を吸って急速に成長しているみたいだった。大半の桜が花開き、草木が色をつけはじめていた。気の早い花見客は今週末にも花見を計画していると思われた。
講義への出席もできるかもしれないと思い、学校へも足を運んでみた。その結果、僕は軽く失神してしまったようだった。他人に迷惑をかけるのは本意ではなかったので、僕はこれからずっと部屋から出ないことに決めた。
三日目に入ると、お腹がしきりに抗議の声をあげはじめた。その声はなぜだかとても切なげで、いっそのことかわいいといっても差し支えないものだった。お腹の鳴る回数を数えてみたが、百も数えないうちに意識が飛んでしまって、また一から数えなおすことが多かった。
四日目に時間の感覚が曖昧になってきた。時間を確認したつぎの瞬間には、時計の短針が半周しているということもあった。
そして気づいたときには部屋は真っ暗だった。僕はよろよろと立ち上がって部屋の電気をつけた。携帯の液晶を見ると五日目が飛んで六日目に突入していたことに気づいた。
そして僕は外へ出ることにした。
認めよう。僕の精神は非常に弱い。僕には餓死は無理だ。
店の扉を開けるとおいしそうな匂いが漂っていて、僕のお腹はひときわ盛大に鳴いた。カウンターに座って、中華そばのAセット大盛りを注文した。あの人がいなくても、僕は幸楽苑が好きだ。
麺を食べつくし、餃子をふたつ残したところで僕はやっと人心地ついた。それから、周りを見回す余裕が出てきた。
タイミングはよかった。僕の目は今まさに入り口から入ってきた人に注がれた。
あの人だった。
僕は驚いた。あの人の服装がおしゃれになっている。今日はコットンのジャケットにロゴの入ったTシャツをあわせていた。下はブラックジーンズで、どことなく使い古した感があった。そしてなにより驚いたのは、彼が隣に男友だちを連れていることだった。僕は今の今まで彼が誰かといっしょにいるところを見たことがなかった。
いつものカウンターではなくテーブル席に腰かけたあの人は、好きだった女の子に振られたのだと語った。僕が今まで聞いたことのある中でもっとも明るい声だった。そして、彼はたいしてショックじゃない、だからもともとそんなに好きでもなかったんだ、と僕の聞いたことのない大きな声で話していた。
彼が連れてきたのは、頭の悪そうな顔をした男だった。男は彼の話を聞いている間中、ずっと曖昧な笑顔を浮かべていた。そして彼が話し終え、沈黙が降りると、男はすぐに話題を変えにかかった。あの人もそれに便乗した。
僕は違うと思った。あの人の前でもなく、隣に座るべきなのは、そんな冴えない男なんかじゃなくてきっと素敵な女の子で、たぶん彼が好きだと言う女の子がいちばん似合っているのだと僕は思った。
「そうだろ……?」
僕は目の前のラーメンのスープに向かって語りかけた。湯気がかすかにちぢれて飛んだ。
彼はもっと弱さを見せたっていい。強がらなくてもいい。恨み言を言ったりしてみてもよかったし、自分の環境の不運さを責めてみたってよかった。誰もそれを言ってあげないのなら僕が言うし、たとえ誰が否定したとしても僕が保証する。
しかし僕はひとりだった。この日、僕ははじめて食べ物を残して店を去った。
僕はいつのまにか多くの聴講許可とわずかの不許可を手にしていた。もっとも気の重かった聴講登録期間は過ぎ去っていた。とはいえ、僕の目の前にはいまだ先の見えない茫漠とした未来が横たわっているかのようだった。
そのひとつがゼミだった。発表など機械的にこなせばよかったのだが、ついやってしまうのだった。その結果、僕は発表を終えたゼミ室で質問も意見もない刺すような沈黙の中に身を置くことになる。
発表内容が高度すぎて質問が浮かばないのだったらいい。論旨が強固すぎて批判を受け付けないのだったらいい。しかし僕の発表というのはそうではなかった。僕の発表はいつも独善的で、個人趣味に満ちているのだ。そこに僕のキャラクターというべきものがあわさって、彼らの沈黙に拍車をかける。必然的に、僕の討論相手は困ったような笑顔を浮かべる教授ひとりということになった。
終了の時刻になって教授が話を締めくくると、僕はやっとまともに呼吸ができた気がした。そしてそれはほかの学生も同様のようだった。
僕は帰りにいつものようにコダマに寄って、いくつか洗剤を物色した。ほぼ定期的にやってきては洗剤を買っていく僕を、店員は潔癖症の人間だとでも思っているだろう。実際、僕自身もそう思わせるように、様々な用途の洗剤をアットランダムに買うようにしていた。しかし今日だけはそれも通らないはずだ。新聞のニュースで硫化水素自殺が流行っていることを僕が知ったからだ。
以前、練炭での自殺が流行ったときは、おいしいサンマが焼けただけで失敗した。しかし今度は失敗しない自信があった。それも、比較的他人に迷惑をかけないやり方だ。「硫化水素発生中」とかいう赤紙を用意する必要もない。
僕は「混ぜるな危険」の洗剤を二つ持ってレジに並んだ。商品を渡すと、店員の若い男は僕のことを一瞬だけ見てすぐに目を逸らした。彼の茶髪がそっけなく揺れて、僕は千円札を渡した。
アパートに帰って部屋の整理をしていると、僕の携帯がおよそ一ヶ月ぶりに鳴った。
「もしもし?」
「俺だけど、最近どうだ?」
電話の相手は親戚の叔父さんだった。
春休みに二日だけ実家に帰ったときのことは思い出したくもないが、そういう記憶に限って脳裏に強く刻まれているものだ。
実家には無職の母親のほかに、地元の専門学校に通う弟と、東京に出ていた妹が両方揃っていた。父親は相変わらず家にはあまり帰ってこないようだった。母親は「おかえり」と言った。僕は「ただいま」と言った。弟と妹は僕の顔を物珍しそうにしばらく見て、それから興味を失ったように目を逸らした。弟と妹の金髪が似たような孤を描いてそっけなく揺れた。
しばらくぶりに踏み入った元僕の部屋は、雰囲気が一変していた。男の部屋特有のすえたような匂いと、そこかしこに積まれた本の匂いが一掃され、人工的な爽やかな匂いにとって代わられていた。その原因は机の上に置かれた真新しい芳香剤にあった。
僕は結局その夜近所のスーパーで買ってきたオードブルを摘まみながらヱビスビールを飲み、しきりに大学の様子を聞きたがる母親に、若干の真実を大幅な嘘の中にまぶして語った。その合間合間に父親への愚痴を口にする母親に対して、僕は安易に頷くことはできなかった。「でも」で始まる言葉で父親の肩を持つような格好になっていたようにも思う。きっと僕は家族の中で冷静かつ冷徹な人間として通っているのだろう。
そして、翌日そのまま新幹線に乗って実家を離れた。郊外には開発の波が押し寄せていた。
「おまえのお母さんに言われたんだよ」
叔父さんは電話口でそう言って続けた。
「さりげなく電話をして様子を聞いてくれって」
そのやり方がすでにまったくさりげなくないのだが、しかし僕はそれよりも気になることがあった。
「様子を聞いてくれってどういうことですか? なんか僕変なこと言いました?」
「ほら、おまえの大学で自殺者が出たっていうだろ」
「え? そうなんですか……」
「知らないかな? ほら、最近話題になってる、あれ。なんだっけな……新聞は取ってる?」
言われなくても僕はすでに立ち上がっていた。隅に積んである新聞を数日分まとめて掴み、今日の分の社会面から眺めていく。
「だからさ、おまえのことが急に心配になったんだと。息子の自殺を心配する親ってのはどうなのか知らんが、まぁそういうもんじゃねえかっていう気もするな。……どうだ、あったか?」
新聞をめくっていた僕の手が三日前の記事で止まった。目線が一点に吸い寄せられる。社会面右側、広告欄の上。
「で、なんだったっけ、あれ」
「……硫化水素、ですね」
「そう、それ。今回は二次被害とかはなかったみたいだが」
「そうみたいですね」
「最後の最後で人に迷惑をかけちゃ話にならないよな。……ま、おまえは大丈夫だと思うが」
「大丈夫ですよ。僕は馬鹿じゃない」
「そうだな。……いや、それだけだ」
「…………」
「お母さんはいろいろ気を使いすぎなんだよ、きっと。家族で唯一大学に進んだってこともあって、自慢と表裏一体ってところじゃないかな。俺のほうからも気を揉んでくれってところだと思う」
「僕は大丈夫です」
「そうだな。まぁ、もしなんかあったら俺に相談してくれよ」
「はい」
「それじゃあ」
携帯をパタンと閉じる音が部屋に響いた。ふたつの洗剤が壁にぶつかって耳障りな音を立てた。
「公園」に足を踏み入れるとふっと風が吹き、芝生と、それからそこに立つ僕を同時に撫でていった。芝生はさぁっと気持ちよさそうな音を立て、僕はここまで歩いてきてかいた汗が引いていきそうな予感を覚えた。風は芝生に生命の息吹を伝え、僕には涼しさを与えるのだと僕は思った。目を細めながら空を見上げると、どこまでも透き通っていきそうな青空の中に、赤ちゃんが作った切り絵のようなかたちをした雲がふたつ浮かんでいた。そうして僕は遊歩道に入った。
桜は満開といってもよかった。いつ花見客がやってきてももうおかしくなかった。しかし僕は、花見客が残していったわずかなゴミさえも発見できなかった。
ふと、すぐ近くの手すりの上に二匹の虫がいるのに気づいた。一見したところアブのように見えたが、よく見ればアブではないことがわかった。アブのニセモノか、と僕は思った。二匹の虫はお互いに背を向けあって、お尻をくっつけあっていた。片方の虫の足がときどきぴくりとする以外に、二匹の虫にはまったく動きがなかった。まるで置物のようだった。
しかしその二匹の虫はすぐにまとめて潰される。ぱんっと金属を叩く小気味いい音がする。虫の潰れる音はまるで聞こえない。感触はほとんどなく、血もまったく流れない。そのままたっぷり一分ほど手すりをさすったあとに手のひらは離れる。白い手すりにはそこだけ色の変な汚れが残る。そして手のひらにも同じような汚れがつく。ヒゲ剃りシェーバーに残るヒゲの残骸みたいなものがところどころに見える。そしてその手のひらは僕の手のひらだ。そういう想像をする。
しかし実際には僕は馬鹿じゃないからやらない。彼は馬鹿だとしても、僕は馬鹿じゃない。
新聞が伝えていた「公園」がこの「公園」なのかはわからない。ドラマでよく見る人型を象った白線も、黄色いビニールテープもなにも無かった。なんの痕跡も残されていなかった。
彼は桜の下で死にたかったのだろうか。西行のように、または梶井のように、花の下で春死にたかったのだろうか。
しかしことはそんなに簡単には運ばない。実際には彼は防護服を着た職員の事務的な手で運び出され、隔離されたところにしばらく放置されただろう。そして、周辺住民の疎ましげな視線を受け、新聞には自殺者としてではなく硫化水素使用者として報道された。
彼は馬鹿だ。けれども僕は馬鹿じゃない。
そのままどのくらいの時間が経ったのかわからなかった。そのあいだ、二匹の虫は足をぴくりとやる以外に動くことはなかった。
しかしそのとき、唐突に風が吹いた。僕は涼しさを感じ、芝生は心地よさそうな音を立て、二匹の虫の片方が急に飛び去って一匹だけが残された。一匹だけ残されてもその虫はまったく微動だにしなかった。僕は虫にさらに近づいた。やっぱりアブでもなく、ハチでもなかった。確かにニセモノに違いなかった。しばらくすると、残されたその一匹もどこかに飛び立った。僕はそれを目で追おうと試みたが、すぐに見失ってしまった。そして「公園」には僕と芝生と遊歩道と白い手すりと広い空だけが残された。
僕は再び歩き始めた。しかし四歩歩いたところで四歩引き返し、手すりを手のひらで思いっきり叩いた。バテョン、という感じの音がした。バテョン、という感じの音がした。バテョン!バテョン!バテョン! 僕は手すりを叩いた。白い手すりには赤い変な汚れが残った。僕の手のひらの皮は剥けた。
それから僕は開店を待ち、コダマでマキロンを買って手のひらを消毒した。初めて買った本物の医療品は猛烈にしみた。
僕は便器に頭を突っこんですべてのものを吐いた。吐いても吐いても口からは次々と黒い液体が出てきた。目や鼻や口からは、涙なのか鼻水なのかよだれなのかわからないものが流れつづけた。唐突に便意を催したが間にあわずにパンツの中に漏らした。
吐き気が治まってくると、今度はバスルームに漂う猛烈な悪臭に我慢ができなくなってきた。僕はシャワーを使ってすべてを洗い流した。その場で裸になって服を洗い、体にシャワーを浴びているともう一度吐き気が襲ってきた。もはや出すものなどあろうはずもない、黒い胃液を吐ききると、それもすぐに洗い流した。バスルームは一見きれいな元通りの姿になったが、悪臭は抜けきらなかった。
換気扇をつけてバスルームのドアを閉める。すると、ドアに引っ張られるように体が傾き、床に膝を打ちつけた。
完全に体の調子がおかしくなっていた。
片手鍋でタバコを百本煮詰めて作ったスープはもうほとんど残っていなかった。砂糖を入れればチョコレートのような味になると聞いていて、実際そのとおりになったのに体は意志に反して抵抗した。数日に渡って続けていたが、ほとんど飲んだそばから吐き出してしまった。その間、昨日か一昨日かその前か、ゼミの教授から二回くらい電話があったが、僕は出なかった。着信履歴に家族と親戚以外の履歴が二件だけ増えていた。
僕はそのまま部屋に戻って、裸のまま硬い床にくず折れた。お腹は十分減っていたが、何も口に入れる気にはならなかった。そうか、餓死とはこうしてやるものなのだな、と思いながら僕は意識を失った。
しかし僕は死ねなかった。
起きるとすぐに部屋の中の異臭に気づいた。鼻の奥が痛くなるほどの異臭だった。鍋の中のスープは干上がって藻が生えたようになっていた。携帯を手に取ると、意識を失ってからたぶん一日しか経っていなかった。デジタル表示は朝の時刻を指していた。教授からの着信履歴がさらに一件増えていた。
僕はバスルームに入ってシャワーを浴びた。バスルームの匂いはほとんど除去されていたが、それがかえって僕の体の臭さを強調していた。僕は浴びていたシャワーを顔にあて、そのままお湯を口に含んで飲み下した。久しぶりのまともな液体に胃が蠕動し、きりきりと痛んだ。
それから服を着て、震える足を引きずるようにして外へ出た。
もはや鳴る元気もないほど、僕のお腹は食べ物を欲していた。しかし僕にはそんなものにはまったく興味がなかった。道ですれ違った若い男が通り過ぎざまに顔をしかめたが、僕はあらゆるものに興味を無くしていた。僕に必要なのはもうタバコしかなかった。
近くのコンビニに入って「いらっしゃいませおはようございます」と僕に声をかけたのは、栗色をしたくせっ毛の女の子だった。化粧はあまり上手くないようだった。胸の名札には「ひるま」と書かれていた。
僕は俯き加減で「ハイライト5個ください」と言った。彼女はレジカウンターの中を移動した。
ひるま、か。どういう漢字を書くのだろう。比留間? それともまさか昼間だろうか。昼間さんが朝コンビニで働いている。僕はそんなくだらない想像をして笑った。だから彼女がなにをしているのか詳しく見ていなかった。
「こちらでよろしいですか?」
と言って彼女が差し出してみせたのは、ひとつのコロッケだった。驚いて見上げると、こげ茶色の瞳がふたつ僕を見ていた。僕は反射的に頷いた。違うとは言えなかった。
紙に包まれたコロッケを丁寧に受け取り、百円を支払って二十円のお釣りをもらっても、彼女は僕を見ていた。
この間がどういう意味を表すのかは問題ではなかった。
ありがとう。また来ます。
僕が言いたいのはたったそれだけだった。それを言えさえすればよかった。
しかし僕はそんなことすら言うことができなかった。声が出なかった。それどころか口すら動かなかった。そして僕はこげ茶色の瞳から顔をそらし、振り返らずにコンビニを出た。
外は春の日差しに満ちていた。僕はタバコを買うために少し離れたコンビニまで歩いた。歩きがてら暖かいコロッケをかじった。
道沿いの桜はもうほとんどが緑の葉に覆われていた。もう少しすれば桜は毛虫の住処に取って代わられるだろう。そうなると、あれだけ賑っていた桜の下から人が消えて、逆に避けられるようになるのだ。
すきっ腹には、コロッケは胃にしみた。衣のかけらが治りかけの手のひらに落ちてチクリと痛んだ。だから僕が泣いているのはそういうことが原因であって、それ以外では絶対にない。
野菜コロッケ80円