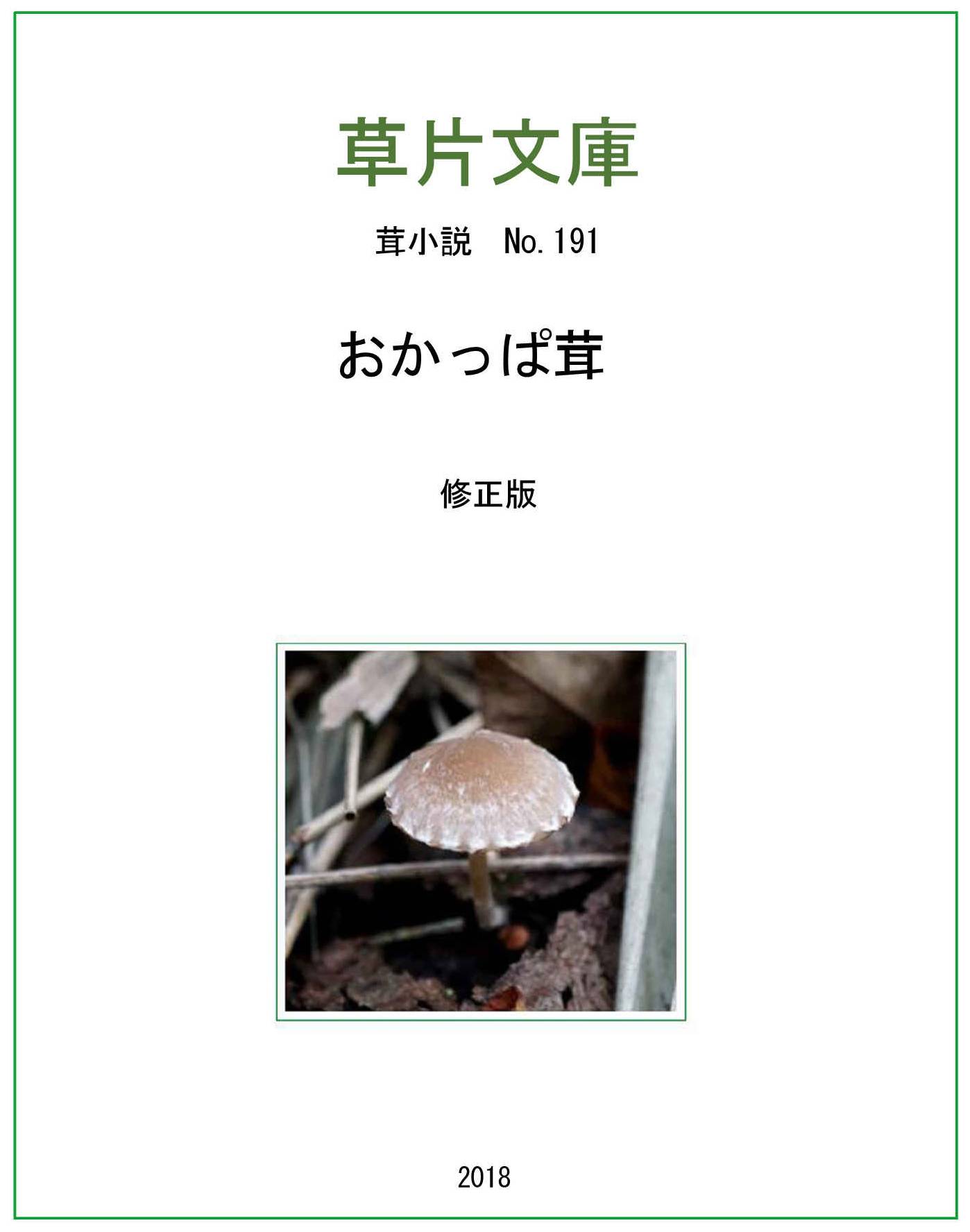
おかっぱ茸
茸のファンタジーです。
朱色の小さな茸が、隣に生えている紫色の茸に打ち明けた。
「にいちゃん、頭の先がむずがゆいの」
「どうしたんだい」
「わからないわ、あ、そうそう、昨日、茶色のもじゃもじゃした毛虫があたいの傘の上に這い上がってきたわ」
「だけど、毛虫は我々を食べるわけではないし、なにもしないだろ」
「ええ、ちょっと、休んだら、またもモコモコと下に降りると行っちゃった」
「それじゃあ、毛虫のせいじゃないね」
「何だろう、上から見ても傘はどうにもなっていないよ」
「でも、かゆいのよ」
「座頭虫の爺ちゃんがきたら、たのんでやるよ」
そこに赤い座頭虫がたくさんの小さな座頭虫を連れてやってきた。
紫色の茸が驚いた。
「子供がたくさんいるんだね」
「茸のぼうず、ちょっと大きくなったな、この子たちは孫だ」
若作りの座頭虫爺さんだ。
座頭虫は細い足を一本、朱の茸の頭の上にのせて、なでた」
「かわゆいの、朱色のお嬢ちゃん」
「あ、気持ちいい、もっと掻いて」
そう言われて、座頭虫はびっくりした。
「どうしたんだい、嬢ちゃん」
「うん、ちょっと前から頭の上がむずむずして、痒くなったの」
「どうもなっとらんがな、そうだ、孫たちや、朱色茸の上に登って、掻きなさい」
座頭虫の孫たちは、いさんで朱色茸をのぼっていった。
「真ん中掻いて」
赤い茸がたのむものだから、座頭虫の孫たちは茸の柄をいそいで登って、傘の上で足踏みをした。
「気持がいいな、寝ちゃいそう」
朱色茸がこっくりこっくり居眠りを始めたので、孫たちはみんな羊歯の上におっこちた。
「ありゃ、朱色茸のお嬢ちゃん寝ちまった、儂たちもいくかい」
座頭虫の爺さんは、孫を連れて餌を探しに行ってしまった。
「ありがとう」
紫色の兄貴はお礼を言って見送った。そのあと紫茸も頭の上が痒くなってきた。
金蝿が飛んできた。
「どこにいくの」
「いい匂いがするんでね、そこに向かってるんでさ」
茸に匂いは感じない。
「何の匂いだい」
「茸だよ」
「僕も茸だけど匂わないかい」
「匂うけどね、止まりたくなるほどじゃないね、」
蠅はスッポン茸の頭についている黒緑色のねばねばの匂いが大好きなのだ。
「ちょっと頭に止まって掻いていってくれない」
「ちょっとだよ」
紫色の傘の上に止まった蝿は、頭のてっちょうに口を伸ばしてぴちょぴちょなめた。
「くすばったい、なめるのじゃなくて、足で掻いてくれないか」
「頭の上が匂っているよ、ちょっとなめたくなるようだね、スッポン茸ほどじゃないけどね」
そう言って、それでも、金蠅は頭の上を掻いてくれた。
「隣にも、匂う茸があるね」
金蠅は寝ている朱色茸のお嬢ちゃんの頭に止まって舐めた。
「いい香りだ」と舌なめずりをして、スッポン茸に向かって飛んで行った。
「あれ、なんだろう、頭の上をなめられた」
朱色茸が目を覚ました
「金蠅の兄さんが頭が匂うってなめていったんだよ」
「あら、いやだ、汚れたのかしら、痒くなったり、匂ったり、雨が降らないかしら、洗わないと」
「そう言えばここのところ雨が降らないね」
二つの茸は木々の中から空を見上げた。秋晴れだ。茸にとってはいい季節だよ。
さて、座頭虫の爺さんと孫たちは、二つの茸の頭を掻いてから餌を探しに、林の下草の中を歩いて行った。
「じいちゃん、あの茸は食べられなかったの」
「食えないことはないけどな、もっと育って、熟した茸の方がうまいんじゃ」
座頭虫は虫やミミズ何でも食べる。茸も好きな奴がいる。
みんなで、しょろしょろと歩いていくと、亀虫が死んでいる。よく見るとそこから橙色の茸が生えていた。
「おい、ほら孫たちよ、いいものがあった」
若づくりの爺さん座頭虫が、亀虫の回りに孫たちを集めた。
「これはな、冬虫夏草という、虫に生える茸なんだよ、こいつは亀虫茸だ。虫の干物と茸がいっぺんに食べられるんだぞ、いいものがあったな」
「どっちから食べるの」
「肉と野菜、どっちでもかまわんよ、食べたい方から食べなさい、だが、両方食べるんだよ」
座頭虫の孫たちはまず、干物になった亀虫から食べ始めた。爺さんは背が高いから亀虫茸から食べた。
「じいちゃん、もうお腹いっぱい」
「旨かったな」
亀虫茸は全部食われてしまい、亀虫も羽が残っているだけだった。
「どこかで昼寝をしような」
爺さん座頭虫は若いつもりだが、やっぱり疲れる。
ちょっといくと、立派な紅天狗茸が生えていた。
「わしゃ、この茸の下で昼寝をするから、おまえたちは遊んでいなさい」
冬虫夏草と虫を食った座頭虫の孫たちは遊びの時間だ。爺さんは茸の傘の下で足を伸ばした。孫たちは大きな茸に登っていくと、紅天狗茸の平らな傘の上を走り回った。白いぼちぼちを飛び越したり大騒ぎ。
紅天狗茸はいやな顔を一つしないで、座頭虫の孫たちを遊ばせていた。
しばらく経つと、紅天狗茸が孫たちに言った。
「おまえさんたち、おもしろいかえ」
「うん、おもしろい、おもしろい」
孫たちは一斉にうなずいた。
「ちょいと頼まれてちょうだいな」
紅天狗茸が頭を揺すった。孫たちはきゃあきゃあと喜んだ。
「頭の上を掻いておくれよ」
「いいよ」
座頭虫の孫たちは、紅天狗茸の傘の上を駆け回りながら、足でカリカリと掻いた」
「おお、気持ちのよいこと」
うっつらうっつらしていた座頭虫の爺さんが、頭の上の方で孫たちが騒いでいるのに気がついて目を覚ました。
「こりゃ、なに騒いでいる」
爺さんが背を高くすると、紅天狗茸の傘の縁から孫たちが顔を出した。
「紅天狗茸のおばさんが、頭掻いてくれって言うから、掻いてるの」
紅天狗茸が爺さんに言った。
「いやね、一昨日から、頭がむずむずして、かゆくなってね、お子さんに掻いてもらってますのよ」
「そりゃ、よかった、孫も役に立てて」
「おや、お子さんじゃないんかね」
「孫だよ」
「若作りの座頭虫の旦那だね」
そう言われて、爺さん座頭虫はまんざらでもない顔をして、
「それじゃ、儂も掻くお手伝いしようかね」
と傘の上に登った。
「このあたりかね」
爺さんは傘の真ん中あたりを足で掻いた。
「おお、気持ちがいいわね」
爺さんは傘の上で背を高くした。紅天狗茸の背も高い。爺さんは遠くまで見渡せる。離れたところにスッポン茸が生えている。そこで蠅がぶんぶんまっている。なにやらもめているようだ。相手は虻のようだ。
「蠅と虻がもめてるようだ」
「スッポン茸のとりあいでしょうよ」
「そんなに、スッポン茸は旨いのかね」
「あの茸はおいしいのよ、だけど蝿や虻は食べるのじゃないの、あのいやな匂いが大好きなのですよ」
「ちょいと行ってみるよ」
「そうかい、気持ちよかったよ、また明日も来ておくれよ」
「ああ、このあたりは毎日通るよ、さあ、孫たちいくぞ」
そのかけ声で、孫たちは茸から飛び降りた。
「ありがとさんね」
紅天狗茸が声をかける。
座頭虫たちはスッポン茸の生えているところに向かった。
スッポン茸の回りでは、金蠅と虻たちがぶんぶんと飛びながら言い合いをしていた。
「俺たちがやる」
「いや、俺たちだ」
なにを騒いでいるかと思いきや、スッポン茸が「傘のてっちょうのまわりが痒くてな、誰か掻いてくれないか」と言ったことから始まったらしい。
金蠅が「自分が掻いてやるよ」とスッポン茸に止まろうとしたら、
「いや俺がやる」と虻が体当たりをした。
それからいざこざが始まって、仲間が集まってきたというわけである。
座頭虫たちが到着するとスッポン茸が困惑顔で、
「まいったな、まさか喧嘩が始まっちまうとは思わなかったな、俺は頭のてっちょうを掻いてもらいたかっただけだがな」、そう言った。
座頭虫は長い足を延ばしたが届かない。べたべたしていて登ることもできない。
「今日は茸の頭が痒くなる日だな」
座頭虫の爺さんがつぶやくと、スッポン茸が、「なぜだね」と聞き返した。
「どうしてだかわからんが、朱と紫の茸の子供も紅天狗茸も頭が痒いと言ったので掻いてやった」
「そうか、それにしても頭が痒い」
蠅と虻はスッポン茸そっちのけで、ぶつかり合いをしている。
そこに蜂が飛んできた。
「お、いいところにきた、蜂どん、尻の針でスッポン茸の頭の先っちょを突っついてくれんか」
座頭虫がたのむと、蜂はおいきたと、スッポン茸の頭を刺した。
「ひょー、利く、気ー持ち、いい」
とスッポン茸は大喜び。
「どうして痒くなったんだい」
蜂は針でちくちくスッポン茸のてっちょうを刺した。
「わかんねえ、急なんだよ、昨日からだよ」
「伝染病じゃないといいけどね」
「そうじゃね、それじゃ、蜂どん、頼んだよ」
座頭虫の爺さんは孫たちをつれて、自分の巣にもどった。
次の朝、朝御飯を食べに、座頭虫の爺さんは孫を連れていつもの道を歩き始めた。昨日のように、亀虫茸のようなバランスのとれた食べ物があるといいのだが、と思いながら、先頭を歩いていく。
孫たちはてんでんばらばらに、爺さんのあとを付いて行く。
朱色と紫色の茸が、昨日よりかなり大きくなって立っている。昨日は子供、今日は青年といったところだ。思春期だろう。何せ茸は一晩で大きくなる。
朱色茸が座頭虫の爺さんを見つけた。
「あら、おじいさん、昨日はありがとう、気持ちがよかったわ」
「オー、すっかり娘さんになったな、兄ちゃんはどうだ」
紫色の茸も座頭虫の爺さんにお礼を言った。
「立派な青年だな、どうだ、好きな子ができたのじゃないか」
紫色の頭にちょっと赤味がさした。
「ほら、ずぼしだろう、だれだい」
紫色の茸は、遠くに見える真っ赤な茸をちらっとみた。座頭虫爺さんはそれをみのがさなかった。
「なんだ、紅天狗茸か、おおどしまだ、やめ、やめろ」
そう言われても、紫色の茸の気が変わるわけではない。
「座頭虫のおじいさん、頭の上の痒いのは治ったんだけど、なんだかこそばゆいの、どうしたのかしら」
朱色の茸娘が頭を下げた。
「ちょっくらみてやろうかね」
孫たちはもう朱色茸の傘の上に登って遊んでいる。一匹の孫が登ってきたじいちゃんに「こんなものが生えてる」と言った。
見ると、赤い茸の傘の真ん中に、黒いぽちぽちしたものが生えている。
「なんじゃろうね」
座頭虫の爺さんはぽちぽちはえている黒いものを長い足でなでさすった。
「あれ、くすぐったい、なにしてるの」
赤い茸は身をよじった。
「黒いものが生えておるんだ、昨日痒いと言ったところだよ」
「何なの、おできかしら」
「違うな、ちょっと抜いてみようか」
「あ、痛い」
「抜いちゃいけないようだな、だけど、今のところくすぐったいだけで悪さをしてないなら、問題ないだろう」
「そうね」
紫色の茸もそれを聞いていて、「僕の頭もくすぐったいんだ、ちょっと見てください」と頼んだ。
「いいよ」
爺さんは紫色の茸に乗り移って、傘の上にのぼった。
「同じように、黒いぽちぽちがあるぞ、何だろうね、触ってみると結構堅いんだよ、もう痒くはないかい」
「うん」
「なら大丈夫だ、わしらはこれから朝ご飯だ、元気でいなさいよ、だがな、あの紅天狗茸はよしなさい」
そう言い終えると、座頭虫の爺さんは孫たちをつれて、朝飯を探しに歩いていった。
座頭虫爺さんは紅天狗茸のところにきた。
「おはようさん、どうだい、頭の上は」
「おや、若いおじいさん、今日も孫のめんどうみかい」
座頭虫の孫たちは断りもせずに、どんどん紅天狗茸を登って、頭の上で遊び始めた。
「じいちゃん、くろいぽちぽちがあるぞ」
孫がそう言ったので、爺さんは紅天狗茸にたずねた。
「頭がくすぐったくないかね」
「ええ、頭の上がなんだかこそばゆくてね、どうなっているのだろうね」
「孫が言ったように、黒いぽちぽちがたくさん生えている」
「なんざんしょ」
「わからんね、向こうの若い茸たちの頭にも生えておった」
「流行病じゃないざんしょね」
「だいじょうぶだ、悪いものじゃなさそうだ」
「向こうの紫の茸、いつもこっちを見ているのよ、うつされたのじゃないわね」
「あの青年はいい茸だよ」
「かっこいいものね」
「じいちゃんが、あの紅天狗茸のおおどしまはやめろっていってたよ」
孫の一匹が余計なことをいった。
「なんてことを、いけすかないじいさんだ、まだあたしだってこれからなんだよ」
紅天狗茸が傘を揺すったものだから、孫たちはみんな茸からおっこちてしまった。
座頭虫爺さんはあわてて、孫を連れて逃げていった。座頭虫は走るととても早いんだ。
さて、なかなか旨そうな朝飯には出会わない。
座頭虫爺さんたちがあちこち見回しながら歩いていくと、とうとう、スッポン茸のところにきてしまった。
スッポン茸の足下には金蠅と虻が何匹も死んでいた。
「どうしたんだい、こいつらは」
「ぶつかって死んじまったんだ、こまったもんだ、ここで腐っちまうと、臭くてかなわんよ」
スッポン茸の匂いの方が臭いけどなと、思いながら、座頭虫じいさんは、
「それじゃ、なんとかしてやろう」
と、孫たちをスッポン茸の下に集めた。
「今日の朝飯は、金蠅と虻だ、たっぷり食べなさい」と言った。
本当はしめしめと思っていたのだよ。
孫たちは死んだ金蠅と虻にたかって食べ始めた。
「座頭虫ってのは、そんなものを食うんだね」
スッポン茸がびっくりしている。
「ところで、スッポン茸のだんな、頭のてっちょうはどうなった」
「むずむずして、なんだかくすぐったいんだ」
「そりゃあな、頭の上の縁に黒いぽちぽちが生えたんだ、他の茸たちもそうだよ」
「大丈夫なのかね」
「他の茸も元気だったよ、心配ないよ」
金蠅と虻の死体はあっというまになくなった。
「うまかった」
孫たちはくちくなった腹をさすっている。
「きれいになっちまったな、ありがたい」
スッポン茸は自分が臭いにもかかわらず、綺麗好きのようだ。
「それじゃ、家に戻るぞ」
爺さんの号令のもと、孫たちはぞろぞろと、住処に戻った。
あくる朝も同じように朝ご飯を探しに家をでた。朱色茸と紫色茸のところにきた座頭虫は、茸たちを見て驚いた。茸の頭から黒い細いものがたくさん伸びて、傘からはみ出している。
「おはようさん、どうしんだい、それは」
「座頭虫のおじいさん、黒いものがもじゃもじゃはえてきて、傘を覆っちゃったのよ、困ったわ」
孫たちは朱色茸の上にのぼって、黒いもじゃもじゃの中に入って遊んだ。
「僕の頭もそうなっちまった」
紫色の茸の頭からも黒いものが伸びていた。
座頭虫の爺さんははっと気がついた。
「そりゃ、毛というものじゃないかね、儂のじいさんから聞いたことがある。その昔この林にも大きな動物が住んでいてな、真っ黒い動物で、あんたさんの傘から生えたものとそっくりなもので覆われていた。その動物は熊と言ったな、覆っているものは黒い毛といっていた。きっとそれと同だ」
「どうしてでしょう」
「そりゃわからん、ただ、このあたりによく出てくる、赤鼠も毛で覆われているが、細くて短いんじゃ、だがな毛というのは体を守もってくれるそうだ、ということは、その頭の毛は茸を守るために生えたのじゃなかろうか」
なかなかうがった話である。
「それじゃ、悪いものじゃないのね」
「だいじょうぶじゃ、さて、孫たち行くぞ」
孫たちは、毛の中でもっと遊んでいたかったのだが、腹も減ったので、茸から降りた。
紅天狗茸が見えてきた。赤い大きな傘から、やっぱり毛が生えている。
紅天狗茸には昨日怒られたこともあり、見つからないように迂回しようと思っていたのだが、背の高い紅天狗茸にみつかってしまった。
「座頭虫のじいさん、またきたのかい」
「いや、いや、昨日はすまなんだ」
「そんなことはいいいんだよ、頭に変なものが生えちまった」
「そりゃ、毛と言ってな、動物は皆生えている。体を守ってくれるありがたいものだ、心配いらんよ、向こうの若い茸たちの頭にも生えておった」
「そうかい、それを聞いて安心したよ、おおどしまなどと言ったことは忘れてあげようじゃないか、あっちの羊歯の下にミミズの死体があるよ」
「そりゃ、ありがたい、今日の朝食だな」
ということで、座頭虫たちは羊歯の下の太ったミミズの死体にかじりついた。今日の朝食もなかなかのものだった。
帰りがけに、スッポン茸のところによってみた。
「どうだい、調子は」
スッポン茸の頭からも黒い毛が垂れていた。
「変なものが生えてきて、べたべたにくっつきそうでいやなんだ」
「大丈夫だよ、それは毛なんだ、頭を守ってくれるさ」
「そうなのか」
座頭虫の爺さんは少しばかり世間話をすると孫たちをつれて、住処に帰った。
明くる朝、朝飯を探しに行こうと、家をでたところで、髪切り虫に会った。
「これから、食事かい」
「ああ、孫たちをつれてね」
「両親はどうしたんだい」
「出稼ぎだよ」
「どこへ」
「隣の林にな、あっちには、旨いものがたくさんあるそうだ」
「子供をおいってっちまったのか」
「孫が小さいので、もう少し大きくなったら、わしが連れて行くことになっている」
「そりゃご苦労ですな、俺は暇でしょうがない」
座頭虫の爺さんは、もしかするとと思って言った。
「一緒に、行かないか、仕事があるかもしれないからな」
「そうかい、それじゃ、お供させてもらおうか」
髪切り虫は座頭虫の爺さんと並んで歩き始めた。
朱色と紫の茸が見えてきた。昨日より髪の毛が長くなってたれている。
「ほら、茸に毛が生えてきているだろう、ぼさぼさだ」
「おまえさんたち大きくなったね」
座頭虫のじいさんが声をかけた。
「座頭虫のおじいさん、おはよう、だけど、髪の毛が伸びすぎちゃって」
「そう思って、ほらいい虫をつれてきたよ」
茸たちに髪切り虫を紹介した。
「髪切り虫のだんな、この茸たちの頭の毛をかってやってくれや」
「そりゃいいとも、ぼうずにしちゃうのかい」
朱色茸は頭を横に振った。
「いや、かっこうよくしてちょうだい」
「どんな頭がいいのかな、七三、リーゼント、モヒカンガリ」
髪切り虫は髪の毛のことをよく知っている。
「なあにそれ、髪の毛なんて初めてだから私わからない」
「それじゃ、おかっぱにしよう、マッシュルームカットとも、ボブカットともいうからな」
朱色の茸はうんとうなずいた。
「マッシュルームって、よその国の言葉で、茸っていうことなんだ、ということは、茸カットだ」
髪切り虫は自慢そうに説明した。
「僕もそうして」
ということで、髪切り虫は二つの若い茸の傘の髪をおかっぱにした。
紅天狗茸も毛が伸びて、傘から長く垂れていた。
「茸カットの名人をつれてきたよ、おかっぱ頭にするんだ」
「それどんなのさ」
「若い女の子用だよ」
髪切り虫が言ったものだから、紅天狗茸のおおどしまは喜んだ。
「それにして」
ということで、紅天狗茸もおかっぱ頭になった。
「なかなか似合うじゃないか」
座頭虫は本当にそう思ったようだ。
「次はスッポン茸だ」
スッポン茸の頭からやっぱり毛があふれ出ている。
「おーい、その毛をカットしてくれる虫をつれてきたよ」
「そりゃ助かるな」
「茸カットだよ」
ということで、スッポン茸もおかっぱ頭になった。
「さて、もどろうか」と座頭虫の爺さんが言うと、孫たちが、わさわさと「まだ食ってねえ」と騒いだ。
朝飯を食べさすのを忘れていたのだ。
スッポン茸がそれをきくと、「向こうのホトトギスの根本に茸虫に半分食われて死んだ茸と茸を食い過ぎて死んだ茸虫がいるよ」
「おお、それはありがたい」
早速、座頭虫のじいさんと孫たちは、ホトトギスのところにいくことにした。
「座頭虫のじいさん、ありがとよ、髪を切るのは楽しいからね、俺はこれから、林の中を歩いて、髪をはやした茸がいたら、おかっぱにしてやるよ、ここでわかれようや」
「ああ、それがいい、また、遊びにきてくれよ」
ということで、髪切り虫は林の中に飛んでいき、座頭虫たちは、死んだ茸と茸虫の朝食にありついたというわけである。
その晩遅くになって、髪切り虫が座頭虫の住処にやってきた。
「夜分すまんが、ちょっといいかい」
そろそろ寝ようかと思っていた座頭虫の爺さんは頷いた。髪切り虫は疲れた顔をしている。だけど嬉しそうだ。
「林の中の茸はみんな毛が生えていてね、全部おかっぱ頭にしてやった、喜んでいたよ、マッシュルームカットはやっぱり茸に似合うね」
「そりゃよかったじゃないか」
「じいさまのおかげだよ、暇でしかたがなかったが、おかげでこの林の茸の床屋になったってわけだ」
「茸は一日で大きくなるから、これから毎日大変だよ」
「やりがいがあるよ、ありがとさん、それじゃ、おやすみ」
この森の茸たちの頭は髪の毛で守られるようになった。みんなおかっぱ頭、マッシュルームカットで、幸せになったわけだ。
座頭虫のじいさんは、寝ている孫たちの脇で、長い足をのばした。
そして思った。
ここは三十年前に壊れた原子力発電所の隣の林の中である。まだ人は入ってこない。だから、この森の茸の頭に毛が生えているのを見たら驚くことだろうな。座頭虫は笑った。いい夢を見よう。座頭虫の爺さんは鼾を書き始めた。爺さんの頭にも毛が生えはじめている。
おかっぱ茸


