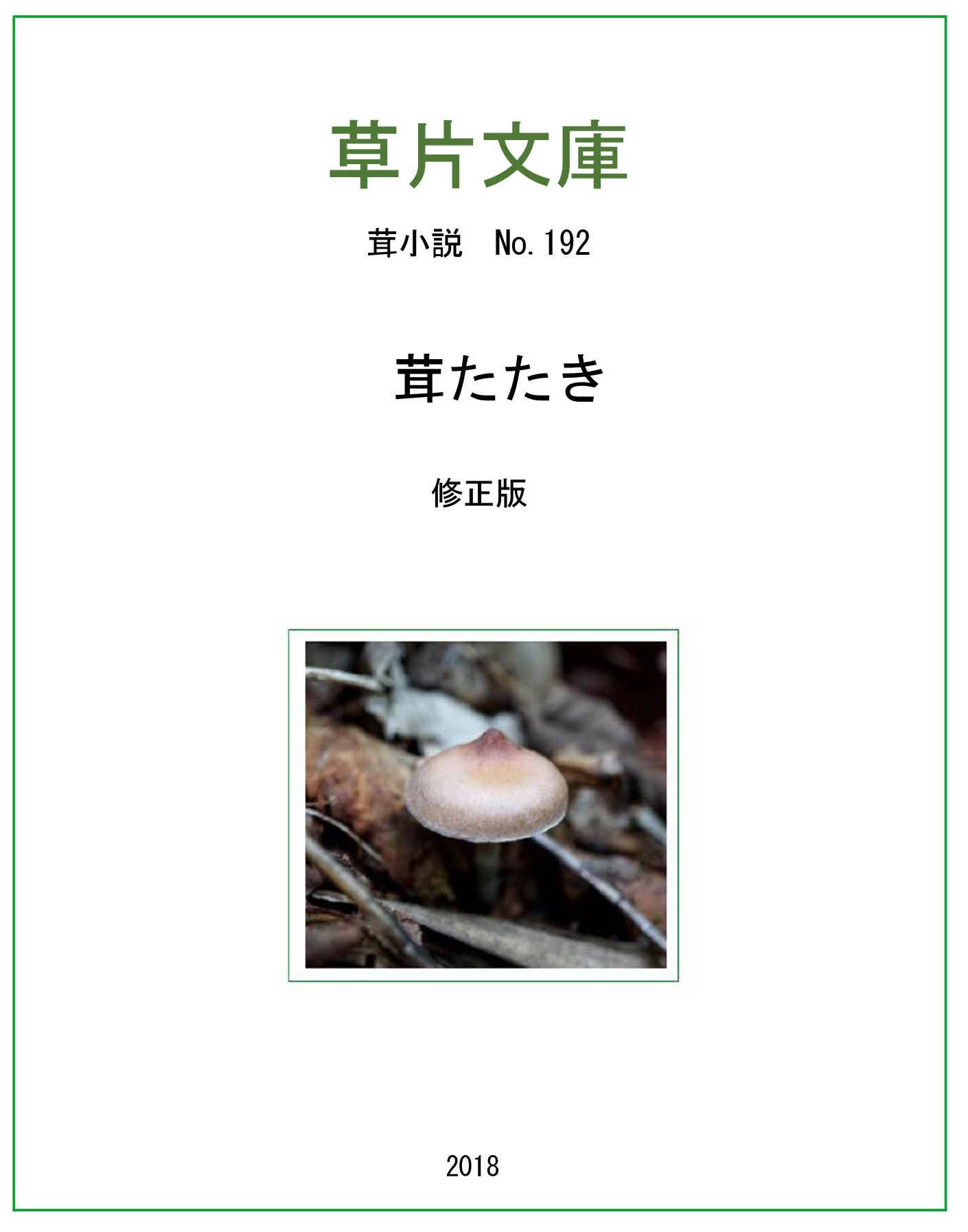
茸たたき
茸の奇妙な小説です。
パン屋で明日の朝食用イギリスパンを買って、電車沿いの道を家に向かってぶらぶら歩いていると、線路のフェンス脇で、ランドセルをしょった二人の男の子がしゃがみ込んで何かを見ている。たまに手を上げて振り下ろすと、しゃがんだままちょっと移動して、下をじーっと見る。しばらくたつと手をおろし何かをたたいて笑いあっている。今度はもう一人の男の子が手を振り上げて、そのまま振り下ろした。またしゃがんだまま二人そろって横に移動している。
なにをやっているのだろう。
近づいてしゃがんでいる子供の頭越しにのぞくと、道脇に生えている白い茸を男の子が手の平でたたいた。
おやおやと思いながら見ていると、たたかれた茸が土の中にはいっちまった。子供たちが横に動くと、そこから白い茸がポコリと頭を出した。
なんだろう。
子供たちは手をたたいて喜んだ。また一人の子が茸の頭をたたいた。たたかれた茸は土の中に消え、すぐに脇から生えてきた。そこでやっと子供たちは私が後ろからのぞき込んでいるのに気づいた。二人とも同時に振り返って私を見た。
「おじさんもやってみる」
一人の子が声をかけてきた。ちょっととまどったが、「面白そうだね」と返事をした。
「いいよ、ほら」
二人がからだをずらした。
私は白い茸の上に手の平を押しつけた。茸はくにょっと曲がった。
「だめだよそれじゃ、つぶれちゃうよ、ポンとたたかなきゃ」
そう言って、一人の男の子が軽く手の平で茸をたたいた。すると、茸は土の中にもぐった。
すぐにまた白い茸が脇に顔をだした。
どうなっているのだろう。
手の平の感触は本物の茸である。
「君たちこの茸いつ見つけたの」
「今日だよ、落ちてた石をけっ飛ばしたんだ、その石が茸にぶつかったんだ、そしたらね茸が土の中にもぐちゃった、それで、消えたところを見たら、穴っぽこになっていて、中は空っぽだった、だけど脇から茸がぽこっと頭を出したんだよ」
近くを見ても穴はない。
「茸がもぐった穴がないね」
「うん、また出てくると前の穴は消えるんだ」
「この白い茸一つだけなの」
二人はうなずいた。
「ここに茸が生えたのは始めてみたよ」
舗装した道だが、茸が生えているところは電車の線路脇のフェンスン下である。土があり草が生えている。
「どうしたんだろうね」
私はそう言ってその場を後にしたが、子供たちはまだ白い茸をたたいて遊んでいた。
家に戻ると、家内が猫にマタタビをやっていた。猫の玉が涎を垂らして寝そべって頭を床にすりつけている。
「クロワッサンあったよ」
家内の明日の朝食である。私はイギリスパン。
「そう、ありがと」
「今ね、小学校の脇の線路沿いの道でね、小学生が茸ひっぱたいていた」
「なにそれ」
「小学生が茸をひっぱたくと、茸が土の中にもぐって、ちょっとたつと脇からまた生えるんだ、またたたくともぐる」
「なに、それモグラたたきみたいね」
「ほんとに茸がでたりはいったりなんだ」
家内が立ち上がって私のおでこに手をあてた。
「熱はないようね」
「ほんとだよ」
家内は大笑いした。
「きっと、新しいゲームおもちゃよ」
そう言われると、そのときには本物に感じたが、ひっぱたいた茸がやけにしっかりしていた、作り物なのだろうか」
「明日そこに行ってみたら」
「ああ」
それで茸の話は終わった。
明くる朝も天気が良かったので散歩にでた。土曜日である。今日は学校が休みなので、子供たちの通学姿がない。
小学校の裏通りにきた。昨日子供たちがいた線路の脇を見た。あった、赤い茸が顔を出している。どう見てもふつうの茸である。と言っても自分には茸の名前はわからない。
まじまじと見たのだが、おやっと思うところがあった。茸に詳しいわけではないが、秋田の温泉宿の次男坊として育ったので、子供の頃は身近に茸がたくさんすぎるほど生えていた。この赤い茸には虫食いがない。子供の頃見た茸はほとんどと言っていいほどどこか欠けていたり、薄汚れていたものである。
やっぱり作り物だろうか。
ちょっと摘まんでみた。弾力がある。プリンプリンしていた。子供たちと同じようにたたいてみた。茸は穴の中に引っ込んだ。見ていると穴が消え、隣から赤い茸が頭を出した。
後ろから声がした。
「もう、とられてら」
子供の声である。振り向くと昨日の二人の男の子がのぞいている。
「あ、いいよ、君たち遊びなさい」
「ほんと、ありがと」
立ち上がると、男の子が赤い茸をたたきはじめた。
「おじさん何回たたいたの」
「一回だよ」
「まだ一回しかやってないんだ、たたきたかったらもっとやっていいよ」
「いや、見てる方が面白い」
男の子がたたきながら言った。
「もう十回だから後九十八回だ」
「それはなんだい」
「百八回たたくとね、違う茸が生えてくるんだ」
「よく知ってるね」
「うん、昨日たたいて遊んでいて、夕方になってきたのでやめようと思ったら、おじいさんが、あと一回たたいてごらん、って言ったんだ、それでたたいたら土に消えたんだけど、すぐ隣に赤色の茸が出てきた」
「それで、そのおじいさんが百八たたくと違う茸が出てくるよって教えてくれた」
「だれなんだろうね」
「たかむらっていってたよ」
「それで赤い茸どうしたの」
「塾に行く時間だから明日にするって帰った、それで今日きてみたらおじさんがいた」
「そうだったんだ、ではおじさんは見ているよ」
のぞいていると、たたかれた赤い茸はぴょこぴょこと引っ込んでは顔をだし、また消えてをくり返した。
「つぎで百八つ」
子供がたたくと、つぎには茶色い茸が顔をだした。
「へえ、おもしろいね」
子供たちはなにも気にせずにたたいて遊んでいるが、なんだか狐に摘ままれているような気持ちで家にもどった。
「どうだったの」
玄関を開けたら家内の声がした。
「茸はあったよ、昨日とは違う色、また少年たちがきてたたいていた」
「ふーん」
「高村って言う人知ってるか」
「この団地の人」
「わからない、高村って名字の人この団地にいたかな、団地の名簿見てよ」
丘陵の斜面を開発した団地には似たり寄ったりの家がたくさん立ち並んでいた。団地の自治会名簿を見ると三百世帯ほどである。最近の若い人は自治会に入っていない人が多いので、世帯数はもっとあるのだろう。それをみても高村という人はいなかった。近くにはいくつか団地があるし、駅周辺にも個人の家はたくさんある。これだけでは調べようがない。
「そのおじさんがどうしたの」
「子供たちに百八つたたくと、違う新しい茸が生えると言ったんだそうだ」
「なにそれ、本当の話なの」
「子供がそう言っていた」
「まるで除夜の鐘ね、煩悩」
そう言われれば、なぜ百八つなのかわからない、当然煩悩という結論になっても不思議はない。
「不思議なことをするたかむらという人なら、大昔いたわよ」
「誰だいそれは」
「名字じゃなくて、名前だけどね、小野篁という人」
「なにやった人」
「閻魔大王さんの手助けをしていた人、地獄に行った人を生き返らせたりしたのよ、黄泉の国に出入りできたの」
「いつ頃のはなしだい」
「平安時代」
「どこにすんでたの」
「京都」
「だけど、何でそんなこと知ってるんだ」
「紫式部よ」
家内は源氏物語を読む会に入って、全部読んだと自慢している。要するに紫式部文学ファンで、庭にも植物の紫式部が大きく育っている。
「篁は紫式部とどういう関係なんだ」
「お墓が隣よ」
「何だ、恋人同士か」
「二人の生きていた時代はちがうのよ、紫式部の方が二百年ほど後なの」
「それじゃ、だめだな」
「おかしいのよ、源氏物語はその当時疎まれてたのよ、嘘で恋愛のことだから」
「嘘や恋愛はいけないのか」
「らしいの、それで紫式部は地獄に行ったのよ」
「そうか、篁が地獄から紫式部を救い出したのか」
「あら案外想像力があるのね、紫式部のその当時のファンが、それじゃかわいそうだから、篁の墓を隣に持ってきて、地獄から救い出してもらったということなの」
「なんてこった、それじゃ、悪人はみんな篁のお守りを買うんじゃないかい」
「そりゃ面白いわね」
「だけど、子供たちの高村さんとは関係ないね」
「そりゃそうね、団地の高村さんを知っている人もいるかもしれないから、近所の人にも聞いてみるわね」
たたくと穴の中に引っ込む茸もおかしいが、百八つたたくと新しい茸が頭を出すと言ったたかむらさんも奇妙である。二つの謎をとく楽しみができた。
「まだ子供たちがいると思うから、もう一度見てくる」
「あなた、子供たちのじゃましちゃだめよ」
家内は猫の玉をいじくっている。
ともかく小学校の裏道に行った。角をまがると、遠目に子供たちがまだ茸と遊んでいるのがみ見える。しゃがんでいる子供たちから離れていこうとしている人の後姿も見えた。茶色っぽい作務衣のようなものを着ている。高村さんじゃないだろうか。
急いで子供たちのところに行き、
「あの人が百八たたくと新しい茸が生えると教えてくれたの」と聞くと、
「そうだよ」と答えが返ってきた。
高村さんは小学校の角を回ろうとしている。
私はあわてて、彼の後を追った。小学校の角にくると、その爺さんは大通りにでるところだった。大通りにでると駅の方向に向かった。少しいったところの十字路で左に曲がれば我が家のある丘陵団地にいく。
高村さんはスタスタと先をいく。歩くのがかなり早い。
後を付いていくと、信号をわたって我が家の団地に入っていった。ちょっとした坂なのだが歩く速度がかわらない。いくつぐらいの人だろう。自分の息が切れる。どの辺にすんでいる人なのか。すると驚いたことに、我が家のある横道に曲がった。高村さんはこの通りにはいないはずだ。通り抜けてどこかに行くのだろうか。
高村さんは我が家の前でとまった。あれっと思うと我が家に入っていく。あ、玄関を開けた。私は走った。玄関を開けて飛び込むと、家内が「なーによ」と飛び出してきた。玉の猫も驚いたように私を見た。
「茶色の服を着た人がきただろう」
そう言うと、家内は不審そうな目で「こないわよ」とまた私のおでこに手を当てた。
「やっぱり熱はなさそう」
どうなっているのだろう、高村さんは確かに我が家の玄関に入った。妄想なのだろうか。
「あなた、茸たたきだとか、百八回たたくとどうのとか、高村さんとか、どうしたの」
答える言葉がなかった。ぼーっと立っていると、
「まだ、その坊やたちはいるの」と聞いたのでうなずいた。
「私ともう一度行くエネルギーはある」
私はまたうなずいた。
それで、家内を伴ってまた小学校裏に行った。すでに三度目だ。
二人の男の子は確かにいた。
家内が近寄ってのぞき込んだ。
「ほんとだ、茸をたたいている」
「面白いんだ、百八回たたくと、新しい茸が生えてくるんだよ」
男の子が家内に説明している。
「百八回って誰に聞いたの」
男の子は顔を上げると、私を指さした。
「そう、でも本当に新しい茸が生えてきたの」
「うん、やってみる」
「やらして」
家内は顔を出していた茶色の茸をたたいた。すると茸が土の中に引っ込んで、ちょっと経つと、隣から顔を出した。
「あら、面白い、もう私はいいから続けて」
家内は立ち上がると、
「あなた、本当だったわね、もどりましょ」
そう言った。
「なにが起こったんだ」
歩きながら家内に言うと
「やっぱり、篁の仕業ね」
私はそう言う世界には疎い。
「家に帰ったら考えましょう」
家内はいやに楽しそうである。
家に帰ると玄関の前に玉がおちゃんこしていた。我家には猫の出入り口があって、二十四時間出入り自由である。
「玉、お出迎えね」
家内に玉がこすりついた。玉は尾っぽを立てて裏の広いほうの庭に歩いていく。猫の後を追って裏庭に行くと藪になっている紫式部の根本に白い茸が生えていた
小学校の裏道で最初に見たものと色は同じだが、まったく違う形をしている。頭の方はでこぼこしていてレースのようなものをまとっている。秋田では見たことはない茸だが、図鑑などでは最もきれいな茸として必ず載っている。
「あ、衣笠茸が生えている、茸の女王様、美しいわね、それだけではないのよ、これツーソンって言って、とてもおいし茸なのよ」
家内もよく知っている。
「それにしても、この茸は竹藪や笹藪に生えるもので、うちの庭のようなところには生えないものよ、どうしたのかしら」
玉がやってきて、ふっくらした前足をその衣笠茸に乗せた。と、ぽんぽんぽんぽんと前足でたたいた。
すると、衣笠茸が土の中にスポッともぐってしまった。
「あれ、小学校のところの茸と同じね」
見ていると、ちょっと離れたところに、ぽこっと頭を出して伸びてきた。
玉は目をキョロットさせて走っていき、また衣笠茸をぽんぽんぽんとたたいた。茸がもぐった。また紫式部の下に顔を出した。
「どうして、こんな状態になるんだ、それに高村さんが俺っていうのはどうしてだ」
なんだかおかしなことが起きている。家内は平気な顔をしている。
「玉、遊んでなさい、私たち部屋に入りましょ」
「どうなってるんだろう」
「世の中なにが起きるかわからないから」
家内はどうしてこの不思議な出来事に理解を示すのだろう。
「ちょっとまってて」
家内はいつものコーヒーを入れて、居間のテーブルにもってきた。
「あなたが追いかけた高村さんがうちに入っていなくなった、子供たちはその人があなただと言った、よく小説ではみかけるシチュエーションよ、そういう場合には必ず何か他のものが化けていると考えるのが順当よ」
「だけど小説の世界だ」
「ええ、でもあなたは見たのでしょ、その高村さんを、もしそうじゃなきゃあなたの妄想で病院いきね」
確かにそうである。
「何かが化けているとしたら、私かもしれないし、うちにいる他の動物」
「まさか、玉が化けているわけじゃなかろうよ」
「わからないわよ、玉が帰ってきたら聞いてみましょうよ」
「猫が話すはずがない」
「ねえ、最近ご近所のお子さんがお母さんに言ったんですって」
「誰だい」
「角の竜田さん、息子さんの裕児君がポケモンゴーがこのあたりでは使えないと言っていたそうよ」
ポケモンゴーというゲームソフトは、全世界を風靡したインターネットを利用した遊びである。スマートフォンなどを見ながら地図をたどって歩いていくと、怪獣が道に現れ、それをとらえて点数をかせいだりするものだそうである。車にぶつかりそうになったり、よその家に勝手に入っていったり、ずいぶん困ったことをおこしていた。それが使えないと言うことは団地にとっていいことだ。グーグルと日本のゲーム会社の合作ゲームだ。
「うちの団地と隣の団地、それに駅の辺りがそういう状態らしいわよ、小学校もはいっているそうよ」
「どういうことなんだ」
「そのソフトを使ってみると、このあたりは真っ白になって、地図も映らないそうなの、だから、ここは怪獣のいない空白地帯だって」
「それがどうしたんだい」
「逆を考えてよ、このあたり普通じゃないから、ポケモンゴーがつかえないのよ」
「普通じゃないって、電波の問題じゃないのかい」
「携帯電話やインターネットは問題ないのよ、ポケモンゴーだけよ」
「ポケモンゴーのソフトに問題があるんじゃないの」
「最近そうなったんだって、それに他いくと使えるのよ」
「じゃ、何のせいなんだ」
「このあたり、なにかの結界につつまれたんじゃない、だからおかしなことが起きるのよ」
「結界ってなんだ」
「ある場所だけ特殊な空間になるということ、心霊スポットのようなもの」
「なんでそんなものがあるんだ」
「わからないわ、神やらが何らかの目的で作っているのよ」
「そうすると、結界の中ではなにが起きてもおかしくないんだな」
そこに猫穴から玉が帰ってきた。
「面白かった」
玉がしゃべった。
「玉、あなた、お父さんに化けたでしょ」
玉がうなずいている。
「どうしてなの、もしかすると、小野篁のせい」
またうなずいた。
「たのまれた」
「タカムラにかい」
「そうだよ」
「なにを頼まれたんだ」
「人の形になって茸を百八回たたくように人に教えろだと」
「それで俺になったのか」
「すまん」
「何で百八回たたくんだ」
「ここに生えた茸は地獄に堕ちた奴らだって、だけど軽微な罪だから地獄の縁で暮らしていた奴らだそうだ、そいつらを極楽に送ってやろうと篁が努力しているらしい、そういう連中を茸にして煉獄に顔をださせ、百八回たたかれると地獄からでられるように、閻魔様と話をつけたようだ」
「たたいた後のあの茸はどうなるんだ、生き返えってもどるのか」
「生き返って、一日かけてこの世を通って、極楽に行くことになるそうだ」
「それじゃ、今庭にはえている衣笠茸は百八回たたかれると人になるのか」
「そうだよ、たたかれた日の夜、零時過ぎってことだから次の日だな、人の世界に戻って、一晩歩き回って極楽に消えていくんだ」
「あれは誰なんだ」
「よく知らんよ、なんでも篁の子孫の一人だとかいってたな」
「玉、小野篁には会ったの」
家内が興味津々に聞いた。
「ああ、会った」
「どんな人」
「いけ好かない奴、自分が閻魔と知り合いなもんだからえばってやがる、庭でおんぶバッタと遊んでいたら、紫式部の下からぬーっと顔を出しやがって、おい、玉、頼まれな、なんて言いやがった」
「それで何でいうことを聞いたのよ」
「へへ、地獄のマタタビはよく利くんだ、そいつをくれたんだ」
「あら買収されたのね、私が買ってくるマタタビよりいいの」
「ああ、残念ながら地獄のマタタビは毒気が強くて、すぐ気持ちがワープするんだ」
「おい、玉、おまえあの茸を百八回たたけ」
「どうして」
「その夜、どんな人間になるか見てみたいんだ」
「自分でやれよ」
「本物の鰹節ご飯やるから」
玉は考えていたが、目をキョロットさせて、
「本節は旨いからな、やってやるよ、明日の朝にたたいておくよ」
「ところで、結界はいつまであるんだか聞いているか」
「百八日なので、後一週間ぐらいだって」
「そうね、三ヶ月前からポケモンゴーが使えなくなったと言っていたわ」
と言うことで、玉はキャッツフードを食べると、「鰹節頼んだよ」と言って、また猫穴から遊びにいってしまった。
「結界って面白いわね、猫と話ができるのよ」
家内はかなり気に入っている。
「明日、鰹節買ってくるよ、削って玉にやってくれ」
「いいわよ」
「明日の夜は早起きしてあの茸がどんな奴になるのか見届けてやる」
「悪いことをした人でしょ、気をつけなきゃ」
「もう悪さはしないさ、極楽に行くわけだろ、ここで悪さしたらまた地獄だよ」
「そうか」
とい言うことで、明日の夜に茸を見張っていることにした。
次の日朝早く、私たちがまだ目覚めないうちに、玉は庭の茸を百八回たたいたようだ。
私が目を覚ましたとき、寝室に入ってきて見上げている。いつものことだ、朝飯をくれと言うことだ。
「ご飯を食いたいのか」
「百八回たたいたら、いや、昨日すでに何回もたたいたから今日は三十八回ですんだよ、ああ腹減った」
「夕飯には本鰹の鰹節を買ってきてやるから、朝はかりかりだ」
「しかたないね」
一階の猫の食事場に降りていって、今日は猫餌のモンプチを皿にいれてやった。
「茸が人間に戻ったらどこに歩いていくのか知ってるのか」
「何でも夜中に町を歩いて、楽しんでから極楽からの迎えを待つそうだよ」
「茸にされた人間は今の人間なのか」
「そうとは限らないようだよ、何百年も茸になるのと待っている奴がいるらしい、なんでも、小野篁しかできないことらしいよ」
「と言うことは、大昔に死んだやつが今の世界に戻ったら驚くだろうな」
「そうだな」
「ところで小野篁は死んだとき、極楽に行かなかったのか」
「現世からはいなくなったが、地獄でお仕事ってわけだろう、何しろ、閻魔大王の大事なご意見番だからな」
「人間だった篁がどうしてそうなったんだろうね」
「地獄の出入り口を見つけちまったんだ、京都の六道の井戸って奴をな、井戸で水を飲もうとしたときに落っこちちまったんだ、意外とどじだよ、しかし地獄に入っちまってからは篁の能力だな、閻魔大王と歌合わせをして負かしちまったようだ、それで篁に地獄に自由に出入り許可が下り、いろいろな能力が与えられたそうだよ。篁が地獄にいる奴の中で、こいつはと思ったら、生き返らせることができる力がね、そして極楽に行くようにしてやることができるんだ」
玉はカリカリを食べるとまた猫穴から出て行った。
庭にでてみると、紫式部の下にあった衣笠茸はもう見当たらなかった。
その日、新宿のデパートで鰹節を買って家に帰った。
夕方、玉には鰹節を削って、たっぷりと秋田小町にまぶしてやった。
「お、うまい、やっぱり本物だ」
二皿も鰹節ご飯を平らげた。
「そうだ、言い忘れたが、地獄から出てきた人間に声をかけちゃいけないそうだ。声をかけて相手が返事をすると、極楽に一緒に連れていかれてしまうということだよ、何でも長い間生きている人間と会っていないので、地獄から戻った人間は話をしたくてしょうがないそうだ」
「そりゃ怖いね、見るだけにしとくよ」
「俺は今日、ちょっと遠出して、遊んでくるから、朝帰りだ」
「そうか、どこにいく」
「教えてやんない」
そう言って玉はでていってしまった。
私は家内に言った。
「今日は早く食事をして寝るからね、夜の十二時前に起きて、どんな人間が現れるか、見ているんだ、お前どうする」
「見なくていい、いつものように寝る」
「どうして、こんな機会はないぞ」
「絶対、話し掛けたくなるもん」
家内はおしゃべりである。
「そうだな、じゃ俺一人で見るよ」
夜の八時にはベッドに潜り込んだ。
目覚ましがなった。
それでも家内はとなりのベッドでいびきまでかいている。
私は着替えると懐中電灯を持って庭にでた。かすかな月明かりがある。
まだ夜中でも寒いといった季節ではない。
そういえば、地獄から出てきた人間に懐中電灯の光を当てていいのだろうか。そうか、今の世は夜でも町中明るいのだから、かまわないのだろう。
目覚ましは十一時半にかけておいたので、十二時までにはあと十分ある。家の軒下に椅子をおいて待った。紫式部の藪の下はぼんやりと薄暗い
あと一分だ。紫式部の紫色の粒々がさわさわと揺れ始めた。
時間だ、いや、まだ出てこない。零時調度とは言っていなかった。しばらく待たなければならいかもしれない。そう思って顔を上げたら、紫式部の土の中から衣笠茸がでてきた。茸は土の上に立つとぐーんと大きくなって、人間ほどになった。大きな衣笠茸はレースをまとった新婦さんのようにきれいだが、なんだか異様だ。
衣笠茸がパカッと割れた。
人間だ、中に人間がいる。
長い黒髪が背中にかかっている。裸の女だ。ちっと恥ずかしいが見てしまえ。
よく考えると地獄で着物を着ているのもおかしい。そのままでてきたのだろう。色の白いふっくらしたきれいな体をしている。
私が立ち上がると、その女性がこちらを向いた。美女の中の美女だ、こんなきれいな女性を見たことがない。
裸のままこちらに歩いてくる。
「どなたじゃ」
透き通るような声だ。
ついつい、懐中電灯をつけてしまった。実にきれいだ。
「名をきいておる」
女が目の前にきた。
「この家の者です」
女の両手が私の顔に当てられた。
「久しぶりじゃ」
唇が私の口をふさいだ。もうわからなくなった。女性がおおいかぶさってきた。
あっと思ったとたん、なんだか蒸し暑いところにいた。隣にはあの裸の女が立っている。私も真っ裸だ。
「何だ、おまえ、また地獄に戻ってきたのか、しょうがない奴だな、それにこの男はどうした、え、またおまえが拐かしたのか、せっかく極楽に行くよう手はずを整えたのに、愛欲は罪だ」
「すみません、篁のおじいさま」
「しょうがない、この男は運が悪いやつだ、しかしこいつが話しかけたのは罪だ。と言ってもの、大した罪ではないな、はやいところ茸にしてやろう、孫が迷惑をかけたようだからな」
家内が庭を歩いている。自分を捜しているようだ。
「どこ行っちゃったんだろう、あの人」
玉が出てきた。
「お宅の亭主、出てきた女に話しかけたんだよ」
まだ人のことばを話している。と言うことは、結界は解けていない。今のうちに茸にしてもらえれば、ここに戻ることもできるのだが。
「え、絹傘茸は女だったの、それじゃ極楽にいったの、死んでもいないのに極楽にいったらどうなるの」
「極楽に行ったかどうかもわからんな」
「どんな女が出てきたのかしら」
玉はちょっと考えた。
「小野篁の子孫と言ってたが、そうだ孫と言っていたな」
「誰なの」
「ちょっとまってくれ、紫式部の下から声が聞こえる、篁の声だ、ちょっと聞いてくる」
玉が紫式部の下の草地に耳を当てている。
戻ってくると言った。
「お宅の亭主は地獄にいるよ、女に拐かされたんだ、あんな堅物でも拐かしちまうんだからたいした女だ」
玉の大きな目がキョロッと笑っている。
「誰なの、小野篁の孫って」
「小野小町さ」
「ひぇ、そうだったの、そりゃ負けたわね」
「もし茸が生えてきたら、百八回たたきなよ、すると亭主がもどってくるよ、何しろ死んでいないので、もどればここにいることができるよ」
「いつ頃になるの」
「わかんないな、この結界は二日しかないようだが、小野小町が誘惑したのだろうから、罪は軽いよ、きっとまた紫式部の下に茸が生えるよ」
「玉たたいて、馬鹿な亭主を」
「おいきた、俺が百八たたいてやるよ」
そう言っている間に紫式部の下から茸が生えてきた。
茶色の網傘茸だ。
玉が百八回たたいてくれた。その日のうちに編笠茸はもぐったままになった。
その夜中、最後の結界の日である。夜の十二時、紫式部の下に網傘茸が再び顔をだし、むくむくと大きくなって、パカット割れた。
中から真っ裸の男が現れた。
懐中電灯の明かりで照らし出された。
「あなた、もどってきたわね」
家内の声が聞こえたと思ったら、いきなり平手打ちが飛んできた。
「女なんか連れてきて」
私が後ろを見ると、裸の小野小町が私の後ろに隠れていた。篁のおじいさんをだまして、いつの間にか俺の茸に入ったのだ。
私はあわてて家内に、
「声をかけるなよ」と言った。
玉が目をキョロットさせて、
「なるほど、いい女だね」
と言ったものだから、
「玉や世話にったのう」と小野小町が返事をした。
空から白いもやもやが降りてくると小野小町と玉をつつんだ。
もやもやが晴れると、そこには誰もいなかった。一人と一匹で極楽に行ったのだ。
「玉、いっちゃいや、亭主をもってって」
家内は紫式部の根元に向かってそう叫んでいた。
裸で庭に立つのは初めての経験だ。やっぱり秋の夜風は冷たい。
茸たたき


