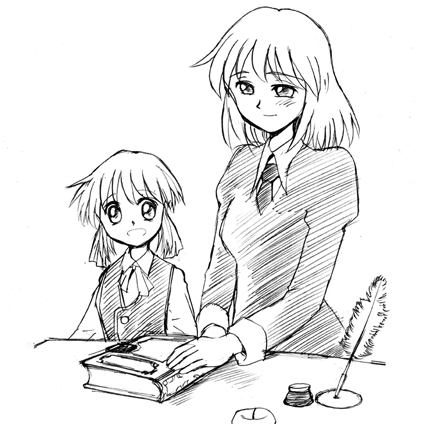
ミュウと魔女の日記
ふうこうだいには、
それこそむかしからたくさんのまじょがいましたから、
まじょのものがたりやでんせつ、まじょのかいた本とか、
たくさんありました。
このものがたりは、『あらしのまじょ』とよばれた
エバーミストというまじょのお話です。
ちなみに、かのじょをしっている人は、みなかのじょのことを
エファと呼びます。
それでは、エファのものがたりのせかいへ。
よいたびになりますように。
ミュウと魔女の日記
「今日の授業は、紅茶を飲みながらやりましょう」
エファのはからいで、ミュウは紅茶とクランベリースコーンを食べながら、エファの授業を受けていた。
授業といっても二人がいるのは学校の教室ではなく、ミュウが住み込んでいるアプリリア先生の家の、隅々まで綺麗に掃除のゆきとどいたリビングが今日の教室だった。
居間の机の上には、紅茶の道具やスコーンをのせたお皿と一緒に、授業で使うらしい小さな小瓶や、大きさも厚さもまちまちな本が置かれていた。
エファの淹れてくれた紅茶はおいしかったし、おやつのスコーンは少しこげていたけどそれが香ばしく。中に入っていたクランベリーの甘酸っぱさと紅茶の相性は絶品だ。
ミュウはスコーンの最後の一かけを飲み込んで、授業でなかったらどんなによかったのに、と思った。
もちろん、口には出さないで授業に集中する。
今、熱心に講義しているエファは、ミュウが物心ついた頃から空想していた魔女そのもの姿をしていた。夜の闇より真っ黒なワンピースと、今は玄関の帽子掛けにある同じように真っ黒な三角帽子。
都会ではない東のくちばしでも珍しくなった魔女らしい服を着た魔女。
しかもミュウの四つ年上なのに、エファはミュウのもう一人の先生アプリリアと同じ施療師だ。
ミュウはこの二人の先生に、魔女になること、さらに施療師になることを教わっている。魔女のたまご(魔女見習い)だった。
エファの授業は、薬草の名前の書き取りとか、暦の計算をひたすら覚えるような、机の前だけで済んでしまうようなことはほとんどない。薬を混ぜ合わせて実験したり、実際に道具を作ったり、夜の森に入ったり、とにかく暇とか退屈といった言葉とは無縁なのだ。
でも、退屈じゃないのと同時に油断もできなかった。今、机の前でしている話しを一つでも聞き逃すと、取り返しのつかないことになることがよくあったから。
「実際にやってみましょうか?」と微笑を浮かべて、ミュウに危険な毒草から薬になる成分だけを取り出させるだけじゃなく、本当に効くのか使ってみることくらい普通にやってしまう。
「……ですから日記といっても、魔女の日記は、そのときの自分を閉じ込める。およそそんな感じです」
エファは、小さな瓶のコルク栓をまるで何かを閉じ込めるように閉めた。
「自分を閉じ込める?」
「そう。記憶が失われないように、心の中で変化をしないように閉じ込めてしまうのです。実際のやり方は次の授業でやるとして、今日は、魔女の日記をのぞいてみましょうか?」
エファは微笑を浮かべながら、金色に光る鍵のついた皮の表紙の本を手前に寄せた。
ミュウはつばを飲み込むような感じでエファの手の中の日記帳から目が離せなくなった。
自分を閉じ込めるのって、どういうことなんだろ? と心の中でつぶやく。
エファは淡い陽光のような髪を一本抜いて、日記帳の鍵穴に差し込んだ。まぶたを閉じて口元でそばにいるミュウにも聞こえない何かをつぶやく。
ミュウのもう一人の先生、アプリリアの名前が聞こえたと思ったのと同時に、日記帳の鍵がカチリと音を立てた。
◇◇◇
魔女のたまごアプリは、真っ暗な油の臭いのする倉庫に入ると、先生に教わったやり方を思い出しながら鬼火を手のひらの上に出した。
「うん、上出来」とつぶやき、自分を褒めたくなる。
鬼火といっても炎ではない。白く光る水晶玉のような光の固まりで、明るく光っていてもまったく熱がなかった。
すぐに鬼火を入り口に掛っていたランプに閉じ込める。こうしないと鬼火はフワフワとどこかへ飛んでいってしまうからだ。鬼火は狭いところに閉じ込められたのが嫌だったらしく、ランプのガラスに二、三度体当たりしたけど、ランプのガラスが破れないのを知ると大人しくなった。
鬼火ランプで照らされた、あまり広くない倉庫の中にはアプリの道具がたくさん詰まっていた。
拾ってきたネジやスポーク、エンジン部品にマフラーや、タイヤ。それらがすべて綺麗に分けられ、整理されていて、街の修理屋さんか機械の工場に迷い込んでしまったかのような、そんな感じ。
アプリは鬼火ランプを天井から伸びているフックに引っかけると、倉庫真ん中に置いてあるバイクのハンドルに手を置いた。燃料タンクの上に薄く積もったほこりを払う。
タンクの冷たさが、まるで長いことほったらかしにされたことを恨んでいるような感じがした。
「ちゃんとメンテしてあげるから」
そう言い訳っぽくつぶやくと、キャスターに乗った工具一式を自分の方に寄せて、洗面器に灯油を入れながら、メンテナンスの準備をてきぱきと進めた。
燃料タンクのキャップを開けて鼻を近づけると、思わず顔をしかめたくなるような異臭がした。丸眼鏡もたまらないとでも言うようにずれる。
ずれた眼鏡を直して、まずはポンプでタンクの中の燃料をオイルジョッキに移すことから始めた。
オイルジョッキに移された燃料は、倉庫の油臭さに負けないような臭い立てる。
「この分だと、吸気器もばらさなきゃだめか」
予想できたことなので、シートを外し、燃料タンクを止めているボルトを手馴れた手つきで外し始めた。
六歳の頃からバイクを面白半分にネジ一本に至るまでバラバラにしたり、逆に組み立てたりしてきたアプリにとって、メンテナンスは自然と鼻歌が出てしまう、そんな気楽な作業でしかない。
鼻歌は今ばやりのバラード。
サビのフレーズを繰り返そうとしたら、不意に、『あいつ』の顔がよぎった。
「ったく」
自分に軽く舌打ちをすると、一度手を止めて、さっきまでの楽しい気分を一つ一つ思い出しながら、また吸気器のネジを外し始めた。
吸気器を洗うのが楽しいと思う。灯油をはった洗面器の中で黒ずんだ部品が、本来の鉛色を取り戻してゆく。
灯油を綺麗にふき取って乾かしながら、エンジンのボルトの一つにメガネレンチをあてがって、「ふん」と力を入れて回す。黒ずんだ水あめのようなオイルがバケツの中に落ちてゆくのを眺めながら、ふぅとため息をつく。
「『あいつ』はこんなとき外でタバコ吸っていたっけ」
半分以上、わざと出したつぶやきに、心が波たつようなことがなかった。何にもないのがとてもうれしい。
エンジンオイルの交換、プラグの点検が終わり、バラバラの吸気器を組み立てはじめた。
楽しい、と思う。まるでパズルを一ピースずつはめていくかのよう。
バイクの吸気器の組み立てと、今、学校で取り組んでいる飛行機エンジンの吸気器が一瞬だけダブって苦笑いしたくなった。
「……結局、三日も学校サボっちゃった。明日から行かなきゃ」
最後にタンクを再びつけると、持ってきた新しい燃料をポンプで移し変えた。
「さて」
一発でかかってよ。と心の中で呟くと、チョークを半引きにしてキックに足をかけた。
息を止めて、思いっきり踏み込む。
はたしてエンジンが甲高い音を上げ、倉庫の中が生ガスくさくなった。
「よしよし」
バイクのライトのスイッチを入れてから、ランプを下ろすと、中にいた鬼火を「お疲れ様」と出してあげた。
鬼火は怒ったように小さな稲妻をバチバチと立てて、倉庫の入り口の隙間から外に飛び出し、空高く上がっていった。
「さ、行こ」
アプリは思いっきり笑いたいのを我慢しきれなかった笑顔で、リズムカルな、でもうるさく唸るバイクを倉庫の外に出した。
ここに長くいるのは頭のいいことじゃなかった。バイクの音で、寮母さんが血相を変えて飛び出してくるのは間違いなかったから。
バイクに跨って、首から提げているゴーグルを眼鏡の上につけて、クラッチを切りギアを入れ、アクセルを開けてゆく。
マフラーにバラバラと言わせながら、家を出て夜の街に駆け出した。
次第に加速していく。
風が気持ちいい。風を切ってバイクで走るのは、ほうきで飛ぶのとはまったく違う。
ほうきで飛ぶときの風と二重奏を奏でるような感じじゃなくって、バイクで走るのは風に抗い切り裂く感じ。でも、それがとっても心地いい。
楕円のライトに照らされた石畳のゴツゴツした感じや、タイヤでしっかり駆けている感じ、車体ののきしむ感じや、エンジンが懸命に動力を生み出し伝えていく感じが、ハンドルを握る手、ステップに置いた足、シートのお尻から伝わってくる。
バイクという、生き物とか自然とかとは、まったく異なる存在をより身近に感じられる。
こういうの忘れてた、とアプリは思った。
バイクに乗るといえば、この半年間は『あいつ』の後ろに乗ることだった。バイクに乗って感じていたのは、『あいつ』の背中の温かさであって、バイクの駆ける感じじゃなかった。
今が、素直に楽しい。ノックアウトを食らっていた三日間が馬鹿馬鹿しく思えた。
今は笑顔でアクセルを開ける。
◇◇◇
「どうでした?」
エファは日記帳を閉じると、ミュウの顔をのぞきこむように聞いた。
「いつものアプリリア先生とは違う感じ」
ミュウは少し目が潤んだ。魔女のたまごアプリの思いがまだミュウの心の中で小さく波を作っていた。
ミュウはこの家に何台もあるバイクを眺めるだけで、まだ一度も乗ったことはなかったのに、たしかに、右手にはアクセルを全開にしたときの振動の痺れが残っていたし、風を引き裂くときの音が今にも聞こえてきそうだった。
「アプリリアが魔女のたまごだった時のものですからね」
「うん」ミュウはちょっと言葉を選んだ後。「なんかいつもより先生を近くに感じられたような気がする」と言った。
「このこと(日記を見たこと)は、アプリリアには絶対に内緒ですよ」
「え、なんで?」と言いかけてミュウは全身の血が氷水になってしまったかのようだった。
「日記の中身を見たと言ったら、晩ご飯抜きどころか、何が起こるのか想像も付きませんから」
エファは何か遠くの楽しい出来事のように言った。
ミュウが何かを言おうと口を開きかけたとき、リビングの扉がノックとともに開いた。
「どう、ミュウちゃんとやってる?」
まるで呼ばれでもしたかのように、ミュウのもう一人の先生アプリリアが入ってきた。
エファと違ってまったく魔女らしくない感じ。さっぱりした洗いざらしのシャツに綿のパンツ。洗い立てのようなボサボサの黒髪。まるで男の人のような格好をしているのに、絶対に、男の人に間違えっこない美人の魔女。
そのアプリリアに、「はい」と、ミュウの代わりにエファが答えた。
ミュウはエファの隣で今にも悲鳴を上げそうな感じで固まっていた。
「今、魔女の日記についてやっています」
「へ~」と言いかけたアプリリアの目が机の上の日記帳に止まって大きく見開いた。
「ちょっとまって、それ私の日記帳じゃない」
アプリリアは鍵のかかった日記帳を取り上げた。
「見なかったでしょうね」
アプリリアは日記帳を胸に抱いてエファを見た。
「鍵はしっかりかかってました」
エファは、ミュウにいたずらっ子のようにウィンクすると、すまし顔でそう答えた。
魔女アプリリアとミュウ
「先生、この前、仕上がった飛行機の試験飛行はしないんですか?」
「そのうちね」
「今日やりませんか?」
「え?」
魔女のアプリリアは弟子のミュウに突然そう言われて、返答に詰まった。
こういうことはめずらしい。アプリリアは、はい、と、いいえ。できることと、できないこと。白黒はっきりさせないといられない性格であったから。
もっとも、魔女にありがちな煙に巻くようなことも必要とあればやったけど、この手の質問は煙に巻くまでもない。
「だめよ」と、少し遅れてきっぱり断る。
「でも、乗ってみたいんです」
「大丈夫よ。試験飛行はいつでもできるわ」
アプリリアは席を立ち上がると自分の食器を洗い場へと運んだ。
「あ、先生やります」
ミュウも席を立ち上がる。
「いいのよ。これぐらい自分でやるわ。それにしても、どういう吹き回し?」
「え? 何のことです」
ミュウの声が妙によそよそしくなるのを感じて、苦い笑いをしたくなった。
嘘が上手なのも魔女に必要な素養なのに。ミュウったら、話しのもって行き方、言葉の使い方、すべて子どもそのものじゃない。と心の中で溜息をつきたくなった。
「飛びに行こうなんて、今までなかったんじゃない?」
アプリリアは食器桶に水をはった。
「え、あ、あの、天気が明日から下り坂だから」
ミュウが苦し紛れで言ったのは本当のことだった。
アプリリアは魔女の当然の習いとして、ミュウにはしっかり「風読み」を教えてあった。十一時に行ったアプリリアの「風読み」でも夜半から、早ければ午後にでも、この青空としばしのお別れの予想だ。
でも、一応は聞いてみる。
「いつから崩れるの?」
「え、えーと夜からです」
「それで、その雨は、いつまで降り続くの?」
アプリリアは食器を洗いながら容赦なく追い討ちをかけた。
「多分、今の時期の雨は二、三日続くと思います」
ミュウの回答にアプリリアは心の中で合格点を与えた。でも、
「多分とか、思うとか、そういうことでではダメよ。そういうときはラジオを使いなさい。山地地方の天気予報と東のくちばし気象台の気圧と気温のデータで、風読みをより完全なものに近づけることができるわ」
こういうとき、アプリリアは自分が一番嫌なタイプの先生を演じているような気がする。
でも肩から力を抜こうとは思わなかった。アプリリアにはアプリリアの施療師像があって、ミュウがちゃんとその施療師像に近づいていくために、努力を惜しもうとは思わなかった。
しかも面白いことに、アプリリアはそういう嫌な先生役が自分によく似合っているような気がしていたし、最近では気に入ってさえいた。
「はい」
ミュウは、少し意地悪なアプリリアの物言いにも、いつものように本当にまっすぐで余計なことは何も考えていない返事をした。
私は、この「はい」に騙されるとアプリリアは思いながら、心の中で頬を緩めた。
アプリリアは洗い終わった食器を食器桶に並べると、鏡のように光るフォークを布巾でしごいた。
数日前に、訪ねてきた師匠筋の古い魔女がひどく感心していたけど。フォークやナイフはこうして使うごとに綺麗にして水気を近づけなければ、くすみや傷みを抑えることができるというのがアプリリアの持論だった。
部屋を清潔に保つのも、日々のちょっとしたこと。嘘をついていることを見抜くのも、その嘘の先にあるものを見出すのも、勘の鋭さ以上にほんのちょっとしたことの積み重ねだ。
「あ、あの先生。試験飛行の話しは?」
ミュウは完全に明後日の方向に行っていた話を元に戻してきた。この言葉の裏に何があるの? アプリリアはミュウの問いに答えずに、少し考えた。
カチャリと音を立ててフォークを引き出しに戻す。
「わかったわ。何を企んでいるのか判らないけど」
「え? ええ? 企むなんてそんな」
ミュウの顔をのぞき見ると、アプリリアは苦笑いをやめて普通に笑いたくなってきた。
この子は絶対に嘘をつくことができない。
「用意をするからキャリアーを(工房の)前に回しておいて。午後から飛びましょう」
「はい」
ミュウの「はい」は、アプリリアが見抜けなかった「何か」を思ってか、ひどく嬉しそうだった。
◇ ◇ ◇
アプリリアはキャリアーをそのままミュウに運転させることににした。
いつもなら嫌がる、飛行機を牽引できる大型トラックの運転も今日は嫌ではない様子。
「どうしたの? 今日に限って」
「話しかけないでください」
ミュウは恐ろしく厳しい調子で言った。
「はいはい」
アプリリアはミュウにこの手の乗り物や機械の操作を色々教えていた。
魔女はたいてい弟子に、自分の特技や芸の一つを教えるものだ。それは母から娘に伝えるようなお菓子の作り方だったり、秘伝のビールの造り方だったかもしれない。アプリリアは特に意識したわけではないけど、ミュウに機械の操作やメンテナンスを教えていた。おそらくそれもまた、少し風変わりであるものの、師匠と弟子の自然な流れの一つかもしれなかった。
運転席のミュウは見た目がものすごく怖い。
眉毛と目がきりりとした顔もそうだけど、前を見るのには背が足りないからと、お尻の下には分厚いキルティング座布団を三枚も敷いていたし。アクセルやブレーキには足が届かないからと、松葉杖を半分にして作った特製の下駄を履いていた。
ミュウの厳しい表情と反比例するかのように、キャリアーはゆったりと走っている。
キャリアーの運転を教えた時、ミュウはべそをかきながら、「先生。キャリアーの運転なんて何の役に立つんですか?」と聞いたのも過去の話だ。
意地悪をするかのような消火栓と、いつも留まっている三輪自動車のせいで危ない三叉路も、牽引する飛行機キャリアーの後輪を軸として、中折れする不思議なコンパスのように、円を描きながら曲がっていく。
ミシンを巧みに使う子だけに、ゆったりとミシンがけしているような、そんな運転の仕方をすると、思う。
アプリリアは荷台のシートをかぶせられた飛行機から、油断のない瞳を周囲に送るミュウの横顔に視線を送った。
「ラジオもダメ?」
アプリリアはミュウに聞いた。
「だめです。話しかけないでください」
肩から力を抜けばいいのに、と思ったけどアプリリアは言わなかった。ミュウの性格からして、肩の力を抜くことに集中して、運転がおろそかになるかもしれなかったから。
キャリアーはウィッシュボーンの街を出ると、海岸筋の道路を港へ向かって走った。整備された道が、左手には畑、右手には海を眺めながら港まで続いている。
空に浮かぶ鯨のような飛行船集団はあまりに大きいので、街を出るとすぐにも見えた。
時間つぶしにはならなかったけど、アプリリアはボードに挟んだ書類を手に取るとペンを走らせた。
魔女がほうきで飛ぶのに誰にも許可は要らないのに、飛行機一機を飛ばすのには、安全のための書類や手続きがいろいろいる。さらに、港に入ってからも、諸々のことをしなければいけない。
安全のためにはけして省くことのできない手間。
アプリリアはその手間を惜しもうとは思わない。見なれた項目の間に横たわる注意書きを空では読まず、必ず目を通した。安全のための手間ならばどんなことでも手を抜くつもりはなかった。
事務所で、書類に最後のスタンプが押されると、軽い挨拶を幾つも交わしながら、アプリリアは足早に、キャリアーから降ろした飛行機の所へと戻った。
あと十分の時間もない。
アプリリアはこの東のくちばしを母港とする飛行機の整備も手かげているおかげで、優先的に離陸の順番をまわしてもらうことができた。この機会を逃すと飛行船の離陸があるので、三十分は待たされる。
いつものようにミュウは、頬を膨らましむくれていた。そのふくれた顔とは正反対の笑顔の地上スタッフたち。
まったく、まったく。と呟く。
「おつかれさま」
「先生、どうも」
とスタッフの男たちは手を上げて答えた。
アプリリアはなぜ、ミュウが頬を膨らませていたのかわかっていたけど、一応儀式のように、
「どうしたの?」
「なんでもないです」
「また、からかわれたの?」
ミュウはむくれたまま、うなずいた。
実は、ミュウは飛行場のスタッフや飛行機乗りたちに人気があるのだ。けど、本人だけがそのことを知らない。アプリリアも、いつものようにそのことには一切触れなかった。こういうことは、ミュウが自分で気がつくべきことだと思っていた。
その代わりに、係留ロープの間で大勢のスタッフ達が走り回る飛行船を指差し、
「さ、気にしない。あの飛行船が上がる前に離陸できるから、急いで」
「はい」
ミュウは皮でできた防寒具の前を閉め、はしごを上った。
アプリリアもはしごを上ってコックピットに体を滑り込ませた。
「やって」
さっきまでの笑顔から顔を引き締めた地上スタッフたちが、飛行機の向きを滑走路の方へと変えていく。
アプリリアは心を落ち着かせるかのように目を閉じた。飛行機の方向転換と誘導が終って、地上スタッフ達が合図と共に離れたところでゆっくり閉じていたまぶたを開いた。
「後席エンジン始動」
ミュウは右手だけで回すハンドルに両手を添えて、自分の重さを乗せるようにして回していく。
クランクシャフトが回っていくのが感じられる。
胴体後部のエンジンに火の気配。
本当にわずかな気配が、燃料を燃え上がらせ、圧搾された空気の体積を爆発的に増大させていく。ピストンが一気に押し下げられエンジンが目を覚ます。
次第に飛行機全体が目覚めていくかのように、プロペラがゆっくり空気を混ぜるかのように回りだし、コックピットにもエンジンの振動が心地よく響き始める。
吸気、圧縮、爆発、排気。四つの行程を人の目では見えない速さで行うエンジンが、最後尾のプロペラを風を切る様な速さで回す。
アプリリアは自分では気がついていなかったけど、ゴーグルの下の、丸眼鏡のさらに下、眼が笑っていた。
飛行機を一路滑走路へと向ける。
雲の動きは、ミュウが予測したものよりもはやく青空を覆いつつあった。
「帰りは雨ね」
アプリリアは発進許可を求める片手を上げると、キャノピーをしめ、エンジン出力を上げた。
エンジン音が空気を震わし、今までのプロペラの回転が、まだまだ本調子には程遠かったことを示すかのように、空気を引き裂き、風を起こし、機体を軋ませる。
この世界の人々がはじめて、ほうき以外で飛んだ時と同じ緊張感に、この飛行機もアプリリアも包まれた。
滑走路のスタッフが掲げたランプが青に変わる。
空を飛ぶために生まれた木と鉄、さらに竜の鱗できた機械が滑走路を走リはじめる。
ガツンと前から頭を押さえつけられるような加速。そのすぐ後に浮揚感が全身を包みこむ。
車輪は地面を離れ、飛行機は空へと飛び上がった。
ほうきとは全く違う、すべてに逆らうような感覚に包まれる。
地上はすぐに小さく遠くなって行き、あれだけ巨大だった飛行船の今や指先ほどでしかない。
操縦竿を握る手から、すべての部品、その一つ一つがかみ合い、心地いい重奏を奏でているのが伝わってくる。
「後席。再加速、雲の上に出る」
スロットルを引き、さらに加速。
雲の白い世界に入り込み突き抜けると、より高い雲の間から顔を覗かせる太陽の光が機体を舐めていく。
視界が空の青さに満たされていく。
アプリリアの心の奥底で、この数日間、師匠筋の古い魔女の来客があってからというものの、絡まっていた古いもやもやがほぐれていくのを感じた。
そういったことを弟子のミュウに隠すことのできなかった自分を叱責することよりも先に、なるほど、と思った。
ミュウはこういうことはすぐに気がつく子なのだ。
施療師とって必須で、訓練や授業ではなかなか得られない感覚をミュウは生まれつき持っている。
「ミュウ、ありがとう。気分が晴れたわ」
「うん」少し、照れたような返事をしたあとすぐにあわてた調子で、「え? なんのことです」と打ち消してきた。
「……まったく」
アプリリアは、そう、つぶやかずにはいられなかった。
ミュウと魔女の日記
『ミュウと魔女の日記』02年冬コミケット無料配布 原題「魔女の日記」
『魔女アプリリアとミュウ』03年秋そうさく畑無料配布
イラスト:藤池ひろし 『Fantasica』 http://www.fantasica.org/

