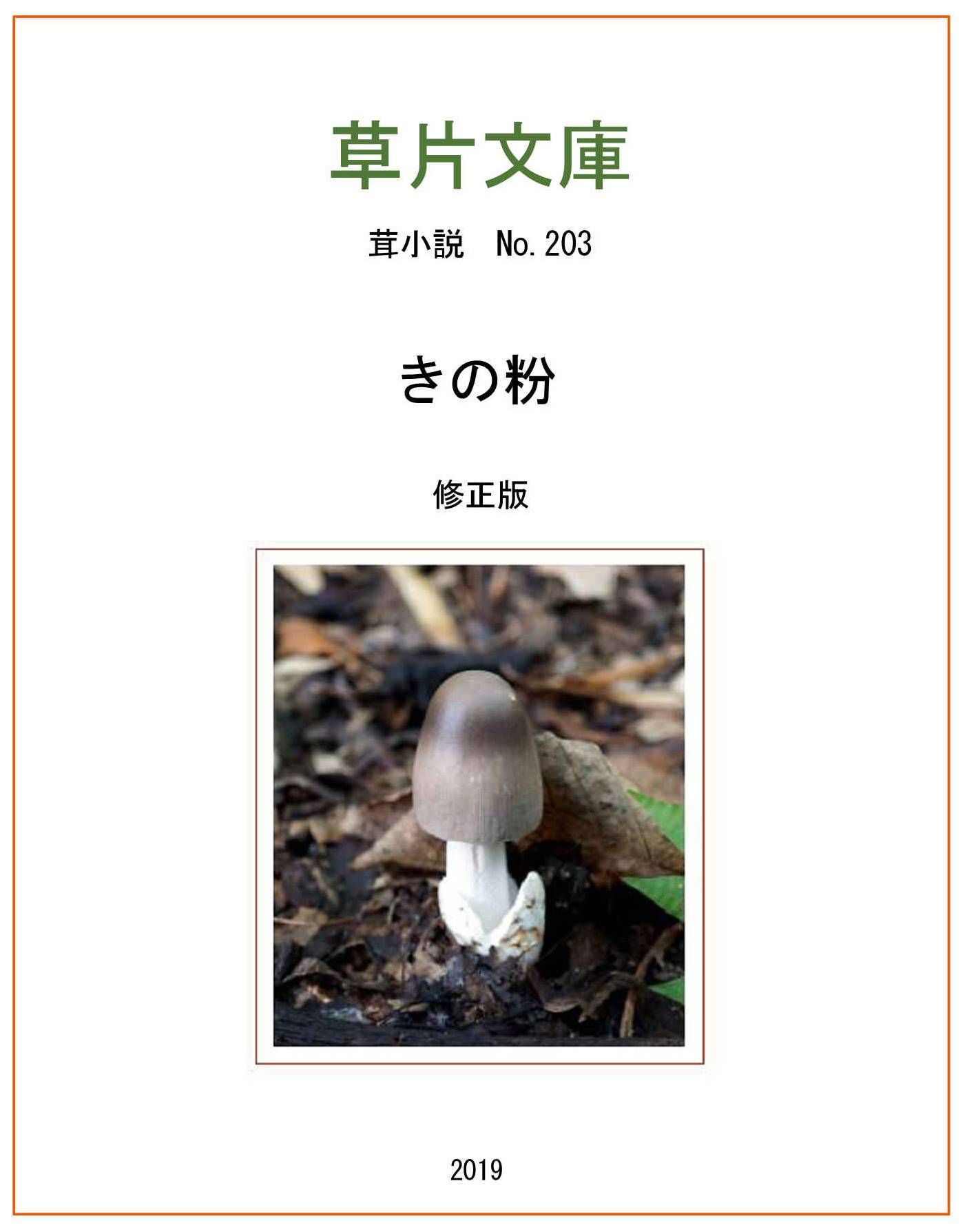
きの粉
キノコ不思議小説です
空から粉が降ってくる。
勤めている小学校の校庭のグランドが白っぽくなっている。真っ白ではなく薄い茶色である。駐車場に止めておいた車の上にもうっすらと積もっている。黒っぽい車だとよく目立つ。
大陸からやってくる黄砂のようでもあるがちょっと違う。なんだかわかっていないが、もっと粉っぽい。これが始まったのが今年の八月半ばである。この町だけのようで、隣の町ではそのような話しはない。
粉が降るのは毎日ではない。二日続けて降ったと思うと、十日後に降ったりする。どうも風の強さと向きに関係がありそうだ。
降ってくるのは夜中のようである。昼間に降ってくるのを見たことはない。夕方洗っていた隣の家の車の上にうっすらと粉がかぶっている。
近所の人たちは埃だと思っている。ただ私はなぜか鼻がいい。埃の匂いでも砂の匂いでもない。なにのちょっと思い出せなかったが今はわかる。
秋になってペンションを営む友人が天然の茸類をくれた。段ボール箱を開けると、ふっと茸の香りが鼻をうった。中には栗茸、平茸、滑子が詰まっていた。茸の強い匂いである。その時、空から降ってくる粉の匂いに似ているのに気づいた。最も粉の匂いはそんなに強くなく、かすかに香る程度である。
粉がなにであるかわからないが匂いは茸のである。
指の先につけて改めて嗅いでみた。やはり茸の匂いだ。茸の胞子なのだろうか。杉花粉のように一度に沢山の茸の傘が開いて飛んだのではないか。
そんなことを友人で市の教育委員会の事務長をしている白瀬に話した。地元の中学校の同級生で、私が今小学校の校長をしているので会議の後に一緒に飲むことがある。彼は環境課に伝えておくよといったが、その後連絡はない。
この町は小さな川の扇状地の上に発達した小都市である。そこそこの山が周りを囲んでいる。その中に奇妙に尖った599メーターの山があって、町から目立ってよく見える。尖り山と呼ばれているが、先が岩でできていて、その部分は尖り岳とも呼ばれる。昔はロッククライミングの練習の場所になっていた。しかし近年岩がもろくなってきたため、頂上に登るのは禁止されている。尖り山の裾から中腹にかけては森があり、いくつかの登り道があるが、頂上近くになると道らしいものは無くなる。
市営図書館にある町の歴史が書かれた風土記には次のようなことが書いてある。
三百年も前の頃、この町は山際に八つの集落がある村だった、村の中を流れる川は水が豊富で、周りに広がる平野は稲作に適した肥沃な土地だった。そこに人が集まり大きな村に発展した。そのころ尖り山は山頂まで木に覆われていたという。頂上に松の木が生え、遠くからもよく見える皆に親しまれている山だった。面白いことに、上から百メートル下ぐらいまで、麓からだと四百メートルより上は松ばかり生えていたという。それも赤松である。ということは松茸が生える。
当時村では庄屋が松茸狩りを管理しており、十月に行われる松茸競争の後に解禁される。
十月なると、あらかじめ庄屋のところの男衆が山に登り、頂上の松の木に松茸が生えているかどうか調べてくる。頃合の良い日に村で選ばれた足に自信のある男達が集まり、頂上の松の木の下に生えている松茸を一本採ってくる競争をする。頂上には庄屋の男集があらかじめ立っていて、確かに頂上の松茸を採ったというお墨付きを渡し、競争する者は採った松茸とその証明を持って駆け下りる。一番に降りてきた男には米一俵、一番大きな松茸を採った者にも米一俵が渡される。一番早くかつ大きな松茸を持って帰った場合にはさらに一俵もらえるという面白い催しだった。そこで採られた松茸は代官さまに献上された。
それだけではなくその山は秋になると麓の木々が紅葉して、赤いべべきたお山さんと歌われて、慕われていたという。松林より下は広葉樹林になっていて、山の中には様々な茸が生え、アケビなどの実もたくさんなって、食卓をにぎわしたということである。松林のなくなった今でも茸はよく採れる。
ある秋の晴れた日に、おかしなことが起こった。尖り岳の天辺の松が燃えてしまったのである。雷が落ちたりしたのなら納得がいくのだが、雲一つない青空の下である。村人たちは何かの祟りではないかと恐れた。
燃えた松の木を調べたが、なぜ火がでたかわからなかった。
さらにその夜になると、今度は山の上の方を覆っていた松の林がすべて燃えてしまった。村をあげて原因を調べたのだがわからなかった。何しろ松茸競争の前だったので、密猟者の見張りのため、庄屋の男衆が交代で山の麓の夜警をしていたのである。最初はその男たちが疑われたが、そのようなことをする者はいなかったし、そのようなことをしても誰の特にもならなかった。
その年からは松茸が一本もとれないという事態になってしまったのである。しかも山の焼けた上の方は土が崩れ落ち、中から岩が現れ、岩山に変わってしまった。逆に山頂の土が流れ込んだ下の林の中はますます肥沃になった。茸が前にも増してたくさん生えるようになったという。庄屋は祟りを恐れ、小さいながらも神社を建て神主を呼んで祈祷をした。そのお陰かどうかわからないが、町は平穏にむしろ発展していったと書かれている。
その出来事が記されている風土記には、その山火事の原因に関する昔話が付記されていた。それがまた面白い茸の物語である。
尖り山の上には松の木が生えており、松の木の下にはお抱えの茸が住んでいた。松に禄をもらってぬくぬくと大きくなって、腋臭を遠慮なくばらまいている威張った奴らである。人間はよい匂いだと言って珍重しているが、茸にとって腋臭にすぎない。本当の匂いというのは菌糸の茸の香りであり、その高貴さこそが茸の価値である。
尖り山の裾のほうにはいろいろな茸がお互いに助け合いながら、場所を融通しあって生きていた。中でも花猪口は茸たちの信望が厚く、茸たちの頭領として采配をふるい、茸たちはうまく棲み分けをしていたのである。
そんなある日、木の上に住んでいる木耳(きくらげ)と花弁茸(はなびらたけ)が地上を眺めながら話をしていた。
「土から生える茸は場所がなくて大変だね」
「よく仲良く生きているね、ありゃ頭領がいいからだよ」
木耳たちは、その昔、土から生えていたのだが、狭くなってきたので木の上に住むようになった。木には前々から猿の腰掛が住んでいたのだが、猿の腰掛が、土に生えている茸に木をもっと利用しなさいと声をかけた。それで木の上に上がってくる茸が増えたのだ。滑子などは木の上に生えるようになったのだが、遠慮して倒れた木に生えるようになった。
「山の上の方には松の木がたくさんあるが、茸たちがすんでいないね」
花弁茸が不思議そうにつぶやいた。
「そりゃあ、松茸が松の木の下を独占しているからだよ、万年茸が言ってたよ、松の木につこうとしたら、松茸に追い払われたそうだ」
「松の木には茸がついていないじゃないか、使わせてくれたっていいだろうに」
「まあ、松茸には松の木が命のよりどころだから、とられてしまうのが心配だったんだろう、わからんでもないがな」
それを聞いていた隣の木にくっついていた猿の腰掛が、
「いや違うんだよ、松茸の奴ら、茸がつくと松の木の汁がまずくなるって言うんだ」
「食い意地がはっているだけなのか」
「そうだ、俺たちが使わせてくれって言ったら、けんもほろろさ」
「けしからんやつらだな」
「誰か、松茸に文句言えるやつはいないのかね」
木の下で聞いていた花猪口が、
「俺たちじゃかなわないんだ、あいつら、松の木のお抱えだから」
「松の木のお抱えってなんだ」
「松の木が気にいって、養ってやってんだ」
「それじゃ、松の木が他の茸をきらってるのか」
「そういうこと、松の木をなくして、ブナや楢の木に生えてもらわなきゃ尖り岳の上の方に茸は棲めないってことさ」
「といっても、松の木にどけっていってもだめだよな」
「松の木を成敗するやつはいないのかね」
そんなことから百年ほど経ったある日、尖り山の麓にはじめてみる茸が頭を出した。真っ黒な傘を持ったずんぐりした茸である。
茸の頭領の花猪口が声をかけた。
「なんて言う茸さんで」
「石頭」
「ほう、珍しい名前だ、あたしゃこのあたりを取り仕切っている花猪口、みんなにはジゴボウといわれていますが、仲良くやってくださいよ」
「いや、いきなり出てきてすまんことです、百年に一度しか生えない茸でござんして、よろしく願います」
とそこにまた別の石頭が頭を出し、前の石頭の傘とぶつかった。かちんと音がして火花が散った。
「おーすごい」
花猪口が火がついちゃ大変と傘を揺らした。
「これは失礼、わしら石頭は頭が固くてぶつかると火花が散るんですわ、みなさんには迷惑にならないように暮らしますからよろしく」
それを木の上からみていた木耳が声をかけた。
「石頭のみなさん、山の上の方は場所がずいぶん空いているんですが、松茸や松の木が独り占めしているので困ってます、上の方も利用してみませんかね」
「そうですか、そりゃもったいない、見晴らしのいいところに生えたいもので、仲間に上の方に生えるように言いましょう」
ということで、山の上の方に石頭が生え始めた。
松茸は生えてきた石頭をどなった。
「ここは俺たちの場所だ、下に生えろ」
「へえ、だけど下の方は茸でいっぱい、ちょっくらいさせてくださいよ」
松茸が新しく生えようとした石頭を押さえつけた。
だが石頭は頭が堅いものだから、松茸など押しのけて生えてきた。
松茸は石頭に体当たりをした。
その拍子に石頭が隣に生えた石頭がぶつかった。火花が散った。
みんなも知ってるだろう。松の木の下は枯れた松の葉っぱが落ちて重なってふかふかになっているもんだ。そこに火花が散ったらどうなるか。
枯れた松の葉に火がついた。それで松林が燃えちまったというわけである。
なんとも面白い伝承である。
しかし最近このあたりに降ってくる粉と関係があるとは考えられない。
町の広報に私が白瀬に言ったことがでた。降ってくるのは茸が粉になったものだという。保健所での検査結果では、胞子ではなく、茸の本体が粉になったもののようだという。やっぱり自分の鼻は正しかった。どこから来るのかはわかっていないが、降ってきたときの風向きを考えると、尖り山の方向からのようだ。
白瀬が用事で学校にきたときに、伝承のことを言ってみた。
「尖り岳の茸ね、確かに可能性はあるけど、岩山じゃ茸は生えていないしね」
確かである。
「でも、もう一度、環境課に伝えておくよ、お前さんの鼻が正しかったからな」
彼はそう言って市役所に戻ったが、数日後電話をかけてきた。
「環境課の人が尖り岳の岩場に行ったそうだ、するとね、確かに茸が生えていたということだ、初めて見る茸だって言ってた。それで茸の専門家に来てもらうことにしたそうだ。科学博物館から茸の研究者が今度の日曜日に調査に来るのだが、一緒に行かないか」
「ロッククライミングはやったことがないから」
「いや、岩山の下のところまで行くだけだよ、岩のところは専門家に任せてね、待っていればいいんだ」
尖り山には山道があり、先の尖り岳の下までいくのは大変ではない。町の人は秋になると茸狩りによく行く。それで私も同行することにした。朝の八時に尖り山登り口に集合である。そこまでは駅のバスターミナルからバスがでている。
科学博物館の人と環境課の人は我々より二時間ほど早く調査に向かうことになっている。白瀬と私、それに町の高校と中学の生物の先生たちが遅れて参加する。
尖り山に登るのは久しぶりである。登り口から少し歩くと林の中の道になり、ちょっとすずしい。歩いていくと道の脇に茸が見えるようになってくる。上るにつれ茸が多くなる。
「だけど粉がよく茸の匂いだってわかったな」
白瀬が歩きながら私に話しかけてきた。
「鼻は昔からからよくてね、女性が香水をつけていると、香水の名前はわからないけど、前と違う香水をつけているとか、今日は強めだとかわかるよ」
「俺の鼻はだめだな、高校時代からそうだったかい」
「鼻が効くことに気が着いたのはもっと大人になってからだよ」
「私が香水をつけているかわかりますか」
一緒に登っていた中学の生物の先生が聞いた。こりゃ困ったと思ったが、ふっとレモンの香りがした。
「わかりませんね、レモン系の香水かな」
そう言ったら彼女は笑顔になった。
「本当に鼻がいいんですね、私香水は使わないわ、でも朝にレモンティーを飲んだわね」
「茸らしさの匂いは、なんだかむーっとしますね」
虫が専門だという高校の生物の男の先生はそう言った。茸の匂いが好きではないようだ。
「土の混じったような匂いですね、茸臭とでも言うのかな、私は嫌いじゃないけど、確かに、汗臭いような感じもします、私なんか図書館の古い本の匂に似ていると思いますけどね」
登っていくうちにその匂いが強くなってくる。生えている茸はあまり匂わないはずなのだが、粉が降りそそいだのだろうか。
尖り山の林を抜けるといきなり岩山がそびえている場所にでる。そこが尖り岳の登り口であるが道はない。ちょっとした広場になっていてベンチが用意されている。上を仰ぐと岩山に白い粉がかぶっている。数人の人がロープづたいに岩の間をのぞいているのが見えた。環境課の人と科学博物館の人たちである。中の一人が我々の到着に気がついて手を振った。
白瀬が手を振った。
「あれが環境課の人で、岩登りの経験がある、地層や植林に詳しくて、土砂崩れ、地割れなどを大学時代に研究した人なんだ、茸も良く知っているよ」
岩山で作業していた人たちは我々を見るとすぐに降りてきた。四人いる。皆、腰に袋をつるしていて、それが膨らんでいる。環境課の人が若い眼鏡をかけた男性を友人に紹介した。
「こちらが教育委員会の白瀬さん、こちらは科学博物館の菌類研究所の主任研究員の甘利先生です」
「甘利です、このあたりの茸を調べるのは初めてです、ずいぶん茸が豊富なところですね、今日は岩山の調査をしましたが、下の林の中も面白そうで、これから調べようと思います」
白瀬が「この人が粉が茸の匂いがすると教えてくれました。中学の同級生で、いま小学校の校長をしています、鈴木さん」と私を紹介してくれた。
「そうですか、甘利です。茸の匂いは独特ですが、この粉の匂いはかすかですね、よくわかりましたね、茸のことよくご存じなのですね」
「いや、鼻がちょっと利くだけで、茸は食べるのが好きですけど、名前などからっきしわかりません」
「そうですか、お陰さまで変わった茸を採ることができました」
彼はそう言うと、私たちに袋の中から、黒っぽい茸を取り出した。
私ははっとした、あの風土記にのっていた茸じゃないだろうか。あれはただの話ではなかったのかもしれない。
「この茸が岩のところにたくさん生えていました。まだ熟していないのばかり見つかりました。傘が黒くて広がっていない饅頭型です。不思議なのは広がっている個体は全くありませんでした」
「名前は何という茸でしょうか」
「新種ですね、ずいぶん堅い茸ですよ」
まさにあの石頭だ。風土記に書いてあったことを言おうか迷ったが、何となく気後れして言いそびれてしまった。
「それに、岩にはずいぶん粉が積もっていましてね、おそらくこの茸が乾燥して粉になったものだと思うのですけど、このあたりはかなり乾燥するほうですか」
中学の先生が答えた。
「ええ、川と山があるわりに湿度は低いと思います、それにしても粉になるほどではないと思います」
「そうですか、ここまできれいな粉になってしまうのは何か物理的原因があるのに違いがありません、このあたりにテントを張って観察を続けようと思います、しばらくおりますのでよろしくお願いします」
「そうですか、大変ですね、必要なものがあったら言ってください」
白瀬が言った。
「ありがとうございます、新しい茸が見つかるということは楽しいことです」
「この茸たくさん採れました、袋にいっぱいです、降ってきた粉を調べた限りでは毒成分ははいっていませんでしたが、食べられるかどうかわかりません、だけど興味がおありなら、持って行かれますか」
彼は袋を開けた。話の種には面白い。
「それじゃ一つ、小学校に持って行って、子供たちに見せましょう」ともらった。
「それなら、もっとおとり下さい」
「中学や高校の生物の先生にもいただけますか」
「どうぞ、頂上に行かなくてもそのあたりを歩くとけっこう出ていますよ」
そういいながら甘利先生は茸を先生方に配った。
「私たちは、下の林の茸を調査していったん戻り、明日、テントを用意して、ここに戻ります、生物の先生方、もし興味がおありならこれから林の中を御一緒にどうですか」
先生方は大きく頷いた。
私と教育委員会の白瀬は登っただけだったが戻ることにした。いつもデスクワークが多くて山登りはからだにこたえる。ということで先生方と環境課の人たちとは別れて下山した。
「変な茸が生えてたな」
「言わなかったが、この町の風土記に、物語としてこの茸がでてきたんだよ、石頭っていう茸なんだ」
「なんだいそれ」
「尖り山の上の方を岩山にしてしまったという茸だそうだ、お話しだけどな」
「面白い話しだな」
「古いもので毛筆書きだ、だけどおそらく明治に書かれたのだろうな、俺でも読める字体だよ、町の図書館にあるよ」
「コピーできるかな」
「そのうちコピーしとくよ」
「甘利先生たちしばらく町にいるから、それまでに数部コピーしてくれるかな」
「わかった」
ということで、3時過ぎに家に戻った。家で小学校に持って行く茸を家内に見せた。家内は触るとちょっと驚いた。
「なんて堅い茸なの、食べられるの」
「まだわからない、だけどこんなに堅いのじゃ食べられないね、明日小学校に持って行って、子供たちに見せるんだ」
家内は籠を持ってきて茸を入れた。
「キッチンにおいておくね」
そう言ってキッチンの窓の脇に置いた。
その晩、寝る前に水を飲みにキッチンに行くと、籠の中の黒い茸の傘が開いていた。白っぽい粉が落ちている。これは胞子だろう。空から降ってくる粉とよく似ている。
夜になると傘が開く茸なんだ。
朝になって。歯を磨いてキッチンに行くと、家内が振り返って私を見た。困ったという顔をしている。
「あなた大変、茸がこんなになっている」
見ると茸がなくなって、白い粉が籠の中に溜まっている。
「粉になっちゃった」
「ほんとだ、胞子が飛ぶと一晩で粉になるんだ、これが尖り山から風に舞って降ってくるんだな」
「ここに置いたのがいけなかったのかしら」
「そんなことはないよ、ちょっと白瀬の奴に電話してみる」
携帯で白瀬に電話すると、彼のところでも同じことが起きていて連絡しようと思っていたところだったそうである。
その日、小学校で週はじめの朝礼で挨拶をし、校長室にもどったとき、市役所から白瀬が電話をかけてきた。
「科学博物館の先生も同じことを言ってきたよ、標本用にビニール袋に入れたものがすべて粉になったそうだ、アルコールに漬けたのだけがそのまま保存され助かったということだ。夜に胞子を出して粉になるようなので、今日テントを張ってその映像を撮影するそうだ。世界でも珍しい茸だろうと言っていた」
「おもしろい茸が生えていてよかったじゃないか、だけど噂になるとみんな採りに行ったり、見に行って岩から落ちたりしたら大変だよ」
「そうだね、とりあえず、町の議会で町の天然記念物にでも指定して、尖り山のこの茸の採取を禁止するよ」
「ともかく、町に特産物ができてよかったじゃないか」
「そうだね、そういったものが今までなにもなかったから、観光課が喜ぶだろう」
「風土記は今日、図書館に電話してコピーしてもらっとこう、市の仕事ということでたのんでいいよな」
「ああ、もちろん、電話しておいてくれれば観光課の者に図書館に行ってもらうよ」
「茸の名前、きっと石頭になるかもね」
「おもしろい名前だよ、それいいね、甘利先生に言ってみる」
その後、この茸の和名は石頭になった。昔からこのあたりに生えた茸だったのだろう。それで風土記にあった物語ができたのに違いない。
甘利先生がテレビにでて、この珍しい茸の発見について話をしていた。町も徐々に名が知らるようになるだろう。
甘利先生は茸の発見についていろいろな科学雑誌にも書いた。町に粉が降ってきたこと、それが茸の匂いがしたことから発見にいたった経緯には私の名前も出ていた。この茸は岩を壊すことから、いずれ岩山が土山になる可能性が触れられていた。そのとき茸の粉が土に混じって肥沃なものとなり松の木などが生えるのではないかということである。風土記の物語の中では松の木を燃やしてしまったが、本物の石頭は松の木を生やす肥料になるのである。
その後、町の名はよく知られるようになり、観光地になった。
石頭は尖り岳だけではなく、周りの山の岩場でもみつかった。町の天然記念物だが、尖り岳以外では採取ができる。採ってきて粉になったものを使い、きの粉パン、きの粉饅頭や、きの粉煎餅、きの粉ケーキ、きの粉餅いろいろな特産品が作られるようになった。特に天ぷら粉のかわりにつかうと、コクがましてあげたものが格別に旨くなった。粉はきの粉(きのこ)としてよく売れた。
大昔、このあたりに住んでいた人たちは、この茸の粉を使って、いろいろな食べ物を作っていたに違いないのである。今その文献がないか調べているところだ。
三百年より前の尖り山はすべてが岩山だったのを石頭が土にして森ができた。山頂は燃えてまた岩山にもどって尖り岳になった。今尖り岳は石頭によって再び土になり、木が生えるだろう。茸はものを腐らすだけではなく、地球に変化を生じさせるような大きな役割も任っているのである。
きの粉


