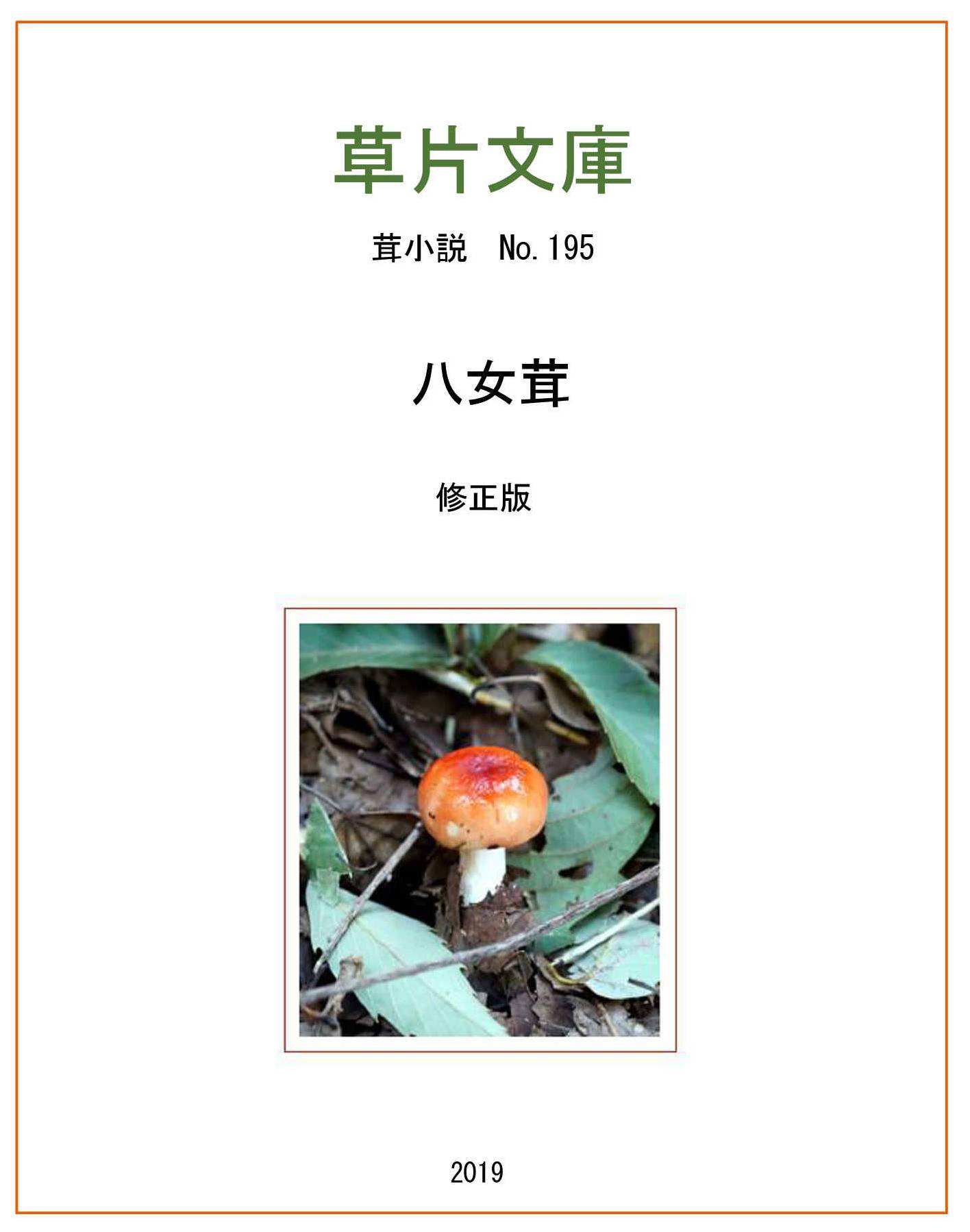
八女茸
茸のSFミステリーです。タイトルを「新幹線の茸」から「八女茸」に変えました。内容も改訂しました。
名古屋で仕事を終え、のぞみに乗って東京に戻った。窓の外からビルの明かりが目に映る。夜の9時、そろそろ東京に着く。荷物を整理し降りる準備をしていたところ、ふと足元に赤いものを見た。なんだろう、よく見ると、赤い小さな茸だ。どうしてこんなところに、と思い拾い上げた。手に乗ったのは赤いゼリーのようなかわいい茸だ。間もなく駅に着くというアナウンスがあった。土産の入った手提げの紙袋に茸を放り込んだ。そのままマンションに帰り風呂の準備をすると、スーツケースから使った下着類を洗濯機にいれた。
名古屋で商談がうまくまとまり、きっとご褒美休暇がもらえるだろう。かなり気が楽になっている。勤めている会社には面白い習慣があり、よい仕事をした者には有給休暇延長の褒美がでる。その判断は会社の総務部でおこなう。たとえば今回のようにちょっと大きな会社と十年間の契約が取れた場合は、会社の昨年の総収入を基として、何日分の収入になるか計算される。もし50日分に相当したら、その一割の5日が有給休暇としてもらえる。昨年の会社の収益が365億だとすると、一日1億である。今回の契約が50億なら50日分ということになる。そういった特別報酬はボーナスに上乗せをする会社もあるだろうし、商品券などの金券を支給するところもあるだろう。わが社では有給休暇を増やして、その時間を副業に当ててよいという考えである。
先輩で二ヶ月の有給休暇を獲得した者がいるが、彼はその間、学校に通って、バーテンダーの資格をとった。それによって会社を引けてからウイスキーバーでアルバイトをして結構な副収入をもらっていた。独り身の私などはどちらかというと趣味の時間として使う。日本のひなびた温泉などをめぐるのが好きなのでそれにあてる。会社に入って五年になるが、一度、一週間もらったことがある。そのときには有給とあわせて北海道二十日間の旅をした。
その制度だと、内勤の者にはご褒美をもらう機会がないと思われるだろうが、会社はよく考えていて、たとえば私が5日間の有給休暇をご褒美でもらうと、24時間かける5の1%、すなわち1・2時間の有給休暇延長が会社員全員にもらえる。それが24時間たまると一日の延長になる。誰かが儲けを得るとそういう形でみんなにもおこぼれがいくのである。さらに利益を得た者が所属する部署の者には全員に5%与えられる。ということで部署の中ではみんなで協力しあうことにもなる。
延長された有給休暇の貸し借りなども自由である。固定されている有給休暇は、貸し借りができないが、誰かの延長分を借りることはできる。
明日会社で正式に相手の会社との契約書をわたすと、翌日には褒美の延長有給休暇の査定がおりる。みんなから祝福も受けることになる。
キッチンテーブルの上に明日持って行く部署への土産のはいった紙袋を置いた。名古屋には何度も通った。名古屋土産ももう底をついた。それで今回は食べ物ではなく、ちょっと気張って有名な陶器の染め付けの小皿を部署の人数分買った。真ん中に果物の柄のある直径が3センチほどの小さなものである。
自分にも一つ買ったのでそれを取り出そうと袋の中をのぞくと、赤い物が目に入った。そうだ、新幹線で茸を拾ったんだ。取り出してみると親指ほどの茸で、電燈の光が透けて、赤い傘がきれいだ。柄がふっくらしているかわいい茸だ。なぜ新幹線などに落ちていたのであろう。
茸を机の上に載せるとまだみずみずしく、転ばないで立っている。
袋の中から自分用の皿を取り出した。自分には白地に葡萄の絵がかれている小皿である。つまみでも入れよう。
皿を机の上に置くと、その振動で赤い茸が倒れ、小皿の上にのっかった。薄緑の葡萄の隣に赤い茸の笠、よく似あう。
風呂からお風呂がわきましたと声が聞こえた。最近の風呂はしゃべってくれる。風呂に入ってビールを飲もうと風呂場に向かった。
一人暮らしで誰がいるわけでもないが、自分の家に戻るとやっぱり落ち着く、風呂上がりのビールが最高だ。買い置きの塩ピーナッツを摘まみながらビールを飲む。
赤い茸がいつの間にか小皿の上で立っている。なんだか前からそこに生えていたような雰囲気だ。秋だから茸の季節ではあるが、売っている茸ではなさそうだし、どうしてあそこに落ちていたのだろう。
キッチンのテレビをつけた。キッチンといっても居間兼用で十畳とかなり広い。ニュースでは横浜でいなくなった猫が名古屋で保護されていることがわかり、飼い主の外国人が大喜びしてインタビューに応じている姿が映し出されていた。トラックの荷台に入り込んで運ばれてしまったらしい。それにしてもそんなに遠くにいってしまったのに飼い主がよくわかったものだ。テレビではその説明をしている。皮膚の下に埋められていたマイクロチップに飼い主の電話番号が登録されていたからだという。便利な物だが、人間にされたらどうだろう。国民全員にそんなことをされたら怖いものだ。そんなことを考えながらふと赤い傘の茸を見た。
この茸に飼い主、いや持ち主がいるとは思えないが、どのような人が持っていたのだろうか。子供が草原で見つけて採ったのを落したのかもしれない。のぞみ13号車18Cである。新幹線では誰が乗っていたのか調べるわけにもいかないが、どのみち明日の朝になれば萎びてしまう運命である。
次の朝、少し早く会社に出た。契約書を総務に提出し。今日中に結果を正式に報告書にまとめ部長に渡さなければならない。
契約書を提出したあと、デスクで報告書を書いていると、同じ課の連中が出勤してきた。
「先輩、いい仕事取れたという話ですね」
自分より二年後に入社した男が声をかけてきた。
「うん、今回こんなにうまくいくとは思っていなかった」
みんなに名古屋の小皿を配った。
「すみません、こりゃ有名な奴だ、女房が喜びます」
年間五千万、十年間の契約を取り付けてきた。彼にもいくらかの有給ボーナスがいくだろう。
できた書類を総務に持って行くと、受付の女の子がにこにこしている。もう知っているようだ。
「部長は社長室にいらしてます、直接報告書を持って行ってください」
少しだが彼女の有給も増える。
中にはいると部長がソファに腰掛け、社長が「おはよう、よかったな、おかげで会社もしばらく安泰だよ」と珍しくデスクから立ち上がった。小柄の彼はいつもでんと椅子に腰掛けたまま話をする。肩幅が広く顔が大きくてしっかりした目鼻立ちなので、そのまま見るとなかなか迫力がある。それを知っていて、得意先の社長がきてもちょっと腰を浮かして挨拶をするとすぐ腰掛けてしまう。
今日は机の脇のソファにきて「座りたまえ」とテーブルの部長の脇を指差した。
「うまくいったね」部長もさすがにいい顔をしている。
腰掛けて書類を差し出すと社長が、
「今度は有給休暇もかなり延長だが、君を係長に推しといたよ」
そういって書類を受け取った。この会社は年功序列で位が上がるが、特別な功績をあげても一つ上に行く。
社長は契約書を取り出すと念入りに確認している。そんじょそこらの会社社長と違うところである。書類の細かいところまで読みとることのできる能力がある。それと発想力の奇抜さはただならない。それでこの会社が著しい成長を遂げたのである。
名古屋での商談について細かに報告をすると、部長もうなずいた。
「あの社長は大ざっぱだが、将来を見通す力があるようだ、後は部長にたのむよ」
社長はそう言ってデスクに戻った。
この会社には面白い仕組みがまだある。通常、契約を獲得した本人がその相手の会社担当になるものだが、この会社では部長がしばらく担当し、その後別の課の者に割り振る。場合によっては獲得してきた部署にまわされることもあるが希である。相手の会社をいろいろな角度からみようという意図である。数年経つと別の課に移ることもある。マンネリが解消され、むしろその方が相手の会社と長く付き合える。
「今度はお手柄でした、総務が延長分を計算していると思うよ」
書類に目を通した部長と共に社長室をでた。
課にもどるとみんながどうでしたと聞いたので、「昇進までついたよ」と報告すると、「わ、それはおめでとうございます」と手をたたいた。一番若い男が言った。
「これで、係長二人ですね」
この仕組みも面白い。わたしが所属する課にはスタッフが5人いるが、いままで係長が1人、平が4人だった。係長だった一人は私より5年上で、やはり大きな契約をとったことで昇進している。部屋のリーダーはいない。合議で次の戦略を練り役割を決めていく。わたしの仕事は終わったので、またみんなで合議して、上から降ろされた事柄に関して、どのように売り込んでいか、どのような相手を探すか決める。その中で私の担当する新たな役割が決まっていく。
「すぐに有給休暇使うのかい」
係長が訪ねたのでうなずいた。この一月名古屋に通い詰めでちょっと疲れている。休暇を捕りたい思いがあった。
「有給だいぶ延びるだろうね」
「ええ」
「楽しんでおいでよ、それから戦略会議をしよう」
みんなもうなずいている。
そこに総務から電話で、有給を二週間延長してくれるということであった。
今回はどこに行こうか、家に帰って旅の本でも引っ張り出してみよう。
「二週間もらったよ」
課のスタッフはそれを聞くと、みんな私を見た。
「うわ、いいな、おめでとうございます、今度はどこに行くのですか」
「まだわからんなあ」
「私だったら台湾」
紅一点のスタッフは海外旅行によく行く。
「またエステか」
彼女は笑ってうなずいた。
会社が引けてマンションの近くの食事どころで夕飯をすませて家に戻った。
キッチンのテーブルの上の小皿の中で赤い傘の茸がしゃきっと立っていた。朝は気がせいていて茸のことを忘れていたが、驚いたことに萎びていない。
乗ったのぞみは博多発である。茸は九州からきたのか、四国からきたのか、山口、岡山、兵庫、大阪、京都どこだろう。
部屋着に着替えビールを飲みながらテレビを見ていると、鹿児島や大分の特産である椎茸の紹介をやっていた。椎茸というと群馬しか思い浮かべなかったのであるが、椎茸はいろいろなところでとれるらしい。
赤い茸が目に入った。どこで採れたんだお前。
この茸の名前はなんというのだろう。茸の図鑑はもっていない。いつも持ち歩いているPCを開いた。インターネットで調べることができる。赤い茸と打ち入れ、検索をかけウェブから画像に切り替えた。赤い傘の茸の写真やらイラストが出てくる。
出てきた出てきた、しかし茸の写真を見ていくと柄まで真っ赤な茸はあまりない。よく出てきたのは卵茸である。それに紅天狗茸。しかしそれらの茸とは形状が違うし大きさが違う、ともかく透きとおるように赤い。一つ柄まで真っ赤な茸が見つかった。ベニヤマタケとヒイロガサとある。確かに色の具合はよく似ているが、落ちていた茸の柄はふっくらとしていて円みがある。茸の名前は難しい。そういえば他の部署だが信州の山奥で育った奴がいる。あいつに見せるとわかるかもしれない。
次の朝、茸をビニール袋に入れ、背広のポケットにしまうと家をでた。
昼休みにその男の部署を訪ねた。同期に会社に入った男である。
「やあ、今回はすごかったな」
彼が片手を挙げてよってきた。彼はもう係長である。
「やっと追いついたよ」
彼は一年前に大きな契約をとって昇進している。
「いや、俺は一週間の休暇延長だったけど、おまえは二週間だって」
私がうなずくと、
「たいしたもんだ」と言ってたたえてくれる。そこが彼のいいところだ。
「いや、その報告に来たんじゃないんだ」
上着のポケットから赤い茸を取り出した。
「なんだい、その茸のオモチャは」
「いや、おもちゃじゃないんだ」
彼に手渡すと驚いてこんなことを言った。
「茸はポケットに入れておくと必ずおれるか、どこか壊れるるものだよ、だけどこれは全く傷がないだろ、だからゴムかなんかのオモチャかと思ったんだ」
言われてみると確かにそうだ。
「どうしたんだ」
「一昨日、新幹線の中で拾ったんだ」
「え、どうして萎びていないんだ」
「わからない、それで茸の名前を聞こうと思って持ってきた」
「俺にか、真っ赤で透き通るような茸は知ってるが、このような形のは知らないな、緋色傘という茸の色に似ているが柄がもっと細い、こいつはポルチーニを小さくしたような形だ」。インターネットで調べたと同じ感想をもった。
「どうして萎びないのかな」
「うーんわからんな」
「おまえさんにわからないならお手上げだ」
「専門家でもわからない茸は多いんだ、何しろ茸は種類が多いし、名の付いていないのがたくさんある」
「そうか、いや時間とらせた」
「お守りにでもしたらどうだい」
「毒茸をか」
「赤いからって毒とは限らないよ、旅行に行くんだろ楽しんでこいよ」
その日の帰りである。コンビニで夕食を買ってマンションに帰る時のことだ。途中に小さな地蔵があるが、脇からミャアと声がした。見ると地蔵の足下に中くらいの茶色の猫がうずくまっていた。立ち止まるとその猫がびっこを引きながらやってきて、自分の足にこすりついた。後ろ足が悪いらし。よく見ると左足から血が出ている。怪我をしたばかりのようだ。
動物は好きな方である。自分のマンションを通り越してちょっと行ったところに動物病院がある。連れて行ってやろう。拾い上げると猫はおとなしく抱かれた。久しぶりに動物の毛の暖かい感触が感じられ、ほっこりした。実家に猫がいたからだ。
動物病院に行くのは生まれてこの方、初めてである。マンションの一人暮らしなので東京で動物を飼ったことは無い。実家には三匹の猫がいたが、好きなときに外に行って、餌が欲しくなると戻ってきた。都会の猫の飼い方とは違う。家族そろって動物好きである。
受付で怪我をしている猫を連れてきたことを言った。幸い患者がいなくて、すぐに診察室に呼ばれた。女性の獣医さんが椅子から立ち上がった。
「あ、ご苦労様です」
女医さんが私から猫を受け取った。おとなしく抱かれている。
「慣れていますね」
女医さんは足の傷を調べていたが、
「怪我をしたばかりですね」と脱脂綿で傷口をぬぐった。
「たいしたことはないですね」と消毒薬らしいものを吹き付けた。猫はびくっと足を引っ込めたが、騒がなかった。そのあと軟膏のようなものを塗って、包帯を巻いた。
「おとなしい猫ですね、どこの猫かご存じないの」
私は頷いた。
「地蔵のところでうずくまっていました、僕を見ると寄ってきたんです」
「あら、猫好きでいらっしゃるのね、おそらく自転車にでもぶつかったんでしょう、自動車やオートバイだと骨が折れてたでしょうね」
「私はどうしたらいいでしょう」
「書類だけ書いてください、治療費は飼い主からもらいます、それまで預かっとくわ、よく慣れていて、飼い主がかわいがっていたのでしょう、すぐ見つかりますよ」
女医さんはなにやらハンデイな機械を持ってきた。
「マイクロチップが入っているといいんだけど」
昨日テレビで言っていた奴だ。
「あ、やっぱり入っていた」
私が書類書きの手を止めて見つめていたので、女医さんは、
「ごらんになる」と手招きをした。
彼女の持っている機械に数字が表示された。先生は脇のワゴンの上にあったPCを開いてどこかのサイトを開くとその番号を照合した。
「名前はお茶、近くにお住まいの方の飼い猫、電話番号ありますから電話します」
そういってデスクに戻ると電話をかけた。
猫は診察台の上でおとなしくうずくまっている。ちょっと頭をなでてみた。気持ち良さそうにしている。
「よかったですね、持ち主が電話にでました、出っていったっきり戻らないので、心配していたところだそうです、歩いて二十分ほどのところの家だそうです、すぐ引き取りにくると言ってました、お礼がいいたいとおっしゃってますが、お待ちになりますか」
と先生が聞いた。
私は書いた書類を渡して首を横に振った。
「飼い主に電話など教えてもいいですか」
それも断った。実家で弟が面倒を見ている認知症の母親を思い出して聞いた。
「マイクロチップは皮膚の下に入れるのですか」
「そうですが」
「人間にも使えますか」
「使えないことはないでしょうね」
「入れるとき痛いですか」
「マイクロチップは小さなものです、このリーダーをかざせば番号が出ます。太めのインジェクターでいれます。ちょっと太いから皮膚に刺したときには痛いかもしれない、どうしてですか」
「いや、田舎の母親が俳諧気味で」
「倫理問題はわかりませんが、まだそのような使われ方をしていないですね」
「その機械を当てられて猫は痛くないですか」
「マイクロチップリーダーですか、やってごらんになりたければどうぞ」
先生が機械を渡してくれた。「猫の首のところに当てて、このボタン」
するとちゃんと数字がでた。機械を自分の左手首に当ててみた。痛くも痒くもない。
「何ともないですね」
左手が上着に触れ、茸があるのを思い出した。茸を取り出して何となくリーダーを茸にかざした。
「あ」
声を出してしまった。
「どうしました」
先生がそばにきて機械を見ておやっという顔をした。
そこには番号が現れていた。
「持ってるもの何ですか」
「茸です」
「あらきれいな茸ね、マイクロチップが入っているのかしら」
「そんなことはないでしょう」
「茸の成長を調べるためとか、どこの産地か記したものだとか、そのためにいれたのかもしれませんよ、大事な茸じゃないですか、マイクロチップは研究用に開発されていたのですよ、魚に埋め込んだり、野生の動物に埋め込んだり、行動や繁殖を調べるためです、でも茸や植物に使うのは聞いたことがありませんね」
先生も興味があるとみえて番号を控えた。コンピューターを開いて検索していたが、首を横に振った。
「出てきませんね」
「この茸どうしたのです」
「新幹線で拾ったのです」
「茸拾ったり猫拾ったり次は何拾うのでしょうね」
と先生は大きな口を開けて笑った。なかなか魅力のある獣医さんだ。
「それじゃあ猫ちゃんよろしく御願いします」
と診察室をでた。
先生の「猫ちゃんありがとうございました」と言う声が後ろから聞こえた。
それにしても茸にマイクロチップが入っているとは思いもよらなかった。
マンションに戻って、茸をまた名古屋の小皿に載せた。再びシャキッっと皿の上で立った。なんとなくただの茸ではないような気になってきた。
次の日、会社でデスクに向かっていると、携帯が鳴った。獣医さんであった。猫の飼い主がお礼をもってきたので渡したいという。会社の帰りにまた犬猫病院によった。
「若い美人の方でしたよ」
そう言って獣医さんは笑いながら包みを渡してくれた。チョコレートのようだ。
「先生どうぞ召し上がってください」
「甘い者はお嫌いですか」
「食べないことはありませんが、おいておいてもなかなか減らないし」
「ご家族の方はお食べにならないの」
「一人です、ちょっと家を空けるのでどうぞ」
「そうですの、私は猫と二人暮らし、いただいとこうかしら、あ、そうだわ、あの茸の数字は不思議なの、インターネットで「番号」と「茸」で検索をかけたら、地図がでてきたわ、それに絵文字のようなものが描かれていました。プリントアウトしておきましたから差し上げましょう」
そういって彼女はデスクの引き出しから紙をもってきた。
明らかに九州の地図であった。それに意味の分からない絵のような字のようなものの羅列があった。茸の採れた場所を示しているのかも知れない。
「マイクロチップのリーダーって高いものでしょうね」
「ポータブルのものだと、一万円ほどで買えますけど、個人が持っててもしょうがないですよ」
獣医さんの名刺をもらって家に戻った。
茸は小皿の上でしゃっきり立っている。まったく萎びていない。やはり研究用に何らかの処理をしたものではないだろうか。研究者が探しているかもしれない。
獣医さんからもらったマイクロチップの情報は、文字はわからないとしても地図は手がかりになる。よく見ると九州の地図の一部に赤い矢印がある。自分でもPCを開いて番号と茸と検索をかけてみた。
確かにプリントアウトしてもらったものと同じものがでてきた。地図の赤い矢印は電気がついているように明るい。誰が掲載したのかサイトを調べたのだが、だだの記号の羅列しかみつからなかった。とりあえず赤い茸と名を付けて、インターネットのお気に入りにしまった。
さて、ご褒美の旅行はどこに行こう、と考えたのだが、赤い茸の九州の地図しか頭の中に浮かんでこない。暗示にかけられたように、九州の温泉に入る気分になってしまっていた。
茸のマイクロチップの地図には地名が入っていない。旅の雑誌の地図とあわせると、どうも大分県あたりだ。大分県は椎茸のほだ木による栽培の発祥の地とある。江戸初期のころにはすでに始めたようだ。ずいぶん早い頃から茸栽培をやっているわけだ。そういうところなら、椎茸に限らず、茸にとって住みやすいところだろう。研究者がいても不思議はない。茸の出所にたどり着くことは無理かもしれないが、旅行に捜索の目的が加わるのも悪くない。解決しなくても問題があるわけではないし、ちょっと犯人探しのミステリー旅行の要素が入って面白いかもしれない。しかも大分なら湯である。たくさんの温泉地がある。そのあたりで湯の梯子をしてこよう。
それで九州旅行が本決まりになった。。
別府、湯布院あたりをはじめとして、茸の出所探しはあっちに行ってから考えることにすればいいだろう。こうして、茸のおかげで旅の計画を作ることができた。旅は道連れ、世は情け、茸と一緒の温泉旅だ。
出張が多い仕事なので旅はなれている。いつも使うキャリーバッグにいつもの旅の道具を詰め込んで出かけた。仕事の時はいざ知らず、遊びに行く時には飛行機は使わない主義である。まず別府に向かった。
東京駅から新幹線で小倉まで、そこから特急ソニックで別府にいく。そこまでは前もってビュウで指定券をとっておいた。
六時間半の電車の旅。中でPCを開いて別府の知識をいれた。別府のどの温泉地にするか決めていなかったが、有名な地獄群に歩いていけるところがいい。
そこまで決めて別府に着いた。。別府には温泉宿は何百もあるという。とても自分で選ぶことはできない。観光案内所に行った。
八つの温泉場があるけどどこがいいですかと地図を示してくれた。地獄に歩いていけるところと言ったところ、鉄輪(かんなわ)温泉がいいでしょうという。いくつもある中から、値段がほどほどの宿に二泊たのんだ。
鉄輪温泉の宿へはバスで十五分から二十分ということだが、タクシーを使った。街の中を走るタクシーから湯煙の上がるのが見える。温泉の町にきたという気分が強くなる。十分ほどでついた宿は落ち着いたたたずまいで印象はよい。チェックインをすますと年をとった番頭さんが荷物を持って部屋に案内してくれた。
「ゆっくりしてくだい」
番頭さんと入れ替わりのように、和服をピシッと着こなした女性が急須を持って入ってきた。
「宿の女将でございます、よくおいでくださいました、お仕事ですか」
「いえ、遊びです」
「よろしいことですね、どうぞゆったりとお過ごしください。分からないことがありましたら帳場のほうにおっしゃってください」
そう言って避難経路と露天風呂の場所を教えてくれた。じきじきに女将がくるとは、大きくない宿だから、昔ながらのもてなしができるのだろう。
「まだ夕飯まで二時間がありますから、町を歩かれるのもよろしいかと思います」
女将は茶碗に茶を注いてくれた。明日地獄巡りをしたいというと地図で行く順番を示してくれた。
「どのくらいかかりますか」
「そうですねまわり方にもよります、一日ではたいへんですね、一泊の方は、着いた日にいくつか行って、帰りの日朝早く出られます、お客様二箔ですから丸一日つかえばいけないことはありませんね、どうぞ楽しんでください」
そういわれたこともあり、その日は露天風呂を楽しんだだけにした。
久しぶりに温泉に入った。夕食は部屋食である。仕事ではビジネスホテルばっかりだったので、贅沢な気持ちになる。
食事を運んできた仲居さんに飲み物は何かと聞かれ、目の前に並んだたくさんの器の中を見た。新鮮な海のものがある。そういえば別府は海の際だ。すごく大きな焼椎茸がある。茸ステーキだ。切ってあるが傘の直径が十センチはあるだろう。
「生ビールお願いします」と言って、さらに「やっぱり椎茸がおいしそうですね」と言ったところ、「お客さん、大分が椎茸の一大産地なこと知っていなさるんですね、こんな大椎茸のステーキは他じゃ食べられませんよ」と答えが返ってきた。
うなずきながら、「ほかの茸もよく生えるんでしょうね」と聞くと、
「山の方に行けばいろいろ採れますよ、由布岳もあるし、ビールすぐにお持ちします」と言って出て行った。
次の温泉地はやっぱり湯布院だろう。
食べ終わって、テレビを見ながらPCを開き、ネットで連絡がきていないか確認をした。そのあと赤い茸を開いた。なぜか地図の大分付近にある赤い矢印が点滅をはじめている。家で開いた時には赤い光の矢印だけであった。どうしてだろう。
茸を上着のポケットに入れておいたのを思い出した。洋服タンスを開け、茸を取り出した。変わりなくしっかりしている。テーブルの上に載せるとピンと立った。元気なものだ。頭をなでたくなるようにかわいい。どのような動物でも飼っているうちに情がわくものである。茸など食べ物としか考えていなかったが、動物に近いような生き物の気がしてきた。
次の日、宿で地獄共通券を二千円で購入し、改めて道順をきいて出かけた。街中をぶらぶら歩くのも久しぶりである。仕事の緊張感も嫌いではないが、やっぱり達成しなければならないような目的が無いのはよいものである。足湯があればちょっと浸かって、土産物屋なども覗きながらあるいた。のんびり歩いたつもりだが、海地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄、鬼山地獄、白池地獄を周ってしまった。血の池地獄や龍巻地獄はちょっと離れている。タクシーを使った方が良いと勧められたが、その二つの地獄にも歩いて行ってしまった。お昼を食べたり、面白そうな店に寄ったり、一日歩きづめである。仕事で外回りをしていたので歩くのはさほど苦にならない。硫黄の匂いに囲まれて歩くのはいつもの生活から離れて、別の国に来ているようだ。
宿に帰って全部の地獄を歩いたと言ったら驚かれた。歩いたおかげで湯の気持ちのよいこと、ビールのうまさは格別だった。
次の日、町で昼を食べて別府駅に行くとたまたま由布院に行く電車があった。二両しかない。あわてて乗って、ちょっと窓の景色をながめていたらすぐついてしまった。十五分ほどだっただろうか。別府と由布院はもっと離れていると思っていたのであっけなかった。そこで、おやっと思ったことがある。大分の温泉、湯布院と覚えていたのだが、山は由布岳と書くし、駅の名前も由布院と書かれている。どちらなのだろう。
駅の案内所のポスターには湯布院の温泉とある。そのことを聞いてみた。
「地名は由布市湯布院町なのです、由布町と湯平町が一緒になって、湯布院町になりました。駅は昔の由布のところなので、由布院となっています、どちらも間違いではありません、お好きなほうをお使いになればいいのでしょう」
ということだった。宿を探すと手頃なところがあったので一泊で申し込んだ。
宿までぶらぶらあるいたが、地獄がたくさんある別府の力強い空気と違い、どことなくゆったりとしていて、全く違う雰囲気だ。あまり離れていないのに由布岳を挟んでこうも違うとは。そういえばどちらも海がある。別府湾は海岸線まで水深が深く、船の航路の一つだが、由布院はちょっと奥になり、別府の奥座敷などとも言われる。近くの有明海は広く浅く、海岸線は干潟が有名である。海のありようも二つの温泉地ではずい分違う。
宿は由布岳の麓にある。ちょっと遠いが歩いた。そばに金隣湖という池のような湖があった。金燐湖の立札には由来が書かれていたが、歴史に疎いので、出てくる人物の名前のイメージがわかなかった。ともかく湖の表面が日の光により金の鱗のように輝いているのを見た人がそう呼んだという。それよりも色々な生き物が生息していて、天然記念物の魚もいるということが面白かった。別府と同じように観光客がぶらぶら歩いているが湯布院は若い子たちが多いような感じだ。
泊まったところは落ち着いた露天風呂のある古い宿だ。湯布院では外には出ないで湯を楽しむだけにした。チェックイン時間より早く着いたが支度ができているのでどうぞと部屋に通してくれた。
着物に着かえ、早速露天風呂に行くと、誰も入っておらず、湯は無色透明で、すがすがしく気持が良かった。別府のちょっと濁ったような湯とは違う趣である。
その宿でも食事は部屋食だった。たくさんの料理を前にしてビールを楽しんでいるとき、ちょっとおかしなことがおきた。壁に掛けておいた上着を見るとゆらゆら揺れている。離れたところにあるのでエアコンの風が当たっているわけではない。何だと思って箸をもつ手を止め、見ていると、上着のポケットから赤い茸が飛び出した。茸は畳の上にぽとりと落ち、ちょいと転がり起き上がりこぶしのようにぴょこっと立った。眼がないのにこちらを見ているような錯覚に陥る。
この茸は我が家でも小皿の上で勝手に立った。どのような能力のある茸なのだろう謎の多い茸だ。ますますどこからきたのか知りたくなる。
箸をおいて、そばによると、畳の上で立っている赤い茸を拾い上げた。触ってみたがただの茸である。指で強く摘まんでみた。ちょっと凹んだがすぐに元に戻った。偶然だろうと思うことにして、茸をポケットに戻した。それにしても上着のポケットからどうして飛び出たのだろう。
席に戻って食事を続けていると仲居さんが飲み物の追加を聞きにきた。生ビールをもう一杯頼んだついでに、どこかいい温泉場がないか聞いた。湯布院まで決めていたが、その次に行く場所を決めていない。行き当たりばったりの旅である。
「車ですか」
「いや、電車の温泉旅、別府を回ってきたんですよ」
「柳川や太宰府にみなさん行くけど、大分の中で温泉というと、久大(くだい)本線沿いに温泉場がありますよ」
「久大本線て知らないんですが」
「あれ、お客さん、別府から乗った電車がそれですよ」
「あ、そうですか、電車の線の名前も見ずに由布院行きに飛び乗っちまったから」
「九大本線はゆふ高原線ってもいうんですんよ、川沿いのいい電車だね、大分から久留米までいくんですよ」
「面白そうだ」
「大分のはずれになるんすけど、大分の小京都といわれてる日田(ひた)なんていいですよ、温泉もいいし」
「それはいいな、それにしよう、どれくらいかかります」
「ゆふいんの森という特急で一時間くらい、日に3本くらいですね、そういえば各駅停車で行っても一時間くらいだから同じかな、ただ各駅停車も本数がなくてね、6時と7時に一本、9時に一本ですよ、そのあとは2時までないね」
「いや、ありがとう」
「ビールすぐお持ちします」
各駅停車で行ってみるのもいいだろう。
仲居さんがビールを抱えてもどってきた。
「朝食は何時になさいますかね6時半、7時、7時半、8時ですが」
「9時頃の各駅で日田にいくので7時かな」
「はい、楽しんできてください」
食事のあとPCを開けて日田の情報を見た。なかなかきれいな町並みだし。滝など見所もあるようだ。茸のマイクロチップの地図情報をみると、赤い矢印が点滅している。そういえば点滅が早くなっているような気がする。
天気のよい日が続いたおかげで旅も楽しい。湯布院9時20分の久大本線各駅に乗った。まっ黄色の二両の電車だ。あまり人が乗っていない。電車は山の間、川の縁をいく。緑と川の流れと、空の青さと、旅の空気を楽しめたのであっという間の一時間だった。
着いた日田駅は想像していたのとは異なり近代的な建築物である。最近建て替えたようだ。駅の案内所のパンフを見ると、日田は城下町だったそうで、古い町並が残っているとあった。宿のことを尋ねたが、観光ホテルのようなところしかない。露天風呂がいいと考えていたので、そのことを言うと、川沿いの一つのホテルを勧めてくれた。駅からはさほど遠くない大きなホテルである。それに決めた。
チェックインは3時。フロントにキャリーバックを預けて、どこに行ったらいいか聞いた。日田市は天領の地で、豆田町は日本でも有数のきれいなところらしい。もらった地図を頼りに豆田町まで歩いた。
お昼を食べた後に町中をぶらつくと、至る所に小物屋があって、好きな人には楽しいだろう。日田紙という和紙が有名だそうだ。目を引いたのは大きな古い薬屋である。店の中には昔からのものが展示されており、歴史を知ることができて面白かった。いいところだ。いつの間にか3時を過ぎている。
ホテルに戻リ、キーをもらった。夕食は大広間である。部屋は洋室だったが設備は整っているし泊まりごこちは良さそうだ。早速川を見下ろす露天風呂に入りビールを買って十階の部屋に戻った。
入口の戸を開けて驚いた。目に入ったのは窓際の丸テーブルの上で立って揺れている赤い茸である。なぜ。
上着はロッカーに吊るしたはずである。その前に落ちたとしてもテーブルの上に立っているはずはない。誰か忍び込んだにしても、茸だけ上着から取り出すようなことはするまい。財布の類は問題なくあった。ホテルの人が緊急の用事があって部屋に入り、落ちていた茸を拾ってテーブルの上に置いたのだろうか。それにしても不思議である。
揺れている茸を目の前にして、ソファーに腰掛けビールのプルトップを引いた。奇妙に思いながらビールを飲み干した。やっぱり赤い茸が自分を見ている。
さて、明日はどこの温泉に行くか、インターネットで日田の地図を検索した。日田を中心にして地図を縮小していくと久大本線の終点が確認できた。久留米である。久留米はもう福岡になる。
次に行くところが決まらないまま夕食の時間になってしまった。
茸をそのままにして、部屋の鍵を持って食事の会場に行った。部屋番号のテーブルに腰掛けた。海の物から山の物がずらりと並んでいる。仲居さんがミニコンロに火を付けにきた。牛肉と野菜が用意されている。焼いてたれにつけて食べろということだ。
「飲み物はなにになさいます、ご飯は食べるときにいってください、味噌汁がつきます」
「生ビールお願いしようかな」
「はい、すぐお持ちします」と戻っていった。
食前酒は梅酒だ。定番である。刺身に箸をつけたところでビールがきた。
「明日違う温泉地にいこうと思うのだけどどの辺りがいいかな」
「湯布院はどうでしょ」
「いや、別府から湯布院、その後ここに来たんだけど」
「それじゃあ、福岡の方だねえ、歴史が好きな人だと八女にいくね、温泉もあるけど、古墳がたくさんあって邪馬台国のあったとこだといわれていますよ」
「お姉さんよく知ってるね」
「はは、あたしが八女の出だからね、お茶が有名、この宿のお茶も八女から入れてる、椎茸もとれるしね、この椎茸も八女のが混じってる」
仲居さんはテーブルの上の煮しめを指さした。
「やめって、どう書くの」
「八の女」そういいながら戻っていった。
どうも歴史や地理に疎い。名前が面白そうだ。
食事をすますと部屋でPCを開いた。目の前には赤い茸が立って揺れている。それを見て、八女を調べる前に赤い茸のウェブを開いた。画面に九州の図が現れると、赤い矢印が緑色に変わって点滅しはじめた。何だろう。絵文字のようなものも緑色にかわった。
そのとき部屋の電話が鳴った。
あわててデスクのところに行って受話器を取った。フロントからだ。
「はい」
「お電話が入っておりますが、八男(やお)という方です」
知らない名前だ。
「つないでください」
電話にでた声は落ち着いた男性の声であった。
「いきなり電話をしまして申し訳ありません、八男と申します。茸から連絡が入り、そちらにおじゃましていることがわかりまし、それで連絡を差し上げた次第です」
茸から連絡とはどういうことだろう。茸のマイクロチップからの発信がとどいたのだろうか。だから矢印が緑色に変ったのか。それにしても、すぐに電話が来るなど信じることが出来ない。
「ええ、赤い茸はありますが、もしかすると、持ち主の方で」
「はい、私どもが飼育しております」
「どうしてここがわかったのですか」
「私どものサイトを開いてくださって、20キロ圏内ならば、茸の発する電波を受信できて位置がわかります」。やっぱりそうか。
ということはマイクロチップを茸に入れた研究者なのか。
「しかし、このホテルにいるということがどうしてわかるのでしょう」
「茸のいるところが、数センチのオーダーでわかります、ホテルの地面より25メーター、ホテルのどの部屋かもほぼわかります、それで電話を差し上げたわけです、どのような経緯で茸を保護されたか知りませんが、茸の様子は至極健康で、ありがとうございます」
茸の状態までモニターしている。
「いや、なにもしていないんですが、東京駅についた新幹線の中で拾いました、偶然に茸にマイクロチップが入っていることがわかったので、あのサイトを開くきっかけになった次第です、それでいつまでも萎れないので研究している大事な茸だと思っていました、ポケットにいれ九州の温泉旅にきました、もちろん茸はお返します」
「それはありがたいことです、これからどちらに行かれますか」
「八女にいこうと思っていました」
「おおそれはよかった、私は八女から電話しています。明日、そちらのホテルに車を回します、よかったら私の家にお泊まりください、掛け流しの湯もありますので」
驚いたことに、茸の持ち主が、明日の十時にホテルに迎えにくるということになった。なんと言うことだろう、信じられない旅行となった。
朝風呂にも入り、部屋でる支度を整えてテレビを見ていると電話が鳴った。お迎えの方がみえているということである。茸を上着のポケットに入れた。
ロビーに行き、宿代を清算すると、帽子をかぶった薄茶色の制服姿の運転手がやってきた。
「八男男爵よりお迎えにあがりました、茸を保護してくださったこととても感謝していると申しておりました。これに八女茸をおいてくださいますでしょうか」この赤い茸は八女茸というようだ。
白い手袋をつけた運転手は黒い箱を取り出し蓋を開けた。その時、ポケットの茸がもぞもぞと動いた。ポンという音がしたような気がしたが、しなかったのかもしれない。ともかく茸がポケットから飛び出し、箱の中に飛び込んで横になった。箱の中は白いシルクで覆われている。
「お帰りなさいまし」
運転手は茸に声をかけて箱の蓋を閉めた。何が起こっているのだろう。
「どうぞ車はあちらです」
片手で私のキャリーバッグをとろうとしたので、「自分で持つから」と彼の後をついていった。
ホテルの玄関には大きくはないが古風なセダンが止まっていた。
運転手がドアを開けてくれた。嘗めした柔らかい皮でできているシートに尻が程良く沈む。運転手は茸の入った箱を助手席に置くと後ろを振り返った。
「一時間ほどかかりますが、もし車を止めたいところがございましたら、お申し付けください。飲み物など脇のクーラーにいれてございます、ご自由にしてください」
見ると脇に白いクーラーボックスがある。
「それではまいります」
「あのー、どちらにつれていかれるのでしょうか」
「あ、失礼しました。八女の八男男爵の館にお連れします。黒木町男岳麓でございます、八滝の近くです」
「八女駅は電車だとなに線になるのですか」
「八女駅はございません。八女に行くには久留米からバス、または鹿児島本線の羽犬塚駅からバスでございます」
「不便なところですね」
「そういう意味では不便ですが、大昔は栄えたすばらしい都市です。行ってごらんになるとわかります、日本の発祥の地でもあり、いやこの世の発祥の地でもあります」
いやに仰々しい、大丈夫なのだろうか。
車は走っていないように感じるほど揺れが少ない。よほどの車なのだろうがどこの車かわからない。
「八男さんは茸の研究者なのですか」
「いえ、育てられています」
よくわからない返事だ。茸の栽培のことだろうか。
車は山間の道を滑るように走っていく。決していい舗装ではないのに不思議である。
川に沿った道を走っている時である、運転手が山側のちょっと広がったところに車を止めた。
「急にすみません、電話なもので」、そういってフロントの受話器を取った。受話器の前の明かりが点滅している。昔懐かしい黒電話の形をしている。
「はい、はい、そういたします」
受話器を置くと運転手が聞いてきた。
「ご主人からでございます、お昼をどこかでしてから、八女古墳群と、八津姫神社にご案内するようにとのことですがいかがいたしましょう」
「お願いします、歴史はからっきしなんですが、昨日仲居さんが邪馬台国のあった場所だと聞いています」
運転手は再び車を道に戻した。
「その大昔、八女には八女大国がございまして、それが邪馬台国だったそうでございます。卑弥呼様は八女大国の日御子様のことという話です」
「それで八女古墳群に卑弥呼が葬られているっていうわけですか」
「いえ、とんでもございません、卑弥呼様はもっと前でぼざいます八女大国の人民を日御子さまが、日本の中に散らばるようにと指図され、その者たちが日本の民のもととなって今の日本があるのです、八女の古墳群は300近くもあります、中でも大きいのが岩戸山古墳ですが、北九州を支配した筑紫君磐井(つくしのきみいわい)の墓といわれています。その豪族たちは、日御子様が八女大国のあと北九州をまかせた者たちでございます」
「いつ頃の話ですか」
「八女古墳群は5ー6世紀だそうです、八女大国は2ー3世紀ごろです」
歴史のある場所である。
「お昼は八女の町で郷土料理でもいかがでしょう」
「いいですね」
車は久留米を通り、八女の町の中に入った。町中の駐車場に車を入れて、我々は町を歩いた。日田と同じように落ち着いた古い建物がたくさん残っていた。昔からという店に案内され、筑紫煮などの八女定食を食べ、さらに町の中を案内してもらった。ただ不思議なことに運転手は赤い茸の入った箱は肌身離さず持っていた。
車に戻り八女古墳群に行くという。岩戸山古墳を車から見るだけでいいと伝えた。八女津神社の方がおもしろそうだと思ったこともあるが、八男男爵という人に早く会ってみたいという思いが強かった。
八女津神社はかなり山に入ったところにあった。あたりにはきれいな森や湖がたくさんある。運転手の話では、森林セラピー基地として国から認定されているところだという。
車から降りて周りを見渡すと岩山や森に囲まれていてすがすがしい。神社は古いもので、いわれを聞かなくても何かふつうの場と違うものを感じる。よく言うパワースポットというものだろう。
「八女津姫神が祀られています、このあたりを治めていた女神です」
「卑弥呼、いや八女の日御子とは関係あるのですか」
「八男男爵さまはないとお思いです」
一通り見た後八男男爵のところに向かった。
町を抜け山道に入った。
「ここは御前岳の麓に向かう道です、手前に男岳があり、その中腹に館がございます」
八女津姫神社から二十分も走っただろうか、すれ違えないほど細い森の中の一本道に入り、ちょっと行くと大きな茅葺き屋根の家が見えてきた。車はその隣のやはり茅葺き屋根のかかった建物に入って止まった。洋館を想像していたのでちょっと拍子抜けだった。しかし建物はがっしりしていて大きい。
「これは、昔の馬小屋だったところです」
車を止め、ドアを開けてくれた運転手が言った。真っ赤なスポーツカーと、サイドカーのついた白い大きなオートバイも格納されている。かなり広い。昔は大きな馬小屋だったのだろう。
馬小屋から出ると、母屋から白髪の髭を伸ばした背の高い老人が出てきた。作務衣を着ている。運転手が赤い茸が入った箱を渡した。老人は箱の蓋を開け、茸を見て微笑んだ」
「元気じゃな」
私の方を向いた。目が澄んでいる。深い湖のようだ。
「いや遠くまで茸を運んでくださってありがとうございました。私が八男男爵です」
老人がよく通る声で挨拶をした。私もお辞儀をした。
八男家は皇族に繋がる家柄だったのだろう。今日本に爵位というものはない。
「どうぞお入りください」
昔ながらの引き戸を開けると、広い土間が続いていた。土間の上は障子が続いている。一ヶ所、開いている部屋があった。八男氏はその部屋の前の石にサンダルを脱ぐと上がり、部屋に入った。私も続いた。黒光りのする木の床である。
八男氏は囲炉裏の前であぐらをかき、茸の入った箱を脇に置いた。私にも「どうぞ」と自分の前の席を指差した。
「どうでしょう、まだちょっと早いかもしれませんが、飲みながら話をしませんか、この茸のこともお話ししましょう、この家の裏に一軒お客様用の離れがあります、掛け流しの湯殿もあります。そこにお泊まりください。どうぞ居たいだけいてください」
新幹線で茸を拾ったばっかりに、こんなもてなしを受けている。おとぎ話のようだ。普通だったら狸に化かされているのではないかと疑うところだ。八男男爵はそのようなことを全く感じさせない。いや、もうたぶらかされているのだろうか。
「八女は初めてのようですな」
「ええ、褒美の休暇がもらえたのと、茸のマイクロチップに九州の絵があったことから、温泉の梯子でもと思って別府と湯布院だけ頭に描いて出てきました」
「今時珍しいですな、みなさんは宿をきちんと取って、予定通りの旅をするが、なにが起こるかわらないところが旅のおもしろさがありますからな」
「私もそう思います、現にここに居るのが不思議です」
「たしかにそうでしょう、おいおいここのことを知っていただきます、それにしても、褒美の休暇とはしゃれた会社ですな」
「ええ、ちょっと変わった仕組みのある会社です」
褒美の有給休暇について説明した。
「進んでいますな、人間を知っている会社で、そういうやり方は皆さん働く意欲を掻き立てられるでしょうな」
「そうですね、それで仕事が終わって名古屋からのぞみに乗ったところ、床に茸が落ちていたのです、全く萎びないし、まさかマイクロチップが入っているとは思いませんでした。研究途中のものを落されたんでしょうか」
獣医さんでの偶然知ったマイクロチップリーダーの話をした。
「そりゃ、我々にはありがたい偶然です、だがあの茸にはマイクロチップも入っていないし、研究用ではないのですよ」
「だけど、マイクロチップリーダーが反応しましたが」
「そうですな、マイクロチップリーダーばかりではなく、スマホの読みとり装置でもかざせば反応します」
そこに若いジーパンをはいた女性が入ってきた。
「おお、このお客様が八女茸を連れてきてくれたのだよ」
女性は「ありがとうございました」と私に向かっておじぎをして、「八女茸を飼育施設につれていきます」と置いてあった箱を拾い上げた。
「ああ、たのむよ」
「先生、お客様、お酒はなにを好まれますか」女性がきいた。
「何でも飲みますがビールをいただけますか」
「わしにもたのむよ、つまみは見繕って頼む」そう言われた女性は箱を持って奥に入っていった。
「あの茸はなににするものですか」
「飼っているのです」
「茸を飼うというのはどういうことでしょう、培養だとか栽培ではないのですね」
「不思議に思われるでしょうね、明日、お見せします」
そこに少し年のいったもんぺ姿の女性がビールと料理を運んできた。
「イノシシの干し肉をもどして味付けしたものです、山の芋と天然椎茸のつまみです、すべてうちで作るものです、ビールを」
と八男氏はジョッキを持ち上げたので、私も同じようにした。
「お尋ねしてもよろしいでしょうか、先生は何を教えていらっしゃるのですか」
「はは、茸の先生ということです、それも明日お見せします」
なんだろう。言葉では説明できないようなものなのだろうか。
「それに言いにくいのですけど、現代では男爵など爵位がなくなっていますが、八女はそういう習慣が残っているのでしょうか」
彼は顔十皺を寄せて笑うと「いや、すみません」と頭を下げた。
あっけにとられ、不思議そうな顔をしていたのだろう。彼は笑いながら、
「私の名前なんですよ、悪い親ですな、こんな名前をつけて、じゃがいものようなもので」と言った。
それを聞いて私ははっと目が覚めたような気持ちになった。
「これは、早とちりですみません」
あやまると、「いやいやみなそう思います、名前が悪いのです、この名前には悩まされます」
この笑いで場がほぐれてきた。というよりなにが起きているのか疑心暗鬼だったのだがそれがほどけてきた感じだ。この八男という名字の男は何か不思議な力があるような気がした。
「八女という場所で、八男という名字は珍しいですね」
「いませんよ他には、私は独り身だし、兄弟もいないので、これで絶えますな」
「きっと深い意味があるのでしょうね、名前の由来を探るNHKの番組などもありますね」
「そうですね、これは私の家の言い伝えです。伝えですから書いた物は残っていません、卑弥呼の子供は八人の女の子、八人のお男の子だったということです。女の首長の世界では男は何人いても意味がなかった。それで名も無くほうっておかれたのです。八人兄弟の末っ子の男が成人してから名前が必要になり、八番目なので八男と名のったということです、私はその子孫なのでしょうかね」
「本当に邪馬台国はここにあったのですか」
「ありました、ただ、八女大国がなまったのでもありません、まったく別のかたちでありました。八夢の国でした。八は末広がりで言い数字と言われていますが、一つには8の字を横に寝かすと無限になります。メビウスの輪ですね。寝ているときに見る夢はどうして起きるのでしょう、人々それぞれの脳が作り出す体験をともなった経験が交錯してできあがった架空のストーリーということになっています。それも間違いじゃないでしょう。実は夢が我々宇宙の原理では解明できない、もっと上の論理の世界からの支配を受けているのです。この八女の地は日御子女王の元に発達した八女大国があった、それとは別に今私がいるこの場所に邪馬台国があったのです。こちらには八夢の国として異次元の世界の隙間があるのです。人間の見る夢はそこから発せられる人間には関知できないシグナルによって造りだされているのです。それを理解できていたのが卑弥呼です。私の祖先でしょうね。
卑弥呼は天の声じゃと言って人々を思うようにうごかしたのです、その天の声とは実際にあり、次元を超えた夢を操る生き物による声だったのです、卑弥呼にはそれが聞こえたのです。その国は八夢大国と言ったのです、それが邪馬台国の姿です」
なかなか信じられる話ではない。
「卑弥呼の八人の娘さんはどうしたのですか」
「さあ、記録はありません、ただ、卑弥呼と同じような能力を持っていたとすると、世界に散っているのではないでしょうか」
「男のお子さんにはその能力はなかったのですか」
「いや、ないとはいえません、それが私です、明日ごらんになればわかります」
なにを見せてくれるというのだろう。
それから夕食の料理が出てきた。素朴なものだったが、おそらくこれだけ良い食材をつかった料理は名の知れた料亭ですら出せないだろう。
母屋の裏にある客用の建物に案内された。黒光りした木の床の上に木製のベッドがおかれ、敷かれている布団は、見かけは地味だが、腰掛けてみるとなんとも気持ちがいい。隣の部屋には掛け流しの桧風呂があり、どの温泉場にいってどのようにお金をかけてもこのような経験は二度とできないと断言できる。
枕元には冷蔵庫もあり飲み物などあらゆる物がそろっていた。
ぐっすり眠ったのは言うまでもない。
明くる朝、さわやかな空気が体を包んでいた。
昨日、赤い茸を飼育室に運んでいった女性が戸をたたいた。食事が用意されているということだ。
母屋に行くと八男男爵は暖炉のところに座っていた。
「眠れましたか」
私はうなずいた。さっぱりした粥と味噌汁、鮎の塩焼き、山菜の惣菜が用意されていた。
「昨日お話ししたことは信じられないと思いますが、これから見ていただくこともおそらくもっと信じることが難しいかもしれません、こういう世もあるんだということ、世間に大きな声で言っても全く信じてもらえないことが、本当にあるのだということを見てください、食べたらご案内します」
食事を終えて八男男爵と女性のあとをついて、裏の山に入った。女性はなぜか霧吹きをもっている。背の高い杉の木が聳え立つその下にはいろいろな茸が生えている。
「これからちょっと登っていただきます」
山の斜面をいくと、広いところにでた。杉の木に囲まれていて、上を見ると杉の木のてっぺんが作る丸い空間に青い空が見える。
広場はもやっていた。空ははっきりと見えるが木の下のほうは蒸気のようなものが漂っている。
男爵と女性が靄の中に入っていった。私もついていった。靄の中に入っても上を見ると丸い空がはっきり見えた。
「ご覧ください」
女性が足下を指さした。
新幹線で拾ったものと同じの、赤く透き通る茸がゆっくりと動いている。羊歯の葉の下で休んでいるのもいる。茸が歩いている。
「どうして」つい声を出した。
「先生が茸を飼育したのです」
「この赤い茸は学名も和名もついていません、私どもは八女茸と呼んでいます、大昔からここに生えていた茸です、当時はただの茸でした。ただ、ちょっと私が飼育したのです。それをお話しします。
私はこの地で代々百姓をやっていた家のものでした。親戚筋の者たちは都会に出てしまい、残ったのは私と両親だけでした。やがて両親も死に一人で畑をやり、山のものを採り暮らしていました。
あるとき、この茸をこの場所で見つけました。赤く透き通るようにきれいな茸でしたので、採るのをやめて、眺めていました。だんだん可愛く思うようになりました。
ある夜のことです、この茸が私の夢に出てきたのです。夢の中で羊歯の下から私に声をかけました、食べずに可愛がっていただいてありがとう、私には名前が無い、良い名前を付けてくませんかと言ったのです。困りました。私には知識がありません、中学を出てすぐに畑仕事でした。ただ、両親はよく我家が卑弥呼の末裔で、卑弥呼と八女大国の日御子とは違うのだと言っていました。知っていたのはそれくらいでした、それで茸の名前を卑弥呼にするわけにはいかない、それは私の先祖です、それで、この八女大国ならいだろうと思い、八女大国の茸、八女茸はどうだ、と茸に言ったのです。赤い茸は喜びました。そうして茸がこう言ったのです、名前をつけてくれてかわいがってくれたからには、あなたは親であり、私は子ども、何でもあなたの言うことを聞きます。それで夢は終わりました。
次の日の夜、またもや夢を見ました。茸は出てこないで、かわりにもやもやした霧のような固まりが出てきました。煙のようなものです。その煙のような物がかわいいペットが欲しいと言いました。猫か犬ですかと聞くと、もやもやしていた煙がはっきりとしてきました。植物でした。クジャク羊歯をごぞんじでしょうか」
私は首を横に振った。
「そうですか、クジャクが羽を広げたように葉を四方にのばすきれいな羊歯です。煙のようなものはそれに似た物になって、茸を連れて歩きたい、と言ったのです。
そうなのです、先ほども言いましたように、これが邪馬台国の卑弥呼に知恵を与えた、八夢に住む種族ではないかと思いました。卑弥呼は人々を鬼道(きどう)という力で支配したといいます、それは夢を支配している生き物と会話ができる力ということではなかったかと思います、卑弥呼は八夢の国の住人に教えを請うていたのです」
「それで、卑弥呼の末裔の八男さんが夢で彼らと会え、また力がだせたということですか」
「お察しの通りです、茸が歩くことはありませんが歩かせなければなりません。そこで前の晩、夢の中で赤い茸が「何でも言うことを聞く」といったことを思い出したのです。
次の日の夜、夢に出てきた赤い茸に動くように言ったのです、すると次の朝、裏の森にいきますと、目の前で赤い茸が頭を出し揺れはじめたのです、それで、おまえさんは八夢大国の愛玩動物になりなさいといいますと、うなずいたのです、それから、私は茸の飼育人になりました」
「おとぎ話のようです」
正直信じられない話である。しかし、彼が「こっちにおいで」というと、赤い茸がぞろぞろと彼の前にやってきて整列したのです。
すると女性が霧吹きで茸たちの傘に霧を吹きかけたのです。
「山ぶどう酒です、これで茸たちの躾をします、犬に餌をやりながら芸当を教えるのと同じです」
そこに森の中に緑色の霧が立ちこめ、我々の前に八男氏の言ったクジャクシダの形をした八夢の国の生きものがいくつも現れた。羊歯は赤い茸を一つ従えて森の中を歩いていく。
「実は、彼女もどうやら卑弥呼の血を少し受け継いでいるようです、本当の意味で八女です、私がいなくなった後、茸の飼育を任せたいと思っています」
男爵が女性についてそう言った。
「八女巫女(みめ)といいます、よろしくお願いします」
彼女は初めて自分を名乗った。目の澄みかたが男爵と似ている。深い目をしている。
「なぜ、新幹線に落ちていたのでしょう」
「茸を連れて遊びに言った羊歯たちは八夢大国の子供です、外に連れ出したいというので許可をしました。羊歯たちは日本中を旅します。そのときも赤い茸を連れて博多から新幹線にのりました」
「羊歯が新幹線にのっていたらおかしいでしょう」
「彼らはクジャク羊歯に似ているので、駅の近くの花屋の店先で鉢に入ってすましています、必ず誰かが買って電車に乗ります。そうやって知らない土地まで旅するのです。そのとき買ったのはおじさんでした、羊歯など野草の好きな人で、それをもって東京行きののぞみに乗り、新山口の自宅に帰りました。そのときクジャク羊歯の形をしていた八夢大国の子供は、疲れて居眠りをして、赤い茸を落としてしまったのです。それで茸は東京まで行ってしまいました」
「旅をしてどこかにいったクジャク羊歯のような生き物の子供はそのあとどうなったのです」
「親が本物のクジャクシダをもって迎えに行くのです」
「赤い茸にマイクロチップは入っていないとおっしゃっていましたが、それはどういうことですか」
「赤い茸の遺伝子にすんでいるところや、名前が刷り込まれていて、それが発信しているのです」
「どうやって」
「わかりません、八夢体国の生物が自分の気に入った茸に組み込みます、異次元の生き物のやっていることです」
林の中ではクジャク羊歯が赤い茸を従えて歩いたり、なにやら話しているような様子が見られた。
「お母様が見えます」
八女巫女が言った。また森の中に緑色の霧がかかった。霧が凝縮すると大きなクジャクシダがいくつも現れた。
「帰る時間よ」
大きな羊歯が言ったように聞こえた。大きな羊歯は赤い茸と遊んでいる小さな羊歯たちの母親のようである。
「ありがとう」
大きな羊歯がよってきて男爵と巫女に言った。
「いつでも遊びに来てください」
大きな羊歯はまたありがとうといった。それで私を見たような気がした。緑色の霧がかかった。それが晴れたときにはクジャク羊歯の生き物は消えていた。赤い茸がふつうの羊歯の下で淡い光に当たって輝いているだけであった。
八男氏が私を見た。
「八雲さん、クジャク羊歯の生き物が言ったことがわかったようですね」
私はうなずいた。私は八雲海(やくもかい)という。
「あなたも、卑弥呼の末裔じゃないでしょうか」
男爵氏が言った。
私のルーツは北海道の八雲町にある。八女のように温泉がある。江戸時代にできた和人の集落で、アイヌとの境界場所である。私の祖先は移り住んだ一人で、医者だったと聞いている。
「どうです、いつかここで茸の飼育をしませんか」
私はうなずきも否定もしなかった。ただ、これからも長いつきあいになるのではないかという気がした。
「この茸の飼育場にはきっと卑弥呼の末裔が自然に集まってくるのではないかと思いますよ、遺伝子にここにくるようなシグナルが仕組まれているのです。ここは新たな邪馬台国になるのです、夢を司る生き物との交流の場になるのですよ」
それには自然とうなずいていた。
「ところで八男さんは赤い茸を飼育する代わりに、あの生物達からなにかもらっているのですか」
「はい、報酬があります、私は働かなくても食べていけます。私の周りに生えている植物はすべて私にとって美味しい栄養源です。動物も食べますが、食べなくても生きていけます。それは八夢大国の生きものが周りの植物を美味しく食べられる物にかえてくれているのです、遺伝子を操作しているのでしょう、もしその原理が分かると、地球から飢餓がなくなるでしょう、卑弥呼の子孫にいつか生命現象の研究者が出てくると信じています」
その日も八男氏の家に泊まった。明日帰るつもりである。
その夜、夢の中に初めて赤い茸が現れた。
「こんちわ、私も連れてって」
赤い茸が飛び跳ねながら言った。私は夢の中で頷いていた。
八女茸


