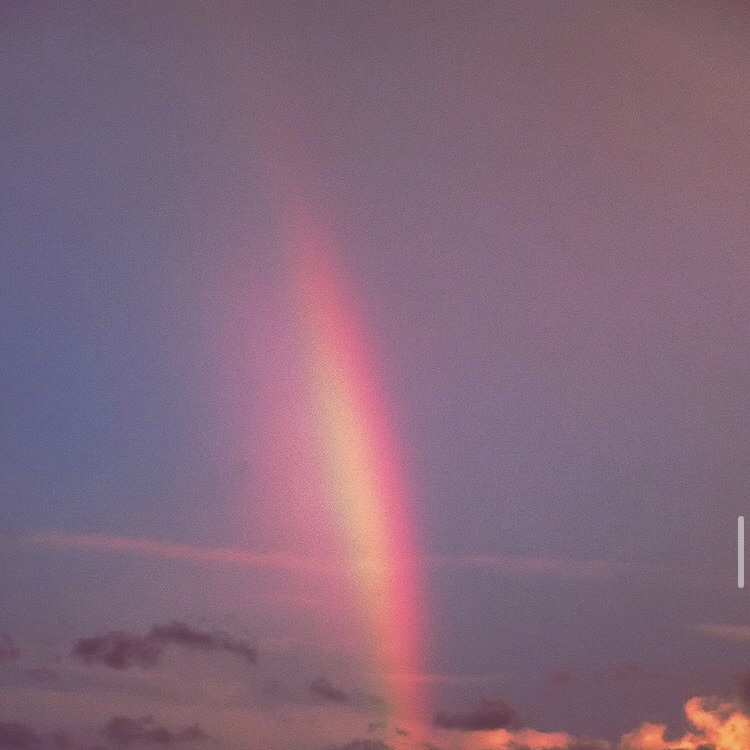
幻と右ほほ
夢を見ているときは
ほかのことを考えないでね
それは、清潔な関係でした。

彼が失踪して、わたしの頭に家があらわれたのはほぼ同じころだった。
黒ぶちメガネの、せいの高い、へら と右ほほだけでかたよった笑いをする口もとには マリリン・モンローみたいなほくろがあった。それが、自然とわたしを安心させた。
ある金曜日。目をさまして なんとなしに新聞をとりにいき、今日の事件に目をおとしたあと 冷めたミルクに口をつけてふとベッドを見ると、もう彼の姿はなかった。
わたしはまず今日おきた事件名をもういちど丹念に読み返した。けれど彼の名はどこにもなく、あぁ というきもちになった。
「……」
トンカントン と彼が家の修理をしている。
いつしかあたりまえなようにわたしの頭のなかに住みついた彼は、ごく自然に持参したバスケットのなかから粗めのライ麦パンを取りだし、修理の工具をふとももに置いてから、大きな口をあけてほおばった。
彼はいつだってそんな風で、失踪してしまう前も、笑いはするけれど無口で、とくにわたしになにかを尋ねることもなく、あたらしいことをはじめてしまった。
「それ、おいしい? わたしは ライ麦ってあんまり好きじゃないけど」
それが憎かったわけではなく、むしろ 置いていかれたというきもちに近かった。
今みたいに、話しかけても返事がかえってくるのは ときどき、わたしの存在を思い出したときくらいで。
でも、決して仲が悪いわけじゃなかった。寝る前はかならず あのかたよったほほえみをこぼして、わたしの頭をゆっくり撫でてくれた。
彼がのこした手紙のようなメモを見つけたのと、彼(頭のなかに住む)がことばを発したのもほぼ同じだった。
ある日、仕事帰りにショートケーキを買ってとくに考えるわけでもなくフォークをまっすぐに差しこむと、カシャリと妙な音がした。
けれどわたしは すぐにそれが彼からの手紙であるとわかった。
いちごのソースと生クリームにはさまれたそれは、丁寧に鶴のかたちに折られていた。
ひらくと、瞬間、声がした。
正確には、頭のなかで誰かが話しかけていた。まぎれもなく、それは彼の声だった。
「え……」
手紙よりも、その声が一層、心からわたしを驚かせた。
彼はバラックのような屋根の上でおごそかに手をふとももの前で組んでいた。
しずかに目を瞑って、しとしとと降る雪だけがやけになまめかしかった。
「僕は人を殺してしまった」
一言。単純にたんたんと、語ったあとは永遠の無だった。
目をかたく瞑ったまま もう彼はなにも話さなかった。雪が黒色の頭にさらさらと 砂糖菓子のようにつもっていった。
わたしはしばし呆然とし、視線のやり場をもとめて にぎった手紙に目をおとした。
“その家から でてください”
すぐさま手紙を握りしめ、まだビニールに包まれている今日の朝刊をつかんだ。
信じられないくらいのはやさで今日の事件を指と目で追った。そこにはちゃんと、彼の名前が印刷してあった。
“絞首殺人 目撃者(女性)が証言”
とともに 整然とのっていた。その目撃者の、女性という文字だけが太字でくっきりと、浮き出ているみたいだった。
頭のなかの彼のことばが、がらがらと流れてゆく。でも、そんなわけはないという根拠のない確信で わたしはしずかに自分の首に両の手をあてていた。
だって あの人の手が、だれかの、くびを 締めたなんて。こうやって……
人さし指、中指、薬ゆびが ひた ひた と首の肉にくいこんでゆく。
少しも苦しい気はしなかった。ぜんぶの指が首をおおっても、まだ彼がしたことの理解ができなかった。
すこし開いたカーテンから、くもった半月がのぞいて、とおくの方からオオツノジカの遠吠えがきこえた。
何度読み返してもその文章は変わることがなく、あまりに指で追いすぎて、その行だけインクがにじんできていた。
きっと、まちがいにちがいない。だって、あんなふうにやさしい微笑みをくれる彼が、単調に日々を生きる彼が、誰かの、わたし以外の首を締めるなんてこと 絶対にありえないから。
「あなたは、わたしに、なにもいってくれなかったわ」
いつもみたいに なにも いわなかったじゃない。いわなかったから、わたしが無理に聞こうとしなかったから、どこかへ行ってしまったの?
バラックの屋根の上で、彼はすうすうと寝息をたてていた。
それから数ヶ月が経ち、あたりまえに彼は頭のなかの家で暮らしつづけている。
とくになにかをするのでもなく、あのケーキから手紙を見つけた日々が嘘だったように、一言も喋らず、たんたんと、ただ生きている。
わたしもあれからとくに変わったこともなく、朝起きたらまず新聞をとり、今日の事件に目を通し、冷えたミルクに口をつけ、彼がベッドにいないことを確認して仕事にいく。
「じゃ、いってくるね」
ほんとうの彼の、死刑宣告はもう出たらしい。結局、人を殺めた理由も、知ることができないまま。
左手で靴べらを立てかけ、つめたいノブを右手で回すといつもより金属みが増した音がした。
途端に入ってくる氷のくうきを とじたまぶたで受け、さて行くかとブーツをならせば
彼と目が合った。
あいかわらず、黒縁メガネで、せいが高くて、マリリン・モンローみたいなほくろがあった。なんで、と声がでた。
出るより先に、思いきり助走をつけるまもなく彼の胸にとびこんでいた。
なつかしい匂いがした。なにもかもが変わらなすぎて、視点がはげしく揺れた。まばたきをすれば、鼻の奥が熱くなった。息を吸うまもなく、わたしは泣いた。
「すまない。」
あたたかい 大きなぬくもりが、頭をゆっくりと撫でた。ひたすら、わたしは褒美をうける子犬のように、上質なブラッシングをうける老猫のように、目を細めた。
あの時、家を出てくれと頼んだだろうと、頭のすぐ横でささやく。
いいの。わたしは、ここで待っていたかったから。
視線が絡む。
ゆっくりとまぶたをあげればもう、頭のなかの家は、すでに消え去っていた。
幻と右ほほ


