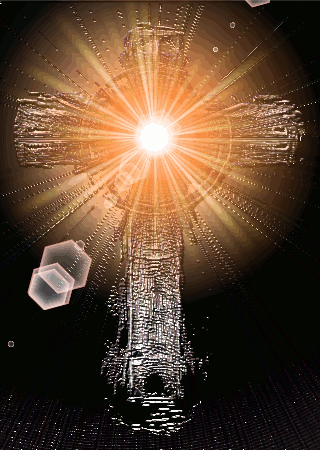
必要悪 ― Schwarz ― Vampir des Einsatz
極彩トワイライトオペラ 第1楽章 漆黒の吸血鬼1
1 静かな湖畔の森の陰から
【Schwarz】黒
黒い漆を塗ったような黒を漆黒と言う。黒の中でも艶のある黒。暗闇の表現の一つとして、全く光のない真の暗闇を漆黒の闇と言う事がある。また、美しい黒髪の表現にも使われる。
黒があらわすものは数多い。吸収・疑惑・悪・汚染・罪科・死・有と無・独立と支配。人を惹きつける黒と言う色には、並ならぬ引力が存在している。
森を抜けた霧の深い湖畔のほとり、艶のない黒で塗装された木製の平屋建ての家屋に住むのは、ある親子。時間は既に深夜だが家には明かりが灯って、親子の賑やかな会話が聞こえてくる。その家からほど近い場所にある桟橋では、波に揺られたボートが桟橋の柱をノックして、森では梟が囀る。真夜中で月もない、霧に覆われたこの場所でも、この家の周りだけは無駄に賑やかだ。
「だから、どこ行きたいんですか?」
ヒラヒラしたミニのワンピースをはためかせ、長い黒髪の少女が漆黒の瞳で見上げ、世界地図片手に迫る。同じく黒髪の父はやれやれと言った風にそれを受け取って、世界全図のページを開いて悩む。
この土地が快適すぎて長居し過ぎた――――約30年。いい加減余所に移ろうとようやく父が言い出したので、ここは思い切って国外に、と思い立った次第である。
「私もうアメリカ飽きました。ヨーロッパ行きましょうよ! お父様元々欧州人でしょ?」
エンターテインメントが発達すればそれでいいと思っている、下品なだけの国に用はない。この国の文化も国民性も、彼女の肌には合わない様だ。聊か父親は呆れ顔をして、隣に腰かけた娘を覗き込む。
「どの口が……お前、生まれも育ちもアメリカじゃないか」
そうなのだが、だからこその不満だ。
「そーなんですけど、いい加減飽きますよそりゃ! 200年ですよ、200年! もう見るとこありませんよ、この国まともに文化遺産も残しちゃいないんだから!」
映画は認める。広大な土地を背景にした自然遺産も認める。しかしやっぱり彼女の肌には合わないらしく、「バロックナイトしたい」としきりに駄々をこねる。アメリカやアメリカ人の何が嫌いと問われれば、それはそもそもの国民性だ。何せアメリカ人のほとんどが、キリスト教の規範的モラルを基礎としているので、驚くほどカトリック原理主義者が多い(だから差別が減らない)。「中絶する奴は人殺し」とか、「同性愛者は地獄に落ちろ」とか、「ユダヤ人死ね」とか、「異教徒は野垂れ死ね」などの過激な発言をする有名人がいたりするが、そういう人たちは「良きキリスト教徒」。レーガン大統領以降台頭している民主党も保守的なキリスト教徒で右派も多い為、数年前までアメリカ軍では同性愛者が除隊されていたくらいで、その際愛国心なんてものは考慮の範疇外だ。カトリックに政治と思想を牛耳られているアメリカは、ここ数十年非常に居心地が悪い。
溜息を吐いた父親が地図を開いて返した。
「じゃぁロッテはどこへ行きたいんだ?」
尋ねられて地図を受け取った少女――――シャルロッテは欧州を覗き込んで、しばらく逡巡すると再び顔を上げ父親に地図を見せる。
「お父様はどこがおススメですか?」
「……ヴァチカン?」
「冗談じゃありません!」
ただの冗談で一々癇癪を起されるので、父親は耳を塞ぐのが既に習慣化している。
全く、うるさい小娘だ。誰だ、こんな躾をした奴は。
こんな躾をしたのは父親のサイラス本人である。母親はシャルロッテ誕生とともに死亡した。だから男手ひとつで育ててきたわけなのだが、いかんせん身内が自分だけとなると、母親に生き写しのシャルロッテをついつい溺愛して甘やかしてしまい、この様だ。
機嫌を損ねたシャルロッテがサイラスのおススメに悉くけちをつけるので、とうとう喧嘩になり始めた。
「あのぉ……」
そんな二人の様子を窺いながら、金髪の少女がやって来た。この少女は見た目は10歳くらいでほんの子供だが、彼女もまた吸血鬼だ。ストリートチルドレンをやっていた子供の頃、厳冬と病気で今にも絶命しそうになっていた刹那、シャルロッテに助けられた。苦肉の策で吸血鬼化されたため、彼女は60歳を超えた今でも子供の姿から変わらない。最初の30年は大人になれないことを嘆いたものだが、流石に諦めがついたし、子供の姿で大人の頭を持っていると、子供の容姿が案外役立つことに気付いた今日この頃である。
そんな子供もどきが親子に差し出したのは一本のダーツ。それを見て色めきたったシャルロッテは、ダーツを受け取り地図を掲げてみせる。
「ハイお父様! 狙わないでくださいよ! 適当に投げてくださいよ!」
狙ったら彼の事だ、百発百中してしまう。それでは面白くない。
ダーツをしげしげと見つめていたサイラスだったが、ふと笑って少女を見る。
「クララ、お前まだこれを持っていたのか」
そのダーツはクララがまだ子供だった頃、サイラスが買ってくれたものだった。子供の頃に助けられて、それ以来引き取って面倒を見てくれた。世話をして遊んでくれて、勉強も教えてもらった。親子と出会ってからのクララは幸せだった。誕生日を覚えていないクララに出会った日が誕生日だと、毎年プレゼントをもらえることが涙が出る程嬉しい。
笑顔で頷いたクララの横で、地図を持ったシャルロッテが急かす。苦笑しながらサイラスが一息にダーツを放った。
「ッキャー!」
「お嬢様!」
本当に適当に放ったものだから、ダーツが地図を突き抜けてシャルロッテの顎に刺さった。それを引き抜いたシャルロッテは怒り心頭になったが、抜いた瞬間に傷は塞がっている。
「お父様ワザとでしょ!」
「はははは」
「笑ってるし!」
サイラスは時々茶目っ気を発揮して、悪戯を仕掛けて悦に入るという悪癖がある。憤慨するシャルロッテとサイラスの間に、オロオロしたクララが割って入った。
「お嬢様落ち着いて……ダーツはどこに刺さりました?」
言われて不貞腐れながらもシャルロッテが地図を覗き込むと、欧州地図の真ん中より少し下、言ってみれば足首に穴が開いている。それを見てシャルロッテは、一思いに地図を引き裂いた。
「お父様、マジですか」
適当に放った結果だ。
「いいじゃないか。実は私もイタリアには行った事がないのだ」
なにせ聖地だ。
「ではイタリア語のお勉強をしなきゃいけませんね! 明日テキストを買ってきます! お嬢様もご一緒しますか?」
尋ねるとシャルロッテは素直に頷いた。
「では次の目的地はイタリアと言う事でいいな?」
その問いには渋々頷いた。
「ま、いいですよ。でもローマはダメですよ」
なにせ聖地だ。ローマ・カトリック教会の総本山だ。
「心配するな。イタリアには“極彩トワイライト”の支部がある」
吸血鬼をはじめとする人型の化け物による秘密結社“極彩トワイライト”と言う物が存在する。彼らはどの種族も長命だったり老けなかったりするので、定期的な引っ越しが絶対的に必要になってくる為に、仲間内で住居を渡り歩くという事をはるか昔からやっている。イタリアは芸術と美食、そして愛の国として名高い為か、住んでいる吸血鬼が2組いて、それぞれ南と北にある。農業を主体とした牧歌的な南か、芸術に愛された北か悩んで、北に行くことに決まった。
話し合いで行先が決まると、早速サイラスは手紙を記して窓を開けた。窓辺に置いていたナイフで指先を斬りつけると、そこから流れ出た雫が2滴、姿を変えて窓の外で滞空する。血で作った2羽の蝙蝠コウモリはサイラスから手紙を受け取ると、真っ暗な空へ飛び立って行った。
お引っ越しの際はコンパクトかつスピーディーに、がモットーだ。
それぞれ荷物は一つずつ、家は家財ごと焼却した。彼らが引きずるのはそれぞれの棺(引っ越し仕様キャスター装備)。簡単な思い出の品などを詰め込んで、3人で港に立つ。
見上げるのは巨大な輸送船だ。アメリカに来た際も航海したらしいサイラスの提案で、今度の渡航は密航となる。昔は切符さえ買えば渡航は簡単だったのだが、今は出入国の際は審査が必要で、パスポートなど持ち合わせていない吸血鬼は不法出国をするしかない。
材木を輸送する船は巨大で、クレーンを搭載した輸送船は港から甲板まで20mはありそうだし、その全長は200m近い。どこかしら潜り込める場所はありそうだ。
波止場からジャンプして甲板の柵に捕まり隠れ、様子を窺う。見える範囲に人影はない。
行先は既にチェック済みで、スペインに上陸する。その後はアルプス越えをしてイタリアに入国する予定だ。慎重に歩を進めて、何とか船倉に潜り込むことが出来た。ここからの航海は最新の高速貨物船であるが2週間近くにも及ぶ。この間にイタリアおよび周辺国の国語を覚えておく。吸血鬼は、特にサイラスの一族は人間と比較して身体能力が特化し、その為に記憶力も随分良い。覚えるだけなら2,3日もあれば十分。後は反復していればその内習得できる。
ただでさえ夜ではあるが、昼になっても光の届かない海の中の船倉は、意外にも快適な船旅を約束してくれた。朝が近づいてくると、棺の陰に隠れて座っていたクララが、うとうとと頭が重そうにし始めた。吸血鬼の真祖であるサイラスと、直系で純血種のシャルロッテは日中も太陽光も平気だが、変異種のクララはさほど強いわけでもなく、太陽の力には抗えない。朝になるとどうしても強烈な昏睡に襲われてしまう。
遠慮するクララを無理やり棺に押し込み寝かしつけ、棺は巨大なコンテナの上に配置したので下からは見えないが、念のため午前と午後に分けてサイラスと交代で見張りをすることにした。一度積み荷を積んだ以上は、船倉に常に人がいるわけではない。そこまで乗組員も暇ではないが、積み荷のチェックの為に時折人はやってくる。午前はシャルロッテが見張りをすることにし、サイラスは就寝。
そうして2週間ほどの船旅を経験した後、船のスピードが緩やかに落ちていくのを振動で感じる。
「あっ、そろそろでしょうか」
クララが言って、瞳を輝かせる。それはシャルロッテも同様だった。初めての欧州、新しい土地、久しぶりに遭遇する異種族の同類にに期待が膨らむ。
どんなところだろう、どんな人たちだろう、これからどんな生活が待っているのだろう。
そう言った期待は、予想外の形で十二分に満たされることになる。
2 主題と変奏
「はぁ、もう……」
ひたすら溜息を零すクララ。
「この部屋カビくさーい。お尻汚れちゃうわ」
不貞腐れるシャルロッテ。
「なんで俺まで……」
処遇に打ちひしがれる人間男性。
サイラスは別の所に連れて行かれた。この3人は現在、新天地の地下牢に絶賛幽閉中である。少し離れて座り込み項垂れていた男性が顔を上げると、悔しげに顔を歪めてシャルロッテを睨んだ。
「テメーのせいだぞこの吸血女! こっから出たら覚えとけよ! 絶対ブッ殺してやる!」
鼻で笑った。
「ハン、エクソシストだか何だか知らないけど、人間風情が何言ってんの? 噛み殺すわよ」
「お嬢様に向かってなんて口のきき方を! あなたそれでも聖職者ですか!」
「うるせぇ! ガキは黙ってろ! 売春宿に売り飛ばすぞ!」
とても聖職者とは思えない暴言である。クララは怒りを通り越して呆れたらしく、深く溜息を吐いてシャルロッテを見上げた。
「あり得ないんですけどこのクソガキ」
「本当よねー。ヴァチカンってどんな教育するのかしら。これが聖職者でしかも司教なんてあり得ないわ」
「ですよねー。世界最大の宗教の教義も、たかが知れてるって言うのがよくわかりました」
「テメーら好き勝手言ってんじゃねーぞコラ! 本来ならお前らとっくに蜂の巣にしてんだよバケモンが!」
ついには失笑した。
「聞いた? 自称エリート君てば強がり言っちゃって」
「自分だって捕まってるくせに何言ってるんでしょうね」
二人で嘲笑すると、怒ったらしいエリート君が殴り掛かってきたが、それを容易く受け流して壁際に押し飛ばすと、「うっ」と呻きを上げて煉瓦の壁に衝突した。その様子を見て
「弱っ」
「エリート君、口ほどにもないですね」
と、再び嘲笑すると、エリート君は更に悔しそうに歯噛みしていた。
結局また3人でわあわあと口論をすることになった地下牢は、深夜だというのに非常に賑やかである。そもそもなぜこんなことになったのか――――
――――イタリア共和国。イタリア半島およびその付け根に当たる部分と、地中海に浮かぶサルデーニャ島、シチリア島からなる。首都はローマ。キリスト教の聖地であるローマには毎年数十万人もの人が足を運ぶ。
ローマ市内には世界最小の主権国家ヴァチカン市国があり、教皇が治めるキリスト教の総本山である。スペインに上陸後フランスを経由しイタリアに入国、シャルロッテ達はフィレンツェへ向かった。
「それにしてもフィレンツェは綺麗な町ねー」
感嘆の声を漏らしながら眺める、花の女神フローラの名を冠した町フィレンツェ。神聖ローマ帝国の支配下に置かれてから何度も君主が変わり、数々の戦争を体験した町。それでいて文化や芸術の発達は秀逸で、大聖堂や美術館が数多く存在し、かの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチや、ラファエロ、ミケランジェロを輩出し、ルネサンス芸術に大輪の花を咲かせた文化の都は、アメリカの街並みと大違いだ。
極彩トワイライト北イタリア支部、それはフィレンツェ郊外の森の中にあった。町から外れて不便だが、吸血鬼達にはちょうどいい距離感と言えなくもない。門のアーチをくぐると、整備されていない荒れた庭園が見える。庭園の端には池もあったりして中々の景観で、整備したらかなり素敵なお庭になりそうだった。広い庭園を抜けてお城の前に到着して見上げる。
「でっ……か」
古い石灰質の石造りの城は近くまで行くと、とても大きかった。広大な庭園に石灰質の真っ白な古城はとても綺麗で、手入れをされていないせいか、白い壁にアイビーが伝っている。今現在住んでいるのは夫婦者の2人だけで、人間だった頃も放浪癖があったらしく、家を手入れする習慣がないらしい。
「あの夫婦は元々盗賊だったからな」
「ボニー&クライドみたいですね」
「似たようなものだ。だが気のいい奴らだぞ」
コロコロとスーツケースの様に棺を引きずり、3人で城の玄関の前に立つ。呼ぶ子を引くと現れたのが、今現在地下牢仲間となっているエリート君、その人だった。
スーツを着て慇懃に礼を取った彼が、明らかな営業スマイルでお出迎えをした。
「ようこそ。サイラス・ジェズアルド・ザイン=ヴィトゲンシュタイン=ルートヴィヒスブルク・バッハ様。主人が大変楽しみにお待ちしておりました」
彼に会うのはサイラスも初めてだったようで、「君は?」と尋ねた。
「私はアドルフ・リストと申します。少し前からこちらでお世話になっております」
その返答と物腰の柔らかい挨拶に安堵したサイラスは、自己紹介に笑顔で返した。
「そうか。ジョヴァンニは元気か?」
「ええ」
そうしてまんまと騙され城に入り、居間に通されるとアドルフの様な男性が数名いた。見ると全員ピシッとスーツを着こなしている。その立ち居振る舞いは一流ホテルマンと遜色なかったが、サイラスならともかく、とても生前強盗だった夫妻が傍に置くようには思えなかった。
ソファに座らされて、アドルフは「主人」を呼びに行った。少しすると階段を下りてきたのは、黒いガウンを身にまとった男性が一人、何やら書類を読みながら降りて来るので、顔は見えない。その男性が書類を読み上げだした。
「娘と侍女を一人連れて来るのでよろしく。サイラス・ジェズアルド・ザイン=ヴィトゲンシュタイン=ルートヴィヒスブルク・バッハ……なぜ?」
ようやく男性は、サイラスが蝙蝠に運ばせたらしい手紙を顔の前から退けた。黒髪に緑色の目をして、とても優美な顔立ちをしていた。その男性の顔を見て、サイラスが顔色を変え立ち上がった。
「お前!」
「なぜあなたが、この名を使っている? あなたにはその資格はないはずだけど?」
サイラスの昔からの知り合いなのはわかったが、会いたかった人物でない事もわかった。サイラスの知り合いなら人間などであるはずがない、だが恐らく敵なのだろうと察知し、剣を引き出そうとした瞬間、アドルフが号令をかけた。
「クリス!」
号令がかかった瞬間、一人の男性がシャルロッテ達の座るソファの周囲にナイフを投げた。それは真円を描いて突き刺さり、その瞬間にシャルロッテ達の周りに鳥籠が出現した。
「これは……」
「結界!?」
シャルロッテ達も立ち上がりクララが鳥籠に手を伸ばすと、触れた部分から青い炎が上がって接触を拒絶する。驚いて声を上げたクララを抱きとめて、その様子を眺めてクスクスと笑う黒髪の男性に視線をやった。
「お前、その眼は」
サイラスの言う、彼の緑色の目。
「ノスフェラートに吸血鬼化されたか」
「そうだよ、兄様」
「えっ兄様?」
驚いてサイラスを見上げると、小さく嘆息した。
「弟だ、人間だった頃の」
「えーうそ! お父様弟なんていたんですか!」
再び驚いて、弟だという男性に向き直った。
「叔父様はじめまして! お父様の娘の、シャルロッテ・プリンツェシン・ツー・ザイン=ヴィトゲンシュタイン=ルートヴィヒスブルク・バッハと申します! 以後よしなに」
自己紹介をして、きちんと礼を取って挨拶をする。勿論100%スマイルでだ。コミュニケーションは心地よい挨拶からが基本だと、サイラスに言われたとおりに感じ良く。
「えっ? あ、うん」
突然の自己紹介に戸惑う叔父。そんな様子は無視する。
「叔父様、お名前は?」
「え? あ、アマデウス・ジェズアルド・ザイン=ヴィトゲンシュタイン=ルートヴィヒスブルク・バッハ、だけど」
「アマデウス叔父様ですね! この子はクララ・ヴィークリンゲンです。私の事はロッテ、この子はクララって呼んでください」
「え? う、うん」
やはりアマデウスは戸惑いながら、隣に立っていたアドルフに振り返る。
「なんか、姪っ子が天然みたいなんだけど、どうしよう」
「折角の殺伐とした雰囲気が台無しですね」
「なんかやりづらいな……どんな教育したんだ兄様」
この二人にも呆れたような視線を投げかけられたが、どう言う訳かサイラスも同じような目をしてシャルロッテを見下ろしている。当然クララもだ。
「えっなに。私なんか間違えましたか?」
自己紹介は大事だ。ただタイミングも大事だ。サイラスは諦めたらしく、このやり取りを無かったことにした。
「……ところでアマデウス。これは一体どういう事だ。どういうつもりだ?」
気を取り直してソファに再び腰かけたサイラスの態度は流石だ。だがさすがのサイラスにも、よもや引っ越し先で弟に会いまみえるとは予想だに出来なかったし、しかもこの様子では明らかに城を占拠されている。ここに住んでいたはずの夫妻の動向も非常に気になる上に、吸血鬼であるはずのアマデウス、その部下がサイラスの様に高位の魔物を封じる事が出来る技術を有した者であることも、とにかく何もかも合点がいかなかった。
サイラス様様で殺伐とした雰囲気を取り戻したことに安堵したのか、アマデウスは対面のソファに腰かけ、その背後にアドルフが控え、周囲に黒服の一団が整列する。
くすり、とアマデウスが笑った。
「別に? ただ単に、兄様が飛んで火にいる夏の虫だった、それだけだよ」
「は?」
少し愉快そうにするアマデウスの説明によると、こういうことだ。
アマデウスは現在、利害関係の一致もあって教皇庁に身を置く聖職者だ。吸血鬼の能力を以てして魔物を狩る、エクソシスト集団の指揮者。世界各国を飛び回るエクソシストの元締めであり、側近であり精鋭部隊の隊長であるアドルフを筆頭とした精鋭たちが、ハイレベルな化け物狩りに駆り出される。
イタリアは仮にも聖地なので、化け物の存在など許されるはずがない。この辺りで時折発生した怪異を聞きつけて、化け物狩りにやってきた。勿論目当てはここに住んでいた夫妻だったのだが、彼らがやって来た時すでにこの城には誰もいなかった。引っ越したのかはたまた危機を感じて逃げ出したのかは定かではないが、とにかく不発に終わってしまったことを嘆いていた、その時。
「蝙蝠が窓から手紙を投げ入れてきた。それで開けてみたら兄様が来るとか書いてるから、これはもう待機するしかないと思ってさ」
正しく飛んで火にいる夏の虫である。話を聞いたサイラスはショックを隠し切れないようだったが、怒りの矛先は人知れず脱走した夫妻に向けられる。
「あいつらぁぁぁ……!」
いつでも遊びに来いヨ、300年はいるからナッ!
そう言っていた眩しい笑顔が憎らしい。
当てが外れるどころか天敵に捕まってしまうとは羞恥の極みだ。しかも天敵のボスの座に腰を据えるのは、にっくき弟。静かに怒気を孕んだ空気を纏い始めたサイラスに、アマデウスは微笑みかける。
「ねぇ兄様ぁ、僕を恨んでる?」
まるで媚びるような笑顔をした。が、お返しとばかりにサイラスは不遜に笑った。
「ふん、相変わらず下卑た笑い方をするものだ。今でもそうやって、男に媚びて股を開いているのか?」
鬼の首を取ったかのようなサイラスに反して、アマデウスは顔をひきつらせた。
「何でそれ今ここで言うかな。最悪」
最悪なことに背後では、部下たちがひそひそと話し始める。
「マジ? 猊下マジ?」
「BL?」
「アッチも開発済み?」
「つーか猊下って実は男の方が好きなの?」
「えっうそどうしよう。俺そこまで猊下の期待に応えらんない」
「俺も」
「俺も」
ついに堪忍袋の緒が切れたらしいアマデウスが振り向いて怒鳴りつけると、途端に部下はしおらしくなって謝罪し始める。が、アドルフは一人だけニコニコと笑っているので、アマデウスは不審に思った。
「いやお前何笑ってんの」
「感心しておりました。前立腺まで開発する、猊下のあくなき探究心は尊敬に……」
「しなくていいよそんな所は! ていうか好きでやってたんじゃないよ! 時代背景!」
「ハハハ、猊下、必死ですね」
「そりゃね!」
憤慨してこちらに向き直ったアマデウスだったが、サイラス親子は声を殺して爆笑した。アドルフの加勢もあってか、予想以上に楽しめて満足だ。
「まぁまぁ叔父様、愛の形は人それぞれですから、私はイイと思いますよ」
「違うつってんじゃん!」
「だが私のケツは貸さんぞ」
「いらないよ! なんなんだ! マジ腹立つこの親子!」
黒歴史を暴露されたうえに、それをネタに笑われる――――実に気の毒ではあるが、サイラスが恨む理由はそれなりには存在する。むしろこの程度で済めば可愛いものだ――――が。
「弟に裏切られ追い落とされ国を追われ、挙句の果てに僕の手ずから処刑されたのが、そーんなに気に入らないんだぁ?」
不貞腐れたアマデウスがそう言ったが、その通りだ。しかしそれはそれでサイラスにしてみれば、暴露されることが気に入らなかった。
「そんなの兄様が無能だっただけでしょー。勝てば官軍」
これを言われたくなかった。
「よく言う物だ。あの時は自国も同盟国も裏切ってイスラム教徒に迎合したくせに、今はカトリックの枢機卿? お前は本当に節操がないな」
精一杯の反撃にアマデウスは鼻で笑った。
「なんとでも言えばぁ。今回もまた嵌められて捕まってる兄様が言っても説得力ないしぃ」
仰るとおりである。再び適度に空気がギスギスしてきたところで、シャルロッテが口を挟んだ。
「じゃぁお父様、ずっと叔父様を恨んでたんですか?」
サイラスは嘆息する。
「恨んだと言えば恨んだが、もう600年以上前の話だ。会わなければその内忘れていた」
実際忘れていた。が、再び会ってみればやはり憎らしい弟だ。600年前に味わった悔しさを再体験させられる羽目になった。サイラスの様子を見て、アマデウスの表情は愉悦に歪む。
「忘れたって嘘ばっかり。忘れられないでしょ、固執してたんでしょ? だから国王の名前を今でも名乗ってる」
「馬鹿者、そこはまた別問題だ。600年だぞ、人間の――――お前の血統も私の血統も既に断絶しているし、最早国もなくなった。よもやお前が吸血鬼化して生きているとは思わなかったからな。一々蒸し返すな」
「えっらそー。捕まってるくせに」
憎々しげに睨むサイラスに、アマデウスはそう言って笑う。深く溜息を吐いたサイラスが、冷たく睥睨して立ち上った。
「驕るなよ」
サイラスが鳥籠に手を伸ばすと、クララが触れた時のように青い炎が上がる。それにも構わずに籠の骨組みに手をかけると、炎はサイラスの腕を駆け上ったが、それは自然と鎮火した。
「わざわざ大人しく捕まってやっているのだ」
掴んだ柵が、ばきんッと根元から手折られる。2つ、3つと柵が折れる頃には、人一人通れるくらいには隙が出来た。
「たかが結界で、この私を制御できる物か。たかだかノスフェラートの血族のお前では、真祖である私の足元にも及ばんと、わからんのか」
その隙を通り抜け炎に包まれて、サイラスは結界を脱し鳥籠の外に歩み出る。それを見てアマデウスは顔色を変え、部下たちはサイラスに向かって一斉に銃口を向けた。その様にサイラスは、不遜に笑う。
「エクソシストか、それなりに訓練も受けていような。その銃弾は銀か? いいだろう、撃ちたければ撃つがいい。しかし、お前らの所持している弾数くらいでは、私は死なんぞ」
おもむろにサイラスが掌を差し出すと、不意に掌に亀裂が入る。そこから流れた血はゴポリと音を立て姿を変え、赤黒い3つの大きな物体が、唸りを上げてサイラスの背後からエクソシストたちを威嚇する。
「犬の餌になるか、謝罪するか選択させてやろう」
サイラスの使い魔である3匹の黒犬“バスカヴィル”が獰猛に唸りを上げる。背後からシャルロッテが顔を覗かせた。
「叔父様、謝った方がいいですよ。今ならお父様許してくれますから」
シャルロッテの言葉を聞いて、驚いた顔を浮かべていたアマデウスは途端に眉を下げた。
「あっじゃぁごめんね兄様」
途端に手のひらを返したアマデウスに、敵味方入り乱れて「切り替え早っ」と呆れた。
「僕的処世術だよ。ホラみんなも銃下してー」
「ハーイ」
部下たちは素直に銃をしまう。どこか安堵しているようにも見える。即座に命令が下って、結界も解かれた。
結界が解かれたことに安堵して立ち上り、シャルロッテもまた掌から剣を取り出した。刀身が紅く、アラベスク模様の装飾が刀身全体彫られ、細身で刃渡りが90cmほどの剣、ダーインスレイヴを握り、サイラスの隣に立って見上げた。
「じゃぁお父様、解放されたことだしコイツら殺しちゃいましょっかー」
「え、ちょ、ロッテ? ここは和解って流れじゃないの?」
待ったをかけるアマデウスに首を傾げた。
「どうしてですか? 折角出られたのに、敵は殺すものですよ?」
「僕謝ったじゃん!」
「謝ったかどうか関係ありますか?」
サイラスを見上げて尋ねると、可笑しそうに笑っている。
「私を侮辱したことに対する謝罪は聞いたが、それ以外には聞いていないし反省もしていない様だしな」
「ですよねー。クララ火傷したしね」
「痛かったです……」
クララが涙目で訴えると、幼気な少女(見た目のみ)を泣かせたことにさすがにアマデウスも良心が痛んだのか、「わかったよ謝るから!」と、とうとうソファから降りて床に膝をつき「ごめんなさい」と謝罪した。
それを見て満足したように笑うサイラスを見上げた。
「じゃぁ謝罪も聞けたところでお父様」
「うん?」
「殺しましょうか」
「鬼か君はぁぁぁ!」
今度はアマデウスが涙目になって訴えた。
「あはは、やだなー冗談じゃないですかぁ。クララが見てる前でそんなことしませんよぉ」
「そりゃまるで、クララが見てなかったらやるって言ってるみたいだね」
「そりゃそうですよぉ」
「そーなの!? 君意外と狂暴だね!?」
「普通ですよぉ、化け物なんですから。叔父様が人間社会に慣れ過ぎなんですよ」
人間と共に人間の常識の中で暮らすアマデウス、かたや化け物街道まっしぐらなシャルロッテ達。価値観の違いは当然だ。軒先のポストを叩き落とす悪戯っ子の気分で、人の首を落とす――――それが化け物だ。
「やっぱ本物は違うなー」
「イカレてんな」
「怖えぇ」
可愛いふりしてあの子、割とやるもんだね、とアマデウスの部下たちは再び与太話だ。それを見ているとなんだかお腹に違和感を感じたので、ソファに腰かけてアドルフに声をかけた。
「ねぇちょっとそこのボク、私お腹空いたー。血あるでしょ? 持ってきて」
「誰がボク……」
「君。ホラ早く動く。それとも君が食料になってくれるの?」
どうも機嫌を悪くしたらしいが、怯んだらしいアマデウスが振り向いた。
「アディ、持ってきてやって。兄様とクララの分も」
「チッ」
「舌打ちすんなバカ」
上司の命令に舌打ちで返答したアドルフは、居間から出て行き少しするとグラスに血を入れて持ってきた。それを見て再び嘆息する。
「なに? グラス1杯って。ケチくさ。デキャンタで持ってきなさいよ」
船旅で多少我慢を強いられていたうえに、シャルロッテ達の摂取量は一度の食事で人一人分だ。毎日血を飲むわけではないが、とてもではないがコップ一杯では足りない。
そんなに飲むのか、とアマデウス達は引いていたが知ったことではない。
「お腹空いちゃうとボク達食べちゃうわよ、さっさと持ってきてよ」
一応グラスをテーブルに置いたアドルフは腹が立ったようで軽くシャルロッテを睨み、アマデウスに視線を移すと「言う通りにしろ」と視線で命令が下ったようで、再び舌打ちをして出ていく。その背中を睨みながら腕組みをした。
「なーにー? あの子態度悪い。目つきも悪い」
つい文句を言うと、アマデウスが苦笑した。
「加えて性格も口も悪い鬼畜野郎だよ。難儀で面倒くさい奴」
「なんでそんな人が聖職者なんですか」
「僕が拾ったから。アイツに関しては教育間違えたって心底反省してんだけど、いかんせんそれ以外がダントツで優秀だから、余計に腹立つんだよね」
周りの黒服たちも頷く。
「そうそう、課長はガキの頃から何やらせても一番」
「頭いいし銃の腕前は一級品。要領良いんだろうなー」
「更に外面の演技力は俳優レベルなもんだから、実績買われてあの歳で司教に大抜擢」
「しかも口が巧いからメチャクチャモテる」
なんだか色々と納得いかないが、格段に納得できない紹介に眉を顰めた。
「聖職者ってモテる必要ないわよね?」
「うん、無いけど課長は神懸かりにモテる」
一人が苦笑しながら言った。
「お嬢は気ィつけたほうがいいよー。アイツ女は金づるか排泄口だって豪語してる最低野郎だから」
「聖職者よね!? そう言うのダメなんじゃないの!?」
「アイツ自由人だからさぁ」
修道士は許されるが、司教や司祭は結婚が許されないという掟がある。その掟に対するアドルフの解釈はこうだ。
「ありゃ特定の女を作るなっつー意味だ」
誤解釈も甚だしいが、とにかく彼はそう言う男だ。アマデウスが項垂れて溜息を吐いた。
「まぁ精鋭のみんなは特例で多少の自由は許してるけどね、アディに関しては本当に反省してるんだよ……」
なぜかアマデウスが落ち込み始めた。余程の曲者なのはわかった。話しを聞いて引いていると、おもむろにサイラスが口を開いた。
「アマデウスの性格を考えると、お前の教育の成果が如実に表れたとしか思えんが」
「だから兄様、その話蒸し返さないでよ。僕それは忘れることにしてんだから」
時代背景とサイラスたちの話を加味した上で考えてみると、アマデウスは自分の美貌を駆使して権力者に取り入っていたのだろう。そう考えるとアドルフが最低野郎になるのも頷けると言う物だ。
「他のみんなは表面上普通なんだけどねぇ、アイツだけ失敗した」
「何を仰いますか、私ほど優秀な者は中々おりませんよ」
いつの間にやらアドルフが居間に舞い戻っていた。
「……お前のそう言うところを失敗したって言ってんの……お前ちょっとは謙遜とかしないの?」
「したら何か戴けるのでしょうか?」
デキャンタを置きながらアマデウスに振り返った顔は、とてもさわやかな営業スマイルだ。
「褒美がないとしないわけ?」
「そう言う訳ではありませんが、金持ちと権力者にはたかることにしているんです」
「ムカつく……お前のその無駄な素直さ、時々殺意が湧くよ」
「またまた、ご冗談を」
「冗談じゃないよ全く!」
余程の曲者だという事は、よくわかった。
少々説明が長くなったが、3人が地下牢に幽閉されるに至った顛末は、ここからが本番だ。ようやく満足に食料に在りついたシャルロッテが、やはりアマデウスの背後に控えるアドルフを見上げた。
「ねぇねぇボク、アディだっけ?」
何の気なしにそう呼ぶと、アドルフは眉根を寄せた。
「あぁ? 気安く呼ぶんじゃねーよバケモンのくせに」
目一杯ガン付けされて、更にこの言葉遣いだ。シャルロッテの怒りのボルテージは一気に沸点に達した。
「何その態度! 普通に話しかけただけじゃない!」
「ハァ? バケモンが話しかけてくんじゃねーよ。うるっせぇな」
それを言ったら身もふたもないんじゃないかしら、アマデウス様も吸血鬼じゃない、とクララは考えた。
「なんなのアンタさっきから! 私何かした!?」
「テメーみてーなんがこの世に存在してることが罪悪だろ。死ね」
「なんですってー!」
まぁ確かにそれが仕事なんだけどよ、それ言ったら猊下も死ななきゃいけねーじゃん、仮にも育ての親なのに、と同僚たちは考えた。
「なによ! 人間なんて私達にしてみれば家畜同等の存在なのよ! ナメた口きいてんじゃないわよクソガキが!」
「誰がクソガキだコルァ!」
我々にしてみれば老人すらもガキだが、私にしてみればロッテもクソガキだ、とサイラスは考えた。
「私達は人間みたいに腐った物なんか口にしたりしない、高貴な種族なのよ! たかだか20年そこらしか生きてない青二才が口答えすんじゃないわよ!」
「んだとコルァ! やんのかコルァ!」
「やってやるわよ表出ろ! 八つ裂きにしてやるわ!」
ぎゃぁぎゃぁうるさい二人に終始間に挟まれていたアマデウスは、最初こそ我慢していたがとうとう耳を塞ぎ、仕舞には喧噪のあまり貧乏ゆすりをし始める。そしてアマデウスの「頼むから静かにして」という意志は見事に伝播し、全員でアマデウスに憐憫の視線を注ぎ満場一致で幽閉が可決された。
ちなみにクララはシャルロッテのおもりだ。サイラスとアマデウスは二人で話したいことがあるというし、エクソシストの中にクララを独りぼっちにするわけにもいかない――――という口実をこじつけられ、面倒な役割を押し付けられたとばっちりだ。
ここでようやく状況が冒頭に戻る。憤慨するアドルフを袖にしていると、廊下からクスクスと声が響いた。どうやら陰からアドルフの同僚たちが、シャルロッテ達の様子を傍観してせせら笑っていたようだ。ニヤニヤしながら現れた同僚たちに、やはりアドルフは舌打ちして見せた。
「クリス、俺の銃返せ。この女撃ち殺すから」
そんな事だろうと思ったので、アマデウスが銃を没収したのだ。当然クリス――――クリストフはそのおねだりには素直に応じずに、地下牢の鉄柵越しに薄ら笑いを浮かべている。
「んなことしたらお前、あの旦那に殺されるぞ。それに何より、俺が怒られる」
「知るか。返せねぇならお前の貸せ」
「やなこった」
ペロリとアドルフに舌を出し、あっさりと断ったクリストフがシャルロッテに向いた。
「つーかさ、お嬢は大人しく捕まってなくても、こっから出られるだろ?」
当然出られる。鉄柵だろうが煉瓦だろうが、正拳突きでドガーンだ。
「うん、出られるけど、お父様の言いつけを破ったら怒られちゃうもん」
お父様は怒るととても怖いのよ、と付け加えると、周りも苦笑して納得してくれたようだった。アドルフには脅威を感じるほどの、ある意味敵なし野郎だが、他のメンバーはアマデウスの言う通り「表面上普通」のようだ。それに幾分か安心した――――と同時に、聖職者などと言う天敵と知己になった身の上を嘆いた。
3 夜想曲
初恋の人はサイラス。今も一番愛しているのはサイラス。サイラスは父であり師であり――――最高の恋人。そうはいっても勿論、恋情などと言う下らないものではなく、泉に揺蕩う睡蓮のように、朝露を享ける萌え木のように、純粋でみずみずしい高潔な愛だ。それでも恋人などと評してしまうのは、サイラス以外にそう言った対象に見える者に、あまり出会った試しがないからだ。
だけどシャルロッテは知っている、指先一つで、キス一つで、その意志だけで世界が変わることを、知っている。
昼前になってようやく牢獄から解放された頃には、クララはすっかり眠ってしまって、抱き上げるシャルロッテの腕の中で瞼を瞑り、規則的な寝息を立てていた。
「クララちゃん可愛いー」
「天使みたいだなー」
普段男所帯で、仮に女性に出会ったとしても大人にしか出会わない聖職者たちには、クララの様な少女の寝顔は刺激が強いらしく、早速メロメロになっている。それを見て笑っていたのだが、一部で「ロリコンが覚醒したらどうしよう」などと言い出すので苦笑した。
「大丈夫よ、クララなら合法ロリが適用されるから」
そう言うとクリストフが首を傾げた。
「何合法って」
「だってクララも皆より年上だし。年齢で考えたらむしろ犯罪はクララの方よ」
それを聞いて何人かはクララを起こさないように注意しながら、声を殺して笑った。
地下から出て直射日光を避けながらあてがわれた部屋に入り、完全に光を遮断してクララを棺に寝かせた。やはり寝顔は妖精のように愛くるしい。
部屋まで案内した最年少のエクソシスト、イザイアがドアから覗いていた。
「ねー、クララちゃんと同じ部屋で良かったの?」
「ええ。クララを一人にするのも心配だし、私も一人は嫌だから」
前の家はここほど広くはなかったし、勿論部屋は別々だった。
だがしかし、サイラスとアマデウスは一体全体どうしたことか、ある事情が解決するまで、この城で同居するなどと言い出したのだ。赤の他人どころか天敵の渦中、何故そんな状況下に身を置かねばならないのか甚だ不満且つ不安になる。
が、サイラスは一度下した決定を曲げることはまずないし、ここから逃げて南へ向かったとして、南支部にエクソシストたちが攻撃を仕掛けるかもしれないと考えると、そんな迷惑を振りまく気にはなれない。そして、この城に住んでいた夫婦がどこに行ったのかも不明なのだが、一時的に城を空けていただけなら帰ってくるだろうし、その時にサイラスたちがいなければ恐らく攻撃を受けることになる。
色々と考えた結果、渋々聖職者と吸血鬼が同居するという、不思議な環境を受容するに至ってしまった。そんな環境下でクララを一人部屋にするのは当然ながら心配だ。懇意にしておいて闇討ち、羊の皮を被った狼かもしれない。聖職者が慈悲深いとは限らない――――と言うのはアドルフの件で十分に学習したし、考える限りアマデウスはとんでもなく狡猾で卑怯、老獪で残忍。そう言った相手が率いる人間を、警戒しておいて損はない。そう判断して、同室の希望はシャルロッテの方から言い出し決定した(寝ていたクララの意見は聞いていない)。
クララを寝かしつけていると、イザイアの後ろから更にひょこりと顔を出したのは、技能派コンビのクラウディオとレオナートだ。ここで一先ず、チーム聖職者の人員とスペックを紹介しよう。
彼らエクソシスト集団の正式名称は、「ヴァチカン教皇庁教理省枢機卿直属対反キリスト教勢力及び魔物強硬対策執行部」と言う。余りにも長ったらしいので、部門ごとに通称が付いており、殲滅組織“神罰地上代行”の彼らが属する精鋭部隊は“死刑執行人”と呼ばれている。最前線で実際に手を下す彼らには似合いで、かつ皮肉だ。
その「ヴァチカン教皇庁教理省枢機卿直属対反キリスト教勢力及び魔物強硬対策執行部」部長がアマデウス。その部の中の「強硬殲滅課」課長で、精鋭部隊“死刑執行人”隊長が、最低鬼畜野郎でおなじみのアドルフ・リスト。エクソシスムの指揮を執るために、位階は司教だ。
幼少から戦闘教育を叩き込まれて育ったアマデウスの教育熱の結晶は、ヴァチカン随一の銃の腕前(殺しの手腕とも言う)と明晰な頭脳を買われて、当然のように隊長の座に就いた、ヴァチカン裏社会ではエリート中のエリートだ。彼を筆頭にした精鋭部隊には、アドルフ同様に幼少からアマデウスに教育を施され、それぞれハイレベルな手腕を持ち、尚且つ特化した技術を持つ部下が7名在籍している。なお、クリストフ以下の位階は皆司祭となる。
クリストフ・メンデルスゾーン アドルフの副官で役職は主任、近接戦闘のスペシャリスト・結界師。アドルフのご機嫌取りと、暴言を標準語に通訳する事が主な仕事。唯一アドルフにマジギレされたことがないのが自慢。いつも半笑い。
クラウディオ・パガニーニ 爆発物開発・処理の技術者。普段危険物を取り扱うためか、極度の潔癖症。
レオナート・マイアベーア 各種武器の開発・整備士。常に硝煙とオイルの匂いが漂い、ごちゃごちゃと部品を広げたりするので、頻繁にクラウディオと喧嘩になる。
エルンスト・ウェーヴァー 狙撃手。普段はチャラチャラしているが、仕事中は人格が変わるらしい。
アレクサンドル・ベルリオーズ 密偵。声色を変え、特殊メイクを駆使した変装で全くの別人になり、たまに周囲を混乱させる。
フレデリック・ブルクミュラー トラップメイカー。幼少時から彼の仕掛けるトラップに嵌らなかった者はいない。悪戯っ子。
オリヴァー・シュトラウス ハッカー。趣味がハッキング。某国の国防システムを突破して、一騒動起こしたことがある。
イザイア・ヴェルディ 最近入隊した新人だが、アドルフが熱心に教育を施した直弟子で、銃の腕はお墨付き。でもアドルフと違い、一番聖職者らしい。
こんなご立派な“死刑執行人”達だが、彼らが戦場に赴くのは、敵が高位の魔物であったり、反キリスト教の超過激派テロ組織だったりする場合で、管理職としての仕事をするアドルフとクリストフ以外は、基本的には暇なのが現状らしい。
「暇は暇で怠いけどよ、俺らも警察や軍と似たようなもんだ。俺らみたいなんが暇で税金泥棒とか言われてた方が、世界は平和だ」
とレオナートが言うので、「確かにね」と笑った。
見ると部屋の前にはなんだかんだ、アドルフとクリストフ以外のメンバーは全員集合してしまっている。地下牢で眠れなかったのでアドルフは寝かせて、その間はクリストフが仕事をしているらしい。他は暇なので、シャルロッテの所に遊びに来た。普通の人間たちと違って化け物に接する機会が段違いに多い“死刑執行人”でも、膝を交えて会話することなどまずないようで、色々と興味を惹かれるらしい。
寝室から出て居室のソファに座るように促すと、喜んでくつろぎ始めた。ここから好奇心を原動力とした質疑応答が繰り出される。
Q・何歳ですか?
A・197歳。
Q・旦那は何歳ですか?
A・実は知らない。
Q・クララは何歳ですか?
A・66歳。
Q・なんでロッテは寝ないんですか。
A・昼間も平気だし、別に今は眠くないから。
Q・今までどうやって血を飲んでいましたか?
A・昔は人間を攫って食べていたけど、今は病院から輸血用血液を盗んでる。絶対健康な血液が飲める、今はいい時代だわ。
Q・人殺しをしたことがありますか?
A・沢山ね。昔はそれで良かったけど今は警察や法律が整いすぎていてやり辛くて嫌。今は嫌な時代よ。
Q・旦那の犬とかお嬢の剣みたいな、ああいうのって他の吸血鬼も出来るんですか?
A・使い魔ね。さぁ、知らない。
Q・実際旦那ってどのくらいの強さですか?
A・一晩でヴァチカンを陥落出来ると思う。
Q・ロッテは?
A・一晩でこの町の人間を皆殺しに出来る。
Q・クララは?
A・この城の人間を皆殺しに出来るくらいだと思うけど、あの子には人殺しをさせたことがないから解らない。
Q・何故ですか?
A・あの容姿だしまだ若いし、元が人間だから。
Q・ロッテは元が人間じゃないんですか?
A・私は吸血鬼を両親に持つ純血種だから、生まれながらに吸血鬼よ。
ある程度質問攻めにして満足したのか、各々「へぇ」と呟きながら頷いている。
今度はシャルロッテが質問する番だ。あちらもそのつもりだろうし、こちらとしても敵の情報を仕入れていた方がいい。彼ら自身には微塵も興味はないが、興味津々な風を装い、身を乗り出して尋ねた。
「ねぇ“死刑執行人”みたいな、“神罰地上代行”のメンバーって沢山いるの?」
クラウディオが頷いた。
「多いよ。俺らも正確な数は把握してないけど、全部で2000人くらいじゃないか」
「そんなに?」
彼らはエリート集団だが、彼らの様な武装神父が2000人もいるとは素直に驚いた。数が多い事と把握できていないことは関係がある。
恐らくは世界中にその人員が配備されていて、その為にそれだけの人口を有し、だからこそ全体像の把握ができない。出来るとしたら教皇クラスの上層部、そしてアマデウスとその官職の直属であるアドルフとクリストフ。
なるほどね。そう言う事ならあの二人とは仲良くしておいた方が良さそう。
そう考えて彼らに視線を移し、新たに疑問が浮かんだため再び無垢スマイルを取り繕う。
「みんなは何歳? みんな叔父様が育てたの?」
エルンストが頷いた。
「最年長が課長と主任で26歳、ディオとレオと俺が24歳、アレクとフレディが23歳、オリヴァーが21でイザイアが17」
「へぇ、イザイアはまだ17歳なのに精鋭に入隊できるなんて、優秀なのね」
「えへへーありがとう」
褒めるとイザイアは嬉しそうに後ろ頭を掻いて、照れて見せた。
んまー純粋な子、とそんな所に感心して、質問を続けた。
「みんながここに来たのは何歳の時?」
「バラバラだよ」
と答えたのはオリヴァー。
「課長とかは5歳とか、物心ついてから来たって言ってたけど、俺なんか赤ん坊の時に来たらしいから」
「ふぅん、じゃぁご両親の事とか何も覚えてないの?」
「あはは、全然。なんで来ることになったのかも知らないんだけどさ、猊下は優しいしみんな仲良いし、ガキの頃もそんな淋しいとか思った事無かったな」
オリヴァーの言葉に回りも同調した。
「周り大人ばっかりだったけどな。ガキの頃は修道会のシスターとかが来てたし」
「懐かしい! お前スカートめくりして怒られたよな。ババァだったのに」
「魔が差したんだよ」
子供の頃の、無邪気でバカで微笑ましい思い出。親がいなくても覚えていなくても、自分が何者かわかっていなくても幸せなのは、家族同然の仲間と楽しく暮らしていられるから。
そう考えて思わず口角の端が上がる。
付け入る隙は十分、この子達なら難なくオトせる。
どうせなら彼らと仲良くして取り入っていた方がいい。そうすればいざ敵対したとしても、彼らの方に躊躇が発生するだろう。狙うべきはその点だ。
そう言う発想に行きついたのは、アマデウス様様だ。かといってアマデウスの様にお色気勝負をするつもりはない。そこまでプライドを捨てたくはない。あくまで「良いお友達」を演じてさえいればいいのだ。
そもそも、サイラスとアマデウスの間で同居をするに至った経緯は、互いの都合によるものだ。
アマデウスは魔物討伐の為にここにやってきた。なのに肝心のお目当てはおらず、しかもその後遭遇したサイラスには勝てそうにない。かといって手ぶらでヴァチカンに戻るわけにもいかない。サイラスの存在を教皇に話せば、教皇は“神罰地上代行”の全戦力を投入しろとでも言いだしかねない絶滅主義者。そうなると、双方にはそれなりに大きなダメージが出る事は必至だ。無暗に損害を出すことは、アマデウスの真の目的にも、他の業務にも重大な支障をきたすので、それは避けるべきだ。
討伐の報告にはある程度の証拠品も必要で、現場の写真や吸血鬼の死体の砂なども提出しなければならない。残弾数や現場写真などを偽造して教皇を騙せたとしても、同業の教理省のメンバーや“神罰地上代行”の人員を確実に騙せるかはわからない。ならば、別の吸血鬼を見つけて討伐してしまえば良い。
サイラスは極彩トワイライトの存在を明かしはしなかったが、極彩トワイライトに所属するメンバーは原則紹介制だ。入会できるのは、人間との社会的共生を望み、かつ種族の存続と人間を含め他種族を侵犯しない良識のある者に限られている。無用な諍いは相互の破滅を呼ぶことになるからだ。
だが中には、ただ殺戮を好む種族や、調子に乗って暴れまわる新人などもいたりする。そう言った化物たちは例え同族だったとしても、人間にとっても極彩トワイライトのメンバーにとっても迷惑極まりない。後先を考えられない短絡的で軽率な者は、化け物であろうが人間であろうが、存在する価値はないと考えている。
よって、極彩トワイライトのメンバーからそう言った迷惑者の情報を提供してもらい、その者を討伐して報告することになった。
それが成功したら、仮に教理省にサイラスたちの通報があったとしても、今後一切無視をするということで、アマデウスとサイラスの間では不可侵条約が締結した。サイラスの方はヴァチカンとの無益且つ無闇な交流は必要としないので、必要な情報と、食料を分けてもらうという事で話がついた。ついでに謝礼と賠償金として、オリヴァーが複数の銀行の睡眠口座にハッキングし、これまた不法に作ったサイラスの口座に総額で10万ユーロ融資してくれたので、時々融資してもらうという事にもなって、それで手を打った。
それともう一つアマデウスの方からサイラスに相談があったらしいのだが、その事は兄弟の秘密だと言って教えてくれなかった。
一先ず、アマデウスたちがこの城にやってきて既に半月以上経過しているという事だったので、偵察と追跡と言う時間を加えてみたとしても、これ以上は時間を取ることはできない。すぐにサイラスは手紙を書いて蝙蝠を複数飛ばし、情報を集め出した。
「旦那、メールとか電話とかで情報集められないんですか?」
その様子を見ていたオリヴァーが尋ねた。
当然電話がある所もあるし、ネットを繋いでいるところもある。と言うよりも、現在においてはほとんどの交流が、非公開のサイトの掲示板上で行われているので、サイラスの元にそのアドレスや電話番号も届いていて知っている。が、サイラスがただ単にそう言った手法が気に入らない、と言うだけの話だ。
「オリヴァーの様な者がいると思うと尚更な。手紙なら読んだら焼き捨てれば済むことだし、情報が漏洩することは気に喰わん」
まさか手紙を送った先が不在でアマデウスがいるとは夢にも思わなかったが、その事は置いておくとしてだ。
実際オリヴァーくらいの腕になると、そのサイトが公開か非公開かなどはあまり関係がない。メールも通話状況も探られてしまうなら、証拠となる形跡を残しておくことは避けた方がいい。
その点、使い魔を使った手紙や口頭なら証拠は残らない。多少の不便さを我慢すれば、電信通信よりはるかに秘匿性が確保できる。
それから3日の間に蝙蝠は返事の手紙を持って戻ってきた。ちなみにその中の一通に、
「最近ジョヴァンニとグロリアがこっちに引っ越してきたよーん。フィレンツェ飽きたとか言って。今そこにサイラスが住んでんだね。お城荒れてっけどよろしくだってさー」
と言う旨の連絡が入っていて、この城に住んでいた夫妻の無事が確認できたことには安心したものの、サイラスは打ちひしがれていた。
とりあえず一番近いフランスに行くことになって、城内は俄かに慌ただしくなった。さっさと仕事を片付けるために“死刑執行人”は全員赴くし、アマデウスも同行する。が、当然ながらシャルロッテ達は行かない。
「この仕事が済んだらヴァチカンに帰るんでしょ?」
スケジュールの調整をするアドルフに話しかけた。
「アンタの顔見なくて済むと思うとせいせいするわ」
「そーか、残念ながらしばらくは俺のイケメン顔を眺めることになるぞ」
「は?」
言っていることが隅から隅まで納得できなかった。討伐が終わればこの城に用はないはずだ。いぶかるシャルロッテをアドルフは横目で見やる。
「ヴァチカンの屋敷は売却した」
「は?」
「この城は既に俺の名義で不動産登録してある。猊下は戸籍がないからな」
「は? ちょっと待ってなんで!?」
寝耳に水とはこの事だ。つんのめって尋ねたシャルロッテに、アドルフはボールペンを指先で弄びながら答えた。
「猊下はヴァチカンから離れた所に住みたいってずっと言ってたし、俺も女がストーカー化して面倒臭かったからな。丁度良かった」
「何その理由!? ていうか私聞いてないわよ!」
「言ったら反対すんだろ」
「当たり前じゃない! ちょっとお父様!?」
どういうことだとサイラスに詰問すると、「まぁそういうことだ」と返ってくる。
「だからどういう事ですか!」
「今後私達は銀行に侵入しなくても金がもらえるし、このバカデカイ城の固定資産税も払わずに済むし、病院に盗みに入らなくても血液が手に入るし、身の安全が保障されている以上は、ひたすら食っちゃ寝できるという寸法だ」
「そんな怠惰な理由で!? そんな理由で可愛い娘が天敵と暮らすことを許すんですか!」
「ロッテに手を出そうとしたら、いかなる理由があろうと殺すと言ってあるから安心しろ」
安心も何も人間に負ける気はしないが、そう言う事ではなく。
ついに立ち上がって喚いた。
「ただの人間じゃないでしょこの人達! 何考えてるんですかー!」
「うるさい」
「ちょ、お前うるせーよ」
サイラスもアドルフも鬱陶しそうに耳を塞いだ。
「キャンキャン喚くなよ、室内犬かテメーは。もう決まったんだから諦めろバカ」
「誰が室内犬よバカ!」
「お前。つかマジうるせぇ。なんか劈く、お前の声」
再び耳を塞ぐアドルフにシャルロッテは室内犬よろしくキャンキャン吠える。やはりサイラスも耳を塞いだのだが、聞き捨てならなかったようでアドルフを睨んだ。
「おい小僧、私のロッテに向かってバカとはなんだ」
「誰が小僧……つか旦那、意外に娘萌えですね」
「うるさい。というか、あぁ、本当にロッテがうるさい」
二人はひたすらに耳を塞いで、シャルロッテの喚きに耐えた。
--------------------------------------------------------------------------------
翌日には城を出かけた“死刑執行人”達は、2日後には戻ってきた。
仕事はスムーズ且つスマートに完遂したらしく、報告書を手にしたアドルフは司教らしくキャソックに着替えて、アマデウスは猩猩色のローブを羽織っていた。
「叔父様、どちらに?」
帰って来たばかりなのに、二人で出かけようとしていた。
「ヴァチカン。長官と教皇聖下に報告だよ」
彼らはヴァチカン内ではキャソック――――所謂神父の格好をしているが、神罰地上代行の存在は公にされていない、秘匿の組織だ。その為、ヴァチカンの外ではスーツに似せた制服を着ていて、サラリーマンに扮しているらしい(マフィアに見えるともっぱらの評判)。
ヴァチカンに行くと聞いて不安に駆られたが、それを察したのかアマデウスが微笑んだ。
「大丈夫、ロッテ達の事は言わないから」
「本当ですか?」
「当然。言ったところでメリットないしね。僕がどやされるだけだもん」
その言葉を素直に信じていいのかはわからなかったが、直接教皇に会見できるのはこの二人だけだし、攻め込んでくるとしても膨大な準備が必要なのは明白だ。いざとなればトンズラをこけばいい。
「そうですか。じゃぁお気を付けて」
「うん。行ってくるね」
アマデウスはそう言って手を振ると、アドルフの肩に手を置いて、その場からしゅるりと収束するように姿を消した。少し驚いて目をパチクリとさせた。
「叔父様も瞬間移動なんか出来るのね。驚いた」と呟くと、その様子を見ていたらしいクリストフが笑った。
「行った事ある場所なら自由自在らしいけど、ヴァチカンいる時はできないつってぼやいてた」
ヴァチカンともなると聖地で、人間の信仰心により極度に魔力が抑圧されるのだ。その為使用できる能力は限られるし、弱い吸血鬼などは立ち入る事すらも出来ない。そう考えると、アマデウスがヴァチカンから離れて暮らしたがったのも納得だ。
一人で思索にふけっていると、クリストフが覗き込んできた。
「“叔父様も”って事はお嬢とか旦那もできんのか?」
頷いた。
「できるわよ」
「お嬢様と旦那様は基本的に何でもアリですよ」
隣でクララが自慢げに言った。すると、周りの留守番組も興味深げに話に入ってきた。
「何ができるの?」と尋ねるイザイアは目を輝かせているが、それとは別に急に気になる事案が発生する。漂う匂いに気を取られて、イザイアが質問したことは華麗にスルーした。
「血の匂いがするわね。怪我したの?」
「えっ、俺の質問無視?」
「撃たれたの? 斬られたの?」
「うわ、無視だ……」
俄かに落ち込むイザイアの腕を、苦笑気味にエルンストが取って袖をめくった。見ると包帯が巻かれて少し血が滲んでいる。
「敵の吸血鬼が撃ってきた弾が掠っただけ。大したことねーよ」
「そう。いや、心配したわけじゃないんだけどね」
「えっ違うの?」
またしてもショックを受けるイザイアは放っておき、怪我をした左腕を取る。「ちょっと見せて」と包帯をほどいて行くと、3cm程銃弾によって抉られた跡があった。それを見ているとどうしても。
「わー! わー! お嬢やめて!」
思わず傷口に顔を寄せると、イザイアは必死にそれから逃れようともがいた。
「いいじゃない、ちょっとだけ。何もしないから」
「何もしないからってなんだよ! ヒィィィ!」
人間がシャルロッテの力に適う筈がなく、難なく傷口に口付けてぺろりと舐めると、直接傷口に触れたためか「痛い痛い!」と暴れている。いい加減に離してやると睨まれた。
「もう痛いじゃん! ビビるし!」
「ちょっと味見しただけじゃない。舐めただけで何もしてないわよ?」
「もー、普通にギョッてするから!」
「だって美味しそうだったんだもの。ごちそう様。美味しかったわ」
「そりゃどーも! 全く!」
イザイアは憤慨していたが、周りはクスクス笑っていて、しまいにはクララが今にも涎を垂らしそうな顔をしている。
「イイなぁお嬢様」
「クララも今度御馳走になるといいわ」
「そうしますぅ」
「イヤイヤ! 何言ってんの! 今度は別の奴に頼んで!」
というイザイアの回避行動に、クララと揃って口を尖らせた。
「どうして? イザイアが一番美味しそうなのに」
「この中じゃイザイアが一番ですよね。若いしお酒も飲まないし煙草も吸わないし」
ねー、と二人で言い合うと、周りがイザイアを囃し立てる。
「おっ、いーなイザイア、モテモテじゃねーか」
「この色男」
「えっ、嬉しくない。こんなモテ方嬉しくない」
カッコイイ、タイプ、ならまだしも食料視点での高評価だ。イザイアとしては不本意極まりない。御免被ります、と首を振る。
「贅沢言ってんなお前、美少女二人に迫られて」
「羨ましいぜこの野郎」
「じゃぁ誰か替わってよ!」
堪らず交代を願うイザイアの言葉に、全員が一歩下って首を横に振った。
「無理。俺愛煙家だから」
「俺アル中だから」
仲間の裏切りを受けて、イザイアはこの日から酒と煙草を嗜むことに決めた。
程なくアマデウスとアドルフが帰ってきて、早速その件を報告すると二人は大笑いした。
が、シャルロッテが水を差す。
「反してアディなんか最悪よね。酒臭いし煙草臭いし硝煙臭いし香水臭いし女臭いし、なんかもう色々臭い」
あくまで食料視点の評価だが、これはこれでカチンときたらしくアドルフはムッとした。
「あーっそ、お前が腹空かして死にそうンなっても、一滴も飲ましてやんねぇからな」
「えっいらない。私そこまで落ちぶれてないから」
「どーゆー意味だコラ」
「そう言う意味。なんか変な病気感染されそう」
言いながら血の入ったグラスを傾けていると、いよいよ怒ったアドルフがテーブルを叩いて怒鳴りつけてきた。
「テメーなに性病扱いしてんだよ! 持ってねーよバカ!」
「わからないわよ。何なら検査してあげようか?」
「余計なお世話だボケ!」
憤慨するアドルフをクリストフが宥めてようやく静かになったが、シャルロッテは終始落ち着いていた。周囲はゲラゲラ笑っている。
コイツ短気ねー。絶対高血圧が原因の病気で死ぬわね。
そう考えて、今度は親切心で病院での検診を勧めてみると、アドルフは更に怒った。
4 ツァラトゥストラはかく語りき
ある夜、アドルフを除いた“死刑執行人”のメンバーが集まって座談会を開いている。
その議題はズバリ。
お嬢とアディが相性悪すぎるんだけど、俺らは仲裁に入るべきなんだろうか――――である。
二人がケンカをするのは内容によっては面白いのだが、場合によっては彼らがシャルロッテに苛立つこともあるし、時にはサイラスが怖気の走るオーラを纏ってアドルフを睨んでいることがある。近頃になってそれに気づき、ハラハラすることの方が増えた。要するにこの二人と同じ空間にいると、周りは気苦労が絶えない。
ケンカの発端は毎回実に下らないもので、どちらともなくケンカを吹っ掛けたり、またシャルロッテが声をかけてアドルフが無視したり、アドルフの話をシャルロッテが袖にしたり、とにかくどうでもいい事から口論が勃発する。
アドルフもそうなのだが、ようやく彼らも気付いた。シャルロッテがただの天然ではなく、意外に聡明で頑固でプライドが高い事に気付いた。そりゃ相性悪かろう、と嘆息せずにはいられない。似た者同士が同じ話題で張り合うと、延々と平行線で拮抗するものだ。大概はクリストフとクララが宥めて、あるいはサイラスとアマデウスが「うるさい!」と叱りつけて強制終了させている。
が、問題はその後の様子だ。ケンカが終息して少しの時間、八つ当たりなどをすることはないがアドルフは機嫌が悪い。反してシャルロッテはケロリと忘れてすぐに別の話題に移り、ケンカなどなかったかのようにアドルフにも普通に会話を振る。それで余計にアドルフが悔しいらしく、機嫌を損ねる。
その甲斐もあって殺伐とした雰囲気が長く継続することはあまりないし、実際シャルロッテが本気で怒ることはまずない。だがそれがアドルフには気に入らない。いつまでもアドルフが機嫌を損ねていると「フン、ガキね」とでも言いたげにシャルロッテが見つめる。プライドの高いアドルフはそう思われることが癪で、素直に機嫌を損ねる事も出来ない。
その様子を思い返し、全員で嘆息する。
「どー見てもアレ、お嬢は遊んでるな」
「伊達に歳食ってねぇな。「面白いわーこの子」とか思ってんだろうな」
「うーん、今までになかったタイプだな」
「あの女一辺泣かしてやりてぇつって地団太踏んでたぞ、この前」
「悔しかろ。特に課長みたいなタイプには」
「でもよぉ」
俄かに同情的な雰囲気になったクリストフの部屋で、クラウディオが頬杖をついて宙を仰ぐ。
「課長ってアレじゃん。女泣かせで女の敵で通ってただろ。天罰じゃね?」
クリストフが半笑いで同調した。
「確かになぁ、アディが口論で負けるところとか珍しいもんなぁ。口でも力でも知恵でも勝てない相手って、男女問わずいなかったんじゃねーか」
「初めての挫折ってか」
「それはそれで見ものだな」
女泣かせが女に泣かされる。因果応報とはこの事だ。
なんだか可笑しくなって苦笑していると、ノックの音が響いて「クララです」と言った。実は特別ゲストとして招待していた。シャルロッテ側の意見も聞いておく必要があると判断しての事だ。
早速話を始めると、クララは途端に不機嫌になった。
「私あの人嫌いです。いつもお嬢様に突っかかって」
「そこはお互い様だと思うけどね」
「まぁ、そうなんですけど。でもお嬢様は時代が違えば王女様ですよ。吸血鬼の中でも最高位の純血種なんですから、一介の吸血鬼と混同されては困ります」
道理で、とプライドの高さには納得だ。言われてみれば確かに、ただでさえ伝説級の存在である真祖を父に持ち、母親も吸血鬼。仕事柄吸血鬼にはよく遭遇するが、純血種に会ったのはシャルロッテが初めてだ。どれほど稀有な存在なのかはわかる。
人間のみならず、並の吸血鬼や化物にすら見下したような態度を取る。確かに種族の優劣としては、吸血鬼の方が人間よりは生物学上優れているのだろう。
そう考えたが彼らはあくまで聖職者だ。当然それでは納得いかないので、反論しようとクリストフが口を開いたところで、クララが続けた。
「あの人に腹が立つのは、お嬢様があの人を気に入ってるからです! なんででしょう!? すごく不思議なんですけど!」
それは実に不思議だ。一緒に暮らしてそう長くはないが、見ていてとてもそうは見えないし、何よりアドルフが気に入られるような点が一切見受けられない。
「え? 気に入ってんの、アレで?」
「多分そうですよ。だってお嬢様、あの人の事だけ文句言うから」
「何でそれで気に入ってんの?」
「わかりませんけど……面白いわーって言ってたし」
やっぱり面白がっていたか、と俄かにガックリする。考え得る限り気に入っている点としては、オモチャ的な扱いが一番近いと推測する。が、やっぱり少し腑に落ちないので、更に情報を引き出す。
「他にはなんか言ってた?」
尋ねるとクララは頬に手をついて宙を仰ぐ。その仕草に「可愛いなぁ」と萌えながら返事を待つ。
「あの子意外と硝子の少年よーとか、人によって態度を使い分ける小憎らしさがいいわーとか、思いやりの欠片もないところが笑えるわーとか」
「え、笑えない……ていうか、普通そこムカつくとこだと思うんだけど」
「ですよね!? 私もそう思うんですけど! よくわかんないわーお嬢様」
「クララでもわかんないのか……懐が深いって事か?」
「それはあるかもねー。でもそれならさぁ、気に入りはしないよね。下手に関わるより適度に距離置きたいタイプじゃない? 課長って」
唸りながらエルンストが言った。
「確かになぁ、俺らは慣れてるけど課長ってひねくれてっから、敬遠してる奴多いよな」
「だよな。色々と誤解を招くタイプ」
それを聞いてクララが、「あ」と声を上げた。
「だからでしょうか?」
「えっなに? 同情って事?」
「いいえ、そうじゃなくて。やっぱり似た物同士って事です」
「どゆ事?」
尋ねるとクララは腕組みをして唸る。その仕草に「めんこいなぁ」と萌えながら返事を待つ。
「さっきも言いましたけど、お嬢様はあの人の文句しか言わないんです。皆さんの事は良くも悪くも言いません」
「それはそれで寂しいな」
クララの言葉にみんなは軽くシュンとして、気付いたクララはすぐに「あ、ごめんなさい」と謝罪した。
「で、それがどういう事かわかります?」
問われて首を捻ると、クララが言った。
「あの人凄くモテるんですよね? 皆さんも同じように遊んだことがあります?」
「アイツほどじゃねーけど、多少はね」
「じゃぁわかると思いますけど、本命の相手と浮気相手の態度違うでしょ?」
そう言われて年長組は「成程!」と手を叩いた。年少組は「どゆ事?」と首を捻るので、クララは年少組を少し見直した。年少組の反応を見て、クリストフが続けた。
「イザイアなんかとくにわかんないと思うんだけどハッハッハ」
イザイアは真面目なので女遊びなどしたりはしない。
「笑わないでくんない」
「ハッハッハすまん。あのな、感情の振り分けがな、違うんだよ。浮気相手とか遊びの女に限らずどうでもいい奴ってさ、こっちがどうでもいいと思って気にしなければ、何言われてもそんなに腹立たねぇだろ。例えそれで嫌われても困らない。どうでもいいから。でも本命の相手とか、どうでもよくない相手とかになると話は違う」
「あ、そっか。仲良くもすればケンカもするね。それこそどうでもいい相手とは当たり障りなくしてりゃいいもんね」
クララが頷いた。
「そう言う事です。お嬢様は基本的に、穏やかでいつも笑顔で親切で人の悪口なんか言わない公平な人柄――――それが通常装備の外面です。お嬢様は誰に何を言われても基本的には怒る事なんかありませんし、傷つくこともありません。それはお嬢様の目には誰でも同じに、どうでもいい相手だと映っているからです」
「でも課長には違うよな」
「そうですそれが腹が立つんです。本当のお嬢様は我儘で自己中心的で天然で人の話を聞いていなくてとても気位が高いんです。お嬢様の目から見てあの人が、お嬢様の感情を消費するに値する人物なのが腹立つんです!」
「なんでだろうな? 惚れてるとか?」
「それはあり得ません絶対に! お嬢様は人間とは恋をしないんです!」
「まぁ、だよな。あんだけプライド高けりゃな。俺らが豚と結婚するって言うのと同じレベルだろうな」
「そうですとも!」
クララの興奮が冷めやらないので、一先ずアレクサンドルが落ち着かせた。何とか興奮が収まったクララが、落ち着いた口調で言った。
「そんなんじゃないんです。お嬢様は自分から他者を寄せ付けたがらないんです。他人が自分のテリトリーに入ってくることを極端に嫌っているんです。あの人もそう言うところがあるんじゃないんですか?」
「あーあるなー」
「似てると言えば似てるかぁ。若い頃の私を見てるみたいだわーみたいな?」
「そうかもしれませんね」
「でもさ、お嬢って基本的に誰にでも優しいじゃん。そう言うのって人が遠ざかって行かないじゃん」
「ええそうですよ」
少し神妙な顔つきでクララが言った。
「お嬢様は人を惹きつけておいて、全力で他人を拒絶しているんです」
「そりゃまた矛盾してんなー。なんで?」
「それは……色々と事情が……」
口ごもるクララに興味を惹かれて、「何、何?」と身を乗り出す。が、クララはぴしゃりと「言えません!」と言い放った。
「気になるならご自分でご確認ください。とにかく、あの人には腹が立ちますが、今のところお嬢様は何も他意はないので、放っておいていただいて問題ありません!」
「えー気になるじゃんよーヒントヒント」
「ノーヒントです! では私は失礼します!」
クララちゃーんまってー、と言うカーテンコールは聞き入れられずに、クララはさっさと部屋を出て行ってしまった。
と思ったら戻ってきた。
「あー驚きましたー」
廊下でシャルロッテと鉢合わせしそうになり、慌てて逃げてきたらしい。彼らの部屋は3階にあって、シャルロッテとクララの部屋は5階にある。クララが3階にいるのは不自然なので、身を隠した次第だ。
結局帰投したクララに話の続きを強請ったが、どうしても話したがらないので、レオナートが質問を変えた。
「クララがお嬢に出会ったのはいつ?」
「今から55年程前です。10歳の時でした」
「どういう出会い?」
「あの時――――」
思い出す55年前、クララの目の前にあったのは冷たく冷えそぼりゴミが散らばり汚いコンクリート、街には次第に雪が降り積もり始め、衰弱したクララの存在すらも覆い隠そうとしていた。
「私戦災孤児だったんです。最初は親戚に預けられたんですが転々として、その内捨てられました」
「第2次世界大戦の後?」
「はい」
戦後復興の最中、国は賠償金を得たとはいえ国民の生活はとても豊かとはいえなかった。特に田舎の貧しい地域は貧困の窮地で、クララの様に身寄りのない戦災孤児は掃いて捨てるほどいた。そう言った子供たちは大概はグループを作って共同生活をし、それぞれゴミを漁ったり窃盗をしたり強盗をしたり、あるいは体を売って生きていた。
クララもそう言った子供たちの集団の中に身を置いていたが、風邪をこじらせて肺炎でも患ったのか、日に日に衰弱していった。生きるのに精いっぱいの子供たちに、クララを病院に連れて行くなどと言う選択肢はない。日頃から犯罪行為をしておいて憲兵や警察に通報するという発想もない。当然のごとく、クララはゴミ捨て場に棄てられた。
冷たいアスファルト、体は凍えて感覚は既になかった。視界に映るのは汚れたアスファルトとゴミだけで、時折通すがる人も誰一人として足を止めたりはしない。次第に息が浅くなって瞼も重くなり、あぁ私は死ぬんだ、そう思った。
こつん。
高いハイヒールの足音が響いていた。
こつん、こつん。
そんな靴を履けるのは、お金持ちだけだった。
こつん、こつん、こつ。
その足音が、クララの目の前で止まった。力を振り絞って瞼を開くと、目の前にあったのは革製の高いヒールのブーツ。それから徐々に視線を上げていくと、ふかふかのフォックスのコートに身を包んだ黒髪の少女がいて、その闇を従えた黒い瞳と視線がかちあった。その瞬間、何かを呟いた。
「なんて?」
「それが、意識が朦朧としていて上手く聞き取れなかったんです」
薄桃色の唇が確かに動いていた。
――――It's the same……amber…….
「琥珀色……同じ?」
「クララの瞳の色の事か?」
「そうだと思います」
アレクサンドルが覗き込んだ。
「同じって、誰と?」
その問いにクララは答えずに、話を続けた。
少女はコートを脱いでクララにかけて、すぐに抱き上げた。隣には男性が立っていて、クララを連れて歩き出す。どこに連れて行かれるのか考えるのも覚束なくなって、その内気を失った。
次に目が覚めた時に目の前にあったのは、ふかふかの毛布と茶色の天井、そして綺麗に結われた自分の金髪と、目が覚めたクララに気付いて笑顔を向けたシャルロッテだった。
「おはよう、やっぱりあなたちゃんとしたら、とても可愛い。私はシャルロッテ。あなたは?」
「……――――っ」
涙が出た。誰かに優しくされたのが、もう何時の事だったかも思い出せずにいたから。
「クララ……ヴィーク、リンゲンです」
「そう、クララ」
シャルロッテは穏やかに笑って、その白い指先で優しくクララの涙を拭ってくれた。温かいベッド、穏やかな笑顔、優しい指先。それが嬉しくて切なくて、折角拭ってもらったのに涙が零れ落ちた。
「クララは今日からうちの子ね」
既に決定事項なのは少し驚いたが、その時はそれどころではなくて、涙が止まらなかった。
これがクララとシャルロッテ、サイラスとの出会いで、後から実は吸血鬼で、クララも吸血鬼になったのだと聞いたときは驚いたものだが、彼らが何者であっても命の恩人であることに変わりはなかった。だから、一生この親子の傍にいてお世話になった分お世話をして行こうと決めた。
「というのがお嬢様との出会いです」
話を聞いて感心したようにクリストフが頷いた。
「へぇ、クララも苦労したんだなぁ。親が死んで悲しかったろ」
「そうですねぇ、子供の頃は散々でした。でもその後が幸せだったから、今はその思い出の方がたくさんあるし、嫌な事なんて塗りつぶされてしまいました」
話を聞いて頷いていた面々だったが、エルンストが尋ねた。
「でもさ、その頃はクララみたいな子って結構いたわけだろ? どうしてその中からクララを?」
「まぁ、この瞳の色も多少関係はあるようですが、お嬢様が言っていたのはですね」
なになに、と身を乗り出す。
同じ事をクララも尋ねたことがあった。その時にシャルロッテは、口元に美しい弧を描いて言った。
「化け物って言うのはね、神が嫉妬するほど美しいか、目も当てられない程に醜くなければ、存在する価値はないの」
それを聞いて圧倒される男性陣。
「う、おぉ。超絶高飛車発言だな」
「うーん、なるほど。でもわかる」
「クララもだけどお嬢も美少女だし、旦那も猊下も美形だもんな」
「旦那様の家系は昔から美形の家系だと仰ってました。亡くなられた奥様も、それはそれは美しい方だったそうで、お嬢様は奥様に生き写しなのだと旦那様が仰ってました」
「なるほどーそりゃ娘萌えもするわな」
うんうん、と頷いていたが、オリヴァーがまた同じ話題を振った。
「そんでさ、クララの瞳の色と、事情って何さ?」
「言いませんてばしつこいなー」
ぷぅと頬を膨らませるクララに「かーわいい」と男性陣は萌え盛ったが、余りにもしつこかったのでとうとうクララは部屋を出て行って、今度は戻らなかった。
クララが部屋に戻ると、シャルロッテが窓の外を見ていた。窓の外では雪が降っていて、木枯らしが窓を打ち鳴らしている。雪明りに照らされた漆黒の髪は、川の流れの様に彼女の肩から背中を滑っている。白い肌に一層映えるその黒に、目を奪われた。
「お帰りクララ。座談会は盛り上がったみたいね?」
シャルロッテが悪戯っぽく笑って言うので、思わず「うぃっ」と変な声が出た。その様子を見てシャルロッテは笑って、クララを傍に手招きする。おずおずと進むと座らされて、後ろから髪を結い始めた。
「別に怒ってないわよ。驚いた?」
「う、はい。知ってたんですか?」
「知らなかったけどォ、さっきクララが階段の所から走って逃げて行ったから、クララの影の中に隠れて聞いてたの」
「うぅ、ごめんなさい」
つくづく何でもアリだ、と落胆した。後ろでシャルロッテがクスクスと笑った。
「だから怒ってないってば。むしろ褒めてあげなきゃと思ってね」
「え、どうしてですか?」
尋ねて振り返ると、前を向くように首を戻された。
「余計な事はちゃんと黙っていたし、あの感情の消費量の話をしたのは100点あげる」
「えぇ?」
むしろ不味いのでは、と思ったが、つくづくシャルロッテはよくわからない。
「彼らがあの話を聞いて、アディに話すかしら? それともアディがそう解釈するように導くか――――とにかく、あっちにはそう思ってもらっていた方が都合がいいの。その為にしてきたことだからね」
「えっ?」
驚いて振り向くと、再び首を前に戻される。
「だってアディは叔父様の側近でしょう? そりゃぁ特別扱いもするわよー」
「えっ、側近だから、ですか?」
「そーよ。私が利用価値もないただの人間を、まともに相手するはずがないじゃない。これから先アディの態度が少しでも変われば、それで及第点。アディはもういいわ。次はクリスねー。でもクリスの方が大変よー叔父様に似てるから」
話を聞いて、久しぶりにクララは背筋がぞっとした。
そうだったお嬢様って、こういう人だった。
常に表面上の演技をしている、誰にでも平等に接することができる。それほどの公平性を持てる人柄が、どれほど冷徹で冷酷な人柄なのかクララは知っている。いつも怒っている人よりも、いつも人の悪口を言う人よりも、誰にでも平等に優しくできる人ほど、人を人とも思っていない。
髪を梳きながらシャルロッテが言った。
「思い出すわねぇ、こんな夜は」
「はい……」
彼らとの話の流れで気になり、少し勇気を出して聞いた。
「お嬢様、あの……」
「あぁ、ファウスト?」
「あ、はい……」
見透かされて少し俯き加減になると、シャルロッテは梳いた髪を編み始める。
「私は人間が嫌いなの。人間はいつもウソを吐くから嫌い。私にウソを吐かないのは、お父様とクララだけ」
シャルロッテがそう発言する理由もクララは知っていて、だけどどう返せばいいのかわからずに「はい」とだけ答えた。
絹糸のように細い、クララの金髪を器用に編みながら、シャルロッテが続けた。
「人間なんて――――」
雪の降る窓の外、夜の暗い空を見上げた。
死んでしまえばいいのに。どうせ死ぬために、生きているんだから。
その呟きにクララは、酷く胸が痛んだ。
5 愛の夢
人間は永遠の存在ではないから。
また明日ね!
その言葉が、
ずっと友達でいてね。
そのまなざしが、
必ず帰ってくるから。
その約束が、必ずしも守られるとは限らない。
その代わり、人間は必ずウソを吐く。呼吸をするように好き好んでウソを言う事もあれば、ウソにする気がなくてもウソになることもある。だからシャルロッテは嫌いだ。
永遠、とか
絶対、とか
そんな言葉を並べたてる人間はこの世で一番嫌いだ。人間は永遠にも絶対にも程遠い。この世界に存在する、永遠で絶対の物は光だけだ。それ以外の物はすべて、この世界に誕生した瞬間から崩壊が始まる。それは宗教においても哲学においても、物理学の世界でも常識なのだ。
そんな事も知らないでそれを求めたり、安易に口にする人間を見ると、殺してやりたくなる。
「なぁなぁお嬢はさぁ」
銃の整備をしながらエルンストが。
「今まで彼氏とかいたことあるー?」
「そりゃーあるわよ。200年近く生きてきて一人もいないわけないじゃない」
そうじゃなくても美人なので、男が放っておかない(でも基本断る)。実際イタリアに来てから、格段に被ナンパ率が上昇した(でもやっぱり断る)。
「あっそれもそうだな。どんな男がタイプ?」
「えー? そーねー」
そんな事を聞かれたのは初めてだったので、少し宙を仰いで考えた。
「私を殺せて、死なない男ね」
「旦那だな」
「まぁ初恋の人はお父様だったわよ。でもお父様は私を殺せないわー」
「え?」
エルンストが手を止めてこちらを見た。
「旦那の方が強いんだろ?」
「実力はね。力はお父様の方が上だけど、お父様は娘の私を殺すことなんか出来ない。私が出来ないように」
「なるほどな。えーでもじゃぁ、お嬢の理想に適う奴なんて、化け物で超強い敵くらいだな」
「敵じゃダメよ、私の事好きになってくれなきゃ」
「えぇ? 惚れた女殺せるわけねーじゃん」
「やっぱりー? 理想高すぎ?」
「エベレストより高いよ」
「あはは。じゃぁ私一生一人もんだわー」
でも、それでも。そうであってもらわなければ困るから。少なくともサイラスは、母に対してそうであったから。
「エリザベートが死んだのはお前のせいではない。私が、殺したのだ」
と、サイラスが言った。サイラスの話を聞いてシャルロッテもいろいろ経験して考えて、やはり母の様になりたいと思った。サイラスやクララのことを思うと、それが正しいのかはわからなかったが、女の幸せと言う視点で見れば、母と同じ道を選ぶ。
だけどシャルロッテは女でもあるが、サイラスの娘でクララの母親代わり。理想の相手になんてきっと出会う事はないから、母と同じ道を辿ることはないのだろうと思う。
「あはは、お嬢はアレだな。理想が高すぎて結婚できないタイプ」
「あーそーねー。でもわかるわーああいう人たちの気持ち。妥協したら負けなのよー」
「あー言うよねー。結婚したいなら妥協すりゃいいじゃん」
少なくとも人間の結婚生活は、妥協と会話と少しの諦めで成立するものだ。
「別にしたいと思ってないから妥協もしない」
「あっそうなんだ」
「そうよー」
言いながら窓の外を見ると、外には雪が降り積もって地面を真っ白に覆い隠している。
――――あーあ、今日は買い物に行こうと思ってたのに。
こんな雪の日は服や靴が汚れてしまうし、傘をさすのが面倒臭いから、外出するのは億劫だ。
が、ふと閃いた。
「エルンスト」
「んー?」
「みんな車の運転できる?」
「イザイア以外は免許持ってるよ。どっか行きたいなら送ってこっか? 公用車だけど」
「うん、あ、そうだ。誕生日近い人誰? その人に送ってもらう」
「えっなにそれ……」
と言いつつエルンストはカレンダーを確認する。今日は2月16日だった。
「えーとえーと、あ! 3月の奴がいた」
「誰?」
「課長」
それは却下だ。「別の人がいい」と言うと笑われた。
「そんなに嫌い?」
「嫌いじゃないしそう言う事じゃないわよ。アディは忙しいでしょ。もっと暇な人」
「あっそう言う事か」
もう一度エルンストは首を捻って考えると、膝を叩いた。
「フレディが1月生まれだ」
「そっか、ありがとう」
と言う訳でまずはオリヴァーの所へ行った。オリヴァーに買い物に行きたいと言って、クレジットカードを作った口座に30万ユーロ(約3千万)融資してもらった(政治献金の裏金を流用)。続いてフレデリックに送迎を頼みに行くと、は快く承諾してくれた。
彼らが使う公用車はライトバンだったので、フレデリックは聊いささか遠慮していた。が、今日行く予定の店では買った物をすぐ持って帰る予定はないし、一先ず移動さえできれば構わない。
「どこ行きたいの?」
「まずは楽器店にお願い」
「了解」
クララも連れて3人で向かった。
楽器店に入るとクララは目を輝かせる。それを見て好きなものを選んでいいというと遠慮していたが、フレデリックを待たせると悪いから、と言うとすぐに駆けだした。
「クララが何か弾くの?」
「クララも、よ」
「えーすごいなー」
感心するフレデリックに笑った。彼らはきっと、銃や仕事で使うもの以外はまともに扱ったこともないだろうし、音楽なんて讃美歌くらいの物なのだろう。
「音楽はいいわ。ミサ曲も好き」
「吸血鬼のくせに」
「演奏する人は敬虔な信者ではないし」
「あっなるほどね」
少しするとクララは黒いケースを持って笑顔で駆けてきた。
「お嬢様、これにします! お嬢様はお決まりになりましたか?」
というか最初から決めてきていたので、後は契約書を書くだけだ。シャルロッテの分も買う事にして、代金を先に支払い手続きを(勝手にフレデリック名義で)していると、フレデリックはクララの持つ黒いケースを指さしている。
「ねぇクララちゃんそれなに?」
「ヴァイオリンですよ」
「えっすごいね」
「お嬢様に教えてもらったんです。この程度のことできなきゃ淑女失格って」
「この程度!? 基礎レベル高けぇー」
「あはは、私もそう思います。でもお嬢様は大概の楽器は弾けますし、声楽もすごくお上手なんですよー」
「スゲェ、パーフェクトお嬢。ハイスペックお嬢」
「そりゃね」
手続きを済ませて振り返った。
「時間だけは沢山あったからねぇ」
「あー無職か」
「失礼な。働いたことあるもん。お父様も。でも面倒くさくなって辞めたわ」
「お貴族様め……」
そこはもう「貴族的働いたら負け症候群」だ。窃盗で食料も金も手に入る昨今(しかも今は貰える)、働く理由を探す方が無理と言う物だ。少なくともシャルロッテは、労働に対して生きがいを感じるタイプではない。何より人間の下で働くという状況は、屈辱以外の何物でもない。
一先ず楽器店での買い物を終えて車に乗り込んだ。クララは助手席で大事そうにケースを2つ抱えている。駐車場から出た後、バックミラー越しにフレデリックが尋ねた。
「次どこ行きたいの?」
「フレディは自分の車持ってないの?」
いつも通りに華麗に質問を無視し、自分の質問をぶつける。
「えっえぇ? えと、みんな持ってないけど。基本仕事以外で遠出する事無いし」
戸惑いながらも返答するフレデリック。いい加減彼らも慣れてきた。
「あそっか。車買うならどこがおススメ?」
「俺ならBMWがいいなー」
「じゃぁそこ行って」
そう言いつけると、運転中だというのにフレデリックが振り向いた。
「えっ車買うの!?」
「前見て」
「キャー!」
「うおぁ!」
思い切り対向車線にはみ出し、対向車は目と鼻の先だった。慌てて急ハンドルを切って何とか事故は回避できた。
「安全運転でBMWフィレンツェ支店までお願いしまーす」
「りょ、了解……」
「ビックリしました……」
前の座席の二人は何とか動悸を押さえて、それ以降は安全運転で目的地へ辿り着く事が出来た。
店内に入り、スタイリッシュに配置された車を見て回る。
「これがカッコいいわー」
黒い車を指さすと、フレデリックが目を剥いた。
「ちょっとそれ一番高い奴!」
高級車と名高い7シリーズの760Liだ。それを聞いて随伴していた店員に振り返る。
「じゃぁこれ頂けるかしら。オプションも付けてください。カラーは黒で」
「かしこまりました!」
店員はキャッホウと言わんばかりに、契約書を取りにその場を立ち去る。何故かフレデリックは顔を覆っていた。
「どしたの?」
「お嬢さ、もうちょっとこう、逡巡とかしよう?」
「なんで?」
「お嬢様のお買い物はいつもこうですよ」
フレデリックはそれ以上の発言を諦めた。契約書にサインしていると、後ろから覗き込んできた。
「なんで俺の名前……」
「さっきも使わせてもらったわよ」
「あそ……ていうか20万越えてるし!」
「そうね。じゃぁ一括で」
「かしこまりましたー!」
カードを受け取った店員はヒャッホウと走り去っていく。いよいよフレデリックは無言になった。
納車は1週間ほど先になりそうだ。城に戻るとすぐにフレデリックはその話をみんなに話して、男性陣は大盛り上がりしている。
「というかお前、余り無駄遣いするな」
とサイラスに怒られたが笑ってごまかした。
「いいじゃないですかぁ。いくらでも湧いて出るんだからぁ」
「湧くわけではないが……まぁいいか」
サイラスが諦めたところでアマデウスが口を挟んできた。
「ちょ、兄様甘やかしすぎ。怒る所だよそこは」
「ちゃんと叱ったぞ」
「全然叱ってないし、ロッテもういないしね!」
いつの間にやらシャルロッテは、その場から忽然と姿を消していた。
「いつものことだ」
父親だけに慣れているサイラスは、さっさと諦めて雑誌に視線を移した。
シャルロッテは周りをあっさり放置して、買ったヴァイオリンを抱えてクララと共に階段を上った。部屋に入るとすぐにクララはケースを開けて、シャルロッテの好みを考慮したのか、バロック・ヴァイオリンを引っ張り出す。
「お嬢様、一緒に弾きましょうよ!」
「折角イタリアにいるんだし、ヴィヴァルディがいいわねー」
うきうきと瞳を輝かせるクララに笑ってヴァイオリンを受け取り、二人で弾きはじめる。バロック・ヴァイオリンの純粋で素朴な音色は、イタリアの乾燥した空気の中に倍音を響かせ、得も言われぬ和音を生み出す。
ヴィヴァルディの「四季」より「冬」。動きの速い音型とフォルテで「冷たく恐ろしい風」を表現した、これぞまさしく冬、と言う曲だ。一先ず第一楽章を弾き終ると、ぷは、とクララが息を吐いた。
「自分で弾いといて鳥肌が立ちました!」
「あははは!」
久しぶりに一緒に弾いた上に、曲調が早く強い曲だったので緊張したようだ。
そうして何曲か弾いていると、途中でふと気づいた。弾きながらちらりとドアを見やると、クララが視線に気付き頷いた。クララが弾きながらドアに近づき、ドア前で演奏を止めて一息にドアノブを回し開けると、一気に男性陣が流れ込んできた。
「普通に入ってくればいいのに」
将棋倒しになった大の男達がイテテ、踏むなバカと言いながら起き上ってくる。その中にはなぜかサイラスもいた。
「お父様まで何やってるんですか」
「いや、なんだか……つられた」
まぁいいやと首を振って部屋に招き入れて、一応リクエストを尋ねてみる。
「G線上のアリア!」
「ヴォカリーズ!」
「ラ・カンパネラ!」
「コン・テ・パルティロ!」
レオナートのリクエストには全員で振り返った。
「伴奏はいいけど誰が歌うんだよ?」
クリストフの当然の疑問にレオナートはケロリと答える。
「課長」
「なんでだよ!」
「ウマイじゃん」
「ぜってーヤダ! 旦那お願いします」
「……嫌だ。小僧がやれ」
と言うやり取りをやっている間に、待ちくたびれたシャルロッテとクララはさっさと演奏を始めた。まずは最初のリクエスト、バッハの「G線上のアリア」だ。他は置いておくとして、リクエストしたイザイアはきちんと聞いてくれている。が、シャルロッテ的には納得いかない。弾き終って口を尖らせた。
「物足りない! 早くチェロ届かないかしら!」
「えっチェロも買ったの?」
「うん、お父様にやらせようと思って」
まんまと巻き込まれるサイラス。
次のリクエストは、ラフマニノフの「ヴォカリーズ」だ。音域からして、シャルロッテが歌う事になった(弾きながら)。
ヴォカリーズとは歌詞を伴わず母音によって奏でられる歌唱法の事だ。溜め息のような旋律と、淡々と和音と対旋律とを奏でていく伴奏が印象的で、繊細で切なげで甘い旋律は、発表当時から人々に人気を博してきた、ラフマニノフがソプラノ歌手に贈った曲だ。
歌い終わると拍手を戴けたが、やはり物足りない。
「早くピアノ届かないかしらー」
「ピアノも買ったのかよ!」
むしろそっちがお目当てだ。
アドルフが呆れ顔をしてシャルロッテを指さし、サイラスに振り向く。
「お宅のお嬢さん、ものすごく浪費癖があるみたいなんスけど」
「今に始まったことではないからな、構わんだろう。どうせロッテは私の言う事など聞きはしないし……」
拗ねるサイラスを見て、アドルフは初めて同情的な気分になった。
そうこうしていると「コン・テ・パルティロ」の順番が回ってきた。
「で、アディが歌うの?」
「誰が歌うか」
断固拒否の模様だ。
「聞きたい、歌って」
「断る」
「ねー歌って歌って」
「嫌だ」
「ねぇお願い、チューしてあげるから」
「それは殺害予告か」
「あらよくわかったわねー、アディは賢いわねー」
「絶対歌わん!」
予想していた通り、へそを曲げてしまった。
本当素直な子ねー。ひねくれ方まで素直なんだから。
そう考えてご機嫌取りに回ることにした。
「わかった、じゃぁ私がサラ・ブライトマンやるから」
「Time to say goodbyeじゃ許さん」
「わかってるよー私も英訳嫌いだもん。あれはボチェッリに対する冒涜だわ」
「だよな!」
ご機嫌取りには一応成功したが、結局アドルフは歌わなかった。
--------------------------------------------------------------------------------
それから数日経って、ピアノと車が届いた。嬉々としてピアノを空き部屋に運び、そこは楽器を持ちこんで音楽室とした。シャルロッテが弾くピアノに合せて、クララのヴァイオリンが響く。少し遠くに霞んで聞こえるそれに耳を傾けて、アマデウスが笑って言った。
「お前は女の扱いは上手いのに、ロッテにはいつも遊ばれているね」
言われてアドルフは少し不貞腐れた。
「私はロッテを女だとは思っておりませんので」
その返答にアマデウスは苦笑して、そうだろうねと笑った。そしてアドルフを始め、“死刑執行人”全員に視線をやった。
「アディはまだいいんだけどね、お前達」
少しだけ強い口調と、すえたような視線。腹に一物も二物も抱えている、そう言った視線を向けるアマデウスには慣れた“死刑執行人”達も、俄かに構えてしまう。
「兄様たちに騙されないようにね。クララはまだいいけど、特にロッテが危険だよ。ああいう手合いは、扱いに困る」
騙されないように、何となく言いたいことはわかる。ピアノと共に届いた車、それは誕生日が近くて送迎をしてもらったフレデリックに贈られた。勿論、車をあげたんだから出かける時は送迎してくれと言う打算も含まれているが、フレデリックは遠慮しながらも大いに喜んだし、贈ったシャルロッテは「脚」以外の何も要求しなかった。
そう言った出来事は今後も起きるのだろう。そうして警戒を解き、懐柔していく。その程度の計略性は図りえた。
「お前達もわかっているだろうけどね、お前達と兄様たちはあくまで敵だ。それを忘れないように」
下手に信頼関係を築いてしまって、いざ有事の際に傷つくのは彼らの方。さすがにこの場では薄笑いも消失してしまったクリストフが口を開いた。
「確かにそうでしょうが、お嬢はともかくクララにはそう言った打算は見受けられません」
「そうだね、どうもクララは世間知らずみたいだ」
想像はつく。シャルロッテがクララを外界から隔離して教育していたのだろう。人間と言う下らなく穢れた者に、綺麗なクララを汚染されてしまわないように。
「まぁクララはいいよ現状維持で。でもロッテには気を付けろよ。彼女は常に警戒しているし、お前達の言葉の端々から情報を拾って、付け入る隙を狙ってる。攻撃を受けると警戒するだけならまだいい、兄様たちの方が攻撃してこないという保証は、全くないのだから」
そこはまるで牧場だった。一見牧歌的なその風景、牧場主が牛や馬を愛情を込めて育てる。そして時が満ちると牧場主は祈りを捧げるのだ。
我らに授けられた糧に感謝します。アーメン。
そうして牧場主は手塩にかけて育てた家畜を殺していくのだ。
「同じ事だよ、吸血鬼から見た人間なんてね」
悔しそうな、悲しそうな、若い聖職者たちを見てアマデウスは笑う。
「そんな顔をしてもダメだよ、お前達は肉屋に並ぶ肉を見て、憐れだと嘆く? 人間だけが特別だと思ってる、その独善的で偽善的な思考は、僕達みたいな吸血鬼は共通して嫌悪してる。僕達にしてみれば、人を殺すことは罪じゃない」
腹が減ったから飯を食う。ただそれだけのこと。
「わかる? 愛情を注ごうが、どれだけ仲良くしようが、殺そうと思えばいつでも殺せるんだよお前達を。彼らがそう言う生き物だという事を、忘れてはいけないよ。彼女たちと友達になれるなんて、夢にも思うんじゃないよ」
難しい顔をする部下たちにそれだけ言って立ち上がったアマデウスは、部屋から出る前にふと足を止め、アドルフに手紙を渡した。教皇庁に行った時に手渡された、アドルフ宛の手紙だった。それを受け取って、アドルフたちも部屋に戻った。
シャルロッテが警戒していることはわかっていた。用事がなければ人前に出てくることはまずない。いつも部屋か音楽室に閉じこもっている。だけど人前でのシャルロッテはいつも笑顔を絶やさずに、明るく親切にふるまっていて、アドルフもいつもくだらない喧嘩をして笑っていたりしたから、忘れかけていた。
用事がなければ会わなくてもいい、わざわざ話しかける必要性がない。少なくともシャルロッテにとって、彼らはその価値のある者達ではないのだ。
くそ、腹立つな。
そう思いながら階段を上っていくと、階段を下りてくるシャルロッテとクララに遭遇した。アマデウスから預かった手紙をポケットに押し込んでシャルロッテを見ると、シャルロッテはいつも通り優しく笑う。
「どうしたのみんなして?」
「別にどうもしねぇ」
「そう」
「お前は?」
「別に、お腹が空いただけ」
そう言うとシャルロッテはニッコリと笑って、そのまま階段を下りて行った。それを見届けていると、クリストフが言った。
「猊下の話を聞いた後だと、あの悩殺スマイルも含み笑いに見えてきた」
フン、と息を吐いて吐き捨てるように言った。
「見えるも何も、実際そうなんだろ。テメーらがあの女に騙され過ぎなんだよ」
昨日の事だ、思い出しても腹が立つ。
シャルロッテがピアノを弾いていた。愛の夢―3つのノクターン―。元はソプラノのための独唱歌曲として書かれた作品だ。シャルロッテが弾いている、第3番変イ長調「おお、愛しうる限り愛せ」は、長く人々に愛される名作の一つ。
ピアノを弾きながら、アドルフに言った。
「詩を知ってる?」
「いや」
シャルロッテは少し笑って、「 O lieb, so lang du lieben kannst!」と言った。
「恋の歌か?」
「ううん、ここで言う愛は人間愛の事」
ピアノを弾きながら詩の内容を語った。
「あなたがお墓の前で嘆き悲しむその時は来る。だから、愛しうる限り愛しなさい。自分に心を開く者がいれば、その者の為に尽くし、どんな時も悲しませてはならない。そして口のきき方に気をつけなさい、悪い言葉はすぐに口から出てしまう。『神よ、それは誤解なのです!』と言っても、その者は嘆いて立ち去ってしまうだろう」
嫌味だな、と思った。
続けてシャルロッテが言った。
「では心を開かない人には、どうしたらいいんだろうね? こちらが開きたくても閉ざされていたら、勝手にドアノブに手をかけて開けてしまってもいいのかしら?」
ねぇアディ、あなたに言ってるのよ。という顔をしていた。
「俺だったら勝手に踏み込まれたらマジギレすっけどな」
「そう? 私はアディなら勝手に入って来ても許すわよ」
鼻で笑った。
「なんだお前、誘ってんのか?」
挑発すると、シャルロッテも挑発的に見上げた。
「そうだと言ったら?」
そんな返答が返ってくるとは思わなかったので、少し面食らった。が、恐らくからかっているのだろうと考えて、溜息を吐いた。
「だとしても断固拒否。吸血鬼に手出すほど飢えてねぇよ」
「そう? 残念ねー。私のような美人も、珍しい種族もなかなかいないのに。自慢になるわよ。まぁ、よっぽどの覚悟がなければ無理だけど」
最後の一言が少し気になって尋ねると、シャルロッテはアドルフの手を引いて、隣に座らせた。そしてアドルフの頬を撫でながら笑う。
「私とキスをするという事は、その人の運命が変わるという事よ。死ぬこともあるし、吸血鬼になることもあれば、それ以外の何かになることもある。体には何もなくても、その人の運命が変わることもね」
あなたにその覚悟はないわよね、とでも言いたげな視線だった。
「ふぅん、少なくともお前に運命なんか変えてほしくねぇな」
髪にまで触れていた手を払うと、笑ったシャルロッテは全く気にしていないようで、軽くピアノを撫でている。そしてもう一度アドルフを見上げた。
「バカね、運命を変えるのは私じゃないわ。運命を操るのはいつだって、あなたの意志による選択よ」
そう言ったシャルロッテが、眩しいほどの笑顔を向けて言った。
「アディはきっといつか、私にキスをねだる日が来るわ。あなたが秘密にしている悲願を達成するために、どうしようもない弊害が発生したときに、思い出すのはきっと私の顔よ」
思わず立ち上がって距離を取った。
心臓がけたたましく動悸し、流れた冷や汗が背筋をなぞった。
なぜ。
狼狽するアドルフに、相変わらずシャルロッテは微笑んでいる。クスッと笑ったシャルロッテはピアノに視線を戻し、再び奏で始める。もう用事は済んだから、さっさと出て行きなさいとでも言うようだった。
クソ、何故。アイツは一体どうして。
それは悟られてはいけないことだった。誰にも知られてはいけないことだった。誰も知らないはずだった。それなのにシャルロッテには見透かされていた。
やっぱりあの女、ただモンじゃねぇな。クソ。
そのことを思い出すといよいよ腹立たしくなり、舌打ちをして部屋に戻った。
6 主よ、人の望みの喜びよ
Erbarme dich, mein Gott, 憐れみたまえ、我が神よ!
un meiner Zähren willen ! 我が涙ゆえに、
Schaue hier 私をご覧ください。
Herz und Auge weint vor dir bitterlich. 心も目もあなたの御前に泣き濡れている。
J・S・バッハのマタイ受難曲は、新約聖書「マタイによる福音書」の26、27章のキリストの受難を題材にした受難曲で、シャルロッテが愛してやまない宗教曲の一つでもある。吸血鬼のくせに――――だが、曲に罪はない。美しいものは美しい(聞いているクララは悶えているが!)。
マタイ受難曲Matthäus-Passion――――39番のアリアは、ペテロの否認の後に歌われるアリア。にわとりが鳴いて「3度の裏切り」というイエスの預言の言葉を思い出したペテロは、罪の意識に泣き出す。有名な「憐れみ給え、わが神よ」(Erbarme dich)のアリアが歌われる。
そんな曲を歌うのはクララへのイタズラではなく、無理やり引っ張ってきたアドルフの為に。
「落ち着いた?」
「うるせぇ」
少し目が潤んでいたが、流石に涙は枯れたようだった。
アドルフは部屋にいた。アマデウスから預かった手紙を握りしめ、一人悲壮に打ちひしがれていた。そのタイミングでシャルロッテがやってきて、良いとも言っていないのに勝手に部屋に入ってきた。椅子に腰かけたまま憮然として追い払おうとしたアドルフに、シャルロッテはアドルフの頭を寄せて緩やかに抱きしめ、静かに言った。
「いいのよ」
今だけは泣くことを許してあげるから、と言っている気がした。
シャルロッテの前でそんな醜態をさらすことは酷く屈辱に感じたし、事情も何も知らないシャルロッテが、何を考えているのかもわからなかった。だけどその時のアドルフはどうしたらいいかが分からずに、自分の感情に逆らう事をしなかった。
クララを追い出して、アドルフに尋ねた。
「恋人だったの?」
アドルフは憮然として「違うけど」と言った。
「アレクが言ってたわ」
「何を」
「アディの女遊びが激しくなったのは、突然だったって。それと、それが始まったのが2年くらい前だったとも」
それを聞いてアドルフは心の中で舌打ちをする。
くそ、あのバカ余計な事言いやがって。
それを見てシャルロッテは、本当に素直だと少し可笑しく思いながら笑った。
「彼女を思うなら、やめた方がいいわ。不毛よ」
「……うるせぇな」
「こんな詩を知っているかしら」
ある夜、二度とは見られないユダヤ女の傍らで、
死骸に添って横たわる死骸の様になっていたとき
この売られた肉体のそばでふと思い浮かべたのは
わが欲望の届かない悲しい美しい人の事だった。
詩を聞いたアドルフは、またしても憮然とする。
「知らん」
「ボードレールよ。代償行為は、悲しいじゃない? あなた顔はいいんだから、素敵な男になりなさいよ」
彼女も同じことを、手紙に書いていた。
「アディを泣かせるなんて、彼女は素敵な人だわ。愛してたの?」
「……違う、と思うけど。わからん」
「でも大事に思ってたのね。それは――――」続けたシャルロッテの言葉に、アドルフは心臓を掴まれたような心持がした。「アディが彼女に、母親の影を重ねていたのね」
敵わない、と思った。
「なんで、知ってる?」
「みんなの話を色々と総合すると、そう言う事になるわ」
幼い頃の事、ヴァチカンに来る前の事を覚えている者もいれば、忘れている者もいる。アドルフは覚えているはずだと、オリヴァーが言っていた。クララがシャルロッテとの出会いの話をした時、「クララ“も”苦労したんだな」と、同じく覚えているであろうクリストフが言った。
アドルフが拠り所にするのはいつも女。彼女は年上の女性で、優しかった――――母親のように。その温もりと穏やかな時間を求めていた。
「彼女と出会ったのはいつ?」
「2年前」
「別れたのは?」
「1か月後」
「純粋ねアディは。ずっと忘れられなかったのね」
そう言うとアドルフはバカにされたと思ったのか睨みつけてくる。それに微笑んだ。
「これからも忘れないでいるといいわ。彼女の事も、アディの気持ちも。今のアディはとても、美しいから」
アドルフは視線を外して、「わかってる」といって部屋を出て行った。少しするとクララが戻ってきて、何の話だったのかと尋ねた。
「アディに手紙が来たのよ、昔愛した女性から」
「へぇ? でもなんでお嬢様がそんなこと知ってるんですか?」
「さっきすれ違った時、ポケットにしまってたから。消印が古いものだったから気になって、影に隠れて覗き見したのよ」
「マジでございますか」
「マジよ。アディには内緒ね」
クララは引いているようだが、手紙の内容を思い出して微笑んだ。
「素敵な手紙だったわ、とても。今度は彼女が、アディの天使になったのね」
綺麗な字で書かれた数枚の手紙は、「親愛なるアディ」その冒頭を汚さない、美しいものだった。
親愛なるアディ
この手紙が届いているという事は、きっと私はもうこの世にはいないのね。私ね、本当はずっと肺結核を患っていたの。女優をやめたのも、そのせい。一人になったのも、そのせい。あの人も会ってくれなくなって、私はとっても淋しかったわ。
だけど、あなたと出会えて本当に良かった。短い間だったけど、素敵な思い出ができたわ。本当にありがとう。
私はあなたと出会って、あなたと過ごす日々がとても楽しかった。毎日毎日あなたが来るのを待って、バカみたいだけど、まるで少女の頃に帰ったみたいな気分で。
あなたに出会うまで、私はもう死ぬのを待つばかりだと思って、自棄になって色々なことを諦めていたの。生きることも自分のことでさえもどうでもよくなって、どうにでもなってしまえばいいと思っていた。
だけど、あなたと出会って、私の生活は彩りを取り戻したような気がして、息を吹き返したのよ。いつの間にか、あなたが私の心の支えになっていたわ。アディ、あなたは私にとっては本物の天使だったのよ。
私は死んでしまうけど、アディは私の魂を天国に導いてくれるわ。私は幸せだったもの。あなたと過ごしたあの短い日々を、夏の夜を、宝物のように愛しく思うわ。
私、幸せだったのよ。とっても楽しかったわ。あなたと出会って、色々なことを話して、聞いて、何度も助けてもらったし、名前も呼んでもらえた。私はあの時泣きたいくらい嬉しかったわ。だから、私が死んだと思って悲しまないで頂戴ね。あなたは何も悪くないわ。あなたと出会えて私は幸せだったんだもの。むしろ、誇らしく思ってもらわなきゃ困るわ。
何と言っても私は大物元老院議員の愛人で元女優なのよ。その私が幸せだと言っているんだもの、名誉でしょう? あなたに今後私以上にプレミア感のある女性が現れるかしら? なかなかいないと思うわよ。
これからあなたが「わからない」と言っていたことが分かるようになった時、少しだけ私の事を思い出してくれたら嬉しいわ。
あなたが最後にくれた思い出は、この病んだ胸に大事にしまっておくわ。そしてお墓の中で私の体と共に滅びるのよ。あなたの思い出を抱いて死ねるなら、こんなに幸せなことはないわ。
あなたの綺麗な声、あなたの綺麗な指、あなたの綺麗な髪、あなたの綺麗な顔、あなたの綺麗な体、全部、忘れないわ。だから、どうかあなたも私を忘れないでいてね。
これからのあなたの長い人生の中で、「そういえばあんな人がいた」と思い出してくれたら、私は天国から手を振ってあなたの名前を呼ぶわ。だから、あなたは私の声が聞こえたら、空を見上げて、私の名前を呼んでね。きっとお返事をするから。約束よ。
アディ、男を磨きなさい。あなたはハンサムで素敵だし、きっと素敵な女性に巡り合えるわ。きっと、色んなことが分かるようになるわ。
私は後悔していることが一つだけあるの。愛人なんて早めに手を切って、誰かと幸せに結婚するべきだったって。私が見たもので美しいと思ったものは2つ。子供を間に挟んで笑いあう夫婦と、仲良く腕を組んで歩く老いた夫婦。その道を選ばなかったことを、何度も後悔したわ。あなたは神父だから、一生独身ね。だけど、あなたにはいつかそういう美しい光景の一部になってほしいわ。
あなたがいつか神父をやめて、素敵な女性と結婚して幸せになったら、とても嬉しいわ。私はきっと自分の事のように喜ぶの。
あなたの身に幸福が降り注ぐように、天国から祈っているわ。私の天使が、幸せになりますように。
アディへ、愛を込めて
カテリーナ・クヴァント
姿を消した恋人、知らぬ内に死んでしまっていた恋人から、時を経て届いた手紙。彼女の言葉を、その遺言を、彼女を思うなら聞いてあげて欲しいと思うのだ。
「アディはその人の事、ずっと忘れられなかったんですか?」
「そうみたいね」
「純愛、ですね」
「そうね」
そう言って笑うと、少し悲しげにしたクララが遠慮がちに尋ねた。
「お嬢様も、誰かを愛したいですか?」
その問いに笑って、自分の指先を眺める。
冬が好きだった。
わ、ロッテの手すごく冷たい。
そう言って繋いだ手をコートのポケットに入れた。
こうすれば温かいよ。
そう言った屈託のない笑顔が好きだった。
俺冬好きだなー。手ぇ繋ぐとロッテ嬉しそうにするから。
そんな冬はもう、来ない。
「ううん、もう、いらないわ。忘れてしまったし」
忘れてしまいたいし、人間は裏切るから。 人間は美しい。人を欺き、慈しみ、裏切り、愛する。これほどの感情を持ちえたのはおそらく人間くらいで、それは限られた生だからこそなのだろうと思う。それらが徹底して不完全であることもまた、羨ましくすら思う。器用だと思う。
が、今のシャルロッテにはどうでもよい事だ。かぶりを振ってクララに視線を戻した。
さりげなくクリストフに探りを入れるように、日頃からクリストフと懇意にしておくよう命令していた。
クリストフが一番仲がいいのはやはりアドルフで、一番信頼しているのも以下同文。子供の頃彼には兄がいて、その兄にアドルフが良く似ていた。傍若無人で横暴で、しょっちゅうおもちゃを取り合いして泣かされたが、クリストフが別の子に泣かされていると助けてくれた。アドルフは今でもそう言うところは変わらないのだと、クリストフは嬉しそうに言った。
「それ聞いちゃうと、アディとクリスってなんかいいですよね」
「ていうかアディ、男の前ではカッコつけるのね。変な奴」
とはいえ、男に好かれる男と言うのは、女にモテる男よりもはるかにいい男だ。少し眉を下げてクララが言った。
「クリスはアディ大好きなんだなぁとヒシヒシと伝わってきましたよ。なんかアディを見る目が変わってしまいそうな話ばかりで、ちょっと癪です」
とクララが苦笑するので、つられて笑った。
「そうね、でも理に適ってるわよ。大体、年長二人は思った通りだわ。怪しいのはディオ達くらいからね」
「えっなにがですか?」
意味が分からない、と首を傾げるクララに、少し声を潜めて教えてあげた。
「予想だけどね、“死刑執行人”達は全員孤児よ」
「あっそれはなんとなく」つられてクララも小声で返した。
「で、孤児になったのは、彼らの家族が皆殺しにされているから」
途端にクララは離れて目を丸くした。その表情に笑った。
「まだ予測で証拠はないけど、恐らく正解。それ程引き摺っているところを見ると、アディもクリスも、目の前で家族を殺害されたんでしょ。情報は大方揃ったから、明日証拠を探してくるわ」
クララは泣きそうな顔をしていた。縋るようにシャルロッテの服の裾を掴んで見上げている。
「本当、ですか?」
彼らの家族の話は真実なのか、と言う意味に解釈して頷いた。
「オリヴァーや覚えていない子には、この環境もさして問題はなかった。だけど覚えている子にはどうだったのかしら。真実を知ったら彼ら、どうするのかしら」
「可哀想です。知らない方がいいことだってあります」
「わかってるわよ、わざわざ教えたりはしないわ」
――――私は、ね。
シャルロッテの答えを聞いて、クララは幾分か安心したようだ。ふと何かを思い立ったような顔をした。
「それともう一つ、やっぱりお嬢様の言うとおりでした。クリスの本当の名前は、ロベルトと言うのだそうです」
やっぱりね、と笑った。事情を考えると、ヴァチカンに来た時点で改名している可能性が高いと考えていた。今名乗っている名前はアマデウスが考えたか、洗礼名か何かだ。自分の本名を覚えているのは、年長組二人と二つ下のクラウディオ達までだろう。フレデリックから下は2歳前後だったことを考えると、覚えていない可能性が高い。
「子供の頃の事を覚えている子たちに、優しくしてあげてね。クララに優しくされたらみんな喜ぶから」
我ながらつまらないことを言う物だと思ったが、聞いたクララは瞳に義務感に似た物を宿して、深く頷いた。
元舞台女優アンジェラ・インザーギ。本名カテリーナ・クヴァント。享年37歳。死因は重度の肺結核。かねてより元老院議員の愛人であると噂されていたが、突然女優職を辞して芸能界を引退。議員がヴァチカンの別荘を貸し与え、日中は医師を付き添わせ療養していた。が、容体は悪化の一途をたどり、彼女の希望により故郷であるトリノの病院に入院、その後容体が急変し重度の発作を起こし死亡。
2年前の晩秋、芸能欄に大きく載った彼女の写真は、生き生きと躍動する女優としての顔で、年増だったが美しい人だった。この訃報がもたらされた時、新聞もテレビも、街中でも彼女の演技が流されていただろう。それを見て、アドルフは自分を責めただろうか。
カテリーナの手紙からヒントを得て、更に新聞をさかのぼる。21年前の記事。
x月x日、ミラノ郊外の一軒家で2名の遺体を発見。この家に住むドイツ系移民アダム・フルトヴェングラーと、その妻カタリーナと思われる。二人の遺体には複数の銃創があり、強盗殺人事件とした。尚、一人息子が行方不明となっている。
x月x日、ボーデン湖より3人の遺体が乗った車を発見。腐敗していたが所持品等により、行方不明とされていたビューロウ一家と判明。が、もう一人の息子ロベルトの遺体が発見されておらず、依然行方不明。
ある程度予想はしていた。イタリアのみならず、フランス、ドイツ、スイス、4国間で発生した事件。昔からイタリアにはマフィアの問題が根強く、今も尚フランスなどで人が突然失踪する事件が発生している。アドルフの目的の一つは確実に、そのマフィアを見つけだし復讐を果たすこと。
ヴァチカンの情報力を使えば、恐らく仇の目星はついている。それでも未だに動き出さないのは――――。
――――状況や時期が悪いのかしら。それとも?
考えたが、余りにも退屈な考察になってしまいそうで打ち消し、ミュンヘンの図書館の隅っこから静かに姿を消した。
その調査内容を携えてサイラスの部屋に行った。
「――――と言う訳なんですお父様。私も話したんだから、そろそろ叔父様の目的を話してください」
この城で同居する事情、アマデウスの目的にサイラスも協力するという形で同居を許可している。それが何なのかシャルロッテには内緒にされていたのだ。
しつこく強請ると、ようやくサイラスは教えてくれた。
アマデウスはノスフェラートの一族。ノスフェラートには2種類の種族があり、アマデウスたちは「地上の者」で、もう一種は「地下の者」と呼ばれる。「地上の者」は「地下の者」から抱擁を受け吸血鬼化した者で、その姿を認識できるのは霊力や魔力を持つ者に限られ、また繁殖する事も出来ない。そして「地下の者」は、この世の物とは思えない醜い相貌をしており、その為に地下に住むことが昔からの倣いだが、彼らは抱擁によっても性交渉によっても繁殖することが出来、また、常に追われる身である。
ノスフェラートの一族「地上の者」は常に「地下の者」、自分を吸血鬼にした者を憎み、打ち倒そうとその執念に駆られ、「地下の者」は「地上の者」から逃げ続けなければならない。それはノスフェラートが誕生した時に、ノスフェラートをノスフェラートたらしめた者を殺害したことにより受けた、解ける事のない呪いなのだ。
アマデウスは幸か不幸か、ヴァチカンと言う後ろ盾を得た。それはどこにいるよりも確実にノスフェラートの足取りを掴める。その為には余計な仕事もしなければならなかったが、アマデウスの悲願を達成するために一番の近道であったことは間違いない。
「なるほど。では叔父様の目標はあくまでも、「地下の者」達の抹殺なのですね」
「そうだ。その目標を達成できぬうちに、私達に攻撃を仕掛ける事はあり得ない。下手に戦力を削いでしまっては元も子もないからな」
「確かにそうですね。少なくとも現時点で、叔父様が私達に攻撃を仕掛ける事は、デメリット以外の何物でもありませんね。それに叔父様から攻撃を受ける義理もありませんし」
「そうだ。まぁ殺した云々ではお互い様だがな」
意味が分からず首を傾げると、昔を思い出したらしいサイラスが苦笑した。
サイラスが吸血鬼の真祖になった時、彼は断頭台に固定されていた。アマデウスの所業と、何度祈っても助けてくれなかった神、この世界を呪い魔に身を窶した。処刑された瞬間に吸血鬼として覚醒し、真っ先に殺害したのが処刑した本人であるアマデウスだった。皮肉にもその為にアマデウスは、吸血鬼としての蘇生を果たしたのだ。その点においては多少の恨みはあるだろう、との事だ。
なるほどお互い様だ、と納得した。ついでに尋ねてみた。
「お父様は叔父様を殺したいですか?」
その質問にサイラスは溜息を吐いた。
「別に、どうでもいい」
本当にどうでも良さそうにそう言うので、思わず失笑した。
もう一つ耳に入れたいことがあると、ドアの方にチラリと視線をやってサイラスに耳打ちをした。それを聞いたサイラスは愉悦に顔を歪める。
「お前は嫌な女に育ったな?」
サイラスの嫌味に笑った。
「仕方がありませんよ、お父様に似たんですもの」
サイラスはその返答に苦笑していたが、ふと顎を撫でて憂いのある顔を浮かべた。
「私に拒否する権利があるかはわからないし、言えた義理ではないのだが、父親としてはいい気分ではないな。お前は本当に、それでいいのか? クララが悲しむぞ?」
サイラスの無駄演技に笑いを堪えて言った。
「ええ勿論。だって私、アディを愛してますから」
そう言って笑うと、サイラスも堪らず大笑いした。
7 アダージェット
アドルフはとにかく、イラついていた。
「お嬢様ご覧ください! 本日は薩摩切子のグラスをお持ちしました!」
「わぁ、クララ気が利くわね。綺麗なグラスは血が一層おいしく感じるわー」
クララとシャルロッテのピクニックに、死刑執行人総出で付き合わされる――――in 戦場。
「みんなが戦ってる姿を見て見たいわー」
と暢気にシャルロッテが言って、勿論全員で大反対したが、いつの間にか車に潜り込んでいた。途中で降ろしてやろうかとも思ったが、そうするとサイラスに怒られそうだったので渋々連れて来たのだ。
シャルロッテはちゃっかりビニールシートや茶器の入ったバスケットを持っているし、クララも血の入ったクーラーボックスを手にしたピクニック仕様だ。お出かけだからとしっかり二人ともおめかししている。
これから戦場に赴くという極度の緊張感を挫かれた死刑執行人たちは、顔を覆って項垂れるしかなかった。
戦場は山間部の既に廃坑となった坑道。そこにノスフェラートの「地下の者」が数名生活をしているとの通報を受けて、やってきた次第だ。
敵が化け物の場合、人間である彼らは物量を投じたとて勝率は低い。だから隠れて近づき、結界を張って動きを抑え込み、そこに攻撃を畳み掛けると言うのがいつもの戦闘スタイルだ。
一見卑怯のように感じるが、闘争において卑怯とは賛辞。アドルフ曰く、「他人の嫌がることをする、それこそが戦闘の極意!」だそうだ。
坑道の出入り口は4つ。内3つは侵入と同時に発破をかけて潰してある。残り1か所から一塊になって進み、見つけたノスフェラートを一人ずつ全員で射殺していく。敵が圧倒的に強くても、一人を数名で徹底的に潰すというスタイルは、戦闘においては常套かつ有効な手段だ。が、彼らに勝手についてきたシャルロッテ達に(しかもイザイアが2人の乗るトロッコを押す羽目になった)初っ端からペースを乱され、現在苦戦中である。
「テメーらもう帰れ!」
全員の心の声を代弁してアドルフが怒鳴りつけるも、「やぁよ」と素気無く断られる。ノスフェラート達も一応武装していたのか、直接攻撃を仕掛けて来るよりも銃で応戦してくる。死刑執行人たちは物陰に隠れて何とかやり過ごしているが、坑道のど真ん中でシャルロッテとクララは、銃弾の飛び交う中マッド・ティーパーティだ。
「あぁもう! ただでさえアイツに関わりたくねぇのに!」
歯噛みするアドルフの隣で、クリストフがマガジンを再装填しながら尋ねた。
「あー例の件? 恥ずかしいんだー?」
「うるせーよ!」
例の件とは手紙の件だ。クリストフだけには話した。勿論それもあるのだが気になるのはそれとは別件だ。
「あっちの影に一人隠れてるわよー」
「うるっせぇな!」
秘跡を受けた、鏡に映らないタイプの化け物でも映るグラスの映像を頼りに、物陰から腕だけ出して発砲する。が、レオナートが改造してくれた大口径のマシンピストル「Cz75 SP-00Custom “PHANTOM”」から放たれた銃弾は、敵の耳を削いだだけだった。
「ウソ!」
「うわ、課長が外した」
「珍しっ。どした」
敵が敵だけに一撃必殺がモットーだったのに、リーダーのアドルフが外してしまうという失態に、周りにも動揺が広がってしまった。
「うるせーなもう! たまたまだろ! テメーら気合入れろ! バカ女たちに惑わされんな!」
発破をかけると「ハイハイ」と周りは返事をしたが、クリストフだけが隣で、「それはお前だろ」と冷静にツッコんできた。
あぁもうやだ。帰りてぇー。
職務放棄したくなったアドルフを悩ませるのは、シャルロッテ。
数日前、手紙の件でシャルロッテと話したあと部屋を出たアドルフは、途中でクリストフに遭遇した。アドルフの様子がいつもと違う事に気が付いて、心配そうにしていた。アドルフを心配するのはクリストフくらいだ。彼がいつも虚勢を張って、普段から一人で何でもできてしまうから、みんながアドルフを心配することはないし、またアドルフも心配されることは嫌いだ。だから、クリストフだけは心を許せる唯一の存在で、いつもなら「なんでもねーよ」と黙る所なのだが、色々と考えるところもあって話してしまう事にした。
クリストフもカテリーナの存在は知らなかったので驚いていたが、「そうか」と少し切なげに笑った。
「よかったな、お嬢優しくて」
耳を疑った。
「優しい? どこが? スゲェ嫌味だろ」
「えっなにが?」今度はクリストフが同じリアクションをした。
シャルロッテの前で泣いたのは、自分でも失敗だったと思う。でも、その後話して少し落ち着いたし、その点に関しては感謝してやってもいいと思った。日頃の恨みはかき捨て、それなりに分別はあるのだが、アドルフが腹を立てたのは。
「あのよ、カテリーナさんの話聞いてさ、普通の感覚ならレクイエムとか歌わねぇか?」
問題は選曲だ。シャルロッテが歌ったのは、バッハの「マタイ受難曲39番」。ここはモーツァルトの「レクイエム ラクリモーサ」の方がカテリーナを追悼するには相応しいというのにだ。
確かにな、と唸るクリストフも当然聖職者なので「マタイ受難曲」の歌詞は知っている。
Erbarme dich, mein Gott,
憐れみたまえ、我が神よ!
un meiner Zähren willen !
我が涙ゆえに、
Schaue hier
私をご覧ください。
Herz und Auge weint vor dir bitterlich.
心も目もあなたの御前に泣き濡れている。
ペテロの否認の後に歌われるこのアリア。キリストが捕縛された後、「お前はキリストの従者ではなかったか」と詰問されたペテロは、保身の為に「そんな人は知らない」とウソを吐く。その裏切りを見越していたキリストの言葉を思い出し、罪悪の為に涙するペテロを謳ったアリアだ。
保身の為にキリストを裏切った憐れなペテロを、彼は可哀想な男だから憐れんでやってくれ、神よ。そう言う歌だ。
シャルロッテがこの歌を歌ったのは、カテリーナがヴァチカンを去って数か月後、彼女の訃報を聞いて、彼女が死んだのは自分のせいだと自責の念に駆られたアドルフが、自棄になって彼女を忘れようと、他の女で紛らわしていた愚行を責めていた。
彼女を真に思うならその死を悼み、彼女の死とアドルフの愛と、その為に抱えた悲しみと罪悪を素直に受け止めるべきだった。シャルロッテは、アドルフがそれらから逃避した弱さを糾弾したのだ。
アドルフがバカをやった、その心の弱さを憐れんでやってくれ、カテリーナ。「マタイ受難曲39番」の歌の通りに。
「な? 嫌味だろ?」
同意を求めるアドルフに、クリストフは苦笑した。
「確かにな。でもお前はお嬢が正しいと思ったから、俺に話そうと思ったんだろ。やっと彼女を思い出にする気になって、俺に話して決意を固めたかったんだろ」
「……うっせ」
見透かされて不貞腐れるアドルフに、またもクリストフは苦笑させられた。
「お嬢は優しいなー。アディを立ち直らせてくれて」
「バカ。あれだって絶対策略の一つだ」
「だとしても、お前の為にはなっただろ。お嬢に感謝しなくてもいいけど、その点は得したと思っとけ」
言われて思わず眉を寄せた。
「損得の問題かよ?」
「損得でいいだろ」
クリストフは若干小賢しいところがある。そう言う部分は小憎らしいと同時に、案外好きだったりする。ひねくれ者で猜疑心が強く、正直者で正義漢のアドルフとは正反対で、小賢しく世渡り上手で腹黒なところがあるクリストフとは、正反対だからこそ相互にない物を補い合って切磋琢磨する――――そう言う親友だ。
一つ息を吐いて、話を続けた。
「アイツに、忘れるなって言われた」
「そうだな。気が済むまで想っときゃいいと思うぜ。辛いだろうけど。その内また彼女のような人に出会うだろ」
「カテリーナさんみたいな人ねぇ」
思い出して、少し苦笑した。
「どんな人だった?」
呼ぶ子を引くと、いつも嬉しそうに玄関先から駆けてきた。それを見て、自分が来るのを待っていてくれたのだと、喜んでいる自分を知った。聖職者として育ったために、世俗的な事にはあまり触れたことがなかったから、芸能や舞台の話なんかはとても興味深く聞いた。恋人だった議員の事や、政治の話も聞いた。彼女にはたくさんの事を聞かせてもらって、一回り以上も年上だったから、最初の内は恋愛対象と言うよりは、人生の先輩と言った目で見ていた。母親と同じ名前だったこともあって、あまり深入りしてはいけない気がして、意図的にそう思っていた部分もある。
彼女が一時的にヴァチカンに滞在しているのだという事は最初から聞いていた。すぐに別れが来ることは最初から知っていた。だから最後に思い出が欲しいという彼女と夜を過ごしたのは一度きりで、そうなりたいと思っていたわけではなかったが、彼女がヴァチカンを去ってから、アドルフの心の中にいつも彼女が住んでいて、彼女はどうして過ごしているか、そればかり考えた。
一人で寂しがってはいないだろうか、一人を怖がってはいないだろうか、天気が悪いと雷に怯える彼女を思い出して、体の弱い彼女を心配して、出来る事ならもう一度彼女に会いたかった。あの夏の日の様に語って、時々アドルフをからかって悪戯っぽく笑う彼女の笑顔を見て安心したかった。
彼女はとても優しかった。舞台女優らしく通る声をしていて、年上らしくいつも余裕があった。
私、お料理得意なのよ。あなたが来ると思ってスコーンを焼いたの。でもあなたの事を考えてたら夢中になって忘れてて、焦げちゃったわ!
アドルフと違って、自分の感情を隠さない、そう言うところが好きだった。
そう、あなた神父さんなの。偉いわね。だけどね、いつも人の懺悔を聞いてばかりではいけないのよ。あなたも語らなければいけないのよ。あなたみたいな人って、案外悪魔に憑りつかれてしまうんだから。何でも一人で背負ってはダメよ。人を頼りにすることで、あなたを責める人なんかいないわ。あなたが頼るのを待っている人が、きっと身近にいるはずよ。
虚勢を張ったりせず、弱さを嫌わず、自分の弱さすらも愛する高潔で強い彼女が、好きだった。
さよならなの。もう会えないの。あなたに会えなくなるのはとても寂しいけど、素敵な思い出が出来てうれしかったわ。
死ぬとわかっていてそれを一切告げずに隠し通し、最期まで笑顔でウソを吐いて演技し続けていた彼女が、好きだった。
「レベル高ぇなー。そんな女なかなかいねーぞ」
「だろ? 他の女なんて頭空っぽで見た目ばっか繕って、媚びる事しか考えてねぇし、自分の都合を押し付けてくる奴ばっかだったし。カテリーナさんがいい女すぎて他がカスにしか見えん」
アドルフはそう言うが、クリストフはカテリーナに対してもう一つ感想を持った。
アディは別れた後もどこかで会えるかもって期待してただろうに、彼女は二度と会えないってわかってて、何も言わなかったんだな。
それはアドルフを悲しませないように、とのカテリーナの優しさでもあるだろうが、同時にとても狡猾だと思った。カテリーナはアドルフを愛したから、病気だと知れたら同情しかされなくなるから、それを恐れた。アドルフの心が自分から離れていかないように、巧妙に演技した。クリストフがそれに気付いても、彼女に恋をしてしまったアドルフは、格言通りそれに気付かない。
恋は盲目って奴か。確かにそんだけ頭の回る女に惚れたら、他の女なんてカスに見えるかもなぁ。勿体ねー。
そう考えて、ちょっとだけ説得を試みることにした。
「いやいや、お前がその女たちに惚れてたら、そう言うのが可愛く見えるんだって」
「はー? そんなの微塵も興味わかねぇ」
可愛くて清楚で優しくて女らしい、という皮を被っているだけの女が一番退屈だったりする。もれなく遊びカテゴリ行きで、一度関係を持ったら後は呼び出すだけだ。飽きたらそれで終わり。
「お前の趣味変わってるなー、普通はそう言う女がモテるのに」
「モテるために『そう言うポーズ』を取ってるのが嫌いなんだよ。俺は知性の欠片もねぇ女は嫌いなの」
「ひねくれてんなお前」
クリストフはどこか呆れた。頬杖をついて不貞腐れたようにアドルフが言う。
「本当に清楚で可憐で優しくて可愛い女なんて、俺はクララくらいしか見た事ねぇぞ」
「確かにな。クララは本物だ」
「化け物でガキじゃなけりゃ完璧だったなークララ」
「そーか? ガキでもいいじゃん可愛いから。化け物じゃなけりゃなー」
顎を乗せていた手から顔を離して、クリストフを見た。
「何お前、ロリコン?」
「クララなら合法だってお嬢が言うし」
「合法……うん、確かにな。でも吸血鬼じゃねーか」
「そーなんだけどクララ可愛いじゃねーか。袖引っ張って遠慮がちに見上げてくる顔とか、スゲェキュンキュンする」
何を思い出したのか、ニヤニヤするクリストフに今度はアドルフが呆れた。
「……お前がロリコンだったとは知らんかったわ。お前の趣味こそ変わってるぞ」
「別に趣味じゃないけどよ、クララが人間だったらなーと思う事はある」
「人間じゃねーからなー。もう最初から対象外だろ」
そう言うとクリストフはどこか神妙な顔つきになった。
「だなー。仮にも天敵だしなー。なにこれ。ロミオとジュリエットみたいな気分になって来た」
クリストフがバカなことを言い出すので、思わず声を上げて笑った。
つられて笑ったクリストフが、何かを思いついたような顔をした。
要するにコイツは、年上で計略的で知的な女がタイプなのか。つまりアディは、自分よりキレる女に振り回されたいんだな。なるほど、アディに振り回される女じゃ、退屈する筈だ。
そう考えて質問した。
「知的な女が好きだって言うなら、お嬢は?」
クリストフ的には考察にぴったりマッチした物件だと思ったが、アドルフはその質問に、千切れんばかりに首を横に振った。
確かに彼女の知性は認める。部屋に入ってきてアドルフの纏う悲壮に気付いたのか、シャルロッテは少し目を瞠って、すぐに切なげな表情をしてアドルフを抱きしめて「いいのよ」と言った。普段なら腕を張って突っぱねただろうが、その時のアドルフは精神的に狭窄していたし、誰かに縋りつきたかったのかもしれない。それを見透かしてシャルロッテはそうしたのだろうと思う。
アドルフの目的を的確に見抜いた点でも、「マタイ受難曲39番」なんかを謳う品性の高さも、その頭の回転の速さ、洞察の鋭さ、思慮の深さは素直に賞賛に値する。
が、いかんせんシャルロッテはプライドが高く高飛車で、自己中心的で我儘だ。それ以前に人間ではない。
「ねぇよ、アイツはねぇよ。つか俺的には、アイツの頭はどうかしてると思う。むしろ怖えぇ。たまに心読まれてるんじゃねーかと思うぞ」
「あ、それは見ててスゲェ思う。つか読んでるだろ確実に。そう言う能力なのか、はたまた経験値の差かは知らんけど」
「怖えぇわアイツー」
「あー化けの皮が剥がされるのが?」
「ちげーよ!」
「つかもう剥がれてるみてーだぞ。アディは硝子の少年だってお嬢が言ってたって、クララに聞いた」
それを聞いてショックを受けるアドルフだったが、俄かに怒りすら感じてきて、拳を握った。
「ムカつく……アイツ絶対俺の弱み握ったと思ってゆすりたかりしてくるんだろうな」
その文句に首を捻りながらクリストフが宙を仰ぐ。
「どーだろーな? 俺なら普段は全然気にしてない風を装って、絶妙なタイミングで脅迫するけどな」
「お前性格悪っ」
のけ反って文句を言うアドルフに、「ハッハッハ、今更」とクリストフは笑い飛ばした。確かに今更だった。クリストフはこういう奴だ。
話がここまでなら、戦闘中のアドルフが手元を狂わせるような事はないのだ。問題はその数日後だった。アマデウスにサイラスを呼んでくるよう言いつけられ、6階の奥、城主の部屋であるマスタールームに足を運んだ。最上階のその部屋は他の部屋と設えが異なり、豪奢な装飾が施されたマホガニーのドアは重い両開きの物で、凝った装飾の真鍮のドアノブが付いている。
そのドアをノックしようとすると、中からサイラスの声とシャルロッテの声が聞こえた。親子で何か話しているようだが、邪魔していいものか。そう考えたが、命令優先と考えなおしてもう一度ドアに手を伸ばそうとした、その時。
「ええ勿論。だって私、アディを愛してますから」
耳を疑った。
え、うそ。聞き間違いだよな。だってなんか、旦那爆笑してるし?
言葉の通りならサイラスが爆笑しているという状況は全く符合しない。恐らく何かの聞き間違いだと思う事にして、少し時間を置いてドアをノックした。返事を受けてドアを開け、サイラスを呼びつつチラリとシャルロッテを見ると、にっこりと微笑まれる。それもいつもの事なのだが。
な、なんか怖えぇ……。
アドルフらしくもなく怯えた。なんとなく血の気が引いていくのを感じながらドアを閉め、サイラスと共に階段を下りていくと、なんだかサイラスが笑っていた。
「なにか?」
「いや、小僧が盗み聞きをしていたのだと思うと、可笑しくてな」
この瞬間、心房が爆発したような錯覚を起こした。
「ははは、まさか。私は何も聞いておりませんよ」
まるで、心臓が頭の中で鼓動しているんじゃないかと思うほどに鼓動したが、何とか営業スマイルで言い繕った。しかしサイラスはやっぱり笑って言った。
「そうか? 目がウソを吐けていないぞ。はぁ、いずれお前が私の義理の息子になると思うと、実に嘆かわしい。はははは」
バレたー! つか気が早い! いやそれ以前にならんけど! そして何故笑う!?
いよいよ混乱しつつ必死に脳内でツッコんだものの、ますます血液が枯渇していく感覚を覚えながら、深い溜息を吐く。
やっぱコイツら怖えぇー!
あの親にしてこの子ありとはよく言った物である。思わず背筋がぞっとした。
が、その後のシャルロッテの態度に変化はないし、アドルフも考えを改めて不誠実な事をしなくなった。それを誰よりも喜んでいたのはアマデウスで、「なんかアディが聖職者らしくなった」などと言っていた。そういう会話を聞くたびにギクリとしてシャルロッテを見るのだが、シャルロッテは聞いていないのか気にしていないのか、全く興味なしと言った風で、要するに相変わらずだった。
クリストフが言った事もあるし常々シャルロッテを警戒していたのだが、そのせいで思わぬ事をイザイアに言われた。
「なんか最近さぁ、課長ってばお嬢の事チラチラ見てるよね。気になんの? もしかして惚れた?」
それは全くの誤解だったので、大層驚いた。
「違う違う! そう言うんじゃなくて!」
「わームキになって怪しいんだ。あ、だから女遊び辞めたんだ?」
「違う違う! それは別件で全然違う!」
全力の拒絶もイザイアには信じてもらえず、「頑張ってねー」と励まされる始末だった。仕舞にはクリストフにも「ハッハッハ、ドンマイ」と励まされて、心の中で泣いた。
本人が状況について行けない間に、何故か四面楚歌になってしまったアドルフだったが、さらに追い打ちをかけるように戦闘に水を差されて、調子が狂いっぱなしだ。
「なぁクリス」
「あぁ?」
「俺帰っていいか?」
「何言ってんだお前、ふざけんな」
やっぱダメか、と落胆していたら、シャルロッテとクララが悲鳴を上げた。何事かとトロッコを見ると、血塗れになっている。
「お父様に貰ったグラスがー!」
薩摩切子のグラスに銃弾が当たって割れたらしい。まるで殺人現場のごとく血まみれになったトロッコの中で、シャルロッテは怒り心頭に立ち上がった。
「大体アンタ達がさっさと片付けないからよ! あんな三下に手こずって、アンタら本当にプロなの!?」
なぜか死刑執行人が怒られる。
「うるせー! つかお前らが邪魔なんだよ! 帰れ!」
「弾外すような奴に言われたくないわよ! もういい! アンタら下がってなさい!」
「あぁ!?」
言いながらシャルロッテはトロッコから降りてきて、クララには顔を出さないように言いつけてトロッコに押し込んだ。シャルロッテは銃弾をその体に受けながらずかずかと歩を進めていく。シャルロッテの体に当たった銃弾は、まるで鋼鉄の板に当たったかのように潰れてその場に転がり落ちる。傷一つないシャルロッテの服と体、その白魚の様な掌から取り出した物は「ダーインスレイヴ」と名付けられた紅い魔剣。
シャルロッテが下段の構えを取った。その瞬間、視界からシャルロッテが消失し、気が付くとノスフェラートの隠れていたコンテナの影から血飛沫が上がっている。
断末魔と、悲鳴と、血飛沫が上がる音が断続的に耳についた。シャルロッテが殺戮をしている、その瞬間を一切目で捉えることが出来ない。それほどの速度であちこちから紅い血潮が立ち上り、やがて坑道の中は静寂に包まれた。
その静寂は、自分の心臓の音が耳に着く程で、流れ落ちようとする汗が肌の肌理を辿っている感覚さえも、ちりちりとした音を伴っているかに感じた。
「はい、お仕舞」
顔や髪、全身に血を受けたシャルロッテがそう言って、剣を仕舞いながら戻ってくる。その姿に誰もが呆気にとられ、息を呑んだ。
黒髪の先からぽたりと零れ落ちる赤い血が、シャルロッテの白い肌に一層鮮やかに映えた。目に入った血を拭うそのさまは、まるで血の涙を流しているかのように見えて、シャルロッテの邪悪な、あるいは神聖なその姿に、アドルフはその瞳を捉えられて動かすことができなかった。全身が総毛だっていた、喉がからからに乾いた。心臓の痛烈な拍動が、しかしそれは不快なものではなく、その拍動でより高揚する精神が、「ただの化け物」であったシャルロッテの評価を、明らかに高みへ変化させたことを知った。
「お、お嬢様……」
震える声でクララが言って、ようやく我に返った。
「あーベタベタするわー。早くお風呂入りたいわー帰りましょ」
クララが怯えているのに気付いて、すっかり魅入ってしまっていたアドルフの隣から、すかさずクリストフが救護用の布をシャルロッテに渡し血を拭くように言った。シャルロッテはそれを笑顔で受け取って、まるで何事もなかったかのようにクララに「お片付けの時間ねー」と微笑みかけた。
以前シャルロッテが言っていた。イザイアが撃たれた時、シャルロッテはその敵の吸血鬼の話を聞いて機嫌を悪くした。
「吸血鬼のくせに銃を使うなんて、吸血鬼を冒涜しているとしか思えないわ。そんな矜持すらも持たない半人前に殺されたのでは、アンタ達も浮かばれないわねぇ。死なないことを祈ってるわー」
シャルロッテは至高の吸血鬼。半人前の化け物は、存在すらも許し難い。彼女にとっては虫けらに等しい、少なくとも彼女の目にはそう映っている。だから、グラスを割られたくらいで殺戮をしてしまう。
なめていた。彼女のプライドの高さを。
それが今は畏敬すら感じる。
あぁ、この女は。
無傷で返り血を浴びて、優しくいつも通りに微笑む冷酷無比なシャルロッテ。
その姿を見て背筋をゾクリとさせるものが、恐怖ではなく芸術的興奮であることが自分でわかった。
――――ロッテはなぜこうも、美しい。
孤高の美、矜持、斜陽の王女の美学。
アドルフはしばらくの間、その芸術的なシャルロッテの様相に心酔していた。
戦地となったのは山間部、と言っても国内ではなくスイス側だ。当然一泊することになるので、宿を取ってある。普段は近所の教会に部屋を借りることが多いのだが、この辺りは田舎で教会があっても空き部屋がない。その為近くのホテルを取っている。ついでに言うと、シャルロッテとクララと言う増員は全くの予定外だったので、部屋を取っていない。新たに部屋を取ることになっても、シャルロッテが
「私にスイート以外の部屋に泊まれって言うの? あり得ない! アンタがどっか行きなさいよ」
と我儘を言って、さっさとアドルフとクリストフが取っていた部屋に入った。
更についでだが、
「私一人でお風呂に入れないの。アディ早く来なさいよ」
と、さっさと服を脱いだシャルロッテが強制連行し、呆然とするクリストフにクララの面倒を頼んだ。その間アドルフはずっと文句を言っていたが、「クララを傷付けてしまったかしら」と少し神妙に言うと、やや大人しくなった。やはり単純だと思う。
ちなみに風呂の件については、クララを拾ってからはクララに風呂の世話をしてもらっていたので、それに慣れてしまった。
浴槽に浸かっていると、髪にシャワーを当てたアドルフが「なるほどね」と言った。
「確かにこんな血まみれの髪を洗わされたら、クララ泣くかもな」
シャワーのお湯を当ててアドルフが髪を梳く度に、長い黒髪にこびりついた血が溶けて、白いタイルを赤く汚しながら水に淀み、排水溝に引きずり込まれていくのが見て取れた。
「でしょう? ていうかもう泣いてたし。こういう時はクリスに押し付けるに限るわ」
「まーな。つかお前アレだな。よく言えば華奢、悪く言えば貧相な体してんな」
「悪く言う必要がある?」
「胸なんてかなり可愛いな?」
「その可愛いは『ささやかな』と言う意味かしら?」
「おっさすが。正解」
シャルロッテの裸をまじまじと見ておいて、リアクションが全く薄いアドルフもさすがだと思う。
伊達に遊んでないわねー。慣れって怖いわねー。
ハッキリ言って、あたふたするアドルフを見たかっただけに残念だ。だがこれはこれで気に入った。シャンプーを揉みこんで、空気を含んで泡立った髪を大きな掌で洗ってもらうのは、なかなか心地よかった。
「うわ、泡めっちゃピンク色してんぞ」
「えー? じゃぁもう一回洗って」
「俺はいつからお前の召使いになった?」
「今日限定でいいわよ。なんかあげるから」
「なんかってなんだよ」
「なんでも。もうすぐ誕生日でしょ?」
ふと手が停まった。
「なんで知ってんだよ」
「エルンストに聞いたのよ。そうでなくても、アディの事なら色々知ってるわよ」
「はぁ?」
覗き込んできたアドルフに、見上げながら笑った。
「19xx年3月25日ミラノ郊外の小都市レッコにて、アダム・フルトヴェングラーとカタリーナの長男として誕生。兄弟はなし。病歴なし。血液型はAB型。両親は銃殺により死亡、肝心の息子は、公的には今もなお行方不明。両親の事件は強盗殺人事件とされ、迷宮入りしたまま既に時効が成立している。12歳から飲酒喫煙を始めた不良で、ヴァチカンきっての異端児にしてエリート中のエリート。ヴァチカン時代のあだ名は「千人斬り」「生殖者」「生けるモテ神」などなど」
言って笑いかけるとアドルフはうんざりした顔をした。
「んだよそのアダ名……俺も知らんかったのに……」
思わず笑ってしまったが、すぐにアドルフに視線を戻した。
「驚いたわねー」
「いや俺の方が驚いたわ」
「私の方が驚いたわよ。この情報を聞いて素直に自分の事だと信じたアディにね」
アドルフは目を剥いてハッとした顔をした。
「知ってたのね、自分が何者なのか」
「……あぁ、知ってた」
視線を外すとアドルフも手を動かし始めて、シャワーで泡を流し始めた。
「いつ?」
「二十歳なる前」
「そう。その時は驚いた? それとも覚えてた?」
一瞬手が停まったが、手が離れて再びシャンプーをつけて動かし始めた。
「多少は、覚えてた。事件の事とかは後で調べて知って……ま、驚いたけど」
「そう。ねえアディ」
「なに」
もう一度見上げると、アドルフの表情は少しだけ悲哀を纏っていた。それに微笑んで言った。
「あなたはカテリーナの愛した天使ね」
「……らしーな」
「と同時に、カタリーナに祝福されて、この世に生を受けた天使ね」
「……さぁ」
どうにも言葉を濁したがるアドルフがなんだか滑稽だった。湯船から手を出して、濡れた手でアドルフの頬を撫でた。
「言って。あなたの本当の名前を、あなたの口から。カタリーナに祝福された天使、カテリーナを天国に導いた天使の名前を、教えて」
アドルフは眉を寄せて強く瞼を瞑り、シャルロッテの濡れた手の上から、泡のついた手で覆って、消え入りそうな声で言った。
「……ガブリエル・フルトヴェングラー」
震える声が、震える指先が、その名が母への愛と惜別を語る。
シャルロッテの濡れた手に、睫毛の先から零れた涙が滲んでいく。
触れたアドルフの手の泡が、涙に溶けてぱちぱちと弾けた。
その様を見ながら、瞳を閉じたアドルフに微笑んだ。
「素敵な名前ね、ガブリエル」
名前を呼ばれて、アドルフはシャルロッテの手を握り締めた。
わずかに意識の残った母は、幼い頃のアドルフ――――ガブリエルを見つめて涙を零した。精一杯微笑んで、消え入りそうな声で囁いた。
「ガブリエル、私の天使。愛してるわ」
母はガブリエルに伸ばそうとした手を、引きとめた。自分の行動でガブリエルの居場所を悟らせないために。涙を零して瞼を閉じた母は、すぅっと力が抜けたようになった。
力の抜けた母の体から、血が流れてきた。フローリングの溝を辿って、ガブリエルのもとへ真っ直ぐに流れ込んできた。
それを見てガブリエルは恐ろしくなった。真っ赤な血が恐ろしくて、母が母でなくなったようで、母の在り様を受け入れたくなかった。そして、「ここから出てはいけない」という母の言いつけを破った。
ベッドの下から這い出て、母の体を揺すった。
「おかあさん、おかあさん」
呼んでも、反応はない。揺すられた体からは、衣擦れの音と、血の滴る音が響くだけ。
「おかあさん……ひっく、おかあさん」
泣いても、もう頭を撫でてはくれない。涙を拭ってくれた指先は、既に血に塗れていた。
「うわぁぁん、おかあさぁん、おかあさん」
泣き縋っても、もう先程までの様に愛しげに名前を呼ばれることはなく、母の声を聞く事は二度となかった。
今はもう誰一人、ガブリエルと呼ぶ者はいない。彼の本名を知っているのはクリストフだけだ。それは、幼い頃の悲劇を覚えているのが、互いしかいなかったからだ。
「ガブリエル。この名前で呼ばれるのは嫌い?」
「……いや」
「そう。じゃぁ誰も聞いていない時は、この名前で呼ぶわ」
「好きにしろよ」
「ええ。あなたの泣き顔を見るのは2度目ね。泣き虫なんだから」
「うるせぇ。人に言うなよ」
「言わないわよ」
まだ26歳だというのに、壮絶な半生だと思う。これほど戯曲的なまでの悲劇が、たった一人の人間に降り注いでいいものかと思う。たったの26年、この間にどれほどの苦悩を抱えていたのか。そう思うと同情位は湧いた。
「ガブリエル、私が名前を呼ぶわ」
「あぁ」
「涙も拭うわ」
「……あぁ」
少し気分が悪そうに返事を返したのを見て、湧き上がる悪戯心。
「なんなら抱きしめて頭を撫でて、子守歌を歌ってあげてもいいわ」
「それはいらんマジで」
「あら人が親切で言ってるのに」
「そりゃ余計なお世話つーんだよ」
「可愛くないわねー」
「可愛くてたまるか」
と、アドルフが可愛くないことを言うので湯船のお湯をかけると、仕返しとばかりにシャワーを顔にかけられた。結局水掛け論ならぬお湯かけ合戦になってしまって、服を着たままだったアドルフはびしょ濡れになってしまった為に、二人揃って機嫌を損ねた。
可愛くないわねー。
可愛くねー女。
似た物同士のケンカは、いつだって平行線だ。
お風呂から出て体を拭いてもらい、髪を乾かしてもらう。その間アドルフはずっとびしょ濡れで不服そうにしていた。
それを少し可笑しく思いながら浴室から出て居間に入る。その間に影を引き寄せると、足元から上ってきた影が体を覆い、ぱさりと黒いシルクの寝間着に姿を変える。
「なにそれ! ズルッ!」
文句を垂れるアドルフはせっせと拭いて着替えを探していた。
「うるさいわねー。それよりクララとクリスはどこに行ったのかしら?」
問われてリビングを覗いたアドルフも、周囲を見渡して首を傾げた。
「あ? あれ、いねーな」
クララをクリストフが慰めていたのだが、風呂場からこの二人のケンカが聞こえてきてやたらと気が削がれてしまったので、部屋を出ることにしたのだ。
見ると、テーブルの上に置いていたはずの、新しく追加で取った部屋の鍵がなくなっていたので、そちらに行ったのだという事はわかった。
今度はアドルフが風呂に入って行ったので、シャルロッテはテレビでも見ていることにした。が、テレビのニュースで非常に面白い物を見かけて、慌てて風呂場に駆け込んだ。その際、ドアの鍵を壊したが気にしない。
「アディ大変大変!」
「何だよなんで入ってくんだよ! 出てけ!」
突然の乱入にばしゃばしゃとお湯を跳ねさせて、慌てて追い出そうとするアドルフは無視だ。
「教皇が前立腺がんで入院ですって! 死ぬわよ! 選挙よね! 叔父様教皇にならないかしら!」
興奮して全くアドルフの話を聞いていないので、いい加減慣れたのか溜息を吐いて湯船に身を沈めた。
「猊下はコンクラーヴェの参政権ねぇぞ。純粋な戦力としての枢機卿位だからな。教会にとっては必要な人じゃない」
口を尖らせた。
「なぁんだ。つまんない。じゃぁ叔父様以外の枢機卿の――――あのしわくちゃのおじいちゃん達がまた教皇になるのねー、つまんないわーつまんないわー。たまには若くて美形の教皇を見たいわー」
教皇に選出される条件は、80歳以下の枢機卿で、枢機卿団の投票により選出される。アマデウスはそれに参加する権利を持たない。勿論アマデウスには教皇位に誰が就こうが全くどうでもいいので、あまり関係ない。
枢機卿はヴァチカンの行政においても重要な役割を持ち、教皇庁の貴族とも呼ばれ、所謂大臣の様な地位にある高級官吏なのだ。教皇に選任されるのは、枢機卿団の中でも主席枢機卿である確率が高い。だとすると、現在教理省の顧問である枢機卿の可能性が高い。
アマデウスは一応教理省に属しているが、あくまで彼の仕事は「ヴァチカン教皇庁教理省枢機卿直属対反キリスト教勢力及び魔物強硬対策執行部」の指揮であり、実際の政権には全く関与できない。教理省には別の枢機卿が配属されていて、所謂そちらが表の顔だ。
「どーでもいいけどさっさと出てけ」
言われてようやく物思いに耽っていたのを中断し、風呂場から出た。
居間に戻ってみたが、やはりクララは戻ってきていない。
一人の部屋で、少し後悔に駆られた。
クララは傷ついたかしら。
クララの前では滅多に人殺しをした事がなかった。今思えば子供の頃から慣れさせておくべきだったと後悔するが、クララにはなんとなくそうして欲しくなかった。
血まみれのシャルロッテを見て、揺らぐクララの瞳に広がっていくものが恐怖だけでなく、失望もその色を伴っていたことを今頃になって思い出した。
だけどクララはわかってくれるわ。あのグラスはお父様に、誕生日に買っていただいたんだし。怒るわよ、そりゃ。
150歳の誕生日、わざわざサイラスが日本まで買い付けに行ってくれた。雑誌で見かけて「これ綺麗」とシャルロッテが言っただけだったのに、それを覚えていてその為に買ってきてくれたのだ。宝物を壊されてしまったら、誰だって怒る。
例えば、あのグラスを割ったのがクララだったら、叱るだけで怒りはしなかったと思う。誰だって粗相をする野良猫を見つけたら、保健所に通報して殺してもらうはずだ。それと同じこと。
――――もし。
考えて、少しだけ動揺した。
――――もし、それがアディたちなら?
状況によってはわからないが、殺さないかもしれない。そう思ってしまったことに、少なからず動揺した。
慣れって、怖いわね――――……。
自分がこうなのだから、きっとクララは余計だろう。クリストフに近づくように命令していたが、どうも必要以上に親交が深まっている気がしてならない。
少しの間悶々と考えていたが、途中でやめた。アドルフも出てきたことだし、とりあえずクララの前では必要以上の殺戮をしないと決めて、クララが戻ってきたらご機嫌取りでもしようと考えた。
8 鐘
「わかってます……あのグラスはお嬢様の宝物だったんです。それで怒るのはわかるんですけど……」
鼻をすすりながらそう言って泣くクララを、クリストフが頭を撫でながらあやしていた。
シャルロッテが怒るのはわかる。だけど、ノスフェラート達を皆殺しにしておいて、まるで何事もなかったかのように自分に微笑みかけた、その事が恐ろしくてならなかった。
きっとシャルロッテはシャルロッテ本人は勿論、クララやサイラスを悲しませる誰かが現れた時、それが誰であっても躊躇することなく殺してしまうのだろう。ノスフェラートを殺害した時のように、無表情で何の感慨もなく、散歩道で見つけた空き缶を蹴飛ばすように。
「今まで、お嬢が殺してるのを見たことは?」
「あります。でもその時は相手が一人とか、捕食の為だったりなので、あんな一方的な虐殺ではなかったんです」
捕食の為に殺すことと、闘争の為の殺戮は全く違うものだ。少なくともクララはそう思っているが、恐らくシャルロッテは同じ事だと考えているのはわかっている。結局死ぬという結末に変わりはないのだから。
「お嬢様は戦争がお嫌いだと仰ってたんです。なのにどうして、殺すことを厭わないのでしょうか?」
問われてクリストフも腕組みをして頭を捻った。
戦争が嫌いな理由は知らない。大概の人間だって戦争は嫌いなので、そこは置いておいても構わない。殺しをするのは自分達も同じだが、好きでやっているわけではなくそれが仕事だからだ。
戦争と殺害は違う。戦争とは流血を伴う政治であり、政治的発言を武力に変えただけの事。政治は意識の集合体だが、殺害は個人の意識だ。恨み、排除、快楽、理由は様々だが、自らで思考し自らの決断で行うと言う部分において、戦場の兵士とは決定的に違う。
「俺らは楽かもな。それが仕事だし、命令だし、どうせもうヴァチカンから離れる事は出来ないし。俺達の人生は既にそう定義されているから、今更迷いなんてない。でも、何物からも自由な人がその手を汚すのは、とても悲しい事だな」
殺すことは遥か昔から罪とされてきたのに、長い歴史の中で人がそれをやめた事などない。死は、殺すことは、人を惹きつける、どうしようもなく抗いがたい美しさを放っている。その強烈な引力を持つ黒渦にアドルフは惹きつけられ、クララは怯え拒絶した。
「なぁクララはさ」
ようやく涙だけは止まったようだった。
「はい?」
見上げてくる、濡れた瞳が愛らしかった――――が、今は置いておくとして。
「お嬢の事嫌いになった?」
「まさか、そんなことありません」
何があってもお嬢様はお嬢様です、と必死に首を振った。
「割り切れない? それはそれ、これはこれ」
シャルロッテが好きなら好きな所だけ見て、苦手な部分に目を瞑る。それが出来たら楽だが、出来ないから泣くのだ。
「お嬢様にやめてって、言ってみようかなぁ……」
クララの呟きを聞いて、クリストフはソファに背を持たれた。
「殺されるのを見るのは、人間と化物、どっちが嫌?」
「殺される相手へは、特に思うところはありません。殺しているお嬢様が苦手なだけです」
やはりあくまでクララも化け物なのだ、と思う。経験がないから、化け物としてはまだ若泣いたりもするが、根底にはシャルロッテとサイラスが施した教育が根付いている。
あぁそうか。クララはお嬢の娘なのか。
シャルロッテが自ら吸血鬼化した愛娘。至高の存在である純血種により吸血鬼化されたクララもまた、一介の吸血鬼とは格が違うのだろう。だが今までその力を振るう事はなく、目にする機会もなかった。意図的にシャルロッテが避けていた。
「避けていたのはクララが、殺すことが罪だと思ってるって、お嬢が知ってたからだろうな。殺害の罪悪にクララが苛まれることがないように。でもお嬢にとって殺害は、罪じゃないんだろ。人間だって人殺しが罪じゃないと公言されたら、安心して人を殺すだろうよ」
人が人を殺さないのは、恐ろしいから。罪を背負う事、罪悪を背負う事、それを恐れているから。その恐怖が払拭されることがあれば、人々は嬉々としてその手を血に染めるだろう――――シャルロッテのように。
ふとクララが考え事をしていたのをやめて、クリストフを見上げた。
「そうですね、お嬢様にとって殺すことは罪ではありません。私や旦那様にとっても。お嬢様はいつか殺されることを、夢見ていますから」
そう言われても意味が分からず頭を捻ったが、ふとエルンストが言っていたことを思いだした。
――――お嬢の好きなタイプって、死ななくて自分を殺してくれる男だってよ。前半はわかるけど後半は意味わかんねーよな。
「愛した男に殺されたいのか?」
問うとクララは少し驚いたような顔をした。
「どうして知ってるんですか?」
「いや知らんけど、なんとなく」
何となくだが、少しだけ分かった。なぜかは知らないが殺されたがっている。だから、殺害全般を悪とは思えないのだ、シャルロッテは。
「お嬢様は美人で聡明だし、お嬢様を愛する人はきっと現れる。その人をお嬢様も愛したら、お嬢様はきっと、その人に殺されたいと切望するんでしょう」
やはり意味不明で「なんで?」と問うと、クララが姿勢を向けた。
「クリスは今でも、私達を殺そうと思う事はありますか?」
それはいまさら思わなかった。他のメンバーはわからないが、殺害命令を遂行しないと殺す、くらい言われなければ、進んで殺そうなどとは微塵も考えていない(なにより勝てる気がしない)。
「殺す気はないって言うか、殺したくないな、特にクララは」
「ありがとうございます。私もクリスとは仲良しでいたいですよ」
クララの花の様な笑顔に、胸に深々と矢が突き刺さる。
うわぁもうクララが神懸かりに可愛い! 何だ、マジか。俺実はマジなのか。
なんだかロマンティックが止まらないクリストフ。
「クリスどうしたんですか?」
「い、いやなんでもない……」
必死に動悸を抑えて顔を背けるが、更にクララが覗き込んでくる。
「どうしたんですかドキドキして? 不整脈ですか?」
「い、いや違う……あやっぱ違わない、うん、そう不整脈」
ていうか聞こえてるのか、と吸血鬼の聴力にオロオロする。
あぁダメだ。俺マジだ。マジでヘンタイだ!
自分の趣味に自己嫌悪し始めたクリストフだったが、ふとクララがクリストフの肩に手を置いて、耳元に顔を寄せて囁いた。
「一つだけいい事を教えてあげます」
「えっ、なななに」
「私とお嬢様を、人間でも確実に殺せる、素敵な方法です――――」
続いたクララの言葉に、思わず目を見開いて離れた。
「ウソだろ」
「本当ですよ。だから、殺されたいんです。わかります?」
「わ、かるけど……それはすごく、可哀想じゃないか。男もクララたちも」
「そうですね。でも素敵な事ですよ」
内緒ですよ、と微笑むクララがなんだかとても可哀想で、同時にひどく愛しかった。
本当は、好きな人とはずっと傍にいたい。仲良く幸せに生きていきたい。死にたくなんてない。相手に自分を殺すような事をして欲しくもない。だけどそれは抗えない、彼女たちが「そういうもの」だから。
「だからね、とてもとても大事な事なんです。殺すという事も、愛するという事も、私達には紙一重なんです。私達はいつでも、愛する人に命を差し出す準備をしていなきゃいけないんです」
たまらず抱きしめたクリストフの腕の中で、クララが優しい声で言った。それを聞いて、腕に力を込めた。捕まえた小鳥を逃がさないように(どうせ勝てないけど)。
「なぁクララ」
「はい」
「おかしいかもしれないけど、俺、クララが……」
「ハンバート・ハンバートですね」
「う……それを言うな」
腕の中でクスクスと笑ったクララが、クリストフの胸に顔をうずめて少し縮こまって言った。
「嬉しいです。クリスは優しいから、私も大好きです」
クララは同族に会ったことはなかったから、人間にしかあったことがない。クララに会って恋をするのは、いつも見た目年齢が同じくらいの年ごろの子供ばかりで、大人からは可愛いと言われることがあっても愛玩とさして変わらなかった。だから嬉しかった。心はもう大人だったから、大人に恋をする。だけど可愛がられるだけの。
だけどクリストフは違った。それがとても、嬉しかった。嬉しかったが、現実的な問題として、それは許されざることだとクララも知っている。
「わかっていますか、クリス。私は吸血鬼で、あなたは人間です」
途端に暗くなったその声に、クリストフは一層腕に力を込めた。捕まえられたと思ったのに、また飛び去ってしまいそうな気がして、離したくなかった。
「わかってる。でもそんなこと、関係ないし」
「関係ないなんて、そこが一番問題でしょう?」
「なんで? 関係ねぇよ。クララは俺が人間なのは、嫌?」
シャルロッテに人間を蔑視するよう叩き込まれて育ったから、クリストフの言ったことを否定はできない。かといって肯定したくもなくて、黙り込んだ。
するとクリストフが言った。
「クララが素直になってくれるなら、俺、人間やめてもいい」
「え?」腕の中で顔を上げた。
「そしたら一緒になってくれるって言うなら、やめる価値はある」
涙が出そうになった。クララはダメだと思っていたから、余計に。でもクリストフは障害を容易く乗り越えて、クララの元へやって来て手放さない。
「それでも嫌か?」
「ヤじゃ、ないです……」
シャルロッテの命令でクリストフに近づいたのに、こんなことを言ったらきっとシャルロッテに怒られてしまうのだろう。
「あの、あの、私……殺されるなら……クリスがいいです」
そう言ったクララは耳まで真っ赤になっていて、それを見たクリストフは少しだけ抱えていた背徳感なんて那由多の彼方に消えてしまって、いよいよロマンティックが止まらなくなった。
「どーでもいいけど遅いわねークララ」
「遅ぇなぁ。俺いい加減眠い。寝たい」
待ちくたびれたシャルロッテと、うつらうつらとし始めたアドルフは、痺れを切らして様子を見に行くことにした。
もしかしたら泣き疲れて眠ってしまって、クリストフがついているのかもしれないし、シャルロッテの所に戻ってくるのが気まずいのかもしれない。ならば迎えに行ってやった方が、わだかまりも残りにくいと言う物だ。
そう考えて辿り着いた、追加で取った部屋に辿り着く直前、クララの悲鳴が聞こえた。何事かと部屋の前に行きドアを開けようとしたのだが、聞こえてきた会話に思わず硬直した。
「あ、い、いた……」
「痛いか? ゴメン、やめようか?」
「いいんです。何回しても痛いってお嬢様も言ってたし、このまま……離れたくないです」
「……辛かったら言えよ? ゆっくりするから」
その会話を聞いて蒼白になった二人の耳に聞こえてくる、クララの悲鳴混じりの嬌声と、クリストフの吐息と、ベッドが軋む音。
「マジか……」
「Oh! Jesus!」
「あ」
ショックのあまりシャルロッテはその場で失神した。声の漏れる部屋のドアと、廊下で倒れるシャルロッテを交互に見ていたアドルフは、溜息を吐いてシャルロッテを担ぎ上げた。
俺のが眠いのに、なんでコイツが寝るんだよ。チクショウ、クリスの奴。あのヘンタイ野郎のせいだ。
心の中でブツブツ文句を言って、頭を抱えながら部屋に戻った。
目覚めて、大分儚い事になっているシャルロッテを、面倒事に巻き込まれた感が否めないアドルフ(結局寝ていない)が連れて行って、クリストフとクララの部屋に行った。結局この二人は戻ってくることはなかったので、そのまま眠ってしまったらしい。時間は既に朝だったので、クララは寝ている。
ご丁寧に鍵とチェーンまでかかったドアを力ずくで開け放つ。その音に驚き起き上がったクリストフの傍らには、すやすやと眠るクララ。
それを見た瞬間シャルロッテは、先程までの背景に薔薇を散らしたような儚さなど消え失せ、その表情は般若の如く一変し剣を出して構えた。
「おのれクリス! 銃を抜きなさい! いざ尋常に勝負!」
「えぇぇぇ!?」
「ちょ、待て待て! 落ち着け!」
シャルロッテが怒るのも無理はないが、ここでクリストフを殺されては困る。アドルフは必死になって止めに入った。暴徒化するシャルロッテをロザリオ片手にアドルフが羽交い絞めにし、走り出せない様に抱きかかえたが、剣をブンブン振り回すので髪や服が徐々に刻まれていく。アドルフが必死にシャルロッテを抑える一方、クリストフは鬼気迫るシャルロッテの形相に、ベッドの隅で怯えていた。とんでもなく狂暴な姑を敵に回してしまったようである。
「許せない許せない! 絶対ブッ殺す! 私の幼気で可愛いクララになんてひどい事を! これは万死に値する重罪よ!」
「だから落ち着けって! 合意の上だって散々言っただろうが!」
散々言われた。人間の中では勿論強いクリストフ。近接戦闘を得意としているだけあって中々質実剛健だが、それでも吸血鬼のクララに適う筈がないのだ。それでも持ち込めたという事は、どう考えても合意の事だ――――と言うのはわかるのだが。
「だからってクララは子供の体なのよ! 胸だってぺちゃんこだし毛だって生えてないのに! そんな妖精のようなクララが、こんな図体ばっか大きくなったような奴にいいようにされたと思うと身の毛もよだつわ! このヘンタイ野郎!」
「そこは否定する要素ねぇけど落ち着けって、もー!」
「どーせクリスの事だから純真無垢なクララをあの手この手で誑かしたのよ! 興味本位でクララの純潔を奪うなんて……許すまじ! クリス許すまじ!」
「その線が濃厚だけど、頼むから落ち着けって!」
どうでもいいけど、さっきからアディのフォローがフォローになってねぇな、と思いながら、とりあえずクリストフは一通りシャルロッテの文句を聞いていた。
アドルフのフォローが下手なのは、普段フォローされる側にいるせいだ。慣れないことをするものではない。
クリストフがおもむろに荷物を漁って取り出したるは、十字架の装飾がついた銀のナイフとおもりのついた銀の鎖。どちらもエクソシスムの秘跡を受けている、対化物用拘束セット。
クリストフがまずは暴れるシャルロッテとアドルフの周りにナイフを投げて結界を張り、更に鎖を投げてアドルフもろともその体に巻きつけた。その瞬間に剣は液状化しシャルロッテの掌に戻っていき、もんどりうって転げた二人は何とか鎖を千切ろうとする。しかし、人間のアドルフには勿論無理だし、シャルロッテにも千切れそうにない。
シャルロッテを羽交い絞めにしたまま拘束されたせいで、シャルロッテが鎖の中で暴れる度にアドルフの背骨が軋んで苦痛で喚く。耳元でギャーギャー喚かれるのでシャルロッテは余計に怒り心頭になって暴れるという、負の循環が結界内で加速していた。
身の安全が確保できたことに安堵して、クリストフは寝ているクララの額に優しくキスをして、ベッドから降りてきた。ギャーギャーと喚きながら結界の中で転がる二人の前にやってきて、半裸で仁王立ちだ。
「俺は何も悪い事はしてない!」
堂々と、そう言い放った。その宣言にシャルロッテは顔を歪めて、ギロリとクリストフを睨み上げる。
「悪くないはずないでしょ! 時代が違えば処刑よ処刑! 私が処刑してやるわよ!」
かつてキリスト教では、小児性愛と同性愛は処刑の対象だった。シャルロッテの死刑宣告に、クリストフは普段通りの薄笑いを浮かべて飄々と言った。
「残念ながらそんな時代は終わったんだよ。ざまーみろ」
「なんですってー! この腹黒! ヘンタイ!」
その文句にやはりクリストフは、シャルロッテの前にしゃがんで笑った。
「ヘンタイでも腹黒でも、クララは好きだって言ってくれたし俺も愛してるし。どこに問題が?」
「大ありよ! アンタ自分が何したかわかってるの!?」
憎らしげに睨みつけるシャルロッテに、クリストフはチラリとクララに視線をやって、再び視線を戻すと優しく笑った。
「わかってるよ。クララが死ぬときは、俺も一緒に死ぬって決めたから」
それを聞いて、クリストフの表情を見て、一瞬で興奮を収めた。
「クララに聞いたの?」
「あぁ」
「聞いて、その上で抱いたの?」
「あぁ」
アドルフには何のことかさっぱりわからなかったが、シャルロッテは深く溜息を吐いた。
「あっそう。じゃぁ昨夜の記憶は綺麗さっぱり削除してあげるわ。クリスのもクララのも」
その言葉に、クリストフは見たこともないほどに顔を歪めて、怒気を漂わせた。
「なんでだよ。俺もクララもわかってるし、覚悟してる。それの何が悪いんだよ。俺は本気で――――」
「本気? バカ言わないで」
クリストフの言葉を遮ったシャルロッテは、嘲笑を含んだように言った。
「私達の話を聞いて、同情が盛り上がって感傷的になっただけでしょ。本気なんて馬鹿馬鹿しい。ただの勘違いだわ。そんな一時的な感情で、クララを傷付けるなんて許せない」
「俺は本気だって言ってるだろ!」
睨み下ろしてくるクリストフに、口角の端を上げて笑った。
「へぇ? じゃぁ証拠を見せて。クララを本気で愛しているというのなら、聖職を捨てて聖書を焼き捨て、私の口付けを受けなさい。クリスが私達の同族になって、クララが死んだ後も愛し続けて、クララを想いながら悠久の時を生き続ける覚悟があるというのなら、認めてやってもいいわ」
シャルロッテの提示した条件に、クリストフは動揺を隠せなかった。クララが死ぬ事はとても悲しい。それならばいっそ一緒に死んでしまいたいと思った。なのにシャルロッテは想いながら生き続けろと、酷な条件を提示する。
クララには吸血鬼になるから素直になれとは言ったものの、正直な話口説くための口実だった。のらくら言い訳をしながらやり過ごそうと思っていただけに、今の段階でシャルロッテに吸血鬼化を迫られるとは予想していなかったのだ。
結局腹黒が裏目に出たクリストフだったが、クララの事は本気だと言える自信はあった。それでもやはり、クララの死後も一人で生きていく未来を考えると、戸惑いが隠し切れなかった。
動揺するクリストフに、更にシャルロッテは言い募る。
「現にお父様はそうしているわよ。本当にお母様を愛してらっしゃったから。それとも、クリスの言った「本気」はそれが不可能なレベルだったのかしら? だとしたらそれは「本気」ではないわ。一時的な感情でクララを惑わせない……」
吹っ切れた。
言葉の途中で、クリストフが近くにあったナイフを床から引き抜いて放り投げた。その瞬間に結界が消失し、シャルロッテ+1を抱き起したクリストフが鎖の拘束も解いた。
「で?」
スッキリした体を撫でてクリストフを見上げると、やはりまだ怒っているらしく睨まれる。
「マジでムカつく女だな。女ってのはすぐに試したがる」
「愛情は確証のある物ではないから不安になるのよ。クララを不安にさせないでくれる?」
「言われなくても、わかってる」
溜息を吐いたクリストフが、ゆっくりとシャルロッテの前に膝をついた。クスッと笑ってクリストフの首筋に手をかけた時、後ろからアドルフが肩を掴んだ。
「おい待て、クリスが吸血鬼化するなんて冗談じゃねーぞ」
「冗談でこんなことをクリスが望むと思う?」
「俺は本気だって、さっきから何度も言ってるぞ」
男に二言はないものだ。しかし、そう言われても納得できなかったらしく、アドルフが間に入ってくる。
「待て待て、仮にも聖職者だぞ。許されるはずがねぇだろ」
「許さないって、誰が? 叔父様? それとも神様? その人たちの赦しがなければ、クリスとクララは愛し合う事が許されないの?」
「いや、そうじゃなくて」
「俺は――――」
説得を試みるアドルフの言葉を遮って、クリストフはいつもの通りに笑った。
「クララに比べたら他の事なんて、知ったこっちゃねぇ」
ラヴが圧勝したようだ。
「あら、見直したわ。随分熱狂的ね」
「まーな」
人種の壁どころじゃない、生物としての差異、年齢も呪いも何もかも、それを超越した恋をしてしまったら、他の事など比較すべくもなかった。
「……お前、バカだろ……」
どこか泣きそうな顔でアドルフが言った。
「そーか? 結構幸せモンだと思うけどな?」
そりゃもう幸せそうに笑うので、仕方なくアドルフも諦めた。
その様子に満足して、シャルロッテがクリストフに再び向き直った。
「じゃぁクリス、覚悟はイイかしら?」
「あぁ」
「辛いわよー我慢しなさいよー」
「……頑張る」
肩に手をかけて、シャルロッテが首筋に顔を寄せた。優しく唇を寄せて、軽く甘噛みした――――かに見えたが、クリストフは途端に苦悶の表情を浮かべて、辛そうに歯を食いしばった。
少しするとシャルロッテが口を離したと同時にクリストフが昏倒し、その体をアドルフが支えた。それを見てシャルロッテは「出来上がり」と笑った。
「これもクララとお揃いよ」
シャルロッテが撫でたクリストフの首筋には、少し赤く腫れた辺りの真ん中に、黒い刺青の様な物で「xxx」と跡が残っていた。この吸血痕は生涯消えることはない、シャルロッテの支配下の証明「ザイン・ヴィトゲンシュタイン一族」の証だ。
気を失ったクリストフをもう一度ベッドに運び、しっかり遮光してクララとクリストフ両方に頭から毛布を被せ、部屋を後にした。
部屋に戻った後二人で今後の事を会議して、シャルロッテが居間に残ってアドルフが寝室で寝ることになった。アドルフは寝ていないし、シャルロッテも失神しただけで寝てはいないのだが、アドルフの所には隊員の誰かがやってくるだろうから、受付と取次は必要だ。シャルロッテが自分で対処するからゆっくり寝るといい、と言うと、アドルフはニヤニヤと笑った。
「どーしたお前、なんか今日はやけに優しいな?」
別に優しいわけではなく、色々と気分が挫けて感傷的になっているだけだ。
「普段からそんな風なら、ちったぁ可愛げもあるんだけどな」
「これ以上可愛くなったら完璧すぎてつまらなくなるわ。うるさいからさっさと寝なさいよ」
「ヘイヘイおやすみ」
「おやすみ、二度と起きてこなくていいわ」
なんてこと言いやがる、と思ったが、ツッコんでいると血圧が上がって眠れなくなりそうだったので、諦めて寝ることにした。精神的にも肉体的にも充実し過ぎた一日だったせいか、5秒で寝た。
シャルロッテが起きて、テレビを見てゴロゴロしている間に、まずはフレデリックとアレクサンドルがやってきた。他の隊員たちは部屋の取り合いをする4人をさっさと放置して休んでしまったので、誰がどの部屋に配置されたのか知らなかった。シャルロッテがいることに驚いていたが、「昨日の仕事の報告書にどう虚偽の報告をするか考えていた」と適当に説明すると、納得いかない顔をしていたが引き下がった。
「で、課長寝てるんだ?」
フレデリックが寝室を指さした。
「そーよ。朝まで報告書作ってたから」
実際はさくっと5分で仕上げた。
クリストフとクララの事は様子を見つつ暫く隠蔽、クリストフの吸血鬼化の件は可能な限り隠蔽。吸血鬼化した為にクリストフは、最早結界師としての仕事をすることは不可能になったので、その仕事は担当を持たないイザイアに押し付ける事にした。
昼間に起きれない人員が出来てしまったので、予定していた時間に宿を出る事は出来ない。クララがいるのでもう一泊連泊手続きをし、夜になったら帰国する、と言い訳の旨を伝えると、アレクサンドルが呆れ顔をした。
「っとに、お嬢がいると経費がかさむなー」
先程同じことをアドルフにも言われた。追加の部屋代は勿論、壊した鍵の修理代も経費で払うことになったので、アドルフがチクチク文句を言っていた。
「商人でもないのに死刑執行人は吝嗇ねー。鷹揚じゃないとモテないわよ」
「俺らお嬢にはかなり寛容だと思うけどね!」
その文句にいつも通りの微笑を纏ってアレクサンドルを見上げた。
「そーね、いつもありがとう。これからもよろしくね。頼りにしてるわ」
シャルロッテの悩殺スマイルに、アレクサンドルは反射的に頷いてしまった。アレクサンドルは自分の行動に、瞬時に自己嫌悪に陥った。
「くそ、何だこの敗北感……」
なぜか落ち込むアレクサンドルを、フレデリックが気の毒そうに肩を叩いた。
アレクサンドルとフレデリックに連泊手続きと、その他諸々を他の隊員たちに伝達するようにお願いして、その後入れ代わり立ち代わりやってくる隊員たちと適当に会話した。
昨夜の件を知らない隊員たちの話題と言えば、当然ながらシャルロッテの戦闘スキルの話になる。あの場でシャルロッテの戦闘を見たとはいえ、余りの速度にその瞬間を全く把握できなかったので、戦う男としては大層気になったようだ。
「そーいえば前から気になってたんだけど、使い魔ってさぁ」
武器開発担当のレオナートは「ダーインスレイヴ」が気になるらしく、シャルロッテの手を取る。
「あの剣だけ? 他になんか出来る?」
「出来るわよ、見る?」
「見てぇ!」と目を輝かせるレオナート。
「見たい!」と同じくオリヴァー。
「見して!」とジタバタと浮かれるイザイア。
その様子に笑って立ち上がる。
シャルロッテがその場でくるりと1回転すると、遅れて黒のワンピースと黒髪が追い付く、その刹那、ワンピースと髪の毛先から夥しい数の蝶が飛び立ち、シャルロッテの周囲を周回し始める。
今は「効果」を抑えているが、この蝶の嵐で飛び交う黒揚羽の鱗粉は、即効性の神経毒だ。他にも蝶を介した情報収集などにも使える、案外便利な能力だ。
「スッゲェー!」と一人レオナートは興奮したが、オリヴァーは「なんか気持ち悪い」と引いていた。反してイザイアは「わー! お嬢服着て!」と顔を赤くした。
ちなみに服の影を蝶に使ったのはわざとだ。
「んもぅ、本当にイザイアは初心なんだからー。可愛いわねー」
「からかうなよもー!」
イザイアの反応が毎度期待を裏切らないとなれば、からかいたくもなる。アドルフと違ってからかいがいのあるイザイアは、シャルロッテの格好のオモチャだ。
そうこうしているうちにアドルフも起きてきて、夕方になってようやくクララとクリストフがやってきた。
ある程度クリストフから話は聞いたようで、クララはそれはそれは居たたまれない様子だった。
二人をソファに座らせて、シャルロッテは対面に腰かけ腕組みをし、足を組んだ。その隣にアドルフも座った。
「アディはいなくていいわよ?」
「ざけんな。ここまで関わっといて、今更仲間外れか」
「いいから」
「何がいいからだ! お前ほっとくと暴走しそうで怖ぇんだよ!」
それを懸念してシャルロッテが失神している間も、アドルフはオチオチ寝ていられなかったのだ。自分が寝ている間に目覚めたシャルロッテが、クリストフを殺しに行くのではないかと考えると、気が気ではなかった。決して失神したシャルロッテの介抱をするためではない。アドルフの目から見てシャルロッテは「自由意志の核弾頭」に等しい。昨日一日で等しくなった。
シャルロッテとしてはアドルフに聞かせたくない話があったのだが、確かに微力ながら抑止力がなければ、暴走してしまわない自信はなかったので、それで良しとした。
手始めにアドルフと会議した内容を聞かせて、二人に承諾させた。
クリストフがシャルロッテの配下の吸血鬼になったという事は、サイラスの配下になったという事だ。吸血鬼の習性上、配下の者についてはその生死や位置情報くらいはわかるので、サイラスにもわかっているだろう。なので、都合上サイラスには事情を説明するが、その他がややこしくなるのでアマデウス以下死刑執行人たちには、クリストフの吸血鬼化は絶対の秘密を厳命した。
想像には難くない。死刑執行人およびアマデウス自身、ヴァチカンの中ですら秘匿の存在だ。その存在を知る者もいるが、周りは聖職者だらけなのだ。当然のごとくアマデウスは迫害に近い扱いを受けているし、死刑執行人たちも良く思われているわけではない。
そこに更に吸血鬼が増員したとなれば、最悪の場合絶滅主義の教皇が、処刑と言う命令を下す可能性も捨てきれないのだ。
シャルロッテとアドルフの説明を聞いて、クリストフとクララは神妙に頷いた。
「それと、クララ」
ソファの肘掛けに肘をつきクララに視線をやると、クララが少し怯えた調子で返事をした。
「クリスに抱かれて嬉しかった?」
クララは顔を赤くして、俯きながら小さな声で「う……はい」と答える。
何もそんなストレートに聞かなくても、と男2人は思ったが、ツッコむと暴走しそうなので黙る。
「そう。じゃぁクララは死ぬ覚悟出来てんのね」
「はい。クリスなら、本望です」
今度はハッキリとシャルロッテを見てそう言った。
そんなクララにクリストフは感動したらしく、熱い視線を送っている。
しかしこの点に関して一切説明のないアドルフは、首を傾げてシャルロッテを見た。
「つかよ、死ぬとか何とか何の関係があるんだよ? 恋人になるだけなのにそんな一大事?」
「そんな一大事よ、私達にとっては」
「なにが?」
「セックスが」
「はぁ?」
アドルフにはチンプンカンプンだ。それが生死を左右するとはどういう事だと頭を悩ませたが、ふと昨夜のクララの言葉を思い出した。
――――何回しても痛いってお嬢様も言ってたし……。
この時は、処女ならそうだろうと思った。だがよく考えたら、銃弾を受けても無傷のはずのシャルロッテが、痛い思いをすることなど考えられなかった。どう考えても性交痛より撃たれる方が遥かに痛いはずだ。
「毎回痛いって、お前でも痛いことあんの?」
「あるわよ。そりゃもう痛いから、二度としたくないわ。慣れないわーアレ」
「普通2度目からは痛くねぇって言うだろ」
「私達は何度経験しても痛いのよ、“永遠の処女”だから」
なんだその素敵な響きは、と思ったが、それを言うと殺されそうなので黙り、再び考える。
痛いのは毎回処女膜が破られるからだ。とすると、吸血鬼の再生力を以て、破れたその場で再生してしまうという事になる。痛みを感じる原因は不明だが、通常痛みとは生命に関わる損傷に対する危険信号の度合いの事を言う。となれば、銃撃されたりなどの外傷は特に痛みも感じないが、性交痛は命に関わるという事だ。
とすると、浮かんでくる結論。
「その程度で痛いって事は、出産なんてことになったらヤバくね?」
「そーよ。だから私のお母様は亡くなったのよ」
なんだか色々と合点がいった。人間女性なら一度しか経験しない、絶叫を上げる苦痛を彼女たちは毎回味わう。しかも出産の際の苦痛に、彼女たちの体は耐えることが出来ない。
昨夜、クララがクリストフに耳打ちした。
「私とお嬢様を、人間でも確実に殺せる、素敵な方法です――――好きな人の子供を産むこと」
だから、どうせ死ぬなら愛する男に。愛する人の子供を身籠って、その生命を紡いで死んでいきたい。相手にその秘密を明かさないことはフェアじゃない。だから理解してもらった上で、覚悟をしてもらう。愛情の表現、妊娠が絶命に直結する――――彼女たちを殺害するという、愛。その覚悟ができる男を、絶対的な愛情を信頼できない限り、彼女達が男に肌を許すことなどあり得ない。
「クララにとって、クリスはその資格者足り得るのね?」
「はい」
真っ直ぐにシャルロッテを見つめて返事をしたクララに、ふぅと息を吐いた。
「まぁいいわ。私の口付けを受けた意気や良し、許したげるわ」
許可を下すと、クララとクリストフは手を取り合って喜んだ。
それを見て付け加えた。
「あともう一つ。クララは多分死なないから安心して」
その言葉に3人ともが、「え、どゆ事?」と眉を顰めた。
「クララは10歳で体の時間が停まってるのよ。クララは人間だった頃、月経来てた?」
問われてクララは口元を抑え、「あ!」と声を上げた。
月経が来ていない、つまりは体が妊娠する用意が出来ていない。妊娠しない以上、何をしてもクララは死ぬ事はない。
「よかったわねー。アンタら好き放題イチャイチャできるわよー。さーて帰ろうかしら」
話は終わり、とさっさと立ち上がり荷物の整理を始めたシャルロッテだったが、待ったをかけたのはクリストフだ。
「ちょい待ち! て事はお嬢、クララが死なないってわかってて、俺に吸血鬼化迫ったのか!」
「そーだけど?」
ケロリと答えたシャルロッテに、クリストフは頭を抱えて悶絶した。
「クソォォ! この性悪女! ハメやがったな!」
「クララをハメたのはクリスじゃない」
「嫌な言い方すんなよさっきからさぁぁ!」
「うるさいわねー」
シャルロッテが適当にあしらうので余計にクリストフは腹を立てたが、慌ててクララがそれを諌めにかかる。
「クリス、嫌でしたか?」
涙目クララはリーサルウェポンなので、クリストフは途端にしおらしくなった。
「い、嫌じゃないけど……」
「クリスが吸血鬼になってくれて、私嬉しかったです。私が死ななくて済むなら、これからもずっと一緒にいられるんだって……クリスは嬉しくないですか?」
「う、嬉しいデス」
それを聞いて途端に顔を綻ばせたクララに、クリストフは白旗を上げた。
実際吸血鬼化した為に、これから老いる事も死ぬ事もなく、二人で生きていける。その事実に変わりはないのだ。そのこと自体は、正直に言うと飛び上がるほど嬉しかった。
「お嬢さんの事は、末永く大事にしマス」
「ダイヤの指輪でも贈るのね」
「そうしマス」
大事なクララをクリストフに取られた。嫉妬が爆発したシャルロッテの小さな復讐は、見事に成功した。
城に帰り、報告を聞いたサイラスの提案により、吸血鬼化を隠すためには恋人になったことは公表した方が都合がいいと言われた。
死刑執行人たちは仕事柄、ほとんどの活動が夜間になる。が、昼間に全く活動がないと言う訳ではない。昼間に起きることが出来なくなったクリストフの違和感が出ないようにするには、付き合っていることを公表して、クララがついて行く(若しくは連れて行く)と駄々をこねたとでもしておいた方がいい。そうすれば昼間の活動を回避せざるを得なくなる。納得はするしほやほやカップルはどことなく嬉しそうだが、シャルロッテとアドルフは苦渋の表情をした。が、今後の事を考えると案外都合がいいかもしれないと、いち早く考え直したシャルロッテが、ならば自分も同行すると申し出た。それを聞いて更に苦渋の表情を浮かべるアドルフ。
「お前が来る必要がどこに?」
「クララを一人、男所帯に放っておきたくないわ」
「クリスがいるなら平気だろ」
「クリスがいるから平気じゃないのよ」
付き合う事は許してやったが、根に持っている。そしてクララを取られてしまったようで、少し悔しい。シャルロッテが口を尖らせるのを見て、サイラスが笑った。
「ははは、ロッテは子離れしないな」
どこか嬉しそうだ。
「お父様に言われたくありませんわ」
言葉のナイフが深々と刺さり、サイラスは俄かに落ち込んだ。が、すぐに開き直った。この辺りは親子だ、よく似た。すぐにクリストフに笑いかけた。
「クリストフを我が一族に歓迎しよう。クララをよろしく」
シャルロッテと違い物わかりのいいサイラスに、クリストフは大層喜んでお礼を言った。
吸血鬼化したクリストフは、今後一切老いる事も怪我をすることも、余程の事がなければ死ぬ事もない。それは人間の目から見ても明らかに不自然なので、長い目で見ても10年以内には姿を消す必要がある。が、彼らはヴァチカンの裏の顔、人に知られてはいけない存在である彼らは、一生涯ヴァチカンの仕事から離れることは許されない。例え逃げたとしても追っ手を差し向けられ、その存在が人に知られる前に、消されてしまうのは目に見えている。
「10年の間に、私とロッテで何かしら対策を立てよう。お前達はとにかく隠蔽に徹しろ。今後の事は我々に任せておけ」
サイラスの決定を受けて、この親子の頭なら任せて問題なさそうだと納得し、3人は素直に頷いた。
3人がサイラスの部屋から出て行って、サイラスと二人、溜息を吐いた。クララをクリストフに近づけた事で、恋人同士になったことは大誤算だったが、予定していた以上の効果は上がった。それには満足だ。愉快そうにサイラスが笑った。
「私には予想の範囲内だったがな?」
「まぁ、お父様はクリスがヘンタイだと御存知だったのですか」
「ヘンタイでなくともクララの様な娘に、心を動かされない男は中々おらん」
その返答を聞いて、男ってバカねーと思いながら息を吐くシャルロッテに、やはりサイラスは愉快そうにした。
「予定通り、クリストフは手に入った。小僧は?」
「アディには母親の事で揺さぶりをかけておきました。アディは繊細なのであまり踏み込むと逆効果だし、もう少し手間が必要そうだけど、こちらの手の内に落ちるのは時間の問題ですよ」
「そうか」
頷いたサイラスが、とても愉快そうに笑ってシャルロッテを覗き込んできた。
「実はな、すごく面白い事を思いついた」
「なんですか?」
「お前を正真正銘のお姫様にしてやろう」
首を傾げた。
「なんです?」
「まぁ聞け」
サイラスの思いついた「すごく面白い事」を聞き、シャルロッテは目を輝かせて手を叩いた。
「それは本当に面白いですね!」
「そうだろう?」
「流石お父様だわ! 鬼才は健在ですね!」
「まだ耄碌するには早いわ」
かつてはその鬼才をふるい、人間時代は王として軍人として悪名を馳せ、狂気の不死王と呼ばれたサイラスだ。耄碌はしていないが老獪な親子二人、新たな遊びを発見して二人でキャッキャと作戦を立てた。
クララとクリストフが付き合い始めた事を公表すると、全員がクリストフの敵に回った。
「副長め……」
「俺らのアイドルなのに抜け駆けしやがって!」
「クララちゃんはみんなのクララちゃんなんだぞ!」
この辺りは予想済みだったので、一斉に攻撃の的となったクリストフを見てほくそ笑んでいたのだが、そこにクララが弁護に入った。
「クリスは悪くないんです。吸血鬼なのに、私が好きになっちゃったんですー!」
クララの弁護を受けて感動したらしいクリストフは、クララの前に跪いてひしっと抱きしめた。
「何言ってんだよ、俺の方が先に好きになったのに」
クララも精一杯腕を伸ばして抱きしめ返す。
「でも私、ずっと子供なのに、クリス……ごめんなさい」
「謝るなよ……今でも……いや今こそ充分、クララは可愛いよ」
「クリス……」
体を離し、見つめ合う二人。完全に二人だけの次元を構築してしまっていたので、テーブルの上に置いてあった果物ナイフを投げたと同時に、銃声が響いた。驚いて目を剥くカップルの顔の間、壁に刺さり刀身を震わせる果物ナイフと、硝煙を上げる弾痕。
「うぜぇからやめろ」
「目障りね、殺すわよ(主にクリス)」
愛用の銃“ファントム”を仕舞いながらアドルフが睨み、ツンと言い放って一瞥するシャルロッテ。カップルに辟易しだした隊員たちは、獰猛な二人に賞賛の眼差しを向けた。この瞬間、シャルロッテとアドルフの間で、妙な連帯感が芽生えた。
一方の二人は顔を青くして、ゆっくりと離れた。
「すみませんお嬢様」
空気読んでませんでした、と申し訳なさそうにするクララに「気を付けるのよ」と優しく微笑んだ。
「すみませんでしたお義母様」
「誰がお義母様よ、拷問の末火炙りにして殺されたいの?」
「ご、ごめんなさい」
クリストフにはあくまでスパルタで行く。こうして二人は目障りではなくなったが、クリストフはシャルロッテを筆頭にした嫉妬の嵐に被災した。
クリストフに嫉妬して、あるいは羨ましがって、しかしみんな最終的には二人を祝福した。その様子をどこか冷めた気分で眺めた。
恋なんていつかは終わるものだ。サイラスはもう200年以上エリザベートを一途に想い続けているが、それは死んだからそうなのかもしれないとも思う。失ってしまったから、あんなにも素晴らしいものに見えるのではないかと思う。もし生きていたら、わからないのではないか。シャルロッテがいるから、エリザベートの幻影に憑りつかれているとも思えた。
吸血鬼、シャルロッテの一族は記憶力がいい。今まで見聞きしたことを色々と覚えている。いい事も悪いことも。いい事を覚えていられるのはとても幸せだと思うが、悪いこともいつまで経っても忘れられずに、執着する羽目になる。それは、長生きするうえでは弊害でしかない。
クララとクリストフ、二人を見て願う。
クララが死なない運命に心から感謝する。
クララを愛してくれたクリストフに感謝する。
その愛が不変であることを一途に願う。
だからどうか、クララを幸せに。
母エリザベートと、サイラスとシャルロッテ。
ザイン・ヴィトゲンシュタインの苦悩を二人が背負わないように、心から願ってやまない。
必要悪 ― Schwarz ― Vampir des Einsatz


