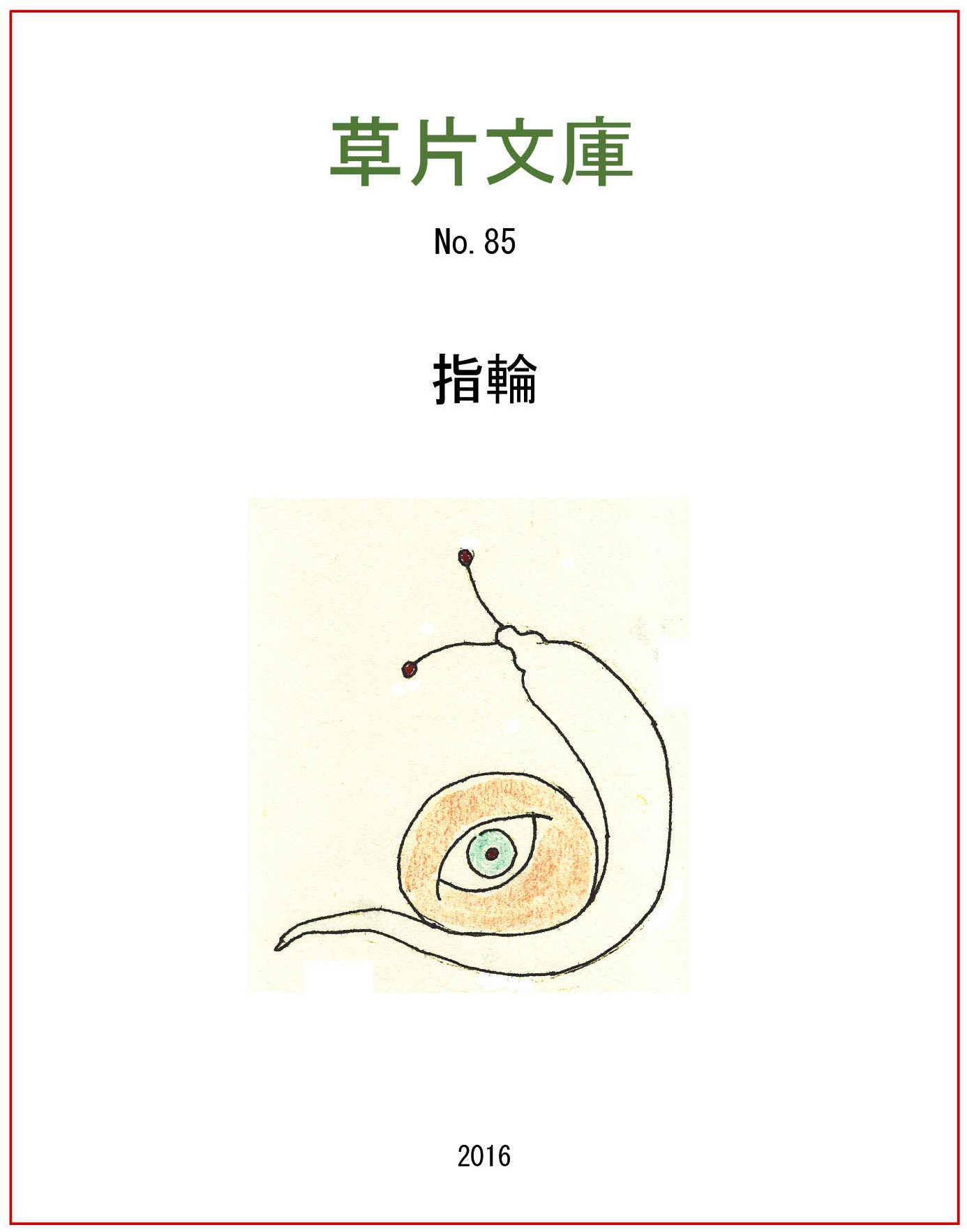
指輪
左手の小指に銀製の指輪がはまっている。銀色の二匹の蛇が互いに絡み合い、向き合って舌を絡ませている。なんとなく気味の悪い顔でもあるし、見方によってはかなりエロティックなものである。脇から見ると雄と雌の様でもあるが、片方の頭から見ると雌と雌の様でもあり、反対から見ると雄と雄の様にも見える。なぜだろう、深く考えたことはないが、小指にはめたその時、そんな風に思った。それ以来、あまり意識をすることなく、はめたままになっている。
この指輪は京都の街中の暗がりで手に入れた。というか買わされた。仕事で京都に来て、一段落した後、飲み屋で飲んでホテルに帰る途中のことである。
小さな通りの暗がりから、黒っぽい服装の女がでてきた。女は黒っぽいというより、ちょっと汚れたねずみ色のシャツと茶色っぽいジーンズをはいていた。だから黒装束のように見えたのだろう。
女は僕に気付くと近寄って来た。
「お願いがあります」
彫りの深い浅黒い顔、太い眉毛、大きな目、アラブ系の人だろうか。日本語はかなり流暢のようだ。旅行者のようでもある。
京都は外人観光客が多い。だから珍しいわけではないが、この夜更けにこんな出会いをするとちょっと戸惑う。
立ち止まると、女はいきなり、「これを買ってもらえませんか」とその指にはめられている指輪を見せた。当然のことこちらも身構えてしまう。
「すみません、お金がいるもので、大事な指輪ですが」
僕が黙っていると、「いくらでもかまいません、お願いします」と、俯いた。
「どうして警察に相談しに行かないのです」
女の話す日本語は丁寧なものである。
「パスポートありません、携帯も持っていないし、一万円あれば知っている人のところまでタクシーでいけます」
不正入国者なのだろうか。
「パスポートはあったのですが、悪い仲間に取り上げられました。友人のところに行けば助けてもらえます」
どうしようか迷った。一万円なら貸してもいいが、関わるとまずいような感じも受ける。
「でも、大事な指輪なのでしょう」
「もし、無事に友達のところに着いたら、友達からもらってあなたに一万円返します、その時、指輪を返してもらえれば私は嬉しいのですが」
そこまで言うならいいかと思い、それじゃあと一万円を渡すと、女は「リリスといいます、電話番号教えてください」と言う。
変なことが起こるといやだとは思ったが、酔っていたこともあり、電話番号を教えてしまった。女はいきなり僕の左手首をつかむと、指輪を僕の小指に直接通した。女の指はかなり細いが、なぜか指輪はすっと僕の小指の根元に入り、その時、二匹の蛇が雌と雄に見えたり、雌同士に見えたり、雄同士に見えたりしたのである。
「これは銀で出来た古いもので、我家に伝わるものです、確かなことは分かりませんが、千年も前につくられたものと祖父から聞いたことがあります。悪魔を寄せ付けないといわれています」
小説に出てくるような話で、あまり信じられるものではない。
女は「ありがとうございました」とずい分丁寧にお辞儀をして、大通りのほうに歩いていってしまった。
改めて指輪を見たが確かにその辺の安物とは違うような雰囲気はある。アンティークは嫌いではないので、損をした気にはならなかった。ただ、女の話を信じたわけではない。電話があれば返せばいいことだし、とりあえず預かっておこうといった程度の気持ちで小指の指輪はそのままにした。
京都にいる間にリリスから電話は無かった。
東京に戻り、部長に京都での商談について報告をすると、自分のデスクに戻った。
左隣の僕より五年早く会社に入ったベテランの女性が、いち早く僕の小指の指輪に気が付いた。
「あら、珍しい、指輪をする趣味があったの」
「いや、事情があって」
「いい指輪ね、高かったでしょう」
「僕にはどのくらいの価値か分からなかったんだけど、知り合いにお金を貸して、その質草のようなもので、お金を返してくれたらこれも返すのです」
「いくら貸したの」
「一万円」
「へえ、十万はするわね、いやもっとかも」
この女性はネックレス、指輪、イアリングなど凝ったものを身につけている。そんな彼女がいうくらいだから、この指輪もそれなりのものなのだろう。
東京に戻ってからも、リリスから電話はかかってこなかった。無事に友人に会えたのならいいのだが、と思いながら、仕事がなかなか順調で休む暇もなく国中を走り回っていた。そうこうしているうちに一年経ってしまった。その間、風呂に入る時も外さなかったし、寝る時もそのままだった。指輪をしていることを全く忘れていた。
僕は係長に昇進した。誰もが祝福してくれた。大きな商談をまとめることができたからだ。おかげでうちのチームそのものが会社の中でも認められた形になり、同僚達も大いに喜んでくれたのである。
祝宴を終え、自分のアパートに帰り、相変わらずの独身用シングルベッドに倒れこんだ。明日は日曜だから寝坊が出来る。一度起き上がりパジャマに着替えると、そのまま朝までぐっすりと寝てしまった。
朝の九時である。夏も終わりの日曜日、この時間でも両隣から音が聞こえてこない。このアパートには似たり寄ったりの独身男が住んでいる。いつもだと七時ごろにはがたごとと朝の支度の音が聞こえる。
僕はベッドに入ったまま、左腕を伸ばして脇の窓を開けた。二階からの景色は家に囲まれた殺風景なものではあるが、青空が少しでも見ることができるのはありがたい。朝という味の付いた風が入ってくる。
左腕をドカンとベッドにだらしなく伸ばし、煙草でも吸おうかと思ったときであった。ピリッと強い痛みが左手の小指に走った。全身がびくっと丸くなるほどであった。一本の太い神経が切れちまったのかねじくれたのか、飛び上がるほどの痛みだ。
寝たまま左手を目の前に持ち上げ小指を見た。その時には痛みは止まっていた。一瞬のことだったのである。
だが小指の先から、ケチャップの混じったような黄色いどろりとしたものが染み出していた。まだ出ている。垂れそうだ。あわてて枕もとのティッシュで拭き取った。紙を見ると膿のようだ。拭き取った後からぬるっとした透明のものがでてきた。ふーっとカツオブシと溝の泥の混じった匂いが鼻をついた。やな匂いだ。
もう一度ティッシュで拭いた。膿んでいる。
どうしたのだろうか。僕は起き上がってベッドに腰掛けると、小指をじっくりと見た。もう膿みは止まっている。棘でも刺さっているのだろうか。
洗面所から薬箱をもってきてオキシフルをつけてみた。泡は出ない。刺さっているようなものもない。消毒薬をつけた。
小指を押してみたが、もう痛くも痒くもなくなっていた。
その日はプールに泳ぎに行き、一遊びして家に帰った。小指のことは忘れていた。
その夜、ベッドにはいったとたん、また小指に痛みが走った。あわてて、起き上がり小指を見ると、黄色い膿みのようなものが染み出ており、溝泥の匂いがした。治ったわけではなさそうだ。ティッシュで拭き取るとティッシュの上に黄色い染みが広がった。小指を揉んでみたが全く痛くもない。にもかかわらず、指先からまた透明のどろっとした液体が出てきた。拭き取ると朝と同様に消毒し今度はバンドエードをつけた。しばらくすると痛みは消え、そのまま横になると、いつの間にか眠ってしまった。
いつもは夢を見るということはほとんどないのだが、その夜は夢を見た。どうも灯りを消さずに寝たかららしい。
いきなり他人の手が僕の顔をなでた。ひゃっとして、ぞくっとからだが振るえた。誰が部屋に入ってきたのだ、その手をぱっと振り払って目が覚めた。自分の左手がベッドの脇に打ちつけられた。左手はしびれて感覚がなかった。
理由がわかった。寝るときにベッドの上で腕組みをして寝ていたようだ。そのために腕がしびれたのである。感覚のなくなった左手が何かの拍子に自分の顔にかぶさり、他人の手が顔をなでたような錯覚に落ち、右手で左手を払ってしまった。
目が覚めた僕は左手を揉み解した。左手がジーンとして、痺れが元に戻ってきた。やがて打ち付けたところに痛みがでた。
時計は三時五分過ぎを示していた。電気を消ししばらくすると再度眠りについた。
月曜日の朝、小指はいつもと変わりなく、全く何もなかったように動かすことができた。また忙しい一週間が始まる。
その日、遅くまで仕事をした。夜の十時半、食事は家の近くのいつものところですませ、帰ると風呂に入って、ウイスキーを一口飲み、ベッドに入った。
その夜、むずがゆさを伴った血液の流れが左手に感じられ目が開いた。布団の中で指を折り曲げてみた。小指だけが思うように動かない。左手を布団から出し、顔の上にあげた。むずむずしていて気持ちが悪い。それがいきなり止まったと思うやいなや、昨夜と同じように、痛烈な痛みがぴぴーーと走った。心臓のほうが爆発するかと思うような痛みである。それがあっという間に過ぎ去ると、今度は痒くなった。痒くて痒くて小指の先っちょが笑い崩れそうだ。右手で小指を掻いた。ぽりぽりと掻いた。気持ちがいい。もっと掻いた。快感はさらに強まった。右手は強く強く左の小指に爪を立てた。痒いときに思いっきり掻く気持ちのよさ、あとのことなど考えない。快楽に没した状態だ。
快感が頂点に達した時、右手にぬるっとしたものが感じられた。ふっと快感が恐怖に変わった。昨日の夜を思い出した。僕は枕もとの電灯のスイッチを押した。
明かりがいきなり目をさした。目が落ち着くと小指が見えた。小指はどろりとした赤黒いもので覆われていた。黄色い汁も混じっていた。
ティッシュで拭き取ると小指を押した。痒くて気持ちがいい。赤黒い汁の中に白いものが搾り出された。白いどろどろが赤い汁に混じり溝泥の匂いを発した。
膿は掛け布団の上に滴り落ち染みとして広がった。
僕は布団を出て小指の汁を拭き取り消毒した。かゆみは終わったが、気持ちが落ち着かなくなった。病名は全く想像がつかない。知っているのは破傷風ぐらいである。だが土いじりをしたわけでもなく、破傷風にかかるようなことをしていない。
医者によってから仕事に行こう。そう思い何とか落ち着いてもう一度眠ることが出来た。
朝起きても小指の先から赤黒い汁に白いものが混じって浸み出していた。布団にだいぶ汚れが付いた。これでは食欲も湧かない。まず医者に行こう。
ほとんど病気らしい病気をしたことがないが、一度インフルエンザで行ったことのある医院が近くにある。
仕事に行く用意をし、会社に遅れることを連絡して、そのまま医者に行った。一時間も待たされたが、診察室に入ると、小太りな女医は僕を覚えていた。笑っている。
「今度はどうしました。風邪ですか」
全くこの医者ときたら失礼なこった。笑う理由はわかっている。インフルエンザで来たとき、僕が注射を怖がったのを覚えているのだ。
「注射しないようにしますよ」
何の病気か分からないのに無責任なことをいう。まあいいか。
「小指が痛くて痒くて膿がしみ出すのできたのですが」
僕は椅子に座ると、医者に小指を突き出した。
「面白い指輪しているのね」
そういいながら女医さんは眼鏡をかけなおすと、小指を見て、
「なんも見当たりませんね」といいながら、指で僕の小指をつまんだ。
「痛いの」
「いや、今は痛くないのですが、寝るとき急にピリッとして膿が出ました、二晩続けてです」
「昼間はどうだったの」
「なんともなかったです」
「傷はないし、炎症を起しているようでもないし、仕事をさぼりたかったのかしら」
全く余計なことをいう。
「いえ、本当に痛かったので」
「折れている様子もヒビがいっている様子もないわよ、小指、誰かに噛まれたの」
何だこの医者はまじめじゃない。
「いや、そんな僕はまじめです」
と言ったら、医者は指輪をつまんで「きつくなさそうだし」
丸っこい顔を、ひしゃげて笑った。
「アルコール消毒をして、ビタミン剤を出しておきますね、疲れているのかも」
アルコール綿で小指を拭き僕の目を見た。
「目が充血しているから、目薬もだしますね」
「はいありがとうございます」と自分から席を立った。
医者はこちらも見ないで「次の人」と叫んだ。それで初診料と合わせて二千五百円もとられてしまった。
薬をもらって仕事場に行くと、となりの女性が、
「お医者によってきたのでしょ、大丈夫」と聞いた。
「うん、薬もらったから」
「どうしたの」
「小指が膿んで」
僕が小指を出すと、「なんにもなっていないじゃない」というから、「薬を塗ったんだ」と言うと、「噛まれたの」と医者と同じことを言った。
ちょっとしゃくに障るので、小指を思い切りしごいてみた。すると小指の先から白い汁がでてきた。
「あ、ほんと、乳絞りみたいね」
女性が目を丸くしたので、「なんか匂いがしない」ときいたのだが首を横に振った。
まあそれで小指に何か起こっていることだけは納得してもらった。医者の前でもこうすればよかったとちょっとばかり反省した。
医者の薬を飲み始めてからもさしたる変わりがなかった。変わったといえば、昼間はおかしくないのに、家に帰ると、とたんに痛みが走るようになった。玄関に入るとそれがおきた。膿がじくじくと出てきて、透明の液体やら乳白色の液体やらが染み出し悪臭が漂う。その匂いたるやまさに溝泥なのだが尋常ではない。部屋中へ汚泥がたまったような気持ちになる。夕食を食べるのさえいやになってしまう。だから、ほとんど外食になった。エアコンで空気清浄を行なうのだが、この匂いが外に洩れたら何事かと驚くのではないだろうか。まず膿を出すと包帯を巻いた。少なくとも包帯が膿を吸収してくれる。寝る前に一度取り替え、朝になって拭き取って会社に行く。そんなパターンになった。
痛む時間はほんの数秒である。だから我慢できないことはないが、匂いで体がおかしくなりそうだ。それに左手の小指だからといって馬鹿に出来ない。家で何かをしようとするとかなり不便さを感じる。
ある日、一日痛みが起きないことがあった。ただ膿は赤黄色く染み出している。その都度拭くのだがすぐ出てきて、白い汁になるとすさまじい匂いが出る。その日から膿の色が赤黒っぽくなり、それに黄色の汁が混じるといった状態になった。
ところが不思議なことは、会社では全く普通の小指だった。その点は助かった。ただこの苦しさを知るものは誰もいない。
秋風が吹くようになった。目が覚め、ベッドの上で両手をあげて伸びをすると、そのままの姿勢で窓を開けた。小指がちょっと窓に触れて包帯がずれた。小指の先でぶら下がっている。小指の先が白っぽく細くなっている。おやおやと思って右手で左手の小指を触るととても硬い。痛みはない。小指を目に近付けて見ると、背筋に水を浴びたようにぞーっとした。それは骨だった。第一関節から先の指骨が露出していたのである。肉が溶けてしまった。腐ったといったほうがよいのかもしれない。
骨を触っても何も感じない。骨を摘まんだところ、あっと声を出してしまった。すぽっと抜けたのである。第二関節から先の骨がすぽんと抜けてしまった。小指の先に穴があいた。
その穴に赤黒い膿が溜まりだした。ティッシュを指先に押し付けると、今度は第二関節のところから肉が崩れてとれてしまった。僕の左手の小指は根元の指輪しか見えなくなった。なぜか指輪は抜け落ちない。
こうして小指がなくなってしまったので、しかたがなく包帯を巻いて会社に行った。
隣の席の彼女は「小指短くなったのね」と不思議そうな顔をした。
「とれちゃったんだ」
「医者には見せたの」
「いいや、行きつけの医者は気に入らないんだ」
「今日、医務室にお医者さん来ているよ、診てもらったら」
そうかその日は週に一度産業医が来る日である。課長に事情を言って医務室にいった。一度喉が痛くて見てもらったことがある。
「どうしました」
僕が入っていくと医者が角ばった顔を向けた。
「顔色や動きは何も問題なさそうだけど」
「小指がなくなりました」
医者がえっと言う顔で僕を見て、「まあ、おかけなさい」と椅子を勧めてくれた。
腰掛けて包帯をとって見せると、何だという顔をした。
「痛くありませんか」
僕は首を振った。
「いつごろから、どういう風にこんなになったんでしょうね」
僕は小指が腐っていった状況を話した。
「細菌性なのでしょうけど、大学病院にいって何の菌だか調べないと、ここじゃ何も分かりませんね、消毒薬と抗生物質を出しておきましょう、紹介状を書きますから調べてもらったほうがいい、それにしても指輪がよく落ちないねえ、指輪より下の組織は問題ないようだから、もう腐食は終ってるね」
ということとで大学病院にいった。レントゲンを撮ったりして調べたが、細菌は発見されず、病名は分からなかった。産業医と同じでもう大丈夫でしょうということだった。
小指がなくなってとうとう一年もたってしまった。左手の小指がないのにも慣れた。友人には指をつめたのかといわれたり、電気鋸でやったのだろうとか言われたが、適当に相槌をうっておいた。
暑い夏が終わったある日、会社で仕事をしていた時に、携帯が鳴った。着信を見ても誰からの電話か分からなかったが電話に出た。男の声がして、たどたどしい日本語で、僕の名前を言って、本人かどうかきいてきた。そうだと答えると、
「家内のリリスがお世話になりました。借りたお金を返したいのですが、どこにお持ちしていいですか」
と言った。もう二年以上前になるだろう。京都でリリスという外国人の女性に一万円貸したことを思い出した。
「あの、京都で貸したお金のことですか」と確かめると、そうだという返事である。
「あれから、彼女と結婚して、いろいろ忙しく、返すのが遅くなりすみませんでした」と話した。
「でも僕は東京だから、機会があったときでかまいません」と返事をすると、
「新婚旅行で東京に出てきています、数日東京にいて国に帰ります」
ということだった。夕方、彼らの泊まっているホテルのロビーで会う約束をした。
東京でも有名な高級なホテルである。足を踏み入れるのが気後れするほど立派なロビーで、あのときの女性と背の高い紳士がソファーに腰掛けて待っていた。
彼は立ち上がると、丁重に自己紹介をし、改めて女性を紹介してくれた。名刺を見ると彼は大きな会社を営む実業家であった。
「私はルシュファーと申します、リリスがお世話になりました」
このような立派な人がいたのに、どうしてあんなところにいたのか想像ができない。それを察したように、彼が、
「この人は闇の組織で売られて東京で働かされていたのですが、たまたま、あるとき京都で働いていた私のことを知って、何とか京都までやってきたのです、この人は私の妹の友達です」
今までのことを詳しく話してくれて僕も納得した。
「どうもありがとうございました」
リリスが封筒に入ったお金を私に渡した。
「お役に立てて、良かったです、連絡がなかったので、どうなったのかちょっと心配でした」
僕は小指にはまったままの指輪を外そうとした。ところがなかなか外れない。肉が盛り上がっているのかもしれない。
「その小指どうしました」
リリスが心配そうに僕の小指を見た。
「もう治ったのですが、悪いばい菌に冒されたみたいです」
僕は小指の指輪を思いっきり引っ張った。彼女はルシュファーに僕の指を見るように促した。彼は僕の小指を困ったような目で見ていたが、彼女に向かって頷いた。それがどんな意味なのか僕は考えもしなかった。
やっとの思いで小指から二匹の蛇の指輪を外すと、ハンカチで拭いて彼女に返した。
「入れたままにしていたので、汚れてしまってすみません」
「いえ、本当にありがとうございました」
リリスは受け取ると、彼に何やらを促している。彼は自分の左手の腕にはめていた、茶色の石でできている腕輪を外して僕に差し出した。
「この腕輪は指輪ほどではないのですが、魔よけのもので二百年ほど前のものです。どうぞこれを左手にしておいてください、指輪を返していただいて、本当に感謝しています」
僕は腕輪などしたことはないが、気持ちなのでありがたく頂戴した。
その日は彼らの招待で、ホテルの中華レストランで上等な食事をして家に帰った。
その二日後、夜中に左手の残っている全ての指に痛みが走り、悪臭が漂ってきた。またかと思ってベッドの上で左手を見ると、指の先から膿が浸み出している。小指のようになくなってしまったら大変だ。ティッシュで膿を拭いて包帯を巻いた。
朝まで眠れず、しかも無性に痒くなり右手でごしごし掻いていると包帯ごとすべての指の肉が落ちてしまい、骨だけになった。さらに骨は見ている先からポロリ、ポロリと落ち、左手のすべての指がなくなってしまった。
僕は起き上がり、骨を拾ってタクシーで大学病院に行った。受付はまだ開いていなかったが事情を話すと、当直の救急医が見てくれた。
「こりゃあ大変ですね」と、レントゲンを撮ったり、前のカルテを持って来て調べたりよくしてくれた。医者の見ている間に左手の手首より先が赤黒くどろどろと腐っていき、すごい匂いを放って溶け落ちてしまった。骨も一緒にである。
初めて他人の前で手が溶けた。
医者もあまりの出来事にびっくりして、ともかくその日は検査のため入院となった。
血液検査でも異常は見つからず、腐敗させるような細菌類もなかった。それから数日入院し、皮膚科や細菌学の教授までわざわざ病室に見にきたが、結論は無理やりとっつけたようなもので、僕には理解は無理だった。
「細胞が自分で死んでしまう病気の一種でしょう、細胞の検査をしますが、他には悪いところもないし、伝染性もないようだから、お仕事されていいですよ」と退院になった。
左手首から先を失った僕は手首の付け根の腕輪が落ちずに付いているのを見て、不思議な気持ちになった。指輪の時と同じようだ。
久しぶりに会社に行ったら課長に、できることをやるように言われた。左手がなくても文章は打てる。営業回りも大丈夫だが、車の運転は特別な訓練を必要とする。身体障害者の手帳をもらうことになった。
左手首の欠損には意外と早く慣れることが出来た。
ある日、京都にまた出張に行くことになった。出張先で商談先の女社長が僕の左手に目を留めた。
「左手はどうなすったの」
僕の左腕をしげしげと見ている。
「ちょっと怪我をして」
僕は病気といわず、怪我と嘘を言った。しかし彼女が見ていたものは左手ではなかった。別のものだった。
「素敵な腕輪をしているわね」
僕の腕輪をちらちらと見ている。
「ずいぶん古そう、高価なものね、私腕輪好きなのよ」
と僕を見つめた。
商談をまとめるには、腕輪が役に立ちそうである。そこで気に入っていただいたのなら、差し上げないこともないようなことを言ってから話をまとめた。かなり大きな契約なので会社は喜ぶだろう。左手首がなくなっても雇ってくれている会社にちょっと恩義も感じている。
「これは記念に差し上げます。僕もいただいたもので、古いものだとは聞いています。癖でずーっとやっていましたが、手先がない手首に腕輪をしておくのもなんですのでどうぞ」
「え、大事にしていたものをただでは悪いわ、本当は食事にでもお誘いすればいいのでしょうけど、今日は先約があるからこれで食事してください」
と封筒をわたされた。
僕は恐縮して、ともかく腕輪を渡し、その封筒をいただいた。そして意気揚々と会社に戻り成果を報告したのである。課長をはじめ、みな僕を賞賛したのは言うまでもない。それに女社長さんがくれた封筒には十万円も入っていたのである。
その日は気分をよくして、いつも買えないような上等なウイスキーを買って家に帰った。明日は土曜日、友達に電話してどこかに遊びに行って、うまいものを食べる約束もした。もらった十万円でおごってやるのだ。
ウイスキーはうまかった。
だが、人生、なにかが足りなかったといまさら悔やんでもしょうがない。
その夜中、全身にぴりーっと痛みが走った。また、と思い目を覚まし、灯りをつけるともう遅かった。体から白い膿が染み出してきていた。
臍が痒い。パジャマの中に右手を入れて掻くとポロリと取れて、右手の指の先もぐにゃりと溶けた。男のものがそそり立ってきて残りの精子が膿となって噴出し、パジャマを汚し、男のものそのものも溶けおちた。その後が痒いのだが掻くことが出来ない。腹の臓物もみな膿となり染み出してきた。溝泥の匂いが部屋に漂ってきた。
やっと分かった。小指の指輪を外したために指先が腐ってしまったのだ。あの指輪は強い魔よけだといっていた。指輪はそこまでで食い止めてくれたのだ。僕の無くなった小指を見たリリスの夫、ルシュファーはどうなるか分かったので、腕輪をくれて、手先だけで食い止めてくれたのだ。それをあの社長にやってしまった。僕は腐っていくしかなかった。
声を上げようとしたが、舌がもうぐずぐずと崩れ落ちていた。脳は元気なようで、これから腐っていく自分を見届けなければならないようだ。
パジャマの袖やズボンの先から溶けた自分の体がベッドの上に流れていく。
明日の朝、遊ぶ約束をした友人たちが、連絡のつかなくなった僕のアパートに来るだろう、そしてベッドの上の膿の溜りを見ることになる。
もう足の骨も手の骨も溶けている。
ベッドの脇に二人の人影が見える。だが眼も溶けてきた。
「ルシュファー、面白いわねえ」
「ああ、リリス、人間が生きながら腐るのを見るのはいつ見てもいいものだな」
そんな会話が聞こえてきた。彼らが来ている。
僕を眺めている。彼らは何者なんだ。
脳ももう膿に変わりつつあるようだ。
僕はこの人生を食い止めることが出来たのであろうか。
どっちみち彼らにつかまったら逆らうことは無理なのだろう。
これが僕の人生なのか。
ルシュファーとリリスの意味も知らず、一人の男が膿となりベッドの上にひろがっていった。
悪魔たちは魔よけの指輪をおもちゃにする。
指輪
私家版幻想小説集「桃の皮、2022、249p、一粒書房」所収
絵:著者


