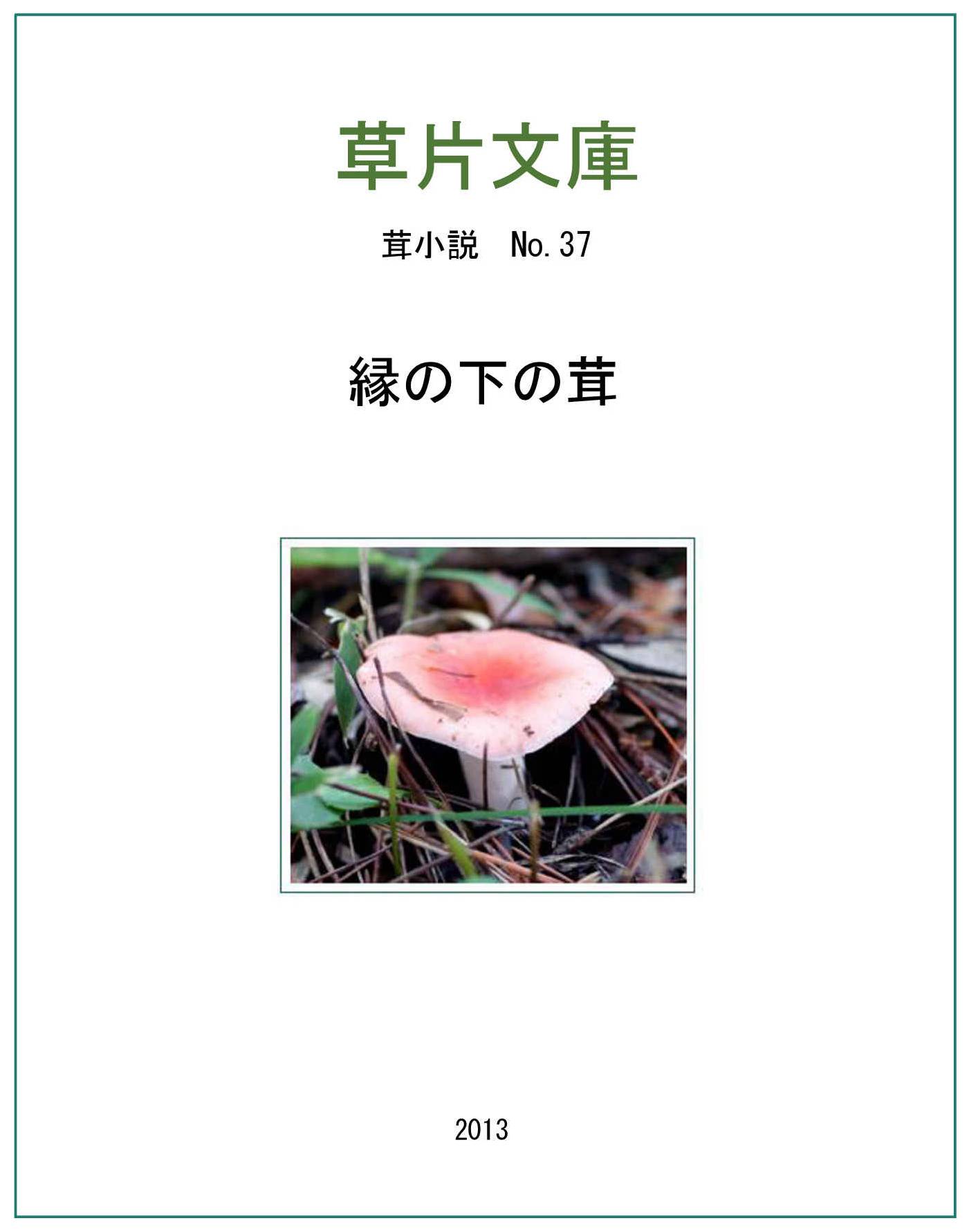
縁の下の茸
昨年一戸建てを購入した。都心から電車で一時間半とかなり遠いが、山の麓の緑の多い住宅地である。五十年前に開発されたところであるから、ちょうど多摩ニュータウンが開発された頃のものである。部屋数は少なく間取りは小さなものだが、建物はノスタルジックな趣のあるものである。縁側があり、猫がひなたぼっこをしていると絵になりそうな建物といったらいいだろう。
四十を越えてまだ独り者、とちょっと斜めの目で見られていることは十分に承知しているが、今のチャラチャラした女どもを伴侶にするなど、反吐が出そうである。要するに好みの女性に出会わなかったのと、仕事も深夜におよぶテレビ関係であったことから、そっちの暇がなかったのである。秒刻みのテレビの世界は、アナウンサーなど、表にでるスタッフも大変だが、裏方の力がないとうまく動かない。
私はニュースの骨子をまとめる役割を担っていたが、つまらなくなってきた。自分で体を動かしてニュースをとってくる記者の仕事の方が面白そうである。そんな思いに駆られるようになり、今までの経験を生かして独り立ちすることにした。
テレビの脚本を書いてもいい、何なら小説も書きたい。ともかく、フリーでやっていくことにしたのである。幸い、大手の民放にいたので、それなりの退職金をくれた。それを元に、家を購入したのである。
テレビ関係の友人からはよく助っ人を頼まれる。それはそれなりの収入になり、やめる前の収入を維持している。これで小説の一つでも当たればいうことがない。
家に移って一月、最近は町にも慣れ、自炊なども楽しめるようになってきた。ただ、数年使われていなかった家だからだろう、台所の天井を鼠が駆け回っている。ある時など、夜遅くに居間で仕事をしていると、畳の上に何匹もの胸に白い輪のある鼠がでてきて私の周りをうろうろした。人が怖くないと見える。こっちの方が怖くなり、しっしっと追い払ったが、のんびりと帰っていった。バカにされているようだ。
それで、猫を飼うことにした。時々一緒に飲みにいくテレビのアナウンサーが、少し大きくなった猫がいるがいらないかと電話してきた。いつか鼠のことを話したからだ。動物は嫌いじゃないが、面倒なので飼ったことがない。
「猫はね、ほっときゃいいのよ、ただ、自由な出入り口を確保してやらなきゃいけないけどね、良さんにはいいんじゃないかな、ほどほどで」
彼女の家で生まれた猫だそうである。幸い我が家の玄関には床下に通じている穴があいている。猫の出入りには問題がない。
そう言うことで、彼女が車で猫を連れてきてくれた。
その猫っていうのが、真っ黒な顔をして、両目のうえに白い丸い模様があり、その上、胴体手足は真っ白、尾っぽは黒、という、面白いお公家顔の猫であった。それだけではない、性格が彼女に似たところがなくもない。なんと、こっちを見ようとしない。それで「この猫俺になじんでくれるのかい」と、聞いたら、「あら、あたしだって、一緒に飲むようになったでしょ、大丈夫よ」という答えであった。
ままよ、とおもい、その猫を我が家へ迎え入れたわけである。
「おい、猫」と呼ぶと、必ず顔を洗う。無視していると、足下に来て、何にもいわずにおけつを僕に押しつける。そいじゃ、なでてやるかと触ると、するりとすりぬけ、反対側に移動する。なんだ面白くないと思っていると、目の前に来て、なんと、ぶちゃっと手足を投げ出して、おなかで畳の上にのびると、手足を動かして、宇宙遊泳のまねをするのである。
そして、僕をきょろっとしたとした目で見る。
おまけに、「にゃあああ」と鳴く。なんだか彼女に似ている。
かわいいしぐさであることは間違いない。
それで、鰹節をまぶした上等なご飯を作ってやることになる。
そんなことで、その猫は「ねこ」と呼ばれながら大人になった、だが、鼠を一匹もとったことはない。それでも鼠たちはいなくなった。猫がいるだけで効果があるのだろう。
ということで、お猫様のおかげで鼠はいない。
「どおお、その後猫ちゃんは」と、彼女からたまに電話がある。
「ぶちゃけているよ、だけど鼠はいない」
「なあに、そのぶちゃけているっていうの」
「両手両足広げて腹で体を支えて、宇宙遊泳するんだ、おまけに、こっち見て鳴く」
「面白いわね、行ってみていい」
「もちろん、いらっしゃい」
ということで、彼女が猫を見に来た。
猫の奴は家になれてきたと見えて、ともかく、その、ぶちゃけている状態をよく呈する。彼女の前でも宇宙遊泳を見せた。
「テレビに出したら大反響ね」
「だけど、俺たちのことも大反響になる」
「そうか、それはだめね」
彼女は相当の美人のアナウンサーである。いくつかの週刊誌は彼女のことをいろいろ取り上げて部数を稼いでいるが、どれ一つとして本当のことはない。ある時は国会議員、ある時はイケメンの年下俳優、いろいろある。それほど美人なのである。ところが、一緒に飲むのは私だけだ。私が一緒にいても誰も何も書かない。テレビの下働きの男と一緒でも、せいぜい仕事の打ち合わせぐらいしか思われないのだろう。もっとも、二十歳近くも離れたうだつの上がらないおっさんと一緒では記事にならないのだろう。ちょっと得している。
「変な猫ね、うちの猫たちにこんなことするのいないのに、良さんの躾よね」
「何もしてないよ、勝手にやってんだ、でも鼠がいなくなった」
「この格好するからじゃないでしょ」
「そりゃそうだ、だがいなくなった、といっても、鼠を捕ってきたことはない」
と、そこに鼠が出てきた。
「あら、いるじゃない」
「ほんとだ、この猫がきてから一度も見たことがない、それにしても、猫のやつ、鼠が目の前にいるのになんで、追いかけようとしないんだろう」
「そうね、鼠ものんびりしているわね、こっち見ている」
彼女がそう言ったとたん、鼠が両手両足を伸ばし、腹を畳につけてべたーとなった。さらに、宇宙遊泳のように手足をばやばや動かした。
「あら、鼠が猫のまねしてる、もしかしたら、猫が鼠に教わったのかしら」
「奇妙だな、この家にはなにかがあるのかな」
「やっぱり、良さんだな、この家を良さんが買ったからじゃない」
「そんなことはないだろう、でも面白いな、確かにテレビもんだ」
「ビデオカメラ持ってるでしょう」
「持ってるが、しばらく使ってないから、使えるかどうかわからないよ」
「使えるようにしておきなさいよ、またチャンスがあると思うよ」
「ああ」
そう言っている間に、鼠は起きあがって台所の隅に消えていった。
彼女は、猫の頭をなぜた。猫は振り返ってにゃあと鳴くと今度は仰向けになって、足をばたばたさせて、目をトローンとさせた。
「なんだか、クスリでも飲んだみたいな動きね、LSDとか吸ってトローンとなってるような格好」
「そうかな、まあいいや、ということで、この猫は、いや鼠も我が家では幸せなのですよ」
「そいじゃ、私たちも幸せに」
彼女は一晩泊まって、朝早く出かけていった。僕の家は、騒がれている彼女にとっても気持ちが安らぐのだろう。
その日、猫が濡縁の下から這い出してきて、上に飛び上がろうとして失敗した。ぽてっと土の上にこけた様はみっともない。なんたるざまだ。二度目にやっと縁の上に乗り、いつものようにべたっと腹を板に付け両手両足をのばしてばやばやした。ガラス戸を開けてみると、猫の顔がひきつれているような、笑っているような奇妙な顔になっている。そこに鼠が縁の下からでてくると、元気よく飛び上がり、猫の顔の前で、猫と同じように腹ばいになってばやばやした。猫の奴、目の前に鼠がいても食おうともしない。だらけている。それにしても猫も鼠もだらしがない。と見ていると、猫がくるっとひっくりかえって上向けになり、手足を伸ばすと、くるりと、もとにもどり、縁から飛び降りた。そのまま縁の下に潜り込んだ。同時に見る間に鼠も飛び降り、縁の下に入っていった。
縁の下になにがあるのだろう。
縁の上から縁の下をのぞき込んだ。
奇妙な光景であった。
ピンク色の茸が一面に生えており、猫がぽくぽくとかじっているのだ。鼠も同じである。
しばらくすると、二匹は縁の上に這い出て来て、またぐでーっとのびた。
毒ではなさそうだが、おかしくなりそうな茸である。
なぜ我が家の濡れ縁の下に茸など生えてきたのだろう。
ちょっとかじってみるか、猫や鼠が死なないなら、強い毒はないのだろう。
手を縁の下にはわせて、一本とった。十センチほどの全身ピンク色のきれいな茸である。
キッチンに持っていって洗った。そのまま傘を少しばかりかじってみた。きゅっと汁がでて、少しレモンのような香りが口の中にただよった。すぐに甘みが口いっぱいに広がった。
なかなか旨い。生のまま食べられそうである。頭をかじりとると、口の中にいれた。歯ごたえはサクサクしていて茸の甘煮のようだ。果物といっていいかもしれない。
数本とってきて、水洗いして皿に載せた。
それをテーブルにおいて、頼まれた脚本の校正をはじめた。ひとしきり直すと、手が自然と茸にのび、かじっていた。おいしい。香りもよく一息つくにはもってこいの果物である。
頭もすっきりして、校正も瞬く間に終わった。茸の皿が空になっていた。
縁の下をのぞいてみると、さっき採ったところにもう生えている。奥の方では猫と鼠がほおばっている。今度はたくさんの茸を採った。
テーブルの上に載せておくと、ついつい手が伸びて食べている。久しぶりにPCを持ち出した。なんだか小説の一つも書きたくなってきたのである。
ワードを開いて、さてなにを書こうかと頭をめぐらすと、ピンクの茸の物語、というタイトルを打ち込んでいた。話のストーリーまでが頭に浮かんできた。団子虫が近くの神社からピンクの茸の胞子を拾い縁の下に運んだ。団子虫は縁の下にたくさん生えていた黴にその茸の胞子を振りかけた。するとその黴からピンク色の茸が生えたのである。神社で拾った胞子は黴に寄生する茸だった。
この物語がすいすいと頭に浮かんできて、ワードに文章を打ち込んだ。
最後のストーリーが浮かんだ。猫や鼠に食われたピンクの茸はその飼い主にも食べられ、飼い主は作家になった気分でPCに向かい、そして猫や鼠と同じように、ゆったりした気分になって腹ばいになると、手足を伸ばした。
なるほど、気持ちのよいものである。手足をゆっくり動かすと、宇宙空間に舞い出た気分になる。
輝く星星に囲まれ、宇宙空間に浮いて、手足をばやばやと動かした。
と、声がした。
「なーにやってるの、電話にもでないし、一週間もそうしてたの」
彼女が来ている。だが宇宙空間から抜け出ることができない。
星に包まれている。あまりにもゆったりと、気持ちがいい。猫と鼠が同じように宇宙空間を泳いできた。
「やー、飼い主、お主も宇宙遊泳か、贅沢に」
「そう、贅沢よ」鼠も言った。
「良さん、起きてよ」
彼女の声が宇宙空間にこだました。
「あ、彗星だ、ぶつかる」
猫や鼠は宇宙空間になれていて手足をばたばたさせて脇に泳いでいった。
「あぶない」
なれていない私は手足の動きをコントロールできない。
そのまま彗星が衝突して私を粉々にした。
「あ、良さん、どこにいったの」
私の体は彼女の目の前から忽然と消えてしまったのである。
そして、この物語はおしまいである。
縁の下の茸
私家版 第十三茸小説集「珍茸件、2022、一粒書房」所収
茸写真:著者: :山梨県小淵沢 2013-9-16


