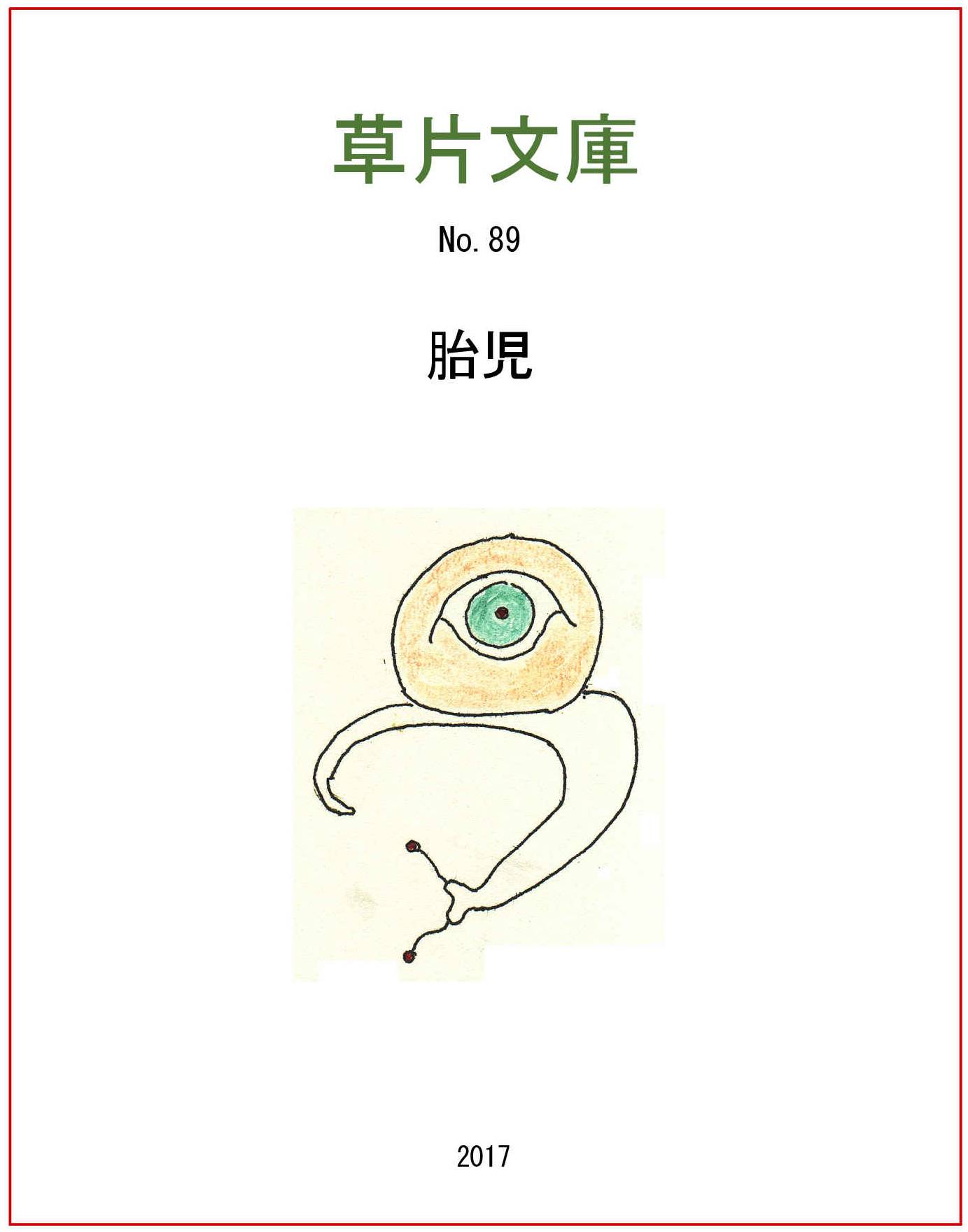
胎児
昔、新聞社に勤めていたとき、事件記者からデスクに変わった頃から、ノンフィクションものを書き始めた。さらに定年退職してからも文筆家として活動している。六十で退職し十年経った。
不思議な事件のことが思い出される。
事件記者になって五年ほど経った頃のことである。あまりにも奇妙な出来事だったので、当時は表に出なかった。取材メモは残っている。それを見て、改めて思い起こしているのだが、そのまま書いても誰も信じないだろう。数人がそれを知っているが、誰一人としてそのことをしゃべろうとしていない。活字になるかならないかは別として、自分の気持ちを整理するため、物語としてPCに打ち込んでいるところである。
それは都内での出来事だったが、差し障りがあるといけないので、個人名は架空のものにした。それは私が三十過ぎのことだから、もう四十年も前の話である。
六月の半ば、ある金曜日の夜、夜中の十二時より少し前に若い女が自殺した。と警察の知り合いから電話をもらった。わざわざ電話をくれるにはわけがありそうだ。すぐに管轄の下山警察署にとんだ。
警察は自殺といったが、まだ自殺と断定されたわけではなかった。年のころ二十三、四、出版社に勤めていた女性で、男関係などはない至極まじめな娘だったようだ。腹を刃物で刺して死んでいること、遺書らしきものは無いことなど、他殺と疑われても不思議が無い状態である。ところが争った跡のないこと、刃物に自分の指紋しかついていなかったことから、とりあえず自殺の線で調べが進められていた。今の世で腹を切って死ぬとは、それなりにセンセーショナルな事件である。しかも女性である。
民放テレビの番組ならかなり大きく取り上げるだろうが、私の新聞社はちょっとした記事で済ますだろう。とりあえず社に電話を入れた。昔は携帯などがなかったので公衆電話が頼りである。どっちみち朝刊にまにあうわけもなく、担当の刑事に事細かな情報をもらって家に戻った。
あくる朝、出社してキャップの白井に詳細を報告した。
「奇妙な自殺ですよ」
隣のデスクに座っているキャップはうなずいた。
「確かにな、裏があるかもしれんな」
「夕方にはもう少し詳しい情報が入りますが、とりあえず夕刊にはどうします」
「やっぱり触れておいたほうがいいだろう、どんな展開になるかわからないからな、明日の朝刊までに原因がわかればいいがな、複雑そうだな」
「担当の刑事も、犯罪や裏の世界には全く関係のない女性だし、職場の関係者に聞いても何も出てこない、みな言うのは動物が好きで、しょっちゅう動物園に遊びに行っているという話だけでした、動物のことをよく知っているし、自分でも猫を飼いたいのだが、マンションの一人暮らしだから無理だとよく言っていたそうです。それくらいですね」
思い出したことがあった。
「あ、それがどうっていうことでは無いんですが、両親兄弟、それに親戚もいないんですよ、いうなれば孤児院育ちでしてね、だからといって暗い性格ではなく、誰とでも仲良かったそうです。ただ男性にはむしろ、ちょっとした恐怖感があるのかもしれません。口を利かないわけではないのですが、仲良くなるっていうことはなかったようです、恋愛経験はなさそうです」
「どうしてなんだい」
「捨て子だったようです、両親兄弟いるかもしれないけれど、わからないというところです、夜中の電話での調べだけだったので、詳しいことは分からないようです」
「ちょっと不幸だね、だからといってなぜ割腹自殺をしたのだろうね、解剖所見はでているのだろう」
「そこが警察もはっきり言ってくれません、何かあるのかもしれないですね、もう少し聞いてみないと」
「よし、やっぱり、夕刊には載せて朝刊までに詳細を明らかにするようにしてくれ、あまり割腹自殺ということを強調し過ぎないように」
「はい、また下山署にいってみます」
下山署にはかなりの新聞社から記者が集まっていたが、情報は朝以来変わっていないようだ。担当の刑事が、
「この件に関しては、夕方、記者会見を行ないますので、記者の方たちは六時ごろきてください」とアナウンスした。なにかありそうだ。
さてどうするか、おそらく多くの記者たちは孤児院に行って、院長なり彼女の知り合いにインタビューするだろう。ここからだと孤児院まで一時間ほどかかる。私はもう少し他のところから調べてみようと思い、彼女の勤めていた鶯谷の出版社を訪ねてみることにした。
「まじめな子ですよ、頭も良くて、文章をまとめるのが上手いので、当社としてもとても助かっていて、大きな損失です。会社では明るくて、全く自殺の兆候なんて無かったし、物取りではないんですかって警察の人に聞いたくらいです」
出版社の係長は驚きを隠せないようである。彼女とよく動物園に行ったという同僚も、あまりにもおかしいと自殺を認めていないようだ。
「動物園は下山動物園ですか」
「よく行くのは下山動物園だったけど、サンシャインの水族館、多摩動物園、それに、アルパカのいる軽井沢などにも遠出していました。私もよく付き合ったの」
「動物園では何が好きだったのでしょう」
「みんな好きでしたよ、どっちかというと猫科の動物かな、レオポンを見たいって見に行こうとしていたわ、ライオンと豹の子ども、どっちも猫猫なんていってた。関西の動物パークに一匹いたんだけど、とうとう死んじゃって見られなかったのを残念がっていた」
「猿も好きだったの」
「彼女、猿の仲間は人間と似てて、ちょっと、と言ってたけど、それでも檻の前で長い間見ていたわね」
そのような話ししか聞けなかった。時間はまだあるので、動物園に行ってみることにした。
動物園は土曜日のせいか、圧倒的に子供連が多い。入口から少し入ると、ヤギやモルモットに触れることのできる小屋がある。その柵の前では、小さな黒い頭が集まって手を出していた。
さてなにするか思案をした。動物園に来たのは久しぶりである。自分が小学生の時に田舎の動物園に連れられていったことをうっすら覚えているだけである。私みたいな男がボソッと一人で立っているのは場違いの感じがするだろう。
駆け出しの頃、新聞記事が足りないときは、動物園に行くと面白い動物ねたが拾えて新聞の空白を埋めることできるよ、と先輩に言われたことがある。
珍しい動物のしぐさとか、双子を産んだとか、写真をうまく撮れば記事にすることも出来る。しかし一度もその目的で動物園に行ったことが無い。当時、刑事事件、特に殺人事件などのほうが記事の書き応えがあると思い込んでいた。若かった。
動物園に入った人たちはコース番号が立ててある通りに行くようだが、私はともかく、自殺した女性が好みの猫科の動物を見に行こうと思った。
歩いていくと、ヤクシカだとかサイを通り越したところにある、新築したばかりのオランウータンの遊び場と宿舎がとても目立った。遊び場の周りは深い堀になっており、三頭のオランウータンが芝の上でのんびりと寝転んでいる。その周りで一頭の子供のオランウータンが大人にからみついたり、追いかけたり、実に無邪気に遊んでいる。人間も含め子供は遊ぶ生き物なのだ。遊びを削いだら真当な大人になれない。
「危険、柵を乗り越えないように」と書かれた新しい板が、周りの堀の前の鉄柵に吊るされている。
何人かの親子連れが熱心にオランウータンを見ている。私も立ち止まった。猫族のところに行くつもりであったが、あまりにもオランウータンたちが気持ち良さそうでしばらく見入ってしまった。
オランウータンの子供が手前のほうに走って来て崖の縁でころがった。その拍子に、手前の柵に目が行くと、柵の内側に花束がセロファンに包まれて置いてあるのに気づいた。花の名前はからっきしだめなのだが、西洋の花であることは分かる。真っ白な花である。あれっと思ったのは、黒いリボンでくくられていたことである。オランウータンに喜ばしくないことでもあったのだろうか。
そんなことを考えていると、いつの間にか青いジャケットを着た男性が、隣に立っていて、私と同じように花束を見ていた。男はいきなり私のほうに顔を向けて、
「おたくさんですか、花束をおいたのは」と聞いた。
「いいえ、私も黒いリボンの花束なので、何かあったのかと思って見てました」
「失礼しました、誰が置いたかごらんになっていませんよね」
そういいながら男は遠慮無しに柵の中に手を伸ばして花束をつかみだした。そのまま男は私のほうを見ずに背中を向けて歩き出したので、気になって声をかけた。
「どこに持っていかれるのです」
その声で彼ははっとしたように立ち止まり、頭を掻くような仕草をして、私のほうを向いた。
「こりゃ、失礼しました、ここの係りなもんで」
彼の胸元を見たら、ジャケットに動物園のマークが入っていた。作業着に長靴でも履いていればもっと早くに気付いただろうが、客と同じような格好だったのでわからなかったのである。しかもピシッとしている。
「今、園外の仕事から戻ってきて、直接ここにきたらこんなものが置いてあるんで、ちょっとあわててしまって、すみません」
「いえ、あまり気持ちのいい花束ではありませんね」
何かありそうである。さりげなく聞いた。
「昨日、オランウータンが一頭死にまして、今日こんなものがあったので」
「そうですか、それはお気の毒でした」
彼は考え込むように呟いた。
「それにしても、昨日と言っても真夜中ですし、関係者しか知らないことですからねえ、花束に黒いリボンがついているのは、知っている人が置いたのでしょうね」
「急に死んでしまったのですか」
「ええ、一番元気だったオランウータンでした、人にもよく慣れていましてね」
「心臓発作とか」
人間も働き盛りの元気な男が脳梗塞や心筋梗塞でいきなり亡くなることがある。
「いえ、違うんですよ」
「どうしたのです」
「うーん、ちょっと、おそらく園長が公にすると思いますので、私からは」
彼は言いよどんだ。そこで、私は「ちょっと話を聞かせていただいていいですか」と彼に名刺を渡した。
「あ、新聞記者さんでしたか、これは、まいった、お話していいかどうか、私にはわかりませんが、課長がいますので、どうぞ事務所にいらしてください」
「お手数かけます」
私は彼の後をついた。
「尾木といいます」彼も名刺をだした。
「今オランウータンのことで、都庁と保健所に行ってきたところです、貴重動物ですので、科学博物館のほうに送られると思います」
「剥製にするのですか」
「本来ならそうするでしょうけど、骨格標本になるかもしれません」
彼はそれ以上言わなかったが、骨格標本と言うことは、外側が使えないのかもしれない。損傷を負っている可能性もある。
倉庫に併設された事務所に入ると、課長の堀田に紹介された。尾木は着かえてから、オランウータンの宿舎に行きますと奥に入っていった。
「尾木君の可愛がっていたオランウータンでした」
尾木氏は均整のとれたスポーツマンタイプで、精悍なピューマのような感じなのに対し、年も違うが、堀田はまるで象のような巨漢である。
「どうぞ、お座りください、とりたてて、秘密にするようなことではありませんが、園として発表するのは手続きが完了してからというところです」
「たまたま、遭遇してしまっただけで、記事にしようと言うことではありません」
「そうですか、ところで八木さんはどうしてこんな時間に動物園にいらしたのです、おそらく尾木君も、なんでこんなにはやく新聞記者さんが来たのか不思議に思ったでしょう、しかも花束もあったし」
「そういうことですか、私はある事件を追っていて、動物好きが関係しているので、何かヒントがあるかと思って動物園に寄ってみただけなのです、六時には下山署に戻らなければならないので」
堀田氏は身を乗り出した。
「大きな事件ですか」
「いえ、女性が自殺したのですけど動機がわからなくて、その娘は良く動物園に来ていたということでした、時間が余ったので来てみただけなのです」
「ほー、自殺と動物園とは難しいパズルのようですね」
なかなか堀田は面白いことを言う。
「いえ、関係付ける必要は無いと思います」
「動物の好きな人は、動物に感情移入をしてしまっていることがあります、その方は自分の好きな動物がいなくなったので自殺したとかいうのではないでしょうね」
「あ、いや、動物は飼っていませんでした、猫科の動物が好きで動物園にはよくきたようです、それを見ようと思っただけで、そんなに深く考えたわけではありません」
「そうですか、猫科の動物たちはみな元気です、よかった、そちらの事件と、死んだオランウータンとは関係なさそうですね」
「すみません、かえって、驚かせてしまったようだ」
「猫の好きな人は、まあ人によりますけど、感情移入が強いかもしれませんね」
そういうものだろうか。
「可愛がりすぎる傾向があるでしょう、だけ、猫は野生的な性質の持ち主だから、そんなに主人が好きなわけではない、だけど好かれていると飼い主は誤解をする」
なるほど、犬とはずいぶん違う。
「そうかもしれませんね、いや動物園で人の性格のことを教わるとは思いませんでした。自殺した女性の性格を調べてみます」
堀田が身を乗り出してきて、ちょっと考えるようなそぶりをしてから私に言った。
「もし、その女性が自殺だったら記事にはしないのでしょうね」
「ええ、場合によりますが、自殺だけですとほとんど記事にはなりません、ただ特殊な場合には違います」
「といいますと」
「変った自殺の仕方をした場合などは、テレビが取り上げますから、新聞としても、載せないわけはいかなくなります」
「殺人なら当然新聞種ですね」
「そうです」
「八木さんは、いうなれば、殺人などの事件記者ですね」
「まあ、そうです」
堀田はちょっと間をおいて話し始めた。
「ご相談したいことがあります、オランウータンのことです、動物が死んでも、人の自殺と同じように、特別なことが無い限り、新聞にはのりません。特に貴重な動物だとか、伝染病だとかは報道されます、これからお話しすることは、公の発表があるまで伏せておいて欲しいのですが、よろしいでしょうか」
私は即座に頷いた。動物園記事で他社と競うなどということはないだろう。
「オランウータンはとても感受性が強く、飼育は難しい動物です。幸い私のところでは尾木君をはじめ数名の霊長類に明るい飼育員がそろっていて大変うまくいっています。子どもまで産ましているのはこの動物園ぐらいです。ところが一頭死んでしまいました。殺されたのです」
私はそれを聞いてびっくりした。殺人ではなく殺猿である。
「誰が殺したのですか」
「わかりません」
「昨夜の十二時ちょっと前でした。夜警の人が園の中を見回りに歩いていると、オランウータンの宿舎から変な呻き声がしたんです。その声といったら腹にぐーんと浸み込んでくる、もの悲しい感じがしたとのことです。夜警の人はオランウータンが腹痛を起しているようだと、担当者に無線連絡をしました。
尾木君がその日の当直で、オランウータンの宿舎に入ると、一頭の雌のオランウータン、マリという名なのですが、マリが寝室の外の通路に仰向けになって苦しそうに息をしていたそうです、マリのからだの脇に血が溜まっていて、胸には短刀が深く刺さって、血がどくどくと出ていたということです。
短刀を抜いてしまうと確実に死ぬと思い、布でその回りを覆うと、急いで救急担当者や私や園長に電話を入れたそうです、私もすぐに行ったのですが、ほとんど虫の息でした。獣医も来ており、間もなく息を引き取りました」
「刺されてそんなに時間は経っていませんね、誰も犯人を見ていないわけですか」
「はい、寝所の鍵はきちんとかかっていたと尾木君はいっていました」
「他のオランウータンはどうしていましたか」
「オランウータンは個々に寝る習慣があるので、それぞれに寝るための小部屋を与えています。小部屋がいくつも連なっており、廊下側からはガラス越しに小部屋の様子がわかります。小部屋の反対側には出入口があり、運動場から帰ったオランウータンはそこから小部屋に戻ります。掃除などもそちらから入って行ないます。小部屋といってもかなり広く、オランウータンたちは用意されている布や葉っぱなどを使って、自分の寝床をこしらえて寝ます」
「小部屋の入口は自分では開けられないのですね」
「はい、鍵をかけてあります、誰かが開けて外に出したとしか考えられません」
「子供がいましたね」
「子供はミドリの子で、ミドリと一緒にちょっと離れたところの小部屋に入れられています」
「雄はいないのですか」
「います、モリオも別の寝床にいます」
「外で見たのは三頭でしたが、もう一匹いるのですか」
「はい、雌のハナですが、それも個別にいます」
「犯行に使われた短刀はどんなものでした」
「刃渡り三十センチほどのもので、プラスチックの柄が付いていました。もう警察に渡してあります」
「オランウータンに恨みを持つ人など考えられるのですか」
「全くありません、動物園に恨みをもつ者もいないでしょう」
「警察はなんといっています」
「わかりません、犯人が捕まっても、不法侵入と器物損壊だけです」
「器物損壊というのはなんです」
「動物を殺したり、傷つけても器物損壊罪になるだけです」
その頃、動物愛護に関する意識が低く、動物が殺されても、そのような罪状しかなかった。今は動物愛護の観点から罪になる。
「短刀を調べれば指紋が取れるでしょうから、犯人が捕まるのは時間の問題ではありませんか」
「ところが、人の指紋が無いのです、マリの指紋はありました、抵抗したのでしょうね、オランウータンにも指紋はあります」
「へんなことを聞きますが、オランウータンの一匹が犯人ということはありませんか」
堀田氏は苦笑しながら大きく首を横に振った。
「まずありません、仲間同士の喧嘩はしますが、このように刃物を使って相手に傷をつけるなどということはありません」
「オランウータンが道具を使うということは無いのですか」
「他の動物園では知りませんが、うちは教えたりしていません、不自然ですから、オランウータンの指紋は登録されており、短刀にはマリの指紋しかありませんでした」
「オランウータンの宿舎はどこにあるのです」
「野外運動場の脇の大きな建物で、冷暖房完備の立派なもので、最近作りました。屋内運動場もそこにあって、木を立体的に配置し、遊べるようになっています。前面は強化ガラスで、観客はそこからオランウータンを見ることが出来ます」
「寝室に入ろうとすると、もし鍵が開いていれば、屋内運動場からも入れますね」
「はい、屋内運動場からは準備室を通り、寝室前の通路から寝室にいけます。準備室には宿舎の廊下から入れますし、準備室がすべてのところにつながる場所になります。動物たちは寝室からでると、一端準備室に集まって、どちらかの運動場に出ます」
「鍵の管理はどうなっていますか」
「すべてのドアに鍵がありますが、使わないときにはかけておきます。鍵は管理室にあります。個々の寝所の鍵は管理室にもありますが、オランウータン担当者ももっています」
「何時ごろ鍵をかけるものですか」
運動場への出入り口は四時の園の閉門時のあと、係員の整備が終わるとかけます。使ってないところはいつもかかっています。寝る小部屋はその時の担当者の判断です。七時ごろには当直担当者と研究をしている者以外はだいたい家に帰ります」
「事件があったときはどうでした」
「七時十分頃だったようです」
「夜警は中も見るのですか」
「何かおかしいと思われる時には入りますが、宿舎内は基本的には当直者が行ないます。その日も尾木君が十一時半に見回りに行っていますが、おかしなことは無かったようです」
「奇妙な事件ですね、動機がわからない、あの花束の出所も、犯人探しのヒントになりますね」
「そう思います」
そこで私が時計を見ると、もう五時になる。そろそろ戻ったほうがよい。
「お話ありがとうございました。すぐに記事にするようなことはしません、警察署に行かなければなりませんので、何かあったら連絡ください」
私は自宅と新聞社の電話番号を記した名刺を堀田に渡した。
「こちらこそまた、これも縁ですので何かご相談するかもしれません、報道関係の知り合いが全くないので、いろいろ教えてください」
私は動物園を後にして、下山警察に行った。
記者室にいくとき、鑑識課のドアが開き黒い半ズボンの少年が出てきて私とすれ違った。場違いの感じがしたのと、ズボンの黒い色が動物園の黒いリボンの巻かれた白い花束が連想された。だがそれはそれだけだった。
記者室には誰もいなかった。顔なじみの刑事が入ってきた。私が駆け出しの頃からの知り合いである。同じ年ということがわかってから、ちょっと親密な仲である。お互いの立場を守りながらの付き合いといったらいいだろう。
「オーイ、メイメイちゃん、来たのが見えたからきたよ、あの自殺の件はまだ進展していなくてね、何も話すことは出来ないよ」
濱田猪造刑事は私のことを、メイメイチャンなどと呼ぶ。私の名前が八木だからだ。しょうがない。
「それじゃ、記事には出来ないね」
「うん、おそらく自殺だろうけどね」
「この件は朝刊に書けそうもないから、もうちょっと教えてよ」
「そうね、事件性がなさそうだし、まだ内緒だが」と声を小さくした。
「妊娠していた」
「男関係はないって言ってたよね」
「うん、その男っていうのが誰だかわからなくてね、ともかく、産婦人科で見てもらって帰ってくると、その夜に自殺したようなんだ、四ヶ月だったからもうおろせないな、子供が欲しくなかったのか、生まれてはいけない子だったかだな」
「刃物はどうしたんだ」
「産科の帰りに、デパートによって買っているんだ」
「やっぱり自殺か、妊娠が一つの原因だね」
「それは確かだ、それでね、短刀がね、腹の中の胎児の頭を刎ねていたんだよ、子どもが憎らしかったんだな、まあ偶然にそうなった可能性もあるがな」
それにはびっくりした。
「ということは、生みたくなかった、相手の男を憎んでいる」
「どうだろうな、もう少し調べれば明らかになるだろう、なにせ遺書が無いからな」
その頃、遺伝子検査などなかった。いまだと胎児の遺伝子検査で相手も特定しやすいのであろう。
「それじゃ、デスクにまだ明らかじゃないと連絡しとこう」
「ああ、それに今のことはまだ誰にも言うなよ」
私は頷いた。そこはきちんと守っておかないと、なにかのときに大事な情報をもらえなくなる。
「今、鑑識課から少年が出てきたが、あれは誰だい」
「少年なんて見てないね」
彼はそう言うと、「また」と奥の部屋にもどっていった。
これで、今日は女の自殺の件も、オランウータン殺しの件も夕刊には載せられないということで仕事は終りだ。デスクに連絡して、一杯飲んで直接アパートに帰ることにした。
日曜日は休みのはずであるが、事件記者というのは休日など関係がない。ともかく警察が動いていれば動かなければならない。ということで日曜日はほとんどつぶれている。しかし今日は何もないはずで、ベッドの中でぐずぐずしていた。
そこに電話がなった。自宅の電話に掛けてくるのは、九州の隼人に住んでいる両親か、刑事の濱田ぐらいだ。手を伸ばしてベッドの脇の受話器をとると、「下山動物園の堀田ですが、八木さんですか」と声が聞こえた。あわてて襟を正すと「はい」と答えると同時ぐらいに「大変なんです、また雌のオランウータン、ハナが一頭殺されました、こちらでお話できませんでしょうか」と勢い込んで堀田がしゃべった。
あわてて、ベッドの上に起き上がると「はい、すぐ行きます」「入口にいらしたら、守衛に堀田まで連絡するように言ってください」という会話をした。
時間は九時十分過ぎである。歯を磨くのを省いて買っておいた缶コーヒーを開けると咽に流し込み、それにしても警察に電話すれば済むものを何で事件記者の俺に電話をかけてくるのだろう。という疑問を持ちながら出かける用意をした。
なんだってオランウータンを殺さなければならないんだ。久しぶりの日曜日を潰されたのでちょっといら立ったが、どんな裏があるのか興味もわいてきた。オランウータンが殺されるということだけでも、ある意味で記事になる。それが二匹も殺された。
タクシーをつかまえて動物園まで飛ばし、守衛に話して待っていると、堀田が急ぎ足でやってきた。
「お休み中すみません、こんなことになって、ちょっと大変なのでご意見をいただこうと思いまして、今度は警察も二人見えています」
「あの、私は新聞記者で警察の人から疎まれていますよ」
笑いながら言ったのであるが、堀田は真顔で「いや、昨日お話が出来てよかったと思っています、報道関係の方のご意見も大事なので、是非お願いします」
そういうことで、今日はオランウータンの宿舎に入り、廊下から一つの小部屋の中でオランウータン担当者と二人の警察官、それに獣医師が調べているのを見ることになった。今回は寝室で殺されている。
「他の小部屋のオランウータンたちは室内の運動場に連れて行かれているのです」
堀田が説明してくれた。
人とほとんど違わない背丈のオランウータンが仰向けになり血を流している。胸には確かに短刀が刺さっている。警察官に説明しているのは尾木である。
すると、「おい、メエメエちゃん、何でこんなところにいるんだ」
後ろから声がした。振り返ると刑事の濱田が笑っている。
「山羊も動物園にいても不思議ないか」
と余計なことを言いながら、堀田に、
「下山署の濱田です」と挨拶をしている。
「あ、これはどうも」
「 現場に案内してもらえますか」
濱田にいわれ堀田が準備室のドアを開けた。やはり廊下に面しているところがガラス張りの窓になっている。廊下から寝床にいるオランウータンも準備室にいるオランウータンも全部見通せるわけである。準備室には体重計やオランウータンの遊び道具などがおいてありかなり広い。
見回したら、準備室には三つのドアがあることがわかった。室内遊び場、室外に出るドアと、寝床の前の通路に行くドアである。我々は寝床の小部屋の前に行った。死んでいる様子を直接見ることができる。
「部長がちょっと行って見てこいというものだからな、だけどなんでおまえさんがいるんだい」
「昨日、あの自殺した女の子のことで動物園に来てみたんだ、そうしたらたまたま、オランウータンの殺害について知ってしまってね、それでいろいろ話をした関係から、課長さんから今日も来てくれという電話をもらったんだ」
「全く、何でこんなことするやつがいるのだろうな、昨日もあったんだろ」
「そうらしいね」
濱田が中に入ると、警察官が敬礼をして状況を説明した。前の時とほとんど同じである。尾木が私に気がついてお辞儀をした。目が赤くはれている。泣いていたようだ。
濱田はオランウータンの胸に刺さっている短刀を、目を凝らすように見ている。
警察官に「短刀を証拠品として、持ち帰るように」と指示した。
おおよそのところを見ると、濱田は後を警官に任せて檻を出た。私にも出ろという合図を送ったので一緒に出ると、園長が廊下に来ていた。
園長は濱田に「申し訳ありません、よろしくお願いします」と腰を低くしてお辞儀をした。
「話は事務所のほうでお聞きします、検死が終わったら、あの担当の方も呼んでください」
濱田と園長、堀田課長、それに尾木と私が事務所のテーブルに集まった。
堀田課長が私に「刑事さんとお知り合いですか」と聞いてきたのでうなずいて「昔からよく知っています」と答えるとなんとなくほっとした顔をした。
その場では二匹のオランウータンの殺害された時刻や、その時の状況が詳しく話された。今回も本当に最初の時と同じだったようである。それととても奇妙なことが報告された。黒いリボンがかかった花束がオランウータンの柵の前にまた置かれていたそうである。
「何が目的なのだろう」
尾木は焦燥しきっている。寝ずの番をしていたようだ。
それにもかかわらずまた事件が起きた。
濱田刑事は、「オランウータンの死因はしばらく外に出さないほうがいいでしょう、犯人を捕まえるためにそのほうがいい」とみなに釘を刺した。
これを聞いた園長は安堵したようだが、私のほうを見た。濱田はそれに気がつき、「そこにいるブンヤさんは大丈夫、書いたりしないから」と勝手に決め付けた。しかし私も頷いた。
話を終えると、濱田は私の肩に手をおいて「ちょっと署によってくれ」と小声で言った。私はパトカーに乗せられて下山警察署に連れて行かれた。
「なんです、あの自殺者のことですか」
そう聞いても濱田はだまったまま、私を鑑識課につれていった。鑑識課の中に入るのは初めてである。ファイル類が棚に奇麗に整理されており、日曜日でも何人かの人が書類に目を通したり、その頃としては珍しいコンピューターに向かっていた。
濱田は空いている椅子に座るように指示した。自分も一つ引き寄せて座った。
「なあ、ブンヤさんに聞くのもなんだが、どう思う」
「どっち」
「猿だよ」
「犯人の足跡もないし、動機も想像できないし、薄気味が悪い、その上、あの花束はなんだろう」
「そうだな」
私がふっと窓際の机を見ると、あの少年が椅子に腰掛けている。机の上の何かを眺めている様子である。
「あの少年は誰」
「え」っと、濱田が振り返ると少年はすっと出て行った。「ほら、今出て行った少年だよ」「誰もいないよ」彼が不思議そうな顔をして私を見た。
なんだかぞくっとしたが、確かにもういない。私は机の上の籠の中にあるものが気になった。「あそこにあるのはなんだい」
「あれは自殺した娘の証拠品だ」
私は立ち上がって机の前に行くと籠の中を見た。ビニール袋に入った短刀、ビニール袋に入った衣類、それにガラス瓶がある。ガラス瓶の中に子宮があった。その中に首の離れた小さな胎児が浮いている。いやなものだ。こういうものを初めて見た。
「これからきちんとしたところに保管されるのだが、仮に置いてある」
「これが四ヶ月の胎児か、まだ小さいね、首が切れたのは偶然かな」
濱田は脇にあった籠の中の短刀に目を留めると、顔色を変えた。
「ちょっと待っていてくれ」そう言うと、鑑識課から出て行った。
私がまた椅子に腰掛けて待っているとあわてて戻ってきた。
「これをみろよ」
彼は机の上にビニールに入った短刀を置いた。一つは娘が自殺に使ったもの、もう二つはオランウータンを殺害した短刀である。全く同じものである。
私も頭の中が混乱した。
「偶然だろうか」
濱田も考え込んでしまっている。
「まさか娘の自殺と、オランウータンの殺害は関係ないだろう、オランウータンは娘の自殺の後に起きている」
「たしかにな、この短刀は何処でも買える」
「両方の事件を関連付けて、もう一度考え直してみるか、とすればもっとはっきりするまで報道は控えてくれ、お宅の特種になるかも知れねえな」
私は頷いた。
それから一週間、二つの事件は全く進展しなかった。デスクのキャップには動物園の殺猿事件のことは言っていない。娘の自殺に関してもとうとう記事にしなかった。
下山署には毎日のように出かけたが、自動車事故や押し込み強盗、万引きや女性へのいたずら程度のものは毎日のように量産されたが、幸いなことに大きな事件はおきていなかった。
土曜日の三時ごろだった、今日は下山署に顔をだして、すぐ帰ろうと社をでた。下山署にはいると、鑑識課のドアが開いて少年が出てくるところだった。黒い半ズボンをはいて白いシャツを着ている。いつも同じ格好である。すれ違いざまふっと自分のほうを見たようだが、気のせいだったのだろうか。そんなことでちょっと鑑識課を覗いてみることにした。
ドアを開けて中を見ると、やはり何人かが机に向かって書類を作成している。その中の一人が私を認めて、「新聞社の八木さんですね」と聞いてきた。
頷くとその女性が「濱田刑事から、八木さんが来たら動物園に来て欲しいと言ってくれとのことでした」と言った。
「そうですか、でもよく鑑識課に顔をだすということがわかりましたね」
「いえ、みんなに言っていました、もし来たらということで、来なければそのままでいいと言っていました」
「電話をくれればいいのに、ところで今ここから少年が出てきてすれ違ったのですが誰ですか」
「いえ、誰も出て行きませんでしたよ」
「そうですか、ありがとうございました」
そう言って警察署を出た。あの少年は誰なのだろう。誰も気づいていないようだ。
土曜日なのに今日もアパートには帰ることが出来なさそうだ、そんな予感がした。
下山動物園の脇にパトカーが止まっていた。守衛に名前を言うと堀田が迎えに出てきてくれた。
「すみません、濱田刑事がお待ちです、私のほうから新聞社に電話をしようと言ったのですが、あいつは必ず来るとおっしゃったので、何もしなかったのですが、よくわかったですね」
「いえ、下山署に顔をだしたら濱田刑事からの伝言があったのです」
事務所に濱田がいた。
「おーきたな、メイメイちゃん、どうだい今日徹夜しないかい」
なんだか判らないが、付き合うほかないだろう。
「いいよ、オランウータンでも虎でも一緒に寝るよ」
「いい心構えだ、実は今夜何かありそうなんだ」
話だと、昨夜、警備員がおかしなことに気がついたということだ。オランウータンの宿舎の脇で青色の光が見えたそうである。その晩は警備員を始め、オランウータンの飼育係りも総出で徹夜で見張っていたそうである。尾木はオランウータンの宿舎の中にいたそうだが、確かに青い光がちらちらと、檻の天井に見えたそうである。しかし見張っていると、いつの間にか消えていたということだった。
「それは、何時ごろですか」
「一時ごろだと思います」尾木が答えた。
「青い光って、懐中電灯の明かりとは違うものでしたか」
「ええ、本当に青色でした」
「懐中電灯に目立たないように色をつけて工夫した可能性はあるな」
濱田刑事が口をはさんだ。
「外に面した窓はないのでしょう」
「ありません」
「と言うことは、外で警備員さんが見た青い光が部屋の中に入ったのではないのですね」
「そうですね」
「それは、何者かがすでに中に入っていたことを意味しませんか」
「うーん」濱田も考え込んでしまった。
「尾木さん、それからずーっと起きているのですか」
「いえ、課長に言われて、昼間は家に帰って寝ました。しかしさっき出てくると、また黒いリボンのついた花束が置いてありました」
「それで、あんたに来るように伝言を頼んだんだ」
「電話をくれればいいのに」
「新聞社に俺から電話を入れるのはまずいと思ったからさ」
確かにそうかもしれない。刑事がブンヤを呼び出すのは個人的なことに限られる。
「守衛室の二階に宿泊施設もありますので使ってください」
堀田が気を使って言った。
「ありがとうございます、だけどそれじゃ意味がないので、我々は檻の前で見張っていますよ、なあメイメイちゃん」
全くここでメイメイちゃんと言わなくてもいいだろう。もちろん頷いた。
予想通りやっぱり家にもどれない。動物園に徹夜で張り込みということになった。
「どうだ、外でメシを食って、七時か八時頃もどろうじゃないか」と誘ってくれたので、濱田と動物園の外に出た。
彼はどこに行っても横丁に入り、仕事の前だろうがなんだろうが臓物の煮込みで一杯飲む。私もよく付き合ったものである。それで彼の性格も知ったし、彼の正確な判断力も判ってきた。だから誘われたら行くしかない。
「今度の事件、不思議だが、きっと絡み合った糸は解けると思う、だが簡単にはいかないな、トリックは全くない、だから俺には想像できないことが起きている」
彼はモツの煮込みを口に入れ、ビールを流し込みながら私を見た。
「なんでしょう」
「なあ、ブンヤさん、あんた警察署に来て、黒い半ズボンの少年を見たと何回言った。俺に二回、今日鑑識に一回、三回も言っている。それはなんだ」
彼は私の言ったことを気にしていない様で、頭の隅で覚えていたのだ。
「え、さっき鑑識の人に言ったのも伝わっているんだ」
「連絡があった、あんたは一体何が見えるんだ」
「いや、何もみえないよ」
「今回の出来事は、あの娘の自殺とつながっている、そう思っているだろう」
私は頷いた。
「もう、そこから現実では解決できないことが根本にあると思うよ」
彼はその話はそこで打ち切った。
少し酒の入った状態で、動物園に戻った。九時になっている。
我々は残りのオスのオランウータンと、子供を持った雌のオランウータンを見張ることにした。
「ちょっと回りを見てから、中に入ろう、もし何か起きるにしても、十二時前後だろう、いつもそのくらいに起きている」
二人して園内のオランウータンの遊び場と宿舎を中心にぶらぶら歩いてみた。何人かの警察官も派遣されているようで、途中で二人づれとすれ違った。警官に化けて入る可能性もあるので、濱田はいちいち警察官の顔を懐中電灯で照らして確認をしていた。警察官の方でびっくりしている。
一時間ほど外にいてから管理室に戻り、堀田と一緒にオランウータンの建物に入った。寝所の前でオランウータン担当者の一人が椅子に腰掛けている。十一時に尾木と交代するということである。宿舎内の廊下の明かりは極弱いものになっている。動物たちへの配慮である。
我々は二人で宿舎内を巡回することにした。屋内運動場を見て回ったり、それぞれの部屋の鍵の状態などをチェックする。寝室の前には食事を準備する部屋や倉庫がある。その中も見るのだが、ひと回りするのにあまり時間がかからない。結局寝るための部屋の前に戻ってきてしまい。椅子に腰掛けているしかなくなってしまう。
尾木がやってきて私たちに挨拶した。十一時になったのだろう。椅子に腰掛けていた担当者が尾木に「オランウータンたちは何事もなく寝ています」と報告している。
尾木が椅子に腰掛けたので、「青い光というのはどこに見えたのですかね」と聞いてみた。尾木は広い宿舎の上のほうを差して空調の風の出る穴を示した。
「外からの光があそこに映ることはありませんよね」
「ええ、奇妙なことなのですが準備室には外の明かりがはいりますから、それが、廊下の何かに跳ね返って寝室に映ったのかもしれません」
「なるほど、そういう可能性もあるのですね」
みんな緊張気味である。
ガラス張りの窓から中を覗くと、モリオは葉っぱを敷き詰めてその上に寝ている。ミドリと子どもは準備室の隣の少し大きな寝室で寄り添って寝ている。これだけ厳重に監視されていれば誰も入ることはできない。
「いつも、こんなに静かなのですか」
周りは雪が降っているときのように物音がしない。空調機の音すら聞こえてこない。
「確かに言われてみればそうですね、ここにこのように腰掛けて見張るということはしたことがなくて、廊下から様子をちょっと見るだけでしたので、音のことを気にしたことがないのですが」
「巡回の時は部屋の中には入らないのですか」
「普通は入りません、ここから懐中電灯で確認します。何かありそうなときには入りますが、よほどのことがない限りそうしません」
それはそうであろう。寝ているのを邪魔してはストレスになる。
「どうだろう、我々はもう一度外を見ないか、中はもうこれ以上の警備は出来ないだろう、尾木さんがいるし」と濱田が私に外に出るように促した。
「じゃあ、尾木さん、ちょっと外を見てきます」
そう言って廊下を歩いていくと、堀田が仮眠室から戻ってくるのに出くわした。
「我々、もう一度外の見回りに行きます、尾木さんが一人でいますのでよろしく」
「はい、後で見にいきます」、彼は頷いて管理室の中に入っていった。
坂を下りると屋外運動場になる。二人の警察官がオランウータンの野外運動場の前で立っている。
「何も異常ありません」
濱田刑事を認めると、敬礼の姿勢をして「我々は、回りをみまわってきます」とその場を離れた。
野外運動場の柵の前に立った。別段なにも見られない。そう思ってふっと、脇の大きな木を見ると、蒼白い玉のような光が枝の中をうろうろとしている。
「濱田さん、ほら、あれ、青い玉がいる」
彼もそれを見て驚いたようにいった。
「昔の人がよく言った人魂のようだ」
青い玉は宙に浮かぶとすーっと、オランウータンの屋外運動場の上に降りた。蒼白い玉の後ろに影のような形が浮かび上がった。影は形を変え、細長くなると、次第に人の形になった。頭ができ手足ができ、そろりそろりと、はいずくばって、オランウータンの屋外運動場を登っていく。次第に形がはっきりしてくると少年になった。少年の首がこちらを向いた。少年の口が青白く光っている。青い玉は少年の口から出ていた。
「あれはなんだ」濱田が叫んだ。
「あ、あの少年だ」と私が叫ぶと
「おい、中に入るぞ」
濱田が私を引っ張るように、今降りてきた坂を駆け上った。
「あの雄のオランウータンだ、あぶない」
廊下を走っていくと、尾木が真っ青になって震えていた。
「男の子が」
見ると、よく寝ている雄のオランウータンの寝室に少年が立っている。
「あれは、人間じゃない」
私が叫ぶと少年が我々のほうを向いて、ふっと笑った、口から蒼白い玉がのぞいている。手には短刀が握られている。
あっという間もなく振り下ろされ、オランウータンの胸に刺さっていた。
「早く、部屋の中に、それに救急道具も」
私の声でわれに返った尾木はモリオの部屋に飛び込んだ。
見るとオランウータンの脇に少年はもういなかった。
尾木のあとからモリオの寝室に入るとオランウータンはまだ生きていた。
「心臓は外れているようです」
尾木は短刀を引き抜くと、血が流れ出す傷跡に強くガーゼを当て止血を施した。やがて待機していた獣医師たちが園内の動物病院から駆けつけ、オランウータンを担架で病院に運び入れた。これから手術なのだろう。血がだいぶ出ているので助かるかどうかは判らない。
後は獣医師に任すほかはない。
「みどり親子を守らなければ」
私が言うと、濱田は「今日はもう大丈夫だ、十二時を過ぎている、今までの犯行はすべて十二時前までだ、明日に備えなければ、これではいくら鍵を確かめてもだめだ」
管理室にみんなを集めた。
みな放心状態である。特に尾木は見る影もないくらい憔悴しきっている。
「何が起きたのです」
堀田はあの少年を見ていない。
「また、やられちまった、今後のことを考えなければ」
濱田が切り出した。
「犯人を見なかったのですか」
堀田は奇妙な顔をした。
「逃げられた」
濱田は言った。彼は少年のことを言わない。何か心づもりがあるのだろう。尾木はむっつりと黙ったままである。私も余計なことは言わないことにした。
「おそらく、また、残った親子を狙うだろうし、もしモリオが助かってもまた狙われる危険性がある」
「これだけ守備をしてもだめだとすると、どうしたらいいのでしょう」
堀田は頭を抱えている。
「動機がわからない、何の目的だ」
同じ解けない鍵があの自殺した娘にもある、そう思ったときふっと、聞かなくては思って「あの、オランウータンの野外運動場の柵のところにある、危険という看板はいつ建てたのです」とたずねた。
堀田氏は何でいきなりという顔をした。
「四ヶ月ほど前に作りました、女性が落ちたので」
「どうして、落ちたのですか」
「きっとあの子どものオランウータンが可愛かったからでしょう、身を乗り出して、ふらっとして落ちたようです、閉園時間間近で誰もいなくて、尾木君がオランウータンを室内に入れようと思って運動場に出たときに気が付いたのです」
「その女性は大丈夫だったのですか」
「ええ、ちょっとした脳震盪でした。もっと打ち所が悪いとひどい状態になっていたかもしれません、結構高さがありますので、それで看板を立てました」
「尾木さんが、発見されたのですか」
彼は頷いて、「尾木が部屋で看病してましたが、救急車を呼ぶよういいました」
「動物園として謝罪をしたのですが、その女性は自分が悪かったのだから、ととても柔らかい方で助かりました」
「なんという方ですか」
「春川しのぶさんといいました」
それを聞いて、私も濱田もあまりにも驚いた。あの自殺した女性である。もちろん、動物園の人は知らない。濱田がどう言うかと見ていると、はっきり言った。
「驚きました。その方は十日ほど前、最初のオランウータンが殺された夜に自殺しました。お腹に子供がいました」
「え、それと、オランウータンの件と関係あるのでしょうか」
堀田氏の質問に濱田はこう答えた。
「彼女はもう死んでしまっていますし、彼女がなにかしようとしても出来ないでしょう」
「偶然なのでしょうか」
「実は、この事件と彼女の自殺に共通点があります、調べても、どちらも動機がわからないことです、奇妙なのは、彼女が自殺に使った短刀とオランウータンが殺された短刀はまったく同じ型のものです」
「その女性の相手の方は分かっているのですか」
堀田は女性の関係者を疑っているようだ。
「その相手もわからないのです」
濱田はそう言って、さらに「今日はもうこれで帰りましょう、夕方またきます、報道は控えます」そう言って立ち上がった。堀田も頷いた。
濱田は黙ったままの尾木のところに行くと、小声で「少年のことは我々三人だけのことにしておきましょう」と言った。尾木は濱田と私を見て、ふかぶかとお辞儀をした。大事にしていたオランウータンが二匹も殺され、一匹は深い傷を負っているのである。大変な気落ちだろう。
外に出た。夜中の三時だからまだ暗い。動物園を出ると濱田がパトカーで署まで来るかと誘われたが、家に帰って寝ると答え、タクシーでアパートに戻った。きっと、また夕方には動物園に来ることになるだろう。風呂を沸かして久しぶりにゆっくりつかった。
十時ごろ気持ちよく目覚めた。天気がいい。昼間はどうするかと思案をしているところに電話がなった。濱田からだった。
「尾木が死んだよ、自殺だ、署に来ないか」
なぜ尾木が死んだのか。もしかするとすべてが解決したのではないか。そんな予感がして下山署に出向いた。
濱田を訪ねると、自分のデスクの脇に椅子をもってきた。そこに腰掛けろということだ。濱田は「終わったようだな」と言った。
「尾木は首をつった。遺書があったよ、すべて私の責任です、とあった」
「オランウータンのことだけなのかな」
「堀田課長は、尾木はまじめな男だったから、自分の子どものようなオランウータンを殺害されて、自責の念に駆られたのだろう、と言っていた」
「でも、犯人はわからないし、動機もわからない」
「なあ、メイメイちゃん、あんた、きっとわかっているのじゃないか、ちょっとこっちに来てくれよ」
彼は立ち上がって鑑識課の部屋に私を連れて行った。春川しのぶの自殺の証拠品の入った籠の前で胎児の瓶を指差した。
子宮が浮かんでいるがどこか違う。首が離れていない。くっついている。
「な、あんたなら、わかるだろう、もうオランウータン殺しは起きないのじゃないか、どうだオランウータン殺しがどうして起きたのか、どうして春川しのぶは死んだのか、教えてくれよ」
私は頭の中でつじつまを合わせようと懸命になっていた。濱田が言った
「春川しのぶが自殺したことは確定させる、精神的不安定でナイフで自害との発表だ、オランウータン殺しは殺虫剤中毒死で、その責任を取って尾木が自殺だ」
「そういえば、昨日刺された雄のオランウータンはどうしました」
「よかったよ、命は助かった。あれだけ血が出たのによく助かった、出来のいい獣医さんだったんだろう、尾木はそれを知ってから自殺した」
「そうですかデスクのほうにはそれなりに報告しておきます、あまり記事にならないようにします」
「そうしてくれると嬉しいね、他社にも特に質問がない限りはこちらからは発表しない、オランウータンの中毒死は園の責任になるが、殺害事件よりもいいと、堀田も了解済みだ」
「そんなことできるのですね」
「そういうもんだ、どうだ、今日、一杯、そこで、メイメイちゃんの名探偵振りを聞かせてくれよ、動機なんかをね、本当のことは判らないけど、お前さんのいうことなら正しいだろう」
夕方、下山駅の周りにあるごみごみした飲み屋街の店で彼と飲んだ。
「どうして、春川しのぶは腹を切って、胎児の頭を切って死んだんだ」
「オランウータンの野外運動場の谷のところに落ちたとき何かあったんだろう」
「そうか、そのとき、やられたのか」
「そうだと思う、それでオランウータンが襲ったと思い込んだ」
「妊娠を知って、オランウータンの子供ができたと思ったのか」
「春川しのぶはレオポンを見たがっていた」
「ライオンと豹のあいのこか」
「簡単にはいかないが、猫科同士なので、子供が生まれることがある、それを知っていたのじゃないだろうか」
「でもオランウータンとヒトじゃできないだろう」
「出来ないと思いますよ、だけど、オランウータンの説明書きにはヒト科とある、それを覚えていて、ヒト科同士で子供ができると思い込んで、自殺したんだろう」
「だが、検死官は胎児のことをそうは言っていなかったぞ、胎児は正常な人間だ」
「と言うことは、人間の男が襲ったことになる」
「あ、オランウータンの担当者、尾木か」
「そうでしょう、あの胎児は尾木の子供だ、尾木もそれを知ったんだと思う」
「つじつまが合うな、お前さんの説明は、だがオランウータン殺しは説明できないだろうな」
「濱田さんが言ったように、説明できないことも重なって起きた」
彼は頷いた。
「あの胎児は男の子だった、オランウータンを殺したのは、尾木に対する復讐だ、違う世界の者がやった復讐と言うことだよ、尾木には子供のようなオランウータンを殺したのさ、だから、オランウータンが憎いのではない、それで花束だ」
「それじゃ、あの娘はあの世に行ってから真実を知ることになったわけだ」
私は頷いた。
「だけど、自分で胎児の頭をはねる事ができるでしょうか、僕は出来ないと思う」
「どういうことだい」
「胎児が、自分の首をはねさせた、そうして、この世に出てくるようにして、尾木に復讐をした。自分を作った責任を取らせた、オラーウータンを殺してね」
「それじゃ、娘は犠牲になったわけか」
「そうでしょう、優しい娘さんだったようだ、オランウータンを殺すなどとは考えないでしょう、みな胎児がやったこと、ただ、花束は娘があの世からおいたのかもしれない」
「メイメイちゃんは人間だね、そのとおりかもしれないが」
濱田はビールの追加を注文した。何か考えている。きっと頭の中で、どこかで妥協しなければならないんだと、自分に言い聞かせているようだ。
「今の世でもそんなことが起こるのか」
「今の世ってどうして存在しているんだろう」
「そうだな、まあビールが旨いということは、俺たちは存在しているんだよな」
彼はそう今度の事件を締めくくって、次の話題に変えた。
私に彼の妹はどうだという話になり、とうとう一緒になり、連れ添って、今年で四十年になる。濱田は退職後信州に引っ込み、畑作りに精を出している。私が書く本のいい読者である。
胎児
私家版幻想小説集「桃の皮、2022、249p、一粒書房」所収
絵:著者


