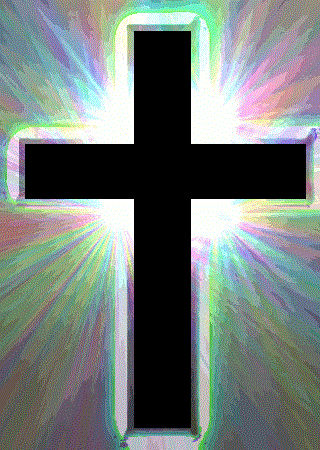
副産物 ― Zinnober ―
1 桜の木の下には
Zinnober 「赭」
シャ・そお
一 アカ、赤色
二 アカい
三 赤土
四 焼き尽くす
三省堂漢字辞典第4版より抜粋
赤の顔料の中でも、硫化水銀の割合が多いものを真赭と呼ぶ。ピンクに近いくすんだ黄赤。
赤は古くから使われた基本色彩語であり、その語源は「明け」にある。夜が明け、太陽と共に現れる色が赤。
そして、赤は火の色や血の色で、「赤」という漢字は火炙りにされる人間の姿を模った物が成り立ちだと言われている。
赭衣とはそのまま赤い着物という意味であるが、上記の成り立ちの所以か、かつては罪人の着る着物とされていて、場合によっては罪人そのものを指す言葉である。
数百年前どこかのバカが悪魔に願ってしまった為に、人口が20億人にまで衰退した現在、世界は頑強な意志の元に統率されている。その意志とはどこかのバカが願った「世界平和」と並行して、「人間の健康的生存」を主軸としたものである。世界を支配する彼らもまた、人間の生存は死活問題であった。
支配者である彼らにとって人間は、文化的文明的にも大いなる役割を果たすものであり、また食料としても重要な存在だからだ。だが支配者階級にいる彼らが「人間ではない」事を知る人間は、ほんの一握りだけ。
どの道それを知ったところで処分されるだけの事であるし、何よりも彼らの目的が支配に留まっていない以上は、表面上世界は平和であった。
生き残っていた人間たちの中には、住んでいた土地を離れ人を求め、大陸に渡った者も多くいた。“ローエングリン”と呼ばれる広大な国、その中の日本人居住区に住む魅霞・小澤も、そんな一人。
魅霞がその人と出会ったのはまだ少し肌寒い春。
桜は日本人のこころだ。桜が嫌いな人はそうそういない。いたとしたら非国民と呼んでもいい。自分が純血の日本人であることを誇りに思う魅霞は、素直にそう思う。
薄紅の花弁が視界を覆った。梶井基次郎の小説ではこうある。
桜が薄いピンク色をしているのは、その下に死体が埋まっているから。
この桜が彼岸桜なら、あるいはそうなのかもしれない。視界を遮り、まるで呼吸すらも阻害されるような錯覚に陥る程の桜吹雪、桜の嵐。風が長い黒髪を攫うと、その髪に桜が纏わりつく。
「まるで、坂口安吾の小説みたい。桜の森の満開の下、一人なら平気。でも二人なら狂っちゃうんですって」
目の前の男性に微笑みかけた。
赤毛の首筋を覆う長髪、人ならぬ人の証、赤い瞳。雪のように白い肌は存在感さえ希薄にさせる。男性の無国籍な顔立ちに、畏怖すら覚える――――冷徹に感じるほどの美貌。
男性は一切表情を崩さない。驚いているでもなく訝しんでいるでもなく、ただその赤い瞳で見据えている。その瞳の中で様々な逡巡が駆け巡っているから、そう言った表情をしているのだろう、そう勝手に解釈した。
「あたしはずっと今日という日を待ってた。ずっとあなたに――――会いたかった」
ずっと待っていた。この時を待ちわびていた。この人と出会えることを。これはきっと運命、いや――――宿命だ。
男性が口を開いた。
「君は……僕を知っているのか?」
「知らないと言えば知らないんですけどぉ。コレをもらったんです」
そう言って右手を差し出した。彼はその手にはまった指輪を見て、気が抜けたかのように薄く瞼を瞑った。すぐに開かれたその双眸には僅かに悲哀を纏っているように見えたが、魅霞につられたように微笑む。
「……そうか。僕と来る?」
「いいんですか?」
男性は頷く。
「名は?」
「魅霞。魅霞・小澤です」
「そうか、魅霞。じゃぁ行こうか」
踵を返した男性を慌てて呼んだ。
「あの、名前」
男性は思い出したように苦笑して振り返った。
「僕はダニエル・ザイン=ヴィトゲンシュタイン・ルートヴィヒスブルク・フルトヴェングラー」
「長っ」
素直に感想を述べてしまった。慌てて口元に手をやってダニエルの様子を窺うと、案の定睨み下ろしている。瞳が赤いせいなのか、余計に怒気が籠っているように見えて怯んだ。
「あ、す、すいません……ダニエルさん」
思わず謝罪すると、ダニエルは小さく息を吐いてスタスタと歩きはじめてしまった。
「あ、ダニエルさん、ちょっと」
追いかけて後を着いていく。桜のトンネルは飽きる事もなく桜を降らせる。
まるで桜の下の死体たちが、二人の出会いを祝福しているかのように。
指輪が繋ぐ、新しい物語。
2 人間失格
現在この国“ローエングリン”では、犯罪に対する処罰は異常と言っていいほど厳罰化されている。当然それは罪人を支配者たちの食料にする為でもあるのだが、そう言った実情は人間には知らされていないし、死刑になった人間の遺体が返却されないのは今に始まったことではないので、それを知る者は一部に限られている。
当然犯罪が起きない為に生活や福祉の保障は他の類を見ないものとなっているし、人口の減少した現在、稀に発生する犯罪者の厳罰は一般市民も希望するところである。
中でも性犯罪に対する罰は厳重なもので、例えば軽度の犯罪、わいせつ物陳列罪でさえも死刑に該当する。そう言った犯罪を犯すものは、のちに重大な犯罪を犯すであろう予備軍と捉えられている為だ。それは未だにこの世界に残されている、どっかのバカの遺産である「天使」を懸念している為だ。
どっかのバカが悪魔に願った世界平和。その為に悪魔は、「世界平和の為には人間は邪魔である」と提唱し、世界中にウイルスをばら撒いた。
新型ウイルス「エンジェル」。
感染経路は接触感染、空気感染、遺伝、あらゆる経路から感染し、その感染力と発症力はペストを上回る。発症した場合の致死率は100%。感染しても発症しなければ健康な生活を維持することができるが、発症した場合は2年以内に確実に絶命する。感染後、一定の条件を満たした後に発症する。
その条件は性交渉。つまり人間は性交渉により発症し確実に絶命し、また遺伝によっても感染する為その子供も罹患する。性交渉により発症するとなれば、人々は自然とそれを避ける。それにより少子高齢化は加速の一途をたどることになり、確実に人間を淘汰するという仕組みだ。
このウイルスが「エンジェル」などという名称がついてしまったのは、発症後の人間の行動によるものである。狂犬病のように脳に作用するこのウイルスが発症すると、誰もが幸せそうな笑顔で死ぬ。その人の持てる全てを人に施し、人に親切にし、それに満足した様に笑いながら死ぬ。どんな極悪人でもそんな風に死んでいく。その様はまるで、天使のようだった。
だから最初の頃はわからなかった。世の中の人がみんな急に優しくなって、世界が変わって、一気に死んだ。ある時、世界各地の政界人を初めとして、多くの人々が世界平和と世界的な援助や福祉を訴えだし、ものの数年で世界は生まれ変わった。
その後一気に人口は減少し、数年後研究者によってウイルスが発見されたが、その後長い時間をかけてもわかるのは影響ばかりで、治療法どころか防疫策すらも見出せずにいた。
悪魔は言われたとおりに願いを叶えた。どの国も国連に加盟し、核廃絶を有言実行し、ウイルスが発症した人間によって、平和を乱す不穏分子は大量に粛清された。
世界平和は成立した。悪魔に願ったバカが死ぬ間際に言った。
「ウイルスは悪魔によってもたらされた。ならばこのウイルスを治療するのは、神の奇跡しかないのだろう」
そう言って謝罪しながら、悪魔に魂を奪われて死んだ。
その言葉を信じた一部の人たちは、神を信仰し足しげく教会に足を運んだ。集団強姦されたシスターが発症し、毎日神に祈りを捧げていたら治癒され何年経過しても死亡しなかった、と言う噂も流れ始めた。
今現在宗教を問わず、人々は信仰によって生きている。信仰により発症を免れた人間たちが、連綿とその血脈を紡いでいる。今尚ウイルスはその猛威を振るってはいるが、その信仰とその教義と、ウイルスの影響もあって、世界は平和を維持し続けている。
支配者階級の者達にとって神への信仰は恐るべきものであるが、人間が絶滅してしまう事に比べれば、自分たちの正体を隠してさえいれば済むことだ。だから人間と信仰と自分たちの都合の均衡を取り計らいつつ、今のところ世界は安定している。
しかし時には異常犯罪者もどこかで出てくるもので、どうしても犯罪をゼロにすることは不可能だ。だからこそ魅霞は、ダニエルとの出会いに歓喜せずにはいられなかった。
魅霞には水萌という双子の妹がいた。二卵性で顔は似ていなかったが、仲の良い姉妹だった。12歳の時、水萌が服をぐちゃぐちゃにして、ボロボロになって帰ってきた。何があったのかと両親が聞いても答えなかったが、魅霞にだけは話した。近所に住む18歳の少年に、乱暴されたのだと。普段は親切だった「近所のお兄さん」に魅霞も水萌も懐いていたから、家で遊ぼうと誘われて疑いもせずについて行った。
水萌は誰にも言わないでと言った。魅霞の両親も薄々は気付いていたようだが、裁判などになった際にはその状況を水萌自身が克明に語らなければならない。そうなると水萌が余計に辛い思いをするから、そう判断して泣き寝入りすることになってしまった。
それから水萌は神に毎日祈りを捧げた。魅霞も祈りを捧げた。どうか水萌が救われますように。だが水萌は再びその少年に乱暴されてしまって、ついに自殺した。
許せなかった。魅霞の両親もとうとう少年を告発することに決めた。しかし水萌が死んでしまって、本人の証言も証拠も何もない。この国は犯罪に対する処罰が厳罰である分、裁判は厳正で厳密に執り行われる。この国では性犯罪に関しては10歳以上なら成人と同様に処罰が下される。せめて水萌の証言があれば、少年を死刑台に送れた。
なのに、水萌の方が死んでしまった。あの時泣き寝入りしなければ、水萌は死なずに済んだかもしれないのに。確実に少年を死刑台に送ることができたはずだったのに。
少年を恨んだ、両親を恨んだ、願っても聞き届けてくれなかった神を恨んだ。
魅霞は家出して、逃亡した少年の後を追った。そしてダニエルと出会って、人間であることを放棄したその時から、運命が変わった。
水萌が死んで半年が経過し、魅霞は14歳になった。魅霞が辿り着いた地域は「諦観者の箱庭」と呼ばれていた。そこに住む人達は生きる事や祈る事をやめてしまった人や、一度でも犯罪を犯し裁きを受けた者達が住んでいる。この国は平和であることが当たり前なので、一度でもどれほど軽度でもいかなる理由があれど、犯罪を犯した者は社会的には人間として見られることはなくなる。雇ってくれる所などありはしないし、金も家も借りることは不可能だ。その事は子供に至るまで周知の事実で、犯罪を犯す者はある程度人生を棒に振る覚悟は決めている。「諦観者の箱庭」は、人間であることを放棄した、あるいはそうせざるを得なくなった人たちの溜り場なのだ。
だが、たまり場である為に犯罪の温床でもある。悪い人間たちが徒党を組んで新たな犯罪を起こす可能性は高い。しかしながら、政府としても不穏分子が一塊になっていた方が監視はしやすい。このあたりの地域は常に衛星や街頭カメラによって監視されており、近くには警察や消防の詰所もある。
魅霞は家出をしてから、諦観者の箱庭でエンジェルが発症してしまった人々と共に暮らしていた。最初に出会った老婆は70歳くらいで、寂れた公園で鳩に餌をやっていた。
老婆が鳩に餌をやりながら涙を零すので、傍に寄って話を聞くと、子供も孫も出来たが、交通事故で娘の家族が死んでしまった。だからもういいのだと言って、祈ることをやめた。それを聞いて魅霞は自分も独りぼっちなのだと言って、老婆と生活を共にするようになった。老婆の住むアパートにはそう言った人たちが老若男女問わず多くいて、彼らが年金や貯金を全部魅霞に渡してくれるものだから、老婆を初めとしてアパートの人たちの看護をしながら少年を探した。
アパートの住人達はみんな魅霞に優しい。ウイルスの影響もあってか、誰もが優しくて魅霞に礼を言って褒めてくれる。魅霞が手を滑らせてご飯をこぼしてしまっても、お風呂のお湯の温度が熱くても、いいのよ、いいんだよ、いつもありがとうね。そう言って何をしても許してくれる。
ただ死を待つだけの彼らが、ただひたすらに優しくなっていく事がとても悲しかった。だがエンジェルの効果は善人になるというだけではなく、世界平和の為に悪を淘汰する思想が生まれると言う作用を持ち合わせている。その為に魅霞の家出の理由を知った彼らは、魅霞の敵討ちを応援してくれた。
「悪い奴はやっつけなきゃいけないよ」
「魅霞、頑張れよ」
そう言って、見舞いに来た人たちにまで聞き込みをしてくれたりして、お陰で少年を見つけ出すことが出来た。
「ヴェロニカばあちゃん」
少年の元に行く決意を決めて、老婆の皺だらけの手を取った。既に白濁した、盲いた瞳を向けた老婆は魅霞の手の上に温かく、大きなルビーの指輪が輝く手を重ねて、優しく微笑んだ。
「気を付けて行ってくるんだよ。ミハイルのとこの倅と一緒に行きなさい。一人だと危ないからね」
最後まで優しい老婆の笑顔に、涙が出た。
ヴェロニカばあちゃん、もうさよならなの。あたしは帰って来れないの。アイツを殺したら警察に自首するから、あたしは死刑になるから。
老婆の笑顔を見ていると、その言葉を言う事がとても辛くてなかなか言い出せずにいた。すると老婆はルビーの指輪がはまった手を離して、少し宙を探る様にして、ようやく見つけた魅霞の頬を撫でた。
「魅霞はいい子だね。あたしみたいな年寄りにも優しくしてくれて、魅霞に出会えると知っていたら、祈るのをやめたりなんかしなかったのにねぇ」
孫が帰ってきたようで嬉しかったんだよ、そう言って笑う老婆の笑顔にまた涙が零れた。
「ヴェロニカばあちゃん、もう少し長生きして。あたしまだここにいるから」
堪らず涙が溢れてきてしゃくりあげながらそう言うと、老婆は頬を撫でながら涙を拭ってくれた。
「魅霞がそう言うんなら、もうちょっと頑張ろうかねぇ。じゃぁ魅霞も、死んだりしちゃいけないよ。世の中にはねぇ、死にたくても死ねない人もいるんだからね」
そう言うと老婆は手を離して、そっと指輪を引き抜くと魅霞に差し出した。それを受け取ると、老婆はまた微笑んで言った。
「台座がね、ロケットになっているんだよ。開けてごらん」
言われて見て見ると、台座と指輪の付け根が開くようになっていた。中から出てきた写真は、金髪の30代くらいの女性と赤毛の20代半ばの男性が映っていた。女性は面影があったので、若い頃の老婆だろうという事は察しがついた。
「この人はヴェロニカばあちゃんの旦那さん?」
「いんや、友達だよ。この人とは魅霞くらいの年ごろからの友達でねぇ」
「へぇ……」
「最後に会ったのはもう20年以上前かねぇ。どこで何をしているやら知らないんだけどね」
そう言って老婆は、少しだけ悪戯っぽく微笑んだ。
「出会ってから最後に会った時まで、全然姿形が変わらなくてねぇ。死んでない事だけは確かなんだよ」
思わず目を見開いて、写真を見ていた視線を老婆に向けた。
「うそ」
「本当だよ。その人は人間じゃなかったからね。ウチの裏の森の廃屋に住んでたのさ、ずーっとね」
ずぅっと昔からそこに住んでいて、たまにある怪異の原因がその男性であることを知ったのは結婚して家を出てから。人に会いたくはないと彼は言っていたけど、とても寂しそうにしていた。だから彼は老婆を手にかける様な事をしなかった。
どこか懐かしむような顔をして、老婆が言った。
「その人は死なないからね、あたしみたいな友達が出来ても辛いだけさ。何度も友達の死に顔を見なきゃいけないからね。最後に顔を見て見たかったけど、どの道あたしにはもう何も見えはしないし、覚える死に顔が増えるのも可哀想だからね。生きたくても生きられない人もいれば、死にたくても死ねない人もいるもんだよ。あたしは死にたくて死ぬんだから、いいんだけどね」
言って老婆は少し可笑しそうに笑った。
「妹の敵討ちを頑張ってほしいって思うんだけどね、魅霞が死んでしまうのは嫌なんだよ……なんて、あたしは何を言ってるんだろうね。矛盾してるね」
そう言って老婆が笑う物だから、魅霞もつられて笑った。
そう言われて「じゃぁ敵討ちをやめる」という選択は魅霞には全くなくて、死ぬ事をやめることにした。
もっと老婆やアパートの人たちの傍にいたいという気持ちもあったが、そもそも魅霞がこの町にやって来たのは少年を追跡し殺害するためだ。その目的は完全に遂行したいと思っていたし、もたもたしていたら少年がまたどこかへ流れていくかもしれない、と思った。
「ヴェロニカばあちゃん、ちょっと出かけて来るね。ちゃんと帰ってくるから」
そう声をかけて指輪を返すと、老婆はそれを指にはめて魅霞を送り出した。
「気を付けるんだよ」
「うん、いってきます」
逝ってくるつもりだったがやめた。征って、帰ってこよう。せめて老婆を看取ってやりたいから。死ぬ事はいつでもできるから。
出かけた先は少年の住むバラック。周りに住むのは罪人や、罪には問われなかったもののかつての居住には戻れない、少年と似たような人間達が住んでいて、治安はとても悪い地域。そこに赴く事はとても恐ろしかったが、目的を果たすことさえできればそれでよかったし、何より魅霞には時間がなかった。
少年がこの地域を離れてしまう事も勿論そうだが、発症してしまっていたら死ぬのは時間の問題だ。どうしても魅霞の手で引導を渡してやりたかった。それに何より、少年が老婆たちの様に優しくなって罪を悔い改めて謝罪するような姿を見たくはなかった。少年が心から悔い改めてそう言うなら聞き入れもしようが、病に浮かされて病によって出てくる言葉など聞きたくもなかった。それほど魅霞にとって、少年が病にかかろうが一切の同情の余地はなかったのだ。
が、覗き込む窓の内側は、魅霞の予想に反した光景が広がっていた。部屋の中を埋め尽くす仏像や護符、数珠を握った手を合わせて大きな仏像に少年が祈りを捧げている。蝋燭の炎に照らされたためか少年の顔色は悪いわけでもなく、優しくなってしまった病人たちから奪ったであろう空の財布が仏像の隙間にいくつも転がっていた。
魅霞の黒い瞳に映る蝋燭の炎が、一際燃え盛った。その瞳の中で燃え上がる炎は姿を変えて、魅霞の瞳と脳の中で激しく暴れのた打ち回る。
救いを求めるというの、水萌をあんな目に遭わせておきながら。こんな人でも救われるというの、水萌は救われなかったのに。
その光景は魅霞の復讐心を更に炎上させるには十分で、また神を呪うには十分すぎた。
少年の姿は、魅霞にはあまりにも悔しかった。悔しさのあまり泣きたくもなかったのに涙が出た。泣いてその場を走り去って、アパートに戻り老婆に泣きついた。
「酷い、酷いよ。神様は酷い。どうしてあんな奴が救われるの。どうしてあんな奴を救うのに、ミナちゃんを救ってくれなかったの」
泣きつく魅霞の髪を撫でて、老婆が諭すように言った。
「神様って言うのはね、本当はね、誰も救いはしないよ。誰でも救うように見えるけどね、本当は沈黙して何もしないんだよ。ただ傍にいて見ているだけだよ。一緒に苦しんだなんて、神様は言うんだろうけどね。世界って言うのは理不尽で、神様って言うのは残酷なんだよ」
神に問う。信頼は罪なりや。
果たして、無垢の信頼心は、罪の源泉なりや。
神に問う。無抵抗は罪なりや?
その問いかけを幾度も魅霞は神にしてきた。その返答はいつも帰って来なくて――――あぁ、沈黙しているのだ、と。
神はいつも沈黙している。この世界は残酷な神が支配している。
ならば世界も神も棄てるしかないではないか、自分の世界で生きて行かなければ、無垢な信頼は裏切られてしまうから。
それから数日後、やはり神は信頼を裏切る。もう少しだけ頑張ると言っていたのに、老婆は容体が急変した。泣き縋る魅霞に老婆は震える手を伸ばして、息も絶え絶えに言った。
「指輪……魅霞に、あげるよ。あたしの事を、忘れないでおくれ」
泣きながらひたすらに頷いて、忘れないと約束する事しかできないことが、とても悲しかった。
震える指先から指輪を受け取ると、老婆はそれに安心したように静かに息を引き取った。
役所に連絡をして、老婆が残していたお金で小さなお葬式を開いた。アパートの人たちも老婆の死を悼んで、恐らく次は自分の番なのだろうと、先に逝った老婆の後を追いかける支度をしたいと魅霞に言い始めて、魅霞は一層悲嘆に暮れた。
「なんで、どうしてみんな死ぬって言うの」
泣きながら訴えてはみたものの、発症した以上は死は確定している。今更どうにもならないことを魅霞も知っている――――それでも。
「魅霞、ゴメンね。魅霞を悲しませたいわけじゃないのよ。だけど……」
「俺達はもう生きるのに疲れたから、いいんだ」
「いいんだよ」
「いいのよ」
「いいんじゃよ」
もう、いい。
その言葉はこの町で、毎日聞こえてくる諦観の合唱。
「最後に魅霞に出会えたから、それで満足。どうか、忘れないでね」
ただ彼らの諦めを受け入れて、ただ彼らの優しさに涙して、ただ彼らを忘れないと約束する事しかできない自分が、悲しかった。
神に問う。信頼は罪なりや。
果たして、無垢の信頼心は、罪の源泉なりや。
神に問う。無抵抗は罪なりや?
いまは自分には、幸福も不幸もありません。
ただ、一さいは過ぎて行きます。
理解するには早すぎる14歳と言う年齢で、魅霞は太宰の言った言葉を、痛いほどに理解した。
3 新世界より
魅霞の話を聞いてダニエルは「そうか」と呟くように言った。
「ヴェロニカは、逝ったんだね」
「はい。この指輪をあたしに託してくれました」
ルビーの指輪。魅霞には少し大きくて、中指の付け根で浮いている。それを外してロケットを開け、ダニエルに差し出した。中の写真を見て、ダニエルは目を細めて指輪を受け取る。
「懐かしいな」
森の奥の廃屋、雨上りの新緑が綺麗で、木漏れ日の差し込む森に感嘆した彼女が写真を撮ろうと言った。写真は嫌いだと何度言っても聞いてくれなくて、後生大事にするとまで言い出して余計に嫌になったのだが、渋々折れて写真を撮った。満面の笑顔の若かりし頃のヴェロニカと、今と全く姿形の変わらない、苦笑気味のダニエル。
写真を見つめるダニエルの瞳には彼女との思い出も蘇っているのか、懐かしさと少しの楽しさと、幾分かの悲しみが揺蕩っている。
「ダニエルさん」
「うん?」
名前を呼ぶと魅霞の方に顔を向けた。
「その指輪、ダニエルさんが持ってて下さい。その方がきっとヴェロニカばあちゃんも喜ぶから」
「君が譲り受けたのなら、君の物だ」
「じゃぁあたしがダニエルさんに譲ります」
ダニエルの手から指輪をつまみ上げて、彼の細くしなやかな小指に指輪をはめた。予想していた通り、彼の白い肌にはルビーの赤が一層映えて、蝋燭の光を映したルビーが濡れたような光をゆらりと反射させた。
「うん、やっぱりダニエルさんの方が似合います」
満足してダニエルに笑うと、「そうか」とダニエルも笑った。
ふとダニエルの体がゆらゆらと揺れた。ダニエルが座っていた膝を上げてがつっと踏みしめると、その揺れは止まる。
「それで、魅霞はどうしたい?」
ダニエルと出会って彼の力を以て、あるいはその力を以てして同族になり、敵討ちを遂行する。もし彼に出会えたら、伝説にある様な「吸血鬼の呪い」も引き受けるつもりでいた。それが過酷なものであっても、その業を背負うには十分すぎる事をする予定があったから、それでもいいと思った。
魅霞が彼に出会ったのは、偶然だった。買い物の帰りに、桜の木の下でキスしているカップルを見かけた。病の存在が恒常化しているので、カップルや夫婦者は性交渉が出来ない代わりに、他の行為で愛情を示すしかない。抱きしめたり手を繋いだりキスをしたり愛を囁いたり、どこにいても街のあちこちでそう言う光景を見かけるのは現在では万国共通で、魅霞の両親もそうであったから見る方も慣れている。
特に気にも留めずにそのカップルの方向に足を向けた時に、女性の方が突然、一瞬で砂塵と化した。
何が起きたのか理解するのは後回しでよかった。魅霞の上げた小さな悲鳴に反応し、横目で見やったダニエルの赤い瞳に萎縮してしまった体を、どのように稼働させるかが問題だった。必死で足に力を入れた。
逃げろ。
逃げろ。
次はあたしが殺される。
が、脚は硬直して微動だにしない。とうとう彼が魅霞に振り向いたとき、その顔を見て一瞬で思考は別方向に追いやられた。
あの人だ。
指輪の写真の、ヴェロニカばあちゃんの友達の ――――吸血鬼。
彼がその人であることを気づき逃げるのをやめた途端に、金縛りから解放された。魅霞の思考は更に急いて、脳内で激しく演算を繰り返す。
どうにかして なんとかして 、今から魅霞を殺そうとするダニエルを止め、尚且つ彼の気を引く言葉を。
考えてようやく絞り出した。
「ずっとあなたに会いたかった」
必死に考えて紡いだ言葉は功を奏して、ダニエルは表情を変えた――――と言う、2時間ほど前の裏話だ。
「実はあたし凄くテンパってたんですぅ」
「……そうか。道理で小説の話なんぞが出てくるわけだ」
「本当ですよねぇ、あたしも何言ってんだろって思いましたもんアハハ」
魅霞は笑っているが、ダニエルの方はと言うと、コイツは本当に大丈夫なのか、と訝しそうにしている。 それに気付いた魅霞がやはり笑って言う。
「だぁいじょぉぶですよぉ。バレないようにしますってぇ」
魅霞は自信満々だ。一応根拠はある。「諦観者の箱庭」は犯罪者及び予備軍の溜まり場なのだが、その為か変わり者が多い。多少の奇行は無視してくれるのがこの町の特徴だ。
ついでだが縄張り意識も強い。強盗なんかに襲われて「助けて!」と叫んだら被害が増大するだけだが、「コイツΛ区のスパイだ!」と叫べば助けてもらえる。ちなみに 魅霞が老婆と暮らしていたアパートはΔ地区で、ダニエルの棲みかはΕ地区だ。
なにより魅霞が最も驚いたのは、ダニエルの棲みかだ。何度も足を運んだ、箱庭の住人達が全幅の信頼を寄せる医者の家だった。ちなみに闇医者だ。
どういう事か尋ねてみると、食料の調達の為らしい。
「あそっか!病院なら輸血用の血液が手に入りますもんね!」
手を叩いてそう言うと、ダニエルは溜息を吐いた。
「いや、輸血用の血液を飲んでも何もならない。必要ではあるけど、人が水を飲む事と変わりはない」
栄養源にはならない、と言うことのようだ。
となると、疑問が浮かぶ。老婆も彼自身も吸血鬼だと言ったのに、血を飲まないとは矛盾している。首を捻っているとダニエルが言った。
「魅霞は本当に僕の仲間になりたいのか」
「はい」
そう言ったし、その理由も説明した。 尚もダニエルは確認を重ねた。
「覚悟が必要だ」
「わかってます」
「定住はできないし、僕の仲間になったところで殺人の罪は消えない。それどころか増える一方だ。君にそれが背負えるのか?」
「……はい」
少し答えに詰まったが、頷いた。
魅霞の返答を聞き、ダニエルはやはり溜め息を吐いた。
「そうか、ならば教えてあげよう。我々『副産物』の血を引くなら、必要なことだ」
ダニエルが語る、「副産物」と揶揄された所以。
彼ら「副産物」と呼ばれる吸血鬼は2派ある。真赭と呼ばれるのが今のところダニエル一人。もう1派が『猩々緋』と呼ばれ、真祖以下約200名。猩々緋は国家の認定を受けており、真祖は「ジークフリートの再来」と渾名されている。それを聞いて、魅霞は飛び上がって驚いた。
「教皇様が!?」
「そうだ。この事は国家機密だ。絶対に漏らすなよ」
「は、はい」
魅霞が驚くのも無理はなかった。
ローエングリンには多数の民族が暮らす多民族国家だ。この辺りの周辺諸国もほぼ似たようなものだが、その為に信教の自由は認められている。が、一応国教と制定されている宗教があり、義務教育の間はそのミッションを教授される。元々が仏教圏やヒンドゥー圏ならば多神教なのでその辺りの抵抗は少ないが、一神教の民族たちはこの制度を嫌う者もいて、宗教がらみのトラブルはたまに発生する。
ウイルスの影響もあって、今はどこの国もどこの民も信心深く信仰心が篤く、ローエングリンの国教の教皇に寄せられる信望は、崇拝に近いものがある。この教皇をトップとする宗教はローエングリンの首都に本拠を構えていて、国政には関与しないものの教皇庁と言う独立した機関があり、教皇と言う独自の地位を以て宗教活動を全面的に指揮監督する地位にある。その教皇の発言力は、ローエングリンの国家元首である大統領を凌ぐと噂されるほどで、祝祭日にローエングリンまで巡礼にやってくる外国人は数多い。
その教皇がこれほど崇められ、更に「ジークフリートの再来」とまで呼ばれているのは、彼の興す奇跡によるものだ。教皇の血を享けた者はエンジェルウイルスが死滅し、例え発症していたとしてもたちどころに完治する。科学者たちは彼が保菌者で血液に抗体が含まれているのだろう、と推測しており、おおむねその説が有力となっているのだが、最も科学者を悩ませているのは、彼が不死の存在であることだ。教皇の血統が密かに継承されているという話もあるが、いかんせん教皇の姿をお目にかかれないので、誰にも真相が分からない。
直接教皇の姿を拝める者は限られていて、大統領以下内閣のトップ数名と、教皇庁に在籍する教皇の子孫と言われる枢機卿の中でも、特に教皇が信頼を置いている十数名に限られている。枢機卿たちは死亡もすれば老けもする。しかし、彼らの祖である教皇は不死身で、変わらず在位し続けている。
教皇の姿を一般人もメディアも見る事が出来ない以上は真偽のほどは定かではないのだが、ずっと昔から教皇に就任しているのは「トバルカイン2世」であることは周知の事実だ。
その謎と奇跡に塗れた教皇が吸血鬼となれば、これはローエングリンをはじめとして教国を揺るがす大問題だ。
話に驚き呆気にとられる魅霞を見て、ダニエルは少し可笑しそうに笑う。
「正確には、教皇は“吸血鬼のような人間”で、吸血鬼ではない。教皇は間違いなく人間だが、彼もまた血を飲まなければ生きられないし、不死身に近い存在だ」
「そうなんですか……」
いまいちよくわからなかったが、ふと疑問に思った。
「ていうか、なんでダニエルさんそんなこと知ってるんですか?」
尋ねるとダニエルは、当然と言った顔をした。
「元々僕も人間で、教会の者だったからね。僕も教皇も、あのウイルスによる副産物。まぁ突然変異の様なものだ」
「えぇっ、そうだったんですか。ていうか教皇と知り合いだったんですか」
「共に生活していたからな」
「ワーオ」
驚きのあまり相槌が杜撰になった。
話が若干脱線したことに気付いたらしく、ダニエルが話を戻した。
「とにかくだ。我々はエンジェルウイルスにより生産された吸血鬼だ。よって、僕はあのウイルスに感染し、発症した人間の血液しか受け付ける事が出来ない。だからこの土地、病院に身を置いている」
そう言う事なら納得だ、と頷いた。
納得して、少しだけ気分が高揚した。自分の予想が当たっていれば、これほど素晴らしい事はない。
目を輝かせながらダニエルを見上げた。
「あの、病気になった人の血を飲んだら、その人の病気治ったりしませんか!?」
「しない」
息を吐く間もなく即答され、ガッカリした。
「なんだぁ……それだったら片っ端から噛みついてやろうと思ったのにぃ」
口を尖らせて言うと、ダニエルは苦笑した。
「ハハ、もしそうなら僕もそうしただろう。それに、もしその様であれば、今頃教皇と呼ばれていたのは僕の方だ」
「……そう、ですね」
ダニエルから僅かに感じるのは、これは羨望だろうか、と思う。その羨望と嫉妬を、長年抑制しているかのような。それとも彼も、「諦観者の箱庭」で暮らすに相応しい諦観を抱えてしまったのか。
少し思い切って尋ねた。
「教会に戻りたいですか?」
「仮に誘われても断固拒否する」
またしても息を吐く間もなく返答される。ここは多少の逡巡を期待していただけに、少し驚いた。
「えっそうなんですか?」
「何を驚くことが? 当然だろう。我々吸血鬼にとって宗教や信仰は敵に他ならない。君も僕と同族になれば、十字架も仏像も、畏怖の対象でしかなくなる」
「あっなるほど」
教皇は吸血鬼の様な人間だから教会に身を置けるのであって、あくまで吸血鬼であるダニエルにとって、教会に連れて行かれることは地獄と同義だ。
ダニエルの言う吸血鬼の習性及び注意点をまとめると以下の様になる。
・日中起きれない、と言う事はないが、日中は力が弱くなる。
・気を付けていないと鏡やガラス、映像に映らない(気を付ければ映る)。
・あまり血液を摂取していない、力の弱い状態だと宗教に関するあらゆるものが畏怖の対象になる(ダニエルはある程度は平気)。
・姿形が変わらない不死の存在であるため、定住する事は出来ないので、定期的に引っ越しが必要。
・不死の存在の為、仮に性交したとしてもエンジェルが発症することはない。今まで真赭はダニエル一人だった為、妊娠できるかどうかは不明。
・喉が渇いた→人間(罹患者)。お腹が空いた→発症者。発症した人間の血液しか力にならない。発症した人間の血液を吸血する際は、激しい苦痛を伴う上に、吸血された相手は必ずその場で死亡する。発症していなければ砂塵となり、発症していれば失血死のような状態で死亡する。
・赤い服を着た者には気を付けよ。猩猩緋以下教会の組織する「エクソシスト」の可能性がある。
話を要約し終えて手帳を見ながら、やはり魅霞は口を尖らせる。
「発症した人の血液しか受け付けないのに、苦しまなきゃいけないんですか」
とんでもない呪いだ、と思う。しかも相手は必ず絶命するとなればなおさら嫌だ。
「こちらも苦しい思いをする上に、とんでもなく不味いぞ」
「えぇー。最悪」
「そうだな。だが、それでも喜ぶ者がいるのだから、仕方がない」
「え?」
意味が分からずにダニエルを見上げると、「その内見せてやる」と言われた。
ふと、再びダニエルの体が揺れ、ダニエルが踏みつけると揺れが収まる。
「とりあえずコイツは病院で預かっておこう。どうするか少し考えろ」
「はい」
ダニエルの足元で伸びている、水萌を殺した少年を見つめながら返事をした。ここに来る途中に事情を話すと、早速ダニエルは少年を拉致してくれた。逃げられても面倒だし、病院にはイロイロと機材があるのでただ殺すよりはイロイロやった方が余程面白い、と言う理由も兼ねているらしい。魅霞としてもただ殺害してしまうよりも、こんな少年でも最後に人の役に立たせてやった方が気分がスッキリすると言う物だ。
時間が遅かったので、ダニエルがアパートまで送ってくれた。アパートの前で礼を言って頭を下げた。
「あの、あたし本当に誰にも言いませんから、仲間にしてくださいね?」
確認の意味も込めてそう言うと、ダニエルが可笑しそうにした。
「そのつもりでなければ、僕の事を話すと思うか?」
それもそうだと納得した。
「ありがとうございます。また明日病院に伺いますね。お休みなさい」
「あぁ、お休み。せいぜい悪夢を見ないように」
「あはは、うなされそうです」
帰っていくダニエルの後姿を見ながら思う。その背中が背負っているたくさんの病人たちの魂。それまでの長い人生の中で背負ってきた、たくさんの感情。
彼の背中は荷物で一杯で、彼の心の中もたくさんの感情が渦巻いて、その脳もたくさんの思い出が詰まっているのだろう。
長い長い時を生きる、新世界となったこの世界の創世から生きる――――真赭の吸血鬼。
副産物 ― Zinnober ―


