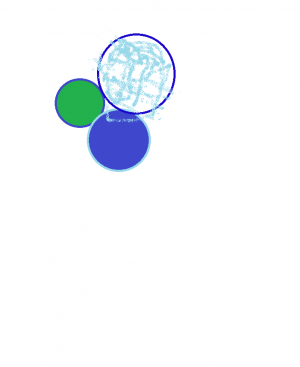夜の左側
真夏の夜の不思議
「地元の大学に進学するなら」
というか
「だったら車を買ってくれよ」
ということでおれが人生で最初に手に入れた車は型落ちのBMWだった。当然容赦なく運転係りにされることになる。
飲み会で一人酒が飲めないことはそういやでもなかったけど、「来いこい」といって誘う連中がおれはいなくてもいいから車来てくれ、という空気をあまりにもあからさまにするのに、おれはだんだんうんざりしていた、大学最初の夏。
「なんだか、ごちそうを食べた上着みたいな感じだな。」
いや、それとはちょっと状況が違うか。これは一人ごとにもならなかった。後ろのシートで乗客は好い加減酔っ払って訳が分からなくなっていたから。一回おれはあまりにも飲んだくれたゼミ仲間を、うっとうしさのあまりその辺に捨ててそのままじぶんちに帰ったんだが、特に文句は言われなかった。被害にあった奴がぐだぐだすぎて何が起きたか分かってなかったからだった。
そんな日があっというまに3ヶ月すぎて、おれとおれの新しい車が好い加減あわれになったおれは、あるバイトの無い夜、長い距離を走ろうと決めた。眠くなったら適当に路駐して寝よう。まさか警察に起こされることも無いだろう。
おれは隣の県へ向かって伸びる道をだただた走る。ライトが照らしているのは分離帯となんかの看板ばかりだ。走れば走るほどすれ違っていく車も無かった。おれはどこまでも一人で走った。
「あれ、おれっていつのまにこんなに一人なんだったけ?」
だんだんそんなことも考えなくなるくらいただただ走り続けた。県境を越えたかどうかも分からなくなってもひたすら走り続けた。
3時間ほども行ったろうか。さすがに疲れて見えてきたコンビニにおれは止まった。好い加減深夜だったから店員も奥に引っ込んでいる。誰も出てこないんならコーヒー万引きしちまおうかな。おれはしばらくペーパーバックの漫画を立ち読みしながら走りすぎて鈍った頭を叩いて直した。
「いらっしゃいませ。」
顕かにさっきまで寝ていたようなバイトが出てきた。レジの中にコーヒーマシーンが設置されている。おれはぼけから回復しきらない店員に気遣って、一番単純なブレンドを一杯買った。
状況は急に変った。
駐車場に戻ると、どこから顕れたのか、だれかがおれの車を覗き込んでいる。
「なんだよ。」
おれは声を荒げた。
「君の?」
覗いていたのはおんなのこだった。
「だったらなんだよ。」
「乗せてよ。」
「はあ?」
「一人でしょ。暇なの。どっかいくなら連れてって。」
おれは車を運転して疲れていて、まともに考えられる頭じゃなかったのかもしれない。夜が煮詰まったところから顕れたような、顕かに怪しいその彼女を乗せるのに、どうしてか逆らえなかった。
「どこまで行けばいいんだ?」
「行きたいとこまでいきなよ。」
「結構走るぞ。」
「大歓迎。」
妙なことになったな。と、思ったのは思考の3割くらいで、残りのおれは願っても無いような奇妙な出来事をむしろ歓迎する気になっていたから、驚くな。
走り出してもおれ達はなにも話さなかった。車は郊外を延々と走るだけで、一向に暗い外以外に何も見えなかった。でも彼女は何を見ているのか、ずっと窓の外に顔を向け続ける。
おまえ誰?
どっから来たんだ?
なにしてたんだ?
聞こうとは思わなかった。聞いても答えない気がなんとなくしていたのだ。それにそんなに知りたい情報でもなかったし。
「ねえ、右側ってどういうことが説明できる?」
彼女が言った。
「なに。それ。」
「だから。右左の右、という言葉を簡潔に説明してみてよ。」
「お箸持つほうだろ。」
「ふふ。私左利きなのよ。」
「だったら左に劣るポジションだ。」
「なあにそれ。」
「右大臣と左大臣だったら左大臣の方がランクが上だ。」
「日本史オタク?」
「そんなほど好きでもない。」
それきり彼女は再び黙った。
おれはいつのまにか自分がどこを走っているのかわからなくなった。彼女を乗せたコンビニをでてからどれだけ走ったのかも分からなくなった。家を出たのは夜11時過ぎだった。好い加減5時間近くは走っている。もうとっくに夜明けの気配が来ていてもおかしくない。しかしおれのライトは分離帯を照らすだけで、窓の外は不気味に真っ暗だった。しかしその黒はどうもおれを安心させた。
「不思議よね。右と左っていったいなんなのかしら。」
「なんでそんなこと気にするの?」
「昔双子の妹がいたの。横向きにしてご飯食べさせてくれたらよかったんだけどさ、いっつも向き合って座ってたから。あのこが右手でお箸持つのみて、私は左手で持つようになっちゃったのよ。
ねえ、単純な現実に限って誰を相手にするかで中身が変っちゃわない?簡単に答えを出したかったら適当に相手を選んじゃえばいいのかもね。」
道路の左側に久しぶりに灯りが見えた。コンビニだった。
「ああ、もういいは、そこで下ろして。」
おれはコンビニの駐車場に入ってエンジンを止めた。
「これ、ちょうだい。」
彼女はおれが買ったものの飲まなかったコーヒーのコップを手にとってドアを開けた。
「とりあえず今日だけは、私の右側はあなたが居たところってことよね。」
ばいばーい。
と言ったかどうか分からないが、そのまま彼女はさっさとどこかへ言ってしまった。
驚くべきことにそこはおれが彼女をピックアップしたはずのコンビニで、時間はもちろん朝だった。7時5分前。
訳が分からないままおれは運転席に座っていた。
出勤途中のサラリーマンかもしれないが、次から次からセダンが止まっては去っていった。
おれは只座り続けた。
その夏のおれの夜の左側が、一切失われたように感じながら。
夜の左側