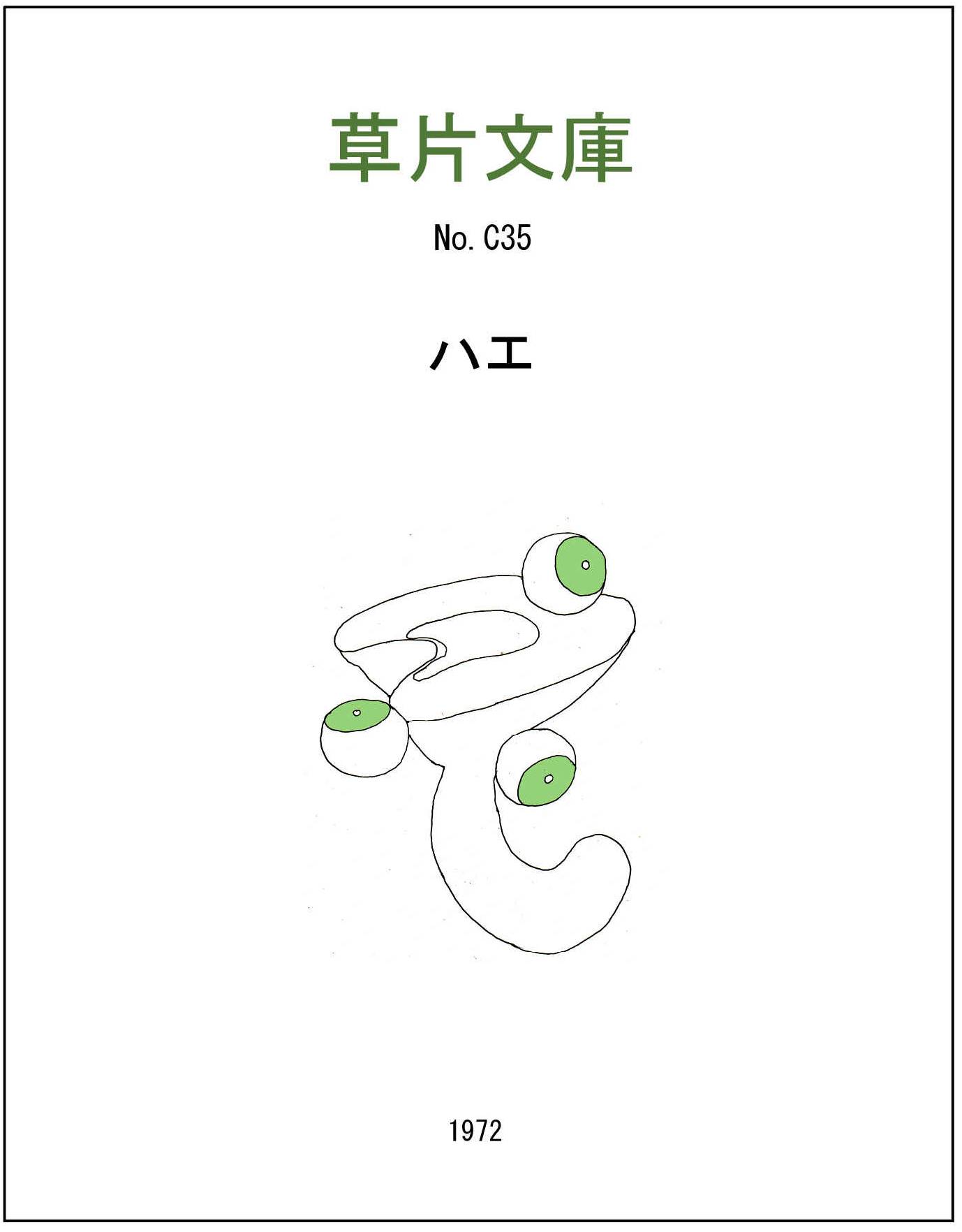
ハエ
銀河系のはずれに浮かぶ一つの茶色い星。明るく輝くその星に、一艘の宇宙艇がよたよたと吸い寄せられていく。
宇宙艇の中では、グリーンランプの点滅する操縦席に、黒く小さくしなびた男が操縦盤に向かってうつむいたままの状態で腰掛けている。干からびた手は、自動操縦切り換えスイッチの上に置かれたままだ。飛び出した眼球はからからに乾き、黒茶に固まった血の氷柱が眼球から垂れ下がっている。
後部座席ではベルトで固定された女が、うめき声を上げていた。腹が小山のように盛り上がって波打っている。女はしきりとうわごとを言い、口角から泡を吹いている。目は釣りあがり瞬きの一つもしない。
茶色の星は宇宙艇のスクリーンを大きく占領していき、やがて操縦者のいない宇宙艇はその星の大気圏に引き込まれていった。
小さな宇宙艇の外郭は炎に包まれ、火の玉となって落ちていく。艇の中は石も押しつぶさんばかりの重力がかかっているに違いない。だが、女は歯を食いしばり、顔をゆがめ、苦痛に耐えている。助ける者などいないのに、何かにすがろうと両手を前に差し出し、腹をかばうようにからだをよじった。ぼきぼきと音がした。そのとたん、女は白目をむき出して意識を失った。背骨が折れたのだ。
このまま行けば、宇宙艇は大地に激突、あえない最後をとげることだろう。
そのとき、茶色の星に思いもしないことがおきた。ぐらっとゆれたのである。星が少しでもいつもと違う動きをすることは、星に異常なことが生じたことを意味する。
大気が渦巻き、激しい風の流れが起きた。猛スピードで落ちる宇宙艇がふわっと救い上げられたのである。激しい大気の流れは、その星の大地のいたるところに開いている洞窟の中に向かっていた。
この星の大地には縦横無尽の穴が開いていた。星の中心には小さなブラックホールがあった。何百年に一度、ブラックホールが大気を勢いよく吸い込む現象が生じた。今がその時期である。
宇宙艇を乗せ風の流れは洞窟の一つにむかっていった。
ローリングしながら宇宙艇は暗闇の中に吸い込まれた。
岩の出っ張りに宇宙艇のアンテナがぶつかった。その弾みで宇宙艇は気流からはずれ、横穴の中に弾き飛ばされた。
宇宙艇は空気の流れにのり、横穴の中を奥へ奥へとすすんでいく。幸い大きなぶつかりもなく、広い場所に出ると、一度バウンドし地面にめり込んで停止した。
どのくらいの時間が経ったのか、宇宙艇は次第に熱が去り、冷たい機械のかたまりになった。
宇宙艇の中で、死んだと思われた女が目を開け、無言のまま椅子からずれおちた。つながっていないはずの背骨を伸ばし、宇宙艇のハッチをこじあけた。宇宙艇から顔を出した女の長い髪をその星の風がはためかせた。
女の顔はゆがみ、目は白くどんよりと宙を見つめている。切り裂かれた喉から血が流れ出し、息をしている様子などどこにもなかった。
女は洞窟の中に這い出ると、手の力で洞窟の奥へと進んでいき、岩のくぼみの中に上向きに倒れこんだ。その瞬間、宇宙艇から赤い原子の炎がほとばしり、洞窟の中が光の中に浮かび上がった。宇宙艇は轟音とともに飛び散り、あたり一面に破片を食い込ませた。
音と光は一瞬にして消え、暗闇にもどったとたん、今度は甲高い音が広い洞窟に響き渡った
「おぎゃー、おぎゃー、おぎゃー」
すでにこと切れている女の両足のあいだに、二人の赤子が手足をばたつかせ、この世の空気を肺いっぱいに吸い込んでいる。この子どもたちにとって、ここの星が生誕の地である。この星の空気も温度も子どもたちに過不足は無かった。
赤子たちは思う存分大きな声で泣き喚くと、一人は疲れたと見えて眠りにつき、一人は喉が渇いたとみえて、爆発した宇宙艇の破片が食い込んだ岩の割れ目から滴り落ちる赤い水をなめた。
時が流れた。
洞窟の壁の暖かい赤い水は、赤子たちを育て上げ、はいはいのできるようになった二人は洞窟のでこぼこを滑り台にして、かすかに流れ込む風の音を子守唄として大きく育っていった。
赤子の一人が洞窟の壁にかぶりついた。歯が生えきらない口でも岩の壁は削り落ち、赤子の口の中に残った。赤子はおいしそうに、くちゃくちゃと口をうごかした。もう一人も壁にかぶりついた。洞窟はまぎれもなく彼らにとって無尽蔵の食材だった。赤子の母親も子ども達がこのような幸運に恵まれていようとは思ってもいなかっただろう。
やがて子どもたちは立ち上がり、一歩、二歩、歩くようになり、習いもしない母星語を操るようになった。あらかじめ脳の中に言語能力が組み込まれていることの証でもある。
光がほとんどない洞窟で、彼らの目は暗闇の中で物を見分けることが出来るようになり、宇宙艇の破片で洞窟の壁を削り取り、柔らかく味のよい岩壁を捜し求めて歩くようになった。
ある日、二人はくぼみの中に奇妙なものをみつけた。
弟の方が恐る恐る手を伸ばした。
「なんだ、これは」
兄も手を伸ばして、さわると、すぐに引っ込めた。
兄は自分の腕に手をやった。
二人はそこにしゃがみこんだ。
「何だと思う」
弟はしつっこく聞いてきた
「俺たちと同じ形だが、かたい」
「触ると、目がおかしくなる」
弟の目から水がおちた。兄も自分の目に水がたまっているのを拭いた。
「目に水が湧き出た」
兄は黙ってうなずいた。
母親の骨は無理のない格好で横たわっている。
弟はにじみ出る涙を拭い去った。
「そうっとしとこう」
兄は弟に立つように促した。
かすかに吹き込んでいた風がはたと止んだ。
それを境に、風の流れが逆になり、渦を巻いて穴の外へと吹いて行った。
渦は宇宙艇の小さな破片を宙に躍らせた。一つの破片が弟の足に当たった。
「痛い」
足から血が流れた。
「血」
彼らはこの言葉をはじめて使った。
弟が足の傷を手で抑えながら言った。
「壁から流れる水とそっくりだ」
弟は手を口に持っていった。
「味も同じだ」
弟は洞窟の壁に傷をつけた。そこから彼らを育てた赤い水が噴出した。
「それは血じゃないよ、ミルクだよ」
兄が言うと弟もうなずいた。
風は更に強くなり、大きな破片が空中を舞い始めた。
「あぶない、壁に穴を掘るんだ」
二人は洞窟の壁を削り、トンネルを掘り始めた。削り取られた土は彼らの食べきれないほどの食料になった。ミルクも染み出してきた。
彼らはめくらめっぽうに掘り進んでいった。
「うわー」
弟の声に兄が上を見ると、赤いミルクが勢いよく流れ出て二人の頭上に降り注いだ。
「ミルクの道を破っちまったんだ、流れないようにな」
二人はでっぱりにしがみついた。必死の思いで流れをやりすごすと、やがてミルクの流れが止まった。
彼らは、トンネルを掘った、どんどん掘った。どのくらい掘ったか分からないが、彼らにとっては永遠のように感じられた。
粘りつくような壁をかき分けていくと、うっすらと光が差し込むようになった。闇になれた彼らの目にはほんの少しの光でも眩しく、目を閉じながら前に進むしかなかった。しかしそれもだんだん慣れてくると、目を開けたまま進むことができるようになった。
そうしている間に二人のからだは成長をとげ青年になった。
光が強くなってくると、最後の硬い層にぶつかった。
二人の手は少しずつその壁を崩し穴を掘った。
プチ。
表面に黒い小さな穴が開いた。
四つの手がその穴から出てきた。やがて真っ白な身体が表面に這い出してきた。
宇宙に浮かぶ、大気を身にまとった巨人。
巨人は長い長い寿命をまっとうし今息を引き取ろうとしている。
歯が欠けた口がかすかに開かれ、少し冷えた最後の息が、巨人にとって埃ほどの宇宙艇の破片を伴って、真空の真っただ中に吐き出された。
死に行く巨人のわき腹を破り、小さな白い虫がウジムシのように顔を出した。そのウジムシは頭を振りながら脱皮をした。
黒くなった二匹のハエは巨人の最後の息に乗り、羽ばたき、自分の本当の故郷の星へと飛び去っていった。
巨人はやがて目を閉じた。
今も巨人は宇宙の外れに浮かぶ。
いずれ、たくさんのハエは宇宙艇にのり、卵をうみつけにやってくるだろう。
真空の宇宙に暮らす巨人の最後は、ハエの子どもたちの食物となり、消えていくことになる。
宇宙の空間に浮かび、暮らしている巨人たちはほんの数人しかいなくなった。真空で生きる生命はもうすぐ絶えることになるだろう。
ハエ
私家版初期(1971-1976年)小説集「小悪魔、2019、276p、二部 一粒書房」所収 IMP17
挿絵:著者


