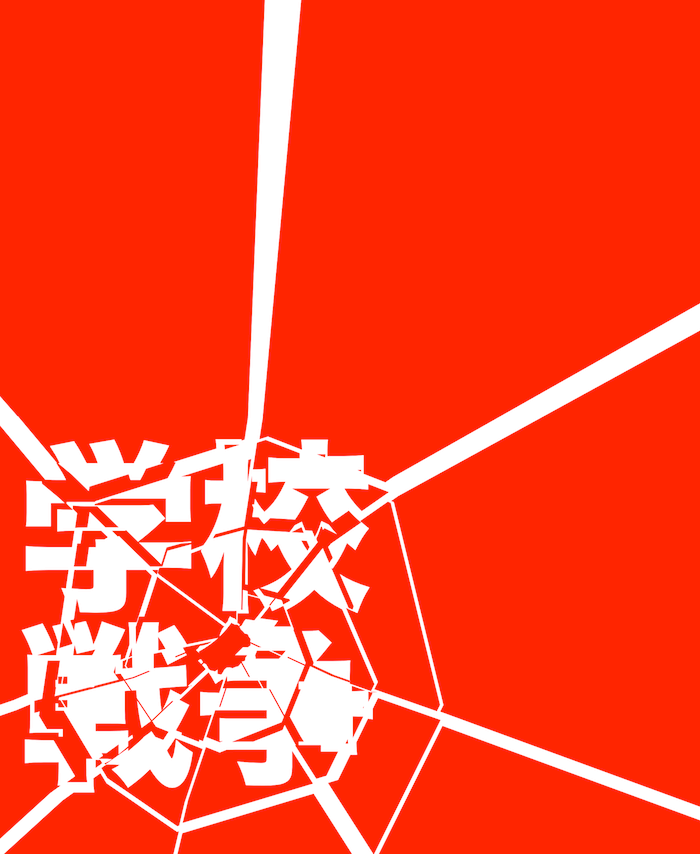
学校戦争 エピソード$02「文芸部のクリスマス」Beta
※この文章はまだ執筆中のものです。一部シナリオや設定、記述に不完全な部分があるかも知れません。また、この小説はシリーズものになっており、この話数はその一部です。
用語説明
・姪禺山高校:この物語の舞台である東北にある地方の高校。大学並みの大規模な設備と在学者数を誇る。外部からの政治的圧力に対抗するために生徒たちの一部は武装化しており、警察の介入の及ばない超法規的な位置づけに置かれている機関といえる。
・緑革軍:姪禺山高校内のほぼすべてを事実上掌握している姪禺山高校の一部の生徒により運営されている軍事的改革組織。全面緑一色の旗が隊旗で、隊員は緑をテーマカラーにした制服を着ている。現在はゴム弾で武装化。
エピソード$02「文芸部のクリスマス」
部屋の天井に付けられた空調はさっきからボォーボォーと唸りながら生暖かい空気を送り出している。折からの冷え込みでどうやら高校内の暖房はフル稼働しているらしい。
健嗣はさっきからパソコンの画面をスクロールしながら、原稿に間違いがないかチェックしていた。──さっきから眠気が出てきた健嗣の意識はまどろんでいた。回転椅子に腰掛けている健嗣だったが、背もたれに寄りかかって半分浅い眠りに落ちている。昨日は5時間しか寝ていなかった。ショートスリーパーの健嗣にはそれで睡眠時間が足りないというわけではないのだが、さすがにこの暖房の暖かい空気に包まれていると眠気を禁じ得なかった。
薄い意識の視界の端の窓の外では一面雲に覆われて白くて明るい空から、やはり白い牡丹雪が降り続いている。雪は午前中に降り出したのだが、まだ止む気配がない
「みんなー、ココア入りましたよー」
扉を開けた部員が部室の外からホットココアを淹れたカップを盆に載せて入ってくる。部室にはポットがないので、わざわざ給湯室からホット・ココアを淹れてきたのだ。その声で健嗣ははっと目を覚ます。どうやら少しばかり舟を漕いでいたようだ。
「おー、ココアだ。」「待ってました!」
部員たちは皆、部屋の中央のテーブルの椅子に座ってココアの入ったカップが配られるのを待っている。カップからは湯気が出ていた。
「あれ、健嗣さん、ココア入りましたよ。健嗣さんの分も用意してます」
「うん?ありがとう。ちょっと今原稿のチェックしててさ。テーブルに置いといてもらえると助かるんだけど」
部員の言葉に健嗣は振り返りぎわそう答える。
「はいー、わかりました。」
「健嗣さん、何の原稿を確認してらっしゃるんですか?」
別の部員が画面に表示されていた原稿について聞いてきた。
「いやさ、今回のクリスマス号に載せる予定の詩をちょっと確認してて。もっと推敲したほうが良いんじゃないかと気になってたんだけど、いまいちしっくり来なくてさ。」
「ヘー、健嗣さんいつもすごい詩ばかり作ってますもんね」
「それほどでも。物好きだよ、物好き」
そう言うと健嗣は手の上でクリップで止められた紙束をバサバサと振った。
「健嗣さんも早くココア飲みましょうよ。甘くておいしいですよ」
先ほどの部員がせきたててくる。
「もうちょっとだけ待っててもらっても良いかな。すぐ終わるから──」
その日、姪禺山高校はクリスマスイブを迎えていた
安留健嗣は姪禺山高校に所属する高校二年生。文芸部に所属している健嗣は、文芸部の副纂として学校生活と共に文芸創作活動に励んでいる。健嗣は主に詩作を主たるジャンルにしており、時々発行される姪禺山高校の文芸部の冊子である『空便』に詩を寄稿していた。
姪禺山高校では新聞部が言論的な活動を担っていたが、それに対して姪禺山高校において文芸部は文芸的創作活動の中心を担う位置づけであり、新聞部と比べるとかなりの弱小部だった。──生徒達の言うところの言うなれば「変人」たちが集まる部活だ。主たる活動は他の部活と同じく放課後に集まってコミュニケーションをとると言うことと、先ほどの文芸部機関冊子の空便の発行である。
今の文芸部には三年生の部長の新妻と一年生が7人ほど(「ほど」というのは幽霊部員も居るので正確な人数はわからないということだ)、そして健嗣の同級生としては女子が幾人かいたが、二年の男子は健嗣一人だった。
クリスマスが近くなってから印刷室にはクリスマスツリーが飾ってある。職員室に隣接した印刷室の中にはコンピュータの端末やプリンタ、そして何台もコピー機が置いてあった。──脇には新しいコピー用紙がたくさん積み重ねてある。
今日はクリスマスイブと言うことで、文芸部はクリスマス号の製本作業の最後の追い込みをしている状態だった。原稿はもうとっくに印刷する状態に入っていたが、健嗣は書いていたときから気になっていた部分があって、もう一度同じ版の詩のデータを自前のノートマシンでチェックしていたのだ。ちなみに健嗣が書いた詩のタイトルは『ヒラギノ』。冬をモチーフにした詩で、出版業に携わるある架空の男性を主人公においた作品だ。
しばらく詩を読み直していた健嗣だったが、直しようがないと思うと、「ふっー」と息を吐いて顔を押さえて、さっきから使っているノートパソコンの画面を閉じた。パソコンのスタンバイランプが白く明滅し始めたのを確認すると、
「よっと、じゃ、俺もいただくかな」
そう言って端末の前の席を立った健嗣は盆の置いてあるテーブルに歩み寄る。そして近くから適当に椅子を引っ張って座ると、「いただきます」と言って皆と一緒にココアを飲み始めた。
「健二さん、ココア冷めてません?」向かいに座っている部員の美奈が話しかけてくる。
「いや、俺猫舌だから、ぬるいくらいがちょうどいいんだ。」
健嗣はそう答えた。周りも部員たちもココアをじっくりと味わっている。
ココアの味は、ほろ苦く、甘いようで、暖かい味だった
◆ ◆ ◆
その後ココアを飲み終わって部員たちはそれぞれの作業に戻る。健嗣も今度は原本の印刷状況の監視にあたっていた。誰もがそれぞれの作業をこなしていたとき、ある部員の一人である〔部員E〕の携帯電話の着信音が鳴った。そのまま部室の外に出て電話に出る〔部員E〕だったが、廊下からいくつか「はい」という声ののちに驚いたような声が聞こえると、また部室の中に戻ってくる。そして部長の新妻のところまで歩み寄ると、おずおずと切り出した。
「すみません部長。私飼っている犬が病気なんですけど、今日になって状態を悪くしたもので病院に運ばれて手術を受けているそうなんです。私今から病院に行きたいんですけど、よろしいでしょうか。」
「あらまあ、そうなの? ええ、残りの仕事なら私たちで処理しておくから、大丈夫よ。それより早く見舞いにいきなさい、飼い主がいないと心配してるだろうから。ワンちゃんお大事にね」
「え、〔部員E〕さんの所のワンちゃん病気なの?それ私初めて聞いた。」
「〔部員E〕さんのところの犬ってゴールデンレトリバーだっけ。たしか数年前から足を悪くしてたんだよね」
健嗣が原本の一部を手にしながら聞く。
「ええ、そうなんです。ここの所体調を崩してたからもしかしたらって思ってたけど、まさかこんなことになるなんて──」
「ねえ、それで助かりそうなの?」
「それが、二つに一つの確率でしか助からないらしいの。私ほんとどうしたらいいのか──ファイドはずっと昔から、一緒に、──暮らしてきたのに……──」
〔部員E〕は顔を手で押さえると今にも泣き出しそうだった。周りにいた部員たちは集まってきて口々に慰める。結局その後〔部員E〕は病院に向かうために部活動から離脱した。
「〔部員E〕ちゃん大丈夫かなー。」と部員たちは〔部員E〕がいなくなった後もことあるごとに心配していた。
一緒に暮らしてきたのに──。手元で作業をこなしながら健嗣はその言葉を反芻して、自分の家族について考えた。健嗣の親は離婚していて今は健嗣は一人で自宅で暮らしている。健嗣は一人っ子で兄弟はいなく、一般的な核家族の家庭で、健嗣ももちろん幼い頃は両親と一緒に暮らしていた。しかし家族関係の事情から健嗣の親はどちらも健嗣を育てないと決めていて、現在は健嗣は経済的には親戚の援助を得て暮らしている。アルバイトもしているのでそれで生活費の足しにはしているが、幾らかは金銭的にその親戚を頼っている状態だ。
健嗣はあの日の両親のことを思い出して、少し顔が引きつる。あの日二人の両親はそれぞれ健嗣の前で「おまえ(あなた)のことは育てない」と言ったのだった。それまで何とか取り繕って一緒に暮らしてきた家族が、決定的に崩壊した瞬間だった。──まだ幼かった健嗣にとってそれは一人取り残されるということだった。
(ダメだな、こんなことを思い出しては。あいつらのことを思い出しても、気分が重くなるだけだ)
健嗣は頭を振ると、目の前の視界に意識を戻す。
健嗣が一人鈍い感情になっているすぐ傍で、部屋の隅では部員の間である論争が起こる。
「えーほんと、太宰治とか夏目漱石とかいいじゃないですか。今の現代の文芸なんてちゃちで稚拙なものばかりですよ。SFとかコメディとかライトノベルとか果ては恋愛だとか。今時の作家が書く小説は全く心に訴えかけてくるものがないと言うか、芸術性がないんです。全くの売名行為で商業主義なんですよ」
この言葉を言ったのは一年の〔部員G〕だ。
〔部員G〕は近代文学の愛好者で、たびたび現代文芸への悲嘆をあらわにしていた。
「えー、いいじゃない、ライトノベル。私好きだよ。筒井和隆さんのSFものとか良く読むし。読んでて楽しいし。」
「いーや、そういうのは文学をわかってないんです。文芸というものはただ単に読む人の好みや欲求を満たしていればいいというものではないんです。そこには芸術としての知的な感性が求められるんですよ。」
しかしその後も二人の喧々囂々の論争は止まらない。そしてついに健嗣のところまで話が振られてくる。
「ねえ、健嗣さん、どう思います?ライトノベルとか商業文学ってそんなに馬鹿にされるものですか? 私はこれと言う作品がたくさんあるんですけど」
「え、俺?」
いきなり聞かれた健嗣は間の抜けたような返事をした。
「そうですよ。私のお気に入りの作家まで批判するんですよ、〔部員G〕は。いいじゃないですかライトノベル。現代詩を牽引する健嗣さんから一言ガツンと言ってやってくださいよ」
「うーん、なんとも言えないけど……。」少しの間考えるようにしていた健嗣だったが、思いつくと言った。
「──俺はライトノベルとか文学だとかそういう括りでどちらが良いとか決めたりはしないかな。もちろん文体も違うしジャンルとしても違うわけだけど、どっちにもいい作品はあると思うからね。ライトノベルは名前のように軽いようでいて実は日常の中で隠れてしまうような題材を掘り起こすっていう性質もあるし、近代の文学の中でも退廃と闘う文学っていうのはあるからね。そういう作品は俺読むし好きだよ。俺はなにか価値があると認められる作品なら、特別ジャンルに縛りは掛ける必要はないと思うな」
しばらく無言で健嗣の言葉を聞いていた部員たちだったが、皆で顔を振って頷きだすと
「うーん、やっぱり健嗣さんは違うな〜。そっか、そういう考え方もあるのか」
と、しばらく部員たちは感嘆するようにてんやわんわだった。
◆ ◆ ◆
時計は二時を回って印刷状態は山場を迎える。
原本の印刷は既に終わり、コピー機でコピーする状態に入っていたが、早めに製本を始めた部員達はいくつかミスが起こっているのを発見した。それは例えば縦中横(縦書きの文書において複数の桁数になる数字をまとめて縦に立てて組むこと)が設定されていない数字があったり、読みづらい単語なのにルビが振られていなかったり、本来縦に印刷されるべき罫線が横に印刷されるなど、ひいてはその線が罫線ではなく長音記号だったりしたこともあった(これらは原本のパソコン上でのレイアウト時に既にあった問題である)。
今までの製本では部員がそれぞれにパソコン上でレイアウトし、持ち寄った原本をまとめて原版を作っていたが、今回の製本では統合した制作環境に挑戦するということでレイアウトはレイアウト担当として部内で決定した部員の〔部員K〕が一括して組版を担当していた。しかし今回彼はレイアウトがなかなかうまくいかないと周囲にも愚痴っていた。
例えば目次ではそれぞれの章見出しのページ数を自動的に目次に反映する設定を行っていたが、その方法で自動的に挿入されるページ数の部分は、縦中横に出来なかったのである。もし縦中横にしようとするならば手入力するのが最も簡単だが、それでは見出しのページ位置が変わった場合に目次にそれが反映されない。レイアウトの時点では内容はいくらでも変更になりうるものだし、手入力にするわけにはいかなかったのである。
また、これは結果的にはうまくいったのだが章見出しのあるページでヘッダをどう非表示にするかも、ヘルプとの格闘だったと彼は語っていた。
そして今回決定的だったのは表紙である。
こちらはグラフィックデザインと言うことで別の部員が担当だったのだが、その部員が作った表紙のデータが左と右、つまり表紙と裏表紙の絵が逆だと言うことが印刷後に判明したのだ。結局表紙と裏表紙の絵を逆に使ってもギリギリ内容的には問題ないと言うことでそれは解決したことになったのだが、他にも抜き差しならないトラブルはかなり起こった。
ここまで製本の問題について書いてきたが、そんなこんなで部員達の間では今度はワープロソフト論争が起き始めた。
今回レイアウトに使われたのは知らない者は居ないと言ってもよいくらいワープロ業界では大御所のマクロソフトのWardだったが、部員の中では日本語ワードプロセッサとして昔からもの書きに支持されてきたジャスツシステムの犬太郎との比較が話題に上った。今回も問題を提起したのは〔部員G〕だ。
「やっぱり日本語を愛するものなら国産のワープロを使いたいところじゃないですか?それに意欲的な機能もたくさん装備されてるし。Wardは輸入品だから縦書きの機能とかは十分じゃないところがあるでしょう」
しかし〔部員G〕が話題を投げかけると、反論の声が返る。
「えー?でも犬太郎はもう古いよ。今どき学校でも犬太郎は使わないし。別にWard使っても大した問題はないし」
「犬太郎は負け犬状態だもんね。もうほとんどシェア奪われてるんでしょ」
しかし〔部員G〕は釈然としない。
「だからこそマクロソフト帝国に対抗しなきゃいけないんじゃないでしょうか。それに犬太郎にはリラックスバックグラウンドと言って画面に表示されるページの背景に美しい壁紙を貼ることが出来るんですよ。日本語入力システムのATOXもついてくるし、マクロソフトのIMEなんて変換効率も悪いし使いづらいですよ」
すると議論に入っていた部員が驚いたような声を上げる。
「えーそんな機能があるの? 確かにそれはいいと思うけどさでもさ、でもWardは最初っからパソコンに付属してくるし、やっぱりわざわざ犬太郎を買うお金って必要あるのかな?」
今回も論議の争点は面倒な方面に進んでしまうようだ。
「うーん」
一瞬考えていた〔部員N〕だったが、
「ねえ、健嗣さんはどうおもいます?この論争に終止符を打つような思考はありませんか?」
と健嗣に話を振ってきた。
「えー、俺?」
話を振られた健嗣は何をどう話すべきか一瞬考え込んだが、
「いや、俺は昔は犬太郎ユーザーだったんだけど、今はMuc OSをメインに使ってるから、犬太郎はMuc OSバージョンは開発されてないから使ってないんだよね。犬太郎文芸とかレイアウトじゃなくて文章打つのに特化してたソフトも発売されてたし、犬太郎は個人的には好きだったんだけど、今はね。さっき〔部員G〕くんが言ってた犬太郎のリラックスバックグラウンドだけど、Muc OSの場合はエディタのウィンドウが画面全体に広がらずにデスクトップの壁紙も見えるからそんなに必要な機能じゃないんだ。」
健嗣がそう言うと、質問をした〔部員N〕が感嘆する。
「へぇー。で、健嗣さんは今は何を使ってるんですか?」
「文章打つのはMuc OS付属のエディタを使ってる。結構これが打ちやすいもんでさ、機能としてはちょっと足りない面があるんだけど、打ちやすさってのはあるね。たしか俺は文字の表示サイズをデフォルトから変えて使ってたっけかな──。ワープロ的な機能が必要になったらeasywordってソフトを使ってる。Muc用のソフトではそれが一番メジャーだからね。日本語入力にはショウビンって名前のソフトを使ってる。確かに使っていて指に馴染む感じはするよ」
健嗣は思いつくと机に置いていた自前のMucのディスプレイを開いてパスワードを打ち込み、ディスプレイを皆の方に向けて、その画面を見せた。青く映えたデスクトップにはeasywordの銀色のウィンドウを背景にした白いレイアウト画面が表示されていた。
「うわー、見たこともないアイコンが一杯! やっぱ極めてる人は違うな〜。」
「ほんとは俺も文章打つのに特化されたソフトを使いたいんだけどさ、なかなかいいのがないんだよね。どこかの開発企業が作ってくれたらいいとは思ってるんだけど。そもそもエディタとレイアウトソフトってのは別々にすべきなんだよね。エディタはこう、余計なレイアウト機能は省いてさ、文章校正機能とかに特化したソフトなら良いんだけど。──」
そんなこんなでその後しばらくワープロソフト談義が続いた。
◆ ◆ ◆
ワープロソフト論争が一段落した後、ガチャ、と音がして印刷室の扉が開くと、
「おっす〜!。ミィちゃんおる?」と女子学生が顔をのぞかせる。
すると「あ、私ならここにいるけど」紙折り機を使って製本していた部員が答えた。
その部員は近くの製本済みの空便を手に取ると「見てみて、描いてもらった挿絵、綺麗に印刷されてるよー。」と言ってその絵の印刷されているページを先ほどの女子学生に見せた。
入ってきた女子学生は漫画研究部の部員で、さきほどの文芸部の部員である友人から挿絵を依頼してもらったので空便に絵を寄稿したのだった。健嗣の記憶では確か板チョコを食べている登場人物の絵だ。その絵の小説は先ほどの「ミィちゃん」さんが書いた小説で、アルビノと言って生まれつき髪の毛が白い人たちを登場人物にした小説だった。
「あー、ほんまぁ。うちの画が文芸部の冊子に載るなんて感激〜〜」
漫研の女子学生が感嘆の声を上げる。
「ほんと、こちらこそ小説に挿絵書いてくれてありがとう。すごいアクセントになってるっていうか、一段とかっこいいよ」
さきほどの部員が答えると、近くにいた別の部員も話に加わってきた
「ねぇ、いいよね〜、その挿絵、さすが漫研部所属って感じで。私、人の絵は描けないんだよね。特に服のよれとかは。私もこんな挿絵欲しいなぁ。」
「うわー褒めていただいてありがとうございます。うちこれから文芸部の専属挿絵家になろうかな〜。」
すると文芸部の部員が思いついたように言う。
「もし良かったら、次出す新入生歓迎号の小説の挿絵描いてくれない? 挿絵があったらもっとキマると思うし。──」
しばらくそうやっててんやわんや話していた部員たちだったが、「じゃーうちこれから漫研部のほうで用事があるから、」と言って漫研の人は印刷室から出ていった。
そしてまたまた部員達の間ではサードラウンドの論争が起こる。
今回の論争はクリスマスはもともとキリスト教圏の西洋から入ってきた習慣だ、日本人は祝うべきでない、とまたもや〔部員G〕が言いだしたのが発端だった。
「だって俺たちキリスト教信じてるわけじゃないでしょ。信じてもいないのにキリストの復活を祝うなんておかしいでしょ」
しかしこの言葉にはすぐにたくさんの反論がくる。
「祝祭日はクリスマスだけじゃなくて色々あるし、それって別に宗教を信じてるかどうかっていう問題じゃないんじゃない?」
「要は日本のクリスマスって言うのは用は単に祝祭日よ。イベントとして盛り上げるためにあるのよ」
その発言に別の部員が答える。
「うわーそれすごい割り切ってるっていうかな考え方だな。でもそれって日本人がそうというだけで欧米とかじゃ違うんじゃないの? 向こうはもっと世界認識とかにそう言った価値観を位置づけてるというか、もっと精神の根本的なところに宗教がある気がするんだけど。」
するとある部員がそれまでの会話から一段落ち着いた声で言った。
「祝うべきとか祝わないべきって言うのはわからないけど、私はクリスマスって言うものが持っている雰囲気とか心遣いというか、聖なる日、って言う粛々とした感覚は大事にしたいな。子供が持っている純粋な夢なのよ、クリスマスって言うのは。大人になったら消えてしまうかも知れないけど、だからこそ大切にしたいなって思えるような──」
周りでてんやわんやのクリスマス論争を行っている間、部長の新妻詩織はずっとコピー機の前に立ってコピー状況を監視している。
小柄で赤色の細目のフレームをした眼鏡に大人びた口調が特徴の新妻は文芸部部長。三年生という受験に追われる身でありながらも、毎回欠かさずに部活動に参加している。ちなみに既に12月の段階で推薦入試で有名大学に合格が決定している秀才でもあり、元カレが居たという事実は部内では有名な話しだった。
部室の奥で新妻がコピー監視している間、それを遠くから見ていた一年の部員の美奈が健嗣に言う。
「ねぇ、健嗣さん部長を恋人として狙ったりしたらどうですか?」
それを聞いてもう一人の部員も急き立てた。
「そうですよぉ。新妻部長は一回元彼と別れてるし、今がチャンス!チャンスぅ!」
「いつも二人だけで仲良く話をしているじゃないですか。部長は気があるのかも知れませんよ」
「うーん、いや、それは違うと思うよ。俺が部長と話しているのは事務的なことだから」
健嗣はテンションの低い声で言う。健嗣はさっきから椅子に座り地道に冊子ののりづけの作業をしていた。
「えーだからそれは健嗣さんが気づいてないだけですよ。」
うーん、と唸ると、健嗣は顔を手の甲でこすりながら言う。
「俺は恋愛とか余り熱くなれる方じゃないんだ。どうしてもときめかないというかさ。まあ、昔は好きな人とかもいたけどさ、今はね。自分で恋愛の詩を作っているくせ何をってのはあるけど、面倒事に巻き込まれるよりは別に独り身でも構わないというか。」
「えー、そんなー、パートナーが居るほうが絶対良いですよー。」
先ほどの部員がゴネる。しかし健嗣は手を休めずに言った。
「うーん、なんというか、俺は自由に気楽で居たいんだよ。縛られたくないと言うか、身軽な方がいいんだ。──俺は何かを背負うだけの重みを受け入れられないほうなんだよ」
少しの間二人の部員は考え込んでいたが、
「ちぇー、気はないかー」
と、健嗣にその気がないことがわかると話題を変えて話し始める。
「あー私もクリスマスぐらい彼氏と一緒に過ごしたいなー。」
「クリスマスも本来は恋人じゃなくて家族同士で過ごすためのものなんですよ。家族で祝って家族愛を確認するという。」相変わらず〔部員G〕が言う。
「えーでもうちの家族と一緒に過ごしてても面白くないしー」
すると部員の一人が背伸びしながら言った。
「やっぱクリスマスと言えばデートでしょ。電飾の街を手を繋いで歩いてさー。私も彼氏がいたらよかったのに。」
周りの話を聞きながら健嗣は幼い頃の家族のことを思い出していた。自分にもあったのだと、そう言う幸せなときが。しかしその暖かな家庭環境は長続きはしなかった。父親が酒に酔うとすぐ暴れる達で、家庭内には生傷が絶えなかった。いずれ大人になっていく健嗣を視る度に健嗣の母親は夫の面影を感じ取り、健嗣に嫌悪感を示すようになった。そして結局健嗣の親は離婚、どちらも健嗣の親権は放棄したのである。そして今の健嗣は自分でアルバイトをこなして生活費の足しにしながら、親戚からの援助を得てアパートで一人暮らしをしていた。
幼い頃のクリスマスを思い出すと、切ないような愛おしいような、そんな感覚に駆られた。よく手を引かれて街を歩いて買い物をしたものだ。あの頃と街は少し変わった。自分の生活は大きく変わった。クリスマスに両親からもらったマグカップ。お気に入りでいつも使っているそのマグカップは、今でも健嗣のアパートの食器棚の中にしまわれている。
(もう俺にクリスマスは二度とこない。)
クリスマスが来るたびに、健嗣はそう心のなかで呟くのだった。
◆ ◆ ◆
コピーがすべて完了すると部員たちは長くて手間のかかる製本作業を行った。今度もまた部員の中でホチキス(ちなみにホチキスと言う名前は商標で、ステープラーというのが正しいらしい)の針は二つ綴じるべきか三つ綴じるべきかで論争が起きる。二つだけだと外側の紙が浮いたりするし、三つ綴じるべきだというのだが、今度はそれがホチキスの使い過ぎではないのかという話になった。
そして部員が丹誠込めて製本した冊子が出来上がったのは午後4時を回ったあたり。部誌を顧問の先生に渡して職員室の先生用の鍵のかかる机の中に入れた後、文芸部の今日の活動は終了した。明日のクリスマスには職員室から先生たちがそれぞれの教室まで空便を持っていきHRで生徒に配布する手はずになっている。
部員たちは冊子が机の引き出しに入れられたのを確認したあと、廊下を抜けて玄関を出ると学生がいつも出入りに使っている裏門の手前に集まって互いにつれづれごとを話始めた。裏門は最近になって姪禺山高校内を掌握した緑革軍の隊員がゴム弾武装して警備している。
「あたしこれからおばあちゃんのいる病院まで見舞いにいかなきゃならないんだ」
「えー。元気にしてるの?そのおばあちゃん」
「うん、別に体調は問題ないんだけど、時々顔を見せるようにしてるんだ」
「せっかくのクリスマスだから彼氏誘って買い物に行こうかと思っててさ」
「えーいいなー、あたし彼氏なんていないから一人きりのクリスマスよ」
「俺は製本でエネルギー使って腹減ったんで近くの吉田屋に寄ってくつもりです」
「そう言えば写真部でクリスマス会を開くから自由参加だってよ、ミッチーもよってかない? 今日はスライドショーを鑑賞するんだとか言ってたけど」
「ごめん、あたし今日お母さんにケーキ買ってきてって頼まれてたんだ。」
健嗣はしばらく自販機で買ったペットボトルのほうじ茶を時々飲みながら、無言でその場にたたずんでいる。
横では新妻部長がやはり部員たちの状況を見舞わすように見ていた。
すると正門の外から深刻な表情をして歩いてくる者がいる。あの手術をしているファイドという犬の飼い主の部員だ。
「あ、〔部員E〕ちゃん。」
その様子に気づいた部員たちが駆け寄って話しかける。
「〔部員E〕ちゃん、ファイドは無事なの?手術は成功したの?」」
しかし〔部員E〕はうつむきながら腕で涙を拭ってしばらく何も言わない。
そして押し出すような声で、
「ダメだったって……。ファイドは死んじゃったんだって。もうあたしどうすればいいか……」
それは手術の甲斐なくペットが急死したという知らせだった。〔部員E〕の泣き声と共にしばらく沈痛の時間が流れたが、その部員がしゃくりあげると部員たちは口々にお悔やみの言葉を言った。その後他の部員に心配をかけたとして〔部員E〕は皆に頭を下げた。
そして下校前のおしゃべり時間も終わり、部員たちはそれぞれのグループに分かれて下校していった。
◆ ◆ ◆
折からの雪は止んで、空は晴れている
健嗣も学校の裏門を出ると、家路についた。
明日もう一日学校に行けば後は冬休みに突入する。一人暮らしの健嗣にとっては辛くさみしい休み期間でもあった
健嗣の靴は雪をギュッ、ギュッと踏み固めながら、一面雪に覆われた道を進んでいく。
視界の隅に輝く冬の太陽を見ながら、健嗣は逆光に陰った街並みを歩いた。夕闇に輝く町並みは、茫洋としてただ美しかった。
──ちょうどクリスマス商戦の大詰めを迎えた街並みはクリスマスムードの装飾であふれていた。
ビルの上に広がるグラデーションの空、道路を走っていく車、道に降り積もった雪、吹き荒ぶ風。
風に吹かれてゴミや枯れ葉が飛んでいく。
こうして平和で穏やかな毎日を送れていることがうれしいと同時に、なぜかそれが儚く散りそうな、そんな恐怖にどことなくとらわれるのだ。自分の目の前から誰もいなくなっていって、当たり前にある平穏が嘘のように消えていくような。俺は忘れているのだ、あの青ざめた空の向こうで、今まさに誰かが痛んでいることを。そしてそうしたときに、俺は何が一番大事なことなのかを、思い出せるだろうか。
──帰り道の途中で、健嗣は街中のある住宅街の一角の路地に向かった。探していたのは健嗣の住んでいる家の近所に住む黒猫のルドルフ。黒々とした毛並みが美しい黒猫で、いつもこの辺りを周ってはいろいろな人から餌をもらいながら暮らしているらしかった。
健嗣がマンションの陰になっている路地裏に入ると、ルドルフはいつもの様に待っていた。遠くの空からは街の喧騒が聞こえる。
「よう、よう、ルドルフ。今日は気分はどうだ? 今日は雪が降ってるし寒いしなあ。風邪引いたりしてないよな」
健嗣がルドルフに話しかけると、ルドルフはニャーと甘えたような鳴き声を出して歩み寄ってきた。
健嗣は腰を下ろしてカバンの中から牛乳瓶を取り出す。その牛乳は学校の学食で出たもので、健嗣がルドルフに与えるためにいくぶんか残していたのだった。牛乳瓶をコンクリートの地面において、持ち歩いている銀色のアルミ製の皿をカバンから取り出すと、健嗣は地面に置いた皿に牛乳を注いだ。
ルドルフは皿に牛乳が注がれると同時に皿の牛乳を飲み始める。健嗣は腰を下ろした状態のまま、ルドルフの毛並みを撫ではじめた。そしてしばらく撫でていると、健嗣はルドルフに話しかける。
「なんだかなあ、こうやって日常を送ってると、ときどき鈍いような重いような虚無感におそわれるんだ。自分はいつまでこうやって生きていくのかなあ、なんて。だってさ、小さい頃はもっと色々と楽しいことがあったろ。理屈抜きに夢中になれることがさ。──きっと神様はこの世に信じられるだけの価値を作りたくないんだよ。それを求めることで世界が変わって行かないように。」
それからしばらくなにともしれぬ日頃のことを語りかける健嗣。遠くの空はオレンジ色が薄くなり、もう夜闇が空を包み込もうとしていた。ルドルフが皿に残った牛乳を舐めているのを見ながら、しばらくルドルフの毛並みを視ていた健嗣だったが、
「まあなあ、猫だしなあ。言葉がわかるわけもないか──」
と一人呟いた。
◆ ◆ ◆
ルドルフへの餌やりが終わってルドルフとわかれた後、しばらく健嗣が歩いた後に家につく頃には、もうだいぶ暗くなっていた。帰宅途中で雪が降り出していて、外は暗闇の中にしんしんと雪が音もなく降り積もっていた。ちなみに健嗣の自宅は徒歩で学校に通える距離にあるアパートだ。
健嗣がアパートの回り階段を上がり、住んでいる部屋のドアの前に立とうとすると、ドアの前に見慣れた顔の人物が立っているが見えた。学校の同級生で友人の玉城だ。ちなみに玉城は文芸部ではなく写真部芸術部門所属だったが、一年の時に同じクラスだった二人はいつも玉城が絡んでくるせいもあって仲が良かった。
「よ、健嗣、だいぶ遅かったな。全くこんな寒い日に人を外で待たせんなよ。どこで道草食ってたんだ? 俺が文芸部に行ったときはもう活動は終わって部員は帰ってるって話だったんだがな」
分厚いダッフルコートを着込んだ玉城がいつものようなぞんざいな口調で言った。
「おまえ、なんで……今日は写真部の活動に行ってるんじゃなかったのか。今日クリスマス会があったんだろ」
健嗣はあっけに取られながら玉城に聞いた。すると玉城は手に持った小さな箱を突き出す。
「ああ、参加してきたよ。だからほら、ケーキもらってきた。 おー寒ー。ちょっと早く中入ろうぜ。いつまでもこんなところ居たら風邪引いちまうよ。」
そう言って玉城は健嗣を急かす、しかし健嗣は聞き入れなかった。
「おまえ何しにきた。別に俺呼んでないだろ」
健嗣はなおもつっけんどんに聞く。しかし玉城は答えた。
「だ、か、ら、ケーキもらってきたから一緒に食わねえか、って言ってんだよ。お前がひとーりさむしーくわびしーくクリスマスイブの夕食を食べるのを思うと、不憫に思えてきたから、心配して来てやったんじゃねえか。」
「心配って何だ。俺は一人で食事食うのなんて慣れてんだよ。それにクリスマスイブまで男と一緒になんて居たくねぇし」
余計なお世話だ、と健嗣は思った。しかしそれでも玉城はなおも食い下がる。
「俺だってそうさ。でも彼女居る訳じゃないし、一人でクリスマス祝うってのもしけてるだろ。」
そして玉城は神妙な顔になると言った。
「──それに、お前今日誕生日なんだろ? だから祝ってやろうと思ってクリスマスがてらケーキもらってきたのさ」
それを聞いて健嗣は絶句した。
「!──。なんでお前俺の誕生日知ってるんだよ。俺教えてねえはずだけど──」
健嗣の誕生日はまさしく12月24日のクリスマスイブの今日だった。しかし、玉城にはそのことは教えてないはずだ。
「ふーん、俺に見抜けないことでもあると思ってんのか? お前のことは何でもわかるさ。お前の頭ン中の情報は全部筒抜けだ」
呆気にとられている健嗣を横目にしばらくおちゃらけていた玉城だったが、
「マクシィだよマクシィ。おまえのマクシィのプロフィールで見たの、今日が誕生日だって。俺がお前のプライバシーまでわかると思うか? 全く真に受けなんなよな」
ほら、と言って玉城はケーキを健嗣の前に突き出す。おずおずと健嗣がケーキを受け取ると、
「おっと、一言忘れてないか?」
「え?」
すると玉城はいきなりかしこまったようにして、
「ちょっと早いけど、メリークリスマス。──そして誕生日おめでとう」
「いえいえこちらこそ……メリークリスマス。祝ってくれてありがとう」
読者の皆さんにも「メリークリスマス。そして良い新年を」──
健嗣が鍵を開けてアパートに入った二人は、ずっと前から使っている大画面のプラズマテレビを付けながらこたつに座りこみ、みかんを並べお茶を飲みながらケーキをつついた。ケーキはストロベリーケーキとチョコレートケーキで、大きさは小さいものの品のよい味がした。そして二人は何ともしれない言葉の掛け合いをしながら、クリスマスイブの夜を過ごした。
窓の外の冷気をすぐそこに感じ取りながら、健嗣は今自分の周りを包んでいるぬくもりを思った。そして玉城の話しかける言葉を聴きながら、ふっと微笑んだ。
「あ、お前今笑っただろ。なんだ、俺なんかおかしいこと言ったか?」
それを見た玉城が絡んでくる。
「何でもない、ただの一人笑いだよ。」
いつまで続くかわからない、そんな儚い幸せであっても、今はこのささやかな幸せをかみしめていたい、そう健嗣は思ったのだった。
雪はしんしんと降り積もる。明日は、ホワイトクリスマスになりそうだった。
■
テーマソング『ai ta 心』UVERworld(gr8 records)
詩『ヒラギノ』柊野 澄香 as 安留 健嗣
ここ柊野の冬景色に粉雪が舞う頃
街に子供たちの聖歌が響く
夜を走るヘッドランプが街の装飾を照らす
美しい灯りの裏で、暗闇が息を潜めている
窓の外に凍えたように光る月が見える
冬のりんごを囓ると甘酸っぱさが口の中に広がる
シズルフルな画面を気にかけながら
ヒラギノの涼しく透き通った文字が
蛍光灯の反射光に白く染め抜かれた紙に現れる
あの頃はこのソリッドなラインに強く惹かれたものだ
大人になる事で失うものと、得るもの
そんな話題がこの季節になると思い浮かぶ
不確かなつながりに涙流したことも
子供の頃は色々なことで頭を悩ませ、苦しんだ……
きっと良い育ちではなかっただろうけど
でも、自分が何を欲しているかわかった者に
まやかしを気にかける必要など無いのだろう
この街で生きていかなければならない
それがわかっていても足元がすくむ思いばかりだ
子供の頃に見ていた夢はもう捨ててしまった──
数年前の聖夜のあの日、あのカフェで
周りの人と話している君を初めて見たときに、
ハッとした感覚があったのを覚えている
臆病な君の、あの無邪気な微笑に
何か大事なもの、失ってはならないものに
気づかされたような、そんなインスピレーション……
きっと人はそれを運命と呼ぶのだろう
窓の外は黒い冷たい空気でいっぱいだった
この世界に美しい言葉があることを僕は信じている
言霊は強く受け止めればそれだけ傷つくもの
暗闇の中で白色光の照らすこの明るい部屋に、
あの日からいくぶんか大人びた君の微笑みがある
ここにひとつの言葉を君に捧げよう
いつもそばに居てくれて、ありがとう
■(2011.9.15)
学校戦争 エピソード$02「文芸部のクリスマス」Beta


