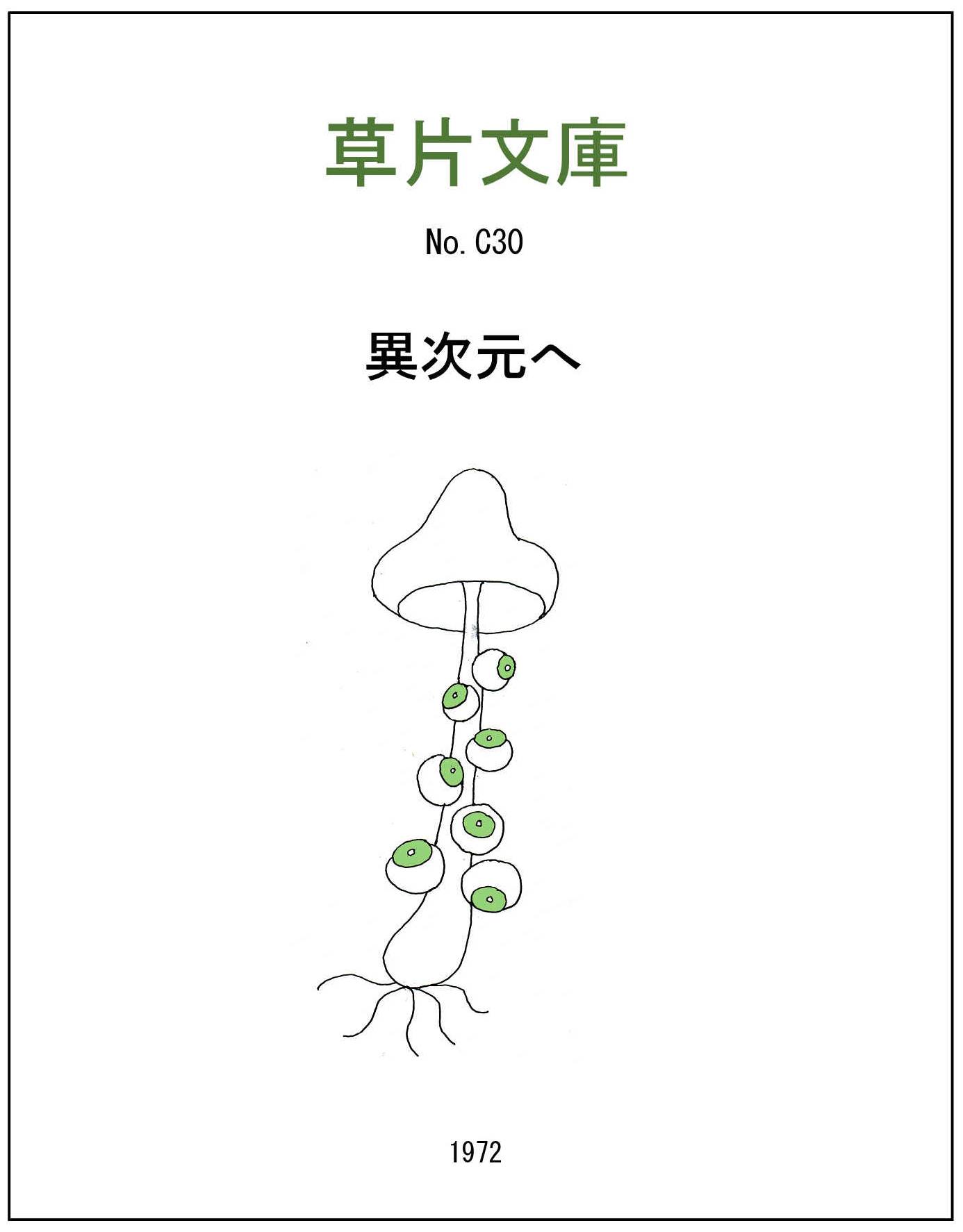
異次元へ
薄いコットンズボンの裾に冷たい風が入り込む。彼はすねに冷たい手が伸びてくるのを意識しながら狭い夜空を見上げた。そそり立つビルの谷間に星が瞬く。
漆黒の空に青銀色に星が光るのを見ることなど何年も無かったことである。
昼間に強い風が吹きまくり、汚れた空気を空の上に蹴散らしたからだろうか。
北極星はビルの角で半かけになり、北斗七星だって水が漏れてしまうような都会の夜にも、星たちは癇癪もおこさず輝いていてくれる。
彼はズボンのポケットに手を突っ込んだままその場に立ちすくむ。
ビルの窓ガラスに星が映し出されている。高いビルに囲まれているその一画から夜空を見上げると、ビルの谷間がプラネタリウムになっている。
ふと脇の窓ガラスに自分の顔があった。その目の中に星が光っている。
「寒い」
星空から吹き降りてくる風は彼から容赦なく彼から温かみを奪っていく。ほころびた襟を立てても冷たい空気が首の周りに忍び込む。コンクリートの匂いが冷たい空気をますます硬いものにしている。
「あーあ」
漏らしため息がほんの少しの間だが襟元を温めた。
彼は天空の星に向かって息を吐きかけた。白い息がちょっと立ち上ったが、ビルに吹き降りる風で顔にもどってきた。
『あの星にはどのような生きものがいるのだろう』
彼の眉間に皺がよった。
『人間はどうしてあの星々に行こうとするのだろう、行かないほうが良いのではないだろうか』
彼は心の中で呟く。
『星の輝きは天の穴から漏れる光か、昔の人は良いことを考えたものだ、あの星が生命を育むことのできるところでも、生命が誕生していないことを祈る。いれば、そいつらのほとんどは苦労して苦労して生きるのだ、俺と同じように。生きてりゃそりゃ苦労するだろう、俺も他人、他星のことなど心配できる立場にないのにな』
彼は自分の考えたことに笑いがこみ上げてきた。
あまり長い間上を向いていたので、首が氷の柱のように硬くなり、目玉なんて冷たい風に吹き晒されてガラス球になっている。
彼は目をしばたきながら、首を何度か右左に動かした。ぼきぼき音がした。
彼は俯いたままやっと足を一歩前にだした。一歩一歩、やがてとぼとぼと歩き出した。でこぼこになったコンクリートが、ごちごちと足の底を持ち上げる。
太った黒い鼠がビルディングの隅から出てくると、あわただしく彼の前を走りぬけた。鼠が空き缶にぶつかってひっくり返した音が、ビルの谷間にドラのように鳴り響いた。
『銀色に輝く星だって冷たそうだが、俺の星ほどじゃないだろう、だが何故あんなにチカチカしているのだ、まぶしいじゃないか、地球もそうなのか』
彼は歩きながらまた星たちを見上げた。夜空ではあんなに近くに隣り合っていても、とてつもなく広い空間が星と星の間にある。旅をするならそういう広いところに行きたい。彼はポケットの中の五十円玉を人差し指で触った。旅どころじゃない、今、彼には寝るところにさえ帰りつくことが出来ない。
「あ」
彼の目に流れ星が映り、流れ星はあたりに銀色の粉を吹き上げた。
彼はその場で意識を失った。
気がついたとき、彼は星一つ無い真っ暗な闇の中を歩いていた。何故歩いているとわかったのか。確かに彼は右と左の足を交互に前に出、からだは前に進んでいたからである。
どこを歩いているのかも分からない。頭がはっきりしてきた彼は、「おーい」と声をあげた。しかしその声は周りの黒の中に吸い込まれていくだけである。目を開いていても見ることができない。しかし不思議なことにそのような状況を怖いと感ずることは無かった。
開放感すらあったのである。冷たい風を受けることも無く、腹が減ったと思うことも無く、はしゃぎたくなるほど自由であった。
彼は声を上げた
「おーう、きゃー、おーい」
跳ねてみた。だが上にはとんでいない。ともかく足を前に交互に出せば自分が動いたことを感じることが出来る。
走ってみた。走ることは出来るようである。一生懸命、暗闇の中を走った。しかも、声を張り上げながら走った。自分の存在を確かめるためだ。
やがて疲れがきた。生きている証拠なのだろう。無性に眠くなった彼は泣き疲れた赤子のように闇の中で丸まった。猫のように、深く深く眠りに落ちた。
どれほどのときが経ったかは分からない、彼は目を開けた。
『どこだろう』
辺りを見回しても無駄だった。漆黒があるだけである。彼は自分が赤子のように縮こまっているのに気がついた。手を伸ばし足を上げた。
よく耐えたものである。どのくらいこの格好でいたのだろう。
彼は立ち上がった。手を泳がせても何に触るわけではない。足の下に手を入れてみた。ここも空間だった。自分は暗闇の中に浮いているのだ。
自分に何が起きたのだろう。ビルの空間から星の空間、そして闇へ。
いきなり彼のからだがふわっと浮いた。今までも浮いていたはずであるが、そのまま動き出した。真っ黒なシャボン玉の中に浮んでいるような気持ちになる。
どこかに流れている。
彼は自分が生まれてきたことと同じようにこの不思議な状態を受け入れていた。
黒いシャボン玉は彼を抱え込んで上に行ったり下に行ったりしながら漂った。
彼はおおらかな気持ちで、為されるがままシャボン玉と共に闇を横切っていく。
シャボン玉の中で、彼は走ってみた。そう、走ると疲れた、すると眠ることが出来る、漂うシャボン玉の中で、彼は全速力で走った、いつもの眠気が襲ってくると、彼は丸くなって眠りに落ちた。
夢の無い眠りは時間がない。ほんの一時だったのか、何万年だったのか分からない。
彼は太陽の光を肌にうけ、気持ちのよい目覚めを感じていた。今しがたまで真冬のビルの谷間で星を見上げていたことなど全く記憶に無い。
春の光は彼の浮んでいる闇の中にそそぎ込まれ、彼を包み込む。
次第に暑さを感じてきた彼は手足を動かそうとしてもがいた。からだが動いたかどうかはわからなかった。
彼が入っている闇の玉を春の風が押し流していく。
風がパタッとやんだ。日の光は彼の入った闇を下に押し下げ、彼は闇に包まれながら下へ下へと降りていく。やがて闇の玉はごちんとぶつかったと思うと、また空中に跳ね上がった。漂った闇はやがて静まり返り、玉は崩れ、ただの広い闇になった。
足の下にひんやりとした土を感じた彼は、昔の記憶が引きずり出され、胸騒ぎを覚えた。
彼の記憶の中にある水の香りを足の下に嗅ぎ取り、足を土の中に伸ばし始めた。やがて足は細かく裂け、土の奥へとすすんでいった。根の先は土の粒子の間から水の分子を吸い取り、毛根から流れ込む冷たい水は彼の胃を満たし、太陽の光を浴びながら、彼はほろ酔い気分になった。
闇は消え去り、頭上では春の光が渦巻いていた。
彼の欲望は頂点に達し、地上へと頭を、芽を吹き上げた。冷たい水を吸った彼は思いっきり葉を開いた。子葉が開き、空気中の二酸化炭素がなだれ込んだ。彼の中で炭水化物が蓄積され、頭を更に上に持ち上げた。葉は増殖し、貪欲に光を吸収した。
大きくなった彼は次第に考える余裕ができた。今の今まで、頭の中にわだかまり、言葉にまとまっていなかった、今だ今だ、今を逃したら死だという声がはっきり聞こえるようになり。光の渦の中に葉を広げ、黄緑色に輝いた。
彼は周りを見渡し、自分を意識し叫んだ。
「私は植物だ、光の味を、水の味が分かる植物だ」
突然襲ってきた自分という意識に、頭の中に例えようも無いジレンマが渦巻いた。それもつかの間、彼は全てを忘れ、春の光に楽しそうに葉を茂らせ、いくつもの蕾を膨らませた。
春の光が一段と強くなった。
彼は最初の蕾をもみほぐし、大きな赤い花を開かせていった。
時々訪れる動物としての心が、赤い花と自分との取り合わせに、笑わずにいられなくなることがある。昔の自分に赤い花を飾る余裕などあっただろうか。鏡で今の自分の姿を映してみたらどうだろう。
花アブのはばたきが聞こえると、彼は飾り立てた赤い花弁を揺らし、自家受粉をしてもらおうと、強くアピールした。
アブは彼の花の中に潜り込んできた。アブの足が無遠慮に花びらを愛撫し、芯にふれてくる。彼は空虚な面持ちで、歯がゆさと無感動と、不釣合いな罪の意識にとらわれた。
花粉がとろけて花粉管が伸び、雌しべの奥にたどり着いた。その時、彼の心にはやっとのことで、植物の本能が染み渡り、渦巻き、叫びたくなるような境地を味わった。
やがて、いつの間にか彼には三つの種ができた。蕾はまだまだたくさんある。真っ赤な花が一つ満開だった。
バスケットを下げて、ちいさな女の子と男の子が丘を登ってくる。
「トム、トム、ここを見てよ、綺麗な赤い花が咲いているわ」
少女は赤い花に近づくと、小さな唇を寄せた。
花は恥ずかしそうに、ゆうらゆうらと揺れる。
「トム」
少女は少年を見た。
少年は蝶ちょを追いかけて丘の上のほうにさっさとのぼっていってしまった。
「トム……」
おいてけぼりを食った少女はつまらなそうに赤い花を見た。
少女はバスケットを下に置くと、花のそばにしゃがみこんだ。
少女は赤い花びらをちいちゃな指でつまむと言った。
「トムはあたちを好きじゃないのかしら、教えて」
少女は花びらをつまんで指に力を入れた。
花びらが一枚落ちた。
「トムはあたちが好き」
また引きちぎった。
「嫌い」
……「好き、嫌い、好き…」
少女が引きちぎる花弁は空高く春の風で舞い上がった。
「好き、嫌い、好き、嫌い」
「あ!」
最後に残った一枚の花びらを少女の指がつまみあげ、引っ張った。
「好き……、トム……」
少女は嬉しそうに、少年の後を追って、走っていった。
その拍子に三つの種がはじけとんだ。
ビルの間の路地に人垣が出来た。
人々が取り囲んだコンクリートの上に、手足がバラバラになった彼の死体がころがっている。
コンクリートの上にのっている手の指は灰色の空を指し示し、開かれた目はコンクリートの亀裂をみつめている。その脇に、三人の赤子が手足をうごめかしていた。
彼は異次元への旅の途中だった……。
異次元へ
私家版初期(1971-1976年)小説集「小悪魔、2019、276p、二部 一粒書房」所収 IMP12
挿絵:著者


