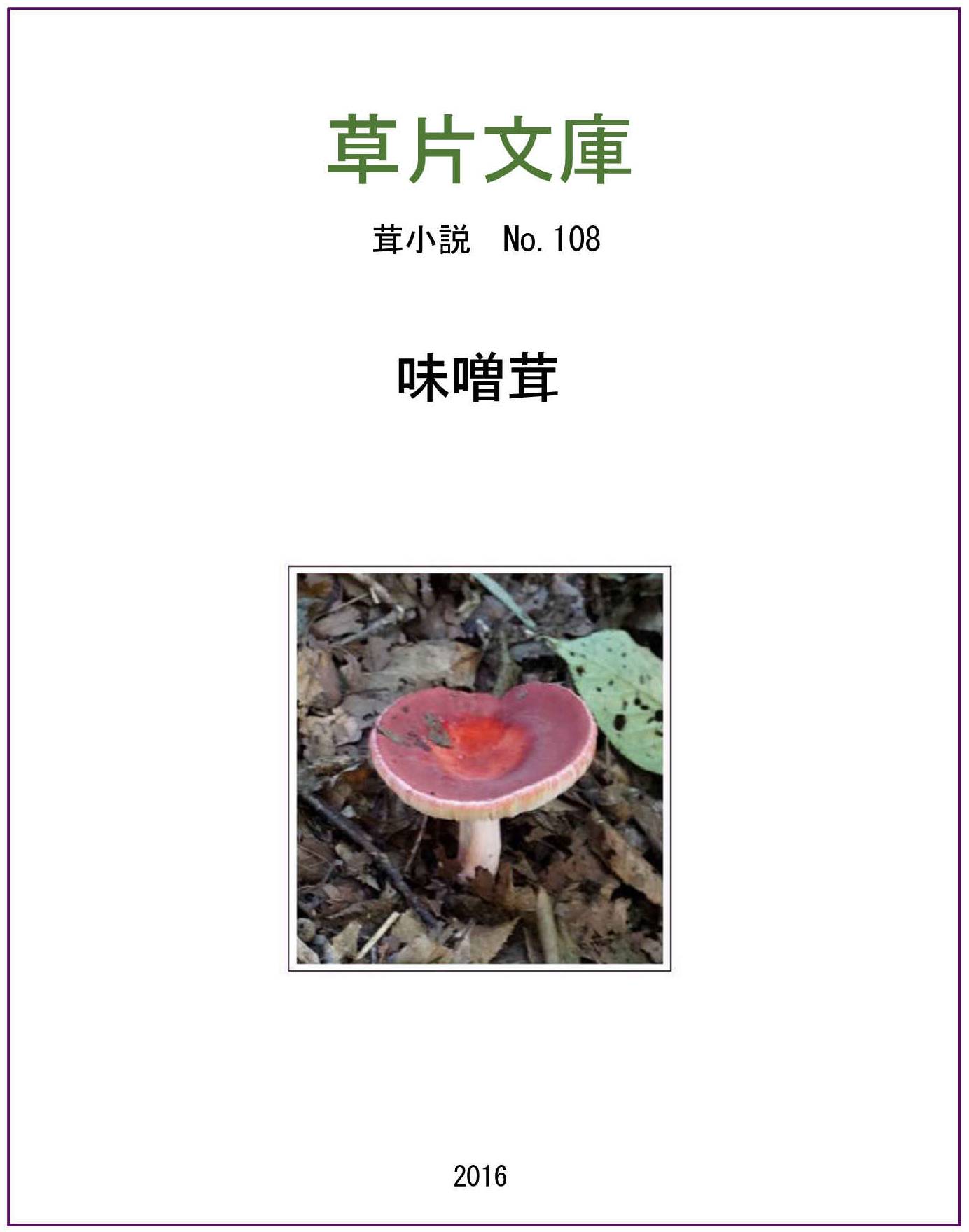
味噌茸
茸発酵研究所、所長 飯田君麿
彼の名刺に書かれている肩書きである。研究所は京王線笹塚駅から歩いて十分ほどのところにある十二階建てのシエニビルで、二階の全フロアをしめている。このビルは一階から二階までが貸しオフィス、三階より上が賃貸マンションとなっている。マンション区域にはワンフロアーに2LDKの住まいが六戸ある。
彼はシエニビルのオーナーでもあり、住まいは十二階の富士のよく見える南側に二軒分つなげた広さの特別につくらせた部屋である。
シエニビルのオフィス街には、世界の茸の輸入会社や、茸の書籍の販売会社、茸グッズの製作や販売を手がける会社などもはいっており、仲間が社長をしている。
茸発酵研究所は、化学実験ができる室、茸の培養室。茸図書室、それに特許関係の部屋からなっており、三人の研究員をやとっている。高度な解析研究は、彼が卒業した都内の大学の研究室や科学博物館研究室と手を組んで行なっている。
彼自身は大学で発酵のメカニズムを研究した。発酵という現象が人間の食に大きく関わっていることはよく知られていることであり、一般の人でも、酒、味噌、チーズ納豆が発酵という現象により作り出されていることを知っている。
彼は大学で学ぶ中で、発酵という現象が食だけではなく、地球の生物が生きる輪の中で、中心的な役割を持つものだと思った。熱心に幅広く研究を進めていった中で、大学院生のときに、新しい酵母菌を発見した。それが特許に結びつくという幸運な人生のスタートをきったのである。
彼がみつけたのは、早く発酵させることのできる酵母菌である。その酵母菌をつかうと、わずか一晩で米を酒にすることをみつけたのである。
ところが、その酵母がつくりだす日本酒は、うまみはゆっくり発酵させた今までのものにかなわなかった。それにしてもこの発見は、安いアルコールの生産に結びつき、おどろくほどの特許料が彼の手にはいったのである。それで自分の研究所を立ち上げたわけである。
大学での研究生活の中で、彼は一冊の古い文献にめぐりあった。そこに書かれていたことを、いつか研究してみたいと思っていたことから、研究所を作ったわけである。
それは学部生のときである。農学部の図書館で、発酵に関わる歴史を調べていたときその本にであった。和綴じのその本は、埃にまみれて棚の上に置かれていた。
何とか読みすすめると、茸に関わる本であった。昔は毒をとるために茸の研究がおこなわれていたものである。茸毒が毒殺に使われ、また薬にもなった。
君麿がみつけた文献は、毒や薬ではなく、不思議な茸の記録であった。麹を使わず、茸で味噌を造るというものである。味噌の樽からはみ出すように赤っぽい茸が生え、それは見事だと書いてあった。その茸の菌糸が、麹菌のように大豆を発酵させ、味噌にするという。ただ、醤油はとれないと書いてある。
麹菌と酵母菌は同じ菌と書いているが、違うものである。麹菌は黴の仲間で、どちらかというと、茸に近い。一方、酵母菌は細菌である。働きも違って、麹は酵素により豆をブドウ糖とアミノ酸に分解する。酵母菌は酵素により糖をアルコールにする。日本酒は米を麹菌でブドウ糖に分解し、それを酵母菌によってアルコールにする二段階必要である。
この赤い茸の菌糸は麹菌と同じような酵素をもっているわけである。
文献を書いたのは、田舎の下級武士で、小さな城の台所を仕切っていたようだ。食料に関しては知識があったとみえ、いろいろな工夫をしている。
赤い茸はその武士が望月の城の台所に行く途中、食料庫の脇に生えているのをみつけ、茸が「あかはえとり」に似ていたことから、食べられないものだとおもいぬきとって、台所のごみ捨てにいれたという。
土間の竈の脇には自家製の味噌を造るため、ゆでて潰した大豆の入った大鍋がそのまま置いてあった。担当者が別の急用を言いつかり、忘れたままだったものだ。まだ麹をいれていなかった。
ところがその夕方、赤味かかった茸が大鍋から何本も生えていた。それをみつけた者は責任者であるその武士に連絡した。彼は台所に来て驚いた。自分が朝見つけてゴミ箱に捨てた茸が味噌の鍋からはえている。のぞくと大豆はすっかり味噌のような形になっている。武士は責任を感じ、茸の生えている崩れた大豆をなめてみた。これまたおどろいた。とてもうまい味噌になっている。武士は湯を持ってこさせ、茸の生えた大豆を椀にいれ飲んでみた。やはりうまい。あかはえとりは毒キノコと知っていたが、一つくらい大丈夫だろうと食ってみた。これまたうまい。
武士は腹も下さず、この赤い茸が大豆を味噌にする働きがあることを悟ったのである。それから赤い茸で味噌をつくる方法を編み出した、と書いてあった。
さらに続きがあった、病に臥せっていた同僚に、その味噌で作ったうどんを食べさせたところ熱は下がり、治ったという。その武士は味噌茸から味噌に何かが移って、病の毒素を消したと考えた。
勇気ある武士は味噌に生えた赤い茸を食べ、そのあとに強い毒茸を食べてみた。すると全く毒の影響がなかった。その赤い茸は解毒作用があると記されていた。これを書いた武士の名前は書かれていなかったが、「あかはえとり」に似た茸を「味噌茸」となずける、と書いてあった。
彼の研究所では、茸の成長促進の方法開発や、新しい茸の利用方法の開発がおこなわれているが、彼の頭の中では、いつか文献にあった味噌茸をみつけたいと思っていたことから、名前を茸発酵研究所としたのである。
文献で味噌茸を見つけた武士は、その茸を「あかはえとり」と呼んでいた。これは「ベニテングタケの方言で、信州や岩手のほうでつかわれており、さらに、望月の城と書かれていることから、信州佐久の望月城の可能性が考えられた。
研究所が軌道にのり二年ほどたったとき、彼は上田の茸栽培の会社の講演会にまねかれ、茸のもつさまざまな可能性について話をした。そのときに、佐久の望月城跡に行った。
佐久駅で降り、駅の案内所で紹介してもらい宿をとった。佐久駅からバスで二十分ほどいったところにある古い宿である。次の日に望月城跡にいくつもりであった。
バスをおりると、そのあたりは、中山道の昔の宿場町だったそうで、ふるびた歴史を感じさせる建物も残っていた。
泊まる宿はバス停からすぐのところにあった。建物はずいぶん古いもので、温泉は江戸時代につくられたという宿である。入口の戸を開けると、たたきは土間になっており、あがったところに帳場がある。
帳場から女将がでてきた。帳場で記帳がすむと、女将自ら部屋に案内してくれた。二階の十畳ほどの畳の間である。
「風呂は帳場の脇を奥に進んだところに二つあります。男女、朝夕で交代します。お食事はお部屋におもちしまる、五時ごろでよろしいでしょうか」
彼はうなずいて、まず一風呂浴びたいと言った。
「今日、お客さんがすくないので、のんびりなさってください、タオル類はお部屋のものをおもちください」
そういって、下に降りて行った
彼はタオルを持ち、部屋を出た。男湯の戸を開けると、中には誰もはいっていなかった。部屋の中の風呂ではあるが、南面の大きな戸が開けたままになっており、庭が見え、半露天風呂の雰囲気である。大きな風呂場ではないが、檜の板が敷き詰められた洗い場と、木の湯殿は、昔のつくりのままのものなのだろう。いい湯である。ふと庭のほうを見ると,庭石の脇からベニテングタケがいくつも生えているのが見えた。あかはえとりがたくさん生えている。だがベニテングタケが麹菌のような働きはもっていないであろう。似た茸を探そう、そう思った。
湯は気持ちがよく、しばらく使って、部屋に戻った。
部屋では女中さんが夕食の用意をしているところだった。
「湯はいかがでした」
「よかったですよ」
「ビールでもお持ちしましょうか、生がありますが」
「お願いします」
皿を並べていた女中さんは、いったん戻って、ビールを持ってきた。コップにビールを注ぎながら、
「ご旅行ですか」
と聞いた。
「仕事の帰りで、ちょっと骨休みです」
「それはいいですね、何のお仕事ですか」
「味噌づくりと、茸の栽培を見学してきました」
「そうですか、このあたりでも、山のほうに行けば茸はいろいろでます、今日の食事にも何種類かはいってます、天然の滑子や舞茸、香茸の炊き込みごはんもつきます」
「それは嬉しいですね、このあたりに茸で味噌を作るというような話は伝わっていませんか」
「うーん、どこでも味噌は作っていたからね、でも、茸でつくるなんてのはしりませんね」
「このあたり特有の味噌なんてないですよね」
「聞いたことないですね、城なんかではたくさん作っていたかもしれませんけどね、保存食としては大事ですからね」
「明日望月城にいきたいんですけど」
「あれは立派な城だったということです、この地域にはたくさんの小さな城があったようですけど、中でも立派です」
「ここからはどういったらいいですか」
「歩くのは無理ですね、望月山の上にあるんですよ、お山がお城だったんです、タクシーで上までいけます」
「いつ頃の城ですか」
「お城は室町でしょうか、戦国時代ともいいますね、ずいぶん昔で、城主がこの辺を統治していたそうだけど、武田に負けて、仲間になったようです」
「明日いこうと思っています」
「タクシーなら近いですよ」
宿の料理はおいしかった。特に茸料理はいい。
スマホで調べたら望月山はふもとから農地になり、駐車場も整備されている。この城は五つの郭からなる強い山城だったようだ。山そのものが望月城跡である。
あくる日タクシーをたのんで、望月城の天守のあった山の上までいってもらった。タクシーの電話番号をきいておき、ぶらぶらと山道を天守閣のあったところまで歩いた。天守閣のあった跡には看板もたてられており、由来なども書いてあった。古びた石づみは歴史を感じさせる。
ぐるりと一周回ってみた。木が生い茂っているので、外は木々の間から見えただけだが、みはらしのいいところではある。木の下にはよく見かける茸が生えていたが、「あかはえとり」は生えていない。
そろそろ、タクシーを呼んでかえろうかと、駐車場に向かう草の中に赤いものがすっくとたっている。柄があかく、一瞬、卵茸とおもったが、そばによると、それはベニテング茸だった。いや、柄が真っ赤だからベニテング茸とはちがうようだ。しかも傘には白いぽちぽちはついていない。卵茸のようだが、卵茸のように傘には筋がなく色も朱色ではなく紅である。根元に壷はない。写真をとり、生えている様子を手帳に書くと、袋にしまった。文献に書かれていた味噌茸でなくとも、新種ならそれなりに面白い。
駐車場でタクシーを呼んだ。だいぶ待ったが、小諸の駅までいってもらった。バスではずいぶんかかったのに、十分もかからずについてしまった。
電車の乗り継ぎはスムーズで、昼過ぎには笹塚の研究所に戻った。
研究所で、望月山でとったあかはえとり似た茸から胞子をとりだし、研究員の一人、石田健二に培養を頼んだ。石田は茸の培養液の開発で学位をとり、研究所に来た男だ。
彼自身はこの茸の名前を調べるため、世界中の茸図鑑を検索した。だが、同じようなものはなかった。
遺伝子解析も、研究所の研究員の一人にたのんだ。その結果、不思議なのは担子菌類であるべニテングタケとは全く違う遺伝子組成で、子嚢菌類の遺伝子を持っているという。チャワン茸やアミガサ茸のなかまのようだ。形は担子菌にちかく、発生はシノウ菌類菌の仲間ということである。奇妙な茸だ。
培養はうまくいき始めた。
三週間ほど経つと石田が呼びに来た。見ると培養瓶の中には菌糸が立派に発達しており、小さな赤い点がたくさん出てきている。
「なんだい、この赤い点は」
石田に言うと、
「そうなんです、赤い点を顕微鏡で見ると、不思議なんです」
PCの画面を示した。たくさんの小さな器型の幼菌が顔を出している。
「チャワン茸みたいだな」
「社長がとってきたあかはえとりの胞子から出たことは確かです、間違えたりしていないし、いくつか培養しましたが、みな同じ状態です」
確かに、どの容器でも同じ赤い点々がみえる。
「これが大きくなったらどうなるのかな」
そういって三日たったところで、石田がやってきた。
「チャワン茸に柄が生えてきました、しかも、チャワンがだんだん平らになってきています、あかはえとりに似た茸になりそうです」
これはとても奇妙なことである。
そして一週間後、培養地からベニテングタケに似た茸がはえてきたのである
「石田君、これを大々的に培養して、どのような茸か調べよう、培養に人がいるだろうから、手伝いを鈴木教授にたのむよ」
「おねがいします、僕も今やりかけの研究がありますのでたすかります。
石田も同じ大学の出身者で、彼と同じ鈴木教授に師事していた。
鈴木教授には研究費の寄付や、研究室の学生にアルバイト代を出したり、場合によっては奨学金をだしている。
都内のその大学の実験室では、発酵や菌類の培養についての研究が今でも進められている。たずねていくと、大勢の学生が研究を進めている。人気のある研究室である。
「先生、また新しい茸をみつけたので、誰かアルバイトで培養管理してくれる人がいないでしょうか」
「うん、いないことはないよ、君の研究所は近いし、アルバイト代はいいし、喜んで行くと思うよ、来年卒業研究を始めるのが六人いるけど聞いておくよ」
「お願いします、どのような茸かわからないのですけど、新種のようです。
「それなら、その茸の培養に関して卒論研究にさせてもらうということでどう」
「もちろんいいですよ」
研究室に戻るとすぐに電話があり、一人の学生が興味を持っているということだった。次の日に来てもらうことにした。
やってきたのは、今どきの女の子にしては珍しい、地味な格好をした小柄な女の子であった。しかし受け答えは非常にはっきりしていた。
「先生から話は聞きました。茸の培養は、実習で一応やりましたので、指示していただければできると思います」
その子は佐和静子といった。石田にひきあわせ、培養室を見せた
「研究室のものとほとんど同じですから、出来ると思います」
とても頼もしいことを言った。
石田にもいろいろ質問をして、うなずいている。
大学の研究室には小さな培養室が五つある。実は彼が指定寄付をして作ったものなので、茸発酵研究所のものとほとんど同じである。
「佐和さんは、卒業したらどうするの」
「醸造関係に就職するつもりでいます」
「大学院はいかないのですか」
「とてもお金がかかって無理です」
彼女は笑顔で答えた。
「それでは明日からでもこれますか」
「ええ、ただ、まだ講義もありますので、朝のうちなら、培養の面倒を見て学校に行くということができます。火曜日と木曜日、土曜日はいつでもこれます」
彼女の予定に沿った、研究所に来るタイムテーブルを作り、その時間にきてもらうことにした。時給二千円でお願いしたら、高額なのに驚いていた。
教授に電話すると、
「それは良かった、出来る子でね、ただ母子家庭でアルバイトしながら頑張っているんだ」、ずいぶん喜んでくれた。
「もし、何か新しいことが出てきて、興味を持つようなら、奨学金をだしますよ」
「そうしてくれれば、とても助かるね」
苦学生ほどいい研究結果をだすものである。大いに期待できそうだ。石田も彼女ならまかせられそうですよと、よろこんでいた。
佐和静子はじつに有能であった。石田の手引きのうまさもあるが、茸の培養地からあかはえとりに似た茸がどんどん生えてきた。
石田と佐和を呼んだ。
「培地に大豆をまぜたらどうなるだろう」
「ゆでるなりして、消毒さえすれば、大豆に栄養があるし、問題はないと思いますけど、どうして大豆なのですか」
石田が不思議そうな顔をした。
「いやね、大学時代に読んだ古い文献に、大豆を発酵させる茸が載っていてね、この茸がそうだというわけじゃないけど、やってみたかったんだ」
「味噌を作るわけですか、しかも、茸でつくる」
さすがに石田である。すぐ意図が通じた。佐和にはまだ意味は分からないようだ。
「なぜ、大豆を混ぜるのですか」
静子が不思議そうに尋ねた。
「実は、こういう文献があってね」
彼は学生時代にであった望月城に勤める武士の書いた古い文献について話をした。
「社長はこの茸、望月山で採ってきたのですね、その文献も望月城のことなんでしょう、可能性がありますね」
「いや、まったくわからないけどね
「私も、図書室にいってみます」
彼女は、次の日には例の文献のコピーをもってきた。
「まだ、古文書はあったのだね」
「ありました。確かに面白い話しですね、でも文献の茸とはだいぶ違いますね」
「うん、違うと思う、だめかもしれないけどやってみようと思っただけなんだ」
「面白そうです」
彼女は好奇心の強い子である。
その日から、茹でた大豆入り培地による茸の栽培を始めた。静子は、「他の茸でも同じように大豆の培地でやってみます」と、マッシュルームやエノキでも試し始めた。
二日すると、彼女が報告しに来た。
「先生が採ってきた茸だけ、培地の中の大豆にも菌糸がはいりこんでいます」
培養室に行くと、確かに、マッシュルームやエノキでは大豆の周りに菌糸が伸びているが、望月の茸のように、大豆の表面に取り付いているのは見られない。
「面白いね、大豆でも培養できるかもしれないね」
一週間すると、
「幼菌がでました」と彼女が言ってきた。
見ると、赤い小さな茸の頭が見える。
「それが大きくなったら、大豆の変化をみて、大豆だけで培養してみよう」
「私もそう考えていました」
佐和静子はうまく行っていることもあり、やる気満々である。大豆を取り出してみると、柔らかくなっていて、指でもつと、ぐしゃっとつぶれ、つーんと味噌の匂いがした。まさかと思っていたことがおきそうだ。
「いい匂いがします」
静子も驚いている。彼は指の先でちょっと舐めてみて、唾をティッシュにだした。
「味噌の味だ、君も舐めてごらん、でも飲み込まないように」
彼女も同じように舐めた後、唾をティッシュで拭き取った。
「お味噌です」
「うん、面白い、大豆だけでやってみてみよう、この発酵した豆は分析にまわすから、いくつか用意しておいてくれるかな」
食物成分の分析会社に、その発酵した大豆を送る手はずを整えた。
「茹でた大豆だけでやるとき、酵母も同時にやってみます」
彼女はそういった。比較対照群として、酵母を使いたいということである。研究能力が高い、こういう子は是非大学院に行ってもらいたいものである。研究が進んだら、奨学金のことを話そう。
その結果、大豆だけで茸の培養はうまくいった。むしろ茸の顔をだすのが早いくらいであった。しかも、酵母より早く発酵が進んでいる。
それらの発酵した大豆の分析結果が出た。
成分の結果はアミノ酸をたくさん含んだ、とてもリッチな味噌になっていることを示している。酵母のものより旨味のアミノ酸が多い。それだけでなかった。面白い成分が含まれていた。セロトニン、アドレナリン、ギャバなど、動物の脳、からだの中で働いている物質で、おまけに副腎皮質ホルモンと同じ作用のある物質が含まれていた。これはすべて、ストレスを和らげる成分である。しかも味噌の中にその成分が溶けだしている。これはすばらしい味噌である。茸で味噌が作れるだけでも驚くことなのに、普通の味噌よりはるかに栄養価が高い。
その年も終りになろうとしていたころである。大豆で培養した茸に異変が生じてきた。
ベニテングタケのような形をしていた子実体にまじって、マッシュルームの形をした茸が、ポコポコと瓶の先からでてきた。ただ真っ赤だった。マッシュルームの菌が混じった可能性を考えたが、真っ赤なマッシュルームは見たことも無い。
静子も彼もどうしてそうなるのか、わからなかった。ただ大豆は上等な味噌となっていた。胞子をとって培養を続けていると、茸の形が卵茸になったり、松茸になったり、大きな猪口になったりする。すべて赤い色をしているが、茸の形が一定しないのである。それはともかく、味噌はきちんとできる。
あまりにも不思議な現象で、とまどっているところに、科学博物館から、遺伝子解析の結果が届いた。
日本では未発見の茸であることは、すでに調べがついていたが、やっと何の種類か分かったと書いてある。
物まね茸の仲間。
こんな茸は全く知らない。
科学博物館に電話をした。茸の専門家はこんなことを言った。
「本当の日本名はまだないから、勝手に物まね茸って呼びました、ある菌は植物にくっついて、自分の細胞を変化させ、とある植物と同じような花を形成させ、花の先にその菌の精子を出して、止まった虫に運ばせる。そんな菌類もいるのです。飯田さんが採ってきた茸はそれとは違いますが、遺伝子の中に、アミガサタケ、茶碗茸、唐傘茸、作り茸、松茸、椎茸、ありとあらゆる形の茸を形成させる遺伝子が存在するのです。どのようなきっかけか判りませんが、どれかの形の茸を作ることになると思います」
「ええ、その通りで、まさに、そのことが、我々の、培養室で起きています。マッシュールームが出たり、榎茸が出たり、松茸が出たり、ただ色はみな真っ赤です」
「ええ、茸の色形成の遺伝子は赤のようです」
「今度、研究所にきてみてください」
「是非いきたいと思っていました」
やってきた科学博物館の茸の専門家は、茸発酵研究所の培養室で、目を見開いたまま、無言で驚いていた。
この茸については、科学博物館、大学と共同で、あらゆる面からの科学論文を書き、和名は、味噌茸と彼が名付けた。
いくつもの特許の出願も行なった。
味噌茸のプロジェクトは大きく走り出した。
健康味噌を作る会社を新たに立ち上げた。
佐和静子は、彼の奨学金をもらい、博士課程まで進むことになった。
味噌茸の解析は、佐和静子の協力を受けて、次のステップにいった。
古文書にあるような茸の毒を打ち消す作用について調べることにしたのである。
動物実験では、この茸を食べたマウスは、毒茸を食べさせても、大丈夫なことから、毒消しの効果は認められる。直接毒性分を注射しても、この茸を食べさせておけば生きていることから、確かであることが証明された。ところが、茸の中のどの成分が毒消し効果をもつのか、いくら調べてもわからない。茸をすり潰して、上澄みを注射しても毒消し効果はなく、沈殿物を食べさせても効果がない。丸ごと食べたときのみ毒消し効果がみられた。この茸の菌糸だけ取り出して、食べさせてみたが、効果はない。ということは、茸になった菌糸を直接食べて、それを動物の消化液か、腸内細菌によって化学反応が起きた結果といえる。
茸を食べさせたマウスの胃の中の物を取り出し、その上澄みに毒茸を浸したところ、毒茸の毒性が消えていた。どのようなタイプの毒でも同様であった。
これは、すごい薬にもなるし、最初考えたように、これによって毒茸もすべて食べることのできる茸になる。
この茸を乾燥させておいても、その効果は保たれた。
大発見である。ただ、胃の中に入ったその茸がどのような物質になって効くのかはいくら調べてもわからなかった。これでは、薬としての特許は難しいかもしれないが、この茸を粉末にしたり、乾燥して、健康補完剤としては特許がとれるであろう。
こうして、数年がたち、佐和田静子が博士をとるときには、海外の、特に茸の好きな北欧、フランスなどのヨーロッパ各国の特許をとった。
これは、あらゆる茸が食用になることから、食料事情の改革をもたらした。味噌は日本の食べ物としてよく知られていたこともあり、彼らが特許をとった健康味噌は、売れ過ぎぐらいに売れたのである。
もう一つおまけがある。この茸の栽培キットを販売した。味噌が造れるのと、うまくすると、茸が生えてくる。その茸はもちろん毒消しの役割として食べてもいいが、とてもきれいな茸が生えることがある。どのような形の茸が生えてくるかわからないところが面白い。ネットにこんな茸が生えたと写真を送るサイトができ、世界中の、まだ見つかってない茸もそこに投稿された。すると、今度は、サイトに投稿された茸の、自然のものを探す人たちが現れ、探し出した人は、その茸に名前を付ける権利が与えられ、人々の新しい趣味となったのである。
さて、この偉業をなしとげた、飯田君麿はなにをしているかというと、甘い茸、塩辛い茸、酸っぱい茸を作ろうとしていた。そのまま食べてもいいが、それから、砂糖、塩、酸を抽出することを考えていた。土の中に菌糸を張っている訳で、土の中の成分を吸い取るのではないかと考えたのである。カルシウムの豊富な茸もいいだろう。さらに、土の中の微量な金属を吸収させるようにして、金などをとるのもいい。彼の頭の中では、人間のからだに必要な成分が、すべて茸でまかなえるような世界を描いていたのである。
味噌茸
参考文献 『奇妙な菌類 ミクロ世界の生存戦略』 白水貴著 NHK出版新書484、2016年
私家版第十一茸小説集「黙茸録、2021、265p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2015-9-20


