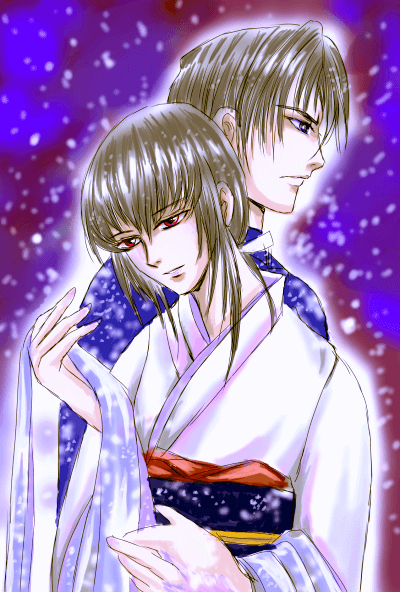
山霞
2005年~2020年作品
序
にび色の空が何処までも広がっている先に、一羽の鷹のはばたきがあった。
鷹は、まだ歳若い少年の手から中空に放たれたのであった。
少年は藍色の庭着のようなものを着て、高く髪を後ろに結わえていた。
その様は、遠目にも白く、すらりと浮き立って見えた。
「殿、いかがでございます。このほどの鷹狩りは・・・・。」
「うむ。苦しゅうないぞ。鷹もほどよく慣れている。御庭番衆は、よい仕事をしているな。」
「御意にござります。」
四方にむかって張られた天幕の中心の椅子に、将軍は腰掛けている。
それは、蒼紫らが仕える江戸幕府の御代様である。
しかし、その面前に出られる機会は、このような鷹狩りなどの時よりほかにはない。
将軍のそばには相談役がいて、蒼紫らの様子を逐一伝えているのである。
鷹狩りをすると言っても、将軍自らが行うのではなかった。将軍は腰掛けたまま言った。
「あの鷹を扱っている者はまだ少年だな。なぜあのような者に扱わせるのだ?」
将軍が珍しく、質問をした。
あわてて相談役が走って行き、蒼紫のそばに立つ御頭に言葉を伝えて戻ってきた。
「おそれながら、もっとも御庭番衆内で今、才能がある若者らしい、ということでございます。」
「ほう。まだ十四五六ほどではないか。余は話をしてみたい。」
「め、めっそうもござりませぬ。あのような下賎な輩は、将軍様の身辺には近づけることはできませぬ。」
「ふむ。そうか。名はなんと申す。」
相談役がまた走って行って戻ってきた。今度は息を切らしていた。
「四乃森、蒼紫、という名でございます。」
「ふむ。四乃森。お取り潰しになった御家人にそのような名の者がいたような・・・・・?はて、余の思い違いか。」
蒼紫はその様子を遠くから眺めていた。
自分たちを支配してやまない存在───将軍家。
自分は武士の地位を剥奪されて、今は下人として生きている。
そう叫びたい気持ちを、蒼紫は抑えていた。
言ったところでどうにもならない。
どうにもならない壁が、自分とあの将軍の間には、ある。ありすぎる。
「蒼紫、行ったぞ。」
老人の言葉に、犬たちがほえて行く先に向かって、蒼紫は走りながら、すばやい動作でまた鷹を放った。
それは鷹とほとんど一体となったかのような見事な動きだった。
鷹の世話をするのは、蒼紫は好きだった。
そのような生き物の世話をするのは、心があたたまる。
敵に対して刃を向ける時に比べ、どれほど心がやすらぐだろうか───。しかし、蒼紫はそのことを決して御頭である老人には告げなかった。
そうしたことを告げると、自分は今のやや安泰とした地位を剥奪され、御庭番衆から追放されるかも知れないからだ。
安寧を夢見ることは、禁じられていた。
ただ、どんなに苦しくても自分は自分の今の道を進むだけだと思った。思っていた───その日までは。
「鷹狩りは見事に仕事をこなしたようだね。」
蒼紫は今、将軍のいた草原からはるかに離れた、忍びの里の一角の番屋に座っている。
目の前に囲炉裏の炎が燃えていて、その前に朱の唇を引き結んだ「月の輪の宮」、笹葉霞が蒼紫と向かい合って座っていた。
葉霞は、女忍者たちの統率者である。
長い黒髪をした、絶世の美女と言っていい。
そして───。
「おまえ、幾つになった?」
葉霞が朱唇をひきあげて聞いた。蒼紫は答えた。
「かぞえで十五になります。」
「それなら遅いぐらいだねぇ。女を知るのは。」
葉霞は目を細めた。
目の前の少年は、まるで自ら光輝く玉のようだ。
───ほんとうに、美しい、少年ね。
葉霞は手を伸ばして、蒼紫の髷に触った。
「私と寝たら、この髷は落とすんだよ。」
蒼紫の表情が、険しくなった。
「なんだい?まさか武士の鑑とかまだ思っているんじゃあないだろうねぇ。」
その一言、一言が蒼紫の神経を逆撫でするようだった。
しかし拒絶や抵抗は許されないのだ。
蒼紫は、あの老人の命で今ここに来ているのだ。
───この者は、母上とは違う。
蒼紫の必死の抵抗する思いは、今それだけであった。
そうして目の前の女を否定したいのだが、女は赤い唇を開いて、蒼紫にとろりと絡み付いてきた。
「最初なんだろ?やさしくするよ。」
葉霞はふふふ、と低く笑うと囲炉裏の火を落とした。
蒼紫は逃れられない腕の下で、ただ運命というものは暗澹としたものだと、感じていた。
爪牙
黒の斬流しを着た浪人姿の侍が、肩で風をきって江戸吉原の一角の茶屋に入って行った。
腰の刀を男衆に預けると、浪人は物慣れた様子で、座敷にあがった。ぼんぼりが開け放した廊下に向かって灯っている。緋毛氈を敷いた上に、客の「なじみの」妓が、いた。
「よう。久しぶりだな。」
言うなり浪人はどっかりとあぐらをかいて座った。その前に、きらびやかな衣装の妓が手をついて言った。一の太夫ではない。しかし、それなりに箔のついた身なりだった。
「志々雄さま、ようお越し。お待ち申しておりましたえ。」
「由美、元気にしていたか。酒。」
杯をつき出すのに、由美と呼ばれた女はなみなみと酒をついだ。志々雄真実と由美であるが、後年十本刀を擁したときの面影は、まだ二人にはない。志々雄はまだ若く、その顔は整っており、頭はそりあげて髷を結っている。由美も年増の色気よりもまだ、若さが目立つ様子だった。その二人が酒盛りを始めると、すぐに音曲を担当する芸子らが、下の席で三味線を引き出した。音の音色が何か暗い。由美は少し気になって、そちらの方を見た。いつもの芸子ではない。が、気にもとめずに由美は志々雄にしなだれかかった。
「志々雄さま、私、落籍したいのです。」
「ん?その話か。それにはまとまった金がいるだろう。俺は京に上ることにした。」
「まあ、京にですか。」
「京では土佐勤皇党が、ばさばさ人を斬っていやがるところだ。俺のような浪人者には、もってこいのところさ。近頃は長州の連中も、天誅に加わっているらしい。幕府も大変だな。」
「志々雄さまは、幕府と勤皇と、どちらの味方なんですの?」
「俺か。俺は強いほうの味方さ。まあ攘夷派だな。幕府はもうとっくに屋台骨がいかれている。」
杯をなめながら言う志々雄の瞳には、冷酷な光が灯っている。
───こわいお人。何人でも斬るおつもりね。
と、由美は思いながら、酌をしながらささやいた。
「土佐に・・・つくのですか。」
「ん?それは聞くだけ野暮というものだろう。」
「そうですわね。失礼しました。」
「まあ行ってみなくちゃわかんねぇさ。」
志々雄はそう言うと、ひとしきり笑った。
と、その時だった。三味線の弦が切れたような音がした。
「・・・・あんた・・・!」
由美の顔が険しくなった。
由美は音をはずした芸子に向かって、しかりつけた。
「新入りだね。ろくに三味線が弾けやしないのに、こんな上座にまでのぼってきたのかい。」
芸子は消え入りそうな声であやまった。
「すみません・・・・。」
「あんた、何か暗いねぇ。もっとぱーっとしなさいよ。酒の席なんだから。」
「はい・・・・すみません。」
すると音をはずした芸子の横についていた、もう一人の芸子がなだめるように小声でつぶやいた。
「巴ちゃん、気にせんでええの。」
「はい。すみません・・・。」
二人は三味線の演奏を、何事もなかったように続けた。すぐに由美は忘れて、目の前の志々雄との楽しいひと時のほうに没頭した。
「君菊さん、ごめんなさい、つい爪がすべってしまって。」
宴がはねた後、廊下を歩きながら巴はまた、先輩の芸子にあやまった。
「いいのよ。あんた気になったんでしょう。土佐勤皇党。」
「えっ。」
巴はどきりとして、目を見張った。その藤色の小袖の上の顔は、驚くほど白かった。
君菊は髷をかんざしでいじくりながら、言った。
「身につまされるのよ。あんたの弾く三味線を聞いているとね。男を───京で殺されたんだろう。」
「はい・・・・・。ご存知なんですね。」
「そりゃあんたの仕事を世話した時に、聞いているからね。武士の娘なのに、吉原で三味線弾きかい。」
「弟を育てるためなんです。」
「それだけとは思えないねぇ。あんた、その男のこと、捜しているんだろ。わかるんだよ。」
「・・・・・・・・。」
「どうやって殺されたか。殺したのは誰か。奉行所はあんたに何も言わなかったのかい。」
「ごめんなさい。そのお話なら、いずれまた───。」
「あっ、ちょいとお待ちよ。」
巴は面を伏せると、廊下を後にした。
巴は思った。
たずねている。
確かに私は、たずねている。
京で、婚約者の清里を殺した者を───。
まず、清里を京にのぼらせた男を見つけ出さないと。
そうしないと、あの人が浮かばれない。
たとえあの人が───私を乱暴に抱いて、江戸に捨てて行ったのだとしても───。
巴は心細さに三味線をかき抱いた。
その軸には、仕込み刀が入っている。
短刀が柄のところに入っているのだ。
なんて悲しい音色だろう。この三味線の音色は。
巴が、音曲と武芸のたしなみが少しあるというのを見て、奉行所は巴をそのような間者に仕立てたのだ。断ることはできなかった。巴を守ってくれる、巴の父も母も今はもういない。弟と二人きり───そこに、奉行所はつけこんだのだ。ただし、まだ巴は真の闇の者ではなかった。そのような者が闇にうごめいていることも知らず、巴はただ短刀一本で、清里が消えた消息をつきとめようというのだった。
───土佐勤皇党。もしくは、長州の者。
今志々雄がもらした言葉が、かすかな手がかりだった。
───京に、のぼらねばならないのだろうか。縁をどうしよう。
巴は不安なまま、鳥追い女の姿になって、吉原の大門の下をくぐった。
話はそれより一ヶ月ほど前にさかのぼる。
雪代巴の婚約者・清里明良は、講武所を出た帰りに、一人の男に呼び止められた。
男とは何度か表通りの普通の茶店で会って、京にのぼる相談をしていたのである。清里はにっこり笑って男に言った。
「飯塚さん。決心はつきましたよ。京都見回り組。腕にそう覚えはありませんが、市内を巡回して回るだけなのでしょう。それで給金がこんなに入ると聞いたら、やはり、所帯を巴と持つ身の上、私も御家人勤めだけでは巴を幸せにはできないと思いまして。」
飯塚────この男は、後に剣心のそばに現れて、長州方の間で暗躍した男だが、このときはまだ江戸にいたのであった。飯塚が清里の仕事を斡旋したのである。飯塚は、この頃は江戸で京都見廻り組の人員を募集しているのを、手伝っていたのである。飯塚は清里の肩を抱くようにして、近寄ると声を潜めて言った。
「兄さん、そいつは結構な話だが、用心してかからねぇと。巴って女・・・・・おまえさんの恋女房だろ?」
飯塚の言葉に、清里はのぼせたように頬を赤らめた。純情な男なのである。
「まだ・・・・女房と呼ぶのではありませんが・・・まだ、婚約者ですから、私は。」
飯塚の目が光った。
「馬鹿言っちゃいけねぇ。京都にはどんな送り狼がいるかわからねぇんだぜ。その前にしっかりと、こう、抱いてやってからでねぇと。」
「そ、そんな、私は・・・・巴とは・・・・。」
「おまえさん、京都で死ぬかも知れないんだぜ。」
飯塚の言葉に、清里の声が裏返った。
「わ、私が死ぬ?そんな、そんなはずはないでしょう?そんな危険な任務ではないと───。」
飯塚がなだめるように言った。
「そうそう。そうだった、そうだった。つい言葉がすべっちまった・・・・・。あやまるぜ。ただ、女を江戸に残しておくんなら、どんな悪い虫がつくかわからねぇ。やっちまったほうが賢明かなあ、って俺は思うのよ。ま、その道の先輩としてだな。」
「・・・・・・・。」
「それにそのほうがおまえさん、職務に専念できるんじゃねぇのかな、と俺は思うのよ。江戸に残してきた女のことが気がかりじゃ、剣先もにぶる、ってもんだな。腕に自信がないならなおさらのこった。」
清里は飯塚の言葉を聞いて、しばらく考えこんでいたが、やがて決心したように言った。
「わかりました。だ、抱けばいいんですね。しかし、巴が私を許してくれるだろうか。」
清里の言葉に、飯塚はからからと笑った。
「何緊張してんだ。てめぇの女房になる女だろ?それが早いか遅いかの違いだけじゃねぇか。ま、肩の力を抜いてがんばりな。それじゃ俺はこれでな。あばよ。」
その清里が京で死んで、巴は奉行所の入り口に立っていた。清里との一夜を巴は思い出す。
───おやめください、清里さま。
───いいじゃないか、巴。京に行くんだから、少しぐらい。悪いようにはしない。
───清里さまが、そのようなことを、私になさるとは───ああっ。
清里に無理やり脱がされて、強引に押し切られた。
それでも私は、清里が好きだと思う───思わないといけない。
そうでないと、死んでいったあの人があんまりにもかわいそうだ・・・・・。
巴はそのことを思うと、心が悲しさにふるえる。
巴は評定の間に座った。清里の死についての取調べである。奉行は巴の前に座り、畳に扇子をつくと、重々しい声でこう切り出した。
「そのほう、清里明良に京都見廻り組を斡旋した男を知っているか。」
巴は小さくかぶりを振った。
「いえ・・・・存じません。京にのぼることは、清里が一人で決めました。わたくしは何も。」
「そうか。」
奉行はそう言うと、人を呼ぶように言い、巴に言った。
「そのほうは聞くところによれば、武芸諸般にも武士の娘としてのたしなみを備え、音曲にもたけておると聞く。市井に埋もれるには全く惜しい人材である。ひとつ、武士としてその類まれなる資質を幕府に役立ててもらいたい。」
巴はあっけにとられた。
話が清里のこととつながっていない。
「私に何か・・・・せよと仰せでございますか。」
「その通りである。実は、京都見廻り組に募集した隊士の多くが、京都で消息を絶っている。幕府の人員が、無駄に浪費されておるのだ。まことに嘆かわしい事態であると言わねばなるまい。次々と隊士補充に応募した者が死んでいくのだからな。」
「それは・・・・・京都に攘夷派がいるからでござりましょう。私は、そんな恐ろしい者たちとは。」
奉行は巴の言葉に含み笑いをもらした。
「そうではない。まず、その方には、京都見廻り組を斡旋した者の名前をつかんでほしいのだ。そのためには、浪士らが出入りしている茶店などを回ってほしいのだ。そちにこれを与える。」
武士の一人が入ってくると、巴にひとつの三味線を押し付けた。
奉行は言った。
「柄のところを抜いてみよ。短剣が入っている。」
巴の顔が真っ青に変わった。
「いっ、いやでございます。」
奉行はなめるように巴の顔を見た。
「ほほう、いやと申すか・・・・・拒否は許されぬぞ。そちの弟・雪代縁の命は、本日より奉行所が預かることにする。」
巴の目が驚愕に見開かれた。
「えっ。」
「だからこれは、そういうことだ。これにて重畳。」
巴はその場で崩れるように倒れた。
───清里は・・・・・清里は・・・・私を・・・・・とんでもないことに・・・・。
いえ・・・・・そう思ってはいけない・・・・・清里さまは、私のために京都で死んだのだから・・・・・・。
巴はまた、吉原の一角に鳥追い女の姿で立っている。戻り女の姿に化けているのである。白い着物を着て三味線を抱えて、ひっそりと立つ巴の姿に目をとめる者は誰もいなかった。
まだ大門は出店の時間ではないので、客の人通りはまばらである。酔客の姿はあまりなく、通りはこれからの夜の支度の人々で少々にぎわっている。巴の立つ前の道を、天秤棒を担いで野菜売りなどがひっきりなしに通っている。巴はおどおどと、大門近くの背の高い杉の木の影に身を潜めて立っていた。そこへ一人のさむらい風の男がのっそりと近づいた。男は低い声で巴に言った。
「三軒先の茶店に入っている。早く行け。」
「はい。」
巴は小さくうなずくと、三味線を抱えて必死の思いで前に歩き出した。
巴はその茶店の座敷に通されると、すぐに三味線を弾くように言われた。巴以外にも二人ほど、容貌の目立たない女がお囃子をたたいていた。巴は集まっている男たちを眺めた。いずれも浪士風の者ばかりだが、車座になって密談をしていて、酒を盛んに注ぎあっている。その中の一人の男が、巴に目配せをした。
「おい。そこの女。三味線はもういい。こっちに来て酌をしろ。」
巴ははっと驚き動揺したが、すぐに面を伏せて、両脇の芸子に目礼をすると、銚子を手に取って男たちに酌をしだした。男の中の一人が、自分の顔に目を注いでいるのがわかった。男は言った。
「こうして近くで見ると、なかなかいい女じゃないか。名はなんと言う。」
「巴と申します。」
言ってから巴はドキリとした。男が、巴の着物の袂から手を差し入れてきた。巴はうつむいて、男の手をじっと我慢している。
と、横に座った男が言った。
「本田殿、その辺にしといたほうが。こいつは客をとる女じゃねぇ。」
「なんだ。俺のすることに水を差すのか。」
「いや・・・こいつはそんな、おとなしい玉じゃねぇですからね。」
と言うなり、いきなり巴の腕を取った。男は飯塚だった。飯塚は巴のあごを手でつかんで引き寄せて言った。
「あんたは雪代巴だろう。俺はあんたの旦那と会ったことがあるんだ。あんたはそれを、こそこそかぎまわっているらしいな。」
巴は必死で言った。
「な・・・・何をなさいます。」
「俺たちのする事を、幕府に言いつけるつもりなんだろ。そうはいかねぇぜ。」
巴は飯塚の手からぱっと逃れると、三味線を手に取った。柄のところを巴は勢いよく引き抜いた。短刀が現れた。ひぃっ、と横に座った芸子たちが悲鳴をあげた。
巴は護身のために短刀を構えながら、きついまなざしで飯塚たちに言った。
「言いなさい。どうして清里に仕事を頼んだのですか。」
「どうして?そりゃ仕事の口があったからだろ。」
「何か裏があって仕事を持ってきた・・・奉行所の方々はそう申しておりました。あなた、私と奉行所へ行きなさい。」
「は?奉行所に行きなさい?こりゃまた俺に命令ですか。あんた、俺がアッサリそんなところへ行くと思ってんのか。」
巴は飯塚がスラリと腰の刀を抜くのを、肝が冷える思いで眺めていた。
───でも・・・・でも・・・でも・・・・・!
巴は震える手で刀を握り締めている。ほかの男たちも、飯塚にならって刀に手をかけた。
と、その時。
ひょう、と何か鋲のようなものが空間に飛んだ。男の一人の眉間にそれは当たった。
「うおっ。」
思わず男が前にのめり倒れこんだ。
「こっちだ。早く。」
窓の外から声がして、二三人の者が入り込んだのを見た気がしたが、巴は見返す暇もなく命からがら外に駆け出た。
茶屋の飯炊き用の裏門を出ると、人気のない小道の先に、一人の老人がちょうちんを持って立っているのが見えた。蓑笠をかぶり蓑を着て、その下に丹前が少し見えていた。しかしその老人は、害意のないように巴には見えた。と、その老人が「こっちに来い」というように巴に目配せをした。
「あ、あなたは。」
巴が息せき切って駆け寄ると、その老人は口に細い吹き矢のものを加えて、何か鋭い音のするものを吹いた。それは、巴を追ってくる男たちの目や鼻に次々と当たった。追ってきた飯塚たちほか二名の武士が叫んだ。
「てめぇ、何しやがるっ。」
老人は吹き矢を口から離すと、重々至極という調子で言った。
「そこまでにしとくんだな。この女を追い詰めるのが、おまえさん方の役割じゃろう。わしは、女を助ける役割りじゃ。」
飯塚の隣の男がにらみつけて言った。
「聞いてないぞ・・・・。貴様、俺らの邪魔をしようって言うのか。」
「邪魔などはせんよ。これからも幕府の人間を京に送り込んでは、長州などの暗殺者に斬らせるんじゃな。それでおまえさん方の『おあし』が出ることについては、わしは何にも言わん。ただ、この女はここに置いておきなさい。これはおまえさん方が目をかけてはならん女じゃ。」
「じじい、指図をするなっ。」
飯塚は老人に斬り付けた。だが、老人はポン、と夕陽に飛んで、飯塚の剣を腰の剣で斬り抜けると、何か飯塚たちに向かってふわりと投げた。
「なっ、なんだこれは。」
飯塚は急に手足が自由にならず、闇の中でもがいた。老人は得意そうに言った。
「ふふふ、昔取った杵柄じゃ。それは拙僧の投げた霞網じゃ。それから抜け出るには、半刻ばかりの時間がいるわい。さ、あんたはわしと一緒に来なさい。いいな。」
と言い、もがいている飯塚に手裏剣を一個ほうって巴に向き直った。老人の言葉に、巴は声もなくうなずいた。そしてああやはりと思った。昔読本で読んだ者にそのような者がいると聞いたことがあった。母に幼い巴は本から顔をあげて「果心居士とはなんですか?」と聞いた。母は「そういう不思議な人がいたそうですよ。」と言った。そして庭の干し物を広げながら、重ねて言った。「戦国の世には忍者がいたそうです。今の平和なお江戸にはいませんけどね。」と言った。
老人は細い木の板が渡してある、お葉黒どぶ横の掘割を渡りながら、巴に尋ねた。
「まだ走れるかね?」
巴は「はい」と言った。老人はそれを聞くと、巴ににこやかに笑った。
「では走ろう。隅田川の水運から逃げる算段じゃ。行こう。」
と言った。巴はほっとした。しかしその吉原から隅田川まで続く斜めの道を老人について走りながら、逃がしてもらえるのだろうかとも思った。その時、浅草不動院の夕刻を告げる鐘が鳴った。
道は平坦であった。しもた屋の家々は静まり、軒を連ねていた。突然家がまばらになって、葦原がしげっているところに木をつらねただけの船着場があった。老人は、「そこから乗りなさい」とそこに泊まっている一艘の手漕ぎ舟に巴が乗るようにうながした。そこへ、思いもかけぬ者が向こうから、吉原の方向から走って来た。
縁であった。
「ねぇちゃん、ねぇちゃーん」
と、誰か小さい者の背に背負われて、あの縁が走ってくるではないか。
巴は思わず涙がこぼれた。努力は報われたのだ。奉行所の「裏」の庭で、あのような者たちの真似事をさせられた自分、「上役」に囲まれて、息が詰まりそうな苦しかったあの毎日。それもみな、この弟のためであった。
縁はその者の背から下ろされ巴の手をひいたが、老人が短く叱責した。「叫ぶでない!早く乗れ」と言った。巴は弟と船に乗った。老人は最後に乗ると、船着場の木を足で蹴って、棹を出した。そしてこぎ始めた。
「蓑をかぶれ!」
老人はこぎながら小声で低く言った。
巴はあわてて弟と船に置いてある荷物の間にある人足用の、数枚置いてある蓑をかぶって息を殺した。船は隅田川の南千住の横の、東に湾曲した場所をのぼりはじめていた。ぎぃーっ、ぎぃーっ、と櫂を漕ぐ音だけが水面にきしんだ。夕闇の隅田川は静かに流れている。巴には短いが長い時間であった。
その同じ隅田川の一角。巴らの乗った舟が出た場所から程近い北東の暗い草原で、死闘が今繰り広げられていた。
葉霞と蒼紫であった。蒼紫はすっかり成長していて、ほとんど大人の男であった。
「やるようになったね。ではこれはどうだい?」
と、葉霞は腰から短剣を引き抜いた。
周りにはやはり女の忍者が数名、蒼紫を取り囲んでいる。
一人は分銅を片手でぐるぐる回している。全員、すさまじい殺気を放って蒼紫に対峙している。対する蒼紫は無言であった。剣を二本、小太刀を手に持っている。狙いどころを探られないようにか、両手とも常にゆっくりと一定の速さで、まるで念仏の舞踊をしているように動かしている。剣先はそれにつれて、いろんな方向に動く。蒼紫の目はしかし、その剣先を見ずに前方の葉霞の顔を凝視していた。
葉霞の顔は薄笑いを浮かべている。そしてそれを見ると、あわせたように、右手に持った長い太刀をおなじように動かしはじめた。一見二人とも、相手を誘っているようにも、遊んでいるようにも見える。しかしこれは死闘であった。
葉霞は蒼紫の脇を狙って第一撃を入れた。キン!という軽い音がして、蒼紫の太刀はそれをはねた。手は交差させている。そこへ分銅が飛んだ。蒼紫は後ろにパッとすり足で飛んだ。
「じりじり追いつめてやるよ。そのまま後ろの隅田川に落っこっちまいな。」
と、分銅の女が言った。葉霞はそれを聞くと、少し顔をしかめて脇の女に言った。
「麗月、殺れっ。」
と言った。
「はいっ。」
麗月と呼ばれた女はやはり葉霞と同じように大刀の女であった。蒼紫と葉霞のように剣を動かそうとしている。しかし、少しその動作に緩慢なところがあった。しかし首をひねり、気合いを「えぁっ!」とこめると、蒼紫に向かって突進してきた。蒼紫はその剣をくるりと体を回転させて受け流すと、葉霞に向かって一撃を加えようとした。行過ぎた麗月と呼ばれた女が前にのめって、倒れようとしている。そこへ、鎖鎌が飛んだ。
彼女らは、葉霞配下の女忍である。「霞五人衆」と呼ばれていた。麗月、星月、壮月、霜月、朔月という五人の手錬による女性ばかりの精鋭部隊である。常日頃から、先代───ということにしておこう。この物語の最後ではそうなるだろう。その蒼紫を実質的に育ててきた老人らに対し、反抗的な態度を見せていた。しかし、葉霞はこの先代の配下の一人であった。葉霞らは先代らとそのような複雑な関係なのであった。
蒼紫は先代らの指示で今、この千住河原でこの者らの巴への追撃を阻止しているのであった。蒼紫がこれまでやってきた任務の中では、一番やりがいのある仕事であったであろう。しかし、彼の内心は複雑であった。自分がその、巴という女をそのような境遇に貶めた一端であったということを、彼は考えているのであった。
鎖鎌を使う朔月は、かなりの手錬であった。ほかの四人の動きをこの女はサポートしている。分銅の女、霜月が一番術が弱い。だから、この包囲の網を抜けるとすればそこだ。蒼紫はそう考えた。
巴の乗る舟は隅田川を出航して、すでに遡行をはじめていた。そのまま無事遡行し遂げ、千住大橋から日光街道で悟られぬようにして自分配下の者を使い北に逃がす。実は、蒼紫は先代とは違う「計画」でそう考えているのであった。先代からの指示は、吉原西にある、日光街道を下ったところにある回向院に隠まえということであった。しかし絶対にそうはさせるものかと蒼紫は考えていた。
ついに、彼の中で何かが充填充満爆発し、主客正邪転倒することになったのである。だがこれは、至極当然のことであったのであろう。この夕闇の迫る時刻が、彼の人生の新たなる分かれ目であった。しかしこの計画を失敗した場合、自分は先代に悟られぬように動かねばならぬ。できるだろうか。しかしやってみせねばならない。
蒼紫はあまり、忍びの「腹芸」が得意ではない。だから忍びの内部でも、ただの先代が育てた術専門の忍び人間として扱われている。そして「あれ」が次期御頭に昇進するのかとも陰口をたたかれていたりした。蒼紫はそうした風評を耳にするたびに、自分が人として劣っているような気持ちがして、なんとも言えない気持ちになった。なぜ人間は表裏一体に生きてはいけないのか。しかし蒼紫のいる「忍び」の世界はまさに「それ」であった。
朔月の鎖鎌が蒼紫の進路を絶つように左右に振り子のように動いている。朔月の鎌が蒼紫の膝を狙って入った。蒼紫はまるまって飛び越した。それを見て葉霞はにやりと笑い、瞬間「壮月!」と叫んだ。二本刀の壮月が、着地した瞬間の蒼紫を狙って、第一撃を入れた。蒼紫はそれを受けた。激しい斬り合いになった。
二人とも丁々発止という感じで受けている。だが壮月が押されていた。麗月が言った。
「そろそろ殺るかい?」
葉霞は楽しそうに言った。
「そうだねぇ。」
葉霞は剣を構え戦っている蒼紫に狙いを定めた。
葉霞と麗月は蒼紫の背後に回って、同時に激突して剣で串刺しにしようとした。しかしその瞬間、蒼紫の姿はなかった。
葉霞は「なにっ。」と言った。あわてて星月と呼ばれる背の低い女が、印を結んだ。高い澄んだ風鳴りのような音が風に響いた。いやそれは、その場に居合わせた者だけが聞いた音だったのかも知れない。「う、うるさいっ!」と霜月、鎖分銅の女が片耳に手を当てて叫んだ。
「静かにしなっ。まだそのへんにいるはずだ。星月の術で動く音を探すんだよっ。」
と葉霞は小声で叱咤し、指示した。葉霞は黒髪の間から、あたりをなめるように見回した。蒼紫の姿はない。星月が印を結んだまま、膝を折り、小さく叫んだ。
「蝶!」
五人の女の目に舞い狂う幻覚の蝶が表れた。蝶の動きは錯綜し、夕闇の中で燐粉が燦々と光り、見ていて目まいがするようだった。そのような幻覚術なのである。おそらく、たまたま通りかかった者には見えないかも知れない。いやその者も巻き込まれてしまうかも知れない。人間の脳波をあやつるそれは、それほどの威力であった。
数分たったようであった。葉霞の顔にさすがに焦りの色が見え始めた。葉霞は
「だめか。落とせ。」
と短く言った。後ろの隅田川の水面が盛り上がった。それはふくれあがり、五人の女を飲み込んだ。水面は沈んだ。水は泥の泥炭地にあふれていって、緩やかになった。
「星月の術は見えていたはずだ・・・・・・・・しかし逃げたか。早く千住大橋へ!」
と、葉霞の意識のような声がした。五人の女たちの姿はそこから忽然と消えていた。
巴の乗る舟は、南千住のカーブのあたりにさしかかった。巴は蓑をかぶって弟と舟の中で息を潜めながら、どこかで斬り合いの音を聞いたような気がした。身が縮こまった。この老人は自分をどこかに売るつもりはなさそうだ。しかし、このような世界に身を置いていて、生きた心地がしないのであった。老人の短い言葉では、隅田川から舟を乗り換えて、どこかに逃がしてくれるのだろうと思った。そして遠いどこかで、籍を変えて自分は生きることになるのだろうと思った。思えば幼い頃からそんな予感があった。巴にはそれがつらかった。
舟がカーブから千住大橋に向かって促行を続けているときだった。突然、両岸に泊めてある舟がこちらに向かって動きだした。老人は「むっ、これはいかん。」と小声で言った。しかし努めて舟を静かに操っていた。巴の乗る舟の後ろに、二艘の舟が忍び寄ってきた。いきなり、その菰をかぶったその舟の中から槍がこちらに向かって、ごん、と突き出した。しかし狙いは老人の方ではなく、巴たちのほうであった。狙いはしかし、間一髪ではずれた。老人がそう舟をせわしく櫂で操ったのであった。しばらく槍と巴の乗る舟との格闘が続いた。老人は最後に槍を櫂でたたいた。「その女を置いていけ・・・・。」と声がして、夕闇の中で数人の男が槍の出た舟から立ち上がった。
「この寂庵を見知り置いてほしいの。」
と、老人は言い、櫂を櫓に置き頭に被った笠を河面に放ると、腰の刀を引き抜いた。舟はまだ上流に向かって慣性の法則で流れている。しかし、ここで足止めを食らうと、このままでは千住大橋で絡め手に捕られてしまう。寂庵は焦った。蒼紫は何をしているのかと思った。
ばらばらと数人が巴の乗る舟に飛び移った。寂庵はそれを剣でなぎ払い二人ほど水面下に突き落とした。ざんぶと音がして、巴の乗る舟が激しく揺れた。巴は立ち上がろうとした。しかし、寂庵が「今立ってはならん!」と叫んだ。「ねぇちゃん、ねぇちゃん」と縁が巴にしがみついてきた。巴はそれをかばった。水しぶきが激しくあがった。その時、縁の背後から小さな影が空中に飛んで、手裏剣のようなものを続けさまに投げた。
「ばかやろう!さんぴんども全員死刑にしてやるぜ!」
「ばかものっ、騒ぎを大きくするでないっ。猩々っ。」
寂庵は死闘を繰広げていた。三艘の舟の間を飛び移りながら、ほとんど軽業師のように敵の男をなで斬りにしていた。次々と男たちは、河底に沈んだ。しかしその騒ぎはもう、千住大橋付近で見えていたようであった。
「猩々、棹を戻せっ、船を逆手に押し上げるんじゃっ。」
「わかったよ。じいさん、後のやつらを頼むぜ。」
寂庵は一艘の船に乗っていた狼藉者をすべて川に沈めると、猩々と呼ばれた小男にすばやく命じた。まだもう一艘の船が追いすがって攻撃をしかけてきていた。カィン!!!寂庵の持つ刀がそれをはねた。男は鎖分銅を投げてよこそうとしていた。男は言った。
「その女はさる場所で必要なのでな・・・・・老人、そろそろ疲れてきたところではないか?」
「バカを言うな。貴様には吹き矢で目潰しでどうじゃ。」
「女を置いていけと親切に言っているのにな。ムッ、ころあいが来たか。」
猩々はその時叫んだ。
「千住の大橋だ!ねえさん、岸をよく見てな。若頭が助けに来るぜ。」
橋の欄干が迫っていた。呼ばれて巴は、この漕ぎ手は、ずいぶん小男なのに巧みに櫂を操っていると思った。
その時岸に人影が数人動くのが感じられた。
「若頭!」
その猩々の叫ぶ頭をかすめて、その数名は楔を放っていた。
「ううっ。」
先ほど分銅を投げようとしていた男たちは、顔に楔が突き刺さって、次々ともんどりうって川面に落ちた。
「へへっ、さんぴんおととい来いってんだ。な、火男?」
「癋見、おれも行くぜ!」
火男と呼ばれた太った男がよたよたとこちらに向かってくるのを、さっと前に出た般若の面の男がさえぎった。
「しっ、早くしろ、おい、女と子供。こちらの岸に向かって早く飛び移れ。」
巴はその般若の面にぎょっとしたが、もはや言う通りにするよりほかないので、般若が手をあおぐのに「はい。」と鷹揚にうなずいた。
そして縁の手を引いて船から跳ぼうとした、その時であった。
「────その娘と子供の命はあずかるぜ!」
橋の上でだれかが叫んで、こちらに紐のようなものを投げるのが見えた。
「まずい!」
誰かが一声、鋭く叫んだ。巴ははっ、として手を空に伸ばした時、誰かに抱えられて自分が向こう岸に降り立っているのがわかった。
どうやら橋の欄干の下部にひそんで巴らを待っていたようなのである。
しかし。
「縁!縁!」
巴は思わず絶叫した。
「ねえちゃん!」
縁の左足にその紐のようなものはすばやくからまって、男はそれをさっと橋の上まで手繰り寄せた。まるで手品を見るかのようであった。
そして縁が大橋の上に立っている片目の男に抱きかかえられて、橋の上をあっという間に北の方角に向かって遠ざかっていくのが見えたのだった。
縁が奪われたのだ。
「なんたる失態。」
寂庵が目をいからせてつぶやいた。しかし欄干の男の投げた紐による攻撃はあまりにもすばやく、防ぐことは無理なことであった。巴が逃れたのは間一髪というよりほかない。
「般若、女を頼む。」
巴を抱えて岸に降り立ったのは、巴の知らない蒼紫その人であった。蒼紫は巴を岸に立たせると、縁の奪われた方角へ行こうとした。
しかし、寂庵がそれを止めた。
「待て。今は追わぬほうがよい。あの者らは、役に立たなければあの子供の命を奪って、すぐに路傍に放り出す。子供の命はあの者らに預けるよりほかない。」
「何かに使うというのか。」
「だからその女と交換とか何か言ってくるのを待つのじゃな。でなければ、女の握っている証拠品との交換じゃ。」
巴は必死で言い募った。
「あの、私が何か持っているというのですか。」
寂庵は重ねて穏やかに言った。
「まあそんな昔のものは今では持っておらぬと思っているが、見た者もいるのでな。とりあえずあんたは小石川の療養所で安息すればよかろう。蒼紫、そこまで連れて行ってやりなさい。」
「はい。」
蒼紫はそれだけ答えた。
巴は思わずまじまじと蒼紫の顔を見た。それはたいそう綺麗な人だった。巴はそう思った。しかし───────。
先ほど夕闇の中で戦っていた音は、この者だったのかも知れない。
彼等は皆濃い藍色の忍び服を着ていた。それは明らかに日常の者のいでたちではなかった。巴はやはり恐ろしいと思い、あわてて目を伏せるようにした。
「では、参りましょう。」
若頭と呼ばれた蒼紫がそれから黙っているので、横合いからにこやかに猩々が言った。巴は静かにうなずいた。
彼等は巴について何かを知っているのであり、だからあの吉原にまで巴を助けに現れたのだ。それが何かは、まだ巴は知らなかった。
小石川の療養所は、隅田川からかなりの距離があった。途中、自分はどうしてこの者たちと一緒に歩かなければならないのだろう、縁はどうしたのだろうと、巴は不安に思った。しかし、奉行所に帰るのは、縁を取り戻すのに得策とは思えなかった。町並みの真ん中に江戸城の天守閣が見えてきた。小石川からは見えるのだった。巴はそのころにはこの者らは、おそらく御庭番衆ではないかと検討をつけていた。
───私の持っているもの・・・・あの小石の入った袋・・・・父と母の形見の品ではないか。
巴はそれも思い当たった。どうしても持っていなくてはならない、人前に出してはならない、と固く母から言い渡された、小さなぽち袋に入ったそれは、緑色の不思議な石であり、暗がりに置くと自然に発光する石だった。ただその色はあまりにもどぎつい緑色なので、巴はあまり好きではなかった。なぜこんなにもこの石は光るのか。巴はいつもそう思った。見るたびに不吉な感じを受けて、父が海の向こうに行ってしまい、母が病死してしまったのも、みんなこの石のせいではないかと巴は思ったりもするのだった。
療養所について、寺のような建物にかくまわれた巴は、彼等御庭番衆たちに布団に横になるように勧められた。巴は疲れていたので、布団に入ったが、自分ばかりが縁を置いて休むのが悲しくなり、枕を涙で濡らした。御庭番衆の者達は、すぐに退出し、巴が泣いているのに気づいた者はいなかった。
ただ、部屋の上がりかまちでこのような会話が交わされていた。
「蒼紫、どうして回光院に連れて来なかったのだ?幕府の役人が待ち構えていたのに。」
「手間取りまして。弟を拉致されました。女も怪我を負い、疲れております。」
「なるほどな。それは失態というわけだ。しかしわしの命令を勝手に変えるとは何事じゃ。上様にご報告したい事柄があったのに、これではまた一から振り出しに戻りそうじゃ。女の身のあらためは明日にでもするとしよう。」
老人と蒼紫の短い会話───それは、すぐに廊下を歩いていく足音とともに遠ざかった。
───寂庵さんではないわ。誰だろう?あの声は・・・・・。
それが、後に先代御頭と呼ばれる人物の声だと知ったのは、巴はもっと後のことであった。
───縁、無事でいて・・・・お願い・・・・!
巴はただ今は、一人で泣くよりほかなかった。
挽歌
巴が小早川の療養所に世話になっていた頃―――。
縁は、千住の近くの古寺の境内にある松の樹の幹に、縄でくくりつけられていた。彼をさらって来たのは、油櫛蝋外と言い、片目の男である。今、その横にはあの、蒼紫と戦った女忍者の葉霞と、あともう一人、酒禍上朱膳という男がいた。総髪の背の高い男で、長い大刀を腰に挿していた。
縁は泣き叫んでいた。
「はなせーっ、はなせーっ、この野郎!はなしやがれーっ」
「よくしゃべる小僧だな。」
朱膳は、うんざりした調子で葉霞に言った。
葉霞は、腰の刀を引き抜き、縁の頬にぺたりと押し付けた。
縁は刀にびくりとし、静かになった。
葉霞は面白そうに言った。
「ねえさんを取り戻したいかい?」
「おまえらが、ここに連れてこなければ、俺はねえちゃんと・・・。」
「はっ、そう思うだろうねぇ。いいかい、私たちはおまえのためを思って、ここに連れてきたんだよ?」
縁は言った。
「だったらこの縄を解けよ!なんでおまえら、俺を縛るんだよ。」
「仕方がないだろう?そうでないと、おまえは逃げてしまうからね。いいかい。ねえさんは、幕府に狙われているんだ。あたしたちは、それを阻止するべく立ち回っているんだよ?ま、おまえに言ってもわからないだろうがね。」
葉霞はそう言うと、忍者服の中から小さい緑の光る破片を取り出した。
「おまえはこれを見たことはないかい?」
縁は目をぱちくりさせた。やはり子供である、誘導尋問を受けているとは思っていない。尋ねられるまま縁は口にした。
「ねえちゃんの持っていた石と似てるな・・・。なんだそんなもん。」
「おまえのねえさんは、これを持っているんだね。それだけ聞けば十分さ。ま、油櫛さまが、おまえしかさらえなかったのは、残念至極と言ったところかね。」
油櫛は言った。
「おいおい。俺が来なけりゃこのふたりはそのまま、幕府の役人に面通しされているところだったんだぜ。」
「それは困るからね・・・・。そこはダンナの働きがあってこそ。ただ、女を連れてこられなかったのは、本当に残念だ。」
それまで黙って聞いていた、朱膳が横合いから言った。
「それはしまっておけ。大切なかけらだ。藩のやつらがそのような品を隠れて作っていたという証拠の品だからな?」
「そうね。」
葉霞はそう言うと、石を元通りのところにしまった。
油櫛は縁に言った。
「小僧、何か剣を使えるのか?」
縁は答えた。
「す、少しなら・・・・。」
「だったら、幕府の役人どもからねえさんを盗みだせ。今おまえのねえさんは、御庭番衆に囲われている。」
「御庭番衆?」
「幕府直属の忍者集団だ。」
「おまえはちがうのか?」
「ちがうとも。ま、関係はしているがな。では縄を切ってやる代わりに、俺たちの言うことを聞け。悪いようにはせん。」
縁は迷った。この者たちの気配には邪悪なものを感じる・・・・しかし、姉の巴の消息は、この者らに尋ねるほかないそうだ。しかも姉の持つ石が関係しているのだという。縁は答えた。
「わかった・・・・・俺、おまえらの言うことを聞く。ただし、ねえちゃんをどうこうしようっていうんなら、貴様たちを容赦しないぞ。」
「ははは、威勢がいいことだな。」
縁は自分が完全に子供扱いされていると思った。しかし、朱膳らは縄を切ってくれた。
「さて・・・・・おまえ、連絡係はできるかい?剣は使えないようだが。」
葉霞はにやりと笑って言った。
縁は答えた。
「うん。」
「じゃあしばらくは、この寺にいな。そのうち、用があるならおまえを呼び出す。勝手に逃げようなんて算段はしないことだね。麗月。」
葉霞が呼ぶと、松の上からひらりと黒い影が降り立った。
「お呼びですか。」
縁の前に、忍び装束の女が一人立っていた。
「おまえ、この小僧の見張りを頼むよ。私たちは、ちょいと野暮用があるんでね。」
「承知しました。」
葉霞、油櫛、朱膳の三人は、縁からはなれて寺の山門から出て行った。
縁は自分も出て行こうとしたが、すぐに麗月の手裏剣にさえぎられた。
麗月は言った。
「ぼうず、おとなしくしていないと命の補償はないよ?」
縁は唇をかみ締め、麗月に従って寺の建物の中に入った。
そのころ、巴は小早川から江戸城近くの御庭番衆の番舎のほうに居を移されていた。小さな中庭がある、小ぢんまりとした邸宅である。真ん中に何部屋かの道場と茶室を備えている。巴はそこの、奥の間に通されていたが、縁についての質問には誰一人として答える者はなかった。ただ、彼女を救出した般若や癋見、猩猩たちとは、剣の練習をするように言い付かったので、打ち合いの練習はしている。蒼紫は姿を見せなかった。そして、あの声の老人も同様だ。ただ、寂庵は巴の身を心配してくれていた。今日も稽古場に彼は来ていた。しかし寂庵は稽古はつけなかった。自分があれほどの手錬であるのを、寂庵はどうもいいものと思ってはいないようなのだった。巴の稽古についても、眉をひそめた顔で見物していた。
「寂庵さん。」
巴は着物の袂を直しながら、見ている寂庵に言った。
「寂庵さんは、稽古はつけてくださらないのですか?」
「ああ・・・・あんたはそこそこ腕が立つからな。それより・・・・。○○藩にいたという話は本当かね?」
「ええ・・・・江戸に来る前にはその藩にいました。父は最初は瑠璃波硝子の職人の仕事をしていました。」
「その硝子の破片か。あんた、それは大切にしまっておいたほうがいい。」
「はい。」
巴は本当は縁の消息を知りたいのである。じりじりと焦がれるようなその思いがあるのを、じっと耐えて御庭番衆の言うままに道場で修練に励んでいるのだった。きっとなんとかしてくれるはずだ、と巴は思っている。私を救いに来た人たちなのだからというのが、その理由なのだが。
寂庵は道場の板敷きのへりに座って言った。巴もそこに腰をおろした。寂庵は尋ねた。
「婚約者の清里明良とは、そのころからの幼馴染かね?」
「はい・・・・彼とは江戸に来た時に知り合いました。いい人でした。」
「いい人か・・・・。で、あんたはその仇を討とうとしている。」
「違います。私は幕府の役人に言われて・・・・奉行所の方たちでしたが。偵察を働くように言われたのです。」
「うん。じゃがこの御庭番衆の御頭も、あんたを勘定方に突き出すつもりでいたんじゃよ。」
「どうして今は、この館に?」
「その、硝子石じゃな。あんたは持ってないことになっとる。わしがそう言えと蒼紫に言った。」
「蒼紫?」
「若頭じゃよ。あんたはそんな硝子石は持っていないことになっとる。」
巴はびっくりした。
「では、絶対に私はこれを持っていることを、誰にも見せてはならないのですね?」
「そうじゃな。そうしないといけないじゃろう。」
寂庵はそういうと、目をしばたかせた。
「その硝子石は自然に光るのじゃろう?」
「はい。仕組みについては知りませんが・・・。」
寂庵は大きくため息をついた。
「それをアメリカに輸出しようとしたやつがおるんじゃ。失敗したがの。その硝子を吹き硝子で作る際には、鉱毒が体内にたまるんじゃよ。恐ろしい光じゃ。それで精錬所は荒れた。最後には放棄され、関係者は放遂された。あんたの親父さんはその一人じゃよ、おそらくな。」
巴は目を丸くした。
「そんなことをどうしてあなたさまが?」
「わしは幕府の蘭学所に勤めていたこともあるんじゃよ。そこでも研究されていた・・・・洋物の事物でらんぷがあるじゃろう?あの代わりにならんかと言うてな・・・・・。」
「はい。」
それは巴にもかすかに思うことがあった。いなくなった父の研究。母は、自分を連れて雪山の峠を越えていった。幼い頃のその記憶────。
「それで父は・・・・海の向こうに旅立ったのでしょうか・・・。」
巴はやっとのことでそれだけ言った。寂庵は答えた。
「いなくなったあなたの父君の消息か。それは残念ながら、わしにはわからん。ただ・・・・あんたのことだが、それが関係して今この屋敷にかくまうことにしている。いずれあんたは、東北にでも弟と旅立たせるつもりじゃ。」
巴ははっとしたが、勤めて冷静に言った。
「北に逃げるのですか。」
「そうじゃな。芭蕉のたどった道じゃ。あんたには気の毒じゃが・・・・・。その○○藩がその硝子を作っていたという確証が幕府は欲しいんじゃよ。ご禁制の品じゃからな。そして、幕府もその研究を再開したいと思っている。欧米に高く売れるのが、先ほどの黒船の騒ぎでわかったからな。あちらの国ではその硝子製品の愛好家が結構いるそうなんじゃ。だから、あんたのその破片だけでも、幕府には重要なものなのじゃよ。」
「そうですか・・・。」
と、そこへ式尉がやって来た。
「おお、式尉、おまえも一言言ってやりなさい。おまえが薩摩藩からこの御庭番衆になったいきさつじゃろ。」
式尉は鷹揚に答えた。
「ああ・・・・・あの幕府ご禁制の硝子食器ですね。」
「そうじゃ。薩摩切子というと、薩摩藩の独檀場だからのう。おまえさんもそれを探るために、江戸城に忍びこんだんじゃろう。薩摩藩では密貿易で、たくさん切子を輸出していたからの。」
「ええ、そうです。若頭に倒された時もそれをさぐっていたんです。あんたもその縁者だから、若頭に助けるように言われたんで、あの場にいたんですよ。」
巴はやっと光明が見えてきた気がした。ただ、ひとつ気になることがあった。巴は尋ねた。
「夫になるはずだった清里ですけど・・・・まさかそれに関係して京で斬られたのでしょうか。」
「それはわからんよ。」
寂庵は言った。
「ただおまえさん、その破片を持っていて、しかも清里殿の仇という負い目があるのを、幕府が見過ごすとは思えん。あんたに何かをやらせるかも知れん。わしたちは、それを阻止したいのじゃ。あんたには自由にこの地から離れてほしいんじゃ。」
「お話、わかります。私もそうしたいのです。ですから、弟の消息を早く───。」
巴がそう言った時だった。
「その硝子石だが、俺に預からせてくれないか。」
声に巴ははっとした。蒼紫がいつの間にか、彼等の座っている板敷きの隅に立っていた。
巴は蒼紫に会って以来、その顔を見るとドキリすることが多かった。彼は、思いたくないが背格好や顔立ちが亡くなった清里に少し似ているのである。清里よりも頭ひとつ高いのが蒼紫であった。そして、清里は蒼紫ほど陰気で美形な青年ではなかった。
──不埒な・・・・。
巴はそんな自分を、心の中で責めていた。ただ、蒼紫に橋げたの下で助けてもらったことは、今でもはっきりと巴は覚えている。まさに巴からすれば神業のようであった。橋の上の男の投げた縄は、縁だけでなく巴にも巻きつこうとしていたのである。その一瞬の間隙を抜いて、蒼紫は巴をさらったのである。蒼紫の失態とこの寂庵は憤ったが、巴にしてみれば、それだけの働きをしてくれた蒼紫という人は、命の恩人に間違いなかったのである。
巴は少し頬を赤らめながら、蒼紫に石の入ったぽち袋を胸から出して差し出した。藍色の布地に、刺し子で花の模様が細かく入っている。口には赤い縄編みの紐と鈴がひとふりついていた。どこから見ても、ただの子供のお守りのようなものであったが、蒼紫は一瞬目を見張るようにした。彼はその何の変哲もない袋に、何か見覚えがあったようなのである。しかし蒼紫は無言で受け取った。中を蒼紫はあらためた。緑の硝子の破片が出てきた。
蒼紫は日にかざしてみたが、昼間の光では発光などしない。可憐な小さな葡萄の房と人の脚が、文様で浮き上がっていた。何かの瓶の破片のようであった。
さらに袋を振ってみると、中から鉄錆びの浮いた鍵がひとつ出てきた。
「葡萄の模様か。海外への輸出品かのう。それとその鍵は、大切なものみたいじゃの。」
寂庵が横あいから言った。
「奉行所ではこれのことは聞かれなかったそうじゃな。」
「はい。たぶん、知らなかったのだと思います。」
「うむ。ま、そうかも知れんがな。やつらの腹の底はわからんからな。」
寂庵はそううなった。蒼紫は冷静に言った。
「たぶん研究した書類入れなどの鍵だろう。持っているだけでも危ないものだ。」
蒼紫はそう答えると、それを服の中にしまった。
「確かに預かっておく。」
「はい。」
「いずれ必ずあなたに返す。今は危険だ。」
蒼紫はそう言うと、向こうに行ってしまった。
巴は口の中で「あ」と言ったが、元来声の小さい巴の声は、蒼紫には聞えなかったようだ。
「あの方が若頭・・・・というのですか。」
巴はしばらくして寂庵に聞くと、寂庵は顔をほころばせた。
「名を四乃森蒼紫と言うてな、少々暗い男じゃが、あれは誠実な男じゃ。心配めさるな。ここにいる、若頭付きの下働きは、みんなあの男の味方じゃよ。」
「そう・・・・ですか。」
巴は少しはにかんだ表情になった。蒼紫と自分をつなぐものができたのが、彼女はうれしかったのである。
──―清里の時はこんな風に思ったことはなかったのに。遺品のかんざしをもらった時も・・・・。
そう思うと、自分の心の動きが巴はよくないと思うのだった。あの遺品をもらった時、どうしてうれしいと顔に出さなかったのだろう。ただ、「ありがとうございます」と目を丸くだけしたのだろう。
──それは、私が清里を愛していなかったから。
と思うのが、巴はとてもつらい。もしそうだとすれば、自分は人非人だと思う。自分が冷たい心の持ち主だと思うのが悲しい。しかし、巴の心は波立たなかったのは事実だった。そして、今蒼紫には心がさざなみ立つのであった。
寂庵はそうした巴の気持ちがわかるのか、一句芭蕉の句を読み上げた。
「『かさねとは 八重撫子の名なるべし』 ───じゃな。おっとこれは弟子の曾良の句じゃ。芭蕉は───『しばらくは 滝にこもるや 夏の初め』 ───じゃな。あんたもしばらくはここで休んでおりなさい。上のほうの騒動が静まってから、弟と一緒にこっそり旅に出ればいい。これも宿世の縁と思ってな。」
「はい・・・。」
巴は寂庵の心遣いが身にしみてうれしいと思った。
巴はその夜、床についていた。なかなかその夜は寝付かれなかった。寂庵の言った父の仕事、そして母の形見を蒼紫に預けてしまったこと・・・・・それらが巴の心をちりちりと焦がし、揺さぶり続けた。やはり蒼紫に渡すべきではなかったのではないか?自分は軽はずみなことをしてしまったのではないか・・・・・。いや、蒼紫は信用できる人物なのだ。しかしそれは考えてみれば、寂庵から言われたセリフだけにすぎない。
不安から巴は起き上がった。巴は体はあまり丈夫なほうではなく、よく生理痛に苦しめられることがあった。その日はたまたま、その日であった。夜中に布団から起き上がり、手許の燭台に火をつけると、巴は武家屋敷の廊下を静かに歩き出した。庭が見渡せる廊下まで出たときだった。
「ねぇちゃん、ねぇちゃん。」
庭の木々の間から、縁のかぼそい声がした。あやうく燭台を巴は取り落とすところだった。
「縁!どうしてここが?」
縁が駆け寄ってくるのを、巴は抱きとめた。
縁はうれしそうに言った。
「もう大丈夫だよ。俺があいつらに言ったんだ。ねえちゃんは、証拠の品を持ってるって。それで出るところへ出れば、ねぇちゃんと婚約したから清里さんが殺されたというのは嘘だって、奉行所に言えば納得してくれるって──。」
「縁・・・・。こちらへ来なさい。」
巴はあわてて、縁を廊下の隅へと導いた。
そこで巴は諭すように言った。
「あなたは敵の手から逃げてきたんでしょう?あの人たちは悪い人だと思うの。」
「だって、そう言ったんだぜ、その、葉霞さんが・・・・・。」
「葉霞さん?」
「そうだよ。すごく強い女忍者さ。なんでも知っているんだよ。その人が俺にそう言ったんだ。葉霞さんは、こっちの御頭に率いられたやつらのことも知っていてさ。若頭の蒼紫って野郎がねぇちゃんを以前に見ていたことがあるって言ったんだ。ねぇちゃんは、そいつに以前から狙われていて、今だまされてるよ。」
「どういうことなの?」
「葉霞さんは、その、若頭と寝たことがあるって言ってた・・・・どういう意味かな?俺よくわかんないけど・・・・。知ってるって。」
「縁、黙りなさい。」
巴はそこまで聞くと、縁に厳しく言った。
「蒼紫さんたちは、いい人たちです。あなたも助けようとしていたのですよ。」
縁は駄々っ子のように言い返した。
「そんなはずねぇよ!ねぇちゃんが、奉行所の命令で吉原で働いていたのを、邪魔しに来たんじゃねぇか。」
「縁、そうではなかったでしょう。一体あなたは何を言ってるの?」
巴は唇をかんだ。縁はどうやら、葉霞という名前の女忍者に手なずけられたみたいなのだ。しかも縁の話では、その葉霞という女は蒼紫とそういう仲みたいなのだ。巴はふらり、と目がくらんだ。何故蒼紫を信じようと思ったのだろう、と思った。しかも硝子石は今、蒼紫の手の内にある。巴は念のために尋ねた。
「縁、証拠の品というのは、その、緑色の光る硝子のことですか?」
「うん、そうだよ。それさえあれば、許してもらえるって。」
「今、私の手許にはありません。」
「ええっ、なんでだよ。」
「蒼紫さまに預けました。」
「えっ・・・・・なんだって?なんでそんなやつに渡したんだよ。あれかあさんたちの形見なんだぞ!」
「わかってる・・・・わかってるわ縁。でも、これには事情があるの。」
と、そこまで巴が言ったときだった。
「女、説明ご苦労さまだな。私たちと一緒に来てもらおうか。」
と、声がして、黒い影が数名庭に降り立った。
笹葉霞の配下の者たちだった。そしてその中心に、葉霞が立っていた。
「上役の頭の固い連中を、説得するのには骨が折れたよ。あんたさえこちらの物になればいいのにさ。この・・・私の持っている硝子の破片と対になっているあんたの物、それが必要なだけさ。」
巴は目を見張った。女は漆黒のつややかな長い髪をしていて、冷ややかな光を目に宿していた。
「あなたが、葉霞・・・・・。」
「そうだよ。あんた、婚約者が死んだのはみんなあんたのせいさ。ま、長州の男に斬らせたんだがね。幕府が。」
「そんな!」
「まわりくどいやり方をするのが幕府のお役人たち・・・・あんたも覚えておくんだね!さあ、こちらに来るんだよ。弟の命が惜しければ・・・・。あんた自身の命もだ。」
巴は縁をかばうようにして、縁におおいかぶさった。
「弟と私をどうする気なのです?」
葉霞は笑って言った。
「出るところに出たら、後は用済み・・・。というか、あんたたちがそのままで生きていたら困るのさ・・・・・○○藩と幕府がその、裏で協力して光る硝子を作っていたとわかれば、薩摩がだまってはいないのさ。倒幕のための証拠品がひとつそろうことになるんだからねぇ・・・・。そうだろう、朱膳の旦那?」
「ああそうだな。」
今度は木陰から、一人背の高い男が出てきた。手には長刀を手にしている。葉霞は朱膳に言った。
「まだ殺すんじゃないよ。縁、ねえさんをうまくおびきだしたじゃないか。誉めてやるよ。ま、その働きさえあれば、私たちとうまくやっていけるかねぇ。女、素直になるんだ。」
巴は叫んだ。
「いっ、嫌です。あなたたちには絶対に渡しませんから。その硝子石を使って、また悪事を働くんでしょう?」
葉霞は答えた。
「悪事だって?私たちは、あんたたちを幕府の追及から救ってやろうとしているのがわかんないのかい?」
「まったくバカな女だ。」
横に立つ朱膳も笑って言った。しかし巴にはわかっていた。この者らにあの石を渡せば、寂庵の言うように、この危険な硝子を誰かが製造するのを再開するはずなのである。それはいけないと巴にはわかっていた。その話をしたときの寂庵は本当につらそうであった。また、蒼紫も「危険だ」と言ったのはそれに違いなかったのである。
──でも、大丈夫。私はどうなっても、あの硝子石は蒼紫様が持っておられます。
巴はそう思った。
「弟を返していただきます!」
巴はそう一声言うと、縁の手を引いて屋内へとだっ、と駆け出した。
「ちっ、追うんだっ。この屋敷の中を、あたしたちが知らないとお思いかい?」
葉霞はそうどなると、腰の刀を引き抜いた。しかしその瞬間───。
苦無が三連、葉霞の頬の横すれすれに飛んで木の幹につき立った。
「──蒼紫っ。」
葉霞は叫んだ。
「そこかいっ。」
葉霞はあやうく剣を交差させた。蒼紫が二刀を手に向かってきたのだった。
「やはりあの女が大事なのかいっ。」
激しい斬り合いが起こった。その間にも葉霞の手下の麗月たちが、屋敷の中に入っていく。そこへ蒼紫側の般若と式尉たちが、それぞれの武器で立ちはだかった。
「癋見に猩々、巴と弟を確保しろ。」
蒼紫が葉霞と渡り合いながら、癋見に言った。
「ひぇっ、わかりましてでござる。」
あわてて答えた癋見と猩々は屋敷の奥の襖を蹴破った。巴たちはその間、座敷の中庭の隅に息をひそんで隠れていた。
「あそこだ!」
猩々が言うより先に、葉霞の手下の者の三人が巴たちを取り囲んだ。
「さて、女ども、私がその女に引導でも渡してやるかな。」
剣を抜いた朱膳が、女たちの輪の中心にいる巴に近づいていた。朱膳は言った。
「圧倒的不利じゃないか。割り印の鉱石は持っているんだろうな、女?」
巴は縁を抱きかかえて守りながら、朱膳に答えた。
「知りません。あなたに渡す物は、わたしにはありません。」
「ほう。殊勝な物言いだ。○○藩の幕府よりの朱印状を隠している金庫の鍵、貴様は持っているはずだが・・・・。」
「・・・・・・・・。」
巴は無言で相手を見ている。庭のほうで蒼紫が葉霞と渡り合っている。わたしも何かしなければ、と巴は思うのだが、縁を守ってかばっている今、それは不可能である。このまま私はこの男に斬られるのだろうか───。でも縁を守れば本望だ。巴はそう思った。───その時。
「貴様ら、我が屋敷を何と心得る。やりたい放題、許すべきものにあらず──。」
巴ははっとなった。老人の声だった。しかし、その声は冷たいものであった。次の瞬間、朱膳の体は巴の前からぱっと後ずさった。
あやういところで、朱膳は老人の高速で走る剣から、からくも退いたのである。葉霞もはっとなった。
「御庭番衆御頭っ。まさか。」
蒼紫と斬り合いをしていたところを、葉霞も退いた。老人は言った。
「そのまさかじゃ。その方ら、神妙にいたせ。さて蒼紫、お前のその様はなんじゃ。これはどうしたことかな。」
老人は黒衣の忍び服から巴の香袋を取り出した。巴は驚いた。蒼紫に渡したはずのものは、この御庭番衆御頭と呼ばれる老人の手に、何時の間にか渡っていたのだった。
「貴様らこれが欲しいのであろう。渡さぬ。今は見逃してやる。去れ。」
御頭の老人はそう言った。蒼紫は目を見張った。
──「去れ」、だと。
それは断じて受け入れられない命令であった。蒼紫はこの、葉霞たちの攻撃については予測していたし、彼等を一網打尽にするつもりで屋敷の中で潜伏し篭城していたつもりだったのである。しかし先代と後ほど呼ばれたこの老人は、何もかも蒼紫の予定を今覆してしまったのだ。
蒼紫が見ているが早いか、葉霞たちは老人の指揮で殺到してくる御庭番衆の雑兵らを尻目に、屋敷からさっと逃げ出した。
「老人、甘いな。」
とだけ、葉霞は言ったが、それも彼女の口元を隠した覆面にさえぎられて、聞えるか聞えないかの声であった。
老人は葉霞らが去るのを見届けると、蒼紫に向き合って言った。
「さて・・・・蒼紫。貴様には言いたいことがわしにはたくさんあるのだが・・・・その女を見張れと言ったわしの言葉も貴様には伝わらなかったようじゃな。この石はしかし、今貴様に渡す。」
「御頭!」
と、老人の脇にいる忍びの男が声を荒げた。しかし老人は続けて言った。
「わしが貴様に命じてやる。貴様にとっては喜ばしいことであろうな。やつらの巣を突き止めた。中山道にある山の峰にある。そこまでその女とともに、やつらを追え。そして証拠の品を持って帰れ。貴様の部下をつけてやる。万が一にもしくじった時には貴様の命はないものと思え。雪代巴。」
巴は呼ばれてこわばった。
「は・・・・はい・・・・。」
「貴様は蒼紫とともに行くのじゃ。元はといえば、貴様の父が犯した誤りじゃからな。その責任を取ってもらう。貴様には働いてもらうことは、他にもたくさんあるからな。」
巴はこの時、その道中がどういうものであるかは想像できなかったので、蒼紫とともに行くことができるのはかえって僥倖であると思った。それでどきりとしながらも、顔は平静に保って答えた。
「はい。」
巴が気丈に答えたのにも、老人は何とも思わなかったようだ。
──この方のお心は、目には読めない・・・・・。
巴はそう思った。冷たい感情の読めない灰色の目であった。老人は言った。
「支度をしろ。明朝にはこの屋敷を立て。宿はかねての手はずのところに取れ。連中は貴様らの邪魔をするだろうが、おいおい倒していくのじゃな。では。」
老人はそう告げると、忍びの者らに「解散」と告げ、奥の間に消えた。
蒼紫らの組の者は老人たちが消えると、寄り集まった。般若は蒼紫に向かって言った。
「若!これははめられましたぞ。」
般若は言った。
「我々のことは、邪魔になったのです。だから、我々だけで街道を下るように言われた。これは罠です。」
蒼紫は答えた。
「言うな般若。行くしかあるまい。」
「その女子供も連れてですか?大変な旅になりますぞ。」
「もとより承知だ。」
「この屋敷でやつらを討ち取って、その姉弟を逃がす手はずが・・・・。」
般若の言葉に、蒼紫は口元まで出かけた言葉を飲み込んだ。籠城策を取ったのは、ひとえに巴たちが忍びとして動けないからであった。しかしそれを彼は口にしたくなかった。ひたすら自分が甘かったのだと、忸怩たる思いであった。
般若と蒼紫の会話を聞いて不安になった巴たちに、寂庵が声をかけた。
「なに、うまくいけばおまえさんがたは、途中で逃げればいいんじゃ。そうなるよ、きっとな。」
巴は無言でうなずいたが、それはできないこととも思っていた。
父の話、あの鉱石の話を聞かされた今、自分は責任を取らなければならないと彼女は気丈にも思い込んでいたのである。
そして、縁は黙っていたが、この場のやりとりを聞いて、何故姉はここから逃げ出さないのであろうかと思い、幼いながらもその不満心を心に渦巻かせていた。彼にとっては姉が蒼紫の言うことを唯諾々と聞いている理由は、「それ」しか思い当たらなかった。姉は、どうやらこの蒼紫という男がたいそう気になっている様子なのである。
──今だってまた失敗しやがったのに。こんなやつ。
と、縁は思っていた。だいたい今も、あのいかめしい老人に、硝子石の袋を掏り取られていたのだ。
──間抜け。それにこの寂庵さんて年寄りも、調子のいいことしか言わないじゃないか。
縁はそう思った。そして、蒼紫らと一緒に行くのはご免だと思ったのだった。
しかし縁はそれらのことを見誤っていたのである。
寂庵は巴らを寝床に促したあと、血のりの落ちた月の照らす部屋を見ながらぽつりと一人ごちた。
「無残やな、兜の下のきりぎりす・・・。蒼紫殿、こたびの旅はあなたにとって、その生涯を決める旅になるやも知れぬ・・・・己のこともまた、己にはわからぬもの・・・・。」
寂庵はもちろん、彼等の旅に先代の追っ手と監視がつくことを考えていた。そして、蒼紫の本当の胸の内も、彼にはわかっていたのである。
道行
蒼紫はまだ髷を結った年若いいでたちで、ある山の峠近くの薄暗い小屋の中で、先代と後に呼ばれることになる老人と囲炉裏の火にあたっている。外は吹雪である。不意に、小屋の戸が風ではなく、はたはたと鳴った。
「あけてあげなさい。」と、先代が言うのに、蒼紫は戸のつっかい棒をはずした。
粉雪の風とともに、二人の親子連れが小屋の中に入ってきた。
菅傘をかぶった、旅装束の母親と娘だ。ひどく疲れている様子だった。蒼紫は戸をすぐに閉めた。
「火のそばに来なさい。」と、先代は二人に言った。
「はい。お世話になります。」
母親は頭を下げた。傘をはずしたところを見ると、品のある顔立ちの婦人と娘だった。
蒼紫はその様を見て、武家の出であろうと検討をつけた。しかし、華美とは程遠い装いの二人だった。下級武士の家の者なのだろう。先代は言った。
「その子はだいぶ疲れているようだ。蒼紫、水を飲ませてあげなさい。」
蒼紫はうなずくと、腰にぶらさげた竹筒の口をはずして、娘にさしかけた。
母親は「すみません」と言うと、筒を取って娘の口元に持っていった。
しかし娘はごほごほと咳き込んで、水を飲もうとしない。先代は蒼紫に命じた。
「熱があるようだ。丸薬を。」
「はい。」
蒼紫は今度はふところの丸薬の入った袋から、熱さましの薬を取り出して母親に渡した。母親はまた頭を下げた。
「まあ、すみません。こんなにもお世話をしていただいて。」
先代は目を細めた。
「何事でもありませぬ。それより、みどもは脱藩ですか。」
母親ははっ、と顔を青ざめさせて言った。
「いえ、違います。私どもはこれから江戸に帰る途中でございます。」
蒼紫はその頃は江戸から離れていたので、江戸に帰るこの親子を懐かしく思った。
そして熱があるらしい娘の様子をうかがった。
黒髪を短く切ったその顔は、たいそう愛らしい娘だった。蒼紫がその頃見たどの娘よりも色が白い。そして、蒼紫のほうを見て「ありがとう・・・・。」と一言返事をしたそのさまは、本当にかわいいものだった。
しかし、自分はこの娘のことを忘れてしまうのだろうな、と思った。と、その時───娘が母親の手を引いて言った。
「あの硝子の細工を、父さまによく見せてあげてください・・・・。」
「ここにおられる方は、父上ではありませんよ。」
「母さま、お願い・・・。」
蒼紫は父親と間違えられているのだ、とは思っていたが、母親が娘の言葉に取り出した袋から出た代物で、その記憶は決定的なものになった。
緑色に光っていたその硝子は───。
「これで気がすみましたか。」
娘は小さくうなずいた。そしてかすれ声でつぶやいた。
「父さま、勝手におもちゃにして持ち出して遊んで、ごめんなさい・・・・。だから早く帰ってきてね・・・。」
「熱が高いのね・・・・。」
母親は小声でそう言うと、すぐに硝子のかけらを元にもどしたが───。
そして先代はなぜ「脱藩ですか。」と声をかけたのか。そしてその娘が巴だとしたら、縁は何故いないのか。まだ生まれていなかったということなのか・・・・。
はっ、と蒼紫は目を覚ました。
今彼らは中山道のはじめの宿場、武州街道の蕨あたりを歩いているところだ。彼がいるのは、その旅籠の二階である。まだ今は平和な道行だった。巴は下の間で弟の縁と休んでいる。もちろん、彼ら御庭番衆は地味な庭師のいでたちで街道を歩いており、旅の目的も伊勢講に出席するためというふれこみである。次の宿場町まではいよいよ上州の山の中だった。彼らを追う葉霞たちはまだ街道筋には現れてはいない。
「若、おはようございます。」
般若が蒼紫のいる部屋にやって来た。例の般若の面はつけたままである。般若の面は見た者のだれもが不気味に思ういでたちだが、狼藉者がこのような歌舞いた面をつけているのは江戸ではよくある事であり、般若もそういうつもりで面をつけている。この般若を思ってか、猩々も同じように能の面をつけている。猩々緋の面だ。山猿に似ている自分を揶揄しての行為であろう。
彼ら御庭番衆はそういう風に、自分を演出するのは得意であるが、そのことについてお互いに問答することはなかった。特に蒼紫の元に集まった者らはそのような個人主義者が多かった。蒼紫自身がそういう性格なのも影響しているのであろう。
般若は言った。
「あの娘を単独で見張れと頭目(先代のこと)から命じられてから半月。このような妙な事態になるとは思いもよりませんでしたな。」
蒼紫は答えた。
「瑠璃波硝子が上様が最近ご執心であるとのことで命じられたことだが、本当はそうではないだろう。あの娘がいた藩の醜聞の後始末ということだな。しかし、目的の峠でその朱印状を見つける前に、あの二人はすみやかに逃がす手はずを取れ。御庭番衆とかかわりがあったということも、すべて消すのだ。」
般若は黙って聞いていたが、少ししてぽつりと言った。
「残念なことですな。」
「何がだ。」
「若にしては江戸にいた頃、熱心にあの娘が婚約者と往来に出るのを、忍んで観察しておられた。確か車夫に化けて往来で見ておられました。今も行動をともにしているのは、願ったりかなったりではないかと。」
「貴様も頭目と同じ物言いをするのか。」
般若は少しおっくうな姿勢になった。そしてあわてて取り繕うように言った。
「何も、私はただ、蒼紫様が普通の人間らしく見えるので、よいと思って言ったまでです・・・・。」
蒼紫は般若に取り合わず、話題を変えた。
「ところで、葉霞たちのほかに、誰が追手になるかわかるか。」
般若は驚いた。そして、やはりそこまで考える蒼紫を頼もしく思った。般若は答えた。
「さあ・・・・真田の里はここから近いですがな。真田忍軍やもしれませぬな。」
「そんなやつらは来ないだろう。おそらく西の御庭番衆だな。」
「翁のところですか。」
「翁は動かん。しかし巴は翁のいる京都に連れ去られる可能性が高い。用心しないといけないだろう。」
「では・・・。」
「巴を連れ去るのは、『闇乃武』だ。」
般若はひやりとした。こういう時の蒼紫は問答無用である。蒼紫は続けた。
「頭目の西の遠征部隊のひとつだ。われらの任務とは別に、巴はやつらに京都に間者として送り込まれるはずだ。それを阻止せねばな。そして───われらとはかかわりのない土地で、この幕府の始末事にもかかわらずに静かに暮らせるようにしてやらねばならん。」
「御意。」
般若は思った。蒼紫は頭目とこのような熾烈な争いを水面下で続けている。これでは蒼紫の身の上は本当に心元ない。しかし自分は蒼紫に大恩のある身の上、背くわけにはいかない。今回のことも、長年蓄積された二人の間の軋轢が生んだことだ。巴はその発端にすぎない、と。
「今日は幸い、いい天気でございますな。この先の横川の関所と碓氷越えは、のんびりと行きたいものです。」
般若は蒼紫の意気込みをそらすように、わざと天気の話題をふった。蒼紫は答えずに部屋を後にした。
蒼紫たち一行は、秋の気配のする街道筋を西に下っていた。宿を下向し、いよいよ関所が近づいてきている。巴と縁を中に入れて、一向は縦一列で歩いている。
巴は関に入る時は緊張した。江戸に入る者、出る者を厳しく吟味する場所だ。彼らは御庭番衆を名乗ってはいないし、関所に出す鑑札も去る筋から渡された「偽物」である。身分や出身は江戸の下町の町民と偽っている。ただ、なぜか巴たちの名前は「雪代」姓のままであった。
関では見事に変装した般若が、「伊勢講の集会に出席するために、中山道を名古屋に下りまする」と奉行に言った。かの源義経の故事のような所作をするわけでもなく、蒼紫らはそのままそこを通された。ただ、奉行は「雪代」という姓名を読み上げた時、少し片頬で笑ったようであった。巴はそれが気になった。
「なに、珍しい名前だから気になっただけであるが」とその中年の奉行は言った。
しかし特に怪しまれている様子ではなかった。奉行は笑顔で「では通られよ」と蒼紫らに申し渡した。関越えはあっけないものであった。
その日は晴天に恵まれていて、道中は葉霞らが仕掛けて来ない今は、山道ではあれ楽なものであった。自然、癋見や猩々などは私語が多くなった。彼らは巴らが気になって仕方がないのである。先を行く蒼紫と般若らは無言であったが。そしてしんがりを守って歩いているのが、式尉と火男であった。体格のいい彼らは、後を通る不審な者が前に行くのを防ぐ「栓」の役割を果たしていた。巴と縁は真ん中で、寂庵と猩々、癋見と歩いていた。
と、癋見が小声で巴に言った。それは先を行く蒼紫らが十分に彼らから離れているところを見計らってであった。
「ねぇねぇおねぇさん、若頭とお話した?」
巴は聞き返した。
「え・・・、なんでしょう?」
「だから蒼紫様と・・・なんにも話したことないの?」
猩々は横からしっ、と言った。
「馬鹿。そんな話すんじゃねぇよ。」
癋見は駄々っ子のように答えた。
「何が馬鹿だ。若頭はあの老御頭に言われて、三ヶ月の間毎朝あんたに見張ってたんだぜ。好きでもないのにそんなこと・・・。」
猩々はこれでなかなか少年なのにしっかりしていた。歩きながら彼は答えた。
「余計なこと言うんじゃねぇ、癋見。若が聞いたら気を悪くするだろ。」
巴は驚いた。三ヶ月と言うと、まだ清里が生きていたころである。
───そんな頃からあの方が私を。
何かドキリとするものがあった。しかし巴はまだ年若い乙女であったので、まずそのことを聞いて頬が赤くなった。彼女はつとめて平静に小声で答えた。
「私は知りませんでした・・・・。何か理由があったのでしょうか・・・・。」
癋見は得意げに言った。
「それはもちろん、あんたと若を仲良くするためさね。」
猩々はまさか、と鼻じろんだ顔になった。そして言った。
「まったくてめぇは頭に花が咲いてんな。あのじじぃが俺たちにそんな親切心でいるわけねぇだろ。俺たちに、瑠璃波硝子の件を押し付けたってぇのによ。」
癋見はそう聞くと、身を乗り出して言った。彼にとってはいい思いつきだったらしい。
「だからそこなんだよ、猩々。本当は好きなのに、別々に暮らしているだろ。その二人を結びつけるのはどうしたらいいか。それには一緒の道中だ。これから仲良くなって、そしてだな、この巴殿もわれら御庭番衆の一員となり、晴れて夫婦になる。こいつは万々歳ですよね。」
「おい。」
猩々が顎をしゃくった。前を歩いていた蒼紫が、眼光を光らせてこちらをにらんでいるのがわかったからだ。もちろん余計なことを癋見がしゃべったからだ。
「おっちょこちょいが。言っちゃならんことを、どうしててめぇは言うんだよ!」
言うなり、猩々は癋見に肘鉄を食らわした。
「痛い、痛いです猩々。なんか俺間違ってますか。」
「ああ、多いにな。」
後ろから式尉が引き取った。癋見は恥ずかしそうな態で頭をかいた。そして巴に言った。
「ごめんなさい、もう言いません。」
巴はしかし、癋見の気遣いがうれしくなり、「はい」と答えた。寂庵はため息をついて言った。
「やれやれ、何を言うのやらと思うたら・・・・。」
しかし癋見の言うのはあながち間違いではないと、寂庵はにらんでいたので、それ以上は言わなかった。老御頭はあきらかに、巴と蒼紫を接近させるように仕向けていたのだ。それは寂庵にとっては蒼紫を思うと、不安材料であった。
だが、癋見や猩々がそこまでわかるわけはない。
「けっ、おっちょこちょいが、そんなこと言ってるから若がてめぇを仲間の中で一番信用していないんだ。馬鹿。」
猩々はあきれたように言った。蒼紫はもう前を向いていた。
これを聞いてますます面白くない顔になっていったのは、巴の横を歩いている縁であった。彼は癋見を殺しそうな顔でにらんでいたし、蒼紫にも目を光らせていた。一見彼は素直に姉の手に引かれていたが、彼は巴の周りを囲んで歩いている男たちすべてが嫌いであった。
縁は実はわざと葉霞らが蒼紫ら一行に潜ませて送った、刺客とまではいかないが、そのような「者」であった。縁にさんざんいろいろなよからぬことを吹き込んで葉霞は彼を野に放った。彼女は縁の心を見抜いていた。必ずやほころびはこの子供から起こると彼女は計算していた。
今彼女たちは山越えの道の端に立っている。そこからは峠をのぼる街道を見晴らすことができる。蒼紫ら一行が通るのはもう間近であろう。関に偵察に出した霞衆の女どもの報告を聞き、葉霞はすらりと刃を抜き払って言った。
「ここで蒼紫を追い落とせないのは、恥ずかしいことさ・・・・・。」
葉霞はそう言うと、二人の女に言った。
「仕掛けるよ。まずあの後ろにいる金魚の糞どもを女からひきはがす。蒼紫と般若は私が殺る。おまえたちは背後からつくんだ。いいね。」
ぱっ、と女たち二人が木々を飛び退った。葉霞はもうひとりの女、麗月と蒼紫たちの前に木の上から躍り出た。蒼紫はしかしさほど驚いていなかった。葉霞は刀をかざして言った。
「どこに行くんだい、蒼紫?女を連れて物見遊山かい?いいご身分だねぇ、伊勢見物かい。その女、悪いがあたし達が用があるんだ。置いていってもらおう。」
蒼紫は答えた。
「・・・・・。どういう要件だ。」
「言うと思うのかい?あたしはね、あんたがわざわざ京にまで上る用をなくしてあげようとしているんだよ。」
「どういうことだ。」
「じゃあ言ってあげよう。その女は瑠璃波硝子の件で、さる筋から人相書きが出ている。それでおまえの御頭はおまえに見張るように言った。それは知らないだろう。」
蒼紫は無言だが、憮然としたおももちで葉霞の顔をにらんでいる。
後ろでやりとりを聞いていた巴は、不審に思った。先ほどの関では普通に通されたのだ。人相書きが出ている・・・・何かおかしい。
巴は横にいた寂庵に「どういうことでしょう。」と小声で尋ねた。寂庵はだまりこくっている。巴の横で猩々と式尉が刃を抜いた。
「・・・・裏筋だ。」
式尉がつぶやいた。巴は目を見張った。「でも」、と言いかけた巴を制して寂庵がつらそうに答えた。
「そうじゃな。おまえさんにすべての責を着せたい闇の勢力がいるということじゃな。」
「それは」と巴が言いかけた時、葉霞たちは斬り込んで来た。蒼紫は剣で受けた。葉霞は高笑いをしながら、蒼紫を追い詰めていった。葉霞は叫んだ。
「おまえは一生、あたしの下働きでよかったんだよ!それを、あのくそじじいがっ。」
くそじじいというのは、後に先代と呼ばれることになる爺だ。葉霞は蒼紫をあおった。
「じじいに目をかけられて、次期御頭かい?あたしたちを追い出して、さぞかし安泰なんだろうねぇ。おまえたちの組織は、あたしがつぶしてやる。あたしたちを追い出したことを、後悔させてやるっ。」
蒼紫は葉霞の剣を受けながら、山道を巴たちの方から離れるように進んでいる。葉霞を巴と縁から離そうとしているのだ。蒼紫は以前に霞衆と戦った時、女たちの剣さばきを体感していて、やはり一番の脅威は葉霞だけと認識している。寂庵はその様子を、やはり女たちの攻撃を剣で受けながら感づいていたが、「いかん。蒼紫。」と思い、叫んだ。
「蒼紫、罠じゃ!」
縁はこの様子を見ていて、巴の袖を引いた。他の御庭番衆たちも激しく女たちと戦っていて、突っ立っているだけでも危険だ。縁は言った。
「ねえちゃん、逃げよう。こいつらなんかほっといて。」
巴は「えっ。」となったが、「なりません。」と厳しく答えた。
「私も戦います。」
そう言って、巴は懐刀に手をかけた。
「だめだよ、ねぇちゃん。」
「でも。」
巴から一間ほど離れた場所で、火男と式尉が霞衆の女たちと戦っていた。火男は火炎を吐いて、巴たちに女たちを近づけまいとしていたが、女の一人が鎖分銅で火男の首に攻撃を仕掛けた。火首は声をあげてどうと倒れた。癋見がそこへすかさず螺旋鋲を放った。
「てめぇっ」
猩々と癋見が、素早く螺旋鋲を放った。女の一人が苦悶の声をあげて倒れた。
「やった。早く、こっちへ。」
猩々は癋見と、巴らが街道筋から山肌を降りた茂みに隠れるように誘導しようとしている。
「うまいぞ、猩々。その調子じゃ。わしもすぐそっちへ行く。」
寂庵はそう言い、巴らの方へ行こうとした。しかし激しい斬り合いを続けながらなので、女をまくことがなかなかできない。
その時だった。蝋外が寂庵の前に躍り出たのは。蝋外は叫んだ。
「しゃらくせぇっ。何を手間取ってるんでぇっ。」
寂庵はからくも蝋外の一撃をかわした。肩の袖を切られている。
寂庵は叫んだ。
「いかんっ。蒼紫っ。」
寂庵が危惧したとおり、蝋外は巴の方に向かって行こうとした。巴はあわてて刀を抜いた。蝋外は歯をむいて笑った。
「なんでぇ女。歯向かおうってぇのか?」
蒼紫は葉霞と対峙しながら、これらの状況を察していたようである。「もらった。」と蒼紫の剣先がそれたと見て葉霞は叫び、大上段にふりかぶり、蒼紫の眉間目がしてふりおろした。しかし。
葉霞が切ったのは、木の枝だった。葉霞はいい枝ぶりの幹がとん、と地に落ちたのを見て目を見張った。
「なにっ。変わり身?!流水の動きかっ!」
黒髪をざんばらと振り乱して、葉霞は巴たちの方を向き直った。蒼紫の気配がそこ目がけて移動している――葉霞はそれを感じた。
「そこっ!」
葉霞は腰の小太刀を抜くと、ひょう、と蒼紫の気配目がけて投げた。そこに蒼紫の実体があるはずだった。
「あ、葉霞さまっ。」
女の一人、麗月が葉霞の刀に串刺しにされて倒れていた。蒼紫はもう蝋外の目の前に立って、巴をかばうべく剣を受けている。
「貴様っ、よくも!」
葉霞は瞬間憤った。飛び退るように蒼紫に向かって突進し、剣を逆手に持ち換えると、巴の前にいる蒼紫の胸目がけて、旋回させた。その瞬間、蒼紫の影からはずむように小さな影が出て、葉霞の剣を受け流した。
「猩々さんっ!」
巴は思わず叫んだ。猩々の肩が斬られて血が噴き出していた。猩々は転がる体を立て直し、剣を構えなおしにらんでいる。葉霞は肩で息をついて叫んだ。
「とんだ邪魔だね。蒼紫っ。」
とその瞬間、蒼紫の蝋外に対しての剣が右腕に入った。しかし剣の入りは浅い。
「うぉっ、てめぇっ。」
蒼紫は剣を突きつけて言った。
「・・・・去れ。」
「そうはいかねぇぞ・・・・。」
その時、彼方から呼子の笛の音が聞こえた。ばらばらと、黒い影がこちらに向かって突き進んで来る。葉霞は眉をひそめた。
「真田忍軍・・・・あの鬼姫か。まずいね。兄さん、ここは引いた方がいい。」
「なんだと。」
蝋外が腕を押さえながら言った。葉霞は答えた。
「あんたも怪我しただろう。麗月と霜月を殺(や)られた。こいつはまたの機会があるだろう?」
「仕方ねえな。おい、青二才。おとといおぼえとけよ。」
彼らがばらばらと立ち去った後、女の死体がふたつと、うずくまっている猩々と蒼紫たちが残された。
「猩々さん、しっかりしてください。」
巴が持ちよりの手ぬぐいの布を口で裂いて、手当している。その時蒼紫たちの横に、二頭の馬が駆け寄り、その一頭に乗る振り分け髪の美少女が声をかけてきた。
「久しいね。蒼紫?その人は?」
面白げに少女は見降ろしている。黒い忍び装束を身につけている。蒼紫はしかし喜んだ様子ではない。口を開いてこれだけを言った。
「・・・助けてもらったことは礼を言う。」
「そうかい。わけありみたいだね。怪我をしているやつがいるみたいだから、うちの館に来るといい。」
少女はそう言うと、早足で駆け去った。
「お頭・・・・。」
癋見が不安そうに言った。般若は続けた。
「真田のところに寄るのは危険です。」
蒼紫は言った。
「行かなければあとがまずい。ここはあれらの緩衝地帯だ。」
巴が不安そうになったのを見て、寂庵が引き取った。
「なに、新宿(しんやど)に寄るようなものじゃ。あんたは心配召されるな。」
「はい・・・。」
一行は先導する真田の忍びたちの影について歩き出した。巴は、自分が次第に目的とははずれた道を歩き出しているような気がしてきた。しかし横を歩く蒼紫は無言だったし、巴から話しかけることもできなかった。巴はそれがつらいと思った。
真田の里は、街道筋から外れた、小高い丘の上にあった。背の高い杉の木が輪中の村のように囲っている。当主は洩矢御沙薙という少女で、何代も続く真田忍軍の正当な血筋の、頭目を名乗るにしては幼い姫である。しかし冷酷な性格であり、蒼紫も何度か会ったことはあるが、任務以上の感情は持ち得ようがなかった女であった。その女の館に通されて、一行は大きな日本間で対峙していた。真田の姫は、付き人の男から丹の朱杯を受け、着流し姿で脇息に寄りかかっている。接待とはいえ、いかにも蒼紫たちを見下している態度が見てとれる態であった。蒼紫たちは正座して座っている。御沙薙は言った。
「・・・・で。蒼紫、旅の途中らしいが。どこに赴くつもりかな?」
「伊勢に参るつもりです。」
ほう、と御沙薙はわざとらしくあいづちを打ち、答えた。
「その女はもう間者にしたのか?違うか。ただの町人だな。おまえがそのようななりで付き添いをしなければならないというのは、重大なことを秘めたことだな?」
「真田の陣内を通過しなければならないのは、旅の途上わかっておりました。礼を欠いたのはあやまります。」
「わかっているのならよい。私が知りたいのは、おまえの旅の理由だよ。京の翁のところにその女を運ぶのではないのか?」
御沙薙は杯をなめつつ、蒼紫に問い詰め続けている。蒼紫は終始乱れることなく、落ち着いて答えた。
「翁は今回の件にかかわっておりません。真田も同様のことにしていただきたい。」
御沙薙は蒼紫の答えを聞くと、手にした杯を畳に投げた。
「貴様。瑠璃波硝子の利権の話を、この私が知らないとでも思っているのか?おまえは今からその謎を暴き、上様に報告するべく旅を続けている。それであのような追放した連中にも狙われているのだ。違うか?!」
巴は御沙薙の冷ややかな罵声を聞いて、心中はっとした。蒼紫からそのような話はまったく聞いていなかった。とっさに、御庭番衆はやはり、硝子の利権を狙って自分に近づいたのかと混乱した。そして蒼紫の横にいるのがいたたまれないと思った。
御沙薙は言った。
「蒼紫。ここは取引をしよう。おまえがこの里にとどまり、御庭番衆の権限の一部を私たち真田に預けるというのなら、その女はここを通過してもよい。硝子の利権にも真田を加えてやるというのなら、なおのこといいが。」
「・・・・・・・・。」
「おやだんまりか。まあおまえが口を開くのは、めったにない。一晩返事を待ってやる。歓待してやるからな?」
と、御沙薙は言うと、あごで付き人に指示し、自分は部屋に下がってしまった。
「御頭・・・。」
一行は館の一室に通されている。癋見と火男が不安げにつぶやいた。寂庵は言った。
「仕方がないことじゃな。蒼紫、抜ける手はずは整えられるか。」
「影を使う。」
「それしかないだろう。巴さんらは忍びの心得がない。」
蒼紫は懐から蝋燭を何本か取り出した。
「般若、通用口を確認できるか。俺たちは抜けられるが、巴たちは無理だ。」
「そうですな。」
寂庵は言った。
「そろそろ野分の時期となったようじゃな。」
巴と縁は、襖を隔てた奥の間で向かい合っていた。縁は言った。
「あいつらなんか相談しているなあ。ねえちゃん、俺たちだけでここを出て行くことはできねぇのかな。」
「仕方がないのです。みなさん、私たちのために戦ってくれているのです。」
「本当かよ?あんなやつ、一緒にいる理由なんかあるの?あいつ、俺たちの父ちゃんがやってた研究が目当てで一緒にいるんだよ。だったらいる理由なんかねぇよ。」
巴は惑乱する気持ちを抑えながら、必死に弟に言い募った。
「そんなことを言ってはなりません。今だって、猩々さんが私たちのために怪我をしたでしょう?迷惑をかけているのです。」
「迷惑?あいつらが勝手に俺たちについてきて、ねえちゃんのことさらって・・・・そうだって葉霞さんも言った。俺はさ、両方の言い分を聞いて、俺なりにちゃんとわかってる。俺だってもう大人なんだ!」
「縁・・・。」
縁はすっくと立ち上がると、涙を振り絞って叫んだ。
「俺だってねえちゃんが殺されないようにって考えてるんだ!ねえちゃんはあの蒼紫ってやつが好きなんだろう?!ひどいや、あんなやつ、死んだ清里さんのことだってもう忘れているんじゃないか!」
「縁・・・・っ。」
その時襖ががらっと開いた。巴はあっと驚いた。中に立っていたのは、寂庵ひとりだけであった。巴は言った。
「あの、他の方たちは・・・・。」
「みなこの館をすでに抜けた。来なさい。ここに影が用意されておる。これはあんたたち二人の形代(かたしろ)じゃ。」
巴はそれを見た。白い布の塊が部屋の真ん中に置いてあった。
「こんなもので・・・。」
寂庵は答えた。
「あんたは夜店の市で、錦影絵というものを見たことはあるかね?あれと原理は同じじゃよ。ただ忍びの術であんたたちが部屋の中でずっと座っている、そのように見える。これはまあ、そうしたものじゃ・・・。」
「どうしてこの館に来なければならなかったのでしょうか。」
「あんたには理解できないじゃろうが、幕府の御威光が昔の戦国の世のように戻ろうとしているのじゃ。もはや幕府は一枚岩ではない。地方の群雄がそれぞれの縄張りを主張し、あんたのように札をかけられた者が通過する際には、何かをよこせと言ってくる。今回の事はまあそうしたことだったのじゃよ。」
「それでは私たちのために・・・・。」
「いやいや。元はと言えばあんたの家がかわいそうな目に会っていたからじゃよ。わしゃあんたに同情している。縁くん、君にはつらいことをしてしまった。もう少しの辛抱じゃ。これからここを抜けて信濃国の下諏訪にまで出れば、甲州街道に再び合流する。そこからあんたたちは江戸に戻りなさい。」
「えっ、でも。」
「あんたは最後までいる必要はない。あんたが持っているはずの硝子石の袋は、今はもう蒼紫が持っている。それさえあればいいのじゃよ。あんたは江戸で名前を変えて暮らすといい。江戸につけば、そのような手はずがあるはずじゃ。」
「・・・・・・。」
「元はと言えば御庭番衆の頭目が蒼紫に命じた始末からじゃった。逆らうことはできないのでな。形だけここまで旅をしてもらった。あんたには気の毒じゃが・・・・弟さんのこともある。わしらのような連中とは、関わり合いにならない方がいいのじゃ。」
寂庵はそう言うと、巴たちを促して部屋を出た。裏口へと進んで行った。巴はすっかり心が死んでしまったようになり、足取りも重くなった。何のために私は今ここにいるのだろうか。いや、考えてはいけない。巴の横の縁はしかし、すっかり上機嫌であった。
「おじいさん、下諏訪にまで行けばいいの?」
「そうじゃよ。途中まではわしが送ってやる。」
「うん、ねえちゃんよかったね。」
巴は言わずにはおれなかった。
「あの、でも、先ほどの猩々さんが怪我したようなことが何度もあるのではないですか?」
すると寂庵は面白そうに笑った。
「ああああいうことがその、甲州街道の帰路の道中にあると?まああんたはそう思うな。あんたがあれの横にいたから、ああいうことになった。あんた一人では何ほどのこともない。」
「でも、あの方たちが危険な目に合われます。」
「あんたは人がいい。あれはそうした任務についている男じゃから、切り離して考えるべきだ。要するに、あれにはあんたが安全な場所に行くように、右から左へ送り届けただけの話なのじゃ。そうしたことは、あれの日常じゃから、いちいち感傷に浸っている暇などない。まあそうした世界は江戸に帰ったら忘れることじゃな。」
巴は「そうですか・・・。」と口の中でつぶやいたが、目に薄い涙が自然に沸いてくるのを抑えることができなかった。
「・・・ねえちゃん?」
縁は巴に少し気配を感じたが、すぐにそっぽを向いた。姉のこういうなよなよとした態度は、縁は好ましく思う時もあったが、いらだつことも多かった。
巴は意気消沈しながらも、ふと気づいたことを寂庵に言った。
「あの・・・・先ほどの戦いのとき、私たち兄弟の人相書きが出ていると敵の者が言いました。それは、大丈夫なのでしょうか。」
寂庵は答えた。
「それはわしらがこれから無効にする。蒼紫が瑠璃波硝子の件を報告できれば、その人相書きは意味のないものになる。すでにあんたにかけられた嫌疑の一部である、秘密の石はわれわれが握っている。用済みということになり、あんたたちにかかわりあう時間も惜しいものになる。さて、ここからだな。」
寂庵は木戸を開いた。
裏口は闇に静まり返り、不気味なほど何の気配もない。すでに時刻は夕闇を過ぎており、館は黒い影になって山のふもとに眠っていた。巴は先ほど見た御沙薙という少女の様子を思った。これはたぶん罠、いえ、そんなことはない。後ろを振り返った時、今までいた遠くの部屋に明かりがともり、障子に人影がふたつ影になって幻燈のように見えていた。あれであの少女はだまされるだろうか。無理だ。巴の脳は呻くようにそう考えた。あの少女はすぐに見破る。今まで出会ってきた女の忍者たちと、あの少女は同種の生き物だ。何よりも蒼紫がすでにあの館にいない。あの少女は一晩とどまるように蒼紫に言った。蒼紫はその約束をたがえている。
巴たちは街道に向かって暗い道を降りだした。ひゅん、とその時巴の頬の横を何かがかすめた。巴は手で触った。血が少し手についた。小さな刃物が飛んできだのだ。巴ははっ、と驚き、とっさに縁の手を握りしめた。
「来たようじゃな。」
寂庵は手にした仕込み杖を抜いた。刃渡りが1メートルほどの長い細い剣である。先ほどの戦闘でも使っていたようであるが、巴はあまりよく見ていなかった。
「時間稼ぎというほどでもなかったが・・・・道は開けた。あとは二人羽織じゃ。姫街道を降りるは道中膝枕・・・・歌うは笙。」
寂庵はそう言うと、小走りに走りながら、剣を振り出した。道なりに黒い影が数名、倒れていくのが見えた。その先に、一人の黒い少女が立っていた。少女は背中から剣をすらりと伸ばしながら引き抜いた。少女はつぶやいた。
「老人。おまえの時は過ぎた。」
風のように少女はまっしぐらに突き進んでいく。楽し気に白い歯をこぼして笑っている。巴は惑乱した。私はこの少女に斬られる。紙のように斬られる。その時巴はあっ、と思った。いないと思っていた御庭番衆のうちの般若が盾となって少女の前に現れ、瞬間一撃を交わした。御沙薙は笑ったようだった。私にはどれほどのこともない、という風だった。般若をやり過ごし、次に火男、癋見の順に御沙薙は切り結んでいく。しかし彼らは御沙薙の突進を止める態まではせず、道標のように御沙薙は式尉まで斬った。これは幻覚?しかし御沙薙の突進が少し緩んだようである。だが寂庵に向かってすごい速さで御沙薙は移動してきている。目指すは間違いなく私だ、巴はそう直感した。御庭番衆たちは御沙薙を防御できなかった、そして寂庵さんでは無理だ、殺される、蒼紫は私を助けてくれない、そう思った瞬間だった。
ガッ、と二艘の剣が空中から鋭く飛来して、寂庵の持つ剣と交差して御沙薙の体に入った。
「貴様・・・・・っ。」
御沙薙は我に返ったようだった。寂庵は言った。
「遠円望の効果はあったようじゃのう。あの蝋燭の光におびき寄せられて・・・・蛾のように直進するとは愚かじゃ。上ががらあきじゃったわい。」
蒼紫が御沙薙の上に蝉のように乗っている。ばしゅ、と両剣を引き抜いた。空間に血の雨がぱっ、と舞い散った。
「そん、な・・・・あお、し・・・・っ。」
御沙薙はようやくそれだけを言い、地に崩れ落ちた。瞳孔を見開いたまま、御沙薙は死んでいた。
巴はへなへなと尻もちをついた。あまりのことに腰が抜けてしまったのだった。蒼紫は影のように横に立っている。御沙薙を冷たく見降ろして言った。
「利権の話を知っているから、消す必要があった。」
寂庵は言った。
「そうじゃな。まあそれがわかっただけでも、あの館に招き入れられたのはよかったことじゃわい。では行くとするかな。巴さんや。」
縁は泣き出しそうな顔になっている。巴にすがりついて言った。
「ねえちゃん、ねえちゃん・・・・。」
癋見は巴ににこ、と笑いかけて言った。
「あ、立てます?こういうこと、下諏訪にまで行ったらなくなりますから・・・。」
巴は必死で首を縦に振って答えた。
「は、はい。」
蒼紫は無言で巴に片手を差し出した。巴はようやくの想いでそれを手に取った。
蒼紫の手は今勤めを果たしたせいか、暖かかった。
巴たち一行は中山道を諏訪方面に下っていた。
今のところはいたってのどかな道中であるが、以前と変わりなく蒼紫は無言だったし、巴はすっかり怖くなって笑顔がその顔から消えていた。碓井越えの前の時とは何もかもが違っていた。蒼紫のことは忘れるように、と前を歩く寂庵は言った。自分もこの先この人と会うことは、二度とないのだろうと思った。そう思うと、下諏訪までの一歩一歩が巴には大切なものとなった。しかしこの時の時間は同じように無情に過ぎていく。それが巴にはつらかった。引き伸ばしたいのか――だがそのようなことは到底無理なこと。また蒼紫は自分のことをどうとも思っていないようにも見えた。
私はただ、失った清里の形代がほしかっただけなのだ。そう思おうとした。しかし蒼紫は清里よりも数倍優れた人間であった。それは見ているだけで巴にはわかった。自分はないものねだりをしていると思った。そんな物欲しそうな女はきっとこの人は、と思った。自分には何の武芸のたしなみもないのにと思った。ただ少し剣術の真似事ができるだけであり、それはあの死んだ御沙薙のような女からすれば、おそらく見下されるようなことである。現に今も蒼紫の足をひっぱっている。私はこの人の生きる世界からは遠い。巴は考えた。江戸に無事戻り、日常生活の中で、私は時々この時のことを思い出す。この人のことを、誰にも言えず・・・・私だけが知っているということで。それを後生大事に囲つだけが自分という女なのだ。なんという平凡さだろう。
蒼紫らは先ほど倒した御沙薙たちも、遺体は並べて沿道にあったむしろをかけた。本当は土に埋めた方がいいんですがね、時間がねぇからと式尉は言った。それも巴には御庭番衆への意外な驚きだった。生きて動いている間は、おのおのの考えがあるからのう。それが人間なんじゃ。死ねばみな等しく塵になる・・・・寂庵は南無阿弥陀仏、と唱え手を合わせた。
「どうして蒼紫様たちがいるということを、あの時言ってくださらなかったのですか?」
巴はたまらずに寂庵にその時少し言い募った。寂庵は「それも術のうちじゃ」と答えた。
「あんたがそのようなそぶりを見せると、御沙薙に気取られる心配があった。腹芸で渡れるようでなければ立派な術者とはいえん。ま、蒼紫の場合はそれの訓練を受けておるからの。これはまあ、嘘をつき慣れているということじゃ。」
横に立ち手を合わせてすぐに向こうに立ち去った蒼紫の顔は、巴の目にはそう寂庵に言われても何の感情も動いていないように見えた。この整った顔の下に、御沙薙をあざむき切り捨てたあの残酷さがある。だが寂庵の蒼紫評は、悪気があって言っているわけではない。それは巴にもわかっていた。ただなんだか巴には、蒼紫の人生がとても寂しいもののように思えた。傾いてはならないと思う巴だったが、清里の爛漫だった性質に比べると、蒼紫は気の毒なぐらい暗い男だった。彼にも笑顔が浮かぶときがあるのだろうか。それはしかし、私には見ることはないのだろう。そう思った。
「湖が見えてきましたね。そろそろです。」
怪我をして待機していた猩々が彼方の青色の水面を指さした。山並みの間に見えた諏訪湖の水面は、陽光にキラキラと輝いていた。その時だった。「あ」と巴は前に少しつんのめった。左足の草鞋の鼻緒が切れていた。巴は歩けなくなった。
「こんな時に。」
巴が申訳なさそうに言ったとき、そばにいた蒼紫が不意にしゃがみこんだ。蒼紫は巴の足から草履をはずそうとした。巴はびっくりしてとっさに足を引っ込めようとした。蒼紫は叱りつけるように言った。
「動くな。」
「・・・・。」
「すぐにすむ。」
巴は内心びくびくしていたが、蒼紫に素直に足を預けた。蒼紫の手が足首に触れたのを感じた。この人の手だ、昨日握った手だ、と巴は思った。瞬間大きく胸の鼓動が弾むのを感じた。蒼紫に気取られただろうか、とうつむき頬が染まるのを巴は蒼紫から見えないようにした。
「御頭。先に行きますぜ。」
と、式尉と火男が歩いていく。二人の様子を、もらい見して肩をすくめたようであった。縁は立ち止まって蒼紫たちに不満そうな顔をしたが、「おい」と猩々に背中をどやされて、前に歩き出した。御庭番衆たちは縁から見れば、やはり怖い兄貴分だった。
蒼紫の作業は数分ほどですんだ。
「これでいい。歩けるか。」
「はい。」
と、その時上空からぽつりぽつりと雨脚がかかり、見る見るうちに本降りになった。巴は菅笠を持っていたが、防げるようなものではなかった。一行は手近な雨宿りのできる場所にあわてて入って行った。巴たちは、先に行った連中とは自然別になってしまった。沿道の古い民家の離れの軒先に蒼紫たちは入った。雨はしばらく降り続くようであった。二人はしばらく押し黙っていた。巴はこの雨がやまなければいいのに、と思った。あと数刻すれば蒼紫とは離れ離れになる。何か一言言わなければと思った。しかし蒼紫に話しかける勇気がなかった。私はどうしてこうなのだろう、と巴はぼんやりと考えた。自分は生まれつき他の娘に比べ口が重い。清里は俺は気にしないよ、と笑ってくれたが、蒼紫はどうだろうか。先に口を割ったのは蒼紫の方だった。
「・・・・この雨のうちは、敵は仕掛けてこないだろう・・・。」
「はい・・・・。」
「あなたには、悪いことをした。すまない。」
「あの。」
蒼紫の言っている意味が漠然としていた。そしてやはり蒼紫は任務のことだけ考えているのだと思った。巴は空を見上げながら歌うように言った。
「御恩は一生忘れません。江戸に帰っても、忘れません・・・・。」
「俺もあなたのことは、一生忘れないだろう。」
巴は蒼紫の言葉に、はっ、とした。これまでとは違う調子だった。というよりも、そのようなことを蒼紫が言うとは思わなかったので、巴は蒼紫の方を振り向いた。
間近に蒼紫の顔があった。蒼紫は指を伸ばして、昨日斬られた巴の頬の傷に触ろうとしていた。「髪に水が」、と言ったようだったが次の瞬間巴は心底驚いた。巴は蒼紫に抱きすくめられていた。心臓が縮み上がるような思いだった。ああうれしい、と巴の心の中のもう一人の巴が言っていた。しかし巴は蒼紫の体に手をあてて、押しのけるようにした。
「あの、やめてください・・・・。」
巴は消え入るような声でそうささやいた。蒼紫の上にかけた両手がふるふると震えた。そしておずおずと蒼紫の体から身を引いた。自分がやっていることは、思っていることと違う、そう思うと巴の心は泣きそうだった。そうではないと巴は思った。もうすぐ別れるのに、明日の保証もなく蒼紫と抱き合うのは巴は嫌だった。この人も清里と同じと巴は思った。それがつらくて悲しかった。頬に一粒の涙がこぼれた。
蒼紫の目にもそれは映ったようであった。蒼紫は目を落として言った。
「・・・・美しい名前だと思った・・・。」
「え・・・。」
「あなたの名前、雪代巴というのが、美しい名前だと思った。俺の母の故郷は上州で、冬には多く雪が積もる。音もなく空から雪が舞い降りる時があるのだそうだ・・・。」
とっさに蒼紫が何のことを言っているのか、巴にはわからなかった。ただすまないという意味で言っているのだと思った。巴は言った。
「あの、これ以上のことは・・・・。」
見上げた巴の目に、蒼紫の顔が映った。巴はその顔を見てはっ、となった。蒼紫は巴を気遣うような、優しい微笑みをその口元に浮かべていた。指先で巴の頬の小さな瑕を指向しながら、蒼紫はそっとささやいた。
「その名前が消されるのは惜しい――血の雨で。」
蒼紫はそれだけ言うと、立ち上がった。巴は蒼紫にとっさにすがりつきたい気持ちを抑えた。こんな時はもう二度とない――おそらくないのだ。巴にはそれがよくわかっていた。蒼紫はやや小降りになった雨の中を駆けて行った。
巴は思った。どうして私は――あの人に好きだと一言だけでも言えなかったのか。蒼紫が自分を求めたのなら、少しだけでも分けられなかったのか。もうあの人の人生と私の人生は、交わることはないのに。
巴はしばらくその場で石像のように動かなかった。
通暁
同刻篠つく雨の中、傘をかぶった男が一人、湯煙のたなびく下諏訪にある旅籠の中に入っていった。連絡係だ。入り口で合言葉を言い、男は文を中の中年の男に渡した。中で男は文を見た。
「動くか。」
と男は言った。闇乃武の辰巳であった。
「辰巳殿、江戸の御庭番衆からの人運びの件で?」
辰巳は後ろで手裏剣をいじっている中條に言った。
「そうらしい。ま、手はずは江戸の頭目から聞かされている。連中は碓井越えのあと、真田忍軍を襲ったらしい。やりすぎたな。この蒼紫という若組頭だが。」
「なるほど。そいつらは京で使う女を連れているのでしょう?」
「そうだ。頭目の話では、わしらが受け取る話になっとる。」
「なぜ真田のやつを殺したんです?」
「さあな。理由はわからん。わしはその女を長州に対する間者に仕立てる話しか聞いておらん。女は自分の旦那の男を京で長州藩子飼いの剣客の若造に殺された。それを落とすのに使うのだそうだ。」
中條はふーん、と言った。
「よくある話ですね。女に仇を取らせるわけですか。」
「ま、そういうことだな。幕府の連中は形から入るものだからな。女はしかしまあまあの上玉だそうだ。わしらはその教育係だそうだ。」
「据え膳は食っちゃいけねぇんですかね?」
中條は言いながら柱に手裏剣を投げた。びし、と音を立てて縦手裏剣が柱に突き刺さった。若者らしく言う中條に、辰巳は含み笑いした。
「それはだめだ。九の一の法が破れるからな。その女には、長州の若者といい夫婦になってもらわねばならん。自分を慕う女をはべらせることで男を弱らせるのだ。呉の西施(せいし)の理(ことわり)にもあるようにな。だから、そういうことだ。」
「そいつは残念です。」
と、中條は言ったが、さほど気にしている様子でもなかった。こんなことはいつものことなのだろう。横にいた角田も剣呑そうに言った。
「女は恋仲になったらあとが面倒だ。」
辰巳は笑って鷹揚に言った。
「ああ。その女にはわしらのいい踏み台になってもらわねばな。それでは行こうか。連中がそろそろここに着くころだ。話は伝わっているはずだからな。」
辰巳らは腰をあげた。
蒼紫らは諏訪湖のほとりにまで来ていた。見晴らしが開けたところで、寂庵は蒼紫に言った。
「わしらには目がついて来ている。ここらで別れた方がよさそうじゃ。」
猩々と癋見が、道端に置かれた石を見つけた。何かのサインだろうか、巴にはまったくわからない目印だった。猩々は言った。
「東に三里の仏・・・。あの丘に見えている寺です。あそこで女子供を引き渡せと言ってきている。」
「やはりそのまま旅をさせてはくれなかった。思ったとおりの展開になりましたね。」
と、式尉は言った。
蒼紫は答えた。
「刻限までに行かなければ追手が来るが、あそこには俺と般若で行くことにする。連中を片付け、任務を果たしたのち、おまえたちと合流することにしよう。」
「え、できるんですかい?そいつは大変だ。」
と、式尉が言った。蒼紫は答えた。
「おまえたちは巴と縁を守って、甲州街道の方へ抜けろ。」
「合流はだいぶ先になるんじゃねぇんですか?だって、頭目が言った葉霞らの根城の峠は、恵那山にあるんじゃねぇですか。そこまで一緒に行った方が・・・。」
「女の足では、あの山に登るのは無理だ。街道からもはずれているからな。敵の本拠地から遠ざけるには越したことはないのだ。」
寂庵は言った。
「苦渋の選択じゃな。まあわしらで守るしかないわい。しかし引き渡しが下諏訪でというのが気になる。これは・・・。」
罠かもしれんな、と寂庵は思った。蒼紫がそのように考えるのを頭目は見抜いているのではないか。しかしそれも、この蒼紫はおそらくわかっている。それでも巴らを安全な道を歩かせたいのだろう。寂庵は心中でため息をついた。
巴は相談している蒼紫らからは少し離れたところの石の上に座っていた。とうとうここまで来てしまった。巴はそう思った。横にいる縁が言った。
「江戸に帰ったらさ、俺ねえちゃんの作った手料理が食べたい。早く帰りたいよな。」
「ええ・・・・。」
縁は路傍の石を蹴って少しけんけんをした。あれから巴は蒼紫の顔を見ないようにしていた。蒼紫も自分を避けていると思った。それが悲しかった。そして江戸に帰ることができても、その先はどうなるのだろうと思った。はじめて寂庵に会ったとき聞いた話では、さらに北の東北地方に逃げる話をされたことがあった。自分はどんどん流されていくのだろうか、蒼紫から離れて・・・・そう思うと、つらくて切なかった。
寂庵たちが巴たちのそばにやって来た。
「では行きましょうか。あの向こうに見えている一里塚が起点です。そこから別れましょう。」
式尉が言った。道は、田舎なので単なる三叉路であった。江戸へ向かう道、京に向かう道と分かれている。こんな道一本で隔てられる。巴は思ったが、それが現実であった。
一里塚の前で、巴は蒼紫に礼をした。
「お世話になりました・・・。」
蒼紫は頭を下げたようだった。日が傾きだしていた。蒼紫の表情は逆光で巴にはよく見えなかった。自分の名前を美しいと言ってくれた、あの美しい人がそこに立っている。そう巴は思った。その光景を忘れないでおこうと思った。
蒼紫は巴が立って向こうに歩いて行くのを、脳裏に刻むようにじっと凝視していた。たった今俺から離れていくのだな、と思った。昼過ぎにあんなことをしなければよかった。そう思ったがその時はどうしても自分を止めることはできなかった。出来心で、と思う自分だったが、あれ以上のことができる自分ではなかったと思った。巴の心を壊さないにはあれが精一杯だった。もとより自分とは住む世界が違う。一緒にいることはできないのだ。だったら何もしない方がいい。そう勤めてきた。
頭目から命じられて、見張るように言い渡されたのが三か月前、瑠璃波硝子の件の関係者で、情報を持っている女ということだった。巴は平凡な日常にいる女だった。毎朝早い時間に起き、寺子屋に通う縁を寺に送り届け、市場で少し買い物をして帰る。むろん毎日見張っていたわけではない。幾日かおきの定点観測だった。見たところ華美な女ではなかったが、何度も目に留めているうちに、抜けるように色が白いことや、整った目鼻立ちをしていることに気付いた。女を見張れという命令を言われたときから、危ういという思いはあった。そのうち巴の家の前に「忌」の張り紙がつき、巴の婚約者が死んだということを知ったとき、自分の心の動きが喜んでいると知り、蒼紫は己れを責めた。しかしその後巴は見ているうちに、硝子の利権をめぐる騒動に巻き込まれていき、自分がそれを助けることができるようになったことは、蒼紫にとっては願ったり叶ったりの出来事であった。だがその不自然なまでの接近に、蒼紫は頭目の手の平で転がされていると思う。しかし巴をもはや思い切ることはできなかった。それであの街道沿いの雨の古家で、行動を起こしてしまった。抱きしめた巴の体は、柔らかくて温かく震えている雛鳥のようであった。それは己れの術者として幾たびも渡ってきた、剣の上での嗜虐心をあおるものであった。そういった衝動については、蒼紫はあの葉霞によって開眼されて以来、そういうものだという自覚はあったが、特に目に留めて注意していたわけではない。しかし、前夜御沙薙を襲ったとき、いつもの自分とは明らかに違う剣の入りを感じて、手練れの手ごたえがあったことはうれしいと思ったが、それらは巴には決して言えない話であった。増してやそのような理由で巴がそばにいてもらいたい、と言ったら巴は眉をひそめるであろう。頭目などは酒の席で、男は剣であるとするならば、女は男をおさえる鞘であろうと言っていた。その猥褻の意味については蒼紫もわかっていたが、本当はそうではないと蒼紫にはよくわかっていた。自分もそういった鼓舞される衝動に支配されている生き物なのだと思った。
しかしそうは言っても、蒼紫は巴が欲しかっただけなのである。自分が御庭番衆でも何でもなく、若組頭の重責も背負わず、あの巴の死んだ婚約者の立場で済んだなら、「忌」の文字をつけられたとしても構わなかったと思った。巴のために死ぬのなら平凡な凡夫の人生でも構わなかった。それぐらい蒼紫は思い詰めていた。
そのような想いで頭がいっぱいになっていたのだろう、あとから考えると迂闊だったとしか言えない選択であった。蒼紫と般若は指定された山寺に近づいてきていた。刻限は酉の刻暮れ六つ(約18時ころ)であった。寺の石段の下で、蒼紫は剣に手をかけた。明らかに上方に潜んでいる気配がある。
「御頭、私が先に。」
と、般若が言うのを制して、蒼紫は抜刀した。石段を上がって行った先に、仁王立ちの男の影が見えた。男は言った。
「連れの者たちはどうした。おまえではない・・・若造。」
闇乃武の辰巳であった。他に一名を確認した。蒼紫は無言で斬りかかった。辰巳は予想していたようであった。すぐに太刀で受けてきた。笑いながら言った。
「女を逃がしたのか、若組頭?すでに街道には探索が出ておる。ぬかったな。」
蒼紫は瞬間、激怒した。刻限まで待ってこの場に来た自分を呪いたくなった。御庭番衆の習いにあまりにも忠実であった自分が間違っていたのだった。この約束は反故されねばならなかった。それを読めなかった。蒼紫は猛攻した。辰巳は押された。その間にも般若は横で中條と応戦している。
「ぬぅっ、貴様、やるなっ。」
と、辰巳が言った瞬間、辰巳は驚いた。自分の横にいたはずの蒼紫の体が、くの字を描いて放物線で辰巳の体に剣先をかすめたのだった。蒼紫はもう着地して次の動作に移っている。この者、何という身のこなし、やはり頭目が目をかけるだけあって、ただの使い手ではない。辰巳は思った。真田の姫を導術で殺したと聞いているが、それもただの技ではなかったのだろう。
辰巳はしかし、老獪な男だった。蒼紫に「待て、待て」と言った。辰巳は言った。
「貴様のしたことは御庭番衆としては正しいことだ。ただ女を逃がしたのは浅墓だった。そういう気持ちはわからんでもないが。」
と言った瞬間、蒼紫のとびかかった剣が辰巳ののど元にかかった。辰巳を信じられないほど恐ろしい力で抑えながら、すさまじい形相で蒼紫は言った。
「・・・街道に行った仲間を呼び戻せ・・・!」
辰巳は締めあげられながら、苦笑して言った。
「無理だ。女たちの確保に働いている。わしを殺すか、いいのか、かたわれが呼子を吹くぞ。十里先まで聞こえる。呼子が鳴ったら女どもは殺す手はずになっている・・・わしが考えたのではない。貴様の頭目の命令だ。」
「なに?」
その時、古寺の大きな木立の影からあの老人が姿を現した。
「そうじゃ、蒼紫。お前の真意を知りたくてな。」
御庭番衆総頭目の老人であった。老人は言った。
「その剣を納めろ。お前がわしの下した最初の硝子に関する命令を無視せずに、この寺にまで約束通りに来たのはほめてやろう。そうでなくてはな。しかしあの女たちは幕府の下した命令に従ってもらう。おまえがどう思いをかけようと、それは無駄なこと。」
蒼紫はわななく手で、辰巳にかけた剣先をはずした。この老人には技の上ではまだ歯は立たないのだ。致し方なかった。老人は言った。
「おまえができることを今から述べてやろう。かねて言っていた場所で、硝子に関する幕府の朱印状を見つけて回収しろ。できるだけ早くだ。一昼夜をやる。できなければ、女たちは京で用立てるまでもない。その首をつなぐために努力しろ。以上だ。」
般若は思わず横から叫んだ。
「そんな無体なことを・・・・!」
老人は般若に言った。
「無体だと?御庭番衆の命令は絶対だ。その命令を破った者には相応の仕打ちをするのがわが努め。馬をつけてやる。早駆けで行くがよい。おまえひとりでな。」
そして重ねて言った。
「真田の者を殺したことも不問にするつもりはない。おまえとしては考えたつもりだったのだろうが。ではな。」
蒼紫は頭目の言葉を首を垂れて聞いていたが、どうしても一言言わずにはおれなかった。彼にはこの場では恥も外聞もなかった。蒼紫は必死に喉に張り付いた声で叫んだ。
「巴は、巴は助かるのですか?」
蒼紫の若者らしい声はしかし、頭目の老人の心を苛立たせただけであったようだ。
「助かる、だと?貴様のそのような物言い、聞きたくもないわ!」
老人はぴしりとそう言うと、付き人の忍びたちとその場をあとにした。蒼紫にとって、あまりにも残酷な結末であった。
般若が付くと言うのを断り、蒼紫は馬に乗った。恵那の山にあるという葉霞たちのアジト、だがその経路は幾筋か道筋がある。どのルートにあるのか見当はつかなかった。馬を走らせている間も、巴たちの安堵が気がかりでならなかった。あの時頭目の命令を無視して、ついて行けばよかった。ただひとつ望みがあるというのは、皮肉だが闇乃武たちが巴らを捕まえたであろうということだ。闇乃武は葉霞たちと違い、頭目の命令で動いており、幕府の命令で巴たちを間者として使う使命で動いている。だから辰巳がああは言ったものの、その場で命まで狙うことはないだろうと思った。それだけが一縷の望みであった。
そのころ巴たちは闇乃武たちとすでに街道筋で遭遇していた。精鋭の二名が抜けた御庭番衆たちだったが、彼らはよく戦ったのだが、にもかかわらず敗北したのは、ひとえに縁のせいによる。縁は、実は葉霞に拉致されていた寺で、辰巳らとも会っていた。姉を取り返したくば、我々の言うことを聞けとさんざん言われていたこともあり、追手の中に葉霞らよりも優しく、見慣れた顔を見出した彼は、彼らが手招きしているのを見て、そちらへと姉の手を引き走り出したのである。辰巳らはそのような中立の者たちであり、またどこへでも顔を出す蝙蝠のような連中なのだった。御庭番衆と言っても一皮むけば下働きはそのような烏合の衆の集まりであり、であるからこそ蒼紫は頭目から厳しく制圧するように普段から言われていたのだった。縁は辰巳の顔を見て、
「あの人たちは大丈夫だよ。」
と言って巴の手を引いたのだった。巴はまろびでる縁を止めようとして、突き転んだ。
「縁、行ってはだめ・・・・・!」
巴は叫んだ。なぜこうなってしまうのかと思った。
その時他の者たちと交戦していた寂庵だったが、辰巳が縁を人質に取ろうとしているのを見て、すかさず斬りこもうとした。しかし。
「てめぇはすっこんでな、爺さん!」
寂庵は声もなく絶命した。中條に前から斬られ、辰巳に後ろから袈裟懸けに斬られていた。他の御庭番衆たちも、闇乃武をはじめとした忍びたちに斬られていた。多勢に無勢であった。蒼紫、大丈夫か、というのが寂庵の最後の意識であった。彼は最後までこの不遇の若者の身を案じて死んだ。
「寂庵さん、あ・・・ああ・・あ・・・。」
巴は寂庵の遺体にすがって泣いた。それを辰巳は黒髪をつかんで乱暴に引き起こした。辰巳は巴に言った。
「なるほど。これはいい女だ。まだ殺しはせん。役に立ってもらうからな。」
「何をなさいます・・・・・。」
「あそこにいるのはあんたの弟だろう。子供だがいい連絡係になりそうだ。これからわしらと京に行ってもらうぞ。」
「いやです・・・・。」
「拒否はできんぞ。貴様は御庭番衆に近づきすぎた。その責を負うてもらう。」
「硝子のことで私たちを・・・。」
「硝子?そんなものはわしは知らん。ただおまえが亭主の仇討ちをするのを手伝ってやろうというだけの話だ。」
その言葉を聞くなり、巴はとっさに舌を噛んで死のうとした。しかしその瞬間派手に辰巳に掌で頬をはたかれた。辰巳は言った。
「貴様。殊勝に何ほどの手柄も立てずに死ぬつもりか。それでも武士の娘か。今日び町娘でも親の仇を討つのが当たり前、犬畜生にも劣るわ。弟の身柄も考えた上でのことか?」
縁は横から巴にあわててとりすがって言った。
「姉ちゃん、こんなとこで死んじゃだめだぞ。清里さんの仇を討つんだよ。この人は正しいことを言っているんだぞ。」
巴は無言で抗議の姿勢で辰巳を見上げている。辰巳は容赦なく笑って言った。
「なるほど、そうか・・・貴様あの男と結縁でもしたのか?それでか。では言ってやろう。その蒼紫とかいう若組頭の身を助けたくば、わしらと行動を共にすることだ。あの男は頭目の副長のような者だからな。おまえは知らないだろうが、次期頭目の席次に上がっている男なのだよ。それがああした任務につかされている・・・理由はわかるか。」
「・・・・・・。」
「貴様の存在であの男の絶対服従を頭目は試したのだ。今回貴様があの男を誘惑したので、あの男は頭目に背いた。それは明白な事実だ。それで頭目は今立腹している。だから貴様はおとなく我々の言うことを聞いた方が、あの男のためなのだよ。」
巴は自分は誘惑などしていなかった、と辰巳に言いたかったがもうその言葉が出なかった。蒼紫が自分のせいで追い込まれている。その境遇に陥っている。私のせいであの方が、と思うといても立ってもいられなかった。その自分に蒼紫のためにできることは一つしかなかった。とっさに巴はそれにすがりついた。巴は静かな声で言った。
「・・・・では私が京に行けばいいのですね・・・・・。」
辰巳はうなずいた。
「そうだな。そこで間者として働いてもらう。簡単なことだ。またその女の手管を使ってもらおう。」
と言って辰巳はやれやれと腰をあげた。そして仲間の忍びたちに言った。
「もうそのへんにしておいてやれ。そいつらにはとどめを刺すな。ほうっておけ。頭目は殺すまでする必要はないと言った。仕置き程度でいいのだ。」
「あいよ。」
闇乃武の者が返事をした。
闇乃武たちは巴たちを引き立てると、その場を後にした。後には猩々たちをはじめとする蒼紫以下の御庭番衆たちの死屍累々が残された。ただ、彼らにはまだ息はあった。
蒼紫は全力で馬を走らせていた。早馬を頭目たちは用意してくれていたが、その馬も一日ぐらいしか持たないだろう。頭目が刻限を決めているのは、蒼紫への圧力の意味もあったが、それだけ幕府方が事を急いでいる証拠だった。ふつうの硝子の製造では薩摩が権益を握っている。その薩摩の台頭へ幕府が牽制を急いでいるということだろう。そのような動きを察知するために、蒼紫はかねてより元薩摩藩隠密の式尉を御庭番衆に引き入れるという事をしていた。しかしそれも、式尉が二重スパイである可能性がないわけではなかった。そのような流動する情勢の中で蒼紫は常に動いていた。今も、甲州街道に行った式尉たちの行方はわかっていない。式尉たちが闇の武を打ち負かしてそのまま江戸に抜けることができていればいいのだが、おそらくそれは無理だろう。あの頭目の様子では、式尉たちは切り捨てるつもりのようだった。要するに自分は頭目に試され、反目した結果式尉たち数少ない部下をはく奪され、元の頭目の単なる下働きに戻されつつあるのだ。それは巴一人に自分の気持ちが動いたから、と蒼紫は思いたくない。悪いのは自分の心の動きだった。巴には悪いところは何ひとつなかった。彼女はただの一般人だった。元のあるべき平和な暮らしに戻してやるべき女だった。それをしくじらせた頭目こそ、蒼紫には憎むべき存在だった。もともと頭目には拾われた時から、蒼紫はすべてを頭目に預けていたわけではなかった。葉霞と一夜を共にせよと命じられた時から、頭目は自分を侵食する存在になった。それが決定的になったのが今回の出来事だった。この任務が終わり次第自分も頭目との今後をどうするか決めねばならないと蒼紫は思った。唯々諾々と従う人形のままでいるのはいやだった。しかし今はどうにもならない。巴の命をつなぐことをしなければならない。
行く手の道が二つに分かれている。ひとつは街道筋であり、もうひとつは橋を渡って廃村らしい家屋が闇の中に数軒見えていた。頭目の示した地図では、そのあたりだという目印しかなかった。場所は恵那山の山麓一帯付近だった。蒼紫は廃村の方に馬を進めた。おそらくこの先に葉霞たちのアジトがある。そこはおそらく御禁制の品の生産や密輸をする拠点だ。ここから中津川に下して港にまで運ぶのだろう。廃村に入っていく道は山道になっている。と、その先に白い刃がひらめいた。
「覚悟しな!」
と、葉霞の部下の二本刀の壮月が、馬を寄せて斬りかかってきた。蒼紫は一瞬で薙ぎ払った。手負いだった壮月はあっさりと斬り殺された。が、壮月の死体は地に落ちた瞬間大爆発した。馬が爆風で倒れて動けなくなった。足止めされたのだった。ここからは徒歩で行くしかない。葉霞の部下の霞五人衆はあと二人いたはずだった。しかし彼女ら以外にもまだ朱膳たちが待ち構えていた。蒼紫はまずい、と思った。爆発音で聴覚が今少し効かなくなっている。しばらくの間だけだが、そこをやつらは狙うはずだと思った。廃村のどこにアジトがあるのかもまだわかっていない。蒼紫は先を急いだ。前方の山肌にレンガ造りの塔がふたつ見えてきた。おそらく硝子製造の高炉である。山中にあるので、異様な光景である。やはりこの地で製造をしていたのかと蒼紫は思った。と、道が急に暗黒の坂を下っているようになった。足元が沈む感覚。まだ山を上がっているはずだ。幻覚か。と、その時暗がりの先にぽっ、と灯りが灯った。火の回りにかすかに動く蛾の群れがある。弱弱しい極彩色の蛾がふわふわと虚空を舞っている。あの蛾がこちらに来る、と蒼紫は思った。五人衆の中の星月という女の幻術に違いない。この女と鎖鎌の朔月がまだいる。
自分は今巴から託された香袋と鍵を持っている。それを自分から奪って、幕府からの藩への硝子製造への朱印状を回収し、しかるべき幕府の上役に届けて、藩の醜聞を白日の元に晒し糾弾する。放逐された元工場跡地に入り込んでアジトにしている葉霞らが動いている理由はそれであり、もちろんはじめに朱印状で許可した者らとは別の対立している勢力だ。それは式尉のいた薩摩藩とつながっている可能性があった。薩摩藩はお家芸の硝子器の製造で、藩での貿易で潤っている。寂庵はそれは密貿易と謗ったが、今や幕府を揺るがす外様大名勢力は、それ自体が一個の独立した国であり、運営会社なのであった。いちいち幕府に許しを請わずともおのおの堂々と貿易をしているのであり、そして諸外国からも軍事物資を買い込み運び入れ藩内の勢力を増強していた。蒼紫はそれらの総元締めの幕府直轄の部下であったが、幕府はもはや心元なく、その権威は失墜しつつあった。この地で瑠璃波硝子の製造をはじめた者らは、その薩摩に一矢報いたかったのかもしれない。薩摩のなしえなかった研究に着手することで、一歩先を行く気概があったのかもしれない。しかし寂庵の言うように間違った研究であったので、計画は失敗し頓挫したのだった。工場の瓦解には対立勢力の影響もあったに違いない。それは幕府政治の失点になることであった。彼らが朱印状のありかをこの地のみならず江戸でも探索していたので、それを阻止してその痕跡を消し朱印状を闇に葬るべく上様に届ける。つまるところそれが蒼紫の今回の任務であった。
つまり蒼紫はその尻ぬぐいで、この地に先代の頭目から派遣されたのだった。先代としても最初は市井にいる巴をただ見張って証拠品をつかめと言っていただけだったから、巴の命まで脅かすつもりではなかったのだろう。しかし巴には葉霞たち対立勢力からの手先の追っ手が現れ、つけ狙うことになった。頭目もそれで面倒になり、硝子密造の証拠品を取り上げた後、巴を手駒にして利用して捨てようとしたのだった。頭目の考えは蒼紫にはわかっていた。利用できる者であればとことん利用する。効率的考えが優先する世界なのである。巴が仇がある女であれば、それを理由に京に送り込む。それで反幕府勢力に少しでも邪魔ができれば、頭目としては巴の利用価値はあったということになる。巴のささやかな願い、父母の形見である硝子の香袋を守って弟とひっそり市井の片隅で生きるという道は、頭目にはまったく価値がないものなのだ。そして自分もまたそうした価値観の中に生きている、ということに蒼紫はめまいのするような思いでいた。なるほど自分と巴は、まったく別の世界に生きる者だった。そして頭目はそのことを巴で試したのだ。蒼紫がまだ市井の世界に未練があるかということをだ。
もともと蒼紫は生まれながらの忍びの出自ではなかったので、折にふれ頭目はその枷を蒼紫に敷いたのである。今回のことも巧妙に仕組まれたそれだった。巴という女を自分に近づけて、それをあきらめさせる。そうして蒼紫の忍従の心を強くさせる。それは今に限ったことではなくて、蒼紫はそうして頭目に「教育」されていた。そして思ったとおり、蒼紫が巴に同情したので、頭目は早速その手の中の玉を取り上げたのである。頭目に唯々諾々と従う人形であるのは嫌だと先に言った。巴らの命さえかかっていなかったら、彼は任務は続けなかったかもしれない。次第に彼の心には頭目への憤りがくすぶり始めていたのであった。
と、音もなく蛾の群れがさっと散開した。蛾の後ろにはそれぞれ鋲が飛んできていた。蒼紫の体が幾重にも別れた。
「流水の動き!爆風にやられてもできるのか?」
星月の叱咤する声があがった。
「しかし音を封じられればっ。」
星月の術で、蛾が乱舞しているところへ、朔月の鎖鎌が飛んだ。朔月が叫んだ。
「我は星月の術でおまえからは居場所は見えない。どこから飛んでくるのかわからないだろう!」
そのとおりで、別れた蒼紫の体のいくつかに朔月の鎌は命中した。倒れる蒼紫・・・だが、それは幻のように消えていく。
「くそっ、本体はどれだ?!」
鎖鎌がひゅんひゅんと空を薙いでいく。
「どれもが影か!」
朔月が憤った時、鎖鎌の鎖に空から棒が一本突き立った。
「なにっ?」
鎖がみるみるうちに、その棒に勢いよく巻き付いていく。
「おのれっ!」
と言った時、一人の蒼紫は短くなった鎖の先の鎌を足で蹴った。
「あっ・・・。」
朔月の喉に鎌は命中した。血しぶきが喉からほとばしった。朔月は声もなく前にのめって倒れた。
「朔月っ!」
と星月が叫んだ。身も世もなく、幻術から身をさらして朔月の体を受けとめた。星月は言った。
「なぜ居場所がわかった?」
蒼紫は言った。
「鎖は操っている一点からしか出ないからな。その移動経路を読んだ。」
星月は決死の形相で印をひき結んだ。蒼紫は言った。
「無駄だ。もう耳は治ってきている。お前の幻術は俺にはきかん。」
「おのれっ・・・・よくも朔月を!」
蛾が狂乱してあたりを飛び交っている。それだけでなく、地の底のような場所にみるみる二人のいる場所は落ち込んでいく。
「地の底で這いつくばって死ね。」
と、星月は言った。暗闇で、蒼紫の体に蛾がまとわりつく。体が重い。泥の中に沈んでいくようだ。
蒼紫が九の字に体を折り曲げた。星月はにやりとした。
「動けまい!我の術はおまえの脳に届いて今その動きを止めた!今串刺しにしてやる。」
星月は笑って剣を突き立てようとして、蒼紫の体から出た小太刀に鋭くかき斬られた。蒼紫は言った。
「・・・・・術にかかったを欺くのは、術者の初歩。」
星月は驚きに目を見開いて横に倒れた。蒼紫の片耳がまだ壮月の仕掛けた爆音で、少し麻痺していたのが幸いした。星月の術は視覚による幻術の他に、聴覚を通じて脳神経に作用する音波をも用いた術であった。それは彼女があの隅田川で見せた幻術の通りだ。皮肉にも、星月は間接的には壮月の放った術によって倒れたのである。蒼紫の先の言葉は、星月を煽るために欺いたものだった。
その時、蒼紫の後ろから一閃して剣がひらめいた。
「なかなかやるじゃねぇか。俺もこんな女の術はきかねぇがな。」
蒼紫は油断していた。後頭部を剣で斬られて蒼紫は前に倒れた。男は言った。
「ま、致命傷じゃねぇ。見てたぜ青二才。おまえは今少し痛めつけてやりたい。女を一人で何人殺したんだよ?」
油櫛蝋外だった。
炎が揺れる気配で蒼紫は目を覚ました。手が荒縄で縛られ、手を広げた形で吊るされている。頭が怪我で傷んだ。血が出ているようだ。しかし意識ははっきりしてきていた。自分がいるのは屋内だと確認した。廃村の中の小屋のひとつのようだ。製造小屋か?レンガ作りの炉があるのが見える。炎はそこにあるものだった。蝋外の影が動いた。火で暖を取っていたようだった。蝋外は振り向いて言った。
「よう、色男。気がついたか?」
言うなり、床に置いてあった桶に入った水を蒼紫に浴びせた。傷口に水が染みて痛む。濡れ鼠の蒼紫に蝋外は言った。
「おまえは面倒なやつだ。葉霞の言っていた、頭目の爺が見せびらかしたぽち袋だかのありかが、体をさぐったがわからねぇ。どこに隠したんだ?大事そうなもんだからなあ。出せよおら。」
蝋外は蒼紫の頭をぐりぐりと押した。そのあと激しく殴った。
「出せって言うんだよ!」
蒼紫は無言だった。蝋外はそうかい、と言うと壁の薬品が並んでいる棚から瓶を一個取り出した。蝋外は言った。
「・・・・こいつは塩酸だ。ここの硝子に混ぜる不思議な黄色の粉を、塊から溶かすのに使っていたらしい。こいつをてめぇのそのおきれいそうな顔にぶっかけてやる。これ以上だんまりを続けるんならな。曲水の宴といこうじゃねぇか・・・・。」
蝋外は面白そうにふふふと笑った。そして蝋外が瓶の蓋を抜こうとした時だった。蓋は瓶が古くて固くて開けにくかったので、蝋外は少しの間蒼紫から目を離していた。と、蒼紫の足が音もなくすうっと蝋外の眼帯近くまで持ち上がり、瓶を持つ手を素早く蹴った。蝋外が片眼であるのと、以前の戦闘で腕に傷を負っていたことに賭けた。目算を誤った蝋外は思わず瓶を取り落とした。
「何しやがる!」
蝋外はあわてた。瓶から塩酸のふきこぼれたものが飛び出したし、瓶も空中に高く舞上がった。蒼紫の足はそれをさらに高く蹴った。恐るべき身のこなしだった。ぱんっ、と瓶は割れて中身があたりに飛び散った。じゅっ、と音がして蝋外と炉の火にもかかったのだが、それは荒縄にもかかったようだった。蒼紫は素早く荒縄から腕を引き抜いた。縄抜けだった。縄は火傷して焦げていたので、あっさりと力を籠めると切れた。式尉も心酔した蒼紫の筋肉の力だった。
「てめぇっ!」
蝋外はあわてて腰の剣を引き抜こうとしたが、蒼紫の拳の方が早かった。蝋外の顔に蒼紫の拳が数発さく裂し、その後頭をかかえてひねるようにした。蝋外はあわてて床の上で手足をばたばたさせた。蒼紫の足を縄で縛らなかったことを蝋外は心底後悔したが、もう後の祭りだった。怪我をした蒼紫を甘く見ていたのだった。蒼紫は言った。
「首を折ると死ぬ。」
「やっ、やめろっ。」
「おまえに命令したやつは誰だ。」
「それは言えねぇっ、畜生、畜生っ!」
「・・・では悪いが死んでもらう。」
やめろ、と大声で叫ぶのを蒼紫は蝋外の刀で一閃した。時間がないのでやむを得なかった。寂庵であっても、この場合はそうしただろう。この場で蝋外を解放することは、任務の中止を意味していた。蝋外がこと切れたのを見計らって、蒼紫は小屋の外に出た。似たような小屋が続いている。その向こうに人影が動いた。黒髪がたなびくのを見た限りでは、葉霞に間違いなかった。葉霞も始末する必要があった。蒼紫は走りながら脇に隠した苦無を投げた。と、その瞬間、小屋の薄板越しにごん、と刀が突き破った。蒼紫は間一髪でよけた。
「しぶといね。」
葉霞だった。壁越しに蒼紫は言った。
「対の硝子を持っているから、用心したのか。」
葉霞は目を見張った。
「!あの時聞いていたのかい!あの女との会話を。地獄耳だね。」
「仕掛けないのは何か理由があるのだろう。」
葉霞は焦っていた。五人衆が全滅し、気配に気づいて駆けつけた時には、蝋外も蒼紫に組み伏せられていた。下手に今出ればまずい。自分が倒されるのは避けなければならない。蒼紫の技は、自分を凌駕してきているのかもしれない。隅田川で対峙した時から、葉霞はそれを感じていた。あの時はまだ互角だった。しかし、今は。五人衆の助けがあってこその互角だったとは考えたくなかった。いくら年を取っていても、私はまだ蒼紫より技は上のはずだ。壁の向こうの蒼紫は言った。
「その硝子、もらい受ける。」
「それはこっちのセリフさね!」
躍り出た葉霞は蒼紫と激しく斬り合った。葉霞の持っている硝子の破片は、工場に最後に残っていた技師の男を拷問して取り上げたものである。もう片方を硝子の研究者だった巴の一家に預けてあるというのを技師から聞きだすまで骨が折れた。聞き出した後、もちろん技師は拷問死させた。死人に口なしなのである。しかしその用途については葉霞は知らなかった。ただ貝合わせのように、合わせたら何か朱印状の場所を示す用途になる物だと思っている。蒼紫は今それを持っているはずだ。そのためにこの男はここまで来たに違いないのだ。
元はと言えば葉霞が今こうしているのも、頭目が成長した蒼紫を徴用するようになり、葉霞らが女であることを主張し頭目に煙たがられ裏切られてその任を解かれたことから、幕府に反抗する勢力と手を組んだことからだった。それらの勢力には幕閣の内部にも内通者がいるのであり、それらの者たちが巴の行った奉行所でも巴たちを待ち構えていたのだ。陽だまりの樹のように、幕府は内部からも瓦解しはじめていた。
巴の婚約者の清里が命を落とすように仕向けられたのも、それらの者たちのはかりごとだったのだろう。蒼紫が考えるに、巴の不幸はきっと偶然ではなかった。誰かその不幸を願った者がいた。それは彼女の父親の硝子の研究からに間違いなかった。少しずつそれは巴の日常を蝕んでいったのだった。蒼紫があの時「その名前が消されるのは惜しい、血の雨で」と言ったのは、まさにそうした彼女の名を表す純白の雪が、争いの血で汚れていくさまから思い付いたセリフだった。どうしてそっとしておいてやれなかったのか。静かに笑っているあの人を。
蒼紫は葉霞の太刀をかろうじて跳ね返した。廃村の建屋が切れたあたりまで、二人は走ってきていた。背後は深い崖になっており、板敷の細い間道が崖に沿って山の上に向かって続いている。その奥に一軒の建物が見えた。感じからして、研究棟のようだった。あそこか、と蒼紫は直観で思った。あの中に何かが隠されているとみてよい。葉霞はそれには気づいていない様子だった。どうやらここは彼らの元からの根城ではなかったようだ。先ほどの蝋外の様子も、出入りの者らを拷問にかけた時に聞いた知識だったのだろう。第一、しらみつぶしに探せば、ある程度彼らが捜している物を、かつて「御庭番衆」の一員であったのなら、見つけるにやぶさかではないはずだ。この葉霞がそれをしていないということは、彼女もわかっていないことが多いということだ。それで今、蒼紫の持つ硝子の切れ端にこだわっているのである。葉霞の剣を受け止めながら、蒼紫は足場を探した。
葉霞は焦っていた。朱膳はもうここに来ているはずだ。なぜ助太刀に現れないのか。私はあの男に見限られているのか。五人衆を蒼紫のために失い、女一匹になって、利用価値がなくなったと見られているのか。いや、そんなはずはない。朱膳には体だって許したのだ。この蒼紫だって私がかわいがってやったこともあった。男たちがこの私を裏切るはずがない。だいたい浪人者だった朱膳にこの硝子の利権の話を持ち掛けたのは、この私なのだ。蝋外があんなにあっけなく死んでしまうとは思わなかった。蝋外なら私の言うことを聞いてくれてたのに。力の均衡が崩れていると葉霞は考えたくなかった。しかし朱膳が現れないのは事実だった。
蒼紫は葉霞の剣と激しく斬り合っている。崖の上に出た。葉霞の髪はざんばらとなり、剣筋も乱れてきていた。体中に蒼紫と渡り合った傷がついていた。と、その時葉霞の走っていた足がふらつき、戸板を踏み外した。葉霞はあっという間に崖から滑り落ちた。そのまま下に滑降すれば葉霞は絶命していただろう。しかし、蒼紫は腕を伸ばし、葉霞の腕をはっしと握った。葉霞の顔に驚愕の色が走った。なぜ蒼紫は自分を助けたのかと思った。しかしすぐに理由に思い当たった。自分の胸元にしまっている、硝子の破片がこの男は入用なのだと。葉霞は蒼紫の顔をにらみつけた。助けてもらいたいのは山々だが、蒼紫に借りは作りたくなかった。だが蒼紫はその筋力で葉霞の体を引き上げた。葉霞が間道に倒れこんだところを間髪入れず、葉霞の体に蒼紫の剣が突き付けられた。蒼紫は言った。
「お前の持っているものを出せ。」
葉霞はざんばら髪の間から薄く笑った。
「・・・・いやだと言ったら?」
「おまえにそんな選択肢は残っていない。あの男のように死にたくなければな。」
葉霞は胸元から硝子の入っている袋をしぶしぶ取り出す動作をした。しかし手渡そうとしたその時、葉霞は蒼紫の体を片足で素早く蹴り挙げた。葉霞はわめいた。
「誰が渡すかよ!上つ方が入用のものなんだ!」
そうどなって走り出した時だった。葉霞の首にひょう、と鋭く音を立てて矢が突き刺さった。葉霞は前につんのめって、そのまま崖から叫び声をあげて転落した。葉霞の手から袋が滑り落ちた。それを取ろうとして、蒼紫も間道から落ちた。間一髪でぱっと受け止めたが、蒼紫の体は崖路の戸板を握った態勢で虚空にぶら下がった。絶命の危機だった。遠くから戸板を踏みしめて近づく足音がした。酒禍神朱膳だった。弓矢をつがえたまま歩いて来る。ぶら下がった蒼紫の目の前に来て、狙いを定めながら朱膳は言った。
「その態勢では立て直すことは不可能だな。」
「・・・・・・。」
「私には、証拠の品はなくともよい。上つ方には、失敗の報告をするまでのこと。この件はもう流れたのだ。おまえも死ね。」
「失敗でいいのか。」
「後始末は大方ついた。あの女が京に旅立ち、死ねばそれでいいのだ。硝子の密造については、証拠はなくなった方がいいのだ。そうあのお方も望んでおられる。」
「どういうことだ?」
「私はただ密造の痕跡を記録し、報告するだけに呼ばれたのだ。その報告ができればいいのだよ。朱印状までは必要ない。貴様と違ってな。貴様の場合は上様に確たる物証を報告せねばなるまい。苦労よの、御庭番衆というものは。」
「あの女というのは・・・・。」
朱膳はふん、と笑った。蒼紫の言葉にさもばかばかしいと言った態だった。朱膳は言った。
「雪代巴、だな。生きているだけでも厄介だと思うお方がおられた。それだけの事だ。そのために私は藩の不始末まで見て回ることになった。愛娘がかわいすぎたんだろう。御庭番衆もその意図に沿って動いてくれたわ。」
瞬間蒼紫の体が中空を飛んだ。葉霞の体を引き上げるだけの筋力がある蒼紫だった。朱膳と問答していたのは、油断させるためもあったのだ。思わぬその敏捷さに瞠目した朱膳は、中空を舞った蒼紫目がけて弓を撃ったが外した。あわてて弓を捨て、腰の刀を引き抜いた。からくも蒼紫の小太刀を防ぐことができた。蒼紫は残りの手で苦無を投げて、その間硝子の袋を中空にほうり、また受け止めて素早く懐に入れた。蒼紫の苦無は数本あった。いずれも朱膳の体に命中した。朱膳は呻いた。背を折り曲げて一瞬苦悶したが、しかしまだ絶命とはほど遠かった。
「なかなかにやる。さすがは御庭番衆、と言いたいが。」
朱膳はそう言うと肩に刺さった苦無の一本を引き抜いて投げ捨て、剣を水平に構えた。蒼紫も小太刀に柄に手を添え、構えた。次の一撃で決めなければならない。朱膳は態勢を整えており、今はまったく隙は見られない。かなりの手練れだった。その総髪が夜風になびいている。その時蒼紫は月の光の他に、薄く光が差してきているのに気づいた。長い夜が明けようとしていた。彼方に赤光の光が雲間から差し始めていた。蒼紫は思った。頭目から命じられた刻限が迫ってきている。硝子の破片は甲乙そろったのは望ましいが、これで朱印状のありかをこれから探さねばならない。その方法をまだ自分は見つけていない。蒼紫はしかし、焦るな、と己を叱咤した。朱印状を頭目に差し出し、巴の救命を願わねばならない。たとえ頭目に退けられようとも、自分はやらねばならない。障害が多くともしなければならない。思いをかけるとはそういうことなのだ。あの人が生きてあるということが、今の自分には大切なのだ。
朱膳の剣がその時、すさまじい光をぎらぎらと放ち始めた。目くらましかと蒼紫は思った。刀をきつく鏡面に磨き上げたせいかと思ったが、日の光の反射というだけではないようだった。瞬間、蒼紫の脳裏に隅田川で仕掛けられた幻影の幻がよみがえった。あの氾濫する泥濘の川の映像、あれをこの敵も仕掛けてくるのか。忍びではないと見たのが甘かったようだ。蒼紫はとっさに朱膳の眉間に向かって、陰陽発止の姿勢で小太刀のひとつを投げた。幻には幻、この剣の影に隠れて攻撃すれば、相手の第一撃の幻覚技のふり幅を防げると思った。朱膳はこの刀の光線のちらつきを利用して、隙をついてくると思われた。それならばこちらも同様に自分の居場所を隠すしかない。
朱膳は蒼紫の姿が一瞬沈んで隠れたのを見た。こちらの光はその目に届いているはずだ。白銀の後光の光が目を焼いているから、こちらの姿もよくは見えぬ、朱膳はそう思った。朱膳の持つ剣の後光はさらに輝きを増し、さながら阿弥陀菩薩のようである。その時、刀に柄剣の短いものがぶち当たった。朱膳は笑った。闇雲にこちらに向かって剣を投げている。私の剣の光で、大方あわてたのだろう。朱膳は言った。
「これぞ我が波浪覇(はろうは)の剣―――死ねっ。」
朱膳は短剣の後ろにまた見えた蒼紫の黒い影に向かって、剣をざんぶと振り下ろした。存分にその剣はその体の上に沈んだはずであった。しかしそれは、まさに蒼紫の流水の動きであった。蒼紫は朱膳が躊躇した一瞬の隙で、己れの影を前方に残し朱膳の後ろに飛びすさっていたのである。それは朱膳には目にも停まらぬ一瞬の出来事であった。
「なにっ?!」
朱膳は叫んだ。気がつけば、自分のみぞおちから勢いよく血が噴き出している。馬鹿な、と思った次の瞬間、蒼紫の剣は真後ろから朱膳の胴にめりこんだ。蒼紫は眉間にしわ寄せて言った。
「・・・・・悪く思うな。任務遂行には妨害だった。」
「貴様・・・・・っ!」
朱膳はどう、とその場に倒れ伏した。からくも退けられた、と蒼紫は思った。朱膳は己れの技に過信していたのだろうが、それだけのことはあったのだろう。心残りなのは、朱膳の言った言葉の謎が、今の自分には見当もつかないことだった。「愛娘」とはいったい誰のことなのだろうか。また、巴が生きているだけでも迷惑に思う者がいるというのは、いったいどういうことなのか。
しかし蒼紫は先を急いだ。先ほど葉霞と対峙する前に見かけた、崖の先の建物に目測をつけていた。釜であるらしい煉瓦造りの煙突が突き出ていた。研究棟はおそらくあのあたりだ。山中にこのような建造物を作るというのはよほどのことである。ここから寂庵も言っていた密造品の硝子器は運び出されていたのだろうか。
蒼紫は廃屋の中に足を踏み入れた。中に人影はなく、上空には烏の群れが舞っていた。古ぼけた窓から光が差し込み、床がきしむ埃っぽい室内には、硝子製造のための釜がやはりあったが、それは小さくて、先ほど蝋外と殺り合った時に室内にあったものとは規模が違っていた。やはりここが研究施設らしい。それならば、どこかにこの硝子片が収まるものがあるのではないか。
蒼紫は掌の上でふたつの切片をつなげてみた。葡萄の文様が描かれているそれは、やはりぴたりと合わさり眼鏡のレンズ玉のような小さな形になった。葉霞が持っていた片方の破片には、女の脚の部分が描かれていた。西洋の泰西画の神話を描いたものにあるような感じだった。いくつか蒼紫はそのようなものを蘭学所にあった書物の中で見た。明らかにそのあたりにヒントが隠されている。
見ていた蒼紫はとっさに思いついた。それは頭目に命じられて、蘭学所に行った時に、見かけた事物である。天が動いているという事を示したというからくり細工だった。たしか須弥山(しゅみせん)儀という名前だった。そしてそこには「万年自鳴鐘」と呼ばれる機械式の置時計もあった。それらは発明家の田中久重によって完成させられたものである。それは嘉永四年(1851年)のことで、今蒼紫が生きている頃よりも十五年ほど前の話である。この置時計は上部に天球儀がはまっていると、蘭学者の技師から説明を受けた。この天球儀は西洋の事物を模したもので、本当の向こうの天球儀は、レンズから光を投射するものだということを。暗闇に光を投射するという仕組みについて、蒼紫は尋ねた。
「その光はどうやって作るのです?」
技師は言った。
「平賀源内殿の申されたエレキテルの力で起こす。ただ、まだ今の日の本ではそれが実現できる技術がない。」、と。
しかしこの施設内にそれらとまったく同じ事物が存在するとは、さすがに蒼紫も思わなかった。あれらの事物は幕府が資金援助をし、肝入りで作らせたものなのだ。が、その原理を用いた物がありそうに思った。この硝子は自然発光すると寂庵は言っていた。ならばその発光の仕方を検査するための機械がありそうだ。それにこのレンズ状の硝子がはまるのではないかと。巴がふと漏らした言葉を蒼紫は思い出した。
「この硝子は、明け方の光によく光るのです。なぜそうなのかは私には存じませんが、母がそう申しておりました。」
蒼紫は朝の光が差し込んでいる隙間を探した。隙間の欄干のような窓は、部屋の奥の方にあった。その奥まったところにその機械はあった。長い首の棹を持つ、ほこりまみれの古ぼけたものだった。地図を作る際に使う方位磁針や分度器に似たものだった。今から百年ほど前に、伊能忠敬もこのようなもので日本列島を測量したのである。見たところたいそう古いもので、いらない工作機械を放置していたとしか思えないものだった。発光検査に使うものではなさそうだ。が、この分度器状のものが気になった。地図を作る際には、このような分度器で、恒星の位置から正確な位置情報を算出する。それが怪しいと思った。蒼紫は機械の首の部分を探した。
あった。
はめ込む部分があり、そこにぴたりと硝子片は収まった。壁から差し込む光がその硝子に当たると、硝子片からは緑色の光線が向こう側の壁から外に、一筋の光となって放ちだした。自分と同じように先人も考えたのだと思うと、蒼紫は少しうれしくなった。
蒼紫は勇んで硝子のレンズを覗いた。しかしその思いは裏切られた。これではどこをその光線が指すのか特定できない。機械は自在に首が振れるし、隙間の幅はある程度ある。隙間から向こうの岩肌が見えていたが、それは一面の苔と雑草が蒸していて、緑の壁を作っていた。あの中のどこかに、この光線の焦点となる箇所が存在するのだ。しかし壁までは距離があり、ある程度特定しないと探すのは時間がかかりそうだった。苔をあの崖の上からめくっていくのか、それをしなければならないのか、と思ったその時、蒼紫の脳裏にひらめくものがあった。
「葡萄の下の女の脚――ヴィルゴか!」
ヴィルゴ、乙女座宮、硝子面には葡萄のつると女の脚が小さく彫られていた。それはふたつの硝子が組み合わさってはじめてわかる図柄だった。測量に使うほどの恒星が存在する、女性の星座というと乙女座しかない。葡萄というのは、乙女座の乙女が豊穣の女神デメテルだという一説があるからだ。蒼紫は黄道十二宮の乙女座の位置について思い出した。乙女座は秋分点の場所にあるから、方位ではおそらく西の、水平面の方角を指す。蒼紫はその位置を特定できた。御庭番衆であるから、簡易磁針を普段から持ち歩いていたのである。西に向かって分度器の機械の首を振らせてみた。同じような岩肌の中に、硝子からの光線が当たって、かすかにきらりと光るものがあった。何かのごく小さな金属片があそこにでっぱっている。あんな岩肌に、誰か小細工した者がいるのだ。蒼紫は崖下に向かって走り出した。時間がない。早く見つけ出さねばならない。
光が当たっている個所は幸いなことに、岩肌の上にはっきりと光点で示されていた。蒼紫はそこまで、忍び鎖で伝って登って行った。それほど高くない箇所に金属の小さな突起があった。その周りはシダや苔でおおわれていた。崖の上部から岩肌に山の地下水が注いでいるらしいかった。その錆が浮いた鉄の突起の周りに、四角い岩にはめ込まれた鉄板がある。なんと、これは引き出しか!蒼紫は驚かないようにした。鍵穴がどこかにあるはずだ。硝子と一緒にぽち袋に入っていた錆の浮いた小さな鍵が、そこには差し込まれるはずだ。蒼紫は注意深く探した。ようやく見つけた鍵穴らしき穴は、シダに隠れた鉄板の隅にあった。蒼紫が鍵穴に鍵を差し込むと、中でカチリとはずれる感触があった。蒼紫は引き出しを手前にゆっくりと引いた。中から油紙に包まれた大きな紙包みが出てきた。この中だ。
蒼紫は引き出しを元に戻し鍵を閉め、紙包みを持って降りた。崖から降りて、紙包みの中を改めた。木に刻印されている鑑札が一枚と、花紋印が押された書状が一枚丸められて入っていた。それらは頭目に渡すべき物なのだが、渡せば硝子製造の儀は上様には勝手にしていたことが、あの巴の父親のいた藩ではばれてしまう。それは巴にとって窮地に立たされるということなのではないか。巴の父親はこの藩の研究にかかわっていたのだから、その責は今以上に巴の肩に重くのしかかるのではないか。蒼紫は先ほどの朱膳の言葉を頭の中で反芻した。「愛娘がかわいくて」と奴は言っていた。誰か上役の、研究の犠牲になった娘がいたということではないか。やはりこの書状は頭目には差し出すべきではない。しかし刻限を過ぎると、頭目は何をはじめるかわからない。どうすれば、と蒼紫は思った。やはり徒手で頭目には臨むしかなさそうだ。蒼紫は崖上にまた登り始めた。時間かせぎではあれ、頭目にははっきりと言っておきたいことがあった。それをするのは今だ。自分の人生はここで終わるかもしれない。しかし、自分は巴に対して義を果たしたことはあったのだと。
それから半刻ほどたった頃だろうか。蒼紫の行方を追って、頭目たちと般若が馬で廃村の中に入ってきていた。蒼紫が制圧したので、頭目らは安全に馬を進めることができた。このような露払いの役は、多くは蒼紫の役割だった。それは今回に限ったことではなかった。般若は蒼紫について行けなかったことを悔やんでいたが、頭目の命令には逆らうことはできなかったのである。般若にも頭目が蒼紫を試していることが、今でははっきりとわかっていた。と、蒼紫の吹く鋭い呼び笛の音がした。蒼紫の合図だ。
「見つけたか!」
と、頭目は言った。手下の者たちと、頭目は蒼紫の前に走り出た。それはあの研究施設の前の小さな広場だった。頭目は馬から降り、周囲を一周して眺めた後、腕組みして蒼紫に近づいて来て言った。
「よくやった。刻限ぎりぎりだが、その手のものを渡してもらおう。」
蒼紫は静かに答えた。
「存在しない物は渡せない。朱印状があったという情報自体が偽りだったと言うことです・・・・・。」
頭目は眉を吊り上げた。
「何?そんなはずは・・・・。」
と、言いかけた次の瞬間、頭目は蒼紫の胸倉を激しくつかんだ。
「貴様、やったのか?」
と頭目はどなった。蒼紫は無言で顔を背けた。周囲の者は驚いて頭目に尋ねた。
「やったって何をです?」
頭目はどなった。
「こやつは書状を燃やした!顔に出ておるわ!探せ!」
と頭目はどなった。そして蒼紫に言った。
「その方、重罪だということは重々承知だな?まず、貴様の体に聞いてやらねばなるまい。その書状のありかを。」
頭目は剣を引き抜き、蒼紫の面に突き付けた。憤怒の形相だった。蒼紫は剣をからくも己が小太刀で受け止めた。押し合いながらの問答になった。
「言え。あの硝子と鍵が収まっていた場所はどこだったかを。さすれば命だけは助けてやる。」
「ないものは、ない。」
「あの女がそれほど大事か!あの女の命と、我ら御庭番衆の存続と、両天秤にかけられると思うてか!」
蒼紫は言った。これまで考えていた言葉だった。それはすらすらと蒼紫の口をついて出た。
「御庭番衆がいかほどのものでしょうか。砂を崩すように女から産まれる命を奪い、それで生き続ける。その、御庭番衆がいかほどのものでありましょうか。」
頭目は蒼紫の言葉に、ぴくりと眉を動かした。
「凡弱のはした女にたぶらかされおって!しかし、その方のそういった心持ち、はっきりと読めたのは正解だったわ!そしてそれを、根こそぎ絶つ機会が与えられたのもな!」
蒼紫と頭目はいったん剣先を離した。双方態勢を整えている。頭目は言った。
「葉霞から奪い、硝子は両方そろったのだろうな?それだけでも差し出したらどうだ?」
蒼紫は無言で硝子を手に握って振り挙げると、地面に激しく叩きつけた。硝子は粉々に割れた。頭目は瞬間逆上した。
「きさまっ・・・・!これほど愚かだとは・・・・!」
そして、頭目は態勢を整えて息を深く吐いた。かかった。これが見たかったのだ。頭目の回転剣舞六連――それはみだりに頭目は披露することはないし、それで殺すことも最近ではめったにない。殺しはもっぱら蒼紫の仕事だった。しかしそれを己れの体で試すことになろうとは。ここで死出の旅路になればそれまで――蒼紫は、己れの未完のそれを、頭目同様に軌跡を描いて同時に動いた。斬。蒼紫の体は頭目の作る真空の暴風に、中空を舞った。般若は思わず瞑目した。
――蒼紫様!
般若が面を伏せたのと、蒼紫の体が地に落ちたのは同時だった。頭目はすでに技を終えていた。頭目は激しく息をついて言った。
「馬鹿者が・・・・まだ殺しはせん・・・・・しばらく寝ていろ・・・・・。」
そして息を整え、周囲の忍び装束に向かって手を広げて声を荒げた。
「部屋の中の機械を動かした跡がある!蒼紫の足跡から見て、その崖の壁のどこかだ!探せ!一昼夜かかっても、調べ上げろ!上様にご報告せねばならん!書状そのものはなくても、連中が隠したという事実は必要なのだ!」
それから二晩かかって、御庭番衆はその崖の鉄製の引き出しをこじ開けた。中には油紙が丸められて入っているだけであった。
暁闇 上
蒼紫の身柄は江戸に護送された。頭目の技でひどく傷ついた彼は、手術をし、怪我の養生をされ、その後頭目の命令で座敷牢に閉じ込められた。自分が生き伸びていることを、最初蒼紫は牢の中で呪った。こうしている間にも、巴は京で九ノ一の法をやらされているのは明白だったからだ。しかし彼は「然るべき日」のために、自分は今体力を養い、温存しておくべきだと思うようになった。それは一見卑怯なことだったかもしれない。矢も楯もとりあわず、脱獄して巴を救いに行くべきだと当然最初に彼は考えたが、すぐにそれを打ち消した。なぜなら今の自分にはそれができるだけの力がなかったからだ。第一頭目の技を破れない今の自分にいったい何ができると言うのか。功利的に物を考えるのは蒼紫の習いであった。結局彼は妥協したのである。しかしそれは、幼い考えの克服だった。巴も自分もだめになる方法は避けねばならなかった。彼は脳裏に刻んだ頭目の必殺技を、幾度も頭の中で反芻した。あれを破る方法を見つけ出さねばならぬ。
巴に再び会うことができる日、それは何時になるのか、蒼紫にはまったくわからなかった。自然彼は、死んだ寂庵から幼い日に習った座禅を、暗い牢の中で黙然と紡ぐようになった。巴とは何時か再会できるかもしれない。それは何時になるのか――その時、巴はすでに自分の手には届かないところで暮らしているかもしれないと思った。彼にはそれでもよかった。巴が一日でも多く生き伸びれたことが、彼にはうれしかった。しかし蒼紫のそれらの想いは、牢に食事を運んでくる般若たちにも決して気づかれることはなかった。彼らには、日の差さない座敷の中ほどで、黙って印を結んで座っていたり、一人黙々と体の行を積んでいる蒼紫を見るだけであった。ただ彼らは、頭目と蒼紫の関係が、後戻りができないところにまで行ってしまったということだけを理解した。それでも頭目は次期御頭に蒼紫を選ぶだろうかと、彼らは蒼紫の身を案じた。
兆しはしかし、上つ方の方から訪れた。蒼紫らがこのほど中山道の探索の旅に出されたのは文久三年(1863年)の秋の暮れの事であった。その頃、幕府内部では新選組を結成させたり、十四代将軍徳川家茂の後見人に一橋慶喜が任じられるなどして、攘夷の機運が高まり、海外への密輸の密造品硝子の話は立ち消えになっていったのである。要するに、以前寂庵が軽口で言ったような「そのような事にかかずらかっている時間も惜しい」という風潮になっていったのである。何しろ朱印状の裏も取れなかった案件であるから、そのことに対する叱責はあったものの、御庭番衆は別のことで動くことになった。それは京での長州藩の暗躍である。頭目はそれにはいずれ自らが向かうつもりであったが、それにはまた下働きの蒼紫らを束ねる必要があった。しかし蒼紫が養生している間は、西の御庭番衆の闇の武で守ってもらおうと思った。それはここ一年間ぐらいだろうと頭目は目算を踏んでいた。
頭目は闇の武の辰巳と、京都御庭番衆の翁に手紙を書いた。「くれぐれも隠密に事を運べ」と頭目は筆で記した。それには京都守護職に任じられた、松平容保公の会津藩への配慮もあった。彼らの子飼いの京都所司代の新選組の邪魔をしてはまずいのである。会津は長州や薩摩と並ぶ、巨大な藩であった。その会津に屋台骨を借りねばならぬのが今の幕府だ。
「しかしこのような時にこそ、おなごの出番はあるものじゃ。」
と、頭目は書の封をしながらひとりごちた。大きな戦の前の前哨戦、そのような時にこそ秘密裏の工作は行うものなのだ。あの巴がその動乱で消えてくれれば、わしの目算はかなったものになる。思えば以前、葉霞の閨に蒼紫を送り込んだ時もそうじゃったな、と頭目は考えた。これを乗り越えて、つけられた心の傷を痛いとも思わなくなれば、今後蒼紫は頭目としてさらに心を鬼にできるじゃろう、と。
「鬼子はいずれ天の子となる。」
と言って、頭目は含み笑いをした。蒼紫はおそらくこの試練を乗り越えるだろうと思った。そうでなければわしの見込んだ男ではない――と。そして、それは頭目の判断では間違いはなかった。蒼紫にはどこか酷薄な情があった。あれには今長い思索の時間を牢の中で強いているのだから、自分をこのような境遇に陥らせた巴という女の存在について、一から考えなおしているはずだ。何しろ回転剣舞で全身を縫い合わせることをしたのだ。
「あの技はちと、蒼紫には酷だったかのう。」
と頭目は言って窓の障子を少し開けた。外には音もなく、根雪が積り出していた。頭目は庭のまだ裸の梅の枝を見ながら低くつぶやいた。
「雪代巴――しばらくは大津の宿で留め置き、それから京に送り出すか。果たしてうまく役だってくれるか。あの女一匹が。」
遠くで小さく寺の鐘の音がした。
巴は今近江路のはずれを闇の武の一行と歩いていた。途中いくつかの宿で待機することもあった。山並みに沿って田畑が続いている先に、その湖水はあった。まるで海のような――と巴は思った。そう言えば下諏訪でも、峠から諏訪湖が見えた時、ほっとした思いが胸に沸いた。あの時は蒼紫がそばにいた。今は違う。琵琶湖は諏訪湖よりも遥かに広く、先は見えないところが偽りの海のようだった。この湖の水は淡水で、涙に似た塩の水でできている海水ではない。だからこの地で私がこの先流すのも空涙だ――と、巴は思った。闇の武たちが勝手に決めている、清里の仇討ちというのも、巴自身が願ったものとはほど遠い。清里はきっと京で死んだ時無念だったろうに、でも私にはかたき討ちなど人を殺すのは恐ろしい。私という女は、と巴は湖に目を落とした。陽の光がきらきらと水面で反射している。あの光だけは蒼紫と見た諏訪湖と同じ、と巴は思った。懐かしいと、そう思った。
近江の宿で縁は留め置かれることになった。その宿で、縁には知られないようにして、巴は流行りの「写真」を撮られた。何のためかはわからなかった。上半身の着物を脱げと言われて、拒否することはできなかった。もちろん巴の手にはその写真は渡ることはなかった。寂庵さんが私の人相書きを無効にすると言ったのに、と巴は悲しかった。こうして九ノ一として生きていくことを強制させられるのかと思った。その写真はおそらく下層民たちの人別帳のようなものに収集されるのだろうと思った。ただ、もしかしてその写真を蒼紫が見ることがあるのかもしれない。蒼紫は次期御頭になる予定があると辰巳は言っていた。蒼紫がもし将来そうなれば、私が京で生きていたという証をいつの日が見るかもしれない。それならば喜ばしいと思った。そう考えて自分を慰めるしかなかった。
巴が京入りしたのは四月の終わりである。季節的には肌寒い日々で、氷雨が数日続いていた。案内された宿の近くには、連日の雨に勢いを増して、鈴蘭の花が道なりに咲いていた。その白い鈴型の花は可憐だが、猛毒。その時、辰巳たちから会合で聞かされた、「清里明良を殺した下手人の男は、まだ少年だ」という話を聞いて、巴が感じ取ったものである。その少年に近づき、油断させる。そして後日辰巳たちの手引きをする。なぜと思った。回りくどいやり方のように巴には思えた。もちろんその少年の命を狙いたいからそう思ったのではない。巴もまた、蒼紫と性質が似ていて、合理的に物を考えるところがあった。その方法は巴の考えでは、着実ではないのである。辰巳たちが人をもっと集めて、少年を闇討ちにした方が確実に思えた。しかし辰巳たちはそれを巴にやらせたいらしい。それが九ノ一の法だ、とだけ辰巳は言った。
「貴様には他の選択肢はないのだ。あの蒼紫という若造の命を救いたくば、努力してみろ。」
と、辰巳は言った。
「江戸と京、それほどの距離にいる男が、死んだ亭主よりも大事だと言うのならばな。」
と。
巴は無言だった。清里の亡霊から蒼紫との仲を止められているような気がした。しかし蒼紫を思いきることは、今や身を切られるようにつらいことだった。どうしてあの人が私の心の中に住んでしまったのだろう、と巴は思った。ただ何も考えずに清里の仇討ちで、と思えば楽になれると思った。しかしそれはできなかった。だってあの人だけが今まで私を救ってくれた、と巴は思った。清里は私を乱暴に抱いて、京に上って一人死んでしまった。死ぬ時は清里も私を思ったのかもしれない、でも結局私を置き去りにして、こんなことに巻き込んで、と巴は思った。辰巳たちのいない場所で、巴はひとり涙を流した。
巴は今大衆酒場で杯を傾けている。外はやはり本降りの雨、その五間先の四ツ辻に、その清里を討った少年に罠をかけている辰巳の仲間が来ている。今からそこへ向かう。もしその少年が倒されていたら、私の任務は終わったことになる。そうなればいいと巴は思った。少年の命の火が消えるのを願う、それは決して褒められた心の動きではなかった。また、その少年が私も間者と見て刃を向けて来るかもしれない。私も斬られるかもしれない。そう思い、巴は一杯だけ冷酒をあけた。それは固めの杯だった。何に向かってと問われれば、蒼紫との死に杯のつもりだった。杯をあおる時目を閉じて、神前の前で蒼紫と向かい合っているような静かな気持ちを想い描いてみた。しかしすぐに我に帰り、居酒屋の喧噪を背に巴は格子戸を引き、紫の藤渦紋の蛇の目傘を広げた。これも歌舞伎舞台の「藤娘」で使う番傘、渡されたのはその少年への演出の一環だろう、その上にかすかに袂に香水をつけている。辰巳たちから「これをつけろ」と渡された、白梅香の香だ。色街や相撲部屋で鬢付けに使うものだったが、何か意味があるのかもしれなかった。しかし辰巳に問うことは許されなかった。そのかすかに酸味のある香りが、子供の頃に食べた一銭駄菓子のにおいのようで、これからその殺人者の少年を見ることになる巴の気分を物悲しくさせた。
京の夜道は暗澹としていた。土砂降りの中を、一歩一歩巴は剣戟の音の方へと近づいた。苦悶の声がして、少年が鎖で攻撃されているところを、信じられないほどの跳躍をして、虚空から闇の武の一員に激しく斬撃を加えたのが見えた。巴は瞬きもせずそれを見ている。かなりの手練れだ。あんな風に清里も殺されたに違いない――と、相手の男の首を少年が唐竹のように刀で割り、血煙がぱっとこちらにまで飛び散って、巴は一瞬足がすくんだが、蒼紫が大丈夫だと言ってくれたような気がして、勇気を出して先に歩を進めた。男を斬った少年が巴の気配に振り向いた時、巴はやっとその言葉を口にした。
「本当に・・・・・あなたは降らせるのですね――血の、雨を・・・・。」
かねてから考えていた、一見相手への称賛に聞こえるが、巴自身蒼紫に言われた言葉を反芻して思いついたセリフだった。――『その名前が消されるのは惜しい。血の雨で・・・。』
なぜか少年が刀をかちゃりと取り落とした音がした。なぜ、と思った時巴の意識は急速に薄れた。最後の言葉は、まるで蒼紫に向かって言っているようだった。巴は虚空に手を伸ばしながら口の中でつぶやいた。巴の顔に涙雨のような雨粒が落ち、その白い顔に斑紋のような血痕の花を広げている。そのかそけき、赤く白い花・・・・・・。
「血を・・・・血を・・・・降らせないで・・・・・・。」
雨の中、少年がこちらに向かって駆けだすのと、巴が倒れるのは同時だった。巴が先ほど口にした酒が、思いのほか強い酒だったのかもしれない。注文時に銘柄など言える巴ではなかった。でも私はこのまま斬られた方がいいのかもしれない・・・・そう思いながら、巴は闇に意識を手放した。
長州藩の遊撃剣士である緋村剣心は、その時何を見たのか最初わからなかった。ただ、人影に敵に剣をふるっているところを見られたと思った。目を凝らして見たところ、雨の中傘を差して立つ白い少女だった。彼はその時、遠い幼い日に見た、人買いに売られていく途中の哀れな女性たちを思い出したのだろうか。彼女たちはその道中で、剣心の目の前でならず者に襲われて殺されてしまった。幼い剣心はその者らの墓を比古の目の前で作ったのである。おそらく少女をとっさに助けなければと思ったのはその為だったのだろう、敵の間者と間を置かずに現れたことを不審に思う暇もなかった。少女が雨道に倒れ伏したからである。剣心はその体を担ぎ上げた。担ぎ上げ、歩きだしながら思った。
これからこの少女を長州の宿に連れて帰れば、おそらく上司である桂小五郎は快く思わぬと思った。しかしその桂にも女がいる。幾松という芸者の女性だ。桂の下働きをしていた剣心は、その事についてやはり、年若い事もあって、心中不服に思っていた。かつての彼の剣の師である比古清十郎にはそのような女性は存在しなかった。いや、いたのかもしれないが、剣心と暮らす山小屋には存在していなかった。半ば世捨て人だった比古のような男の方が世の中では珍しいのだ。京で暮らすうちにそう思う剣心だったが、その山を下りるなという師の命に背いた以上、比古を懐かしく思うことは許されなかった。しかし今その下で働いている、桂にあてつけるようにしてみたいと心の底で思った剣心の気持ちには、そのような二人の男の比較があったのだ。この少女には一夜の宿を貸すだけだと思った。行きずりの女を連れ帰ったというだけの話だ。明日にはもうこの少女は別のところで、自分のことも忘れて元気に暮らすに相違ない。自分はただ、たまたまそこに居合わせただけだと思った。剣心のその時の感じ方はそのようなものであった。
ただ、少女が口にした「血の雨を降らせるのですね」というセリフは、剣心の心の虚を突くものだった。血と聞くと思うことがある。左頬にこのところ、薄く血がにじんで口が閉じない一筋の傷ができている。あれは去年の三月頃の出来事だった。春先の寒椿が咲いていたのを覚えている。その寒椿の乱れ咲く生垣の近くで、剣心は男を一人斬った。頬の傷はその時につけられたものだ。男の生きようとする執念はすさまじかった。何度斬りつけてもなかなか死なず、剣心はとどめの剣をその頭骸骨に突き刺した。男は京都見廻り組の者で、幕府の役人の護衛役だった。しかしそのような者は他にもいたのだ。数限りなくそのような者らをこれまで討ち取ってきた。だが古傷が治らないのは、その男の時だけだった。このところ剣心の腰ぎんちゃくのようにして付き従っている検分役の飯塚が、それを見て言ったものである。
「その傷には、死んだ男の念が入っちまってるな。念を抜くには女だぜ。」
剣心は飯塚の言を無視した。色街で遊ぶことでは、返ってその死んだ男に恨まれてしかるべき話だ。しかし飯塚にはそういうところが多かった。剣心には、頬の傷にはそうした忸怩たる思いがある。その決してふさがらない傷は、己自身の心のありようにも似ていた。その血を少女は指摘していた。
従って、剣心としては小萩屋のおかみに着物が濡れた巴の身柄を託した後で、一晩たてば彼女はまた市井に戻るものと思っていたから、次の日の朝巴が仲居の藤色の小袖を着て、御膳を運んでくるのを見て驚いた。巴は仲間たちの好奇の目に動じず、「巴と申します。以後お見知りおきを。」と答えて茶碗にお櫃からごはんをよそって差し出している。飯塚が巴が配膳を終え立ちあがったのを見計らって、
「で、『具合』はどうだった?」と剣心に尋ねた。
剣心はむっとして、剣の鍔を鳴らして立ちあがった。巴を助けたのはそのためではないのだ。自分の下心を指摘されるのも苦々しいことだった。剣心はたまらず、廊下で巴の手を取り、呼び止めた。
「何をしている?」
巴は積み上げられた膳を持ちながら、剣心に振り向き軽く礼をして答えた。
「昨夜は危ないところを助けていただき、ありがとうございます。ここのおかみさんに人手が足らないから、入ってくれと頼まれました。」
「昨日はどうして。」
「酔っていたんです。」
それだけ言うと、巴は回れ右でつ、と歩を進めた。取りつくしまもなかった。剣心はこの宿は今は長州派の根城だから危険だ、と言いかけてその言葉を飲み込んだ。それを知らせることすら用心しなければならなかった。何よりも昨晩ああして現れたのだ。しかし剣心が懸念しているうちに、巴は小萩屋の臨時下働きとして雇われることになった。不思議なのはここのおかみの態度で、巴がいることを彼女は歓迎している風ではなかったが、出て行くように持っていかなかったことだ。裏に何かある、と思う剣心の元に、飯塚がいつものように、巴の素性を桂に報告しているのが耳に入った。
「言葉にかすかに江戸なまりがありますね。おそらく江戸方面から来た女性でしょう。見たところ武家の出、しかし下級武士の女に間違いありません。素性はそれしかわかりませんが、隊士たちのいい空気抜きになるかと。見たところ上玉ですし、ああした女が尽くしてくれることは、隊士たちの気勢があがります。」
桂は飯塚の言葉に鷹揚にうなずいたが、こうも答えた。
「しかし緋村が襲われた辻に、現れたのだからな。同様に庭番衆のたぐいかもしれん。用心に越したことはないのだ。」
飯塚は桂に軽快に笑って答えた。
「あんな女のひとりや二人、どうってことはありませんや。むしろこちらの味方に引き入れるぐらいの気構えが大切です。長州派はこれからですぜ、旦那。吉田松陰先生が亡くなって以来、沈んだ一門を盛り上げるためにも、女は必要です。次につなぐためにもね。」
「そうだな。」
剣心は無言で二人の立ち話の会話を聞き、羽目板をきしませて階段を上って行った。それがあの騒動の三ケ月ほど前の話だった。季節は移り、夏の日になった。蝉が鳴き始めた頃も巴はまだ小萩屋の宿で働いていたし、剣心も天誅を加える毎日だった。そのある時、桂が苦々しい顔をして、幾松に見送られて会合の部屋を出てきた時があった。
「もっての他だ、京に火をつけるなど。」
と、桂は叱咤の小声で言い、廊下に立つ剣心に気づいて「聴いていたのか?」と声をかけた。剣心はいつもの習いで「俺は何も」と答えた。剣心の桂の用心棒の仕事は、そのようなものであった。
その日も剣心はふだん寝起きしている二階の六畳部屋に入り、積み上げた読み本の束に背を預けて、刀を抱き目をつむった。読み本は勇壮な武者ものがほとんどで、無学な剣心は桂たちの読んでいる難解な漢文の国学書にはほとんど目を通さない。市井で売っている、それらのゾッキ本のようなものを好んで集めているのだ。しかしそれらに描かれている物語の中の武士たちの活躍と、自分の今の状況とには恐るべき乖離があった。桂たちのところにそんな剣心がやって来たのも、いわゆる市井で言うところの「世直し」をするためだった。桂の言う難解な水戸学をはじめとする国学は、剣心にはわからない。しかし比古に剣を教えられて以来、それを世の中で役立ててみたい思いは止められなかった。でなければ、あんなに痛い思いをして幼少時から比古に剣を習った意味がなくなるのだ。比古は自分をただ単なる一子相伝の伝承の使い手にしたかったようだが、それでは己の人生ではない。剣心にはそういう思いがあった。しかし、その結果がこの日常かとも剣心は今考えている。切り刻んでも切り刻んでも、敵は現れた。一度剣を取った以上、そうなるな、とかつて比古に言われたことがあった。だからあの今に比べればやさしく穏やかだった日々、あの比古のもとにもう一度帰りたい、と思う気持ちがあった。しかし自分はそれを否定しなければならぬ。夢うつつに、剣心は剣を取り、和室に静かに眠る巴の首に剣を突き立てた。否定しなければならぬ――剣心ははっ、と驚いて目を覚ました。間近にその巴の白い顔があった。とっさに剣心は剣を抜いて巴に斬りかかった。巴が声もあげず身をすくめるのがわかった。剣心は叫んだ。
「君はっ。」
ばん、と巴の体を横にはらった。巴が畳に尻もちをつくのを見て、剣心は驚いて息をついて言った。
「寝込みを襲うとは、君はいったい・・・。」
巴は答えた。
「寝込み?」
「武士の急所だ。どんな使い手でも、眠っている時には隙ができる。君はそれを、今した。もう構わないでくれ、俺には・・・。」
巴は畳に手をつき、乱れた髪をなおして起き上がって言った。
「そんなつもりはありません・・・。この前、手洗いであなたが頬の傷を気にしていたから、つい覗いたのです。すみませんでした・・・・。」
剣心は思わず頬に手をやった。そう言えば、手洗いで傷口と顔を洗っている時に、音もなく後ろで立っていて、てぬぐいを渡してくれた仲居がいた。あれが巴だったのか。
剣心は巴に尋ねた。
「この傷、気になるのか。」
「血が出ていましたから・・・。口が閉じないみたいですね。膏薬を差し上げます。下から取ってきます。」
「いや、いい。」
「でも。」
「俺は、血を流した方がいいんだ。それぐらいのことはしているから・・・。」
剣心は答えた。我ながら自分に酔った言い方だと思ったが、それ以外に言葉が出なかった。巴はそれをけげんそうな顔で見ていたが、不意に言った。
「お掃除するのに部屋に入りました。このあと少し時間があります。つきあってくださっていいですか?おかみさんから暇をもらいました。」
「え・・・・。」
「今日は祇園祭ですから。」
それだけ言うと、巴は階段を降りて行った。剣心は狐につままれたようだった。相変わらず何を考えているかわからない女性だ。しかしやはり、間近で見た巴の表情は美しかった。自分は巴に心を動かされているから、今あんな夢を見たのだと思った。その通りで、剣心は我知らず、巴の姿を目で追っていることが多かった。あの雨の日巴を助けたことで、彼には特別な思い入れがあったのだ。あの雨の中傘を差して現れた巴は、思い返すと舞台に立つ藤娘よりも可憐に思えた。その巴に祇園祭に誘われた。浮足立つ気持ちは抑えられなかった。何よりも今巴が同情して、傷口に膏薬を塗ると言ってくれたことが剣心の気持ちを動かした。それは男所帯では得られなかったやさしさだった。
巴は剣心と祭を見に行く支度をした。久しぶりに着る着物で、仲居の制服の藤の小袖を脱ぎ例の白い小袖を出して着た。今より二週間ほど前、桂に廊下で呼び止められて、部屋に招かれたことがあった。少し君と話がしたい、と言われた。幾松がいるのに、と巴があきらめたように部屋に行くと、桂はふつうに座敷に座っていて、座布団を巴に進めた。巴は桂を少し見直した。性的な意味で呼ばれたのではなかったのだ。桂は言った。
「話というのは緋村のことだ。君はあれをどう思っているのか。あれが君のことを時々見ているのは知っているな?」
巴はかすかにうなずいた。剣心にはわざと一見冷たくふるまうようにしていた。剣心は蒼紫よりも年若い少年で、蒼紫と比べて見ていて気の毒なぐらい気持ちが顔に出る男だった。巴がそれらしいそぶりを見せると、気にしているのは明らかだった。連絡で会った時の辰巳からそのようにしろと言われた。そして、巴自身の気持ちもあった。清里を討ったのはこの剣心なのだ。それは検分役を勤めている飯塚の言葉からも明らかだった。最初巴は飯塚と京で再会した時、信じられない思いでいっぱいだったが、やがてそれもあきらめた。そのような二重スパイの浪人ものが京には大勢いるのだ。そのような輩から身を守るようにすることで、巴には精一杯だった。飯塚とはしかし距離を置き、ふだんはそ知らぬ顔をするようにしていた。そのような毎日は巴にとって針のむしろだった。桂は話を続けた。
「話というのは他でもない、君に私の幾松のようになってもらいたい。緋村にとっての。それが一番だと思う。緋村という世直しの抜き身の剣を収める鞘になってもらいたい。私はあれには酷薄なことをしているのだ。ひとりの前途ある青年の未来を、私の将来のために買ってしまっている。それは緋村にとって、とてもつらいことだ。だからせめて君が、彼の心の支えになってもらいたい。」
巴は答えた。
「それは私に、緋村さんと夫婦になれということでしょうか?」
「そうだ。そういう意味だ。緋村と正式には所帯を持つことにはならないかもしれないが、彼の身の周りを世話してやってもらいたい。まだすぐにとは言わない。しかしその心づもりはしてもらいたい。もちろん給金は出すつもりだ。」
「お金のために夫婦になれと言われるのですか。」
「君の気持ちを考えていないわけではない。しかし緋村は、長州藩の天道の世直しのために必要な力なのだ。考えておいてくれ。以上だ。」
巴は部屋を退きながら、これで辰巳の計画していた通りになったと思った。まるで辰巳と桂が以心伝心でつながっているようだった。あまりにもすんなりと九ノ一の事が運んで、巴は自分の前途がすべて計画されているものではないかと思い、暗澹とした。剣心とこれから夫婦生活を送るのはつらすぎた。清里のこともあったが、蒼紫のことがあまりにもその心に重くのしかかった。蒼紫は今どうしているのか。蒼紫の助けなど絶望的だ。ただあの人がどうしているのか、どう思っているのか知りたい。一刻も早く私はここから逃げ出したい。そうした思いが顔に出ていたのであろう、ある時小萩屋のおかみが暖簾の影から手招きし、「これ角の葵屋の旦那はんに持っていってんか。」と言って、花菖蒲を切った大きな花束を巴に手渡した。
「今日は水無月祀りなんえ。ええ色やろ、紺の。」
「はい・・・・。」
「後であんたにも水無月のお菓子あげるさかいな。この花、あんたに似てるな。日の当たらんところでは映える、お天道さんの元では泣く――。」
巴は菖蒲の花束を抱えて、小萩屋の数軒先の角にある、紺の長暖簾のかかった宿屋に入った。紺に白抜きで「葵屋」と染め抜かれている。暗く長い路地の奥に、人影が見えた。老人だ。
巴は戸口から声をかけた。
「お花を御持ちしました。ここへ置いておきます。」
老人が答えた。
「小萩屋さんからの使いかね?その花は水につけた方がいい。裏庭の方へ来なさい。」
「はい。」
巴が勝手口の方に回ると、背の高い老人が現れた。
「あなたは雪代巴さんじゃな?小萩屋さんから話は聞いている。ささ、こちらへあがりなさい。花はそこの樽につけて。」
と言われ、縁側に座るようにすすめられた。老人は麦茶を湯のみに入れて差し出すと、巴に言った。
「あんたと少し話がしたい。わしは通し名を翁と言うてな・・・・・寂庵という老人をご存じじゃな?」
巴は目を丸くした。
「まさか、あなたは・・・。」
翁は腕組みをして答えた。
「そのまさかじゃ。あなたのことは、般若からの伝書鳩であらかた伝え聞いとる。あんたには気の毒じゃが、わしの力ではその九ノ一の法ははずすことはできん。辰巳の言うとおりに動くしかない。こんなことしか言えんわしを許してほしい。」
巴はかぶりを振った。
「翁さまとは今日お会いしたばかり、そのようなこと。」
「わしは京都御庭番衆を預かる身じゃが・・・・江戸に逆らうことはできん。しかし辰巳のやり方にはわしも不服がある。そこでじゃ。」
と、翁は立ち上がり、屋敷の奥から一振りの短刀を持ってきた。巴の前にその黒塗りの短刀を差出し、翁は言った。
「この刀は蒼紫の亡くなった母親の懐剣じゃ。」
「え。」
巴は目を見張った。蒼紫と自分のことまで、伝聞でこの翁という老人には筒抜けになっているのかと思った。翁は言った。
「あんたの護身用に持っておりなさい。しかし自らに刃を向けてはならんぞ。あくまで、己の身が危ないと思うたら、それで相手を脅すことじゃ。わかったな。」
「・・・・・・・。」
「武家の女ならば必ず持つようなもの、このようなものも持たせずに探索をさせるか。辰巳のやつめ、おぬしをおなごと思うてあなどっておるわ。あんたももともとは武士の出じゃろう?」
「どうして翁さまがこの刀を・・・・。」
翁は目をしばたかせた。
「もともとあれはわしが、江戸にいる頭目のところへ連れて行った経緯があってな。あれにはわしはその事で恨まれていると思う。その刀はその時の遺品じゃ。」
「そうですか・・・・。」
「頭目は母離れのために蒼紫からこの刀も取り上げて、江戸へ連れて行った。まだ幼い頃じゃったのう。あれはいくつの時じゃったかのう・・・・。」
巴は刀を手に取ってみた。漆塗りの軽い刀だった。蒼紫の使っていた小太刀とよく似ていた。懐かしくて、巴の両目からつい涙がぽろぽろとこぼれた。翁はそれを見て、あわてたようだ。
「おおお、これはいかん・・・。小萩屋さんで気取られてはまずいのじゃ。時間を置いて帰りなさい。そうそう、持ってきた花を活けてもらおうかのう。そこに花瓶がある。どれでも好きなものを選びなさい。心を落ち着けて、心静かに活けてから帰りなさい。」
巴は翁に礼を言うと、縁続きの座敷に上がり込み、小半時かけて花菖蒲を活けた。そのすらりと長い花茎は、蒼紫の折り目正しいたたずまいを思い出させた。翁は巴の活けた生け花を、「立派なものじゃな」とだけ評した。葵屋からの帰り道、巴は何度も帯の下の懐剣を確かめた。
その夜、小萩屋の女中部屋で皆が寝静まったあと、巴は寝床から起き上がり、そっと懐剣を窓の月明りの下で抜いてみた。巴の顔がうっすらと銀の刃の上に映った。もうあの時の刀傷は、自分の顔の上には残ってない。消えてしまった。あの街道筋の雨宿りの場所で、蒼紫が指で触れた傷はなくなってしまった。それは蒼紫が、私の身を守ってくれたから、敵からの遺恨の傷を残さなかったのだ――そう思った。しかし思い出だけと思うのが悲しかった。
しかしその遺恨の傷が大きく頬に残っている剣心と、これから祇園会に行くのだった。巴は鏡の前で白の着物を確かめ、帯に懐剣をはさんだ。最初の雨の出会いの時の白装束。剣心は知らなかったが、彼を足止めするように言い渡された極秘任務だった。なぜなら今日、池田屋で新選組が長州志士を討ち取る算段が動いているのだ。抜刀斎がそこに現れるのは、得策ではないのだった。こんな事をなぜ私に、と思う巴だったが、巴はその先鋒を担がされているのだ。抜刀斎はそれぐらい幕府側から恐れられており、正攻法では攻めることができないと思われているらしかった。
巴は剣心と、最初に出会った時に入った居酒屋で向かい合って杯をあけた。剣心は巴よりも見たところ年若かったが、特に臆することもなく巴と杯を傾けた。桂たちと色街で、芸姑の酌を受けることもあったのだろうと思った。剣心が言った。
「君はいける口なのだな。」
巴は答えた。
「少しぐらいなら。たしなみとして飲んでいました。郷(さと)は貧しくとも武家でしたから。」
「そうか。俺も元は武士ではない。こういうものを飲むのも、ここへ来て初めてだ。」
「そうですか・・・・。私はだめですね。お酒にたよってばかり。」
剣心が目を見張った。
「たよるほど飲まずにはいられなかったのか?君が?」
「いえ、そういうわけでは。」
巴は困ったようにふ、と目を伏せた。沈黙があった。蒼紫のことを思ってあの時この酒場で杯をあけた話をしてみたかったから、あえて「お酒にたよっている」と言った。お酒にたよっている、それは蒼紫という男にたよってばかりいる、だめな自分のことだった。しかしそれは決して打ち明けてはならない話だった。剣心には自分はまっさらな女でいなければならなかった。清里のことも蒼紫のことも、話してはならない事だった。
剣心が巴が黙り込んだので身じろぎした。このままでは間が持たない。やはり自分は口下手だからだめだ。そう思った時に剣心が言った。
「河原の方へ行ってみよう。山車(だし)が出ていると思うから。」
「はい――。」
剣心が立ちあがった。ついて行かなければならなかった。巴もあわてて席を立った。
その数日前――。
京都守護職・会津藩預かり新選組は、壬生の屯所で、四条小橋で炭薪商を営む枡屋善右衛門こと古高俊太郎を捕縛していた。それも京都市中に多数の長州藩士が潜伏しているとの報を受け、別動隊組織が日々巡回をし、探索した結果わかったものだった。古高を捕らえたのは武田観柳斎で、古高は組副長である土方らに拷問を受け、自白したのが朝彦親王の襲撃計画・京都焼き討ち計画・孝明天皇の拉致計画などであった。そのため新選組隊士たちによる京都市中の大規模な探索が開始されることになり、これが池田屋事件へとつながっていくのである。
その何度かの市中探索で、三番組隊長である斎藤一は、一番組隊長である沖田総司とともに、天誅の札を置かれた何人かの轢死体を検分した。時刻は薄明の夜である。提灯を手にした隊士が照らす横で、斎藤は言った。
「剣の入りから見て、かなりの使い手だな。暗がりで見たものは、赤い髪をした男が逃げるのを目撃したそうだ。」
沖田は言った。
「流派は何だと思われますか?」
斎藤は答えた。
「わからん。一撃必殺の感じから見て、居合抜きが得意なやつみたいだ。お前の天然理心流の見立てならどうだ?」
「そう言う斎藤さんはどうです?無骸流なら簡単に倒せるでしょう?斎藤さんの得意技の牙突は、居合抜きみたいなものです。」
竹刀での練習試合のようににこやかに言う沖田に、斎藤はたしなめるように言った。
「沖田くん。言葉というものは発する前によく咀嚼し、よく吟味してから舌の上に乗せるべきものだ。注意したまえ。」
斎藤の言葉に、沖田は明るく笑って答えた。
「あはは、豊玉師匠のようなことを言いますね?」
豊玉師匠というのは、副長土方の俳句をひねる時の雅号である。斎藤は答えた。
「副長助勤を務める身とあっては、その言も賛同しかねることだな。土方さんは、今回汚れ役を買って出られたのだ。君なら拷問など悲鳴を上げて逃げるだろう。責任感がなければできんぞ。」
「はいはい。」
斎藤たちは検分を終えたので、夜道を歩き出した。斎藤は言った。
「今度の襲撃にもこの下手人の男が出てくるとなると厄介だ。」
「僕はその人と戦ってみたいな。どうせ先は長くないんです。腕試ししてみたいですよ。」
「そういう事を言うな。病は治せよ。」
「はい、斎藤さん。斎藤さんはいい人ですね。」
「なにがだ。」
「僕の父親みたいだから。」
「何を言うか。」
斎藤は叱るようにそう言うと、すたすたと前を歩きだした。もう梅雨明けの頃で、月の明るい夜だった。
その彼らが歩いた路地からそう遠く離れていない河原で、今剣心と巴が所在なげに歩いている。河原で二人並んで立ち止まった。遠くで祭りのお囃子の音がしていた。巴は川面を見て言った。眼前には、鴨川の暗く黒い水が見えるばかりだった。巴はつぶやいた。
「・・・・人の言うままに剣を取って、その判断も他人の手にゆだねて・・・。それでいいのですか、あなたは。」
剣心に対してついに言ってしまったと巴は思った。しかし重ねて巴は言った。
「あなたがいつまでそうしているのか・・・・私はそれを・・・・それをできれば見届けたい・・・・。」
苦しい言葉だった。自分に嘘をついていた。見ていたいのはこの人ではない。しかしそう言わねばならない。剣心は答えた。
「君から見ればそう見えるのだろう。俺がしていることは、確かに殺人剣だ。しかし同時に太平の世を作るための礎(いしずえ)になっている。意味があるんだ、俺にとっては。」
「そのために人の命を奪ってでもですか。」
「そんな話をするために俺を誘ったのか。」
巴は剣心の語気に一瞬怖気づいた顔をしたが、言い募るように言った。
「すみません・・・。でもどうしても言っておきたかったのです。その頬の傷を見るたびに・・・・その傷をあなたにつけた人は、どんな思いで死んでいったのだろうと・・・・。そう思うと・・・・・・。」
剣心はため息をついて言った。
「君は優しすぎる。剣と剣とのぶつかり合いでは、そんな余裕はどこにもない。やるかやられるかだけだ。俺もいつも死ぬ気で戦っている。そういうものだ。」
巴は剣心の言葉に、少し顔をそむけつらそうに言った。
「もう思いなおされることは、ないのですね・・・。」
「すまない。君は俺とは違い過ぎる。」
剣心は答えた。それは巴に対する気持ちの整理だった。巴に祭りに誘われたことで舞い上がっていた。しかし巴は自分を全面的に受け入れてくれる女性ではなかった。巴なりに考えがあるのだ。それは剣心にとって、他人の気持ちの新鮮な確認だった。
と、その時群衆の中から飯塚が現れた。息せき切って駆けてきたらしかった。
「おう、緋村、ここにいたのか。大変だ。そこの河原町の池田屋で、謀議をしていた宮路さんたちが、新選組に襲われた。」
「なにっ?!」
「ここも危ない。早く行け。」
「俺は宮路さんたちを。この人を頼みます。」
剣心は巴を飯塚の方へと押し出した。
と、巴が剣心の袖を引き、手を握りいやいやとかぶりを振った。巴の白い額に冷や汗のようなものが浮いている。剣心は一瞬その巴の哀し気な顔を見つめたが、すぐに前へと駆けだした。巴は自分に剣を取るなと言っているのだ。それは承諾できないことであった。不戦論では、世の中は動かない。そう剣心は考えていた。
その頃池田屋では、密議をしていた長州志士たちに、新選組の先発隊の近藤隊が乱入して襲い掛かっていた。後に近藤勇が書いた書簡によると、新選組は七名を討ち取り、四名を負傷させて、二十三名を捕縛したらしい。
池田屋は木屋町通りにあるごく普通の料理旅館であり、狭い階段の上に何室かの部屋があり、長州志士たちはその一部屋で密集していた。新選組が来るという連絡を急に受けて、部屋の者は素早く部屋の灯りを吹き消したが、すでに時遅く、ばらばらと階段を上って来る隊士たちに次々と斬られた。永倉新八、沖田総司、谷万太郎、武田観柳斎、島田魁、原田左之助などがその主な隊士であった。
中でもやはり、沖田総司の働きは目覚ましかった。二階の濡れ縁で、沖田は二名ほどを斬った。中一名は喉首に刃を突き入れて殺した。しかしその時、沖田の口元から喀血の前哨線のような血がほとばしった。かがんで咳をする沖田に、永倉が言った。
「沖田さん、血が出てる。」
沖田は口元をぬぐい、剣を握りなおした。剣の柄元は、血のりでてらてらとした手触りだった。沖田は息をはずませて言った。
「大丈夫です。それより下を御用改めで固めないと。土方さんたちはまだですか。」
「土方隊ももうすぐ来ると思う。」
「下を見てきます。」
沖田が階下に降りると、土方隊が到着したところだった。周囲を警笛の笛で固めている。中心を副長である土方が固めていて、「京都守護職会津藩預かり、新選組である。御用改めだ、町の者は入ってくるな!」と声を張り上げていた。御用の提灯が並んだその横には斎藤一もいた。
そこへ到着したのが剣心であった。祭りで膨れ上がった群衆をかき分けて、彼は新選組の前に躍り出た。剣心は居並ぶ隊士の一人を素早く斬った。風が舞うようだった。
「なんだっ、貴様は?!名乗れ!長か?!」
隊士たちが口々に叫んだ。剣心は低くつぶやいた。
「名など、無用!」
池田屋の二階の窓からは火が出ている。長州志士たちはすでに斬られたのだ。自分は来るのが遅かった。女と語り合っていたせいで、と思うと、剣心の心には己れと新選組への憤怒が沸き上がっていた。その剣心を沖田が認めた。
「赤い髪・・・・・あの長州藩の使い手。」
沖田は剣心を見て、隊士たちをかき分けて剣を下げて前に出た。構えて言った。
「どこの流派か知りませんが・・・・、天然理心流試衛館・沖田総司でお相手をいたします。いざ。」
剣心がだっ、と踏み込んだ。沖田が考えていた通り、居合抜きの間合いで来た。剣の振りが早い。これは野の剣だ、と沖田が感じた時からすさまじい斬り合いの連続になった。と、双方態勢の立て直しで引き分けた時、沖田はまた咳をした。口元から血が出ている。
それを見て、剣心の眉間にしわが寄った。巴の言葉が胸によみがえった。――血の雨を降らせるのですね――、剣で斬り捨てている時は何とも思わなかったのに、相手が病から血が出ていると、そう感じたらしかった。それは明らかに体を損なっている様子だからだ。剣心は思った。無造作に斬り捨てている時は、今まで俺は何も感じていなかった――それは奇妙な出来事だった。
と、その時、斎藤がすらりと剣を抜いて前に歩み出た。
「沖田くん、下がっていたまえ。こいつは俺が相手しよう。」
沖田はそれを見て、不服そうな顔をした。
「いえ、僕がやります。」
すると横から副長の土方が、沖田の肩を叩いて言った。
「総司、斎藤にやらせてやれ。こいつは俺でも歯が立たんかもしれん。」
「土方さん・・・・。」
土方は言った。
「斎藤、仕留められなくてもいいぞ。ここから追い立てろ。邪魔になる。」
斎藤は土方の言葉に薄笑いをすると、牙突の構えを取った。剣心はそれを見て、剣を引いた居合いの低い姿勢を取った。牙突は太刀筋を見せている。しかし、どこに突きが入るかはわからない。剣先を裏に返しているから、その切り上げで体の隙に突きが入る。それは深い。剣心は従って、己れの太刀筋を隠したのだった。斎藤は心中笑った。こいつなりに考えたな、と。
しかし次の瞬間斎藤は目を剥いた。居合の剣心の脚は俊足だった。斎藤の突きを受け流して、数打入れると、彼はそのまま走り去った。斎藤は土方の言うように剣心を追い立てることはできた。しかしそれがぎりぎりであった。それは剣心にとってもそうであった。斎藤とはほぼ互角だった。生涯にわたる斎藤との因縁の始まりがそれであった。土方は言った。
「野剣使いだな。ああした小僧を長は奇兵隊で使っているようだな。」
沖田がそれを聞いて、ぽつりと言った。
「名乗らなかったですからね。素性も定かでない者なのでしょう。不憫な・・・。」
斎藤が言った。
「あの者、かすかに梅の香りがしたな。女の残り香か。」
沖田が返した。
「梅の残り香――白梅香でしょうか。確か芹沢の女もつけてましたね。お梅でしたっけ。」
芹沢とは、前年土方らが粛清した先の局長の名前である。
「そうだ。ぞっとせんな。この季節に、狂い咲きか。」
斎藤はそう言うと、剣を振って鞘に納めた。
剣心は息せき切って、小萩屋の戸を叩いた。中からおかみと飯塚が出てきた。飯塚が言った。
「ここも危ない。お前、大津かどこかへ逃げろ。」
「桂さんは無事なんですか?」
「たまたま別の寄り合い所に出向いていた無事だった。それも宮路さんらと、京の大火策で袂を分かっていたせいだ。」
「それはよかった。」
と、そこへ桂が幾松とやって来た。
「どこぞへこれから行かはるんですか」と、幾松はおかんむりな様子だった。もともと芸者だった幾松は、のんびりとしたところの多い女性だった。桂は幾松に言い含めるようにした。
「俺はこれから身を隠す。京にいるのは危険だ。幾松、おまえとはしばらく会えない。緋村、お前も身を隠せ。大津に手筈がある。巴さん。」
物陰から、巴が白装束のまますっ、と幽霊のように現れた。
「緋村のことを頼みます。緋村、大津で巴とふたりで夫婦者として暮らせ。ほとぼりが冷めるまで。くれぐれも長州藩の武士であることを悟られるな。」
「はい、桂さん。」
「ではな、頼んだぞ。」
桂が行ってしまうと、おかみが奥から風呂敷包みを出して巴に手渡した。おかみは言った。
「当座のものをたたんでおいたし。あ、巴ちゃん、花菖蒲の言葉を覚えてるか?」
巴はびっくりしたような顔をした。とっさに剣心の前で、と思った。何も言えずにいる巴に、おかみは鷹揚な調子で答えた。
「日陰では映える、お天道さんの元では泣く。あんたもがんばりや。」
巴はおかみの言葉に、大きく頭を下げた。何も言わなかったけど、この人は私の事はみんな知っていた、と思った。そんな人なのに、どうして長州志士の世話をしていたのか、その理由については巴には皆目見当もつかなかった。
翌朝の早朝、剣心と歩いた大津への道のりは、京街道で一日ほどだった。途中、いつも花を小萩屋で買っていた、大原女の女性たちとすれ違った。花売り娘らは巴に尋ねた。
「あれ、巴ちゃんどこへ行きはんの?その人は?」
巴は頭を下げて答えた。
「大津です。この人は私の夫です。」
暁闇 下
京都北山杉の奥の字に、比古清十郎の草庵はあった。かつてかの義経が幼少時に住んでいたという、鞍馬山もほど近い場所である。比古はたまにふもとの村に生活に必要なものを買いに行く。彼は趣味と実益を兼ねて陶芸を営んでおり、それでたつきを得ているのである。庵の裏庭には小さな畑があり、それでほぼ自給自足で野菜を育てている。剣心が幼い頃は、野菜の当番は主に剣心の役割りであった。今日も比古はふもとの村に生活必需品と酒瓶を買いに降りていた。帰りは夕暮れ時になった。山の落ちる陽は早い。酒瓶をぶら下げて、比古は家路を急いでいた。と、その前方に気配を感じた。いるな、と思った。木立の中に闇の者が潜んでいる。比古はめったに使わない腰の木剣に手をかけた。
ほとんど彼は剣を折っている。自分から進んで剣を振るうこともない。ある事がきっかけで、彼は剣を捨てたのだった。ふだん人とも交わらず、ここに居を構えている彼にあえて剣を問いに来る者もない。いるとすれば、それは昔の比古を知る者しかいなかった。比古は言った。
「庭番衆か。闇の武かな?こんな人里離れた隠遁者に何の用だ?」
しばしの沈黙があった。薄暗い杉木立の静寂の中、しわがれ声が響いてきた。術者の声だった。比古は静寂に耳を澄ませた。声は言った。
「若造、おまえに特に用はない。ただおまえの内弟子を、これからおまえが会ったような方法で痛めつける。わしはそう決めている。大切な内弟子が壊れるのが見ものでな。」
「この俺を若造呼ばわりするとは、貴様は辰巳か。」
「左様。貴様がその隠遁生活にあぐらをかいている間に、我らはあいかわらず仕事を続けている。そのような卑怯者には似合いのことをしてやる。」
と、その時大風に乗って辰巳の体が比古に飛びかかってきた。比古は剣の棹で受け流した。
「ふん、腕はなまっておらんようだな?」
と、老獪な身のこなしで山道に着地すると、辰巳は言った。比古は尋ねた。
「内弟子というのは剣心のことか?」
「そうだ、噂ぐらいは聞いておろう。京で今人斬りをしておる。長州藩の奇兵隊の募集に応募してな。長州の高杉晋作の配下から、この京に戻ってきた。それは知っておろう?」
「馬鹿弟子がどういう事をしていようが、俺とは袂を分かった以上、俺はそれについて言うことはない。貴様にはとんだ邪魔だったようだがな。」
比古の言葉を聞いて、辰巳は破顔した。
「なに、貴様ほどのことはない。しかし計が成ったのでな。これから貴様の内弟子には死んでもらう。あの弟子の技を完成させるのには、何年かかった?それがすべて無駄になる。貴様の努力、鍛錬、忍耐、それがすべて水泡に帰すのだ。こんなに面白いことはない。」
「なに。」
思わずにらみつけた比古に、辰巳はさえぎるように手をあげた。
「おっと、今山を降りるなよ。弟子の居場所も探すな。貴様には我らの眼が張り付いている。弟子は貴様同様、女と今ねんごろになっておる。その女が・・・・、さて、どうなるかな?わしはその飼い桶を見張る役割だ。貴様も生き物を世話したことはあろう?面白いぞ、飼い殺しというのはな。剣を使うだけが戦法ではないのだ。」
と、言うが早いか、辰巳の姿は突風の渦巻きの中にかき消えた。後には比古への哄笑だけが残された。比古は油断したと思った。辰巳に今一矢報いるべきだった。辰巳の話の方に気を取られていた。比古は唇をかんで言った。
「ちっ・・・、飼育かよ。」
比古はしかし、その場で立ち尽くすしかなかった。剣心の身を案じる比古だったが、彼もまた古い盟約に縛られる身の上だったのだ。比古は思わず無言で天を仰いだ。
剣心らが大津で住むことになった廃屋はそれほど荒れたものではなく、地主が当面住む者がいないということで空き家として置いていた農家であった。それがどうして長州派の武士が住むように手配されたのかは、巴にはわからなかった。長州派にも新選組にも、大阪あたりの豪商が気軽に金を貸しつけていると聞いている。それは小萩屋で下働きしている中で巴の耳にも入り、きっとそのような筋からのことであろうと巴は思った。なぜなら貧農の家には見えなかったからである。土間と二間ぐらいしか部屋はなかったが、上級武士の家にあるような立派な衝立が、畳の間にあらかじめ置いてあった。衝立には夫婦の鶴の狩野派風の絵が描かれており、目にした巴の気持ちを不安にさせた。
当初剣心は巴とは距離を置き、寝間も巴とは別にして、衝立の向こうで刀を抱いて眠っていた。巴は一人で夜具を使った。しばらくの間はそうだった。昼間は剣心は庭で薪を割り、裏の畑を鍬で掘り起こしたりしていた。
「昔にやったことがある。稲田は無理だろうが、畑ぐらいなら何か作れるかもしれない。」
と、剣心は言った。
「しかしそれには種や苗が必要だ。大津の市まで行ってみよう。危険かもしれないが。」
と、剣心は畑から腰をあげた。巴は鷹揚にうなずくしかなかった。
次の日二人は大津の市場まで足を運んだ。農家の家からは半日ほどの距離で、途中歩きづらい箇所では剣心は巴の手を引いてくれたりした。街道筋を歩くと、自然に蒼紫と歩いた中山道のことを思い起こされて、巴はうつむき加減で思い出に耐えていた。
なぜあの思い出はもう自分からは遠いのに、甘美に思えるのだろうと思った。それは理屈ではなかった。そして、いつ私はこの任から解かれるのだろうと考えた。剣心とどれぐらいこれから暮らすことになるのだろうと思った。と、その時巴ははっとした。市に並んだ商材の中に、女性が使う鏡があった。それに自分の顔が反射して映ったのを見て、巴は一瞬胸を打たれたのである。今蒼紫のことを考えていた時、あの夜懐剣に写したような顔が映って見えた。それは誰かからの鋭い指摘のような気がした。
思わず剣を呑んだような姿勢になった巴を、剣心がいぶかしげに見て、鏡に目を留め、「欲しいのか?」と尋ねた。
巴はあわててかぶりを振ったが、剣心は「いくらだ」と売り子に尋ねて、その黒ぶちの漆鏡を買ってしまった。渡しながら剣心は言った。
「女性だから、顔が気になるのだろう。俺の顔の傷も気にしていた。」
「すみません・・・。」
「いいんだ。」
剣心はそう言うと、農家の苗の並ぶ方へ歩いて行ってしまった。巴は思わず鏡をかき抱いた。鏡を大切に持ちながら、この想いは剣心には決して知られてはならないと思った。湖からの風に、巴の腰の領巾(ひれ)がはたはたとはためいた。
その日も夕餉の支度をし、風呂を用意し、あたふたと巴は動いた。剣心はいつものように衝立の影で刀を抱いて眠っている。池田屋の変があってから、もう二月ほどたっていた。外は秋の気配が漂いはじめていて、夜は少し肌寒い。巴は寝ている剣心に近寄り、上掛けをかけてやった。そのややあどけない寝顔の様子に、弟の縁のことが思い出された。闇の武の、自分に対する人質の縁だった。縁は今どうしているだろうと、巴はぼんやりと剣心の寝顔を見つめ、また奥の文机に戻った。机の上に書きかけの秘密の日記がある。思い立ち、最初に大津に来た頃からつけはじめた日記である。以前は真面目につけていなかった。それもこれも、いつか蒼紫が読んでくれたらと思い、つけはじめた。ただし、蒼紫のことは書いてはならなかった。何時剣心がこの日記を目にするかわからないからである。ただ、剣心が見るかもしれないと思い、巴は京で清里が討たれた話を箇条書きで書き留めた。それは忘れてはならないことだった。
清里が今になって、巴は不憫でならなくなった。恋愛という気持ちではない、しかしあの人はもうどこにもいないのだ。そして自分は清里を殺した剣心と共に今暮らしている。清里がその様子を見たら、どれほど悲しむだろう。そう思うと、巴は日記の筆を留め、瞼を押さえることが多かった。清里の冥福を祈る気持ちで、巴は剣心と出掛ける折には道端で傘子地蔵などを目にすると、「少し待ってください」と言って立ち止まって手を合わせた。巴の様子に、剣心も黙って手を合わせてくれた。そのような日々が二か月ほど続いた。
異変は薬籠を持って訪ねて来た飯塚の訪れだった。
「よう。元気そうじゃないか。」
と言って、飯塚は大きな荷物を背中から下した。「薬」というのぼりまで持っていた。剣心は尋ねた。
「飯塚さん、これはなんですか?」
「なんだじゃねぇよ。これは薬の原料だ。これからここで商売をはじめてもらおうと思ってな。薬売りだ。夫婦でしていたら怪しまれねぇ。もう人斬り稼業は終わりだ。」
「え。」
「岩見銀山、知らねぇか。結構儲かる商売なんだぜ。薬の知識はねぇか。」
「そんな、無理を言わないでください、俺には医学の知識なんか。」
「なくてもどうってことはねぇ。これ見ろ、この帳面に調合方法が書いてある。このとおりにして、売っていけばいいんだ。塗り薬や散薬は売れるぞ。」
「飯塚さん、もう人斬りはしなくていいという話は本当なんですか。俺はもうお役は御免なんですか。」
「仕方ねぇだろ。俺も詳しくは聞いちゃいないが、長門の方では今幕府派の連中がのしてきている。高杉さんも今牢に入っている。」
「それは本当ですか。」
「ああ。またおまえの手を借りることもあるかもしれないが、それは何時になるかわからねぇ。ひょっとしたらこのままって話もありかもな。桂さんも逃げの小五郎と陰口をたたかれている始末だ。」
「そうですか・・・・。」
と、飯塚は巴に目を留めた。飯塚は横に黙って座る巴の顔を見て、
「あんたまだ緋村とは・・・・。そうですか。」
と言った。そして重ねるように言った。
「ま、俺も連絡係だから。巴さん、あんた今日から薬屋の女房だ。それじゃ緋村、邪魔したな。」
と言って立ち上がった。剣心が「送って行きますよ」というのを、「いらねぇよ」と言って飯塚は菅笠をかぶり帰って行った。
剣心は飯塚が置いていった荷物をはじめはぼんやりと眺めていたが、急に立ち上がり、「よし」と言って荷ほどきをはじめた。巴はいぶかしく思い、「どうしたのです?」と尋ねた。剣心は少し笑って言った。
「どうして気がつかなかったんだろう。俺はこれをやるべきだったんだ。」
と言った。巴は言った。
「どんな薬かわかりませんよ。」
「それでも、人斬りよりはいい。これはいいことだ。ずっといい事だよ、巴。」
そう言うと、剣心は脱力したような顔で天を仰いで笑った。その目に涙が浮かんでいるのを見て、巴は少しはっとなった。それほど剣心にとって、人を斬る事は重圧だったのだとわかったのだ。彼は自由に開放されたのだった。そして同時に人斬りの技の輝かしい業績からは離されたのだ。巴が剣心に無理やりっぽく抱かれたのはその二日後だった。
「かならず幸せにするから。形だけではない、俺は君のことが好きなんだ。」
と、剣心は懇願して言った。狭い家屋から夜、巴は逃げ出すことはできなかった。巴にはその勇気はなかった。もし自分がこれまで蒼紫の周囲に見えた、手練れの女忍者ほどの勇気があれば、それが可能だったろうに、と思うと、剣心に抱かれた後、相手が眠っている隙に巴は声を殺して目を泣きはらした。剣心が悪い人ではないと思おうとした。しかしどうしてもそう思えなかった。そしていったんそういう関係になったとたん、剣心は夜は必ず巴を求めるようになった。若いだけあって、薬売りという生活の基盤ができたとなれば、それは無理からぬことであった。
剣心らは薬を調合し、自宅から数軒離れた人里まで降りて、のぼりを立てて売り歩いた。意外にも剣心は商売ができた。巴が思っていたよりも彼は腰の低い人だった。おそるおそる話しかける村人の老婆や老人たちに、よく相談に乗ってやった。腰が痛いだの、耳が聞こえないという話に、彼は親身になって耳を傾けた。巴は剣心が「太平の世を作るためなんだ」と言っていた言葉が、事実そうなのだと思い知った。村の子供らにおもちゃの木刀でたたかれても、彼は怒ったりしなかった。一緒になって鬼取りをして遊んだ。その様子は、以前剣心が対峙した沖田総司の逸話にあるようなものだった。しかし元来巴は無口な女だったので、その輪の中には溶け込めなかった。村の子供の一人が巴を指さし、「あのおねえちゃん怖い」と言うのを、巴は黙ってうつむいて聞くしかなかった。騒がしい子供は苦手だった。
巴は子供、と聞いて胸に暗点のような染みが広がっていくように感じた。むろん懸念されたのは妊娠である。あれだけ剣心に抱かれているのだから、妊娠しないはずがなかった。そして、どうやら自分はその為にここにいるのではないかと思った。その為に、と思う話は、巴にはあまりにも残酷だった。それは清里の仇の子供なのである。それでも巴は剣心が以前に言っていたように、蒼紫の母親の懐剣で「寝込みを襲う」ような事はしたくなかった。巴には心労が重なっていった。
それだからだろう、薬売りを終えて村からの帰り道、巴は道でつき転んだ。剣心は酒瓶を手にしていたが、巴を振り返って片手を差しだした。巴は息も絶え絶えだった。酒瓶は、この頃剣心が夜に比古のように晩酌を楽しむようになったからである。季節は秋も深まり、粉雪も舞う頃が近かった。
「大丈夫か。」
と、剣心は言った。巴はその手をすぐに取れなかった。剣心は重ねて言った。
「俺は君を、守る。君と君につながる命を。」
巴の目がいっぱいに見開かれた。
「だから何も心配しなくてもいいんだ。君は・・・・。」
巴がようやく立ち上がったのを支えるようにして、剣心はつぶやいた。
「置いてきたんだな、あの刀。今後君は、そんなものは持たなくていい。そういう世の中にする。こうして微力でも、世の中の役に立って、君と一緒に。」
剣心の言葉を聞いて、巴の目から涙がはらはらとこぼれ落ちた。ようやくの想いで巴は「すみません」と蚊のなくような声で答えた。胸が詰まってもう何も考えられなかった。
次の朝、裏の畑に冬の朝霜が降りて、一夜のうちに葉物類の野菜がしおれてしまった。氷雨が降る中、剣心があの巴の藤傘を差して、巴が枯れた野菜を触っているのを眺めていた。巴にも傘をさしかけている。剣心は言った。
「こういう事はよくある事だ。しかし他にも植えているものがある。冬が来る前に、間に合ったな。そんなに気を落とす事はない。」
巴はしかし、剣心の言葉が耳に入らなかったようだ。
「そんな・・・どうして・・・・そんな・・・・どうして・・・・。」
巴は葉を何度もなでながら、小声でささやき続けた。枯れてしまったのは自分の蒼紫への想いのように思えた。違う、私が今こうしているのは、あの方の為だ。あの方が清里のように死なずに生きて・・・・!そう何度も巴は心の中で反芻した。
その夜、巴は夜中に手水に立った。規則通りだった生理は今月も来ていなかった。巴は手水の壁にもたれて、しばし目を閉じた。暗がりで蒼紫の顔を思い浮かべた。あの時美しい名前、と言ってくれた人。手水の臭気が今の自分に似合っているような気がして、そのまましばらくその姿勢でいた。月明りの窓に鈴虫が来て鳴いていた。
しかしその次の朝、巴は家の前の道に、連絡の置き石が置いてあるのを目にした。今では巴にも、少しだけはその意味がわかる。辰巳らに教えられたのである。石は、「夕暮れ前に出てこい、先の御堂で待つ」という意味だった。何週間か置きの辰巳らへの連絡の頃合いが来ていた。巴は朝から洗濯などにせいを出すと、昼過ぎに畑仕事をしている剣心に、「すぐに帰ってきます。下の村まで」と言って家を出た。剣心は不審に思っている様子もなかった。現に彼は家の中を見て、すぐに畑仕事に戻ってしまった。家中の窓辺に普段は飾っていない、芒と野菊が活けられた花瓶が置かれているのを見ても、「巴がまた飾ってくれたんだな」と言っただけだった。
巴はお堂に出向く時、念入りに髪をとかして後ろでくくり、あの漆鏡で顔を見た。目で蒼紫に救われた時の傷跡を探したが、それはやはりどこにも見つけられなかった。指先で、そのあたりを少し触った後、剣心の頬の傷口のあたりをなぞってみた。何かこみあげる思いがして、巴は鏡の蓋を閉じて箪笥の引き出しにしまい、代わりにあの懐剣を取り出した。確かめるように帯に差すと、戸口を開けて外に出た。歩いていく途中、夏祭りで買ったものの、秋になり枯れたので捨てられた酸漿(ほおずき)の植木鉢を目にした。少し目に留めてまた歩いた。江戸にいた頃、清里や縁と夏祭りにあのような植木鉢を市で買ったのを思い出した。幼い縁はほおずきの実を清里のように、口の中で鳴らすことができないと言ってむくれた。懐かしい心温まる思い出だった。それを今思う幸せを巴は少し思った。
辰巳とその仲間はお堂の中で座って巴を待っていた。その横に巴はあの縁の姿を認めて、驚いた。今までどんなに願っても縁は連れてきてくれなかったのだ。それがどうした風の吹き回しだろう。一瞬もう任務は解かれるのかもしれないと巴は期待した。しかしそれは見通しが甘かった。
巴ら姉弟の涙の再会の後、辰巳は巴の報告を聞き、剣心がもう抜刀斎としてではなく、町の薬売りとして生きているという話を聞くと、得心したようだった。
「それほど骨抜きになっているのなら結構な話だ。腕の方もさぞかし鈍っていることだろうて。」
巴は冷たく答えた。その巴の体には縁がしがみついて辰巳をにらんでいる。
「そうですね。そろそろ弟を返していただきたく存じます。」
「返してどうするね?」
「抜刀斎が戦えなくなったらそれでもういいのでしょう?私は江戸に帰りたいのです。」
「うむ?それはならんな。おまえはもう、そんな体ではないだろう?」
ゆらり、と辰巳が立ちあがって、巴の襟元に乱暴に腕を差し入れ、ばっ、と襟を抜いて上半身をあらわにした。巴は叫んだ。
「何をなさいます!」
辰巳は好色な目で巴の胸元を見て言った。
「ほう、抜刀斎が吸ったからの色ではないな?黒くなっておる。孕んだよな?」
巴は顔を真っ赤にして前を隠した。指摘されたのは乳首の色だった。妊娠腺が出ていたのだ。周囲に立つ、辰巳の仲間の闇の武たちがそれを見てにやにやと笑った。辰巳は言った。
「あとはおまえが間者であった事を抜刀斎に告げるだけだ。内通者が自分の女房と知った時の顔が見ものだわい。ま、それはもう少し後でもよい。やつがその腹の子をどうするかを考えると面白い。おまえの手引きで長州派が池田屋で討たれたと知ったら、果たしてどうするかな?」
巴は辰巳の言葉に総毛立った。
「それは嘘です、私はそんな事していません!・・・・なんてひどい・・・・。」
「ひどいだと?女の喜びを知り、赤子まで授かって、どこがひどい。清里で得られなかった幸せを、清里の仇の男で得られたのだ。おまえのその生きざまの方が数倍ひどいわ。」
横に立っていた縁は二人の会話を聞き、やっとその意味がわかり、巴に叫んだ。
「どうしたんだよ、ねぇちゃん。なんでそんな仇の男の言いなりになって、子供なんて作ったんだよ。おかしいよ、ねぇちゃん。」
「縁・・・。」
「どうしちゃったんだよ、ねぇちゃん、ねぇちゃん!」
縁は喉をふりしぼるように叫び、巴から離れると激しく地団太を踏んだ。巴はただ、それを見ているばかりだったが、ある事を思いつき腰の懐剣に手をやった。巴が懐剣を引き抜いて、己れの首を突き刺そうとしたのと、辰巳の分厚い手が払うのはほぼ同時だった。
「ああっ。」
巴はその場に倒れ伏した。辰巳は言った。
「自害など考えるなよ?貴様が死んだら、弟も道連れだ。弟を殺したくなくば、その命勝手になくすことはならんぞ。縁、来い。姉さんはまだ抜刀斎に用がある。」
縁は辰巳と巴を見比べていたが、やがてつぶやいた。
「なんだい、こんなやつ俺の姉ちゃんじゃないやい。姉ちゃんはもっと、強くて正しい人だ。」
そう言うと、縁は辰巳に手を引かれて行ってしまった。巴はその場でしばらく泣きぬれていた。さすがに、辰巳の仲間たちは孕んだ巴をどうこうはしなかったようだ。罰が悪そうにして、すぐに彼らはその場からいなくなってしまった。
ようやく巴は立ち上がると、投げ出された懐剣を手中に収めた。はだけた着物を直し、落ち着いた巴は、剣心に言おう、と思った。自分の口からはっきりと言わねばと思った。
それから二三日後、大津には初雪が降った。今年はじめての雪だったのに、だいぶ降り積もった。外に出られないので、剣心は昼間は商売の帳面つけをし、晩は巴と晩酌を取った。
「どうぞ。」
と言って、巴は酌をし剣心の杯に酒をついだ。土間には収穫した野菜がたくさん並べられている。白菜に小芋、にんじんなどいろいろだ。剣心の膳には巴が今しがた料理したばかりものが並んでいる。行商人から仕入れた秋刀魚もつけられていた。
「・・・・すみません。」
巴の声に、剣心が箸を留めた。巴は続けた。
「おろしにする大根がなくて。」
「俺は別に構わないが。」
「でもなんだか気が抜けたようで。」
剣心は土間を見やった。収穫した中には冬大根はあった。巴が料理をしなかったのは、何か別の理由だ。剣心はそう思い、箸をおろした。
「俺に何か話があるのか。」
「・・・以前あなたから話を少し聞きました。こうしてあなたは昔、暮らしていたのですね。畑で採れたものを食べて、畑を耕して。・・・・あなたは聞かないのですね。私のことを何も。」
「俺は、君がそばにいてくれるだけでいいんだ。」
「・・・・私の話を少ししましょう。私には言い交わした人がいました。」
剣心は巴の言葉にはっと目を見張った。巴は続けた。
「でも、動乱の京で亡くなりました。二年ほど前のことです。」
「それで君は京へ?」
「はい・・・・。夫となる人を訪ねてこの京にまで来ました。夫は、夫は・・・・。」
そこで巴は言い淀んだ。
「・・・・夫は・・・斬り殺されて・・・・・。・・・・・に・・・・。」
巴の声はかすれた。喉が詰まったようになって、言葉が出なかった。なんて私は勇気がない、と思った。あなたに、とどうして言えないのか。なぜそれが、そんなにも恐ろしいと思うのか。しかし巴の口はその言葉を発することができなかった。
巴の唇が震えているのを見て、剣心は畳に目を落として言った。
「それであの時君は俺に・・・あんな事を言ったのか。殺される人の気持ち、とか言ったな。」
「ええ。」
「君の言うことは正しかった。あれから君とこの里山の暮らしを経て、その事を考えるようになった。俺自身が人斬りでなくなった事もあったが・・・。以前の俺はそういう事を考えなかった。いや、考えないようにしていた。それはやはり間違っていた。君の言うように、ひどい事だったのだ。」
「ええ。」
「それを教えてくれたのは、君だ。君は俺にとって、第二の恩師だ。そして、俺の妻だ。」
「・・・・・。」
「たとえ正式に祝言を挙げてなくても、俺にとって生涯の妻は、君以外には考えられない。どうかこれからもそばにいてほしい。」
巴はやっと言葉を継いだ。
「夫となる人は、文武はからきしで、武芸のたしなみもなく、ただ功名を挙げたいがために、京に上りました。でも、何より努力の人でした。私の幼馴染だったのです・・・。」
「それは寂しいことだったろう。」
「はい。幼い縁ともよく遊んでくれました・・・・・。」
その時、巴は吐き気を感じてうつむいて手で押さえた。もどしそうだった。あわてて台所に駆け寄り、洗い桶のひしゃくで水を飲んだ。と、剣心が後ろから来てそっと巴の体を抱き抱えて言った。
「もしかして、君・・・・。そうなのか?」
巴は振り向き、無言でうなずいた。剣心はそれを聞いて、飛び上がらんばかりに喜んだ。
「俺に子供ができたのか、君との?こんなにうれしい事はない。赤子は君に似てきっとかわいい。こんな暮らしばかり続けてはいられない。子供には俺と違って、新時代の学問をさせよう。俺のようになってはいけない。」
剣心が世にある父親のような事を言いだすのを聞き、巴はただただ笑顔で「はい」とうなずくばかりだった。その夜は剣心は巴の体を大切そうにさするだけで、何もせずに横で寝た。
――この人は、私の幸せをくれた人・・・・・。
剣心の寝顔を見ながら、巴は思った。
――そしてその幸せを奪った人・・・・・・・。
別れよう、そう思った。しかしこの身では蒼紫の前にも自分は出られない。蒼紫は許してくれないだろう。あれほどの人が、他人の手付き女に、生涯を誓うとは思えない。私はこういう運命なのだ。剣心には誤解されたままでよい。私がいなくなった事で、少しだけ私の今の気持ちがわかるかもしれない・・・・・、巴はそう思った。それは形を変えた、ささやかな剣心への復讐だった。巴はおなかに手をやった。なんとかしてこの子を産んで、縁と三人で暮らすことを考えようと思った。縁もいつかはわかってくれる。仇の人にも優しくした意味が、あの子にもきっとわかってくれる。巴はそう思い、涙ぐんだ。
翌朝、巴は剣心よりも数刻早く目を覚まし、身だしなみを整えると戸口から消えた。
「さようなら・・・・、私を愛した・・・・三人目のあなた・・・・・。」
かそけき声で、そう言った。剣心が目を覚ました時、巴はすでにいなくなっていた。剣心はあわてて家中を探した。
「巴、巴?」
と、その時剣心の背後の戸が開いて、飯塚が入って来た。剣心はうろたえてこう言った。
「あ、飯塚さん。巴を見かけませんでしたか?今までここにいたんだが・・・。」
飯塚はいつものように笑っていなかった。ぼそりと言った。
「あの時の内通者が割れたぞ。巴だ。」
剣心は目を見張った。信じがたいセリフだった。
「内通者というのは、いったい何時の時の・・・・・。」
「寝ぼけんじゃねぇ。池田屋だ。」
「池田屋・・・・。まさか、あの時の?!」
「その、まさかだ。おまえあの時一緒にいたんじゃねえのか?とんずらかきやがったな。持ち物なんか残してねぇか?探せ、ほら。」
剣心はあわてて巴が使っていた文机の引き出しをあけてみた。中には買ってやった黒塗りの漆鏡と、日記帳が残されていた。それをあわてて開いてみた。
『先の三月、京に上った婚約者の清里明良さまが、長州藩志士に討たれる。下手人は、緋村抜刀斎という名の男――』
と、巴が筆書きしたページがぱらりと開いた。かんざしが栞がわりにはさんであるせいだった。古い安物の鉦かんざしだった。剣心は日記帳を取り落とした。頬の傷口が開いて、血がぱたぱたと土間にこぼれ落ちた。
曙光
とんとんからり とんからり
とんとんからり とんからり
剣心の耳には今機織りの織機を踏む音が響いている。それは子供の頃、剣心が寝物語に聞かされた昔話である。
『機を織っていたのは鶴じゃった。つうはな、与ひょうにその正体を見られてな、鶴になって飛んで行ってしまったんじゃよ・・・・・』
飯塚から巴らしき人物を、下の村に行く途中の御堂の近くで行きしなに見かけたという言葉に、剣心は走り出した。それを不審に思う暇もなかった。会って謝らねばならない。巴に会って、自分は謝らねばならない。
飯塚は続けて言った。
「そのお堂だがな、そこにはきっと、巴の仲間がいるはずだ。だまされていたと思うか、おまえは?そういう女だったと思うか?」
剣心は頬の傷を押さえながら答えた。傷口がじくじくと痛んだのは、心の痛みか。剣心は言った。
「・・・・巴は、違う。きっと脅されていたんだ。俺は巴を連れ戻す。おなかには赤ちゃんがいるんだ。俺の子なんだ。」
飯塚は剣心の頬を思いきり張った。頬から血が飛び散る勢いだった。剣心は土間でひっくり返った。飯塚は叫んだ。
「馬鹿野郎!目を覚ませよ、今日び女郎ならそれぐらいのことをすらぁ。おまえはだまされてたんだよ!俺も!おまえも!長州派のやつらも!」
「女郎・・・?」
「おうよ。元は武家の娘だったか知らねぇが、今は女郎に成り下がった女だよ。おまえの事も馬鹿にしてたんだ。人斬りやめて、真人間になりましたってな。すっかりケツの毛まで抜かれちまったって。」
剣心は頬を押さえて叫んだ。
「違う・・・・違う・・・・・違う!」
そう鋭く叫ぶと、戸口に立てかけてあって、長いこと使用していなかった刀を握り、剣心は外に駆けだした。
雪道を、一足踏むごとに頭の中に機織りの音とシャンシャンと祇園祭の鈴の音(ね)の音が木霊して、雪がちらつくように目の前を舞って、剣心は思わず一瞬瞠目した。あの時の巴の姿がすべて嘘だった。しかしそれは自分が巴の婚約者を辻斬りで斬り殺したからだ。だから、巴はそうなった。悪いのはすべてこの俺なのだ。剣心はその時そう思った。彼は、もともとそういう事が、すぐに飲み込める人間だったのだ。飯塚の言い草は許し難かったが、時間がなかった。これから巴を連れ戻して、許してもらう。そして、元の生活に戻ってもらう。情けないことだが、自分には男の沽券や恥などと思う気持ちは巴に対しては決してない。巴はきっと、許してくれる。手をついて謝って、もし婚約者を斬ってしまったことで女郎に身を落としていたのだとしたら、これから先は押しいただいて、決して裏切ることはしないと膝をついて誓う。そう剣心は考えた。
その時剣心の前方に、一人の黒装束の男が現れた。男は巨大なブツを振り回しながら言った。
「一番手、角田、その首もらい受ける。」
男は大きな斧を腰に引きつけている。遠心分離の力で、緩急自在に操って剣心の行く手を阻んで行く。剣心は素早く飛びのきながら、叫んだ。
「頼む、そこをどいてくれ。行かせてくれ。」
「悠長な事を云うな。」
「おまえを殺したくない。巴と約束したんだ。」
「ハッ、約束だと?人斬り風情が何を言うか。粉微塵にして・・・。うお?」
剣心は動いている角田の斧の背に足を駆け、身軽に飛んだ。一回転し、一足飛びに角田の頭を飛び越して、先に進もうとした。と、そこへうなぎのような黒い手がするすると地面に現れて、剣心の背を駆けあがって一気に引き裂いた。
「ぐっ・・・!」
剣心は声を呑んでのけぞった。闇乃武の一員、八ツ目無名異の仕業だった。しかし剣心は素早く剣を返し、回転させ、八ツ目の飛び退った顔目がけて鋭くぐさりとえぐった。
「ふぐぅ!」
八ツ目は動物のような鳴き声をあげた。その黒装束の男は細身だが、その体はまるで軟体動物のようだ。そのまま木の上に飛び移って、ぎゃあぎゃあと声を上げながら逃げ出した。
「なんだあいつは・・・。」
と、あっけにとられた剣心が言った瞬間、角田は手にした縄を引いた。瞬間八ツ目の体が大爆発した。角田は言った。
「結界のひとつが今なった。これで貴様の聴覚はなくなったわ。これからじわじわと闇乃武で貴様の体の器官をそぎ落としてくれるわ。」
「そうかよ!」
と、剣心は言うと、角田の頭上に飛んで、斬撃を加えた。見事な一撃だった。
「なんだ・・・・?なまってはおらんのか・・・・?あの女の報告は嘘だったのか・・・?」
と、角田は言ったが、そのままどう、と雪道に倒れ伏した。剣心はその角田の体を足で蹴ると、道を急いだ。
「くそ、ちょっと聞えづらくなったか・・・。」
剣心はつぶやいた。と、しばらく行った林にさしかかった地点で、鋭い音がして、苦無が数発飛んできた。剣心は間一髪でよけた。ほとんど聞こえないかの音だった。中条が投げたものだった。木陰から現れた中条は言った。
「やるじゃねぇか、さんぴん。いや、人斬り抜刀斎だったか。町中でちんたら辻斬りしていたやつに、こんな山中で戦えるはずがねぇな?」
「巴の仲間か?」
「あああいつね。おまえの女だっけ。気軽に味見させちゃくれねぇ、いけてねぇ女。あんなこけし人形みたいな女のどこがいいの?」
「てめぇ・・・・・俺も山にいたことがあんだよ。おまえの脳天勝ち割ってやる。」
「そうかよ。やれるもんならやってみな。」
剣心は居合抜きの構えを取った。なぜこいつらは俺を狙う、と思った。最初からこの罠が仕掛けられていたのか?しかしなぜ巴を間者にして、俺と所帯を持たせて半年間も放置していたのか。まるで所帯を持たせること自体が目的のような奴らだ。最初から俺を倒すのが目的なら、巴を使う必要はなかったはず――剣心の脳はそう回転していた。まさか俺の子供を作るのが目的で?しかし子供なんて必ずできるものでもあるまい。何かが背景に動いている。しかし剣心の頭ではそれ以上のことは追い切れなかった。桂がもともと巴と所帯を持つように言ったのだ。そこで剣心の思考は止まってしまった。桂が反長州派であるはずはないのである。
剣心はだっ、と駆けだして中条に斬りこんだ。しかし中条は素早く後退してよけた。第二撃も入らない。中条はあざ笑って
「当たらねぇよ。」
と、言った。剣心は焦った。なぜ斬れない。もしかして技のレベルが落ちてきているのか。長い間巴と農園生活をしていて、剣を触っていなかった。さっきの角田への第一撃はまぐれだったのか?と、中条は手裏剣を続けさまに投げながら言った。
「殺したくないとかほざきやがったな?甘くなりやがって。そういう野郎は大好きさ!」
身軽に雪の中を飛んで移動している。剣心はそれを剣ではじいて、やはり吸い着くように移動している。しかし次の瞬間中条は剣を逆手に持ち直すと、一気に剣心目がけて斬りこんできた。雪の塊を押しながらで、剣心は後ろに押された。そのまま雪の塊ごと木にぶつかった。剣心は呻いた。体が吹き溜まりの中に沈んで、足をとられた。
「くそ、動けねぇ。」
しかし次の瞬間、剣心は後ろ拳で木の幹を激しく叩いた。梢の上に積もった雪がどさっ、と降ってきた。中条の視界が一瞬見えなくなった。そこを剣心は、雪駄で中条を激しく蹴りだした。中条はつんのめって後ろに倒れた。剣心はそこをすかさず突きを入れた。中条はしぶとくて、何度も上から突き刺したがなかなかその剣は命中しない。と、中条はぱっ、と雪の塊を握って剣心の顔目がけて投げつけた。その隙に逃げ込もうとした。剣心は叫んだ。
「逃がすかよ!」
剣心は後ろから剣で羽交い絞めした。剣心の剣の刃が中条の顔の間近ぎりぎりに迫っている。しかし中条は腕の力でそれを押しとどめている。双方力の押し合いが少しばかり続いた。しかしその時、中条は薄笑いを浮かべて言った。
「かかりやがった・・・・。やっぱり甘いんだよ、てめぇはよ!」
中条はそう言った次の瞬間、地面に伸びた縄を素早く引いた。瞬間中条の上半身が消え、爆音がさく裂した。中条は瞬間移動したように飛び退っていた。剣心は爆発をまともに食らい、体中に傷を負った。剣心は顔を手で覆い、つぶやいた。
「ちくしょ・・・・目が・・・。」
片目が開かない。ふらつく体で雪道に剣を突きさして、態勢を立て直した。剣心はつぶやいた。
「と、巴・・・。」
「ざまあねぇな。」
と、中条は不敵な笑いを浮かべて横にひらりと降り立った。そして剣を振りきって剣心に振り下ろそうとした。
「死ねよ、おらっ。」
しかし次の瞬間、剣心のすさまじい速さで伸びてきた剣先に、中条は後ろへと吹っ飛んだ。喉笛を一撃で突きさされていた。剣心の得意技の居合だった。剣心はふらふらとしながら、言った。
「当てることはできたか・・・勘はそれほどまだにぶっちゃいないか・・・。」
剣心はそうつぶやくと、ふらふらと血だらけの顔で雪道を歩き出した。
「巴・・・・。待ってろ・・・。今助けに行くからな・・・・。」
その頃お堂では、巴が辰巳に捕まっていた。くつわをかまされ、後ろ手に縛られている。弟の縁を道の途中で見つけ、連れ戻そうとして辰巳につかまったのだった。辰巳にとってはそれはわけない仕事だった。横にいる縁はいつの間にやら、巴の家に置いてあったあの藤色の傘を抱きかかえて手に持っている。辰巳とこっそり巴らの様子を見に来た折に盗んだものに相違なかった。巴は縁に言いたい事が山ほどあったが、さるぐつわをかまされているので、無理であった。
辰巳は言った。
「もうすぐ貴様の新しい亭主がやって来る。やって来たら貴様を殺すだろう。なにしろ、長州派の者らが死んだ事件で、貴様が手引きしていたのだ。それができなければ、武士ではない。」
「・・・・・・。」
「わしはそれを見届けたら、やつをも殺すつもりだ。田園期間はどれほどだったかな?約半年間か。それほどの間、一度も剣を持たず、貴様とのんきに夫婦生活を営んでおれば、技の切れもなくなっているというもの。しかも己の妻を手にかけた直後だからな。」
縁は辰巳に尋ねた。
「そんな女は死んだ方がいいって事かな?」
辰巳は笑って大きくうなずいた。
「そうだ、そうだ。ご先祖様に申訳が立たんだろう。仇の子供を孕むような女は。」
と、その時お堂の扉がきしみながら開いた。幽霊のように、ぼろぼろになった剣心が片手に剣を下げて立っていた。戸に寄りかかりながら剣心は言った。
「巴・・・・。」
辰巳は笑って仏像の前から腰をあげた。
「来たか。その女が裏切者なのはもう知っておるな。貴様にくれてやる。長州派の武士らしく、不貞の女を始末しろ。」
剣心は無言だった。顔面血だらけで、鬼のような形相で辰巳をにらんでいる。しばらくしてからやっと剣心は口を開いた。
「敵の情けは受けねぇ・・・・。」
一歩一歩、びっこをひきずるように剣心は歩き、巴の縛られている傍に近づいた。巴は涙がいっぱいの目で剣心を見つめている。その瞳がいっぱいに見開かれている。剣心はどうしたのか。彼は、巴のそばに寄ると、その剣で縄を切ったのだった。そして言った。
「すまねぇ・・・・。傷、また開いちまった・・・・。」
巴はぼろぼろになった剣心の頬に、無言でそっと手をやった。
辰巳はその二人の肩を寄せ合う姿に、逆上したようだった。
「貴様っ、なぜ殺さん?それでも長州派か。片腹痛いやつめ。来いっ。」
辰巳は剣心の襟首をつかむと、猫でも放り投げるように、お堂の前の雪だまりに投げ込んだ。そのまま剣心の体をその拳でどつきはじめた。剣心は応戦したが、戦意がなくなっているのか、かなり一方的に剣心は辰巳にやられている。彼は、巴に会って、それでもう目的は達成したのだと思ったのだった。彼はもう長州派を背負ってはいなかった。巴さえ無事でいてくれたらそれでよかったのだ。そして全身がもう、限界に近付いていた。中条が至近距離で爆発させたので、その傷が心も体もむしばんでいたのである。そのままでは辰巳に殴り殺されるのは必至だった。巴はその様子を見て、いったん顔を背けていたが、次第に助けるよう、剣心に近づいていた。もうやめてあげて、と心が悲鳴をあげていた。
目の前に剣心の怪我をした血の華が点々と雪にこぼれている。それはまるで、寒椿が道に落ちているかようだ。巴はその赤い光点を灯すようにその後を歩いている。こっちだよ、こっちだよ、と声がした。巴、こっちだ。いや、こっちだよ。声は清里でもあり、蒼紫でもあり、剣心でもあるようだった。その時辰巳がにやりと笑ってあの黒い懐剣を取り出し、剣心に振り下ろすのがスローモーションで見えた。帯にはさんでいたのを、何時の間にか辰巳に盗られていたのだ。巴はとっさに虚空の先に手を伸ばした。いけない、それは渡したらだめ・・・!あの人の・・・・!この人をその剣で殺さないで・・・・!
剣心は巴が割って入ったのに、剣を瞬間持ち直して、辰巳に素早く手をかけた。しかし――――。
「いけねぇ・・・・っ。」
巴をよけるように剣を振れなかった。痛恨の一撃だった。巴と暮らしていたから、剣先がにぶった。巴を守れなかった。生涯剣心を縛ることになるものだった。巴は剣心の目の前で、辰巳ともども斬られていた。
「巴っ・・・・!」
剣心は巴のおなかから血が飛び出るのを凝視した。目が皿のように大きくなった。剣心は、己れの目がめりめりと地の果てまで裂けたような気がした。
「うわ・・・っ、あっ、あっ、あぁあっ・・・・・・っ!」
剣心はそう絶叫すると、剣を放り出して巴に駆け寄った。巴に対して何か口にしなければ、と思ったが、あうあうという気の抜けた音しか出なかった。巴に対して謝るどころではなかった。一番してはならない事をしてしまった。
「か、仇をかばって・・・、わからぬの・・・おなごという者は・・・・。」
後ろで辰巳が呻きながら絶命していた。
お堂から一部始終を見ていた縁は、やっとその時言った。
「ねぇちゃん・・・・ねぇちゃん・・・・ねぇちゃんーーーーー!」
縁はそう叫ぶと、傘を取り落として口をぱくぱくさせた。子供らしい想像力の欠如で、まさか本当に姉が死ぬとは思ってもみなかったのだ。今となっては、優しい姉だった。縁はそれを今になって思い知った。
剣心は負傷した巴を抱きかかえると、その手にあの懐剣をしっかりと握らせた。握らせながら、涙がぼろぼろとこぼれた。なぜ巴がそれに手を伸ばしたのか、自分をかばうようにしたのか、それについては剣心にはわからなかった。ただ、彼にはしなければならない事があった。
ぐさり、と剣心は己れの頬に懐剣を突きさした。あの傷口の上だった。巴が断末魔の中、はっ、とした顔をしたが、そのまま一緒に手を添えるようにした。そのまま十字傷になるように、彼は手を動かした。はらった。雪原に刀から血がぱっと飛び散った。巴が安心したような顔つきになった。何事かを彼女は為し終えたのだった。
「これで・・・・いいのね・・・・あなた・・・・・・。」
かそけき声でそう言った。それが巴の最期だった。雪代巴は絶命した。
湖面に音もなく雪が吸い込まれている。ただひとつ、湖面に立つ鳥居が、静かにそれを見ている。一羽の白鷺が、鳴きながら湖面を飛び立った。廟廟と風は吹いていた。
桂が剣心の住む家を訪れたのは、その数日後だった。飯塚からの報告を聞き、薩摩と長州との連携について頭を痛める毎日だった桂だが、その所用を押して大津の里にまで出向いたのである。家のあたりに着く頃には、夕刻になった。
戸を開けた時、かすかに饐えた匂いがした。中で女が布団に寝かせられていて、その前に剣心が白装束で座っている。飯塚の話では、事件が終わってからもう少しの時間が経っている。異臭の元は死体の腐敗だろう。十二月頃の寒い時期とはいえ、腐敗はする。しかしそれを無視して剣心はその枕元に座っているのである。桂は横に座って言った。
「大変なことだったな。連れ合いを死なれたのは、おまえだけではないが。高杉の連れ合いの、宇野も死んだそうだ。二言目には、宇野の飯が食いたいと俺に言うよ。」
「・・・・・・。」
「おまえにはもう人斬りは。」
と桂が言った時、剣心はさえぎるように言った。
「桂さん。俺は、腹を斬るべきなんでしょうか。」
「腹を?女のことでか。」
「そうです。」
桂は嘆息して言った。
「自分を責めるのはよくない。君は立派だった。」
「でも、巴はもう戻ってきません。それを考えると、俺も死ぬべきじゃないかと思うんです。でも、腹が斬れない。どうしても斬れない。どうしても・・・・・。」
そこで、剣心は肩を震わせて言った。
「巴をこんな境遇に陥らせた奴がいると思うと、どうしても腹なんて斬れないんです!」
桂は剣心の肩をたたいて言った。
「もうそんな事は考えるな。わかった。君はもう長州からは切り離す。これからは君の自由だ。君の後任の男を誰か探すとしよう。それからその死体は早く焼いた方がいい。いつまでもそうしておいてはだめだ。君の気持ちの整理をつけて、荼毘に伏すといい。ではな、帰るからな。」
剣心は桂に頭を下げた。
「今までありがとうございました。」
「うん。元気でな。」
「はい。」
桂は剣心に軽く礼をすると、そそくさと席を立った。剣心の居が不気味だったからで、長居は無用と考えたからである。剣心に恨まれているのは自分も同じだ、と戸を閉めながら桂は考えた。そして次の後任にはあの男か、と記憶の中で見当をつけていた。
「やはり抜刀斎の名前を使わせた方がいいか。二代目ということで。」
と桂は歩きながらひとりごちた。遠くで犬の遠吠えがした。
剣心が巴を野焼きにしたのはその次の日の朝で、畑で使うもみ殻をその体にふりまいた後、薪に火をつけた。少し異臭がしたが、死体はよく燃えた。燃やす前に、何度も顔を確かめ、口づけもした。死体が骨になった後、少し冷やしてから畑のそばに穴を掘って、埋め始めた。墓石になる石を探して、上に置いてひとごこちついた時、背後に人の気配を感じた。
比古清十郎が立っていた。
「それが女の墓か。」
剣心は黙ってうなずいた。比古は言った。
「実は二度ほどここを訪ねたんだよな。遠目に見て、得心して帰って行った。馬鹿弟子が、心をやっと入れ替えたんだと思った。俺のような暮らしをしていて、嬉しかったよ。俺の来るのが遅かったのは謝る。」
剣心は答えた。
「あんたの世話にはならない。」
「そうか。ここで暮らすのか。女の墓を守って。それもまたいい人生だ。」
「そんな事はしないぜ。もう帰れ。こんな時だけ来るような奴には・・・・。」
剣心は墓に手を合わせた後、じっと前方を見据えている。比古は笑って言った。
「旅に出るのか。それもまた一興。支度金をやろう。」
と、比古は袂から金の布袋を取り出した。どさりと地面に落とした。
「それを持って、北の町に行け。場所は袋の中の地図に書いてある。そいつを訪ねるんだな。そいつが使えるようになったら、俺以上だ。」
「あんた面白がってるな。」
「うん、そう聞こえたか?では早々に帰るとしよう。おまえの人生だ。邪魔はせん。」
比古はそう言うと、立ち去っていった。剣心は墓の前に膝まづいた姿勢のまま、比古を振り返りもしなかった。
その夜、剣心の住んでいた家は一晩にして燃やされてしまった。下の村の村人たちが驚いて次の日に見に来たが、後は無人の抜け殻だった。後にはひとつの無縁墓と、放置された畑だけが残された。
江戸城ではその頃、前年八月十八日の政変の後、蛤御門の変で朝敵として長州藩の攘夷派が一掃されていたのが、再び藩内の幕府派の俗論派が反幕派に奪回され、高杉晋作らが藩内の実権を握ったことで、幕府内で再び長州征伐を行うべきだという話になり、十四代将軍家茂が上洛し第二次長州征伐が発令されることになった。
その京都上洛に伴って、蒼紫ら江戸城の御庭番衆も京に上ることになり、その支度を頭目らも行い始めた。それは慶応元年(1865年)の二月頃のことであった。頭目は、かねてから座敷牢に軟禁していた蒼紫を、その事でついに解放したのである。蒼紫は牢の中で毎日地道な修行を積んでいたので、体力は回復していた。
まず、座敷に通された蒼紫は、頭目から一通の書状を畳の上に滑らされた。
「これを開けてみよ。」
と、向き合って座る頭目が言うのに従って、蒼紫は封を切った。中から奉紙が一枚出て来た。
頭目は続けた。
「京の翁からの書状じゃ。短すぎるが、このほどの九ノ一の計は成ったということだ。」
蒼紫は封の中の奉紙の『破れり』という黒々とした筆文字を、穴が開くほど見つめた。蒼紫はその時何を考えていたのだろうか。彼はしかし一言もその胸の内の言葉を発しなかった。
しばらくしてから、蒼紫は口を開いた。
「・・・それは、闇乃武は全滅したということでありましょうか。」
「そうだな。しかし、長州派は大打撃を受けた。さる筋にも申し訳が立った。これでよい。」
頭目はそう言うと、席をすっ、と立った。腕組みをし、窓の外の梅の木を見ながら頭目は続けた。
「たかが人斬りの男一人に、あれだけの陣を張った意味、貴様は無意味だと思っている顔だな。」
「いえ。そのような事、今は考えておりません。」
「女のことは整理したか。」
蒼紫は畳に目を落として、答えた。
「若気の至りでありました。あのような者に、想いをかけるのは無意味でした。せめて九ノ一として役に立ったのが幸いかと。」
頭目は大きくうなずいた。
「ならばよい。蒼紫よ、わしもあの時は貴様に己の技を見舞ったが、それでも絶命せずに今こうしてわしと会話していられるという事は、見事であると言うほかあるまい。その紙一筋の差を埋めるべく、今後も精進せよ。」
「はい。」
「そして、他でもない、それほどのわしの技の後継者は、わしにはおまえ以外に考えられない。このほどの上洛の折には、京都御庭番衆の者とも立ち合いの上、おまえの御庭番衆御頭の襲名儀式を摂り行いたい。全御庭番衆の前で、おまえを新番頭(しんばんがしら)として披露するつもりだ。今後はわしはおまえの補佐役に回る。」
「そのようなこと・・・・。」
蒼紫が当惑したような顔をしたのに、頭目は微笑んだ。
「驚いたか。そもそも今回の硝子の一件も、おまえのその腕を試す意味もあった。」
そこで蒼紫は一礼をした。
「朱印状を紛失したのは、面目しごくもございませんでした。」
「よい。もう上の方でも、この件は面倒な事例になっておった。今は長州派の勢いをそぎ落とす方が先決じゃ。その為にも、あの女は多いに役に立った。緋村抜刀斎という男、すっかり腕の方が落ちてしまったらしい。京の翁からの書状ではそのような事が書いてあった。」
「はい。」
「人型の兵器をひとつつぶしたのじゃ。おなごながらあっぱれな女であった。ではな。下がるとよい。お前も女には用心せい。」
「は。襲名の儀はありがたき幸せでございます。あのような事があったのに。」
「よいよい。もう水に流せ。ではな。」
蒼紫は頭目の座敷を退き、般若たちのいるところへ戻った。廊下を腕組みをして歩いて来る蒼紫に、般若は声をかけた。
「お体の方はもうようございますか。若、出所おめでとうございます。」
「今俺に話しかけるな。」
蒼紫は一言そう言うと、般若の方も見ず廊下の向こうに消えてしまった。般若が襲名式の話を知ったのはその次の日であった。若はきっと、嬉しくて俺たちに黙っていたんだろう、と猩々と癋見はうれしげに噂したが、般若は一番最後に蒼紫をあの時見ていたので、胸の内に暗雲のようなものが湧いてくるのを止められなかった。蒼紫のあの時の顔は必死そのものだったからだ。約一年間牢につながれていた間、蒼紫は何を考えていたのか、それを般若は一人想像した。そして頭目はそれに気がつかないのか、もしくは目をそらしていると思った。
京までは蒼紫たち御庭番衆は、大名行列からつかず離れずで東海道を下知されて行った。もちろんその途上で中山道のあの硝子製造の恵那山近くに立ち寄ることもなかった。しかしその途中、京までの最終段階で大津の宿を通過した。蒼紫はその時、確かに本陣近くの宿にいたはずだった。般若は夜遅くまでその姿を見ていた。何故般若が蒼紫がいなくなったと思ったかと言うと、蒼紫の服のすそが次の朝少し夜露に濡れていたからだ。夜の内にどこかへ行っていた。しかし、それには頭目たちも気づいていなかった。蒼紫の態度はまったく普段と変わりなく、何も考えていないように見えた。頭目の指図に従い、頭目の乗る馬を引いて黙って歩いたりしていた。猩々がつい蒼紫に、「今回はうまくやりましたね」と言ってみても、蒼紫は「ああ」と答えて、横顔で少し笑っただけであった。若にしては珍しく上機嫌だ、と般若はその時考えた。そして、やはり江戸で思ったことは思い過ごしだったのかと思いなおした。
京では蒼紫たちは葵屋とその周辺の宿に陣を取った。将軍家茂の天皇への拝礼の後、幾日かして、襲名式は翌日であった。翁が出迎えたが、特に会話があったわけではなかった。その頃翁と蒼紫はそれほど親しい間柄ではなかった。江戸にほとんどいる蒼紫は、頭目とのつきあいの方が深かったのである。翁も頭目の手前、蒼紫に巴の事であえて話しかけることはしなかった。通り一遍の礼を済ませ、部屋に入った蒼紫は般若に、「少し歩いて来る」と言って、夕刻葵屋を出た。襲名式を明日に控えて、その様子は普段と変わりないものであった。
般若は後をつけた。蒼紫は路地をくねくねと曲がり、ある寺の境内に入って行った。そしてその寺の裏の墓地にまで来た。そこに少年がひとり立っていた。そこへまっすぐ彼は歩いて行った。少年はふらふらと立っているようだった。般若はその顔に見覚えがあった。あの巴とともにいた雪代縁だ。今は浮浪児のようななりをしている。般若は聞き耳をそば立てた。蒼紫の言葉が風に乗って断片的に聞こえてきた。
「・・・すると姉さんはそうして死んだんだな?」
「そうだよ。あんた俺を雇ってくれるのか?」
「ああ。食い扶持には困らないようにしてやる。」
そこで縁は顔をあげて叫んだ。
「いやだ!頭の中であんたに呼ばれたような気がしてここまで来たけど、それだけは絶対に嫌だからな!おまえの情けは受けねぇ!」
「意地を張るな。」
「おまえのせいで姉ちゃんは死んだんだ!覚えてろ、いつかきっと、仕返しをしてやる!」
と、縁は大声で叫ぶと、蒼紫から離れて駆けて行ってしまった。その時般若は、縁の髪の毛が雪のように白くなっていることにはじめて気づいた。そして蒼紫はその時、その髪に手で触れようとしていた。しかしその手はあきらめたように下されたようであった。その様子に、般若は少しどきりとしたものを感じた。なぜなら蒼紫の顔は少し笑っていたからである。それは同情というよりも、何事かを縁の上に為した笑いのように見えた。
般若たち御庭番衆は、忍びの心得があり、幻術も幾分か物にしている。現に葉霞の配下の女忍者たちには、そのような者たちが多かったのだ。それなのか、と般若は思った。だが、縁は京や大津にいたのだ。江戸で牢につながれていた蒼紫に、そのような事が可能なはずはあるまい。と、般若は思いなおした。あれはただの見間違いだろう。若はただ縁の子供らしい物言いに笑われただけだ。そう思い、蒼紫から見えないようにしながら般若は宿に帰った。だがなんとなく居心地が悪かった。もしかして、若は自分が尾行した事もわかっていたのではないか。そう思った。
翌朝の襲名式はさる料亭で開かれた。格式はあるものだったが、目立たない路地に面した、知る人ぞ知るような場所だった。京にはそのような密談に使うような料亭がたくさんあるのだ。
会合は午後から行われた。その日は雪が朝から深々と降り、京の底冷えのする一日だった。向かって右に江戸から来た江戸城御庭番衆、左に京都御庭番衆の面々が座った。上座の席には老御頭と、新しく新番頭になる蒼紫が座った。一同黒の紋付袴でずらりとそろえている。癋見や火男たちは普段着慣れない着物なので、落ち着かない様子だった。
翁はしばらく見ないうちに成長し、黒装束の正装で男ぶりが上がった蒼紫の顔を見つめていたが、やがて目をそらして目の前の杯を取った。酒が料亭の仲居たちによって注がれている。仲居たちも黒の着物でそろえている。翁も酒を受けた。上座の蒼紫たちも杯を持っている。並べられた膳には酒肴が盛りだくさんであった。
頭目が立って音頭を取るように言った。
「御庭番衆新番頭、蒼紫のことをひとつよろしく頼む。では、幾久しゅう。」
一同声をそろえて「幾久しゅう」と言った。後は宴会になり、翁も立って老頭目に酒を注いで回った。横に座る蒼紫は静かに膳のものをつついている。いや、近寄って見てみると、杯を膳に逆さに返して、ほとんど何も口にしていない。彼は黙ってただそこに座っているだけなのである。もともと無口な男であったが、と翁はその様子を少し不審に思った。
翁は二人を取り持つように、頭目に酌をしながら声をかけた。
「この度は真におめでたい事でござる。何時頃から次期頭目を蒼紫に、と思われましたかな?」
頭目は答えた。
「そうじゃな。昨年これを飛騨にやったあたりからだったかな。」
「遠国御用ですか。」
「左様。不要の者をうまく片付けてくれたのでな、恩賞を与えねばならぬと思ったのじゃ。わしも歳じゃしのう。」
「不要の者とは・・・闇の武でありましょうか。」
「まあそうじゃな。われら東とそちら西の御庭番衆の間で、ちと厄介者になりつつあった。しかしそれもうまく用立てて全員始末する事ができた。これもうまく立ち回ってくれての。葉霞とか言う追放した女忍者もおったろう?あれも一緒に始末してくれたわ。」
「それは何よりでござる。ささ、蒼紫も一献。」
翁がお銚子をすすめると、蒼紫はそこでやっとうつむいた顔をあげた。そして言った。
「すまぬことですが、俺は下戸なので、酒は飲めませぬ。」
蒼紫の言葉に、老頭目は破顔した。
「何を言うか蒼紫、めでたい席に。おまえが主賓なのだぞ。三々九度の杯でも、おまえは断るのか?横にわしのような老人ではなく、好いた女房がおったとしても?無粋な奴め、一杯だけでも飲め飲め。」
老頭目はだいぶ酌をされて酔っているようだった。翁はその時、座っている蒼紫の膝の上の手が、固く握られて白く固められている事に気づいた。何かを思って蒼紫は今緊張している。それは新御頭に任命されたからだろうか。そこで翁はある事に気づいて、頭目に尋ねようとした。座はざわざわと騒々しくなっていて、声はよく聞こえない。翁は言った。
「あの女はもう死にましたかな?確か九ノ一だった・・・・。」
頭目は答えた。
「あの女?さっき申した女か?笹葉霞とか言う元上忍か。」
「その女のことではなく・・・・。」
「蒼紫を預けたこともあったな。これが飛騨で始末した。そのことか。聞きたいのは。」
その時、横で黙って座っていた蒼紫が、「いただきまする」と言って翁の指した杯をあけた。その飲みっぷりは一気で、下戸という感じではなかった。しかしその後、蒼紫はまた膳に杯を伏せて置いてしまった。翁は二人の間の妙な空気にだんだん気づいてきた。
「では、失礼いたしまする。京都のこと、くれぐれも今後ともよろしく。」
と、翁は言うと早々に席へと戻った。そして蒼紫の懐剣の話を、やはりあの頭目の前でしなくてよかったと思った。後日あの話は蒼紫にしてやるべきなのだろうな、と翁はぼんやりと考えた。あの雪代巴という女性は闇の武とともに死んだのだろう。自分は緋村抜刀斎のその後を尋ねる頭目の文に返事は出したが、詳しく検分していたわけではなかったから、わからない事がたくさんまだある。しかしあの二人は何かをよく知っている。いずれ機会があれば尋ねてみようと、翁はその時思った。
やがて夜になって会はお開きになり、御庭番衆のだいたいの面々はしたたかに酔って、千鳥足でそれぞれの宿舎に戻って行った。何年かに一度の無礼講ということであった。蒼紫や翁、頭目などの重鎮の面々は最後まで残っていて、相談事をした。それは主に政治向きの話であり、将軍家が今後どうするかという話や、長州藩や薩摩藩の攘夷派の噂についてであった。蒼紫は二人の話に時々あいづちを打っているほかは、ほとんど聞き手に回っており黙っていた。
「外は雪ですな。」
と、翁は料亭から出る時に傘を差して言った。折からの雪は、かなりのぼたん雪に変わっていた。
「葵屋までご一緒しましょう。足元には気をつけてください。」
と、翁が言うのに、頭目はいらんと手を振って傘を差した。後から蒼紫も傘を差して同行した。その時には蒼紫の様子は特に普段とは変わりなかった。
蒼紫は二人の後ろを無言で歩いていた。
京の夜道は静かであった。新御頭と言ってもこれまで通り、頭目の傀儡であることは明白であった。今後も自分は頭目の意のままに操られる人形に過ぎないのだと思った。降り積もる雪を踏みしめる足音が、足元からきゅっきゅっと響いて、それが蒼紫にはたくさんの巴の哀し気な悲鳴の声に聞こえた。それは心が泡立つような感覚だった。自分が今こうして傀儡とは言え栄光の道を歩めるのは、死んだ巴のおかげと思うのが、たまらなかった。頭目がよろよろと酔いで歩いている後ろで、彼は傘を投げ、静かに抜刀した。
もちろん彼は頭目の話を耳にした時、信じられないという思いはあった。だが目の前の頭目がこの『破れり』という墨文字を書いたのだ、と直観で確信した時、彼は殺意を芽生えさせたのだ。彼は数少ない手がかりを元に、大津で巴たちが暮らしていたはずの場所に深夜に抜け出して行ってみた。そこで焼け跡の瓦礫の中から、あの死んだ母の思い出の懐剣と女物の鏡の破片を見つけ出した。なぜ見つけられたのかは、蒼紫自身にもよくわからなかった。勘、ではあったのだろう。しかしそれらを見つけた時、それがそこにある理由を推理して、頭目への憎しみが沸き起こった。自分は明確にしくじったのだ。以前に中山道の分岐点でも自分はしくじった。またしても自分は、と思うと、彼は歯噛みしたいほどの想いに駆られた。その場でひとしきり声を殺して、死んだ巴のために男泣きに泣いた。その後、焼け跡のそばに真新しい無縁墓が立てられているのを見て、彼の気持ちは最高潮に達した。巴の墓と無人の焼け跡。捨てて行ったのだ、その緋村抜刀斎という男は。こんな事が許されていいはずがなかった。憤りに体中が震えた。
その彼にとっては重大な犯罪の一端を担った男は、今目の前を無防備に歩いていた。蒼紫はまず苦無を鋭く投げた。苦無は頭目の脚に突き刺さった。
「?!」
頭目は驚いた様子だった。そして次の瞬間、振り向いて抜刀して蒼紫に斬りかかってきた。
「――遅い!」
蒼紫はそう言うと突進して、呉鉤十字で頭目の首をめった刺しに斬った。あまりにも素早い動きだった。それに対して酔いが回っていた頭目は、やはり緩慢にしか動けなかったのである。このために蒼紫は宴会場でずっと酒を断っていたのであった。翁は驚いて蒼紫を止めようとしたが、時すでに遅しであった。
蒼紫は技で倒れた頭目の体の上に飛びかかり、その体をめった刺しにしている。ものすごい勢いだ。血が四方八方に飛び散り、それは凄惨な現場であった。頭目も痛みに呻き声をあげている。牢の中では、真面目に頭目の必殺技を破る方法を考えていた蒼紫であったが、それももはや意味はなかった。ただ一刻も早く目の前の頭目を殺害する方が先であった。そのような事を牢の中でのんびりと思索していた自分についても、彼には呪わしかった。そのような必殺技に呪縛されていた自分が、今の蒼紫には何よりも恨めしかった。
蒼紫はぐさり、と呉鉤十字でかき斬った頭目の首に、また剣を突き刺している。そして憎しみのままに深くえぐった。蒼紫の勢いに言葉をなくして呑まれて見ていた翁はその時、遠くでぴりぴりと警笛の音がしたのに気づいた。ばらばらと、特徴のある浅葱色のだんだら模様の羽織を着た男たちが、こちらに向かって駆けてきた。
「新選組である!そこで、何をしているのか?」
新選組が、京の夜間警備で見廻りをしていたのだった。翁は傘を向けて蒼紫を隠して言った。
「何事でもない。我らは江戸城御庭番衆である。うちうちの事で処罰する事があった。御引取り願おう。」
隊士たちの中から土方歳三が現れた。土方は言った。
「そうとも見えんが。殺しとして報告させていただくのが所存。」
翁は言った。
「必要はござらん。我らでこれは、処分させていただく。新選組の方々には、関係ござらん。それとも、将軍家直属の我らに、会津藩預かりのそこもとらが、言える立場とでも?」
土方はそれを聞くと、苦笑いをした。
「なるほど、市井の者とは違うというわけですな。わかりました。邪魔立てしたのは申し訳ない。」
すると、横に立つ斎藤は土方に耳打ちするようにした。
「副長、あれは、ただの殺しではありません。」
「言うな、斎藤。面倒は起こしたくねぇんだ。」
と、言うと土方は「引き上げるぞ」と、一同に言って回れ右をした。斎藤はしかし、引き上げる時殺人現場を窺うようにした。蒼紫が頭目の殺害を終えて、座り込んで呆然としていた。血だまりに座り込んで目を怒らせているその様子は、一匹の慣れぬ野生の獣のようであった。この男の顔は覚えておこう、とその時斎藤は思った。
幕間
蒼紫は頭目を殺害した罪で、謹慎処分は受けたが、牢獄に入るわけでもなく、あくまで幕府側からは謹慎という事にとどまった。それは折からの長州征伐があり、次期御頭が決まらないことで戦列からの離脱は困るということで、御庭番衆内の内紛ということで処理されたのである。もちろん内部的にはそれ相応の軋轢は生じた。しかし京都の翁が蒼紫の後見人として立候補することで、圧力をかけて一応の収束は成ったのであった。
それと言うのも、前頭目が気に入らない部下を次々と粛清していたので、御庭番衆内でもすでに前頭目に対する批判はあったのである。不満を抱いていたのは蒼紫だけではなかった。しかし、前頭目を襲名式の日に殺害したことで、蒼紫についての風評を悪くしたのは事実であった。また前頭目には、回転剣舞などの技を後継できないという理由で、絶縁状態にあった息子夫妻が越後長岡の地にいるという事で、そちらを推すむきもあったのである。蒼紫は言わば前頭目とは血縁関係にない人物であり、御庭番衆の世襲制を考える者らにとっては、目の上のたんこぶであった。前頭目を殺害したとあれば、なおさらである。しかしそれらを制するよう、翁は蒼紫に進言した。越後にいる息子夫妻は御庭番衆とは無縁の郷士生活を営んでおり、もともと前頭目から破門同然の扱いを受けていた。それを擁するのは御庭番衆の弱体化になると翁は考えたのである。翁は葵屋の離れ座敷で、蒼紫に向かって言った。
「越後の息子夫妻は嫁の方の巻町姓を名乗っており、操という一人娘がいるそうじゃが、まだ幼い娘じゃ。それを担ぎ上げなど、もっての他じゃ。おまえもそう思うじゃろう。父親の息子の方は、前頭目から書状付で離縁されておるから、これを担ぎ上げる事はままならんじゃろう。」
「いくつになる娘なのですか。」
「今六歳ぐらいになるかのう。おまえとは十五歳ほども歳が離れとる。そういう娘と、次期御頭を争うというのは、いくらなんでものう。おまえにはその分、しっかりしてもらわねば困る。」
「わかっております。」
「江戸へ帰っても、規律を乱すような事はしないでもらいたい。まあおまえには言わんでもいいことじゃろうが。それで話というのは、雪代巴さんのことじゃ。おまえは何か知っておるな?」
「いえ。何も。」
翁は蒼紫の返答に、居住まいをただした。蒼紫の、あまりにもそっけない返答であった。翁は続けた。
「そうか。般若からの伝書鳩で、おまえたちがその娘さんを守るべく旅をした伝が書いてあった。このほど闇の武に加わりそちらで九ノ一の法をすることになったから、京都でも微力でもよいので力になってほしいと書いてあった。あれはおまえが書かせたのか?」
「それは般若が独断で書いたものでしょう。当方は座敷牢につながれていたので、関知せぬことです。」
「部下が勝手にやったという事でいいのか。おまえの動向を見て、やむにやまれぬ事で筆を取ったと見たが。」
「その人はすでに鬼籍に入っております故、翁からのお気遣いは無用のことかと。」
「本当なのだろうな。わしはその人におまえの母の懐剣を思わず預けたのじゃが・・・不要のことだったと言われれば、あいすまなかった。命を落とす九ノ一の例はよくあることじゃ。こだわりがないのなら、それでよい。」
「は。」
「今は心静かにして、亡くなった前頭目の冥福を祈るのじゃ。おまえがあれを殺害したのは、おそらく技についての意見の相違じゃろう。そういう事にしておく。」
翁はそう言って席を立った。形ばかりの物言いになった、と翁は思ったがそれ以上は蒼紫には言えないでいた。蒼紫についての扱いについては、まさに腫物に触るような感じであった。あの事件以来、蒼紫が前にもまして、ぴりぴりした雰囲気を身にまとうようになったからである。それは新御頭の任務からだけではなかった。
蒼紫は将軍につき従い、長州攻めの任についた後、また江戸に戻っていった。長州攻めでは幕府軍は敗走し、七月に将軍家茂が病死し、その年の九月、長州と幕府の間で休戦協定が結ばれたからである。十二月に徳川慶喜が十五代将軍に任じられ、しばらくは戦禍はなかったのだが、その次の年の十月に大政奉還の話が幕府内で持ちあがった。話を持ち出したのは、土佐藩の山内容堂であった。すでに九月に薩摩・長州・安芸の三藩が討幕の挙兵を上げていた。
その頃蒼紫は独自の諜報活動で、先の年の一月の薩長同盟の密談の折に、緋村抜刀斎らしい人物が会合の席で警護に当たっていたという情報をキャッチしていた。蒼紫は緋村抜刀斎の実際の顔を見知っていたわけではない。しかし脳裏にそれらしい「人物」の短い映像が浮かぶことがあった。座敷牢で長時間黙祷していた折から、そのような事象が浮かぶようになった。最初は蒼紫はそれは雑念だと思っていた。巴らしい人物の映像が浮かんだ時は、己れの性的欲求から出たものだろうと思った。しかしそれは、映画のようにはっきりした「映像」なのである。実は先ほど話した大津の巴らの居住地に蒼紫が向かう事ができた理由も、それらの背景に映っていた山並みや田園の形から、蒼紫は推察して訪れたのであった。その頭の中で「見た」映像と同じ家々が広がっている事に、最初蒼紫は驚嘆した。しかし、それも直に神仏の加護であると納得するようにした。彼に備わった能力は、おそらく透視能力の一種である。しかしそれも、忍者たちの世界では特に珍しいというものでもなかった。蒼紫もそのような能力が得られたから、特に自分をすぐれていると思った事はない。しかしそれをなんとか利用して、目的の緋村抜刀斎に近づけないものかと考えていた。
緋村抜刀斎はまだ京にいるらしいと言う話だった。蒼紫は京に行く機会をうかがっていたが、十二月に王政復古の大号令が示され、将軍慶喜は将軍職を辞し大阪城に退去することになった。その折、蒼紫は江戸を立った。部下の般若式尉癋見火男猩々らを連れての旅であった。最後には大阪城に入る予定であったが、蒼紫はまた中山道をたどり、あの恵那山の問題の廃村に入って行った。般若は蒼紫がまっすぐに大阪に行くものと思っていたから、この途中の寄り道には不審に思った。しかし旅の途上蒼紫の口数は少なく、何かを思い描いているようであった。すでに御庭番衆は幕府の部下でもなくなっていた。徳川幕府が空中分解したからである。その事について、蒼紫は勝海舟という老人に会って、江戸城内で話をした事があった。勝はこう言った。
「おまえさん、おまえさんらの御庭番衆の仕事はなくなるね。そういう世の中になるさ。あしは、この城を無血開城したいのよ。無血ってわかるかね。無抵抗の美学さ。おまえさんみたいな血の気の多いやつには、阿呆らしい事と思えると思うが。」
蒼紫が黙っていると、老人はにこやかに言った。
「おなごはさ、無抵抗に男を受け入れる。しかし最後にはおなごが子を作って勝つんじゃ。あしはメリケンに行ったが、あちらではそういう考え方がある。戦うだけがえらいんじゃないさ。民百姓が不必要に死なずにすむ方法を考えねばならん。」
「御庭番衆は解体しようと思います。」
蒼紫はぽつねんと言った。それはかねてから思っていた事だった。
老人は蒼紫の言葉に大きくうなずいた。
「そうかね。今まで恩恵にあずかってきた、山の衆たちは怒るじゃろうが、なんとかなだめて去るように持っていくんじゃな。ま、がんばりな。」
老人は蒼紫の肩をぽん、と叩くと向こうへ行った。
蒼紫が御庭番衆の解体を思っていたのは、実は襲名式の前からだった。すでに徳川三百年の歴史には、終止符が打たれようとしていると、蒼紫は牢の中の長い思索で考えていたのである。その解体の前に、障害となる前頭目を取り除く事は、蒼紫には必要なことであった。巴からの恨みだけではなかったのである。
恵那山の廃村に着くと、蒼紫はあの廃屋の小屋に入って行った。部下たちは初めて来る場所なので、興味津々であった。と、蒼紫は服の下からあの硝子の破片を取り出した。あの時前頭目の前で粉々に割ったはず――のそれは、実は蒼紫がこの製造所の床から適当に拾った発光硝子の破片であった。蒼紫の演技力が物を言ったのである。腹芸とまではいかないものの、蒼紫もそうした危ない橋を渡り歩いていた。この時蒼紫の取り出した破片の数は、なぜか三つであった。
「三つありますね。」
と、覗き込んだ猩々が言った。指さし、言った。
「これとこれを組み合わせると、ひとつ余ります。」
「そうだ。こちらの破片はどちらとも組み合わせることができる。そうだな、式尉?」
蒼紫の言に式尉ははっ、とした顔になった。
「まさか、知ってらっしゃる・・・・。」
「そうだ。あの時、おまえが硝子をすり替えようとした。まだ上屋敷に俺たちが滞在していた時だ。俺はおまえがすり替えようとした元のものを保存して、おまえのものを前頭目の懐にねじ込んだ。ここにあるのは、そのふたつの破片と葉霞が持っていたものだ。」
「元どおり・・・・俺よくわからない。」
と、癋見が頭をひねった。蒼紫は説明した。
「こういう事だ。式尉は薩摩藩の書状のありかがわかる方の破片があったから、それを隠した。俺はそれを隠し持っていた。おそらく薩摩藩につながる物と判断した。しかし前頭目の前ではその事実を隠蔽したのだ。」
蒼紫はそう言うと、問題の硝子の破片をつなげた。組み合わさった破片の中の女の脚の数は四つになった。
「二人の女の脚――ふたご座だ。南南東の少し上だな。」
式尉は笑って首を振って言った。
「まいりました。御頭がそんな、壺振りみたいなまねをなさるとは。俺が二重密偵でも飼っておられたという事ですか。」
「薩摩の動向も知りたかったからな。おまえを通じて見ていた。この硝子の件も、元は薩摩が出所だろう。」
式尉は嘆息した。
「そうですね。薩摩からの書状は見つかりましたか。」
「あの時見つけて移動させておいた。この分度器のふたご座の方角には松の木がある。その根元を掘ってみたところ、箱はあった。書状の箱は崖下のある場所に、幕府からの朱印状とともに移動させた。上様には紛失という事にしておいた。」
「なぜそこまで我ら薩摩をかばったのです?」
「その理由はおまえが一番よく知っているだろう。薩摩につながる、さる藩の御家騒動だな。話せ。」
式尉は重い口で話し出した。さる藩―――それほど大きくはないが、格式のあるある藩である。そこの殿さまの愛娘の幼い姫が、薩摩が下請けにしてよその藩に製造させていた発光硝子を部屋の中に飾っていて、ある日突然死んだこと―――殿さまは娘がその硝子がたいそう綺麗だというので、部屋の中に何十本も緑の硝子の瓶を飾らせていた。病弱な娘は、その瓶に花を活けたりして、寝床から喜んで見ていた。
「それがある日突然、亡くなってしまい、硝子の呪いだと言って大騒ぎになりました。薩摩にもその罪が問われて、藩としても秘密裡に製造していたものを、一挙に書状の証拠ともども葬ることにしたのです。その輸出地点がこの地だったのです。」
蒼紫は式尉に尋ねた。
「死んだ時の様子は?」
「硝子の発光で死んだという話でしたが・・・。それであの光がよくないと言って・・・。」
「いいから話してみろ。なんでも聞いた話を。」
「死亡した時、部屋の中に梅のような香りが充満していたそうです。息が詰まるみたいな匂いで、あわてて窓を開け放したそうですが。その姫は、発光硝子の発光をよく見るために、部屋を閉め切って薄暗くしていたそうです・・・・。」
「青酸瓦斯だな。」
「えっ、なんですって?」
「蘭学の書物にあった。塩酸に庭の肥料で使う消石灰などを混ぜると、その瓦斯が発生する。発光硝子の瓶の中に入れられていたのだ。青酸瓦斯は窒息死する。」
「そんな馬鹿な?!」
「俺の見立てではそうだ。硝子の光のせいではない。」
蒼紫はそこで立ち上がった。
「その姫が死んだから、巴がああした任務に就かされたのだろう。よくわかった。」
癋見が驚いたように言った。
「巴・・・・がどうして?」
「硝子の研究者の娘だったからだ。生きて幸せでいるだけでも、憎かったのだろう。幕府側にその事実も知られたら、巴にはさらに追及の手は及んだに違いない。」
「そんな・・・・。」
癋見たちが言葉をなくしているのに、蒼紫は続けて言った。
「御庭番衆は終わりだ。おまえたちに来てもらったのは、最後の旅を飾る意味もあった。俺はこれから行くところがある。しばらく会えないかもしれない。」
猩々は叫んだ。
「そんなのは嫌だ!なんでそんな事言うんですか?幕府がなくなっても、俺たちは御頭のそばに・・・・。御頭は、いつまでたっても御頭です!」
猩々の目には涙が浮かんでいた。蒼紫は優しく猩々に答えた。
「機会があればまた会えるだろう。猩々、山に帰るのだな。般若、頼みがある。」
「なんでしょうか。」
「おまえのその面には換えがあるのか?ひとつ俺に貸してくれないか。いつか返す。おまえのその顔を晒すことになるが・・・・。」
般若は首を振って答えた。
「蒼紫様が必要とあらば、この般若、面のひとつやふたつ・・・・・。」
そう言って般若は般若面を顔からはずして、蒼紫に捧げ渡した。般若の醜い焼けただれた顔が直に現れた。変装をするために焼いた、と周囲には言っていたが、その実戦禍に巻き込まれて焼けた顔だった。般若は言った。
「お別れになるのですか?」
「大阪には顔を出す。その後のことはわからん。ではな。」
蒼紫はそう言うと、ゆらゆらとその場からかき消えた。流水の動きであった。残った癋見や火男たちはその場で泣いた。般若は言った。
「今生の別れではない・・・・あのお方には、すべき事があるのだ。」
と。
蒼紫は一同から別れた後しばらくして、一人でさらに深い山を目指した。そこはアルプス岳のどこかの平沢だった。一面に黄色い山野草が咲いている。季節はもうすぐ春だった。雪がまだ沢のあちらこちらに残っている。五月頃だったろうか。
ひときわ見晴らしのいい場所を蒼紫は見つけた。眼下に白い雲海が広がっている。遠くにかすんで、青い北アルプスの峰々の先が見える。天界の場所がそこだった。
蒼紫は刀の柄の先で地面を削って掘った。そしてその穴に、風呂敷包みに包んできた、あの女物の鏡の破片をざっ、と開けた。鏡は粉々だったが、日の光に反射して破片がきらきらときらめいた。そこに蒼紫は丁寧に土をかぶせた。
「ここなら寂しくないか。」
と、蒼紫は言った。少し笑った。蘭学所の泰西画で見た天上の絵と似ていた。永世天国、と題された宗教画だった。
蒼紫は少し大きな石を目印に置いて、それからあの懐剣を取り出して供えた。
しばらく黙祷して手を合わせた後、蒼紫は懐剣を握った。
「これだけもらっておくぞ。」
そう言って、蒼紫は懐剣を懐にしまって山を下りた。
北帰行
その後蒼紫を見かけた者は少なかった。ただ一度、蒼紫が北越から戻ってきて、幼い操を連れて京都の翁の葵屋を訪ねたことがあった。部下も何名かその時はいたようである。それは北越戦争で長岡の城が落ちた頃で、明治元年(1868年)の話で、まだ二年ほど後のことである。その間蒼紫がどこでどうしていたか、知る人はほとんどいなかった。蒼紫は戦禍で両親を失った操を救い、新潟から京都まで連れてやって来た。蒼紫は操を葵屋に預けて少しの間滞在したが、すぐにいなくなってしまった。幼い操が蒼紫と短い期間だが仲良く暮らしたのは、御一新が成ってから後の話である。その、数少ない消息のひとつが江戸の町にあった。
ある魚河岸沿いの通りの、金物研ぎやである。暖簾をくぐり、一人の背の高い男が入って行った。
「これを研げるか。」
と、男は言った。金物やの親父は男の差し出した懐剣を手に取って、刃を抜いてみた。火事で焼けた跡があった。親父は言った。
「これはだめだね。火事で燃えちまってる。研いでも斬れねぇ。鋳型で鋳直した方がいい。包丁なんかにしてみたらどうかね。」
男は親父の言葉に、柔和な笑みを浮かべて言った。
「このままの形でなんとか保存したいのだが。母の形見でな。」
「おさむらいさんの御母堂ですかい。亡くなって何年になります?」
「弟を妊娠していてな。死んで何年になるか・・・・。その時の火事でな。」
「へえ、そうですか。それはお気の毒な話です。これは預かっときます。研ぐだけでいいんですね?斬れねぇけど。」
「ああ。頼む。」
男はそう言うと、店を出て行った。蒼紫が出て行ったのを見計らって親父は言った。
「おい、これ、回しとけ。わけありだ。」
と、親父は職人たちに懐剣を渡して言った。職人は尋ねた。
「わけあり?そんな風には見えなかったですが・・・。辻斬りのたぐいじゃねぇでしょ。ただの形見の刀を。」
「弟を妊娠していただぁ?そんなに年の離れた兄弟があるわけねぇや。こりゃ古くて去年あたりに火事にあったもんだ。ま、さむらいなんてそんなやつばっかりだがな。」
と、親父は言った。
蒼紫は今北の地に向かおうとしていた。
抜刀斎の消息はなかなかつかめなかった。
一度、京に滞在しているという情報を元に、それらしい人物を当たってみた事があった。張りこんでいて、この男がどうやら薩長同盟の会合にいたらしい、とわかったのだが、蒼紫の脳裏に浮かんでいる人物とは微妙に違う気がした。問題の緋村抜刀斎の映像は、蒼紫がまったく面識がないせいか、はっきりとした図像で浮かんでこない。かろうじてわかるのは、巴と並んだ時自分ほど背が高くないという事ぐらいだった。映像は細切れで断片的にしか見えなかった。しかも巴が死んだ今、その映像はまったく見えない。かすかな記憶をたよりに蒼紫は動いている。それも御庭番衆としての後始末をしながらの任務であった。
その京で今観察している緋村抜刀斎という男は、特に腕が立つという風でもなかった。ごくふつうの腕前、しかし持っている剣が邪剣のたぐいで、改造刀を所有している。それで長州に歯向かう者たちを夜ばさばさと斬っていた。司令を出していたのは桂小五郎で、これも以前に流れていた風評のとおりだった。しかし何かがおかしかった。その緋村抜刀斎には、蒼紫が巴の映像で感じた、ある種の品位のようなものが感じられない。巴は映像の中で、抜刀斎と受け答えをしていたが、それは蒼紫としているような具合の、落ち着いた声色の声だった。巴にああした声を出させる男、と思って蒼紫はその緋村抜刀斎を考えている。
それが決定的に違うと蒼紫が思ったのは、問題の緋村抜刀斎が京の島原通いの常連だったことである。島原にはなじみの芸姑がいるらしく、毎晩とはいかずとも、かなりの日数そこで遊んで帰る。もしこれが本当に抜刀斎だったら、と思うと蒼紫にはあまりにも非情な男と映った。巴は縁の話では、抜刀斎の子供を妊娠していたのである。それを斬り捨てて、今は島原で遊んでいる。もしそうなら、到底許せるものではなかった。
蒼紫がつけはじめてから数日後、問題の緋村抜刀斎は一人の男を斬った。それはあの飯塚であった。桂からの指令は口封じであった。人斬りの検分役を長く勤めていた飯塚は、桂らが幕府の役人たちを多く始末した記録を残していたし、またその情報を知っていた。それは薩長同盟を成立させた桂にとって、邪魔な存在だった。政治の表舞台に立つには、居てもらっては困る男だった。飯塚もそれに気づいて高跳びする寸前、寂しい路地で飯塚は第二の緋村抜刀斎に一撃で斬られた。それは剣心や巴をも欺いた者の末路であった。わずかばかりの路銀を握り締めて飯塚は死んだ。
蒼紫が犯行を決意したのはその二日後の事である。油の樽を用意し、蒼紫は京の路地で緋村抜刀斎の訪れを待った。島原の入り口の大門から少し行った裏寂しい場所だった。もう日暮れの頃合いだった。蒼紫はこの機会を逃した場合の誤算について考えていた。もし違っていても、ああいう男なのだし、元幕府方だった自分は長州派への積年の恨みもある。何よりもこの機会を逃したら、ああしたさげすみたくなる男を、二度と葬ることはできないのだ、と。
第二の緋村抜刀斎、もうおわかりの通り志々雄真はこの日も島原でなじみの由美と楽しいひと時を終えて帰宅する最中だった。由美は江戸から呼び寄せて、この島原で芸姑をやらせている。志々雄が呼べば、由美はいそいそとついて来た。志々雄には人斬り稼業で金目もあったし、何よりも由美を満足させる事ができる男だった。志々雄はそれでも、金魚鉢の金魚を楽しむような感じで、由美の落籍をいまだおいているのだった。それにじれてたまらない様子の由美を見るのは楽しかった。俺に首ったけだからな、と志々雄は酔いの回った頭で考えて悦に浸っていた。
志々雄がその角を曲がった時だった。般若の面をつけた藍色の作業着を着た背の高い男が前方の暗がりに立っていた。男は何か言ったようだった。
「・・・緋村抜刀斎だな?」
「なんだてめぇは。俺を誰だと心得る。天下の志々雄真さまだぞ。」
がなり立てた志々雄に対して、男は道路上の樽を手前に蹴った。志々雄に向かって飛んだその樽は頭上で破裂した。何か液体のようなものが志々雄の体にざぶっ、とかかった。
「何しやがる!てめぇ、生かしちゃおけねぇ!」
びしょぬれになって刀を抜こうとした志々雄に、男の手から火弓のようなものが素早く飛んだ。数発、その矢は志々雄の体に刺さったとたん、猛煙をあげて炎があがった。蒼紫は言った。
「・・・・おまえも炎に焼かれて死ね。」
熱い熱いと志々雄が大声で呻いているところへ、仲間のさむらい達が通りの向こうからばらばらと現れた。仲間たちは通りに積んである防火用の桶の水をかけたりして、炎を消そうとしている。どうやら志々雄は助かったようだ。蒼紫も実は、それほど島原から離れていない場所で犯行に及んだのは、志々雄が助かる可能性がある場所として選んだのであった。
助けたくはなかった、しかし・・・・と蒼紫は考えている。巴があの男と半年間暮らして子を得ていた事。巴はあの男を助けようとして死んだという事。巴の心変わりとは思いたくない。しかし巴はあの男を愛していたのだ。せめて、あの無残な廃墟の有様と同じ様子を、その男の体の上に再現することで、この胸のつかえを取り去りたい。
志々雄はその後、島原の由美のところで体を介抱されたが、全身にやけどを負って、人斬り稼業からはずされる事となった。志々雄はその般若面の男を恨んだ。志々雄は包帯だらけで寝そべっている枕元でつぶやいた。
「確か俺に、『緋村抜刀斎だな』と言っていた・・・・。由美、俺は確かに人斬りはしていたが、人さまにそれほど恨みは買っちゃいねぇつもりだ。桂の指令で全部殺していたんだからな。あれは、俺の前任の男の事なんじゃねぇのか。大津で半年ほど遊び暮らしていたらしい。今は雲隠れしてやがる。そいつが怪しい。」
由美は手桶からてぬぐいを絞りながら、言った。志々雄の熱さのまだ残る顔を拭いている。
「そうなのかねぇ・・・・。こんなになっちまって、もうおあしも出ないとなるとどうすりゃいいのさ。」
「いや、由美。俺はやるぜ。見てな。また元通り剣を握るぜ俺は。まずはその『先輩』を探し出して、話を聞いてみてやる。俺の天下取りはそれからだ。」
「天下取りなんて、戦国の世じゃあるまいし・・・。」
「それができるのさ。桂小五郎だって、元はたいした野郎じゃねぇ。時流に乗りやがったからあんな具合になっちまった。ちょっとした事で追い風がくれば、俺だってな。」
「そうかい?」
由美はそう答えると、志々雄の包帯だらけの顔を見て、やはり頼もしいと思った。この人はこんな目に会っても少しもへこたれちゃいないね、やはり私の見込んだだけの男だわと考えた。由美は言った。
「いい温泉場に行こうよ。体の傷を治すにはさ。当面はあたしが稼いだ金があるから。」
「悪いな、由美。」
「いいのよ。」
由美は志々雄と会った頃のことを回想していた。両親は幼い頃、押し込み強盗に斬られて死んだ。その男と似た改造刀・無限刃を持っていた男、それが志々雄だった。最初は寝首をかいてやろうと思った。そのために近づいた。しかし今は・・・・。
「結局男なのかねぇ。」
と、由美は背中で独り言を言った。
蒼紫はその頃、志々雄真が当の抜刀斎ではないという情報をやっとの思いでつかんでいた。桂たちの密談を聞いたのである。桂たちは、京での誅殺をもうたたんで、討幕軍に合流する相談をしていた。遅きに失した話だった。あれが失策だったのか。巴の仇討ちなど、自分ひとりで思い込んでしている事なのか、と蒼紫は自分を責めた。巴のために頭目を殺し、緋村抜刀斎と目した男を火あぶりにした。しかし巴は帰ってこないし、巴が死んだのは別の男のためだ。思えばあの中山道で抱きしめた時も、巴は自分を拒むように手を差しかけたではないか。巴の本当の気持ちをあの時聞き出したわけではなかった。そんなあやふやなものを、自分はこれまで追い求めていた。見返りがあると期待していたわけではなかったが、蒼紫にはあまりにも寂しかった。
旅先の宿で夜、蒼紫は研ぎから帰って来た母の形見の懐剣を抜いてみた。この刀を敵から取ろうと巴は手を伸ばしていたのだと言う。縁の話ではそうだった。その時巴はどう思っていたのだろうか。その緋村抜刀斎を助けるために、手を伸ばしていたのだろうか。蒼紫の顔に微苦笑のようなものが浮かんだ。
「翁がこれを巴に渡しさえしなければ・・・・。」
渡さなければ、巴は死ななかっただろうか。緋村抜刀斎とどこかで幸福に暮らしたのだろうか。俺の事も忘れて。蒼紫はそうつぶやいた後、しばらく動かなかった。眠りのような昏睡に落ちた。
蒼紫はどこかの高原に立っている。巴らしき人物が、霧の中で手招きしている。こちらです、と巴は言っている。あのアルプス岳で見たような雲海が目の前に広がっている。あそこにいます、と巴は指さした。蒼紫は我が目を疑った。今まではっきりと見えなかった緋村抜刀斎その人らしき人物が、水汲みの桶を歩いて運んでいる。桶を運んで彼は山小屋の中に入っていった。それは現実なのか、と蒼紫は巴に尋ねた。巴は大きくうなずいた。はい、生きております。あの人は私を自由にして、なぐさみものにして、まだ生きております。でも、命を絶つほどの事はありません。私の子供は生まれなくてよかったのです。と、巴はすらすらと話した。だって私が好きだったのはあなたなのですから。あなたも私のことが好きでよかった。そのおかあさまの刀を血の雨で汚さないでよかった。あの時のあなたの言葉を覚えてらっしゃいますか・・・・・・、と、巴は顔をあげ、蒼紫の手を取り花のような笑顔で笑った。そしてその姿は霧のように薄れていった。
蒼紫はそこで目を開けた。
「おまえはそれでいいのだろうが・・・・・。」
蒼紫はそう言うと、腰をあげて手荷物の中の地図を取り出した。地図をぱらりと広げて、北の方角の山を探した。東北だ。
「官軍の進路の方角に向かっている・・・・。」
蒼紫は低くつぶやいた。
剣心はその頃、東北地方のある深い山地にある、新井赤空の鍛冶小屋に居候していた。刀鍛冶の赤空は最初剣心を無視した。比古の入れた手紙の中には、赤空の住む豪の地図と、「逆刃刀を言ってもらい受けよ」と書いてあった。剣心が逆刃刀と言っても、赤空は無言のままで、一言「強くなりたいってのか」と言った。そしてあっちへ行けと手で追い払った。
剣心はしばらくそこで赤空の身の回りの手伝いをした。逆刃刀は自分に欠けている技を磨くために、必要な刀だった。噂に聞いた事があったのだ。刃がふつうとは逆に峰側についているから、持つ手に手心を加えねば斬れないという話だった。ふつうでは斬れないという事から、剣心は巴の腹の赤子を斬ってしまった事から、自らが「『殺さずの剣』を持つべきだ」という事に旅の途上で思い至った。それにぴたりとはまっているのが、ふつうでは斬れない逆刃刀だった。比古はおそらく剣心がそういう心の傷を抱えると知っていたのだろう。剣心もまた比古の敷いたレールに沿って動いていた。剣心はその刀ならば、自分はまた新しい道が開けてくるのかもしれないと思った。一時は切腹を考えるまで思い詰めていたが、巴のような悲しい女性を生み出す世の中というものに、剣心の正義感はまた向かっていた。
剣心は赤空との食事時にこう言った。
「赤空殿、俺は強くなりたいわけではありません。逆刃刀は、むしろ弱くなってしまう刀です。しかし刀を捨ててしまって、人斬りであった事を忘れてしまいたくない。世の中が変わっても、俺は巴を守れなかった事を、戒めとして持っていたい。そのために逆刃刀は必要なのです。」
赤空は剣心の言葉を聞くと、ふふ、と囲炉裏端で肩をゆすって笑った。
「戒めね。おまえさん、御一新てのを知ってなさるか。もうすぐ世の中が変わっちまって、誰も刀なんざ持たなくなるのよ。俺は最後の一代ってことで、子供らとの家庭も捨てて、この山に来てるんだ。もういらなくなる刀を打ってるのよ。安土桃山の世に、秀吉が刀狩りってのをやりやがった。百姓たちから刀を取り上げたのさ。今度の新政府もそれをやるよ。おまえさんは、それでも逆刃刀を持つのかね?骨董品にしちまうのがオチさ。」
剣心は赤空の言葉を聞くと、居住まいを正して言った。
「今まで話しませんでしたが、俺は人斬りで、子供まで斬ってしまったことがあります。そんな俺が、ふつうの生き方なんてもうできません。ふつうではない刀が必要なのです。」
しばらく沈黙があった。やがて赤空は言った。
「武蔵を気取るのかね。まあいい。おまえさんはもともとあんまり人を斬るようにはできていない。それが何の因果か人斬りになっちまった・・・・、そういうやつに逆刃刀も使ってもらった方がいいかもしれん。わかった、打ってやるよ。ただし、人はあんまり斬れねぇ。それは覚悟しとくんだな。」
「はい。」
次の日から赤空は滝で水垢離をし身を清めてから、何日もかけて逆刃刀を打った。剣心も一緒に滝行をした。山すそを降ってくる滝の水を見ていると、巴と最初に出会った時の雨の夜が思い出された。ふ、と涙が湧いたが、滝の水で何処かへと洗い流されていった。
年号はすでに明治元年(1868年)に変わっていた。新選組は一月の鳥羽伏見の戦いの敗走後、甲陽鎮撫隊と名前を変えたりして、北上して討幕軍と戦っていた。局長の近藤勇は流山での戦いの後、捕縛され板橋で処刑された。慶応四年(1868年)四月のことであった。残った土方たちは会津を目指して行軍したが、会津を守って戦うかで隊内で激論が交わされ、残った斎藤を隊長に会津勢は戦うこととなった。土方たちは分かれて奥羽越列藩同盟の方へと進軍した。
斎藤は勝沼の戦いで敗走し、有名な母成峠の戦いで官軍と死闘を演じた。この後彼は旧幕軍を離れたというが、行方は杳として知れなかった。会津藩は八月に落城、同年九月、最後に残った奥羽越列藩同盟の仙台藩が官軍に降伏し、本州はすべて官軍の制圧下となった。残ったのは北海道の松前藩である。蝦夷地はしかし、莫大な土地があるということで、ここに旧幕府軍は蝦夷共和国を打ち立てるという計画を発表し、すでに官軍に下っていた松前藩へと侵攻した。彼らは十月に藩内の五稜郭を占領し、十一月に松前城を陥落させた。
新選組はこの頃には隊士が二十名ほどにまで減っていたのだが、このあたりで人員を募集し、桑名・唐津・松山藩の藩士が加わりまた百名ほどの数に復活した。蒼紫と斎藤が潜り込んだのは、この再募集の時であった。斎藤は人相を変装し、山口二郎の名前を名乗った。京で諜報活動をしていた頃、名乗っていた偽名であった。蒼紫の方もそれらしい名前を名乗っていた。彼らはもちろん同時に顔見知りで入隊したのではない。それぞれ隊士募集の応募に行き、入隊してから斎藤にはわかった。あれはあの時京で見た男の顔だと思った。しかし蒼紫の方は気づいていなかった。そのような傭兵の一人として目立たなくしていたからである。蒼紫の目的は剣心に会うことであった。剣心は官軍の中の一人として、北上してくるに違いないと思った。そのような「透視見」が散見された。彼は新選組として、北の地でその訪れを待つことにしたのである。必ずや旧幕府軍に一矢報いるために現れるに違いないと思った。
蝦夷地は冬が早い。十月の松前城の陥落の際には、城門の前で敵砲撃手を、開門と同時に鉄砲で狙えとアドバイスしたのは、名を偽っていた斎藤である。しかしその次の十一月に、その松前藩の者らに、幕府軍の軍艦の旗艦である開陽を座礁させられてしまった。この座礁には、土方は相当の落胆をした。十二月には諸外国に対して、蝦夷共和国の名前を土方らは承認させた。なんと独立国になったのである。蒼紫はそれらの戦いに対して、言われれば素直に従って参戦していたが、特に組していたわけではなかった。あくまで傭兵の部外者が蒼紫であった。そして、その様子を、幕府御庭番衆の職だった者として、じっと観察している斎藤がいた。
翌明治二年(1869年)の三月中旬、官軍である新政府軍の艦隊が北上してきた。開陽の沈没で海軍力が弱まっていた旧幕軍は、新政府軍の最新鋭艦である甲鉄を乗っ取る作戦を立案する。二十一日、回天と他二艦は函館を出港し、二十五日に宮古湾に停泊する甲鉄に攻撃を加えた。この作戦には土方歳三も参加しているが、三十分ほどの戦闘で多数の死傷者が出て失敗に終わった。蒼紫が剣心を目視したのは、この時の攻撃であった。
最初蒼紫は甲板で、多数の上船した幕府軍兵士たちを押す剣心の姿を認めた。間違いなく、その男であった。剣心はしかし、剣で斬り捨てるのではなく、峰打ちで敵を倒しているようであった。手加減をしているらしい。なるほど、妻を斬り殺した男だとそういう事になるのか、と思い、蒼紫は懐から般若面を取り出しておもむろに顔につけた。傍で見ていた斎藤は、「おい、それは」と思わず言った。戦闘に必要なものと思えなかったからだ。
斎藤は蒼紫がふざけているのだと思った。京にいた頃の新選組ならば、到底見過ごされぬ事である。しかし今は土方も軍参謀に近くなっており、隊士も氏素性のわからぬ者が大半だった。傭兵のこういったやつらが思い思いの戦闘をするから弱くなる、と斎藤は思った。それで止めようとしたが、蒼紫はすでに船上に駆けあがっていた。
剣心は背の高い男がお面をつけて、自分に向かってまっしぐらに甲板を突き進んで来るのを認めた。なんだあの男は、と思った。剣心は今では、多数の官軍の中で埋没した存在として、影の助力をするようにしている。京に人斬りでいた頃のような、突出した働きをしなければならないと考えていない。従って、蒼紫が見て取ったように、峰打ちで味方の進路を開くといった作業を地道に続けているのだった。逆刃刀はそういった働きには、よく答えてくれた。なにしろ刃の部分が歯ではないのである。しかしそういった自分をマークして、その男は突如現れたのだった。何かある、ととっさに剣心は思った。何よりも顔を般若面で隠している事が怪しかった。剣心はすぐに思った、これは巴のいた忍者集団に所属していた男だという事を。そしてやはり出たかと思った。
思えばこの為に、巴と暮らしていた住まいを無残にも焼き払い、思い出の品々を焼け跡に放置したのだった。それは剣心の仕掛けた罠だった。それに乗ってくる奴がいつか必ず現れる。そう思って彼は旧幕軍の後を追ってきたのだ。巴についての手がかりが、あの時点ではまったくなかった剣心の苦肉の策であった。従って彼は、巴と暮らした住居からは、巴の日記帳一冊を持ちだしただけである。そしてそれを旅先でめくっているうちに、ある晩ページの袋の中に袋綴じで薄い桃色の紙がはさまっているのを見つけた。綴じ紐をはずして開けてみた。それは一枚の恋文だった。巴の細い文字が筆で書かれていた。
『追わないでください。何もしないでください。何も傷つけず、ただあなたを思っていたい。――雪代巴』
剣心はそれが自分に向けての言葉ではないと、直観で悟った。なぜなら表側のページからは決して見えないように綴じられていたからだ。自分に向けた言葉は、あの簪がはさまっていたページに書かれていた言葉に相違なかった。そのようにして、この日記帳は残されていた。
剣心はその恋文をしわくちゃにして破ろうとしたが、かろうじて思いとどまった。そして、元通りに日記帳の中に大切に戻してやった。巴の本心が見えてしまった以上、剣心は自分のしてきた事が砂を噛むような事だったと悟った。赤子まで作ったのに、巴は別の男が好きだったのだ。そんなことがあるのか、と思った。そして己が運命にひとしきり泣いた。それは剣心が逆刃刀を手にした後だった。
剣心は回天から甲鉄の甲板に飛び移った蒼紫の第一撃を受けた。
二刀流で流れるような動きだった。対して剣心は使い慣れない逆刃刀だが、よくこらえて受けた。蒼紫が二刀で陰陽交叉で剣を折ろうとしたのを、刀ではじいた。峰側が刃だから、できた事だった。すぐに蒼紫は剣心の刀が通常のものではない事に気づいた。陰陽交叉は利かないとわかった。
蒼紫は剣心の首を呉鉤十字で狙うことにした。しかしなかなか剣心の首に隙はできなかっとた。激しい連打の応酬になった。
陰陽撥止などの投擲の技は狭い甲板で、一刀を失うことになるので危険だった。それだと一撃必殺でなければならない。と、剣心がとんぼを切り、蒼紫に上空から一撃を加えた。剣心は背が低いので身軽なのである。剣心としては、蒼紫に巴の事を尋ねたい気持ちがあった。そのため、必殺の構えではない感じの戦いになった。蒼紫はかろうじて受けた。蒼紫の心に焦りが生じはじめた。やはり、頭目の技を破る事を完成させなかったから、こうなったのか。この相手は抜刀斎と言われていた通り、思った以上にやる男だ。
その時だった。背後の人込みの中から、包帯だらけの男がかき分けて、二人の対峙している間に割って入った。志々雄真だった。
志々雄は般若面の男に見覚えがあったので、その般若面が攻撃しているやつが自分の『先輩』なのだとすぐにわかった。志々雄は無限刃を引き抜いて、二人の間にめちゃめちゃに斬り込んできた。何やら獣じみた叫び声をあげていた。「うらあ!」かもしくは「っんぱい!」だっただろうか。剣心と蒼紫は思わぬ珍客の乱入に、双方瞬時に後退した。志々雄は剣心に剣を突き付けて叫んだ。
「先輩、あんたのせいで俺は・・・・っ!」
蒼紫はその志々雄に一撃を見舞った。志々雄はもんどり打って後ろに倒れた。
その時、甲鉄の大砲がドンと数発とどろいて、回天に対して気勢あげた。回天の指揮を執っていた土方は「まずい。引き上げだ」と言った。間髪を入れずに甲鉄のキャビンからガトリング銃を押して出て来た一群があった。そのまま機関銃を旧幕軍に対して乱射しはじめた。
斎藤はそれを見て、旧幕軍に声をかけた。
「引け、引けーっ。おい、貴様も退くんだ。そこのお面野郎。穴だらけになるぞ。」
蒼紫は引くのにためらっていたようだったが、最後に回天へと飛び移った。そのまま彼らの艦は甲鉄から退いた。敗退である。蒼紫は遠ざかる海上の甲鉄をにらんでいたが、やがてあきらめて面をはずした。そこへつかつかと斎藤が近寄り、一発顔を殴った。斎藤は言った。
「戦場は武芸の稽古場じゃない。貴様は余計な事をしでかした。貴様のせいで、味方の撤退が遅れた。いったいどういうつもりだ。祭りの面か。」
蒼紫は答えた。
「稽古や祭りに見えたのなら謝る。そんな余裕はなかったのでな。顔を知られたくなかった。それだけだ。」
「知り合いだったのか。」
「・・・・・・。」
「まあいい。今度から注意しろ。」
蒼紫はその後無言で、斎藤の問いかけには一切応じなかった。御庭番衆だったのだろう、との質問にも彼は黙して答えなかった。斎藤は根負けして、蒼紫から離れて行った。
その翌月の四月、旧幕軍は函館の松前口で敗走した。五月には新政府軍は函館を総攻撃することにした。その間剣心の前に不思議と志々雄は姿を見せなかった。宿営地で、剣心はそれらしい包帯姿の男を探したが、見つからなかった。全身を包帯で巻いたその姿は、まさしく蘇ったミイラの死体のようであった。自分への恨みを叫んでいて『先輩』と自分の事を呼んでいた。おそらく桂の用意した、自分の後継者の男に間違いなかった。京都時代のことで恨みを買ってしまっていると思った。そしてそれはあの般若面の男もそうだ。
あの男がそうなのか、と彼は巴の亡霊に問うた。巴の幻は時々感じることがあった。しかし巴は黙然と立っていて、彼の質問には答えなかった。生きている時がそうであったように、巴は従順だがその心の中は見通せない女だった。剣心は答えない事が答えなのだと思った。自分をここまで追ってきたのだから、おそらくそうなのだろう。おそるべき執念だ。
俺はあの男に負けてしまうのかと思った。
新政府軍は函館山の奇襲作戦を取った。新選組が守っていたが、七百人あまりの長州勢で襲いかかり、函館山を陥落させた。その報は五稜郭で指揮をとっていた土方にも入り、彼らも一本木関門まで出陣した。土方がこの時の砲撃で倒れたのは有名な話である。蒼紫たちもその陣にいた。斎藤は言った。
「ここも終わりだな。」
土方の訃報に、斎藤は立ち合わせたのだった。土方とは激論の末会津で物別れになった。その土方が最後どうなるか見届けたかった。それでここまで来た。その後は、俺は俺で生きるまでの事、そう思った。しかし京の新選組では土方の隣で、副長助勤を務めていたのだ。だから最後まで着き従った。それは斎藤のけじめだった。しかし俺は土方に殉じるつもりはないと思った。斎藤はそういう男だった。斎藤は土方の亡骸が安置されている幕屋から出て、煙草を一服した。
そこへ蒼紫がやって来た。蒼紫は言った。
「もういいのだな。離れても軍規を乱す事ではあるまい。」
「なんだ。あの時の事を気にしていたのか。もう負けは確定だ。どこへとなり行けばいい。蝦夷共和国は、幕府はこれで消滅だ。」
「そうだな。」
蒼紫はかすかに笑うと、またあの般若面を顔にかぶった。「おい、なんだその面は」と斎藤が問いかけたのにも、蒼紫は振り向かなかった。すでに戦場は死屍累々とした平原が広がっていた。そこを蒼紫は歩いて遠ざかっていく。
「死んでもいいのか・・・・?」
と、思わず斎藤は言った。
剣心は戦場を歩いている。かなりの戦いだった。逆刃刀で戦うには骨が折れた。これもしかし、長州が仕掛けた最後の戦いと思えばこそだった。と、そのよろよろと歩いているところへ、突然地面に腕が伸びてきて剣心は足を取られた。志々雄の包帯だらけの腕だった。側溝に潜り込んでいたのだった。志々雄はぎらぎらと目を輝かせて言った。
「俺はよう・・・まだ体がほんちゃんじゃねぇ・・・だからあんたが弱るのを待ってたんだよ・・・・。」
「き、貴様は・・・。」
「先輩の名前をまだ聞いてなかったなあ・・・。俺は緋村抜刀斎と名乗れと言われてよう・・・。それで、名乗ったんだわ。そしたらよう・・・・・こんな目に会ってよう・・・・。」
剣心は志々雄を振りほどこうとしたが、志々雄はその体で剣心にのしかかってきた。蛇がのたうつような感じだった。体がぴたりと着くと、体中から熱を発しているのがわかった。
「熱いか・・・・熱いだろ・・・・・俺は火傷が治らねぇ・・・・ふつうの火傷じゃねぇぞこれは・・・・・ずーっと熱いままだ・・・・。先輩もこんな具合になったらどうだ・・・・。」
「や、やめろ・・・・・。」
「俺はあんたを・・・・・。」
と志々雄が言った時だった。一発の銃声がとどろいた。蒼紫が歩きながら、捨ててあったゲーベル銃から発射したのだった。志々雄の鉢がねの頭にそれは命中した。志々雄はのけぞって倒れた。
「死・・・死なねぇぞ・・・・俺はぁ・・・・。」
と呻いて志々雄は剣心の上で倒れた。
剣心は歩いて来る蒼紫の姿を見た。散発的に砲声が聞える中で、硝煙にけぶって、逆光になってその顔は面をつけていてよく見えない。と、蒼紫は銃を投げ捨てて、胸元から黒い懐剣を少しばかり取り出して剣心に見せた。剣心の目が大きく見開かれた。あの、巴の取ろうと手を伸ばした剣だ。それを大切そうにその男は持っている。間違いない。巴の恋文の男があれだ。
剣心は志々雄の体の下から必死に動こうとした。と、その志々雄の体を蒼紫は乱暴に蹴って、脇へどかせた。
「緋村抜刀斎だな?立て。」
蒼紫はそう言うと、剣心の胸倉をつかんで立ち上がらせた。剣心はよろよろと立って、逆刃刀を握りしめた。そして蒼紫に問うた。心の中が悲しみで満ち溢れてくるようだった。
「巴の男か・・・・?」
「それは貴様だろう。」
「いや、おまえだ!」
瞬間、剣心は蒼紫に向かって斬りかかった。最後の俊足だった。持てる力のすべてを出し切って賭けた。逆刃刀でなければ、この時倒せたかもしれない――後になって、剣心が後悔したのはそれだった。
蒼紫は剣心の斬撃を避けて動いた。回転剣舞。ただ一足の踏み込み。これが必要なことだった。頭目が秘して決して自分に教えなかった極意、それを蒼紫は剣心を追う長い旅の中で見出した。それは巴の亡霊との「対話」がなければなしえぬことだった。それは真に長い旅であった。
剣心の体に次々と斬撃が加えられた。その数は六つ。着地して、蒼紫は待った。剣心が倒れ伏すのを――。
「俺を、殺す、のか・・・・。」
倒れた剣心は蒼紫に言った。蒼紫は答えた。
「致命傷にはならぬようにした。巴を殺したのはおまえの過ち・・・・。その責は負ってもらう。許せ。」
剣心は蒼紫の言葉を聞いた瞬間、憤りの言葉を吐いた。
「おまえがいたから巴はああなったんだ!おまえらにだまされて、腹に子を作って、俺はそれを殺してしまって・・・・。おまえには巴を愛する資格なんてない!いつかまたおまえに会って、今以上の事をしてやる・・・・・!」
そして剣心はその場で、巴の名を大声で悲痛に何度も泣き叫んだ。しばらく風に吹かれて蒼紫はその様子を見ていたが、やがて立ち去って行った。「待てというのならば・・・。」との言葉を残して――。
時は変わって明治の世の中である。もう深夜に近かった。元新選組の鵜堂刃衛はいつものように、まだ刀を持っているごろつきから刀をせしめるべく、ふらりと帝都の街角を歩いていた。酔い覚ましに誰を斬ろうと考えているところへ、背の高い男が橋梁の向こうに現れた。瓦斯灯にけぶってその顔はよく見えない。刃衛は刀に手をかけた。しかしそのまますれ違った。
男に何か瘴気のようなものを感じたからだ。男に何者かが付き従っていると思ったが、それは何かは刃衛にはわからなかった。しかしそれも、刃衛が相手の精神を縛る「心の一方」を会得しているからうっすらとわかった事であった。刃衛はすれ違いざまに男につぶやいた。
「お兄さん、あぶないねぇ。」
男は無言のまま刃衛の横を影のように通り過ぎた。茶色のコート姿でポケットに手を突っ込み、手には長い拝刀を手にしていた。刃衛は気になって男を振り返り見た。
確かに跫音は響いていたのに、霧のように、男の姿は忽然と消えていた。
――完――
あとがき
足掛け十年以上はかかっただろうか。最初にこの話を思いついてから、それぐらいは経っていると思う。記録で確認できるのは2005年からで、それから十五年間ずっと考え続けていた作品だ。遅筆なのは仕方ないとして、いい案が浮かばず、途中何度も途中放棄を考えた。それがなんとか書けたのは、いろいろな時流の変化があった。新しいライティングソフトを導入したのも大きい。これで毎晩少しずつ書く訓練ができた。そうでなければ到底書けなかっただろう。長編を書いたのは久しぶりで、本当につらかった。なんとか完結したのは本当にうれしい。
蒼紫と巴の物語をねつ造してみたかった。OVA追憶編は非常によくできた作品だが、どうも私にとっては今ひとつ食い足りない気持ちがあった。単なる私にとってのベストな組み合わせという以上に、そうした私なりの考えの上で、彼らを配置してみたかった。それも昔に読んだ世界の名作文学のようなものでやってみたかった。もちろん力など及ばず、その惨憺たる有り様は見てのとおりだ。おかしな点、不自然な展開、そういったものは多々あると思う。もちろん誤字脱字もいつものとおりにあるに違いない。しかしそれは今の私には確認はできない。御高覧いただいた上で、そういった点はご留意いただきたい。
物語を展開していく上で、ものすごくネックになったのは、追憶編の緋村抜刀斎の存在である。OVAのキャラと変えてしまっているのは、本当に申し訳ない。しかしあのキャラでは私は書けなかった。まったくこういった事はよくないと思うのだが、個人的に好きな黒バスの赤司征十郎の顔を思い浮かべて書いていた。師匠が比古清十郎なので、名前がジュニアみたいでいいかと思ったのである。従って、元の剣心を思って読むと、いろいろと不都合な点が多々あるかと思う。セリフとかまったく違ってしまっている。もし間違われて読まれた方には、本当にすまないと思っている。ただどうしても私は、原作の初期設定の剣心が苦手で、あれだけは我慢できないとかねがね思っていたので、今回変えさせていただいた。それはだいたい東京編のあたりの剣心で、OVA追憶編のものではないのだが、やはりつながった部分が多いので、気持ちとして違うものにさせてもらった。もともと蒼紫ファンの私なので、どうしてもそういう感じなのである。重ね重ね剣心ファンの方たちにはお詫び申し上げる。
話の主軸になっているウランガラスは現物も見た事がないし、その危険性もよくわかっていない。ただ原子力爆弾がなければよかったのにという私も気持ちを織り交ぜて、そういう話を展開させていただいた。もちろんまったく正史にはない歴史上のねつ造話である。ウランガラスの特性のおおげさな点と同時に、これもコミック原作のものということでお許しいただきたい。ウランガラスについては、エミール・ガレの美術書の写真で見てから、使ってみようかと思い立った。アールヌーボーの頃の芸術家だから、幕末の頃なのでいいかと思った。その他たくさんの事項を調べてネタに使った。大変な作業だった。しかしそれだけやってもまだまだ不十分だった。時代小説を書いておられる世の作家の方々は、どれほどの調べものをなさっておられるのだろうか。本当に頭が下がる思いだ。
書いていく上で今回支えになったのは、YouTubeやニコニコ動画でこの頃流行りのMMDの映像である。ものすごくよくできている。キャラが立体的に動いて踊るので、本当に生きているみたいで、時々見ては執筆の疲れを慰められていた。また山下達郎さんの「rainy day」と鈴木祥子さんの「優しい雨」という曲にも慰められた。どちらも雨がテーマの曲で、作中のふたつの雨の場面にぴったりの名曲だと思う。
蒼紫巴はどうやらネット上で私だけが主張しているカップリングで、公式の組み合わせとは全く相反するものだ。私が考えた物語も、単に私が自分の横槍で考えてしまったものだ。それでも、もし最後まで読んでくださる人がいるとすれば、こんなにうれしい事はない。それではまた何かの次回作で、お目にかかれれば幸いであります。
2020年 7月1日 おだまきまな拝
付記・同人誌版の「山霞」前編を御持ちの方へ・・・作中の中山道の旅のくだりで「春頃」となっているのは「秋頃」の間違いです。年表を用意せずに書いていて、私の不徳の致すところです。ここに訂正しておきます。
山霞


