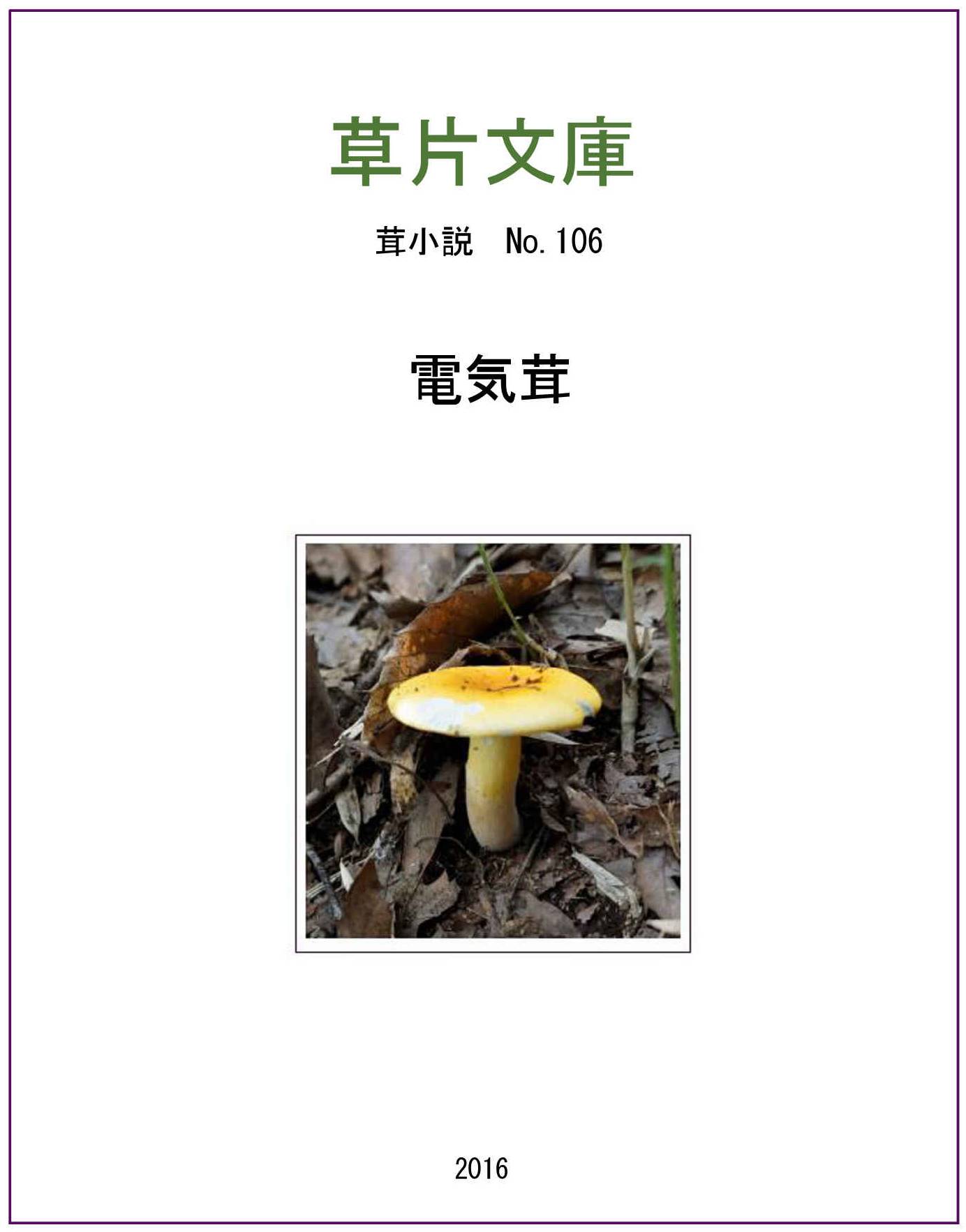
電気茸
信州の山奥で、針金玉人は茸を探して歩いていた。電気を作り出す茸を探しているのだ。手にしていたのは微量の電気を測定できる機械である。その装置を茸に向かってかざすのはもちろんだが、地の中に縦横無尽に張り巡らされている菌糸にも向けている。
こういうことを始めて三年になる。大学をでて、長野の茸の栽培会社に就職し、休みの日には山歩きをして、珍しい茸を採取すると同時に、電気を作り出す茸を探し歩いているのである。
高校生の頃、玉人は茸の菌糸に雷が当たると、茸がよく生えるということを、雑学の本で読んだことがあった。サボテンに音楽を聴かせるとよいという話も書いてあった。どれも本当のこととは思っていなかったが、ある日、茸の発育に関した、テレビの教育番組で、土に強い電気を与え、茸を育成させる装置を開発した大学の先生がいることを紹介していた。玉人は大学の先生がまじめに取り組むようなことなら、本当のことだろうと、興味をもちはじめた。それで植物の研究が出来る大学を探して受験したら、なぜか一発で受かった。
大学の講義を聴くうちに、茸や植物の性質を少しずつ理解できるようになってきた。茸の本体は土の中の菌糸である。土の中の菌糸を構成する細胞は、電流を受けると、花である茸を生やすような性質がある可能性もわかってきた。そもそも、細胞というものは電気を作っている。そういったことから、植物や茸と電気が決して関係のないものではないことが玉人の頭の中で理解され、整理されたのである。
大学二年になった玉人は植物生理学の講義を聴いて、逆がないものか気になり始めた。逆とは茸の菌糸の細胞が電気を貯め、放出することがないかということである。刺激を受ける仕組みがあるなら、その刺激が細胞の中に電気を起こさせるとか、電気がそのまま細胞に入り、電気を貯めることができないかということである。そういえば、動物では当たり前のことである。電気ウナギや、電気ナマズは発電装置をもっている。そういう細胞があるということは、電気を生み出すことのできる茸があっても不思議はないことになる。
四年生になったとき、卒業研究は茸にしよう、玉人はそう決めたのであるが、彼の大学に茸の専門家はいない。そこで植物生理学の教授のところに相談にいった。
「茸を調べたいのですが」
「僕は菌類のことはよく知らないが、植物生理学の先生で、細胞レベルで高等植物と菌類の違いを調べている人がいる、よく知っている人だから紹介できるよ、形の上では僕のところについて、その人のところで研究すればいい」
「はい、どこの先生ですか」
「信州の大学で研究を進めているよ、それで、何をしたいんだい」
「電気を貯めたり、作ったりする茸がないか調べたいのですが」
「僕はそのような茸を知らないが、それだと、生理学より、茸の生理生態を調べている先生と茸探しをした方がよいかもしれないね、もっとも、電気を出すかどうかをチェックする物理的知識も必要になる。それは、きっと電気を作る動物を研究している先生に教わるといいね、ということは、科学博物館のようなところのほうがいいかもしれないね」
しかし、玉人はそうせずに、相談した自分の大学の先生に師事することにした。そこで植物の細胞そのものをしっかりと学ぶほうが、後々何をするにしてもよいだろうと判断したからだ。したがって、大学では高等植物のエネルギーを作り出す細胞の構造について学んだ。ミトコンドリアと葉緑体である。どちらもエネルギー生産に関係し、自分で増えることのできる装置である。動物にも菌にも葉緑体はない、それじゃ、動物にあって植物にないのは何かというと、動くことのない植物や菌類はからだが伸び縮みするための細胞をもっていない。要するに筋細胞が無い。それに、それを指令する細胞、神経細胞はない。
筋細胞も神経も細胞の膜の電位差により電気を作り出す。電気ウナギの電気は筋細胞の変化したものである。それでは植物の細胞の膜には電位差はないのだろうか、あるに違いない、とすれば筋細胞や神経細胞にまではいかないにしても、電気を作り出す細胞が植物や菌にあっても不思議は無いことになる。
玉人の理論はこうして作り出されたものである。
大学を卒業して、長野の茸栽培会社に入り、自分の推論を証明するために、趣味をかね、電気をだす茸探しをしているのである。
茸の栽培会社でも雷と椎茸の成長に関しては興味を持っており、その会社の研究部門では、茸の培養池に電気を流して調べることもしていた。玉人もスタッフの一人として加わった。そこでの知識も発電茸を探すのには役に立つ。
放電された電気を関知する装置を持って、茸の探索に出かけるのである。人間の脳波も電気である。脳波をとらえるには頭の表面に微量な電気を拾う装置をつけなければならない。脳波ほど微量なものであると大変であるが、電気の感知器を改良して、電気ウナギや電気ナマズの電気の百分の一ほどでも関知できるものを作り出した。
山を歩くと、結構、この感知器が動く。しかし、ほとんどが茸の出すようなものではなく、大気の中の現象のためのようだ。雷のごく小さいものなのだろうか。蒸気と空気の作り出した微細な電気があるのだろう。なかなか生物からでたものを拾うことはない。反対に、彼は雷と同じように強い電流を放出する装置をもって、茸の生えそうな地面に電気を流して、その場所を地図上に印をしていくこともしていた。次に来たとき、そのあたりの茸の生え具合を見るのである。その場所のとなりに、電気を流さないでおくところも作った。流したところと流さなかったところの比較である。彼はサイエンスをやってきた人間だから、必ず比較対照群を作る。
このように、彼は椎茸の栽培に関わりながら、休日には山歩きをしていたのである。
茸会社に勤めて二年目の秋のことである。いつものように、山の中に入っていると、放電している場所があることを示すシグナルがでた。
測定器をみると、近くの斜面から電気がでている。その方向を見ると、猫が通れるほどの小さな穴がある。水が染み出しているが、水は下草の生えている地に浸み込んでしまっていて流れにならない。入口の周りは羊歯に囲まれている。測定器を穴の付近に近づけてみると、針が大きく振れた。
空中の物理的現象の可能性が強いだろうと思いながら、彼は穴の中を懐中電灯で照らし、のぞいた。穴そのものは深いものではなく、奥は手が届きそうである。壁から水が浸み出している。山の水脈が通っているのであろう。しかし、強くはないが、風が吹き出しているということは奥にさらに小さな穴でも開いているはずだ。
おやっと思ったのは黄色っぽいものが穴の壁に見える。懐中電灯を向けると、明かりが、壁からいくつか固まって生えている黄色い茸を照らし出した。奥から出てくる風によってふらふらと揺れている。
電気がこの親指、五、六センチほどの小さな茸からでているとは思えないが、と手を伸ばした。人差し指の先が黄色い茸に触れたとき、ちくっと、針で刺したような痛みが走った。条件反射で彼の腕が引かれた。指の先を見てもなにもなっていない。もう一度手を伸ばして茸をつかむと、またちくりとした。
がまんして、茸を一本採った。外の明るいところで見ると、至って普通の形をした茸である。しかし、測定器を向けると針は激しく揺れた。
茸が電気を出している。
黄色い茸は成熟しており、胞子ができている。本当に電気を作っているかどうか、培養し確かめてみたい。玉人は黄色い茸をいくつかとると、採集籠にいれた。
その時点で自宅に戻った。
彼の自宅は町のはずれの山の裾にある一軒家である。古く小さな会社が見つけてくれた家だ。会社に自転車で十五分と近くて便利であり、小さな庭もあり、近所の家の猫や野良猫の通り道になっている。
彼は自宅の一室を研究室のようにして、茸の標本を作ったりしていた。顕微鏡やちょっとした実験のできる道具はそろえていた。
採ってきた黄色い茸の写真を撮り、胞子を取り顕微鏡で見た。イグチの仲間だろうか、胞子が米粒のような形をしている。
金属製の柄つき針で傘の先に触れたとき、もつ手がぴりっときた。電気がでている。かなり強い電気を放っているようだ。この茸が電気を作るか貯めていることは明らかである。
細胞を切り出して見る必要がある。それは会社の研究室で行ったほうがいいだろう。
次の朝、会社の研究部門にもっていき、新しい茸を見つけたことを報告し、茸の培養の許可を得た。すぐに準備を始め、一方で数日かけて、黄色い茸の顕微鏡標本をつくった。細胞の様子を見るためである。
高倍率の顕微鏡で見ると、一般の茸の細胞と少し違うところがあった。細胞の核のまわりにある、ゴルジ体と呼ばれる構造がほかの茸のものと違った。細長い膜が重なっていて、その間に酵素を含み多くの機能をもつ。その重なっている膜の数がずいぶん多いようだ。電子顕微鏡で調べてもらうともっとはっきりする。
玉人は蓄電装置を思い出していた。
細胞の中の物質もいろいろな方法で同定することができる。一般的な免疫組織化学法なら、玉人にもできる。それから数週間かけて、膜の中のものを調べた。
ゴルジ体の中にはタンパク質に作用する酵素がたくさん存在するが、免疫組織化学で調べた限りでは、この茸には全くなかった。ではゴルジ体は何をやっているのだろうという疑問がわく。自分で出来ることはそこまでだ。会社の許可を得て、サンプルを卒業した大学の研究室にもっていき、電子顕微鏡で調べてもらうことにした。
その結果、通常のゴルジ体とは違う構造を持つことがわかり、金属の粒子がついているらしいことがわかった。教授も興味をもってくれて、手助けをしてくれた。
金属の種類を特定するため、理工学部の金属部門の教授に電子顕微鏡写真を見せた。金の可能性があると指摘され、その教授に茸を採ってきてわたし、金の含量を計ってもらった。その結果、かなりの量の金を有していることが明らかになったのである。海にいるホヤも金をもっている動物として知られているが、それと同じくらいの割合で含んでいるという。
黄色い茸は細胞のゴルジ体の中に、本来ある酵素ではなく、金の粒子を貯めている可能性が示唆されたわけである。ただ、細胞の中の金がどのような役割を持つのか、放電能力と関係あるのか調べなければならない。
そうこうしているうちに、会社の研究室での培養がうまくいき始めた。ガラス瓶に植えた胞子が菌糸に伸展し、瓶の口から黄色い茸が生え始めた。
培養室の棚に並べておいた十本の瓶すべてから黄色い茸が生えていた。ただ八本の瓶にはぎっしり生えているが、二本の瓶からはたった一本である。
玉人は電気の測定をした。八本の瓶の茸からは強い放電があった。一本しか生えていない二つの瓶から電気は感知できなかった。毎日結果だった。
玉人は黄色い茸、すべてに発電能力があるわけではないのだろうと思っていた。
次の日は雨ふりだった。気温がずいぶん下がり一時、送風が弱まった。十本すべての茸から電気がでなくなった。あくる日は天気もよくなり、前と同様、八つの培養茸から電気が感知された。
培養の棚の上を見ると瓶の茸が揺れている。天井にあるエアコンの風があたっている。昨日の寒い日は、茸が揺れていなかったことを思い出した。風が電気に関係があるだろうか
玉人は棚の一番上においておいた十本の茸の瓶を中ほどの棚に移した。
次の日、すべての瓶から電気が感知されなかった。
風に吹かれ揺れると電気が作られる、だが止まるとでない。一本しか生えていないとでない。そうか、擦り合っている茸だけに電気があるということは、原因は静電気だ。この茸は静電気をためる能力があるのではないだろうか。
それに気がついた玉人は一本しか生えていない茸をガラス棒でこすった。すると、その茸から電気が関知できた。
黄色い茸を採った穴でも、茸は群れて生えていて、風にふかれていた。
玉人は電気を作る茸を発見し、その仕組みも解明したのである。
さらに、細胞のゴルジ体にある金の役割を考えた。培地に金粉を入れると、発電能力が格段にあがることが明らかになったのである。菌糸が金を取り込んで、茸の細胞の中に金をため、静電気を蓄電する能力を高める仕組みがこの茸にはあるのである。
黄色い茸の使い道は多い。
玉人は会社にそのことを報告し、考えられる使用方法の特許取得の準備をはじめた。会社でも何人かが手伝ってくれることになった。
家に帰ったら、近所の猫が庭で茸を転がして遊んでいた。近寄るとぱくっとくわえて逃げていった。猫は茸を食べないだろう。黄色い茸はまだ食べたことがない。会社には採ったものを何本もわたしてある。もうとっくに毒茸かどうか調べたはずである。毒だとはきいていないので、食べられるのだろう。
何本か採ってきた茸は冷蔵庫にいれてある。食べてみよう。
黄色い茸をまな板に載せ、セラミックのナイフで傘の部分を切った。どのような味か、傘の頭の先を少しばかりかじった。唇にぴりっと電気が走った。柄の部分をかじると、ピリッと来ない。柄には電気がたまっていないようだ。味は普通の茸だ。特においしくもない、食用茸としてはむかないだろう。
乾燥させた黄色い茸の放電を調べたこともある。しなびてしまっていても。電気は抜けることはなく、傘の先端に溜まっていた。やはり、電気を何かに利用するしかないだろう。
どのように黄色い茸を有効に使うか、茸で発電しても元が取れるわけはない。
しかし蓄電量はそれなりにある、大学の理工学部で調べてもらった結果では、一本の茸で市販の単三乾電池ほどの能力がある。1.5ボルトだ。一度に一瞬にすべてを放出することもできるので、電気ショックに使えるかとも思ったが、現実性がない。小説の上なら殺人にも使えるかもしれない。
玉人は十本ほど、傘だけとって一つにまとめ、マタタビをまぶし自宅の庭に置いた。見ていると、野良猫がやってきて、なめたとたんぎゃーっと叫んで、飛んで逃げてしまった。なかなかの威力である。ちょっとかわいそうなことをした。
黄色い茸を見つけて一年がたった。
静電気を蓄電する茸、学術的には大発見ということで、玉人は学会にも呼ばれ、研究発表では好評を博した。
会社も卒業した大学も応援してくれ、新しい茸として、世界にも名が知れるようになった。和名は単純に「電気茸」としたが、学名にはtamahitoが加えられている。
論文にも名前が入り、学位の申請を促されている。
玉人はこの茸を大きく育て、強い電気が出せるようにならないか、会社の研究室で培養を続けていた。こういった研究は時間がかかる。
二年たち、培地の栄養素を工夫したおかげで、数倍の大きさの茸にそだてることができた。
電気の蓄電能力は倍ではなく四倍になった。高さが十センチほどの茸から、瞬時だが、六ボルトほどの放電があった。しかし、それを利用する方法がなかなかみつからない。
なかなか利用研究が進まない秋のある日、信州一帯に雷雲が発達し、彼の住んでいるあたりが黒い雲で覆われた。朝早くから稲光が走り、大きな音と共に雷があちこちに落ちた。雨も急に降ってきて、土砂降りになり、あたり一面、川が流れているように水がながれた。
その日は会社にはいかず、久しぶりに自分の家で、乾燥した電気茸を前に、どのようにしたら効率よく電気を取り出せるか考えていた。
そのとき、いきなりばりばりばり、と稲光がひかり、どしんという音と共に、雷が近くに落ちた音がした。部屋の中はぴりぴりと、電気が走ったかんじである。
デスクの上の黄色い茸の粉が青白く光っている。雷の影響のようだ。玉人は電気の探知機のスイッチを入れ、粉の上にセンサーの先を向けた。六ボルトほどしかでていなかった粉末が、百ボルトを示している。センサーを当て続けると、5分ほどして、もとの六ボルトに戻った。雷の電気を吸収して放電したと考えられる。この茸は、空気中の電気も吸収することができることがこれで明らかになった。
玉人は黄色い茸の生えている穴のある林の当たりも、今日はすごい雷に襲われていることだろう。穴に生えている黄色い茸はどうなっているだろう。発見してから五年ほどたつ。電気茸は研究室でふやすことができるようになったので、研究には自然の茸は使わなかったので、五年ほど行っていない。明日は天気がよくなったら、行ってみよう、玉人は用意をした。
次の日、うって変わって秋晴れのすばらしい天気だった。
玉人は久しぶりに山歩きの格好をして、電気茸の生えている山に向かった。久しぶりで、かなり足が重い。呼吸が荒くなる。それでもその林に行き着くと、元気が出た。
林の中にはいった玉人は驚いた。少し黄色くなり始めた羊歯や下草の間に、黄色い茸、電気茸がいたるところに生えている。猫の頭ほどの小さな穴の中にしか生えていなかったのが、林の中一面に増えている。彼の見立てでは、長い時間かけて広がったのではないように感じた。昨日の雷のせいじゃないだろうか。それというのも、どの茸も成長過程が一様で、生えて一日目ほどの若い者である。
微電流の探知機を茸のほうに向けると、かなりの電気が放出されていることが分かった。彼は手袋をとって、指で茸に触れた。ぴりっときた。一つの茸から5,6ボルトは出ているだろう。かなり強力だ。静電気をためたのではなく、昨日の雷の電気を吸収したのではないだろうか。
林の奥の懐かしいたくさん生えている電気茸を踏みつけながら、やっと穴にたどりついた。羊歯などに囲まれている様子はむかしとかわらない。電気の探知機を穴に向けると、大きく針が揺れた。茸が生えているのだろうとおもい、穴の中を懐中電灯で照らすと、大きな一本の黄色い茸が生えていた。
気候や土の条件が少し変わると、茸の生え方ががらっと変わったりする。今までたくさん生えていたのが一本もなくなったり、他の茸がわんさか生えたりする。
このあたりも様子が変わったのだろう、一本では静電気がでないから、この黄色い茸からは電気は作られていないはずである。しかし、電気探知機のメーターの針が振り切れている。微電流を測るものであるから、容量以上の電気がでているということだろう。この茸も昨日の雷から電気を吸収したのに違いがない。
玉人は茸をとるために、手袋をはめた手を伸ばすと、茸の柄をつかみ引き抜いた。
手袋をしているのに少しピリッと来た。かなりたくさんの電気をためたのだろう。
玉人は穴からとった電気茸を採集箱にいれた。
傘の襞の胞子の状態を見るために、手袋をはずして、ルーペを取り出し、大きく育った茸の傘を持って裏返そうとした。
そのとき、ボッと音がして、玉人の髪の毛が逆立ち、頭から黒い煙がたちのぼった。
彼は木の下にびっしりはえていた電気茸の上にたおれた。電気茸から放電する光が放たれ、彼から炎があがり、真っ黒な炭になってしまった。
数日後、林の中で炭になった彼は発見された。
そのとき、電気茸はすでに枯れ、姿かたちはなかった。
新聞の片隅に、電気茸の発見者、玉人博士が、山奥で研究中に雷に打たれて亡くなったと、小さく載っていた。
電気茸
私家版第十一茸小説集「黙茸録、2021、265p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2016-6-26


