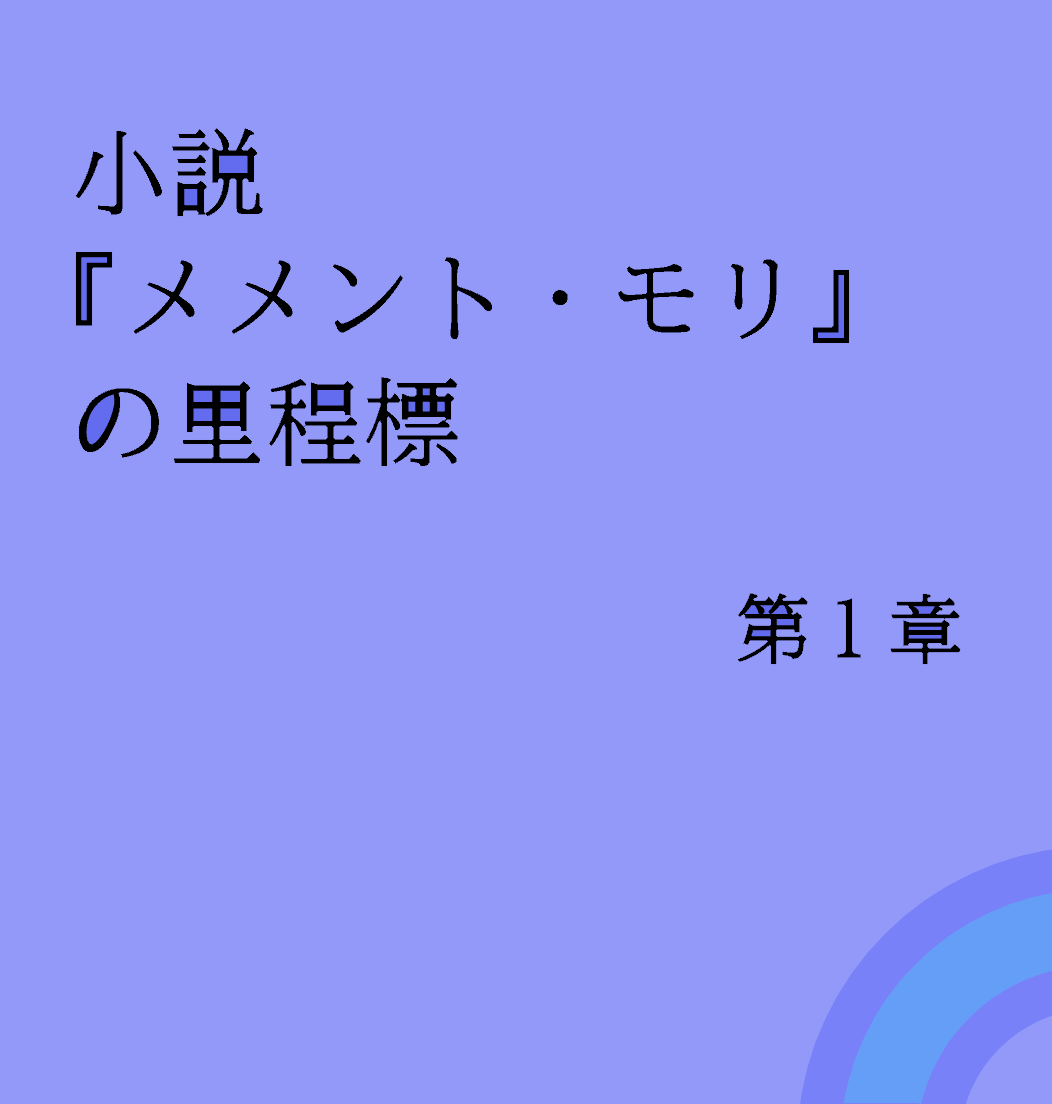
小説『メメント・モリ』の里程標 第一章
一 「小説家の僕」は喫茶店で
「先生、今回はまた、何故少年を主人公に?」
「そう、ですね」
言葉を切った僕と彼との間を、ウェイトレスの運ぶコーヒーの香りが柔らかく包み込む。
「こちらホットコーヒーとアイスティーになります」
目の前で白いソーサーとカップが、かちゃりと小さな音を立てた。持ち手の部分が絡みつく蔦のように細工されている、凝った作りのカップだった。
「ありがとうございます」
僕は顔を上げずにウェイトレスへ礼を告げた。テーブルの向いに座る打ち合わせ相手は、彼女の目の方を見て笑顔で軽く頷いた。
「以上でご注文の品はお揃いでしょうか」
「はい」
「では、ごゆっくりどうぞ」
彼女の淡白な声音、その素っ気ない口調が、過去の友人の声と少し重なった。
去っていくウェイトレスの後ろ姿を追うように振り返る。腰に巻かれた白いリボンが彼女の歩調に合わせてふわりと揺れた。
清潔そうな白、それは僕の好きだった色だ。
「ミデルフォーネさんは、先の戦争の際はどちらに?」
唐突な僕の質問に、彼は帽子の褄に軽く触れてから肩を竦めた。
「私ですか。親戚揃って、海外へ高飛びですよ、大声では言えたもんじゃありませんがね。知人が南にいまして。あそこは幸い、大戦には中立でしたから。そちらにしばらく居りました」
「そうでしたか。海を渡るのには随分苦労されたでしょう」
「まぁ、あの時代ですからね。逃げるにしろ残るにしろ、苦労しなかった人なんか居なかったでしょう」
「そうでしょうね」
「先生は、ずっとこの街に?」
「いえ、生まれはずっと西です。家族親戚も大戦初期にほぼ失って」
淡々と情報を提示しながら、彼の目をじっと見つめた。
「大戦終結はノモモギで迎えました」
ミデルフォーネの眼の色が、面白い程に変わる。
「の、ノモモギ、ですか、あの終わった都市の……」
「えぇ」
「で、では、今回の作品は、その頃の思いをモチーフに?」
「モチーフ、と言いますか。実体験を基に書いて行くつもりです」
「実体験……ですか。ノモモギの生き証人である先生の。なるほど、それで先生が十代半ばの頃が舞台に。ああ、つまりそれが主人公が少年である所以ともなる訳ですか」
漸く自身が投げ掛けた質問の答えが返って来たとばかりに、彼は大きく何度も頷いた。そして思い出したように、革の大きな黒鞄からペーパーバックを数冊取り出した。
「いつもそんなに持ち歩いておられるんですか?」
「いやいや、今回はちょっと特別に。ええと、これと、これと……」
中から選び出された二冊が、僕の前にすっと差し出される。
「著者であられる先生は、ご覧になるまでもないとは思いますが」
彼はこめかみを掻きながら、アイスティーで唇を濡らした。
「先生の作品は、単体で書籍化されているもので過去六冊。あ、勿論。編集を担当させて頂く前のものも、全て拝読しております」
店内の蓄音機から流れる音が止み、一瞬の静寂が訪れた。そして再び上品なクラシック曲が控えめに流れ出す。
「そして、あの賞の候補作として特に際立った作品はこの二点」
二冊の題字、『廃屋に風船を浮かべて』と『嘴に緑のオリーブを』が目に留まる。どちらも僕が数年前に雑誌へ寄稿し、後に本として出版された小説だ。
「受賞こそ逃されましたが、素晴らしい作品でした。私は今でも、こちらの嘴にの方が審査員の得票数自体は上回っていたと信じていますよ」
「高く評価して頂いていることには、深く感謝します。でも買い被り過ぎですよ」
「いやいや、本当に」
「大賞を獲られたミノワ先生の作品は、表現が豊かで、本当に心に沁み入るものでした。描かれる少女の髪の質感までが、現実に触れているように感じられる程の圧倒的な没入感。僕には到底真似できません」
「確かにミノワ先生の技量は認めます。情景の描写は一流ですし、起承転結がしっかりしていて分かりやすい。これといった非は無い。しかし、どうしても私は……」
彼は拳に力を込め、テーブルをこつんと叩いて沈黙した。ミデルフォーネの濁した言葉を僕自身が引き継ぐ。
「……おっしゃりたいことはこうですね」
コーヒーカップの持ち手に指を絡ませ、陶器の感触を味わった。
「僕の作品が戦争を描いていたから選ばれなかったのだ、と」
「そうです」
一段と声のトーンを落とし、彼はさらに拳を強く握った。
「今や言論の自由は保障されています。勿論、戦争をテーマにした作品は既に幾つも出版されています。それでも、全くもって足りない、認識が。戦争があったことを、多くの人間が忘れようとしている」
「果たしてそれはいけないことでしょうか」
「悪いと言うつもりは私にもありません、積極的な意味を持つ場合にはです。かさぶたはやがて剥がれ、傷はいずれ癒えていく。それ自体は自然なことです。人は絶えず前進する。しかし傷を負った事実、それをもたらした己の恥ずべき真実が消えてなくなるわけではありません。それを隠し、あまつさえ無かったこととして葬れば、いずれ同じ過ちは繰り返されます、そうでしょう? そして世間はその過去を、消し去りたい過去を掲げて歩く者に、正しい評価を下そうとしない。直視しようとしないんです!」
「戦争を……本当に憎んでいらっしゃるんですね」
「勿論です!」
力強い即答だった。
「先生もそうでしょう」
ガラス窓の向こうを歩く人々の姿が目に入る。重厚なコートに身を包み、北風をはねのけて歩む者と隅々まで暖められた喫茶店でアイスティーを楽しむ者。
僕は答えなかった。
「先生の作品は社会批判文学として注目されつつあります。この二作品はどちらからも、あの大戦への批判がひしひしと伝わって来る」
「……批判を、込めるような書き方はしていません。そういう捉え方もあるのかもしれませんが」
あくまで平坦にかわす僕の言葉に、彼はあからさまに眉を顰めた。僕は一度息を吐いてから、口を開いた。
「ミデルフォーネさん。以前から、この点についてはお話しなくてはと思っていました」
店の奥、柱時計が時を知らせる鐘を打っている。
「僕は勿論、編集者としてのあなたを高く評価しています。あなたが担当して下さった作品はほぼフィクション。言ってしまえば誤魔化しのきく世界観のものでした。それでも、あなたは時代背景や作品内の時間の流れに矛盾が無いよう、丁寧に資料にまとめて下さいました。誤字脱字は見逃さないし、執筆締め切りに間に合うように絶妙なタイミングでの催促も欠かさない」
普段ならば、「そんなお世辞はよして下さい」と顔を赤くするタイプのミデルフォーネに、何の変化も見られない。これはいよいよ僕の言葉に気が回らないほどに、彼を熱くする何かがあるらしい。
「それでもです、ミデルフォーネさん。僕たちが同じものを目にしても、同じものを見ることはできない。一読者としてのあなたのご意見には、書き手として賛同しかねる場面が多い」
「私はね、先生。先生にはこれからも、こうした作品を書いて頂きたいのですよ」
案の定僕の言葉とは無関係に、彼の語調はどんどんと強まっていく。
「戦争をテーマにしたものを、ということですか」
「そうです。いや実際には、何も先の大戦にこだわらなくてもいいんです。こういう、人々が目を背けている、気付かないふりをしている現実を形にし、世に送り出せる人間は絶対に必要なんですよ」
彼は汗をかいているアイスティーのグラスを掴むと、勢いよく飲み干した。溶けかけた最後の氷が、底に張り付いて、やがて消える。
「それを編集長は!」
急に張り上げた怒声と、振り下ろされたグラスの底が奏でた打撃音に、喫茶店の奥の席の老人がこちらへ首を伸ばしている。グラスが割れてはいなかったからか、ウェイトレスはやってこなかった。
「バルフォン編集長に何か言われたんですね。彼は何と?」
「『賞を獲って頂くために、スリオルト先生に戦争物はご遠慮願いなさい』と」
「なるほど、それで」
今朝からの彼の苛立ちは、あの編集長の圧力から来ているのか。
僕はテーブルに両肘をつき、指を組んだ。
「確かに先生には是非とも賞を獲って頂きたい、その気持ちは私とて同じです。でもそこで戦争物は避けろなんて、あんまりじゃないですか。それを歴史ある我が出版社の編集長が口にする。それじゃああんまりだ、あからさまだ」
頭に血が上ってしまい、上手く言葉にならない様子の彼を前に、僕は組んでいた指を解いた。そして右手を伸ばし、彼の鼻の高さでぱちんと音を立てた。急に毒気を抜かれたようにぽかんとする彼に、僕は静かな物言いを保ったまま告げる。
「まず、最初にお断りしておきます。僕は今回の作品の内容を、変更するつもりはありません」
「それでは、こ」
瞳を輝かせる彼の続く言葉は手で制した。
「ただ、ミデルフォーネさんのご期待に添えるかと言うと、そうも行かないと思います」
「それはどういう……」
「確かに僕は次の作品の背景として、戦争を選びました。登場人物の一人は当時の僕自身です」
「自伝、ということですか」
「どうでしょうか。お恥ずかしながら、自伝作品に触れた経験があまりないもので、そういったものにあたるのか判断しかねますが。いずれにせよ、十代の少年少女の言動が、戦争を否定するものに繋がるとは言い切れません」
「しかし、現実に戦争に巻き込まれた子供達の様子を描かれるのですよね? 読者は自然と、そういうことを感じ取るのでは」
「あの時、あの場に居た僕達の感覚を一言で表す、適切な表現が見当たらないのですが……どうあってもミデルフォーネさんの思っておられるものとは異なる気がします」
「それでも、今回の作品のテーマを変えるおつもりは無いと」
彼はあごに手を当てて黙り込んだ。僕の発言の意味を考えているのか、説得の手段を探しているのか。構わずに僕は続ける。
「大規模な戦闘、戦禍に巻き込まれる子供。確かにこの響きだけを取り出せば、世間は戦争批判を思い浮かべる。立ち直り切れていない今の社会に出すには、傷が新しすぎるのでしょう。でも僕はここで、このタイミングでどうしてもこの作品に取り掛からなければなりません」
僕は自分の鞄から一枚の紙を取り出してテーブルに置き、彼の前にすっと滑らせた。
「これは?」
「十年ほど前の、手紙、のようなものです」
「お読みしても?」
「はい」
親愛なる友に捧ぐ
まず謝らなくちゃいけない。ごめん。
僕にはどうしても、あの日々を英雄譚としては書けそうにないんだ。
でもきっと、ナナらしいって、いつか言ってもらえると思うから。
僕らしく、最後まで書き通すと、僕らの神の名にかけて誓うよ。
ナナ
「この“ナナ”というのは?」
「当時の“僕”の名前です」
「名前……ナナ?」
彼は何か古い記憶を呼び覚ますように遠い目をした。
「僕らは当時の仲間たちと約束をしていました」
「約束、ですか」
「はい。この戦争を生き延びた者が、僕達の英雄譚を書こうと」
「英雄譚、ナナ……まさか先生! ……あの“メメントモリ”の?」
「そういうことです」
「はぁ、それで終結時はノモモギに……」
彼は驚きを隠せない様子で、口を手で覆って震えた。
「それならば、あぁ、いや、そうですね」
「僕はどうしてもこの作品を書き上げたい。ご助力、お願いできないでしょうか」
深く深く頭を下げる。僕は、どうしても、約束を果たさなければならなかった。
「勿論お引き受けいたします。いや、ご満足頂ける程お力添えできるかどうかは分からないのですが……」
戸惑う彼の次の言葉を、頭を下げたままじっと待つ。
「……そうですね、編集長の方は、私から説得してみます。彼もこの話題には、必ずや興味を持つはずです。言論思想を扱う者の端くれとしてこれ程名誉なことも無い。ですが……」
言いたい事は分かっていた。
「正直、どう言っていいのか。本当に、こんな、ご本人にお会いできるなんて、えぇ」
「すみません」
動揺を隠せない彼の額には大粒の脂汗が浮かんでいる。
「僕自身、それほど肝の据わった人間ではありません。ですから、ルポルタージュというより、限りなくフィクション作品に近い形を取らせていただくつもりです」
「そうですね、そうしていただけると出版社としても……」
カラン。
喫茶店の扉が開くのと同時に、上部に取り付けた鐘が鳴る。
僕らはそこでお互いに深く呼吸をした。
「この先の詳しいお話は、出来れば僕の書斎で聞いて頂きたいと思います」
「はい、それは、そうですね」
「僕の家の住所は分かりますか?」
「えぇ、以前車で先生のご自宅前を通りかかった際に、編集長から」
「では、お出迎えに上がらなくてもお越しいただけますね」
「このままお伺いする、というのは?」
「いえ、僕の方は構いませんが」
僕は少し笑い出しそうになるのを堪える。真っ青な顔の担当編集者の膝が小刻みに震えていることに、気付いているのは僕だけの様だ。
「ミデルフォーネさんには、少しお時間が必要かと思いまして」
「そう、ですか……」
「明日の昼ごろは空いておられますか?」
「はい、勿論。私の方は何時でも構いません」
「お昼のご用意もできますが、僕の用意した食事では安心して召し上がって頂けないでしょうから」
「と、と、と、とんでもない!」
我ながら意地悪な冗談だと思ったが、彼は真に受けてしまったようだ。
「では明日の十三時に。軽食をご用意しておきます」
「はい……」
ちょうど横を通りかかったウェイトレスに目配せをして右手を上げる。
「伝票をお願いします」
呆気にとられている彼を無視し、二人分の会計を済ませる。何時もは編集部が持つ飲食代を僕が払った事にも、彼は気が回らないようだった。
「ミデルフォーネさん、あなたがもしこのまま然るべき所へ駆け込んだとしても、僕は決してあなたを恨んだりはしない。これは神の名に懸けて絶対です」
「そ、そ、そ、そんなことは!」
「では、明日、お待ちしています」
カラン。
僕は喫茶店を後にした。
残された彼の思考が正常に動き出すまでにどれくらいを要したのか、僕は知らない。
二 「とぼける僕」は病室で
走る、走る、走る。
肉体から精神だけが飛び出してさらに僕の前を行く。脚が追い付かない。
走る、走る。
後ろから迫っているのだ。何が? 一体何が迫っているのだろう。
鬱蒼とした森の中、生い茂る草、闇にまぎれた木の根に躓きそうになる。
腰のベルトに挿していたはずの拳銃が、ふと軽くなる。
落したのか? ダメだ、それが無いとダメなんだ。
焦る、焦る、焦る。
振り返るんだ、戻るんだ、拾うんだ。
でもそんな時間は無い。
追い付かれる、迫っている。すぐそこに――
何時の間に船を漕いでいたのか、気が付くと外はうっすらと明るくなっていた。
カーテンから漏れる幽かな朝日が病室内を包む。様々な計器の中央、白いベッドカバーがぼんやりと浮かび上がって見えた。
「ごめん、ちょっと寝ちゃってたみたいだ」
僕はゆっくり息を吐いてから、椅子の背凭れに身体を預けた。
「……ねぇ、僕、ちゃんとやれるかな?」
掠れた様な声が出た。勿論答えは返ってこない。
十年前、あの手紙をこの枕元へ置いたときから、返事をずっと待ち続けているのに、君は一向に目を覚まさなかった。
「君は僕の事、自信家だなんて言ってたけど、そんなことないでしょ?」
僕は思い出し笑いをする。
「……昨日のミデルフォーネさん、面白かったなぁ」
お気に入りだった喫茶店の、カランという鐘の音が頭の中で響いた。
「今日の昼食はね、サンドウィッチにしようと思うんだ。あの店の味に似せて、ハムとたまごの。あ、チーズも入れようか」
手をそっと伸ばすと、辛うじてシーツと布団の隙間に届く。そのまま指を差し込み、そこにある動かない左手に僕の右手を重ねた。
「君はチーズ、好きだったね」
強く握ったら折れてしまいそうに細い指に、熱を送り込む。
「ほんとはね、一度、ミデルフォーネさんに、会わせてあげたかったんだよ」
昨日の彼の動揺っぷりを思い出す。
「僕の五人目の担当さん、ほんとに面白い人なんだから」
著名人の前でも臆することなく熱弁を奮う雄姿、作者を置いてけぼりにするほどの作品愛、どれを取っても、今までの担当編集者の中で、彼のような人物はいなかった。
「そろそろ見回りの看護婦さん、来ちゃうかな」
そっと手を離し、立ち上がる。面会者用の椅子を壁際へ戻すと、目尻にうっすらと涙が浮かんだ。
「薄情者のナナが分かれに涙するなんて、聞いて呆れるよね」
独りで話し続けることに、すっかり慣れてしまったこの十年間を想う。長かったような気もするし、あっという間だった気もする。
「先生が薄情者、ですか?」
いつの間にか廊下へ出る扉が開いていて、出入り口に凭れるように人が立っていた。
「自己分析もままならないようでは、作家は務まりませんよ」
冷たい視線が刺さる。彼女はポケットへ手を入れたまま白衣を翻し、こちらへ近付いて来た。僕は取り立てて驚く事もなく、彼女と向き合う。
「そうだね。もうそろそろ潮時かもしれない」
彼女からは薬品のような、それでいて甘いような香りがした。
「引退なさるおつもりですか?」
問い掛けに答える代わりに、僕は肩を竦める。
「そんなことより、こんな時間にこんなところでどうしたの?」
「それはこちらの台詞です。今日の面会時間開始までは、あと四時間あります」
僕は先程より大袈裟に肩を竦める。彼女は大きな溜息を吐いた。
「最近、院内を徘徊する霊が出ると、患者の間で噂になっています。精神的に……不安定な方が多いですから、この病棟は。そんな戯れ言と一蹴する訳にもいかず、こうして研修医が幽霊狩りに駆り出される始末です。大概にしていただかないと」
「うーん、徘徊してはいないんだけどな。僕が来るのはこの部屋だけ、それも最短ルートで」
「屁理屈をこねる暇があるなら、早く痕跡を消して出て行って下さい」
「全く、君らしい」
彼女へ笑い掛けながら、部屋の備品の位置を確認する。全てがここを訪れる前と変わっていないことを見届けてから、椅子の背に掛けていたコートを手にした。
「……顔色、優れないようですね」
出て行けと言いながら、彼女は僕の進行方向にすっと立ち塞がった。
「そうかな」
「体調管理もできないのですか、あなたという人は」
口調は相変わらず尖っていたが、彼女が本気で心配しているような様子を見せるのは珍しい。何となく嫌な予感がした。
「ごめん。昨日は、というよりもう今日か。ちゃんと寝てなくてね」
「……何時からここに?」
「一つ前の見回り時間のすぐ後、かな。ちょっと顔が見たくなって」
僕はベッドを振り返る。
「何故です」
今日の彼女はなかなか引いてくれない。いや、彼女は昔から勘が異常に鋭くて、押しもかなり強い。
「大したことじゃないよ。次の作品の構想を練っていて、煮詰まってしまっただけ」
「あなたは何時からそんなに、嘘を吐くのが下手になったのですか」
彼女が詰め寄って来る。僕はそのまま動かずに、じっとその瞳を見つめ返した。彼女の顔がさらに近付き、唇が触れ合いそうになる。それを僅かに首を傾けてかわした。
「……意地悪な人」
恨めしそうに彼女は言い、すっと僕から離れる。前髪で一瞬顔が隠れたが、彼女がこんなことで泣くはずもないことは分かっていた。
刹那、僕は彼女目掛けて細長い小箱を投げた。彼女は器用に片手でキャッチすると、面を上げて怪訝な顔をした。
「何ですか、これは?」
「君へのプレゼント」
「また下手な嘘を。私に物を贈ったためしなど無いくせに」
彼女は小箱を軽く振った後、何も言わずに蓋を開けた。取り出された万年筆は、薄ぼんやりとした病室の中で輪郭を曖昧にしている。
「先生のお古なら要りませんよ」
「一応、万年筆としては新品だよ」
「万年筆としては、ですか。一体何をリメイクなさったのだか」
「君はやっぱり隅に置けないな」
苦笑いする僕を他所に、暫く万年筆を掲げて眺めていた彼女は、それを胸のポケットに挿した。そして小箱は左手に持ち直し、白衣ではなくズボンのポケットへ仕舞った。
「そろそろ巡回の者が来ます。早くお帰りになって下さい」
「君こそ。こんな時間に病院内をうろうろして、新たな霊の噂が立っても知らないよ」
「ですから私は見回り中で……」
「君の担当曜日、僕が把握していないとでも?」
一瞬ぽかんと無防備に開いた口元をさっと引き締めて、彼女は僕を睨む。
「やはり、先生には“薄情”より“意地悪”の方がお似合いです」
「褒め言葉として受け取っておくよ」
彼女はほんの少し表情を崩した後、踵を返して病室を出て行った。その分かりにくい気遣いに感謝する。
「あと五分は居られるかな」
もう一度この部屋に二人きりにしてくれた彼女へ、心の中でありがとうと呟く。
僕はベッドの枕元へ、十年間祈り続けたその場所へ近付く。
「また後で。必ず迎えに来るから、ね」
そこに何時かのあの笑顔を思い浮かべる。そして、音にはせずに唇の動きだけでその名を呼ぶ。
呼び掛けに応えるように、声が聞こえた。
「最後の一人にしないで」
空耳だと分かっていたけれど、はっきりと言葉を返す。
「うん、一人で逝かせたりなんかしないよ」
僕はベッドに背を向け、片手を挙げた。
自宅書斎の柱時計が、十四時を知らせる鐘を鳴らした。
目の前のテーブルに用意していた紅茶はすっかり冷めてしまい、サンドウィッチのパンも暖炉の火に当てられて乾燥し始めている。僕は一人、コーヒーのお代わりを淹れるために立ち上がった。
「やっぱり。予想通り、かな」
溜息が洩れる。
ミデルフォーネに科した難題は、本来僕が一人で負うべきものだ。だから、彼がどんな行動に出ても、僕にそれを責める資格はない。それでも、僕の描いたシナリオ通りに物事が進まない事を、心の何処かで期待していたのだと思う。
十三時に、ミデルフォーネは現れない。これは僕のシナリオの序章だ。
暫く開く事のなかったデスクの引き出しへ、僕は手を掛けた。
三 「切り出す僕」は書斎で
三十分程まどろんだだろうか。外でバンという大きな音が聞こえて、意識がはっきりとする。
片方だけ開けて置いた窓から外を覗くと、門の前に小さな車が一台停まっている。どうやら車のドアを慌てて力いっぱい閉めたようだ。
手前には、帽子を押さえながら玄関へと急ぐミデルフォーネの姿があった。何時だって必死な彼の様子を見ていると、自然と笑いが込み上げてしまう。
程なく玄関ベルが鳴る。僕は窓から上半身を乗り出して、真下の彼に声を掛けた。
「開いていますよ。そのまま二階へお越し下さい」
「は、はい!」
階段を全速力で上がって来たのだろう、彼は肩で大きく息をしていた。
「も、も……申し、訳、ない」
「大丈夫ですよ」
「いや、先生、本当に、こんな」
彼は苦しそうに喘ぎながら、頭を繰り返し下げる。僕は彼を促して、来客用の椅子へ座らせた。
「本当に気にしていませんよ。昨夜は私用で出掛けていて、十分に寝ていなかったものですから、丁度仮眠を取ることができました」
「それと、これとは、別で」
「それに……来て下さっただけで、僕はあなたに感謝しかありません」
「いや、私が、先生を、お待たせして、しまうなんて、こんな失態」
彼は息を整えようと、深呼吸を始めた。今まで待ち合わせ時間に遅れたことのなかった彼は、一時間半の遅刻でこの世の終わりのような深刻な顔をしている。
「……お一人、なんですね」
僕はわざと、探るような視線を向けてそう尋ねる。
「はい、本来なら、編集長を、連れて来るべき、だったのでしょうが……」
そう言い掛け、途中で僕の質問の真意を汲み取ったのか、彼は急に焦り始めた。
「いやいや、一人ですよ! 通報なんて! 勿論しておりませんよ!」
猛烈に首と手を振り動かす彼を見ていると、つい意地悪をしたくなってしまう。「そんな嘘を吐かなくても良いんです、通報する方が正しい道なのですから」と言わんばかりの落ち込んだ声音で、溜息交じりに言葉を返す。
「あなたは本当に、分かりやすい方ですね……」
「いや、本当です先生、信じて下さい! 私は先生の味方です! 神に誓って、断じて軍に告げ口なんて!」
「ふふっ、分かっていますよ。冗談です」
堪えきれず笑い出した僕を見て、彼は力無くふうと息を吐いた。
「し、心臓が止まるかと思いました。先生もお人が悪い」
彼は胸ポケットからハンカチを取り出し、盛大に浮き出た額の汗を拭った。
「人が悪いも何も、懸賞金の懸けられた大犯罪者ですからね、僕は」
「せ、先生!」
ブラックジョークはお気に召さなかったようだ。駄々をこねる子どものように彼は声を荒げた。笑いながら僕は右手を挙げて合図をすると、彼を部屋に残して一度席を立った。
淹れ直した紅茶を持って戻って来た時には、彼の額の汗はすっかり引いていた。
「冗談はここまでにしましょう、先程は失礼しました」
「いえ」
「今日は、もしや、編集部から直接ここへ?」
「はい、そうですが、それを何故?」
「バルフォン編集長と同じ銘柄の、煙草の香りがしたものですから」
彼は自分の背広の袖の辺りを鼻元へ近付けた。
「そうですか? 私にはさっぱり。でも、そうです、先程まで編集部で話を」
「それで、編集長は何と?」
「ああ、そうでした、まずはこれを」
彼は尻ポケットから、よれた四つ折りの紙を取り出し、こちらへ真っ直ぐ差し出した。それを受け取り、彼の向いの椅子に腰掛ける。
「誓約書、ですか」
「はい、何とか説得しまして。まあ、こんなにもお待たせしてしまう程、交渉に時間がかかったのですがね。要約すると、先生に関する一切の情報を秘匿する、といった内容です」
「よく、編集長が、これにサインを」
「まあ、そこは騙し打ち、みたいなものですよ」
「というと?」
文面を目で追いながら尋ねる。
「先に、スリオルト先生から大ネタを仕入れて来ましたから、まずここにサインして下さい、と」
颯爽と用紙を差し出す彼の姿が脳裏に浮かんで、思わず苦笑する。
「絶対にベストセラー間違いなし、各種小説賞で受賞間違いなしの大傑作だと訴えまして。まあ、それでもサインまでにかなり手が掛かりましたよ。あの人の頑固は筋金入りですからね。その後、事の次第を話し始めたら、途端に血相を変えて、誓約書を返せだ何だと。そこらじゅうのものを手当たり次第投げてきたりもしましてね。火のついたマッチを束でやられた時なんか、他の作家先生の原稿が危うく燃え上がるところで、もう、それは大騒ぎでした」
「僕のせいで、申し訳ありません」
頭を下げた僕に、彼は素早く弁明する。
「いやいや、先生! そういう意味ではなくてですね! 先生を責めるつもりでは。頭を上げて下さい!」
僕は顔を上げ、彼の外見を注意深く確認した。
「怪我はされませんでしたか?」
「それは大丈夫です。丈夫なのだけが取り柄みたいなもんです、この通りぴんぴんしていますよ」
彼は両腕をぶんぶんと回して見せた。
「それは安心しました」
「そんなことより、先生」
襟を正して向き直ると、今度は彼が深々と頭を下げた。
「お約束の時間に遅れてしまい、本当に申し訳ありませんでした。その……心配しておられたのではと、気が気ではなくて」
僕は首を横に振った。
「ミデルフォーネさんが通報しない事は信じていました。いえ、信じていたというよりも、確定事項のようなものです」
「そこまで先生に信頼して頂けるとは、光栄です」
「ただ、そうですね。誓約書をご用意頂けるとは、思ってもみませんでした。勿論、バルフォン編集長が、サインして下さるとも」
「私に出来る事はせいぜいこれくらいです。原稿が仕上がるまでは先生と私とで隠しおおせたとしても、出版に漕ぎつけるまでに先生の素性を明らかにせざるを得ない時がきっと来ます。それならば先んじて、少しでも先生の不安を除けるのであれば、と、その一心で」
「ありがとうございます」
「それから、編集長の態度で少し……」
一瞬言い淀んだ彼だったが、腹を決めたように力強く僕の目を見た。
「実は、編集長とは、袂を分かつつもりでいるんです」
「それは……」
「今回の件で決心が固まりました。元々戦争を扱った作品を敬遠する編集長のやり方は、納得が行きませんでしたし。あの人は何かこう、人間としての熱が感じられないというか……」
彼は紅茶のカップに口を付ける。
「先生は、冷静な方ですし、物腰も柔らかくて、涼しげな印象がある。それでも、ちゃんと人間としての根っこと言うんでしょうか、そこに温かいものを感じるんですよ。でもあの人からは、それが感じられない。見た目はまあ、厳つくてあれなんですが」
僕は黙っていた。
「編集長はあの通り保守的な人ですから、誓約を破るとは考えにくい。ですが、いつ取り返しに乗り込んで来ても可笑しくない。無論、その時は全力で先生を援護致します」
彼は次第に早口になる。
「ですから、大変申し訳ないのですが、出版自体は少し先になってしまうかもしれません。まずは私の再就職先から探さねばなりませんからね。個人で出版社を立ち上げるには、私では力不足な上に金銭的にも現状は難しいですから。あっ、でもそうなると、先生は他社の担当に鞍替えされるなんてことも!」
話をどんどん独りで進めてしまう彼の様子が余りにも何時も通りである事に、僕は胸を撫で下ろした。
「ご心配には及びません。“メメント・モリ”の話題は、おいそれと他人に話せるような内容ではありませんし、第一僕は、ミデルフォーネさん、あなただからこそ、この件をご相談しようと思ったのです」
「いやあ、先生。そのお言葉だけで、一生付いて行けそうです」
満面の笑みを浮かべる彼に、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。
「僕の方からも一つ、宜しいですか?」
「何です?」
「ミデルフォーネさんはここへいらした時に、“軍に告げ口はしていない”とおっしゃっていましたね」
「はい。それは勿論、神に誓って、断じてそのような事はしていません」
「バルフォン編集長は、“軍に報告すべき”とおっしゃったんでしょうね」
「はい。『“メメント・モリ”を野放しにしておく訳にはいかない。直ぐに陸軍の何某氏にお伝えしなければ』と」
「陸軍、ですか。その軍部にいるという方の名前は……」
「すみません、確かに聞きはしたのですが、耳慣れない名前だったもので。ええと……」
「もしや、ツェリュビャツァイ……」
僕が口にした名を聞いて、彼は手を打った。
「そうです、そんな名前でした。ご存知なのですか?」
その問いには答えず、テーブルに肘を突いて指を組む。
「大戦終結から、もう十年以上になります」
急に話を変えた僕の言葉に、彼は首を傾げた。
「ええ」
「あれから敗戦国の軍部は一部を残してほぼ解体、戦勝国でも軍備縮小が世界的な基本方針です。嘗ての要人は立場を追われ、どの国にも、政治的、経済的な主要ポストに就く、軍人は居ません」
「はい」
「そして今や犯罪の種類、程度に関わりなく、取り締まりは新たに発足した警察機構が担当しています」
「ええ、そうでしょう」
「つまり犯罪の報告先は全て警察機構になる。過去の戦犯者に関しても、同様の扱いです」
頻りに瞬きをしながら、彼は黙り込んだ。
思い込みの激しい面はあるものの、彼は決して察しの悪い人間ではない。しかし、流石にこればかりは伝わらなかったようだ。
「さて」
組んでいた指を解き、立ち上がる。
「そろそろ、本題へ入りましょう」
「先生、先程のお話は一体……」
「何れ分かる事です。僕の口からお伝えするより、ご自身の目で確認なさる方が、理解が早いでしょう」
彼は何か言いたげな様子だったが、口を挟むことなく頷いた。
「それでは、お話を聞いていただく前に」
書斎の壁際、戸棚の上に用意していた箱を手に戻る。彼は訝しげにその箱を見た。
「な、なんです? それは」
「これは僕から、ミデルフォーネさんへの感謝の印です」
僕が箱の淵に手を掛けた瞬間、彼が息を呑んだのが分かった。少しからかいたくなったが、これ以上彼の不安を煽るのは流石に不憫で、そのまま蓋を開ける。
「それは……靴? ですか」
「ええ。以前、靴底の擦り減りが早いとおっしゃっていたでしょう」
「はい。よく覚えておられましたね」
「印象深かったものですから。まだあの砂利道はそのままで?」
「ええ、そのままです。大通りから自宅まで、ブロック三つ分、瓦礫のような砂利道ですよ。子供もあれから随分重くなりましてね。抱き上げたまま歩く事が多いですから、さらにこの通りです」
彼は自身の靴の踵を少しこちらへ傾ける。確かに大分擦り減っているようだ。
「尚更丁度良かった。サイズは合うと思うのですが」
箱から取り出した一揃えの革靴を差し出す。
「今、ですか?」
「はい」
彼は少し戸惑ったようだが、僕の手から黒光りする革靴を受け取ると、そのまま自分の靴を脇に置いて新品の靴に足を差し入れた。
「おお、ぴったりです」
「それは良かった、最後に少しでもお返しが出来ればと思っていたものですから」
「最後なんて、先生、何を」
続けて彼が言い掛けた言葉を手で制して、僕は言う。
「それでは、時間が惜しい。暫く僕の話を聞いて頂けますか」
四 「後事を託す僕」は書斎で
外は真っ暗になった。自宅前の通りに在る筈の街燈が、今日はまだ灯されていない。
上手に相槌を打ちながら一心に耳を傾けてくれた彼が、吐息を漏らす。
「きっと私はまだ先生の過去の、ほんの一握りしか、お聞きしていないのでしょうが……」
椅子に深く背を預け天井を仰いだ彼は、微かに震えていた。
僕は手元に置いていた六枚の紙切れを、彼に広げて見せる。
「これは?」
「先程お話しした、作品のメモです」
「ほう、これが」
彼は一番右端の一枚を手に取った。
「『僕らはそれを“メメント・モリ”と呼んだ。そして』」
次の一枚に彼は手を伸ばした。
「『ああいう場面で、嘘を吐く趣味は無いよ』……随分とその、断片的? ですね」
「はい。当時のことで思い出した会話やエピソードを、片っ端からこうして書き留めてあります。その内、日付が分かるものには……」
ある一枚を手前に引き寄せて指差す。
「左下に数字を振ってあります。この四桁がそうです。まあ、あまり多くはありませんが」
「なるほど」
「それ以外は、お読み頂いて、ストーリーパズルのように組み合わせて行くよりありません」
「なるほどなるほど。では初めは、これを並べ替える作業から始めれば良いのですね。大筋の流れは今お聞きしましたし、日付のあるものでしたら私でもお手伝い出来そうだ」
彼は納得が行ったというように繰り返し頷いた。
「そして、先生がエピソード間の繋ぎとなる部分を書き足しておられる間に、私が誤字脱字の確認を」
「いえ、それらの作業は、ミデルフォーネさん、あなたにお願いしたいと思っています」
上手く状況が呑み込めないといった様子で、彼が大きく瞬きをする。
「それらと言うのは?」
「本日お話した過去の出来事と、僕の残したメモを基に、物語全容を組み上げて頂きます」
「いやいや、先生!」
僕の言葉を遮り、彼は右腕と首を大袈裟に振った。
「幾ら何でも私では、そんな重要な部分までお手伝いなんて、流石に」
「僕があなたに期待しているのは、助手ではないという事です」
身を乗り出し、彼の手からはらりと落ちた紙きれを手元へ集めながら、何でもない事のように言う。
「あなたに、作品を書き上げて頂きたいんです」
彼はぽかんとした表情のまま固まった。
「あ、ああ、先生、すみません。どうも先程お聞きしたお話の衝撃で、耳が上手く機能していない様でして。ええと、もう一度……」
咳払いをする振りをして、込み上げて来る笑いを堪えた。そして、今度はきちんと彼に向き合い、しっかりとした口調で告げる。
「ミデルフォーネさん。僕はあなたに、この作品の執筆を託したい」
「え、ど、どういうことですか?」
慌てる彼の顔を見詰めたまま、僕は手に持ったメモをさっと暖炉へ投げ入れた。紙は一瞬明るく火を纏い、やがて黒い灰になりながら消えた。
「せ、先生!? 突然何を……」
「これは見本として、今日お見せするために用意したもの。一種のダミーです」
既に固く閉じている窓を横目に、僕は立ち上がる。
「同じ内容のものも含め、きちんと別に保管してあります」
「一体……?」
彼が言い終えない内に、二階の書斎の扉が内側へそっと細く開かれた。
「スリオルト先生、不用心ですぞ」
渋みのある落ち着いた声が、扉の隙間から流れ込む。そこには一人の大柄な男が立っているはずだ。
「こんな暗い時分に、玄関の鍵を開け放しのままとは」
「バ、バルフォン編集長?!」
ミデルフォーネは驚いた様子で椅子から飛び上がった。
「編集長、いらしたんですか! 一緒には行けないとおっしゃっていたじゃないですか! 気が変わったんですか? まさか先生から直接、誓約書を取り上げるつもりじゃ」
「バルフォンさん、残念です」
僕はまだ姿の見えない彼に、努めて温和にそう言った。
扉がさらに少し此方側に動き、磨かれた革靴、その右足のつま先が、ゆっくり内側へ入って来る。サリエカド・バルフォンらしい、大きな歩幅を思わせる一歩だった。
そして間を置かず、視界に彼の右手が現われた。胸の高さに固定されたそこには、案の定僕の方へ真っ直ぐ向けられた銃口があった。
「スリオルト先生、こちらこそ残念だ」
彼はちらとミデルフォーネの姿に目を遣り、僅かに顔を顰めた。
「編集長、一体何の真似です、それは!」
ミデルフォーネが叫ぶ。
「君は黙っていなさい。全く、既に帰宅したと思っていたのだが」
バルフォンは僕へ視線を戻すと、大きく肩を竦める。
「まあ、これは嬉しい誤算でもある。そうでしょう、先生」
「何故ですか?」
「先生はこの男を随分買っていたでしょう。戦犯者のあなたのことだ、この家ごと爆破するのではと警戒していたのですよ。しかし、彼がまだ此処にいる今、勿論そんなことはなさらんでしょうな」
彼は口の端を持ち上げ、得意な顔をした。
「せ、先生。な、何が、どうなって……?」
「ミデルフォーネ君。君がこれ以上、この件について知るべきことは何も無いのだよ」
冷たく射る様なバルフォンの視線が飛ぶ。ミデルフォーネは怯むことなく噛み付いた。
「誓約書は! 編集長! あなたはあれにサインをしたはずでしょう!」
「誓約書? 君は一体この期に及んで何を寝ぼけたことを言っている。紙切れ一つで社会の平穏は訪れない。圧倒的な暴力を前に、精神論で道は開けない。そうでしょう、スリオルト先生」
「ええ」
溜息を交えて僕は肯定した。
「先生まで何を!」
ミデルフォーネの悲痛な呼び掛けに、少しだけ心が痛む。彼の払った努力を思うと申し訳なかった。しかしそれに対して、僕が報いる術はない。
「まあ君が誓約書の写しを然るべきところに預けていたとしても同様だ。ダルト・スリオルト名義の新誓約書で持って、取り下げて貰えば良い。事務処理とは、所詮そんなものだ」
頭に血が上ったせいか、ミデルフォーネはわなわなと震え始めた。その様子を意に介さず、バルフォンは続ける。
「誓約如きで社会は成り立たん。そう、我々に選択肢など、初めから無かったのだよ」
バルフォンが本当に引き金を引くとは微塵も思っていないのだろう。僕は今にも銃口の前に飛び出しそうなミデルフォーネの腕を掴み、ぐっと部屋の奥、窓辺からも出入り口からも遠い壁際へ押し遣る。
「……軍の方々は外ですね」
「ああ。一緒に来て頂けますかな。無論、抵抗するなら発砲しても構わないと、上から許可は頂いていますがね」
「そうですか。よく彼らが許可しましたね。僕が死んでしまうと、色々と困ることもおありでしょう」
「はは。偉大な作家ダルト・スリオルトは、あの出来事の全容を世に出すおつもりとのことでしたな。その件が知れ渡れば作家人生はおろか、人生設計がご破算だ。構想段階で他人に話を振るはずがない。更にご丁寧に、打ち合わせ場所にそれまで我々業界関係者が訪れることを許されなかった自宅を指定した。小説用の草稿が既にあるのでしょう? 万が一の場合は、死体を横目に家探しすれば十分ということですよ」
「そう、ですか……」
「先生! 先生が行かれるなら私も一緒に!」
「ミデルフォーネさん、危ないですから、あなたは其処から一歩も動かないで下さい」
「そんな、せんせ……」
「動かないで!」
叱責するような口調と共に、僕はミデルフォーネを軽く睨む。彼は唾を飲んだ。
「バルフォンさん。僕も戦争を生き延び、仲間を踏み台に命を手にした者として、ここで見す見す死にたくはありません」
「ほほう、それで?」
バルフォンの口調が嘲笑気味に変わった。
「ここで抵抗するつもりは、初めからありません」
「はは。もう少し、悲痛な表情を作る所からやり直した方が良いのではないかね? 飛んだ大根役者だ」
「僕の言動が演技に見えますか」
「君、言葉巧みに私を油断させる算段かもしれないが、そうは行かんよ。私も昔は軍にいてね。無論、君らを盤面の駒のように使う側の人間だ。十年そこら位で腕も目も衰えんさ」
彼は構えた右手の位置をしっかりと固定したまま、大仰に首を振った。
「そのようですね、と素直に応じたい所ですが、そうも行きません。一つだけ、呑んで頂きたい提案があります」
「命の手綱を握られた状況で、提案と来たか。条件と言わなかっただけまだ優秀だ。何だね?」
「彼を、ミデルフォーネさんの命の安全を、保障して下さい」
「先生!」
背中にミデルフォーネの苦しげな声を浴びる。振り返らず腕を伸ばし、彼が前へ出ないように牽制する。
「彼は既に事情を知ってしまったんだろう。君が話したせいでね。既に私の権限でどうこう出来る問題ではない」
「ならば僕が誓約書を書きましょう」
「何と書くつもりだ?」
「拷問の後、全てを背負って要求通りの遺書を残し、自害する、と」
一瞬目を見開いた後、バルフォンは冷笑した。
「面白い。それならばツェリュビャツァイ氏の心も動くかもしれんな。良いだろう。私も彼の編集者としての腕は買っていてね、此処で失うには惜しい人材だ」
彼は一頻り乾いた笑い声を上げた後、真顔になり顎で僕を指した。
「では君、そのまま両手を頭の上に」
僕は天井を仰ぐ。
「ミデルフォーネさん、僕はあなたと共に仕事が出来て、本当に良かった……」
そして、ゆっくりと両手を挙げる。
「全く、安っぽい感傷で勘が鈍ったのか?」
低く唸るように呟き、バルフォンは僕へ軽蔑の眼差しを向けた。
「失望したよ。面白い活劇が見られるものと期待していたのだが。スリオルト先生、いや、“メメント・モリ”のナナ。君はもっと賢い人間だと思っていたがね」
「そうですね。本当に」
バルフォンの右手人差し指の動きが、視界の隅でスローモーションのように見えた。
「あの方からの指示はね、抵抗しても“しなくても”だ」
「本当に、残念です」
「先生!」
三人の声が重なるのと、パンッパンッ、という破裂音が響くのは、ほぼ同時だった。
ごん、という鈍い音の後、深緑色の絨毯に色濃い滲みが広がる。
「あ、ああ、あ、せ、せんせい」
顔にこそ出さなかったが、あまりに期待外れな展開に、僕は心底うんざりした。
久しぶりの痛みが、意識を覆う。それは僕らの少年時代の象徴、懐かしさの結晶だ。
そう言えばミデルフォーネは、先の戦争時は中立国へ逃げていたと言っていた。もしかすると、目の前で血が流れるのを見るのは初めてだったかもしれない。
彼には重ねて、悪い事をしてしまった。
五 「その後の僕」は書斎で
「せ、せん、せい、ち、血が……」
「ああ」
我に返って振り向く。
絨毯に這いつくばり、ミデルフォーネは歯をがちがちと鳴らしていた。彼の視線は、僕の左手の指先を示していた。
「僕、ですか?」
指先を確認しようとしたが、思うように左腕に力が入らない。二の腕に銃弾を受けていた。どうやら銃弾は貫通しているようだ。流れ出た血液が衣服の中を伝い、袖口から現われて、中指を撫でながら真っ直ぐ、落下する。
「せ、せんせい」
「ああ、これくらい平気ですよ。流石に、掠り傷です、とは言えないですが」
素早く手近にあったタオルを丸めて脇の下に挟む。ネクタイをすっと外し、右手と口を使って肩の辺りをきつく縛った。
「へ、へん、しゅう、ちょう、は?」
震えながら、彼は絞り出すように声を発した。
「恐らくは、もう」
僕は書斎の出入り口へ歩み寄る。扉は完全に開き切らず、下部にゴム製のくすんだボールを噛んで、中途半端な状態を保っていた。
「し、死んで、いると……?」
ミデルフォーネから死角になった位置、半開きの扉へ額をぶつける形で、バルフォンの身体がずり落ちている。
「ええ」
「あ、ああ、そんな……」
彼はよろよろとふらつく足で立ち上がろうとして、また足が縺れた様に転んだ。
「編集長が、死……そんな」
「このような悲惨な現場に巻き込んでしまい、申し訳ありません」
「そんな、先生が謝ることじゃ……た、偶々、偶然、ですよね。撃ち所が悪かった、だけで」
僕は彼の視線を辿り、その先を遮るように死体の横へ屈み込んだ。
「せ、先生が編集長を殺……そ、そんなこと」
扉に凭れている、バルフォンの頭を少し浮かせる。眼球に光体を近付けて反応を見る心算でいたが、確認するまでも無く彼の絶命が見て取れた。僕は密かに安堵した。
「そ、そもそも、先生は銃なんてお持ちじゃなかった……そうです、私は見ていましたから! ああそうだ良かった、先生は潔白ですね。すみません、つい動転して、先生を疑うなんて事を」
ほっとしたように彼は浅く息を吐いた。
「とすると、撃ったのは裏の家の方ですか? 先生のお知り合いで? そうであっても、ひ、人を撃つなんて……いやいや、た、偶々、そう、偶々先生が銃で脅されているのが窓越しに見えて。それで慌てて何とかしなくてはと、こう、向こうの家の窓から引き金を、そうですそうです」
何時ものように、どんどんと話を作り上げてしまう彼に、何と言ったら良いものか少し迷った。本当に彼は先の大戦時、安全国から一歩も出なかったのだ。そしてこれが、人が死んだ現場に居合わせた人間の正しい反応の仕方なのだろうと、僕は他人事のように思った。
「……いえ、偶然ではありませんよ」
傍へ近付き、彼を転ばせる余計なものを爪先で振り払う。右手を差し出して彼を立たせながら、こちらもそっと息を吐いた。
「確かに銃弾一発だけで全てが済むとは誤算でしたが……」
嬉しい方の、と付け加えるのは止めておいた。自身の左袖の辺りに手を当てる。そこに隠し持っていたナイフを手のひらで軽く撫でた。これを振るう悲惨で残忍な光景を、一編集担当者へ見せずに終えられたことに、心の中で感謝した。
「僕は確かに、彼を殺すつもりでした」
「いや、いや、そんな、先生!」
思わず、というように彼は僕の両肩を勢い良く掴んだが、穴の開いた左腕に気付いたのかぱっと手を離した。
「先生! そそそ、その腕は!」
負傷部分を凝視し、彼は叫んだ。袖から先に垂れた血液にしか、気付いていなかったのだろう。間近で見た銃撃痕にかなり動揺したようだった。
「落ち着いて下さい。肩と脇で止血していますし、見た目ほど酷くはありませんよ。痛みもほとんどありません」
「す、すみません。びっくりしてしまって……」
ミデルフォーネは急に俯き、一人で頷き始めた。
「ああ……そうだ、そうですね。落ち着け落ち着け」
自己暗示を掛けるように、彼は「落ち着け」を繰り返した。
「……そう、先生は私の命の恩人です。身を呈して、こんな怪我までされながら、守って下さった。あそこで撃たなければ、先生は死んでいたかもしれない。私だって殺されていたでしょう。編集長は……そういう人間だった。そう、これは、ただの正当防衛です! そうでしょう?」
「いいえ」
僕は淡々と首を振る。
「そんな、先生……」
「僕自身は生命の危機を感じてはいませんでした。勿論、慌てた隣家の住人の助け、という訳でもありません。そもそも、彼が此処を訪れるずっと前から、此方側の銃は牙をむいていた」
彼は息を呑んだ。
「あなたに、謝らなければならないことがあります。ミデルフォーネさん、あなたにだって、僕は銃口を向けました」
天井に目線を移した僕に釣られて、彼は書斎の隅の天井へ顔を向けた。
「傍目からでは分からないと思いますが。この書斎には木製彫刻の廻り縁があるでしょう。その天井の隅の部分、あの中は、銃を埋め込む事の出来る作りになっています。僕はこの家に住み始めた頃からずっと、書斎の護衛役の手入れを怠ったことはありません」
彼はあんぐりと口を開けた。僕は彼に完全に背を向ける。
「子供騙しのからくりです」
「か、からくり?」
「はい。ごくごく簡単な。別の事象の連鎖で、引き金を引く仕掛けです。僕には彼が今日、僕の殺害を依頼されて、ここを訪れるであろうという確信がありました」
「かく、しん……」
「そして彼が、あの場所で立ち止まるだろうと読んでいました。いえ、そう誘導していました」
「え?」
「安っぽいシナリオでしょう?」
一人笑う僕に、彼は何も言わない。
「活劇にしては盛り上がりに欠ける。矢張りもう、僕は小説家を引退した方が良さそうですね」
きっと苦しげな表情をしているであろう彼に、僕は応える事が出来ない。
「バルフォンさんは旧陸軍の関係者です。僕は過去に、彼と面識があります。その上官である、ツェリュビャツァイ氏の名もその時に。彼らは小汚い少年兵の顔など、覚えていなかったようですが」
「編集長が元軍人……軍……思えばそうです」
意外にも、彼は落ち着いた声で呟いた。
「編集部で、私と編集長のあの会話の流れで、軍と言う単語が出て来た事自体が不自然だった。編集長の口から、その単語が出た段階で、私は変だと気付くべきだったのですね……」
「いいえ。ミデルフォーネさんが気付かなかったのも、無理はありません」
僕は首を横に振った。
「あれから十年も経って、まさか解体されたはずの陸軍が、未だ組織立って機能しているなんて。まして、名の知られた出版社の編集長が、その片棒を担いでいるなんて。小説の題材としてさえ安直です」
「事実は小説よりも奇なり、ですね。私もまさか、この言葉を身を持って経験することになるとは……」
自嘲気味に笑った彼の声は、随分疲れているようだった。
「先生に、こんな事をお聞きするのは、あれなんですが……復讐、という事ですか」
少し遠慮勝ちに彼が尋ねた。僕はもう一度首を横に振る。
「あれは何年前でしょうか。原稿を雑誌社に持ち込んで、初めて編集長席の前に通された時、僕は直ぐにバルフォンさんが、以前軍に居た彼だと気付きました」
その時のことを少し思い浮かべた。
「それでも、特別、感情が掻き立てられたりはしませんでした」
懐かしい痛みが再び蘇る。
「確かに過去の彼に纏わる出来事は、目を覆いたくなるようなものです。しかし、現在の彼の生死によって、失ったものが戻って来る訳でも、未来が明るくなる訳でもない。だから、彼が真っ当に、普通の人間の人生を歩んで行く、というのなら、それで構わなかった」
僕は彼に向き直る。
「ミデルフォーネさん、僕はあなたに恩を売る積もりはありません。復讐も恩義も結局の所、残された人間の自己満足だというのが、僕の持論です」
「でも、私は……」
右手を広げて彼の前に出し、その以上の言葉を遮った。
「これ以上、ゆっくりお話しする時間はありません。外の人間が、何時入って来ても可笑しくない」
頭の中で思考と情報が処理し切れていないのか、彼は危機感の無い呆けた様子で佇んでいた。僕はその肩にそっと手を添えて歩みを進める。
「隣の寝室へ行きましょう。そこから階段を通らずに、一階のキッチンへ降りられるようになっています」
隣室へと続く扉を開け、彼の背を推す。
準備は既に整えていた。端から丸めて捲っておいた絨毯を跨ぎ、床板の一部に手を掛ける。
「梯子を降りたら、流し台の下を開けて下さい」
彼はぼんやりと僕の顔を覗いた。
「先生は? 先生もご一緒ですよね?」
六 「小説家だった僕」は
「僕にはまだ遣る事がありますから、ミデルフォーネさんは先に下へ」
「しかし……」
「大丈夫です、ここで彼と心中したりなんかしませんよ」
僕の軽口に、彼はバルフォンの遺体のある方角を振り返る。見えるのは勿論寝室の壁だけだが、呆けた彼の心を現実に引き戻すのに効果はあったようだった。
正方形に切り取られた床板を片手で持ち上げ、階下へ続く梯子を下ろす。
「さあ、早く」
「……先生」
「何でしょう」
「私は、ヒューレッド・ミデルフォーネは、自分の口にした言葉は必ず果たす男です」
「ええ」
「それはこれまでも、これからも変わりません」
「はい」
「私は、どんなことがあっても、ダルト・スリオルトの味方です」
真摯な情熱に溢れたその瞳へ、僕の姿が映り込んでいる。
「ありがとうございます。あなたで、本当に良かった」
床板を嵌め、絨毯を敷き直した途端、大きな溜息が出た。
「ミデルフォーネさん、ここぞって所で格好良いんだから。最後の決め台詞、あれは流石に、僕のシナリオには無かったな」
すっかり十八番になってしまった独り言が、暗い寝室へ響く。頬の筋肉が緩む。
「あー、ごめんなさい」
ミデルフォーネの純真過ぎる誠実さに当てられた所為か、緊張の糸が、切れた。
心なしか寒気がする。動悸がした。心臓が脈打つごとに、言い様の無い痛みが体中を這う。
「つー」
呻きにもならない呼気が、舌と上顎の間を貫けた。頽れた不格好な姿で、歯を食い縛る。
撃たれたのは左腕の一カ所だけだったが、思いの外具合が良くない。
こんな所で倒れる訳には行かないと、自分自身に言い聞かせる。迷う暇は無かった。
封印していたデスクの引き出しから、胸ポケットへと忍ばせていた錠剤の粒を取り出し、唇の先で銜える。ベッドの枕元へ置いていた水差しに手を伸ばし、そのまま差し口を自らの口内に突っ込んだ。大量の水が勢いよく、体内へ薬を流し込む。口の端から溢れた水が絨毯へ、垂れた。
ミデルフォーネが編集部で引き留められ、約束の時間に遅れて来ること、バルフォンが此処へ暗くなってから現われること、全て僕のシナリオ通りだった。最初の難所を無傷で切り抜けられる等と甘く見ていた訳ではなかったが、この手段をこの段階で使う羽目になるとは、少し辛い。
「……メメント・モリ」
デスクの引き出しの奥に、たった一つ巣食っていたこの悪魔に、僕が頼る事になるなんて笑ってしまう。
「今の気分は、“死を想え”の方だ」
効果は早いはずだが、痛みが引くのを悠長に待っている訳には行かない。
「どうか、正気の内に……」
胸中で祈りながら、僕は文字通り重い腰を上げた。
まず、バルフォンを書斎へ招き入れる。無論、彼が二本の足で歩いてくれるはずはなく、右腕の有りっ丈の腕力で引き摺り込んだ。唯でさえ体躯の優れた彼は、生気を失った後も大きな存在感を見せていた。
次に、戸棚から鋼鉄製のペール缶を引っ張り出し、栓を開ける。
「……復讐、の心算は、無かったはず、だったんだけど」
バルフォンの遺体を前に、胸の奥に高揚感が生まれている事に気付いた。何処か心の奥深くで眠っていた悪心が顔を出す。それにたっぷりと染み込ませる様に、僕はうつ伏せの彼に油を注いだ。
「ほんと、苦しまずに死ねるなんて、贅沢だね」
ペール缶を傾けたままミデルフォーネが脱いだ靴の上を通過し、進む。窓辺のカーテンへ燈油を振り掛けた。立ち込める臭いに遣られたのか、無性に喉が渇いて、首元を爪で掻く。
「ミデルフォーネさん、もう行ったかな」
そして、暖炉の火に白い蝋燭の先を近付ける。新たな光が生まれたように、そこへ移った火を確認し、蝋燭立てに刺した。既に燃料を失いつつあった暖炉から、最早温かさは感じられなかった。
「ぼくらはー、ふらすー……」
口を突いて出たのは、戦時下で仲間が歌っていた、あの歌だ。
「はやくーにげーこめー……」
僕は大きくて薄い鉄板で、煙突へと続く通気口を塞ぐ。
「そーうさー、なかーまはーずれはー……」
蝋燭立てを持ち、再び出入り口へ近付く。そこから部屋をぐるりと眺めた。
特に思い入れのある場所では無かった。壊すなら、本当は大切なものと一緒が良かった。その方が凄く、心が痛いから。心の痛みは記憶に焼き付いて、きっと離れないから。
「……ああ、こんなことなら、クランベ、連れ込んでおくんだったかな。なんてね」
手を離れた蝋燭立てが、曲線を描く。白く浮かび上がった蝋燭と心許無い火は、大きな異物の背に当たり、一瞬で窓辺まで明るい一筋の道を作る。
仕上げに僕は、全ての熱を封じ込めるように書斎の扉を固く、閉じた。
通りを足早に抜け、角を曲った辺りで、後方から大きな爆発音が聞こえた。
「小説の草稿、其処には無いのに」
面識の無い人間に同情する程、僕は優しい人間では無い。
「唯ね、火傷は苦しいんだ。だから、少し、ごめんなさい」
窓辺から見えた火に、彼らは慌てて書斎へ駆け込んだのだろう。軍人というには迂闊で間の抜けた人達を、ほんの少しだけ不憫に思った。
一筋の涙が頬を伝うのは、矢張りあの薬のせいだろうか。
左腕の止血は何時の間に緩んだのか。
気付くと、僕の歩いて来た足取りを示すように、背後にぽたりぽたりと血痕が続いていた。病院の廊下はぼんやりと白く、酷く霞んで見えて歩き辛い。
耳鳴りがする。イツカの、あの歌が聞こえる。
特別病棟の四階、奥から三番目の部屋の扉を、ノックをせずに引いた。
「おかえり」
そう言って迎えてくれはしない君に、僕は言う。
「迎えに、来たよ」
ボリュームを下げて欲しいくらいなのに、頭の中の歌声はどんどん大きくなる。
そっと、ベッドから伸びているゴム製のチューブを手に取り、そこにナイフの刃を当てた。
「きっと彼、大丈夫だ。僕らの物語、ちゃんと……」
呂律が回らない。
――必ず守られる約束と言うものは、既に果たされたのと同義だから。
「ね。約束。最後、じゃ、無いよ」
発している筈の、自らの声が聞こえない。
――だからもう、心配すべきことは何も無いよ。
「ナナ、らしい、か、な……」
自分が今、立っているのか座っているのかも分からない。
ああ。
「どうか、どう、か……」
僕は祈った。
僕は、僕らの人生は、案外悪いものじゃなかったと、今はそう、思う。
小説『メメント・モリ』の里程標 第一章


