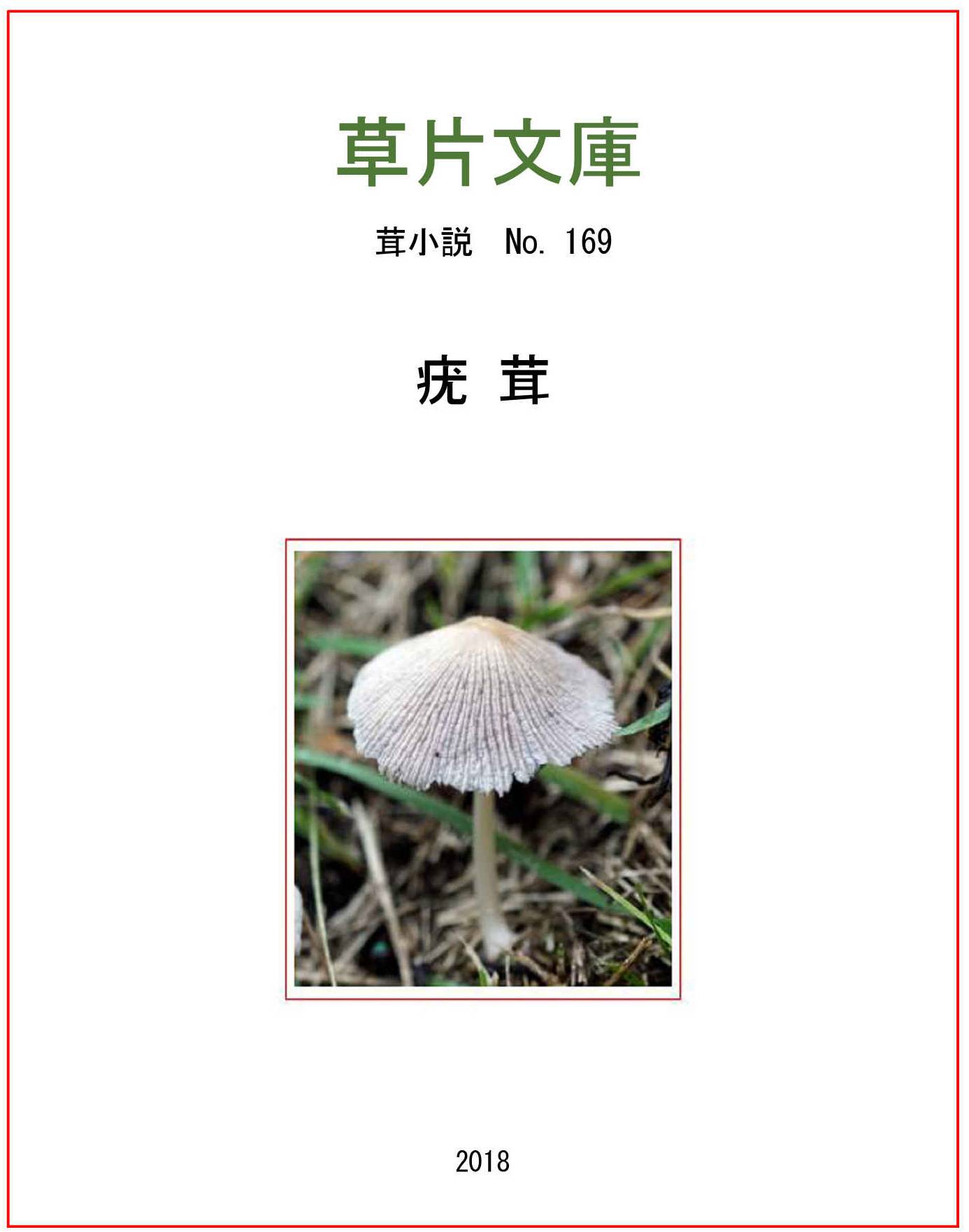
疣茸
友人からもらった文庫本を読み終わったところである。小学館の書き下ろしの文芸文庫で、普段は文芸と名の付いたような本には近づきがたく、買い求めたことはないのだが、友人がこれは面白いから是非読めとくれた。友人は日野原和夫という、大学の同級生で、隣町で皮膚科を開業している。
くれた本は「イボ記」というタイトルで、若い作家さんが書いたものだという。西沢雅野という女流作家だ。疣の専門医が読みたくなるタイトルだ。
私は代々の産婦人科医で、医院を継いで四代目の院長である。家内が事務長をしており、しっかり者で、管理はすべて任せている。私の妹も産科医、弟は麻酔科医で、私は外来を中心とし、入院出産は妹と弟が担当している。さらに手助けを頼んでいる内科医と精神科医、それに昔から代々この医院に勤めてくれている助産婦さんがいて、古くからの看護婦さんたちもおり、私はとても楽をしている。
弟や妹のように社交的な趣味は持っていないので、空いた時間はもっぱら専門書を読むことで過ごしている。大学で研究を続けたかったのだが、父親の死亡により家を継がなければならなくなった。今でも専門雑誌には必ず目を通す。それにより新しい知識と技術を知り、妹や弟を研修に行かせたりすることで、医院の基盤を強めていると自負している。
週に一度くる精神科医は分娩を控えた妊婦さんの気持ちを和らげてくれる大事な働きをしてくれている。それもこの病院の評判を高めている一つだ。
その精神科医が私に専門書ばかり読んでいないで、少しはスポーツでもやれ、何か趣味のことをやった方がいいと言う。しかし、はいそうですかと、すぐに好きなことがわきでるわけはない。
そんなことを言われたと皮膚科の友人に言ったら、読み終わったばかりの「いぼ記」をくれたのである。文学書など久しく読んだことがない。そういうことで読み始めたのだがなかなか面白かった。女子大生の足裏にできた疣が認知症をわずらう祖母の心の動きでうずくのである。娘の家庭の模様と娘の部活動での出来事を絡めた面白い話だった。同時に所収されていた「おしえない」はシュールな傑作である。
面白かったと日野原に電話すると、そうだろうと言って、おかしなことをちらっと言った。
「その本を読んだ後に、やけに疣の患者が来るようになってね、偶然にしてはおかしいんだな」
「ウイルス性の疣がはやりだしたんじゃないのかい」
そう言うと、友人は「ウン、その可能性もあるけどな、疣がからだの色々なところにできてるんだ。今までとはちょっと違う」と言った。
本を読んだこととは関係はないだろうが、どのようなことでも不思議と偶然が重なるものである。
病院に隣接して私の住まいがある。二人の子供は都内に下宿して大学に通っており、家内と二人暮らしである。戦争直後に建てられたもので広い庭の手入れは人の手を借りないとできない。
家内は病院のマネージで遅くまで働いているので、外来が終わると私はいつも先に家に戻る。食事の用意などは家政婦さんがすべてやってくれるので、家に戻ると、二階の自分の部屋で本を読むか、天気の良いときは縁から庭にでて、歩いて木々の様子を観察するぐらいのことしかしない。
その日も書斎で新しく届いたジャーナルに目を通していると、吉原さんが私を呼びにきた。吉原さんは六十をちょっとすぎた通いの家政婦さんである。
「先生、庭の方から女性が入ってきて先生に診てもらいたいと言っているんですが、どうしましょう」
我家の庭の入り口が、医院の玄関の近くにあるので、時々、間違えて入ってきてしまう人がいる。そのたぐいだろうと思って、一階の座敷に降り、縁側にでた。
庭に背の高い女性が立っている。三十になったかならないかの、なかなかの美人だ。紺色の地味な服装だが、どこか垢抜けている。
女性は少し赤らんだ顔を上げると、
「先生すみません、これができてしまいました」
つーっと近寄ってきて、大きな目で私を見た。
見ると、鼻の脇に大豆ほどの大きさの薄茶色の膨らみができている。
「疣ですか、うちは産科で、皮膚科に行かれた方がいいと思いますが」
「ええ、知っております、皮膚科は隣の町まで行かないとありませんし、私の友人が先生の病院で子供を産んだのですが、入院しているとき疣も取り除いてもらったと言っていたものですから、来てしまったのです。病院の入口が閉まっていたので、庭の方に回ったら、お手伝いさんに会ったものですから」
確かに、子供を産むために来院した女性の足にできた疣を治療してあげたことがある。子供が産まれてから足に疣があると大変だろうと気を利かせたのである。ふつうの疣であれば治療そのものはこの病院でも難しいわけではない。
「この病院の診察カードはお持ちですか」
女は首を横に振った。
弟と妹は仕事が引けると、車で自宅に帰ってしまう。今日はもういないだろう。
「疣はすぐ大きくなるわけではないので、ほかの病院に行ってはもらえませんか」
「明日、お見合いで、すぐに取りたいのですが、無理でしょうか」
疣はすぐに取れないわけではない。しかし、
「疣がとれても、最初は傷になり、元の皮膚になるのは時間がかかりますよ、とりあえずちょっと見ましょうか、病院の入口に回ってください、鍵を開けておきます」そう言うと、女性は庭から玄関にまわった。急いで除去治療しても絆創膏を張らなければならない。どちらがいいのか本人にきめてもらおう。
まだ残っている家内に病院の入口を開けるよう電話し、白衣をきて家をでた。
その日は分娩患者がいなかったので、看護師の福田さんが診察室の後片付けをしている最中だ。
「患者さんて、まさか緊急の出産なんかじゃないでしょうね」
裏口から病院に入ると、家内が聞いてきた。首を横に振って、「疣」と一言いって、診察室に入った。
福田さんがちょっと笑って、「疣って、あの疣ですか、手伝いましょうか」と言ってくれた。
「あ、そりゃあ助かるな、話をするだけだから、一緒にいて、本人に納得してもらえるよう助けてください」
福田さんは人を扱うのが上手である。
家内が入口にいた女性を診察室に連れてきた。
「どうぞ」
椅子を勧め、改めて顔を見ると、見たことのないような立派な疣であった。
「いつ頃からでてきました」
かなり前からじわじわと大きくなったと考えられる。ところが、
「昨日からです、いきなり大きくなりました」と彼女は言った。
ちょっと驚いた。日野原が言っていたウイルス性の疣か。
「正直言いますと、この種の疣はすぐには取れないですね、明日のお見合いに間に合いませんね」
そう言うと、福田さんが助け船を出してくれた。
「あなたのお肌おきれいね、この疣にこういうファンデーションを塗ってみると、疣が隠れますよ」
その女性は福田さんが差し出したチューブを手に取った。こういうものは男にはわからない。
「これなら知ってます、駅の近くの薬局にありますね」
「ちょっと塗ってみますか」
福田さんは鏡をもってきた。女性はチューブから肌色のものをひねりだし、疣にぬたくった。
「ほんと、目立たないわ、ありがとうございます、買って帰ります」
「疣ができる前に何か特別なことをしましたか」
すこしは医者らしいことも聞かなければと思い、そんな思いつきを言った。
「いいえ、昨日友達と、茸料理屋に行ったくらいです、その夜に疣はまだできていませんでした」
私の町は東京から特急で一時間ほどのところにある信州の小さな町である。信州の中でも茸がよくとれるところで、茸の培養会社がいくつかある。
「茸料理と疣は関係ありませんね、お見合いが終わったら、隣の駅の日野原医院に行ってみてください。きれいに取ってくれますよ」
そんなやりとりの末、患者は帰っていった。私は福田さんに礼を言って、再び家に戻った。
ところが、次の朝、治療が始まってから驚いた。妊婦さんの二人に一人が、疣ができたと訴えてきたのである。
その日の午前中に来た妊婦さんの疣は、外見上は特殊なものとは思われず、急いで治療をする必要も無いようであった。しかし、とりあえずは日野原皮膚科に行くように勧めた。
面白いことには、昨日の夕方庭に来た女性と同じように、みんながみんな疣が急に噴出したという。特別なことをしたのかどうか尋ねると、一様に茸を食べたと答えた。食べた茸は必ずしも同じではなく、椎茸の場合もあるし、エリンギだったり、占地だったりした。茸で疣ができるなどと言うことは聞いたことがない。この地方だから、茸を毎日口に入れるのは当たり前といっていい。偶然だろう。
といっても、少しばかりひっかかる。昼休みになってから、日野原に電話をした。
彼は診察中であった。一時をかなり過ぎてから電話がきた。
「なんだい」
「いや、うちの妊婦に疣が多くてね、何人かそちらに行くように言ったよ、この間、君が疣の患者が増えたと言っただろう、やっぱり多いのかい」
「そうか、やっぱりな、今日も患者が多くて、午前中の診察が今終わった」
「妊婦が言うには一晩で疣が育ったそうだ、それと、みんな何らかの茸を食っているんだ」私がそう言うと、
「確かにあっというまに大きくなるようだが、俺は茸のこと聞いてないよ、まさか食ったもので疣になるってことはないだろう、でも、まだまだ患者がいるんで、聞いてみるよ」、驚いたような声をしていた。
「何かわかったら教えてくれよな」
「ああ、もう一つ気になるのは、疣がみな大きいんだ、それで患者には次の日にレーザーでの除去手術にきてもらっている、午後は遅くまで手術だよ」
そのような話だった。
それから、二日後である。日野原から電話があった。
「それがねー、おまえさんが言ったように、みんな茸を食っている、だけど関係ないと思うけどね、それでね、話は変わるが、疣のことだけど、患者の疣の種類はいろいろでね、ところが、検査するために、少し切り取ろうとしても、どの疣もかたくて、組織が切り取れないんだ。骨切りバサミでやっととったよ、検査会社に調べてもらっているところさ、どんなウイルスがいるのかわかったら知らせるよ」
そう言って彼は電話を切った。
それからも疣を持った妊婦さん、患者さんがたくさんいた。みな茸をたべたそうだ。
一週間後に彼から電話で報告があった。
「どの患者の疣にもウイルスがいたよ、たいして心配はいらないものだけど、何であんなにウイルスが広がったのかな、それにしても一晩で大きくなるというのは今までのウイルスとは違うようだ」
「そうなのか、何かでウイルスが変異したのかな」
さらに十日後にこんな電話をかけてよこした。
「変なことがわかったよ、じつはね、うちの患者で、茸を食べていないのに疣がある人が三人いてね、二人は老人性の疣だ。残りの一人が問題なんだ。近くの大学の女子学生なんだが、陸上部に所属している。それで、ずいぶん前から足の裏に疣ができていてね」
「まるで、あの小説だね」
「うん、ちょっと似ているけど違うよ、陸上部で中距離の選手なんだ。この町の農家の子でね、毎日家の裏山を走ってトレーニングをしているんだ。一月前に疣ができて、うちでレーザーで焼ききったんだ。ところが、またでてきて今度は膿んでしまったんだ。だめだというのに山道を走ってしまうのでなかなか治らない」
「そうだろうな、それでどうしたの」
「最近、膿が出て、その跡がひどくなったとみせにきた。どうしたのか聞いたら、裏山の林の中の山道を走っていると、足の裏が痛くて仕方がない。それで靴を脱いでみると、大きな疣に膿がたまって今にもつぶれそうだったそうだ。それで家に戻るつもりで、道端の石の上に足をとりあえず下ろした。すると、疣がつぶれて膿が飛んだ。石の脇には茸が生えていて、膿が傘にかかったらしい。女子大生はタオルで足をふくと、靴を履きなおして、それでも家にもどったということだ」
「その膿のかかった茸がウイルスをばらまいたとでも言うのかい」
「うーん、わからんが、その茸が胞子を飛ばしたとすると、それから生えた茸にウイルスがついていたかもしれないけどね」
「だがな、どうして胞子のウイルスがみんなの食べた茸につくのだ」
「このあたりで売っている茸は近くの培養農家のものばかりだよ、膿がついた胞子が農家にふりそそげば、今のようなひろがった状態になる可能性はあるな」
「すべてを否定はしないけど、なんだか無理があるね、それに疣のタイプが必ずしも同じじゃないって言ってたろ」
「そうだな、売っている茸に疣のウイルスがついているか検査を頼んである、それですっきりするさ」
ということであった。
ところが、次の電話で彼はすべての茸に女子大生の疣のウイルスがいたと報告してきた。驚いたことである。
彼に聞いた。
「しかし、茸と一緒に食べたウイルスは口の中の抗ウイルス作用で弱まらないかい、接触で皮膚につけば疣になる可能性はあるだろうけど」
「確かに抗体ができればそうなるな、だけど血液の中からはウイルスは検出されなかったんだ、ということは、皮膚のレベルでの感染だろうな」
「それなら、ウイルスのついた茸を食べたために疣になったわけじゃないね」
「そうだな、茸を持って、ウイルスが手に付いて、皮膚にそれがもぐりこんで疣になったと考えるのが妥当だな」
それから数日後、彼からまた電話があった。
「おかしいんだよ、このあたりの医者仲間や、保健所とも連絡を取ったが、笑われちまったよ」
「なんで」
「疣の患者が増えているのはうちだけのようなんだ、ほかの医者や保健所では変わったことがないようだ」
「うちも多いよ」
「偶然なのかな」
「そういうことも考えられるよ、たまたま「イボ記」を読んだところだったので、仮説を立てちゃって、それがデータとよく一致しちゃったからそう思ったのかもしれないよ」
「そうかもしれないね」
そんな電話だった。
これで終りかと思っていたところ、そうはいかなかった。彼が変なことを電話で言ってきた。
「疣からウイルスがでたのは言ったよね、それもあの女子大生のものと同じウイルスが」
「だから、感染を疑ったのじゃないか」
「それがね、疣はあるけど、疣の周りの組織からウイルスがいきなりいなくなったんだ。二十人もいる疣の患者からこの三日でウイルスが消えちまった」
「それはいいことじゃないか」
「まあね、しかし、ウイルスがいないのに疣がどんどん成長している」
「いったん細胞分裂がはじまればしばらく止まらないのじゃないか」
「そうだが、ちょっと異常なんだ、疣の中に変なものがある」
「何があるんだい」
「今まではなかったんだが、ウイルスがいなくなったら現れた」
「それでなんだったんだ」
「茸の胞子だ」
「どの茸の胞子だ」
「一夜茸、女子大生の膿をかぶった茸のようだ」
「疣にどのように入ったんだ」
「ウイルスと一緒に入ったんだろう」
「そりゃおかしいよ、胞子がからだについたって、あんな大きいもの丸ごと皮膚にもぐりこむことはないだろう」
「どうも、あの女子大生が踏んだ一夜茸はふつうじゃない」
「なんだい、それ」
「ウイルスを食っている、傘にかかった疣の膿にいたウイルスが好きになって、胞子はウイルスを食いながら風にのり人につく、胞子から離れたウイルスは皮膚に入り疣を作る、それも一晩でだ、皮膚の表面に付いていた胞子は出来たての疣にもぐり込み、増えたウイルスを食いつくし、喰った胞子が疣を急速に発達させたのだ」
「胞子がどうやってウイルスを食うんだ」
「いや、わからん、おれの仮説だ」
「胞子がウイルスを運ぶなどというのはSFだね」
「疣の中の胞子は休眠状態なんだ、腹一杯になって寝ている」
「それでどうなるんだ」
「電話じゃ長くなるよ、今度の日曜日空いているかい」
「ああ、医院は休みだ、出産を控えたのがいても大丈夫だよ、妹と助産婦がいる」
「久しぶりに飲もうか、そこで続きを話すよ」
彼は何かにとりつかれているようだ。昔はこんな変な仮説を言うようなやつではなかった。理路整然としていて、学会発表でも火の打ち所のない話をしたものである。やけに疣と茸にこだわっている。私が疣の患者が茸を食べているなどと言ったのがいけなかったのだろうか。なにかありそうである。
ということで、日曜日の夕方会うことにした。彼とはずいぶん直接会っていない。そういえばあの本を医師会でもらったとき以来だから三ヶ月以上経つ。これまでの疣に関する話はすべて電話だった。会えば彼の考えていることも分かるだろう。
「明日、日野原と会うんだ、夕飯いらんよ」
家内はうなずきながら、
「日野原さんとは久しぶりね、そういえば、ほら疣が急にできて見合いに行くのだから取ってくれ、と言ってきた女の人覚えている」と聞いてきた。
庭から入ってきた女性だ。私はうなずいた。
「スーパーに行ったら、買い物にきていたのよ、それで声をかけたの、そうしたら、顔にたくさん肌色の絆創膏貼っていたのよ、疣が増えたのかと思って、話しかけたの、向こうも覚えていて、話したかったらしくて、中の休憩所でコーヒー飲んだのよ」
「何してる人なの」
「茸の会社の人、海外経験が長いそうよ、茸の輸出担当だって」
「それで疣はどうなったって」
「おかしいのよ、見合いはファンデーションでうまく隠したからよかったそうよ、助かったって言ってたわ、もっとも彼女が思うような人ではなかったので結婚にはいたらなかったようだけど、そのあとに、疣はとっておこうと思って、日野原さんにかかったということなの、ところが治るどころか、疣がどんどん増えてしまったって、あれ藪医者よって怒っていた、今大学病院にいってるって」
「おかしいな、日野原は優秀だけどな」
「私もそう言ったのだけど、あの娘がもっと変なことを言うのよ」
「何だって」
「あの先生、疣が大好みたいだって」
「疣の専門家だからな」
「あの先生の奥さんも疣が好みたい、って言ってたわよ。日野原さんの奥さんて秋田美人よね」
「うん、秋田の茸の会社の社長の娘だ、細い感じの人だったな」
「疣が好きってどうして思ったのかしらね」
「わかんないな」
おかしな話である。ともかく明日会うと何か分かるかもしれない。
日野原とは、彼の病院の近くにある寿司屋で会うことにした。
少し早めに行って、ビールを飲んで待っていると、彼は茶色の上着をラフにはおって、ふらりと店に入ってきた。いつもはどちらかというと急ぎ足で、忙しい様子で入ってくる。一人で病院を切り盛りしているばりばりの現役の医者である。
今日はずいぶん様子が違うと思っていると、
「やー」と片手ををあげ、店の主人に向かってちょっとお辞儀をして、私の前に座った。よくくるようだ。
「いらっしゃい、先生ビールですか」
主人が聞くと、「頼むよ、それにいつものね」と注文をした。
「久しぶりだね、元気そうで何より」
彼は運ばれてきたジョッキにちょっと口を付けた。いつもだと一気に半分は空けてしまう。やっぱりどこか違う。
「忙しいんだろ、一人だと大変だね」
「まあ、だけど気楽だよ」
そういいながら、上着の内ポケットから、二枚に折った紙を取り出し、私に差し出した。
紙の中に顕微鏡写真がはさまっていた。
「大学の方に頼んで、疣を調べてもらったんだ」
写っていたのは疣の中に埋もれている胞子だった。実体顕微鏡という、組織や臓器の全体像を捉える比較的倍率の低い顕微鏡で撮影したものだ。
「疣にどうやって胞子が入ったのかいろいろ考えたのだが、やっぱり、女子大生の疣の膿がかかった一夜茸の胞子がウイルスをとりこみ、その胞子が飛んで、このあたりの人たちに取り付き、ウイルスを放出して、疣をつくり、繁殖したウイルスを再び食い尽くしたとしか考えられない」
「そんな菌類いないだろう」
私は、やけに彼が自分の仮説を信じたがっているような気がして不思議だった。とても科学的な男のはずだったが。
「今まではみつかっていないけどね」
「胞子が皮膚組織の中に入るなんて無理だろう」
「胞子が取り込んだウイルスが皮膚に穴を掘り、胞子が皮膚の中に潜み込む、ウイルスがそこを疣にする、胞子はウイルスを食べて、栄養にして、そこに居座る」
「それからどうなるんだ」
「発芽するまで寝ているんだ」
やはりSFである。そんなこと信じられるわけはない。
「疣から胞子を取り出せないのかい」
「それが、電気メスでも切れないくらい堅い疣になっている。要するに胞子が身を守っているんだ」
「だけど、そんな茸があるわけないだろう」
「新しい冬虫夏草だ、疣茸だ」
冬虫夏草は虫や虫の幼虫に寄生して殺してしまう茸である。
「まさか、人の疣から茸が生えてくるのかい」
「茸の生き残りの新しい戦略かな」
彼は寿司を摘みながら、当たり前のように説明を続けた。やはりおかしい。
「膿をかけられた一夜茸の復讐かもしれないぞ」
私がちゃかしたのにも関わらず、「いや、そうかもしれんな」、なぜか彼はしんみりと言ったのには驚いた。
「俺だって、信じられないよ」
「なあ、一度うちに診察にきた女の人がいたけど、その女性に家内が偶然にあったら、疣がたくさん増えていて、日野原先生は疣が好きだって言ってたってよ」
「ああ、知っている、茸産業に勤めている人だよね、英語の達者な」
「うん、なんだか奥さんも疣が好きだって変なことを言っていたようだぞ」
「そうか、どうだい、食いおわったら、ちょっと我家によって行かないか」
「いいけど、なんでだい」
「いや、家内に会っていってくれ」
なんだかおかしい。
「ずいぶんお会いしていないね、お元気なのか」
「ああ、元気なことは元気だよ、きっと長生きする」
変な答えである。
それで、食べ終わったあと、彼の病院に寄ることにした。病院の三階が住居になっている。彼の自宅に行くのは、彼が開業したての頃一度寄っただけで、その後はない。
居間に通されると、すぐに奥さんが入って来た。奥さんは病院の手伝いをしているが、あまり表に出るような人ではなかった。私は学会があると、家内を連れてでかけたものだが、日野原は一度も奥さんと一緒に来たことはない。
「お久しぶりです、奥様もお変わりありませんか」
彼女の声は若い。それに五十半ばのはずなのに三十代にしか見えない。
「ええ、ありがとうございます、奥さんはいつまでもお若いですね」
「あら、ご冗談を、あなた、お酒にします、お茶にします」
奥さんはちょっと笑顔になって彼に聞いた。
「どうする」彼が私に聞いたので、ビールをだいぶ飲んだし、お茶をもらうことにした。
「実はね、その疣茸、もう防ぎきれないとわかったので、共存することにしたよ」
彼の言っていることがわからなかった。
お茶を持ってきた奥さんもテーブルの前に腰掛けた。
「こいつの腕を見てくれよ」
奥さんが袖をまくって二の腕をだした。色が白い。とてもきめの細かい肌だが、そこに疣が一つあった。
「もうすぐだよ、彼女がその気になれば、こうなるんだ」
彼がそう言い終わらないうちに、疣から、茶色の茸が生えてきた。
私はびっくりして声にならなかった。
茸が傘を開いた。奥さんは微笑んだ。
「疣茸は、どんなウイルスより怖いんだ、ウイルスだけなら退治できるが、この茸の胞子はいったん皮膚にはいると取り出せない」
奥さんの腕から生えた茶色の茸から茶色の煙が立ちのぼった。
「でも、疣ができたところを大きく切り取ればいいだろう」
「いや、人が考えていることわかるんだ、ほら」
彼がそういうと、奥さんが片足を見せてくれた。義足をつけていた。
「疣のできた足を切ったんだ、足の疣の中の胞子はそれに気が付いて、足を切る前、手術を始める前に、足の皮膚から動いてしまった。この茸の胞子は人の脳で考えていることが分かる、疣のあるところを取り除こうとすると、胞子はリンパ液にはいって、他の皮膚に逃げて疣をつくり、茸を作り出すんだ、すぐに大きくなって、胞子をまくと、しおれていく、まさに一夜茸、このあたりではすでにかなりの人にとりついている、だから疣の患者が多いんだよ」
「え、あの茸産業の女性の疣からも茸が生えるということか」
私はまだ信じられずに聞いた。
「患者さんすべてからね、日本中に広まるのも時間の問題さ」
奥さんの腕からでた茸の茶色の胞子が私の周りを漂っている。私は手で追い払った。
「無駄だよ」
彼はそう言って私を見つめた。
「そう、君も、もう逃げられないんだ」
彼の腕からも茸が生えてきた。
「だけど、疣茸は人を殺すことはないよ」
彼は笑いながらそう言った。そして、
「だけど、食べると猛毒なんだよ」
とも言った。
そして大声で笑い出した。奥さんも笑った。
彼らは手や足からその仕掛けを取り外した。
「最近、手品にこっててね」
「あなた、ウイスキーの用意しますね」
奥さんが立ち上がった。綺麗な足をしている。
それから、そのトリックを作る苦労話をきかされ、三十年もののグレンユーリーロイヤルを堪能して家に帰った。
その話を家内にすると大笑いになった。
次の朝、気持ちよく目覚めた。
ふと腕を見ると、大きな疣ができている。あくびが途中で止まった。
また、振り出しに戻った。
疣茸
私家版第四茸小説集「茸怪夢、2023、267p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 17-10-20


