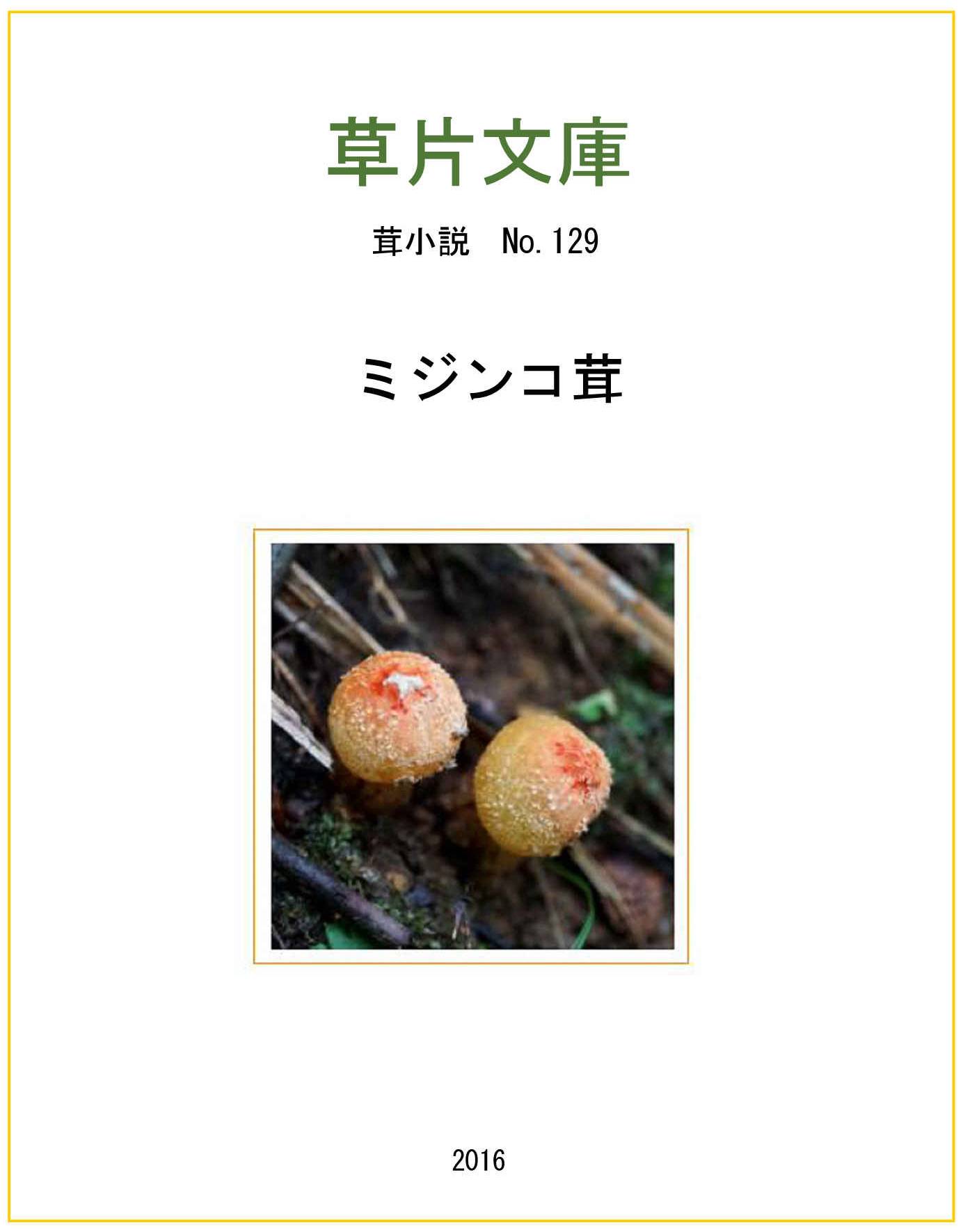
ミジンコ茸
退職してから、毎日のように近所に散歩に出かけるようになった。七十を過ぎての退職であり、もう新たな仕事に就くことはせず、のんびりと、好きなカメラいじりでもすることにしている。虫や花の写真を撮るのが好きだ。最近のデジタル一眼カメラは性能がよく、接写レンズを使えばプロ並みの面白い虫の写真が撮れる。今の人には当たり前だが動画も撮れる。虫たちの営みを撮影することができる。
家は多摩丘陵にあり、近くに自然公園があることから、写真の材料には事欠かない。
自然公園の中央に、かなり大きな池がある。その周りは整備されており、植えられた木々の間にベンチがある。老人たちが腰掛けて世間話に花を咲かせていたり、一人でのんびりと水に浮かんでいる鳥を眺めたりしている、のどかな風景だ。
公園を取り囲む丘陵の林の中も散歩にはとても良いところである。麓にはいろいろな種類の紫陽花が植えられており、その時期になると、わざわざ見に来る人もかなりいる。
はずれの一角に小さな沼があり、水が湧き出している。沼はだいぶ離れた池に、地下のどこかで繋がっているらしい。沼の際には朽ちかけた社があり、半開きになった格子戸の片方が外れていて中が丸見えだ。何も入っていないが、昔は地蔵か神物が置かれていたに違いない。
沼は石で囲まれていて、辺にはがまの穂綿が繁殖しており、糸トンボがひらひら舞う、なかなか優雅なお気に入りの場所である。
周りにはロープが張られ、子ども達に対する注意書きがたてられている。しかしロープももう朽ちていて意味を成していない状態である。水は踝ほどしかなく、おぼれるようなことはないが、本当に小さな子供には危ないだろう。人があまり行かないので、虫の写真を撮ったり、沼の中の生き物を眺めるにはもってこいの場所である。
その日、通りかかると、沼の中に緑色の塊がふかふか浮いているのが目に入った。大きな物ではない。親指ほどである。浮き草にしては大きすぎるし、なんだかおかしな動きをしている。あたかも動物のようである。
ロープを跨いで縁に立つと、浮いている物がわかった。緑色の茸である。なぜ茸がこんなところに浮かんでいるのだろう。茸が水の中に生えるわけはない、林に生えたものが落ちたのだろう。それにしても緑色の茸というのは珍しい。苔でもくっついたのであろうか。茸の形をした毬藻の一種かもしれない。
とりあえず写真を撮った。
枯れている蝦蟇の穂綿を引き抜くと、緑色の茸の形をした物をかき寄せた。見ると、藻の類ではなさそうだ。緑色のれっきとした茸のようである。
つまみ上げると、ふかふかしていて普通の茸の感触ではない。スポンジみたいだ。傘も襞も柄もすべて緑色だ。ビニール袋に入れた。家にもってかえろう。
この公園に散歩に来るようになって、デジカメで撮ったものを図鑑で調べたりしているうちに、かなりの生物通になってきた。現在、自宅の水槽にはみなが飼うような金魚やメダカはいないが、この沼や池で捕まえたゲンゴロウ、コミズスマシ、タニシなどが入っている。浮き草の下で、こういった虫たちが生活をしているさまを見るのはなかなか楽しいものである。ほどほどに飼ったら、また元に戻してやることにしている。タニシだけは最初に入れたままで、元気にガラスにくっついている。
水槽の中にはミジンコも発生しており、ちょっちょっと動くさまは可愛い。ただ、老眼鏡をかけても、姿かたちははっきりしない。ルーペで見るのも良いが、今では便利な器具があり、それを水槽に向けて置くと、パソコンに拡大された映像が映る。簡易なデジタル顕微鏡である。小さなものが生きたまま、目の前に面白い形をさらけ出すとても楽しい道具だ。特にプランクトン類は動きが面白く私のお気に入りである。水槽の中の生き物たちの写真や動画がずいぶんたまった。
沼で拾った緑色の茸は、いきなり水槽にはいれなかった。中の虫たちが驚いて大騒ぎをするだろう。そこで睡蓮鉢の水をくんできてボウルに入れ、その中にビニール袋から落とした。緑の茸はポチャンとボウルの底に沈むと、ぶくぶくあわがでた。
泡が少なくなった。水槽に入れるかと思ってみると、こんどは小さな緑色の虫がうじゃうじゃと水の中に出てきた。ボウルの水は緑色になり、茸は白くなってしまった。
緑色の虫は水の中を上へ、下へと動いている。その動きはミジンコそっくりである。ミジンコ茸をつまみ上げてみた。スポンジのようにすかすかになっている。
緑色のミジンコとは珍しい。ミドリムシのように、葉緑素を持っているのではないだろうと思うが。もしそうなら大発見だ。顕微鏡で見なければ。
机の上の水槽にボウルの水をいれた。思っていた通り、ゲンゴロウがびっくりして金魚藻の中に隠れた。緑色のミジンコのような連中は、一瞬パーッと水槽一面に広がった。だがすぐにガラス面に寄ってきてちょっちょと動き回っている。
私はいつものように、机のPCを開き、デジタル顕微鏡を接続した。先端を水槽に向けると、PCの画面に緑色のミジンコが現れた。タマミジンコの形をしているが、真緑色である。緑虫を食ったのかもしれないと思ったのだが、どうも腹の中が緑色ではなく周りの殻が透けた緑色だ。ミジンコは蟹などと同じ仲間の甲殻類だから、殻をもっている。
水槽の中には、ミジンコの餌になる植物プランクトンがいるはずだから、餌の心配は無い。しばらく様子を見ていると、緑色のミジンコたちは面白い動きをするようになった。卓上ライトの光の方向にちょっちょっちょっちょと動いていく。レンズを向けてみると、確かに一方に寄ってきている。やがて一つに集まった。緑色のミジンコがひしめいている様子は可愛いものである。
光の方によってきたのだ。このミジンコには走光性があるようである。卓上ライトを反対側に持っていってみた。緑色のミジンコたちはすぐさま光のほうに泳いでいくと集まった。倍率を上げてみた。なんだこりゃ、集まった緑タマミジンコたちは二本の手をお互いにつないで輪っかになっている。
ミジンコたちはふわふわと輪になって回転し始めた。面白いどころではない。周りの緑のミジンコたちも手をつないで輪になって、輪が上下に重なっていく。とうとう、それは茸の形になった。
茸の形になると、光は関係なくなったようで、その形のまま水槽の真ん中に移動してふらふらと揺れた。動き出していたゲンゴロウたちが、また浮き草の中に身体をもぐりこませた。前からいた普通のミジンコはと見ると、遠巻きにしてやっぱりちょっちょと動いている。気にしている様子はない。
親指ほどに育った茸は、だんだん膨らんでくる。毎日、顕微鏡を見ることになった。
数日後、手をつなぎ茸の形を作っている緑色のタマミジンコが、茸の中に子どもを放った。ミジンコの子どもが茸の中で泳ぎだした。こどもは数日で大人の形になり、みんなで手をつないだ。一週間も経つと茸の中はミジンコの詰め物になった。茸の形になってどうするのだろう。
緑色のミジンコもはじめてだが、群体になって茸の形を作るとはおかしな習性がある。茸の形になってなにがよいのであろう。たくさんが集まって大きく見せて、天敵の魚から逃れる小魚はよく知られている。ミジンコがそんなことをするとは思えない。
乾燥させた白い茸があるのを思い出した。沼にあった緑の茸だ。緑のミジンコが出てしまったなごりだ。スポンジのようでもあるが、穴が小さいので、白い高野豆腐のようだ。
水槽の中で緑色の茸の形になったミジンコたちを割り箸でつついてみた。ミジンコたちはぱーっと水の中に広がって水槽が緑色になった。沼から取ってきたときのように、白いスポンジのようなミジンコ茸は残っていない。手を離しただけのようだ。とすると、沼では白い茸を食べるためにミジンコが集まっていたのだろうか。乾燥した白い茸を水槽に入れてみた。茸は水を吸って、水槽の底に沈んでいった。しかし、緑色のミジンコは見向きもせずに、勝手に泳ぎ回っている。
水槽に向けて卓上ライトを当てた。再び、ミジンコたちが手をつないで茸の形になった。今度は驚かさないように見守ることにした。
一週間ほど経つと、ミジンコの茸の形から空気の泡がぶくぶくと出始めた。ミジンコが泡を吐き出すはずがない。ミジンコが葉緑体をもっていて、光に反応して、酸素を作っているのだろうか。もし光合成の反応が起きていたとしたら、でんぷん質や脂質や体の中の必要なものを作り出し、エネルギーを生産していることになる。動物が光合成により自分の体の中に必要なものを作り出すという仕組みは聞いたことがない。
泡が出始めて三日経った。相変わらず、茸の中から空気の粒が水面に向かって上昇していた。私はまた割り箸でつついてみた。緑色のミジンコはぱーっと散り散りになり、水槽の水が緑色に染まった。ミジンコが散った後におかしなものがある。あの白いミジンコ茸である。水の中を漂っている。前に入れたミジンコ茸もそのまま水底にあるということは、白い茸状の物はミジンコたちが作り出したということになる。緑のミジンコは光により茸の形に集まり、光合成によりミジンコ茸を作り出している。
食べてみよう。私は突拍子もないことを思いついた。ミジンコが作り出したのであるから毒であるはずはないと思ったのである。旨ければ、ミジンコ茸の養殖ができるとも考えた。
ミジンコ茸を取り出すと、水で洗い乾燥させた。その後バターで炒めた。食べてみると、なんと旨味のある茸だ。卵の味にも似ている。驚いたことに、舌触りは松茸にも似てしゃきっとしている。見た目の似ている凍み豆腐に味は全く似ていない。緑のミジンコが作った茸は珍味である。
それにしても、緑ミジンコたちはなぜ茸を作るようになったのだろうか。ミジンコの子供が今も水槽にいるが、白い茸を食べたりはしていない。子どものためにつくったのではない。緑のミジンコたちは白い茸ができてしまうと、無関心になってほうってしまう。何の目的のためにこのミジンコたちは光合成能力を身体に備え、白い茸を作るようになったのだ。その謎を知りたい。その謎を解く鍵は沼にあるに違いない。
その日朝早く、公園の沼に行った。沼は変わりなく、糸トンボが飛び、水の底には、蜻蛉の幼虫、カワゲラ、タニシなどがのんびりと生活をしている。真っ黒なオタマジャクシが群れている。蟇蛙の子供だ。時期的に遅いオタマジャクシだ。
沼の水の中に茸はない。緑色のミジンコはたくさんいて、オタマジャクシの頭の上や尾っぽにたくさんくっついている。なにをしているのだろう。オタマジャクシは草食だからミジンコは食われる心配はない。
ともかく緑色のミジンコがいることは再確認できた。沼の中で白い茸を作るのを見てみたいものである。これから夏に向かい光は強くなる。沼の中で白い茸が作られていくのを見ることができるのではないだろうか。沼はあまり深くない。接写のビデオカメラを買おう。それで水槽で茸が作られていくところを撮影しよう。私はそう思って、早速、機材をそろえた。それなりに費用はかかったが、とても面白い映像になるだろうと期待がもてた。
まず水槽で試すことにした。ビデオカメラを調整し、緑タマミジンコたちに向けた。光を当てれば緑ミジンコが茸を形作り、光合成でミジンコ茸を作り出すだろう。やってみた。予想通り撮影は上手くいった。
緑色のミジンコたちが茸の形に集まり、茸の成分らしきものを身体から分泌させていく様は見事である。自分の周りに茸の成分を分泌し、やがてそこから泳ぎ出ると、スポンジ状のものが残ることになる。出るさまも面白かった。外側のミジンコが水の中に泳ぎ出ると、その内側のミジンコが外側のミジンコが出た穴にぽっこりと顔をだし、泳ぎ出る。顔をだしたところは閉じられてしまうが、それより奥のミジンコが顔をだす。見ていて飽きない。
この映像をどこかに流すにしても、緑ミジンコの名前を知りたい。誰かに専門家を紹介してもらい、ミジンコの種類を同定してもらおう。科学博物館に問い合わせるのもいいだろう。
家での撮影が終わったのは、五月の連休の最後の日になった。それから本格的に沼に通うことにした。ビデオカメラを抱えて沼の脇に行き、三脚を設置し、もってきた椅子に腰掛けた。沼の中を覗いてみると、オタマジャクシはもういない。緑色のミジンコだけが水の中でワサワサ動いていた。これならば光が当たれば茸の形になっていくだろう。カメラを向けてためし撮りをする。再生してみるとミジンコたちが泳ぐ様が可愛らしく写っている。自然の中で観察すれば茸を作る理由もわかるだろう。
その場所はお昼頃にならないと日が射し込まない。待っていると、まだ日が差し込まないのに、緑色のミジンコは集まりはじめた。日の動きを予測できるようだ。あわてて撮影を開始した。
沼の中では上から撮影するので、ミジンコが手をつないで輪っこになる様子はよく分かる。陽が当たりはじめると、緑ミジンコたちは重なっていき、茸の形を作り出した。これなら見た人は納得するだろう。
白い茸が作り始められるまで、ミジンコが増えなければならない。光を当て続けた水槽でも数日かかった。一時しか日の当たらない沼では一週間以上かかるかもしれない。案の定、日の光がなくなると、ミジンコたちが手をつなぎ、茸の形になるのはゆっくりとなり、夕方にはほとんど動きがなくなった。
私は毎日のように通い、十日目にしてやっと充実したミジンコの茸の形ができあがった。撮影していたミジンコの茸の脇でも、ほかの群が茸の形を作っていた。見渡すと、数十個ある。
沼の上から見ると、いくつかのミジンコの茸から泡がではじめた。白いミジンコ茸を作り始めたのだ。それも十日ほどかかっただろう。もうすぐ六月になる。
その日、茸から出る泡が少なく弱くなった。夕方まで見ていると、次第にミジンコたちが作った茸から離れていく。夕焼け空の下で観察を続けると、ミジンコたちは完全に茸から離れ、沼の縁で上に行ったり下に行ったりしていた。沼の中では白っぽいスポンジのようなミジンコ茸がふらふらしている。
白いミジンコ茸はどうなるのだろう。今日は徹夜で見張ろう。空が紺碧になってきた。大きな月がでている。そういえば今日は満月である。
家にいったん帰り、予備のバッテリーと電灯付のヘルメット、それに腹の足しになるものをもって、沼に戻った。空は暗くなったが、月明かりが沼を照らし出す。もう八時になる。水の中は変わりがなく、ミジンコ茸は沼に沈み、底から生えているようにゆらゆら揺れている。
月が大きく沼の真ん中を照らした。沼辺を覗いていると、反対側の社から、ぎいいという音が聞こえた。風も無い。あわてて顔を起こして社を見ると、朽ちかけた入口の戸がかたりと外れた。なんだろうと目を凝らすと、黒っぽい人型の生きものが、社の中から現れて、沼の中にざぶんと飛び降りた。
川獺か。いや、川獺は絶滅したはずだ。狸や狐なら水に入ったりしないだろう。
そいつは水の中を歩いて、私のほうに向かってきた。背筋がすーっと冷たくなった。月の明かりに照らされて、緑色の顔が見えた。長い髪、黒い眼、広がった口。
沼の真ん中あたりからざざーと音が聞こえてきて、水の波が沼の辺に押し寄せた。沼の底の茸がゆらゆら揺れている。
河童だ、幻影か、河童が沼の中を歩いてくる。しかも抱えているのは、小さな河童だ。河童の子どもだ。夢を見ているのだろうか。手がすくんで、ビデオカメラがうまく操れない。もうすぐ目の前に来る。
河童は片手で子どもを抱き、片手に緑色のものを持っている。盛んにそれを口に持って言って、口を動かしている。きゅうりだ。きゅうりを食べている。最後の一かけを食べてしまうと、その手を沼の中に突っ込んだ。かがんだ拍子に、頭に皿が載っているのが見えた。河童は白いミジンコ茸をつまみあげた。それを子供の河童に与えた。
河童の子供はミジンコ茸を両手で持つと、口に入れて旨そうに噛んだ。子河童のつぶらな目が親を見た。母河童はまたミジンコ茸を沼の中からすくって子供に与えた。子供は旨そうに食った。
二人は近づいてくる。母河童は私が見ているのに気がついた。きっと笑ったのであろう。大きな目の周りに皺を寄せ、私を見て頷いた。ミジンコ茸を沼からとるとまた子どもに与えた。すぐにもう一本とると、私の目の前に来て、そのミジンコ茸を差し出した。私はふるえながら両手をさし出すと茸をつかんだ。お礼を言いたかったのだが、まともな声にならず、ありがとうとは聞こえなかったに違いない。しかし河童は頬に笑窪のような皺をよせた。
私はくちゃくちゃとミジンコ茸をかんだ。すでに炒めて食べたものだ。その時も旨いと感じた。母河童は子供と私に交互に白い茸を与えた。
沼の中のミジンコ茸が見つからなくなると、母河童は子供を抱いて立ち上がった。後ろの甲羅も緑色だった。
母河童は沼の真ん中に向かって歩いて行く。
私は我に帰り、写真機を河童に向けた。河童は立ち止まるとこちらを振り返り、口を開けて笑った。
私はシャッターをきった。その瞬間、カメラのレンズが大きな音とともに破裂し、白い煙が上がった。そこにはもう、河童の姿はなかった。
ぎいい、社の扉が閉まるところであった。
その後、その昔、沼は河童沼と呼ばれていたことを郷土誌で知った。
緑色のミジンコは河童の子供の食べ物である白いミジンコ茸を作り出していたのである。
私はこのことを誰にも言わないことにした。母河童がミジンコ茸を私にくれたのは、そうしてくれということを言いたかったのに違いない。
自宅の水槽では緑ミジンコが手をつないで、茸の形になっている。やがでミジンコ茸ができるだろう。ミジンコ茸を食べると、なんとなく身体がホカホカしてきて元気が出る。白い茸の成分のせいだろう。長生きをもらったような気がする。いくつも乾燥させ、冷蔵庫にしまってある。簡単に戻して食べられることもわかった。
もう一度河童に会いたくて、水槽で作られた白いミジンコ茸を持って、夜中に沼に行くのだが、あれからまだ会えない。いつか現れるだろうと期待している。いずれ沼がなくなっても、私のところにくれば、いつでも茸があることを伝えておきたいからである。
乾燥した白い茸をあの社の中においてきた。矢印をつけた我が家の地図も置いた。いつか気が付いてくれることを祈っている。
庭の睡蓮鉢にも緑色のミジンコが増えている。
ミジンコ茸
私家版第十二茸小説集「万茸鏡、2022、267p、一粒書房」所収
茸写真:著者 秋田県湯沢市小安 2018-9-30


