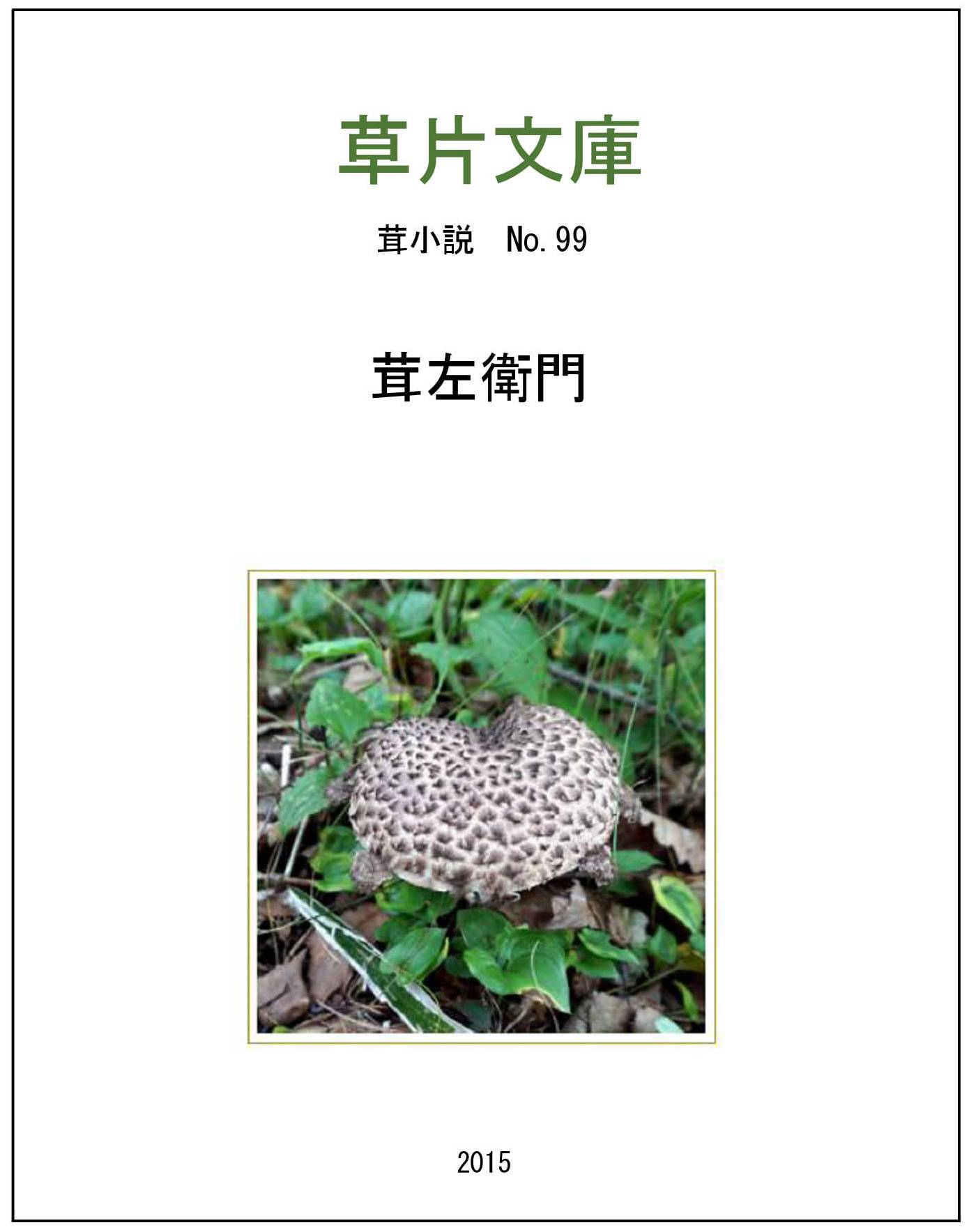
茸左衛門
大阪城下は賑わっていた。落雷で崩れ落ちた天守閣が再築されたばかりである。
人の往来の激しい大通りの角ごとに物売りがでている。富山からきた薬売りは侍姿の派手ななりで刀を振り回し、自分の腕に傷をつけるや、滲み出した血を拭き取り、富山の軟膏をなすりつける。血が止まり、傷が治った腕を、集まった人々に見せびらかす。
一人ちょっと目を引く軟膏売りがいる。大きな図体に髭だらけの大きな顔、油染みた紺の着物の袖から太い毛もくじゃらの腕が出ている。
右に持った刀を振りあげ、左の手の平に蛤をのせ、みなの方に突き出した。
「さてお立会い、ここにとりいだしたるは、不老不死の茸からつくった薬だ、万年茸ではないよ、あれはからだのお薬、これは違うよ、体だけではない、おつむにも効く薬だ。頭の中の悪い物をみんな吐き出しちまう。まずはお立会い、ほれ、この通り、刀で腕を切ってみる」
見ている者はいつものように、軟膏売りが左腕に刀をあて、傷口から血がうっすらと出てくると思っていた。
ところが、その軟膏売りは、左腕に刀をふりおろし、すっぱり腕を切ってしまった。腕が大道にころんところがる。軟膏売りはあわてず騒がず、刀を台の上におくと、落ちた左腕を右手で掴んだ。
「さて、お立会い、この切った左手の切り口にこの薬を擦り付ける、そうして、このように」
軟膏売りは、左腕の切り口に切り落とした腕をくっつけた。
「ほーれ、ほーれ、ほーれ」
と言っているうちに、切り取られた腕の指が動き出し、あっという間に元に戻った。
なかなかうまい手妻(てずま)である。
「このように、体にも効く、それに頭にも効く、この霊薬は、信州諏訪の山奥で人知れず生える茸なり、この茸は泡茸と申すが、千年に一つ見つかるかどうかという珍しいもの」
軟膏売りは懐から赤黒い茸を取り出した。
「この茸に一年のあいだ酒をかけてやると、たらりたらりと、赤い汁を垂らし始める。その汁集めて、三日三晩煮詰めたのがこの泡薬だ」
どこかで聞いたような口上だ。軟膏売りは蛤に詰めた軟膏をみなに見せた。
「今日は特別じゃ、これを一両と本当は言いたいところだが、一分でいい、ゆずってしんぜよう、馬鹿にも効く薬だ」
こんな商売では生業がたたないのではと思うが、その軟膏売りは顔色もよく、汚れてはいるが着ている物も悪くない。
一分とは庶民にとって馬鹿高いと思うが、それでも二人ほどが買い求めていた。景気がいいご時勢なのだろう。
見ていた茸左衛門(じざえもん)は泡茸という茸にも興味があったが、その男が行なった手妻がまた面白い。
茸左衛門も一つ買い求めた。
「お武家どの、何に使いなさるかな」
紙に包んだ蛤の泡茸を手渡しながら軟膏売りが茸左衛門にたずねた。
「いや、その茸に興味があったので試してみようと思いまして」
「試すとはいかがなことをするおつもりかな」
軟膏売りは、本当の侍のような口の訊き方をした。怪訝な顔をしている茸左衛門に気がついて言い直した。
「失礼いたした、儂は富山の素浪人で、茸右衛門(じうえもん)と申しましてな、茸から薬を作っております」
茸左衛門は薬を受け取りながら、内心、相手が武士だったことに戸惑っていた。それに名前が茸右衛門とは、右左の違いだけではないか。町民相手の方がいろいろ訊ねやすいのだが。
「あの手妻のことを知りたいのかな、それともこの泡茸かな」
と言いながら、袖口から、黒赤い茸と手妻の道具を取り出した。木でできている切った先の左手と手首を覆ってしまう木でできた筒で、切り口に血がついている。
「手妻は難しいことではない、刀を振りおろすと同時に、作り物の左腕を落とし、切られた左手をかばうようにしながら、先の切られた義手を左手にはめてしまうのだ、みんなは転がった左手のほうをみている、そのすきにじゃ」
「達人でございますな、私は茸左衛門ともうします」
これには相手も驚いたようだ。
「右と左の違いだけではござらんか、して、名字はなんと申される」
「万年と申します」
「なんとなんと、儂も万年、こりゃどこかで繋がりがあるやもしれぬが、お主様はこの地の生まれか」
「はい、浪速でございます」
「わしの代々は富山でござるから、偶然のようであるな、昔は富山のとある大名にかかえられていた薬師である侍の家であったが、その大名が没落して、今では諏訪に住んで、茸をとり、このようなことをしておる」
「わたしの家は、大阪の城の薬師の一人でございました」
「太閤のか」
「はい、その後、徳川家のお大名にお仕えするようになりました」
「そりゃあ偉い、おみそれつかまった、儂などと話しておると、具合が悪かろう」
「いえ、そんな、泡茸のこと、まだ教えていただいておりません、どこぞで一献やりながら、いかがでございましょうか」
「そりゃあ、望むところだが、よいのであろうか」
「まだ、私は薬を学んでいる学途上の者、いろいろ知りたいと思うております」
「教えることなどないが、この茸については儂しか知らん、話してしんぜよう」
こうして茸左衛門と茸右衛門は飯屋にはいった。
「昼間から飲めるなんざあ、何年ぶりか」
茸右衛門は根っからの酒好きのようだ。
席に着くと、自分から酒の注文をした。
茸左衛門は体が小さく、茸右衛門の半分もないかもしれない。色も白く、酒は一合も飲むともういらなくなる。当然のこと、このような店での振舞いはなれていない。
「茸左衛門どのも酒でよいか」
彼がうなずくと、茸右衛門は彼の酒も注文した。
「それで、どのようなことを学ばれているのか」
「茸の毒でございます」
「毒とな、毒消しでも作るのかな」
「はい、それもありますが、逆もあります」
「ふむ、人殺しに使うのか」
「いえ、毒を薄め、薬を作ります」
そこへ酒が運ばれてきた。
「豆はないか、それに当りめなどもってまいれ」
茸右衛門は酒をもってきた主人に言った。
「それで、茸左衛門どの、どのような薬を造られたのかな」
彼は手酌ではじめた。あわてて茸左衛門は徳利をもち、注ごうとしたが、彼が押し留めた。
「気になさるな、酒は自分で飲みたいだけ飲むのがうまい」
茸左衛門は持ち上げた徳利の口を自分の猪口にむけた。
「どんな薬を作ったかな」
「私は、まだ一つ、月夜茸の毒をおろし薬にいたしました」
「おろさなければならぬ女子がたんとおるのか」
「はい」
「奥ではないな、どこにおる」
「女密偵でございます、体を張って情報をとってまいります」
「確かに、して、その薬は体に害が少ないのか」
「はい、使った後、すぐに月の物がきます」
「ふむ、それはよい薬かもしれぬ」
「しかし、私は、作ってみたい薬があります」
「それはなにか」
「一度死に、一年後に生き返る薬でございます」
「うむ、不老不死の薬と言うと思っていたが、なぜ一年後に生き返る必要があるのかな」
「その間、年をとりません、一年後に目覚め、半月ほど暮らし、また、その薬を飲むのでございます。五十年たっても、半月が五十回、すなわち、二十五ヶ月、およそ二歳しか年をとりません、私は今十八、二年後にその薬を完成させれば、五十年たっても二十四でございます。二百年たっても、三十でございます」
「たしかに、そうだが、なぜ一年ごとに半月目覚める必要があるのかな、二百年後に生き返れば、二十のままであろう」
「いきなり、二百年後の世にはいりますと、その世に頭が追いつかないでしょう、一年ごとに半月ほど、その世界に慣れておくのでございます」
「賢いのう、儂にはそのようなことは考えられぬわ、だが、一年、半月という、その時を寝ている身体が、いや頭がいかにして知ることができるのであろう」
「体の中には、時を刻む働きがあるといわれております、その働きに効く薬でなければなりませぬ」
「ふーむ、面白い、儂はもうすぐ四十になる、五十年後にはまだ四十二か、まだ寿命ではないな、そのような薬があったら、わしも飲んでみたいものだ」
「茸はいろいろなものを含んでおりますうまく見つけることができれば、そのような薬も作れなくないと考えております、そこで面白そうな茸があれば、いろいろ試すことにしております」
「ふーむ、この泡茸には眠くなる作用や、若さを保つ作用があると聞いたことがある、そなたにあずけよう、もし足りないなら来年にはもっとたくさん探して持ってこようぞ」
泡茸というのは本当に珍しい茸のようである。
「ありがとうございます」
茸右衛門は酒をすでに三本ほど空にしている。
「おやじ、もう一本だ」
「どこにお泊まりですか」
「いつも野宿か、寺の本堂のわきなぞじゃ」
「どうぞ我が家にお泊まりください」
「いや、奥方に嫌われよう、遠慮しよう」
「私は独り者、幸い、部屋はいくつかあり、数人の奉公人もおります、ご心配は無用でございます、代々薬を作る家でございます、薬を調合する部屋もあります」
茸右衛門はうなずいた。
「それでは、少し歩かねばなりませんが、続きはわが家でいかがでしょう」
「そうか、それならばじゃまをさせていただくとしよう、かたじけない」
彼は懐から泡茸をとりだすと、茸左衛門に手渡した。茸左衛門は懐紙に包むと懐に入れた。
茸左衛門の家は大阪城からすこしばかり離れた山里にあった。古くからある家と見えて古式豊かな大きな家である。敷地には様々な果物の木が植えられており、それに接して広い野草園があった。
立派な門をくぐり玄関にたつと、中から老人がでてきて茸右衛門を見た。
「若さま、おかえりなさいまし、お連れ様がおいでですか」
「ああ、茸右衛門様だ、諏訪のこの茸をいただいた」
茸左衛門は懐紙を広げ赤黒い茸をみせた。
「おおこれは、もしや若様のお父上が探していた茸かもしれません」
茸左衛門は茸右衛門に老人を紹介した。
「この者は家のすべてを取り仕切っている茸兵(じへい)でございます、薬のことも良く知っております、よろしくお願いしたします」
茸兵とよばれた老人は、深々とお辞儀をすると、茸右衛門を玄関に案内した。
茸兵が奥に声をかけた。
「お客様がお見えだ」
若い女子衆が水のはいった桶をもってきた。
「いらっしゃいませ」
女は入口に腰掛けた茸右衛門の草鞋を脱がせ、足を桶の中につけた。
茸右衛門の足を洗うと水が真っ黒になった。
「こりゃ、すまぬ、なにせ一月ほど風呂に入っておらぬ」
「風呂もすぐ沸かさせます、いかがでござりますか」
茸左衛門が風呂をすすめた。
「そのあと、酒を用意しておきます」
「これは、至れり尽くせりで、儂には盆と正月がいっしょにやってきたようだ」
茸右衛門は大笑いした。
食事をとりながら、茸右衛門は自分のことを仔細に話しはじめた。
「儂はのう、こんなにごつい手をしてるがの」
彼は手の裏をみせた。茸左衛門の手の倍の太さがあるであろう。ところが指の先を見ると、きれいな爪をしており、細くとがっている。
「自分で言うのもなんだが、以外と器用でな」
「確かに私の指先と同じほどでございます」
「細かな薬の調合は得意であった」
「それでどのようなお薬をおつくりになっていたのでしょう」
「儂は毒を作っておった」
「それは恐ろしい」
「儂の仕える城の奥方様に頼まれてな、だから、そのころは羽振りがよかったのじゃ、毎晩宴会よ」
「奥方様はどのようにその、お薬をお使いになったので」
「気に入らぬ跡継ぎに使ったようだ、儂は言うなりに薬を作っておった、だが、やはり悪いことはできぬ、とうとう跡継ぎ問題は大事になり、富山の大城の前田様に知れることになって、攻められ家はつぶれた。
儂は浪人になり、諏訪にながれ、何とか薬を作って暮らしておる。たまにこのように尾張や浪速にもでてきて、遊んで帰ることにしておる。家に帰っても誰がいるわけではないが、薬草や茸の生えているところはよく知っておるし、町の医者からは薬の注文はくる、住みやすいのだ」
「茸右衛門どの、先ほどお話しした薬を作るお手伝いをしてくださいませぬか、いかがなものでしょう」
「ふむ、一度、諏訪に帰って、この茸を集めてからでよいかな」
「はい、それまでに、この泡茸の汁を調べておきます」
「それならまた泡茸を採ってまいる、この茸は奥山の一つ、泡山でとれる茸、険しい山で上の方はいつも寒く、珍しくその寒い岩場にでる茸でな、赤い汁を持つ茸じゃ、千年に一回生えるというのは口上で、そうは見つからぬが、いつでも生えておる」
「その茸の御代と路銀は私どもで前もってお支払いいたします、ここでお手伝いいただければ、その分はその時お支払いいたします」
「それは助かる、茸を採って一月ほどで戻れると思う」
こうして、茸右衛門は七日ほど茸左衛門の家に逗留し、一通りの薬を作る課程を見ると諏訪に帰っていった。
茸左衛門は夢中になって泡茸を解析した。
泡茸をつぶして、猫に食わして調べた茸左衛門は、泡茸が他の茸より、毒性が少なく、だらんとなって、よく眠るようになることを明らかにした。その効果は、眠った後に、体が冷たくなり、すなわち体温が低くなり、息が少なくなり、心の臓の動きが小さくなるという、茸左衛門の目的に適したものであることが分かった。便利なことに、薬の量に依存し、目覚めるまでの時間が長くなることである。
さらに、つぶして汁をとり、それを日に干して粉薬にしても同じような働きをもつことを知った。生よりも少ない量で睡眠効果がでる。
しかしそれだけでは人間にどれほどの量を処方すればいいのかわからない。なにも食わず飲まずで、二十年も死んだ状態になって、生きたまま保たれなければならないのである。乾燥した泡茸を人に飲ませて様子を見るしかない。
茸左衛門がそこまでつきつめたところで、茸右衛門が泡茸を籠いっぱいに背負って、諏訪から戻ってきた。
「茸左衛門どの、今回はずいぶん多くの泡茸が採れましたぞ」
「ありがとうございます」
茸左衛門は茸右衛門に今までの成果を話して聞かせた。
「それは面白い、たった一月でそれだけのことを調べあげたとは、さすが茸左衛門どのだ、それでこれからどうなさるのかな」
「猫に今までより多量の泡茸薬を飲ませ、一月眠らせて見ようと考えております」
「それは良い、ただ、眠るのと死ぬのは違いますぞ」
「はい、私は見たことがないのですが、寒いところの木鼠は冬の間死んだ状態になるということを聞いたことがあります、泡茸で猫が冷たくなりました」
「おお、そうですか、富山の木鼠は冬死んだようになる、しかし、ゆっくりだが、心の臓は動いておる、死ぬのと全く違う」
「泡茸はそのような状態になるようです」
「それはいい、我々の持つ熱が下がり、心の臓の動きがゆっくりになれば、木鼠のように、長く寝たままになることができますな」
「はい、茸右衛門殿の言う通りでございます、ただ、からだが弱っていくのを妨げなければなりません、二十年元気に寝たままでなければならないのです」
「そうであるな、からだの隅々まで、元気な状態でいるようにする薬草を混ぜなければならぬな、水が大事じゃな、水がなくなるとわしらのからだは干からびてしまう。からだに水を保つ薬草を混ぜるとよいかも知れぬ」
「私には思いつきませぬ」
「うむ、茸じゃ、チョレマイタケと申してな、その根の部分が良いな」
「その茸は存じております、茸平に採りにいかせます」
「泡茸にはからだの隅々まで力が出るような薬がはいっておる、二十年もつであろうが、途中で目が覚めぬよう泡茸の眠らせる働きをもう少し強くしなければならぬな」
「なにかありますでしょうか」
「うむ、熊の胃ではなく、腎の上にある豆のような臓をすり潰し混ぜると、他の薬の働きが数百倍にもなる、貴重な薬にはそれを混ぜて、効きをよくするものじゃ、少しの量で病が治る」
「しかし、これから熊を射止めて、その臓を取り出さねばなりませんな」
「いや大丈夫じゃ、わしの爺様がそれを見つけて薬にしたものを城に納めておった。今はほとんど使っておらぬが、まだ少し残っている。いつもわしの持っている袋の中にあると思うので見てみよう」
茸右衛門は皮袋の中からいくつかの薬を取り出した。その中に熊腎散と書かれているものを見て、「お、あった」と、茸左衛門に差し出した。
「これをどれほど混ぜればよいのでしょうか」
「ふむ、ほんの少しじゃ、だから、これだけあればたくさんつくれる」
「そうでございますか」
という次第で、茸右衛門は泡茸とチョレマイタケを乾燥し粉にした。茸左衛門は泡茸とチョレマイタケを混ぜた泡茸薬を鰹節に混ぜ、猫に量をかえて食わせ、毎日のように猫の様子を観察した。
茸左衛門が調べた結果、まずほんの一匁の十分の一の量で、猫は一月眠ることがわかり、さらに茸右衛門が持ってきた薬をまぜると、その十分の一の量でよいことがわかった。
「人では猫に与えた十倍、一匁で一月眠ることになりますが、茸右衛門殿が持ってきた薬を使うと十分の一匁でよく、一年はその量の十二倍、さらに二十年は二百四十倍、二十四匁となります」
「ふむ、そうすると、泡茸一本で十分だな」
「粉にすると、減りますので、泡茸二本ほど必要になります」
「儂がとってきたのは百本以上あるだろう、とすれば、二人とも五百年は寝ることができる」
「五百年たつと私は五十近くになります」
「わしは、七十近くなる、生きておらんじゃろう、途中で寿命がきたらどうなると思われるのかな」
「寝ている最中に自分の寿命がつきますとそのまま召されます」
「それはいい、お主は二百年後から生活を新たにはじめるのかな」
「そのつもりですが、その時がどのようになっているか、それによってはもっと長く眠ります」
「それがよい」
「ところで、儂が最初の試しを行なおう、一月程寝てみたい、本当に飲むのはその後の方が良かろう」
「それでよろしいですか」
「よいさ、ちょっと若返ることになる」
ということで茸右衛門は酒に泡茸薬と熊腎散を混ぜてぐいっと飲んだ。
しばらくすると、旨い酒だと言いながら横になると寝てしまった。
茸左衛門は手伝いの者を呼び、茸右衛門を布団に寝かし、毎日観察をした。体の熱がどんどん下がりやがて冷たくなったが、心の臓は時々動いている。息も一時に一度ほどはしているようである。茸左衛門が興味をもったのは、これも日に一度程であるが、茸右衛門の目がきょろきょろと動いているようなのだ。しかも股間がもりあがっている。眼の様子は寝ている猫でも見ることができた。蘭学の師範の話を聞いたことがあるが、夢を見ている時にはそのように目が動くそうである。ということは、二十年寝ている間、全く記憶がないのではなく、楽しい夢を見ることが出来るかもしれないのだ。いやな夢だと困るのだが、茸右衛門が起きたら聞いてみることにしよう。
一月は瞬く間に過ぎた。
茸右衛門は大きな欠伸とともに目を覚ました。
「よく寝たわい」
大きな声を上げて起きあがった茸右衛門は、
「水を所望する」
と、また大きな声をあげた。が、枕元に薬缶があるのに気がつき、自分からとると、ゴクゴクと飲んだ。
「水が旨いわい」
「茸右衛門どの、お目覚めですな」
「おう、茸左衛門どの、気持ち良く寝られましたぞ、もう一月経ったのかな」
「はい、ちょうど一月にございます」
「それだけ年をとらなかったわけだな」
「寝ている間はいかがでした」
「おう、そりゃあ、楽しかったわい、若い女子の夢ばかり見ておった、みんな違う子でな」
「茸右衛門様の経験の豊かさがそうさせたのでございましょう」
「なんだ、堅苦しい言い方をするのう、たくさんの女子を泣かせたからの」
「食したいものはございますでしょうか」
「酒だな、それに、白い飯もほしい」
「用意してございます」
すぐに家の者が酒に肴、それに白い飯と味噌汁をもってきた。茸右衛門は早速、めざしをかじり酒を飲んだ。
「二十年寝た後にはこういうことを自分でしなければならないな」
「はい、寝ている周りに水と干米、味噌、梅干しなどをおいておく必要があります」
「そうだのう、それで人にじゃまされずに寝る場所はあるかな」
「この屋敷の裏は丘の林になっております、そこに深い穴が掘ってございます、茸倉と呼んでおりますが、その中で茸の栽培や酒造りを行っております。どれも薬の元になる茸でございます、その奥にすでに部屋を用意してございます」
「それはすごい」
「はい、我が家が続く限り、そこへは他人がはいることはありません、また、二十年ごとに私が目覚めて、半月の間にいろいろ整えるつもりでございます。
「ものは相談じゃが、そなたは二十年ごとに一つ年をとるが、わしは百年、そのまま寝てみたいのじゃ、するとそなたと年が近くなる」
「たしかにそうです、わかりました、そういたします」
茸爺とごく内輪の者だけにその話をした。寝ている間、邪魔をしないように言い含めたのである。ちょっとでも起すと死に至ると脅かした。
もろもろのことを終えた後、茸左衛門と茸右衛門は茸倉の奥に入り、それぞれ必要な泡茸薬と熊腎散を混ぜ飲んだ。
二人は薬の効き目が奏して予定通りに眠りについた。
本人にとって二十年はあっという間のことである。
茸左衛門はまさしく二十年後に目覚めた。屋敷をまかされていた茸爺は還暦をすぎていたが、まだ元気に薬の製造を行い城に納めていた。
「若様、時代が変わり、今は徳川家宣さまが後見にございます」
たった二十年でかわるものである。目覚めてから半月の間、茸左衛門は屋敷のことに精をだし、爺の息子にこの屋敷をまかせ、また眠りについた。
そうして、最初から百年たって目覚めたとき、江戸時代の太平の世であった。
茸右衛門は少し前に目覚めたとみえ、寝所にはいなかった。書き置きがあった。
「ちょっと、江戸まで行って参る」
元気そうでなによりである。
また茸左衛門は二十年寝て目覚めた。
茸右衛門はおらず、また書き置きがあった。
「江戸で好いた女子ができた、そいつと一生過ごすことにする、残った泡茸薬と熊腎散はそちにまかせる、好きなように使ってくれ、世話になった、うまくことが運ぶことを祈る」
とあった。
茸左衛門は、それから二十年を何度も寝た。やがて目覚めると、明治の時代になり、他所の国の者が日本に入ってくるようになった。それも終わり、やがて昭和という時代になって、他所の国と戦争をしており、次に起きたときには恐ろしく速い乗り物ができていた。自分の住んでいる千里は万国博というお祭り騒ぎの最中であった。さらに、二十年二十年と寝ると、昭和も終わり、平成という世になり、日本語はまったく違った言葉になっており、それだけではなく、アメリカという国の言葉をだれもが話すことが出来るようになっていた。そして令和の時代になり今の私がある。
世界を制覇した茸印の薬屋の社長である。長時間の麻酔薬は私のところしか作ることは出来ない。
二十年眠ることのできる薬は、今では機械というもので大量に作り出すことが出来るのである。宇宙旅行を目指す人間に必須の薬であった。
これからをどうするか、回りを見極めて決めたいと思っている。みな月に行きたいと考えているようであるが、もし薬を改良し、五百年、いや千年眠っていることができるとすると、何を見ることができるであろうか。
千年の薬が出来て私は使った。私は目覚めた。
あたりに人はいなかった。ただただ、ぴりぴりする風が吹いていた。放射能の風のようである。
アーサーCクラークが書いたように、みな地球を見限って離れていったようである。きっと茸印の睡眠薬は役に立ったことであろう。
茸左衛門
私家版第六茸小説集「茸童子、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野富士見町16-9-15


