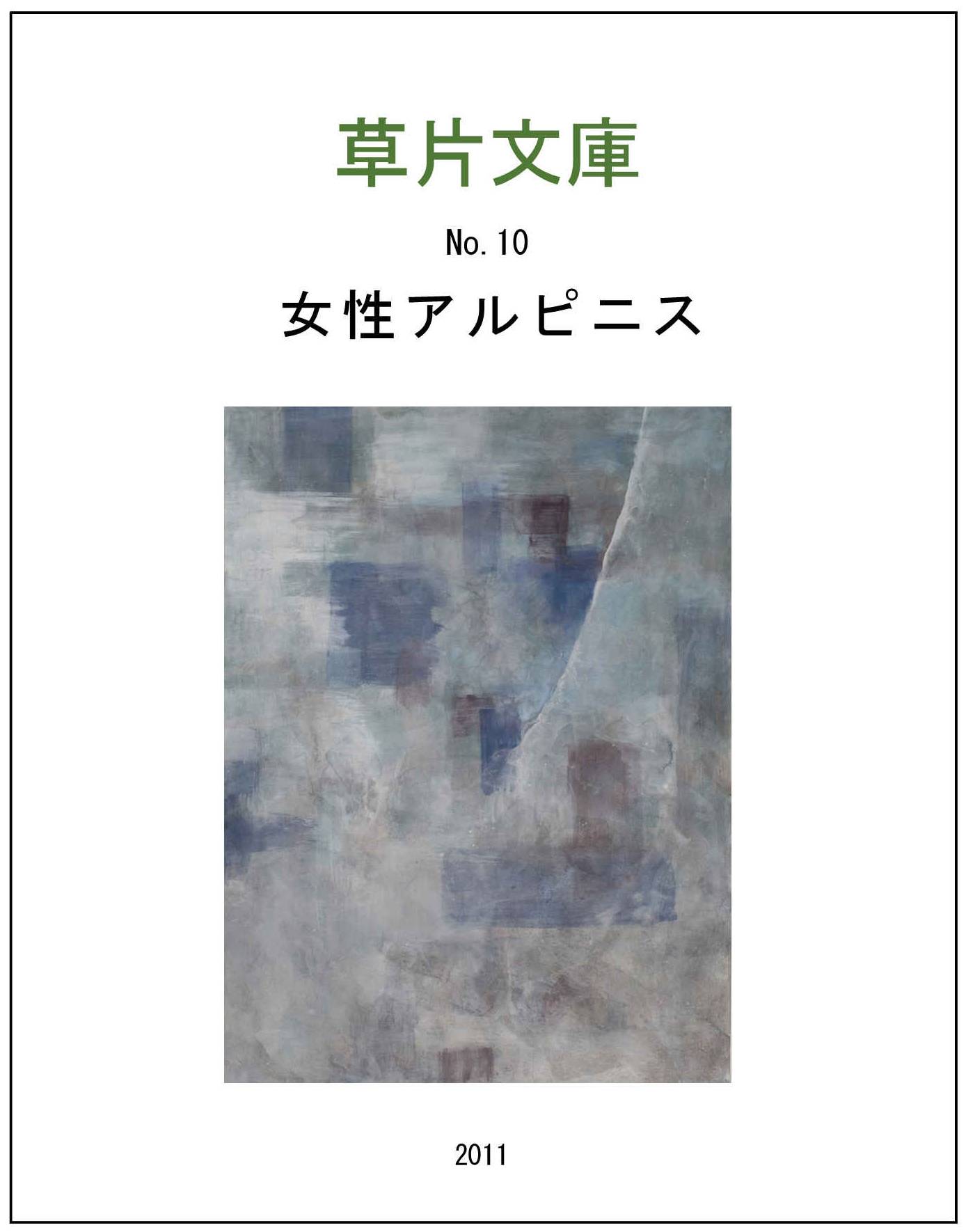
女性アルピニスト
雲ひとつない青い空の真ん中にぎらぎらと太陽が強い光を注いでいる。といって、決して暑いわけではなく、涼やかな風が髪を揺らしていく。
リュックをしょった私は、岩山の出っ張りに腰掛けて広がる平野、遠くの山々、日本海を眺めている。
私は八つの時に親と一緒に富士山に登った。もしそれを最初とすると四十年の登山経歴をもつ女性アルピニストということになる。海外の多くの名のある山、特に冬山を制覇し、それなりに名が知られている。
重装備を背負い、歯を食いしばって登る登山。それが今までの私の生きがいだった。しかし、雄大な景色を見て、その怖さを知って、それを征服した気になって、また登りたくなって、の繰り返しに、何かが足りないような気持ちになっている。日本の山をゆっくりと登りたいと思うようになった。歳のせいもあるかもしれない。
といっても、鳥海山は二千メートルを越える東北では最も高い山の一つである。しかも険しい顔も持っている。夏でも頂上付近には雪が残り、南側には雪渓がある。この雪渓をふもとから見ると心の字のような形をしていて、心字渓谷と名がつけられている。何か迷いのあるような自分の心にも答えが見つかるかもしれないと、この「こころ」にひかれて、新たな登山の最初の山として鳥海山を選んだのである。
その雪渓を超え、今、頂上より少し下った岩の窪みに腰掛け、遠くを眺めている。遠くを見ていると、どぎつく光る太陽の下のほうにもくもくと雲が湧き出してきた。きれいな入道雲である。青い空に湧き出る雲は生き物のように私の上に覆ってくる。入道雲の下は黒く渦巻いている。
雨が来るのかと見上げると、白いものがちらちらと落ちてきた。太陽の下で雪が落ちてくる。私は水筒のふたに雪を受けた。雪だ。ふわふわの大きな雪がゆっくりと日の光を浴びて落ちてくる。おかしさがこみ上げてきた。そう、これは夢なのだ。私は冬の鳥海山に登っているはずだ。夢の中で真夏の空から雪が舞い降りてきて、私はそれを水筒のふたに受けている。
あっという間に雪が山盛りになった。すると、雪の山のてっちょうが赤く染まった。私は口を寄せて赤くなった雪をなめた。懐かしいイチゴ水のかかったかき氷の味と、ふわっとした冷たい雪の結晶が口の中に広がる。夢の中でなければ味わえない。最高だ。しかも、のどが渇いていたところだ。
青空の太陽の下でまだ雪が降っている。眼下を見ると、赤いスーツを着た女性が岩を登ってくる。右手にはきらきら光るナイフをかざしている。ナイフの光が私の心臓を照らした。ちょっとドキッとした。とあっという間に、目の前に女性がいた。
すらっとした若い女性である。母に少し似ているが、色の黒い母と違い、白い肌が青空にまぶしい。手に持った金属が太陽に反射してまた光った。あっと思ったとき、それが目の前に差し出された。声にはなっていなかったが、雪のカキ氷をおくれと言ったようだ。差し出されたのは銀でできたスプーンだった。節くれだった指がしっかりと匙をもっていた。紅花の口紅で染めた赤い唇がまた動いた。私が何も言わないのでいらだっているようだ。わたしはあわててイチゴ水のかかった雪を彼女の前に差し出した。
女は口を大きく開けた。スプーンを雪の中に差し込むと、赤いイチゴ水のかかった雪を掬い取って口の中にいれた。開けた口の中は真っ赤になった。匙の上の雪は舌でなめ取られた。女が笑った。おいしいということだろう。笑うと左側だけにえくぼがよるのは母ではなく私に似ていた。
空の色が変わった。女は後ろ向きになったと思うと、あたふたと、私の目の前を降りていく。最後はすうっと空気の中に溶け込んでいった。
空の色は薄い青になり、細い雲がたなびいている。いわし雲だ。眼下では黄や赤の葉に覆われた木々の海である。東北の秋の一番きれいな景色だ。少し寒いような風が頬に当たる。遠い山々がかすんでいる。日本海の色も銀色がかってきたようだ。岩に風が当たると、ひゅうっといった音がする。
頭の上に何かが触れた。振り返ってみると、脇の岩の間から一本のススキが生えていた。風に吹かれて、ふらっとお辞儀をすると、私の耳の脇にまで穂先が触れる。穂先が触れると子宮の先がジーンと熱くなった。
もう、二十年も前になるだろう。生涯で唯一私に触れた男性がいる。若い女性の登山家として私の名が世に出始めた頃である。彼はその頃すでに良く知られた登山家であった。練習を兼ねたアルプスへの登山を、彼をリーダーとしておこなった。その時、私は危ないところで命を落とすところだった。ハーケンへのザイルの結びがゆるかったのだ。私は岩場から落ちた。そのままでは明らかに死んでいただろう。下にいた彼も巻き添えにした。だが、彼の腕の力は私を支え、自分の命も守ったのである。
無事ふもとに下りたとき。私は自分の未熟さを知り、山への執着を捨て、彼の裏方に生涯をささげようと思った。私はぎごちなくも私からそれを申し出た。彼がどういう気持ちであったか今でも私には分からないが彼もそれを受け入れてくれた。
その後、仕事のこともあり日本に帰ってからはなかなか彼と会う機会がなかった。半年も経って、彼が再び登山隊の隊長としてヨーロッパにいく前日、二人だけの時間をもつことができた。彼がごつい指を私の耳の脇に繊細にはわせたとき、私はそれだけで気が遠くになった。しかし、彼はその遠征で雪崩に巻き込まれて死んだ。それ以後、私に触れる男は誰もいなかった、というより、私が拒絶した。
目の前に広がる秋の空から、雪が舞ってきた。ススキの穂に雪が積もり始めた。私の周りにも柔らかな真っ白な雪がふきかかった。
カタカタと音がした。下を見ると、また赤いスーツの女が眼下の岩場をふしだらけの手で登ってきた。右手を上に伸ばし指を岩にかけ伸び上がる。髪の毛が白くなっている。今度は左手を伸ばし、岩を捉え、ぐーんと上半身を伸ばした。首が伸びて顔だけ私の目の前に来た。顔にはしわがより、大きな一重の赤い目が私を見た。女は私の目の前で四つんばいになると、赤い口紅の引かれた唇を閉じたまま、赤い舌を伸ばした。舌先は器用にススキの穂についている雪をなめとった。
女が笑った。うまい、と言った。最初に降った雪はうまいねとも言った。
女は私を見た。私の心臓がカタカタと変わったうち方をした。女ははいつくばって、土や岩の上の雪をなめた。女の口の周りには土が付いてつぶつぶの唇になった。
あたりの木々の葉が枯葉色になり、はらはらと落ちると眼下に舞っていった。あっという間に冬の雪空に変わった。私の周りに雪が降ってくる。女は私の後ろからのしかかってきた。私の髪の毛に積もり始めた雪を赤い舌でなめとっていく。
私の前までやってきた女はすっくと立った。思っていたより背が高く痩せている。細い目の脇のしわが動いた。女が笑ったのだ。女は私の眉毛に付いた雪をなめた。鼻に積もった雪もなめた。女は私を見た。赤い唇を私の唇に押し付けると、赤い長い舌を私の舌の上に重ねた。私の舌の上にふんわりとした雪の結晶が積み上げられた。女は着ているものをとると、素裸になってするっと私の口の中に入った。女は躊躇することなく喉の奥に進み、長い爪をした人差し指と親指で喉頭蓋をつまむと持ち上げ、喉頭に入った。やがて肺の中に雪が降り始め、胸が冷たくなっていった。
夢はまだ覚めない。
周りは雪景色に変わった。遠くに見える山の頂が真っ白に光って見える。
私の肺に入った女は雪でまわりを埋め尽くすと、肺静脈を通って心臓に入った。朱色に染まっている心臓に女が雪をふりかける。心臓の動きが鈍くなっていく。女は動脈を通ると、手の先や足の先を駆け巡った。私の指の先の細胞が雪で埋もれていく。
細胞の中の核の周りは蜘蛛の巣のように雪の結晶が連なり、核の回転が鈍り、やがて止まった。細胞が一つ一つと凍っていく。
女はまた心臓にもどり頭に行く動脈に入り込むと、ゆっくりと血液に乗って脳の中に入ってきた。女は真っ先に、側頭葉の奥に行くと、神経細胞を冷たい手でなで回した。神経細胞はぽ、ぽっと光ながら雪の中にうずもれていく。ふっとあったかい気持ちになった。不安がなくなった。凍りついたのは扁桃体と呼ばれるところだった。後頭葉に女の手がのびた。ぷちっとテレビを消すときの音がしたような気がした。そのとたん、鳥海山の目の前に広がっていた雄大な白い山並みが突然消えた。私の目は開いたまま雪で覆われている。音も消えたのだが、しんしんと振る雪の音はどこかで聞こえていた。痛みもなく、冷たさも感じない。それでもこのように夢を見ているのは、まだ脳の働きは雪の冷たさに耐えているのだろう。
女は脳幹にある神経細胞の長く伸びた突起に、そば粉を振りまくように雪をふりかけた。心臓や肺は完全に動きを止めた。ただ骨盤の上の子宮だけにぬくもりがあった。
私は子宮の中に逃げ込んだ。子宮には湖があった。鳥海湖のように澄んだきれいな水であった。私はその中に浸った。体温で暖められた温水であった。私は気持ちのよさに眠くなり、母の胎内にいた頃のように湖の中で丸くなった。
女が私に気がついた。
「やっぱりそこだったな、暖まりなされ、そこしかないのじゃ、最後に女がいくところさね」
女は丸まった私の前ですっくと立ち上がった。真っ白なかさかさなしわの深い肌、細く長い手足、たれた乳房、足元までも達しそうに伸びた陰毛。おかっぱ頭の老女は切れ長の赤い目で私を見た。女の細長い手が、私と母をつなぐ臍帯をもてあそんだ。女は羊水に雪を降らせた。だんだん冷えてくる周りの水に私のからだはますます硬く丸まっていった。女は胎児になった私にも雪を振り掛け、私は固く凍っていった。すべての細胞が凍りつき、柔軟性では誰にも負けなかった私のからだは塊となりひびが入った。
著名な女性アルピニスト、東北の冬山で遭難か、行方不明。一月も経つとこんな見出しで新聞が私の名を書きたてるだろう。私は決して日本の冬山を見くびったりしたわけではない。下調べを綿密に行い、誰も登らないルートで冬の鳥海山を楽しもうとしただけなのだが雪崩に巻き込まれた。岩のくぼみに運よく引っかかったのはよいが、両足を骨折して歩くこともできず、このように夢を見始めたのである。もう、私の脳も寒さに耐え切れないだろう。からだの中に入った雪女は、私の死を限りなく幸せなものにしてくれた。夢もそろそろ終わりだ、薄れていく。
ほとんど真っ黒な無意識に近い状態になったとき、いきなり脳の中に真っ白な玉があらわれ内側から私の顔を照らし出した。雪の塊のように真っ白な玉の中に、あの雪女がいた。その顔は私そのものであった。私は脳から這い出した。雪が裸の私のからだを覆った。そこには白装束の雪女がいた。日本の雪山で死をみとる雪の司として山と人を守る雪女はこのようにまた一人生まれでたのである。私の骸が岩の窪みにもたれかかっている。深い雪に埋もれている。万年雪になると私の骸は永い間見つかることはないだろう。
雪が吹雪く中、岩場でビバークしている男性がいる。もう意識がほとんどない。私は男性の目の前に浮かんだ。男性の目には若く色の白い日本の女性が、長い黒髪をたらし見つめているのが映っているのだろう。私は男性の唇の隙間から中に入った。男性の肺に雪を降らせ、心臓を冷やし、脳にいく。ここは日本ではない。私も登ったことのあるヨーロッパの高い崇高な山である。この男性はスイスのベテラン登山家である。私は日本の雪女が地球のどこにでも行くことを知った。
私の最後は子宮だった。男は最後にどこに逃げていくのだろう。これから時間をかけて見届けようと思う。
彼が幸せのうちに眠りにつくようにするのが私のつとめである。
女性アルピニスト
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


