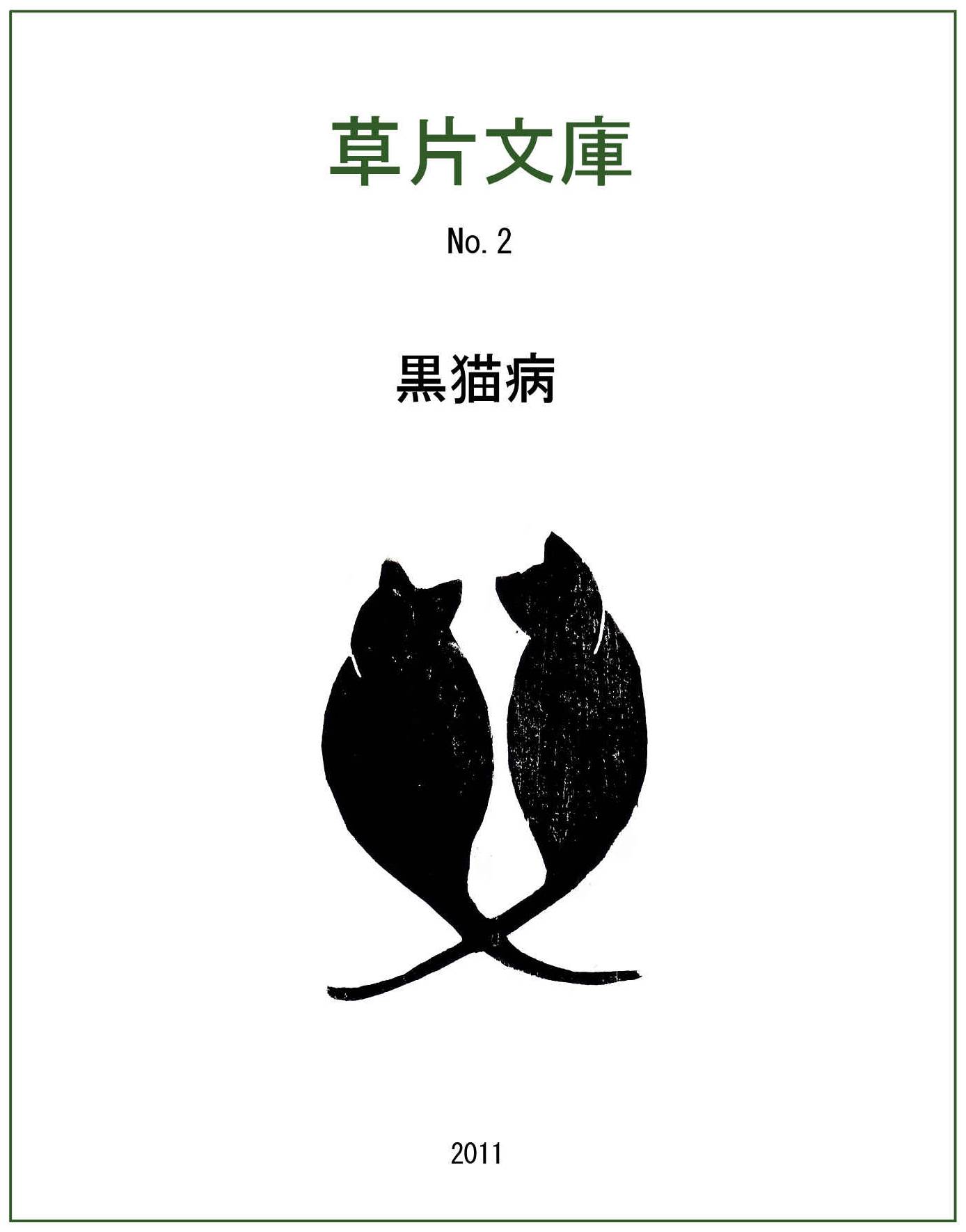
黒猫病
九十(くじゅう)朗(ろう)が口入屋から隣の村に使いを頼まれた帰り道のことである。
峠の道筋にある六角堂の前を通りかかり、ふと脇の生い茂った夏草の中を見やると、どこの者ともわからぬ骸(むくろ)が丸まって崩れ落ちている。髷はすでにくずれ、頭の一部は骨が見え、着古した袖からは茶色の皮膚がこびりついた指の骨がのぞいている。
侍であったことは着衣でわかる。
九十郎は立ち止まって骸をちらりと見た。
何があったか知らぬが、ほっとかれる屍も哀れである。しかし自分として何をしてやることもできぬ。
近づいてみると、草の中に汚れた脇差が落ちている。むしろこの古びた剣を生かすほうが供養になるであろうと手を伸ばす。
九十朗は刀を手にとった。鞘から中身をとりだすのに力が要るのは錆びが浮いている証拠である。
しかし抜き身にすると、薄茶けた刃の間から、なぜかしっとりとくる鉄の鈍い光が九十郎のみぞおちの辺りをぐーんと押した。
切りたい。
九十郎は思う。刀を手にとるといつも思う。切りたいと思う。汗が噴出した。
いかん、と思いながら、抜き身のまま、六角堂の前を早足で下り始めた。
途中、息が切れた。汗が滴り落ち、立ち止まった。辺りを見た。木に囲まれた山道である。気を静め、なんとか刃を鞘に収めた。
それまで誰一人として自分の脇を通ることのなかったことは幸いであった。
九十朗の偽らざる気持ちである。もし人がいたら殺めていたかもしれない。
息を整えると九十朗は再び歩き始めた。
日が翳ってきた。
里近くになり、道脇の崩れかかった古屋の屋根の上に黒いものがちらりと見えた。
きた、飛んできた。九十郎は拾った剣を抜いていた。
斜めに振り下ろした。
ぎゃという声ととも九十郎の右手がしびれた。
振り下ろされている剣。
切れていない。真っ黒な動物が反転して、赤いしぶきを上げて草むらの中に落ちた。
黒い紐が九十朗の網笠を打った。
落ちた黒い尾はうねうねとうねって道で跳ねた。
猫のほうが早かったのだ。
尾を失った黒い猫は真っ赤に染まった尻を見せ、一時振り返ったが、一心不乱に逃げていく。命拾いだ。
九十郎は汗でまみれた顔を袂でぬぐうと、赤くなった拾った剣を目の前にかざしてみる。光っていた。輝いていた。ついぞ今までは鈍い光を放っていた剣が赤い血の合間からギラリと光を反射し、九十朗の顔さえも映していた。
ふむ、なぜだ。
九十朗は剣をひと振りすると、袂から紙を取り出し、一拭きして鞘に収めた。
つぎに抜くときは人を殺めることになる。
自分の腰に差している脇差を道端に捨て、拾った刀を腰につけた。捨てたのは竹光であった。
汗をぬぐい町に向かって歩き出した。
しかし、ほどなく歩いたところで、ふっと立ち止まった。
九十朗は来た道をいくばくか引き返し、道の草むらに投げうった竹光を拾った。
腰の剣をはずし、元の通り竹光を差した。
左手に持った剣がずしっと重く感じるられる。
この剣を売ろう。
そう決めたのだ。自分には竹光が似合う。九十朗はそう思った。
住まいに戻った九十朗は刀を売りにいった。
「見事なものでございますな、お売りになってよろしいので」
店の主は念を押した。
九十朗の懐は暖かかった。
やはりあの剣は相当のものであったか。しばらくは毎日酒が飲めるほどの銭が手にはいった。
九十朗はあまり酒を飲むほうでもないが嫌いではなかった。久しぶりに酒屋へ寄ると一升ほど買い求めた。
徳利をつるし、魚屋で干した鰯を買い、長屋にもどった。
たった一間の狭い部屋には傘張り内職の道具が場所を占めていた。乾かしておいた傘をたたみ、板の間に胡坐をかくと茶碗に酒を満たした。
最初の一杯はやはり喉に沁みる。
あそこで朽ちていた侍はどこの誰であろうか。名のある者であったのであろう。売るときにあらためて見た脇差は汚れてはいたが、ちょっと拭き取ると黒塗りの中に抱き茗荷のみごとな紋が浮き出てきた。
ふむ、うまい。九十朗は誇りを捨てていた。
魚の匂いを嗅ぎつけた隣の三毛猫が入口の戸の隙間から入ってきた。遠慮のない雌猫である。九十朗は鰯を投げた。鰯をくわえた猫はあわてて外に飛び出した。
竹光を手に取って抜いた。ただの竹である。これが良い。わしには似合っている。
竹光をもつ前は幾人の首を撥ねただろう。
昔のことだが、九十朗はとある小藩に勤めていた。上からの達しとはいえ、自分には関わりがない者の命をたくさん頂戴してきた。ただ、信条は崩すことなく自分の義務を果たした。それは、相手が声を出す前に首を切り落とすことであった。苦痛はないはずだと九十朗は信じていた。いまだ命があることが不思議なほど他人の命をいただいたが、その信条がわが身を守ってくれていたためだとも信じている。その時に、名刀といわれる「黒密」を殿より頂だいした。
黒蜜は五郎入道正宗や粟田口吉光など名の知れた刀工の刀ではない。小さな藩ゆえ、そのような大それた刀があるはずはない。しかし、頂いた刀は殿が大事にされていたもので、正宗の師とも父ともいわれる國光がかくれて作った妖刀とされてはいたが銘はない。反りのない、まっすぐな、九十朗のような刀であった。
それにしても腕が落ちた。あの六角堂で拾った脇差は確かに錆びが浮いており、それが抜きを遅くしていたのはあるが、それにしてもあの速さなら首を落としていたはず。しかし、首が落ちず、尾が落ちた。黒猫が異様に早かったのか。
まあ、良い。黒猫の命は助かったのじゃ。酒もうまい。
まじめに遅くまで傘張りをする九十朗にしては珍しく、その日は早寝であった。
あくる日
九十朗は、口入屋に行った。
「昨日隣村から帰った」
「へえ、ありがとうござんした、始めてのお仕事でお疲れ様でございやした、あの村はどうでしたですか」
口入屋の三次は坊主頭を下げ、上目ずかいで九十朗を見た。
「貧乏な村だ、崩れそうな家が多かった、しかし、思うていたより広い村で、鳥使いの定とかいう男、探すのにちと苦労した、山際と聞いて道沿いかと思っておったが、沢沿いにかなり奥に入ったところであった、あの銃を渡すとき、あやつはわしを見なかった、何かたくらんでおるな」
「いえ、そんなことはありませんで、鳥を撃つくらいしか能のない男でございます」
「銃が買えそうな身分には思えなかったが、しかも、あの銃は新しいものであろう、わしも始めてみる形のものであった」
「九十郎様。詮索は無用で」
「そうじゃな」、九十朗は懐から定の受け取り状を三次に渡した。
三次は九十朗に手間賃の百文を渡した。
「だんな、もう一つ、頼まれてはいただけやせんでしょうか。旦那じゃなきゃできねえってもので、いかがで」
「人を切るのでなければよいが」
「滅相もござんせん、人を切るようなことはお願いしやせん。手紙とある物を隣村の庄屋の娘、染に届けるって仕事でございます、だだ親に見つからぬようにということで」
「また、隣村か」
「へえ、手間賃は結構よいので、一両の半分で」
「そりゃ豪勢じゃな、たったそれだけの仕事でか、恋文か、まさかなあ、じゃが、裏がありそうな」
「いえいえ、そんなに怖いものではありやしやせん、中身はあたしも知りませんが」
「うむ、引き受けてもよいが」
「九十朗様、お引き受けいただくには、誰に頼まれたか聞かんことです、中の物もご覧にならんように願います」
「それだけの金を出すのだからそうじゃろう、大きな屋敷か」
「さほど大きくはありやせん、おさんどんを除けば四、五人の若衆がいるだけだと思いやす、旦那は人が良いし、おかみさんもその辺のばあさんとかわりがないようで」
「そうか、娘は一人か」
「へえ、一人娘でさ」
「娘は外に出ることがあるのであろうか、顔がわからぬ」
「へい、あっしも娘のことは知りやせん、もしかすると、そこが難しいのかもしれませんで、器量よしとは聞こえておりやすが」
「いつまでじゃ」
「一日で終わらないかもしれやせん、急ぐことはないそうで、四、五日で渡せないときには、必ずお持ち帰りくださいとのこと、その時の手間賃は半分になりますが」
「うむ、わかった、それだけの金じゃ」
「本当に旦那じゃなきゃこの仕事はむずかしいかもしれやせん」
「そんなもんか、二、三日、野宿かもしれんな」
「へえ、峠に六角堂がありますが、あそこを根城にしてくださいまし」
しかし、九十朗は首を横に振った。
「あそこか、あそこはだめだ」
「なぜで」
「武士が死んでおった」
「お、そりゃ、いやなものをご覧になった、番屋にお届けで」
「いや、ほうってある」
「それじゃ、あっしが届けておきやしょう。
確かにあの六角堂じゃ村から少し離れておりますな、では、村の東に流れている淺川の橋の袂に漁師小屋がございやすが、そこなら今は空いております、ご自由にお使いくださってかまいやせん、一筆書いたものをお持ちいただき、見回りの者が万が一覗きましたらお見せくださいやし」
「知っておるのか」
「漁師のまとめ役の花蔵とは懇意にしておりやす、めったにいきませんが良い鮎が釣れます」
「村を良く知っておるな。それならこの役目、そちがやればよいものを」
「いや、少しは顔を知られておりまして。庄屋にも会ったことがありやす、花蔵と一緒に飲んだことがありますんで、娘は知りませんが」
「そうか」
「それでは、明後日行くとしたいが、それでもよいか」
「へい、もちろんで、お気をつけてお願いしやす、ものをお渡し願えれば、あと半分の手間賃をお渡ししやす、前の半分は今お渡しいたしやす、持って行っていただくものは朝には用意しておきやす」
三次は二分の銭を包んだ。
「あいわかった」
九十朗はもらったものを袂に入れると長屋にもどった。
昨日からよく金が入る。九十郎は不思議な気がした。
その日も傘張りはしなかった。
出かける日もよく晴れた。
九十朗は長持ちからいつもは使わない一張羅を取り出すと袖に手を通した。
旅支度を整えると作っておいた握り飯を持ち口入屋に寄った。
「これはまたお早いお出かけで、それに、めっぽう立派なお侍姿」
「今回の使いにはこのような姿のほうが良いような気がしてな」
「その通りかもしれやせん、感のいい九十郎様だ」
三次は奥から持って行くものを出してきた。細長い菓子折りのようなものが風呂敷に包んであった。
「手紙もこの中に入っておりやす」
三次は風呂敷包みを九十朗に渡した。
「壊れ物ではござんせん」
「うむ」
「よろしくお願いいたしやす」
九十郎は包みを抱えると、網笠をかぶり、隣村に足を向けた。
村につくまで半日はかかるだろう。
朝が早いのでまだ暑さを感じない。むしろ気持ちがよい。
町中を離れ、田の脇を一時も歩くと隣村への道の入り口に来た。ここから、いくつかの山を越え、いつぞやの峠を通ると、最後は村まで下りの一本道になる。
黒猫の尾を切り落とした集落に来た。いくつかの廃屋が点在している。あのときは道沿いの家の屋根から黒猫が飛びかかってきたのだ。
その時は考えなかったが、なぜ猫が拙者に向かって飛んできたのだろうか。このような寂れたところに猫がいるのも不思議である。
葺かれていた茅がほとんどなくなった崩れた屋根を見た。今日は何も居ない。
九十朗はゆっくりと歩いて行った。
空にうっすらと雲がかかってきた。暑さが少しだけ減った。歩きやすい。九十朗は竹筒の水を飲んだ。
黙々と歩く。やがて峠の六角堂に来た。侍の死骸はもう片付けてあった。
ここから村までは下りではあるが、まだ少し時がかかる。九十朗は六角堂の縁に腰を掛けると握り飯を食った。
ちらっと動物らしいものが脇を駆け抜けた。
イタチか、いや、この昼日中に出てくることはあるまい。
九十朗は三次に持たされた地図を見た。先だって訪れた場所とは反対の山際である。しかしさほど遠くない。
さて、と腰をあげ空を仰いだ。
空の高いところを鷹が獲物を足でつかんで飛んでいく。大きな動物だ、猫ににているが。
村の中に入った。暑いせいか村人は家からでていない。街道沿いに油屋などの店が居並ぶその村では、最も繁華なその通りですら誰もいなかった。店は開け放たれている。店先に並んでいる売り物は貧相なものである。盗人も入るまい。
全く人に出会うことはなかった。
田の脇の山際の道を歩いていくと、やがて遠くにぽつんと一軒家が見えてきた。北側に風除けの木が植えられ、きれいに手入れがされている。庄屋の家である。近づくにつれ、三次が言っていたのとはだいぶ違い、大きな屋敷であることが見てとれた。
九十朗は庄屋の家を通り越した。門から見た限りでは人の気配がない。百姓から相当絞り上げなければこのような家を作ることはできまい。三次の申していたことは本当のことだろうか。
まずは家の出入りを調べねば。
九十朗は通り過ぎると淺川に向かった。淺川はさほど大きくないが水がゆったりと流れ、川底のごつごつした石も透き通って見えるきれいな川である。流れの中に魚の陰が見える。鮎であろうか。
淺川にかかる橋を渡ると反対側の岸近くに開け放たれた小屋があった。これが、漁師の休憩所であろう。九十朗は中に入ると立てかけてあった筵を土間に引いてごろりと横になった。日が暮れるのをまとう。歩き続けてきた九十朗はすぐに眠くなった。
九十朗が目を覚ましたのは日が暮れてだいぶたってからである。よく寝てしまったようである。小屋の中は暗く、周りが薄っすらと見える程度である。
外に出ると、月明かりがあった。これならば、庄屋の家に行くこともたやすい。九十朗はいったん小屋に入り、持ってきた残りの握り飯をほおばると、荷物をもって、庄屋の家に向かった。
庄屋の家では一つの部屋に明かりが灯り、開け放たれた部屋の中が外からも良く見えた。それにしても人気が感じられない。
九十朗は足音を忍ばせ庭に入った。
庭の木の脇に忍び寄ったとき、明かりの灯った部屋に娘が一人入ってくると、なにやら部屋からもちだした。顔は良く見えなかったが、着ているものからすると預かり物を渡さなければならない庄屋の娘のようである。
少し様子を見ることにした。
それから半時、まったく人の気配がしない。そろそろ猟師小屋に戻るとするかと思った矢先、門の外からなにやら人の声がして、二人の提灯を持った若衆を前に、庄屋らしき男とその妻らしき女が屋敷に入ってきた。玄関には、先ほどの娘と思しき者と、一人の年取った女が出迎えに出てきた。
「では、明日もたのむぞ」
庄屋の声が聞こえる。
その一言で、二人の若衆は提灯を一つ持つと帰って行った。
ふむ、四人暮らしなのだろうか。九十朗は首をひねった。こんなに大きな家に、夫婦娘に手伝いの女一人というのは地味といえば地味である。庄屋の親もいないようだ。やはり三次の言った様な者たちなのだろうか。九十朗は庄屋の家を後にした。
小屋の羽目板の隙間から朝日がさしてきた。
九十朗はまだ暗いうちに起き、すでに身支度を終えていた。
そろそろよかろう、先に布をかぶせた竹光を腰に差すと小屋を出た。
道の脇の草に朝露が光っている。
庄屋の屋敷の前に来た。
庄屋の家は開け放たれており、かまどからは煙が立っている。
九十朗は旅人を装うことにした。
門をくぐり玄関先に立った。
「おたのみ申す」
九十朗の声は良く通った。
玄関が開き、きりりと鉢巻をした若衆が、「なにか」と、九十朗を見た。もう若い者が手伝いに来ている。
九十朗は傘をとった。
「拙者、旅をしてまいった者で隣の町にまでまいる。用意をしてきた米も使い果たし、このあたりには飯を食わせるところもなく、この家の前にきたところ、朝飯の支度をしているようであり、できれば少しお分け願えぬかと、あつかましくも門戸をたたいた次第、お足はあるがいかがであろう」
若衆は、居直ると、「わかりましたでございます。今主人にうかがってまいります」と奥に入って行った。
間もなく、庄屋とおぼしき男が顔をだし、
「お武家様、若い者からご事情をうかがいましたでございます。むさいところでよろしければ、お上がりくださって、朝げをお召し上がりください」
とんとんびょうしに話が進んだ。
「それは、かたじけなく、ありがたく頂戴したい」
九十朗は草鞋を脱いだ。
若衆は桶に水を張って九十朗の足元に置いた。
足を洗い、渡された布でぬぐうと、九十朗は脇差をはずして上に上がった。
案内された部屋に入ると、
「木兵衛と申します。まだ、米がたけておりませぬ、もう少しお待ちください。昨日遅くまで寄り合いがあり、今日は皆、起きたのがおそうございました」
庄屋が九十朗のあとを追うように部屋に入ってきた。庄屋は九十朗の前に座って手をついた。
三次の言うように確かに人は良さそうである。
「かたじけない。こちらこそ無作法にも突然門戸をたたき、あいすまんことでござる。拙者、九十朗と申す、頼まれ物を町にまで届ける役目でここを通った」、
嘘をついた。
そこへ、色の白い身の細い娘が茶を持ってきた。
「娘の染でございます、九十朗様じゃ」
「染にございます」お辞儀をしてかがんだ姿は優雅である。
三次の言うように器量は良い。
娘は少し首を傾げると、細面の顔を九十朗に向けた。長いまつげが動き、九十朗を見た。手を伸ばすと九十朗の前にゆったりと茶碗を置いた。
その時、
「庄屋さま」
奥のほうから庄屋を呼ぶ声が聞こえた。
「何じゃろう、大きな声で」
庄屋は立ち上がると、「ちょっと失礼をして、向こうを見てまいります、染ちょっと頼むよ」、と部屋を出ていった。
庄屋が戸を閉める間際に黒いものが飛び込んできた。黒猫である。
「おや、黒、だめじゃないの」
娘が、あわてて、黒猫を抱き上げると外に出そうとした。
「いや、染どの、かまわぬ、それより、ここにお座りいただけますかな」
染が九十朗の前に座ると、黒猫も染の脇に両足をそろえた。
こんなに都合よくいってよいものであろうか。
九十朗は、染に手紙と風呂式包みを差し出した。
「口入屋の三次に頼まれ申した。誰にも見られず渡すようとのことであった」
染は承知していたとみえ、手紙は胸にしまい、九十朗の目の前で包みを解いた。
細長い塗り箱が出てきた。染は箱の蓋をとった。
染は九十朗を見た。九十朗の目を見つめると、微笑が顔に浮かんだ。
開けた箱を九十郎の前につつーと押し返した。
九十朗は中を見た。
いかん、九十朗の右手が震えた。黒い朱塗りの懐刀だ。少し長めのつくりが立派なものである。
染が言った。
「このお刀、どうぞ手にとってごらんくださいまし」
染の声を聞く前に九十朗の手が自然と懐刀へ伸びていた。鞘から刃を抜いた。良い刀だ。目の前にかざした。きらりと光った刃は九十朗のみぞおちをぐーんと押した。
その時、黒猫が九十郎めがけて飛んだ。
九十朗は、懐刀を斜めに振り下ろした。切れていない。
黒猫の尾が切り離され飛んだ。まただ。
刃が赤く染まった。
九十朗の手があふれんばかりの血で、真っ赤に染まっていく。
なぜだ
九十朗は前を見た。染の首がころんと畳にころがった。
なんだ
いかん、血に染まった懐刀を捨てた。
懐刀は倒れている染のからだの脇に落ちた。
九十郎は自分の竹光をとると腰につけた。廊下にでると玄関に走り、はだしのまま庄屋の家を飛び出した。その後は走りに走った。
峠の六角堂までまっしぐらに走った。息が弾んだ、六角堂で立ち止まった。
懐から紙を出すと手を拭いた。
いったい自分は何をしたのだ。黒猫の尾を切った。染の首が落ちた。
額の汗をぬぐった。ふと見ると夏草の中に朽ちた侍の骸がまだあった。不思議だ。行くときにはなかったと思うが。場所を違えて見たのであろうか。
拙者の手は、なぜ、染を切ったのか。そんなはずはない。あの刀の長さでは膝三つとはいえ離れていた染の首が落ちるはずはない。
染どのが首を出したならばああなるが。
町にもどらねば。お尋ね者だ。
九十朗は気も虚ろで、町までの道を歩いた。
長屋につくと、自分の家に倒れこんだ。
夜遅く、疲れた顔をして九十朗はすでに閉っていた口入屋の戸を叩いた。
しばらくすると、明かりが灯り、がたがたと戸を開けて三次が起きてきた。
「やはり、九十朗様で、おいでになると思っておりやした」
九十朗を中に招き入れた。
「お帰りなさいやす、お見事なお仕事、残りの二分でございます」
三次は九十朗に金を包んで渡した。
九十朗は声が出なかった。
やっとしぼりだして、「お染どのを殺した」と一言。
「へい、存じてやす。お見事なあっという声も出ない間(ま)のお仕事」
「わしは、お尋ね者だ」
「いえ、ご心配要りませぬ。お染殿の懐中には自分で書かれた別れの手紙があり、明らかに自害、鳥追いの定は猟銃で自害、好きあっても結ばれることのない二人を、九十郎様が結んで差し上げたんでさ」
九十朗の目は、空(くう)を見ていた。二人ともわしがやったのか。
それからの九十朗の目は空を見ることが多くなった。
傘張の最中も九十郎は突然手を止めると、障子の隅を見つめて半時もそのままの姿でいることがあった。
九十朗はそこにきりっと立つ黒猫を見ていた。
黒猫はただ九十朗を見ているだけであった。尾はない。
染殿は自分から首をさしだしたのか。そうなのか。
時折、傘張り内職の元締め、寛治が尋ねてくる。傘が以前の半分も出来上がってないのを見て、からだの不調はないかと九十朗に尋ねるのだが、特に変わりはないと九十朗は答える。寛治は金に困らぬのだろうと気にもせず戻った。
九十朗は米と入用なものを買いにほんのときたまに外に出るだけとなった。
染のことがあってから三月経った。日が暮れるのが早くなり寒くなった。酒を飲む気になった九十朗は脇差を腰につけ、徳利を持つと外に出た。少し欠けた月が周りを照らしている。
長屋を出て横丁を曲がったときである。黒いものが塀の上から飛び掛ってきた。
九十朗は竹光を抜くと一気に振り下ろした。手ごたえはなかった。周りを見ても何もいない。徳利が落ちて割れた。
ふむ、気のせいか。
九十朗は竹光をしまい酒屋へむかった。
酒屋の親父が時々来る九十郎に笑顔を見せた。
「毎度ありがとうございます」
「徳利を割ってしまった、新しいものを都合してくれ」
「へえ」
徳利に酒をそそいでいる親父に、奥から黒い猫が出てくると擦りついた。
九十朗が少し身を引いた。
親父は酒が満たされた徳利を九十朗に渡した。
「近頃、野良猫が多くなったようで、とうとうこの黒がいついちまいまして、猫はお嫌いで」
少し身を引いていた九十朗は背を正すと袂から金をだした。
「いや、そのようなことはないのだが、とある猫に良く似ていたものでな」
「黒猫は皆似ていますなあ」
親父は笑った。
九十朗は徳利をぶら下げると店を出た。寒い。
長屋に帰り、家の戸を開けたとき、九十朗は徳利を落しそうになった。
黒猫が三匹、押入れの前に座っている。
九十朗は中に入り、土間の脇に徳利を置いた。黒猫は一斉に立ち上がって九十朗に飛び掛った。
九十朗は竹光を振り回した。手ごたえはなく、黒猫の姿は消えていた。
九十朗は酒をあおった。
そのころから九十朗は長屋の角や、店屋の前で、一人で竹光を抜き、空を切っていた。誰かを傷つけるわけでもなく、町の者たちは遠巻きに見るだけであった。
呉服屋の前で九十朗はいきなり竹光を抜いた。店の暖簾から顔を覗かせた店の娘が九十朗を見た。九十朗は竹光を収めると叫んだ。
「お染どの」
その声で、娘はあわてて店の中にもどった。
そんな様子を通りかかった良覚寺の住職、良菜が立ち止まって見ていた。
良菜和尚が九十朗に声をかけた。
「お武家殿、寺までいらっしゃらぬか、お話を聞かせていただけませんかな」
九十朗は空を見ている目をそのまま和尚に向けた。
九十朗は無言で頷くと、和尚の後についた。
寺は近くであった。
良菜は九十朗を本堂に案内すると向かい合って座った。
「お武家殿、どうなされました」
九十朗は顔をしかめながら、黒猫の尾をおとし、お染の首をおとし、鳥追いの定に自害のための猟銃を渡したことを話した。
さらに言った。
「和尚殿、それ以来、黒猫がたびたび私のところを訪れ、時には飛び掛ります。剣を抜くのですが、切れず、だが消えていきます」
「ふむ、黒猫が現れますか。黒猫病ですな」
「黒猫病と申すのか。私は病か、どうやったら直るのか」
九十朗の目は霞んでいたが、和尚を見ようとしていた。
「どこぞでもいい、ご自分で決めたところにまいられよ」
「何をしに参らねばならないのでしょうか、和尚」
「お武家殿の剣の腕に、黒猫どもが集まってくるのです。黒猫の目の届かぬところにまいられよ。そこで、静かに暮らされよ」
九十朗は頷いた。
「かたじけない」
諭された九十朗は長屋にもどった。
九十朗は旅の支度を始めた。旅のための金はまだあった。
大家のところにいった。
「九十朗様、どうなされたので」
突然来た九十朗に大家は心配顔で尋ねたが、九十朗はいつもとは違い、はっきりと、
「旅に出てまいる。世話になった、一年でもどるが、その時まで、部屋を空けておいてくれ」
そう言って、一年分の家賃を大家に渡した。
それを聞いて安堵した大家は、硯を取り出し受け取りをしたためた。
「それはたいそうなお旅で、どちらに行かれるのでございますか」
と尋ねた。
九十朗はそれには答えなかったが、
「半年で行き着くところである」
と言った。
大家は、
「それは遠くでございますな、気を付けて行っておいでくださいまし、病などにかかりませぬよう、つつがなくお戻りくださいまし」
戸口まで出て九十朗が長屋にもどるのを見送った。
九十朗はその足で、傘張り内職の元締めにも、口入屋にも旅に出る旨を伝えた。酒屋に行き一升をたのんだ。
「九十朗様、今日はお元気のご様子」
「いや、明日より旅に出る」
「そうでございますか、お仕事で」
「そのようなものであるが」
酒屋の親父は一升徳利にあふれんばかりに酒をついだ。
黒い猫だけは怯えるように九十朗を見た。
長屋にもどると、九十朗は襖をあけ、郡の中から古びた書付を取り出した。中を開くと「九十朗の黒蜜をあずかり候」としたためてある。書いたのはどうやら九十朗の知人らしい。九十朗はしばらくそれを眺めていたが、改めてたたむと小さな郡にしまった。
旅の支度が済むと酒を湯飲みについだ。
しばらくぶりに酒の味がした。
九十朗はゆっくりと飲んだ。
しばらくすると、部屋の隅にに三匹の黒い猫が姿を現した。
九十朗は湯飲み茶碗を床に置いた。
黒い猫たちは九十朗を見上げると、前に来てきりっと座った。
九十朗は黒い猫たちに顔を向けた。
「わしは、あの黒蜜を溶かすように古道(こどう)に言うつもりだ」
古道は刀を預けた九十朗の仲のよい友であった。九十朗は黒蜜を抜くと人を切りたくなることを古道につげ、預かってもらったのだ。その友も妖刀を預かるのは嫌がった。だから、友にもかかわらず預り証などというものを書いたのである。
黒い三匹の猫はじっと九十朗を見て顔を横に向けた。
九十朗は、
「黒蜜を溶かすだけではだめか」
と猫たちに問いただした。
黒猫たちは微動だにしなかった。
良菜和尚の言ったことが思い出された。
黒猫たちは九十朗の剣の腕に集まる。
刀ではなく、九十朗なのだ。
九十朗は頷いた。
その時、黒い猫たちは消えていた。
あくる日、九十朗は旅に出た。
一年、二年が過ぎた。
だが、いつまでたっても九十朗は戻ってこなかった。
六角堂の脇の生い茂った夏草の中に、どこの者ともわからぬ骸が、丸まって崩れ落ちている。髷はすでにくずれ、頭の一部は骨が見え、着古した袖からは茶色の皮膚がこびりついた指の骨がのぞいている。そばには錆びることのない剣が落ちていた。
黒猫がじーっと骸を見つめていた。
黒猫病
私家版幻視小説集「黒い猫、2015、330p、一粒書房」所収
木版画:著者


