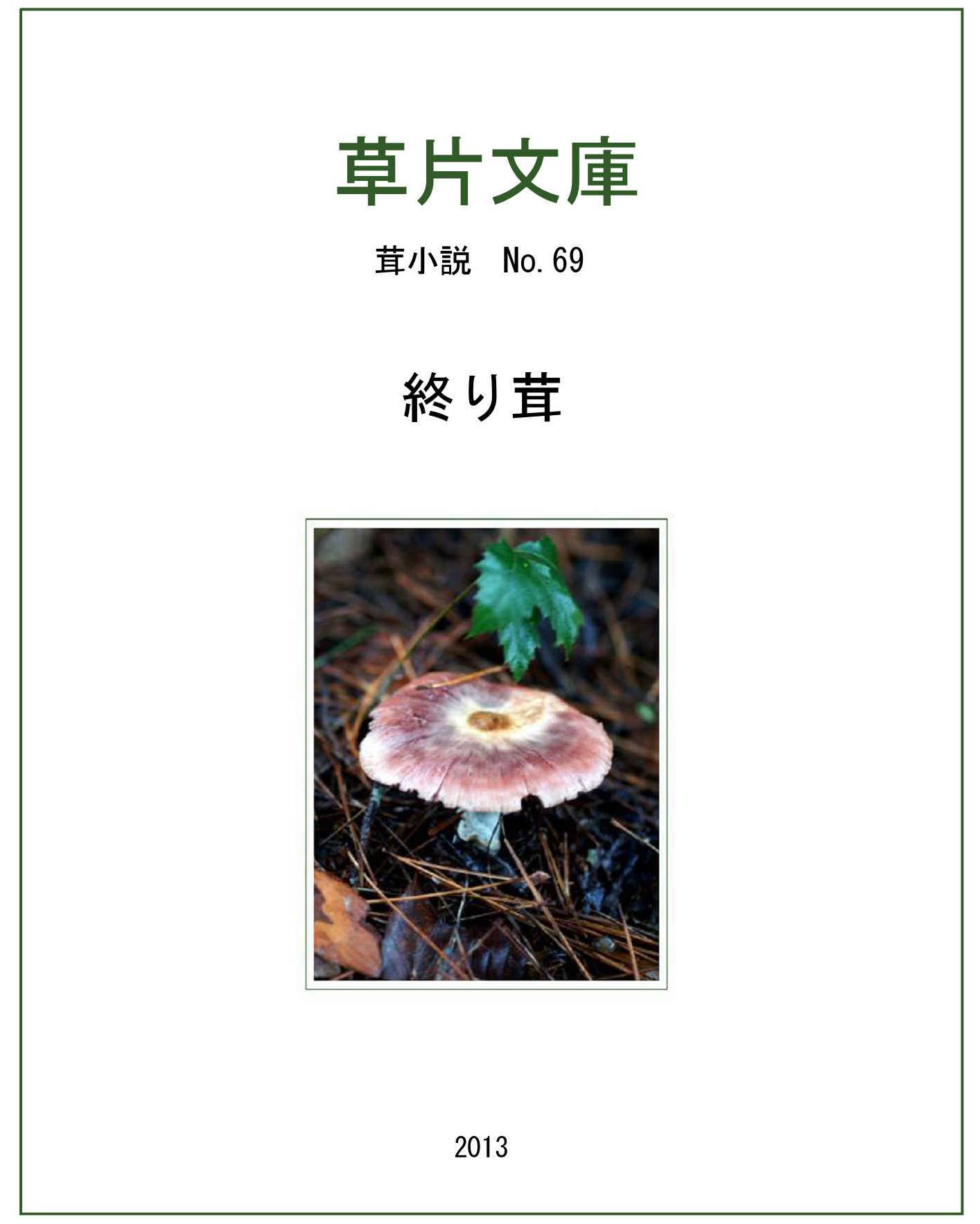
終り茸
山の麓に大きな森が広がっている。森の片隅にそれはきれいな池があった。水は澄み、なま温くもなく、冷たすぎることもなく、いつもさらさらと池底の砂から湧き出て、池の隅から地の中に吸い込まれていく。
池には白い鯰や白い山椒魚、色々なものたちが程々に仲良く暮らしていた。
今、白山椒魚は温泉治療に行っている、そこに白い蝦蟇(がま)蛙がやってきてすまいたいと申し出た。
きたばかりの白蝦蟇蛙は、古参の白鯰には頭があがらない。
「ほれ、あそこの茸を食べてみなされ」
白鯰に言われて、白蝦蟇蛙は、池から這い出た。
林の一角の草原に真っ赤な大きな茸がどしんと立っている。
白蝦蟇蛙は真っ赤な茸のところにのそのそと近づいていった。
赤い茸は傘の上の毒々しい疣を膨らませ、苦々しく白蝦蟇蛙がくるのを見ていた。
赤い茸のそばまできた白蝦蟇蛙はたずねた。
「おまえを食えと言われているが食ってよいか」
赤い大きな茸は苦々しく答えた。
「食いたいか」
「そうでもないが、鯰が食えと言う」
「なら食うな、ほんとに食いたい奴がきたら食わしてもやろうものを、おまえなんぞに食われとうないわい」
「そういわず食わしてくれ」
「いやじゃ」
そういわれた白蝦蟇蛙はすごすごと池に戻った。
池の水面から顔を出して、一部始終を見ていた白鯰は白蝦蟇蛙をしかった。
「なぜ食わなんじゃった」
「茸が食べられとうないと言った」
「なんと情けない、なぜ、がぶっと噛み付かん」
「毒かもしれん」
「おまえの毒の方がよっぽど強い、あんな茸にゃ負けるわけがない」
「そういうが、それなら、おまえが食えばいい」
「わしにゃあ、毒がない」
「地震を起こすことができるじゃないか」
「あれは、百年生きて、体にたまった毒をエネルギーとして捨てなきゃならないときにしかできない」
「いくつになりもうした」
「白寿じゃ」
「じゃ、来年地震を起こすのか」
「ああ、大きい奴をつくってやろう」
「それじゃ、来年、あの茸を食えばいい」
「いや、あいつは、今年百になった毒茸じゃ、地震の毒じゃ太刀打ちできない」
「それでなぜ俺には食えるというのじゃ」
「おまえは白蝦蟇だ。毒のエネルギーはすごいときく」
「いやだめじゃ、だが、なぜあの茸を食わなければいけないんだ」
「お主は知らぬとみえるな、もっとも向こうの池から移ってきたばかりだから仕方がないが、あの茸は、ほれ見てみろ」
赤い茸は黒い胞子をあたりにまき散らしている。少し離れたところに生えている周りの木々の葉がはらはらと青いまま落ちていく。とうとう、木々の葉はすべて落ちてしまった。
「あの茸は毒を周りにまき散らしているのだ」
葉をおとした木々は干からびて倒れてしまった。
「なんと、すごい毒だ、食いつかなくてよかった、俺もやられていた」
「たしかにそうかもしれんな、おまえがやられてしまうと、儂(わし)も後味が悪かった」
倒れた木々に、真っ赤な猿の腰掛けが生えはじめ木は見る見るうちに朽ちていく。
「恐ろしや」
「うーむ」
そこに真っ白な山椒魚が池に帰ってきた。
「ずいぶん長いこといなかったが、どこの温泉に行っていたのじゃ」
白鯰が聞いた。
「向こうの山にある温泉に浸かってきたのよ、だいぶ体がくたびれたからな」
「いい温泉か」
「うむ、身体の毒がかなり消えた」
「それはよかったのう」
「白い蝦蟇蛙殿がきたのか」
「おう、おまえが温泉に行っちまうと、すぐに、あちらの池からきたのじゃ」
「白鯰の爺が面倒なことを言ったのであろう」
「あの茸を喰えといわれた、新入りは必ずやらなきゃならんと言われた」
「いつもそうじゃ、そんなのは白鯰が勝手に決めたことよ」
「だまらっしゃい、誰かがあの茸を退治しなきゃ、この森は死んじまう」
「おまえはなにもしないじゃないか、俺が代わりに食らいついて傘のところを少しかじったら、白い体に真っ赤な疣(いぼ)が沢山できて、かゆくて大変じゃった。それで温泉に浸かってきたのじゃないか」
「わしゃ、池からでられないから仕方がなかろう」
「それで、白蝦蟇蛙は茸を食いに行ったのか」
「行ったが、茸に断られた、食いたい奴には食わしてもいいと言った」
「食わなくてよかった、あいつを退治するには、ほかの手を考えるしかないのだよ」
「どうやればいいのですかな」
白蝦蟇蛙が白山椒魚にたずねた。
「温泉でいっしょになった白蝮(まむし)のじいさんは、あいつには色仕掛けがいいと言っていた」
「なんと、色仕掛けか」
「じゃが、茸に色仕掛けとはどのようなことぞ」
「うーん、やはり、化けねばのう」
「どうじゃ、白鯰のじいさん、何かに化けて水の中に引き込んだらどうだ」
「わしゃ、化けるのは苦手じゃ」
「珍しいものに化けて、水の中におびき寄せ、池に沈めてしまえ」
「池が毒でつかえなくなる」
「山の植物たちのために仕方があるまい」
「そうとして、なにに化ければいいのかのう」
「茸の気を引くものじゃ」
白蝦蟇蛙が言った。
「茸は蝿が好きじゃ」
白山椒魚は長い間茸を観察していた。百を越えた山椒魚は、赤い茸がかわいらしく林の中に顔を出したときから知っている。
「蠅とはまた、どうしてじゃ」
「茸の周りに金蠅がたむろしていることがある」
「あれは、世の中のことを金蝿に教わっているのだ、だから、あの茸は物事をよく知っている、一筋縄にはいかんな、金蝿に化けても誘うことはできん」
「どうじゃ、白鯰、人間の男に化けて水の中から、あの茸を誘ってみろ」
白山椒魚が提案した。
「そんなことで、茸がここまでやってくるだろうか、大体、赤い茸は女なのか」
「そんなことは知らん、やってみるまでよ、ほれ、形のいい男に化けて水の中から顔をだせ」
白鯰はしかたがないか、と呪文を唱えると、男に化けて水面に立った。
「どうじゃ、茸、こちらへこい」
赤い茸は化けた男を見ようともしない。
白山椒魚と白蝦蟇蛙は笑った。
「おまえ様は、なにに化けたのだ」
「人の男じゃ、有名な奴よ」
「そりゃ、聖徳太子といってな、確かに有名だが、男としてつまらん」
「では誰になればいい」
「はて、かっこいい男とな、うーむ、むずかしい、あの茸はなよなよが好きか、りゅうりゅうが好きか」
「なんじゃ、なよなよ、りゅうりゅうとは」
「光源氏か力道山」
「では最初に、光源氏」
そう言って白鯰は光源氏に化けた。
「おい、着物をつけていてはだめだ、脱げ」
「おお、そうか」
水の上には裸の光源氏が立ち上がった。すると、赤い茸の頭が揺れた。
「おう、赤い茸が答えておるぞ、これは上手くいく」
白鯰の光源氏は恥ずかしそうに、大きな目を赤い茸に向けた。赤い茸の周りに白い煙が立ち上った。煙が消えると、そこには絶世の美女が裸で現れた。
「おう」白山椒魚と白蝦蟇蛙は目を見張った。白鯰の光源氏の目がその美女にすいついた。
光源氏のかわいらしい逸物がそそり立ち始めた。
「あ」と白山椒魚と白蝦蟇蛙が声を上げたとき、光源氏が水の上を走り出して、茸の化けた美女に抱きついた。光源氏が美女に覆いかぶさると、美女の手が光源氏の背に回され、ぎゅっと抱きしめた。
「ぎゃー」大きな声がすると、光源氏は白鯰に戻り、赤い茸の下でのたうち回っている。
「陸じゃすぐ死んじまう、助けるぞ」
白蝦蟇蛙が飛び出した。
白山椒魚も飛び出した。
白蝦蟇蛙と白山椒魚は大きな白鯰を転がして池まで運び、水の中に落とした。
白鯰はぐったりはしていたが、なんとか息を吹き返した。
「おお恐ろしや、なんという茸だ、わしゃ自分のからだをどうしようもなかった、勝手に女に向かって走ったのじゃ」
「妖術使いの茸じゃな」
白蝦蟇蛙が言うと、白山椒魚が答えた。
「いやいや、人間のことをよく知っているのだ、女が男をどのように誘うか心得ている。儂等は人間の女のことをこれっぽちも知らんのだ、それなのにこのよう方策をとってしまったのは大きな過ちだ、まあ、鯰が助かってよかったわい」
一時休戦だ、鯰と蛙と山椒魚は水の底にもぐった。
あの茸を始末しない限り、この周りの木はみんな枯れてしまう。
「もう何十年も試みているが、いっこうに上手くいかないのはどうしてかのう」
「考えを改めねば」
「新しくきた白蝦蟇蛙の御仁は、我々の試みてきたことをどう思われる」
白蝦蟇蛙は答えた。
「うむ、そもそも、茸とは何ぞや」
「茸とは茸よ」
白鯰は大雑把である。
「なんだそれは、飯も食わぬ、植物とは違い光もいらん、ほかのものを腐らして生きておる」
白蝦蟇蛙はさらに言った。
「茸を知らねば倒せぬ、敵を知ることが相手の弱みを握ること」
「そうじゃ、蛙殿の言う通りじゃ」
「だが、どうやって、あの茸のことを知るのだ」
「茸と仲のよい金蝿を手(て)懐(なず)けようぞ」
「どうやったら金蝿をこちらに呼ぶことができようか」
「蠅は匂いに寄ってくる、きっと茸が臭い匂いを出しているのだ」
「我々には感じないがな」
「なにか、池の中に蝿の好きな匂いのもとはないか」
「死んだ白泥鰌はどうだ」
「白泥鰌が死んだのか」
「ああ、二日前に」
「あの白泥鰌が死ぬとはな」
「どうして死んだのだ」
「自殺と他殺じゃ」
「どうしてだ」
「この池に飽きたそうだ、あやつはまだ還暦だったのにな」
「どうやって自殺した」
「しゃべりすぎたのじゃ」
「誰になにをしゃべったのだ」
「あの赤い茸に、ありったけの雑言を浴びせた、さすがの茸ももっと赤くなって怒っておった、そうしたら、胞子をしゅーっと水面に顔を出していた白泥鰌にかけたんだ。それを吸い込んだ泥鰌が、もっと悪口を言い続けたら、とうとう、胞子を鰓に詰まらせて死んでしまった。だから、他殺でもある」
「そうか、それならば、茸をやっつけるために死体をさらけ出しても恨むまい」
白鯰が白泥鰌の死体を池の底から水面に持ち上げ、白山椒魚と白蝦蟇蛙が池の辺に引っ張りあげた。
彼らは水の中から死体を眺めていた。
肉がふやけ腐り始めると匂いがただよってきた。
にもかかわらず、金蝿たちは赤い茸にまとわりついているが飛んでこようとしない。
白泥鰌の肉が腐り落ちてしまっても、いっこうに金蝿は寄ってこない。とうとう、白泥鰌は骨だけになり、その骨もさらされ匂いがなくなった。
「なぜ金蝿は寄ってこないんじゃ」
白鯰は首をひねった。
ある日、白泥鰌の骨に真っ白な金蝿がとまった。
白蝦蟇蛙が顔を出した。
白金蝿は食われるのではないかと身構えた。
「もし、白金蝿どの、ちと話がある」
白蝦蟇蛙が言うと骨から白金蝿は飛び上がった。
「いかないでくだされ、決して貴殿を喰らおうとか、傷つけようとかいうのではない、教えてほしいことがある」
白鯰と白山椒魚も顔を出した。
それを聞いた白金蝿は、まだ疑い深げに、それでももう一度泥鰌の骨に舞い降りた。
「何をだ」
「実はわれわれ、あそこの赤い茸には大変困っておる、木々が枯れてしまうのでな、何とか退治したいと思っておるが、我々は茸のことを全く知らぬ、教えてほしい、金蝿たちに教えてもらおうと思うたが、まったく近寄ってこない」
「そりゃそうだ、金蝿たちは赤い色が大好きだからな」
「なんと、匂いではないのか」
「ああ、それと、おまえさん方のほうが、あの赤い茸と仲がよいのかと思っていたが違うのか」
「どうしてそんなことを言うのだ、全く違う、この白泥鰌も半分茸に殺された」
「儂も体中に疣ができて大変だった」
白金蝿が言った。
「おまえさん方、泥鰌の死体をなぜここに置いた」
「金蝿たちがくると思ったからだ」
「茸のからだが何処にあるか知らんようだな。この土の中にあるのだぞ、おそらくあの茸のからだは池を取り囲むほどでかいものだろう。いずれ山全体に広がる。茸は土の中に菌糸という白い糸の網を広げている。それが茸のからだで命だ。茸がなくなっても、菌糸からまた出てくる」
白鯰と白蝦蟇蛙と白山椒魚はぎょっとした。
「おまえさんたちは、ここに白泥鰌の死体をおいて、肉汁を土に浸み込ませた。それは茸の栄養になる、だから餌を撒いたようなものだ、それで仲がよいと思ったのだ」
三匹は顔を見合わせた。
「儂らはあほなことをしたもんだ、それで菌糸を殺すにはどうすればよいのかな」
「俺は知らん、どこかで知ったら教えにきてやる」
「ありがたい、よろしくたのみますじゃ」
白金蝿は飛んでいった。
それから一年が過ぎた春のある日、蠅が池の水面を飛び回っているのに、腹の減った白蝦蟇蛙が気がついた。白蝦蟇蛙は金蝿なら飛びかかろうと、池からそっと目玉を出した。ところが、そいつはいつぞやの白金蝿である。
「お、白金蠅殿、久しぶりじゃ、菌糸をなんとかできますかな」
白山椒魚と白鯰も水面に顔を出して尋ねた。
白金蝿は顔を横に振ってこう答えた。
「あやつの菌糸を絶やすのはなみ大抵のことではできない、ただ、茸を食う虫がいると茸蝿が教えてくれた。普通の奴らでは無理だが、白茸虫なら赤い茸を食らっても大丈夫だということだ、土の中の赤い茸のからだは退治できぬが、一度茸を退治すれば、よほど条件がよくないともう茸はつくれないだろうということだった。」
「ほう、それで、白い茸虫はどこにおじゃるかな」
「うむ、百年に一匹生まれる白い茸虫を探すのは容易ではない、茸がたくさん生えているところに行って、出会いを待つしかないだろうな」
「いや、白金蝿殿、貴重な情報をありがとうございましたな」
「なんの、俺は赤い茸に群がっている金蝿たちが嫌いでな、追い払いたいんじゃ」
そう言うと白金蝿は飛んでいった。
「白茸虫を探すのは大変そうじゃな」
「なんとしても探さざるをえまい、もう一度儂が旅に出よう」
白山椒魚が岸辺に這い上がった。
「儂は、長いこと温泉場に行っておった、そこにはたくさん茸も生えておったし、温泉には物知りの白い大蛇がおった、その老人に聞いてみるのも良かろう」
「お主がたよりだ、是非頼む」
白鯰と白蝦蟇蛙が水面から顔をもたげて見送った。
温泉場にやってきた白山椒魚が、白大蛇の老人と話をしている。
「白い茸虫とな」
「どこぞで探せばよいかの」
「ついこの間まで、腰を痛めたといって、温泉に浸かっておったぞ」
「おお、そうか、それで今はいずこかな」
「たしか、住まいは東の方の山だったと思うが、しかとは知らぬ」
「行ってみようかの」
「よせよせ東の山といってもいろいろある、大変なことだ、ここで待つのも一つだ、腰の持病があると言っておったから、またここに来るやもしれん、いや来ると思うぞ」
「そうかその方が楽だし、たしかかもしれませんな」
こうして、白山椒魚は再び、毎日毎日、温泉に浸かる日々を送った。
「いい湯だが、白茸虫はなかなかこんな」
「うん、そればかりはわからんな」
「ずーっとこなかったらどうするか考えておる」
「あわてるな、くるまでずーっと湯に浸かって楽しんでおれ」
「そうだな」
白山椒魚と白大蛇は毎日湯に浸かって、同じ会話を繰り返していた。
そうやって一年が過ぎた。
そして、とうとう白茸虫がやってきた。
「お、白大蛇のじいさん、おや、白山椒魚のじいさんもいるのか」
「のお、白茸虫の親方、腰の具合はどうだい」
「痛くての」
「湯にゆっくり浸かりなよ」
「そうするよ」
白茸虫が湯に浸かった。
早速、白山椒魚がたずねた。
「ちと聞くが」
「なにかな」
「茸を退治したくての、森の木を倒してしまう茸じゃ」
「ふーむ、茸はこわいぞ、土の中は茸のからだでいっぱいじゃ」
「我々の住んでいる池のほとりに真っ赤な大きな茸が生えておってな、それを退治したいのだ」
「もしかすると、鬼紅天狗茸じゃなかろうか」
「そういう名前かもしれん」
「そうだとすると、そいつは相当大変な茸だ、ただ、俺の腰にはよく効く薬になる」
「それはいい、是非食べてくれまいか」
「だめといわれても俺は行くぜ」
そこへ、真っ白の鬼蜻蜒(やんま)が飛んできた。
「なかなかいい湯のようだな」
「わしゃ、もう二年も浸かって、白茸虫の御仁がくるのを待っておった」
白山椒魚が答えた。
「そりゃ、豪勢な、そんなにいい湯か」
「儂なんか、ここに棲んでいる」
白大蛇が答えた。
「それじゃ、俺も入ろう」
白鬼蜻蜒は湯に浸かると、飛んできた金蝿をぱくりと食った。
「おまえさん金蝿が好きかの」
「おーさ、大好物だ」
「金蝿が集まるところがあるが、行く気がないか」
「行ってもいいが、せっかくいい湯にきたんだ、少しは浸かっていたいものだ」
白茸虫もうなずいた。
「おいらも少し浸かっていきたい」
こうして、わいわいと、湯に浸かって瞬く間にまた一年が過ぎ、やっと腰を上げた。
「さて、行こう」
白山椒魚が誘うと、「儂も行ってみたい」と白大蛇もついてきた。
白山椒魚は三匹をつれて池に戻った。
「なんと」
白山椒魚は驚いた。池の周りに何十本もの赤い茸が生えていた。
白山椒魚たちは赤い茸をよけながら草地を這って、何とか池にたどりついた。
「長い間、どこにいたんじゃ、赤い茸がにょきにょき増えてあせっておったぞ」
足音を聞いて白鯰が顔をだした。
「おおよ、この白茸虫の御仁と、白鬼蜻蜒に白大蛇のみなさんと、お湯に浸かって、茸をやっつける算段を練ってたのよ」
「よろしう頼みますわ」
白蝦蟇蛙も顔を出した。
「なーに、あの茸は儂の腰痛にきくんだ、こちらこそありがたい」
「あっちもな、あのぶんぶん舞っている金蝿は大好物なんでな、嬉しい旅だったよ」
「俺も、なにかできるかな」
白蛇が言うと、白鯰はうなずいた。
「いやはやありがたい、白大蛇殿、どうであろう、池の周りの草地に穴をあけてはくれまいか」
「そりゃ、おやすいこと、ついでに中にいる蚯蚓(みみず)でもいただこう、だが、どうして土に穴をあけるのだ」
「白山椒魚がいない間に白金蝿がきてな、土の中のあの茸のからだ、すなわち菌糸と申すが、それを退治するには掘り返すのがよいとのことであったのだ」
「掘り返すと、菌糸がどうなるんじゃ」
「菌糸に日が当たると干からびるそうな」
「おお、そうか、そりゃやりがいがある」
「では、そろそろ始めるか」
白鯰はえいとばかりに光源氏に化けると水の上に浮かんだ。
赤い茸たちは、あざけるかのように、きれいなべべを着た女たちに化けた。
しかし、今度は、白茸虫が女たちを襲い、頭から食べだした。
白い鬼蜻蜒は飛び回る金蝿を片っぱしから喰っていく。
こうして赤い茸はとうとう、すべて食べられてしまった。
白大蛇が草地を掘り返し、白蝦蟇蛙もそれを手伝った。
白大蛇も白蝦蟇蛙も蚯蚓や虫をたらふく食った。
土は掘り返され、鬼赤天狗茸はとうとう消滅した。
やれやれと、池のほとりにみんな集まった。
「腰の痛みもとれちまったよ」
白茸虫が腰をさすった。
「とうとう、あの茸をやっつけましたな、これもみなのおかげ、これで、林も助かりましたわい」
「どうですな、温泉に浸かりに行きませんかな」
「それはいい、だが、儂は水から出られませんので、留守番じゃな」
白鯰はつまらなそうである。
「いや大丈夫じゃ」
そう言った大白蛇は尾を丸め、からだを巻いて、中に水をすくって入れた。
「どうじゃ、この中にお入りなされ」
「これはすごい、運んでくださるか」
「楽なものよ」
そういうことで、皆そろって、戦勝祝いの湯浴みに出かけた。
大きな岩場の露天風呂では、毎日のように湯に浸かって、ドンちゃん騒ぎ、あっという間に五年が過ぎた。
「そろそろ、池に帰りますかな」
白鯰は冷たい池の水が恋しくなったようである。
「そうですな、湯にはまた浸かりに来こようじゃないか」
白山椒魚と白蝦蟇蛙、それに白鯰は帰り支度をした。
「帰りも送ってくださるか」
白鯰が白大蛇に聞くと、
「おおよ、もちろん」
そう言って尾を丸めて湯を入れた。
「いいですな、帰りも湯に入りながらとは」
白蝦蟇蛙と白山椒魚はうらやましかった。
「それじゃ、大きなのをつくりますからな、そこにみなさんもお入りなされ」
白蛇は尾っぽで大きなプールをつくった。
三匹はそれに浸かると、
「それじゃ、よろしく頼みます」
白大蛇に言った。
「儂たちはもともとここの者、残りますが、また遊びに行きますぞ」
白茸虫と白鬼蜻蜒は湯に浸かったまま言った。
「鬼紅天狗茸を絶滅さしたのは皆さんのおかげ、感謝いたしまする」
というわけで、湯に浸かりながら、みんなは池に戻った。
池の周りは、若木が伸び始めていた。
池は変わらずきれいな水を静にたたえている。
白蛇は三匹を池にいれた。
「役目も終わったし、儂も帰るとするか」
「どうもかたじけない、何から何まで世話になった、また来てくだされ」
「みなさんも湯あみにおいでくだされ」
大白蛇は尾をふって戻って行った。
明くる日、久しぶりに冷たく澄んだ水の中で一晩過ごした白鯰と白蝦蟇蛙と白山椒魚は、気持ちよく目を覚ました。
水面で三匹は顔を見合わせた。
「温泉もいいが、この澄み切った清らかな冷たい水もいいものじゃな」
とうなずいた。
三匹は見るともなく、草原の端に目をやると、驚きの声を上げた。
「ありゃ何じゃ」
真っ青な大きな茸がでんと生えている。そこには金蝿がわんわん飛び回り、ときおり、真っ黒な煙を茸が吐き出している。
「あの茸はなんだ」
「鬼紅天狗茸がなくなったので、進入してきたのだ」
「青い茸など知らぬぞ」
「ないこともないが、このようなものは知らぬ」
青い茸から黒い煙が立ちこめると、周りの若木たちの葉が落ちてしまい、枝も枯れてしまった。そこに小さな猿の腰掛けが生え、木はみんな朽ちていく。
「恐ろしや、鬼紅天狗茸と同じように、林を枯らしてしまう茸だ」
「また、青茸と戦になるのか」
「この年になると、面倒だな」
「ほんとに」
「もう一度、白金蝿に青い茸のことを聞いてみるか」
その数日後、都合のよいことに、白金蝿が飛んできた。
「おや、三匹とも戻ったのか、戻らなければいいのに」
「なぜじゃ」
「あの青い茸は、終り茸と呼ばれていてな、なんにでもとり付いて、それを終わりにする茸なんだ、この山はもう終わりじゃ、みなさんも、どこぞ違うところに居をかまえなすったほうがいいんじゃないかね」
「そんなに怖い茸か」
「そうだ、あの茸にかかると、みんな死んでしまう、今吹き出している胞子を吸い込んだら最後じゃ」
見ている間に金蝿が落ちていった。
「青い茸は蠅にはよい匂いがしてな、俺もそれに引かれて来てしまった、そうしたらあそこに終り茸がある、逃げようと思ったら、お主らがいた」
「そうか、それはすまぬ、儂等は儂等で考える、早くお逃げなさい」
白鯰が言った。
「そうしよう、それじゃ気をつけてな」
白金蝿は森の出口のほうに勢いよく飛んで行った。
白鯰は他の二匹に言った。
「儂は、どうせこの池から出られん、お二人はまた温泉にでも行かれるとよい」
「そうはいかん、儂等も池を守るぞ、やりなおしてみようぞ」
白山椒魚と白蝦蟇蛙は白鯰に化けるように言った。
白鯰は若い美女になって水面に浮かんだ。
それを見た青い茸は、胞子を吐き出しながら、美男子に化けた。
青い茸が化けた美男子は我慢しきれないように、根本からちぎれ飛んで、鯰の化けた美女に抱きついた。鯰は美男子を水の中に引き入れた。白山椒魚と白蝦蟇蛙も齧りついて、水の底まで美男子を引きずりおろした。今度はうまくいったのだ。
池の底には洞穴があった。三匹は茸の化けた美少年をその穴に押し込め岩でふたをした。
美少年は穴の中で青い茸に戻り三匹に言った。
「出してくれ」
「おう、言うことを聞けばだしてやる」
「なんでもいい、かなえてやる」
「おまえさんは終り茸、世の中のあらゆることを終わらせることができるのだな」
「おおせのとおり」
「では、人間の世を終わらせることができるか」
「できないことはない」
「それじゃやってもらおうか」
「それをするには、時間がかかる、それでもよければやってやる」
「そうか、どれくらいかかる」
「数え切れないほどの年月がかかる、しかしかならずやる」
「時間がかかってもよい、必ず人間を始末しろ」
「判った、なぜ人間を始末するのだ」
「この池の水を奇麗に保つためだ」
「お前達も池の中に糞をしているではないか」
「たしかに、だが、糞は植物の栄養になる」
「人間もそういうかも知れぬ」
「儂等が気持ちよく住めればよいのだ、ともかく人間を始末せい」
「利己主義め、もう一つ条件がある」
「なんだ」
「お前たちが、この池からどこかに移ることだ」
「なぜだ」
「この池を奇麗に保つためだ。」
「口の減らない奴だ、わしらが移れば人間を始末するのだな」
三匹は頭を寄せてなにやら相談をした。
「どうじゃ、手を打とう、この池を明け渡すので、山の反対側に池と温泉をつくってくれまいか」
「よし、作ってやる」
三匹は岩をどけて、洞窟から青い茸を放した。
すると、青い茸は山と地に頼んで、山の反対側に小さいながらも温泉と池を作った
「さて、わしはどうやって温泉にいけばよいかな」白鯰が思案していると、青い茸は「大丈夫だ」そう言うと、竜巻をおこし、池の水ごと三匹を新しい池に移した。
温泉は小さいながら、なかなか眺めのよいところにあった。
それから三匹は新しい池にすんで、たまに温泉に入った。
年寄りの三匹がいなくなった池の中には、若い山椒魚や、オタマジャクシ、鯰の子供が元気に泳いでいた。
「やっと、あの年寄りたちをどけましたな」
大鬼紅天狗茸が池の周りに顔をだした。
青い終り茸が答えていた。
「終わらすのが私の役目、大鬼紅天狗茸殿もまたがんばってくだされ」
「わしら大鬼紅天狗茸は、増えすぎた木は野原にして、光を当てる。山は元気になる。またそこに林ができる。このように山を守る役目を持つのにあの動物たちはとんとわかってくれなかった」
「年とった動物はみなあんなものだ、自分のことしか考えず、みな自分が正しいと思う」
「ところで、終り茸殿、本当に人間の世を終わらせるのかな」
「はは、自然と亡びるものよ」
「そうだな」
青い終り茸と大鬼紅天狗茸は笑った。
終り茸
私家版第二茸小説集「茸女譚、2017、265p、一粒書房」所収
茸写真:著者 山梨県北杜市小淵沢 2013-9-16


