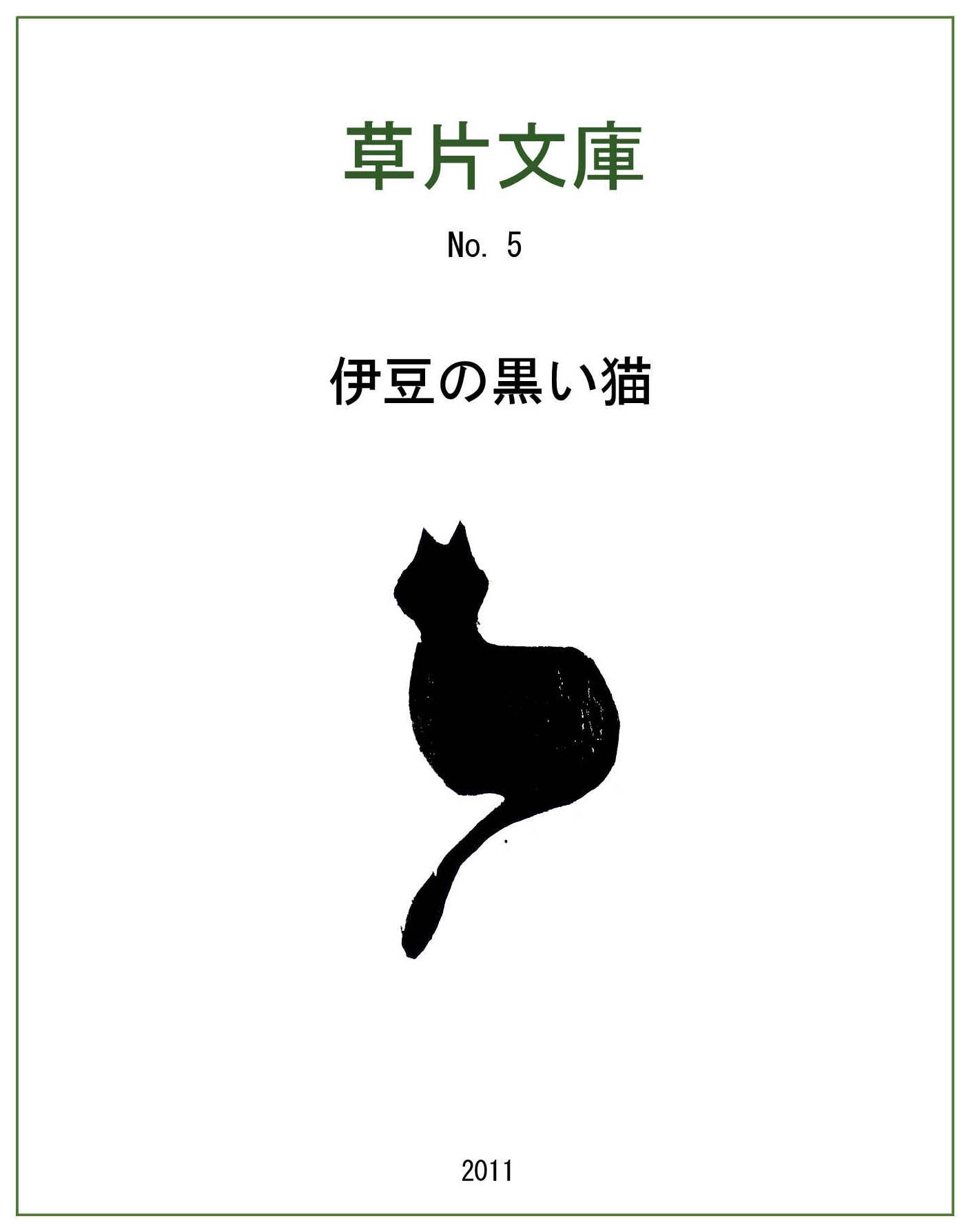
伊豆の黒い猫
鈴虫は伊豆網代の友人のアトリエに行くことになった。数年会う機会がなかった友人が夏の間パリに行くことになり、留守番をかねてこないかとの誘いが半月ほど前にあった。友人は最近名が売れ始めた日本画家である。緑色を基調とした抽象画が銀座の画廊の目に留まり、何回か個展を開くうちに、海外にも知られるようになってきた。
鈴虫の父親は銅板画家であった。鈴虫も美大時代から木版を始めたが、素人に毛がはえた程度のものとの思い込みから、個展を開くようなこともしていない。それでも、挿絵の依頼などがちらほらくることと、父親の残したもので暮らしていける程度の収入はあった。
父親は虫が好きで、虫の銅版画では日本の一人者であった。鈴虫という名は父親がつけたものである。父は八年前に惜しまれながら病気で逝った。母も後を追うようにしてその二年後に突然の動脈瘤破裂で死んでしまった。
ここのところあまり気乗りがしなくて版画にも手をつけていない。それならば友人のアトリエにいき、気分転換するのもいいだろう。アトリエを自由に使っていいといわれているが、版画の製作よりも、版画の題材を探しに行きたかった。だから、スケッチブックを持っていけば事足りる。
多摩動物園の裏手になる南平の丘の一番上にある父親のアトリエから日野の町の眺望は最高である。しかし、生まれたときから三五年もいると、感激もわかなくなっている。海を見て一月暮らすのは新鮮さをとりもどす良い機会でもある。友人は予備のアトリエの鍵をすでに送ってくれていた。
明日から八月という日、鈴虫は荷物をまとめると駅に向かった。南平の丘を下る途中に神社があり、冬場はそこから富士がよく見える。ただし、富士と同じような形の山が富士の真ん中を隠しているのがいつも残念であった。この山は大室山というらしいが、これから行く伊豆にも大室山がある。
京王線の高幡不動でモノレールに乗り換え、多摩センターで小田急に乗り、新百合ヶ丘経由で小田原に出た。東海道線に乗り換えると車窓に青い海が広がる。海の近くに住んだことがないので少しわくわくする。
海に突き出した山のかなり上のほうにまでたくさんの家が見える。ああいう家に住むと、急な道をずいぶん登らないといけないのだろう。南平の丘にある自分のアトリエどころではない。友人のアトリエも山の上にあると聞かされている。
鈴虫は熱海で東海道線を降り、伊東線に乗り換えた。熱海から伊東線で三駅いくと網代である。伊東線も海沿いを走る。海の景色に見とれている間に網代の駅についた。
駅の外に出ると、暑いが風が顔に当たる。こぢんまりとした駅前にタクシーが一台客まちをしている。駅舎は普通の家のつくりでかわいらしい。
網代は漁港でよく知られているが、駅前から海は見えない。駅前の網代温泉と書かれたアーケードからまっすぐに道がのびていて、お店屋さんが軒を連ねている。鈴虫はその道を歩いてみた。少し歩くと干物の店があった。きびなごの目刺しや、干した烏賊がきれいに並んでいる。きれい、おいしそう、鈴虫は立ち止まった。
そのまま歩いて行くと海にでるようである。友人のアトリエには歩いていけないこともないようだが、夏の午後の日差しを浴びて家を捜しながら坂を上るのはきつい。鈴虫はそこから駅にもどるとタクシーにのった。
手帳に書いた住所を見せると、ああ、あの家ねと運転手はすぐに車をだした。車は今もどったアーケードの道にはいり、海岸沿いの道にでると、右折して、港を過ぎ、海に突き出た山の上に向かった。海が眩しい。
「あの画家さんのお知り合いですか」
運転手がきいた。
「ええ、フランスに行っている間、私が借りたんです」
「ああ、やっぱり画家さんで」
「いえ、画家というほどではないのですけれど」
そんな話をしている間に、アトリエについてしまった。タクシーで五分ほどだが、かなり急な坂道をのぼってきた。歩くとかなりかかりそうだ。
必要なときには呼んでください。と運転手は会社のカードを渡してくれた。ここは乗物なしでは大変だろう。
彼のアトリエは、高台の海に突き出たところにあるずいぶんしゃれた建物であった。クリーム色の南京じたみの木壁に、濃い赤茶色の瓦がのっている屋根、イタリア風かフランス風か、どちらとも言えるし言えないような建物だ。
入り口の大きな木のドアの脇に、西洋風の家には似つかわしくない、これまた大きな信楽焼きのたぬきが一升徳利をつるしてでんと鎮座している。
鈴虫が近づくと、たぬきの置物の陰から白っぽい猫が二匹走り出し、庭のほうに飛んでいってしまった。
友人が猫を飼っているとは聞いていないので野良であろう。漁港に野良猫はつき物である。
鍵を開けて入ると、いきなり三十畳ほどもある広いアトリエであった。何も掛かっていないイーゼルが大小三つほど白い漆喰の壁際に置いてある。友人のオープンな性格がそのまま出ている。庭に面したところは大きなガラスのはまった引き戸になっており、海が見渡せる。
隣にもう一つ部屋があるようだ。扉を開けてみた。倉庫だった。友人の絵が展覧会から戻ったままの形でしまってあった。絵の道具や踏み台、シャベルまで置いてある。
二階に上がると、海を見ることのできる広いダイニングキッチンがあり、テラスが張り出している。風呂場からも海が見えた。反対側に寝室と書斎がある。みなゆったりとしたつくりで、これから一月気持ちよくすごせそうだ。
ダイニングキッチンにある大きな冷蔵庫を開けてみた。一月分はもちそうなチーズやハムや、ビールやらがぎっしり詰まっていた。友人の心遣いだ。昔からそういうところがある。
電話が鳴った。ダイニングキッチンの入口脇に電話があることに気がついた鈴虫は受話器をとった。
「おいでになっとりましたか、私、お手伝いするように言われてます、倉谷アサといいます。これから伺いますが、よろしいでしょうか」
友人はお手伝いの人が二日に一度は来ているので不自由していないと言っていた。その人だろう。私のいる間も頼んでおいてくれたようだ。
鈴虫は、「はい、よろしくお願いします」、と返事をして受話器を置いた。
電話のところには近所の電話番号の書いてある紙が置いてあった。出前をしてくれるところが書かれている。特に、新鮮な魚を届けてくれる漁港の卸の店には赤丸がつけてあった。漁りたての魚をさばいて届けてくれると友人は電話で言っていた。
そうこうしているうちに玄関の呼び鈴が鳴った。
階下に降りてドアのチェーンをはずすと、戸が開いて恰幅のいい女性が入ってきた。
「倉谷アサと申します。家の中のことをお教えするように言い付かっております」おじぎをすると、
「これは、今日取れた金目の刺身です。夜、召上がってください」
彼女はさっさと二階に上がって冷蔵庫に入れた。
「それに、天城のほうでつくっている山葵も持ってきておきました。摺るものはその引き出しにはいっていますので」
後について上ってきた鈴虫に食器棚を指差した。
アサは、言葉少なではあるが要領よく家の中のことを教えてくれた。友人はあまりしゃべるほうではない。だからアサも余計なことは言わないようにしていると言った。
「とても、シャイな人ですね、でも優しくていい方です」
友人をほめた。
風呂場は露天ではないが、バスタブは石でできており、温泉の掛け流しだそうだ。
アサは料理の材料なども頼めば買ってきてくれるということだった。子どもはもう家から離れ、漁港に勤める主人との二人暮らしで、時間をもてあましているから何でもする、遠慮するなと、頼もしいことを言ってくれた。しかも、友人は一月分の給料も前払いして行ったとのことだった。
「一階とキッチンの掃除は私がします。絵を描きになるとお聞きしておりますで、どうぞ家の中は任せてください、私の家の電話番号はそこの電話帳にあると思いますで、いつでも連絡してください」、と電話のところを指差した。
その日はそれだけで帰ると言い、鈴虫が玄関先まで見送ると、アサはずいぶんしゃれた緑色のスクーターにまたがって、それでは、と一度振り返ると、勢い良く走り去った。
鈴虫はよいスタートだったと幸せな気分になった。といって、版画の絵が描けるような気分にはまだなっていない。
自分の荷物を寝室にいれると、一階のアトリエに降りた。私にはこんな広いアトリエはいらないなあと感じながら部屋を見渡した。
庭に出てみた。遠く海の果てを見ることができる。船が何艘か沖合に見える。夕方になっても夏の日差しはまだ暑い。
庭に何本か木が植わっているが名前はわからない。端にある椿ぐらいはわかった。大きな椿の木である。庭は特に管理はしていないようでクローバーが覆っていた。蛇イチゴが赤い実をつけて、ところどころに彩を添えている。
白い猫が家の脇から現れた。鈴虫に気がついて立ち止まると、顔を鈴虫のほうに向けた。左右の目が金と銀と異なっている。昨日玄関にいた猫の一匹だろうか。
鈴虫がおいでおいでをしたが、悠然と庭を横切ると海の方に消えてしまった。
どこに行ったのかと、庭先にすすむと、アトリエが断崖絶壁に建っていることがわかった。下は海である。めまいがしそうだ。手すりがなかったらそのまま落ちてしまう。白い猫はと見ると、切り立った岩場を上手に歩いてアトリエの隣の林のほうに歩いていく。しかし振り返った猫の両目が青である。さっきの猫とは違うようだ。その猫もあっという間に視界から消えた。
鈴虫はしばらく海をながめアトリエにもどった。
二階に上がると掛け流しの風呂に入り、海の白波をぼんやり眺めた。夜は金目の刺身でビールを飲んで朝まで何も気がつかずにぐっすりと寝た。
朝、きらきら光る海が遠くに見えた。朝食をとり、アトリエに降りると、庭の椿の下に白い猫がいた。昨日食べ切れなかった金目の刺身がふた切れほど残っているのを思い出した鈴虫は二階にとりに行った。
もどってきて庭を見ると、椿の下では白い猫が二匹になっていた。刺身を持って、猫に近寄った。鈴虫は刺身を差し出した。二匹の猫は全く逃げようともせず、刺身にも興味を示さなかった。鈴虫は刺身を下におくと青い目の白い猫の頭をなでた。白い猫は一瞬目を瞑ったが、また大きく目を見開いて鈴虫を見た。
もう一匹の頭もなでた。その白い猫の目は黄色だった。二匹の白い猫たちが首を同じ方向に動かした。鈴虫がそちらを見ると、アトリエの脇から、白い猫がもう一匹、こちらに歩いてくるところだった。白い猫はゆっくり近寄ってくると、刺身にはめもくれずに鈴虫の前にいた白猫たちの真ん中に座った。この猫の目の色が金と銀だった。
鈴虫はその猫の頭もなでた。三匹は声も上げず、嬉しそうな顔をするわけでもなく、じーっとしていた。三匹とも毛並みがよく真っ白である。兄弟なのだろうか、どの猫も鈴虫の目を見つめていた。
鈴虫は写真機をとりに戻った。もどってくると三匹の猫はまだそこにいた。何枚もの写真を撮った。鈴虫がアトリエに入ってもガラス戸ごしに猫たちがいるのがみえた。二階に上がってベランダから庭を見るともういなくなっていた。
その日、スケッチブックを抱えて、網代の町を歩いてみた。アトリエから歩いて十分も下ると網代湾に行く。こぢんまりとした漁港で、第三種網代漁港の看板がたっている。地震、津波、すぐ高台に避難の看板がある。そういえば伊豆も地震の多いところだ。
湾の周りを歩いてみた。防波堤に釣り人たちの姿がある。黒っぽい網がたくさん干してある。ここは定置網漁がさかんだという。
網がもこもこと動いた。そこから白い猫が顔を出した。鈴虫を見るとあわてて網の中にもぐりこんだ。アトリエにいた白い猫たちより一回り小さい。網の中が住処なのだろうか。この熱いのにそんなことはないだろう。遊び場にしていたのかもしれない。見ていたがもう出てこなかった。どこにいったのだろう。それにしても白い猫の多い町だ。
鈴虫がアトリエに来てから一週間が経った。その間、鈴虫はスケッチブックを持って、ただぶらぶらと町を歩いただけであった。版画のいい題材はみつからなかったが、いろいろな猫たちに出会った。スケッチブックには漁の網と猫がたくさん描かれた。
昼過ぎにアトリエに戻ると、庭の椿の下に必ず二匹か三匹の真っ白な猫が行儀よく座ってアトリエのほうを見ていた。
椿の下は涼しいのだろうか。どこに住む猫だかわからないが、特に餌をねだるわけでもない。白猫を版画の題材にすることもできると思いスケッチもした。しかし鈴虫の頭の中ではなかなか版画にまで発酵してくれなかった。
網代に来て八日目、鈴虫は他の町に行ってみることにした。アサが言うには、大室山、小室山、一碧湖などきれいなところがあるという。
スケッチブックを抱えた鈴虫は網代駅でJR伊東線の路線図を目でたどった。伊東から先はJRではなく、伊豆急行になる。下田までいくことができる。その日、鈴虫は下田の手前の伊豆熱川に行ってみることにした。そこも温泉で名前が知られているところだ。
乗った伊豆急下田行きは六両だったが、伊豆高原から前三両しか下田方面には行かず、最後部に乗った鈴虫は前の車両に移動した。熱川には網代から四十分ほどもかかった。もっと近いと思っていた鈴虫は伊豆半島の大きさを改めて実感した。
伊豆熱川駅は高台にあり、階段を降りていくと小さな駅前にでる。右手に勢いよく蒸気の上っているのが見えた。源泉が駅前にあり、それを覆う木でできた櫓からもうもうと蒸気が上がっている。そばには足湯があった。白っぽい櫓はいかにも温泉街に来たという気持ちにさせる。
もくもくと立ち上る蒸気は風向きで自分のほうに来たり、山の上のほうに流れたり、変化は見ていて飽きない。鈴虫はスケッチブックを開くと、櫓を描いた。蒸気はそのものを描くのも難しいが、上がる様子をとらえるのはさらに難しい。だが描いていて楽しい。一瞬に集中していないと、蒸気の上がるさまはあっという間に変わってしまう。写真も撮った。
時間をかけてスケッチしていたこともあり、気がつくとお昼近くになっていた。すぐ脇の魚料理の店に入ると、地魚のにぎりがあった。これも伊豆の楽しみの一つである。かわはぎ、金目、鯵、ここで獲れる魚が八巻でてきた。
鈴虫は、食事を終えると、海に向かって坂を下っていった。駅からすぐのところにも、もうもうと湯煙を上げる櫓があった。道を通っているとしぶきが飛んでくる。その櫓も時間をかけてスケッチをした。さらに下ると伎楽面の博物館があり、そこを右に下っていくと、海岸についた。砂浜の海岸をしばらく散策すると元にもどる途中に、お湯かけ弁才天の社があった。その脇にも源泉の櫓がある。根元の黄色っぽく硫黄のこびりついた岩が版画のイメージをそそった。
鈴虫は源泉の櫓を版画のテーマにすることにしようと思った。また来ることにしてその日は家に帰った。
アトリエでは、アサが来て掃除をしていた。
「アサさん、熱川に行ってきました」。
「ほー、それはよござんした。ここ網代の温泉も落ち着いていていいんですがね。熱川の迫力には負けますわ。なにせあそこは百度のお湯が噴出しよりますからねえ。源泉の櫓はいいねえ、温泉に来たって感じだね。だが、網代の魚の味はどこにもひけをとりませんよ」。
「そうですね」
「温泉卵を食べましたかね」
「いや、ただ、櫓を見てきただけです」
「そうかね、あそこは花火もいいね」
アサは、せっせと掃除を済ますと、今日はさわらを冷蔵庫に入れておきましたから、召し上がってください。と帰って行った。
アサを送って、アトリエから庭を見ると、白い猫が三匹こちらを見ていた。もらったさわらを少し皿にとると、猫のところにもって行った。椿の下の猫は鈴虫が近づくと一斉に見上げた。
「さわらは食べるかしら」と、皿を猫たちの前に置いた。まだ暑い中、椿の下はスーッと涼しい風が吹いていた。というより、ひんやりとした。
だから猫たちがいるのかと、鈴虫は納得した。
白い猫たちは皿の上のさわらを仲良く食べはじめた。
この猫たち、金目をあげたときには食べなかったのに、さわらは食べるのね。鈴虫は漁港の猫達は気に入った魚しか食べないのかと思ったが、なぜ金目を食べないのだろうか。私は大好きなのに。
網代に来て二週間がすぎた。熱川には何回も通った。いろいろな形の源泉の櫓は絵になる。木でできたものはもちろん、鉄でできた櫓の、時代を感じさせる錆びた状態のものも嫌いではなかった。それぞれの歴史を感じることができるのと、蒸気の吹き上げは櫓を生き物のように見せていた。それを版画にしたい。と鈴虫はふつふつと沸いてくるエネルギーを感じるこの頃である。たまったスケッチを木版の原画にする作業を始めている。あと半月で友人は帰ってくる。それまでに、下絵を仕上げておこう。見てもらうのもいい。やっともとの自分に戻れる感じがした。。
その日は、外に出ることはなく、広すぎるアトリエで原画作りに没頭していた。暑い日が続くが、クーラーは使わず、窓を開け放して、庭から入ってくる風ですごした。汗をかいたら掛け流しの風呂がある。ざぶんと入ってまた作業にもどる。たまらない楽しさである。
庭を見ると、午後の最も暑い時間なのに、椿の木の下に白猫が集まってきた。源泉の櫓に猫を配置するのも悪くない。猫のスケッチもたまっている。
いつもの三匹の猫が椿の木の下に並んでこちらを見ている。と、また、白い猫が一匹のそりのそりと椿の木の下にやってきた。そして、また一匹、また一匹、そしてまた一匹、こんなことがあるのだろうか。七匹の白い猫が、勢ぞろいをして、行儀よくアトリエのほうを向いておちゃんこをしている。めったに見ることのできない光景である。
鈴虫は写真を撮るために外に出た。猫達は逃げもせず被写体になった。七匹の白猫が椿の木の下に集まるのを写真に収める機会などまずない。鈴虫はそばによると、白い猫たちの頭をなでた。椿の下は日がさんさんと照らしているのにもかかわらず、ひんやりとして、むしろ冷たいくらいである。
なぜだろうと思っていると、猫たちは立ち上がり、今度は輪になって座った。猫たちが囲んだところでは冷たい風が渦巻いている。鈴虫が七匹の猫の囲んだ場所に手をやると、クローバの葉がぽろっと落ちた。凍っている。
どうして?
と、七匹の猫がいきなり消えた。
え?
振り返った鈴虫の目に、チラッと白い猫たちが走り去るのが見えた。猫たちが囲んでいたところを見ると、きらきらと氷が光っている。この熱いのになぜ。
なかに何かあるのだろうか。
そう思った鈴虫はアトリエにもどった。倉庫に真新しいシャベルが置いてあることを思い出したからだ。鈴虫はシャベルを持って椿の木の下にもどった。猫が囲んでいたところを掘ると土が凍っていて硬い。回りを掘り、シャベルを深く突き刺して持ち上げると、凍った土の塊がコロンと飛び出した。
鈴虫は凍った土の塊をシャベルではたいた。凍った土がぽろぽろと落ちると、氷の塊が現れた。透きとおった氷の中には真っ黒な猫が埋もれている。
え?
シャベルを放り出して、鈴虫は黒い猫の入った氷を草の上に置いた。暑い日に曝され、しばらくすると、周りの氷が溶けて黒い猫が現れた。猫の黒い毛から水が滴り落ち始めた。死んでいる。
黒い猫はぐったりとクローバの上に横たわった。
水浸しの黒い毛がびしょびしょにぬれて光っている。
どうして氷に閉じ込められたの。
鈴虫は黒猫の頭をなでた。
白い猫がアトリエの角からこちらを見ている。
冷たい猫のからだが太陽の熱でほんのり温まった。
鈴虫の指が猫の頭に触れたとき、ふっと黒猫のからだが動いた。
鈴虫がびくっとして手を引くと、黒い猫のまぶたが動き、ほんの少し目をあけた。
黄色の目が鈴虫を見た。
え、生きてる。
鈴虫の心臓がどくんと脈打った。
鈴虫は濡れてびしょびしょの黒い猫を抱き上げた。
あわててアトリエにつれていくと黒い猫をタオルで包んだ。
しかし、黒い猫はぐったりしたままだった。
鈴虫は黒い猫を二階の風呂場につれて行った。たらいに湯を満たし、水を加えてぬるま湯にすると、その中にゆっくりと浸した。ふわっと黒い猫の毛が湯の中に広がる。
猫を洗いながら、生きていたのね、
と声をかけた。
湯からあげるとバスタオルにくるんで、ベッドの上に横たえた。
黒い猫はわずかだが、からだを動かして、今度ははっきりと鈴虫を見た。
黒ちゃん
鈴虫が声をかけた。
その日、黒い猫は首を上げるようになり、よろけながらも歩くようになった。鈴虫は黒猫を看病をした。
三日目には立ち上がりニャーと鳴いた。
やがて、黒い猫は気持ちよさそうに身づくろいをするようになった。鈴虫の与える刺身の残りも食べた。
黒い猫は鈴虫のそばに来て座った。
鈴虫は黒い猫を抱き上げ頬ずりをした。
鈴虫は凍っていた猫が生き返ったことに奇妙な安心感を覚えた。その不思議さを考えることをしなかった。鈴虫は黒い猫の柔らかい毛をなでた。
それから、黒い猫がいつも鈴虫のそばにいるようになった。キッチンで料理をしていると黒い猫は鈴虫の足にこすりついた。寝るときには必ず足元で丸くなった。どういうわけか、白猫たちはあれ以来庭には現れなくなった。
鈴虫の原画作りははかどった。いろいろな角度から源泉の櫓に猫たちが配置された絵ができていった。
アサが来ると黒は陰に隠れて姿を見せなかったが、アサがおいていく刺身を喜んだ。
アサは張りが出てきた鈴虫の顔をみた。
「お変わりになりましたね。不思議な雰囲気のお嬢さんになられました。きっと絵が楽しくなられたのでしょうね。あの方も、絵に没頭し始めると不思議なお顔になられましたから」
鈴虫は何も言わなかったが、そうかもしれないと自分でも思った。
「このところ、床に黒い猫の毛が落ちてますね。黒猫が入ってきているようです。大丈夫ですか」ともアサは言った。
鈴虫は微笑んだ。
「黒い猫がたまに遊びに来るの、かわいいわよ」。
「そうですか、黒猫は幸運を呼ぶとも言うし、悪魔とも言うし、不思議な猫ですね」。
それからは、アサは猫用に刺身の切れ端を持ってきてくれるようになった。アサも猫が嫌いではなさそうだ。
ある日の夕方、アトリエで絵の整理をしていると、黒が庭に出たがった。
鈴虫が戸を開けると、黒は椿の木の下にむかって歩いて行った。
途中で立ち止まり、振り返るとこっちにおいでといった表情で鈴虫を見た。鈴虫もアトリエから庭に出た。
黒は椿の木の下に来て、再び鈴虫のほうに顔を向けた。鈴虫も黒を見た、そのとたん、すーっと、黒の姿が土の中に吸い込まれ、消えてしまったのである。
え?
鈴虫は、あわてて椿の木に駆け寄った。黒が消えたあたりを手で触ってみるとひんやりと冷たい。夢なのだろうか。
庭の隅々、アトリエの周りを歩いてみたが黒はいない。
もう一度掘り出してみようかと思ったがなぜか怖かった。掘っていなかったらという怖さがあった。鈴虫は暗くなるまで庭にたたずんでいたが、黒の姿は消えたままであった。
その夜、黒のいなくなった空虚感で、鈴虫はベッドに入ってもなかなか寝付けなかった。そもそも氷の中から猫が出てきたことも信じられない話である。本当に黒はいたのだろうか。考えれば考えるほど、自分の記憶に混乱をきたしていく。もやもやとした思考が繰り返される中、いつか眠りにおちたようである。
寝室に光が差し込んできた。霧の中にいるような気持ちで鈴虫は目をあけた。何時だろうとからだをそらせ枕もとの時計を見た。十時を回っていた。足を動かすと、いつもの重さを感じてはっとなった。見ると足元に黒が寝ていた。
鈴虫の詰まっていた胸がすーっと楽になった。
「黒」
鈴虫は黒の頭をなでた。
「どこいってたの」
庭へのガラス戸を開けておいてよかったと鈴虫は思った。黒はぐっすりと寝ている。
鈴虫は黒を起こさないようにベッドからでると、着替えをして一日の準備にとりかかった。
黒は起きる気配がない。
鈴虫は、安堵したせいかその日の版画の原画作りははかどった。黒は餌も食べず、そのまま一日中寝ていた。
夜になり、一階のアトリエで鈴虫がそろそろ寝ようかと道具をたたんでいるところへ、黒は二階から降りてきた。
「黒ちゃんご飯食べる」
鈴虫が声をかけても、黒は鈴虫のほうを見ることなく、庭への出口のところで立ち止まった。昨日と同じことが起こるのではと躊躇をしている鈴虫に、黒が振り向いてグニャーとないた。開けてほしいという声である。鈴虫は戸を開けた。黒は椿に向かってゆっくりと歩いていく。
胸の動悸が聞こえてくる。鈴虫は黒の後を追った。消えてしまうのでは。
しかし、黒は椿の下に来ると、立ち止まり、行儀よく足をそろえて鈴虫が来るのを待った。鈴虫はしゃがむと、両手を黒の顔に伸ばした。黒の毛の感触が指先に触れたと思ったとき、鈴虫は黒とともに暗い穴の中に吸い込まれていった。
気がつくと鈴虫は星空のもとでブナの木に囲まれた道を歩いていた。黒が前を歩いていく。道の脇の猫(ねっ)越(こ)岳という標識が眼にはいった。しばらく歩くと、巨木があった。黒はそこで道から外れ林の中に入り、山を登っていった。ほどなく頂上に着いた。うっそうと木に囲まれた草地であった。
草の中に真っ白の猿が二匹いた。猿が鈴虫に気がついて振り向いた。
その瞬間、鈴虫はベッドの上にいることに気がついた。黒はいない。夢か。
その日、掃除に来たアサにたずねた。
「猫越岳ってどのようなところなのかしら」
アサは珍しく手を止めて、
「行きなさるかね、いいとこですよ。古い火山で、西伊豆と天城湯ヶ島の間にある山ですよ。二五〇万年前に海底から噴火してできた、伊豆で最も古い山だといわれています。本当かどうかはわからんですが、噴火をしたときに、驚いた猫が西伊豆から天城に峠を越えて行ったことから名づけられたといわれるのですよ。かなり歩きますが、いいハイキングコースになっていますよ」
詳しく話をしてくれた。
昨夜見た夢の場所が本当にあるらしい。
「最近、波勝崎の猿が猫越の峰に現れるって話がありまよ。しかも、真っ白の猿なんだそうです。珍しいですね」
あの猿たちだ。
アサが帰ってから、鈴虫は庭に出た。かんかんでりにもかかわらず、椿の下はやはりひんやりとしており、クローバが凍っている。
その時、ぐらっと、地面が揺れた。地震だ。アトリエを見ると大きく揺れている。
鈴虫はよろけた拍子に、凍った地面に両手をついた。凍ったクローバの葉がぽろぽろとこぼれた。手のひらが冷たくなり、痛さを感じながら、鈴虫はふたたび真っ暗な中に落ちて行った。
昨夜の夢と同じように、鈴虫は夜空の下で、猫越岳の頂上にいた。
木々に囲まれた広場の真ん中で、真っ白の二匹の猿が二本足で立ち、向かい合って言い合っている。
「おぬしは黒姫がどこにいるか知ってるのじゃろう」
「知らぬ知らぬ、わしゃ知らぬわい」
「おぬしが知らぬわけはない、隠したにちがいない」
「なぜおぬしはそう思うのじゃ」
「お主の顔は赤い」
「赤ければなんじゃ」
「火の下に隠したのじゃ」
「わしではなくて、火の神じゃ」
「そうか、火の神が黒姫をおかくしになったのか」
「そうだ、そうだ、火の神にお尋ね申そう」
「申そう、申そう、火の神に申そう、黒姫をお返しくだされ、お返しくだされ」
二匹の猿は謡いながら踊り始めた。
「申そう、申そう、火の神に申そう、黒姫をお返しくだされ、お返しくだされ」
猫越岳の広場の真ん中が、赤く光始めた。赤みが増し、やがて炎となり、中から真っ赤に焼けた固まりが吹き出てきた。
猿たちは赤く渦巻くマグマの固まりの回りで跳ねた。
「冷まそう、冷まそう、冷まそうぞ」
「そうじゃ、冷まそう、冷まそうぞ」
赤く燃えた固まりは黒くなり、冷めると、真っ黒い猫になった。
黒い猫は行儀よく前足をそろえ猿たちを見た。
広場の脇ので見ていた鈴虫は思わず、あ、黒と叫んだ。
「火の神は黒姫をお返し下された」
「そうじゃ、お返し下された」
「お礼申そう、お礼申そう、火の神にお礼申そう」
「そうじゃそうじゃ、お礼申そう、火の神様、お礼申そう」
二匹の白い猿は広場を所狭しと跳ねまわった。
黒い猫は紺色の花をつけている椿の木の前に来ると、ゆっくりと立ち上がり、一礼し、ゆるゆると、長い黒髪をたらした女になった。女は椿を一輪折り、くるりと鈴虫のほうを向いた。黄色の目をした女だった。長い黒髪がからだに絡みつき、髪の間から白い皮膚が透けて見える。
二匹の猿は飛び跳ねるのをぴたっとやめると、女の両脇でひざまずいた。
風のうなりが楽曲になった。
女は音にあわせ、静かに舞いながら、鈴虫のいるほうにすすんできた。
笛の音のような、琴の音のような、鼓の音のような風のうなりの中で女の華麗な舞がはじまった。
その時、再び地面が大きく揺れた。
また地震だ、鈴虫は近くの木につかまった。揺れは大きくなり、木々が擦れ合い、大きな地響きも聞こえた。
猿が跳ね回った。
「火の神が黒姫をお召しじゃ、身代わりによこせじゃと」
「そうじゃ、お召しじゃ、黒姫はもどらなければならぬ」
「そうじゃ、黒姫はおもどりにならねばならぬ」
「そうじゃ、そうじゃ、もうここにはおれぬ」
猿たちが消えた。
女は黒い猫にもどり、鈴虫を見た。
「黒」
揺れながら鈴虫は声を上げた
黒い猫は黄色の目を鈴虫に向け微笑んでいる様でもあった。
身代わりって何だろう。鈴虫の頭にそんな疑問がふっとわいた。
そのとたん、黒い猫は真っ赤に燃えマグマになった。
大きな揺れがくると、木々がたおれ、赤く燃える黒猫の上にかぶさっていった。
地響きとともに、地面がわれ、真っ赤な猫が土の中に吸い込まれていくのが見えた。
猫が消えてしまうと、鈴虫の目にはなにも見えなくなり、気がつくと鈴虫は、ベッドの上で揺れていた。
揺れはすぐおさまった。
鈴虫はアトリエに降り庭に出た。月が輝いている。あたりは静かで海の音しか聞こえてこない。椿の下は黒くこげていた。
鈴虫は体中の力が抜けていた。頭の中は真っ白のまま、いつの間にか部屋にもどり、深い眠りに落ちていた。
あくる朝、アサから電話があった。大きな地震だったが大丈夫かという心遣いの電話だった。大丈夫だと伝えると、よかったと電話を切った。
また、電話がなった。それは、警察からだった。思わぬ知らせで鈴虫は声も出なかった。友人の訃報であった。パリからウイーンに行く電車が事故を起し、それに友人は乗っていた。友人は病院で一週間後に亡くなったとのことであった。最初は意識もはっきりしており、大丈夫だろうと思われていたのが、急に脳出血で亡くなったそうだ。打ち所が悪かったのだろうとのことであった。
意識のあるとき、見舞いに行った大使館員に、鈴虫にアトリエをいつまでも使ってほしいと言っていたとのことである。
警察は、「とりあえずお知らせします。書類などについてはお伺いした時にお願いします」と電話を切った。
友人には身寄りがない。
電話を受けた鈴虫はどうしたらよいかわからずただ途方にくれていた。
まもなく警察が来て、彼の持ちものが詰まった大きな皮のトランクを持ってきた。アトリエの権利書の書き換え方だとかいろいろ教えてくれた。
刑事の一人が言ったことである。
昨日の電話で言わなかったことがあるということであった。奇妙なことで、言いづらいが、やはり言っておいたほうがよいという上司の判断でお教えしますとのことであった。フランスの病院でなくなった彼の遺体が紛失したということであった。鈴虫はどのように葬式をするのかも分からず、どうしようかと思っていたが、それもできなくなった。
鈴虫は、本当に亡くなったのですかとたずねた。
刑事がそれは間違いがないと言った。DNA鑑定用の資料もとってありますとのことであった。
彼とはとうとう会えずじまいだった。数年前に最後に会った日のことがかすかに思い出される。鈴虫に強く胸にこみ上げてくるものがあった。
警察が帰ったあと、庭の椿の木の下で、七匹の白い猫が輪になって座っているのが見えた。こちらを見ている。
鈴虫は急いでアトリエから庭に降り、椿の木の下に行った。白い猫たちがいっせいに鈴虫を見た。猫の囲んでいたところがきらきらと光っており、ひんやりとした空気が流れてきた。
鈴虫はアトリエから、シャベルをもってきた。
白い猫達が消えた。
黒が帰ってくる。
鈴虫は夢中でシャベルを力いっぱい差し込んだ。
土の塊が出てきた。
鈴虫は土をはたいた。
凍った黒い猫がいた。
鈴虫はそのまま二階の風呂場に運んだ。
凍った黒い猫に湯をゆっくりとかけた。
土が流れ、氷が解け始め、やがて、黒が湯殿に横たわった。
黒をたらいの中に入れ、湯を入れた。
黒は目を開け、ニャーと鳴いた。
鈴虫は目に涙をためて、黒の毛を洗い、タオルに包んだ。
次の日の夜、黒はベッドの上で起き上がると、鈴虫を見た。
鈴虫は、
「何?」
と、黒の頭をなでた。黒は手足を伸ばして気持ちよさそうにふたたび横になると、溶けるように人のかたちになった。友人になった。
彼は言った。
「一緒に住もう」
何年ぶりかに会った彼は変わりがなかった。
彼ははだかのまま立ち上がると、アトリエに降りて行った。
一階のアトリエから彼のトランクを開ける音が聞こえる。
立ち尽くしていた鈴虫はあわててアトリエに降りた。
彼は、昔のように、しゃれた赤いシャツを着て、おいてあった鈴虫のスケッチを見ていた。
「いいねえ、版画の道具をそろえよう」
そういうと鈴虫のほうに日に焼けた顔を向けた。
そのときから、鈴虫は今でも、網代のアトリエで彼とともに生活をしている。ただ、彼が鈴虫と話をするのは夜だけである。フランスのこと、絵のこと、鈴虫はいろいろのことを聞かせてもらった。昼は黒い猫が鈴虫に寄り添っている。
白い猫たちが、時折アトリエの中にも遊びに来るようになった。
夢ではない、彼の繊細な長い指が鈴虫のほほをなでる感触と、黒い猫の柔らかな毛に触れる鈴虫の指の感触は、混ぜ合わさることはない。鈴虫が生きている今の世界なのである。
伊豆の黒い猫
私家版幻視小説集「黒い猫、2015、330p、一粒書房」所収
木版画:著者


