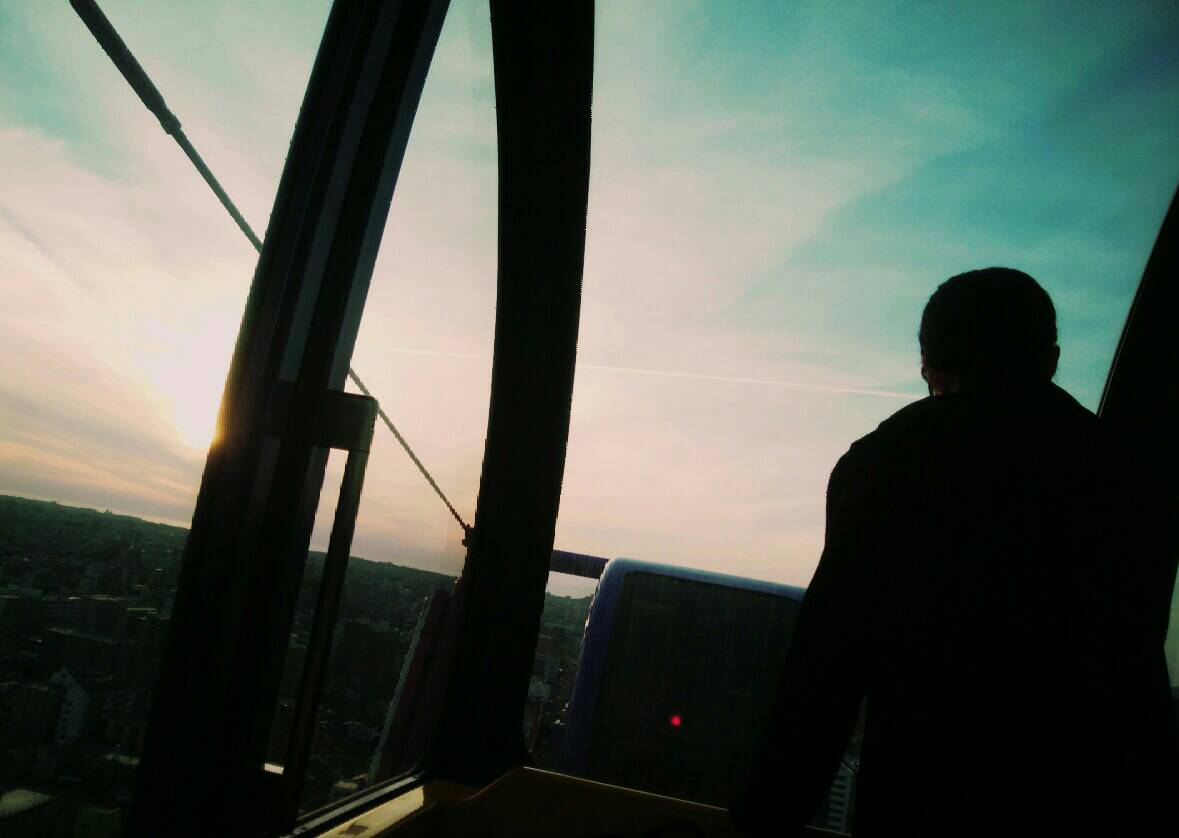
神様
ふれる。桜色の刺青が、あなたの背中で脈打つようにどくどくと動く。あなたの熱を、私はごく近くに感じる。
おだやかに雪の降りつもる山荘で、あなたの草臥れた茶色の靴を、私は燃やしていた。ぱちぱちぱち、音をたてて火の粉がちいさく飛び散る。私の不健康そうな白くほそい手は、弾かれたように引っ込む。焼け焦げた臭いだ。開けはなされた扉から入る冬の陽射しが、灼けるように熱い。これはおかしいと思ったら、夢なのだった。
起きると、雅愛の気配を感じた。彼からふわりと桃の匂いがつたわる。人工的なものではなく、まっすぐな果物の香だ。冬に桃はなるのだろうか。大丈夫ですか、と彼の柔らかな声がした。
「雅愛。ごめんなさい、なんともありません」
夢のなかで鮮明にみえた気がした色は、ぜんぶ私自身が創造したものだったのかもしれない。
乱れた呼吸を落ち着かせるために、空気をすいこんでゆっくりと吐く。大きな掛け時計、ざぶとん、金魚鉢。雅愛の家を、頭のなかで思い描く。
「そうですか。ずいぶんうなされていたようで、起こそうか迷っていました」
私の髪に、雅愛の薄いてのひらが載った。このひとは、やさしい。子どものころ病弱だったという彼は、人の纏う空気に敏感だ。
「……風が、ごうごう聞こえます」
私がつぶやくと、そうですね、と考えるように雅愛がこたえた。
彼の声と気配がうすれて、かわりにぎしぎしと音が鳴った。彼が縁側の板を踏む音だ。外からは雨のにおいがする。私は畳の奥で、きっと今日もはだしの雅愛をみつめた。冬なのにな、と思う。射るような西日をかすかに感じる。
一年前の冬、私は海にきていた。ひとりで、旅行鞄ひとつと杖だけを持って、すみなれた親戚の家を出た。彼らはよく心配してくれていたけれど、私ははやく自立したかった。自分だけで、あるけるようになりたかった。
しらない町の夜の海はなんだか余計に寒くて、薄いコートで来たことを後悔していたら、あなたが来た。雪で埋もれた砂浜を、ざくざくと踏みしめる音がした。
「夜に、こんなところで、あなたはなにをされているんですか」
すこし怒ったような声だった。振り向きざまによろけてしまって、こける、と思ったら、あなたは私の体を支えて「落ち着いて。僕は、植村雅愛といいます。ここの土地の人間です。三十三歳。教師をしています。散歩に来ただけですので、あなたに危害は加えません」と続けざまに言った。
場違いな自己紹介をする彼がおかしくて、笑ってしまった。彼はやっと安心したように「ちょっと、座りますか」と提案してくれた。
「はい。すみません、私、目が悪くて。杖を取っていただいても、いいですか」
彼がひと呼吸置いてから「わかりました」というのを聞いて、いきなり言うことではなかったかな、とちょっと反省した。
「どうぞ」
杖を渡してもらって、ようやくあるきはじめる。彼は私とおなじ速度を保ってくれていて、ありがたかった。
「私は、翠といいます。二十三歳です。あるいていたら、ここに来ていました」
「翠さん。自分の体を、大事にしてください」
見透かされたような気がした。ほんのすこしだけ、今日ここで生涯を終えてもいいかもしれないと思っていたこと、私がいなくなったところでなにも変わらないと思っていたことを、言いあてられたような気持ちだった。
わかりました、としずかに答えると、彼はながい息をついてから、「おおかた、家出でもしてきたんでしょう。あなたが高校生だったら、僕は迷わず補導しますね」とわらった。
「……わたし、学校きらいだったんです。雅愛さんに捕まえられるんだったら、もっとはやくに家出すれば、」
そこまで言って口をつぐんだ。
「住むところがないんだったら、うちに来ればいい」
彼はまだ、ちょっと怒っているようだった。私たちはその夜、雪に降られながらあるいた。彼の家に着いて、すぐにお風呂を借りた。熱いお湯が気持ちよかった。ここにいることをゆるされたのだと思うと、心の奥までじんとあたたかくなった。
■
ふいに、煙草の匂いがした。私のとなりで、雅愛が煙草をすっているようである。いまなんじですかと訊くと、「さてなんじでしょう」と返ってくる。雅愛は寝なくていいの。いいんだよ、夜更かししたいときもあるでしょう。言葉が雑になっている。きっとほんとうは彼も眠いのだ。布団にもぐったまま、彼のいるほうに手をのばす。そっと背中にふれた。
「ここに、蝶があるんでしょう?」
「そう。眠れない?」
雅愛の声は、きれい。私は雅愛のはっきりと浮き出た背骨や、彼の体に彫られた蝶がすきだ。この世界を、万遍なく肯定されていると思えるから。
彼は、私の神様だった。唯一、私をゆるしてくれているような気がした。
「雅愛がいなければ、私は、きっとなにもできないと思う」
うわごとのように言った。雅愛は「そんなふうに思うのは、あなたの勝手だけど。僕はそうは思わない」と、煙草を灰皿に押しつけた。
「雅愛って、やさしいな」
「ほんとうにやさしい人間は、弱っている人間に近づかないだろうね」
そう言って、彼がふいに私の髪を撫でた。
「もう寝なさい。おやすみ」
香った。また、桃の匂いだ。薄膜のような憂いを帯びた甘い匂いは、心に直接ふれるような声は、私をおかしくする。月明かりがこうこうと畳に押し入ってくる。それらは私の瞳を、髪を、心を、ゆっくりと焦がしていく。
「雅愛、私、生きていられません」
布団に横たわったまま、私は訴えた。両手で目を覆って、仰向けなんかで、ふざけた恰好で訴えた。
「私は、苦しいんです。苦しくないのに、こんなに痛いの。痛いんだ」
雅愛は「大丈夫だよ。夢だ」とやさしく繰り返した。私は反発した。そんなはずはない。だって、ここに雅愛はいるのに。
「あなたはまた、僕に会いに来てくれる。僕はそれを、知っています」
雅愛はどこまでも涼しい空気を纏っていた。どこにいるの、と訊くと、馬鹿だなあ、あの山荘だよと笑われた。
「雅愛は、ここにいたでしょう? 畳で、煙草を吸っていて、大きな手で、私の髪を撫でた。あの桃の匂いがしたの。それで、私は、私は、」
聞き分けのない子供のように、私は何遍も雅愛に説いた。
「雅愛。どこにいるの。もう会えないの」
彼の薄い羽織が、私の頬をかすめる。瞬きすれば消えてしまいそうな雅愛を、ちからいっぱい抱きしめた。
「会えるさ」
彼の言葉ははらはらともういちどだけ、私の耳に届く。目の前に、雅愛の蝶があった。私の手許に降りてくる。あかるい桜色の蝶の羽は、光が当たるたび透けてみえた。
「無事なの」
「元気だよ」
「そう。雅愛が元気なら、私、それでいいや」
いちど意識を手放すと、濁った川がみえた。蝶が、薄墨を流したような空をふわりふわり漂う。その瞬間、鮮やかな花の咲く荒野に出た。私はもうずっとものを見ることは叶わなかったはずなのに、あなたの蝶と、呑み込まれるほどにそこに大きく広がる景色だけは、ちゃんと見える。
私はあの山荘にいた。雪がちらちらと舞っていた。遠くに大きな崖が見える。手の甲には美しい蝶が在った。それは紛れもなく、雅愛のつぎの姿だった。それだけでいいと思えた。今度は私が雅愛とともにあればいいと、思った。
神様


