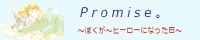
Promise。~僕がヒーローになった日~
不器用の優しさが心地が良い。君がいて僕がいてちょっぴりの勇気。大きなことはできないけど、僕なら君なら守れるものがある。ゆっくりとだけど確実に育んで行こう愛という花。
プロローグ
軒下にぶら下げてある風鈴が鳴り、中田明日歩(なかたあとむ)は徐にそちらへ目を向けた。
開け放った窓から差し込んだ光が、徐々に部屋を明るくしていく。
襖で隔てたその部屋は、座卓が置かれ、所狭しと物が置かれ、昔ながらの茶の間である。
柱や壁にまで、ぎっしりと思い出が詰まっている部屋である。
テレビが置かれ、その横にはキャビネット。
中には、母、奈緒の宝物と言っても豪語ではない品物が並べらえていた。
ほとんどが、父のものであるトロフィーや、なぜかヒーロー戦士のフィギア。そしてたくさんの家族写真。
どこからともなく香ってくる甘い匂いに、明日歩はふっと頬を綻ばす。
「こんな時に不謹慎だな」
独りごちり、母親の顔に布を戻した明日歩は、茶の間へと入って行くと、一枚の写真を手に、庭へ降り立つ。
こんな風に思える日が来るなんて、思わなかった頃の自分が、そこには映っていた。
最後の家族写真になるとは、思いもせずに、そっぽを向く自分に、明日歩は苦笑いをする。
この日は確か、明日歩がもう少しで高校の入学式という三月の終わりだった。
日差しが柔らかい、丁度、今日のような日だったのを、よく覚えている。
毎度お騒げせの父、歩(あゆむ)は、何を思ったのかその日は、やたらテンションが高く、帰るなり、庭へカメラと三脚を持ち出したのだった。
そんなことも知る由もない明日歩は、夢うつつ状態でいたのだが、ハッとして飛び起きることになる。
あろうことか、大声で、自分の名前を呼び出したのだ。
朝の8時と言ったら、世の父親が出勤して行く時間だ。当然、往路に面した庭での出来事に、誰もが何事かと目線を送っては出勤していく様を、明日歩は部屋に居ながらにして、容易に想像が出来た。
「ちょっとタンマ。あのくそ親父、何してくれちゃってんの」
明日歩は恐る恐る舌を覗き込む。
おおよそ想像はついていたが、現実を突きつけられた明日歩は、絶句してしまっていた。
垣根から顔を覗かせるご近所さんへ、丁寧に、歩は説明をしはじめる。
何やってんだよ。こんな朝っぱらから。
明日歩は紙を掻き毟り、耳を塞ぐ。
こんなのが日常茶飯事の、中田家なのである。
「あら、兄をしていらっしゃるの?」
「ああおはようございます。朝っぱらからお騒げせして、すいません」
「関根さん、これからごっ出勤ですか? 行ってらっしゃい」
「おはようございます」
いつもこんな感じで人が群がって来るのだ。
複数に膨れ上がった声の主を見ようと、もう一度明日歩は首を伸ばす。
「あら明日歩君、おはよう」
目が合ってしまい、慌てて明日歩は首をひっこめる。
そんな明日歩にお構いなしに、賑やかな話声が庭先で響いていた。
「朝からお騒がせしてスイマセン」
「いえいえ、全然かまわないですよ」
「あんまり天気がいいから、家族写真を一枚撮りたくなりましてね」
「そう言えば明日歩君、もうそろそろ高校生?」
「はい。おかげさまで」
「あら」
隣りの榊さんの声だた。
「おはようございます」
母、奈緒の声が混じる。
「まぁ、奈緒さんはいつ見ても若々しいわね」
「そうでしょう。オレ、この服が一番好きで」
自慢することかよ。
年甲斐もない格好する奈緒が、明日歩は嫌いだった。
ケラケラと笑い合う声。
もはや世も末だ。
明日歩は眉間を寄せ、寝返り打つ。
すべてのものを遮断したくて、頭から布団を被る明日歩だった。
父親は近所で評判が良い。
あまり意識したことはなかったが、何度か、明日歩君のお父さんは格好いいから良いな、と言われたことがある。
みんなが言うからそうなんだろうけど……。
明日歩にとっては最悪な印象しかなかった。いつもおかしな恰好をしている母親ばかり味方するし、ヒーロー番組を食い入るように見ては、明日歩も正義であれ、と言うのだ。
幼いころは、それでも良かった。むしろ、物分かりがいい父親だって尊敬の眼で見ていた時期もあった。しかし、それは小学校上がるまでの話。いくら何でも代の大人がヒーロー番組を真剣に見るっているのはどうなんだろう? 思って当たり前だと、今でも明日歩は確信している。奈緒に何度も注意されても止められないグッズ集め。そこに、男のロマンがるって言ってたけど、結局わからずじまいだった。
そして問題は、母親、奈緒の身なりだった。
何が悲しくて、こんなお姫様ルックをするのか、なぞに過ぎない。
何かの余興ですか?
聞きたくなるその恰好を、平然として街を歩く母親が、嫌いで嫌いで仕方がなかった。
反発もたくさんしてきた。
それでも……。
庭に影が落ち、明日歩は空を見上げた。
白く光る飛行機が一機飛んで行くのが見え、その後を追いかけるかのように雲が伸びて行く。
☆
今まで賑やかに聞こえていた声が急に静まり、明日歩はそっと窓から表を覗き見る。
ん?
嫌な予感が脳裏を過った。
ドカドカと階段を上がってくる音が聞こえ、鍵を掛ける間もなく、部屋の扉が勢いよく開く。
「明日歩、起きているんだろう?」
明日歩は咄嗟的に、布団を被り直していた。
こういう子供じみたところが、明日歩は大嫌いだった。
布団の上から明日歩の躰を、歩が容赦なくユサユサ揺する。
嵐が過ぎ去るのを待つ気分だった。まともに話して通じる相手ではないのは、百も承知なのだ。
執拗に揺さぶられ、明日歩は怒鳴りたい衝動をじっと堪えていた。
怒ったら負け。 歩の思う壺になる。
明日歩が修得した、歩の攻略方法だった。
そう言う人なんだ、親父って人は……。
つい、明日歩は思い出し笑いをしてしまう。
怒って言い返しているうちに、いつの間にか歩のペースに巻き込まれてしまっている。何ていうのはざらだった。
あの頃、何かにつけて尖っていた。あんなに大好きだったのにな……。
幼い頃、明日歩は歩の帰りが待ち遠しかった。
今か今かと、誰よりも早く起きて玄関で待つのが日課だったのだ。
それを知っている歩は、いろんな方法で帰って来ていた。それこそフェイントをかけ、庭から居間へ回ってみたり、お面を被って脅かされたこともあった。時には、声は歩だったのに、奈緒が何故か戸口を開けて入って来て、がっかりした所で、後ろからワッとされる。それから、歩は必ずと言っていいほど明日歩を抱き上げ、お役目ご苦労さん、と労ってくれるのだ。
髪をくちゃくちゃに頭を撫でられ、幼いながら、誇らしく思ったものだ。
歩に抱かれ、どっかりとこの縁側に座る。
淹れたてのコーヒーが香って、歩の顔がくちゃっとなる。
「奈緒が淹れてくれるコーヒーの香りと、明日歩の笑顔がオレの幸せ」
この頃の、歩の口癖だった。
何の抵抗もなく、ただ嬉しい感情だけを身に纏い、明日歩は歩の首にしがみついていた。
明日歩は鼻の奥がツーンと痛くなり、写真に目を落とす。
参ったな。父さんの言ったとおりだ。
鮮明に呼び起された記憶に、明日歩は鼻を一つ啜り上げる。
「ほらいいから、早く起きろよ」
布団を剥がされそうになった明日歩は、何が何でも剥がさせまいと、布団を握る手に力を入れていた。
「折角の門出だからさ、一緒に写真撮ろうぜ」
卒業式の日も同じことを言っていた。ましてや、今日は何でもない平日の朝だ。
必死で抵抗する明日歩に、歩は嬉々とした声で言い放った。
「無駄な抵抗だ。その手を放しなさい」
身長が伸び始めていたころだった。
頭へ引き上げられた布団は当然、足がはみ出される。
浅はかな自分を呪ったのは、その直後だった。
丸見えにされた足の裏を、攻撃してきたのだ。
くすぐったさに、自ら布団をはぎ取った明日歩は、勝ち誇ったように見下ろす歩に悪あがきで抵抗を企てた。
「何すんだよ」
「おはよ、明日歩君」
弾んだ歩の声に、明日歩はムッとする。
「明日歩君、頭隠して尻隠さずだよ」
にやにやとする歩を、明日歩は睨みつけるが、これも逆効果。
「おっ、良い面構えになって来た。それこそわが息子。それこそヒーローになる男というものだよ」
何かにつけて、歩は明日歩をヒーロー戦士に仕立て上げたがる。
冗談抜きで、マジウザい。
そんなことを言おうものなら、歩は笑顔を崩さないまま明日歩に、渾身の一撃を企ててくる。
細身のくせして、歩は腕節がいい。何故か合気道やら太極拳を使ったりして、かなりの手強さを持ち合わせている。体格的には互角だと思うが、何故か敵わない。それが明日歩が抱く、父親像だった。
「これに着替えろ」
昨日出来上がって来たばかりの高校の制服を指し、ニッと白い歯を零す歩に、嫌だと悪あがきをするが、頭を抱え込まれて数回叩かれた明日歩は、敢え無く降参させられてしまった。
「早く着替えろよ。奈緒も外で待っているから」
その言葉に、明日歩はゾッとなる。
近所の人との会話から、大体察しが付く。
ぜってぃやだ。
部屋を出かかった歩が振り返る。
「早くしろよ」
念を押す歩の笑みを見て、明日歩はうんざりする。
きっとこのミッションは、やり遂げられるまで、この攻防戦は一日中続けられるのは、目に見えて分かった。
そうなると明日歩の行動は素早かった。
大急ぎで着替え、階段を駆け下りてくる明日歩に気が付いた奈緒が微笑む。
明日歩の唯一のコンプレックス。
「明日歩、おはよう」
レースやらフリルがいっぱいのピンク色のドレスに、ボンネット。それに、手にはレースの手袋までしている奈緒に、明日歩はげんなりする。
どこの国のお姫様だよ。
「よし家族揃ったな」
嬉しそうに言う歩にムッとしながら、明日歩は庭へ降り立った。
そっぽを向いて映る自分の姿に、明日歩は苦笑いをする。
☆
全てがハチャメチャだった。
歩は仕事の制服にマントを翻し、レンズを覗き込んでいた。
「明日歩、表情が硬い。て言うか、笑え」
ムッとした顔で、明日歩は歩を睨む。
「その渋面は、今はお預けにしろ。スマイルだよスマイル。分かるか。笑顔作れ。それが幸せの秘訣だ。笑いたくない時にこそ、人は笑うんだ」
無茶苦茶な理屈に、明日歩は腹を立てて、そっぽを向いてしまう。
「よーし、撮るぞ」
大急ぎでセルフタイマーを掛けた歩が、二人の元へ駆け寄って来ると、意図も簡単に奈緒を抱き上げる。
キャッと短い悲鳴の後、シャッターが切れる音。それを数回繰り返し、それぞれ一人ずつの写真を撮った後、この茶番劇から明日歩は解放された。
奈緒が朝食を作りに台所に消えて行き、縁側で歩はコーヒーを啜りながら、上手いと感嘆する。
明日歩も所在無く、歩の横に座り、少し考えてから口を開く。
「何で今日じゃなくっちゃ駄目だったんだ? もう1週間もすれば入学式なんだから、そん時に、1枚撮れば良かったんじゃないの」
コトリとカップを置いた歩が、う~んと大きく伸びをしながら立ち上がる。
「なぁ明日歩、この花を植えた時のこと覚えているか?」
歩は沈丁花の前に進み、振り返る。
「ああ」
「早いもんだな。あれから10年も過ぎたんだな。小さかったお前に無理言ってすまなかったな」
「何だよ今更」
「いや別に。ただ一度、謝っておきたかったんだ。あん時、ああ言うしか出来なかったからな。甘えたい盛りに、奈緒は絹代ばあちゃんの世話で忙しくしていたしな、オレはオレで仕事が夜勤に変わっちまって、不安がる明日歩の気持ちを汲んでやれなかったからさ」
「別に、そんなの良いよ」
そうかと言いながら、歩が肩を竦めてみせる。
茶の間はすっかり朝の気配を取り込んでいた。
突風が吹き、歩のマントがひらひらと泳ぎ、甘ったるい沈丁花の香りが辺りに広がるのを、明日歩は思い出し、ふっと顔が綻ぶ。
沈丁花を一厘もぎ取ると、鼻の傍へと持って行く。
「本当、意味が分からない」
呟く明日歩に、歩は声を上げて笑っていた。
ヒーローの花か。
そう呟いた明日歩は縁側に腰掛け、そのまま寝転がる。
この家に引っ越して来たのは、明日歩が3歳になったばかりの春だった。
躰を壊し、入退院を余儀なくさせられていた奈緒の母親を一人にしておけないという理由からだった。
まだまだ小さい明日歩には、そんな事情など知らず、ただ優しい絹代ばあちゃんと暮らせるということが、嬉しくて仕方がなかった。
引っ越しの日、絹代ばあちゃんの膝の上で、片付けが済むのを待つ明日歩を、庭に居た歩に呼んだ。
そして、植えたばかりの花を前に、歩が口にする花言葉。
あまりに幼すぎて、歩が教えてくれた意味など解らなかったが、大好きな母親とばあちゃんを護って欲しいと言われ、明日歩はそれが嬉しくって、うんと頷く。
ご褒美に、歩が高い高いをしてくれて、その日から明日歩はこの甘い臭いがする花が好きになった。
沈丁花。
栄光。不死。不滅。信頼。
「……どれもこれもヒーローに必要不可欠なものだろ。だから、ここにこの花をヒーローの花と任命する。この花に誓って、オレと明日歩はヒーローとして、奈緒や絹代ばあを護ることを誓います」
「誓いましゅ」
父さんに持ち上げられ、空はどこまでも近く感じられた出来事だった。
あのまま、無邪気なままでいられたらどんなに良かっただろう。
日を追うごとに、絹代ばあちゃんの具合は悪くなり、病院で過ごす時間が増え、明日歩はなかなか会えずにいた。
ようやく帰って来た絹代の傍を、片時でも離れようとしなかったのは、庭に沈丁花がある限り、大丈夫だと信じていたから……。
起き上がれなくなった絹代ばあの布団に潜りこみ、明日歩は歩に買ってもらったヒーローの本を開き、何度も何度も説明を聞かせ、ばあの守る役目は僕なんだと言っては、頭を撫でてもらうのが、毎日の日課だった。
だから、ばあがもう帰らない人になった日も、庭の沈丁花をもぎ取って来た明日歩は、歩に抗議を必死にした。
「うちにはシナナイ花があるって言ったじゃない。絹代ばあのめん目すぐに開くよね」って。
明日歩は熱くなった目頭を隠すように、腕で覆う。
――何もかも遠い日々。
「不貞腐れて、こんな写真要らないという明日歩に、いつかこの日が愛おしく思える日が来る」
そう言っていた歩を、バカにしてたけど、まさか本当に来るなんて思わなかったよ。
もっと笑えば良かった。
明日歩はそっぽを向いてしまっている自分を何度も悔いる。
第一章 不良と正義
「明日歩、昨日泣いてたでしょ?」
不意に背中を叩かれ、明日歩はぎくりとなる。
声だけで誰なのか、予想はつく。
この世で関わってはいけない相手、おずおずと明日歩は振り返る。
思ったとおり、そこには不敵の笑みを浮かべた西沢知美(にしざわともみ)が立っていた。
明日歩はそれとなく視線をを外す。
ゆっくりさりげなく……。
何事もなかった様に歩き出そうとする明日歩だったが、そうはさせてくれないのが西沢知美だ。
なぜか知美は、幼稚園の頃から、明日歩に執拗に絡んで来る。
男勝りの口調で、ずかずかと人の心に入り込んでくるあたりが、あまり好きになれない明日歩である。できれば関わり合いたくないのだが、気が付くといつもそばに居て、お節介をしてくるのだ。
これを回避する秘策は、引き攣り笑顔で明日歩は首を伸ばす。
「居た!」
知美には克己である。
友達に軽口を叩きながら歩いている赤川克己(あかがわかつみ)を見つけ、駆け寄って行く。
知美は克己といるときは、余計なちょっかいはだしてこない。理由は分からないが、幼稚園の頃からで、行き成り肩を掴まれた克己が、訳が分からないまま知美とご対面させられる。
「克己、どいて」
「うるせぇブス」
「言ったわね」
「本当のこと言って、何か問題ですか?」
「もう、雑魚は黙っていて。私は明日歩に用事があるの」
「シッシ。明日歩には一生お前との用事はないってよ」
思わず大きく頷く明日歩を見て、知美はムッとなる。
「いい。覚えておきなさいよ」
プリプリと怒りながら歩いて行く知美を見て、明日歩はホッとする。
とにかく、知美には克己だ。
しかし、知美は余裕の笑みを浮かべていた。
それが一時的なものだということを、明日歩は身に染みて痛感させられてしまう。
「あんたね、バカなの?」
明日歩の前を陣取った知美が、呆れ顔で言う。
苦々しい笑みを浮かべた明日歩は、自分の運のなさを呪うしかなかった。
「こういうのを腐れ縁って言うんだな」
入学式の時、歩(あゆむ)が面白そうに呟くのを、明日歩は忌々しく思っていた。
知美が、わざわざ奈緒と歩に挨拶に訪れていた。
明日歩の気も知らない知美が、嬉々とした笑みを浮かべ挨拶をしにやって来るのが見え、歩が肩で小突く。
「今年も一年間、明日歩君と同じクラスで過ごすことになりました。不束者ですがよろしくお願いします」
「まるで、嫁入りみたいな挨拶だな」
歩に冷やかされ、知美が頬を赤くする。
認めたくない現実に、明日歩はつい大きなため息を吐いてしまっていた。
地獄の一年の始まりである。
天敵である、克己は奇しくも隣のクラスに籍を置いている。
幻滅する明日歩を見て、知美がニンマリする。
そんな明日歩の嘆きを聞かされた克己が、ゲラゲラと笑いながら冷やかす。
「この際だから夫婦になってしまえば」
軽かるが敷くそんなことを口にしては欲しくない明日歩は、目くじらを立てる。
冗談じゃない。
それが克己の笑いのツボにはまり、笑いが止まらなくなる。
「そんなに怒るなら、本人に言えばいいじゃん」
笑いを堪えながら言う克己を、明日歩は睨む。
それが出来たら苦労はしない。
知美には、言ってやりたいことは山ほどある。
行ってしまった後、どんな仕打ちが返って来るかと考えるだけで、恐ろしくてできないのだ。
これは、幼稚園の頃からずっと変わらない。
悪魔的存在なのだ。
☆
誰が、この女を学級員になんかさせた?
位を与えられた知美は、水を得た魚のように、俄然はじりだす。
学級委員バッチをしっかり付け直した知美が、髪を払って笑う。
ショートヘアにその動作は絶対に必要ないだろう、と思いつつ、明日歩は逃げ出すタイミングを計る。
「明日歩だけだよ、提出してないの」
ほらきた、と明日歩は視線を机へ落す。
「もう本当にだらしないなぁ。機嫌、今日までって、昨日も私、言ったよね」
明日歩の目の前に、知美は部活の申し込み用紙とペンを差し出す。
部活は、全員参加するのが校則だ。
この部活決めには、少々曰くつきだった。
幼いころ、何かとビービー泣く明日歩を見かねた歩は、片っ端から武術なるものを習わせようとした。
駅前にある柔道道場に行った時、あまりの怖さでおもらしをしてしまった。それが引き金になり、本格的に鍛えさせようと、あの手この手で、連れ出しては空手に剣道と入門させられた。
どれもこれも長続きはしなかったが、唯一、剣道だけは一年間もった経緯がある。
嫌がる割に、明日歩はメキメキと上達を見せた。
こうなると、志士を目指せと豪語する歩に、気弱な明日歩は従うしかなかった。
しかし躰というものは正直なもので、上達すればするほど、明日歩は元気をなくしていった。
原因不明の腹痛と発熱に、悩まされるようになったのだ。
それが、剣道に関連していることに気が付いたのは、母親の奈緒だった。
奈緒は奈緒でまた、薄々勘付いていたものの、天才剣士と褒められ、有頂天になっている歩に言い出せず、腕の中でぐったりと眠り込む明日歩の髪を撫でては、目を潤ませる日々が何日も続いていた。
しかしそんな二人に転機が訪れる。
しばらく仕事の都合で送り向かいをしていなかった歩が、練習に付き添うことになったのだ。
歩とて、親の端くれ。一人息子の様子がおかしいことくらい勘付いていた。
道場には行かず、公園に車を止めた歩が微笑む。
キョトンとする明日歩を、歩は抱きかかえ歩き出す。
嬉しいやら恥ずかしいやらで、明日歩の頬は緩む。
「よいっしょ。明日歩、重くなったな」
明日歩を下ろした歩が腰をポンポン叩きながら、笑って言う。
日が傾く中、のんびりとした時間を過ごした。
遊び疲れ、隣に座ってきた明日歩に、歩はポツリと聞く。
「明日歩、オレに、何か言いたいことあるんじゃないのか? 何でもいいから正直に言ってごらん」
明日歩の顔がみるみる崩れて行く。
今まで我慢していたものがあふれ出した明日歩は、切れ切れに言葉を繋ぎ始める。
「ぼく、剣道を辞めたい」
「それはどうしてだい。練習が辛いからかい?」
明日歩は大きく首を振って、袖口で目をごしごし拭う。
「まきちゃん、泣いちゃったんだ」
ん? と歩が首を傾げる。
「ぼくが、試合、先に出ちゃったから。ぼくが、勝っちゃったから。いっぱいいっぱい泣いちゃって、ぼくは試合、出なくてもいいよって言ってあげたんだけど、そしたらもっと泣いちゃって、それから口、利いてくれなくなっちゃったんだ」
「それは仕方がないことなんだ。それが勝負の世界なんだ」
「ぼくは、勝負なんてしたくない。真紀ちゃんの頭を叩くのも、胴を入れるのも嫌だ」
そう言うと、明日歩は号泣して言葉にならなくなってしまう。
その日から三日間、高熱を出した明日歩を見て、歩と奈緒は顔を見合わせる。
泣く泣く剣の道を辞めたのだったが、両親としては、折角培ったものを生かして欲しい、と剣道部を勧めるのだ。
悪くない世界。頭で分かっている明日歩だが、心が納得しなかった。かと言って、やりたいものが見つからないのも実情。できることなら、帰宅部ってものに所属した明日歩だった。
「保護者欄なら、私が代筆してあげるわよ。ほら印鑑だってあるのよ。早く書きなさいよ」
上から目線で言う、言い方が好きじゃない明日歩である。
ムッとしていることなどまったく気が付いていない知美が、お構いなしに続ける。
「もう、剣道部にすればいいじゃん。一応経験者なんだしさ。明日歩ならさ結構いい線いけるんじゃない」
うるせぇ! と言ってやりたいが、面倒になるのは分かっている。
明日歩は黙って立ち上がる。
「まさか、逃げる気?」
知美が、勘を働かせる。
こういう抜け目のないところが、明日歩は苦手なんだよな。
隙を狙って、明日歩が走り出す。
「待ちなさい」
ついでに、お節介な所も……。
間一髪で男子トイレに逃げ込んだ明日歩に、廊下で知美が逃げるなと喚き散らかす。
やれやれである。
ここまで逃げて来たは良いが、次をどう切り抜けるかが問題だった。この様子では、しっかり表で待ち構えているはず。
洗面台に腰掛け、手を拱いている明日歩は、しまっていた個室の一つが開き、目を輝かす。
願ったり叶ったりだった。
「中田じゃん」
個室から、ベルトを締めながら、克己が出て来たのだ。
救いの神に、明日歩は顔を緩ます。
それを見て、克己は何を勘違いしたのか、変な説明をし始めだす。
「超でっかいのが出て、びびったぁ。こぉんなんだぜ」
克己は、手で大きさを表して見せる。
訊いてないし、それにこの喋り方……。
克己はすぐに、感化されてしまう悪い癖がある。きっと先輩の影響だろうけど。明日歩は苦笑した。
「学校で、うんこなんかしてんじゃねぇよ」
「いや俺は、時と場所は選ばない男だから。じゃあ」
じゃあって、手も洗ってねぇぞ。それより、盾が、勝手に出て行かれても困る。
明日歩は焦って、克己を呼び止めた。
「サッカーは楽しい?」
「おお。俺は未来のJリーガー選手だかんな。ここの先輩にも負けん気がしないぜ!」
へって、克己は笑った。
へって……。
克己の大口は、今始まったことじゃないけど、奥に閉まったままのドアが気になった明日歩は、口の前でシーッと指を立て見せるが、調子に乗った克己の豪語は、そう簡単に収まらず、最後には世界の王者までに達する話になってしまっていた。
さすがにまずい。話が大きすぎる。声もデカい。完璧に聞こえている、そう思った明日歩は克己を回れ右させる。
背中を押され、訳が分からないままでいるか罪を縦に出てきた明日歩を、知美が待ってましたと言わんばかりに声を張り上げる。
「明日歩!」
こんなことをしても無意味なことなんて、明日歩にも判っている。知美が言わなくても、担任が口を出してくる。当然、どこかの部へ所属させられるのもだ。だけど当然ぶって、無理強いさせられるのが、どうにもこうにも納得できない明日歩なのだ。
明日歩は、克己を知美に押し当てて、廊下を全速力で逃げ出す。
階段で足がもつれて転びそうになりながら、一階まで降り、昇降口で靴を履き替えようとしていると、知美が近くで練習を始めていた運動部の奴に、声を掛ける。
「そいつを捕まえて!」
まずい。同じクラスの奴がいる、そう思った途端、明日歩に女子たち数人の手が伸びて来ていた。
「絶対逃がさないでね」
「分かった」
分かるな!
明日歩は道をふさがれ、右側に反れて走り出す。
扉が見えた。隣の校舎に続く扉だ。焦っているせいで上手く開けられない。この扉はもともと錆びてて、ただでさえ開けにくい。
「ちょっと、何で逃げんのよ」
仁王立ちの知美に首根っこを掴まれ、明日歩は観念するしかなかった。
克己も、面白がってやって来る。
「もう今日提出しないと、私が怒られるだって。保護者欄は私が書くって、言っているでしょ。おばさんにも、承諾してもらっているから大丈夫だから。明日歩はここだけ記入すればいいの」
なんで、お前がオレの保護者なんだ。ざけんじゃねぇよ、と言ってやりたい。だけど、明日歩にはそれを言う勇気がない。
知美にじりじり迫られ、克己がにやにやと笑う。
クソッ! 逃げらんねぇ。
観念した明日歩に、知美が手にしていた用紙を差し出し不敵の笑みを浮かべる。
「サッカーやれば良いじゃん。俺と一緒にやろうぜ」
口を挟む克己を、知美が一睨みする。
「ほら」
知美が、勝ち誇ったような笑みで、ペンと用紙を明日歩に突き出す。
明日歩は渋々と受け取った紙に、陸上部と書き入れる。
「陸上部?」
克己と知美が、声を揃えて言う。
「何で? サッカーにすれば良いじゃん」
「剣道部じゃないの? 仮入部でも先輩に褒められていたじゃない?」
困惑した顔をしながら、明日歩は不貞腐れた口調で、何でと言い返す。
「あれは父さんが煩いから、顔を出しただけで、別にやりたかったわけじゃないし」
「だって、だってさ。幼稚園の頃やっていたじゃない? ママが言ってたわよ。明日歩君は天才剣士だって」
明日歩は顔を顰める。
一回や二回、大会で勝ったくらいで、大人は大騒ぎしすぎなんだ。相手に打たれるのが怖いから、先にやっつけないと、自分の身が危険だから必死になっただけで、それがどうして、天才とか言われるのか意味が分からない。
納得が出来ない知美は、なおも食い下がる。
「あんたは弱っちぃんだから、剣道みたいなので鍛錬した方が良いって」
「おめーは、ぐだぐだうるせんだよ。と、明日歩が申しております」
明日歩は目をひん剥き、克己を見る。
知美の表情がみるみる鬼と化し、腰に手を当て、何ですってと据わった声で言う。
明日歩は、違うと手を胸の前で動かすが、面白がった克己はさらに続けた。
「黙れこのブス。by明日歩」
「言ってないってば」
「ほれ、魔王に食べられてしまえ」
克己が歩の背中を押す。
まともに明日歩の体当たりを受け、知美がよろける。
完璧に面白がっている克己を恨みつつ、明日歩は一目散に、昇降口目指す。
靴をはき替えながら後ろを見る。
知美は追っては来なかった。
ホッとする明日歩だったが、油断は禁物である。
昇降口を出た明日歩は、後ろを振り返ることもせずに全速力で校門を出て行く。
そんな明日歩を、渡り廊下で知美は見ていた。
「もしかしてお前、剣道部?」
同じように隣で見ていた克己に言われ、知美はムッとなる。
「悪い?」
「ご愁傷様」
「うるさい。、だから、克己は嫌いなんだ」
行ってしまう知美に向かって、克己が悪たれを吐く。
「ばーか。明日歩がお前なんか、相手にするかよ」
「うるさい」
言い返す知美の瞳は、薄っすらと濡れていた。
☆
そんなこんなしているうちに、明日歩たちは五月を迎えていた。剣道部に入らなかった明日歩に、少々がっかりした顔を見せた両親だったが、思いがけず走る才能があったことを知り、今ではすっかりスプリンタースターになれ、などと言って、余るくらいの期待をかけてくる有様だった。
そして初めての試験に挑んだ明日歩と克己は、角谷のベンチに並んで座り、のんびりとアイスを食べていた。
日差しは、すでに夏を思わせるくらい暑い。
さっきから明日歩のアイスが溶け、ポタポタと地面に黒いしみを作っている。
かどや。
正式名称は金田商店というらしいが、誰もそう呼ばない。中学校に行く最後の曲がり角にあるから、かどやだ。
学校から死角になっているこの店は、明日歩たちの憩いの場所になっている。部活が終わって帰る途中、ここで買い食いをする。これがなかなか乙で堪らない。
本当は、今日から練習再開なのだが、明日歩はちらちらと克己の顔を盗み見る。
何があってもサッカーが一番の克己の様子がおかしいのだ。
試験期間に入り、練習が自粛させられるのを嫌っていたのに、そのことについて、一言も触れなかったのも謎の一つだが、練習再開するというのに、この沈み様は尋常じゃない。
弁当を一緒に食べようと誘いに行った明日歩を、克己はここえ誘ったのだ。
何か食べるものを買ったら、学校に戻るもんと思っていたが、アイスを買った克己は、ベンチに座り動こうとしなかった。
さっきまではしゃいでいた克己は、黙々とアイスを齧っている。
明日歩は、何を言っていいのか分からずにいた。
考えてみると、ここ何日か、克己の様子はおかしかった。
朝、会っても、あの軽佻な喋りがなく、気味が悪いほど静かだったのだ。
もともと勉強が得意では無い克己である。初めての試験勉強に、うんざりしているもんと、気にも留めずにいたのだが、考えてみると、克己の口から、まったくサッカーの話を聞かなくなったのは、初めてだった。
「あっ!」
明日歩のアイスが、地面に落ちる。
「だっせぇ」
克己はそう言いながら、そのアイスをめちゃくちゃに踏み潰す。
残念がる明日歩をチラッと見た克己が、ポツリと呟く。
「……俺、学校、辞めちゃおうかな」
あまりの衝撃に、明日歩は克己の顔を見入ってしまっていた。
今までに見たことがない、克己のさびしそうな横顔である。
「何か、つまんねぇよな、学校って」
明日歩は、喉の奥が痛んだ。
「義務教育だから、無理じゃねぇ」
カサカサの声で言う明日歩に、克己が引きつった笑みを向ける。
そのまま帰ろうとする克己に、明日歩は慌てて声を掛ける。
「練習行かないの?」
振り返り、克己は小さく笑いを残し走って行ってしまった。
練習したくない気持ちは、明日歩にもよく分かった。しかし、克己の場合、少し違うように思えた明日歩はその日、克己が置いて行ってしまったカバンを届けがてら、家に寄ってみた。
応対に出てきたのは、妹だった。
それっきり、明日歩は克己と会っていない。
克己は部屋に引きこもってしまったのだ。
いつも強気で、軽佻だった克己が登校拒否になってしまうなんて、明日歩には想像できなかった。
何となく、後味が悪い明日歩は、気には留めていても、なかなか克己の家へ足が向かずにいた。
☆
「ちょっと聞いた?」
知美が、ものすごい剣幕で教室に入って来たのは、克己が学校に来なくなってしまってから、一週間目の月曜日だった。
「克己のバカ、何で学校に来ないと思う?」
知美が明日歩の前を陣取り、顔を寄せてくる。
「先輩に、ボコられたんだって。何か余計なことを言ったんだってさ。それで先輩の反感をかったとかでさ、サッカー部の子から聞いてもうびっくり。明日歩、あいつから何か聞いていないの? 私が思うに、あいつのことだから、ベラベラと相当バカなことを言っちゃったんだよねきっと、じゃなきゃ、先輩たち全員が怒るなんてしないもんね」
その話を聞いた明日歩の顔色が悪くなる。
心当たりが大有りの明日歩なのだ。
明日歩の脳裏に、しまったままのドアが浮かぶ。
もしあそこに上級生の誰かがいたとしたら、完璧にあの豪語はサッカー部の先輩の耳に入ったに違いない。克己は確かにサッカーは上手い。だけど縦の社会とか、ルールとかに皆無と言っていいくらい疎い。それで何度か失敗もしているはずなのに……。
忠告するたびに見せていた笑顔を思い出した明日歩は、頭を抱えてしまう。
「明日歩、あんた何か知っているの?」
知美に詰め寄られ、明日歩はつい仰け反ってしまう。
確信はない話だ。迂闊に言って、大きくされては困ると思った明日歩は、言葉を濁す。
「あのさ、こんなのは、私が言うのもどうかと思うけどさ、心配にならないの? 友達でしょ? 幼馴染みなんだよ私たち。力になってあげようとか思わないわけ?」
苦笑する明日歩を見て、知美がいきり立つ。
「ちょっと、訊いてんの? あんた、友達が学校へ来なくなっちゃっているんだよ。それ放っておいて平気なの?」
知美はみんなの注目を浴びてしまっていた。
今にも泣きだしそうな目で睨まれ、明日歩はしどろもどろだった。
痛いところを突かれてしまっていた。
明日歩は、かどやの一件が頭から離れなかった。
そんなこと言ったって。
明日歩にだって言い分はある。
試合続きで、練習だってあるし、行っている暇ないんだから仕方がないだろ。友達だから、何でもかんでも力になれるって、思うなよ。俺だって、俺だってな。
腹の中でたらふく文句を言った明日歩は、嘯く。
「行ってるよ」
「本当?」
語尾を上げて、知美は怪しむ。
本当本当と繰り返す明日歩は、内心焦りを感じていた。
「もう仕方がないなぁ。私も一緒に」
「いや、最初は俺一人が良いと思う」
明日歩は慌てて知美の言葉を遮る。
それだけはどうしても避けたい、明日歩だった。
何度か足を運ぶが、克己は一向に部屋から出てここ様とはしなかった。毎日のように知美にはなじられるは、練習はきついはで、明日歩はパンパンになってしまっていた。
七月に入り、拍車がかかる。
このままでは身が持たないと思った明日歩は、ある決意をしていた。
今日も大会を終わらせて、明日歩はその足で克己の家へやって来ていた。
一週間もすれば、夏休みにはいてしまう。
明日歩は何としても、克己にまたサッカーの練習に出て欲しいと思っている。何がなくてもサッカーをしているときの克己は、キラキラとしていた。無理無理させられている明日歩と違って、克己がサッカーへ向ける情熱は、まったく別物。こんなことで終わりにさせたくないのだ。
克己の部屋を見上げ、明日歩は大きく深呼吸をする。
さんざん考えて、明日歩は昔、克己とやった遊びを思い出していた。
ガサガサと伸びた枝を伝っていく。
あの頃は低学年で、躰も小さく、何より体重が軽かった。
何本か枝が折れる音を聞きながら、やっとの思いでベランダに飛び移った明日歩は、克己の部屋の窓を叩く。
ゲームをしていた克己が目を真ん丸にして、開けてくれた。
「隊長、作戦成功であります」
明日歩は、敬礼をして見せる。
ご自慢の体脂肪率の姿は全くなく、二倍以上に膨れ上がった克己が力なく微笑む。
その先の言葉が思い浮かばない明日歩を無視した克己が、またゲームをし出す。
何度か話し掛けたものの、まったく反応を示さない克己に、明日歩はやれやれと首を振る。
話すのはあまり得意ではない明日歩である。
おしゃべりな克己に相槌を打って、いつも会話を成立させていた二人なのだ。
ベッドの上にあったものをおもむろにどかした明日歩を、克己がチラッと見る。
何を思ったか、明日歩はカバンから出したものを並べ始め出していた。
消毒液にヘアカラー。裁縫セットにファンシーショップの袋。
何がしたいんだという目で見ている克己に、明日歩は引き攣り笑顔を見せる。
「克己、氷ねえ?」
無視しようとする克己の顔を覗き込み、明日歩は一字一句切って尋ねる。
「だ、か、ら、こ、お、り」
そんな明日歩を、克己は舌打ちをして煙たがる。
ここで怯むわけにはいかない明日歩だった。
かなりの気合を入れて、ここへやって来ているのだ。
正直、吐きそうである。
「オレ、変身することに決めた」
いきなり胸を張って言う明日歩を見て、克己は笑いそうになる。
「変身って、バカかお前?」
「バカはどっちだよ」
「何、ケンカしに来たわけ?」
「ちげーよ。良いから氷」
「氷なんて、何に使うんだよ」
「良いから早く」
「大体これ、何?」
「変身道具」
「はっ、何がしたいの俺んちで?」
そう言われても困る明日歩だった。
何とかしてやりたい気持ちはあるのに、明日歩には名案が浮かばなかった。どんどん月日は過ぎて行ってしまい、毎日のように知美は攻めたてて来るしで、そんな時だった。ご飯を食べ終わって、風呂に入るのも面倒に思っていた明日歩の目に、秘策が飛び込んで来る。
直感が走り、名案が閃く。
テレビ画面を食い入るように、明日歩は見ていた。
「新しい自分に出会える。あなたも変わって、出かけてみませんか」
ヘアカラーのCMだった。
単純に、納得してしまった明日歩は、これしかないと思い込んでしまっていた。
本当は克己を変身させればいいのだが、知美にその案を打ち明けた時、思いきりバカにされて、変更せざるを得なくなってしまう。
「髪なんか染めたら、ますます先輩とかに目をつけられちゃうじゃん」
ごもっともの意見に、明日歩は委縮してしまう。
「でも、案外それいいかも。普段そんなこともやりそうもない明日歩が、勇気振り絞ってやってあげたら、明日歩以上に単純な克己なら、感動してくれるかも」
端々に、苛立ちを覚える明日歩だったが、やると決めてしまった以上、引っ込みがつかなくなってしまっていたのも事実。
「そっかな」
「そうだよ。絶対いけるって」
薬局屋で品定めをしているところに知美が現れ、嫌な笑みを浮かべる。
こういう笑みを浮かべるときに知美は、ろくなもんじゃない。
嫌な予感は的中だった。
店を出た途端、悪乗りをした知美はこれも有だよねと、袋を差し出してきた。
訝る明日歩に、知美はひらひらと手を振る。
「私のおごりよ。お礼は明日、私に一日付き合ってね」
え?
袋の中身は、髑髏のピアスだった。
「あとで連絡するね」
ええ。そう言う条件なら、絶対いらないと、突き返したい明日歩だが、自転車で来ていた知美の姿はあっという間に見えなくなってしまっていた。
こうなったら破れかぶれの明日歩である。
「そんなことをしたら、ヤバくねぇ」
「ヤバいに決まっているでしょ。んなこと言われなくたって、知っているし」
「何でキレているんだよ」
「良いから早く、氷だよ氷」
舌打ちをした克己が階下へ氷を取りに行き、明日歩は泣きたい気分になった。
☆
明日歩がそんなことをしようとしているとは、微塵も思いもしない奈緒は、物思いに耽っていた。
今朝も、明日歩と口論になってしまった奈緒である。
原因は些細なことだった。
なるべく、あれこれと口やかましくしないよう努力はしているが、つい口を出してしまうのは、母親の性である。
忘れ物はないかという奈緒に、明日歩は突っかかって来たのだ。
大きな大会前、緊張しているせいだろうと思うが、口が過ぎるその態度を、奈緒は咎めた。
最後は、腹立ちまぎれに玄関を思いっきり強く閉めて、明日歩が出かけて行った。
どうしたものかと、毎日のように、奈緒は明日歩に頭を抱えさせられている。中学生になり、学生服を着た明日歩は、身長が高いせいか、やたら大人びて見える。小学生相手とは違う、迫力があるのだ。
反抗期のど真ん中の明日歩の扱いは難しい。
頼みの綱である父親の歩はいたって冷静で、泣きつく奈緒に、放っておけばいいと言うばかりだった。
その歩は今、留守をしている。父親である光彦の具合が悪く、両親が住む静岡に行っているのだ。
いつまで続くことやらと、奈緒は深い溜息を吐く。
明日歩の反抗期はもう二年以上続いている。
このまんま、まともに口をきいてもらえないままになってしまうのではと、奈緒を恐怖が襲う。
そんな悩みを抱えていたから、尚更だった。
試合に出かけて行った明日歩が、別人になって帰ってきた衝撃は、言葉に居表せないほど大きなものだった。
髪が赤茶色に染められ、耳にはピアスまでが嵌められているのだ。気持ち、眉も薄くなっている気がする奈緒だった。
わなわなしている奈緒を一瞥した明日歩が、無言で階段を上がって行く。
「明日歩、ちょっと待ちなさい」
つい大声を張り上げてしまった奈緒を、明日歩はまるで無視で、自室へと行ってしまう。
もう限界だった。
縋る思いで携帯を握りしめた奈緒は、そこで思い止まる。
父親と最期の別れをしようとしている人に、こんな報せ、してもいいものなのか奈緒は思い悩んだ。
部屋をノックしても、応答はなかった。
夕飯に呼んでも、明日歩は一向に姿を見せようとはしなかった。
散々迷い、奈緒は歩にメールで近況報告を済ますと、再び明日歩の部屋をノックする。
歩から早速返事が戻って来る。
その内容を見て、奈緒は涙がジンワリ滲みだす。
(それは面白そうだ。今すぐ帰るよ)
(面白がらないで)
(これは失敬)
帰って来ると言っても、翌日になると思っていた奈緒だったが、深夜ごそごそと布団に入ってくる気配に、飛び起きてしまう。
「ごめん、起こした?」
「歩」
「ただいま」
大きな欠伸をしながら言う歩に、奈緒は思わず抱き付いてしまっていた。
「もう大丈夫だから、心細い思いさせてごめんな」
奈緒は大きく首を振る。
それを見た歩は目を細め、奈緒を強く抱きしめる。
翌朝、こっそり出かけようとする明日歩は、茶の間で寛ぐ歩に遭遇し、ぎくりとする。
明日歩に気が付いた歩は、何もなかったかのように、穏やかな笑みでおはようと言ったきりで、普通にコーヒーを啜り、新聞を読んでいた。
思ったより寛大、と思ったのも束の間だった。
「さて」
そう言って新聞をとじた歩が、明日歩を見てニヤッとする。
背筋がゾクッとなる。
こういう目をする時の歩は、良くないことを企んでいるのだ。
「明日歩、出かけるのか?」
相手が奈緒なら、無視をするところだが、歩だとそうはいかない。
ポケットから財布を取り出し、手招く。
「小遣い、足りてないんじゃないか。どこへ行くんだ」
「遊園地」
「今日は良いなぁ。一日天気、良いみたいだし、誰と行くんだ? 彼女とか」
「んなんじゃねよ」
「にしても、身だしなみは大事だぞ。どれどれお父さんがしてやろうじゃないか」
明日歩は身構える。
美味いことを言って、髪を切るつもりだと、明日歩はてっきり思ったが、歩が取り出したのははさみではなく、ワックスだった。
がっちりセットをした明日歩を見て、歩は笑みを零す。
「行って来い。充分楽しんで来いよ」
拍子抜けしていた明日歩は、歩に押され出かけて行く。
納得できない奈緒が、歩を睨む。
「男の子は、一度くらいはこういう時期があるもんだよ。かわいいもんじゃないか。すぐに落ち着くから、そうカリカリしなくても大丈夫だから」
穏やかに笑う歩につられ、笑ってしまう奈緒だった。
駅に向かって歩き出したものの、明日歩は落ち着かなかった。
普通の親なら、どうしたんだろうと思う。
怒られる覚悟はしていた。
何なんだよ。
すっかり分からなくなってしまった明日歩である。
しかし、ぐちゃぐちゃになった頭で、明日歩は一つ思い当ったことがある。それは明日歩が六年生の時だった。奈緒の着る洋服が、どうにも許せない明日歩は、わざと授業参観の知らせを見せないことがあった。それはすぐにばれ、奈緒と言い合いになってしまったのだ。確かに、他の母親とは違ってフリルが多い服を着ているのは、分っていた。女子たちに、あのお洋服かわいいなって言われて、悪い気はしなかった。しかし、それが一変する出来事が、明日歩に起こってしまったのだ。いつも愛想よく話し掛けてくれていたクラスメイトの母親たちが集まって、何かを話しているところだった。盗み聞きする気はなかった。通りかかった明日歩のことに全く気が付いていない母親たちは、奈緒の噂をしていたのだ。
「またあんな格好して」
「あの人、齢おいくつなのかしら」
「三十は優に超えているわよね」
「私の娘だって、あんな格好してないわよ」
「あら娘さんおいくつ?」
「17歳」
「ええ、そんな大きな娘さんがいたの?」
そこまで聞いて、明日歩は家まで走り帰った。
家に戻ると、のんきに奈緒が話しかけてきた。
見ればフリフリの洋服を着ていて、明日歩は、カッと頭に血が上る。
「明日歩、おやつあるわよ」
「いらない」
「どうしたの? 機嫌悪いわね」
普段、奈緒と仲良く喋っている母親だった。明日歩は恥ずかしさ口惜しさで、涙が止まらなかった。そして思ってしまったのだ。そもそもあんな格好で学校へ来る母親が悪いって。そこから明日歩は奈緒にたてつくようになり、一緒に居たがらなくなったのだ。
参観日が来るたび、二人は決まって口論になる。
「くんなったら、くんな」
「どうしてよ? 親が参観日に行くのは当たり前でしょ?」
その日も似たようなことになり、二人とも引っ込みがつかなくなってしまっていた。
「うるせぇ、くそばば。そんな恰好をしている親なんかいねーんだよ」
目を大きく見開く奈緒を、明日歩は尚更許せない気持ちになる。
非番で、ちょっと知り合いの所へ行って来ると出かけていた歩が、庭から何事かと顔をひょっこり見せたのは、そんな時だった。
歩は絶対に奈緒の味方をする。
何があってもだ。
明日歩は独りぼっちになった気がして、思わず家を飛び出す。
冬の初めだった。
薄着で飛び出してしまった明日歩だったが、帰るに帰れず公園のベンチで丸まっていると、人の気配がして顔を上げると。歩がニコニコとして立っていた。
叱られると思った明日歩は、すぐに顔を伏せてしまう。
けど歩は、黙ったまま隣に座って来た。
フワッと上着を着せられ、抱きしめられた明日歩の目に、涙が込み上げてくる。
「星が、綺麗だな」
明日歩は鼻を啜り、何も答えなかった。
「なぁ明日歩、明日歩は奈緒のことが嫌いか?」
好きとか嫌いとか、そういう次元じゃない。常識の問題だ。
明日歩は俯いたまま、首を大きく横に振ってみせる。
「あんなことを言うなよ。奈緒、泣いていたぞ」
泣きたいのは、ぼくの方だ。
明日歩は、足元の石を蹴る。
じっと見ている歩の視線を感じ、俯いたまま、明日歩は口を尖らせた。
「父さんは、あんな格好をされて、恥ずかしくないの?」
怒った口調の明日歩に歩は、そうだなと腕を組む。
「確かに、他のお母さんが着ている服に比べて、奈緒の着ている服は可愛らしいけど、それがどうしていけないのかな? 服なんて所詮、肌を隠す道具だろ? 問題は中身だと思うけどな」
明日歩は、チラッと歩を見る。
「でも、みんな、笑っているよ。年甲斐もない服だって」
「そうか、みんながか……」
うーんと伸びをした歩は、明日歩の肩を抱く。
「なぁ明日歩、例えば誰かが、奈緒の着ている服が、最新式で格好いいとか可愛いって言うだろ、そしたらみんなが同じ格好をし始める。ファッションってそういうものなんだ。だけど奈緒は、自分の感性を曲げず、貫き通している。それって、素敵なことだと思わないか?」
「思わない」
不貞腐れて言う明日歩に、歩はゲラゲラ笑った。
「みんながみんな、同じだとつまらないだろう」
「つまらなくても良いよ」
ブスッとした声で言い返す明日歩に、歩は目を細める。
「そんなこと言うなよ。奈緒が待っている、帰ろう」
明日歩の頭を撫でた歩が、ハーと息を吐き出す。
目の前に目の前に白く広がった行きは、瞬く間に消え、歩がニッと歯を見せる。
「明日歩、お前もやってみろ」
言われるままに明日歩も息を吐き出す。
それは何度か繰り返され、歩が空を見上げながら言うのだ。
「よく、ため息をつくと、幸せが逃げると言われるけど、オレは悪いことじゃないと思う。こうして、たまには息を抜くのも、大切なことなんだよ」
ゆっくり歩きだす歩の背中が、妙に大きく感じた瞬間だった。
明日歩には、歩がよく分からなかった。
いい歳をして、ヒーロー番組を真剣に見たり、あんな恰好をして歩く奈緒を、素敵だと言ってみたり、どうかしていると思う。それに、いつも奈緒奈緒って……。
明日歩の視線を感じ、歩が振り返る。
ん?
首を傾げる歩から、明日歩は何も言わずに、視線を外す。
そして、一生ぼくには、理解できない、とその時明日歩は思ったのだった。
だから、歩のあの反応はあながち間違ってはいないことに気が付いた明日歩は、待ち合わせ場所へと足を速めた。
途中、のろのろと躰を重そうに歩いている克己に遭遇した明日歩は、後ろから飛び乗り、大ひんしゅくを買う。
改めてみる明日歩の姿に、克己は笑ってはいけないのだろうけどと言いながら、大爆笑する。
「誰のおかげで、こうなったんだと思っているんだよ」
口をとんがらせて言う明日歩に一応謝るが、まるで心が籠っていなかった。
駅に着き、明日歩は人に見られている気がして、やたら前髪を気にする。
「お前、気合入れすぎじゃねぇ」
言われて、明日歩は顔を赤くする。
セットされたのはいいが、明日歩は自分の姿を鏡で見てこなかったのだ。克己に言われて、初めて頭に金粉スプレーをされていることに気が付いた明日歩である。何かを振り返らえた記憶はあったが、まさかこんなものを用意していたとは思わなかった明日歩は、トイレの鏡を見てがっくり肩を落とす。
童顔である明日歩に、この髪形は全然と言っていいほど、似合っていない。恥ずかしくて仕方がないのだ。
遅れてやって来た知美は、じゃれ合っている二人を見つけ、ホッとなる。
「それにしても壮大だな」
一歩前へ出た知美が振り返り、にやにや言う。
赤茶色の髪を立て、髑髏のピアスをしている明日歩と、デブになった克己と一緒に遊べる日がまた来るとは思ってもみなかった知美である。喜びは、ひとしおなのは、しょうがないこと。本人たちはまるで知らないだろうけど、この二人、女子には人気があるのだ。きっと、気弱な明日歩がこんな恰好をして歩くのは、そう滅多にないことだと思うと、喜びがにじみ出て来てしまう知美なのだ。
知美が面白がって明日歩の前髪を触りまくる。
「止めろよ」
無造作に髪を掻き上げる明日歩を見た瞬間、知美はドキッとして、言葉が出なくなってしまう。
「知美、涎が出ているぞ」
克己に耳打ちをされ、知美は顔を赤くする。
明日歩と喋りながら階段を上がって行く克己の尻目がけてカバンをぶつけた知美が、追い抜いて行く。それをまた克己が追いかけ、久しぶりの感覚に、明日歩は笑い転げる。
二人揃うと、いつもこうだ。
ホームで電車を待っている人たちが、大騒ぎしている二人を訝る眼差しで見ているのに気が付いた明日歩が、克己の上着を引っ張る。
「何だよ明日歩」
「こんな所で、騒ぐなよ」
ボソッと呟く明日歩を見て、克己と知美が二人して顔を見合わせる。
「シンポだ!」
なぜ今ここでその言葉が発せられたのか、明日歩には全く分からなかった。
怪訝な顔をする明日歩を見て、克己が首に腕を回してくる。
「お前も大人になったな。こんな髪をして、こんなもんまでつけている不良少年とは思えん」
克己の言葉に、知美が大きく頷く。
「どういう意味だよ」
克己がニヤッとする。
「君不良。僕、ただの少年」
明日歩はグッと喉を鳴らす。
誰から見ても、今の状態では、克己の言葉が正論だった。
「じゃあさ、陰でオレのこと、ピー助とか言うなよ」
「無理」
克己と知美の声がハモる。
この二人は何かというと、大泣きして登園していた時のことを持ち出しては、明日歩をからかうのだ。
幼稚園の二年間、二人はずっと一緒のクラスだった。
前へ出るのが苦手な明日歩の手を、グイグイ引っ張る知美から奪い返す役目が、克己だった。
どういうわけか、この縮図は誰かに言われたからとかではなく、自然と出来上がっていた。
べそをかく明日歩に、克己はいつも怒るのだ。
「ちゃんと嫌だっていえよ。あんな雌ゴリラ、怖くないやい」
克己はその頃、背が低く、今ほどすばしっこくなかった。ケンカもそれほど強くなかったのだが、負けん気だけは誰よりも強かったのは、明日歩に印象深く残っている。
とにかくサッカーが好きで好きで、その話しかしてこないのだ。
笑っている克己を見て、明日歩はホッと胸を撫で下ろす。
大騒ぎで着いた遊園地で、俄然知美が張り切りだす。
乗り物を三つ乗ったところで、明日歩と克己は飽きはじめているのに、知美だけがやたら元気だった。
「あいつ、性別間違っていないか?」
知美がトイレに行った隙に、克己が明日歩に耳打ちをしてきた。
「確かに。あれが女だと、オレは認めない」
本人いないのをいいことに、明日歩がフンと鼻を鳴らし、胸を反って見せる。
「ぜってー、実は男でしたって言いそうじゃん」
克己が悪乗りをして、合の手を入れる。
「あるある。て言うかあいつ人なの?」
いつもの克己に戻っていた。
嬉しくなった明日歩が相槌を打つと、克己が知美の物まねを始めだす。
ひとしきり笑って、克己が腹を押さえながら言う。
「あいつさ、ぜってートイレから帰ってきたら、乗り物全制覇するわよ。なんて言いそうじゃねぇ」
「言うよ。絶対あいつなら言う。何せ不敵な女だからな」
何も知らずに帰ってきた知美が、さぁ、全部の乗り物に乗るわよと宣言した途端、二人は一斉に噴き出す。
こんなに二人がなぜ笑うのか分からない知美である。
「だって高い入場料、取られてんのよ。当たり前でしょ」
「ケチ女」
「煩い。デブ」
また始まってしまった二人の追いかけっこの始まりである。
閉園時間ギリギリまで粘って、乗り物を全制覇を成し遂げた三人は、流石にクタクタだった。
すっかり暗くなってしまった道を、会話もなく歩いていると、突然、知美が立ち止まる。
「もう少し遊んでいかない?」
知美が、公園を指差して言う。
明日歩と克己は一緒の方角だが、知美は、ここで曲がっていかなければならない。
「いやだよ。もう遅いし」
明日歩がボソッと答えると、知美が腰に手を当てて、だったら送って行ってよと口を尖らせる。
「何で?」
克己と明日歩が声を揃える。
「女の子が、こんな夜道を一人で歩くのは、危険でしょ?」
「女の子?」
明日歩が首を傾げる。
「ここに女の子っていたっけ?」
「克己!」
パッと二人が散り、公園の中を逃げ回る。やっとの思いで克己を捕まえた知美が、克己の頭の上に、何かを置く。
「ま、これからしばらくは受難だろうから、これでも持ってお行き。じゃあね。おやすみ」
知美が後ろ向きで手を振って帰って行ってしまうと、克己は頭の上に乗せられたものを不思議そうに眺め、首を傾げる。
明日歩も、克己の手元を見て呟く。
「合格祈願?」
澄ました顔の地蔵の足元に、ピンクの文字で書かれたお札が、ヒラヒラと風になびく。
「なぞだ」
克己が呟く。
「なぞ過ぎるだろ。やっぱり、不敵な女だ」
明日歩が難しい顔をして、人差し指で眉間を、軽く叩いて見せる。
「バカか?」
その仕草を見て克己は、今にも泣きそうな顔で明日歩を、小突く。
「学校、行きたい」
克己がぼそっと呟く。
「え? まさか休む気だったの? この髪、チミが染めたんだよ。これは共犯者も一緒に、怒られて貰わないと、ボクチンとしては割りに合わないっすよ。頼みますよ。しぇんしぇい」
「先生じゃねーし」
明日歩が克己に、頭を突き当てて行く。
「……分かった。分かった。行きます。行かせて貰います」
「当然です」
「ありがとう」
克己の声は、涙で擦れていた。
翌朝、学校は大騒ぎになった。
不登校になっていた克己が、登校してきただけでもニュースなのに、大人しい明日歩の変わり様に、誰もが唖然とさせられてしまっていた。
校門を潜り抜けようとする明日歩を、生徒指導の主任が腕を掴む。
「やっぱり無理だったか?」
呟く明日歩は頭を小突かれてしまう。
予想はしていたことである。
それほど驚くことではなかった。
呆然と立ち尽くす克己の腕を、知美が引っ張る。
「何だあいつ」
背後から聞こえてきた声に、克己は肩をビクつかせる。
じろじろ見られている気がして、克己の足が竦んでしまっていた。
「バカね。自信過剰過ぎ。皆明日歩見てんじゃん。っていうか、ここで帰るとかなしだからね。何のために明日歩があそこまでしたか、考えなさいよ」
顔を引き攣らせた克己の腕を取った知美は、グイグイと引っ張って行く。
克己の変貌ぶりに、何人かの女子が、がっかりだねと言う声を聞きながら、知美は職員室の様子を伺う。
「どうした。何か用事があるのか?」
剣道部の顧問に見つかり、ばつが悪い顔をする知美だが、思い直して明日歩のことを訊いた。
「ああ、中田か。まったくやってくれるよな。剣道部にさえ入ってくれればあんなことはさせなかったのにな。また強引に連れて来いよ」
知美は苦笑した。
顧問は明日歩が仮入部してきた時から、ずっと目をつけていた。今でも自分が育ててみたいと思っているらしく、ことある毎に知美に言って来る。
知美は礼儀正しく頭を下げると、一目散に進路相談室に向かった。
進路相談室。
小さな部屋にくくりつけのガラスケース。
ずらりと並べられている高校の資料。店頭で売られているものばかりなのに、ご丁寧に鍵が付けられている。
こんな物、盗む奴はいないのに……。
「明日歩」
明日歩がビクンと肩を震わせ振り返ると、知美が心配そうな顔を覗かせていた。
「大丈夫?」
大丈夫なわけがない。
明日歩は、軽く首を竦めて見せる。
「克己は、無事に教室にぶっこんだから。じゃ、健闘を祈る」
何の戦いだよ。本当に、知美はなぞだ。
「あら西沢さん?」
担任の槻岡の声に飛び上がった知美は、慌てて後ろ手てドアを閉める。
「丁度良かった。一時間目と二時間目は自習にするから、黒板に書いておいて。みんなをくれぐれも騒がせない様にね。頼みましたよ」
「分かりました。失礼します」
槻岡が進路室に入って行くのを見届けた知美は、言われたとおりに黒板に大きく自習と書くと、また教室を飛び出して行く。
明日歩の変身は、予想外に大きく扱われている気がする。容姿が乱れている奴なんて、学年に三人くらいは普通にいる。髪の色も怪しい奴はかなりいるし、学校の対応に憤慨しながら、知美は明日歩を見守れる場所を探し回る。
明日歩は、自分の考えの甘さに愕然としていた。
初犯なら、厳重注意されて、すぐに髪の色を戻せばいいと思っていた。ピアスだって今日はしてくるつもりはなかったのに、髑髏はグロすぎるから、こっちの方を付けて行きなさいと、奈緒のピアスを歩に渡された。引っ込みがつかずに素直に嵌めて来てしまったけど、参った。
せっかく痛い思いして開けたんだから、ちゃんとつけておけよって……。
ここでは狭いからと会議室に通された明日歩は憮然としていた。
「もうすぐ親御さんもお見えになられるから、それまで反省しているように」
担任である槻岡を、明日歩は恨めしく思う。
お門違いなことは重々承知のうえ、非は全部自分にある。
明日歩は、自分お考えの浅はかさに、髪を掻き毟る。
奈緒が来る。来てしまう。たぶん、歩も一緒だ。どうせ呼び出しをするなら、父親のほうだけにしてくれと、頼めばよかったと、明日歩は真剣に思う。
しばらくして、廊下の方から声が聞こえてきた。
明日歩は耳を澄ます。
槻岡と話しているのは、明らかに歩だった。
ドアが開らき、神妙な顔をした二人を見た明日歩は、落胆しきる。
「中田君、ご両親が見えたから、行きますよ。そう落ち込まないの。自分がしでかしちゃったことなんだから」
まさか落ち込んでいるのが両親揃ってのお出ましのこととは知らない槻岡が、明日歩の肩を軽く叩く。
奈緒は、色は黒を着ているけど、大きなフリルの襟がついた白のブラウスに黒のベストとスカートの裾からはアンダーコートのフリルが見え隠れしていた。それに比べて、歩は綿シャツに、ジーンズ姿でラフすぎる格好に、何を思ったか細い黒縁のメガネを掛けている。
遅れて学年主任の村沢と、教頭の桐原が入って来た。
明日歩と同様、集められた教師たちも同じことを思ったらしく、表情があからさまに険悪なものになっていた。
気を取り直した桐原が、呼び出した概要を喋り、それを村沢が補足する。槻岡は新任の教師で、一字一句落とすまいとメモを取る。
「要するに髪の色を、戻せっていうことですか?」
ことの重大さを、どう表現しようかと大袈裟に説明する教師達に対し歩は横柄な態度を取り始める。
「かいつまんで言ってしまえばそうですが、ここで大事なのは彼の心に何が起きたかで、これからのケアが大切だということで」
「つまり、明日歩が不良になったと、村沢先生は言いたいのですか?」
言い返したのは、奈緒の方だった。
明日歩は、えっと目を上げた。
奈緒にしては、珍しいきつい言い方である。
「そのようなことは申してはおりません。ですが、こういう小さなことが要因になりうるってことです」
「髪を染めただけで?」
素っ頓狂な声で言う歩に、教師達が顔を見合わせる。
「中田さん、容姿の乱れが一番危険なんですよ」
槻岡がきつい声で言うのを、奈緒はおとなしく聞き逃さずにいた。
「この子は、不良にはなりません。何か理由あって、こんな格好をしているんだと思います。むしろ、そうやって決めつけてしまうのが、問題ではありませんか?」
歩も大きく頷く。
こんな状況に耐えきれるほどの図太い神経を持っていない明日歩である。
「僕は、どうしたらいいんですか?」
「髪の色を直してくることと、反省文三枚明日までに提出しなさい」
桐原の言葉に明日歩は、立ち上がって謝ると、一目散で飛び出して行く。
「まだ話は終わっていませんよ」
遠くで槻岡の声が追いかけて来たが、無視をした明日歩は靴を履き替え外に出る。
「おーい明日歩」
呼ばれて明日歩は校舎を見上げる。
克己が大きく手を振るのが見えた。
すぐに教室へ引き戻されていき、明日歩は肩を窄める。
これで良かったと思うしかない、と明日歩は思うことにした。
とりあえず、これで知美に攻めたてられることはなくなったのだから。
明日歩が飛び出して行った後、しばらく歩たちは教師相手に押し問答を繰り返していた。
歩たちの無茶苦茶な言い分に、教師たちは喧々囂々になり、半ば飽きられられて解散してきたのだが、校門の前で知美が待ち構えているのを見つけた二人は顔を見合わせてしまう。
「どうかしたの?」
奈緒の質問に、一呼吸置いた知美が凛としてみせる。
そんな姿を見て、二人は思わず微笑む。
「ごめんなさい。私、明日歩に口止めされていたんだけど、どうしても黙っていられなくって」
知美は一気に話しきり、頭を下げる。
「知美ちゃん、話してくれてありがとうね」
「気を使わせちゃって、申し訳ない。明日歩には俺から良く言って聞かせるから、知美ちゃん、まだお昼食べてないんだろ? 早く教室に戻らないと」
「でも、明日歩は絶対に悪くないです。だから」
「大丈夫よ。正義心が強いのは父親譲りだから。ね、歩」
「まぁな。バカさ加減も俺そっくりだ。あれだな。正義の味方はこのくらいが調度いのかもな」
「何を言っているの。皆を巻き込んで、こんなかわいらしいお友達を困らせて、少しは懲りて貰わないと」
「そっか」
「そうですよ」
「知美ちゃん、本当に心配かけてすいませんでした。これに懲りず、明日歩と仲良くしてやってください」
知美は、感激で涙が出そうになり、慌てて二人に頭を下げ、校舎へと戻って行った。
そんな知美を見て、かわいいわねと歩と奈緒はほほ笑みあう。
「少し遠回りして帰ろう」
奈緒は嬉しそうに、歩に日傘をさしかける。
「だけど血筋って、凄いわね」
「ああそうだな。これで安泰。正義の味方は永遠に不滅だってか」
「まぁ」
父親の病気のこともあって、こうしてのんびりと二人で歩くのは、本当に久しぶりだった。
通りかかった金子商店の前。
置かれた木のベンチに、男の子が一人で座って、アイスクリームを食べていた。店の中から老婆が出て来て、その男の子に話しかけながら、花の手入れを始めるのを見て、二人は目を細め合う。
「こんにちは」
二人に気がついた老婆に挨拶され、二人も会釈する。
「お孫さんですか?」
歩に尋ねられた老婆が、柔らかい笑みで答える。
「近所の子なんですよ。ちょっとだけ、ここでお留守番ね」
男の子がコクンと頷く。
「預かって差し上げているんですか? 偉いですね」
奈緒の言葉に、老婆は目を細め首を振る。
「ちっとも偉くないんですよ。私達は歳をとっているから、いつぽっくりいくか分からないでしょう。子供らもみんな他所に行ってしまっているしね。こうしてこの子たちが昼も夜も関係なく遊びに来てくれているのは、私達も助かっているんですよ」
「持ちつ持たれつですね」
歩の言葉に、老婆が嬉しそうに頷く。
「お互い様が役に立って、私たちはそれで、長生き出来ているんです」
男の子の母親が迎えにやって来て、二人はそこで話を終え、離れて行く。
「変わっていないなぁ」
奈緒が言うと、歩はそうなの、と訊き返す。
「あの人には、よく叱られたな。他所の子供も自分の子供も同じ。悪いことは悪いのって」
「へぇ、奈緒にもそんな時代があったんだ」
「中学の時はね、ちょっとだけやんちゃだったの」
「ああいうのを、正義の味方って言うんだろうな」
呟く歩に、奈緒は微笑み返す。
その頃、先に帰って来ていた明日歩は、自分の部屋に戻る気になれず、茶の間でふて寝をしていた。
玄関先から歩たちの声が聞こえ、明日歩は耳をそば立てる。
「あの教師はなっていないな」
歩の言葉に、明日歩は眉根を寄せる。
「いまどきピアスの一つくらい普通よね。赤ちゃんで、開ける子だっているご時世よ」
「この際だから転校させるか」
だんだん不安が募り、明日歩は居ても立っても居られない気持ちになる。
明日歩は薄目を開け、入って来た二人の様子を伺う。
「こんなもので、染め直させなくっても、十分に似合っているわ」
「オレもそう思う」
耐え切れなくなり、起き上がった明日歩は、歩が手からその箱を引っ手繰ると、洗面台へと飛び込んで行く。
余計なことを言っても言われたくもなかった明日歩は、何も考えずに箱を赤て中身を出す。手順は昨日やったばかりで覚えている明日歩に、躊躇いはなかった。
「明日歩、手伝おうか」
入ってこようとする奈緒に、明日歩はドアを体で押さえ阻止を図る。
「……30分経ったら教えろ!」
「教えろじゃないでしょ。教えてくださいでしょ」
明日歩はその場に座り込み、頬杖をついて考え込んでしまっていた。
何であんなんだろうと、明日歩はつくづく思う。
ドアがノックされ、奈緒が時間を知らせに来た。
そして再び鏡を見た明日歩は、絶句する。
少し赤身は取れたが、それでもまだ髪は茶色かった。
ごみ箱をあさり、拾い上げた箱を見て、明日歩は愕然となる。
……モカブランって。はぁ?
箱を」をちゃんと確認すれば良かった。あり得ない。
勢いよく洗面所のドアを開けると、奈緒が、あら、上手ね。今度私もしてもらおうかしらと、のんびりとした口調で言って来る。
「どこの親が、元の色に戻せって言われて、この色を買うんだよ? 間違ったのか」
詰め寄る明日歩に、奈緒は涼しげな顔をして、あなたの髪の色ってその色だったでしょ、と平然と答えた。
だから、嫌いなんだ。
床屋代をふんだくって玄関を出る明日歩を、歩が呼び止める。
「出かけるのか? 不良君」
どうしてこんな親なんだろう?
「やっぱり不良になると、睨みが違うな」
腹を立てるだけ無駄ってことか。
諦めにも似た感情が沸き起こり、明日歩は黙ったまま自転車を走らせた。
幻の不良はすっかり丸坊主の少年に生まれ変わり、責任を感じた克己が、しつっこいくらい謝る。
翌日、女子は頭を撫でさせろと煩いし、散々だった明日歩は部活へ出る気になれず、家にいた。
ベッドに寝転がり漫画を読んでいると、開けっ放しにしていた窓から聞こえてくる声に聞き覚えがあった。
そっと、明日歩は下を覗く。
思ったとおり、克己の母親だった。
「明日歩君のおかげでうちの子、学校に行けるようになったわ」
「お役に立てて何よりです。でも、立ち直ってくれて、本当に良かったわね」
「本当。私、あの子のこと、少し買い被ってみたい」
「克己君、しっかり者だから、つい大丈夫って思っちゃうのよね。うちの明日歩とは段違いよね」
「そんなことないわ。明日歩君がいなかったら、本当にありがとうって伝えて置いて」
ないがチラッと部屋を見上げるのが見え、慌てて明日歩は首をひっこめる。
「それでね、ついでって言っちゃなんだけど、明日歩君にお願いがあるの?」
明日歩は耳をそば立てた。
「もう少しで期末テストでしょ? うちの子、ずっとお休みしていたから、ただでさえバカなのに、部活も辞めるって言ってるし、取り付く島もないと言うか……」
「あら、明日歩だって似たようなものよ」
「またまた。西沢さんから聞いたわよ。明日歩君って勉強ができるって」
知美の奴……。
どういうわけか、家庭教師をやらされる羽目になった明日歩は、中学校生活の大半を克己と過ごしている。
部活を引退した今では、誰の家なのかわからないくらい克己がいる。奈緒は子供が二人できたみたいで嬉しいと言って、克己の妹まで呼ぶようになり、しょっちゅう二人で、お菓子作りに励むようになっていた。
起き出して来た歩に試食を薦める声が、日常に溶け込むようになったのはその日からだった。
第二章 不滅のヒーロー
「進学する学校、決めたか?」
すっかり勉強に飽きてしまった克己が、ベッド伸びをしながら寄り掛かると、雑誌をペラペラめくりながら明日歩に訊く。
「俺、推薦取れそうなんだ」
「サッカーで?」
明日歩は二次関数を解きながら言うと、克己がテーブルを勢いよく叩く。
「絶対に強くなって、Jリーガー選手になるから」
突然の決意表明に驚いた明日歩は、呆れるやら腹が立つやらで、ムッとした声で克己に言い放つ。
「だったら、勉強なんかいらないんじゃない? おまえ、もう家に帰れよ」
「フフフ、明日歩君、それはあまーい。今時、そんなのは通用しない。僕チン、いずれかかは、海外進出なるものを視野に入れて考えなければならないだのだよ。学問くらい窘めておかないと、パツキンの彼女は作れません」
どこから来るんだその発想と自信は?
何を思ったのか、がっしっと、あきれ顔で首を傾げている明日歩の手を握り、克己はニヤリとする。
「君の力なしでは、僕チンの未来はないんだよ」
その手を振り解いた明日歩は苦笑しながら、顔を近づけて来た克己のおでこを指ではじき、本気に帰れと命じる。
克己が帰ってしまった部屋で一人、明日歩は送られてきた高校のパンフレットを机の上に並べ、眺める。
どれも奈緒が目を輝かせて喜びそうな高校だ。何となくそれが嫌で、明日歩は行く高校を決めかねていた。
――放課後、教室の前に椅子が並べられ、自分の順番が来るのを待ちながらしかめっ面の明日歩である。
この日が来るが、嫌で嫌で仕方がなかった明日歩だった。
いくら言っても治らない奈緒の服装に、うんざりなのだ。克己を立ち直せるつで、にわか不良になったことが引け目になってしまった明日歩は、文句言う資格などないだろ、と歩に言われ、何も言い返すことが出来なかった。
ニヤッとする歩の顔が目に浮かび、明日歩は顔を顰める。
まったく、どういう親なんだよ。
明日歩の心うちなどあとからやって来た親と話し始める。
クラスメートの女子が、明らかに奈緒の格好を見て、驚いている様子だった。
最悪。この一言に尽きる。隣のクラスの前に座る親が目に入る。
きちんとした服装だった。
これだったら、まだジーンズとかで来てくれた方がどれだけ良かった、と明日歩はつくづく思う。
明日歩の順番が巡って来た。
担任は、あの村沢である。
あの事件と関係なく、明日歩は、どうもこの置き狸のような村沢のことが好きになれずにいた。
内申書を落としたまま、村沢が最初に口を開く。
「やはり、推薦で行きますか?」
「出来れば、陸上の素質を延ばせればって、考えているんです」
「で、中田の希望と知っては、どこが良いんだ? 先生としては中田の学力と照らし合わせてこの学校あたりが良いと思うんだがな」
明日歩の成績は良い方だ。陸上選手としてもそこそこの成績を収めている、どちらかというと、村沢が好意を持つ生徒の部類に属している。評価も悪くない。申し分がないはずの明日歩だが、奈緒とのやり取りを聞いて行くうちに、段々苛ついて来てしまっていた。
二人に目を向けられ、明日歩は内から吹き出すものを堪えられなくなる。
陸上選手とひとくくりにされてしまうのが嫌だった。
「行かねぇよ。高校なんか行かねぇし」
つい口が滑って出てしまった言葉である。
奈緒が驚いて、明日歩の名前を叫ぶように呼ぶ。
黒縁の眼鏡越しに、村沢が見てくる。
ジリジリとした感覚が蘇り、二年前のことが脳裏を過って行く。
絶対、こいつの言いなりにはならない。なぜかその衝動が頭から離れなかった明日歩である。
「中田、何を考えているんだ。今はふざけて良い時じゃないぞ。言葉を慎みなさい」
「そうよ明日歩、先生の仰る通りよ」
咎められ憎悪に近いものを明日歩は抱く。
そんな格好で来るやつに言われたくない。
弁解するのも撤回するのも面倒に思えた明日歩は、勢いで言い継ぐ。
「走るために高校なんか行かねーし、て言うかウザい」
「何、言っているの?」
「ふざけるんじゃない。これからの人生を決める、大切な相談だ。もっと真剣に考えなさい」
「はいはい。じゃ、一番家から近い南高校で」
「中田なら、もっと上のランクの高校に行ける。もっとまじめに考えなさい」
「そうよ。陸上はどうするの? 南高校じゃ」
「じゃあ、やっぱ行かねー」
村沢の目が、完全に怒りを顕わにしていた。
明日歩はどうにでもなれという気持ちだった。
村沢が、交互に二人の顔を見てくる。
もううんざりだ、と明日歩は思った。
走ることは嫌いではないが、当然のように話されるのが嫌で嫌で仕方がないのだ。
「明日歩、待ちなさい」
奈緒が静止するのを無視して、明日歩は教室を飛び出す。
校門までかけて行った明日歩は、そこで我に返り、やってしまったと思う。
口から出てしまった言葉、今更どうすることも出来ない。あとのことを全く考えていなかった明日歩だった。
「あれ明日歩、もう終わったの?」
知美が声を掛けても、まるで気が付かない様子で明日歩は校門を出て行く。
自分でも何がしたいのか分からなかった。
克己の話を聞いて、羨む反面、それだけでいいのかって気持ちになっていた。頭の中がぐちゃぐちゃになり、どうにでもなれと明日歩は駆け出す。
走りたくて走ってきたわけではない明日歩である。知美に追い詰められて、苦し紛れに書いたのが運の尽き。人にとやかく言われることではない、明日歩だった。
☆
明日歩は突然起こされ、何事かと歩の顔をジッと見る。
「さぁ着替えた着替えた」
寝ぼけ眼で洋服を着替えされた明日歩は、有無なしに車に押し込められてしまっていた。
徐々に明けて行く空を見て、歩がきれいだなと話し掛けて来るが、明日歩は寝たふりをして無視をする。
歩の突拍子もない行動は、今始まったことではない。そこに奈緒が絡むと性質が悪い。 薄目で、現状を確認する。
車は首都高速に乗り、鎌倉方面へ向かっているようだった。
もしかして、静岡のおばあちゃんに何かあったのかとも思ったが、奈緒が一緒に乗って来なかったことに気が付き、明日歩は内心、ホッとさせる。
窓を開ける音がして、冷たい空気が中へ入り込んでくる。
磯の香りがして、近くに海があることが分かった。
明日歩は目が明けたくて、うずうずしていた。
眠気などもうとっくになくなっていた。
言われることは分かっている。進学のことだ。昨夜も遅くまで奈緒と言い争って決着つかないままだった。明日歩は、ぎゅっと目を瞑り直す。
「明日歩、起きろよ。海だよ海。いや~気持ちが良いな」
歩は上機嫌だった。鼻歌が聞こえてきて、明日歩は眉を顰める。
車は大きく揺れ、砂浜をしばらく走れせてから止まった。
歩は車から降り、大きく伸びをしながら嬉しそうに叫ぶ。
「海だぞ。海」
躰を大きく揺すられ、明日歩は渋々目を開ける。
目の前に広がる海を見て、明日歩の心は躍りたくなるが、そこは我慢。
「明日歩。海だってば、海」
そんな満面の笑みで言われても、15歳になって海ぐらいではしゃげない。そんなポーズをとって見せたが、嬉しさは否めない。頬が綻びそうになるのを堪えながら、目一杯面倒臭いを前面に押し出し、車から降りる。
「そう意地を張りなさんな。ほれ」
しばらく、後部座席をごそごそと漁っていた歩が、二カッと歯を見せ、明日歩にグローブを放って寄越す。
グローブ? しかも補手用って。
キョトンとしている明日歩を見て、歩は自分が持っていた方のグローブを差し出す。
「そういうことじゃなくって」
「何だよ、はっきりしろよ。俺はどっちでもいいだぞ。こっちがいいなら、ほらそっち寄越せ」
「ちげーよ」
「じゃあいいんだな。取り替えてやんないぞ」
嬉しそうにする歩を見て、明日歩はついつられて笑ってしまう。
「て言うか何でグローブ?」
「実家でこれ見つけたら、無性に明日歩とキャッチボールが、やりたくなってな」
行き成り離れていたかと思うと、ボールを投げられ、明日歩は慌ててミットを小脇に挟み、そのボールを素手で受け止める。
「だったら、わざわざ海までくる必要はなかったんじゃねーの」
「良いから早くやろうぜ。よし来い」
バシッ常節でグローブを鳴らした歩が、歯を見せる。
風がゴウゴウという中、グローブに収まるボールの音が混じる。
「いいボール、投げるなぁ」
明日歩はくすぐったい気持ちで、歩からの返球を受ける。
ミットにボール収まる音が心地よい。それと同時に、じんと手がしびれる。
歩が徐々に距離をとり出し、かなりの距離があるのにも拘らず、スーッと伸びグローブに収まってくる。確実で重い球に、明日歩はさっきまでの不機嫌ポーズを返上させられてしまっていた。
「父さん、野球したことがあるの?」
「ああ、昔にちょっとな」
明日歩は少しだけ変なのと思いつつ、そうなんだと返球する。
「結構、上手かったんだぞ。なかじぃはそん時の仲間」
「へぇ」
ますます信憑性が薄い話になってきている。一度もそんな話を、誰からも聞かされたことがない。ましてや、歩とキャッチボールをするのも、初めてだ。中島が何度か遊びに来た時に、やったことはあるが……。しかし、その時も遠目で、にこにこしながら見ているだけだった。静岡に住む歩の祖父母も、そんな話を微塵もしたことがない。そんな内情を知ってか知らぬか、歩が投げたボールが大幅にそれ、明日歩は慌ててボールを追いかけて走り出す。
「あ、悪い。さすがに限界だ」
歩は近くのテトラポットに腰掛けると、首に巻いていたタオルで汗を拭く。
戻って来た明日歩にも、座れと場所を空けた。
波が泡立っている。海カモメがうるさい。
だけど、明日歩は少しも気にならなかった。
明日歩は歩を盗み見る。
歩は、穏やかな顔で波を見ていた。
聞きたいことが山ほどあるが、素直になれない明日歩である。
明日歩はポケットに手を突っ込み、背中を丸め寒がって見せる。
「寒い。勘弁してよ。有り得ないでしょ。受験生を、こんな寒い海に連れて来る親の気がしれない。風邪でも引いたらどうするんだよ」
悪たれを突く明日歩を見て、歩はガシガシと頭を撫でる。
「ちょっとぐらい大丈夫だ。お前はそんな軟な人間じゃない」
「そう言う問題じゃなくってさ」
口を尖らせて言う明日歩を見て、歩は笑みを零す。
「明日歩、知っていたか。親ってさ、死ぬまで親なんだぜ」
歩はまっすぐ海を眺めていた。
「前に、昇おじさんに言われたんだ。オレも今の明日歩みたいな顔をしていた気がする。何、言ってやがるんだってな。でも、今は凄く後悔している」
空を仰ぐ歩の頬に涙が流れ落ちる。
歩は、父親を亡くしたばかりだった。
「参るよな」
ごしごしと顔を拭いた歩が、明日歩に微笑みかける。
「オレもあったんだ。大人が敷いたレールに乗っかったまんまなんて、真っ平だって。あん時の母さんの顔は、今でも忘れられないな。まったく嫌になるぜ。こんなところまで似やがって。オレ、奈緒にその話聞かされた時、かなりヤバいと思ったぜ。マジ即効帰って、奈緒に謝らんとって、で、帰ってきたわけですよ」
歩がうーんと伸び上がる。
「嘘でしょ」
信じられない気持ちでいっぱいでいる明日歩を見て、歩はガシガシと頭を撫でる。
「だから止めろって」
「良いじゃねーかよ。かわいくって仕方がないんだからよ」
「子ども扱いすんなよ。マジムカつく」
「何だよその言い方」
逃げ惑う明日歩の頭を歩は執拗に撫でまわす。
他愛のない戯れをしばらく続けた後、ふと真顔に戻った歩が明日歩の肩を叩く。
「帰るか」
コクンと頷く明日歩を見て、歩は目を細める。
「お前も大きくなったな。今身長どのくらいある?」
「163センチ」
「すぐに追い越されちまうな」
歩は明日歩の顔をジッと見つめる。
「何だよ」
「あん時のかあさん、どんな気持ちだったんだろうなって思ってさ。自分より大きな息子相手にさ、俺、滅茶苦茶怒鳴っていたしな。凄く怖かったと思う。でもさ、実は心のどこかで悪いって思っているんだよな。明日歩、お前もそうなんだろ? 勢いで行っちゃったものの引っ込みがつかなくなっちゃっているんだと、オレは思う。親も必至だろうけど、子供だって必死なんだよな。自分の将来がかかっているんだもんな。オレにしてもそうよ。大人からしては馬鹿げている話かもしれないけど、プロ野球選手になるよりもあんときのオレは、大真面目に、ヒーローになりたかった」
「ヒーローって」
「笑うなよ。漠然的だったんだ。野球しかしてこなかったから、具体的なものが思い当たらなくってそうなっちゃったんだけど、今思えば、人を助けられる人になりたいってことだったんだと思う」
「おっそ」
「そう言うなよ。今はちゃんと警備員として、仕事をまっとうしているんだからさ」
歩は笑ってまた明日歩の頭を撫でに行く。
「もうマジうざい」
「進路、お前はどうしたいんだ?」
真顔で聞かれ、明日歩は返答に困る。
「ま、オレも偉そうなことを言えないけどな、なんせ親に高校なんか行っている場合じゃないって喚き散らしていたんだからな」
二人は、ゆっくりと時間をかけて車まで戻って来ていた。
シートに腰を落ち着かせた歩がハンドルを握ったまま、明日歩を見る。
「なぁ明日歩、お前の気持ちは少なからずとも分かる。でもな、奈緒はオレが一生を掛けて護るって決めた、惚れた女なんだ。だから泣かせないでくれよ。あんな悲しそうな奈緒の顔、オレは見たくないんだ」
じっと見つめてくる明日歩の肩を、歩は抱き寄せる。
「お前もいつか、大切な人が出来れば分かると思うけど。この人だけは悲しませたくはないって、男の純情って奴さ。汲んでくれ頼む」
まったく、と明日歩は思う。
奈緒が絡むと、歩はいつもこうだ。
だからいつも聞き入れなければならなくなる。
間違ってはいないんだろうけど、何だか悔しくなる。
車にエンジンが駆けられ、大きく車体が揺れ動きだす。
言い返す言葉なんかなかった。
でも明日歩にだって意地はある。
陸上で行くのではなく、実力で高校へ進むことに、この時明日歩は決めていた。
☆
二人は、海岸沿いのレストランに、昼食を摂るために入った。
今日の歩は、いつになくお喋りだった。
ウェートレスが忙しく動き回っているのを眺めながら、オレも昔、こういう所でバイトをしたことがあると言い出す。
歩は滅多に、昔話をしない。野球をしてたのだって初耳だった。
「父さん、本当に野球したことあんだ」
「まぁな。甲子園にも行ったんだぞ」
得意げに言う歩に、明日歩は疑いの眼差しを向ける。
「本当だって。今度、なかじぃが来たら聞いてみな」
歩は、ウェートレスの動きを目で追う。
「意外と笑顔を絶やさずに接客するのって、出来そうで出来ないものなんだ。特に週末なんか、足はパンパンになるし、人ははけないしさ」
ウエートレスが付け合せのサラダを運んで来る。
明日歩は眉を顰める。
とにかく、歩の様子がおかしい。やたらと昔の話をしたがり、家を出た経緯まで話し始めたあたりで、急にどうかしたのと聞いてしまったほどだった。
笑って誤魔化されてしまったが、こういう顔をしている時の歩は決まって、何かを企んでいる。コーヒーを何杯もお替りした挙句、奈緒を泣かしたらおまえでも容赦しないと、念を押され、明日歩は渋々約束されて、家路の途に就く。
エンジン音を聞いて、家から出てきた奈緒を見て、歩は顔を綻ばせる。
奈緒も同じ笑顔で答えているのを見て、明日歩はムッとしながら車を降りて行く。
奈緒を素通りしようとした時だった。
「おい明日歩、男同士の約束はどうした」
「ごめん」
奈緒はその一言が聞けただけで満足だった。
涙ぐむ奈緒を歩は肩を抱く。
「良いドライヴだったよ」
それだけで報われた気がする奈緒だった。
その夜、明日歩は夕食もそこそこに部屋へ戻って行ってしまっていた。静岡から帰ってきてすぐのドライヴで疲れてしまったのだろう。歩は茶の間で転寝をしてしまっていた。奈緒がそっと毛布を掛けようとした時だった、手を掴まれ歩の胸に抱き寄せられたのは。
「もう歩ったら、脅かさないでよ」
「奈緒、ただいま」
「歩、お帰りなさい」
口づけをした二人は笑い合う。
「ごめんな奈緒。ずっと明日歩のこと任せっきりで」
「うん。でも大丈夫だったよ。困ったときはいつでも歩、飛んで帰って来てくれていたし、今日だって、疲れていたのに、ありがとう」
「当たり前だよ。オレも明日歩の父親なんだから。それに、オレは奈緒のヒーローだからな、お姫様のピンチを助けるのは当然だよ」
「歩」
胸に顔を沈めてきた奈緒の髪を、歩は優しく撫でる。
「奈緒、一つだけ頼みがあるんだけど聞いてくれるか?」
「何?」
「明日歩のこと。もう少し長い目で見てくれないか。男の子ていうのはさ、どうしても母親を煙ったがる時期があるもんなんだ。あいつはあいつなりに悩んでいるんだと思う。きっとやっていることも言っていることも間違っているって解っているんだ。俺たちも子離れして行かないとな。少し辛抱は必要だけど、これも明日歩が大人になって行くためなんだ。あいつがしたいようにさせてやろう」
奈緒はコクンと頷く。
久しぶりに歩の腕に抱かれ、奈緒は満たされていた。
翌朝、ブスッとした明日歩が奈緒に進路表を差し出す。
奈緒が進めた学校ではない名前が記載されていて、つい笑ってしまう。
似たようなことがあったことを思い出したからだ。あの時も散々大騒ぎして、決めたんだった。
「俺、陸上部にしたから」
そう言って胡坐をかいて座ったことを昨日のことのように、奈緒は思い出していた。
数日後、一枚しか持っていないスーツに袖を通した奈緒が学校に現れ、明日歩は麺を食らってしまった。
くどいくらい受験校を確認され、奈緒は凛としてそれを崩さなかった。
「明日歩が決めたことですから」
何となく明日歩はそれがこそばゆかった。
初詣客でにぎわう神社。
家族揃って合格祈念を済まし、歩はトウモロコシをおいしそうに頬張る。渋々ついて来た明日歩は友達の姿を見つけ、行ってしまうのを見届けながら、奈緒が歩に話しかける。 「ねぇ歩、あの子に何を言ったの?」
あんなに話すのも嫌がっていた明日歩が、素直に今日も一緒にお参りに来るなんて、奈緒には考えられなかった。
「昔々の話をしただけだよ」
境内の脇、池に架かった橋を渡りながら、鯉を見つけた歩が、でかいなと言う。
「そう言えば歩の昔話って、私、聞いたことがなかったわね。私も聞きたいな」
「大した人生を送ってないから」
歩はトウモロコシを食べ終わり、ごみ箱ごみ箱と話しをはぐらかして、先を歩いて行ってしまう。
そんな歩を小走りで追いつく奈緒の手を握り、微笑む。
「今が幸せだから、良いだろ?」
「もう、ずるい」
奈緒が言うと、歩はケラケラ笑った。
友達と射的をしているのを見て、二人は微笑みあう。
「明日歩、あまり遅くならないでね」
「了解です」
答えたのは、克己だった。
ざわざわと賑やかさを増し、いつの間にか大勢で楽しみだすのを、歩は眩しそうに目を細める。
「後で、みんなを連れて行ってもいい?」
「おお連れて来い。美味いもん、用意して待っているから、早く帰ってこい」
「ヨッシャ。おばさん、オールしてもいいっすか」
胸の前でポーズをとって見せる克己の頭を、明日歩が叩く。
「調子こくな。俺たち、一応受験生なんだからな」
「分かってるって。だから一緒に勉強を」
「嫌だよ正月早々、克己と受験勉強なんて」
「良いな。俺、数学で分からないとこあるんだけど、教えて欲しいな」
「ああそれだったら私も、理科、教えて欲しい」
「じゃあこれから中田の家でやらねぇ」
「おおそうしろ。何ならオレも勉強みてやろっか」
「結構です。おじ様とおば様は、ゆっくり正月をしていてください」
知美にぴしゃりと言われ、歩は吹き出す。
「奈緒、なんかこういうの良いね」
明日歩の接し方で悩んでいたことがまるで嘘のように、晴れ晴れとした気持ちで迎えられ、いい年を越せそうな気がする奈緒だった。
――そして春。
家からほど近い高校に進学を決めた明日歩を挟み、歩は一枚の記念写真を撮った。
☆
「明日歩、ちょっと待ちなさいよ」
知美が大声で叫びながら、廊下を走って明日歩を追いかけて来る。
それを聞いた明日歩は、無条件で足を速めていく。
「ちょっと、待てって言っているでしょ」
教室に逃げ込める寸前のところで、明日歩は知美に捕まってしまった。
「あああ知美、何、何か用?」
空々しく振り返る明日歩を見て、知美が一気に捲し立てる。
「さっきから呼んでいるのに、どうして止まらないの?」
「え、ごめん。考え事をしていたから全然気が付かなかった」
「気が付かないですって。嘘言っているんじゃないわよ。明らかに聞こえていたよね、足、速めたよね」
「ごめん」
「ごめんで済んだら警察はいらないわよ」
「大袈裟な」
明日歩はたじたじになりながら、克己を恋しく思う。
「もう、今月の予定表を渡そうと思って、ずっと探していたのよ。まったく、クラスが違うと、不便で仕方がない」
明日歩は苦笑する。
やっと知美から離れられると喜んでいたのに、合格発表の日、知美が目の前に現れた衝撃は口では言い表せないほどだった。
「ああ、明日歩もこの学校だったんだ」
見せた笑みが悪魔に思えた。
「あら」
「おはようございます。また三年間、よろしくお願いします」
「こちらこそ。へぇ知美ちゃんもね、一緒だったんだ。良かったじゃないか明日歩」
ブスッとする明日歩を見て、歩は楽しげに笑う。
明日歩の心の内を知っていて、歩はわざと冷かしてくるのだ。
「このこの色男。あの子、絶対にお前を追っかけてきたんだぞ」
親の方へ戻って行く知美を見やりながら、歩は明日歩を肘で小突く。
悪趣味も、甚だしい。
だから困るんだて言ってやりたいけど、面倒に思えた明日歩はそこで口を噤んだ。
バラ色の高校生活に翳りを見せた瞬間だった。
そして、問題はこれだ。
日程表を差し出され、明日歩は苦笑する。
あろうことか、知美は陸上部のマネージャーを買って出たのだ。
弱小チームで、顧問もまるで経験がない先生が担当している。部員は7人で、満足に走れるやつはいない。奈緒がこの学校を反対した理由がそこにあった。進学校で、部活動に重点を置いていない。特に運動部に関しては、皆無に近いものである。そんな部にマネージャーはいらないと思うのだが、どうやって取り次いだのか、知美は陸上部のマネージャーとして君臨するようになった。
「斉藤先生、やる気があるのかしら?」
不意に訊かれ、きょとんとする明日歩の背中を、知美は叩く。
「もうしっかりしてよ」
この背中叩きには、かなりのトラウマがある。
「仕方がないなぁ。中学時代のメニューだけでは、インターハイは目指せないのよ。私が調べるには……」
そっと明日歩は知美から離れて、一気に教室の中に逃げ込む。
まだ話は終わってないでしょ。と言う知美を無視して、席に着く。
「いいのか?」
唯一、陸上部仲間の前橋哲平が、訊いた。
良いも悪いも何の関係もない。と言う明日歩に、またまたと信じようとしない。
どうも二人は、恋人同士という風に定着しているらしいが、否定して歩くのも面倒な明日歩は、そのまま放ってある。
それにしても顧問の斉藤は、生まれてこの方、運動などしたことがないんじゃないかと思えるほど疎く、陸上競技はただのかけっこくらいにしか思っていない。
公立高校の教師が故に、仕方なく陸上部の顧問に就かされているだけで、出来れば専門である物理学を極めたいという人物だ。
そんなのは、入学する前から百も承知していたはずだけど、やはり不満は出る。
しかし、明日歩はそれを口にするわけにはいかなかった。
「奈緒の反対を押し切ってこの学校に決めたんだ。何があっても弱音は吐くな。陸上は続ける。それだけがオレの条件だ」
こんなことなら、黙って私立に行っておけば良かった。
歩の顔が頭にチラつく。
☆
「中田、まじめに数学のノートって取ってるか?」
ウオーミングアップを済ませた前橋が、シューズに履き替えている明日歩の横に座り、訊いた。
「たぶん」
「今、ある?」
「ない」
明日歩の代わりに、知美が答える。
前橋は高跳びの選手だ。生真面目な明日歩と違って、要領だけで生きている傾向がある。授業中も、半分以上が寝ているが、成績は悪くない。
「哲平君、今は何をする時間でしょう?」
知美の目がギロリと睨む。
「チッ、鬼女房め。明日歩も苦労するな」
知美はコラッと怒っているが、満更でもないという顔で、口元が緩む。
「違うって言うの」
明日歩が呟く。
「秋に向けて合宿をしよう」
無理の一言で却下された知美は、刈谷奈波(かりやななみ)を引っ張り連れて来ていた。
走ることよりも参考書に興味がある先輩達も、この刈谷奈波の笑顔には勝てないらしい。
「お役にたてるかどうか分かりませんが、よろしくおねがいします」
語尾が上げた喋り方と両頬に笑窪を作った笑顔の挨拶をされ、ぐうの音も出なくなってしまっていた。
これには明日歩も脱帽だった。
弱いより強いに越したことはない。やるからには、勝ちに行きたいのは、当然の摂理である。
気をよくした知美が言い連ねる。
刈谷奈波は、学年で可愛いという評判の子だ。その子が合宿中、手料理を振る舞うなどと訊かされて、反対をしていた前橋も先輩たちも、一ころだった。
斉藤には、勉強の時間もとってると言い、むしろ勉強するための合宿だと言っても過言じゃないと迫る。
「今度の模試を見ていて下さい」
満面の笑みを浮かべる。
「勉強と部活を両立させるなんて、斉藤先生も褒められてしまいますね」
「そういうのは、成績を出してから言いなさい」
「大丈夫です。中田はやってくれる男ですから」
明日歩の知らない取引を交わした知美は、斎藤からもあっさり三日間の合宿をもぎ取ったのだった。
例年より暑い夏が到来し、明日歩はいくつかの大会に出場し、確実に実力を伸ばしていた。
☆
暑い夜だった。
奈緒はあまりの暑さに目を覚ましていた。
少し迷ってから起き上がり、水を飲むとそのまま涼みに、庭へ出る。
茶の間から零れる灯りに照らされて、庭の朝顔やきゅうりの葉がにわかに映し出される。見上げた先、満月とはいかないが、丸く夜空を照らしている。星もまばらに見える。
大きく伸びをした奈緒は、遠くの空がぼんやりと明るくなっているのを見つける。
朝焼けではない、人工的な明るさだ。
ふと、歩の言葉を思い出す。
「便利は不便」
歩は、よくこう言っては壊れたものを修理してくれる。
あって当たり前のものが壊れてしまうと、途端に、何も出来なくなってしまう。
あの時も空を見上げた歩が、東京は便利だけど不便だよね、と微笑みかけていた。
見上げた先には、漆黒の闇に広がる満天の星があった。
本来ならこの空にも、あの日と同じ無数の星が存在していて、はくちょう座やこと座、それにわし座の中を流れる天の川が見られるはず……。
歩は大三角を指差し、七夕伝説を話した。
幼い頃から慣れ親しんだ伝説がやけに胸に染みて、奈緒は涙ぐんでしまったのを覚えている。
「愛し合う者が離れ離れで暮らすなんて、オレには考えられない。オレは一秒でも長く奈緒の傍にいたい」
今思えば、あれは、プロポーズだったのかもしれない。
二人は、それから間もなく一緒に暮らすようになった。
奈緒はもう一度大きく伸びをしてから、庭の草花達にたっぷりと水を与え中へ戻る。
夏の夜明けは早い。
しかし、時計を見上げた奈緒はがっかりしてしまう。まだ六時にもなっていなかった。 歩が帰って来るまでには、たっぷり時間はある。明日歩も、昨日から合宿で留守している。
何となく布団へ戻る気になれなかった奈緒は、コーヒーを淹れ、腰を落ち着かせる。朝食の支度は、歩の顔を見てからでも遅くない。久しぶりの夫婦水入らず。のんびりと過ごそう。そう言って出かけて行った歩の笑顔を思い出し、奈緒はクスっと笑う。この日を指折り数え、何かを企んでいることは見え見えなのに、必死で隠すあたりは何年経っても変わらない歩である。最近では、よっぽど明日歩の方が大人びている。
奈緒は読みかけの本を開いたが、すぐに睡魔が襲ってきて、そのままテーブルにうつ伏せてしまう。
軒下に吊るした風鈴がチリンと鳴り、今度は本物の朝が東の空を明るくし始めていた。
☆
「おかしい……」
歩は時計を何回も見直しては、そう呟く。
交代時間はもうとっくに過ぎていた。三枝がまだ出勤をして来ない。連絡もなしで、こんなに遅れたことは一度もない。
三枝はどちらかと言えば神経質で、一分でも遅れそうな時でも、きちんと連絡をしてくるような性質のはず。
嫌な胸騒ぎがする。
帽子を被り直し、朝の巡回を済ませたら、三枝の家に電話してみるかと立ち上がった時だった。
「すまん。すまん……遅くなった」
そう言いながら、三枝が汗だくで飛び込んで来た。
「どうかしたんですか?」
息を切らして奥の部屋で着替えをしている三枝に、歩は話しかける。
「いやぁ参った。出かけに女房の奴が、具合悪いと言い出して……」
「え、そうなんですか? 仕事に来ちゃって大丈夫なんですか?」
三枝の歳から考えても、奥さんもそう若くないだろうと、歩は心配そうに中を覗き込む。
「ああ。熱が少し高かったが、風邪でも引いたんだろう。歳をとったせいか、ちょっとしたことでも大袈裟に騒ぐんだ。最近」
三枝は顔を顰める。
「一人娘を嫁に出した頃から、少しボケが始まっているようで、今日も、子供のように泣きじゃくって、離れようとはしなかった」
そう喋る三枝は帽子を被る。
歩の勧める水を一口飲み、ニッコリする三枝だが、どこか元気がない。
「一人にして、大丈夫なんですか?」
「ああ。娘に来てもらった」
三枝はそう言うと、曇った顔で腕時計を見て慌てる。
「まずい」
巡回する時間はとっくに過ぎていた。
急いで私服に着替えた歩が、警備員室を先に出て行った三枝に追いつく。
総合受付には、もう患者が何人か長いすに座って、診察を待っている。
「じゃあ。あとはよろしく頼みます」
「ああ、悪かったな。明日と明後日は休みだったな。ゆっくり休んでくれ」
歩は帰りかけて、振り返る。
「三枝さん、オレで出来ることなら何でも協力しますから。遠慮なく言ってください。交代時間を、少しずらしても構わないですから」
三枝は涙が出そうになった。歩にありがとうと頭を下げながら、見送る。
外に一歩出ると、ムッとした暑さに、歩は顔を顰める。
朝からこれじゃ、先が思いやられる。
急ぎ足で駅に向う歩は、携帯を取り出し、奈緒にメールを送った。
いつもなら、電車に乗っているか、下手をすると朝食を食べている時間だ。
駅に降り立った歩の喉は、すっかり乾き切っていた。大急ぎでホームに入って来た電車に飛び乗ったせいだろうか、この暑さも手伝い、喉が痛むくらいの渇きに、歩は躊躇いながら、商店街の入り口にある自動販売機に向かう。
いつもなら、奈緒が淹れてくれるコーヒーが楽しみで、我慢してしまうのだが、こんな事で熱中症になってもつまらない。昨日、担ぎ込まれてきた人を思い出し、やれやれと首を振る。
商店街はまだシャッターが下り、しんと静まり返っていた。
歩が自動販売機にお金を入れていると、その脇をサッカーのユニフォームを着た少年が二人で駆けて行き、そのあとを小さな男の子が追いかけるように過ぎて行く。
「待ちなさい! 智弘! 危ない!」
母親に違いない女性の声に、歩は何の気なしに振り向き、咄嗟的に体が動いていた。 ブレーキ音が、静けさを劈いて行く。
一瞬の出来事だった。
車のクラクションが鳴らされ、こだまする悲鳴。
歩は男の子を突き飛ばし、次の瞬間、鈍い衝撃が体中を覆いそのまま記憶を失くす。
「誰か、誰か、救急車を……」
するすると歩のポケットから飛び出した携帯電話が、自動販売機の下に滑り込む。
☆
――奈緒は、ハッとして目を覚ます。
テーブルの上に置いた携帯電話が、着信を知らせるように点滅を繰り返しているのに気が付いた奈緒は、頬を緩める。
歩からのメールだった。
(少し遅くなるけど、心配しない様に)
ハートマークが5個も踊っているメールに、奈緒は頬を緩ます。
(何時頃のお帰りですか?)
歩に負けないくらいハートマークをつけると送信ボタンを押し、そのまま携帯を持って、奈緒は庭に出る。
歩に早く見せたかった。赤や紫の朝顔に並んで小さく実ったきゅうりを。
一向に戻って来ない返事に、奈緒は顔を曇らせる。
歩のことだから、慌てて電車に飛び乗って、それっきりになってしまったのだろうと自分に言い聞かせるが、しかしそれにしても連絡がこなすぎる。あれから優に30分は過ぎている。
心配になった奈緒は、もう一通メールを送ってみる。
(何かあったの? 何時、帰れる?)
待っているのがもどかしくなった奈緒は、電話へ切り替えるが……。
強く押し当てた受話器からは呼び出し音が虚しく繰り返され、無機質な音声に切り替わる。
焦りと不安が、奈緒を混乱させていた。
どうしてこんなにも胸騒ぎがするのか、奈緒自身判らなかった。
時計の針は10時を指そうとしていた。
会社に携帯を忘れただけかもしれない、そう自分に言い聞かせながら奈緒は、震える指で会社へと電話を掛ける。
すぐにその電話は繋がり、三枝へと回された。
三枝は三枝で、電話と聞かされ、妻に何かあったのかと受話器にかぶりつく。
「あの、中田がいつもお世話になっています」
それを聞いた三枝は安堵するとともに、何事かと眉を顰める。
「あの、恐れ入りますが、主人は何時ごろ退社いたしましたでしょうか」
自ずと三枝の目は時計を見やっていた。
8時前には、歩と別れていた。ここ2、3日の歩の口っぷりを思うと、もしやどこかで奥さんのためにサプライズを用意しているのではと、三枝は気を回し、自分が遅刻してけりを遅くなってしまったと、大げさに話し、只管に謝る。
どこか、寄り道でもしているのでしょうと言われても、奈緒の不安は消えずにいた。
確かにそう言うときもあったが、奈緒に心配を掛けないように連絡をしてくれていた。ましてや、ここまで電話がつながらなかったことなどなかった。念のため、携帯を会社に忘れていないか調べて貰ったが、それもないらしい。
三枝との電話を切ってからも、奈緒は落ち着かない気持ちで歩の帰りを待って行った。
突然、家の電話が鳴り、奈緒は飛び上がってしまう。
滅多に掛かってくることがない家電に、奈緒は恐る恐る手を伸ばす。
そそっかしい歩のことだから、どこかで携帯を落としてしまったのかもしれない。それならそれでいい。だから連絡が出来なかったと、しょげた声で言う歩を想像しながら、奈緒は受話器を耳に押し当てる。
だが、奈緒の期待は裏切られてしまう。
伝えられた名前に、奈緒の心臓が早まって行く。
何を言われているのか理解できなかった。ただ、心臓の音だけがやけに大きく聞こえ、呆然としたまま、同じ言葉が頭の中で繰り返す。
警察って何?
事故って……。
受話器を置いてからも、震えが止まらなかった。
呆然と一点を見つめ、奈緒は歩の名をうわ言のように呼び続ける。
夜勤が明け、薫子は眠い目を擦りながら一旦は外へ出たのだが、ロッカーに忘れ物をしたことに気が付き、取りに戻っていた。
サイレンが聞こえ、薫子は顔を顰める。
これで、またデートはお預けになってしまうのかと思うと、憂鬱な気分だった。
看護師としては不謹慎だが、子供の搬送じゃなければいいのにと、ついつい本音が出てしまう薫子である。
徐に携帯を取り出す薫子は、前から慌てふためいて駆けてくる事務局長に、まったく気が付いていなかった。
「倉嶋さん、ちょっと待った」
顔を赤らめている事務局長を見て、薫子は吹き出してしまう。
「良いから来て」
行き成り手を掴まれた薫子は、初めて事の重大さに気が付く。
「事務長、何かあったんですか」
「中田君が、時期で運ばれてきたんだ、緊急オペになる。家族代理で承諾書へサインをして欲しい」
「歩が?」
「うちの身分証明書を持っていたから、ここへ運ばれてきたらしい」
「容体は、どうなんです?」
「私にも詳しいことは分からないが、厳しいらしい。榎田先生が、すぐに君を連れて来いって」
冷静沈着の榎田がそこまで言うくらいだとしたら、相当にまずい状態だと悟って取れる。
「ご家族とは」
「警察から連絡はいっている」
処置室に飛び込んで行った薫子は、横たわる歩を見て愕然となる。
「倉嶋か」
「榎田先生、歩の容態は?」
「左が全滅だ。頭蓋骨にも損傷が認められる。助かるかどうか保証は出来んが、手は尽くす。あとで家族にも説明はするが、かなり厳しいオペになると思っていてくれ」
「どうして……何をやっているのよ歩。今日、奈緒さんとデートするんじゃなかったの? どこまで馬鹿ななのよあんたって人は。もう目を覚ましたら、お説教よ。今日という今日は許さないんだから」
「倉嶋さん、ここは榎田先生に任せて僕らは表へ出よう」
事務局長に促され、処置室を後にした薫子は、すぐに気を取り直し連絡とるべき人へ片っ端から電話をし始める。
握りしめていた携帯が鳴り出し、奈緒は現実へと引き戻される。
これが歩だったらとどんなにいいのだろうと、表示された名前を呆然と眺めてしまっていた。
メールが入る。
もしや、冗談だよっていう歩からのものかと、藁をもつかむ思いで奈緒はメールを開く。
薫子からのものだった。
(奈緒さん、とにかく電話に出て)
折り返し掛かってきた電話に、奈緒はノロノロと出る。
「奈緒さん? 今、どこ?」
緊迫した薫子に、現実味が帯びてくる。
「家です」
掠れた声で答えた奈緒の言葉に薫子の声が被さる。
「歩はうちの病院にいるわ」
「はい。さっき警察から連絡を頂きました」
「もう出られるの?」
「何を持って行けばいいのか分からなくって」
「何をのんびりしたことを言っているの。いい、取りあえず保険証さえあればいいから、急いでこっちに来なさい」
「はい」
「奈緒さん、気をしっかり持ちなさいよ。あなたまでが事故に遭ったら、洒落になんないんだからね。明日歩には、明日歩には連絡したの?」
まるで上の空になっている奈緒を、薫子は歯がゆかった。
「タクシーが行くように手配をするから、あなたはそれに乗ってきなさい。分かった?」
「一刻を争うの。何もしなくていい。身、一つで来なさい。あとのことはいくらでも同にだって出来るから。じゃあ切るわよ」
こんな場面、いくらでも出くわしている薫子だが、相手が身内となると話は違う。
じっとしているのが辛かった。
正面玄関で、まだかまだかと奈緒の到着を待つ。
その間も、頻りに電話を掛け続けている。
やっと来た奈緒の顔を見た薫子は、思わず涙が込み上げて来そうになっていた。
寸前でグッと堪えた薫子は、気丈に振る舞う。
憔悴しきった奈緒を待合室の椅子に座らせると、薫子は赤ランプを怖い顔で見つめる。
手術が始まって、間もなく一時間が過ぎようとしていた。
バタバタと、廊下を走ってくる音が聞こえ、そちらの方へ目をやった薫子は、小さく手を上げて見せる。
薫子から連絡を受けた中島の到着だった。
出先で、到着に時間が掛かってしまったのだ。
「明日歩とは?」
赤ランプを心配そうに見上げながら、中島に尋ねらえた薫子は首を横に振る。
「まだ。何度も掛けているんだけど、繋がらなくって」
「俺から掛けてみようか」
中島が携帯を手にした時だった。
ソファーで項垂れている奈緒の携帯へ、明日歩から電話が掛かって来たのは。
まるで耳に入っていない奈緒に代わって、薫子が電話を預かる。
あまりの暑さに午前の練習を早めに切り上げた明日歩は、ロッカーに置いていた携帯が、点滅を繰り返しているのに気が付き、顔を顰める。
出かけ際、歩のテンションが思い浮かぶ。
どうせろくでもないことを言い出すのだろうと、何お気なしにけいたいを見た明日歩は、尋常ではない数の履歴を見て、ギョッとなる。
分単位で入れられていた。
どれもこれも、奈緒と薫子のものである。
留守録にも何件かメッセージが残されているようだった。
またくだらないいたずらだろうと、明日歩は思った。
サプライズ好きが高じて、いろいろの人を空きこむことが多い歩である。
その一人に、薫子が使われることも少なくなかった。
それに、頼みがあると言いかけて、途中で話をうやむやにされた軽も手伝い、すぐに連絡するかどうか疎まれた。明日歩の周りは役者揃いなのだ。うかうかと騙されたくないという思いも手伝って、しばし考え込んだ明日歩だったが、騙されてあsげるのも、親孝行の一つかと、思い直し、取りあえずメッセージを聞くことにした。
録音メッセージは、どれもこれも連絡を寄こせというものばかりで、奈緒に関しては、あまりの声の小ささに、上手く聞き取れなかった。
「もう面倒くさいな」
独り言ちりながら、奈緒へ電話を掛ける。
「明日歩、午後は暑つすぎるから、自習室で夕方まで勉強してから、練習再開に変更なるって……」
電話を掛けていることを知らない前橋に話しかけられ、明日歩は軽く手を上げ返事をする。
思いがけずすぐに電話に出られ、あとむは、え? と思う。
「母さん、何だよ? 変な留守録で聞き取れなかったぞ!」
「明日歩?」
返ってきた声が、薫子のもので二度びっくりした明日歩は、眉を顰める。
隣のロッカーで着替えていた前橋が、歩の声に手を止め、耳をそば立てる
「薫子さん? あれ間違えたかな俺。母の携帯に変えたつもりだったんだけどな。まぁいいや。何度か連絡を貰ったみたいなんだけど、何だろ?」
「いい、気を確かにして聞いてよ。歩が事故に遭ったの」
緊迫した声で言う薫子に、ついつい明日歩は笑いそうになってしまう。
また大がかりなと思いつつ、明日歩は大袈裟に驚いて見せる。
「まじで? で、親父の容態は」
「今、うちの病院で緊急手術中よ。詳しいことは後で説明するから、とにかく、すぐにこっちへ来なさい」
「えっと、そう言われても俺、まだまだやることがあって」
「何を言っているの。父親が死にそうなのよ。冗談とかじゃないのよ」
叫ぶように言われ、明日歩は携帯を耳から遠ざける。
「薫子さん、俺が話す。変わって」
「明日歩聞いているか? これはな、歩の悪いサプライズなんかじゃない。何ならオレが迎えに行ってやるから、校門の前で待っていろ」
「中島さん、本当の本当の話なんですね」
「あいつは悪ふざけしても、命にかかわるような嘘を言ったことがあるか?」
言われてみればそうである。
神社で怪しいものを見つけたとかの類は言っても、そんなことはなかった。
「いや、電車で言った方が早いと思うから良い」
「分かった。気を付けて来いよ」
明日歩の様子を心配して、前橋が顔を覗き込む。
「どうした中田、顔が真っ青だぞ。大丈夫か?」
「親父が事故に遭った。悪い、俺行かなきゃ」
「ああ早く行け。顧問には俺から話して置く」
「頼んだ」
頭の中が真っ白になってしまった明日歩は、途中、知美に呼び止められたのも気が付かずに、学校を飛び出して行くのだった。
刻々と時間は過ぎて行き、明日歩が到着してもなお、手術は続けられていた。
ようやくランプが消えたのは、夕方近くだった。
医師が重い表情で出て来る。
その表情から、薫子はないかあを読み取ったようだった。
「ご説明しますのでこちらへ」
看護師に促され、重い足取りで別室へと揃って入って行くと医師が、数枚のレントゲン写真と、ダメージの大きさが淡々と説明を始める。
誰もがその真実と向き合うことが出来ずにいた。
「本当に申し訳ございません。手を尽くしましたが、残念です」
納得なんかできるわけない。
目を赤くした中島が、もっと為す術はないのかと、医師に食って掛かる。
奈緒は明日歩に支えられ、やっとその場を取り持っていた。
「なぁ先生、頼むよ。助けてやってくれよ」
退室しようとする意志の胸ぐらを掴む中島を、薫子が窘める。
「中島さん」
薫子に首を振られ、中島は愕然となる。
無数の管に繋がれて、包帯でぐるぐる巻きにされている歩の姿も、今日、明日の命だと言う医師の言葉も、まるで、映画かドラマでも見ているような感覚で、明日歩は見ていた。
泣き崩れ何度も父親の名前を呼ぶ奈緒の姿も、信じるものですか、と言う怒りに満ちた薫子の声も、そんなバカなと涙を流して、見ていられないと出て行ってしまった中島の靴音も、明日歩には絵空事のようにしか思えなかった。
「昨日までぴんぴんしていたんだぜ。誰が信じるっていうんだよ。洒落になんないだろ? 何やってんだよ? 今日、サプライズするんだろ?」
込み上げて来る涙をグッと堪えながら、明日歩は歩に話しかける。
歩の意識はかなり混濁し始めていた。
うわごとを繰り返す歩に、奈緒を手を握りしめ、微笑む。
明日歩は許せない気持ちでいっぱいだった。
「何の夢、見ているのかしらね」
「どうせくだらないことでしょ」
「早く帰って来て歩さん。私、寂しいよ」
愛おしそうに歩を撫でる奈緒に、明日歩は何も言えなくなる。
朦朧とする意識の中、一点の光が歩の目を目がけ飛び込んできていた。
ん? 歩は眩しさに目を瞬かせる。
「これは私の命です」
え?
「この光を手にした者は、戦わなくてはなりません」
燦然と輝く光を掲げた女性が、歩に微笑みながら、差し出す。
受け取った歩は、誰とと首を傾げる。
「分かりません。それはあなたが決めることです」
少し考え込んだ歩が、パッと目を輝かせて顔を上げる。
「オレはヒーローになります。奈緒だけを護るヒーローに」
叫ぶ歩の手の中で、光がしぼみ始める。
「待ってくれ」
歩は慌てて光りを掲げてみるが、光はみるみるとしぼんでいく。
「そうだ、コスチュームさえ着れば……、やっぱヒーローって言ったらコスチュームでしょ」
「その光をなくすと言うことは……」
「待て待て。変身。あれ、おかしいな」
女性の声が遠くに聞こえ、光が微かになってしてしまう。
「……だからコスチュームさえあれば」
歩に耳を傾けていた奈緒がそっと呟く。
「そうね。すぐにでも家から取ってきましょうね。あなたはヒーローですものね。こんなことで死んでらえないわよね」
みるみる光は萎み、歩はすべての光を失う。
歩の頬に、一筋の涙が流れ落ち、その言葉を最後に、永遠に帰らないしとになっなった。
――父さんが死んだ。
冗談にもならない。
明日歩は怒りに任せて壁を殴る。
中島が頭を抱え、泣き伏す。薫子に支えられた奈緒は、歩の名前を繰りかすばかりだった。
長い一日が終わり、すっかり陽が高くなっていた。
その眩しさに、明日歩は目を細める。
何があっても死なないと思っていたのに。あっさりと逝ってしまった。
蜩の声が一段と大きくなる中、明日歩は奈緒の肩を抱くように病院を後にする。
中島が車を回してきて、二人は後部座席へ乗り込む。
事務的な処理は、従妹の薫子がすべてを請け負うってくれている。一先ず家に戻り、歩の帰りを待つことになったのだが、歩の死を告げられてから、奈緒は一滴の涙も流していない。
奈緒はハンカチをギュっと握りしめ、一点を見つめたまま、何を話しかけても上の空だった。
もう少しで家というところまで来て、雨が降り始める。
連日連夜の暑さで暖まった地面から、ムッとした熱気が上がって来る。
大急ぎで家の中に入ると、明日歩は奈緒に横になることを勧めた。間もなくして、薫子の妹、由紀子がやって来て、それからはガタガタと葬儀の準備が進められて行った。坊さんの手配にお返しの品。戒名に訃報の知らせに区役所に提出する書類の数々。お金の出し入れに、どれもこれも、まるで他人事のように話が進められていく。
二度と目を明けることがない歩を横たわらせ、誰もが無言になる。
よろよろとした足取りで、歩の傍にやって来た奈緒は、見ていられないほど憔悴しきっていた。
ツーンと鼻の奥が痛くなってきた明日歩は、居た堪られず庭へ出る。
朝顔の蔓がきゅうりの方まで侵略を始めている。細く小さな身を付けたきゅうりの横に、ひっそりと沈丁花の木。全て歩の思いでに繋がってしまう。
明日歩の目から涙があふれ零れだす。
そして明日歩は思い出していた。
遠い遠い昔、肩車され、男を見込んで頼まれた約束のことを。
☆
「明日歩、おいで」
この家に引っ越して来た日だった。
歩が手招く。
明日歩が無邪気な声を上げながら駆け寄って行くと、泥だらけの歩が得意気な笑みで抱き上げる。
「これ、いい匂いがするだろ? 沈丁花って言うんだ」
「ジンチョウゲ?」
「そう、沈丁花」
にっこり微笑む歩の額に汗が滲み、それを軍手を付けた手が拭う。
春の日差しがきらきらしていた。
明日歩をひょいと肩に乗せた歩が、嬉しそうに言う。
「だいぶ重くなったな」
明日歩は明日歩で、グーンと空に近付けた気がして、ワーッとはしゃぎ声を上げ喜んだ。
「なぁ明日歩、花っていうのは不思議な力があるんだ」
「力あるある。もりもり」
「もりもりか。そうかもしれないな。花には、花言葉っていうのがあるんだ」
「ハナコトバ?」
「そう花言葉。誰が考えたんだろうな。きっと大昔の人が、この花を見た時にはこうなったとか思いながら考えたんだろうな」
「うん、明日歩も考える。空、ヤッホー」
「そっかそっか。空、ヤッホーか」
歩は明日歩を地面へ降ろし、明日歩の鼻を抓んで笑う。
「止めろう」
手から逃れようとする明日歩を、羽交い絞めした歩がゲラゲラと笑い声を上げる。
ひとしきり笑った後、歩は屈み明日歩と目線を合わせる。
もうその顔からは笑みは消えていた。
幼いながら、明日歩もギュッと口を結ぶ。
「沈丁花の花言葉はさ、栄光、不死に不滅だろ。それに青春の喜びっていうのもある。何か錚々たるものを感じないか」
連ねられた言葉の意味が分からない明日歩がきょとんとなってしまう。
「少し難しいかな? 分かんないよな。でもそれでもいい、そういうことを言っていたなって覚えていてくれれば」
そう言いながら歩は、明日歩の頭をガシガシと撫でた。
「なぁ明日歩、父さんはな、沈丁花ってヒーローのような花だと思うんだ。だから今日、この庭に植えた」
「うん。植えた」
日差しが傾き、花が揺れる。
「なぁ明日歩。父さん一つ、君を男として頼みたいことがあるんだけど、聞いてくれるかい?」
真剣なまなざしを向けられ、明日歩はコクンと頷く。
「父さんな、夜、仕事に行くことになったんだ。そこまで分かるかい?」
言っていることは分かった明日歩は頷いたものの、不安な面持ちになる。
「絹代ばあちゃんの躰は、弱っている。それは明日歩も知っているだろ? 家のこととかばあちゃんのこととかで母さんは疲れている。夜は特に疲れが出るものなんだ」
明日歩にとっても夜は厄介な存在だった。
うっかり目を覚まそうものなら、そばに誰もいないと分かった途端、泣きじゃくる。
今までは狭いアパートで、隣の部屋にいた奈緒たちが来てくれたが、恐る恐る明日歩は後ろを振り返る。
何度かお泊りに来たことがある。
寝るのは二階の部屋。
抱っこされて上り下りしなければならなかった。
風が吹くと、あちらこちらがガタガタと音を鳴らすのも明日歩は知っている。
じっと歩に見られて、明日歩は泣きそうになりながら見つめ返していた。
「そこで明日歩を男と見込んで、頼みたいんだ。オレがいない時間だけでいい。二人を護ってやって欲しい」
「でも……」
「でも何だ、明日歩」
「お化けが出たらどうしたりいいの? ボク……」
「そっかお化けか。明日歩なら大丈夫。オレの子だからやっつけられる。だって明日歩はヒーローの子なんだから」
それは歩の口癖だった。
ゆっくりと陽が沈み辺りが暗くなり始めた頃、親戚たちが集まり始める。
一目だけでも挨拶をさせて欲しいと、近所の人たちが歩の顔を眺めては、ハンカチで目を覆う。
黒い高級車が家の前で止まり、中から出て来た人物が足早に家の中へ入って来る。
その人物を見て、中島が力なく、ああ来てくれたんだ、と声を掛ける。
コクンと頷き、あいつはと尋ねた。
「隣りの部屋で寝ているよ。会ってやってくれ」
中島にそう言われ、その人物は襟を正し、仏間へ入って行く。
「中島さん、あの人」
明日歩に尋ねられた中島は、仏間に目をやりながら小さく微笑む。
「ああ、間宮徹だ」
驚きのあまり、大きな声を出しそうになった明日歩は、慌てて手で口を塞ぐ。
「あいつら、親友なんだ」
間宮の泣き声が漏れて来て、明日歩も仏間に目をやる。
奈緒の表情は硬く、話しかけられたことに答えているようだが、明日歩は中島をチラッと見る。
中島も、その表情を気にかけているようだった。
「母さん、大丈夫かな」
「ああ大丈夫だ。奈緒さんはそんな軟じゃないはずだ」
笑みを浮かべた中島に肩を叩かれたが、明日歩は不安を拭いきれなかった。
病院を出てからの奈緒は、一滴も涙をこぼしていなかった。
ただ茫然と、歩のそばに座り、顔を眺めるばかりでいる。ろくに食事もとっていない状態だった。
人が続々と集まり、狭い茶の間はあっという間に人であふれかえす。
葬儀場は今日でも使えると言われたが、ここに集まった誰もがそれでは奈緒さんと歩が可哀想すぎると反対をした。
「ここで一日ゆっくり、過ごさせてからでも遅くあるまい。歩と酒も一緒に飲みたいし」
ずんぐりむっくりとした男性が、にっこりと明日歩に微笑みかける。
この人も、テレビや映画で見たことがある人だった。
「僕、野村と言います。小さい頃、何度か会った事があるんだけど、覚えていないかな」
「ないですよ。最後に会ったのは、2歳の時でしょ」
中島が言う。
かなり酔いが回っているらしく、呂律が回っていない。
「君はさ、本当に幸せもんなんだぞ」
野村の言葉に、明日歩がたじたじになる。
「僕かぁ覚えているな。君が生まれた日のことを」
「はいはい。もうそのくらいにしときなさいよあなた」
この人も知っている。脇役だけど、よくドラマとかに出ている女優さんだ。
「木綿子、でも、僕は話したい」
「はいはい。もう分かったから、今日のところは帰りましょ」
「嫌ダメだ。僕は話したいんだ」
「もうこんなに酔っちゃって、明日歩君、本当にごめんなさいね。この人、悪気はないのよ」
「木綿子さん、良いじゃないですか。今日は歩のお弔いなんだから、聞かせてあげましょうよ。どんだけ歩が、明日歩の誕生を喜んだかを」
目を真っ赤にした薫子が言うと、隣に座る由紀子も頷く。
横に座っていた中島が、明日歩の頭を抱え込む。
庭のきゅうりは収穫期を迎えていた。
二度と目を覚ますことのない、歩から離れようとしない奈緒は、やつれ果て、化粧っ気のない顔は青白く、黒い服を着ているせいもあって、別人のように見える。
昨日から霧雨が降っていた。
あんなに暑かったのが嘘のように、涼しい風までが吹いている。
「歩らしいな」
中島が受付の準備をしながら、呟く。
通夜の時間までには、少し時間がある。
手伝いを買って出てくれた隣に住む夫人が、そんな二人の元へやって来る。
「もう少し、ゆっくり見送ってもいいんじゃないかしら。あんなに仲が良かった夫婦ですもの。奈緒さん、気持ちの整理が付かないんじゃないかしら」
「そうですね。それも一理あると思います。だからこそ、こんな悲しい行事は早く終わらせてあげなければいけないないんじゃないかしら」
「そうおっしゃりますけどね。あの憔悴の仕方、見ているのが辛くって」
「お優し言葉、ありがとうございます。でも、別れを長引かせても、辛くなるだけだから」
「本当に気の毒で気の毒で。あんなに仲が良い夫婦だったのに」
涙ぐむ夫人に、二人は丁寧に頭を下げる。
「まったくあいつったらどうしようもないバカ。奈緒さんを一人にして」
夫人が行ってしまうと、薫子は空を見上げ涙声で言う。
「こんな気の使い方なんかいらない。あのバカ、今度会ったらとっちめてやる」
泣きはらした目でぎこちなく笑うが、すぐに泣き顔に変わってしまっていた。
翌日、雨こそ降っていないが、そんなに暑くならず、葬儀はしめやかに執り行われていた。
一般人とは思えないほどの弔問客が、列を作っている。
一人一人に頭を下げながら、明日歩は、どういう繋がりなんだと首を捻る。
テレビや雑誌で見かけるような人や、どこの人だよと訊きたくなるような年配の人までが、口々に生前は良くしてもらったと礼を言っては、焼香を済ませて行くのだ。
その先頭にいたのが、島根である。
島根はぐちゃぐちゃな泣き顔で、奈緒に封筒を手渡してきた。
「もっと早くに返しに来れば良かった。すいません。少ないけど、全然足りないけど、これ、先輩に借りた金です」
しばらく考え込んでいた奈緒が、何かを思い当ったように少し目を見開いてから、微笑む。
一緒に暮らしだしたばかりの頃、歩が給料袋ごと失くしてしまったと、帰って来た時があった。
「何とかなるよね」
「本当なの? 警察には届けたの? 」
「そんなの面倒だからいいよ」
話を誤魔化されてしまっていた。
「大丈夫。歩は、そんな小さな男じゃないわ」
島根は、せめて罪滅ぼしに葬儀の手伝いをさせて欲しいと言って、今は薫子に代わって、中島と受付をしている。
葬儀が終わり、いよいよ出棺の時だった。
小さな男の子を連れた若夫婦が、奈緒の元へと歩み寄って来たのは。
父親であろう男性は、地面に頭を擦り付けるように謝り出す。母親の後ろで怯えるように隠れる男の子の足には、包帯が巻かれている。
奈緒も明日歩も、その人たちが誰なのか一目で分かった。
奈緒はそっと屈み、手を引かれている男の子と目線合わせてから、微笑んだ。
「ボク、いくつ?」
奈緒の問いかけに、男の子は手を大きく開いて見せる。
「そう、5歳なんだ。あんよ痛む?」
男の子は母親の後ろに隠れるようにしがみ付く。
そして、首を大きく横に振ってみせた。
「智ちゃん、ちゃんと謝って」
母親が無理矢理、前へ出そうとするが、頑として男の子は動こうとしなかった。
「あのね、あのおじちゃんはヒーローなんだよ」
奈緒は、写真の中で笑う歩を指差す。
「ヒーローって大変なんだ。どんな状況でも必要であれば命を掛けても、助けに行かなければならない任務があるのよ。分かる?」
男の子は母親にギュッとしがみ直し、コクンと頷く。
「本当に申し訳ございませんでした。謝っても許されないことって解っています。もしあの時ご主人が助けてくれなかったら、この子の命はなかったと思います。こんな場で礼を言うなんて、失礼だと思います、でも言わせてください。ありがとうございました」
「もう済んだことですから、どうかお気になさらないで」
泣き崩れる母親を慰めた奈緒は、そっと微笑んで見せる。
「そうだおばちゃん、僕にお願いがあるんだ訊いてくれる?」
頷く男の子を見て、奈緒は一度歩の遺影写真を振り返り、にっこり微笑む。
「あのおじちゃんが守ったその命を、大切にして欲しいの。約束だよ。指切りげんまん」
奈緒が小指を差し出すと、男の子はそっと小指を重ねてきた。
また、明日から暑さがぶり返してくると、テレビのアナウンサーが明るい声で話している。
歩がいなくなっただけで、茶の間がこんなに広く感じるとは、奈緒は思いもしなかった。
明日歩は、明日から練習に戻ると言って、自分の部屋へ上がって行き、中島と薫子がさっきまでそこのテーブルに座っていたが、さっき帰って行った。
「やっと落ち着きましたね」
奈緒は小さくなってしまった歩に、語りかけるように話しかける。
ガランとした部屋に一人で座り、白く浮かぶそれに縋りたいのか怒りたいのか分からず、奈緒はいた。
「歩、私ね頑張ったのよ。あなたの……、ヒーローの奥さんらしく、きちんと挨拶して、あなたが護った命は5歳だって……。何で? 何で何も言ってくれないの? いつものように、そっかそっかって言ってよ。やっぱ俺、偉いって、自慢してよ。そしたらね、私、まったくアなったって人は、誰のためのヒーローなのって言ってあげるから。んなこと言うなよ奈緒って、あなたは困ったように頭を掻くの。素いsたらね、仕方がない人ねって、あなたのためにコーヒーを淹れるから。うまいうまいって飲むんでしょ。そうやってずっとしてきたじゃない。もうこんな冗談止めてよ。ねぇ歩、嘘よね。嘘って言ってよ。歩、カッコつけすぎだよ。こんな小さくなっちゃって。どうやって私を護ってくれるの? 歩、言ってくれたじゃない。よぼよぼになっても奈緒だけは護りきってやるって……。オレが一人になることがあっても、奈緒は一人にしないって言ってくれたじゃない。お願い、私を一人にしないで。これからどうやって生きて行けばいいの?」
この夜が終われば、みんな当たり前のような毎日が始まる。
奈緒のそれからの記憶はない。空っぽの世界で、歩を探しているのだ。
納骨を済ませると、奈緒は一人で起き上がることも出来ずに、ぼんやりと天井を見上げて過ごす日々が続いている。
生きる気力を失ってしまった奈緒である。
歩の育てていた花は枯れ落ち、もう見る影もない。
奈緒は朝を迎えるのを拒み、食べることも辞めてしまった。
感情がうまくコントロールできず、無表情になり、何を言っても反応を示さなくなってしまっていた。
心配した薫子たちが、知り合いの医者に診てもらおう言ってくれたが、明日歩はもう少しだけ待って欲しいと頼んだ。
自分の母親が、こんなに簡単に壊れてしまうなんて、信じたくはなかった。
「何が、ヒーローはコスチュームがないとだよ。死ぬ寸前までほざいてんじゃねぇよ。 明日歩は、微かに動いた手を握り返し、期待に満ちた奈緒の目を思い出していた。期待までさせて言うセリフかよ。涙なんか流すくらいなら、死ぬんじゃねーよ」
散々、悪たれをついてから明日歩は、自分の部屋の押し入れを開ける。
――秘密基地。
明日歩が、自分の部屋に存在するもう一つの部屋を教えれられたのは、幼稚園に通いだして間もない頃だった。
なかなか幼稚園になじめず、泣く明日歩に、歩は男同士の約束だと言って、この場所を教えてくれた。
小さな空間を見せられた時、明日歩はワクワクしたのを覚えている。
「ヒーローは凄いぞ。このコスチュームに変身するだけで、どんな敵にも立ち向かって行けるんだ。明日歩の場合はこの制服だな。この制服は、明日歩をきっと強くしてくれるアイテムがいっぱいだぞ」
そう言って、制服に不器用な手つきで武器を装着してくれた。
いびつに縫い付けられたアップリケを何度も握りしめて通った道は、いつも歩の背中があった。
死ぬ前の日も、歩は、明日歩の部屋の押入れに上がり、奈緒には内緒だぞと言って笑っていた。
明日歩は暗がりから箱を引っ張り下ろす。
いつだって父さんはそうさ。
「明日歩、入るぞ」
仕事に出かける前やってきた歩は、どこか落ち着きがなかった。
「合宿って、いつまでだ?」
「明日から三日間だけど……、言わなかったっけ?」
「聞いた」
「じゃあ何で聞くの?」
ベッドの上に置いてあったユニフォームを明日歩に渡しながら、歩は答える。
「大事なことだから、確認だよ確認」
「大袈裟だな。自分の時もあったでしょ?」
「あった。夏休みは、ほぼ合宿状態だった」
ニヤニヤする歩に、内心、面倒臭いなと思いつつも、明日歩は話を合わせる。
「へぇ、そうなんだ」
「えへへへ、そうなんだですよ。明日歩君」
嫌な予感がする。こういうノリの時の歩は、ろくなもんじゃない。
「さっきからなんだよ? 気味が悪いな」
にやにやと始終しまりがない顔で、ベッドに座り、明日歩を眺めている。
「だから何?」
歩はポケットから二枚のチケットを出し、高く掲げて見せた。
「デートよ。デート。何十年ぶりかの」
荷物を詰める手を休めない明日歩に、歩は執拗にデートだぞ。凄いだろ? な、訊いている? と繰り返し訪ねる。
明日歩は仕方なく手を休め、にっこりとしてやる。
「ああ。よかったね」
わざとらしく棒読みでそう言うと、満足そうに歩は頷く。
こういう時の歩は、少年の顔になる。
「で、何が言いたいわけ?」
苦笑して聞く明日歩に、歩は大袈裟過ぎるリアクションをして見せる。
「今まで、誰かさんのおかげで、二人っきりという時間が持てなかったからな」
「それはすいませんでしたね」
「まぁ息子よ。そうかっかしなさんな。君が悪いとは、誰も言っていないぞ。むしろ感謝している。君が公立高校に進学してくれたおかげで、こうして贅沢なデートを敢行できるのだから」
贅沢?
この父親は時々、とんでもないことをやらかしてくれる。芝居がかった口調の歩に、明日歩は恐る恐る訊き返す。
「贅沢って?」
「聞いて驚くなよ。ミュージカルを見て、その後は六本木ヒルズで豪華なディナー。ワインなんか堪能して、夜景が一望できる最上階とはいかなかったが、そこそこいい部屋へチェックインだ。あとのことは聞かないでくれ。これは大人の世界だから。しかも奈緒は知らないサプライズだぞ。すっげーだろ?」
年甲斐もなくはしゃぐ歩に、明日歩は、もはやここまで来ると病気だなと、観念する。 目を輝かせている45歳の父親に向って、この上ない笑顔を作る。
「良かったね。楽しんできてよ」
きっとこの言葉を求めているんだろうと、明日歩は最上級の良い息子を演じてみせる。
「大事な記念日は、このくらい祝わないとな」
「何の?」
二人には山のように記念日がある。明日歩がうんざりした声で訊くと、歩はニヤッとした。
「聞きたいか? でも教えない」
……本当に、この親父は。
薄暗い部屋に月明かりが差し込み、奈緒は天井を見上げていた。
息をするのも辛い。仏壇に飾られた動かない歩の笑顔を見るのも辛かった。
スッとふすまが開き、ぼんやりと光が差し込んでくるのに気が付いた奈緒が、そっと顔を動かし息を飲む。
ヒーローのコスチュームに、仮面を小脇にかかえた歩が、奈緒と呼びかけている。
「あ、ゆ、む?」
「奈緒、もう泣かないで」
ずっと聞きたいと思っていた声だった。
「歩、歩なの?」
「ああそうだよ。奈緒」
歩はそっと頷くと、仮面を被り近づいて来る。
会いたくて、会いたくてたまらなかった。
奈緒は震える手を伸ばし、歩の首に腕を回す。
夢でも嬉しい。生暖かい感触が伝わってくるのが嬉しかった。
目だけが仮面から出ている。
あの優しい目だ。
歩に支えられるように起き上がると、奈緒は胸にしがみついてしばらく泣き伏した。
ずっとそうしたかったんだと、奈緒は初めて気が付く。
「歩……」
「奈緒、もう泣かないで。奈緒の笑っている顔がいっち番好きだから」
「歩……」
奈緒は歩の胸に縋り付くように、何度も名前を呼び続けた。
「歩、どこにも行かないで」
「オレはどこにも行かない。ずっと傍に居る。だから元気出して」
ふんわりと頭に置かれた歩の手が優しく、何度も髪を撫でる。
華奢な肩に、伸びる柔らかな声。似ているけど全然違う。
「歩、歩」
その優しさに奈緒は癒され、久しぶりにぐっすりと眠った。
目が覚めると、奈緒はおぼつかない足取りで茶の間へ入って行く。
そこには、焦げた目玉焼きときゅうりの塩もみが食卓に並べられ、明日歩が照れくさそうに歩そっくりな声で、おはようと笑う。
奈緒は何も言わずに、きゅうりの塩もみを一口食べ、微笑んだ。
第三章 意地とプライド
奈緒は隣町のスーパーに働き出すようになってから半年が経ち、庭には生命の強さを思わせる朝顔が弦を伸ばし、その横にはきゅうりの苗が植えられている。
慌ただしく過ぎて行く時間の中で、もうすぐ歩が亡くなってから、初めての夏が来ようとしていた。
高校二年生になった明日歩は、歩の身長を追い越していた。
「明日歩、時間」
知美が腕時計を指しながら叫ぶと、一気にスピードを上げ、グランドを一周して明日歩が戻って来る。
「早くしないと間に合わなよ」
急き立てる知美の傍らで、ベンチに座る森崎が冷ややかな目で明日歩を見た。
「随分と、いい身分だな」
この森崎と新学期早々、明日歩は揉めてしまっていた。
家計を助けるために始めたアルバイトに、この森崎は良い顔をしないのだ。
才能を買っての、言動だからとなだめる知美に、ムキになるのを何度か止められていた明日歩である。
森崎幸一。
この春に、転任してきたばかりの体育教師だ。陸上の経験も豊富で、斉藤とは雲泥の差がある。
明日歩の活躍により、成績が伸びて来た陸上部への配慮だった。
「どういう意味ですか?」
始まった、と知美はおたおたと、二人の間に割って入ろうとするが、今日はいささか一筋縄ではいかない雰囲気が漂わせていた。
「意味? そんなのも聞かないと分からないのか? 今、この時期がどんなに大切なものなのか、おまえは分からないとは、随分お粗末なエースだな」
きつい目つきで睨み返す明日歩の傍ら、知美は変われば変わるもんだと、あきれるやら感心するやら見入ってしまっていた。
あの虫も殺せないような弱虫で泣き虫の明日歩がだ。
知美は密かに優越感に浸ってしまっていた。
自分だけが知る明日歩である。
親友の克己だって知らない、男らしい明日歩。
にやけそうになる顔を引き締め、知美は口を挟む。
「先生、中田君は家庭の事情で」
「君には、聞いていない」
ぴしゃりと言われ、知美は口を噤むしかなかった。
ただならない雰囲気に、部員たちが集まり始めていた。
フッと目線を外した明日歩が、折れたのはその時である。
「すいません。でも俺、少しでも家計を助けないとですから」
これ以上、自分のせいでみんなの練習を停めさせてはならない、という判断をした明日歩だったのだが、森崎としては納まりがつかず、言い繋ぐ。
「そういう家庭はいくらでもある。それなりの援助も受けられるはずだが……。手続きが分からんでもないだろ。かっこつけんでも、人の助けが必要なときは、有難く受けるべきだと思うがね」
アルバイトを決めて来た、と言う明日歩に奈緒は、似たようなことを言っていた。
「私を舐めないで。あなた一人くらい何とでもなるのよ」
こんな顔をするんだと驚くほど真剣な眼差しで言われ、一度は怯んだが、明日歩は自分を押し切った。
まさか、ここにきて、同じことを言われるとは思っていなかった明日歩である。
「そのことは、了解済みになっているはずです」
「ああ、斉藤先生とはな。俺は認めていない」
はらはらしている知美を横目に、明日歩は投げやりになり始めていた。
4月の当初からずっと考えていたことがある、明日歩である。
「それじゃどうしたらいいんですか?」
「中途半端な気持ちでやられては、まじめに頑張っている奴らに失礼だ。士気が下がるって言ってんだよ」
その言葉は、明日歩に突き刺さる。
誰もが明日歩を気遣って口にしてこなかったことである。それに気づかないふりをして、練習を抜け出すのは、もう限界だということは、明日歩自信が良く分かっていた。
誰もが息を飲みこんで、そんな二人を見ていた。
きっときっかけが欲しかっただけ。
明日歩は静かに口を開く。それよりも早く、森崎が言葉にする。
「部を、辞めてくれないか」
分かり切っていることだった。
カーッと明日歩の顔が赤くなる。
「分かりました」
言い捨てるようにその場を立ち去る明日歩を、知美が引き止める。
ずっと考えていたことである。
これは単にきっかけですぎない。
知美の手を振り解き、気づくと明日歩は駆け出していた。
☆
「先輩、どうしたんですか? さっきから変な顔をしてますよ」
ぼんやりとしている明日歩を、心配そうに結城あずさがのぞき込んできた。
結城あずさは、一か月前に入って来たばかりの初々しい高校一年生だ。
「変な顔って失礼な」
どうにも年下には思えないノリで、あずさはいつも絡んで来る。
「でも、こんな顔をしていましたよ」
自分の顔を抓みあげて見せるあずさに、明日歩は苦笑しながら頭をコツンと軽く叩く。
「そんな顔をしてないだろ」
「やっと笑った。その方がいいですよ先輩は。折角のいい男が台無しになるところだったわ。救出作戦成功ですね」
「何だそれ?」
あずさがわざとらしく、フーと言いながら額を拭く。
この子には、本当に調子を狂わされてしまうな。
すっかり和まされた明日歩と目が合ったあずさが、ちょこんと首を傾げる。
「先輩をそんな顔にさせる原因って何だったんでしょうね?」
自分のこめかみを指で叩き、どこまでもおどけてみせるあずさに、明日歩は吹き出してしまう。
「ま、いろいろ」
両腕を組んだあずさが、大げさに頷いて見せる。
「生きていると、いろいろありますよね。って、いらっしゃいませ」
接客へ向かうあずさから、なぜか目を離せない明日歩だった。
週末ということもあって、店は混み合っていた。
気を紛らわすには、ちょうど良かった。
歩との約束を忘れたわけではない。でもあの時とは条件が変わってしまったんだ、と自分に言い聞かせる明日歩である。あとは、奈緒にどうやって切り出すかだった。反対されたアルバイトが原因なんて、口が裂けても言えない。だから言ったじゃない、と言われるのも明日歩のプライドが許さない。願うは、おしゃべりな知美が告げ口をしないでいてくれればと思う。
接客に身が入らない明日歩である。
「先輩、しっかりしてくださいよ」
テーブルを片しながら、あずさに言われ、明日歩は苦笑いをする。
まったくなっていない一日である。
終業時間になるのを、これほど待ち遠しく思ったことがなかった明日歩である。それと同時に、気が重くなるという、複雑な心境に陥っている明日歩を追いかけて来たあずさが並ぶ。
珍しいことではなかった。
何度か途中まで一緒に帰ったことはある。そこに特別な感情はなかった。帰る方向が一緒だってことだけだった。通っている学校のことや、店で起こったことをチラホラ話すってもので、意識などしたことは一度もない。
「先輩、途中まで一緒に帰りましょ」
そう言われ、明日歩はドキッとなる。
「ああ」
二人で自転車を引っ張りながら歩く。
「今日、忙しかったですね」
「週末だし、給料日後だし」
「想像していたよりもハードで、驚いちゃった」
「そっか、結城さん初めてだ」
「もう初めてだらけで、記念日にならないです」
「記念日って」
明日歩はつい笑ってしまう。
「笑わないでください。これでも真剣に話しているんですからね」
「いや、ごめんごめん。うちの両親と同じこと言っているなって思って」
「え? そうなんですか」
「そうそう。昔さ、しょっちゅういうもんだからカレンダーに書き出したことがあったんだ。そしたらさ、一年中記念日で埋まることに気が付いてさ、それを言ったら親父、明日歩が俺たちの記念日を知った記念日とか言い出して、お祝いをしようって、あの店へ連れて来てくれたんだ」
「そうなんですね」
「訳分かんねーとか言いながら、ハンバーグ定食食べたの、よく覚えている」
「ユニークなお父様なんですね」
「ユニーク過ぎて、参っちゃったけどね」
「でも素敵ですね。そうやって親のこと話せるのって、私も一度、会ってみたいな」
何のこなしに言われたあずさの言葉に、明日歩は鼻の奥がツーンと痛くなる。
「もういないんだ」
半白ほど置いたあずさが、目を伏せる。
「もしかして、亡くられたんですか?」
「ああ去年の夏、事故であっけなく死んじゃった。全く散々人のこと引っ掻き回して、最後に言った言葉がさ、まったくふざけてんだ」
泣きそうな気分になった明日歩が、気を紛らわすように空を見上げる。
「先輩、我慢しないでください」
そう言う声がおかしいことに気が付いた明日歩が見ると、目一杯に涙を浮かべたあずさが微笑で見せる。
ストンと明日歩の中に、何かが落ちる。
こんな話をしたことはなかった。
高校に入る時のことや、歩と約束したこと。そして、母親を助けるため、その約束を破ってしまったこと。あずさは明日歩の話を聞きながら、目を大きくしたり細めたり、口に手を当てたりしては涙ぐんだ。余計なことは言わず、聞き役に回ってくれるあずさが、有難かった。
心が軽くなって行くのを感じながら、明日歩はとめどなく話し続ける。
「でも先輩、辞めちゃって大丈夫なんですか? 大会、もうそろそろですよね?」
あずさに唐突に訊かれ、明日歩は一瞬、言葉を失う。
「聞いちゃまずかったですか」
あずさが小首を傾げ尋ねる。
散々悩んで、自分では腹を決めていたつもりだった明日歩だが、改めてあずさに突っ込まれ、ドクンと心臓が脈打つ。
あずさと一度も部活のことを話したことはなかった。
あずさに、不安な顔をされ、明日歩は慌てて言い繋ぐ。
「いや、大丈夫。まさか結城さんから、そんなこと訊かれるとは思わなかったから、少し、驚いちゃっただけだから」
「そうなんですね。でも私じゃなくても、その話を聞いた百人中百人が同じことを聞くと思うけどな」
「またそんな大げさな話にして」
「大袈裟なんかじゃありません。先輩時は自分を知らなすぎです。先輩、超有名人なんですよ。月間何とかに載ったりして、注目度半端じゃないですからね」
「何とかって、たまたまその時は調子が良かっただけで、高校行ってからは、全然だし」
あずさが躊躇いがちに明日歩の顔を見る。
緩やかな坂道を登りきったところで、二人は立ち止まっていた。
目の前に交差点が広がっていた。
信号が点滅して、赤に変わる。
あずさはこの交差点を渡らなければならなかった。
数台、車が通り過ぎて行くのを、ぼんやりと二人で眺めていた。
「こんなこと言ったら嫌われちゃうかもだけど、私、先輩には陸上部に戻るべきだと思います」
「顧問ともめちゃったから、無理っしょ」
「もう修復不能なんですか?」
「たぶん」
「でも、勿体ないじゃないですか。今まで頑張ってきたのに。先輩、走るの、諦められるんですか?」
「オレが甘かったんだと思う」
明日歩は、ガードレールにもたれ掛る。あずさもその横に並んだ。
「甘いって?」
あずさと目が合い、明日歩は焦って目線を外す。
「士気が下がるって顧問に言われた時、そりゃそうだって、素直に思っちゃったんだよねオレ。誰も何も言わないことをいいことに、俺、思い上がっていたんだと思う。考えてみればひどい話だよな。自分のメニューは熟したから良いってもんじゃないよな。個人競技だとしても、チームな訳だし、顧問はそこを底を指摘しただけで、何も悪くねぇけど、何かさ、俺、意地になっちゃって」
明日歩は泣きそうだった。
「そっか。辛いですね」
「正直参った」
あずさに頭をポンポンされて、明日歩は目を見開く。
「男の子って、大変ですね。だけど先輩なら大丈夫です。だって間違ってなんかいないですもの」
そう言うあずさの瞳から、大粒の涙が流れ落ちる。
「そんなこと、簡単に言うなよ」
「簡単じゃないですよ。バイトしているときの先輩も悪くないけど、走っているときのキラキラしている先輩を見れなくなるのを、悲しむ子が沢山いると思います。その一人は私です」
「あ、ありがとう」
やるせない気持ちで明日歩はあずさを見つめ返す。
「先輩、ガンバです」
胸の前で小さくポーズをとるあずさに、明日歩は苦笑する。
そんな簡単なことじゃないと、思えて仕方がない明日歩だった。
通り過ぎて行く車のテールランプが二人を照らし出して行く中、沈黙が続いていた。
「はい。中田先輩、私、結城あずさ、ここで一曲歌いたいと思います」
突然何を言い出すのかと思い、明日歩が眉根を寄せる。
大きく深呼吸をして歌い出すあずさに、明日歩は慌てて制止させた。
「急にどうしちゃったの?」
「私、弱っている人の励まし方、この方法しか知らないから。いけませんか? 音痴だけど、気持ちは沢山籠っています」
「うんそれはスゲー伝わってきた。でもここで歌わなくてもいいかな。その気持ちだけで」
「そうですか。残念」
「残念なのかよ」
一頻り笑いあった明日歩が、フッと空を見上げる。
昔もこんなことがあったことを、明日歩は思い出す。
奈緒と喧嘩して、家を飛び出したものの素直に家へかえられずにいた明日歩を、歩が迎えに来てくれた。
ぼんやりと空が滲んで行く。
「親父なら、どうすんのかな、こういう時?」
「そうですね。どうするかな?」
「もし生きていたら、ボコボコに殴られちゃうのかな」
「多分それはないと思います」
驚く明日歩を見て、あずさは微笑む。
「会ったことはないけど、たぶん先輩のお父様だもの、先輩がしたいように見守ってくれると思います」
「そっかな」
明日歩は、言葉を詰まらせる。
「大丈夫。先輩の思うがままにです」
不覚にも涙を流してしまった明日歩は、まともにあずさの顔を見られずに黙って頷く。
「でもこれだけは忘れないでください」
あずさは指でカメラのアングルを作り、明日歩を捉える。
「陸上界の王子様って言われているんですよ。練習してて視線感じたことありません?」
「知らん」
そう答えつつ、知美がぼやいていたことを思い出す。
自分のメニューをこなすことで頭がいっぱいだった明日歩である。顧問とのことがあって、フェンス越しの景色のことなど、まるで頭になかった。
「私も」
言いかけたあずさの携帯が鳴り出す。
あずさがdayスプレイを見て、顔を顰める。
「母親からの電話に慌てて出たあずさが、自転車片手に明日歩を見る。
明日歩も立てかけあった自転車を手に、行けの合図を送る。
申し訳なさそうに頭を下げるあずさに、明日歩は笑顔で手を振る。
あずさは喋りながら、横断歩道を小走りで渡って行く。
自転車に跨ったあずさが、向こう側で大きく手を振るのを見て、明日歩は手で払う。
一気に現実に戻された明日歩である。
家の前、明日歩は中へ入るのを躊躇う。
知美からのメールが届いていた。奈緒には何も知らせていないらしい。止めるって言ったのは、一時の気の迷いだったと思っているらしい。あの後、顧問は部員から相当責められたことも書いてあった。全面的に顧問に非があると言い切られ、明日歩は心が痛んだ。
意を決し、帰ってきた明日歩を、何も知らない奈緒が出迎える。
待っていなくてもいいというのに、奈緒はいつもご飯を食べずに待っていてくれる。歩がなくなってから、人が変わったように、服装も動きやすいものを着るようになっていた。
「何? さっきから人の顔をじろじろ見て」
奈緒はデザートにと言って、リンゴの皮をむいていた。
あんだけの啖呵を切っておきながら、どんな顔をして切り出せばいいんだ? リンゴを一切れ口に放り込む。
「だから、何?」
笑って言う奈緒に、明日歩は覚悟を決めて頭を下げた。
「母さん、ごめん。オレ、陸上辞めるかも」
「そう」
あっさり言われ、明日歩は拍子抜けしてしまった。
「怒らないの?」
「何で?」
「何でって? 良いの? 俺、本気で言ってんだけど」
「だってそう決めたんでしょ?」
「そうだけど。本気の本気だよ」
「良いじゃない。明日歩が決めたことなら」
ムキになって言う明日歩に、平然と奈緒は答えた。
予想外の反応に、明日歩は何とも言えない気持ちになって部屋に戻る。
もっと大騒ぎすると思っていた。高校受験の時のように泣かれるんじゃないかと……。
☆
月曜日の朝、明日歩は早めに登校していた。
がらんとした職員室、森崎はまだ来ていないようだった。
今日は朝練がない日である。
廊下の窓から、ぼんやりグランドを眺めながら、明日歩は森崎がやって来るのを待っていた。
明日歩は変な気分だった。
アルバイトをやると決めた日から、放課後時間が取れない分、明日歩は早朝練習に力を入れていた。身体的にはかなりきついかったが、明日歩にも意地がある。
アルバイトをしたいと言った時、奈緒が出した条件は、部活も勉強も手を抜かない立った。きつい条件を出せば、明日歩が妥協すると思ったのだろう。奈緒の魂胆を見透かした明日歩は、がむしゃらになっていた。今考えると、アホらしいことだが、一度決めたことを曲げるのは、どうしても嫌だったのだ。
チラホラやって来た教師たちに声を掛けられ、明日歩は曖昧な笑みでやり過ごす。
学校全体が賑やかさが増し、ようやくやって来た森崎が、ぼんやりと外を菜g目ている明日歩に気づき、足を止める。
明日歩が何の気なしに振り向く。
一瞬にして、気まずい空気が二人の間に流れる。
言うことは頭の中で何回も繰り返しおさらいしてきた明日歩だった。
緊張の面持ちで、明日歩は一歩踏み出す。
ただならぬ様子に、とおりすがった教師が顔を顰めて行く中、明日歩は着実に森崎に近づいて行った。
「先生、これ持ってきました」
そう言われ、森崎の片眉が上がる。
「オレなりに考えました。先生の言う通りだと思います。短い間ですが、お世話になりました」
ポケットで温めていたものを明日歩に差し出され、森崎は無言のまま受け取る。
数秒間が空き、明日歩は森崎に頭を下げるとその場を立ち去った。
だんだん実感が湧いてきた明日歩は、無意識でグランドに出ていた。
まっすぐ前を見据え スタートラインに立つ。もうこんな緊張感は味わえないだろうと思うと、ジンと込み上げて来るものがある。けど、自分の出した結論に後悔はしていない。明日歩は、自分に言い聞かせる。
深呼吸してから一度目を閉じ、そしてダッシュ。
これでいい。走るのはどこでも出来る。顔にあたる風が冷たい。悪くない。タイムもきっと良いはずだ。
その頃、森崎もまた複雑な思いで、明日歩の退部届を見詰めていた。
「森崎先生、大丈夫ですか?」
向かい側に座る菅原が、メガネを拭きながら尋ねる。
森崎は明日歩の退部届を引き出しにしまい、体よく言葉を交わす。
「何のことでしょうか?」
「恍けなくてもいいですよ。もう学校中で噂になってますよ」
顔を顰める森崎を見て、菅原は眼鏡を拭きながら言い繋ぐ。
「あいつのどこがいけなかったんです? 僕は信じられないなぁ。進学重視のこの学校を、違う視点へ向けさせたのは、中田の成果だと思いますがね」
嫌味がたっぷり含まれた物言いに、森崎はむっつりとする。
「先生、元担任として、この学校の先輩として一つ忠告しておきます。あまり目立ったことをされない方が良い。特に中田に関しては」
「それはどういう意味ですか?」
「言ったまんまです。あいつ一軒な寄って見えるでしょ。それが意外や意外、骨っぽい男でしてね。教師にも生徒にもファン、多いんですよ。弱小だった陸上部の名をとどろかせたのも、中田があってこそですからね」
「そうおっしゃられても、本人が辞めたいっていうんだから仕方がないでしょ」
「まぁそれはそうなんですけどね、だけどどうなんでしょうね。他がだまっていても校長が何ていうか、何せ、中田はこの学校きっての広報材料ですからね。玄以あいつ目当てで入学してきた生徒、結構いるみたいだし、文武両道校とした方が、聞こえは良いですしね」
「私立でもあるまいし、そんなの関係ないでしょ」
「そんなことはないでしょ。志望者が増えればそれだけ質の良い生徒が集められる。やっぱり校長たちとしては、気になる点でしょ」
菅原の言葉通りかもしれない、と思ったのはそれからすぐだった。
血相を掻いた教頭が森崎を呼びに来たのだ。
事態が一転二転と進展していく中、明日歩は頭をすっきりさせようと、無我夢中でグランドを走っていた。
突然現れた哲平に両手を広げられ、行く手を阻まれた明日歩は余儀なく足を止める。
肩で息をする明日歩は、しばらくその後ろに部員が集まっていることに気が付かなかった。
「おまえさ、何やっちゃてんの?」
「え何? て言うか何で怒ってんだお前」
「何のんきなこと言ってんだよお前。自分がないをしたのか分かってんだろうな」
肩を掴まれ、明日歩はやっと事態に気が付く。
「もしかして、退部のこと?」
「おーよ」
「わりぃ。お前にはちゃんと言うつもりだったんだけど、もうばれちゃったんだ」
「あのな」
「あんた、頭でも狂っちゃったの? 何でそうなるのよ。大会、もう目前なのよ。なのに止めるって何? あんな森崎の言葉なんか無視すればいいじゃない。皆あんたの事情何え分っているし、今までちゃんと結果出してきたじゃない。胸、張っていればいいのよ」
涙ぐんだ知美に胸ぐらを掴まれ、明日歩は予想外に大事になってしまっていることに、戸惑いを隠せずにいた。
「俺も、先輩が部活辞める必要ないと思います」
一歩前に出て言ったのは、一年生の久我だった。
普段は口数が少なく、黙々と走る印象しかない久我に言われ、明日歩は苦笑してしまう。
「えっとだな、誤解はして欲しくないんだけど、森崎先生の言ったことが多少なりにも起爆剤になったことは認める。だけど決して言いなりになったわけじゃないから、それは分かって欲しい。やっぱこういう半端は良くないって、オレ自身が考えて決めたことなんだ。大会目前でこんなことを言い出したのは悪いと思う。でもだからこそ、決断が必要なんだと思ったんだけど……」
言葉が尻つぼみになり、明日歩は一秒でも早くこの場から逃げ出したかった。
本令が鳴り、明日歩はホッとする。
「授業が始まるぞ。全員教室に戻れ」
菅原だった。
「後でもう一度、ゆっくり話そう」
知美にそう言われ、明日歩は顔を強張らせる。
一度決めた決心を揺るがされたくない明日歩だった。知美の性格上、強引に引き戻そうとするだろう。そう思うと、胃のあたりがギュッと痛くなる。
「中田は、校長室に行くように」
すれ違いざまに言われた明日歩は、えっと立ち止まる。
「校長が、話があるそうだ」
まじまじと見て明日歩の肩を、菅原は労うように軽く叩いた。
もっと簡単に思っていた明日歩である。
予想外の展開だった。
「中田、言動はもう少しよく考えてからするもんだぞ」
明日歩は笑って誤魔化す。
自分なりに思い悩み、考えた末に出した答えだった。
大人の目論見など、知ったことではない。
しかし、通された部屋の物々しさを見て、明日歩は吐き気をもようしてしまっていた。
入って来た明日歩を、森崎が振り返り見る。
当たり障りのない笑みを浮かべる校長の手には、今朝、森崎に渡した明日歩の退部届が持たれていた。
「呼び出して悪かったね。さぁこちらに座りなさい。森崎先生も」
「あの」
「さぁいいから、ここへお坐りなさい」
威厳のある言い方に、明日歩は従わざるを得なかった。
「今日君にここへ来てもらったのは、この件なのだが。もし良かったら詳しいことを聞かせて貰えないだろか」
「詳しくと言われても、陸上を止めようと思ったから、退部届を出しました。ただそれだけです」
「うん。事実上、ここにこんなものがあるわけだし、それは認めるが、そのいきさつを校長としては、知りたいと思うのだが。教えてはもらえないだろうか。君から言いにくいと言うならば、森崎先生から先に」
「言い辛いとかじゃなくって、もっと早くこうするべきだったんだと反省しています」
「それはどういう意味だね」
「父が亡くなり、部活なんてしている場合じゃないと思ったのが実直な考えでした。しかし、母の強い希望もあって、部活を続けることに決めるのと同時に、母への負担を減らしたいとも思いました。いろいろと話し合って、両立できるならばと言うことで今まで、自分なりに頑張ってきたつもりでしたが、森崎先生に指摘され、目が覚めました。僕は全く周りが見えていませんでした。一緒に頑張っている友や仲間を、知らず知らずに不快な思いをさせていたんだと、気が付いたんです。僕はアルバイトを辞める気はありません。走ることは好きです。それよりも大切にしたい気持ちがあるんです。散々力沿いをしていただいたのに、申し訳ありません。でも、この答えを出したのは、森崎先生のせいじゃないってことだけは断言できます。僕はずっとこのことについて悩んできました。むしろ背中を押してもらったと感謝しているぐらいなんです」
「中田君の気持ちはよく分かった。しかし、ここまで伸ばしてきた才能、そうみすみす手放していいのかね。やはり森崎先生の行き過ぎた指導があったからじゃないのかね」
目の前で、腕組をして目を閉じている森崎に目をやった明日歩は、きっぱりとそれを否定する。
ドアがノックされ教頭に導かれ、奈緒と見ず知らずの中年男性が中へ通される。
反射的に奈緒の服装を見てしまう明日歩だった。
シックなスーツ姿に、明日歩はほろ苦いものを感じる。
きっとこれが普通なことだろうと、思う。
だが身につまされてしまうのも事実。
もし歩が生きていたら……。
校長へ会釈する奈緒を、明日歩は複雑な心境のまま見つめる。
中学生だった頃の自分に言ってやりたい思いで、明日歩は胸がいっぱいになる。
そう嫌わなくても、幸せならいいじゃねーかって。
髪を一つに束ねた奈緒が、明日歩を見る。
向けられた目には、ほんのり強いものが感じさせられる明日歩である。
それは、自分が信じたことを貫きなさい、と言っているようだった。
「これはこれは」
校長が立ち上がり、つられて森崎も立ち上がる。
「このたびは、うちの息子がお騒がせいたしまして」
奈緒は深々と頭あを下げる。
別に、謝ることじゃないし、と内心、明日歩はムッとなりながらそれを見ていた。
「滅相もありません。明日歩君の頑張りで本校の評判は上々で、こちらこそ大変ご不愉快な思いをさせてしまいまして、何て申し開きしていいものやら、今、その算段を踏んでいたところなんです。さぁどうぞこちらへ。監督不行き届きで、実にお恥ずかしい。ご子息にこんなものまで書かせてしまい、驚くやらなんやらで、森崎先生、突っ立っていないで、君からもきちんと謝罪をしなさい」
「校長先生、それには及びません。これは明日歩が決めたことと存じてます」
「ですが、大事な大会を控えて、退部っていうのは、無責任でしょ」
「そうですね。校長先生が仰る通りだと思います。責任の取りようがございません。ですが、わたしとしては、本人の意思を尊重してあげたいと思っています。きっと、考えあっての行動でしょ。事実上、無責任と言われても仕方がないことも重々承知の上でのこと。どうかその辺りを汲み取って頂けたら、幸いなのですが」
「私も教師生活を、だいぶ長くさせていただいてますが、たまにあるんですこういうこと。中田君に寄せられる期待の重圧感は、それ相当のものでしょう。耐えきれなくなるのは、無理もありません。ですから私どもは全力でサポートを」
「校長先生。さっきも言ったとおり、僕はそんなことで決めたんじゃないんです。分かってください」
黙っていられなくなった明日歩に、皆の視線が集まる。
「いや思っていた通り。良い目をしている。勝負師の目だ」
ドアの前で押し黙っていた男性が、ニコニコと明日歩に握手を求めてきたのは、その段だった。
「ここは私に免じて、穏やかに行こうじゃありませんか。中田さんが困っていらっしゃる。申し遅れました。わたくしこういう者です」
陸上競技選手強化委員会。久我山庸一。
奈緒に名刺を渡した後、明日歩にも丁寧に同じものを差し出した。
「中田君の話は、息子からかねがね聞かされていましてね、今日も息子から一大事と連絡を受けて、これは放っておけないと馳せ参じさせて頂いた次第です」
そこで初めて、校長も正体を知ったようで、眉間に皺が寄る。
どうやら、学校側は明日歩の身内だとばかり思っていたようだった。奈緒は奈緒で、やたら親しげに道順を案内してきたので、学校関係者と思っていた。
困惑する面々を前に、涼しい顔をした久我が話を続ける。
息子とはまるで大違いで、軽佻な喋りに、明日歩は圧倒させられてしまっていた。
「ここに失礼させてもらうよ」
どっかりと目の前に座った久我の喋りは快調だった。
是非、強化選手の一員として向かい入れたいという段になり、校長が咳払いをする。
そんな軽んじた話題ではない。
一個人が決められることでもないはず。明らかに先走った話と言うことは誰にもわかることであった。
空気を呼んだ久我氏が、身を引き、自信満々の笑みをみんなに向けてくる。
「当然、テストは受けて貰います。息子の派内を聞いて、わたしなりに調べさせてもらいました。実は練習も何度か拝見させてもらっています。それを踏まえて、いけると判断したことを、承知して欲しい。私はよく誤解をされるんです。きっとこの喋りがいけないんだと、自分でも自覚をしているんですが、どうも改まって喋るのが苦手で、気に触ったら謝ります。改めて教会の方から、通知をさせてもらいます。どうか、良い答えを出してもらいたい。退部結構。それならうちで練習に専念すればいい。実力が付けば、スポンサー契約も夢じゃない。そうすれば君が描く自分に一歩近づけるんじゃないかな?」
的を射た話である。反論することは何もない、ないのだが……。
明日歩は奈緒をそっと見る。
手にしているハンカチを、奈緒はギュッと握りしめていた。
たった一言で、周りを飲み込んだ久我がにっこり微笑む。
勝ち誇った笑みを浮かべる久我山は、次の瞬間、目をパチクリさせる羽目になる。
静かに目を上げた奈緒の一言が、原因だった。
「久我山さんっておっしゃいましたかしら、今はそんな話、どうでも良いことですの。大事な話がしたいので、退座するか、黙っていていただけます」
毅然とした物言いに、久我山は言い返すことが出来ずにいた。
奈緒はゆっくり目線を森崎へ向ける。
森崎は唖然とした顔で、その場に立ち尽くしている状態だった。
奈緒は席をすっと立ち上がると、明日歩にも倣うように促す。
「森崎先生でいらっしゃいますか? このたびは明日歩が大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。このような大ごとになってしまって、本人も驚いていると思います。もう少し慎重に行動すべきだったと、親子ともども反省をしておりますので、どうか、穏便に気をお納めください。この子も未熟ながら、気をもんで出した答えです。家族の目から見てもここまでよくやって来たと思います。先生の指導の下、頑張らせたいという思いもありますが、こればっかりは親が口を挟むことでもないでしょ。短い間とは言え、先生の叱咤ご鞭撻は、明日歩にとって優衣義なものになりました。ありがとうございます。これに懲りず、温かい目で見守って頂けたらと、図々しいのを承知のうえ、お願いします」」
深々と頭を下げる奈緒に倣って、明日歩も頭を下げる。
頭を上げた奈緒が、校長へゆっくり視線を変えていく。
ハンカチを握り直すのを、明日歩は見逃さなかった。
「明日歩が真剣に悩んで出した結果です。どうか校長先生このまま、その退部届はお収め下さい」
「しかしですね、お母さん」
「もう、この子は、自分のことを決めて行かなければならない年齢です。大人が口出しするのは辞めておきましょ」
きっぱりと言い切る奈緒だった。
問答無用で二人で退室を果たし、すっかり動揺しきっている明日歩に、奈緒は微笑みかける。
「あなたは心配しないで、勉強、頑張りなさい」
こんなに強い人だったのかと、明日歩は帰って行く奈緒を見ながらつくづく思う。しかし、それが惰性だってこともよく知っていた。
わずかに足が震えているのは、遠目でも分かる。
案の定、駅に着いた奈緒は放心状態になっていた。
気を落ち着かせるため、奈緒はバックに忍ばせていた歩の写真を取り出す。
決して動くことがない笑顔に、奈緒は指を這わす。
「なぁあいつを信じてみないか」
支えになったのは、いつかの歩の言葉だった。
「これでいいのよね。歩」
奈緒の目に、薄らと涙が滲む。
☆
――長い一日だった。
部活もなく、明るいうちに帰るなど滅多にない明日歩は、真っ直ぐに家に帰る気にもなれず、駅前のショッピングモールをぶらついていた。
靴屋の前、聞き覚えのある声に振り返ると、あずさが友達と歩いて来るのが見え、自分でも信じられないほど大きな声で、明日歩は名前を呼んでしまっていた。
面を食らったような顔をしてこちらを見ているあずさに、明日歩は頭を掻く。
数秒してから、明日歩はとんでもないことをしてしまったことに気が付く。
あずさの顔が固くなっているのだ。
その隣に居合わせていた友達が、何事かと目をパチクリさせて、何かをやたら聞いているようだった。
こういう場面になれていない明日歩である。
成り行きに任せるしかないと思った明日歩は、無理して明るい声を作る。
「ごめん、声かけて悪かったかな?」
「大丈夫」
そう言いつつ、あずさは隣りに居る友達を、チラチラ見る。
相手を気遣う余裕などない、明日歩である。
「今日、暇ある?」
勢いに任せて言い切った明日歩の目には、あずさしか映っていなかった。
「今はちょっと」
目を伏せて言うあずさに、じれったさを感じた友達が口を開く。
「別に良いじゃん。うちら、ただぶらついてただけだから。中田明日歩さんですよね。私、あずさの友達で高坂まりです。嬉しいな。まさかあずさと中田さんが知り合いだったなんて、話聞いていなかったからびっくり。私、中田さんのファンで、何度も南高校へ練習見に行ったりしているんですよ。もしかして、気づいていたりしてくれていたりして」
愛想笑いを浮かべながら、その傍らで表情を硬くするあずさを明日歩は気になっていた。
「カラオケでも行きます?」
腕を取ろうとするまりの手を、明日歩は咄嗟的にかわす。
「ごめん。ちょっと二人っきりで話したいんだ」
「私とですか」
「本当に申し訳ない。結城さんと二人っきりにさせてもらえないだろうか」
「嫌だな。何マジになっているんです。冗談ですよ。ほら、あずさも何とか言ってあげなさいよ」
「あの先輩」
「何てね。オレも冗談。悪かったな。じゃあ」
「待ってください。今日、シフト入っていたの、忘れていました。ごめんまり、先輩、それを教えに来てくれたみたいだから、私、行くね」
あずさに腕を掴まれ、明日歩は目を瞠る。
「大丈夫なの?」
コクンと頷くあずさだが、それは嘘だってことは歴然だった。
「オレのこと、気にしなくてもいいよ。あの子、気が強そうだし、面倒になるんじゃないの?」
「平気です。それより先輩、どうしてこんな時間にこんなところ、ウロチョロしているんです? それを私に聞いて欲しかったんでしょ」
まったくと、明日歩はまじまじとあずさを見る。
初めて会った日から、この子には歯が立たないと思ってきた明日歩だが、改めて実感させられていた。
きっとこんなことをしたら、ただ事では済まないだろうに。
取り残されたまりが怖い顔で睨んでいた。大丈夫と言うわり、あずさの顔は今にも泣きだしそうである。
明日歩は今、確信した。
だが、それを口にするのは少々抵抗がある。
勢いでファーストフードの店に入り、適当に注文して席に着く。
窓側に座ったものの、何となく罪悪感が込み上げてくる。
何となく、まりが後をつけてきているような錯覚を覚えてしまっていたからだ。あずさも同じことを思ったのか、頻りに窓へ目を向ける。
ソーダー水を一口飲んだあずさが、フッと肩で息をする。
「バカみたい。何を気にしてんだか。私と先輩はそういう仲じゃないっていうの。あの子。前に話していた友達で、先輩の練習やら試合やらつき合わされていたんです」
「そうなんだ」
「そうなんですよ。だけど先輩とバイト先が一緒だってこと、話さなかったんです」
ソーダー水をストローでかき回しながら言うあずさは、明日歩と目を合わせようとはしなかった。
「教えてあげれば良かったじゃん」
「ですよね。ああ女って面倒くさい。これは私のいじわるです。あなたが好きで好きで堪らない人と同じ職場で働いているのよっていう、優越感がきっとあったんだと思います」
「言うね」
「私、結構高飛車なんです」
やっと目を上げたあずさに、明日歩は目を細める。
初めての衝動がそこにはあった。
そんな明日歩を見てあずさが首を傾げる。
ヤバイと思った明日歩は、あずさを直視できずに俯く。
「先輩?」
心配そうに顔を覗き込んで来るあずさに、これ以上みっともない姿を見せたくない明日歩である。
自分でもくだらないプライドだと思う。がしかし、好きになった女の子の前、格好つけないのは男の性である。
「先輩ったら、どうしたんです?」
気持ちを切り替えて顔を上げる明日歩だった。
二階席、駅から出て来る人を一望した明日歩は、もう一度あずさに、大丈夫と尋ねる。
「大丈夫ですよ。それより先輩、部活は?」
「辞めた」
あっさり明日歩に答えられ、あずさの大きな瞳をさらに大きして驚く。
「本当に辞めっちゃったんですか?」
改めて訊かれ、グッとくるものがあった。生活の一部だったものが、急になくなるのは変な感じがする。正直、今はその話題に触れられたくはないかもと、ぎこちない笑みを向ける明日歩に、あずさは容赦なく訊いてくる。
「まさかとは思ったけど、本当に辞めっちゃったんですか?」
「今日、退部届出してきた」
じっと見詰められて、耐えられなくなった明日歩は俯く。
「本当にそれで良かったんですか?」
良いとか悪いとかの問題ではない。仕方がないことなんだ。説明するのも、かったるく思えた明日歩は、言葉を探す。
「先輩?」
顔を覗き込むように聞いてくるあずさに、明日歩は辛うじて笑みを作ってみせる。
「まぁしゃーないでしょ」」
言いながら、自分に言い聞かせる明日歩だった。
そんな明日歩をにこりともせずに、あずさはじっと見詰める。
明日歩はその瞳をまっすぐ見るのが怖かった。
何もかもを視とおされてしまいそうで、しかし、あずさには分かって欲しいと、心のどこかで思っている自分が居た。
「先輩、無理しているでしょう?」
「無理なんかしてないよ。清々してるよ。これで何の気兼ねなくバイトにも行けるし、前から行きたいと思っていたライヴとか、遊びとかにも行けるしな。あれだったら今度の日曜、どっか遊びに行く?」
最後の方は明日歩の願望である。
言ってしまってから、ハッとあずさを見る。
言われた本人はまるで関心がないように、しばらくストローを弄んでからフッと明日歩を見てくる。
「先輩、嘘はダメですよ」
「嘘なんて」
「目が、悲しよって言ってます」
「そんなこと……」
言いかけた明日歩は目を瞠る。
真剣なまなざしで見つめるあずさの目から、涙が零れ落ちていた。
やっぱりあずさにはかなわないと、明日歩は観念する。
「正直ショックだったかな。走るの好きだったし、でもあそこまで言われちゃうとなぁ、やせ我慢もするしかないっしょ。意地とかプライドとかもあるし、それに、金、大事あるよ」
「お道化ないでください。先輩、せかっく頑張って来たのに、全部台無しになっちゃうんですよ。そんなの悔しいじゃないですか。意地とかプライドとかそんなもの、どうでも良いじゃないですか。先輩は自分を知らなすぎです。走っている先輩は本当にきれいで、キラキラしているんです。だからね、辞めたらだめです」
涙ながらのあずさの力説に、明日歩は圧倒させながら言い繋ぐ。
「好きでもどうしようもないことって、あるじゃん。オレ、バイト辞めるわけにはいかないし、仲間とかに迷惑かけるわけにもいかないしさ」
「それは違うと思います。迷惑だったらもうとっくに、ハブられているでしょ。先輩が今しようとしていることこそ、裏切りです」
きりっとした目で言われ、明日歩は息を飲む。
「でも、もう退部届出しちゃったしな」
「そんなの、御免なさいって謝って、撤回すればいいじゃないですか」
「簡単に言うね」
「簡単ですよ。幼稚園児だって出来ます。先輩は何歳ですか? それも意地とかプライドとかが邪魔するんですか? 私の知っている先輩は、もっと謙虚で優しくて、走るのが大好きで、まっすぐな目を持っている人です」
痛いところつかれて、明日歩はむっつりとなってしまう。バイト先で見るあずさとはまるで別人のように思えた。見つめられて、目が外せなくなる。知美とまた違う強さを感じるあずさだった。
「できないよ」
絞り出すように言う明日歩に、あずさは言葉を切らなかった。
「私は反対です。絶対先輩は走るべきです。意地悪なんかに負けないでください。認めさせてやろって、気負うってください。それで先輩が苦しくなったら、私どんな手助けもします」
あずさの気持ちは嬉しかった。
明日歩とて、迷いはある。
あずさの気持ちに応えられる言葉が見つからなかった明日歩は、コーラを一気に吸い上げて、噎せる。
「大丈夫ですか? 炭酸をそんな勢いで飲むから。それにしても先輩って案外、男していますね」
涙目になっている明日歩に、あずさはそう言いながら、紙ナプキンを渡す。
「一応、男17年間してます」
「そういうことじゃなくってなんていうか、私ずっと先輩ってもっと軟弱な人かと思っていました。線も細いし、いつ見てもニコニコとしているし、この人、怒ったことがあるのかしらって思うくらい、優しいし。皆が王子様っていうの分るなって」
あずさはそこまで言って、ハッと自分の口を手で塞ぐ。
「深い意味じゃなくって、一般論ですよ。誤解しないでください」
無意識に、明日歩はあずさの頭を撫でる。
「ありがとう。そう言ってくれるの、結城さんだけだよ」
「そんなこと、ないですよ、先輩、案外鈍感だから、気づいてないだけですよきっと」
ばつが悪くなったあずさは、窓に視線を移す。
「ならいいけど」
しんみりとした気分になった明日歩も倣って、外をぼんやりと眺める。
疲れた、の一言に尽きる一日だった。
森崎に痛いところを突かれて、転がるように事態が展開していった。
何となく目が合い、明日歩が先に席を立つ。
帰り道、二人は言葉数少なく歩いていた。
坂を上りきり、一旦立ち止まったあずさが、明日歩に何か言いたげに見るが、何も言わず自転車を漕ぎだす。
何を思ったのか信号を渡り切ったあずさが、応援を始める。
まだ人通りがある時間だった。
恥ずかしいやら嬉しいやらで、明日歩は早く行けと言う意味合いで、手を払って見せる。
ピョンピョン跳ねながらしばらく手を振ったあずさが行ってしまい、明日歩は肩を窄める。
ほんのり募る温かいものの正体が、何かを知るべく克己にメールを打つ。
だいぶ遅れて返事が戻って来た。
おめでとう、それは恋です。キッスはお早めに。
克己らしいメールに、明日歩は頬を緩ます。
恋か……。やっぱそうか。
そう思っただけで、明日歩は、耳まで赤くなる。
思わず叫びたくなった明日歩は衝動を抑えるため、布団を頭から被る。
悔しいが、歩が言ったとおりだと思う明日歩だった。
第四章 夏の微熱
翌日の学校は、さらに騒ぎが大きくなっていた。
明日歩が部活を辞めた理由が、なぜかすり替えられてしまっていた。
群がる人だかりの向こう側で、知美が怖い顔をしているのが見えた明日歩はゾッとなる。
あながち間違った情報ではないが、それが分を辞めた理由ではないことは明白にしなければならない。
そう思いつつも、どこから手を付けていいものやら、お手上げ状態の明日歩だった。
話が話を呼んで、収拾がつかないのだ。
「おいお前、西沢という妻がありながら何をしてくれちゃっているんだ?」
バンと机を哲平に叩かれ、明日歩は顔を顰める。
「妻って、お前が勝手に勘違いしているだけで」
「いや違うね。俺の目には少なからずそう映っていたね。考えて見なよ。口は悪いが、お前を見る目は違っているというか、あそこまで面倒見てくれる奴、他にはいねーぞ。親父さんがなくなった時だって、ずっとお前のそばに居てさ、良い奴だなって、マジ思ったんだぜ俺」
そう言われても……。
確かに知美は甲斐甲斐しくいろいろと面倒を見て来てくれた。だけどそれとこれとは別もんじゃん。心がないのに、フリをする方がかえって失礼だと、オレは思う。それに、うわさは本当なんだ。告白はまだしてないけど。
明日歩は腹の中で力説を解くが、哲平が超能力者ではない限り届くわけがなく、案の定である。
「西沢にはちゃんと、誤解を解いておけよ。オレ、いくらでも協力するぜ」
などと言われ、明日歩は苦笑するしかなかった。
哲平が言うことにも一理ある。
このまま逃げ続けるわけにはいかない、死活問題だってことは、明日歩にも重々判っていた。だけど顔を見ると、言い出せなくなってしまうのが、明日歩である。
放課後を待って、知美が明日歩を呼びに来る。
取りついたのは、哲平だった。
逃げ出せない状況である。
渋る明日歩の背中を哲平が押し、知美が腕を掴む。
吹奏楽部のプープーという、間が抜けた音がやたら耳につく中、知美は有無も言わさず、明日歩を校舎裏まで引っ張って来ていた。
手を放し振り向いた知美はきつい目つきで、明日歩を見る。
「私の言いたいこと、分っているんでしょ?」
蛇に睨まれたカエルの気持ちが、分かる気がする。
たじろぐ明日歩に、知美は追い打ちをかける。
「真意は? 私に嘘は通用しなわよ」
腕組みが出て来てしまった以上、白状しなければ殺されえしまうかもしれない。命の危機を感じながらも、この期に及んで明日歩はいつもの癖で、つい恍け態度を取ってしまう。
「えっと、言っている意味が……」
「あのね」
グイと胸ぐらを掴まれ、明日歩は降参のサインを出す。
「西沢さん、暴力は」
「何が西沢さんよ。あんた何を考えているの? 大会はもう間近だよ。辞めるって何? 全然意味が分かんないんですけど」
「だからそれはオレなりに考えて」
「考える? 本当に考えたの? ただ森崎先生に居たいとこ疲れて、意地、張っているだけじゃないの? あんた、本気で走ること諦められるの? あんなに好きだったじゃない。お父さんとも約束したんじゃないの? 守らなくっちゃ駄目じゃない」
「そんなこと、西沢さんには関係ないだろ」
毒吐く明日歩を、、知美は信じられないという顔で見つめる。
「何なのよその言い方? 人が心配してあげているのに、そんな言い方、ないでしょ」
明日歩は知美の手を振りどいたのはその段だった。
「あのさ、西沢さんの気持ちは凄く有難いけど、もう放っておいてくれないかな? 俺たち高校生になったわけだし」
「な、何よ。明日歩のくせに生意気」
「もうそういうの良いから。悪い。オレ、バイトあるから行くわ」
「待ってよ明日歩。話はまだ終わってない。逃げないでよ」
スカートをギュッと握った知美が叫ぶ。
ぎくりとした明日歩が振り返る。
強がっては見たものの、やはり横暴で無敵の女。この位置つけは明日歩に永遠不滅であって、足が竦んでしまっていた。
「どうなのよ」
俯き加減で低い声で訊く知美にたてつくことなどできっこない。
「どうって言われても、もう決めたことだし、陸上部には戻る気はない」
頑張って言い返した明日歩に、知美は納得がいかない顔で訊き返してきた。
「どうしてそんなに簡単に捨てられるの? おかしいじゃない。やっぱりあの噂が原因じゃないの?」
ぎろりとみられ、明日歩は縮こまる。
「噂って」
「もう恍けないで。明日歩、昨日女の子と歩いていたでしょ。私、見たんだから」
見られていた。
逃げ場を失った明日歩は、絶対絶命の危機に追いやられてしまっていた。
「ズバリ聞くけど、あの子と付き合ってたりするの?」
無下にすることは簡単だった。
克己に言わせれば、マジうざい、だけど、助けられていたのも事実。
覚悟を決めて口を開いたものの、やはり出て来てしまうのは言い訳じみた言葉だった。
「あの子は、バイト仲間で、偶然街で会ったから、たまにはお茶でもしようかという話になっただけ。全然部活辞めたことと何も関係ないから」
「本当に本当? 嘘だったら針千本飲ませるわよ」
「あのな」
「あんたはね、自覚が足らなすぎるのよ。いい、人より頭一つ背が高いっていうだけで、あんたは目立っちゃうの。顔だって」
一瞬言葉を詰まらせた知美は顔を赤らめる。
「悪くないんだから。女の子と二人っきりなんて噂になるの、当たり前じゃない」
最後の方は全く聞き取れない声で話す知美だった。
「いい、とにかく練習には来なさい。これは命令よ」
腰に手を当てる知美を見るたび、明日歩はつい思ってしまうのだ。
こいつと結婚する相手に、深く同情するわ。
「聞いてんの?分かったら返事くらいしなさいよ」
「だからオレは」
「私は辞めさせないんだから。明日歩が戻りにくいっていうなら、私、学校に掛け合ってもいいわよ。森崎先生を顧問から外してもらえるよう、頼んであげる」
明日歩は、もううんざりだった。
「何度も言うようだけど、本当にオレのことは構わないで。これはオレ自身の問題で、西沢さんには口を挟んで欲しくない」
いつになく強気で明日歩に出られ知美はたじろぐ。
「嫌だなそんなに怒らなくても、ほらさ、ずっとそばで私明日歩のがんばり、見て来たからさ、つい熱くなっちゃってさ。それにあの噂でしょ。恋愛とかが絡むと、何かと面倒だなって思ったりして。明日歩、悪くないよなと、思うしさ、森崎先生が何ぼのもんじゃいって、思っちゃいけないの? 私は明日歩を守りたいだけなの」
うわーヤバイモードは言っちゃっている。
スカートをぎゅっと握りしめて、必死の姿とか見せられた明日歩にとって、それは恐怖であって、逃げ出したい気持ちを駆り立てられてしまうものだった。
「ごめん西沢さん。本当にオレ、もう行かなくっちゃ」
ここは逃げるに限る。
踵を返す明日歩に、知美は言い繋ぐ。
「明日歩は知っているの? 森崎先生、今ヤバい感じになっちゃっているんだよ。私が動かなくても、森崎先生がこの学校を去るのは時間の問題だと思う」
「それってどういうこと?」
「あんたのファンがどれほどいるか知っている? その子たちがだまっていると思う? 今日だって、二クラスでボイコット騒ぎがあったらしいよ。部員のみんなも、顧問て認めないって言い出しているし、それにね、職員室でもそれに似た意見が出ているらしいよ。あんたはそれでいいの? 走るの辞めて、先生を辞めさせて、そんなの明日歩らしくないよ」
明日歩は返す言葉がなかった。
突きつけられた現実に、ただただショックで、頭の中が真っ白になる。
知美の涙の説得に振り返ることなく、明日歩はそこから逃げ出すのだった。
☆
事態が動いたのは金曜日の放課後だった。
騒ぎもようやく落ち着き、明日歩はバイトへ行くまでのわずかの時間を図書館で過ごすようになっていた。
奈緒は滅多に明日歩のすることに口出しはしてこない。その分、歩との約束が、明日歩の心にずっしり圧し掛かって来る。
走るのを辞めてしまった以上、残された約束はただ一つ。学力を下げないである。大学へ進む気が全くない明日歩は、身を入れて勉強する気にもなれずにいた。
図書室にある分厚い本を探した明日歩は、うわの空でページを捲って行く。
あずさのことを考えていた。
自分の気持ちをどう伝えればいいのか、まったくわからじまいなのだ。克己に相談しても、告ればいいじゃんの一言で片づけられ、それが出来たら苦労しねぇっていうの、と毎度同じ結果が織りなされるという有様だった。
この浮いた時間、あずさと過ごせたらどんなにいいだろう。
外を眺めながら、ぼんやりそんなことを考えていた明日歩は、人の気配に気が付き、ゆっくり視線を戻し、目を大きくする。
疲れた顔をした森崎だった。
「話がある。ちょっと付き合ってもらえないか」
何の話だろうと、明日歩は眉を顰め森崎の後に続いた。
それにしてもと思う。
森崎は明日歩のクラスは担当していない。部活を辞めてしまったいまでは、一週間のうち、会うのは一、二度で、見かける程度のものだった。
だいぶ白髪が増え、もう少し貫録があったように思える背中が、廊下の隅までたどり着くと止まる。
「お前は一体、何もんだ」
しゃがれた声が余計しゃがれてた声で、唐突に訊かれ、明日歩はきょとんとなってしまう。
振り返った目は真剣そのもので、だからよけい明日歩は言われている意味が分からなくなってしまう。
「あの先生、何を仰りたいのか」
あからさまに息を吐き出した森崎が、右頬を視きりに撫でる。
「俺としては、お前のような才能があるやつが思う通りに練習もできずにいることが、勿体ないように思えて仕方がなかった。なまぬるい気持ちでは、トップは目指せない。言葉が足りなかったと言われればそうかもしれない。中田、お前がしようとしていることは素晴らしい。でもそれはお前だけに通用することで、他のものからしては、どうなんだろう? 必死に努力してもがき苦しんでいる奴らの思いは報われるのだろうか。俺はおまえひとりを守ることより、部員全体を守りたいと考えた。この考えは、何があっても変える気はない。だがだ。だが時と場合によってはその信念を曲げなくてはならなくてはならない時もある。頑固を通せば角が立つのも知っている。俺はそうして48年間を生きて来た。教師になって20年以上になる。こんな思いをしたのは初めてだ。全力でみんながお前を守りたがる。なぜだ? 中田、しつっこいようだがお前は何者なんだ?」
苦しそうに言う森崎の額に、くっきりと刻まれた皺は、以前にはなかったような気がする。重たい空気が流れ、明日歩の中に罪悪感がチラつき始めていた。
「すいません。オレは何者でもありません。普通の生徒です。まさかこんなに先生に迷惑をかけるとは、思ってもいませんでした。オレはただ、母親だけに負担を掛けたくない一心だけだったんです。オレがバイトをすることは、母親も反対しました。先生が言うように、家計は私に任せろと。でも、父親が亡くなって、オレがこの人を護らなければなんて心に誓ってって……、自分のことは自分で何とかしようって。でもそれが迷惑になると言われれば引き下がるしかないのかなって、思ったりして」
支離滅裂になる明日歩に、森崎は力なく笑ってみせる。
「もうそのことはいいんだ。この一週間、お前の頑張りは、嫌っていうほど聞かされたよ。お前の思うように、やっていいから、この通りだ戻って来てくれ」
森崎は疲れ切ってしまっていた。
森崎は人に注意をすることはあっても、されることはない教師生活を送って来ていた。怖いとさえ言われた時期もあった。生徒のみならず、同僚にまで苦言を呈され、それでも信念は曲げたくはないと思っていたのだが、こうして生徒に頭を下げなければならない自分が、情けなく思う。万感の思いが込み上げて来る。なにくそと思うが、森崎とて守らなければならないものがある。多少の痛手を受けても、ここは曲げるべきと判断したのだ。
深々と頭を下げる森崎に、明日歩は戸惑う。
そんなつもりなどさらさらなかった明日歩である。
バイトを辞めるか部活を辞めるかの二択。明日歩は部活を辞める方を選んだだけ。森崎の言葉が影響したのは確かだが、それほど大袈裟なことではなかった。それはとっくに解決したものと思っていた明日歩だった。
数秒間を置いた明日歩。
知美や哲平に真意を確かめるには、少々気まずい明日歩である。しかし、自分が知らないところで、何かが起こっているのは確かだった。頭がクラクラしてきて、明日歩は吐きたくなってきた。
「少し、考える時間をください」
「分かった」
顔を少しだけ上げて答えた森崎は、踵を返す。
戻って行く後ろ姿を見ながら、明日歩は身につまされてしまっていた。
何が母親を守りたいだよ、と一人ごちる明日歩だった。
そして、 バイトの帰り道、坂の途中で明日歩は立ち止まり、あずさも併せて、足を止める。
盛大なため息を吐く明日歩に、あずさは何も言わずにいた。
「今日、顧問に戻って来いって言われたんだ」
ぽつりと言う明日歩の顔を、あずさは黙ったまま見つ返す。
「オレはどうしたら良いと思う?」
一人では答えが出せずにいた。
戻らなければ森崎の立場はどうなってしまうんだろうと思う半面、自分の出した答えを曲げるのも癪に障る明日歩である。こんなことを言ったらきりがない。それは十分すぎるほど分かっているのだけど……。ギュッと胸のあたりが締め付けられ、明日歩は笑みを作る。
「先輩はまじめすぎると思う。もっと自分をさらけ出してもいいと、私は思うなぁ。だって、誰も間違っていないしどれも正解じゃないから。私もよく分からないけど、それでいいんだと思う。だって私たちはまだまだ子供で、分らないことだらけの未熟もんですよ先輩。今から悟りきってどうするんですか。自分の気持ちに正直にですよ。走りたいなら、帰れる場所があるのなら、私は戻ればいいと思う。それに対してきっと、誰も怒らないし、誰も傷つかないと思うけどな。私、単純すぎますか?」
あずさん言葉は的を射ていた。
あずさの真剣なまなざしにやられ、明日歩は目の置き場に困る。
カッコ悪っ。
ツーンと来るものを感じながら、明日歩は空を見上げる。
何となく二人はまた歩き出し、言った無しを停めたあずさだったが、そのまま横断歩道を渡り、向こう側から明日歩の名前を呼び、大手を振る。
「フレーフレー先輩。頑張れ頑張れ先輩」
あのバカ。
こんな公共の場で、決して大声を張り上げられるようなタイプの子じゃないことは、一緒に働いていて、よく分かる。無理をしてくれているのが伝わってきて、明日歩は、それが嬉しかった。
ぺこりと頭を下げたあずさが、性懲りもなく胸の前でポーズをとってみせる。
明日歩は照れ隠しに、手で追い払ったものの、帰って行くあずさから目を話すことが出来なかった。
一大決心したことをそう容易く覆してもいいのかオレ?
揺るがない決意だったはずなのに、部屋に戻った明日歩は悶々と悩む。
今更どの面さげて戻るっていうんだよ。
投げやりになった明日歩はベッドに寝っ転がり、天井を眺めているうち、明日歩はフッと歩の得意げな顔が思い浮かぶ。
「オレの宝物が入っているから、絶対に盗み見るなよ」
あの日、年甲斐もなくはしゃぎ声で言う歩に、明日歩は眉を顰め、内心バカにしていた。
宝でもないだろう、いいおっさんが……。
「はいはい。頼まれても絶対に見ません」
そういう明日歩を見て、歩は少年の目で笑って見せた。
しかし、その約束はすぐに破られた。
奈緒を励ますために開いた箱の中身を見て、明日歩は正直驚いていた。
そこには明日歩の思い出の品々がしまわれていたからだ。
飛び起きた明日歩は押入れから箱を引っ張り出し、ごそごそと中をあさる。
あった。
なかなか幼稚園になじめずにいる明日歩のため、カバンにぶら下げてくれた父と母人形。ほぼテルテル坊主にしか見えないその人形をギュッと握りしめる。
「どんなに立派な武器を手にしていても、結城がなければただのがらくたに過ぎない。明日歩には頑張ってその勇気を見に付けて欲しい。大丈夫だ、俺らはいつだってそばに居る」
幼かった明日歩に、魔法を掛けるのには充分だった。
そして、あずさの言葉が重なる。
こんなの許されるはずがない。しかしと明日歩は思う。
……父さんは能天気でいい。悩み事なんてなかったんだろうな。
大会まであと10日。間に合うかな。
教室の前、森崎が通りかかるのを見計らって、明日歩が呼び止める。
周りにいた生徒が、ざわめく。
森崎が、ギョッとした顔をして立ち止る。
「先生オレ、やっぱり陸上、したいです。走りたいんです。お願いします。陸上部に戻らせてください」
「……仕方がないな。今日から出て来られるのか」
「はい」
明日歩が満面の笑みで答えると、一斉に拍手が巻き起こる。
「明日歩、どういうこと?」
騒ぎを聞きつけてやって来た知美に聞かれ、明日歩は苦笑いを浮かべる。
自分が撒いた種が、こんな事態を引き起こしてしまうなんて思いもしなかった。その思いを正直に、明日歩は奈緒に話した。
こんなこと、話すべきではないと思ったが、話さずにはいられなかった。自分の浅はかな考えで、多くの人に迷惑をかけてしまったのは事実だ。ましてや正論を唱えてくれた先生を追いつめてしまった。
「間違いは誰にでもあるもの。その間違いにどう対処するかが、大切だと思う。今、明日歩が出来る精一杯をしてごらんなさい」
……自分に出来ること。
奈緒にそう言われ、何をしていいか分からなかったが、ふとその時思い出した言葉があった。
「人生何が起きるか分からない。だから今を精いっぱい生きる。これっていい言葉だろ。勝てると思っていた相手に惨敗して、めちゃくちゃ悔しくって泣いていたオレ達に顧問が言った言葉だったんだけど、オレ、その通りだなってその時に思っちゃったんだよね。バッターボックスに立った奴がさ、あまりにへっぴり腰だからオレ達、油断しまくっちゃったんだよね。本当、今考えると失礼な話だよな。相手が本気でいる以上、こちらも本気で戦うのが礼儀なのにさ。お陰で負けなくてもいい勝負に負けちゃってさ。挙句の果てに、あんなのに打たれるなんてって、泣いている自分がいてさ。恥ずかしいのったらありゃしない。その時からオレは決めたんだ。自分に正直に生きる。人を見下さないって」
真冬の海で、歩が話してくれたものだった。
一晩寝ないで考え、明日歩はこの方法しか思いつかなかった。
みんなの前で恥をかく。自分の非を認め、自分に正直になる。このやり方が正しいのかはわからない。それでも……。
頭を掻きた明日歩が、だって、走りたかったから。と答える。
「まったく、人騒がせな人ね」
「すいません」
一斉に笑いが沸き起こる。
廊下を曲がりきった森崎は、ふと足を止め振り返る。
突然のパフォーマンスに、どんな顔をしていいものやらと焦ってしまったが、あいつのこういうのに魅了されるんだな。変に納得させられてしまう。
自然と口元がほころぶ。
「完敗だ」
森崎は呟いた。
スタートラインに立つ。
心地の良い緊張感が全身に広がって行く。ゴール前、知美がストップウォッチでタイムを計る。哲平が綺麗な弧を描いてバーを越えて行く。
この数日間の出来事が、まるで嘘だったような気がする。早くあずさに会いたい。会って、このことを報告したい。
あずさと一緒にいられる週末が待ち遠しかった。メールや電話なんかじゃなく、直接会って話したい。
給料日後の週末の店内は、うんざりするほど客で賑わっている。時計ばかり気になって、仕事に身が入らない。
ようやく店を出て、黙々と坂道を上って行く。そんな様子を気にしながら、あずさも黙ったまま横に並んで歩いた。
坂道を上りきって、いつもの交差点が見えると、明日歩は歩く速度を落とす。
「少し、話していかない?」
明日歩の言葉に、あずさは嬉しそうに頷く。
二人で、自転車をガードレールに立て掛ける。
「オレ、陸上部に戻った」
「え? 本当。良かった」
一瞬驚いた表情を見せたあずさの瞳から、ポロポロと涙が落ち始める。
「ごめんなさい。私、ああ何で涙、出ちゃうんだろう」
慌ててハンカチを探す明日歩を見て、あずさは鼻をすすりながら笑顔を作る。
「オレは何回、結城さんを泣かせれば気が済むんだ?」
やっとハンカチを見つけた明日歩が、差し出しながら言うと、あずさが首を大きく振る。
「私こそごめんなさい。でも私、嬉しくって」
ドクンと、明日歩の心臓が高鳴る。
「オレと付き合って下さい」
自分の言った言葉が、耳の中でワーンと広がって行く。
泣き笑いするあずさが頷く。
体中が熱くなり、心臓が早鐘のように鳴っている。
ヤッターと右手を振り上げて喜ぶ明日歩の傍らで、アジサイが風に揺れていた。
意気揚々と迎えた大会。
当然である結果が待っていた。
自分の甘さを思い知らされた明日歩は、その日、アルバイトを辞めた。
その後、あずさと待ち合わせ話をしている自分が居るのを、至極不思議なな気分だった。
あれほど大騒ぎをしたあれは何だったんだろう、と思う。
あずさが柔らかい笑みで見つめ返してくる。
心が軽くなって行くのが分かった。
それからというもの、明日歩は走ることに没頭し、そこそこの成績を収めることが出来た。
もう悔いを残すことはない、と言い切る明日歩だった。
「中田は進路は決まったのか?」
シューズを履き替えている明日歩に、森崎が訊いた。
「たぶん就職」
「もう走るのは、続けないのか?」
明日歩が顔を上げる。
「勿体ないじゃないか。強化選手に選ばれて練習にも参加してきたんだ。これから磨きをかければ、もっといいタイムが出せるんじゃないか?」
「これ以上、親に無理させられないですよ。最近、体の調子が悪そうだし、金稼がないと」
「どこかの会社の、クラブチームに入るっていう手もあるぞ」
明日歩は噴出す。
「もう中途半端はこりごりだ」
「それもそうだな。俺も人に恨まれるのは勘弁だ」
「帰ります」
台風が接近し始めていた。電車が止まる前に練習を早めに切り上げになった。
校門を出ると、真っ赤なジャガーが止められていて、人目を引いている。その横で高そうなスーツを着た女性がきょろきょろと、誰かを探しているようだった。
「明日歩」
誰? 哲平が尋ねる。明日歩はきょとんとして目を凝らす。
由紀子さん?
「やっぱり由紀子さんだ。どうしたんですか?」
サングラスを外した由紀子が、嬉しそうに手を振りながら、近寄ってくる。
「ちょっと、あなたに頼みたいことがあって」
「悪い。親戚のおばさんなんだ」
「はじめまして。親戚のお姉さんの島根由紀子です」
「島根って」
「詳しい話は車でするから、乗って」
由紀子はスタイリストをしている。業界では名が知れているらしい。
急発進させた車は、あっという間に高速を走ったいた。
家とは反対方向に進む車の中、明日歩は躰を強張らせる。
「島根がね大ピンチなの。ギャラは弾むからカメラの前に立って、ちょっとだけポーズをとってくれればいいから」
「いいからって、無理です。降ろしてください」
「それこそ無理よ。こんな所で降りたら、あなた死ぬわよ」
姉の薫子は饒舌で、会うと捲くし立てられて、たじたじにさせられてしまうが、妹の由紀子は物静かのはずだ。虫も殺せないんじゃないかという雰囲気を持っていたのに、この強引さは薫子以上だ。それにこの運転。速度オーバーの警告音が鳴り続けている。
大粒の雨がフロントガラスを叩きつけはじめ、ようやく速度を少し落とした由紀子が苦々しい表情を浮かべる。
台風上陸のニュースがラジオから流れ、急がなくっちゃと由紀子は呟く。
横殴りの雨。ワイパーが忙しく動く。周りの景色が分からない。道路わきに車を寄せて、落ち着くのを待つのが無難な選択なはず。現にそういう車を何台も見かけた。がしかし、由紀子はそうはしなかった。速度こそ落とし、慎重な運転に変わったが、止めるわけにはいかないのよと、自分に言い聞かせるように車を走らせ続け、気が付くと、車をどこかの駐車場に滑り込ませていた。
車のライトに向って、男性が手を振るのが見えた。
「待っていたよ。明日歩君、よく来てくれたね」
うん?
明日歩はその男性に見覚えがある。うろ覚えで、思い出せそうで思い出せない。
「みんなは」
「首を長くしてお待ちしてます」
足早に歩く二人の後を、明日歩も追いかけるように続く。
――島根修二。
歩の葬儀の日に、くちゃくちゃのお金を謝りながらもってきた人だ。すっかり見違えていて、分からなかった。
エレベーターに急かされ乗せられると、最上階のボタンを押した島根に由紀子が間に合うかしらと尋ねる。
「ぎり、セーフ」
にっこりと答える島根が、チラッと明日歩を見る。
「あのー」
ただならぬ様子に怖気づいた明日歩が口を開いた途端、エレベーターが開き、瞬く間に見知らぬ大人たちに囲まれてしまっていた。
あれよあれよと部屋に案内され、半ば強引に押されてはいった部屋を見回し、愕然とする。
物々しい雰囲気が漂い、強面の男性が入って来た明日歩を見るなり怒鳴りつける。
「やっと気やがったか。さっさとしろよ。まったく何様が来たかと思ったら、ガキかよ」
「すいません浅井さん。もう少しだけお時間下さい」
「チッ。へたな仕事しやがったら、二度とお宅の仕事、引き受けないからな」
「またそんな意地悪言って」
愛想笑いをする由紀子に背中を押され、明日歩は奥の部屋へ連れて行かれる。
それからが大変だった。
鏡の前に座らされたかと思うと、前髪を上げられ、目を瞑れやら口を閉じ路やら、べたべたと顔に何かを塗られ、それが終わったかと思うと二人がかりで服を着替えさせられた。
「あの、由紀子さん」
「黙っていて」
その顔があまりにも薫子に似ていて、ゾッとなる。
注射を嫌がる明日歩の腕を、無残に押さえつける時に見せるあの笑みだ。どんな抵抗もかなわないと諭された明日歩は、がっくりと肩を落とす。
やるしかなかった。
初めてだらけで、明日歩は半ばやけ気味にポーズをとっていた。
ないが気にくわないのか、やたらに細かい注文を付けてくるカメラマンを、明日歩は恨めしく思う。
すっかりやる気をなくしている明日歩に、由紀子がニコニコと手を振ってくる。
何なんだあの笑みは。
「お待たせ。ごめんね遅くなっちゃって」
にこやかに入って来た女性を見て、明日歩は唖然となる。
きれい、としか例えようがなかった。
真っ赤なドレスを身にまとった少女が、当たり前のように明日歩の隣に立つ。
「待っちゃったよ。瑠夏ちゃん今日もかわいいね」
さっきまで不機嫌丸出しだったカメラマンの目じりが下がり、悔しいが、明日歩はホッとさせられる。
これで解放されると思ったのも束の間、ツーショット写真に代わり、さらに注文が付けられ、明日歩はげんなりする。
ポスター一枚とるのに、どんだけだよ。モデルとの絡みなんていらないと思うんだけど……。
明日歩は半べそ状態だった。
ダブルベッドにバラの花びらを散らすって、何の撮影だよ。
「よし、そのままキスして」
カメラマンの発言に、明日歩がそれはと言返す。
「すいません。メイク直します」
「顔を近づければいいから、それっぽくして」
懇願するように言う由紀子に、渋々頷いてはものの、ぎこちない動きになってしまう明日歩を見て、瑠夏がクスッと笑う。
それだけでも心外なのに、思いがけない出来事に、明日歩は口をパクパクさせる。
有ろうことか、かわいいと言って頬にキスをされてしまったのだ。
まだ、あずさともしたことがないのにだ。
みるみる顔を赤くする明日歩に、瑠夏は面白がるように顔を近づけて来る。
「良いねその表情。そのまま、どんどん近づいて行っちゃおう」
グイと腕を引っ張られ、頬をくっつけられたり抱き上げさせられたりと、何が何だかわからないまま、撮影が終わった。
モデルの子が先に帰って行き、明日歩はソファーでぐったりともたれかかったまま、放心状態になる。
「悪かったな」
島根が横に座り、缶コーヒーを差し出す。
「疲れたー」
由紀子も挟むように、明日歩の隣に座る。
「あの……これって……」
「頼んでいたモデルがね、急病で来れなくなっちゃって。売れてる子だから、ぎりぎりまで粘って待ったのに、ドタキャンされて焦ったわよ」
「そんなのに、オレが出ても良かったんですか?」
「それなら思いっきり、新人ぶつけてやれって、由紀子が言い出してね」
「あら、あなただって怒ってたじゃない? 思い知らせてやるんだって。上玉探せって。ぎゃふんと言わせてやるぞって、言ったでしょ」
クスクス笑う由紀子に、そうだったかなー、と島根が嬉しそうに歯を見せる。
明日歩は二人の会話についていけずに、目を瞬かせる。
「ここはね、立ち上げたばかりのプロダクションで、何かと足元を見られちゃうんだ」
というより、二人の関係が分からない。
やたら親しげに話す二人だった。
「明日歩、本当にありがとう」
明日歩に抱き付いてきたかと思うと、頭をくしゃくしゃにしながら撫でてくる由紀子だった。
「これで何とかしのげるわ」
その言葉に、明日歩は疑問を抱く。
本職でもない素人で、本当に役に立ったのか、怪しいものだった。
明日歩は、一気に疲労が眠気になって襲ってくる。
そんな明日歩を見て、二人は声を揃える。
「やっぱ、歩にそっくり」
「俯いた感じが似ているよな」
「寝顔なんか、間違えちゃうわよ」
ブルブルと頭を振って、眠気を飛ばす明日歩を見て、二人はゲラゲラと笑い出す。
弄ばれながらも目敏く明日歩は、二人の指に輝くものを見つけていた。
視線に気が付いた由紀子が、見せびらかすようにしてにっと笑う。
「いいでしょう」
眠気と戦いながら、明日歩は頷いて見せる。
半分は夢の世界へと足を突っ込んでいる状態だった。
「こんな恋のはじまりがあるんだから、僕たちも始めてみませんか?」
突然変なことを言い出され、明日歩は目を擦りながら、島根を見る。
「この人ね、有ろう事か歩の葬儀の日に、こんなこと言い出すのよ」
島根が頭を掻く。
嬉しそうに笑って話す二人に悪いと思いつつ、明日歩は睡魔に勝てずにいた。
「前から気になっていたんだけど、会うチャンスがなかなかなくってね。歩さんに何度かお願いはしてあったんだけどな」
「歩はそういうのは疎いから、相談する相手を間違っていたのよ。もっとさ、野村さんとか木綿子さんに頼めば良かったのよ。ま、それでも結局、歩が結び付けてくれたようなものだけどね」
眠気が少し治まり、明日歩は葬儀の時の島根を思い出す。
男の人が号泣するのを初めて見た明日歩である。それが。島根だった。まさかその人の再会がこんな形になるとは思いもしなかった明日歩である。
明日歩の心を読み取った島根が、頭を掻きながら言う。
「出会いなんてもんはそんなもんです。仕方が二ですよね。それが運命だと僕は思う」 「お疲れ。じゃあまた」
力説する島根に、明日歩は同感だった。
バイトをしなければあずさに出会えなかっただろうし、辞めると騒がなければ、あんなに親しくなれずにいたと思う。そう考えると、運命という言葉はあながち大げさではないような気がするのだ。
バカにされると思っていたのか、頷く明日歩を見て、島根は嬉しそうに肩を組んで来る。
「君もいるんだね。青春だね。嬉しいなぁ。やっぱり泊まって行きなよ。一晩語り明かそうじゃないか」
そう言われ、携帯を確かめた明日歩は、マジかと頭を抱える。
とっくに日付が変わってしまっていた。寝る時間がないことを知り、明日歩はがっくり肩を落とす。
機材を片し終わったカメラマンが声を掛けてきたのはそのタイミングだった。
「お疲れ。じゃあ、また」
またはないと思いつつ、明日歩は苦笑で頭を下げる。
「さ、バカなことを言ってないで、私たちも帰りましょうか。明日歩、明日も学校でしょ」
「もちろん、今日も学校あります」
「休んじゃえばいいのに」
「そういうわけにはいきません」
「そうかい。それは残念」
残念って……。
立ち上がった明日歩に島根が握手を求める。
「しかし、本当に君は歩さんに似ているな」
「そうっすか」
「うん、だから言わせて欲しい。僕、やりましたよ。由紀子と結婚できました。どんなもんだい」
「え?」
「初恋だったそうだ」
島根が耳打ちをすると、明日歩は由紀子を見る。
「また、頼むな。今度は本業の映画に出て欲しいな」
疲れ切った笑みで返す明日歩を、島根は抱き寄せ、念を押す。
「頼んだぞ」
頼まれても困る話に、明日歩は苦笑いでその場を離れた。
外に出ると、台風は温帯低気圧に変わり、風だけが名残惜しそうに吹き荒れていた。
ゆっくりと駐車場から車を出した由紀子が、明日歩をチラッと見る。
「明日歩は大学はどこを受けるの?」
後ろを振り返り、有名なホテルだったことを確認した明日歩が向き直り、一呼吸置く。
「受けない」
「え? そうなの。奈緒さんの話しだと、国立も狙えそうだけど、安全圏は慶応か早稲田みたいって言ってたけど」
「ああそれ。たぶん実力テストの結果を見たんだ。オレ、適当に書いただけなんだけどなぁ」
シートに深く座り直した明日歩は、自分が知らないところで勝手に話を貰ているのが気にくわなず、むくれる。
「嬉しそうに話してたわよ」
明日歩はプイと横を向いてしまう。
これだからと、明日歩は思う。
うんざり顔をする明日歩を見て、由紀子はクスクスと笑い始める。
「何がおかしいんです?」
「歩も、時々そんな顔をしたなって思い出しちゃった」
「親父が?」
「納得いかないとね。いつもそんな顔をしていたっけ」
自分ではあんまり似ていないと思う明日歩は、そう言われるのが嫌だった。
更にむくれる明日歩を見て、由紀子はかわいいと喜ぶ。
太刀打ちが出来ないと悟った明日歩は。目を閉じる。
もう眠気はとっくに飛んでしまっていた。
「もう寝てないでしょ。逃げないでちゃんと答えなさい」
腿を叩かれた明日歩は渋々目を開け、由紀子を見る。
「あんたね、奈緒さんの気持ちも考えんさいよ。大学行かないでどうする気なのよ」
「別に大学行くだけが偉いわけじゃないでしょ。就職して、さっさと親から独立したいわけですよ」
「独立って、あんたあの家、出るつもりなの?」
「そうじゃなくって、経済的にって意味です」
「そうなんだ。それだけの覚悟があるなら、安心ね。それで就職先は見つかりそうなの?」
「給料は大したことはないけど、何社か候補はある」
「そっか。安いんだ。だったらさ、うちにおいでよ。今日のお礼もあるし、そうしなよ。ギャラも弾むからさ」
ギャラって……。
業界人だから、給料のことをついそう言ってしまうのかと、明日歩は受け流すが、しかしそうではなかった。
由紀子が目を輝かせ、言い繋ぐのを聞いた明日歩は全力でお断りする。
「あなたなら、いいモデルになれそうだし」
「無理無理無理。絶対に無理」
「そこまで言わなくても」
「無理なものは無理です」
「ああそう言う所も、歩なのよね」
「親父はもういいっす」
由紀子は眩しそうに目を細める。
腕を組み、外に目を向ける横顔は、歩そのものだった。
本気で考えてみてと言う由紀子に、苦笑で手を振り別れた明日歩は、茶の間から漏れている明かりを見つけ、まだ、起きていたのかと呟く。
「あのね明日歩、甘えてあげるのも親孝行になるって知っている? 奈緒さん、あなたを大学まで行かせるつもりで、歩が残したお金を一銭も手を付けていないらしいわよ」
由紀子が、別れ間際に言った言葉だ。
「母さん起きろよ。こんな所で寝ると、風邪を引くぞ」
転寝をしている奈緒の躰を揺する。
「あ、寝ちゃったんだ。お帰り。もうこんな時間なの」
寝ぼけ眼で時計を見た奈緒が、大あくびをしながら、明日歩も早くお風呂に入って寝なさいよと言って、茶の間を出て行く。
やるせない思いが胸を締め付けて来る。
仏壇前、明日歩は歩の写真を黙って見つめる。
だんだん腹が立って来た。歩の笑顔が憎らしき思えて来る。
もし、父さんが生きていたらオレはどうなっていた?
陸上に、もっとのめり込めていたかもしれない。あずさとも、もっといろんな所に遊びに行けてたかもしれない。
言ってやりたいことは山ほどあった。サプライズをするって言っていたくせに、死んじまったのだって、まだ許していない。あんなコスチュームを着る羽目になったのだって。ふつふつと不満が込み上げて来る。どうにもならないって分かっていても、もう一度、戻って来いよ。と言いたくなる。
クソッ。
明日歩は頭を掻きむしった。
「中田、大学受けるんだって?」
「みたいね」
窓の外、明日歩が久我山と楽しげに歩いて行くのをぼんやり眺めている知美に、奈波が話しかける。
「告った?」
え? 知美が目を見開き奈波を見る。
「中田、人気あんのよね。卒業が近いし、狙っている子、結構いるよ」
向きを変えて寄りかかるように立った奈波が、クラスの女子を何人か指さし、知美にやばいなと笑いながら言う。
「バカじゃない」
自分の席に着く知美の前の席を陣取った奈波がいつになく真剣なまなざしを向けていた。
「告白すればいいのに」
「するわけないでしょ」
教科書に目を落としたまま答える知美に、何でって、教科書を奪った奈波が首を傾げる。
「何でって、何で?」
「好きなんでしょ?」
奈波に平然と言われ、すっかり動揺しきった知美の目が泳ぐ。
「分かりやすいよね、知美って。分からないのは、世界で一人だけだよねきっと」
奈波は窓の方を見て、ニヤリと笑う。
「中田はちゃんと言ってあげないと、その恋は一生、成就されないよ」
返す言葉がない知美は、取り返した教科書を黙々と読んでいるふりをする。
今までは何かに格好つけて、そばにいることが出来たが、さすがに大学までは追いかけては行けない。その情報すら入って来ない。知美とて、焦りを感じていなかったわけじゃない。そのことを突かれると、チクチクと胸が痛む。
あと三か月で会えなくなってしまう。会ったとしても今までのように話せるのだろうかと思うと、自然と涙が零れ落ちる。
知美は推薦で決まっていた大学を蹴って、最後の悪あがきで、明日歩が選びそうな学校を山掛けして受けるつもりでいた。
帰り道、参考書を選びながら、偶然明日歩に会えないかと期待してしまう自分がいる。
哲平から聞いてもらう手も考えたが、理由を聞かれると面倒だから止めた。前みたいに冗談で訊ければいいのだけれど、高校というのは、どうしてこんな区別をするのかしらと、恨めしく思うことが何回もある。
文系と理数系では、教室も違えば、階まで違ってしまう。三年になり、酷いことに棟まで違うようになった。
知美はつい唇を噛んでしまう。
さらりと何でもこなしてしまう明日歩が、憎たらしかった。
進学希望ではないくせに、特進クラスって何ですか? とぼやく知美に、明日歩は一度だけその話をしてくれたことがあった。
父親との約束で、手を抜くことが出来ない、という話だが、それににしてもそこまで頑張る必要ないじゃない。私が守ってあげるって言っているのに、バカ明日歩。
ひとしきり愚痴った知美は、がっくりとうなだれる。
何となく、ずっと分かっていた。けど認めたくなくて……。
知美はぶんぶんと首を振る。
奈波の言葉が痛かった。
その日の放課後、知美は気晴らしをするため、駅ビルに立ち寄る。
本屋で参考書を物色しているうち、知美はだんだん腹が立ってきた。
大体、何でいつもギリギリにあいつは進路を変えるんだ? 高校を受けないって言ってみたり、もう就職だって、言ってじゃない。
腹を立てても仕方がないのは分かっている。でも、もっと前に決めていてくれれば、こんなにやきもきしないで済んだのに。ママやパパを説得しなくっちゃじゃない。
どうにも気が収まらない知美はそのまま階を変え、聞き覚えのある声に、ふと足を止める。
思ったとおり、明日歩と克己がアクセサリー屋で、品定めをしているところだった。
こんな偶然、凄い。
「明日歩」
目を輝かせた知美に声を掛けられた明日歩は、ぎくりとなってしまっていた。
全くそれに気が付かない知美は、何のためらいもなく二人の元へ寄って行くと、当然のように仲間に加わって行く。
しかし、見れば女性ものばかり並ぶ棚である。
「誰かのプレゼント?」
「げっ、何でお前がこんなところに居るんだよ。ていうか混じってくんなよ」
克己が迷惑そうに言うと、良いじゃないよと言い返しながら、明日歩をチラッと見る。
相変わらず、我関せず。の姿勢を保ったまま、明日歩はアクセサリーを見比べていた。
「お母さんの探してるの?」
そうであって欲しい。願いながら、知美はネックレスを手に取りながら訊く。
一瞬躊躇した明日歩が、彼女のなんだけど、どれが良いのか分からなくってと答える。
知美の心臓が、バクバク言い出す。
「そうなんだ」
甲高い声を出す知美に、おめーは引っ込んでろ、と克己に言われるが、何でよーと言い返す。
引っ込みがつかず、これなんていいんじゃないと吟味し始める知美を見て、克己が露骨に嫌な顔をしてみせる。
「良いから、帰れよシッシ」
克己に手で払われ、やっと帰るタイミングを見つけて、その場を離れる知美だった。
二月の終わりの日、久しぶりだった。
グランドに陸上部部員が全員集まる。
去年、哲平が編み出した三年生追い出しコンパは、今年は久我山が引き継いだ。
「えっと、適当な先輩たちが考えてくれた適当競技会をしたいと思います」
「何だそれ」
哲平が突っ込む。
「黙って」
知美に睨まれ、哲平は肩を竦める。
今年も紅白戦だと言う久我山に、公平に振り分けろよと哲平がけちをつける。
「お前は黙っていられないのか」
森崎に突っ込まれ、みんながどっと笑う。
白が明日歩で、赤が哲平が率いる。残りはくじ引きで振り分けると告げた久我山が、顔を顰める。
「どうかしたの?」
知美が訊いた。
「1人足りない」
「え?」
「32人いなかったけ?」
哲平が人数を数え直す。
見物人の方に目をやり、分かったと言うと、後ろの方にいた奈波を引っ張り出してきた。
「こいつも一応、部員じゃなかったっけ?」
知美と明日歩は顔を見合す。
「ええ、私、走れない」
甘ったれた声で奈波が言うと、後輩の女子がざわつく。
「たしか、陸上部のマスコットギャルじゃなかったっけ?」
明日歩が知美に尋ねる。
「ごめん。忘れてた」
知美が首を竦める。
しかし、奈波が体育の授業を真面目に受けているのを見たことがない森崎に、走れんのかと訊かれた知美は、さぁと首をかしげる。
「何とかなるっしょ」
そう言う哲平を、恨めしそうに奈波が見る。
「そんな目をしないの」
「だって~」
「お遊びなんだから。あいつの気持ちを汲んでやんなよ」
「あんたが言うか。あんただってね~」
「奈波っ」
その先を言わせまいと、知美は慌てて奈波の腕を引っ張る。
「奈波は俺のチームにもらいな。俺がこいつを負ぶって走るから、明日歩は西沢を負ぶってやれ」
久我山を押し退け、積極的にチーム分けする哲平を見て、明日歩は思わず笑ってしまう。
「へえ~奈波をね。ふーん」
「うるせいや」
明日歩の突込みを、一言でねじ伏せた哲平が、さっさと始めようぜと久我山を急かす。
今年は哲平の発言で、おんぶ走りと最後の激走と、キャプテンは二回走ることになった。
「誰の主催だか分からない」
ぼやく久我山の首に哲平が腕を回す。
「人の恋路を邪魔をする者は報われないよ」
脅しを入れられやけくそに二つ返事をする久我山を見て、明日歩は最後まで傲慢だなと知美に話し掛ける。
「そうだね」
上の空の答えを返えさられ、えっと首を傾げる。
奈波の用意、ピーと言う間の抜けた笛の音を合図に、レースが始まった。
スタートから笑えた。
犬走りで走って行く森崎を、スキップで久我山が後追う。次は、二人三脚で走るのと後ろ向きに走って行く奴との対決だった。片足とびの奴がいると思えば、トレーに水を入れたコップを乗せて走る奴が追いかけて行く。
リレーの中盤、哲平に負ぶわれた奈波が100メートルを激走して行く。奈波が悲鳴を上げる。
「ちゃんとしがみついていろよ」
そう言いながら、明日歩は先に走る哲平を追いかける。
この順番も、哲平の差し金で決められていた。
「意外と重いな」
「失礼な」
怒りながら、知美の顔が緩む。
哲平チームにかなりのリードをとられて、バトンタッチをした明日歩が、そっと屈み知美を下す。
「大丈夫か?」
下された知美が、地面にへたり込む。
「もっと丁寧に扱いなさいよ」
「あ、ごめん」
知美は、プイと横を向いてしまう。
明日歩は、そんな知美を気にも留めずに、もうレースの応援を始めている。
知美は唇をかみしめ、地面を見つめていた。
リレーは、チキンレースになっていた。
抜きつ抜かれつの、いい勝負だ。
残すところキャプテン同士の200メートルだけになり、明日歩の目が真剣になる。
「明日歩、勝負だ」
そう言って、哲平が駆け出して行く。
「望むところだ」
明日歩が叫んだ。
遅れて、明日歩がバトンを受け取る。
哲平はトラックの半分まで行っていた。
明日歩がどんどん加速していく。集まっていた誰かが、早いと呟く。
ゴール直前、明日歩は哲平を交わし、チームに勝利を齎した。
知美の目から堪えられず涙があふれ出す。
暗くなった帰り道。
さっきまで一緒に歩いていた、奈波と哲平は、いつの間にか二人で姿を消していた。
二人きりで歩くのは初めてである。
幼稚園の頃からずっと一緒だったのに、つねにおややかつみが一緒だった。
知美は明日歩を意識しすぎて、何も喋れず、じっと自分の足元ばかり見つめてしまっていた。
そんな知美に気を留める様子を見せず、明日歩も黙ったままだった。
公園の前、知美がふと足を止める。
ん? と首を傾げる明日歩に、知美は笑顔を作る。
「少し寄って行かない」
一瞬間を置いた明日歩が頷く。
知美はまっすぐブランコに向かって歩く。
「何か久々。懐かしい。ブランコの意思ってこんなに低かったけ」
ブランコに座った知美が明日歩を見上げる。
困ったように笑う明日歩を見て、知美は俯く。
「あのブレスレット、彼女に渡したの?」
「まぁな」
「喜んだっしょ」
「オレ、ああいうの分んなかったから、あん時はありがとうな」
「礼なんかいいよ。それよりさ、一つ聞いてもいい? 明日歩の彼女って、前に一緒に歩いてた子?」
訊く知美の声が震えていた。
鎖を握る手が凍てつくのを、知美は必死で堪える。
明日歩は言葉を探す。
「ねぇどうなの?」
答えるべきかどうかを思い悩む明日歩だった。
なかなか答えない明日歩を見返る知美と目が合う。
ピーンと張りつめた空気が頬を指して行く。
いつかこんな日が来る。
はっきりさせなければと、お互いが思っていた。
明日歩は照れ笑いをしながら頭を掻く。
「いつ見られたんだろう?」
「奈波が見たって」
ブランコを飛び下りた知美はその勢いで、ベンチへと場所を変えていく。
ベンチに腰掛けた知美は、じっと地面を見つめる。
「バーガーショップで、楽しそうだったって」
「ああ、あん時か」
知美は、頷く明日歩を上目使いで見る。
「座れば」
そう言われ、明日歩は少し間隔を置いて座る。
知美がフーと大きく吐きだした息が、白くふわりと広がり消えて行く。
「あのさー、私のことを、明日歩はどう思っているの?」
どうって、明日歩は頭を掻いた。
「明日歩と初めて会ったのは、あの滑り台だった。覚えている?」
知美が言っている意味が分からず、明日歩が首を傾げる。
「覚えていないよね」
知美は俯いて呟く。
何も答えられない明日歩は、チラチラと時計を見てしまう。
「私じゃ、私じゃだめだったの?」
声を震わせて聞く知美に、明日歩は目を泳がす。
はっきりしない明日歩を見て、知美は寂しいそうに笑う。
「鈍感。ずっと見ていたんだよ。明日歩だけをずっと」
「え? 何で泣いてんの? え、ええーっ」
不意に見せられた知美の涙に、明日歩は焦る。
「ね、その子よりもずっとずっと前から、明日歩のことが好きだったんだよ。絶対、その子よりも、私の方が明日歩のことを知っている。でしょ? 私の方が」
「……ごめん」
「謝るな。私がみじめになるじゃないか」
「ごめん」
「あんたみたいなひ弱な奴、守れるのは、私くらいなんだから」
「ごめん。知美がオレのことを思ってくれている以上に、あずさのこと好きなんだ」
いつも逃げ腰で、はっきりしない明日歩の口を衝いて出た言葉は、知美が一番聞きたくなかったものだった。
袖でごしごしと涙を拭った知美が、明日歩の足を踏みつける。
「痛っ」
「バーカ。なに本気にしてんの? ……なんちゃってに決まっているじゃん。明日歩のくせに生意気。彼女作るなんて100億万年早いっていうの。騙されtれいるんじゃないわよ。もう嫌だなぁ、自分でもびっくり。涙出せるなんて。私、女優志願しようかな?」 「西沢さん?」
凛とした知美が、涙をぬぐいながら立ち上がる。
「あんまり幸せそうな顔をしたから、からかっただけよ。誰があんたみたいな人、好きになるものですか」
「そ、そうだよな。ああ、驚いた」
明日歩が胸を撫で下ろして、ほっとした顔をしてみせる。
知美は鼻を啜りあげる。
「ね、明日歩。お願いがあるの? 殴らせて」
「え?」
突然、明日歩の右頬が熱くなる。
「こんな美人が、14年間も傍にいたのに、気が付かなかった罰よ」
捨て台詞を残して、知美は公園から飛び出して行き、明日歩は肩を竦める。
うやむやにしてしまっていた罰があたんだろうと、明日歩は頬を摩りながら思う。
あずさへの好きという気持ちが膨らんで行くたび、知美がどんな思いをしていたのか初めて気が付いた明日歩だった。
付き合ってもいないのに、妙に捨てられた気分になってしまった明日歩である。
曲がり角、あきらめがつかず、知美がその場にうずくまって涙していたことを、知る由もなかった。
第五章 らいむらいと
くだらないことかもしれないけど、そう前置きをした明日歩が大真面目にあずさの顔を見たのは一年前。
二人でのんびり公園に来ている時だった。
カバンからごそごそと何かを出したかと思うとそれを広げ、明日歩はにっと笑ってみせる。
「何でも計画は必要だと思うんだよね。ほら引き寄せパワーっていうやつ、オレ実践してみようかと思ってさ」
何を言い出すのかと思ったあずさが、思わず吹き出してしまう。
「笑うなよ」
「ごめん、でも急にどうしたの?」
「いやぁ今までの自分を振り返ってさ、行き当たりばったりの人生だったなって反省をしたわけですよ」
「へぇそうなんだ」
「そうなんだ。それで、オレは考えました。この先どうやってどんな風に生きていきたいかって」
「それはそれは壮大なことですね」
「じゃじゃん」
明日歩が拡げたのは年表だった。
わずかな野望が踏まえられている年表を目にして、あずさは明日歩の顔を見る。
「あのこれ、結構無理があると思うけど」
あずさが言っているのは、二人仲良くキャンパスライフのあたりのことだった。
「そうなの?」
「明日歩、私の実力、知らなすぎ。もう数学なんかやばいってもんじゃないし、英語は何を言いたいのかさっぱりだよ。完璧、お手上げ状態で、試験の度、死にたくなるんだからね」
「大袈裟な」
あずさは大きく頭を振ってみせる。
「嘘じゃない。何ならテスト、見せてあげましょうか」
そんなことを自信満々に言われてしまった明日歩は苦笑いで返すしかなかった。
しかし、そんなことでくじける明日歩ではないってことを、あずさは知らずにいた。
自分が空いている時間を利用して、あずさに勉強を教える、と言い出したのだ。何のための、目指せ教職員なのか、オレ様の実力を知りたまえ。そう胸を張られ、あずさは騙された気持ちで勉強に取り組み、そしてこの日を迎えていた。
「1556、1557、……1562。あった!」
あずさは大喜びで明日歩に飛びつく。
難関校と呼ばれる大学の合格だった。
薄っすらと涙を浮かべたあずさを抱きながら、明日歩も安どの息を漏らす。
それからというもの、明日歩の計画は加速をつけ、着実に推し進められていった。
忙しい時間をやりくりさせながら、明日歩は就職にすべてをこの春から打ち込むために大学の単位はほぼ三年間で制覇し、残すは教育実習をのみである。
花見がてらやってきた公園で、明日歩はあずさの膝枕で寝転ぶ。
「実習はいつから?」
「来週から」
「ふう~ん」
つまらなそうに言うあずさに、明日歩はニヤニヤとする。
「オレと会えないのが、そんなに寂しい?」
軽い冗談のつもりだったが、あずさに素直に頷かれ、明日歩は顔を綻ばせる。
「ご心配なく。連絡はちゃんとまめにするし、行くって言っても母校で、家からそんな遠くなしさ。あ、なんならこっそり見に来るって言うのはどう? 昔みたいにさ、フェンス越しの彼氏ってことで」
「ばかっ」
あずさに鼻をつままれ、明日歩はゲラゲラと笑い出す。
起き上った明日歩が、大きく伸びをして立ち上がりあずさの手を引っ張り立たせる。
明日歩には、あずさに見せていない未来計画があった。
それはまだ先の計画で、今言うことではない。
浮かない顔をするあずさの肩を抱き、明日歩は髪へキスをする。
あずさが不安に思っていること、少なからずわかっているつもりの明日歩である。だからこそ、一日も早く、一人前の大人になりたいと願うのだ。それには教職免許の取得と、就職活動が重要視されてくる。
寂しいのは今だけ。
それはあずさも分かってくれているもんだと明日歩は思っていた。
しかし、あずさはそうではなかった。
不安と常に隣り合わせの恋。自然と漏れてしまう溜息。
高校生の時から抱いている悩みだ。明日歩はもてすぎる。本人に自覚症状がない分、なおさらたちが悪い。明日歩は優しい。だけど、明日歩を好きになればなるほどあずさは、自分の醜さに打ちのめされてしまっていた。
誰にでも優しくしないで、などと言えるはずがない。そんな明日歩だから好きになったのも事実なのだから。
ふわっと頭に乗せられた手に、あずさはドキッとなる。
「じゃあオレ、バイトだから行くね」
コクンと頷くあずさに、明日歩は微笑む。
「あずさ、好きだよ」
この一言で、あずさはいつも救われていた。
だけど……。
颯爽と去って行く明日歩の後姿を眺めながら、あずさはフーッと肩で息をする。
最近、なぜかこの不安症候群に取りつかれてしまっている、あずさだった。
☆
――教育実習一日目。
これほどまで、自分はこんなに真剣に教師を見詰めていたことがあったかと。自問したくなるくらいの眼差しに、明日歩は嫌な汗をかかされてしまっていた。少し前まで、自分も右端の列の前から3番目で授業を受けていた。そんな自分に代わって、眼鏡がずり下がりそうな男子生徒が、今ではノートを取っている。
職員室も、在学中にお世話になっていた先生の大半はもういなくなっている。
「いやー、よく来た」
緊張の面持ちでやって来た明日歩をにこやかに出迎えてくれたのは。真っ黒に日焼けした森崎だった。
卒業してから4年、すっかり風貌が変わり、柔らかい印象になった森崎に、明日歩は目を細める。
「久しぶりです」
「挨拶はあとあと」
頭を下げる明日歩を半ば強制的に更衣室まで連れて行った森崎は、自分のジャージを手渡す。
「当然、後輩の面倒も見てくれるんだろ? 先に行っているから」
顔を覗かせるくらいは考えていたが、まさかコーチを頼まれるとは思っていなかった明日歩は、つい苦笑いでッ心にもないことを言ってしまう。
「マジですか?」
「お前な、卒業してから冷たすぎるだろ? あの哲平すらたまにOBとして練習を見に来てくれてんだぞ」
「哲平がですが? オレには何にも言ってなかったけど」
「大体お前、哲平とも連絡撮り合ってないだろ?」
「あいつそんなことまで喋ってんですか?」
「最近の明日歩ったら、冷たいんですぅ先生って具合にな」
驚きである。まさかあの森崎がこんな冗談を言うなんて、思いもしなかった明日歩だった。
森崎に促されるように向かったグランドで、明日歩はさらに驚かされてしまっていた。
廃部寸前だった陸上部は、明日歩がいたころよりも部員は増え、粒揃いになっているではないか。これが森崎のなせる業だと思うと、自分がしでかしたことの大きさを知り、明日歩は穴があったら入りたい気持ちでいっぱいになる。
それに加え、部員たちのたっての希望で、明日歩は久しぶりにスタートラインにつくことになった。
独特の緊張感が、躰の奥の奥をギュッと絞り上げて行く。
戦う相手は、春の大会で入賞を果たした者や、それに次ぐ勢いがある有望選手だと、森崎が説明する。
趣味程度にしか走っていなかった明日歩である。結果は散々だったが、走りながら、やっぱり走るの好きだなと、感じられた一瞬でもあった。
「先生、やっぱ、早いですね」
息を切らして、話しかけて来た男子生徒の顔を見て、明日歩はおやっと思う。
「僕、刈谷真琴と言います。姉、奈波を知っていますよね?」
なんとなく眼元が誰かに似ていると思っていた明日歩は、納得する。
「お姉さん元気?」
「はい。今、留学しています」
意外な言葉を聞かされた明日歩は、ついおうむ返しをしてしまっていた。
「はい。姉の夢は、国際結婚らしいです」
「国際結婚?」
すっとんきょうな声で訊き返す明日歩に、真琴はケラケラと笑いだす。
「親も呆れていました。居ませんよねそんな奴。英語もまともに話せないのに、私にふさわしい人は、日本にはいないわって、一人で決めて金貯めて行っちゃいました」
「凄いね君の姉さん。そんな風には見えなかったけど」
「そうでもないです。自分の目的のためなら、何でもできちゃう人ですよ、うちの姉は」
ふっと見せる表情が、奈波にどこか似ていた。
何はともあれ、無事に実習を終わらせた明日歩は、あずさをランチに誘っていた。
「教育実習どうだった?」
「うんまぁまぁだったかな」
「ふーん、それは良かったわね」
「あとは教員採用試験パスするのみってところかな」
「やっぱり目指すのは高校教師?」
「できれば、久々に恩師と会って、ああこの人みたいな教師になりたいなって思ってさ」
「高校教師か」
呟くあずさの額を、明日歩は指で突っつく。
「何心配してんだよ」
「別に、心配なんてしてませんよーだ」
「だったら良いけど」
どこかとげとげしい言い回しに、明日歩は眉を顰める。
あずさは、大学に入ったころから髪を伸ばしている。色も変え、軽いウエーブが入れられていた。化粧も薄っすらとするようになり、高校生だった時とは、比べ物にならないくらい綺麗になっている。あずさが心配することなど、何一つないのに……。
「そう言えばさ、同級生の弟がいてさ、それがそっくりで驚いちゃったよ」
「へぇ、すごいね」
「なんか、怒ってる?」
いよいよ放っておけなくなった明日歩の問いに、あずさはプイと顔を反らし、どんどん先を歩いて行ってしまう。
「待てって。あずさ。マジ何怒っているんだよ?」
「いいえ、10日以上も連絡をしてくれなかったことなど、私は全然怒っていませんから!」
あっと思った明日歩が、苦笑いであずさの肩を抱こうとして逃げらてしまう。
教育実習の間、明日歩は一度も連絡を入れていなかった。
メールも開いていたが、ついつい後回しにしているうちに、返信しそこなっていたのは事実だった。何の反論もできない明日歩である。しかし、これほど機嫌が悪くなるとは、思ってもいなかったのも事実。そういうことには割と寛大だったはずのあずさである。 「ほら、不慣れなことをしていたから、そっちに時間を取られていたし、陸上のコーチも、恩師からの頼み事だから断れないだろ? 授業の準備だってしたかったし……。バイトも休みたくなかったから」
「そうね、恩師は大切よ。恋人よりもね。仕事だってしなきゃ大変。そんなの分かっているわ。私だってきっとそうするわ。でも、ほんの数秒でも一行でも、明日歩の声が聴きたいって思っちゃうのは、いけないこと?」
瞳が潤むあずさを見て、すっかり動揺してしまう明日歩だった。
「いや、だから、えーっ。今度、上手いもんでも食いに行こう。ごめん。本当は今日って言ってあげたいんだけど、どうしてもバイト抜けられなくって」
「もういい。私もバイトあるし、午後の講義が始まっちゃうから、もう行くね」
「あずさ」
「ごめん、一人になりたい」
後を追いかけて行ってやりたいのは山々だったが、あずさの背中に手を合わせると、キャンバスを後にする明日歩だった。
後ろ髪を引かれる思いで、明日歩は家路を急いでいた。
珍しく、奈緒が早く帰って来いと言うのだ。
用事なら今言って、という明日歩に、深刻な顔を見せるものの、奈緒は帰って来てから話すの一点張りで、あずさには悪いが、おちおちゆっくりしていられる気分ではなかった。
玄関を開けた途端、目に飛び込んできた男物の靴に、明日歩は眉を顰める。
見るからに高級そうな革靴を履く人物は、一人だけしか明日歩には思い当らなかった。しかし、中島が来るなら来ると、どうして言わなかったのだろうと、茶の間へと首を傾げ入って行った明日歩は思いがけない人物に、会釈され、一瞬動きを止めてしまっていた。
間宮徹?
「久しぶりだね。中田の葬式以来だから、もう何年になる?」
なかなか言葉が出ない明日歩に、間宮は親し気な笑みとともに、握手を求めてくる。
「いやぁあん時も思ったけど、本当に君、中田にそっくりだな、背格好も同じなんじゃないか」
どういう顔をしていいのか、まったくわからない明日歩の顔が引きつる。
「悪いね。急に押しかけて来ちゃって。明日歩君はもう何歳になる?」
「22になります」
「そうか。間違ってないな」
「間違ってないって、何がですか?」
その言葉の意味が分からず、思わず訊き返してしまう明日歩だった。
「言われている意味が分からんよな。実は君に折り入って話があって、今日は伺わせてもらったんだ。本題に入るその前に、これを見て貰えないだろうか」
大き目な封筒を差し出され、明日歩はきょとんとする。
「これは?」
唖然とする明日歩に、間宮はにっこりと微笑む。
お茶を運んで戻って来る奈緒を待って、間宮は話しを進める。
中から出てきたのは一本のDVDだった。
「島根は知っているね。あいつからの、いや違うな、俺ら仲間からのささやかなプレゼントだ。奈緒さんは、きっと喜んでもらえると思うけど」
明日歩の頭の中は、完璧に真っ白になってしまっていた。
呆然としたまま、明日歩は再生ボタンを押す。
――砂嵐、浮かび上がる二人の男のシルエット。そしてタイトルバック。
春風一番。
その題字を見た奈緒が、ぽろぽろと涙を零し始める。
間宮の目にも光るものがあった。
その映像は明日歩にとって信じがたいものだった。
突拍子でもないことをしでかす父親だとは思っていたが、舞台俳優だった話など、一度も聞いたことがない明日歩である。よりによって、ヒーロー戦士もどきの格好をした父親の姿に、呆れはしたが、グイグイ物語の中へ引き込まれてしまっているのに、大きな驚きを感じたのも確かだった。そして最後の場面に奈緒までが登場し、二人はめでたく結ばれ舞台の向こう側へと消えて行くというものだった。
目を瞬かせる明日歩に、間宮は是非、この物語の続きをやりたいといい出す。
まるで現実味が湧かない話である。
狐にでも抓まれたような面持ちの明日歩に、間宮はもう一本、違うDVDを差し出す。
「ここからが本題。ぜひこちらも見て頂きたい」
言われるがまま明日歩はDVDを差し替えると、その映像に口をあんぐりとさせる。
最初に見せらた続きだってことは一目瞭然だった。
舞台から降り立った歩が光になり、一瞬、真っ黒になった画面に一点の光が灯り、やがて大きな夕陽になる。
人のシルエットが重なり合う。
カメラアングルが変わり、歩が映し出される。
見覚えのある服装。少し奮発して買ったと言っていた三つ揃いだ。
いつ撮ったんだろう?
ぼんやり思っている明日歩の意図を読み取った網谷が、注釈を入れ微笑む。
「亡くなる一か月前くらいだったかな? ふらりと事務所にやって来て、サプライズをするから協力してくれって言って来たのは」
歩が何をしたいのか、明日歩にはさっぱり分からなかった。
映し出された瞬間、歩は歌を歌いはじめたのだ。いたって真面目に、ああこんな顔もするんだなぁと思わせるような影ある表情が、意外過ぎて奈緒の顔を見てしまったくらいだった。
「この劇中歌、いいだろ? これは中田が自分で作詞作曲したそうだ」
歌い終わったところで、間宮は停止ボタンを押す。
「君には話してあるって聞いているけど?」
しばらく考え込んでいた明日歩が、あっと小さな声を上げる。
間宮が思い出したようだねと、嬉しそうに言う。
確かに、亡くなる前にサプライズの話は聞いていた。けど、それとこれがどうつながっているのか分からない。
「何かの記念日だとは聞いています。でも、それがどうして舞台に出ろと言う話になるのかが、まるで見当がつかないけど」
「やっぱりそうでしたか。結局言い出せなかったんだろうなって、思っていました」
「言い出すも何も、いったい何を考えていたんだ親父の奴」
「この企画、是非やらせて欲しいと言ったのは、野村の方です。明日歩君が了承してくれるなら、親子共演でって話が盛り上ったくらいです」
「親子共演って、冗談じゃない。僕がそんなのに出るわけないじゃないですか」
ムキになって言い返す明日歩に、間宮は柔らかい笑みで返す。
「結論を出すのはもう少し待ってもらいたい」
終わりだと思ったビデオは、まだ続きがあった。
暗がりに浮かび上がる歩の背中。
徐々に明るさが増し、ぼんやり浮かび上がるステンドグラス。
「オレは幾年も愛する人のために闘い続けて来た。それは今も変わらない。愛する人の笑顔を護るためならなんだって出来ると、ずっと思っていた」
じっと見据えていた目線が、ふっと落とされる。
「でも、もしかしたらオレは間違っていたのかもしれない。今もあいつは、悲しい目をする。その意味さえ聞けずに、分らないんだマリア。オレはオレなりにあいつを愛し守ってきたつもりだ。何が足りない? 金か? 名誉か? そんなものに目をくらませるような女じゃない。じゃあなぜだ。なぜあんな顔をする? 俺が選んだ戦い方は、間違っていたとは思わないが……。教えてくれ。マリア」
黙々と祈り続ける歩の背後の扉が開かれ、まばゆい光が画面いっぱいに広がる。
「ここまでが中田の構想です」
「歩は、歩は、もう一度、役者として生きることを決心してくれたんでしょうか」
そう訊く奈緒に、間宮は煙草を取り出し、フーと一息吐き出してからゆっくりと答える。
「なら良かったんだけどね。これはあくまでも、結婚記念のサプライズ。もう一度、明日歩と舞台に立って、あの日の思いを完結させてあげないと、奈緒が笑えないって中田の奴が言ってねぇ、ここの先は明日歩に演じさせたらどうだろって」
「はい?」
目をむき出す明日歩を見て、間宮は目じりを下げ話を続ける。
「あいつの考えはこう。扉を開けたのは明日歩で、希望の光になり、二人を幸福に導いてくれたから、良かったじゃないかってもんに仕上げたかったらしい」
アバウトすぎる話に、明日歩は呆れ返ってしまう。
「そうか、君は知らないんだね。奈緒さんと中田が知り合った齢を。23歳の時でしたかな奈緒さん」
そう言われ、明日歩は何となく歩が考えていたことが分かるような気がした。
間宮の顔がニヤつく。
つまり、出会い記念日、サプライズを早々と考えていたってことになる。歩ならやりかねないことである。
愕然とする明日歩に、間宮が手を差し伸べてきた。
「決まりだね」
どうしてそうなってしまうのか、皆目見当がつかない明日歩の手を強引にとり、間宮は嬉しそうに握手する。
「待ってください。オレ、やるとは」
「君は断れないよ」
「はい?」
したたかな笑みで言う間宮に、明日歩は目を見開く。
「是非、やってみたいんだ。もうこの先の台本もできている。あいつは居なくなっちまったけど、思いを形にしてやろうじゃないかって。幸い、中田そっくりの明日歩君、君がいる。何とかいけるんじゃないかって話になってね。二人の火付け役になってしまった俺としては、その責任も果たしたいし、中田同様。俺自身も奈緒さんが引きずっているものをそろそろ降ろさせてあげたいしね。それに中島が一番、この上演を強く望んでいるんだ」
「どういうことですか?」
「ご覧の通り、中田は昔俺らと芝居をしていたことがある。この舞台は最初で最後の晴れ舞台。あいつは、脚光を浴びて生きて行くことよりも、生まれて来る君や、奈緒さんとの平凡な日々を選んだ。あいつにとっては後悔なんて一つもなかった。けど」
一旦言葉を切った間宮は、奈緒に目を見る。
「ずっと思っていたの。やはり、歩には舞台に立って欲しいって」
「あいつは頑固だからな。そんな気持ちは分かっていても一度離れた場所、おめおめとは戻れないと考えたんだ。そして、奴は奴なりに知恵を絞ったんだろうな。明日歩の中に光るものがあるって、オレには出来ないけど、明日歩になら出来るって。あいつにも充分あるって言うのに」
勝手すぎる話に、明日歩は憤慨するが、あっさり実力の差を見せつけらてしまい、口ごもらされてしまっていた。
――間宮が帰った後、明日歩はリーフレットに目を落としていた。
光の彼方に何が見える?
あなたにとっての正義はなんですか?
らいむらいと。
丸文字で書かれたその題字の下には、庭に咲く沈丁花が、淡く映し出されている。
こんなものまで作って、断らせない気満々じゃないか。
明日歩は大きなため息をつき、淡いブルーの表紙が付けられた冊子を奈緒の前に置いて、困った様に笑う。
自分の気持ちを一番理解してくれるのはあずさである。
早速相談するため、明日歩はあずさと待ち合わせていた。
「何?」
昼食を一緒に食べているあずさの前に、間宮が持ってきた封筒を出す。
「中を見て」
学食の一番右端の席で、サンドウィッチを抓んでいるあずさは紙ナプキンで、手を拭いてから、なあにと中身を取り出す。
台本とリーフレット。DVDはさすがに持って来ていないが、話の流れでは、それも見せようと思っていた。
あずさは、驚いたように顔を上げる。
「これは、大学主催のものではないわよね? それになぜ明日歩が主演のところへ名前が書かれているの?」
「参ったよ。親父の奴が、死ぬ前に仕込んでいったものらしいけど……、寝耳に水って正にこのことを言うんだな」
力なく言う明日歩は、深い溜息をつく。
もうこれで何回目だろう? 昨日からずっとこの状態で自分では答えが出せずに、あずさへ助けを求める明日歩。
ガブリと水を飲み、あずさの様子を伺う。
「でも、ここまで手を込んでいるのを見ると本気よね? 断れないんじゃないの?」
あずさは冷静に分析をし、的確な指摘をする。
明日歩は間宮とのやり取りを思い出し、苦々しい表情を浮かべる。
「事情は分かりました。でも、それはオレの意思に反することでまったくもって芝居に興味がありません。ですからその話は」
う~んと唸った間宮が、顔を顰める。
「何千枚も刷られたポスターや、リーフレットを回収するのは無理だろうな。賠償金が発生してしまうが、君、払える?」
真顔になった間宮に言われ、喉を鳴らした明日歩はおし騙されてしまっていた。
明日歩も負けまいと、断る権利はあるはずだと食い下がった。
間宮は追い打ちをかけるように、裁判沙汰にまで発展するけどと、暗い表情で不気味な笑いを浮かべられ、明日歩の背中にゾッと寒いものが走る。
「そうなんだよな。どうすりゃいいんだ? 賠償金なんか払えれーし」
明日歩は頭を抱え込む。
そんな経緯も正直に話す明日歩を見て、あずさは小さく笑ってみせる。
「私は良いと思うけどな。こんなチャンスは滅多にないことだし。面白そうじゃない?」
あずさにあっさり言われた明日歩は、ムッとしながら口を尖らせる。
「ただでさえ忙しいのに、これ以上仕事を増やされたら堪らない。決めた。こればっかりは親父の頼みであろうが、母さんの願いであろうが、オレは断る。断ってみせる」
――その翌日、明日歩は5階建てのオフィスビルを見上げていた。
深呼吸をして、勢い付けて自動ドアの前に立つ。
その様子を不審に思った警備員がすぐにやって来た。
それだけで舞い上がった明日歩は、社長に会いに来たと言うと目を逸らしてしまう。
怪訝な顔を見せる警備員が、これ見よがしにどこかへ連絡を取るのを見て、明日歩はすっかり逃げ腰になってしまっていた。
「出直します」
「お会いになるそうです。そちらのエレベーターで3階までお越しください」
え?
流石に一人でっていうわけにはいかなかったらしく、エレベーターには警備員も同乗していた。
③階のボタンを押した警備員が、チラッと顔を見られ、明日歩は愛想笑いを浮かべる。
滅多に味わえない緊張感である。
ふと明日歩は自分の名前を名乗っていないことに気が付き、警備員の顔を改めて見てしまっていた。
対応が陳腐すぎるのだ。
実は不審者扱いで、警察が来るまでの間、どこかへ閉じ込められるとか……。
想像が想像を呼んでしまい、明日歩は昔のトラウマが蘇ってしまっていた。
奮起して何かを成し遂げようとすると、必ずと言って、思いがけない方向へ話が展開してしまう。今回もその流れに似ていた。
背中に冷たいものが流れるのを感じつつ、明日歩の目の前の扉が開く。
「中田明日歩!」
ドアが開いた途端、目がクリッとした女性にそう言われ、明日歩はドキッとなる。
「本当にそっくりよね」
その女性にパッと手を取られ、こっちよと連れて来られ、今はソファーに座らされている。
彼女はじろじろと眺めてから、うーんと唸ってこの一言を発していた。
「あのぅ?」
困ったように話しかける明日歩に、彼女の大きな目が更に大きく開かれ、急にゲラゲラと笑い始める。
「ごめなさい。パパがいつも酔うと話してくれているのよ。あなたのお父さんのこと。パパの机には、今でもあなたのお父さんが舞台用に撮った写真が飾られているのよ。見る?」
この雰囲気、知っている気がする明日歩である。
「ちょっと待っててね。すぐ戻って来るから」
明日歩の返事など聞かずに、彼女は跳ね上がるように立ち上がると、そのままどこかへ行ってしまった。
出ばなをくじかれ、怖気づいた明日歩は、このまま逃げだしてしまおうと試みるが、あえなく失敗に終わってしまっていた。
数秒もしないうちに、彼女が戻って来て、勢いよく明日歩の隣に座ったかと思うと、持ってきた写真を目の前に突き付けてきたのだ。
「ほらそっくりでしょ?」
勝ち誇ったように笑われ、明日歩はリアクションに困った。
「良いよね。イケメンって、何を着ても似合っちゃうだもん。一度、お会いしたかったなぁ。ねぇ、お父様って、どんなお方だったの?」
「はぁ」
「やっぱりお家でもかっこいいのよね。うちのパパとは大違い。一度でいいからこういうパパで、ドライヴとかしてみたかったな」
「ドライヴ?」
「子供の頃、凄く憧れていたんだ。こう片手でハンドル切ってバックさせて、抱っこされて車を降り立つってやつ。ほらよく車のCMとかであるじゃない。うちのパパだと狸に抱かれている子熊的な絵になっちゃうのよ」
どう答えて良いのか分からないでいる明日歩を、彼女は指で作ったアングルで見てくる。
「やっぱいい。私の想像していた通り」
明日歩は押されっ放しで、一瞬、自分が何をしに来たのか目的を見失いかけてしまっていた。
「今度の公演は楽しみよね。この続きになるんですもの。感動のヒロインとヒーローの行く末よ。絶対にハッピーエンドにしてねって、パパにお願いしてあるのよ」
置いて行かれっ放しの明日歩である。
「早くやりたーい」
思っていることを喋り切って満足したらしく、彼女は両手を上げ、叫びながら明日歩を見てくる。
「ね」
微笑まれ、明日歩は引き攣り笑顔で頷く。
帰りたい一心だった。
「今日のところは」
何とかねじ込んだ明日歩が腰を浮かせた瞬間、彼女が何かを思い出したように自分の口を、手で塞ぐ。
「あ、ごめんなさい。自己紹介しするの忘れてた。私、今度あなたと共演することになった野村美春です。お互い初舞台だから頑張ろうね」
小首を傾げて、美春は手を伸ばして来た。
「野村って……」
「ここの社長の娘」
「娘」
「ああ、何だ親の七光りかって、今思ったでしょ。失礼ね。そんなの全然あるから。利用できるものは何でも利用する。ハングリー精神が必要なのよこの世界は」
「ハングリー」
「ああバカにしているんでしょう。あなただって突き詰めて言えば、親の七光りみたいなもんじゃない」
「オレ、そのことでここへ来たんだけど、野村さんとか間宮さんはいないの?」
美春の表情がみるみる変わり、ぷーと不貞腐れるようにソファーにもたれ掛り、みーんないないよ、と口を尖らせる。
「パパは打ち合わせがあるって出かけているし、ママはお姉ちゃんとテレビ局に行っているわ。間宮さんはどこかで撮影しているんじゃない。私が相手だとご不満?」
慌てた明日歩は、そういうわけじゃないけどと苦笑いで言うと、躰を起き上がらせた美春が、ニッと笑ってみせる。
「まぁいいわ。これから長い付き合いになるのに、つまらないケチをつけたくないわ。許してあげる。だけど今回だけよ」
この展開の速さにはついていけないなと、知美以上に手強さを感じた明日歩が、困ったなぁと呟く。
さすがに、その言葉を聞いた美春も、どうかしたのと声のトーンを落として訊いた。
「オレ断りに来たんだ。芝居なんかしたことがないし、向いてないから」
「……向いているかどうかなんてやってみないと分からないじゃない? それに甘いわよ。あのパパ達の張り切り方を見ると、絶対にあなたを舞台に立たせるわね」
そう断言した美春は近くにあった雑誌を開いて見せる。
よく見かけるファッション雑誌だ。
せっかくだから、ラフな感じのも何枚か撮ろうよと言ったのは、由紀子だった。悪乗りして、やんちゃ系にしてみるかと帽子をかぶせてピアスを嵌めさせたのは、迎えに出て来た男性だった。あっそうだーと手を叩いて、スタートラインに立った時の気持ちになって、こっちを見てと、硬い表情をしていた明日歩に声を掛けたのは、島根だった。
そしてその写真が見事に乗せられている。
「ええ? これって紳士服売り場の広告じゃなかったの?」
「騙されたわね。きっとみんなぐるね」
明日歩の顔は青ざめた。
「これって」
「いい線行っていたのよ。投票もぶっちぎりの一位だったって聞いているわ」
美春が顔をくっつけるようにして説明をされ、明日歩はそっと躰を反らす。
「このままデビューさせようって話も出ていたらしいんだけどね、中島常務がストップをかけたのよ」
驚きだった。
「何も聞かされていないんだ?」
美晴に同情の目を向けられ、明日歩は妙に惨めな気持ちになる。
「前からあなたのお父さんと約束してあったんですって、明日歩にはきちんと自分の意思で動けるようになるまで、大人が口を出さないって」
知らないことだらけで、まさか陰でそんな計画が進められていたかと思うと、明日歩はだんだん腹が立ってきていた。
「それだけじゃないのよ。これを見て」
また別の雑誌を差し出され、明日歩は唖然とする。
「これは不可抗力。カメラマンが気に入って掲載してしまったらしいの。ちなみに隣に居るのは私の姉の瑠夏」
タキシードを着る明日歩の隣で、真っ赤なドレスを着た女性が肩に手を掛けている奴だった。
「これなら横顔ショットだし、まぁ大袈裟にはならないだろうってことで穏便に済ましたって言ってたけど、アスター社はこれのおかげで何とか生き残れたって話だったわね」
明日歩は目が点になる。
どれもこれも明日歩の知らないことだらけだった。
口紅の宣伝用ポスターに使われたという説明を聞いたあたりから、頭がくらくらしてきた。
「まぁ、お互いもう20歳は越えているんだし、自分の行動には責任を持たなきゃね」
意味深に笑う美春に、どういう意味と力なく明日歩は訊いた。
「意味なんかないわ。このプロジェクトは始まってしまっているの。パパは、歩には逃げられたけど、あなたはしっかり捕まえておくって張り切っていたし、常務も今度こそは完封してもらうって意気込んでいたしね。それに」
いったん言葉を切った美春は、明日歩をじっと見つめる。
「あなたのお父さんの遺志だもの」
にこっと微笑まれた時には、明日歩は観念していた。
美春に稽古日程なる物を持たされた明日歩が、立派過ぎるビルを出たのは、日がだいぶ傾いてからだった。
――明日歩の初舞台は、歩の命日に幕を開けた。
燦然と輝く光を捨てた親子が平凡に暮らしていたが、そこに歳をとってよれよれになった間宮演じる、老人が救いを求めてやって来るところから物語は始まる。
戦い続けてきた老人に残された時間はあとわずか。しぼみかけた命の最後の光を何のために使っていいものかと悩み苦しみ、それが果てる前に託しに来たのだが、光を失ってしまう以前の記憶は、既に歩から消し去られていた。
不思議そうに見つめるだけで、言葉すら話せずにいるかつての戦友に愕然としながら、息子にそっといきさつを話し、光を託して行く。
明日歩の一人二役だ。
正体の分からない老人が置いていった光に、好奇心旺盛な明日歩は次第に取り付かれて行ってしまう。
「息子よ、その光はまやかし。心弱きお前が持つものじゃない」
一瞬、光が大きくなり全てを思い出したかのようにそう告げ、病に伏していた父親も最後の時を迎えてしまう。
だんだん好奇心が大きくなってしまった明日歩は、光に駆りたてられるように旅に出ると言い出す。
何のためにと、恋人である美春の必死に止めるが、漲る知りたいと言う欲望を抑えきれない明日歩は、その手を振り切って旅だってしまう。
旅は過酷なものだった。
光に導かれ歩く先にはいつでも得体の知れないものが、襲い掛かって来る。それが何か分からす、目には見えないものとの戦いだ。
がんじがらめに光に支配された明日歩は、父が抱いた幻想や老人が作り出した世界に頭を抱える。
ぼうっと輝く光を見ているうちに漲ってくる力。
全てを手に入れたはずなのに、影のように寄り添って来る不安と欲望。傲りや偽り。雑踏の中、せせら笑う声に苛まれ、耳をふさぎこんで絶叫する明日歩。
それでも光は、先へ進めと導く。
恐怖を感じた明日歩は光を布で何重にも包み、故郷へ逃げ帰り、旅の間中頭から離れなかった美春を探し回る。
川辺に座っている美春を見つけた明日歩は、愕然と立ち尽くす。
美春が楽しそうに、かつての友人であった雅哉と話していたのだ。
鈍い光が、明日歩の心に差し込む。
「裏切り者。僕だけを愛していると言ったじゃないか」
「落ち着いて、私は今でもあなただけを愛しているわ」
「嘘をつけ」
「お前は狂っている」
雅哉は明日歩の手で鋭く光るものを見つけ、逃げ出して行く。
「お願い。私の話を……」
「嫌だ。お前は俺のものだ」
鈍い光に操られれるまま美春の言葉を聞かず、すべて信じられなくなってしまった明日歩は、友人に盗られてしまうくらいならと、恋人の美春を殺めてしまう。
――訪れる絶望の闇。
明日歩のすべてを覆い尽くし、がっくりと膝を落とす。
老人がぼんやりとした光に包まれ、後方に現れる。
「おまえが望みとは、それか?」
老人が問う。
「違う」
「おまえは何がしたい?」
明日歩は首を振り続ける。
廃人となった明日歩が、うな垂れる。
その傍に老人がゆっくりと歩み寄って行く。
「わしの果たせなかったものは、何だったか見つけてくれたか?」
明日歩は、虚ろな目で老人を見上げる。
「わしもいろいろして来たがのう」
そして、明日歩の血に汚れた手を見て、目を細める。
「殺してしまいたいほどに、わしは誰かを愛したことなどなかった」
「殺して……、殺していいものなんかない」
泣き崩れる明日歩。
老人は目を見開く。
「愛は、愛はそんなに醜いものじゃない。父さんが護りたかったのは、大切な人の笑顔で束縛じゃなかった」
「だが、手放したくはなかったから、おまえは自らの手で殺めてしまったんだろう?」
「俺が、俺が馬鹿だったんだ。彼女が望む幸せなら……、祝うべきだった」
頭を抱え込む明日歩。
老人は遠くをじっと見ている。
「わしもな、結局は戦いに戦い抜いてきたがのう、最後にどうしても勝てなかったものが、一つだけある」
明日歩は、老人をじっと見詰め返す。
「孤独じゃよ。消しても消しても込み上げてくる闇は、どんな栄光があってもどんな大金があっても消せぬかった」
明日歩は、肩を震わせて泣き始める。
老人はそんな明日歩の肩を抱く。
「おまえさんの父親は大したものだ。それをすぐに見破り、おまえ達家族のためにだけ生きることを選んだ」
台本にはない台詞だ。
「わしも、わしもな、もっと早く気が付くべきだった。あの光の向こうには得体が知れない厄介なものが待っていたかも知れんが、それに飛び込む勇気を持つことが大切だと」
死んだはずの恋人の美春が現れ、光を高らかに持ち上げる。
「これは私たちの希望の光です。憎しみも悲しみも喜びもすべてがこの光が教えてくれる。生きろと輝く」
老人はふっと笑みを漏らすと、明日歩の背中を押した。
「この光はな、おまえの父親がわしに託したものだ。正義に満ち溢れ、友を思い愛に生きた勇者の光に濁りはない」
驚く明日歩に老人は頷いてみせる。
「すまなかった」
老人はそう言い残し、その場に朽ち果てる。
「この光は私の心臓です。この光を手にした者は戦い続けなければなりません……」
木綿子の声だ。姿はない。
老人の懐から光が天に向かって伸びていく。
「光の向こうには何が見える? 喜び? 悲しみ? 憎しみ? それとも……。すべてに打ち勝った時、ヒーローは誕生する。難しいことじゃない。誰かを思いやる心。感謝する気持ち。それが力になり光を放つ。その先にはおまえにしか出せない答えがある。戦うことを恐れるな。さぁ、あの光の彼方へ……、行くがいい」
歩の声が響き渡る。
「死を予期していたのかな?」
テープを流す役目を果たした中島が呟くと、野村が肩を竦めてみせる。
ふらりとやって来た歩が、この舞台の構想を伝え、これをふざけて録音した。目を輝かせ、奈緒の驚く顔を想像しながら嬉しそうに、ああでもないこうでもないと言葉を選ぶ歩の姿を二人は思い出し、目を潤ませた。
第六章 光の向こう側
舞台は、大好評のうちに幕を下ろしていた。
「中島さん、これからあの子はどうなるのかしら?」
奈緒は墓の前で手を合わせ終わると、中島に尋ねる。
「たぶん、明日歩君は忙しくなると思います」
「そうですか」
奈緒が静かに頷く。
中島が予想した通り、明日歩はすぐに脚光を浴びるようになっていった。
舞台が終われば、普通の暮らしに戻れるとばかり思っていた明日歩である。
取材を一本、悪いけど受けてくれが、今は次から次へと仕事を入れられ、息つく暇もないくらいの忙しさである。
あずさとは携帯が繋がらないし、中島は話しを摂り合ってはくれないわで、明日歩のイライラは募るばかりだった。
幕を下ろしてから3か月が過ぎようとしていた。
アルバイトは、舞台稽古に集中するため、とっくに辞めさせられてしまっていた。あずさに会うどころか、まともに学校すら行けていない状態の明日歩は、我慢の限界だった。
「中島さん、話違うじゃないですか? らいむらいとだけって約束でしたよね? 何ですか、CMとか連ドラとか、全然意味が分かんないんですけど。学校もいけてないし」
後部座席でむっつりという明日歩をバックミラー越しに見た中島が、目尻に皺を寄せ言い繋ぐ。
「機嫌悪いな。仕事、面白くないのか? やりたくてもやれない奴の方が多いんだ、文句を言わず頑張れよ」
「面白いとかそういうことじゃなくって、オレ、一応学生なんっすよ。学校行かないとでしょ」
「そんな無理して学校に行かなくても、明日歩、ほとんど単位取れているみたいだし、卒論さえ書けばって話だったんじゃなかったっけ」
「誰情報ですか」
「え? 奈緒さん情報」
「何それ、信じられない」
「そうカッカしないで、あと一本、取材で今日は終わりだから、そしたら好きなだけ勉学に励んでいいから」
怒り過ぎて最早何も言い返す気が起きない明日歩は、そのまま無視をして目を瞑ってしまう。
舞台に出てみようかなという明日歩に、あずさは満面の笑みで、応援するねと言ってくれていた。
だから舞台初日と千秋楽の両日、席を用意した。しかし、あずさが見に来てくれたのは初日だけだった。
何度電話をしてもその日を境に、繋がらなくなってしまったのである。
そして、もう一つの明日歩の悩みの種が美春だった。
「ヤッホー、明日歩。これから暇だよね。カラオケ行こう」
取材が済むなり、美晴が腕にぶら下がって来る。
「離れて。行かないし」
「ええ冷たい」
「冷たいって」
「美春ちゃん、明日歩は論文書くのに忙しいから遊びの誘いはまたにしてね」
「ええつまんない、少しくらいいいじゃん」
腕を振り払われた美春は、頬をふくらますがすぐに機嫌を直し再び腕へぶら下がる。
「じゃあ美春も一緒に行く。勉強を教えてよ」
「だから」
ずっとこんな調子で、ついに恋人じゃないかなどという如何わしい週刊誌に報じられてしまったのだ。
それでも臆面にもしない美春に、明日歩はほとほと困らされてしまっていた。
中田家には家訓がある。
『人生何が起こるか分からない』
物心ついたころには、常にこの言葉が付いて回り、だからというわけではないが、手を抜くと言うのがどうも苦手というか、嫌だ嫌だと言っているうちに月日があっという間に過ぎ、完璧に身動きが出来なくなってしまっていた明日歩だった。
何を恐れているのか、やたら警護が固い中島達に、明日歩はうんざりさせられていた。それでも何とか時間を作り、あずさが居そうな場所を片っ端から捜し歩くのだが、不思議なくらい会えないのだ。
カフェも駅前のショッピングモールも、バイト先にも顔を出してみた。しかしどこを探してもあずさはいないし、誰も居場所を知らなかった。時間は刻々とすぎ、明日歩の思いとは正反対に、次の舞台が決まり、ドラマ出演も決まってしまう。
ヒーロー戦隊のオーディションも受けろと、社長命令だと中島が伝える。
そんなものに出てしまったら、一年間は拘束させられてしまう。これは是が非でも待逃れなくてはと、明日歩は全力で断るが、受からなければ出たくても出れないからという甘い言葉に乗せられてしまったのが運の尽き。
結果を中島から聞かされ、明日歩はがっくりと肩を落とす。
来秋には出演が決定をしてしまった。
もう後戻りができない状態だった。
挨拶に行く明日歩を見て、プロデューサーが藪から棒に、以前、君そっくりな人間にフラれたことがあると笑って話しだす。
「すいませんと土下座をして、オレの一存で劇団とは関係がないんです。オレの器の問題なんですって確か言っていたな」
監督は煙草を銜える。
「君は、なしにしてくれよ」
明日歩の肩を軽く叩かれ出て行ってしまったが、きっと歩の話をしているんだとすぐに分かった。
結局、父さんの尻拭いじゃないかと明日歩は、不貞腐れる。
歩にレールでも敷かれたように、とんとん拍子で決まって行く中、あずさとの距離が離れて行くのが分かった。
相変わらず連絡は取れずに、中島に言っても探すどころか諦めろと言われる始末だった。
共演が多い美春との恋の噂が報じられたことも、今度出るドラマの話もしたかったのに、あずさに話したいことは山のように会った。今後のことだって相談したい明日歩である。
正月くらいはのんびり母さんと過ごさせてくれと、明日歩は中島に頼む。
素人の明日歩を舞台を立たせるため、稽古場に近い方が良いと、野村が便宜図ってくれた部屋に、今は一人で住んでいた。
すべてが大げさすぎて、明日歩にはとてもじゃにけどついて行けなかった。
野村は新しい舞台に向けて用意を始めているというし、島根も映画監督の血が騒ぐと言われ、そんな大人たちの目論見を突っぱねられない自分が悔しくて、腹立たしくて仕方がない明日歩だった。
しっくりいかない思いで、明日歩は外を眺める。
見慣れた街並が流れ、あの坂道へと差し掛かった時だった。
一瞬だったが、間違いなくあれはあずさだった。
「止めて」
急停止した車から、転がるように明日歩は飛び出して行くのを、中島は目を細める。
「あずさ」
突然、明日歩に目の前を立ちふさがれ、あずさは動揺を隠しきれずにいた。
「何してんだよ」
怒りを顕わにする明日歩に、あずさは顔を強張らせる。
「何でもいいでしょっ」
突き放すような言い方をされ、明日歩はすっかり頭に血を上らせてしまっていた。 「何だよその言い方。どうして電話がつながらないんだ? 何度も学校に探しに行ったのにいねーし、メールだって見てたんだろ? 何で返事がねーんだよ。ていうか携帯替えたの聞いていないし」
「私だって忙しいのよ。明日歩だってそういうことあったじゃない。いちいち報告していられないわよ」
「それ、どういう意味だよ。仮にもオレたち付き合ってんだから、そういう連絡って密にする必要、あんじゃねーん」
「もうそんなの沢山」
あずさに手を振りはらわれ、明日歩は愕然となる。
「あずさ?」
「明日歩、もう鈍感すぎ」
真っ直ぐにあずさに見詰められ、明日歩は目を見開く。
「携帯の番号を替えられた時点で、いい加減気が付いてよ。もう終わりにしない? やっぱり無理だったんだよ。明日歩と私の住む世界は違うの」
「何、言ってんだよ」
「明日歩は自分を知らなすぎるのよ」
「あずさ、オレは前にも話したかと思うけど、教師になって」
「もう良いって言っているでしょ。もう疲れたの。びくびく他の女の子の目を気にしながら、一緒に居る私の気持ち、明日歩には分かりっこない」
「あずさ。お願いだ。少し冷静になって、ゆっくり話し合おう」
「話すことなんてない。放して」
クラクションが鳴らされ、中島が手招く。
「明日歩」
「呼んでいるわよ。早く行きなさいよ」
何が何だか分らなかった。
力づくで中人が明日歩を車に乗せ、急発進させて行く。
だんだん遠ざかるあずさに、頭を抱え泣きだす明日歩だった。
「可哀相だけど、今は恋愛はご法度だ。あずささんの気持ちも汲んでやれ」
バックミラーに映る中島を、明日歩は睨みつける。
ぼんやりと、テレビに映る息子の笑顔を見ながら、奈緒は本当にこれで良かったのかと考えてしまう。確かに歩が果たせなかったものを継いでくれるのは嬉しかった。舞台に立つ明日歩と歩が重なり、涙が止まらなかった。悔いても悔いきれないあの日の選択肢。それでも、この子を産んで育てたいという気持ちは、変えられなかった。もう少し自分が強ければ、もしかしたらあの場所に歩は凛とした姿のままで、立てていたかもしれない。が、それはあくまでも歩の人生であって、明日歩のものではない。
――ガタン。
玄関が開く音が聞こえ、奈緒は顔を顰める。
酔っぱらった明日歩だった。
「こんな時間にどうしたの? 今日は一人なの? 中島さんは一緒じゃないの?」
「どうしてですか~。自分の家に帰るんですよ。一人に決まっているじゃないですか」
ようやく、ブーツを足から取った明日歩はそれを投げ捨てると、よろよろと立ち上がり、茶の間へ入って行く。
「腹減った~」
お腹をさすって言う明日歩に、奈緒は眉を顰める。
いつもの場所に腰を落ち着かせた明日歩は、ガチャガチャと落ち着きがなく、チャンネルを回したかと思うと、食事を運んで来た奈緒を認めると、ひっきりなしに話し続けた。
「まっつちゃんって、母さん覚えてる? 中学の時の同級生。ばったり駅前で会ってさ、一杯やるかって話になったんだ。で、克己も呼ぼうぜって話になってさ、そしたらあいつ海外に行っていて、俺、全然知らなくってさ。友達の夢が叶っているっていうのに。まったくなってないよな」
「仕事で何かあったの?」
「何で?」
「様子おかしいから」
「な~んもないですよ。な~んも。いたって良好。すべてよし。見事なもんですよ」
そう言ったかと思うと、明日歩はフラフラと立ち上がる。
「どこ行くの?」
「風呂入って、寝ます」
「ご飯は?」
「やっぱいいや。悪いけどアシタ食べます。明日歩君は疲れちゃいました。では母上、お休みでござる」
ベッドに躰を投げつけると、明日歩は腕で目を覆う。
中島と口論したうえで聞かされた言葉は、信じがたいものだた。
あずさから望まれた別れだった。
てっきり中島達の入れ知恵だとばかりと思っていた明日歩である。
「彼女は彼女なりに、だいぶ前からお前との交際を悩んでいたらしい」
寝耳に水だった。
「そんなわけないじゃないですか? 俺らうまくいっていたし」
「そう思っていたのは、多分お前だけだ明日歩」
「頭を冷やして、よく考えてみろ。思い当たる節があるんじゃないのか」
「そんな」
明日歩はハッとなる。
教育実習の時のやり取りを思い出していた。
「でもあれは」
「彼女にとって、不安材料になる愛が、耐えきれなくなったんじゃないかな」
明日歩はもうそれ以上、何も言えなくなってしまっていた。
一人酒を浴びるように飲み、明日歩は静かに決めたのである。
明日歩の聖なる反逆は、夏を目前に実行に移された。
忽然と姿を消してしまったのだ。
前日まで、普通に仕事をこなしていた明日歩である。
あずさの一件で、ぎくしゃくしたもののそれは既に和解していた。
積極的に仕事に取り組んでいたし、豊富まで語っていた明日歩である。
対応に追われる中島の元へ、奈緒から連絡が入ったのはその時だった。
少し様子がおかしいからと切り出され、中島ははやる気持ちを抑え、嘯く。
「ああそちらに戻っていましたか? なら良かった。体調が良くなかったみたいだから、休みをやったんです」
「でも撮影が入っていたんじゃありませんか?」
「いえいえ、それは来週からで大丈夫なので、明日歩君にはゆっくり躰を休めるように伝えてください」
隣でやり取りを聞いていた野村が、安堵する。
「久しぶりの休暇だ。ここ一年、まともな休みがなかったしな」
電話を切った中島は、野村の言葉に苦笑いをする。
「入るわよ」
木綿子がコーヒーを運んで入って来る。
「明日歩が辞めたい理由って、女性問題?」
コーヒーを配りながら訊く木綿子に、中島が頷く。
「あの子よね。高校時代から付き合っている……、名前なんて言ったかしら?」
「結城あずささん」
「その、結城あずささんって子に、中島君、会って来たんでしょ? 話し合いはついているものとばかりと思っていたんだけど」
「ああ。明日歩のデビューが決まってすぐに、学校近くの喫茶店でな。でも、こちらが話す前に、彼女から大丈夫ですって言い出されてな、驚く俺に、覚悟はしていましたからって、手切れ金として用意したお金も、一切受け取ってくれなかった。明日歩は売れちゃいますよね。あのマスクだし、高校の時もかなりモテていたしって、言ってな。てっきり泣かれるもんだと思ってたから、拍子抜けしちまったくらいだ。な~んか夢を見ていたような気がしますって笑って言ってくれてな」
「で、彼女は言葉道理に、明日歩の前から姿を消した」
木綿子の言葉に中島は、ああと頷く。
「まさか、明日歩があそこまで御執心だとは思わなかったな」
野村がため息交じりで言うと、木綿子が明日歩だからじゃないと言う。
「要するに蛙の子は蛙ってことよね。明日歩の中にしっかりと、歩のDNAが流れているってことでしょ? 一筋縄ではいかないって、どうして分からなかったの? まったく、嫌になるくらい似ているわね。これじゃ歩と同じじゃない。さて、どうします? 劇団マーブルの存亡がかかっているわよ。野村社長に中島専務。今度は失敗しないで下さいよ」
「さて、どうしたもんかな専務」
中島は、さあと肩を竦める。
あずさは、明日歩の舞台が決まると覚悟をしていた。
ただでさえもてる人。テレビや舞台に出ればどうなるかなんて想像がつく。明日歩には話していなかったが、あずさは学校で嫌がらせを受けたことがある。それが原因で友達を一人失っている。
その友達……、まりは明日歩の熱狂的なファンだった。
明日歩に偶然会って呼び止められたあの日、彼女はどういうことと嫉妬の目を向けた。私にも分らないと首を振るあずさに、どうだかと聞く耳を持たずに、プイと横を向かれてしまった。
本当にあずさは、陸上のことはまったく知らずにいた。家でも学校でも、絵を描いているかピアノを弾いている内向的な生活を送っていた。滅多にテレビも見ないし、雑誌も読まない。アルバイトを始めたのは、そんな自分を変えたかっただけだった。
まりに引っ張って行かれるまで、明日歩が陸上をしていることすら知らなかった。
まりは、あちらことちらに酷いことを言いふらし、二度と口を利こうとはしてくれなかった。
それでも耐えられたのは、明日歩がいつでもそばにいてくれてからだ。しかし、今度ばかりは、そういうわけにはいかない。
明日歩の事務所のものだと言って、あずさは呼び出されていた。
ガタイの良い男性が申し訳なさそうに、目の前に座り、言いにくそうに実はと切り出され、あずさは覚悟を決めた。
「明日歩君のことですよね」
コクンと頷くのを見てから、フーッと息を吐き出す。
「分かっています。私がいたら邪魔ですよね」
「邪魔とかじゃなく、今はあいつにとって大事な時期だから、少しだけ控えて欲しい」
「大丈夫。明日歩君が舞台に立つって決まってから、いつかこんな日が来るって私、分かっていたんです。私、しばらく三重の祖母の家に行こうかなって、考えているんです」
予想外の展開に中島は、黙ったままあずさの言葉に頷く。
そして、せめての報いだと言って中島が差し出す封筒をじっと見つめたまま、あずさは首を横に振る。
「ずっと分かっていたから」
あずさは目を潤ませたまま、呟く。
付き合って下さいと告白された日から、いつかこんな日が来ると思っていた。
そう言うあずさは、精一杯の笑みを向けてみせる。
大人たちのもくろみは、いつでも明日歩の意に反している。
だからこの家が嫌いなんだ。オレは普通で良かったんだ。母さんが父さんのフィルムを見て、あんな顔をするから、こんなはずじゃなかった。今頃は採用試験にパスして、めでたく教壇に立っているはずだった。仕事が落ち着いて、お金が貯まったら、あずさにプロポーズをしようと思ったのに、どこでボタンを掛け違えたんだ?
明日歩は顔を手で覆う。
何度迷っても、難問を突き付けられた時も、そばにはあずさが居てくれた。答えを導き出してくれたのはあずさだった。
あずさなしでは考えられない、オレの人生なのに。
「オレはさ、たくさんの人を護るよりも、たった一人の人を護るヒーローになりたかったんだ」
冬の海、歩が嬉しそうに笑って言った言葉だ。
「奈緒はオレの一番大切な人だから笑っていて欲しいんだ。いつかお前も分かるよ、オレの気持ちが。この人だけは泣かしたくないって」
畜生。クソ親父。あんたのせいじゃないか。
明日歩は起き上がり、全力疾走で自転車を走らせる。
絶対にあきらめたくない。
見慣れた風景が飛ぶように流れ、無我夢中で明日歩はあずさの家のチャイムを鳴らしていた。
応対に出てきたのは、弟の孝文だった。
思いっきり迷惑そうな声で何か用と言う。
「あずさは、あずささんはいますか?」
上ずった声で言う明日歩に、孝文は怪訝な顔を見せ、いませんと答えた。
「そんな訳ない。学校にもバイト先にもいなかった。家にいるんだろ? 頼む、会わせてくれ。会って話さなければならないことがあるんだ」
「帰ってくれ。姉はいない。迷惑だ。帰れよ」
「頼む。本当に頼むから」
家の中に戻ろうとする孝文の服を掴み、明日歩は必死に食い下がった。それでもふり払われ、閉まってしまったドアに向かい明日歩は大声を張り上げる。
「あずさ、中にいるんだろ? 一分でいいから話しをさせてくれ」
「姉ちゃんからはっきり言ってやらないと、あいつは辞めないよ。近所の人も気が付いているだろうし、警察沙汰にしたくないなら、自分で決着付けろよ。俺は知らないからな」
戻って来た孝文がお手上げだと言って、ソファーに寝転がり、テレビのスイッチを入れる。
『チョコチョコはーとチョコチップ。一人で食べてもおいしい。恋人と食べればもっとおいしい。はーとチョコチップ』
軽快な音楽と、明日歩の弾けんばかりの笑顔の映像が流れ、孝文が目配せをすると、あずさはドアチェーンを掛けたまま、ドアを開けた。
二週間ぶりに仕事に復帰した明日歩は病名が付けられ、各方面に謝って歩くのが最初の仕事になった。
何もなかった様に明日歩は黙々と仕事を熟して行く。
不気味なほど沈黙を保ち、脇目も振らずに片っ端から来る仕事に没頭して行く明日歩を見ているうちに、中島と野村は歩を思い出していた。
「あいつもバカみたいに働いていたな」
バーのカウンター席、中島がポツリと呟く。
バーボンを一口飲んで顔を顰めた野村が、そんなこともあったなと頷く。
「これからどうすると思う。明日歩の奴?」
うーん。野村は唸って、またグラスを口に運ぶ。
「そっくりだな。親子って、こんなに似るもんなのか?」
野村が、とろんとした目で中島を見る。
「一人の女性を一途に愛しやがって。どんだけ、あいつの周りには綺麗な人がいると思っているんだ?」
「そうだ。美春の気持ちを弄びやがって」
「みはる? 美春って本気だったの?」
野村が頷く。
「俺も最初は冗談かと思っていたんだけど、本気だったみたいで、週刊誌に恋人なんて書かれて、あの喜びようたらなかった。切り抜きをファイルにして、お守りのように大事にしまってあるって、木綿子が言っていた」
「どうしたもんかな」
中島が頭を掻く。
「困った困った」
野村がおどける様に言うと、二人はグイッと同時に酒を煽る。
明日歩は決心を固めていた。思い付きでも何でもない。
「ごめんなさい。私、好きな人が出来たの。これ以上、私に付きまとわないで。お願いだから。私の幸せを奪わないで」
そう言われショックだった。
自分が思い続けることがあずさを不幸にする。そんなこと思ってもみなかった。しばらく何も考えられずにいたが、もうそろそろ仕事に戻ってこないかと、部屋を訪れた中島に言われ、明日歩は素直に頷いた。逃げたりはしない。自分に正直に生きるだけだ。新たな人生。本来あるべき姿に戻ろうと。
東京を離れ、違う場所でもう一度自分の人生をやり直す。
今年いっぱいは、精一杯勤めさせてもらって、その先は自分で切り開いていく。
歩が果たせなかったヒーロー戦士をやりきった。もう何も文句はないはず。
ゆっくりと地下鉄の階段を下りて行く。
きちんと話さなきゃな。
ドアの近くに立つ明日歩を見た乗客がヒソヒソと話す声が聞こえ、握手を求められる。こんな生活もすぐになくなる。快諾しそれに答えた明日歩は、にっこりと微笑んで見せた。
こんなのオレじゃない。
駅から地上に上がって来た明日歩は目を細める。
最初に見た時もすげーと思ったけど、やっぱすげーな。
足早に中に入って行くと、警備員が丁寧に頭を下げる。それが妙に可笑しくってつい笑ってしまう。
「何ですか?」
「いやいや何でもないんだ。ごめんなさい。社長いるかな?」
「一時間ほど前に、出社されております」
「ありがとう」
手を振り、明日歩はエレベーターに乗り込む。
バシバシと自分の頬を叩き気合を入れ、明日歩は最上階のボタンを押した。
社長室のドアをノックをすると、すぐに野村の声が帰って来た。
一礼して入って行くと、野村と中島、それに間宮までが顔をそろえて待ち構えていた。
木綿子がすぐにコーヒーを運んできて、全員で揃ってソファーに座る。
事務所はこんなに立派なのに、ソファーだけが古臭い。何回も皮を張り替えられてはあるが、年季が入っているのは一目で分かる。
「明日歩、話って何だ?」
野村が煙草に火を点けながら訊いた。
それに合わすようにみんなの顔が、一斉に明日歩に向けられる。
一呼吸おいてから、オレ、役者辞めますと言う明日歩に、フーンと木綿子が気の抜けた返事をしただけだった。
テーブルに置かれてあった本を一冊、手にした間宮がペラペラとページを捲り、にやっとして、これ面白いなと言う。だろう。俺もなかなかいい出来栄えだなと思っているんだ。今回は、俺も手伝ったんですよと中島が嬉しそうに話すと、へーと感嘆する間宮に、私も久々に出るんだと、木綿子がコーヒーを口に運び、もしかして親子共演? と間宮が冷やかしを入れる。まるで明日歩の話が聞こえてない様に交わされる会話にムッとしながら、明日歩は声を荒げた。
「聞いています? オレ、本気だから。もう決めましたから。反対しても無駄っすから。スケジュールの調整をお願いします」
立ち去ろうとする明日歩を、中島が呼び止める。
「辞めてどうするんだ?」
「教員の採用試験を受けて、教師になります」
「教師か、教師も悪くないな」
野村が煙草をもみ消し、意味深な笑みを浮かべる。
「そうだな悪くない」
間宮も頷く。
だからと振り返ると、野村が楽しそうにペンと紙を持ち出して、何かを書いていた。
「今度の舞台はそれで行こう。教師と生徒の恋愛ものだな。教師役が明日歩だろ。先生を好きになってしまう生徒役は美春で決まりだな」
野村がペンを走らせる。
「オレは、間の抜けた教頭の役がいい。野村は人が良いだけの気弱な校長ってところだな」
間宮が口を挟む。
「瑠夏はそのままね。美春の姉役で、妹の相談に乗っているうちに自分も明日歩のことを好きになってしまうっていうのはどう?」
「おお、木綿子さん冴えている。それいい」
間宮が手を叩いて喜び、中島もさすがだなと笑う。
「愛と青春のグラフィックだ。結末はどうしたい?」
野村が明日歩に目を向けた。
「真面目な話をしてんだ。今年いっぱいでオレはこの世界から足を洗う。仕事の整理をお願いします」
ムッとして言う明日歩に木綿子が、本気だよみんなと微笑んで、本を差し出した。
……春風一番。
今度のは、面白いぞと言う野村。
中身を見て、明日歩はみんなの顔を見回す。
「映画版?」
「島根が撮らせろって煩くて、それに歩が残した映像と、お前のが上手くリミックス出来る。歩が死んで8年経って俺らも、相当齢を食っちまったしな。ここらでドッカーンと大きな花火を打ち上げておかないと、あの世に行っても浮かばれないからな。お前の来年のスケジュールはこれ一本だけだ。時間をやるからちゃんと自分が進むべき道を考えてみろ」
野村が目に皺を寄せて笑い、間宮も中島もそれに合わせて頷く。木綿子は目頭を指で押さえている。
明日歩も泣きそうになり、下を向いた。
だから大人は、嫌いなんだ。
眠らない町。
父さんが、最初に東京へ出て来て思ったことだそうだ。交差点で信号待ちしている明日歩は、途切れることなく渡って行く人の群れを見て、そんな言葉を思い出していた。
あれは確か中三の頃、嫌がるオレを無理やり連れだって初参りに行く途中に話していた。
「オレんとこも相当賑わうけど、ここほどじゃなかった。なんか疲れちまうよな。気が抜けねーっていうかさ」
それを聞いて、バカじゃねーのと思ったけど、こんなの普通だしっていうか、この齢で親子そろって歩く方がキモいんですけど。そんなことを思っていた。まさか、自分が年末年始くらい親子水入らずにさせろなんて言葉、吐くとは思いもしなかったあの日。
オレンジ色の外灯にホッとしながら、扉を開く。
「おかえり。早かったね~」
「ああ。ただいま」
オレは、この人を笑わせたかっただけなんだよな。父さんとの約束だったのに。結局、悲しませてばかりだ。
一年の節目を迎え、賑やかなお笑い番組を見ながら、二人で久しぶりに笑った。
除夜の鐘が聞こえ、二人でそばを啜る。
父さんがいた頃は、ここで決まって新年の決意を叫ばされていた。どんな意味があるのか、さっぱりわからない我が家の恒例行事。そんなものがここにはたくさんあった。嫌がるオレに執拗に迫ってくるあの父さんの顔も、今は何て言うか、もう一度会いたい。
明日歩は、フーと息を吐き、箸を置いた。
この一年半、何だったんだろ?
間宮が突然やって来て、歩のサプライズを敢行すると言われ、ずるずると入ってしまった世界は、煌びやかすぎて目がくらみそうだったなと、しみじみ思う。
「母さん、オレ、結婚したい人がいたんだ。ずっと好きで好きで、運命の人だと思ってたんだけどな。俺じゃダメだってフラれちゃったんだ。絶対、上手く行くと思ったのに、そんな自信は木っ端みじんにされちゃって、参ったよ」
お茶を啜る奈緒は、フーンとテレビから目を離さずに、気の抜けた返事を返す。
「今年は、映画を一本撮って、それで終わりだ」
「少し、詰め過ぎていたみたいだから、良かったんじゃない?」
汚れた食器を一つにまとめ出した奈緒に、手伝うよと明日歩も皿を持って一緒に台所について行く。
「……オレ、引退しようと思う」
奈緒は皿を洗いながら、そうと答えた。
「そのあとは、教師になろうと思うんだ」
明日歩は、皿を洗う手をじっと眺めていた。
皺だらけの手だ。結婚指輪がぶかぶかになってきたと言って外されている指。
「母さんは、父さんと結婚した時どう思った?」
何気なく口を継いで出てしまった言葉だった
奈緒が水を止め、手を拭くと指輪を嵌め直す。
「私は、結婚しないつもりだった」
指輪を弄りながら言う奈緒の顔を、明日歩は驚いたように覗き込む。
いつだって、二人は結ばれるために生まれて来たかのように、仲が良かった。信じられないと言う明日歩に、奈緒は遠い日を懐かしむように、目を細める。
「歩は本当に優しくって、私を心から愛してくれていた。だからこそ、私は歩の夢を潰してはいけないって思ったの。だってそうでしょ。あんなに素敵な人よ。私と歩じゃ釣り合うはずがない。歩には、もっともっと輝いて欲しい。独り占めなんかできないって、部屋を飛び出したの」
茶の間に戻り、自然と二人は歩の写真に目をやる。
「でも、違っていたのよね。歩はそんなものは、何も望んではいなかった。平凡で普通の幸せがあれば良かったのよ。笑って話をしたり、どうでも良いことで喧嘩になってしまっても、謝って、許して許されて……」
奈緒が、ハーとため息をつく。
「ちょうどそこだった」
奈緒は、明日歩が座っている場所を指さす。
「奈緒さんと、結婚させてくださいって、頭を下げたの。あんなに素顔になることを嫌っていたのに。髭も髪もきれいさっぱりさせて、何年も一緒に暮らして来たのに初めて見る歩だった。本当にこんな人から、プロポーズされているのかと自分を疑ったわ」
奈緒は、目頭を押さえる。
「明日歩、その人のことを愛しているなら、きちんと向き合いなさい。本当に自分はどうしたいのか、どうすればその人が幸せになれるのか、嫌になるくらい悩んで考えて、決めたら絶対に変えちゃダメ。一生報われなくなるわよお互い」
明日歩は、何も言えなかった。
ただ、ちゃらちゃらと愛してあっているだけの両親だと思っていたのに。
散々待たせた相手だ。今度はオレが待つ番だ。一生報われない思いでも良い。
それが、明日歩が出した答えだった。
あずさの卒業の日。
自分の卒業式にさえ出席できなかったのにと苦笑しながら、明日歩は卒業生に紛れて一番後ろの席に座り、会場を見回す。
何千人もいる卒業生の中から、あずさを見つけ出すなんて無謀だ。馬鹿げているのも分かっている。きっと出会えたら奇跡だと思う。
長い祝辞に欠伸をし、うとうとしているうちに式典は終わる。
一斉に吐き出される卒業生と、その関係者でごった返すロビー。ぶらぶらと、あずさの姿を探す明日歩に気が付いた何人かに話しかけられ、曖昧な笑顔とサインを残し、会場を逃げ出すように、明日歩は、タクシーを拾い大学に向う。
きちんと気持ちの整理をつけるつもりだった。
ガランとしたキャンパスを歩く。
顔見知りの警備員が、快く通してくれた。
二人でよくお喋りしたベンチに座ってみる。昨日見たドラマのことを話すあずさ。滅多にテレビを見ないと言っていたのに、友達と会話が弾まないからと、一生懸命情報収集して、それを明日歩にも教えた。どうせバイト三昧で何も知らないでしょと言って笑っていた。
校内をゆっくり一回りしてから、警備員に会釈して外に出る。
どうせなら、二人で行った場所を全部回ってやろうと思った明日歩は、駅とは反対方向に歩き出す。
すぐそばにあるイタリアンの店に、待ち合わせによく使ったファーストフード店。その先にある託児所で、あずさはアルバイトをしていた。そこからちょっと奥まった場所に、二人で偶然見つけたカフェテラスがある。白を基調とした板打ちの壁に、溢れんばかりに飾られた花の名を、嬉しそうに教え、イタリアを思わせるその佇まいに、惚れたとまであずさは言っていた。
ドアベルが、心地よい音色を奏でる。
明日歩は窓側の席に座り、モカコーヒーを頼んだ。
これからのことを、考えなければならなかった。
映画の撮影は始まったばかりだ。ゆっくりと、無理のないスケジュールが組んである。監督は気心が知れた島根だ。由紀子は、勿体ないと言い続けている。薫子は子育てがひと段落したからと、訪問看護師として復帰を果たし、明日歩の良い相談相手になってくれている。
なるしかならないよな。
明日歩は、教習所に通うつもりでパンフレットを開く。
午後のカフェテラスは、のんびりしていた。元々、人で賑わう店ではなかったが、大学が休みになると、尚更静かなんだろう。客は明日歩一人だった。
ドアベルが鳴り、何気なく明日歩は目を上げる。
袴姿の女性だった。
卒業式の帰りかなと思いながら、すぐに目線をパンフレットに戻す。
「ダージリンティーをミルクで」
明日歩は驚いて、また顔を上げる。
聴き覚えのある声だった。
明日歩は、跳ね上がるように席を立つ。その女性客の前まで行き、確信に変わる。
奇跡だ。
「すいません。ここいいですか?」
雑誌をペラペラと捲っていた女性が、目を上げる。
バイト先に、晴れ姿を見せに行った帰りだった。もう一度だけ明日歩と行った思い出の場所が見たくなり、あずさはこの店に来た。
店員が、心配そうに二人の方を見ている。
「明日歩?」
店員がホッとした顔になり、紅茶を用意し始める。
「一目見た時から好きになりました。お嬢さん、もし良かったらボクとお付き合いしてくれませんか? 友達からでも構いません。お願いします」
明日歩は右手を差し出し、頭を下げる。
あずさはクスクスと笑って、涙をこぼし、そして、小さく頷く。
「ばかっ」
☆
ホテルの一室。
明日歩は椅子に座ったり立ったりを、幾度も繰り返していた。
大きな窓には、漆黒を縁取るようにどこまでも続くライトが映し出されている。誰もが魔法を信じたくなる特別な夜。
式はちゃんと上げなさい。やってあげなきゃダメ。あずささんが望んでいるなんて嘘。女の子は誰でもヒロインになりたがっているものよ。私がそうだったように。明日歩は歩の初舞台の先を知らなかったわよね。そう言って、奈緒はビデオを入れる。最初で最後の父さんの舞台映像。頭を抱え、遠くを見据えた歩が叫ぶ。俺が俺がしたかったことはこんな事じゃない。永遠の命を手にしても、莫大な富や栄光も何になる? 俺はそんなものは要らない。欲しいのはあいつの愛。愛する人を護りぬける勇気さえあればいい。二つの光が共鳴し一つに吸い込まれ、一瞬、大きく輝く光の中に歩の姿が消えていく。そんな終りだったはず。
これは?
「私と歩の結婚式。歩らしいでしょ。私が一番望んでいる姿で、私を幸せにしてやりたかったって」
舞台の上でプロポーズし、永久の愛を誓った。
父さんらしいと、明日歩は苦笑して言った。
「それでも、覚悟は相当なものだったのよ。どこから見ても私と歩とは不釣り合いでしょ。そこを護りぬくのが男なんだって、歩は言ってたけどね」
だからじゃないけど、この日に二人の幸せな姿をプレゼントしてやりたいと思ったんだ。母さんと父さんが結ばれ、俺が生まれて来たことがどんなに素敵だったか。
「明日歩、お待たせ」
由紀子が、顔を覗かせる。
「今世紀最高の美女に仕上げたわよ」
「ご苦労様」
ソファーで寛いでいる中島が声を掛けると、由紀子が大げさに疲れたと向かい合わせるように座る。
「何が因果かしらね。親子で花嫁の世話をさせるなんて」
由紀子は、煙草に火を点ける。
「あん時も大変だったな」
「そうよ。金はないけど、めーいっぱいきれいな花嫁さんにして欲しいなんて言うんだもの。それも内緒でって。あの時ほど歩を憎んだことはなかったわ」
二人に遠い目で見られた明日歩は、えっと首を傾げる。
まったくだと言う中島に、でも憎めないのが歩だったと由紀子とゲラゲラ笑いだし、二人は立ちあがった。
「じゃあ後でな」
中島が手をひらひらさせ、由紀子も煙草を消し、一緒に出て行ってしまう。
不意に孤独が押し寄せて来る。
空気がぴーんと張りつめ、心地の良い緊張感が全身にみなぎる。
一生一度の大舞台。
きっとそれが今日なんだ。
この日を迎えられるとは、思わなかった。
――初夏の海辺を二人で眺めていた。
「映画も完成したし、来年には教壇に立てるように頑張るから、オレの傍でずっと一緒に、年を取って行ってくれないか?」
目を大きく開いたあずさが首を横に振る。
「オレと一緒になるのが嫌なのか? 役者は辞める。もう嫌な思いをさせないから」
「違うの。役者を辞めなくていい。私、強くなろうと思う」
あずさが微笑みかける。
波が光っている。日差しがまぶしい。
「そのまんまでいろよ。オレが護ってやるから、あずさはあずさのままでいい」
あずさは首を横に振る。
「それじゃだめなんだと思う。私はあなたを照らす灯台にならなきゃだめなの。それに明日歩だって、もう気が付いているんでしょ?」
ん? 明日歩が首を傾げる。
「私、ずっと考えていたの。あなたを攻めたこともあったわ。あんな顔じゃなかったらいいのに。もっと性格がひねくれてれば違ったかもって」
「ひどいな」
「そうひどいの。私は最低な女だった。自分に言い訳してばかりで、全部明日歩のせいにしていたの」
「そんなことないよ。あずさはいつだって、オレの灯台だった。間違わずにこうしていれれるのも、温かい光が導いてくれたからだよ」
きらきらと水しぶきが光り、明日歩は大きく伸びをした。
この海で、父さんが人を愛することの尊さを教えてくれた。どんな犠牲を払ってもその人を護る強さも弱さも、あの日、教わった気がする。
潮風にあずさの髪がなびく。
「孝文にね、あ、弟の名前なの。好きなら好きでいいじゃねぇかって、怒られちゃったの」
「無理よって言ったらね、あの子なんて言ったと思う?」
「なんだろうな」
明日歩が笑いながら答える。
「同じ人間だろう? 問題はないんじゃねーのって。そんな簡単なことじゃないって思ったけど、その通りなの。私は明日歩が好き。それは何物にも代えがたい真実だって」
今にも泣きだしそうなあずさの笑顔を、明日歩は抱き寄せる。
「もしも、もしも神様がいるなら、本当に運命でつながっているなら、きっと奇跡は起こるはずって、オレも信じていた。あずさ、結婚しよう。一緒に幸せになろう」
頷くあずさの頬に涙が伝う。
父親に連れられ、あずさが明日歩の下に歩み寄って来る。
一歩一歩踏みしめて。
父さん見えますか?
オレ、この人を一生掛けて護れるヒーローになります。
父親の手からあずさを受け取る。
娘には苦労はさせられないと、反対をされた。
何度も何度も足蹴にされ、挫けそうになった。役者じゃない自分ならと考えた日もあったんだ。
奈緒の横を二人で歩く。
オレはいつだって一人じゃなかった。気が付くと、こうして優しい眼差しを向けていてくれる人がいた。支えにもなってくれた。それがあなた、中島さんだ。
目を赤くした中島に会釈をすると、二人は神父の前に立った。
「お前もいつか分かるさ。人を愛するってすばらしいってさ。オレの場合は奈緒。お前はどんな人を選ぶのかな?」
この人がオレの選んだ人だよ。母さんに負けないくらいオレが幸せにしようと決めた人だ。何度だって誓うよ。この人だけは泣かさないって。
そして父さん、オレ決めたんだ。
もう少しこの光の世界で、頑張ってみようと。飲みこまれないようにそこから見守っていてくれよ。よろしくな。
第七章 春風一番
自分の居場所。そんなものを父さんは探していた気がする。
明日歩は、隣でじっとスクリーンを見つめている母親、奈緒の横顔を見ながら、そんなことを考えていた。
あの能天気でハチャメチャな考えを押し付ける感じが嫌で、そのくせどこかでいつも意識していた。
ゆっくり動く歩の背中。
「よくこんなフィルムがありましたね」
「これは本人も知らないかもしれないな」
訊く明日歩にニヤリと笑った中島が言うと、慌てたように島根が、言い訳を始める。
「隠し撮りじゃないぞ。いろんなパターンで撮って置こうって言いだしたのは歩さんの方で、カメラが向いていると思うと表情が硬くなっちまうから、適当に自分が気が向いた時に撮っておいてくれと言われたんだ」
「そんな慌てて弁解しなくても」
苦笑する明日歩に、中島がそっと肩に手を置く。
「お前の親父は、そういう男だった」
明日歩は長く息を漏らすと、首を振る。
「おかげで、オレはこんな目に遭っている」
歩の鼻歌が、真っ白な雪景色の中に響き渡る。
一面の雪景色。
ザクザクと音を立て、一人の青年が新しく降り積もった雪道に足跡を付けながら歩いて行く背中。
教会が見え、足を速めた光一役の明日歩が教会の扉を開く。
「神父様、おはようございます」
「ああ、おはよう」
私服姿の神父が、にっこり微笑む。
「父さん、またこんな所に来て、母さんはもうここにはいないよ」
一人、うな垂れ座る歩の後姿が映し出される。
中島は目を細める。
最初で最後の大舞台を控えている歩に、芝居に専念しろと忠告したのにも拘らず、このセットだけは自分の手で作りたい、と言い張った。
参考にさせてもらうため訪れたチャペルだった。
マリア像を目の前にして、奈緒に対しての不安が一気に噴き出して来た歩は、うな垂れるように、一心で祈りだしたんだ。
この後、遅れて来た中島に声を掛けられ、歩がさびしそうに笑って見せたのを、今でも鮮明に覚えている。
それがどうにも、やりきれない気持ちにさせられてしまったんだった。
「なんて情けねー顔をしてんだ」
と言ったものの、フッと胸を締め付けるものを感じ、中島は目を反らしてしまっていた。
「神父様、本当にごめんなさい。また父さんが訳が分からなくなっちゃったみたい」
「私は大丈夫。それより、病気の方がかなり進行してしまっているようだね」
光一は目を伏せ、ポツリと呟く。
「母さんが死んでから何もかも変わっちゃったんだ」
一心に祈る背中に目をやる神父。
「和寿(かずひさ)は、幸恵ちゃん一筋だったから無理もない」
「父さん、帰るよ」
ここからは、明日歩の二役で演じられていく。
無理やり父親の腕を引っ張る光一は、神父を不満気に見上げる。
「ここに何があるって言うんです。どうして父さんはここに来たがるのか、僕にはさっぱりだ」
教会のステンドグラスがキラキラと光り、マリア像に抱かれる天使が、静かに影を落とす。
家族で楽しく暮らしていた日々。
あまり裕福ではなかったが、母さんはいつもニコニコとして温かな食事を用意してくれていた。
幸福だった。
母さんに見守られながら、父さんと自転車の乗り方を教わる自分の姿は誇らしく、目を瞑っただけで、その光景が浮かんでくる。
僕らはいつでも一緒だった。
市場まで父さんを迎えに行き、三人で手を繋ぎ帰る道。決まって父さんは同じ歌を口ずさんでいた。あの日、母さんが倒れ、全てが一変してしまったんだ。ベッドに横たわる母さんの傍らで、父さんまでがまるで光を失ってしまったように、沈んで行った。
病状はみるみる悪くなってしまった母さんは死に、父さんの中から全ての光が消滅してしまった。
そんなことをぼんやりと考えているうち、光一はうとうととしてしまい、ハッとして目を覚ます。
空になってしまっているベッドを見て、焦って部屋を飛び出して行く。
勢いよく開くドアに、危うくぶつかりそうになる老人、間宮の登場に奈緒は目を細める。
光一はギョッとしながら、
「スイマセン。慌てていたもので」
頭を下げ、そのまま立ち去ろとする光一を老人は慌てて呼び止める・
「ちょっと待たれ」
その声に、光一は思わず振り返る。
目を瞠ってしまっていた。
身の振る舞いも着ているものも、この街には似つかわしいものだった。
「こちらは、松角さんのお宅かのぅ」
そう尋ねられ、光一は驚いた表情で小さく頷く。
「和寿さんは御在宅じゃろうか」
老紳士が重ね尋ねる。
いよいよ光一は訝かる目で、老紳士を見る。
和寿を訪ねて来るものなど、誰一人いなかった。親戚すらいないと聞かされている。和寿の過去は誰も知らない。知っているのはただ一人、母親だけだった。その母親もすでに亡くなっている。
「あなたは……」
光一の表情を読み取った老紳士は、帽子を取り深々と頭を下げる。
そして、にこやかな笑みで言葉を連ねた。
「古い知人で、吉永と言います」
「父は居ません」
老紳士を探るように見つめていた光一は、きっぱりそう言い切る。
「急いでいますので」
踵を返し走り出す光一に、吉永は老人とは思えないほどの大きな声を張り上げた。
「待って下され。今日、どうしても大事な話があって参りました。是非、居場所を教えてはもらえないじゃろか」
そんな言葉に構っている余裕など、光一にはなかった。
糸が切れた風船のように、どこかへ飛んで行ってしまうのではないかという危機感が、いつでも光一に付きまとっていた。
その理由は分からない。
しかし、確実にその恐怖は目の前にまで迫って来ているのは間違いではない確信が、光一にはあった。
説明が出来ないその確信である。
画面いっぱいに広がる海。
どこからか和寿の鼻歌が聞こえ、吉永と光一は風に吹き晒されながら、焦って姿を探す。
二人は岩壁に立ち、何かを思いつめたように和寿は鼻歌を歌って居るのを見つけ、ギョッとなる。
「父さん、こんな所で何をしているんだよ」
光一の声を無視したまま、和寿はじりじりと前へ進み出る。
そんな傍らには、同じように肩で息をしている吉永もいた。
「松角、久しぶりじゃのぅ。元気でやっとったか?」
その声に和寿は歩みを止める。
「儂じゃ儂、覚えておらんか? 吉永じゃ」
困惑するように和寿が吉永を見る。
「父さん、早くこっちに来て、そこは危ないから」
光一が手を伸ばし、和寿の足元から小石がゴロゴロと落ちる。
その場にへたり込む父親を、光一は家へ連れ帰り、薬を飲ませて寝かせると、待たせていた吉永を目の前に、つい深いため息を吐いてしまう。
「父はずっとこんな感じなんです」
寂しそうに笑って話す光一を見て、吉永は目を細める。
「儂は、吉永という者じゃ。わけあって君の父親である和寿さんとは疎遠になっていたのじゃが」
探るように吉永は光一の目を見つめる。
口に運んでいたカップをテーブルに置き、光一は和寿が寝ている部屋に一度目をやってから静かに口を開く。
「どうせ父が、ろくでもないことをしたんでしょ?」
吉永の顔をまともに見ることが出来ず、カップに目を落としたまま光一は話し始めるのだった。
「昔は、あんな父さんじゃなかったんです。いつもにこにこしていて、冗談が好きで、笑いが絶えない家だったんです。それなのに、どうしてこんなことになってしまったんだろう。母さんが死んだのは、僕だって悲しい。だけど、悲しんでばかりはいられないでしょ? それなのに父さんは、まるで言葉を忘れてしまったように何も話さなくなってしまったんです。力強かった腕も細くなっちゃって、信じられます? 港で一、二位を争う力自慢の父親が、日に日に衰えて行くんです。何ですかあと半年の余命って? 僕には理解できないことだらけで……」
光一は辛そうに顔を歪める。
「他に変わったことがなかったかい?」
光一は目を見開く。
吉永に静かに微笑み返され、光一は唇を噛みしめる。
「父さんは、何故かわからないけど、母さんが死んでしまった日から、隣町にある教会に通うようになったんです。ああ、信仰がどうのとかじゃなく、誰もいない教会でステンドグラスを、ただ、じっと見つめているんです。誰が何を聞いても、ただじっとね。仕事はちゃんとしていたし、食事の面倒とかは近所の人たちが手伝ってくれていたから、まぁあれだけ仲が良かった二人だったから、ショックが大きすぎたぐらいにしか考えていなかったんです。けど、父さん、だんだん物忘れがひどくなってきて、僕のことすらわからなくなってしまうこともあって、皆が病院に連れて行った方が良いって言うし、僕のことは沙世の母さんが預かるって言ってくれたんです。すいません。沙世というのは、ここをしばらく行った家の娘で、幼馴染なんです」
それを聞いた吉永は、柔らかな笑みで頷いてみせる。
必然的に顔を赤らめた光一は、テーブルに置かれた自分の手に視線を置き、話を続けた。
「それからしばらく、僕たちは別々に暮らしたんです。父さんの病気は一過性のもので、おそらく母さんを亡くしたショックが大きすぎてそうなったんだろうって、診断が下りました。だから気長に待てば良くなる。そう思っていたんです。けど、何年過ぎても、父さんはこんな調子で、そしたら、父さんにも癌があるって……」
光一はそこまで話して、言葉を詰まらせてしまう。
ずっと黙って話を聞いていた吉永が、カバンから大事そうに何かを取り出すと、テーブルの上に置く。
頭を抱えていた光一は、その音に気が付き、顔を上げる。
「この光は不思議な力があってのぅ」
包んであった布を外しながら言う吉永を、目を大きくし見る光一だった。
「儂と松角を繋いでいるのはこの光。あ奴は全てを儂に託してしまって、何もなくなっていると思っているのじゃろうが、それは違ったのじゃ」
吉永は布を被せ直し、肩を竦める。
「あいつの中に、少しだけ光は残っている。そのわずかな光と共鳴し合い、儂らはまた出会うことが出来た。なぁ、運命とは皮肉なものじゃのぅ。儂がここに来たのも、自分には、残された時間が少ないと分かったからじゃ。あ奴にこの最後の時間をどうやって過ごすべきか、相談するつもりじゃった」
「ではあなたも」
吉永は寂しく微笑む。
「この光を拾ったのは、お互いが、人生という岐路に立たされていた時じゃった」
布越しに光が不気味な音を立てて、明るさを増す。
「君には、聞いてもらっといた方が良いようじゃ」
そして、吉永は遠い昔、二人に起きた話をし始める。
光一は、布越しに光に目が釘付けにされていた。
光が大きくなる。
酔いつぶれる和寿が、大きく映し出される。
若かりし日の歩の姿だった。
奈緒の目からは止めどもない涙があふれ出す。
「オレが何をしたって言うんだ。ふざけんな。女なんて腐るほどいるんだ。お前みたいな女こっちから願い下げだ」
「お兄さん、もうそのくらいにしときなよ」
酒のお替りを頼む和寿を、スナックのママが窘める。
ふらふらと街を彷徨い歩く和寿は、通りすがりの男性に肩がぶつかったと因縁を吹きかけ、揉み合いの喧嘩を始め、敢え無く、ゴミ置き場に投げ捨てられてしまう。
「調子にのんなよ。この酔っ払い」
絡まれた男性が行ってしまうと、和寿は意味不明なことを喚き散らし、暴れまくる。
そして、足元で光るものを見つけ拾い上げた。
「ウワッ。何だこれ」
光が増し、和寿は思わず叫んでしまう。
電話が鳴り響くオフィスの一角、難しい顔をした吉永がドアをノックする。手には何か紙切れを持っていた。
「社長、これは一体どういうことですか?」
「見ての通りだよ。君には下請け会社を立て直しに行ってもらう。君ならこんな事、朝飯前だろ?」
ふてぶてしい笑みに、吉永は腹を立てる。
「私は、今回の人事には納得いきません。なぜ、私が左遷されなければならないのでしょうか? 私が上げた実績は社長も御存知ではありませんか? あなたから、称えられたこともある」
「フン。君は何時まで、そんなくだらない昔の栄光にしがみついているのかね? 君ね、時代は容赦なく進化しているんだよ。そのスピードについて行けない者は、当然、敗者になる! つまり君は、負けたんだよ。私は忙しいんだ出て行きたまえ」
強い口調で言われた吉永は、会社を飛び出して行く。
「ふざけやがって、俺が負け組になるはずがないんだ」
天を仰いだ吉永は、空から何かが落下してくるのを見つけ目で追う。
それは近くにあったゴミ置き場に落ち、不気味な光を放っていた。
光を持つ二人は気が大きくなり、和寿は数人の女性と付き合い自由気ままに過ごしていた。
一方、吉永も辞令を吹き飛ばす勢いで、仕事を熟す。
町で偶然二人はすれ違い、持ち歩いていた光が不気味な音を立て共鳴し始める。
「お互いが、欲しがっている力をこの光は与えてくれた」
現実の吉永が、ため息交じりで言う。
「そんなの、誰も信じませんよ」
絞り出すように言う光一に、吉永は苦笑いをする。
「あの頃は、儂も松角も若かった。欲望だけでこの光の力を借りてしまったんだが、この年歳になって、それじゃいけなかったんじゃないかのぅと、思い始めてのぅ、この残された時間、儂はどう生きていいものか知りたくなってのぅ」
「そんなもの、好き勝手に使えばいい。少なくても僕の父さんはそうしていると思う。何も言わないし、何も覚えていない。記憶がないんだきっと」
投げやりに言う光一に、吉永は光を持たせた。
「年寄りの頼みじゃ。聞いてもらえないかのぅ。どうやって過ごすのが一番なのかその目で、確かめて来てほしい」
断る光一に無理矢理、光を預けたまま、吉永は帰って行ってしまう。
その経緯を全部、恋人の沙世に話し、光一は光を包む布をそっと開けて見せる。
眩しさに目を瞬かせる沙世を見て、凄いだろと得意になって光一は言った。
「ダメよ。これは危険なものなのよ。その老人の話だけじゃ、信憑性が薄すぎるわ。現にあなたのお父さんも、こうしておかしなことになってしまっているじゃない」
「父さんは、病気さ。医者が言っているんだ。あんな爺さんと一緒にしないで欲しい」
「ね、光一。変な気は起こさないで」
「大丈夫だよ。心配性だな沙世は」
ならいいけど、と言いながら沙世は、光一を心配そうに見つめる。
光一は、この光の正体が知りたくてうずうずしていた。
日ごとに躰が弱まって行く父親に、ついに光一は衝動が抑えきれなくなり訪ねてしまう。
光を見せられた和寿は、目を大きく見開き、恐る恐る手を伸ばす。
「いかん。こんなもの。お前には必要がない。すぐに海に捨ててきなさい」
はっきりとした口調で言われた光一は、驚く。
もう何年もまともに喋らなかった父親が、こんなしっかりとした口調で喋るなんて、思いがけないことに動揺はしたものの、尚更好奇心を煽られてしまった光一だった。
「頼まれたんだ。あの吉永っていう人に」
「それを手にしたものは、苦しい思いに晒される」
ベッドから必死で起き上がり言う父親に、圧倒された光一は、一旦は光を引き出しにしまい込むが……。
――数日後、フラフラとした足取りで和寿が教会へ入って行く。
ステンドグラスに光が当たり、色とりどりの光を床に落としている。
椅子に座りしばらく眺めていた和寿が、涙を流す。
「あなたは罪深い。戦いが終わることなどないということを、オレに教えてくれなかった。マリア、教えてくれ。オレが出した答えは正しかったのか。あいつが時折見せた悲しい目、あれは何だったんだ? オレはあんなもの手にするべきじゃなかったんだ」
床に七色の光を落としたマリア像が、静かに微笑む。
透き通るような青空が一面に広がり、神父の祈りの声に喪服を着た人々がハンカチで目がしらを押さえ、和寿との別れを済ませ互いの肩を抱き合い慰め合う。
一人ステンドグラスを見上げて座っている光一を見つけた沙世が、静かに隣に座る。
「逝っちゃったね」
沙世に言われ、光一はああと頷く。
夜明けを待って、光一は誰にも何も言わずに町を抜け出す。
父親は死ぬ間際まで、あの光を捨てろと言い続けていた。あの老人もあれから一度も姿を見せずにいた。
光一は、毎日こっそりこの光を眺めていたが、だんだんこの町を出て大きなことを成し遂げたいという衝動に駆られ出していた。急に大きなことを言い始めた光一に、沙世は眉間に皺を寄せ、再三忠告したが、ついに昨夜、おまえには関係ない。ぼくにはぼくの生き方がある。と言って止める手を振り払ってしまった。
上京した光一を最初に待ち構えていたのは、舘野という男だった。
吉永を訪ね歩いているうちに一人の男と繋がり、それが舘野だった。
舘野は調子がいい男で、住むところと仕事を世話してくれ、何かと光一に便宜を払ってくれるようになる。
「どうして、そんな親切にして下さるんです?」
「いや、理由はないけど。吉永さんにはいろいろよくしてもらったから。それに困っている人を見捨てるような真似、私には出来ないんでね」
胡散臭さをぷんぷん臭わせているが、光一はその親切に甘んじてしまう。
「まぁかわいい坊や」
舘野に連れて行かれた店のママが、目を輝かせる。
「こいつ、吉永さんの知り合いらしいんだけど、しばらくここで使ってやってくれ。よろしく頼むわ」
「ママ、この子、私が可愛がってあげたい」
「陽子はすぐに若い男を食べたがる」
「だって、この子きっと童貞よ」
「ま、上京したてだから免疫ないんで、お手柔らかに頼むわ」
光一はボーイとして働きだす。
舘野に頼まれ、人にあったり、物を預けに行ったりすることが何度かあったが、一端の大人になった気になっていた光一は、目つきの悪い男に呼び止められる。
男は警察を名乗り、光一は隙を見計らって逃げ出す。何がどうなっているのか分からなかった。
一旦、部屋に戻った光一を追っ手はすぐにやって来た。
自分が、何から逃げているのか分からずにいた。
途中、老婆にぶつかってしまい、光一はひたすらに謝る。
「正樹。正樹でしょ。そんなに慌ててどうしたの?」
「おばあちゃん、ぼく正樹じゃない。ぼくは」
追手が迫って来るのが見え、光一はすかさず老婆を利用することを考える。
「ばあちゃん、家はどこ? ぼくが送るよ」
すぐ近くのアパートを指さされ、光一は咄嗟的にその老婆を負ぶって部屋へ飛び込む。
「正樹、もう悪さはしないでって、あれほど言ったのに」
老婆は光一の上着ポケットにお金をねじり込む。
「これであの人たちに謝ってきなさい」
「おばあさん、違うんだ。これは受け取れない」
光一はお金を突き返し、引き留める老婆を背に走り出す。
カバンの中、光が異様な音を立てていた。
お金を引き出そうと銀行に入った光一は、目を見張る。
店のママに冗談で進められた株が、高騰し始めていた。
光が大きくなり、光一は全額引きだし、証券会社へ向かう。
売り買いは、笑いが止まらないくらい上手く行っていた。
ホテル暮らしをし出した光一の下に、一人の女性が現れる。
「私の心臓、返してください」
唐突に切り出された光一は、一笑してから手で追い払う。
翌日も、マリアと名乗る女は光一の前に現れた。
「その光は私の心臓です。それを持つと言うことは」
「ええいうるさい。あっちに行け。警察を呼ぶぞ」
光一はシャワーを浴びに浴室に入って行く。
鏡の中、再びマリアが現れる。
粉々になった鏡を見下ろした光一は血だらけになった拳を垂れさげながら、泣き崩れる。
幻覚が付きまとうようになっていた。
ふらふらになった光一は、故郷に逃げ帰り、そこで沙世と孝信が楽しそうに話しているのを目撃してしまう。
「おまえ、ぼくがいない内に沙世に手を出しやがって」
いきなり飛び掛かられた孝信は、光一を突っぱね逃げ去る。
「いつ、こっちに戻ったの?」
沙世の言葉に耳を貸さない光一は、嫉妬の目を向ける。
「あいつとはいつから何だ。もう寝ちまったのかよ」
「何を言っているの? 孝信とはここで偶然会ったから世間話をしていただけよ。あなたこそ、何の連絡もしないで、他に女が出来たんじゃないの」
キッと睨む光一を、沙世も負けじと睨み返す。
「ああ、良い女は沢山いたよ。ぼくみたいな優秀な男には、掃いて捨てるほど女が付いて来る」
「それは良かったわね。だったらその人たちとよろしくすればいいじゃない。私がどこで、誰と話したって何とも思わないでしょ」
「ああ思わないね。だけど、お前は僕のものだ。誰にも渡さない」
「あなた、狂っているわ。私はあなたの所有物じゃないのよ」
沙世は怒って行ってしまい。一人取り残された光一に後悔の念が、一気に押し寄せてくる。
「違うんだ。そんなことが言いたかったんじゃないんだ。ぼくは、ぼくは……」
その夜、光一はナイフを隠し持ち、沙世に会いに出かける。
光一に呼び出された沙世は、不機嫌な顔で何と言う。
「さっきは悪かった」
前を歩いていた光一が、振り返る。
沙世は光一の手に光るものを見つけ、身体を固くする。
「沙世、ぼくと一緒に死んでくれ。孝信なんかに渡さない。沙世はぼくの隣に居るのが一番ふさわしいんだ」
「光一、止めて。私と孝信は本当に何でもないの。お願い。信じて」
「っ沙世」
ぐったり倒れ込む沙世を抱きかかえ、光一は我を取り戻す。
「ち、違う。ぼくは、ぼくは……」
フラフラと立ち上がり、後退りをする光一は誰かにぶつかり、目を見開く。
ぼんやりと月明りに照らされた顔は、吉永だった。
「わしの果たせなかったものは、何だったか見つけてくれたか?」
光一は、虚ろな目で吉永を見上げる。
「儂もいろいろして来たがのう」
そして光一の血に汚れた手を見て、目を細める。
「殺してしまいたいほどに、儂は誰かを愛したことなどなかった」
「殺して……、殺していいものなんかない」
泣き崩れる光一。
吉永は目を見開く。
「愛は、愛はそんなに醜いものじゃない。父さんが護りたかったのは、大切な人の笑顔で束縛じゃなかった」
「だが、手放したくはなかったから、おまえは自らの手で殺めてしまったんだろう?」
「ぼくが、ぼくが馬鹿だったんだ。彼女が望む幸せなら……、祝うべきだった」
頭を抱え込む光一。
吉永は遠くをじっと見ている。
「儂もな、結局は戦いに戦い抜いてきたがのぅ、最後にどうしても勝てなかったものが、一つだけある」
光一は、吉永をじっと見詰め返す。
「孤独じゃよ。消しても消しても込み上げてくる闇は、どんな栄光があってもどんな大金があっても消せぬかった」
光一は、肩を震わせて泣き始める。
吉永はそんな光一の肩を抱く。
「おまえさんの父親は大したものだ。それをすぐに見破り、おまえ達家族のためにだけ生きることを選んだ。儂も、儂もな、もっと早く気が付くべきだった。あの光の向こうには得体が知れない厄介なものが待っていたかも知れんが、それに飛び込む勇気を持つことが大切さを」
死んだはずの沙世がぼんやりと光に照らされ出す。
「これは私たちの希望の光です。憎しみも悲しみも喜びもすべてがこの光が教えてくれる。生きろと輝く」
沙世がにっこり微笑む。
吉永はふっと笑みを漏らすと、光一の背中を押した。
「この光はな、おまえの父親が儂に託したものだ。正義に満ち溢れ、友を思い愛に生きた勇者の光に濁りはない」
驚く光一に老人は頷いてみせる。
「すまなかった」
吉永はそう言い残し、その場に朽ち果てる。
「この光は私の心臓です。この光を手にした者は戦い続けなければなりません……」
マリアの声が光一の頭の中に響く。
吉永の懐から光が天に向かって伸びていく。
「光の向こうには何が見える? 喜び? 悲しみ? 憎しみ? それとも……。すべてに打ち勝った時、何かが誕生する。難しいことじゃない。誰かを思いやる心。感謝する気持ち。それが力になり光を放つ。その先にはおまえにしか出せない答えがある。戦うことを恐れるな。さぁ、あの光の彼方へ……、行くがいい」
大きな夕陽に浮かぶシルエット。
和寿が振り返り微笑む。
そしてその光の中に、鼻歌を歌った和寿は消えていく。
夢?
ハッとして起き上がった光一は、目を擦る。
葬儀会場を後にする沙世と光一。
「あの吉永って言う人、自分の死を誰かに看取って欲しかったのね」
立ち止り煙突を見上げ、沙世はため息をつく。
光一は無言のまま、沙世に促されるように空に消えて行く煙を見上げる。
「私、あなたのお父さんに頼まれていたの。あいつはいつか光の虜になって、この町を飛び出してしまうだろうけど、待っていて欲しいって」
「父さんが?」
コクンと頷いた沙世が、ちょこんと首を傾ける。
「あの光は人の欲望の塊なんですって。その人の奥底に沈んでいるものをあぶりだされてしまうけど、それはやがて濾過されるはずだから、あいつなら乗り越えられるとオレは信じていると、お父様が言っていたわ」
「ぼくには何一つ言わなかった」
「仕方ないわ。お父さんも苦しんでいたのよ。一度はあの光を手にしてしまったのよ。微かに自分の中に残る欲望が、また目を覚ますんじゃないかって、怯えていたのよ。お母様があんな早くに亡くなってしまったのも、あの光が何らかの影響を及ぼしていたんじゃないかと、考えていたみたいだし」
ザクザクと真新しい雪の上に、足跡を付けて二人は歩いて行く。
沙世は教会の扉を開く。
二人して中に入って行くと、光が差し込むステンドグラスを見上げた。
「この絵」
光一が呟く。
今まで気が付かなかったけど、あの夢に何度も出て来たマリアと言う人に似ている。
「神様っているのかな」
沙世が呟く。
そうか。父さんはここに答えを探しに来ていたのか……。
光一は沙世の手を握り、行こうと微笑む。
沙世がコクリと頷き、二人が出て行ったあと、ステンドグラスは燦然と光を放つ。
そしてモノクロの思い出のシーンが、静かなバラードに合わせて流れる。
――光の彼方、あなたは何を見つけますか?
懐かしい日々を綴るようにエンディングロールと共に映し出されて行く。
それは細やかな幸せの日々。
本当の家族写真を使いたいと、島根が言い出した時には、明日歩と奈緒はかなり困惑した。明日歩はともかく、奈緒は一般人だと申し出る二人に、根気よく説得を図ったのは、中島だった。
「これは中田があなたへ残したラブレター。他の誰かにあてこむなんて、俺には考えられない」
強い眼差しに、奈緒は押されて承諾をしてしまった。
「明日歩、ありがとう」
目を赤くした奈緒に頭を丁寧に下げられ、照れ笑いで明日歩は、出来栄えはどうと尋ねる。
父さんが母さんに残して逝ったラブレター。ありきたりの言葉だけど、オレには図りしれない二人だけの時間。そして、この人たちの思い。それをだいの大人たちが寄ってたかって仕上げたこの映画は、きっと一生の宝物になっちまうんだろうな。聞かなくても分かっている答えに、また頬を緩ませる。
――中田歩。あんた、いったい何もんだよ。
扉を一歩外に出ると、その眩しさに明日歩は目を細める。
中島が用意した記者会見。
「一介の駆け出し新人にそんなの必要ないんじゃねーの」
そう言う明日歩の言葉を無視して、良いから早く行って来いと背中を押す。よろめきながら、明日歩は後ろを振り返る。すっかり禿げ上がった頭に、ニット帽をかぶった野村が、シッシッと手を払ってみせる。その横で、ガンバと胸の前でポーズを取る木綿子。奈緒に関しては、ただ泣くばかりで、その肩を抱くであろう歩の写真を明日歩に見せ、間宮がにっこりと微笑む。
だからあの日と同じに、少しだけ勇気を振り絞り、オレは前へと進み出られる。
こんな日が来るなんて、想像もできなかったあの日。
明日歩は目を細め、遠い日々に思いを馳せ、重い扉を押し開けた。
エピローグ
――日差しが柔らかく、花壇に植えられているインパチェスが揺れている。
奈緒が座る車椅子を、孫の司が押して行く。
庭で倒れて救急車で運ばれてから、奈緒はずっと同じ景色を何か月も見ていた。こうして外に出られるのも久しぶりである。
「司は何歳になったの?」
「10歳だよ」
奈緒は最近、同じことをよく訊く。
「そう」
嬉しそうに頷いて微笑む奈緒。
あずさは、三人目の子がお腹に入っている。今、検診を受けているところだ。今日は珍しく明日歩も一緒に来ていたが、医師に大事な話があると呼ばれて行ってしまっている。
病室に二人きりになると、奈緒は司に外へ連れ出すよう頼んだ。
「奈緒ちゃん、もう寒いから帰ろう」
心細くなった司が言うと、奈緒はか細い声で、あと少しだけと頼む。
ヒラヒラとモンシロチョウが舞い、陽だまりが暖かな午後だった。
「司に、おばあちゃん、お願いがあるんだけどな。聞いてくれる?」
息をするのも苦しそうな奈緒が、にっこりと微笑む。
そして、司は何度も大きく首を振る。ボロボロと大粒の涙がこぼしながら、何度も何度も、そんなの嫌だーと叫んだ。
――それから間もなく、奈緒は、静かに眠るように息を引き取った。
チリン。
軒下に吊るしたままの風鈴が鳴る。
明日歩はゴロリと躰を横たえ、目を閉じた。
いつか大切に思えるその日が来る。その日のためにと、歩がはしゃいだ声で言っていた。笑えって。母さんのレースだらけのピンクのワンピースも、父さんが纏う甲冑も気に入らずに、そっぽを向いてしまったあの日。
どうして笑わなかったんだろう? 簡単なことだったのに。父さんの言うとおりだ。こんなに恋しく思う日が来るなんて思わなかった。
オレはバカだ。
「パパ」
明日歩は、司の声で起き上がる。
「おお、着替えて来たか。みんなは?」
「未来(みく)がぐずって仕方がないから、少し公園で遊ばせてから来るって」
「そうか」
「パパ、大丈夫?」
ええ? と苦笑しながら、何でだと訊く明日歩に、司が今にも泣きそうな顔で答える。
「奈緒ちゃんが、明日歩は別れが苦手だから傍にいてあげてねって、言ってたから」
明日歩は、奈緒が横たわっている方を見る。
「パパ、奈緒ちゃんがね、仏壇に、お手紙を入れておいたから読んでねって言ってた」
明日歩は、急いで仏壇の引き出しを開ける。
線香やろうそくがしまわれているその下に、忍ばせるように薄いピンク色の封筒は置かれていた。
いつの間に……。
☆
『明日歩へ』
黒い文字で書くのは、堅苦しくて寂しくて仕方がないので、私の好きな色で書きます。
あなたが生まれてくれたことを、私は感謝しています。
本当よ。
あなたが居なければ、こんな幸せはなかったでしょう。
あなたが生まれてから、毎日が戦争で、毎日が楽しくって、子育てって大変だなという幸せがあったから、私は強くなれた気がするの。色々ありすぎて、くたくただったけどね。
それでね、歩そっくりのあなたが、私のために変身してくれたあの日、私も変身することを決めたのよ。
知らなかったでしょう。
もう泣かないって。
どんなことがあっても笑っているお母さんでいようって。
そしてね、護られてばかりではない強いヒロインになるって決心したのよ。結構頑張ったのよ。
私には歩が残してくれたたくさんの愛がある。思い出がある。だから大丈夫大丈夫って、何度も自分に言い聞かせて、頼りないお母さんでごめんね。いつも心配かけていたわね。
いつ頃からだったかしら、あなたが私に何も文句を言わなくなったのは。
歩と同じ目で私を見てくれるようになったのは。
たくさんの愛をありがとう。
あなたのその優しさが、その笑顔が、すべてが私の宝物。
いつかまたあなたに会えるのなら、私はまたあなたのお母さんになりたい。
ヒーロー役させちゃってごめんね。今までご苦労様。
私は、幸せものね。生涯で二人のヒーローに出会えるなんて。
もういいの。もう大丈夫。
今日からは、あずささんたちのためにだけのヒーローになって下さい。
これから私が行く場所には、歩が待っていてくれる。
ねぇ明日歩、ずっとずっとこの日が来るのを待っていたのよ。
歩はどんな顔をして迎えてくれるのかしら。
私、泣いちゃうかも。
遠くで見守っているからね。
本当に本当に今日までありがとう。
二人のヒーローに愛されたヒロインより
……母さん、知っていたんだ。
奈緒らしいピンク色の便箋で縁はレースに模られてある。水色の丸まった文字。
明日歩は、天井を仰ぎ見る。
そんなカッコいいものじゃなかった。
本当は、あんなことした自分が、少し恥ずかしく思っていたんだ。こんなことをして、何の意味があるんだって。父さんが居ない時は、オレが護るっていうのが父さんとの約束だった。そんなのとっくに時効だって思いつつも、どうしても母さんが病気だって認めたくはなかった。
あの日思ったんだ。
結局、オレは父さんには敵わないって。だってそうだろ、オレが何を言っても駄目だったのに、立ち直らせたのはやっぱり父さんで……。
でも、そうじゃなかったんだ。
「あのね、奈緒ちゃんに僕、話、いっぱい聞いたよ」
そう言う司を、明日歩は力いっぱい抱きしめる。
「司、あのね、私は、もう少しで大切な人に、会いに行かなければならないの。その人は、ずっと星になって、私を待ち続けていてくれている人でね、やっと、その人に会いに行けるの。少しだけ寂しくなるけど、とても幸せの。だから、泣かなくていいのよ。会えなくなる前に、言っておかなくっちゃね。今まで沢山の愛をありがとう。明日歩はね、きっと言葉にすると寂しくって怒るから、手紙を書いておいたから。もし、私が、二度と目を覚まさなくなったら、渡してあげてね。司は良い子ね。明日歩そっくりの目をしている」
蝶がどこかへ飛んで行ってしまい、奈緒が微笑む。
「奈緒ちゃんの大切な人って、おじいちゃん?」
「ああ」
明日歩は頷くのが、精一杯だった
誰にも変わりは出来ない、母さんを護るたった一人のヒーロー。
あずさが4歳になったばかりの未来を連れて、庭に入ってくる。義父母も一緒だ。
明日歩は何かを思いついたように、二階へ駆け上がった。
この部屋には秘密基地がある。父さんと二人だけの秘密の場所だ。
天井を外す。
ヒーローグッズやビデオに紛れて、歩が書いたラブレターを忍ばせてある三つ揃いのスーツ。どれもこれも馬鹿げていて、嫌いだった。
なのにクソッ。愛おしくて堪らない。
やっぱり……、これも気が付いていたんだ。きちんと虫干しされている。
明日歩は、歩の三つ揃いに着替え、内ポケットに手を突っ込む。
「えへへ。初めて書いたんだラブレター。奈緒、どんな顔をするかな。喜んでくれるかな? オレの字、下手だけど読めるかな? 明日歩、お前ちょっと清書してくんないかな?」
「ばかじゃねーの。そんなのばれるし、母さんに伝わんないだろう」
「そうだよな。うんそうだよな。奈緒はオレのことなら何でも分かっちゃうからな。下手な字も何とか解読してくれるか」
「何なら読み上げてあげれば?」
「おお明日歩天才。その手があった」
子供みたいにはしゃぎやがって。
ラブレターをそっと開いてみる。
奈緒が一番好きだ、愛しているよ。これからもよろしく。
こんなのいつも言っていたじゃないか。おかしくて涙が出て来た。
「……相変わらずバカだな父さんは。な、母さん」
愛している文字が滲んでいる。
あなたたちの息子で良かった。
明日歩はもう一度部屋を見まわし、マントを掴んだ。
明日歩は、庭にカメラを引っ張り出した。
歩が使っていたものだ。
孝文が、フィルムを買ってきたよと、手を振ってやって来る。
これで全員集合だ。
年老いたあずさの両親、ずんぐりとした姉思いの弟、孝文。あずさに抱かれた未来は甘ったれで頬に涙の跡が残っている。司は、父さん譲りの頑固者だ。泣きそうな顔でカメラを見ている。
母さんが、大好きな人に会いに行ける大事な記念日。
歩がしたように笑って笑ってと、明日歩は声を張り上げる。そして、誰一人かけても成り立たない大切な家族写真を何枚も撮った。
いつかこの日が愛しく思えるその日のために、母さんと父さんの再会のためにみんなで笑った。
父さんが言う通り、あの日、世界で一番優しい風は確かに吹いたんだ。
二度と笑えないと思った母さんが、笑ってくれた。微かに涙の跡を残して。
上着の袖を通した時、もしかしたらヒーローになるって、こういうことなのかなって、何となく分ったような気がした。カッコつけでも何でもない。自分に勇気を持たせるため、変身って言ったんだ。全部自分の為だった。
庭に一陣の風が吹き抜けて行く。ふんわりと、甘い香りが広がり、明日歩の背中でマントが翻る。
「あずさ、ここに住もうか?」
「そうね。素敵ね」
明日歩は、あずさと手を繋ぐ。
司と未来がふざけ合い、笑い声をあげている。
「あなたはあなたらしく、家族を護ればいいのよ。ここは、私一人でも守れる。この家は、そういう家なの」
結婚式の日、奈緒が言った言葉だ。
それでも一人にしておけないという明日歩に、奈緒は優しく微笑み、一人じゃないわよと、仏壇の上で変わらない笑みを浮かべる歩に目をやる。
「どんなに離れていたって、歩は私のことを護ってくれている。歩はそういう人なの。だから寂しくはないわ。あなたはあなたの人生を歩めばいいのよ。私は大丈夫」
……母さん、もういいよね。オレ、ここに戻って来ても。
風鈴が、チリンと音を鳴らす。
今度はオレが築く番だ。大切なこの場所には、いつでも愛があふれている。ヒーローの花が咲く庭と、父さんと母さんの思い出。これからの未来。
「パパ、ボク、ヒーローになる」
「あたちも」
≪FIN.≫
Promise。~僕がヒーローになった日~
春になるたび、匂って来る沈丁花。この時期になると、無性に読み返したくなるのがこの作品です。愛って、何なんでしょうね。親子って何でしょうね。反発していたはずなのに、気が付くと同じような生き方をしてしまっているようなこと、ありませんか? こんな恋が出来たらいいなと思い描いて書いた作品です。いわゆる自己満足品です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

