
盟約紳士 Om.
スカイ・ソロウ・ティア

どうかこの音が君に届くように。
そんなことをずっとずっと願ってきた。
でも僕は知っている。
君がとうの昔に居なくなったことを。
届かない願いってどこへ行くんだろう。
例えばピアノの音色みたいに、
残像を残して消えてしまえばいいのに……。
僕が生まれたのは、オーストリアの片田舎。音楽家が育った町だ。そこで僕は10歳まで過ごした。
幼い僕は、白と黒の色しか知らなかった。すなわち、ピアノの色だ。封建的な僕の父親は、息子をピアニストにすることに全精力を傾けていた。僕の指先は、ずっと鍵盤の上にあったと思う。生まれる前から弾いていたんじゃないかと思うくらい、僕はピアノを叩き込まれた。
ピアノの才能は、多分無かったと思う。
それでも僕が、一応はピアノ弾きという体裁をたてて教会で演奏できたのは、ひとえに父の熱意(ほとんど狂気だ)と、睡眠時間よりも長い、ピアノと向き合った時間のお陰だろう。
教会で弾くようになって2年、12歳のときに来なくていいチャンスが訪れた。
たまたま教会に来ていたベルリーニという実業家が、僕の腕に目を留めて、僕をフランスの知人に紹介した。
小さいのによく指が動くと、ベルリーニとその知人――後の僕の師匠、サン先生だ――に褒められた。嬉しくはなかった。ベルリーニは僕にフランスに留学するべきだと勧めた。多少は援助してくれると言った。そんなことは望んでいなかった。
ただ、父は乗り気だった。手放しで喜んだ。僕を褒めはしなかった。自分の指導が良かったのだ、自分は間違っていなかったのだと悦に入った。気に入らなかった。
僕はサン先生に師事することになった。
サン先生は、ピアノの世界ではさほど有名ではなかったけれど、色んなコネを持っている人だった。
父はサン先生を貶した。あんなヤツ、ピアノの腕も下手なくせに、単なるビジネスマンだと。あいつの持っているコネを使ってお前は上に上がればいいと言った。サン先生の前ではへりくだる父を、僕は心の中で軽蔑していた。
サン先生はピアノを教えていた。本気で育てている弟子は僕一人だったけれど、金持ちの娘や息子に、週に2回ピアノのレッスンをしていた。サン先生は大変な褒め上手で、金持ちの親子はサン先生を好いた。というより、彼の褒め言葉を好いた。というわけで、サン先生は金持ち連中から人気があった。
僕は金持ちではない。田舎者で貧乏者だ。金持ちというのはあんまり好きではない。サン先生に付いて行った先の、僕と同い年くらいの子どもたちを、好きになれなかった。向こうも僕を田舎者だと嫌っていたからお相子だ。
14歳になったばかりの、6月18日だった。
サン先生は新しい生徒を教えに行くのだと言った。君も付いて来なさいと。また金持ちの子どもの下手なピアノを聴かなきゃならないと思うと苦痛だったが、素直に従った。
セレナ=クラウンというのが、今回サン先生が指導する新しい生徒だった。
セレナはピアノを弾くのは初めてだった。買ってもらったばかりのピアノの椅子に座って、緊張しながらサン先生を見ていた。
いつもの通り、サン先生は上手に生徒を褒めた。僕からすれば雑音だけれど、サン先生はそれを天使の音色だと言った。
小一時間のレッスンのあと、セレナは僕にピアノを弾くのかと訊いた。僕は弾くと答えた。セレナはにっこり笑って言った。
「じゃあ今度のレッスンは、貴方が教えて」
*
新しい仕事が増えた。
僕に生徒ができたのだ。
セレナ=クラウン 13歳。
フランスの大手デザイナーの箱入り娘。
週に2回、僕はセレナの先生になる。
「ねえ、シャーロック。今度はショパンを弾いてほしいわ」
セレナはピアノの椅子から下りる。
「君はショパンが弾けるの?」僕は呆れて言った。「ショパンを練習するというなら、僕が弾いて教えるけど、演奏のために弾けというのなら断るよ」
セレナは両手を組んで僕を見つめる。
「ねえ、お願い。私、シャーロックのピアノが好きなの。ショパンを聴いたら真面目に練習するわ」
セレナはいつも、僕にピアノを弾くよう〝お願い〟をした。セレナは、ピアノを弾くのはあまり好んでいないようだったけれど、ピアノを聴くことは好んだ。
僕はショパンを弾いた。セレナが好んだ『子犬のワルツ』を。セレナは耳を澄まして聴いている。実は、僕のピアノを聴くセレナの表情を、僕は密かに好んで盗み見ていた。
セレナが講師に僕を指名して、サン先生は驚いた。何かの間違いだと思った。でもセレナは僕がいいと譲らなかった。僕に直接は言わなかったけど、サン先生は悔しがっていた。
「だっておじさんって怖いんだもの」
セレナは僕を指名した理由をそう言った。
「シャーロックは親しみが湧いて良いわ。こうして気軽に話ができるもの。私、大人って嫌いなの」
「でも僕らは大人になるよ」
「ならないわ」セレナはきっぱりと言った。「あんな嫌な大人には絶対ならないの。私、子どものまま大きくなりたい」
大抵の子どもは、早く大人になりたいと言うものなのに、セレナは反対のことを言った。セレナは変わった子だった。田舎者で貧乏な僕を馬鹿にしなかった。
「金持ちって嫌いなの」
自分も金持ちのくせにそう言った。
セレナ=クラウンとの日々はそうして続いた。セレナがピアノを弾くよりも、僕が弾く時間の方が、たぶん長かった。
「シャーロックはピアニストになるの?」
モーツァルトを弾いた後で、セレナが僕に訊いた。
「さあ? 父親はそう望んでいるよ」
「私はシャーロックの望みを訊いたのよ。ピアニストになりたいの?」
「なりたくないね」僕は正直に言った。見破られそうで、セレナに嘘をつけなかった。「ピアノが好きなわけじゃない。商売道具なんだよ。僕は学校にも行ってないし、他に技術があるわけじゃない。ピアノしか持ってないんだ」
「もったいないわ、シャーロック。貴方はとても繊細で綺麗な音を出すのに。ピアノを好きになれば、もっともっと上達するわ」
僕はピアノを見た。
白と黒の単調な色。とっくに見飽きたもの。「好きになれそうにないな。本当は見るのも嫌なんだ」
「なれるわ。大丈夫」
セレナはにっこり笑って言った。
「どうして言いきれるの?」
「シャーロック、本当は音楽が好きなのよ。多分ね……枷をとって自由に演奏できれば、世界中の人を魅了できるわ」
いつになく熱弁をふるって、セレナは僕に近付いた。ピアノにしか触れたことのなかった僕の指に、セレナの指が触れた。
「ねえ、シャーロック。貴方に足りないのは運だわ。ピアノを好きになるきっかけが、大舞台に上がるチャンスが、掴めていないだけなの。貴方は世界一のピアニストになる。というか、私がそうなって欲しいと願ってるのね」
セレナは僕の手を握って、僕らは手を繋いだみたいになった。
にっこりと、セレナは笑った。
「シャーロック。私、貴方が大好きよ。だからずっと、ずっと私と居てね」
*
また、願ってもいない転機が訪れた。
サン先生が、僕をイギリスにやると言う。そこで新しい師匠について音楽を学び、一年後のコンクールを受けろと言う。そのコンクールは若手の登竜門で、優勝すればピアニストとしての道が約束されていた。
イギリスへの渡航費用を出したのは父だった。彼はせっせと働いて、僕のために金を稼いだ。いや、僕のためじゃない。『ピアニストの父』として、周囲からの称賛を得るための資金だった。
イギリスへ渡ることをセレナに話した。セレナは大喜びだった。飛び回って僕を祝福した。
「コンクールで優勝すれば、ピアニストね! 応援してるわ。何か私に出来ることはないかしら?」
「残念ながらないよ、セレナ。ここで結果を待っていて」
「一年後のコンクールね。楽しみにしてるわ。私、絶対に聴きに行く」
喜ぶセレナに、言えなかった。僕が優勝なんて出来ないことを。
この世は金が支配する世界。音楽界も然り。上位入賞するのは、金持ちの子どもたちばかり。僕みたいな貧乏人は、審査員に贈るものはない。
ピアノの技術の優劣を決める明確な基準は無い。かけっこみたいに、目に見えて勝敗が出るわけではない。優劣を決めるのは審査員の心のみだ。その審査員の心を決めるのは、残念ながらピアノの音色じゃない。
そんなことをセレナに言えない。彼女に醜いものなど見せたくなかった。音楽は綺麗なものだと信じていてほしかった。
船が出港する日。12月の寒い日だったのを覚えている。
見送りに来ると言っていたけれど、セレナの姿は見当たらなかった。セレナに言おうと思っていたことがあったけれど、それは一年後まで胸に仕舞うことにした。
優勝なんてできない。そんなことはわかっている。胸を張って堂々とセレナに会うことは出来ないだろう。
船が出港した。
汽笛を鳴らし、海原を進む。
僕はイギリスへ向かう。大嫌いな音楽を奏でに行く。
きっと一年後。またフランスへ戻って来るんだと、一年後の自分を想像しながら。
でも。
僕はコンクールで優勝するどころか、演奏することも、出場することすら出来なかった。
僕は、サン先生の知人のヴェロッティ先生の指導を受けた。厳格で、にこりともしない人だ。だけど、ピアノへの情熱を持っている人。僕はその情熱が重苦しかった。
嫌々ながらコンクール用の面白くもない曲を弾く日々。セレナと過ごしたときの何倍も長い時間に感じられた。
コンクールの一ヶ月前。
父が逮捕されたと報せが入った。
*
貧乏人であることを恥じている人だった。
音楽は、金持ちのやるものだった。楽器は高価で、コンクールに出るには金が要る。
父は音楽家になりたがった。でも家は貧しかった。フラストレーションは息子にぶつけられた。僕は父の身代わりになった。
父は無理してピアノを買い与えた。僕のためと言っていたが自分のためだ。
父は無理してイギリスへの渡航費用を貯めた。息子の名誉の欠片を貰うためだ。
毎日毎日、あくせくと働いた。元来、父は怠け者の性質がある。そんな人が寝る間を惜しんで働くなんて無理だったのだ。不満は募る。それを解消するために、彼は手を出した。
父の逮捕容疑は麻薬所持だった。
逮捕されたとき、彼は軽い中毒だった。警察の病院に入院するという。
貧乏人の上に、父が逮捕されたとあって、コンクールへ出場することは不可能となった。何事にも厳格なヴェロッティ先生は僕との師弟関係を解消した。
一瞬で、僕にはなんにも無くなった。
唯一の仕事道具だったピアノに触れなくなり、僕は異国で一人ぼっちになった。
犯罪者の息子が、ピアニストなんてなれるわけがない。眩いスポットライトの下に立てるわけがない。
ピアノを失って、喪失感に襲われた。
僕にはピアノしかなかった。それがどれだけ嫌いなものであっても、それしかなかった。あの白と黒の鍵盤に、もう触れない。
煙突掃除夫になった。僕には学もなく、なんとか字が読める程度だった。家もない。住み込みで働ける煙突掃除になるしか方法がなかった。
掃除道具は僕の手に合わなかった。僕の手はブラシを握るためにあるんじゃなかったはずだ。ショパンが、モーツァルトが懐かしかった。
イギリスへ来て2年が経った。
煙突に登って思い出すのは、セレナのことだった。
あのフランスでの日々。彼女はもうすぐ16歳になる。元気で過ごしているだろうか。僕がピアニストになることを、自分の夢にしていた。それは父と同じだったけど、全然違うことのように思えた。
セレナ。どうしているだろう。天真爛漫な子だ、僕のことなんて忘れているかもしれない。
イギリスへ来て3年半が経った。
僕は17歳になった。もう何年もピアノを弾いていない。
イギリス人の言葉にももう慣れた。煙突掃除も前ほど苦ではなくなった。貧乏な生活には、元々慣れていたから、それは全然構わない。
ただ、僕の胸は空っぽだった。
でも何かを渇望していた。
夜ごと思い出すのはセレナのことだ。
フランスの箱入り娘。どうしているだろう。ずっと居てねと言っていたのに、あんなにも明るく僕を送り出したのは何故? 僕は、セレナは泣くんだと思っていた。なのに今、僕が泣きたくなっている。
言いたかったんだ。必ず戻って来るから待っててと。あの日、君に会えていたなら――
〝盟約。結ぶ?〟
声が聴こえた。
煙突掃除の帰りだった。夜道は真っ暗で、誰が潜んでいてもわからない、レンガの路地。
でもその声は、僕の内側から聴こえた気がした。
「……Pledge(盟約)?」
〝そう。盟約。貴方が私を受け入れるというのなら、貴方は私を見ることが出来る〟
「それってどういう……?」
〝Give and takeってことよ。Child(ぼうや)〟
ハスキーな女の声だった。
僕は答えた。
「結ぶよ。盟約」
頬を撫でられた、と思った。その指先が見えた気がした。
ふと気付くと、目の前に女性が立っていた。
スタイルのいい女性だ。パイプ煙草を吸って、天を仰いでいる。
紫煙が空に昇っていった。
「Child(ぼうや)はやめてね」
僕が言うと、女はこっちを見た。
「名前は?」
「シャーロック=リフィル」
「ソネット。よろしく、シャーロック少年」
僕は、ソネットの盟約者になった。
*
ソネットは誰の目にも映らない。彼女のハスキーな声も(歌ったらいいのにと思う)、彼女が吸うパイプ煙草の紫煙も、僕以外の人間には見えない。
煙突掃除の契約主から与えられた狭い部屋で、僕とソネットは共同生活を始めた。
「それ、そんなに美味しいの?」
窓辺に腰掛けてパイプ煙草を吸うソネットに、僕は声をかけた。
ソネットはパイプ煙草をくるりと回して、持ち手を僕に向けた。
「吸ってみたら?」
金色の長いパイプ。恐る恐る吸ってみると、わかっていたことだが噎せた。
ソネットはパイプ煙草を僕から奪った。
そしてまた、美味しそうに吸う。こうして、彼女の横顔を見るのは何度目だろう。
「シャーロック。あんたの望みさ、セレナ=クラウンを探し出して会うことで変更ないね?」
僕は頷いた。
ソネットの瞳が僕を向く。
「あんたが私に与えるもの、決まった?」
僕はもう一度頷いた。
Give and Take――これは取引だ。
悪魔にとられるものは魂だと思っていた。けれど、ソネットはそれ以外のものでもいいと言う。
「ピアノの技術を。まだ僕には残ってるはずだ。僕からピアノを奪ってよ、ソネット」
「……」ソネットは僕を見る。「参考までに教えてあげるけど、あんたを世界一のピアニストにすることも出来んのよ?」
僕は首を振った。そんなのになりたくなかった。
ソネットは、小さく息を吐き出して、パイプ煙草を置いた。
「シャーロック。あんたに文字を刻まなきゃならないんだけど、何処がいい?」
「文字?」
「盟約者に刻んでおく決まりなんだよ。他の人間の目には見えない。契約内容を、忘れないように記しておく。で、身体のどの部分がいい?」
「どこでもいいよ」
僕は左腕を差し出した。
ソネットは人差し指を、僕の肌に触れさせた。
「Skill of piano……」
そう呟いて、ソネットは文字を記した。
〝Sk.〟と。
痛くなかった。簡単に文字は記された。
「盟約完了したら――つまり、あんたがソフィア少女に会ったら消えるから」
「……〝セレナ〟ね」
「あー、それそれ。心配しないで、ちゃんと探し出すからさ」
ソネットはひらひらと手を振った。僕は若干心配になる。
人でない者との盟約。僕はそれで、セレナと会うことに決めた。
僕のことなんて、セレナは忘れているかもしれない。落ちぶれた僕になんて会いたくないかもしれない。彼女の天真爛漫な性格も変わってしまっているかもしれない。
それでもセレナに会いたかった。
何もかもを失くして、ただ一つ心に残っているのが、3年半前のセレナとの思い出だった。願わくば、もう一度あの日々を。
そのためには音楽なんて要らない。
僕にピアノは要らない。嫌いなんだ。嫌いなものは捨ててしまえばいい。
ピアノを失った僕を、セレナは嫌うかもしれない。
でも、今まで僕を縛ってきたピアノを捨てて、自由になって、セレナに会いたい。僕らの間にピアノを挟まなくても、僕らは近付けるはずだ。
3年経って、やっとわかった。
セレナ。僕も君が大好きだったんだ。
*
ソネットは変わった人だった。
『人』というのはおかしいかもしれない。ソネットは人じゃない。僕の望みを叶えるためにやって来た使者だ。
「人間みたいに、食事をとる必要なんて無い」ソネットは言った。「私らに必要なのは『エナジー』。生物から得られるエナジーが無いと動けない。だからこうやって、定期的に人間からエナジーを奪うわけ。盟約によってね」
人間はエナジーの塊で、ソネットは血や髪や感情や、魂からでもエナジーを得ることができる。それを受け取る代わりに、そのエナジーを一部使用し、願いを叶えてくれる。僕にとっては、寿命も減らないし要らないものも捨てられるし、一石二鳥だった。
ソネットとの生活は上手くいった。彼女は他人に干渉しない。僕のことを尋ねはするけれど、三秒後には忘れてしまっているような気楽さだ。ソネットの淡白さを僕は気に入った。
彼女は、僕の『スキル』を奪ってセレナを探す。全部持っていっていいと言ったのだけど、彼女は少しずつ少しずつスキルを奪っていった。
「いっぺんに貰って、セレナを見つける前に使い切っちゃったら悪いでしょ」
そのとき必要な分のエナジーを受け取って、ソネットはセレナを探しに行く。セレナは引越しをしていて、なかなか見つからない。ソネットは僕の側から離れている時間が多くなった。
『その夜』は、たまたまソネットが僕の側に居た。
セレナを探し始めて10日が経った日だった。
*
煤だらけになった服とともに、僕は借り住まいしている家に帰還する。
くたくたになって歩いていると、隣のソネットが言った。
「シャーロック。あんた、悪魔に尾けられてる」
「えっ?」
「振り返らず、気付いてない振りをしな」
ソネットは表情を変えず、小声で囁く。
背筋が寒くなった。
悪魔が、僕の後ろに――?
「ソネットの知人?」
「いいや、知らない。というかシャーロック。あんた誤解してるけど、私は――」
「何でもいい。突っ切れないの?」
僕の声は少し震えている。
「攻撃を仕掛けてくる様子はないみたいだね。見張ってるっていうか」
「それってソネットを見てるんじゃないの?」
僕は悪魔に尾行される覚えなんてない。
「かもね。私、行く先々で人気者だから」
ソネットはさらりと言って、それから何も喋らない。
悪魔の足音は聞こえない。気配もない。悪魔が僕からどれくらい離れた位置にいるのか見当もつかなかった。
「僕の命は守ってくれるの?」
ソネットに訊いたら、彼女は淡白に答えた。
「仕事が終わるまではね。盟約者」
*
セレナの実家、クラウン家はフランスから離れているようだった。セレナの消息は、いまだ掴めない。
僕は、煙突掃除に身が入らなかった。何度も足を滑らせて落ちそうになったり、延々と同じ箇所を磨いていたりした。
頭の中では、ピアノの音が鳴り響く。
僕がセレナに聴かせた数々の曲。
延々とめぐる旋律。いい加減嫌になるのに、音楽は離れてくれない。僕が弾くピアノを嬉しそうに聴いていたセレナの顔を、同時に思い出す。
その日の仕事は、教会の神父からの依頼だった。教会の煙突に登った僕が、仕事を終えて降りると、講堂がざわめいていた。
仕事が終わったことを告げて、さっさと礼金を受け取りたいのだが、神父はそれどころではないらしい。数人の、スーツを着た人間と真面目に話をしている。内容はすぐにわかった。今日、本国から司祭が視察に来るのだが、聖歌隊の伴奏者が来られなくなったらしい。代わりが見つからず、彼らは慌てていた。
話が終わるのを待っていると、神父を囲む一団の一人と目が合った。
彼は驚いて僕に近寄る。
「…シャーロック?」
その顔に見覚えがあった。
「シャーロック=リフィルだろう? オーストリアの教会で弾いていた……」
頷くと、彼は喜んだ。最初に僕をオーストリアから連れ出した、実業家のベルリーニ。会うのは五年ぶりだった。
「君のことは聞いているよ。可哀想に、コンクールにも出られずに……。今はイギリスに居るのかい」
「煙突掃除をやってるんだ。生きていくためにね」
ベルリーニは僕を可哀想な子どもとして見ていた。僕はちっとも可哀想なんかじゃない。ピアノに縛られる生活よりよっぽどいいと思っていたところなんだから。
ベルリーニは後ろを振り返り、驚くべきことを言った。
「みんな、聞いてくれ。解決策が見つかった。ここに居るシャーロック=リフィルが伴奏を弾く」
「!?」
僕も、神父を囲む一団も目を丸くした。
ベルリーニは僕を彼らに紹介した。
「シャーロックは天才ピアニストだ。僕は彼のピアノを聴いたことがあるが、この子は将来有望だと感じた。不運から才能を開花させることはなかったが、彼の腕は保証する。どうだろう、彼に演奏を任せてみては」
その場がざわついた。
僕はベルリーニに言った。
「待ってください。僕はもう何年も弾いていない。伴奏なんて――」
「大丈夫、今日のメインは聖歌隊。ピアノのコンクールじゃないんだ。それに、曲はかつて君がオーストリアで弾いていたものばかりだ」
「だからって……」
神父と話していた一団が、僕に近付いてきた。
「手を洗ってきなさい、煙突掃除の少年。まず君のピアノを聴かせてもらいたい」
「そんな」
僕に断る権利などなかった。大人たちは、無理やりに僕をピアノの前に座らせる。
艶やかな黒鍵と白鍵。
僕の胸がドクンと鳴った。僕は喜びを感じている。もう弾きたくないのに、弾きたくないはずなのに、弾きたいと感じる。
僕の指は伴奏を奏でた。もちろん、指の動きは鈍い。思うように動かない。当たり前だ、ずっと練習していない上にソネットに技術をとられている。出来は散々だった。
が、神父たちは「これならいける」と喜んだ。あの演奏のどこが、と毒づいてやりたかったが、もう少し弾いていたい気になったので、彼らの言う通り正装し(貸してもらった)、聖歌隊の伴奏をすることにした。
午後になって司祭の一団がやって来た。
僕は聖歌隊の伴奏をした。
出来は良くなかった。聖歌隊と息が合ったとも思えないし、聖歌隊自体、あまりレベルが高くはなかった。
それでも拍手喝采、僕は司祭から褒められた。
「君はいい。どうかね、今度コンクールに出てみないか」
僕は断るつもりだった。ピアノは懐かしくて楽しかったが、コンクールとなると別だ。強制されて弾くことなど楽しくはない。
が、ベルリーニや神父たちが乗ってきた。
「いいですね」
「是非この子を舞台に立たせましょう」
この人たちは音楽を知らない。だからあんな演奏を素晴らしいなんて褒められるんだ。僕は担ぎ上げられ、またピアニストを目指さなければならなくなった。
*
戻ってきたソネットに一部始終を話すと、彼女はあっけらかんと言った。
「それは不運だったね」
全くだ。僕は煙突掃除を辞めさせられ、明日には教会に引っ越すことになっている。
「人が聞けばこの上ない幸運って言うんだろうけどね」ソネットは僕に近付く。「そんなとこ悪いんだけどさ、シャーロック」
「うん、わかってる。持っていって」
彼女は「Thanks」と、僕の腕からエナジーを抜き取る。
僕はまたピアノの技術を失う。父に、サン先生に、ヴェロッティ先生にピアノを叩き込まれたあの時間が失われていく。同時に、セレナの『夢』も。
「ソネットは、どれくらいの時間生きてるの?」
尋ねると、彼女は意外そうな顔をした。
「珍しいね。あんたが他人に興味を持つなんて。執着してるのはセレナ=クラウンだけなのに」
「たまには訊きたくなるんだよ。それで、答えは?」
「憶えてない」
ソネットはさらっと言った。
「ソネットから見ると、僕ら人間って滑稽な生き物なの?」
「さあ。興味ないからね。私から見れば、人間も動物も一緒。人間は『話せる動物』『話せる植物』と何ら変わらない。ああ、あと『複雑な感情を持ってる生き物』かな」
「複雑ね……」
「人間の感情もエナジーの一つだからね。出来れば美味しい感情を持ってる奴の側に居たい」
「どんな感情が美味しいの?」
「味覚は人によって様々だけど、私は激情が好き。怒りとか憎しみとか、まあ前向きな気持ちも美味しいけどね」
「じゃあ僕に憑いたのは残念だったね」
ソネットは首を振った。
「そういうのが好きだからあんたに憑いたんだよ」
「え?」
ソネットは、パイプの先で僕の胸を軽く突いた。
「自分で気付いてないんだね。あんたはずっと『我慢』をしてきてる。その我慢の向こうには、怒りや憎しみがマグマみたいに溜まってる。それを観察するのが私の趣味。いつ噴火するかって、ドキドキするじゃない?」
「……そんなものなの?」
ソネットは珍しく笑って、僕からパイプを離す。
僕に激情があるなんて自覚はない。僕の心は常に凪だ。怒りなんて感じない。ただ流されるだけ。抗う力がない僕は、激流に呑まれないようにしているだけで精一杯なんだ。
「そんで、シャーロックはピアニストになるの?」
いきなり話が飛ぶ。
「なれないよ。ピアニストになりたいと願ってる奴がこの世に何万人いると思う? 彼らは毎日毎日寝る間も惜しんで練習してるんだ。やる気がなくて、しかもブランクのある僕がピアニストなんて無理だ」
「その上、私に技術(スキル)を取られちゃね」
「よくわかってる」
望んでもいない幸運が舞い降りるたびに、僕は嫌になる。
さっさと終わらせてしまおう。どうせ僕なんて、舞台に上がることは出来ないんだから。
ピアノなんて要らない。
僕が欲しいものはただ一つなのに、それは僕の手からどんどん離れていく気がする。
*
僕の予想を裏切って、僕は周囲の期待に沿い、ピアニストに近付いていった。
司祭の後押しもあって、無事コンクールに出場した僕は、二次、三次と予選を勝ち進み、本選への出場が決まった。
司祭やベルリーニが僕を押してくれたので、衣装や練習環境は完璧だった。父が逮捕されたという過去も、彼らの力で封じられているようだった。
本選はフランスで行われる。再びあの地に戻れることを嬉しく思った。
フランスに行ったのは、教会で伴奏を引き受けてから僅か一ヶ月しか経っていない頃だった。
ソネットも一緒に行った。彼女は最近、僕からスキルを取ろうとしない。
「せめて、あんたのコンクールが終わるまで待ってやろうと思って」
「必要ないよ」
「あんたの激情がさ、最近ちょっと昇華されちゃって悲しいんだよ」ソネットは言った。「ピアニストとして凱旋して、それでセレナに会えたら最高なんじゃないの?」
ソネットの言葉が的をついていて、居た堪れなくなった。
勿論ピアニストになんてなりたくない。それは、父や周囲から強制されてきた象徴だから。
けど、セレナは僕がピアニストになることを願っていた。あんなにも嬉しそうに、僕をイギリスに送り出していた。ピアニストとしてフランスに戻ったら、彼女はきっと笑ってくれる。地に堕ちた僕の姿を、知ることなんてなくなるんだ。
フランスに渡る船に乗っているあいだ、ソネットは背後を気にしていた。
「また居るね。悪魔」
すっかり忘れていたが、悪魔の尾行はまだ続いているらしい。
「ソネットに付いて来たの?」
「私かシャーロックか……。一回、話つけてきた方がいいかしら?」
ソネットはちらりと目線を動かす。
彼女はつまらなさそうな顔をした。
「隠れちゃった」
僕に、ソネットに、付き纏う悪魔。
どうか僕らの邪魔をしないでほしい。セレナに会うという僕の望みを、破壊しないで。
かつて僕等が出会ったフランスへ。
ようやく、僕は戻ることが出来た。
*
本選は一週間後に行われる。
もう時間はなかった。満足できる技術もなかった。
僕は、セレナの屋敷があった場所へ赴いてみた。そこはもう別の人が住んでいて、クラウン家ではなかった。住人に聞いても、クラウン家の人たちの行き先はわからないという。
この広い世界で、僕とセレナは再会することが出来るんだろうか?
セレナはお金持ちのお嬢様だ。もう婚約者が居て、順風満帆に暮らしているかもしれない。それとも――ほんの微かな可能性だけど、僕に会いたがっているかもしれない。僕らが離れた四年前と何も変わらずに。
本選の三日前。
有望株の2名が、怪我によって欠場することが知らされた。ベルリーニと司祭は「チャンスだ」と囃した。
それでも僕の不利は変わらない。四年のブランクは大きすぎる。僕の指先は、前のように動いてくれない。
本選が始まって、何と僕は勝ち進んだ。本番では思いのほか良い演奏ができたし、審査員たちは僕を評価した。表現力が素晴らしいとのことだった。ベルリーニと司祭が賄賂でも送ったんだろうと思った。だって僕より上手な人は沢山いるんだから。
本選の三次、これが最後だ。
フランスに来て二ヶ月。これで優勝者が決まる。
袖で出番を待っていると、ソネットが声を掛けてきた。
「ピアノのことはわかんないけどさ、あんた上手いんだね。シャーロック」
「そんなことないよ」周囲に聞こえないよう、小声で話した。「運が良かっただけだ。たまたま僕を評価する審査員が集まっただけ」
「運も実力のうちって言うけどね。私にスキルを取られてなお決勝戦なんて、ブランクさえなきゃ今ごろ世界的ピアニストだったかもね」
ソネットの言う通りなら良いと思った。僕の腕は優れているんだと。四年前、僕はコンクールに出られなかったから、客観的な実力を測れないでいた。本当に、僕にピアノの才能があるのなら――
優勝できるはず。
君が客席に居ると信じて弾くよ、セレナ。
そうしたら、どれだけでも心のこもった演奏ができそうだ。
*
ほんの数ヶ月で、人生が激変した。
かつて父が望んだ地位に僕は立った。
「優勝おめでと。シャーロック」
誰よりもさらりとソネットが祝いの言葉をくれた。
優勝したことで、僕は広いアパートに住めるようになったし、食事に困ることもなくなったし、何より『ピアニスト』の称号を手に入れることができた。
僕は苦難のピアニストとして名を広めた。ベルリーニが上手く宣伝してくれた効果だろう。僕はフランスでちょっとだけ有名になった。
父から手紙が来た。細々とした字で、おめでとう、本当に良かったと綴られていた。
「望んでいないものばかり手に入るものだね。ソネット」
ピアノの練習を終えて横になり、ソネットに話しかけた。
「人生思い通りにいかないさ」
ソネットはパイプ煙草をふかしている。
煙突掃除をしていた頃が、もう懐かしい。
「あんたのスキル、取れなくなったね」
来週には単独コンサートが待っている。お偉方が何人か聴きに来る。上手くいけばスポンサーになってくれるだろう。
「取る必要ないか。あんたの評判は、きっとセレナ=クラウンの耳にも入る。会いたきゃ向こうから来るだろう」
今のところ、セレナから連絡は来ていない。
もっと有名になって、フランスの誰もが知るピアニストにならなければ。
「どういう形であれ、盟約完了すれば腕の文字は消える。あんたがその文字を背負っているのもあと少しだね」
Skill of piano――『Sk.』
ソネットが僕に刻んだ文字。
盟約完了すれば消え、ソネットともお別れだ。
不意にソネットが窓の外を覗く。
「また例の悪魔?」
ソネットは答えない。
背中しか見えないので、彼女の表情はわからない。ただ、か細い声でソネットが僕に尋ねた。
「シャーロック。あんたが出場したコンテスト、優勝するのってそんなに難しいわけ?」
「え。うん、優勝すれば単独コンサート上演権や栄誉が与えられるからね。各国から選りすぐりのピアニストが集まるんだ」
「………」
「ソネット?」
彼女は窓を開け、身を乗り出した。
「どっか行くの?」
振り返り、「散歩」と答えたソネットは、そのまま飛び出して行ってしまった。
「ソネット……」
部屋でのんびりしているのが好きな彼女が、衝動的に出て行くなんて初めてだった。
「まあ、いいか」
人でない存在にも色々あるんだろう。僕は寝転び、温かなベッドで眠った。
*
夢を見た。
僕に都合のいい夢だ。
単独コンサートの最後、拍手喝采の中、花を持ってきてくれる女の子がいる。
その子と僕は会ったことがある。ずっと前に、僕の生徒だった女の子。
セレナ=クラウン。
大層美しく成長して、僕に微笑みかける。
〝おめでとう、シャーロック〟
君に聞きたいことがあるんだ。
僕と離れたとき、寂しくはなかった?
僕に会いたいと、思っていてくれた?
君に言いたいことがあるんだ。
ようやく君の夢を叶えてあげられた。
僕はずっと君に会いたかった。
会ってどうしたいと考えていたわけじゃないけれど。
ただもう一度話を。
君の声に。
君の笑顔に。
会いたいと思っただけなんだ。
ようやくここまで来れたよ、セレナ。
*
僕はセレナと会うことが出来た。
ソネットは僕の望みを叶えてくれた。
…半分だけ。
「ごめん」
と、彼女が言った。
僕は、頷くことも、声を出すことも出来なかった。
「もっと早く会わせてやれてればね」
〝Selena=Krown〟
彼女の名前が刻まれた、石。
それが何を意味するのか、僕は理解したくなかった。
〝1910.5.10〟
その日付の意味を知りたくもなかった。
僕が、フランスに着いた日。
少しの希望を感じていた日。
君に会えると、信じていた頃。
慟哭が聞こえた。僕の声だ。
わかりたくなくても、わかっている。
僕はセレナと会うことは、二度と出来ない。
*
「起きてる? シャーロック」
声が聞こえた。
ソネットだ。
「…まだ居たの?」
目が、少ししか開かない。腫れているからだ。僕は、身体中の水分が無くなるくらいに泣いた。苦しくて、何度も身体を壁にぶつけた。酒も、煙草もピアノも、僕の苦しみを軽くしてはくれなかった。
ソネットが近くに居る。倒れている僕のすぐ側に。
「盟約はまだ完全に完了してないんだよ。もう、完了できなくなったけどね……」
ソネットが僕の腕に触れた。
身体が少し、楽になる。
「あんたから頂いたエナジーをちょっと返したよ。元気出た?」
元気はないけれど、目は開いた。
なんとか起き上がることも出来た。
「ねえ、ソネット。人間って食べなくても死なないんだね。心が切り裂かれることがあっても、心臓が破裂したりはしないんだね。案外、頑丈にできてるんだ」
ソネットは僕の隣に居る。
散らかった部屋の中。割れた食器、破れたカーテン。乱雑な僕の心とおなじ。無事なものは何もない。
腕が痛い。お腹が痛い。頭も痛いし、何よりも心が痛む。だけどその痛みで、僕は生きていると思い知る。
「あれから何日経った?」
三日、とソネットが答えた。
「ソネット。僕を壊して」
うつむいて、僕はお願いをした。
僕の悪魔に。
「もう一度盟約を結ぼう。今度の望みは僕を壊してくれること。殺してくれること。お返しに何でもあげる。全部持っていってよ。だから」
「人の話は全部聞きな。Boy」
僕の頭をポンと叩き、ソネットは僕を見る。
「…話?」
「セレナ=クラウンが墓の下に眠ることになった理由、あんた知りたくない?」
「………」
僕は顔を上げた。
ソネットの瞳は、これまでになく真っ直ぐだ。
「知りたい」
真っ赤な瞳をソネットに向けて、答えた。
彼女はパイプ煙草を手の中で廻す。
「私もちょっと責任を感じてるんだよ、シャーロック。あんたのスキルを全部奪ってとっととセレナに会わせてやれてりゃよかった。今さら言っても仕方のないことだけど……。で、その罪滅ぼしにタダで教えてあげる」
ソネットは煙草をくゆらせる。
白煙が昇っていく。
「事故死。馬車に轢かれたんだよ。…表向きはね」
「表向き?」
その言葉が引っ掛かった。
「裏があるっていうの? じゃあ、事故死じゃないってことだね」
ソネットはなかなか口を開かない。じれったくて、彼女を急かした。
「ソネット!」
パイプ煙草を口から離し、ソネットが言った。
「ねえ、シャーロック。あんたの出場したコンクール、本当に難易度が高いんだってね。優勝すればピアニスト。栄誉と多額の金銭が得られる。ピアニストの卵たちがこぞって参加する、格式高いコンクール」
「それが? 今は関係ないことだよ」
ソネットは首を振った。
「シャーロック。あんた言ってたね。毎日毎日血を吐くくらいに練習してる奴らがいる、ブランクがあって更にスキルを取られた自分が優勝なんて出来ないって。あんたの言う通りだった。あんたは、あのコンクールで優勝なんて出来るわけなかったんだよ」
「……どういう、意味?」
背筋が凍る。
ソネットの目線。
そうだ、彼女は人間じゃないんだと思い出す。
「知りたい?」
怖い。
知るのが怖い。
嫌な予感がした。今まで生きてきた中で、一番――
でも僕は、悪魔の手を取った。
「…教えて。ソネット」
そして僕は、真実を聞かされる。
*
明日は僕の単独コンサートだ。
ベルリーニも司祭も楽しみにしている。有名な実業家や、金持ちたちが沢山見に来る。
その中にセレナ=クラウンの姿は無い。
君のためのコンサートなのにね。
一体僕は何のために音を奏でるのだろう。
そいつは路地を歩いて付いて来る。
もうすぐ日付が変わる頃。
住宅街から少し離れ、工場地帯に入りかかる。レンガの道で、そいつはハッとする。僕等を見失ったからだ。
そいつは慌てて走り出す。
ソネットが声を掛けた。
「Good Evening. Devil」
僕等を尾行していた悪魔が振り返る。
ソネットはいつの間にかパイプ煙草をふかしている。その紫煙が、今は僕を守る、心強い武器みたいだ。
「初めまして、悪魔」僕はそいつを見据えた。「ぼんやりとしか見えないけど、でも居ることはわかる」
長身の男の姿だった。身なりもよさそうだ。盟約者には人でない者をとらえる力が宿るが、ソネット以外の者はよく見えない。
悪魔は僕等を警戒しているようだ。
「返して欲しいものがあるんだ」
僕は悪魔に言った。
悪魔は答えない。
「あんたがセレナ=クラウンから奪ったものだよ、Devil……いい加減喋ってくれない?」
ソネットのパイプ煙草が悪魔を向く。
悪魔は一歩、僕らに近付いた。
「奪った、もの?」
男の声だ。
悪魔の声。
「あんたは、セレナ=クラウンの望みを叶える代わりに彼女の『幸運』を奪った。まだ残ってるなら、渡してくれない?」
悪魔がまた、僕等に近付く。
でも怖くない。それよりももっと深い感情が僕をえぐる。
悪魔に向かって、僕は言った。
「セレナと取引したんだろう。僕をピアニストにする代わりに幸運を渡すって。お前は、セレナから幸運を奪い、その幸運を僕に使っていた。だから――」
まやかしの栄光。
考えてみれば、あんな幸運あるはずがなかった。僕がピアニストになれたのは、数々の偶然と幸運。偶然ベルリーニに会い、幸運にも才を見出され、ライバルが欠場し、審査員に認められ、優勝を果す。
あれらは全て、セレナの一生分の『幸運』。
あの拍手喝采は、セレナが僕にくれたもの。不運だった僕にくれたもの。偽りの栄光。
「お前が僕に付いて来ていたのは、僕に幸運を与えるためだ。セレナから奪った幸運を! タイミングを見計らって幸運を与え、僕をピアニストにする。セレナが死んだのも、幸運を失ったからだ。〝不運にも馬車に轢かれて死ぬ〟。こんなことが起こったのは、全部――」
「そう。私との取引のためだ」
悪魔が放つ、どす黒い声。
僕の全身が逆立った。
瞬きのあと、僕は離れた場所に居た。
さっき僕が居た道が、粉々に砕け、煙が立ち上っていた。
ソネットが僕を放し、僕は地に降りた。
「避けたか。まだエナジーが残っていたかな」
悪魔が僕等を振り返る。
「有り余ってるわ。シャーロックに貰ったばかりだからね」
ソネットがにやりと笑う。悪魔がぴくりと反応した。
「新たな盟約を結んだってわけ。シャーロックの望みは、あんたからセレナ=クラウンの幸運を取り戻すこと。殺してでもね」
悪魔がフッと笑う。
「上級悪魔の私に、勝てると思うか? 命知らずめ!」
悪魔が手を振り上げる。
竜巻がこっちに向かってくる!
ソネットは僕の前に立ち、パイプ煙草を前方に掲げた。ものすごい爆音のあと、目を開けると僕は生きていた。
火の檻――
その中に僕とソネットが居た。
「申し遅れました。私の名はソネット。かつての王の守護者、ランズの一人。……命知らずはそっちだったみたいね」
風が止み、火の檻だけが残る。
ソネットは檻を抜けた。
「ランズ……」
悪魔が一歩退く。
ソネットがくるくるパイプ煙草を回すと、炎が円を描いて彼女を取り巻く。
「さて。あんたに勝ち目はないけど、お利口さんになったかしら? 素直に『幸運』を渡す?」
「大半は譲渡済みだ。シャーロック=リフィルをピアニストにするために使った」
「まだ残ってるはずでしょう? エナジーを奪って願いを叶えるだけじゃ、こっちにメリットはない。自身の栄養にするために、一部エナジーを貰い受ける。その分を頂戴って言ってんの」
悪魔は答えない。ソネットが間合いを縮めようとすれば、悪魔は下がる。
「もう、満足したはずだ、シャーロック=リフィル」悪魔が僕に言った。「この上まだ幸運を望むか? 強欲な人間だ」
僕はぐっと拳を握る。
「僕は……、幸運が欲しかったわけじゃない。ピアニストになりたかったわけじゃない。ただ、セレナにもう一度会いたかった。セレナを殺してまで、ピアニストになんてなりたくなかった!」
彼女の喜ぶ顔が見られないなら、何の意味もない。僕はもう何も惜しくない。欲しいものは、なくなってしまったのだから。
「セレナ=クラウンもお前に会いたがっていたよ、シャーロック」
悪魔が僕に話し掛ける。
離れた位置に居るのに、まるで耳元で囁かれているようだ。
「船が出港する日に風邪で寝込んで、お別れが言えなかったとずっと悔いていた。お前の父親が逮捕され、コンクールに出られなかったのを知って、君の不運を嘆いたと言っていた。シャーロック、シャーロック……あの娘の側に居た10ヶ月、何万回も君の名を聞いた。百年は忘れられそうにないな、君の名前」
凍りつく。僕の目が、耳が、心が。
セレナの姿が、僕の頭に蘇る。
「イギリスになんか行かせたくなかったとも言っていた。ずっと側でピアノを教えていて欲しかったと。だけど、君の未来を妨げることになると必死に笑顔を作っていたそうだ。健気な少女じゃないか。彼女の幸運を使って君はピアニストになった。結果、彼女は死んだ。その地位を大切にしたまえよ。彼女の命を削って得たものなのだから」
身体が、動かない。
錆び付いてしまったみたいに。
心が壊れそうだ。割れて飛び散った破片で、僕自身死んでしまいそうだ。
ただ一言。
力を振り絞って、言った。
「ソネット。盟約を果たして」
「OK、盟約者」彼女は答える。「檻から出ないでよ。死にたくなければね」
「ランズ……。いいだろう、その骨を奪って俺がお前の力を得てやる」悪魔が不気味に笑う。「これで私が、ランズの一員に――」
「甘い!」
一瞬だった。
攻撃を仕掛けようとした悪魔に、ソネットのパイプ煙草の先が向く。
業火に包まれ、悪魔の姿は消えた。
灰も残らなかった。
炎の檻が止む。
ソネットが、僕に近付いた。いつものようにパイプ煙草を銜えて。
「セレナ=クラウンの僅かな『幸運』。どうする?」
ソネットの片手にあるもの。僕には見えないけれど、僕はそれに触れた。
「…僕に頂戴」
セレナの幸運が、僕の中に。
不思議と温かい気持ちになれた。これは彼女の感情? 僕と会うことをずっと夢見てくれていた、セレナの……。
「ごめん、セレナ……。僕は、君の夢を……」
涙が止まらない。君の温かさに触れて、僕は自分の罪を自覚する。心が痛い。優しい刃物で、僕の心が抉られる。
「シャーロック。おめでとう」
ソネットが、僕の肩に手を置いた。
「日付が変わった。今日はあんたのコンサートだ」
*
これは僕の夢ではなかった。
父の、先生の、周囲の大人たちの願望だった。
僕をピアニストにすること。
彼らは、それによって得られる称賛が欲しかっただけ。
でも君は違った。
君が喜んでくれるなら弾こうと思った。初めて前向きに、ピアノという楽器と向き合うことが出来たんだ。
君が聴いてくれないなら何の意味もない。もう、喜びなんて感じない。
僕の両手は震えていた。コンクールでも震えたことなんてなかった。
もう僕は弾けない。ピアノの技術は全て、ソネットに渡してしまった。
君は悪魔と取引をした。自らの幸運と引き換えに、僕をピアニストにするように。
僕はソネットと盟約を結んだ。自らのピアノの技術と引き換えに、セレナと会えるように。
セレナと取引をした悪魔を倒すために、僕は再びソネットと盟約を結んだ。僕の残りの技術全てを、そのとき、ソネットに渡した。そしてそれは、悪魔を倒すために使われた。すなわち、僕のピアノの技術はもう昇華してしまったということだ。
君が僕に与えてくれたものを、僕は捨てた。
要らないと、捨ててしまった。
この手はもうピアノを奏でられない。でも時は、コンサートの始まりを告げる。
「その文字、消してやれなくなったね」
開演前にソネットが言った。
僕の腕の『Sk.』の文字は、消えずにそのまま残っている。セレナとの再会を果せなかったので、盟約が完了しないことになり、文字は残ってしまうのだ。
「いいよ。これは僕の罪の証」
もう弾けない腕を掲げる。
「ちょうど、Selena=Krownのイニシャルだ。この文字を見るたびに、僕はセレナを思い出す。僕の罪を思い知る」
「あんたに罪なんてないと思うよ。シャーロック」
僕は首を振った。
「セレナを死なせてしまった。そして、彼女が命をかけて僕にくれたものを、僕は捨ててしまう。今から」
「……」
「客席で聴いててよ。ソネット」
舞台の上に立つ。
拍手で迎えられた。
僕は深くお辞儀をして、ピアノと向き合う。
白鍵と黒鍵が、ただの二色の色にしか感じられない。
ねえ。セレナ。
君への気持ちは消えずに僕の中に残っている。
君を想って奏でた音は、どこへ行くんだろう。
ピアノみたいに。
美しい音色と共に、消えてしまえばいい。
客席がざわつく。
僕がいつまでも弾かないからだ。
ベルリーニが、司祭が、焦りながら僕を見ているんだろう。
僕の手は震えていた。弾けない。
僕は立ち上がって、客席を向いた。
君は言ったね。僕は本当は音楽が好きなんだと。もっと自由になればいいと。
ピアノじゃなくても、いい?
音楽を続けていれば、贖罪になるだろうか。
僕は歌った。
君が好んだ曲を、大きな声で。
伴奏も何もない。ただ気持ちの限りに声を出した。
目を開ければ、きっと客席を立つ人々が見える。
それでいい。
僕が聴いてほしいのは、ただ一人。
僕の心の中の、君一人なんだ。
*
「ゼロだね。シャーロック」
コンサートの後で、ソネットが僕に言った。
「ゼロって?」
「全てを失ったってこと。綺麗さっぱりね」
「ああ……、本当にね」
見上げたらそこに月があった。
面白いくらい僕には何にもない。ピアノも失くし、人々は僕から去り、何ひとつ持っていない。
「音楽は続けるつもり?」
「うん。この文字を背負って生きていこうと思う」
Sk.
セレナ=クラウンと共に。
「一生残るんなら、もうちょっと丁寧に書いてやれば良かったね」
ソネットはパイプ煙草をふかす。
煙草を吸い終わると、ソネットは立ち上がった。
ソネットとの別れのときだ。
「悪かったね、シャーロック。結局盟約を果せなくて」
「いや……。ソネットが側に居てくれて良かった。少しは救われていたと思う」
「なら良かった」ソネットは少し笑う。「次のコンサートまでに、少しは歌を磨きな。あれじゃ客が集まらないよ」
「コンサート……多分、今日のが最初で最後だよ」
僕は片手を差し出した。
ソネットは僕の手に触れ、僕等は握手する。
「さよなら、ソネット」
僕とソネットは目を合わせる。
短いあいだの、僕の盟約相手。
「元気で」
最後まで淡白に、ソネットが別れを告げる。
彼女の後ろ姿が遠ざかっていく。
その背中が見えなくなるまで、立ち尽くしていた。
失うものはこれで最後。
僕は一人で生きていく。この文字とともに。あがないのために、音楽を続けて。
いつか音楽を心から好きになれるだろうか。君が言ったとおり、僕が本当は音楽を愛しているのなら……。
強制されたものではない、僕が望んだ音楽を続けていく。
届かない音を。君のためだけに。
*
パイプ煙草が美味しい。
私は昔のことを思い出していた。
もう百年も前の、不運な音楽家の話。
あれから、シャーロック=リフィルがどんな人生を送ったのか知らない。ただ、私は一度もシャーロックの名を耳にすることはなかった。
あの少年は、一生を音楽に捧げたのだろうか。それが、自分が死においやった(と信じている)少女への償いだとして。いや、人間ってのは立ち直りの早い動物だ。案外、それからの人生は幸せだったかもしれない。別れのときのシャーロックは、覚悟を決めた顔をしていた。
「ん?」
私は立ち上がる。
「〝呼ばれた〟」
東国からだ。誰が呼んだかもすぐにわかった。
「…仕方ない。行ってやるか」
久し振りに、会いに行こう。同じ立場の奴等に。
移動には飛行機を使った。百年前にはなかった乗り物だ。人間は、刹那的といっていいほどめまぐるしく進歩する。
空港に降り立ち、荷物を片手に歩いていると、子どもが私に向かって片手を上げた。
「Good afternoon!」
一瞬、誰だかわからなかった。でもその子どもが『人でない』ことはすぐにわかった。
「久し振り、ソネちゃん。百年ぶりくらいかな?」
「ああ……」
私は子どもに近付いた。
サングラスの下の瞳が、私を捉える。
「ちょっと大きくなったんじゃないの? いや、変わらないか」
「僕ら成長しないって。人間じゃないんだからさ」
にっこり笑って、子どもは私の腕に絡みつく。
「ソネちゃんもアル爺に呼ばれて来たんでしょ? 一緒に行こうよぉ」
「そうだね……。どうやら皆呼ばれてるようだし、たまにはランズ全員で食事会ってのもいいか」
「あ、僕ね、東京見物したい。大っきなタワーがあるんでしょぉ? ソネちゃん一緒に行こ」
「あの野郎に会ってからね。まずはあいつの屋敷が先」
「はぁーい。アル爺に会うのも楽しみだな☆」
少女はスキップで先を急ぐ。
「さて……、今度は何が始まるのか」
私は空を見上げる。
煙草のか細い煙が、儚く昇って消えた。
水月ハ君ノ内ニ宿ル

ガラクタみたいな音のチャイムが鳴った。
これで今日の講義は終わりだ。
俺の周囲のガリ勉たちは、教科書を大事そうに上等な鞄に仕舞ったり、教師に質問に行ったりしている。
大きく欠伸をして教室を出ようとすると、教師に呼び止められ、お説教を聞かされた。言われることはいつも同じ、お前はやる気があるのかと、それだけだ。
やる気なんてあるわけがない。周囲の金持ちのガリ勉の同類になるのも御免だった。彼らの興味は勉強、勉強、ひたすら勉強。エリートという言葉に憧れる餓鬼どもだ。
ただ、一部の金持ちの息子は、俺みたいな貧乏人に興味を持つ。ジホン、ミソン、イヒョン、イルシクの四人は俺に近寄ってきた。
「また先生直々の『個別指導』か?」
「出来損ないがこの学校に来たのがそもそもの間違いだって、わかってんのか?」
ケラケラ笑いながら俺に近寄る四人はとても暇そうに見える。俺をからかって退屈しのぎをしたいのだろう。
「ジホン一派の説教は聞き飽きたよ。じゃ、俺帰るから」
ひらひらと手を振って帰ろうとすると、その手を掴まれた。
「調子に乗んなよ、貧乏者。今日は俺の個別指導、受けてもらおうか?」
リーダー格のジホンが、俺の手に力を込める。
「――痛っ!」
声を出したのは、俺じゃなくてジホンだ。俺の手を掴む力が緩んだので、手を解放させてもらった。
「どうした、ジホン?」
「誰だ、俺の足蹴ったの!?」
ジホンは後ろを振り返る。ミソン、イヒョン、イルシクは首を振る。
「あーあ」
俺は呆れ声を出す。ジホンが俺を睨んだ。
「てめえか、ユン!?」
「ジホンの前方に居た俺が、どうやって後方から蹴れんだよ」
ジホンは顔を真っ赤にして三人を睨む。犯人は、ジホンの後方に居た彼らの中の誰かだと思っているのだ。ジホンは彼らを疑い、怒声を浴びせている。
「あー、いやいや、それくらいにしてやれよ」
「俺に指図する気か!?」
「違う違う。ジホンに言ったんじゃなくて――」
ジホンは俺から離れ、三人を攻め立てる。
その間に、俺は彼らから離れ、帰宅の路に着いた。
私立ソエウル学院。
ここは、金持ちの子どもたちが集まる進学校だ。金持ちの中でも、エリートコースが約束された奴らが集まる。学院のレベルは、国で指折りの高さだ。俺の周りはガリ勉か、そうでなければさっきのような連中ばかりだ。
「いくらなんでも、鉄パイプで殴ったらあいつ死ぬだろ」
俺の隣の奴に声を掛ける。
そいつの名はロイ。8~12歳くらいの外見をした、子どもだ。
「ユンしゃん。僕あいつ嫌いなんでし。蹴り一発じゃ足りないでし」
ロイは物足りなそうに鉄パイプを振り回す。外見に不似合いな行動だ。
「んで、ロイ。夕飯は何食う?」
ロイはぱっと笑顔になる。
「僕、刺身が食べたいでし」
「刺身? そんなもん高過ぎて買えねえよ」
「お刺身がいいんでし!」
ロイは譲らない。こういうところは本当に子どもみたいだが、ロイは実は俺よりずっと長く生きている。
もしかして、人間とは時間軸が違うのかもしれない。ロイは精神的にも大人とは言えないし、外見も然りだ。
俺が一ヶ月前に会ったロイは、人間じゃない。ロイ曰く、『盟約相手にしか見えない存在』、だが『害じゃない』。ロイと俺は盟約を結び、共生関係にある。
一ヶ月前。
市場で手に入れた果物を手の中で転がし、ボロ家への路を歩いているときだった。
いきなり、服を引っ張られた。つんのめって振り返ると、誰も居ない。でも服は確かに引っ張られている。
「??」
風でもない。服の端っこは、確かに何かに握られている。
〝これ返すでし〟
子どもの声が聴こえた。
俺のポケットに、鉛筆が差し込まれた。
「ん?」
〝忘れ物でし。お返ししましゅ〟
それは確かに俺の鉛筆だった。でも、ここにあるはずがないけれど。これは昨日、ジホンに盗られたものだ。
〝お返しと言っては何でしゅが、僕と盟約を結びましゅか?〟
「盟約?」
〝取引でし。僕が何でも望みを叶えるでし。だから、お返しに――〟
「わかった、いいよ。結ぼう」
あっさり決めると、声はしばらく黙った。
〝…もっとよく考えた方がいいでし。僕が悪いヤツだったらどうしましゅ?〟
俺は笑った。
「そんな風に言うヤツは、大体が正直者だ。俺はユン。お前は?」
不意に、そいつの手が見えた。それから徐々に、姿が形を成していった。
「ロイズレッド=アルジャイン=ランベルク=リーノ=フェロン=ワイズⅡ世でし」
「長っ」
今やハッキリと姿が見えるようになったそいつは、俺に向かってえくぼを見せた。
「〝ロイ〟でいいでし」
盟約を結ぶことを約束する、〝仮盟約〟。それを結ぶと、相手の姿を捉えられるようになる。
俺とロイの共同生活の始まりだった。
「ロイさあ、もうちっと韓国語覚えた方がいいぜ」
ロイは無垢な顔で俺を振り返る。
「僕ちゃんと話してるでし」
「語尾がさあ……。〝です〟だよ。言ってみ?」
「でし」
「いや~……」
満点を取った子どもみたいに、ロイはにっこりと笑う。
「それよりユンしゃん。僕、刺身が食べたいでし。僕のお腹はお魚を求めてるんでし」
真剣な目で俺を見つめるロイ。
今日は俺が折れることにした。
「しゃーねーなあ。んじゃ、盟約だ。ほい」
手のひらを開くと、ロイは羽ペンを取り出して文字を書く。
「くすぐってえ」
「我慢でし♪」
書かれたのは〝Ha.〟という文字。
「げっ、また髪か」
「行きましゅよ~」
ロイはぶんぶんと腕を回し、いきなり俺に飛びつく。避ける間もなくロイは俺の髪の毛を数本むしり取り、見事着地した。
「エナジーゲットでし☆」
ロイの手の中で、髪が白髪に変わり、消えた。
ロイは盟約相手から何か一つを奪い、そこから〝エナジー〟を手にする。そのエナジーを自らの力に変換し、盟約相手の望みを叶えるのだ。
「こないだ貯めたエナジーがあんだろ。それ使えないの?」
「それは貯蓄分でし。いざとなったとき、ユンしゃんの身を守るためなんでし。まあ、貰うのはエナジーじゃなくても、物でもいいんでしゅけど――ユンしゃんの持ち物で僕が欲しいもの、無いんでし」
「まあ貧乏人だしな。だったら学院の金持ち連中に憑けば良かったんだぜ?」
「僕、根性曲がった奴等は嫌いでし」
俺も真っ直ぐではないと思うんだが、ロイは俺を選んだ。理由は未だわからない。
ロイの身体が、ふわりと宙に浮いた。
「じゃ、行ってくるでし」
「よろしく。家で待ってるからな」
手を振ると、ロイはにこりと笑って手を振り返す。すぐにロイの姿は空の彼方に消えた。
何事もなかったように、俺は道を歩いて行く。左手に抱えた教科書が重い。広場を抜け、商店街を抜け、裏通りの湿った路地に着く。しばらく歩くと、俺の暮らすボロアパートに辿り着く。
俺の部屋は二階の端。立て付けの悪いドアを開けると、かび臭いにおいがする。柱はガタがきてるし、床は歩くたびギィギィ鳴る。地震が来たら、かなりの確率で倒壊するだろう。
俺がこの町に来て学院に入学したのは二年前のことだ。故郷の村には、両親と、五人のきょうだいが暮らしていた。その『きょうだいたちの中で一番出来がいいから』という理由で両親は俺をここへ寄越し、何の偶然か俺は入学試験に合格し、奨学生として入学した。
奨学生枠は、各学年に一人。他の三百人弱はみんな金持ちの息子や娘だ。貧乏人は、その中で異質な存在。同じ人間と見られていないようなもの。皆、俺を遠巻きにする。その中で近付いてくるジホンたちは、案外変わり者だ。
ここは望んで来た場所ではない。まあ、故郷の農村で暮らすのもここに居るのも大差はないが、好んで学院に居るわけではなかった。
「おっかしーなあ……。入学試験に受かるはずなかったのに」
ごろんと横になり、しかし今さら言っても仕方のないことだと考えるのをやめる。
そのうちにロイが帰ってきた。
「ただいまでしー。…ユンしゃん、眠ってるんでし?」
「勉強してんの」
目を開けると、俺の前に魚があった。
「買って来たの?」
ロイは首を振る。
「釣って来たんでし」
「………」
釣って?
目をぱちくりさせていると、ロイがあっさりと言った。
「市場に新鮮なものは無かったから、盗るのやめたんでし。僕が釣ったやつの方が美味しいでし」
「すげえな」
もっと褒め称えてやりたかったが、あいにく言葉にならなかった。その大きな鯛を、ロイは台所に持っていく。
「すぐに夕飯でし。ユンしゃん、皿」
「はいはい」
俺は起き上がる。
ロイは手際よく魚をおろし、刺身にして皿に並べた。ロイの器用さは宝だ。
テーブルがないので、ダンボールを代わりにして料理を並べる。ロイと向き合って食事をするのは、これで90回目だ。
「いただきましゅ」
「はい、いただきます」
ロイの魚は新鮮で、俺は今までこんな美味い魚を食べたことがなかった。
「お前、漁師になれんぜ、ロイ」
「ユンしゃんは学者になるんでしか?」
魚に目を向けたまま、鋭くロイが俺に訊いた。こいつは時たまこういう不意打ちの質問をする。
「俺の頭脳レベルわかっててそれ言うのかよ。この前のテスト、何点だったか覚えてるか?」
「国学30点、理科12点、語学28点、数学8点。全部100点満点、学年288位」
「俺より下が2人居たってのがすげえよな」
「1人は欠席でし。ユンしゃん……もう少し真面目にやるでし。実力を出すんでし」
「俺に実力なんか無えよ。入学試験に受かったのもマグレだもんな」俺は鯛を口に運ぶ。「これマジで美味いぜ、ロイ」
「そうでし? 喜んでもらえて嬉しいでしゅ」
ロイは満面の笑みを浮かべ、新鮮な鯛を食べた。
食後の後片付けは俺がやった。家事の役割分担ができているのだ。調理と食材の仕入れはロイ、俺は片付け。お互いの苦手部分を補う、完璧な分担だ。
ボロアパートの共同風呂から上がって部屋に戻る。窓を開けると、清々しい風が入る。このアパートで唯一好きなのは、風通しがいいところだ。
「ユンしゃん。明日も学校行くんでし?」
「ああ。明日サボると単位を落としちまう」俺はタオルを片手にロイに近付く。「ほら、ちゃんと髪を拭け。風邪ひくぞ」
「あはは、ユンしゃん。僕は人間じゃないから、平気でし」
ロイは笑って、それでも大人しく俺に髪を拭かれている。世話のかかるヤツだ。
食後に水を一杯飲んで、俺とロイは寝転がる。ロイはパジャマを着て寝る。更に布製の、二等辺三角形のだらんとした帽子をかぶる。三角形の先には丸いボンボンが付いている。ロイはそれを愛用しているのだ。
「お前さあ、どっから来たの? ロイ」
ロイはもう目を瞑っている。
「んー……色々でし。世界各国廻ってるんでし。韓国は初めてでしゅが」
「何のために?」
「盟約者を探すためでし……」ロイは欠伸まじりに話す。「僕らは、時折エナジーを貰わないとまずいんでし。僕、好き嫌い激しいから、気に入った人間じゃないと盟約者にしたくないんでし」
「そんで俺?」
「ユンしゃんのことは気に入ってるんでし」ロイの声が小さくなる。「僕もう寝ましゅよ……」
「ああ、おやすみ」
すぐにロイの寝息が聞こえてくる。
時たま盟約を結んでエナジーを取り、それ以外はこうして一緒に生活をする。奇妙な生活だが、話し相手が居るというのは悪くない。
(でもまあ、いつまでも続くわけでもないだろう)
共に過ごして一ヶ月。
ロイとの共同生活は上手くいっていた。ロイは出て行く様子もない。俺も追い出すつもりはない。きっと、去るときは不意に出て行くのだろう。散歩に行くと出て行って、戻って来ないみたいに。
毛布とも呼べないタオルをロイに掛け、俺も目を閉じた。
*
俺の一日はこうだ。
まず、ロイに起こされる。そうすると大抵朝食ができているので、それを食べる。俺が皿を片付ける。ロイが今日は学校に行くのかと尋ね、行くと答えると鞄を持ってくる。
学院に着くと大体2時間目が始まる時間だ。俺は教室に入り、寝る。昼には起きて、広間でロイと食事をとる。午後の授業では欠伸が絶えず、帰り際に教師に叱られる。
家に戻り、食事をして風呂に入り、寝る。ロイが居ても居なくても、まあ同じスケジュールだ。
その日は学院で、卒業課題についての説明を受けた。一年弱かけて、卒業課題に取り組まなくてはならないのだ。
俺に与えられた課題は数学だった。ぶ厚い冊子をぱらぱら眺め、鞄に押し込む。
「ユンしゃん。それ難しそうでしね」
「んー」
気のない返事をして廊下を歩いていると、ジホン一派と出くわした。彼らも課題の冊子を持っている。
「よう、ジホン」
こっちから挨拶すると、ジホンは不敵に笑って俺を見た。
「よう貧乏者。お前も課題は貰えたか?」
「まーな」
「俺は数理だったぜ。アルファマーの定理だ。貧乏者、お前は?」
「ユンしゃんにはちゃんと名前があるでし!」
ロイの言葉は、ジホンには聞こえない。
「俺も数学だよ。定理は違うけど」
ジホンと取り巻きはケラケラ笑い、お前に数理ができるのかと詰る。ミソンが俺の鞄を奪い、冊子を見つけた。
「げっ、こいつ生意気。フェレスタの証明だぜ」
「ユンには無理だろ。こりゃ落第だな」
彼らは一通り笑い、最終的にジホンが鞄ごと俺の教科書類を窓から投げ落とした。ロイがそれを落とすまいと窓から飛び降りようとしたので、慌てて止めた。
鞄は、弧を描いて池に落ちた。
「無駄なもんは捨てるんだな、ユン。これで荷物がなくなった。肩が楽だろ」
ジホンたちは大爆笑だ。俺はロイを止めるので必死だった。今にも彼らに突進しようとしているのだ。
「ユン。お前、何だその格好」
「いや……」
ロイが見えないジホンらには、俺が何を抱えているかわからない。暴れるロイを、必死に押さえつける。
「荷を軽くしてくれて礼を言うよ。じゃあな、ジホン」
とにかくロイを引っ張ってその場を離れる。教科書を捨てて満足したのか、ジホンらはもう突っかかってこなかった。
「ユンしゃん何してるんでし!」
校舎裏でロイに怒られた。
「何って……」
「あんなにされて、何で黙ってるんでし! 反撃するんでし! あいつらユンしゃんのこと馬鹿にして……、ユンしゃんは……!」
「あーもう、泣くな」
「泣いてないでし」
ロイはぷいっと横を向く。
頭を掻いて、とりあえずロイの気を鎮めようと努めてみる。
「あのな、ロイ。俺には教科書なんて必要ねえよ。最初から要らないものだったんだ」
「教科書がどうとかじゃないんでし。ユンしゃんは怒らない。ジホンたちに何をされても、全然気にしない。人との関わりを持とうとしないんでし」
「あー、うん。それはそうかも」
頷くと、ロイは俺の目をじっと見つめた。
「ユンしゃんの心は常に凪。何をされても感情は一定で、変わらないでし。誰もユンしゃんの心に干渉できない。それは強いことでし。でも、本当に感動したり、人を愛したり出来ないってことなんでしよ!」
「話題がすり替わってんなあ」俺は苦笑する。「仕方ねえって。昔からこうなんだよ。だけど見抜かれたのは初めてだ。すげえな、ロイ」
涙を手で拭いてやると、ロイは鼻をすすった。
「ユンしゃんは海みたいでし。何でも飲み込んでしまう。誰も海には勝てないでし」
「変なこと言うなあ。現に俺、色んなものに負けてんぜ?」
「それは勝ちを譲ってるんでし。ユンしゃんが本気を出せば、多分――」
「たぶん?」
ロイはキリッと眉を釣り上げた。
「月も壊せるでし」
「…いや~……それは無理じゃないかな」
*
ロイと暮らして二ヶ月が経った。
出会った日から、俺とロイは変わらない。お互いの存在が、お互いに影響を及ぼすことがないということだ。どちらかが消えても、どちらかに支障はない。依存と真逆の関係。
その日は学院が休みで、天気も良く、俺たちはピクニックに出掛けた。ロイと話がしたいので、なるべく人気のない場所を選ぶ。大通りでロイと話すと、独り言が目立ってしまう。
「今日のお昼は僕が焼いたパンでし」
ロイはスキップをして、俺の先を歩く。結局、俺たちが向かったのは学院だった。休日の学院には誰も居ない。
柵を飛び越えて中に入ると、スキップをしていたロイがいきなりコケた。
「おいおい……大丈夫か?」
ロイは地べたに寝そべっている。起こすと、ロイは泣き顔になっていた。
「ユンしゃん~……」
「どっか打った?」
ロイは首を振る。
「平気でし。ちょっと膝に擦り傷作ったくらいでしゅ」
「あ、これ落としたぜ。何だ、この布の袋――」
ぶ厚い布の袋を拾うと、中から何か出てきた。
カツン、とそれが地面に落ちる。
瞬時にロイの顔色が変わった。
「ん? 鍵か、これは――」
気付くと目の前に鍵が無い。ロイは青い顔で両手をぎゅっと握っている。
「お前、いつ拾――」
ロイは慌てて周囲を見渡す。
「Someone Here!?」
「あ? いや誰も……」
英国語だ。ロイはほっとした様子で手のひらを開く。
「これは……、誰かに見つかったらまずいんでし」
「そのボロい鍵が?」
ロイは頷いた。
木製でもプラスチックでもない。それは汚れていて、白く、歪な形をしていた。果たして鍵としての役割を果せるのか疑問だ。
ロイの手のひらより少し大きいそれを、ロイは大事に袋に仕舞い、ポケットに入れた。
「僕には必要ないものだけど、でもとっても大事なんでし」
ロイは服についた砂を払い、いつものように俺に笑ってみせた。
「驚かせてごめんなしゃい。早くご飯食べるでし」
「ああ……」
俺とロイは互いに互いを干渉できないけど。
このとき初めて、ロイの心の奥を垣間見たと思った。
食事をとるのは、池のほとりにした。
俺は、ロイが作ったパンを袋から出し、一つをロイに手渡した。袋にはまだ四つのパンが入っている。
「ユンしゃん。僕、本屋になりたいんでし」
唐突にロイが言った。
「本屋?」
「そう。ずっと前からの夢なんでし。本だけじゃなく、色んなものを売ってみたいでし」
「って言っても、お前の姿誰にも見えないんだぜ? 妖怪相手の商売やるしかねえな」
「勿論でし。悪魔や妖怪、精霊たち相手の商売でし。楽しそうでし?」
「あー、どうだろう。俺、お前以外のそういうのに会ったことねーから」
ロイはごろんと寝転がる。
「でも今のままじゃ無理なんでし……。僕、追われてるんでしゅよ。世界各国を巡ってきたのも、半分は逃げて来たからなんでし」
「お前、前科何犯なんだよ」
「違いましゅよ~。僕の境遇が悪いんでし」
ロイは足をばたつかせ、はあ、と溜息をついてからパンを齧る。
「あ、これ美味しいでし」
「お前、料理も案外うまいよな」
「『案外』は余計でし」
ロイは俺の隣でパンを齧る。池を眺めながら、俺もそうした。
「…日差しが強くなってきたな」
俺は帽子を深くかぶる。
「ユンしゃん、その帽子可愛いでし」
「俺、ボーダー柄が好きなの。いいだろ、これ」
「うん。僕がお店出したら置いてあげましゅ」
よろしく、と言って池を、空を眺める。
のんびりしている。
俺には将来の展望がない。俺が学院に入ったことを手放しに喜んでいた両親は、俺を政治家や学者にさせたいみたいだった。確かに、この学院の出身者は大体政治家か医者か大学の教官になっている。でも俺は、そんな人生を望んでいるわけではない。かといって、何かやりたいことがあるわけでもない。このままで、日々が過ぎていけばいいと思う。
二つ目のパンに手を伸ばそうとしていたとき、背後に気配があった。
そいつらも俺に気付いた。見慣れている、ジホンたちだった。いつもの四人だ。俺は呆れて言った。
「賭博は禁止されてんぜー」
四人の動きがぴたりと止まる。
「何で……っ」
「ポケットからカードが見えてんだよ。それに、話し声もちょっと聞こえたしな。幾ら賭けるかって」
ジホンらは不敵に笑い、俺に近付く。
「密告しねえから安心しろよ。俺なんかが言ったところで誰も信じねえだろ」
「それもそうだな」ジホンは腕を鳴らす。「ところで貧乏者が休日の学院で何してんだよ。こそこそ勉強か?」
「昼飯だよ。見て分かれ」
俺は手の中のパンを示す。
ジホンはふっと笑った。と思ったら、ジホンの拳が俺に飛び、俺は後方に吹っ飛ばされた。
頬がじんじん痛む。目を開けると、ジホンの姿があった。俺の胸を踏みつけ、立ち上がれなくしている。
「ユンしゃん!」
俺は片手でロイを制す。
「ユンしゃん、盟約を結べばそいつに勝てるでし。倒せるんでし!」
「うるせえよ……。インチキで勝ってどうする」
「あ? 何か言ったか」
ジホンが足に力を込める。少し息苦しくなった。
「貧乏者が、勝手に学院に入って来んじゃねえよ!」
パンの入った袋が放り投げられる。ジホンの手下たちが、俺の荷物を次々と池に放り込む。俺の、帽子も――
それらは酷くゆっくり見えた。ひとつひとつが、池に沈んでいく。俺の、数少ない所有物が。
「ははははは!」
下品な笑い声。手を叩く音。
気付いたときにはジホンたちは居なかった。遠くで笑い声が聞こえる。俺はしばらく、呆然としていた。
「ユンしゃん」
ロイの声。
俺の目の前に、いつものロイの顔。
「珍しく怒ったでし?」
「あの野郎……俺の帽子投げやがった」
「そこが気に障ったんでし?」
ロイは呆れている。
「何よりお前のパンを台無しにした。あれ美味かったのに」
「パンならまた焼けましゅ。ユンしゃん、頬を」
ロイが俺の火照った頬に触れる。
ひんやり冷たい。
「気持ちいい」
ロイはにこりと笑った。
「僕は〝水〟なんでし。このまま冷やしておいてあげましゅ」
「珍しく優しいな」
「いつもでし」
本当に水に冷やされている感触だった。頬が熱を失っていく。
「ロイ」
「何でし?」
「月を壊して来てやろうか」
ロイはきょとんとする。
それから、ニコッと俺に笑みを向けた。
「是非お願いしましゅ」
*
翌日、学院に行った。サボりたかったのだが仕方ない。
さらに、俺としては珍しく、その次の日も学院に言った。学院が騒然としていることに、すぐに気付いた。
「何でしゅ?」
「さあ?」
人だかりの中央に居たのはジホンだった。教師たちが周りを固め、さらにその周りを学生たちが囲っている。
「すげえな、ジホン!」
「アルファマーの定理の新しい解法を編み出したんだって?」
「大発見じゃん」
学生たちが興奮ぎみにそう呟いている。
「アルファマーってジホンの卒業課題でし?」
「だな」
少し離れて高い場所から覗いてみると、ジホンは中央で鼻を高くしていた。教師たちも学院始まって以来の栄誉だと称えた。
「こりゃ今日は講義どころじゃねーな」
「でし」
帰ることにした。これ以上ここに居ても意味はない。
人だかりをすり抜けようとすると、ジホンが器用に俺を見つけた。
「よう、劣等生! 俺の活躍を聞いたか?」
「ああ……」
ジホンの顔は勝利に酔っている。にやにや笑って薄気味悪い。
「国立大学の推薦状が貰えるそうだ。俺が学者になったら、下働きにでもしてやるよ」
「ああ、ありがとな」
俺はそう言って、ジホンから離れる。人だかりは、ジホンの名前を大合唱していた。
「感じ悪いでし」
「仕方ねーよ。大発見らしいからな」
俺はボーダーの帽子をかぶり直し、ロイに言った。
「俺、昼飯は麺が食いたい」
「同感でし。食べに行くでし」
ロイと並んで、市場まで歩くことにした。
*
開け放した窓から、ひんやりとした風が入る。
俺は目を閉じ、窓辺にもたれていた。
「ユンしゃんー。ご飯できたでし」
ロイの足音。近付いてくる。
「何してるでし?」
「勉強してんの」
「そうでしゅか。じゃあ邪魔しないでし」
ロイはあっさり引き下がった。テーブル代わりのダンボール周辺でカタカタ音がするから、食器を並べているのだろう。
いい匂いがしてきた。俺は目を開ける。
「勉強終わったでし?」
「んー」
のそのそとダンボールに近付き、ロイが「いただきましゅ」と手を合わせる。俺もそうした。
今日の夕飯は魚の煮付けだ。夕方に俺の髪と引き換えたエナジーで得た夕食。
「何の勉強してたんでし?」
「睡眠学習」
ロイはふっと笑う。
「嘘でしゅね。卒業課題でし? 出来そうでしゅか?」
俺はぴたりと手を止める。
ロイを見ると、いつもと同じ笑み。
でもそれが、不敵な笑い方に見えた。
「知ってましゅ。ユンしゃんは本当に勉強してたこと。卒業課題、ユンしゃんは全部憶えてましゅ。それどころか、いつもの講義の内容も、ユンしゃんは全部暗記してましゅ。ユンしゃんには教科書もノートも本当に必要ない、頭の中で計算できてしまうんでし」
「……それは買いかぶりだろ?」
ロイは首を振る。
「ユンしゃんは本当に、本当に頭が良いでし。天才なんでしゅ。講義なんてユンしゃんには退屈なだけ。簡単すぎるんでし」
「俺のテストの点知っててそれ言うか?」
笑って言ったが、ロイは笑わなかった。
「先々月のテスト、数学9点。先月のテスト、8点。今月は7点。1点ずつ、わざと下げてましゅね。こんなこと普通できないでし」
「………」
ロイは食器を置き、俺を見た。
「ユンしゃんには上を目指そうという意欲がないでし。その気になれば本当に何でも出来るのに、やろうとしない。世の中なんて、ユンしゃんには退屈なだけでしか?」
「ロイ……」
ロイは俺から目を離さない。
「僕にはそれがもどかしいんでし。ユンしゃんは何でも出来る力を、頭脳を持ってましゅ。でも誰にもそれを見せない。何ででしゅか?」
「……」俺は少しのあいだ返答に詰まる。「例えばその天才が俺だとして、頭が良いことを周囲に知られたら必ず妬まれ、恨まれ、過剰な期待をされ、良いことなんてあるわけないだろう? 過去の天才たちはみな不幸な人生を送ってると、俺は思う。普通の幸福な人生なんて送れやしないんだ。だったら黙ってた方がいい」
「宝の持ち腐れでしゅね」
ロイは小さく息を吐き出し、また言った。
「ユンしゃんはこれまで、力を抑えてきた。その明晰な頭脳を知られないようにしてきた。それでも、有名な学院に入り、教師からも期待をかけられてるんでし。黙ってたって、滲み出てしまうんでしゅよ」
「期待? かけられてるか?」
「入学試験の成績、ユンしゃんはトップだったんでし。奨学生枠だけでなく、全ての学生の中で1位でしゅよ。職員室に忍び込んで確かめたから、間違いないでし」
「お前、そんなことを――」
「だからみんな言うんでし。やる気があるのかって。手を抜くなって。気付く人間は気付くんでしゅよ」
俺はヒラヒラ手を振った。
「空論だな、ロイ。俺は馬鹿な劣等生って方がよっぽど信憑性があるぜ」
この話題を終わらせたいと思った。俺は煮魚に手を伸ばす。
「……アルファマーの定理」
ぼそっと、ロイが呟いた。
「ジホンの卒業課題がどうかしたか?」
「解いたのユンしゃんでし?」
確信に満ちた声だった。
俺を見抜く、ロイの瞳。
「ジホンには解けない。僕にはわかるんでし。あいつの頭のレベルじゃ、あの定理を解くのは無理でし」
ロイは軽く右手を上げる。
その手が歪む。水だ。片手が水に変化し、ゆらゆらと透き通る。
「僕は人間じゃない。ランズの一員なんでしゅ」
「ランズ?」
「かつて、一人の孤独な王が居た……。王は自らのガーディアンを、自らの骨から造ったんでし。正確には、骨と自然属性からですが。僕は〝水〟属性。水の者は人の知性を好む。知性の高い人間のエナジーは最高のご馳走なんでし。だから、僕には〝天才〟が分かる」
「お前、実は……すごいんだな」
俺が言えたのはそれだけだった。ロイの腕は元に戻っていく。
「ユンしゃんが見た〝鍵〟。あれがオーランドの骨なんでし。あれを狙う悪魔や精霊は本当に多いんでしゅよ。骨を手にすれば、強大な力を得ることが出来るからでし。僕の前に〝水〟のランズだったロイⅠ世も狙われ続け、それが嫌になって僕に骨を渡したんでしゅ」
「渡した?」
ロイは頷く。
「ずっとずっと前に、ロイⅠ世と僕は出会った。その頃の僕は、ヨーロッパの片田舎の精霊だったんでし。ロイⅠ世は、僕に骨と名前を渡し、ランズの地位から降りた。強大な力は僕のものになったんでし。それ以来、僕に安息はありませんでしたが」
ロイは俺を見て、少し笑った。
「僕とユンしゃんは似てましゅ。大きな力を上手く扱えず、振り回されてばかり。だからそれを誇示せずに隠す。それでも近寄ってくる者たちは、みんな敵。ほら、そっくりでし」
首を傾けて俺を見るロイ。
何だか少し悲しそうな笑みだ。
「でもね、ユンしゃん……。長いあいだそうしていくうちに、どうしても力を発揮しないといけない場面が何度もあったんでしゅ。どうしても相手を倒さないといけないときが。僕は何人もの妖魔や悪魔や、時には同族も倒した。そうでないと、この骨が奪われ、力が悪用されるからでし。僕はこの骨を守らなきゃならなかったんでし。こんな力、要らないけど、でも捨てられなかったんでしゅよ。それは僕が持っているのが一番良かったから」
ユンしゃん、とロイが呼んだ。
「たまには力を解き放つんでし。…もっと早くこう言えば良かったんでしゅけど……。ユンしゃんがジホンを出世させるなんて意味不明なことをする前に」
「何であれを解いたのが俺だと?」
「解けるのがユンしゃんしか居ないからでしゅよ。大方、ジホンの机の中に解答のメモでも忍ばせておいたんでし? ユンしゃんが二日続けて学院へ行くなんておかしいんでしゅよ」
「…は、あははは」
俺は笑った。腹を抱えて。
ロイが俺を見ている。
「ユンしゃん?」
「すっげえ空論だよ、ロイ」
「この期に及んでまだしらを切るんでし?」
ロイは呆れている。
「俺は天才じゃねえって」
「ユンしゃんは天才でし」
言い切るロイに、俺は笑って言った。
「俺は貧乏者で劣等生の『ユン』なの。さ、飯食おうぜ? ロイズレッド=アルジャイン=ランベルク=リーノ=フェロン=ワイズⅡ世」
*
小さい頃から、俺は何にも興味を持たなかった。
学校なんてつまらなかったし、話の合う奴も居なかった。娯楽だって俺には何が楽しいのかわからなかったし、家も居心地は悪かった。
世の中は乾燥していて、味気ない。
それでもここで生きていくためには、力を出してはいけなかった。制御し、気をつけて気をつけて生きてきた。少しでも気を抜けば周りの全てが敵になる。俺を馬鹿だ、怠け者だと相手が思っていてくれる方が楽だった。
それでも両親は俺に学院の試験を受けさせた。ひとえに他のきょうだいたちの出来があまりに悪かったからだ。
入学試験では手を抜いた。
わざと何問も間違えた。俺が受かるわけなかった。
が、俺は受かった。酷い学校だ、あんな成績で合格するなんて。いっそ白紙で出してやれば良かったと後悔した。両親も町の人間も手放しで喜び(妬む同級生も勿論居た)、俺は町から離れた。
学院では勿論、力を出さなかった。貧乏者は金持ちに勝ってはいけない。もしそうすれば、劣等生でいる以上の不運が襲ってくる。金持ちが牙を剥けば、俺を破滅させることなど簡単だ。
全てが面倒だ。全力を出すよりも、適度に力を抜く方がよっぽど難しい。
それでもこの町へ来て、一つだけ興味を持つことに巡り合えた。
それは、俺の同居人。
ロイⅡ世が話した、ランズという存在だ。
「ジホンはもう英雄でしね」
学院で、人だかりの方を見つめてロイが呟いた。
俺は教室の片隅から、ジホンの緩んだ笑みを眺めていた。
あれから一週間。新聞の取材が何件も来て、ジホンは天才少年として名を馳せた。有名大学への進学も決まった。
「可哀想になー。ちょっと酷いことしちまったかな」
ぽつりと呟くと、ロイが俺を見た。
「どういうことでし?」
「ほら、あいつ馬鹿だろ。実力が伴ってないのに力を得ちまったわけ。そういう人間って、どうなると思う?」
ロイは考える。それから、顔色が徐々に曇っていった。
「ユンしゃん、意地が悪いでし」
俺は笑った。
「天才の復讐ってそういうやり方なんでしゅか? メモ一枚で復讐なんて」
周りに聞こえないよう、こっそりと笑う。誰も彼もジホンの方を見ている、大声を出しても気付かれなかったかもしれない。
「あいつ、どうやって破滅するかな。学者になって難問を前にして、初めて何も解けないって気付く。今まで散々持ち上げられたのに、無能だってわかる。必ずどこかでボロが出るはずだ。ああ、学者にすらなれねえか。進学しても成績は散々だ。周囲からの期待が重荷になる。周りも段々気付くさ、馬鹿だって。あいつから離れていく。あいつは過去の栄光に縋り続ける」
「遠まわしに意地悪するために、アルファマーを解いたんでしね?」
「ああ。面白れえだろ。……でも、それも最初だけだったな。もう飽きた」
緩んだジホンの顔は見飽きた。あれが絶望に変わる未来を、俺はもう見えている。
「長い計画でしゅね。当分ジホンは英雄でしゅよ?」
「持ち上げられる期間が長いほど、叩き落されたときに痛いのさ。可哀想だから、さっさと叩き落してやろうか?」
「え? 出来るんでし?」
俺は紙切れをロイに手渡す。ロイはそれを眺めた。
「これ」
「そ。それが、奴に渡した解法の本当の正解。あのやり方じゃアルファマー解けねえんだよ」
ロイは、信じられないという目で俺を見つめる。ジホンの大合唱が聞こえる中、俺たちはこそこそと話をした。
「じゃあ、あの解法は間違ってるんでし!?」
「そ。0.0001の計算間違いが含まれてる。その計算違いで、アルファマーの定理は成立しない。誰もそれに気付いてない。例えば、奴の解法を掲載した新聞に、匿名でそれを投書したら――さあどうなる?」
俺が笑うと、ロイも笑い返した。意地の悪い笑みだ。
「本当に遠まわしな意地悪でし。ユンしゃんがやったってわからないでしゅよ」
「それがいいんだよ。そうすりゃ、俺が復讐されることもない。これが正しい復讐の仕方だ」
俺は壁から背中を離し、歩き出す。ロイも付いて来た。
「ここも飽きたな。つまんねえ」
「ユンしゃんは最初っから、何にも満足なんてしてないでし」
それが当たりだ。今までそんなことを俺に言う奴は居なかった。
ボロアパートで、ロイが鍋を作った。恐らくそれが最後の食事になることを、俺はなんとなく悟っていた。
「ユンしゃんは、人間の世界なんか飽き飽きしてるんでし?」
湯気越しに、ロイが問いかけた。
「ああ、そうだよ」
「こっちも似たような世界でしけど――少しは退屈しのぎになるかもしれないでし」ロイは俺を見ない。「ユンしゃん。こっちの次元に来てみましゅか?」
俺は少し笑い、ロイを見つめる。
悪魔。精霊。妖怪。そのどれでもない、ランズという存在。
俺は、ロイに言った。
「骨をくれよ、俺に。人間でもランズになれるか?」
「なれましゅよ、多分。人間からランズになった話なんて聞いたことないでしゅけど」
ロイは、ポケットから布の袋を取り出す。
それが、神秘的なものに見えた。
「ずっと、この骨を譲渡できる存在を捜してたんでし。僕は、僕より頭の良い人にこれを渡そうと決めてたんでし」ロイは俺を見つめる。「そして、ようやく見つけました」
ロイの手の中の、鍵型の骨。
それが光を放った。
「今からこれをユンしゃんに譲渡します。覚悟は?」
「いいぜ」
手のひらを開いて差し出す。
光を放った骨が、俺の手に落ちる。
水に包まれた、と思った。
俺の指先が、腕が、身体が、部屋中が。
全てが水と化す。
そして、圧倒的な力を感じた。
水の向こうの、ロイの姿が霞む。
「ああ、これで解放された――これでやっと、本屋になれる」
「お前まさか、本屋になるために?」
呆れて笑った。
ロイも水の膜の向こうで笑っている。
「また会いましょう。今度は別の立場で」
ロイの顔が波に揺られる。
段々と見えなくなる。
「…お前、本当はちゃんと話せるんだろ?」
にこりとロイが笑った――ように感じた。
「何の話ですか? ユンさん」
水を伝播して伝わる想い。
ロイが俺に手を伸ばし、俺の右手に触れる。
小さく握手。
「さようなら。楽しかった」
「俺も」
手が離れ、
ロイが去る。
「いつかまた」
「ああ。どこかで」
水が俺の内に戻る。
圧倒的な力の洪水。
ロイⅠ世が、Ⅱ世が守り抜いたものが、俺に宿る。
そうして全てが終わったとき。
俺はいつものようにボロアパートに居た。
でも違う。
世界が違う。
俺はもう、ここで暮らしていい存在じゃない。
「…さて。行くか」
最後に俺のものだった帽子を置いて。
違う世界を旅しに、出掛けた。
*
考えてみれば、ランズという立場について俺は詳しく知らない。
でも、ランズになって四半世紀、ようやく分かりかけてきた。骨を狙ってきた奴等や、噂で聞くのだ。ランズがどれほどの存在か、ランズになった後で知った。
この世の覇者オーランド。
それに次ぐ力を持つランズ。
つまりは、この世のナンバー2だ。まあ、そのナンバー2『ランズ』が何人か居るのだが。とにかく凄い力を、俺は得たことになる。俺の頭脳なんかよりもっともっと凄い。
「ロイの奴……。そんなに凄いなら先に言っとけよ」
〝水〟の力は俺に上手く合った。力の使い方も覚えたし、ランズとしての生活にも馴染んだ。学校や社会という枷が無くなった分、前より自由だと思える。
ロイとはあれ以来会っていない。骨を失ったあいつは、どうしているだろう。自由になれただろうか。
いつものように、屋根の上から町並みを眺めていると、俺の内の〝水〟が揺らいだ。
「ん?」
何か、遠くから響いてくる〝音〟。
これは――
「呼ばれた? 俺」
映像が浮かんでくる。俺の知らない奴。
こいつも、骨を持ってる……?
立ち上がり、東を眺める。
「行ってみるか。面白いことあるかもしんねーし」
屋根から飛び降り、着地。
さて……、
今度の目的地は、東。
なあ、ロイ。
俺はまだ月は壊せていないけれど、
少しはそこに近付けてる気がする――
ヴェルナンディの鎖

ねえ、あなたに名前をあげる。
とっても愛らしいあなたに。
ずっとずっと側にいてね。
私がずっとずっと、名前を呼ぶわ。
そうね……、こんなのどうかしら?
Your name is Velnandy.
いいよ……、じゃあ契約しようか。
僕に名前を付けた君に。
君が僕に与えるのは、ずっと先でいいよ。
君が望むとおりにしてあげる。
僕が君に与えるもの。
それは、僕の守護。
僕がずっとずっと守ってあげること。
I am your Guardian.
*
ここはドイツ東部の街。
あたしの家は、小さな丘の上に建っていて、山脈を覗く美しい風景が見られるのだそう。
町には時代遅れな水車が幾つかあって、山脈や自然の美しさに、観光地として賑わっているんだそう。
あたしの部屋は二階の中央。
ベッドはふかふかで寝心地がいい。棚はあたしの好きな木のさわり心地。パパとママは優しい。家政婦さんもいいひと。
わかっているのはそれだけ。
感じられるのはそれだけ。
「ねえ、ヴェルナンディ。つまらないわ。外の景色ってどんなのかしら?」
〝見てみたいの? エリィ〟
「いつか見てみたい。今、無理なのはわかっているの。いつか、あたしの目に光が宿るときは来るかしら」
〝君はそれを望むの? この世に綺麗なものなんてないよ。見たら君が穢れるだけさ〟
「ねえ、ヴェルナンディ? あたしね――」
コンコン。
ドアをノックする音。
ママだということは、すぐにわかった。足音でわかる。目が見えないあたしは、聴力が優れているから。
「エリィ。朝食よ。あなたの好きなエッグトーストを作ったわ」
「はぁい、ママ。いつもありがとう。頂くわ」
ママはあたしの手を取って立たせる。
いつもと同じ朝。
変わることはない日常。
あたしはエルザヴェート=ドット、12歳。
ドイツの生まれ。育ったのもドイツのこの家。
あたしは生まれつき目が見えない。色を知らない。景色を知らない。美しさを知らない。
色を、世界を、知ってみたいと思う。今は、音から世界の欠片を得ている。
一体、見えるってどういうこと?
パパやママの顔って、どんな?
あたしの、顔も?
パパやママはあたしを可愛いと言うけれど、本当かしら。だって――
「不細工エルザ! 今日も可愛くねえっ」
クラスメイトのシュヴァルツはいつもあたしを貶すから。
あたしはぐっと唇を引く。相手になんかしてやらない。
「酷いわね、シュヴァルツのやつ」
「エリィ、とっても可愛いのに。あいつ、本当は貴女のこと好きなのよ」
「貴女に近付けないから拗ねてるんだわ」
女友だちは優しい。あたしを大事にしてくれたし、あたしも彼女たちが好きだった。
授業は、視覚でしかわからないことは、先生や友だちが言葉で伝えてくれた。あたしは成績も悪くなかった。
シュヴァルツはそれが気に入らなかったのかもしれない。目の見えないあたしが、みんなの輪に入って大事にされているのが。
ある日、体育の授業のあとだった。
あたしは体育倉庫でボールを探していた。体育も、できるだけ参加していたけれど、どうしても出来ないときは裏方をしていた。ボールが茂みに入ってしまったので、新しいボールを倉庫へ取りに来たのだった。
だけど、今日に限って見つからない。手探りで探していると、誰かが入ってくる気配がした。
すぐにシュヴァルツだとわかった。
「遅せえよ。何してんだ、トロいな」
「今持っていくわ」
ようやく見つけたボールを、シュヴァルツが奪った。
「お前、いい気になんなよ。みんなお前をちやほやしてるけどな、本当はみんなお前なんか邪魔だと思ってんだよっ」
「シュヴァルツ……?」
「何だよ、みんなエルザエルザって。お前なんかどっか行っちゃえばいいんだ」
そのとき、確かあたしは泣いた。
目頭が熱くなった。苦しくて泣いた。
シュヴァルツの足音が、二歩分聞こえたときだった。
ガララララ!
すごく大きく、何かが倒れる音が聞こえた。
振動がした。
埃が舞い上がったのだろう、くしゃみが出そうだった。
先生が、級友が、倉庫へやって来た。
「どうしたんだ!」
「シュヴァルツ!?」
大丈夫か、とか、ドクターを、という声が聞こえた。
シュヴァルツに何かあったのだとわかった。
背筋が寒かった。何か大変なことが起こったのだ。
あたしが事情を聞かされたのは、シュヴァルツの手術が済んだあとだった。
倉庫の中に置きっぱなしになっていた鉄柱が、倒れて来たんだという。シュヴァルツは下敷きになった。一命は取り留めたが、後遺症が残るかもしれないという。
「エリィ。貴女が責任を感じることはないわ」
「そうよ。事故なんだから」
「でもエリィ、聞かせておくれ。何か、変わったことはなかった? そう……、君が何か蹴ったりとか」
「エリィ。気にしなくていい。あれは事故だったんだ」
「ねえ、ヴェルナンディ。シュヴァルツが鉄柱の下敷きになったわ」
〝ふうん〟
「あたしの所為かしら。あたし、本当はあいつなんか死んじゃえばいいって思っていたの。あたしがそんなこと考えたからかしら」
〝エリィが気にすることないよ。あんな奴、怪我して当然なんだから〟
「人が死ぬのを望むのはいけないわ。ヴェルナンディ。あたしよくわかったの。怖い。とっても怖いわ」
〝大丈夫だよ、エリィ。前から言ってるじゃない。僕がずっと君の側に居るって。君を守り続けるって、あの日に決めたんじゃない〟
「ああ、ヴェルナンディ……。あなただけは離れないで。あたし、ヴェルナンディが居ないと生きていけないわ」
〝大丈夫……。あの日の契約どおりだよ、エリィ。ずっと君を守ってあげるからね。約束の日が来るまでは〟
*
事故から2年半。穏やかな秋の日だった。
家族会議が開かれた。
「あなたの進学のことよ」
と、ママが言った。
「盲学校に行くか。このまま進学するか。よく考えて決めなさい」
高校は、今までよりずっとレベルが高くなる。ママは、盲学校に進んだ方いいのでは、と言っているのだ。
あたしは今までどおり進学するつもりだった。高校までの一貫校なのだ。慣れた環境の中で暮らしたい。
でも……。
友人と居て、出来ないことが多いことに気付かされる。
両目を閉じているだけで。
友人のおかしな顔に笑ったり、運動をしたり、出来ないなんて。周囲にも気を遣わせてしまう。なんだか、一人で城に篭もっている方が楽かもしれない。
家族会議から一週間経った日は、あたしの15歳の誕生日だった。
友人たちがあたしの家に遊びに来た。あたしは家の中を案内し、最後に自分の部屋へ招き入れた。
「素敵な部屋ね、エリィ」
「この装飾とっても綺麗」
部屋のデザインはママが決めた。あたしは一切決めていないけれど、そこは黙っておいた。
「あら。可愛いぬいぐるみ」
一人がそれを手に取ったようだ。
「でしょう? あたしのお気に入りなの」あたしは微笑む。「あたしが6歳のとき、パパが買ってくれたテディベアなの」
「アンティークじゃないのかしら、これ。とっても高価そう」
あたしはテディベアを撫でる。あたしの大事なテディベアだ。
「あら、エリィ。こっちの本、全部読んだの?」
一人は本棚に近寄っているらしい。
「ええ。点字が付いてる本なの。大体は読んだわ」
「へえ~。読書家なのねえ」
友人たちは物珍しそうにあたしの部屋を観察しているみたい。他人を部屋に入れるなんて滅多にないことだから、ドキドキした。この部屋がどういう状態か、他人の視点で見てもらえる。
「エリィって城の中のお姫様みたいね」
一人がそう言った。他の子たちも頷いているみたい。
「そうかしら?」
「そうよ。とっても可愛いし」
「閉ざされた城の中にひっそりと佇むお姫様って雰囲気が貴女にぴったりよ」
友人たちは「そうそう」と相槌を打っている。
「そう言ってもらえると嬉しいわ。あたしね、白馬の王子様が迎えに来てくれるっていうシチュエーションを待ち望んでるの。子どもっぽくて呆れちゃうけど」
「いえいえ、エリィ。それは全ての女の子の夢よ」
「でも、エリィなら本当に白馬の王子様が現れそうね」
友人たちはそう言って盛り上がった。
あたしの子どもの頃からの夢。
20歳の誕生日に、王子様があたしを迎えに来てくれる。うんと小さい頃からの願望。
王子様は、あたしを窮屈な世界から救い出してくれる。新しい世界は希望に満ちていて、何もかもが綺麗で、幸せに溢れている。そんな夢。
年齢を重ねるにつれ、それがどれだけ無謀で有り得ない幻想かわかる。それでも心のどこかで望んでいた。
もし現れてくれたなら。
あたしはきっと、迷わず付いて行くわ。
〝15歳の誕生日おめでとう。エリィ〟
「ヴェルナンディ。祝ってくれるの?」
〝もちろんだよ。こうして、1日1日と過ぎて行く。君が僕に会える日も近付くんだから〟
「ヴェルナンディ。ありがとう。あたしね、どんな友人よりもあなたが一番好きよ。あなたになら何でも話せる。本当に、何でも」
〝嬉しいよ。君は昔からずっとそのままだね。素直で心が綺麗。いい? 絶対に汚れちゃだめだよ。この世の醜さを知っちゃだめだ。絶対にね〟
「あーあ……今日は疲れちゃったなあ。もう寝よ」
〝おやすみ、エリィ。良い夢を〟
「おやすみ。ヴェルナンディ。また明日ね」
*
結局、あたしはそのまま進学した。
高校では付いていけないことも多かったけど、日々過ごしてはいけた。ただ、とても疲れた。もう、何も知らない小さい頃のようにはいかない。周りがあたしに気を遣っているのがよくわかるし、こっちも周りがあたしをどう思っているのか、ヒヤヒヤするばかりだった。
声のトーンで、仕草で、人を測る。
ああ、嫌。色んなことが面倒だわ。休みの日も、友だちと遊ぶことなく、家に篭もっていることが多くなった。
その夏の日は嫌なことがあった。
あたしは神経質になってたし、心落ち着かなかったのも確か。
隣の空き家に、家族が引っ越して来たのだ。父親と、高校生の息子と娘が一人ずつという組み合わせだ。その父親はすごくいい人で、娘のアンジェとも仲良くなった。ただ問題は、息子だった。
息子のジェイは、あたしの家側の部屋に住んでいる。そして、あたしの部屋は彼の部屋に割りと近い。
ジェイはミュージシャンを目指していた。日夜ギターを演奏した。あたしの両親は共働きなので、両親はそれほど迷惑を被っていないようだったけれど、あたしは参った。目が見えないために耳はよく聴こえる。危険を察知するために発達した機能だ。あたしには、ジェイのギターや歌は騒音だった。
何度かジェイに申し入れたけれど聞いてもらえない。ほとほと困っていた。
そんな、暑い夏の日だった。
隣家から突然、出火した。
火事だった。
「エリィ! 逃げるのよ!」
夜だった。ママはあたしを起こし、抱えた。
「お隣が火事なの! こっちにまで火が回るかもしれないわ。早く逃げるわよ!」
「待ってママ。ヴェルナンディを連れてって」
「そんなこと言ってる場合じゃないわ! 早くしないと――」
焦げ臭いにおい。
あたしは叫んだ。
「お願い、ヴェルナンディを! 一緒に連れて行って。じゃないとあたし――」
あたしは手探りでヴェルナンディを探したが、パパがあたしを担いでしまった。
「ヴェルナンディ!」
燃えてしまう! あたしのヴェルナンディが!
必死に叫んだ。ヴェルナンディが居ないと、あたしは耐えられない。人生に耐えられない。
パパとママはあたしを引っ張り出した。見えないあたしには、隣家がどれくらい燃えているのかわからなかった。
消火作業は夜通し続いた。
あたしたちの家は無事だった。奇跡的だと、消防士が言っていた。
隣家は全焼した。そして、ジェイが瀕死の重傷を負った。
逃げ遅れたのだ。そして、火を見てパニックに陥り、窓から飛び降りた。運悪く地面が固かった。彼は集中治療室に居る。
彼の愛したギターが、譜面が、全てが燃えた。あたしを困らせたものは、なくなった。
「ヴェルナンディ。無事で良かった。あたし、あなたのことが心配で心配で――」
〝エリィ。僕は人間じゃないんだから、あんな火では死なないよ〟
「本当に、本当に良かったわ。ヴェルナンディ、あなたを置いて逃げてごめんなさい。愛してるわ、ヴェルナンディ」
〝そんなに謝らないで、エリィ。いいんだよ。それより、君を悩ませていたものが無くなったでしょう?〟
「ジェイは一命を取り留めたけど、当分は入院ですって。お隣の一家は当然引越しよ」
〝もう君は騒音に困らないよ。君の心が蝕まれることはないんだ。ああ、スッキリした〟
「怖いわ、ヴェルナンディ。シュヴァルツのときみたい。あたしが嫌だと思ったものが、酷いことになってしまうの。どうしてかしら、何だか……」
〝エリィに危害を加えるものは赦せないよ。この世で一番綺麗な心を壊すのは絶対に駄目。だからね……、これからも僕が守ってあげるよ。エリィ、安心して。これからもずっと、そのままでいてね〟
*
18歳の春のことだった。
人生の転機が訪れた。
「朗報よ! エリィ!」
そう言って部屋に飛び込んで来たママの声は弾んでいた。
「どうかしたの?」
「あなたの目が見えるようになるかもしれないの」
あたしは、持っていた点字の本を取り落とした。
「どういうこと?」
「手術ができるようになったのよ。ドクターも見つかった。あなたを是非手術したいって。素晴らしいわ、エリィ」
「あたしの目、見えるようになるの?」
「そうよ!」ママはあたしを抱きしめた。「新たな手術法が開発されたの。ああ、医学の進歩って素晴らしい。あなたは患者第一号ですって。大丈夫よ、臨床テスト済みですからね。危険は無いの。見えるようになるのよ!」
あたしは悲鳴を上げた。
目に、光を宿すことができる。
見える。ママの顔もパパの顔も、自分の髪も瞳の色も輪郭も!
それはそれは、本当に人生の転機だった。
そこから急落していくあたしの人生の。
「ねえ聞いて。ヴェルナンディ。あたしの目、見えるようになるんですって」
〝知ってるよ。聞いてた〟
「凄いわ! 景色を、あなたを、見ることができるわ」
〝僕は反対だよ。嬉しくない。エリィ、君は世界を見ちゃいけない〟
「もちろん喜んでくれるわよね? ヴェルナンディ。ああ、最高の気分!」
〝エリィ。君はそのままで居てくれなきゃ。醜いものを見たら、君の心は蝕まれるよ〟
「ヴェルナンディ……。見えるようになったら真っ先にあなたを見るわね。あたしの大切なあなたを」
〝エリィ。駄目だ。僕は君のその澄んだ心が大好きなんだよ。この世は全て醜い。汚れてるんだ。絶対に駄目だよ、エリィ!〟
「手術を受けるわ」
〝エリィ。僕は嫌だ。絶対に絶対に阻止するからね!〟
*
予定通りいけば、年内に手術が行われるはずだった。
何回も検査を受けたし、ドクターとも会って話した。リスクの少ない手術だという話だった。
パパもママも賛成した。友人たちも、先生も。あたしの目は見えるようになるはずだった。
ところが――
暗黒の時の到来。
まず最初に、ドクターが倒れた。心不全だという。彼はそのまま帰らぬ人となった。
次に、パパとママが揃って交通事故に遭った。命は助かったものの、当分のあいだ入院することになり、あたしは一時親戚のもとで過ごした。
次に、心不全で亡くなったドクターの後任が、工事現場で鉄骨に敷かれて亡くなる。
さらにその後任も――もうこれ以上は言いたくない。
いつしかあたしは死神って呼ばれるようになった。あたしは不運をもたらす。誰もあたしの手術をしようとはしなくなった。
自分が恐ろしくなる。あたしに近付いた人々が、次々と不幸な目に遭う。医療関係者じゃなくても、あたしに近付くと酷い目に遭った。死神と噂されるようになって、引越しをした。でも新しい地でも、不幸が続々と襲ってきた。
でもそれは、全てあたし以外の人間に。
あたしには起こらない。まるで守られているみたいに。怖い。どうして。普通じゃ起こらないことばかり起こる。
あたしは19歳になった。
今や、あたしに近付いてくれるのはパパとママだけ。誰も彼も、あたしから離れた。何度か引越しをした。でも駄目。変わらなかった。
「神様のお告げなのかもしれないわね」
あたしの髪を撫でて、ママが言った。
「お告げって?」
「手術をするなって」ママは溜息を吐き出した。「最初は、手術が決まった頃から……ドクターからだった。手術をしたら、貴女、良くないのかもしれないわ。手術が失敗するとか……」
「ママ」
「そうだな」パパが相槌を打った。「パパもそう思う。いや、そうとしか思えない。この不幸の連続は、人ならぬ者の意図としか思えん」
「パパ……」
そうしてあたしの手術は延期になる。
もともと、誰も手術をしてくれないんだし。
あたしに近付けば病気になり、事故に遭い、精神に異常をきたす。もういっそあたしが消えてしまおうかと思うくらい、辛いことだ。
あたしは一歩も家から出なくなった。
そうね……、まるで、城の中で王子様を待つ姫君みたいに……。
「怖い。周りの人たちがどんどん不幸になっていく。あたしは魔女なのかしら?」
〝言ったでしょう、どんなことをしても阻止するって。これで君は手術しなくてよくなる。嬉しいよ、エリィ〟
「どうして? どうしてなの、ヴェルナンディ!」
〝君の心を守りたいから。エリィの心は聖水みたい。僕はエリィの心がそのまま欲しいんだ。約束の日までに穢れたら困るんだよ〟
「ヴェルナンディ……」
〝あともうちょっとだよ。もう少しで楽になる。きっと〟
「ヴェルナンディ……。あたし……」
〝今日はもう遅い。眠った方がいいよ。目を閉じて。おやすみ、エリィ〟
*
19歳の夏だった。
あたしの手術をしてくれるというドクターが現れた。
「これまでのことは気にすることはない。不幸な出来事が重なっただけだよ。なあに、大丈夫。安心して任せなさい」
アメリカの優秀なドクターだという。優しい声で、信頼できると感じた。
あたしは迷っていた。ドクター――ジャン先生まで、これまでみたいに不幸な目に遭うのではないかと。それなら手術はやめた方がいい。
パパとママも消極的だった。口には出さなかったけど、手術すべきではないと思ってる。
あたしは塞ぎこんでしまった。やめるとも受けるとも決められずに。
手術は受けたい。そして、見えるようになりたい。あたしの目に光を。
でも、これまでのことを考えると、どうしてもできない。事故、病、生きて戻らなかった人たち。あたしを死神と呼んだ人たちの声が蘇る。
迷っているあたしを見かねて、ママが散歩に連れ出してくれた。
あたしたちはこの町に移ったばかりで、あたしを死神と呼ぶ人はこの町には居なかった。
町はわいわい賑わっていた。色んなにおい、音。眩暈がしそうだ。こんな人だかり、本当に本当に久し振り。
「ねえママ。路地はどんな色? 空は、みんなの着ている服は?」
「そうね、色とりどりよ。色の洪水みたい」
あたしの頭の中に、『色』のまがい物が浮かぶ。あたしが想像する『色』というもの。
やっぱり、見てみたい。
この世界を。人々を。景色を。
羽をもらえるというのなら、羽ばたいてみたい。殻にこもっているのは嫌。
それでも……。
頭に蘇るのは、数々の悲劇。
シュヴァルツもジェイもお医者さまも、みんなみんな不幸に……。
人を不幸にしてまで、羽ばたきたくはない。
それなら、初めから翼を持たないほうが――
「うわっ、ごめんなさい!」
あたしは誰かにぶつかった。
あたしと同じくらいの少年の声だ。
「大丈夫でしたか? 本当にごめんなさい、お嬢さん」
あたしに謝ってる。ママとパパ以外の人があたしに声を掛けるのは久し振りで、あたしは返答に詰まった。
「いえ……」ママが答える。「平気よね? エリィ」
「あ、うん……」
あたしは頷く。
少年のホッとした気持ちが伝わってくる。
「可愛いお嬢さんですね。母子でお買い物ですか?」
「ええ、気晴らしに」
「それはそれは。楽しんでください」
少年は去っていったみたい。
あたしは、一言くらい彼と話せば良かったと後悔した。
「ママ。今の人、どんな感じ?」
「そうねえ……。ドイツ人じゃないわね。中国人かしら」
「ドイツ語喋ってたね」
「留学生かもしれないわ」
声の感じがすごく良かった。丁寧で、優しい。何だか気になった。
「さあ、そろそろ昼食にしましょう。エリィ」
ママはあたしの手を引いて、食堂に連れて行った。ここもとても賑わってくる。
「あなたのランチを貰ってくるわね。座って待っていて」
ママはあたしを座席に残し、ランチを取りに行った。
混んでいるのがわかったので、ママはすぐには戻って来ないだろうと予測した。退屈だ。足をぶらぶらさせて待っていた。
「あれっ、さっきの」
ドキッとした。この声、さっきの少年だ。
「お母様はどうなさったんですか?」
「いま……、ランチを取りに」
会話ができた。あたしと少年で。
少年はあたしに近付いたみたいだ。
「エリィさん?」
「あ、はい」
さっきママがあたしを呼んだ名を、この人は覚えていた。
「不躾で申し訳ないんですけど……何かお悩みではありませんか?」
「え…」
「顔に書いてあります」少年の声は柔らかい。「何か、重大なことがあるんじゃありませんか?」
「ええ……」
あたしは話した。目のこと、手術のこと。これまで何人もの人が不幸になったこと。何故話しているのかわからない。でもこの人は、ヴェルナンディみたいに話しやすい。聞き上手なのかもしれない。
「それは、大変でしたね。ああ、すみません。大変なんて一言で片付けてはいけませんね」
「いえ、いいんです」
あたしは首を振った。
この人はたぶん、あたしを見てる。でもあたしはほんの少し顔をうつむけた。馬鹿みたい。どうしたって目は合わせられないのに。
「エリィさん。思い切って手術を受けませんか」
「え――でも」
「きっと今度は上手くいきます。そんな気がするんです。あなたの目は、きっと、色んなものを映すことが出来ますよ」
「そしたら……」
「はい」
「あなたを見ることができるかしら」
少年は微笑んだ。あたしにはわかる。
彼の手があたしの手に触れて、あたしは飛び上がりそうになった。
「ええ、できます。それだけじゃない、もっともっと色んな素晴らしいものを見ることができますよ」
*
少女から離れ、店の外から観察する。
母親が戻ってきて、二人で食事をとっている。
「で、間違いないの?」
彼女が僕に訊いた。
「間違いありませんね。あれです。エリィさんと話してるとき、物凄い顔つきでこっちを睨んでましたよ。正直ちょっと怖かったです」
「怖がってどうする。あの子、このままじゃ危ないんでしょう?」
「ええ。ですから、標的をこっちに移してもらうしかありませんね」
窓越しに見える。しばらく観察して、後を尾けることにした。
「預かった剣はちゃんと持ってる?」
「ええ。税関で引っ掛からないか心配でした」
「それは大丈夫、魔力が効いてるだろうからね」
「だったら魔力でドイツまで寄越して欲しかったですね。飛行機に乗って列車でここまで……時間かかりましたよ」
エリィたちの後をつけていくと、一軒の古家に着いた。どうやらここが彼女らの家らしい。
「とにかく……、絶対に引き離さなきゃ。場合によっては」
はるばる運んできた剣の柄に触れる。
「頼りにしてるよ、剣道四段」
「三段です。あの、いざとなったら手助けお願いしますね」
「私、剣道は苦手だったの」
「そんな……」
「聞いて、ヴェルナンディ! 王子様が現れたわ」
〝あんなの王子じゃないよ。ただの餓鬼さ〟
「20歳の誕生日にはまだちょっと早いけど、来てくれたんだわ。王子様が。ああ、誕生日にはまた会えるかしら」
〝エリィ。誤解してるよ。あんな東洋人、君に相応しくない〟
「ヴェルナンディ……。一瞬あなたが現れたのかと思ったくらい、素敵な人なのよ。名前くらい聞いておけば良かった!」
〝エリィ……〟
「あたし、手術を受ける。そしてあの人を見るの。アメリカに行く覚悟ができたわ」
〝………〟
*
あたしたち一家は、手術を受けるためにアメリカに渡った。20歳の誕生日の、8日前のことだった。
パパとママは消極的だったけれど、あたしがどうしても受けたいと言うと、あたしの意思を尊重してくれた。神に祈った。今度こそ何事も起こらず、成功しますようにと。
何度も検査を重ね、手術にあたって何の問題もないとジャン先生から太鼓判をもらう。
「気を抜いて。大丈夫だ。上手くいくよ」
ジャン先生はあたしを励ました。
受けると決めたけれど、あたしの指先が、手首が、震える。ジャン先生に、何度も身辺に気をつけるように言った。その度に先生は「大丈夫だ」と笑い飛ばした。
不安だった。怖かった。でも後には退けない。
あたしには見たいものがある。あの人に会えると信じて、気持ちを奮い立たせる。
手術は、あたしの誕生日に決まった。君の目に光を与えることが誕生日プレゼントだと、ジャン先生が言った。
願わくば、あの人にもう一度会えますように。
誕生日に、あの人に会うことが出来たら最高。
できるかしら。
今、こんなにも震えているのに。
「エリィ。きっと大丈夫」
「信じるんだ。エリィ」
パパとママはあたしを応援している。
どうか今度こそ、あたしの目が治りますように。何事も起こりませんように。誰も不幸になりませんように……。
手術の前日、あたしは明日の手術のために入院していた。
ママに頼んで、ヴェルナンディを連れて来てもらった。これで心細くない。あたしはヴェルナンディの隣で眠る。
病院は静かだ。ここは個室で、何の音もしない。夜勤のドクターやナースが同じ階に居るので、何かあったらナースコールで呼べる。ヴェルナンディも居る。一人じゃない。
うとうととしてきたとき、それは起こった。
物音。
誰かの気配がした。
起き上がるのが怖くて、布団にくるまっていた。
誰?
ドアが開けられてる。
どうしよう、ドクターを呼ぼうか。
「今度は邪魔させませんよ」
え?
この声、あの人の。
あたしの王子様の声だ。
「どうして何度も何度も、手術を妨害するんです? エリィさんに憑いて、彼女とどんな盟約を結ぼうっていうんですか」
誰と話しているの?
心臓が高鳴る。
何故だか顔を上げちゃ気がした。
「話しても無駄みたいですね……。姉さん、エリィさんをお願いします」
「任せて」
今度は女の人の声。
誰かがあたしに触れた。
そのとき。
『戦い』は始まった。
*
目の前に、人ならぬ者がいる。
エルザヴェート=ドットに憑いている、悪魔か精霊か……そいつは、こっちに攻撃を仕掛けてきた。預かった剣を抜き、咄嗟にそれを防ぐ。
そいつはその剣に驚き、退いた。
「それ……、ただの武器じゃないね」
「お察しのとおり。俺の盟約相手から借りてきたものです。オーランドの骨が埋め込まれた剣です」
相手はぴくりと反応する。
「貴方の名前は?」
尋ねると、相手は「ヴェルナンディ」と答えた。
「俺の名前は――」
「いい。興味ない」
あっさり言ったヴェルナンディは、少年の風貌をしている。14歳前後に見える、可愛らしい少年だ。
「お前、どうして僕の邪魔をする? あと一日なのに。ずっとずっと、僕は明日を待っているのに」
「明日になったらどうするつもりです?」
ヴェルナンディはにこりと笑う。邪気のない顔で。
「エリィと正式に契約する」
「代償に何を得るつもりですか?」
「勿論、エリィの魂だよ」
当然のように、ヴェルナンディは答えた。
「僕は明日のために、ずっとずっとエリィを守ってきた。エリィの心が汚れないよう、醜いものを排除して。ようやく明日、エリィの綺麗な魂が僕のものになるんだ」
「エリィさんを殺させはしません。それから、貴方の持っている骨も返してもらいます」
「へえ。骨が見えんの?」
俺は首を振った。
「俺の盟約相手はランズの一人です。彼は、骨の共振を利用してずっと貴方に語りかけてきた。呼んでいたんです。貴方はことごとく無視しましたね。でも、貴方の大体の位置はわかっていた。だから、俺が遣わされたんです。骨を持っている貴方を見極め、危険な者であれば、骨を奪って帰ってこいと」
「この骨は、僕がランズから奪ったものだよ。今さら取られるなんて嫌だね」
「ランズを倒して骨を奪うなんて、よく出来ましたね。貴方は悪魔ですか?」
「精霊。でも、ただの精霊じゃないよ。僕は骨を得た」
ヴェルナンディが片手を上げる。俺は身を引いた。
エリィがナースコールを押そうとしているのを、姉さんが止めた。
「みんな眠らされているの。無駄よ。それより逃げなきゃ」
「何が起こってるの? あたしにはわからない。ねえ、見えているなら教えて」
「私にも見えない。ただ、どうやら貴女に憑いている奴が、うちの弟に危害を加えようとしているみたい」
ヴェルナンディのすらりとした両手に、鎖が現れる。先には刃物が付いている。
「へえ。そっか、お前が僕を見えるのは――」
「盟約者だからです。それもランズの力を借りてる。油断しない方がいいですよ」
ヴェルナンディは笑った。
「人間が、僕に勝てるっていうの!?」
鎖がこちらに迫ってくる。すんでのところで避け、鎖の先の刃が壁に刺さった隙にヴェルナンディに剣を向ける。彼は軽やかに避けた。
ヴェルナンディは鎖を振り回す。
やっぱり速い。人間が精霊に勝とうなんて無理か。
「真詞、負けそうなんじゃないの?」
姉さんが声を掛けてくる。
「はい、少々」
「何か手伝えることある?」
「ええと、じゃあ応援してください」
「がんばれー真詞ー」
あまり心がこもっていない。
ヴェルナンディの鎖の刃がこっちを向き、再び襲い掛かってきた。何とか剣を向けるが、力負けして吹っ飛ばされた。
壁に叩きつけられる。動けない。
「僕に勝てるわけないじゃん。人間って馬鹿」
ヴェルナンディの声。
目を開ける。ヴェルナンディが、エリィに近付く。
「姉さん、エリィさんを……」
声を絞り出して、危険を伝える。姉さんは頷いた。
「エリィに危害は加えさせない。相手になってやろうじゃないの」
「姉さん、精霊はもうちょっと左に居ます」
「あ、こっち?」
姉さんは向きを変える。
「いや、俺から見て左なんで、姉さんから見て右――」
「うるさいよ、人間たち!」
「…姉さん。精霊が怒ってます」
何とか立ち上がる。頭がズキズキ痛んだが、構っていられない。
後ろからヴェルナンディに切りかかる。彼はそれを避けた。エリィからは離れた。
俺はエリィの前に立つ。
「絶対に、契約を結ばせはしない。…エリィさん。彼は、あなたの魂を取ると言っています。あなたを殺すってことです」
「……あたしを?」
エリィの声はか細い。
「はい。あなたの綺麗な魂が欲しいそうです。あなたはヴェルナンディに魂を与え、その代わりヴェルナンディはあなたを守っていた……いや、守るなんてもんじゃない。あれは守護じゃない」
「……ヴェルナンディ?」エリィの声が震える。「そんなまさか。だって、ヴェルナンディは」
ヴェルナンディが時計を眺め、フッと笑った。
「0時を廻ったね。おめでとう、エリィ。君の20歳の誕生日だ」
「エリィさんの誕生日?」
「ええ、そう」エリィは頷く。「確かに、日付が変わればあたしの誕生日です」
「この日を待っていたんだぁ……。僕が君の魂を貰う日。ようやくこの日が来た」
ふと、左側に何か見えた――と思ったら、気付いたときには俺は再び吹っ飛ばされていた。ヴェルナンディは鎖をくるくる回し、エリィの腕を引っ張った。
「うわっ!?」
姉さんからエリィが離される。
エリィの耳元で、ヴェルナンディが囁く。
「…僕の声が聴こえる? エリィ」
エリィはハッと身を固くする。
「ようやく君と話せるね。エリィは言ったよね、20歳になったら迎えに来てって」
「…そんな」
エリィの顔が青くなる。
「僕は今までエリィを守ってた。エリィの心が汚れないように、醜いものを知らなくて済むように。僕はエリィの綺麗な魂が、ずっとずっと欲しかったんだぁ。僕、頑張ったよ。君の心が汚されないようにって」
「…あなたは……ヴェルナンディなの?」
「そうだよ。だって君が名付けたんだよ。君の6歳の誕生日にね」
「6歳の、誕生日……?」
力を振り絞って、ヴェルナンディに剣を向ける。
「エリィさんを……放してください」
「何だ。まだ生きてたの?」
ヴェルナンディの右手はエリィ。左手は鎖。
「次は絶対殺すよ」
「ヴェルナンディ……。君はエリィさんを守ってなんかいなかったんです。君の鎖で彼女を縛りつけ、不幸にしていただけです。彼女の魂を、とらないで……」
「僕、お前大っ嫌いだ」
鎖が振り下ろされる。俺は剣で防ごうとする。
駄目だ、間に合わない――
「ヴェルナンディ!」
鎖を振り下ろす手が、ぴたりと止まった。
エリィの叫びで。
「お願い、殺さないで。あなたはヴェルナンディなのよね? あたしの友だち。ずっと一緒に居た、あたしの――」
「そうだよ、エリィ。思い出してくれた? あのときの約束を」
「ヴェルナンディは人を殺さないわ」
エリィがきっぱりと言った。
ヴェルナンディの顔が歪む。
「あたしのヴェルナンディが人を殺すなんて嘘。殺さないで。その人は――」
「こいつはエリィの王子なんかじゃない!」
今度はヴェルナンディが叫んだ。
「僕に迎えに来てって言ったのに。僕がエリィを迎えに来たのに。こんな人間、エリィの王子じゃないよ!」
「でもあなたも違うわ!」
ヴェルナンディが、ひどく傷付いた顔をする。悲しい、裏切られたというような――
その刹那、ヴェルナンディの手からエリィが離れる。姉さんが、エリィを保護し、部屋の隅に移る。
「エリィを返――」
不思議と音はしなかった。
確かに切った感触はあった。
ぽたぽたと、剣に血が滴る。
「お…前……」
ヴェルナンディの左顔面に傷が走る。
「言ったはずです。契約させはしないって」
ヴェルナンディがよろめく。
もう一度剣を振り下ろす。ヴェルナンディはそれを避け、エリィが眠っていたベッドから何かを取って抱える。剣先をヴェルナンディに向け、突進する。よろめきながら避けたヴェルナンディは、窓から飛び降りた。
慌てて窓に駆け寄る。ヴェルナンディの姿はない。
「逃げた……?」
僕はその場に座り込む。一気に力が抜けた。
「ふあ~……」
「真詞、大丈夫?」
姉さんが近寄る。
「ああ、はい……。幸いここ、病院ですから。診てもらえます」
「じゃあ、眠らされた医者を叩き起こしてくるわ。エリィ」
姉さんに呼ばれたエリィが、「はい」と返事をする。
「ちょっと真詞の側についててくれる? 何か死にそうだから」
「死ぬつもりはありませんが……」
「よろしくね」
エリィの肩にポンと手を置いて、姉さんは病室を出て行った。
バタンとドアが閉まる。
困ったように立ち尽くしていたエリィが、一歩、こちらに近付いてくる。
「そっち……ですか?」
「はい。ここに居ます」
手を差し伸べ、エリィの手に触れる。彼女の手は温かかった。
「一体、今、何があったんでしょう? ヴェルナンディが実在したんですか?」
「実在って……。そういえば、ヴェルナンディは貴女に名前を貰ったって言ってましたね」
僕の隣に、エリィが座った。
「ヴェルナンディって、テディベアの名前なんです。6歳の誕生日にパパから貰って、あたしが名前を付けました。今もそこのベッドの上にあるはずです」
「ベッドの上?」身体を起こして見てみる。「何もありませんよ」
「そんなはずないです。ママに持ってきてもらったから」
「あ、もしかして」
去り際にヴェルナンディが持って行ったもの。あれが、テディベアだったのかもしれない。
「あたし、ヴェルナンディが最高の親友なんです」エリィが話した。「6歳の頃からずっと、辛いことや嬉しいことがあるとヴェルナンディに話し掛けてました。ぬいぐるみに話しかけるなんて子どもっぽくて恥ずかしくて、ずっと秘密にしていたんですけど」
「話し掛けたときに、20歳になったら迎えに来て欲しいって話、したんじゃありませんか?」
「ええ……」エリィは頷く。「20歳の誕生日に王子様が迎えに来てくれたら素敵ねって。あたしの密かな夢だったんです」
「たぶん、それをヴェルナンディが聞いたんですね」
エリィは首を傾げる。
「あのテディベアには、恐らく精霊が宿っていた。住処にしていたのかもしれません。それがエリィさんの手に渡り、ヴェルナンディと名前を貰った彼は、エリィさんに憑いた。彼は勝手にエリィさんと契約する気になっていたんです。〝20歳の誕生日になったら、君の前に姿を現す。それまで君を守るから、誕生日に魂を頂戴〟って……」
「あたしを守る?」
「はい。その守るという意味が過剰すぎたんです。今まであなたの周りの人間が不幸になったのは、全てヴェルナンディがやったことだと思います。あなたを守ると」
「……」エリィは呆然としている。「あたしがずっと、ヴェルナンディという精霊に守られていた? ヴェルナンディが人を不幸にした? あたし……そんな」
混乱するエリィに、言った。
「今、考えなくていいことです。時間をかけて理解していけばいいんです。あなたには、まだまだ時間がありますから。それに――」
俺は彼女に微笑みかける。見えないとしても。
「あなたは今、他のことを考えなきゃ。ようやく目が見えるようになるんですよ」
彼女は顔を上げる。
「今日は、あなたの手術の日です」
*
5時間に渡る手術は無事成功した。
俺と姉さんは、しばらくアメリカに滞在していた。そして、手術が終わって二日経った日に、エリィに会いに行った。
彼女はまだ入院していた。病室を訪れると、中から彼女の母親が出てきた。お見舞いだと伝えると、中へ通してくれた。飲み物を持ってくると、母親は病室を出て行った。
「エリィさん。こんにちは」
彼女の目が、確かに僕を捉えた。
「その声。王子様!」
「えっと、すみません……王子ではないです」
「あ、ごめんなさい」エリィは口元に手を当てる。「ええと、シンシさんでしたっけ」
「はい。我妻真詞と言います」
「私は我妻玲美。真詞の姉」
姉さんはエリィに微笑みかける。エリィも微笑みを返した。
「まだ、ぼんやりしていますけど、あたしの目、見えるようになったんです。素敵……。やっぱりとっても素敵だわ。想像どおり」
「そう褒められた顔でもないですけど」
「いいえ。お会いできて嬉しいわ」
微笑んだエリィは、とても幸せそうだ。
「これから視力も回復していくんですか?」
「ええ、ドクターはそう仰っているわ。包帯を外した瞬間、すごく眩しかったの。今は慣れたけれど……。ねえ、真詞さん、玲美さん。世界ってとっても綺麗ね。あたし、とても感動しているの」
俺も姉さんも、嬉しくなって笑った。
「病院以外の綺麗なものも、沢山見られるわ」
「ええ……、ありがとう」
小首を傾けて笑うエリィは、満ち足りているようだった。ヴェルナンディの言うとおり、彼女の魂はとても綺麗なんだろう。
ふと、彼女は視線を落とす。
「あたし、今でも信じられないの。ヴェルナンディに精霊が宿っていて、あたしを守っていただなんて。でもそう言われると、思い当たることが幾つかあるわ……。寒い日に毛布をかけてくれた。ママもパパもそんなことしていないって言って、あたしとっても不思議だったの。あれ、ヴェルナンディだったのね」
「多分、そうでしょうね。そうやってちゃんと守っていたときも、確かにあったんですね……」
懐かしそうな顔で、エリィは頷く。
「悪い人じゃないわ。あたしが、ヴェルナンディをちゃんと受け入れてあげれば良かった」
エリィは空を見上げた。
「こうして手術を受けてわかったの。ヴェルナンディだけじゃない、あたしは多くのものに守られてきたんだって。目に見えなくても、確かにあたしを守ってくれる存在がいるんだって。その人たちに、ちょっとずつでもお返しできたらって思うわ」
エリィは、僕と姉さんを見てにこりと笑う。
「もちろん、あなた方にも」
俺の顔は自然と綻ぶ。
「もう十分ですよ。エリィさんの目が見えるようになって、すごく嬉しいんです」
「私も。本当に良かったわ、エリィ」
俺も姉さんもエリィも笑った。どこかに少しの切なさを潜ませて。この空を、夢を、ヴェルナンディを思って。
エリィの母親が、戻ってきた。
「ごめんなさい、自販機が故障中で――」
「お気遣いなく。もう行きますから」
俺は立ち上がる。
「え」エリィは寂しそうな顔になる。「行っちゃうの?」
「日本に帰らなきゃいけないんです。帰る前にエリィさんにお会いできて良かった」
「………」
「きっとまた会えるわ」姉さんが言った。「是非日本に遊びに来て。歓迎するわ」
「玲美さん……」
姉さんはエリィの手に触れて、軽く握手をする。俺も、エリィと握手をした。お別れの合図。
部屋を出る直前、エリィの声がした。
「真詞さん! 玲美さん! ありがとう」
俺たちは振り返り、エリィに手を振る。
彼女は俺たちを見て、笑顔で手を振り返す。
病室を出て、俺と姉さんは日本へ帰るために空港に向かった。
「あー……アルに怒られるんだろうなあ。結局骨を回収できませんでしたから」
「だね。でもいいじゃない、一人の女の子を助けられたんだから」
姉さんが、俺の背中をポンと叩く。
「痛っ…! ねえさん……俺の傷、まだ完治してないんですよ……」
「ああ、ごめんごめん」
軽く言って、姉さんは俺の袖を引っ張る。
「真詞! 空、見て」
「え?」
顔を上げると、そこに七色の虹。
「ああ……」
世界には、綺麗なものもある。俺はたまにそれを思い知る。
「真詞。貴方に盟約を結んだランズが何属性か賭けよっか」
「いいですよ。えっと、アルは光ですから、残りはー……」
「火や水じゃない? 私、水に一票」
「じゃあ俺は――」
綺麗なものばかりじゃないけれど。
少なくとも、今、俺の頭上で虹は美しくそこに在る。
定めの糸
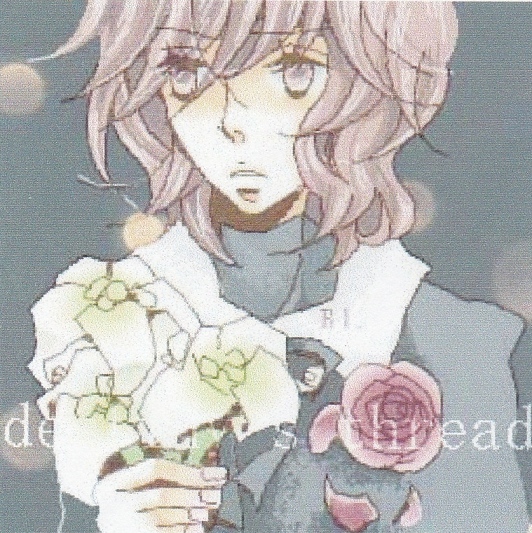
鞄の中には財布、ハンカチ、映画の前売り券。忘れ物はない。私は深呼吸して、バスを待った。
今日は9月9日、日曜日。
これから出かけるところ。
今日この日を何度シュミレーションしたかわからない。バスに乗って、駅に着くのはきっと私の方が早い。吉岡は、きっと時間ぴったりにやって来て、遅れてごめんと私に詫びる。軽くお茶をしてから、目当ての映画を見に行く。
そう。今日は私と吉岡の初デートの日だ。
私の名は、風間高菜。カザマ・タカナととても発音しにくい名前。あんまり気に入っていない。
私と両親は、この田舎の村に引っ越してきたばかり。両親はもともとこの村の出身で、戻ってきたというわけ。
私たち一家には、二年前にとても辛いことがあった。町を離れざるをえなかったことが。でも今、この村に越してきて、やっと気を抜くことができた。
転校した高校で、吉岡と会った。吉岡は、過去のことを知ったうえで私と付き合おうと言ってくれた。とても嬉しかった。
そんな吉岡と、一緒に出かけるのは初めてだ。私は浮かれていた。
バスは時間どおりに到着した。この小さな農村での移動手段はバスしか無い。
運転手にお金を支払い、バスに乗り込む。冷房がきいていて涼しかった。
(あれ…)
バスには先客が居た。この村で見たことはない人だ。都会的で、綺麗な女の子だった。大学生かもしれない。
ドアが閉まって、バスが走り出す。
私は終点まで乗っていく予定。
途中、バスは五人の乗客を拾った。みんなバラバラに座る。
車窓から見える景色は一緒。山と、田んぼばかり。終点までまだ時間がある。
私は意を決して、女の子に近付いた。
「こんにちは」
声を掛けると、彼女は目線を私に向けた。表情は変わらない。
「隣、いいですか?」
彼女は頷いて、バッグを退けた。
近くで見ると、本当に綺麗な子だとわかった。髪を染めていて、肩くらいまで伸びた髪はふわふわとして可愛い。でも表情はクールだ。
「あの……、この村の方じゃ、ないですよね」
女の子は頷いた。
「何処から来たんですか? あ、私、風間高菜っていいます」
「……」彼女は私を見た。ぞっとするほど素敵な目だ。「相沢月香。私は、遠くから来たの」
「ツキカさん。綺麗な名前」
私が微笑むと、相沢月香も少しだけ微笑んだ。
もっと彼女と話がしたくて、私は質問をした。
「この村が故郷なんですか? なんか月香さんて大学生って感じ。帰郷とか?」
「いいえ。私はここの生まれじゃないの。ただ、少し気になることがあって……」
「気になる?」
月香さんは視線を前方に向ける。
「このところ、この辺りでひき逃げ事件が連続しているのを知っている?」
「あ、はい」思わぬ話題で驚いた。「犯人、まだ捕まっていないんですよね。怖いな」
相沢月香の表情は真剣だった。真剣に、ひき逃げ犯のことを考えているような。
「あの……、月香さんって刑事?」
「まさか。違うよ」月香さんは少し笑う。「ただ、私には追わなきゃならない相手がいるの」
そのとき、彼女の小指の指環に気が付いた。窓からの光に反射して光ったのだ。
「あ、その指環……もしかして彼氏から?」
月香さんは、ああ、と指環を見つめる。
「これは違うの。そういうのじゃなくて」
「でも、彼氏いそうですよね。いるんでしょう?」
「昔、いたことはあったけど……」月香さんは何故か悲しそうな顔をして、私を見た。「あなたも、きっと素敵な彼氏がいるんじゃない?」
話題を逸らされているとは思ったが、その話題は嬉しかったので、乗っかった。
「これから初デートなんです。吉岡っていう、同級生と」
「それは良かった」
妹を見るような目で、月香さんは微笑む。
相沢月香は物静かな女性で、それでいてどこか芯が強そう。引力で人を取り込んでしまいそうだ。本当、『月』みたい。
「彼氏、優しい?」
「ええ、とっても。抜けてるところもあるんだけど、それを補って余りある良い奴です」
思い出すだけで頬が緩む。これから吉岡とデートだと思うと心が弾んだ。
月香さんは、優しい目で私を見た。
「あなた、私の妹に似てる」
「月香さん、妹がいるんだ。私みたいって、どんな子ですか?」
「名前が花香っていうんだけど、花みたいな子」
「私は花みたいじゃないですけど……」
「いえ、似てるわ」月香さんはそう言って、私を見つめる。「年はいくつ?」
「17です。高校2年」
「妹と年齢も一緒」
「月香さんはお幾つなんですか?」
「私は、18歳」
「あ、じゃあ、高校3年生?」
月香さんは微笑むだけで答えない。
私は月香さんに親近感を抱いた。
「月香さんみたいなお姉ちゃんが欲しかったな、私。花香さんがうらやましい」
「きょうだいはいないの?」
私の心がズキッと疼く。
「兄は、いましたけど……。一緒には暮らしてません」
月香さんは、「そう」と返事をした。
バスはいくつも停留所を過ぎる。乗降はなかった。
農村で、道が整備されていないために、時折揺れた。目的地までは、まだ遠い。
相沢月香は、お人形みたい。とびきり上等で高級なドール。ホント、こんな人がお姉さんだったら自慢しまくりだろうなあ。
「あれ…。道、違わないか?」
乗客の一人がこぼした。
そんなはずはない。こんな簡単な農村、道を間違えるはずが――
「あ、本当だ」
「違うよ。運転手さん!」
窓の外の景色。それは、山へ登る険しい道だった。バスは加速し、私は身体のバランスを崩す。咄嗟に月香さんが私を支えた。
「ごめんなさい」
「いいえ」
月香さんは真剣な表情だ。
バスは加速し続ける。揺れで気持ちが悪い。
「運転手さん!」
乗客が止めようとするが、誰も運転席まで辿り着けない。歩けもしない、ひどい揺れ。
山道を登って行く。森が深くなる。私は怖くなった。
「嘘、どうして……」
怖くて縮こまる私の身体を、月香さんが抱きしめる。
「大丈夫。きっと」
その声は落ち着いていた。
おかしい。運転手がどうかしてしまっている。窓の景色は凄まじい速さで変わり、エンジン音と振動が響いてくる。急カーブに差し掛かるたび、身体が投げ飛ばされそうになる。
怖い、怖い! 一体何がどうなってるんだろう。
私は、思いっきり叫んだ。
「お願い、止めて――!!」
乗客からも悲鳴があがる。パニックだ。でも、逃げ出すことも出来ない。
こんなの、映画の中だけしか起こりえないことだと思っていた。どうしてこんなことに? 私はここで死ぬ!? お兄ちゃんにも会えず、吉岡にも――
「板垣浩輔」
月香さんが言った。
「え…?」
「運転手の名前。書いてある」
「よ、読めたの?」
「私じゃないけどね……。そう、板垣ね。どうもこの人が、連続ひき逃げ犯らしいよ」
月香さんは立ち上がる。揺れで彼女の身体が倒れそうになる。
「月香さん……」
「止めてくるわ。あの運転手」
「でも」
「一人で平気ね?」
頷くしかなかった。
月香さんの声は決意に満ちていた。
「出来るでしょう、バスを止めること」
月香さんは、少し笑ったようだった。
「死神でもそんなこと気にするのね。それくらい……一分で捕まえてくれればいい」
誰かと、話してる?
「ああ、死神じゃなかった? でも私にとってはそれと同じだわ」
月香さんが、小指の指環に手を伸ばす。
指環を、はずす――?
その刹那。
バスは大きく横転し、上下が逆さまにひっくり返る。
落ちたと思った。
山道を転げ落ちる。
死ぬ――
誰かに抱きかかえられた。
私は目を開けられない。
ジェットコースターよりも何倍も激しい衝撃と音と速さに、叫ぶことすら出来なかった。
ドオオォン!
バスが落ちた音。
私はそっと目を開ける。
崖から落ちたバスは、少し離れたところで炎上している。
私の側には、他の乗客が居る。
バスから投げ出されたにしては、おかしい。私と乗客たちは固まっている。
燃え上がるバス。
今まで私が乗っていたもの。
「…生きてる……?」
上手く呼吸ができない。涙で視界が歪む。心臓が、痛いほど早く打つ。
「たすかった……」
私の側には、気絶している乗客。
が。
私の足下に血が流れてくる。
その方向に目をやる。
「月香さん……?」
彼女は、倒れていた。
彼女の左胸から、とめどなく血があふれる。苦しそうに、何度も咳をしている。
「月香さん!」
叫んで近寄ろうとするが、腰が抜けて立てない。這いずって、何とか会話ができる距離に近付いた。
何か呟いている。
「…ジョーカー……。あとよろしく……」
「月香さん!?」
彼女は、私じゃない何かを見ている。
そちらに目を向けると、制服を着た運転手が、燃え上がるバスを背にして立っているところだった。
「死んでない……なぜだ……みんな死ねばいいのに」
運転手の声。狂ってる。彼は、こちらに突進してくる。
が、運転手の足が止まった。彼の身体は浮き上がり、地面に叩きつけられる。
砂煙が舞う。運転手の身体は、木の蔓で巻きつけられ、身動きがとれない。
「今、何が……」
何が起こったんだろう。
バスの炎もおさまった。焦げ臭い匂いが鼻につく。
「いけない。月香さん――」
振り返ると、月香さんの右手が上がっている。
まるで誰かに手を取られているみたいに――
彼女の小指に、指環が嵌められる。
まるで……誰かに、嵌められているように。
きらりと指環が光った気がした。
月香さんは目を開ける。
「……一分もかからなかったね」
彼女は何事もなかったように立ち上がる。
「月香さん!? 大丈夫ですか」
彼女の服は血まみれだ。が、もう流血してはいないようだった。
月香さんは、申し訳なさそうに私に言った。
「驚かせてごめん。デートにも遅れてしまうね」
「えっと……?」
〝おい、娘〟
「!?」
低い男の声。
どこから聞こえてくるの!?
〝今見たことは秘密にしておけよ。月香はここに居なかった。警察が来たら、あの運転手を突き出せ〟
「ジョーカー。あまり乱暴な口はきかないで」
月香さんが言うと、声は止んだ。
私は混乱していた。ひどい怪我を負っていた月香さんが、平然と立っている。運転手が何故か宙に浮き、縛り付けられた。
一体……。
「高菜。ごめんなさい。私のことは誰にも話さないで。私、本当は死んでいるはずの人間なの」
「…天使……?」
「そんなものじゃないわ」月香さんは笑った。「私は数年前の事故で、深い傷を負ったの。さっき貴女が見た、あの傷ね」
血まみれの彼女を思い出す。左胸からの出血。
「死ぬはずだったんだけど、私はジョーカーと盟約を結び、身体の時間を止めてもらった。この指環……、ジョーカーと私はこの指環で繋がってる。これは生命維持装置」
「………」
「ただ厄介なのは、さっきみたいなときは指環を外さないとジョーカーの力が使えないってこと。普段は私を生かすために力を使っているからね。さっきみたいなことがあると、私は指環を外す。ジョーカーの力は解放される。ただし、私への生命維持の力がなくなって、私の身体の時間は進む――」
月香さんは、力を抜いて笑った。
「難しかったかな?」
理解できなかった。そんなこと……。でも、そうでなければ説明がつかない。
「どうして……。何のために」
訊くと、彼女は悲しそうな顔をした。
「妹をね、殺されたの。ひき逃げ犯に。ちょうど私は、今の高菜と同じ……デートに行くところだった」
月香さんは空を見上げる。まるでそこに過去が映し出されているかのように。
「花香は世話焼きで、デートに着て行く服とか靴とか、色々選んでくれた。心配になったんでしょうね、花香はこっそり付いて来たみたいなの。待ち合わせ場所に向かうとき、すごいスピードで車が突っ込んできて、そのときに……花香は私をかばった。結局、二人とも轢かれてしまったんだけど」
月香さんの表情が痛々しい。見ていられないほどに。
「この村でひき逃げ事件が頻発していると知って、もしかして犯人じゃないかって来てみた。そしたら、ジョーカーがあの運転手を見つけた。あいつは深い闇を抱えてる、きっと何かやるって言うからバスに乗ってみた。その結果がこれ。あいつ、間違いなくひき逃げ犯ね」
〝警察だって無能じゃない。あいつをマークしていただろう。追い詰められたあいつは、バスで乗客と心中することを選んだ……そんなところか〟
「花香を殺した犯人じゃないね」
運転手は気絶して、ぴくりともしない。
月香さんは運転手に目をやっていたが、やがて視線を逸らし、私を見た。
「怖い思いさせたね。大丈夫、警察を呼んでおく。ここに居て」
私の肩に手を触れて、優しく笑ってから、月香さんは私に背を向けて歩き出す。
「ま……待って、月香さん!」
「何?」
彼女は立ち止まる。
「その……、私のお兄ちゃんのことは」
「………」
「風間喬吾。ひき逃げで指名手配されています。お兄ちゃんは、高校生二人を轢いて逃げた。その二人は……、姉妹だったと聞いています」
月香さんは振り返らない。
私は泣いていた。
「ごめんなさい。でも信じてください。お兄ちゃんは、そんなことする人じゃないの。絶対に違う。私と両親は、お兄ちゃんの無実を信じてる。あの……、でも、月香さんは」
涙を拭く。
そして問う。
「もしお兄ちゃんが犯人だったら、復讐するつもりですか?」
風が吹いて、砂煙が舞う。
月香さんの声がした。
「もし……、あなたの兄が犯人であればね」
砂の煙がやんだ。
月香さんはもう居ない。
私の目が、再び涙をこぼす。
もし、お兄ちゃんが本当に花香さんを殺していて、月香さんがお兄ちゃんに復讐するときがきたら……、きっと、私は止められない。
絶対に、止めることなんてできない。
*
血まみれになった服をどうしようか散々考えた。いつもこうだ。ジョーカーの力を解放すると。
「風間ではなかったな」
ビルの屋上で、ジョーカーが煙草をふかす。
「うん。…妹が居たのは不覚だった」
「決意が揺らいだか? 風間を殺せば、あの少女は泣くぞ」
私は首を振る。
「揺らがない。花香は、もう泣くことも出来ない」
ジョーカーの煙草の煙が風に乗って遠くへ行く。
花香の時間は、あのとき止まった。
私の時間も、あのときのままだ。
失ったものを取り戻せるわけでもない。復讐をすれば泣く者がいることもわかっている。
それでも私は、足を止めない。
「行こう。ジョーカー」
茨の道を進んでいく。この手で復讐を遂げるまで。
マリオネットの憂鬱

世界には無能な奴らばかり。
全く、嫌になるよ。
少し頭を働かせればわかることなのに、それをしない怠け者ばかり。
あー、本当、嫌になる……。
「アーサー。今回の視察はどうだった?」
自慢の髭を撫で、葉巻を口に銜えて父が訊いた。
「散々でしたね。あれじゃ使い物になりません。今すぐ取り壊して幼稚園にでもするべきです」
「幼稚園? どうしてだい?」
心の中で溜息を吐きながら、僕は答える。
「周辺地域に住宅が沢山建っています。今に、あの地域は子どもだらけになりますよ」
「なるほどな。アーサー。今度の会議の議題としよう」
「ありがとうございます」
僕は窓の外を眺めた。
黒いベンツ。僕は後部座席から流れる景色を見ていた。
ここはフィンランドの一都市。開拓が進み、父の仕事にくっついて僕もやって来た。
僕は、アーサー=ラトクリフ=カーター。英国人だ。今年で15になる。周囲からは子ども扱いされているが(父含む)、もう立派な大人だと自負している。ビジネスでは絶対負けない。
退屈なフィンランド。景観が良いのはもう見飽きた。いつまでここに居なきゃいけないんだろう……。
「うわっ!?」
運転士の叫びとともに、車がひどく揺れる。
急ブレーキの音のあと、大きく揺れて車は停止した。幸い後続車がいなかったので、追突されることはなかった。
「何事だ!」
父の声。
「すみません、旦那様。その、子どもが――」
「子ども? 轢いたのか」
「いえ、お父様。そのような衝撃はありませんでした」
父が車から降りた。僕もドアを開け、様子を覗いた。
確かに子どもだ。道路に横たわっている。気絶しているようだ。14歳くらいに見える。短いチェックのジャケットに、白いフリルのスカート。髪型も、とても可愛らしい。
「その、この子が飴を舐めながら道路に飛び出してきまして――」
「外傷はないようだ。驚いて気絶したのか」父は少女を抱きかかえる。「屋敷に連れて、念のためドクターを呼ぼう。大丈夫だろうけれどな」
気絶した少女は車に乗せられ、再び発進した。
「それにしても、いきなり路上に飛び出すとは。この地域の子どもは教育がなっていないな」
「我が学園に入学している者は、そのようなことはしないよう教育しなければなりませんね」
僕らの家は、この地域で学園を経営している。慈善事業というやつだ。僕も、視察に行ったことがある。無能なガキどもが戯れていた。あいつら、勉強する気はあるんだろうか。学園のレベルは高いはずだけれど。
15分すると屋敷に着いた。
巨人でも跨いで通れないだろうというほど高い門が、電動でガラガラと開く。
車は、屋敷のドアの前まで走った。
「アーサー」父が言った。「悪いが私はもう一件仕事が残っている。代わりにドクターを呼んでおいてくれるか」
「承知しました。お父様」僕はにこりと微笑む。「行ってらっしゃいませ」
父は頷いた。僕は車から降り、使用人に少女を運ばせる。
車が行ってしまい、僕は呟いた。
「全く……、面倒なことは僕に押し付けるんだ」
ドクターを呼ぶように言い付け、僕は自室に戻った。ここに居ると、英国に戻った気分になる。
ベッドに横になる。そうすると、僕の一番大好きな人形と目が合う。
フランスの職人の手作り。今にも動き出しそうな青い目の女の子。実物の人間より若干小さいそれは、椅子に座ってこっちを見ている。
僕は父との二人暮らし(使用人は居るが)。でも、父は仕事で忙しく、あまり会うことはない。今日みたいに、時折視察に連れて行ってもらったときに会うだけ。話すのは仕事のこと。
僕は学校に行っていない。家庭教師がやって来る。屋敷から出ることもあまりない。
このままでいい。多少の不満はあっても、このままいけば、僕は父の後を継ぎ、事業のトップに立てるんだ――
ガシャン!
割れる音。食器?
悲鳴みたいな声も聞こえる。
僕は立ち上がった。一体何の騒ぎだろう。僕は静かな場所が好きなのに。
騒ぎの場は、客用の食堂だった。
「きゃはははは!」
悲鳴みたいな叫び声。
それを見て、僕は怒りを通り越して唖然とした。
散らかった部屋。テーブルの上で踊り狂う少女。翻弄される使用人……。
「これは、一体……」
「アーサーお坊ちゃま!」執事のバーナードが僕に気付いた。「申し訳ありません。実は――」
事情を説明しようとしたバーナードの頭に、バナナの皮が乗っかった。
「きゃっははははー♪」
テーブルの上の少女が投げたのだ。
その少女は、さっき拾った女の子だった。倒れたとき頭でも打ったのだろうか。異常だ。
「バーナード。何とかしろ。あのクレイジーガールを止めるんだ」
「は、必死でやっておりますが……」
使用人たちが捕まえようとするが、少女は蝶のようにひらりと避けた。僕の前まで逃げてくる。
少女は、僕に気付き、きょとんとした顔をする。僕は少女に言った。
「こら。お前は拾ってもらった恩を感じないのか。全部片付けろ」
少女は僕をじっと見る。
「な、何――」
すると、いきなりニッと笑い、僕に飛びかかった。僕は後方に倒れる。
「坊ちゃま!」
「あっははは、坊ちゃまだって」少女は僕の腹の上で、手を叩いて笑う。「ねえ。君がここで一番偉いのぉ?」
「重い……退け……」
少女を捕らえようと、バーナードが飛びかかる。が、少女はひらりと避け、バーナードが僕に倒れてくるという悲惨な結果となった。
「馬鹿! 退けっ」
「申し訳ありません!」
「きゃははは」
少女は大笑いし、僕の顔を覗き込む。
「僕はフィフィ。一応名乗ってあげるよ。よろしく、偉そうなガキ」
「なっ……」
「坊ちゃまに向かってなんてことを!」
少女は大声を上げて笑いながら、部屋を荒らしまわる。
我慢の限界を超えた。
「このガキをつまみ出せ!」
*
今でこそ色々な事業展開をしているが、僕の家は、元は貴族の一族だった。僕は貴族の血を引いている。それが誇りだ。
誰にも崩させない。僕のこの生活を。僕は父を超える社長になって、栄光の人生を築くんだ。ゆくゆくは国王も認める器になってやる。
「無理じゃないのぉ~?」
ハッと振り返ると、僕の部屋にあのクレイジーガールが居た。
「お前、つまみ出されたんじゃ……どこから入った!?」
「窓からだよ」
少女はにっこり笑う。
「窓からって、ここは3階――」
「それよりさぁ」
少女は僕に近付く。
「僕、盟約相手探してるんだけど、なってみない?」
「は?」
「たまには高飛車なガキに憑くのも良いよね。それなりに楽しめそう♪」
「何を言ってる?」僕は眉をひそめる。「あー、待て待て……。本当にドクターが必要か? お前、あのとき頭打ったのか」
「あったま悪いなあ。盟約者になるかって訊いてんの」
「盟約者??」
「つまりさ」
突然、少女が倒れた。何の前触れもなく。
「え……ええ!?」
ぴくりとも動かない。
〝放っておいていいよ。それ人形だから〟
「は? 人形? ていうかこの声はどこから」
〝君だけに語りかけてんの。あのね、僕の姿、盟約者にしか見えないんだよ。人形の中に入ってたのは、そうしないと人間と遊べないから。普段は僕のこと、誰にも見えないの〟
「これは、一体……」
〝で、盟約っていうのはね、要はギブアンドテイク。君の好きそうな言葉だよね。僕が望みを叶えてあげるから、僕に何か寄越せ〟
「夢だ。これは夢だ。こんなの嘘だ」
〝頭固いなぁ~。君、何か望みないの? 僕が叶えてあげるんだよ。こんなチャンスないよ〟
「騙されないぞ。そう言って僕の魂を奪うんだろう。殺されるってことじゃないか!」
〝君の魂なんか要らないよ。そうだな~この屋敷、綺麗なもの沢山あるから、装飾品をちょーだい☆〟
「え、そんなんでいいのか?」
〝君の魂よりよっぽど良いもん♪ で、僕は何をすればいい?〟
「ちょっと待ってくれ。考えるから」
突然、僕の前に顔が現れた。さっきの少女が上から覗き込んでいる。
「うわっ!?」
「仮盟約、完了ー。僕の姿が見えるでしょ?」
「あ、ああ……」
少女はにっこり笑った。
「僕の盟約者さん。よろしく♪ あ、僕、ピーマンとニンジン食べられないからよろしくね」
「何だって?」
少女は僕から離れ、胡坐をかいた。それも、宙に浮かんで。
「だからぁ、ご飯。ピーマンとニンジン抜きね」
「お前、浮いて……っていうか、僕に飯をたかるのか!? お前、その――人間じゃないんだろ? 自分で何とかしろ」
「嫌だなあ。それじゃ君を選んだメリットがないじゃん。お腹すいたー」
少女は手足をばたつかせる。五月蝿い。思わず耳を塞いだ。
「わかった。民に施しくらいやろう。シチューならいいな?」
「ニンジン抜きー」
少女が注文をつけた。
「あ、それと」浮いたまま、少女が僕に近付いた。「僕の名前『フィフィ』だから。ちゃんと正しい発音で呼んでね。じゃないと返事しないから」
その時から、とんでもないクレイジーガールが僕に憑くことになった。
*
「フィフィ。お前の腹は際限を知らないのか」
僕の目の前に積まれた皿。正面に座っているはずのフィフィの姿が見えない。
ドアがノックされ、追加の食事が運ばれてくる。
「あの、お坊ちゃま……」バーナードがおずおずと言う。「これで32皿目でございますが、あの、御身体は大丈夫でございますか?」
「あ、ああ……」
これを全部僕が食べたことになっている。だが、本当のことを言おうにも、フィフィの姿は誰にも見えない。クレイジーガールの言ったことは本当だった。フィフィが入っていた人形は、見ようによっては死体に見えるので、クローゼットの奥に隠した。
「美味しー☆ やっぱり良いなあ宮廷料理」
「ここは宮廷じゃない」
バーナードが眉根を寄せる。独り言を言ったと思われた。「もういい」とバーナードを下げさせて、僕はフィフィと向き合った。
「それで、僕の望みを叶えるというのは本当か」
「僕、嘘つかないよぉ」
フィフィは31皿目を空っぽにした。
「口を拭け。見苦しい」
タオルを差し出すと、「もう一皿食べるもん」と突っ返された。
「そうだねえ……。じゃあ、ご飯貰ったことだし、僕の力を見せてあげる」
フィフィは右手を上げた。
その途端、雷鳴が轟いた。驚いて外を見る。
「え……そんな。急に空が真っ黒に――」
ピカッと、空が光った。
ガラガラガラ!
物凄い音と振動。雷が落ちた! 屋敷は停電した。
「なっ……」
「あははは、良いね、その驚きの感情」フィフィは大笑いし、僕に言った。「僕はね、雷の属性なの。人を驚かせるのがだーい好き☆ だから、君みたいにビビリな子は大好物なんだよ」
「誰がビビリだっ……」
声に力が入らない。雷が落ちたときは死ぬかと思った。よく見てみると、雷は庭の木に落ちたようだった。
「坊ちゃん! 大丈夫でございますか」
バーナードの声。
僕はフィフィと向き合う。
「…とりあえず信用しよう」
「その上から目線。気に入らないなぁ」
言葉とは真逆に、フィフィはニッと笑った。
*
フィフィ=アルトネット。それが僕に憑いたクレイジーガールの名前だ。
「言うなれば、僕は王族なんだぁ」
椅子に座って足をぶらぶらさせ、フィフィは言った。
「王族? お前が?」
「鼻で笑ったね。でも本当だよ。オーランドっていう王がね、骨と雷から僕を作ったの」
「話が見えないな」
「それはアーちゃんの頭が悪いんじゃないのぉ」
「だっ……」僕は絶句する。「誰が〝アーちゃん〟だ」
「あれえ、気に入らない?」
「当たり前だ!」
「坊ちゃん!」運転席のバーナードが振り返る。「どうかなさいましたか?」
「い、いや……。何でもない」
僕は空咳でごまかす。となりでフィフィが笑った。
「だからね、僕は骨をとられたら死んじゃうの。ただの雷になっちゃうんじゃないかなー。元の身体がないからね。酷いよねえ。たとえばさ、ロイズレッドって水属性のランズが居たんだけどぉ」
「水? ランズ?」
僕の理解そっちのけで、フィフィは話す。
「ロイズレッドはねー、ランズが嫌になったの。で、骨を手放したんだけど、そうするとランズは死ぬんだ。だけど、骨を貰った奴もまた手放しちゃってさ、でもね、その子生きてるんだ。元々の身体があったから、それに戻ったの」
「?? 訳がわからない。つまりランズって何だ」
フィフィは僕に顔を近付ける。僕は思わず後退する。
「From Auland’s Bornとか、Auland’s Childとかぁ。つまり、オーランドから造られた者ってことだよ。フロム・オーランズ・ボーン……オーランズ・チャイルド。その略なんだ」
「へえ。で、オーランドって誰だ」
「だから、王様だよ」
「現国王はそんな名ではないぞ」
「あーもう、理解力ないなあ、アーちゃんは」
フィフィは、ごろんとシートに寝転がる。
「坊ちゃま」バーナードの呼び声。「着きましてございます」
「ほら起きろ、フィフィ」僕は小声で話す。「それとも車に残るか?」
「つまんないのは嫌――ッ」
「うわ……ああ!?」
ドアが開けられる。
バーナードが唖然として僕を見る。
「坊ちゃま。どうなさいました……?」
「重い! 乗るな!」
「坊ちゃま?」
フィフィに押しつぶされた僕は、起き上がれない。フィフィは僕を踏み台にして車から降りた。
「クレイジーガールめ……」
「あっ、ここ学校だよぉ。アーちゃんの学校?」
「僕の父親が所有する学校だ。僕も特別顧問の立場についている」
僕は車から降り、埃を払った。
「坊ちゃま」バーナードは心配そうにしている。「ご気分がお悪いのでしたら、病院に――」
「必要ない」僕はきっぱりと言った。「それから、お前は車で待機していろ」
「はい?」
「週一回の学園の視察くらい、一人でできる」
僕はカツカツと靴音を鳴らし、学園の門を通る。門番が僕に頭を下げた。
「坊ちゃま! しかし、お一人というのは――」
「うるさい。父には内緒にしておく。いいからお前は待機だ」
バーナードを振り切って、僕は学園に足を踏み入れる。
父の経営する学園。これは本業ではない。会社のイメージアップのための、慈善事業だ。営利目的ではないため、授業料は安い。入学テストに受かりさえすれば、庶民でも入れる。ただし、学園の評判を落とすような素行の悪い者は、テストの成績がいくら良くても入れない。
学園の入学者は、中流から上流階級まで様々。あまりの貧乏人は、教育を受けていないことが多く、テストに受からないので居やしない。
学園は、経営も安定し、評判も良い。ここは僕の社会勉強のための場でもある。僕の仕事は、主に学園の視察。〝学園の生徒と同年代の少年の目で、学園を視察し、改善点などを発見してほしい〟と、父は言った。
「綺麗な空気の学校だね」フィフィは落ち着きなく校舎を見回す。「自然がいっぱいだからかな。エナジーがいっぱい」
「あまり話し掛けるなよ。独り言を言っていると思われる」
「アーちゃん。学食食べてみたい」
「…人の話を聞け」
頬が引き攣る。フィフィと居るには我慢が必要だ。こんなガキのために何故僕が我慢を……。
廊下の奥から、校長が駆けて来た。父が学園の指揮を任せている、一応は上流階級の二世だ。尤も、家柄は僕らの足下にも及ばない。
「アーサー様! ようこそいらっしゃいました」
ほら、こいつも僕にへりくだる。
「視察をさせてもらう。いいな?」
「は、ご存分に」
頭を下げる校長の横をすり抜けて、僕は校舎を見回る。
人の心の中が見えたらいいのに、と思うことがある。どれくらい僕を嫌っているのか目に見えたらわかりやすい。知っても仕方のないことだけど……。
生徒たちが僕をどう言っているのかも知っている。気取った奴だと。そんなの仕方ない、生まれが違うんだから。
僕は高貴な存在。他の奴らとは違う。誰もが僕にひれ伏す。
でも、誰もが僕を蹴落とそうと密かに狙っている――
「みんな真面目に勉強してるねー」
教室を覗いて、フィフィが言った。
「僕が見ているからだ。サボっていたと告げ口されてはまずいだろう」
「ふーん。あ、でもあの窓際の子、絵本読んでる。絵本作家になりたいのかなー」
「さあな」僕は踵を返す。「帰るぞ。フィフィ」
「1年生と3年生のクラスはいいのぉ?」
「いい。帰る」
廊下を歩き、来たときと同じ道を辿る。校長の聞き飽きたお世辞を途中で遮って、僕は車に乗り込んだ。
「僕あの学校気に入っちゃったな。また行こうね」
「それが仕事だ」
素っ気なく言って、それからは何を聞かれても答えずに外を見ていた。
僕はいつだって気を抜けない。取って食われてしまったら終わりなんだから。スピードを落とすな。弱みを見せるな。僕は高貴な存在だ。そういう生まれだ。
ふと車の中に目を戻すと、フィフィが測るように僕を見ていた。僕の視線に気付くと、ふいっと目を逸らす。
そう、誰にも心は見せられない。
誰の目にも映らない、このクレイジーガールにも。
*
「ご馳走様でしたっ☆」
フィフィは今日、8皿目で食べるのをやめた。
「どうした、人間らしくなってきたな」
「僕はランズだよぉ。あのね、もう大分エナジー吸収できたの。効率は悪いけど、食べ物からでもエナジーとれるんだよ」
「ふうん」
バーナードを呼んで皿を下げさせる。
午後8時。フィフィはクッションをぎゅうっと抱きしめて(僕のクッションだ。フィフィが気に入ってしまっている)、ベッドに横になる。
「そこは僕が寝る場所だ」
「いいじゃん。大体、君が僕にくれた部屋、ここより狭いんだよ。扱い悪くない?」
「十分だろう、居候が」
フィフィの所為で、僕は大食いの異名がついてしまっている。成長期だと言い張れないほどの量だ。
ごろんと寝転がるフィフィに、僕は言った。
「仕事しろ。僕が望みを言うからそれを叶えるんだ」
「はーい☆」
「僕の望みは――」
「あ、待って、わかるよ」フィフィが僕を制した。「アーちゃんの望みは、彼女が欲しいってこと」
「違う」
フィフィはにっこり笑う。
「なぁんだ。僕、てっきりそうだと思ってたよ。ね、アーちゃんはどんな子が好みなの?」
「フィフィと真逆の女だ」
「それってどんな?」
「自己主張せず、大食いでもなく、僕の言いつけに逆らわない女」
「それって彼女じゃないよぉ。お手伝いさんだ。で、アーちゃん……脇道に逸れたけど、僕に叶えて欲しいことって、何?」
クッションをぎゅうっと押しつぶし、フィフィは僕に尋ねた。
僕は、望みを言った。
「…人形に、命を与えて欲しい。出来るんだろう?」
フィフィはにやりと笑った。
「Yes, of course」
僕はクローゼットを開け、その奥からフィフィの人形を取り出す。
「あれ、僕の人形じゃん」
「違う、この奥にあるんだ」
フィフィに悪戯されそうで、隠したのだ。
それは、古いけれどとても綺麗で、今にも動き出しそうな陶器の人形。僕が小さい頃に亡くなった、母様の品だ。
背丈は僕の肩より少し低い。人形は、少女だけれど少し大人びていて、着ている洋服も若干大人っぽい。フリルの付いたヒラヒラじゃないところが僕の好みだった。
知的な才女。そんな人形だ。
「アーちゃんの好みのタイプだね」
フィフィが人形を眺める。
「お前はもともと、人形に入って動かしていた。なら、これも動かせるな?」
「僕が入るの?」
「やめろ。人形のイメージが崩れる」僕は心底嫌がった。「そうではなくて、魂を与えるとか」
フィフィは微笑する。
「アーちゃん、この子のこと好きなんだねー」
「いや、その……」
「やっぱりねえ」フィフィはにっこり笑う。「いいよ。動かしてあげる。アーちゃんの叶わぬ恋、かなえてあげる。僕、良い子だからね」
フィフィはベッドから飛び降り、人形の手に触れた。
「ちょっと時間かかるよ。明日の夜まで待って」
「ああ、わかった」
フィフィは人形を眺め、僕を振り返って自信満々で言った。
「この子、アーちゃん好みの人形に仕上げてあげるね。絶対絶対、アーちゃんが喜ぶようにしてあげる☆」
*
チャイムが鳴って、私は、二冊の教科書を鞄に仕舞った。
今日の講義はこれで終いだ。私は立ち上がる。ここに長居しても意味はない。
いつもなら、すぐに帰れた。が、今日はクラスメイトのサンドラに引き止められた。
「ねえ、リズ=サンタフェラー。今日、家でパーティーを行うんだけど、いらっしゃらない?」
サンドラは派手な女の子だ。誰彼構わずベタベタと付き纏う。彼女は、新たな『お友だち』の標的を私に向けたらしい。
「ごめんなさい。私、そういうパーティーはあまり得意じゃなくて……」
「あら。気軽なパーティーよ? 軽装でいいの。あなたでも来れるわ」
中流階級の娘のあなたでも来れるわ、と言っている。ああ、わかりやすい。この人は上流階級の娘であることに過剰な誇りを持っている。
「それでも、やっぱり……私が行くとお邪魔になるだろうから。楽しんできて」
丁重に断ると、サンドラはつまらなさそうな顔をした。
「あなたって本当に個人主義ね。もっとお友だちを作ればいいのに。じゃないと人生楽しくないわ」
「ええ……、そうかもしれないわね」
そのとき、教室の窓際から歓声が起こった。
「アーサー様がお帰りになるわ!」
「えっ、アーサー様が?」
サンドラはすぐさま反応し、窓に駆け寄る。
『アーサー様』はこの学園の経営者の御曹司で、超が付く上流階級だ。
私は興味がなかったので、さっさと鞄を抱えて帰った。
女の子たちは、アーサー様が好きだ。もしお気に入りになって結婚なんてことになれば、一生安泰だ。男の子たちは、それをやっかみながらも、もし彼と親交を深められれば将来自分の得になる。だから、アーサー様にへりくだる。
私はそういう駆け引きが苦手だし、嫌い。でもそれを口にすれば――ひとたび本心を出せば、必ず爪弾き者にされる。私は構わないが、私をこの学園にやった両親の会社が困る。私の会社と取引のある会社の息子や娘がたくさん居るのだ。
息を殺して、生活する。
いっそ感情なんてなくなって、何も感じなくなれば楽なのに……。
*
人形に魂を与える――
そんなこと、夢だと思っていた。人形が動けば良いのにと思いながら、人形を見つめた日々。それが現実になる。
フィフィ=アルトネットの手によって。
その日は上の空だった。家庭教師に、体調が悪いのかと訊かれたので、そういうことにして早めに勉強を切り上げた。
部屋のドアを開けると、部屋の中央の床に、人形が置かれていた。
隣のフィフィは、僕に気付くとニコッと笑った。
「ちょうど準備が終わったところだよぉ」
「そうか……」
僕は蝶ネクタイを緩め、息を呑む。ドアの鍵を閉め、誰も入れないようにした。
人形が動く。僕の思いのままに。僕の心臓は胸から飛び出そうだ。
「コレを、人形に入れれば終わりなんだけど」フィフィの手に小さな小瓶。綺麗に光っている。「アーちゃん、この子に名前付けてよ」
「人形にか?」
フィフィは頷く。「この子、今から意志を持つんだよ。名前を呼べなかったら可哀想」
「ああ……、そうか」
少し考えて、決めた。
「〝ジル〟だ」
フィフィはにやりと笑う。
「OK。じゃあジル。Happy Birthday! 今日は君の目覚めの日だ」
フィフィが小瓶を傾ける。
柔らかな薄紅の光が、静かに落ちていく――
それは、人形の『ジル』に触れ、瞬く間に人形の全身に広がった。綺麗だった。やがて光が収まる。
「フィフィ……」
僕の声は掠れて小さい。
「Si……目が覚めるよ」
口元に指を当てて、フィフィが言った。
ジルの瞳が動いた。指先が、足が、動く。僕は腰が抜けそうだった。嬉しくて。
やがてジルは起き上がり、辺りを不思議そうに眺めた。
「動いた……」
僕の声が聴こえて、ジルの瞳が僕を見る。不安そうにしている。
フィフィが近付いた。
「やあ、ジル。初めまして。僕はフィフィ。あっちは僕の盟約相手(オーナー)のアーちゃん」
僕は咳払いをする。
「アーサーだ」
「………」人形は訝しげに僕らを見る。「ジルって、私の名?」
綺麗な声だ。僕は感動した。
「ジル」僕は彼女に近付いた。「君は今日から僕のものだ。僕の言い付けに従うんだ……いいな」
不安そうなジルの目に、僕が映る。フィフィは見事に役目を果たした。この人形は僕の――
理想、と思った。が、次の瞬間、僕の頬は痛みで熱くなる。小気味良い音と共に。
「偉そうに言うんじゃないわ。ガキが」
理想……のはずが。
フィフィは僕の背後で、ケラケラ笑っている。
*
僕の一日は、バーナードに起こされるところから始まる。
朝食をとって庭の散歩、家庭教師の指導を受けて父との定期連絡、自由時間のあとで食事。時たまパーティーに呼ばれることと、週一回の学園の視察以外、僕はあまり屋敷から出ない。
「坊ちゃま。最近、お部屋にいらっしゃらないようですね」バーナードが僕のカップに紅茶を注ぐ。「家庭教師の指導も別室でとは……。何か心境の変化でも?」
「うるさい。そういうときもある」
僕は不機嫌を顔に表し、それ以上の質問を遮った。
確かに僕は、部屋にあまり寄り付かなくなった。部屋に戻りたくない。
が、寝るときは自室だ。僕は夜になって、渋々部屋に戻る。
廊下を歩いていると、僕の部屋の中から女の笑い声が聞こえる。ぎょっとして、慌てて部屋に戻った。
「フィフィ! ジル! うるさいぞ」
部屋の中の二人の女。
子どもみたいなクレイジーガール、フィフィ。
外見だけはクールな人形、ジル。
二人の目が僕を向いた。僕は急いで部屋に鍵をかける。
「アーちゃんの声の方がうるさいよぉ」
「同感。それよりご飯は?」
ジルはツマミを口に含み、片手にグラスを持っている。
「人形のくせに何故食べる必要がある!?」
「味覚があるからだよ」ジルは当然のように言った。「美味しいんだもの」
僕は渋々、夕食の残りをジルとフィフィに差し出す。二人は笑みを浮かべた。
「あー、僕の好きなトマトチキンだぁ」
「あ、私、これ嫌い。フィフィにあげる」
「わ、やったあ!」
「だから、静かにしろ」僕は再度言った。「フィフィはともかく、ジル……。お前の声は人間に聴こえるようだ。バーナードが、女の声が聴こえたと言っていたぞ」
「大丈夫。執事が来たら人形らしくしておくから」ジルはフォークを片手に持つ。「頂きます」
フィフィとジルは笑顔で食事をとる。静かにしろと言ったのに、食事中も騒がしい。
僕は深く深く溜息を吐いた。
ジルが僕の人形となって早3日。
この展開は、僕の思い通りの正反対。
あれほど端整で麗しい人形が意志を持てば、理知的で物静かな意志を宿すと思ったのに……。実際のジルは、僕の言うことなんか何も聞かない。ツマミが大好きで(特に燻製が好みだ)、昨日は酒の味も覚えてしまった。まるでオヤジだ。
僕はこっそり、フィフィに問いかけた。
「あの傍若無人な人形を何とかしろ。性格を変えるんだ」
「えー、アーちゃん好みの子でしょぉ?」
「何処がだ! とにかく何とかしろ」
「変更はできないよぉ」
僕は愕然とした。
フィフィだけでも困っていたのに、更に居候が増えてしまった。しかもフィフィは、盟約が完了したというのに去る気配がない。
「屋敷の好きなものを持っていっていい。とにかく帰れ」
「僕の家はここだもーん」
フィフィは居ついてしまっている。最悪だ。
しかし、人形の性格を変えるのには、フィフィの力が必要だ。出来ないと言っていたが、何とかしてもらうしかない。これでは詐欺だ。
ジルの性格が変わらないまま、十日が過ぎた。フィフィは散歩に行ってくると出掛け、僕は部屋で勉強をすることにした。
「何の勉強?」
ジルが僕に訊いた。
「語学だ。色々な言語を身に付けているに越したことはないからな」
「それって商談のために?」
僕は頷いた。
ジルは、僕の教科書を奪う。
「何するんだ!」
「たまには外に出ればいいのに。散歩でもして気持ちを切り替えないと。最近、ずっと眉間に皺が寄ってるよ」
「誰の所為だと……!」
教科書を取り戻そうとするが、ジルはそれを部屋の端に投げてしまった。
「この我侭ドール!」
「我侭王子! 大っ嫌い」
ジルは拗ねて部屋の隅に座り込む。
「……」
僕はほんの少しだけショックだった。いくら中身が気に入らないとはいえ、ずっと大切にしていた人形に嫌いだと言われたからだ。ジルに見破られないよう、僕は彼女から目を離した。
「……外に出たい」ぽつりと声が聴こえた。「ずっと部屋の中じゃ息が詰まる」
「人形が歩いてみろ。目立って仕方ない。息が詰まるなんて、人間みたいなことを言うな」
「はいはい、人形で悪かったわね。わかってるわ」
ジルの声は不機嫌だ。声質はとても良いのに、言っていることが勘に障る。
僕は振り返ってジルに言った。
「お前、もっと素直で可愛くなれないのか。このままじゃ、僕はお前を粗大ゴミにするしかない」
「そっ……!」ジルの頬が引き攣った。「命を持った人形に向かって、よくそんなことを言えたわね! その高飛車で最低な性格直しなさいよ、馬鹿王子!」
「そっちこそ、大人しく主人に従ったらどうなんだ!」
「誰が主人!? 私に主人がいるの!?」
「ただいまーあ」フィフィが戻ってきた。「散歩楽しかったよぉ……って、あれ、部屋の空気が重いかんじ」
僕もジルも押し黙っている。さすがのフィフィも雰囲気の悪さに気付いたようだ。
「まあいいけどさー。ケンカも程ほどにして仲良くしなよぉ。せっかく一緒に暮らしてるんじゃん」
「私、嫌よ」ジルが言った。「こんな我侭王子と生活するなんて。実家に帰らせてもらいます!」
「実家。へえ、実家か」僕は挑発的にジルを見る。「お前に実家があるのか? 何処だそこは」
「うっ……だからそれは」
ジルは言葉に詰まる。
「ジルの家はここだよぉ」フィフィが言った。手に飴を持っている。「あーもう、どうして上手くいかないのかなあ」
フィフィはベッド脇に腰掛け、足をぶらぶらさせた。
「アーちゃん。お腹へった。ごはん」
「勝手に持ってこい」
「いや、出来るけどさぁ……。アーちゃん冷たい。最近僕の扱い悪くない?」
「居候が勝手なことを……。どうして僕の周りにはクレイジーな女ばかりが集まるんだ」
僕は頭を抱える。ああもう、こんな部屋に居たくない。僕は立ち上がった。
「食事を持ってきてやる。有難く思え。しばらく待っていろ」
バタンとドアを閉め、廊下を歩く。
全く、とんでもないことになった。フィフィが来て以来、僕はイライラしてばかりだ。
応接間でバーナードに命じた。
「食べ物を持ってこい。二人前だ」
「坊ちゃま……。あの、猫でも飼っていらっしゃるのですか?」
「猫よりタチが悪い」
ぼそっと呟いた。
「はい?」
「いいから持ってこい」
「はい、ただいま」
厨房へ歩き出そうとしたバーナードが、ふと足を止める。
「そういえば、先日お話した、入院した生徒の話ですが――」
「見舞い品は送ったか?」
「はい、坊ちゃまに言われたとおりに。それで、容態なんでございますが」
「いい。興味がない」
バーナードは言葉を詰まらせ、「食事を持って参ります」と下がった。
自分に反抗する者は嫌いだ。黙って僕に従っていればいいのにと思う。特に、うるさくわめく女は嫌いだ。
でも僕は、心の醜い人間も嫌いだ。僕を蹴落とそうと近付いてくる人間も、父の権威が目当てで寄ってくる人間も、大嫌い。
ふと思った。
じゃあ、僕の好きな人間ってどんなだろう?
嫌いな人間は思い浮かぶ。
でも、好きな人間は誰一人浮かばない。
自分以外は、全て敵。
貴族とはそういうもの。名家とはそういうもの。孤独を嫌がっては生きていけない。
そう、孤独だ。いい言葉じゃないか。僕にぴったりだ。
大好きだった人形が僕を嫌いになって、僕もその人形を嫌いになる。これでこそ孤独。トップに立つ人間。
これでいいんだ。みんなが敵。みんな嫌い。
そう、これで。これで……。
*
フィフィとジルが来て以来、僕の寝床はとられた。二人がベッドを占領し、僕は一時期、床に敷いた布団で寝ていた。ありえない。すぐさまもう一つベッドを用意させた。
その夜は、フィフィの寝息が規則的に聞こえる静かな夜だった。
なんとなく寝付けなくて、椅子に座って月を眺めた。
「んー…」
ジルの声だ。起きたらしい。
「あれっ……アーサー。何でまだ寝てないの」
「関係ないだろう」
「ないけどさ」
ジルはベッドから降りる。
「アーサーは将来、お父様の後を継いで社長になるんでしょう? それに疑問は持たないの」
「疑問だって? 何故持つ必要がある」
「なんか、無理やり背伸びしてるみたいに見える。精一杯虚勢張ってさ。あ、別にケンカ売ってるんじゃなくて。時々痛々しく見える」
「はっ…人形に何がわかる。虚勢を張らなければ商談なんて上手くいきっこない。お前は助言をしているつもりか?」
「人形のくせにって言いたいんでしょ」ジルは眉をつり上げる。「悪いけど、人形でも何故か人の気持ちはわかるの。本当、生意気で高飛車でムカつくんだけど……何かちょっと、私と似てるところがある」
「お前と僕が? 人形に言われたくない」
「あんまり他人を見下してると痛い目みるよ」ジルは僕を睨む。「まあいいけど」
ジルはベッドに寝転がる。まるで自分の部屋みたいに寛いで。
「あー、お酒飲みたい。晩酌がしたい」
「酒を飲む人形なんて聞いたことがない。見た目の品が良いだけに残酷な光景だな」
「あ、ちょっと、私のこと褒めた?」
「お前の外見が良いと言ったんだ。中身は最悪だ」
「お互い様でしょ」
ジルは目を閉じる。
「明日は晩酌の…お酒持ってきてね……。おやすみ」
すぐに寝息が聞こえてくる。早い。
「まさか今までのは寝言だったんじゃないだろうな」
ジルはすやすや眠っている。隣でフィフィが「特製お団子ー」と寝言を言った。
「食い意地の張っている奴らだ」
眠っているフィフィとジルは、まるで姉妹みたいに見える。
僕にきょうだいは居ない。フィフィとジルの間にも入れない。
「やっぱり僕は一人じゃないか」
人でない者に憑かれても、人形に意志を持たせても。
僕は布団にくるまって、眠った。
*
その三日後。
久々に父と会った。時間が空いたというので一緒に食事をとることにした。
僕はレストランまで足を運んだ。父は既に到着していた。僕が席につき、食前の飲み物を手にとると、父が言った。
「アーサー。お前の作った学園の改善報告を読ませてもらったよ。池に柵を作る案は良いな」
「学園にはそれなりの階級の奴も居ますからね。学園内で事故が起こったらまずいんですよ」
スープが運ばれてきた。
父は髭を触る。
「ふむ。そういえば、生徒が一人倒れたそうだな。幸い、倒れた場所が学園じゃなかったから、学園の責任は問われなかったが」
「持病じゃないんですか?」
突然倒れたとしか聞いていない。
「ああ、持病はなかったそうだよ」父は後方の秘書に尋ねる。「彼女はどんな状態なんだね?」
「20日のあいだ意識不明で危険な状態です」秘書は答える。「倒れた原因はわかりません。日に日に呼吸が弱くなっているそうです」
「検査はしたのか」
「はい。しかし、原因がわかりません」
僕はスープを飲んだ。まあまあの味だ。
「伝染病でないのならいいのですが。学園内にウィルスを撒き散らされたら困りますね」
「本当にな。まあ、我が学園の評判を落とすことにはなり得ない。中流階級の娘だしな」
「うちの会社とは取引のないところなんですね?」
「ああ、そうだ。名前は何だったかな」
「リズ=サンタフェラーです」
カラン、と音が鳴った。
僕がスプーンを取り落としたのだ。
「どうした? アーサー。顔色が悪いようだが」「………」僕の目は見開いて、手は震える。もうスプーンを持てない。「あの、僕、今日は帰ります。ちょっと体調が優れなくて」
「それはいけない。すぐに休みなさい」
父が秘書に目配せし、すぐに車が手配される。
歩けないほど、全身の力が抜けていた。
僕は、僕としての体裁を保っているだけで精一杯だった。
倒れた少女の名が、繰り返し繰り返し頭に浮かぶ。
リズ=サンタフェラー……
どうして、彼女が……。
*
ドクターが帰っていったあと、僕は自室のベッドに寝かされた。フィフィは部屋の隅に移動し、ジルは人形の振りをして動かないでいた。
お粥の湯気が見える。時間が経つにつれ冷めてきて、湯気は消えていった。
何の音もしない。でも自分の心が喧しい。
いつの間にか夜になっていた。僕は動けない。少し眠っていたのかもしれない。それすらもわからない。
起き上がる。自分の心が痛む。これは後悔か、それとももっと別の感情か。
フィフィが毛布にくるまって眠っている。
ジルの姿がない。
部屋から出るなと言っておいたのに、あの人形……。
タオルケットを肩から掛けて、僕は部屋を出た。
廊下は真っ暗だ。空気はひんやり冷たい。
そういえば、小さい頃はよく夜中に起きて、母様と夜の散歩に出かけたものだ。夜は怖かったけれど、母様が居れば怖くなかった。散歩の後は、ぐっすり眠れた。もう遠い昔の話。
ジルはベランダに居た。遠くを見ている。少し風が吹いていた。
「何をやってる。こんなところで」
自分の声がひどく弱々しいことに気付く。夜でなければジルに聞こえていなかっただろう。
彼女は振り向くと、少し驚いた顔をした。
「見つかっちゃったか。部屋に篭もりっきりもつまらないから、夜中にたまに抜け出していたの」
「ふうん」
ジルから少し離れたところに立って、ベランダの手すりに体重を掛ける。夜にここから景色を見るのは初めてのことだ。
「アーサーは何に落ち込んでいるの?」
「落ち込んでなんかない。風邪だ」
ジルは僕を見て、「嘘ばっかり」と笑った。
「わかるよ。何かに傷付いてるんでしょう? わかった、仕事で失敗したんだ」
「そんなことはない。大体、失敗してこんなに落ち込むような大きな仕事は任されていない」
夜風が冷たい。何も羽織っていないジルは寒いんじゃないかと思ったが、彼女は人形なんだと思い出した。
「…学園の女生徒が倒れた。死ぬかもしれない」
ぽつりと、僕は言った。
「アーサーの友だち?」
「いや……ただ知っているだけだ」
ただ、彼女の存在に気付いていただけ。
視察に行くと、周りの生徒が勉強する振りをしている中、彼女だけが絵本を読んでいた。最初はムッとしたが、そのうち、それが彼女独特の抵抗なんだとわかった。抗っても仕方のない、社会とか、権力とかそういうものへの。そうやってひどく痛々しい抵抗をしている彼女は、深い孤独を背負っているように見えた。
認めたくはないけれど、リズ=サンタフェラーは自分に似ていた。
「その子のことが好きだったの?」
「さあ。わからない。でも気にはなっていた」
視察のたびに、彼女のクラスを覗くようになった。窓際の席で、ひたすら本を読んでいる子。名前と経歴を調べた。中流階級の娘で、成績はふつう。冷静で、知的で、目立つことを望まない女――そんな印象だった。
「死なないといいね、その子。元気になったら会いに行ってあげなよ」
「まさか……。会ってどうなる。会話することなんてないし、向こうも戸惑うだろう」
ジルが、僕に近付いた。
「アーサー。人間の命なんて限りがあるんだよ。やり残したら後悔するでしょう。…また、人形に何がわかるって言われそうだけどね」
「いや……たぶん、その通りだ。それでも僕はきっと行動できない」
ジルはぽかんとした。
「何、その素直さ。アーサーじゃないみたい」
「うるさい。黙っていろ」
ぷっと、ジルが笑い出す。なんだか恥ずかしくなってきた。タオルケットを、ジルに放り投げた。
「え、何。くれるの?」
「僕はもう戻る。片付けておけ」
ベランダに背を向けて、歩き始める。
「ありがとう。アーサー」
背後から、ジルの声。
それは無垢な声で、僕は何故だか泣きたくなった。
涙が流れてしまわないよう、僕は駆け足で部屋に戻った。
*
翌日のことだ。
僕は、リズ=サンタフェラーの見舞いに行った。
「坊ちゃま。ご興味がないのでは……」
「うるさい。お前は外で待っていろ」
僕は、見舞いの品を持ち、病室に入った。
静かだった。
カーテンが風に吹かれて揺れる。
リズ=サンタフェラーは眠っている。口元に呼吸器が付けられている。
「抗おうとしていたくせに。こんなに弱いのか」
少女の手足は細く、小柄だ。こんな小さな身体で、たった一人、生きていけるわけがない。
僕は椅子に腰掛けて、リズ=サンタフェラーを見ていた。一時間くらいそうした。
声を掛けていればよかっただろうか。
入院したのが彼女だとすぐ知っていれば、まだ意識があったのだろうか。
僕には何の力もない。リズ=サンタフェラーを治すことはできない。元気になっても、彼女に話し掛けることも、まして笑わせてやることも出来ない……。
「アーちゃん」
フィフィの声。付いて来ていたのか。
「何だ」
「お腹へったよぉ。僕、パスタ食べたい」
仕方なく振り返り、気付いた。
そうだ。僕には力がある。フィフィという存在が居る!
「フィフィ!」
僕はフィフィの腕を掴む。
「盟約だ。この子を治せ。僕のものなら何でも持っていっていい。だから――」
「出来ないよぉ」
フィフィはきっぱりと言った。
「何で……」掴んだ手から、力が抜ける。「何でも叶えるんじゃなかったのか。人一人を治すくらい、何故出来ない!」
「アーちゃん、声大きい」フィフィは顔をしかめる。「だってさ、その子の目を覚ましたらジル死んじゃうよ?」
「な……」
何を言っている?
「どうしてそこでジルが出てくるんだ」
フィフィは僕の手を振り払い、ベッドに飛び乗った。
「アーちゃん、この子のこと好きでしょ。僕、わかってたんだ」
「それが……」
フィフィはリズ=サンタフェラーの髪を撫でる。
「アーちゃんはこの子と話をしたかったんだよね。でもシャイで出来ない。だから、代わりに人形を側に置いておくことにしたんだよねー。ジルってさ、なんとなくこの子に似てるよね」
「………」
その通りだった。
僕は薄ら寒くなる。
「僕、盟約相手の望みは完璧に叶えるシュギなんだ」
フィフィは小瓶を取り出して見せた。
綺麗な光が入っていた、その瓶――
「リズ=サンタフェラーの魂を半分、ジルに入れたんだ。だからジルは、イコールこの子ってこと」
ガタン!と音がした。
僕が椅子から落ちたのだ。
フィフィの笑みが、悪魔の笑みに見える。
「この子が思ってたような性格じゃなくて、アーちゃんガッカリしたみたいだけど、それは仕方ないよね。人間、見かけだけじゃ中身はわかんないんだからさ。僕、ジルとアーちゃんは仲良くなって欲しかったなぁ」
フィフィは足をぶらぶらさせる。
僕は震えていた。
「この子の魂を奪って……、僕の願いを叶えたのか……」
「うん。人形に意志を宿すのって、ほんと難しいんだよぉ。でも、人間の魂があれば別。半分だけ持ってったのは、全部持ってくと自分がリズだって自覚まで持っちゃうから。彼女は自分が人形だと思っててくれなきゃ」
フィフィはリズに目を移す。
「でもこの子、もう駄目だね。半分だけの魂で身体を維持できるわけがない。そろそろ限界かな」
僕は、力を振り絞って立ち上がった。
「人を殺せなんて命じていない! 誰かを死なせてまで、願いを叶えろと言った覚えはないぞ!」
「何で泣いてるの? アーちゃん」
気付かなかった。僕は涙を流していた。
フィフィが僕の涙に触れようとするが、それを僕が遮った。
「…アーちゃん、本当にこの子を好きだった。この子を側に置いておきたかった」
「そんなこと望んでない。お前の妄想だ」
「じゃあ、ジルって名前も偶然?」
フィフィはにこりと笑う。
「Lizを逆から読むとZil……あの人形の名前になる。アーちゃん、僕に嘘は通じないよ」
悔しかった。何故だか悔しい。フィフィを壊してしまいたいと思った。
「怒ってるね。でも何で? アーちゃんの望む通りにしてあげたのに」
「こんなこと望んでない! リズ=サンタフェラーの死なんて」
「死なないよぉ。死ぬのは身体だけ。リズは生き続けるよ、ジルとして」
「違う……違う、僕は!」
本当の僕の望みは、人形を動かすことじゃなくて。
僕は、彼女が孤独に潰されないように。
彼女が笑えるように。
側に居なくても良かった。でも話してみたかった。だから、人形を……。
「リズ=サンタフェラーの目を覚まさせろ。ジルは……もう、人形に戻していい」
フィフィの表情が変わった。
「ジルを殺す気?」
「自分の身体に戻すだけだ」
僕はゆらりと、フィフィに近付いた。
「盟約を結ぶぞ、悪魔。代償に僕の魂を持っていっていい。好きにしろ」
「……」
フィフィは僕を見ている。
フィフィの手が、僕の頬に伸びる。
頬に、何か書かれた。
〝Do.〟
僕から離れたフィフィは、少し笑っていた。
「要らないよぉ。こんな孤独ぶった魂なんて」
フィフィの姿が見えなくなる。
声だけが聴こえる。
〝望みどおりにしてあげるよ、盟約者。僕は優しいんだ〟
空が暗くなる。
雷?
〝それとね、僕は悪魔じゃないよ。王の守護者、フィフィ=アルトネット。また会うことがあったら、よろしく〟
落雷が起こった。
部屋が暗くなる。
僕の手に、小瓶があった。
綺麗に光る魂が入っている。
涙を拭って、僕はリズに近付いた。
「ごめん……」
小瓶を傾ける。
光る魂が、彼女に浸透していく。
さようなら、ジル。
それから……、
おはよう、リズ=サンタフェラー。
*
もうすぐ夕暮れになろうとしている。
その日、僕は初めて父の言い付けに逆らった。会談をすっぽかし、お忍びで学園の門の側に立っていた。
帰っていく生徒たちは、誰も僕だと気付かない。帽子をかぶり、眼鏡をかけて変装した。
目的の人物が現れて、僕は声を掛けた。
「リズ=サンタフェラー!」
彼女はぴたりと足を止める。
制服姿のリズは、僕を振り返った。
「誰?」
僕はリズに近付いた。
「体調はどう? その……、退院してからの調子は」
「良好だけど……。あの、本当にあなたは?」
僕は眼鏡を外し、帽子をとった。
リズが驚く。
「アーサー様! あ、あの、申し訳――」
「静かに。目立ってしまうじゃないか。本当に騒がしい女――あ、いや」
コホンと咳払いして、再び帽子を深くかぶる。
リズは恐縮して、僕をちらりと見た。
「あの、アーサー様。入院中はお見舞いに来てくださったそうで……ありがとうございます」
僕は笑えてきた。あのジルと違いすぎる。
「アーサー様?」
「今日は君を茶に誘いに来た。時間はあるか?」
「え、あ、はい、勿論。でも、何故私を?」
「理由なんかあるか。せっかく元気になったなら、美味いものを食べろ。確か、ローストビーフが好物だったな?」
「はい。でも何故、アーサー様が私の好みをご存知なんですか?」
「いいから行くぞ。人生の時間は短い。悔いを残してはいけないからな」
リズ=サンタフェラーの手を引っ張る。
今日は執事も居ない。僕とリズの二人。
笑い声が聞こえた。
リズ=サンタフェラーが笑っている。
「はい。それには同感です。アーサー様」
僕も笑った。
「『様』は要らない。アーサーと呼べ。ところで、食事はローストビーフでいいんだな?」
手を引っ張っていたはずが、リズが僕の隣に立ち、まるで手を繋いでいるかのような格好になる。
僕は孤独が好きだったけど、二人で並ぶのも悪い気分じゃない。
世界には退屈なことばかり。
変わりばえのない日常。
僕の部屋からはジルの人形がなくなっていた。
そして僕は今、リズ=サンタフェラーとお茶をしに行く。
それでいい。
少しずつ変わっていけばいい。
きっと、こういうのも……
「悪くない」
リズと僕が、声を合わせて笑った。
盟約紳士 Om.


