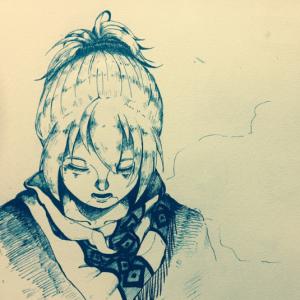四季の歌
四月の雪が溶けて
「さむい…」
もう四月だというのにまだ雪が溶けきらない。
路傍の片隅で黒くなっている雪の塊に春樹は白いため息をついた。
一週間前やっと夢の小学生になれたのに、春樹の卒園式にも入学式にも桜は間に合わなかった。
背中に背負ったまだピカピカの黒いランドセルも、この灰空の下ではどこか寂しげだ。
異常気象とまで言われている今年の空はまだ春を連れてくる気はないらしく。
寂しげな桜の木の枝の間をまたハラハラと雪がちらつき始めた。
春樹がまたはぁ、と溜息をつき道の角を曲がったその時。
「わっ」
どんっと勢い良く人とぶつかり、春樹は尻から道に倒れ込んだ。
「あ、ごめんね!大丈夫?」
上から聞こえる声に顔を上げて、春樹はハッと目を丸くした。
それは彼がぶつかった中学生くらいのその少女の、透き通るような肌の白さでも、桜の花を彷彿とさせる愛らしい顔立ちでも、風のような心地よい声に対してでもなく、彼女の鷲色の瞳から、雨の雫のような涙がホロホロと尽きることなく流れているからだった。
「ご、ごめんなさい!」
春樹は自分がぶつかったせいだと思い慌てて立ち上がって謝った。
「え…?なにが?」
「だって…、泣いてるから…」
キョトンとした少女を春樹はバツが悪そうに見つめた。
「ああ…、これは、違うの」
少女が自分の頬を触って儚げに微笑む。
春樹は無性にその少女のことが気になって、学校の事など忘れて彼女の手を取った。
「あっちにね、公園あるんだ。僕でよかったらお話きかせて?」
春樹がそう言うと、少女は少し目を見開いてから柔らかに微笑んだ。
「お名前なんていうの?」
「春樹。春日屋春樹」
小さな公園の隅にある錆び付いたブランコに並んで座った二人は、ポツリ、ポツリと言葉を交わし始めた。
さっき降った雪でブランコは少し湿っていた。
「お姉さんはなんて名前?」
「ん~…。内緒。春樹くんの好きな呼び方でいーよ」
「えー?僕は教えたのに…」
春樹がそう言うと、少女は少し困った顔で「ごめんね」と笑った。
「んー………とねぇ…じゃあ、ゆき!」
「ゆき…?」
少女は目を微かに瞬かせた。
「うん!うちの犬とおんなじ名前!ね!ゆきちゃん」
「ぇえ~?」
ゆきと呼ばれた少女は、また眉毛を下げてそれでもちょっと嬉しそうに笑った。
「ねえ、なんで泣いてたの?」
春樹は雪の笑顔に安心した。
そしておずおずとゆきに尋ねた。
ゆきは眉を下げたまま目を細め、キィ、キィ、とブランコを揺らした。
それにあわせてブランコの影も地面をゆらゆらと揺れた。
「ん…。私ね、もうすぐここから離れなきゃいけないんだ。…というより、本当はもっと前に行かなきゃいけなかったんだけど、私のわがままでここにとどまっちゃってるの…」
少しおどけた様な表情で誤魔化すように髪を触る。
「どうして行きたくないの?ひどいとこなの?」
「んーん。逆かな。私がここが好きなだけ。今年の冬ね、私よく泣いてたんだ。私泣き虫だから…、でもね、ここのみんなは私の涙を綺麗だって言ってくれたの」
雪の声が少し弾む。
「それが嬉しくて…。ここが大好きになった。でも私がいることで私を褒めてくれたみんなに迷惑がかかるから…。私は早くここを離れなきゃならない」
「そう、なんだ…」
春樹はキィ…とブランコを漕いだ。
聞きたいことは色々あった。
なんで泣いたの。なんで迷惑なの。なんで。でもそのどれもが彼女を追い詰める気がした。
自分の中の言葉はどれも幼くて、自分はどうしょうもなく子供だと実感した。
また、キィ、キィ、、ととなりのブランコが揺れ始める。
「春樹くんはさ、お花好き?」
「うん!」
春樹はパッと顔をあげた。
「なんのお花が好き?」
「んー、ひまわりも好きだしーチューリップも好きだしー…、あ!桜も好き!…でも今年はまだ咲かないんだー。入学式に間に合わなかった」
春樹は公園をぐるりと囲う寂しげな桜の木を見つめ言った。
「そっか…」
隣のゆきも春樹の見上げる桜の枝を物憂げな目で見つめた。
「春さん、どこで寄り道してんのかなー」
それを聞いたゆきはまた柔らかく微笑んだ。「春さんは優しいからきっと待っててくれてるんだよ」
「なにを?」
「冬さんが旅に出る準備を」
ゆきがふわりと立ち上がる。
「でも、早くしないと夏さんに先こされちゃうんじゃない?」
春樹はブランコに座ったままゆきを見上げた。
「…そう、だね。ねえ春樹、春は好き?」
「うん。好き!」
「…冬は?」
「んー、俺寒いの苦手だからなあ」
春樹は勢いをつけてブランコを漕いだ。
錆びたブランコはキィキィ激しく鳴いた。
「あ、でもね!今年の雪は今まで見てきた中で一番きれいだったの!なんかね、冷たいのに温かいの!変だよね。なんかね、にこーって笑っちゃう感じなの!」
春樹は激しく揺れるブランコから思いっきり飛び出した。
ガチャガチャと鎖の部分が喧しく音を立てて、ブランコはあべこべに暴れた。
春樹はジィンと痛む足を振り切って雪に振り向き、目を丸くする雪に向かってにぃっと頬をあげた。
「だからね、俺もし冬さんに会えたら、ありがとうって言うんだ!」
「そっか…。そっか。そうなんだ…」
ゆきはまたそのキラキラと光る瞳から涙を流した。
「ゆき…?」
「私、行くことにするよ。もう寂しくないから」
「あれ?また降ってきた」
ゆきに呼応するように曇天の空から白い雪が落ちてくる。
「大丈夫。すぐやむよ」
「…ね、また会える?」
「うん。きっと会えるよ」
「ほんと?」
「うん。また、一年後、雪がふる頃に」
春樹が瞬きをする間に、ゆきは姿を消していた。
「ゆき?どこ?…ゆき?」
雪も、もうやんでいた。
次の日はまたもや異常気象だった。
今までなんの音沙汰もなかった春が、一晩で桜並木の桜を全て開花させたのだ。
通学路も、あの公園も、学校の校庭も優しいピンク色に染まった。
なのに春樹は何故だかちっとも嬉しくなかった。
下校途中、春樹は寄り道した。
あの公園で、昨日まで向こう側の空を見せていた桜の枝を見上げながら、ゆきを思い出していた。
今はもうその枝はその先の空を見せてくれない。
もう雪は降らない。
春樹は知らぬうちに涙を流していた。
「どうしたの?」
声のした方をむくと、そこには凛々しい顔立ちの、王子様という言葉がぴったりとハマるような青年が立っていた。
「なんか、悲しくて。…桜も春も大好きな筈なのに、……大切な人がいなくなっちゃったみたいで…」
「いなくなってないよ」
青年は雅紀の頭をぽんっ、と撫でた。
その掌はビックリするくらい優しくて、匂いも大きな花束をもらった時みたいに、春樹をふわりと包んだ。
その不思議な青年は、少しゆきと似ている気がした。
「あいつはまた、優しい雪を連れてやってくるよ」
「ほんと?」
「本当だよ。約束する。だから、笑って?俺たちは君たちを笑顔にするために生まれたんだよ」
ざああっと風が吹いて桜が散る。
思わず目をつむった春樹の耳に「ありがとう」とどこか懐かしい声が聞こえた気がした。
目を開けたとき、そこにはもう誰もいなかった。
晴天と紫陽花
雨が降らない。
西川は窓越しに空を見上げた。
日に日に濃さを増す青空は、雨を運んでくる気配など微塵も感じさせない。
デスクの上に広がる小テストに丸をつけながら、鬱陶しい日差しに目を細めた。
中学生たちの拙い字を延々と追う作業は案外気が滅入る。
「なんだかな」
西川は雨が好きだ。
雨が降ると実家の庭を思い出す。
決して広くはないが、母がこまめに手入れしている庭には、毎年この季節に綺麗な紫陽が咲く。
西川はその紫陽花の花びらが雨に打たれて濡れる様や、青々とした葉につく小さなカタツムリたちがとても好きだった。
「西川先生」
声をかけられてそちらを向くと、世界史の田上先生が立っていた。
「どうしました?」
西川は至って平然と返事をしたが、その視線は田上の清潔なシャツからうっすらと透けるブラジャーを捉えていた。
「先生のクラスの池坂さん、2限の授業中に携帯をいじっていたので没収したんです。放課後先生から返しておいて頂けませんか?」
「ああ、かまいませんよ。俺からも言っておきます」
そう西川が答えると、田上は笑顔で頷いて持っていた黒いスマートフォンを西川に手渡した。
「お願いします」
左手で髪を耳にかけ、田上はカツカツと靴音を鳴らして職員室を出ていった。
田上は美人だ。そして若い。
聖職についている西川だが、あわよくば、と思ったことが何度かある。
呑みの席で潰してそのまま…、と企てたこともないことは無いが、如何せん相手がウワバミでこちらが潰れてしまった。
「ふっ」
雨が降らなかろうが、田上を抱けなかろうが、大して人生は変わらない。
きっと雨が降って田上を抱けても、次の日には流れるような平凡な日常が西川を先へ先へと追いやっていく。
頭の中で雨に濡れた実家の紫陽花がそんな西川を責めるようにゆらゆらと揺れていた。
「小学生の時にもやったと思うが、今お前らが持っているリトマス試験紙で、酸性、中性、アルカリ性を知ることが出来る。今日はそれを応用した実験をやっていく」
西川は移動教室の授業はあまり好きではない。
なぜなら大概の生徒は通常の授業より20%位集中力が下がるからだ。
理科室のでかい机を挟んで向かい合った友達と消しカスを飛ばしあったり、足を蹴りあったり、背もたれのない丸椅子で遊んでひっくり返ったり。
「いいかー、終わらなかったら今度のHRの時間を実験の続きに回すからなー」
そういうとあちこちから次々とブーイングが起きる。
次のHRは時間が余り、かつその時間どこのクラスも体育館を使ってないということで、西川のクラスがレクリエーションとしてバスケをやってよいと今朝決まったばかりなのが最大の原因だろう。
なぜだか知らないが中学生は異様にバスケが好きだ。
「嫌だったらさっさと終わらせるの!はい、プリント見ながら進めて。終わったらプリントの表に記入、考察、まとめ!出来たやつから持ってこい。終わったら自由にしてよし!」
西川の声に生徒達はブツブツいいながら実験を始めた。
なんだかんだこの年頃はまだ素直だ。
それに実験というのは始めたら大体の子は面白くなって勝手にドンドンやってくれるもんなのだ。
その間西川はさっきの丸つけの続きをしたり、提出されたプリントのチェックをしていればいいのだから、始まってさえしまえばこっちのものなのだった。
「ハイじゃあそこまでー。できてない奴もプリント前の箱に提出して。道具は各自元の場所に戻すこと。薬品は班のリーダーが前に持ってきて」
終業五分前になって西川は生徒達に声をかけた。
途端に椅子を引く音やまだ少し高い生徒達の声、ガラス同士の当たる音で理科室中が満たされる。
2班の池坂が薬品を教壇に持ってきて、西川とパチッと目が合った。
「池坂」
「はい?」
やや反抗的な声で池坂が返事をする。
彼女は不良とまでは行かないものの少し校則を破り気味で、少し教師に反抗的な生徒だ。
思春期、反抗期、と呼ばれるものをしっかり順調に迎えている。
ただ根はしっかり者のイイコちゃんのようで、友達にも慕われているし、なんだかんだみんなが嫌がる班のリーダーを「おっけ、あたしやるわ」なんて言って引き受けたりとなかなか姉御肌なようだ。
「田上先生からスマホ預かってるぞ」
「え、なに、西てぃー返してくれんの?」
「西川"先生"、スマホ持ってきてごめんなさい。って言ったら今返してやる。それ以外なら放課後俺がお前の家に届ける」
そう言って羽織っていた白衣のポケットから池坂のスマートフォンを取り出すと、池坂は可愛い顔を心底歪めて「うわ、きも」と言った。
たまたまプリントを持ってきてそばで聞いていた吉崎も「西てぃー変態っぽい」とヘラヘラ笑った。
「よし、家に届けます」
「まってまって!西川先生ごめんなさい!もう持ってきません!」
それを聞いて西川は満足そうに頷いて池坂にスマートフォンを渡した。
「まあどっちにしろ今日家庭訪問でお前の家行くんだけどな」
西川がずるい顔でにやっと笑うと、池坂はさっきよりさらに顔を歪めて「はー!?ずるっ!てか、え、今日かよ」と口をひん曲げた。
「お前口悪いなぁ…、ほら、挨拶するから座れ」
手でいけいけ、と指示すると池坂は恨めしそうな顔で西川を睨みながら自分の席に戻って行った。
「はい日直ー。挨拶!」
「起立」
ガタガタっと生徒が立ち上がる。
「れーい」
「「あーーしたーー」」
やる気なさげな礼とともに生徒達は荷物を持って理科室を出ていった。
何気なく池坂のプリントをチェックする。
「うん。全部あってるな、考察も良くかけてる。あの反抗期が受験までに終わればいいがなー」
そしてその下にあった吉崎のプリントを見る。
「…だめだこりゃ」
to be...
四季の歌