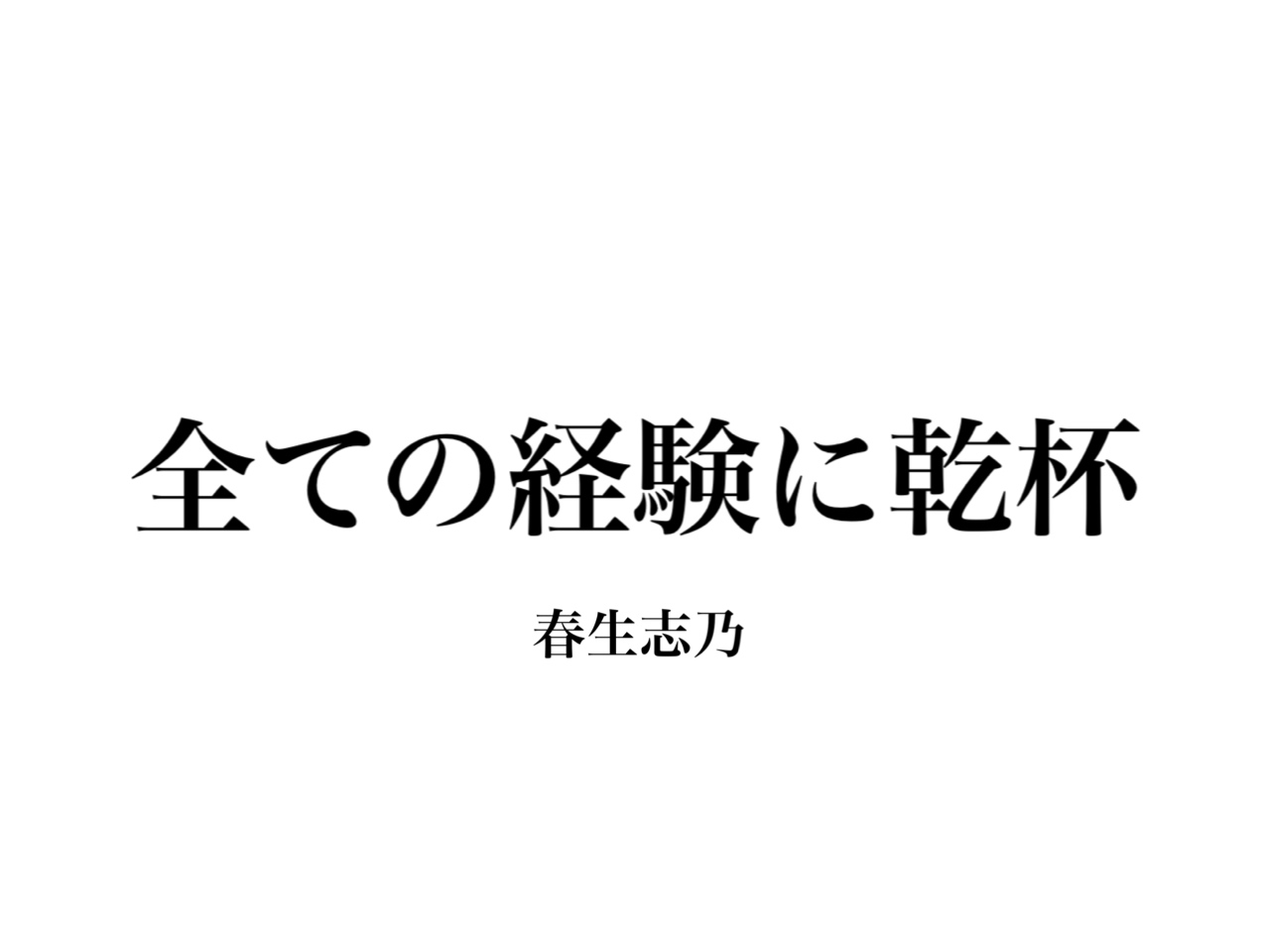
全ての経験に乾杯
生まれたころから私の人生には一本の糸が引かれていました。
私はその一本の線をただひたすら、無闇やたらに歩いてきたのです。
生まれたての私はその一本の線を「運命」だと、知らなかったのです。
私の小学生の頃と言えば、変な子供でした。
変、というのは一言で言えば子供にしては硬すぎる人間です。
その一本の線に強いられていた言葉は「真面目」でした。
私はひたすら真面目に生きる、という事しか頭にありませんでした。
真面目に生きれば、全てが上手くいく、そう思い込んでいたのです。
親のいいつけを守ること、学校へ毎日行くこと、宿題を必ずやること、全てそろえばそれが小学生にとっての真面目なのです。
わたしはただがむしゃらに、その真面目という言葉に全うしました。
それはそれで、子供は褒められて伸びるものですから、私はそこそこ伸び伸びしました。
伸び伸びしつつもやはり子供ながらにしても「遊び」というものは大事になってきます。
その頃私はインターネットばかりしていました。
子供ながらに普及し始めたインターネットをころころ手玉に取るように転がしつつ、人間と言うものが如何に悪く醜くて、存外な生き物だというのを知ったのです。
私は子供という子供では無かったのかもしれません。
子供の癖に人生を知ったような口を効き、親を困らせた事もありました。
けれどそれは、大人だけが知ることを許された一つの秘密に過ぎないのです。
子供が知っては行けないこと、と言うのは、大人が身勝手に決めた、知られたくないただの猥褻で醜く汚いものだったのかもしれません。
私はそれをべらべらと話し始めるようになると、大人は硬直しました。
私はインターネットの記事やまとめたものを読み漁った為に、大人、と言うものの半分を知りました。
それが大人になるとどうなるか、なんて子供は想像もできませんし、しようともしません。
ただそれが、私が子供だった頃のお話です。
中学校に上がると、私は吹奏楽にのめり込みました。
小さな体で、大きな「コントラバス」という存在に出会いました。
それは未知の生物でした。
大きくて茶色く、中は空洞になっていて、その真ん中にはコントラバスを支える太い木が一本刺さっています。
私は自分が小さい存在なので、コントラバスという大きな存在に好感を抱きました。
私は今までしてきた勉強よりも、コントラバスという存在が気になって気になって仕方なくなりました。
朝は誰もいない開いたばかりの学校で、ひたすらコントラバスを弾きました。
それが一年続くと、ある春の朝、いつもは来ない顧問の先生が私のところに来ました。
「毎日毎日、みんなより早く来て一人でメトロノームとコントラバスに向かっているのは寂しくないのか」
私はすぐに答えました。
「全然寂しくなんかありません」
なぜ私がすぐにそう答えられたのか、と言いますと、私の家庭は大きな玉に乗ったピエロのようにグラグラとしていたのです。
私は家が嫌いでした。
真面目という一本の線は、実は親から強いられていたものだと知ったのです。
それに私の家庭は離婚をして、母が男を連れ込んでいました。
コントラバスにのめり込んだのは、その点が大きかったのかもしれません。
私の事情を知ってからか、先生はその日から、みんなが来るまでの間、マンツーマンでコントラバスの知識について教えてくれました。
それはなんと今までとは違う景色でした。
先生が教える音色が私とは大きく違いました。
私は真面目を守り続けた人間でしたので、先生に負けたくない、という思いが沸々と沸いてきました。
そこからは必死にコントラバスだけを見ました。
何も、家での大人の事情なんて事も考えなくなりました。
私はコントラバスと先生に救われていたのです。
次の春、先生は転任することになりました。
私はその話を聞いて、その場で泣きました。
救われていた一つの欠片が欠けた時でした。
けれど、先生は一曲私達に残していきました。
その曲を、今でも聴くととても懐かしくなります。
そして先生はもう一つ残したものがありました。
それは役職を決める、一枚の紙でした。
次期顧問の先生が読み上げた時、私は安堵しました。
私は木管楽器を仕切る、パートのリーダーとして任命されたのです。
これは私と、私の姿を見ていた先生の信頼の証だと、気付いたのです。
私は引退まで、その役職を精一杯やり続けました。
これは引かれた線ではなく、私が導き出したものでした。
高校生に上がり、私は念願であった「バイト」と言うものを始めました。
最初はうきうきしていたものの、いざ始めるとなると、それは小学生の時に知った「大人の汚いところ」というものがはっきりとわかるものでした。
言われたことを一つでも間違えたら怒りを食らう、お金に関しては一つ一つが大きい存在で、そこに文句をつけようものなら、さらに怒りが飛びました。
その結果、私は高校に上がり、また真面目という人間へと戻ったのです。
交通費、学費、自分へのお金、全てを満たすため、働き続けました。
それは入学した春から、卒業するまでの春まで続きました。
何度も腸が煮えくり返り、殺したい、という感情に苛まれました。
それは誰しもが有る経験かと思います。
私はそんな犯罪者になるほど、この人間に人生の半分渡せるか、とやはり思いとどまり、しかしその葛藤は辞めるまで続きました。
その代わり、心の中ではその人間を何度も殺めました。
それで自分の怒りが収まるか、と言えば嘘になりますが、社会というものは「そうするしかない」のでした。
私が真面目を極めている中、兄は所謂「ニート」という存在になっていました。
私は兄を何度も蔑みました。
真面目に生きている私にとって、悠々としている兄は怒りの矛先にしかなりません。
何故同じ母親から生まれているのに、兄だけ、私と違い優遇されているのか、さっぱりわかりませんでした。
学校を辞め働きもせずに家にいるのに何故母は何も言わないんだろう、私は文句も言わず学校へ行き、順位を落とさずバイトをして迷惑を掛けずにいるのに、私と兄は何が違うんだろう。
そこで私が行きついたのは「愛」でした。
兄は母に愛されている。
けれど私は母に愛されていない。
そういう大人の闇を見たのです。
けれど私は反抗しませんでした。
しない、というよりできなかったのです。
愛されていない存在が、でしゃばる幕ではないと自覚いたしました。
そして「愛」というものを嫌いました。
私は悩んで悩んで、お腹の奥底に黒いものがどんどん沸き、けれどそれを発散させる方法が分からなかったのです。
その時に出会ったのが「文を書く」と言う事でした。
全ての怒りはそこで発散できるものだと分かったのです。
しかし今度は、その思いは誰にも理解されない、という事実に直面しました。
その頃私は「鬱病」というものにかかってしまいました。
塞ぎこみ、向上心が無くなり、文を書く意味さえも見いだせなくなりました。
心はもう無くなってしまったかのように消えかかっていました。
しかしその夏に私は新たな出会いというものをしました。
それは国立大学の大学院で心理学を勉強している中国人の方でした。
私の第二の先生と呼べる人になります。
私は今までの文を見せました。
その先生に、私の価値観というものを全て教えたのです。
そうして意見を交わしているうちに自然と心が癒えてきました。
今まで誰にも理解されなかった価値観や思考が理解されたときでした。
そこで私は鬱病というものから抜け出せたのです。
感謝してもしきれません。
先生は私が卒業するのと同時に居なくなってしまいましたが、きっとどこかでこの文を読んでいらっしゃると思い、心からお礼を言いたいと、そしてまた出会いたい、と思っています。
そして最後の難関である、大学へと上がりました。
私は先生の教えや、親からかけられない愛情を抱え、再び再出航したのです。
講義がない日はバイトを八時間、そして家に帰ると医療の勉強をしました。
私が意気込んでいる六月、私は櫛来も肺炎にかかっていました。
そしてそれと同時に、愛犬の死を目の当たりにしました。
死と言うものは一瞬で儚いものでした。
私が死に直面したのはこれが初めての事でした。
入学して真面目を貫いた中、その時ばかりは肺炎の事もあり、講義には参加しませんでした。
私は死を目前にする愛犬に、今までの事を全て話しました。
愛犬との思い出や、今までの自分の行いを振り返りただ泣きました。
人間の勝手な思い込みかもしれませんが、その時愛犬は私の涙を見て、重い体を上げ、寄り添ってくれた様に思います。
私は人間の「愛」など信用はしていませんでしたが、愛犬への「愛」は完全なものでした。
私はお別れをする時、歌を歌い、届けました。
それは今までのお礼と、また私のところに戻って来てね、という感情での歌でした。
しかし愛犬が居なくなり、私の心の穴はどんどん広がっていきました。
そして勉強やバイトに来る日も来る日も追いかけられ、私は一回生の秋、その穴の底へ落ちていきました。
それは二回目の「鬱病」でした。
大学はほぼ休学の状態となり、真面目という刻印も消え、体重は七キロほど落ちました。
全てが無気力で、愛犬の元へ行ってしまいたい、そんな感情を抱いていました。
そこから薬との闘いになりました。
体重の減少もそれの一種でした。
私は無気力の中、友人に外へ連れていかれたりしていましたが、それは友人からの「愛」だったのかもしれません。
けれど、その時の私は仇返ししかできませんでした。
ある冬の寒い日、友人の紹介からAという男性を紹介されました。
最初は明るく振る舞い、鬱と言う事を感じさせないよう接していましたが、隠すことも疲れ、打ち明けました。
それは以外にも理解されました。
ボロボロで死ぬ寸前の私を引き留めるかのように登場したのです。
私は初めて人と「お付き合い」をすることになりました。
私のその時の感情は軽薄でしたが、Aはそれでもいいと言いました。
その時、私は嫌っていた人間の愛と言うものを直球に受けていたのでした。
ある憂鬱とした曇りの日、私は一件のペットショップに立ち寄りました。
ふらっと動物がいる方へ向かうと、一匹の犬に出会いました。
私は何故か直観で分かりました。
これは愛犬の生まれ変わりだ。
それは天から降ってきた言葉のようでした。
すぐ様、私は契約を済ませ家に連れて帰りました。
愛犬は、生まれ変わって、くよくよしている私をみて、早々と戻ってきてくれた、そう思うと、涙が止まりませんでした。
そこから三か月、私は起きてから寝るまで、愛犬の生まれ変わりと信じる、第二の愛犬と過ごしました。
そしてAという存在と、愛犬の効果か、私の鬱病は回復に向かってきています。
私が生まれた時に見た、その一本の線、それが今の私の運命だと気付く事が出来たのです。
私が私であれるのは、全てこの一本の線から成り立った、運命の思し召しなのだと、そう思います。
全ては生まれた時からこういう人生なのだと決まっていたのかもしれません。
大変という中にもそういう様々な奇跡という事もあるのだと分かったのです。
ならば私はその運命にこう言葉をかけると思います。
全ての経験に乾杯


