
赤砦の奇跡
戦国時代に武将と共に駆け回った馬の物語。
其の壱

母馬は最後の力を振り絞り大きく嘶くと地面に崩れ落ちた。仔馬の黒くそして長い両脚から上はまだ母馬と繋がったままでいる。その様子を見守っていた与平は慌てて母馬に駆け寄ったが、 次の瞬間、仔馬は長い眠りから覚めたように突き出した二本の脚をゆっくりと動かし始めた。
無理に引きずり出せば仔馬を傷つけてしまう可能性がある。然りとてこの状況が続けばいずれこの子も息絶えてしまうであろう。あれこれと考える余裕は与平にはなかった。
与平は中にいる仔馬の位置を確認しながら既に息絶えた母馬の腹に小刃をゆっくりと当てた。母馬が幼い頃に野原で走り回っていた光景がふと脳裏に過ぎった。刃先を押し当てたもののそこから先が進まない。しかしその間にも与平の視線の先にある二本の脚は必死に生きようとバタつかせ与平に救いを求めていた。
「すまない…」
与平は小さく呟くと母馬の下腹に刃を入れた。突き出た脚の長さからして相当大きな仔であることは間違いない。母馬の馬体も大きく、また今回が初産ではなかったので与平はこのような事態になるとは想像だにしなかった。仔馬の両脚を掴み、与平は一気に地面に引きずり出す。体内に残っていた羊水と母親の血に染まりながら仔馬は漸くこの世に生を得た。
ふぅ、ふぅと仔馬から荒い息吹が聞こえた。余程苦しかったのであろう。しかし濡れた体を舐めてくれる母馬はもうこの世にはいない。与平はぬるま湯につけておいた布を絞り、直ぐに仔馬の体を拭こうとした。
普通は産まれてから仔馬が立つまで一刻、そして歩行がしっかりするまで更にもう一刻はかかる。しかし仔馬は何事もなかったようにムクリと立ち上がった。スラリと伸びた長い前脚はしっかりと自身の体を支え、よろめく素振りさえ見せない。それはまるで今まで泥遊びをしていた古馬が起き上がる姿となんら変わりはなかった。与平は狐につままれたように口をポカンと開けたままその様子を見るしかなかった。
仔馬は足元に横たわる母親に近づき匂いを嗅いだ。少しの間、母親の側に寄り添っていたがもう動かないと悟るとそのまま月明かりが差し込む出窓の方へ歩き始めた。漆黒の馬体、大きさは普通の仔馬より頭一つ飛び出ている。はじめて頭上に浮かぶ月を見つめる仔馬の瞳はまるで炎を宿しているかように真っ赤であった。
「赤目…」
与平はそっと呟いた。
与平は急いで隣の馬屋に向かった。直ぐに赤目に乳母を当てがわなければならない。かなり年季の入った馬屋であるが、そこには丁度一週間前に珍しい月毛の仔馬を出産を終えたばかりの母馬がいた。
与平が馬屋に駆け込むと母馬は我が子に乳を与えているところであった。腹を空かせた仔馬が必死に母馬の下腹を突いている。与平は顔を顰めた。
「すまん、母さんを連れて行くよ」
与平は月毛の仔馬に諭すように言うと嫌がる母馬を無理やり引き離し、赤目が待っている馬屋へと戻った。
我が子でない仔馬に乳を与えるにはまず塀をつくり、自分の子供の匂いをその子につけてから隠すように授乳させなければならない。そうしなければ乳母は自分の子供でない事に気づいてしまい、その仔馬を蹴飛ばしてしまうからだ。与平は馬房の柱に乳母を繋ぎ止めると塀の準備に取り掛かるために納屋へと急いだ。
その途中、与平は塀を作ってから乳母を連れてくるべきであった事に気づいた。順番が逆である。これでは全く意味がないではないか…。しかしもう後戻りは出来ない。与平は頭を抱えた。
赤目は振り返り、乳母を黙って見つめた。余程与平の手入れが良いのか栗毛の馬体は艶を得て十七歳という年齢を感じさせない。黄金色の長い前髪が馬屋の入口から吹き込む夜風に揺れ、その隙間から乳母と目が合った。
それまで目の前に横たわる母馬の亡骸を見て恐怖と怒りで耳を絞りあげて嘶いていた乳母であったがその目を見るや否や急に大人しくなり、その赤い瞳に釘付けになった。その目に決して逆らう事が許されない自然の摂理ようなものを垣間見たのであろう。
赤目は一歩、また一歩と乳母に近づいた。乳母と鼻先が触れるところまで近づくと乳母はゆっくりと頭を垂れた。赤目はそれが合図であったかのように乳母の腹下に頭を突っ込み、勢いよく乳を吸い始めた。
与平が古びた戸板で作った即席の塀を手にして馬屋に戻ってきた頃には普通の馬の親子の姿がそこにあった。
「一体、どうなってるんだ。全く…」
与平は自分一人が慌てふためいていた事が馬鹿らしく思い、即席の塀を馬房の外へと放り投げた。
暫くして隣の馬屋から残された月毛の仔馬の嘶きが響き渡った。姿が見えなくなった母馬を必死に探しているのだ。
乳母は我に返り嘶きが聞こえた方向に目をやった。我が子が気になるものの決して赤目を振りほどいて暴れることはなかった。今優先すべきは我が子ではなく目の前にいる赤目に乳を与える事、その事を彼女自身が知っているかのようであった。
赤目に母馬を乳母として当てがったはいいがこの月毛の仔馬に乳を与える馬はいない。ただ今回は自分の子ではないと知った上で乳母は赤目に乳を与えている。折角この世に生まれてきた命、月毛も何とかして救ってやりたい。
与平は暫く考えた末、隣の馬屋に残された月毛も赤目のいる馬屋に連れてくることにした。この二頭のうちのどちらかを母馬は選び、残された仔馬に乳を与えることを拒むかもしれない。それでもこの方法しか二頭とも生き残る可能性はあるまい。
赤目はおぼつかない足取りで与平に連れてこられた仔馬に気づくと急に乳を吸うのを止めた。くるりと背を向けて再び出窓の方へと戻った。月毛の仔馬は恋しかった母馬に寄り添い、再び乳を求めると思われたが、その場を動こうともせず黙って赤目の様子を伺っている。赤目はその視線に気づいたのか振り返り月毛を見た。今度は月毛が母馬には見向きもせず赤目にゆっくりと近づき、まだ乾ききっていない赤目の体を丁寧に舐め始めた。
与平は赤目が覗いていた出窓から夜空を見上げた。つきはじめた桜の蕾を月が優しく照らしている。それはまるでこの幼い二頭を見守っているようであった。
其の弐
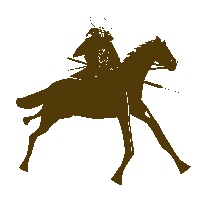
産まれて一ヶ月が経った頃、与平は乳母と月毛、そして赤目を近くの牧草地へと放してやった。四角になるように所々に杭が打ち込まれ、一本の縄で繋いでいるが人の膝下ほどしかない縄の位置では柵としての機能は殆どない。しかし与平が飼う馬達はそこから先は行ってはいけないと知っているようでどの馬もその縄を越えることはなかった。
赤目ははじめての草地を縄沿いにゆっくりと歩き始めた。一歩また一歩と草を踏み倒す音が聞こえる。赤目の首下くらいしかない月毛は必死に赤目を追いかけていた。赤目と比べて歩幅が狭いので常に小走りの状態である。赤目は時折立ち止まり、迷惑だと言わんばかりに首を大きく振って月毛を威嚇した。どうも後を取られるのが好きでないらしい。月毛はそんな赤目の心中を察することもなく赤目のそばを離れず、飛び跳ねて赤目の注意を引こうとしていた。
乳母は初めての外遊びをする二頭に我関せずと淡々と久々の青草を食べ続けている。時より耳を二頭のいる方向へ向けるが、見上げることはなかった。与平が彼らを見ていると安心しているのかもしれない。この一ヶ月間、二頭の仔馬に乳を与え続けているためか薄い皮膚の下からくっきりと肋骨が浮き上がっている。
赤目は不意に立ち止まり乳母の様子を見た。乳母が口にしている青草が気になったようだ。足元に茂る青草に顔を近づけて匂いを嗅いでみる。生えたばかりの上下二本の前歯を器用に使って青草を噛み切り飲み込んだ。そしてもう自分は大丈夫だと言いたげに食べては乳母を見るを繰り返した。
乳母がこの世を去ったはそれから間も無くであった。動かなくなった母馬を必死に起こそうと月毛は何度も母親を鼻で突いて嘶いた。そんな月毛を慰めるかのように赤目はずっと側に寄り添っていた。
一年が経つと赤目の背丈は五尺六寸ほどまで伸びていた。普通の大人の馬ですら四尺以上にはほとんどならない。
与平は赤目には生後半年くらいから荷役の仕事を手伝わせていた。その甲斐もあってか日々の山の登り下りでトモは大きく引き締まり、前肩の筋肉ははち切れんばかりに膨れ、それはまるで漆黒の鎧を纏っているようであった。
赤目は与平に対しては従順で賢い馬である一方で、他の輩が体に触ろうともすれば忽ち耳を絞って立ち上がり、威嚇する素振りを見せていた。
そのためか赤い目をした馬の化け物がいるという噂はあっという間に国境まで広まった。
紅葉の葉も落ち始めた晩秋の夕暮れのことであった。仕事を終えた与平が赤目を連れて我が家に帰る途中に峠の向こうから馬に乗った侍が姿を現した。土埃をあげながら道の真ん中を駆け上がり、こちらに向かってくる。与平は赤目を道端に寄せて立ち止まり、頭を下げて男をやり過ごそうとした。しかしその思惑とは裏腹に侍は手綱をしごくのを止め、与平の前で馬を止めた。
「おい、そこの。その馬はお前の馬か?」
歳は四十半ばであろうか、切れ長の目に細く整えられた口髭、下っ端の侍ではないことは与平にも想像ができた。
「さ、左様ですが…」
「その大きさで普通に走れるのか?」
「もっぱら力仕事ばかりさせていますので走らせたことは一度も…」
「そうか…」
男はニヤリと笑った。その笑みはどこか悪戯っぽかった。
「ならば、今からその馬を走らせてみよ。拙者の馬と勝負じゃ。もしお主の馬が勝てば褒美をやろう。負けてもそれはそれでよい。拙者の馬がやはり速かったということじゃ」
与平は困惑した。これまで赤目に跨ったことは一度もない。この馬が産まれて一目見たそのときからこの馬に自分が跨ることはおこがましいと与平自身が感じていたからである。荷役の時も常に引き馬の状態で赤目に接しているのはそのためだ。そして何よりいくら賢い馬であっても人を乗せた事もない馬がいきなり真っ直ぐ走るとは思えなかった。
すると不意に赤目が頭を垂れた。与平の気持ちを悟り「乗れ!」と言っているような気がした。
与平はおそるおそる赤目の背に跨った。そこから見える景色はこれまで馬に跨って見てきたどの景色とも違っていた。青く高い空が近づき、一里先まで遠くを見渡せ、何よりも万物がより小さく見える。隣の馬に跨る侍も例外ではなかった。与平の鼓動が一気に高まった。
男は大きな掛け声と共に馬の脇腹に脚を入れた。馬はその合図に応えて勢いよく走り出した。男が 振り返ると赤目はまだ一歩も踏み出していない。
「赤目よ、少しだけ走ってくれるか?流石に前に行く素振りをしなくてはあのお侍を怒らせてしまう」
与平は両脚の脹脛でゆっくりと赤目の脇腹を包み込んだ。それを待っていたかのように赤目は大地を蹴った。一歩そしてまた一歩と大きく地面を掻き込む。後脚を蹴り出した後に次の脚が地面に接するまでの時間が長い。与平が瞬きをする間にまた別の景色が視界へと飛び込んできた。
男は赤目が走り出したことを確認すると己の馬に鞭を一発入れて目一杯追い始めた。馬はそれに反応しもう一段速さを増した。荒くなった馬の吐息が男にも伝わった。しかしそれも束の間、あっという間に大きな影が男の右側を過ぎて行った。まさにそれは黒い疾風のようであった。
男は手綱を握って馬を静止させ、大笑いしながら与平に向かって叫んだ。
「あぁ、参った、参った。お主の勝ちじゃ」
男は懐から赤い巾着を取り出し、その中から数枚の金貨を掴むと与平の足元に放った。
「これで暫くはお主もその馬も喰うには困らんだろう」
与平は生まれて初めて金貨なるものを見た。この地で造られている甲州金である。地面に落ちた金貨を不思議そうに見ながら一枚一枚拾い集める与平に向かって男は言った。
「わしの名は虎昌。気に入ったぞ、お主の馬。また会いたいものだ」
虎昌はそう言い残すと馬の尻に一発鞭を入れ、再び山道を駆け登って行った。
其の参

天文二十年、雪が降りしきる寒い夜であった。
先程から容赦なく横なぐりの雪が家の壁を叩いている。与平は囲炉裏の周りにくたびれた布団を敷くと掛け布団を頭から被って丸くなっていた。風雪が隙間の開いた門戸を震わせカタカタと音を鳴らし、なかなか寝つけない。
ふと耳をすますと風の音に紛れて馬屋の方から幾度か馬達の嘶きが聞こえてきた。寒さのせいで馬が震えているのか、さもなくば冬眠しそこねたクマが腹を空かせて山から下りてきたのかもしれぬ。
与平は直ぐさま起き上がり、先程まで着ていた広袖を再び羽織った。念のために鍬を右手に持つ。
そっと戸を開け表に出ると吹きつける冷たい雪風のせいで一気に身体の芯が冷えた。雪は膝下まで降り積もり、白い吐息で一寸先が見えない。やはり明朝にしておけばよかったかと少し後悔しつつも与平は歯を震わせながら馬屋に向かった。
三つの馬屋のうち一番手前の馬屋が赤目と月毛の馬屋であった。馬屋の出窓からそっと中の様子を覗いてみると赤目が耳を絞り苛立っているのが見えた。赤目は与平の視線に気づくといきなり後脚で壁を蹴飛ばし、板二枚分ほどの大きな穴を開けた。月毛の方はピッタリと赤目に寄り添っている。こちらも何か言いたげに与平を見ている。二頭の様子がおかしいのはどうやら寒さのためではなさそうだ。
与平はとても嫌な予感がした。絶対に行くべきではないとわかっていた。ただ馬はこの二頭だけではない。二頭が産まれるずっと前から共に一緒に汗水垂らして働いてきた馬達が無事であることを確認したいのだ。与平は悴んだ手に息をかけながら残り二つの馬屋の見回りに向かった。
鈍い音がたて続けに響いた。それは風の音に掻き消されない程に大きく、そして木の枝を折る音にしては低い音だった。
しばらくすると与平が入った馬屋の中からゆっくりと黒い獣が顔を覗かした。ツキノワグマであった。六尺以上はあろうか、普通のツキノワグマより頭一つ飛び出ている。そいつは臭いを嗅ぐような素振りで頭を左右に振りながら赤目の馬屋に向かって歩き始めた。地面を踏みつけるたびに雪が軋み叫び声を発し、そしてその跡は僅かな朱が混ざっていた。
赤目は月毛を奥に誘うと自分は馬屋の入り口に戻った。クマは馬屋の中で動いた赤目に標準を合わせた。赤目の瞳がその視線を捉える。その瞬間クマは大地を蹴って赤目に襲いかかった。蹴散らした雪が大きく宙に舞った。大きく開かれた口からは剥き出しとなった鋭い牙が赤目の首筋を狙っている。それを待っていたかのように赤目はクルリと背を向けた。そして二本の後脚で豪快に蹴り上げた。双方の蹄がクマの顔面を捉えた。何かが砕け散り、千切れる音がした。クマはその場で崩れ落ち、二度と動く事はなかった。
夜明けと共に一頭の馬が駆け上ってきた。その馬に跨っている男に赤目は見覚えがあった。虎昌である。虎昌はあの日を境に赤目に会いによくここを訪れていた。
「な、なんという事だ。与平…」
ツキノワグマが出てきた馬屋の前で虎昌は呆然と立ち尽くしていた。まだ溶けきれぬ残雪が所々で赤く染まっている。
驚く虎昌に向かって赤目は大きく嘶いた。虎昌は我に返り、声のする方角を見た。赤目が出窓から顔を出してこちらを見ている。虎昌は用心のために刀を抜いて赤目のいる馬屋に向かって走った。
馬屋に近づくにつれ虎昌の歩調はゆっくりになり、入口の少し前で足を止めた。ません棒の下に首から上を失った大きなクマの死骸が横たわっていた。虎昌は眉を細めながら引き千切られた断面を見た。そして赤目の膝下が紅く染まっていることに気づいた。
この馬はデカイだけではない。賢く、速く、そして強い。
「なぁ、赤目よ、わしと一緒に来るか?」
赤目は虎昌の声に応じなかった。言葉を理解しているのか虎昌に背を向けた。その赤目の仕草に虎昌は笑いながら赤目に言った。
「安心せい、月毛も一緒じゃ」
其の肆

虎昌は内山城に陣を引いていた。守護代の小山田虎満は一年前に信濃地蔵峠の戦いで倒れ、それ以来虎昌がこの城を守っている。
緑多い小高い山々の一つの山頂に築かれたこの城は麓を一望できる。国境に近いという事もあり、ここに常駐する侍達は腕っ節に自信がある猛者どもが集められ、その天辺に立つのが虎昌であった。
虎昌がここ内山城に赤目と月毛を連れてくるや否や二頭の周りにはあっという間に人集りができた。
騎馬隊の侍達だけでなく女、子供に至るまで一目見ようと我先へと両馬のもとに駆け寄った。ただ赤目の異様なまでの大きさとその瞳に恐れ慄き、なかなか側まで近づくことができない。美しい月毛にも何とか触れてみたいが、その月毛も赤目の後ろに隠れてしまい、こちらも指を咥えて見るよりほかなかった。
与平からあの勝負がなければ一生赤目に乗ることはなかったと聞いていた。赤目には万物が逆らえぬ何かを持ってるという。それまでずっと馬と共に生きてきた男にそのような言葉を言わせた赤目、虎昌は人さえも屈服させるこの馬と共にこの戦国の世を生きたいと心底思っていた。
故に虎昌は生前に与平が言っていたように赤目が自分から頭を垂れるまで跨るまいと決めている。城への帰り道とて虎昌は自分の馬に跨り、二頭を引いて帰ってきた。
己の背に乗せる輩は己が決める。それで良い。そして選ばれた者だけが赤目の上でもう一里先を見渡し、疾風のように野山を駆け回ることができるのだ。
翌朝まだ陽が高くなる前、虎昌は月毛に馬の扱いが上手い又十郎を当てがった。まずは鞍を乗せるのに慣れさせる必要がある。その重さは月毛の十分の一以上、かなりの負荷である。赤目には側でその様子を見せていた。周りの馬は皆その背に人を乗せ縦横無尽に走り回っている。赤目はどのような反応を示すであろうか、虎昌は密かに楽しみにしていた。
戦では月毛はその美しさ故どうしても目立ってしまう。余程腕っぷしに自信がある者しかこの馬には跨りたくはないであろう。とはいえ、赤目と月毛は一心同体、付いて離れずの仲にある。月毛を残して赤目だけを戦に連れて行く事はまず無理であろう。戦に連れて行く以上、最低限の訓練は必要である。それは月毛のためでも赤目のためでもない。当然それは跨る者のためである。
月毛は百貫にも満たない大きさであったが、鞍を乗せても嫌がる素振りは全くなかった。その姿で赤目の前を何度も行き来している。それはまるで「格好良いだろ?」と赤目に見せつけているようでもあった。
又十郎は手綱を引いて月毛を停止させた。そして不意に鐙に足をかけ素早く月毛の背に跨った。月毛はさすがにその重さに驚き何度か尻っぱねを繰り返したが、又十郎が二、三度首筋を叩くと落ち着きを取り戻した。
又十郎は脇を締めて曲がる方向に手綱を引きながら反対側の足で脇腹に合図を送った。月毛はその合図を理解し見事に時計回りに円を描いた。更に続けて数回強めに脚を入れると月毛は速歩へと切り替わった。今度は逆方向へ手綱を引く。月毛はいとも簡単に反時計回りの速歩へと切り返しを行った。又十郎はニヤリと笑った。
「虎昌殿、これならあと半年もすれば立派な騎馬になりますよ」
決してお世辞ではないことはその顔を見れば一目でわかる。虎昌は良い意味で期待を裏切られた。そして少し伸びた顎髭に手をやりながら、月毛の俊敏さに目を細めた。
戦では人馬一体、鞍上が出した指示への馬の反応が遅いと命取りになる。前方に危険が迫ればそれを回避するために即座に左右に切り返し、相手の後ろへと旋回しなければならない。そのためにも俊敏性は戦において不可欠なのだ。どうやら赤目の背後に張り付いているだけの臆病な馬ということではなさそうだ。
虎昌はふと視線を赤目へと移し反応を見た。赤目は優しい陽だまりの中でウトウトとしている。虎昌は笑いを堪えながら下を向いて首を振った。
「甲山の猛虎」と呼ばれながら、これまで戦で百人以上を斬ってきた。刀の柄に染みついた相手の返り血は何度擦ろうが二度と落ちることはない。
虎昌は使い慣れた甲冑に手を伸ばした。しっかりと汚れは洗い流され光沢は蘇っているが、よく見ると当世袖の所々が刀傷で剥げて白くヒビ割れている。いつしか自分も戦で斬られ大地を赤く染めて息絶えるのだろうか。虎昌は刀傷の溝を指で辿りながらあの時の残雪に飛び散った血跡を思い浮かべた。そして意を決したように立ち上がった。
「熊若、熊若はおるか?」
虎昌は信玄が仕えさせた俊足の忍衆である熊若を呼んだ。熊若は渡り廊下を軋ませることなく静かに部屋に入ってきた。 細身で物静かな男だ。
「熊若よ、今から書状を書く。親方様に届けてくれ」
信玄への手紙は己が率いる部隊の甲冑を赤に統一したいという嘆願書であった。そこには二つの理由が記されていた。
一つには戦後の甲冑を洗い流す際の手間が省けること、そして二つ目は「赤色」の効果、つまりは赤は血の色であり戦場でその姿を見せることにより戦う前に相手に恐怖を与えるというものであった。
信玄は書状を読み終わると声高々に笑い、熊若に伝えた。
「よかろう。その甲冑、仕上がり次第持って参れ」
兜から脛当まで真っ赤に染まった甲冑が出来上がったのはそれから数ヶ月後であった。
赤の塗料には高価な辰砂が使われている。兜には飯富の家紋と共に金色に輝く鹿角が高々と天に向かって伸びていた。
虎昌は赤甲冑を身につけるとそのまま屋敷の外に出た。向かう先は赤目の馬屋である。甲冑が擦れ合う音に周りの侍達が一斉に振り返った。虎昌のその異様な容姿に驚きを隠せないでいる。後退りをし尻餅をつく者、食べかけの団子を落とす者、そして興味深げに虎昌の後を追う者、誰もがこの見た事もない赤い甲冑に目を奪われた。
虎昌が馬屋の前に立つと流石に赤目も驚いたように一、二歩後ろずさりしたが、その瞳はずっと虎昌を見つめたままでいる。馬は猫や狸などの小動物と同様、相手と目が合うことを嫌う。獲物として見られているような気分になるからであろう。しかし赤目は違った。緋色のその瞳は常に自信に満ち溢れ、何よりも強者が纏う慈愛も兼ね備えている。
「赤目よ、儂にはその資格があるか?」
虎昌は馬房のません棒を外した。側にはいつの間にか赤目を着飾る真紅の障泥の胸繋、そして赤鞍が用意されている。
赤目は馬屋の外に出て虎昌が側に来るのを待っている。そしてゆっくりと瞳を閉じて頭を垂れた。虎昌は赤目の肩口に頬を当てた。
「絶対に後悔はさせぬ、絶対にだ」
其の伍

陽が西へと傾き夕焼けが山の端に落ちる頃、義清は戦で荒れ果てた城内の庭を見つめていた。
踏みつけられた草花が生き残るために大地の恵みを吸い上げようと互いに競っているかように思えた。おそらく春を待つこともなく萎れ朽ち果てる者達はいずれは生き残った者の良い肥しやしとなるであろう。今の己の身と目の前の草花を重ね合わせながら義清は大きく溜息をついた。
一度は敵に奪われた葛尾城であったが、景虎の助けを借りて何とか奪還することができた。しかし信頼していた家臣の裏切りが発端で、あろうことか生まれ育ったこの城を一度でも手放してしまったという失態が頭の片隅から離れない。いくら腕っ節に自信があろうともこれでは一国の主人として失格である。
景虎とは親と子ほどの年が離れているが上杉家の内紛を十九歳という若さで治めただけでなく、その後も近隣諸国へ救いの手を差し伸べるなど懐の深さには男としての資質は己より上かもしれぬ。
義清は頭を振った。
このまま朽ち果ててはなるものか。信玄は必ずや再びここを攻めてくる。奪われたものは奪い返すのが彼奴の流儀だ。その前に何とかして奴の出鼻を挫き、この国を守らねば…。
義清の脳裏には十五年前のあの日の敗走が色濃く焼きついていた。北条討伐のため出兵し手薄になった武田の城を諏訪頼満と共に攻め入ったときのことであった。この不意打ちは誰もが成功すると信じていた…たった一人の寡兵が現れるまでは。
奴が馬上から繰り出す槍は風を斬る音ともに立て続けに兵士の体を貫き、そして一度振り回せば、幾つの兜が宙に舞った。同じ槍の使い手としてあの槍捌きを思い出すと今でも震えが止まらない。
ただ己にもこれまで武田の重鎮を倒し、幾度も彼らの攻撃を交わし撤退させたという自負がある。再びこの頭を下げたくはないが、信濃に攻め入ろうとする武田を討ちたいとする景虎とは必ず利害は一致するはず。ここは再び景虎の力を借りて多勢で一挙に攻め落とすしかあるまい、あの内山城を。
一週間後、春日山城の大広間に義清と景虎の姿があった。
「義清殿、お気は確かか?」
景虎は涼しげな眼差しで義清を見つめた。血気盛んな年頃だが景虎はそのような一面を一瞬もみせず、全てを内に封じ込め相手につけいる隙を与えさせない。
「景虎殿、内山城は急な斜面を四方八方から登らずして落とすことは困難な城、敵兵は五百足らずだが信玄が選んだ猛者達で守られた先陣の小城でござる。国境に近いここを落とせば必ずや武田の勢いは止まりましょう」
「強者揃いといっても我が軍で五千騎というのは些か多過ぎでは?それでは本陣が手薄になるというもの。村上殿の兵は三千騎とお聞きしたが聞き間違いか?」
義清は奥歯を噛み締めた。そして気を落ち着かせるために茶を一気に啜った。
「景虎殿が幼少の頃、遠い昔に我は今の内山城の城守と一戦を交えたでござる。奇襲作戦で成功すると思いきやそいつ一人に九十人以上の首を取られ余儀なく引き返したという苦い思いがありんす。そいつは既に拙者と同様老いぼれなれど不意打ちとは言え我が軍は武田の攻勢に破れ城を受け渡した程度の腕並、景虎殿の軍との力とは雲泥の差でござる。この義清、内山城が落ちた際には景虎殿の重臣が城代となることに全く異論はございませぬ。故に何とかお願いできませぬか?」
景虎の瞳が微かに揺れた。景虎は義清のこの言葉を待っていた。長尾と武田の領地の狭間で苦しんでいるこの村上が己の領土の鼻先の城を長尾の城と呼ぶことに口を出さないということであれば、武田だけでなく織田や芦名からの防御の布石にもなる。
「そこまでの覚悟が義清殿にあったとは…。良いでしょう、この景虎の五千騎を義清殿に託しましょう」
義清は深々と頭を下げた。伏した口元は微かに笑みを浮かべている。
内山城が景虎に落ちれば今後我が国の前に長尾の壁ができる。即ち武田は否が応でも景虎と直接対決となる。互いに好きなだけやり合えばよい。その隙に我らは次なる戦に備えて立て直す。
互いに兵力が落ちるようであれば信玄だけでなく景虎とも一戦を交える覚悟はできている。全ては義清の狙い通りであった。
其の陸

朝霧に紛れて無数の影が蠢いていた。盆地であるが故、山の中腹までが白一色に覆われ、山頂からは麓を見下ろすことができない。
ただ耳を澄ますと微かに地面を叩く音が木霊し、幾十にも重なり合って一定の旋律を刻んでいるのがわかる。百頭以上の騎馬が列となって山頂を目指し山道を登る音であった。馬一頭がやっと通ることができる急斜面を馬達は黙々と登っている。首を上下に振ったり、気配を感じて嘶く馬は一頭もいない。戦うために厳しい訓練に耐えた選ばれし馬ばかりであった。
騎馬の動きに遅れまいと道なき傾斜を甲冑を擦り合わせながら兵士どもが這いつくばり前へ進もうともがいていた。絡み合う蔦の表面が露で滑り彼らの行く手を阻む。しかし彼らは確実に前へと進み、その黒い大群は山全体を覆い始めていた。
総勢八千という兵の先頭には黒毛馬に跨る義清の姿があった。その表情は引き締まり、この多勢をもってしても満身創痍になってはならないと自分を戒めているようにも見える。その背後には村上の旗を掲げた騎馬隊が続き、暫く間隔を開けた後、長尾の兵がそれに続いた。
景虎は山の麓に留まり、己の軍旗が通り過ぎてゆく様子を眺めていた。この奇襲に武田の者達が白旗を上げるのは時間の問題であろう。総勢五千の兵を義清に託したものの果たしてそこまでの必要があったのか今でも疑問が残る。しかしこの戦で万一負けることがあるにせよ、それは義清が指揮した戦であり、自らの名を穢すことはない。また勝てば五千もの兵を差し出した長尾軍の功績により後の内山城を領地とする大義名分となる。景虎にとって義清の申し出により援軍を差し出したという事実があればそれでよかった。
義清が攻略にもたつくようであれば、武田の援軍が来る前に自らこの山を駆け上がり、戦いの幕を引くつもりであった。
この異様な空気に椋鳥が敏感に反応した。目を覚ました一羽が鳴きながら小枝から飛び立った。それに気づいてまた一羽が飛び立つ。気がつけば真っ白な靄の中を無数の椋鳥達が縦横無尽に飛び回り、慌ただしくまだ眠りについている仲間達に向かって警告を発した。
その鳴き声に城内で寝ていた者達も何事かと目を覚ます。虎昌もその一人だった。
「者ども、どうやら客人が来たようだ。早々に準備に取り掛かれ」
初めての赤備えを纏った戦に虎昌だけでなく城内の男達の鼓動が一気に高まった。八百の兵は着替えを済ますと互いの容姿を見せ比べ、どちらが強そうかを競い合った。男とはいつの世でもやる事は同じである。
三十頭の騎馬全てに真っ赤な鞍が載せられた。その中には赤目と月毛の姿もある。 一通り馬具をつけ終えると又十郎は月毛に跨り、速歩、駈歩へと戦いに備えての準備に入った。又十郎に続き他の者も自分の馬に跨った。赤目は馬房の中からその様子を見ていた。前脚で地面を掻いて虎昌が来るのを待ちわびている。
「とうとうお主の出番じゃのう、赤目」
虎昌はニヤリと笑いながら馬房の前に立った。右手には赤目が見たこともない虎昌の背丈ほどの長槍が握られている。虎昌の容姿を見るなり赤目は興奮し、激しく首を上下に動かし始めた。
虎昌は赤目を馬房から出してゆっくりと跨った。
「おおぅ…」
虎昌は声を漏らした。
赤目の力強い鼓動と呼吸が全身に伝わってくる。どんなに長く的を外さぬ槍よりも、そして如何に強固な甲冑よりも心強く感じた。全身に力が漲り、この歳にして興奮が冷めやらない。
「さぁ、行くぞ、赤目。思う存分に駆け回るのだ」
虎昌を乗せた赤目は城門に向かって走り出した。
ウトウトとしながら寝惚け眼の子供らが母親に促され次々と大広間に集められた。城の中で弓も届かず一番安全な場所であるが、一度城内に敵を入れてしまうと逃げ道はなくなる。ましてや侍は全て城の外で敵を討つために各々の役割を全うしなければならない。どれだけの兵が攻めてきたのか知る由もないが、ここにいるのは武田の中でも強者揃い、中でも虎昌がいれば百人力、戦に負けることはないと誰もが信じていた。
其の漆
虎昌は敵方が現れる前に門を開かせた。
赤砦の奇跡


