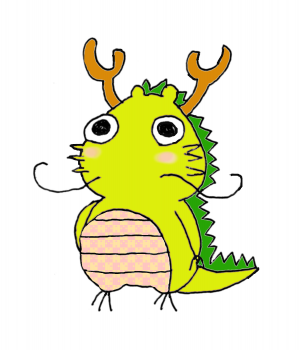戦う君に、花束を
どうも、こんばんは。農家の嫁と申します。
また新たに話が書けそうになってきたので、こそっとおかさせていただきます。ハヤブサさん×シュバルツさんのBL要素が入った小説でございます。楽しめる方だけどうぞお楽しみください。
ハヤブサさんがある国のお姫様をボディーガードする話です。
ちゃんとボディーガードできるかどうか、いささか不安な面もありますが、作者は楽しんで書きますので、皆様も楽しんでいただけたら、これ幸いでございます。
軽く、登場人物紹介をさせていただきますね~。毎度毎度、同じメンバーですみません。好きなんですよ、この人たち………。
・リュウ・ハヤブサ……『龍の忍者』の異名を持つ伝説の忍者。神をも討滅する力を持つ。
・シュバルツ・ブルーダー……リュウ・ハヤブサの恋人にして、アンドロイド忍者。
その身体は、『DG細胞』という特殊なもので構成されている。
・キョウジ・カッシュ……優秀な科学者。シュバルツの生みの親。
・ドモン・カッシュ……キョウジの弟。稀代の格闘家。
・東方不敗マスターアジア……ドモンの師にして格闘家。キョウジに心酔している。
ユリノスティ王国
・ナディール・エル・シャハディ……ユリノスティ王国の王女。王位継承権第1位を持つ。
ハヤブサのボディーガードの対象者。
・ノゾム・ユラ・シャハディ……ナディールの腹違いの弟。王位継承権第2位を持つ。
・ミヤコ・ユラ・シャハディ……ノゾムの実母。ユリノスティ王国現女王。
・ガエリアル・ブル・ジャハディ……ユリノスティ王国の現王。
・イガール・ジェスティ……王国に使える武官。
主な登場人物は、こんな感じでございます。
頑張って書き上げていきますので、生温かい眼で見守ってくださいね~。
よろしくお願いいたします。
序章
「ハヤブサ……。もう………!」
シュバルツは必死に懇願するが、ハヤブサは離そうとはしてくれない。限界を訴えるシュバルツを押さえつけて、なおも楔を打ち込み続けた。
「ハヤブサ……ッ! ああっ!」
甘く震えるシュバルツの身体を堪能する。
この身体をしばらく味わえない、と、ハヤブサは知っているから、なおのこと、彼の身体に溺れることを、彼は選択していた。
もっと。
もっとだ。
もっと乱れてくれ。
もっと溺れさせてくれ。
俺のことを────
愛している。
愛しているシュバルツ。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
悲鳴のような嬌声。
キシ、キシ、と、音を立てて軋み続けるベット。
二人の嵐のように愛し合う時間は、しばらく終わりが訪れそうになかった。
「日本を離れる?」
ようやく一段落ついて、少し落ち着いた様子のハヤブサにそう言われて、シュバルツは驚いたような声を上げていた。
「ああ……。しばらくの間だがな」
シュバルツの前髪を撫でながら、ハヤブサはその面に、少し寂しさを含んだ笑みを浮かべる。実際、この愛おしいヒトとしばらく会えなくなるのは、ハヤブサにとってはかなりきつい案件だった。本当ならば、一週間に一度といわず、毎日でも会いたいヒトであるのに。
「………難しい、仕事なのか?」
「どうだろうな……」
案ずるようなシュバルツの問いに、しかしハヤブサは、即答することを避けていた。実際自分でも、仕事の内容をどう判断したらよいのかわからない代物であったから。
仕事を持ち込んできたのは、某国で軍の幹部をしている『アーサー』という男だった。
その内容は、ある国の姫がその国の女王となるべく戴冠式を終えるまで、その身をガードしてほしい、と、言うことだった。
────この仕事は、実にお前向きだと思うぞ、リュウ。
話をしている最中、アーサーはちらりとこう言った。
それが、少しハヤブサには引っかかっていた。
自分は、確かに腕利きの『忍者』 その腕と『神力』は、時に『神』と呼ばれる存在をも討滅してしまう。
だから、自分が働いてしかるべき場所は、魔物がうごめく暗黒世界か、血なまぐさい戦場であるべきであって、戴冠式の準備をしている優雅な城の中など、およそ自分がいるべき場所からは、最も離れているような気がしてしまうのだ。
まして、次期国王になろうかというお姫様の相手など、自分には、いささかお門違いなような気がしてしまって────
「………もし、必要ならば、私も手を貸そうか?」
「…………!」
愛おしいヒトからのその言葉に、ハヤブサははっと我にかえる。見ると、シュバルツがひどく心配そうな色を瞳にたたえて、こちらをじっと見つめていた。
「それには及ばない。大丈夫だ」
シュバルツに心配されたことが素直に嬉しいハヤブサは、自然とその面に、やさしい笑みを浮かべる。
「しかし………!」
なおも食い下がろうとした愛おしいヒトの唇を、ハヤブサは指でそっと塞いでいた。
「平気だ。これは俺が受けたミッションだ。それに、お前やキョウジを巻き込むわけにはいかない」
「ハヤブサ……!」
そう。
これは、自分が『龍の忍者』として引き受けた『仕事』
それに、関係のない第三者を巻き込むことがあってはならない────これは、ハヤブサが仕事を引き受ける上で、頑なに守り続けている『理念』だった。
自分の仕事をシュバルツが手伝ってくれるのならば、それはもちろん嬉しい。
しかしそれは、一科学者として、平和な日常に生きているキョウジを、シュバルツにつながる人々を、自分の血なまぐさい世界に巻き込んでしまうことを意味する。
それはだめだ、と、ハヤブサは強く思った。
自分は、シュバルツやキョウジの安寧を願いこそすれ────自分の住む暗黒世界の厳しさに触れたり、傷ついてしまうことを望むものではないのだから。
「案ずるな、シュバルツ。少し時間はかかるかもしれないが、必ず俺は、お前のもとに帰るから────」
「ハヤブサ……」
「だから、シュバルツ………」
ハヤブサは想いを込め、その頬に触れながら口を開く。
「もう一度、お前に触れても、いいか………?」
「……………!」
自分のすくそばで、生まれたままの姿をしている愛おしいヒトが、少し、身を強張らせる。その白い肌には、自分が愛した爪痕が、まだうっすらと残されていた。
先程まで散々抱かれた身体。ダメージが残っていないかと問われれば、それは少しうそになった。
しかし────
(ハヤブサが……ハヤブサが、望むなら………)
シュバルツは、その面に笑みを浮かべながら、ハヤブサの頬にそろそろと手を伸ばした。
赦しの意思────
ハヤブサには、それだけでもう十分すぎて。
「シュバルツ……ッ!」
唇を奪い、再びその身体を求めた。
チュ、チュ、と、響く水音。軋むベット。悲鳴のような嬌声が、あたりに響き渡り始めて────
「ああ………! あああああ………!」
結局シュバルツが意識を手放すまで、その行為は続けられてしまうのだった。
第1章
「………………」
目的地に向かう飛行機の中で、ハヤブサはアーサーの話と渡された資料を、反芻し直していた。
今から向かう場所は、『ユリノスティ王国』────人口50万人にも満たない、小さな王国だ。
ハヤブサはその日は珍しく、骨董で良い掘り出し物を手に入れていた。
慎重に器に磨きをかけて、ショーケースの中にそっと飾る。その見映えと趣にうん、と、頷いているときに、店の出入口のベルが来客を告げていた。
「はい」
接客のために顔を上げたハヤブサだが、そこに居る人物の姿を認めた瞬間、ハヤブサの面に貼り付いた仏頂面が、さらに険しいものになった。
「何だ。お前か」
突き放すような声の響きに、店の戸をくぐったアーサーは苦笑してしまう。
「『何だ』は無いだろう。随分なご挨拶だな」
がっしりとした体格に、刈り込んだブロンドの髪。それよりも少し濃い色の口髭を蓄えた男は、ハヤブサの機嫌を特に取ろうとするでもなく、ズカズカと店の中に入り込んできた。
「お前、客じゃないだろう。冷やかしなら帰ってくれ」
「そんなつれないことを言うなよ。客よりももっと、お前を儲けさせてやれるかもしれないのに」
「お前の持ってくる仕事は、ろくなものがない」
そういってしかめっ面をひどくするハヤブサに、アーサーは声を立てて笑っていた。
「まあ落ち着け、龍の忍者。依頼を受けるにしても受けないにしても、とにかく話だけでも聞いてくれないか?」
「………………」
アーサーにそう言われて、断る理由も見当たらない。ハヤブサは、話を聞くことを選択していた。
「リュウは、『ユリノスティ王国』を知っているか?」
「ユリノスティ王国?」
アーサーの言葉に鸚鵡返しに答えながら、ハヤブサは自身の持つ情報を、頭の中で検索してみる。目的の情報は、すぐに出てきた。
「あの、海沿いの小さな王国か? それがどうした?」
今時にしては珍しく、王政が営まれていて、その風光明媚な土地柄ゆえに、観光業で成り立っている、小さくて平和な王国────それが、ハヤブサのその王国に対する認識だった。
「そうだ。その王国だが……最近、どうもきな臭くなってきていてな」
そういいながら、アーサーが少し難しい顔をする。
「これは最近の話だ。そのユリノスティ王国の地下に、レアメタルの豊富な鉱脈が発見されたんだ」
「─────!」
アーサーのその言葉に、ハヤブサもハッと息をのんだ。豊富な地下資源の発見は、たいてい喜ばしい出来事ではあるのだが、それは同時に、莫大な利益を生むが故に、凄まじい争いの火種になってしまうものでもあるからだ。
案の定ユリノスティ王国内ではその利益をめぐって、内紛が起きつつあるらしい。
「それでも王国を支配するシャハディ家の求心力はまだ強い。何とか国を一つにまとめて、表面上だけでも平和を保っていたのだがな………」
ここでアーサーは、やれやれとため息を吐いた。
「国王であるガエリアル・ブル・シャハディ殿が、病に倒れてしまったらしい」
「な…………!」
「そこで、国が一気に傾きそうになったのを、その娘であるナディール姫が支えているんだ……。健気な話だろう?」
「それはそうかもしれないが………」
ハヤブサはここで少し眉を顰める。ユリノスティ王国の抱える複雑な事情は把握したが、まだ肝心のアーサーの依頼内容が見えてこなかったからだ。
「……で? お前がここに来た目的の『依頼』って何だ?」
だから、単刀直入に切り込んでみる。それに対してアーサーは、その面に満面の笑みを浮かべた。
「リュウ、俺が頼みたいのはこの『ナディール姫』の護衛だ」
「─────!」
絶句して、息をのむハヤブサに向かって、アーサーは一枚の写真を投げてよこした。
そこには金色の流れるような髪を無造作に一つにまとめ、軍の礼装のようなものをまとった少女の姿があった。大きな藍色の瞳が、少女をなお一層凛々しく印象付けていた。
「四六時中こんなかわいらしい娘と一緒にいられるんだ。悪い話ではないだろう?」
「あのなぁ………」
ハヤブサは、ずきずきと痛む頭を抱えずにはいられなかった。
「なぜ、お前がこの王国の、こんな立ち入った事情に踏み込んで、俺にこんな依頼をしてくる? これは、他国の内政干渉に当たるのではないのか?」
「まあ、確かにそうかもしれないな」
アーサーはそう言って、肩をすくめる。
「我が国にとって、この国の王位がどうなろうが、誰が莫大な利益を得ようが、直接的に関係があるわけではない。だから、放っておいてもいいのだが、我が国の立場的に、この地域で紛争が起きるのは困るんだ」
「……と、言うと?」
低い声で問い返してくるハヤブサに、アーサーはあっけらかんと答える。
「答えは簡単だ。この国が面している海は、我々にとって非常に重要な物資の水路に当たる」
「……………!」
「それが、この地域に紛争が起きることによって、安全が確保できなくなったら困るんだ。この水路が使えなくなるということは、あらゆる物資の流通が遠回りを余儀なくされ、我が国の経済に、深刻な打撃を与えることになる」
ハヤブサは思わず、大きなため息を吐いていた。
「そうか……。そういうことか……」
「それに、この王国のシャハディ家と、我が国の関係は非常に良好に保たれている。それが他の者に代わってしまったら、水路の使用にべらぼうな関税をかけられたり、最悪略奪の憂き目にもあいかねない。我が国にとって、シャハディ王政の倒壊は、デメリットの方が大きいんだ」
「なるほど……」
「俺がここに来た理由、納得してくれたか?」
重たそうに写真に視線を落とすハヤブサに、アーサーは改めて声をかける。
「まあな……」
ハヤブサは、眉を顰めながらも納得をした。
確かにそうだ。
義理や義侠心だけでは、結局のところ動かない。人も国も。
己に対する明確なメリットが見えてこなければ、その重い腰を上げないものなのだ。
「……と、言うわけで、リュウ。この依頼には、俺の国も一枚かませてもらう。戴冠式までナディール姫を守り通してくれたら、成功報酬に我が国の気持ちも上乗せさせてもらおう」
「………! お前が直接の依頼人ではないのか?」
驚くハヤブサに、アーサーはにやりと笑みを浮かべた。
「正式な依頼人は、ユリノスティ王国の内大臣だ。俺は、その仲介をしているに過ぎないんだよ」
「………………!」
「………その内大臣をしている『カライ』という奴とは、古くからの知り合いでな……。その………そいつが、本当に途方に暮れていたものだから………」
「─────!」
伏し目がちに言ったアーサーのその言葉で、ハヤブサは彼の本心を察知してしまう。
今ここで、一番義理人情に突き動かされて行動しているのは、誰あろう、実はアーサーなのだと。
旧友のために。
一人で国を支えるために奮闘している姫のために。
自国がユリノスティ王国を支援するための理由を懸命に考えて、国の連中を説得して────
こうして今ここに、彼は立っているのだ。
国の利益が第一だとうそぶきながら、旧友のために、自分ができる限りの手を打とうとしているのが分かった。
(くそっ!)
ハヤブサは小さく舌打ちをする。
やられた。
だから嫌なんだ。
こいつの依頼を受けるのは。
どんな難しいミッションであろうとも
自分は絶対に、断れなくなってしまうから────
「………分かった……」
「リュウ⁉」
ため息交じりに返事をするハヤブサに、アーサーも顔を上げた。
「お前のその依頼、受けよう」
「そうか……!」
ハヤブサのその言葉に、アーサーは心底ほっとしたような表情を浮かべる。ハヤブサもやれやれ、と、もう一度ため息を吐いた。
「では、カライ内大臣には、こちらから連絡を入れておこう。ユリノスティ王国への便も手配しよう。リュウ、何時が都合がいいんだ?」
一刻も早く現地に向かってほしいのだが、と、つついてくるアーサーを、ハヤブサはまあ待て、と、制した。
「俺にも多少準備の都合がある。明後日の便を頼んでもいいか?」
「それはまあ、お安い御用だが────」
そこまで口を開いたアーサーが、その面に少し険しい表情を浮かべた。
「だが、リュウ……気をつけろよ。あの王国に潜む『影』は、簡単ではないような気がする」
「…………?」
怪訝な表情を浮かべるハヤブサに、アーサーは少しためらいがちに言葉をつづけた。
「実は……あの王国の内情を探るべく間諜を送り込んだのだが────誰一人として、帰ってはこなかった」
「─────!」
「単なる『内紛』というだけでは、片づけられない何某かの事情が起こっているような気がするんだ……。うまくは言えないが………」
「……………」
(そうか……。だから、俺に依頼することを思いついたんだな? この男は……)
ハヤブサは、またやられた、と、心の中で舌打ちをした。
やはりというべきか、アーサーはちゃんと相手の力量を見て、その仕事を振ってきている。
そんな人間がこちらに振ってくる仕事など、どう考えたって簡単な内容で終わるはずの
ものではなかったのだ。
「それに、冗談抜きでナディール姫を狙う連中は、たくさんいるぞ」
さらにアーサーは、ぼそっと、とんでもなく不吉なことを言ってきた。
「ナディール姫は、一国の王となるには若すぎるが、国民からは大きな信頼を寄せられている。ユリノスティ王国の内紛を願う者、そこを乗っ取ろうとたくらむ連中からしてみれば、これほど厄介で邪魔な存在もないだろうな」
「な────!」
「だから気をつけろよ、リュウ。幸運を祈る!」
そうしてアーサーは、最敬礼をして、店から出て行った。
「……………」
ハヤブサは回想を終え、ふっと小さくため息を吐きながら、飛行機のシートにもたれる。
これから自分が向かうユリノスティ王国。ここが、非常に厄介な事態に巻き込まれているということだけは、はっきりとアーサーの話からは伝わってきた。
だから自分は、「飛行機の手配は、明後日にしてくれ」とアーサーに頼んでいた。
戦場に赴くための自身の準備の時間もほしかったし、何よりも、愛おしいヒトと触れ合うための時間も確保したかったからだ。
(シュバルツ……)
瞳にひどく心配そうな色を浮かべながら、こちらを懸命に見つめてきた愛おしいヒト。
(ああ、十分だな)
ハヤブサは、その時に感じた幸せな気持ちを反芻する。
この気持ちを持ち続けている限り自分は、限りなく幸せに生きて、そして、死ぬことができる。ハヤブサは、そう確信していた。
恐れることは何もない。
自分はもう────一生涯分の幸せを、この手の内に持っているのだから。
(少しの間だけ、仮眠をとるか)
ハヤブサはそう決意して、毛布を改めてかぶりなおした。
ユリノスティ王国に入り、ナディール姫のそばについてしまえば、もう自分は、ゆっくり眠ることも、おそらくできなくなってしまうだろうから。
(シュバルツ………)
せめて夢の中だけでも、彼のヒトに会いたい。
ハヤブサはそう願いながら、何時しかまどろみの中に身を置いていた。
「ロバート・フィッシャーさん……」
空港の検閲官は、提出されたパスポートと、目の前で佇む青年の姿を見比べる。パスポートにも不備がなく、写真と間違いなく同一人物だと確認した検閲官は、滞りなく入国手続きを進めていた。
「こちらには、どういう目的で?」
問いかけに、青年は穏やかに答える。
「写真撮影と、戴冠式の取材です」
青年の職業欄を確認したを確認した検閲官は、なるほどと納得した。この王国も、戴冠式が行われる日が近づいてきている。それゆえに、世界各国からそれを取材に来る彼のようなジャーナリストが増えてきていたからだ。
「なるほど、良い旅を」
「ありがとう」
青年はパスポートを受け取ると、一つに束ねた亜麻色の長い髪をさらりとなびかせながら、トレンチコートを翻し、静かに歩き始めていた。
こうしてロバート────リュウ・ハヤブサは、ユリノスティ王国に入国することに成功したのだった。
空港から路面電車に乗り、一路目的地の城へと向かう。
石畳の路面に、歴史を感じさせる重厚な古い街並み。この王国が、大きな戦火にも遭わず、平和な時を長く刻んできた証拠だと、ハヤブサは感じていた。
街には、たくさんの人で賑わい、活気にあふれている。
歩いている人種も民族も多様で────「観光業で成り立ってきた」という、この国の懐の深さを感じさせた。
(なるほど、いい国だな)
少し開けた場所に行けば、海が見える。反対側に振り返れば、雪を冠した、美しい山々が見えた。
本当に、飽きることのない美しい景色の数々────『仕事』などでなければ、もっとゆっくり腰を据えて、この街の歴史ごと、じっくりと探求をしたいところだ。
だが今は、それどころではないので、ハヤブサはあきらめて目的地へと向かう。城に着く一つ手前の駅で路面電車を降りて、そこから歩くことを彼は選択していた。
探索の下心がないのかと問われれば、それは少し嘘になるが、これはれっきとした『仕事』の一環だった。カライ内大臣との約束の時間までは、まだかなり余裕がある。ハヤブサはその間に、城の周辺の『下見』をしておくつもりだった。
何せ、今回の仕事は『ボディーガード』だ。ガードの対象者が、この辺りを生活圏内にしている以上、どこで敵に襲われるか分からない。この周辺全てが、自分にとっての『戦場』になる可能性があった。
その時に、どこをどう動けば対象者の安全を確保できるか、自分がそれを把握できていなければ話にならない。ハヤブサは、時折風景の写真を撮りながら、周囲の探索を始めていた。
どの道が、どの道とつながっているか。
どの路地が行き止まりか。
身を隠すための場所は、下水道の有無は────
龍の忍者はゆっくりと、頭の中に地図を構築していく。
やがて道は、ハヤブサを市場へと導いていた。
道端に開かれている露店には、海の幸、山の幸が所狭しと豊富に立ち並び、ハヤブサにこの国の豊かな自然を、改めて教えてくれていた。ほかにも、民芸品やアンティークが、ところどころに顔をのぞかせて、ハヤブサにその存在を主張してくる。
「……………」
特に、『アンティーク』や『古民具品』の類は、アンティークショップを経営しているハヤブサにとっては、かなり心惹かれる対象だった。
(いやいや、いかん、いかん。仕事………!)
必死に頭を振り、地図を構築する作業に戻るハヤブサであるが、その地図の中に、この店は要チェックだと、赤ペンで二重丸を入れることを忘れはしなかった。きっとこれは、仕事にも自分の趣味にとっても、いい目印になるだろう。
「お兄さん、観光かい? このジュースぜひ買っていって! おいしいよ!」
「ありがとう」
声をかけてきた女性に礼を言い、素直にそのジュースを購入する。ついでにハヤブサは、ナディール姫について探りを入れてみることにした。
「ああ、ナディール姫かい? あんた、戴冠式を見に来たの?」
「ああ、そうだ。………このジュース、うまいな」
「そりゃあそうだよ! 採れたてのフルーツを絞っているんだ。おいしくて、栄養も満点だよ!」
ジュースをほめられた小太りの老婆は、嬉しさを隠すことなく、その面に満面の笑みを浮かべる。
「戴冠式も、ぜひ見て行ってあげて! 姫様の晴れの舞台だから!」
「ああ。ナディール姫様は最高だ」
その隣で話を聞いていたのであろう、ワインを手にした老人が嬉しそうに声をかけてくる。
「あの御歳で、常に我らのことを考えてくださる、このワインの出来同様、素晴らしいお方だ!」
「姫様がお父上に代わり、王位を継いでくださったら────この国も、安泰ね」
人々の口からは、彼女に対する好意的な言葉が数多く出てくる。これは、彼女に対する盤石の『信頼』の現れでもあった。
「そうか………」
だがハヤブサは、それを聞きながら、逆に身が引き締まる思いがした。
人々に『慕われる』ということは、それと同じくらい彼女のことを『憎んでいる』存在も、少なからずあるはずだからだ。
────冗談抜きでナディール姫を狙う連中は、たくさんいるぞ……。
アーサーの言葉が、現実味を帯びて頭の中を回る。ハヤブサは一つ、大きく息をした。
「それで、ナディール姫は、普段どのように過ごされているのだ? やはり城の中で、政治や公務に立ちまわっているのか?」
彼女の普段の様子を知りたくて、口を開く。すると町の人々は、目をしばたたかせながら互いに視線を合わせると、相好を崩した笑顔を見せた。
「そりゃあ、姫様はねぇ」
「やっぱりねぇ」
「あ、ちょうどあそこにいる。あれが、そうなんじゃないのか?」
「えっ?」
あまりにも意想外のことを言われて固まるハヤブサに、「あそこにいる」と伝えてきた老人は、彼の横に来て、親切に教え始めていた。
「ほれ、あそこ。あそこに、金髪の娘っ子がおるじゃろう?」
「……………」
老人に教えられるままにハヤブサはそちらへ視線を走らせて────言われた通りの金の髪の女性を見つけて────固まった。
「…………えっ?」
何故なら、『王女』というにはあまりにも普通の町娘の格好をしすぎた『ナディール姫』が、確かにそこにいたからだ。
「ええっ!?」
にわかに信じがたいハヤブサは、アーサーから渡された『ナディール姫』の写真と、自分の目の前で、楽しそうに店のおばちゃんと会話をしている金髪の少女を見比べる。
しかし、悲しいかな、見比べれば見比べるほど────この写真の人物と、目の前にいる少女は同一人物なのだと、ハヤブサに訴えかけてくるだけであった。
「おや、あんた、いい写真を持ってるね。その恰好はメアリカン合衆国の大統領と会っていた時の物じゃないか」
老婆がハヤブサの持つ写真を見て、嬉しそうに声を上げている。
「セメルさん、そんなことがよく分かるなぁ」
「そりゃあそうさ! 姫様の格好は、すべてチェックしているもの!」
嬉しそうに話す老人たちの横で、ハヤブサは激しい頭痛に襲われていた。
(それはそうだろうな……。アーサーはここの軍属だから………)
こういう写真を撮ることはたやすかっただろうと、ハヤブサは思う。この写真が撮られた経緯が思わぬ形で判明したわけだが、今はそんなことは本当にどうでもいい。
問題は────
「すまないが、ちょっと聞く」
「なんだい?」
楽しそうに話し込んでいる老人たちに、ハヤブサは声をかけた。確認したいことがあったからだ。
「ナディール姫は………いつもあんな感じなのか?」
この事態は、今日だけの暴発的なものであってくれ、と、祈りながら、ハヤブサは尋ねる。しかし、その期待は見事に裏切られることとなった。
「ああ、そうじゃよ?」
「─────!」
あっけらかんと肯定してくる老人たちに、ハヤブサは絶句していた。
「姫様は、よくわしらのところに来てくださるよなぁ」
「公務もお忙しいのに、その合間を見て抜けてきてくださっているのかのう?」
「保育施設や学校にも、時々顔をのぞかせているみたいだね」
「ほんに、姫様は、わしらのことを気にかけてくださっておるのう」
そういってのんきに笑いあう老人たちの横で、ハヤブサは頭を抱えずにはいられなかった。
(嘘だろう……!? 狙われている渦中の真っただ中の奴が……ッ!)
アーサーから聞いた話を鑑みて、彼女の周りは、もっと緊迫した空気に包まれていると思っていたのに。
当の本人が、まさかこんな無防備にふらふらと出歩いているとは思いもしなかった。
何を考えているんだ!?
自分が死ねばどれだけのことが起こってしまうか、その自覚があるのか!?
思わず、彼女の胸ぐらをつかんで、そう問いただしたくなってしまう。
(いやいや、落ち着け……! リュウ・ハヤブサ……! 彼女だって一国の王女だ……。彼女の周りには、さぞかし優秀な護衛が………その警備団が……)
一縷の望みをかけて、ハヤブサは彼女の周りに目を凝らした。
しかし。
ハヤブサがどんなに頑張って探してみても、彼女に『警備』と呼べる存在は、後ろについてきていた兵士二人のみ。
(嘘だろう!?)
では、その兵士がものすごく腕利きなのでは、と、ハヤブサは兵士たちの腕を試そうとして────
「……………!」
腕を試すまでもなく、自分は彼らを瞬殺できてしまう、と、あっさり悟ってしまう。
(うおおおおい!! なんだこの状況は!! 殺し放題じゃないか!!)
もはや何らかの罠が存在するのではないか、と、疑ってしまいたくなるぐらい、彼女の周りは無防備だった。
「お前さん、大丈夫か? どこか具合でも悪いのか?」
「─────!」
ナディール姫の方を見たまま固まってしまったハヤブサに、老人が心配そうに声をかけてくる。ハヤブサは、はっと、我に返った。
「い、いや……。何でもない。大丈夫だ」
慌てて、取り繕った笑顔を見せる。だが、うまく笑えてはいないだろう。
「お前さん、本当に大丈夫か?」
案の定、老人たちが心配そうに、こちらの顔を覗き込んでくる。
「なんだか、顔色が悪いのう……」
「まさかあんた……! うちの姫様に、何か………」
「それはないな。一国の姫君をどうこうするなど、恐れ多い」
老人たちの訝しんだ眼差しを、慌てて躱す。
「確かに、それもそうじゃの」
ハヤブサの言葉に一応納得してくれたのか、老人たちも身を引いてくれた。ハヤブサは、ほっと胸をなでおろしたが、同時に少し苦々しい気持ちにもなった。
(しかし、こんなに簡単に姫の居場所を、周りの人間が余所者に教えてしまうとはな……。もし俺が本物の刺客だったら、どうするつもりなんだ……)
「ジュース、ありがとう」
礼を言って、その場を離れる。そして、目の前にいる姫の姿を見て、ハヤブサは一つ、大きなため息を吐いていた。
ナディール姫は、町の者たちと話をしながら、普通に市場でのショッピングを楽しんでいるように見える。平和だが、あまりにも無防備すぎる姿だ。
(やむを得んか……)
本来ならば、正式なルートを通して姫と面会をし、ガードする了承を得ねばならないところではあるが────
この、いかにも「私を殺してください」と、言わんばかりのこの状況。看過するにはあまりにも危険すぎた。
「……………」
ハヤブサは、黙って姫のボディーガードの任務を開始した。どうか、このままここは何事もないようにと、祈りながら────
「おばさん! ありがとう!! ここのスムージー大好き!!」
ナディール姫は、本当に嬉しそうに礼を言う。
「ああ。またいつでもおいでね」
礼を言われた女性の方も、和やかに手を振っていた。姫のはち切れんばかりの笑顔を見るのが、彼女は本当に好きだと思った。
店から出たナディール姫は、スムージーを食べながら、市場の道を歩く。その姿は本当に、ただの町娘にしか見えない。初対面の人が彼女をこの国の『王女だ』と、見抜くのは、かなり不可能に近いだろう。
それでもナディール姫の後ろからついてきている兵士たちからしたら、生きた心地がしなかった。自分たちは城から脱出したナディール姫に気がついて、たまたまついてきたに過ぎないのだから。
「姫様~。もう、帰りましょうよ~」
兵士の一人が、情けない声を上げる。
「そうですよ~。万が一何かあったらどうするんですか?」
もう一人の兵の表情も、もはや半泣きになっていた。兵士たちも、今のナディール姫を取り巻く状況が、かなり不穏なものになりつつあることを、なんとなく察知していた。それゆえに、一人で城から出ていこうとした彼女を制止することも放置することもできず、ついてきていたのである。
「あなたたち………」
情けない声を上げながらついてくるお供に、ナディール姫は苦笑しながら振り返った。
「私のことは放っておいて、帰ってくれてもかまわないのに……」
「そういう訳には参りません!!」
ナディール姫のその言葉に、兵士の一人が語気を強めて反論する。
「いいですか!? 姫様は今、とても大事な立場にいらっしゃるんですよ!?」
「そうですよ!! それなのに、万が一の事態が起きたらどうします!? 我々も含めて城の全員の警備の物が─────!」
「イガールには、ちゃんと断ってから出てきたわ」
ナディール姫は、ため息交じりに兵士たちに答えた。
「イガール隊長にですか?」
鸚鵡返しに兵士たちが口を開く。ナディール姫のこの言葉は、彼らにとっては少し、意外なものであったらしい。
「そうよ。出ていく前に声をかけたもの。いつものように、『今日は市場にいるわね』って……」
「……で、隊長はなんと?」
「『お待ちください! すぐに行きます!』って、言ってくれてたんだけど……」
ナディール姫は、ここでペロッと舌を出した。
「待っている時間が惜しかったから、そのまま出てきちゃった」
ずるっと、二人の兵士が同時にこける。
「ひ、姫様~~~~~!」
「せめて、隊長を待ちましょうよ……!」
「待ちたかったんだけどねぇ……」
ナディール姫は肩をすくめる。
「待てない『事情』ができちゃって………」
「…………!」
兵士たち二人は、もう呆れるよりほかはない。
この姫のことだ。おおよそ家庭教師か侍従長に説教されるのが嫌で、逃げ出してきた、と、言ったところなのだろう。
それにしても────
「かわいそうに……イガール隊長、今頃しくしく泣いていますよ……」
兵士の一人が憐れみたっぷりに言う。もう一人もうんうんと頷いていた。
「いや、必死に姫様を探して走り回っているかもしれませんね……」
「隊長が、慌てふためいている様が、目に浮かぶ……」
「まったくだ……。胃薬の量が増えたりして……」
そういいながら、兵士二人が大っぴらにため息を吐くものだから、ナディール姫も、多少良心の呵責が疼いた。
「そ、そんなに言わなくてもいいじゃないの……! 後でイガールと侍従長には、ちゃんと謝るわ……!」
唇を多少とがらせながら、ナディール姫は歩を進める。
「でも、ごめんなさい……。この、町へ行く『視察』だけは、どうか続けさせて……」
「姫様……」
「これは、『約束』だからね。父上と、亡き母君との間に交わした………」
「……………」
そう言いながら歩くナディール姫の後ろ姿が、哀しみを帯びているような気がして────兵士たちも、もう何も言えなくなってしまう。
「………それに、城に籠っていたって………」
「………姫様……?」
兵士たちの怪訝そうな声に、ナディール姫もハッと我に返った。
「な、何でもないのよ! あ、それよりも、あなたたちの名をまだ聞いていなかったわね。貴方たち、名はなんというの?」
「えっ! えっ!? 俺たちですか!?」
唐突なナディール姫の質問に、兵士たちはかなり慌てていた。まさか、王族の人間が、自分たちの様な者の『名前』など、聞いてくるとも思っていなかったからだ。
「と、トマスに」
「モガールであります!」
慌てて名乗る。すると、ナディール姫もにっこりと微笑んだ。
「トマスに、モガールね。二人とも、しばらくの間よろしく頼みます」
「は、はい!!」
姿勢を正して最敬礼をする兵士二人に、ナディール姫はくすくすと笑う。
「じゃあ、行きましょうか」
踵を返して歩き出す姫の後ろを、兵士たち二人はかなり舞い上がった足取りで、ついて行っていた。
「……………」
ハヤブサは、その3人から少し距離を置いて、後に続いていた。その間、彼の優れた聴力は、この雑踏の中で交わされた3人の会話を、余すところなく聞き取っていた。
(つまり、この姫が町に出歩くのには、確固たる理由があるのだな……。と、言うことは、日々の行動予定に、この街歩きは入れなくてはならないのか……)
この雑踏の中、対象者をガードするということは、実際のところ、かなり厳しい。できれば、戴冠式まで────城に籠っていてほしいところではあるが。
それに、どうやらナディール姫は、何だかんだと言って、ちゃんと頼りになる軍人に、一言伝言を置いてここにきているらしい。つまり、その軍人が来るまでの間、自分はこの姫をガードすればいいのだ、と、ハヤブサは悟っていた。
どうやらその軍人は、『くそ』がつくほど真面目な人間らしい。ナディール姫を、何時までも一人にはしておかないだろう。
だから頼む。どうかそれまでは、何事も起きないでほしい。
相手の信用を得られない状態で、相手を『守護する』ということは、非常に難しいことであるのだから。
祈るような気持ちで、ハヤブサは姫たちの後ろをついて行っていたのだが。
事態は、悪い風にしか転がらないもので。
「それ」は音もなく飛来してきた。
ハヤブサは、持っていたペンで、叩き落すことを選択する。
ストン、と、音を立てて、それは地面に刺さった。
小さな、吹き矢のような得物─────それと同時に、ナディール姫に向かって、四方より『殺気』が迫ってくる。
(狙われているぞ! 気づいているのか!?)
ハヤブサが前方に視線を走らせてみても、姫と兵士たちは、相変わらず楽しそうに談笑をしているだけだ。
「ちぃっ!」
ハヤブサは小さく舌打ちをする。それと同時に、地面を強く蹴った。殺気よりも早く、自分はナディール姫のそばに行かねばならぬのだ。
走る道すがら、姫に向かって吹き矢を構えている者を見つける。延髄を打って昏倒させた。だが────これで終わりではない。明確な殺気は、まだ姫の周りに存在している。
龍の忍者は、さらなる加速を足に命じた。
かすかに聞こえる、矢羽の音。
冗談ではない。
俺の目の前で
ガードしようとしている対象者を
傷つけさせて、たまるか─────!
その矢が姫の身体に到達するよりも先に、ハヤブサは間一髪、その間に体を入れていた。
矢を叩き落そうと腕を振った瞬間、その腕は屋台の果物の山に、勢いよく当たる。
バンッ!!
派手な音がして、果物が辺りに飛び散った。
それと同時に、ハヤブサは姫に向かって飛んできた二本の矢を、見事防ぎきることに成功していた。
「きゃっ!!」
「うわっ!? な、なんだぁ!?」
突然、自分たちのそばに乱入してきたトレンチコートの男に、ナディール姫と兵たちは、素っ頓狂な悲鳴を上げる。ハヤブサはそれを背に庇いながら、振り向きざまに叫んでいた。
「狙われているぞ!! 気づいてないのか!?」
「ええっ!?」
姫が驚きの声を上げると同時に、雑踏の中から男が一人、はじかれたように走り寄ってくる。
手にコートをかけて、手元を隠しているが────その下に、白銀の刃が殺気を伴って煌めいているのを、ハヤブサは見逃さなかった。
「─────ッ!」
ダンッ!!
攻撃してきた腕をとって、地面に叩きつけるように投げ飛ばす。その後ろから、さらなるうち手が姫に襲い掛かろうとしてきた。
「借りるぞ!!」
ハヤブサはとっさに、近くの屋台のガス台の上に乗っていた中華鍋を手にとって、応戦する。討ち手の鉤爪と中華鍋がぶつかり、ガキン!! と、派手な金属音と火花が、辺りに飛び散った。
「何事だ!?」
「きゃ─────ッ!!」
「わしの鍋~~~~!?」
突如として沸き起こった騒乱に、その周辺はたちまちのうちにパニックに襲われる。そんな中、ナディール姫は、己が取るべき行動を悟り、迅速にそれを実行に移していた。
「トマス!! モガール!!」
「は、はいっ!!」
「なんでしょう!! 姫様!!」
弾かれたように振り向く兵たち二人に、姫は真剣な表情で呼びかけた。
「走るわよ!! ついてきて!!」
言うや否や、ナディール姫は脱兎のごとく走り出す。
「えっ!? ち、ちょっと!!」
「お待ちください!! 姫様~~~~!」
それを見たトマスとモガールも、慌てて後を追っていた。
「……………!」
それを見たハヤブサも、姫の後を早急に追わねばならぬと、悟る。
「死ねい!!」
そう言いながら、武器を振りかぶってきた討ち手に向かってハヤブサは────
無言で、熱々に熱されていた中華鍋の底を、その身体に押し付けていた。
「ぎゃあああああああっ!?」
ジュッ! と、音がして、香ばしい匂いがする。
討ち手が悲鳴を上げてひるんだ隙に、ハヤブサは、その顔面に思いっきり拳を叩き込んでいた。
「すまん! 世話になった!」
ハヤブサは手短に礼を言うと、少し引っ込んだ中華鍋を、律義にガス台の上に返す。そのまま彼もまた、ナディール姫の後を追って、走り出していったのだった。
「姫様!? お待ちください!!」
「いったいどこへ行こうというのですか!?」
声をかけてくるトマスとモガールに、ナディール姫は足も止めずに口を開いた。
「とにかく走って!! 人のいない方に逃げるの!!」
「えっ!?」
「な、何故ですか!?」
姫の言葉に二人はさらにびっくりする。
普通、自分の身の安全を考えるのなら、こういう場合は人ごみの中に紛れ込むのが常識だろうと思ったからだ。
しかし、ナディール姫はそれに頭を振る。
「だめよ! 狙われているのは私だから─────人ごみの中ににいたら、皆が襲撃に巻き込まれてしまう!」
「────!」
「それよりも、追っ手をできるだけ皆から引き離して、なおかつ可能ならば倒しながら、振り払うべきだと思うの! 大丈夫! ここは私にとっては庭みたいなものよ! 逃げる手段など、いくらでも────」
「おい」
その時前方に、いきなり人影が飛び出してきたものだから、3人ともが死ぬほど驚いて、その足を止めてしまっていた。
「きゃ───っ!?」
「ひ、姫様!! 我らの後ろへ!!」
「お、おい! 貴様!! 何者だ!! ひ、姫様に無礼を働いたら、承知しないぞ!!」
トマスとモガールが、ナディール姫をその背後に庇い、おっかなびっくりといった風情で、槍をハヤブサに向けてくる。
「………………」
しばらくそれを無言で見つめていたハヤブサであったが、やがて、はあ、と、大きくため息を吐いた。
「勘違いするな。俺は、お前たちの味方だ」
「信じられるか!!」
トマスの、悲鳴のような声が斬りかかってくる。
「お、お前が、俺たちの味方だという、証拠はあるのか!?」
「証拠と言われてもな」
ハヤブサは、この任務に忠実な兵たちの態度に苦笑しつつも、もう一度、溜息を吐いた。
この極限の状況────実は、信じることの方が疑うことよりも100倍難しい。それをハヤブサは、知っている。
兵たちの自分に対する対処は、実に正しいのだ。
「………明確なものはない。信じてもらうしかない」
(あ………!)
ナディール姫は、ここで気づいた。
目の前の、このトレンチコート姿の人は、先程私たちを、助けてくれた人ではないのかと。
「狙われているぞ!! 気づいてないのか!?」
そう怒鳴りながら、襲ってきた人を投げ飛ばしたあの人が、確かこのトレンチコートを着てはいなかっただろうか────
だが、味方のふりをして近づいてくる暗殺者も、よくいるし、よくある話だ。ナディール姫は、沈黙することを選択していた。
そして、無言で問いかける。
あなたは、誰ですか?
敵?
それとも、味方────?
「そ、そんな言葉だけで、信用できるか!」
「み、味方だというのなら────もっと姫から離れてもらおう!」
「断る。それはできない」
兵士二人の言葉を一刀両断にしたハヤブサの態度に、その場の空気が凍り付く。
ハヤブサからしてみれば、これ以上姫から離れたら、守ることが困難になるが故に、そう言ったのだが。
自分たちの要求が言下に否定された者たちからしてみれば、そういう風には解釈できない。ただ、自分たちの要求をはねのけた『敵』としての認識を、強くしてしまう。
「こ、断ると、言うのなら………ッ!」
トマスが、目に涙を浮かべながらも一歩、踏み出し、震える槍先をハヤブサに向けてくる。
「……………」
しばらくそれを無言で見つめていたハヤブサであったが、やがて、ふっと、溜息を吐いた。
「……もう少し、腰を入れろ。そんなへっぴり腰では、俺を倒すことなどできんぞ」
「…………!」
(さて、どうしたものか)
正直ハヤブサは、目の前の状況に辟易してしまっていた。
姫たちの信用を得るどころか、不信を募らせているこの状況。
口下手な自分を、少し恨む。
どうして自分はこういう時に
もっとうまく、立ち回ることができないのだろうか。
しかし、落ち込んでいても仕方がない。
このままでは、お互いに進むことも引くこともできないのだから。
(怖い……!)
トマスは目の前の男に槍を向けながら、恐怖を拭い去ることができずにいた。
何故だろう、怖い。
武器を持っているのは自分で────相手の男は身構えてすらいないのに。
何故か自分は、決して打ち壊すことのできない巨大な壁に向かって、槍を向けている。そんな心持がしてならなかった。
できれば逃げ出したい。
今すぐにでも。
だが─────自分のすぐ後ろには、姫様がいる。
姫様を置いて逃げるなど─────兵のすることではないのだ。
その信念だけを支えに、トマスは槍を構え続けていた。
「……………」
しばし、沈黙が続く。
そのまま、膠着状態に陥るかと思われたとき─────ハヤブサが、動いた。
ダッ!! と、力強く地面をけって、猛然とこちらに向かって突っ込んでくる。
「ヒ………!」
トマスは正直、「死んだ」と、思った。
だが、動いた男は、こちらを攻撃しては来なかった。
自分を通り抜け、姫と、モガールのそばも通り抜けて────
ガンッ!!
自分たちに迫っていた討ち手の攻撃を、体を張って防いでいた。太刀を受け止めた腕は、袖が破れ、下から黒い籠手のような物が、顔をのぞかせていた。
「槍を貸せ!!」
討ち手の太刀と自身の籠手で、つばぜり合いをしながら、ハヤブサが叫ぶ。
「うわ、はいっ!!」
その気迫に押されるように、モガールが槍を差し出す。ハヤブサは片手でそれをつかみ取ると、あっという間に討ち手を撃退してしまっていた。その間、わずか0.5秒あるかないか。あまりにも鮮やかすぎて、まるで手品か何かを見ているような心持になってしまう。
「走れ!!」
敵を撃退したハヤブサが叫ぶ。
「逃げるのだろう!? 早く!!」
「─────!」
ハヤブサの叫び声に、ナディール姫が、はっと我に返る。
「行きましょう!!」
ナディールの声に、兵士二人もハッと我に返る。走り出したナディール姫に続いて、彼らも走り出した。もちろん、ハヤブサもそのあとに続いていた。
狭い路地を、ナディール姫は迷うことなく走る。
「ここは、私の庭」
その言葉を証明するかのように、彼女の走りは縦横無尽だった。
それでも、刺客たちの追撃は執拗だった。
狭い路地に次々と刺客が現れ、ナディール姫を討とうとしてくる。
ハヤブサはそれらを、時に手裏剣で
槍で
拳や回し蹴りを使って、対応していた。姫たちが走り抜けた後には、気を失った刺客たちの身体が、折り重なるように転がる結果となった。
(妙だ)
刺客たちを倒しながら、ハヤブサは思う。
刺客たちの目的は、はっきりと一致していた。『ナディール姫を殺すこと』────これはもう、疑いようがなかった。
しかし。
この刺客たちは────
───冗談抜きでナディール姫を狙う連中は、たくさんいるぞ……
アーサーの言葉がハヤブサの中で、現実味を帯びて回る。
(くそっ! アーサーの奴……! 厄介な案件を押し付けやがって……!)
敵を撃退しながら、ハヤブサはいつしか唇を、強くかみしめていた。
「うわ………!」
トマスがはずみで転んでしまう。
「トマス!!」
『案の定』ナディール姫がトマスを庇おうとする。
「姫様!?」
「姫様!!」
そんな二人をモガールが庇おうとして、ちょっとした団子状態になった。それを、刺客たちが見逃すはずもない。
「馬鹿めが!!」
「死ねい!!」
ここぞとばかりに刺客たちが群がってきた。
(チッ!)
この3人がそうなることは想定内なので、ハヤブサは特に慌てはしない。
「覇ッ!!」
3人を背に庇い、刺客たちを槍で一掃する。
「…………!」
驚いたようにこちらを見るナディール姫。それに向かって、ハヤブサは怒鳴りつけた。
「立てっ!! 早く!!」
「ヒッ!!」
「うわ、はいっ!!」
兵たちがナディール姫を助け起こしながら、慌てて立ち上がる。4人は再び走り始めた。
「こっちよ!」
ナディール姫が、郊外のマンホールから、地下へと飛び込む。トマスとモガールが、後に続いた。ハヤブサも一瞬立ち止まり、追っ手がかかっていないことを確認する。それをしてからハヤブサも下水道に飛びこみ、下からマンホールの蓋を閉めていた。
しばらく、狭い水路の中を走る。
いくつかの水路を潜り抜け、いくつかの分岐を走り抜け────
やがて、地下にしてはやけに広い空間へと躍り出ていた。
「みんな、怪我はない?」
地下の空洞に、ナディール姫の声が響き渡る。
「はい!」
「大丈夫であります! 姫様!」
姫の問いかけに、兵士二人が元気よく答える。
「よかった」
ナディール姫はくすくすと笑ってから、ハヤブサの方に視線を向けた。
「あなたは?」
「えっ?」
声をかけられたハヤブサの方が、少し目をしばたたかせる。ナディール姫はハヤブサの目をまっすぐ見て、もう一度、声をかけてきた。
「あなたは、大丈夫? 怪我はない?」
「あ……ああ。平気だ」
特段傷を負ったわけでもないので、素直にその旨を告げる。すると、ナディール姫も「よかった」と、屈託のない笑顔を見せた。
「ありがとう。どこのどなたかは存じませんが、おかげで助かりました」
そう言って、頭を下げようとするナディール姫を、ハヤブサはやんわりと押しとどめた。
「礼には及ばない。俺は、俺の『仕事』をしただけだ」
「『仕事』………ですか?」
小首をかしげるナディール姫に、ハヤブサは頷く。
「ああ。そのうち城の者から正式に話があると思うがな……。俺は、お前の『ボディーガード』として、雇われに来たんだ」
「え…………?」
びっくりした表情を見せるナディール姫に対して、兵士二人はぱっと輝いたような笑みを、その面に浮かべていた。
「すごい……! 姫様! よかったではないですか!」
「そうですよ! この人にガードしてもらえるなら、百人力ですよ!」
「……………」
対して、ナディール姫は、なぜか複雑な表情をその面に湛えている。
「姫様?」
しかし、トマスが怪訝そうに声をかけた瞬間、ナディール姫の表情も、ぱっと、明るいものになっていた。
「そうね……。本当に、その通りだわね!」
そのまま3人で、よかった、よかったと笑いあっている。それを見たハヤブサは、やれやれとため息を吐いていた。
「いろいろとお前に聞きたいことがある。質問してもいいか?」
ハヤブサの問いかけに、姫は「どうぞ」と頷いていた。
「お前は………俺を『信用』するのか?」
「はい」
姫は笑顔で即答する。
「あなたには、私を殺す機会など、いくらでもありましたもの」
「……………!」
姫のその言葉に、そばにいたトマスとモガールの顔色が変わる。
「でもあなたは、私を殺さなかった……。それで、十分だと思います。貴方を『今』信じるには────」
(ほう………)
ハヤブサは、姫の回答に感心する。
彼女は、冷静に相手を観察している。そして、『今、信じる』という言葉────
これは、相手に100%『信』を置いている言葉ではない。この先どう転ぶかは分からないが、今この瞬間だけは、こちらに『害意がない』と、彼女は判断しているのだと、指し示すものだった。
なかなか、利発な娘のようだ。どうやら、能天気に『姫』をやっているわけではないらしい。
「では、もう一つ聞く」
「はい」
「お前は今日街で、複数の刺客たちの襲撃を受けたわけだが────」
ハヤブサは話しながら、襲ってきた刺客たちのことを思い出していた。
刺客たちは当然、服装もバラバラなら、襲ってくる手段もバラバラだった。おおよそ、統制の取れた集団戦で挑んてきている、とは、言い難い。
しかし、いかんせん数が多すぎた。
そして、その攻撃手段も、戦い方も、多岐にわたった。
まるで、彼女を『殺そう』とするルートが『一つではない』と、言わんばかりに─────
「いつも、町に出ると、あれだけの刺客に襲われていたのか?」
もしも、毎回そうなのだとしたら、これは大問題だ。
いかなる理由があっても、町に出歩くのはしばし遠慮してもらわねばならぬ、と、ハヤブサは思ったのだが。
「いいえ」
ナディール姫は、静かに首を横に振る。
「あれだけの刺客に襲われたのは、今日が初めてです」
「…………!」
「いつもは、城の中の方が────」
伏し目がちに、ここまで口走ったナディール姫が、はっと我に返る表情をした。
「そ、そうだ! お城といえば────」
兵士二人の方に視線を走らせながら、明らかに作った笑顔を見せる。どうやら、城の中の事情を、兵士たちには聞かせたくないらしい。
「……………」
ハヤブサもそれを察して、敢えて今は、姫の作り笑いに気づかないふりをした。
ただ、後で必ず事情は聞かねばならぬとも、思った。
「ここ、地下にしては広く拓けているでしょ?」
「そういえば……!」
姫に指摘されて、兵士たちもハヤブサも周りを見渡す。下水道の狭い通路を抜けてきたのに、ここは天井も高く、柱や壁に使われている石の質も違う。人の手で丁寧に作りこまれた空間────ハヤブサの歴史好きな血が騒いだ。
「ここには昔、この国が敵に攻められた時に備えて、建築された、王族の隠し城があるみたいなの」
「隠し城………」
言われてみれば、柱や壁のところどころに、必要以上に丁寧な装飾が施されているのが見て取れる。
「これが、その名残なのか?」
ハヤブサの質問に、ナディール姫は首をかしげる。
「分からないの……。実際に攻め込まれたこともないし、一度も使われたことがないらしいから、その存在を直接確認した人はいない………」
ここで、ナディール姫は、屈託のない笑みを面に浮かべる。
「でも、地下を探索していると、ところどころこういう空間に行き当たるから、この辺りに城があったんじゃないかなぁ、って、思うの! ねぇ、こういう発見って、わくわくしない? 宝さがしみたいで!」
「地、地下を探検って………!」
「姫様……! そのようなことを、されていたんですか……!」
ナディール姫のその言葉に、兵士二人が頭を抱えてしまっている。両方の気持ちが分かるハヤブサは、もう苦笑するしかなかった。
「うん! 小さい時から暇なときに少しずつやっていたの。だから、この辺りに地下の通路は、大体網羅しているわよ!」
そう言って、エッヘン! と、言わんばかりに胸を張るナディール姫。素直に頼もしいと、ハヤブサは思った。その地下通路の地図、ぜひ、こちらにもレクチャーしてほしいものだ。
「そういえば……」
ナディール姫が、ハヤブサの方に向き直る。
「まだ、あなたの名前を聞いていなかったわね。御名は、何とおっしゃるのですか?」
「ああ……。俺の名は────」
特に名を隠す理由もなかったので、ハヤブサは素直に名乗ろうとする。しかしその時、彼の優れた感覚は、迫りくる『殺気』を捉えていた。
「……………!」
唸り声。
禍々しい気配。
悟る。
これは、『人間』の物ではない。
「おい、そこのお前」
ハヤブサは唐突に、モガールに声をかける。
「な、なんでしょう?」
ちょっとびっくりしたように顔を上げるモガールに、ハヤブサは持っていた槍を差し出した。
「これはお前の得物だろう。返す」
ぽいっと、無造作に投げられる槍。モガールは慌てて受け取っていた。
「それで────姫を守れ!」
「えっ!?」
唐突に言われて固まる3人を背に守るように、ハヤブサは立つ。
「来るぞ……! 殺気だ……!」
「そ、そんな……!」
にわかに信じられないナディール姫は、否定するように首を振る。
「おかしいわ……! だってここは、誰にも知られていないはずの場所なのに……!」
「姫様……!」
トマスとモガールは、そんなナディール姫を守るように囲んで、そして槍を構えた。今ここに、ハヤブサの言葉を疑う者は、誰もいなかった。
警戒を強めるハヤブサたち。
そこに、唸り声が聞こえてくる。
「何!? 何なの!?」
「ひ、姫様!!」
「どうか、我らのそばを離れずに!!」
じりじりと固まる3人を背に守るように、ハヤブサが立つ。
唸り声は徐々に大きくなり、辺りの壁に反響し、包み込まれるかのような錯覚を覚えた。
やがて、闇からのそりと巨大な獣のような物が、姿を現した。
4つ足歩行で、一見オオカミのように見えたが、そう呼ぶにはその身体はあまりにも巨大すぎた。
異形の生き物────ハヤブサがそう判断するまでに、時間はかからなかった。
「お前の国は、モンスターも飼っているのか?」
「そ、そんなはずないわ!!」
ハヤブサの皮肉ともいえる物言いに、ナディール姫は懸命に首を振る。
「さんざん地下を歩き回ってきたけど、あんなのに遭ったことない! 絶対に、今までいなかった物よ!!」
「ひ、姫様!!」
トマスが悲鳴のような叫び声をあげる。見ると、オオカミのようなモンスターが、その数を増やしていた。
「うそでしょ……!」
ナディール姫が、絶望に染まった小さな悲鳴を上げる。
モンスターたちは四方から、ハヤブサたちを囲むように迫ってきた。
「ひ、姫様……! 我らが、命に代えてもお守りします……!」
「わ、我らがあのモンスターを引き留めているうちに……! 逃げてください……!」
槍を構えたトマスとモガールの顔色は、もはや蒼白になっている。
それでも二人は、懸命に姫を守ろうとしていた。
「そ、そんな!! 駄目よ!!」
ナディール姫が、はじかれたように叫び声をあげる。
「あなたたち二人を置いて逃げるなどできない!! 皆で生き延びなければ────!」
(4体か……)
背に互いを庇いあう主従を感じながら。ハヤブサは、ふっと小さく息を吐いた。
────この仕事は、実にお前向きだと思うぞ、リュウ。
(ああ、確かにそうだな)
アーサーの言葉に、ハヤブサはもう苦笑するしかない。
ああ、確かにこれは、
これ以上ないくらい────『俺向きの』仕事だ。
グルルルルルルル………
灰色の長い毛に、金色に光る鋭い目。大きな牙は不吉に光り、口からはよだれが垂れ続けている。自分たちよりもはるかに上背のある、モンスターの巨体。獣臭と殺気が、辺りに充満していた。
「……………」
トマスとモガールは、今、走馬灯のようなものを見ていた。
無理だ。
如何に目の前で自分たちを守るように立つ男が『強い』とはいっても─────
これだけ巨大なモンスター4体を相手に、勝ち目があるわけがない。
自分たちはどうなってもいい。
だが姫様は。
姫様だけは、守りたい。
ああ
どうか
神様─────!
グオオオオッ!!
獣の咆哮が響き渡る。
誰もが己の死を意識した刹那。
男のトレンチコートが、宙を舞った。
それと同時に、飛び出してくる黒い影。
「覇──────ッ!!」
響き渡る、裂帛の気合。
一瞬光を放った白銀の煌めきは、あっという間に一体めのモンスターを屠っていた。ドオッ! と、大きな音を立てて、モンスターの巨体が頽れる。
「え………?」
呆然としている間に、黒い影はもう次のモンスターに襲いかかっていた。
その俊敏にして苛烈な動きを、何と表現すればよいだろう。
信じられぬことだが、モンスターたちは攻撃らしい攻撃もできないままに。
あっという間に黒い影に倒されてしまっていたのである。
最後のモンスターが断末魔を上げるのを、ナディール姫たちは、ただ茫然と聞いていた。
しばしの沈黙が、訪れる。
ブンッ! と、刀を大きく一振りすると、黒装束を身にまとった男は、その刀を背中の鞘の中に納めていた。
「怪我はないか?」
振り向いた男は、その面まで黒い覆面で覆っていた。覆面の間から僅かにのぞく色素の薄いグリーンの瞳が、鋭い光を放っている。
だが、ナディール姫は直感的に『理解』していた。
この姿こそが──────自分たちを守ってくれていた男の、本来の姿なのだと。
だから、ナディール姫は問いかけていた。
「貴方は─────?」
あなたは。
あなたはいったい何者なのですか?
「俺の名前は、リュウ・ハヤブサ」
黒装束の男は答えた。
「見ての通り────『忍者』を生業とする者だ」
第2章
「いや~~~『忍者』! 格好良かったなぁ!」
「あれだけのモンスターを、一瞬で!! すごすぎる!!」
ナディール姫の先導で、城へと帰る地下道の道すがら、トマスとモガールの楽しそうな声が響く。彼らはまだ、先程の興奮から冷めやらないらしい。
「『忍者』って、やっぱり姿が消せたりするのかなぁ」
「影にもぐったり!」
「壁抜け出来たり!!」
「火を噴いたりするんだろうか……!」
「JAPANISE NINJA !! 格好いい~~~!」
「……………」
ハヤブサは、トマスとモガールの会話を、顔を引きつらせながら聞いていた。
自分は確かに、姿を消したり、影にもぐったりはできない。
できないが─────
何ということだ。
そういうことができる奴を────俺は一人、知っている。
(『あいつ』を見たら、こいつら大喜びしそうだな……。しかしたぶん、あいつがここに来ることはないだろうが……)
「着いたわ」
ナディール姫の言葉に、ハヤブサは思考を中断させる。姫が水路の壁の隠し扉のようなものを開けると、その向こうに、上へと続く梯子があった。
梯子を上り、地表に出ると、目の前に城を裏側から見た景色が広がっていた。どうやらこの地下道は、城の後ろ側と繋がっているらしい。
「トマス、モガール」
「はい!」
「なんでしょう、姫様!」
呼びかけられた兵士二人が、姿勢を正す。ナディール姫は、そんな二人に優しく微笑みかけた。
「今日は、ご苦労様でした。私と街に出ていたことは話しても大丈夫ですが、ここの出入り口のことだけは、他言無用でお願いしますね」
「了解しました! 姫様!!」
「われら今日のことは────絶対に口外いたしません!!」
そう言って、兵士二人は敬礼して、姫と別れた。
「……………」
ナディール姫は大きくため息を吐くと、無言で歩き出す。その後ろについて、ハヤブサも歩き出した。
「ハヤブサ様……」
「『様』はやめろ」
少し驚いたように振り向くナディール姫に、ハヤブサはつっけんどんに返した。
「俺の存在をいちいち気にするな。俺は『仕事』でお前についているだけだ」
「でも………」
「それに、俺はどの道城に行かねばならん」
「えっ?」
きょとん、とするナディール姫に、ハヤブサはなおも言葉をつづけた。
「そろそろ、俺のクライアントと会わねばならん時間だ。正式に、お前のボディーガードの依頼を受けねばならん」
それを聞いたナディール姫の表情が、少し明るいものになった。
「では────ハヤブサ様は、私の護衛を、引き受けてくださるのですか?」
「戴冠式までだがな」
ハヤブサはナディール姫に、腕組みをしながら答える。
しかし、実際のところどうなのであろう。
ナディール姫の護衛は、本当に戴冠式までで大丈夫なのであろうか?
狙ってきた刺客の数といい、地下のモンスターといい、姫を取り巻く問題は、かなり根深そうな気がする。見極めてみなければ分からないが。
「俺のクライアントは、カライ内大臣と聞いている。その内大臣にはどこへ行けば会える?」
「えっ!? カライ内大臣が?」
ナディール姫は、少しびっくりしたような声を上げた。
「そうですか……。カライ内大臣が……」
それから少し、彼女は考え込むようなしぐさをする。彼女にとってもクライアントとして上がった名前が、少し意外なものであったらしい。
「分かりました、ハヤブサ様……。私も確認したいことがありますので、カライ内大臣を一緒に探しましょう」
行きましょう、と、言って、ナディール姫は歩き出す。ハヤブサも、そのあとからついて行った。
「お義姉様!」
城に入ると、黒髪の利発そうな、身なりのいい少年が、ナディール姫に声をかけながら走り寄ってきた。
「ノゾム!」
ナディール姫も、嬉しそうにその少年を迎え入れている。どうやら二人は、近しい関係にあるのだろうなと、ハヤブサは思った。
「お義姉様、また外に行かれていたのですか?」
「うふふ、そうよ」
それを聞いた少年が、心底うらやましそうな表情を浮かべる。
「いいなぁ、お義姉様……! 今度私も連れて行ってください!」
「そうね……。もう少し落ち着いたら─────」
「なりませんよ。ノゾム」
その場に女性の声が、ぴしゃりと響き渡る。
声のした方に視線を向けると、緑青色の豪奢なドレスを身にまとった女性が、毅然とそこに立っていた。
「王族のあなたが、そんなところに行く必要はありません。危険すぎます」
「母上……」
「お義母様……」
少年はナディール姫に縋りつき、姫はその女性に対して畏まった。どうやら、その女性はナディール姫よりも身分が上位の者になるらしい。ハヤブサは目立たぬように壁際に下がり、その様子を見つめていた。
「あら、ナディール、こんなところにいたのですね」
「はい。お義母様には、ご機嫌麗しゅう……」
そう言って、ナディール姫は礼に則り、丁寧に畏まる。それに対して、女性は、チラリ、と視線を走らせると、はぁ、と、忌々しそうに溜息を吐いた。
「ナディール……。貴女はまた、そんな町娘のような恰好を……」
「………………」
女性の言葉に、ナディール姫は、ただ沈黙を返す。
「まったく、あなたという人は……! 何度言えばわかるのですか!? あなたは『王族』としての自覚が足りなすぎます!! このままでは、いい恥さらしですよ!?」
(自覚がないだと?)
ハヤブサは、この女性の言い分には、かなり理不尽なものを感じたが故に、何とも複雑な心持になった。
ナディール姫に『王族』の自覚が足りないなどということは、断じてない。
彼女は自分が危機に陥った時、まず市民の安全を考えた。
自分を命かけて守ろうとする、兵士たちを庇おうとした。
優しすぎる─────だが、『王女』として大切なものは、すでに自分の物として、その身に纏っていた。
彼女に『王族としての自覚がない』と、言うのなら、いったい誰が、『王族の自覚』を身に着けていると、言うのだろう。
(ぜひとも、ご教授願いたいものだ)
壁際で沈黙を貫いているが、ハヤブサは実際かなりムカついていた。
もしも、このままこの状態が続けば、ハヤブサは、姫に向かってどうでもいい小言を、ねちねちと言いまくっている女性の頭の上に、何か落とすことを画策してしまっていたかもしれない。
しかし、そうなる前に、闖入者がそこに走りこんできた。
「ひ、姫様~~~~~~~~~!!」
それは、騎士然とした男だったが、半泣きの声を上げていた。銀の長髪をなびかせながら、ナディール姫の前に転がり込むように、跪いていた。
「イガール!」
驚いたように声を上げる姫に対して、男はその面に、心底ほっとしたような表情を浮かべた。
「良かった……っ! 姫様が、ご無事で………!」
「ごめんなさいね、イガール……。ただいま帰りました」
「姫様……!」
(ああ、こいつがナディール姫が話していた武人か)
姫の前で泣き崩れそうになっている男を見ながら、ハヤブサは得心していた。
なるほど、人のよさそうな武人だ。腕の方はともかくとして、兵士たちや姫が、彼に信頼を置くのもよく分かる。
「イガール!! これはどういうことなのですか!?」
対して、ナディール姫にねちねちと小言を言っていた女性の怒りが、今度はイガールに向かっていた。彼に説教を邪魔されたことが、よほど面白くなかったらしい。
「ナディールは、また勝手に街に出歩いていたようですし……! イガール!! あなたはそばについていなかったのですか!? ナディールが出ていこうとしたら、止めるように言いつけておいたでしょう!!」
「王后様……! 申し訳ありません! しかし────」
「ナディール姫様!! 聞きましたぞ!?」
イガールが何事かを言おうとしたとき、そこにまた闖入者がやってきた。見ると、口髭を蓄え、眉間に深い縦ジワを刻み、気難しそうな顔をした。初老の男が、ズカズカとこちらに向かって歩いてきていた。
「たった今、街の者から報告を受けました……。姫様、刺客の襲撃に遭われたそうですな」
「なんですと!?」
「まあああ………!」
初老の男の言葉に、イガールと王后から、同時に声が上がった。
「何てこと────! やはり、ナディール。貴女に『王族』としての自覚がないから───!」
(いや、今それは関係ないだろう)
ハヤブサは心の中で突っ込むが、口に出していないので、それは当然誰にも伝わらないままに、話は進む。
「姫様……! ですからあれほどお待ちくださいと────ウッ!!」
イガールが急にかがみこむからどうしたのかと思えば、「胃痛が………っ!」と、彼は己が腹を抑えて、しくしくと泣き出していた。
(気持ちはわからんでもないが……)
ハヤブサは、半ばあきれながらその様子を見ていた。
こんな状況だ。さぞかし、彼はストレスが溜まっていることだろう。
「イガール!! あなたはナディールのそばにもついていないで────いったい何をしていたのですか!?」
王后の怒声がまっすぐにイガールに襲いかかる。
「いや、それがその……」
弱弱しくイガールが口を開いた時、そこに兵士が走りこんできた。
「イガール隊長! こちらにおいでたのですか!?」
「どうした?」
問い返すイガールに、兵士が敬礼をする。
「はっ!! 先程病院から連絡があり、隊長がお助けしたご婦人が、無事に赤子を出産したようです!!」
「…………!」
兵士からの報告に、一同がハッと息をのむ。
「本当か!?」
「はい! 母子ともに無事なようです!! 病院からくれぐれも隊長によろしくと、言付かってまいりました!」
「それは良かった……」
ほっと、安堵の息を吐くイガール。しかし、周りの注目が自分に集まっていると悟ると、彼は慌てて畏まった。
「……イガール……」
「も、申し訳ありません! 姫様!!」
声をかけてきたナディール姫に、彼は深々と頭を下げる。
「本来ならば、姫様を第一の優先とせねばならないところを────!」
しかし、ナディール姫は、イガールの詫びの言葉にフルフルと首を振る。
「いいえ……。詫びは不要です。イガール……。貴方はとても、良いことをしましたね」
「姫様………!」
「私たち王族は、国民あっての王族です。私たちは何を置いても、まず国民の命と安全を、最優先にせねばならないのです。貴方のとった行動は、騎士として正しい……。私は、そんな貴方を、誇りに思います」
「姫様……っ!」
イガールはナディール姫の前で、感涙に咽んでいる。初老の男は、やれやれと首を振っていた。
「姫様もイガールも甘すぎる……! よろしいか? 姫様は命を狙われておるのですぞ!? 騎士であるならば、何を置いても姫の護衛を優先すべきはず。妊婦の件も、イガールが自ら行かず、部下に任せるなどの対応の仕方が、あったはずではないのですかな?」
「そ、それは……!」
イガールが、グッと言葉に詰まっている時、隣にいた兵士が助け舟を出すかのように、口を開いた。
「お言葉ですが、内大臣……。イガール隊長の前には、妊婦だけではなく、次から次へと助けを求める市民が現れまして……」
(内大臣?)
ハヤブサは思わず、初老の男の顔をまじまじと見つめる。
まさかこの男が、自分の『クライアント』だと、言うのだろうか。
「はあ?」
対して、「内大臣」と呼ばれた男は、驚きに目をむいていた。
「何を言っておるのだ、お前は……。そのようなこと、現実にあるわけがないであろう!?」
「いえしかし、現実に次から次へと助けを求める市民が……」
「すみません、まるで呪われているかのように……っ!」
「隊長や皆で、必死になって対処したんですけど……」
真顔で言葉を紡ぐ兵士の横で、イガールはさめざめと泣き続けている。
(たぶん、本当のことを言っているんだろうな……気の毒に)
ハヤブサは、この人の良すぎる隊長に、同情の念を禁じえなかった。おそらく、国が平和な時であったなら、彼はこれ以上ないというぐらい、優秀な警備隊長でありえただろう。
しかし─────
「……お主の気持ちもわからんでもないが、今は非常時である。姫様の警護を優先するように」
「申し訳ありません!」
まさに正論の前に、彼は頭を下げるしかなかったのであった。
「……まったく……! 姫様も姫様だ! 今回は運よく助かったからいいようなものの、また刺客に襲われたら、いかがなさるおつもりなのか………!」
「大丈夫ですわ、カライ内大臣」
まだ怒りが冷めやらぬ風の内大臣に、ナディール姫が声をかけていた。
「私に『護衛』がついてくださいました。その方が守ってくださるので、大丈夫です」
「『護衛』ですと?」
カライ内大臣が、少し驚いたように顔を上げる。ナディール姫は頷くと、彼に見えるように、ハヤブサの方を指し示した。
(この状況……できればこのままやり過ごしたかったのだがな)
ハヤブサはそう思って苦笑するが、そうも言っていられない。ナディール姫を護衛するのであるならば、ここの関係者とは、しっかり面通しをしておかねばならないと、感じていた。
「……………」
ハヤブサもカライ内大臣も、互いに無言で見つめあう。探りあうような視線が、ぶつかり合った。
「………お主が来るのは、今日の夕刻と聞いておったが……?」
(ああ、間違いなくこいつが俺のクライアントだな)
約束を交わした時間────これは、自分とクライアントの間でしか、知らない内容の物であったが故に、ハヤブサはそう確信する。
だが、自分がアーサーから頼まれた護衛だと証明する手段に、ハヤブサは少し苦慮した。
この目の前にいる人間の、誰が味方で誰が敵か分からないこの状況下で、果たして、『アーサー』の名前を出してもいいものなのだろうか。
「……下見も兼ねて、少し早く来ていたんだ」
ハヤブサは、ぶっきらぼうに言い放つ。
「夕刻には、そちらに向かう予定にしていたのだが……」
「刺客に襲われた私を、この方が助けてくださったんです」
ナディール姫が、ハヤブサに助け舟のようなものを出した
「この方は、本当によく守ってくださいました。この方がいなければ、私も無事では済まなかったと思います」
「左様か……」
そういったカライ内大臣の目に、安堵の色が一瞬浮かんだのを、ハヤブサは見逃さなかった。
おそらく、カライ内大臣は、ナディール姫の味方──────そう、判断しても差し支えないようだった。
「其方……念のために、名を聞いておこうか」
「俺の名前は、リュウ・ハヤブサ」
だからハヤブサは、カライ内大臣の問いに、素直に答えた。彼を信じたが故に。
「リュウ・ハヤブサ……。そうか………」
カライ内大臣は、口の中で小さく反芻すると、頷いたように見えた。
(もしかしたら、アーサーから俺のことを直接聞いているかもしれないな)
ハヤブサは、なんとなくそう感じていた。
「よかろう。ハヤブサとやら……これから、姫様の『護衛』として────」
「んまあ!! この由緒あるシャハディ家の城に、余所者を受け入れるというの!?」
カライ内大臣の言葉が終らぬうちに、王侯のヒステリックな叫びが響き渡った。
「私は反対です! ナディールに『護衛』だなどと、大げさな!!」
「しかし、王后陛下───」
カライ内大臣が、多少うんざりした声を上げていた。
「ガエリアル王が、病気でお倒れになった今────実質的に王の代理をしておられるのはナディール姫であること、皆が認めて居るところです。その姫に何かあれば────」
「我が子、ノゾムがいるではないですか!!」
女性の叫びに、ナディール姫に縋りつくように抱きついている少年が、びくっと、身を強張らせていた。
「ノゾムは、ナディールと違って、立派な男子です! 正当な跡取りはノゾムのはずです!」
(子供の前で、する会話ではないな)
ハヤブサは、かなり苦々しい思いで、目の前の状況を見つめていた。
かわいそうに、ノゾムという少年は、ナディール姫に縋りつきながら、完全に怯えきってしまっているように見える。それを抱きしめるナディール姫も、辛そうな表情をしていた。
ハヤブサははっきりと思う。
こんなもの────情操教育上、悪影響しか出ない。
「しかし、ナディール姫に代理をと望まれたのは、ほかならぬガエリアル王ですぞ」
カライ内大臣も負けてはいない。王后のヒステリーともいえる叫びを、柳に風と受け流していた。
「とにかく、この者にはナディール姫の『護衛』としてついてもらう。そうすることが、我が国にとって───」
「まあ! 内大臣! あなたともあろうお方が、各方面への許可も取らずに独断で、このどこぞの『馬の骨』とも知れぬ者を、勝手に城にあげるというのですか!?」
(馬の骨………)
あまりにもはっきりと、ここまで罵倒されたこともハヤブサの人生の中ではそうない経験なので、ハヤブサは、怒りを通り越して笑いすらこみあげてきた。
確かにここでは自分は余所者で、『馬の骨』と罵られても仕方のないことではあるが────
(ここまで罵倒されると、いっそすがすがしいな)
ハヤブサがそうやって、覆面の下で笑いをかみ殺していると、それまで黙って下を向いていたナディール姫が、突如として声を張り上げていた。
「お義母様!! いくらお義母さまでも失礼です!! ハヤブサ様は、決してそのように言われて良い方ではございません!!」
「んまあ!! ナディール……! あなたは王后で、あなたの『親』に当たる私に、逆らおうというの!?」
全く予想だにしていなかったその反撃に、王后がわなわなと震えている。しかし、ナディール姫も、一歩も譲らなかった。
「親であろうと大后であろうと、他人をそうやって意味もなく見下してはなりません! これは、我ら王族の中で受け継がれている、大切な『教え』ではありませんか! それをないがしろにするなんて────!」
(え、ええと……。この事態って、もしかして俺が原因か? 俺が悪いのか?)
突如として始まってしまった親子喧嘩を前に、ハヤブサは目が点になってしまっていた。
自分としては、王后に『馬の骨』と言われたからと言って、傷つくことはない。王后の言葉など、自分にとってはその辺のカエルの鳴き声と大差ないから、気にも留めないし、傷つきようもないのだ。
(シュバルツ辺りにそうやって罵られたら、立ち直ることもできないだろうがな……)
そう感じてハヤブサは苦笑する。
大切な人に、大切に思われていたなら、それでいい。
それ以外は、割とどうでもいいのだ。
(しかし、この事態……。どう納めればいいのだろう……)。
ナディール姫と王后が言い争っている状態を、放っておいていいとも思えないが────
(かといって、俺が口を挟むのもなぁ……)
有効な手段が思いつかないから、ハヤブサは途方に暮れてしまう。
本当に、こういう時にうまく立ち回れない自分に、少し自己嫌悪を感じる。
やはり自分には、こういった『ボディーガード』の類の仕事は向いていないのではないか────そう思ってしまう。
「お待ちください! 王后様! 姫様!」
その時、それまで黙って下を向いて跪いていたイガールが、声を上げた。
「何事じゃ? イガール」
カライ内大臣がイガールに振り向くと、彼は顔を上げ、一歩前に進み出ていた。
「恐れながら申し上げます。どうか、そこにいるハヤブサ殿と私で、『試合』をさせてほしいのです」
「試合じゃと?」
かなり驚いたように、カライ大臣は聞き返す。イガールは、腹を痛そうにしながらも、頷いた。
「聞けば、ハヤブサ殿は、姫様をすでに守ることに成功し、姫様の信頼も、かなり得られているご様子。私と致しましても、ハヤブサ殿の腕を測りたいのです」
「イガール………」
ナディール姫も、この実直な隊長の言葉に少し驚く。
珍しいこともあるものだと思った。
彼が、自ら進んで、他人と剣を合わせようとするなんて。
「城の護衛を任されている、騎士隊長としてお願いいたします。ハヤブサ殿の腕を把握することは、皆様にとっても、私の任務にとっても必要なことだと思いますので────」
「……………」
ハヤブサは、腕組みをしながらこの騎士隊長の言葉を聞いていた。
確かに、あいさつ代わりに軽く腕を披露することは、ここの人間の信用を得るためにも、インパクトを与えるためにも、ある程度必要な措置ではあるのだろうが────
(姫の信用はすでに得ている。そこまでする必要はあるのか?)
「ハヤブサ殿、どうであろうか」
考え込んでいるところに、イガールに声をかけられて、ハヤブサははっと我に返った。
イガールの方に視線を投げると、彼は懸命に縋るような眼差しで、こちらを見ている。
(引き受けた方がいいのか………)
ハヤブサは、何かあきらめにも似たような心境に襲われていた。宮仕えとは、なんと厄介なものなのだろう。
「俺の方は構わない……」
とりあえず、ここにいる大人を全員殴りたい。そういう衝動を覆面の下に隠しながら、ハヤブサは答えていた。
「王后様は……?」
「ま、まあ、イガールがそう言うのなら………」
イガールの問いかけに、王后もようやく文句を言うことを引っ込める。彼女の口を封じ込めることに成功しただけでも、この戦いを引き受ける甲斐がある、というものなのだろうか。
「では、話は決まりましたな」
カライ内大臣が、粛々と言葉を紡ぐ。
「王にも話を通してきます。この戦いの結果いかんで、ハヤブサとやらの処遇を決めるとしましょう。よろしいですかな? 王后様、姫様」
「いいわ」
「分かりました。内大臣」
王后と姫がそれぞれ頷いたのを確認してから、カライ内大臣は一礼して踵を返した。
「ノゾム、行きますよ」
王后に呼びかけられた少年は、びくっと身を強張らせる。しばし彼は、ナディール姫に縋りつくようにつかまっていたが────
「ノゾム!!」
大后に強く呼びかけられて、彼は「はい」と、あきらめるように返事をして、彼女のもとへと歩を進めた。
「ナディール、あなた……随分とその男に入れあげているようだけど、せいぜい恥をかかないようにすることね」
チクリとナディールに向かってそう言った大后であるが、姫が顔色一つ変えずに礼をしたのを見ると、「なんてかわいげのない『義娘』なのかしら!」と、嫌みを言いおいて、去っていった。
(いや、いろいろ問題があるのは、お前の方じゃないのか?)
ハヤブサはその後姿を、かなり呆れながら見送っていた。
「ふう………」
大后の姿が完全に見えなくなってから、ナディール姫は顔を上げる。
「姫様……!」
その彼女に向かって、イガールが声をかけていた。
「姫様、大丈夫ですか……? ご不快な思いを………!」
「私は平気よ。大丈夫」
それに対してナディール姫は、穏やかな笑顔を見せていた。
「それよりも……ごめんなさいね。なんだか、変なことになっちゃって……」
「いえ、私は大丈夫です。これで、大后から姫様を守れるのなら……」
(ああ、やっぱり、そういうことなのか)
ハヤブサは、なんとなく得心しながら、目の前のお互いにいたわりあう主従を見つめていた。
「しかし、大后も言いすぎです。何もあそこまで言わなくても────」
「イガール、それ以上は言わないで」
憤るイガールを、ナディール姫が優しくなだめる。それから彼女は、ハヤブサの方に向き直った。
「ハヤブサ様も……ごめんなさいね。変なことに巻き込んでしまって……」
「申し訳ない。大后様は、戦いの類を見るのが大変好きなお方です。姫様から気をそらすために、とっさにああ言ったのですが………」
引き受けてくださって、ありがとうございます、と、この実直な騎士隊長は頭を下げる。
「気にするな。俺は別に構わない」
ハヤブサは、腕を組みながら、小さくため息を吐いた。
もとより、自分に選択権などない。
やはりこの戦い────ある意味、とんだ茶番劇だ。
「しかし、ハヤブサ殿……あなたと剣を合わせたいと思ったのは、事実です」
イガールが、穏やかなまなざしをまっすぐ向けてくる。
「大事な姫様の『護衛』をお任せするのです。姫様のためにも、私のためにも、ハヤブサ殿の剣の腕は、ぜひ、知っておきたかったのです」
「そうか。わかった」
ハヤブサもまた、イガールをまっすぐ見つめ返して、頷いた。
この戦い────確かに茶番だが、この主従のためにも、まじめに戦わねばならない、と、感じた。
「それでは姫様。私はこれで」
実直な騎士隊長は、立ち上がって一礼をする。
「では、ハヤブサ殿────後で、『闘技場』で、お会いしましょう」
そう言いおいて、彼は去っていった。
「イガール………」
ナディール姫は、しばらくイガールが去っていった方を見つめ続けていたが、やがて、ふっと小さくため息を吐いた。
「ごめんなさい、ハヤブサ様……。本当に………」
「…………! なぜ謝る?」
謝ってくるナディール姫に、ハヤブサの方がむしろびっくりして、見つめ返してしまった。
「えっ? でも………私のせいで────」
「『お前』は何も悪くないだろう?」
「──────!」
「違うのか?」
「え、えっと………」
まさか、ハヤブサからそんなふうに言われるとは思っていなかったナディール姫は、ただひたすらに戸惑ってしまう。
「で、でも………私が、お義母様のご機嫌を損ねてしまったから────」
「『お前』が何かをして損ねているわけではないだろう。どっちかといえば、あの女が勝手に、お前に突っかかっているように見えたぞ」
「……………!」
「それに、お前はいちいち俺のことを気にしなくていい」
「えっ?」
小首をかしげるナディール姫に、ハヤブサはぶっきらぼうに言い放った。
「俺がここにいるのは、ほかの奴らみたいに、お前や王家に対する忠誠心などではない。クライアントに頼まれているから、ここにいるんだ」
「……それは、どういう意味ですか?」
ハヤブサの言わんとしているところが、いまいち理解できないナディール姫は、小首をかしげる。ハヤブサはそれに向かって、ぴしゃりと言った。
「簡単に言うなら、『金のため』だ」
「─────!」
「俺は、お前が思うほど善人ではないし、お前の抱えている国の事情やお前自身に興味があるわけでもない。おそらく、お前がこちらに気を配るほど、俺はお前のことを、思いやってはいない………」
「ハヤブサ様……!」
呆然とするナディール姫に、ハヤブサは言い聞かせるように言葉をつづけた。
「だから、お前は俺に気を配る必要はない。俺は、仕事が終われば帰る。そういう存在なのだから」
「………………」
ナディール姫は、しばしハヤブサの方を無言でじっと見つめていたが、やがて、「分かりました」と、小さく頷いた。
「では、私も着替えます……。部屋までの守護を、お願いします」
「承知した」
歩き出すナディール姫に続いて、ハヤブサも歩き出していた。
(でもきっと、この人はそんなドライな人ではない)
歩きながらナディール姫は、ハヤブサに対して感じたことを反芻していた。
確かに、この人は強かった。
その剣は苛烈で、激しかった。
だけどこの人は、馬鹿にしなかったではないか。見下さなかったではないか。
力は及ばないのに、懸命に私を守ろうとした、トマスとモガールのことを。
それどころか、守ってくれていたではないか。私たち3人のことを────
きっと、違う。
『金だけが大事だ』という人なら、おそらくこんな戦い方はしない。
報奨を得る条件である私を守ることだけに専念して────もっと早い段階で、トマスとモガールのことは見捨てていたはずだ。
(信じよう)
ナディール姫は、ハヤブサに対してそう断を下していた。
きっとこの人は、優しい人だ。
そして、信頼に足る人なのだ。
だから、私は信じよう。
その目的が、お金のためであっても、何のためであってもいい。
その人格を
その優しさを
私は信じよう。
(また、『甘すぎる』って、お父様やカライ内大臣に、怒られてしまうかな)
そう感じて、ナディール姫は苦笑する。
会ったばかりの人間を、そんなに簡単に、信じてしまっていいのかと。
それは、確かに、政治家としての資質には、欠ける行為だ。
でも基本、人は信じるものだとナディール姫は思っている。
人を信じることができずして
どうして────この先、『シャハディ家の一員』として、国を支えていくことが、できるだろうか。
「おかえりなさいませ、姫様」
部屋に帰ると、侍従であるロゼッタが出迎えてくれた。
「着替えます。手伝ってくれますか?」
「承知いたしました」
ハヤブサは、姫と侍従が会話をしているそのわずかな隙に、素早く部屋中に視線を走らせて、異常がないか確認する。周囲にも殺気はなく、今すぐ姫に、危害が及ぶ恐れはなさそうだった。
「俺は、外にいる。何かあったら呼べ」
それに、ナディール姫は「はい」と返事をする。それを確認してから、ハヤブサは、部屋のドアを閉めていた。
────思ワヌ事態トナッタナ……。
どことも知れぬ闇の中、仄暗い声が響く。
────姫のボディーガードが来るのが今日の夕刻と聞いていた。だから、そいつが来る前に、一気に片を付けようとしたのだが………。
────『下見』に来る可能性を、考慮していなかったな……。詰めが、甘かった……。
────だが奴は、今から『闘技場』に来るらしい。
────オアツラエ向キダナ………。
ククククッと、陰鬱な笑い声が、辺りに響き渡った。
────邪魔ナ輩ヲ、ココデ一網打尽ニシテヤロウ……。
悪意に満ちた笑い声が、辺りに響き渡っていた。
「姫様。準備が整いましたので、大后様が。ハヤブサを連れて、闘技場に来るように、とのことです」
「分かりました。参ります」
シャラ……と、衣擦れの音を響かせながら、ナディール姫は立ち上がる。花浅葱色を基調としたドレスに、金色の長い髪が見目良く映る。こうしてみると、彼女はどこからどう見ても、紛うことなき品の良い王女だった。
「………どこか、変ですか?」
部屋から出てきたナディール姫は、ハヤブサの視線を感じたのか、立ち止まって問いかける。それに対してハヤブサは「いや………」と、頭を振った。
「やはり、お前は王女だ、と、思っただけだ」
その言葉に対して、ナディール姫は、面ににこっと笑みを浮かべた。
「ウフフ、ありがとう」
一応、褒め言葉と受け取って礼を言う。
「でも本当は────この格好、苦手なんですけどね……」
「何故だ?」
問いかけるハヤブサに、ナディール姫は少し困ったように微笑んだ。
「だって、こんな格好だと、いざというときにとっさに動けないじゃないですか」
「…………!」
「実際困るのよね~。どうしてこんな長いひらひらしたスカートが必要なのかしら」
「もう! 姫様は、またそのようなことを!」
侍従のロゼッタが、あきれ果てたような声を上げた。ナディール姫と年頃がよく似た、かわいらしい女性だった。
「だめですよ! 変な格好をしていったら、また大后様に怒られてしまいます!」
「やっぱり、軍服の方がいいわ。ロゼッタ! 今からでも軍服に変えましょうよ!」
「だめったらだめです!」
「何でよ? 闘技場に行くのに!?」
「だめです! 今回の『試合』には、王様も顔を出されます」
「えっ? お父様が!?」
(……………!)
このロゼッタの言葉には、姫だけでなく、ハヤブサも驚いていた。
病に伏しているというガエリアル王。まさか、こんなに早く対面できるとは、思ってもいなかったからだ。
「だからこの『試合』は、王室としての公の行事の意味合いが濃くなります。ですから姫様には、きちんと正装をしていただかないと、困ります!」
「はいはい、分かりましたわ」
ロゼッタの怒り声に、ナディール姫はやれやれ、と、肩をすくめていた。
「ちゃんと『お役目』を果たしてきます。それでいいでしょ? ロゼッタ」
ナディール姫の言葉に、ロゼッタは満足そうに頷く。それを見てハヤブサは「いいコンビだ」と、思った。
「それでは、行きましょうか」
ナディール姫の言葉に、ハヤブサは頷く。そのまま使いの者とともに、闘技場へと歩き出していた。
城から出て、馬車で移動していく。石畳の道を山に向かって進んでいくと、その裾野に、コロッセオのような建物があった。
(ずいぶん、古い建物だな……。いつの時代に建てられたものだろう)
いろいろと、自分の中の学術的好奇心が疼く。もしも時間ができれば、この国を本当にゆっくり観光したいと、ハヤブサは思った。
しかし、今は残念ながらそれどころではないので、気持ちを切り替える。
しばらく待っていると、イガールを乗せた馬車が到着した。中から、武装したイガールとカライ内大臣がその姿を現す。
「イガール………!」
心配そうに走り寄るナディール姫に、イガールは優しく微笑み一礼をすると、ハヤブサの方に向き直った。
「ハヤブサ殿……。よく、受けてくださった。よろしくお願いいたします」
そう言って、穏やかに挨拶してくるイガール。武装したその手には、巨大な剣が握られていた。
(大剣使いか……。まるで、斬馬刀のような豪剣だな……)
「身体の方は、大丈夫なのか?」
問うハヤブサに、イガールは軽く苦笑した。
「薬を飲みました……。大丈夫です」
そこに、闘技場の方から司祭然とした男が歩み寄ってきた。そして、厳かに口を開く。
「二人の戦士よ……。よく来た。戦士はこちらの方へ」
「待て」
案内しようとした司祭に、ハヤブサが待ったをかけた。
「俺が戦いに出ている間、姫の『護衛』から外れざるを得ないのだが……」
「─────!」
「あ…………!」
ハヤブサの言葉に、イガールとナディール姫が、同時に息をのむ。
「彼女の安全を、確保する手段はあるのか?」
ハヤブサにしてみれば、元よりこの戦い自体、あまり気乗りしないものだった。
それに、この戦いを見たいと強く望んでいたのが、大后だというのも、ハヤブサの中では引っかかっている。
だから、この口実を盾に、彼女の安全が確保ができないのなら、姫と二人で帰ってもよかったのだが────
「なるほど、確かに一理ありますな」
ハヤブサの懸念に、カライ内大臣が答えた。
「では、姫様は特別に、王の御傍でこの戦いをご覧になっていただきましょう」
「……それが、何か対策になるのか?」
疑問を示すハヤブサに、イガールが答えた。
「ハヤブサ殿……。我がユリノスティ王国の民にとって、『王』の存在は絶対なのです」
彼は説明する。『王』の存在は絶対であるが故に、それに対して暗殺を企てる国民は、皆無に近いのだと。
(国民が暗殺を企てるのなら、多少はその手段は有効かもしれないが────俺みたいな外国からの暗殺者が来ていた場合、その理屈は通用しないと思うがな)
「………………」
そう感じたが故に、ハヤブサは難しい顔をして沈黙を貫く。そんなハヤブサに対して、カライ内大臣が口を開いた。
「もちろん、我らの王に対する警護も、万全を期します。それにハヤブサ、王后やイガールのみならず、我らも強く望んでいます。『貴方の剣の腕を見てみたい』と」
「─────!」
「大事な姫様の護衛を任せるのです。そう思うのは、当然でござろう」
驚くハヤブサに、さも当然だと言わんばかりに、カライ内大臣は言葉を続ける。
「期待していますぞ……。『龍の忍者』とやら」
その一言に、ハヤブサはハッと息をのむ。
「つまりこれは……俺の『採用試験』も兼ねているわけだな………。なるほど……」
姫の信用は得ているとはいえ、まだほかの人間たちにとっては、大后の言葉を借りるのなら、『どこぞの輩ともわからぬ馬の骨』で、あるのだ。この戦いは、避けて通れぬものと、悟る。
ハヤブサは、小さく息を吐くと、その姿勢を正した。
「承知した。では、案内してもらおうか」
司祭然とした男は、厳かに頷き、踵を返す。イガールとハヤブサも、そのあとに続いていた。
(イガール……。ハヤブサ様………)
その去っていく後姿を、ナディール姫は心配そうな眼差しで見つめ続けていたが、
「姫様。どうぞこちらへ」
と、カライ内大臣に声をかけられて、はっと我に返った。
「分かりました。参ります」
シャラ……と、衣擦れの音を立てて、ナディール姫もまた、歩き出していた。
コロッセオの中に入ると、観客席はすでに、見物のための兵士たちで埋め尽くされていた。観客の地響きを伴った歓声に、二人は迎え入れられていた。その慣習の中には、当然トマスとモガールの姿もあった。
「お、ハヤブサ殿が出てきた!」
「だ、大丈夫かな……。ハヤブサ殿……」
不安そうに見つめるモガールの肩を、トマスが軽く小突く。
「大丈夫だよ! あんなに強い人、俺見たことないし」
「それはそうだが、イガール隊長だって、相当強いらしいぞ?」
「そうなのか?」
モガールの言葉に、トマスが驚いたように振り向く。それに対してモガールも、「いや、俺も噂でしか聞いたことがないんだけど」と、念を押した。
「なんでも隊長は、うちの国でも数少ない、実戦の経験がある人らしい」
「本当か?」
驚くトマスに、モガールが頷く。
「えっ、でもうちの国って───」
「始まるぞ!!」
誰かの叫び声に、二人の会話も中断される。皆の視線は闘技場の二人へと、注がれていった。
(姫はあそこか………)
闘技場の中で、ハヤブサがまず確認したことは、王と姫の所在だった。闘技場の観客席の中央部分に、ボックス席のようなものがあり────王族の人々は、皆そこに集まっているようだった。
(心配はないと思うが、この状況……。やはり、少し危険だな……)
自分が彼女を守ろうとするには、少し距離がありすぎる。そして、この歓声────これでは、いくらハヤブサの耳が超人的に良いと言っても、彼女を狙う狙撃手の音を、聞き洩らす可能性が大いにあった。
「………………」
ハヤブサは、静かに息を吐く。
(集中……! 集中するんだ……!)
『気』を張り巡らせろ。
自分の周りにも。
姫の周りにも。
観衆の息遣い。
音─────
すべて、自分の物とするんだ。
「ねえ、お義姉様、あそこにいる黒い忍者って強いの?」
ボックス席で、ナディール姫の隣に座っているノゾムが、こそっと問いかけてきた。
「ええ。強いわよ」
ナディール姫は笑顔で答える。
4体のモンスターをあっという間に倒した。彼の腕は、間違いなく本物だ。
「ドモン・カッシュより強い?」
「ドモン・カッシュ?」
義弟の口から出た聞きなれぬ名前に、ナディール姫は思わず聞き返す。ノゾムは瞳をキラキラと輝かせながら、頷いた。
「お義姉様知らない? 格闘家だよ! ものすごく強いんだ!」
そういって、彼は元気よく「えいやッ!」と、拳を打つ格好をする。
「ああ……そういえば………」
格闘家と言われて、ナディール姫もようやくその名前の人物の情報を思い出していた。
「ドモン・カッシュ」────スポーツ新聞やテレビなどで、時々その名前を見かける。その強さゆえに、いろいろな格闘大会に出場しては、彼は優勝をかっさらっていた。テレビでもノゾムがよく好んで、格闘系の番組を見ていたことを姫は思い出す。
「ねえ、『忍者』ってことは、あの人は日本人なのかな?」
「うう~~~ん、日本人……かどうかはわからないけど、名前は……日系っぽい感じだったかなぁ」
ナディール姫は、義弟の問いかけに首をひねる。
確かに、『リュウ・ハヤブサ』とは日本人っぽい響きのような気がする。しかし、あの亜麻色の髪といい、色素の薄いグリーンの瞳といい、彼の容姿は、あまりにも一般の日本人からは、離れすぎているような気がしてしまうのだ。
「いいなぁ……。日本人なら、ドモン・カッシュと知り合いだったりするのかなぁ……?」
「そ、それはどうかしらね……」
義弟のその分析には、ナディール姫も苦笑するしかない。
日本は確かに島国だが、人口は1億人近くいる。そんな中で知り合いになる確率など、太平洋の中に落とした一粒の真珠を見つけるよりも、低いような気がしてしまうのだ。
「ねぇねぇ、お義姉様………!」
「ノゾム、静かにしなさい」
近くに座っている大后から、ぴしゃりと言われる。
「はぁい」
彼は少し口をとがらせるように返事をしたが、おとなしくそれに従っていた。しかし、ノゾムの身体はナディール姫にぴったりと寄り添うようにくっついている。
(可愛いな……)
ひっついてくる義弟の体温に、少しの安心を覚えながら、ナディール姫の表にも、少し、柔らかい笑みが浮かぶ。しかし、闘技場のほうにむけられた彼女のまなざしは、ひどく愁いを帯びたものになっていた。
イガールとハヤブサの戦いの行方が、心配でたまらなかった。
「ハヤブサ殿………」
白銀の鎧をまとったイガールが、正眼で大剣を構えながら、穏やかに声をかけてくる。
「貴公のような戦士と剣を合わせられること────誇りに思います」
「………………」
対してハヤブサは、特段構えも取らず、ただ、静かにそこに佇んでいるだけだった。
「この戦い……どうか、手加減なしでお願いいたします」
「……………!」
「私も本気です。この戦い────姫様のためにも、貴公の力量を見極めなければなりませんので─────」
そう言って、彼は白銀の甲冑で、その面を覆う。
その刹那。
彼の身体から、凄まじい殺気が立ち上がる。
(な─────!)
彼の穏やかな様子とは、あまりにもかけ離れたその熱量に、ハヤブサは瞬間気圧されそうになった。
「…………!」
グッと、気合を入れなおす。
あわてるな、と、自分に言い聞かせる。
この戦い、イガールを殺すわけにはいかない。
かといって、自分も負けるわけにはいかない。
そして、姫も守らねばならぬ。
なかなかに厳しいパワーバランスを要求されていると、ハヤブサはすでに悟っていた。
だから、イガールの力量を見極めながら────戦術を組み立てていこうと思っていたのだが。
「ハヤブサ殿………。来ぬのなら、こちらから参る!!」
瞬間、イガールが吠えた。
それと同時に、ダンッ!! と地面をける音がする。
(早………!)
とっさに、体を後ろに反らす。ハヤブサのその眼前を、大剣が凄まじいスピードで通り抜けていた。
空を切った大剣。そのまま、通常ならばスキができるはずなのだが。
「うおおおおおおおっ!!」
強引に身体ごと向けられる切っ先が、まっすぐハヤブサに向かう。
「─────ッ!」
やむを得ず、ハヤブサも抜刀をした。
ガンッ!!
大剣と龍剣がぶつかり、青白い火花が飛び散った。
「受け止めるとは……! さすが……!」
ぎりぎりとつばぜり合いをする最中、甲冑越しにイガールの声が聞こえてきた。
「……………!」
ハヤブサは、逆に歯を食いしばっていた。
このイガールの突進、自分は、弾き返すつもりでいたのに。
なんという膂力。
突進力─────
ズル、と、ハヤブサの踏ん張る後ろのほうの足が、半歩下がる。
「うおおおおおおおっ!!」
普段のイガールからは考えられないほどの、獣のような激しい咆哮。大剣に伝わる力が、さらなる加速をする。そのまま彼は、大剣ごと、ハヤブサをさらに後方へと押し込もうとしたのだが。
ガッ!!
わずかに生じた隙を、ハヤブサに突かれたのであろう。イガールのほうが逆に、後方へと弾き飛ばされていた。
(どうする?)
痛みに呻くイガールを見つめながら、ハヤブサは思考を回転させる。
(この戦い─────どうやって、けりをつける?)
イガールを殺したくはない。殺してはいけない。
彼は敵ではないのだから。
だが、この状況───生半可な決着のつけ方では、誰も納得などしてくれないだろう。
どうやってしのぐ?
イガールを再起不能に陥れずに、どうやってこの状況をしのげばいいのだ?
「……どうした……。ハヤブサ殿……!」
よろめくように、イガールが立ち上がる。
「隙だらけの私を討ってこぬとは……。手心を加えられたか……?」
「……………!」
「……手加減は無用。本気で参られよと、申したはずだが?」
そう言って、イガールが剣を構える。ハヤブサは内心舌打ちをしていた。
(冗談ではない!)
コロッセオの観客に、ぐるりと周囲を囲まれたこの状況。姫の暗殺を狙う者が、今この場にいない保証はないのだ。
誰が自分の戦いを見ているのかもわからない状況で、手の内のすべてを晒すことなど、とてもではないが出来なかった。
「はあああああああっ!!」
またも、イガールが突進してくる。思考をまとめることもできないままに、ハヤブサはそれを剣で受けた。ギャリィッ!! と、派手な火花を散らして、受け止められる大剣。ハヤブサは、その力を利用して、絡めとるように弾き返す。しかし、イガールのほうも負けてはいない。さらに重ねるように、猛然と大剣での突きのラッシュをハヤブサに仕掛けてくる。
「うおおおおおおおっ!!」
「りゃああああああっ!!」
裂帛の気合とともに、舞い上がる粉塵。
飛び散る火花。
踏み込む足音とともに、響く斬撃音───
「す、すごい……!」
観客であるトマスとモガールも、いつしか息をすることすら忘れそうになるほどに、二人の戦いに魅入られていた。しかし、二人の間で行われている太刀の応酬が早すぎて、トマスもモガールも、もう戦いの正確な状況をすることは、とっくの昔に放棄している。
「ど、どっちが勝っているんだろう……?」
「わ、わからない……」
ただ二人ともが強く願っていた。
隊長もハヤブサ殿も、どちらも無事でいてほしいと。
ガキィッ!!
もう何回響いたかわからない派手な金属音とともに、二人の身体が左右に分かれる。
「……………」
ハヤブサは剣を中段に構え、静かに佇んでいたが、イガールのほうは肩で息をしていた。
「隊長……!」
イガールの方がもはや劣勢であること、誰の目にも明らかになりつつあった。
コロッセオの上空には、いつしか暗雲が垂れ込め、唸り声のような雷鳴が、不吉に鳴り響いていた。それと同時にポツ、ポツ、と、天から雨が降りはじめている。
(もう十分だな)
カライ内大臣は悟っていた。
これ以上のこの戦いには、国のためにも姫のためにも、何の意味も為さないと。
我が国一番の剣の使い手であるイガールと、互角に渡り合った龍の忍者。
その腕は、これで十分証明されたと言ってよかった。
「皆の者───」
それ故に、カライ内大臣は立ち上がり、この戦いに終わりを告げようとしたのだが。
「お待ちなさい」
怜悧な声が、カライ内大臣の行動に待ったをかけた。
「まだ戦いは終わっていないではないですか。この戦いを止めること、まかりなりません」
「そんな────! 大后様!!」
カライ内大臣が、悲鳴のような声を上げる。
「恐れながら、これ以上の戦いは無意味です。あの者の技量を図る、その目的は達した! 止めさせないと、どちらも無事ではすまなくなってしまいます!」
「でも、『戦士』が剣を構えているのですよ?」
大后が、「だからどうしたの」と言わんばかりに反論をした。
「イガールにはきつく言い含めてあります……。どちらかが倒れるまで、闘技場を出ることは許さないと」
「そんな!! お義母様!!」
これにはナディール姫もたまらず立ち上がってしまっていた。
イガールのような真面目な人に、そんな命を下したというのなら、彼は本当に───己が倒れるまで戦い続けてしまうだろう。
「お座りなさい。ナディール」
大后はぴしゃりと押さえつけるように言い放つ。
「これは貴女のためでもあるのです。勝手な行動は───」
「どこが私のためなのですか!? イガールもハヤブサ様も、失ってはならない人たちです!! これ以上の戦いは無意味です!!」
叫ぶや否や、ナディール姫はボックス席から走り出していた。もちろん、二人の戦いを止めるために。
「姫様!! なりません!!」
当然、姫の警護に当たっていた兵士たちが、彼女を止めようとする。しかし。
「行かせてやりなさい」
それまで黙っていた王が、口を開いた。
「お父様!?」
「陛下!?」
驚く姫と大后に向かって、王は言葉をつづけた。
「ナディール……。お前が止めるべきと思うのなら、行きなさい」
「お父様……」
「止めれるものならな」
ズバッと言い切られた王の言葉に、ナディール姫は、はっと息をのんでいた。
「真剣に戦っている者たちであればあるほど、その仲裁は難しいぞ………」
「……………」
ナディール姫は、少し考え込むように下を向いていたが、やがて、その顔を上げた。
「行きます……! だって、この戦い─────意味があるとは思えないもの……!」
そう言い置くと、彼女は長いドレスを翻して、ボックス席から走り出していた。
「愚かなこと……。止められるはずもないわ………」
その後ろ姿を見送りながら、大后は口の中でつぶやいていた。
「身の程を知ればいいのよ」
彼女の心の内を映すようなどす黒い空に、稲光が走り、雷鳴がとどろく。大粒の雨が、コロッセオ全体を濡らし始めていた。
(ク…………)
仄暗い笑いが、闇の中に響く。
(サア……舞台ハ整ッタ………。一網打尽ニシテヤル………)
「……………」
ハヤブサはただ、静寂の中で剣を構えていた。雨が、静かに彼の身体を濡らしていく。
ここまでのイガールの戦いは、実に見事だと思った。彼は、間違いなく一流の戦士だ。彼と剣を合わせられたこと─────誇りに思わねばなるまい。
「……………」
イガールは肩で息をしているが、その身に宿す殺気は、確固たるものになっていく。
(ああ、終わりが近いな)
イガールと相対しながら、ハヤブサはそう感じていた。次の一撃─────おそらく彼は、それにすべてをかけてくるだろう。
(どうすれば、いい?)
彼の息遣いを感じながら、ハヤブサは自問自答し続けていた。このままではどう足掻いても、どちらかが、いや、下手をすれば両方が、傷を負うことは避けられない。下手をすれば、命を落とすことにもつながりかねなかった。
そんな事態は、断固として避けたい。
自分のガードの対象であるナディール姫を、ひどく悲しませてしまう事になる。それだけは、何としても避けたい。
しかし、どうすればいい?
それを避ける方法が
方法が、見つからない。
どうすれば
どうすれば
どうすれば─────
「……………!」
不意に。
ハヤブサの全身を、ザワ、と、いやな感覚が襲った。
それは、何度も死地をくぐり抜けてきた彼だからこそ持ち得た、『死』に対する『嗅覚』のようなものであった。それが、彼に強烈に訴えかけてきたのだ。
危ない。
死ぬぞ。
このままでは、お前は死ぬぞ─────
何かの、誰かの凄まじい『悪意』を感じる。
コロッセオの空気が変わった。
殺気が押し寄せてくる。
何だ?
この殺気は、いったい誰のものだ─────?
「…………!」
ナディール姫は、懸命に階段を駆け下りていた。
足に、長いドレスがまとわりつく。これが邪魔で仕方がない。
早く、早く走って。
もっと早く─────!
ドオオオオオン!!
雷鳴が、地響きを伴って鳴り響く。
(近い……。危ないかもしれない)
ナディール姫は、危機感を強くした。
この雷の近さ─────下手をしたら、観客である兵士たちに落ちる可能性もあった。
兵士たちを、避難させる必要がある。でも今、本当に危ないのは、闘技場で戦っているあの二人の方だ。
だめだ。
やめてほしいと思った。
この戦いは本当に────何も生み出さないものであったから。
「─────!」
ヒールが脱げた。
(邪魔!!)
彼女は迷わず両方共を脱ぎ捨てた。裸足で、彼らのもとへと急ぐ。
闘技場の入り口が見えた。
あと少し。
迷わずドアの取っ手に手をかけ、開ける。
「ハヤブサ様!! イガール!!」
ドドン!!
地響きを伴って、鳴り響く雷鳴。
闘技場の二人は、こちらに振り向かない。自分の声が、雷鳴にかき消されてしまったのだと、ナディール姫は悟った。
イガールは、今にもハヤブサに斬りかからんとしている。
(ダメ!!)
ナディール姫は、迷わなかった。
彼女は二人の間に割って入るべく、地面を蹴っていた。
「な─────!」
ハヤブサは気づいた。闘技場のドアが開き、そこから姫が飛び出してきたことに。
しかし、イガールの方からは死角になっているせいで、彼はこの闖入者に気づいていない。
姫が何事かを叫んで、こちらに向かって走ってくる。
それと同時に、突き刺さってくる『殺気』
それは、明確な意思を持って、こちらを屠らんと、迫ってきているのが分かった。
(いかん!!)
まるで、魅入られているかのように、殺気に近づいてくるナディール姫。
(馬鹿野郎!! なぜ来た!?)
来るな! と、ハヤブサは叫ぼうとする。
その瞬間、空一面が白銀に光り、耳をつんざくような轟音が、上空から降ってきた。
誰もが、コロッセオに雷が落ちたのだと悟る。
びりびりと地面が揺れ、雷が空気を割いた風圧が、辺りを襲い、その場にいた兵士たちからは悲鳴が上がった。
「隙あり!!」
イガールも、地面を蹴った。
当然だ。
姫に気を取られた刹那、自分は、隙だらけだった。
『勝負』をしているのだ。こんな隙を、見逃す方がおかしい。
「お、おい……! あれ……っ!」
トマスが声を上げたのは、コロッセオに祀られている巨大な『戦いの神』の像に、異変が起きていたことに気づいたゆえだった。
剣を振り上げていた像の腕が、ぼろ……と、音を立てて落ちた。
腕の根元からは、煙が上がっている。さっきの雷が、そこに落ちたのだと知れた。
その落ちた腕と、それに握られている大剣が
ゆっくりと
魅入られているように
まるで、天罰でも下すかのように
闘技場にいる
ハヤブサと
イガールと
走り寄ってくる、ナディール姫の上へ──────
「……………!」
危ない、と、声を上げる暇もなく。
その大剣と腕は
ズウウウウウウウン! と、轟音を立てて
闘技場に、落ちていた。
激しい土埃が舞い、一瞬、闘技場の様子が見えなくなる。
しかし、誰もが絶叫していた。
最悪の結末しか、見えなかったからだ。
無理だ。
あの状況で
誰が、こんな事態を想定した?
誰が、これを避けられる、というのだろう。
「うわあああああっ!!」
「隊長が!!」
「姫様が!!」
「嘘だろう!? 姫様がいたのか!?」
「ハヤブサ殿ォ───!!」
パニックを起こしかける兵士たち。
その刹那、場を支配するかのような、大音声が響き渡った。
「皆!! 静まれ!! こちらを見ろッ!!」
その声はボックス席から聞こえてきた故に、皆は一瞬、王が叫んだのかと思った。
だが違う。
王にしては、若すぎる声。
兵たちは振り返って─────息をのんだ。
何故ならそこには
闘技場で戦っていたはずの
黒の忍者の姿が、あったからだ。
黒の忍者は抜刀をして、王と王妃の前に設えてあるテーブルの上に、辺りを睥睨するかのようにして、立っていた。
「皆!! 姫はここにいて無事だ!! だから、静まれ!!」
果たして、黒の忍者のその言葉の通りに、ナディール姫の姿が、彼の後方にある。
そして、闘技場には、剣と腕の瓦礫のすぐそばで、茫然と座り込んでいる、イガールの姿も────
「え…………? え…………?」
兵士たちの誰一人として、そこで何が起きたのか、正確に把握出来た者は皆無であった。
闘技場にいたはずの黒の忍者が、なぜ、あのようなところにいるのだろうか?
ナディール姫は
イガール隊長は
どうやって、助かったというのだろう
「……………」
落ちてくる剣と腕。
突進してくるイガール。
それよりも早く、自分たちの間に入ろうと、飛び込んでくるナディール姫。
その瞬間、ハヤブサの『龍の忍者』としての集中力が、極限にまで高まる。
すべての音が消え去り、無音になる。
周りの動きが、すべて、緩慢なものとなった。
コロッセオの中の、一人ひとりの息遣いが、手に取るようにわかる。
その中で、判断する。
今ここで、何が起きているか。
どういう状況か。
どこに何が来るか。
何が自分にとって危険で、どう動けば避けられるか。
そして、見極めた。
皆を守るために、自分がとるべき行動は─────
飛び込んできたナディール姫を抱き込み、イガールの突きをかわす。
そのまま彼の腰のあたりを、思いっきり蹴り飛ばす。
そして自分は、姫を抱きかかえたまま、落ちてくる瓦礫を利用しながらボックス席へと跳躍した。
ハヤブサがここに来たわけは、二つある。
一つは、姫の安全確保のため。
そして、もう一つは────
黒の忍者が引き起こした『奇跡』とも言っていい状況に、場内は、シン、と、水を打ったかのように静まり返る。
そんな中、やはりというべきか────真っ先に我に返り、口を開いたのは大后であった。
「そこの者!! 無礼ですよ!! 王の御前で、そのような態度は────!」
「………………」
ハヤブサは黙して答えない。
ただ、振り向きもせず、抜刀したまま、テーブルの上に立ち続けていた。
「降りなさい!!」
威圧的な声に、やっとハヤブサは、ちらっと目線を大后に走らせる。しかし。
「断る。それはできない」
大后の物言いを、一刀両断にした。
「な………! な…………!」
はっきりと拒絶された格好になった大后が、わなわなと震えている。
(おのれ……! 無礼な……! こうなったら、力づくで────!)
強引な命を下すべく、大后が息を吸い込む。
だが、彼女が言葉を発するよりも先に、テーブルの上で立ち続ける、黒の忍者が叫んだ。
「右斜め前方!! ここを狙っている者がいるぞ!!」
「─────!」
その声に、皆が一斉に、黒の忍者が刀で指示した方向を見る。
すると、一人の兵士が無言でコロッセオから逃げ出していた。
「侵入者ぞ!! 追えっ!! 追え────ッ!!」
カライ内大臣の叫び声に、周りの兵士たちが一斉に動き出していた。
「……………」
そんな中、ハヤブサはもう一度、周りに『気』を張り巡らせる。
コロッセオの中の気配を探るが、こちらに向かって射るような殺気を向けてくる者は、もうこの中には存在しなかった。
(もう、大丈夫か……)
ハヤブサは無言で、龍剣を鞘にしまうと、ようやく、そのテーブルから降りていた。
「……………」
ちらり、と、大后に視線を走らせると、彼女は「う………!」と、小さく呻いて後ずさっていた。声をかける気にもなれなかったので、ハヤブサはそのまま、すたすたとその横を歩いて通り抜けていく。
ガエリアル王は、その姿を無言で見送っていたが、やがて、大きく息を一つ吐いた。
自分たちは、あの黒の忍者に守られたのだと、彼はすでに悟っていた。
「……………」
呆然と座り込んでいるナディール姫のそばに、ハヤブサは歩み寄っていく。
「怪我はないか?」
ハヤブサがそう声をかけると、ナディール姫は、はっと我に返ったように、顔を上げた。
「あ…………」
そこにあったのは、ハヤブサの静かな視線。自分に怪我はなかったので、ナディール姫は「はい」と、頷いた。
「そうか」
ハヤブサは短くそういうと、すたすたと歩きだしていた。
ここには、警備の兵もいる。自分が、彼女のそばにべったりとついていなくても大丈夫だろう─────彼はそう判断した故であった。
(ツ………!)
背中と肩に、焼けつくような痛みが走る。姫を庇ったときに、イガールの剣と瓦礫によって、ハヤブサは傷を負っていたのだ。あの状況───やはり、無傷で切り抜けるのは、至難の業であった。
しかし、ここで倒れるわけにはいかない。
弱みを見せるわけにもいかない。
周りに『味方』などいないのだから。
「カライよ………」
内大臣に、王が声をかける。
「はっ! 何でしょう、王様」
「あの者に、姫の警護を頼んだのは、お前か……?」
「御意にございます」
カライ内大臣はそう言ってかしこまる。王は頷くと、言葉をつづけた。
「あの者に、姫の警護に就くように、正式に手配せよ」
「─────!」
「頼んだぞ」
「ははっ!!」
頭を下げるカライ内大臣に、王は手を上げて答えていた。
「皆の者!! この場はこれで仕舞じゃ!! 皆、それぞれの持ち場に就くように───」
カライ内大臣の言葉に合わせて、コロッセオに集まっていた兵たちもまた、各々解散するために立ち上がっていた。
「義姉様……大丈夫ですか……?」
解散のざわめきの中、呆然と座り込んでいるナディール姫に、義弟であるノゾムが声をかけてきた。
「へ、平気よ……。大丈夫……」
ナディール姫は笑顔を作るが、声が上ずってしまう事を止めることができなかった。
(結局、私のしたことは何だったのだろう)
彼らの戦いを止めたい。
その願い一つを持って、駆け出して行ったのに。
何もできなかった。
止める間すらなかった。
何が起きたのか、理解することすらできないままに、ただ、守られてしまっただけと、悟る。
(何て、無力なんだろう)
あまりにも非力な自分に、姫は少し、自己嫌悪に陥ってしまう。
「義姉様………?」
ノゾムの、自分を案ずるような声に、彼女ははっと我に返った。
(いけない……! ノゾムを不安にさせてしう……!)
「大丈夫よ。ありがとう」
姫はそう言って、笑顔で立ち上がっていた。いつまでも座りっぱなしではいけない。ちゃんと、立ち上がらなくては。
ドレスに付いたほこりを払って、ナディール姫はノゾムににっこり微笑みかける。だが、その姿を見たノゾムの方が、顔色を変えていた。
「義姉様!! 血が────!!」
「えっ?」
ノゾムに指摘されて、改めてドレスを見てみると、確かに、血飛沫のようなものがドレスに付いていた。
「えっ? 何で? 私は怪我なんてしていな────」
(………………!)
ここで、ナディール姫は、はっと思い当たっていた。
あの瞬間、自分を庇ってくれたハヤブサのことを。
イガールの切っ先の前に、無我夢中で飛び出した自分。
絶対に────無傷でなど、済むはずもなかったのに。
なぜ、自分は、けがを負わなかったのか─────
「あ…………!」
床に、点々と血痕が続いていた。
それは、正しくハヤブサが歩いた道筋と、一致していた。
「ハヤブサ様………!」
ナディール姫は弾かれたように、走り出していた。
ボックス席の外の廊下に出てきたハヤブサは、壁にもたれかかって、思索にふけっていた。
あれは、いったい何だったのだろう。
あの殺意は
あの悪意は─────
妙にタイミングよく落ちてきた雷も気にかかる。
まさか、こちらに悪意を向けてきたものは、雷をも操る力を持つ、と、いうことなのだろうか。
(ありえない……と、言いたいところだが、な……)
自分は、雷をも操る存在と戦うことも間々あるので、完全に否定できない事実に苦笑してしまう。そういう場合は本当に、これ以上ないというぐらいに『俺向きの仕事』に、なってしまうわけだが─────
(アーサーのやつ……! ここまで調べがついていたから、俺に仕事を振ってきたんじゃないだろうな……!)
彼の爽やかな笑顔を思い出すたびムカついてくる。帰ったら冗談抜きで、割増料金を請求してやろうかと思ったりした。
それにしても、あの崩れ落ちてきた『像』
あれは、いったい誰を狙った?
俺か?
イガール殿か?
それとも、まさかあそこに姫が来る、ということを予測したとでも。
(……しかし、何であんなところに姫が来たんだ……)
自分たちの戦いの方に、ためらうことなく走り寄ってきた姫。その姿を思い出すたびに、ハヤブサは頭が痛むのを抑えることができなくなる。
(あの馬鹿……! 何をしに来たんだ……! 死んだら、どうするつもりだったんだ……!?)
この世はバカばっかりなのか、と、ハヤブサが深いため息を吐いた時、彼に声をかけてくる者がいた。
「……ハヤブサ殿……」
「…………!」
それが誰かと気が付いたハヤブサは、壁から身を起こしていた。そこにいたのは、自分が先ほどまで剣を合わせていた、イガールその人であったから。
自分は先程、イガールを助けるためとはいえ、その腹を思いっきり蹴り飛ばしていた。
だから、ハヤブサはそれを案じた言葉をかけようとしたのだが、それより先に、イガールの方が、ハヤブサの前に両手をつき、頭を下げていた。
「申し訳ない!! ハヤブサ殿!!」
「イガール殿……」
「あの瞬間、私や姫様を、守ってくださったのでしょう!?」
ここで、廊下に走りこんできたナディール姫も、イガールとハヤブサのそばに近寄ってきた。
「あなたが咄嗟にああしてくれなければ、私も、そして姫様も死んでいた……! 最悪、私は姫様を殺していたかもしれない……!」
「イガール………」
ナディール姫は、頭を下げ続けるイガールに声をかけようとする。しかし、それよりも早く、イガールの方が口を開いた。
「姫様を殺してしまっていたら、私はたとえ助かっても、もう、生きてはいないでしょう………!」
「あ…………!」
彼の言葉に、ナディール姫は、胸にナイフを刺されたような衝撃を受ける。自分がどれだけ、無謀なことをしでかそうとしていたか、今更ながらに気づかされてしまって、彼女は唇をかみしめていた。
「本当に……! 申し訳なかった! ハヤブサ殿……!」
「イガール!! ごめんなさい!!」
彼女はたまらなくなって、頭を下げ続けるイガールの前に走り寄り、その手を握っていた。
「迷惑をかけたのは私の方です! 私が軽はずみな行動をしたから─────!」
「いえ、姫様……! 私の方こそ、姫様に気づかずに……!」
「ハヤブサ様……! イガールは何も悪くないのです! お義母様にきつく命じられて、あんな戦いを───!」
「………だろうな」
ハヤブサは、深いため息とともに口を開いた。
「俺もお前も、『役目』を互いに果たしただけに過ぎない。だから、気にする必要はない」
「しかし、ハヤブサ殿……!」
「それに、この国に、お前ほどの剣の使い手がいる、ということを知れただけでも、俺にとっては収穫だった」
「……………!」
ハヤブサに剣の腕をほめられたのがよほど意外だったのか、イガールは少し、顔を赤らめていた。
「ここは、長く戦争をしていない国だと聞いている。それなのに、その腕前─────どこか、武者修行にでも出ていたのか?」
「ここに来るまでは、『傭兵』をしていたんです」
ハヤブサの問いに、イガールは柔らかい笑みをその面にたたえながら答える。
「あちこちの雇われ兵をして、流れ流れてこの国に来ました。城の前で行き倒れていたところを、ガエリアル王に拾っていただいて………」
「イガールは、本当によく働いてくれたのよね」
「与えられた任務を忠実にこなしていただけです」
そのまま、ほのぼのと微笑みあう主従。ハヤブサは、はあ、と、ため息を吐いていた。
こういうのは嫌いではないが、なんだか毒気が抜かれてしまう。
毒気が抜かれると、ゆるんでしまうから注意が必要だと、ハヤブサは感じていた。
「イガール隊長! こちらにいらしたんですか!?」
兵士たちがわらわらと、彼の元に走り寄ってくる。イガールは立ち上がって、それを出迎えていた。
「隊長! よくぞご無事で……!」
「ハヤブサ殿も……! よくぞ、われらの隊長を助けてくださった……!」
「この通り、御礼申し上げます!」
「隊長! お怪我はございませんか!?」
兵たちは口々に、イガールを案じたり、ハヤブサに礼を言ったりしている。彼が兵たちにとても慕われているさまが、見て取れた。
「私は平気だ。それよりも、ハヤブサ殿の方が────」
「俺も平気だ」
ハヤブサはぶっきらぼうにそう言い放つ。
イガールが案じてくれるのはうれしいが、まだ彼に「怪我をしている」といった弱みを見せる気にはどうしてもなれなかった。
何故なのだろう。
ここにいる人たちの善良性は、疑う余地もないのに──────
「……………」
ナディール姫は、ハヤブサの言葉に瞬間眉を顰めるが、少し思うところがあったので、その場では口を開かなかった。
「それよりもお前たち、どうしたのだ? 持ち場に戻るよう指示があったはずだが?」
「そ、それが隊長……」
「詰所の方に、助けを求める市民が来ていて……」
「なんだと?」
イガールの顔色が、少し変わる。
「どういう事態だ? 緊急ならば───」
「いえ、緊急といえば、緊急なような、そうじゃないような気がするんですけど」
「え?」
きょとん、とするイガールとナディール姫に、別の兵士が声をかけてくる。
「助けてほしいのは、その………『猫』なんだそうです」
「猫?」
二人の頭の中に、同時に「ニャオン♪」という、可愛らしい猫の鳴き声が鳴り響く。
「子猫が、ものすごく高い木の上に登っちゃったみたいで」
「自力では、どうしようも、降りられなくなってしまったようで」
「今、詰め所にいた兵士たちが、助け出そうと頑張っているんですけど、これが、なかなか……」
「苦戦しているみたいで………」
それを聞いたイガールは、少し苦笑したが、すぐにその顔を引き締めた。
「よし、行こう。その子猫は、救出してやらなければな」
それでは、と、イガールは一礼をしてから、コロッセオから出ていく。後には、ハヤブサと姫だけが残っていた。
「………………」
イガールの後姿を、姫が見送っている。
「………………」
その横顔を見ながら、ハヤブサは思った。
(彼女は、イガール殿に、何か特別な感情を、抱いているのかもしれないな………)
自分は、そういう色恋沙汰にさとい方ではないので、確信が持てるわけではないが、彼女がしているその眼差しには、多少なりとも覚えがあった。
自分も、愛おしいヒトを見送るとき
あんな眼差しをしているような気がするから────
(シュバルツ……)
脳裏に、愛おしいヒトの、優しい笑顔が浮かぶ。
(ハヤブサ……)
木漏れ日の中、優しく佇んでいる、大切なヒト。
会いたい、と、願ってしまった、その刹那。
「う…………!」
背中と腕の痛みを、身体が思い出してしまう。ハヤブサは低く呻いて、壁にもたれかかってしまった。
「ハヤブサ様……!」
ナディール姫が、弾かれたように走り寄ってくる。
「大丈夫ですか!? 怪我を───!」
「平気だ……。すぐ、治る………」
「大丈夫なわけないじゃないですか! 血がしたたり落ちているのに!!」
「……………!」
姫に指摘されて、ハヤブサは初めて、自分の足元に散らばっている血痕に気づく。
「傷の手当てをしましょう!」
「……あとでするよ」
姫の提案を、ハヤブサはうっとうしそうに却下する。だが、姫も引き下がらなかった。
「だめです!! 今すぐしましょう!!」
「落ち着いたら、自分でする。大丈夫だ」
頑なに拒絶しようとするハヤブサに、姫は大声を上げていた。
「困ります!! 貴方は私の『護衛』なんです!!」
「…………!」
「『護衛』ならば─────貴方の体調が万全じゃないと、私が困ります!! いざというとき、身体が動かなかったらどうするんですか!?」
「姫…………!」
「治療しましょう! 今すぐに!!」
「しかし………」
なおも、怪我の治療をためらうハヤブサ。ナディール姫は、そんな彼の態度を少し不思議委に思ったが、すぐにその原因に思い当たっていた。
(きっと……この人は、周りは敵だらけだと、思っているんだわ……)
だから、安心して、怪我の治療をすることもできない。
だがその気持ちを、彼女は痛いほど理解していた。
現に自分も今─────
城の人間の誰が敵で、誰が味方か
全然区別のできない、気の休まらない状況に、置かれているから─────
「わかりました。信頼できる『医師』が、必要なのですね……」
「えっ?」
唐突に言われた姫の言葉を、一瞬理解できずに、ハヤブサは目をしばたたかせる。すると姫は、一人でうん、と、大きく頷いていた。
「では、ハヤブサ様! 参りましょう!」
「えっ?」
「この国で、私が一番信頼できる医師のもとへ、つれて参ります!」
「い、いや、治療は自分で───」
「行きますよ! ハヤブサ様! ついてきてください!」
「お、おい!?」
ハヤブサが止める間もなく、ナディール姫が走り出す。ハヤブサも、あわてて後を追いかける羽目になった。
コロッセオから出る道すがら、カライ内大臣に行きあたる。
「姫様。どちらへ?」
渋い顔をして問いかけてくる内大臣に、ナディール姫は元気よく答えた。
「少し、街まで行ってきます!」
「そんな恰好でですか!?」
ドレス姿の姫に、あきれたように物言いをつける。しかし。
「着替えている暇ないの!」
ナディール姫は、格好なんか気にしてられない、と、言わんばかりに叫び返していた。
「事は緊急なの! 夕刻の執務までには帰るから───!」
「お一人で行かれるのですか? 供の者は?」
「私には、最強の護衛がついてるから、大丈夫!」
「…………!」
あんぐりと口を開ける内大臣の横を、ハヤブサが軽く会釈をしながら通り抜けていく。それを見たカライ内大臣は、やれやれ、と、ため息を吐いた。
「決済を待つ書類がたまっておるのです。早めに戻られますように!」
後ろから追いかけてくる、カライ内大臣の声に、ハヤブサはやれやれと、ため息を吐いていた。
それから数刻後。
二人は町はずれの、とある小さな診療所に来ていた。
やはりというべきか────ドレス姿のナディール姫は、いい意味でも悪い意味でも、とても目立つ。
「刺客の心配はしていないのか?」
問うハヤブサに、ナディール姫はにっこりと笑みを浮かべる。
「さっき、あれほど派手に襲撃してきたのです。それを全部返り討ちにしているようなものですから、すぐには襲ってきませんよ」
「……………」
姫の言葉にあきれ返りながらも、ハヤブサはなるほどな、と、納得もしていた。
確かに、街で襲ってきた刺客たちは、自分がことごとく退けている。それに対する対策が立たないうちは、よほどの馬鹿でない限り、こちらに近づいては来ないだろう。
一方、診療所の人たちは、単純にナディール姫の訪問を喜んでいた。診察目的ではない近所の人々までもが顔を出し、診療所は、ちょっとした『集会所』の様相を呈してきていた。
「お姫様! 久しぶりだね~! いつ以来だい?」
「来るってわかっていたら、もっときれいに掃除していたのに!」
「うふふ、ごめんなさいね」
皆に囲まれて、ナディール姫も楽しそうに笑っている。
「時間がなかなか取れなくて……でも、みんなことを忘れたことはないわ」
「『来れない』ってことは、『健康だ』ってことなんだろう? いいことじゃねぇか」
ハヤブサを治療しながら、老医師がぶっきらぼうに言葉を紡ぐ。
「『病院』なんてもんは、そんな再々、来る場所じゃない」
「もう、お前さんったら! 姫様の顔が見れてうれしいくせに!」
その横で、彼の連れ合いである看護婦にそう指摘されて、医師はふん、と、鼻を鳴らしていた。
「……ほれ、できたぞ。……まったく、鍛えておるとはいえ、あんまり無茶はせんようにな」
包帯を巻き終わった老医師が、やれやれ、と、ため息を吐く。ハヤブサは、軽く頭を下げていた。
「………しかし、まるで『筋肉の鎧』じゃな……。どれだけ鍛えたら、そうなるんじゃ……」
「……………」
ハヤブサは、それには答えずに、黙々と服を着ている。
(寡黙者同士……。会話が弾まないことこの上ないわね……)
そんな様子を見ながら、横にいた看護士は苦笑するしかなかった。
「先生、ありがとう……。お世話になりました」
そう言って、頭を下げるナディール姫に、老医師は眉を顰めながら声をかける。
「お姫さん、あんた………」
「はい?」
「………ちゃんと飯、食べてるか?」
「…………えっ?」
「前テレビで見た時よりも、痩せてないか?」
「あらやだ、姫様! ダイエット!?」
隣で聞いていた看護士や、周りの女性たちが、ものすごい勢いで食いついてきた。
「だめよ~! 姫様! 貴方まだ19歳でしょ!?」
「ダイエットなんてしないで、しっかり食べないと!」
「どこか体調悪いの!?」
「えっ? ダイエットなんかしてないんですけど……!」
慌てふためくナディール姫に、周りの女性たちがうらやましそうにため息を吐く。
「じゃあ、太らない体質なのかしら?」
「いいわね~。私なんて、水を飲んだだけで太るのに……!」
そう言って、女性たちは明るく笑い合う。ナディール姫も、その中で楽しそうに笑っていた。
「じゃあ、お世話になりました」
ハヤブサの治療を終えて、ナディール姫は帰ろうとする。
「もう帰っちゃうの?」
「夕飯、うちで食べていくかい?」
女性たちは口々に彼女を引き留めようとしたが、「夕方の執務があるから」と、少し名残惜しそうに断っていた。
「気をつけて帰るんだよ!」
看護師の言葉に、ナディール姫は元気に手を振って応えていた。その一方で、診察室では、老医師が深いため息を吐いていた。
(確か、王には持病の類などはなかったはずなのだがな……。急に倒れたのが少し引っかかる……)
だが、健康体に見える者でも、思わぬ病魔にやられて、急に倒れるのもよくある話だ。だから、こちらの気の回しすぎだろうが、老医師は少し気になっていた。
(あの、『お付きの者』とか言っていた、今日診た患者のことといい………少しやせた姫といい……何か、よからぬことに巻き込まれておらねばよいが……)
自分のこの物思いが、『杞憂』の類のものであってほしい。老医師はそう願いながら、ハヤブサのカルテをデスクの上に置いていた。
「あんまり時間がないから急ぎますよ。走れますか?」
姫の問いかけに、ハヤブサは「問題ない」と、返す。
「では、行きます!」
ドレス姿の姫が、ダッシュを開始する。ハヤブサももちろん、そのあとに続いていた。
夕刻近くになり、姫たちが走り抜ける市場には、夕飯向けのおいしそうな総菜が、軒先に並んでいる。肉が焼ける香ばしいにおいや、果物の甘い匂いが、鼻腔をくすぐってきた。
(お腹すいたな……)
走り抜けながら、ナディール姫は自身の空腹を、猛烈に意識する。今日はいろいろありすぎて、ろくに食事らしい食事も、とれていなかったからだ。
しかし今は、時間がないうえにドレス姿。こんな格好で市場で買い食いでもしようものなら、義母の機嫌をものすごく損ねてしまうだろう。
その八つ当たりが、自分に来るのならまだいい。だがそれが、ノゾムやほかの人たちに、牙をむいてしまったら。
それを考えると、ナディール姫はものすごく陰鬱な気持ちになる。やはりだめだ。周りの人たちをつらい目に遭わせるぐらいなら、自分が空腹に耐える方が、まだましだった。
「……………」
それにしても、今日は肉のたれの匂いが、一段と強烈だ。まるで、後から追いかけてきているような─────
そう感じたナディール姫は、なんとなく後ろを振り返る。
そして─────
絶句した。
「ん? どうした?」
何故ならそこには
大量に、肉やら果物やらパンやら飲み物やらを抱えた
リュウ・ハヤブサの姿があったからだ。
「どうした? 何か用か?」
ハヤブサはそう言っている間にも、タレのついた焼き鳥の串肉のようなものを、一本ぺろりと平らげている。
「え………? え…………?」
あまりにも意想外のものを見てしまって。ナディール姫の足が止まる。そのまま呆然と口を開けてみている間にも、ハヤブサはサンドイッチを、まるで飲み込むかのように平らげていた。
「ど、どうしたんですか? それ………」
「ああ、この食料のことか? その辺の店で買ったんだ」
「え………?」
「『血』が足りてなかったんでな」
ハヤブサはぶっきらぼうに、そう言い放つ。
「自分でエネルギーを補充していたところだ。お前は俺のことなど気にせず、自分の用を果たしてくれ」
「え、えっと……。でも、あの………!」
「どうした?」
ナディール姫がまだ納得していないように感じたので、ハヤブサは問い返した。すると、彼女は素直に、疑問を口にしていた。
「い、いつそんな、買い物する暇なんて、あったんですか………?」
自分たちは確かに、全力で市場を走り抜けていたはずだった。
とても商品を見たり、買い物をしたりする余裕なんて、なかったはずだったのに。
「代金は、ちゃんと置いてきているぞ」
ハヤブサはこともなげに言う。重視しているのはエネルギーの補給だ。だから、手っ取り早く食べられそうな目標を見つけたら、ハヤブサは迷わずそれを手にしていた。その際に、屋台に代金を置いてくることも忘れはしなかった。
ただ、普通に店主と交渉をして、品物を手に入れ、代金を払うといった、一般的なプロセスを経ていないので、店主の方が
「泥棒された!?」
「ん? このお金は何だ?」
と、思うかもしれないが、今は非常事態なので、その辺は勘弁してほしい、と、ハヤブサは思っていた。
(いいなぁ……)
ハヤブサが持つ数々の食料品に、ナディール姫の食欲は素直にそそられている。
「ん? どうした?」
あまりにもじっと姫からみられるので、ハヤブサの方が、ぎゃくに、少し居心地の悪さを感じていた。
「……まさか、ほしいのか?」
「い、いいえ!」
ナディール姫は、あわてて首を振る。
「じ、時間もないですし、こんな格好で立ち食いなんて………!」
そこまで言った瞬間、ナディール姫の腹の虫が「グ~~~~~~~!」と、大音響を奏でる。
「そんなはしたないこと…………! すみません欲しいです」
ズルッ と、ハヤブサはこけそうになった。
「朝からほとんど、食事らしい食事ができていなくて………」
消え入りそうな声で、言い訳めいたことを話すナディール姫の姿に、ハヤブサはやれやれ、と、ため息を吐いていた。
「………で? どれが欲しいんだ?」
まだいくつか持っている食料品を、ずいっと彼女の前に差し出す。
「えっと………」
ナディール姫は、そのうちの一つに手を伸ばそうとする。しかし、ためらいがちに逡巡していたその手は、すっと引っ込められてしまった。
「どうした? ほしくないのか?」
怪訝そうに首をひねるハヤブサの前で、ナディール姫は少し悲しそうな顔をして、下を向いてしまった。
「やっぱりダメ……! この格好で立ち食いなんかしたら、お義母様のご機嫌を、損ねてしまうから………」
「─────!」
ハヤブサは、少しびっくりしたようにナディール姫を見つめていたが、やがて、はあ、と、ため息を吐いていた。
「………部外者の俺が言うのも何かもしれないが、お前は少し、あの大后に気を使いすぎなのではないのか?」
「……………」
「いちゃもんをつけたい奴というのは、お前がどんなことをしていても、言いがかりをつけてくるものだぞ」
「…………!」
「気にせず、食いたいのなら食え! 食事がとれるときに取るのは、サバイバルの基本だ」
「サバイバル………」
ハヤブサの言葉をじっと聞いていたナディール姫であるが、やがて、ぐっと握り拳を握り、前を向いた。
「そうですね! 食事はとれるときに、取っておかなくっちゃ!」
そう言ってナディール姫は、明るく微笑む。そうなると、周りの雰囲気が、ぱっと花が咲いたように華やかになるから、ハヤブサは本当に不思議だと思った。
やはり彼女は、こうやって明るく笑っている方が、よく似合う。
「よし! では、どれが食べたい?」
もう一度、ハヤブサは食料品を、ナディール姫の前に差し出す。
「じゃあ、これとこれ!」
彼女が指示したホットドックとジュースを、ハヤブサは渡す。すると、ナディール姫はそれに豪快にかぶりついていた。よほどお腹がすいていたのだろう。勢いよくバクバクと食べているさまは、とても一国の王女様とは思えない。
「おいしい……! やっぱり、マルティンさん所のホットドックは最高!!」
「……まさか、どこの店のホットドックかわかるのか?」
これにはハヤブサの方が驚いてしまう。ナディール姫は、えへへ、と、笑いながらうなずいた。
「そりゃあ、伊達に食べ歩きはしてませんからね! ここの市場の知識に関しては、誰にも負けませんよ!」
「そうか……」
「あ! ねぇ! 後もう一軒だけ、どうしても食べたいものがあるのですが、そちらに寄ってもいいですか?」
そう言って懇願してくるナディール姫のほっぺには、レタスの切れ端がついている。だがそういう彼女の顔も、悪くはないな、と、ハヤブサは感じていた。
城に帰ると、案の定、カライ内大臣の、顔に怒筋を張り付けた表情が、出迎えてきた。
「姫様………」
声音こそ静かだが、ものすごく怒っているのが伝わってくる。
「ごめんなさい! すぐ着替えて、執務室に行きま~す!」
部屋までナディール姫は猛ダッシュをする。
部屋に付くと、やはり、難しい顔をした侍従長と、心配そうな顔をしたロゼッタが、出迎えてくれた。
「姫様……! どこに行かれていたのですか? お着替えもなさらずに………」
「姫様……! 心配していました……!」
「ごめんなさいね。侍従長、ロゼッタ……。すぐ着替えるから、手伝ってくれる?」
「かしこまりました。姫様」
「キャッ!! 姫様……! 血が………!」
着替えを手伝おうと、ドレスに触れたロゼッタが、そこに血がついているのを見て、悲鳴を上げていた。
「ああ、大丈夫。これは、私の血ではないのよ。私を助けてくれた『護衛』の者で────」
「へっくしょん!!」
そのころ噂になっているハヤブサは、廊下でくしゃみをかましていた。部屋では姫の着替えているのだ。さすがにそんな所まで、べったりとくっついている訳にはいかない。
「その方の治療をしていて、遅くなりました。……本当に、ごめんなさいね」
「なら、いいですけど……」
侍従長が難しい顔をしている横で、ロゼッタは少し涙目になっている。
「そ、その方は大丈夫なんですか………?」
「ええ、大丈夫ですよ。お強い方ですもの」
「よかった……! よかったですねぇ、姫様……!」
ロゼッタが、心底うれしそうな表情をする。ナディール姫も、「ええ」と、頷いていた。
「姫様、今度こそ………!」
「えっ?」
「今度こそ、その『護衛の方』が、長くいてくださるといいですね……! このところ、すぐ行方不明になったり、辞めていかれる方ばかりでしたから……!」
「……………」
ロゼッタの言葉に、ナディール姫の表情は一瞬曇る。だがすぐに、「そうね」と、笑顔で頷いていた。
「お待たせしました!」
ナディール姫が執務室に走りこむと、すでに机の上には、決済待ちの書類が山と積まれていた。
「うそでしょ!? こんなにあるの!?」
思わず悲鳴を上げるナディール姫に、カライ内大臣が、ぴしゃりと現実を告げる。
「夢でも幻でもございません。紛うことなき、圧倒的現実でございます」
「…………!」
「だから私は申し上げたはずですよ。『今日の街歩きはおやめください』と」
「うう…………」
グッと縮こまるナディール姫に、カライ内大臣は、さらにちくりと追い打ちをかける。
「これでも急ぎの書類を優先させておるのです。それらの書類は、何としても今日中にお目と押し頂きますように!」
「は……はい…………」
「各部署の担当の者は、隣の部屋に待機させております。決済の際に質問がございましたら、声をかけられますよう」
「……………」
ナディール姫は、最早、気の毒なほどたじたじになっている。それでも彼女は大きなため息を一つ吐くと、執務室の椅子に座った。早速、書類の一枚目に目を通している。
「……………」
それを見届けたハヤブサは、姫の邪魔にならないよう、執務室の壁際に、静かに陣取っていた。
部屋にはしばらく、ナディール姫の、ペンを走らせる音と、ハンコを押す音が響く。ハヤブサがそれを見守っていると、カライ内大臣がそばに寄ってきた。
「ハヤブサ殿………少し、よろしいか?」
姫の死角になるように、二人は少し場所を移動する。そこで、カライ内大臣が、改めて声をかけてきた。
「ハヤブサ殿………先ほどは、姫のみならず、王や大后までもお守りくださり、ありがとうございました……! このカライ、この通り頭を下げて御礼申し上げます……!」
これには、ハヤブサの方が少し面食らってしまった。
「いや別に……。俺は単純に、自分の『仕事』をしただけだ」
腕を組んで、ぶっきらぼうにそう言い放つ。いちいち礼を言われることでもないだろうと思った。
それでもカライ内大臣は、頭を振って、言葉を続けた。
「いえいえ、これで国がどれだけ助けられたかわかりません。やはり、アーサー殿を頼って正解だった……」
「……………」
アーサーと、このカライ内大臣は旧知の仲だと、ハヤブサは、アーサー本人から聞いている。だから、彼の口からアーサーの名前が出てきても、ハヤブサは特段驚かなかった。
ただ、このカライという男だけは、城の中で信用してもよさそうだと、ハヤブサは思った。
「ハヤブサ殿……。このようなこと、本来ならばあなたのような赤の他人に聞くことではないかもしれぬ。だが……率直な意見をお聞かせ願いたい」
「?」
目線をちらりと走らせると、カライ内大臣は、まっすぐハヤブサの方を見つめてきた。
「ハヤブサ殿は……この国と、姫君のこと………どう見立てられた?」
「………………」
カライ内大臣がどのような答えを求めているかは、残念ながら見当もつかない。だからハヤブサは、感じたままを口にすることを決断していた。
「………観光にも適した、いい国だと思う。姫も、年若いが、今のところ、よく責任を果たしているとみる。……しかし、この城の警備はザルだな」
「…………?」
怪訝そうに眉を顰めるカライ内大臣に、ハヤブサは言葉を続けた。
「姫の部屋からここに来るまでの間、姫は3回刺客に襲われている」
「な────!」
「3回とも未然に防いだ。だから、彼女は襲われたことなど気づいていない。一人は仕留めることに成功したが………」
残り二人には逃げられてしまった。姫の警護として彼女のそばから離れられない以上、ハヤブサも必要以上に刺客を深追いすることはできなかった。
「そんなことが………!」
カライ内大臣が呆然とつぶやく。ハヤブサは腕を組んだまま、一つため息を吐いた。
「もう少し、警備体制を強化した方がいい。刺客に入り込まれすぎだ」
「…………!」
カライ内大臣は、低く呻いた。それから、深々とため息を吐いていた。
「………いったい誰が、姫様のお命を、かくも執拗に狙っているのであろう……」
「心当たりは?」
ハヤブサは、念のために問うてみる。すると、カライ内大臣は、ものすごく複雑な表情をその面に浮かべていた。
「それが、分かりかねるのです……。『無い』というよりも、『有りすぎて』……………」
「……………」
「だが今────姫様を失うことは、この国にとってあってはならない事態です。ハヤブサ殿も見たでござろう? 姫が如何に、この国の民たちに慕われているかを………」
「………………!」
「その姫が、何者かの手によって誅殺されてしまえば、民たちが絶対に黙ってはいない。姫の敵を討て、真犯人を引きずり出せ、と、暴動が起きる。この国は二つに割れ、内乱の事態に陥ってしまう─────」
(確かに、そうかもな)
姫を囲む民たちの笑顔を見て、ハヤブサもそう感じていた。今あの姫に何かあれば、民たちが絶対に黙ってはいないだろう。
「国としては、そのような事態は断じて避けたい。我が国は長きにわたり、『戦争』という厄災から免れてきました。これは、是が非でも続けていかねばならぬものと、私は考えておるのです」
カライ内大臣の瞳に、強い意志が宿っている。ハヤブサは黙って聞き続けていた。
「しかし……我が国が内戦状態に陥ることを、望んでいる存在が数多くあることも、また、残念ながら事実です」
カライ内大臣の額に刻まれた縦皺が、さらに深くなる。
「姫君は女性で、為政者となるには確かに若すぎる。しかし、民に慕われ、王となる資質は十二分に備えているお方だと、私は期待しておるのです。彼女ならばこの国を、平和に導いていけるでしょう」
「………………」
「ハヤブサ殿………! どうか、戴冠式まで姫様を……! 姫様をお守りくだされ……! これは、ガエリアル王の意思でもあるのです………!」
「案ずるな」
ハヤブサは、短く答えていた。
「『仕事』はする。そのために、俺はここにいるのだから」
ハヤブサとカライ内大臣がそんな話をしている間にも、ナディール姫は一つ一つの書類に、裁決を下す手続きをし続けていた。
(お腹すいたな………)
書類にハンコを押しながら、ナディール姫のお腹は健康的に空腹を訴えてくる。
(でも、今日は少しましかな……。市場で少し、食べることができたから……)
きゅるるるる、と、鳴るお腹を宥めながら、彼女は執務を続けていた。
(今日の夕飯は、食べられるかな………)
大きなため息が一つ、書類の上に零れ落ちていた。
(すっかり遅くなっちゃった………。急がないと………)
少し暗くなった城の廊下を、ナディール姫はパタパタと走る。
(お義母様とノゾムは………もう、先に夕飯済ませてくれるわよね……)
そう考えながら走っていると、食堂からちょうど、義母とノゾムが出てくるところと鉢合わせた。
「あ……………!」
ナディール姫は、あわてて端に寄り、頭を下げて畏まる。
「あら、ナディール、ずいぶん遅かったこと。食事は、先に済ませましたよ」
「はい」
静かに返事をするナディール姫に向かって、義母は、ふん、と、鼻を鳴らした。
「………まったく、食事の時間も守れないのかしら………! 情けないこと……!」
「……………」
黙って、彼女は頭を下げ続けている。そんな彼女に向かって、ノゾムが心配そうに、そっと声をかけてきた。
「お義姉様…………」
「大丈夫よ」
ナディール姫は、ニコリと微笑みかける。
「ノゾム、行きますよ」
大后に声をかけられて、少年は「はい」と、返事をする。去っていく親子の姿を、姫は黙って見送っていた。
食事をする部屋に入り、席に着く。テーブルの上には、スープとサラダが置いてあった。
「本日の前菜でございます」
給仕が、グラスに恭しく飲み物を注ぐ。姫はそれを食べようとして────
「………………!」
唐突に、スプーンをテーブルの上に置いた。
「姫様?」
怪訝そうな顔をする給仕に、ナディール姫はニコリと微笑んだ。
「今日の食事は、もう結構です。下げさせてください」
「え…………」
「私は明日も早いので、もう休みます。ご苦労様でした」
そう言って、彼女はドレスを翻して、すたすたと歩いていく。後には呆然と佇む給仕と、湯気の上がったスープが、テーブルの上に残されていた。
「おい」
これにはハヤブサもかなり驚いて、その真意を確かめるべく。前を歩く彼女に声をかけていた。すると。
「─────!」
振り向いた瞬間、その場から距離を開けるように飛びのかれ、姫に身構えられたから、ハヤブサはさらに驚いてしまう。
「どうした?」
多少、眉を顰めながら声をかけると、姫も、はっとなって我に返っていた。
「ご、ごめんなさい。ハヤブサ様………!」
「いや、いい。警戒することは悪いことではない。気にするな」
「は、はい………」
そう返事したものの、下を向いてしまうナディール姫。その様子が気になったハヤブサは、再び問いかけていた。
「それにしても、どうした?」
「えっ?」
「お前は、腹が減っていたのではないのか?」
「………………!」
何故、ハヤブサがそのことに気づいているかというと、耳のいい彼は、執務室でナディール姫の腹の虫が鳴る音を、散々聞かされていたからだ。
(腹が減っているんだな……気の毒に……)
市場で、幸せそうにホットドックをほおばっていた、姫の顔を思い出す。
食べることが好きなのは、いいことだとハヤブサは思っている。健康に生きている証拠なのだから。
その姫が、一口も口をつけずに、食事を断るなど─────これは、どう考えても、おかしすぎると思ったから。
「………………」
対して、ナディール姫は、しばらく驚いたようにハヤブサの方を見つめていたが、やがて、ふっと、その面に笑みを浮かべた。しかし、その笑みは、いつものような闊達な笑顔ではなく、どことなく、暗い影を背負ったものだった。
「毒が入ったスープを飲んで、自殺しろ、と、言うんですか?」
「な─────!」
絶句するハヤブサに、ナディール姫はさみしげに笑いかけた。
「残念ながら、私には分かる手段があるの。目の前にある食事が、『毒入り』か、そうでないかを見分けるための手段が…………」
「………………」
「ごめんなさいね。ハヤブサ様………。驚かせてしまって……。でも私はまだ、死んであげる訳にはいかないから………」
(そうか……! そういうことか………!)
ハヤブサはようやく得心する。
ナディール姫が、何故『姫』という立場にありながら、空腹感に喘いでいたのか。医者に「瘦せたのか?」と、言われるほどに────
それはそうだ。
食事を安心して、満足に食べることもできなければ、誰だって、いやでも痩せていってしまう。
「………………!」
ハヤブサは、ぎり、と、歯を食いしばっていた。
彼女は自分が安住できる『城』という居住地にいながら、そこにはいない。食料を安心してとることができない状況など─────過酷な戦場にいることと、同義ではないか。
「……明日も早いわ。もう、寝なくちゃ……」
そう言って、彼女は前を向いて、もう、歩き出している。
ずっと、戦ってきたのか。
そうやって、独りで。
これだけのものを背負って
街で、ああやって笑っていたというのなら────
(『食べられない』ということは、『寝られない』のではないのか?)
ハヤブサはふと、思い当たる。
ここを『戦場』と考えるのならば、彼女に平穏な眠りなど、保証されてはいないだろう。
「……………」
周りの気配を探ってみる。すると、案の定、『刺客』と思われる殺気を感知していた。しかも、それは複数に及んでいる。
(………警備を強化してくれ、と、言ったのに、これでは意味がない……)
そこまで考えてから、ハヤブサははっと気づいた。
違う。
「警備を強化していない」のではない。
「手引きをしている者がいる」のだ。
姫の暗殺を企む者が
刺客たちを呼び込んでいるのだと─────
あのカライ内大臣が、自分の忠告を聞き入れなかった、とは考えにくい。
彼の警備強化の裏をかいて、何者かが姫の元へ刺客を送り込んでいる。
そう考えた方が、はるかに自然だった。
誰だ?
誰が一体、そんなことを────!
絶対に、犯人を捕まえなければならない。
だがそれよりも今は、早急にやらねばならないことがある。
「…………!」
ハヤブサは、ぐっとこぶしを握り締めていた。
「ロゼッタ、ありがとう」
ゆったりとした部屋着に着替えて、ナディール姫はにこりと笑う。
「今日はもう大丈夫だから……あなたももう下がって、休んで?」
「姫様………」
「ね………」
ロゼッタは案ずるようにナディール姫を見つめていたが、やがて、渋々頷いていた。
「何かありましたら、お呼びくださいませね」
そう言って、彼女はドアの向こうに消えていた。それを見送ったナディール姫は、ほっと溜息を吐いていた。
(きっと……今日も、部屋で寝ない方が、安全なんだろうな……)
ここのところ、ナディール姫にとっては、城の中にいる方が、かなり身の危険を感じるようになっていた。いきなり目の前にナイフが落ちてきたり、バルコニーから突き落とされそうになったり。
ハヤブサがそばについてくれている今のところは、そんな攻撃は止んでいるが。まだ油断はできない。今晩も、絶対に、何かを仕掛けてくるはずだ。
そして、あいかわらず、食事には毒を入れられ続けている。
安心できない。
何もかもが。
城の人たちは、何を考えているのだろう。
私など、もういなくなってしまえばいいとでも、願われているのだろうか。
「………………」
しばらくベッドに座り込んで、じっと一点を見つめていたナディール姫であるが、やがて、ブン! と、大きく頭を振った。
(しっかりしなさい……! ナディール……! 私が死んでしまったら、誰がノゾムを護るというの………!)
王となるには、まだ幼すぎる義弟。
やはりだめだ。
彼にすべてを押し付けて、死ぬことなどできないと思った。
まだ、生きなければ
せめて、ノゾムが一人前になる、その日まで。
顔を上げる。
(そういえば、ハヤブサ様は……?)
着替えるから今は、姿が見えなくても仕方がないと思うが、少し前から、その姿を見ていないような気もする。
(俺のことなど気にするな……)
あの人はそう言ってくれたが、ナディール姫は自分のうかつさを痛感した。
何ということだろう。彼に、『休む場所』を、まだ提供していない。
どこで休めばいいかわからなくて、途方に暮れさせてはいないだろうか。
不意に。
部屋のドアがコン、コン、と、ノックされる。
「─────!」
一瞬、身体をこわばらせるナディール姫だが、彼女はすぐに平静を取り戻した。
「はい」
枕元に置いてある短剣を手に、立ち上がる。何が起きても対処できるように、油断なく身構えた。
カチャ……と、ドアが開いて姿を見せたのは、ノゾム付きの召使だった。
「姫様………申し訳ありません………」
「どうしたの?」
問いかけてくるナディール姫に、そのメイドは申し訳なさそうに頭を下げた。
「ノゾム様がまた………。姫様がそばにいないと、眠れない、と、仰って……」
「そうですか……」
姫は優しく微笑むと、そっと短剣を枕元に置き、薄い絹の上着を羽織る。『武器』を持って、義弟に近づくわけにはいかないから。
「わかりました。参りましょう」
「いつもいつも……申し訳ありません……」
「いいのよ」
そのまま静かに、部屋の出入り口に歩んでいくナディール姫。ただ、部屋から出るとき、その長い廊下の暗さゆえに、少しの恐怖を感じた。
「ハヤブサ様………」
小さな声で、頼るべき護衛の名を呼ぶ。すると。
「どうした?」
姿は見えないが、声だけが返ってきた。
「い、いえあの………ノゾムの部屋に、参ります……」
「そうか」
たったそれだけの短い返事。だがそれは、ナディール姫の心に、確かな安心感を与えていた。
(大丈夫……。傍にいてくださっている………)
信じられる。
不思議だった。
今日、会ったばかりの人であるのに。
ぎゅ、と、胸の前で手を握り締めて、彼女はまた、歩き出していた。
「お義姉様!!」
ナディール姫がノゾムの部屋に着くと、泣きぬれた義弟の顔が、そこにあった。
「ノゾム……」
「お義姉様……!!」
すがるように手を伸ばしてくる義弟の身体を、優しく抱きしめる。
そのまま、わんわんと大声て泣き続ける彼の背中を、なだめるように撫で続けた。
「お義姉様……! お義姉様……ッ!」
「ノゾム………」
「怖い……! 怖いよ………っ! 独りで眠りたくない………!」
「大丈夫よ……。貴方もう8歳でしょう?」
優しく言い含めながら、義弟の身体をベッドに寝かしつけ、自分もその横に入って添い寝をした。
「ほら………貴方が寝るまで、一緒にいてあげるから………」
「………うん……」
甘えるように、自分の懐に潜ってくる義弟。そっと、その髪をなでてやると、ぎゅっと、服をつかんできた。
「お義姉様………」
「なぁに?」
「お義姉様は………ずっとそばに、いてくれるよね……? いなくなったり、しないよね……?」
「……………!」
「お義姉様………!」
「もちろんよ、ノゾム………!」
心配そうに見つめてくる義弟を、姫は優しく見つめ返した。
「私はどこにもいかないから………大丈夫………」
「うん…………」
懐で、しばらくもぞもぞとしていた義弟であるが、やがて、静かになり、穏やかな寝息を立て始めた。
(暖かい………)
寝心地のいいベッドと、ふわふわの羽毛布団。そして、義弟のぬくもりに、ナディール姫も、つい、睡眠に引きずられそうになってしまう。ここのところ、寝不足な状態が続いていたから、余計に────まどろみへの欲求は、抗いがたいものがあった。
(でもだめだ)
ナディール姫は、必死に己を叱咤する。
朝まで自分たちが一緒に寝ていたと、義母にばれたら、自分だけでなく、ノゾムにまでその怒りが向いてしまう。それに、自分は命を狙われている身。自分を共にいない方が、ノゾムの安全は、守られるだろう。
「……………」
ナディール姫はノゾムが完全に寝たのを確認してから、ベッドから抜け出していた。
「姫様………」
部屋から出ようとすると、ノゾム付きの召使が声をかけてきた。
「ノゾムはもう寝たから………今宵は、大丈夫だと思う。後は、よろしくね」
「はい……。畏まりました……。でも、あの……姫様!」
「なぁに?」
「……また、以前のように……ノゾム様と一緒に寝ていただくわけには、いかないでしょうか………?」
「………………!」
「ノゾム様は、まだ8歳なんです……! ずっと、姫様とご一緒にお休みになっていたのに……! いきなり『一人で寝ろ』と、言われても────」
「でも、いつまでも子供でいられないのも、確かだわ」
召使の言葉を、ナディール姫の静かな言葉が遮った。
「お義母様の言うことも、もっともなのよ。ノゾムもそろそろ、王族の一員としての自覚を、身に着けていかなくてはいけないと思う………」
「そうかもしれませんが………」
まだ、納得していない様子の召使に、ナディール姫は、優しく微笑みかける。
これは、試練なのだ。
私にっても
ノゾムにとっても
そして、ノゾムを思いやる、この召使にとっても───
「ノゾムをよろしくね」
ナディール姫はそう言い置くと、静かに部屋から出ていった。
「ハヤブサ様……」
暗い廊下に出ると、ナディール姫は、すぐにその名を呼ぶ。
「どうした?」
声は、すぐに帰ってきた。
「ハヤブサ様……。私はそろそろ、休もうと思っています」
「そうか」
「ですから、ハヤブサ様も、どうかお休みに」
「俺は俺で、勝手に休む。気にするな」
「ですが、きちんとした部屋で、お休みにならないと……」
「……………」
ハヤブサは、潜んでいた場所から姫の前に姿を現す。
「案ずるな。俺はここの客人ではない」
「ハヤブサ様………」
「俺は、『仕事』をしに来ているだけだ。本来ならば、こうしてお前の前にも、いるはずもない人間だ」
そう言いながら、闇に溶け込むような色の忍び装束をまとった『忍者』が、目の前に立つ。
確かにその姿は、西洋の『城』という場所に存在するには、あまりにも異彩を放ちすぎているように、見えた。
「言ったはずだ。お前は、俺のことはいちいち気にしなくていいと」
「そうですか……」
ハヤブサの言っていることは、理屈ではわかる。彼に、余計な気遣いは不要だ、ということも。
しかし、ナディール姫は、言いようもないさみしさを感じていた。
自分は、誰にも必要とされていないような、変な錯覚を覚えてしまう。
(きっと、疲れているのね)
ナディール姫は、自嘲的に笑う。
よく眠れていないせいだ。
よく食べられていないせいだ。
ああ
いったいいつまで
いつまでこんな生活を続ければ─────
「…………!」
はちきれそうになる心を、彼女は無理やり抑え込んだ。
しっかりしろ、ナディール。
お前に、泣く場所などない。
「わかりました………」
そう言って、ナディール姫は歩き出す。夜の、己の身の安全を、確保するために。
(今夜は、どこで夜を明かそう)
そう考えながら、2、3歩足を運んだところで、ハヤブサに呼び止められた。
「おい」
「なんですか?」
ナディール姫は足を止め、振り向きもせずに返事をした。
彼女にしては、かなり失礼な態度をとっていることになるのだが、彼女はもうそれを改める気にもなれなかった。「気を使うな」と、言ってきたのは、向こうなのだから。
「どこへ行く?」
「どこって………寝る場所へ」
「お前の部屋は、反対方向だろう?」
「……………」
ふっと、小さく息を吐く。
「………寝るには、部屋は、一番危険ですので」
自分は、命を狙われているのだ。
部屋のベッドの上など─────刺客たちがもっとも狙ってくる場所ではないか。
(やはりそうか………)
自分の読みが当たっていたことに、ハヤブサは苦々しさを覚える。
彼女は今、食事も睡眠も、取り上げられていた。
思った通り─────彼女は今、過酷な戦場にいるのだ。
ならば、俺が取り戻してやる。
せめて、安らかに眠ることができる場所を。
「………そうだろうな。あれだけ刺客が入り込んでいれば……」
「……………!」
静かに紡がれたハヤブサの言葉に、ナディール姫は驚きを隠せなかった。思わず、振り向くと、黒の忍者の静かなグリーンの瞳と、視線が合った。
「刺客たちは………どうしたんですか?」
ナディール姫の問いに、ハヤブサは事もなげに答える。
「全員、始末した」
「──────!」
「……捕らえて、誰の差し金か、拷問にでもかけて、吐かせた方がよかったか?」
ナディール姫は、勢いよく首を横に振った。ハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐いていた。
「……お前の部屋周りは、入念にチェックしてある。近づいてくる殺気も、今はない。部屋に戻れ。この城の中では、お前の部屋が、おそらく今は一番安全な場所だ」
「ハヤブサ様………!」
「俺の言うことが、信用できないか?」
呆然と佇む姫に、ハヤブサは問いかける。すると、これにも彼女は勢いよく首を振った。
(それにしても、いつの間に……?)
魔法のような展開に、彼女はただ、あんぐりと口を開けるほかはなかった。
全然気が付かなかった。
この人はいつの間に、そんな戦いをしていた、と、言うのだろう。
「朝まで、お前をちゃんと守ってやる。それが、俺の仕事だから」
「……………!」
「ベッドに入って、しっかり寝ろ。睡眠不足は、いろんなものを狂わせるぞ」
ハヤブサの言葉に、彼女ははっと、息をのむ。
確かにそうだ。
明日もいろいろと激務が待っているのに。
こんなところで倒れている場合では、ないと思った。
でも、いいのだろうか?
本当に
本当に────
ベットで朝まで眠っても───?
「案ずるな」
目の前の黒の忍者が、力強く言葉を紡ぐ。
「そのために、俺がいるのだから」
ナディール姫は、半ば夢見心地で、部屋までの道のりを歩いていた。ドアを開け、明かりをつける。
「………………」
しばらく呆けたようにベッドを見つめていると、ハヤブサから声をかけられた。
「どうした? まだ、不安か?」
「ハヤブサ様………」
「ベッドも確認してある。毒針の類は、仕掛けられていなかったぞ」
「─────!」
ハッと、息をのむナディール姫に、ハヤブサは淡々と言葉を続けた。
「俺は、専門ではないが、『殺し』に関しては、それなりに知識はある。お前を殺すために暗殺者がとる手段や行動も、ある程度は読むことができる───」
「……………!」
「………俺が、怖いか?」
「い、いいえ!」
ナディール姫は、あわてて首を振った。
怖いか、と、問われた瞬間
グリーンの瞳が、寂しげに揺らめいたように思えたから。
怖くはない。
怖いとは、思わない。
ただ────想像がつかなかった。
人の命を屠り
殺しの知識を淡々と話す。
この人は今まで
どんな道を歩んできた、と、言うのだろう。
「ハヤブサ様……。ありがとうございます」
心のままに、礼を言い、頭を下げる。その刹那、彼女の腹の虫が、再び「ぐう」と、大きな音を奏でた。
(しまった……! ちょっと心が緩んじゃったから………!)
あわてて咳ばらいをし、ごまかす。しかし、顔がほてるのを抑えることができない。
(恥ずかしい……! 聞かれちゃったかな……?)
「あ、あの……! 私そろそろ────!」
しどろもどもになりながらも、彼女が『休みます』と、言おうとしたとき、ハヤブサの方から姫の方に何かを投げ渡してきた。
「?」
きょとん、としながらも、それをパシン、と、受け取るナディール姫。不思議そうに手の中の丸い物体を見つめていると、ハヤブサがぶっきらぼうに口を開いた。
「食え」
「えっ?」
「それは、忍者用の非常食だ。小さいが、腹持ちがいい。栄養価も高い」
「……………!」
「食え。腹が減っているのだろう?」
「ハヤブサ様………!」
「毒は入っていないぞ? 味は保証しないが……」
「で、でもこれは、ハヤブサ様のでは………!」
「俺の方に気を使うな。何回言わせる」
そう言いながら黒の忍者は、顔を覆っていた覆面をずらす。その下には、半ば呆れ返ったような、ハヤブサの表情があった。
「俺は市場の買い食いで、十分に腹を起こしている。お前も見ていただろう?」
「あ…………!」
ハヤブサにそう言われて、ナディール姫も思い出す。
市場を走り抜けながら、両手いっぱいに抱えた食料品を、あっという間に口に入れて、平らげていた彼の姿を。
「それは『非常食』だから、当然まだ予備もあるんだ。だから、お前は気にせずそれを食え」
「ハヤブサ様………!」
「食え。腹が減っていては、眠れないだろう」
「……………」
じっと、手の中の非常食を、彼女は見つめ続ける。その姿を見ているうちに、ハヤブサの中で、別の懸念が生じてきていた。
もしかして、「こんな変わりすぎた物なんか、食べられない」と、思われてはいないだろうか。
そうなると、この状況は食料品の押し売り状態になるわけで。
しかし、今はまともに料理したものなぞ、彼女の前に出すことも用意することもできないから、これで勘弁してほしい、と、ハヤブサは思っていた。
腹が減ったままでは満足に眠れない。
これは、確かなのだ。
「眠る」ことにだって、存外体力は使う。
「……やはり、無理か? それは、食べられそうに───」
「いえ、いただきます」
ハヤブサの言葉が終わらないうちに、ナディール姫は手の中の物に、かぶりついていた。
口の中いっぱいに、確かな歯ごたえと、香ばしい香りが広がる。
これは昔、どこかで食べたことがあるような、懐かしい味がした気がした。
これは、何だろう。
いつどこで、味わったものなのだろう。
ふとよみがえる、懐かしい、記憶。
幼いノゾムと、ピクニックに来ていた、あの時。
皆で笑い合っていた、あの───
「……………!」
ぼろ、と、大粒の涙がこぼれる。
いけない、と、彼女がそれをこらえようとしても、まるで堰が決壊してしまったかのように、次から次へとあふれ出してきてしまっていた。
「ご………ごめんなさい! これは………っ!」
あわてて涙をぬぐうナディール姫。ハヤブサもまた、少しあたふたと視線をそらしていた。
「べ、別に泣くことは、悪いことではない………」
「ハヤブサ様………」
「泣いてもいい。だが、それはちゃんと食べろよ」
そう言って、龍の忍者は姫の前からフッと、姿を消す。
「あ…………!」
驚いたナディール姫が、その姿を求めるように、2、3歩足を進ませると、すぐに、どこからともなく声が響いてきた。
「姿は消すが、常に俺は、お前の近くにいる」
「……………!」
「何かあったら呼べ」
そういい置いて、その声の主の気配は、闇の中へと溶け込んでいった。
(ハヤブサ様………)
再びナディール姫は、手にした非常食にかじりつく。
(おいしい………)
おいしいから、食が進んだ。
そして、涙が止まらなくなった。
泣き止まなければ、と、彼女は思うが、それはどうにも無理な話であった。
一度堰を切ってしまった感情は、あとからあとから、彼女に涙をあふれさせていた。
泣くことは悪いことではない、と、あの人は言った。
だからきっと、今だけは泣いていい。
泣いていい。
この涙を止める術を、自分は知らないのだから。
ぐすぐす、と、大粒の涙を流し、嗚咽をしゃくりあげながら、彼女は寝るための身支度を整えていた。
そのまま、ベッドへと入る。
寝心地の良い、ベッドマットレス。
ふかふかの羽毛布団。
程よい高さの枕────
(いったい、何時ぶりだろう……?)
彼女にとっては、本当に久しぶりに寝る、自分にとってのベッド。
また、涙があふれてきた。
優しい布団の感触が、彼女に温かい、優しい、そして、懐かしい記憶を思い出させる。
また、あの頃の様になれるだろうか。
やわらかい日差しの中、皆で穏やかに笑い合って────
お父様
お母様
そして─────
──────姫様…………。
まどろみの中、優しくも懐かしい声が、聞こえたような気がしていた。
(………眠ったか……)
ナディール姫の嗚咽が、穏やかな寝息に変わったのを確認してから、ハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐いていた。
過酷な環境の中、独り、いろいろなことを抱え込んで、頑張っていた姫。
ある意味、何もかもがはちきれそうになっていた彼女を支えれば、多少は泣くかもしれない、とは、思っていたのだが。
まさかあそこまで大粒の涙を流して、泣いてしまうとは。
(参ったな………)
女性の涙を見るのは苦手だ。その涙を慰める術を、自分は持ってはいないから。できれば、これ以上彼女を泣かせるようなことは、したくはない、と、ハヤブサは思った。
しかし、彼女を取り巻く事態は、思った以上に深刻だ。看過できない問題が、いくつもある。
とりわけ、すぐにでも対処しなければならないのは、食事の問題だろう。食事に毒を入れられ続けているなど、悪質すぎる。それを実行している犯人を見つけて、早急にその根元を絶たねばならないだろうが─────
実際問題、自分が四六時中、厨房に張り付くのはほぼ不可能に近い。自分は、姫の護衛に就かなければならないからだ。城内でも命を狙われている彼女。その傍を離れるのは、危険すぎた。
独りでは無理だ。誰かに協力を仰がなくては。
(だが…………誰に頼る……?)
場内に、彼女に対する明確な『悪意』が存在していることを、ひしひしと感じる。頼る相手を一つ間違えてしまったら、自分も彼女も、共倒れになってしまう可能性が否定できなかった。
誰に頼ればいい?
誰を信じればいい、というのだろう。
(真っ先に思い浮かぶのは、イガール隊長だが…………)
「………………」
何故だろう。あの男はあまり、頼れないような気がする。
人柄もよく、兵や民たちからも慕われ、剣の腕もたつ人物なのだが────
(押しが弱いな………)
そう感じて、ハヤブサは苦笑していた。
周り人間の要望を聞くことは、悪いことではない。しかし、聞きすぎるのもどうかと思う。
彼はもう少し他人の意見をはねのける勇気も持たないと、周りに気を使いすぎて、つぶされてしまうような気がしてしまうのだ。
(惜しいな……。剣の腕が立つだけに……)
だが仕方がない、と、ハヤブサは思う。
剣の道に生きる人間は、人の間でうまく立ち回って生きていくには、得てして不器用すぎるものだから。
(正直、自分がもう一人欲しいな………)
そう感じて、ハヤブサはため息を吐く。
自分と同等の能力を持った仲間が、もう一人欲しい。
そうすれば、一人は姫の護衛に就き、その間にもう一人が、城の中をあちこち探りまわることができる。
姫に対する攻撃を防戦するだけではなくて、反撃に移ることも可能になってくるのだ。
「………………」
(しかし、俺と同等の能力を持った人間など─────)
ここでハヤブサは、はっと思い当たった。
いる。
いるではないか。
「間諜」という能力値においてなら
俺と同等か、それ以上に高い力を発揮する奴が─────
ハヤブサにとっては最愛のヒトである、シュバルツ・ブルーダーの姿が脳裏に浮かぶ。
彼は姿を消し、人の影の中に潜むことができる。
縄抜けができ、壁も自在に通り抜けられる。
そして、DG細胞という特殊な物体でその体を構成されているがゆえに、『不死』──────凡そ、間諜活動においては、これ以上ない、というぐらい『チート級』の能力を持った存在だった。
(呼ぶか……?)
連絡する手段はある。
事情を話せば、彼はきっと、力を貸してくれる。シュバルツは、そういうヒトだという確信があった。
彼が来てくれるだけで、自分にとっては、どれほど心強い存在になるだろう。
しかし─────
「……………!」
ハヤブサは、ぐっと唇をかみしめていた。
だめだ。
これは自分の『仕事』なのだ。
シュバルツは、本来ならば、関係のない第3者。こちらの事件とはかかわりなく、平穏に暮らす権利が、彼らにはあるのだ。それを侵してはならないと、ハヤブサは強く思った。
それにきっと、頼りすぎてはだめだ。
自分は今まで『独り』で仕事を請け負ってきたのだ。これからもそうするべきで、そうあるべきなのだ。
そうしなければ、きっと自分は、どんどん彼に頼ってしまって─────
自分はいつでも、彼を求めるようになってしまう。
深いところで、自分の『業』に、キョウジやシュバルツを巻き込んでしまう。
それは、許されることではない、と、ハヤブサは思うのだ。
(自分は、シュバルツの『業』に巻き込まれたがっているのに………勝手な話だよな………)
そう感じて、ハヤブサは苦笑してしまう。
兎角人の心は厄介なものだ。
自分は、いくらでもシュバルツのために消耗することを望むのに、シュバルツが自分のために消耗することは嫌がるだなんて。
(……今居ないヒトのことを考えても仕方がない。現実的なことを考えなくては)
独りで、姫の護衛として対処する以上、やれることには限界がある。戴冠式を終えて、彼女が王位についてしまえば、『王国の民』たちは、彼女に手出しができなくなるようであるから、それまで暗殺をしのぎ切るのも、確かに一つの手だが────
(……もうしばらく、様子を見るか。明日には明日の風が、吹くかもしれない。何か事態に進展が、あるかもしれないのだから……)
ハヤブサはそう考えながら、自身も身体を休めることにした。これからのことを考えるならば、本当に────自分が疲労で倒れるわけにはいかないのだから。
「……………」
周りに殺気がないことを確認しながら、ハヤブサは、浅い眠りについていた。
第3章
その日も姫は、朝から多忙を極めていた。
朝食に、やはり毒が入れられていると、ハヤブサは見て取ると、彼は姫を強引に市場の『視察』へと連れ出していた。
もちろん、彼女に朝食をとらせることと、自身の食料を仕入れることを、目的としている。
あまり時間がない中で行われた『視察』は、当然あわただしいものとなった。
「おじさん! また今度ね!」
「もう行くのかい? もっとゆっくりしていけば……!」
「ごめんなさい! 時間がないの~!」
そう言いながら、彼女は脱兎のごとく、店の前から走り去っていく。その後ろから姫に寄り添うようについていった黒い影が、店の商品の半分以上を持って行っていたりして、それに見合う代金を、屋台の上においていたりするのだが、店主はその事実に気づくのに、少し時間がかかっていた。
「ハヤブサ様……! むちゃくちゃです! もう少しゆっくりしてはいけませんか!?」
「何を言う! むちゃくちゃなのは、お前のスケジュールの方だろう! 何だ、あの過密な予定は!!」
正式な『朝食』が終わったときに、カライ内大臣の使いの者がやってきて、彼女に今日の予定を告げていったのだが、そのあまりの過密さに、ハヤブサの方が目を回しそうになっていた。
「まず、9時より、朝の執務を執り行っていただきます」
と、まあ、ここまでは普通だった。
「そのあと、9時半より日本のテレビ局の取材、10時より某国の外務大臣との謁見、議会への出席、そのあと、交換留学生との謁見、そのまま昼食。13時30分より商業、漁業、農業の代表者会議への出席。小学校への視察、午後の執務、謁見20件、そののち夕食、と、なっております」
(ほぼ秒単位だな………)
ハヤブサが頭を抱えている横で、ナディール姫もあんぐりと口を開けていた。
「ええっ!? そんなに予定があるの!?」
使いに来た者は、ちらりとナディール姫に視線を走らせると、ゴホン、と、咳払いをした。
「内大臣に言わせると、これでも予定を削られたそうにございます」
「……………!」
「ですから、くれぐれも勝手な行動などはせず─────」
使いの者がそこまで言ったとき、もう目の前にはナディール姫はいなかった。ハヤブサが強引に連れ出していたからである。
「ハ、ハヤブサ様!?」
「お前は、朝食に口をつけていなかったな? また毒を入れられていたのか?」
ナディール姫を抱きかかえながら、問うてくるハヤブサに、姫はあいまいにうなずいた。
「え、ええ、まあ………」
「ともに食事をしていた大后とノゾムの様子は普通だったな。彼らの食事に毒を盛られることはないのか?」
「そうですね………」
ナディール姫は、複雑な表情を浮かべた。
「お義母様とノゾムの食事に、毒を入れられたことはないと思う。もし分かれば、私が止めるから……」
「一つ聞いていいか?」
ハヤブサの問いかけに、ナディール姫は「どうぞ」とうなずいた。
「お前はどうやって、食事に『毒』が入っているかいないか、見分けているんだ?」
「それは、これです」
彼女は胸元から、一つの銀スプーンを取り出す。
「この表面は特殊なもので加工されていて───『毒』が食事の中に入っていたら、反応して変色するようになっているんです」
ほう、と、感心するハヤブサに見せてから、彼女はその銀スプーンを大事そうに胸元にしまった。
「お義母様とノゾムのスプーンにも、同じ物がつかわれています。でも、私のスプーンだけすり替えられていたら困るから、こうして何本かストックを持つようにしているの」
なるほどな、と、ハヤブサはまた感心した。さすがに、自分が護衛に就くまでに、この環境を生き延びてきただけのことはあるな、と、思った。
「どころでハヤブサ様……」
「どうした?」
「私を抱えて走っていますが、これからどちらへ行かれるご予定ですか?」
「市場だ」
ハヤブサはぶっきらぼうに答える。
「朝食は、とった方がいい。執務に差し障るぞ」
「え、でも、交換留学生との謁見を兼ねた昼食会は、たぶん料理が食べられると思うから………」
「俺の、食材の調達も兼ねているんだ」
ナディール姫の反論を、ハヤブサは一言の元に却下した。
「俺の目の前で、空腹で倒れるのは許さん。何が何でも食べてもらうぞ!」
「うそでしょ~~~~~~!?」
悲鳴を上げている間にも、ナディール姫の身体はハヤブサによって強引に、場外へと持ち出されてしまっているのであった。
こうして、現在に至る。
「ハヤブサ様……! もっとゆっくり……!」
「ゆっくり優雅に食っている時間なぞあるか! パンは水と一緒に流し込め! これは栄養の補給だ!!」
「そ、そんなこと言われましても………ゲフッ!」
満足な咀嚼もできず、何度ものどに食事を詰まらせるナディール姫。彼女が市場から自分の部屋に戻ってくる頃には、別の意味で息も絶え絶えになっていた。
「ひ、姫様……。大丈夫ですか……?」
ロゼッタが、顔を引きつらせながら心配してくる。
「大丈夫、だけど………ちょっと待って………」
ロゼッタが近づいて来ようとするのを、手で制する。呼吸をゆっくりと整えてから、顔を上げた。
「顔にレタスがついてますよ」
「!!」
侍従長の指摘に、頬を赤らめながら慌てるナディール姫。頬に手をやると、なるほど確かに、レタスをくっつけてしまっているのが分かった。
「………まったく。姫様は、これから他国のテレビ局の取材を受けるんですよ? 変なところが映らないように、お気をつけくださいますよう」
「わ、分かってるわよ………!」
小さく唇を尖らせるナディール姫。そんな彼女の服装を整えるべく、ロゼッタが周りを忙しく動き回っていた。
「姫様………どこの国のテレビ局の取材を、受けられるのですか?」
ロゼッタの問いに、ちょっと考えてから、ナディール姫は答えた。
「確か………『日本』と、言っていたような……」
「日本? ………聞いたことはあるような気がしますが、どこにあるんでしたっけ……?」
「東洋の島国ですよ。ですが、経済大国で、我が国にとっても大切な交易国です」
ロゼッタの問いに、侍従長がすらすらと答える。
「こうしてマスコミを通して、各国に我が国を知ってもらうことは、大変意義のあることです。ですから、くれぐれも粗相のないように! お願いしますよ! 姫様!!」
ビシッと言い切られる侍従長の言葉に、ナディール姫は「はぁい」と、少し畏まって返事をしていた。
(日本のマスコミは、いい意味でも悪い意味でも、フットワークが軽いよな……)
ハヤブサは姫たちの会話を、部屋の外で聞きながら、やれやれとため息を吐いていた。
そして、この「日本のマスコミの取材」という出来事が、ハヤブサとナディール姫にとって、思わぬ「風」を、呼び込むことになるのであった。
それは、日本のマスコミの取材が、ほぼ終わるときにおこった。
「最後に、お姫様や王子様の方から、何か我々に質問はありませんか?」
それまで、ナディール姫と、ノゾム王子に質問をしながら話を進めていたコメンテーターが、笑顔とでそう聞いてきた。
「何でもいいですよ? 我々の仕事のことでも、日本のことで、何か知りたいことでも………」
「…………………」
それまで、ナディール姫の横で、おとなしく座っていたノゾムが、もじもじとしながらであるが、口を開いた。
「あの…………」
「どうしました? ノゾム王子」
穏やかに問うてくる、男性のコメンテーターの態度に安心したのか、ノゾムはおずおずと口を開いた。
「………この中で、どなたか『ドモン・カッシュ』と、会ったことがある方は……いらっしゃいませんか……?」
「ドモン・カッシュ!?」
少し驚いたような声をコメンテーターがあげると同時に、少し離れたところで、誰かが「ブ─────ッ!!」と、何かを吹き出すような音を上げた。
「!?」
全員が驚いてそちらの方に顔を向けると、覆面を少しずらして、口元をぬぐっている黒い忍者の姿がある。
「……………!」
あまりにも意想外のものを見てしまって、固まるテレビ局のスタッフの面々。
「は、ハヤブサ様……? どうされたんですか……?」
「や……俺のことは、気にしないでくれ………」
そう言って、ハヤブサの姿がすっと消える。
「え………? え………? 姫様………? 今の………?」
「忍者っぽい人が、いたような………?」
「ええ。『忍者様』ですわ」
ナディール姫は、にこやかに答える。
「今のは護衛の方です。故あって、ああいう格好をしてもらっています」
「ああ…………」
姫の言葉に、テレビ局の面々は納得していた。
(『日本のマスコミ』が来るから、サービスしてくれていたんだな……)
(『忍者のコスプレ』かぁ……。よくできていたなぁ……)
各々が、各々の中に、勝手に理由を結論付けて、自己完結してしまったのである。
よくよく考えれば、惜しいことを彼らはしていた。
『龍の忍者』のスクープ映像をとらえる、いい機会であったのに。
「ノゾムは、ドモン・カッシュ様が好きなのよね?」
姫の言葉に、全員が、はっと我に返っていた。黒髪の王子が、はにかみながらもこくん、と頷く。その可愛らしいさまに、テレビ局のスタッフの目は、ノゾムにくぎ付けになっていた。
(やれやれ………)
ハヤブサは物陰で、ほっと胸をなでおろしていた。しかし、いったん動揺してしまった心は、なかなか平静には戻ってはくれなかった。
(しかし……ドモン……。『ドモン・カッシュ』だって?)
思いもかけぬ『知人』の名前─────だが、よくよく考えてみれば、ドモンは結構名の通った「格闘家」である。世界中に『ファン』がいたとしても、別におかしな話ではない。
しかし────
本当に─────
(シュバルツに連絡したい………ッ!)
この衝動を堪えるのに、ハヤブサは必死にならなければならなかった。
弟想いな彼のことだ。
弟の『ファン』がいると聞けば、どれほど喜ぶことだろう。
そして、ノゾムも、ドモンに会えれば喜ぶのは、目に見えてはいるが………
(弟の方には連絡を取りたくない……! 俺が来てほしいのはシュバルツの方なんだ………っ!)
ハヤブサは座り込んで、しくしくと泣き出してしまっていた。
会いたい。
シュバルツに会いたい。
阿呆か、俺は。
彼に会えなくなって────
それほど日が経っているわけでもないのに。
(………何をやっているんだ? あいつは……)
そんなハヤブサの様子を、姫をつけ狙う刺客の一団が見ていた。
(座り込んで泣いているぞ)
(隙だらけだ)
(チャンスだ……! やっちまえ!)
だが当然、泣いていても『龍の忍者』なハヤブサに、刺客たちが敵うはずもなく。
ドンガラガッシャ───ン!!
ハヤブサの機嫌が悪かったがゆえに、その刺客の一団は、かなり乱暴に撃退される羽目に、なってしまったのだった。
「いや~、おかげさまで、いい映像が撮れました。編集して、日本で放送させていただきますね」
「この後の、交換留学生との食事会の様子も、取材させていただきます! よろしくお願いいたします!」
カメラマンの言葉に、ナディール姫は「はい」と頷く。最初からその予定であったので、特に問題もなかった。
その取材映像は、すぐに編集されて、日本の夕方のニュースで紹介された。
ノゾムの「ドモン・カッシュのファンだ」と言う映像は、ニュース番組とは別に、動画投稿サイトに公開されていた。
これは、まったくその取材スタッフの好意からであった。
ノゾムの愛らしさと、忍者が映りこんでいるという、映像的には非常においしい出来だったのだが、ニュース映像としては、残念ながら使いにくい。
そこでスタッフは、姫とノゾムに動画投稿サイトにこの映像を上げることを、提案していた。
「うまくいけば、ドモンさん本人が、映像を見てくれるかもしれませんよ」
その言葉に、ノゾム本人が動画をネットに挙げることを強く望んだ。
王后にも許可を取りに行くと、意外にも許可は、あっさりと下りた。
「ノゾムの顔と名前が世界に広く知られることは、我が国にとってもいいことです。ノゾムは将来、何といっても『王』になる身なのですから───」
こうして、その映像はネットに乗ったのである。
格闘家であるドモンの名と、『忍者』が映りこんだ映像は、日本でちょっとした拡散力を伴っていた。
そしてそれが─────たまたまネットサーフィンをしていた、ドモンの兄であるキョウジ・カッシュの目に留まったのである。
「あれ、これ、ハヤブサじゃない?」
日本の東京で、論文の合間の息抜きをしていたキョウジが、その映像に思わず声を上げていた。
「何っ!?」
それまで、窓際で黄昏ていたシュバルツが、勢いよくキョウジのそばに寄ってくる。
「ほら、これ。ちょっと映像を戻すから、よく見てて」
キョウジが手元のマウスを操作して、シュバルツにその映像を見せる。
王子と姫の後ろに控えていた黒い忍者は、確かに、紛うことなき『リュウ・ハヤブサ』その人の姿であった。
「どこの国の映像なんだ? これは……」
「話から察するに、『ユリノスティ王国』の、王子様とお姫様が映っているみたいだね」
シュバルツの問いに、キョウジが答える。
「ここの王子様が、どうやらドモンのファンみたいで………」
「そうか………。ドモンの………」
ここで兄二人は、しみじみと感慨に浸る。
世界中にドモンのファンがいることは、情報として知っていたが、こうして改めてそのファンの存在に触れると、なんともうれしい気持ちになるものだ。
「それにしてもハヤブサ……。そんなところにいたのか………」
ぽつりとつぶやくシュバルツの言葉に、キョウジが反応する。
「やっぱりハヤブサは……『仕事』に行っているの?」
「ああ……。『しばらく日本を離れる』と、言っていたから………」
「そして、例によって例のごとく、『行先』は聞いていない?」
「そうだ……。『仕事に関係のない第三者は巻き込まない』それが、彼の流儀だからな……」
少し、シュバルツの声のトーンが落ちる。キョウジは思わず、そちらの方を振り向いていた。
「………心配?」
「……………!」
シュバルツは少し、驚いたようにキョウジの方を見たが、すぐに頭を振った。
「いいや………。心配はしていない。ハヤブサは十分『強い』から………」
ただ少し、淋しい、と、シュバルツは感じていた。
そう。
ハヤブサの言い分はわかる。
『プロとして、第三者は巻き込まない』という、その姿勢にも共感できるし、納得もできる。
ただ少し、『淋しい』と、思った。
どんな時でも、『仕事』の時は、こちらを頼りにしてはくれないんて─────
(そんなに、私は頼りない存在なのだろうか……)
違う。
ハヤブサは、決してそんなことは思ってはいない。
ちゃんと頼ってくれている。
必要としてくれている。
でも────
(………まったく、ぜいたくな物思いだよなぁ……。『恋人』として、これ以上ないくらい愛されているのに、まだ、彼に必要とされたがっているだなんて………)
いつの間に、こんな欲張りになってしまっているのだろう、と、シュバルツは軽く自己嫌悪に陥る。その横で、キョウジは映像を見ながら、しきりに首をひねっていた。
「あれ………? 変だな………? 何か………」
「どうした? キョウジ」
シュバルツが問いかけると、キョウジは映像から目を離さずに、答えてきた。
「シュバルツは、この映像の中の『蜘蛛』………見える?」
「蜘蛛?」
素っ頓狂に問い返すシュバルツに、キョウジは頷いていた。
「うん。蜘蛛。女の子の方の肩に………」
「………………」
シュバルツは、キョウジに言われるままに目を凝らして映像を見るが、蜘蛛を見つけることはできなかった。
「………何もいないぞ?」
「ええっ!? そんなはずは………!」
びっくりするキョウジに、シュバルツはやれやれ、と、ため息を吐いた。
「『蜘蛛』など────どこにでもいる生き物だし、そんなに大騒ぎするほどの物でもないだろう、キョウジ。肩に乗った蜘蛛ぐらい、ハヤブサが何とかするだろうし……」
「そんな生易しいものじゃないんだよ! シュバルツ!! ものすごく大きい蜘蛛が────!」
そこまで叫んだキョウジが、ここではっ、と気がついた。
「………あれ? もしかして、この『蜘蛛』が見えているのって、私だけ………?」
「………………」
「………………」
シュバルツとキョウジは、しばし互いにじっと見つめ合う。
そして、先に口を開いたのはやはり、キョウジの方であった。
「もう一度、確認するけど、シュバルツ………」
「ああ」
「シュバルツに、あの『蜘蛛』は、見えていないんだよな………?」
「ああ………」
シュバルツは淡々と頷く。
「私には、あの姫君は、普通の状態に見えている………」
「……………」
「……………」
再び部屋に、沈黙が訪れる。
「ちなみに、キョウジ」
「何? シュバルツ」
「『蜘蛛』って……どういう風に、見えているんだ?」
「うん………」
キョウジは少し考えてから、手元に鉛筆とメモ帳を取り寄せた。
「口で説明するよりも、見てもらった方が分かりやすいと思うから、ここに図を描くね」
そう言いながら、キョウジはすらすらと女性の身体をメモ用紙に書いていく。さすがに、医療の心得があるだけはあって、その絵はさながらカルテに書かれる人体図のようだ。
「これが、あの映像に映っている彼女の身体だとしたら、その『蜘蛛』は、彼女の身体にこう………」
そう言って、キョウジはその絵に、大きな蜘蛛を一匹、彼女の背に背負われているように書き込む。
「…………! そんなに大きな蜘蛛がいるのか?」
驚くシュバルツに、キョウジは頷いた。
「うん。なのに、周りの人たちが、何も反応していないのが不思議で────」
「………………」
「………やっぱり、ハヤブサにも見えていないんだよね……。これは、私の目の方が、おかしいのか………な………?」
「……………!」
(違う。キョウジはこんなことで『噓』を言うような人間ではない)
実はキョウジは、死んで『霊体』として彷徨ったり、死にかけたりした経験があるせいで、『霊感』のようなものが、変に身についてしまっているようであった。なので時折、常人には見えないものを、見てしまったりするときがある。
それが、あの姫君の身に起こっている『異常事態』を、『蜘蛛』という形を通して、キョウジに知らせているのだとしたら? そして、ハヤブサが、「それに気づいていない」のだとしたら……?
「キョウジ……」
「何? シュバルツ」
問い返すキョウジに、シュバルツは、まっすぐ答えた。
「………ユリノスティ王国に、行ってもいいか……?」
「……………!」
「ハヤブサのことを信用していないわけじゃないんだ……! ただ、心配で……」
「シュバルツ………」
そう。ハヤブサは十分『強い』
自分の手助けなどなくとも、彼の力量ならば、たいていのことは乗り越えられるということを、シュバルツは知っていた。
だから、自分の心配は、彼からしてみれば『余計なおせっかい』に当たるのかもしれない。
蜘蛛のことも、ハヤブサは察知していて、敢えて気づいていないふりをしているだけなのかもしれない。
『仕事』のこととなると、彼は第三者の介入を嫌がっている。だから、自分がそこへ向かって行って、口を出したら──────最悪、嫌われてしまうかもしれないが……。
(嫌われてもいい。行こう)
シュバルツは、そう断を下していた。
嫌われる恐怖よりも、ハヤブサを心配する『ココロ』の方が、彼の中では勝ってしまっていたのだ。
「………………」
キョウジはシュバルツをじっと見つめる。
深く、静かなまなざしをしているシュバルツ。彼の決意は固いのだと知る。
「わかった。行っておいで」
だからキョウジはそう言った。止めても無駄だと悟っていたから。
それにあの『蜘蛛』からは、かなり不吉なものをキョウジは感じ取っていた。
それをハヤブサに知らせに行く、ということは、悪いことではないはずなのだから。
「キョウジ………」
佇むシュバルツに、キョウジはにこっと微笑みかける。
「ついでに、あのノゾム王子様の話も聞いてきてあげなよ。ドモンに会いたいのなら、私たちの方で、それは手配してあげられるかもしれないし」
「……………!」
キョウジの言葉に、シュバルツははっと気づく。
(そうか………! 口実………!)
何も、ハヤブサに忠告に行くだけを目的にする必要はない。
『ドモンの兄』として、あの国に入るだけの『口実』を、自分はすでに持っているのだから。
「わかった。ありがとう、キョウジ」
シュバルツの言葉に、キョウジはうん、と頷く。
それを見てからシュバルツは、キョウジの眼前からフッと消えた。彼がそのまま、目的地に向かったのだと、キョウジは悟っていた。
(シュバルツ……。どうか、気を付けて………)
キョウジは窓を開けて、空を見る。重い雲が垂れ込めてた。
(一雨来るかもしれない)
キョウジは少し不安な心を抱えながら、シュバルツが去っていったと思われる方向を見つめていた。
それから2、3日が過ぎた。
ハヤブサはナディール姫を護衛し続けていたが、それは、どちらかと言えば、防御の方に重きを置いた戦いになっていた。
相変わらず、姫を狙う刺客たちは引けを切らないし、食事にも毒を入れられ続けている。
(このままでは、埒が明かないな……。姫を狙ってきているルートを、一つでも大元からつぶしていかないと────)
そう考えたハヤブサは、一度、刺客の一人を捕らえて、ナディール姫の前に引っ立てたことがあった。
「こいつから、依頼主が誰か聞きだしてやろうか?」
ハヤブサはそう言ったのだが、姫の方が首を横に振った。
「それは必要ありません。その人は解放してください」
「………………!」
ハヤブサは驚いて彼女を見る。ナディール姫は、静かなまなざしでハヤブサとその刺客を見つめていた。
静かだが、強い意志を感じる眼差し。
彼女を説得することは、無駄だと知れた。
「…………だ、そうだ。運がよかったな」
やれやれ、と、ため息を吐きながら、ハヤブサは刺客を解放する。刺客は這う這うの体で逃げていった。
「………どういうつもりだ?」
刺客が完全に逃げたのを確認してから、ハヤブサはナディール姫に問いかけた。
「いつまでも防戦一方では、埒が明かないぞ。お前を狙う者があるのなら、一つでも潰すことを考えた方がいい」
「ハヤブサ様は、犯人を特定するべきだ、と、言うのですか?」
「当然だろう」
ハヤブサは、ナディール姫にそう問い返されたことに、少し驚いていた。
「お前に害意を持つ者を、身近に置いておいて、いいのか?」
「………………」
ナディール姫は、少し考え込むように沈黙したが、やがて、顔を上げた。
「それでも、だめです。自分の身を護るために、誰かを処罰するようなことをしたら、絶対にダメです」
「────!?」
「だめです。きっと一人でも誰かを自分の身を護るためだけに処罰してしまえば、私は次々と、沢山の人を罰していかなくてはならなくなる」
「………………!」
「それは、血塗られた道です。血塗られた玉座です。そんな王が、どうして国を平安に導くことができましょう。誰が、そのあとをついてきてくれる、というのですか?」
「それはそうかもしれないが────」
ハヤブサは、少し困惑してしまう。
彼女の言い分も分かるが、それは、理想論に過ぎる、というものではないだろうか。
現実問題として、命を狙ってくるほどに、向こうは敵意をむき出しにしているのだ。それにはそれなりの対処をしなければ、国は一つにまとまらないし、守ることもできないのではないか、と、ハヤブサは考えてしまうのだ。
「………ごめんなさい。私の言っていることは、甘すぎると、十分に自覚しています………」
そういって、ナディール姫は哀しそうに瞳を伏せた。
「それでも、私は─────」
「………分かった」
ハヤブサは、一つ大きなため息を吐いた。
「ならば俺は、お前の望み通り、降りかかる火の粉を払うことに徹しよう。それでいいな?」
「………! ハヤブサ様……!」
驚いたように顔を上げた姫は、すぐにハヤブサに謝ってきた。
「すみません……! ハヤブサ様には、ご負担と、迷惑を………!」
「良い、気にするな。俺は『仕事』をしているだけだ」
姫の詫びを、やんわりと拒否する。
(覚悟はあるようだが……実際に、そのような局面で、そのような決断をしたことは、まだないのだろうな………)
そう感じてハヤブサは嘆息する。
犯人を探し出すことを、かたくなに拒否する彼女。それはまるで、その犯人と向き合うことを、恐れているようにも見えた。
気持ちはわかる。
信じていた人間、愛している人たちから裏切られる事によって受ける傷は、決して小さいものではないのだから。
だが、向き合わなければ。
いずれは対峙しなければ、物事は前に進んではいかない。
彼女が『王』としての資質を問われるのは、まさにその時だろう、と、ハヤブサは思った。
「……すまなかったな。寝る前に。明日も早いのだろう? もう寝ろ」
そういって、ハヤブサが踵を返そうとするのを、姫の小さな声が引き留めた。
「ハヤブサ様………」
「ん?」
その声にハヤブサが振り返ると、ベットの上で小さく座り込んでいる、ナディール姫の姿があった。
「ハヤブサ様は………」
「どうした?」
「私が王位に就くまでは、そばにいてくださるのですよね……? 急に、いなくなられたり、しませんよね………?」
姫が、言わんとしていることを、咄嗟に測りかねて、ハヤブサは小首をかしげる。ナディール姫の消え入りそうな声は、なおも続いた。
「今までも、ハヤブサ様のような方はいたのです。命を狙われだしてから、私の護衛についてくださった方が、何人か………」
「………………」
「でも…………皆、すぐにいなくなってしまって………」
そう。
ハヤブサが来るまでに、姫の『護衛』となった人物が、いないわけではなかった。
(姫様! お守りいたします!)
そう言って護衛を名乗り出てくれた兵士や戦士たちが、何人かいた。
だが、それらの人々は皆、急に彼女の前から姿を消した。
身内に不幸があり、城勤めが困難になったり、突然、理由もなく、職をやめていった者もいた。
ひどい場合には、行方不明になり、何日か後に、遺体で発見されたこともある。
「……………!」
息をのむハヤブサの前で、ナディール姫は顔を手で覆っていた。
「………もう、あんなふうに、人がいなくなるのはいや……! 私を護ろうとしてくれたばかりに、誰かが不幸になったり、命を落としてしまったりするのは……!」
「………………」
「お願いです……! 私の前から姿を消さないでください……! 貴方やイガールまで、いなくなってしまったら、私は─────!」
(また、イガール殿の名前が出たな)
彼女と話していると、時折出てくるイガール将軍の名前。
たまにしか会う機会がないが、会ったときは穏やかに微笑みあい、そして、去っていくイガールの後姿を、いつまでも目で追っている彼女。
『護衛』として、彼女を四六時中見ているからこそ、気づいてしまう事がある。
それを彼女に自覚させることが、いいことなのか悪いことなのかは、ハヤブサには分からない。
彼女の『恋路』に、自分がどれだけ手助けしてやれるかどうかも、分からない。
だが、問いかけずにはいられなかった。
それは、自分も同じように、誰かを恋い慕う気持ちを、抱え込んでいるせいであるからかも知れなかった。
「姫………お前は………」
ハヤブサは一瞬ためらったが、言葉を続けた。
「イガール殿のことが………好きなのか?」
「─────!」
瞬間、びくっと身をこわばらせ、固まってしまう姫。
しかし、すぐにその面に、柔らかい笑みを浮かべた。
「ええ。好きですよ」
「………………!」
あまりにもあっさり認められたことに、ハヤブサの方が逆に驚いてしまう。だが姫は、その柔らかい笑みのまま、言葉を続けた。
「好きだからこそ、彼には幸せになってもらいたい……。そう、願っています……」
そう言ってほほ笑む姫のまなざしの儚さが─────どこかの誰かを彷彿とさせて、ハヤブサの心を、ザワ、と、波立たせていた。
─────ハヤブサ……。私はいつだって願っている……。お前の『幸せ』を………。
そう言って、優しく微笑むあのヒトも、同じような眼差しをしてはいなかっただろうか。
ただ、相手の幸せのみを純粋に願うヒト。
そのヒトは、幸せの『輪』の中に、かたくなに『自分』を入れようとはしなかった。
─────私はいいんだ……。私には、その『資格』がないから……。
(『資格がない』ってなんだよ)
腹が立つから、その身体を何度も乱暴に抱いた。
俺の『幸せ』には、絶対的にお前が必要なのだと───彼に分かってほしかったから。
刻み付けるのに
彼は相変わらず、そんな笑みを浮かべるときがあるから────
何故だ。
姫から、彼と同じような匂いを感じる。
感じるがゆえに、少し苛立った。
「お前は………」
口を開いてから、ハヤブサは必死に己に自制をかけた。
馬鹿止めろ
これ以上口出ししてどうする。
彼女の人生に、俺は責任をとれないのに────
「………………」
ハヤブサは大きくため息を吐く。
そうだ、落ち着け。
これ以上は、本当に
『余計なおせっかい』になってしまうのだから。
「ハヤブサ様………?」
沈黙したハヤブサを心配したのか、姫が怪訝そうに声をかけてきた。
「すまん、変なことを聞いた………」
それに対して、姫はフルフル、と、首を横に振る。
「すみません……。私こそ、変なことを言ってしまって………」
(変なこと?)
ハヤブサは少し考えてから、姫と直前に交わした会話を思い出す。
「消えないでほしい」と言われた。彼女にしては珍しい、愚痴に近いもの。
(別に変ではないが………)
彼女だって人間だ。弱音や愚痴の一つや二つ、出ることもあるだろう。
「気にするな」
そう言って、ハヤブサは彼女の部屋から出ていく。しばらくすると、彼女の部屋からすすり泣く声が聞こえてきた。
(参ったな……)
ハヤブサはため息を吐きながら、その声を聴いていた。
姫は、皆の前では明るく闊達に振る舞う姫であるが、夜、独りになると違う。
暗がりの中、独りで涙を流す時が、間々あった。
泣き声を聞くのは苦手だ。こちらの胸まで苦しくなるから。
何とかしてあげたいと願うが、ここで自分が抱きしめに行くわけにはいかない。自分にはもう、抱きしめるべき人がいるから。
それに、姫が『抱きしめてほしい』と願っているのも、俺ではないだろう。
彼女が本当に、自分のそばにいてほしい、と、願っている人は─────
「……………」
(肝心の、向こうの気持ちがいまいちわからんのだよなぁ……。本当に、あの男は情けないというか、押しが弱いというのか………)
ハヤブサの頭に浮かぶのは、もちろん騎士隊長であるイガールの姿。
イガール隊長の後姿を目で追っている、ナディール姫の姿。
しかし、姫もイガールも、忙しいのもあるが、お互いに会うこともほんのひと時で、会話を交わすこともあまりない。しかもイガールの方は、割とどうでもいいような、よくないような雑用に、常に振り回されている。あれでは、ナディール姫の支えになるには、役不足すぎるのではないかと感じてしまうのだ。
彼女がいる立場は、責任も重く、大きい。彼女に降りかかってくるすべてに、今のように「はいはい」と言っていたら、それこそ潰されてしまうのが目に見えている。それが分かっているから、ナディール姫も、一歩、彼に対して踏み込めないのではあるまいか。
(かといって、イガールの方の気持ちを、確かめるにしてもなぁ………)
ハヤブサはここで、頭を抱えてしまう。
姫の予定は多忙を極め、とてもイガールとゆっくり話す暇など取れない。
しかも、姫自身があちこちから狙われてもいるせいで、ハヤブサはひと時たりとも姫のそばから離れられない状況になっている。こんな、身動きの取れない状態では、イガールの気持ちを確かめに行くことにまで、到底手が回らなかった。
(ああ……! 真面目にもう一人、自分が欲しい………っ!)
ハヤブサはそう感じて、深くため息を吐く。
やはり、この状況、一人ですべてを対処しようとしたら限界がある。
もう一人、仲間が欲しい。
もう一人、信頼できる仲間がいれば────今の状況から、一歩でも二歩でも踏み出していけるだろうに。姫をつけ狙う敵勢力に対しても、防戦一方にならなくて済むのに。
(シュバルツに連絡したい………っ!)
強くそう思ってしまって、ハヤブサはもう何度、転がりまわったか分からない。
考えれば考えるほど、有能な諜報活動能力を持った、愛おしい俺の恋人。喉から手が出るほど、彼の存在が欲しかった。
しかし────
(ダメだ……! 彼らに迷惑をかけるわけには………!)
これは、自分が請け負ったミッションなのだ。ならば、対処すべきなのは自分なのであって、彼らにまで粉をかけるのは間違っている。彼らには彼らの、平和な日常を営む権利があるのだ。それを、自分の都合で乱すわけにはいかない。
それに、彼らに頼る習慣をつけるのは、きっとよくない。
彼らに頼ることを覚えてしまったら、自分は仕事を請け負うたびに、彼らを巻き込んでしまう事になる。そうなってくると本当に、彼らから平和に生きる権利を、自分が取り上げてしまう事になりかねないのだ。
だめだ。
自分が望むのは、キョウジの幸せであり、シュバルツの幸せなのだ。
それを手助けこそすれ─────阻む存在にはなりたくなかった。
それに、よく考えろ、リュウ・ハヤブサ。
仕事場にシュバルツが来る、ということは、今こうして眠ろうとする自分の隣に、シュバルツがいるわけで。
「…………………」
自分の横で、穏やかに眠る、愛おしいヒト。
長いまつげ。
整った顔立ち。
薄く開いた唇から漏れる、甘やかな寝息。
「ん………」
自分の前に、無防備に投げ出される、きっちりと服を着こんだ美しい肢体が───
(……どこからでも、乱してくれ……。ハヤブサ………)
と、言われているようで
ああああああ!! もう!! 辛抱たまらんというか仕事中だろうがお前は──────!!!
と、自分で自分に突っ込みを入れる事態になりかねないので、やはり、シュバルツに連絡を入れるのは、よくないような気がした。
(平和になったら、連絡しよう)
ハヤブサはそう決意を固めて、身体を休める決心をする。
そう。
この国のごたごたが収まって、平和になれば、シュバルツと二人、この国をゆっくり観光すればいい。
「ドモン・カッシュに会いたい」と、願うノゾムの気持ちにも、きっと答えてあげられるだろう。
「………………」
まだ、姫のすすり泣く声が聞こえてくる。彼女の心が、未だ落ち着きを取り戻さないのだろう。
泣くことが必要ならば、存分に泣けばいい、と、ハヤブサは思う。それで、彼女が明日、また、皆のために笑うことができるのであるならば。
(だが………やはり、きついな………)
孤独に塗れる彼女の涙─────早く、掬い取ってくれる者が、現れればいいのに。
そう願いながら、ハヤブサもまた、短い眠りに落ちるのだった。
その日も朝から多忙を極めた。
相変わらず、目が回るほどの過密スケジュール。そんな中でも姫の非常食の確保だけは、ハヤブサは何とか成功させていた。
相変わらず、食事に毒は入れられ続けているし、刺客は引けも切らない。
大后とその一派と思われる者たちから、嫌味を言われたり、嫌がらせに近い行為をされたもりしている。
(なるほど、並みの神経の者であれば、参ってしまうかもしれんな………)
そう感じて、ハヤブサは苦笑する。
しかし、大后やその他の者たちからの嫌味など、ハヤブサからしてみればカエルの鳴き声のようなものなので、特に頓着するものでもない。それよりも気の毒なのは、大后以外の者たちが、自分に嫌味を言いに来るときである。皆、自分に対して気の毒なほど腰が引けているので、失笑を禁じ得ない。
こういう滑稽な風景も、イガールと一騎打ちをして、こちらの腕を見せつける機会を得た、その賜物だろうか。
(そんなにいやなら、このような命令従わなければいいのに)
へっぴり腰な者たちに呆れかえるが、これが宮仕えの悲哀という物なのだろうか。
迎合する気持ちも、胡麻をする気持ちも理解できないから、同情する気にもなれないが。
「ハヤブサ様………大丈夫ですか?」
「平気だ」
ハヤブサはぶっきらぼうに答える。こんなこと─────姫に気を遣わせるほどのことでもない。
それよりも、今日も姫を狙う者たちに関する情報の進展がない。こちらの方が大問題だ。
いつまでも、このままでいいはずはないのだが。
「……………」
結局、有効な打開策を見出すこともできないままに、その日の夕食を迎えた。
相変わらず遅くなった夕食の時間。大后とノゾムの姿は既に無く、食堂には、彼女の分の食事だけが並べられていた。その脇では給仕が、礼に則って頭を下げて、姫を迎えている。
(また、給仕の人間が違うな)
これには、ハヤブサは少し前から気付いていた。
なんといっても、姫には毒入りの食事が出され続けているのだ。もし、姫の毒殺が成功した場合、真っ先に疑われるのが給仕であるから、尻尾きりの役割が与えられているのだろう。したがって、給仕から毒殺の犯人を探し出そうとしても、それは徒労に終わる、ということになってしまう。
ハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐く。
どういうからくりをしているのかは知らないが、よくもまあとっかえひっかえ、次々と給仕の人間を変えられるものだ、と、感心してしまう。
(それにしても、今日の給仕の奴は、やけに背が高いな)
ハヤブサは、ナディール姫のそばに控える給仕を見ながら、ふっと感慨にふける。
ちょうど、俺の愛おしいヒトも
あれぐらいの背の高さで─────
………………………………
────────!?
信じがたい思いで、その給仕をまじまじと見つめる。
2度3度と見つめなおして、ある確信を得たハヤブサは、つかつかとその給仕のそばに歩み寄った。
「おい」
「な、何ですか?」
いきなり黒の忍者に睨み据えられるように声をかけられた給仕は、かなり驚いたように身を固くしている。それには構わず、ハヤブサはその腕を乱暴につかんだ。
「あっ!」
「は、ハヤブサ様!?」
ナディール姫もかなり驚いて、二人の様子を見ている。ハヤブサはそれには構わず、給仕の手を逃げられないように、がっちりと捕まえる。そのまま、顎のあたりに手をかけた。
「お前………『シュバルツ』か………?」
まじまじと、その顔を見つめると、給仕は、ふっと相好を崩したような笑みを見せた。
「や、やあ………。ハヤブサ………」
そう言いながら、給仕は己の顔の皮をバリバリとはがす。すると下から、ハヤブサにとってはなじみの、黒髪に黒目の、東洋人の顔立ちをした青年が現れた。
「………………!」
驚くナディール姫とハヤブサに向かって、「シュバルツ」と呼ばれた青年は、人懐こい笑みを見せる。
「なんでばれた? しっかり変装してきたつもりでいたのに………!」
「ばれいでか!!」
ハヤブサは思わず大声を張り上げていた。
「お前……! 俺をなめているのか!? その程度の変装で、俺の目をごまかせるとでも思っていたのか!!」
「いや、ごまかせるとは思っていなかったけどな……。ちょっとばれるのが早かったなと……」
「何の用だ!? 何しにここに来たんだ!!」
ハヤブサの殺気立った怒鳴り声に、しかしシュバルツの方も怯むことなくあっけらかんと答える。
「や、ちょっと、短期のバイトをしに」
「バイト?」
目をぱちくりとさせるハヤブサに、シュバルツは頷いた。
「そうそう、バイト。ここの給仕に雇われたんだ。ちょうど人を募集していたみたいだったから─────」
「バイトって………こんなところにまで、わざわざ出稼ぎにきたのか?」
しばらく目をしばたたかせていたハヤブサであるが、やがてその面に、ふっと笑みを浮かべた。
「何だ、そんなに食うに困っているなら、お前が働かずとも、俺がお前を隅から隅まで責任をもって養って」
「余計なお世話だ!!」
シュバルツの背負い投げが、ハヤブサにきれいに決まっていた。
「どうしたんですか!? 怒鳴り声が────!」
あまりの大音に、警備兵が駆け込んでくる。
「何でもない! 大丈夫だ!」
ハヤブサは憮然と答え、シュバルツはいつの間にか、元の給仕の格好に戻っている。ものすごい早業だ。
「……また刺客ですか?」
呆れたように言う警備兵に、ハヤブサは「そんなところだ」と、返す。警備兵はやれやれ、と、深い溜息を吐いた。
「何か我々に出来ることがあれば、遠慮なく仰ってください!」
兵士はそう言って敬礼して持ち場に戻る。場が落ち着いたのを確認してから、ナディール姫は口を開いた。
「あ、あの………こちらの方は…………?」
そう言って姫は、ハヤブサの方に振り向く。
「ああ………こいつは『シュバルツ・ブルーダー』と言って、俺のこいび」
バキャッ! と、シュバルツがハヤブサを殴り倒した。
「………友人です。ハヤブサと同じ、忍者をやってます」
「痛い!!」
がばっと跳ね起きるハヤブサを、シュバルツはジト目でにらみつける。
「阿呆なことをお前が言うからだろうが! 自業自得だ!」
「うううう………。シュバルツが冷たい…………」
「え…………えっと…………」
ナディール姫は、かなり戸惑い気味になってしまう。何故なら、ハヤブサの様子が、いつもと全然違うからだ。
「忍者様………ですか。ハヤブサ様のご友人………ですか?」
目をしばたたかせるナディール姫に、シュバルツはにこっと微笑みかけた。
(毒は入っていないよ)
「……………!」
シュバルツは小声でそう言って、給仕の仕事に戻っていく。これにはナディール姫も、ハヤブサも驚いた。
「……………」
半信半疑で、ナディール姫は、銀スプーンをスープにつけてみる。スプーンの色は、変色しなかった。
「………………!」
姫は、恐る恐るスープを口に含む。
(美味しい………!)
懐かしい味がした。
シェフのスープの味。
本当に、久しぶりだと、思った。
「おい、お前、どういうつもりだ? いったいどうしてここに来た?」
給仕として、壁際に控えるシュバルツのそばに歩み寄って、ハヤブサは小声で話しかける。シュバルツは軽く笑うと、同じく小声で話し出した。
「ああ………。ここの王子の『ドモンに会いたい』って言っていた動画を、キョウジが見つけて………」
「─────!」
「あれにお前も一瞬映っただろう? それで、お前がここにいるってわかって………」
「俺を追ってきてくれたのか!?」
ハヤブサの顔が、ぱっと輝く。シュバルツは苦笑した。
「追ってきた、と、言うか………伝言がある、というか………」
「何だ。淋しいなら淋しいと言ってくれればすぐにでも────いてっ!!」
シュバルツに思いっきり足を踏みつけられて、ハヤブサは小さく悲鳴を上げた。
「人の話を聞け!! 仕事中だろうが!!」
「そうでした………」
涙目になるハヤブサをしり目に、シュバルツは姫に次の食事を勧める。ナディール姫は、少し銀スプーンをつけると、また、食べ始めた。
「そうだ、シュバルツ」
再び壁際に来たシュバルツに、ハヤブサは声をかけた。
「お前………姫の料理の『毒』に気が付いたのか?」
「………! やっぱり常習的に『毒』が入れられていたのか?」
シュバルツにそう問い返されたことに、ハヤブサは少し驚く。だが、気を取り直して頷いた。
「ああ。姫は命を狙われている。俺は、姫の『ボディーガード』として、ここに雇われたんだ」
(そうか………! それが今回のハヤブサの『仕事』………!)
シュバルツはここで初めて、ハヤブサのミッションを理解する。
ハヤブサからしてみれば、一番の機密事項をあっさりシュバルツにしゃべっていることになるのだが、そんなことにも気づかずに、シュバルツの話に食いついていた。姫の『毒殺』をもくろむ者の手掛かりが掴めるかもしれないのだ。なりふりを構ってなどいられなかった。
「どうして────『毒』に気が付いたんだ?」
「いや、話せば長いような、短いような話になるんだけどな?」
シュバルツは、少し苦笑しながら話し出す。
あの動画から、ハヤブサがユリノスティ王国の城にいる、と、判明してから、その王国に向かったシュバルツ。
(普通に姿を消して潜入してもいいが、何か城に、探りを入れる方法はないものか……)
そう思案しながら歩いていたシュバルツの目に、『給仕募集中』の張り紙が飛び込んできた。
「城の隅っこで、皿洗いでもさせてもらいながら、城内を探ってもいいか、と、考えて面接に行ったら、すぐに採用されて────」
割り当てられた仕事が、皿洗いでも掃除でもなく、いきなり『ナディール姫の給仕』だった。
「……………!」
「こんなのすぐに、『おかしい』って思うだろう? ぺーぺーの新人が、唐突に『王女様の給仕』だなんて………! ふつうは王族に失礼がないように、ベテランの給仕を使うものではないのか?」
「確かに………」
ハヤブサは苦い顔をする。
だが、毒殺を目論んでいる者たちからしてみれば、ベテランの給仕や、自分たちの縁故の者など使いにくいだろう。どのようにでも扱える、『新入り』にやらせるには、確かにうってつけの『仕事』だ。
「厨房の雰囲気も、何かおかしかったな……。私にこの仕事が振り分けられたと皆が知ると、『今度のは何日持つかな?』とか、『せいぜいがんばれよ!』とか、何か変な言葉をかけられたりしたし───」
「ほう…………」
やけに低い声が響いたので、シュバルツがぎょっと顔を上げる。すると、ひどく殺気立ったハヤブサの姿がそこにあった。
「誰だ、お前にそんなことを言ったのは」
「や、私のことはどうでもいいから」
シュバルツは必死にハヤブサを宥める。このままだと彼が、厨房に乗り込んでいって、そこにいる人間を、片っ端から締め上げる可能性が出てきた。
「それで、一応簡単な研修をしてから、この仕事に就いたんだけど、仮にも『姫』に食事を出すのに、『毒見役』もいなかったから───」
不審に思ったシュバルツが、食事の『毒見』をすると、案の定、致死量の『毒』が、その中に入っていた。
「……………!」
「だから、その食事は全部捨てて、中身を変えてから、持ってきたっていうわけさ」
そう言って、シュバルツは軽く笑う。ハヤブサは、ただただ恋人の慧眼に、感心するほかなかった。
「食事の中身を変えていること……気づかれているのか?」
ハヤブサの質問に、シュバルツは少し考え込んだ。
「今のところ気づかれてはいないとは思うが………『姫が食べた』という時点で……ばれるだろうな………」
「………………」
ハヤブサが少し険しい顔をして、黙り込む。その向こうで、ナディール姫が、『正式な夕食』を、久しぶりに完食していた。
「ありがとうございました……! ええと、シュバルツ様………でしたっけ? 久しぶりのシェフの食事、おいしかったです」
「どういたしまして」
姫の言葉に、シュバルツはにこやかに答える。ナディール姫は椅子から立ち上がると、優雅に一礼をした。
「今日の食事、『大変結構でした』と、シェフにお伝えください」
「かしこまりました」
シュバルツも、礼に則り頭を下げる。そのままナディール姫は退出をし、後には食器を片付ける、シュバルツ一人が部屋に残されていた。
部屋から出て、廊下を少し歩いたところで、姫はハヤブサに呼び止められた。
「姫、この後の予定は、特に何もなかったな?」
「ええ……。今日はもう、あとは部屋に帰って休むだけです。でも、どうされたのですか?」
少し、小首をかしげるナディール姫に、ハヤブサはにやりと笑いかけた。
「シュバルツの後をつけてみるか?」
「えっ?」
「たぶん………面白いものが見られるぞ?」
「面白いもの………ですか?」
面白いものとは何だろう、と、ナディール姫は考えてみるが、皆目見当もつかない。そうしている間に、テーブルの上を片付け終わったシュバルツが、サービスワゴンを押しながら、廊下に出てくる。
(ついてこい)
そんなシュバルツを見ながら、ハヤブサが無言で手招きをする。ナディール姫も、特に反対する理由もなかったので、大人しく従っていた。
(どうせ今日も、あの姫はディナーを食べないだろう)
厨房で、給仕が帰ってくるのを待ちながら、コックであるイワニコフは、かなりの苛立ちを感じていた。
(くそ……っ! 忌々しい………! なんて勘のいい娘なんだ。あいつがさっさと毒を呷って、死んでくれりゃあ、こっちだって毎回毎回、こんなややこしい物思いをしなくて済むッてぇのに………!)
この不健全な苛立ちは、彼の中では処理しきれず、結果、周りへの『八つ当たり』となって、表に出てくる。主にその犠牲者となるのは、新しく入ってきた給仕であった。
サービスワゴンの上に、そのまま帰ってくる姫の食事。それを見て、「お前の給仕の仕方が悪かったから、姫様は食べなかったんだ!!」と、有無を言わさず散々打ち据えてやるのが、彼の中では日課となっていた。
新人の給仕は、たいてい抵抗もできずに、こちらのされるがままに、暴力を受け入れるのが常だ。一方的に相手を蹂躙できる環境に、イワニコフはひそかな快楽を覚えつつあった。
(新しく入った給仕は、背ばかりが高くて、ヒョロヒョロした奴だったな……。果たして俺様の剛腕を、何発耐えられるかな……?)
知らず、ほの暗い笑いがイワニコフの面に現れる。同僚や、ほかの給仕たちは、そんな彼をかなり遠巻きにして様子を見ていた。うっかり彼の理不尽な八つ当たりのとばっちりを食らうと、ろくなことにならない。新人一人が犠牲になれば、自分たちの平穏は守られるのだ。そう思えば、あの新人を見殺しにすることなど────彼らにとっては容易いことだった。
そんな不穏な空気が流れている厨房に、その事態を承知しているのかいないのか────シュバルツの変装した青年が、鼻歌を歌いながらサービスワゴンを押して入ってくる。そのまま彼は、食器を洗い場の方に運んでいこうとしたのだが、その前に、イワニコフの小太りな身体が立ちふさがった。
「おい」
「何ですか?」
きょとん、としながら、その青年は立ち止まる。イワニコフはあたりを睥睨するように身体を揺らしながら、青年に問いかけてきた。
「姫様は、食事をちゃんと食べてくださったんだろうな……!」
いえ、召し上がってはくださいませんでした、というのが、今までの流れだった。
しかし、この日は違った。
青年は、その面ににこっと人懐っこい笑みを浮かべると、穏やかに答えた。
「ええ。食べてくださいましたよ」
「─────!?」
ぎょっと、驚いてイワニコフがサービスワゴンの方を見ると、確かに空の食器が並べられていた。
「姫様から『大変おいしかったです。シェフによろしくお伝えください』と、伝言を承ってまいりました」
「……………!」
どよ、と、厨房の中の空気がざわめく。
(あの新人、姫様に料理を食べさせたのか……)
(すごいな……。どういう魔法を使ったんだ……)
もちろん、その称賛の言葉は口には出されない。イワニコフの八つ当たりが、こちらに向かってくるのが、目に見えているからだ。
しばらく呆けたように、あらぬ方向を見つめていたイワニコフであるが、はっと我に返ると、シュバルツに詰め寄ってきた。
「ひ、姫様は………!」
「はい?」
「ひ、姫様は……! 間違いなく、料理を食べたのか……?」
「ええ、食べましたよ」
シュバルツはあくまでも、にこやかに答える。イワニコフは、思わず身体に震えが来るのを止めることができなかった。
「で、では………姫様は………」
「はい」
「姫様は、そのあと………」
「ですから、『大変おいしかった』と」
「……………!」
シュバルツの、至極当たり前な答えに、イワニコフはぐっと、言葉に詰まる。確かにそうなのだが、自分が聞きたいのはそう言うことではないのだ。
(どういうことだ!? あの毒は、即効性のはずだ!! 口にしたのなら、あの女は無事でいるはずがないのに………!)
「あの…………」
シュバルツに声をかけられて、イワニコフははっと我に返る。顔を上げると、申し訳なさそうな顔をした青年がいた。
「何だ!?」
「そろそろ、そこを退いてはいただけないでしょうか? 食器を洗いたいのですが………」
「……………!」
自分の巨体が通路をふさいでいる、と、気が付いたイワニコフは、とりあえずそこから横に退く。その前をシュバルツが、サービスワゴンを押しながら、静かに通って行った。
「……………」
しばらくそれを、見るともなしに見ていたイワニコフであるが、やがて、あることに気づいた。
(………! 食器が違う─────!)
サービスワゴンの上に並ぶ空になった食器は、自分が姫に食事を盛りつけたものと、違うものだ。よく見ると、サービスワゴンの下の方に、自分が使った食器が、無造作に積み上げられていた。
(こいつ────!)
イワニコフは眩暈がするほどの怒りを感じた。つまりこいつは、たかだか給仕の分際で、勝手にシェフの料理や食器を、勝手に触ったことになるのだ。
これは、あからさまに越権行為だ。
給仕として、正しい心構えを教え込まねば───!
「おい、お前」
「何ですか?」
青年が、人のよさそうな顔をして振り向く。ザワ、と、イワニコフの中の嗜虐心がうずいた。
おあつらえ向きだ。
こいつは今から、俺のサンドバックにしてやる。
「そのサービスワゴンの上に乗っている食器…………俺が出したものとは違うな………」
「…………!」
シュバルツの眉が、ぴく、と動く。厨房の空気が、一気に凍り付いた。
(あの新人なんてことを……!)
(殺されるぞ……! イワニコフさんの料理を勝手に触るなんて………!)
「お前……! 俺が作った料理をどうした?」
「料理ですか? 姫様に出しましたけど………」
「噓をつくな!!」
イワニコフの大声が、厨房に響き渡る。
「姫様が食べた食器と、俺が盛りつけた食器が違う!! 貴様!! 俺が作った料理をどうしたと聞いているんだ!!」
悪鬼のような形相で問いただしてくるイワニコフに、しかしシュバルツはあっけらかんと、答えた。
「ああ、それは捨てました」
「─────!」
厨房の気温が、体感的に一気に下がる。誰もが生きた心地がしていない中、シュバルツののんきな声が響き渡っていた。
「だって、あんな物姫様に出せるわけないでしょう。あれにはど─────うぐっ!!」
バキッ!! と、イワニコフがシュバルツを殴り飛ばす音が響き渡る。そのまま倒された彼に、イワニコフの暴力が、さらに襲いかかてきた。
「ふざけるな、貴様!! シェフの料理を給仕の分際で!! 心得違いも甚だしい!!」
殴る蹴るのすさまじい暴力。周りにいる者たちが眉を顰めて固まっていると、「仕事に戻れ!! これは、見世物じゃないんだ!!」と、怒鳴り散らしていた。
「………お前には、相応の『躾』が必要なようだな……!」
イワニコフが、シュバルツの襟首をつかんで締め上げる。
「う…………!」
低く呻くシュバルツを見て、イワニコフは満足そうに笑った。やはりこいつは、背ばかりが高くて、ひょろっこい優男だと、確信する。
「来い!! 貴様には別室で、『給仕の心得』を叩き込んでやる!!」
そのままシュバルツを強引に立たせると、その手を無理やり引っ張っていた。
(あの新人……今日で終わったな………)
(可愛そうに………)
そんな二人の様子を、厨房にいる者たちは目の端でとらえながら、深いため息を吐いていた。
イワニコフはある部屋の前まで来ると、乱暴にドアを開ける。そこにシュバルツを放り込むと、自分もその部屋に入り、後ろ手に鍵を閉めていた。
「ここはな……調理道具を置いてある倉庫だ。鍵も、俺が預かっている」
そう言いながら、イワニコフが、勝ち誇ったようにシュバルツに迫ってくる。
「ここに人はめったに来ない……。防音も無駄に効いててな。ここで泣こうが喚こうが、外には聞こえない寸法ってわけだ」
「はあ」
それに対してシュバルツは、やけに気の抜けた返事をする。イワニコフは一瞬「ん?」と、なったが、シュバルツの態度を勝手に解釈していた。
(どうせ、恐怖で顔の表情をなくしてしまっているのだろう)
人間というのは面白いもので、真に恐怖を感じると、表情をなくして固まったように、身動きが取れなくなってしまうものである。それを一方的に嬲るのもいいが、どうせなら、「すみません!! ごめんなさい!! 助けてください!!」と、泣きわめかせてみたかった。
だから、もう少し恐怖を与えてやるか、と、イワニコフは、わざと足音を大きく響かせながら、シュバルツに向かって一歩、踏み込んだ。
「調理器具があるってことはな………。わかるか? お前を七面鳥みたいに、捌くことも可能というわけだ」
「はあ」
「俺が、血を見るのを怖がっている、と、思うなよ? 俺はコックだ。その気になれば、お前を三枚におろすことなど、朝飯前なのだからな!」
「はあ」
「……………!」
散々脅しているのに、気の抜けた返事をするばかりのシュバルツ。こうも同じ返事をされると、怖がっている、というよりも『馬鹿にされている』と、感じられるのは気のせいなのだろうか。
「お前!! ふざけているのか!?」
怒鳴りながらシュバルツの前の床に、大きな鉈のような包丁を、ダンッ!! と、突き立てる。
「そういえば、お前は俺の料理を捨てた理由を、何か言っていたな……。何を言っていた?」
「…………!」
ピクリ、と、シュバルツの眉が動く。それを、シュバルツの動揺の表れと見て取ったイワンコフは、彼の襟首をつかむと、強引に引き寄せた。
「あっ!」
「………お前、何を知っている?」
「………………」
沈黙を返すシュバルツ。イワンコフはその襟首をぐっと締め上げた。
「うっ!」
「………吐いてもらうぞ。お前の正体、情報、すべてをな……」
「……………」
「黙ろうとしたって無駄だ………。人間には耐えられない苦痛っていうのが、いくつもあるんだよ。まず、そのきれいな顔を、ぐちゃぐちゃに切り刻んでやろうか………」
そう言って、イワンコフは床に突き立てた包丁を引き抜く。そのままシュバルツの頬に、ぴたりとあてがおうとしたとき、彼から声をかけられた。
「あの」
「何だ? 話す気になったのか?」
「いえ、そうではなくて」
イワンコフの言葉に、シュバルツはフルフルと首を振る。
「そろそろ─────私から、手を放した方がいいですよ」
「は?」
シュバルツが何を言っているのか分からず、イワンコフは目をしばたたかせる。
「何を言っているんだ? お前は……。ふざけているのか?」
イワンコフからしてみれば、圧倒的優位を保っているこの状況。そこで「手を離せ」とか言われても、意味が分からないし、理解不能だった。しかし、目の前にいるシュバルツの表情は、真剣そのものだ。
「いえ、ふざけているわけではなく」
真顔で、彼は首を横に振っている。
「本当に────手を放した方が、いいんだけど………」
「命乞いなら、素直にそう言え!」
「いや、命乞いとかじゃなくて」
シュバルツは真顔のまま、話し続けた。
「手を離さないと、あなたが危ない」
「は? 危ないだと? 脅しているつもりか?」
「いや、脅しとかじゃなく」
「お前……! いい加減にしろよ! 恐怖のあまり、気がふれたか?」
「いえ、本当に────」
パラ、と、天井から小さな礫が降ってくる。
「手を放した方が………」
その礫が落ちてくる量は、だんだんと、増えていって─────
ドカン!!
派手な音を立てて、上から黒い物体が降ってくる。それはイワンコフに正確にヒットすると、そのままのしかかってきた。
「いいですよ~~~と、忠告したんだけどなぁ………。遅いか」
やれやれとため息を吐くシュバルツの前で、イワンコフが体勢を立て直そうと足掻いていた。
「な、なんだぁ!? ぐえっ!!」
イワンコフの上に降ってきたのは、リュウ・ハヤブサだった。彼はものすごくいい笑顔でイワンコフの襟首を捕まえると、自分の方に引き寄せた。
「尋問部屋までの、案内ご苦労」
「いっ!?」
「聞いたぞ? ここは防音がしっかりしていて、どんなに泣こうが喚こうが、決して外には聞こえないんだってな」
「ひっ!?」
「おまけにここは、立派な調理器具がそろっている……。俺はお前を、捌き放題、と、言うわけだ」
「……………!」
さ~っと、顔色が変わるイワンコフに向かって、龍の忍者はとてもいい笑顔を向けた。
「姫、入ってきていいぞ」
「姫!?」
ぎょっと、顔を上げるイワンコフ。すると、いつの間にかドアのところに移動していたシュバルツが、ドアをそっと開ける。すると、硬い表情をしたナディール姫が、ドアの向こうから現れた。
「あなた…………!」
ナディール姫の大きな碧い瞳が、厳しい光を帯びている。ギリ、と唇をかみしめるイワンコフの襟首を、ハヤブサが乱暴につかんだ。
「お前、シュバルツに何を聞こうとしていた?」
「う……………!」
「はいてもらうぞ………? 洗いざらい………! お前の知っていることを………!」
「ひ…………!」
完全におびえるイワンコフに対して、ハヤブサはにっこりと微笑みかけた。
「お前は、『俺のシュバルツ』に、結構な暴力をふるってくれたよなぁ?」
「おい」
シュバルツが一言突っ込みを入れるが、ハヤブサの方がすでに聞いていない。彼の目が完全に据わっているのが、姫から見てもよく分かった。
「この尋問………楽に終わると思うなよ………?」
無言で、逃げ出そうとするイワンコフ。しかし、龍の忍者がそれを逃がすはずもなく。
「ひ、ひええええええ!! お助け~~~~~!!」
間抜けな悲鳴を上げるイワンコフを、ハヤブサがずるずると物陰へと引っ張っていった。
「あ……………」
後を追おうとしたナディール姫を、シュバルツがやんわりと引き留めた。
「たぶん、君は見ない方がいいな。精神衛生上、あんまりよろしくなさそうだから」
「シュバルツ様………!」
ナディール姫が、切羽詰まった色を瞳にたたえて振り向く。シュバルツは穏やかに微笑みかけた。
「あの………シュバルツ様………! 大丈夫でしたか………?」
「ん?」
「厨房で、あのような暴力を………」
「ああ…………」
シュバルツが少し考え込むようなしぐさをする間にも、ハヤブサの『尋問』の音が、部屋に響き渡っていた。
「ぎいえええええええええ!!」
「………人間には耐えがたい痛みがあるんだってな……。俺が知っている奴を教えてやるから、何かの折に役立ててくれよ!」
「うぎゃああああああああ!! 助けてくれ~~~~~!!」
「あの程度、別にどうってことないよ。相手の油断を誘うために、わざと喰らったふりをしただけだから、私自身は、痛くもなんともないんだ」
「そうですか………」
ナディール姫は、少し胸をなでおろすしぐさをする。だが、まだその表情は硬く、顔色も蒼白なままだった。
「ですが、シュバルツ様……!」
ナディール姫が顔を上げた瞬間、また、向こうから怒鳴り声が響いてくる。
「お前、シュバルツの顔を何発殴った!? 俺の愛おしいシュバルツの顔を、何発蹴ったんだ!!」
その言葉に、ナディール姫が「え…………」と、固まってしまう。シュバルツが「あちゃ~!」と、頭を抱える間、イワンコフの「いぎゃあああああああああああ!!」という、間抜けな悲鳴が響き渡っていた。
「あの、シュバルツ様?」
「何だ?」
ナディール姫が、顔を引きつらせながら問いかけてくる。
「変なことを聞いてすみません………! 貴方は、ハヤブサ様とは、どういったご関係で………?」
それに対してシュバルツは、苦笑しながら答えた。
「いや、だから友人──────」
「いいか!? シュバルツを好きにしていいのは!! 『恋人』である俺だけだ!! あの身体のつま先から髪の毛一本に至るまで!! すべて俺の物なのだからな!!」
「ひいいいいいいいいいいっ!! 助けて~~~~~~!!」
「え……………!」
ナディール姫が再び、固まってしまう。その横でシュバルツは、頭を抱えていた。
(助けて~~~~~! はこっちだ!! あの馬鹿!!)
同性愛の問題は、微妙だ。ナディール姫にそちらの『理解』があればいいが、嫌がる人は、徹底的に嫌がられてしまう。
自分は、ハヤブサが恋人、ということで、どう思われようとも特に構いはしないのだが、ガードをする対象者を気持ち悪がらせては、話にならないと思うのだ。
「………友人のつもり、だったんだけど………」
ため息を吐きながら、やっとのことでそれだけを話す。
「はい…………」
ポカン、としているナディール姫をちらり、と、シュバルツは見ると、「その……すまない………」と、小さな声で謝った。
「え…………?」
「『同性愛者』がそばにいることで、不快な思いをさせてしまったのなら────」
「大丈夫です! それはありません!」
ナディール姫はぶんぶん、と、勢いよく首を横に振った。
「『全てのことに、偏見を持って接してはならない』……これは、シャハディ家に伝わる『家訓』です。その………ハヤブサ様と、シュバルツ様が『恋人同士』という事実には、びっくりしましたが………」
ナディール姫は、うん、と、頷いて顔を上げる。
「それだけで、ハヤブサ様やシュバルツ様を、奇異な目で見る必要は、ないと思います。特にハヤブサ様は………十分に信頼に足るだけのことを、今まで私にしてくださっているのですから………」
「そうか………」
穏やかに返事をするシュバルツに、ナディール姫もにっこりと、微笑みかけた。その時物陰からは、まだハヤブサがイワンコフを『尋問』する音が響き渡っていた。
「も、もう話します話します!! だから助けて!!」
「は? 何を言っているんだ? お前」
「えっ?」
涙目で目をしばたたかせるイワンコフに、ハヤブサはにやりと微笑みかけた。
「お前がシュバルツに振るった暴力が、この程度で許される、とでも、思っているのか?」
「えええええええ!?」
「さあ、続きをするぞ!! もう少し、耐えられそうだな!!」
「ひっ! ひいいいいいいいいいい!! お助け~~~~~~~!!」
イワンコフの間抜けな悲鳴が響き渡る。これにはナディール姫もシュバルツも、さすがに彼が気の毒なような気がしてきた。
「……本当に、ハヤブサの奴は『信頼に足る』ことを、今までしてきているのか……?」
「だ、大丈夫です……。たぶん………」
シュバルツの問いかけに、ナディール姫も、顔を引きつらせながら苦笑するしかなかった。
それからハヤブサが、イワンコフの『尋問』を終えるまで、もう少しの時を要した。物陰からハヤブサが、縛り上げたイワンコフをずるずると引きずって出てくる。
「間違いなく、すべてを話すんだな?」
「は、はいいいい!」
「よし」
ドサッ! と、音を立てて、イワンコフの身体が姫の前に投げ出された。
「………………!」
それを、硬い表情で見やるナディール姫。イワンコフはそんな姫と一瞬、視線を合わせると、「へっ!」と、悪態をつきながら、顔をそらした。
「…………で? 実際とのところどうなんだ? お前は姫の料理に誰が『毒』を盛っているのか、知っているのか?」
ハヤブサがかがみこんで、イワンコフの顔を覗き込むようにしながら問いただす。「ひええええええっ!!」と、イワンコフは悲鳴を上げると、勢い良くしゃべり始めた。
「たたた、確かに、『毒』を姫の料理に入れていたのは俺だよ!! これでいいんだろう!?」
「誰の指示で、毒を入れた?」
ハヤブサの問いに、イワンコフは声を張り上げた。
「ここの料理長である、シェフだよ!!」
「……………!」
「うそ………!」
イワンコフのその言葉に、ナディール姫とシュバルツの顔色が、同時に変わる。ハヤブサは、イワンコフの胸倉を乱暴につかんだ。
「本当か!? その言葉に──────噓偽りはないだろうな………!」
「ぐ、ぐえ……っ! う、嘘じゃない!! 本当だって………ッ!!」
「……………ッ!」
ハヤブサは、ぎり、と、唇をかみしめながら、イワンコフから手を離す。床に放り出されるように尻もちをついたイワンコフは、気道と肺に大量に流れ込んできた空気に、激しく咽せていた。
「………何なら、シェフに直接確かめてもらってもいいぜ……。俺は、あいつの指示であんたの料理に毒を入れていたんだから………!」
「そんな………!」
知らず、よろり、と、ふらついてしまうナディール姫。それを、シュバルツがそっと支えた。
「大丈夫か?」
こちらを案ずるようなまなざしを、シュバルツにむけられる。それを見て、姫もハッと、われに返った。
「だ……大丈夫です……。ありがとう………」
小さく礼を言って、彼の腕から静かに離れた。
(しっかりしなさい……! ナディール……! ちゃんと真実と向き合わなければ………!)
そう自分に言い聞かせながら、強く拳を握り締める。
倒れている場合ではない。
逃げている場合ではない。
このような悪意など────
ずっと向かい合ってきたものじゃないか。
「………シェフはたぶん………明日のスープの仕込みをするために、厨房に、まだ居ると思う………」
シュバルツが、ぽつりと言葉を落とす。ナディール姫は、はっと顔を上げた。
「姫、どうする?」
ハヤブサが、まっすぐな視線をこちらに向けてくる。
(迷うことはない)
姫は覚悟を決めた。
恐れてはならない。
真実を知ることを。
「厨房に、行きます」
姫の言葉に、忍者二人は頷いていた。
「…………………」
シェフは、厨房で煮込まれる食材を見ながら、陰鬱な気持ちをぬぐえずにいた。
こんなこと続けるのは、絶対によくない。それは、分かっている。
だが、今の自分に、何ができるというのだろう。
「シェフ、こちらの掃除、終わりました」
「食材の仕込み、終わりました!」
見習いのコックたちの言葉に、シェフは頷く。
「よし、お前たち……………」
もうそろそろ上がれ、と、シェフは二人に声をかけようとする。だが、それより先に、見習のコックたちが驚きの声を上げた。
「ひ、姫様!?」
「─────!」
驚いて顔を上げるシェフの前に、ナディール姫が厨房に入ってきた。
「シェフに話があります。申し訳ありませんが、人払いをお願いしていいですか?」
姫の顔色は蒼く、その表情は硬い。
(ああ、来る時が来たか)
シェフはその瞬間、すべてを悟った。
終わらせる時が、来たのだと。
「シェフ………」
見習いのコックたちが、心配そうにシェフを見つめてくる。
「大丈夫だ。お前たちはもう、上がれ」
シェフは多少苦笑しながら、彼らにそう、指示を出した。
「わかりました………」
見習いのコックたちは頷いたが、何度もこちらを振り返りながら、厨房を後にしていた。後ろ髪をひかれているさまが、見て取れた。
(そんなに心配しなくてもいいのだが……)
シェフは、複雑な想いで、その二人の後姿を見送っていた。
彼等にそんな風に心配してもらえる『資格』など────自分はとっくの昔に、失ってしまっているのだから。
「シェフ………貴方に、確認したいことがあります」
厨房に、完全に二人きりなったと確認してから、ナディール姫は口を開いた。
「ハヤブサ様、シュバルツ様………どうか、入ってきてください」
姫に呼びかけられて、忍者二人が厨房に入ってくる。ハヤブサは縛り上げたイワンコフを、シェフの前に投げ出した。
「………………!」
少し驚いた風に見える、シェフに向かって、ハヤブサがぶっきらぼうに口を開く。
「こいつが、姫の料理に『毒』を入れていた」
「………………」
シェフは、沈黙したままであった。ハヤブサは言葉を続けた。
「こいつが言うには、シェフ、『お前に頼まれて、毒を盛った』と、言うのだが─────」
「………………!」
シェフが、唇をぎり、と、嚙み締めたように見えた。
「本当のところ………どうなんだ?」
「………………」
沈黙するシェフを、ナディール姫は食い入るように見つめる。
彼は、姫が幼いころから厨房に勤め、父であるガエリアル王にその腕を認められて、料理長に上り詰めた、たたき上げの人だ。父からの信任も厚く、姫もまた、彼の料理を愛していた。
だから
だからこそ、だ。
(違う、と、言ってほしい)
姫はそう祈りながら、シェフを見つめていた。
違う、濡れ衣だ。
そう言ってほしかった。
彼がそう言ってくれるのなら、自分は────
いくらでも彼の言葉を、信じられる、と、思った。
だが。
シェフの首は、縦に動いた。無情にも。
「ええ………。そうです………」
「シェフ…………!」
姫は小さく悲鳴を上げる。それに対して、シェフは淡々と言葉を続けていた。
「私が………イワンコフに頼んで………姫の料理に、毒を………入れていました………」
「そんな………!」
姫の周りの景色が、勝手にぐにゃり、と、ゆがむ。天地が分からなくなって、ひっくり返りそうになったのだが、誰かの力強い腕が、それを阻んだ。
「あ……………!」
振り返ると、シュバルツが自分のすぐ後ろに立って、支えてくれていた。
「………………」
彼の、ひどく哀しみを帯びた眼差しが、自分を見つめている。それを見たナディール姫は、瞬間我に返った。
(しっかり………! しっかりしなさい! ナディール………!)
どのような事実を突きつけられても、『受け止める』
そう、覚悟を決めたのではなかったのか。
「あ………りがとう、ございます……。立てます」
ナディール姫は、シュバルツの腕から、そっと離れた。
(独りで、ちゃんと立たなければ)
歯を食いしばって、前を向く。
ここで泣き崩れるわけにはいかない、と、思った。
ここで倒れてしまったら─────
自分は二度と、独りで立てない。
そんな気がしてしまったから。
「では、シェフ………。もう一つ聞く」
ハヤブサは深くため息を吐きながら、問いかける。
ここまで来たのだ。
もう、隠し事をしないでほしい、と、祈っていた。
「毒を入れるよう指示を出したのは……誰かに『そうしろ』と、命じられたから、か……?」
「……………!」
ピクリ、と、シェフの頬の筋肉が動く。
「そこのところは、どうなんだ………?」
「それは…………!」
ハヤブサの問いかけに、シェフは明らかに動揺していた。
それは、間違いなく『黒幕』の存在を、伺わせるものであった。
「シェフ………!」
ナディール姫は、祈るようにシェフを見つめていた。
「お願いです……! もう隠し事はしないでください………!」
「姫様………」
「シェフ……! どうか………!」
「……………っ!」
姫は、必死だった。
今まで彼が、自分たちのために料理で尽くしてくれたことを考えると、とても彼を恨む気にはなれなかった。たとえ、どんな理由があろうとも。
唇をかみしめ、拳を握り締めているシェフ。
彼は、明らかに苦しんでいるように、見えた。
自分を毒殺したい、と、本心では願っていない可能性があるのだ。
だから、話してほしかった。
理由を。
真実を。
それを知ればこそ、自分がシェフの手助けをすることも、可能になるのではないだろうか。
「…………………………」
しばらく下を向き、身体を小刻みに振るわせながら、沈黙を貫いていたシェフであったが、やがて、拳をぐっと握りしめ、その顔を上げた。
「…………分かりました」
「シェフ………!」
「真実を、話しましょう………」
「…………!」
シェフの言葉に、ナディール姫の表情が、わずかに緩む。だが次の瞬間、その表情は凍り付くこととなった。
何故なら。
「それは─────」
そう言ったシェフが、いきなり立ち上がる。彼は厨房の奥に走りこむと、片づけてある一本の包丁を手に取り、それを己が喉に勢いよく突き立てようとしたからだ。
「─────!!」
姫は、襲い来る悲劇を予見する。だが、どうすることもできずに、立ち尽くしか、もう出来なかった。
(ダメ!!)
叫びたいのに、声さえ出ない。
だがその時。
「いて───────ッ!!」
誰かの、どことなく間抜けな叫び声の響きに、瞬間、皆の呪縛が解けた。
ハッと、シェフの方を確認すると、シェフの前でシュバルツが、手を押さえながらのたうち回っている。
「いてっ!! いてててっ!! 止め方を間違えた!!」
「え……………」
それを見ながら、茫然と立ち尽くしているシェフの手には、包丁は握られていない。よく見ると、それはシュバルツの手の方に、突き刺さっていた。
「シュバルツッ!!」
ハヤブサが慌てて、シュバルツの方に駆け寄る。
「シュバルツ……! 大丈夫か!?」
「あはは、あは………大丈夫だよ………いてっ!」
シュバルツが、また悲鳴を上げる。ハヤブサが、彼の手から包丁を引き抜いたからだ。
「馬鹿野郎……! 無茶をする………!」
「平気だよ………。しかし、その包丁よく切れるな……。さすがに、手入れが行き届いている厨房だ」
「そんなことを言っている場合か! この馬鹿!!」
忍者二人がギャーギャーと言い合っている横で、シェフが茫然と立ち尽くしていた。
「あ…………………」
シェフが、小さな声を上げる。それに、シュバルツが反応して、振り向いた。
「何を抱えているのかは知らないが、死ぬのはよくない」
「…………………」
シュバルツの言葉に、シェフははっと息をのむ。
「ここでのあなたの軽率な『死』は、敵にメリットを与えるだけで、状況は何も変化しない。それどころか、あなたが本当に『守りたい』と願っている人たちを、ひどく傷つけることに、なってしまうだろう………」
「……………!」
「それでも、どうしても死にたいというのなら……こちらとしても、もう止めようがないが……………せめて、死ぬ前に足掻いてみないか………?」
「あ………………!」
「ちゃんと戦って……それから死んでも、遅くはないと、思う」
シュバルツの言葉に、シェフはこぶしを握り締める。そんな彼に、ハヤブサが改めて声をかけた。
「シェフ…………お前にとって、目の前にいる姫は、頼るに値しない存在か……?」
「─────!」
「助けを求めることも、出来ない相手か?」
「それは…………!」
シェフは改めて、姫を見つめる。
ナディール姫の藍色の大きな瞳が、食い入るようにこちらを見つめていた。
涙をたたえたその瞳────だが彼女は、涙をこぼしてはいなかった。
「シェフ…………」
身体の前で組み合わせれている華奢な手の形が、祈りをささげているようにも、見えた。
シェフは、思う。
自分が一番信頼しているのは、がエリアル王。それは、間違いないし、揺るぎようもない。
自分は王と、その家族のために、ひたすら料理の腕を振るってきた。だから当然、姫も幼いころから知っている。
父王と王妃の愛情を、一身に受けて育って行く姫。
「多少やんちゃなところもあるが、自慢の娘だ」
王がうれしそうに話していた姿を、シェフは昨日のことのように、思い出すことができた。
しかし、レアメタルの鉱脈の発見によって、国の情勢が不穏化し、王も病気で倒れてしまう。
独り、国を支えようと奔走する姫。
自分は、それを支えよう、と、願っていたのに─────
自分の、シテシマッタ コト ハ
「あ…………! あ…………!」
ずるずると、崩れるように座り込むシェフ。
「シェフ………!」
姫は、その傍に走り寄っていた。
「姫様…………!」
顔を上げるシェフ。姫は、その手を取ろうとする。
「シェフ……! 大丈夫ですか………?」
しかしシェフは、その手を払いのけるように、さらに地面に這いつくばるように頭を下げていた。
「申し訳ございません………! 姫様………! 私は、何ということを………!」
「シェフ………!」
「いくら『人質』を、取られていたとはいえ………! 私は………っ!」
シェフのその言葉に、その場にいた全員の、顔色が変わる。そう、イワンコフでさえも。
「人質!?」
「な─────!」
「………………!」
「お、おい……! シェフ……! お前、裏切るのか!?」
イワンコフの言葉に、シェフは顔を上げた。
「もうだめだ!! 私はもう何も隠し通せない!! たとえそれで、自分が死んでも………! 人質となっている妻や子が、殺されてしまっても────!!」
「そんな…………!」
シェフの衝撃的な叫びに、茫然としてしまう姫。そんな彼女の目の前で、シェフははらはらと涙を落とし続けていた。
「申し訳ございません!! 姫様………!! 私のやったことは、許されることではない………!! 命乞いも、言い訳も致しません!! どうか、存分に裁いてください……!!」
「冗談じゃねぇ!! シェフの自殺に巻き込まれてたまるか!!」
対してイワンコフは、声を荒らげていた。
「俺は、頼まれてこいつの監視をしていただけだ!! 俺は裏切っていないぞ!! 俺は何も悪くない!!」
縛られたイワンコフが、じたばたと暴れだす。彼はそのまま、ナディール姫をにらみつけていた。
「だいたいだな……! そこにいる女が、何もかも悪い!!」
「え……………」
突然の怒りの矛先が自分に向けられたことに、ナディール姫は戸惑ってしまう。イワンコフは、さらに畳みかけてきた。
「お前が毒を喰らってさっさとくたばらないからだ!! わからないのか!? お前は生きているだけで、大勢の人間に迷惑をかけているんだぞ!! お前が─────!!」
「黙れッ!!」
ダンッ!! と、激しい音を立てて、ハヤブサがイワンコフの頭を踏みつける。イワンコフは「ぐえっ!!」と、カエルが潰れたような声を上げるしかなかった。
「これ以上……姫に対して何かを言ってみろ………! 俺はこのまま、貴様の頭を踏み潰す!!」
「ひっ!?」
間抜けな悲鳴を上げるしかない、イワンコフ。そこにシュバルツが、「ハヤブサ」と、声をかけてきた。
「止めるなよ、シュバルツ………! お前が止めても、俺は────!」
殺気だった眼差しを向けてくるハヤブサに、シュバルツはにっこりと微笑みかけた。
「馬鹿だなぁ。真っ先に頭をつぶすだなんて……。そんな、簡単に殺してやってどうするんだ」
「へっ!?」
シュバルツの言葉に、全員の目が点になる。
シュバルツは、あくまでも爽やかに微笑んでいる。
微笑んでいるが─────
その瞳は、完全に据わっていた。
つまり彼も、相当怒っていたのである。
以下は、ブチ切れた忍者同士の、冷静な会話をお楽しみください。
なお、発言がたいへん物騒なので、ガイドラインに従って自主規制音を入れさせていただきました。かなり読みにくくなってしまったことを、ここに深くお詫びを申し上げます。
「それよりも(ピ───)を(ピ───)して、(ピ───)した方がよくないか?」
「ひっ!?」
あまりにも物騒なことを言われて、固まってしまうイワンコフ。それに対してハヤブサは、「ああなるほど」と、頷いていた。
「確かに、(ピ───)を(ピ───)して、その上に(ピ───)をした方が、効果が上がるか………」
「いや、もう少し(ピ───)を(ピ───)した方が、こいつの身体には効くんじゃないか?」
「そこから(ピ───)して、(ピ───)する手もあるな……」
「えっ? 人間の肉って、そんな風に捌けますか?」
忍者二人の会話に、シェフまでもが加わってくる。
「いや、さすがに人間では、まだ試したことはないが………熊や猪だったら、そうやって捌くと旨味が出るな」
「そうなんですか……。なるほど………」
「(ピ───)を(ピ───)してから、(ピ───)して………」
「(ピ───)したところに、塩を揉みこんで………」
「いや、その前にひと手間かけて、(ピ───)をした方が………」
「あの、すみません」
姫に声をかけられて、男たち3人は、会話を止めて振り返った。
「どうした?」
「いえあの…………そろそろ、許してあげて、いただけないでしょうか……?」
「えっ?」
きょとん、と、目をしばたたかせる男たちに、ナディール姫は気の毒そうに、イワンコフの方を指し示す。
「あの方………気を失ってしまってますので………」
「……………!」
男たちがイワンコフの方に視線を走らせると、彼は口から泡を吹きながら、白目を剝いて倒れこんでいた。
「たしゅけて………。食べられりゅ…………」
彼の、うわ言のような小さな声が、厨房の中に哀れに響き渡っていた。
「おい」
ハヤブサが、イワンコフの襟首をつかんで、彼を起こす。
「ひぃっ!?」
「気が付いたか?」
「ひいいいいいいっ!!」
イワンコフは、ハヤブサから逃れようと必死に足掻く。だがそれは、徒労に終わっていた。
「お前、今度姫に無礼な口をきいたら、どうなるか分かっているんだろうな?」
「も、もう絶対にそんなことは言いません!! だから助けて!!」
「ハヤブサ様………!」
ナディール姫も、必死にハヤブサを見つめながら、首を横に振っている。ハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐いた。
「よし、じゃあ、お前が知っていることを洗いざらい吐いてもらうぞ。隠し立てすると、どうなるか………分かっているな?」
ハヤブサの言葉に、イワンコフはこくこく、と頷く。
「よし」
ハヤブサはそれを確認すると、ようやくイワンコフから手を離した。
「では聞くぞ……。お前はだれの指示で、この細工を実行した?」
イワンコフが落ち着いてから、ハヤブサが問いかける。イワンコフは勢いよく口を開いた。
「ち、直接えらい奴と話をしたわけじゃねぇ!! ただ、依頼主はシロア国の奴だと言っていた!!」
「シロア国!?」
ナディール姫が、はっと息をのむ。
シロア国とは、ユリノスティ王国の近くにある大国で、豊富な資源と資金力を背景に、たびたび近隣諸国の国境を脅かしていた。ユリノスティ王国にも当然、その圧力はかかってきていて、父王の時代から、シロア国の属国になるように、たびたび要請されてはいた。
「我が国には、我が国の誇りと伝統がある。申し訳ないが、どこの属国にもならん!」
と、父王はそう言って、それをはねのけ続けていたのだが。
「………………!」
父王が倒れ、自分も亡き者になってしまえば、幼いノゾムと王妃では、シロア国の圧力をはねのけることはできないだろう。それどころか、そのごたごたに乗じて、この国の自治権を完全に奪い取ってしまいかねない恐怖を感じた。
「……やっぱり、シロア国の奴らも……! そこの女が目障りなんだろうよ!!」
「へ~~~~」
イワンコフの言葉に、シュバルツが妙に軽い声で反応する。その声を聴いたイワンコフは、縮み上がっていた。
「ひいっ!! 俺じゃねぇ!! シロア国の奴らの意見だ!!」
「…………!」
姫が、ぎゅっ、と、唇をかみしめている。ハヤブサは、さらに質問を続けた。
「お前の役目は、毒を盛るだけか? 人質がどこにいるか知っているのか?」
「ああそうだ! 俺は、姫の料理に毒を盛る係をしていたんだ! ただ、「人質がどこにいるかまでは知らねぇ!!」
「本当か?」
ハヤブサの問いに、イワンコフはこくこくと、首を縦に振る。
「本当だ!! 知っていたら、俺は絶対に人質の場所を話している!!」
「絶対だな?」
イワンコフは必死にうなずいていた。
「信じてくれ!! 嘘は言っていねぇ!!」
「ハヤブサ様………」
ナディール姫が、取りなすようにハヤブサに声をかけてくる。
涙目で、蒼白な顔色で必死に答えているイワンコフに、情けをかけているのだろう。
(優しすぎるな……)
そう感じて、ハヤブサは少しため息を吐く。
こいつは単純な『悪党』だ。
姫がわざわざ情けをかけるほどの者でもないのに。
「わかった……。姫のとりなしもあることだし、お前が嘘を言っていない、と、信じて………もう一つ、聞く」
「は、はひ………っ!」
縮み上がりながら返事をするイワンコフを、ハヤブサは睨みつけていた。
「………人質が『生きている』保証は、あるのか?」
「─────!」
「それは………!」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫も、そしてイワンコフも息をのんでいた。『人質』の安否など、保証もされていないし、イワンコフ自身も、さして興味も持っていなかったからだ。
だが、その疑問には、シェフがいち早く答えていた。
「きっと、人質たちは生きてます………」
「シェフ………!」
「なぜ、それが分かるんだ?」
ハヤブサの問いかけに、シェフは顔を上げた。
「いつも人質たちに、私の『料理』が届けられていたようなのです」
王や城の者たちの賄いを作っているときに、「いつもより2食余計に作るように」と、指示を出されていた。それを厨房の片隅に置いておくと、いつの間にかその食事がなくなっていて─────
そして、また知らぬ間に、帰ってくる空の食器。
その食器の傍らには、小さなメモ書きが添えられていた。
「今日のスープはおいしかったわ、とか、今日のは塩気が多いわね、とか………。その日の料理の感想が、その紙には書き添えられていて………。それが、妻の筆跡だったものですから……」
「間違いないのか?」
問うハヤブサに、シェフは力強く頷いた。
「ずっと、長年見てきているのです。あれは、妻の筆跡に、間違いありません」
「そうか………」
その言葉に、ハヤブサはふむ、と、考え込む。
「な、なぁ……! もういいだろう!? いい加減、俺を解放してくれよ!!」
ハヤブサの束縛が緩んだ瞬間、イワンコフが叫んだ。
「これで、俺の知っていることは全部話した!! もうここからは出ていくし、何があっても、この国には二度と近づかねぇ!! 約束するよ!! だからお願いだ!!」
「………………」
ハヤブサはそんなイワンコフをじっと見据える。
確かに、彼から得られる有益な情報は、もう無さそうであるし、彼ははっきり言って小物の類の悪党だ。イワンコフをこのまま拘束していても、意味はないし、こちらのメリットも薄いだろう。
だがハヤブサは、あえて姫に問いかけていた。
「姫………。お前は、どうする?」
実際、この場でイワンコフの生殺与奪の権利を握っているのは、ナディール姫だと、ハヤブサは思った。彼女は、シェフの上司にもあたるし、何といっても、イワンコフに直接「毒」を盛られていた彼女は、事実上、一番の被害者でもあるのだ。
だから、姫自身が望めば、イワンコフに報復する権利が彼女にはある、と、ハヤブサは考えていた。
しかし
やはりというべきか────姫は、報復を望まなかった。
「その方を、解放してあげてください……。嘘は言っていないようですし、反省もしているようですから……」
「ひ、姫様!!」
イワンコフは表情をパッと輝かせていた。
「ありがとうございます!! 姫様にお許しいただいたこのご恩は、決して忘れません!! もう二度と、あなた様の暗殺も企てません!! この通り───神の御前で、お誓い申し上げますです!! はい!!」
(お調子者め!!)
ハヤブサは内心イラついていた。
こういうことを言うこの手の悪党が、改心する可能性など、絶望的に低い、ということを、ハヤブサは既に知ってしまっている。この男も、ナディール姫の甘すぎる裁定に、心の中では小躍りして、舌を出しているに決まっているのだ。
だがもちろん、ナディール姫は裁定を覆さない。彼女の望むままに、ハヤブサは、イワンコフを戒めていた縄を、解いていた。
「ありがとうございます!! 姫様!!」
身体が自由になったイワンコフは、床に額をこすりつけるように土下座をして、礼を言う。
「食われなくてよかったな」
苦笑しながらシュバルツにそう声をかけられ、イワンコフは「ひええええええっ!!」と、悲鳴を上げていた。
「そ、それでは俺はっ! ここで退散させていただきますっ!! お、お世話になりましたっ!!」
そう言って、イワンコフは取る物も取りあえず、猛ダッシュで出ていく。後には、忍者二人とナディール姫、そして、シェフが、残されていた。
「姫様………!」
ナディール姫が呼びかけに振り向くと、シェフが申し訳なさそうな顔をして、そこに立っていた。
「シェフ…………」
「申し訳ございません!! 姫様………! 私が不甲斐ないばかりに……!」
「違うわ! シェフが悪いわけじゃない! 貴方だって、被害者ではないですか……!」
「ですが───!」
「………すまないが、礼を言うのも責任を取るのも、もう少し後にしてくれないか?」
ハヤブサの憮然とした声が、二人の会話を中断させた。
「えっ?」
振り返る二人に、ハヤブサがぶっきらぼうに言葉を続ける。
「事件はまだ、解決したわけではない」
「え…………」
戸惑うナディール姫に対して、シェフは、はっと、息をのんでいた。
「『人質』の救出が、まだだ」
「─────!」
ナディール姫も、ここでようやく残された課題の重要性に気づく。ハヤブサの言葉に、シュバルツも頷いていた。
「そうだな……。さっきの話から察するに、人質はまだ生きている可能性がある………。ならば救出は、急いだほうがいい」
「いえ、それは───!」
シュバルツの言葉に、シェフは慌てて首を振った。
「私どものことは、どうか構わずに………! 脅されていたとはいえ、あなたに毒を盛ってしまったのは、事実です……! 云わば、『裏切り者』も同然です……! そんな私どものために、貴女のお手を煩わすわけには………!」
「何を言っているの!? だめよ!!」
ナディール姫は、弾かれたように叫んでいた。
「長年貴方が私たち王族に尽くしてくれた功績を考えるなら、貴方はもう、私たちにとっては身内も同然です! あなたの家族もそうです! シェフ、貴方は─────私に『身内を見捨てろ』と、仰るのですか!?」
「姫様………! しかし………!」
「ううん、『身内』とか、そうではないとか─────そんな問題じゃない! 私たち『王族』には、国民を守る『義務』と、『責任』があるの………! 今、それが危険に晒されているというときに、守ることを放棄するわけにはいかないわ!」
「いや、しかし………!」
なおも、救出をためらおうとするシェフの手を、ナディール姫はぎゅっと、握った。
「お願い、シェフ………! 貴方の家族を守らせて……! 私のためにも、そして、お父様のためにも………!」
「………………!」
「貴方や、その家族に何かあれば、お父様が一番悲しむわ」
「─────!」
その一言が、シェフの心を一番深く刺した。
「王が…………!?」
呆然とつぶやくシェフに、ナディール姫は頷いた。
「ね………。だからお願いです。人質の救助に当たらせてください……! 今まで貴方に助けられた分、そして苦しめてしまった分を、どうか、私に返させて……!」
「姫様………っ!」
シェフから、滝のような涙が零れ落ちてくる。
どうして
どうしてこの方は、
こんなにも、お優しいのだろう。
自分は、裏切ったのに。
一時でも、この方を『毒殺』しようと、していたのに────
「………………」
ハヤブサは小さくため息を吐きながら、その様子を見つめていた。
姫の性格は、『王』としては甘すぎると思うし、彼女の言葉は『青い』と思う。
だが困ったことに、自分はそんな彼女のことを、『悪くはない』と、感じてしまっているから厄介だった。
そしてきっと、シュバルツもまた────
「─────!」
ここでハヤブサは、ぎょっと、息をのんでしまう。
何故ならシュバルツは、と、言うと。
ナディール姫とシェフの様子を見ながら、はらはらと、涙を落としていたからだ。
「あ………! ハヤブサ………!」
自分の視線に気づいた愛おしいヒトが、あわてて涙をぬぐっている。
「す……すまない……! もらい泣きを、してしまって………」
そう言って、涙を拭う手が
震える唇が
涙で潤んだ瞳が
あまりにも可愛らしくて、色っぽくて、愛おしかった、ものだから────
「……………」
ハヤブサは、何かをあきらめたように、一つため息を吐く。
シュバルツのそばに、つかつかと歩み寄っていって────
バキャッ!!
いきなり、シュバルツに殴り倒されていた。
「痛い!!」
ガバッと跳ね起きるハヤブサを、シュバルツがジト目でにらみつける。
「自業自得だ!! この馬鹿!!」
「『自業自得』って………! 『まだ』何もしていないだろう!?」
「『まだ』ってことは………何かする気だったんだな?」
「えっ?」
罪のない顔をして、爽やかに微笑むハヤブサに、シュバルツもにこやかに微笑み返す。
「一体、何をする気だったんだ?」
「何をって………」
目の前で、あくまでもにこやかに微笑んでいるシュバルツ。ハヤブサは「フ………」と、小さく笑うと、その頬に手を伸ばした。
「それは、お前に────」
バキャッ!!
再び、殴り倒されるハヤブサ。
「痛い!!」
叫びながら起き上がるハヤブサに、シュバルツの怒鳴り声が飛んできた。
「阿呆か!! 今は、そんなことをしている場合か!? 仕事中だろうが!!」
「いやでも、お前があまりにも可愛らし」
「…………………」
ぎろり、と、殺気だった眼差しでシュバルツに睨まれたので、ハヤブサの恋心は結構真面目に傷つけられていた。
「ううう………。シュバルツが冷たい………!」
座り込んで、さめざめと泣くハヤブサ。いつの間にかその様子を、ナディール姫とシェフが、顔を引きつらせながら見つめていた。
(何だろう……。ハヤブサ様の様子が、いつもとすごく違う………)
あまりにも情けない姿を見せるハヤブサに、ナディール姫は戸惑ってしまう。
何故だろう。
ハヤブサの感情に
ものすごく「色」がついているように、見えてしまうのだ。
でもそれは、悪いことには見えない。
むしろ──────
「姫様………?」
シェフに案じるように声をかけられ、ナディール姫は、はっと、我に返った。
「あ……ごめんなさい。ええと、人質の救出を………」
そこまでナディール姫が言った、その時だった。
「危ない!!」
声とともに、一陣の風が、ナディール姫の身体をさらった。
その瞬間、姫の居た足元の床に、カチカチ、と何かが当たる。
「な、何だ!?」
「シェフ!!」
ハヤブサが戸惑っているシェフの身体を、強引に引っ張る。
刹那、二人がいた場所が、ドオン!! と、派手な音を立てて爆ぜた。
「きゃ───ッ!!」
思わず悲鳴を上げてしまうナディール姫。
「大丈夫か?」
シュバルツに声をかけられ、はっと彼女は顔を上げる。ここでようやく、自分を庇ってくれたのはシュバルツだったのだと、気づいた。
「シュバルツ様………!」
「何事ですか!?」
近くにいた警備兵たちが、厨房に走りこんでくる。しかし。
「うぐっ!」
「ぐわぁっ!」
いきなり彼らは、首のあたりから血を吹き出して、倒れていた。
「な────!」
息をのむシュバルツ。
さらに、警備兵たちが走ってくる足音が聞こえてくる。
「何だ? 何だ!?」
「厨房からだ!」
「爆発でも起こったか!?」
「近寄るな!!」
ハヤブサが大声で叫んだ。
「えっ?」
「おい、人が倒れているぞ!」
「大丈夫か!?」
「近寄ってはだめだ!!」
シュバルツも叫ぶが、兵士たちの足は、すぐには止まらない。何人かの首が、同様に切り裂かれてしまう。
「だめだ!! 何かあるぞ!!」
ようやく兵士たちも足を止める。よく見ると、厨房の入り口付近に、テグスのような物が張り巡らされていた。
「それ以上近づくな! 近くに殺気を感じる……!」
兵士たちの足が止まったのを確認してから、ハヤブサは呼び掛けた。
「狙われているのは、この部屋の中だ……! だから、これ以上近づくな!」
「……………!」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫とシェフが、はっと、身を固くする。
そんな二人を忍者二人は庇うように立ち、辺りを警戒していた。
(ククククク………)
仄暗い笑い声が、あたりに響き渡る。それと同時にハヤブサが、刀を一閃させた。
「─────!」
キキン、と、小さな金属音が響き、何かが床に突き刺さった。
(ほう……。コノ小さな獲物ニ気づくカ………。ナカナカニ感がイイ………)
「誰だ!?」
刀を構えながら、ハヤブサが叫ぶ。正体不明の声は、また笑い声を響かせてきた。
嫌な声だと思った。
人とも、そうでないものとも取れるこの声は、こちらの感覚を逆なでしてくるから。
(ソウ邪険にするナ………。お前たちに代わっテ、『あの男』ヲ『始末』シテヤッタトイウノニ………)
「……………!」
ハヤブサの眉がピクリ、と動き、シュバルツの顔色が変わる。ナディール姫とシェフは、息をのんでいた。
「…………どういう、ことですか………?」
震えながらも問いかけるナディール姫。それに対して『声』の主は、嘲るように、「クッ」と笑った。
(南の庭ヲ見てミロ………。お前ニ毒を盛った男ガ、哀レナ死体になって転がっテいるゾ………)
「何ですって!?」
叫び声を上げるナディール姫に対して、その声は、愉快そうに笑い声を立てていた。
(オヤ………ソコマデ顔色を変えることはナイだろウ? 姫………お前にとっテあの男ハ『害悪』以外ノ何者でもナカッタハズダ………)
その指摘がある意味正しすぎたから、ナディール姫は、ぐっと唇をかみしめていた。
確かにそうだ。
あの男は、人質を取ってシェフを脅した。
料理を『毒』で汚染して、自分から、シェフの料理を取り上げた。
『給仕』として厨房に入っていた、無抵抗のシュバルツに対する、一方的な暴力────あれすらあの男が日常的に行っていた『行為』だというのなら、自分は、あの男を『許す』ことのほうが、難しいように思う。
でも
それでも────
「行き過ぎです! 殺してしまうなんて………!」
(ソウカ? コレハ本来なら、お前がセネバナラヌことだゾ? 害悪は断罪シテ、処罰せねバならヌのに………)
「それは………!」
ぐっと言葉に詰まるナディール姫。声は、さらに畳みかけてきた。
(マッタク………とんだ『甘ちゃん』ダナ、お前ハ………。オ前みたいな奴ヲ『王』トシテ仰がねばならヌトハ………。コノ国の連中モ、気の毒なコトダ………)
「………………!」
ハッと、息をのむナディール姫。
それに対してハヤブサは、『否』の声を上げようとする。
だがそれよりも先に、廊下にいた兵士たちの方が騒ぎ出していた。どうやら廊下の方にも、この『声』が漏れ聞こえていたらしい。
「なんて失礼な奴だ!!」
「そうだそうだ!!」
「我らの姫様を、悪く言うな!!」
「そうだそうだ!!」
『黙レ!!』
突如として殺気が爆ぜ、廊下の方で轟音が響き渡る。次いで、兵士たちから悲鳴が聞こえた。
「やめて!! やめてください!!」
ナディール姫の、悲鳴のような絶叫が響き渡った。
「兵士たちを撃つのは、やめてください!! 貴方の狙いは、この私のはずでしょう!!」
ナディール姫は立ち上がり、忍者たちの守護よりも前に、その身を進ませていた。
「撃つのなら……この私を撃ってください! 他の人たちを、無闇に巻き込まないで………!」
(…………………)
姫のその言葉に、声はしばらく沈黙する。
殺気は充満したままだが、その静寂は長く続いた。
だがやがて、小さな笑い声が、部屋に響いてきた。
(姫………お前ノ申し出ハ魅力的だガ、今は、ヤメテオコウ………)
「えっ?」
キョトンとするナディール姫に対して、『声』は、薄ら笑いを含みながら答えた。
(お前ノ後ロに控えテイる奴ヲ………私とシテもこれ以上、刺激しタクナいのでね………)
「………………!」
その言葉に、ハヤブサはピクリと、眉を吊り上げていた。
そう。彼は懸命に、『声』の出所を探っていた。
あと少し。
あと少しで、その居場所をつかめそうであるのに。
「………………」
シュバルツは、静かに身構えていた。
姫に対する攻撃が少しでもあれば、それは自分が身代わりに引き受けるつもりで、彼はそこに立ち続けていた。
(今日ハ………この辺りデ、私も引き上げルコトにしヨウ……。だが、引き上げル前に………姫、お前に一つ、教えてオイテヤル……)
「何ですか?」
怖じることなく、問い返すナディール姫。『声』は低く笑うと、愉快そうに言葉を続けた。
(殺シテおいタあの男ダガ………実は、あイツは、『シェフの監視』以外にモ、『ある役目』を背負ってイタ………)
「役目………?」
(アノ男は、ある時間にナルト、ある場所ノ『門』を、閉めニ行ってイタ………。それが、ドウイウ役割ヲ果たしていたカ、分カルか………?)
「………………?」
小首をかしげるナディール姫を、『声』は、嘲るように低く笑った。
(そノ門は……『人質』ヲ監禁してイル場所ニ、『水』が流れ込むノを防グ役割を果たシテいタノだ………)
「な─────!」
「何ですと!?」
「嘘でしょ………!?」
「……………!」
その言葉に、四人の顔色が、さっと変わる。『声』は、満足そうに笑い声を立てていた。
「クククク………! アノ男が死んでシマッタかラ、もう、ソノ門を閉メル者は誰もイナい。ソレが何を意味スルか………お前たチハ、もう、分カルな?」
「そんな………!」
シェフが、小さな悲鳴を上げながら、座り込んでしまう。
「シェフ………!」
ナディール姫がそばに駆け寄り、助け起こそうとするが、シェフはただ、小さく身体を震わせながら、うずくまるばかりであった。
(時間にしテ、人質たチノ命は、あト3時間、と、言っタトコろだな……。シェフ………! お前は我ラヲ裏切っテ、秘密をばラシタのだ………。だかラ、『報い』を受けテモらうぞ………!)
「ああ…………!」
震えるシェフの体に寄り添いながら、ナディール姫はきっと、顔を上げた。
「なんてことを……! 人質となっている方たちに『罪』は無いでしょう! それなのに────!」
(アア………。そうダな………。『人質』たチニ、『罪』はナい………)
『声』は、ククククッと、仄暗く笑った。
(『罪』がアルのは、『お前』ダ、姫───!)
「─────ッ!」
ガツン! と、何かに殴られたような衝撃を、姫は受ける。『声』は、無情にも、尚も続いた。
(分かラナイのか………? 今回の事態ハ、『お前』ガ招いタノダ………! お前が、さっさと毒ヲ食ラッテ死なナイから………! 少し、オ前は自覚ヲシタ方がいいゾ? お前は生きてイルダけで────)
「そこだっ!!」
裂帛の気合とともに、ハヤブサはくないを投げる。くないは壁に居た何かに突き刺さって、そのまま床に落ちた。
(………生きテイルだけデ………大勢の人間に迷惑を、カケテイル………。ソレを、忘れルな…………)
嫌な残響を残して、その声は、消えた。
「………………」
呆然と、たたずむしかないナディール姫。ハヤブサはそれを見やりながらも、自分が投げたくないが、何を捉えたのかを確認しに行った。床に転がったくないのそばに歩を進めると、その先には、小さな『蜘蛛』が突き刺さっていた。
(蜘蛛か………)
ハヤブサは、それを手に取ってじっと見つめる。
その蜘蛛は、どこにでもいるような、何の変哲もない物のように、ハヤブサの目には映っていた。そこに、特に仕掛けがあるわけでもない。
(妙だな……。あの『声』はいったい………)
ハヤブサは、思索にふけりかけるが、首を横に振って、我に返った。
これの詮索も大事だが、今は、それどころではない。
他に、やるべきことがあるからだ。
「………………」
(生きているだけで、迷惑をかけている、だなんて………そんなこと、分かってる………!)
ナディール姫は、唇をぎゅっと、かみしめていた。
わかっている。
今の自分の『立場』は、とても微妙で、自分の存在を歓迎している人たちばかりではない、ということを、ナディール姫はとっくに自覚していた。
冗談抜きで、自分の存在が『目の上のたん瘤』になっている人たちは、数多く存在していいることだろう。
どうすればいいの
どうすればいい、というのだろう
その人たちの望み通り、自分が死ねば、すべてが丸く収まる、とでも、言うのだろうか。
(違う)
ナディール姫は、首を横に振る。
その人たちの望み通り、自分は死んでもいい。
だけどそれは『今』ではない。
『今』ではないのだ。
(でも…………)
姫は、うずくまって小さく震えている、シェフの姿を見る。
この人が、ここまで追い込まれてしまったのは、間違いなく『自分』のせいだ。
どうすれば、いい?
どうすれば、いいのだろう
やはり、私は─────
「ナディール!!」
ハヤブサの叫び声に、彼女ははっと、顔を上げる。すると、真剣にこちらを見つめている、『龍の忍者』の姿が、そこにはあった。
「ハヤブサ様………」
「人質を助けに行きたい!! 力を貸してくれ!!」
「え…………?」
ハヤブサの申し出に、ナディール姫はかなり戸惑ってしまう。
人質を助け出せるのなら、もちろん自分はそうしたいし、その行為に反対する理由もない。
しかし、「力を貸してくれ」とは、どういうことなのだろう。
自分が、何かの役に立てるとは、到底思えないのだが─────
「わからないのか!? ナディール!!」
自分の申し出に、瞳をぱちくりとさせているナディール姫に向かって、ハヤブサはもう一度叫んでいた。
「今の話で、人質の居場所の検討がある程度ついている! だが、早急に救出に行くには、俺一人では無理だ!! お前の力が、必要なんだ!!」
「え………? 私の力が、ですか………?」
戸惑うばかりのナディール姫に、ハヤブサの言葉の補足説明をするべく、シュバルツが一歩、前に進み出た。
「あの『声』は、人質たちの居場所に関して、結構な手掛かりを残してくれた……。だから、迅速に対応できれば、十分に救出は可能だと思う」
「本当ですか!? それは!!」
シュバルツの言葉に、シェフはがばっと顔を上げた。シュバルツは、静かにうなずいていた。
「まず一つ。人質たちがいる場所には、水が流れ込む、と、あの声は言っていた。水は高いところから低いところに流れ込むのが常だ。だから、かなりの高確率で、人質たちは地下に居る、と推測ができる」
「地下………!」
ナディール姫は、はっと息をのむ。
脳裏に、この町全体に張り巡らされている、複雑な地下水路の景色が浮かんだ。
「二つ。あの声は、ある門を閉めなければ、人質たちがいる場所に、3時間ほどで水が流れ込む、と、言っていた。と、言うことは、流れ込む水の取水口は、水の中に沈んでいる場合と、そうではない状態の時がある、と、言うことになる」
「………! と、言うことは、水は海から流れ込む、ということですか?」
シェフの問いに、シュバルツはうなずく。
「その可能性が高いな。潮の満ち引きが確認できれば、もっと確証が得られるのだが………」
そう言いながら、シュバルツは厨房の入り口付近で、倒れた仲間を手当てしている兵士たちに、視線を走らせる。
「誰かこの中で、今日の干潮と満潮の時刻を分かる者はいないか?」
「俺が分かります!」
兵士の一人が手を上げた。
「お前、そんなものをチェックしているのか?」
同じく倒れた兵士を手当てしていた同僚に、問いかけられたその兵士は、「俺の祖父ちゃんが漁師なんだよ」と、多少苦笑気味に答えていた。
「漁師にとって、潮の流れを把握するのは、必要不可欠なことだからな……。祖父ちゃんがしょっちゅう潮の満ち引きを確認してくるから、俺もチェックする習慣がついちゃって………」
そう言いながら、その兵士は、懐から取り出した携帯端末を、素早く操作する。彼がその時刻を把握するまで、30秒とかからなかった。
「午前2時35分! 満潮! 今から約、3時間後であります!」
その答えに、周りの兵士たちからも、おお、と、声が上がる。シュバルツも、「やはり、そうか」と、頷いた。
「そして3つ目。人質たちが監禁されている場所は、おそらく、ここからそんなに離れてはいない……」
「なぜ、そんなことが分かるんです?」
眼をしばたたかせながら問いかけてくるシェフに、シュバルツは微笑みかけた。
「シェフ、貴方の料理が、人質たちに届けられていたからだ」
「─────!」
その言葉に、一同ははっと息をのむ。
「ここからかなり離れているのなら、そんなことは不可能なはずだろう。実際、貴方の料理が届いているのなら、それが可能な距離に、人質たちは居る─────と、言うことになる」
「あ…………!」
「分かるか? 姫……」
呆然とたたずむナディール姫に、ハヤブサは改めて声をかけてきた。
「ハヤブサ様………!」
「地下。海から流れ込む取水口とつながっていて、この近辺─────ここまで、人質たちの場所の見当はついているんだ。姫、心当たりはないか? 人目につかず、人質を監禁可能な空間がある、この近くの地下の場所を────」
「………………!」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫の頭の中に、いくつかの場所が思い浮かぶ。ナディール姫は、ぎゅっと、こぶしを握り締めていた。
(助けられる………?)
目の前に現れた、小さな希望の光。
あとはそれを、つかむか否かだ。
リスクはある。
今は夜。昼でさえ暗い地下など、ふつうは、誰も入っていかない。複雑に入り組んだその水路は、不用意に入り込んだ者を、容赦なく暗黒の深淵へと、飲み込んでいってしまうだろう。
それに、先日、自分たちを襲ってきたモンスターの存在も気がかりだった。
あれにまた襲われたら─────
(怖い…………!)
恐怖に胸が詰まる。
だけど────
「………………」
ナディール姫は、すがるように見つめてきている、シェフの顔を見る。
自分を、まっすぐ見つめている、ハヤブサの顔を見る。
(行こう)
恐れる必要も、迷うこともない、と、思った。
皆を『守る』のが、自分の役目であるし
自分には、『最強の護衛』が、ついてくれているのだから。
「分かりました………。行きます」
頷いたナディール姫に、周りから、おお、と、ため息のような歓声が上がった。
「姫さま!」
「姫さま! 我らもお供いたします!」
共に行くことを志願した兵士たちに、しかし、ナディール姫は、首を横に振った。
「いいえ、大丈夫です。それよりも貴方たちは、仲間の手当てと、城のことを………シェフを、頼みます」
「姫様………!」
「あなた方は、大丈夫ですか………?」
姫はそう言いながら、倒れている兵士たちのそばに駆け寄る。
「わ……! 我らは、大丈夫であります!」
「かすり傷なので………!」
「そう………。よかった………」
負傷した兵士たちだが、みなそういって元気に答えていた。死人が出なかったのが、不幸中の幸いだったと、ナディール姫は、ほっと、胸をなでおろしていた。
「シェフ………」
ナディール姫は立ち上がり、シェフの方を見つめる。
「姫様………」
「………………」
(この人を本当に、ひどい目に遭わせてしまった………)
そう感じたナディール姫は、いつしか唇を強くかみしめていた。
彼のみならず、その家族までも、命の危険にさらしている。
自分が生きているだけで迷惑をかけてしまった、まさにその典型だと、思った。
彼に泣いて謝りたい。
死ぬほど、自分を責め抜きたい。
でも、今はまだ、それをするべきではないと、感じる。
彼に、彼の家族を返さなくては。
すべては、それをしてからだ。
そう強く決意して、それから彼女は、ハヤブサの方に振り返った。
「ハヤブサ様、行きましょう」
ハヤブサはうなずく、姫を連れて部屋から出ていこうとする。それを、「待ってください!」と、兵士たちが呼び止めた。
「貴方たち………連れて行くわけには───」
少し困ったように立ち止まるナディール姫に、兵士たちは「違います!」と、首を振りながらも、次々と声をかけてきた。
「姫さま! 地下に潜るのならば、きちんと準備をしていった方がいいです!」
「このライトをお持ちください!」
「手袋も!」
「ロープもありったけあったほうがよろしいのでは!?」
「そうだな、ロープはあった方が助かる」
その提案にハヤブサがうなずくと、兵士の一人が「分かりました!」と、走り出す。
「俺は、イガール隊長に、報告してくるよ」
「イガール隊長はどこにいるんだ? 宿舎か?」
傷ついた仲間の手当てをしながら問いかけてくる兵士に、隊長の方に行きかけた兵士は苦笑しながら答えた。
「いや、執務室に居たと思うよ。あの人、相変わらずいろんな用事に振り回されていたから、仕事が終わってないみたいなんだ。確か報告書を書くとか何とか言って、執務室に行くとか言っていたから……」
「隊長、執務室で寝ているんじゃないのか?」
「あり得るな……。いくら城の警備を強化しても、次々と入り込んでくる姫様に対する刺客に、隊長、だいぶ悩んでいたから………」
(イガール………!)
兵士たちの会話に出てくるその名前に、ナディール姫の心はざわめき、自分のことで、彼の心を煩わせてしまっている事実に、心を痛める。
でも、ほんの少し
「うれしい」と、感じてしまうのはなぜだろう。
自分のために、彼が心を砕いてくれている事実が『嬉しい』
不謹慎だ。
彼はそのせいで、深く悩んでしまっている、というのに。
「ナディール、どうした?」
「………………!」
ハヤブサに声をかけられ、ナディール姫ははっと我に返っていた。
「いえ、何でもありません。行きましょう、ハヤブサ様」
そう言って、ナディール姫は厨房から出ていく。ハヤブサも、あとについて、出て行った。
「…………姫様………!」
その後ろ姿を見送ったシェフが、頽れるようにうずくまっている。そこにシュバルツが歩み寄り、そのそばに膝をついていた。
「……ハヤブサは、『助ける』といえば、必ずそれを成し遂げる男です。ですからシェフも、絶望に早まらず、信じて待っていただけませんか?」
「君は………!」
シュバルツの顔を見て、シェフははっと息をのんだ。
「………今日採用した、新人の『給仕』だね……。すまない………。私は君が、理不尽に八つ当たられたり、暴力を振るわれたりしているのを、見て見ぬふりをしていたのに………」
「や、私は平気なんで、どうか、お気になさらずに」
シュバルツは苦笑しながら、首を横に振る。
あれは、相手の油断を誘うために、わざと受けていたようなものであるから、自分としては、痛くもかゆくもないのだが。
(やはり、周りにいらない気を遣わせるのが、この手法の欠点だな……。もう少し改善の余地はあるか…………)
シュバルツがそう考え込んでいたところに、ロープを持った兵士が、厨房に走りこんできた。
「ロープを持ってきた! 姫様は!?」
「さっき、ここから出て行ったぞ」
「そうなのか? どっちへ行ったんだろう………!」
ロープを持ったまま、途方に暮れる兵士だが、思わぬところから助け舟が入った。
「地下への入り口なら、俺、分かるぞ」
「本当か!? モガール!」
名乗り出てきた同僚に、驚く兵士たち。モガールは頷いた。
「お前、どうして地下への入り口なんて、知っているんだ?」
「あははは……ちょっと、いろいろあって………」
同僚の疑問を、モガールは苦笑いでかわす。まさか、ナディール姫本人と、心ならずも地下を探検してしまったこと、言えるわけもない。
「ま、まあ、とにかく急ごう。事態は一刻を争うんだ。場所が分かるなら案内してくれ」
「OK ‼ 任せてくれ!」
「私も行こう」
走り出そうとした兵士たちに、シュバルツが声をかける。
「貴方は?」
問うてくる兵士に、シュバルツは軽く笑って答えた。
「怪しい者じゃない。ハヤブサの『友人』だ」
その言葉に、周りの兵士たちから、「おお」と、どよめきが上がる。
「やはり、お強いんですか?」
「『忍者』なのですか?」
興味津々な眼差しと質問の数々に、シュバルツは苦笑するしかない。
(おいおい………。ハヤブサの奴、何をやらかしているんだ………!)
ハヤブサが何か、兵士たちの尊敬を浴びるような行為をしたのは一目瞭然だが、どうしてこんな風に変に『忍者』に興味を持たれているのだろう。
「その質問には、追々答える。だが今は、一刻を争う事態なのだろう? 先を急ごう」
「そうですね!」
「急ぎましょう!」
ロープを抱えた兵士とシュバルツは、モガールを先頭に、厨房から走り出していた。
ナディール姫とハヤブサには、すぐに追いつくことができた。ナディール姫が一度部屋に寄り、身軽な格好に着替えていたため、まだ地下の入り口まで行っていなかったのだ。
「姫さま!」
「ハヤブサ殿! ロープをお持ちしました!」
兵士から渡されたロープを、ハヤブサは受け取る。その後ろにシュバルツがいるのを見て取ると、ハヤブサは、彼に声をかけていた。
「シュバルツ、入り口まで、ついてきてくれるか?」
「それはお安い御用だが………中まで入らなくて、いいのか?」
問い返してくるシュバルツに、ハヤブサは頷く。
「ああ……。お前には、『命綱』を託したい」
「……………!」
少し驚くシュバルツに、ハヤブサは軽く笑った。
「俺は夜目も利くから、闇を恐れるものではないが………地下の通路は入り組んでいて、構造も複雑だ。どこを通ってきたか確認する意味と、脱出をたやすくするために、俺はこうして、ロープを身体に巻き付けて、地下に入るから────」
そう言いながら、龍の忍者は己が体にロープの端を括り付ける。それを終えてから、ハヤブサはシュバルツに、ロープを託した。
「シュバルツ。それを持って、ここで待っていてくれるか? 何かあれば、合図をよこす」
「分かった」
シュバルツが頷き、ロープを手に取ったのを確認してから、ハヤブサは踵を返す。ナディール姫とともに、地下への入り口に入ろうとしたとき、兵士たちが、姫に呼び掛けた。
「姫さま!」
「何?」
振り向くナディール姫に、兵士たちは明るく笑いかける。
「姫さま! 頑張ってください!」
「応援してます!」
「俺たちはいつだって、あなたの味方ですから!」
「ありがとう」
ナディール姫が微笑むのを見て、兵士たちも嬉しそうに笑った。
「では、行ってきます。後を、頼みます」
そう言って、姫とハヤブサは、地下へ続く通路の中へと入っていく。兵士たちは、そんな彼女たちを、「頑張ってください!」と、大きく手を振りながら見送っていた。
「姫様…………無事に、シェフのご家族を見つけられるといいな……」
同僚の言葉に、モガールも頷いた。
「そうだな…………」
そのまま、しばし地下通路の入り口を見つめていたモガールであるが、やがて、ポツリとこう言った。
「なあ、ヤッセ………。今、俺たちの国は、王が病気でお倒れになってから、後継者の問題で、少し揺れているけれど………」
「うん」
ヤッセと呼ばれた同僚の兵士は、同意をするために頷く。
「俺は、もし『主君』を選べるのなら、姫様がいい、と、思っている………」
「モガール………」
少し驚くヤッセを、モガールはまっすぐ見つめ返した。
「だって姫様は、どんなに危地に陥っていても、絶対に、俺たちを見捨てようとはしなかったんだ………」
そう言いながらモガールは、姫と街を散策した時のことを、思い出していた。
彼女は、刺客に襲われて逃げる時も、常にこちらに気を配っていた。
モンスターに囲まれた時も、こちらを必死に庇おうとしてくれた、あの手の震えを、いまでも鮮明に思い出すことができる。
あの時に決めた。
自分が命懸けで守るのは、この人なのだと。
「そうだな………。俺も………」
ナディール姫が、常に周りのことをおもいやり、行動している姫であることを、ヤッセもよく承知していた。だから、モガールの言っていることが、よくわかった。
「誰が何と言おうと、俺も、姫様の味方になるつもりだ」
ヤッセの言葉に、モガールもうん、と、頷く。
「…………………」
シュバルツも、黙って横で話を聞いていたが、ナディール姫の人柄を理解していた。
(そうか……。だからハヤブサも、必死になって彼女を守ろうとしているんだな………)
ハヤブサが仕事熱心なのはいつものことだが、この仕事に関しては、特に力が入っている、と、シュバルツは感じていた。
普段通りのハヤブサであるなら、彼が『仕事』をしている場に自分が顔を出したならば、まず怒る。有無を言わさず、追い返そうとしてくるのが常であったのに。
今回に限っては、それがない。それどころか、彼女を守るために、自分に頼ることを、躊躇うことすらしなかった。
それだけハヤブサも必死なのだ。
ミッションの達成以上に、彼女を守りたい、と、彼も願っているのだろう。
シュバルツは、祈る。
どうか、『悪意』に負けないでほしい、と。
『生きているだけで迷惑をかける』
それは、ある意味当たり前のことなのだ。
人は、生きている限り、場所をとる。
他者とのかかわりを持たずには、いられなくなる。
『迷惑』をかけずに生きている人間など、この世にはいないのだから。
「…………………」
こうしている間にも、縄が、シュバルツの手の上を滑っていく。ハヤブサの動きを感じていた。
「俺、もう少し継ぎ足す用のロープを持ってきます!」
「俺も手伝うよ!」
そう叫んで、モガールとヤッセが走り出す。
(ハヤブサ………! 姫………! 二人とも、どうか無事で………!)
シュバルツもまた、そう祈りながら、わずかな合図も捉え漏らしがないよう、その手に全神経を集中させていった。
「真っ暗………!」
地下に降り立ったナディールは、思わずそう漏らしていた。兵士たちに借り受けたライトを点けても、あまり視界が確保できないので、少しの心細さを感じた。
「そうでもないぞ? ところどころに光が差している……。今宵は、月が明るいんだな」
対してハヤブサは、自身も闇の中に溶けませながら、そんなことを言っている。
「そうなんですか?」
ナディール姫は、きょとん、としながらも、ハヤブサの言葉に従って、目を凝らしてみる。すると確かに、通路のあちこちに、青白い光がわずかに差し込んでいるのが見えた。
「きれい………」
思わず、素直な感想が、漏れ出てしまう。この時間に、この通路に来ることなどなかったから、余計に、未知の景色に感動を覚えていた。
「のんびり感慨にふけっている暇などないぞ、ナディール」
苦笑しながらもハヤブサは、彼女にそう声をかける。闇に怖気るどころか、その美しさに感嘆の声を上げる彼女の姿は、素直に好ましいと思ったが。
今は、一刻を争う事態なのだから。
「ここからは、お前の地下通路に関する知識が頼りだ。この近くで、満潮時に水中に沈むのはどのあたりだ?」
「それはこっちです。こっちの方────」
ハヤブサの問いに、ナディール姫は淀みなく答える。
「この先に、下に降りる階段があるんです。その先は、満潮時には水がたまっていて、進めなかった覚えがあるから………」
果たして彼女の言葉通り、少し進めば下に向かって階段が伸びていた。ハヤブサたちは、迷わず下に向かって階段を駆け下りていた。
階段を降りると、少し開けた空間に出た。地面にはところどころ水がたまっていて、二人が足を踏み出すたびに、水滴がパシャリと、音を立ててはねた。
「この辺りで、人を監禁できるような場所に、覚えはないか?」
「わ、分からない……! 『人を閉じ込める』なんて、そんな考えで、この辺りの景色を見たことなんかないもの………!」
(それはそうだ)
自分の問いかけに戸惑うナディール姫の姿に、ハヤブサはある意味納得する。
この優しい姫は、そんな風に人を陥れることなど、考えたこともないのだろう。
「誰かいないか!?」
だからハヤブサは、まず大声で、呼びかけてみることにした。
敵であろうが味方であろうが、誰かいるのなら、反応が返ってくるはずであるから。
「…………………」
暗い通路に、ハヤブサの声の残響音が響く。しばし、耳を澄ませてみるが、帰ってくる反応は、皆無であった。
「ロアンヌさん!! ミレイさん!!」
ナディール姫も、ハヤブサに倣って呼びかける。しかしやはり─────声は暗黒に吸い込まれるばかりであった。
(この近くには、いないのか………?)
ハヤブサがそう考え込んでいると、ナディール姫から「ハヤブサ様」と、呼びかけられた。
「どうした? ナディール」
「この水路は、もう少し先に続いているんです。もっと進んでみましょう」
「そうだな」
姫の提案に、ハヤブサも素直に従っていた。
二人とも、人質を見つけるまでは帰らない────
その強い想いで、一致していた。
「大変だ!!」
一方厨房では、イガール隊長の様子を見に行っていた兵士が、血相を変えて走りこんできていた。
「どうしたんだよ? セペタ」
問う兵士に、セペタ、と呼ばれた兵士は、慌てふためきながら答えた。
「イガール隊長が、泡吹いてぶっ倒れてる!!」
「ええっ!?」
「かろうじて意識はあって、『水……………。水……………』って、うわごとみたいなことを言っていたから、取りに来たんだけど………」
「大変だ………!」
その場にいた兵士たちの顔から、さ~っと、血の気が引いていく。
「と、とにかくそこのコップに水を入れて、持っていこう!」
「担架は居るか?」
「用意しておいた方がいいかもな」
「俺たちはもう大丈夫だ……! だから、イガール隊長の方へ行ってくれ!」
手当てを受けていた兵士たちが叫ぶ。その言葉を受けた2、3人の兵士たちが、水を持って、あわただしく厨房から出て行っていた。
「………まさか、イガール隊長まで、『毒殺』されかけた、とか………?」
厨房に残った兵士たちで、イガール隊長が倒れた原因の推理大会が始まる。
「いや、それはないだろう。どっちかといえば、『過労』の方じゃないのか?」
「ここ最近、隊長が俺たちより早く帰るところ、見たことないもんなぁ」
「ていうか、宿舎に帰っているのか?」
「寝ていない可能性も────」
「…………………」
兵士たちの話を聞きながら、シェフは静かに立ち上がった。自分の本分を、思い出したのだ。
(そういえば、明日の料理の仕込みの途中だった…………)
ガステーブルの上に、スープの鍋が乗っている。いろいろあったせいで、料理は中断してしまい、当然のことながら、中のスープは冷めてしまっていた。
(このスープ…………もう、明日の料理には使えないな………)
シェフはそう感じてため息を吐く。このような中途半端な料理など、王族の方たちに出せようはずもない。だから、本来なら、捨てなければならないものではあるのだが────
(イガール殿の栄養補給には、ちょうどいいものになっているかもしれない………)
そう思ったが故に、シェフはそのスープを温めなおしていた。
「………………」
ガスコンロの上で、順調に鍋が熱せられ、小さな気泡が、鍋の底からスープの中に沸き立ってくる。厨房の中に、おいしそうなスープの匂いが立ち込め始めた。
「お、いい匂い」
「本当だ………」
兵士たちもしばし、調理場に立つシェフの後姿を見つめる。
コト、コト、と、小さく音を奏でる鍋。
「…………………」
味見をして、調味料を少し足す。味が整ったところで火を止め、小さな器にスープを入れて、シェフは振り返った。
「………どなたかこれを、イガール殿のところに持って行ってくださいませんか?」
「隊長に?」
少しびっくりしたように問い返す兵士に、シェフは頷いた。
「……お話から察するに、イガール殿は食事もろくに取られていないご様子……。ですので、どうかこれを。イガール殿の、助けになるかと思います」
「分かりました! そういうことなら! 隊長も、喜ぶと思います!」
兵士の一人がそう言って立ち上がると、最敬礼をしてスープを受け取る。そのまま彼は、スープを大事そうに抱えて、厨房から出て行っていた。
「………あなた方も、どうですか?」
その兵士を見送ってから、シェフは厨房に残っている兵士たちの方に振り向く。
「えっ!? いいんですか?」
驚く兵士たちに、シェフは、小さく笑って答えた。
「ああ。どうせこれは、捨てなければならないものだ。それならば少しでも、君たちの足しになれば……………」
「本当ですか!? シェフ!!」
「うわあ! やったぁ!!」
「そういうことなら、喜んで!!」
兵士たちは喜び勇んで、器を持ってシェフの前に並びだす。それからしばらく厨房の中は、スープの香ばしいにおいと、それを食べる兵士たちの、温かい笑顔であふれていた。
(やはり、皆の幸せそうな笑顔はいいな………)
皆の、その幸せそうな顔を見ながら、シェフは、自らの原点を思い出す。
自分の作った料理で、皆に、幸せになってもらいたい。
その願い一つを抱えて、自分は、この道を歩む決心をしたのではなかっただろうか。
それなのに、自分は何をやっていたのだろう。
家族に迷惑をかけ
姫様に、迷惑をかけ
挙句─────
シェフは、思う。
もう自分には、『城のシェフ』として、料理を作る資格など、ありはしないのではないだろうかと────
(だが、明日の朝食は作らねばならないだろうな………)
そう感じて、シェフは深いため息を吐く。
今自分が身を引いたら、実際問題として、明日の王族の朝食に、大きな影響が出てしまう。ただでさえ、周りに迷惑をかけすぎている自分。これ以上、迷惑をかけるわけにはいかない、と、思った。
進退を決めるにしても、朝食を作った後にしなければ、と、シェフが考えていた時、イガール隊長が、兵士たちに付き添われながら、厨房に入ってきた。
「隊長!」
「隊長!? 大丈夫ですか!?」
食事をしていた兵士たちが、皆一斉に顔を上げ、彼の方を見る。イガールは、そんな兵士たちに、ふらふらと力なさげに手を上げて応えると、よろよろと、シェフの方に歩を進めていた。
「シェフ………すまないが…………」
「ど、どうしました?」
イガールのあまりの顔色の悪さに、シェフは思わず息をのむ。案ずるように彼を見つめるシェフの前に、イガールがふらふらと、空になった器を差し出してきた。
「………さっきのスープの………お代わりを、もらえない、だろうか…………?」
「お代わりですか?」
驚いたように問い返すシェフに、イガールは「ああ」と頷くと、その場でしくしくと泣き出した。
「実はさっきのスープを飲んだことで………昨日から、何も食べていないことに気が付いてしまって………!」
(ああ………)
(隊長………! それで………)
イガールの言葉に、その場にいる皆が、体調の悪そうな彼の状態に納得する。
それもそうだ。
あれだけ激務をこなしているイガールが、何も食べていないのなら─────なるほど、倒れそうにもなるわけだ。
「分かりました。どうぞ」
シェフは軽く苦笑しながらも、イガールにスープをよそう。
「ありがとう」
イガールは、丁寧に頭を下げると、手近にあった椅子に座り、静かにスープを飲み始めた。
「ああ………人心地が付く………」
「………………」
スープを飲みながら、心底ほっとしたような表情を浮かべるイガールを、シェフは黙って見つめていたが、やがて、また、調理場に向かっていた。
「………もう少し、何か食べられるのなら、食べたほうがいいかもしれませんね……。何か作りましょう。ありあわせの物ですから、簡単なものしか作れませんが………」
「いや、しかしそれは─────」
遠慮しようとしたイガールを、シェフは手で制した。
「どうか遠慮なさらずに………。余っている食材です。それが、誰かの力になるのなら────食材たちも、本望でしょう」
「そうですよ! 隊長! 食べないと!」
「こんな大変な時に……倒れている場合ではないでしょう!?」
シェフの言葉を受けて、兵士たちも、彼に食事を強く勧める。
「そうか………。そうだな………」
兵士たちの言葉に、イガール隊長も納得したようにうなずくと、改めて椅子に腰を掛けなおしていた。
「………………」
しばらく、シェフの調理する音が、厨房に響く。やがて、おいしそうな匂いが、厨房に満ち始めていた。その匂いに、食欲をそそられた兵士たちの腹が、ぐう、と、元気良く音を立てる。それを聞いたイガールが、軽く苦笑しながらも、シェフに声をかけていた。
「シェフ、申し訳ないが、ここにいる皆の分も、少しでいいから作ってやってくれないか? 皆、腹が減っているようだ」
「もちろんです。最初からそのつもりで、少し多めに作っています。皆さんの分もありますよ」
「ええっ!? 本当ですか!?」
「やった………!」
喜ぶ兵士たちの顔を、見るともなしに見ていたイガールであるが、あることに気づいて、その顔色が変わった。
「怪我をしている者がいるな……。どうした? まさか………!」
「いや、これはその」
「ちょっと………」
「姫様を狙う刺客に、襲われまして………」
「ええっ!?」
大声を出して、はじかれたように立ち上がったイガールであるが、またへにゃへにゃと、座り込んでしまっていた。
「た、隊長!? 大丈夫ですか!?」
「あ、あの……! そんなに心配しないでください! 我々は、大した怪我はしていませんので!」
慌ててフォローしに来る兵士たちを、イガールはちらりと見やると、頭を抱えながら、深いため息を吐いていた。
「………なぜ、こうも姫様を狙う刺客が、何人も入り込んでくるんだ……。警備は強化しているはずなのに………」
そう言いながら、頭を抱え込んでしまうイガール。兵士たちもそんな隊長に、声をかけようがなくて、おろおろするしかなくなってしまう。
「た、隊長………」
「あまり思いつめないで………」
「ハヤブサ殿も、姫様のそばにいてくださっていますから………」
「あの方がいらっしゃる限り、姫様は安全ですよ」
「それはそうかもしれないが………」
兵士たちの言葉に、イガールは軽く笑みを見せる。だが、その表情はすぐに暗く曇ってしまった。
「姫様…………」
切羽詰まったように落とされる、イガールの言葉。厨房の中に重苦しい空気が立ち込めたが、そこにシェフの料理が、コトン、と、音を立てて、イガールの目の前の、テーブルの上に置かれた。
「どうぞ……。お口に合うかどうかはわかりませんが………」
丁寧に煮込まれた野菜と肉の匂いが、皆の鼻腔と食欲をくすぐる。
「ありがとう」
礼を言って、一口目を味わう。
「………………!」
次の瞬間、イガールの食事の勢いが増した。どうやら、かなりおいしかったらしい。
勢いの良い食べっぷりに、シェフの表情が優しいものになる。
「皆さんもよろしければ、どうぞ」
シェフの勧めに、兵士たちから歓声が上がる。そのまま厨房は、しばし夜食タイムになだれ込んでいた。
「そういえば、姫様はどうした? もう部屋で、寝ておられるのか?」
ある程度食事を終え、落ち着いたのか、だいぶ顔色の良くなったイガールが、顔を上げて兵士たちに問いかける。
「あ………えっと………」
兵士たちは、互いに顔を見合わせていた。
どこまでこの隊長に報告をしたらいいのか、皆が、それぞれ図りかねているらしい。
「…………………」
しばし、奇妙な沈黙が、厨房を支配する。そんな中、シェフが、イガールの方に、一歩、前に進み出ていた。
「…………イガール殿………」
「どうしました?」
暗く、沈痛な面持ちのシェフを、イガールが怪訝そうに見上げる。しばし、シェフの口元が逡巡するかのように、小さく震えていたが、やがて、意を決したのか、その顔を上げていた。
「…………実は、私は…………」
(………………!)
ここで、兵士たちははっと気が付いた。
まさか、シェフは
イガール隊長に、姫様を毒殺しようとしたことを
打ち明ける気 なのでは─────!?
だめだ、と、その場にいた全員が、思った。
だって、シェフこそが、
姫様の刺客たちによる、一番の『被害者』なのではないのか。
だから、兵士の一人がとっさに叫んでいた。
「隊長!! 実はシェフは、人質を取られているようなのです!!」
「人質!?」
物騒な言葉の響きに、イガール隊長は、思わず素っ頓狂な声を上げてしまう。それに兵士たちは各々「はい」と、頷くと、それぞれに言葉を続けていた。
「奥さんと、娘さんが、姫様を狙う刺客に、人質として取られたらしくて」
「ここに勤めていたコックの一人が、手引きをしていたようであります!」
「その刺客は、『その男は始末した』みたいなことを言っていたな」
「人質の存在を知った姫様が、ハヤブサ殿と一緒に救助に向かわれていて………!」
「姫様が!?」
さらに、驚くべき単語が兵士の口から出てきたから、イガールの顔色が、さ~~~~っと、青白くなっていく。
「あああ、隊長!」
「馬鹿ッ! 余計なことを言いやがって! せっかく隊長の顔色がよくなってきていたのに!」
「だ、だってよ……! 姫様のことも、報告しないわけにはいかないだろう……?」
「そ、それはそうかもしれないが………」
「いや、ぜひ報告してくれ。警備隊隊長として、姫様の動向は知っておかねばならぬ。君の判断は正しい………」
そう言いながら、イガール隊長は、改めて椅子に座りなおす。
「…………で? 姫様がどこへ救助に向かわれたか、分かっているのか?」
「あ…………えっと………」
兵士たちは、ここでも互いに顔を見合わせていたが、やがて意を決した一人が、口を開いていた。
「姫様は…………地下へ向かわれました」
「地下だと!?」
そう叫んだイガール隊長の顔色が、青いのを通り越して、真っ白になってしまっていた。
「クシュン!!」
地下に、ナディール姫のかわいらしいくしゃみが、響き渡る。
「風邪か?」
そう問うてくるハヤブサに、彼女は首を横に振った。
「いえ、平気です。大丈夫………」
そう言いながら、彼女は周りを見渡す。
もう何度も、シェフの奥さんと娘の名前を呼んだ。しかし、何の反応もない。
(この辺りには、いないのかもしれない………)
そう考えた姫は、断を下した。水没する地下通路は、確か、ここだけではなかったはずだ。
「ハヤブサ様」
「ん?」
答える龍の忍者に、姫は言葉をつづける。
「これだけ呼び掛けても反応がない、と、言うことは、この辺りにはいらっしゃらないかもしれません………」
「確かにな」
「ほかにも、水没する水路があります。そちらを回ってみましょう!」
「承知した」
ハヤブサは、姫の提案に頷くと、彼女の手を引いた。
「では、行くぞ! 案内をしてくれ」
「はい!」
ハヤブサは、来た道をUターンする。ロープがもつれて絡まるか、と、一瞬思ったが、すぐに、その心配は杞憂であることに気が付いた。ロープは、ハヤブサの動きを制限することなく、絡まることもなく、ハヤブサに忠実についてきてくれている。
(シュバルツ………!)
彼の存在を、彼のサポートをロープ越しに感じて、ハヤブサは嬉しくなってしまっていた。
(このロープ………彼とつながっているんだよな………)
いかん、いかんと思っていても、ついつい、幸せに浸ってしまう。その頬が緩むことを、抑えることができなかった。
ああ………
つながっているこのロープが
俺とお前の『赤い糸』となって
永遠に二人を、離さなければいいのに────
「ハヤブサ様!」
あることに気づいたナディール姫が、大声で叫ぶ。
「危な─────!」
ゴン!!
派手な音を立てて、ハヤブサが前方の岩肌にぶつかっていた。
「だ、大丈夫、ですか………?」
痛みにその場にうずくまってしまうハヤブサに、ナディール姫が恐る恐る声をかける。
「へ、平気だ……。大丈夫………」
ハヤブサは必死にそう返すが、痛みで涙がにじむのを、抑えることができない。
(阿呆か、俺は……! 今は仕事中だ! こんなめでたい感慨に、ふけっている場合ではないというのに…………!)
懸命に、痛みと格闘するハヤブサ。ナディール姫は、しばらくそんな彼をじっと見つめていたが、やがて、「クスッ」と、小さく笑っていた。
(笑った?)
思わず顔を上げるハヤブサ。そんな彼と目が合ったナディール姫は、はっと、息をのんで口元に手を当てていた。
「あ…………! ごめんなさい……。こんな時に、不謹慎、ですよね………」
慌てて謝るナディール姫に、ハヤブサも「いや………」と、返す。『不謹慎だ』というのなら、それは、お互い様だと思った。
そう、不謹慎だ。
人質の命が、かかっているのに。
だが、『笑える』と、言うことは、彼女が精神的に安定しているということを表している。それは、悪いことではない、と、ハヤブサは思った。
「さあ、ナディール。次は、どっちへ進めばいい?」
「はい。もう一つ右の階段を下りてみましょう。あの先にも、少し拓けた空間があったはずです」
「よし」
姫の案内に、ハヤブサは素直に従っていた。
「誰かいないか!?」
行く道々で、ハヤブサは大声を出す。
「ロアンヌさん!! ミレイさん!! いたら返事をして!!」
ナディール姫も懸命に呼びかけるが、相変わらずこちらの声に対する反応はない。ただ、残響音が、空しく闇に吸い込まれていくだけだった。
「ここにもいないのかしら………!」
人質がなかなか見つからない事実に、ナディール姫は少し焦り始める。
「焦るな、ナディール」
彼女の焦燥を感じ取った龍の忍者が、そう声をかけてきた。
「人質は、必ずこの近くにいる。探していけば、必ず見つかる」
「ハヤブサ様………!」
「今、一番やってはいけないことは、探すのをあきらめることだ。違うか?」
「あ……………!」
その言葉に、ナディール姫は、はっと息をのむ。
そうだ。
ここで自分たちが手を引いてしまったら
シェフの奥さんと娘さんは、永遠に助けられなくなってしまう───!
「大丈夫だ。満潮まであと2時間以上はある。落ち着いて────確実に一つ一つの場所を、探していくんだ」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫は「はい」と、返事をする。ハヤブサも「よし」と、頷いた。
「さあ、見つけるまで走るぞ! 必ず人質たちは近くに居る。声をかけ続けるんだ」
そうして二人は、再び走り出す。必死に、声を張り上げながら。
「ロアンヌさん!! ミレイさん!! いたら返事をして!!」
ナディール姫の声が、地下通路に響き渡っていた。
「……………」
牢の中でロアンヌは、寝苦しさを感じていた。
(なぜ、こんなに眠れないのかしら………)
ロアンヌはそう感じて、寝台から身体を起こす。窓から差し込む月の光が、とてもきれいだと思った。
この牢に監禁されてから、もう一週間近く経つ。
いろいろと不自由もあるし、不安も尽きないが、唯一ここにきて、嬉しかったことは、『良人の料理が食べられる』と、言うことだった。
(あの人の料理をこんなに食べられるなんて……いったい何時ぶりだろう)
月明りを見つめながら、ロアンヌは思い出に浸る。
出会ったときは、あの人はまだ見習いだった。
厨房の片隅で、黙々と皿を洗い、先輩について、懸命に料理の技術を磨いていた。
城仕えのメイドの仕事で、遅くまで城に残っていた私に、よく賄いを食べさせてくれた。
「俺はいつか、料理を極めたい。食べた皆が、幸せな笑顔になってくれるような、そんな料理が作れる、シェフになりたいんだ」
それがあの人の口癖。そしてほどなく、私は彼にプロポーズされていた。
彼曰く、「君の料理を食べる顔が好きだから」という理由らしかった。私は、彼の料理を、よっぽど幸せそうな顔をして、食べていたのだろう。
それから幸せな蜜月期を経て、一人の娘───ミレイにも恵まれた。
そして、丁寧な料理を作り続けていた彼は、城の厨房で認められ、いつしかそこの最高責任者である『シェフ』の称号を、その肩に背負っていた。
彼は城の厨房に詰めるようになり、家に帰ることが少なくなっていた。
結果、私は、いつしか彼の手料理を、食べる機会も減ってしまっていた。
だけど、彼は幸せそうであったし、自分も特に、その状態に不満があるわけでもなかった。
一人娘のミレイも、気立ての良い、やさしい子に育ってくれていた。
このまま、穏やかに年を取って、ともに死んでいくのだ─────と、なんとなく、思っていたけれども。
まさか自分の人生に、こんな『人質』として監禁される、という事態が起こるだなんて。
自分のことはいい。だけど、自分がここにこうして拘束されている事態は、彼に果てしなく迷惑をかけていることはもう、疑う余地もなかった。
どうして、自分は監禁されたまま、おめおめと生きているのだろう。
死んでしまった方が────
「駄目よ!! 母さん!!」
そう思うたびに、一緒に監禁されている娘に、強く励まされてきた。
「どんなことになっても、簡単に死ぬのはよくない! 絶対に、父さんを悲しませてしまうわ!」
娘の、強いまなざしが、自分をまっすぐに見つめてくる。
年若い彼女はいつだって、生きることをあきらめようとはしなかった。
「きっと、父さんだって歯をくいしばって耐えているのよ! 『私たちを助けたい』って。その想いを、無駄にしてはいけないと思うの!」
「ミレイ………」
「頑張りましょう、母さん。きっと生きていれば、助かるチャンスもあるはずだから────」
そう言って、前を向き続ける娘は、いったい誰に似たのだろう。
娘がいなければ、自分はとっくに死を選んでいたかもしれない。それほどまでに、ロアンヌにとって、彼女の存在は、大きな支えとなっていた。
(どうしたのかしらね。こんな、今までのことを物思うだなんて………)
まるで、走馬灯のような景色。まるで、自分が今から死ぬみたい、と、ロアンヌはそう感じて苦笑する。
自分はどうなってもいい。
だが、娘のミレイはまだ年も若く、先行きもある。何とか助かってほしい、と願っているが─────
(それにしても、やけに眠れないわね……。今宵は、本当にどうしたのかしら………)
そう感じたロアンヌは、寝台の上で姿勢を変えながら、窓から差し込む月明りを見る。
外から聞こえる波の音も、今宵はやけに近くに感じる。そのせいだからだろうか。
(本当にきれい………。今宵は、満月かしら………)
そう思いながら、しばらくぼうっと、波音を聞きながらその景色を見ていたロアンヌであったが、やがて、あることに気づいた。
(なんてこと……! 窓が閉められていない………!)
それが何を意味するのか。その恐ろしい事実に気づいたロアンヌは、思わず傍で寝ている娘のミレイをたたき起こしていた。
「ミレイ!! 起きてちょうだい!! ミレイ!!」
「う………ん…………。なぁに? 母さん…………」
もぞ、と、娘が寝台から起き上がる。それを待ちかねたかのように、娘に縋り付いていた。
「ミレイ!! どうしましょう……! 窓が開いている………!」
「え……………?」
母が何を言っているのか、咄嗟にをの意図をはかりかねる娘は、きょとん、と小首をかしげてしまう。母は、そんな娘に、懸命に訴え続けた。
「分からないの!? ミレイ!!」
「えっ? だから、何が?」
「あそこの窓が、開いているのよ!!」
「窓? 窓くらい開くでしょう?」
何当たり前のことを言っているのだろう、と、言わんばかりの娘に、ロアンヌは頭を振ると、必死に言葉を続けた。
「違うのよ!! いい? ミレイ……! この牢は、海より低い場所にある! あの天井近くにある窓でさえ、満潮時には沈むようになっているの!!」
「え? う、うん………」
「もうすぐ、海の潮が満ち、満潮になってくるはず……! いつもなら、あそこの窓が閉められているのに、今日は、閉められていない!!」
母の言う通り、確かに、あそこの窓が開いている。
「このままあそこの窓が閉められなければ、この部屋に海水が流れ込んできてしまう………! 私たちは、溺れ死んでしまうわ!!」
「──────ッ!」
母の言葉の意味を、ようやく娘も『理解』する。あまりにも絶望的な事態に、彼女も思わず息を呑んでいた。
「ま、窓……閉められないの……?」
娘の質問に、母は頭を振る。
「無理よ……。あんな高いところにある窓を、閉められると思う………?」
「………………!」
母の言葉に、娘は茫然と、天井近くにある、小さな窓を見つめる。
鉄格子のはめられた窓からは、青白い月の光が、部屋に差し込んできていた。そして、波音も響いてきている。
「今までは、時間になれば、あの窓は閉められていた……。だから、私たちはこうして無事に、過ごすことができていたのだけれど………」
「母さん………!」
「あの窓が、閉められていない、と、言うことは…………」
つまり、自分たち人質を『殺す』決定が、下されたということになる。ロアンヌはがっくりと、座り込んでしまっていた。
「そんな…………!」
ミレイが、茫然とつぶやく。その場にはしばし、重い沈黙が垂れ込めた。
「…………………」
(仕方がない………)
ロアンヌは、座っている間に、覚悟を決めた。
『人質』が殺される事態になる、と、言うことは、あの人が、私たちの命よりも、自分の命よりも─────自分の『信念』を貫いた、と、言うことになる。
それに殉じたが故の『死』であるというのなら、誰を恨むことがあるだろう。
ただ─────
自分よりはるかに年若いミレイが─────
母親が顔を上げると、ミレイが壁にとりついて、窓の方に向かおうとしている。しかし、垂直にそびえたつ壁は、ミレイに登られる事を、頑なに拒否していた。
「な、何をしているの? ミレイ……!」
ずるずると滑り落ちてきた娘に、ロアンヌが声をかける。
「何って………窓を、閉められないかな、と、思って………」
「だ、駄目よ! 危ないわ!!」
叫ぶ母親を、娘はちらりと見やると、その唇を尖らせていた。
「もうすぐ死ぬかもしれないって時に───『危ない』なんて言葉、意味がないわ母さん」
「………………!」
娘の指摘に、ロアンヌははっと、息をのむ。
確かに、そうかもしれないが────
「それよりも、どんなことをしてでもいいから、生き延びることを考えなくちゃ! 何もしないで、ただじっと死を待つなんて、私はいやよ。母さん」
「そ、そうかもしれないけれど……」
「協力して、母さん!」
娘は、母親の手をぎゅっと握る。
「何とか、生き延びる努力をしましょう!」
娘のまっすぐな眼差しを、ロアンヌは、ただ、見つめ返していた。
暗闇の中、ハヤブサとナディール姫の、走る足音が地下通路に響く。
(もう4か所回ったけれど………ここにもいない………!)
ナディール姫の顔には、焦燥の色が濃く浮かんでいた。ハヤブサに「焦るな」と忠告されるが、彼女はもう、気が気でなかった。あれから、どれだけ時間が過ぎたのだろう。海の水は、どれだけ満ちてきているのだろう。
「………………」
じりじりとした気持ちに襲われているのは、ハヤブサも同じだ。さすがに年季の入った地下通路。その入り組んだ複雑さは、捜索を容易にはさせてはくれなかった。ナディール姫の案内なくば、とてもここまで探して回ることはできなかったであろう。
焦るな。
落ち着け。
人質は、必ずこの近くにる。
生きて────救助の手を、待っているはずなのだから。
「ナディール、次へ行こう。これ以上向こうへ行けば、城から離れすぎてしまう」
「はい」
さんざん声を張り上げて、捜索した水路を後にする。ナディール姫は走りながら、必死に地下通路の構造を思い出していた。
(さっきの角から反対側に曲がったところの先にも、確か、下へ降りる階段が、あったはず………!)
「ハヤブサ様! こちらへ!」
「わかった!」
ナディール姫の案内に従って、ハヤブサは素早く壁に印をつける。自分たちがどこをどう走ったか、どこを捜索してきたか─────その印を見れば、一目瞭然になるようになっていた。
果たして、ナディール姫が指示した階段の先には、まだ何も印が付いていない。捜索がされていない通路だと確認してから、ハヤブサはその先に進んでいた。
階段を駆け下りて、しばらく行くと、龍の忍者の足が止まる。
「どうしました?」
問いかけてくるナディール姫に、ハヤブサは「シッ」と、唇の前に人差し指を立てて、(静かにしろ)と、合図を送る。
「……………!」
ナディール姫が、はっと身を固くして、ハヤブサの後ろに控える。ハヤブサは周囲の安全を確認してから、そろそろと壁際から奥の空間に、視線を送った。
「………ナディール、ビンゴかもしれんぞ」
「えっ?」
「………向こう側の通路に、『灯り』が見える」
「─────!」
ハヤブサの言葉の意味を悟り、息をのむ。
「ナディール………。このあたりに、城から通じる『地下室』があるのか?」
「いいえ」
ハヤブサの問いに、ナディール姫は首を横に振った。
「確かに、城に『地下室』の類はありますが………こんな場所にはなかったはずです」
「ここに、別の何かの施設があったりするのか?」
「いえ、そんな話も聞いたことはなくて………」
「なら、知らないうちに、ここに誰かが勝手に灯りを設置した、と、言うことになるな」
「………………!」
その言葉に、ナディール姫は、得体のしれない何かの『悪意』のようなものを感じて、身を固くする。ハヤブサは、そんな彼女の方に振り返ると、手を差し伸べた。
「この先へ行くが………ついてこれるか?」
「行きます」
ナディール姫は即答していた。ここまで来て、「引き返す」という選択肢は、彼女の中には存在しなかった。
「よし」
ハヤブサは頷くと、静かに歩き出す。ナディール姫も、その後ろを、静かについていった。
しばらく歩くと、ハヤブサが手を出して、ナディール姫に、それ以上前に進むな、と、合図を送る。ナディール姫も、はっと身を固くして、息をひそめた。
「ナディール、そこに隠れていろ」
ハヤブサは、ナディール姫を、岩陰へと導く。
「ハヤブサ様?」
「この先に、強い殺気を感じるんだ」
「─────!」
身をこわばらせるナディール姫の肩を、ハヤブサは優しくポン、と、たたいた。
「案ずるな。俺は簡単にやられる気はない。息をひそめて、何があっても声を立てるな。気配を消して、潜んでいるんだ」
「はい、わかりました」
ナディール姫は、静かにうなずく。
「そして、万が一、俺がやられた場合────」
「ハヤブサ様………!」
表情を硬くするナディール姫に、ハヤブサは苦笑する。
「そんなに強く案じなくていい。あくまでも、『万が一』の処置だ」
「でも…………」
「事態は常に『最悪』を、想定しておいた方がいい」
「────!」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫は、はっと、目を見開く。
最悪の事態を想定しろ。
そうだ、これは
父からも、よく言われていた言葉ではなかったか───
「分かるか? ナディール」
ハヤブサからの問いかけに、ナディール姫も「はい」と頷く。
本当は、こんな想定はしたくない。
したくはないが─────
「よし」
姫が頷いたのを確認してから、ハヤブサは言葉をつづけた。
「万が一、俺がやられてしまったら、お前は速やかにこのロープを伝って脱出し、シュバルツにすべての事情を話して、彼に頼れ」
「シュバルツ様に?」
きょとん、と、しながら問い返してくるナディール姫に、ハヤブサは軽く微笑んだ。
「あいつも、俺と同じくらい腕が立つ『忍者』だ」
「…………………!」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫は驚きを隠せなかった。
なんということだろう。
ハヤブサほどの剣の腕が立つ人間が、もう一人、この世に存在するなんて。
「それに、義理堅い男だ。あいつなら、頼るお前をぞんざいにはねのけることは、絶対にしないだろう………」
姫にそう話しながら、ハヤブサは、(すまない、シュバルツ……)と、心の中で謝った。
完全に、巻き込んでしまった。彼を。
本来ならば、この事件には全く関係のない、『第3者』であったのに────
「分かりました。ハヤブサ様」
姫は力強くうなずいたが、こう続けた。
「でも、あくまで私の『護衛』は、ハヤブサ様、貴方です。それを、簡単に変える気はありませんから───」
「姫…………」
「ですから、絶対に、戻ってきてください」
姫の言葉に、ハヤブサははっと、息をのむ。
「貴方ならば、『人質の救出』というミッションを、無事に達成できる………私は、そう信じていますから」
姫の言葉に、ハヤブサはその面に、軽い笑みを浮かべる。
「そうだな………。任せておけ」
「はい!」
力強い姫の返事に頷くと、ハヤブサは静かに彼女のそばから離れていった。
「…………………」
そのまま、龍の忍者は、道の中央を歩いた。
一人で。
堂々と。
身を隠すことすらせずに、ゆっくりと、その足を進めた。
(さあ、ここに侵入してきたのは『俺独り』だ)
通路の向こうに灯る光を睨みつけながら、ハヤブサは歩き続けた。
敵をすべて、自分に引き付ける───
姫を守りながら敵中を突破するには、これしかない。
さあ来い。
俺にかかってこい。
一人残らず─────確実に斬り捨ててやるから。
しばらく歩くと、空気の流れが変わった。
ウウ、と、低い、不吉な呻り声が響いてくる。
(来た…………)
ある意味、懐かしい響きに、ハヤブサは身を引き締める。
やはり────この国は確実に、妖の物を『飼っている』
誰の仕業かは知らないが、この国に居座る『暗黒』が、一筋縄ではいかない物である、と、言うことは、もう明白のようだった。
「さあ、来い……!」
龍の忍者は静かに龍剣を抜刀しながら、その身から殺気を迸らせていた。
「キャ…………!」
ミレイは小さな悲鳴を上げながら、壁から滑り落ちていた。その体が、ベッドの上に落ちて、小さく跳ねる。
「ミレイ!!」
ロアンヌが駆け寄って介抱する。ミレイは2、3回頭を振ると、がばっと起き上がっていた。
「あとちょっとだったのに………!」
ミレイはそう言いながら、悔しそうに天井近くにある窓を見つめる。窓からは不吉な波の音が、ザブ、ザブ、と、部屋の中に入り込んできていた。
「もういいわ……! ミレイ………!」
ロアンヌは思わず、ミレイに縋り付いていた。
「これ以上はもうやめて………! 怪我をしてしまう……!」
「だから母さん! 死ぬかもしれないって時に、ちょっとの怪我を心配するのは、意味がないんだってば!」
「ミレイ………!」
呆然とするロアンヌを振り払うように、ミレイは立ち上がった。
「もうちょっとで手が届く……! あと少しだもの………!」
壁際に寄せられたベッドの上に、テーブル、椅子、そのほか、台になりそうならば何でも積み上げて、ちょっとした小高い山を、ミレイは部屋の中に作り上げていた。それでも、そこから窓に手を届かせようとしたら、彼女はさらに垂直にそそり立つ壁を、手と足を使って登っていかねばならないのだが。
(痛…………!)
何度も壁上りに挑戦した彼女の手足は、すでにあちこちがすりむけて、血がにじんでいた。
それでも彼女は、あきらめずに壁に挑んでいく。
「……………………」
ロアンヌは、そんな娘の姿を、複雑な面持ちで見守っていた。
自分たちは今、『人質』として、捕らえられている。
捕らえた者たちが、自分たちの『死』を決定したというのなら、そう簡単には覆らないだろう。万が一、ミレイが窓を閉めることに成功したところで、こちらに向かってくる明確な殺意は、必ず牙をむいてくるはずなのだ。
それは、『水死』よりももっと惨たらしい方法で、自分たちを殺しに来るかもしれない。
だから、いま払っているミレイの『努力』は、全くの徒労。無駄なあがきになる可能性が高い、ということを、すでにロアンヌは気づいてしまっていた。思い込みと努力だけで、すべてが切り抜けられるほど、現実は甘いものではないのだ。
それなのに、必死にあがき続けるこの娘に対して、自分は、親としてどう接してやれば良い、というのだろう。
「く……………!」
ロアンヌのそんな葛藤を知ってか知らずか、ミレイはひたむきに、壁に登り続けていた。
金属と金属がぶつかって、弾ける音。
獣の唸り声。
雄たけび。
断末魔の悲鳴─────
物陰でナディール姫は、ただ、ハヤブサが戦う音を聞き続けていた。
大丈夫。
あの人は、強い。
きっと、この戦いも、切り抜けてくれる。
信じ続けること─────
自分のできることは、これしかなかった。
やがて─────
シン、と、静まり返った戦場。
パシャ、パシャ、と、水がたまった通路を、誰かがこちらに向かって歩いてくる音が聞こえてくる。
(……………!)
ほんの少し、身を固くする。だがそれは、杞憂だったとすぐに悟ることになった。
「ナディール」
龍の忍者が、こちらをのぞき込んでくる。姫は、少し表情を緩めながら、立ち上がった。
「ハヤブサ様………!」
「もうこの近くに敵はいない。もう少し奥へ進もう」
ハヤブサの提案に、ナディール姫は「はい」と頷く。二人はそのまま、奥へ向かって走り出していた。
(ハヤブサが動いた………)
シュバルツは手の内で、ハヤブサのロープの動きを感じ取っていた。静かにたたずんでいるように見えるが、彼の精神は極限まで研ぎ澄まされ、手の内のロープに、全神経を集中させている。その額からは、汗がしたたり落ち始めていた。
(きっと、釣りをしている人も、こんな感覚なのだろうな………)
そう思ってしまって、シュバルツは少し、苦笑する。
ハヤブサを、釣りをするための『餌』というのなら、これほど物騒な『餌』もないだろう。この餌は、相手に黙って食べられることは絶対にない。どちらかというと相手を捕食し、消化する側になってしまう方だ。
そして、この獰猛な餌は、シェフの奥さんと娘さんを助けたい、と、願って、地下通路を泳ぎ回っている。
心優しき勇猛な『餌』────シュバルツは素直に、好ましい、と、感じていた。
ハヤブサの、無事を祈る。
どうか皆を引き連れて、帰ってきてほしい─────
「あ、隊長!」
ロープを継ぎ足す作業をしていたモガールが、そう声を発して立ち上がる。果たして彼の見つめる方向から、イガール隊長がばたばたと走りこんできていた。
「姫様が地下に入った場所は、ここか!?」
「あ、はい!」
「この場所であります!」
イガールの問いかけに、モガールとヤッセが敬礼をしながら答える。
「そうか………」
イガールはしばらく、地下への通路の入り口をじっと見つめていたが、やがて「姫様……!」と、小さく叫びながら地下通路に入っていこうとした。それを見た兵たちが、慌てて彼を引き留めていた。
「うわっ! 隊長! だめですよ!!」
「そうですよ! 危険すぎます!!」
「しかし、姫様が────!」
そう言って、兵たちを振りほどこうとしたイガールであるが、「う………!」と、小さくうめいて、その場に座り込んでしまっていた。
「ほら……! 体調が万全じゃないのに……!」
「地下は、通路が複雑に入り組んでいます! 不用意に入るのは危険すぎます!!」
「うう…………!」
「姫様のそばには、ハヤブサ殿が付いています! だから、大丈夫です!」
「ハヤブサ殿………」
イガールは、茫然とその名をつぶやく。
「………………」
へたり込んでいたイガールであったが、そのままドカッと、腰を完全におろしてしまっていた。
「隊長………?」
「大丈夫で、ありますか………?」
覗き込む兵たちに、イガールは、一瞬顔を上げ、軽く笑みを見せると、はあ、と、深いため息をついて、がっくりとうなだれてしまった。
「姫様は…………」
消え入りそうな声で、イガールは言葉を落とす。
「どうして…………ハヤブサ殿ばかりに、頼るのであろうか…………」
「えっ?」
「隊長?」
きょとん、とする兵士たちに気づいているのかいないのか、イガールの独白はなおも続いた。
「私では、姫様のお力になるのは、不足、なのであろうか………」
「いや、隊長………」
「それは…………」
兵たちは、落ち込む隊長の姿を見て、兵たちは、気の毒になるやらあきれ果てるやら─────複雑な心境に襲われていた。
「姫様は、隊長のことを頼りにしていないわけではない、と、思いますよ」
「どちらかといえば、隊長がお忙しそうだから、遠慮されているのでは?」
「………………」
兵たちの言葉を黙って聞いていたイガールであるが、やっぱり、がっくりとうなだれていた。
「確かに、そうかもしれないが…………」
「隊長………」
「城の方々は、結構私に用事を言いつけてくるのに、姫様だけに言いつけられないのは………」
(それは隊長がもう少し雑用を減らせば、解決できるのでは………?)
兵士たちはみな一様に、強く心に思ったが、その言葉が口に出されることはなかった。
「……………………」
シュバルツは、手の中のロープの感触に全神経を集中させていたが、兵士たちとイガールの話も、なんとなく耳に入ってきていた。
よくわからないが、あのイガールという男もまた、ナディール姫のことを好いているのではないだろうか、という感想を、持った。
牢の中で、バキッ! と、音を立てて、机の脚が折れる。
「キャ…………!」
バランスを崩したミレイは、再びベッドの上に落下していた。
「ミレイ!!」
「いたたたた…………!」
何とか起き上がりながら、ミレイは崩れ落ちた家具の山を見る。もう一度くみ上げるのは、ほぼ不可能そうであった。
「あ……………」
「ミレイ…………」
呆然とそれを見つめるミレイを、ロアンヌは、抱きしめた。
「もう、十分よ、ミレイ…………」
「母さん………」
「貴方は十分、よくやったわ」
「………………!」
母に抱きしめられながら、ミレイはグッと、唇をかみしめる。
窓の外では満ちてくる波音が、不吉な音を奏でていた。
ナディール姫の手を引いて、走り続けるハヤブサ。
「………………!」
彼は急に立ち止まり、姫を物陰へと導いた。どうやらまた、『殺気』を捉えたらしい。
(今までの通路と違って、この通路はモンスターがたくさん出てくる……。人質たちの場所も、近いかもしれんな………)
「誰かいないか!?」
龍の忍者が叫ぶ。すると、応えてくるのは、モンスターの唸り声ばかりだ。
「うおおおおおおっ!!」
襲ってくるモンスターを瞬殺する。地下に潜ってからの時間を鑑みるに、おそらく、潮が満ちるまでの時間的猶予も、もうそんなには残っていないだろう。最悪、人質を救出することもかなわないまま、撤退せざるを得ない可能性も見えてきていた。
「誰かいないか!?」
祈りを込めて、龍の忍者は叫ぶ。
人質が救出できなかったという結末は、何としても避けたい。そんな結末を迎えてしまったら、姫もシェフも、誰も報われないではないか。
そんな悲劇を彼女に背負わせてしまったら、彼女はもう二度と、闊達に笑うことなどできなくなってしまうだろう。
「誰かいないか!?」
焦るな。
落ち着け。
人質たちは、必ずこの近くにいる。
いるはずなのだから。
敵を屠った龍の忍者は、姫の手を引いて再び走る。
「誰かいないか!?」
ハヤブサの声は、狭い通路の奥に、反響しながら吸い込まれていった。
「……………!」
母親に抱きしめられていたミレイが、顔を上げた。
「どうしたの? ミレイ」
母親は、腕の中の娘に声をかける。
「………声が聞こえる……」
「声?」
怪訝な顔をするロアンヌに、ミレイは頷いた。
「そう、声。母さん、聞こえない?」
「………………」
娘に言われるままに、耳を澄ます。しかし、ロアンヌには波の音しか聞こえなかった。
「何も聞こえないけど………」
素直にその旨を告げると、娘は少し、目を見開いていた。
「うそ………! 確かに、聞こえていたのに………!」
「─────」
その時、ミレイの耳には、確かに声が聞こえてくる。彼女は思わず、立ち上がっていた。
「ほら……! やっぱり声が聞こえるわよ、母さん!」
「え………………」
ロアンヌは、そんな娘を案ずるように見つめる。
「大丈夫? ミレイ」
自分には声が聞こえないから、娘の言葉が理解不能だった。
どうしたのだろうか。
もしかしたら、『死』が迫ってくる恐怖で、気がふれてしまったのではないだろうか?
「ちがうわ! 母さん!! 本当に、声が聞こえるんだってば!!」
娘は叫ぶや否や、部屋のドアに向かって走り出す。そこに縋り付くように立ち止まると、ドアを勢い良くたたいて、叫びだした。
「ここに!! ここにいます!! 誰か来て!! 助けて!!」
ドンドン!! と、ドアをたたく音が、部屋の中に大きく響き渡る。
「ミ、ミレイ………!」
母親は茫然と、娘のその様子を見つめていたが、やがて、はっと我に返った。
わかっている。
救助など、来ない。
すべては、無駄なのに────
そう悟っているから、娘を止めようとする。しかし、娘から、嚙みつかんばかりに怒鳴り返された。
「何を言っているのよ! 母さん!! 声が聞こえたのよ!? 助けに来てくれているのかもしれないじゃない!!」
「で、でもミレイ……! 『声』だって、私たちを助けに来ている、とは限らないじゃない………! 私たちをここに閉じ込めている人たちが、嘲笑いに来ているのかも、知れない………」
ロアンヌは知らず、唇をかみしめてしまう。
『来ない』と、分かっている救助を求める声は、
さぞかし『滑稽に』この場所に響き渡っていることだろう。
「嘲笑われていたって!! そんなこと、どうでもいいじゃない!! 母さん!!」
娘はそんな母親に向かって、思いっきり怒鳴り返していた。
「たとえ近くで、敵が嘲笑っていたって、本当に助けに来ている人だって、いるかもしれないのに!!」
「ミ、ミレイ………!」
「ごめん、母さん……! 私はまだ、生きること、足掻くことをあきらめたくはないの………!」
そういう娘の瞳から、一筋の涙が零れ落ちている。
「……………!」
「馬鹿にされたって、嘲笑われたって─────私は、助けを呼ぶわ、母さん」
娘にこうまで言われて、母親は、もう何が言えただろう。
「助けて!! 誰か来て!! 私たちはここにいるわ!!」
娘が再び、どんどん、と、ドアをたたきながら、大声で叫び始める。その後ろで、母親は、あふれる嗚咽を堪えることができなかった。
「……………!」
モンスターを斬り伏せながら、龍の忍者の優れた聴力は、確かにその『声』を捉えていた。
(声が聞こえる……! 助けを呼ぶ声が………!)
「覇────ッ!!」
龍の忍者の『絶技』は、その場にいたモンスターを一掃した。周りに敵意がないことを確認してから、ハヤブサは姫の元へと走り寄った。
「ナディール!!」
「ハヤブサ様!」
「ナディール、『声』だ! 『声』が聞こえる!」
「声?」
青い瞳をしばたたかせるナディール姫に、ハヤブサは、力強く頷いていた。
「ああ。間違いない。助けを呼ぶ声だ!」
「──────!」
はっと、息をのむナディール姫の手を取り、ハヤブサは彼女を立ち上がらせる。
「助けられるぞ! ナディール!」
「………………!」
「人質は、間違いなくこのそばにいる………! 助けることが、できるんだ!!」
助けられる?
本当に────?
「ナディール、もう、あまり時間も残されていない。お前も人質たちに呼びかけを行ってくれ」
「ハヤブサ様………!」
「何があろうと、俺は、全力でお前を守る! だから、頼む!」
「分かりました」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫も頷く。
確かに今は、なりふり構っている場合ではない、と、彼女もとっくに気が付いてた。
「声は、この奥から聞こえる!! 行くぞ!!」
「はい!!」
ナディール姫とハヤブサは、地下通路を勢いよく走りだしていた。
「ロアンヌさん!! ミレイさん!! どこにいるの!?」
姫の高い、力強い声が、通路に響き渡る。まさに、狙われている標的者(ターゲット)の声─────それに引き寄せられるかのように、モンスターたちが次々と、その通路に姿を現していた。
「ちいいいいっ!」
この戦いのリスクを、ある程度覚悟していたハヤブサは、特段あわてることもない。
姫に害が及ばないよう、最速の、最短の方法で、群がる敵を倒していく。
「ハヤブサ様!! 助けを呼ぶ声は、どちらから!?」
分かれ道が来るたびに、姫が振り返って確認をしてくる。
「右だ!! 右の道を行け!!」
そのたびに、龍の忍者は声を聞き取り、姫に指示を出した。
「はい!!」
姫もハヤブサの言葉を疑うことなく、まっすぐに足を進めていく。
周囲に響くのは、戦いの喧騒の音。
だが姫は、特に気にすることもなく。足を進めた。
自分はいい。
自分には、盤石の、『最強の護衛』が付いていてくれる。
彼がそばにいる限り、自分は、何を恐れることがあるだろう。
それよりも、一刻も急がねばならないのは、人質たちの発見だ。
彼女たちは今まさに、『死』への明確な恐怖を感じながら、この時を過ごしているのだ。
早く助けてあげたい。
早く
早く─────!
必死に足を動かすナディール姫の前に、一体のヒト型のモンスターが飛び出してくる。
「──────!」
一瞬、息をのむナディール姫。だがすぐに、龍の忍者の鋭い声が響いた。
「頭を下げろ!! ナディール!!」
「………………!」
言われたとおり、その場にしゃがみ込むナディール姫。そのすぐ上を、鋭い羽音とともに、何かが飛来していった。
「ギャッ!!」
正確に眉間を射抜かれたモンスターが、もんどりを打って倒れる。眉間に突き刺さっている、一本の矢。それを見て初めて、ナディール姫は、ハヤブサが弓を射たのだと理解していた。
「ハヤブサ様………!」
「立てっ!! 走るぞ!!」
「はい!!」
ハヤブサが、手早く弓をしまいながら叫ぶ。ナディール姫も、返事と同時に立ち上がり、再び走り出していた。
「ミレイさん!! ロアンヌさん!! お願い!! 返事をして──ッ!!」
彼女は、声を限りに叫び続けていた。
「…………………!」
ドアをたたき続けていたミレイに、その声ははっきりと届き始めていた。彼女はドアをたたく手を止め、ロアンヌの方に振り返っていた。
「母さん………! 聞こえる………!」
「え………?」
「聞こえるのよ!! 姫様の声が!!」
「姫様の………?」
泣きぬれた母親の手を引いて、ミレイはドアのところに導く。そこで、ドアに耳を当てるようにと母親に頼んだ。
「………ほら……。よく聞いて。聞こえるでしょう……? 姫様の声が……!」
「……………?」
娘に乞われるままに、半信半疑ながら、ドアに耳を当てるロアンヌ。
すると。
「─────」
確かに、聞こえた。小さいが、間違いなく、ナディール姫の声────
「そんな…………!」
思わず、口に手を当てて息をのむロアンヌ。そんな母親に、娘はそっと寄り添ってきた。
「ね………? 確かに、来ていたのよ………! 姫様が、私たちを助けに………!」
「そんな!! だめよ!!」
いきなり、ロアンヌがはじかれたように叫ぶ。
「母さん!?」
驚くミレイに、母親は言い聞かせるように答えていた。
「いけないわ……! 姫様にこんなところに来させるなんて………! 私たちのために、姫様を危険にさらすことになってしまう……!」
「もう!! 何を言っているのよ!? 母さん!!」
ミレイは怒鳴りつけるように叫んでいた。
「私たちを助けに、ここまで来ている姫様が、私たちを助けずに、ここから逃げるってあり得ると思う!? あの姫様の性格なら、死ぬまでこっちを探し続けてしまうわよ!!」
「……………!」
「それよりも私たちがしなければいけないことは!! 一刻も早くこちらを姫様に発見してもらって!! 姫様とともに、危険地帯を脱出するべきだわ!! 違う!?」
「そ、それはそうかもしれないけれども………でも………」
「母さんも叫んで!!」
なおも、変に躊躇おうとする母に、娘は強く叫んでいた。
「早く!! 私たちの『死』に、姫様を無駄に巻き込まないためにも!!」
「…………………っ!」
ロアンヌは、ぐっと唇をかみしめていた。
娘の言っていることはわかる。
確かにそうだ。
一刻も早く、姫様とコンタクトを取らなければ
こちらの意思を伝えることも、できないではないか。
「………分かったわ………」
母親が頷いてくれたから、娘は嬉しそうに微笑んでいた。
「じゃあ母さん! 一緒に叫びましょう!」
「そうね」
こうして母子は、部屋の中で大声を出し始めた。ドアをたたき、壁をたたき、必死になって大声を上げた。
「私たちはここよ!! ここにいるわ!!」
「姫様!!」
「ここよ!! ここに来て────ッ!!」
窓の外からは、大きな海鳴りが迫るように響いていた。
(息苦しい………)
ロアンヌは、そう感じて、大きく息を吐いていた。
不思議だ。
海の水が、見えているわけでもないのに。
確実に、こちらに『迫ってきている』────そう、感じられるのは、なぜなのだろう。
(私はどうなってもいい。だけど、姫様は、そして娘は─────助かってほしい)
ロアンヌは、何時しかそう祈りながら、懸命に叫んでいた。
「…………………!」
ナディール姫が、はっと顔を上げる。彼女たちの懸命の叫びが、姫の耳にも、ついに届いたのだ。
「ハヤブサ様!!」
「聞こえたか!?」
はじかれたように振り返るナディール姫に、ハヤブサは問いかける。彼女は、力強くうなずいていた。
「行きましょう!! もう、近くのはずです!!」
言うや否や、間髪入れず走り出す。
龍の忍者も、すぐにそのあとについて、走り出していた。
「ミレイさん!! ロアンヌさん!!」
「姫様!!」
「私たちはここです!!」
「姫様─────!!」
「待っていて!! すぐに行くわ!!」
徐々に、近づいていく互いの声。
もうはっきりと、『会話』としてやり取りできるようになっていた。
しかし。
「あ……………!」
ナディール姫の目の前にたはだかるのは、行き場のない袋小路。
「うそ…………!」
ナディール姫は、思わず壁に縋り付くが、そこにはただ、分厚くて冷たい岩肌があるだけだ。
「ミレイさん!! ロアンヌさん!!」
「姫様!!」
ナディール姫の呼びかけに、二人の声は、すぐ近くから帰ってくる。
「どこ!? どこにいるの!?」
「ここです!!」
「私たちはここにいます!!」
声は確かに、この向こうから聞こえてくる。しかし、この岩の壁を超える手段が見当たらなくて、ナディール姫は唇をかみしめていた。
(すぐ近くにいるのに………!)
姫は壁を、ドン! と、強くたたく。この向こうに回る通路はどこだろう、と、彼女が考え始めた時。
「どけっ!! ナディール!!」
「───────!」
龍の忍者の叫び声に、ナディール姫は、弾かれたようにそこから飛びのく。
刹那。
「覇あああああああっ!!」
ハヤブサの凄まじい『気』が込められた拳が、まっすぐ岩壁に打ち込まれる。
ドンッ!!
激しい轟音とともに、振動する空気。
「……………!」
ナディール姫は、耳をふさぎながら、思わずその場にうずくまっていた。
ガラガラと、周囲の岩が崩れる音。
粉塵が舞い、息苦しさに襲われる。
だがすぐに、新鮮な空気の流れを感じて、ナディール姫は顔を上げた。
「怪我はないか?」
見ると、龍の忍者がこちらを振り返り、手を差し伸べている。
「……………!」
信じられぬことだが、ハヤブサの前には巨大な穴が開き、その向こうに新たな道が見えていた。
ハヤブサが、目の前の岩壁を、その拳で打ち抜いたのだと、知れた。
「声は、この向こうからだったな?」
「は、はい………」
ハヤブサに助け起こされながら、ナディール姫は何とか返事をするが、声が上ずることを、押さえることができなかった。
改めて、ハヤブサの強さの一端を思い知る。
信じられない。
あの岩壁を、拳一つで打ち抜くだなんて。
「時間がない、ナディール。『最短距離』を進むぞ」
「ハヤブサ様……!」
ハヤブサに返事をしながら、ナディール姫は息をのむ。
『最短距離』って、何だろう。
まさか─────
「覇あああああああっ!!」
ドゴォッ!!
バコォッ!!
それから二人の道行きは、まさしく『直線』だった。
龍の忍者は躊躇うことなく前へ進み、自分たちの『障害』となり得る壁は、容赦なく破壊していった。
(い、岩って………こんなに簡単に打ち抜ける物だったかしら………)
ナディール姫は、そんなハヤブサの後ろ姿を見ながら、自分の『常識』が揺らぐのを感じる。ハヤブサの膂力の前には、総ての障壁が、意味を成してはいなかった。
「姫様!! 姫様!!」
「ロアンヌさん!! ミレイさん!!」
声を頼りに、二人はひたすら、前に進む。
そしてついに────ハヤブサたちは、人質がその向こうにいる、と、思われる壁の前まで到達していた。
「ロアンヌさん!! ミレイさん!! 返事をして!!」
「姫様!!」
「姫様!! 私たちはここにいます!!」
返ってくる声の反響を聞いて、龍の忍者は、あることに気がついた。
(かなり下の方にいる?)
二人の声が、自分たちの足下から聞こえてくる感覚を得る。だが、この岩壁一枚隔てた向こう側に、人質たちの存在があることは、もう、疑いようもなかった。
「──────」
だからハヤブサは、印を結び、『真言』を唱えながら、自身に結びつけている縄を、思いっきり波立たせていた。
「波─────ッ!!」
ハヤブサの『気』を乗せた縄の『しなり』は、違うことなく、シュバルツの手元へと、送り届けられていた。
「………………!」
ロープを握る手に、ハヤブサからの『合図』を感じ取ったシュバルツは、はっと顔を上げる。
「どうされました?」
彼の異変に気がついたモガールが、縄を継ぎ足す作業の手を止めて、シュバルツに問いかけてくる。
「………ハヤブサからの『合図』だ」
「ええっ!?」
シュバルツから、ぽつりと落とされた言葉に、周囲の空気が、ざわ、と、揺らめく。
「姫様に、何かあったのでしょうか!?」
「まさか、地下で何か、悪いことが………!」
「いや、ハヤブサからの『気』は、そんなに悪い印象は受けなかった………」
兵士たちに応えながら、シュバルツは、己が手に受けた、ハヤブサからの『気』の感触を確かめる。
これは、『非常事態』を告げるモノではない。
どちらかと言えば────
「………これは、推測だが………おそらく、人質を『発見』したのではないのか………?」
シュバルツのその言葉に、周囲の兵士たちから、おお、と、歓声が上がった。
「我々も、このロープを伝って、現場に向かった方が良いのでしょうか!?」
「何か、手伝えることがあるなら────」
色めきだつ兵士たちを、シュバルツは、まあ待て、と、制した。
「ハヤブサから、脱出する手段について、もう一度連絡があるはずだ。それを、確認してからにしよう」
シュバルツはそう言うと、ロープをたぐり寄せはじめる。
「何をなさっているのですか?」
兵士の問いかけに、シュバルツは手を動かしながら応えた。
「ロープを、少し張っておこうと、思って………」
「ロープをですか?」
聞き返す兵士に、シュバルツは「ああ」と、頷いた。
「ハヤブサが、連絡する手段として、このロープを使ってくる可能性が高い。だから、その合図を聞き取りやすくするために、な」
「了解しました!」
「我らも手伝います!」
「頼む」
モガールとヤッセの申し出を、シュバルツも受ける。3人は急いでロープを手繰り寄せ始めた。
「失礼だが、そちらの方は?」
シュバルツの存在に気づいたイガールが、周りの兵士に問いかける。
「あ、えっと…………」
「我々も、よくわからないのですが………」
周りの兵士たちも首をひねった。しかし、それは無理からぬ話であった。シュバルツは今日、『給仕』として、この城に雇われたばかりの存在。そんな人間を、誰が詳しく知っている、と、言うのだろう。
しかし、その場にいた兵士たちは、誰一人としてシュバルツを『敵対的な存在』とは認識してはいなかった。
何故なら、厨房で『未知の存在』から襲撃を受けた時、懸命に姫やシェフを、ハヤブサと共に護っていたシュバルツの姿を、彼らは覚えていたからだ。
だから彼らは、この言葉を選択していた。
「隊長! あの方は、少なくとも我らの『敵』ではありません!」
「どうやら、ハヤブサ殿の知り合いの様であります!」
「ハヤブサ殿の?」
イガールは、驚いたように顔を上げる。
「ハヤブサ殿の………」
イガールは、しばらくシュバルツの横顔を、じっと見つめていたが、やがて立ち上がり、その近くに歩み寄っていた。
「誠に申し訳ない。貴殿は、ハヤブサ殿の知り合いか?」
「……………!」
縄を手繰り寄せていたシュバルツは、手を止めて、イガールの方に振り返った。
「ああ。私はシュバルツ・ブルーダー。ハヤブサとは、知り合いだ」
「シュバルツ殿か………」
イガールは、しばらくフム、と顎に手を当てながら頷いていたが、やがて顔を上げ、シュバルツの方に右手を差し出した。
「私の名は、イガール・ジェスティ。この城の警備隊長をしている。城の者が、貴殿に世話になったようだな、礼を言わせてもらう」
「いや…………」
シュバルツも右手を差し出し、イガールと握手を交わした。
切れ長の瞳をした、金髪の青年。彼の手のひらには、剣を振り込んでいるが故にできる、硬いタコができていた。
彼は、シュバルツの瞳をまっすぐ見つめながら、握手をしている。
実直そうな青年。だが、その顔色が少し青白いのが、シュバルツは気になった。
「シュバルツ殿! もっと縄を引きますか?」
はっと、シュバルツが振り返ると、ハヤブサとつながっている縄が、地面に垂れない程度に張っているのが分かる。
「いや、これで十分だ。ありがとう」
シュバルツは礼を言って、その縄をモガールたちから受け取った。
「……………………!」
今まで、自分とつかず離れずで、余裕を持ってついてきた縄が、ピン、と、張られたことに、ハヤブサは気づいた。
(シュバルツ……! 合図に気づいてくれたんだな………)
流石だ、と、ハヤブサはほっと、胸をなでおろす。彼は素早く周りを見回して、今の状況を把握すると、縄を細かく指で弾き出した。
(頼む………! シュバルツに、伝わってくれ………!)
龍の忍者は、祈りにも似た思いで、縄を指でたたき続けていた。
「…………………!」
縄から伝わってくる感触に、シュバルツは、はっと、息をのむ。ハヤブサからの『伝言』だと、悟った。
「シュバルツ殿……?」
シュバルツの周囲の空気が、急に張り詰めたことに気づき、怪訝に思ったヤッセが、彼の顔を心配そうにのぞき込んでくる。
(少し、静かにしていてくれ)
シュバルツは手を上げて、ヤッセにそう合図を送ると、縄から伝わってくる感触に、集中しだした。
(………モールス信号………!)
その暗号に気づいたシュバルツは、しばらく目を閉じて、龍の忍者からのメッセージに集中する。
(なるほど………心得た!)
シュバルツは、一度だけ強く、その縄を引く。それをしてから、彼は縄から手を放した。もう、この縄は、必要のないものだからだ。
「シュバルツ殿!?」
その行動に驚くヤッセたちの方に、シュバルツは振り返ると、こう叫んだ。
「この城から一番近い、海側に切り立った崖は、どっちの方向だ!?」
「崖でありますか?」
「東側にあるな」
「しかし、シュバルツ殿……その崖が、どうかされましたか?」
「そこから、ハヤブサが出てくるんだ。人質を連れて────」
問いかけてくる兵士たちに、シュバルツは明確に答えを返す。彼の言葉に、兵士たちは、「おお!」と、ざわめいた。
「その崖はどこだ? 案内してくれ! おそらく、救助には手助けが必要になる………!」
「了解しました!」
シュバルツの言葉に、ヤッセとモガールは敬礼を返す。
「こちらへ! 我らが案内いたします!」
「ありがとう」
シュバルツは礼を言うと、走り出したヤッセとモガールの後をついて、走り出していた。
「我らも行こう!」
イガールは、周りの兵士たちに声をかけた。
「隊長!」
「姫様も、シェフのご家族も出てくる! 人手は、多い方がいいだろう」
「はっ!」
「了解しました!」
シュバルツたちの後について、イガールと兵士たちも、そこから走り出していた。
(シュバルツ……! わかってくれたか………?)
一度強く引かれた後に、パタッと力無く、地に落ちた縄。それは、シュバルツが縄から手を離したことを示していた。
きっと、シュバルツはこちらの思いをくみ取ってくれている。
ハヤブサはそう信じて、次の行動に移ることにした。
もう時間がない。
ここでの躊躇は、人質と姫の命を奪ってしまう。
「ミレイさん!! ロアンヌさん!!」
姫の呼びかけに、人質たちは「はい!!」と、返事をしてくる。
もうかなり近い。
そして、やはり─────かなり下の方から、その声は聞こえてくる。
わかる。
きっとこの壁の向こうに、間違いなく人質たちは居る。
「そこにいる者!! 聞こえるか!?」
「は、はい!!」
「貴方様は……!?」
ハヤブサの呼びかけに、中から戸惑った声が返ってくる。
「俺は、リュウ・ハヤブサ。ナディール姫の『護衛』をしている者だ!!」
ハヤブサは、そう説明してから、言葉をさらに続けた。
「今からそこに向かって、『出入り口』を作る!!」
「ええっ!?」
「そんなことができるのですか!?」
中から帰ってくる、半信半疑な声に、ナディール姫は苦笑していた。
無理もない。
自分だって、ハヤブサが、ここまでどうやって到達したのか─────その一部始終を見ていなければ、この龍の忍者の言葉を、とても信じることなど、できなったであろう。
「この人の言うことは、本当よ!!」
だからナディール姫は、ハヤブサの言葉をフォローするように、彼女たちに声をかけた。
「この人は本当に─────ここの壁に、穴を開けることができるの!!」
その時、窓からバシャッと、音を立てて、海水が部屋の中に入り込んでくる。潮が満ちて、跳ね上げられた波しぶきが、窓を超え始めたのだ。
「水が─────!」
ロアンヌが、悲鳴に近い叫び声をあげた。
一度水が浸入し始めたら、この部屋は、あっという間に海水に満たされてしまうだろう。
それが分かるが故に、明確な恐怖に彼女たちは襲われていた。
「いいか!? 落ち着いてよく聞いてくれ!! 今から俺は、この壁をぶち抜く!! だから、自分たちの頭を守りながら、できるだけこの声から、離れた場所に移動してくれ!!」
「お願い!! ハヤブサ様の言うとおりにして!!」
ナディール姫も、懸命に声を張り上げて呼びかけた。
「必ず、助けます!! だからお願い!! 私たちを信じて!!」
「……………!」
ミレイとロアンヌは、言われたとおりの行動をする。窓からは、バシャッ! パシャッ! と、激しい音を立てながら、水が、もうひっきりなしに部屋に入り込んでくるようになっていた。
ハヤブサは、床に垂れている縄を手繰り寄せ、適当な長さを確保してから、手近にあった石の柱に、その縄を手早く括り付けていた。
「縄を頼む!」
姫に短くそういうと、ハヤブサは、静かに息を吐く。
目の前の壁を見つめながら、己の丹田と拳に、『気』を極限まで集中させた。
「覇あああああああッ!!」
ドゴォッ!! と、轟音をとどろかせて、打ち込まれる拳。
咲かれた空気が、粉塵を巻き上げ、ナディール姫の鼓膜を揺らす。
「……………!」
耳を覆い、目を閉じ、歯を食いしばって、その衝撃に耐える。
やがて、静寂が訪れ、新しい空気を頬に感じた。
瞳を開けると、大きな穴の開いた壁の前にたたずむ、ハヤブサの姿がある。
「ハヤブサ様」
ナディール姫が声をかけると、一瞬振り返ったハヤブサが、小さくうなずく。彼はそのまま、壁の向こうに飛び込んでいた。
「あ……………!」
椅子やら机の天板などを使って、頭を覆っていた二人が、物音に気付いて顔を上げる。見慣れぬ黒装束を身にまとった一人の男が、部屋に飛び込んできていた。
「二人とも、こちらへ!!」
男は叫びながら走り寄り、こちらに向かって、手を差し伸べてくる。
「は、はい!」
二人は、ハヤブサに向かって、手を伸ばそうとする。
その刹那、部屋に入り込んでくる水の量が増した。ついに海面が、窓を越え始めたのだ。
「キャ…………!」
その水量の激しさゆえに、ミレイとロアンヌは固まってしまう。
「ちいいいいいっ!」
ハヤブサは大きく舌打ちをすると、二人の身体を強引に抱え上げる。流れ込む水に逆らいながら、壁に向かって走り始めた。
「のぼれ!! 早く!!」
ハヤブサはミレイにロープをつかませ、自分はその後ろからロアンヌを抱えて部屋から脱出を試みる。
容赦なく流れ込む海の水。逆巻く濁流は、ハヤブサたちの身体を、水底に引きずり込もうとした。
「手を止めるな!! 上がれ!!」
ハヤブサは、懸命にミレイを励ましながら、水に抗い、壁を登り続ける。時折滑り落ちそうになるミレイを、下から支え続けた。
「ミレイさん!!」
ハヤブサの空けた穴からは、ナディール姫が身を乗り出して、こちらに向かって手を伸ばしている。
「姫様!!」
ミレイの伸ばした手を、姫がつかみ取る。ナディール姫は、力いっぱいその手を引き、ミレイは部屋から脱出することに成功していた。
「ミレイさん……! 大丈夫………?」
「姫様………!」
ミレイは弾む息を整えながら、何とかナディール姫の問いかけに返事をする。
信じられない。
まさか本当に、姫様が、自分たちを助けに来てくれるだなんて。
そして自分たちは
これで助かったのだろうか───
「ミレイ………!」
ハヤブサとともに脱出してきたロアンヌが、ミレイの方へ駆け寄ってくる。
「母さん………!」
ミレイは、縋り付いてくるロアンヌの身体を抱きしめた。
そのまま、しばしむせび泣く母娘。ナディール姫は、よかった、と、見つめていたが、同時に、胸をぎゅっと締め付けられる想いもしていた。
本当に、皆をひどい目に遭わせてしまった。
わたしのせい─────
「悪いが、感慨にふけるのは、あとにしてくれないか?」
空気を切り裂くような龍の忍者の声に、ナディール姫は、はっと我に返った。
「ハヤブサ様………」
「そこかしこから、水が流れ込んでくる音がする」
危険な事実を伝えてくるハヤブサの言葉に、一同ははっと息をのんでいた。
そう。
今いる場所は、満潮時には水路になっているところ。
つまりは、ここも『水に沈む』場所なのだ。
「ここも直に、水に沈むぞ! 早急に脱出しなければ────」
「でしたらハヤブサ様! こちらへ!」
ナディール姫は、力強く叫んでいた。
「少し進んだ場所に、吹き抜けになっている場所があります! そこから上に登れば────!」
「よし、分かった! 行こう!」
叫びながらハヤブサは、自分の身体に括り付けていた縄を切る。もうこの縄は、必要のないものだからだ。
「案内してくれ! ナディール!」
「はい! ミレイさん、ロアンヌさん! こちらへ!」
一同はナディール姫の案内に従って、その場から移動を開始していた。
少し走ったところで、果たして、ナディール姫の言葉通り、目の前の空間が拓ける。そびえたつ岩肌のところどころに隙間があり、淡い月明かりが差し込んできていた。夜の優しい風が頬を撫で、穏やかな波音が耳を通り抜けていく。
(きれい………)
優しい景色に、一瞬見惚れてしまうナディール姫。だが、すぐに、首を振って我に返った。
そう
いまは、
こんなところで立ち止まっている場合ではないのだ。
(良し………! 狙い通りの場所だな………)
周りの景色を見て、ハヤブサは一人、頷いていた。
波の音の響き方からして、この岩壁の向こうは、すぐに海だ。
そして、月明かりが差し込んでいる、ということは、ところどころの壁には隙間があり、外への脱出を容易にする、と、言うことだ。
シュバルツには、「海沿いの崖から脱出する」と、伝えてある。
どこでもいいから岩壁を派手にぶち抜けば、耳の良いシュバルツのことだ。きっと気づいてくれるだろう。
ハヤブサは素早く周りを見渡して、姫やミレイが登れそうなルートを探す。
(あそこでいいか)
比較的なだらかな斜面に、とっかかりとなる岩の凹凸がある。少し上に進めば、休憩できそうな踊り場のような場所も点在していた。
そのルートに見当を付けると、ハヤブサは己の懐から、鉤爪のついた縄を取り出す。
それを、勢いよく崖の上方に投げ、しっかりと引っかかったのを確認してから、皆の方へ振り返っていた。
「さあ、これを伝って、上に登って行け! 急げ!!」
「はい!」
ナディール姫とミレイは、躊躇なくロープをつかみ、上へと登り始める。
「わ、私は………」
ロアンヌはしり込みしていた。年老いた自分が、こんな急峻な崖を登れるはずもない。
「早く!!」
ハヤブサが手を差し伸べるが、彼女は首を横に振るばかりだ。
「……………!」
このままでは埒が明かない、と、踏んだハヤブサは、彼女の身体を強引に抱え上げる。そのまま彼もまた、崖を登り始めていた。
彼らが少し上に登ったところで、その場所にも水が流れ込んでくる。
「あ…………!」
流れる水音の激しさと、濁流の勢いに、ナディール姫の視線は奪われ、その身体が硬直してしまう。
「下を見るな!!」
龍の忍者が、彼女のすぐ下で叫んでいた。
「上だけを見て、まっすぐ進むんだ!!」
「は、はい!」
ナディール姫は、必死に縄をつかんで、登り続ける。どうにかこうにか、最初の踊り場までたどり着いていた。
「みんな、大丈夫!?」
「ええ………」
「何とか………」
皆が、踊り場の上で互いの無事を確かめ合い、ほっと息をついている間に、龍の忍者はさらに上方を見上げていた。休憩できそうな踊り場が、もう少し上ったところにあり、その近くの隙間から、月明かりが漏れ出てきている。下の自分たちが居た場所は、流れ込む海水で埋め尽くされ、さらにその水かさを増そうとしていた。
(………もう少し、上がった方がいいな)
周囲の状況を鑑みたハヤブサは、そう判断した。
「ナディール、もう少し上に上がろう」
彼の判断に、否やを唱える者はいない。姫たちは、ハヤブサの渡してくれたロープを伝って、もう一つ上の踊り場を目指した。
「キャ……………!」
小さな悲鳴とともに、ミレイの身体がずるっと滑り落ちる。
「─────!」
ナディール姫がそれに気づいたときには、ハヤブサがその下で、ミレイの身体を支えていた。
「……………!」
いかに龍の忍者が豪腕であるとはいえ、ロアンヌを抱きかかえながらロープにつかまり、さらに落ちそうになっているミレイを助け上げるのは、いささか苦戦を強いられた。
それでも、彼女を離してなるものか、と、ハヤブサはぎり、と歯を食いしばる。腕と腹筋に、ありったけの力を込め、彼女の手を再びロープに掴まらせようとしたとき、彼は気づいてしまった。
ミレイの手が、すでに傷だらけである、ということに。
「な……………!」
思わず、小さく呻いてしまうハヤブサ。こんな状態の彼女の手に、これ以上ロープを握らせるわけにはいかない。
(どうする?)
二人を抱えて登ることも、かなり力づくになってしまうが、できない話ではない。ぐ、と、身体に力を入れなおした時、上から声をかけられた。
「ミレイさん!!」
見ると、ナディール姫が、必死にこちらに向かって手を伸ばしてきている。
「姫様………!」
ミレイも、懸命にナディール姫に向かって、手を伸ばしていた。
ハヤブサは、姫に彼女を任せて、自身もまた、ロアンヌを抱えなおして、岩肌を登り始めた。
「ミレイさん……! 大丈夫?」
踊り場についたナディール姫が、さっそくミレイを案じている。彼女もまた、ミレイの手のけがに、気づいてしまったのだろう。
「へ……平気です………。大丈夫………」
手を隠しながら、軽く笑うミレイの横に、ロアンヌが近づいてきて、寄り添うように座る。
「すみません、姫様……! この子ったら、牢の中で、かなり無茶をして───」
「母さん! そんなこと、こんなところで言わなくっても……!」
「もう、何度も何度も、牢の壁を登っているんです」
「………………!」
その言葉に、思わず息をのむナディール姫。
「母さんってば!!」
ミレイの方は、ロアンヌに対して、抗議のような声を上げている。
「これぐらいの怪我、大したことないんだから余計なことは言わないでよ! 母さん!! こんなもの───」
「大したことなくても、放置はまずいだろう。手を出せ」
ハヤブサのぶっきらぼうな言葉が、ミレイの言葉を遮った。
「えっ? あ……! いたっ………!」
ハヤブサに手を取られたミレイが、悲鳴を上げた。ハヤブサがミレイの手に、水をかけだしたからだ。
「洗わないと消毒できない。少し、我慢しろ」
そう言いながら龍の忍者は、ミレイの手に手早く治療を施していく。
「手際が良いですね……」
ナディール姫は、ハヤブサの治療を進める手を見つめながら、感心していた。
「必須技能だ」
それにたいしてハヤブサは、不愛想に返事をしていた。怪我が多い職業柄、自分でも他人でも、手当てをする機会が必然的に増える。ただそれだけの話だ、と、ハヤブサは思った。
「できたぞ。だが、しょせんは応急処置だ。後で、ちゃんとした医者に診てもらえ」
「あ、ありがとうございます……」
ミレイは少し涙目になりながら、包帯を巻かれた手に、ふうふう、と、息を吹きかけている。よほど、消毒の薬が染みたのだろう。
(しかし………彼女に、これ以上この岩壁を登れ、と、要求するのは……無理だな………)
ハヤブサはミレイの様子を見ながら、そう感じてため息を吐く。
ミレイはよく見れば、足も膝も、すでに傷だらけだった。
本当に、何度も何度も、牢の壁を登っては落ちてを、繰り返したのだろう。
そんな彼女に、これ以上無理をさせるわけには、いかなかった。
「…………………」
ハヤブサは黙って、さらに上方の岩肌を見つめる。月明かりが差し込んでいる隙間までは、あともう少し距離があったが─────
(打ち抜けるか………? ここから、あの場所を………!)
龍の忍者は、静かに息を吐きながら、拳を構える。
大丈夫だ。
あの距離ならば、俺の『気弾』は届く。
打たねば。
ここから、皆で脱出するために。
シュバルツに、自分の居場所を知らせるためにも。
「少し、荒事をする。皆、身を低くして、頭を庇って互いを守りあってくれ」
「は、はい………!」
ミレイとロアンヌは、言われたとおりの姿勢になるが、少しいぶかしげな顔をしていた。
そんな中、ナディール姫だけは、ハヤブサの次の行動をある程度予測する。その衝撃に備えて、二人をかばいながら、身構えていた。
「波ああああああ………!」
ハヤブサが、己の拳に静かに『気』を集中させていく。それが、極限まで練り上げられ、研ぎ澄まされたとき─────龍の忍者は、迷わず気弾をその手から放った。
「覇──────ッ!!」
ドゴォッ!!
雷鳴のような轟音とともに、打ち抜かれる岩壁。
(シュバルツ………! どうか、気づいてくれ………!)
ハヤブサは祈るような思いで、崩れる岩壁を見つめ続けていた。
「……………」
城から、少し離れた海沿いの崖のうえで、シュバルツは目を閉じて佇み続ける。『音』を拾い続けるためだ。
ハヤブサは、必ず出てくる。
皆を連れて。
そう『約束』を、交わしたのだから─────
ドゴォッ!!
その時、少し離れた場所で響いた轟音を、シュバルツの耳は捉えた。
「ハヤブサ!!」
そう確信したシュバルツは、弾かれたように走り出していた。
「我らも行こう!!」
当然のごとく、イガールと兵士たちも、そのあとに続いた。
「………………!」
「あ………………!」
ミレイとロアンヌは、目の前に起こった、奇跡のような出来事に、ただただ呆然とするしかない。
なんということだろう。
目の前のこの人は
この場所から、あの壁を、『撃ち抜いた』と、言うのだろうか。
「ハヤブサ様」
一方、ナディール姫の方は、もう特段驚くこともなくなっていた。
この人なら、これができて当たり前─────そんな心情ですらあった。
もしかしたら、自分の『常識』の崩壊が、どこかで始まってしまっているのかも、知れないが。
姫の呼びかけにハヤブサが振り向くと、まっすぐにこちらに視線を投げかけている、彼女の視線がある。
「皆を頼む」
ハヤブサがそう言うと、ナディール姫は、力強くうなずいていた。それを確認したハヤブサは、頷き返すと、そこから一人、岩肌を登り始めていた。
するすると、崖を登っていく龍の忍者の姿を、ロアンヌとミレイは、ぽかん、と、口を開けて見守るしかない。
「に………人間、って………あんな風に器用に、身体を動かして………壁を登っていけるものなのね………」
「そうね………」
娘の独り言に、ロアンヌはそう答えると、フ、と、小さく笑った。
「貴方の登っている姿は、あんな感じじゃなかったものね。もう本当に、危なっかしくて───」
「もう! 母さんったら! そんなこといちいち思い出さなくていいのに────!」
むくれるミレイを見ながら、ロアンヌは笑いをこらえきれないでいる。
それは、どこにでもある母娘の、心の底からの平和な光景。
よかった、と、心の底からナディール姫は、思う。
できればこの先も、ずっとこんな景色が続いてくれたらいい、と、願った。
不思議だ。
海水の流入は止まらず、下からの水かさは増す一方。自分たちはまだ、完全に危地を脱しているわけではないのに。
なぜこうも、自分たちは、元の日常に『戻れる』気で、いられるのだろう。
上方に引っ掛けた縄を回収したハヤブサは、自身が穿った出入り口へと、身を運んでいく。
そこから外に顔を出した、刹那。
「ハヤブサ!!」
自分の穿った穴のすぐ上にいて、こちらをのぞき込んでいる、愛おしいヒトの顔。
「シュバルツ………!」
知らず、心底ほっとしたように、表情を緩める龍の忍者。
「……………!」
それに気づいたシュバルツも、彼とともに気が抜けかけそうになるが、すぐに首を振って、「馬鹿」と、ハヤブサを軽く小突いた。
「気を抜くのはまだ早いだろう? まだ、助かっているわけじゃない」
「ああ。そうだな」
シュバルツの言葉に、ハヤブサも、すぐに正気に返る。シュバルツは、一本のロープを伝ってここまで下りてきてくれていて、その上では複数の兵士たちが、そのロープを支えてくれているようだった。
「シュバルツ殿! ハヤブサ殿や姫様はいらっしゃいましたか!?」
崖の上から、兵士たちが心配そうにのぞき込んでいる姿が見える。
「ハヤブサ、姫と人質になっていた人たちは?」
シュバルツの問いに、ハヤブサは、穴の方を指し示していた。
「皆無事だ。あそこにいる」
シュバルツが穴の中をのぞき込むと、なるほど確かに、少し離れた踊り場のようになっている岩間の上に、女性3人が固まって座り込んでいる。シュバルツと視線の合ったナディール姫が、こちらに向かって手を振っていた。
「俺は今から、彼女たちをここまで運んでくる。シュバルツ、その後を頼んでもいいか?」
「ああ」
頷くシュバルツに、ハヤブサは微笑み返す。
やはり、彼は
自分にとっては得難い『相棒』なのだと、ハヤブサは強く自覚していた。
そして、何よりも愛おしいヒト─────
「では、シュバルツ、この縄を頼む」
ハヤブサは、自らの『命綱』とも言える縄を、シュバルツに託す。それをした彼は、また、穴の中へと降りて行った。姫たちの元へと─────
「皆! ナディール姫と、人質となっていた人たちはここにいる! 今から出てくるぞ!!」
シュバルツは、ハヤブサから託された縄を、自身が持ってきた縄と結びつけながら、上に向かって叫んでいた。その声を聴いた兵士たちから、「おお……!」と、どよめきが上がる。
「シュバルツ殿! どうか、お気をつけて!」
「縄は、我々がしっかりと抑えていますので!」
「ありがとう」
シュバルツが兵士たちに手を振ると、兵士たちも嬉しそうに応えていた。その横で、イガールが、食い入るようにこちらを見つめている姿が見える。
(やはり、姫が心配でたまらないのかな)
イガールのその姿を見ながら、シュバルツはなんとなく、そう感じていた。
ストン、と、龍の忍者が、身軽に踊り場に舞い降りてくる。皆がそろっているのを確認してから、ハヤブサは改めて、3人に手を差し伸べていた。
「今から一人ずつ、俺が出口まで運ぶ。最初に、誰が来る?」
「………………」
3人は、互いに顔を見合わせながら、しばし思案にふけっていたが、やがて、それぞれがそれぞれ、自分以外の人間を指さしていた。
「姫様、お先にどうぞ」
「そうですよ、姫様」
ロアンヌとミレイは、ナディール姫を先に行かせようとする。しかし、それには姫の方が、頑なに首を横に振っていた。
「何を言っているの!? だめよ!!」
「ですが、姫様………」
ロアンヌは、少し困ったように口を開いた。
「王族をお守りするのは、我々国民の『義務』ですから………」
その言葉にナディール姫は、「違うわ!」と、強く反論していた。
「その義務を負うのは、我ら王族の方です!! 私たちは、国の人々がいて、初めて『王』となりえるのですから───!」
「でも、姫様……! 姫様には責任もお立場も、私たちよりはるかに重いものがあるはずです……! ならば、私たちよりも先にここを────」
「………その重い責任があるから、私はなおさら、貴方たちより先に、ここを動くわけにはいかないわ」
ナディール姫の、固い意志を孕んだ声が、その場に響く。ロアンヌ母娘は、はっと息をのんでいた。
「お願いします、ハヤブサ様。私をここから連れ出すのは、一番最後にしてください。そうしなければ、私は父や国民に、顔向けができなくなってしまいます」
「……………!」
きっぱりと姫にそう言い切られて、一体だれが、反論できるだろう。ハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐いていた。
「ならば、二人のうち、どっちが先に行くんだ?」
ハヤブサはそう言いながら、今度は母娘の方に、手を差し伸べる。しかし、ここでも、母娘は互いに譲り合おうとした。
「お願いします。母さんを先に────」
「駄目です。ミレイ、貴方が先に行きなさい」
「でも、母さん………!」
「駄目ですよ。子供は、親より先に死んではいけません」
「……………!」
その言葉に、一同ははっと息をのむ。
「お願いよ、ミレイ……! なんと言われようとも、私は………! 貴方を私より先に、死なせたくないの………!」
そのまま、すすり泣くロアンヌの声が響き渡る。その姿に、皆はもう何も言えなくなってしまった。
(確かにそうだな……。子が親より先に死んでしまうのは、一番の『親不孝』だ)
ハヤブサはそう思いながら、亡き母に思いを馳せる。
自分を生んですぐに、天に召されてしまった母。
だから、自分には『母親』に関する記憶もないし、その思い出もない。
だが母は、自分を身籠った時から、その誕生をとても心待ちにしていた、と、ハヤブサは人づてに聞いていた。
心優しい母─────
もしも母が生きていたら、自分が危険な任務に赴くたびに、「死んでほしくない」と、嘆かせることになったのだろうか。
「よし、決まりだな。一番最初にミレイを、次に、ロアンヌを運ぶ。ナディール……お前は最後でいいな?」
「ええ。十分です。ハヤブサ様」
ナディール姫は、そう言って頷き、笑顔を見せた。ハヤブサの決断に、否やを唱える者は、誰もいなかった。
「では行こう。ミレイ、俺につかまれ」
「は、はい………!」
ハヤブサの差し出した手を、ミレイが握り返す。ハヤブサはミレイの身体を抱きかかえると、自身が穿った穴に向かって、再び岩肌を登り始めていた。
「ハヤブサ」
出入り口に着くと、シュバルツが手を差し出してくる。
「頼む!」
ハヤブサは、ミレイをシュバルツに託すと、再び穴の中へと入っていった。
「大丈夫か? 上へ行くぞ」
シュバルツは、ミレイを抱きかかえると、崖を上へと登っていく。
「シュバルツ殿! こちらへ!」
「がんばれ! あと少しだ!」
崖の上では、数人の兵士たちが身を乗り出すように覗き込んで、こちらに向かって手を差し出している。兵士たちの手が届くところまで、シュバルツがミレイを運ぶと、皆の手が、ミレイを上へとひっぱりあげていた。
「大丈夫か?」
「早く火のそばへ! 身体が濡れている!」
「毛布を持ってきた! タオルもいるか!?」
ミレイを助け上げた兵士たちが、彼女の様子を見てあわただしく動き始める。
「シェフを呼んで来い! 早くご家族に会わせてやるんだ!」
イガールの叫びに、「了解!」と、兵士の一人が走り出す。イガール自身は、崖から身を乗り出すように、下を見つめ続けていた。
「次はお前だ。行くぞ」
ハヤブサは、ロアンヌに向かって手を差し出す。
「姫様………!」
ロアンヌは、案ずるようにナディール姫の方を見つめる。
「大丈夫よ」
ナディール姫は、そんなロアンヌに、やさしく微笑みかけていた。そんな彼女の足元には、傘を増した海水が、もうかなり近くまで迫ってきていた。
(急がなければ……)
ハヤブサは拳を握りしめる。もう本当に、ぐずぐずしている時間は無いと悟った。
「ナディール、なるべく早く戻るが……身の危険を感じたら、少しでも、上へ移動しておけ」
「ハヤブサ様」
「必ず迎えに来るから」
そう言い残して、ハヤブサはロアンヌを抱きかかえて、踵を返した。踊り場の上には、ナディール姫が1人、残された。
するすると、岩肌を素早く上っていく、龍の忍者の後ろ姿を、暫し瞳で追うナディール姫。その足元に、跳ね上がった海水が、パシャリ、と、かかる。
「……………!」
(もうこれは、少しでも上に上がった方が良さそうね)
ナディール姫はそう決意して、岩壁を上へとゆっくり登りはじめていた。
「この人を頼む!」
出入り口で待っていたシュバルツに、ロアンヌを託す。そのままハヤブサは、再び洞窟の方へと振り向いて、ナディール姫がいた踊り場が、水没している事に気がついた。
「──────!」
息を呑み、姫の姿を探す。すると、踊り場から少し上の岩場にしがみついて、ゆっくりと上へと上っている、ナディール姫の姿を見つけた。
「ナディール!!」
「ハヤブサ様………!」
ハヤブサの呼びかけに気づき、顔を上げるナディール姫。その瞬間、足下の岩場が小さく崩れた。
「キャ…………!」
さすがに悲鳴を上げ、少しバランスを崩すナディール姫。
「今行く!!」
龍の忍者は短く叫ぶと、岩場を飛ぶように移動してきた。
「手を離すな!!」
超人的な身体能力を駆使して、岩壁を移動しながら、ハヤブサはナディール姫に呼びかけ続ける。そして、あっという間に、彼はナディール姫の元に到達していた。
「掴まれ!!」
ハヤブサの呼びかけに、ナディール姫も懸命に、その手を伸ばす。二人の手は、がっしりと重なり合い、ハヤブサはナディール姫を、己の方に引っ張り上げることに成功していた。
そのまま龍の忍者は、ナディール姫とともに、地下の通路から外へと出る。
「大丈夫か?」
今までと同じように、出迎えてくれる愛おしいヒト。その表情を見ると、やはり、自分の中の何かが緩んでしまうのを、ハヤブサは感じていた。
「シュバルツ、姫を頼む」
故に、ハヤブサは姫をシュバルツに託した。少し、その場で一息つきたい、と、願ってしまったせいかもしれなかった。
「分かった」
そんなハヤブサの態度を、特に疑問に思うこともなく、シュバルツは姫を彼から受け取り、崖の上へと登っていく。登り始めて少ししたところで、上から声をかけられた。
「姫様!!」
その声に、ナディール姫の方が、びくっと、少々過剰に反応する。少し不思議に思ったシュバルツが、上を見上げると、こちらをのぞき込んでいるイガールの姿が、視界に飛び込んできていた。
「あ……………!」
腕の中のナディール姫が、彼に向かって懸命に腕を伸ばし始める。気のせいか、その頬が、少し赤らんでいるようにも見えた。
(これは………)
シュバルツは、ピン、とくるものがあった。それがゆえに、彼女を地上に助け上げる役目は、イガールに託そう、と心に決めていた。
「姫様!!」
「イガール………!」
主従は互いに、懸命に手を伸ばしあう。イガールの手が、姫の手に触れた。
(もう、大丈夫だな)
シュバルツは、姫をイガールに託そうとする。
その刹那だった。
イガールの手から、姫の手が、ずるっと、滑るように離れる。
「─────!」
悲鳴を上げる間もなく、ナディール姫の身体が、下へと落ちて行ってしまっていた。
「しまった!」
「姫様!!」
誰もが、襲い来る悲劇的な予感に、悲鳴を上げる。
だがその悲劇は、あっさり回避されていた。ちょうど下に、龍の忍者がいたからである。
「おっと…………」
ハヤブサは、落ちてくるナディール姫の身体を、難なくキャッチしていた。
「ハヤブサ様………!」
「大丈夫か?」
受け止められて、驚いているナディール姫に、ハヤブサは声をかける。その横を、物体がものすごい勢いで駆け下りて行って、下の方で止まっていた。よほど急ブレーキをかけたのだろう。はずみで崩れ落ちた岩が、勢いよく水面に落ち、バシャバシャと、派手な波音を立てていた。
「うわっ、とと………」
下の方で体勢を立て直しているのが、シュバルツである、と、気づいたハヤブサは、あきれたように声をかけていた。
「シュバルツ……。大丈夫か?」
それに対してシュバルツは、多少苦笑しながらも、ハヤブサにひらひらと、手を振ってこたえる。
「いや、彼女が落ちたから………。でも、無事ならば、よかった………」
それに対して、ハヤブサはやれやれ、と、ため息を吐く。
(ちゃんと、フォローに走っていたんだな……。律儀な奴だ………)
そういうところも『好ましい』と、思ってしまうから、本当に困ってしまう。
どうやって───この愛おしさを、こらえればいい、と、言うのだろう。
「先に上がっている。後からゆっくり来い」
ハヤブサは、そうシュバルツに声をかけて、姫を抱きかかえながら崖を登り始めた。シュバルツは、そのハヤブサの言葉に、手を上げて応えていた。
ナディール姫が、ハヤブサとともに上に上がると、ミレイとロアンヌが、シェフと対面を果たしていた。
「すまない………っ! みんな………! よく、無事で………っ!」
「良人(あなた)………」
「父さん………!」
親子は歓喜の涙を流しながら、たがいに抱きしめあい、無事を確認しあっている。
(良かった………)
ナディール姫は、その姿を見ながら、ホッと胸をなでおろす。それと同時に、締め付けられるような痛みも感じた。
この家族を、こんなひどい目に遭わせてしまったのは、紛れもなく、自分のせいだからだ。
自分が、生きているせいで。
自分が、命を狙われているせいで─────
(お前は、生きているだけで、周りに迷惑をかけている存在なんだ)
厨房で言われた言葉が、胸によぎって、ナディール姫は何時しか、唇を強くかみしめていた。そんなとき、彼女に声をかけてくる者がいた。
「姫様………」
「イガール………」
ナディール姫が振り向くと、イガールが、ひどく申し訳なさそうな顔をして、たたずんでいた。
「姫様………。先ほどは、申し訳ございません………!」
「え…………?」
少し戸惑うナディール姫に向かって、イガールは頭を下げ、言葉をつづけた。
「姫様のお手を、しっかりと取れず………」
「いえ、それは違います! イガール!」
はじかれたように、ナディール姫は叫ぶ。
「貴方のせいではありません! 私が、貴方の手を、しっかりと握れなかったから────!」
「落ちていく貴女を見た時………『死んでしまったか』と、思いました………」
「………………!」
「ご無事でよかった………」
そう言って、イガールが、心底ほっとしたように、大きな息を吐いている。そのさまを見たナディール姫は、なぜか、ひどく胸の奥が、かきむしられるのを感じた。
「…………心配、してくださったのですか……?」
姫の問いに、イガールは柔らかい笑みを浮かべながら頷く。
「ええ………。姫様がご無事で、何よりです」
「……………!」
ぐっと、胸の奥が詰まるのを感じる。
鼻の奥が厚くなり、瞳から、勝手に涙があふれていた。
「あ……………!」
姫は、慌てて涙を隠そうとする。
馬鹿、駄目だ。
こんなところで、泣いてどうする。
イガールは『役目』で心配してくれているだけ。
『主君』の『娘』の無事を、ただ、安堵しているだけ。
彼の言葉に、それ以上の、意味はないのに─────
だけど、自分は、うれしかったのだ。
どうしようもなく、うれしかったのだ。
密やかに『想い』を寄せる人に、自分を案じてもらえたことが────
馬鹿だ。
馬鹿だ。
こんなことで、涙がこらえられなくなってしまうだなんて。
「ふ………………」
「姫様…………?」
イガールが、怪訝そうにこちらを見ている。早く泣き止まなければいけない、と、ナディール姫は強く思った。これ以上、泣くのはだめだ。これ以上の涙は、彼に迷惑をかけることに、なってしまうから。
泣き止め。
早く。
これ以上の涙は無意味だ。
やらねばならないことがある。
言わねばならないことがある。
だけど、一度乱れてしまった感情は、なかなか彼女を放そうとしてはくれなかった。
「姫様………」
涙を流し続けるナディール姫の前で、呆然とたたずんでしまうイガール。
「………………」
実はハヤブサは、かなり苛々しながら、その様子を見つめていた。
(「姫様………」じゃ、ないだろう!? あのバカ野郎が!)
彼女に、あんな涙を流させておいて、どうして抱きしめてやらないんだ、あの男は。
『好き』という気持ちがあるのなら────何も恐れることは、ないだろうに。
「彼女は王族だ。気持ち一つで、どうこうなるものでもないのだろうな………」
いつの間にかハヤブサの横に来ていたシュバルツが、そっと、呟いてくる。
「シュバルツ」
振り返るハヤブサに、彼は手を軽く上げて応えていた。
「彼女の置かれている『立場』を考えるのなら、そう簡単には抱きしめられないと、思うぞ」
ハヤブサの考えをなんとなく察しているのか、シュバルツが諭すように言葉を紡ぐ。
「立場か」
ハヤブサは、シュバルツの言葉に、軽くため息を吐いた。
「そんなもの、俺は気にしないがな………」
ハヤブサのぼそりと落とされた言葉に、シュバルツはやれやれ、と、肩をすくめる。
「それは、『お前』は、そうかもしれないが────」
そのまま彼は、イガールの方に、視線を走らせた。
「そこまで『覚悟』を決めた者など、普通はなかなかいない。イガール殿も、姫の置かれている立場を鑑みてしまって、二の足を踏んでいるのではないだろうか」
「………………」
ハヤブサは、シュバルツの言葉には答えず、一歩、前に出る。
好きなのだろう?
お互いが
お互いを。
ならば、一歩、踏み出すべきなのではないのか。
ハヤブサは、単純にそう考えてしまう。
本当ならば、護衛する対象の『恋心』の面倒を見るのまでは、依頼の範囲外のことだ。だから、余計な手出しなどせず、静観するのが、プロとしては正しい心構えなのかもしれない。
だが、何故だろう。
黙ってみていることなど、できそうになかった。
それは、自分もまた、恋をする痛み、辛さを、知ってしまっているせいかも、しれなかった。
「………………」
泣いているナディール姫は、無防備で、隙だらけだ。だからハヤブサは、手の中にそっと、小さな『気弾』を作り、彼女の足元に向けて放ってやる。
「─────!?」
姫の足元で爆ぜた『気弾』は、彼女の身体からバランスを奪う。そのままナディール姫は、前のめりに倒れてしまいそうになった。
「姫様!」
それを近くにいたイガールが、とっさに支える。
「─────!」
しかしその状況に、姫は身体を硬直させてしまっていた。
何故ならこれは。
自分から、イガールの胸に飛び込んでしまったも、同然なのだから。
「あ……………!」
「………………!」
硬直しているのはイガールも同じなのだろう。姫を支えた格好のまま、固まってしまっている。
「いっ!?」
「馬鹿ッ!! 見るな!!」
「し、静かに、何気ない風を装っているんだぞ………!」
周りの兵士たちも、いろいろと何かを察知しているのだろう。皆必死にあらぬ方向に視線を泳がせ、自分たちを『空気』と化そうとしているのが見て取れた。それがゆえに、その場は異様な緊張感が漂う空気が流れこんでいた。
「お、おい…………!」
これがハヤブサの仕業である、と、勘づいているシュバルツは、少し慌て気味に、彼に声をかけた。なんにせよ、これは先走りすぎているのではないか、と、感じてしまったからだ。
「………………」
それに対してハヤブサは、特に何も答えることはなかった。ただ腕を組んで、二人の様子を静観しているのみだった。
とにかく、きっかけだ。
二人に必要なのは、最初の一歩を踏み出すことなのではないかと、ハヤブサは感じていた。
互いの思いを確かめ合ってこそ、次への一歩が進めるのではないか。
(イガール………!)
今すぐ、この腕の中から離れなければならない、と、ナディール姫も、理性では分かっている。
しかしどうしたことか、身体はそこから一歩も動いてはくれなかった。
いや、動くことが出来なかった。
ナディール姫にとって、イガールとは。
子どもの頃は、単純に憧れていた存在。
それが、何時しか恋心に変わっていたのだと、自覚したのは、一体何時のことだっただろうか。
その人に今、自分は抱きしめられているのだ。
年頃の女性としての、気持ちが震えてしまうことに、どうして歯止めをかけることが出来るだろうか。
(でも違う)
『王族』として、王位を継ぐ覚悟を固めている『ナディール姫』が、懸命に頭を振る。
ちがう、ダメだ。
これ以上、彼に抱きしめられていてはいけない。
自分が望むのは、彼の平穏、彼の幸せ────
それは、自分の隣にいたのでは、彼は決して、実現できないのだ、と言うことを、姫はとっくに気づいてしまっていた。
だから、離れなければならない。
早く
早く────
(………とか、考えていそうだな……。あのお姫様は………)
ハヤブサはそう感じて、ため息を吐く。
ナディール姫都、ともに過ごすようになってから、彼女の思考回路がある程度読めてきたハヤブサ。妙にまじめなところ、自分を顧みない具合などは、愛おしいヒトと重なるところもある。
誰よりも、他人の幸せを願う彼女だからこそ、幸せになってほしい、と、ハヤブサは願った。
そして、彼女を幸せにできる存在は、すぐそこにいるイガールなのだが─────
行け。
少しでも、彼女のことを『好き』と、感じているのなら、抱きしめてやれ。
ハヤブサは少々、イガールをにらみつけるように見つめる。
イガールの方に、少しでも姫を『女性として好きだ』と、思っている、というのなら、迷うことなどないはずだ。この二人の間に横たわる問題など─────乗り越えられない物では、ないのだから。
(隊長………!)
兵士たちも、想いは同じようだ。
皆、二人から視線はそらしているが、必死に、彼らのことを、応援しているように見える。
行け。
二人とも
互いの『想い』を、
確かめ合ってくれ
「イガール………!」
彼の腕の中にいるナディール姫が、小さく身じろぎをした。
どうやら彼女は、彼の腕の中から、脱出する心づもりであるらしい。
「そ、その……! そろそろ………」
「………………!」
しかし、その動きを、ほかの誰あろう、イガールが阻止していた。彼は、明らかにナディール姫を、腕の中に引き留めていた。
「え…………!」
(おっ?)
その場にいた全員の視線が、イガールの挙動にくぎ付けになる。
「姫様………!」
(おおっ!?)
(行けっ! 隊長!!)
(姫様も、しっかり……!)
全員が固唾を飲んで、そのさまを見守ったがゆえに、その場の空気には、何とも言えない緊張感が張り詰める。だが、兵士たちは皆─────二人のことを、応援しているようであった。それぞれがこぶしを握り締め、「行け、行け」と、小さな声で繰り返している。
「イガール………?」
おずおずと、問いかけるナディール姫。それにイガールが、何事か、口を開きかけた時。
「一体、何をしているのです!? これは!!」
いきなり、甲高い女性の声が、その場に響き渡った。
その声を聴いたナディール姫は、慌ててイガールの腕の中から飛びのき、イガールもあわててかしこまる。
兵士たちも、各々隊を組みなおして、整然と整列し、怒鳴りつけてきた女性に向かって最敬礼をした。
ハヤブサは、口の中で小さく舌打ちをする。
何故ならそこには。
ナディール姫にとっては、ほぼ『天敵』と化している、『王太后』の姿が、あったからだ。
「お義母様………!」
驚いたように見つめてくるナディール姫を、大后は、険しい目つきでにらみつけていた。
「どういうことなのです!? これは!!」
王太后は、辺りをにらみつけるように見渡しながら、さらに声を張り上げていた。
「庭に、我が城のコックと思われる者の遺体が転がっている、と、報告を受けて城に来てみれば、詰所には誰もいないし! イガール!! あなたはこんなところで何をしているのですか!?」
「は、はい………!」
怒鳴られたイガールは、ただ恐縮してかしこまっている。ハヤブサは、小さく「チッ!」と、舌を打っていた。
全く余計なタイミングで、この女は出てきてくれたものだ。
本当にあと少しで、二人の気持ちが確かめ合えたというのに。
「お義母様! イガールを責めないでください!」
ナディール姫が、イガールをかばうかのように、その前に飛び出してきた。
「イガールは、私たちを守るために─────!」
「『守るため』!? ナディール………! 貴方また、狙われたのですか!?」
「…………!」
王太后の言葉に、姫はグッと、言葉に詰まる。そんな彼女に、王太后は「うんざりだ」と言わんばかりに、ため息をついていた。
「全く……! 貴方が王の代理を務めるようになってから、本当に、こんなことばっかりだわ!! いったい、どういうことなのかしら!!」
斬り付けるような王太后の言葉に、ナディール姫は、グ、と、唇をかみしめるしか、対応する術がなかった。
だって、事実だ。
今回の騒動も、自分が狙われたせいで、引き起こされたようなものだ。そこに、反論の余地などないのだから。
「………………」
黙りこくってしまったナディール姫に、王太后は、忌々しそうにため息を吐く。
「この城の中が、不穏な空気に包まれているのも、みんな貴方のせいなのよ!? そのあたり自覚があるの!? どうして黙ってしまうのかしら!?」
「王太后様………」
「イガールは黙っていなさい!!」
何事か言いかけたイガールを、ぴしゃり、と、押さえつけるように王太后は怒鳴る。
「大体、貴方まだ昨日の分の報告書を、出していないじゃないの!! こんなところで油を売っている場合ではないでしょう!?」
「申し訳ありません!」
恐縮しながら、頭を下げるイガール。それに、王太后は、ふん、と、鼻を鳴らすと、周りの者たちにも非難するかのように声を張り上げていた。
「貴方たちも! こんなところに集まっていないで、さっさと持ち場に戻りなさい!! こんなに緩み切った警備だから、城の中にいろんなものが入りこんでくるのです!!」
(不穏にしているのはお前じゃないのか?)
ハヤブサは、かなり苛つきながら、王太后の方を睨みつけていた。
実際、今現実に、ナディール姫のことを、『疎ましい』と、はっきり思っているのは、ほかならぬこの王太后だ。彼女が姫に対する殺人を企て、刺客を送り込む画策をしていても、おかしくはない。
「ハヤブサ」
自分のたたずまいから、何かを察したのだろう。シュバルツが声をかけてくる。
「余計なことはするなよ……。今、何かを王太后に仕掛けたら、そのとばっちりは『お前』ではなく、『彼女』に行く」
「……………!」
痛い『事実』を突き付けられて、ハヤブサもぐっと押し黙るしかない。
シュバルツの言っていることは、正しい。
正しいのだが────
ハヤブサは、つくづく思う。
自分には、『宮仕え』は決して向いてはいないのだと。
身分
権勢
序列───
そんなものに気を使い、縛られなければならないなど、何とバカバカしくて厄介なものなのだろう。
「ナディール!! また貴方はそんなみすぼらしい恰好をして!! さっさと着替えてらっしゃい!! 全く、王家の恥さらしもいいところだわ!! イガールは、早急に報告書の提出と、庭の遺体の片づけと犯人捜しを始めなさい!! こんな朝早くからたたき起こされて! 本当に、いい迷惑だわ!!」
ヒステリックに怒鳴り続ける王太后。ハヤブサがそれに、いい加減ブチ切れそうになっていた時、思わぬところから、救い船のようなものが、そこに駆け込んできた。
「お母さま!! お義姉様!!」
「ノゾム!?」
義弟の姿に驚いたナディール姫は、思わず素っ頓狂な声を上げる。
それもそのはずで、今の時刻は朝の4時。少し、夜が白んできているとはいえ、ノゾムのような子供が起きだすには、まだ早すぎる時間だったからだ。
「まあ、どうしたの? ノゾム。そんな恰好で外に出てきては、風邪をひきますよ?」
王太后が、ナディール姫に対するときとは打って変わって、恐ろしく優しい声音でノゾムに声をかけている。こうもあからさまに人によって態度が違うと、ハヤブサなどは失笑を覚えてしまうのだが、パジャマ姿のノゾムは、そんなことを、気に留める余裕もないのだろう。母の言葉が終わるのももどかしげに、手に持っていたタブレットを母に向かって差し出していた。
「お母さま!! これを!! これを見てください!!」
「どうしたの? ノゾム。そんなに慌てて────」
「ドモン………!」
「えっ?」
ノゾムの口から出てきた思わぬ単語に、ハヤブサとシュバルツが同時に顔を上げる。
「ドモン・カッシュから、僕宛にメールが来てる!!」
第4章
「はぁ…………」
執務室でナディール姫は、疲れ果てたようなため息をついていた。
その横にはカライ内大臣が、眉間に深いしわを刻んで立ち、ハヤブサが難しい顔をして腕を組んでいた。
苦笑しながら立つシュバルツの横には、ノゾムが縋りつくようにくっついて立っている。
かなり、不可思議な状況だが、ここに至るまでには、本当に、いろいろとあったのだ。
「ドモン・カッシュからメールが来た、ですって?」
ノゾムからタブレットを受け取りながら、王太后が怪訝そうに眉を顰める。
「はい、お母さま!」
ノゾムは嬉しそうにうなずきながら、王太后にメールを指し示す。
「これです! このメールが………!」
「これですか?」
王太后は、ノゾムに指示されるままにそのメールを見て、すぐに眉をひそめていた。
「何です? この不愛想なメールは………!」
そのまま、王太后は、不愉快そうにノゾムにタブレットを突っ返す。
「こんなもの、相手にする必要はありませんよ、ノゾム。偽物に決まっています」
「偽物………」
少し、がっかりしたように、王太后からタブレットを受け取るノゾム。
「ノゾム………」
義弟が沈んでしまった様子を、気の毒に思ったナディール姫が、彼に向かって手を差し出した。
「私にも、見せてくれる?」
「はい、お義姉様」
幼い義弟は、素直にタブレットを差し出す。
「どれがそうなの?」
姫がそう聞くと、義弟は慣れた手つきで、その端末を操作していた。
「これです。これが───」
「…………………」
義弟に指し示されるままにそのメールを見て、ナディール姫の方も、眉をひそめていた。
「本当にこれ?」
問い返す義姉に、義弟も、こっくりと頷き返す。
「うう~~~ん………」
ナディール姫が、かなり複雑な顔をするから、ハヤブサも、思わず一歩、前に進み出ていた。
「俺も、見せてもらっていいか?」
ドモン・カッシュとは、知らない間柄ではない。メールを見れば、真偽の判断ぐらいはつくのではないか。ハヤブサは、そう思ったからだ。
「いいですよ」
ハヤブサの要求に、ナディール姫はあっさりと応える。差し出されたタブレットをのぞき込んで、ハヤブサもまた、何とも言えない気持ちになった。
ハヤブサの目の前に差し出された、一通のメール。
そこにはただ一言。
「お前、俺に会いたいのか?」
とだけ、書かれていたからだ。
(愛想もくそもないな………)
ハヤブサは、あきれたようにため息を吐く。
仮にも、面識もなく、一応『王族』の人間にメールをよこすのだ。それなりの気配りをして、しかるべきなのではないかと、思うってしまうのだ。
だがまあ、ある意味、この不愛想なメールも、ドモンらしいといえば、ドモンらしいのだが。
「ああ、それは本物のドモンからだよ。なるほど、あいつも、あの動画を見たんだな」
「─────!?」
突如として聞こえてきた言葉に、その場にいた全員が、ぎょっと、顔を上げ、そちらの方を見る。すると、ハヤブサの後ろから、タブレット端末をのぞき込んでいたシュバルツと、視線が合った。
「シ、シュバルツ様………?」
「ん?」
ナディール姫が、恐る恐る、と、言った塩梅で問いかけてくる。シュバルツはそちらに笑顔を向けた。
「このメールが『本物のドモン様からだ』と……どうして、断定できるのですか……?」
「ああ………。私は一応、『ドモンの兄』だから───」
「ええええええええええええっ!?」
突如として響き渡る、驚愕の大合唱の嵐。シュバルツが「しまった!」と、思ったときには、時すでに遅く、全員が、眼をぎりぎりまで見開き、食い破らんばかりに、こちらを見つめていた。
「本当に!?」
「シュバルツ殿が!?」
「ドモン・カッシュの!?」
「いや………えっと…………」
シュバルツは少々たじろぎながら、必死に逃げ道を探そうとする。だがそれよりも早く、彼はあっという間に城の者たちに、取り囲まれてしまった。
「ドモン・カッシュの兄………」
「いわれてみれば、似ているような………」
「だが、ドモン・カッシュに兄弟居たっけ?」
その言葉に、一同がフム、と、首をひねる。その中で、ノゾムが一人
「いますよ」
と、冷静に応えていた。
「ドモン・カッシュには、確か、お兄さんがいて………」
ノゾムが、慣れた手つきで端末を操っている。
「そういえば、ノゾム様は、ユリノスティ王国一の、ドモン・カッシュのマニアだったな」
「データベースをこしらえているって、聞いたことがあるぞ?」
「雑誌の記事とか、全部スクラップ帳に保存してあるとか……」
(マニア………)
兵士たちの話を聞きながら、シュバルツはもう苦笑するしかない。
キョウジも相当な「ドモンマニア」といえるが、果たしてそれを上回るほどだろうか、と、シュバルツが思索している間に、ノゾムは目的の記事に、たどり着いていた。
「あった。この項目だ。お兄さんの名前は、『キョウジ・カッシュ』と言って─────」
そこまで行ったノゾムは、キョウジの画像から、シュバルツの方に視線を移す。
「え…………」
そして、そのまま固まってしまった。
なぜなら、そこにいた『シュバルツ』の顔は
どこからどう見ても、『キョウジ』の顔を、瓜二つなことに、気づいてしまったからだ。
「……………」
それは、兵士たちも同じのようで、キョウジとシュバルツの顔を見比べて、皆、あんぐりと口を開けている。
「………………」
「………………」
しばし、奇妙な沈黙が、その場を支配する。シュバルツは微笑んではいるが、明らかにその頬が、ぴくぴく、と、引きつっていた。
「あの…………」
ノゾムが口を開いた瞬間、シュバルツが己の顔に、がぼっと覆面をつける。
「あ…………!」
だが、ノゾムが小さな悲鳴を上げた瞬間、ハヤブサが、シュバルツの覆面を、がぼっと取り外していた。
「お……! おい………!」
慌てるシュバルツを、ハヤブサはじとっと、にらみつけていた。その手にはシュバルツの覆面が、しっかりと握られている。
「こうして名乗ったんだ。いまさら、隠れようとするのはよせ」
「いや、しかし………!」
シュバルツは、名乗ったことを、少し後悔してしまう。
自分は、あくまでもキョウジの『影』
だから、こんな風に、キョウジの代わりに、自分が注目を浴びることなど、あまりよくないことのように思うのだ。
「心配するな、シュバルツ。悪いようにはしない」
ハヤブサは、シュバルツの覆面を懐にしまいながら、口を開く。
「それよりもシュバルツ、ノゾムを見てみろ」
ハヤブサに指し示されるままに、シュバルツはノゾムの方に視線を走らせる。そこで、ぎょっと、固まってしまった。
なぜなら、ノゾム王子は
いっぱいに涙をたたえた瞳で
すがるようにこちらを、見つめていたからだ。
「お前、この子のこの眼差しを、振り払うのか?」
「うう…………!」
痛いところを突かれて、シュバルツはぐっと、押し黙るしかない。
「あきらめろ、シュバルツ。乗りかかった船だ。この子の期待に、応えてやれ」
ハヤブサの言葉に、シュバルツはがっくりと、頭を垂れる。そこで深くため息を吐いていると、ノゾムから、「あの………」と、そっと、声をかけられた。
シュバルツが顔を上げると、ノゾムが食い入るように、縋るようにこちらを見つめている。
(参ったな………)
シュバルツは軽く苦笑すると、ノゾムと同じ目の高さになるように、腰をかがめた。
本当に参った。
子どものこんな眼差しなど────抗うことが、出来なくなってしまうではないか。
「あの………貴方は………」
「何だ?」
「本当に………ドモン・カッシュの、おにいさん………です、か………?」
「ああ、そうだよ」
シュバルツはノゾムの質問に、笑顔で答えた。
そう────自分は確かに、『ドモン・カッシュの兄』その定義は、間違ってはいないと思う。ドモンは私のことも兄と呼び、とても慕ってくれている。でも『キョウジ本人か』と、問われれば、首をひねるしかないのだけれども。
「………………!」
目の前でシュバルツに頷かれてノゾム少年は、感極まった表情をその面に浮かべた。全身を震わせ、喜びを露わにし出した。
「あ………! えっと………! その…………!」
瞳をキラキラと輝かせながら、手足をばたつかせ、必死に言葉を紡ごうとするノゾム。
「は、はじめまして……! こ、こんにちは………! 僕の名前はノゾム・ユラ・シャハディ。は、8歳です……! す、好きな食べ、食べ物は……!」
そのまま、必死に自己紹介をしようとする。緊張しすぎているのか、あからさまにろれつが回っていなかった。
「ま……! 待て………! ちょっと、落ち着こうか………」
シュバルツは、慌ててノゾムを制止しようとする。
自分は、ドモン本人ではない。あくまで『兄』で、しかも、『兄のようなもの』なのだ。それなのに、そんなに舞い上がってしまったら、ドモン本人に会ったら心臓が持たないのではないかと、心配してしまう。
「落ち着いて……。私は君が、そこまで舞い上がるほどのモノではないんだ」
(舞い上がるけどなぁ)
ハヤブサは腕を組んで、深いため息を吐く。
全く、この男は、自分の存在がどれほどのものか、分かっていない。
俺が、お前がそばにいる、というだけで、
どれほど舞い上がり
どれほど幸せな気持ちを、味わい
どれほどその身体を抱きしめたい、と願っているか
全く、分かってくれていないのだ。
「で、でも………! そのっ………! 僕は………!」
「とにかく深呼吸をして……な………」
ノゾムにやさしく微笑みかけるシュバルツ。その後ろ姿を見て、何かを思わないハヤブサではない。その優し気なまなざしと、ノゾムを思いやる心根と仕草に、どうしても、ハヤブサの心中では、割と邪な想いが、鎌首をもたげてきてしまう。
今すぐ抱きたい。
お前の心を
その身体を
暴いて
晒して
奪って─────
お前の中を、俺だけで、満たしてしまいたい。
(シュバルツ………!)
悶々としながら、シュバルツの後姿を見つめるハヤブサ。
そこに、突如として、鋭い女性の声が響き渡っていた。
「なりませんよ! ノゾム! その男から離れなさい!」
「え…………!」
その声に、ノゾムの身体は硬直し、周りの兵士たちも、驚いてその声の主の方を見る。
するとそこには、ひどく険しい目つきで、シュバルツの方をにらみつけている、王太后の姿があった。
「お義母様!?」
驚きの声を上げるナディール姫を、王太后がきっと睨みつける。
「良いですか? ノゾム……! 私たちは『王族』です。私たちの持つ権力を目当てに、近寄ってくる輩はたくさんいるのです。それを常に、忘れてはなりません!」
「で、でも………」
ノゾムは、弱弱しく反論をしようとする。だが、彼が言葉を発する前に、それは封じ込められてしまった。
「貴方が『ドモン・カッシュに憧れを抱いている』というのは、世界中に知れ渡っていることです! それを『悪用しよう』と、近づいてくる輩など、それこそ五万といるのですよ!? そこの男が、貴方を陥れようとしていない、という保証が、どこにあるというのです!?」
「─────!」
母の言葉に、ノゾムは、気の毒なほどに顔面蒼白になってしまっていた。
「お義母様!!」
それを見たナディール姫が、たまらず声を上げる。
「お義母様!! その言葉は失礼すぎます!! ここにいるシュバルツ様は、先ほどまで私たちのために───!!」
「お黙りなさい!! ナディール!!」
ナディール姫の叫びを、王太后はぴしゃり、と、払いのけていた。
「良いですか!? 貴方は能天気で、人を信じすぎるきらいがあるから、忠告して差し上げます!! 人を陥れるために、最初は善人のふりをしてこちらに取り入ってくる輩など、それこそ吐いて捨てるほどいるのですよ!? その男が、まさに『ドモン・カッシュの兄』だという保証が、どこにあるというのですか!?」
「……………!」
王太后のその言葉に、ナディール姫は息をのみ、シュバルツは苦笑していた。
確かにそうだ。
今この場で、自分が確かに「ドモンの兄」だと、証明する手段が、実は無いに等しいということに、シュバルツは気づいてしまっていた。「自分は怪しいモノではない」と、証明するのは、存外、難しいものなのだ。
「とにかくノゾム、その男から離れなさい!」
「う……………!」
ノゾムは顔を引きつらせながら、その場に固まってしまっている。見かねたナディール姫は、ノゾムと王太后の間に、割って入っていた。
「お義母様……! シュバルツ様を、どうなさるおつもりなのですか……」?」
「決まっているでしょう? ひっ捕らえて、私が直々に検分いたします」
「─────!」
その言葉に、ナディール姫とノゾムの顔色が、同時に真っ青になる。シュバルツは哀しみ故に、その眉を少し顰めていた。
「『ドモン・カッシュの兄』だなどと名乗るなんて、怪しすぎる……! 尋問して、真の目的を確かめなければ───!」
「ほう」
王太后がここまで口走った時、やけに殺気立った声が、その場に響き渡っていた。
「…………………!」
全員がぎょっとなって、その声の方に振り返ると、ひどく殺気をその身にまとわりつかせている龍の忍者が、王太后の方をじろり、と、睨みつけるようにして、立っていた。
「シュバルツを、捕らえるだと………?」
ハヤブサの前で、『シュバルツに危害を加える』ことを匂わせる単語は、ある意味絶対に言ってはならない言葉であった。ハヤブサの心の中は今─────最近、シュバルツに触れられていないことも手伝ってか、あらぬ方向に妄想が暴走し始めていた。
以下はハヤブサの妄想が暴走している賜物なので、興味のない方、無理な方は読み飛ばしてくださって結構です。それ以外の方は、作者の完全なる趣味の世界ですので、どうか生暖かい眼差しで見守っていただければ、これ幸いかと存じます。
薄暗い牢の中で、両手首に鉄の輪をはめられ、天井からつりさげられた鎖に、つながれているシュバルツ。上半身の服ははぎとられ、その白い肌を看守たちの前に晒していた。
「さっさと吐け!!」
うなりを上げた鞭が、シュバルツの白い肌を、容赦なく穿つ。
「ああっ!!」
肌には痛々しい蚯蚓腫れの痕が、いく筋にも走っている。この牢の中で行われた責め苦の激しさを、うかがわせていた。
「う………! く………!」
唇をかみしめ、苦痛に耐えるシュバルツ。身体が小刻みに震え、汗が、白い肌の上を艶めかしく伝い落ちていた。
「あ…………!」
シュバルツの唇から漏れる吐息に、看守の一人が、ゴクリ、と、生唾を飲み込む。
「………お頭、一つ、責め方を変えてみてはいかがですか?」
「責め方を変える?」
部下からの提案に、看守長が振り向くと、提案した部下はしたり顔で頷いた。
「こいつを、レイプしてやるんです」
「…………!」
「な────!」
部下の言葉に、看守長は驚いたように目を見開き、シュバルツは思わず声を上げていた。
「人間は、快楽には耐性がなく、抗いようがないって話です……。どんな奴でも、たっぷりと身体の隅々までかわいがってやれば、音を上げるんじゃねぇでしょうか」
「それもそうだな」
看守長もその言葉に、にやりと笑って頷いた。
「よし、そいつの服を剝げ。たっぷりと可愛がって、雌犬のように哭かせてやるんだ」
「や!! やめろっ!!」
シュバルツは顔色を変え、懸命に抗おうとするが、拘束されている身では、しょせん、無駄なあがきにしかならず─────
(ああ………! いや………! 助けてくれ……! ハヤブサ………!)
絶望に涙する、シュバルツの白い肌に、男たちの武骨な手が─────
「へ~~~~~~~~~」
妄想が、そこまで到達してしまったときに、ハヤブサはかなりブチ切れてしまっていた。龍の忍者から発せられたどす黒い殺気が、辺りの空気を切り裂き、異常な緊張感を、その場にもたらしていた。
「お、おい………! ハヤブサ………!」
ハヤブサから感じられる、おかしな空気に、シュバルツがたまらず声をかける。
「そこまで過剰反応することは、ないと思うぞ、ハヤブサ。私は別に、少々捕らえられたって────」
「捕らえられて、万に一つでも間違いがあったら、どうするつもりなんだ」
声をかけてきたシュバルツを、ハヤブサはぎろり、と、睨み返す。
「お前が他人から振るわれる暴力に痛めつけられるのを、黙って見ていろ、と、言うのか?」
「そういうわけではないが………」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは少し辟易してしまう。
自分の身体は『不死』だ。たいていの傷は、少し時間がたてば治ってしまうし、捕らえられたところで、縄抜けもできるし、壁抜けもできるから、全く持って、問題にもならない。それを、ハヤブサは知っているはずなのに。
「心配するな。(お前にとって)悪いようにはしない」
ハヤブサはそうって、一歩、前に進み出ようとしている。その様相は、どう見たって、これ以上事態を悪くする気満々だった。
「な、なんです? お前は………!」
殺気立つハヤブサに、しかし王太后も、傲岸な態度を崩さない。ハヤブサを真正面から、ぎり、と睨みつけている。
「この私に向かって、そのような態度─────許しませんよ!! ここをどこで、私を誰と心得ているのですか!!」
「……………!」
その言葉に、周りにいた兵士たちは、はっと顔色を変え、各々姿勢を正した。しかし、ハヤブサは、眉一つ動かさない。
関係ないのだ。
たとえ、目の前にいるのが何であろうが、『神』と名乗る存在であろうが────
俺の大事なヒトを傷つける、というのであれば、容赦はしない。
「う……………!」
小さな呻き声に、シュバルツがはっと気が付くと、自分のすぐ目の前で、ノゾムの小さな身体が小刻みに震えている。
「大丈夫か?」
シュバルツが小さく声をかけると、「あ…………」と、声を上げたノゾムが、縋るようなまなざしを向けてきた。
(おいで)
シュバルツが手を差し出すと、ノゾムはそっと、身を寄せてくる。しかし、身体の震えは止まらず、表情も硬く───その顔色も、蒼白なままだ。
(良くないな)
シュバルツは、ノゾムの小さな手を握り返してやりながら、眉を顰めた。
こんな状況─────この子にとっていいことなど一つもない。早くなんとかしてやらなければ。
(私が、大人しく捕まればいいではないか)
シュバルツはそう思い立つ。自分がつかまりさえすれば、とりあえず、この場を丸く収めることができる。それに、捕まることで、城の内部深くに入り込むことで─────見えてくることも、あるのではないだろうか。
(捕まろう)
シュバルツはそう決意して、顔を上げる。立ち上がろうとすると、小さな手が、ぐっと手をつかんできた。
「……………!」
シュバルツが少し驚いてそちらの方を見ると、必死の形相で縋り付いてきている、ノゾムの姿が見える。
「ノゾム………」
シュバルツは優しく声をかける。ノゾムを怖がらせたり、不安な思いをさせたりするのは、シュバルツの方としても本意ではなかった。
「離してくれないか?」
「……………っ!」
ノゾムは、両目いっぱいに涙をたたえながら、必死に首を横に振っていた。母親に、自分を捕まえさせるわけにはいかない、と、思っているのだろう。
(優しい子だな)
だからこそ、これ以上、彼の心を煩わせるわけにはいかない。
シュバルツは、強くそう思った。
「大丈夫だから………な?」
「でも………!」
ノゾムは、懸命にシュバルツを引き留めようとした。
今、この人を自分の母に捕まえさせることは、絶対にしたらいけないと思った。そうしなければ、後ろの大人たちの『殺気』が、完全に取り返しの付かないところまで膨れあがってしまう。ノゾムはそう感じていたからだ。
そんなのはだめだ。
何とかしたい。
強くそう思うのに、自分は、どうすればいいのか、まるで分らなかった。
歯がゆい。
無力な自分が。
「ノゾム! そこから退きなさい!!」
母から、鋭い声が飛ぶ。だがノゾムは、懸命に首を横に振った。
聞けない。
聞きたくない。
いくら母の『命令』でも。
「ノゾム!! この母の言うことが聞けないの!?」
「……………!」
ぐっと、歯を食いしばって、シュバルツに縋り付く。「大丈夫だから、離れて」と、シュバルツに優しく言われるが、それにも懸命に首を振った。
(困ったな………)
シュバルツは途方に暮れてしまう。
この小さな手を振り払う術を、自分は持ち合わせていないからだ。
「………仕方がないわね………!」
母の、低い声が響く。
これは、またいつものように激しく切れて、理不尽に八つ当たられるように怒られる前触れだった。恐怖を感じて、ノゾムは身を固くする。
(あ、駄目だ)
シュバルツは思った。これ以上この状況を続ければ、この子の心がパンクしてしまう。だから、縋り付いてくるノゾムの手を、何とか身体から離そうとした。
だが、ノゾムは懸命に抵抗してくる。シュバルツがそれに途方に暮れていると、自分たちを背に庇うように、ハヤブサが王太后の前に、立ちふさがっていた。
「……………」
「……………ッ!」
王太后とハヤブサの間に、殺気と緊張が膨れ上がる。それが、極限まで達しようとしたとき、突如として、女性の激しい怒声が、その場をつんざくように響き渡っていた。
「いい加減にしてくださいッ!!!」
「!?」
全員が、ぎょっとなってそちらの方に振り向くと、ナディール姫が、かなり険しい目つきで、ハヤブサと王太后を睨みつけていた。
「お義母様! お気遣いありがとうございます! ですが、ここは引いていただけませんか!?」
「『引け』ですって!? どういうことなのナディール!!」
「文字通りの意味ですわ。お義母様」
王太后の問い返しを、ナディール姫は、しれっと受け流す。その目つきが完全に据わっていたので、ハヤブサは思わず頬がひきつるのを感じた。
完全に怒ってしまっている。
あの温厚な姫が。
「………………」
ハヤブサは、王太后に対する構えを解いた。二人の『戦い』の行方を、静観することにしたのだ。
「シュバルツ様の検分は、私が致します。ですからどうか、引いていただけませんか!? お義母様」
「んまあ! ナディール!! 貴方みたいな甘い心がけの人間が、相手の正邪を判断することなど─────」
「私はここの責任者です!! お義母様!!」
ナディール姫の大声が、辺りに響き渡っていた。
「私は、父であるガエリアル王より、その全権を託されているのです!! すべての責任は、この私にあります!!」
ナディール姫の、張りのある、凛とした声が響く。
「シュバルツ様の正邪は、私が責任を持って検分いたします! ですからお義母様!! どうかここはお引き取りを!!」
「まあああ……! なんて口の利き方なのかしら!? 貴方より目上の、王太后たる私に向かって────!」
王太后の、忌々しそうにナディール姫を睨みつけている。しかし、ナディール姫は、眉一つ動かさず、そこに立っていた。
「そのようなことを言って……! 何かあったらどうするつもりなのかしら!? その責任を、すべて被ると────」
「当然ですわ。お義母様」
ナディール姫は、表情を変えずに言い放つ。
「このことで何か『咎』を受けるのなら、それは、責任をもって私が受けます!!」
(シュバルツの正邪については、俺が全面的に保障するがな)
二人の話を聞きながら、ハヤブサは思う。
シュバルツの根本に流れている物は、キョウジの『良心』
それ故に彼は、これ以上ないというほど、善良な思考回路の持ち主だった。
そのシュバルツが、このナディール姫やノゾムに対して、何か害をなすなど考えられない。
「………………」
現にシュバルツは、縋り付いてくるノゾムをやさしく抱き返しながら、その背をそっと撫でている。
その、どこまでも優しいまなざしが
仕草が
たたずまいが────
(ああ何かもう、可愛らしいというか、愛おしいというか、辛抱たまらん、というか………っ!)
ハヤブサは、うっかりシュバルツに萌え剥げそうになって、そのまま抱きしめそうになって、色々困った。
今ここでそれをするには、あまりにも周りに人が多すぎるし、状況も、予断を許してはいない。
それなのに─────
どうしてこんなにも、
こちらの心をシュバルツは、激しく揺さぶってくるのだろうか────
「とにかくお義母様!! この場はどうか、お下がりください!! 王から全権委任を受けた私が、責任をもって処理いたします!!」
そう言って、ナディール姫は、王太后に「城に帰れ」と言わんばかりに、腕を城の方へと伸ばす。
「……………!」
王太后は、ぎり、と、唇をかみしめていた。
あまりにも
あまりにも────屈辱だった。
しかし、王の名前まで出されてしまえば、自分は、下がるしかなくなってしまう。
「………覚えてなさいよ……!」
じろり、と、姫を睨み付けながら、言葉を投げつけるが、ナディール姫は顔色一つ変えない。
「フン!!」
王太后は忌々しそうにため息を吐くと、大仰にドレスを翻しながら、ようやく城の方へ足を向けた。畏まって頭を下げるイガールの前を通り過ぎるとき、彼女はイガールに向かって声を荒らげた。
「イガール!! 後で話があります!! 早急に、私の部屋に来るように!!」
「は、はっ!!」
「なりません!! イガール!! 貴方には、早急にやるべき事があるはずです!!」
王太后の命令を遮るかのように、ナディール姫の声が飛んできた。
「中庭に、遺体があったのでしょう!? ここでコックをやっていたイワンコフの可能性があります!! そちらを直ちに調査して下さい!!」
「姫様………!」
呆然とこちらを見つめるイガールの方に、姫はちらり、と、視線を走らせてから、再び王太后の方に、険しい目を向けた。
「………それとも、お義母様のイガールに対するご用は、この緊急性を上回る物だ、とでも言うのですか!?」
「…………………!」
王太后は無言で踵を返し、足音荒くその場を後にしていた。その後から、王太后の後ろに最初から控えていた、2、3人の武官たちが、慌ててその後に続いていた。
「…………………」
王太后の姿が見えなくなって、その場のぴりぴりした空気が少し、緩む。ナディール姫は、一つ大きく息を吐くと、直ぐに顔を上げた。この場を収めるために、まだ、出さねばならぬ指示があるからだ。
「誰か、ミレイさんとロアンヌさんを、病院へ連れて行ってあげて下さい。虜囚になっていたのです。健康状態を診てもらって下さい」
「はっ!」
姫の命を実行すべく、2、3人の兵士が動き出す。
「シェフは、ミレイさんとロアンヌさんに、付き添ってあげてください」
「え…………」
姫の言葉に、シェフは戸惑いを隠せないかのように、声を上げた。
「し、しかし………。あなた方の食事の用意が………」
その言葉を聞いた姫は、軽く苦笑していた。
「そんな心配はしなくて良いわ。1日2日ぐらいの私たちの食事なら、何とでもなります」
「し、しかし………!」
「そうよね? ノゾム」
義姉に問いかけられたノゾムは、懸命にコクコク、と、頷いていた。
「だから、遠慮無く、奥さんと娘さんの傍に、付いていてあげて下さい」
「わ、分かりました………」
姫にそうまで言われては、シェフも折れざるをえない。ミレイとロアンヌと共に、兵たちにつれられて、病院へと向かっていった。
「さてと、シュバルツ様」
シェフたちがの姿が見えなくなったのを確認してから、ナディール姫はシュバルツの方へと向き直った。
「私と共に、執務室に来ていただけますか?」
「ああ……。構わないが……」
シュバルツが頷くのを見て、ナディール姫の面に、やっと少しの笑みが浮かんだ。
「では、執務室に参りましょうか。誰か、カライ内大臣に、執務室に来るよう連絡を取っておいて下さい」
「はっ!」
姫の言葉に、兵士が頷いて走り出す。それを見届けてから、シュバルツの方に振り返ったナディール姫は、シュバルツに縋り付きながら、じっとこちらを見つめているノゾムと、視線が合った。
「ノゾムは…………」
ナディール姫は、義弟に声をかける。
「ノゾムはどうする? 自分の部屋に帰る?」
姫の問いかけに、ノゾムはぶんぶん、と、勢いよく首を振る。そのままぎゅっと、シュバルツに縋り付いていた。
(これは、意地でも離れないつもりね)
義弟の意思を正確に読み取って、ナディール姫は苦笑する。
「じゃあ、ノゾムも一緒に来る?」
姫の言葉に、ノゾムは一瞬表情を緩めるが、直ぐに、その面に緊張の色が浮かんだ。
「お義姉様……。シュバルツ様を検分するって、どうするの? まさか、酷いことをするの………?」
「そんなことはしないわよ」
ノゾムの言葉に、ナディール姫は少し、呆れたように笑った。
自分がシュバルツを尋問など、出来ようはずもない。そんなことをしようとしたら、烈火の如く怒り狂う人間が、自分の傍に控えている。
ハヤブサは、このシュバルツという人間に、並々ならぬ信頼を置いているのがよく分かった。
(嘘か本当か分からないけど………『恋人』って、言っていたし……)
『仕事』と、言いながら、本当に、命かけて自分を守ってくれたハヤブサ。
その彼が『信』を置く人間であるならば、信用してもいいのではないか、と、ナディール姫はひそかに思っていた。だから、今から行う『検分』も、シュバルツという人間が、信じるに値する人かどうか、確認する作業になるだけだろう、と、ナディール姫は思っている。
(シュバルツを、尋問か………)
ナディール姫が、シュバルツに無体なことをするなど考えられないので、ハヤブサはそのあたりのことは、まるで心配していなかった。
どっちかというと、シュバルツを尋問するなんて、おいしいシチュエーション、ぜひとも味わってみたいと、邪な想いが、頭をよぎったりしている。
以下は、ハヤブサの妄想であり、作者の完全なる趣味の世界なので、読み飛ばしてくださって結構です。やばい、と、思ったら、Uターン推奨です。
それ以外の方は、いい加減、二人のいけない場面を書きたいと、願う作者の欲求が、暴発しているので、生暖かく見守っていただければ、これ幸いかと存じます。
「ハヤブサ………」
涙目のシュバルツが、縋るようにこちらを見つめてきている。両手足の自由を奪う縄が、ギ、と、軋んだ音を立てていた。
「お、お願いだ………! もう、許し………!」
「許さない」
彼の懇願を、一刀両断にする。乱れた衣服を、さらにはだけさせながら、あらわになった白い肌を、指先で嬲るように愛し始めた。
「あ…………! あ…………!」
切ない声で喘ぎ始める、愛おしいヒト。
軋む縄が、
揺れる肌が、
漏れる吐息が────
いろいろと、たまらないから──────
「ナディール」
「どうしました? ハヤブサ様」
振り返ったナディール姫に、ハヤブサは思わず口走る。
「シュバルツを尋問するのなら、ぜひ俺にや」
ドカッ!!
派手にぶん殴られて、ハヤブサはこけてしまう。
「痛い!!」
涙目になりながら顔を上げると、ノゾムを抱きかかえたシュバルツが、ジト目でこちらを睨みつけていた。
「お前、今、姫に何を言おうとした? 何を考えているんだ」
「えっ?」
「『えっ?』じゃないだろう」
シュバルツが、氷のような眼差しを向けてくる。それをハヤブサは、鉄面皮ではじき返していた。
「どういうつもりだ? 私を尋問とかどうとか言っていたが」
「姫を手伝えたら、と、思ってな」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサはしれっと返す。
「お前の清廉潔白が証明されれば、いいだろう?」
「それはそうかもしれないが────」
ハヤブサに同調しながらも、シュバルツはなおも、冷たい眼差しを、ハヤブサに向け続けていた。
「ちなみにお前、私を尋問するとしたら、どうやってするつもりだったんだ?」
「えっ?」
「『えっ?』じゃないだろう?」
忍者二人は、本日二度目の同じやり取りをしていた。
「質問に答えろ、ハヤブサ」
鋭い眼差しを、向けてくるシュバルツ。そのまなざしすら、自分には愛おしく感じられてしまうから、もういろいろ手遅れなのだろうな、と、ハヤブサは思った。
「私を、どうやって『尋問』するつもりだったんだ?」
「フ………決まっているじゃないか……」
ハヤブサは、とびっきり優しい笑顔を、シュバルツに向けた。
「それはお前を、ベッドに縛り付け」
ドカバキッ!!
シュバルツの容赦ない鉄拳制裁が、ハヤブサに飛んだ。
「阿呆か!! お前は!! どうしてそういう方面に話を持っていこうとするんだ!?」
「ひどい……! シュバルツが冷たい………!」
「自業自得だろう」
さめざめと泣くハヤブサに、シュバルツの容赦の無い突っ込みが入る。龍の忍者は、真面目に心が傷ついていた。
「一生懸命、お前に触れたいのを、我慢しているのに………ッ!」
「仕事中だ。それぐらい、我慢して当然だろう」
「うぐっ………!」
シュバルツの言っていることは、限りなく正論だ。
正論なのだが────
(絶対、分かっていないんだ、こいつは………! 俺が、お前にどれほど恋い焦がれているか。どれほど必要としているかを………!)
俺はいつでも願っているのに。
お前に触れたいと。
抱きたいと。
叫んでいるのに。
愛していると。
もどかしい。
どうしてその総てが、彼に伝わらないのだろう。
もっとうまく、伝えられたら────
「何をやっているんだ? ハヤブサ。置いていくぞ」
「……………!」
シュバルツに呼びかけられ、ハヤブサははっと我に返る。
そのままとぼとぼと、ハヤブサはシュバルツの後ろについて、歩き出していた。
こうして、現在に至る。
執務室の椅子に座って、ナディール姫が深いため息を吐いているところに、カライ内大臣が、難しい顔をして入ってきた。
「このような早朝より、何事です? ノゾム様とともにいる、そちらの方は何者なのですか?」
「実は………」
ナディール姫は、カライ内大臣に、昨晩起こった出来事をかいつまんで説明を始める。その間、ノゾムは、ずっとシュバルツに縋り付くようにくっついていた。
「大丈夫だよ」
時折優しくそう言われ、「離れてもいい」と、言われるのだが、ノゾムは彼のそばから離れる気には、どうしてもなれなかった。
この人は、大好きなドモンとつながっている可能性がある、と、言うのも大きかったが、この人から感じられる「掛け値なしの優しさ」から、離れがたかった、と、言うのが、一番大きな理由だった。
生まれついた時から『王族』であったが故に、ノゾムの周りには、常にいろいろな大人がいた。その大人たちの大半は、優しくしてくれる代わりに、こちらに何らかの『見返り』を求めてくるのが常だった。
それは、『地位』であったり、『金銭』であったり、『便宜』であったり、様々だ。
「良いですか? ノゾム……! 私たちは『王族』です。私たちの持つ権力を目当てに、近寄ってくる輩はたくさんいるのです。それを常に、忘れてはなりません!」
この母の言葉は、まさに正論だった。『見返り』を与えることができなければ、大人の持つ『優しさ』は、自分の前から簡単に、消え失せてしまう。
(怖い……!)
何度も何度もそれを体験させられてきたノゾムにとって、周りの『大人』は、ある意味恐怖の対象でしかなかった。自分はまだ子供で、周りの大人たちからの『期待』に応える術を、十二分に持ち合わせていないから、余計にその恐怖は倍増していた。
だからノゾム少年は、可能な限り母や義姉の後ろに隠れて、その恐怖から身を守る術を身に着けるのは、自然の流れであったといえる。
そんな中、シュバルツから向けられてきた『優しさ』は、ノゾム少年にとっては衝撃だった。
その優しさは、どんな状況になっても、ぶれることがなかった。
ただひたすらに、自分の身と心を、案じてくれていた。
母から『怪しい人間』と決めつけられ、不利な状況に追い込まれて行っても、その姿勢は変わらなかった。
「大丈夫だから、離れて」
そう言ってほほ笑むその眼差しは、決してこちらからの『見返り』を、求めてはいなかった。
信じられなかった。
そんな優しさを自分に向けてくれるのは、『母』や『義姉』といった、身内しかいない、と、思っていたから。
だからこそ────
だからこそ、だ。
決してこの人のそばから、離れてはいけない、と、思った。
それどころか、『守らなければ』と、強く思った。
だから、縋り付くようにその傍らに引っ付いた。
周りの大人たちが、この人を『捕らえる』というのなら、それを阻止するために。
姉に対しては厳しい母だが、自分に対しては、異常なほどに甘い母であるが故に。
自分がそばについていれば、母はこの人に無体なことはできないはずだ。
必要とあらば、どこまでもついていく。牢に放り込まれるのならば、ともに放り込まれてもいい。
お願い。そばに置いて。
自分には、『人質』としての価値が、あるのだから─────
ノゾム少年は、そう願いながら、必死にシュバルツに縋り付いていた。
「落ち着いて………大丈夫だよ」
シュバルツはそう言って、優しくノゾムの背や頭を撫でるのだが、少年は必死に縋り付いてくる。
(無理もないか)
シュバルツは軽く苦笑していた。先ほどのハヤブサと王太后、そして姫との間で起きたやり取りは、この子にとっては過酷なストレスでしかなかったはずだ。
(まだ、ショックが抜けていないのだろうな)
シュバルツは、そう慮って、ノゾムの好きなようにさせよう、と、思っていた。少年の心が落ち着けば、また、ゆっくり話もできるだろうから。
「………………」
覆面をかぶりこんだハヤブサは、二人の様子を『表面上は』穏やかに見つめているように見えたが、内心は、いろいろと『萌えさかる』炎で大変であった。
シュバルツの、ノゾム少年を、穏やかに見つめる眼差しが
気遣うように、頭や背に、あてがわれている優しい手が────
(ああああ、もう、愛おしいというか愛らしいというか、辛抱たまらんというか………っ! 今すぐベッドに押し倒させろこの野郎~~~~~~!!)
と、叫びながら、あちこちを駆けずり回って暴れまわって、叫び散らしたいところではあるが────
「…………………」
難しい顔をして、執務室の椅子に座り、ため息を吐いているナディール姫が、目の前にいる。今は、そういうことをしている場合ではない、と、ハヤブサは自分で自分に言い聞かせて、じっと我慢をしている状態であった。
しかし、うらやましいのは、ノゾム少年の立場だ。
実に羨ましい。
自分だって、シュバルツにあんなに優しく見つめられたいと、願ってしまう。
(俺だって、あのくらいの少年だったなら……!)
じっと二人の様子を見つめながら、つい、そんな物思いにふけってしまう。
自分ならば、どんなに年が離れていようと、シュバルツに恋に落ちてしまう自信がある。
………と、言うわけで、毎度やってまいりました妄想タイムであります。完全なる、作者の趣味の世界であります。生暖かい眼差しで、見守っていただければ、これ幸いに存じます。
少年ハヤブサが、シュバルツをじっと見つめている。そっと手を伸ばすと、愛おしいヒトは、優しく握り返してくれた。
「好きです……!」
万感の想いを込めて、告白をする。
しかし。
「そうか、私もだよ」
そう言って、優しく微笑む愛おしいヒトの顔が、完全に『子供をあやすときの顔』そのものだったから─────
「うわあああああああああっ!!」
ハヤブサは思わず、大声を出してその辺を転がりまわってしまっていた。
嫌だ。
こんな、哀しい想いはいやだ。
自分の本気の恋心が、まるで相手にされないだなんて。
やはり、シュバルツには、自分の想いがきちんと伝わるのがいい。
「愛している」
そんな自分の恋心を、相応に受け取ってもらえなければ、耐えられない。
そう考えると、今の自分の年齢で、シュバルツに出会えたのは、実にラッキーだったといえなくもないのだろうが─────
「うううう………シュバルツ………!」
部屋の隅で膝を抱え込んで座り、床に『の』の字を書きだすハヤブサ。それを、部屋にいる全員が、あきれ果てたように見守っていた。
「………いったい、何をやっておるのですかな? あの者は………」
「………気にしないでください。あれは、病気のようなものなので………」
カライ内大臣からこぼれる言葉を、シュバルツも、苦笑しながらそう答えるしかなかった。
(なんでハヤブサはああなってしまうんだ? 私は別に何もしていないだろう?)
まさか、自分がノゾムに向けている視線が、ハヤブサを無駄に萌え上がらせているのだということに、まるで気づきもしないシュバルツは、疑問に首をひねるしかない。
「病気……ですか?」
そう言って問い返すナディール姫の表情が、少し緩んでいる。
「病気だな」
シュバルツの答えに、ナディール姫は軽く笑っていた。それを見たノゾムの表情から、ようやく緊張の色が消える。
「大丈夫か?」
それに気づいたシュバルツから、そう声をかけられる。ノゾムははにかみながらも、「はい」と、答えていた。
「ノゾム………」
ナディール姫も、自分のピリピリした態度が、義弟に余計な気を使わせていたのだと悟る。
「ごめんなさいね。もう、そんなに緊張しなくても良いわよ」
「お義姉様……」
問い返す義弟に、義姉は、フッと、優しく微笑みかける。
「分かりました………」
ノゾムの面にも、少しの笑みが浮かぶ。シュバルツに縋り付くのは止めたが、まだ彼のコートの裾を、ぎゅっと握り込んでいた。
「…………」
シュバルツは苦笑しながら、ノゾムの手にそっと触れる。おずおずと伸ばされてきたその手を、シュバルツは優しく握り返していた。
「…………………」
それをハヤブサが、羨ましそうに見つめているのが、ナディール姫からは丸見えだったりする。
(本当に………何て言えば良いのかしら………)
ちょっとカオスな状況に、ナディール姫は、笑いを堪えることの方が難しくなってきていた。しかし、何時までもこのままでいるわけにはいかないので、ナディール姫は顔を上げた。
とにかく、今はっきりさせなければならないのは、シュバルツの『正体』だ。
それに白黒つけなければ、この場は収まらない、と、ナディール姫は悟っていた。
「しかし、思い切ったことをされましたな。聞きましたぞ? 王太后を怒鳴りつけるだなどと………」
「内大臣………」
「これ以上────王太后の御不興を買われたら、如何致します?」
カライ内大臣の言葉に、ナディール姫は、少し投げやりっぽいため息を吐いていた。
「仕方が無いじゃない……。あの場はああでもしなければ、もう、収まりが付かないところまでいっていたし────」
固唾を呑む兵士たち。
怯えた表情のノゾム。
王太后に対して、今にも斬り下げんばかりに、殺気を放っていたハヤブサ────
あのまま放っておいたら、色々、取り返しの付かないことが、起きてしまうと悟った。
だから、自分は抜き放ったのだ。
『王の代理』という『伝家の宝刀』を。
「それに………お義母様には、何をやっても怒られたり嫌われたりするのだから……気を遣うのも、今更だわ…………」
そう言って、肩をすくめるナディール姫に、カライ内大臣も「そうですな」と、同意するしかない。それほどまでに、もう傍目に見ても、王太后のナディール姫に対する態度は、険悪なものと、なりつつあったのだ。
「失礼いたします」
そこに、イガールが執務室に入ってきた。手には、報告書のようなものを持っている。
「イガール」
視線を向けるナディール姫に対して、イガールはある程度まで歩を進めると、そこで姿勢を正していた。
「姫様。ご報告申し上げます」
イガールの静かな声が、執務室に響く。
「中庭に『遺体』があり、確認を取りましたところ、厨房で働いていた『イワンコフ』で相違なかったようです」
「……………!」
イガールの言葉に、執務室の空気がぴり、と、緊張を帯びる。彼は、淡々と報告を続けた。
「遺体を病院へ搬送して、現在『死因』を特定中です。検死をした医師の話によると、死後大体6時間ぐらい経っているようです。つまり、深夜帯に命を絶たれたと推測されます」
「そうですか………」
イガールの話を聞きながら、ナディール姫は、深いため息を吐く。
その検死が正しいのなら、イワンコフは、自分たちと別れてから直ぐに、命を絶たれてしまった事になる。
確かに、彼は悪人だったが、気の毒なことをしてしまった。
どうすれば良かったのだろう。
やはり、あの場で逃がすことはせず、捕らえて、彼の安全を、牢で確保するべきだったのだろうか────
「…………………」
(馬鹿だな………。思い悩んでも仕方がない。こんなことに『正解』なんて、ないのに………)
「お義姉様…………」
「………………!」
ノゾムの、自分を案じるような小さな声に、ナディール姫は、はっと顔を上げる。自分の表情が、また、険しいものになってしまっていたことに気が付いた。
「大丈夫よ」
慌てて、笑顔を取り繕う。心配そうにこちらをのぞき込んでいたノゾムが、その笑顔を見て、ようやく表情を緩めていた。
「ほかに、何かイワンコフについて、分かったことはありますか?」
ナディール姫の問いかけに、イガールは改めて報告書に目を落とす。
「郊外のアパートに、部屋を借りていたようです。家族もなく、独り暮らしでした。所持品も検分しておりますが、今のところ、新たに何か進展があるような手掛かりは、発見されておりません」
「そうですか……。一応、報告書を見せていただけますか?」
「どうぞ」
ナディール姫の要求に、イガールは素直に報告書を差し出す。
「………………」
黙って報告書に目を通し始めたナディール姫だが、やがて、そのお腹から「ぐう」と、大音量が聞こえてきた。
「健康そうで、何よりですな」
それを聞いたカライ内大臣が、失笑気味に口を開く。
「し、仕方がないじゃない……。朝ごはん食べてないんだもの……。真面目にお腹がすくわよ……」
それに対してナディール姫は、そう答えて唇を尖らしていた。
(むりもないか)
ハヤブサは、やれやれとため息を吐く。実際ナディール姫は、ほぼ徹夜状態で、食事もろくに取らずに、この執務室の椅子に座っているのだから。
「何か食事を調達してきてやろうか?」
「いいんですか!?」
ハヤブサの提案に、ナディール姫は勢いよく顔を上げる。その食いつきの良さに、ハヤブサは多少面食らったが、すぐに頷いていた。
「ああ。市場の、いつもの物でいいのだろう?」
「はい! ありがとうございます!!」
表情を輝かせながら、礼を言うナディール姫。シュバルツがそれを(可愛いな)と、ほほえましく見つめていると、横でノゾムもハヤブサの方に身を乗り出しているのが分かった。
「ハヤブサ」
シュバルツの呼びかけに、ハヤブサが振り返る。
「ん?」
「この子の分も、お願いして良いか?」
「……………!」
ノゾムが、びっくりしたようにシュバルツの方に振り返る。ノゾムと視線の合ったシュバルツが、ニコ、と、微笑んだ。
(くそっ!! 可愛い………!)
うっかり萌え上がったハヤブサは、彼を抱きしめたくなる衝動を、必死に抑えつけなければならなくなった。
「行ってくる。シュバルツ、姫を頼む」
ハヤブサは短くそう言うと、執務室を後にしていた。
「…………………」
ハヤブサが去った後の執務室は、暫し沈黙に包まれる。そんな中、ナディール姫は、1人黙々と、イガールの報告書を読み続けていた。
「よく分かりました。ありがとう」
ナディール姫は、イガールに報告書を返す。
「また何か、新たに分かることがありましたら、報告して下さい」
「はっ!」
イガールは一礼して、報告書を受け取った。そのまま、礼に則り、踵を返して執務室を出て行こうとする。
「イガール」
それを、ナディール姫が呼び止めた。振り返るイガールに、ナディール姫が少し、心配そうな眼差しを向ける。
「顔色が少し悪いようですが、大丈夫ですか?」
「姫様………!」
「報告は急ぎません。少しでも休んで、体調を整えておいて下さい」
「ありがとうございます。姫様」
ナディール姫の言葉に、イガールが柔らかく微笑む。彼は軽く会釈をすると、執務室から外へ出て行った。
「イガール殿」
外に出て、少し歩いたところで、イガールはハヤブサに声をかけられた。
「ハヤブサ殿」
彼は少し意外そうに、足を止める。
「どうされたのですか? 貴方は、市場に向かわれたはずでは────」
疑問を呈するイガールに、ハヤブサは軽く苦笑した。
「勿論、これから向かうが、少し貴殿に頼み事があってな」
「頼み事ですか? 何でしょう」
私に出来ることであれば────と、律儀に応えるイガールに、ハヤブサは頷いていた。
「何、たいしたことではない。イワンコフの持ち物を見ることが出来れば、と、思って」
「持ち物ですか?」
きょとん、とするイガールに、ハヤブサは頷いた。
「急ぎはしない。都合がついた時でいいから、声をかけてくれ」
「分かりました」
二人は頷き、そして、互いの向かう方に、各々歩き始めていた。
「さてと」
ナディール姫は、改めてシュバルツの方に向き直った。
「私は、貴方のことを検分しなければならないのですが─────」
「………………!」
ノゾムが、硬い表情をして、シュバルツに縋り付く。
「そんなに構えなくても大丈夫よ」
ナディール姫は苦笑していた。
実際、彼女はシュバルツを、そんなに疑っているわけではなかった。
と、言うか、かなり信用していた。
シュバルツの今までの行動を見ていれば、彼の人柄の良さが伝わってくるし、自分が信頼を置いているハヤブサが、彼を手放しで信用しているところを見ても分かる。普段、大人にめったに心を開かないノゾムが、すがるようにシュバルツに懐いている、と、言うのも、ナディール姫の中では、かなり彼に対してプラスの方向に、評価が働く要因になっていた。
シュバルツは、善良な人間だ。これはもう、ナディール姫の中では、疑いの様のない事実だった。
だから問題は、彼の正体。
彼は本当に、『ドモン・カッシュ』の兄なのだろうか。
それが『事実』なら、本当にすごいことだが、一体それを、どうやって確かめれば、いいというのだろう────
(私が『ドモンの兄』というのは、動かしようのない事実だが………)
シュバルツもここで、途方に暮れてしまう。
自分が、『ドモンの兄』と、証明する手段など、本当に持ち合わせてなどいないのだから。
「……………」
ノゾムは、シュバルツの顔を、不思議そうにのぞき込んでいた。
彼は確かに、『キョウジ・カッシュ』と同じ顔をしている。しかし、『キョウジが忍者』という情報は、自分も持っていないから、それをどう受け止めればいいのかわからなくて、困惑した。
この人は、いったい何者なのだろう。
本当に、ドモンのお兄さんなのだろうか。
「あの」
ナディール姫は、意を決してシュバルツに声をかけた。ここで頭を抱えていても、埒が明かないからだ。
「何だ?」
顔を上げるシュバルツに、ナディール姫は直球をぶつけてみる。
「貴方は本当に、ドモン・カッシュ様の、兄上様なのですか?」
「そうだ」
それは、れっきとした事実なので、シュバルツは頷くしかない。
「では………それを証明するものは?」
「無いな」
これも事実なので、シュバルツはそう答えるしかない。
「……………」
ナディール姫が頭を抱えていると、ノゾムがおずおず、と、口を開いてきた。
「あの………お義姉さま」
「なあに? ノゾム」
「あ………えっと…………」
少し逡巡していたノゾムだが、やがて、意を決したように顔を上げた。
「シュバルツさんへの質問…………僕が、やってもいいですか?」
「…………………!」
驚くナディール姫に対して、ノゾムは懸命に訴えかけていた。
「ぼ、僕なら、ドモン・カッシュに詳しいし、この人の真偽を、確かめられると、思います……」
「……………」
ナディール姫は、しばらく、そんなノゾムの様子を黙ってみていたが、やがて、フッと、その面に笑みを浮かべた。
「いいわ。やってもらいましょう」
「姫様!?」
隣にいたカライ内大臣が、驚いたような声を上げる。それに対してナディール姫は、屈託のない笑みを見せた。
「だってそうでしょう? 実際、ノゾムの方が私よりも、『ドモン・カッシュ』に詳しいわけだし」
「確かに、そうですが………」
カライ内大臣は、不安故に眉をひそめる。ただでさえ、引っ込み思案なノゾムが、そんな大役が果たせるだろうかと、考えてしまったからであった。
「大丈夫よ、カライ内大臣」
対してナディール姫は、明るく笑いながら、カライ内大臣に言葉をかける。
「せっかく、ノゾムがやる気になっているのよ? ここは、彼に任せるべきだわ」
「しかし、ノゾム様にはまだ経験が………」
まだ、渋い顔を見せるカライ内大臣に、ナディール姫は苦笑していた。
「だから、その経験値を積ませる、良い機会だと思っているの」
そう。誰だってはじめから、何でも出来るわけではない。
一つずつ、経験を積んで、それを糧として、成長していくのだ。
(シュバルツ様は、悪人ではない)
これは、ナディール姫が心の中で持っている、確かな想いだった。
だからきっと、シュバルツがノゾムに対して、傷つけるようなことは、絶対にしないはずだ、と、ナディール姫は思っている。
「ノゾムだって、何時までも私たちの後ろに隠れているわけにも行かない。そうでしょ? カライ内大臣」
「それはそうかもしれませんが………」
「ノゾムには、いずれこの国を継いでもらう事になるのだから………」
「姫様!?」
「お義姉様!?」
「……………!」
不意に零されたナディール姫の言葉に、その場にいた全員が驚いていた。さらり、と言われたことだが、この国の根幹に関わる、重要な事案を、彼女はあっさり口にしたことになるのだから。
「そんなに驚くことではないでしょう? これは、前々から考えていたことなの」
鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしている皆に、ナディール姫は苦笑しながら応える。
「今は、こうして『王代理』としての立場をもらっているけど、私はあくまでも、臨時の王のような者……。本当の『王』になるべきは、ノゾム、貴方だと、私は考えているのよ」
「お義姉様………!」
対してノゾムは、ただただ驚いていた。
まさか、義姉がそのようなことを考えていただなんて、夢にも思わなかったからだ。
「だから私は、貴方が成人すれば、王位を譲る。それが自然の流れだし、そうするべきだと、私は思うの」
「あ……………」
対してノゾムは、ひたすら戸惑うしかない。自分はこれからも、母や義姉の後ろに、付いていくものだと、思っていたから。
「勿論、直ぐ、と言うわけでもないし、成人するまでは、私は貴方を全力で護る。それが、私の『役目』だから」
「お義姉様………」
「驚かせてごめんなさいね」
ナディール姫は義弟に対して、優しい笑みを見せる。
「でも、ノゾム。覚えておいて欲しい……。さっき言った言葉は、間違いなく私の本心だから」
「…………………」
ノゾムは、ぐっと唇を噛みしめて、義姉である姫を見つめていたが、やがて、「分かりました」と、頷いていた。
「ありがとう」
ナディール姫が、そう言って優しく微笑む。それを見たノゾムも、(ああ、良かった)と、思った。
義姉のことは好きだ。
義姉の、優しく笑う笑顔が好きだ。
義姉が、こんな風に柔らかく微笑んでくれるのならば、自分が今、義姉に対して頷いたことは、間違ったことではないのだろう。
義姉の、役に立ちたい。
力になりたい。
そのために、自分が前に進むことが、必要だ、と、言うのなら。
ノゾムは顔を上げると、シュバルツの方に改めて向き直った。
「では、シュバルツ殿。質問をさせてもらっても良いですか?」
そう言って、小さな王子は、シュバルツにまっすぐな眼差しを向ける。
「どうぞ」
シュバルツもそう言うと、少し下がって膝を折り、畏まった。こうすることで、ノゾムより、少し低い視線になる。彼が自分に質問しやすいように、と、言う、彼なりの配慮であった。
「え………えっと…………」
口を開く少年の頬が、少し赤らむ。
もしかしたら、憧れの『ドモン・カッシュ』の身内かもしれない人に、質問をするのだ。彼がそうやって緊張してしまうことも、無理からぬ事であった。
それでも少年は、口を開く。
自分は、前に進む、と、決めたのだから。
「ええと、では………ドモン・カッシュの生年月日を答えて下さい」
「19××年7月24日だ」
「家族構成は?」
「父と母と、兄がいる。両親はもう、亡くなってしまったが………『レイン・ミカムラ』という、恋人がいるよ」
「レインさん……やっぱり、恋人なんですか?」
「一緒に住んでる。近々結婚する、と、言っていたが………」
その言葉を聞いたノゾムの表情が、ぱっと明るい物になる。
「やっぱり!! あの、全世界が見守る中でドモンさんがレインさんにプロポーズをしたのは、今でも語りぐさになっていますよね!! 結婚式って、何時なんですか!?」
「それなんだよなぁ」
その質問を聞いたシュバルツが、少し難しい顔をした。
「いかんせん、2人とも忙しすぎて、なかなかそういう暇が取れないみたいなんだ……。さっさと段取りをつけてくれれば良いのに」
(うわあ………!)
ノゾムは、自身の中の興奮が、抑えきれずにいた。
今、目の前のシュバルツが話していることは、間違いなく────ドモンと近しい者でなければ、知り得ない内容のものだからだ。
(もう間違いない……! シュバルツさんは、ドモン・カッシュの関係者だ………!)
しかし、ぬぐえない疑問も一つある。
この、目の前にいる、どこからどう見ても『キョウジ・カッシュ』(ドモンの兄)に見えるこの人は
どうしてここにいて
どうして『シュバルツ』などと名乗っているのだろう。
「ノゾム、どう?」
義姉に声をかけられて、ノゾムははっと我に返る。彼女の方に振り向くと、ナディール姫は優しい眼差しを、義弟に向けていた。
「その人は、ドモン様と、関係がありそうかしら?」
「はい、お義姉様」
ナディール姫からの問いかけに、ノゾムは素直に頷いていた。
「間違いなく、この人はドモン・カッシュに近しい方と、見受けられます。ただ………」
「ただ………どうしたの?」
「えっと………その………」
ノゾムは、シュバルツの方にちらり、と、目線を走らせた後、口ごもってしまう。
(ああ、なるほどな)
シュバルツは、ノゾムが口ごもる理由に思い当たってしまって、苦笑していた。
確かに、自分は『キョウジ・カッシュ』でもあるのだが、正確に言うなら、キョウジ本人ではない。DG細胞によって作り出された、『アンドロイド』で、『キョウジの影』と、言っても良い存在だった。ノゾムも、その辺りのことを感じ取って、首をかしげているのだろう。
どうして────『学者』であるはずのキョウジ・カッシュがここにいて、『シュバルツ』などと名乗っているのか。
その辺りのことを『説明しろ』と、言われたら、自分も、返答に窮してしまうのが現状だった。
どう答えるべきなのか。
どうすれば、皆が納得できる答えを、説明できるというのだろう。
「そいつは間違いなく、『ドモン・カッシュの兄』だぞ」
その時執務室に、そう断定する声が響き渡る。皆がそちらの方に顔を上げると、執務室の入り口に、市場で買ってきたであろう食料を、両手いっぱいに抱えている、リュウ・ハヤブサの姿が、そこにあった。
「ハヤブサ様」
顔を上げたナディール姫が、もう一度「ぐう」と、大きなお腹の音を鳴らす。それを聞いたカライ内大臣の面に、失笑に近い笑みが浮かんだ。
「……仕方がありませんな。少し、休憩にしましょう。これ誰か! 姫様に茶をお持ちしろ!」
「かしこまりました」
部屋の隅に控えていた侍従が、頭を下げて退出していく。
「私も、しばし下がらせてもらいましょう」
「内大臣」
少し驚いたように見上げるナディール姫に、カライ内大臣は、珍しく優しい笑みを姫に向けた。
「近くの控室にいます。執務に戻られるときに、声をかけてください」
「ありがとう……」
少し戸惑いながら礼を言うナディール姫に、カライ内大臣は一礼をすると、執務室を退出していった。
「ほら、買って来たぞ? ちゃんと食べておけ」
「ありがとうございます………!」
ナディール姫は、ハヤブサからいそいそと食材を受け取る。
「ほら、ノゾムも」
姫からフランクフルトを差し出され、ノゾムも嬉しそうに受け取っていた。
そのまましばし、姉と弟の和やかな食事風景となる。忍者二人は、それを邪魔してはならぬ、と、そっと、部屋の端に身をよけて、それを見守っていた。
「本当に、仲がいい姉弟だな……」
シュバルツがそっという言葉に、ハヤブサも軽く微笑む。
「そうだな……。血は半分しかつながっていない、義理の姉弟だが………」
「そうなのか?」
少し驚いたように振り向くシュバルツに、ハヤブサは頷いていた。
「姫の本当の母親は、彼女が幼少の時に、亡くなったらしい。王は後妻をめとり、生まれたのが、ノゾム王子、というわけだ」
ハヤブサは姫の護衛をしながら、彼女に関して調べた情報を、シュバルツに渡す。些細なことかもしれないが、こういう情報の共有も大事なことだ、と、ハヤブサは思っている。
「ノゾムとナディール姫、姉弟にしては、容姿が全然違うだろう?」
「確かに、そうだな……」
ハヤブサの指摘に、シュバルツも頷かざるを得ない。ナディール姫は、流れるような金の髪だが、ノゾムは髪も黒く、どことなく東洋系を思わせる顔立ちをしていた。
二人で仲睦まじく食事をしていた姉弟であるが、しばらくすると、ノゾムがクルリ、と、忍者たちの方に振り返り、2人のそばに歩み寄ってきた。
「あの………どうぞ」
手に持っていたフランクフルトを、おずおずと差し出す。
「いや、俺はいい」
ハヤブサは当然のごとく遠慮した。自分はもう、食材を買い出しに行くついでに、朝食は手短に済ませていたからだ。
「でも…………」
それを聞いたノゾムが、少し寂しそうな顔をする。その表情を見たシュバルツが、優しく微笑みながら、ノゾムに声をかけていた。
「そうだな……。せっかくだから、いただこうか」
「おい、シュバルツ!?」
ハヤブサは、少し驚いたように、シュバルツを見た。
シュバルツは、DG細胞でその身体を構成されている、不死のアンドロイドだ。その動力源は『ヒトのココロ』であるがゆえに、彼は固形の燃料を積極的に摂取する必要がない。そういう存在であるのに。
しかし、ハヤブサの愛おしいヒトは、その面に屈託のない笑みを浮かべた。
「いいじゃないか。せっかくこちらのことを思いやって、こう言ってくれているのだから」
そう言って、シュバルツは「ありがとう」と、ノゾムからフランクフルトを優しく受け取る。その時ハヤブサは、(ああ………)と、なぜか一人で合点していた。
シュバルツの動力源は、『ヒトのココロ』だ。ノゾムのこういった、『純粋に、他者を思いやるココロ』と、言うものは、シュバルツにとっては、最高の『食事』になるのではあるまいか。
(可愛らしいなぁ……。本当に………)
知らず、萌えてしまって、自身も幸せな気持ちのままに、シュバルツから渡されたフランクフルトにかじりつく。そのまま何気なくシュバルツの方に顔を向けて─────ハヤブサは、そのままの姿勢で固まってしまっていた。
長い、肌色のある程度の太さのモノに、かぶりつくシュバルツの横顔。
(エ………! エロい…………!)
わかっている。シュバルツがかじりついているのはフランクフルトだ。
なのに何故だろう。
ハヤブサには、どうしてもフランクフルトが、別の何かに見えてしまう。
ああ、シュバルツ。
どうせかじりつくなら、俺のものを口に含んでほしい。
「ん…………!」
涙目になりながら、苦しそうに息をするシュバルツの口内に、思いっきり─────
「ごちそうさま」
その声に、はっと我に返るハヤブサ。見ると、フランクフルトを完食したシュバルツが、優しく微笑みながら、そばにいたノゾムにそう声をかけている。まだなんとなく熱を抑えきれないハヤブサは、知らず、ノゾムに声をかけていた。
「ノゾム」
「はい? なんでしょう、ハヤブサ様」
振り返ってくるノゾムに、ハヤブサは言葉をつづける。
「今度は、シュバルツにバナナを食べさせてくれ」
「えっ? バナナをですか?」
「そう、バナナを。皮をむくところから────」
「何くだらん妄想をしているんだ!? お前は!!」
ここで、ハヤブサの意図を正確に察したシュバルツから、鉄拳制裁が飛んでいた。
「ど、どうしたんですか?」
いきなりのシュバルツのこの行動に、かなり戸惑ったナディール姫から声をかけられる。それにシュバルツは、思いっきり爽やかな笑顔を向けていた。
「ああ、気にしないでくれ。こいつが馬鹿なだけだから」
「シュ……シュバルツ………」
ふらふらと呻きながら起き上がったハヤブサを、シュバルツは、また、ゴン!! と、殴りつけている。
(こ、これは………きっと、あまり深く突っ込まない方が、良いパターンね………)
ナディール姫は、顔を引きつらせながらも、なんとなく察していた。これはきっと、立ち入ってはいけない『大人な事情』がありそうな案件なのだろう。
やがて、カライ内大臣も執務室に戻ってきて、執務が再開された。
「シュバルツ様が、『信頼に足る』人物である、と、言うことは、私も重々承知しております」
ここまで言ったナディール姫が、少しため息を吐いた。
「……問題は、『ドモン・カッシュ様の兄』であるかどうか、その真贋であると、思いますが────」
「……そうですな。ノゾム様の話では、ドモン殿の関係者である、ということは間違いなさそうですが────」
カライ内大臣も、難しい顔をしている。ノゾムも、戸惑い気味の顔をしている。それを確かめる有効な術が、今のところ、本当にないからだ。
「確かめる方法なら、あるぞ」
皆が途方に暮れている中、龍の忍者の声が響く。
「それは、どのような方法ですかな?」
じろり、と、にらみつけてくるカライ内大臣に、ハヤブサは軽く笑って答えた。
「簡単なことだ。『本人』に、ここに来させればいい」
「ええっ!?」
「何ですと!?」
「本人ですか!?」
「お、おい、ハヤブサ────!」
部屋にいる皆が、それぞれに驚きの声を上げる中、ハヤブサの意図を正確に理解したシュバルツが1人、彼に呼びかけていた。
「まさかお前、本当にドモンをここに呼びつけるつもりか!?」
「簡単だろう? お前がいれば」
「それはそうかもしれないが────」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは少し苦い顔をした。
「だがそんなことをしたら、騒ぎが起きる。ここにいる皆に、迷惑をかけてしまうことになるぞ」
「では、どうするのだ? お前は、自分が『ドモンの兄』だと証明する手段を、何か持っているのか?」
「……………!」
その言葉に、有効な反撃の言葉を持ち合わせていなくて、シュバルツはぐっと、言葉に詰まった。それを見たハヤブサは、さもやれやれ、と、言った体を装って、深いため息を吐いた。
「今のままだと、ナディール姫は、城内の安寧を保つために、お前を牢に放り込まなければならなくなるぞ?」
「ええっ!?」
誰よりも大きな声を上げたノゾムが、縋るように義姉の方に振り返る。ノゾムの視線を受けたナディール姫は、それに向かって「ないない」と、首を横に振っていた。
今のところ、シュバルツの正体に関しては『灰色』だが、限りなく『白に近い灰色』だとナディール姫は思っている。疑わしくもない者を、牢に放り込むようなまねなど、できようはずも無い。しかし、龍の忍者はさらに畳みかけてくる。
「それでもいいのか?」
「駄目です!!」
ノゾムが、必死の形相でシュバルツに縋り付く。
「その子を、ずっとそうやって縋りつかせておくつもりか?」
「う…………!」
ハヤブサの指摘に、シュバルツはグッと言葉に詰まる。ハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐いた。
「な? その子のためにも、さっさとこの問題に決着をつけた方がいい。第一お前が牢に放り込まれたら、俺はお前を詰問するために、毎晩牢に行かないといけな」
ドカッ!! バキッ!!
ハヤブサの意図を正確に読み取ったシュバルツが、またも彼に鉄拳制裁をふるっていた。
「ね、ねぇ……。お義姉様……」
「何? ノゾム」
「ど、どうして、シュバルツ様は……あんなに怒っているの……?」
「さあ…………」
ノゾムのその質問には、ナディール姫も苦笑しながら首をかしげるしか術がない。よくわからないが、『大人の事情』が深くそこに絡んでいるのではないか、と、彼女はなんとなく思っていた。
「馬鹿なこと言っていないで、さっさと話を進めろ! お前は────!」
「ううう………! シュバルツが冷たい………!」
さめざめと泣くハヤブサに、ナディール姫が顔を引きつらせながら声をかける。
「あの……大丈夫ですか?」
「気にしないでくれ。これは、病気のようなものだから」
そう言ってシュバルツはさわやかにほほ笑んでいるが、どことなく怒りのオーラを感じる物だから、ナディール姫も、この問題はこれ以上突っ込んではいけない、と、判断していた。
(変わった『病気』もあるものね………)
彼女が、自分もこの『病気』にかかっている、と、共感するのは、もう少し先の話なりそうであった。
「それにしても、本当にドモン様をここに呼べるのですか?」
ナディール姫の質問に、ハヤブサは起き上がりながら答えた。
「問題ない。こいつがいるから、すぐにでも飛んでくる」
「すぐにでもって………!」
驚くナディール姫をよそに、ハヤブサはシュバルツに声をかけていた。
「シュバルツ、ドモンの予定は、今特に埋まっていなかったよな?」
「ああ…………」
だがシュバルツがその問いに答えるよりも早く、幼い声が執務室に響きわたっていた。
「ドモン・カッシュ様は、特に今、試合の予定は入っていませんね」
「─────!?」
全員が、驚いてその声の方に振り返る。すると、そこには慣れた手つきでタブレット端末を操る、ノゾム王子の姿があった。
「ドモン様は、ちょうど一か月前に、世界超級格闘王選手権に出て優勝してから、3か月ぐらいは予定が入ってなかったはずです。何か公になっていない、ほかの用事が入ってはいるかもしれませんが───」
「……合っているのか?」
「………正解だ」
ハヤブサの確認に、シュバルツは頷くしかない。
「3か月後にまた、『宇宙バトルロワイヤル』という大会に、シードで出場されるから、それに備えて体調を整えられているのかもしれませんね……。チケット取れているから、見に行きたいけど………」
ちらり、と、ナディール姫に視線を走らせるノゾム。姫は、苦笑していた。
「お義母様に、相談してみましょうか」
姫の言葉に、少年の瞳はぱっと明るく輝いていた。
「じゃあ、ここに呼びつけても、取り立てて問題はない、と、言うわけだな」
ハヤブサの言葉に、少年は弾かれたように振り返る。
「ほ、本当に、呼ぶんですか………?」
「当然だ。直接確認した方が、話は早いだろう」
「あ……! あう…………!」
ハヤブサの話を聞いたノゾムが、固まってしまう。
「お、おい………!」
いろいろまずいものを感じたシュバルツが、思わず声を上げていた。
「ちゃんと手段は選んでくれるんだろうな? あんまり騒ぎが起きるような真似は────」
「心配するな、シュバルツ」
シュバルツの言葉を聞いたハヤブサが、にやりと笑った。
「最短でこちらに来るよう、呼びつけてやる」
「な────!」
固まるシュバルツを横目に見ながら、ハヤブサは懐から携帯電話を取り出していた。
「なあ、兄さん」
パソコンに向かうキョウジの後姿を見ながら、ドモンは少々むくれっ面をしていた。
ここは、日本の東京。その郊外にある、アパートメントの一室に、ドモンは兄を訪ねてきていた。
大きな大会が終わり、そのあとのマスコミの対応とか、関係者各位への挨拶回りとか、巡業とか巡業とかボランティアとか、シャッフル同盟の仕事とか、とにかくいろいろな雑事をこなして、やっとできた空き時間に、ドモンは兄を訪ねてきていた、というのに。
「どうしてシュバルツは、いないんだよ?」
実の兄であるキョウジには会えたから、もちろんうれしい。しかし、自分はシュバルツにも会いたかった。久しぶりに、彼に組み手の稽古をつけてもらいたかったのに。
「仕方がないじゃないか。ちょっと用事を頼んだんだ」
ドモンの質問に、キョウジは振り返らずに答える。手元には、山のような書類があり、キョウジは黙々と、それをパソコンに打ち込む作業を続けていた。
「そのうち帰ってくると思うからさ……。帰ってきたら、改めてこちらから連絡を入れるから………」
「う~~~~ん…………」
パソコンに向かい続ける兄の後姿を見ながら、ドモンは唇を尖らせ続ける。
キョウジはキョウジで、大変そうだった。だからここは、自分が一つ大人になって、駄々をこねないようにしなければならない、と、ドモンは頭では、そう自分に命じ続けているのだが。
(でも、このまま帰るのもなぁ……)
久しぶりにまとまった休みが取れたのだ。このまま、兄のそばから離れてしまうのも、なんとなく勿体ないかな、と、ドモンは思った。
(もうちょっと、そばに居ようか……。何か、手伝えることがあるかもしれないし)
部屋に、軽快なキーの音が響き続けている。一心不乱に打ち込みをつづける兄の後姿を見ながら、ドモンは妙な懐かしさを感じていた。
(そういえば、小さい頃も、こんな感じの光景を見た気がする………)
優秀な科学者であったドモンの父母は、よく家を留守にして、研究所に寝泊まりしていた。必然的に、自分は兄と二人で留守番する機会が増えていた。
自分が遊んでいるそばで、机に向かっていることが多かった兄。
退屈を持て余してしまった自分は、ついつい、駄々をこねてしまって、よく兄を困らせてしまっていたような気がする。
そんな自分に、兄は、いつも笑顔で────
(兄さん………)
ブルルルルルッ!
ドモンが知らず感慨に浸り始めていたとき、不意に、懐にしまい込んである携帯電話が振動した。
「!?」
少し驚いて、携帯電話を取り出すと、外部からの着信を、知らせる光が点滅していた。
(誰だ?)
電話をかけてきた相手を確認しようと画面を見て、ドモンは、思いっきりしかめっ面になっていた。
なぜならそこには
彼にとってはある意味『天敵』といっても過言ではない
『龍の忍者』の名が、そこにあったからである。
ブチッ!!
速攻で通話を終了するボタンを押すドモン。
「どうした?」
手を止めて振り返るキョウジに、ドモンは「間違い電話だ!」と、ドモンはぶっきらぼうに言い放つ。すると、間髪入れず、今度はキョウジの方の携帯が、鳴り出した。
(誰だろう?)
キョウジが携帯を取りだしてみると、着信相手の欄に、『リュウ・ハヤブサ』の文字がある。当然、キョウジは電話に出る方を選択した。
「もしもし?」
「キョウジ………」
耳元で、聞きなじみのある『龍の忍者』の声がする。
「どうしたの?」
「ドモン・カッシュと連絡取れるか?」
問い返すキョウジに、ハヤブサが素早く答えてくる。
「急ぎの用事?」
声の調子からそう判断したキョウジは、ハヤブサに問いかけてみる。すると、
「なるべく、早いほうが良い」
と、言割れたから、キョウジはドモンの方に、ちらりと視線を走らせながら、口を開いた。
「ドモンなら、今、目の前にいるよ?」
「代わってもらって良いか?」
「分かった」
キョウジも、特に反対する理由はなかったので、素直に頷く。そのまま彼は、ドモンに向かって己の携帯電話を差し出した。
「ドモン」
「何だよ?」
「ハヤブサから」
「──────ッ!」
「今度は切らずに、ちゃんと話を聞いてやれよ?」
キョウジは苦笑しながら、弟に諭すように言う。兄に色々見抜かれたドモンは、多少決まりの悪そうな顔をしながら、キョウジから電話を受け取っていた。
「………何の用だ!!」
かなり不愛想に、電話に向かって口を開く。
「いきなり切るとは、ご挨拶だな」
電話の向こうからも、紛うことなき『龍の忍者』の、不機嫌な声が返ってきた。お互いに、「こいつとは話したくない」と、思っているところで、意見の一致を見ているらしい。
「わざわざ電話をかけてきやがって………! つまらない用事だったら承知しないからな………!」
電話越しに、唸り声をあげる。それに対して電話の向こうの龍の忍者が、軽くため息を吐く音が聞こえてきた。
「つまらないかどうかは、貴様が判断して決めろ」
「何?」
「いいか? 俺は事実だけを伝える。ドモン・カッシュ。お前は『ユリノスティ王国』のノゾム王子に、『俺に会いたいのか?』と、メッセージを送ったな?」
「………………!」
そう。動画投稿サイトで、自分にメッセージを送るノゾム王子の姿を、ドモンも見つけていた。
(へえ、ノゾム王子って、こんな顔をしていたのか………)
時折くれるファンレターや、SNSのメッセージなどで、ドモンも実は、少し前から、ノゾム王子の名前だけは知っていた。
「試合会場にも、熱心に足を運んでくださっているようですよ」
レインとともに、試合の斡旋をしてくれるマネージャーからも、そう声をかけられた。
「ふ~~~ん………」
しばらく、その動画を見るともなしに見るドモン。そんな彼の後ろから、レインが声をかけてきた。
「会いに行ってあげないの?」
「えっ?」
少し驚いて顔を上げるドモンに、恋人兼マネージャーでもあるレインが、たおやかにほほ笑みかける。
「可愛らしいじゃない。こんなに慕ってくれているのに………」
「う~~~~ん………」
それに対して、ドモンは、少々難しい顔をして唸り続けていた。
確かに、ファンとの交流は、積極的に行いたいと思っているし、ノゾム王子が瞳をキラキラと輝かせながら、『会いたい』と、言う様は、見ていて悪い気はしなかった。
しかし、もう少しでまとまって取れそうな貴重な休みの日に、用事を入れたくない、という思いがあるのも、また、正直な気持ちだった。
どうするべきなのか。
この子の願い、さらっと受け流してしまってもいいのだろうが────
「キョウジさんに、相談してみたら?」
レインからの提案を、「そうだな………」と、ドモンは素直に受けていた。どういう形であれ、兄と話ができる口実ができるのは、ドモンにとっては喜ばしいことであったから。
さっそく電話をかけて、事のあらましを相談する。キョウジからの返事は、
「連絡を取ってみれば?」
で、あった。
もちろんキョウジは、『ユリノスティ王国』の事件に、ハヤブサとシュバルツが巻き込まれているのを知っている。それを踏まえての、答えであったのだ。
だからドモンは、ノゾム王子と連絡の取れるSNSをレインに調べてもらって、メッセージを送ったのだが。
「ああ、送ったぞ? それがどうかしたか?」
ぶっきらぼうに答えるドモンに、ハヤブサから、さらにとげを含んだ声が返ってきた。
「それのせいで、今、シュバルツに余計な嫌疑がかかっているぞ?」
「えっ?」
何を言われたか、瞬間理解できずに固まるドモンに、ハヤブサがさらに畳みかけてくる。
「『本当に、ドモン・カッシュの兄なのか』と疑われて、牢に入れられそうになっている」
「何っ!?」
「お、おい、ハヤブサ!?」
かなり物騒なことを弟に言い出す龍の忍者に対して、シュバルツも驚きの声を上げる。だがハヤブサは、かまわず言葉を続けた。
「もう連れていかれそうになっているぞ?」
「おのれ、言わせておけば………っ!」
ドモンはわなわなと小さく震えていたかと思うと、携帯に向かって大声を張り上げていた。
「今すぐそっちへ行く!! 兄さんを牢に放り込む、という輩は、全員叩きのめしてやるから、覚悟しやがれっ!!」
ドモンはそう叫ぶや否や、脱兎のごとく部屋から飛び出していた。
「あ、ドモン、私の携帯………!」
キョウジは叫びかけて、自分の携帯がベッドの上に転がっているのを発見する。
(別に、壁も窓もぶち破られて行かなかったし、実はかなり冷静だったりするのかな、ドモンは……。ああ見えて)
ベッドの上の携帯を拾い上げ、どこも壊れていないことを確認してから、やれやれ、と、ため息交じりに苦笑する。
(絶対にひと悶着起きるよなぁ。大事にならなければいいけど……)
そう思いながら、キョウジが窓から空を見上げていると、不意に、背後から声をかけられた。
「わしも、そこへ向かった方がいいのか?」
「……………!」
ぎょっと、キョウジが驚いて振り向くと、誰もいなかったはずの部屋の壁際に、いつの間にか一人の銀髪の老人がたたずんでいる。
ただ、『老人』と、称するには立派すぎる体躯と、鋭い眼光を見れば、彼が『ただ者ではない』と、周りに感じさせるのに、十分すぎる印象を、その人は周りに与えていた。
「マスター………」
キョウジに『マスター』と、呼びかけられた老人は、にやり、と、笑う。
「そうですね。ぜひ、お願いします」
「承知した」
老人は短くそう言うと、ふっと、その場から姿を消す。
「………………」
キョウジは、無言で窓から空を見上げていた。そこには相変わらず、穏やかな天気が、上空に広がっていた。
そのころ、ユリノスティ王国の執務室では、ハヤブサが穏やかな顔をして通話を切っていた。
「よし」
「『よし』じゃないだろう!?」
シュバルツは思わず、抗議の声を上げていた。
「あんな言い方をしたら、本当にドモンは、一直線にここに向かってきてしまうぞ!? 騒ぎが起きたらどうするんだ!?」
「いいじゃないか。これで、お前にかかっていた嫌疑が晴れるのならば」
シュバルツの物言いを、ハヤブサはしれっと受け流していた。
「本人にここに来てもらって、証明してもらうのが、一番の早道じゃないのか」
「それはそうかもしれないが………」
「やっぱり、ドモン・カッシュ様が、今からここに来られるのですか!?」
シュバルツのすぐそばで、幼い声が上がる。忍者たちがはっとそちらの方を見てみると、頬を限界まで紅潮させたノゾム王子が、小さく震えながら、唇をパクパクとさせている。
「あ………! あう………!」
「ええと、ノゾム王子………。とりあえず、落ち着こうか」
シュバルツは苦笑しながら、ノゾム王子に声をかけた。このままでは、いろんな意味で、この小さな少年の、心と身体がもたない、と、彼は判断したからだ。
「いくらドモンが超人的な力の持ち主だ、と、言っても、そんなすぐにはここには来られない。彼は今、ここからはるか遠く離れた、『日本』にいるのだから………」
「そ、そうなんですか………?」
そう言って振り返った少年の瞳に、少し、『正気』の色が戻りつつある。シュバルツは笑顔で頷いた。
「普通のルートで考えるなら、最低9時間はかかるはずだが────」
「お前の身の安全がかかっている。ドモンは、もっと早く来るだろうな」
「そ、そうなんですか?」
ハヤブサの推測に、ノゾム王子は驚いたような声を上げる。
「6時間以内にここに着いたら、大したものだ」
「6時間………」
ハヤブサの言葉に、ノゾム王子はちらっと時計を見る。そして、「長いなぁ………」と、ため息を吐いていた。
「仕方がないじゃない。来てくれるのは間違いないようだから、私たちはそれを待ちましょう」
「お義姉様………」
「ね? ノゾム………」
ナディール姫は、義弟に優しく声をかける。それにノゾムも、素直に「はい」と、頷いていた。
「じゃあ、お義姉様!! その間に、シュバルツ様に、僕のコレクションを見てもらってもいいですか?」
「まあ、ノゾムの部屋を?」
少し驚いたように問い返すナディール姫に、ノゾムは元気良く頷いていた。
「そうね………」
ナディール姫は、少し思案していた。
『ノゾムのコレクション』というのは、『ドモン・カッシュ』に関係する記事や、グッズの数々だ。それらを彼はコツコツと集めて、部屋にきれいに展示するように飾り付けてある。ちょっとした、『ドモン・カッシュの博物館』状態になっていた。
シュバルツが本当に『ドモンの近親者』である、というのなら、それはある意味、最高のもてなし、になるだろうが─────
「ノゾム、あなたの今日の予定は?」
義姉からの問いかけに、ノゾム王子は、はっと、姿勢を少し正してから答えた。
「午前中に、歴史と政治学と経済の勉強、午後からは習い事です」
「そう………」
ナディール姫は、そう返事をすると、静かに顔を上げた。
「ではノゾム。貴方にもう一つ、重要な命令を下します」
「はい。なんでしょう? お義姉様」
少し身構える義弟に、姫は優しく微笑みかけていた。
「貴方に、そこにいるシュバルツ様の『監視役』を命じたいのです」
「……………!」
ナディール姫の言葉に、ノゾムははっと顔を上げた。
「シュバルツ様の正体が、はっきり白黒決着がつくまで、貴方がシュバルツ様を、責任をもって『監視』していてほしいの」
「お義姉様………!」
「できますか?」
ナディール姫の問いかけに、ノゾム王子の表情が、みるみる明るいものになっていった。
「はい! 任せてください!! お義姉様!!」
(なるほどな)
ナディール姫の命令を聞きながら、シュバルツは苦笑していた。
確かに、正体のはっきりしない自分を、城内に野放しにするわけにはいかないし、このままでは、ノゾム王子も、自分のそばから離れそうにない。
だからこの命令は、今の状態を打開するための、苦肉の策である、とも、言えた。
「シュバルツ様も─────それでよろしいですか?」
「ああ。私の方に、異議はない」
(シュバルツを監視………羨ましい………)
ハヤブサは、義姉の命令を聞いて、無邪気に喜ぶノゾム王子と、それに優しく微笑みかけるシュバルツの様子を、じっと見つめながら、深いため息を吐いていた。
シュバルツを監視するだなんて、なんて羨ましい任務なのだろう。
できればノゾム王子と、今すぐ立場を代わってほしいぐらいだ。
それこそシュバルツを、逃げられないように拘束して、隅から隅まで、しっかりと『監視』をして─────
「あ………! ハヤブサ………! もっと、奥の方まで………っ!」
とか、涙ながらに言わせてみたい。そんな阿呆な欲望が、ハヤブサの中でぐるぐると渦を巻いて仕方がなかった。
「ハヤブサ」
呼びかけられて、ハヤブサがはっと、顔を上げると、目の前に、愛おしいヒトの、氷のように冷たい視線がある。
「シ……シュバルツ……」
「聞いての通りだ。私はしばらくノゾム王子と行動を共にするが…………お前は、きちんと自分の『仕事』をしろよ」
「……………!」
ぐっと、言葉に詰まるハヤブサをよそに、ノゾム王子が、シュバルツに無邪気に声をかけてきた。
「では、シュバルツ様! 私の部屋に行きましょう! お見せしたいものがあるんです!」
「分かった」
ハヤブサに向けていた表情とは打って変わって、優しい眼差しをノゾム王子に向けるシュバルツ。二人はそのまま手と手をつないで、仲良く執務室から出て行ってしまった。
「……………!」
がっくり、と、膝を抱えて座り込んでしまうハヤブサ。彼はそのまま、しくしくと、泣き出してしまっていた。
「何をやっておるのですかな? あの者は……」
「ハヤブサ様? 大丈夫ですか?」
カライ内大臣と、ナディール姫から、呆れたように声をかけられる。それに対して、ハヤブサは
「俺のことは、気にするな………。仕事を続けてくれ………」
と、力なく返すのが精いっぱいであった。
「では、お言葉通り、姫様────その他の業務の報告を続けましょうか」
内大臣が、淡々と言葉を紡ぐ。ナディール姫も、「よろしく」と、頷いていた。
「では、報告いたします。北方のラナンの住人たちから、訴状がいくつか届いております」
「訴状ですか?」
「はい。『家畜が殺された。原因を調査してほしい』とか、その他諸々の諸経費についての監査要求など─────」
「最近、ラナンからの要請が多いわね……。どうしたのかしら?」
カライ内大臣から報告書を受け取りつつ、ナディール姫がポツリ、と、こぼす。
「左様ですか? 以前からこれぐらいの頻度で、要請を上げてくる地方ではありましたがな……。何せ、大国との国境近くの村です。『どんな些細なことでも報告せよ』と、歴代の王が、ずっとあの村に命を下して居る場所でもありましたので……」
「そうですか………」
ナディール姫は、カライ内大臣の話を聞きながら、報告書に目を通し続けていた。
廊下を、ノゾムはシュバルツの手を引きながら、うれしそうに歩いている。たが、少し進んだところで、その表情を急に曇らせた。
「どうした?」
驚くシュバルツに、ノゾムは切羽詰まった顔で、シュバルツの手を引いた。
「ごめんなさい。こちらへ……!」
そのまま彼は、柱の陰にシュバルツを導き、そこに身を潜めた。
「…………………?」
怪訝に思いながらも、ノゾムに付き従うシュバルツ。硬い表情の彼が、伺うように覗き込む廊下に、やがて、王太后が姿を現した。
「…………………」
王太后は、厳しい表情をその面に張り付けたまま、すたすたと廊下を通り過ぎていく。ノゾムは、全身を硬くしながらその様子を物陰から見守っていたが、王太后の姿が見えなくなったのを確認してから、ホッと、大きな息を吐いていた。
「すみません。もう大丈夫です」
そう言ってノゾムは、笑顔になる。しかし、その青白い顔色は、一つも「大丈夫だ」とは、言っていない。シュバルツは、少し眉を顰めた。
不思議なこともあるものだ。ノゾムと王太后は、実の親子のはずなのだが。
『母親』の姿を見るのに、どうして『実の子供』が、こんなにもおびえた表情を浮かべなければならない、というのだろう。
「シュバルツ様! 僕の部屋はもうすぐです! 行きましょう!」
そう言って、少年は明るく笑う。それを見たシュバルツも、この問題にはすぐに踏み込んではいけない、と、感じた。今はこうして明るく笑ってくれているのだから、その時間を、少しでも長く楽しませてやることの方が、肝要だろう。
今はまだ早い。
自分が、この問題に踏み込むとするならば。
この少年の信頼を、もう少し得てからだ。
「分かった」
シュバルツも笑顔で頷き、少年についていった。
しばらく歩いていくと、今度はイガールと廊下で出会った。
「あ、イガール………」
「ノゾム様」
ノゾムの姿を認めたイガールは、端により、礼に則り乍ら頭を下げる。ノゾムはその前を通り過ぎようとするが、シュバルツの方が、イガールに声をかけていた。
「失礼。貴殿は確か……」
「イガールです。騎士隊長を務めております」
そう言ってイガールは、静かに頭を下げる。それに対してシュバルツは、「ちょうどよかった」と、声をかけた。
「えっ?」
少し意外そうに顔を上げるイガールに、シュバルツは、少し、決まりの悪そうな顔を向ける。
「いや、貴殿に一つ、託(ことづけ)ておかねばならん、と、思ってな……」
「託ですか?」
問い返すイガールに、シュバルツは頷いた。
「ああ………。もう少ししたら、ドモン・カッシュが………。『私の弟』が、この国に乗り込んでくる、と、思うのだが……」
「ドモン・カッシュ殿がですか?」
驚いたように声を上げるイガールに、シュバルツは申し訳なさそうな顔を向けた。
「すまない。かなり普通じゃない状態で、ここに来ると、思う……」
「普通じゃない状態」
シュバルツの言っている意味が、正しく理解できずに、イガールはオウム返しに言葉を紡ぐ。それに対して、シュバルツはただ、頷くしかなかった。
「だから、イガール殿の権限で、国の警護に当たっている兵士たちに、命を出しておいてくれると助かる。『激昂している赤いマントの男には近づくな』と………。でないと、余計なけが人が出ることに、なってしまうから───」
「は、はぁ………」
その言葉に対してイガールは、ただただ、きょとん、としたような反応をしている。無理もない、と、シュバルツは苦笑していた。ドモンの人類の規格外のような強さなど────実際、その目で見てもらわなければ、分かりづらいものであるだろうから。
「では、頼みます」
シュバルツは、会釈をして、イガールと別れる。ノゾムは、イガールの方に、チラリ、と、視線を走らせたが、特に声をかけるでもなく、シュバルツとともに歩きだしていた。イガールは、その二人の様子をしばらく見送っていたが、彼もまた、反対方向の方へ、歩き出していた。
「シュバルツ様! ここです! こちらが、僕の部屋です!」
ノゾムが、元気よく自分の部屋のドアを開ける。執務室や廊下にいた時とは打って変わって、少年の表情は、年相応の、明るいものになっていた。
「ノゾム様」
部屋の中で控えていた召使が、ノゾムに向かって頭を下げる。
「メリル! 今戻りました!」
それに対して、ノゾムも明るく答える。そして無邪気にそのそばへと走り寄って行った。少年がこの召使に、大いに信頼を寄せている、ということが、はた目にもよくわかる光景であった。
「ノゾム様、そちらの方は?」
メリル、と呼ばれた召使が、入り口付近に佇むシュバルツに気づいて、ノゾムに問いかける。それに対してノゾムは、とても嬉しそうに口を開いた。
「『シュバルツ様』だよ!! ドモン・カッシュのお兄さんかもしれない人なんだ!!」
「まあ、ドモン様の?」
ノゾムの言葉に、メリルが驚いたように顔を上げる。少年は、元気良く頷いていた。
「それで、お義姉様の命令で、僕がしばらく、この型の『監視』をすることになって───!」
「えっ?」
ノゾムの言葉についていきかねるのか、メリルはひたすらきょとん、と、している。
「すまない、私の方から補足説明をさせてくれないか?」
シュバルツは、苦笑しながら、2人の会話の間に入る。そして、今までのことのあらましを、かいつまんでメリルに説明をしていた。
「なるほど、大体に事情は、分かりました」
シュバルツの説明を聞いたメリルが、納得したようにうなずいた。
「この方が、ドモン・カッシュ様のお兄様かもしれなくて、これからもしかしたら、ドモン様がこの城に来られるかもしれないって、言うことなのですね」
「そう! そうなんだよ!」
そこまで話してから、主従は互いに、たがいの顔を見つめながら、しばし沈黙していた。
「……………」
「……………」
「……………?」
この、妙な沈黙に、シュバルツは首をひねるしかない。しかし、主従の邪魔をするわけにもいかないので、彼も静かに見守ることを、選択していた。しばし、部屋に、奇妙な静寂が舞い降りる。
だが、やがて、見つめあっていた主従が同時に、わたわたし始めた。
「まあ、ノゾム様本当に!? 本当にドモン様がいらっしゃるのですか!?」
「そ、そうなんだよ、メリル……! ど、どうしよう……! 僕……!」
「大変ですわ……! 今すぐ掃除を……! あ……! お茶菓子の用意もしなくては………!」
「ドモン様は、どんなお茶菓子が好きかなぁ? あっ! どれにサインをもらうか考えておかなきゃ……!」
「お、おい、ちょっと……! ちょっと待ってくれ……!」
たまらずシュバルツは、主従に声をかけた。二人が舞い上がりすぎている、と、感じたからだ。
「少し落ち着こうか……。ドモンが来るまで、まだ相当時間がある。今からそんなに飛ばしていては、本人を目の前にしたとき、ばててしまうぞ?」
「あ…………!」
「そ、そうだけど………」
メリルの方は、少し落ち着きを取り戻していたが、ノゾムの方は、まだ少し、興奮が冷めやらぬようであった。
「で、でも……! ドモン様がいらっしゃるのなら………!」
「そういえば、君は私に見せたいものがあったんじゃないのか? よければ、見せてもらってもいいか?」
シュバルツに優しくこう言われ、ノゾムもようやく、落ち着きを取り戻したようだった。
「そうでした……! シュバルツ様! こちらへ来てください!」
少年は、うれしそうに、シュバルツの手を引いて、歩き出すのだった。
「こちらです……! こちらの部屋を、みてください!!」
部屋の奥の小さな扉を、ノゾムは開ける。その部屋に入ったシュバルツは、知らず小さく感嘆の声を上げていた。
それもそのはずで、その部屋の壁には、ズラリと、ドモンのポスターや写真、そしてサイン色紙等が飾られてあり、ショーケースの中には、ドモンのことを特集した雑誌や記事、新聞紙、そして彼に関連したグッズなどが飾り付けられてある。ちょっとした、博物館状態になっていたからだ。
「よく、これだけ集めたな……」
感心したようにつぶやくシュバルツに、メリルがそっと、補足説明をしだした。
「ノゾム様が、直接手に入れた物も何点かあるのですが、国民の皆様も、とても協力してくれまして………」
「皆が、いろいろと教えてくれたり、手に入れたグッズを譲ってくれたりしたんです。本当に、みんなのおかげです………」
少年が、はにかみながら呟く。
少年ノゾムにとって、『ドモン・カッシュ』という格闘家は、純粋に、憧れの存在だった。
ドモンの戦い方は、苛烈にして、直線的だ。相手がどんなに巨大で、強そうに見えても、彼は怯むことなく立ち向かっていく。
その強さに
激しさに
豪胆さに
憧れた。
父や母や、義姉の後ろにすぐ隠れてしまう自分には、絶対に持ちえないものだ、と、感じてしまっていたから───
(ドモン様は、自分の弱さや情けなさに、悩んだりすることって、あるのかな)
少年はそう考えてから、きっと、ないのだろうな、と、思う。
それほどまでに、『ドモン・カッシュ』という格闘家は、少年ノゾムにとっては、絶対的な存在であったのだ。
(あ、これすごいな)
シュバルツは、展示されてある資料の一つ一つを、丁寧に見つめながら、時折、感嘆の吐息を漏らす。
キョウジも、そして自分も、世界でたった一人の大切な弟の生きる道を、応援しているし、誇らしくも思っている。だから当然、ノゾムと同じように、弟のことを特集している記事や雑誌、新聞などはスクラップしてあるし、グッズなども一通り買って、コレクションしてある。だから当然、シュバルツにとっては、見たことがある記事、グッズの方が多い。
しかし中には、シュバルツが見たこともないようなものもある。特に、雑誌の記事などは、日本では手に入りにくいものが多いだけに、シュバルツの目を一段と引いていた。
(いいなぁ。写真撮らせてもらえないかな……)
などと、考えてしまったりしている。キョウジやドモンに見せてあげられたら、きっと喜んでもらえるだろう。
「お、ドモンのサインがある。これは、直接もらえたのか?」
一枚の色紙の前で、シュバルツが足を止める。それを聞いたノゾムが、いそいそとシュバルツのそばに走り寄っていた。
「はい! そうなんです! 本当に偶然、書いてもらえて───」
それは、ドモンが近くの国に興行に来た時に、お忍びで見に行っていたときのことだった。どうしても、ドモンを直接見たかったノゾムは、大勢のファンとともに、スタジアムの周りで、いわゆる一つの『出待ち』をしていた。
そして、運良く、ドモン・カッシュが外に出てきてくれた。
「……………!」
ノゾムは大勢のファンたちの間に交じって、懸命に、ドモンに向かって、色紙とペンを差し出す。その色紙を、ドモンは手に取ってくれた。そして、サインをしてくれたのだ。
日付も、メッセージもない、何かの記念であるわけでもない、本当にシンプルなサインなのだが、少年ノゾムにとって、それは、何物にも代えがたい宝となった。だからその色紙は、この部屋の中で、一番よく見える場所に、大事に大事に飾られていた。
そう。
あの瞬間、自分とドモン・カッシュの間には
確かに、同じ時間、同じ空間を共有していたのだ。
それは、その証たる物だった。
これを見れば、頑張れる。
この時のことを思い出せば、自分の心の中にも、確かに、勇気の光が灯った。
「ドモン様は、僕のことなんて気にもとめてないかもしれません。でも僕は、本当に嬉しかったから────」
「そうか………」
ノゾムの話を聞くシュバルツの面には、優しい笑みが浮かんでいた。ノゾムも、本当に幸せそうな顔をして、ドモンの話をシュバルツにしていた。
(ノゾム様……なんて穏やかな表情を………。良かった………)
それを見た侍女メリルも、幸せな心持ちになっていた。
この穏やかな光景が、少しでも長く続けば良い。
メリルは、何時しかそう祈らずには、いられなかった。
ナディール姫は、午前の執務をこなしながら、ずっと、頭の隅で考え続けていた。
(………やはり、ラナン地区に、一度足を運んでみるべきなのかしら……)
やはり、要望と嘆願書の頻度が、前よりも上がってきている気がする。これは、「気のせいだ」と、流してしまっては、いけない問題のように感じられた。
「カライ内大臣」
これからのスケジュールの調整を相談してみよう、と、彼女は内大臣に声をかけた。が、そこに、執務室の外で控えていた警護の兵士から、「姫様」と、声をかけられた。
「何事か?」
問い返す内大臣に、兵士は口を開く。
「シェフが目通りを願っておりますが、通してよろしいでしょうか?」
「シェフが?」
ナディール姫は少し驚いて、問い返していた。シェフは確か、家族に付き添って、病院にいるはずであったからだ。
(どうしたのかしら………)
少し、その真意を測りかねて、彼女は知らず、ハヤブサの方を見てしまう。
「…………………」
腕組みをして、壁際に静かにたたずんでいたハヤブサであったが、ナディール姫の視線に気づいて、彼は静かに頷いていた。
「いいわ。お通しして」
ハヤブサの同意を得られたことに、勇気を得たナディール姫は、シェフに謁見の許可を出す。
「失礼いたします」
シェフがかしこまって執務室に入ってくる。その後ろから、厨房で働いていたコックたち二人が、付き従って入ってきた。
「どうしたのですか?」
問いかけるナディール姫に、シェフは頭を垂れると、懐から一枚の封書を差し出した。
「実は……お暇をいただきたく………」
「─────!?」
ぎょっと、固まるナディール姫に向かって、シェフはさらに平身低頭した。
「私のやってしまったことを鑑みるに、とてもこれ以上、ここで働くことなどできません……! どうかこの辞表を、受け取っていただければ………!」
「あ……………!」
実は、シェフを首にする気など毛頭なかったナディール姫は、ただただ、戸惑うしかない。
「おぬしたちもそれに、同意しておるのか?」
呆然としてしまうナディール姫に代わって、カライ内大臣が口を開いた。シェフの後ろに控えるコックたち二人が、少し苦い顔をして、その辞表を見つめていることに、内大臣は気づいたからだ。
「いえ、我々は、シェフが辞められることに反対しています」
「その辞表を取り下げていただきたく、お願いを申し上げに来ました!」
「お前たち!?」
驚いて振り返るシェフを、コック二人が怒気を食んだ目で睨みつけていた。
「やめてしまわれるなんて………冗談じゃないですよ!」
「そうですよ! スープの仕込みのコツも、まだ教わっていないのに!」
「教えてもらわなければいけないことが、まだたくさんあるんです!」
「いや、しかし…………!」
シェフは戸惑いを隠しきれなかった。自分がやってきたことを考えると、とても許されることではない、と、思えてならなかったからだ。
「私は、王や姫様たちの『信頼』を、裏切ってしまった。もうここで働く資格など、持ち合わせてはいないのです」
「シェフ………」
ナディール姫は、大きく息を吐いた。
シェフの言い分もわかる。
王族に『毒』を盛ることなど、普通なら、到底許されることではない。
しかし、彼は、彼の宝物である『家族』を人質に取られ、已むに已まれずこの蛮行に及んでいたのだ。それを、彼だけにすべての責任を負わせて、その首を斬るのは何かおかしいのではないか、と、ナディール姫は感じていた。
『責任』というのなら、私たち王族にも『責任』がある。
彼の愛する『家族』を、守れなかった『責任』が。
「一つだけ、言わせてください。貴方は、『私たちの信頼を裏切った』と、言っていましたが、貴方はまだ、私たちの『信頼』を、裏切ってなどいません」
「えっ?」
かなり驚いたように顔を上げるシェフを、ナディール姫はまっすぐ見つめ返していた。
「厨房では、確かに『異常事態』は起きていました。ですが、その間、貴方の料理を食べていた、父や義母やノゾムから、何か、料理の味について、文句が出たり、注文が出たりしましたか?」
「いえ………」
そういうことは全くなかったので、シェフは、首を横に振るしかない。それを見たナディール姫は、少しの笑みを、その面に浮かべた。
「ね……。貴方の仕事は、『料理を作ること』 その役目を、貴方はきっちりとこなしていた。あれだけ異常な状況に置かれていたにもかかわらず、です」
ナディール姫はそう話しながら、シュバルツに助けられて、久しぶりに食べることができた、シェフのスープの味を思い出す。それは、何も変わらずに、ナディール姫の舌に染み込んできた。
シェフは、ずっと変わらずに、スープの仕込みを丹念にしていたのだと、知る。
たとえそのスープが、毒に穢されるものだったとしても。
「姫様………!」
シェフはただ、呆然と、姫の言葉を聞いていた。
違う。
自分はあの時、どうすればいいのか分からずに。
ただ、身体に染みついた習慣的な行動を、反復していたに過ぎないのに。
「あなたがもし、私たちの『信頼』を裏切る、と、言うことがあるとするならば、それは、料理の技を、途絶えさせてしまうこと………」
「──────!」
「貴方のその『味』を、誰にも伝えずに、辞めてしまうこと─────」
「あ…………!」
「違いますか?」
「………………ッ!」
シェフは、ぐ、と、唇をかみしめていた。姫の言っていることは、ある意味正論だ。
正論だが─────
「そうですよ! シェフ!!」
後ろに控えていたコックたちが叫んだ。
「われわれに、シェフの技を、ちゃんと教えてください!!」
「お前たち………」
呆然と、2人のコックを見つめるシェフに、ナディール姫はさらに言葉を続けた。
「その役目を終えるまでは、貴方がここを辞めることを、許可することはできません」
「姫様………」
「キチンと、責任を果たしてください。シェフ……」
「しかし………」
シェフは、まだここに残ることに、少しの躊躇いを覚えていた。
自分は、姫を殺すことに加担したのだ。いわば、彼女の敵対勢力に、加担したも同然だ。
そんな自分がそばにいることが、厨房に居座ることが、彼女にとって、果たしていいことなのかどうか───考えてしまうのだ。
「姫様……。私は一度、心ならずもあなたの敵対勢力に加担し、接触をしています。私を殺そうと、彼らが再びやってくるかもしれない。姫様……。貴方にも迷惑をかけてしまうかもしれません……」
「………お前が今生きている、ということは、敵方にとっては、お前が生きていても、特に問題はない、と、言うことだ」
その時、それまで黙っていた龍の忍者が、おもむろに口を開いた。
「お前が、敵に直接つながるような情報を、何も持っていないからだろう。もしも敵方にとって『生きているだけで都合が悪い』と、言うのなら、とっくに殺されているはずだ」
そう。
この場合、敵につながりがある可能性があったのは、殺されたイワンコフだ。
やはり、彼を捕らえるべきだったか、と、ハヤブサは軽くため息を吐く。だが、ナディール姫の性格では、彼を捕らえることを潔し、とはしないだろうし、この城の警備状況では、イワンコフを殺意から守り切ることは、ほぼ不可能であっただろう。捕らえて投獄したところで、おそらく、牢の中で殺されてしまう確率が高い。
(仕方がないな………)
こういう場合、焦っても仕方ないことを、ハヤブサは経験上知っていた。自分は自分のやり方で、敵の手掛かりに接近していくだけだ、と、思った。
「確かに私は、私に指示を出してきたイワンコフ以外は、実質的に何も知らない……。今、生きているのは、そういうことなのかもしれませんね………」
そう言って、シェフは少し自嘲的に笑う。
「シェフ………」
ナディール姫は、改めて声をかけていた。
「とにかく今日は休んで……仕事ができそうになれば、また来てください。私たちはいつでも、貴方の料理を待っていますから………」
「姫様………!」
あとは言葉にならず、咽びながら畏まるシェフ。それを見守るナディール姫の横で、カライ内大臣が、やれやれ、と、ため息を吐いていた。
「失礼いたします」
その時、執務室のドアがノックされる。「どうした?」と、内大臣が声をかけると、執務室の入り口を守っている兵士から、答えが返ってきた。
「イガール殿がおいでですが、お通ししてもよろしいでしょうか?」
「イガールが?」
少し驚いたように顔を上げるナディール姫。その横でカライ内大臣が、「よし、通せ」と、兵に指示を出していた。
「では、私共はこれで」
シェフは、そう言って頭を下げると、執務室より退出していた。
「失礼いたします」
それと入れ替わるように、イガールが、手に書類をいくつか持って、執務室に入ってきていた。
「イガール」
彼の顔を見た姫の顔が、心なしか明るいものになる。
「大丈夫なのですか? 少しでも、休めましたか?」
「は、大丈夫です。姫様」
ナディール姫の気遣いに、イガールははにかみながら答える。
「イワンコフが亡くなった時の状況と、城の警備体制を、私なりにまとめて、見直してみました。それと、こちらはハヤブサ殿に」
イガールは、一枚の写真を、ハヤブサに渡す。
「イワンコフが身に着けていたものをまとめて、写真を撮りました。……と、言っても、大したものはないようですが………」
「………………」
ハヤブサは、無言で写真に目を通す。
確かにイガールの言うとおり、写真に写っているのは、ボールペンや、メモ用紙、腕時計といった、どこにでもある、ありきたりな物だけだった。
「それで………何か、分かりますか?」
「………………」
その問いかけに、特にハヤブサは答えない。イガールが、しばらくその横顔を除きkんでいると、カライ内大臣から、声をかけられた。
「イガール………。城の警護の人数を、もっと増やすことはできぬのか?」
「はっ! それは私も考えましたが、いかんせん、国境の警備もあり、予算の関係工、これ以上警備隊の人員を増やすのも難しく─────」
(………そうなのよね……)
ナディール姫は、眉間に少ししわを寄せながら、イガールの話を聞いていた。
確かに、そうなのだ。
限られた国家予算の中では、これ以上警備隊にばかりに、経費を回せないのが実情であった。
本当に、小さな小さな国力。
そんな中、地下に眠るレアメタル鉱脈の発見は、国にとって、明るいニュースになるはずだったのだが。
「………そういえば、レアメタルの鉱脈を調査に行った調査隊からは、何の報告も入っていないのですか? 時間的に、そろそろ何らかの報告が入っても、おかしくはないのですが───」
「そうですな。そろそろ報告が入るころですが………」
ナディール姫の言葉に、カライ内大臣もそう答える。
「今のところ、異常は報告されておりませんが………。心配ならば、迎えの隊を手配させましょうか?」
「そうですね。できれば────」
ナディール姫がそう答えた時、『それ』は、唐突に始まった。
「ご注進!! ご注進申し上げます!!」
執務室のドアが勢いよく開くと同時に、一人の兵士が転がり込むように入ってきていた。
「どうした!?」
カライ内大臣が驚いたように声をかけると、その兵士は息せき切って報告を始めた。
「ただ今、国境の警備隊から、不審者に検問を突破された、と、連絡が入っております!」
「何じゃと!?」
「不審者ですか?」
「……………!」
執務室にいた者たちが、一瞬、色めきだつ。
「どのような者であったか、その者の特徴の連絡は、入っているのか!?」
「は、はっ!」
イガールからの問いかけに、兵士は慌てて持っている報告書に、目を通しながら読み上げ始めた。
「国境線を破られたのは、am10:06!! 赤いマントを羽織っており────」
(ああ、なんだ。ドモン・カッシュか)
その報告を聞いた瞬間、ハヤブサは不審者の正体を看破していた。そして、おもむろに懐から懐中時計を取り出し、時間を確認する。
(俺が電話してから、3時間………)
『3時間』という現実に、ハヤブサはしばし、目をしばたたかせる。
(早くないか?)
「ドモンは日本にいる」と、言うシュバルツの言葉が正しいのなら、彼は間違いなく、ほぼ地球の反対側に、いたことになるのだから。
「兵士たちが総動員で当たっておりますが、止められません!! 不審者は、まっすぐ城へ向かっております!!」
「何っ!?」
カライ内大臣の顔色が、蒼白になる。
「すぐに迎撃態勢をとれ!! 姫様は、安全な場所に避難を────!!」
「その必要はない!」
イガールの言葉を、龍の忍者の妙に冷静な響きを含んだ言葉が止める。
「どういうことですか?」
振り返ったナディール姫に、龍の忍者はちらりと視線を走らせると、ぶぜんとした口調で、話し始めた。
「分からないのか? 不審者の正体は『ドモン・カッシュ』だ」
「えっ?」
「はい?」
「何ですと?」
ハヤブサの言葉に、ナディール姫とイガールと、カライ内大臣が、三者三様に、目をぱちくりとさせていた。
「ドモン様が来られるのは、夕方近くのはずでは………?」
ナディール姫の、ある意味もっともな言葉に、ハヤブサもため息交じりに返事をするしかない。
「俺もそう思っていたのだが、現実に、奴はここに来ている。どんな手を使ったのかは知らないがな」
「は………はあ………」
戸惑い気味に返事をするイガールに、ハヤブサは冷静に告げていた。
「とにかく、そいつの前に下手に立ちふさがるな、と、兵士たちに伝えておけ。猪突猛進してくるあいつを止められる存在など、そうはいないのだから」
「そ、それはそうかもしれませんが………」
ハヤブサと一騎打ちをした経験があるイガールは、彼の腕と、彼の言葉はある程度信用できる、と、思っている。
しかし────
「ミルタ区の、検問所を突破しました!」
「道路を横断中の、牛がはね飛ばされた模様です!」
「SNSで、不審者が暴走する様子の画像が、次々と上がっております!!」
「市場で混乱が起きています!!」
「隊長!! 何か指示を!!」
こうしている間にも、兵士たちが次々と、悲鳴に近い声で叫びながら、執務室に転がり込んでくる。
「姫様! やはり、この騒ぎを放置するわけには────!」
振り返るイガールに、ハヤブサは「無駄だ」と、諭した。
「下手な抵抗は、怪我人や死人を増やす。それよりも────」
ここまで話した龍の忍者が、顔を上げた。
「もう、来るんじゃないのか?」
「えっ?」
きょとん、となるイガール。その奥から、地鳴りのような足音が響き、それが、徐々に近づいてくる。
やがて
ドカン!! と言う派手な音と共に、執務室のドアが破壊されて、その役目を終了していた。
「おのれっ!! 俺の兄さんを拐かそうという、不届き者はどこのどいつだッ!!」
叫び声と共に、赤いマントが執務室に、飛び込んでくる。
ついに────『ドモン・カッシュ』が、ユリノスティ王国に到達した瞬間だった。
第5章
「兄さんをピンチに陥れた、不届き者は貴様かっ!!」
ドモン・カッシュは叫びながら、何故か一直線にリュウ・ハヤブサの方に向かっていった。まっすぐに放たれた拳が、ハヤブサの頬を捕らえる寸前、ハヤブサの拳が、それを受け止めていた。
「なんで俺に来る!?」
拳をはじき返しながら叫ぶハヤブサに、ドモンはなおも徒手のラッシュを浴びせかけた。
「貴様が兄さんと関わると、ろくな事にならん!!」
フッと、小さく息を吐いたドモンが、ハヤブサに回し蹴りを放つ。
「貴様が兄さんを嵌めて────捕らえられるように仕向けたのだろう!!」
「そんなことするか!!」
ハヤブサもドモンの蹴りを、己が足で受け止めていた。
シュバルツを捕らえさせるなど、とんでもないことだ。
いや、捕らえたい、と言う下心はある。
座敷牢に監禁して、抵抗できないように手足を縛り付けて────
「あ………! ハヤブサ………!」
涙目でこちらを見つめるシュバルツを、思う存分かわいがって、その身体を堪能したい欲望は、常に携帯しているが─────
シュバルツを陥れて、自分以外の輩の手に渡すことなど、考えられないことだ。
「忘れたのか!? 『お前の兄がピンチに陥っている』と、連絡を入れたのは、俺だ!!」
ガツン!! と、派手な音を立てて、2人の正面で、拳と拳がぶつかり合う。
「………なあ、真面目に聞いても良いか?」
拳同士でつばぜり合いのような状態になりながら、ハヤブサはドモンに問いかけていた。
「お前、ここまでどうやって来た!? お前は日本にいたはずだろう!!」
それに対してドモンは、フン、と、鼻を鳴らしながら答える。
「世界中の伝手とコネを、フル活用しただけだ!!」
そう。ハヤブサから連絡をもらってからの、ドモンの行動は、早かった。
世界中の知り合いに声をかけて、日本からユリノスティ王国まで、3度の軍用機のスクランブルを可能にした。それが出来るほどに、彼か世界中に持つ伝手とコネは、実は強力な物だったのだ。
「俺から兄さんを奪う者は!! 誰であろうと粉みじんにしてやるッ!!」
ハヤブサからわずかな隙を見いだして、ドモンは渾身のアッパーを放つ。
「この………! やれるものならやってみろッ!!」
それを、少し身体を反らして、紙一重で飼わしたハヤブサもまた、ドモンに向かって全力の正拳を放つ。
「!!」
ドモンは咄嗟に腕を交差して、それを受け止めたが、ハヤブサの膂力に推されて、少し後ろに、強制的に下げられてしまう。それが酷く、面白くなかった。
「おのれっ!!」
ドモンは、更に、攻撃の熱を加速させた。
「猪口才な!!」
負けずにハヤブサも応酬する。城の執務室内に、あり得ないほどの戦いの風が吹き荒れていた。
「姫様!!」
カライ内大臣が、ナディール姫を咄嗟に庇い、執務室の端へと導く。
「……………!」
イガールが、2人の争いを止めようとしていたのを見て取ったナディール姫は、咄嗟に彼に声をかけていた。
「イガール!! シュバルツ様を!!」
「姫様!?」
振り返るイガールに、ナディール姫は必死に呼びかけていた。
「この2人の戦いを止められるのは、シュバルツ様しかいらっしゃらない!!」
「─────!」
「早く、シュバルツ様を呼んできて! イガール!! このお二方の戦いで、執務室の窓や壁が、これ以上壊されないうちに!!」
「で、ですか……!」
イガールは、少しこの部屋から出ることを躊躇していた。
「ですが、姫様の御身の安全は………!」
「大丈夫!! 私にはハヤブサ様がついているから!!」
「……………!」
ナディール姫のこの言葉に、イガールは、はっと息を呑む。
「ハヤブサ様は、どんなときであろうと、必ず私を護って下さいます!! ですから、大丈夫です!!」
「姫様………!」
呆然と見つめ返すイガールに、ナディール姫はまっすぐ見つめながら頷き返す。
「承知致しました!」
イガールは軽く頭を下げると、くるりと踵を返して、足早に部屋を出て行った。
(ち……! 姫め……! しっかりと、痛いところを………!)
ドモンと戦いながらも、ナディール姫の声を聞いていたハヤブサは、内心舌を巻いていた。
そこまで盤石に信頼されてしまったら────それに応えぬ訳にはいかぬではないか。
「おい!! ドモン・カッシュ!! 分かっているだろうな!!」
ハヤブサは、戦いながらドモンに呼びかけていた。
「あそこにいる姫を、断じて戦いに巻き込むなよ!!」
「言われずともっ!!」
ドモンもまた、拳のラッシュを放ちながら、ハヤブサに叫び返していた。
「俺の狙いは、最初っから貴様1人だ!! リュウ・ハヤブサ!!」
「だから!! なんで俺がターゲットになるんだ!!」
拳をいなし続けるハヤブサに、ドモンは噛みつかんばかりに叫んでいた。
「貴様が兄さんを拐かそうとしているからだ!!」
「拐かしてなどいない!! 言いがかりだ!!」
ハヤブサも反論するが、ドモンの方が最早聞く耳を持っていない。更に、戦いの熱を加速させてきていた。
「うるさい!! いつもいつも、何かあれば兄さんにべったりくっつきやがって!! 兄さんは俺の物だ!! 俺と兄さんの間に、お前が入り込む隙などない!!」
「……………!」
この言葉には、ハヤブサも多少、かちん、と頭にきた。
(隙がないとか、笑わせる……! 結構隙だらけだがな……!)
大体、シュバルツは俺に想いを寄せてくれているんだ。
俺がいなくなってしまったら、あいつは酷く哀しむって、事を、この馬鹿弟は、何時になったら理解してくれるのだろうか。
「俺はシュバルツと風呂に入ったことがあるぞ?」
ついつい、シュバルツと仲が良いアピールを、してしまう。しかし、ドモンの方も負けてはいない。
「それがどうした!! 風呂ぐらい俺も一緒に入る!!」
「共に寝たこともあるぞ……!」
「兄さんと添い寝など、俺も子どもの頃からしょっちゅうだ!!」
(な、何かしら……。このお二方の会話が、微妙に成り立っていないような気がする……。気のせいなのかしら………)
2人の戦いながらの会話を聞きながら、ナディール姫は、笑顔を引きつらせながら、眉をひそめるしかない。その横で、カライ内大臣も、やれやれ、と、大仰なため息を吐いていた。
「姫様。あんな体の龍の忍者を、ご信用なさるので?」
ちくり、と、ナディール姫をつついてくる。それに対してナディール姫は、「当然です」と、頷いていた。
「今までの彼の行動を見ていれば────疑う余地は、ないと思いますけど?」
「それはそうかもしれませんが………」
カライ内大臣が見やる先で、リュウ・ハヤブサは、ドモンに向かって、思いっきり『あっかんべ~』をしている。
「シュバルツは俺の物だ!! 断じて、貴様の物ではないからな!!」
「おのれ言わせておけば………ッ!」
ぶるぶる震えるドモンを見つめながら、カライ内大臣は呆れたように口を開いていた。
「あのような大人げないことをしておっても、まだ信用なさる、と、仰るのですか?」
「ええと………」
ナディール姫も、だんだん自信がなくなってきていた。
「し、信用できるはずです…………多分」
「多分」
「ええ……多分」
顔をひきつらせながら見つめる主従の前で、不毛な戦いは、ひたすら続けられていた。
「シュバルツ殿!!」
ノゾムの部屋に、イガールが走り込んでくる。
「どうしました?」
問い返すメリルにイガールは、少しまくし立てるように叫んでいた。
「直ぐにシュバルツ殿を呼んでいただけないか!? 姫様がお呼びだ!」
「どうした?」
イガールの声に反応して、シュバルツが奥の部屋から、すぐに出てくる。「ああ、シュバルツ殿!」と、イガールもそのそばに走り寄っていた。
「すぐに執務室に来ていただきたい!」
「執務室に?」
少し、きょとん、とするシュバルツに、イガールは少し、手足をばたつかせながら、事態の説明を試みていた。
「ドモン殿が………!」
「ドモンが?」
「その、執務室に乗り込んできて………」
「えっ?」
シュバルツは、少し眉を顰めながら、おのが腕の腕時計を見る。
「………本当に、ドモンが来たのか? 早すぎないか?」
「私もそう思ったのですが………」
シュバルツのもっともな言葉に、イガールも顔を引きつらせるしかない。
「現に、執務室でその………暴れておりまして………」
「何っ!?」
驚くシュバルツに、イガールも困ったように言葉を続けた。
「主に執務室にいる、ハヤブサ殿に突っかかって行っているような感じです」
「……………!」
(ドモン………! あの馬鹿!!)
シュバルツは知らず、目眩のようなものを感じていた。
確かにハヤブサの伝言は、ドモンを思いっきり挑発していたが。
それにしてもまさか、そのままハヤブサに、突っかかっていくとは────
あまりにも突っ込みどころが多すぎて、シュバルツは開いた口がふさがらなくなる。
とにかくドモンを落ち着かせねば、と、強く思った。
「よし分かった。執務室へ行こう」
シュバルツがそう言って、歩き出そうとしたとき、彼の後ろから、声をかける者がいた。
「待って下さい! シュバルツ様!!」
彼が振り返ると、ノゾムが後ろから追いかけてきていた。
「私も、一緒に連れて行って下さい!」
少年は、シュバルツをまっすぐ見つめながら、言葉を紡ぐ。
「しかし………少し危ないかもしれないぞ?」
シュバルツは、少し案ずるように返事をする。
執務室では、ドモンとハヤブサの戦いが起こっているのだ。2人とも実力が拮抗しているが故に、お互いがお互いにヒートアップしてしまっている可能性が、大いにあった。彼らの戦いに、周りの何かが破壊されない、と言う保証は、申し訳ないが、出来かねた。
だが少年は、背筋を伸ばしたまま、頭を振った。
「構いません。連れて行って下さい」
「しかし………!」
まだ少し躊躇っているシュバルツに、ノゾムはまっすぐ言葉を続けた。
「お忘れですか? シュバルツ様」
「?」
「僕はお義姉様に、『貴方を監視する役目』を、与えられているんです」
「──────!」
「それを、違えるわけにはいきません! だから、一緒に連れて行って下さい!」
そう言って、少年は、まっすぐ手を伸ばす。
「………………」
シュバルツはそれをじっと見つめていたが、やがて、少し笑って頷いた。
「分かった……。共に行こう」
「はい!!」
シュバルツの許しが出たことで、ノゾムの面に、ぱっと、明るい笑顔の花が咲く。
「では、ノゾム様! シュバルツ殿! こちらへ!」
イガールが2人を案内するように、走り出す。シュバルツはノゾムを抱きかかえると、その後について走り出していた。
「お気をつけて、行ってらっしゃいませ!」
その姿を、侍女メリルは頭を下げて、見送っていた。
一方執務室では、ドモンとハヤブサの、白熱してはいるが、どことなく不毛さを感じさせる戦いが、なおも続いていた。
「ええい、ちょこまかと!! 避け廻らずにさっさとやられろ!! この唐変木がぁ!!」
ドモンが怒りながら、拳を振り回している。それに、ハヤブサも、フン、と、鼻を鳴らしていた。
「フッ! 貴様の蠅が止まりそうな拳なんぞに、当たってやる義理はない!!」
「なにぃ!?」
「貴様こそさっさとやられろ!! 難癖つけられて、いい迷惑を被っているのはこちらだ!!」
「難癖ではないぞ!? お前が兄さんにつきまとっているのは事実だ!!」
「……………!」
「兄さんに近づく悪い虫は────俺がきっちりと打ち払ってやるっ!!」
「出来るものならやってみろッ!!」
全く、訳が分からない理由で、お互いに一歩も譲らない両者。ナディール姫は困惑していた。
二人のバトルが勃発しているこの状況では、当然この部屋は執務どころではなく、部屋の外では、書類を持ってきた者、待つ者が牢かに列をなす事態になってきた。
(困ったわ……。このままでは……。でも………)
この二人の激しすぎるバトル────兵士たちに止めさせるには、あまりにも危険すぎた。
その思いは、カライ内大臣も同じなのだろう。少し苛々しながら、2人のバトルを見つめているのが、傍目にもはっきりと分かった。時折、小さく舌打ちをしている。
(やっぱり、私が無理矢理にでも、止めるべきなのかしら……)
そう感じたナディール姫が、一歩、踏み出そうとする。
だがその時、ナディール姫は、ハヤブサの背中の怪我を思い出していた。
イガールとハヤブサの戦いを止めようとして、自分は二人の間に強引に飛び込んだ。
その結果、何を引き起こしてしまっていたか────
「う…………」
深く、切り裂かれた龍の忍者の背中。
総て、何も考えずに無防備に飛び込んだ自分を、ハヤブサがイガールの剣から、庇ってくれた結果だった。
ハヤブサの怪我も、勿論ショックだった。
しかし、それよりも、酷く動揺し、深く謝罪をしてくるイガールの姿に、姫は衝撃を受けていた。
「姫様に何かあれば、私も生きてはいません………!」
全身を震わせながら、深々と頭を下げてくるイガール。
自分は、彼に取り返しもつかないほどの傷を、負わせてしまうところのだったのだ、と、突きつけられた。
何の策もなく、無防備に危険地帯に飛び込んではならない。
特に、誰かを深く傷つけてしまうのならば、なおさら─────
それが、自分があのトラブルから学んだ『教訓』だった。
(……………!)
だから今、自分があの二人の間に割り込むわけにはいかない。自分には策もなく、有効な手段もないからだ。
でも、このままの状態では良くないことも、また、事実であった。
どうすれば良いのだろう。
ナディール姫が途方に暮れていたとき、『それ』は、訪れた。
「彼を頼む」
その声の主は、そう言って、姫の傍に『ノゾム』少年を置いていく。
「あ…………!」
「お義姉様」
少年は、姫のそばにそっと寄りそう。姫が顔を上げると、革のロングコートを着た青年の後ろ姿が、そこにあった。
「いいか!? はっきりと言ってやるっ!! 兄さんは俺の物だ!! よそ者のお前が、好き勝手して良い相手なんかじゃないんだからな!!」
ドモンのその言葉に、ハヤブサの中で何かが、完全に切れた。
「分かった……! そこまで言うんなら、こっちだって言ってやるっ!!」
龍の忍者が、肺に大きく息を吸い込み、口を開く。
「いいか!? シュバルツはもう俺の物だ!! その可愛らしい喘」
ここまで口走ったハヤブサが、いきなりドモンの視界から姿を消した。
「!?」
ぎょっと、息をのむドモンの目の前に、ものすごい勢いでハヤブサを無言で殴りつけている、シュバルツ・ブルーダーの姿が出現する。
「兄さん!?」
「………………」
どかどかとハヤブサを殴りつけているその拳には、容赦も慈悲も、まるで存在しないかのごとくに苛烈だった。唖然と、立ちすくむドモンの目の前で、あっという間にハヤブサが、シュバルツによって、ぼこぼこに叩きのめされていく。
「に、兄さん………?」
流石に少しハヤブサが気の毒になったのか、ドモンが、シュバルツにそろっと声をかける。するとシュバルツは、ものすごくいい笑顔で、ドモンの方に振り返っていた。
「やあドモン。来ていたのか」
「あ、ああ………」
あまりにもさわやかなその兄の笑顔に、ドモンもこれ以上、ハヤブサとのバトルを続けられなくなってしまう。顔を引きつらせながら頷いていると、兄がつかつかと近寄ってきた。
「それにしても、ずいぶん早かったな。どうやってここまで来たんだ? お前は確か、日本にいた、と、思ったが?」
「日本とロシアの空軍に頼んで、戦闘機にスクランブルをかけてもらったんだ!」
「………………!」
思ったよりも物騒な、そして強力なコネを使ってきた弟に、シュバルツは思わず絶句する。
「兄さんが危地に陥っているのなら────俺は、地球の裏側からでも、駆け付けてみせる!!」
(そうだった……。こいつには、世界中に伝手があるんだった……)
頼り甲斐があるというのか、物騒すぎるといえばいいのか─────複雑なため息を吐きながらも、シュバルツはナディール姫の方に振り返った。
「御覧の通り────『ドモン・カッシュ』だ」
「……………!」
はっと、顔を上げるナディール姫に、シュバルツは、にこっと微笑みかけた。
「これで────私の嫌疑は、晴らしてくれるのかな?」
「あ………!」
シュバルツの言葉に、我に返ったナディール姫は、慌てて義弟の方に振り返った。
「ノゾム………どう?」
「は、はい………!」
ノゾム少年の頬は、紅潮し、その身体が小さく震えていた。その、大きな黒い瞳も、涙がたたえられて、ウルウルと潤んでいる。
(無理もないわね………)
そんな義弟の様子を見て、ナディール姫は少しばかり苦笑する。
無理もない。
憧れて憧れてやまない人が
今─────確かに、彼の目の前にいるのだから。
「ま、間違いなく………ドモン様本人だと、思います………!」
「ああ。俺は、間違いなく『ドモン・カッシュ』だ」
ノゾムの姿に気づいたドモンもまた、構えを解いて、身にまとっていた殺気を解いた。
ドモン・カッシュという男は、多少短気でぶっきらぼうだが、基本、優しい性格をしている。自分より力の弱い者には、滅多なことで、その牙を剥いたりはしなかった。
「疑うのならば、俺に質問をしろ。俺がまぎれもなく『ドモン・カッシュ』本人である、ということを、きっちりと証明してみせる!」
「いえ、もう充分です。ドモン様」
ナディール姫は、静かに言葉を紡いだ。
自分が見聞きしていた通りの容姿。
『ドモン』のことをよく知っているノゾムの、この反応。
そして、ハヤブサと互角に渡り合ったその腕─────
彼は間違いなく、世界的に有名な格闘家の『ドモン・カッシュ』本人である、と、彼女も確信が持てたからだ。
「シュバルツ様も………疑ってしまって、申し訳ありませんでした。どうか、お許しください………」
そう言って、頭を下げるナディール姫。それを、シュバルツは慌てて制した。
「そんな風に頭を下げないでくれ……! 疑うのは、君の立場では仕方のないことだ」
「ですが………!」
「私は、嫌疑が晴れさえすれば、それでいいから」
そう言って、シュバルツはニコ、と、優しく微笑む。それを見たナディール姫の表情にも、ようやく笑顔が戻った。
「ありがとうございます……。シュバルツ様……」
そう言って、彼女はやはり、頭を下げる。
「ああ…………」
(頭を下げるのを、止めさせたかったのだけどな~)
シュバルツはそう思って苦笑し、姫の横でカライ内大臣も、やれやれ、と、今日何度目かの、盛大なため息を吐いていた。
「内大臣………もう、シュバルツ様の身元は証明されました。もう、疑う必要はありませんね?」
「そうですな……。問題はないかと思われます」
「良かったな、シュバルツ」
いつの間にか立ち直っていたハヤブサが、シュバルツのそばで、にこっと微笑みかける。それに対してシュバルツは、
「何だ、まだ生きていたのか」
「フ………俺にとって、あの程度の打撃、むしろご褒美だ」
そう言って不敵に笑うハヤブサに、シュバルツは「変態」と、冷たい言葉を投げつけた。
「ううう………」
真面目に心を傷つけられた龍の忍者は、座り込んで『の』の字を床に書きだしてしまう。
「いちいち落ち込むな!! 鬱陶しい!!」
シュバルツに怒鳴られたハヤブサは、「それは無理だ………」と、膝を抱えてしくしくと泣き出し始めた。
彼だけだ。
自分がこんなにも、無防備に振り回されてしまうのは。
彼が滑り込んできた、この、心の奥深い場所だけは
どうあがいても、鍛えることができないから────
「やれやれ………」
シュバルツは小さくため息を伝えると、ハヤブサのそばにつかつかと歩み寄ってきて、そのそばに膝をついた。
「そうだ、お前に伝えておきたいことがあるんだ」
小さな声で、そう言われる。
「?」
ハヤブサが顔を上げると、シュバルツはその耳元で、小さな声で囁いた。
「……………」
シュバルツのその囁きに、ハヤブサの瞳が一瞬見開かれる。
だがすぐに、彼はにやりと笑うと、「シュバルツ……」と、その名を呼びながら、彼のヒトの肩を抱き寄せた。
「?」
シュバルツは不思議そうにしながらも、そのハヤブサの動きに身を任せる。すると─────
(愛してる………)
熱く囁きながら、ふっとその耳に、息を吹きかけられるから─────
「お前は本当に……! いい加減にしろッ!!」
ハヤブサはまたも、シュバルツに散々叩きのめされてしまったのだった。
「もう私たちは、ここに用はないのだろう? ドモンもせっかく来てくれたことだし、彼にノゾムの部屋の物を見せてもいいか?」
そう言って、にっこりとほほ笑むシュバルツに、ナディール姫も苦笑するしかない。
「そうですね……。ドモン様の都合がよろしいのであれば………」
そう言って、姫はドモンの方を見る。
ドモンはまず、兄を見て、それから縋るように見つめてくる少年ノゾムを見て────頷いた。
「ああ。俺は別に構わないぞ」
「……………!」
その言葉に、それまで少し硬く強張っていたノゾム少年の表情に、ぱっと花が咲いたような笑顔が宿る。
「じゃあ、決まりだな。行こうか」
にこやかに言うシュバルツに、ドモンもノゾムも、素直に従っていた。
「ハヤブサ、お前は仕事をしっかりやれよ」
シュバルツの、多少棘を含んだ声が、執務室に響く。
「うううう……………」
シュバルツにたたきのめされたまま、突っ伏して、低く呻くハヤブサ。
「………………」
シュバルツがほほ笑みながら、ノゾムに言葉をかける。「はい!」と、少年は元気よく頷き、ドモンもそのあとに続いた。
「………………」
「ハヤブサ様? 大丈夫ですか?」
突っ伏したままのハヤブサに、ナディール姫が心配そうに声をかける。
(ううう……! ひどい……! 俺はただ、ちょっとシュバルツに、親愛の情を示したかっただけなのに……!)
そのまま、さめざめと泣き続けるハヤブサ。
本当に、ひどいと思う。
「愛している」と、伝えるだけで、
どうしてここまで、叩きのめされなければならない、と、言うのだろう。
「………俺のことは気にせず、仕事を続けてくれ……」
本当に、それだけを返すのが精いっぱいだった。
それを見ていたカライ内大臣は、やれやれ、と、ため息を吐く。
「では姫様、執務の続きを再開させましょう。これ以上の遅延は、各方面に被害をもたらしてしまいます」
「そうですね。では、執務に戻りましょうか」
ナディール姫も同意し、外で強制的に待機させられていた、文官たちも入ってくる。
「では、私もこれで。調査隊の件、手配しておきます」
そう言って、イガールは敬礼をして、踵を返す。その背中に、ナディール姫の「ありがとう」という言葉が向けられていた。
「イガール殿」
執務室から廊下に出たところで、自分を呼び止める声に、イガールが振り向く。すると、そこには龍の忍者がたたずんでいたから、彼は少し驚いてしまった。
(いつの間に……!)
彼は確かに、先程まで執務室の床に突っ伏していたはずなのに。
それに対してハヤブサは、つかつかとそばに寄っていくと、「イワンコフの持ち物の件、世話になった」と、彼に礼を言ってきた。
「いや、あの程度の手配など、お安いご用ですが………」
イガールが少し怪訝そうな顔をしながらも、そう返事をすると、龍の忍者はにやり、と、笑った。
「存外役に立った。これで、外国からの刺客の侵入は、大幅に減らせるかもしれんぞ?」
「そんなことが……!?」
驚いて息を呑むイガールに、ハヤブサは力強く頷く。
「早速手を打たせてもらう。引き留めて悪かった」
それだけ言うと、龍の忍者はまた、するり、と、執務室に戻っていく。
「……………」
イガールは暫し、呆然とそれを見送っていたが、やがて、はっと我に返ったように踵を返していた。
ノゾムの部屋に入ったドモンは、まず、そのコレクションの量に圧倒された。
(すごいな………)
壁一面に貼られたポスターや写真
丁寧にスクラップされた記事
並べられた雑誌やグッズの数々に感心する。
(俺、こんなにインタビュー受けてたっけ………)
記事を見ながら、思わず首をひねってしまうほどだ。
「キョウジも結構この手の記事は、集めているのだがな……。あいつの場合は総てデータ化しているから………」
シュバルツの言葉に、ドモンは少し驚いてしまう。
兄の部屋は、いつも研究のための書籍や書類が散乱していて、自分の記事やグッズなど、見たこともなかったからだ。
「キョウジのマグカップやタオルは、たいてい、お前関連の物なのだがな」
「えっ? そうなの!?」
驚くドモンに、シュバルツは少し苦笑してしまう。
「そうだ……。気づいていなかったのか?」
注意力がたりないぞ、と、シュバルツに軽く揶揄されて、ドモンは知らず、変な汗が出てしまう。
「私から言わせてみれば、キョウジほど、お前(ドモン)のマニアはいない、と、思っていたのだがな……。これは本当に、たいした物だ。
「そうだな………」
ドモンが感心しているところから、少し離れたところで、ノゾムははにかみながらたたずんでいる。彼は、先程からずっとこんな感じであった。
「せっかくドモン様がいらしているのに────声をかけられないのですか?」
その様子を見かねた、召使いであるメリルがノゾムに声をかけても───彼は顔を真っ赤にしながら、首を横に振るばかりであった。
「あ…………」
ドモンが不意に、軽く声を上げた。
「どうした?」
シュバルツが声をかけると、ドモンは「ああ……」と、曖昧に返事をしながら、一枚の色紙の前に歩を進めていった。
「これは………」
自分がサインした色紙の前で、足を止めるドモン。それに、ノゾムも「あ」と、小さな声を上げていた。
「この色紙………」
そう言いながら、ドモンがノゾムの方に振り返る。ドモンと視線が合ってしまったノゾムは、身を強張らせながら、知らず一歩、身を引いてしまっていた。
「怒っているわけじゃない。怯えるな」
少し、呆れたように言うドモン。
「う…………!」
なおも尻込み続けるノゾム。そんな彼の背中を、メイドのメリルが優しく支えた。
「大丈夫ですよ……。そばに行きましょう、ノゾム様……」
その背中を押しながら、ノゾムと共にドモンのそばへと足を進める。ノゾムがそばに来たところで、ドモンが再び口を開いていた。
「この色紙は………」
「う……………」
「どうした? どこで手に入れたんだ?」
「あ………う…………」
完全に舞い上がって、固まってしまうノゾム。
(無理も無いか)
その様子を、シュバルツは苦笑しながら見守っていた。
ノゾム少年は、自分が「ドモンの兄」と悟った瞬間も、こちらが心配になるぐらい、舞い上がっていたのだ。ましてや『本人』を目の前にした少年の心境は、如何ほどの物であろうか。
「………………」
ドモンはしばし、固まり続けるノゾムをじっと見つめていたが、何を思ったのか、色紙のそばに置いてあった、赤い帽子を手に取ると、おもむろにノゾムの頭に、ガボッと、かぶせた。
「!?」
思わず、びっくりして顔を上げるノゾム。それをじっと見ていたドモンが、ポン、と、一つ、合点がいったように手を打った。
「お前、あの時の子供か!」
「えっ?」
「知っているのか?」
ドモンの意外過ぎる反応に、ノゾムとシュバルツが、同時に驚いたような声を上げる。それに対して、ドモンはシュバルツの方に振り返って頷いた。
「ああ。この子のことは、少し印象に残っていたからな……。覚えていたんだ」
そう言いながら、ドモンは『あの日』のことを思い出していた。
「ドモン、今日も出待ちの子たちが、外でたむろしているわよ?」
試合の前日、ドモンは調整のために、スタジアムのトレーニングルームに、ひと汗流しに来ていた。程よく筋トレを終え、少しクールダウンをしていた時に、窓際に静かにたたずんでいた、恋人兼マネージャーでもあるレインに、そう声をかけられていた。
「毎度毎度……。奴らも飽きないもんだな。俺がここにいるって─────どこでそんな情報を仕入れているんだ」
その言葉に対して、レインは肩をすくめる。
「仕方がないじゃない。それだけ貴方は、人気があるってことよ」
「………………」
それに対して、ドモンは特に何も答えない。椅子に座り、タオルを頭からかぶって、フ~っと、大きくため息を吐いていた。持っていたペットボトルのスポーツドリンクを、一気に飲み干して立ち上がる。
「たまには、サインとかしてあげたりしないの?」
「スポンサーに頼まれた分はしている。何も問題ないだろう」
レインの言葉に、ドモンは目だけをちらり、と、動かして、ぶっきらぼうに答える。
「それはそうかもしれないけれど………」
レインは少し、唇をすぼめる。
確かに、スポンサーと、その縁故の者を大事にする姿勢は、間違ってはいない。だが、それだけでは、純粋に『ドモンを好きだ』と、言ってくれているファンの人たちと、触れ合う機会が激減してしまうように、思うのだ。
「貴方を『好きだ』と、言ってくれている人たちのことを、もう少し大事にしても、罰は当たらない、とは思うけど」
だからレインは、さりげなくドモンに忠告してみた。彼に好意的なファンとの適度なふれあいは、彼にとってもきっと、良い刺激になる。レインはそう信じているからだ。
「………………」
それに対してドモンは、特に答えを返すでもなく、窓から外を見るともなしに見ていた。丁度、地上から5階ぐらいの高さに相当する、トレーニングルームの窓からは、外で出待ちしている、と、思われる人々の姿を、よく見ることが出来た。
そこには、老若男女を問わず、色々な人々が、各々楽しそうに話しながら、手に色紙やらカメラやらを持って、懸命に出入り口付近をのぞき込んでいる。
ある意味、ドモンにとっては見慣れた光景────
だがその時、建物から車道を隔てた反対側の歩道にいた、赤い帽子をかぶった少年の動きが、ドモンの視線をなんとなく引きつけていた。
赤い帽子の少年は、彼の傍にいた少年よりも少し背の高い金髪の少女に、必死に何かを頼み込んでいる。少女は少年の言葉を聞いて、しばらく考え込むようにしていたが、やがて、一つ大きく頷いていた。
「………………」
金髪の少女は、赤い帽子の少年の前に座り、何事かを言い聞かせている。少年は、コクコク、と、2、3度頷くと、嬉しそうに建物の方に走り寄ってきて、そのままで町の集団の中へと入っていった。
「………………」
金髪の少女は、少年と話した場所でたたずんだまま、心配そうに少年の方を見つめている。
(姉弟だろうか)
二人の様子を見たドモンは、なんとなくそう感じた。
少し、年の離れた姉と弟。
それは、自分たち兄弟の姿を、ドモンの心に呼び起させた。
自分よりも大きくて、何でもできる兄。
その兄に近づきたくて
その兄の、気を引きたくて
いろいろあがいて
甘えて
駄々をこねて────
そんな俺を、兄は、いつも見守ってくれていたのに。
ちょうど、あの路地で見守る、少女のように
「……………」
ドモンは、自身のトレードマークにもなっている、赤いマントを羽織ると
無言で、トレーニングルームから、外へと出て行った。
「ドモン・カッシュが出てきたぞ!!」
意想外のその姿に、出待ちをしていた者たちは、驚きの声を上げる。それは次の瞬間、歓声へと変わり、皆がそれぞれ、手に持っている色紙やメモを振ったり、カメラを構えたりして、ドモンに自分の存在をアピールしだした。
ドモンは、差し出される色紙やメモにサインをしながら、目の端で、赤い帽子の少年を探した。
目的の赤い帽子は、すぐに見つかった。
赤い帽子の少年は、周りの人たちにもみくちゃにされながらも、懸命に色紙をこちらに向かって、差し出そうとしていた。
『差し出そうとしていた』と、言うことは、彼はうまく、それができてなどいなかったのである。実際のところは、色紙を抱きかかえたまま、右に左に、ふらふらと翻弄され続けていた。ドモンが最初から、その少年を目標にしていなければ、その存在にすら気が付かずに、終わっていたかもしれない。
ドモンは徐々に、その少年との距離を詰めると、タイミングを見計らって、少年の手から色紙を掬い取っていた。
「あ…………!」
思いっきり見開かれた、黒目がちの少年の瞳と、視線が合う。
意外に東洋系の顔立ちが、余計に、昔の自分を彷彿とさせた。
「………………」
特に声をかけるでもなく、ただ、普通にサインをする。
せめて、名前を入れてやりたかったが、この状況で彼にだけそれをするのは、あまりにも不自然すぎた。
(頑張れ)
だから、その想いを込めて、色紙の隅に、自分にしか分からない『印』を、そっと入れる。
こんな、一格闘家のただのサインに、この少年を支える力がどれほどあるのかなど、自分は知らない。
だが、サインを手渡した時の、少年の輝いた表情を見た時─────それだけでも、このサインをした甲斐はあったな、と、ドモンは思った。
「あ…………! う………!」
少年が、瞳を潤ませながら、大事そうに色紙を抱えている。
ドモンはほかの色紙やらメモ帳などにサインをしながら、しばらくその少年の様子を見守っていた。
少年は、ドモンに向かって深く一礼をすると、ファンの間に紛れて姿を消した。だが、しばらくすると、反対側の道路の歩道で、たたずんでいる少女のそばに、少年の赤い帽子が姿を現していた。
少年は、金髪の少女のそばで、嬉しそうにもらってきたサインを見せ、少女に頭を撫でられている。
少女の眼差しには、親愛の情が深く湛えられ、その唇が、「頑張ったわね」と、動いた。
それに対して少年の唇も、「お姉様」と、動く。
(やはり、兄弟か……。似てないけど)
姉は弟を思いやり、弟も、そんな姉を、まっすぐ慕っているように見える。
どうか、姉弟共に、仲のいいままで、人生を歩んでいって欲しい。
仲睦まじい兄弟を見ると、ドモンはそう願わずにはいられなかった。
自分は、それに一度失敗してしまっているから、余計にそう願うのかもしれなかった。
自分は、兄を疑ってしまった。
信じることが出来なかった。
兄は────弟である自分にひたすら、優しい人であったのに。
それを信じることが出来ずに、周りに与えられる情報に振り回されるままに、本当に、兄をこの手で殺めてしまう寸前まで行った。これは、自分の人生の中でも、最大級の大失態だと、ドモンは今でも思っている。
こんな、馬鹿みたいな失敗をするのは、自分だけで十分だ。
そう思いながら、姉弟を見守っていると、彼女たち二人の声をかけてくる、兵士風の『大人』がいた。
その兵士を見た姉弟二人の表情も、ぱっと明るい物になる。3人はその場で少し、言葉を交わした後、笑顔のまま、反対方向へと歩き出していた。
(もう、大丈夫だな)
それを見たドモンもそう感じて、彼もまた踵を返して、その場から離れ、スタジアムの奥へと歩を進めていた。
その時の話は、それで終わり。
こうして、サインをした少年とも、もう会うことはない。そう思っていたのに。
まさか、あのときのサインが、こんな風に大事そうに飾られていた、だなんて。
彼がその後も熱心に、自分のことを応援し続けてくれていた、だなんて。
一体誰が────想像しえただろうか。
「そうか………あの時の子が………」
ドモンが、赤い帽子をかぶったノゾム王子を、まじまじと見つめる。飾られているサイン色紙には、自分が入れた『印』が、確かに隅の方に、入れられていた。
「あ…………! あう…………!」
それに対してノゾム王子は、もう答えを返すどころではない。
ドモン・カッシュと、こうして身近に会えた、というだけで、もう信じられないほどの夢見心地に見舞われているのに、まさか、彼の方が、自分との邂逅の瞬間を、覚えていた、だなんて。
あまりにも信じられない『奇跡』の連続に、ノゾムの小さな心臓は、もう、爆発しそうなほどに、その鼓動を速めていた。
「このサイン、とっていてくれたのか………。そうか………」
少し照れくさなくなって、頬をポリポリと、指でかくドモン。それに対してシュバルツが、「おい、ドモン」と、声をかけていた。
「何だ? シュバルツ」
振り向いたドモンに、シュバルツは苦笑気味の顔を見せる。
「ちょっと、ノゾム王子の方を、ちゃんと見てやれ」
「えっ?」
「倒れそうになっているぞ?」
「えっ?」
「ノゾム様!?」
シュバルツの指摘に合わせて、ドモンとメリルが、同時にノゾムの顔をのぞき込む。
果たしてノゾム少年は、シュバルツの言葉通り、完全に目を回してしまっていた。そのうち、彼は立っている姿勢も、保てなくなって─────
「………………」
ふらり、と、無言のまま、少年の身体が傾ぐ。
「ノゾム様!!」
「おっと………!」
それをドモンが、慌てて支えた。
「ほえ……………」
ドモンの腕の中で、完全に目を回してしまっている少年は、か細い子猫のような声を、あげていた。
それからノゾム少年の意識が戻るまで、少しの時を必要としたのだった。
(幸せな夢を、見ていた気がする………)
まどろむ意識の中、少年ノゾムは、そう思った。
そう。
あれは夢。
自分の『願望』が高じて、都合のいい、夢を見てしまったのだ。
だって、現実にそんなこと、あるわけないじゃないか。
あのドモンが
ドモン・カッシュが
サインをもらいに行った、自分のことを
まさか、覚えていた、だなんて────
(ああ、目が覚めてしまう)
ゆるゆると、ノゾム少年は、意識の覚醒を自覚する。
目が覚めれば、きっといつもの日常が────
「おい」
「──────!!」
ノゾムの視界いっぱいに、自分をのぞき込んでくる『ドモン・カッシュ』の姿があったから、少年はかなり混乱した。
「え………? あれ………?」
「気が付いたか?」
混乱する少年に、ドモンがさらに問いかけてくる。
「覚えているか? お前は俺と話していて、急に倒れてしまったんだ」
「あ…………!」
ドモンの言葉に、ノゾムの脳裏に、今までの経緯が蘇ってくる。
「あう…………!」
信じられない心地だった。
『夢だ』と、思いこもうとしていたことが
全て、今、目の前でまさに起こっていた『事実』だったなんて。
「………………」
また、意識が遠のきそうになるノゾム。それを、ドモンが慌てて引き留めた。
「お、おい! しっかりしろ! 落ち着け!!」
「あ…………」
「ドモン」
シュバルツの声とともに、ドモンの目の前に、一つのコップが差し出される。
「水だ……。ノゾム王子に飲ませてやれ」
「あ、ああ………」
兄から受け取った白いコップを、ドモンはノゾムに差し出した。
「ほら、水だ。飲めるか?」
「あ………ありがとう、ございます………」
ノゾムはドモンからコップを受け取ると、そろりそろり、と、水を飲み始めていた。
(おいしい……)
水を飲む少年の視界には、やはり、こちらをのぞき込んでくる、ドモン・カッシュの姿がある。
(夢じゃないんだ………)
水の冷たさと喉の潤いは、少年に、少しの冷静さと、現実を直視する力を、もたらしつつあった。
「落ち着いたか?」
ドモンからの問いかけに、少年は素直に「はい」と頷く。
まだ少し、心臓は早鐘をならしていたが、話が出来ないほどではない、と、思った。せっかく、憧れの人が目の前にいるのだ。また気を失うのは勿体ないような気がした。
そのノゾムの様を見たドモンも、やれやれ、と、ため息を吐く。
「いちいち俺の姿を見て、舞い上がることはないぞ。お前だって『王子』じゃないか」
「………………」
それに対して、ノゾム少年は、少し沈んだ顔をした。
「?」
その少年の表情に、ドモンは首をかしげる。
この少年が、自分の言葉に反応して、この表情になった、と、言うことは分かるのだが、何が原因になっているのか、さっぱり見当がつかないからだ。
「…………!」
それに対して、シュバルツは少し、察するところがあった。だから、少年に問いかけていた。
「ノゾム君、一ついいか?」
「はい、何でしょう」
顔を上げる少年に、シュバルツは少し笑みを見せながら、飾ってあるサインを指し示していた。
「このサイン………」
「はい」
「君がその気になって、君の『立場』を利用すれば、もっと簡単に手に入れることが出来たのではないのか? わざわざ、ファンたちの間に交じって、出待ちなどせずとも────」
「………………!」
「そういえば………!」
シュバルツの言葉に、ドモンは改めて、ノゾムの方に振り返る。ドモンの視線の先で、ノゾムは、唇をかみしめていた。
そうだ。
ノゾムは子供とはいえ、一国の王子なのだ。
彼が、そういうルートで臨みさえすれば、ドモンのサインなど、いくらでも簡単に、手に入れることができただろうに。
それに対して、ノゾムは少し、険しい表情をしていた。
「………そういうのは、嫌だったんです」
少年は、低い声で言葉を紡ぐ。
「『王子』という立場を利用して、ドモン様からサインをもらっても………僕自身には、何も残らないような気がして………」
他のグッズとか、雑誌の記事とは、皆の力を借りても、ある意味仕方がないと思う。
だが、『サイン』だけは─────
『サイン』だけは、自力でもらいたい、と、ノゾムは願っていた。
このような想いは、自己満足の類かもしれない。だが、自分が好きになった『ドモン・カッシュ』は、おのれの身一つで、相手と戦う格闘家であった。彼の前には、すべての身分も権力も、無意味なもののように思えてならなかった。
ならば、と、ノゾム少年は願う。
自分が彼の前に立つときは、無意味な身分や権力の鎧をまとうのは、止めようと。
身分と権力に、がんじがらめになっている醜い『王子』としての自分ではなく。
普通の、一人の人間として、彼の前に立ちたかったのだ。
「ただ、ドモン様の前を、通り過ぎる存在でもいいんです。覚えてもらえなくてもいい。ただ、一人の人間として、ドモン様の前に行きたかった……。ただ、それだけなんです」
「そうか………」
ノゾムの話を聞きながら、ドモンは少し、おのれの頬をポリポリと掻いていた。
だが、ノゾムの、自分に対するアプローチの仕方は、実に正しいと、ドモンは感じていた。
もしも彼が、『王子』という立場を利用して、自分に相対していたら、自分はおそらく、この少年のことを、ここまで印象深く覚えていることはなかったであろう。自分に呼び掛ける、彼の動画を見ても、現に自分は、何も感じることはなかったのだから。
彼が、姉と仲良さそうに話をしていたから。
皆の間に入って、必死に色紙を差し出そうとしていたから。
それを、姉が遠くから、懸命に見守っていたから──────
「そういえば、お前、お姉さんはどうした?」
ドモンはノゾムに問いかけていた。
「えっ?」
きょとん、と、する少年に、ドモンはさらに、問いを投げかける。
「お前、姉さんがいただろう」
「え……は、はい…………」
「姉さんは──────」
「おい、ドモン」
弟の天然な質問に、シュバルツは少し苦笑しながらも、言葉を続けた。
「気づいていないのか? お前はもう、彼のお姉さんに会っているぞ?」
「えっ?」
「え…………!」
ドモンがきょとん、と、首をかしげるのを、ノゾムは信じられない、と、言った面持ちで見つめていた。
(冗談、を、言っていらっしゃるんだよね……? だって、さっきまで、この人はお義姉様のいらっしゃった部屋で………!)
あんなに義姉の近くで、ハヤブサと戦っていた、と、言うのに。
まさか、その存在に、気づいていなかったとでも────
対してシュバルツは(やっぱり)と、苦笑していた。
我が弟ながら、頭に血が上ってしまうと、どうにも周りに注意と関心を払わなくなるから困る。
「いいか? ドモン。ハヤブサがいた部屋は、この城の中で政治の中枢を司る、『執務室』だ」
「それぐらいわかっている!」
「なぜ分かった?」
シュバルツの質問に、ドモンは少し、鼻を鳴らしながら答えた。
「何か、女王や大臣風の偉そうな奴らが、ちょっと高級そうな席に座っていたからな! 部屋も、それなりに装飾されていた、豪華そうな部屋だったし!」
(あ、思ったよりも、周りをきちんと見ていたな)
弟の意外な観察眼に、シュバルツは少し、胸をなでおろしていた。しかしやはり─────今一つの、配慮が足りない。
「いいか? ドモン。ノゾム殿は、この国の『王子』だ」
「ああ。承知している。だからどうした」
ドモンのその言葉に、ノゾム王子は、少し複雑な表情を、その面に浮かべる。シュバルツは軽くため息を吐きながらも、言葉を続けた。
「『王子』ということは、ノゾム殿はこの国の『王族』と、言うことになる」
「ああ。当たり前の話だな」
シュバルツの言葉に、大いに頷くドモン。
「だからな? ドモン」
「ああ」
「ノゾム王子の『親族』も、『王族』と、言うことになるんだ」
「ああ。だから?」
「ドモン……。お前がいた、あの『執務室』には、誰がいた?」
「誰って………。ハヤブサの野郎と─────」
ドモンは、兄に答えながら、部屋の状況を反芻する。
「何か、偉そうな大臣と………『姫』っぽい奴と………」
「うん」
「『姫』っぽい………」
ここまで口走ったドモンが、あることに思い当たった。
「ん? 姫?」
「そう、『姫』だ」
「姫…………」
そう言ったまま黙って腕を組み、しばし考え込んでしまうドモン。
「………………」
「………………」
「………………」
沈黙するドモンを、シュバルツとノゾムが、黙って見守っていた。
しばらくの静寂の後、ドモンは、ポン、と、おのが手をたたいて顔を上げた。
「あの姫が、お前のお姉ちゃんか!」
「そうです!」
ノゾムは嬉しそうに声を上げる。シュバルツは、多少呆れたように口を開いた。
「おい、お前まさか、本当に気づいていなかったのか?」
「分かるわけないだろう? 俺の前にサインをもらいに来たときは、本当に二人ともが、普通の格好をしていたんだから!!」
シュバルツの言葉に、ドモンは慌てて言い訳をする。
自分だって、悪気があったわけじゃない。本当に、気が付かなかったのだ。
自分がしたこの「特別なサイン」と、赤い帽子がこの場になければ、自分は永遠に、この二人があの時の姉弟だと、気づくことはなかったであろう。
それぐらい、2人の格好の印象には、ギャップがあったのだ。
「そうか………。あの姫が………」
そう言いながらノゾム王子の顔を見て、ドモンが少し首をひねる。
「?」
ノゾムは、そのしぐさを怪訝そうに見ていたが、シュバルツは少し、察せられるものがあったから、さりげなく口をはさんだ。
「ナディール姫とノゾム王子は、『異母姉弟』なのだそうだ」
「そうなのか?」
少し驚いて、ノゾムの方を見るドモン。少年は、力強く頷いていた。
「はい。そうです。お義姉様と僕は、父だけが一緒なんです」
「ナディール姫様のお母さまが、病を得て、お亡くなりになられてしまったんです」
それまで黙ってそばに控えていた侍女メリルが、そっと口を開いてきた。
「もともとノゾム様のお母様………現王太后様は、ナディール姫様の母君の、おつきの侍女だったのです。それが、姫様の母君がお亡くなりになる際、後事をその方に託されて─────」
「メリル!!」
メリルのその言葉を聞いた、ノゾム王子の顔色が、なぜか変わった。
「メリル!! だめだよ!! それ以上、この話をしては!!」
叫びながら、必死にメリルにしがみつくノゾム王子。
「ノゾム様……」
「どうした?」
ノゾムの意外過ぎる行動に、ドモンは少し面くらい気味に声をかける。シュバルツも、少し驚きながらも、2人の様子を静かに見守っていた。
「駄目だよ!! メリル!! ドモン様!! これ以上、この話を聞いてはだめです!!」
「ダメって………。どういうことだ?」
対してドモンは、きょとん、としながらも、質問を重ねた。ノゾムがあまりにも切羽詰まった様子であったのが、ドモンは、とても気になって仕方がなかった。
「……………!」
対してノゾムは、ぐっと、唇をかみしめながら、メリルにしがみつき続けていた。黒目がちの大きな瞳には、うっすらと涙すら浮かんでいるように、見える。
「どうした?」
ノゾムのその様子に、ドモンは重ねて問いを投げかけていた。少年の、あまりにも切羽詰まった雰囲気が、かえって、ドモンに『捨て置いてはいけない』と、言う印象を与えていた。
「ドモン様………」
ドモンの問いかけに、メリルの方が、顔を上げる。ノゾムは、相変わらずメリルにしがみついたまま、首を横に振り続けていた。
「メリル……! もういいよ。この話はやめてほしい……!」
「ノゾム様………!」
メリルは、しがみついてくるノゾム王子をしばらく見つめていたが、やがて、静かに口を開いた。
「ですが、ノゾム様………。このままではいけない、と、言うことも、薄々感じていらっしゃるのでは、ないのですか?」
「……………!」
メリルにしがみつきながら、はっと、目を見開くノゾム。
「このまま黙っていては、きっとだめです。ノゾム様……。すべてが、ノゾム様の望まない方に、向かってしまうのではないですか?」
「でも………」
ノゾム少年は、まだ何かをためらうかのように、視線を逸らす。
「でも、駄目だよ、メリル……! これ以上話したら、きっとメリルがいなくなっちゃう………!」
「…………!」
ノゾム王子のその言葉に、ドモンとシュバルツは、同時にハッと、息をのんだ。何か、得体のしれない『闇』のようなものを、そこに感じた。
「メリルまでいなくなったら、僕は………!」
「ノゾム様………」
その主従の様子を見て、ドモンは声をかけようとする。しかし、それに、自分の中の何かが、一瞬「待った」をかけた。
待て
いいのか?
この子の抱えている『闇』は、きっと、簡単なものではない。
踏み出した最後、自分もそれに、巻き込まれてしまう可能性が大だ。
それでもいいのか?
それでも─────
「………………」
(愚問だな)
ドモンは、そんなことを考えた己に、少し失笑をした。
小難しいことを、自分の単純な頭で考えたって無駄だ。
年端も行かぬ少年が、切羽詰まった顔をして、追い詰められている。今の状況を、放置しておくことの方が、きっと問題なのだ。これをこのまま黙って見過ごしてしまうことなど、自分にはできない。
これに自分が首を突っ込んだことで、何か不具合が起こるのならば、それはまたその時に、考えればいいだけの話だ、と、思った。
「メリル」
「はい、ドモン様」
ドモンに声をかけられて、メリルは顔を上げる。それに、ドモンはさらに言葉を続けた。
「何を話そうとした? 言え」
「え…………」
「ドモン様!?」
「……………!」
ドモンのその言葉に、その場にいた三人から、それぞれ驚きの声が漏れる。それには構わずに、ドモンはさらに言葉を紡いだ。
「俺の力を借りたいのだろう?」
こちらの望みに、一直線に切り込んでくるドモンの言葉に、ノゾムとメリルは思わず目を見開く。
「ドモン………!」
シュバルツは、軽く動揺していた。
まさか、ドモンの方が、ノゾム王子の抱える『闇』に、こんなにも一直線に切り込んでくるとは、思ってもいなかったからだ。
兄として、「弟を、止めなければ」と、シュバルツは思った。
ドモンが踏み込もうとしている問題は、そう簡単に第三者が係っていいものではない。
国の権力争いに巻き込まれて、下手をすれば、命を落としてしまう可能性だってあるからだ。
生半可な想いで、首を突っ込もうとしている、というのなら────それに歯止めをかけるのが、兄の役目だと思った。
「おい、ドモン……!」
呼びかけるシュバルツに、ドモンはちらりと視線を走らせると、それを遮るかのように口を開いた。
「止めるなよ、兄さん………!」
「………………!」
「俺の方に、迷いはない」
静かに、そう言い放つ。
助けを求めている、このノゾム王子と侍女メリルに、手を差し出すこと─────少なくとも、自分に迷いやためらいはなかった。
彼らの救難信号を、見過ごしてしまうことの方が、きっと、自分の中では悔いが大きく残る。ドモンは、そう、確信していた。
そして、何よりも─────
ドモンはちらり、と、こちらを心配そうに見つめているシュバルツの方に、視線を走らせる。
人が良すぎる兄。
優しすぎる兄。
兄さん、貴方こそ───
貴方こそが、願っているのではないのか。
この主従に、手を差し伸べたいと
手を差し伸べてほしいと─────
ここに、自分と兄の間に、意見の違いはない。
「無い」と、確信しているからこそ、自分は一歩を踏み出すのだ。
「………ノゾム様を、お守りくださる、と、言うのですか?」
メリルの言葉に、ドモンは力強く頷く。
「……………!」
信じられない、と、主従は同時に目を見開いた。
「では、ドモン様────」
メリルがドモンに一歩、踏み出そうとする。そこに、ノゾムが必死の形相でしがみついてきた。
「だめだよ! メリル!! 『助け』を求めれば、メリルが────!!」
「ノゾム様………」
メリルは穏やかにほほ笑むと、しがみついてくるノゾム少年の頭を、そっと優しくなでていた。
「ノゾム様……。私はもう、いいのです。それよりも、手を差し伸べてくれる人がいるのならば、その手を取るべきです」
「でも……! メリル………ッ!」
「いったいどうした?」
それまでことをの成り行きを静観していたシュバルツが、主従に向かって口を開いていた。
「メリル……。君はのその眼差しは、死を覚悟した者のようだな」
「………………!」
シュバルツのその指摘に、ドモンとノゾムが、同時に驚いてメリルの方を見る。皆の注目を浴びたメリルは、困ったように─────しかし、穏やかに、微笑んでいた。
「………『ノゾム様付きの侍女』になってから、私は実は、まだそんなに日が経っていないんです。『前任者』がいて────」
それは、メリルも尊敬していた先輩にあたる侍女だった。だがある日、その侍女は突然行方知れずになった。
王太后に命じられるままに、今の部署に配置になって、そこに待っていたのは、部屋の隅で怯え切ってしまっていた、ノゾム少年の姿─────。
(このままではいけない)
もともとまじめで、誠実に仕事に取り組む彼女は、ノゾムにかいがいしく仕えながら、彼の心を解きほぐすことに専念する。
そして、ノゾム王子の『信頼』を勝ち得るごとに、見えてきた。
ノゾム王子の前途に、広がりつつある巨大な『闇』が。
その『闇』が、先輩を『殺した』可能性が─────
「誰にも言わないで………!」
ノゾムが、メリルに初めて『助け』を、求めてきた夜に、少年は泣きながら、彼女に訴えかけてきた。
「誰かに言っちゃうと、メリルまで、いなくなってしまう………!」
「ノゾム様………!」
「メリルまでいなくなってしまったら、僕ば………!」
「……………!」
「ごめんなさい、メリル………! 話してしまって、ごめんなさい……! 助けを求めてしまって、ごめんなさい………!」
そのまま、しがみつきながら、「ごめんなさい、ごめんなさい」と、何度も謝罪を繰り返す、少年。
「……………!」
なぜ、このようなことで、年端も行かぬ少年が、何度も謝らなければならないのだろう。
その理不尽さに、憤りのような感情を、メリルは胸の奥底に感じていた。
だが、だからと言って、ノゾム王子を取り囲むこの事態に、自分は、何ができるというのだろう。
何も────何もできないではないか。
ノゾム王子のために、何かをしようとしても、無力な自分は、先輩と同じ末路を歩んでしまうことが、目に見えている。
メリルは、ぐっと、己が唇をかみしめるしかなかった。
(せめて、ノゾム様が穏やかにお過ごしできるよう、私は尽力をしよう)
そう決意を固めて、ノゾム王子と接する日々。
しかし、彼を取り巻く状況は厳しく、少年の笑顔は、徐々に失われつつあった。
それを黙って見ているしかない自分が、メリルはどれほどふがいなかったか────
だが今、目の前に、ノゾムに手を差し出してくれる、屈強な戦士がいる。
ならば、もう迷うことはない。迷ってはいけない。
この少年の瞳が、これ以上、悲しみに曇らなくて済むのなら─────その手に、少年を掴まらせるべきなのだ。
それをして、自分が、例えどうなってしまったとしても。
「『行方不明』………君は、単純に『失踪』とは考えていない、と、言うことか?」
シュバルツの問いかけに、メリルは「はい」と、頷いた。
「私が尊敬していた先輩は、何の理由もなしに、ノゾム様のおそばを離れるような方では、ありませんでしたから………」
「メリル………!」
必死にしがみつくノゾム少年をなだめるように、メリルは微笑んだ。
ある日、突然失踪してしまった先輩。
家にも帰っていない。
何か、置手紙のようなものもない。
本当ならば自分は、血眼になって、彼女の存在を探さねばならないのだろうが────
探すことすら、できなかった自分。
それが、自分の限界─────
そう悟ってしまったが故に、無力さと、絶望が募った。
だから、自分はもういい
もう、いいのだ。
メリルは覚悟を決めて、ゆっくりと口を開いた。
「そう………王太后様は─────」
次の瞬間、メリルの目の前に、白銀の煌きが走る。
すぐそばで、カツン、と、小さな金属音が響き、気が付けば自分のすぐ後ろに、シュバルツの背中があった。
「え…………」
「兄さん!!」
呆然とするメリルを背に庇うかのように、シュバルツが立つ。その手には、短刀が逆手に握られていた。
「この殺気……。確かに、ただ事ではないようだな………!」
シュバルツがそう言って、不敵に笑う。
「確かにな」
ドモンも、静かに賛同していた。
現に耳が痛くなるほどの殺気が、この部屋に充満している。
(気に食わんな………)
ドモンも、油断なく辺りを見回していた。
何か、仄暗い『悪意』に満ちたような殺気が、周りに充満している。しばらくそのまま身構えていると、どこからともなく、不可思議な『声』が響いてきた。
………女……。それ以上しゃべるな………
声は、暗いが、どことなく高圧的な響きを含んで、あからさまな脅しをかけてくる。
「………………!」
メリルとノゾムが、同時にその身を硬くして息をのむ。すると、ドモンが、ふっと鼻で笑いながら、口を開いた。
「メリル。構わん。続きを言え」
「え………!」
「で、でも………!」
戸惑う主従に、ドモンはさらに言葉を続けた。
「言え。向こうが『言うな』と言うのなら、なおさらだ」
───女、しゃべることは許さん。
そう言いながら、どこからともなく『影』が、部屋の中に侵入してくる。その影は、黒い装束を身に纏い、顔には白い面のようなものが貼りついていた。黒くくりぬかれた目が、三日月のように湾曲し、見る者に、異様な圧と、恐怖を与えていた。
───話せば、命が無くなる、と、知れ。
いつの間にか、複数の『影』たちが、周りを取り囲んでいる。
「ひ…………!」
メリルに縋り付いているノゾムが、小さな悲鳴を上げる。
「ノゾム様……!」
メリルがそんな王子を案ずるかのように、抱きしめ返していると、ドモンがその主従を背に庇うように立ちながら、なおも言い放っていた。
「構わん! 言え!! あの時兄さんが守らなければ、お前はとっくに命はないんだ!!」
「──────!」
ドモンの言葉に、メリルははっと、息をのんでいた。
「ドモン!! 来るぞ!!」
シュバルツの、鋭い叫び声が上がる。それと同時に、影たちが一斉にドモンたちに襲い掛かってきた。
「吻!!」
ドモンはためらうことなく、まっすぐにその拳をふるう。
ドゴォッ!!
派手な音を立てて、相手の腹の付近にめり込んだその拳は、ドモンに『あること』を伝えてきた。
(……………!)
それに気づいたドモンは、一瞬目を見開く。だがすぐに丹田に力を入れなおし、もう一段強い拳を、相手の腹に叩き込んでいた。
「ギャッ!!」
小さな悲鳴を上げた黒装束の者は、腹からバラバラに破壊されて、その塵が四散した。
「兄さん!! こいつら、人間じゃない!!」
拳に伝わってきた、人間ではあり得ぬ手ごたえに、ドモンはシュバルツに、注意喚起のための叫び声をあげる。
「そうらしいな!」
シュバルツも、逆手に構えた刀で、敵を切り裂きながら、ドモンに短く応える。シュバルツに切り裂かれた黒装束の者も、ばらばらに砕け散りながら、消えて行っていた。
(手応えが、軽すぎる)
シュバルツは、敵を切り裂きながら、思う。まるで、影を斬っているかのようだ、と。
(まさか……『術』?)
この、唐突な現れ方といい、手応えの軽さといい、数の多さといい─────
周囲にこれだけの妖の物たちが潜んでいたはずなのに、自分たちがまるでその気配に気づかなかった、とは、考えにくい。
それよりも、『術者』があらかじめこの部屋に『何か』を仕込んでいて、何かのきっかけで『術』が、発動するように仕組んでいた、と、考える方が、むしろ自然だった。
「うざったい!! なんだこいつらは!?」
倒しても倒しても、次から次へと群がってくる敵に、ドモンも少し辟易気味になっている。そんなドモンに向かって、シュバルツは叫んでいた。
「ドモン!! これは、何かの『術』の可能性がある!!」
「『術』だとぉ!?」
おうむ返しに叫ぶドモンに、シュバルツは頷いていた。
「気配を探れ! ドモン!!」
「兄さん!!」
「どこかに─────『術』の源があるはずだ!!」
(術の、気配……!)
ドモンは兄の助言に従って、戦いながら周りの気配を探る。
群がる悪意。
そのどす黒い気配を蹴散らし続けていると、確かに、悪意の流れのようなものを感じる。
(……………!)
ドモンは本能的に、流れが淀み、固まっている場所に拳を打ち込んでいた。
「でりゃっ!!」
打ち込まれた拳が、闇を払い、悪意を吹き飛ばす。その瞬間、シュバルツの視界に、小さな『光』が飛び込んできた。
「そこっ!!」
すかさずシュバルツの小太刀が、光に向かって飛ぶ。捕らえた、と、思った刹那、その光は『鳥』の形に姿を変えた。小太刀は鳥の尾羽をわずかにかすめ、ガツン、と、音を立てて壁に突き刺さった。
「しまった!」
シュバルツが叫ぶと同時に、ドモンの赤いマントが宙に舞う。
「でぇい!!」
ドモンの放った拳は、過たずにその鳥を捉え、砕いていった。
その刹那、部屋を覆い尽くしていた影が消え────ノゾム王子の部屋は、元の平穏な状態へと、戻る。
「あ……………!」
呆然と立ちすくむ主従に、ドモンは振り返り、ぶっきらぼうに問いかける。
「おい、怪我はないか?」
「は、はい…………」
少し、うわずった声で答えるメリル。ノゾム王子は、暫し惚けたように、ドモンの方を見つめていたのだが。
「………………」
ノゾム王子は、そのまま無言で昏倒してしまっていた。
「ノゾム様!!」
メリルがその身体を、慌てて支える。
「ノゾム様……! しっかりなさって下さい……!」
メリルが懸命に呼びかけるが、ノゾム王子からの返答はない。ただ、その胸が穏やかに上下をしていたから、彼は気を失ってしまっているだけなのだと、知れる。
(無理も無いか)
シュバルツは思った。
この少年の周りには、あまりにも色々なことが起こりすぎている。年端もいかぬ王子の心は、それに対処しきれなかったのだろう。
「少し、休ませてやった方がいい」
だからシュバルツは、メリルにそっと声をかけた。
「見たところ、王子の顔色は悪くないし、呼吸も穏やかだ。単純に、気を失っているだけだろうから」
「は、はい……!」
メリルたちは、ノゾム王子をベッドに寝かしつけることにした。
「ところで、先程君は、何を話そうとしたんだ?」
ベッドの上で、昏々と眠り続けるノゾム王子を見つめ続けるメリルに、シュバルツは声をかけた。
「今なら、何も邪魔は入らない。ノゾム王子に聞かせることもない……。話しやすいのではないのか?」
シュバルツの言葉に、ドモンは顔を上げてメリルの方を見る。メリルも「あ……」と、小さな声を上げた。
「良ければ、話してくれないか?」
「分かりました」
メリルは、覚悟を持って頷いた。
もう、話すはずのことであったのだから、それをして、自分がどうなろうとも、もう、悔いはないと思った。
「今の王太后様は、先程も申しあげたとおり、前の大后様にお仕えしていた侍女だったのです。大后様が病気でお亡くなりになるときに、今の王太后様に、後事を託されて────」
後事を託された侍女の名は、『ミヤコ・ユラ』と、言った。
彼女は一時期、ナディール姫の侍女も務めていただけあって、姫ともとても仲が良かった。
父王から、『彼女を后に迎える』と、告げられた時も、姫は喜んで二人を祝福し、2人を本当の両親のように慕った。ミヤコもまた、姫を自分の子供のように可愛がっていた。
やがてミヤコと王の間に、子供を授かる。それが、ノゾム王子だった。
王太后となったミヤコに、初めてできる『実の子』
王位継承権が絡んでくるだけに、誰もが、ナディール姫がどうなってしまうのか、心配をしたものだが────
この王家には、そんな心配は杞憂だったと、人々はすぐに悟ることになる。
王妃と姫は仲睦まじく、まるで本当の母娘のように、ノゾム王子の成長を見守っていた。
このままずっと平穏に、王家の時は流れていくのだと、誰もが信じて疑っていなかったのだが。
「私がここに来るようになった時には、もう、王太后と姫様の間には、かなりぎすぎすした空気が流れていました。だから、先輩にこの話を聞いた時、にわかに信じがたくて……」
「………………」
メリルの話を、ドモンはきょとんとした表情で、シュバルツは複雑な面持ちで聞き続けていた。
(なるほど……それで、ノゾムとあのお姉ちゃんは、「似ていないな」と、思ったんだな……。しかし………)
ドモンは思った。
自分などは単純だから、『家族は仲良くあってしかるべきだ』と、思ってしまうのだが、『血がつながっていない』と、言うだけで、ここまで家族仲はこじれてしまうものなのだろうか? それとも、『王家の権力』みたいなものが、人の心を捻じ曲げてしまうものなのだろうか?
(分からん………)
うう~~~ん、と、考え込むドモンの横で、メリルは、眠り続けるノゾム王子の顔を、少し哀しげに見つめていた。
「私は……ノゾム様付きの侍女を王太后様から命じられた時、こう言いつけられていたのです。『ノゾムを、ナディール姫には近づけるな』と………」
「………………!」
メリルのその言葉に、ドモンとシュバルツは、同時に息をのむ。
「私は最初、王太后様に命じられるままに、ノゾム様を姫様から遠ざけようと試みました。しかし、ノゾム様の方が────」
「いやだ!! お義姉様近づいては駄目だなんて、絶対に嫌だ!!」
メリルの言葉に、いやいや、と、首を振りながら、ノゾム王子は反論してきた。
「でもノゾム様………! これは母君様からの────」
「うそだ!! お母さまが、そんなことを言うはずがない!!」
「ノゾム様………!」
「だって、お母さまが言ったんだ!!」
涙ながらのノゾム王子の大声が、部屋に響く。
「『お義姉様と、仲良くしなさい』って……! それが、お父様とお母様と、お義姉様の母君様の望みだから………。それが、みんなの幸せに、つながっていくのだから……!」
「ノゾム様……! でも」
「『お義姉様は、命がけで僕を守ってくれるから、貴方も大事にしなければいけない』と、そう僕に言ってくださったのは、お母さまなんだ!!」
「……………!」
ノゾム王子のその言葉に、メリルはただただ、呆然とするしかない。そんなメリルの目の前で、少年の瞳から、大粒の涙が零れ落ちていた。
「ねえ、どうして………? どうして、お母さまは、僕にそんなことを言うの……? 僕は、どうすればいいの……? 何を信じたら、いいの………?」
少年のその問いかけに、メリルは、返す答えを持たない。
「怖い……! 怖いよ……! 周りの大人たちが………! お母さまが……! 僕は、怖い………!」
「ノゾム様………!」
メリルの呼びかけに、少年は、急にハッと、我に返ったような表情になった。
「待って……! 違うよ、メリル……! 今の言葉は忘れて……! 僕は、大丈夫だから………!」
「ノゾム様………!」
「僕は、本当に大丈夫………」
「………………」
そう言って、一つも大丈夫じゃないような表情で、『大丈夫だ』と、言い張り続ける少年に、メリルは何が言えただろう。
「承知いたしました」
メリルは、静かに頷いていた。そして、できうる限り穏やかにほほ笑んだ。
「大丈夫ですよ、ノゾム様。私は、何も聞いてはいません」
「メリル……!」
「ですからノゾム様……。どうか、私のことはお気になさらず、今まで通りにお過ごしください」
少し驚いたようにこちらを見つめてくるノゾム少年に、メリルは静かに頷いていた。
「私は今まで通り────ノゾム様に、お仕えするだけですから」
その言葉通り、メリルは、ノゾムに忠実に仕え続けた。
ノゾムが希望すれば、ナディール姫の元に通うことを、メリルは取り立てて止め立てはしなかった。
姫と、普通の姉弟のように、仲良くし続けたい─────
それが、ノゾム王子のたっての願いだと、メリルはもう、悟ってしまっていたからだ。
だから、自分はそれを邪魔しない。できうる限り、それを忠実に助け続けるために、動く。
そう決意して、メリルはその通りに行動し続けていた。
「まあ……! また、ノゾムを姫などに会いに行かせて………! 貴女は何を考えているの!?」
時折、王太后から、チクリ、と、嫌味を言われたが、メリルはそれを、柳に風と受け流していた。
「申し訳ございません。以後、気を付けます」
謝罪をする気のない謝罪で、頭を下げ、王太后に取り繕いの姿勢を見せる。そのまま王太后は、ノゾムの方にも、何か、言葉を投げつけるかと見守っていたが─────
「………………」
意外にも、王太后は、ノゾムの方をじっと見ているだけで、それ以上彼に、何か声をかけるでもなかった。そして、そのまま立ち去っていくことが、間々あった。
不思議なこともあるものだ、と、メリルは思った。
どうして、ノゾム王子自身には、王太后は、きつい言葉を投げつけないのだろう?
やはり、『自分の実の子供には、嫌われたくない』と、言う『母親』としての心理が、彼女に働いているからなのだろうか。
「………どうして、王太后様が、姫様に辛く当たり、ノゾム様を遠ざけようとなさっているのか、私にはわかりかねます……。人の心は移ろいやすい物、と、よく言われてもいますが……」
メリルは、王太后の話をしながら、首をひねるしかない。
王家とは
王家を取り巻く『権力』とは─────
こんなにも容易く、人の心を歪めてしまうものなのだろうか?
もしかしたら、王太后の周りに、心を歪めてしまうだけの『異常事態』が、起きているのかもしれない。
でも、それを調べるには、自分はあまりにも非力すぎたし、危険すぎた。
「もう、本当に────ノゾム様のために、私はどうすればいいのか……。どうして差し上げるべきなのか………」
ベッドの上で眠り続けるノゾムを見つめ続けるメリルの瞳に、光る物が宿る。
本当に、ノゾムのために何も出来ない自分が、歯がゆくて仕方が無かった。
「メリル。すると君は…………」
それまで黙っていたシュバルツから声をかけられる。メリルは「はい」と、顔を上げた。
「君は………王太后の周りを、調べてみるべきだ、と、思っているのか?」
「は、はい………」
メリルは、少し躊躇いながらも頷いた。
「どうして、そう思うんだ?」
少し不思議そうに問いかけてくるドモンに、メリルは少し、困ったように微笑んだ。
「先輩から聞いた話と、今の王太后様の態度が、あまりにも違いすぎたから────だから、知りたくなったんです。王太后様と姫様の間に、一体何があったのか……。王太后様自身に、一体何が起きているのか………」
そう。
おそらく先輩は、それを調べようとしたに違いない。
そして、帰らぬ人に────
「そうか………」
シュバルツは、しばらく腕を組んで、何かを思案するかのように瞳を閉じていたが、やがて顔を上げた。
「分かった。メリル………話してくれてありがとう。後は、私たちに任せてくれないか?」
「え………?」
少し驚いたように顔を上げるメリルに、シュバルツはにこりと、微笑みかけた。
「きっと、この先は、私やハヤブサの領分なんだ」
「……………!」
「君の言う通り、王太后の周囲は、一度きちんと調べておいた方がいいのかも知れないな……。姫を取り巻く問題を解決する糸口も、もしかしたらつかめるかもしれない……」
「では……! ノゾム様や姫様や、王太后様のために、お力添えいただけるのですか?」
縋るように聞いてくるメリルに、シュバルツは力強く頷いた。
「元よりそのつもりだ。私もハヤブサも、そのためにここにいるのだから───」
「兄さん」
シュバルツのその言葉が終わらぬうちに、ドモンが声をかけてきた。
「どうした? ドモン」
問い返してくる兄を、ドモンはまっすぐ見つめ返す。
「兄さん。俺も、ここに残ってノゾム王子の護衛についてもいいか?」
「……………!」
シュバルツは、かなり驚いたように瞳を見開き、メリルもかなり驚いたように「いいんですか!?」と、ドモンに問いかけてきた。
「ああ。乗り掛かった舟だ。俺もできれば、ことの顛末を見届けたい」
「しかしドモン……。お前にはお前の仕事があるはずだろう」
シュバルツの言葉に、しかしドモンは頭を振った。
「しばらくは、大きな大会も、試合もない。俺がここにとどまっても、問題はないと思う」
「それは、そうかもしれないが………」
シュバルツは、少し戸惑ってしまう。
確かに、ドモンがノゾム王子の護衛についてくれる、というのならば、正直、これ以上心強いこともないのだが─────
(しかし、何故だろう)
弟の行動が、シュバルツは少し疑問だった。
なぜ、ドモンは、ノゾム王子に、そこまで肩入れをするのだろう?
『自分のファンだから』と、言うだけでは─────少々、思い入れが過ぎているような気もするのだが。
「う………ん…………」
ここで、ノゾム王子が軽く身じろぎをする。どうやら、意識が戻ってきたようだった。
「あ………。僕、は…………?」
ゆるゆると、ベッドの上で身を起こす少年に、メリルが「ノゾム様」と、案ずるように駆け寄っていた。
「ノゾム様、大丈夫ですか? どこか痛いところは、ございませんか?」
「あ……うん………。大丈夫………」
少し戸惑いながらも、特に身体に異常は感じなかったので、ノゾムは正直に答える。その少年の前に、ドモンが歩み寄っていた。
「ドモン様……」
少し驚いたように、顔を上げる少年を、ドモンは真正面から見つめる。
「おい、倒れる前のことを、お前は覚えているか?」
「え………? あ…………!」
少し戸惑ったように、ノゾムは声を上げたが、すぐに、はっと、息をのんでいた。どうやら、何があったのか思い出したらしい。
「て、敵は……? みんなは、大丈夫だったの………?」
「大丈夫だ。あの程度の敵にやられるほど、俺たちは弱くない」
ノゾムの案ずるような言葉に、ドモンはきっぱりと言葉を返す。
「それよりも、ノゾム。お前に、確認しておきたいことがある」
「は、はい……。なんでしょう」
少し戸惑い気味に見上げてくる少年に、ドモンは、おもむろに口を開いた。
「お前、姉さんを好きか?」
「えっ?」
「姉さんのこと、大切に思えるか? 信じることが、できるか?」
「もちろんです!」
ドモンの質問の意図が分からなくても、ノゾムは正直に、きっぱりと言い切った。
「僕は、お義姉様が大好きです! お義姉様のことは、信じられるし、信じたい、と、思っています!」
これは、ノゾム王子の中では譲れぬ想い、譲れぬ願いだった。誰に何と言われようとも───
義姉を、悪く思いたくもなかったし、疑いたくもなかった。
「そうか」
ドモンは短くそう言うと、ノゾム王子の直ぐ目の前に膝をついて座る。きょとん、と、瞳をぱちくりさせている少年の手を、そっと取った。
「なら、お前はそのまま────その想いを貫け………!」
「え…………!」
「ドモン様………!」
ドモンの言葉に、ノゾムとメリルは少し戸惑う。そんな二人に、ドモンは更に、言葉を続けた。
「お前がそれをするのなら、俺は、全力でお前を支えるから────」
「ド、ドモン様………!」
ノゾムは少し、『信じられない』と、言ったような面持ちで、彼の言葉を聞き、握られている手を見つめていた。
「何故…………!」
このドモンの行動と言葉は、自分には過ぎた物のように、ノゾム少年は思えた。だから、問い返さずにはいられなかった。
何故
何故
何故なのか、と………。
それに対してドモンは、少し、自嘲的な笑みを、その面に浮かべていた。
「俺は、そうやって信じることが、出来なかった事があるから」
「……………!」
そのドモンの言葉に、それを傍で聞いていたシュバルツの方が、はっと、息を呑んでいた。
「俺は昔、とある「事件」に巻き込まれた時………俺は、周りから『兄が犯人だ』と、聞かされ、そう思い込まされていた………」
「ドモン様………」
ドモンの話を聞きながら、ノゾムは、思い当たることがあった。
ドモン・カッシュが高名な格闘家になる前───世界を揺るがした、ある一つの『事件』が起きた。
ただ、その『事件』には、『緘口令』が布かれているのか、ノゾムがその事件について調べようとしても、詳しく知ることはできない。しかし、どうも、ドモンの身内が事件の中枢にかかわっていたらしい、ということだけが、うっすらと確認することができる程度だった。
故に、その事件でドモンがどのような想いをし、どのような体験をしたのか、ノゾムは、うかがい知ることができない。けれども、今、こうして目の前に立っている『ドモン・カッシュ』という格闘家は、ノゾムにとっては、間違いなく憧憬の対象であることに、何ら、変わることはない、と思った。
たとえ、ドモンから、どのような過ちや後悔を、告白されたとしても─────
「俺は、周りから与えられる偽の情報のままに、兄を疑い、諸悪の根源として、この手で殺そうとしていたんだ………」
「え…………!」
「おい、ドモン………!」
少し、驚いて小さな声を上げるノゾム。シュバルツもドモンに向かって、一歩、踏み出そうとする。
しかしドモンは、そんなシュバルツの動きを手で制して、なおもノゾムに語り続けた。
「俺は、今でもそのことを後悔しているんだ……。なんて、未熟だったのだろうって」
そう。
自分は、知っていたはずなのに。
自分の兄は、優しくて、信じるに足る存在である、と。
幼いころから、十分に、分かっていた、はずなのに。
信じられなかった。
信じきれなかったのだ。自分は。
周りの『偽の声』に、簡単に、振り回されてしまっていた。
後悔だけが、ただ残った。
「俺は、お前にはそんな想いはしてほしくない、と、願っている………」
ドモンの脳裏に、サインをもらいに来ていたときに見た、ノゾム王子とナディール姫の、仲睦まじく微笑みあっていた姿がよぎる。
もしも、その姉弟を、誰かの明確な『悪意』が踏みにじり、その仲を引き裂こう、と、言うのなら。
(許さん………!)
ドモンは何時しか、己が拳を強く握りしめていた。
理不尽に振り回される兄弟の悲劇など─────自分たちだけで、十分だ。
「お前は姉さんを、信じ続けていろ!」
「ドモン様………」
「信じ続けることの方が、実は難しい……。俺はそれを、知っているから……」
「……………!」
しばらく、呆然とドモンを見つめていたノゾム王子であったが、やがて、はっと、我に返ったかのように、小さく息をのむと、「分かりました」と、こくりと頷いていた。
義姉を信じ続けること─────それはそのまま、自分の望みでもあったからだ。
「よし」
ドモンもノゾムに頷き返すと、兄の方にくるり、と、振り返った。
「と、言うわけで兄さん。俺はしばらくこいつのそばに─────って、あれ? 兄さん?」
シュバルツの方に振り返ったドモンが、変な顔をする。
それもそのはずで────ドモンの視線の先のシュバルツは、彼らに背を向けて、その肩を震わせていたからだ。
「うううう………」
気のせいではなく、瞳からきらりと光るものが、零れ落ちている。
「兄さん?」
「わっ? ドモン!? 急に声をかけてくるな……!」
シュバルツは慌てふためいていたが、完全に不意を突かれた格好になっているのは、誰の目にも明らかだった。
「兄さん……」
「ちょ、ちょっと待ってくれ、ドモン。もうちょっとで落ち着けるから……」
その言葉とは裏腹に、シュバルツが落ち着くまで、もう少しの時間を、必要としたのだった。
「それにしても、ドモン………」
「何だよ、兄さん」
少しぶっきらぼうに答えてくる弟に、シュバルツは少し、感慨深い笑みを見せた。
「嬉しいよ……。お前はちゃんと、他人を思いやれる、優しい人間に育っているのだな………」
「な…………っ!」
兄からの不意打ち的な言葉に、今度はドモンの方が、顔を赤らめねばならなくなった。
「た、他人を思いやる、なんて、当たり前の話だろう……! そんな改めて言うほどのことでもないはずだ……!」
「そうだけどな……」
慌てるドモンを、シュバルツは優しく見守っている。ドモンは、少々の居心地の悪さを感じていた。
「と、とにかくだ……!」
ドモンは、一つ、大きく咳払いをした。この妙な空気を変えるには、話題を変えるのが、一番手っ取り早いのだ。
「俺はしばらく、ノゾム王子の傍に滞在させてもらう。文句はないだろう? シュバルツ」
「ああ。お前がいてくれるのなら、私としても願ったり叶ったりだが────」
シュバルツの方が、少し思案するような表情を浮かべる。それに、少し思い当たるところのあったメリルが、口を開いた。
「少なくとも、王太后様と、姫様の許可がいるでしょうね」
「許可か………」
ドモンが考え込む横で、ノゾム王子も何かを思案するような顔をしている。それを見たシュバルツが、少し苦笑しながらも口を開いた。
「とにかく、私はハヤブサのところに行って、事のあらましを話してくる。ドモン、ノゾム王子のことは頼んだぞ」
「分かった」
ドモンが頷くのを確認してから、シュバルツの姿が、部屋からふっと消える。後には、ノゾム達三人が残された。
「あの、ドモン様」
しばしの沈黙を、ノゾムの声が破る。
「どうした?」
振り返るドモンに、ノゾムは少し逡巡してから、再び口を開いた。
「あの……。もしも、ここにドモン様が滞在して下さるのならば……お願いしたいことが、あるのですが……」
「願い?」
きょとん、と、目をしばたたかせるドモンに、ノゾムは深く頷いていた。
「…………!」
ノゾムの部屋で発動した『術』の気配────それは、執務室にいたリュウ・ハヤブサにも、当然の如く伝わっていた。
(何が起きているか、確かめに行くか………?)
ハヤブサは一瞬そう考えるが、直ぐに思いとどまった。
(いや、ダメだ。ここには、ナディール姫がいる……)
ノゾムの部屋で発動した『術』が、こちらに対する陽動の目的も、十二分にあり得る話だ。それに、ノゾムにはシュバルツとドモンがついている。あの二人が揃っていて、敵に後れをとるなど、まず、あり得ないだろう。
「………では姫様。ラナン地区への視察を行う予定で、話を進めてよろしいですか?」
カライ内大臣の声で、ハヤブサははっと我に返る。
「ええ、お願い」
姫がそう答えながら、手元の書類にペンを走らせている。どうやら、目の前の閣議が終わりを迎えるようであった。
(しかし……『蜘蛛』だと………?)
書類を片付けるナディール姫を見守りながら、ハヤブサはシュバルツに言われたことを思い出していた。
─────キョウジが言っていた。あの姫の肩には、大きな蜘蛛が乗っていると
「………………」
ナディール姫の護衛に着いた初めのころに、城の様子を探ろうとして、あまりにも城の中の『術』の気配が強すぎて、断念したことを思い出す。
探るために『気』を込めて、一瞬見えたのが、『蜘蛛の糸』のイメージ。
一人でこの城で、ナディール姫の護衛をせねばならなかったときは、最低限の蜘蛛の糸を払い、姫の安全のみを、最優先として、行動するよう心掛けてきたが─────
今は、シュバルツも、そして、不本意ながらも、ドモン・カッシュもこの城にそろっている。こちらも戦力的には、充実してきていることになるのだ。
(仕掛けるか………?)
ナディール姫の身体から『蜘蛛』を取り除くのは、おそらく簡単だ。だがそれは、敵方に直接打撃を与えることになり、そこから思わぬ形で術と悪意を連鎖させ、城の者たちや姫を、危険にさらすことになりかねない。
それでもいずれはその『悪意』とも戦わねばならない。それは、紛うことなき事実であった。
「………………」
ハヤブサがそうやって思案をしていると、いつの間にかナディール姫が、目の前に立っていた。
「ハヤブサ様、参りましょう」
姫にそう声をかけられて、ハヤブサはおとなしく後に従うことにした。
「明後日に、ラナン地方に参ります。ハヤブサ様、ついて来てくださいますか?」
「それは構わないが」
歩きながらハヤブサは、ナディール姫に問いかけていた。
「ナディール、一つ聞いてもいいか?」
「はい、なんでしょう?」
「ラナンというのは、そんなに大事なところなのか? お前が直接出向かねばならないほど──────」
「ええ。そうです。ハヤブサ様」
ナディール姫は、迷わず即答していた。
「前にも少し話したと思いますけど、ラナン地方は、我が国の一番北方に位置する、大国と国境を接している地方にもなります。住んでいる住人も少数民族で、独特の文化を持って、生活しています」
ナディール姫の話によると、その地区は、王国に属してはいるものの、自治区と表現した方が、近いという。
「レアメタルの鉱脈は、当然地区の地下にも存在しています。ですから、利害関係をめぐって、少しややこしいことになりつつあるのも、また事実で………」
そう言うナディール姫の瞳に、深い憂いの色が宿り、ため息が唇から漏れる。
難しい。
国が貧しいよりは、豊かになった方が、皆が幸せになれる、と、思っていたのに。
豊かになればなったで、どうしてこうも次々と、複雑な問題が浮かびあがってくるのだろう。
「だから私が直接行って、話し合いの場を設けたほうがいいと、思ったんです。ラナン地区の人たちを含めた王国の皆が、いい方向に足並みをそろえることができれば………それが一番、ベストなのでしょうけれど………」
「………………」
ハヤブサは、黙して答えない。歩きながらナディール姫は、やがて笑顔になり、顔を上げた。
「さあ、早く昼食を食べねばなりませんね! 昼からの閣議に間に合わせるよう、急ぎましょう! ハヤブサ様!」
昼食に向かう姫の足取りは、あくまでも軽やかで、とても、しっかりとしたものだった。
「そこにいたのか、ハヤブサ」
ナディール姫の食事に付き添っているハヤブサのもとに、シュバルツがやってきた。
「話したいことがあるんだ。少し、いいか?」
ハヤブサは、ちらりとナディール姫の方に、視線を走らせる。食事をしていた姫の手が、止まった。
「改まったお話であれば、別室でお伺いを」
そう言って立ち上がろうとする姫を、シュバルツは手で制した。
「ああ、大丈夫だ。大した話ではないから」
そう言うとシュバルツは、続けて口を開いた。
「実は、ドモンが………しばらく、ノゾム王子の傍に、滞在したい、と、言っているのだが………」
「まあ、ドモン様が?」
ナディール姫が、少し意外そうな顔をする。
ドモン・カッシュは、名の知られた格闘家。それであるが故に、ここでの滞在など、望むべくもない、と、思っていたが。
「もしかして、ノゾムが何か、ドモン様に無理を言ったのではないでしょうか?」
少しそう思ってしまったナディール姫は、思わずシュバルツに問いかけてしまう。それに対してシュバルツは、苦笑しながら頭を振った。
「そうではない。この滞在は、ドモンの方が、強く望んだんだ」
「まあ………!」
「……………!」
シュバルツのその言葉に、ナディール姫は素直に感嘆の声を上げ、ハヤブサは、少し複雑な表情を、その面に浮かべていた。
ドモン・カッシュの力を借りられるのは嬉しい。嬉しいことの筈なのだが────
素直に喜べないのは、何故なのだろう。
「構わないだろうか」
問うてくるシュバルツに、「私は、構いません」と、ナディール姫は即答していた。
「良かった」
シュバルツはにこっと、笑顔をナディール姫に向けると、ハヤブサの方に向き直った。
「ハヤブサ、少しいいか? 話があるのだが」
「ああ、いいぞ。話とは何だ?」
ハヤブサがシュバルツの方に向き直ると、「ちょっと………」と、シュバルツが手で(部屋の外に出ないか?)と、合図を送ってくる。
「……………」
ハヤブサは、無言で周りに『殺気』や『悪意』がないか探る。今なら、少しくらい姫の傍から座を外しても、とくに問題はなさそうだった。
「直ぐ近くにいる」
ハヤブサは姫にそう言い置くと、シュバルツと共に部屋から出て行った。
「で、何だ? シュバルツ、話とは………」
ハヤブサがシュバルツに問いかけると、彼は懐から、握り飯を取り出した。
「厨房で握ってきた。昼食まだだろう?」
「お、ありがとう」
シュバルツから受け取り、早速ほおばる。塩加減が絶妙だった。
(どうせなら、梅干しも欲しいな……)
ハヤブサがそう日本に想いを馳せていると、シュバルツが「話してもいいか?」と、切り出してきた。
「ああ、いいぞ」
ハヤブサが頷くと、シュバルツは話を始めた。ノゾムの部屋で聞いた、メリルの話を────
「……………!」
ハヤブサはただただ、絶句するしかない。
何ということだ。
姫を取り巻く環境も、相当ひどいと思っていたが─────
「ハヤブサ。私は王太后の周囲を、少し探ってみようと思う」
ハヤブサは、少し驚いて、その面を上げる。
「………危険だぞ?」
心配そうに眉を顰めるハヤブサに、シュバルツはにこり、と、微笑みかけた。
「案ずるな。私がそう簡単に死なないこと、お前も知っているだろう」
「それはそうかもしれないが………」
ハヤブサにしてみれば、シュバルツが怪我をする、と、想像しただけで、もういたたまれない気持ちになるのに。
目の前で穏やかに笑うこのヒトは、自身の身の安全に、あまり頓着してくれないから本当に困る。
どう言えば伝わるのだろうか。
お前は俺にとって、誰よりもかけがえのない、大切な存在だ、と、言うことを。
「キョウジも心配していたし、乗り掛かった舟だ。それに、実際私も………ドモンと同じ気持ちだし」
「………………!」
はっと、ハヤブサは息をのんだ。
確かにそうだ。
互いに、憎みあう必要もないのに、周りの理不尽によって仲たがいさせられる兄弟の悲劇など────誰が好んで見たい、と、思うだろうか。
「分かった……」
ハヤブサも、これ以上シュバルツの行動を、止め立てすることは出来ない、と、知れた。
「では、王太后の件は、お前に任そう。いいか? シュバルツ」
「勿論」
シュバルツは力強く頷いていた。
「俺からも、一つお前に伝えておくことがある」
「何だ?」
ハヤブサからの言葉に、シュバルツは顔を上げた。
「刺客の件だがな……。イワンコフの持ち物から、外国からこの国に、刺客を派遣している『ルート』が分かった」
「…………!」
「メアリカン合衆国の知り合いに、その『ルート』を叩き潰すよう、依頼してある。これで、海外からの刺客の流入は、ぐっと減らすことができるだろう」
「そんなことができるのか?」
「ああ」
少し驚くシュバルツに、ハヤブサはニコリ、と、微笑みかけた。
「だがな、これは、相手の手札をそぎ落とすことを意味する。もしかしたら、相手の攻勢が、さらに強まる可能性もある」
「そうか……」
「だから、油断するなよ、シュバルツ」
「分かった」
まっすぐこちらを見つめて、頷くシュバルツ。
そんな彼を見ると、どうしても、実感させられてしまう。
このヒトは、何者にも代え難い
自分の、愛おしいヒトなのだと
だから────
「それと、シュバルツ。もう一つ」
「どうした?」
少し怪訝そうにこちらを見るシュバルツに、ハヤブサは一歩踏み込んで────
「……………!」
強引に、その唇を奪っていた。咄嗟に身を引こうとするシュバルツの身体を捕まえて、更に自身の舌を、その口腔の奥深くに侵入させる。
「ん………!」
逃げようとするシュバルツの舌を、絡め取って吸い上げる。
「んぅ………! ん………く………」
「……………」
(愛している……)
万感の想いを、唇と舌と、抱擁する腕にこめた。必死に離れようと足掻いていたシュバルツだが、やがて、震える身体から、徐々に力が抜けていき────
「ふ…………」
トン、と、頽れるように、背後の壁にもたれかかってしまった。シュバルツの逃げ場がなくなり、抵抗も止んでしまったことをいいことに、ハヤブサの、シュバルツに対する口腔の蹂躙は、執拗に続いた。辺りに暫し、舌と舌が絡まる水音と、熱い吐息が響き渡る。
「…………」
そっと、ハヤブサがシュバルツを解放すると、熱で瞳を潤ませ、奪われ続けた酸素を取り戻そうと、ゼイゼイと息を喘がせる妖艶なシュバルツの姿が、そこにあった。蹂躙され尽くした唇が、互いの唾液できらきらと濡れて光り、呑みきれなかった唾液が伝い落ちる様が、シュバルツの凄絶な色気に拍車をかけている。
(ああ、綺麗だな)
素直にそう感じたハヤブサは、もう一度彼に触れたくて、そっとその頬に手を伸ばす。
その瞬間。
「この……! いい加減にしろっ!!」
ドゴォッ!!
シュバルツの鉄拳制裁が、ハヤブサの鳩尾に、思いっきり綺麗に、めり込んだのだった。
「ぐえっ!!」
蛙がつぶれたような間抜けな声を上げながら、ハヤブサは悶絶する。それを、氷のような冷たい眼差しで、シュバルツが見下ろしていた。
「何考えているんだ! お前は………! 仕事中だろうが!!」
「そ、そうなんだけど………」
ハヤブサはしくしくと、泣き崩れていた。
シュバルツの身体に触れられないままに、一体どれだけの時間が流れているのだろう。
ハヤブサの心の中に、愛おしさばかりが降り積もる。
触れたい。
彼の最奥に、触れたいのだ。
「キスぐらいいいじゃないか……! 減るもんじゃなし……」
「馬鹿、キスだけで済まなくなったら、どうするつもりなんだ!」
「ううううう………」
シュバルツのもっともな言葉に、ハヤブサも低く呻くしかない。だが、自分の中でくすぶり続けるこの想いを、どう処理すればいい、というのだろう。
「じゃ、じゃあシュバルツ………」
「何だ?」
つっけんどんに返事をしてくるシュバルツに、ハヤブサはめげずに言葉を続ける。
「この仕事が終わったら………俺のために、時間を取ってくれるか……?」
「仕事が終わったらな?」
さらり、と、言葉を返すシュバルツ。その言葉を聞いた途端、ハヤブサはがばっと跳ね起きた。
「本当だな!?」
「──────!」
そのハヤブサを見た瞬間、シュバルツは悟った。自分はこの仕事が終わったら、ハヤブサに抱かれる約束をしてしまった、と、言うことを。
(しまった………!)
後悔したが、後の祭りである。目の前には、ものすごく幸せそうな顔をした、龍の忍者の姿がある。
「……………!」
そんな彼の姿を見ていると、シュバルツの方も、なんだか毒気が抜かれてしまった。
好きな人の、幸せそうな笑顔を見るのは、嬉しい。
嬉しいから、ついつい、彼に、何もかもを許してしまっている自分がいる。
いいのだろうか。
『DG細胞』という、特殊なもので構成されている、人ならざる自分は
『人間』であるハヤブサと、本来ならば、深くかかわりすぎてはいけないのだが────
「シュバルツ………」
「う…………」
ハヤブサの、その優しい微笑みに、シュバルツの方はいたたまれない居心地の悪さを感じる。
だから──────
「馬鹿。さっさと持ち場に戻れ。仕事をおろそかにするんじゃない」
つっけんどんな物言いをして、ハヤブサを突き放すことを選択していた。その言葉に、ハヤブサも「そうだな……」と、少し残念そうに、シュバルツから距離を取っていた。
「……………」
それを見て、シュバルツは少しほっと息を吐く。
彼のそばにいて、これ以上
自分の方こそ、平常心を保つことが難しくなりそうだったから─────
ハヤブサからもたらされる『熱』に、自分がどれだけ煽られているか、揺さぶられているか─────
彼は気づいているのだろうか?
「では、私は行く。お前も、仕事に励めよ」
「ああ」
ハヤブサが頷いたのを確認してから、シュバルツは踵を返して、その場を後にしていた。ハヤブサも、しばらく彼が去った方向を名残惜しそうに見ていたが、やがて顔を上げて、姫の護衛の任務へと戻っていっていた。
そのころ、メアリカン合衆国では。
ハヤブサから連絡を受けたアーサーが、とある高官と接触をしていた。
「やあやあ、ヒメイネス殿。お元気そうで何より」
「アーサー殿? 何用だ?」
少し小柄で、小太りなその男は、アーサーの顔を見るなり、少し不快そうに眉を顰める。そんな彼の表情にはお構いなしに、アーサーはずけずけと言葉を続けた。
「何、難しい話ではありませんよ。貴方が連絡を取っていた、シロア国の高官から、『貴方に話を聞くように』と、教えてもらったものですから」
「……………!」
「ユリノスティ王国の周辺の海路の権益について─────と、お話すれば、お分かりになられますかな?」
少し険しい眼差しで、ヒメイネスを睨みつけるアーサー。すると、ヒメイネスの方が、いきなり無言で踵を返した。そのまま脱兎のごとくその場から逃げ出そうとする。
しかし。
「逃げても無駄ですよ! ヒメイネス殿!」
そう叫んだアーサーが手を上げると、四方から武装した兵たちが出現し、そのままヒメイネスを取り囲んでしまう。
「ゆっくり聞かせていただきましょうか……。シロア国と、ヒメイネス殿の間で、一体どんな約束事をされていたのか……。ユリノスティ王国に対して、どんな画策を企てていたのか………」
「ひ………!」
「連れて行け」
アーサーの言葉に従って、兵たちがヒメイネスを連行していく。その後ろ姿を見ながら、アーサーは、ユリノスティ王国からこの情報をもたらしてくれた、龍の忍者に思いを馳せていた。
(これでいいのだろう? リュウ……。外国からの、敵対勢力の流入は、この件でだいぶ減らせるはずだ……)
元々、ユリノスティ王国の基盤が揺らげば、それに隣接する大国のシロア国に、何かと有利になる状況が発生する。そして、死したイワンコフが持っていたライターが、シロア国の諜報員が持っている、特殊な仕様の物だった。ハヤブサはそれを、アーサーに伝えたのである。
腕利きのエージェントでもあるアーサーは、その情報からイワンコフの背後を洗い出し、メアリカン合衆国内でシロア国に内通していた者を、見つけ出すことまで成功していたのである。
この件は、シロア国をけん制するための、いい材料になることだろう。
(外の勢力を抑えることは任せろ、リュウ……。だから………姫を頼むぞ………)
アーサーが見上げる先の空には、抜けるような青空が、広がっていた。
「どういうことなのです!? これは!!」
城内の、とある一室で、王太后の叫び声が響き渡る。昼間なのに日の光が差し込まないその部屋は、常に暗闇に包まれていた。
「話が違うじゃないの!! 小娘1人片付けるなど、造作もないことだと貴方が───!」
王太后は、誰かに向かって怒鳴りつけているようである。しかしこの部屋は、暗がりに包まれているため、太后と話しているのが誰なのか、うかがい知ることは出来ない。しかし、辺りの空気が重苦しいほどの『悪意』に囲まれている、と、感じるのは、この部屋の暗さばかりが原因ではないだろう。
「全く本当に………! う…………!」
怒鳴り続けていた王太后が、急に苦しみ出す。しばらく呻く声が続いたかと思うと、小さな声で縋るように、「早く……! 『例の物』を……!」と、絞り出すような声が、暗がりの中で響いていた。
「早く……! 早く………!」
しばらくの、沈黙が続く。
「……………」
やがて、衣擦れの音と共に、王太后の声が、暗闇でまた響いた。
「本当に………これを続けていれば、何もかもがうまくいくの……?」
「……………」
またも、闇の中で沈黙が続く。
どうやら、会話をしているような空気の流れはあるのだが、その会話を聞き取れた者は、実際に話をしている者たち以外は、皆無であった。
「………では、私はもう行きます。全く……! なんて気分が悪いのかしら!」
捨て台詞を残して、王太后は部屋から出て行く。
後にはただ、暗闇と沈黙が、部屋を支配するばかりであった。
姫の暗殺を企てる者は、苦虫を噛み潰したような顔をしていた。
とにかく、腹立たしかった。
全てが、腹立たしくて仕方がなかった。
この国の存在は、許してはおけぬ。
この国は、滅びなければならないのだ。
それ故に、自分は手を下した。
この国を、強く支えていたのはシャハディ王。
だからそれを倒せば、この国の屋台骨は、根幹から揺らぐと思っていた。
だが、こちらの意図に反して、国を強く支える人間が現れた。
それこそが、ナディール姫であったのである。
しかし、言ってみれば、たかが小娘一人。
自分が手を下さずとも、彼女の命は、簡単に取れるもの────と、ある意味タカをくくっていた。
けれども、ふたを開けてみればどうだ。
姫は殺されるどころか、刺客たちから己の身を巧みに守り、シャハディ王以上に、国を強く支えだしている。
おまけに、『龍の忍者』と呼ばれる、厄介な護衛まで、国内に招き入れて─────
「リュウ・ハヤブサだと!?」
姫の暗殺を依頼した相手に、たびたび驚きの声を上げられた。
「冗談じゃない! 俺は、この仕事は降りるぜ!」
なぜだ、と、問いかける自分に、相手は顔を引きつらせながら言葉を続けた。
「お前、『龍の忍者』を知らないのか……。よっぽどモグリだな」
「もぐりだと?」
自分が眉を顰めると、相手は真顔で忠告してきた。
「いいか……。一つ教えておいてやる。この界隈で生き残りたけりゃあな……。絶対に、敵に回しちゃいけない相手、ってぇのが存在するんだ。そのうちの一人が、『龍の忍者』だ」
「……………!」
「この業界に、長くいる奴ほど、俺と同じ反応をすると思うぜ……。奴とまともにやりあうだけのメリットと理由が、俺の方にはない。お前が出してきた条件でも、俺には割に合わなさすぎるんだ」
唖然と息をのむ自分を尻目に、その殺し屋は、さっさと踵を返していた。
「いいか……。この件は、俺は何も聞いていないし、関わりもない。今後一切、連絡を取らないでくれ」
(馬鹿な……! 報酬は、向こうの言い値の倍以上を上乗せしたのだぞ……! それでも、『割に合わない』と、言うのか……!?)
殺し屋が去った方向を見つめながら、『それ』は、苦々しい怒りに、身が震えるのを感じていた。
(……やはり、我が直接手を下すことを考えねばならぬか……。不浄の人間は人間同士で、始末をつけさせるに超したことはない、と、思っていたが……)
小さく舌打ちをしながら、その存在は、薄暗い廊下を無言で歩き出していた。
第6章
早朝、ノゾムはひたすら、走り続けていた。
足は重く、息も絶え絶え。振る腕はもう棒のようになって、感覚もなくなりつつある。だがノゾムは、懸命に走り続けていた。
「まだまだ! 後1㎞は走ってもらうぞ!!」
近くではドモンが、ノゾムのペースに合わせるように、ゆっくりと併走しながら声をかけている。
まるで、特訓をつけているかのような光景────これは、ノゾムがドモンに願ったことであった。
「ここにドモンが滞在する間、自分を鍛えて欲しい」
彼はドモンに、そう自分の意思を伝えていたのだ。
「いいのか?」
ノゾムに頼まれたとき、ドモンは思わずまじまじと、彼を見つめてしまった。
色白の、か細い身体をしたノゾムは、どう見ても戦うことに向いているとは、言えなかったからだ。
「構いません!」
ドモンの少し躊躇うような空気を、敏感に感じ取ったノゾムは、必死に食い下がっていた。
「僕だって、男です! いずれは、お義姉様を、お守りしなければならないんす!」
これは、ノゾム自身、常日頃から考えていたことであった。
怖いからと言って
幼いからと言って
何時までも義姉や大人たちの後ろに、こそこそと隠れるように色々なことをやり過ごしている、自分。
このままで、いいはずがない。
このままで、いいはずがないのだ。
「…………………」
必死に食い下がってくるノゾムを、ドモンは少し苦い顔で見つめる。
自分が訓練をつけるのなら、それはかなり、過酷なものとなる。
この、色白でか弱いノゾム少年が、それに耐えきれるとは、到底思えないのだが──────
(いやだ!! 俺だって、いつまでも兄さんのおまけなんかじゃないんだ!!)
「………………!」
不意にドモンの脳裏に、師匠の前で食い下がっていた、幼かったころの自分の姿が蘇っていた。
窮屈だった家を飛び出し、東方不敗の前で、「修行をつけてくれ!」と、わめいた自分が、ちょうど10歳。今目の前にいる、ノゾム少年と、同じ年だ。
「………………」
あの時、わめく自分をじっと見つめていた東方不敗が、何を考え、何を思っていたのかなど、今の自分には知る由もない。
だが、東方不敗は、自分の師匠となってくれたではないか。
必死に縋り付こうとした自分を、師匠は突き放さなかった。だから、今の自分がある、と言っても過言ではない。
必死にわめく自分と、目の前のノゾム少年の、姿が重なる。
ならば、今こそ自分も、師匠と同じように行動するべきなのではないのか。
彼から受けた恩を、少しでも返すために。
「………俺の訓練は厳しいぞ? ついて来れるか?」
「はい!! ぜひお願いします!!」
ノゾム少年は、迷いなく即答していた。
厳しい修行こそ、自分の望むところだったからだ。
彼がそう決意を固めていたところに、義姉であるナディール姫に、呼び出されていた。
「私は、明日からラナン地方の視察に行ってこようと思っています」
「視察ですか?」
義姉の言葉に、ノゾムは少し驚いたような声を上げる。その横で、同様に王太后も、驚いたように目を見開いていた。
「ええ。大臣たちとも話し合って、決定したの」
対してナディール姫の面には、あくまでも穏やかな表情が浮かんでいた。
「ノゾムも、そして、お義母様もご承知の通り、ラナン地区は我が国にとって、治安を維持するためにも、レアメタルの鉱脈的にも、重要な拠点です。この地区から最近、頻繁にいろいろな報告が上がってきています」
そう言いながら、姫は机の上に、書類の束を、ドン! と、音を立てて置く。どうやらこの分厚い書類の束が、全部、ラナン地区から送られてきた、訴えの数々らしい。
「もちろん、中には取るに足らない報告もあります。しかし、見ての通り数も日々多く、少し前に派遣したレアメタルの鉱脈の調査団が帰ってきていないのも、少し気になります。ですから一度、私が直接行った方がいい、と、判断したのです」
「お義姉様……!」
呆然とするノゾム王子の横で、王太后が少し苛ついたような声を上げていた。
「ナディール、貴方がこの城から出るのは勝手ですが─────その間の、国の執務はどうなさるおつもりなのです?」
「その間は、ノゾムとお義母様に、お任せしようと思っています」
「え…………!」
「まあああ………!」
この姫の言葉に、2人は同時に声を上げる。よほど意外なことだったらしい。
「そのように、驚かれることではないでしょう」
対してナディール姫は、少し苦笑気味の笑顔を、2人に向けていた。
「ノゾムも、王族の一員です。お父様が病を得て、私がここを離れる時─────王の代理として、国の執務を執ることは、当然のことではないですか?」
「そ、それはそうかもしれませんが………」
少ししどろもどろになるノゾム王子に対して、王太后は沈黙を貫いていた。ただ、その目つきは、どこか苦虫を噛み潰したような、険しさを含んでいるように見えた。
「大丈夫よ、ノゾム」
動揺を隠しきれていない義弟に対して、ナディール姫は笑顔を向けた。
「私が留守にする期間は、そう長くはありません。すぐに帰ってきます」
「本当ですか?」
不安そうにこちらを見つめてくる義弟を、姫は優しく頷き返していた。
「本当よ? 今まで私が、嘘をついたことがあった?」
「ない………」
「ね?」
姉の笑顔に、ノゾムは頷き返すしかない。それを見て、ナディール姫もにこりと微笑み返していた。
「聞いての通りです。カライ内大臣、私が留守の間、ノゾムをよろしく頼みます」
「はっ。承りました。姫様」
姫の言葉に、白髪の気むずかしそうな面を湛えた老人が、静かに頭を下げていた。
「ですが姫様。一言申し上げたき儀がございます」
「何ですか?」
振り返るナディール姫に、その老人は、鋭い眼差しを投げかけていた。
「我ら閣僚がお待ち申し上げますのは、あくまで姫様、あなた様のご帰還でございます」
「……………!」
内大臣の言葉に、執務室にいたほぼ全員が、はっと息を呑んでいた。
「どうかそのことを、お忘れなきように!」
そう言って内大臣が、じろりと王太后を睨み付ける。
「まあ……! なんて無礼なんでしょう!」
王太后が震えながらそう喚くが、内大臣は、特に気にもとめずに、元の姿勢に戻った。王太后は、しばらく内大臣に、何か言いたげに睨み付けていたが、「お母様……」と、ノゾムに不安そうに声をかけられて、舌打ちしながら視線を逸らしていた。どうやら彼女も、ここは黙ることを選択したらしい。
「分かりました。カライ内大臣。貴方の言葉、しかとこの胸に留め置きましょう」
姫の言葉に、カライ内大臣は、恭しく頭を下げる。その様子をじっと見つめながら、ハヤブサは、内大臣と話したことを思い出していた。
────ハヤブサ殿………。姫様は、死ぬ気でござろうか……。
それは、少し前のことだった。執務室で、黙々と書類にサインをしている姫を護衛していたとき、カライ内大臣が、そう声をかけてきていた。
「? どういうことだ?」
話が今ひとつ見えてこないハヤブサは、多少、眉をひそめながら、内大臣に問い返した。姫は、確かに命を狙われてはいたが、自ら死にに行くような気配など、決して漂わせてなどいなかったからだ。
内大臣は、一つ大きなため息を吐くと、重々しそうに、その口を開いた。
「姫様は、『ノゾム王子に王位を譲る』と、仰っておられた……」
「ああ。確かに、そう言っていたな」
ハヤブサは、ナディール姫がノゾム王子に話していたことを思い出していた。
姉が義弟に王位を譲る。どの時代でも、どの国でも、ある話だと思った。
だから───
「何か、問題でもあるのか?」
「大ありです」
問うハヤブサに、内大臣は真顔で答えていた。
「我が国にとって『王』とは、特別な存在です。一度王位に就いたら、その人間は、俗世間からは隔離された存在となり、死ぬまでその『王位』を全うされるのが通例です」
ハヤブサは、黙って耳を傾けていた。内大臣は、言葉を続けた。
「しかし姫様は……義弟であるノゾム様が成人なされたら、王位をお譲りになるという……」
「そうだな」
頷くハヤブサに、内大臣は強く頭を振っていた。
「よくありません! これは非常に、よろしくないことなのです!」
「…………?」
話が見えず、眉をひそめるハヤブサに、内大臣は訴えるかのように言葉を紡いだ。
「良いですか!? 先程も申しましたが、姫様は『代理』とは言え、王位を継いでいるお立場であらせられます! つまり姫様はもう、『人間』として、俗世間に戻る資格を、失っておられるのです!」
「……………!」
内大臣の言葉の内容に、ハヤブサは思わず息を呑む。それに対してカライ内大臣は、小さく自嘲的に笑った。
「そのようなこと、下らぬ、と、思われるのでしょうな」
「……………」
ハヤブサは、どう反応をしていいのか図りかねたから、無言を貫く。内大臣は、構わず言葉を続けた。
「今の時代において、王位に就いたぐらいで、『人間の資格を失う』などと、ナンセンスな話だと思っております。しかし同時にこれは、『王位を巡っての権力争いを避ける』という事柄に関しては、絶大な効果を発揮している、と、個人的には考えております」
ユリノスティ王国における『王』は、1世代に1人、と、厳格に決められていた。良くも悪くも。
王位に就いた人間は、この国の象徴の座に座る代わりに、世間一般から、完全に隔離された状態になってしまうのだ。
そしてそれは、王位を退位した後も、その状態は持続された。
『現人神』に近い立場に立つ『王』に、最早『人間』の価値観、権利などは適用されない。
だから、歴代の王たちは、その命が尽きるまで、『王位』に座り続けるのが一般的だった。
勿論今までの歴代の王の中には、様々な理由で、王位を次の世代に譲った者たちもいる。しかし、王位を明け渡した者たちが、その後、国の記録の舞台に立つことはなかった。その存在は、抹消されたに等しかった。
「抹消された者たちに、政治の利権に口出す権利など、あろうはずもない。こうして王室は、醜い権力争いに政治が巻き込まれることを避け─────長きにわたり、この国の内政の安泰と、王室を、守り続けていたのです」
「………………」
ハヤブサは、沈黙を守り続けていた。
国の内政が荒れる原因の一つに、権力者による利権の争いは、確かにある。
それを防ぐ手段として、このシステムは、確かに、有効な物のようにも思えるが─────
「しかし、様々な事情で、早くに自らの『王位』を、次の者に明け渡した王たちはどうなってしまったのか────」
聞けば、ナディール姫も、ノゾム王子が成人すれば、王位を譲る意思があるという。
だから、カライ内大臣は、調べられる範囲で、自力で調べた。
王位を譲った『元国王』が、その後、どのような運命をたどったのかを。
結果は、カライ内大臣が想像していたよりも、かなり悪い物であった。
良くて、修道院に一生幽閉、もしくは国外に永久追放。中には、自ら死を選んだ王もいる。
(良くないな………)
カライ内大臣の額に、縦皺が深く刻まれる。
ノゾム王子が成人するとき、ナディール姫は御年28歳。まだまだ花も盛り。人生はこれからの年齢だ。
姫は、ノゾム王子に王位を譲った後、どうする気なのであろう。
まさか、そのまま『死』を選ぶつもりでは、ないだろうか────
「……私は最初、王から姫様に、『王の代理』をお頼みになられた、と、告げられたとき、半ば懐疑的な気持ちで、姫様を見ていました。王になるための英才教育を受けてこられたとはいえ、まだ18歳の娘です。代理とは言え、王の役目を背負うことなど、とうてい無理、と、思っておりました………」
だが実際、ふたを開けてみるとどうだ。
彼女は実に、王として相応しい行動をしていた。
勿論、未熟なところは多々あったが────
王として、何を大事にしなければならないか。
彼女はすでに、それを身につけていたのだ。
「姫様と執務をとるようになって、私は確信しました。この国を背負って立てるのは、姫様しかいない。この国が、姫様を失うようなことがあってはならないのです。例え、どのような形であったとしても………」
「……………」
「ハヤブサどの……! 何とか、何とか姫様をお守りし通す方法は、ないのであろうか……!」
縋るように、こちらを見つめてくるカライ内大臣に、ハヤブサは軽くため息を吐きながら、頭を振った。
「『王位』につくまで護衛するのが、俺の仕事だ。それ以上のことを要求されるのは、筋違いという物だ」
ハヤブサの言葉に、カライ内大臣が、はっと息を呑む。
「きっと、王位を譲った後の姫を死なせないようにするのは、お前の役目だと思うし、彼女の人生に手を差し伸べるのも、俺の役目ではない。俺以外の、誰かの役目だ」
「………………!」
カライ内大臣は、小さくため息を吐きながら、ハヤブサから視線を逸らした。
「確かにそうですな……。出過ぎたことを申しました」
「いや……」
「姫様の手を取る者も、きっと…………」
ここまで話した内大臣は、深いため息を吐いた。
「………せめて『あの者』が、もう少し、しっかりしていてくれたなら………」
(あの者?)
ハヤブサは少し考えた後、ああ、と、軽く察した。
「あら? カライ内大臣? 内大臣はどこですか?」
その時、執務をしていたナディール姫が、内大臣に呼びかけてくる。
「はい、こちらに」
内大臣が姫の前に小走りで進み出ていくと、ナディール姫は嬉しそうに、書類の束を見せてきた。
「カライ内大臣、見て下さい! 市民から、イガールに対する感謝の手紙がこんなにきてます」
「は、はあ………」
カライ内大臣は、多少顔をひきつらせながら、市民からの手紙に目を通す。手紙には確かに、『感謝の言葉』が並べられていたが───
内容が、庭の草刈りだの、行方不明になっていた猫を探してもらっただの、溝掃除をしてくれただの、仕入れを手伝ってもらっただのと、牧歌的な内容が続く。
個人としては、全く善良なのだろうが────
『王』としての資質、と言う観点から考えると、疑問に激しく、首をひねらざるをえなくなってしまうのだ。
勿論、目の前に起こる、日常的な小さな出来事を、おろそかにしていいわけではない。
しかし、『それは王としての仕事なのか』と、問いかけてしまうと───
それに対してナディール姫は、嬉しそうに書類の束を眺めている。
「やはりイガールは……きちんと仕事をしているのですね。市民の皆に、こんなに慕われて………」
(仕事をしている……? どうだろうな………)
ハヤブサも、若干苦笑いながら、その書類の束を眺めていた。
イガール騎士隊長の『仕事』と言えば、本来は城の警備であり、ナディール姫をはじめとした王族の『護衛』であるはずだった。現状では、その任からは、大いに逸脱している、と、感じてしまうのは、気のせいだろうか。
「しかし、姫様───」
カライ内大臣は、咳ばらいをしながら、ナディール姫に問いかけていた。
「よろしいのでしょうか? イガール隊長は、いささか雑用に追われすぎているような気がしますが…………」
「そうね………」
ナディール姫は、少し苦笑しながら答えを返す。
「でも、いいじゃない。イガールは望んで、そうしているところがあるから………」
「姫様………」
「ねぇ、カライ内大臣」
額に縦ジワを深く刻む内大臣に、ナディール姫がそっと呼び掛けてきた。
「内大臣は……イガールが、初めてこの国にきたときのこと、覚えてる?」
「イガールがですか?」
そう答えてから、内大臣はフム、と、あごひげに手を当てながら、思索にふけった。
イガールは確か、この国に来る前は、傭兵をやっていたと聞く。
ある朝、城の門の前で行き倒れていたところを、いつもの如く、城から抜け出そうとしていた、幼かったナディール姫が発見したのだ。
ぼろぼろに傷つき、薄汚れた格好をしていた武人。普通ならば、門前払いをしていても、おかしくはなかったのに。
姫の父であるガエリアル王は、イガールを追い払わなかった。
それどころか、彼に食を与え、住む場所を与え、そして、仕事さえも与えたのである。
最初は、生気のない眼差しで、淡々と仕事をこなしていたイガール。
だがある日、イガールがものすごく嬉しそうな表情をしている事に、姫は気づくことになる。
「どうして、そんなに嬉しそうなの?」
幼かったナディール姫は、疑問を素直にイガールに告げていた。するとイガールも、嬉しそうに答えていた。
「ここはいいです……。平和で………。人々も、微笑んでくれるし、感謝の言葉をくれる……」
「?」
きょとん、と、した表情を浮かべる幼いナディール姫に、イガールは、優しいが、少し、苦笑気味の表情を浮かべていた。
「この世界しか知らない姫様には………想像もつかないかも知れませんね……。私が生まれ育った地域は、もっと荒んでいたんです。殺しあいが常に起こるような、紛争の絶えいない場所でした……」
物心がついたときには、既に家もなく、両親もいなかった。
非力な子どもである自分が、それでもこの世界で生きることを望むのならば、軍隊に入らなければならなかった。
強くならねばならぬ。
人よりも、抜きん出なければならぬ。
弱い
足手まとい
周りから、そう烙印を押されれば、自分は直ちに切り捨てられ、その先には『死』しか待ち受けていなかった。
生きるために、命じられるままに武器を振るった。たくさんの生命を、奪った。
血と硝煙と、生命への冒涜が、自分の総てだった。
そうではない。
それだけが、世界の全部ではない。
そう言って、優しく手を差し伸べてくれた人も、居たのだが。
その存在は、ことごとく理不尽な暴力によって排除されてしまった。時には自分の手で、その人を殺さねばならなかった。
憎しみと、暴力と、哀しみの連鎖────
嫌になった。
何もかもが、嫌になった。
そんなある日、気がつけば、自分は紛争に紛れて、部隊の仲間を襲ってきた敵ごと皆殺しにしてしまっていた。
生き残った自分は、逃げた。
ただひたすら、逃げた。
世界を、自分を呪いながら逃げた。
もう嫌だ。
消えてしまえばいい
死んでしまえばいい────
こうして、呪いに塗れた自分は、ユリノスティ王国の城の前で、行き倒れていた。
そんな時、ナディール姫と、ガエリアル王に出会ったのだ。
「ここは、優しくていいところです……。何よりも、人を殺さなくてすむのがいい………。護ることを躊躇わなくてすむのが、嬉しい………」
イガールはそう言って、優しいが、少し陰りを帯びた眼差しを湛えて、微笑む。
幼かったナディール姫は、イガールの話を理解することは、難しすぎた。
ただ、ナディール姫は、イガールが、何か大変な目に遭って、深く傷ついているのだろうな、と言うことを、なんとなく理解していた。
そして、この国の人々の優しさが、彼の傷を癒すのには、必要なのだ、と、言うことも。
人々の感謝の言葉を受けながら、優しく微笑むイガールの横顔。
いつの間にか、自分は彼を好きになっていた。
そう。
これはきっと
自分にとっては『初恋』だった。
彼の、優しさが好きだ。
彼の、幸せそうな微笑みが、好きだ。
彼の姿を見ただけで、その日は自分も、一日中幸せだった。
父王に、姫がそのことを告げると、ガエリアル王は、娘の頭をやさしくなでながら、言葉を紡いだ。
「そうか……。イガールは、幸せそうだったか………」
「はい、お父様」
頷く姫に、父王は優しく微笑みかける。
「ナディールよ……。覚えておきなさい。人は誰しも、この世に『生』を受けた以上、幸せに生きる権利がある……。しかし、生まれ落ちた場所や環境によって、それが難しい者もいるのが、現実だ……」
「はい………」
「生まれてくる時代も場所も、環境も、人は選ぶことはできない……。ならばこそ、せめて、この国に生きる者たちの、幸せに生きる権利を守り抜く。それが、我ら王家の役目だと、わしは心得ている………」
「お父様………」
「ナディールよ……。お前にも、その『想い』を、引き継いでほしいと、願っている………」
イガールの、ここに至るまでの歩みを知ってしまった姫には、父王の言葉は、素直に胸に入ってきた。
そうだ。幸せになってもらいたい。
生まれてから今まで、環境に踏みにじられて生きてきた、彼のような人にこそ─────この国で、幸せになってもらいたい。
それが適うのであるならば、これから自分が歩んでいく、逸脱の許されないレールのような人生にも、大きな意味が、きっと生まれてくることだろう。
「はい、わかりました。お父様」
だから姫は、力強く父王に頷いていた。
もう十分だ。
この人生に、自分は十分、胸を張れると思った、から。
私はこの道を生きていく。
父の意志を継いで───
「私は、イガールには幸せになってもらいたい、と、願っています。でも………イガールを、私の横に縛り付ける気は、毛頭ないのです」
「姫様………」
「だって、イガールの人生は、もう、苦労の連続だったから────」
ナディール姫は、屈託のない笑顔を、内大臣に向けていた。
「だから、これ以上、彼の人生に不必要な苦労なんて要らないじゃない? 彼は優しい心のままに、これから思う様に生きるべきなのよ。私はそれを、全力で護る。そう決めているの」
「………………」
カライ内大臣は、姫のその言葉の前に、何も言えなくなって黙り込んでしまう。ハヤブサは少し、眉をひそめていた。
(確かに……イガールの幸せを願うのならば、姫の選択肢は、ある意味正しいと言えなくはないが………。本当にそれは、イガール個人の幸せに繋がっているのか? 肝心のイガールの『ココロ』がどこにあるのか分からないのに────その結論は、少し性急すぎではあるまいか)
ナディール姫の気持ちはわかる。
彼女はきっちりと、イガールに恋をしていて。
だが、自分が置かれている『立場』では、彼を不当に縛り付け、彼の人生そのものを、自分のために浪費してしまいかねない。
彼女はそう考えている。だから、彼女はイガールに、自分の『想い』を告げることはないだろう。このまま、この道を歩んでいくのであるならば。
だが、イガールの方は。
彼は、姫に対して、どのように想っているのだろう。
ただの、『上司の娘』としてみているのだろうか。
それとも─────
(姫様が死ねば………! 私も生きてはいません………!)
ハヤブサがイガールと初めて戦ったときに、彼が見せた、あの涙を思い出す。
あれは、『忠義』としての涙だったのか。
それとも、それ以上の意味が────
(肝心の彼の『気持ち』が、全くわからんのだよなぁ………。せめて、ゆっくり話をする機会でもあれば、こちらだって何かしら、手を打てることがあるかもしれないのに………)
人の恋路だ。あまり第三者が口出しをする、というのも野暮な話かもしれないが。
もしも、イガールが、姫に対して『恋慕』に近い感情を抱いているのなら、『理解してやれる』と、感じていた。
自分が愛している『シュバルツ』もまた、本来愛するのであるならば、あまりにも『禁忌』に近い存在であったから。
『DG細胞』という、特殊な物で身体を構成されている彼は、いわゆる一つの『人外』であった。それは、『人のココロ』をエネルギー源として稼働するが故に、シュバルツは生きていくために食料を必要とせず、無限に近い再生力を細胞自身が持つが故に、不老不死に近かった。
だが、『DG細胞』は、人間に感染し、暴走する危険性もはらんでいるが故に、彼は人間の世界から一歩身を引いた存在であろうとしていた。DG細胞の塊のような存在が、凶悪性を帯びず、その人格を保っているなど、実は稀な例だ。たいていはDG細胞の凶悪性に呑まれ、感染をまき散らしながら、大量殺戮を行う存在に成り下がってしまう。
シュバルツは、いつか自分もそのような存在に堕ちてしまうことを、とても恐れていた。だから、ハヤブサの、シュバルツに対する『想い』を知った時、彼は最初、必死に逃げようとした。
「駄目だ!! お前に、DG細胞が感染してしまったら、どうするんだ!!」
捕まえて、彼を犯そうとしたときに、彼のヒトの口から出てきた言葉は、ただひたすらにこちらを案ずる、けなげな言葉。
そんなお前だから
そんなお前だから、俺は────
彼とともに、生きたいと思った。
彼のそばに、寄り添いたいと、願った。
たとえ、共に死ねずとも
たとえ、彼と共有できる時間が、刹那の一瞬だったとしても─────
自分の存在が、彼の孤独を癒す一助になれたのなら
それだけで、自分の人生は、もう充分豊かに彩られると思った。
きっと、そこに『後悔』はない。
『後悔』だけは、無いのだ。
(不思議だよなぁ……。こんな気持ち、きっと、シュバルツと出会わなければ、俺は知らないままだったなんて………)
ふっと、小さく苦笑しながらハヤブサは思う。
後悔─────
そう、後悔だけは、してほしくなかった。ナディール姫にも、イガールにも。
難しいことでは、あるかもしれないが。
「さあ、イガールにもノゾムにも、今の閣議で決定したことを、伝えなくてはね」
姫は屈託なく笑いながら、手元の書類を片付けていた。
こうして、姫とハヤブサは、数人のお供をつけて、ラナン地方に旅立つこととなった。
「姫様……! 私もお供致します!」
姫に留守居役を申し渡されたとき、イガールは珍しく、強い口調で姫の供につくことを願い出ていた。しかし、姫はそれを、やんわりと断っていた。
「いいえ。イガールには、留守をお願い致します」
「姫様……!」
呆然とした表情を浮かべるイガールに、ナディール姫は優しく微笑みかけていた。
「イガール……。貴方には、この城の守りと、ノゾムのことをお願いしたいのです」
「……………!」
「数日のこととは言え、ノゾムは『王代理』を努めます。しかし、ノゾムはまだ年若い……。しっかりとした支えが、必要なのです」
「そうかも知れませんが……」
イガールの額に、少し縦皺が刻まれていた。彼が、この命に承服しかねているのが、伝わってきていた。
「姫様………! ラナン地区での姫様の身の安全は、誰が守るのです!?」
「心配要りません。私には、ハヤブサ様がついて下さっています」
「…………!」
「最強の護衛が、私を護って下さるのです。何も心配する必要はありません」
そう言って、姫はにこりと微笑む。イガールは、酷く複雑な顔をしていた。
(その複雑な表情の、意味するところは何だ?)
ハヤブサはそう考えながら、イガールを見つめるのだが、当然、彼にイガールの心情総てを、読み解けるわけでもなく。
「…………分かりました、姫様」
畏まるイガール。姫は、優しく微笑みかけていた。
「イガール……。貴方は、城の皆や、町の人たちに頼りにされているのだから、留守居役を、どうかよろしくね」
「はっ」
「………………」
ハヤブサはその光景を、何とも言えない気持ちをまとわりつかせながら、見つめていた。
確かに、相手のことを思いやる、と言う行為は、大事なことだ。だが、何か────ナディール姫の、イガールに対する思いやりは、どことなく空回っているように見えるのは、気のせいだろうか。
シュバルツが、自分のことを思いやってくれるのは、とても嬉しい。
だが、思いやりが過ぎて────彼が全く、自分のことを頼ってくれなくなってしまったら、自分は、どう思うだろう。
(ハヤブサ……。私のことはいいから、お前は、自分のことを優先してくれ……)
そんなことを愛おしいヒトから言われたら、腹立たしさと情けなさが相俟って、泣いてしまいそうになってしまう。
その気遣いは、嬉しくなどない。
むしろ哀しい。
シュバルツ、お前にとって俺は、そんなにも頼るに値しない存在なのかと、首根っこをひっつかんで、怒鳴りつけたくなってしまうだろう。
頼らない、と言うこともまた、相当に残酷だ。
頼って欲しい、と、相手が願っているのならば、なおさら。
姫はその辺り、どう考えているのだろう。
このイガールの表情は────
(あいつの気持ちが、全くわからんのだよなぁ……。せめて、あいつとゆっくり話す機会があれば………)
ここまで考えてから、ハヤブサは、軽くため息を吐く。
これ以上、2人の関係に踏み込むのは、明らかに、自分の『任務』の範疇を越えている。それこそ、『野暮』というものだろう。
「ハヤブサ様、行きましょう」
「分かった」
姫に呼び掛けられたハヤブサは、顔を上げ、彼女の後に続いた。
あとには、礼をして二人を見送る、イガールと内大臣が、残されていた。
こうして、ナディール姫は城から旅立ち、ノゾム王子が、その間の代理を務めることとなり、現在に至る。
ドモン・カッシュがノゾム王子のそばで面倒を見る、ということに、ハヤブサは、幾何かの不安を感じないでもなかったが、シュバルツが時々様子を見てくれるようなので、特に心配する必要もないだろう。
これで、心おきなく、ラナン地区までの汽車の旅を………。
汽車の旅を………
汽車の旅?
「おい」
ハヤブサは、窓際の席に座って、外を見つめているナディール姫に、思わず声をかけていた。
「ん?」
振り返った姫の口には、口いっぱいにパンが頬張られていた。
「ふぁんは、ほようでふふぁ? はやうははま(何か御用ですか? ハヤブサ様)」
「ものを食べながら、しゃべるな……!」
半ば呆れたようにハヤブサが言うと、「ふぉへんははい(ごめんなさい)」と、言いながら、もごもごとパンを食べ続けていた。
「お待たせしました。ハヤブサ様。何か御用でしょうか?」
パンを食べ終わってから、改めて姫は、ハヤブサの方に顔を上げる。ハヤブサは、少し頭をガシガシと掻きながら、言葉を続けた。
「あのな? ナディール……」
「はい」
「なぜ、『汽車』なのだ?」
「えっ?」
「いや、『えっ?』とかではなく」
ハヤブサは軽くため息を吐きながら、根気よく言葉を続ける。
「どうして、ラナン地区への移動手段に、『汽車』を選んだのだ?」
「それは………ラナン地区まで向かうのに、『汽車』が、ちょうどいい交通手段でしたから………」
姫のこの言葉を受けてハヤブサは、自分の問い方が間違っていたことを悟る。
「いや、『汽車』自体が、悪いのではない」
「はい」
「どうしてわざわざ、『この汽車』に乗った?」
「えっ?」
「『えっ?』じゃないだろう?」
きょとん、とする姫に対して、ハヤブサは本日二度目の、同じ会話を続けた。
「いいか? ナディール………。お前は─────」
ハヤブサが口を開いた瞬間、通路をまたいで隣の席に座っていた老女が、「おや? 姫様じゃない?」と、声をかけてきた。
「あ、はい。こんにちは!」
老女からの声かけに、ナディール姫は、明るく元気に返事をする。ハヤブサは、言おうとした言葉を中断し、会話の邪魔にならぬよう、身を隅の方に寄せねばならなくなった。
「姫様、珍しいところでお会いしますなぁ」
「姫様は、どちらまで行かれるので?」
元気よく挨拶をした姫に気が付いた乗客たちが、次々と、彼女に声をかけてくる。
そう。
『乗客』
ここでハヤブサは、盛大にため息を吐く。
あろうことかナディール姫は、ラナン地区まで向かう交通手段に、普通に一般乗客も乗り込んでくる、特急列車を選んでいたのである。
しかも、彼女がとった切符は、指定席でも何でもない、正真正銘の普通席であり、彼女が今している格好も、その辺の旅行者と何ら変わることない、普通の格好であったものだから、本当に、汽車の中の風景は、どこにでもある旅の景色と、同じようなものになっていた。
唯一、普通の旅情の風景の中に、違和感があるとするならば、彼女の周りに、武装をした兵士たちがいる、と、言うことぐらいであろう。
ただ、その兵士たちも─────
「いや~、今回のくじ引き、当たってよかったなぁ!」
「弁当、何持ってきた?」
「俺は、この先のクチカネ駅の弁当を頼むつもりでいるんだ!」
「あそこの牛タンバーガー! うまいんだよな~!」
「お~い、誰か、俺の水筒を知らないか?」
と、言った具合で、各々の席で、思いっきり旅を満喫している。それぞれの武具は、きちんと武具入れの中に行儀よくしまわれて、一つにまとめられて、邪魔にならないように、汽車の壁際に、そっと立てかけられて、一人の兵士がその傍で番をしていた。しかし、その兵士も、鼻歌を歌いながらスマホをいじっていたりする。
(修学旅行か!!)
ハヤブサは思わず、目の前の光景に、そう突っ込まずにはいられなかった。姫は姫で、乗客たちと親しげに話しをし続けている。
全く以て、平和すぎる、特急列車の中の風景─────
ハヤブサも、『姫の護衛』という任務がなければ、座席に座り、車窓でも眺めながら、転寝の一つでもしていたいところだ。
全く、この姫は何を考えているのだ。
身分の高い人間が、専用車両で移動する意味を、きちんと理解しているのだろうか。
要人が、専用車両で移動するのは、別にお高くとまっているから、というわけではない。
護衛の問題があるのだ。
要人は常に、多かれ少なかれ、命を狙われる危険を孕んでいる。それから身を護るために、そして、その騒ぎに一般市民を巻き込まないために、『移動手段』として、専用の車両があるのだ。
それに要人が乗ってくれれば、護衛をする側としても、かなり負担を減らすことができる。その乗り物自体も、中に居る人をしっかりと守る機能が付いているし、護るべき対象を、その乗り物と人といった具合に、きちんと絞り込むことができるからだ。
それなのに、今目の前で繰り広げられている、この状況は何だ。
姫の命を狙っている者がいたら、四方八方から殺し放題ではないか。
無辜の市民も、巻き込まれ放題ではないか。
だからハヤブサは、姫に申し入れた。
この移動手段は、危険すぎはしないかと。
「そう? 大丈夫だと思いますけど」
それに対して姫は、あっけらかんと答えた。
「最近、命を狙われる回数が、すごく減ってきているじゃないですか」
「……………!」
姫の言葉に、ハヤブサはグッと、言葉を詰まらせる。
だが、確かにそうなのだ。ハヤブサが、イワンコフの持ち物から、この国に流れてくる外国の殺し屋のルートを特定して、それを叩き潰してから、姫が命を狙われる回数が、極端に激減した。それでもまだ、狙われていないことはないのだが、下手をしたら、このまま平和に生活できるのではないか、と、勘違いできるぐらいにはなっている。
「大丈夫だよ! この国で、姫様の命をどうこうしようなんて考える輩は、そうは居ないよ!」
ハヤブサと姫のやり取りを聞いていた、少し大柄な夫人が、にこやかに声をかけてきた。
「そうだとも! 姫様のお命を狙うだなんて、とんでもない! そんな奴がいるのなら、わしらが叩きのめしてやる!」
女性の隣で、その伴侶と思われる恰幅の良い男性も、腕に力こぶを作りながら笑い声を立てる。相席していたほかの乗客たちも、皆それぞれに「うんうん」と、頷いていた。
「皆様……! ありがとうございます………!」
それに対してナディール姫は、少し驚いたように目を丸くして、それから立ち上がって、皆に向かって改めて、丁寧に頭を下げた。
「姫様………!」
その姿に、皆がそれぞれに笑顔を返すから、車内には、和やかな空気が満ち溢れた。
(なるほど確かに、姫は皆に慕われている。ここで暗殺を心配するのも、『杞憂』というものかもしれない)
そこまで考えたハヤブサは、はっと我に帰って、ブンブン、と、頭を強く振った。
確かに、姫は皆に慕われ、この空間は、何も問題ないように見える。
しかし、常に忘れてはならないのは、彼女が人に好かれる人間であればあるほど、同じぐらい、彼女を嫌う人間も、存在する、と、言うことだ。
油断してはならない。
彼女を取り巻く『悪意』が、皆無なわけではないのだから。
それにしても─────
「ハヤブサ様! この列車の車内販売のパン、とってもおいしいんですよ! ハヤブサ様も、おひとついかがですか?」
そう言いながら、ナディール姫が、無邪気にパンをハヤブサに勧めてくる。
(緊張感が………ッ!)
ハヤブサは、思わず頭を抱え込んでしまう。
全く、目の前のこの『姫』は、一体何を考えているんだ。
自分が『姫』である、と
命を狙われている立場なのだと
理解しているのであろうか。
姫の顔を見るたびに、小難しい顔をして、くどくどと説教をしていたカライ内大臣の気持ちを、ハヤブサはかなり理解する。
なるほど、これでは彼女に対して、説教の一つや二つ、かましたくもなる、というものだ。
「それにしても、ラッキーだったよなぁ。この旅路に同行できたのって」
姫とともにパンをほおばっていた兵士の一人が、嬉しそうに口を開く。
「あら、そうなの?」
少し驚いて振り返るナディール姫に、兵士たちは得意そうにうなずいていた。
「そうですよ! この旅路に同行するの、結構競争率が高かったんですよ!」
「ほぼ全員が参加して、くじ引きをしたよなぁ」
「イガール隊長が、嬉しそうにこの話を持ってきて─────」
「イガールが!?」
その言葉に、ナディール姫が、かなり驚いたような声を上げていた。
「ええ。隊長が、兵舎でくつろいでいた俺たちのところに来て」
「いろいろと、説明してくれたんだよな」
「非番の連中にも声をかけて───」
「みんなが行きたがったから、どういう方法でメンツを選出するか、話し合いをして────」
当然、その話し合いは熱を帯びた。
メンバーを選抜するための、ありとあらゆる方法が検討された。
その結果
「最終的に、恨みっこなしの『くじ引き』で、決めることになったんです」
「くじですか?」
ちょっと驚いたように目をぱちくりとさせるナディール姫の横で、ハヤブサはもう顔を引きつらせるしかない。『くじ引き』は、確かにある意味平等で、確実な手段ではあるのだが。
聞けば、どうしても外せない用事がある者を除いて、ほとんどの兵士たちが、そのくじ引きに参加したと言う。狭い兵舎の部屋に、くじを引くために集まってくる兵士たち……。
よくよく考えれば、シュールすぎる絵面だ。
この国の警備体制とか、緊張感といった類のものは、一体、どこへ行ってしまったというのだろう。
「それで決定したのが、俺たち10人、というわけです」
トマスが嬉しそうに、ナディール姫に微笑みかける。彼は運良く、この道行のメンバーに選ばれていたのだ。
「モガールの奴は外れてしまったから、すごく残念そうにしてました」
トマスはそう言って、肩をすくめる。ナディール姫は、くすくすと笑っていた。
「あちこちからお土産を頼まれちゃったから、向こうに着いたら探さなきゃいけないんですよねぇ。何かいい物あるかなぁ」
「それだったら、このガイドブックに………」
そう言いながら、姫が荷物から冊子を取り出す。
「お、俺もガイドブックを一応持ってきたんですよ! 姫様のとは、違う出版社から出ている物ですけど」
「あら、貴方たち、ラナン地区に行くのなら、イルム通りにあるチーズ屋さんが、絶品よ!」
共に話をしていた老婦人まで、その話の輪の中に加わってきて、本当に車内の空気は、どこかの旅番組で見られるような、平和すぎる光景になってきていた。
(本当に……ッ! 修学旅行か………ッ!)
ハヤブサが頭を抱えてしくしくと泣いている横で、盛大なため息を吐く若者がいる。ハヤブサが振り返ると、そこには、カライ内大臣より、今回の道行きの同行を命じられた、彼の補佐官の一人が立っていた。
「噂には聞いていましたが………まさか、これほどとは………」
彼は眼鏡を持ち上げながら、苦笑気味に笑う。短めの亜麻色の髪と、整った身だしなみが、まじめで誠実そうな印象を、彼は人に与えていた。
「ハヤブサ殿、今回の道行きに同行させていただきます。ハーシェル・イルトと申します。よろしくお願いいたします」
そう言って、彼は右手を差し出す。
「ああ…………」
彼も、軽く握手を返す。それが終わると、ハーシェルは、もう一と大きなため息を吐いた。
「カライ様が姫様に同行するのを、かなり二の足を踏んでいらっしゃったから、ある程度覚悟はしていたのですが………。本当に、緊張感がなさすぎですね」
「同感だ」
ハヤブサも、ぶっきらぼうに同意の意を伝える。
これは、遊びに行くわけではない。大国と国境を面して、いつ、侵攻の憂き目にあってもおかしくはない地区に行くのだ。多少の危険も付きまとうだろうから、もう少し緊張感を持って、事に当たってほしいものだが。
「カライ内大臣が、行くときに『胃薬を持って行け』と、言った意味が、やっと分かりました……。この道行で、私の役目は、姫が変な方向に行かないよう、歯止めをかけることなのですね……」
そう言って、はあ、と、三度ため息を吐く。
「大丈夫かな………」
うなだれるハーシェルに、ハヤブサはぴしゃり、と、声をかけた。
「大丈夫かな、ではない。やってもらわねば困る」
「……………!」
「姫の命がかかっているんだ。それを、心得ておいてくれ」
「は、はい!」
ハーシェルが、固い表情をして、持っているかばんを、ぎゅっと抱え込む。
ハヤブサも、軽くため息を吐きながら、姫の警護の任務に戻った。
その二人の前では、相も変わらず、緊張感の大幅に欠如した姫たちの光景が、繰り広げられていたのだった。
汽車で揺られること半日。ユリノスティ王国の最北の地、ラナン地区へと一行は到着する。
駅に意気揚々と降り立ったナディール姫を出迎えたのは、ラナン地区の代表者であるワヒム氏と、各村からの代表者たちの一行であった。
「姫様ようこそお越し下された。このラナン地区へ。しかし、連絡を受けたときは、わが耳を疑いましたが、本当に、この普通列車の便で来られるとは……」
白鬚を湛えた、恰幅の良い老人が、にこやかに、しかし少し呆れたように口を開く。
「ワヒム区長………お久しぶりです。でも、誰がこちらに連絡を入れたのですか?」
「カライ殿からです」
「……………!」
問いかけたナディール姫に、ワヒム氏はずばりと答える。固まる姫に、老人は、少し相好を崩したような笑顔になった。
「姫様は、全く相変わらずですな。わが友人を、あまり苛めないでいただきたいものです」
「い、苛めているつもりなんてないわ……! ただ、来る前にちょっと観光を、と、思っただけで───」
ワヒム氏の言葉に少し押され気味になっているナディール姫を見ながら、ハヤブサが、「おい」と、ハーシェルに小さく声をかけていた。
「何でしょう? ハヤブサ様」
「あのワヒムという男は、何者だ?」
「あの方は、ラナン地区の『長』ですよ」
ハーシェルが、そっとハヤブサに説明をする。
「あのように、穏やかな風貌をした方ですが、昔は我が国の軍のトップを務められていた方です。カライ内大臣とは、同じ時期にガエリアル王に仕えていらっしゃる縁もあり、親しい間柄だ、と、伺っております」
(なるほどな)
ハヤブサは、ハーシェルの説明を受けながら、一人納得する。
ワヒムという男、白髭をたたえた老体然とした容貌であるのに、その所作には、全くと言っていいほど、隙が無かったのだから。
軍属、軍のトップという経歴を聞いて納得をする。
さぞかし、優秀な軍人であったのだろう。
そして、このような軍人が、わざわざこの地に『長』として派遣される辺りに、この国における、この地の重要性が見え隠れしているな、と、ハヤブサは感じていた。
「では姫様。迎えの車を用意してあります。それで庁舎に参りましょう」
「分かりました……」
「ご存知の通り、問題は山積しております。遊びに出る暇など、無いのですからな」
「はい…………」
ワヒム氏の後を、姫がとぼとぼとした足取りでついて行っている。よほど、ラナン地区の散策を楽しみにしていたのだろう。
(気の毒だが、同情の余地は、あまりないな)
ハヤブサは、半ば呆れながらもその様子を見守っていた。
そう、これは、遊びに来ているわけではない。
立派な、政務の一つなのだ。そのあたりを自覚して、姫には事に当たってほしい、と、ハヤブサは思った。
姫の後に続いて、兵士たちも一様に皆、トボトボとした足取りで歩を進めている。
(息ぴったりか)
『ナディール姫とその仲間たちの、愉快な珍道中』になりかねない景色に、ハヤブサが頬を引きつらせる横で、ただ一人ハーシェルだけが、
「ワヒム様がいてくださってよかった………」
と、小さなため息を吐いていた。
ラナン地区は、人口1万人。大国であるシロア国との国境沿いにある、比較的標高の高い場所にある自治区だった。自治区の北側には、シロア国との国境を守る要にもなっている、アレイド山脈が聳え立っている。
人が住む場所からちょっと進めば、そこにはもう溶けることのない白い天然雪が、その山肌を覆っていた。
ラナン地区の中心部にある『庁舎』に、到着した一行は、さっそく執務室に案内される。
姫が上座に静かに歩を進めるその前に、ワヒム以下、地区の長たちが、皆畏まって頭を下げていた。
「姫様、よくお越しいただきました」
「皆、出迎えご苦労様です」
執務室に、姫の凜とした声が響き渡る。それを聞いた姫に同行してきた兵士たちから、少しざわついた声が上がった。
「どうした?」
それを聞きとがめたハヤブサが、兵士たちに声をかける。すると、トマスが、苦笑いをしながら問いに答えた。
「いや、あの……。姫様が、あまりにも違うから、びっくりして……」
「えっ?」
きょとん、とするハヤブサに、別の兵士がフォローするように、口を開く。
「ああ、トマスは、まだ執務室の警護に当たったことがなかったっけ?」
「そうなんだ。俺は、ここに来てまだ、日が浅い方だからな」
「俺もそうなんだ。まだ外回りの警護しか、当たったことがなくて………」
「今回、姫様の警護に当たれたのって、本当にラッキーだよなぁ」
(そりゃあ『クジ』だからな)
ハヤブサが、少し呆れかえるように見つめている前で、兵士たちの話はなおも続いた。
「大体、俺たちが見かける姫様は、執務から抜け出して、市場で買い食いしているのが、主だったから」
「おいしそうに飯を食って、にこにこと、楽しそうに笑っているイメージだよなぁ」
「本当に、普通のお嬢さん、って感じで」
「いや、しかし………」
ハヤブサは、思わず口をはさんでいた。
「公式行事で、姫の姿を見ることもあるだろう? それを見たことはないのか?」
ハヤブサの言葉に、兵士たちは各々顔を見合わせる。
「いやぁ、見たことは見たんだけど」
「すごく、遠くからだったし」
「何か、別人を見ているようでなぁ」
「『姫様っぽいな~』って感じで」
「………………!」
ハヤブサは、兵士たちの話を聞きながら、頭を抱え込みそうになるのを懸命にこらえていた。
確かに、姫の態度は普段から緩い感じで、黙ってその辺を歩いていたら、本当に、普通の町娘と区別がつかないほどだ。
だが彼女も、仕事をするときはきちんとまじめに、王族の威厳と誇りを持って、誠実に職務を遂行しているはずなのだが。それが、あまり広く認知されていない状態は、いかがなものだろうか、と、思ったりもする。
その横でハーシェルは、ただ一人、姫と区長たちの会話を、黙々と記録し続けていた。
おそらく、カライ内大臣に報告する書類の作成も、兼ねているのだろう。
「………確かに、家畜に対する被害が、増えているようですね……」
姫が、書類を片手に、少し難しい顔をしている。ワヒム区長も、渋い表情をしていた。
「左様です。このように、自然豊かなところです。牧畜をしている以上、多少の獣害はつきものですが、少し、数が多すぎるような気がするのです」
「我々も、対策は立てているのですが、何か、後手に回っている、というか………」
「通常の手口では、通用していないような………」
「分かりました」
姫は頷きながら、手元の書類を少し整理する。
「その件については、あとで現地を視察しましょう。そのうえで、もう一度皆と話し合えば、有効な対策が立てられるかもしれません」
「了解しました」
姫の言葉に、皆が一様に頭を下げる。
「それと、もう一つ。備蓄してある食糧庫で、盗難騒ぎが─────」
「少し、待ってください。ワヒム様」
ワヒム区長の言葉を遮るように、姫が口を開く。
「それよりも先に、話し合わねばならないことがあります」
「話し合い……何でござろうか?」
姫の言葉に、ワヒムは少し眉を顰める。『食料の盗難』以上に、話し合うべき重要課題があるのだろうか、と、思ったからだ。
しかし、ワヒム自身もまた、姫が持ってきた話の重要性に、息を呑むこととなった。
「調査団のことです」
「調査団?」
「少し前に、地下のレアメタル鉱脈のことを調査するために、この地に調査団を派遣する、と、カライ内大臣からこちらに、連絡があったはずです」
「そういえば………」
ワヒムはふむ、と、頷いてから、口を開いた。
「確かに数日前、カライ殿から連絡を受けておりますな。それが、どうかされたのですか?」
「その調査団から、連絡が途絶えてしまったのです」
「えっ?」
ワヒムが、あまりにも意外そうな声を上げるので、姫も思わず顔を上げた。
「何か……話を聞いていませんか?」
「いえ………」
ワヒムが懐から白いハンカチを取り出し、己の汗を拭き始めた。
「どうしました?」
姫の問いかけに、ワヒムから帰ってきた答えは、かなり意外なものだった。
「調査団が、来ていたのですか?」
「えっ?」
ナディール姫は、キツネに抓まれたような心境になる。二人は、たがいに目を二、三度しばたたかせた後、姫の方から口を開いた。
「1週間ほど前に城を出て、こちらに向かったのですが………」
「1週間前?」
ワヒムは腕を組みながら、首をひねり始めた。
「………私どもの方では、その調査団の姿を、見てはおりませんが………」
「………えっ?」
驚き、息を呑むナディール姫の前で、ワヒムは皆の方に振り返っていた。
「この中で、誰か『調査団』の姿を見た者は?」
その問いかけに、ラナン地区の各地から集まってきた長たちは、一様に首を横に振る。
「いえ、全く」
「私どもの方でも、見てはおりませぬ」
「………どういうことなの? これは………」
あまりのことに、動揺が隠し切れないナディール姫に対して、ワヒムは状況を整理するために、口を開いた。
「確かに、カライ殿から、『この地に眠るレアメタル鉱脈を探るための調査団を派遣する』と、連絡は受けておりました。ですから、私どもとしては、いつ来るのかと待っておったのですが………」
「見ておりませぬな」
「ええ、まことに」
「そんな………!」
姫は混乱しながらも、自身も頭の中で、状況を懸命に整理していた。
カライ内大臣は、確かに、調査団を派遣したと言っていた。
イガールからも、『調査団から定時報告があった』と、報告が上がっていた。
なのに、ラナン地区では、『調査団の姿を見ていない』という。
どういうことなのだろう?
自分は確かに、調査団の出発式に、立ち会ったはずなのに。
彼らは間違いなく、現地に旅立ったはずだ。
それが、どうして、ここに着いていないのだろう。
本当に、行方不明になってしまったのだろうか。
そして、それを誰かが隠蔽していた可能性が────
「………………!」
初めて、明確な『悪意』を感じて、ナディール姫の背中に、冷たいものが走る。
誰?
誰が、本当で、誰が嘘を言っているの?
いったい何を信じれば─────
「これはやはり、早急に、現地に赴く必要があるな………」
それまで黙っていた龍の忍者が、ポツリ、と口を開く。それを聞いて、姫もはっと我に返った。
「そうですな。姫様、わしもその意見に賛成です」
ワヒムも、ハヤブサの言葉に頷いていた。
「そのような不確かなことが、この地区で起こっているなど、ここの責任を預かる者として、捨て置くわけにはまいりません。早急に調査されることを、望みます」
彼の言葉に、その後ろに控えていた長たちも、皆刻々と頷いている。
「ワヒム様………」
「もちろん、調査をされる、というのなら、我らも全面協力いたします」
「ぜひ、調査を。姫様……!」
「では、私はカライ内大臣に、調査団がどこへ向かう予定だったか、問い合わせてきます」
皆の言葉を受けて、それまで議事録をつけていたハーシェルが、あわただしく席を立つ。
「頼みます」
ハーシェルの姿を見送りながら、ナディール姫は、身体が小さく震えるのを、止めることができずにいた。
何故
どうして
調査団が行方不明になっている、というのなら、どこへ行ってしまったのだろう。
そして、その事実に
どうして誰も、今まで気づかなかったのだろう───
調査団の団員にも、家族や恋人が、いたはずだ。
その人たちも、まだ何も気づいていない、というのだろうか。
「おい、トマス、お前大丈夫か?」
その時、自分の後ろに控えていた兵士たちから、その声が聞こえてきた。
姫は、はっと後ろを振り返っていた。
見ると、トマスの顔色が、白くなってしまっているのが分かる。
「大丈夫ですか!?」
姫が、はっと、弾かれたように立ち上がる。それを見て、トマスの方が、慌てて首を横に振った。
「いえ、姫様! 俺は大丈夫です! ただ………」
「ただ………?」
問い返す姫に、トマスは懸命に笑顔を向けた。
「ただ、俺も、その調査団の任務に、就く可能性があったんだ……。それを思うと………」
「そうですか………」
姫は、少し眉を顰めると、小さくため息を吐きながら、席に座りなおした。
「では姫様。我らのそのほかの訴えは、その書類にまとめています。目を通しておいてください」
ワヒムの言葉に、姫も「分かりました」と、姫も短く答える。そのあと、もう少し、諸々の話し合いが続いた。
その後ろで、トマスのそばにいた兵士が、彼に声をかけていた。
「おい、トマス」
「何だよ」
「お前が、調査団の任務に就く可能性があったって………」
「ああ………」
「どういうことか、聞いてもいいか?」
トマスはその問いに頷くと、口を開いた。
「おれは、『新入り』だと話しただろう? ここに来て、まだそんなに日が経っていないんだ」
自分は、いわゆる自国の内戦のごたごたから逃れてきた、避難民だった。家族ともはぐれ、独り、この国に流れてきていた。
(これからどうしよう………)
途方に暮れていたトマスの前に、城の警護団募集の張り紙が。
指定された場所に行くと、結構な人だかりがあった。警護団募集の報せに集まってきた人々のようであるが、自分と似たような境遇の人間が、それなりにいる、と、トマスは感じていた。
(最近は、どこも物騒だからなぁ……。この国のように、平和に暮らせていることの方が、実は結構稀な例なのかもしれない……)
軽い面接と、簡単な書類の提出だけで、あっさり警護団に入隊できたので、少し拍子抜けした。自分は、身元を保証してくれる人がいない、いわば浮浪者も同然の身であったから、雇われることは難しいだろう、と、考えていたからだ。
「ここの隊長の、イガール・ジェスティ殿も、この国に流浪してきた人らしいから、そういうところにこだわりはないのかもしれないぜ」
「やっぱり、あの噂は本当だったんだな……。この国は、難民に優しいって」
「俺も、落ち着いたら、故郷から家族を呼び寄せようかな……」
自分と同期に警護団の団員になった者たちが、そう話しているのを、トマスは聞いた。
自分と似たような境遇の人たちが多かったことに、トマスは胸をなでおろすと同時に、複雑な気持ちにも襲われていた。
皆、寄る辺もなく、ここに流れ着いてきた人たちなのだ。
どうして、世界はこんなにも『平和』ではないのであろう。
「そんなときに、調査団の話が隊長から持ち込まれたんだ……。何でも、採用と、昇進試験も兼ねているからって、選ばれたのは、ほとんどが、俺と同期の人たちだったんだ……」
自分が選ばれなかったのは、単に調査団に入れる人数の限界値の問題で、運もなかっただけだ、と、トマスは思った。
ただ、調査団に入れなかった、ということで、悲観する気にはなれなかった。
自分は、全くの独り身で、護るべき家族もない。出世を急ぐ必要は、これっぽっちもなかったのだから。
「残念だったな。お前にも、土産を買ってきてやるよ」
知り合って、少し意気投合したばかりの男が、少し残念そうに笑いながら、握手を求めてくる。
「ああ、よろしくな」
トマスも笑って、握手を返して、その男と別れた。自分は、その後城の外回りの任務を命じられていた。
そして、モガールとともに、街歩きに出ていたナディール姫とともに騒動に巻き込まれたりしながら、今に至るというわけだった。
「……調査隊が行方不明、と、言うことは、あいつも、それに巻き込まれたんだろうか……。それが、ちょっと、気になって………」
「そうか………」
トマスの話を聞いていた兵士たちが皆、何とも複雑な面持ちになっていた。
「大変だったな………」
「調査団の人たち、無事だといいな……」
各々が、トマスにそう声をかける。トマスも、「ありがとう」と、穏やかに礼を言っていた。
「………………」
ハヤブサは、少し離れたところから、兵士たちの話を聞き続けていた。龍の忍者の優れた聴力は、兵士たちの会話を、余すところなく捉えていたのである。
(………それにしても、調査団の構成メンバーが、少し気になるな………)
トマスの話を聞きながら、ハヤブサは、軽い違和感を覚えていた。
彼の話を整理すると、今回のレアメタル鉱脈の調査団は、城に来て、まだ日の浅い兵士たちを中心に選ばれているようである。
しかし、それは何故なのだろう。
この国にとって、レアメタルの鉱脈、というのは、何物にも代え難い、重要事項のはずだ。
それを、その調査を─────入隊して日が浅い兵士たちに、やらせるものなのだろうか。
(……それとも……故意に、入隊して日の浅い、身寄りのない者たちを、調査団に『選んで』いた………?)
「………………!」
何のために?
何が目的で?
ハヤブサは、そこに潜む、仄暗い『悪意』に寒気を覚える。
最初から、その調査団を『行方不明』にさせるのが、目的であった、と、言うのなら。
この国に来て、日の浅い、身寄りのない者たちは、まさにうってつけの人材だ。行方不明になったところで、『探してくれ』と、騒ぐ身内がいないからだ。それだけ、発覚を遅らせることも可能だ。
(……誰が、こんなことになるように手配したのだ?)
ハヤブサはそれを考えようとして─────
ひどく、暗澹たる気持ちになる自分を、自覚する。
これを手配できる城の人間は、限られていて
それが誰であろうとも、姫がひどくショックを受ける結果になることに、変わりはないからだ。
姫は、城にいる人たちを、とても信頼している。
それが、裏切られることに、なるのであるから。
(いや、まだ、そうと決まったわけではない)
ハヤブサは、ブンブン、と、首を横に振る。
決めつけるのはよくない。
これはまだ、『可能性』の一つである話に過ぎない。
しかし、事態は常に、『最悪』を想定しておくことが、生き延びるためには必要になってくる。
(油断をしてはいけない)
もとより、姫に向かってくる暗殺者を、水際で阻止せずに、入るに、狙うに任せ放題にしていた城なのだ。背後から撃たれることを、常に想定しておかねばならない、と、ハヤブサは思った。
「では………明日から、よろしく頼みます。今日は、ここまでにしましょう」
姫の、凛とした声が、部屋に響き渡る。家臣たち一同は畏まり、ハヤブサは顔を上げた。
「皆様方、宿舎に案内させていただきます」
そう言って、恭しく頭を下げる侍従の言葉に、皆、粛々と従っていた。
夜更け。
姫が、窓からベランダに出てくる。
「眠れないのか?」
その姿を見つけたハヤブサが、姫に声をかけた。
彼女は一瞬、びくっとその身をこわばらせて、ハヤブサの姿を確認してから、ようやく、その面に笑みを見せた。
「ハヤブサ様………」
その微笑みの硬さゆえに、ハヤブサは表情を曇らせた。
最初に出会った頃に、戻ってしまっている。
ひっきりなしに刺客に襲われて、自分の部屋のベッドで、眠ることすらできなかった、あの頃に。
(無理もないか)
ハヤブサは、苦い思いを噛みしめていた。
誰が敵で、誰が味方かわからない状態に、また、彼女は舞い戻ってきてしまったのだから。
「………いったい……何が起こっているのでしょう………」
硬い笑みを浮かべたまま、姫は、ポツリと言葉を落とす。
「行方不明になってしまった、調査団の方々も……城のことも………ここでの、皆さまの話も………」
「…………………」
ハヤブサは、黙して答えない。
自分は、その問いに対する明確な答えを、持ち合わせてはいなかったからだ。
「……いったい、どうすればいいの……? 何を、誰を信じれば─────」
「………誰を、何を信じるかは、自分で決めろ」
はっと、顔を上げる姫を、ハヤブサはじっと見据える。
ひどく突き放すような物言いだが、今は、こうするよりほかに、道はなかった。彼女は今─────ふらつくことを、許される立場ではないのだから。
「『俺を信じろ』とは言わん。俺は、お前に忠義立てをする立場にある人間ではないからな」
「ハヤブサ様………」
姫の瞳に、哀しみの色が濃く宿る。龍の忍者は、少しきまり悪そうに視線をそらした。
「ただ………少なくとも俺は、お前の味方だ。俺は、クライアントから、『お前を守れ』と依頼されている。その仕事を請けている間は、それを、反故にするわけにはいかないからな」
はっと、顔を上げる姫。龍の忍者は視線をそらしたまま、動かない。
ただ、姫は、ハヤブサの言葉は、素直に『信じられる』と、感じていた。
何故だろう。信じられる。
この人は、絶対的に、自分の味方になってくれると、信じることができた。
不思議だ。
この人には、王家や国に対する『忠誠心』は、無いというのに。
それでも彼を、自分が信じることができるのは、一体どうしてなのだろう。
(……きっと、この人が、『自分の信念』を貫き続けていることを知っていて、私はそれを、『信じる』ことができるから、なのだわ)
皮肉なものだ。
上に立つ者として、一番信じる寄る辺となるべき『忠義心』が、実は、それほど『信』が置けないものなのだ、と、悟らされる格好になるなんて。
「…………………」
姫は大きく、一つ息を吐いた。
(大丈夫、落ち着け)
ここでの安全は、保障されている。龍の忍者が、何があっても、私を守ってくれるだろう。
きっと、見極めなければならないのだ。
目の前にいる相手が、本当に、信じるに足る相手なのかどうか。
『王家』という特権やフィルターを通さずに、見ていく必要がある。
もっと、その人の、根本的な部分を、だ。
「ありがとうございます、ハヤブサ様………」
「礼を言われる筋合いはない」
姫の言葉に、龍の忍者はぶっきらぼうに答える。それでも姫は礼を言った。いや、礼を言うべきだと思った。彼の存在があるおかげで今宵は─────
安心して、眠りにつけそうだったから。
「休みます」
ナディール姫は、静かに身をひるがえして、部屋に入っていく。
「ああ、ゆっくり休め」
ハヤブサの言葉に、姫は微笑みながら頷いた。
「…………………」
姫が部屋に入ってから、ハヤブサはふっと、一つため息を吐く。
前途はあまり、はかばかしくない。きっと、姫には、大きな試練が待っていることだろう。
そしてそれが終われば、彼女は王位に就く。
そうなることで、何物にも犯しがたい、神聖な存在となる姫は、身の安全は半永久的に保障されることになる。自分もそこで、めでたくお役御免だろう。
ただ、彼女個人の『幸せ』を、考えるのであるならば─────
「………………」
夜なのに、万年雪をたたえている山肌が、青白く光っている。
風が刺すように冷たいのは、ここの標高が高いせいだけではないだろう。
考えても仕方ないことを、考えようとしている。
自分にそう言い聞かせて、吹っ切ろうとしているのだが、なかなかにうまくいかなかった。
龍の忍者にとって、まんじりともせず明けぬ夜は、まだしばらく続きそうであった。
第7章
翌朝。
天気は快晴。
いつもの姫であるならば、その景色に喜びの声を上げ、朝の空気の中、元気よく飛び出していたことであろう。
しかし、ナディール姫は今、とてもそのようなことをする気にはなれなかった。
調査団を取り巻く一連の出来事が、彼女の胸に、重くのしかかっていたのである。
(いったいどうして……。何が起こっているというの……)
姫は問いかけ続けるのだが、当然のごとく、それに対する明確な答えが、帰ってくるわけもない。
それを今から調べて、その中に潜む『真実』に近づいて行かねばならない─────それが、今、自分に課せられている『使命』だった。
せめて、レアメタルの調査団の人たちの無事を、祈らずにはいられない。
いくら、この国に流れてきて、日の浅い人、身寄りのない人たちだけで構成されていた、と、言うものであったとしても、それで、その人たちの安否を、おろそかにしていい、ということは決してない。
皆がそれぞれにそれぞれの事情を抱え、悲しみや苦しみを背負いながらも、やっとこの国に流れてきたのであるならば───受け入れる側の国としても、その人たちの幸せの手助けをする義務が、生じているはずなのだ。
調査団の人たちが生きているのならば、速やかに救助せねばならない。そして、事情を聴いて───
(うん………。よし………!)
姫は、一つ深呼吸をした。
とにかく自分は、できることを一つずつ、片づけていくしかないのだ。
その時、部屋のドアを、何者かが「コンコン」と、ノックする音がした。
「はい」
一瞬、身を硬くして、それでも在室の返事をする姫。だが、外から聞こえてきた「開けてもいいか?」と、問いかけてきた龍の忍者の声に、肩の力が一気に抜けるのを感じた。
「どうぞ」
許可を出すと、ドアが静かに開く。ハヤブサの姿を認めた時、姫は、ホッと、小さく一つ息を吐いていた。
「少しは、眠れたか?」
色素の薄いグリーンの瞳が、少し案ずる色をたたえながら、こちらをまっすぐ見つめてくる。姫は、少し、嬉しい心持を感じていた。それは、恋人以外には不愛想な龍の忍者が、根源的に持つ『優しさ』の一部を、垣間見ることができたからかもしれなかった。
「はい」
顔に、笑みを浮かべる。
きっと自分は、うまく笑えている、と、思う。
「行きましょう」
そう告げて、部屋から出ていく。龍の忍者も、静かにあとからついて来てくれた。
しばらく進むと、兵士たちが待機していた。
「姫様………」
兵士たちは皆、表情も一様に固く、そして案ずるように、こちらを見ている。
「みんな…………」
兵士たちの中にトマスを見つけて、ナディール姫ははっと息を呑んでいた。
────俺たちが引き留めている間に、逃げてください………
モンスターに襲われて、絶体絶命だったときに、トマスは確かにそう言って、自分を逃がそうとしてくれていた。
彼の話を信じるのなら、トマスはここに来て日が浅いはず。にもかかわらず、彼は自分のために、命を懸けてくれていたのだ。
これは、考えれば考えるほど、すごいことのように思う。
自分は、それを、決して当たり前、と考えてはいけないのだ。
向けてくれるその『心』に、感謝の気持ちを、決して忘れてはならないと、思った。
(うん……。うん………。よし………!)
もう一度、深呼吸をして、自分の考えを腹に落とし込む。
兵士たちが命を懸けて私を守ってくれるように、私も、皆を守っていこう。
兵士たちだけではない。
この国にいる皆を
王家に忠義立てをくれるとか、くれないとか、そんなのは関係なく。
この国の、皆を守る。
それが、私の『役目』だから─────
「姫様………」
硬い表情をしたまま、押し黙ってしまった姫に、皆が一様に心配をする。
「大丈夫ですか?」と、声をかける前に、姫の方が顔を上げ、そして、驚くほどに柔らかい笑みを、その面に浮かべていた。
「皆、大丈夫ですか? よく眠れましたか?」
「……………!」
「は、はい!!」
「そう、よかった」
ニコリ、と、微笑む姫。それにつられて、兵士たちの面にも、笑みが浮かぶ。
「皆、朝食は食べましたか?」
姫の問いかけに、皆は一斉に姿勢を正した。
「はい! 姫様!!」
「我々は、朝食を済ませました!」
「いつでも、出ることができます!!」
「そうですか……。では──────」
「お前は、朝食がまだだろう」
その時、姫の背後から、ぴしゃりと声が飛んできた。
はっと姫が後ろを振り返ると、龍の忍者が腕組みをして、ジト目でこちらを睨んでいた。
「朝食を食わずに出るなど、俺が許さん。ちゃんと朝飯を食え」
「え………でも………」
「お前に倒れられたら、ここにいる全員が迷惑を被るんだ」
「う…………!」
ハヤブサの正論に、反論する術を持たないナディール姫。それに対してハヤブサは、やれやれ、と、ため息を吐いていた。
「ここの者たちが、お前のための朝食を用意してくれている。それを、ちゃんと食べろ。総ては、それからだ」
「はい」
龍の忍者の言葉に、姫は素直に頷いていた。
宿の者に、案内されるままに食堂に向かうと、テーブルの上に、既に朝食が並べられていた。先程、盛り付けられたばかりなのだろう。食事からは、暖かそうな湯気が、ゆらゆらと立ち上っていた。
(美味しそう………)
空腹を意識して、姫は席に着く。すると、龍の忍者が近寄ってきて、そっと小さな声をかけてきた。
「ナディール、毒味用のスプーンは持ってきているか?」
「──────!」
はっ、と、一瞬息を呑むナディール。だが直ぐに、彼女は懐から、そのスプーンを取り出していた。
「これは、肌身離さず持つようにしていますから、ここに。ちゃんと持っています」
姫もまた、小声でハヤブサに答えながら、そっと、そのスプーンを見せる。龍の忍者は頷くと、再び口を開いた。
「俺を含め、兵士たち何人かで、『毒味』は一応してある。今のところ、異常はなかったが───」
「……………!」
姫が振り返ると、食堂付近で待機している兵士たちが、こちらに向かって、『大丈夫ですよ』と、言うジェスチャーをしていた。おそらく彼らが、『毒味』をしてくれたのだろう。
大丈夫。
私は一人じゃない。
きっと、この問題も、乗り越えられる。
皆がそばに、いてくれるから────
スープから、温かな湯気が上がっている。スプーンをつけてみても、それは変色しなかった。
(おいしい……)
姫は朝食を食べながら、少し、人心地を取り戻していた。
食事が終わり、ハーシェルと合流する。
「姫様。カライ内大臣に,調査団が向かった地点を問い合わせてみました。それで、帰ってきた答えが、これです」
そう言いながら、ハーシェルが地図を広げる。その地図上には、3か所の印がつけられていた。
「まあ、3か所も?」
姫が、少し驚いたような声を上げる。ハーシェルも、少し眉を顰め気味だった。
「すみません……。カライ内大臣も、イガール殿も、調査団がこれのどこに向かったか、まではわからないみたいです」
「そうですか………」
「報告では、鉱脈が見つかりそうな場所がこの3か所で、どこからまわるかは、調査団を率いる隊長に、任されていたようです」
「………………」
『イガール』と、『カライ内大臣』の名前に、姫の胸に、ツキリ、と、痛みが走る。
この二人は、真っ先に信じなければならない、城の『要』であるのに。
「その辺りは、ナイクト地区だ。ロジオル殿の管轄だな」
姫たちとともに地図をのぞき込んでいたワヒムが、そう言って後ろを振り返る。その言葉に、ナディール姫ははっと、我に返っていた。
「左様か。では、うちの地区より一人、若い者を案内につけましょう」
長い白ひげを蓄えた老人が、ひげを手でしごきながら、穏やかに口を開く。
「よろしく頼む」
ハヤブサはそう言ってから、姫の方に視線を向けた。
「それでいいな? ナディール」
ハヤブサの意見に、姫も静かに頷いていた。
「この者が、貴公らを案内する。ワシの地区では、一番の射撃の名手だ。名は、『ロシャール・ハムイ』という」
そう言ってロジオルが、一人の青年を姫の前に連れてきた。
「ロシャール・ハムイです。どうか、『ロシャ』と、お呼びください」
少し細身で、長身短髪の青年が、そう言いながら、静かに姫に手を差し出してくる。
「よろしくお願いします」
姫と握手を交わした後、ロシャは、ハヤブサの方にも手を差し出してきた。
「………………」
ハヤブサは、黙ってロシャと、握手を交わす。細身だが、手のひらは厚く、そして硬かった。そして、雪焼けをしている肌に、鋭さを含む眼光。腕のほどはともかくとして、彼が相当『銃』を、撃ち馴れている者だと、ハヤブサは感じていた。
「まず、ここから一番近い場所に行きましょう。私がご案内いたします」
ロシャの言葉に、皆頷いていた。
「まず、最初の地点は、この洞窟です」
慣れた足取りで山肌を歩いていたロシャが、一つの洞窟の前で立ち止まる。見るからに深そうな洞窟に、姫は少し、息を呑んでいた。
「姫。お前はどうする?」
洞窟に入ろうとしていたハヤブサであるが、その直前に、姫の方に振り返っていた。
洞窟に共についてくる、と、なると、それなりに危険な目に遭う可能性はある。
だからここは、姫には『出入り口付近で待機する』と、いう選択肢もあるのだが。
「ここにいるか?」
その問いかけに、しかし姫は、小さく頭を振っていた。
「いいえ……共に行かせてください。ハヤブサ様」
「しかし───」
反論しようとしたハヤブサに、姫は縋るように口を開いてきた。
「ごめんなさい……。危険が伴うのも、私が足手まといになってしまうのも、重々承知しております」
「ならば………」
「ですがハヤブサ様……! 私は、調査団の安否を確かめに来ています。ならば私も、その捜索に加わるべきだと思うのです……!」
「その理屈はわかるが………」
ハヤブサは少し、眉を顰めた。
「現場の最前線で走り回ることが、指揮官の仕事ではないだろう。後方に待機することも、時には必要だ」
「………………」
ハヤブサの言葉に、黙り込んでしまう姫。だがやがて、ポツリと、小さな声を落とした。
「ですが、ハヤブサ様…………。今の私にとって、ハヤブサ様のおそばより安全な場所が、もう無くて…………」
「……………!」
姫の言葉に、ハヤブサははっと、息を呑む。
「ごめんなさい………。私は今、誰が敵で誰が味方か─────わからなくなってしまっているみたいです…………」
そう言って、哀しそうに瞳を伏せるナディール姫。
(確かにそうだ)
姫の言葉に、ハヤブサは一人頷いていた。
姫の周りには、明確な『悪意』が存在している。彼女は今────『味方』と思っている人間から、いつ背後から撃たれても、おかしくない状態だった。
彼女を安全な場所に、と、こちらが配慮を働いても、それが彼女を却って、敵のど真ん中に放り込んでしまう、という事態にすらなりかねない。
やはり、多少危険でも、彼女には常に、自分の目に届くところに居てもらうのが、自分の任務的にも正解なのだろう、と、ハヤブサは判断していた。
どちらにしろ、罠に近づきつつある。
姫に対する、明確な『悪意』が迫ってきているのならば。
「姫様!! 我らがお守りいたします!!」
少し離れた場所にいた兵士たちが、姫の傍に駆け寄ってきて、口々に訴えてきた。
「姫様をお守りするのが、我らの役目……! 姫様とここに来られて、我ら光栄であります!」
「微力ながら、お力になります!!」
「みんな……!」
姫は、はっと息を呑んでいた。
そうだ。忘れてはならない。
自分には確かに、底知れぬ『悪意』が向けられている。
しかし、この兵士たちのように、なけなしの『善意』を向けてくれる存在も、確かにあるのだと言うことを。
勇気をもらう。
暖かさをもらう。
それは、自分が前に進むために必要な、希望の光となった。
「ありがとう………」
姫は静かに礼を言う。
「いや、とんでもないです。姫様!」
「少しでもいいことが報告できるよう、頑張りましょう!」
「調査隊の奴らだって、きっと無事ですよ!」
そうやって、明るく笑う彼らにつられて、姫の面にも、いつしか笑みが浮かんでいた。
「よし、ロシャ。案内してくれ」
ハヤブサの言葉に、ロシャは静かにうなずいていた。
薄暗い洞窟の中を、一行は進む。
雪山の洞窟であるから、もっと中は冷え冷えとしていると思われたが、中は意外にも暖かかった。
「地熱の効果ですね」
先頭を歩くロシャが、淡々と言葉を紡ぐ。
「この山脈には、活火山がいくつかあります。そのおかげで、麓には温泉の恩恵にあずかれるし、雪解け水が、豊潤な土地を作ってくれるのです」
「……………」
姫は、ロシャの説明を聞きながら、なるほど、と、1人頷いていた。
城の中で、大臣達や、専門の学者から講義を受けて、この国の自然の成り立ちは、『知識』としては知っていた。だがやはり、現地に赴き、その中で生活している人の話を直接聞くのでは、響いてくる『言葉の重み』が違う。自然の営みが、実感を伴って、姫の中に入ってきていた。
(やっぱり……お父様の言う通り、現地に赴くのって、大切よね……)
自分が、『為政者』として、この国にどれだけ居られるかは分からない。
だが、自分がその地位にいる間は、なるべく現地に足を運ぼうと、姫は決意を新たにしていた。
しばらく、一行は洞窟の中を進む。
しかしやがて、先頭のロシャが、その足を止めた。
「引き返しましょう」
ロシャの、静かな声が響く。
「何故ですか?」
少し意外に思った姫の問いかけに、ロシャが明確な答えを返していた。
「この洞窟には、人が入った気配がありません」
「…………!」
ロシャの指摘に、ハヤブサもはっと気づく。
「人が入れば、洞窟内には、それなりの痕跡が残ります。それが全くないことを鑑みると、調査団は、この洞窟には入っていないのかも知れません」
「あ…………!」
ロシャの言葉に、姫もようやく得心がついた。
それもそうだ。
誰も入っていない洞窟を捜索したところで、調査団を発見できるはずもなく、それは全くの徒労に終わる。
「調査団は、他の洞窟に向かったと推測されます。ですから、引き返すことを進言致します」
ロシャはそこまで言った後、少し周りを見回しながら、小さな声で呟いた。
「それに………山が………」
「どうした?」
忍者であるハヤブサは、常人よりも耳がいいが故に、その声を拾う。反射的に問いかけていた。
「あ! いえ、そんなたいしたことではないのです。私の感覚的な問題で……!」
ハヤブサに自分の独り言のような呟きを聞かれて、ロシャの方が驚いたのだろう。少し狼狽気味に彼は答えていた。
「感覚だと?」
問い返すハヤブサに、ロシャは少し苦笑しながら答えていた。
「猟師の感覚のようなものです。今日の山は、獲物が捕れそうにない、と、いった感じの……」
「そんなことが分かるのですか?」
驚くナディール姫に、ロシャは、少し肩をすくめる仕草をした。
「いえ……これは私の『感』のようなものです。あまりあてにはならないのですが………」
そう言った後、ロシャは、少し眉を顰めていた。
「何か………山が………」
「山が………どうかしたのか?」
「………………」
ロシャは、黙してそれ以上は答えない。
だがハヤブサは、その彼の態度に、かえって確信を深めた。
(やはりロシャは………山に異常を感じている………)
ロシャのように、常に自然と、そこに息づく命と接している人間の『第6感』は、結構あてにして良い、と、言うことを、ハヤブサは経験的に知っていた。間違いない。確かにこの山には、何らかの『異常事態』が起こっている。
まだ周囲に、殺気や不吉な気配は、近づいてきてはいない。
しかし、必ず何かある。
ハヤブサは、静かに覚悟を新たにしていた。
「彼の言うとおりです。この洞窟を出ましょう」
姫の下した決断に、皆異論無く頷いていた。
それから一行は、二つ目の洞窟に入る。
その洞窟も、人が入った気配はなく、引き返すことになった。
と、なると、残りは一つ。
「もしも、本当に調査団が来ていたのなら……この洞窟に、入って行ったことになりますが……」
「………………」
全員が無言で、洞窟の入り口を見つめる。一見、何てことはない洞窟に見えるが、そこから吹いてくる風の中に、かすかに『妖気』めいたものを感じたから、ハヤブサは、少し眉をひそめていた。
「な、なぁ……。何か、風が冷たくないか……?」
兵士達も、何かを感じるのだろう。小声でそう呟きながら、互いに身を寄せ合っている。
「確かに………あまり、よくなさそうな洞窟ですね………」
ロシャも、少し険しい目つきで、洞窟を見据えている。
「そんなに悪いのですか?」
問いかけるナディール姫に、ロシャは少し、苦笑した顔を向けた。
「私が、狩りをするだけの目的であるなら、絶対に、ここには入りません」
「……………」
ナディール姫が、青い顔をして、無言でハヤブサのそばに寄ってくる。
(やはり、不安なのか……)
命を狙われている彼女からしてみれば、この洞窟は、自分に向かってくる『悪意』や『死』が、漠然と手招きしているように見えているだろう。
「ここに残るか?」
ハヤブサは、そう言いそうになる。
しかし、思いとどまらざるを得なかった。
今の彼女は本当に、どこから狙われているか、分からない状況にあるのだから。
何かあった場合、同行してきた兵士達の腕では、心許なかった。
だから、自分は姫と洞窟の出入り口にとどまり、兵士達だけで、調査に行かせる選択肢もあるにはあるのだが。
「………………」
ハヤブサは、姫に着いてきた兵士たちを、改めて見る。そして、洞窟から微かに流れ出てくる、妖の気配を鑑みる。
(駄目だ………)
ハヤブサは、ため息とともに、結論付けざるを得なかった。
この兵士たちだけで、洞窟の探索に行かせるには、あまりにも、彼らの力量が不足しすぎていた。彼らだけでは、下手をしたら犠牲者が出てしまいかねない。
そのような事態になってしまうこと─────姫は決して、潔しとはできないだろう。
「では、行こう」
ハヤブサは、短くそう言った。
これが罠であろうとなんであろうと、事態を打開するためには、前に進まねばならぬ。
もしも、目の前に『悪意』という名の壁が立ち塞がる、というのならば、自分たちは、それを食い破って、その先に行くだけだ。
「そうですね。行きましょう」
姫もまた、ハヤブサのそばで頷いていた。
彼女の表情は硬く、顔色も青ざめてはいるが、瞳には、力強い意志の光が宿っていた。
彼女もまた、戦う気でいるのだ。
前に進む気でいるのだ。
「中にいる調査団の人たちが、助けを求めているかもしれませんから………」
姫の言葉に、兵士たちもはっと、その姿勢を正す。
「姫様! 行きましょう!」
「我ら命に代えても、姫様をお守りいたします!」
「ありがとう……」
姫の言葉に、兵士たちは力強く頷く。その様子を、ロシャはしばらく無言で見ていたが、やがて、静かに口を開いた。
「では、私があなた方の露払いを務めましょう」
そう言いながら、彼は猟銃を、背中に背負い直す。
「頼む」
ロシャを、どこまで信じていいのかは分からぬが、今は、この地に詳しい彼の力が必要だった。だからハヤブサも、彼の申し出を受け入れた。
ロシャは、ハヤブサに対して頷き返すと、洞窟の中に入って行った。
「行きましょう」
姫もそのあとに続いて歩き始める。その傍に、ハヤブサが寄り添った。
「よ、よし……! 俺たちも行こう!」
兵士たちも、多少おっかなびっくり、と、言った風体はあるが、その後ろに付き従った。
しばらく歩いたところで、ロシャが足を止めた。
「………どうやら、この洞窟に調査団が入ったようですね」
「そうなの!? なぜ分かるの!?」
姫の驚いた声に、ロシャが地面を指さして答えた。
「……地面に、足跡があります」
「─────!」
ロシャの指摘に、ハヤブサも地面に目を凝らす。なるほど確かに、地面には、複数人の足跡が、点々とつけられていた。
「しかも、比較的新しい……。靴の跡も、あなた方兵士たちが履いている物と、同じもの、と、推測できます」
「うへっ! 本当かよ……!」
トマスが、素っ頓狂な声を上げて、自分の足の裏を見る。ハヤブサも素早く目を走らせて、兵士たちの靴の裏の紋様を確認した。なるほど確かに、兵士たちの靴の裏と、地面についている足跡の紋様が、一致する。
「行きましょう。生きている方が、いるかもしれません」
姫は顔を上げて、躊躇いなく前に進み始めた。恐怖よりも、『助けなければ』という使命感の方が、彼女を突き動かしているらしい。
「ひ、姫様~~!」
「待って下さ~~い!」
少々腰が引け気味の兵士たちが、そのあとに続く。
ハヤブサとロシャも頷きあって、それから走り出していた。
洞窟内をしばらく走ると、足元に、何かが転がっているのが見つかる。
「荷物だ!!」
兵士の一人が、その傍に走り寄る。
「姫様! これは、軍から支給される鞄です!」
「もう間違いない……! やっぱり、調査団はここに来たんだ……!」
そう言いながら、トマスが鞄を開けて、中を確認する。中には、非常食や救急用のキットが、きれいに整理されて入っていた。
(襲われたな)
ハヤブサは、瞬時にそう判断する。
探索において、絶対に手放してはいけない物が入っている鞄を、こんな風に無造作に落としていくなど、普通は考えられないからだ。
「……何か来ます」
ロシャが、猟銃を構えながら、警戒した声を発する。
「!!」
兵士たちはとっさに姫を庇い、それをさらに背後に庇うようにハヤブサが立つ。皆が警戒を強める中、『それ』は姿を現した。
「………………」
ひた、ひた、と、静か足取りで、こちらにゆっくりと近づいてきたのは、兵士の姿をした『人間』であった。
「お、おい……!」
その姿を認めた瞬間、トマスはその兵士の前に飛び出す。
それもそのはずで、彼はトマスに『土産を買ってきてやる』と、言いおいて、調査団の任に就いた兵士だったからだ。
「無事だったんだな!? 心配したぞ!」
「………………」
「お前ひとりだけか!? 他の皆は?」
「………………」
トマスの問いかけに、男は黙して答えない。
最初に、その異変に気が付いたのは、龍の忍者であった。
「トマス!! そいつから離れろ!!」
「えっ?」
トマスが、ハヤブサの方に振り返った瞬間。
ドグォッ!!!
派手な轟音とともに、目の前の男の身体が、真っ二つに裂ける。その中から、黒い、無数の蛇のような物体が、一斉に飛び出してきた。
「うあ………!」
あまりの事態に、トマスの脳は、周囲の状況の理解を拒む。ただ呆けたように、その光景を見つめることしかできなかった。
やはり、いち早く反応したのは、龍の忍者であった。
「トマス!! 離れろ!!」
抜刀しながら、ハヤブサは人間『だった』男に向かって走る。しかし、黒の蛇の方が、一瞬早く、トマスの腕にとりついてしまった。蛇たちは、ずぶずぶ、と、音を立てながら、トマスの腕に潜り込んでいってしまう。
「ぎゃあああああああああ!!」
激痛と、目の前で繰り広げられるあまりにもグロテスクな光景に、トマスは絶叫していた。蛇たちはさらに、腕からトマスの身体の方に進み、彼を食らいつくそうとしている。
「ちぃっ!!」
龍の忍者の決断は早かった。
たとえ、彼から後でどう恨まれようとも
『生命』には、代えられないのだ。
迷いのない白刃は、浸食されたトマスの腕を、一刀のもとに斬り落とす。
「────────!!」
声にならない悲鳴。
飛び散る鮮血と、切断された黒蛇の遺骸。
「止血をしてくれ!!」
ハヤブサはトマスの身体をひっつかむと、強引に兵士たちの方に押し戻した。そのまま、男の身体から、なおも湧き出てくる黒蛇たちと相対する。
「覇———————ッ!!」
蛇たちの身体を両断する。しかし、まだ幾何かの蛇が、ハヤブサの攻撃を避け、その背後にいる無防備な獲物たちに、襲い掛かろうとしていた。
ダンッ!!
乾いた銃声が、辺りにこだまする。ロシャが猟銃を発射したのだ。
ロシャの射撃は早く、そして正確だった。姫たちに向かう蛇を、ロシャの発射した弾丸が、次々に粉砕していく。
「トマス!!」
姫はというと、ハヤブサにトマスを託されてから、彼に向かって必死に呼びかけていた。
「トマス!! トマス!! しっかりしてください!!」
「う………! う………!」
低く呻くトマス。
その周りで兵士たちが、彼を止血するために、走り回っていた。
「もっと白い布を持って来い!!」
「しっかり押さえろ!! 緩めたらだめだ!!」
「トマス!! 死ぬなよ!!」
兵士の一人が、必死になって叫んでいた。
「死ぬような傷じゃない!! 絶対に、生きるんだ!!」
ダンッ!!
銃声とともに、動いていた最後の一匹の黒蛇が、肉塊となって飛び散る。それを見届けたロシャが、大きな息を吐きながら、構えていた猟銃を、下ろしていた。
「………これで、最後でしょうか………」
「いや…………」
龍の忍者は、ロシャの問いかけに、不吉な答えを返す。
現に、龍の忍者はその気配を捉えていた。
こちらに向かって迫ってくる、どす黒い、邪悪な気配を。
「………来るぞ」
ハヤブサは、苦無を6本取り出すと、印を結びながら、苦無に向かって『気』を込める。
「叭っ!!!」
ハヤブサの手から放たれた苦無は、トマスの治療を続けるナディール姫と、兵士たちの周りを囲むように、地面に突き刺さった。刹那、苦無自身に、ボウ、と、青白い光が灯る。
「これは?」
問いかけるロシャに、ハヤブサが短く答えた。
「結界だ」
「結界………」
反芻するロシャに、ハヤブサは少し補足説明をした。
「少しだが、『邪』を払う力がある。あまり強力ではないが─────」
「……確かに、何か『力』を帯びているようですね。特殊な波動を感じます」
「分かるのか?」
ハヤブサは、少し意外そうに、ロシャに問いかけた。それに対してロシャは、少し苦笑したような表情を見せる。
「私の一族は、どうやら『魔女』の流れを汲むものらしいのです」
ロシャの一族は、はるか昔───『魔女狩り』が盛んだった地域から、この国に流れてきていた。
特に、何か能力があったわけではない。ただ、人より『感が良い』というだけだったと伝え聞いている。
だが、自分の一族には、普通では考えられないような技が、伝わってきていたりするので、『魔女』という出自も、あながち間違いでもないのでは、と、ロシャは思っている。
「そのせいかどうかはわかりませんが、常人には感じられない『気配』のようなものを、時々感じることがあって………」
「ならば、分かるだろう? 今、こちらに向かって進んでくる『邪悪な気配』が……」
「確かに、そうですね……」
ロシャは、猟銃に、弾を込めながら言った。
「ただ狩りに来ているだけなら────とっくに、逃げだしているところです」
「魔の気配が強い。普通の武器では、通用しないかもしれん」
「……………!」
ハヤブサの言葉に、猟銃に弾を込めていた、ロシャの手が止まった。
「戦う手段はあるか?」
ハヤブサの問いかけに、ロシャは少し考え込むような仕草をしたが、やがて、自分の荷物の中から、一つの銃取り出し始めた。
「これならば、通用するかもしれませんね……」
その銃は、全体的に、白銀色の光を、うっすらとその身に纏わりつかせていた。そのせいか、どことなく神聖な『気』を感じるのは、気のせいだろうか。
「我が家に代々伝わる、『魔除け』の銃です」
そう言いながら、ロシャは銃を素早くチェックすると、懐から取り出した、白銀の光を放つ弾を、銃に丁寧に込めだした。
「銃も、特別性です。『魔除けの呪い』の儀式を経て、作り上げられたものです。もしかしたら、これなら効果があるかもしれませんが………ただ………」
「ただ……? なんだ?」
ロシャが少し口ごもったので、ハヤブサが問いただす。すると、彼は苦笑しながら言葉を紡いだ。
「あんまり、弾数を持ってきていないんです」
「……………!」
「こんなことになるんだったら、もっと、備えておくべきでした」
迂闊だった、と、ロシャは笑うが、なぜか、その笑顔が、『追い詰められて焦っている』と、言うよりは、『この窮地を楽しんでいる』と、言う風に見えてしまうのは、気のせいだろうか。
(余裕があるな………)
ハヤブサは確信する。やはり、この『ロシャ』という男は、相当に場数を踏んできているのだと。
おそらく、腕は相当立つだろう。
問題は、彼を信用していいものかどうか。
味方であるならば、これほど心強いことはないのだが。
(シュバルツ………)
ハヤブサは一瞬、遠く離れた場所にいる、恋人に想いを馳せる。
この局面、彼がここにいてくれたなら、これほど、心強いこともないだろうに。
彼はどんな時でも、絶対的に、自分の味方になってくれるから。
(…………!)
ハヤブサは、ブン、と、大きく首を一つ振った。
ここにいないヒトを、当てにしても仕方がない。自分の運命は自分の力で、切り拓いていくしかないのだ。
ふう、と、深く息を吐く。
近づいてくる、魔の気配。
「………来るぞ」
龍の忍者は、小さく警告を発した。
その言葉に、ハヤブサの築いた円陣の中にいる者たちは身を固くし、ロシャは、静かに銃を構える。
「お前たちは、その円陣の中から出るなよ」
ハヤブサは、兵士たちに忠告をした。
「互いに身を寄せ、護りあえ。そうすれば、『術』の効果が高まる」
「……姫様は、我らの中心に」
兵士の1人が姫に告げ、皆が、姫を背に庇うように、その周りを取り囲む。
「我らが姫様を、お守り致します!」
「……………!」
ダメ、と、姫は言いそうになる。しかし、その言葉が口から出ることはなかった。
これが、自分の『役割』なのだ。
これが、自分の『役目』で『立場』なのだと、そう悟ってしまう。
酷く痛感する。
自分の無力さを。
こういう時────護られるしかない自分は、なんて非力で、役立たずなのだろう。
だからこそ、肝に銘ずる。
絶対に、足手まといにだけはなってはダメだと。
落ち着け。
呼吸をすることを忘れるな。
大丈夫。
自分には、『最強の護衛』がついている。
必ず、彼をはじめとした皆が────脱出に繋がる糸口を作ってくれるはずなのだ。
そのきっかけを
そのチャンスを
見逃す真似だけは
絶対に しない。
刹那。
空気の流れが変わる。
洞窟の中が、一段と暗くなる。
シュルルルルル………
その音が、『何物かが洞窟の岩壁を這ってきている時に出る音』なのだ、と、悟った瞬間、姫の背中に寒気が走った。その音は、複数に枝分かれをし、こちらに猛スピードで迫ってきていた。やがてその影は、姫達のいる洞窟の空間に到達し、その周囲を壁伝いに、ぐるりと取り囲んでいく。
そして、確認する。
あそこにいるのは、我らの『獲物』
『獲物』ならば────
食らう べし
影の一つが鎌首をもたげ、壁からまるでミサイルが発射されたかのような勢いで、姫たちに迫っていく。
シャアアアアア!
闇の中、鋭い光を放つ白い牙は、過たず、兵士の喉仏を嚙み砕いたかに見えた。しかし、すんでの所で、頭は胴から切り離され、黒い血をまき散らしながら、四散してしまう。
「!?」
兵士達は、何が起こったのか、咄嗟に理解することが出来ない。その間にも、胴から切り離され、四散する頭は、四方に及んだ。
「あ…………!」
そのうちに、兵士の1人が気づく。蛇状の頭の間を壁伝いに疾走する、黒い影の存在に。
龍の忍者は、終始無言であった。
声すら立てずに、蛇の頭を次々と討滅している。
闇の中に紛れて繰り広げられる、静かなる戦い────では、何故、その兵士が龍の忍者の存在に、気づくことが出来たのか。
それはひとえに、抜刀された『龍剣』が放つ、まばゆいほどの白銀の燦めきが、有ったが故であった。
ハヤブサはひたすら、口の中で魔封じの『呪』を唱える。
それによって生じた、魔封じの力を、そのまま龍剣に伝える。
剣は、その力のままに、ハヤブサの無音の気合いと供に、蛇たちを粉砕していった。
(す、すごい………!)
圧倒的な強さを誇る者の動きは、また、美しさを伴っているものなのだと、その兵士は知る。彼は、何時しか恐怖することすら忘れて、彼の動きに魅入られていた。
(数が多すぎる……)
戦いながら、リュウ・ハヤブサは思った。先程から蛇の頭を落とし続けているのだが、どうしたことか、終わりが見えない。蛇たちの勢いと数は、増えていく一方のように感じられた。
(もしかして……『本体』が近いのか?)
嫌な予感がふつふつとわいてきて、ハヤブサは暗澹たる気持ちになる。
ここに、自分独りだけならば、特段恐れるものもない。
だがここには────自分が、護るべき者たちがいる。
この者達を庇いながら戦うのは、あまりにも危険すぎる、と、ハヤブサは判断していた。
引き潮だ。
とにかくここから脱出しなければ、皆が危ない。
しかし────
「……………!」
ハヤブサは、トマスを抱え込んでいる姫を見て、唇を噛みしめる。
彼女は、この状況においても、脱落者が出ることを、潔しとはしないだろう。「脱出は皆で」と、言い張り、独りだけ助かる、と言うことなど、断固として拒否してしまうはずだ。
隙を作らねばならぬ。
姫を『護衛する』と、言うのであるならば。
怪我人を抱えて、それでも皆で脱出できるだけの隙を────!
無茶ぶりだ。
だが、やらねばならぬ。
いや、やってみせる!
龍剣の閃光が、周囲の複数の蛇たちの頭を粉砕する。だが、それを逃れた一匹が、姫達の方に飛びかかろうとした。
「…………!」
しまった、と、ハヤブサが口の中で、小さく叫んだ瞬間。
ドン!!
派手な轟音と共に、蛇の頭が吹っ飛ばされていた。
次いで、漂ってくる火薬の匂い。
ロシャが、銃弾を放ったのだと、ハヤブサは悟っていた。
「よし! 効いた!」
ロシャから、思わず声が上がる。
「すげぇな! あんた!」
近くでそれを見ていた兵士の一人が、ロシャに声をかけた。それにロシャは、少し困ったような笑みを見せる。
「………ただ、いかんせん、弾の数が少ないのが、難点で………」
「少ないって………何発だ?」
「10発!」
バシッと、言い切られた言葉に、その場にいた全員が、はっと息を呑む。もちろんハヤブサも。忍者である彼は、戦いの最中、ロシャの言葉を拾っていたのだ。
「今1発撃っちゃったから、残り9発かな」
そう言いながら、再び銃を構えるロシャ。ハヤブサは、ぎり、と、唇をかみしめていた。
9発────想像以上に、少なすぎる。
ロシャをあまりあてにしすぎてはいけない。彼の銃は、本当に、ここぞ、という時に、使ってもらわなければ。
(くそっ!)
今は、状況に絶望している場合ではない。
手と足を動かせ。
絶対に、道を切り拓くんだ。
「覇あああああああああ!!」
裂帛の気合とともに、ハヤブサの身体から放たれる、神気をまとった黒龍。その龍の飛翔は、周りにいた無数の蛇たちを、あっという間に粉砕した。
今だ、走れ!
ハヤブサはそう叫ぼうとした。しかし、新たに湧いてきた蛇たちが、あっという間に、ハヤブサが開いた退路を埋め尽くしてしまった。
「チッ!」
ハヤブサは小さく舌打ちをする。
だが、一度駄目だったからと言って、あきらめるわけにはいかない。
もう一度
もう一度だ。
『気』を整えるために、ひとつ、大きな息を吐く。
その時、兵士から
「何だあれは!?」
と、悲鳴のような叫び声が上がっていた。
「どうしました!?」
ナディール姫が驚いて振り向くと、悲鳴を上げた兵士が、恐れおののいたように、ある一点を指さしていた。
「ひ………姫様………! あ、あれ………ッ!」
「え…………?」
兵士が指さす方を見ると、ひたすらな『闇』が広がる。
だが、よく見ると、そこに蠢く何かがあった。
「何………?」
恐怖を感じたが、目を凝らす。
このとき彼女は何故か、『それを確認しなければならない』という思いの方が強かった。
やがて、蛇の威嚇の声とはまた別の、地を這うような声が、姫の耳に届きだす。
「……………!」
常人よりも夜目が利き、聴覚が鋭い龍の忍者は、それが故に、その正体をいち早く看破していた。
『それ』は、ずず、ずず、と、いざるような歩き方をしていた。
二息歩行の獣か。
いや、そうではない。
複数の足が生えている。
人間の足だ。
否────人間『だった』者たちの足だ。
(調査団の者たちか………!)
ハヤブサは、ぎり、と、歯を食いしばった。
姫の願いが、最も残酷な形で、踏みにじられてしまったことになるのだから。
「そんな………!」
姫も、それに気づいてしまったのだろう。絶望の色の混じった悲鳴を上げる。そばにいた兵士たちも、調査団の者たちの、あまりにも無残な姿に、皆がそれぞれに、言葉を失っていた。
そんな中、ただ一人ロシャだけが、冷静に銃をその本体に向けていた。
ドン!! と、響く轟音。
ロシャの放った弾丸は、ずるずると歩いてくる調査団の者たちの頭の一つに、正確にヒットした。
「ギャッ!!」
頭を撃ち抜かれたクリーチャーの動きが、一瞬止まる。
「効いたか!?」
叫ぶロシャに、「いや、まだだ!!」と、ハヤブサからの警告が、かぶさってきていた。果たして、龍の忍者の言葉通り────そのクリーチャーの動きが止まったのは一瞬で、また、唸り声をあげながら、じりじりとこちらに向かってきている。
「く…………!」
ロシャがもう一度銃を構える。
「ロシャ! 待て!!」
ハヤブサが、蛇の大群と戦いながら叫んだ。
「無闇に銃を撃つな!! 一撃必殺できる場所を見つけなければ────!!」
「………………!」
ぎり、と、歯を食いしばったロシャが、一瞬、銃の構えを解く。だがすぐに、構えなおした。
「でも、このままでは────!!」
ずず、ずず、と、いざるように近づいてくるクリーチャーの、足を撃つ。だが、その歩みは止まらない。
「俺はいやだ!! こんなところで死にたくない!!」
悲鳴のような、ロシャの声が、洞窟内に響き渡った。
「おふくろと親父と、5人の弟妹が、俺の帰りを待っているんだ!!」
その叫びを聞いた時、ハヤブサは確信した。どうやら、ロシャが抱えている『生きて帰りたい』と、願う気持ちは本物だと。
その気持ちだけは、今ここで、信用するに足るものなのだと。
「ならばなおさら、冷静になれ!! ロシャ!!」
龍の忍者は、懸命に呼びかけた。
「この手の類のクリーチャーは、表面ばかりを傷つけてもだめだ!! この身体を動かす、『核』のようなものがある!!」
「え………!」
「それを撃ち抜け!! そうすれば、奴を倒すことができるはずだ!!
「核!?」
「核だって!?」
ハヤブサの言葉に、兵士たちが反応する。
助かるかもしれない、可能性が見えてきたのだ。自分たちも何か手助けができないか、と、思ったのだ。
龍の忍者は、戦い方が分かっている。あのクリーチャーを動かす、『核』のようなものを探せばいい。見えるところにあれば一番いいのだが、身体の奥深くに『核』がしまい込まれている、というのなら、表面をそぎ落として、そこをむき出しにすればいいだけの話だった。
だが────
(くそ……ッ! どうやって、それを実行すればいい!?)
ハヤブサは、蛇の大群に囲まれてしまっている現状を憂う。
自分一人ならばいい。
しかしここには、護るべき者たちがいる。
自分が彼らのそばを離れてしまったら、あっという間に、魔獣の餌食となってしまうだろう。
それだけは駄目だ。
『姫の護衛』という任務を請け負っている以上、姫を喪う可能性がある行動は、断固として避けねばならぬ案件だった。
できれば、姫たちに近づける前に、あのクリーチャーと直接戦いたい。おそらく、この中であれと互角に渡り合えるのは、自分だけだろう。戦って、核さえ見つけ出せたなら、ロシャの腕前とあの弾丸なら、確実にあのクリーチャーを葬り去ることができるはずだ。
(せめて………俺と同じ腕を持つ戦士が、もう一人いれば………!)
一瞬、脳裏に愛おしいヒトの姿が浮かぶ。ハヤブサは、慌ててブン、と、首を振った。
いつの間にか、頼ってしまう癖がついている。
独りで戦っていたときは、思いもしなかったことなのに。
「撃て撃て────!!」
兵士たちが一斉に、クリーチャーに向かって発砲し始めた。弾は、クリーチャーに何発か当たる。しかし、当然のごとく、その歩みは止まらない。
「あきらめるな! 撃て────!!」
兵士たちは懸命に、銃を撃ち続ける。
「……………!」
ロシャは、兵士たちの行動を、複雑な面持ちで見つめていた。
彼らの銃弾は、クリーチャーにはダメージが与えられていない。全くの無駄な行動にも思える。
だがそれを
『無駄』と、斬り捨てるか。
それとも────
「……………」
ロシャは、無言で銃を構えた。
万が一つの『奇跡』にかけるために。
「……………!」
兵士たちの行動は、当然ハヤブサも見ている。
何とか、手助けをしてやりたい、と、思う。
彼らの行動を、無駄だと嘲笑う選択肢は、当然ハヤブサも、持ち合わせてはいかなかった。
だが、現実は、彼らの銃弾は、ただクリーチャーの薄皮一枚を削り取るぐらいで、全くダメージを与えられてなどいない。それどころか、クリーチャーの接近は、それから派生していると思われる蛇たちの勢いを、ひどく強くさせていた。
(くそっ!)
襲い掛かってくる蛇たちを、斬る。薙ぎ払う。討滅する。
だがそれが間に合わなくなるほどに、襲ってくる蛇たちの勢いが激しい。
時折、ハヤブサの防御をすり抜けて、姫たちのそばまで接近してしまう物も出てくる始末だ。
「ギャッ!!」
その蛇たちは、ハヤブサの貼った結界に触れると、悲鳴を上げながら消滅する。
「─────ッ!!」
しかし、結界に触れられることで、ハヤブサの方に、少しずつダメージが跳ね返ってきていた。
やはり、引き潮だ。
これ以上ここにとどまり続けると、何らかの犠牲が出てきてしまう。
龍の忍者の生存本能が、そう強く警告を発するのだが、打つ手がないのが現状だった。
身動きが取れない。
姫一人を強引に連れ出しても、彼女は絶対に拒否するだろうし、そのあと、彼女の護衛の任に就けるかどうかも怪しくなってくる。
そういう彼女であるからこそ、兵士たちも必死に彼女を守ろうと足掻いているのだ。その主従の想いを踏みにじる真似など、出来ようはずもない。それが故に、その行動の選択肢は、最初から消されているも同然だった。
(何か手はないのか? 何か手は────!)
考えることを、止めてはいけない。
それは、絶対だった。
思考することをあきらめてしまっては、それはすぐに自らの『死』へと直結してしまう。
あきらめてはいけない。
『生』への執念を。
しかし、ならばどうする?
何か方法はないのか?
何か、何か─────
皆がぞれぞれに必死に足掻く。
そんな中──────思わぬ助け舟が、突然に訪れてきた。
戦う君に、花束を
書きあげられるよう頑張ります。