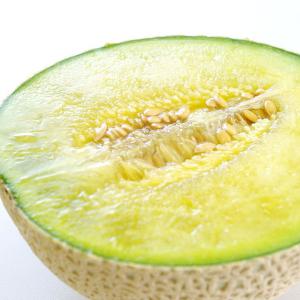鳥小屋
1.夏休みの終わりに
文鳥が死んだ。夏休みも終わり頃、関東近郊の温泉旅行から帰ってくると、乾いた羽を閉じてケージの底に横たわっていた。最初に発見したのは沙耶だった。
「さっくん、トビが……」
帰省する前に、水も餌も十分に用意しておいた。これまでは週の半分近く家を空けるようなときには親しい友人に預かってもらっていたが、二、三日程度なら何ら問題はなかった。それで今回もという運びになったわけだが、その末の突然の死。餌箱には穀類が、タンクにも水が残っている。少なくとも、餓死ではないはずだった。死因はわからない。けれど、聡たちが家を空けている間に、文鳥は人知れず鳥知れず一羽ぽっちで死んだ。
沙耶はケージの前にへたり込んでいた。体をぴくりとも動かさず死骸にひたと視線を注ぐ。涙も嗚咽も漏らさない。現実を頑なに拒否しているのだと聡には判る。
「餓死じゃないみたいだし、例え俺たちが家を空けなかったとしてもトビは死んでたよ」
「わかんないよ、そんなの。それすら、わかんない」
沙耶は冷たいトビを掌に乗せ、長い栗色の髪を垂らしながら、やっと泣いた。
「……例えそうだったとしても、ひとりで死なせちゃった」
聡は傍らで、ひくつく沙耶の背中を撫でた。沙耶がぽつり言った。
「……さっくんは哀しくないよね、やっぱり」
一寸、聡の掌が止まった。けれど、すぐにまた背を擦り始める。そんなことないよ、と長年の連添いには繕えぬ弁解を口にしながら。
トビを飼い始めたのは五年前のこと。同棲を始める記念としてペットを飼いたいと沙耶が訴えたのがきっかけだった。当初、聡は反対した。世話に手間がかかるし、臭いもする。そう主張しても中々引かない沙耶に降参し、ならば植物にしようと提案した。それなら、水やり程度で済む。植物なら日々の成長がわかりやすく目に見えるから、過ごした年月がわかりやすそうだと沙耶は言った。けれど、動物が良いと曲げない。撫でたら啼いて、お腹が空いたら騒ぐような、そんな手間のかかる生き物が良い。そうだ、鳥が良い。うんと可愛い鳥を飼おうよ、私がきちんと面倒みるから。
普段は自身の欲望を強く出さない沙耶だが、こうと決めたら引かない。説得を諦めた聡は辟易しながらも一緒にペットショップへと向かった。そこで沙耶が見初めたのが、トビだった。小さく、そして控えめな色彩。聡も妥協できる範囲だった。店員は羽の筋肉を切ることを勧めた。ケージを掃除する際の脱走を防げるそうだ。切らないでください、沙耶はそう応えた。そうしてふたりと一羽の同居生活が始まった。
トビという名前は、鳶に由来する。沙耶が中学生の頃、家の上空ではよく鳶が啼いていた。山が深い沙耶の故郷だ、盛夏には蝉が、錦秋には鈴虫が、厳冬には雪が啼く。そして、鳶も啼く。幼い沙耶には、その声が山の神様の楽の音に聴こえたという。四季折々の音はその季節が始まってしまえば、すべて日常の背景音になる。けれど、鳶の啼き声は、いつも予兆なしに響いた。日常の膜を破るようなその声は、彼女に形而上の存在を想わせた。
やがて沙耶も、声の主が鳶だと知る。山の神様は、自由に空を飛ぶ鳥だった。少女は、いつか自分も……。山の神様に自身の将来を重ねた。文鳥を見たとき、沙耶は山の神様を思い出した。そうして二一六〇円でふたりに購入された文鳥の雛はトビと名付けられ、かごの中でひっそりと生涯を終えた。聡は沙耶の背から離れて荷解きに戻っていた。衣類を洗濯機に入れ、歯ブラシや整髪剤など、細々とした道具をあるべき場所に収めていく。ちらり見ると、沙耶は依然ケージの前に座っている。透き通るような、陽光を吸えば更に軽やかな栗色の髪が、今は重く彼女の表情に影を落としていた。
――死骸はどうすればよいのか。
聡は窓を開けながら考えていた。よく餌を購入していた店舗が引き取ってくれるものなのか、それが駄目なら燃えるゴミとして出しても良いのか……。
「ご飯は……食べられる?」
沙耶の分まで片付けを終えた聡は、そう訊ねた。食べる、短く発した。
移動の疲れを残したまま昼食を作るのは面倒だろうと、帰りに東京駅で購入しておいた駅弁をダイニングに広げると、ふんだんに盛られたカニやイクラ、ウニなどの魚介が姿を表わす。海無し県の帰りということもあり、沙耶が魚介を食べたいと言ったのだった。北海道産の海の幸弁当、一個一二六〇円。聡は正直、長年の慣習から旅行に行くだけなので、旅行先はどこでも好いと考えていた。けれど今は、目の前の海の幸弁当が他の種類に変わっていた可能性を思い、海沿いの温泉地を択ばずに良かったと実感している。ふたりは弁当をもそもそと口に運んだ。
「埋めに行こう」
ぱっと沙耶が顔を上げた。
「埋めるって……どこに」
「近所の公園に」
「良いの、そんなことして」
「良いに決まってるじゃん」
沙耶は弁当を口に含み、やがて呑みこんだ。
「ほら、さっさと食べて行こう」
ふたりは百円ショップでシャベルとタワシを購入し、近所の公園を訪れた。住宅街にあるため普段ならば子供たちで賑わうこの公園も、今日は人が少ない。夏休みもあと数日で終わる。きっと子供たちは家に籠り宿題を片付けているのだろう。明日から、そんな子供たちと格闘する日々がまた始まる。沙耶は園内に生える一際高い公孫樹の下にトビを埋めた。俺が掘るよ、聡はそう言ったが、いいから。さっくんはケージを洗ってきてよとタワシを渡された。ケージを洗い終え公孫樹に戻ったときには、沙耶は埋葬を終えて、安物の園芸用シャベルを土に刺し、合掌していた。聡はトビの埋葬に参加を許されなかった。
夜、沙耶は聡の脚に自らの脚を絡め、手で彼の脇腹を優しく擦り、首筋を吸った。月に数度しかない彼らの弄りの、中でも珍しい沙耶からの求め。長年連添った恋人たちの、徒労感にまみれた夜の務めだった。そこに、性的な興奮は薄い。それを純真な心の繋がりと見做すには、あまりに義務的な営みだった。けれど、今晩の沙耶は微熱を帯びていた。聡はそれを、喧嘩の後の性行為のようなものか、単に寂しいのか。そう当たりをつけ、応じた。
この同棲も、当初は結婚を見据えたものだった。それがいつしか、暦が五度巡った。既に事実婚のようなものだ、後は書類を出すだけ。判を押せば何かが決然と変わるとは思えない。結局、このだらだらとした日常が続くだけ。それならば……と、ふたりともこの一歩を踏み越えない。後押しがない、きっかけがない。結局のところ、展望がないのだった。
果て、ふたりは眠った。そして、翌日も過ぎた。
目覚めると隣に姿がない。起きぬけの格好でリビングに行くと、沙耶は既に化粧を始めていた。おはよ、と呆けた声をかけ、洗面所で歯ブラシを口に入れキッチンへ。いつも通り調理台の上に置かれた皿にはトーストとハムエッグが用意され、傍らに置かれたコーヒーメーカーにはちょうど一杯分が沈んでいる。マグカップに注ぎ、朝食をリビングテーブルへ持ってゆく。そして、洗面台に戻って口を濯いだ。洗顔クリームで顔を洗い、電動シェーバーで髭を剃る。
鼻孔を擽るファンデーションの匂いを嗅ぎながらの朝食。口に運びながら携帯端末でSNSの更新を確認していると、
「さっくん、私もう出るよー」
マスカラを塗りながら、沙耶が言う。
急いで口に含み食器を片付けて、クローゼットからスーツと半袖のシャツを取り出した。お待たせ、と声をかけると、沙耶も終えていた。戸締りを確認し、部屋を出ようとしたところ、部屋の隅にあったゴミ袋を手渡される。生ゴミ臭いんだから、続けて言われる。生ゴミ。袋片手に振り向くと室内に不自然に空いたスペースがあった。トビがいた場所だった。
昨日の沙耶は、やはり寂しげだった。俯き、口数も少ない。それが、今朝には普段通りの振る舞いに戻っていたので、それ故聡はトビの死を忘れかけていた。一日過ぎ、沙耶の哀しみは薄れたのか。と、彼は考えたが、一昨日クローゼットに仕舞ったはずのケージが置いた場所になかったことに思い当たる。奥底、うかつに眼に入らない場所にしまったのだろう。
陽光が肌を刺す。むわっとした暑気が襲い、汗がじんわりと膨らんだ。ゴミ捨て場に袋を置き、ふたりは駅へと歩きだした。
「今日は友美とご飯食べに行ってくるね」
低いパンプスで地面を蹴りながら沙耶が言う。
「じゃあ、俺も末田でも誘って呑み行くかな」
ふたりはいつも通り駅で別れた。沙耶は渋谷区のIT会社でエンジニアとして働いている。一方、聡は江東区で小学校の教員として勤めていた。
電車に揺られながらメッセージを一件送る。二つ返事だった。山の手線に乗り換え、総武線に揺られゆく。駅に着けば、見知った顔の生徒たちが列をなしており、彼らがばらばらに挨拶をしてくる。そして、近所の人々も。総武線から更にローカル私鉄に乗り越えた東京都の隅っこ。ここは聡の、勤務地でありながら故郷でもあった。
「Dorothy Little Happy最高。いやあ、ほんとにね。八月頭にお台場でTOKYO IDOL FESTIVALが開催されたんですよ。もうね、最高、でした。まだ開催七回目なんだけど、今年の参加アイドルはひゃく、ごじゅう、よんくみ、です。この数ね。凄いわ。アプガとか、モ!とか、有名どころだとでんぱ組とかね。まー凄い面子が揃ったわけですけれども、Dorothy Little Happy。KANAちゃん。ダントツに最高でした」
デスクに座るなり、隣に座る末田が捲し立てた。乏しい語彙とは裏腹に目が輝いている。続く末田の感想が唾の礫となって聡のデスクを濡らすのを、不快感を露わに拭きながら、適当に相槌を打つ。
末田は聡の同期で、また小学生以来の幼馴染でもある。とは言え、同級だった小中学生の頃から特別親しかったというわけでもない。明るい性格で運動もできたためクラスの中心人物だった聡と反対に、末田はいつも教室の隅にぽつんと坐していた。空と本をよく眺めた少年は中学に上がると美術部に入って僅かな友人も出来たが、聡から見れば彼らは地底人に過ぎなかった。陽光の煌めきを知らず、薄黴の生えた白熱電球が仄く照る洞窟に住む、脂身から肉汁滴る牛豚(にく)も喉を潤すあまい果実も味わえない、蚯蚓や百足(ゲテモノ)を生食する地底人。やがて、地底人は迫害されるようになった。迫害とは言え、劇的に惨いことはしない。「みなさあん。これが、世にも珍しい地底人であります。」と見物人を笑わせるだけだ。その見物人の一人が聡だった。
高校進学を機に別れたふたりは、当然連絡を取り合わない。別々の人生を歩んで来て、このかつての学び屋で偶然の再会を果たした。末田は眺める対象が本と空と画布から、思春期の少女たちになっていた。あのときの地底人はこうして大人になってみると、自分と何ら変わらぬ人間に思えた。
時刻は八時十五分。一時間目が始まる十五分前。隣接した校長室から恰幅の良い校長が現れ、その傍らで教頭が声を張った。教員たちが立ちあがったのを認めるように頷くと、校長が口を開いた。
「皆さん、おはようございます。」
教員たちは複唱した。
「長い休み、ゆっくり出来ましたか。とはいえ、我々は教師、聖職者ですから。長期休暇とは言え、羽目を外し過ぎるということはなかったと信じておりますが」
教頭がこちらを、というより末田を一瞥した。彼の趣味は総じて評判が悪い。
「二学期には文化祭も開催されます。多くの保護者、近隣住民の方々がいらっしゃいますが、そのときに我が校の評判を損なうことのないよう、今学期も大いに励んでください」
そう言い、自室に戻って行った。教員たちは再び座り、やがてぱらぱらと担当クラスに向かって行った。聡も席を立った。
教室には黒々と焼けた生徒たちがいた。未だ細く未発達な肢体がこんがり仕上がっている中で、六十の瞳が爛として輝いている。
挨拶を済ませ、全体集会があるから体育館に移動するよう告げる。生徒たちは立ち上がり、ぞろぞろと教室を出て行った。その際に、幾人かの生徒たちに先生夏休み何してたの、などと話しかけられ、色々したぞ、と応えながら、ほら雑談は後にして体育館に行けと、声をかける。わあ、先生恐い、ワンピースを着た少女たちはけたけたと笑いながら駆けてゆき、ほら廊下走るなよと再度声を張る。空になったのを確認し、聡も教室を後にした。
熱気がむわりと籠る体育館の中で校長の長弁舌を聴くのは教師側になってもやはり苦痛で、今から二十年前に彼らと同じく体育座りで早く終わんないかなあとぼんやりしていたのを思い出す。末田が肘打ちをするので確認すると、聡の担当クラスの生徒がひとり、船を漕いでいた。
始業式なので挨拶が終えれば下校となる。皆、夏休みの思い出について語らい、この後の予定について相談し合っていた。少年たちの黒い皮はところどころ剥けてピンク色になっており、それらを勲章のように見せびらかしてはポリポリと掻いて、皮を床に散らす。引っかき傷や痣も同様。すべてが冒険の思い出である。少女たちの方がやや大人で、身体の傷を自慢する少年たちを冷ややかに嗤いながらも、既に好いた男子がいるのだろう。その瞳には小動物のように透明な輝きが宿っていた。
職員室に戻って明日からの授業の準備や今学期のイベントの詳細などを確認していると、彼の担当クラスの飯島倫子と門倉真澄が来た。両手には問題集と紙の束を抱えている。
「先生、夏休みの宿題です」
聡はデスクの一角を空け、礼を言った。
「お、えらいなあふたりとも。特に飯島は女の子なのに、重たい荷物持って偉いえらい」
末田が倫子の頭を撫でると、彼女は頬を赤らめ俯きながら、日直ですからと漏らした。一寸視線を感じた聡は、真澄の頭を撫で「真澄もありがとうな」と改めて言った。彼は痒いのを我慢するかのように、頬を強張らせ唇を上向かせた。
「……おい、末田。今のもアウトだ」
倫子と真澄が去った後、他の教員に聴こえないよう耳打ちをする。
「え……今のも、なのか。」
予想外という風に呆ける末田。彼は生徒へのスキンシップが激しい。意識しての行動なのかは不明だが、特に女子生徒において。更に、それは倫子に対してより顕著であった。以前、ふたりで呑んでいる際に、末田の好きなアイドルの対象年齢はどこまでなのか、小児性愛の傾向があるのではないかと確認したことがあった。聡だけではなく、他の教員も関心を寄せている問題でもある。その傾向があるならば、教員として非常に危うい。末田はそれを否定したが、そう否定したところで、風向きが悪いのは変わらない。そこで末田は、過剰なスキンシップを取ったときには注意してくれと聡に頼んでいたのだった。
「また一層気をつけなくちゃだなあ」末田はそう言い、誇張気味に肩をすくめた。
「ところで、久しぶりだし呑みに行かない?また余計に出すよ」
聡が注意をしたら、呑みに行く際に多く出す。これがふたりのルールだった。
「ごめん。今日は沙耶とご飯食べる約束してるから」
じゃあぼくは帰ってDorothyのDVDでも観るかな、末田が腕の筋を伸ばしながら言う横で、聡の脳裏には去り際の倫子の表情がぬめりとこべりついていた。あとけない内に篭る、諦念を含んだ嫌悪感。まさか……と、冷たい汗が襟を湿らせていた。
十七時、ベルが鳴る。定時を迎えた教員たちは、初日だからということもあり、足早に消えてゆく。ひとり、またひとり帰ってゆく中、末田も既に消えていた。十九時には晩夏の空は暗い。見計らい、聡は校舎を後にした。
聡は鴬谷駅で降車した。駅近くのコンビニでビール数缶と適当な乾きもの、煙草一箱を購入して、山手線の線路に沿うように建つホテル群の一角、その一室に入った。
「せんせえ、遅いよ」
ガラステーブルに置いたビールをぷしゅっと開き、小ぶりな唇からくぴりと一口呑んだ後、艶やかなマスカラが煌めく二重瞼で上目遣いに彼を舐め、鼻先に缶を差し出す。愛生(あき)が緩やかに缶を傾ければ、聡は鼻先に甘たるい愛生の口紅の香りを感じながら嚥下する。口に含みそこねたビールが顎を伝い襟に染みた。愛生はそのまま、聡の舌を吸った。口内で絡まる愛生の舌が徐々に微熱を帯びてゆく。聡は愛生の握る缶を手に取ってテーブルの上に置き、彼女をそっと押し、ベッドの上に横たわらせた。……。
再び口にしたとき、ビールはすっかりぬるくなっていた。
「飯、注文するけどどうする?」
部屋に用意されていた出前表を掲げて聡は訊ねた。女は煙草を吸いながら首を振った。
「ごめんね、今夜は早く帰らなきゃ。倫子が待ってる」
帰り際の倫子の表情が頭を掠める。愛生は、飯島倫子の母だった。
愛生が部屋を出ていった後、聡は丁寧に体を洗った。上がると、服にも消臭剤を振りまいてホテルを後にした。
2.読書感想文の不思議
帰宅した聡は、鞄から読書感想文の束を取り出した。放課後、凛子が運んでくれたものだった。リビングテーブルの上に広げてビール片手に採点を始めてゆく。
いつ頃からか聡は、読書感想文の採点には明確なルールを課していた。
一つ、通読した様子が見られるか
二つ、著者が訴えたいテーマに触れているか
三つ、日本語として正しい文章になっているか
平たく言えば、読む、理解する、書く。これら三つが読書感想文の意義である、それが聡の考えだった。言語力を育むことが読書感想文の目的だと解している聡にとって、情緒は二の次。次点に評価されるものに過ぎない。
教員の中には、情緒を高く評価する者もいた。テーマの理解や正しい日本語を使うこと以上に、豊かな感性の発露を何より重視して採点を行う教員。聡は内心、そういった教員たちを馬鹿にしていた。確かに、子供たちの感性には時折、目を瞠るものがある。愛と純真に満ちた解釈や、超然とした楽観的かつ希望的解釈……。子供は無地の紙だ。そして、成長とは白紙に色を塗りたくってゆくことだ。我々の仕事は、それが美しく調和の取れた色合いになるよう補助することにある。その為に必要なのは、チューブから美しい色を捻り出すことではなく、配色に対する理解を得させること。そういった考えの元、聡は採点を続けていった。
頁が進めば、ビールも進んだ。ほろ酔いになりながらも明確な基準を守ってさくさくと進めていくと、ただいま、と沙耶の声がした。顔が赤く、足元が覚束ない。すっかり良い気分になっているようだった。彼女はソファに座る聡を見つけると、
「あ、お酒呑みながら仕事してる。いけない先生だ」
と言いながらソファ越しに彼に抱きつく。
「私もお酒呑む」
と、呟くが、それを制して聡は立ち上がり、冷やしておいたビールを空けて呑んだ。
「沙耶呑みすぎ。もう今日はやめときなよ」
「もしかして最後の一本?最悪だ」
そう言いながら、ソファの背に腹から倒れ込んだ。聡は再び採点に戻った。
「読書感想文か……懐かしいな」
重心をソファの背に預けたまま、ぴんと背中を張り九十度に体を曲げた沙耶は、原稿用紙を一枚手に取り眺めていた。放っておくと、やがて腕をぴんと伸ばしずるずると滑り落ちて行った。体がテーブルの下に隠れ、太ももだけが露わに残る。
「なにこれ。この子凄いうまいよ」
体勢を立て直し、聡に差し出して言った。
「親御さんが書いたのかな。私だって、こんな上手くかけないもの」
『驟雨の都』を読んで
奥伊豆の山懐、鄙びた温泉街で男が蝶を眺める場面から物語は始まる。邯鄲の枕を引かずとも、蝶は幻。異界へ誘うモチーフである。男は世相から外れた保養地で、さらに人の外へと向かう。そこで、男は化物との甘い幻に溺れる。
本作は大正を舞台に民話を扱った、古典主義的な小説である。その意義は西洋化に甘い夢を見た時世に日本の伝統を、夢として捉えなおそうという試みにある。化け狐の女が「私たちはこれから、蹂躙されるのさ。アンタたちに何度も殺される」と言う。この言葉は、平成を生きる我々をも貫く言葉なのだ。
低学年の頃、私は蝶の羽を切ったことがある。蝶は地べたでぴくぴくと体を動かしていたが、私はそれをケラケラと笑った。おそらく、その蝶は数日で死んだろう。そのように異界を葬った我々でも、夜には夢を見る。夢は内部にある。それでも、我々は外部の夢たちを今も殺し続けて生きている。
名前には門倉真澄とある。成績も運動も平凡、特筆するところのない生徒だ。悪戯だって進んで行うような子ではない。そもそも、悪戯で小学五年生が書ける文章ではなかった。では沙耶の言う通り、保護者が書いたのか。けれど、何の為に。こんなことをしたところで、子供の内申が悪くなるだけ。益はない。
第一、読書感想文の課題図書は主催の社団法人が毎年決めており、聡が勤める小学校もそれに沿って宿題を課していた。その結果、校、県、国の優秀作品が決められる。自由読書の賞も存在しているが、聡たちの学校ではそれを認めていなかった。そして、門倉が書いた『驟雨の都』という書籍は、課題図書ではない。
聡は携帯端末で書名を検索した。けれど、期待した結果が出てこない。
「……なんか不気味ね」
沙耶はそう言い、風呂場に消えた。やがて水の流れる小気味良い音が聞こえてきた。聡はビールを煽りながら、ひとり考えあぐねていた。
一日の授業も終わり、後は事務作業を残すだけ。末田は翌週末に催されるライブに想いを馳せていた。
ユニットは『Fami.』という地下アイドル。動画サイトを中心に活動してライブはあまり行わないといった、身体を伴ったコミュニケーションよりも、ネットを通じた活動に重きを置いているのが特徴だった。例えば、SNSでのやりとり。Twitterでの一リプライが三百円、メンバーからファンへの一分間メッセージ動画なら三千円と、そのサービスは多岐にわたる。ただ、身体的なコミュニケーションは徹底的に除外されているため、通話や握手会の類は禁止されていた。稀に開催されるライブも一風変わる。場所は毎回異なる賃貸マンションの一室。室内には家具が一式用意され、ダイニングソファは長年の荷重から人ひとり分沈み、ラグには醤油らしき染みが淡く広がる。キッチンには調理器具が、シンクでは使用済みの食器が水桶に沈む。ときには、室内に干された衣類に幼げなリボン付きの下着が混ざることもあった。
設定では、彼女たちには身よりがない。母も父も不在。友達と呼べるのはグループメンバーだけ。幼い彼女たちは「優しい大人」から助けを乞うことでしか生きていけないため、こうして春を売っているそうだ。そこに、彼女たちのパトロンたるファンたちが彼女たちの住まいを訪れ、設定上の彼女たちの日常空間内で、ある者はソファ、ある者はダイニングテーブルから彼女たちのパフォーマンスを眺めるという仕組みになっていた。
末田が時折、厭らしい笑みを浮かべながら齢十五ほどの少女たちについて夢想していると、教室から戻ってきた聡が隣のデスクに腰かけた。表情がどことなく重い。「どうした。なんかあった?」妄想をやめて聡に訊ねる。
大したことじゃないんだけど。という言葉から始まった話は、少し奇妙なものだった。
あれから数日後、夏休みの宿題すべての採点を終えた聡は、件の読書感想文について訊ねるため門倉を放課後に残らせた。書いた動機を聴いても門倉は居心地悪そうに体を揺するだけで、口は固く閉ざしたまま。質問を変えることにして、あれは誰が書いたんだと訊ねてみても、口を開いてはくれない。
その後も辛抱強く問い続けたが、結局門倉が口を割ることはなかった。普段は気の弱い門倉がここまで意固持になるからには何か理由があるはずだった。が、そこまでの道程は遠い。埒があかない、そう思った聡は書き直しを命じ、そうして問答から三日経った今日のつい先ほど、読書感想文の再提出を受けたのだった。顛末を話すと、聡は二枚の原稿用紙を末田に渡した。
一枚目、確かに上手い。読書家であった末田が読んでも納得の出来だった。決して、子供が書けるようなものではない。通読し、用紙を捲る。
二枚目、……平凡な出来だった。紆余曲折する論旨に時折崩れるてにおは。成績ならば可、十人いれば六人がこの程度、という位の出来だった。
「……これは教師としては、対応に困るね」
末田の意見は尤もだった。
文化祭では様々な展示や発表が行われる。各クラブや委員会の成果掲示に自由研究の発表のほか、目玉であるクラス対抗の合唱コンクールなど。保護者が子供たちの学校生活を理解できるような内容が揃うわけだが、予定には読書感想文の発表も組み込まれていた。
これは、保護者からの批判により一度は廃止された慣習だった。演劇の主役を複数人で演じることに端を発し、徒競争の横一列ゴールイン、合唱コンクールでひとり大声で唄う生徒を規制までさせた平等の掛け声は、やがて静まった。競争を未来に持ち越したところで、意味はない。むしろ不平等さを子供に教えることが大切ではないか。ただし、あくまでルールは平等であるべきだと訴える者が多かったため、発表会の復活とともに、作文は課題図書のみに限定されたのだった。
そうして、各クラスから選ばれた優秀者は体育館で発表を行い最優秀賞が決定される。それが校内代表となり、県の優秀賞作品候補に登録されるという流れになっていた。
門倉が本当に自らの実力で書いたのならば、この文章力を以てすれば校内代表は確定。内申書にも大きく箔が付く。
「ぼくなら、もっと詳しく話を聞くかな」
「いいよ、一度書き直させたわけだし。ネットでコピペでもしたんだろ」
そして、倫子の感想文も見せてくれと末田がせがむ。押しに負けた聡がそれを手渡すとそれを読み、感嘆の声を上げた。
「去年より上手になってる。しっかり読書をしている証拠だね」
興奮する末田から倫子の作文を取り返して、これやるよ、と門倉が書いた一枚目の作文を渡した。受け取った末田は、顔を顰めながらもそれを自らの抽斗にしまった。
3.幽霊
教頭に呼ばれたのは翌週のこと。日中の授業と毎週火・木曜に行う放課後の合唱練習も終わり、職員室でコーヒー片手に僅かな休憩を取っていたとき、不意に名前を呼ばれた。隅にある応接スペースで向き合うと、教頭は砂を噛むような表情をしていた。困ったねえと呟く様は、まるで演技をしているように嘘くさい。聡は詳細を訊ねた。
「区の外れに廃ビルがあるだろう。もう何年も解体されずに放置されている。君のクラスの生徒たちがそこに忍び込んだらしい。それで、警備員に捕まったそうだ」
驚きは少なかった。子供たちが行う悪戯でも比較的軽い方で、むしろ聡は安堵しているくらいだった。
「それで、警察には」
「届けていない。私たちに任せてくれるそうだ」
これも予想の範疇だった。不法侵入程度なら、余程のことがない限り警察には通報しない。所詮は子供のやったこと。彼らも大ごとにはしたくないのだろう。
内々に処理してくれ……、教頭が言う。但し、と続けた。
「これをきっかけに生徒たちの中で、タンケンが流行しても困る。慎重にね」
聡は時折、教頭のこの権威主義的な態度が癇に障った。教師を続けていれば、人は多かれ少なかれ偉そうになる。最早、職業病の一種だ。思春期の頃に観た学園ドラマに、必ず登場した抑圧者としての教師。そのイメージが教頭と度々重なった。また、その重なりに気がついたとき、聡は薄ら寒い気持ちを味わいもした。ああ、俺は今その教師になっているんだ。
内々に、かつ慎重に。その言葉を聡は了承した。
翌日の放課後、聡は教頭から名前を聴いた生徒たちを残した。生徒たちが次々に下校し、校庭からは朗らかな声が響いている。残された生徒たちは面々を見渡し、その顔ぶれから事態を理解しているようだった。聡は生徒を横一列に座らせた。
「……みんな、残された理由はわかっているな」
生徒たちは聡と目を合わせないよう俯いている。中でひとりだけ、視線のかち合った生徒がいた。門倉だった。彼も忍び込んだうちのひとりだった。
「なんでこんなことをしたんだ。いくら人が住んでいない建物だと言っても、やっていい事と悪い事の区別くらいつく歳だろう」
生徒たちは何も答えない。
「……どうなんだ、門倉」
門倉は大きく肩を揺らした。生徒たちは伏した目を一斉に上げて彼を見る。その様子から、原因は門倉にあるらしいことが察せられた。追い打ちをかけようとしたときひとりが、せんせい、と零した。門倉です、門倉が悪いんです。一瞥すると、門倉は身体を強張らせている。
「門倉が幽霊見えるって言うから。あそこの建物、出るってみんな言ってたから。それで本当に見えるのか証明するんだって……」
噂があるのは事実だった。今や廃ビルと化した建物は聡がこの街を出るときにはまだ営業しており、それなりに賑わってもいたし、実際に聡も利用したことがあった。その建物は、かつてはラブホテルだった。保護者会でも早く建物を潰して欲しいという不満の声は挙がっていたが、その彼女らの気持ちと幽霊話が立つ根はおそらく一緒なのだろう。
「門倉、本当なのか」
声をやわらげ訊ねた。門倉はためらった後に、ゆっくりと頷いた。
「なんで幽霊が見えるなんて言ったんだ」
しかし、門倉は何も言わない。聡はその沈黙を図りかねた。一端区切ることにして、息を大きく吐いた。
「お前らなあ、自分のしたことわかっているか。不法侵入って言うんだ。大人がしたら警察に逮捕されている。お前らだって、今回は警備会社の人が赦してくれたからいいけど、本当だったら警察署に連れていかれてもおかしくないんだ」
警察、その言葉に生徒たちは動揺を露わにする。みんなの顔に「でも門倉が……」と浮かんでいるのが読み取れた。
「門倉が悪い、お前らそう思っているのか。けどな、囃したてたみんなも悪い。お前らは、一用にいけないことをしたんだ。警察署に連れていかれて、先生とご両親と警察とで、みんなでお前らを怒っていたんだからな」
両親という言葉に対する反応は、「警察」以上のものがあった。両親に報告されるのか、否か。彼らの最大の不安はそこにある。
「今回は家族の方には黙っておくから」
生徒たちは顔を綻ばせたが、但し、と続けると瞬く間に表情が曇る。
「今回の事は誰にも口外するなよ。もう誰かに喋ったのなら、しっかり口止めしておきなさい。もし、他の生徒からお前らが廃墟に忍び込んだという話を聞いたら、残念だけど報告させてもらうぞ」
そう言い、生徒たちを下校させた。不平を露わにランドセルを背負って出てゆこうとする彼らのうち、門倉だけに聡は声をかけた。
鱗雲が晩夏の空を覆っている。とっぷり暮れて夜になるのか、再び陽が昇り朝が訪れるのか。明暗どちらに転ぶか判らぬ色、鈍重な雰囲気が校庭を満たしていた。聡は門倉を連れて校庭を歩いた。職員室の隣に建つ体育小屋、校庭の隅に広がる芋を植えた畑、疲れの見えるサッカーゴール……。聡は無言だった。門倉は黙って聡の後ろをついて歩いた。
やがて、鳥小屋に着いた。金網の中ではインコや文鳥が宿り木にとまり、鶏がトサカを揺らしながら糞まみれの地面を闊歩している。なかで一羽、どうにも似た鳥がいる。……トビ。
この頃、沙耶の様子がどこかおかしかった。明らかに、トビが死んだことが影響していた。どうすれば元気になるか、いっそこの中から一羽盗み、家に迎えようか。鳥なんてどれも変わらないだろう。そんなことをしても沙耶が喜ばないのは判っていながら、自嘲的に考えていた。
「本当に見えるんです」
唐突に門倉が口を開いた。やっとか、聡はそう思いながら、
「……幽霊のことか?」
「うん」
「それで、お前から行こうって言いだしたのか?」
「ち、違います。幽霊が見えるって言ったら、あいつら。証明してみろって。それで皆をうちに呼んだんです、俺の部屋にいつもいるから。それなのに、なんでかわかんないけど、その日はいなくて。そしたら、嘘つきだ、嘘つきだって。……言うから」
「それで、あの廃ビルに行こうって言いだしたのか?」
「じゃなくて。だったらあの幽霊ビルに行って見つけてみろって言われて、悔しかったから、見つけてやるよって言っちゃって……。けど結局、すぐ捕まって幽霊どころじゃなくなっちゃったんだけど」
「そうか。囃し立てられただけだったんだな。けど、だめだぞ。幽霊が見えるなんて嘘をつくのは」
門倉はおし黙った。鳥が大きく啼く。聡が横目で様子を窺うと、門倉の表情には暗い影が浮かんでいた。
「嘘じゃありません。本当にいるんです、俺の部屋に」
「……どんなユウレイなんだ?」
「おじいちゃんです」
聡が、おじいちゃんと繰り返すと、暗闇が頷いた。
「いるんです、こないだから。本当のおじいちゃんじゃなくて、なんか、おじいちゃんの兄弟みたいなんだけど……」
朝露が葉先から零れ落ちるように門倉は語った。彼の曽祖父の兄弟がこの夏から現れるようになったこと、毎夜現れては枕元に立ち彼をじっと見つめていること、彼の教科書を読み、『羅生門』に眼を留め「あいつが今でも……」と漏らしたこと、着物姿の老人は白い髭を蓄えており、そして、夏休みのある日、彼に命じて読書感想文を書かせたこと。そのときの彼は、まどろみの中にいるように無私で、老人の漏らす言葉をつらつらと、さながら自動筆記のように書きつけたようだった。
「ぼくが書いたあの本、じいちゃんの書いたものらしいんです。けど、本にもならなかったって。それで、悔しくて出たんだって」
ユウレイについてこれ以上口外するなよと嗜める聡に、門倉はそう残して帰った。ひとり残された聡は自らの甘さを悔いた。生徒たちを怒ることが出来なかったことではなく、門倉があれ程確信に満ちてユウレイを信じていること、その純真さ。それが危ない。曲がり角には魔物がいた。その強大さはわからない、もしかしたら、杞憂に終わるかもしれない。けれど、聡にはその存在を正確に感じ取ることができなかった。既に太陽は沈みかかろうとしていた。校舎では職員室だけに白熱灯が光っていた。
「生徒の家にユウレイが出るらしいんだ」
沙耶はコンビニで購入した蒸し鶏肉にレタスとトマトを加えた簡単なサラダをつまみにビールを呑んでいる。今日は残業で遅くなると聞いていたため、聡は愛生とともに夕食を済ませていた。
「どんな?」
「……先祖らしい。曽祖父の兄弟だって言っていたな。バカバカしい」
「幽霊かあ。実はね、私も子供のときに見たことあるんだ」
「初耳だね。どんな幽霊だった?」
「交差点で亡くなった猫でね、地縛霊になっちゃってたの。真っ赤な毛並みでね、それはもうかわいかったんだから」
そう言い、液体が喉を通る小気味良い音を鳴らした。
「おい、バカにするなよ」
「バカにするなって、してるのはさっくんの方でしょ。子供たちをさ」
普段はこうやって棘のある言葉を吐く性格ではない。しかし、この頃の沙耶は感情の波がどうも読みにくく、その不安定さこそが最近の沙耶の変化だった。
「けど、ご先祖さんの幽霊か……。私も大切な人の幽霊になら逢ってみたいかも」
そう言い、沙耶は遠い目をした。聡は幽霊でも、などとは思わない。まず、幽霊など決して存在しないのだから、仮定としても在り得ない。それが彼の考えだった。父は思春期の頃死んでいた。父方の祖父母は遠方に住んでおり、父の葬式以後逢っていない。そもそも、平日毎日通う故郷の町に住む母親にさえ、高校卒業以後殆ど逢っていなかった。理由は、別に逢いたいと思わない。たった、それだけの理由。そして、充分過ぎる理由だった。……。
4.君のお父さんになりたい
末田はダイニングソファに座っていた。ここは秋葉原の電気街口を末広町方面にやや歩いた先の細い路地に建つ、何の変哲もないマンション、その一室。簡素な白い机の上には深緑と茶の糸で織られたラグが敷かれ、木かごには廉価な果物が納められている。末田がバナナを頬張ると、それが合図のように室内が暗くなった。
ふわあ、よく寝たあ……と甘たるい声が暗闇に浮かぶ。パチッとテレビ台の辺りが眩くと、肩甲骨まで伸びた黒髪をぼさぼさにさせた、ギンガムチェックのパジャマ姿の少女が現れた。欠伸をしながら、んー、と弛緩した糸のような声を響かせていると、突如、大きな声をあげた。
「あ、やば!みなさん、もう来られてたんですね」
目を丸く広げながら口もとを大げさに掌で隠し、ちょっとみんなーと扉を開けて隣室へと逃げ込む。やがて、声色の違う少女たちの慌てる声が何層にも重なって、上下ジャージやスウェットにクラスパーカー、なかには丈の長いシャツ一枚を羽織り下着が覗けそうな姿の少女たちが現れ、ごめんねこんな格好で、今日だって知らなかったからびっくりしたよー。でも、大丈夫。みなさん、今日は楽しんで行ってくださいね!と叫び、重低音が響きだした。
未だ幼さを残す細い肢体をくねらせ、少女たちが唄う、踊る、そして、頬笑みかける。ポップチューンのリズムに合わせて裾をひらり翻すと、四方に設置された大型家具店で見かけるようなスタンドライトが、強、中、弱、と段階的に明滅し、サビに入ると一斉に輝いた。
末田と似たような風貌の男たちは思い思いの場所に座り、自身の推しメンのうちわやサイリウムを振り回しながら応援している。時折、少女たちは男たちの目の前に立ち、肌を舐めるように息を吐き、そして、寂しげな表情で笑う。男たちは動かない、動けない。抑制しないと欲望に駆られ、この部屋を去ることになるからだった。以前、興奮のあまり欲望を抑えきれずに露わにしたペニスを少女に掴ませた男がいたが、その後、彼らのコミュニティ上でペニスマンと呼ばれるようになったその男をこの疑似空間で見た者はいない。
楽しみにしていたライブを観ながら、末田は憂鬱だった。平素ならば周囲と同様にサイリウムを振りながら汗と猥褻な眼光を飛ばす末田だが、今日は他人の子の授業参観に訪れたように気持ちが離れている。よく見ると、それは彼ひとりではない。室内には彼と同じように俯く男が幾人かおり、彼らも末田同様、サイリウムをじんまりと握り締め続けていた。やがて、その内のひとりが静かに部屋を出て行った。末田にはその気持ちが痛いほど理解できていた。
数曲が終わるとMCが入った。少女たちの芸ない喋り。やがて、中心メンバーのひとりが、不在者の存在を詫びた。
「ユキちゃんのこと、信じてあげて!だって、私たちもユキちゃんのこと信じてるもん。ユキちゃんが私たちのこと、裏切るわけない!」
次の曲は、ユキちゃんとみんなの為に……そう続き、再び歌が始まった。
ユキちゃんは男と寝た。SNSで流布された写真は半裸の若い男の乳首を舐める少女のもので、せめてもの抵抗の証か、それとも単なる戯れか、目元を掌で隠していた。けれど、まずは頬にぽつんと浮かぶほくろが一致すると叫ばれ、そしてブレスレット、笑った際に浮かぶ八重歯が止めとなり、完全に一致したと泣き叫ばれた。しかし、パトロンたちへの追撃は止まらない。写真は次々に追加されてゆき、なかには少女が布団の上で避妊具片手に横たわるものも混ざっていた。ユキちゃんは十四歳だった。末田がそっと部屋を出ると、扉は重く閉じた。
十五歳から歩きなれたこの街だ、眼を瞑っていても歩けるさ。この角を曲がれば同人誌専門店、そこを更に曲がりひたすら歩けばメイド喫茶、店に入る前ちらりと空を見やれば緑髪の看板娘が笑ってる。そうだ、実際に眼を瞑って歩いてみよう。入店する気もないのに店の前に立ち空を見やる、金融会社の広告だった。十三年間通う中で、この街は確かに変貌していたのだった。
中学生のとき、末田の同学年にひとりの美少女がいた。艶やかな黒髪にぱちっとした二重瞼。目鼻のよく通った端正な容姿には十代中頃にして女の色香も備わった。少女はあまり笑わない。人と群れない。他のそのような同級生を根暗だと揶揄する連中も、彼女に対してはその美しさにただ眩んでいた。当然、放課後に呼び出されることも頻繁だった。彼女ほど校内の人気ない場所を訪れた生徒もいなかっただろう。末田も彼女を想う大勢の内のひとりだったが、臆病な彼は行動に移せなかったため、彼女と言葉を交わした事はたったの一度しかない。その一度の体験を、彼はひたすらにキャンバスに描いた。幾枚も幾枚も。春夏秋冬の、朝夜の、幼少期と成人後の幻視を……。
長かった制服の袖がぴたりになった頃、末田は積み重なった膨大な画を全て燃やした。美少女は妊娠したのだった。教員も同級生も、誰も相手のことを知らなかった。その後、少女が学校に来ることは一度もなかった。河原で白煙を上げる画布の群れ、朱色に染まった幻の女は黒々と炭に変わりゆく。煙が眼に沁みた。空へ辿る一筋は今後の茫漠なときを想わせた。あのときのことはよく覚えている。これで末田は、少女に二度裏切られたのだった。
「あれ、今日はライブじゃなかったの?」
定連の店に入ると、ブレザー姿の店員にそう訊ねられた。顔を見ると、見慣れたハンコ絵のような容姿にユキちゃんが重なり、嫌悪感が込み上げる。末田は顔をそむけ適当に言葉を返すと、今日のお兄ちゃん変なの、と言いながら店員は消えた。
今、ここで。飾られた模造花を眺めていると、その裏に、男たちの姿が透けて見えるような気がした。その男は、不思議と聡のイメージと重なる。この娘らは全員、影でユキちゃんと同じ行為をしている。腹底からどうしようもない、胃液が込み上げるような深い苛立ちが生まれ来る。末田は童貞だった。
末田は最近、かつての美少女を頻繁に思い出していた。それは、昨年度飯島倫子を担任として受け持ってからであり、そして、授業参観でかつての美少女、愛生と再会してからだった。愛生は相変わらず美しかった。
愛生は今、上野のホステスで働いている。金を払えば逢えた。この街にいる少女たちより額が多少大きいだけで、かつては全く触れ会えなかった人を、金さえ払えば何時間でも拘束することができた。あのガラス細工のような瞳に自分だけを映すことができた。けれど、末田は彼女の下を訪れたことがない。
ねえ、ぼくが君をどれくらい好きだったと思う?あれからずっと、君だけを想っていたんだ(嘘だ)。本当だよ(嘘だ)、君は多分覚えていないと思うけれど、俺達一度だけ、話したことがあったろう。あの日のこと、今も忘れない(本当は忘れている。何度も反芻して、強固な思い出を作っているだけだ)。嬉しい、君と再会出来て嬉しいよ。これも、倫子のお陰だ。好きだ。君が好きだ。十年越しにやっと言えた。俺は、彼女のお父さんになりたい。お父さんにしてくれないか。
「え、ワリキリってこと?ホ別三万なら」
少女が言う。我に帰った末田の眼の前には制服姿の少女がおり、周囲を見渡せばそこは神田明神の境内。メイドカフェでデートサービスを注文し、店員のひとりと恋人を模して歩いていたのだった。
「え、ぼく声出してた?」
「うん。お父さんになりたいって。で、どうなの」
「あ、ああ、いやあ……。ごめん」
末田は全力で走った。すごすごと逃げ、上野駅で降り繁華街へと抜ける。うるさいキャッチを掻い潜り、店の前まで来た。この階段を降りれば愛生がいる。けれど、この街を行き交う女性たちは皆成熟しており、彼が日ごろ相手にしてもらっている少女たちとは違う。今、彼は臆していた。そして、引きさがった。
その日、末田は動画サイトで自慰に耽り、眠りに就いた。
5.ふたりの女は
「困ったことになったねえ……」
はあ、聡は返答ともため息ともつかない声を漏らした。またか、と悪態をつきたい気持ちも裏腹に、そのような事態が生じているのは確かだった。
この頃、生徒たちは妙に浮足だっていたが、ともすれば文化祭が近いからだとも考えられる。しかし、聡はそれが間違っていることにすぐに気付き、事実、やがて証拠も見つかった。発見者は六年に担任を持つ男性教諭。或る日の放課後の教室、生徒が誰もいなくなったことを確認するため教室に赴いた際に、ふとゴミ箱の中を見ると、ノートの切れ端などに混ざりひらがな五十音と鳥居の記された紙が捨てられていた。あの不法侵入を契機に流行ってしまったのは、タンケンではなくユウレイ探しのようだった。翌日の朝の会で、男性教諭は用紙を棄てた者を確認したが、挙手をする生徒はいなかった。
事態が俎上に上ったときに聡は、悪い予感が当たったと悔む一方、コックリさんは息の長い遊びだなどと感心していた。狐憑きなど古い慣習だ。聡の母親世代でも信じる者は多くないし、そもそも東京生まれの聡にとっては狐狸の類を目にすることさえ稀である。
「俺たちの世代でも流行ったかな?」
騒ぐ教師たちの蚊帳の外で末田に訊ねた。しかし、末田から返事はなく、胡乱な眼付で呆けているだけだった。おい末田、と肩を叩く。彼は首を跳ねらせて妙な声を上げた。
「え、ああ、どうしたの?」
「……いや。生徒たちの中で心霊ブームが起きてるらしいぞ」
「心霊かあ。それが原因で繊細な子がいじめられなければいいけど……」
口を閉じれば、末田はまたぼんやりとし始めた。呆れた聡は放っておくことに決めたが、末田の言う事にも一理ある。子供たちのいじめには縁故がない。嫌悪はなく潮流だけがあり、一端生まれたその流れには誰も逆らわない。無邪気ゆえの過ち。聡はそれを、これまでの教員生活で実感していた。今回、その潮目は門倉に見られた。元を辿れば発端は彼にある。そのため彼を囃し立てる生徒も多く、聡はこの頃、数人にからかわれムキになって否定する門倉の姿を何度か目にしていた。感情的になった人間ほど馬鹿にしがいのある者はいない。それは、子供たちの世界でも同じこと。彼はそういった場面に出くわすと、あまり騒ぐなよ、とやんわり注意した。こういったときには教員が直接的に介入しない方が良い。下手をすると、その注意によって本格的ないじめへと発展してしまうことがある。
そのように末田と並んで傍観していると、教頭に同僚が集まってる中へ呼ばれてしまい、困ったことになったねえと嫌味たっぷりに告げられたのだった。
「ほら、発端はキミの担任のクラスだろう。慎重にって意味、伝わらなかったかな」
同僚たちから横目で視線が届く。その中身は同情だった。
「ともかく、これで事故でも起きたら大変だから。みなさん、鎮火に回ってくださいね」
教頭が周囲を見渡して言った。ふと、遠くを見て、
「ほら、末田先生。あなたもね。話、聞いていましたか?」
末田は再び、妙な声をあげた。
夕方、学校から鴬谷に向かった聡は、求め合った後のだるさを全身に残しながら、傍らで寝煙草を吸う愛生の躰を撫でていた。愛生の肌は未だ若々しく、ほっそりとした肢体も肉感的で美しい。聡の身体に残る倦怠感こそがその魅力の証左だった。そして、沙耶の下ではとうに過ぎ去った熱情だった。
「流行った……のかな。私にはわかんない。友達いなかったし」
聡は事後の一幕として校内での心霊ブームを話していた。どのみち、保護者にも遅かれ早かれ連絡が廻ることだろうし、何より愛生はママ友が少ない。地域に根づいて生きる人の多い下町らしく、幼少期から目立っていた彼女は皆から距離を置かれていた。その為、連絡が廻らなかったにしろ彼女から話が漏れることはない。
「倫子は興味あるのかな。わかんないのよね、あの子。あまり話さないから」
倫子は頭の良い子供だった。実際、書き直しを命じた門倉の読書感想文の不出来から、クラス内での優秀賞は倫子に与えられていた。彼女は早熟だった。それは環境から早く大人になることを義務づけられた、宿命的な早熟さだった。
「頭の良い子は総じてあまり喋らないものだよ」
嘘が半分混ざる。知性が口数を減らすことはあれ、倫子の場合はそれだけではないだろう。聡は育児放棄だと睨んでいた。元々、十六歳で子を産んでから、愛生は両親に支えられて生きてきた。今の倫子があるのは、きっと祖父母の影響なのだろうと察しがつく。
事実、育児放棄は満更外れていない。倫子を産んでから愛生は何度も娘と向き合おうとした。が、日々の疲れから男の元に奔走し続けた結果、娘の笑顔を見ることが辛くなった。男が変わる度に辛苦は増す。遊び疲れてもう楽になりたいと心を決めた人もいた。何人もいた。しかし、男たちは皆去ってゆく。
母としてどうあればよいのか。仕事終わり、アフターを求める四十男の手をやんわりと払い常のほろ酔いで娘の眠る顔を眺めるときにそう考えることもあったものだが、その娘の容姿が月に年に自分に似てくる。玉のように美しい。早晩この娘も自らの魅力に気がつくだろう。そのとき、娘はきっと娘を孕む。その娘は、きっといずれ、私になるはずだった。私は娘に男狂いする罪障しか残してやれない。ほかに何を残せるというのか。私に何が出来るというのか。愛生はいつかの夜、さめざめと涙を零した。その日から、以前より一層倫子と距離をおくようになっていた。
愛生は煙草を深く吸った。いま私の身体を撫でている男もいずれ去る。私たちは未来のことを話さない。それでも、この男がどこか遠くへ連れて行ってくれるのではないかと期待している。女が恋をする相手は、決まって自分を世界の果てまで連れて行ってくれる人だ。逆を言えば、惚れた人ならばどこに行ってもそこが世界の果てとも言える。恋から遠く離れた愛生は、それでもなお、世界の果てまで辿りつきたい。そう思っている。
「ふうん、そんなものなの」そう言い、再び深く吸った。そして、火を消しながら聡を視界に捉えて言う。「父親が欲しいとか思ってるのかな……」
そう残し、彼女は浴室に消えた。その後ろ姿に、それは果たして……と、聡は訝しんだ。けれど、愛生に限ってそんなことはないだろう。これまで奔放に生きて来た女が、と高をくくった。正直、聡にとってどうでもよいことでもあった。もし、そうであるならば、次に移る他はないな、聡はそう考えていた。そんなことより、風呂に入りながら我々はもう一度交わるだろう、いつものように。彼は既に熱く滾っていた。
「ただいま」
リビングに入ると、普段着のままの沙耶がいた。タレントたちが有識者から常識を正されるというバラエティ番組を観ながら、ホットティーを呑んでいる。
「遅かったね。何してたの?」と彼女は言った。
「末田だよ。あいつと呑んでた」
そう応えると、沙耶はカップ片手に立ち上がり、聡の傍らを抜けてキッチンに向かった。風呂上がりの髪が濡れていた。蛇口から水が数滴、等間隔に垂れる。沙耶はぼんやりとそれを眺めている。そんな彼女を、聡は見つめていた。
「末田くん、恋人でも出来た?」
「出来ていないんじゃないか。あいつは昔からモテないから」
「……あなたと違って?」
沙耶は聡を見た。鋭い目つきだった。
「まさか。でも、どうして急に末田の恋愛事情が気になったんだよ?」
沙耶は再びシンクに眼を落す。
「末田くん、女の人みたいな香水つけるようになったんだなって」
突如、沙耶はカップをシンクの縁に叩きつけた。鈍い音とともにカップは砕け、破片がぽろぽろと床に落ちた。沙耶の掌には、崩壊を免れたカップの柄だけが握られている。破片が傷つけたのか、沙耶の指先からは血が浮き出ており、指先から何とも繋がらぬ柄へ、そして床に散らばる欠片の一片に垂れた。
沙耶は家から出て行った。恋人の衝動的な行為から呆気にとられた聡は、彼女が出て行った玄関を眺めた後、ゆっくりと破片を片付けてビニール袋に入れ玄関の隅に置いた。その後、雑巾で細かい破片と彼女の血を拭った。
電話をかけたが、出ない。メッセージも入れておく。そして、沙耶の大学以来の親友であり、聡も親交のあった友美に電話をかけた。
「久しぶり。あのさ、沙耶から何か連絡来てない?」
「来てないよ。何、またケンカ?」
「……うん、そんなとこ」
「……あのさあ、聡君。私が言うべきことじゃないかもしれないけど、もうさ、いい加減にしなよ」
「何を?」
「してるんでしょ、浮気」
「……してないよ」
「ウソ。てかさ、これで何回目なの?」
「だから、してないって」
「……あくまで認めないってわけ。沙耶、こないだ泣いてたよ。トビが死んだとき」
「……?あのときは沙耶、家でも泣いてたよ」
「聡君はわかってないよ。全然わかってない。沙耶がどんな気持ちでトビを飼い始めたのか、死んじゃったときにどんな気持ちだったのか。……はあ。まあ、いいや。私がとやかく言えた義理じゃないよね。沙耶から連絡がきたら伝えるから。それじゃ」
聡はソファに座り、破片を掃除する際に指を傷つけなかったか、自らの掌を眺めていた。数分後に来た友美からの連絡によると、沙耶は彼女の家に向かっているそうだ。よろしく、と返信すると、別れるの薦めておくね、と返信が来た。携帯端末をテーブルに置くと、聡はソファに横になり深く身体を沈めた。
友美の言う通り、浮気などこれが初めてではない。沙耶にばれただけで三度、それ以外も含めると何度かわからない程こなしてきた。客観的に見ると女癖の悪い男、恋人を蔑にする最低な男と見られる。それは聡にもわかっていた。が、殊更前者に対しては同意しかねた。聡はセックスを何ら特別な行為ではなく、男と女が挨拶の延長線上に行うものだと捉えており、それはつまり、彼にとって多くの女性が「オンナ」でしかないことを意味していた。そしてその「オンナ」たちの多くは、聡に性的な魅力を見出した。その交感を悦んだ。
聡にとってセックスはあくまで日常の延長線にある事柄、瑣末な行為だった。けれど、その瑣末な行為こそが聡の、人生の大きな愉しみだった。沙耶への罪悪感は、その日常的な一歩を踏み止まらせるにはあまりに弱い。そして、浮気が明るみに出る度、酷く哀しみはするものの、沙耶が別れを切り出すことはなかった。つまり、赦した。それにつけこみ、聡は浮気を繰り返していた。
しかし、その人生の悦びは遠のこうとしている。ソファの上で心身ともにぐったりと寝そべる聡の下半身、その重要な快楽器官さえも疲れ果てている。それだけではない。脂臭い肌や減退しつつある食欲、そして疲労の残りやすくなった体……。その正体が加齢にあるのは間違いなかった。
勤め始めてから一年経った頃、年配の教員に連れられてコスチューム・プレイを愉しめる店を利用したことがあった。その際に聡は看護服姿の娘と愉しんだが、今の自身の生活はその行為によく似ていると感じていた。愉しむ為に、ある現実を模す。聡の人生、そして生活には何ら本物がなかった。聡は誰かの人生を模しており、決して聡自身の人生ではないように思えた。その空虚さから逃れる為の熱意は単なる欲情としてのみ存在しており、掴まえたと思ったら迸る射精でしかない。
看護師プレイを愉しんだ彼は翌週末にも同じ店を訪れ、今度は小学生を相手にした。もちろん、安っぽい児童用の服を来た童顔の成人女性ではあったのだが、サービス中に娘から先生と呼ばれる度に、聡は興奮するより多くの違和感を覚えた。教師ではない他の誰かにとって、その設定を愉しむ為に金を払う価値のあるリアルなのだ、と。
それから暫くのあいだ、聡は自身の人生に対して肯定感を得られていた。けれど、その感覚も長くは続かなかった。やがて、漫然と目の前のことを片付けるだけになってゆき、再び性交に逃げた。これでいい、これでいいはずだと思い込んだ。なのに時折、徒労感が間欠泉のように噴き出るときがあった。
本来、恋人とは世界の中に築かれる閉じた小世界である。が、聡たちはそれを構築できなかった。彼らを包む膜は穴だらけで、その穴を永い間、沙耶が塞ぎ続けて来ていた。しかし、その穴はすぐに開く。それもそのはず、その穴を作るのは聡だった。時折膜を破り、外界の蜜を吸いに出かけていたからだ。けれど、その蜜はじきに甘くなくなる。ただ、ぐったりと横たわる他、今の聡にするべきことはなかった。……。
6.墜落
周縁の東京は夜が深い。古汚い街は街灯が薄暗く小道を少し入れば闇の淵。行き交う誰もが身を固くして、互いの肩を睨み合っている。道中、少年たちは人と出会わない。人の気配を感じれば、民家の間のさらに細い脇道に蹲って息を潜めた。道行く仕事帰りの人々は、彼らにとってこの世ならざる者たちだった。姿が消えると少年たちは、弾む心を懸命に抑えながら先を急いだ。夜更けの街をうろつくなど初めてのこと。これは冒険だ、誰もがそう感じていた。
少年たちは廃ビルに着いた。彼らはそのまま敷地内に入らず迂回して、細い脇道を行く。そのまま道を抜けてビル裏に建つ民家の門をしれっとくぐる。家屋からは暖色の明かりとともに、人々の談笑とテレビの音が漏れ聞えた。少年たちは家で寛ぐ母を想ったが、それはすぐに好奇心に上書きされる。民家の奥に立つ石塀を乗り越えて廃ビルの敷地内に降り立った。そうして、鍵の空いた小窓からビル内への侵入に成功した。先日の不法侵入の際、少年たちは表門から入りすぐに捕まった。それを少年らのひとりが中学生の兄に話したところ、あそこは裏から入れば警備員は来ない、そう助言を与えたのだった。
しいん、と静寂が耳に痛い。浮ついた心が急に冷め、身を縮こませ自然と手を繋ぎ合う。鼠が走る音に肩を跳ねらせ、背後から聴こえる人間社会の名残に襟足を掴まれていた。携帯端末を持つ少年が周囲を照らしながら、一歩、踏み出した。それは少年たちにとって意味のある一歩だった。続いて全員がそろそろと足を動かした。
少年たちは恐る恐る扉を開けた。そこは広いエントランスで、先日、少年たちが警備員に捕まった場所だった。暗闇を見渡すと、顔が見えないよう隠された受付や、暗く何も映さないディスプレイが薄らと確認できた。誰かが、いるか、と訊ねた。誰かが、ううん、見えない、そう応えた。じゃあ、次行くぞ。
少年たちは重たい扉を開けて非常階段を上って行く。滞った空気は少年たちが幾層にも重なる床の埃を舞わせる度、新たな生命を得たように鈍く泳ぎだす。その重たさにつられて少年たちの足取りも重くなった。たった一階分の階段が永遠のように思えた。少年たちは再び重い扉を開けた。
二階に抜けてまず眼に映ったのは、壁。左右には廊下が広がっており、一方に携帯端末を向けると突き当りの壁が茫と浮かぶ。それほど長い廊下ではなく、部屋数もさほど多くはなさそうだった。怯える少年たちは扉をひとつひとつ開けてゆく。部屋の中心に大きなベッド、そしてテレビと鏡面台も備わり、バスルームにはゆったりとしたバスタブが設えられている。室内は荒れ放題で割れた空き瓶や煙草の吸殻の散乱、グラフィティ・アートなど、悪童のマーキングが見て取れた。何部屋か見て回ったがどの部屋も同じような造りのようで、冗長性のある空間が恐れを緩慢化させる。二階の部屋をすべて確認し終える頃には、既に飽き始めている者もいた。もう帰ろうよ、誰かが言った。三階が最上階なんだ、そこを見終わったらな。誰かが言った。
三階も同様の造りだった。結局同じだよ、帰ろう。そう言おうとしたとき、誰かが口を覆った。眼を見合せ、しぃっと黙らせる。
声がした。少年たちではない人の声。廊下の左側から響いている。退屈し始めていた面々はひやりと張る背筋の感触を歓び、互いに顔を見合わせれば誰もが暗闇に表情を輝かせている。携帯端末のライトを消した一行は手探りで音の在り処へと向かった。
一歩歩く度に音が近くなる。ぼそり聴こえる音は、どうやらふたり分らしい。扉の前に立つとはっきり聴こえる、男と女だ。幽霊ではなかったことに肩を落とす者もいたけれど、大半はこんな夜更けに一体何をしているのだろうと好奇心を燻ぶされた。音をたてないようゆくりと扉を開けてゆき、屈んで四足になって室内に入る。声の正体たちは興奮していた。そのため、少年たちに全く気が付かない。
黒髪をツインテールに結んだ女が立っていた。女は学生服のスカートを穿くのみで、あとは裸。小ぶりな乳房は未だ形良く保たれており、それは純粋な若さだった。女と向き合う形で、男がベッドに腰掛けている。やめてくれ……僕が悪かったから、男がそう声を張った。すると女は、お兄ちゃんが誘ったんじゃない、と応えながら、男の頭を撫でた。
そのまま膝の上に乗り、腰をくねらせ、男の頭を抱きしめる。そして、手はジーンズ越しに股間をまさぐった。男は懇願するように、やめてくれと何度も繰り返した。本当はこうして欲しいくせに。ほんとキモい、このロリコン。女はそう罵倒しながら、やがてジッパーを下げ、熱く隆起した性器を握った。女が手を上下に動かす度に男は、やめてくれやめてくれ……と繰り言をしながら唇を噛み涙を流した。が、刺激に耐えかねた男はやがて唇に刺さる歯を抜き、ちろりと舌を出した。乳房は汗の味がした。ほろほろと崩れないよう絹豆腐を舌先で転がすよう口に含んだが、存外、繊細ではないらしい。飴玉のように強く吸った。その間も、彼は涙を流し続けていた。
少年たちは強い興奮に襲われていた。けれど、その源泉がわからない。ただ、すべての子供たちが豆粒のような性器を堅くしていた。幽霊の事は頭からすっかり消えていた。
「そろそろ、入れよっか」
男は我に返ったように乳房から口を放し、いやよいやよと幼子のように首を振った。女は多少苛立っていた。
「いい加減にしなよ。ここまで来てしないとかあり得ないでしょ。それとも、もっと卑猥な言葉で誘われたいの、お兄ちゃんは。あ、お父さんの方がいいかな?」女は嘲るように続けた。「その子小学生だっけ。私じゃあ、おばさんね」
男は立ち上がり、女をベッドの上に押し倒した。けれど、躊躇がある。
「センセ、大好きだよ。だから、ひとつになろうよ」
女はファム・ファタールだった。男の内面を正しく理解し、打てば響く言葉をきちんと用意している。男はその言葉に背中を押され、中に入った。
忘我にいたのは少年たちだった。眼前の行為の意味はわからないけれど、何か凄いことが行われており、それが原因となって下腹部に抗い難い力が生まれつつある、そのことだけは理解できた。少年たちには、女は悦んでいるように見えた。表情はわからないが、嬌声には時折笑い声が混じる。反面、男は苦しそうだった。ひたすら何かに耐えているようだった。やがてひとりの少年が股間を弄り始めた。おい、お前何やってるんだよといえども、少年はふたりの行為を眺めながら股間を触り続ける。うっと声を漏らし、とろんとした目つきを湛えながら、少年は手の動きを止めた。他の誰もが、一体何が起こったのか理解不能だった。しかし、ひとつわかった事がある。このよくわからない行為には、突然な終わりが訪れること。その瞬間、俺達は逃げなければいけないこと。
男の動きは激しさを増す。そして、予測通りに唐突な終わりが訪れた。痙攣する腰を深く女の躰に押し付け、苦悶に顔を歪めている。ところを、少年が携帯端末で撮影した。誰だっ、と末田は叫んだが、少年たちの身軽さは確かだった。後には末田と女だけが残されていた。
「ごめん、撮られちゃったみたいだ」
「いいよ、別に。ガキだったし、特定とかにはなんないでしょ」
女はそそくさと服を着始める。末田は強い後悔に襲われていた。しかし、同時に清々しくもあった。末田は財布から万札を五枚取り出して渡した。女はブラウスに身を通し身支度を済ませると、札束と末田を交互に一瞥し、札束を手で払った。ガラスの破片が散らばる床にはらはらと万札が落ちゆく。
「このクソが。お前一片死んだ方がいいよ。教師の癖に恥しくないわけ。良い大人がさ、失われた青春取り戻そうってまじキモい。死ね、ほんと死ね」
末田が何も言い返さずにいると、拾えよ、女はそう言った。末田は身を屈め手探りで万札を探り、途中、硝子の破片で指を切った。血濡れた万札を五枚、すべて彼女に渡すと無造作にブラウスのポケットに入れた。
「嘘だよ、お兄ちゃん」
茫然と立つ末田の唇に自らを重ねて女は言った。
7.人生の熱意
にーわのシャベルがいーちにーち濡れて
あーめがあがってくーしゃみーをひとつ
指揮棒をひらひら動かす聡の前では生徒たちが二列に並び唄っている。一カ月あまりの練習の甲斐もあって流石に声が揃っており、この分なら保護者にも聴かせられると聡は安堵していた。文化祭は既に今週末に迫っていた。文化祭は午前中の前半に各教室での自由研究の発表、後半には体育館に移動しての読書感想文優秀者の発表。そして、午後に合唱という流れになっている。研究発表はどのグループも完成しており、読書感想文発表者の倫子も緊張さえしなければ大丈夫だろう、そして合唱もこの出来だ。例年通りの文化祭になりそうだ、そう胸を撫で下ろしていた。
聡が安心している理由はそれだけではない。この頃、幽霊騒ぎがすっかり落ち着き始めていたこともあった。何年何組の誰々が帰り道に人語を発する猫を見た、誰々がいつも長袖を着ているのは幽霊に憑かれているからで右肩には人の顔をした痣があるらしい、他にも定番の、誰もいないのに音楽室からピアノの音が聴こえたなど、過熱の一途を辿った心霊ブーム。それがここ数日間、すっかり影をひそめていた。文化祭が近くなり、関心がそちらに移ったのだろうと聡は理解していた。けれど、男子生徒が妙にそわそわしているのが気になってはいた。
放課後の練習を切り上げて職員室に戻っても末田の姿が見えない。まだ放課後の練習を行っているのか。流石に熱心だなと思っていると、同じく五年に担任を持つ教員が聡の下を訪れた。
「末田先生のこと聴きましたか」
聡は首を横に振った。
「……未成年を買春したらしいですよ」
やめて欲しいですよねえ、こんな文化祭直前に……。迷惑そうに顔を歪めたが、その裏側には賎しい光が宿っていた。教員は携帯端末でとある画像を見せた。薄闇の中で横たわるスカートだけを身に着けた女と、その上に被さる男。女は顔を背けており確認できないが、ぼんやり映った苦悶を浮かべる男は末田によく似ていた。
「この写真、どうやら生徒たちの間で出回っているみたいなんです。彼らがどうやってこんな写真を手に入れたのかはわからないですが……。ともかく最悪ですよ」
そう言うと教員は自分の机に戻り、隣の教員とまたぞろ話を始めた。見渡してみると、殆どの教員たちが近くの者たちと密やかに話しをしており、その多くが末田に関することらしかった。
――でもまだよかったわ……自分の生徒に手を出さなくて。
結局、定時を過ぎても末田は戻って来なかった。
お前さ、援助交際したってほんと。携帯端末でメッセージを送る。暫くすると既読マークが付き、本当だよ、と返信が来た。お前バカだろ。自分でもそう思う。……辞めんの。だね、懲戒免職ってやつ。逮捕とかは。それは大丈夫っぽい。いつまで学校来るの。もう無理っぽい。明日荷物片付けて後任の先生に引き継いだら、もうおしまい。
「せめて、文化祭まではいたかったよ」
ぷはあ、とビールを呑み干して末田は言った。お兄さん、ビールおかわり、と赤ら顔で続ける。
「けど、生徒たちに回ってんだろ、あの写真。なら保護者も当然知ってるだろうし、文化祭で囲まれてみろ。学校的にもそれは避けたいがためのこの判断なんだろ」
上野の居酒屋街の喧騒に身を包まれながらそう応える。
「というか、なんで援助交際なんかしたの」
聡は訊ねた。並々と注がれたジョッキに末田は手を伸ばした。
「相手は学生じゃないよ。十八歳だから条例的には問題ない」
「けど、援助交際は成人相手でも犯罪だ」
末田はもどかしそうに返答を詰まらせ、割り箸でポテトサラダをつまんだ。聡は何とはなしに箸先を眺めていたが、ふとテーブルの上の料理を見てみれば、ポテトサラダのほか焼き魚に煮物など、あっさりとした料理ばかりが目立つ。聡は店員を呼んで鶏のから揚げともつ煮を急ぎ頼んだ。末田は店員がメモを取る間、所在なさげに割り箸を何度も動かし、目線を落していた。店員が去った後、末田はそっと口を開いた。
「ぼくさ、小さい頃、いじめられてたでしょ」
聡は認めた。けれど、いじめられていたのは彼だけではない。地底人たち全員がそうだった。地底人への迫害は当たり前の風景だった。
「辛かったよ。なんでこんな目に合うんだろって思った。けど、聡はいじめなかったよ。聡の友達は皆ぼくをいじめてたけど、聡は違った。だから、今こうして呑んだりできる」
見当外れだった。聡が当時を振り返って思うことは、ただ俺は傍観者だったということ。周りの連中は男女問わず地底人で遊んでいた。それを当たり前の光景としながらも、内申を悪くすることだとわかっていたため、加担しなかっただけだ。ただ、傍観者もみじめな地底人たちを腹底では嗤っていた。
「学生時代に良い思い出なんてないよ。みじめで、辛かっただけ。だからぼくは教師を目指した。ぼくみたいな子をひとりでも多く減らすために。そうすれば救われる気がしたんだ。それで勉強も頑張って、実際に教員にもなった。でも、努力すればするだけ、走れば走るだけ、暗い気持ちが色濃くなってゆくだけだったんだ。ぼくがさ、救われる思いがしたのは、或る同級生のことを考えるときだった。飯島愛生だよ」
一寸、聡の心臓が跳ね上がった。平生を装おうとビールを口に含む。
「飯島さんが、ぼくを助けてくれたことがあったんだ。放課後、校舎の裏で連中に囲まれてさ。ズボンを脱がされてパンツ一枚だった。それでパンツも脱いでオナニーしろって迫るんだ。そこに飯島さんが通りかかってさ、多分男子生徒から呼び出されていたんだろうね。涼しい顔してた。何でもないよって表情だった。それで、そのままの表情でこっちに来ると、連中を諌めたんだよ。「みっともない」って。飯島さんが連中にあの美しい眼差しをじっと注ぐと、彼らは散って行ったよ。彼女はモテたから、惚れてた奴もいたんだろうね。そうして残された僕に、大丈夫?って聴いてくれた。僕は恥しくて、ありがとうって言うこともできなかった。すると、彼女も消えた。凛としていた。この世のものとは思えなかった。それで好きになったんだ。……けど、彼女は突然姿を消してしまった」
そうだ、妊娠した彼女は学校を去った。やがて倫子を産み、それからずっと花を売る生活をしている。
「あのときは本当にショックを受けたよ。けど、暫く経って大学生くらいになると思いだすこともなくなってたんだ。そして教員になって、倫子が現れたんだ。倫子は美しかった。まだ幼く、ほんの些細なことで表情を綻ばせる。けれどその中に怜悧な刃物のような鋭さがあって、飯島さんそっくりだよ。そして、授業参観で飯島さんにも再会した。あの頃とちっとも変ってなかった」
「それで、当時達成できなかった想いを遂げる代わりに、援助交際を?」
末田の目がぎらりと光った。
「……そうだよ。二重三重の代替物として援助交際をしたんだ。あの頃、聡たち皆が利用していたあのホテルで。きっと、飯島さんも使ったあの……」
聡にはよくわからない感覚だった。常にセックスが隣にある聡には、性欲の為に人生を棒に振る気持ちは微塵もわからない。ただ、滑稽な奴だと呆れるばかりだが、一つだけことがあった。
「それで、お前は救われたのか?」
末田は口を噤んだ。聡は待ったが、返答は意図したものと異なっていた。
「なあ、飯島さんのお店すぐ近くなんだ。今から行ってみないか」
初来店なのは聡も変わらない。が、そこは慣れたもので何ら気を張っていない聡と比べ、提案者の末田は目を泳がせている。ここは末田が愛した未成熟な女たちを拵えた花園にはない、直截な刺激で溢れていた。夜の蝶の登場に末田のグラスは震えたが、蛹たちの相手では到底考えられないことだった。彼は買春した女性を想った。変わらず震えたが、不思議と心が落ち着く気がした。
「あら、先生方お久しぶりです。いつも娘がお世話になっています」
場に似合わぬ言葉を発しながら愛生が現れた。大きく胸元が開いたミントグリーンのドレスに身を包み、ダークブラウンに染めた髪はゆるく巻かれ淡いイエローのコームでまとめられている。煌びやかな姿に末田の目は眩んでいた。
「お……お久しぶりです飯島さん」
「ええ、末田さん。けど、ここでは葵って読んでくださいね」
末田に微笑みを投げた後、愛生は視線を流しながら聡に目配せた。それを、聡は反らした。
末田には愛生が、聡には若い娘が付いた。娘は入店から日が浅いようで会話にぎこちなさが残っており聡の方が気を揉んだが、聡が積極的に話を振れば彼が若いということもあり簡単に懐中を開いた。時折、傍らふたりの話に耳を傾けると、愛生がうまく手綱を握っているようで話が弾んでいる。酒のせいか、末田も徐々に落ち着いて来たようだったが、その瞳は溺れているように見えた。
「ね、聡さんって、葵さんの彼氏さん?」
若い娘が耳元でそっと尋ねる。値踏みするように聡を見つめた後に視線を流して傍らのふたり、殊に末田をまんじりと眺め冷やかすように頬を上気させた。この状況を把握した上で愉しんでいる娘の無粋な態度に聡は苛立ちを覚えた。違うよ、俺は彼女の娘の担任だと聡が否定すると、ふふ、と笑みを零す。
「それで、ぼくは昨年度の担任」と末田が会話に混ざる。聡は内心慌てたがどうやらすべて聴こえていたわけではないらしい。「と言っても、ぼくはもう教師じゃないんだけどね」
「どうしたの、末田さん。辞めちゃったの?」
愛生は保護者たちの集まりから縁遠いため未だ事情を知らない。安堵した末田は含みを持たせた表情で応えた。
「……そうですか。長い間お疲れさまでした」
愛生と末田は再びグラスを重ねて小気味良い透明な音を響かせる。一口含むと愛生は、
「それで、新しい赴任先は決まっているの?」
末田には硝子の反響音が特別な音色に聴こえたらしく、その波紋広がるトニックを舌先で探るように味わいながら、努めて軽やかに答える。
「いいえ、決まってないんです。教師はもうおしまいです」
「あら、もったいない。末田さん、良い先生だったのに」
末田はそっとグラスを置き目を伏せた。今回の顛末に罪悪感を抱いている末田にとって愛生からの称賛はやや心苦しいだろうなどと、同僚として末田さんはどんな先生だったのですかと底意の知れた目を爛と訊ねる娘に、良い先生だったよと答えながら聡は考えていた。
「末田は良い教師だったよ。教育熱心でどんな子にも優しくて人望も厚かった。特に、いじめとか、そういう問題に関しては熱心だったよな」
「そうだったんですね。例えば、何かあったんですか?」と愛生。
「そうですね……。一昨年の今くらいの時期だったと思うんですけど。今くらいの時期って、いじめが発生しやすいんです。夏休みの浮足だった気分が抜けきらないまま、文化祭や体育祭とか行事が続いて非日常感が切れないからだと思うんですが。まあ、それはともかく。文化祭の練習で一際音痴の子がいまして」
うちの子?と短く発する愛生に、一昨年ですから今の六年生の話ですよと末田が耳打ちをする。
「で、音痴だけならまだしも、その子は歌うのが好きだったらしい。つまり、外れた音程にも関わらず大きな声で歌う。当然、バカにされますよね。それが嫌でその子は小さい声で歌うようになって、そうしたらその遠慮がちな様子が面白かったんでしょう、他の授業のときに末田に指されたときにも、みなが笑うようになった。と、まあ。ここまではよくある話です」
末田を一瞥するとくすぐったそうに鼻の穴を膨らませていた。
「そこで末田は、個人レッスンに付き合ったんです。昼休みや放課後なんかに、その生徒とふたりきりで練習して、見事上達させたらしい。その上達っぷりにいじめていた生徒たちも関心して、逆に練習に精が入り、一昨年は見事グランプリを受賞したんです。……って、合ってたよな、末田?」
「う、うん……。よくそこまで覚えてたね」
「凄く生徒想いなんですね。」と愛生。
「うーん、中々そこまでできなそう」と娘。
「いや、やっぱりね。いじめはいけないことですから。何とかそれをやめさせたいなって思って、けれど教員が力づくで介入したところで上手い解決にならないんです。そこで、力づくではない解決方法って何だろうって考えたときに、まずは君がやっていることは楽しいことで、それは正しいことだよって教えてあげたかったんです。それを恥しいと思わせないためには、皆に笑われなくなるしかないから。だから、僕も歌は下手なんですけど、一緒に練習をしました」
「いじめっ子たちを見返したわけだ、その子も偉いね」と娘が言うと
「それは違いますよ」末田はやんわりと言った。ぽかん、と呆ける娘に、
「さっきの聡の話は、たまたまの話ですから」
とだけ、ぽつり言う末田に娘は頭を傾げている。一方、愛生はじんまりと末田を見つめていた。
「その子が偉かったのは確かです。けれど、歌が上手くなって彼が救われたのは、結局彼が皆に本当には嫌われてなかったから。それだけです。決して、これでいじめが解消されるなんて、ぼくに確信があったわけではありません」
「じゃあ、何で教えようと思ったの?」愛生が訊ねる。
末田は暫く喋り通しだった口を潤すため、水滴に濡れたグラスを持ち煽った。
「せめて、音楽の楽しさだけでも忘れて欲しくなかったから」
末田はすっかり出来あがっているようで、胡乱な眼つきになってきていた。
「ぼくが中学生のときにいじめられていたの、飯島さん覚えていますか?」
末田のグラスに新しいカクテルを作りながら、飯島は頬笑んで首を曖昧に傾げた。傍から見るに必要以上の衝撃を受けた様子の末田は、眼を細めながら相槌をする。
「ぼくはいじめられてたんです。そのときの、ぼくの友達は本と画布だけだった。でも、彼らはぼくを充分に助けてくれていた。辛いときにはいつも傍にいてくれた。だから、彼のいじめを救うことはできないかもしれないけれど、中学生や高校生になってからまたこんな目に合うかもしれないけれど、ぼくにとっての本や画布が彼にとっての音楽になれたなら、そう思っただけなんです」
言い終わると、末田は再びグラスを煽り、ふん、と鼻息を鳴らした。すると愛生は末田の腿に手を重ねて置き、そっと彼の頬に顔を近づけ、囁いた。
「先生は、立派だと思います。本当に、本当に。」
末田はそのやわい感触に肩を揺らしたが、その後に続いた言葉が酔いに溺れる男の心を更に深部へと誘った。末田は小さく嗚咽を漏らした。愛生は彼の腿と背を擦りながら、慈しむように末田を眺めていた。娘は眼の前の光景が信じられないらしく、大げさに表情を歪めて聡に顔を向けた。やめろ俺は客だぞ、と聡は声に出さず囁きながらも、内心穏やかではない。
美談を語ったのは、はなむけのつもりだった。が、当然底意地の悪さも交る。お前が妄想逞しく溺れたところでこの女は俺のものだという奢り、優越感に浸る悦びを味わっていたのに、この光景は何だ。愛生は末田に確からしい視線を注いでいた。盗人は性欲を刺激する。けれど、それが盗人として成立しない末田だからこそ、単なる児戯として扱えた。それだけではない。末田の美談を語る内、次第に違和感を抱き始めている自分に気が付いていた。これは決して「美談」ではない。ありふれた末田の話、確かに末田は子供たちを愛していた。子供たちに自らの来歴を重ねてはいたが、彼には教員として勤めていく為の強い動機があり、裏打ちされる行動の如何には全て、愛が通底していた。彼の人生には熱意があったのだ。一方で自らの人生には熱意がない、それを今、聡は思い知らされたのだった。
腹底で憤怒が燃える聡は舐めるように末田を睨んだ。一方、末田は愛生に擦られながら未だ嗚咽を漏らしていたのだが、感極まったのか突然、
「愛生さん、僕は中学生の頃からあなたをずっと……」
と漏らし始めていた。滑稽でしかない男の姿を娘はせせら笑いながら聡の顔色を窺っている。
「ありがとうございます。けど、だめ。私みたいなのに、末田さんは勿体ないですよ」
愛生はにんまりと笑って頭を下げた。
聡は末田の背中を擦っていた。末田は薄暗い路地に蹲り安酒に痙攣する胃からすえた吐瀉物を漏らしている。自動販売機で購入した水を手渡すと、彼は喘ぐように呑み干した。聡は酸い臭いに顔を歪めながら上を向いた。狭い空に星は見えない。今夜は曇天だった。
末田を傍らで見守りながら、葵さんは今晩早上がりですよという娘の耳打ちを思い出す。聡は今晩会おうよとメッセージを送った。が、すぐには連絡が来ない。光る画面を茫と眺めて乾いた夜風に酔いがきりりと冷めて来た頃に、我に返れば呻きの変化に気付く。視線を刺せば、末田の相貌が街灯に濡れていた。口周りは黄色く光っている。
ぼくは駄目な奴だよ……。末田が呟く。知ってる、と聡は答えない。
援助交際をして、憑きものが落ちた気がしていたんだ。不思議とスッキリした気分だった。ああ、もうコンプレックスは消えたんだって思った。でも、悪いことをした、いけないことをしたんだっていう罪悪感は、あれから常にある。
呂律の回らない舌で末田は続ける。
あの援助交際は僕に必要なことだった。けれど、あれは絶対にするべきことではなかったんだ。そんな、そんなぼくを愛生さんは「立派です」って言ってくれたんだ。
知らないからだろ、今度は口に出した。
「それでも、それでもあの言葉に救われた。ぼくの人生が肯定された気がしたんだ」
携帯端末が震える。ふと確認すれば、今夜は遅番なのごめんね、という愛生からの連絡だった。店から続いていた聡の苛立ちは既に頂点にある。眼の前の男は十年越しに同じ女に惚れ直していたのだが、女にとってその年月は性の享楽舞台から階を一段ずつ転げ落ちてゆく日々でしかなかった。彼女の人生の頂点は既に過ぎ去っていた。そんな女が、改めて、見初められた。
吐瀉物にまみれ路傍にへたり込む男が、聡には眩しかった。自身を苛む劣等感から幼い少女の偶像を求め続けて来た男は、その反面、自身を何一つ満たさないと知った上で、自らの職能をフルに発揮し社会に応えて来た。そして想いの強さ故、この度、道を踏み誤った。が、ここで彼は希望を得ようとしている。その希望とは聡の快楽のことだ。それが、この男は気に食わない。
「愛生は子供が産めないんだ」
末田は表情を歪めた。その事実よりも、それを何故お前が知っている、という風に。
「倫子を産んだ障害らしい。そんな女でも良いのか」
愛生の身体は美しい。乳房も、腰のくびれも、滑らかな肌も、男を満足させて尽きない。けれど、女としての本質的な機能は失われて既に久しい。彼らが初めて交わった際に非妊の不必要な理由を聴き、聡は強く興奮した。彼女の美や官能とは、きっと不在が作る女の魅力なのだろう。
「聡が飯島さんの何を知ってるんだよ。……というか、聡。まさか」
「さあね。でも、お前みたいな奴を愛生が相手にするとは思えないな」
人一倍に愚鈍な末田でも流石に判り始めていた。ゴシップとして聴く分には心浮かす話も、自身が好いた女(ひと)ではそうもいかない。末田の胸中では愛生への想いと倫子への憐憫、そうして沙耶への同情が混濁し言葉が見つからない。煩悶した末田が、
「倫子の父親になる気があるのか」
やっとの思いで振り絞った問いだった。
「ないよ。種もわからない奴の親になんて」
その言葉に、末田は屹然とした眼つきで応じた。不愉快な視線だった。お前みたいな援助交際野郎に女を奪われるわけがないだろう、そう思いながら末田に背を向けた。末田は追って来なかった。
8.ひとりぼっちの男
苛々とした気分のまま帰路に就くと、玄関先に陶器の欠片が落ちているのに気が付く。それは沙耶が消えるときに割っていったマグカップの柄だった。今までここにあったのに気が付かなかったのか、それとも……。仄かに期待した聡がドアを開けると、しかし暗闇だった。電気を付けると、しいんと静寂が空気を満たす。初めて、沙耶の不在を寂しく思っていた。欲しいときに欲しいものがないことが、これほど寂しいものなのかと実感せざるを得ない。
冷蔵庫から水を取り出してソファに座る。口をつけ茫とした。何だか妙に落ち着かない。そこで、彼は電気を消して、部屋を再び真っ暗にした。これで良い、そう思った。
もう、末田と会うことはないだろう。惜しいとは思わない。思うとすれば、愛生を末田に取られてしまったときのことだろう。愛生は、末田になびくだろうか。あの童貞に。いや、それはないだろう。万が一、そういう事態が生じたとしても、元々飽き始めていた女だ。代わりを見つければそれで済む話。それよりも、別れ際の聡を睨んだ末田の表情が脳裏から離れない。蝋燭が最後の一瞬に大きく燃え上がるような、終える人間の最後の輝きを見た気がしていた。その瞬きを、一寸、美しいと思ってしまった。聡のがらんどうな体内で反響音が鳴っている。
そうだ、酒だ。酒を呑もう。すっかり冷めた酔いを取り戻そうと冷蔵庫を開けると、何もない。近くのコンビニで買うか悩んだが、いや、どうせ外に出るなら誰かと呑もう。真っ先に沙耶が浮かぶ。あれから、沙耶からの連絡は一度も来ていなかった。思いきって電話をすると、もしもしと声がした。
「久しぶり」
「……うん。久しぶり」
彼女の声に時折、走行音が交った。外にいるようだった。
「すまん、俺が悪かった。一度話し合いたいんだ」
「……そう。じゃあさ、さっくん。今から迎えに来てよ」
「え、今から?帰りの電車なくなるよ。近くならタクシーで行くけど」
「いま、長野」
「え、長野って。もしかして実家?」
「ごめん、うそ」
「なんだ。びっくりさせるなよ。で、ほんとはどこにいるの?」
愛生は言葉に詰まりおし黙る。適切な言葉を探しているようだった。
「……私の実家って、ほら、長野の山奥じゃない。だから秋になると、そう、あき。ほら、秋になるとすっごく紅葉がきれいで、今の時期はね、もう真っ赤に燃え上がってて。さっくんも前、この時期来てくれたよね。あれ、綺麗だったね」
「……そうだね。綺麗だった」
「やっぱりさ、故郷って特別だよ。東京で暮らしててさ、別に何ら違和感とかなく生活しているのにさ、紅葉見たり、鳶の鳴き声を聞いたりすると、ガツーンって頭叩かれたような気分になる。強い郷愁感って鈍器みたいに重い。そういうとき、長野に帰って暮らすのも悪くないかも、って思う」
「東京出身の俺にはわかんない感覚だな。けど、初耳だね。沙耶がそんな風に思ってたなんて」
「言うの初めてだからね。でさ、そうなった場合、私は誰と一緒にいるんだろうとも思う。ねえ、さっくん。私がどうしても長野で暮らしたいってお願いしたら、一緒に来てくれる?」
「……東京を離れるなんて考えたことがなかったからな。でも、そうしないと別れるってんなら、仕方ない。行くよ」
「コンビニは遠いよ、娯楽施設なんてろくにないよ」
「おう、我慢する」
「……ふふ。ありがと。けど、さっくんには無理だよ。狭い社会だから、浮気性のあなたは耐えられない。私が恥しい思いをすることになっちゃう」
「……ごめん。もうしない。絶対しないから」
「……うそつき。けど、大丈夫。私は東京にいたいって思うんだ。この街でやりたいこととか、特にないんだけどね。」
「そっか。それで、今どこにいるんだよ。迎えに行くから」
「ん、いいや。まだ帰りたくない。もう少し、このままでいさせて」
「……もう少しって、どのくらい」
「土曜日。土曜日には連絡するから」
「……わかった。待ってるよ。沙耶、好きだよ」
「……うん、ありがと。それじゃ」
その晩、夢を見た気がした。自分の唸り声に起こされて汗でぐっしょりと濡れたシャツを変え、もう一度床に入るとすぐに眠ることができた。朝、目覚めると手元には、夢の残り香があった。何かを夢見た気がしたけれど、それは既に失われている。しかし、それは最初からなかったものかもしれなかった。
文化祭を明後日に控える中、学校はいつもと特段変わりない。けれど、最後の放課後練習を終えて職員室に戻ると、隣のデスクが綺麗に片付いていた。知らない間に末田が来て、片付けを済ましていたらしい。
聡の机の上に一枚の紙が置かれていた。いつぞや門倉が提出した不問扱いの読書感想文。末田に見せた際、そのまま捨ててくれと渡したものだった。末田はどういうつもりでこれを残したのか。これが末田ならばきっと、この作家について調べるのだろう。その上で事情を聴いて門倉の才能を理解しようと努めるのだろう。しかし、俺は末田ではない。あんなくだらない人間ではない。そう苛立ちを覚えながらも聡を図書室へと運ばせたのは、つまるところ、羨望だった。
放課後の図書室にはまだ生徒が疎らに残っている。彼らは一心不乱に文字の羅列を追い、体を空想の世界に浸している。なかには、大人も読むのを億劫に思うような分厚い本を抱える生徒もいた。また室内の隅には、男子が数人集い一冊の本を回し読みしていた。その光景に聡自身も覚えがあり、この頃の男子たちの忙しなさにも合点がいった。やがて、彼は国内小説の棚の一角で背表紙を追った。
唯一の手掛かりは、芥川龍之介と彼の文人が知人だったという点だけだ。そこで、芥川の日記と伝記書を読めば何か情報があるかもしれないと考えた。受験勉強の際に詰め込んだ知識で芥川が夏目漱石の門下生だったことも知っていたため、夏目漱石の伝記本も探す。けれど、そこは小学校の図書室。目当ての本が置いてあるはずもない。諦め、けれど諦め切れず、最寄の区立図書館にでも行こうと思い、本棚から離れて窓を一瞥したところ、その手前に飯島倫子の姿があった。児童向けの厚いファンタジー小説を読んでいる。聡は歩く方向を変え、少女の傍らに立った。
「偉いな、飯島。こんな厚い本を読んで」
声をかけたのは、この少女に対する罪悪感からだった。それは、聡が元々持っていた罪悪の種に、末田が成長剤を散布した結果の花だった。その色は不正直な灰色をしていた。
「べつに……そんなことないです」
倫子は聡を睨んだ。また、この眼だ。明らかな敵意と侮蔑を込めた、純粋な怜悧。鋭い刃先が聡に向けられている。
「読書もいいけど、明後日は感想文の発表だろう。ちゃんと出来そうか?」
声を掛けたことに後悔しながらも去り際には早かったので、着地点へと向かえるような問いを投げる。大丈夫です、そうか頑張れよ、これで会話は終了するはずだった。
「私たち、ふたりで大丈夫ですから。これ以上、お母さんに関わらないでください」
そう言い放ち、本をそのままに少女は走り去って行った。呆気に取られた聡は、辺りを見渡した。誰も彼のことを気にしている生徒はいない。皆、読書に没頭している。聡は本をあるべき場所に片付けると、図書室を後にした。
苛立ちの種は尽きない。まさかあんな子供にまで馬鹿にされるなど、聡は思ってもみなかった。俺達はそもそも、軽い遊びの間柄だ。でなければ、あんな売女(ばいた)と一緒になる訳がない。そんな売女と俺を同列に扱った末田と倫子、そして自分の立場も弁えず分不相応な願いを持つ愛生。血が繋がっていないどころか誰が父親かもわからない小生意気な娘の父親に、数百の男の性器を咥えて来た欠陥のあるオンナの夫に、俺がなる筈もない。まだいる。沙耶だ。勝手に一週間もいなくなり、果ては冗談めかして一緒に故郷へ帰ろうとぬかす。全員、勝手だ。
頬を撫でる風が、すっかり秋だった。さくり、と音がしたのは、路肩に積まれた落ち葉を踏んだため。一歩歩く毎に、さくり、さくり、音が鳴る。空を仰いでやっと、ここが公孫樹並木の通りであることに気付いた。黄色く色づいた葉が空を鮮やかに照らし、これからの厳しい季節の到来を、まずは祝福してみせている、そんな風景だった。人通りも多く、この景色を見る為にわざわざ訪れている人もいるようだった。
幼い頃、まだ父親が生きているときに、親子三人でここに来たことがあった。両親の事を思い出すのは随分久しぶりだった。母は、今この街でどうして暮らしているのだろうか、ふとそんなことを想った。そして、死者を想った。聡は、自身が生まれたときの父の年齢に差し掛かろうとしている。
公孫樹並木はずらり高い。深い藍色に染まる空と黄色に塗り上げた葉のコントラストは美しい。この土地から養分を吸って彼らは大きく育った。思えば、トビを埋めたのも公孫樹の下だった。あの公孫樹はここまで立派ではない。まだ若芽なのだ。しかし、彼はトビの命を養分に、きっとこのように大きくなるのだろう。それはトビの生命の証であると同時に、沙耶の愛だった。あの埋葬に聡は関わっていない。
皆、勝手じゃないか。俺だってそのひとりだ……。小気味良い音を響かせながら、並木通りを歩いて行った。
9.死後に残るもの
区立図書館は病院に似ている。古びた公共施設の辛気臭い空気。人がいるのに誰も喋らず、時折紙の擦れる音だけが響き渡る静寂。そんな雰囲気と本棚に納められた夥しい本が聡を圧迫させた。
芥川全集と漱石全集、そして両作家の伝記書を大量に机に積んで読み始める。ひとまず、漱石門下生について読む。めぼしい者はいない。次に、芥川の交友関係、そして書簡集などを紐解いてゆく。が、記述はない。彼の人生を一通り追っても、彼の文人は歴史の層から顔を出さない。ならば、と思い同時代を生きた森鴎外、菊地寛、谷崎潤一郎、そうして川端康成にまで辿り着いた頃には、すっかり辺りは暗くなっていた。辺りを見渡すと人も疎ら。正味、聡は飽き始めていた。読みかけの本を閉じて一息つく。
なぜ、こんなことをしているのか。がらではない、帰るか。そう思いながら遠くをぼんやりと眺めた視線の先、本棚の一角に女性の姿が見えた。図書館員らしく深緑のエプロンを巻いたその女性は、返却された本を一冊一冊丁寧に棚へと納めてゆく。聡はぼんやりと女性を見つめ続ける。女性は聡の目線に気付かず黙々と作業を進める。女性は時折、本棚に抱かれるように姿を消したが、それでも細かい音は聴こえる。見えないだけで作業は続いている。と、再び半身を現した。ひとりの若い女性の働く姿を一方的に眺めれば、そこには卑猥な欲望が宿った。しかし、このときの聡は違っていた。確かに欲望はあったが、それ以上に寂しくもあった。
半身の女が聡の目線に反応した。中空で視線がかち合った両者はどちらも譲らない。けれど、やがて女がその姿を消す。そしてまた半身を露わにしては、互いの視線を絡ませ合う。妙な戯れだと擽ったい気持ちでいると、女は本棚から顔を出して何かを確かめるように目を細めて聡を見つめた。意表を突かれた聡は肩を揺らしたが、その視線を受け止める。どこか見覚えのある顔だった。すると、女がやって来た。
「あれ、聡くんじゃない。私、中学一緒だった池内だけど、覚えてるかな?」
聡は池内のことを殆ど覚えていない。思い出す映像の端にいつも切れかかって映るだけで、一度でも話したことがあったのかさえ定まらない。しかし、女は美しくなっていた。容貌の魅力という点では愛生に劣るものの、若さという無条件な魅力を越えた生命力に満ちていた。
「聡くん、噂聴いてるよ。学校の先生なんだって?」
「そうだよ。でも、何で知ってるの?」
「そりゃあ知ってるよ。うちの図書館の廃棄になる本をたまにあなたの学校に譲ったりしているからね。司書の先生が言ってたよ。あなたと、あとほら。あの目立たなかった男の子。末田……くん?だっけ」
急に登場した末田の名に驚いて、聡は言葉を詰まらせ適当に返事をする。その後、末田くんは元気、と訊ねられた際にも濁した返事をしたが、その曖昧さに池内は何かしらを感じたらしく、それ以上追及しては来なかった。
池内は魅力的だった。知的で適度に朗らかで外見も悪くない。なによりニットのセーター越しにふっくらと膨らむ乳房が欲望をそそった。
最寄りの居酒屋に移って既に小一時間。こうして話していて、相手も満更ではない様子に思える。良い機会だと何度も思おうとしたが、それでも結局は寂しさが強く押し寄せる。眼の前にはこんな魅力的な次の女がいると言うのに、何を躊躇しているというのか。
「……私ね、実は。作家を目指してるの」
酔いも回って来た頃に池内はつま開きに言った。さも、重大な事柄を打明けるように。聡も同じく、さも重大なことだという風に応じる。
「それでこうして近所の図書館でバイトしながら小説書いたりしてるの。時々はやんなっちゃうこともあるよ。けど、そこそこ愉しんでる」
そのとき、なんでこんな言葉が出て来たのか。苛立ちに負けたのか、はたまた夢追い人という点で末田のことを思い出したのか。ともかく、次の瞬間に聡は、『驟雨の都』について訊ねていた。作家志望ならば、何か知っているかもしれない。そう淡い希望を抱いて。しかし、その望みは直ぐに終えた。池内は首を横に振った。知らない、聞いたこともないと。肩を落とした聡は、件の顛末を語った。池内は興味深そうに耳を傾けていた。聡が語り終えると、池内は暫し考えた後、遠い目をした。
「そっか……何ていうか、不思議な話だね」
「そうなんだ。もしそんな作家がいないとすれば、悪戯に決まっているんだけど。しかし、そんな悪戯をするような子でもないし」
「悪戯かどうかは私にはわからないけど、私からすればどっちでも素敵な話に聴こえるな」
聡は意図が判らず真意を訊ねた。すると、池内は目尻を垂らし、うっとりとした表情で語った。
「実在を問わず、結局、彼は小説家として未完の人だったわけだよね。本を出版することが出来なかった。当然、後世にも残らなかった。何をどんな風に書いたのか全く知られず、その影響関係も存在しない。そんな芸術家は、仮に実在していたとしても存在しなかったのと一緒だと思う」
熱を帯びる言葉。そして、続ける。
「フランツ・カフカって知ってるよね?」
流石に知っている名前だった。二十世紀を代表する作家。朝目覚めると虫になっていた高名なグレゴール・ザムザ、そのぎちぎちとした肉体にリンゴをめりこませながら息絶えた哀れな官吏の父としてのフランツ・カフカ。
「生前、カフカは一冊しか本を出していないの。碌に読まれず、その本の殆どを自らで買い取ったらしい。存命中に日の眼を浴びなかったという点では、ゴッホや宮澤賢治と似ているよね。ともかく、彼は売れなかった。けれど、書いたわけだ。そうして、病に伏せってしまうの」
池内は一端、言葉を止めた。聡の相槌を求めているようだった。
「それで、どうしたの」
「原稿を全て燃やしたの。とは言っても、病から自分で行うことはできないから、親友に頼んで。自分の死後、原稿を全て燃やしてくれ。一片も残らずにだ、って」
「……何でそんなことを頼んだのだろう」
不可解だった。仮に自分が死ぬ存在であるならば、自分の代わりに作品を残したいと思うだろう。少なくとも、聡はそう考える。せっかく努力をして生んだ作品だ。むしろ、親友に精力的に活動してもらい、死後にこそ正当な報酬を得たいと思う。それが普通なのではないか。この疑問に対する池内の回答は、あっさりしたものだった。
「カフカって完璧主義者だったらしいよ。実際、自身が書いたものには終生手を加え続けたらしいからね。そんな未完の作品を世に公表されることに耐えられなかったんじゃないかな」
不満足な回答だった。芸術家の場合、汚名でも何でも後世に名が残った者が勝ちだろう。自分の名が生き続けてることを求めるのではないのか。
「話を戻すね。結局、現在カフカは世界中で読まれているよね。つまり親友が裏切ったわけだ。これは読まれるべき作品だ、って。そうして今がある。今日の文学があるの。カフカだけじゃないよ。ヘンリー・ダーガーという画家がいるけど、彼も大体、同じようなものなんだよね。一歩間違えば存在しなかった芸術家。つまり、彼らの存在こそがひとつの存在を浮かび上がらせていると思う」
聡は、ぽかんと口を開いていた。わけの判らない話だった。池内は興奮を面に掲げ、爛爛とした目付きでうっとりと広大無辺なロマンを語る。なぜ、俺は今こんな話を聴かされているのだ。
「つまり、原稿を燃やされたカフカだよ。そのような人々が、おそらく沢山いた。彼らの屍の上に、フランツ・カフカは城を建てたんだ。だから、誰もその城門に辿り着くことはできないんだよ。そうして、その内のひとりがその『驟雨の都』の作者さんなんだよ。ロマンがあるよね。カフカ的亡霊が、自らの子孫に憑いて再度夢を果たそうとするなんて」
「でもね、私は思うんだけど。そうやって不存在な存在の上に立っているのは、私たちも同じなんじゃないのかな。実際、聡くんは三世代前のご先祖の名前を言える?」
聡は黙って首を振った。
「私だって無理。言える人の方がきっと少ないよね。でも、先祖がいたから、私たちは生まれてこられた。大きな仕事を成して後世に名が残る人もいる。その一方で、その文人や我々の先祖のように、何も残せなかった人や残したけれど匿名の人として消えた多くの方々がいる。世界はそういった幽霊たちに支えられているんじゃないかな」
消え入るような声で語った後、こないだの新人賞では最終候補まで残ったから、後少し。ここからの壁が厚いのはわかってるけど、ここまで来たんだ。頑張るよ私は。そう語る池内を前にして、聡の性欲はすっかり消沈していた。その代わり、寂しさがこれまで以上に強く押し寄せている。別れ際、彼女が言い残した言葉が聡の胸に深く突き刺さっていた。
「聡くんは自分のいなくなった世界に何を残したいって思う?」
10.鳥小屋
文化祭は盛況の中に進んでいた。普段より落着きのない子供たち、正装に身を包んだ聡たち教員。そして、子供たちの成長を噛み締めて笑みを浮かべる保護者たち。校内が浮足立っていた。
午前の部も前半が終わり、読書感想文の発表が始まった。ひとり、またひとりと発表をしてゆく中で凛子の出番が来た。
倫子は環境汚染に関する課題図書を選んでいた。これまで人類は、進歩と称して勝手をした。地球温暖化・森林伐採・乱獲による鳥獣の絶滅、そして原発事故……。そんな、母なる星を脅かす問題を集めた本。彼女は、それを自身に重ねて訴えた。
人類に警鐘を鳴らしたところで、鐘の音が届く範囲は限られている。共振する者となれば、尚更少ない。けれどその持続可能性を求めて人類は星を継ぐ後世に想いを託す。親から子へ、子から孫へと継ぐ地球への慈しみに関する本について、倫子は同意と共に、ささやかな祈りを告げる。大人は確かに勝手だ。けれど、私たち子供もいずれ、大人になる。そうして、きっと、星を汚すのだ。でも、私たちは大人の勝手を見て来たから、きっと少しだけ、優しくなりたい。だから大人は、そんな私たちの想いを汲んで、警鐘に耳を傾けて欲しい、と。私たちに大人を、自分自身を信じさせて欲しい。これは、倫子と愛生の関係そのものだった。娘は発表中、一心に母親を見つめていた。職員席から愛生の表情を窺うことはできなかったが、遠目に映る愛生の肩は時折震えて見えた。
午後になり、合唱に移った。一組一組、稚気溢れる歌声を披露してゆく。その歌声が聡の奥底にささくれのような小さな痛みを萌した。その痛みが最も激しくなったときは、一学年下のクラスのときだった。そのクラスは四年生にしては足並みが揃い、高く幼い声は体育館を七色に揚々と照らした。
やはり、末田は良い教師だったのだ。彼には教師になる動機があり、子供たちに対する態度には愛が伴っていた。汚名を負って消えた今でも、それは変わらない。この合唱は別離の歌だった。その歌は単身者用アパートで眠る末田までは届かず、パイプ椅子に何度も腰を浮かす聡の下腹をちくり刺すだけだが、生徒たちからの挨拶であることに変わりはない。この先、復職することはないだろうが、末田はきっと子供と触れ合って生きてゆくのだろう。
すべての行事が終わり肩の力がすっかり抜けた後、教壇の上で学級日誌やノートの類をまとめながら教室内を見渡せば、至る所で親子が睦み合っている。大人たちは久しぶりに再会した同級生の子を持つ親同士で歓談に耽る。子供たちは無邪気に笑い母親のスカートの裾を引きながら、クラスメイトと話している。みな、そわそわしていた。早く学校を出て、遊びに行きたいという風に。聡は職員室に戻ることにして教室を出た。
廊下に、愛生と倫子がいた。愛生は屈んで倫子に目線を合わせて会話をしていた。始めて見る表情だった。これまで、親子ふたりで過ごすときにはいつもこんな表情をしていたのか、それとも……。考えたところで、聡には想像することしかできない。愛生が聡に気付いた。上目遣いに聡を眺め、やがて、笑った。その表情に妖しい影はない。彼女の含みのある笑みに充てられ、聡は幾度も勃起させられた。しかし、今日はぴくりとも反応しない。このとき初めて、愛生と心が通じ合った気がした。ああ、そうか。終わったんだ、この女とは。そう思い、親子の隣を過ぎて行った。
職員室に向かう途中で角を折れ、生徒用の下駄箱を抜けて外に出た。外は明るく、青空が広がっていた。校庭では生徒たちがサッカーをしている。
「あら、先生。いつも息子がお世話になっております」
振り向くと、門倉真澄を中心に据えて中年の夫婦が立っていた。挨拶ついでに学園での門倉の様子を訊ねられて適当に応えていると、門倉がサッカーに混ざるため校庭へと駆けて行った。大人たちだけが残される。ふと、門倉の読書感想文のことを思い出した。
「あの、実は……」
と顛末を話す。この話を人にするのは何度目か、自分でも驚くほど流暢に話すことができた。しかし、両親の神妙な顔つきは最後まで崩れなかった。
「それはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。けれど、それは悪戯だと思いますよ」
母親がそう答える。どうやら、学校と家とで、門倉の性格は違うらしい。
「あの子ネットが好きなんです。多分それで、どこからか引っ張って来たんですよ」と笑いながら言う。「そもそも、私たちどちらの家系も、祖父に兄弟はおりません」
そう言い、夫婦は去って行った。釈然としない想いだった。本当に只の悪戯だったのか、それにしてはあの日の門倉の態度は真に入っていた。狐につままれたような気分じゃないか。夫婦はサッカーに混ざったばかりの我が子を呼びよせ、少年は渋々ふたりの中央に収まり、校門へと向かう。
幸福な後ろ姿だった。かつて聡も、あの中央にいたことがあった。しかし、その空間は父が死に母と疎遠になって、今や青年期から離れようとしているかつての少年が収まるには、小さすぎるスペースであった。
ふと、沙耶の顔が頭に浮かんだ。今日は彼女が帰って来る日である。携帯端末を開いてみると、メッセージが届いていた。今、校門のところにいる、という内容だった。
目を凝らして遠くを見る。確かに、ひとりで校門に立つ女性がいる。沙耶だ。遠目でも判別できる。彼女がこうして学校に来るのは初めてのこと。わざわざ勤務先まで何をしにと訝しみながらも駆け寄ってゆくと、多くの親子が沙耶と行き交う中で、或る一組が、飯島親子がまさにすれ違うときだった。女たちの視線がかち合ったとき、親子は立ち止る。まだ遠い聡には女たちの表情は窺えない。やがて、愛人がしんなりと礼をする。正妻はそれをじっと睨む。父なし子は憎むように敵の女を見上げる。そして、破裂音が響いた。愛人は頬を抑えて立ち止まったが、その唇から血が一筋滴る。が、親子は何も応じずに娘が先導して歩き始め、母は連れられるように姿を消していった。
聡が沙耶の下に着いた頃には、親子の背中は小さくなっていた。沙耶は校門の石塀に身を預けて立っている。存在に気付くと沙耶はじっと聡を見つめた。何も言わない。何か言って欲しい。それが今まさにすれ違って行った女への悪言でも自身に対する恨みでも、何でも良い……。聡にはもう次がない。そのためいくらでも次の自分の潔白を証明できる気がしたが、罪悪感よりもその焦燥が身を焼き痛む。やがて、沙耶が囁いた。私、妊娠したみたい、と。それでたまらなくなって、ここまで来たの。
予想もしない言葉だった。もちろん、動揺した。けれど、その後に萌した感情は果たして、安堵だった。ああ、これで解放されるのかというのが、聡の心中の本音だった。
校庭では少年たちが球を追い走っている。腐乱に走り回り、秋の寒風が吹きすさぶ中を身ひとつで転げ回り、その様は楽しげだ。その中には廃ビルに忍び込んだ面々も多く見える。彼らは門倉と同様に幽霊を観られたのか。彼らが観たものは本当には何であったのか。聡の学年では末田の性事件にあてられ、急速に性に関する興味が上昇している。そこで学校側では通常は六年生に向けて行われる女子に対する性知識の教育を、今回に限り五年生に向けて行うことに決めた。
聡は死んだ父親のことを想った。父の死後、肩の力が抜けたかのように活力が衰え、その亡霊のような姿が嫌で母親とも距離を取った。何かを両親から貰ったという感覚が、聡にはない。そんな聡が自らの子に託すとすれば、熱意だった。我が子には熱意ある人生を送って欲しい。自分はきっと、今更そんな人生は送れない。けれど、血を分けた子供がそのような人生を全うすれば、何だか救われるような気がした。結婚しようか、聡はそう言った。
聡と沙耶は校庭を眺めていた。妖精たちは風を切り、一心にボールを追っている。ひとりの少年が強くボールを蹴ると仲間の頭上を大きく越えて、校庭の隅に建つ鳥小屋へと当たった。その衝撃に驚いた鳥たちは大きく劈き、羽のある者は強く羽ばたいた。しかし錠はすっかり閉ざされている。彼らがそのまま、遥か上空まで飛び上がれることはない。鳥たちは束の間に小屋の中を飛び回っていたが、それも次第に収まって宿り木に羽を落した。
鳥小屋