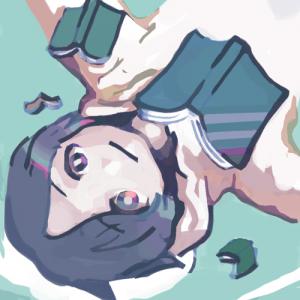爪を剥ぐ人
初めて書いてみたミステリです。
女子高生爪剥ぎ事件を追う主人公と閑崎は事件の犯人を突き止めるが……。
ホームルーム十分前の朝の教室は、独特な賑やかさによって今日も一日の始まりを知らせている。各々が数人ずつのグループを作り、様々な情報を話題として交換して盛り上がりをみせている。
僕は規則正しく並べられた机の最前列にある自分の席に座り、読書をしていた。
「えっと、おはよう」
斜め後ろから声をかけられ、振り向くと山口君が立っていた。
「ああ、おはよう。今日はなんだか雨が降りそうだね」
僕は教室の窓へと一度視線を流し、山口君の挨拶に適当に応じる。
「あの、これ。読み終わったからさ」
山口君は少しだけ居づらそうな表情を顔で作りながら、手に抱えていた一冊の本を僕に渡してきた。数日前に僕が彼に貸していた本だった。ブックカバーはされておらず、表紙には歪なフォントで「世界オカルト事件簿」と書かれている。
「ありがとう。どう、面白かった?」
僕は山口君から本を受け取りながら聞いてみる。答えにはさほど興味はなかった。山口君は僕の隣の席を気にしながら「面白かったよ。また今度、よかったら違う本を貸してね」と言い、自分の席へと歩いていく。途中に群がるクラスメイト達を邪魔そうに避けながら、自分の席へと座ると頭を伏せた。
「閑崎。君は僕が貸した本。読み終わったのか?」
机の横に掛けられた鞄に「世界オカルト事件簿」をしまいながら、隣の席に座っている女生徒に話しかける。
閑崎は自分のものではない机に座り、暇そうに両足をブラブラと揺らしながら、視線を遠くに向けていた。どうやら。というより言うまでもなく、山口君は彼女を気にして居づらそうな顔をしていたらしい。クラスの人気者と日陰者とでは、気が合わないどころか、歯車の種類すら違うのだろう。
「ん、え? ああごめん。まだ読み終わってないよ」
そう言って教室の入り口方向に向けていた視線を切り、やっと話は終わったのかい。といった感じで僕に視線を移す。閑崎には山口君が眼中にも入っていないらしい。僕は山口君に同情をしようとして、面倒くさくなって止めた。
「そんなことより、気になることがあってさ。読書をしている暇はないんだよ」
閑崎はもう一度視線を教室の入り口へと向けた。その視線の先を追って見ると、何人かの生徒達が集まり、教室内へと続く道を詰まらせている。騒ぎの中心には一人の女生徒がいた。頭と右手の中指に白い包帯を巻いている。閑崎はその女生徒を見て、ほんの僅かに口元を笑わせている。彼女のその少年のような顔の、微妙な表情の変化に気付いているのは、僕だけだろう。
「中指。これで三人目だ」
僕はそう言って、閑崎と視線を揃える。
教室内で様々な会話をしていたクラスメイト達も、包帯を巻いて登校してきた女生徒の存在に気付いて近寄っていく。みるみるうちに、女生徒は集まってきた生徒達によって見えなくなっていった。
「うん。これで三人目。そろそろ、もしかしたら警察が動き出しちゃうかもしれない。ね」
閑崎は一瞬だけ、困ったような表情を見せた。
ホームルーム開始直前のチャイムが鳴った。担任の教師が出席簿を手で拍手をするように叩きながら、教室内へと入ってくる。ガヤガヤと騒いでいた生徒達が、各々の席へと散って行った。
「今日の放課後、残ってて。話をしよう」
閑崎はそう言い残し、腰を下ろしていた机からぴょんと飛びストンと着地し、自分の席へと歩いて行った。
女子高生爪剥ぎ事件。
午前中の授業が終わり、昼休みに入る頃。今朝の出来事は既に学校中に知れ渡ったらしく、そのような名称がちらほらと聞こえてくるようになっていた。
一人目の犠牲者が出たのは、先月。約一ヶ月前の事だった。あるひとりの女生徒が夜、暗く人通りの少ない帰り道を歩いている途中。後ろから金槌か何かで、後頭部を殴られて気絶させられた。右手に走る激痛に目を覚ますと、辺りには誰もおらず、右手の親指の爪が剥がされていたそうだ。
二人目の犠牲者も同じように、右手の人差指の爪を剥がされたらしい。それが丁度、一週間程前の出来事だった。
犯人は何故、こんなことをするのだろうか。普通ならばそう考えるのが、普通だ。だけど、僕や閑崎はそういった犯行の理由にはあまり興味がない。僕達が興味があるのは、犯人という人間と事件の奇怪性だけだ。強いて言えば、犯人が何を思い、何を考えながら、何をしたか。それにこそ興味があった。異常者が起こす普通ではない事件に、充分な動機なんて存在しない。衝動と欲求。そうしたかったからした。それだけで彼らは実行出来る。それだけで異常。そういった普通ではない事。僕はそういうものに惹かれる。
二人目の犠牲者が出た当初は、事件性も低いらしく警察は本格的には動かなかった。せいぜい町内に変質者出没注意の張り紙がされた程度の事だった。
だけど、これで犠牲者は三人になった。さすがに警察も重い腰を上げて、事件の捜査をし出すかも知れない。それはつまり、この奇怪な事件の犯人にとって、次の犠牲者を出すのに不都合になることは明瞭。
そして、それはつまり。この僕が困ることになる。
午後の授業も全て終わり、教室からは生徒達が次々と消えていく。僕は全ての生徒達が出て行くまで、自分の席に座り読書をして待った。
「お待たせ」
閑崎が教室に現れたのは、生徒達が下校し、教室内に僕ひとりとなってから数分後だった。一緒に帰宅をしていた友達(ということらしい)に、忘れ物をしたから先に帰ってて、という理由をつけて戻ってきたそうだ。
夕方の教室は電気も消えて薄暗い、窓から見える空はすっかり晴れていて、オレンジ色の夕日が室内を薄く照らし、セピア色に染めていた。教室内には僕と閑崎の二人だけで、時々廊下からは部活を終えた生徒や教師たちが歩いていく足音だけが聞こえる。
「そろそろ、事件の調査をしようと、思うわけ」
閑崎は朝と同じように、僕の隣の机に腰を下ろしてからそう言った。
事件とは勿論、爪剥ぎ事件のことだろう。犯人の正体にも興味があるのかも知れないが、彼女にはおそらく、僕と同じく違った別の目的があるのだろう。その為に、この爪剥ぎ事件について調査をし、あわよくば犯人と接触をしたいらしい。
僕は反対出来なかった。反対しなかった。こうやって楽しそうな閑崎を見るのは嫌いではない。
「一人目が親指、二人目が人差し指、そして三人目が中指。これは事件の連続性を示す最大の証拠なわけで、そして被害者はこの先も出るということも示してる。これくらいは誰でも分かる範囲だね」
閑崎は楽しそうに事件の概要を勝手にまとめ始める。
おそらく犯人は女子高生の爪を五枚、もしかしたら十枚剥がしたいのだろう。流石に二十枚ということはないと思う。もしも犯人が女子高生の爪を二十枚剥がすというのなら。僕は犯人を神聖化しよう。
そして、おそらく犯人は剥がした爪をコレクションとして持ち帰っているらしい。良い趣味だと思った。
「犠牲者は全員うちの学校の女生徒。現場は全てうちの町内。わざわざ遠くの町から爪を剥ぎに来るってこともないと思うし、犯人は多分町内の誰かよね。もしかしたらこの学校の生徒かも」
それはさすがにこじつけではないだろうか。と言おうとして止める。閑崎はおそろしく感のいい奴だ。今の考察も、おそらく直感で出た結論に無理矢理に理由をはめこんだようなものだろう。そしてそれは、妙な信憑性を纏っている。
「心配なのは、途中でビビって止めちゃうことと、警察が調査をし始めて犯行を起こせなくなること。前者はありえないと思うけど。やっぱり後者が不安だよね」
閑崎は独り言のように呟きながら、時折うんうんと頷いてなにやら考えている。その度、肩まで伸ばした黒髪が小さく揺れた。
「今日はあたしはこれから、いつも通り図書館に行くからさ。明日の朝、現場に行ってみよ。被害者の三人から場所を聞いてるから。ね」
机からぴょんと飛んでストンと着地し、こっちを向いて閑崎は言った。
楽しそうに笑っている。目は笑っていなかった。
次の日の朝。僕は閑崎に渡された地図を頼りに、一人目の被害者が親指の爪を剥がされた現場に向かっていた。残りの二人目三人目の犠牲者が襲われた場所は、近くであるからという理由で、閑崎が一人で調査をするらしい。
冬の朝は想像以上に冷え込んでいた。呼吸をする度に吐いた息が白く凍りつき、風にさらわれて消えていく。辺りは濃い朝靄で覆われていた。
閑崎の書いた地図はまるで暗号のように複雑で、現場に辿り着くまでに数度迷ったが、なんとか到達することが出来た。
そこは駅の裏側の道を少し進んだ所にある、小さな公園の前の歩道だった。僕の頭に、何故駅の近くでありながらここまで迷ったのか、と疑問符が浮かんだ。
現場は閑散としていて、朝のジョギングをしているニット帽を被った男性(おそらく)が霧の中に消えて行くのが見えただけで、他には人の気配は無かった。
とりあえず僕は、寒さに凍えながら現場の周辺を調べ始める。運がよければ、犯人の証拠になる落とし物等があるかも知れない。
公園内に生えた木々から落ちた大量の落ち葉が、道の脇に小さな山脈のように積もっていた。そのせいで、証拠となるものを探すのはなかなか大変だった。
次第に空が明るくなり、朝靄もだんだんと晴れてきている。落ち葉の山脈をあさり始めて三十分が経ったころ、僕は近くの自販機でホットコーヒーを買い、無人の公園のベンチに座り休憩をしていた。公園には質素な雰囲気が漂っている。遊具といえば鎖が所々錆びたブランコと像を模した小さな滑り台、それに落ち葉によって半分以上が埋もれてしまっている砂場だけだった。敷地内の周りには木々が囲むように並び、時折風に吹かれて落ち葉を降らせている。
そもそも、この現場。一人目の犠牲者が襲われたのは今から一ヶ月も前の事だ。そんな長い時間を経て事件の手がかりとなるような証拠を探そうというのは、無謀ではないだろうか。そんなことを考え始めた時、時刻は既に午前六時半になろうかというところだった。制服を着ていない僕は、登校準備をする為に一旦家に帰宅しなければいけない。そろそろ帰るかと思いベンチから腰を上げた時、一瞬。ほんの僅かだけ誰かの視線を感じた。首だけを動かして辺りを確認するが、既に視線の主は居ない。
僕はそれ以上は別段気にすることも無く、帰路へと歩を進める。
一ヶ月が経ったとしても、犯人は現場に戻ってくるものだ。
登校準備をするための一旦の帰宅途中、偶然にも閑崎にばったり遭遇した。僕が閑崎の書いた暗号のような宝の地図のことを指摘すると「見かけによらず頭が悪いね」なんて言われた。
続けて僕は現場調査の結果報告をする。事件の手がかりになるような収穫は何もなかったことを告げると、閑崎は意外にも無関心そうに頷くだけだった。
そっちの収穫はどうかと聞くと、待ってましたとばかりに閑崎は報告を開始した。
閑崎は第三の犯行現場で、山口君と会ったらしい。丁度、現場の調査を終えて帰ろうとした時に、珍しいことに山口君の方から声をかけられたそうだ。どうやら彼も、個人的にこの事件に興味を持ち、調査をしていたらしい。
「そこで彼と情報交換をしたんだよ。あたしが持っている情報なんてのはあまり役に立たないだろうけれど、山口君はとっても有益な情報をくれた」
「その、有益な情報とは?」
僕はわざとらしく期待したふりをして、閑崎を急かす。
閑崎はわざとらしく一旦間をおいてから、山口君から貰ったという情報を口にした。
「爪剥ぎ事件の犯人は、尚崎君。だってさ」
次の日の放課後。今日も何事も無く授業が終わり、昨日と同じく生徒達は次々と教室から消えていく。部活に行く人、そのまま下校する人と目的は様々だが、普通教室だけが存在するこの校舎からは、放課後になると人気が一気に薄れる。
今日は閑崎はそのまま図書館へと行き、僕は特に早く帰宅する用事もないので、教室内の自分の席で読書をしていた。切りの良い所まで読み終わると、鞄を手にとって廊下へと出た。
廊下の窓から校庭を見下ろすと、陸上部の部員達が統制のとれた掛け声と共にグラウンドを走り回っている。
下駄箱へと向かう最中、階段の踊り場で話し声がする。なんとなく覗いてみると、三人の女生徒が一人の女生徒を囲んで責めているようだった。責めている女生徒の一人は、頭と右手に白い包帯を巻いている。特に会話の内容に興味は無いが、巻き込まれるのは御免なので、相手方からは見えない位置で廊下の壁に寄りかかり携帯電話を弄る。授業中は切っていた電源を入れると、一着だけ閑崎からメールが届いていた。
メールの内容を確認し終わると、丁度女生徒達の揉め事も終わったようだ。校舎内には静寂が戻っている。
僕は壁から背中を離し、階段を降りようと廊下を曲がる。目の前に女生徒が座り込んでいた。
先程まで三人の女生徒に囲まれ、なにやら責められていた女生徒である。目の前に僕が現れたことに気付いたのか、女生徒は俯いていた顔を上げて僕の顔を見た。クラスメイトである藍坂さんだった。僕は無視するわけにもいかず、適当に取り繕って声をかける。
「あ、えっと……。大丈夫? 立てる?」
なんとなく手を差し伸べてみたが、藍坂さんは自分だけで立ち上がった。
「ごめん。ありがとう」
藍坂さんは暗い性格の持ち主で、クラス内では山口君ほどではないが、周りに馴染めていないようで、いつも隅っこでひっそりとしている。彼女はそのまま振り返って足元に落ちていた鞄を手に取り、階段を降りていこうとする。その時に微かに右手の甲に痣が見えた。僕は呼び止めた。
「藍坂さん。ちょっと待って」
藍坂さんは階段を二三段だけ降りた位置で立ち止まり、不思議そうに振り返って僕を見る。
「ごめん。時間があったら少しだけ、話を聞かせてくれないかな」
「話。ですか」
「そう。さっきさ、君はなんであんなに責められていたのか」
「……」
言いたくないのだろう。だが予想は着く、藍坂さんを囲んでいた三人の内の一人、爪剥ぎ事件の三人目の犠牲者だ。おそらく、それ絡みのことだろう。
「実は、僕は訳あって爪剥ぎ事件を調べていてね。間接的とはいえ君もこの事件の被害者だと思って。藍坂さんの話を聞きたいんだ」
相手を見透かしたように説明する。藍坂さんは少しだけ迷ったような表情を見せたが、「わかりました。私としても、聞いてもらったほうが楽になるかも知れないし」と僕の要求に応じてくれた。
放課後の図書室には、生徒は僕達二人と眼鏡を掛けた図書委員が一人だけ。図書委員の生徒は本の貸出の受付に座っている。貸し出した本の期限チェックをしているらしい。
僕達二人は、規則正しく並べられた四つの長テーブルの一番奥に座っている。
話を聞いてみると、藍坂さんは爪剥ぎ事件の容疑者として疑われているらしい。いや、疑われている。というよりかは、一方的に、理不尽に決めつけられているだけのようだ。
彼女は学年で人気の男子生徒と親しい間柄ならしく、それを前からよく思っていない連中に目を付けられたそうだ。つまり嫉妬が原因の虐めだった。
爪剥ぎ事件が発生する前から、小さな嫌がらせはあったらしく、今回の事件はその仕返しではないだろうか。と思われるところもあるだろう。
二人目の犠牲者が出た時から、少しずつ責められはじめ、この間三人目の犠牲者が出たことによってさらに虐めはエスカレートしていった。と藍坂さんは時折目に浮かべた涙を見せながら教えてくれた。
「いっそ、私も爪を剥がれれば。そうすれば、疑われることも無くなるんじゃないか。なんて、最近はそう思い始めて……。だから、事件を調べている貴方にこの話をしたんです」
藍坂さんは涙を溜めた目で、右手の薬指を見つめる。見つめられた手は震えていた。
彼女の言葉の中からは僅かばかりの疑う生徒達への殺気と、自分への自虐が混じっている。だけど、自分で自分の爪を剥がすのは難しいだろう。出来たとしても、犯人との手口が違うことから、疑いは晴れにくい。むしろ疑いを避けるためにやったのではないかと、そう思われる可能性も少なくない。
「そっか。ありがとう。貴重なご意見、なんて言ったら失礼かもしれないけれど、間違いなく事件調査の手がかりになったよ」
「あ、はい。こちらこそありがとうございます。なんだか相談にのってもらっちゃったみたいで」
藍坂さんは自分が無意識に自分の薬指を見ていることに気付いていなかったらしく、はっとなって僕を見てお礼を言った。
「あ、それと。私からも聞きたい事が……」
そう言いかけた時、後ろから彼女を呼ぶ声が聞こえてきた。静かな図書室に響き渡る声は、男の声だ。
図書委員の生徒に注意を受けながら、男子生徒は藍坂さんに近付き、腕を持って立ち上がらせる。
「こんな所に居たのか。ほら、早く帰ろう」
おそらく、先程話に出ていた親しい男子生徒だろう。僕も何度か話に聞いたことがある。なんでも一年の時から陸上部のエースに輝いていて、勉強も出来る、いわゆる完璧超人という奴だ。無意識に頭に浮かんだ完璧超人という言葉から、ふと閑崎を思い出した。
「ごめんね。ちょっと待って。まだ聞きたいことがあって」
急かす男子生徒に腕を持たれながら、藍坂さんは僕の目を見て質問をした。
「貴方は、この事件の犯人を知っているんじゃないですか? これは私のただの感ですけど、そんな気がします。出来たら、教えてくれませんか?」
今朝に閑崎から聞いた情報を思い出す。
――爪剥ぎ事件の犯人は、尚崎君。だってさ。
少しだけ考えたフリをした後、男子生徒の顔を見る。どうやら僕らの話にはあまり興味が無いらしく、早く帰りたいといった表情をしている。
「いや、僕にもまだ犯人はわからない。そのために藍坂さんの話を聞きに来たんだから。でも」
先程の閑崎からのメールの内容を思い出しながら、一旦間を置いて、藍坂さんに情報を渡す。
「今日の夜、十一時頃。学校の近くに流れる川沿いの桜並木道。そこに行けば、何か分かるかも」
「え、それって……」
藍坂さんが何かを言おうと片足を一歩前に出した時、またもや図書室に響き渡る声。
「尚崎! ちょっといいか!?」
またもや図書委員の生徒に注意を受けながら、室内へと入ってくる男性教師が一人。
「やばっ。生活指導の丸山だ。俺今日部活サボってたんだった。早く行こう」
男子生徒は、藍坂さんの腕を強引に引っ張り、去っていった。
家に帰ると、母が居間でソファーに座り、テレビを見ていた。テーブルにはコーヒーが半分程入っているカップが置いてある。僕は自室へと行く途中に母に「ただいま」と自分の帰宅を告げる。
「あら、おかえり。微妙な時間に帰ってきたわね。どうしたの?」
「別に何でもないよ。帰る途中に書店に寄って来ただけだから」
無意識に、自然に口から嘘が出た。本当のことを言ったとしても問題はないけれど、僕はこうして無意識に、自分と社会とを平均化させるために嘘をつく。それが僕の癖であり、僕の生き方だった。
母は「そう、最近物騒らしいから。気をつけてね」と言ってテレビへと意識を戻した。どうやら爪剥ぎ事件の三人目の犠牲者が出たことは、既に母に伝わっているらしい。それ以上母からの言及がないことを確認し、僕は階段を上り自室へと向かった。
鞄を適当に置き、制服を着替える。今日の夜の、閑崎との約束の為だ。
着替え終わってベッドに座ると、自然に溜息が出た。
携帯電話を開き、閑崎からのメールを確認する。約束の時間は十時頃だ。それまでに空いている空白の時間は大きい。
ベッドに背中を預け、携帯を横に置いて、藍坂さんとの会話を思い出してベッドから徐に起き上がる。そのまま数歩だけ歩いて机の前の椅子へと座り、木製の机に備え付けられている幾つかの引き出しの、一番上の取っ手を掴んで引いた。引き出しの中からペンチを取り出して、冷たい感触を確かめる。
ペンチを眺めながら、閑崎のことを思った。もしもの事態はなるべく避けなければいけない。閑崎の為でもあるけれど、僕の為だ。
夜の十時前、すっかり辺りには暗闇が広がり、色彩を奪われた人気のない夜道を、一定間隔で小さく照らす街頭が道標のように見えた。
僕は白い息を吐きながら、爪剥ぎ事件の第一現場へと向かう。閑崎との約束の時間まではまだ十分程余っているが、早めに出向いても問題は無い。
夜の公園は相変わらず無人で、敷地内に一本だけ設置された街頭が、唯一水色のプラスチック製ベンチだけを弱々しくライトアップしている。僕は街頭から離れた位置にある、小さな滑り台に隠れるように背を預けて、携帯電話の時計を見る。時刻は夜の丁度十時。滑り台の端から顔を半分だけ出して、一人目の被害者が親指の爪を剥がされた辺りに視点を合わせ、目を凝らした。
約束の時間から数分ばかり経過した頃、駅方面の道から歩いてくる人影が見えた。閑崎だ。おそらく図書館からの帰りだろう。両手に息を吹きかけ、温めながらゆっくりと歩いてくる。閑崎の後方、十メートルばかり離れた辺りにもう一つ人影があった。黒いジャケットを着て、ニット帽を深く被っている。暗闇とニット帽で顔は見えないが、体格からして男。それも高校生くらいの若さの青年だろう。
閑崎と男の距離は少しずつ、しかし確実に狭まっていく。二人の距離が五メートル程まで狭まろうとした時、静寂を打ち破る轟音が響いた。電車だ。近くにある線路に電車が通る音だった。先程までゆっくりと歩いていた男は、電車の通過音を合図に一気に閑崎に近寄る。右手には、金槌を持っている。
「閑崎!」
僕は叫び、滑り台から離れて公園の外へと飛び出す。電車の音で僕の声は閑崎に届かないらしく、彼女は未だゆっくりと歩いている。既に男は閑崎の真後ろだ。男は金槌を振りあげ、閑崎の後頭部をめがけて振り下ろす。
電車は通り過ぎ、遠くから僅かに線路を走る音が聞こえる。
「あら、尚崎君。こんな夜に偶然だね」
閑崎は男の背後で右腕を掴み後ろに回し、男を身動きのとれない状態にしていた。男の足元に、先程まで右手に持っていたはずの金槌が転がっている。
「まさかとは思ったけれど、こんなに思い通りに行くなんて思ってなかったよ」
閑崎は複数の矛盾が重なったセリフを呟きながら、楽しそうに、ニヤニヤと口元を笑わせながら、掴んでいた男の右肩を外した。体内にある骨が外れる嫌な音が辺りに響いた。男は悲痛の表情に顔を歪ませ、うめき声をあげた。次に左腕を掴み上げ、同じように脱臼させる。またもやゴキンと鈍い音が響く。男の両腕は糸が切れたかのように、だらしなくぶらさがる。これで彼が閑崎に抵抗することは不可能になった。
閑崎は「さてと」と作業的な独り言を呟きながら、男を無造作にアスファルトの地面に倒した。コートのポケットからペンチを取り出す。
「おい、閑崎」
僕は閑崎に声を掛ける。いまならもう僕の声は閑崎に届いているはずだ。だが閑崎は僕を一目も見ずに、うめき声を上げている男の右手を掴んでペンチを近づける。
「待てって」
僕はペンチの先端を掴むようにして止めた。うめき声をあげてのた打ち回る男の頭から、ニット帽が外れる。
「邪魔しないでよ。尚崎君」
閑崎はニヤニヤと口元だけを笑わせながら、ペンチを掴んでいる手に力を込める。僕の掌の中で、ぶちりと肉が潰れる音が聞こえた。
「今ここで山口君の爪を剥いだら、誰が犯人になるんだよ。そもそも爪剥ぎ事件の犠牲者は全員女性だ。男の被害者が出たら、疑いがばらける可能性もある。危険だ」
僕はペンチを掴んだ手を離さずに、閑崎を説得する。掌から手首へと、赤い血が線を引いた。
閑崎は、激痛に涙を流しながら息を荒くしている山口君と、僕と、ペンチを順番に見てなにやら数秒だけ考え込んだ。
「なるほど。ごめん。あたしが悪かったよ。止めるよ。それでいい?」
意外にも閑崎は素直にペンチから手を離した。
「それでいいよ」
僕はほっとして溜息をつく。吐き出した白い息が風に吹かれて消えていく。立ち上がって閑崎にペンチを返す。
「それに閑崎、このペンチじゃあ、爪を剥がすのは一苦労だ。もっと小さいやつを使わないと」
「え、そうなの。爪なんて簡単に剥がせるもんだと思ってた」
閑崎はわざとらしく驚いたフリをして、またなにやら考え込んだ。うんうんと頷く度に、肩まで伸ばした黒髪が小さく揺れた。
しばらく考え込んだ後、閑崎はニヤニヤと口元だけを笑わせながら、僕の目を見た。
「じゃあさ、尚崎君にお願いをしよう。聞いてくれなきゃ、山口君の爪を両手両足全部剥いじゃうかも。ね」
閑崎は笑っている。目は笑っていない。
僕は真っ黒に塗りつぶされた夜空を見上げながら、深く溜息をついた。右手をポケットの中に入れて、ペンチの取っ手を掴んで感触を確かめる。
携帯電話の液晶画面に映る時刻を確認すると、そろそろ十一時になろうとしていた。
ホームルーム十分前の朝の教室は、独特な賑やかさによって今日も一日の始まりを知らせている。各々が数人ずつのグループを作り、様々な情報を話題として交換して盛り上がりをみせている。
僕は自分の席に座り、いつも通り読書をしていた。
しばらく本のページに視線を落としていたけれど、突然生徒達がざわついた為、頭をあげた。
教室の入口方向に視線を向けると、沢山の生徒達に囲まれている藍坂さんがいた。頭と右手の薬指に白い包帯を巻いている。彼女は生徒達に囲まれながらも僕の視線に気付いたのか、こちらを見て口元だけを僅かに笑わせた。目は笑っていなかった。
「これで四人目。でも、これで終わりだね」
隣の席の机に腰を下ろしていた閑崎が、クラスメイト達に囲まれて見えなくなっていく藍坂さんを見ながら、楽しそうに言った。彼女のその、少年のような顔の微妙な表情の変化に気づいているのは、僕だけだろう。
「そういえば。昨日、生活指導の丸山は何の用だったの?」
藍坂さんから視線を切り、閑崎は僕の方を見て言う。なんでこの人は、そんなマイナーな情報を持っているんだろう。彼女のクラス内での人気を利用した情報網は、使われていない旧校舎の一室で情報屋を営むことのできるレベルに達しているのかもしれない。
「別に面白いようなことじゃないよ。僕はほら、丸山の地理のテスト。赤点だったからさ」
「そっか。君、地図とかまったく読めなかったもんね。グーグルアースもビックリだよ」
閑崎は腰を下ろしていた机から、ぴょんと飛んでストンと着地し、僕に振り返ってから「じゃ、放課後ね」とだけ言い残して自分の席へと歩いていく。丁度、ホームルーム直前のチャイムが鳴った。
今日は、山口君は学校を休んでいた。
放課後。今日も全ての授業が終わり、終了のチャイムと共に生徒達は次々と消えていく。僕は自分の席に座り、読書をしながら閑崎を待った。
「ごめんごめん。お待たせ」
閑崎が現れたのは教室内に僕一人となってから数分後だった。今日も忘れ物をした、と同じ理由で戻ってきたらしい。どうやら閑崎はおっちょこちょいという設定らしい。
「待ってないよ。けど、こないだから貸してた本。もう読み終わってるんだろ? そろそろ返してくれ」
閑崎は読書スピードが早い。だけど同じ本を繰り返す読む癖があった。その為に読んだ本の内容は正確に覚えている。僕の貸した本は、既にもう読み尽くされているだろう。
「うん。持ってきたよ。その前に、ほら。早く」
急かしながら閑崎は僕の隣の机に座って手を差し伸べる。僕はポケットから消しゴム程の小さな透明のビニール袋を取り出して閑崎に渡した。中に藍坂さんの右手薬指の爪が入っている。
「やった。ありがとね」
閑崎は僕から藍坂さんの爪を受け取とると、大事そうに制服のポケットにしまいこむ。続けて手に持った鞄から一冊の本を取り出して、僕に渡した。本にブックカバーはされておらず、表紙にはゴシック体のフォントで「幼児連続バラバラ殺人事件」と書かれている。
「どうも。で、面白かった?」
僕は本を受け取りながら、なんとなく聞いてみる。答えには興味がない。
「うん。面白かったよ」
閑崎は笑った。目は笑っていない。
僕は閑崎のその表情が、好きだった。
爪を剥ぐ人
乙一さんのGOTHに触発されて書いたのが高校一年生の頃。今でも思い出に残る作品の一つです。
うまくトリックが機能してくれているのか不安なところがありますが、今になってもこの作品以上のミステリは僕には書こうとは思いません。