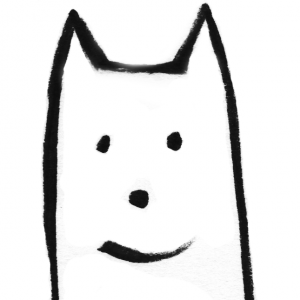Mouseion(ムセイオン)
初めまして、Hello1103(ハローイチイチゼロサン)と申します。
「物語の音楽」をコンセプトに制作活動している2人組です。
さて、このMouseion(ムセイオン)という小説はもともと同名の組曲に添えられた物語で、モデルは実在した古代アレクサンドリア図書館です。
語り手たるMouseionと、時を隔ててMouseionに永遠を求めた2人の男を通して、人の「知識の継承」「永遠」とは何かを問いかけます。
また先人の文化的な遺産が誰かの身勝手な理由で失われることに対する「怒り」も表現しています。
本作を読んで何か感じていただけると幸いです。
The Theme Of Mouseion
私は人に寄り添うもの。
人は長い時を生きることができない。それでいて、生命の長さに見合う分だけの幸福を謙虚に求めて天寿を全うする者はほとんどおらず、大半はやや手に余るほどの宝物をかき集めようとするが、求める物をすべて手に入れ、満足して生涯を閉じる者はさらに少ない。そして、生み出した業績、発明、信頼が大きいほど、彼らは肉体の死を恐れるようになる。
その瞬間は間もなく訪れる。ある者は死の床で未完の大作を思い涙を流した。ある者は戦場で最愛の妻と子を脳裏に浮かべながら大地に血液を染みこませた。その一滴一滴がすこしずつ結晶化して文字となり、丁寧に折りたたまれて本に納められ、私に保存されてゆく。本の中に安置された結晶に触れることで、後の人々はもはや形を留めていない過去の人物を想い起こすことができるのだ。
私に問いかけることは、あらゆる時間を超えること。
あらゆる場所を超えること。ヒトの過去に問いかけること。
原初の人が生まれたころ、そこに文字はなかった。知識は口伝の形をとり、急流の飛び石を渡る兎のように人の容れ物を渡ってきた。足を踏み外して溺れた兎もあれば、割れた石とともに沈んだものもあった。
やがて人の間に文字が生まれた。
新しい容れ物を手に入れた知識は少しずつ凝集し、形を成してゆく。
とある少年は、親の手から渡された本を通して遠い時代の出来事を知った。青年期となると、闘いに勝利し生き抜くための鍵を求めて再び本を開く。やがて年老いた頃、自身の存在が間もなく消えることを予感し、経験則を文字に変えて書架に納めた。
樹は新しい枝葉をつけ、さらに生い茂る。
ある時代には偉大な王がいた。世界の3分の2を手中に収め、その威光は地の果てにまで届いた。王都の中心には巨大な図書館が造られ、国内で刊行されたあらゆる書物が集められただけでなく隣国からも発行物が寄進され、比類無き蔵書数を誇ることとなる。
そうして、私の中にはすべての時代の、すべての場所の人の知識が容れられた。
情報と情報が接続され、個人がその生のうちに持ちうる知識の総量をはるかに越えた情報の集積体が組み上がるうち、やがて、集合体は人に似たひとつの意志を持つようになった。
私の蔵書は増えてゆく。
今は亡き人のこころも文字となり、その上に、しんしんと、新しい人のこころが積もる。
私は人に寄り添うもの。
(Mouseion) は、数十年の生しか許されぬ人間たちの知識を鎖のように繋ぎ、あるいは屍と未だ存在すらしないものを知識の鎖で繋ぎ、未来へと広がっていくのだ。決して切れてはならない意味の架け橋。
しかし、私は予期する。
私が人の似姿であるゆえ、私にも死が訪れることを。
全てを包むほどの炎によって人類が私を失うだろうことを。
人は知らぬ。短き生ゆえに知らぬ。
私を失ってはならないことを知らぬ。
幾星霜の昔から続く言葉の灯火が、種の歴史そのものなどとは。
飽くことなく繰り返される過ちを止める言葉が私に納められているとも、
種の限界を乗り越える智慧がそこから出でる可能性にも至らぬ。
知る前に年老いて、死に行くのだから。
あるいは。私がいなくとももはや必要な言葉が充分に人の間に満ちたのであれば。もしくは自分たちの過去を捨てることで新しい世界を切り開くのであれば。私は人の手を離れ、残らず灰となっても構わぬ。
巡路
今は昔、人の中にいくつもの国が生まれ、いくつかの国と歴史が消え去った 頃の物語。
西方に巨大な帝国があった。勇敢な王の下に遠征を繰り返し、11の国を滅ぼし、世界の3分の2を掌中に入れ、あらゆる芸術品を帝都に集めたとされる。都は栄華を誇り、「闇を払う都市」「太陽の都」と称された。中央広場から一直線に延びる大通りに沿って劇場や博物館、図書館が造られ、民衆は山海の珍味と帝国市民としての誇りを肴に美酒に酔い、毎夜観劇に興じたという。
そんな喧噪の中心地からはるか東方、帝国編纂の世界地図においては『人の住まう事なき辺境』の一行で処理され、支配も遠く及ばない大山脈。それを越え、さらに峠をふたつ越えた先の盆地に村があった。周囲の山々と深い森は戦火から集落を隠す壁となり、また、豊かな水と果実を湛え、そこに住む人々を常に潤した。
住人は穏やかで賢く、村の豊穣と照らし合わせるように多くの知識を蓄えていた。発達した灌漑施設のおかげで作物はすくすくと育ち、誰も飢えを知らなかったし、布に卵白を重ねて塗ることで雨傘を作ったり、複数の木を組み合わせて横笛や太鼓などを作り出す工芸の技術も有していた。
ところで、その国には文字がなかった。
一つも、ただの一つも文字がなかった。
言葉は音としてそこにあるだけだった。どんな出来事も、どんな戒めも、ひとつの物語として歌に乗せて伝えられ、形をとどめることなく霧のように消えていく音楽を注意深くとらえ、心に保存し、よく知り、よく考えた。だから、子供たちも、そのまた子供たちも、先人に劣らず賢かった。
ただ、文字が生まれることはなかった。
文字というものの存在すら知らない村人たちは、しかし不便に思うことなど 無かった。重い荷物を台にのせて皆で担ぐように、有するすべての知識をすべての人間で共有する。物も、人も、安定してひとつの形をとることなど滅多に無いのだから、台には同じく流転の性質を持つ歌を用いる。彼らにとってはそれは求められた最適解ですらなくて、単純に、ただひたすらに繰り返 されてきた行為だった。
文字を知らない村人たちは、不安に思うことなど無かった。
ある一人の男を除いては。
男は村はずれの広い草原と、そこに差し込む朝日がとても好きだった。東の山を眺めると、つい先程まで闇に紛れていた稜線から、直視できないほどに 煌びやかな光が漏れ出す。まばたきを三つ数える間に、山も、それを隠す霧も、燃え立つような紅色に染まった。
彼を呼ぶ声。振り返ると、朝日を受けて金色に輝く麦畑が眼に飛び込んできた。その中に立つ黒髪の少女。彼と同じ年に生まれ、多くの時を共に過ごし、お互いが村の立派な一員となった今でも彼を最も良く知る人だった。黄金の景色の中でひときわ目立つ黒く大きな瞳で真っ直ぐに彼を捕らえると、少し厚めの唇をわずかに歪ませ、微笑んだ。 小さめの歩幅でゆっくりと麦畑をかき分け、男の左脇にまでやってくると、山々を見上げて目を細めた。頂上から吹き下ろす風は彼女の長い髪を揺らし、また麦の穂を揺らしながら背後へと抜けていく。しばらくの後、男の顔を見上げる。わずかに唇が動いたけれど、言葉を紡ぐことはなく、そのまま前に向き直ると、男の肩にそっと寄りかかった。
ああ、おれの知るこの世界はあまりに美しい。昇りゆく太陽も、染め上げられる山々も、自分の愛する人も、その思いも。このうちのどれかひとつでも、枯れて死に至る瞬間を想像するだけでおれの心は凍りつかんばかりだ。この光景を消えゆくままにすることなど許されない。
どうか、この世界を、永遠に固定したい。
しかしこの身はいつか年老い、背負った記憶とともに土くれとなる。子供たちに物語を歌い聞かせたとして、代を重ねるたびに美しさは褪せていってしまうだろう。 いや、もしもこの村そのものが災厄に飲み込まれて失せてしまったら、誰が物語を継いでくれるというのか。誰がこの世界を遺すというのか。
男はその日から歌に頼らない伝承を求め歩いた。あらゆる知恵を持つはずの古老たちに訊いても、彼の記憶を、彼の納得する形で固定する方法は見つからなかった。彼は深く落胆したが、しかし諦めきれるものではない。村の外には広大な世界があり、村の人間とは姿形の全く異なる数多の人とその集落がある。伝え聞くところによれば西の果てには巨大な帝国が存在する。太陽の動きすらも制御する技術を持ち、その地では永遠に昼が続くのだという。そこにはきっと理想の方法があるに違いない。
七の夜を数える間、男は悩み続けた。村を発つことは、自らがこの上なく愛するこの世界と一時でも別れることを意味する。村内に外の世界を直接見聞きした者はひとりもおらず、また、自分の生まれる前に数人が村を出たというが、今に至るまで故郷に帰ってきてはいない。一時といいつつ、今生の別れとなるかもしれない。
...重く考えなくとも手がかりくらいはすぐに掴めるだろうし、老いぼれるまでには充分に戻ってこれるだろう。そう考えるたびに、なにか暗い塊がひとつづつ胸に詰まっていくような気がした。
さらに七つの夜を越え、八つ目の朝を迎えたとき、 幾度となく眺めた麦畑を朝日が徐々に染めゆく中、男は決意した。陽が昇りきらぬうちに家族に別れを告げると、その足で愛する少女の家へと向かった。
見送りの間、ふたりはひとつの言葉も交わさなかった。
やがて村のはずれの麦畑まで来ると、男は少女の手を取ると、必ず答えを掴み、この地に戻ると約束した。少女はいつものように真っ直ぐに彼を見つめ、微笑みながらいつまでも待っている、と伝えた。
そして手を離すと、彼とその長い影が草原の果てに消え去るまで、微笑みを崩さず、下げた両手を硬く組んでその姿を見送った。
(冒頭にはこれ以上のことは書かれていない 。)
雪原を越える
ここには何も存在しない。
宿の主と暖炉を囲む。西に10日ほど進んだ先の都市を目指す、と話すと、主は、西の一帯はこの国と『太陽の帝国』との戦線になっていて雲霞のように矢が飛び交っている、死にに行くのでなければ引き返した方がよい、と言った。そこで迂回路を尋ねたところ、返答は、北に見える山を越えるしかないが、あれは人の立ち入る所ではないから止めた方が良い、広大なうえに年を通して雪が溶けることがなく、とても抜けることはできないだろう、という冷たいものだった。痩せた頬と眼窩の皺が特徴的な主は、男の若気をなんとか諫めようとしたが、何度危険を伝えてもその意志が変わらないのがわかると、男を哀れむような、それでいて厄介事を遠ざけるような視線を注ぎながら別れの言葉を吐いた。
翌朝早くに男は出立した。主からは川沿いを進んで山頂の右側を抜けるのが良いと教えられたが、麓から見上げる限りでは山頂は見えず、ここからどれほどの距離があるのか測りかねた。餞別にと渡された木綿の肩掛けを羽織り、足を踏み出す。周囲の空気がひんやりと重くなったように感じた。
剥き出しの岩が転がる川岸は歩きづらいが見通しは良かった。黙々と、ただ歩き続ける。川が途切れ、山頂を望む頃には陽が落ち始めていた。見知らぬ場所で無理はできない。天幕を張り、夜を明かした。
寒さと薄明かりで目を覚ます。
外に出ると、見慣れないものがあたりにちらついているのを目にした。空から降る綿のような粒。これが雪というものか。自分が育った山とはずいぶんと違うものだ。
山頂が近づくにつれ風がいちだんと鋭くなった。
体温を剥ぎ取っていくような寒さに震えつつ、残りの距離を一歩一歩縮めていく。ふとあたりを見回すと、先程から降り続く雪が岩肌に積もり、周囲から色彩が消え失せていた。低木すら見当たらない厳しい地形だ。若く健康な者でなければ確かに行き倒れてしまうかもしれない。
そして、ついに稜線を越えた。
瞬間、大きく広がる光景に、男は膝を折り、絶望した。
思えば、故郷の山はどの季節も色彩に満ちていた。
深緑の碧も、暁の朱も、蒼天も、みな美しかった。
ここにはどれも存在しない。
人間の眼は動いている物に注目する。さらさらと囁く枝葉を渡る栗鼠に、木漏れ日から覗く空。つい、と横切る雲雀。木陰に腰を下ろしてそれらを眺めるのがとても好きだった。ここにはどれも存在しない。
否、何も無い場所などあるはずがない。この地には自分が認識できる物がひとつとして無いだけだ。足下から天空までが無色の材質に埋まっている。視界の先、ひたすらに地平線まで雪原が広がっていた。
遠近感が失われ、この先の人里までどれほどあるのか見当もつけられない。疲労と寒さでしわがれた脚で来た道を戻るか、このまま突き進むか、足下の雪を見つめる男の脳裏に浮かんだのは宿の主の言葉だった。麓へ戻ったとしても先へ通じる道は無いのだ。男はうなだれたままゆっくりと立ち上がり、肩掛けを正すと北に向かって尾根を一歩降りた。
慣れない雪山に何度か足をとられながら斜面を下りきり、平原に差し掛かるとさらに雪が強くなった。ごっ、ごっ、と耳元で鳴る風雪に耐えながら歩みを進める。交互に前に出るつま先を四十歩くらいまで数えていたが、やがてわからなくなってしまった。進退を迷った尾根は中間地点ですらなかったのかもしれない。
もう随分歩いたように感じる。
今、足を止めたらおそらく二度と前に踏み出せないだろう。
ほぼ本能のようなもので歩いていた。
機械的に動かしている脚がずっと視界に入っている。
気がつくと右の腿が大きく割け、切れ目から白い液体が流れ出していた。白い血というのは見たことがないが、極寒で血まで凍ってしまったのだろうか。中指で液体を掬って舐めると、やわらかく甘い味が広がる。故郷の空に浮かぶ丸い雲はきっとこんな味だろう。それは確かに自分の血だった。
右肩からは淡い緑色の液体が滲んでいた。数滴を掬い取り、口に運ぶ。この味は知っている。家の東に生えていた桃の葉の味だ。果実があんなに甘いのだから葉もそれなりに食べられるだろうと試してみたが、全く期待したような味ではなかった。
左胸から滴る薄茶色の液体を口に含む。
この味を忘れたことは片時としてない。
故郷で豊かに育つ小麦の味。
あの麦畑で固く結んだ約束。
おれは誓いを遂げねばならない。
うなだれていた頭を上げ、風の暴力に対抗するように強く息を吐いた。
この土地を越えるのだ。その先に必ず答えがある。
まだ見えない雪原の果てを求め、再び歩み始めた。
知識の大樹 - 古代図書館
帝都内政官の手記より抜粋
帝国歴243年 第7番目の月 20番目の太陽が昇った日
東夷の地より一人の男来たる
藍毛黒眼、深い青色の衣をまとう
誰とも異なる言葉を解し
誰も耳慣れぬ旋律を紡ぐ
夜に中央広場で聴いた歌である。珍しい風体をした男。一部で話題になっている。聞くところによると、その者が干魃に苦しむ町に赴き杖で地を突いた。現地の若者がそこを掘ると、たちまち水が噴き出し川となったという。男には水を操る龍が見えるのだそうだ。
帝国歴243年 第9番目の月 9番目の太陽が昇った日
医師の努力虚しく王の病状は悪化の一途をたどり、今月に入ってからは一度も朝議に顔を出されない。王は齢23、死に連れ去られるにはあまりに早い。内政官の一人が東夷の男の召喚を提案するが、反対も多く保留となった。
帝国歴243年 第9番目の月 18 番目の太陽が昇った日
帝都一の医師も王の病巣を見つけられぬ。万策尽き、東夷の男の召喚が決定された。
帝国歴243年 第11番目の月 8 番目の太陽が昇った日
王の病状は徐々に快方に向かっている。内政官の中にも東夷の男を良く思わない者がおり、怪しげな呪術で病を隠しているだけではないかと警戒しているようだが、私が見る限りではそのような様子は無い。
帝国歴245年 第1番目の月 3番目の太陽が昇った日
王が男に再び謁見を許す。治療に成功したかどの報償を王より直接尋ねられると、男は自分の知る世界を永遠に残す法を求めた。神の子でも、まして王族ですらない者が永遠に触れようなどという不遜な考えに不快感を露わにする者もあったが、王は寛大に対処し、私に男を王立図書館へ案内するよう命じた。なぜ私が。翌日に赴く旨伝えると、男は今すぐ行きたいと駄々をこねた。まずは帝都に住む者としての礼儀から教えねばなるまい。
帝国歴245年 第1番目の月 4番目の太陽が昇った日
激務の隙間を縫って男を王立図書館へ連れて行く。神聖な場所に入る前であるから風呂へ寄ったが、八方から好奇の目に晒され非常に恥ずかしい思いをした。道すがら図書館の説明をする。帝都の全知識がその建造物に収まっている、と説明すると彼はにわかに興奮しだした。図書館に入り、実際に蔵書を目にしても、どのようにして記録が行われているか理解できない様子だった。驚いたことに男の出身地には文字が存在しないという。書記官を呼び、文字とは何であるかの説明と、専属の書記をつけ、男の持つ全知識を書物として図書館に納めたい旨を伝えると、男はたちまち涙を溢れさせ、膝から崩れ落ちた。「これこそが、自分が求め続けたものだ」と。夜になっても一向に帰ろうとしないので、館内の一室に男を住まわせること となった。
帝国歴245年 第1番目の月 12番目の太陽が昇った日
男は故郷で語り継がれていたありとあらゆる物語を語り始めた。星読み。気象。工業。医学。薬学。音楽。測量。恋愛。民話。専属の書記官だけでは間に合わず、図書館に勤める全書記官が交代で彼のもとに訪れ、その口から歌うように紡がれる言葉を一字漏らさず文字に変換ていく。夜を徹して記録が続いている。男の健康状態が危惧される。
帝国歴245年 第11番目の月 1番目の太陽が昇った日
ひとつ、またひとつと男の歌う物語が図書館に納められていく。東夷の異質な知識体系はいまや帝国中の学者・知識人の関心事である。皆がこぞって彼の知識を求め、図書館はかつてない活況を呈している。しかし当の本人は図書館の奥に篭もり、書記官以外の誰とも会おうとしない。私すら入室を拒否されることに対しては、感謝の心の欠如と捉えざるを得ないだろう。
帝国歴247年 第16番目の月 6番目の太陽が昇った日
男が目に見えてやつれていっている。休息を勧めたが、相変わらず何かに取り憑かれたように歌い続けている。東夷の物語は既に200巻を超えた。その多くは帝国にとって非常に有用であると思われる。
帝国歴248年 第3番目の月 20番目の太陽が昇った日
男は冬枯れを知らない桃源郷と、そこに住む美しい女性の物語を歌い終えると、静かに永遠の眠りについた。全く安らかな笑顔であった。
偽書と戦火
この街が「太陽の都」と呼ばれなくなって久しい。
かつて広大な領土を支配し、街とともに私を産み出した帝国はとある世代に生まれた愚かな君主によって道を踏み外し、支配下にあった無数の国家の反乱によって滅亡した。次にこの地に興った国は実に穏やかであった。領土を拡げず、協調外交を掲げ、また歴史を重んじ、人々がこの街の名としてありし国のものを、つまり「ソルトスレイニア」を与えることを許した。一連の政策が功を奏して 200年ほど生き長らえたが、一人の国王側近の讒言によって衰退し、野心旺盛な隣国に滅ぼされた。
周囲に渦巻く無数の戦火から数百年の長きにわたり私を守ったもの。それは、智慧という形無きものに対して世界中の人々が背負い続けた畏敬の思いであった。
私を構成する一字一句、細胞のひとつひとつが過去を生きた人間の写し絵であること。私を失えばその細胞もまた死滅し、けして復活することは無いということ。人間がそれを知る限り、また祖先を愛する限り私は存在する。
ところで、200年程前から若干他とは色味の異なる人間が現れだした。古い知識を癌とみなし、自らとその子孫が生み出す新たな平和で世界を覆い尽くそうとする者達。彼らは同じ神を信じ、希望と正義感に満ち溢れ、敵を打ち払い領土を拡げてきた。私の周囲を見るに、彼らの願いは成就されつつあるようだ。「陽の沈まない国」と喩えられた帝国ソルトスレイニア。そこから数えて5つ目の国が誕生して7年、この街は再び争いに揺れている。
-
その日、若き図書館守はソルトスレイニアに新たに赴任する将軍を迎えた。
この1年で街の状況は大きく変化した。数年前に北方で興ったばかりの新しい国が急速に領土を拡げ、内乱が続いていた周辺地域を呑み込み、ソルトスレイニアを支配することとなったのだ。既存の為政者は排除され、街は直轄領となった。
この国は「過教」と呼ばれる宗教を国教に据えていた。生まれてから200年程度の比較的新しい宗教で、源泉には慈しみと気品を湛えているが、分派には苛烈なものも見られた。
街の新たな為政者となるロタ・エルモ将軍は敬虔かつ急進的な過教徒として知られる人物で、神の名の下に異教徒や無神論者を容赦なく弾圧したため、 自然科学をはじめあらゆる部門の学者から非常に恐れられ、また激しく忌み嫌われた男である。彼にとっては国際的学術都市ソルトスレイニアも異端者の溢れ返る汚濁であったし、その中心に座する図書館はまさに腐敗の巣窟であった。
その男が図書館の視察を求めた。間もなく悪名高きロタ・エルモ将軍が自分たちの前に姿を現すとあって、館の正面入口前に集まった関係者はみな一様に重苦しい表情をしていた。
目の前に馬車が停まった。中からまず現れたのは護衛兵。見慣れない意匠を散りばめた鎧を着込んでいる。次に丸く大きな目をした若い男。線が細く、帯剣はしていない。そして深紅の軍服をまとった眼光鋭い大柄の男。背丈も胸囲も図書館守の二倍はありそうな体を窮屈そうに馬車の外に出し、一歩、一歩と距離を縮める。逆光に阻まれ、相貌がよく確認できない。将軍と思わしき男は館長らの最敬礼を見慣れない礼で返し、歓迎の口上を遮ると、案内を促した。
館内を視察する間ずっと、将軍の表情は厳しかった。国際的にも評価の高い学者が終始将軍の脇につき、至る所で説明を加えたが、原型をとどめないほど平易に噛み砕かれた言葉でさえ彼の心には届かないようだった。
過去が幾層にも積み重なる館内で、エルモは明らかに異質であった。自らの信じる未来だけを見据える彼は、図書館を構成するどの人間とも、所蔵されているどの本とも同じ時間を生きていない。まるで彼の周囲に時間の断層ができているようでもあった。
一通りの視察を終えたところで、側近らしき男が将軍に耳打ちをする。
それを聞き終えるや否や間髪を入れずに将軍が発した言葉、
「地下室を拝見したい」
それを聞いて館長は顔色を失った。
なんとか話を逸らそうとさまざまに方便を立てたが、自身の言が将軍に対し てわずかの影響力も持ち合わせていないことを悟ると、重い足取りで地下室へと続く扉の鍵を開けた。
図書館には確かに地下室が存在した。 しかし、収蔵品のほとんどが現在では入手困難な貴重品であることからその 存在が秘匿されているうえ、部外者の立ち入りが厳しく制限される領域である。中には世界中でここにしか存在を確認されていないような本も納められており、図書館をはじめとするソルトスレイニアの博物館群が時代と国境を越えて保護されてきた理由の中核となる場所がまさにこの地下室である。
燭台に火を灯しながら仄暗い通路を進む。 将軍が棚の前で立ち止まり、説明を求める度に、図書館守は燭台の赤い炎に照らされる将軍の表情が醜く歪むのを見ることとなる。
ひときわ将軍の不興を買った書架があった。
およそ500年ほど前に編纂され、はるか東方のあらゆる風物を書きとどめた800巻余りの記録。その中には異国の神々が描かれた巻物もあり、子供が好むおとぎばなしとして一般的に知られていた。
数ある東方のおとぎばなしに触れ親しむ家庭は多いが、それらに唯一の原典が存在することにまで思い至る者は少ない。
さらに、その世界に強く恋焦がれ、図書館に人生を捧げてでも原典に触れようとする人間は極めて稀である。
将軍が醜悪な視線を投じた黒い巻物。それは、図書館守が最も愛した物語だった。
-
視察を終えた地下室は再び静まりかえり、燭台の蝋芯が焦げる音だけが図書館守の耳に響いた。木製の椅子をきしませ、ひとり呟く。
エルモのあの横顔。貴い本たちに無遠慮に浴びせられる汚い視線。
館を出る間際、側近に何か耳打ちしていたな。どんな言葉を吐いていた。「異端の書をすべて炎に沈め、不道徳者たちが去った後に新たな信仰の街を造るのはどうか。」などと言っていたのではないか。あの男は図書館に納められた豊かな果実を恣意のままに毟り取るだろう。過教に都合の良い情報ばかりを残し、価値が理解できぬものはすべて握り潰すだろう。
それだけではない。自分の気に入らない書物を、歪んだ美意識のもとに改竄することすらありうる。
あの美しい物語も。
東方の大地に昇りゆく太陽、染め上げられる山々。吹き下ろす風に揺れ、柔らかくささやく麦畑。長い黒髪のたなびく美しい少女。その思いも。
どれかひとつでも、醜く歪められた形で後世に伝えられることなど許されない。
どうか、この世界を、永遠に固定したい。
-
その日、ソルトスレイニアの中央広場で大規模な火災が発生した。図書館から起こった火の手は乾燥した空気を伝って急速に燃え広がり、街のおよそ半分を炎に沈めた。市民はソルトスレイニアの歴史と名誉を象徴する (Mouseion) が灰と化してゆくのを目にし、ある者は膝を折って失意に震え、またある者は泣き叫びながら火に飛び込んだという。
ソルトスレイニア市民にとって、あるいは後世の人類にとって、この火災において不幸なことが3つあった。
火事の発生が皆寝静まる真夜中だったこと、乾期の只中で空気が乾燥しているうえ中央広場から市街地に向かって強い風が吹いていたこと、エルモをはじめとする過教徒が消火活動に非協力的で、荒れ狂う炎が過教徒の施設に迫るまで動こうとせず、また残る市民だけでは市街地を守ることで精一杯だったこと。
太陽暦899年のこの事件は、後世の人間には「急進的な過教徒であったロタ・エルモ将軍が異教徒の施設を焼き討ちした事件」と伝えられており、現代の慣用句として残る「エルモの所業(またはエルモの過ち。勝手な行いで子孫や後任者に迷惑をかけること)」はこの一件を語源とする。
事実、(Mouseion) の消失によって膨大な量の知識が人の間から失われ、結果として人類の歴史は100年後退したと言われる。
灰の歌
生、また死の神はあまねく人に手を差しのべる
人の似姿も等しくその時を迎え
私は世界から永遠に失われた
私の中に休息を得たいくつもの物語もまた
無数の灰となって風に散った
物語を識る人よ、どうか悲しんでほしい
今日このときに消えた命のうち、
あなたが憶えている数だけ涙を流してほしい
やがてあなたが顔を上げるとき、その眼に飛び込むもの
大地に落ちた実が根を張りそこかしこに芽吹く姿
大樹の陰が消えた場所にも、また陽が差して木が育ち
いずれ多くの人を憩わせるだろう
そのころにはあなたの雨がやめば嬉しく思う
ああ、すべての人間を憶えている
この体のあらゆる要素、枝葉のひとつひとつ
はるか昔に永遠を求めて砂漠を渡り、
雪原を越えて私に出会った男のことも
今でも耳をすませば遙か東方から
いつか聴いたあの歌が聞こえてくる
灰は空に舞い上がり、風に乗って世界を巡った
どうかすべての物語が、それを求めるこどもたちに届くように
どうかすべての物語が、それが望むとおりに
人の間で語り継がれてゆくように
灰はやがて土となる
Mouseion(ムセイオン)
ありがとうございました。
もし楽曲にも興味をお持ちいただけたら特設サイトにお越しください。
http://hello1103.com/mouseion/