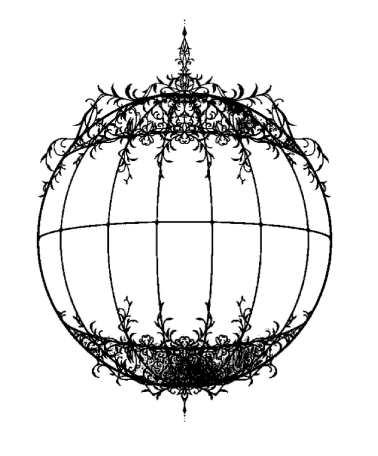
言ノ花庭園
花言葉で会話をする少女と、少女を愛した青年と、2人を見守る男の話。
画像は黒猫さんが描いてくださったものをこちらで白黒に加工させていただきました。
プロローグ
人魚姫は深い深い海の底へと向かいました。
そこに棲む魔女に、願いを叶えてもらうため。
彼女は、魔女と約束し
“声”と引き換えに、大切な人のもとへゆくことを、赦されたのでした。
始まり
真昼の日差しが、大きなテラス戸から差し込む。
十八畳はあるだろう広い部屋の壁は太陽の光を反射させるほど白く、床は白と黒のタイルを交互に組んだパレスになっている。
部屋の隅にはダブルサイズのベッド、その横には壁面本棚、テラス戸の隣には本棚と同じ大きさのクローゼットがスペースを取っていた。
部屋の真ん中にはガラス張りのローテーブルが置かれ、この白い部屋を眩しく映し出している。
整然とまとめられ、生活感のない様子とは打って変わり、ちょうどテラス戸からの光が入り込まない部屋のもう半分のスペースには、
床を覆い隠す黒いシートが敷かれ、その上には絵を描くための画材が乱雑に置かれていた。
大小長短、細いものから太いものまで何十本という筆が種類ごとに筆立てに詰め入れられている。
新品なものなど一本もなく、すべてが使い込まれたように汚れ、しかし、そのすべてが大事に手入れされていた。
いくつかのバケツが重ねて置かれ、様々な絵具が色ごとに、用途ごとに箱に入れられている。
汚れ、折れ、いくつもの紙が挟まっているスケッチブックも何十冊と積まれて壁に寄せられ、
その近くには大小様々なキャンバスが、何十枚も重なり合って壁に立てかけられていた。
ペンキや絵の具が飛び散った跡があるイーゼルの上には、まだ何ものにも染まっていない白いキャンバスが一枚置かれている。
どうやら、この部屋は寝室兼アトリエらしい。
テラス戸を出ると、そこは中庭だ。
芝生は綺麗に手入れされ、庭の中央には三人用のシックなガーデンテーブルとガーデンチェアが設置され、
その空間だけ隔絶したように周りを灌木と雑木が取り囲んでいる。
日が当たれば緑が艶を帯び、家の庭とは思えないほど幻想的な景色を作り出していた。
そんな庭の芝生の上で、一人の整った顔立ちの青年が、花のような愛らしさを持つ小さな少女を膝に跨らせて座っていた。
少女と向き合い、ベージュ色の、空気を含んだように柔らかい長髪を撫でる。
少女は首を傾げ、桃色の目は表情もなく青年を見つめていた。
それから、その小さな手に握られているニゲラの花を見せ、今度は反対側に首を傾げる。
青年はその様子に思わず笑うと、髪を撫でるのをやめ、今度は少女の頬を撫で始めた。
「何でもないよ。ただ、花乃は変わらず愛らしいなって」
頬を撫でられ、くすぐったそうに片目を瞑った花乃は未だに不思議なものを見るような目をしながらニゲラの花を握り続け、首を傾げる。
ニゲラの花言葉は当惑。どうやら、花乃はニゲラの花を見せながら首を傾げることで「どうしたの?」と伝えていたらしい。
青年は耐え切れなくなったように花乃を強く抱きしめ、頭に顔を埋める。
「可愛いよ、ひな……可愛い……」
花乃は少し苦しそうに青年の胸を押すが、青年は構わず花乃を抱きしめ続け、においを嗅ぐように息を吸う。
「良い香い……日向と花とひなの香い……」
「傍から見ると変態よ、泉光」
女性のような口調にも関わらず、声は低い男性のもの。泉光と呼ばれた青年は横目で声がしたほうを見る。
そこにいたのは、長身の男性。健康的な肌に、紫色のメッシュが入った黒髪は生まれつきのパーマのようで自然なうねりを作っていた。
「あとひなちゃんが苦しそう。離してあげなさい?」
「……何しに来たの、樹季さん」
「何しにって失礼ね。あなたたちのお昼作って持ってきてやったんじゃない」
樹季と呼ばれたその男は両手に持っていた皿を見せる。載っているのはツナマヨとたまごのサンドウィッチだ。
泉光はそれを一瞥したあと、すぐにまた花乃のにおいを嗅ぐことに戻る。
「ひな、可愛い……」
その様子に樹季は呆れたようなため息を吐き、サンドウィッチの載った二枚の皿をガーデンテーブルの上に置く。
それから困ったように腰に手を当てた。
「いつまでやってるの? せっかく作ったんだから、早くお昼食べちゃいなさいよ」
「お昼についてはありがとう。でも、見てわかる通り僕は今忙しいからね」
「どこが忙しいのよ、全く……。ひなちゃんはお腹すいたわよねー」
話の通じない泉光に好きにさせていた花乃は樹季に目を向ける。
樹季に対して腕を伸ばそうとした瞬間、泉光に抱きすくめられた。
「花乃も僕と過ごすのに忙しいから」
笑顔で言い切られ、花乃はまた困惑した表情を浮かべた。動くこともできずにじっとしていたその時。
ぐぅー
お腹の音が鳴った。泉光の抱きしめる力が弱まり、花乃は恥ずかしそうにお腹を押さえる。
「あら、ひなちゃん、やっぱりお腹すいていたのね」
樹季に笑顔で言われれば、花乃はオイランソウの花を見せて頷く。
花言葉はいくつかあるが、その中にはあなたに同意するという言葉がある。
「ほら見なさい。あなたに抱きしめられて動けなかったから、言い出せなかったんじゃない」
「お腹すいたね、ひな。食べようか」
泉光は樹季の言葉を無視して何事もなかったかのように花乃に言えば、花乃は目を輝かせ、大きく頷く。
二人はガーデンチェアに座ると、手を合わせる。
「いただきます」
花乃もお辞儀すると、樹季を見上げた。
泉光の変わりように呆れていたが、花乃の視線に気が付くと優しい笑みを浮かべる。
「どうぞ。いっぱい食べてね」
満面の笑みで頷いた花乃は早速、たまごがたっぷり挟まったサンドウィッチを手に取ると、小さな口で頬張る。
細かくされたゆで卵が負けないように、かといって減らしているわけでもないちょうどよいバランスのマヨネーズ加減と、
パンのしっとりした食感と甘みが口で混ざり合い、花乃は満足そうな顔をしてじっくりと味わっている。
「ひなちゃんに気に入ってもらえてよかったわ。泉光の分はマヨネーズ少し多めにしてあるから……って」
泉光は未だに自分の分には手を付けておらず、じっと花乃が食べる様子を、口元を緩ませて見守っていた。
樹季はそんな泉光を冷めた目で見る。
「さっさと食べてもらえるとありがたいんだけど?」
「それではひなの食べている様子が見れないだろう?」
「見てないで食えって言ってんのよ」
言われても泉光は花乃を見つめ続ける。
さすがに視線に気が付いた花乃は泉光の方を見ると、食べかけていたそのサンドウィッチを泉光に差し出し、首を傾げた。
「食べる?」と聞いていると分かった途端に、泉光は目を見開き、次の瞬間には顔を覆った。
「ひなの……食べかけ……僕に……」
よく聞いてみると涙声で、どうやら感極まって泣いているらしいと分かった。樹季は諦めたように笑う。
「もういいわよ。ひなちゃん、そこのバカ放っておいて、あとで一緒に買い物にでも行きましょう?」
泉光が泣き出したことに慌てふためいていた花乃だが、樹季に言われるとまた目を輝かせ、何度も頷いた。
しかし、それに泉光も反応し、ようやく顔を上げると樹季を睨むように見た。
「僕から花乃を引き離してどうする気なの?」
「泣き止むの相変わらず早いわね。あんたがいつまで経っても食べ終わらないのが悪いのよ」
「外の世界は危険が多すぎる。ひなに何かあったらどうする気?」
「家の中でも常に泉光っていう危険に晒されてるんだから、変わりないわ」
「僕はひなを愛しているだけだよ。とにかく、僕の目の届かないところへ連れ出すなんて許さない」
「ならあんたも来ればいいのに」
「人間がうじゃうじゃいるんだろう? 断るよ」
「あんた本当に人間嫌いねぇ、外に出なきゃ治るもんも治らないわよ? ロリコン」
「人間を好きになる気はないし僕はロリコンじゃない。人間の中でも子どもは一番嫌いだ。あ、ひなは特別だよ」
泉光は黙々と食べ進めている花乃の頭を優しく撫でてやりながら付け足す。
「とにかく、いい加減部屋から出ないと新しい刺激もないわよ?」
「人ごみに入るくらいなら刺激がないほうがマシさ」
頑なに外へ出ることを拒む泉光にとうとう樹季も困り果ててしまった。
泉光も考えを変える気はないらしく、そっぽを向いている。
そんな泉光の手に、温かで柔らかな感触が伝わり、そちらに目を向けた。
お昼を食べ終わったらしい花乃が、泉光の手を両手で握り、潤んだ目で見上げていた。
その目からは「一緒に行こう?」という思いがひしひしと伝わってきて、さすがに泉光も揺らいでしまう。
「でも……」
ついに花乃は泉光から手を離し、その手にはキンセンカの花を握る。
キンセンカの花言葉はそのほとんどがネガティブなもので、
その中の一つ、失望を表すように花乃は明らかに落ち込んだ様子を見せる。
泉光もその様子を見て焦り、慌てて言った。
「分かったよ、僕も行くから……だから、もうそんなに悲しい顔をしないで?」
顔を上げた花乃は笑顔になり、椅子から立ち上がると喜びを表すようにその場で小さく跳んだ。
そんな花乃に泉光も安心し、笑顔を見せる。
花乃は座っている泉光に抱きつき、頬にキスをして離れると、食べ終わった皿を持って台所の流し台へ持っていくために部屋を出た。
樹季ははしゃいでいた花乃を笑って見送ると、泉光に目を向ける。
泉光は頬にキスをされたことによるショックで顔を赤くし、目を覆っていた。
「早くしなさいね。あの子、待ってるんだから」
「……そうするよ」
泉光は素直に返事をし、皿に載っていたサンドウィッチを平らげた。
身支度を済ませると、花乃を真ん中に、三人で手を繋いで街へ出たのだった。
ボーイミーツ・フラワーガール 前編
太陽の順番が回り、外を明るく照らし出す。真上に昇る頃には草木にまんべんなく光を与え、
花々は誇らしげに顔を上げて輝きを反射させる。心地よい風が吹き抜け、青空には雲が流れていた。
そんなよく晴れた清々しい天気だというのに、とある一軒家のテラス戸は閉め切られ、カーテンすら開けられた様子はなかった。
せっかくの中庭も静まり返り、空からやってきた小鳥たちが芝生をつつき、時たまソプラノの鳴き声を響かせている。
テラス戸の向こう側、部屋の中まで静に包まれていた。白い壁は部屋の明かりを跳ね返し、外と同じくらいの明るさを保っている。
そんな部屋の中で聞こえるのは外の小鳥の鳴き声と、キャンバスを筆で擦る音のみ。
泉光は、木製パレットに指を入れ支えながら、
その上にのせた多種の油絵具を器用に混ぜ合わせて描きかけのキャンバスを彩っていく。
描かれているのは幻想的な風景の中で、ピンクのロリータドレスを着た長髪の少女が、花束を抱えて座り込んでいる絵。
そこに一切の抜け目はなく、繊細に、そっと労わるように、泉光の手によって絵はより不思議な雰囲気を帯びる。
そんな泉光が時たまキャンバスから目を離し、イーゼルの後ろを覗くように見たあと、再びキャンバスと向き合うことを繰り返す。
彼の目の先にいるのは、絵と同じ色、同じ形のドレスを着て、絵の少女と同じように花束を抱えている花乃だった。
どうやら、花乃が絵の少女のモデルとして描かれているらしい。
花乃は花束を持ちながらも動かないようにその場に座り込む。
身じろぎ一つせず、ぼんやりと前を向き続けるその姿は、精巧に作られたフランス人形を彷彿とさせた。
泉光は目を向けるたび、じっと動かずにいる花乃に目を細めて笑みを浮かべる。
「可愛いよ、花乃」
そう言われても花乃は動くことなく、垂れたピンク色の目は伏し目になり、
呼吸が深くなると慌てて背筋を伸ばして体勢を立て直すことを繰り返す。
しかし、それも五分後には前のめりになっていき、座り込んだ体勢のままこくんと頭が垂れ、反射的に顔を上げる。
再び花乃に目を向けた泉光も流石にその様子に気が付き、首を傾げた。
「ひな……?」
呼ばれ、花乃は開けることで精一杯の目を泉光に向けるが、
すぐにまた瞼の重さに耐え切れずに目を細め、視界がぼやけていく。泉光は椅子から立ち上がると、
花乃に近づき、目の前で片膝をついてしゃがむと壊れ物を扱うように頭を撫でてやる。
「どうしたの? ……もしかして、眠い?」
花乃は頷くと同時にこくりと前のめりになるとそっと泉光に支えられた。
泉光は立ち上がると花乃を抱き上げる。幾重にも重なったドレスのレースがふわりと持ち上がり、
横抱きにされた小さなお姫様は安心したように表情を和らげる。
「今日はお昼寝にしよう。ゆっくりおやすみ、僕の可愛いお姫様」
小さく頷いたと思うと、花乃の持っていた色とりどりの花が白いケシの花に変わっていく。
白いケシの花言葉に眠りという言葉がある。「おやすみなさい」と伝えたいのだろう。
花束が白ケシに変わったすぐあとに、花乃はすやすやと寝息を立てて眠り始めた。
両手で花束を持ち、眠る様子は白雪姫や眠れる森の美女を彷彿とさせる。
泉光は花乃をそっとベッドへ運ぶ。ゆっくりと寝かせると、小さな花乃には大きすぎるシンプルなベッドが、
王室のベッドのように華やかになったように感じられた。安らかに眠る様子に泉光は穏やかな笑みを浮かべた。
小さな両手から花束を取り上げ、サイドテーブルに置いたあと、花乃のふっくらとした柔らかい頬を軽く指で突き、そっと撫でた。
「ひなちゃん、泉光、お昼よー」
二人を呼びながら部屋に入ってきたのは樹季。紫のメッシュを入れた少し長めの黒髪を後ろで束ねている。
朝から作業をしていた部屋の半分を見渡しても誰もいないことに首を傾げ、樹季は再び二人を呼ぼうとした。
「静かにして、樹季さん」
泉光の声が生活のスペースとして使われているほうから聞こえ、樹季はそちらに目を向ける。
樹季に目を向けることなく、眠る花乃を見つめる泉光の姿を見ると呆れ顔になった。
「いるなら返事しなさいよね、全く……」
言いながらも三人分の昼食を乗せたお盆を持ちながら、部屋の真ん中にあるガラス張りのローテーブルにお盆を置く。
それから、樹季は泉光に近づき目の前で止まった。
「ひなちゃん、お昼寝?」
「さっき眠ったばかりだよ」
「朝からずっと動かないで頑張っていたものね。あとでひなちゃんにお礼言いなさいよ?」
「言われなくても、毎日毎時間毎分毎秒、ちゃんとひなを可愛がるよ」
「あんたが言うと犯罪のにおいしかしないわ」
「ひなが犯罪級に可愛いのは知っているよ」
花乃を見つめながら幸せそうに笑う泉光に樹季は冷めた視線を送るが、
本人は気にする様子もなく未だに花乃の頬を撫でている。
少しすると、仰向けだった花乃は寝返りをうち、体を泉光に向け、何かを探すように小さな手を伸ばしていた。
「ひな……?」
どこか不安そうに、何かを探すように手を伸ばす花乃を見て泉光も不安になり、そっとその小さな手を握った。
すると、花乃は安心したように微笑み、また安らかな寝息を立てる。泉光が握っている手は、同じように泉光を握り返していた。
「ひなっ……」
あまりの嬉しさに泉光の目は潤み、花乃の手を握ったまま口元を押さえる。
一部始終を見守っていた樹季は、また呆れたようにため息をついた。
「ったく……人間子ども嫌いのあんたが、いつからひなちゃん依存犯罪者になったんだか……」
呟きながら、樹季は昔の二人を思い出した。今は花乃に依存するように溺愛している泉光と、
眠りながらも泉光の手を握り返す花乃に、喚くように叫ぶ姿の泉光と、頭を抱えて怯えた様子の花乃が重なった。
「……ほんと、変わったわよね」
今と昔の姿を比べ、この平和な様子に、樹季は知らず安堵した笑みを浮かべていた。
******************
一年半前
二十二になった青年はひたすら絵を描き続けていた。
画材を選ばず、ひたすら動物や風景、彼独自の世界をキャンバスに描き出す。
幻想的で繊細、今にも動き出しそうな立体感と空間の使い方は、天才と呼ばれるのもなるほど、納得ができた。
しかし、壁に立てかけられたどの絵にも人間は描かれていなかった。
多種多様な生き物を描いた森の風景、自然と一体になりつつある廃墟、空に浮かぶ島、海面が輝く海の中、
どの作品にも人間の姿は影すら見当たらない。
それらの絵を描いている本人の目はどこまでも暗く、目の前の作品以外、何も見えていない様子だった。
希望もなく、未来もなく、ただその場を凌ぐように描き続ける姿は近寄りがたく、孤独を思わせた。
「泉光、たまには休みなさいよ。あと、ちゃんと食べなさい。
朝ごはんそのままじゃない。今何時だと思ってんの? もう昼よ、昼」
青年のアトリエを兼ねた部屋に入ってきた、長身でシンプルながらも洒落た格好をした女性口調の男性は困った様子で、
ガラス張りのローテーブルに置かれたままになっている皿に目を向けた。
ラップがかけられたまま、更には時間が経って乾燥し、見て分かるほど硬くなってしまったおにぎりが、
手を付けられた様子もなく三つ並べられている。
男性、樹季は深いため息をつくと、テーブルの皿を持ち上げ、筆を動かし続ける青年、泉光の後ろ姿に声をかける。
「せっかく食べやすいようにおにぎりだけにしたのに……。食べ物は大事にしなさい?」
「……ご飯より描きたい絵がある。それだけだよ」
それがいつもの返事。二人で暮らしてから六年は経つ。
さすがにもう慣れたが、やはり今のままでは泉光が衰弱してしまう。
「あんたいい加減になさい? その描きたい絵を描くためにも、ちゃんと食べないと、倒れて描けなくなるわよ?」
「……」
泉光は返事をしなかった。樹季は泉光の横に立ち、彼が熱心に描いている絵を見た。
色とりどりの明るい花畑に、その先まで続く青空が印象的な絵だ。しかし、やはりそこに人間は描かれていなかった。
「……今回もいい作品ね。でも、そろそろ人を描こうとは思わない?」
「人間は嫌いだよ。樹季さんも知っているだろう」
「好き嫌いしてちゃ、いいものも描けないわよ? クライアントからも、あんたの描く人間を見てみたいという方も多いわ。
たまに、自画像を描いてほしいなんて人もいるし。そろそろ受けてみない? そういう仕事」
「断るよ」
即答され、樹季は再びため息をついた。
「あんたねぇ……いい? いつまでも自分の描きたいものだけで稼げるわけじゃないのよ?」
「僕は今まで描きたいものを描いてきた。でも、売れなかったことはない。
それは、美術商のあなたが一番よく分かっているだろう? だって、僕の絵を売っているのは、樹季さんなんだから」
「それは……そうだけど……」
「なら問題ないよ」
「そういうことじゃないの! 絵が売れるとか売れないとか、それももちろん大事よ?
でもね、新鮮さっていうのも必要なの。今は風景とか動物とか幻想的な景色とか、評価されているけどね?
そう遠くないうちに、潮が引くようにクライアントの足は遠ざかっちゃうわ。なぜなら、新鮮味が足りないから。
今のうちに“こういう絵も描ける”っていうのを示していかないと……」
「……はぁ、分かったよ。分かったから少し静かにして」
泉光は苛立ち気味にそう言うと筆を置き、そこで初めて樹季のほうを向いた。
承諾したことを意外に感じた樹季だったが、泉光がその気になったのなら何でもよかった。
「ようやく分かってくれたのね」
「おっさんのうるさい話しを延々と聞かされていたら嫌でも理解はするよ」
「いい加減、口の利き方には気を付けなさいよ?」
おっさん、と言われたことに少し皺を寄せたが、ここで噛み付くようなことをすれば
気分屋の泉光がそっぽを向いてしまうことは容易に想像ができた。
「何でもいいけど、僕に人を描かせたいなら、モデルを連れてきて」
「……ええ、いいわよ。どんな子?」
「髪の長い十歳の女の子」
「はぁ?」
思わず声を出してしまった。泉光は人間の中でも子どもが一番嫌いなのだ。
「子ども嫌いの、あのあんたが? 子どもをモデルに?」
「不満があるならやめるよ」
脅しのように言われ、樹季は口を紡ぐ。
「分かったわよ……口答えすんなってことね」
「分かってるじゃないですか。ちなみに、ただの髪の長い十歳の女児じゃないよ。
髪質はやわらかくて少しクセがあって、色は茶色系統、肌が白くてモデル体型。
身長は百四十センチ未満で大人しい、顔の整った子ね」
「……は? え、ちょ、何よ、その注文、全部そろった子を連れて来いって!?」
「何か不満?」
「大ありよ! もっとこう、何か妥協は出来ないの?」
「出来ないね。もともと子どもは嫌いだって知っているだろう?
それくらいの奴じゃないと描きたくない。見るに堪えないよ」
「だからってあんたねぇ……」
「嫌ならやめる。それだけさ」
泉光の自己中心的な態度や頑固さに、樹季は心労によるストレスで大きなため息をつく。
しかし、ようやく泉光が自ら嫌いなものに挑戦しようとしている。そのチャンスを潰してはならない。
「……いいわ。見つけてきてあげる。ただし連れてきたらちゃんと描くのよ? あと、一応は“仕事”としてのモデル探しよ」
「いいよ、約束する。報酬もね」
「じゃあ、アタシは出かけてくるから。新しいキャンバス用意して待ってなさい!」
意気込んだ樹季は部屋を出ていくと扉を閉めた。それを見送った泉光はため息をついたと思うと、
口元だけ笑みを浮かべ、どこか遠くを見るような虚ろな目をした。
「……いるわけないよ。だって……あの人は……もう……」
呟いた泉光は、再び描きかけのキャンバスと向き合い、筆をとって彩り始めた。
勢いで街に出てきた樹季だったが、腕を組み、頬に手を当てながら途方に暮れていた。
「はぁ……見つけてくるとは言ったものの、泉光の要望に全部当てはまる子なんて……」
諦めそうになるが、首を横に振り、気合を入れ直す。
「いいえ、あんなに具体的に要求してきたんだから、きっとそんな子がどこかにいたのよ。
いないわけじゃないわ。探す前から諦めるなんて、あんたらしくないわよ樹季! よし!」
自らに喝を入れると、改めて見つけてやるという決意を固める。
「まずは手始めに子どもがいそうなところね。
顔の整った肌の白い子なら、芸能関係になら、それなりにいるはずよ。
アタシの人脈なめんじゃないわよ……見てなさい、泉光!」
再び希望を持った樹季は早速スマートフォンを取り出し、
知り合いが経営している芸能事務所へ連絡をし始めた。
数分の会話の末、許可を得たのか樹季は電話を切ると勝ち誇ったような笑みを浮かべる。
「ふふふっ、案外楽勝かも」
浮かれた気分で連絡を入れた事務所に向かう樹季は、
泉光からの要望がいかに困難を極めるものなのかを、まだ知らなかった。
夕方。太陽がその日の役目を終えようと沈んでいくなか、樹季は公園のベンチに座り込み、項垂れていた。
「はぁ~……事務所を六カ所に、児童施設を五カ所、公園その他、
子どもの集まりそうな公共施設を数カ所、顔が利く小学校も全滅……
こりゃ重労働どころじゃないわよ、泉光……報酬はきっちり巻き上げてやる……!」
悪くない顔立ちの額に皺をよせ、腕を組み、頭を悩ませる。
樹季が見てきた先ではそれなりに顔立ちの良い子や肌の白い子、
髪の長い子や茶色系統の頭髪の子、身長の小さい子やモデル体型の子はいた。
しかし、顔立ちは良いが日に焼けていたり、肌は白いが髪が短かったり、髪は長いが黒髪だったり、
茶髪だが活発の子だったり、小さいが七歳だったり、
モデル体型だが身長が高かったりとパーツは持っているがすべてを揃えている少女などいなかった。
どれか一つを妥協すれば、あの泉光のことだ。仕事を断るだろう。
何としてでも、せめて外見だけでも完璧にそろえた子を用意しなくてはならない。
「って言っても……もう! なんなのよ! なんであんなに拘んのよ!」
そうぼやいたところで、樹季は気づく。そういえば、泉光が人に対して拘ることなど今までになかった。
人間嫌いで人に興味を持たない泉光が、頭の中に既に思い描いていたような人間像を要求してきた。
「まさかあの子、最初から人を描く気だったのかしら」
考えると、なんとなく先ほどまで感じていた怒りは収まった。
泉光もただ好きな物を描いていたわけではない。
きちんと頭の中では今まで挑戦してこなかったことに挑戦しようという気持ちがあったのではないだろうか。
樹季は考えを巡らせ、気を取り直す。
「ようやくあの子がその気になったんだもの、きっと一人や二人、見つかるはずよ。
この街にいないだけで、他の場所にはいるかもしれないし……。とりあえず、明日は違う街の事務所に……」
樹季が携帯を取り出し、どこかに連絡を入れようと電話帳を開いたときだった。
「申し訳ございません……」
公園の隣の施設から、女性の深刻そうな声が聞こえ、樹季は手を止めてそちらに目を向けた。
花壇を挟んでいたために見えにくく、樹季は立ち上がり様子を見る。
そこにいたのは、建物の前で頭を下げる髪を結んだ眼鏡の女性と、
女性と対峙する一目で上質なものだと分かるスーツを着込んだ男性。
「うちでは、もう、子どもを預かることは……」
「もちろん、タダでとは言いません。相応の報酬も用意しますよ」
「そういう問題ではありません! うちには、子どもの面倒を見れるだけの人手と、場所がないんです。
それに、そちらの子はお話によると……」
「分かっています。ただ、うちでももう預かれないんですよ。
でも、この子に両親はいませんし、ここに断られたらもうないんですよ」
男性はそっと、隣にいたらしい小さな少女の背中を押し、前に出した。樹季は目を疑う。
少しクセのあるベージュ色の髪は膝辺りまで伸び、空気を含んだようにふんわりと風に揺られ、
長袖のワンピースを着ているが首元から覗く肌の色は白く、柔らかくも整った顔は悲しげに俯き、
遠くからでも分かるピンク色の目は地面を見つめ、小さな両手で本を抱えていた。
その姿があまりにも小さく見えたのは、縮こまってしまっているからという理由だけではなく、
本当に身長が小さいからだろう。ワンピースの下から覗く小さくもすらりとした脚や幼いながらもあるくびれはモデルのようで、
だからと言って病的に痩せているわけではないことはふっくらとした頬や見ただけでもみずみずしいと分かる肌から分かる。
樹季は目を擦ってまた少女をよく見える。一つも違えることなく、泉光の求めていた人間像を全て揃えている少女だった。
「うちは一時的な保護施設です。もうこれ以上は保護できません。何より、その子には……」
「ちょっといいかしら?」
考えるよりも先に、このチャンスを逃す理由のない樹季は花壇を隔てて思わず声をかけていた。
声をかけられた女性も、少女を連れている男性も、少女も樹季に目を向ける。
「その子、受け入れ場所を探しているんですって?」
「そ、そうですが……」
女性の口調で話をする樹季に、男性は戸惑っているようだったが今は気にしている暇はない。
「ここに入れられないの?」
「ええ……申し訳ないのですが、こちらはもう手一杯で……
お金の問題ではなく、きちんと子ども一人一人と向き合えるだけの人手が足りないので……」
「ふーん……。ねえ、あなた、そのお嬢さんは施設じゃないと引き渡せないの?」
「い、いや、そういうわけではないですが、その……この子には両親も親戚もいませんから……」
「そうなの……。ねえ、そのお嬢さん、アタシが引き取ることはできない?」
突然の樹季の提案に男性はたじろいだ。少女は不安げに樹季を見つめていた。
「そ、そんな、そもそも、あなたはどちら様なんですか?」
「待って、ここからじゃ話がしにくいわ。そっちに行くわね」
そう言って、樹季は公園を出ると隣の建物に続く道を歩き、三人の前に現れた。
「アタシは通りすがりの民間人。もっと言えば、フリーのデザイナーで、ある画家専門の美術商をしているわ」
「デザイナー……? 美術商……? そんな方がなぜ?」
「いえ、ちょっとモデルを探していてね。ちょうど、そのお嬢さんみたいな子。
うちは家も広いし、部屋もあるわ。お嬢さん一人置いておくのも問題ないし」
「い、いえ、ですが……」
「あなた、その子の顔、ちゃんと見たの?
ここで延々と引き取れ、引き取れないって押し付け合いみたいに……その子が何したって言うのよ」
男性は言葉を詰まらせるが、間をあけてからため息をつき、話を始めた。
「この子は特別なんです。ただの子どもではありません」
「何よ、ただの可愛らしいお嬢さんじゃない」
「違います。彼女は……理解しがたいかもしれませんが、特別な力を持っているんです」
「超能力とか?」
「いいえ。この子は、自身の手に、多種多様な花を自由自在に出すことができるんです」
樹季は男性に対して変な物をみるような目を向けた。その視線に男性は睨むように返す。
「本当なんです! 彼女は、声は出せますが言葉を話すことができません!
読むことはできますが書くこともできないんです!
人の字や文を見てそれを真似ることはできますが、自分で思ったことや感じたこと、
伝えたいことを書いて伝えることもできません。
ですから彼女は、その自由自在に花を出せる力を使って、花言葉と身振り手振りで会話をするんです」
「はぁ……? よく分からないけど、嘘ではなさそうね?」
「嘘なもんですか! ほら、見せてあげなさい」
突然、話を振られた少女は体が強張り、怯えるように男性と樹季を交互に見たあと、
視線の圧に耐え切れず、震えた小さな手を前に出すと、その手からパッとゼラニウムの花を出した。
その様子に、先ほどの女性は小さな悲鳴を上げ、樹季は口元に手を当て、素直に驚く。
「まあ……!」
少女はゆっくりと樹季に近づくと、彼を上目遣いで見上げたまま、
先ほど出したばかりのゼラニウムを震える腕で差し出す。樹季はそっと、少女から花を受け取った。
「あら……くれるの?」
見上げたまま頷いた少女は、またゆっくりと後退した。
「その花は確か……えっと……」
「ゼラニウム、ね」
名前が思い出せずに頭を悩ませる男性をよそに樹季は答えた。
驚いた男性が樹季のほうを見ると、少女が樹季に向けて本を広げて見せているのが見えた。
どうやら、渡した花のページを見せているらしい。
「その本、お花と花言葉の図鑑だったのね」
樹季が優しく言えば、少女は少し安心したのか、頷いた。それから、本の花言葉の欄を指さす。
「えーっと、ゼラニウムの花言葉は……愛情、尊敬、信頼、思いがけない出会い、予期せぬ出会い……
ああ、もしかして、アタシに“思いがけない出会い”って言いたいの?」
分かってもらえたことに安堵した少女は、初めて微笑み、頷くと、本を閉じて頭を下げた。
「初めまして」と言いたいようだった。
樹季は感心したように笑うと少女の前にしゃがみ、その小さな手を取り、唇で軽く手の甲に触れた。
ほんのりと顔を赤くさせた少女は、今は自分と同じ位置にいる樹季を真っ直ぐ見る。
「初めまして。笑ってるほうが可愛いわよ、あなた」
少女ははにかみ、しっかりと本を抱きしめ、俯いてしまった。
「うふふっ、可愛い。ねえ、あなた、お名前は?」
聞かれた少女は困ったように辺りを見渡すが、どうしようもなくなり、挙動不審になる。
「……その子は、花に乃ちと書いて、花乃です。
私はあとから知り合ったのでどういう経緯かは知りませんが、その名前とその子だけが残されていたそうです」
答えられない少女に代わり、男性は答えた。立ち上がった樹季は、改めて男性と向き合う。
「花乃ちゃん、ね。ところで、あなたはこの子とはどういう関係なの?」
「私は研究員です。その子の花を出す不可思議な力について、研究していました。
しかし、花を出す以外の力もなく、特に新しい種類を作り出せるわけでもなく、害をなすわけでもないため、
研究の必要がなくなったんです。うちで預かったままということもできないので、こうして受け入れ施設を探していたんです……」
「……そう。ようは厄介払い? 自分勝手なのね」
男性は反論できずに俯いた。花乃の本を抱きしめる力も強くなる。
「仕方が、ないんです……」
「ま、あなたたちにも事情ってもんがあるんでしょうね? アタシがとやかくいうことではないわ。
でも、その子にだって選ぶ権利がある。大人の事情で研究されて、大人の事情で厄介払いなんてたまったもんじゃないわよ」
「……」
「結局、ギリギリになって受け入れ先を探してるだけじゃない。どこだってよかったんでしょ?」
何も言えずに俯き続ける男性を花乃は怯えた目で見上げた。
その視線に気がつき、自分に恐怖した様子の花乃に哀れむような、同情するような目を向けた。
「……その、通りです……言い訳は、できません……」
「そこのレディもレディよ。この子に不思議な力があることにあんな声ださなくてもよかったんじゃない?」
ずっと黙っていた女性も話を振られ、そう言われれば何も言い返せなくなり、申し訳なさそうに俯いた。
その様子に呆れた様子の樹季は、最後に花乃に目を向ける。
「……ねえ、花乃ちゃん。よかったら、うちに来ない?
ちょっとおかしなやつが一人いるけど、悪い子ではないの。あなたなら、もしかしたら仲良くなれるかも?」
花乃は目を見開き、樹季を見上げた。ゆっくりと腕を伸ばそうとした瞬間。
「そ、そんなどこの人かも分からない人に、預けられませんよ!」
阻むように男性が声を上げた。それに樹季は腰に手を当て、冷めた視線を送る。
「あなたねぇ……それが自分勝手っていうのよ。
それを決めるのはあなたじゃない。アタシはお誘いしてるだけ。分かる?」
「ですけどっ!」
「あー」
男性がまた何かを言おうとした瞬間、子どもの可愛らしい声が聞こえた。
驚いた大人たちは、ゆっくりと花乃に目を向ける。花乃は大人たちを見上げながら、口を開いていた。
「あー」
「花乃ちゃん? 何か言いたいことがあるの?」
花乃は頷くと、ゆっくりと樹季の前に歩み寄り、手を伸ばした。
「うー……」
「……一緒に、来る?」
「うー!」
花乃は笑顔になり、頷いた。樹季はゆっくりと、花乃の小さな手を取り、繋ぐ。
「と、この子はアタシたちのところに来たいみたいだけど」
「あ……いえ……」
「安心しなさい。この子はちゃんと面倒見るわ。約束する。
ニュースかなんかでアタシが子ども虐待とかなんとか流れたら、その時はアタシを遠慮なくどうとでも言いなさい。
でも、アタシはこの子を気に入ったから、ちゃんと、自立できるまで面倒見るわよ」
「は……はぁ……」
「じゃあ、そういうことだから。あ、そんなに心配ならこれ、あげるわ」
樹季がポケットに手を入れ、取り出したのは連絡先が書いてある名刺だった。
押し付けるように男性に渡すと、花乃の手を引き、歩き出す。
「気になったら連絡ちょうだい。ついでに、もしデザインの仕事かなんかあるなら、どんどん寄越しなさい。
これでも、腕は確かなんだから。じゃあね」
花乃を連れて颯爽と去っていく姿に男性も女性もその背中を見送ることしかできなかった。
立ち去る前に、花乃は樹季と手を繋ぎながら後ろを振り返り、小さく別れの手を振った。それに男性も思わず手を振り返す。
そのうち、樹季と花乃の後ろ姿は遠のいて行き、残った男性も我に返ると施設の女性に頭を下げ、その場を去ったのだった。
これが、ひねくれた青年と不思議な少女の、ボーイミーツガールの始まりになるのだった。
ボーイミーツ・フラワーガール 中編
オレンジ色の光に照らされている道を樹季と花乃は手を繋いで歩く。
どこか不安げに手を握りながら、本を抱きしめる花乃に、樹季はそっと声をかけた。
「そういえば、花乃ちゃんはいくつ?」
聞かれた花乃は困ったように辺りを見渡す。伝える手段を探しているのだろう。
それから、思いついたように立ち止まると、樹季から手を離し、本を数ページめくる。
樹季にその本を広げて見せ、ページ数を指さした。そこに書いてあった数字は九。
「九ページ……? ああ、九歳って言いたいのね?」
花乃は何度も頷く。
「うふふ、なんだかこういうの、ジェスチャーゲームを思い出して楽しいわね。お誕生日はいつなの?」
聞かれると、花乃はまたページをめくっていき、本を広げて樹季に見せる。
しゃがんだ樹季は花乃の小さな指が指さす項目に目を向けた。
「誕生花? えっと……四月十五日……。じゃあ、来年で十歳になるのね」
再び頷いた花乃。樹季はその様子に柔らかな表情を浮かべたあと、気になり、本に再び目を向ける。
「白いワスレナグサの誕生花……。えっと、花言葉は……“私を忘れないで”……なんだか、切ない花言葉ね?」
樹季は立ち上がり、花乃が本を閉じて小脇に抱えると、手を繋ぎ直し、泉光の待つ家への帰路を歩き出した。
陽も落ち、家に着いた二人。花乃は初めて見るのであろう、大きな一軒家を見上げ、目を見開く。
「今日からあなたが暮らす家よ。これから三人で仲良くしていけたらいいのだけど……」
樹季は一抹の不安を拭うことができないものの、
さすがに子ども嫌いだからと言って手を上げることはないだろうと考え直す。
そもそも、嫌いならばモデルとして関わる以外、自ら関わり合うことはしないはずだ。
「じゃ、入るわよ」
花乃の手を握りながら玄関の鍵を開け、中に入った。
玄関の電気が点いており、埃一つなく綺麗に掃除されたそこを、花乃は物珍しそうに見渡した。
樹季が扉を閉め、鍵をかけてから靴を脱いで上がろうとしたとき。
「遅いよ、樹季さん。明日、新しいキャンバス買ってきてほしいんだけど……」
奥から出てきた泉光が、帰ってきたばかりの樹季に声をかけるが、
その横に本を抱えた花乃を見つけ、目を見開いた。
それから、明らかに不機嫌そうに眉間に皺を寄せる。
「ただいま、泉光。先に“おかえりなさい、お疲れ様”の一言くらい言いなさいよ。
今日一日、あんたのために働いたんだからね?」
「……どこから連れてきたの? そこの」
敵意剥き出しの視線に、花乃は思わず固まり、震えてしまう。
それでも、その桃色の目は泉光から視線を外すことができず、おろおろしてしまう。
「この子、今日からうちで面倒見るから。よろしくね、泉光」
「聞いてないよ、そんなの」
「言ってないもの、当たり前じゃない」
「何で、連れてきたの」
「あんたが要求したからよ。髪は茶色系統で長くてふわふわ、身長が小さくてモデル体型、
色が白くて大人しい、そして何より可愛いでしょ? この子、すごいのよ」
得意げに話す樹季の話にも、眉間の皺は余計に険しくなる。
「……いるわけないだろう……だって……あの人は……」
「あんた何言ってんの? とにかく、モデルとしても問題ないでしょ。
まあ、あんたが認めなくてもここに置いとくけどね。アタシ、この子のことすごく気に入っちゃったし」
樹季は花乃の両肩に手を置き、花乃と同じ目線になる高さにしゃがむと、
頬を擦り合わせる様子を泉光に見せつける。
花乃はどこか恥ずかしそうにしながらも、未だに怯えているのか本を強く抱きしめ続けた。
その様子に、泉光は冷めた視線を送り続けるが、踵を返してまた部屋の奥へと歩き出す。
「何でもいいけど、お腹空いた。悪いけど、適当に何か用意してくれるとありがたいな、樹季さん」
「はいはい、言われなくたって作るわよ!
ったく、人使い荒いというか、アタシは家政婦じゃないのよ、この引きこもり!」
不満をぶつける樹季に対して、泉光は片腕を軽く挙げただけで振り返りもせずに部屋に戻ってしまった。
それに苛立ちを募らせ文句を言い続けていた樹季だが、
いつの間にか心配するように見上げてきていた花乃の視線に気づき、安心させるように頭を撫でてやる。
「心配しないでちょうだい、いつものことよ。あの子、泉に光って書いて泉光っていうの。
あれでも名の知れている画家でね。あなたを連れてきたのも、泉光の要求してきたモデル像に、
あなたがぴったり一致したから。とてもわがままで、困った子でね。人間が大嫌いなのよ。
今まで絵にも人間を描いてこなかったの。でも、今回初めて人を描いてやろうって気が起きたみたい。
それで、要求してきたのがあなたみたいな子。髪が茶色系統で長くて、身長が小さくて、細すぎない可愛い女の子。
だから、泉光はとっつきにくいと思うけど、我慢してモデルになってあげてくれないかしら?」
樹季の丁寧で分かりやすい説明に、花乃は不安を感じながらも首を傾げる。
正直、泉光とやっていける気がしない。
あの、敵意しかない目を浴び続けながら、動かないでいることを考えると胃が痛く、吐き気を感じるほどに緊張する。
しかし、せっかく拾ってもらった身だ。期待に応えなくてはならない。
それに、泉光と全く仲良くできないわけではないはずだ。
花乃は前向きに考えると気を引き締め、本を強く抱きしめ直し、大きく頷いた。
それを見た樹季は花乃の頭を撫でる。
「ありがと、花乃ちゃん。じゃあ、ご飯作るから、待っててくれるかしら?」
それに、今度は嬉しそうに頷く花乃。
子どもらしい感情を表現する少女に安心し、樹季は微笑むと花乃をダイニングに案内した。
ダイニングにはテーブルがあり、その周りに囲うようにお置かれた四脚の椅子のうちの一つに花乃を座らせ、
樹季はダイニングに備え付けられたオープンキッチンのスペースに立ち、その様子を花乃はじっと見守っている。
「もらったお花、今はコップに活けておくわね」
そう言って、透明なガラスコップを取り出すと軽くゆすぎ、水を入れると挨拶代わりにもらった花を生けた。
ようやく、手を洗った樹季は食事の用意を始めた。
冷蔵庫から挽肉、玉ねぎ、にんじん、ニンニク、牛乳を出したと思うと、手際よく下ごしらえしていく。
ニンニクと玉ねぎをみじん切りにし、油を引いたフライパンで炒める。
香ばしい匂いが立ち込めている間、ステンレスのボウルにひき肉と調味料、牛乳に浸しておいたパン粉を入れる。
炒めている玉ねぎがキツネ色に変わったところで火を止め、少し冷ましてから挽肉の入ったボウルの中に入れた。
すべてそろったところで混ぜ合わせ、こね回していく。
あまりに綺麗な手際に、いつの間にかその様子を見入っていた花乃は目を輝かせていた。
視線に気づき、そちらに目を向ければそんな花乃の表情に樹季は思わずクスッと笑う。
「花乃ちゃん、一緒にこねこねしましょうか?」
その言葉に、花乃は笑顔になり、大きく頷いた。
抱きしめたまま離さなかった本をテーブルに置き、椅子から降りると樹季のいる台所に回る。
「それじゃあ、まず、ちゃんと手を洗いましょうね」
張り切り、真っ直ぐに手を挙げた花乃は流しの蛇口をひねると、
その小さな手を石鹸で洗う。ウキウキした様子が見ているだけでも伝わり、樹季は思わず笑った。
花乃の手伝いもあって夕食の準備が一人でやっているときよりも早かった。
というのも、最初は手探り状態ではあったものの、花乃の物覚えが良いのもあり、
一度教えればその通りにやってくれるのだ。
テーブルの上にトマトとサニーレタスをシーザードレッシングで和え、
輪切りにしたゆで卵を添えた簡単ながらもボリュームのあるサラダに、
肉汁をたっぷりと内に湛えたハンバーグはデミグラスソースの代わりに焼肉のタレがかけられている。
今にも崩れてしまいそうな、しかしきちんと四角形を保っている角切り豆腐が入ったみそ汁には、
ひらひらと若布が泳ぎ、硬くも水っぽさもなく炊き上がった白米をよそったお椀を並べれば、立派な夕食の席となった。
樹季は満足そうに並んだ品の数々を見て頷く。
その隣で、ずっと目を輝かせている花乃に目を向ければ、視線に気づいた彼女は樹季を見上げた。
「花乃ちゃんもお疲れ様、すごく助かったわ。それに、すごくおいしそうじゃない?」
花乃は満面の笑みを浮かべると、大きく頷いた。それにじんわりと心が温まり、樹季は花乃の頭を撫でた。
「もう、可愛いんだから!」
言われれば、恥ずかしそうに俯く花乃。それにまた「可愛い!」と言って、樹季は頭を撫でまわす。
ようやく手を離すと、樹季は乱してしまった花乃の髪を正してやる。
「さあ、花乃ちゃん。テーブルの上の本は別のところに置いて、先に席に座ってて。
アタシはあのクソ……ゴホン。泉光を呼んでくるから」
うっかり花乃の前で綺麗とは言えない言葉を使いそうになったが、改めて言い直す。
花乃は不思議そうに首を傾げたが、すぐに言われた通り、テーブルに置きっぱなしにしてしまっていた本を持ち、
自分が座る椅子の背に立てかけた。椅子に座り、大人しく前を向いて待つ。
「ほんとにいい子ね。じゃあ、少し待っててちょうだい。すぐに連れてくるわ」
ただ前を向き続けて頷く花乃を見たあと、樹季は泉光の部屋へと向かった。
「泉光、ご飯よ。出てらっしゃい」
ノックをしながら、部屋にいるだろう泉光に呼びかける。
どうせまた、絵に没頭しているのだろうと分かっていながらも、
いつかは返事をして自ら出てきてくれることを今でも諦め半分に期待している。
だが、今日もまた、ノックをして呼んだくらいでは、泉光は出てきてくれることはなかった。
予想通りの反応にハァ……と深いため息をついた樹季は、ドアノブを回して部屋の扉を開ける。
「泉光、聞いてるの? ご飯できて……」
言いかけた途端、言葉を失う。
植物油脂臭と、絵具を落とすために使われるシンナーのにおいが混ざり合い、じわじわと、蝕むように肺に溜まる。
その渦中で、ひたすら筆を動かし続けている姿は荒々しく、
白いシャツは黒や赤、青色の汚れが目立ち、頬や首にもその絵具が飛び散っていた。
そこでいつも通り、彼が絵を描いていることには変わりないはずだった。
しかし、今の彼は何かを怯えるように、何かを遠ざけようとするように、
同時に、追い求めるようにキャンバスに色を重ねていく。
昼間に見た、煌めく青い宝石の空と、光を放つ一面の花畑は、灰色の空と生を失った枯葉の山へと姿を変えていた。
塗り潰し、塗り潰し、また、塗り潰す。
心をかき乱されている様子に、樹季は数分にも思える数秒の間、声をかけることができなかった。
だが、このままにしておくわけにもいかない。
「……泉光」
樹季の呼ぶ声に、泉光はようやく手を止めた。ゆっくりと顔を向け、樹季の姿をその目に映す。
いや、その目は樹季に向けられてはいるが、彼を映すことも、他の何かを映すこともなかった。
どこまでも虚ろで、どこまでも暗く淀んでいる。そこにどんな感情が渦巻いているのかは、到底理解はできなかった。
しかし、そこにあるものは決して”美しい”と形容できるものではないことは、嫌でも伝わってきた。
「……どうしたんですか、樹季さん」
感情が籠っているわけでも、何も感じられないわけでもない。
息苦しくなりそうな、気まずさという生易しい言葉では足りない、重さ。
いっそ清々しいほどの負の感情は、眩暈すらも覚える。
樹季はそれらに耐えながら、出来る限りの平然を装い、にこやかな笑みを浮かべた。
「お腹空いてるんでしょ? ご飯できてるから早くいらっしゃい」
「……ああ。うん……ありがとう……すぐ行くよ」
心ここにあらずの様子で、泉光は樹季の言葉に答えた。
樹季はそれ以上、言葉を発することなく、部屋から出ると扉を開けたままにして花乃の待つダイニングへ戻った。
花乃の隣に樹季が座り、二人の向かいに泉光が座る。
泉光は着替えることも、顔の絵具を拭うこともなく、手だけを念入りに洗って席に着いた。
汚れたままの泉光と向き合っている花乃は、怯えるわけでも、眉をひそめるわけでもなく、ただ不思議な物を見る目で見つめていた。
そんな花乃の視線に気づきながらも、気に留める様子はなく、目を向けるわけでもなく、
泉光はひたすら無言で、先ほどのような様子は出さずにすまし顔でいる。
しかし、だからといって花乃に心開いている様子がないことも明白だ。それでも、花乃は泉光を見つめ続けた。
「……なに?」
注がれる視線に、泉光は「鬱陶しい」と言わんばかりの棘を含んだ低い声で訊く。
思わずびくついた花乃は反射的に俯いてしまった。その行動に、泉光はまた苛立ちを覚える。
「……悪い事をしたと思ったら謝るって、誰かに習わなかった……?」
その言葉に、花乃はさらに縮こまってしまう。
「泉光、いい加減になさい。怖がってんじゃない」
「ジロジロ見ておきながら用がないのも、どうかと思いますけど」
「この子、声は出せるけど言葉が話せないの。でも、その代わりにすごいことができるのよ?」
最初は泉光の態度に険しい表情を浮かべていた樹季だが、
花乃の話になるとどこか楽しそうに声を弾ませる。
泉光との温度差が激しいが、気にしていない。
「……それで、その”すごいこと”って? 言葉も使えないのに」
心臓が尖ったもので刺されるような感覚を覚えるが、花乃はただぎゅっと両手を握ってじっとしていた。
樹季は隣に座る花乃の頭をそっと撫でてあげる。
「花乃ちゃん。アタシに見せてくれたみたいに、やってくれるかしら?」
言われた花乃は、樹季を見上げたあと、再び俯く。
少ししてゆっくりと手を出すと、握りしめていた掌を広げた。
するとそこに、小さな青紫色の花が現れた。
突然現れた花に、さすがに泉光も驚いたらしく、花乃の小さな掌の花を見ながら、微かに目を見開いている。
その様子に、樹季は満足げな笑みを浮かべた。
「どう? すごいでしょ?」
「……何したの、それ」
「この子はね、どんな花でも自由に出せるの。
それで、言葉を話せない代わりに花言葉と身振り手振り、あと、表情とかで会話をするのよ。
あら、そういえば、まだ自己紹介してないじゃない!」
説明をしながら、ふと、まだ花乃のことを泉光に紹介していないことに気づいた樹季は笑顔のまま紹介する。
「改めて、この子は花乃ちゃん。花に乃ちって書いて、ひなのって読むんですって。可愛いわよねぇ、ほんと」
「……まあ、別に何でもいいよ。話すことはないし、騒がしくないに越したことはない」
いただきます、と泉光は手を合わせると食事に手を伸ばし始めた。
冷たい態度に、花乃はまた肩を落とす。樹季は深いため息をついたあと、花乃の頭をまた優しく撫でた。
「アタシたちも食べましょ」
花乃はその言葉に頷き、樹季と共に手を合わせる。
いただきます、の合図で言葉に出来ない代わりに頭を下げ、箸を動かした。
食事を終えると、花乃は自分が使った食器を洗い場へと持っていく。
それと共に泉光や樹季の分の食器を持っていき、自ら手伝おうという意思を見せる。
それに樹季は感心した様子を見せた。
「あら~助かるわ~。ほんとにもう、可愛いしいい子だし天使ね?」
「年寄りのおっさんにはありがたいでしょうね」
樹季は泉光の嫌味な言葉や笑みに、一瞬眉間に皺が寄るがすぐに笑顔を保ち直す。
花乃の手前、今日はそう簡単に挑発には乗らないと決めている。
そうとは知らずに、一通り汚れた空の食器を流し台に持って行った花乃は再びテーブルへと戻って来る。
その際に泉光の顔を盗み見ると、再び俯く。
「じゃあ、僕は戻るよ。ご馳走様でした」
泉光がそう言って席から立ち上がろうとした。
気づいた花乃は慌ててティッシュ箱から紙を一枚引き抜くと、
未だ座ったままの泉光に背伸びをして、頬についている絵具をそっと拭う。
突然の行動に、泉光は身動きできずに目を見開いた。
脳裏に、小さな少年が笑顔の少女によって頬をハンカチで拭われるイメージが駆け抜ける。
顔をはっきりと思い出せないその少女は、少年に向かって何かを言うように口を動かしていたが声も言葉も聞き取れない。
駆け抜けたイメージに、泉光は思わず花乃を突き飛ばした。
「ちょ、泉光?!」
樹季も思わず立ち上がり、花乃に駆け寄り、体を起こしてやる。
突き飛ばされた花乃も、「何があったのか分からない」という顔で泉光を見上げていた。
しかし、それは泉光も同じだ。何があったのかは分からない。
ただ、花乃の触れ方や行動に衝撃を覚えたことは確かだった。
泉光は花乃を突き飛ばした手を見たのち、何も言わずにダイニングを出た。
「泉光、ちょっと待ちなさい! どうしたっていうのよ! ちょっと!! 戻ってきなさい!!」
だが、泉光は止まることなく部屋へ戻り、扉を閉めた音が家に響き渡った。
「全くもう、何だって……。花乃ちゃん、大丈夫? 怪我はない?」
言われて、花乃は初めて我に返ったようだった。
それから、慌てたように樹季に顔を向け、「大丈夫」だというように頷く。
安心した樹季は微笑み、花乃をそっと立たせる。
「無事で何よりだわ。……ごめんなさいね、普段は手を出したりする子じゃないの。
様子もおかしかったみたいだし……」
花乃はすぐさま頭を横に振ると、落胆と後悔が入り混じった様子で俯いた。
すると、花乃の手には、太い茎に紫色の小さな花がいくつも咲いている植物が握られていた。
「この匂い……ヒヤシンスかしら?」
俯きながらも小さく頷いた花乃。
紫色のヒヤシンスを持ったまま、先ほど座っていた椅子の上に置いてある本を広げ、それを樹季に見せる。
本は多種のヒヤシンスと共に花言葉などの情報が併せて掲載されていた。
その中に、紫色のヒヤシンスがあり、その花言葉は「ごめんなさい」とある。
「……花乃ちゃん、自分が泉光を怒らせちゃったと思ってる?」
花乃はぎゅっと強くヒヤシンスの茎を握り、また、頷く。
「まあ……そうね……もしかしたら、いきなり顔を拭かれて、びっくりしたのかもしれないわね。
……でもね、大丈夫よ。あなたにはちゃんと、謝れる。そういう気持ちがあるもの。
だから、そんなに悲しい顔をしないでちょうだい? 明日、ちゃんと謝りましょう? アタシが一緒に居てあげるわ」
ようやく顔を上げた花乃は、樹季の言葉に少しだけ笑みを浮かべた。
頷くと、ヒヤシンスの花は見る見るうちに花の形を変え、細長い風鈴のような小さな花になる。色は紫色のままだ。
すぐさま花乃はページをめくり、樹季に示す。
「カンパニュラ……花言葉は……感謝、誠実、節操……。あなたが伝えたいのは、感謝かしら?」
今度は先ほどよりもはっきりと微笑んだ花乃は、カンパニュラを樹季に差し出した。
小さな手からそれを受け取った樹季は笑う。
「どういたしまして」
ひと段落し、ため息をついた樹季は再び花乃を見下ろす。
「さて、花乃ちゃん。あなたの部屋に案内するわ。それから、お風呂の使い方ね」
軽く片目をウィンクさせて言う樹季に、花乃は目を輝かせたと思うと大きく頷いた。
それから、樹季に連れられて、今日から住むことになる部屋へと向かった。
部屋に戻ってきた泉光は扉を閉め、鍵をかける。息を荒げたまま、ゆっくりとその場に座り込んだ。
少女に触れられたときのイメージが強く脳裏に焼き付き、頭から離れない。
「はぁ……はぁ……」
ただダイニングから部屋に戻ってきただけで体力がなくなるほど、泉光も軟弱ではない。
しかし、今は呼吸が整わないほど、心が掻き乱されている。心臓が痛い。肺が引きつりそうだ。
筋肉が張ったような痛みと、忙しなく響く動悸で、余計に呼吸が出来なくなる。
喉が渇ききり、奥から錆び付いた味が滲む。冷や汗が止まらない。
震えが、言いようのない感情が、湧きあがる何かが、ただ、涙が止められない。
焼き付いて離れないあの人の、”彼女”の姿が、少女と重なってしまう。
似すぎていた。何もかも、似すぎていたのだ。だが、少女は別人だ。
少女は、”彼女”が大切にしていたものを、持っていないのだ。”彼女”はもう、いない。
もう二度と会うことのない”彼女”は、どこにもいない。いるはずがない。いなくなってしまったのだから。
「なのに……なんでっ……」
似すぎていたのだ。ただ、それだけだ。一目見たときから、似ていた。それだけだ。
泉光は泣いた。暗い部屋で扉に寄りかかったまま、蹲って座ると嗚咽を抑え、ただ、泣き続けた。
ボーイミーツ・フラワーガール 後編
花乃は夢を見ていた。眩い光の中で、自分よりも小さな子どもと遊ぶ夢。
子どもが花乃に絵を描いては見せ、何かを話している。
それに花乃は微笑み、子どもの頭を撫でてやれば、はにかんでいた。少女か少年かはわからなかった。
だが、どこか懐かしく、切ない。一体、誰なのだろうか。顔をよく見ようと、子どもの頬を包んで顔を上げさせた。
小鳥のさえずりが聞こえる。花乃は天井を見つめていた。
真っ白で広いそれは、カーテンの隙間から入り込むわずかな陽を反射し、全体を明るく照らしていた。
体を起こし、辺りを見渡す。今横になっていたベッド以外には化粧台と椅子があるだけの簡素な部屋。
六畳もあるそこは、小さな少女には十分すぎるほどの広さだった。
花乃はベッドから降りると、窓に歩み寄り、ゆっくりとカーテンを開ける。
視界は真っ白になり、咄嗟に目を瞑った。徐々に瞼の上から光に慣れ、花乃はゆっくりと目を開いた。
広がる景色に眩しさも瞬きも忘れた。
他の住宅からは少し離れた場所に建てられているここからは、綺麗に辺りを見渡せた。
今、花乃がいる二階のこの部屋からは、広い空の下に瓦屋根や屋上のある家々が建ち並んでいることが分かる。
新しい場所で、初めて迎えた朝は快晴とは言えない、灰色がかった青空だったか、日差しは穏やかで過ごしやすい。
花乃は窓から離れると、部屋を出て一階へ向かった。
リビングに出ると、そこには誰もいなかった。
開け放たれたカーテン、大きなはめ殺しの窓から差し込む光で部屋は隅々まで柔らかく照らされていた。
一羽の小鳥の鳴き声が、外でか細く聞こえた。
花乃は壁にかけられた、シンプルなデザインの振り子時計を見る。針は午前七時半を示していた。
いつも目を覚ましている時間だ。しかし、この家にとってはまだ早い時間なのか、泉光と樹季の姿は見えなかった。
与えてもらった部屋で、家の中が動き出すまで大人しくしていようと考えたその時だった。
バニラが焼ける香ばしく、甘い匂いが漂ってきた。嗅いでみると、微かに卵の匂いも混ざり、急にお腹が空いてくる。
匂いの先を辿ると、そこはダイニングへと繋がっていた。花乃は恐る恐る、リビングの隣のダイニングへと向かった。
扉から覗くように見てみると、昨夜夕食を作ったダイニングカウンターの向こうで、
樹季が鼻歌交じりに何かを作っている様子が見えた。
カウンターの上、控えめな、しかし目に入る位置に置かれたガラスコップの中には、昨日あげた花が二輪飾られ、
樹季は時たまそれを視界に捉えると微笑んでいた。
その時、視界の端に映ったものに気づいたように、花乃が覗いている扉に目を向けた。
「あら花乃ちゃん。おはよう、早いのね」
声をかけられた花乃は驚きで一度、扉を閉じそうになったがすぐに落ち着き、再び顔を出した。
それからゆっくりと扉の後ろから出てくると、姿勢を正して頭を下げた。
「はい、おはよう。お腹空いたでしょう? もう少し待ってて」
言われた途端、花乃のお腹が代わりに返事をするようにぐぅと控えめに言った。
樹季がきょとんとし、少し恥ずかしくなるが、次には笑われ、余計に恥ずかしくなる。
「うっふふふ、可愛いわねぇ。すぐに出来るわよ」
俯きながら、花乃は頷く。それから、ゆっくりと顔を上げると、作業を見つめるために樹季の隣にやってきた。
近くにあった折畳みの踏み台を持ってくると、邪魔にならない場所に置き、その上に立った。
ボウルの中にはカスタード色の粘りのある生地が入っていた。
それをお玉でひとすくいすると、バターを溶かした丸いフライパンにゆっくりと流し入れる。
すると、それは綺麗な円を描き、甘いバニラの香りが立ち込めた。
まだ少しぼんやりとしていた頭も冴え、その匂いと綺麗な円に、ときめきを隠せない様子で見つめていた。
フライパンの上で生地はふんわりと膨らむ。両面を焼き過ぎず、しかしきちんと焼目のついた仕上がりにすると、
用意していた皿の上に載せた。花乃の顔と同じくらいの大きさのパンケーキが一枚。樹季は得意気に花乃に皿を渡す。
「はい、どうぞ。おかわり欲しいときは教えてね、何個でも作っちゃうわ」
花乃はひたすら目を輝かせて頷いた。
パンケーキの載った皿をテーブルに運び、樹季があらかじめ用意していたバターと常温の蜂蜜、
冷えたブルーベリージャムも次々とセッティングしていく。
その間にも樹季は次々とパンケーキを焼いては皿に載せ、
最後の一枚はフライパンを持ったままテーブルに向かうと、花乃のパンケーキの上に重ねた。
「もう一枚重ねておくわね。冷めないうちに食べちゃいなさい」
微笑みながらウィンクをされると、花乃は嬉しそうに笑い、頷く。
フライパンをコンロの上に戻した樹季は、花乃のものよりも、
大きめのパンケーキが一枚ずつ載せられた皿を二枚、テーブルのそれぞれの席に置いた。
「これでいいわね。さて、あの夜更かし坊やを起こしてくるわ。花乃ちゃん、席に着いていて」
花乃はどこか不安そうにしながらも頷き、席に着いた。その時。
「誰が坊やですか。これでも成人してますよ、樹季おじさん」
噂をすればなんとやら、泉光がダイニングに入って来た。
樹季は「おじさん」呼ばわりされたことよりも泉光がこの早い時間に目を覚まし、ダイニングにやってきたことに目を見開いた。
「泉光……珍しいじゃない、こんな早くに起きてるなんて……」
「たまたまですよ」
泉光はチラと花乃を見ても何も言わず、自分の席に着く。
それと同時に花乃は立ち上がり、座る泉光の横に行くと両手で服をぎゅっと握った。
その様子を横目で見ながら、冷めた視線を送る。
「……何か用?」
花乃は泉光を真っ直ぐ見た後、綺麗な角度に頭を下げた。
流石に驚いた泉光は、頭を下げる花乃に顔を向ける。そんな彼女の横に、樹季が歩み寄って立っていた。
「昨日のこと、謝りたいんですって。ずっと気にしていたのよ」
微笑み、説明する樹季。
その横で頭を下げながらもどこか震えているようにも見える小さな少女に、泉光は再び目を向けた。
いつまでも頭を下げ続ける花乃を見つめていたが、やがて視線を外す。
「別に、怒っていないよ。僕も突き飛ばしたことは悪いと思ってる。
ただ、いきなり触ったりしないでくれるかな。人間は嫌いなんだ。特に子どもは……」
言いながら再び横目で見てみると、既に顔を上げていた花乃は目を輝かせて泉光を見ていた。
予想に反した反応に、目が微かに動いた。それからすぐに笑みを浮かべた花乃に、途中までの言葉を飲み込んだ。
「ほんと、素直じゃないわねぇ」
「……」
からかうように言う樹季の言葉に眉間に皺を寄せ、泉光はそれ以降、花乃にも樹季にも目を向けず、
呟くように「いただきます」を言うとパンケーキにバターと蜂蜜、ジャムをかけ、一口大に切って食べ始めた。
花乃も樹季も顔を見合わせ、微笑み合うとそれぞれの席に着き、
手を合わせて「いただきます」をしてからそれぞれの好みの味にして食べ始めた。
朝食が終わると、泉光は席から立ち上がった。
「今日から描くから。準備しておいて」
それだけ伝え、ダイニングを出て部屋に戻ってしまった。
食後のホットミルクを飲んでいた花乃は首を傾げ、コーヒーを飲みながら新聞を読んでいた樹季の服を引っ張る。
気づいた樹季は花乃に目を向けた。
「どうしたの、花乃ちゃん」
服を掴む手とは反対の手にはラベンダーが握られ、小首を傾げていた。
「えーっと、ラベンダーは確か……」
花乃は思い出したように席から降り、自分の部屋へ向かおうと扉に向かおうとした。
「そうだわ、”疑問”ね!」
驚いた花乃は樹季を振り返り、座る彼の横に立つと、瞬きを繰り返しながらも頷いた。
そんな花乃の様子に樹季は得意げな顔をすると、その小さな鼻を指で軽く押して離した。
「あなたとお話しがしたくて、昨日ちょっと勉強しちゃった」
その言葉に、花乃はまた目を見開くが、次には嬉しそうに笑い、
ラベンダーを握っていた手にはカンパニュラの花も一緒に握られていた。
「どうしたしまして。それで、そのラベンダーは”さっきの泉光の言葉はどういう意味か”って意味の疑問でいいのかしら?」
何度も頷く花乃の頭を撫でた樹季は微笑む。
「そうね、今日からあなたをモデルに絵を描くってことかしらね。
モデル用の衣装はあるから、着てみてくれる?」
花乃はそれに笑顔で応えた。
食器洗いや片づけを二人で終えた後、泉光の指定したモデル用の衣装を花乃に渡した。
病衣にも見える白い長袖のワンピース。
「サイズ合うか分からないけど、着てみてちょうだい。小さいことはないと思うけど、大きかったら、縫ってあげるわ」
早速、二階の与えられた部屋に服を持って戻った。
身支度も整えて、降りてきた花乃。
汚れ一つない清潔な白い長袖のワンピースは、首元から覗く白い肌とあまり区別がつかなかった。
もともと花乃が着ていたワンピースに酷似しているが、決定的に違うのは、ガウンのように前を紐で留めているという点だった。
樹季は降りてきた花乃の前に立つと顎に手を当て、真剣な眼差しで見つめていた。
視線を注がれ、言いようのない恥ずかしさを覚えるが、職人のように真面目なその目からは視線を外すことができなかった。
ようやく小さなため息をついて微笑んだ樹季に、花乃も緊張が解けて微笑み返した。
「サイズ、ちょっと大きいけど、これくらいがちょうどいいみたいね。
でも、どうしてこんなに質素な衣装を要求したのかしら。
せっかく可愛いんだから、もっと可愛いのにすればいいのにねぇ。あ、花乃ちゃん、胸のところ苦しくない?」
聞かれると花乃は顔を赤くさせ、俯きながら、膨らみを隠そうと自身の胸を潰して抑える。
その様子に樹季は不思議に思ったが、すぐに理解すると「しまった」という顔をする。
「ご、ごめんなさいね? デリカシーのないことだったわね……苦しくないならいいのよ?
本当にごめんなさい、今のことは忘れて?」
胸から手を退けた花乃は頷く。どこか気まずい空気になり、樹季は泉光の部屋まで花乃の背中を押し始めた。
「さ、早く行きましょ、泉光を待たせるとまた文句しか飛んで来ないんだから!」
困惑しながらも進み続け、泉光の部屋の前に立つと、樹季が扉をノックした。
「泉光、入るわよ」
扉を開けて中に入る。
カーテンは閉め切られ、隙間から光が差し込んでいるはずなのに、部屋は不気味なほど薄暗く、静かだった。
そんな僅かな光しか頼りのない中、泉光は床に座り、ベッドに寄りかかりながら本を読んでいた。
樹季たちが来たことには気づいていながらも、気にしている様子はない。
「あんたねぇ……暗いところで本読むんじゃないわよ」
樹季は泉光の許可も待たずに部屋に入ると、真っ直ぐカーテンに向かった。
光だけでなく紫外線まで遮断する厚手の生地を掴む。
両腕を思い切り広げると同時に部屋は光を反射させ、一瞬、目も開けられないほど眩しくなる。
思わず目を強く瞑っていた花乃は、瞼から透ける光に慣れ、ゆっくりと目を開けた。
テラス戸の向こうに広がる景色に息を呑んだ。
雑草が伸び放題でいる中にも小さな花が咲き、
長く放置されているとわかるガーデンテーブルやガーデンチェアにまで蔦が絡まり、落葉と枯葉が散乱し、
鳥やリスといった野生動物が食い荒らしたような跡がそこかしこに残る荒れた中庭。
シンプルで、灌木や雑木を囲むように植えた箱庭のような造りのそこは、おとぎ話の秘密の庭園そのものだった。
「ちょっと泉光、あんた中庭の風景にいるのを描くのよね?」
「そうだけど」
泉光は本から顔を上げることなく樹季の言葉に答える。
「何よ、この荒れ具合! こんなところに女の子を長時間も座らせる気?」
「嫌ならやめてもらっても構わないよ」
ようやく本を閉じ、ベッドの上に放る。
その言葉は樹季に向けてというよりは、扉の前で隠れるように立っている花乃に対しての言葉だった。
立ち上がった泉光の冷めた視線は、真っ直ぐ花乃を突き刺し、言いようのない威圧感を与える。
扉の影から泉光を見上げる桃色の瞳がほんの少し、不安定に揺れた。
それは恐怖や不安ではなく、何か別の感情からくるものだったが、それを理解することは、今の花乃にはできなかった。
意を決した花乃はゆっくりと部屋の中に入る。
文句を言いながら、専用の箒を使って落葉や枯葉を掃いている樹季のいる中庭に裸足で踏み入り、
見た目よりも柔らかな雑草だらけの芝生の上を歩く。水気を帯びてひんやりとした草は、くすぐったくも心地よかった。
「ちょ、花乃ちゃん、裸足なんて危ないわよ!」
だが、花乃は気にすることなく、部屋からは遠すぎず、近すぎない場所で立ち止まる。
くるりと半回転して振り返れば、産毛のように柔らかな長い髪がふわりと舞った。
未だに薄暗い部屋にいる泉光を真っ直ぐに見つめ、微笑んだ。
微かに、泉光の眉が動いた気がした。
しかし、すぐに他所を向いてしまった泉光はイーゼルとキャンバスを持つとテラスに置き、
椅子を持ってくると立てかけたキャンバスの前に座った。
「樹季さん、邪魔だから退いてもらっても?」
「じゃ、邪魔って何よ! 掃除しないあんたの代わりにアタシが……」
「その子、今から描くから。そこにいられると集中できない」
その目は真剣そのもので、樹季は思わず口をつぐんだ。
花乃を見下ろせば、視線に気づいた彼女が樹季と目が合い、微笑む。
それはまるで、「大丈夫」「ちゃんとやるよ」と言うように、安心させるような笑みだった。
そんな表情を見ては何も言えなくなった樹季はため息をつく。
「あまり、無理しちゃだめよ?」
微笑み返し、頭を撫でた樹季は箒を泉光の視界に入らない場所へ置くと、サンダルを脱いで部屋に戻った。
「いい泉光? ちゃんと休憩させるのよ?」
泉光は返事をすることなく、花乃を見つめては何か考え込んでいる様子だった。
真剣で、絵のことしか考えていない目。こうなると、泉光は人の話など微塵も聞いていない。
諦めた樹季は大人しく、泉光の部屋を出て行った。
残された泉光と花乃。ただ見つめられるだけで何も指示がない花乃は、そこで立ちすくみ、徐々に気まずさを覚える。
「……その場に座り込んで。早くして」
ようやく指示を得ると、花乃は慌てたようにその場で丸くなり、座る。
「脚は地面につけて広げて。両脚の間にお尻を落とす座り方、分かるだろう」
花乃は言われた通り、丸くなる座り方から、地面に両脚を広げて折畳み、座り込む体勢になる。
いわゆる女の子座りだ。泉光は満足そうに頷く。それに、花乃は嬉しくなる。
「君、花が出せるんだろう?」
突然の問いに、花乃は理解するのに数秒を要したが、質問の意味が分かると何度か頷く。
「じゃあ、好きな花でいいから、花束を作って両手で持っていて。目を伏せて、花を見つめるようにしてて」
花乃は躊躇いながらも、好きな花を思い浮かべる。
どの花も好きだが、咄嗟に思いついた花が両手から溢れるように出てきた。
紫色の、散房状に偏側性の花を咲かせている。スターチスだ。
スターチスの花束を作り上げた花乃は、それを両手に持って膝の上に載せ、目を伏せるように俯き、花を見つめる。
長く細い睫が細かく揺れ、微かに涙で濡れている。
ほんの一瞬、息を呑んだ泉光だが、すぐに鉛筆を取り出す。
「始めるから、そのまま絶対に動かないように」
言われた花乃は、微かに頷いた。泉光は、キャンバスに下書きを始めた。
太陽が遥か頭上に位置し始める。
時たま、雲が太陽を隠すが、それでも昼となると肌にジリジリとした熱を浴びせてくる。
幸いにも、中庭に差し込む光は、周りの灌木や雑木によって遮られている。
その中心に座り込んで花束を持ったまま動かないでいる花乃には、木漏れ日程度の光しか届かない。
花乃は僅かにも動くことなく、スターチスの花束を見つめる絶妙な俯き加減のまま、既に何時間も経過している。
泉光は絵具を絞り出した木製パレットを左手に、右手で筆を動かし続ける。
キャンバスに下地の色を塗り、その上から色を重ねていく。
ふいに、扉がノックされ、開かれる音が部屋に響いた。
しかし、泉光も花乃もそれに気づくことなく、ただ自身の役目を全うし続ける。
「泉光、花乃ちゃん、入るわよ」
そう言って入ってきたのは、盆に二人分の昼食を載せた樹季。
部屋の中心にあるガラス張りのローテーブルの上に、刻み海苔を振りかけた、たらこスパゲッティの皿を置く。
茹でたてのパスタはバターの艶を帯び、サーモン色のツブツブしたたらこが絡まり、食欲をそそる匂いを漂わせる。
樹季は二人が見向きもしない様子にため息をつき、泉光の隣に立つ。
「お昼、出来てる……」
言いかけた彼の目に飛び込んだのは、初めて見る、泉光の描く人の絵であると同時に、
人形のように時間の止まったまま中庭に座り込む花乃だった。
木漏れ日に照らされた花乃は、存在を逸しているように見えた。
人間ではない、次元を超えた何か別の存在。崇高で純粋な、
見ているだけで生気を吸われそうな、それでいて命すら与えそうな存在。
この世に天使や女神が存在しているのだとしたら、間違いなく、
今の花乃のような姿をしているのだろうと思わせる、圧倒的な存在感。
あまりの神々しさに見惚れるが、すぐに振り払うと花乃の首元に汗が伝っていることに気づいた。
泉光の額にも同じように玉の汗が流れ、しかし、二人はそれを拭うことなくモデルと画家という役割を続けている。
「ちょ、泉光! いったんストップよ、ストップ!」
樹季は、泉光が再び筆で絵具を掬うタイミングで彼の右手を掴んだ。
それでようやく気付いたように、泉光は樹季を見上げる。微かに息を荒げ、汗が止まらずにいる。
「……樹季……さん……」
「あんたまさか、あれからずっと休んでないの!?」
「……」
泉光は答えず、真っ直ぐにキャンバスの絵と見つめ合う。
人間を相手に、これほど集中できるとは、彼も思いもよらなかったのだろう。ざらつくキャンバスをそっと指で撫でた。
「んじゃまさか、花乃ちゃんも……!」
花乃に目を向ければ、彼女もようやく糸が切れたように芝生の上に丸くなって横になっていた。
相当我慢していたのだろう、脚を伸ばすのも一苦労しているようだ。
「花乃ちゃん!」
すぐに花乃に近寄ると、小さな少女を抱き起す。深く呼吸をして、意識が朦朧としている様子だった。
「花乃ちゃん、大丈夫? 今すぐに水飲みましょう、立てる?」
視線が定まらない中、花乃は微笑むと頷く。ゆっくりと起き上がり、ふらつく足で立ち上がる。
しかし、歩く度にふらつき、やっとの思いでテラスに辿り着いた。
その後ろを始終、樹季は不安そうに手を伸ばそうとしては引っ込めることを繰り返す。
泉光はようやくキャンバスから目を離し、ようやくテラスに辿り着いた様子の花乃を椅子に座りながら見ていた。
ぼんやりと、少女がテラスに上がろうとしているのを見ている。
「花乃ちゃん、無理、しなくていいのよ? ほら、手を貸して」
しかし、花乃は首を横に振った。自分の力で部屋まで辿り着こうとしていた。
そのために、樹季の手は再び伸ばすことと引っ込むことを繰り返し始めた。
花乃がようやく腕の力でテラスに上がろうとした瞬間、ふいに体が軽くなった。
顔を上げると目の前には泉光がいたが、彼は何もしていない。
後ろを振り向けば、見かねたらしい樹季が花乃を抱き上げていた。
「もう、見てられないわ。無理しないの、分かった?」
花乃は目を見開くが、すぐに微笑み、頷いた。樹季の手によってローテーブルの前に座らせられた。
次には花乃の両手でようやく掴める大きさのガラスコップに入った、冷えた水を渡された。
「はい、ゆっくり飲みなさい」
言われた通り、渡された水をゆっくりと飲み干す。
すると、いくらか気分も良くなり、朦朧としていた意識もはっきりとしてきた。
改めて泉光を見ると、自身の手を見つめて俯いていた。
そんな泉光の元に樹季が歩み寄り、泉光の肩を掴んで自分の方を向かせた。
それからの行動は、花乃にも理解が追いつかなかった。
大きな音を立てたと思った次の瞬間には、泉光の右頬は赤く腫れあがり、樹季の手も赤くなっていた。
「いい加減にしろよ、クソガキ」
低く荒っぽい声に、花乃は思わず肩を震わせた。
昨日までの樹季からは想像し難いほどに険しい表情と、怒気を帯びた声には、十分な迫力があった。
「いいか、泉光。何がそんなに気に食わないのか知らないが、お前の勝手に花乃ちゃんを巻き込むな。
小さい子どもが長時間、同じ体勢で太陽の下に居れば命の危険があることを忘れるなよ。いいな」
「……」
それでも返事をせず、目を逸らす泉光。それが再び癇に障り、樹季が手を挙げたとき。
脚に重みを感じて下を向いた。
見ると、花乃が小さな体で樹季の長い脚にしがみつき、これ以上、泉光への折檻をさせまいと止めていた。
今にも涙の溢れ出しそうな目で樹季を見上げている。
樹季も泉光も、そんな花乃の様子に微かに驚きを見せていた。
樹季は落ち着きを取り戻した様子で、視線を合わせてしゃがむと頭を撫でた。
「ごめんなさいね、怖かったわよね……アタシが大人げなかったわ」
再び立ち上がると、泉光と向き合う。
「……殴ったことはごめんなさい。でも忘れないでちょうだい。この子の命が、危なかったこと」
「……」
微かに頷いたように見えた。気まずい空気が流れる中、花乃は泉光に濡れたタオルを差し出した。
樹季が一緒に持ってきていたおしぼりだ。それを自分の頬に当てるフリをして、再び泉光に差し出す。
どうやら「これで冷やして」と言っているようだ。
しばらく差し出されたおしぼりを見た後、泉光は首を横に振り、部屋を出て行ってしまった。
花乃は、俯いておしぼりを見つめる。すると、肩にそっと手が置かれ、隣にいる樹季を振り返った。
「お腹、空いたでしょう? お昼食べましょう。泉光なら大丈夫よ、戻ってきたら食べるだろうから」
そう言われると、花乃のお腹は小さな音を立てた。
恥ずかしそうに顔を赤くさせ、お腹を押さえる。樹季はようやく力が抜けたように笑った。
「うっふふ、早く食べちゃいましょうね」
頷いた花乃は、たらこスパゲッティの皿が置かれたローテーブルの前に座り直し、手を合わせてお辞儀をすると食べ始めた。
洗面台で水を出し、鏡を見る。頬は赤く腫れているが樹季も加減はしたのだろう。
痛みは徐々に引いて、それほど酷いというわけではない。それなのに、熱を持ったそこは目立って仕方がなかった。
水で冷やしながら顔を洗う。蛇口をひねって止め、再び鏡を見た。暗く淀んでいた目は、何も見えてはいなかった。
無意識に頬に手を当てる。そうすると、頬が脈打っているように感じた。それからゆっくりと、頬に当てていた手を見つめた。
「……僕は……また……」
あの時、花乃がテラスに上がろうとしたとき、手を伸ばすことを躊躇った。
あの状態では流石に危ないことなど、泉光にも分かった。
だから、どうにかしなくてはと思い、花乃の前に立った。しかし、助けを出すことはできなかった。
助けなくてはならない存在を前にして、泉光は手を差し伸べることができなかったのだ。触れることを、躊躇った。
次第に、泉光の中の感情に抑えがきかなくなっていた。
花乃を見る度に感じる苛立ちも、それとは違う、もっと別な感情も、ただ誰かに似ているというそれだけで抉られる過去の想いも、
すべてが混ざり合い、蝕んだ。
それでも、おしぼりを差し出そうとした小さな手と、柔らかな表情に目の奥が熱く、息苦しくも心地よく感じた。
どう処理をすれば良いのか分からない、向き合いたくない心を、今はただ頬の痛みのせいにするしかなかった。
しばらく頭を冷やした泉光は、微かに空腹も感じ、樹季の用意した昼食をとるために部屋へ戻ることにした。
それから数日。あれから、泉光の態度に微妙な変化が見られた。
朝早くから、花乃をモデルに絵を描き、花乃は体勢から位置まで、初日と変わらないように努めてモデルをこなす。
しかし、一時間ほど経つと泉光は筆を置き、席を立つ。
「飽きた。続きはお昼の後で」
それだけ言い、自身はベッドに寄りかかって座り、本を読み始める。
その間、花乃が何をしていようと我関せずといった様子で読書を続ける。
不愛想だが、それが泉光の気遣いなのだと気付くのにそう時間はかからなかった。
初日には用意されていなかった水やコップが、いつの間にかテラスの上に用意されていたり、
そのまた翌日にはタオルも置かれていたりと、泉光なりの心遣いであると察した。
花乃はそれらに感謝しながら、水を飲み、タオルで汗を拭く。初日以来、対して問題は起きていない。
不器用だが、根は穏やかなのだと、一番初めにこの家に来たとき樹季に言われた言葉を思い出す。
泉光は本当に優しい人物なのだ。そう考えただけで、花乃は少しずつ、泉光と打ち解けられる気がした。
何か出来ることはないか。考えた花乃は、自分に出来ることを考える。今すぐに、泉光に対してできること。
花乃にできることといえば、一つしかない。早速、辺りを見渡す。目に入ったのは、先ほどまで水を飲むのに使っていたコップ。
思いついた様子で笑うと、コップに水を注いだ。
本を読む泉光の元へ、花乃は近づく。
気づいていながらもそちらに目を向けることなく、読書を続ける泉光の横にコップが置かれた。
それからコップに何かを入れた花乃は、すぐに泉光から離れてどこかに行ってしまった。
花乃が去った後に、泉光は気になり、彼女が置いて行ったコップを見た。
水が注がれているそこに、カンパニュラの花が活けてあった。
不審に思い、コップを持ち上げ、花を見る。
視線を感じてテラス戸の方へ目を向ければ、影から見ていた花乃が慌てた様子で顔を引っ込めた。
呆れてため息をつきながら、再び花に目を向ける。紫色の、風鈴のような小さな花がそっと揺れた。
花は嫌いではない。不思議と心安らぎ、泉光の頬が微かに緩んだ。
影からまた覗いていた花乃は、初めて見る泉光の穏やかな表情にくすぐったい気持ちになった。
笑われたような気配にまた花乃に目を向ける。いつまでも笑顔でいる様子に、次第に不機嫌になり、泉光は目を背けた。
「ご飯よー」
その声とともに三人分の昼食を持った樹季が、部屋を開けて入って来た。
ガラス張りのローテーブルを囲んで、三人で昼食にする。これも、ここ数日の習慣だ。
泉光と花乃のぎこちなくも、均衡の取れた画家とモデルの関係も二週間が過ぎた。
ある日、泉光は「気分が乗らない」という理由でその日は絵を描くことを休むことになった。
当然、花乃も休みになり、急にやることがなくなってしまった。
ここに来てからやっていたことと言えば、泉光のモデルや樹季の手伝い、数日に一度、
カンパニュラの花を活けていたコップに花を一輪ずつ増やしては泉光に届けることくらいだ。
花を一輪ずつ増やすと、泉光は必ず気づいて一度だけ、その花を見て表情を柔らかくした。
それを見たくて、花乃は花を贈ることを続けていた。
モミジアオイやユリオプステージー、フヨウ、スズラン、ブバルディア……多種多様な花は、
どうやら泉光を少しでも楽しませているようだと気付いた。
だからと言って、泉光が花乃に心を開いているわけではないことも分かっていた。
花を届ける度に見せる穏やかな表情は、花乃を見る度に曇り、すぐに目をそらしていた。
絵を描いている間に向ける視線にも、痛々しさを覚えた。
それでも、花乃を恨んでいるわけでも憎んでいるわけではないことも、すぐに分かった。
度々、泉光が花乃に触れようとするように手を伸ばす仕草をするのだ。
しかし、すぐにその手は別の物を掴み、最初からそれを取ろうとしていたんだと言い訳するようだった。
そんなこともあり、花乃は決意していた。「泉光と必ず打ち解ける」と。泉光とは上手くやっていける気がした。
これを機に、彼の人間嫌いや子ども嫌いが良くなっていくかもしれない。そう思うと、急に彼と接することが楽しくなっていた。
不愛想に返されても、険しい顔をされても、冷めた視線を送られても、
「きっと仲良くなれる」という根拠のない確信を胸にめげることなく接し続けていた。
今日は、一日休みだ。時間なら有り余っている。この時間を使って、
何か出来ることはないかと花乃はダイニングで本を読みながら考えていた。
「あら、花乃ちゃん。こんなところで、本読んでたの? 退屈じゃない?」
樹季に声をかけられ、花乃は本から顔を上げると微笑み、首を横に振った。
「そう。本を読むのはいいことね。じゃあ、アタシはそんな花乃ちゃんのためにおやつでも作ってあげちゃおうかしら」
すぐに台所の方へと入った樹季はエプロンを首にかけ、紐を腰で縛る。
花乃はその様子を見た後、思いついたように本を置き、樹季の元へ小走りに近寄った。
「どうしたの? 本読んでていいのよ?」
辺りを見渡し、目当てのものを見つけると、近くにあった段ボールの上にのぼり、隅に寄せられていた一冊の本を引っ張り出した。
「あら……花乃ちゃん、レシピ本読みたかったの?」
首を横に振り、その場でパラパラとページをめくり始める。
目的のページを開くと、樹季に思い切り差し出した。思わず仰け反りながらも、ページに書かれている料理を見る。
「花乃ちゃん、これが食べたいの?」
再び首を横に振り、小さな指で載っている写真を指さした後、自身のことを指さす。
数秒、その意味について考え、ようやく理解すると微笑んだ。
「これの作り方、知りたいのね?」
理解されたことに安堵し、満足げに笑った花乃は大きく頷いた。
樹季は身につけたばかりのエプロンを脱ぎ、二人は早速、本に書かれていた材料を買いに買い物に出かけた。
その日の空は、曇っていて、涼しい風が吹いていた。
翌日。外は風が吹き荒れ、雲が低く、遠くで雷が鳴っていた。
暗い灰色は街を覆い、湿った空気が肌に張り付く。テレビの天気予報が、午後からは雷を伴う豪雨になると報じる。
午前の晴れない気分の中、花乃は部屋でいつもの体勢をとりながら、泉光は部屋の中で花乃の絵を描く。
中庭は風が騒がしく、とても外で絵を描けるような天気ではない。
スターチスの花束を伏し目になりながら見つめる花乃を描いたキャンバスに、不機嫌な顔をしながら色を塗っていく。
平筆で絵具を掬っては何度も塗っていく。
それまでキャンバスをなぞるように、慈しむように塗っていたはずなのに、徐々に乱暴に、塗り潰すように筆を動かしていた。
以前よりは打ち解けてきたはずの泉光から、電気で弾かれるような空気が漂う。
遠くの空でまた唸り声が響いた。異変を感じ取り、普段は動かずにいる花乃も顔を上げ、不安の色を浮かべた目を向ける。
それに気づかず、泉光はひたすらキャンバスの中の少女と向き合い、
眉間に皺を寄せ、筆と布が擦れ合う音が荒く響き、歯ぎしりをする。
「違う……違う、違う、全然違う、違う!!」
苛立たしげに低く、怒気を含んだ声で叫ぶ。筆と絵具のパレットを床に落とし、顔を覆い、頭を抱えた。
立ち上がった花乃は泉光に駆け寄り、彼を見上げて見つめていた。
「違う……こんなのあの人じゃない……こんなの……こんなのっ……」
「うー……」
泣き出しそうな声で呟き続ける泉光に、花乃も言いようのない眼差しを向け、声をかける。
ようやく気が付き、花乃を見下ろせば眉間の皺が深くなった。
「何で、勝手に動いてるの……?」
「うぅ……」
威嚇する低い声に花乃の体が強張った。小刻みに震え出すが、それでも泉光を真っ直ぐ見つめ続けた。
泉光はその目にも顔を苦痛に歪め、立ち上がり、描きかけのキャンバスをイーゼルごと突き飛ばした。
キャンバスはイーゼルから離れ、叩きつけられる音とともに遠くに投げ出された。
怯える花乃を見下ろしながら、ついに泉光は声を上げた。
「僕が良いって言ってないのに勝手に動くな! だいたい、お前は一体なんなんだ!
何から何まで、あの人にそっくりで、何で、何であの人の姿で、あの人の仕草で、そんな顔して、やめろ!
何で、何で、何で、なんで! あの人はもういないのに!
お前は、お前はあの人じゃないのに、仕草も姿もあの人で……でも中身は……あの人じゃなくて……
一体なんなんだよ……お前は、お前はっ!!」
言われている言葉の意味など理解できるはずもなく、花乃は震える手を伸ばし、ヒヤシンスの花を差し出す。
いつの間にしていたのか分からない、絆創膏だらけの小さな手に握られたそれに、
余計に癇癪を起した泉光は、花乃の小さな手を弾いた。
「もうこれ以上、僕の心を掻き乱さないでくれっ!
お前を見てると……見てるとっ……痛くて仕方ないんだっ……!」
赤くなった手を抑えながら見つめる花乃と、泉光の目が重なった。
どうしようもなく痛くなるほど、悲しい色をしていた。
それなのに、その奥には優しさを含み、複雑に絡み合い、どうしていいのか分からなくなった。
「出ていけ……! これ以上傷つける前に……! もう、二度と、僕の前にっ……!」
言葉が最後まで聞かず、花乃は逃げるように部屋を出ていく。
廊下で樹季の驚く声が響いていたが、すぐに玄関の重い扉が閉まる音がした。
息を荒げ、泉光は目を覆い、その場に膝をついて座り込んだ。
「あぁ……!!」
叫んでも、その目から涙が流れることはなく、ただ胸を掴み、床を思い切り叩いた。
「ちょっと、泉光どうしたの!? 何があったのよ!!」
異変を知った樹季が、盆にお茶菓子を載せたまま、泉光の部屋に入ると言葉を失った。
倒れたイーゼル、歪んだ描きかけのキャンバス、床で散ったヒヤシンスの匂い、床にひれ伏し抑えの利かなくなった泉光。
近くで雷が落ち、部屋は一瞬、逆光で暗くなる。
樹季は何も言わずに持っていた盆を床に置き、花の散らばったヒヤシンスの元に歩み寄り、
蕾だけになってしまったそれを拾い上げ、笑顔もなく泉光を見つめた。
「……どうしたのよ、泉光」
「……わからない……もう……わからないんだっ……」
泉光はうずくまり、震える手を見つめながら、声を押し殺して答えた。
深くため息をついた樹季は辺りを見渡し、ローテーブルに添えられた、色とりどりの花を見つけた。
新鮮な水の入ったコップに活けられたそれを持ち上げ、そっと花に触れる。
「花乃ちゃん、迎えに行ってあげたら?」
「……どうして……僕が……」
「あんたが、花乃ちゃんのこと好きだからよ」
「僕はっ!」
「違うっていうの?」
初めて顔を上げた泉光に、樹季は真っ直ぐ視線を向けた。
「最初ね、あんたが細かくモデルを指定したところから疑問に思ってたの。
あんなに人間嫌いだったあんたが、細かく指定してきた。
それって、過去にあんたが知り合った人物ってことでしょ? だから、あんなに細かい指定ができた。
いざ連れてきたら、あんたはわけの分からないことを呟き始めた。”あの人”って、ずっと。
あんたは花乃ちゃんに、その”あの人”を見ていた。
でも、それも花乃ちゃんと接してるうちに、あの子自身を見るようになってたんじゃない?
接し方が分からなくなって、それでも健気に真っ直ぐ自分と接そうとするあの子に」
「違うッ! 僕は子どもなんて、人間なんて嫌いだ! 僕が人を好きになるなんて」
「それでもあんた、描き続けたじゃない。ずっと、飽きもせず、あの子を見つめて」
「それはっ……」
「それにもう一つ。あんた、この花、捨てなかったわね。それどころか、水を何度も替えて」
今度こそ、泉光は言葉を失った。心臓が痛むほど脈を打ち、再び抑えつけた。
「アタシ、これを最初に見たのは二週間とちょっと前くらいだったかしら。
それなのにずっと水は綺麗なまま。花も元気いっぱいね。あの子からもらった、この花たち」
「……」
「本当に嫌いなら、とっくに捨ててるし、絵を描くのもやめてる。
無関心でも一緒、水を替えたりしないし、どっちにしろ描くのをやめてる。
だって、あんたはそういう奴だから。自分のしたくないことはしない、興味ないことには興味ない、そんな奴」
返す言葉もないまま、俯いた。絵を描いている途中から気づいていた。
絵が、泉光の心の中にある”あの人”ではなく、花乃自身になっていくことに。それが酷く恐ろしかった。
描くうちに、”あの人”の面影を持ちながらも全く異なる花乃に変わっていくことが。
”あの人”のことを忘れてしまうことが。恐ろしくて仕方がなかった。裏切りになる気がして気が狂いそうだった。
自分が”あの人”を忘れてしまえば、もうこの世には彼女を覚えている人がいなくなってしまいそうで怖くて仕方がなかった。
幸せになることが怖かった。花乃を傷つけることで保とうとした。それが無意味だと知りながら。
「どうせ、あんたのことだから、花乃ちゃんを好きだと思ってしまえば、
あんたの言う”あの人”を忘れちゃうんじゃないかとか考えてるんでしょ」
図星を突かれ、泉光の動きが止まる。
「馬鹿ねぇ、ほんと。そんな長い間、想い続けてた人を忘れるなんてできるわけないじゃない。
どんなに幸せになったって、どんなに人を愛したって、昔想っていた本気の相手は、忘れないものよ。何年経ってもね」
項垂れ続ける泉光の横にしゃがんだ樹季は、花弁のないヒヤシンスとコップの花たちを泉光の目の前に置いた。
「このフヨウの花言葉、知ってる?」
そう言って指差したのは、アオイに形の似た全体が桃色の花。真ん中がワイン色の、愛らしい花だ。
「花言葉はね、繊細な美しさ」
項垂れていた泉光の頭が、微かに上がった。
「で、このブバルディアは親交、こっちの黄色いユリオプステージーは円満な関係、
スズランは幸福の訪れ、モミジアオイは温和。そしてカンパニュラは、感謝、よ」
既に顔を上げた泉光は、花を見つめ、小刻みに震える手でそっと、怯えるように触れた。
花弁は静かに揺れ、決して泉光を拒むことなく、指と触れ合った。
「全部、あんたに向けての言葉なのよ。あの子が唯一使える、言葉なの」
「こと……ば……」
「そして、こっちの散ってしまったヒヤシンス。これ、ごめんなさいって意味よ」
「僕……は……僕は……」
「あの子、ずっとあんたと仲良くしたがってたわ。これ」
一度立ち上がり、泉光の傍から離れた樹季が持ってきたのは、盆に載せていた一皿のお茶菓子、
シナモンの香りが心地よいアップルパイだ。
しかし、売っていたものにしては歪で、樹季が作ったにしては不慣れなものであることが一目で分かった。
「花乃ちゃんがね、昨日、急にこれを作りたいって。きっと、あんたに何かしたかったんでしょうね。
アタシには一切手伝わないでって言うみたいに必死にジェスチャーされて。
それで、口頭だけで作り方を一つずつその場で教えて、あの子、全部一人で作ったの。
歪よね。味も、ちょっと甘すぎちゃって。手もいっぱい切ってね。だけど、頑張って作ってた。
あんたのために。不思議よね、アタシ、一言も言ってないのに、あんたの好物当てちゃうんだから」
中の甘く煮詰めたリンゴとあんずのジャムが生地からはみ出し、形は崩れバラバラで、
見た目はとてもじゃないがおいしそうには見えなかった。
それでも、弾いたあの小さな絆創膏だらけの手や、真っ直ぐに見つめる桃色の瞳、
花を差し出す度に笑う花乃が、どうしようもなく愛おしくて。
目の前の不出来なアップルパイも、今まで見てきたどんな食べ物よりも美しく、おいしそうに見えた。
立ち上った泉光は真っ直ぐに玄関へと走った。
靴も履かずに扉を開ければ、目の前が見えないほどの雨が降っていた。
しかし、泉光はその中に傘も持たずに飛び込んだ。
残った樹季は深いため息をつき、呆れたように笑った。
「ほんと、お馬鹿なガキねぇ」
呟き、イーゼルを立て直した。
泉光はあてもなく、豪雨の中を走り続けた。視界がぼやけるほどの雨。
時たま通る車のライトのみが明るい。衣服は水を吸って重く、張り付いて動きにくい。
冷たい雨は体温を奪い、強く降り注いでは体力も奪っていく。それでも、泉光は走り続けた。
我武者羅に、一心に、小さな少女の、花のようなあの子の姿を探して。
どれくらい走っただろう。分からなくなるほど、ただ夢中で走り続けていた体は限界を訴え始める。
もともと外にはほとんど出ない。体力など限られていた。
しかし、泉光は体の限界など知らないフリをして走っては止まり、ふらついては歩くことを繰り返す。
この雨の中、帰る場所もなく彷徨っているのではないだろうか。
小さな身一つで、誰もいない中、佇んでいるのではないだろうか。たったひとりで、震えているのではないか。
そのきっかけを作ってしまったのは自分であることを理解しながら、泉光は必死に目を凝らした。
あの小さな体で行ける場所など限られている。そう遠くには行っていないはずだ。
早く探してあげなくては。謝らなくては。伝えないといけないこともある。今度こそ、伸ばさないといけない手がある。
今度こそ、守らないといけない約束がある。見つけてあげなくてはいけない。
それが、少女を傷つけてしまった自分の役目。そして、もう二度と失いたくない自分の気持ちへの答えだ。
再び走り出した泉光は、森林公園に向かった。当たり前だが人の姿どころか、動物の影すらない。
それでも泉光は中を探し回った。案の定、誰もいるはずもなかった。
別の場所を探しに行こうとしたその時、泉光の視界が小さな靴を捉えた気がした。
近づいて見ると、公園と森林を隔てる低い柵の目の前に、片方だけの小さなサンダルが泥だらけになって転がっていた。
泉光は、初めて花乃が家に来た時に履いていたものだと直感すると、柵を越えて森林の中へと走った。
奥へ奥へと、暗い木々の間を走る。
どうやら一般人が中に入ることは想定されていないらしく、道らしい道はなかった。
それでも、泉光の片手に収まるほど小さなサンダルを握ったまま、小さな人影を探し続けた。
心臓が痛い。呼吸が苦しい。体は疲労を訴え、重い服を引きずって走る。
長い時間にも思えるほど走り続け、泉光はようやく、拓けた場所に出た。
その頃には、雨も家を出てきたときよりも弱くなっていた。泥だらけになった靴下だけの足のまま、泉光は辺りを見渡した。
すると、大きな切り株に丸くなって座り込む、一人の少女を見つけた。
片方にはサンダルを履いているが、もう片方は裸足で汚れていた。
ようやく見つけた、小さな少女に、泉光は足音を立てながら近づいた。
音に気が付いた花乃は、ゆっくりと顔を上げ、目の前の人物の顔を見上げた。
その目は驚愕で見開き、理解できないと言いたげに口を開けていた。
深く息を吐いて安堵した泉光は花乃の目の前に膝をつく。それに合わせて、花乃も泉光と顔を合わせるように向き合った。
泉光は、握りしめていたサンダルを、切り株からぶら下げていた裸足の足に履かせた。
居場所を見つけたサンダルはぴったりとはまった。
切り株から恐る恐る降りて立ち上がった花乃は、
小さな手を泉光の頬に当てようとして止まり、ゆっくりと引っ込めた。その次の瞬間。
凍えた体は温かく包まれ、細い体は折れそうなほど強く抱きしめられ、
小さな頭は薄くも逞しい胸に押さえつけられ、泉光の心臓の鼓動がよく聞こえた。
驚くことしかできない花乃が顔を上げれば、頬に雨とは違う、生暖かな雫が滴った。
泉光の顔を見れば、子どものように涙を溢れさせながら、花乃を見つめていた。
「ごめん……ね……ごめんね……ごめん……ごめんっ……」
花乃を強く抱きしめながら、泉光はただ謝り続けた。
傷つけてごめんね、身勝手でごめんね、酷いことを言ってごめんね、たくさんたくさん、ごめんね。
君を離して、ごめんね。多くの謝罪が、花乃の心に、泉光の涙と共に滲んでいく。
「……ありがとうっ……!」
向き合おうとしてくれて。たくさんの花をくれて。アップルパイを焼いてくれて。
何度でも笑ってくれて。たくさんの言葉をくれて。”あの人”を思い出させてくれて。僕とまた、出会ってくれて。
「ありがとう……!」
花乃の大きな桃色の瞳からは、次から次へと想いが溢れた。泉光を抱きしめ返し、背中をさする。
それから花乃は離れると、彼をそっと胸に抱きしめた。泉光は、花乃に縋るように抱き付き続け、胸に顔を埋める。
涙が止まらずにいながらも、花乃は微笑み、そっと泉光の頭を撫でた。
“だいじょうぶ、だいじょうぶ”
声は聞こえない。それでも、そう言ってくれているのだと確信できた。泉光は、泣き続けた。
花乃はただ、その小さな手で包み込んだ。一つの切り株と、静かな雨が、二人の傍に寄り添っていた。
僕と私とアタシの始まり
しばらくすると、雨は止んでいた。
泉光に膝枕をしながら、彼の頭を撫でていた花乃はそれに気が付くと、空を見上げた。
いつの間にか澄んだ茜色の空が広がっていた。
泣き止んだ泉光は目を開け、花乃の膝の上で、空を見上げて目を細める。
ようやく体を起こし、花乃と向き合うと片膝をついて手を差し出した。
「……帰ろう、花乃」
差し出された大きな手と、微笑む泉光を交互に見つめ、幸せそうに笑った花乃はその手を取った。
立ち上がった泉光と手を繋ぎ、森林を抜ける。
行きは長く感じた道も、帰りはすぐに元の公園に出ることができた。
改めて見渡せば、大きな水溜まりがそこら中にでき、空の茜色を映していた。
また別の水溜まりには、病院の看板が映し出され、泉光は顔を上げた。
目の前に大きな総合病院を見ると、顔をしかめた。
隣で手を繋ぐ花乃を見れば、同じように病院を見上げて泉光の後ろに隠れた。
「……病院は嫌い?」
聞かれた花乃は、俯くと微かに頷く。
「……僕も、病院は大嫌いだよ」
震える小さな手を二度と離さないように強く握り、泉光は歩き出した。
「行こう」
花乃はただ、引かれるままに歩き出した。
家に着く頃には満天の星が姿を見せ、赤色は夜に溶け込み、次の空へと向かっていた。
二人の帰りを待っていた樹季が玄関を開けると、
ずぶ濡れで汚れながら、固く手を繋ぐ姿に微笑みながら呆れてため息をついた。
「おかえり。さっさとお風呂、入ってらっしゃい。用意できてるから。風邪引くわよ」
「……樹季さん」
「何よ」
「……ありがとう」
泉光からの素直な感謝など、しばらく聞いた覚えのなかった樹季は微かに目を見開いたが、すぐに台所へと向かう。
「どういたしまして。ほら、早くお入り。ご飯も出来てるわ。あと、今日のデザートは花乃ちゃんの作ったアップルパイね」
泉光と花乃は顔を見合わせた。花乃が笑えば、泉光も笑った。
二人は家に入ると、玄関の扉を閉めた。
夜。風呂を終え、夕食も済んだどころで、花乃は疲れからかリビングのソファーで眠ってしまった。
それを見た泉光は花乃を抱え上げ、そっと自分の部屋のベッドに寝かせた。
ぐっすりと安らいだ表情で眠り、寝息を立てている。微笑んだ泉光は、布団をかけた。
ふと、アトリエにしているもう半分のスペースが気になり、目を向ける。
倒したはずのイーゼルが立て直され、その上に少し歪んだ描きかけのキャンバスが立てかけられていた。
絵に近づき、ざらつく布を指で撫でる。
「……もう……いない……」
もう、それを悲しいとは思わなかった。ただ、寂しかった。
いないと頭で理解していても、長年、心が受け入れられなかった。
それでも、今なら素直に、もういないのだと、受け入れることが出来た。
それは忘れるというわけではなく、泉光の中で区切りがついたということに過ぎなかった。
似ているからという理由だけではないと、今なら自信を持って言える。花乃は彼女の代わりではない。
外見は似ていても、花乃と彼女は別人だ。花乃は花乃、彼女は彼女。ようやく、気持ちにケリを付けることが出来た。
「泉光、入るわよ」
その声と共に、両手に湯気の立ったマグカップを持った樹季が部屋に入った。
花乃がベッドで寝ていることに気が付くと微笑み、音を立てないように泉光の傍に寄る。
「コーヒー。あったまるわよ」
「……もらうよ」
カップを受け取った泉光は、一口含むと再び絵と向き合った。
コーヒーを流し込みながら同じように絵に目を向ける。
「……歪んじゃったわね」
「うん……」
「描くの?」
「うん」
「そう」
再びカップに口を付け始めた樹季。
泉光がはっきりと返事をすることも珍しかったが、ここ最近は珍しいことばかりでもう驚くことはしなかった。
「……ねえ、樹季さん」
「んー?」
「……花言葉の本……持ってない?」
泉光の表情を見れば、どこか気恥ずかしそうに、目を合わせないようにしていた。
過去に一度しか見たことのなかったその表情に、樹季は笑った。
「ええ、あるわよ。アタシもちょっとずつ覚えてたから。でも、なかなか大変」
「おじさんには大変でしょうね」
「あ? 喧嘩売ってんの? 花言葉の本、絶対あんたに貸さないから」
「……すみません、でした」
今までこんなにも素直に謝ったことのなかった泉光からの言葉に、樹季は思わず飲んでいたコーヒーを噴き出しそうになった。
素直に謝ってでも、どうしても読みたいのだろう。
それほどまでに本気でいる泉光は初めて見たかもしれない。
「分かったわよ。あんたに素直に謝られるって、気持ち悪いわね。あとで本、持ってくるわ」
「出来れば今、持ってきてくれない?」
「……はいはい、ちょっと待ちなさい」
深いため息を吐いた樹季は部屋を出た。
数分すれば、持っていたマグカップの代わりに辞書ほどの厚さの本を差し出した。
「随分……分厚いんだね」
「世界にはまだ発見されてないだろう植物も多いんじゃないかしら。
これからきっと、もっと分厚くなるわよ。あとこれ、花乃ちゃんが持ってた本と同じ」
「……これ、全部覚えてるんだね」
「でしょうね。ページまで覚えてる。何度もめくられた跡もあってボロボロだったし」
「今夜、一晩預かるよ」
「あら、気が済んだらでいいわよ」
「……どうも」
「アタシも頑張って覚えなきゃね。あの子とお話しするために」
樹季は泉光の手からマグカップを取り上げた。
「それじゃ、おやすみなさい。あんまり遅くなっちゃダメよ」
泉光と本を残し、樹季は部屋を出た。
泉光は早速、花乃の眠るベッドに寄りかかりながら、最初のページから読んでいく。
何時間が経っただろう。夜は更け込み、泉光の部屋にはサイドランプの暖色の明かりだけが灯っていた。
休まず読み進めたはずだが、まだ三割ほどにしか満たない。残り七割。
流石に目は疲れを訴え始め、目を瞑った泉光は静かに休ませる。息を吐き、瞼の上を指で押さえた。
微かに、寄りかかっているベッドの上で眠る花乃が身じろぎした気がした。
視線を向ければ、寝返りを打ち、華奢な肩は息をする度に上下する。
緩やかに波打つ産毛同然の長い髪は、小さな顔にかかり、花弁のように繊細で柔らかな頬をくすぐっていた。
暖色の人工光の下でも、稲穂にも似たベージュ色の髪は艶を帯び、輝く。
ベッドに音を立てずに上がった泉光は、その頬にかかった髪を指先で、壊れ物を扱うように払った。
掌に収まるほど小さな頬に手を当て、
少しでも力を入れてしまえば崩れてしまいそうな危うさと脆さに慎重になりながら、そっと撫でた。
安らかに眠る横顔に目を細め、自然と口元が緩まった。
眠る花乃は温かさを感じようとするように、泉光の手に顔を押し付けて眠り続ける。
「……花乃」
呟き、頬を撫でてやる。すると、花乃は眠りながらも笑みを浮かべ、泉光の手に縋った。
長い睫が小刻みに震え、幸せそうに眠る。
「おやすみ、花乃」
白い頬に唇を寄せ、再びベッドを降りて先ほどと同じ体勢になり、本の続きのページをめくる。
花乃がモデルをする際に、花束にして持っていたスターチスの花だ。花言葉は、永遠に変わらない。
泉光にとって、何か意味を持つ言葉に思えた。同時に、これから先、今度こそ、永遠に変わらずに。
ページをめくっていき、花と花言葉に目を通していく。
いつの間にか、章の区切りまで進んでいた。この章の最後に載っていたのは、見覚えのある花だった。
一番初め、花乃に不思議な力があると知った日に、小さな掌に握られていた花だ。
紫色の、小さな花、ツルニチニチソウ。
「花言葉は……追憶……」
追憶。たった二文字の単語が、泉光に微かな違和感を与えた。
しかし、その正体はいくら考えたところで、分かるはずもなかった。
泉光は、正解を導き出せないときに感じる、もどかしさを拭い去るように次の章へと進む。
夜は息をひそめながら、その色を濃く、深くしていった。
太陽が昇った。朝陽がカーテンの隙間から差し込み、樹季の瞼を刺激する。
眩しさに目を開けた樹季は、体を起こすと前髪をかき上げた。
「……さて」
ベッドから降り、カーテンを勢いよく開く。全身に心地よい日光を浴び、体が活動を始め、頭が目を覚ましていく。
窓の前で伸びをした樹季は、腕を下げるのと同時に思いきり息を吐く。
時間は朝の六時半。二人が起き出す前に、やるべきことを終わらせる必要がある。
部屋を出て下に降り、リビングのカーテンも開け放つ。
燦々と部屋を照らし出し、隅々まで朝陽が降り注いだ。清々しい朝だ。
「いい朝だわ。いいことありそうね」
呟き、微笑んだ樹季は台所に入り、朝食の準備を始めた。
朝食を作り終え、時間は午前七時。いつもなら、今は泉光の部屋で寝かされているだろう花乃が起き出す時間だ。
その数十分後に泉光が顔を出し、三人で朝食を取る。それが、花乃が来てからの、この家の日常だ。
しかし、今日は七時を二十分過ぎても、花乃は姿を現さない。それどころか、泉光も顔を出さない。
昨夜のことで、二人は相当疲れているのだろうか。
それとも、すぐに風呂に入ったとはいえ、雨に打たれてずぶ濡れになったのだ。風邪でも引いているのだろうか。
心配になった樹季は、朝食にラップをかけると急いで泉光の部屋に向かう。
自然と足早になり、泉光の部屋の扉を目の前にすると、ノックする。
「泉光、入るわよ」
返事も聞かずに、樹季は勢いよく扉を開け放つ。そこで見た光景に、思わず息を呑む。
「ひなは本当に小さいね。花みたい」
泉光は花乃を膝に乗せて床に座り込みながら、そっとその柔らかでもちもちとした頬を撫でていた。
抵抗することなく、ただ困惑しながらも頬をほんのりと赤くさせ、
その色と同じ色のボタンの花を胸辺りで控えめに、手に握っていた。ボタンの花言葉は恥じらい。
泉光は目を細めて微笑み、花乃の頬を撫でていた手は彼女の頭を撫で始める。
「恥ずかしいの? 僕は好きだよ」
その言葉に、花乃ははにかみ、ボタンで顔を隠してしまった。それにくすくすと笑う泉光。
樹季は言葉を失う。昨日の昼までの態度とは別人のように変わった泉光に、目が痙攣し、表情も困惑と、その気味の悪さに歪む。
「み……う……?」
ようやく絞り出した声も微かにしか響かない。
しかし、運よく気が付いた泉光は扉の前に立つ樹季を見ると、先ほどとは変わり、いつものすました顔をする。
「あぁ、樹季さん。おはようございます。何か用ですか?」
「え……あ……いや……何か用っていうか、もうご飯できてるんだけど……というか……あんた、誰……?」
「……僕だけど。とうとう呆け始めましたか?」
「失敬ね! アタシはまだまだ若いわよ!」
つい、いつもの癖で言い返した樹季は我に返った。
改めて泉光の様子を見てみると、やはり今までとは正反対の態度に違和感を覚えてしまう。
仲良くなったことは良いことだが、少し急すぎる。樹季は困惑を隠しきれないまま、首を傾げた。
人に対して、こんなにも穏やかでいる彼は初めてだった。
長年、泉光と共に生活しているが、彼が樹季に対してこれほど心を開いたことは、ほとんどなかった。
それどころか、始終、顔を緩ませている泉光など、一生涯ないことだと思っていただけに、
今回の彼の様子は、樹季には異物といって差し支えない。
未だに困惑は消えないものの、花乃が嫌がっている様子もなく、
泉光も可愛がり始めたことに関しては安堵し、樹季は長く息を吐く。
「はぁー……。何でもいいわ、仲良くなったならそれが一番よ」
考えることに疲れた様子で、半ば思考を放棄し、呟く。
しばらく花乃を膝の上で可愛がる泉光と、それに様々な反応を示す花乃を眺めていたが、
いつまでも花乃を離す様子がないことに、流石の樹季も微笑ましさや呆れを通り越して危険を感じ始め、
手を叩いて二人の注目を集めた。
「はいはい、仲良しなのは分かったわ。朝ご飯できてるんだから、さっさと食べにきなさい」
そう言って先に部屋を立ち去ろうとして、ふと気づいたように樹季は立ち止まった。
「そういえば、泉光、あんたさっき、花見ただけで会話……」
振り返った瞬間、いつの間にか後ろにいて花乃と手を繋ぐ泉光が、樹季に借りた花言葉の本を押し付けた。
「覚えたよ。もう必要ない」
「覚えたって、あんた一晩で……!?」
泉光は答えず、ただ一瞬だけ、樹季に微笑んだ気がした。
いつもとは違う泉光に、いつものように振り回される樹季。
それでも、彼が変わろうとしていることを感じ取り、樹季は笑みを浮かべた。
ダイニングに向かう後ろ姿を見ながら、呆れてため息をつく。
「流石ね」
好きなことには一途になれる泉光の長所だ。一見、無理難題に思えることでも、すぐにこなしてしまう。
しかも、それを完全に自分のものにしてしまえる。
花乃と会話をしたい、その思いだけで、彼は辞書のように分厚い本の内容を網羅してしまったのだ。それも、たった一晩で。
樹季は二人のあとに続いて、ダイニングへと向かった。
三人は席に着く。昨日までは樹季の隣に座っていた花乃も、今日は泉光の隣に椅子が並べられている。
ふと隣を見た泉光と、その視線に気がついた花乃は顔を合わせた。泉光の優しい笑みに、花乃はつられて微笑んだ。
その様子を黙って見ていた樹季は、未だに泉光の態度に違和感を覚えながらも、顔を合わせて笑い合う二人を優しく見つめていた。
「さ、手を合わせて」
樹季が合図をすれば、二人は素直に手を合わせる。
「いただきます」
「いただきます……食べよう、ひな」
「うー!」
お辞儀をした花乃は、言われると嬉しそうな声を出した。
その愛らしさに、泉光は彼女の頭を撫でる。
「へぇ、花乃ちゃんだから“ひな”ね。じゃあ、アタシもひなちゃんって呼んでいいかしら?」
花乃は樹季に顔を向けると、笑顔で頷く。
小さな手には、真ん中に橙色を灯した紫の花弁の花が握られている。
「あら。えっと、その花は……」
「サフラン。花言葉は陽気、歓喜。ひなは、喜びを伝えたいんだね」
間を空けることなく、花を見た途端に花の名前と花言葉まで迷うことなく答えた泉光に、
花乃は頬がほんのり赤くなるほどの笑顔を見せる。
「あんた……ほんとに一晩で全部……」
「ひなと、ちゃんと話がしたいから。当たり前だろう?」
その言葉に、樹季は僅かに驚きの目を向けるが、すぐに目を細め、愚問だったことを反省した。
「そうね。アタシも頑張って早く覚えるわ。ひなちゃんと、ちゃんとお話したいもの」
「あうー!」
「ふふっ。ひな、可愛い」
その日の朝食は、どこかくすぐったくて、それでも、穏やかで優しい味がした。
******************
「もう、あれから一年半なのね」
呟いた樹季は、一緒に眠ってしまった泉光と花乃を見つめ、微笑んだ。
思えば、あれから少しずつ、泉光は変わった。
それが良いか悪いかは分からないが、本人たちが笑っている、それでいいと思えた。
彼らが幸せで、それを見守れることが、幸せだとはっきり言える。
「アタシも、変わったのかしら。そうだといいわね。
……あんたはただ、こんな幸せがほしかったのかしら……大事な家族をずっと見守っていられる幸せ。
……ねえ、姉さん」
微かに揺らいだ瞳は、髪の長い女性の影を見た気がした。
それも瞬きをしてしまえばすぐに消え、残ったのは、無垢な顔で眠り続ける二人の“家族”。
「……さて、アタシも仕事に戻りますか。あの名刺、役に立つものね」
樹季は、とある研究所から依頼されたポスター作製のため、自室へ戻った。
これは、ひねくれた彼と、不思議な彼女と、優しい彼の、大切な日々のお話。
花を手向けに
陽は長くなり、肌をジリジリと焼き付ける刺激的な日差しは弱まることを知らない。
少し前までは梅雨の時期で、連日振り続けた雨は止んだが、
晴れた空の下で湿気を兼ね備えた空気の中にいると蒸し焼きにされているような暑さに参った。
薄着をした思春期前の子どもたちが、長い休みを謳歌し、
甲高い声を住宅街に響かせてこの炎天下の中を駆けまわり、
植木に住み着いた蝉の鳴き声の重なりは、メロディのない合唱のようで煩わしい。
耳にいつまでも残る音の数々が響く中庭に、人影はなかった。
飛んできたスズメや、普段はそんなスズメを狩ろうとする迷い猫も、今は大人しく雑木の木陰で休息を取っていた。
二階の部屋の窓や、他の窓は採光のために開け放たれているというのに、テラス戸は閉め切られていた。
ガラスは結露を起こし白く曇っている。部屋の中はカーテンに遮られ、外から覗くこともできない。
テラス戸の向こう側、部屋の中は冷たい人工風が充満し、
季節は真夏だというのにそこだけ初冬のように肌寒かった。
気温差でガラスは白く曇り、水滴が競うように次々とガラスの表面を滑り落ちていき、下に小さな水溜まりを作っていく。
風を吹かせる機械は、静かなモーター音を立て、ただ文字通り機械的に部屋全体を冷やしている。
一人の青年が、ベッドに寄りかかり、本を読んでいた。
憂い顔で、気だるげに伏せられた目は黙々と文章を追っていた。
時おり、その痩身からは想像のつかないほど異様に膨らんだシャツが、
生き物のように蠢いても、彼は動じることなくページをめくり、本を読み進める。
「泉光! いい加減、出てきなさい!」
声とともに、部屋の扉が開かれた。
すると突然、廊下から本来の生温い風が入り込み、べたつくような空気が出来上がる。
さすがに泉光もピクリと目を動かしたと思うと、ゆっくりと本から顔を上げる。
「……樹季さん、さっさと扉、閉めてもらえませんか?」
不機嫌に仁王立ちする樹季に、泉光も不機嫌な声で返す。
深いため息をついた樹季は、部屋に入ると扉を閉める。
少しすると、部屋の中は再び冷凍庫のように冷え始める。
樹季は体を震わせ、自身を抱きしめるように腕を組んだ。
「な、何よ、これ、寒すぎるわよ?」
「出口は先ほど閉めた扉からどうぞ」
「あんたねぇ……。いいから、部屋から出なさい!
適度に外に出ないと、その軟弱の体がまた軟弱になるわよ」
「馬鹿暑い外に馬鹿みたいに出て行って馬鹿みたいに過ごすなんて、ただの馬鹿だよ」
「あんた世の中の人たちに謝りなさいよ」
「僕は本当のことを言ってるだけさ」
泉光は既に樹季から目を離し、再び本に目を向けていた。
呆れ気味の樹季は少しの間、その様子を観察していたが、ふとあることに気づくと辺りを見渡す。
「あら、そういえば、ひなちゃんはどこなの?
あんたがひなちゃんから目を離すなんて珍しいわね?」
「ん、あぁ、ひななら……」
言いかけると、泉光の異様なまでに膨らんでいたシャツが再び蠢き始め、
彼の開いたシャツの首元から、小さな少女の頭が出てきた。
「ここにいるよ」
「あんたどこにひなちゃん入れてんのよ!!」
「僕たちは今一つになって……」
「ひなちゃん、今すぐ出ておいで!」
花乃は言われた通り、再び泉光のシャツの中に潜り込んだと思うと、ゆっくりと裾のほうから出てきた。
白いノースリーブのワンピースに身を包み、太腿まである緩いウェーブのかかったベージュの髪がふわりと揺れ、
潤んで澄んだ桃色の目は、眠気を帯びていた。
「あぁ……ひなの温もりが……」
「あんたこの暑さでよく温もりを求められるわね」
「僕が求めたわけじゃないよ。ひなが寒いみたいだったから、僕の胸の中で温めていたんだ」
「黙りなさい、ロリコン変態野郎」
「僕が愛しているのは花乃だけで、ロリなら誰でもいい奴らと一緒にしないでくれる?」
「というか、寒がってるならエアコンの温度上げてあげなさいよ」
「上げたら僕に近づかなくなるだろう?」
「温度上げるわねー」
樹季は泉光の言い分を無視すると、ガラス張りのローテーブルに置いてあったエアコンのリモコンを操作し、
気温を上げた。部屋はすぐに暑くも寒くもない温度になり、花乃は機嫌よく、泉光の隣に座ると、同じように本を読み始めた。
「全くもう……外には出ない、ひなちゃんにはセクハラする、人の話は聞かない。
泉光、あんた大人でしょ? しっかりしなさい」
「気が向いたらね」
「今すぐ気が向きなさい」
花乃は大人二人のやりとりに目を向け、首を傾げた。
視線に気づいた樹季が微笑みかければ、花乃もそれに笑顔で応える。
それにホッとため息をついた樹季は一度気持ちを落ち着けると、本に目を落としたままの泉光の前に立った。
「泉光」
「なんですか」
「出かけるわよ。準備なさい」
「はい?」
初めて驚きの反応を見せた泉光は、目の前に立つ樹季を見上げた。
樹季は泉光を見下ろしたまま、薄らと口角を上げた。
「ひなちゃんも。今日は遠出するわよ」
「なんで」
「夏と言えば?」
「エアコンきいた部屋で本を読む」
「そういうの、求めてないわ」
冷たく言い放たれ、いつもなら気にしない泉光もどこか不機嫌な顔をした。
「もう、子どもじゃないんだからちゃんと答え……」
「墓参り」
その言葉に、樹季だけでなく花乃も動きを止めた。
隣に座る泉光を、ゆっくりと見上げる。
その横顔は、いつものと変わらない憂いと儚さを含んでいたが、寂しさが見えた気がした。
「夏には墓参り、なんでしょう?」
「……アタシはもっと夏祭りとか、そういうものが出てくると思ってたわ」
「僕がそういうの興味ないの、知ってるでしょう」
「夏祭りに行けば、ひなちゃんの浴衣姿が見れるわよ?」
「樹季さん、近くでやる夏祭りってある?」
花乃の浴衣の話を聞いた途端に、掌返しをした。
既にいつもの泉光に戻っていて、静かに泉光を見上げていた花乃は再び首を傾げた。
「でも、そうね……墓参りよ」
「それで、なんで僕たちまで墓参りに?」
「あなたたちに、会ってほしい人がいるのよ」
「樹季さんのご家族と僕たちにはなんの関係もないですよ」
「あんた冷たいわねぇ、一緒に住んでる以上はアタシの保護下にいるのよ」
「僕はもう大人なので保護は必要ありませんよ」
「大人は自分で身の回りのことするのよ?」
「子どもをいじめないでください」
「こんの、いけしゃあしゃあと!」
樹季は憎らし気に泉光を睨みつけるが、すぐに興味を失くす。
「まあ、今はいいわ。とにかく、これから行くから、準備して」
「だから僕たちは関係ないって」
頑なに断ろうとする泉光のシャツの袖が引かれた。
隣を見ると、花乃が泉光のシャツを掴み、寂しそうな目を向けていた。
いつの間にか、シャツを掴んでいる手とは別の手に、星型に五枚に花弁が裂けた、赤く小さい花の集まりを持っていた。
ペンタスの花だ。
「ペンタス……ひな、お願いってこと?」
頷く花乃に、泉光は頭を掻いた。ペンタスの花言葉は願い事。
花乃は「一緒に行こう、お願い」と言っているのだ。少しして、泉光は微笑むと花乃の頭を撫でた。
「うん、行くよ。ひなとなら一緒に行く」
花乃は嬉しそうに笑うと立ち上がり、泉光に抱き付いた。
泉光は幸せそうに恍惚な表情を浮かべ、抱きしめ返す。
「決まりね。レンタカー借りて来たから安心してちょうだい。
車で三、四時間だから、お弁当も作っていくわ」
「……分かったよ。それで、必要なものは?」
「あなたたちは着替えと、黒い服があれば十分よ。
こっちでお線香と新聞紙とマッチ、ついでにおはぎとお弁当も用意してるわ。あと、ヒマワリの花束」
「ヒマワリ? 普通、菊とは百合の花じゃないの?」
「あら、興味ない割には詳しいじゃない」
「……別に、僕だって行ってなかったわけじゃない」
「……そうだったわね。まあ、そうね。ヒマワリは、特別なの」
「ふーん。で、墓参りって、誰の?」
泉光は花乃を抱きかかえたまま立ち上がり、読んでいた本をベッドに放った。
樹季は珍しくしばらくの間を空けていることを不審に思い、泉光は花乃とともに樹季の顔を見た。
樹季はどこか遠くを見つめながら、ただ表情もなく答える。
「姉さん」
「……は?」
「アタシの姉さんのお墓参りよ」
「……兄弟いたんですね」
「ええ。……東雲夏希。アタシの、八つ上の姉よ」
その横顔は、感情が読み取れないほどに、遥か遠くを見ていた。
なのに、どこまでも、ただどこまでも、悲し気で。
外に響く蝉の声が、やけに大きく響いていた。
ニチリンソウの君へ
東雲樹季は子どもの頃、無口でプライドが高く、喧嘩っ早い少年だった。
容姿はその頃から整っており、チャームポイントは左目にある涙黒子だ。
周りの女子からは熱い視線や言葉を浴び続け、彼女たちには応えるように優しさを持って接していたが、
それを快く思わない男子には目の敵にされていた。物を隠されたり、壊されたりしたことは一度や二度ではなかった。
時には、男子の輪に入れられず、追いやられることもあった。
そうすると、自然と女子との交流が増え、そんな樹季をからかう男子は増えた。
それをプライドの高い樹季が許せるはずもなく、喧嘩は絶えなかった。
殴り合いをしては生傷を増やし、相手にも怪我をさせることを繰り返したため、
相手方の両親や自分の両親、担任との話し合いは尽きなかった。
樹季は必ず母親に叱られながらも心配された。それが、樹季が小学四年生の夏までの話だ。
そんな彼が変わるきっかけになったのは、八つ上の姉の存在だった。東雲夏希。当時十八歳。
彼女は明るく純粋で、東雲家には太陽だった。
栗毛色の背中まである髪をなびかせ、右目には涙黒子があり、
細い輪郭と薄い唇、少し垂れ目な目は可愛らしく優しい印象を与えた。
無口でプライドの高かった樹季も、そんな姉には素直で言うことも聞いた。
共働きで忙しい両親の代わりに面倒を見てくれていたのが大きな理由だろう。
家に帰ると、夏希は、顔や腕に絆創膏を貼ってばかりの樹季に屈託なく笑いかけた。
「お~? 樹季くん、また喧嘩したのね~?」
他意がないと分かるおちゃらけた言い方に、樹季は思わず顔を緩めた。
しかし、夏希と目を合わせる勇気はなく、少し顔を逸らして頷いた。そんな彼に夏希はただ微笑み、頭を撫でた。
「そう。樹季が無事でよかったわ」
純粋な心配と安堵に、樹季はくすぐったくなる。
見上げれば、中腰で自分と顔を合わせる夏希が笑い、樹季を抱きしめた。
「喧嘩もいいし、一匹狼ぶるのもいいけど、お母さんもお父さんもあなたのこと心配してるのは忘れないでちょうだいね。
もちろん、あたしも」
「……別に、いっぴき狼のつもりないし」
「素直じゃないわねー! あっはは」
夏希は、樹季のまだ柔らかな頬を突いた。不満に顔を歪めるが、そんな表情すらも夏希は笑った。
「もーそんな顔しないのよ! せっかくの綺麗な顔が台無しじゃない。
樹季、お化粧したら女の子みたいに綺麗なのよ?」
「うっさい! 俺は男だよ!」
「女の子に見えるくらい、いいじゃない。顔が整ってて綺麗ってことよ。
将来は何かしら? モデルさん? 俳優? アイドル? 楽しみね」
「姉ちゃん!」
「うふふふ。あなた、絵も上手だから、芸術家なんかもいいかもしれないね。
そんな綺麗な顔と、大事な手、傷つけちゃダメよ。あなたが持ってるもの、ちゃーんと有意義に使わなきゃ」
傷らだけの両手を、夏希の細くも大きい手に包まれた。
今はまだ、姉より身長も体も何もかもが小さく、樹季は悔しさと同時に、それに包まれる安心感に身を委ねていた。
周りから聞く姉や兄の話など、口喧嘩や取っ組み合いをしたり、悪口の言い合いばかりだということで、
好きだと言おうものならシスコンだブラコンだなどとからかわれ、兄弟を馬鹿にされる。
そんな人間を冷ややかに見ながらも、樹季も姉の話を同級生にすることなどほとんどなかった。
プライドがシスコンと呼ばれることを危惧し、何より、姉のことまで馬鹿にされることが許せなかった。
それほど、自分たち姉弟は周りの兄弟よりも仲が良く、樹季は夏希を姉として好いていることを自覚していた。
「……姉ちゃんのほうがきれいじゃん」
照れくさく、はっきりと言えなかった言葉は口の中で声を曇らせただけだった。
夏希も「ん?」と言葉を返すだけで、何も聞こえなかったらしい。
もしかしたら、初恋だったのかもしれない。優しくしてくれる、家族から見ても綺麗な、年上の女性。
まだ幼かった樹季には、憧れだったのかもしれない。樹季は、眩しそうに目を細め、僅かに口角を上げた。
その日から、樹季は喧嘩をしなくなった。
やはり、からかわれることや挑発されることはあったが、そういった人間を自分の視界から排除した。
また喧嘩をすれば、自分も同じ穴の狢だと認めてしまうと、姉の言葉が頭を過る。
〝あなたの持ってるもの、ちゃーんと有意義に使わなきゃ〟
有意義に使う。それがどういうことかは、まだ十を超えたばかりの樹季にはいまいち分からない言葉だった。
だが、彼らの挑発に乗るということが決して姉の言うようなことに沿っていないことは確信していた。
樹季が小学校を卒業する頃になると喧嘩を吹っかけてくる男子もいなくなっていき、
その大人の対応に惹かれる女子は増え、そのまま中学へと上がった。
中学に上がった樹季は、小学校にいた頃よりも幾分か愛想が良くなった。
小学校の終わりから町を歩くとモデルや芸能事務所のスカウトにあうことが多くなっていたからだ。
最初は不愛想に対応をしていたが、一緒にいた夏希に声をかける輩も出てくると対応を変えた。
無愛想な樹季より、愛想がよくパッと見は大人しい夏希のほうが声をかけやすいと思われたのだろう。
そのため、樹季は愛想よく他人と接し、夏希に火が飛ばないようにする技術を得た。
学校でも愛想をよくしているほうが何かと優遇されると学び、どこでも愛想よく笑いかけ、
優しい物腰で話すことを繰り返しているうちに身についた。
すべては、大好きな姉を守るために始まった身の振舞いだった。
そんな彼が、中学で男女から人気を集めることになるのは、必然のことだった。
いつしか、妬みや羨望からの嫌味もかわせるようになっていた。しかし、そんな樹季にも、未だに慣れないことがあった。
家に帰ると、いつも通り、リビングにいるであろう家族に声をかけた。
「ただいまー」
声変わりを終えて、少し低くなった声が空間に響く。すると。
「おっかえりー! 樹季、今日もお疲れ様―!」
首回りに重みを感じ、頬には柔らかな別の頬の体温が伝わる。
抱き付いて頬擦りする夏希は、自身の身長とあまり変わらなくなった思春期の弟に構わず、嬉しそうに笑った。
「ちょ、姉ちゃん、やめろって!」
「樹季くん照れてるー」
「そんなんじゃねーから! いいから離れろって!」
大学に入り、二十歳にもなって、中学に上がった弟に抱き付く神経が理解できなかった。
それでも強く拒絶したり、振り払うことをしなかったのは、
樹季自身がそうされることを嫌がっていないからだと、本人は自覚していない。
「しょうがないわねー。樹季がそんなに嫌なら離れてあげる」
夏希は駄々をこねる子どもをあやす口調で、樹季から離れた。
未だ不機嫌な顔をする樹季は、大きなため息をつく。
「あのさ、二十歳越えて弟に抱き付くって恥ずかしくないわけ?」
「全然? いつまで経っても可愛い弟よ」
「普通は思春期の弟に気を遣うとか、弟が生意気だから関わらないとか、
彼氏がいるから弟に無関心とか、色々あるだろ?」
「そうなの? あたし、弟なんて樹季が初めてだから分からない!
あと恋人いたら家族に無関心になるの? どうしよう、あの人が家族に無関心になっちゃってたらあたしのせいだわ!」
天然なのか、わざとなのか。しかし、顔が青ざめ、「どうしようどうしよう」とつぶやく様子は、本気で心配している様子が伺えた。
前に、初めて連れてきていた夏希の恋人は、夏希より二つ上の年上で、誠実で優しい印象を持った。
正直、夏希に恋人が出来たことには複雑な思いもしたが、今ではその恋人が樹季にも優しく、
時にはご飯を奢ってくれたり、樹季の行きたいと言った映画や展示会のチケットを取っては一緒に行ってくれたりと、
本当の弟のように接してくれることで樹季も彼を慕っていた。
何より、彼が傍目から見ても夏希に優しく、一時期まだ信用しきれなかった頃にこっそりと二人のデートの尾行をした際でも、
さり気なく夏希を思っての行動が散見され、それが彼の夏希に対する愛情であり真剣に交際している証だと感じ取れたことが、
樹季が彼に姉を任せるきっかけになった。
夏希と同じように天然さがあり、どこか抜けていて、しかし笑顔を絶やさない。
二人はどこか似ていて、とても気が合っていた。悔しいが、夏希を幸せにできるのは彼しかいないと確信している。
夏希は未だに動揺している。初めてできた恋人を心配するのはいいが、ここまで取り乱されると樹季もため息が尽きない。
「あーもー鬱陶しい! 姉ちゃんの恋人だろ? しっかりしろ。あんたが惚れたのはそんな男じゃないだろ」
樹季の言葉に夏希はハッとなる。次第に口元が緩み始め、嬉しそうに頬を包む。
「うふふ、あの人ったらすっごく優しいの。
お母さんやお父さんのことも心配してくれたり、自分のご両親も旅行に連れて行くし……。
あ、あとね、樹季のことすごい可愛がってるのよ、知ってたかしら?」
「はいはい、知ってる、知ってますよ。俺部屋に戻るから」
「あーん、もう行っちゃうの?」
「鞄置いて着替えるくらいさせろ!」
リビングから部屋に戻るため、樹季はそれだけ言い残すと二階の部屋へと戻って行った。
夏希は寂しそうにその後ろ姿を見ていたが、すぐに笑みを浮かべた。
ある休日。樹季は久々に予定のない休日に、リビングで絵を描いていた。
母が思わず買ってしまったと言って飾っているヒマワリのデッサンだ。
集中し、目を離さずに細部まで描き込んでいる。
手も腕も、頬まで汚しながら、しかしそれらを気にすることなくより写実的になるように描く。
それは中学生とは思えないほどに繊細で、リアリティのある絵だった。
「いーつーきっ!」
そんな樹季の目の前に現れたのは、余所行きのカスタード色のワンピースに身を包んだ夏希だった。驚いた樹季は思わず仰け反る。
「ね、姉ちゃん!」
「うふふ、ごめんなさいね。驚かせちゃったわ」
「驚くに決まってんだろ!」
怒鳴る樹季に夏希は悲し気に目を細める。それに、ハッとなった樹季は持っていたスケッチブックと画材を置いた。
「驚くに決まってんだろ。姉ちゃんじゃなくてもびっくりする……」
その言葉に弟の優しさが見え、夏希は微笑んだ。
謝りはしないが、怒鳴ったことを反省して、「決して夏希だったから怒鳴ったわけではない」と言ってくれている。
「本当に、ごめんね? あっ」
夏希は樹季の描いていたデッサンを見ると目を輝かせた。
「樹季、やっぱり絵、とっても上手ね! あたし、こんなに写真みたいな絵、見るの初めて!」
スケッチブックを持ち上げようと手を伸ばした瞬間、樹季はそれを裏返して見えないようにした。
どこか恥ずかしそうに俯きながら、満更でもなさそうに目を逸らす。
「あんま見んなよ」
「あらまあ、照れちゃって」
「照れてねーよ!」
うふふ、と笑う夏希は、樹季がデッサンしていたヒマワリに近づくと花に顔を近づける。
「ヒマワリ、素敵よね。あたし、ヒマワリがお花の中で一番好きよ」
その様子を横目で見ながら、ふと「絵になるな」と思ってしまった自分に腹が立ち、樹季は頭を掻いた。
少し苛立ち気味に近くに用意していたおしぼりで手を拭く。
「で、何か用?」
「そうだったわ!」
夏希はスカートを翻し、樹季に改めて向き合うと、彼の目の前に再び立ちはだかる。
樹季の手からおしぼりを取ると、顔についていた汚れも拭き取ってあげる。
「出かけるわよ、準備なさい!」
「は?」
「柾さんと三人で色んなイベント回りするの! 柾さんが樹季も一緒に行こうって」
嬉しそうに言う夏希に圧倒された樹季は、そのまま流れでついて行く選択肢以外は与えられなかった。
待ち合わせ場所に、待ち合わせ時間通りについた樹季と夏希は、待ち人を見つけた。
すると、夏希が手を振って、こちらに気づいた待ち人は、心からの喜びを隠しもせず表に出しながら駆け寄ってきた。
「まさ……」
「夏希!」
駆け寄った勢いで、夏希を抱きしめた。
夏希は倒れそうになるが、しっかり抱きしめられ、倒れることはなかった。
嬉しそうに抱きしめ返す夏希を見ながら、二人に尻尾があれば勢いよく振っているだろうと思う樹季は、
周りの目も気にせず好意を互いに示すことにため息を吐く。
瀧澤 柾。二十二歳で、今年からデザイナーとなった。
夏希が大学に入り、文芸サークルに入った際に知り合った先輩が、柾だった。
似ている二人はすぐに気が合い、好きな作家も本も、好みの音楽も一緒で、好きな食べ物も嫌いなものを一緒、
見たい映画も笑いのツボも、考え方も。笑い方までそっくりな二人が付き合うことになるまで時間はそれほどかからなかった。
天然だが、着る物はいつも清楚で、シンプルだが動きやすく洒落ている。
柾の影響を受け、樹季も気づかれないように、柾に似た服を好んで着るようになった。
樹季を自分の弟のように可愛がって大事にし、夏希を心から愛し愛されている人物。
未だに抱き合い続ける二人。そろそろ二人を引き離そうと、樹季が渋々近づく。
「姉ちゃん、柾さん、ここ公共の」
言いかけたとき、柾のすすり泣く声が聞こえた。夏希を抱きしめながら、離す気配もない。
「な、なつ、なづぎぃ」
「柾さん、どうしたの?」
「あいしっ……あいしてるっ、愛してる」
「柾さんっ……」
すると今度は夏希まで頬に涙を伝わせ、柾を強く抱きしめ返した。
「まざぎざ、あいしてまずう……」
泣きながら愛を伝え合う二人を異様な目で見る道行く人々と、顔を歪ませ白目を向く樹季。
二人は抱き締め合い、愛を伝え合いながら、泣き続けた。
ようやく泣き止んだ二人に樹季は顔を引きつらせながら、今は近くのカフェで向かい合って座っていた。
カフェの新作メニューとして掲げられていた洒落たコーヒーと紅茶をそれぞれで頼み、
互いの飲み物を一口ずつ交換する親密さを目の前にしながら、炭酸が抜けきる寸前の甘ったるいコーラを飲む。
「あのさ、俺は一体何を見せられてるの?」
「んーあたしたちの愛の深さ?」
「だりぃ……」
柾は夏希の頭を撫で、それから改めて樹季に目を向けた。
「ごめんね、樹季。あそこで泣くつもりはなかったんだけど」
また少しだけ、目に涙を浮かべた。
「夏希が可愛すぎて愛しすぎてなんかもう無理……尊い……」
「あら、柾さんったら」
目の前でじゃれ合う二人に樹季の眉間には皺が寄り、コーラを飲んでいたストローを噛んだ。
「で、俺はいないほうがよかったんじゃない? 二人で勝手にいちゃついてればいいだろ」
「ごめんごめん。今日は僕の我がままで連れてきてもらったんだよ」
そう言いながら、柾が取り出したのはプレゼント用に包装された四角く分厚いものだった。
それを樹季に渡すが、渡された本人は不思議な目でそれを見る。
「なに、これ?」
「プレゼント。この前、誕生日だったでしょ」
その言葉に、樹季は目を丸くして、柾を見た。
始終笑顔で、夏希と二人で優しい視線を投げかけてくることに耐え切れず、少しだけ目を逸らした。
「な、これ、渡すだけなら、姉ちゃんに渡せばよかっただろ」
「直接渡したかったんだ。大事な弟だから」
どこかくすぐったく、恥ずかしい。樹季にとっては、柾は理想の兄だった。
優しい姉と、その恋人であり兄のように慕える存在がいて、急に照れくさくなる。
「あ、ありがとう」
「ねえ、樹季。開けてみて?」
夏希に促され、樹季は包みを丁寧に剥がし、中身を見た。それは分厚い料理本だった。
「料理本?」
「樹季は手先が器用だから、料理も出来るんじゃないかと思ってね。将来きっと役に立つだろうし。
もしよかったら、それで覚えて。いつか僕たちに食べさせて。楽しみに待ってるから」
プレゼントのセンスの良し悪しは分からないが、これが中学生に贈るものではないことは確かで。
それでも、樹季は嬉しく思い、僅かだが確かに頷いた。
「まあ、いつかね」
「うん。楽しみにしてる」
笑う二人に、樹季は目を逸らす。
それでも頭の中は、本の料理で自分でも上手く作れるものがあるだろうかと考えていた。
その日、三人は柾が計画した順でクラゲと光のイベントを行っている水族館、
ファッションについての展示を行っている近代美術館、白い花だけを集めたイベントを行っている花の庭園を回った。
樹季は柾の見せてくれる世界に魅入られながら、脳に見たものを刻んでいった。
中でも近代美術館で展示されていた白いウェディングドレスは、その後に見た白い花たちの光景と相まって印象的だった。
それから二年後。樹季は中学三年生になった。
あの日、夏希と柾にもらった料理本をもらってから少しずつ料理を覚えた。
二人の予想通り、樹季はどんどんその才能を開花させていった。
今では、週に三日ほどは樹季が夕食を作るまでになり、両親にも好評だ。
夏希は無事に生花を取り扱う大手の会社に入社し、それと同時に柾と婚約関係になった。
二人の仲は固く深く、誰もが当然のようにそれを祝福した。
結婚式は夏希の仕事が安定し、資金もある程度貯まるであろう一年後の八月の中旬、彼女の大好きなヒマワリの咲く時期に予定された。
樹季は美術を本格的に学ぶため、美術専攻の高校に志望校を絞った。
家から通える範囲であれば片道一時間も二時間もかかる遠い高校も検討した。どの高校も美術推薦で受けている。
樹季は第一志望であり、美術に特に力を入れている私立高校にトップの成績で合格することができた。
家からは遠いが、美術のためなら頑張れる。樹季の前途は明るかった。
一年後には、大好きな姉が大好きな義兄と結婚し、家族が増える。
美術を学びたいだけ学び、デザイナーという夢の一歩を踏み出す。
人生は少しの退屈と、少しの希望と、そして少しの幸せでできている。十五の大人びた少年は、そう信じていた。
冬が近づく秋の終わり。周りが勉強に明け暮れる中、樹季は既に受験を終え、のんびりと過ごしていた。
学校の授業も名ばかりで、実際はこの時期になると自習が多くなっていた。
勉強に集中する者、おしゃべりをする者、机に突っ伏せて眠る者と様々だ。
そんな中、樹季は本を読んでいた。ウソしか吐いてはいけない話、破壊衝動に魅入られた少年少女の話、
ハーバリウムに見立てた男女関係の話……。統一性のない短編を一冊の文庫にした、退屈な小説だ。
それでも暇つぶし程度にはなる。何度目かのため息を吐きながら、本にしおりを挟む。
窓際の席で頬杖をつき、窓の外を見た。まだ冬と言うには早いが、寒い日が続いている。
空は青く澄み渡り、雲一つなかった。晴れた空の柔らかな日差しが心地よい。
「東雲! 東雲はいるか!」
自習となり、教師のいなかった教室の扉が開かれ、数学の教師が入って来た。
彼は学校の中で厳しくもユーモアのある教師として人気を誇っている。
無気力そうな表情と無愛想な物言い、ふざける生徒の言動を受け流しながらもきちんと対応し、
たまに意地悪な問題を出しては悩む生徒を見てイタズラな笑みを浮かべる。それが不思議と不快にならない。
そんな彼が普段の無気力な目を見開き、少し声を荒げて勢いよくやってきた。
誰もが作業の手を止め、口を閉ざし、顔を上げる。樹季も例外ではなく、
普段の数学教師の様子を知っているからこそ、自分の苗字を呼ばれてもすぐには反応できず、我に返るまでに数秒要した。
「あ、はい、います」
ようやく言葉を理解した樹季は席を立ち、軽く手を上げる。
「今すぐに職員室に来い! ご家族から緊急の連絡だ!」
家族からの連絡。教師を焦らせるほどの何か。
樹季は何があったのか考えるよりも先に、机の間をすり抜け、教師が開けた扉とは反対側の扉を開けて廊下に飛び出し走り出した。
すれ違いざま、教師が「俺の机の電話だぞ!」と伝える。樹季はそのまま、職員室へ向かった。
それから、何があったのか覚えていない。
職員室に息を切らしながら入った樹季が数学教師の電話を取って出た途端、父親の声が響いた。
内容は半分しか聞き取れなかったが、とりあえず早く帰ってこいという言葉は聞こえた。
あんなにも取り乱した父親の声を聞いたことがなかった樹季は、ただ事ではないことを知り、
電話を切ってその足で学校を飛び出した。全速力で家に帰り、鍵のかかっていない玄関の扉を開け放った。
上履きのままだった靴を脱ぎ捨て、リビングの扉を開けた。
声もなく泣いている母を抱きしめて落ち着かせる父がいた。夏希はそこにいなかった。
「姉さんは……?」
どんよりと重く、長い沈黙。吐き気を催すほどの暗さと空気に樹季は心臓が痛くなる。
夏希に何かあったのか。何があったのか。どうしたのか。
とにかく何か言葉がほしい。夏希が無事であるという何かを。
ようやく、父親が顔を上げ、声を絞り出す。
「柾さんが……刺された」
柾が刺された。言葉の一語一句を頭の中で想像することはできる。それが何と読むのかも理解できる。
だが、それがどういう意味なのか、理解することを拒んでいた。
「柾さん、営業に行く途中の交差点で、子どもを狙った通り魔に、刺されたらしい……。
近くにいた、子ども連れの親子が刺されそうになったのを、庇ったと、親子連れから、夏希が聞いたらしい……。
犯人はすぐに取り押さえられて、捕まったけど、柾さんの容態が悪いみたいで、
今、病院で予断を許さない状況だと、夏希から連絡があった……」
親子? 通り魔? 庇った? 予断を許さない? 樹季の頭の中をぐるぐると同じ言葉が回っている。
急激に体温が冷えていく。両親ですら、既に息子同然に接している人。
来年の夏には結婚をして、夏希と幸せになるはずの、兄になるはずの人。何よりも誰よりも、姉が愛する人。
樹季と両親は、ただ黙って次の連絡が来るまで待っていた。
病院で柾に付き添っていた夏希から連絡がきたのは、日付が変わる少し前だった。
電話から聞こえた夏希の声はとても静かで、感情を読み取ることはできなかった。
それでも、一つだけ確かに、聞き間違えようもなく言っていた。
<柾さんが、亡くなりました>
夏希が淡々と報告するその後ろで、年配の女のものと思われる声が泣いているのが聞こえる。
微かに聞こえる言葉は確かに、「マサキ」と呼んでいた。
失血がひどく、加えて血液型が特殊だったため血液を探すのに手間取ってしまった。
見つかったが、輸血が間に合わなかった。そう医師に告げられたそうだ。
スピーカー状態にした電話から聞こえてきた報告に、樹季たち三人は何も言えなかった。
言う言葉など何もなかった。柾が死んだ。その事実だけが空間を支配していた。
それから過ぎる時間ははやく、素っ気ないものだった。
柾が死んでから数日後には通夜が開かれ、葬式が行われた。
その間、柾の両親はやつれた顔をして、樹季の両親は、ショックを受けている柾の両親の代わりに式を取り仕切り、
準備をした夏希のサポートをしていた。柾が庇ったという家族も顔を出し、深く頭を下げていた。
柾の両親は、夏希たち家族に感謝していた。夏希は、結婚せずして未亡人となった。
葬式から数日後。日々は元の姿を取り戻しつつあった。
テレビのニュースでは、捕まった通り魔の話が数十秒だけ流れた。
通り魔の男が捕まったこと、そして親子連れの家族を庇った男が亡くなったということ。
柾の名前は出されず、ただ事実だけが伝えられていた。
夏希はあの日が過ぎても一度も泣かず、怒ることも取り乱すこともなく、
柾がいなくなる前のままの笑顔で日々を過ごしていた。
婚約者を亡くした人の振舞いには思えず、樹季は苛立ちを覚えていた。
それでも、もしかしたら彼女なりの心の自衛なのかもしれないと思い、深く追求することはなかった。
両親も夏希を心配していたが、笑顔の彼女にどこか安堵しているようだった。
きっと夏希なりに立ち直ろうとしている。前を向こうとしている。そう思っていた。
「ねえ、樹季。今度、柾さんと新しくできたカフェに行こうって約束してるの。一緒に行かない?」
最初は何を言っているのか分からなかった。からかわれているのか。
いや、夏希に限ってそんなことはしない。言葉もその微笑みも、本気のようだった。
樹季は不審に思いながらも、もしかしたら生前約束していたことを叶えようとしているのかもしれない。
それならと、一肌脱ぐことにした。
約束していたという日曜日。夏希はデート用の清楚で可愛らしいワンピースに身を包んでいた。
小さな紙袋を持ち、樹季と共に駅前に行く。
樹季が新しくできたというカフェの場所を看板で見ていると、
夏希は待ち合わせの目印に使われる銅像の前で辺りを見渡しながら誰かを探しているようだった。
自分と姉以外に誰か来るのだろうか。場所を確認し終えた樹季は、落ち着かない様子の夏希に近づく。
「姉さん、誰か待ってるの?」
「え? 柾さんに決まってるじゃない。今日は三人で一緒に行く約束でしょう?」
「え……」
何を言われているのか分からなかった。柾はもういない。
それは、その最期を看取り、式まで取り仕切った夏希が一番よく知っているはずだ。
それでもふざけているわけでも、惚けているわけでもなく、樹季が何を言っているのか分からないという顔で答える夏希。
「それにしても遅いわね。迷子かしら? うふふ。
柾さんったら、もう何度もここで待ち合わせしているのに、困った人ね」
「姉さん、何言って」
「あの人、ひどいのよ? さっきから連絡してるのに、電話にも出ないし、メールも返してくれないの。
何かあったのかしら? いつもなら真っ先に連絡をくれるのに」
「姉さん」
「もしかして、携帯の電源が切れちゃったとか?
あ、でもそれなら、公衆電話を使ってでも連絡くれるし……。
ほんと、どうしちゃったのかしらね? うふふ」
「姉さん!」
夏希の肩を揺さぶり、大きな声で呼ぶ。
すると、周りが驚いたように二人を見たが、やがて興味を失くしてまたそれぞれのしていたことへ戻る。
「樹季? どうしたの?」
「どうしたは姉さんのほうだよ! さっきから何言ってんだよ」
「何って、あたし、何か変なこと言ったかしら?」
「さっきから柾さん、柾さんって……。どうしたんだよ。だって、柾さんはもう」
「樹季ったら、今更あたしたちのラブラブなところ見るのが恥ずかしいっていうの?
もう、あたしたちもうすぐ夫婦なんだから、それくらい普通にするに決まってるじゃない」
「そうじゃなくて」
「そうだ! 式には樹季が料理を作ってくれる? あたし、あなたの作るご飯大好きよ」
「だから」
「ねえ、樹季」
ふと、夏希が目を細め、ふわりとした笑顔を浮かべた。
樹季の脳裏に「ヒマワリ」という言葉が浮かんだ。
「あたしたち、幸せな家庭を築けるかしら」
鼻の奥がツンとした。熱くなる目頭を落ち着かせるために眉間に皺を寄せ、下唇を噛んだ。
こんな顔を見せないために、樹季は俯く。両手は爪が食い込むほどに拳を握る。
「樹季?」
俯く弟を心配して、夏希は声をかける。樹季は震える声を押し殺し、答える。
「できるよ。姉さんたちなら、世界一幸せな家庭、作れる」
夏希は嬉しそうな笑顔を浮かべ、樹季を抱きしめた。
「あなたが言うならきっと、出来るわよね」
「うん」
樹季は夏希を抱きしめ返し、いつの間にか越していたその肩に顔を埋めた。
「……結婚、おめでとう」
「ありがとう」
姉弟はただ抱きしめ合った。深い悲しみと、小さな幸せの間に取り残されて。
日輪草の君に贈る、これが最後の言葉だった。
祝福のブーケトス
あの日、結局夏希は柾を夜まで待った。頑なに居座ろうとする姉を樹季は半ば強引に連れ帰った。
柾から樹季に、体調が悪いからまた日を改めようと連絡がきたということにした。
不満よりも先に体調が悪いと聞いて心配な顔を浮かべる様子が何とも夏希らしく、同時に哀れで仕方なかった。
姉は本当に、柾がまだ生きていると信じ込んでいる。
そうだ。夏希は悲しみで泣きわめくことも、憎しみや恨みで怒りを覚えることもしてこなかった。
泣いても、怒っても、いつも必ず笑顔を浮かべる東雲家の太陽だ。
悲しみに暮れることも怒りに狂うことも、彼女には分からないのだ。
なら、夏希は、どう受け止めているのだろう。愛する人を、誰かの身勝手で失った、その言いようのないモノを。
冬。気温は零度を下回る日が続いている。
まだ一か月以上も前だというのに、既に街はクリスマスに向けて準備をしている。
夜は点々と青いイルミネーションが点き始める。これから数を多くして、街は煌びやかな夜になっていくのだろう。
秋が終わり、冬を過ぎ、春が来て、夏が始まる。幸せの始まりだったはずの、夏が。
夏希はあれからもずっと笑顔で過ごしていた。仕事にも行き、時たま友人たちと食事をする。休日には大抵、家族と過ごした。
やはり未だ腫れ物を扱うような両親の態度は変わらず、樹季は複雑な気持ちでその様子を見守る。
ただ一人、夏希だけが柾を失う前のように振舞っていた。返事が来るはずのないメールを打ち、取られることのない電話をかける。
両親が柾の両親に連絡し、夏希が向かっても留守を装うか、
誤魔化すようにお願いしたいと頼んでいるのを樹季は聞いたことがあった。
出来るだけ、夏希を近づけさせないようにするとも。
そのため、夏希が柾の家や実家を訪ねたところで、柾に出会うことも、彼が死んだ事実を思い返すこともない。
柾の両親も夏希を娘同然に思っていることもあり、理解を示して協力してくれた。
誰かが夏希に伝えない限り、きっと彼女は知ることはないのだろう。思い出すことも、ないのだろう。
柾がいなくなってから、数か月が経った。クリスマスも正月も過ぎ、バレンタインが近づいていた。
夏希は未だ、柾が生きていると信じている。
クリスマスを共に過ごせなくても、正月に連絡がなくても、
この数か月会うことすら出来ていないことも、夏希は不満を覚えていなかった。
電話の電波も届かない、ネットも繋がらない場所へ長期出張していると苦し紛れの嘘を聞かされても信じた。
なぜ柾から直接その話をされなかったのか疑わないのだろう。
なぜ愛し合っているはずの自分に何も言わずに知らないところへ行ったことに怒りや不安を覚えないのだろう。
なぜ、柾を信じて笑っていられるのだろう。樹季には、到底理解することはできなかった。
そして同時に、頑なに柾がいないことを認めようとしない、疑うこともしない姉に、次第に苛立ちを募らせた。
卒業式が近づいた。樹季の周りが、日々そわそわと浮足立ってきていた。
中学最後の思い出を作ろうと連日カラオケに行く者たちや引退した部活動に入り浸る者、
離れる前に叶わずとも想いを伝えたいという者。樹季はただいつも通りの日常を過ごしていた。
友人たちと談笑に耽り、空いている時間には絵を描き、本を読み、時たま遊びに誘われれば行く。
想いを伝えに来た者に対しては、丁重に断りを入れ、思い出を汚さないように努めた。
それでもどこか上の空で、柾の死はやはり樹季にも影響を及ぼしているのだとじわじわと自覚していた。
だからこそ、姉の振舞いが苛立ちを与えるのだ。
姉が柾の死を受け入れない限り、樹季は柾の死を表立って悲しむことも偲ぶこともできない。
乗り越えることができない。姉に同情する限り、樹季はずっと、前に進める気がしなかった。
どこかで誰かが気づかせなくてはいけない。そしてその誰かに、自分がなってやろう。
両親も、柾の両親も、夏希の友人知人たちも、近所の人間も、誰も気づかせてやらないのなら、それなら弟である自分がやる。
それが姉にしてやれる、唯一のことだった。姉には前を向いてほしい。
きっとそれが、周りにも姉にも、樹季にもいいことになるのだから。
三月初め。樹季は中学を卒業した。
いつもは少し着崩す制服を久しぶりにきちんと着こなし、胸ポケットに赤い花のコサージュをピンで留めた。
ひとりひとりが卒業証書をもらい、また自分の席に戻る。
学年問わず人気のあった樹季の名前が呼ばれ、証書を受け取った瞬間、在学生の席から女子たちの鼻をすする声が多く聞こえた。
それから滞りなく式は終わり、教室に戻って担任の最後の話を聞いて、クラスの集合写真を撮った。
中学生活最後の挨拶をして、皆はこの中学校の生徒ではなく、それぞれの進路を決めた個人となった。
泣き合うクラスメイト、いつもとは違うことをして興奮気味の友人たち、
普段話したこともなかった人間とせっかくだからと会話を交わす。
樹季は教室を出るなり、後輩の女子たちに囲まれ、制服のボタンをせがまれた。
服を乱暴にされることを好まなかった樹季はそれを予測して、あらかじめ用意していたチロルチョコを彼女たちに配った。
憧れの先輩からの最初で最後の贈り物に、彼女たちはその場で歓喜し、泣き崩れる者も現れた。
別れを惜しまれる中、樹季は笑顔で彼女たちに手を振り、また、友人たちとの最後の会話を楽しんだあと、
この日を境にすると決めていたことを成し遂げるため、真っ直ぐに家へと帰った。
鍵のかかっていない玄関の扉を開けた。靴を確認すると、両親の靴は見当たらなかった。
式が終わるなり、今夜はご馳走にすると言って買い物に出ている。
しかし、姉の夏希のものである白いパンプスはそこにあった。
三人で式に出席していたはずだが、式が終わるなり先に帰ったと聞かされていた。
伝えるなら、今この日、姉と二人のこの時しかない。
樹季は決意を新たに、家に上がった。
階段を上り自分の部屋の向かい側、「なつき」と書かれたネームプレートをかけている部屋をノックする。
「姉さん、帰ってる?」
返事はない。樹季は息苦しくなる感覚に耐えながら、もう一度ノックをする。
「ドア、開けるよ」
ドアノブを回し、ゆっくりと扉を開いた。白と黄色でまとめたシンプルで綺麗な部屋。
ラグの上に置いた白いローテーブルの前に座り、夏希は手紙を書いていた。
「姉さん」
樹季が再び声をかける。すると、夏希はようやく顔を上げて彼に目を向けた。
白い長袖ワンピースの袖とスカートはふわりと朝顔形に広がり、美しかった。微笑む彼女は見惚れる樹季に微笑みかける。
「おかえりなさい、樹季。卒業、おめでとう」
「ああ、うん……。ありがとう」
目を逸らしていた樹季は再び夏希に目を向ける。優しい笑顔。いつもこの笑顔に救われてきた。今度は、樹季が救う番だ。
「姉さん、あのさ、話があって」
「話?」
夏希は持っていたペンをテーブルに置き、立ち上がった。樹季に近づき、部屋の中に入るよう促す。
「そんなところにいないで、入りなさいな」
「あ、うん」
「ふふ。樹季、こんなに大きくなってたのね。もうあたしの背丈、超えちゃってる」
嬉しそうに言う夏希に思わず顔が綻んだ。見下ろす姉の唇には、艶やかなバラ色のリップ。
長い睫はくるりと上を向き、優しい大きな瞳は潤んでいて愛らしかった。
「あのさ、姉さん」
「あ、そうだ! 樹季もお手紙書く?」
「え?」
話を遮られ、突然の問いに疑問符しか浮かばなかった。ウキウキとした様子で再びテーブルの前に座った。
手紙を持ち上げ、その内容を目で追っているようだった。
「今ね、柾さんにお手紙を書いていたの。
ほら、今、電波も何も届かないところでお仕事してるって、お義母さまとお義父さまが言っていたでしょう?」
また、柾の話。そうだ。今日はこれを終わらせにきたのだ。そのためにここにいる。
苛立ちが募るばかりで、自然と手に力がこもった。悔しさと腹立たしさで、下唇を噛んだ。
「だから、お手紙なら届くんじゃないかしらと思って。
あ、でも住所が分からないから、これはお義母さまたちに預けようかしら?
その方が、確実よね。ね、樹季、そう思わない?」
夏希の笑顔が、語りかけるような優しい声が、すべてを慈しむ眼差しが、何も知らない声が。そのすべてが、〝憎らしい〟。
俯いたままでいる弟を心配して、夏希は声をかける。
「樹季? どうしたの?」
「……よ」
「え?」
「いい加減にしろよ!!」
怒鳴られた夏希は、大きな目を真ん丸と見開いた。
息を荒げる樹季は、怒鳴ってから抑えきれなくなった今までの言葉をただ吐き出した。
「もういい加減にしてくれよ、いい加減目を覚ませよ、忘れてんじゃねーよ!
ひとりだけ忘れて楽すんなよ、みんな辛いんだよ、もうやめてくれよ!
もういないんだよ、どこにもいない、出張なんてしてないし連絡なんて一生取れないんだよ!
死んだんだよ、義兄さんは死んだんだ、
柾さんはもう死んだんだよこの世にいないんだよいい加減認めて受け入れろよ前見て進んでくれよ、もううんざりなんだよ!!」
溜め込んでいただけの言葉を夏希にぶつけた。「柾は死んだ」頭では理解していたつもりだった。
心もそれを受け入れていたはずだった。それなのに、口にすることがこんなにも引き裂かれそうな思いだとは思わなかった。
頬を伝って口に入り込んだそれは、塩辛くて仕方なかった。
「……そう、ね」
初めて聞いた、姉の寂しさと優しさの混じり合った声。
大きく見開いた目から溢れているものは、一体どんな感情と温度が共存しているのだろう。
立ち上った夏希は樹季の前に立ち、そっと彼を抱きしめた。
「そっか……そうだったのね……。柾さん、もう、いなかったのね。そっか。だから、何も返してくれないのね
。そっか、そうよね。じゃなかったら、あの人がこんなにも長い間、連絡してくれないなんてありえないもの。
そうよね。そっか。みんな、あたしに気を遣ってくれてたの。あなたもずっと、何も言わないでいてくれてたの。
そうなのね。そっか。ずっと辛い思いしてたのね。あたしだけ、忘れちゃってたのね。そう。そっか。ごめんね。ごめんなさい」
自分を納得させようとする物言い。きっと夏希を傷つけ、柾の死を否定されると思っていた樹季は、意外な反応に驚きを隠せなかった。
「姉さん……」
「ずっと、ごめんなさいね。ごめんなさい」
顔を上げた彼女は微笑んでいた。いつもの笑みだった。東雲家の太陽。
ヒマワリのような明るく優しい、いつものその人だった。
「あの、姉さん」
「前を、向かなきゃね。ちゃんと」
夏希からそう言われ、樹季は黙り込んでしまった。自分で言ったことのはずなのに、なぜだか拍子抜けだった。
こんなにもあっさり認められてしまうものなのか。それなら、もっとはやく指摘してもよかったんじゃないか。
どうしてこの人は、ここまで笑っていられるのだろう。先ほど流していたはずの涙はもう、そこにはなかった。
「ただいまー」
「樹季、夏希、帰ったぞ」
階段の下、玄関の位置から両親の声が聞こえた。カサカサと複数のポリ袋が音を立てている。
どうやら、今日は珍しく買い込んできたらしい。さすが、ご馳走を作ると言っていただけのことはある。
「さ、樹季。お父さんとお母さん、迎えに行きましょ」
「え、あ」
「ほら」
夏希は樹季の手を握り、部屋を出る。引っ張られるままに階段を下り、玄関に両親を迎えに行く。
「おかえりなさい!」
「おかえり……」
「ただいま。うふふ、もう、二人とも手なんて繋いで、いつまで経っても仲良しね」
「樹季、そろそろ姉離れしたらどうだ?」
「ばっ! そんなんじゃない!」
頬を赤くして否定する樹季に、小さな笑いが起きる。
「あたし、何か手伝うわ。今日は何作るの?」
「そう? 今日はね、樹季の大好きな物ばかりよ」
「よかったわね、樹季!」
喜ぶ姉の顔に、樹季はホッとため息をついた。
まだ少し、時間はかかりそうだが、きっと今の夏希になら乗り越えられる。前を向けるだろう。
そう確信した。樹季はただ微笑み、頷く。
東雲家の食卓は豪華に飾られ、その日、柾がいなくなってから初めて、心から笑える食事の時間を家族で過ごすことができた。
それが、最後に過ごしたみんな揃っての食事だった。
あの日から、夏希は柾の名を口にすることはなくなった。変わらない笑顔で日々を過ごしている。
ひとつ、変わったとすれば、夏希が朝と夜の食事の席に着かなくなったことだ。
朝は誰よりも早く起きて出勤しているか、休みの日になると昼過ぎまで部屋から出てこない生活になっていた。
顔を合わせれば特に変わった様子もなく、具合が悪いわけでもなさそうだが、どこか引っかかる。
高校入学前、春休みに入った樹季は母親に頼み、夏希に事情を聞くように促した。
「なんで母さんが聞くのよ。あなたが聞けばいいじゃない」
「なんか、こう、俺男だし……」
「だから?」
「だから、その」
樹季は頬を赤らめ、目を逸らした。口の中でもごもごと言葉を発するが、それが母に聞こえるはずもなく。
「なに? 聞こえないわ?」
「あーもう! だから、姉さんが女特有の悩み持ってたらどうすんだよ! 俺じゃ聞けないだろ!」
「女特有の悩みって?」
ああ、姉さんの天然さはこの人からきているのか、そう思わずにはいられなかった。
樹季をからかっているわけでも意地悪をしているわけでもなく、この母親は本気で分かっていない。
情けなさに泣きたくなるのを抑えた。
「いいから、姉さんに最近どうしたのか聞いてみて……自分の娘のためだと思って……」
「え? ええ、分かったわ。そうね、最近ちゃんとご飯食べてるのかも分からないし、
あの子が食べたいもの聞くついでに聞いてみるわ」
「ついででもいいから、頼むよ」
それだけ言い残して、樹季は自身の部屋に戻った。
次の日の昼過ぎ。夏希がいないことを確認した樹季は、台所で洗い物をしていた母親に声をかける。
「母さん」
「あら樹季。今日も予定はないの?」
「ないよ。……食器、拭くよ」
そう言って、樹季は乾いたタオルを持ち、母親が洗い終わったものから順に拭いていく。
「うふふ、ありがとう。あなた、反抗期の割に優しいのね」
「一言余計だ」
優しいと言われて照れ臭かった半面、「反抗期の割に」という言葉はいらない一言だった。
「それで、姉さんに聞いたの」
「なにを?」
「最近どうしたのかってこと」
「ああ、それね」
母親はくすくすと笑った。
「最近、お仕事忙しいんですって。夏希、企画のリーダーになったから、その準備とかで朝も夜も働きづめみたい。
だから、今日は夏希の好きなものでお弁当作って渡したの。そしたらあの子、泣き出しちゃって」
「泣き出した?」
「そう。泣きながら笑ってね。〝ありがとう、お母さん〟なんて。余程嬉しかったのね。
こっちも嬉しくなって、一緒に泣いちゃった。最近、あの子、憑き物が落ちたみたいな顔してるの。
柾さんがいなくなってしまってから、ショックでその記憶だけが抜けちゃってたのに。
最近じゃ、柾さんのことも話さなくなっちゃって。……嫌いになったのかしら」
寂しそうに話をする母親に、樹季は一瞬、息が止まった。
あの時、樹季が怒鳴って言ったことは、樹季と夏希しか知らない。それになぜだが罪悪感があった。
本当に柾の死を思い出させてよかったのだろうか。
いや、これでよかったのだ。その証拠に、母親も憑き物が落ちたような顔をしていたと言っている。
今、夏希は前を向いている。家族も前を向いている。悪いことなど、何もない。
「姉さんに限って、そんなわけないだろ。今でも、に……柾さんのことを想ってるよ。絶対」
「……そうね。あの子がずっと、愛してる人だもんね」
安堵する母親に、樹季も口元を緩めた。その時。リビングのコード付き固定電話がけたたましい音を響かせた。
二人して驚き、母親は泡だらけの両手と電話を交互に見て慌て出す。
それに気づいた樹季は拭いていた食器とタオルを置いて電話に向かった。
「俺出るから」
それだけ母親に伝え、直後に樹季は受話器を取る。
「もしもし、東雲です」
相手の声が聞き取れない。
周りの雑音と女性と思われるその声は興奮のためか、言葉にならない言葉を叫んでいるようだった。
ただ事ではないというのは明らかだった。
「もしもし? どなたですか? 落ち着いてもらわないと聞こえないです」
樹季の言葉で相手は深呼吸を始めたのか、息を吸ったり吐いたりを繰り返す音が聞こえる。
「もしもし? もしもし?」
〔あの、あの、夏希の家ですか!〕
「そう、ですけど」
〔わたし、夏希の同僚で、夏希と海に来てて、それでいなくなってて、そしたら夏希が! 夏希がぁ!!〕
「あの落ち着いてください! 姉さんがどうしたんですか! 姉さんに何があったんですか!」
泣きじゃくる相手の反応に、樹季は更に焦りを覚える。
手汗が止まらず、喉が渇き、吐き気を催すほどの心臓の痛み。
前にも一度、こんな気持ちになった気がする。
〔夏希が海で溺れたの!!〕
夏希が海で溺れた。すべての思考が止まり、時間も動いていない気がした。
零れ落ちる。すべてがなくなってしまう。
電話の向こうから、夏希が運ばれた病院の名前が聞こえた気がした。知っている病院だ。
樹季は子機を戻すことなく放り出し、玄関に走った。靴を履き、扉を開けて玄関を飛び出す。
「樹季ー?」
異変に気づいた母親が、戻されていない子機を拾って耳に当てた。
樹季は最寄りから三駅先の病院がある町まで我武者羅に走った。
足をもつれさせ、人とぶつかり、道にあった段ボールやごみ袋も構わず、蹴り飛ばしてでも走ることをやめなかった。
心臓が破裂しそうだ。呼吸もままならない。それでも足を動かした。
地面を蹴って、姉の元へ向かった。柾が運ばれたのと同じ病院へ。
耳の傍で、誰かの声が聞こえる。聞き慣れた、優しい声。声はずっと名前を呼んでいた。
「樹季」
はっきりと聞こえ、樹季は目を覚ました。最初に目に飛び込んだのは、自分の部屋の天井だった。
息を切らして起き上がる。思い出して、思わず叫んだ。
「姉さん!」
「なぁに?」
返事をされ、改めてベッドの横にいた姉を見た。心配そうに樹季の顔を覗き込む。
「大丈夫? ずっとうなされてたわよ」
「姉さん? 溺れて、病院にいたんじゃ」
「どうしたのよ急に。夢でも見た?」
夢。そうか、ただの夢だったのか。そうだよな、姉さんが溺れるはずがない。
泳げないのだから、自らそんな危険な場所に行くはずがないのだ。今までのはただの悪い夢で、ようやく現実に帰ってきた。
安堵した樹季は夏希に微笑み、その手を握った。
「よかった……」
「あら、あなたから握ってくれるなんて。あたし、お姉ちゃんで幸せね」
「うるせえよ」
「うっふふ。ねえ、樹季」
「ん?」
改めて目を合わせる。夏希はいつものように笑っていた。
「たくさん、ありがとうね。あたし、幸せよ」
「なんだよ急に」
姉さんは、ただ笑った。
見えたのは、知らない部屋の天井だった。ぼやけた視界に映る父親に似た男の顔。
鼻にくる薬品の臭いと、口回りを圧迫させる感覚。
生暖かな息が口元に広がり、それが自分の呼吸だと知るのに時間がかかった。
男は泣きそうな顔をして、樹季の名前を呼んでいた。
「樹季、樹季! 目が覚めたか!」
おぼろげに見える男の口の動きと声が揃わず、ぼんやりする。確か、さっきまで部屋にいたはずだ。
悪い夢を見て、起きたら夏希が無事でいて、笑っていた。
なのに、夏希の声は聞こえず、静かな機械音と目の前の男の声だけが響いている。
「樹季! 父さんのことが分かるか!」
父さん。ようやくはっきりしてきた頭で、目の前の男が父親に似た誰かではなく、父親本人であることを認識した。
ゆっくりと瞬きを繰り返せば繰り返すほど、ここが夢の世界ではないと理解する。
では、さっきの姉との会話は何だったのだろう。自分は一体、なぜ身動きが取れないでいるのだろう。
父親はどうして、そんな安堵に満ちた顔をしているのだろう。
「……父さん」
「ああ、ああ! 父さんだよ、分かるか?」
「なんでここに?」
「母さんから連絡があったんだ。お前が飛び出したっていうのと、夏希のことで……」
急に、父親の様子が変わる。未だにはっきりとしない脳でも、その変化にだけは気づけた。
「おれ、どうして……」
「お前、走ってここまで来ただろう?
看護師さんが言うには、いきなりお前が病院に飛び込んできて、姉さんって叫んで、倒れたんだ。覚えてないか?」
思い出そうとすると、脳が鼓動している感覚に襲われ、処理落ちした機械のように頭が熱くなった。
樹季はゆっくりと首を横に振る。
「そうか……。あんな距離を全力で走ったら、呼吸も心臓も乱れる。
体が耐え切れなくて、倒れたんだろうって先生がおっしゃっていた。
命に別状はないらしいから、安心しろよ」
優しく語る父親の声に、思わず口元が緩み、樹季は微かに頷いた。
それから、ずっと気になっていて思い出せないことを聞く。
「ねえさん、は……?」
父親の肩がびくついた。それでも満面の笑みを向けて、声を震わせる。
「姉さんのことは心配するな、母さんと父さんがちゃんとついて……」
涙が伝った。いつの間にか少し老けて、何本か皺が出来た頬を両目から溢れる光るものが這う。
震えた手が、力の出ない樹季の手を強く握った。
痛い程のそれに目を細めたが、今まで笑って泣くような姿を一度も見せたことのない父親のその表情が衝撃で目が離せなかった。
「夏希は、太陽だからなっ」
その言葉はどんな意味を持っていたのだろう。安心しろという意味だったのだろうか。
それとも、もっと別の意味だろうか。父親はそれ以降は何も言わず、ただ黙って涙を耐えている様子だった。
なぜ泣いているのか、理由を問おうと口を開いたその時。男性の医師が数人の看護師とやってきた。
「息子さん、目を覚まされましたか?」
父親に淡々と話しかける医師。父親は俯きがちになりながら「もう大丈夫みたいです」とだけ答えた。
医師は次に横になる樹季に近づき、呼吸のためのマスクを取った。
いくつか今の状態や体調について聞かれ、答える度に看護師がバインダーの用紙にペンを走らせていた。
一通りの問答が終わったあと、医師は一息ついた。
「息子さんはもう問題ないでしょう。入院の心配はありません。
ただ、しばらくは無理な運動を控えるようにしてください」
「はい、ありがとうございます」
医師と看護師は会釈をすると病室の出入り口へ向かう。
医師たちの後ろ姿を見送るために首だけそちらに向けた樹季はゆっくりと瞬きをして、それをお礼の代わりにした。
医師は部屋から出ていく前、足を止めて再度、体ごとこちらに向けた。
どこか複雑な表情をしていて、それでも口から出された声は淡々としていた。
「お嬢さんのこと……本当に、申し訳ありません」
父親は何も言わずに俯き、ただ何度も頭を下げていた。
医師はそれ以上何も言わず、看護師たちを連れて今度こそ去った。
父親は膝に置いていた手を握りしめ、何度も何度も自身の太腿を殴った。力の加減などないように見えた。
驚いた樹季が弱々しくも動かせるようになった手、で父親のその手を止めようと腕を伸ばした。
「とうさん、父さん、何してんだよ、やめ」
嫌な予感に心臓が締め付けられるような痛みを覚え、樹季は小さく唸った。
その声に父親が気づくと、今度は泣きそうな目で伸ばされた樹季の手を握りしめる。
「樹季大丈夫か、苦しいか、痛いか? お願いだ、お願いだからお前は無事で、ずっと生きてくれっ!」
その言葉に、樹季は一瞬、息が止まる。
今までに見たことない父親の様子、医者が去り際に残した言葉、そして父親の放った一言。
それが示すことなど一つしかない。理解したくないのに事実だけが頭に浮かんで脳を支配する。
「……とう、さん? なに、言ってんだよ? ねえさんも、いるだろ?」
嘘だ。これは、また父親が披露するたちの悪い冗談だ。
いつだって父親はその場に相応しくない冗談で家族を白けさせる。
優しい姉だけが、それに笑ったり、動揺したりする。最後には「冗談だよ」の一言で、また家族を呆れさせる。
それが東雲家にいつの間にか出来上がった一つの流れだ。だから、これもきっとその一つだ。
「冗談だよ」の一言を次には放つだろう。そのはずだ。そうでなくてはおかしいのだから。
だが、父親はただ、糸が切れたようにその場で項垂れるだけだった。
樹季の手を握る力も弱々しくなり、電池の切れたおもちゃのようにそこに座り込む。
「父さん? なあ、冗談だろ? また、父さんのたちの悪い冗談だろ?
ほらもう分かってるから、早くいつものあれ言って終われよ。
ここ病院だぞ、縁起悪いにもほどがあるだろ。今なら、俺がどっかで休んでる姉さんの代わりに笑ってやるからさ。なあ」
心臓の痛みを気にしないように、噎せたり唸ったりするのを我慢しながら、いつもの調子で言ってみる。
しかし、父親から返事はない。ただ沈黙だけが病室を支配する。なぜだろう。
前にもこんな空気を味わった気がする。少し前、そう、柾が亡くなった知らせを受けたあの時と――。
「……嘘だ」
本当は分かっている。嘘ではない。今この瞬間が現実であることなど。
では、さっき見た姉はなんだったのだろう。きっとあれが現実で、今ここにいるのが夢なのだ。
夢なら早く覚めなくては。ここが現実だろうとなかろうとどっちでもいい。
樹季にとってこれは夢で、そんな夢からは早く目を覚まさなくてはいけない。
「嘘だ、嘘だ、嘘だ、嘘だ、こんなの夢だ、夢だ、夢じゃないとおかしいんだ、だってさっきまで姉さんはいたんだ、
ずっといたんだ、いなくなるわけない、これは夢だ、夢、そうだこれは夢だ、夢なら覚めないと、覚めないとっ!!」
樹季は抑えきれずに自分の頭を一心不乱に殴り始めた。
気づいた父親が慌てて樹季を取り押さえるが、
いつの間にか力強くなっていた息子はその手を振り解いてでも自分を傷つけようと暴れた。
付けていた点滴用の針が中で折れてしまうのを恐れ、慌てて点滴を取った。
暴れて、夢だ嘘だと叫ぶ息子を再び取り押さえながら、父親は「誰か! 誰か!」と叫んだ。
ただ事ではないと駆けつけた看護師が樹季の様子を見てすぐに担当の医師を呼びに駆けて行く。
数分、二人は格闘しているところへ先ほどの医師はやってきて、看護師も加勢し、数人で暴れる樹季を取り押さえる。
すぐに別の看護師が鎮静剤の入った注射器を準備し、医師に手渡すと、彼は手際よく樹季にそれを打った。
まだしばらく暴れるのをやめない樹季を少しの間、押さえつけていると、ようやく薬が回り、
樹季は意識が朦朧とし始め、再び眠りについた。
次に目を覚ました時には数日が経っていた。目が覚めて意識もはっきりしてきた頃に、すべてを聞かされた。
一週間前、夏希は仕事で抱えていた企画を既に完成させていたらしい。
あとは最終調整だけという段階で、突然、その日に辞表を提出した。
会社のほうで今までも一切悩んでいるような素振りを見せなかっただけに、
抜けてはいるが仕事に熱心で企画も最後までやり切ったような彼女が、その直後に辞めるとは考えもしなかったという。
辞表は受け取ったものの、休暇の扱いにしていたそうだ。
この一週間、夏希は家族にそのことを言わず、いつものように、出勤するフリをしてどこかで時間を潰していたのだろう。
夏希を知る者の何人かが、彼女らしき人が結婚式場をぼんやり眺めていたり、
ウェディングドレスのショップの前で立ち止まっていたのを見かけている。
きっと、柾との結婚に思いを馳せていたのだろうと、事情を知る者は思ったらしい。
そしてあの日。母親が弁当を持たせた日。
突然会社を辞めたことや、いつもと様子が違うことを心配した同僚が、気分転換にと夏希を海に誘った。
彼女は喜んで誘いを受けた。そして彼女は、同僚とバーベキューを楽しみ、
母親からの弁当を一口食べる度においしいと喜んで泣いた。そんな様子がおかしくて、いつも通りの彼女に同僚も安心した。
しかしその後、自由時間として目を離しているときに、夏希は浜辺にサンダルを置いて、いつの間にか深いところまで入っていた。
泳ぎたいのだろうと気にしなかったが、自由時間を終えても夏希は戻っていなかった。
他のメンバーたちと手分けして探しても見つからず、異変に気づいたのは、
浜辺のサンダルが波にさらわれて流されているのを見つけてからだった。
泳ぎが得意な者が海の深いところまで入ってみると、溺れている夏希を見つけた。
急いで引き上げ、救急車に連絡をした。その後に、同僚の一人が夏希の携帯電話から東雲家へ連絡をした。
そんな話を聞かされていた樹季だが、すべて上の空だった。ただ白いだけの天井に目を向けたまま何も見ずにいた。
何がどうして、なぜ、どういう経緯で、どんな心境で、何がどうなって、そんなことはどうでもよかった。
そんなものは何も意味を成さなかった。
何をどうしようと、夏希が死んだことには変わらないのだから。
自殺だった。泳げないはずの夏希は自ら海に入り、戻れないところまで自らの足で向かった。
夏希は死ぬ覚悟をしていたのだ。だから、家族には何も言わなかった。だから、母親に弁当を手渡された時に泣いた。
それでも止まらなかった。夏希は、それほどまでに、柾を愛していた。
樹季は退院し、葬式も終え、家族は重くどんよりとした空気を漂わせた。
母親は外に出ず、毎日泣いて過ごした。父親も外に出るのは仕事のためだけで、休みの日はずっと夏希の写真を眺めていた。
樹季は、高校が始まるまでの間、そんな家にいることを拒んで外にいることが多くなった。
スケッチブックを持って、外の景色を見ているときだけが安らかな気持ちでいられる気がした。絵を描くことはできなかった。
このままではせっかく合格した美術科ではやっていけないと分かっていても、脳裏を過る優しさに手が止まる。
スケッチブックを開き、筆記用具を手にしても、何も描くことはできなかった。
雨。そんな暗い生活を続けていた中、春が近づくこの季節に豪雨が降り始める。
外に出ることもできず、母親は寝室に引きこもり、父親はこんな日でも仕事に出かけなくてはいけず、
樹季は部屋の窓からじっと雨が降る外を眺めていた。降りしきる雨音以外に聞こえる音はなく、辺りは静かで落ち着いた。
しかし、どこか居心地が悪く、外を眺めることをやめた樹季は意味もなく部屋を出た。
飲み物だけでも取りに行こうと考えて階段を下りようとしたが、目の前にある夏希の部屋に目が留まった。
夏希に柾の死を伝えたあの日以来、彼女の部屋には入っていない。
なんとなく、姉の気配を感じたくて、樹季はその扉を開けた。
中は、何も変わっていなかった。ベッドも机もそのままで、待っていれば夏希が帰ってくる気がした。
生活感に満ち溢れ、今にも夏希がこちらを振り返り、笑顔で名前を呼んでくれる気がする。
だが、部屋は暗く、そこに太陽はなかった。太陽は、もう二度と昇らない。
姉の好きだった香水、部屋の消臭剤の匂い、日に当てた布団の匂い、そして姉の甘く優しさに満ちた匂い。
すべてはそこにあった。樹季は中に入り、ベッドの上に座った。
自分の使っているベッドと同じく、固すぎず柔らかすぎないちょうどいいベッド。
まだ夏希が高校生の頃、たまに朝寝坊していたときには起こしに来ていた時が懐かしい。もうそれは出来ないのだけれど。
ふと、テーブルの下に敷かれた座布団が少しだけ盛り上がっているのに気がついた。
腕を伸ばして座布団を退けてみると、そこには紐で括られた手紙の束が二つあった。
それぞれ違う封筒で厚さもバラバラだった。差出人の名前は東雲夏希。これは夏希が書いていたということになる。そして宛先は。
「柾さん……」
宛先の欄には「柾さんへ」という文字と端のほうに小さく日付が書かれていた。
手紙の束は後ろに行くほど後の日付になっている。柾が死んでから少し経ってから一通目の手紙を書いていた。
長い間、彼女はこの手紙を書き溜めていたようだ。行く当てのない手紙を。
樹季は一番上の手紙を束から引き抜き、封を開けて中を取り出した。
勝手に見るのはどうかと思ったが、最期まで柾を愛していた姉が何を綴っていたのか気になって仕方がなかった。
二枚重なった便箋の内容を目で追う。
そこには他愛のない日常のこと、約束の日に樹季と一緒に待っていたのになぜ来なかったのかと問う言葉、
心配しているという気持ち、柾への愛の言葉があった。そして最後には名前と、「今どこにいますか」の言葉で締められていた。
次の手紙を取り出し開ける。やはり中の便箋には、日常の報告と家族の話、仕事の話、
柾への愛の言葉、最後には一通目と同じ言葉が書かれていた。
次もその次も変わらず、いつもの夏希の調子で書かれ、一喜一憂が活き活きと綴られていた。
そして最後には決まって、愛の言葉と消息を訊ねる言葉。読む度に姉がそこにいるようで、樹季は安堵した。
一束目の半分に差し掛かって、また同じような日常の話とその日あった特別なことの話が書いてあるところまでは同じだった。
そしてこれも愛の言葉と消息を訊ねる言葉で締められる……はずだった。愛の言葉までは同じだった。
しかし、最後に書かれている言葉が変わっていた。その言葉に樹季は目を見開いた。
「もう……天国には、着きましたか……」
樹季は慌てて日付を確認する。書いてあったのは、樹季が夏希に柾が死んだことを指摘する半年も前の月日。
次々と手紙を取っては開け、中を確認する。
最後の言葉は「そちらはどうですか」「何が見えますか」「あたしのこと見守ってくれていますか」
「待っていてくれますか」「また会えますか」……夏希は明らかに柾の死を認識していた。
家族にも周りにも柾が生きているように振舞っていたのに、手紙の中の彼女は、その死を受け入れていた。
なぜ気づかなかったのだろう。なぜ何も言ってくれなかったのだろう。なぜそんな振舞いを続けたのだろう。なぜ。なぜ。なぜ。
樹季の中には疑問が浮かぶばかりで、頭の中は破裂寸前だった。
脳をなぜに支配されたまま、樹季は最後の手紙を開けた。日付は、卒業式の日のものだった。
〔柾さんへ
そちらに春は来ましたか? こちらは、桜の花の蕾が膨らみ始めています。
今日はとてもいい日です。とても喜ばしい日です。樹季が中学校を卒業しました。
四月になったら、あの子も高校生になります。美術科の高校よ。
あの子は絵が上手だから、きっと楽しんで、素敵な芸術家になるわ。
あたし、あの子の描く絵が大好きよ。あなたも好きだったよね。とても誇らしい気持ちです。
これからあの子は、たくさんのものに出会って、たくさんの人と出会って、今より成長します。
大好きなものと一緒に過ごしていって、これから先好きな人もできて、幸せになって。
嬉しくて、羨ましいです。
……でも、今日はあの子に怒られてしまいました。
あたし、ずっとあの子やお母さんやお父さんや、お義母様やお義父様、他にも色んな人に
迷惑や心配や悲しみ、不安を与えていたみたい。
ずっと、柾さんは生きているように振舞うことで、みんなの中にもいるって。
ちゃんといるんだって、忘れたくなくてやったことは、みんなを苦しませてしまいました。
そうよね、だって、あなたはもういない。それなのに生きてるように振舞うのは、苦しいだけ。
そんなの考えれば分かったことなのに。……あたし、ずっと認めたくなかったんだわ。
みんなのためにって言って、本当は自分のために、生きてるあなたを作り出しただけ。
樹季はずっと、あなたの死と向き合っていたのに。あたしはずっと逃げてしまった。
あたし、幸せ者ね。みんなに心配されるくらい愛されて。弟に叱ってもらえて。
……会いたい。すごく、会いたい。もっとたくさん、話たいことがあったのに。
もっとたくさん、行きたいところあったのに。見たいものがたくさんあったのに。
もっともっと、たくさんたくさん、一緒にいたかった。あなたと一緒に生きたかった。
あたしを置いていかないでほしかった。会いたい。あなたに会いたい。
愛してるわ、柾さん。
あいにいくからね
夏希〕
手紙はそれですべてだった。この手紙だけ、あちこちに丸く皺が出来ている。
きっと、夏希のものだろう。乾いて痕になったのだ。樹季は手紙をしまった。
何も言わずに立ち上がり、白いクローゼットの隣に置かれた化粧台の前に座った。
鏡の前に映る自分は、ひどく醜く思えた。こんなことでは、綺麗だと言ってくれた姉を失望させてしまう。
樹季は台に置かれていたファンデーションに手を伸ばし、それをじっと見つめる。
しばらく見つめたあと、ケースを開け、優しく撫でるように顔に塗り始めた。
隅々まで、いつもより少し明るい肌色になった顔。かれは最後に、夏希の口紅を手に取った。
いつも付けている、艶やかなバラ色の口紅。彼は躊躇うことなくそれを自身の唇に塗った。
蓋を閉じ、元の場所に置く。瞑っていた目を開け、目の前の鏡を見た。
下手くそな化粧だった。しっくりこない、ただ顔に塗っただけの荒い物だった。
それでも、頬を伝うそれは、ファンデーションと共に流れ、顎の先で滴る。
「ねえさん」
目の前にいたのは、確かに夏希だった。自分の顔に、確かに夏希がいた。鏡に映る自分の顔に手を伸ばす。
「泣かないで、姉さん」
溢れる涙を拭おうと鏡を撫でる。それは虚しく、無慈悲に零れ落ちる。
この日を境に、東雲樹季は、夏希と生きることを決めた。
******************
青い空が広がる大きな道で車を走らせながら、
樹季は後部座席に並んで座る花乃と泉光に姉の話を語って聞かせた。もうじき三時間ほど経つ。
花乃はその目にいっぱいの涙を溜め、両手にはいつの間にか、紫に青の入った小さな花が集まって出来たシラーと、
花の形が松虫に似た薄紫色のマツムシソウが握られていた。シラーの花言葉は寂しさ、マツムシソウはいたわりの心。
バックミラーからその花を見た樹季は微笑む。
「ありがとう、ひなちゃん。でも、アタシはもう大丈夫よ。姉さんも義兄さんも、アタシの中で生きてるもの。
それに……姉さんにあんなこと言ったアタシにも、あの人が死んでしまった原因があるわ。
あの人は分かっていたのに、アタシは追いつめちゃった」
ミラー越しに見える樹季の笑みと寂しそうな表情に、花乃は元気づけようと笑い返した。
そして二つの花をヒマワリの花に変える。そのうちの一本を泉光に差し出した。
目を瞑って黙っていた泉光は花の匂いを感じて細目を開けると、花乃からのヒマワリを受け取る。
「ありがとう、ひな。僕にくれるの?」
花乃はその言葉に頭を横に振った。泉光は少し傷ついた。
彼女は手を合わせ、祈りを捧げるジェスチャーをする。
「……おっさんのお姉さんにあげればいいの?」
「おい、聞こえてるわよ」
おっさんという言葉に頷くかどうか迷うが、姉にあげるという意味では当たっているため、花乃は頷いた。
ため息をつき、少しの間ヒマワリを見ていた泉光だが、すぐに花乃に微笑んだ。
「分かったよ」
満足げな顔をする花乃の頭を泉光は撫でる。
顔を綻ばせ、笑う彼女を抱きしめようとするが、シートベルトに阻まれた。
「くそ……こんなベルトさえなければ!」
「シートベルトは安全のために付けるものよ。そう、安全のために」
微かに舌打ちするが、すぐに車の外に目を向け直す。
すでに周りは静かなところを走っていて、遠くにぽつぽつと墓地が見え始めた。
「着くわよ」
その言葉と共に、車は駐車場の空いているスペースに止められた。
エンジンが止まり、樹季はシートベルトを外して車の外に出る。
背伸びをし、辺りを見渡している間に後ろの二人も出てきた。
「泉光、トランクに積んだ荷物出してついてきなさい。ひなちゃんは花束持ってくれる?」
元気に手を上げて早速花乃は助手席に置いてあったヒマワリの花束を取り出し、
先ほど自分で出した一輪を握りしめながらしっかりと胸に抱える。一方泉光は、不機嫌な顔を隠しもせず露にした。
「こんな暑い中、僕に荷物持たせて歩かせていいんですか?」
「それ脅しのつもり? いいからさっさとやりなさい。ひなちゃん、もう向こうで待ってるわよ」
そう言って樹季が指をさした先には、こちらに手を振る花乃の姿があった。眩しい姿に泉光は胸を押さえる。
「僕、花乃を抱えて行くのに忙しくなるので、荷物は樹季さんに譲ります」
「何言ってんの馬鹿なの? はいはい、持った持った」
いつの間にかトランクから荷物を取り出した樹季は、泉光の手に荷物を握らせ、花乃と共に先を急いだ。
泉光は花乃にしか目が行かず、荷物を持ったまま彼女を追うようについていく。
着いた場所にあった墓石には「東雲家之墓」と書かれていた。樹季はそっと、墓石を撫でる。
「ただいま……姉さん」
そっと呟いた声に、泉光も花乃も黙っていた。
樹季もそれ以上は何も言わず、やるべきことをやり、それを終えると三人でヒマワリを供えた。
手を合わせ、それぞれが挨拶を終えて目を開ける。
「……行きましょ。両親にも紹介するわ」
そう言って、樹季は早くそこから去りたいと言わんばかりに踵を返し、歩き始めた。
「樹季さん」
だが呼び止められ、振り返る。泉光は一点を見つめたまま、淡々とした声で言った。
「もう帰るんですか」
「そうよ。もう用事は済んだし、それにあんただって早く帰りたがってたじゃない」
「ええ。今すぐにでも帰りたいですね」
「じゃあ、どうしたのよ」
「……これ、見ないで行くんですか」
「は?」
意味の分からない言葉に、樹季は疑問符を浮かべる。再び墓の前に立ち、泉光の視線を辿ってそこを見た。
そこには、先ほどまでなかったはずの白い花が今にも満開になろうとしていた。
「何よこれ。さっきまでなかったじゃない。ひなちゃん、何かしたの?」
泉光の隣に立ち、同じように花を見つめていた花乃はその言葉にすぐ首を横に振った。
「こんなこと、花乃は一度もしたことなかったでしょ」
「じゃあ、これ、何で」
「誰かが、何か伝えたいんじゃないんですか?」
泉光の言葉に樹季は息が止まる。彼の顔を見ると、その顔は冗談を言っているようには思えなかった
。その表情はどこか鋭く、しかし寂しげに映った。樹季は再び花に目を向ける。
墓に寄り添うように咲いているそれは、目の前で、ゆっくりと花を広げた。
「これ……」
目の前で起きた不可思議な出来事よりも、樹季は花に驚きを見せる。
「クチナシの花ですね」
「クチナシ……」
脳裏をあの頃の記憶が過る。夏希と柾がまだ生きていた頃、三人で見た白いウェディングドレスと、白い花の庭園。
幸せだった頃の、幸せな時間。
「姉さん」
呟いた言葉は無意識で、樹季は地面に膝をつき、そっとクチナシの花に触れる。
ふわりと優しく、柔らかな白い色。見る人を惹きつけ、明るく照らす太陽のような。
震える手は花を壊さないように添える。
「……樹季さん、クチナシの花言葉、知ってますか?」
「へ?」
泉光を見上げ、次に花乃に目を向ける。花乃の大きく円らな目は潤み、それは白く柔らかい頬を濡らす。
それでも精一杯の笑顔を浮かべて、泉光の手を握っていた。
「クチナシの、花言葉は」
――とても幸せです――
言いかけた言葉を誰かが囁いた気がした。聞き慣れた懐かしい、優しい声が。
――あたし、幸せよ――
いつか見た夢で、その人は同じことを言っていた気がする。
――とっても幸せ――
太陽はそこにいた。陽の光が樹季の頬を撫でた。
「あぁ、あぁぁ、ねえさ、姉さんっ!」
樹季は止めることもできずに嗚咽し、その場に蹲った。泣きわめく声は三人にしか聞こえない。
花乃は泉光の手を離れ、樹季に抱き付いた。幼子をあやすように、彼がいつもしてくれるように、その背中をさする。
供えたヒマワリの花たちが、笑むように、風に揺られていた。
言ノ花庭園


