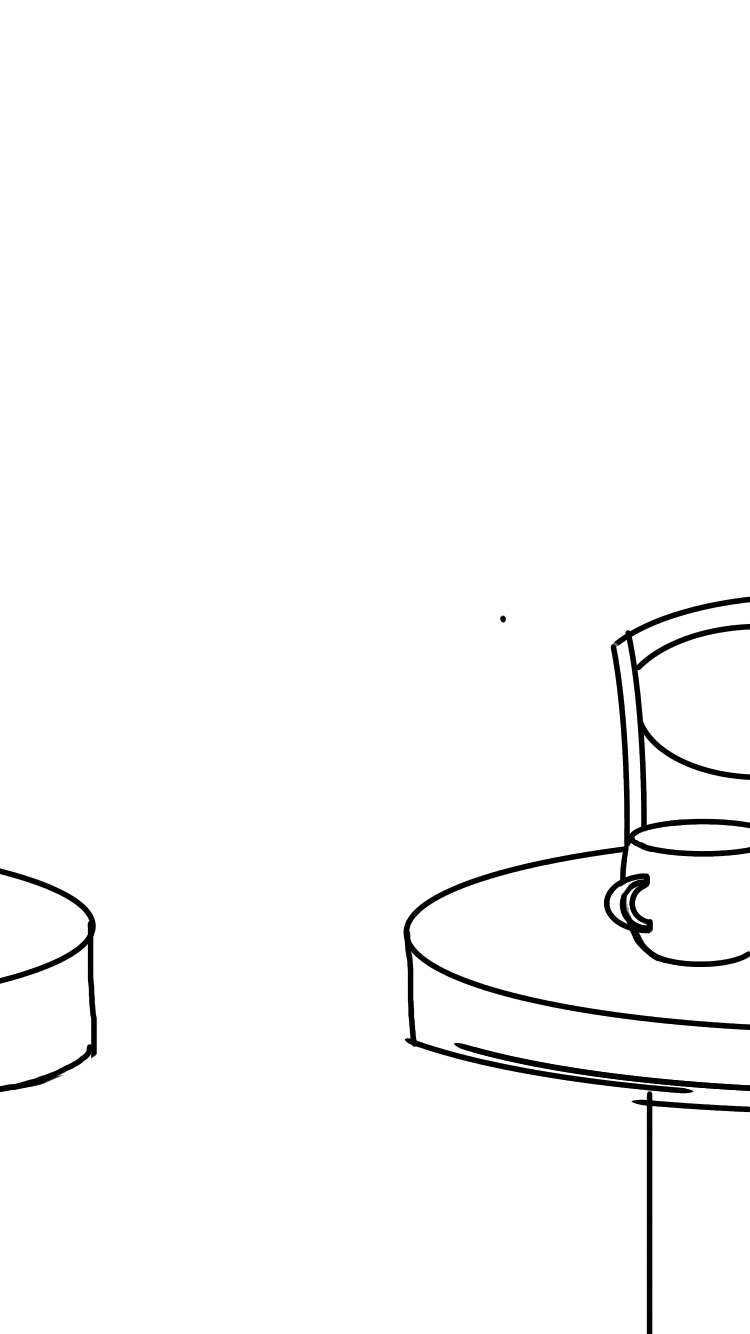
隣の女
某コーヒーショップで出会った女性二人を横目に
そのままの日時で書き上げたものです。
小説というよりは実況中継に近いそれですが。
一応小説ということにさせてください。
9月1日火曜日午後3時10分
東京郊外の小さい駅にピッタリとくっついて数年前に都会の喧騒に憧れるように様変わりしたデパート。
その中にあるコーヒーショップはまったりとしたBGMと、
家事の息抜きに訪れた主婦の雑談と暇を持て余した子供達の声で溢れかえった矛盾を絵に描いたような状態である。
学校の終わった高校生が来るのにもまだ早い。
そんな一定の客層に埋め尽くされた席の隅で、
一人携帯をいじりうなだれる若い女がいた。
隣の女は耳にイヤホンをつけ
きっと自分にとって丁度いいBGMをかけていることだろう。
携帯をいじってはコーヒーを飲み、いじっては飲みを繰り返す中で
女は一つため息をつく。
隣に座る女子高生を一瞥し、
面白くっもなんともないという表情でまたため息をつくとまた携帯を動かし、
耳にはめていたイヤホンを外して携帯を直接耳に当てる。
「ねえどうするの?」
隣の女の口調はいささか不機嫌というものを文字通りに表している。
相手は友達のようだ、
「駅から出てすぐのところ、
そうそう。じゃあね」
隣の女は耳から携帯を離してまた画面と見つめ合い始める。
きっと画面の向こう側でもその友達と会話を続けていることだろう。
それから幾分もたたないうちにコーヒーショップには似合わないガムシロップをそのまま飲まされるような鼻に付く匂いが香ると。
もう一人の女が隣の席に座る。
もともと座っていた隣の女からはしなかった、人の手で作った甘い匂いである。
私はうんざりしながら自分のコーヒーに口をつけるが、
今日に限って甘いコーヒーを注文したことに
こんなに後悔させられる日もなかなかないだろう。
ふうっと息をつきまた横目で隣の女たちの会話に耳を寄せる。
「そのネイルかわいいね、どこでやってもらったの?」
気がつくと隣の女たちは自分らの指の先を彩るネイルに話題を変えていた。
爪の先では店の照明を反射して光るストーンがゆらゆらと輝く。
「あーこれ、この間と同じ場所」
「そうなの?かわいい、私もこの間かえてもらったばっかりなの。」
かわいいだの綺麗だの、
もう少しうまい表現はできないのだろうか。
これでは何がどのようにかわいいのか全く伝わってこない。
この色もいいねだとか、
この模様はこうだとか、
せっかくこだわってお金を出して自分を着飾るのならば。
同じだけのお金をかけて内面も磨いたほうがいいのではないだろうかと。
ついつい愚痴っぽくなってしまう内面を吐き出すのは文字だけにとどめておこう。
そのとき
「もういこうか。」
そういって後から来た女は立ち上がる。
「そうだね、どこかでご飯食べていこう」
そして隣の女も立ち上がる。
二人の女表情を緩めて楽しそうに会話を弾ませながら立ち去った
離れて行く甘ったるい香水の匂いにも、少しは鼻が慣れていたことに気がつく。
立ち去った香りにふと
見ず知らずの人間をこうも観察してしまっている私という存在は
今この店であの香水よりもはるかに異質であろうと。
考えすぎか
15時50分
そろそろ帰ろう。
立ち上がってジャケットとカバンを持ち立ち上がる。
駅の改札に向かうためにデパートの中を歩くともう一度香るあの匂い。
二人の女。
やっぱりあの匂いは慣れられないな。
そんな 元隣の女。
隣の女
女子高校生と書いて登場させた私と。
二人の女にはその後もその前も何もありません。
関わったとすれば彼女が怪しげに私に視線をくれたその瞬間だけでしょう。
日常によくあるそんな光景も、ときに輝くように、ときに恐ろしく。
そんな風にかけるような語彙力と表現力をつけられたら。
もっと文章の枠が広がるのだろうなと。
おもっています。
一期一会ですから。

