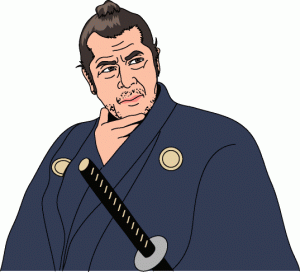片脚の鳩
1
素知らぬ顔をして歩く人の目には一々優しさがない。
おれがこうしてわからぬ様を極めているのだから、誰かしら声をかけてきてもいいようなものである。元来、おれは乗り物を嫌うたちである。わざわざ金をかけて免許証なぞをとる意味も理解できないし、飛行機などもってのほかである。船であれば漂う海の白波に多少の愉悦を感じることはできても、小さな小さな小窓から馬鹿の一つ覚えにただ青いだけの空を見せられて何を感じろというのか。ひたすら窮屈である。電車も好かん。きいきいと痴話げんかの女のような音を立ててけたたましく街を走り回っている様子はいかにもばからしい。自転車だなんて、これまでに持ったためしもない。向かいから向かってくる人間の歩調をちらちらと様子見しながら急ぐなんて、なんと忙しいことか。歩道を走れば交通法違反だと言われ、路側帯を駆ければ運転手の冷たいまなざしに晒される。なんとも業の深い乗り物である。誰が好き好んであんなものに乗るものか。バイクとて好かぬ。おれの友人は一時の爽快感に身を任せ、大通り横の簡素な交差点で子供を一人ひき殺した。これはたまらない。そして報われない。頼まれても運転するものか。昔よく父はおれを後ろに乗せたものであったが、それももう過去の話である。聞けば家計の足しにしたらしい。そんなものだ。乗り物とは。
そんなおれが地下鉄に乗らなければいけなくなった。
好いて乗るものか。仕方なく乗るのだ。子供が泣き叫んでいるような音を立てて走る鉄の箱に。
田舎から出てきて、ターミナルに着いたのがつい一時間ほど前。これまでの道中はバスであった。そんなに嫌なら走ってこいと言われずとも、そうできるならそうしていた。これもまた、仕方なかったのである。それから地下に降りて、切符を買い、ホームに到着した。下宿の管理人の話によれば、上りの電車に乗って、三つ目の駅で下車すれば、あわせてものの二十分で到着するらしい。「少し遅れそうです」との電話を先ほど入れたところ「ああ、まだそんなところにいらしてるンですの。早く乗っちゃったらよろしいのに」と返してきたものだから、「これでも急いでいるんですから、もう少しだけ待ってください」とだけ答えて切ってしまった。
何も考えない間抜けならばさっと無謀に乗り込むんだろうが、おれはそうではない。用心深い男なのだ。目的地に到着する電車がまず何時にくるかを調べねばすまない。確かに先ほどから泣き叫ぶガキが過ぎ去ってばかりいるが、あれらはすべておれを目的地まで運んでくれるかどうかわらかないガキである。こんなものに乗るわけにはいくまい。であるからこうして先ほどから、ホームの時間表を見つめているのであった。
2
ようやく腹を決めて乗り込んだおれは、顔も知らぬ人間に時の背を押され足を踏まれながらなんとか三つ目の駅で降りる。あのばばあ、一度文句を言ってやらねば気が済まぬ。というのも、おれが到着する頃合いであれば電車は混まないという話を偉そうにしていたのだ。それがどうか。父からもらった革靴は三度踏まれたぞ。おまけに情けない顔をした学生どものくだらない話を押し付けられた。あんな低俗な話をされたのでは心が持たない。席に横並びになっている群衆は決まってイヤホンを付けて素知らぬふりである。ばかな学生の将来を案じたような顔をしているものはどこにもいない。入口付近にいたおれならいざ知らず、真正面で押し付けられていた男などは瞼すら閉じていたときている。全く、都会というのは無関心極まりない。おれの地元では考えられないことである。
三つ目の駅で降りた後は、三番出口から地上に出るのだそうだ。全く、馬鹿の一つ覚えに同じ数字ばかり連呼するものだ。「覚えやすいって、評判なンですから」と自慢げにばばあは話していたが、それは貴様の周りの人間が猿か犬か程度ものだから覚えやすくて評判なのであって、おれのような真っ当な人間には幼稚すぎるのだ。聞けばおれが世話になる下宿には学生が多いそうだ。親族以外を部屋に連れ込むのは禁止で、大層静かだそうだが、終始人と扱ってもらえないのなら大変だろう。
さて、出口を出た後は非常に簡単であった。タクシーを捕まえるべきだと言われていたが、金も無駄であるし、これ以上乗り物にも乗りたくはなかったので、歩いた。何のことはない十分程度の道のりだ。都会の人間は乗り物にやたらと執着するようだが、我々には足がある。あとは根性さえあれば、この程度の道は問題でない。それがどうにもわかっていないから、この都市はこれだけがらんどうなのだ。
下宿に到着する頃にはすでに日も暮れ始め、夏にもなり切れない春であるから、すでにあたりは暗くなっていた。「御免ください」と一声かけると、想像以上に若作りの混んだばばあが右手の扉を押し開いて現れた。五〇代くらいだろうか。これでも仕事柄、人を見る目はある。人の虚構を見破るには、目を見るだけで十分なのである。
「あらあら、ずいぶん遅くなって。さぞお疲れでしょう。お部屋は七号室ですからね。早めに荷解きをして、お休みなってください」
「ええ、そうさせていただきましょう。鍵をもらってもよかったでしょうかね」
「あら、お渡しになっておりませんでした? 困りましたねえ。お父さんがいないと、私じゃわからないもンですからねえ」
弱ったのは此方である。管理人が部屋の鍵を持っていないというのだから間抜けな話である。おまけに二度ほどあたりを見回した後、「あっ」と短く声を出したばばあは身に着けていた割烹着に手を入れて鍵を取り出した。疲れる女である。
「ごめんなさいね。渡さなくちゃと思って、入れておいたンでした。そら、どうぞ」
「どうも。夕飯は七時でいいんですね」
「そうです、そうです。うちは朝夜ともに七時から八時ですから」
「了解しました」
階段は見かけ以上に老朽化している。これじゃ毎日ババ抜きだ。
廊下は細く、両脇には各部屋がずらりと整列していた。各部屋の横には簡易的なポストもあるようだ。おそらくここに届いた荷物はすべて一度あのばばあの目を通ってから、ここに配られる手はずなのだろう。おかしな話である。部屋の前まで来るのなら手渡しせよ。足音を聞いて、いなくなったのを見計らってから取りに出なくてはいけないなんて。郵便とはそんなややこしいものでもないはずだ。
荷解きをしていると、扉をたたく者がいる。何者かと出てみると、案の定ばばあであった。「なんでしょう」と尋ねると、「お仕事はいつからでしたっけ。物忘れが激しくて」と言われたので「明日に一度職場に向かって顔合わせがあります。が、正式な仕事初めは明後日からになります」とだけ返した。物忘れも何も、初めから仕事始めの日取りなど説明してもいない。忘れた忘れたと、一体何を忘れたのか。「明日のご出立は」としつこく聞いてくるものだから「七時半には家を出ようと思っております。道筋もまだ曖昧ですから」と返す。にこにこと何が面白いのか、ばばあはうんうん頷きながら「良いことです。良いことですなあ」と答えた。どうやら朝飯を食わない学生が多いのだそうだ。その理由も大方察しが付く。ただ、寝過ごす程度ならかわいいものである。もし麻雀やらで騒ぐのであれば、規則など抜きにしておれがこらしめてやりますと、心なしか一層大きな声で言ってやった。相変わらず、ばばあはにこにこと笑っている。
夕飯は可もなく不可もなく。生まれてこの方美味いものを食いたいと思ったことはない。最低限食えればそれで良し。腹に収まり熱になるものなら良し。食事にこだわりなどない。好きがないように、嫌いもない。そういう意味で、彼女の作る夕飯は良かった。不味くなければ、それでいいのだ。
畳にあらかじめ送っておいた布団を敷く。荷解きは完全には終了していなかったが、明日のこともある。朝一番に飯を食って、すぐに出かける手はずであるから、早めに寝ることにした。
気付けにと、入川さんからもらった日本酒をちびちびと飲んでみる。上等な酒だ。おれの地元の酒である。前の職場でもこいつがよく出ていた。なんだかいう品評会に出そうと考えているんだがどうか、と酒蔵の関係者に一度相談されたが、突っぱねた。点数がほしいなら優等生の酒でも造ればよい。この地でしか作れぬ酒に、誰が点数などつけられるものか。思えば中々雄弁であったと思うのだが、その半年後に、市役所の知り合いから品評会の結果が散々であったことを聞かされた。実際に販売しているものの声を無視するからそうなる。そもそも、偉そうに点数をつけているやつに限って、自身が何点かを知らないものだ。そんなものにこきおろされたところで、おれの務めていたホテルで人気であったことは間違いないのだから、間違いないのだ。そらみろ。今日もこんなにうまい。
なんだか悦に入ってきたところで、すでに閉めてあった襖をあけて窓台から外を見やると、そこはベランダになっていた。和室にベランダとはどういう了見をしているんだと思ったが、日当りのいい日には布団でも干して外出できるというものだ。また煙草も吸える。隣人は気にしなければいけないが、おれは間抜けな学生とは違う。自分の領分でないなら、たとえ煙でも向かわせぬ。
窓台を超えてベランダに出てみた。外はすでに夜である。星は見えない。殺風景な空だ。それに、やたらと車の走る音が多い。何をそんなに急いでいるのか。そうして急ぐ一分一秒にいかほど価値があるというのだろう。外で軽く呑んだ後、おれは一本だけ、煙草に火をつけた
3
翌朝は六時ちょうどに目覚めた。少しばかり遅い目覚めである。地元では通常五時半出勤であったから、五時にはすでに起きていなければいけなかったが、酒も入っていて、どうやら寝過ごしたらしい。
朝飯が七時だと聞いていたので、一時間のうちに支度をすべて終わらせておくに限ると思い立ち、いそいそと支度を始める。とはいってもこの体をもっていけば事足りるのであるから、昨日着ていたスーツを壁にかけ、新しいシャツを取り出した。これは新生活であるからと、美子に渡されたもので、実はネクタイも一緒に買ってもらったのだが、元来験を担ぐ男であるから、ネクタイは大事にしまっておいた。新しい職場ではそこそこの仕事が与えられると聞いている。制服があればよしともいかないだろう。ならば、初出勤の時に身に着けたいと考えるのは、女々しいだろうか。
顔も洗い、髭もそり終え、さてどうするかと思い立ったあたりでまだ飯まで四十分ほどある。なんだか気が落ち着かないので、窓台から身を乗り出し、外に出た。シャツもスーツも身にまとっていないのだから、下着一貫である。外は曇りであった。すっきりとしない空である。やけに音も少ない。このあたりは田舎も都会も変わらない様子である。味気ないが、悪くない。まずは顔合わせ。うまくいけば昼過ぎには帰ってこられるはずだ。こんな気分になる必要は全くないのだが、用心深い男であるから、頭の中でホテルまでの道のりを思い描いてみる。聞けば今度のホテルには恐ろしい女将がいるらしい。直接関わり合いになることもないだろうが、同じ職場である以上顔を突き合わせて何も言わないというわけにもいかない。地方の系列ホテルからこんな都会の本部のおひざ元まで飛んできたのだから、ぎゃあぎゃあと嫌みを言われてもかなわない。挨拶くらいはしっかりしておくべきだろう。
なに、一年経てば、異動願いを提出することができる。美子とのこともある。彼女としかるべき関係になったならば、子供だってもうけなくてはいけない。こんな人情味の薄い灰色の都会に居座り続けていても良いことなど何一つないし、美子にこっちに越させるなど、もっと欠点だらけの悪策だ。給金ははずむと言われていたが、送る相手の顔が近くにない以上、何十億もらおうと同じである。羽振りがよかろうと、どうせ今まで以上にせせこましく貯金するだけだ。そしてそれが、ちょっとばかり味気のないものになるだけである。おれは博打を打たない男だった。おまけに趣味というべき趣味もない。酒も呑むし、煙草もやるが、ほかに金を回しているところと言われてもいまいちピンとこない程度には、散財をしない男だ。
しかし一年か。
途方もない年月に見える。あの性格が変な方に捻じ曲がった料理長の心を開くにさえ、こんなに時間はかからなかった。そう考えると、おれにとって一年というのは少し長すぎるように思える。地方はどこも困窮している。外国人観光客をだしにして何とか生き延びているが、本部が切り捨てるのも時間の問題だろう。であるからこその異動なのだと思っている。異動申請は素直に受理してもらえないはずだ。おそらく四国の方に飛ばされるかもしれない。あそこは中々にうまい汁を吸っているとのことだ。やはり日本人ならば日本人を相手にしてこそ商売が捗るというものなのだろう。あと七年はつぶれまい。しかし四国に飛ばれても喜べない。おれは単純に美子のところへ帰りたいのだ。考えようによっては困窮しているからこそ出戻りは容易なのかもしれぬ。となれば後は時間の問題だけか。いいや、出戻りしたとして、本部からの派遣待遇で迎えられては気が休まぬ。そう考えると、おれの将来も中々、このあたりが分水嶺のような気がしてならなかった。
「ふう」と一息ついてから、煙草に火をつけた。ちょうど向かいの家からランドセルを背負った子供が三人出てくるところである。特にはしゃぐ様子もないが、学校が憂鬱そうな様子でもない。いいことだ。おれも、子供を育てるならああいう子にしたいと思う。
コンビニで買った安いライターに火がともり、加えた煙草が煙を吐き出し始めた。三度ほど煙を吐いた後、ふと右隣から視線を感じる。おれを見ているものがいる。しまった、ここは下宿だ。各部屋はベランダでつながっているのだ。おれと同じようにベランダで朝の空気を吸う者がいてもおかしくはなかった。挨拶しなければ――。そう思いながらふと右を向くと、誰もおらぬ。おかしなこともあるのだと、思った途端、そのすぐ左手、ベランダにかけられた柵の上に、鳩がいる。首をこちょこちょと左右前後に動かしながら、しかし眼だけはこちらを捉えていた。でっぷりと太った鳩はおれにおびえることもなければ、煙草の火を恐れることもしていない。なんとも太いやつ。こうして目が合ってもなお動かないというのだから、おれの加えている物が食い物にでも見えているのか。
しばらくこいつと向き合っていると、くるくるとくぐもった声で鳴き始めた。陰気で情けない声である。腹でも好いているのだろうか。それだけ太っているのだ、確かに腹はすくだろうが、連れて行って一緒に朝餉を頂くわけにもいくまい。かといっておれは先日到着したばかりだ。冷蔵庫にも何も入っていない。
「おまえにあげられそうなものは何もない。もっとめぼしい人間がいるだろう」
理解できるわけもない。相変わらずくるくると喉の奥で鳴らしながらおれを見ている。まさかこの鳩、おれが来る前より、ここは自分の領分であったとでも言いたいのか。なおふてぶてしい。ならば金を払え。おれはあのいけ好かないばばあと契約を結んでいるのだ。正当にここで煙草をふかせる権利を持っている。おまえはどうか。仕事は何をしている。安定した収入はあるのか。
全くばからしい。ばからしいが、少しだけ愉快な気分になった。存外かわいらしい奴である。情が移ったなどということはあり得ないにしても、この鳩を追い出す理由はなかった。
「いたいンなら、好きにするといい、どのみち昼は仕事だ。飯でも糞でも好きにするがいい。いや、糞は困るかな。まあ、節度を持ってくれればいい」
返事は相変わらずくるくるであったが、なかなか見どころのある鳩だ。近頃はまともに返事すらできない輩が多い。近くの大学から来ていた三人のバイトのうち一人は明らかにおれを、年が近いということでなめていた。まったく、親のすねをかじって私学の肥やしになった輩とはそんなに偉いのか。おれは大学を出ていないが、こいつのように親のすねをかじるのは高校でやめにした。青年とはそういうものだ。もう一人のバイトは、これがまた中々見どころがあるやつだったが、鳩にはかなわぬ。要するに、その程度だ。声ばかり大きくって、仕事がとんとできやしない。あんまりにも周囲から繰り返し怒鳴られているものだから、叱られたらその都度書き記せばかものと一度叱ってやったら、せっせと手帳に書き記すようになった。今度は「日記をつける仕事をして金をもらっているんじゃないんだぞ貴様」と言ってやったらバイトを辞めた。金をもらった恩義を忘れるような輩は鳩以下だ。もう一人は女であった。であるから部署が違う。受け入れは元来女性がやるのが角が立たぬ術であるから、そちらに回ったようだ。一度飯に連れて行ってやったら頬を少しだけ赤くしておれの肩に頭を預けてきたものだから、恐ろしい。未だ妻でなくとも恋人ならいると言うと、途端に平然と歩くようになるものだからこれも鳩以下である。
「その点おまえは見込みがある。楽にしていなさい」
そう了解を出してやって、窓台から中に戻ろうとした。すると、ひょんなことに気付く。というのも、何やらコイツ、部屋と部屋の境にある簡素な柱に身を預けているようなのだ。その原因なのだろう。脚が片方ない。「なんだおまえ、脚をどこへやった」と聞いても答えない。男には男の鼻っ面というものがある。たとえこいつが喋れたところで、話はしないだろう。
おれはと言えば、なんだか居た堪れなくなって、そっと手を伸ばしてみた。何をしようと思ったわけではない。ただなんだか、居た堪れなかったのだ。それだけである。しかしおれの手は空を切った。結局あいつの鼻っ面を傷つけるだけだという行為に気付けなかったおれの失敗である。鳩はすぐさま飛び立ち、柵を離れていった。行くあてはあるのだろうか。食いぶちはあるのだろうか。おれはうまい具合に朝飯がのどを通らなかった。
4
「うちはアルバイトの子らで持っているようなものですから」
そんな情けない言葉を聞いたのは、勤務先についてすぐのことだった。一体何のことかわからず、一通り中を案内されている道すがら「はあ」とだけ返すことにする。時刻はチェックアウトでごそっと静まった頃合いである。チェックインの時刻はどこも系列ホテルなら同じだと聞いている。ここもおそらく、しばらくは静かだ。
「いえね、ここから三駅ほど行っていただくとね、大学が三つほどあるんですなあ。そのあたりからアルバイトの子らが、まあ苦労して来るわけです」
「車でも持っているのですか。羽振りが良いことで」
「いえいえ、電車が走っておりますから。武藤さんはまだ慣れていらっしゃらないでしょうが、すぐにどこにでもいけるようになります」
おれはなんだかばかにされた気がしたものだから、何か一言この副支配人に言い返してやろうと思ったが、うまい具合に言葉が出なかったものだからやめにした。そもそもアルバイトを憎んでいるわけでもない。ばかなガキでなければ、それでいいのだ。
「そんじゃあ、おかけください。ここは基本受け入れに使っておりますが、アルバイトの子らの面接にも使うんです。上等なソファーでしょう」
「素晴らしいですね。私のいたホテルでも、こういうものをお出しできればいいんですが。少しばかりこれより固いですから」
おれの返しの何が愉快だったのか、大変おかしそうに笑い声をあげた後、二度せき込んだ。大笑いしたのちに死ぬのならさぞ幸せだろう。
「仕事ですがね」
「ええ」
「武藤さんには、レストランのリーダーをやってもらおうと思ってるんです」
「伺っています。一階と二階の設備まで任していただけると」
「ええ、ええ。ただ防音のことは言わんで下さい。苦情が来ておりまして、今夏改修予定となってますから」
笑った方がいいのかと思って一度だけ鼻を鳴らしたが、少しだけ嫌みがさしたと思って慌てて咳払いをしてみた。以後つらつらと話を聞くに、任される仕事は多い。責任も中々重いものを与えられるらしい。その後副支配人と共に支配人や事務の面々と顔合わせし、各部署を巡った。料理場はどこも同じ、相変わらず職人気質な流れ者が多い。おれを目の敵のようにする算段だろうが、そうはいかぬ。一年だ。どのみちおれは、一年で消えてみせる。
最後に夕食の支度をすでに始めていたレストランに向かった。とはいってもすでに昼休憩でほとんどが自宅に帰っているという事だったので、もう一人のリーダーのみと顔を合わせる。競馬とパチンコが趣味の、どこにでもいそうな愛煙家であった。うまくやれる自信はあるが、うまくやりたいとも思わない。名前を仙田と言った。年は三十前半くらいだろうか。にこやかだが、目の奥が笑っていない。こういう輩は要注意だ。人より多くの着火装置をもっているものだから、様子を逐一伺っておかなくてはならない。
案の定、昼には解散となった。一度レストランの景観をチェックし、料理台や休憩所にも目を遣った。アルバイトがどうかは知らないが、社員はなるほどいい仕事をする。
「元気がないね、武藤さん。緊張しているのかね」
「いいや、そういうわけじゃありません。ただ、少しばかり煙草が吸いたくなりまして」
「はっは、いいことです。どうです、一緒に。ここの喫煙室はすごいですよ。かくいう私も、ここに来る前は北海道にいたんですがね。ここにきて一番びっくりしたのは喫煙所の設備なんですから。さあさあ、どうぞ」
「仙田さんは、今日は夜は入っていないんですか」
「あら、どうして」
「今休憩中でしょう。帰りたいとは思わないんですか」
「なるほど。いえその通り、私は今日は早番でしたから。それに加え明日は休みときている。これは吉兆ですな」
片手で少しだけスロットをひねるしぐさを見せ、仙田はおれを喫煙室に入れる。中は確かにすばらしい。空調が効いていて、排気が十二分に行われているようだった。おまけに自販機もあるというのだから驚きだ。
「ここをね、潰して、物品庫にしようとしていたのが、二年前です。いやあ、わかっとらんのですよ」
「はあ、わかっとらんですか」
「わかっとらんですなあ。特にうちの支配人の頭は固いですからな。武藤さんも気を付けた方がいい。どれだけ素晴らしい進言をしても、一度駄目と言ったらもう聞かないんです。この喫煙所だって、副支配人をなんとか味方につけて残してもらったんですから。レストランの外には回ってみました?」
「いえ、まだ。何かあるんですか」
「ありますとも。というのもですな。レストランから宴会場までの連絡通路があるでしょう。あそこの屋根に、よく鳩が止まるんですなあ。糞をするからたちが悪い」
「鳩、ですか」
「ええ、鳩です」
勢いよく鼻から煙を吐く仙田に対し、おれはなんだか煙という煙が途端に鬱陶しく思えてきた。うちにくる片脚の鳩も、ここにきているのだろうか。残飯は倉庫に一時保管するようだから、食い扶持としては非効率だろう。
そもそもおれは、ここまでくる道中にそこまで多くの鳩を見ていない。ならば、ここに屯しているとい鳩は一体どこから来るのか。また、そもそもというならば、あの片脚の鳩はいつ片脚になったのか。
「まあ、大変だとは思いますが、頑張りましょう。なに、ずぶの初心者ってわけでもないんですから、大丈夫。そんな顔をしなくても、すぐに慣れます。アルバイトの子らも、良い子ばかりですからな」
「いえ、不安ってわけじゃありません。おっしゃる通り、初めてではありませんから。これでもこの業界に四年いるんです。すぐに慣れます」
「そうですか。ならなんでそんな顔で煙草をやるんです」
「そんな顔、とは」
「いやあ、いかにも曇天というような様相ですがね」
「はあ。しかし、それは元からでしょう。おれはこういう人間で、こういう顔立ちなんですから」
「そンなら、いいんですがね」
さて、とわざとらしく席を立った仙田は、そのまま「お疲れさまでした。これから稼ぎに行くので、それじゃあ」とだけ加えて去って行った。
仙田の話を聞いて、外からレストランに寄ってみると、鳩などいなかった。確かに糞はいくらか散見されるが、問題になるようなものでもあるまい。
空は朝と打って変って快晴の模様を極めていた。空気が濁っている気がする。一度だけ、メインエントランスから垂直に伸びるホテルを見上げてから、そのまま背を向けた。煙が鼻の奥にまだ詰まっているような気がして、思わずうつむいてしまった正午であった。
5
家に帰ってから特に何をしたというわけでもない。流行りを逸した漱石を読んでいたが、なんだか気分が晴れなかったものだから、すぐにやめた。次に美子の声が聞きたくなったものだから、電話をしてみた。どちらもつながらず、三度目につながらなかった時には四度目への執着も失せてしまって、布団を敷いて横になって、また漱石を読んだ。ふと車の轟音が聞こえる。どうやら窓を閉めないまま外出してしまったらしかった。
そういえばあの片脚の鳩はどうなったことだろう。この快晴の下、あいつは相変わらずどこかによしかかって、飯にありつける瞬間を待っているのだろうか。
そんなことを考えると嫌に居た堪れなくなってきたものだから、腰を上げて、一度だけ煙草を吸おうと外に出ることにした。
制服ももらった。普通の従業員とは全く違う恰好である。明日からおれはあれに身をまとい、仙田らと共に、アルバイトやほかの従業員をまとめねばならない。昔、一度だけおれは客にけがをさせたことがあった。大量に注文の入った酒を何度も何度も往復して運んでおれは、ふと気が抜けてしまったのだろう。なんだというのだこの阿呆どもはと、ふらり力が抜けたのかもしれぬ。気づけばドリンクカウンターのすぐそばでグラスを落とし、しっちゃかめっちゃかにしてしまった。さらに運が悪かったのは、それを客の一人が踏んだと云う事だ。おまけにその女性は「気にしないでください」というものだからなおたちが悪い。おれは報告会でこのことについて問い詰められたが、大勢が味方をしてくれた。なにせあのときのおれは、流行りの伝染病による社員の穴を埋めるのに必死で、毎朝五時に出勤しては閉店までいて、時折日が変わるまでホールで常連の相手しなければいけないことだってあったのだから、そもそもが働かせすぎだというわけである。みんなの心遣いは大変嬉しかった。支配人もそれで納得してくれたようであった。これもまた嬉しかった。しかし、同時にみじめでもあった。確かにおれは疲れていた。疲れていたが、自分の体調を管理できないような愚か者でもない。少なくともその自負はある。この時だって、おれの体調には何ら問題はなかった。けだるさや疲労感は否めないが、そんなものは誰にだってあるもので、皆自身で自身をしつけて仕事をしているものだ。
だから、「無理をさせてすまなかった」と頭を下げる支配人の姿を思い出すと、今でもみじめな気持になる。おれこそ鳩以下である。やつは片脚でも必死に生きているのに、おれはなんだ――という気持ちになる。謝られる謂れなどない。だがこのときのおれは、「私が悪いんですから、そんな頭を下げられて困りますよ」とすら言えなかった。あまりにもみじめで、年甲斐にもなく泣きそうになっていたのである。おそらく、何も考えぬ子供に踏みつぶされる瞬間の蟻も、こんな気分なのだろう。
しかしてそんなおれがリーダーである。出世したものである。今のおれをみたら、みんななんというだろう。明日、レストランに立っているおれをみて、かつての同僚は何というだろう。あと一年である。随分と長い。
「やれやれ」
いつの間にか声が出ていた。右手には取り出した紙煙草が一本指に挟まれていた。考えすぎである。気分が優れないのは、嫌いな乗り物に揺られて、これから一年間出勤しなければいけないということによるものだろう。じきに慣れるに決まっている。あの鳩が、いまだに自分が片脚であることを気にしているものか。そんなわけはない。あいつはあいつで適応したはずなのだ。
網戸一枚になっていた窓台から身を乗り出して煙草に火をつけた。と、そこで今朝と全く同じ場所に、やつがいるのを見つけた。
本当は窓を開けた瞬間に気付いていたのだが、なんだか恥ずかしかったものだから、こんなわざとらしい真似をしてしまったのだろう。
しかし、よく見てみると今朝の鳩ではないように見えた。なぜなら、こいつには片脚があるのだ。両脚でしっかり立っているのだ。でっぷりとした体形に、ふてぶてしくくるくると鳴くあたりはそのままなのだが、なにせ脚がある。
こいつは違う――と慌てて自分の疑念を否定して見せると、鳩が一度だけくるくると唸った後、右脚だけをまげて腹に隠すようなしぐさをした。その片脚にも見える姿は、まさに間違いなく、今朝に見た鳩である。
「なんだおまえ。脚、あったのか」
おれはそれ以来、ベランダで煙草を吸っていない。
終
片脚の鳩
読了ありがとうございます。この作品は本当はシリーズにする目的で書いたものでありまして。機会を作ってつらつらと彼について書いていきたいと思っております。
さて、新生活とはかくも厳しいものであります。時間の問題であることはわかっているから、刹那的な享楽によってすらも自分を誤魔化せない時間が訪れるという確信は、ひとえに臆病だからなのでしょうか。幸せかどうかなんて、今更議論されるべきものでもありません。それこそ、流行りを逸しているのです。ただ、僕にとって、武藤は少しだけ幸せそうに見えます。見たいように見るものですから、幸せかどうかもまた、見様によるのでしょう。
それでは、次回もよろしくお願いいたします。