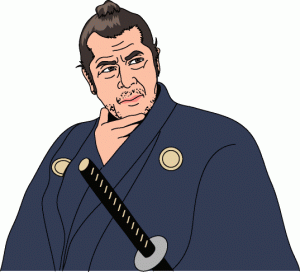竹の社 ――後篇――
1
飯を食わせることに喜びを感じるような人間というのは、まず間違いなく母親気質である。
おかわりを求めてくるようなその姿というものこそ、料理を与えられる側の人間には到底理解できない、母親気質なのだろう。
おれの下宿において、飯を作るのは気立てのよさそうな笑顔をする、一組の夫婦。飯時になってもおれが顔を出さずに、たとえばバスケットボールの試合を見ていたりするときは、決まっておばさんがおれの部屋にやってきて、上品にドアをたたく。「もし、おばさんですけれど。ごはんできていますよ。そろそろ食べに降りてきてくださいな」という具合。
彼女の美しいところは、決して無理に返事を強要しないことだ。おれはドアを開けずに「今行くから、まだ食堂を閉めないでいてくださいな」と答えたところで、無礼だと沸点に到達することなんてないし、当然無理に部屋に上がろうともしない。
プライバシーだなんていう今風の言葉を知っているかは危ういところだが、しかし彼女には、その心得があるようだ。
おじさんはおじさんで、おれの気を察するのがうまい。
彼の揚げるてんぷらはひどくくどくて食べられたものではないが、工具箱を握らせれば問題はなかった。人にはできることできないことがあって、たとえばおれには飯は作れないが、兄にはできない、バスケットボールができる。兄はおれにはできないような言い回しができるが、おれのように愚直にはなれない。
おじさんについていえば、それは車の塗装であったり、家具の製造であったり、自転車のパンク修理であったり、男の気遣いであったりするというわけだった。
奉仕させてほしい――と言えば、響きは大変脳足りんのようだが、奉仕する側がそういった要求をすることは少なくはない。そのことを、おれは下宿で学んだ。
母親気質。
この傲慢ちきで横柄なおれの母親にも、どうやらそういった面はあったらしく。
「おかわりがほしいです」と、ばかみたいに真っ直ぐ欲求を伝える少女に対し、にこにこと偽りない笑顔を浮かべている。
思えば、おれも兄も、飯を食わない子供であった。
おれや兄が、かつておかわりをこれほどまでに要求する少年であれば、母のしわのいくらかはこうして存在していなかったのかもしれないのである。
「十雨、君、本当におなかを壊すぞ。アイスだって、結局二本食べたんだから」
「あれは別腹だわ」
「腸を冷やしちゃいけないんだ。本当だぞ」
「もう温まったわ。今は夏なのよ。見て。ごはんだって、こんなにおいしそうに湯気を立てているわ」
おれの食器はもう空だ。米粒一つ残っていやしない。
さっさと部屋に戻ってこいつの両親にメイルしてもいいのだが、一度そうしたとき、やけに怒っていたことを考えると、どうにも待つしかない。
おかずだってないのに、白い飯だけをうまそうにかきこむ十歳児の姿は、なんとも大物なように見える。
「なあに、食べたいの」
「いらんよ」
「あげないわ」
本当に、頭が痛くなる。
さて、夜である。
大学四年であるおれには、卒業論文という厄介な代物が残っているのだが、まだ夏だということを加味すれば、慌てて今片づける必要もない。
計画的に先送りにすることは、決していけないことではないのである。
「――よし、送った。写真も送ったし、問題ないだろう」
「なんて送ったの」
「今日もおたくのお子さんは、ただ飯を三杯もおかわりしました、とな」
「失礼な。労働ならしたわ。今日は、しかも竹ぼうきを扱ったのよ。いつもは私が濡れ雑巾なのに」
「君がやるって言ったんだろう。それに、そんな風な言い方をするのなら、今日の駄賃はいらないな」
「いる。いるわ。はやくよこして」
金汚い。
実に金汚い女だ。
将来、ろくな女になりはしない。
そうは思ったが、しかしおれには駄賃をやらないという選択肢はない。なぜなら、これは慣例だからだ。
神社の掃除をして、お参りをする。そうしたら、最後にお駄賃百円だ。
「まだ、入っているの」
「まだあるさ。おばあちゃんは、相当ため込んでいたようだから」
「ふうん。貸して」
がらがらとうるさいアルミの貯金箱を、ベッドの上に居座る十雨に渡す。
中には百円玉が恐ろしい数入っている。おれが貯めたのではない。おばあちゃんが貯めたものだ。
そして、おばあちゃんが、おれに残したものだ。
「打緒、いくらとったの」
「失礼な。言っただろう。おれは中身には手を付けていないとも。本当だ」
「私がおばあちゃんの家からこれを見つけたときは、もっともうっと、重かったわ」
「それはお前に渡っているんだ。アイス代だって、おれの財布から出た金だぞ」
「打緒のときも、百円だったのよね」
「そうさ」
「なんで? なんでおばあちゃんは、お駄賃を上げたのかしら。ねだったの」
「ねだるわけないだろう。ある時、急におばあちゃんに渡されたんだ。今日のお駄賃と言って」
「ふうん」
「なんだ」
小さな両手でアルミの貯金箱を抱え込み、十雨は黙った。
まだ子供である。
急ブレーキと急発進は、子供の性分だ。
まれに大人でもそれらをする輩がいるが、あれは尻にダイナマイトでも仕込んであるのだ。
何かしていなければ落ち着かないから急いで何かをして、結局疲れて急に何もしなくなる。
嗚呼、うちの兄がその典型であった。
「私も、おばあちゃんと掃除したかったわ」
「仕方ない。おばあちゃんだって、好きでしていたわけじゃないんだ。あれは一種の、習慣だったから」
「好きじゃなかったのかしら。本当に」
「神社は好きかもしれないな。でも掃除が好きという人間を、おれは知らないな」
「それじゃあ、あてにならないわ。おばあちゃんは、掃除が好きだったのかも」
おれは――おれたちは――おばあちゃんが一体全体神社にどういう思い入れがあって、いつごろから掃除をはじめていたのかすら知らない。
何も知らないくせに、こうして後を引き継いでいる。
それは不気味なことだ。
おれも十雨も、単に浅ましい人間なのかもしれない。
すっとぼけた人間はいくらでもいるが、おれの下宿のおばさんやおばあちゃんは、気立てのいい出来た女だった。
おれたちには、おおよそ届かないのかもしれない。
十雨の懐に抱えられたアルミの貯金箱をみると、心の底からそう思った。
2
おばあちゃんが死んだ。
このことを聞いたのは、うちの母親からだった。
というのも、狭い町である。いつも一人で神社を掃除しているおばあちゃんが、とあるひと夏だけは、誰か知らぬ男と掃除をしているとわかれば一気に広まる。
そのうえ、おれの家は中学の時にこの、町に越してきた身分であった。生まれてからずうっとこの町にいるという人間も顔を知られていると思うが、下手に目立つような形で町にやってきたおれは、今ではすっかり町の人気者だ。
暇な老人どもがおれを見つけては遠くから何かを隠れるように話す。兄は一度、近所の小学生に「臆病者だ」と罵られたことがあった。何事かとわけを聞けば、簡単なことで。その子らの両親は、おれたち一家のことを、都会から逃げてきた臆病者だと、毎夜食卓で噂しているらしかったのである。
おれと兄は都会ではいじめられていて、おれたちの両親はそれから逃がすために、こんななにも見どころひとつない田舎に越してきたと。そういう尾ひれ付で、おれたちは見られていたというわけだった。
虫かごに入れられたように、くだらない日常を憂いているだけの退屈なぼんくらどもが作ったにしては割とできた話だが、事実はもちろん違う。おれたちがここに引っ越してきたのは父親の転職がきっかけで、それ以外に何も理由などない。
ないからこそ、噂されたのだろう。
兄は教師を殴りつけて、父さんに思い切り頬を殴られていたし、おれは同級生ともみあいになって、前歯を三本ほど頂戴してやった。父さんはおれを殴りつけはしなかったが、母さんは泣いて謝っていた。
みっともない。
不当に虐げられていたおれたちのどこに、非があったというのか。影のようにじいっと暮せと、そんなばかなことを言う大人なのか。
ただ、今回ばかりは、そのくだらない、下劣な住民どものつながりのおかげで、おれの両親のもとにおばあちゃんの死の知らせが入ってきて、おれに伝わったのだから、下品な人間も使いようである。
いや、もしかしたら、おれを痛めつけようとしたかったのかもしれぬ。
おれのせいでおばあちゃんは死んだ――とかなんとか。
実際のところは知らない。が、人の死にまでその下劣さを持ち込むような愚か者なのであれば、いつでもおれが殴りに行ってやる。前歯三本では済まさぬ。骨の三本は勘定に含まれるだろう。
三年の冬に帰省し、知らせを聞いたおれは、ストーブの前でじっとそんなことを考えていた。
そして、なんとかしておばあちゃんの墓に花を添えなければとも思った。
加えて、神社は、では秋から放ったらかしなのではとも思った。
高校生の時に買ったスキーウェアに身を包んで、おれはクリスマスなどという節操のない日に外に出かけた。
確か雪が降っていたように思う。
おれの町はよく雪が降る。
やれ隣の人間の敷地に積もった雪が自分の敷地にはいっただの、低劣なこの町の住民どもは毎日のようにいざこざを起こす季節である。
同じ下等な人間同士仲よくせよとも思うが、それができぬからこその下等さである。第一、「この雪はおれのもので、あの雪はお前のもの」だなんて、なんと傲慢なのだろうか。雪は雪だ。誰のものでもない。
この年の冬も、両親はそんな除雪事情に悩まされていた様子であったが、おれには関係のないことだ。
神社までの道中で何人かの人間とすれ違ったが、こうして帰ってくれば帰ってきたで、噂はされるものらしい。
悉く腐った町である。
曲がり角でおれの方を見て何かを話しているばばあ二人に向かって、一度「こんにちは」と大きな声であいさつしてやった。
やつらめ、おそろしく驚いた様子でおれを見ていた。普段見開かないものだから、まぶたも痙攣したいのではないか。
おばあちゃんを見習え。
あれはいい女だった。気立てがよくて、やさしくて、どことなく気品がある。この町にだって、できた人間はいたのだ。
石段は、案の定雪が積もって一本の坂のようになってしまっていた。
ざくざくと長靴で踏みしめながら上がっていると、ふと、耳におかしな音が入ってくる。
ざくざく――。
ざく――。
何のことはない。何者かがおれをつけているらしかったのである。
近所のくそがきなのかもしれない。ならば一度と言わず二度、痛めつけてやる必要がある。
そんな風に考えながら、思い切り後ろを向くと、そこにいたのは見知らぬ少女であった。
髪は鈍い金色。この豪雪地帯を歩く格好としてはいくらか不安が残るような、薄い防寒着を着ている。ミントのような淡いグリインのダウンに、下にはいているのはふつうのスラックスだったろうか。覚えているのは、信じられないことに、その丈が七分しかないということだ。
手袋、帽子、一切なし。
ざく、ざく――。
自分の肉体になにか恨みでもあるのか。執拗に痛めつけなければいけない理由でもあるのか。インドの修行僧には、自ら苦痛を課すという者もいるようだが、おれにはその少女が、なんらかの宗門に下っているようには見えなかった。
その歩みは遅く、おれはしばらく、上から少女を見下ろしていたのだが、いつまで経ってもやってこないので、しまいには下ってみせた。
「おれに、何か用かね」
「たぶん」
「たぶん?」
いよいよ不審である。
おれをからかっているのだとしても、いまいちキレがない。息も上がってしまっているし、今にも石段の上の真っ白な坂を下り落ちて行ってしまいそうだ。
「たぶん、私が探しているのはあなたなんだと思うの。たぶん、よ。確証はないの」
「ふむ。なら、誰を探しているのかを聞こうか。探し人の名前は」
「知らない」
「知らない? 名もわからぬ人間を探すのは、並大抵の作業ではないぞ」
「この神社を、掃除しているという若者を探しているの」
若者と、確かに少女はそういった。
いやに大人ぶった、かわいげのない子供だと思った。
「それはおれのことではないな。おれは、年末だからと実家に帰ってきた大学生なんだ。ここを掃除している人間ではない」
「私の探し人は大学生だわ」
「大学生なら、意外とこの町に多いがな」
「あなた、どうして神社に向かおうとしていたの」
「気の迷いさ。暇なんだ。今日はクリスマスだろう。こんな町でクリスマスを過ごすというのだから、これはもう気の迷いだ」
「ねえ、なんでそんなウソをつくのよ」
偉そうに金に染めた頭をした少女は、じいっとおれを見つめた。
十中八九、この町の人間ではないのだと確信した瞬間である。
この町には、おれを含め、そんな目をする人間はいない。
「おばあちゃんと神社の掃除をした若い大学生って、あなたのことでしょう。町の人にいろいろ聞いても答えてくれはしなかったけれど、そうに決まっているわ」
「悪いな。この町の人間は、よそ者に厳しいんだ」
「あなたもなのね」
「違う。おれは、そんなこの町の人間に厳しいんだよ。君が、この町の人間なんだと思ったから」
小学生くらいだろうか。
しかし雰囲気が大人びていて、中学生だと言われれば納得してしまう。
どちらであっても、頭を金に染めるようなやつがまともな学生だとは思わないのだが。
「やっと見つけた。ねえ、お話がしたいわ。上まで上がっちゃって、お話しましょう」
「おれは問題ないがね。君のその恰好はなんだ」
「あなたみたいな恰好の服、持っていないもの」
「両親は、どこにいる。女児を連れまわしているだなんて変な噂、立てられたくないぞ」
「親は家。仕事しているわよ」
「はあ? なら君は、一人で来たのかい」
「そうよ」
「片道千五百円で?」
「どうして値段まで知っているのかしら」
確信した。
まさかとは思っていたが、この少女はおばあちゃんの孫である。
この町の人間でなく、九つくらいの見た目で、おばあちゃんと繰り返していることを考えれば、すぐにわかった。
おれの察しがいいのではない。
それはまるで、この少女がおれにさっさと理解をさせてしまおうとしているかのようだった。
「ほら、上がりましょう。ふう。ちょっと休憩してから。足も冷たいし」
出会った時から、十雨は図々しかった。
この後おれは、結局この少女をおぶって神社に向かったのである。
3
冬の神社は雪が積もり、夏なんて問題にならないほど静かだった。
ちらちらと雪がこれでもかと降り続いていて、おれたちはさも当然かのように、屋に覆われた賽銭箱の右隣に腰を下ろしたのである。
「ほら、これを尻に敷といい。冷たいだろうに」
「いいの。帽子なんかに座っちゃって」
「まともな恰好をしてから、そういうことは言うんだ」
周りの雑木林は真っ白。
じいっと奥を見つめれば、雪景色は一枚の生物にすら見えてくる。昔から、おれはだだっ広い景色に一面雪景色というのが、好きでないのだ。
怖気がする。
世界の終りだなんてことが、もしそこまで迫っているのだとしたら、それはきっとこんな景色だ。
「それで、今日は、ここになにをしに?」
「ああ、おばあちゃんが死んでしまったと聞いて。神社の具合はどんなものかと見に来たのだよ。おれは、彼女が冬にどんな掃除をしていたのかも知らないものだから、意味があるかと言われれば難しいけども」
「おばあちゃんは、冬は掃除していなかったのよ」
「聞いたのかい」
「うん。おばあちゃんは、冬はお参りだけなのだそうよ。この賽銭箱の雪を――こうして――払ってから――お賽銭を入れる。それだけなんですって」
「ふうん。お参りは、かかさなかったんだな」
きっと五円に決まっている。
真ん中に穴の開いた、あの不恰好な小銭を入れていたに違いない。
「君は、おれに何の用かな。座ったのだから、早く聞かせてもらいたいものだけど」
「待って。その前に」
ダウンの前を開けて、ごそごそと何やら自身の腹部をまさぐる。
女性の所作についていちいち首を突っ込むものではないと、いんちきな二枚目は言うだろうが、おれの隣にいるのは少女である。
所作云々をとやかく言われるには、まだ早いだろう。
遠慮なく覗き込んでやる。
すると、見えたのは、ピンク色をしたウェストポーチだった。
「なんだい、それ」
「あ、まだ見ちゃダメ」
そのウェストポーチに時間的に変動するような価値があるものか。
どうせ見るのならいつ見ても同じに決まっている。
だが、左手でぐいぐいとおれの肩を押し返す少女のしぐさがあまりにも拙くて。おれはどうにも、気を折られてしまうのであった。
「あなたに、渡さなくちゃいけないものがあって」
「おれに? まだ知り合って間もない、君から?」
「私からじゃないの。おばあちゃんから」
出てきたのは、アルミの貯金箱だった。
安っぽくて、それでいて重厚さもない。
そのくせ、「これを、はい」とおれの膝に置かれた瞬間、おれは驚かされた。
重い。
やけに重い。
アルミの貯金箱だと思ったが、実は銭入れ口の模様の入ったアルミの塊なのかもしれぬ。
「ごめんなさい。開けて、見ちゃった」
「見た? 何を」
「お金。百円玉が、たっくさん」
手袋をはずして、アルミのふたを外す。
しゃりん、というアルミの擦れる音が響いて、林の中に消えていくようだ。
見給え。
雪はこんなにも、切ない。
「何もない」
「え? お金があるでしょう」
そうじゃない。
そういう意味で言ったのではない。
おれは、この時、きっとおばあちゃんから何らかの説明があると思っていたのである。
死者からの言伝が、きっとなんらかの形で存在しているものだと、考えていた。
しかし中身は一面鉛色。
見れば小汚い百円玉まで入っている。
「あなたにも、意味が分からない? おばあちゃんから言い渡されていたのだけど。『あのお兄ちゃんに』と」
「いいや、意味は分かるよ。わかるとも」
わかる。
これは、おれがもらっていたお駄賃だ。
おばあちゃんは、きっとこうして百円玉のみをせっせと貯めていたのだろう。世間の下劣な人間どもならいざ知らず、あのような細かいところまで気遣いのできる女ならばできるに決まっている。
そして、おれがもらっていた駄賃はここから捻出されていたものだったのだ。
掃除を終え、おばあちゃんの家まで道具をもっていってやる。
「それじゃあ」とおれが言うと、決まっておばあちゃんはおれに駄賃をくれた。百円一枚だ。これ以上もなかったし、これ以下もなかった。
買い物に付き合ったり、玄関先の掃除をしてやったりは、すべて終えて駄賃をもらったうえで、おばあちゃんが切り出すかどうかによってのみ取り決められていた。
これは、おれがもらいきれなかった駄賃である。
そして、おばあちゃんがわし切れなかった駄賃である。
「おばあちゃんは、これだけを残したのかね」
「ええ、それだけ。渡せばわかるから、と」
「ほかには、本当に何も?」
「そうよ。強いて言うなら、あなた以外は決して見てはならないと。――なあに、泣いているの?」
「どうだろうな。ともかく、苦しいよ」
悲しかったわけではない。
もちろんそういった情は、いくら無機質なおれでも持ち合わせはある。
だが、この時ばかりは、そういった類の感情はおれの中にはない。
今でこそようやく理解できる。
あれは、悔恨だ。
悔しいのだった。
あれだけ人の良いおばあちゃんが、おれに残したものが薄汚い銭などであったことが、とても悔しかったのだ。
おれの見立てに間違えがあるものか。
おばあちゃんは、器量良しで、出来た女だった。
だが、最後に金なぞという汚れたものを残していく、不出来な女でもあった。
それが、言いようのないほどに悔しかったのである。
「なあ、聞いていいかい」
「もちろん」
「君。君だ。君の名前は、何か。おれの名前は打緒。箙打緒というのだけど」
「急に、なあに?」
「急ではないんだ。おれはばかでない。同じ後悔は、二度もせぬ」
「十雨。櫛色十雨。あなたの知るおばあちゃんの、たった一人の孫よ」
「そうか、では十雨。聞きたいのだけど。遺品の整理は、君のご両親がしたのかね」
「そうよ。秋ごろにね」
「君のご両親は、おばあちゃんからおれの話を聞かされていただろうかな」
「どうでしょう。けれど、知らないことはないわ。だって、私がおばあちゃんから聞いていたあなたのお話を、たくさんしているもの。すべてじゃないわよ。たくさん」
「そうか。ならそうだな。どうだろう。おれは、今すぐにでも十雨のご両親に会いたいな。いや、合わなくちゃいけないことになったのだ」
「大変。急に用事ができるものなのね、大学生って」
「そうだとも。おれは数多いる大学生の中でも、とびきり急に用事が決まることの多い男なのだ」
言い知れぬ悔恨に包まれたのちの話。
おれは、十雨の両親と電話で話すことになる。
それは単純に、認めたくなかったのだ。
おばあちゃんがおれに残したものが、こんなアルミ缶ひとつなわけがない、と。
だからあの竹ぼうきをどうしたのかと、聞きたかったのである。
捨てていてみろこの人でなしどもめ、覚えていろ。
はやる気持ちを抑えもせず、おれは問うた。名を明かして、素性を明かして、すぐに問うた。
「おばあちゃんの家に、竹ぼうきがあったはずなんです。小奇麗とは言い難いのですがね。そこそこ大きい、いいやつなんです。覚えておられないですか」
返答は、簡単である。
もちろん覚えている――と。
なにせ、それの保護をしろと吠えたのは、この時おれの隣にいた小さな金の少女だというのだから。
4
「ねえ、打緒」
「なんだ」
「明日は、どっちをやりたい?」
「どっち? ああ、濡れ雑巾と、竹ぼうきか」
「うん。どっち?」
暗闇の中に、十雨の声が聞こえた。
何もないおれの部屋に敷かれた布団の中には、まず間違いなく小さな金髪の少女が身を収めているはずである。
「選ばせてくれるのかね」
「特別にね。今日は私が選んだもの」
「そうか。じゃあ竹ぼうきだな」
「やっぱり」
「予想通りか」
「もちろん」
ドア越しに、少しだけ人の声が聞こえた。
おれの両親だろう。
どうせいやらしい内緒話でもしているに決まっているのだ。
隣の部屋で兄がなにをしているかだの、おれの就職活動はどうだだの。くだらない。実にくだらない時間である。
「ねえ」
「なんだ。今日はやけに眠りにつくのが遅いな、十雨」
「気分じゃないの」
驚いた。
この少女、毎晩気分で眠っているときた。
大きく出たものだ。
十雨が賢いのは、こういった言い方ができるところなのだ。
頭がよくて、おれとは見えている世界がまるで違う。それでいて、兄のように下品にとらえているわけではなく、むしろおばあちゃんのように――。
「明日、宿題を見て頂戴。夏休みの」
「いいよ。算数か」
「うん。いい?」
「いいとも。明日な」
「本当に?」
「疑り深いな。どうしたんだ。今日の君は、ちょっと変だぞ」
夏は嫌いだ。
だが、こういう時間は嫌いでもない。
「こうして夏休み中打緒の家に泊まり込んでいることが、迷惑じゃないかしら」
「迷惑ねえ。今更だと思うがね。去年の冬だって、もっと言えば今年の春だって、十雨はおれの神社の掃除を手伝うために泊まりに来ているじゃないか」
「ねえ」
「なんだ」
「ねえ打緒」
「聞いているよ」
「お駄賃が百円って、安いと思わない」
「今度は文句かね」
「そうじゃなくって」
ごそりと、おれの隣で音がした。
遮光カーテンの隙間から入る薄い暗さが、十雨の瞳と金の頭を輝かせていた。
「私たち、何のために神社の掃除をやっているの」
「さあね。だが、君の言うように、金のためにやっているわけではなさそうだよな」
「そうよね。じゃあ楽しさかしら。私は、じゃあ打緒に会うために掃除をしているの。それとも、掃除をするから打緒と会えて、楽しいの? 一年中じゃなくて、たとえばひと夏だけ、楽しいの?」
「おれだって楽しいよ。打緒がいてくれて、楽しい。打緒が泊って行ってくれて、楽しい。一緒にパソコンでNBAを見る相手がいるっていうのは、すごいことなんだ。君はわからないかもしれないけどね」
ただきっと、そういうところに答えはないんじゃないかと思っている。
きっと、十雨も。
「おばあちゃんは、どうして掃除をしていたのかしら」
「さあな」
「楽しかったのかしら。私も、打緒もいないのに。お駄賃だって、もらえないのよ」
そういわれると、妙だ。
おれはおばあちゃんの何もかもを知らないが、こうして十雨に言葉にされると、それが一層奇妙なことなのだと感じさせられる。
おばあちゃんは、何のために掃除をしていたのだろう。
「おばあちゃんも、実のところはわかっていなかったり、するのかもしれないね」
「あのおばあちゃんも?」
「あのおばあちゃんも」
慣例。
そう、すべては慣例なのである。
おれにも、十雨にも、きっとおばあちゃんにも見えていないものだ。
「お金じゃないのだよな。おれも、十雨も。でもそれって、すごいことだ。おばあちゃんは、本当にすごいことをしていたんだと思う」
「うん。でも、おばあちゃんはそう思っていなかったかも」
「そうだとも。例えば、おれは音楽がない世界には耐えられそうにない。でもおばあちゃんは、それに賛同してくれただろうかな。またたとえば、十雨は冬にダウン一枚着て外に出ようとしていた。おれには信じられない。けど、十雨本人にとってみれば、どうだろうな」
「だって持っていなかったもの。スキーウェアも」
「その金の頭だって、おれに言わせればいかれている。なんだその頭はと、おれが教師なら両親を学校に呼び出している。でも。でもだぜ、十雨。そんなのはさ、薄い、表面でしかないんだ。そして。そしてだ。これはおれの経験上の話だから、間違いないのだけど。物事っていうのは、それがたとえ何であっても、表面っていうのはざらざらで薄汚れたように見えるものなのさ」
「ふうん」と短く発せられた十雨の語気はどこか楽しそうで、笑っているようにも聞こえる。
そんな風に聞こえたことが嬉しくて、おれはたまらず十雨の頭を一撫でしてみる。
触れてみても、何を考えているかはわからずじまいであった。
「打緒って、あれよ。あれだわ」
「なんだ。何かね」
「ピュア。ピュアで繊細な、臆病者だわ」
おれの両親は意地汚くて醜い連中だが、母の作る飯はこの世で一番美味く、父の運転するバイクはこの世で一番爽快感がある。
おれの兄はずる賢く、賢しいだけが取り柄の揚げ足取りだが、この世で一番、多く物事が見えている男だ。
そしておれは――おれは、どうなのだろう。
そのことを探すために、おれは明日も、小さな少女とともに、あの神社に向かうのかもしれない。
鈴虫すら鳴かない、そんな一晩のことであった――。
おわり
竹の社 ――後篇――
夏前に雪を降らせてみたかった。それだけで始めたこの作品でしたが、個人的にかなり気に入っています。ですが、NBA成分があるかどうかと言われるとかなり怪しい……。初志貫徹。次回こそはと息巻いておりますので、次の作品もぜひよろしくお願いします。
さて、この刹那主義で破滅的な人間であるところの私には、どうにも日々というのは甘美なものであります。蠱惑的で、恐ろしいまでにきらびやか。都会に移り住み、特に最近そう感じています。結局、どこであっても私は惑わされる存在なわけで。そこに田舎だとか都会だとかを言うのは、所詮後付に過ぎないのでしょう。人を見る。出来事を見る。何かと接するときは、どうにも外しがたいこの色眼鏡を外してみたいと思うのは、自分から見ても相当滑稽であります。
読了をいただいた皆様には、ひたすらの感謝を。本当にありがとうございます。また会いましょう。それでは。